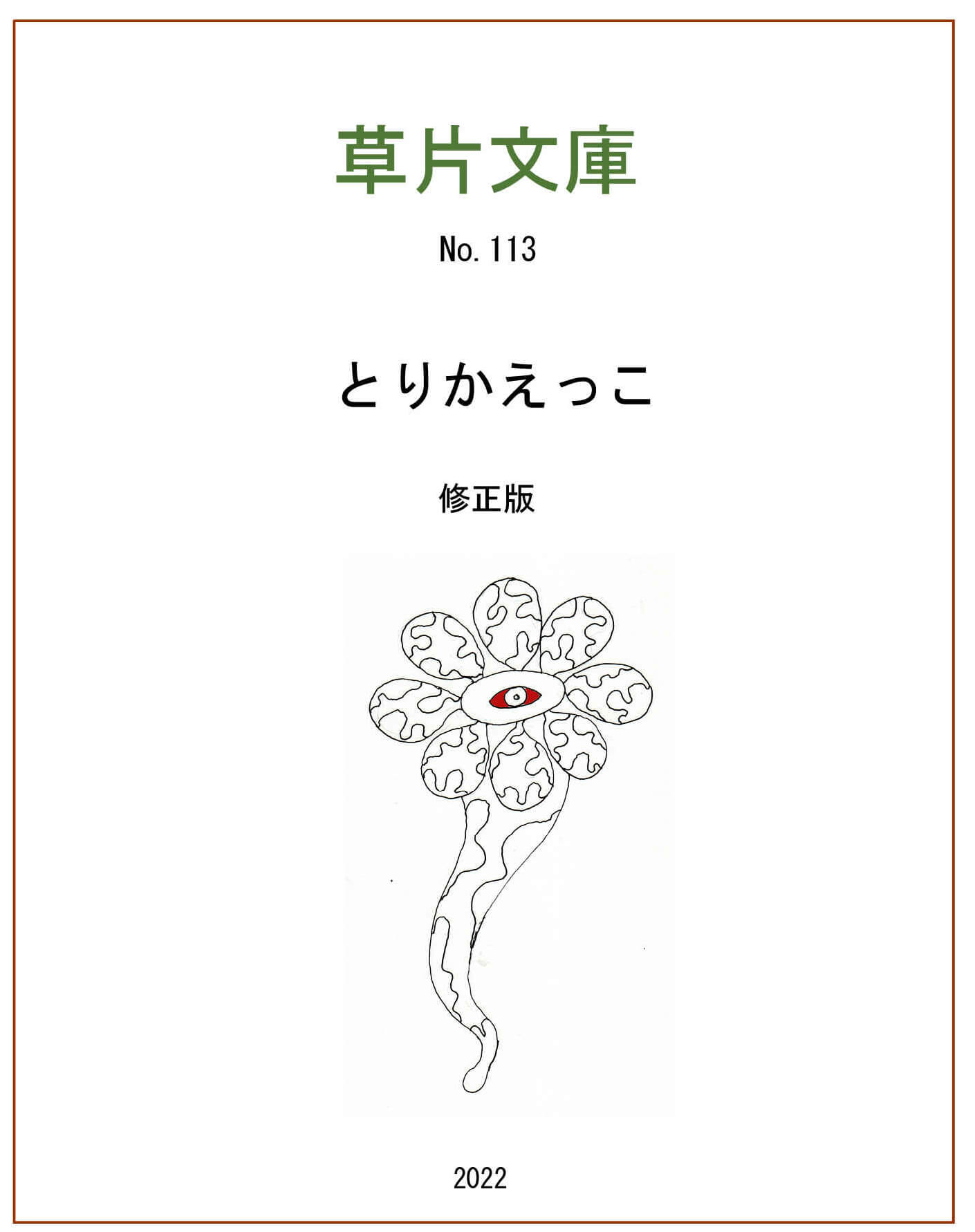
とりかえっこ
奇妙な小説です。縦書きでお読みください。
私の友人は、自分のもっているもの、他の人のものに取り替えるのが好きと言うより、生き甲斐だった。しかも必ず、あいてに渡すもの、すなわち、自分が持っているものの方が上等でなければ気がすまなかった。
どうしてそうなったか。彼は自分で告白をしたことがある。
小学生の時だ。ある一人の女の子が、いつもきれいな上等な服を着て、筆箱だって、銀座の伊藤屋で買ってもらったフランス製だった。入っていた鉛筆もドイツ製の青いステッドラーとかいう絵描きが使うものだった。彼女には取り巻きが何人もいて、女王様のように振る舞っていた。
私の友人はそういう女どものあつまりを興味なく眺めていたそうである。5年生の二学期になったとき、転入生がクラスに入ってきた。さっぱりした黒い服を着た女の子で、父親の仕事で小学二年のとき、フランスのストラスブルグに行って、戻ってきたということだった。日本語は少したどたどしかったが、問題なくみなと打ち解けた。
その子はフランスで買ったしゃれた筆箱をもっていた。中には日本のトンボの鉛筆だった。女王様の女の子はすぐその筆箱に目を付けた。漢字を書くのが少し苦手の転入生に近づいて、何くれとなく世話をやいた。転入生はその行為を素直に感謝した。
ある日、女王様の女の子がいつもとは違うセルロイドのそこいらで売っている青い筆箱をもってきた。
友人はそれに気がついて、あの伊藤屋の高い筆箱はどうしたんだろうと思ったそうだ。
女王様は転校生の机の前に行って、その青い筆箱をおくと中からステッドラーの鉛筆を出し、転入生に漢字を教え始めた。
転入生の席が友人の後ろだったので、皆聞こえてきたそうだ。
「いい筆箱ね」
女王様が言った。
「ええ、ストラスブルグで買ったの」
「私もほしいなー、どこかで売っていないかな」
女王さんがねだっている。すると、転入生は「いいわよ、取り替えましょ」
といって、入っていた鉛筆を机の上に出す音が聞こえた。そうしてとりかえっこをした。友人が振り向くと、女王さんはやったーという顔で、自分の席に戻った。転入生はにこにこして、何事もなかったように、漢字の書き取りに励んでいた。
友人は、転入生の少女を、かわいいなあとか、すてきだなーと少しは思ったが、ともかくかっこいいなーと思ったという。
友人は市立中学校に入学した。その転入生は東京の私立中学にいったので、それ以降会うことはなかった。あの女王様は地元の私立中学校だったので、ときとして町でみかけることがあったが、挨拶もしたことがなかった。
彼は中学生になって、陸上部と弓道部にはいった。彼の親は地元の中堅どころの卸会社で、それなりにゆとりのある生活をしていたこともあり、運動に使う靴や弓はかなりのものを買い揃えてもらうことができた。彼の頭の中にはあの転入生の女の子の顔ではなく行ったことがこびりついていた。
弓道部で一番安い弓を使っていた下級生に、自分の少しよい弓と取り替えてくれといった。下級生が理由がわからず、躊躇していると、彼は「その弓だと、今度の大会でいい成績を出せそうな感がするんだ」と言った。下級生は彼の持っている弓にはあこがれていたこともあり、それならばと取り替えた。
その結果、彼は個人優勝をして、その下級生もよい成績を出したことから、団体優勝を勝ち取った。
それは彼に大いなる喜びをもたらした。
中学生になって、買ってもらった時計を、同級生のものと取り替えたこともある。もちろん彼の時計はそれなりのメーカーのもので、同級生の時計はマイナーな会社のものだった。しかし、それ以降、卒業するまで彼は取り替えた時計をしていた。
高校に入ったとき、万年筆を叔父がお祝いにくれた。あまり万年筆を使う機会がなかったが、上着の内ポケットに入れていつももっていた。同じクラスの中に、将来作家になりたい子がいた。有名な年をとった作家が万年筆で原稿を書いているのをテレビで見て、その子は小遣をため、パイロットの万年筆を買い、よく自分の机で小説のようなものを書いていた。文芸部に入いった彼は、原稿用紙にむかって、いつも部室で清書をしていた。あるとき、友人がポケットにパーカーの万年筆を入れているのを見た、その同級生は、いい万年筆持っているね、と羨ましそうに言った。友人はすぐに取り替えっこをした、もし本がでたら、くれよなと言って、パーカを渡したそうである。
大人になって、本当にその同級生は作家になり、友人に、出版したたびに、本を送ってくるということである。
高校時代、友人は陸上部と今度はボクシング部にはいり、いい成績をだして、しかも、勉強にもせいをだして、よく知られる有名大学の政経学部にはいった。
そこで僕と同級生になったのだ。彼はアルバイトもしていたが、本もよく読んでいて、ずいぶん値の張る有名な哲学者の書いた本なども読んでいた。僕には高くて買えないほんであった。僕は学費をアルバイトでまかなっていた。食費ももちろんである。親は何とか下宿代だけは送ってくれていた。
彼は僕が読んでいた古本屋で買った、一冊100円の文庫本やぞっき本を、自分も読みたいからと、一冊と一冊といいながら、高価な哲学書と文庫本を取り替えてくれた。僕はいつか返そうと思っていたから、喜んで受け取っていた。
ある時彼に聞いた。
「君は何でも人が欲しがるとあげちまうが、本当に大事なものないのかい」
「そのときは大事だとそう思っていた」と答えた。
大事なものなら手元から放さないだろうと思い、そういうものがあるのか聞いた。
「なにが一番大事なものなんだ、一番大事なら人にあげたりしないだろう」
彼は首を傾げた。
「いのちかい」と聞くと、
「いや、そうじゃない、もしそうなら、いまのぼくはいない、誰かの命と取り替えっこしていて、死んでいる」と言った。
理屈である。
「僕はね、血が欲しいと言われると、あげてしまうんだ、だから献血車のそばには寄らないんだ、血をくださいと言われるとかならず献血してしまう」
「まあ、献血は向こうの方で、献血する間隔や、君の血液の状態などを調べるから、君には害がないだろう」
「そうだね、腎臓がほしいとか、肝臓がほしいとまだ言われていないが、そういう人が来たらあげるだろうな」
「医者が相談にのるから、コントロールされるさ」
「ほんとはね、大事なものだなあ、と思ったものが次の日は必ずしもそうじゃなくなるんだ」
「大事なものは毎日変わるのかい」
ときくと、そのようだ、と言う。
「永遠に大事なものがほしい」
彼女はできない、すぐ、誰かにあげてしまう、というかとられてしまう。彼が自分の元に長い間、自分のものとして、おいておけない性格を見抜かれてしまうから、彼女の気持ちが他の男に移ってしまうわけだ。
どうしてそうなったか聞いたところ、冒頭に書いたような経験をしていて、どうもそうなったんだ、と言った。ストラスブルグから転校してきた女の子が向こうで買ったとてもしゃれた筆箱を、取り替えてあげているのを見てからだ。その娘の性格のよさもあるが、筆箱をもらってしてやったりというクラスの嬢王の性格がいやだなーと頭に染み着いたこともあったからだろうという。
「直すことはできないのかい」
「直した方がいいだろうか」
「困ることがおきるかもしれないから、ほどほどにするようにしたほうがいいね」
「うん、そうすべきなのはわかっている、だけど、誰かが欲しそうだと思っていることに気づくとあげたくなるんだ、これは気に入ったと思って買うのだけど、欲しそうな目で見られると、そのものが大事じゃなくなるのかな、ものばっかりじゃないんだよ」
「ということは、買って自分のものにしてしまうからいけないんじゃないか、買わなければいいわけだ」
と僕が言うと、彼はそうだなという目で僕を見た。
「買わないで、自分のものとは何だろう、もちろん自分の身体以外だよ」
「なにがあるかな」
「そうだよ、友達というのは自分のものではないから、人にあげたりするようなものじゃないね、誰と友達になってもいいんだものね」
「そうだね、そういうものは問題ないんだ、きっと、友達のような立場のものをまわりのおけばいいんだね」
「そうだよ」
「どうしたらいい」
「みんな借り物にすれば、人にあげることはできないよ」
「そうか、君の言うとおりだ、着ているものや、文房具や、何でも借りればいいのか」
「そうしなよ」
彼はそれからすべてものを借りて使っていた。元々すんでいるのはリースのマンションだから問題はない。
彼はそうやって、私とともに大学を卒業して、九州の商社会社に入った。僕は東京の新聞社にきまったので、なかなか会うこともなくなった。
だが、ネットでは連絡を絶やさなかった。能力のある男だったから、仕事はバリバリやっていたようである。借りたマンションに、借りた家具や道具をそろえ、猫まで借りて、一緒に住んでいるという。
数年後である。彼はその会社の社長になっていた。そのころも、僕とはネットではやりとりをしていた。
ネットで、「だがなー、奥さんがほしいが、借りるというわけにいかないんでね、どうしたらいい」
と言う難題のメイルがきた。
そのころ、僕は結婚して、子供が一人いた。ふっと頭をよぎったのは、彼がすてきな人と結婚して、すばらしい奥さんじゃないかとでもいうと、取り替えようと言い出すのではないかと、変な心配だった。
借り物の奥さんは無理だな。奥さんの派遣会社などあるはずはないし、いかがわしい派遣会社になってしまう。万が一旨く結婚して、子供ができたら、かわいい子とでも言われれば、取り替えましょうと言いかねない。
すてきな奥さんですねと言われないような人と結婚すればいいのだろうが、そんな人は誰一人としていない、誰でもいいところはあって、魅力は感じられるものである。
さて困った。なんと返事をしていいのだろう。
奥さんともってはいけない宗教家になりなさいとでもいうか。妻帯が許されていない宗派もある。だが彼は奥さんがほしいようだ。
まず考えたのは、奥さんがほしいという考えをやめた方がいいということだ。
そのことをメイルに書くと、「なぜだい」と。わからないようだった。
「結婚をするということは、奥さんを自分のものにするわけじゃないよ、奥さんは一人の人間でいつまでも彼女は彼女のもので、君のものになるわけじゃない、合意の元に一緒に子供を作って、死ぬときも一人さ」
「確かに君の言うとおりで、理屈ではわかるけど、誰かが僕の奥さんがいいといったら、あげたくなる」
それじゃ困る。どうしたらいいんだろう。
「いい方法がないかしばらく考えさせてよ」
と、メイルをおわらせた。
それにしてもどうしたらいいのだろう。
それから一月ほどして、彼からメイルがきた。
「結婚するよ、解決したんだ、会ったときに話すよ」
ほどなくして、結婚式の招待状がきた。
九州の博多の一流ホテルで披露宴だ。そこを宿にとった。
ホテルの会場に行くと、彼がやってきて、にこやかに「久しぶり」と手を挙げた。連れてきたのは、誰でもがきれいでかわいらしい人と思うほどの魅力のある人だ。
「これが彼女、僕の奥さんになる人」と相手を紹介してくれた。とりあえずおめでとうと言ったのだが、すてきな奥さんだねえと言いたかったのだが、喉まで出掛かって、やめた。かれが「それじゃお前にやるよ」といいかねないからだ。
彼は笑いながら「おい、言いたいこといえよ、俺はもう前の俺じゃないよ」
といって、「式が終わったら、話すよ、俺たちも今日はこのホテルに泊まるから」
彼女と式の用意をしに行った。
夜になり部屋の電話がなった。
彼からだった。ラウンジに来いと言うことだ。
十五階のラウンジに行くと、彼が一人でビールを飲んでいた。
「奥さんは」
「後でくるよ、その前に君には話しておきたかったんだ」
そういって、僕のビールを頼んでくれた。
「いや心配かけたからな」
「どういうことなんだい」
「なおったんだよ、普通になった」
「どうして」
「自分の好きなものを人にあげてしまう僕の性格を気に入った人がいてね、欲しいっていうんだ」
「性格をかい、性格を人にあげることができるのかね」
「できたんだ、きっと性格じゃなくて、病気だったのかもしれない、移ったんだよ」
「それでなおったのかい」
「うん、さらに社長になった、前の社長は会長になった」
「どういう意味なんだ」
「僕の性格をほしがったのは社長でね、社長に性格をあげたんだ、そのあとね、僕がお嬢さんをほしいっていったら、社長が一番大事にしていた娘さんを僕にくれたんだ」
「ほら、ワイフがきた」
ラウンジの入り口に彼女がきた。化粧を落とした彼女は本当にきれいだった。
「いや、きれいなひとだね」
彼はそれを聞いてうれしそうに「ありがとう」といった。あげようとは言わなかった。
「別荘ももらったから、家族で遊びにおいでよ」
と誘われた。
昔だったら、いい別荘だねと言うと、僕のものになったかもしれないと思うと、何とも自分の根性がさもしく感じられはずかしくなった。
「どこにあるの」
「長崎の小さな島にあって、島ごともらっちゃったんだ」
「是非行くよ」
それに、彼にそうっと「会長さんのものは、みなほしがったほうがいいよ、それじゃないとみんな他の人のものになっちゃうから」と言った。
彼は「うん、言われなくてもわかってる、前の自分の性格だから」と笑った。
奥さんが彼の隣に座った。
にこっと微笑んで、僕を見た。
「これからもよろしくお願いしますわ」
前のままの彼だったら、べたべたに褒めて、自分の嫁さんと交換できたのにと、残念に思うほど、素敵な女性だった。
とりかえっこ


