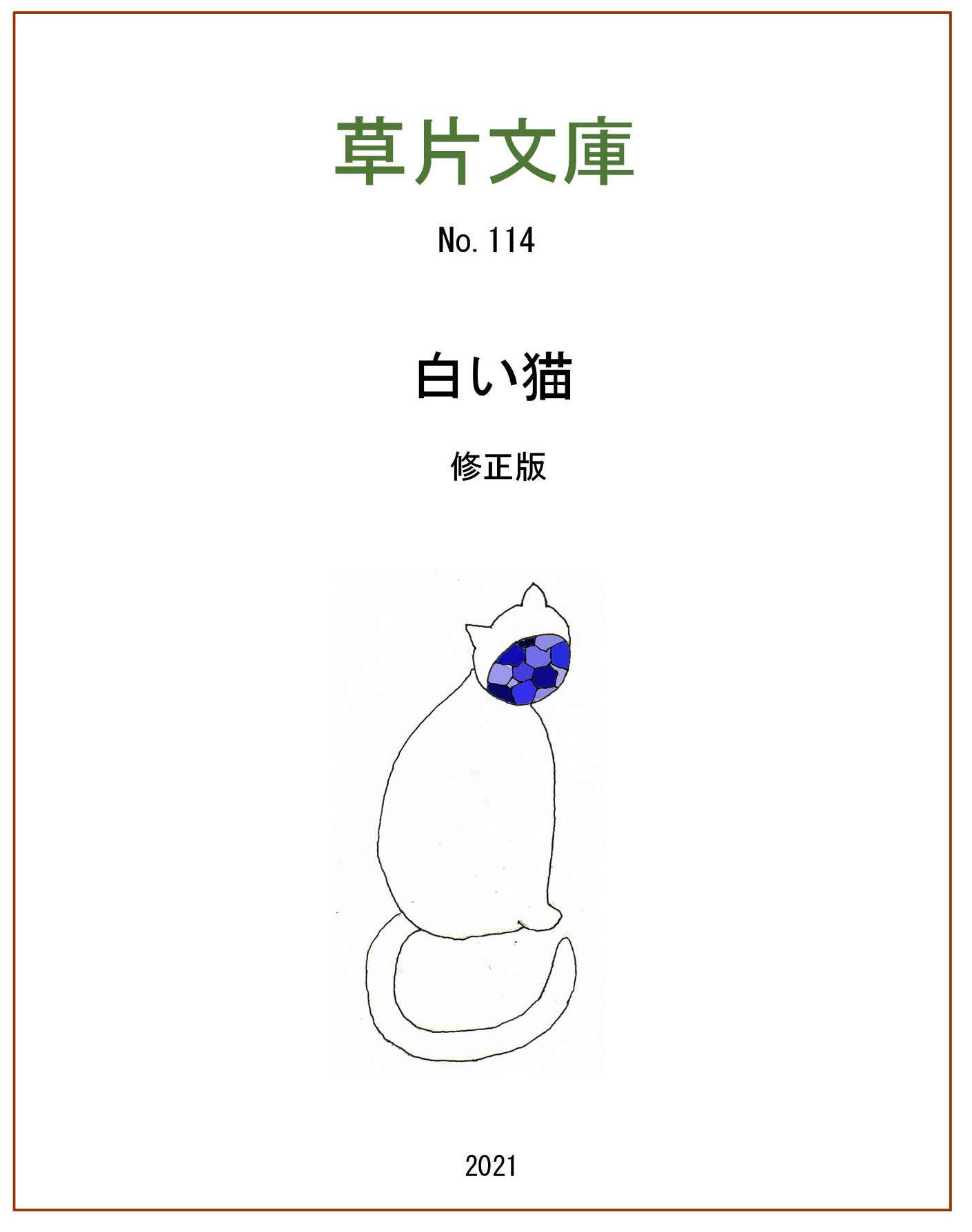
白い猫
白い猫ミステリー 縦書きでお読みください。
二年前にコロナが収束し、やっと世の中が落ち着いて、自分も大学三年になった。まともな対面教育を受けることができるようになり、就職先も内定した。
四年になった年は、なぜか太陽の黒点が増えて、時期嵐が来ているということだったが、我々の生活には、支障などあるわけがなく、卒業研究を気持ちよく進めていった。十月になると、どうやらできあがり提出を終え、十一月には卒業がほぼ確定となった。
そうなると、卒業旅行である。冬の温泉につかろうか、ということになり、クラスメート六人で、秋田の温泉宿に行くことにした。宿は山間にあり、周りには小高い山が連なっている。格好のスキー場である。特によく知られたところではないのだが、旅好きのクラスメートがみつけてきた場所である。三泊四日の小旅行である。スキーをしなくても、雪の山歩きも楽しいし、何よりも温泉がいい。
宿は大きくも小さくもなく、木造の二階屋で築二百年になるという、歴史を感じる建物だ。修繕しながら使っているという。内湯と露天風呂があり、露天風呂の雪景色は、自分にとってもは初めてであり、いつまでも浸かっていたい気分になった。もてなしも素朴で、社会にでたらもう一度きてみようと思う宿であった。
六人のうち三人はスキーが目的、自分を含み残りの三人はのんびりと、雪の中を歩いて温泉にはいるのが目的である。強いて言えば写真でもとるかというところである。
着いた日は温泉と夕食を楽しみ、活動は次の日からだ。三人はスキーを担いで、のこりの自分と二人の女性は、写真機をもち、ザックを背負って、スキー場の脇の道をのぼった。
上に着いて、三人はそれじゃあといって、スキーをつけ滑る用意をした。そんなに長い距離ではないので、あっという間にしたに行ってしまうのではないだろうか。と思ったが、三人ともまだ経験が浅く、この程度がいいということだ。リフトがあるが今は動かしていない。スキー客を呼ぶことはあきらめている感じだ。
我々三人はスキー場の上から、山の尾根をゆっくり歩き始めた。
雪は目を見張るほど積もっているわけではないが、木々の間に積もった雪は、東京では感じることのできない、新鮮さをもたらしてくれる。時々、どさっと、木の枝から雪が落ちてくる。反対側の高い山を見ると、やっぱり白一色で、木々の上にもこもことつもっている。秋田にきているという実感がわく。
しばらく歩くと、西斜面が開けた雪の原になっていた。木が生えておらず、夏には草地になるのだろう。
「あれ見て」
一人の女性が雪の中で動く白い小さなものを指さした。緩やかな斜面の雪の上で、何かが飛び跳ねている。
「兎じゃない」
我々は少しばかり尾根から下に降りた。急な坂ではないので、危ないこともない。雪の原にところどころ丸く雪が積もっているところがある。降りながら、その高まりを触ったら、雪が落ちて、切り株の端が見えた。丸っこく雪が盛り上がっているところは切り株のようだ。この斜面に生えていた木はみな切られている。本来なら林だったのだろう。スキー場にでもしようとしたのだろうか。
ちょっと降りると、小さな白い生き物は、兎の子供であることがわかった。
自分もそうである。
写真機を構え、ズームをひいた。子兎が三匹、じゃれあっている。
女性たちも写真機を持っている。彼女たちは写真部なので、自分よりも写真に関しては詳しい。自分のカメラは確かに一眼だが、お任せでしか撮ったことがない。
彼女の一人が「きっと、どこかに親がいるんだろうな」とつぶやいた。
自分はディスプレーの子兎たちを見ていて、どこかおかしいと感じた。
三匹の白い兎はぴょんぴょこ跳ねて、シャッターを押すタイミングを探す暇がない。ともかく何枚も撮った。彼女たちの一人は連写をしているようだ。
自分はカメラから目を離し、下のほうにいる子兎たちを自分の目で見た。
やっぱり何か違う雰囲気がある。伸びやかに飛び跳ねている三匹だが、遠目に見ると、一匹の動きが、ほかの二匹とどこかずれている。
もう一度ズームにして、ディスプレーをみた。子兎だから、耳はさほど長くは見えないが、動きの違う一匹は、さらに短いような気がした。それに顔が丸い。真っ白であることは同じだが、どうもおかしい。
二人の同級生はもうカメラを別のところに向けていた。一人は木の枝から落ちる雪をとらえようとしている。もう一人は、切り株につもった丸い高まりや、風によって作られたと思われる雪の上の紋をねらっていた。
「雪の作る造形はすごいわね、もう少しその辺歩こう」
尾根の上に戻っていく。自分はディスプレーをみていて、動きの違う一匹は猫にみえてきた。そうだ、尾っぽがあるじゃないか。白い長い尾っぽがある。
兎の子供に白猫の子供が混じっている。
「いくわよ」
尾根に戻った二人が声を上げた。
「いまいくよ」
と、カメラから目を離して、兎を見ると、大人の兎が現れた。母兎だろう。子兎は母兎に向かって突進し、あとをついて、降りていってしまった。
あれは猫だったと思う。見間違いだろうか。
二人の女性に「あの小兎の一匹がおかしくなかった」と聞いたのだが、「なにが」といったので、猫に見えたとはいいづらく、「なんだか」と答えて終わってしまった。
二泊三日の雪のたびは楽しいもので、いい思い出になった。
家に帰った、撮った写真をPCで拡大してみた。やっぱり、小兎の中の一匹は白い子猫にしか見えなかった。
大学にいって、もう一度、みんなで喫茶店に集まろうということになった。そこでは、やはり雪の中のすごさ、綺麗なことの話になった。一緒に歩いた二人の女性に、「山の斜面で見た子兎の一匹がやっぱり猫のようだよ」と言ったら、彼女たちは、「なにいってるの、子兎がかわいく写っていたわよ」と、その後、写した写真をメイルで送ってくれた。ただ、三匹が転げ回っているところが写っていたが、三匹の顔と尾のところが同時に画面に写っているのはなく、それだけだと確かにみな子兎だ。
「いい写真がとれて、どれか、写真の賞に応募しようと思っているの」、と二人ともメイルに書いてきた。
彼らとは卒業式まで会う機会はなかった。
卒業式のとき、彼らは春休みにどこかにまた行こうと計画を立ててくれたのだが、自分は会社の入社式までに読んでおくように、就職先から貿易に関わる法律や、関税の分厚い書類をわたされ、とても時間的に余裕がなく、残念だったが行くことはできなかった。彼らの数人で暖かい九州に旅行に行ったと、メイルで写真を送ってきてくれたが、それどころではなかった。
就職先ではともかく、春休みに勉強したかいがあって、仕事にすぐなれた。先輩たちもいい人たちで、とても勉強になったし、仕事はつらいようなことはなかた。来年は、自分の貿易担当の地域が決まり、言葉はもちろんだが、相手の国の産業について熟したうえで、その国を先輩と回って、商談の雰囲気を学ぶことになる。
そうなると、もう自分の自由になる時間はほとんどないだろうと思い、初めての夏休みに、クラスメートと行った、秋田の温泉にもう一度行きたくなった。夏の温泉もいいだろう。一緒に行った連中に声をかけたのだが、それぞれ、違う方向にすすみ、日程があわないどころか、夏休みがない会社もあり、一年目から余裕だねと言われてしまった。
仕方がない、一人旅をすることにした。今年も太陽の黒点がたくさん現れ、磁気嵐がひどいそうだが、特に自分に感じられるような、気候の変化は感じられない。ただ、昨年と同様にずいぶん暑い夏である。こういうときに涼しい地方に旅をするのはいい。
宿は少し割高だが、一人でも泊まることができた。女将さんは、覚えていますよと、声をかけてくれた。食堂は広い座敷に、様式のテーブルと椅子がおいてあった。前にきたときは、座布団に座って食べたのだが。最近はこんな田舎にまで外国の方がいらっしゃるので、変えたのですよ、と女中さんが言っていた。
食事が運ばれてくると、女中さんについて、真っ白な尾っぽの長い猫がついてきた。
女中さんが、自分のテーブルにご飯をよそいにきたら、猫もとことこついてきて、自分を見上げた。赤っぽい目をした、ちょっと不思議な顔の白い猫だ。
「雌ですか雄ですか」
手を出すと、丸っこい顔をこすりつけてきた。
「雌なんですよ、今年になって、四月頃だったかしら。近くの猟師さんが、連れてきて飼ってくれないかというんです、なんでも、猟に行って兎をしとめたら、そばにこの猫が兎にこすりついて鳴いていたのだそうです。まるで母猫に対するような仕草で、人を怖がらなかったので、連れてきたということなんです。猟師さんはこのあたりでは少なくなった熊うちで、家をあけることが多いので、飼えないということでした、それで女将さんがうちの猫にしたのです」
それをきいて、どきっとした。子兎と一緒に遊んでいた猫を思い出したからだ。あの猫も真っ白だった。猫を見ると猫も自分をみた。覚えている?という顔だ。
自分はうなずいて、「何という名前です」
「白、っておかみさんがつけたんですよ」
「兎と一緒だったからですか」
「ええ、それもありますけど、白兎のようにぴょんぴょんとはねるように走るんですよ、それで、白」
女中さんは笑って、次のテーブルに行った。白い猫もついていった。尾っぽを立てて、しゃなりしゃなりと歩いていく。兎じゃないな。なんとなく一人で笑った。
このあたりは夏でも夕方は涼しくて気持ちがいい。露天風呂に入って、風に吹かれるのは都内では味わえない。
男用の露天風呂にはいっていると、白がのそのそと、風呂の脇を横切って、裏山の方に歩いていった。
自分しか入っていなかったので、「白」と声をかけると、ちょいと振り返って、赤い目でこちらを見ると、ああ、あのときの大学生か、といった顔をして、長いしっぽをぴょこぴょこうごかして、行ってしまった。
露天風呂からでて、帳場のあるエントランスのところにくると、白がみやげ売場の入り口で顔を洗っていた。
「もう戻っていたんだ」
独り言のように、白の頭をなでると、にゃーと声を出して自分を見た。
「白はさあ、山に行って、誰かと会って、もどってくるんださ」
通りかかった番頭さんが笑顔で言って、白の頭をなでていった。
みやげ売場に、冷えた生ビールお持ちしますと張り紙がしてあった。缶ビールもうっているが、やっぱり生がいい。帳場にほしいことを言うと、すぐもってきてくれるという。
部屋に戻って、窓の外の景色を眺めていると、女中さんが生ビールをもってきた。
「どうぞ、内線0を回していただければすぐにでももってきましゅで」
おばあさんに近い女中さんが、窓際のソファーに座っている自分の前にビールをおいた。
「ありゃ、白がついてきちまった」
見ると、白が部屋の中に入ってきて、自分のそばにやってきた」
「すみましぇんな」
「いや、かまいませんよ、後で出しておきます」
「猫はお好きそうで」
「ええ、好きですよ、動物は」
白は自分が前のソファーに飛び乗るとおちゃんこをした。
「この猫は、お客さんが好きで、くっついていって、かわいがられているんですよ、そのまま、朝までいることもありますよ、若い女の子のお客さんなんて、大喜びで、帰り際にもらえないかなんて人もいましたなあ」
「朝までいてもかまいませんよ」
「ちょっと前に、白が朝までいた男のお客さんが、白がいたらいい夢を見たよ、なんて言ってましてな」
「朝までいて、おなかが空かないのでしょうか」
「朝と夕にだいたい時間を決めてやっているので、大丈夫のようだなあ、ごゆっくり、空いたジョッキは部屋の前に出しておいていただくと助かります」
そういうと、女中さんはもどっていった。
うまい。
白が、飲んでいる自分を見て、喜んでいるような顔になっている。顔面に毛の生えている猫でも、目を見ていると笑っているのがわかる。
白い雪の季節もいいが、夏の緑の季節も、秋田の山の中は気持ちがいい。
あっという間に飲んでしまって、やっぱりもう一杯飲みたくなった。立ち上がって、白に手をだすと、頭を押しつけてきた。電話でビールを頼み、ソファーにもどると、白がテーブルを横切って、自分の膝の上にきた。柔らかい毛並みが気持ちいい。
「あれ、お客さんの膝の上にのっかっちまっているんで、大丈夫ですかね」
ビールを持ってきた若い女中さんは笑いながら、ジョッキをテーブルの上に置いてくれた。
「大丈夫ですよ」
女中さんが空のジョッキを持って出て行くと、白がニャアと鳴いて、新しいジョッキを傾けている自分の顔をみた。
「うまいねえ」と声をかけると、「ほんと、おいしそう」と、声が聞こえた。
もう酔ったかと、白の耳を摘まむとすうっとのびて長くなった。尾っぽを触ると、長かった尾っぽがシューっと縮まって、ころっとした。ぴくぴく動く。白兎だ、と白を見ると、白い猫だ。また笑っている。
ジョッキをもってない方の手を、白がじょろっとなめた。ざらざらしている。猫だ。
明日は一日なにをするか。山をぶらぶら歩いて、植物の写真でも撮るか。と計画をたてていると、とことんややまがいい、という声が聞こえた。とことんやまは、スキー場やキャンプ施設のあるところだ。
そうか、去年兎の写真を撮ったところに行くのもいいだろう。雪で真っ白だったところが、夏はどのように変わっているのか。
ビールを飲み終わると、白は自分の膝から降り、長い尾っぽを水平に揺らしながら、出口の方に向かった。自分も空のジョッキを持って後をおい、戸を開けジョッキを廊下に出した。白は廊下にでると、振りむくでもなく、ゆらゆらと階段の方に歩いていった。
もう一度、露天風呂に行くことにした、遅くなると男女が入れ替わるはずだ。
入ってみると、どちらも宿の裏の山に面しているので、景色はそんなに変わらない。誰も入っていない。自分が湯にはいると、白が現れ露天風呂の脇を歩いていく。まただ。ちょっと立ち止まると自分を見て、にゃっと鳴き、藪に入っていった。
明くる朝 大広間で食事をしていると、ビールをもってきた女中さんが、お茶をもってきた。
「おはようさんで、よう眠れましたかね」
「ええ、やはり、このあたりすずしいですね」
「白は一緒でしたか」
「いえ、あの後部屋から出ていきましたよ」
「そうでしたかね、男の人が一人で泊まると、必ず、夜はそこの部屋に入り込んで、一晩いるんですよ、それでね、男の方が帰るときに、白がふとんにはいってきて、いい夢を見たとおっしゃるんで」
どういうことかわからないといった顔をしていたのだろう、女中さんは、
「男さんの楽しい夢ったらねえ」と笑った。
「夏だから、ふとんにははいらないんじゃないですか」
「そうだね、白には初めての夏だもんね、ごゆっくり」
食後、カメラを持って宿をでた。旅館の前の県道をいくと、スキー場のあるとことん山に行く。道路の反対側は山に挟まれた小さな川が流れている。
ぶらぶら歩いていくと、程なくスキー場、とことん山入り口の看板が見えてくる。
そこを曲がると、町営のスキー場とキャンプ場の管理小屋がある。キャンプ場にはかなりの人がきているようで、数台の車が止まっていた。バンガローよりもう少し上等な家が、林の中に点在している。子供たちが走り回っているのが見える。
左側斜面がスキー場になり、草原になっている。脇には上にのぼる道がある。前にきたときは雪に覆われていた。上っていくと、周りの山がよく見えるようになっていく。
リフトの終点から、のぼってきた道を隔てて、小高い丘の連なりが見える。道の反対側には小さな流れがあるはずだが見えない。
そこから去年と同じように尾根づたいに歩いた。林の中は少しひんやりする。前歩いた記憶を頼りにしばらく行くと、木が切られている斜面にでた。やっぱり草の中に切り株が転々とある。雪が盛り上がっていたところだ。この斜面で兎の親子を見たのだ。子兎の一匹が猫のように見えたのだ。
なぜ木を切ってしまったのだろうか。ここもレジャーの施設でもつくろうとしたのだろうか。スキー場にしては小さいし、目的はわからない。
兎が出てこないかと見ていると、斜面の下の方で、白いものが動いた。兎かと思ったが尾っぽが長い。猫のようだ。白ではないだろうか。斜面をあがってくる。ひょいと大きな切り株に乗った。やっぱり白だ。すると、その後ろの草ががさがさとうごいた。白はその気配で、切り株から飛び降り、走り出した。後ろから何かが追いかけている。薄茶色の動物だ。耳が長い、兎だ。自分はあわてて写真を構え、シャッターを押した。
白が追いつかれた。兎が白の背に乗りかかっている。なんだ。交尾しているのか。そんなはずはない。兎が身体をふるわせると、白がにげた。また、兎が追いかけていく。下におりていく。あっという間に林の中に消えていってしまった。
じゃれているようにはみえなかった。写真機のディスプレーに撮った画をだしてみると、交尾のようなかんじだ。ズームにしてみる。白の顔はよくわからないが、白の背の上にいる兎の顔はしてやったりという顔だ。だが兎が猫と交尾をするわけはない。遊んででもいたのだろう。去年ここで一緒にいた子兎かもしれない。白は宿の裏山づたいに、兎に会いにここに来ているのではないだろうか。
また現れないかと見ていたが出てこなかった。
尾根をさらに歩いていった。木に囲まれて歩くのは、気持ちのいいものだ。森林浴はきからでる何とかという物質が働くからだと、宣伝で読んだことがあるが、まさにその通りである。
しばらく歩いたのち、スキー場に引き返した。斜面をキャンプにきている子供たちが走り回っている。
下に降りると、大きな切り株のところに人が集まっていた。管理小屋の人らしい女性が、周りの人たちに説明している。
切り株の周りに真っ赤な指のようなものが生えている、手のような形のものもある。
「この火焔茸はめったにでないのですが、今年はたくさんでています、さわると皮膚がただれ炎症をひき起こします、お子さんたちばかりでなく、大人の人にとっても大変な毒キノコです、食べると死にます、脳にひどいダメッジをあたえます、是非気をつけて、お子さんを守ってください」
「もし触ってしまったらどういたらいいですか」
質問がでた。
「水で洗ってください、すぐ管理室の方にきてください、ひどかったら救急車を呼びます」
ずいぶん恐ろしいキノコがあるものだ。こんな話が聞けるのも秋田らしい。まだ八月の半ばなのにもう茸だ。
珍しい話が聞けて満足し、いったん宿に戻った。宿でお昼を頼むことができる。このあたりの名物のうどんも食べられる。稲庭うどんといった。しかも部屋に持ってきてくれる。
持ってきた女中さんに、白を山の中で見たことを話した。
「あんこは、よく山さ行くからね、どっかの猫にとっつかまらなきゃいいけどね」
「どこかって」
「このあたりの家は、みんな猫を飼ってるからね、大人になったばかりの雌猫は、みんなねらわれとる」
そういって、女中さんは「あら、ゆっくりたべてたんしょ」と最後は方言丸出しで部屋を出ていった。
兎とつるんでたとは言わなかった。
うまいうどんだった。食べたあとすぐに川に降りてみた。小さな流れだが、きれいな水で、石の間を泳ぐ魚が見える。反対側は山の斜面で、木々が生い茂っている。
木々の間に動くものが見えた。猫のようだ。数匹の猫が何かのあとをついているようだ。白黒、茶虎、さび、三匹いる。三匹がいきなり走り出した。薄茶色のものが逃げていく。兎のようだ。先頭の茶虎が追いついて、兎の上に乗りかかった。
兎が食いつかれたらかわいそうだなと見ていたのだが、どうも違う。馬乗りになっている猫は兎の首もとにかみつくと、腰をふるわせた。交尾をしてるんじゃないか。
午前中は白が兎に交尾されているような光景を見た。今度は兎に猫が交尾をしている。どうなっているのだろう。あわてて、カメラを向けてズームで引き寄せ写真を撮った。春まだ早い時期に、蛙の雄が流れている板切れや、他の雄に抱きついて離れないという映像を動物番組でやっているのを思い出した。動物は本能行動だから、反射的にそういった行動が生じるんだと、説明していたようだ。だが、都会ではそんな光景をみることはない。兎と猫が種を間違えることはないだろう。というのも、その番組で、ほ乳類は視覚もだが、嗅覚が大事で、発情した匂いが引き金になって、それは同じ種の相手にしか通じないものだというようなことを言っていた。
秋田のこのあたりは鷹揚なのだろうか。兎はまた逃げ、猫は山の上の方に追いかけて見えなくなった。
名前がわからないが、岸にきれいな花が咲いている。写真を撮りながら河原を歩いていき、下流の方で県道にあがった。道の脇にはところどころに、宿屋はもちろんだが、そのあたりの特産品の販売所や、雑貨屋があった。特産品を売っている店には、野菜の漬け物や、とり立ての野菜もおいてあった。会社へのみやげはなにがいいか見て回ったが、特に思いつかない。宿の販売店で買うことにして、店を出ようとしたら、白が駐車場の方から歩いてきた。こんなところまで遊びにきているのだ。
自分の脇にくると、見上げてにゃーと鳴いた。頭をなでてやると、こすりつけてきて、そのまま店の方に行ってしまった。
秋には紅葉がきれいだそうだ。この温泉郷の夏は山の中を楽しんだり、川に行って水遊びがいいそうだ。それにやはり温泉に浸かって、ビールを飲むのが一番のようだ。
そう思って、もう宿のほうにもどることにした。
どどどどという音が響いてきて、立ち止まって見ていると、ハーレーダビッドソンの集団がやってくる。自分の脇を通り過ぎて、あっという間に行ってしまった。千ccクラスの大型バイクが六台も連なっていくと、戦車が全速力で通り抜けたようだ。そのあとは静けさがもどった。乗っていたのはおそらくいい年の人たちだ。最近は退職してから、大枚をはたいて大きなバイクを買って楽しむ人が多くなったという。
足元を見ると、白が道の端でおちゃんこをして、自分がくるのを見ていた。いつの間にか追いついたようだ。やっぱりバイクに驚いて立ち止まっていたのだろう。
自分が歩き出すと、白も歩きだし、あとをついていきた。そのまま宿の入り口に着いた。
帳場にいた番頭さんが、「おやおや、白と一緒におでかけでしたか」と白髪交じりの太い眉毛を下げて、にこにこと声をかけてきた。
「あの土産物屋で一緒になって、帰ってきたんです、ずいぶん遠くまで遊びに行くんですね」
「そうですね、兎と一緒にいたということだから、このあたりは白の庭のようなもんで」
番頭さんが白を抱き上げた。白が番頭さんの顎をなめた。
「今日泊まる人たちが、これからきますから、今、露天風呂は貸切ですよ、どうぞ楽しんでください」
番頭さんは白を床におろした。
「そのつもりでもどってきました」
「このあたり、特に見るものはないですからね、山歩きぐらいでしょう、楽しめるのは」
「お土産を買おうとおもってますが、なにがいいですか」
「このあたりはうどんが有名だし、塗り物もあるけど、手頃なのは乾麺あたりでしょう、饅頭もあるけど、まあ茸饅頭は都会では珍しいかもしれんけど」
うどんと茸饅頭をいくつか買った。会社の同じ課の人たちへの土産である。
その夜、八時頃だろう、また、生ビールを部屋に持ってきてもらった。風呂に浸かった後はどうしても飲みたくなる。今度も、白が女中さんと一緒に入ってきた。
「どうぞ」
昨日とは違う人だ。
「あら、すみません、猫が入ってきたしまった」
白を外に出そうとしたので「いいですよ」と、声をかけた。
「そうですか、猫の嫌いな人もいるから」
と、一緒にでてしまった。本人が猫嫌いなのではないだろうか。ものたりないので、戸を開けてみた。女中さんはいなかったが、白は入り口でおちゃんこをしていた。自分を見上げると、スルッと脇を通って、昨日のように窓際のソファーの上にのった。
自分も腰掛けて、ビールを飲み始めたのだが、「おいしそうね」と声が聞こえたような気がした。窓から庭を見ても人がいる様子はない。
ジョッキをテーブルにおいて、前にいる白を見ると、「遠慮しないでどうぞ」と声がする。
白を見ると、にこっと笑った。猫が笑うわけはない。
ビールを飲み終わり、まだ飲み足りない感じだ。もう一杯たのんだ。昨日と同じだ。
持ってきた女中さんが「おや、猫が入ってますね」と気にするようだったので、自分が連れてきたんだと言った。
「それならいいんですけど、空のジョッキは廊下に出しておいてください」ともどっていった。
白は椅子の上で丸くなってしまった。
そろそろ布団にはいるか。まだ十時にならないが、テレビをつけてもNHKと秋田放送しか映らず、天気予報を見るだけで十分である。
畳の上で寝ることは旅館に泊まるときぐらいしか経験がない。育った団地は板の間しかなく、ベッド暮らしであった。両親も団地育ちだったので、田舎もなく、高校の修学旅行で、旅館に泊まったときが初めての経験かもしれない。畳の匂いはどちらかというと好きである、
二泊の旅行でも十分に気分転換にはなった。八ヶ月前ここにきたときとは全く違った景色に見える。みんなときたときは騒いだ家のといった感じだった。女性が三人、男が三人、特に恋愛感情を持った間柄の二人はいなかったので、高校の修学旅行に似かよっていた。それでも、食堂で浴衣姿の女性陣を見ると、膨らんだ胸元が気になったものだった。まだ半年なのに懐かしい。みんな仕事になれるのに苦労しているのだろう。
電気を消してそんなことを考えていたら、頭をなにかがつついた。驚いて見ると、白が顔の脇で見下ろしていた。頭をなでると、枕の脇に座り込んだ。じーっと見つめられていると、つい背中に手が伸びてさすっている。白は気持ちよさそうに、ゴロンと背中を自分の左肩にくっつけて、よこになった。白の柔らかい毛をなでていると、昨年ここにきたときのことが、目に浮かんできた。
一緒に山を登に行って、ウサギの写真を撮ったふたりの同級生のうち一人は、とある会社の宣伝部にいった。写真を撮るのが好きだったから、いい就職ができたと喜んでいた娘だ。特に特徴がなかったが、どこか落ちついた顔をした、バランスのとれた小柄な身体つきをしていた。ふと、落とした箸をおうとして、身体をしたにしたとき、膨らんだ襟元から、かわいらしい整った乳がちらっと見えてしまったとき、ドキッとしたことを思い出した。今回誘うのに電話をしたら、元気な声で、今度フランスに行って、マーケットで、うちの会社の製品の写真をとってくるの、と嬉しそうに言っていた。
ふと脇を見ると、彼女が脇に寝ていて、顔を自分の方に向けていた。自分の手が彼女の浴衣の中に入れられ、膨らみの先をつかんでいた。手は彼女の身体をまさぐり、足の付け根に指が触れたとき、ぴくっと彼女が動いた。あっと言って、彼女がのけぞった。そのまま、自分も精をはなって、眠りについた。
朝、ぱちっと目を覚ますと、白が布団の脇で寝ていた。ふと、昨日の夢を思い出して、白の背中をなでた。白が手足をのばしてのびをした。時計を見るとまだ四時である。
やけに目覚めがいい。風呂に入ろう、タオルを持って部屋を出た。白をどうしようかと思ったが、よく寝ているようなので、そのまま露天風呂にいった。
誰も入っていない。身体を洗い、まだ暗い庭の先の裏山を見ていると。兎が顔を出した。薄茶色の兎で、山で白と一緒にいた兎に似ている。耳をピント立て、前後ろに動かして、こちらを見ている。
そこへ、露天風呂に白が歩いてきた。
部屋のとは閉めてきたはずだ。自動ロックだから出られるはずがない。いや、もしかすると、窓には鍵をかけていなかったかもしれない。
白は兎に近づいていくと、兎の鼻先に自分の鼻先をつけると、ふすふすとお互いに匂いをかいだ。そのあとすぐに、薄茶色の兎はうなずくような仕草をして、林の中に戻っていった。白もくるりと後ろを向くと、風呂の方に歩いてきた。
当然、脇を回ってこちらに戻るのかと思っていたら、そのまま露天風呂の中にゆっくりと、はいった。顔だけ出して、泳ぎ出すと、自分のそばにやってきた。
「いいゆですね」
白がそういった。いやそのように聞こえた。
「朝早い露天風呂は空気もひんやりして気持ちがいいわ」
そういって、自分の脇で顔をあらっている。手を止めると、白が言った。
「ここは、自由の国なのよ、人間だ、猫だ、兎だっていうことは意味がないの、皆同じよ」
どういうことなのだろう。そう思って、白を見ると、夢に出てきた同級生の彼女がそこにいた。
彼女は自分を見ると体を押しつけてきた。黒い目が印象的だ。そのあとはもうわからなかった。夢と同じようにもつれ合った。彼女の息が目の前で漏れた。
ぼーっとなっていると、白が林の中に消えていくところだった。
どのくらい浸かっていたかわからないが、部屋に戻ると、また布団の中に入った。
「昨日、白はお客さんの部屋にずーっといたんですかね」
朝食の会場で、女中さんがご飯をよそいながら聞いた。自分がうなずくと、
「そりゃあ、楽しんだでしょう、男のお客さん、みんなそういうよ」
と不思議な笑いを残して、となりのテーブルに行った。
同じようなことを、宿泊代を払うために帳場にいったときも言われた。
送迎バスに乗り込むとき、白も玄関まで出てきた。ちらっと自分の方を見ると、宿の中に入っていった。そのあとバスは駅に向かった。
いい旅だった。不思議な旅でもあった。
次の日に、土産を持って会社に行くと、先輩たちがが、土産のお礼とともに、顔つきが変わったねと言った。
「そうですか」
というと、女性の先輩は、
「大人になったね」
などといった。新入社員である自分はともかく会社では一番若い。
それから忙しい日がつづいた。
十月の半ば、台風がきた。上陸はしなかったが、関東をかすって北上したことで、風雨は強くなった。テレビニュースを見ていると、動物のトピックスが報道された。
秋田の泊まった温泉郷が映った。アナウンサーが、
「ここの旅館で、耳の長い猫の赤ちゃんが産まれて、評判になっています」
そういって、自分の泊まった宿の玄関が映り、売店の脇においてある箱の中で、白が生まれて二週間ほどの子供の身体をなめていた。子供たちはどの子も薄茶色で、耳が普通の猫の倍ほども長かった。
そのあと、山の斜面で、自由に遊び回っている猫の映像が映り、兎や野鼠も飛び回っている様子がでた。
「動物たちにとって自由の国です」
地方のアナウンサーがそう言った。
あの動物たち、東京の動物たちとはどこか違った。人間との境を感じさせない、違う世界の動物のような気がした。
まさか、磁気嵐の影響があるわけではないのだろうが、あの温泉郷には違う次元がうずまいているように感じたものだった。
白い猫


