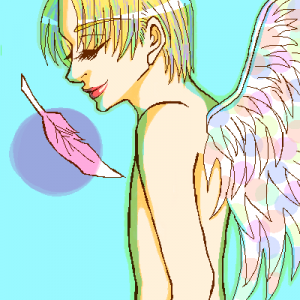My Son
大半の人間が寝静まる、午前も遅い時間。
薄暗いリビングでひとり、出窓に座りながら、どこを見るともなく、丸いガラス玉のようなブルーグレイの瞳を見開いている男。
こいつがこういう状態のときは、最高にハイになって気分がいいときか、反対に人生最低の気分ですってときだっていうのを、俺は知っている。
そして、今は後者の気分だってことも。
「そこで寝るのは勘弁してくれよ、アダム」
そう声をかけると、ギギ、と音のしそうな人形のような動きで、奴がこちらを向いた。
「8歳のときならまだしも、今のお前の体を部屋まで運ぶのは、俺にはムリだぞ」
わざとらしく溜息を吐きながら、アダムの向かい側のフットチェアに座る。
何も言わないところを見ると、誰かが近づいていいくらいには気分が落ち着いてきたんだろう。
世界のすべてを否定して拒否するよりはずっとマシだ。
「眠るような気分じゃないんだよ」
アダム独特の気怠げな声を出しながら、再び窓の外へと視線を送るのを見やりながら、「そうか」と返す。
いつもよりも声が掠れていて、知らない奴が聞いたらきっと風邪でもひいていると思うだろう。
もちろん、俺はそうじゃないことを知っている。
「さっきまでプロムでバカ騒ぎしてたなんて、嘘みたいだ」
そう言いながら窓枠に顔をもたれるアダムは、静かに瞳を閉じた。
まるで、何も見たくないと言うように。
「何考えてたんだ?」
本当はこんな風なことを聞くべきじゃないのかもしれない。
特にこいつのように、繊細で緻密な、俺とは正反対のような人間には。
俺もこいつ相手でなかったらきっと、こんな聞き方はしなかっただろう。
それでも、以前気になってどう思うか聞いてみたときに、こいつは「それがあんただし、他の奴みたいに変に気を遣われるより楽だ」と言い放った。
だから俺は、この態度を崩さない。
「俺も、ケイティのママの彼氏や、ローズの親父と同じような最低な男だって考えてた」
「何言ってるんだよ、お前」
思わず顔をしかめてそう言えば、ガラス玉の瞳を再び見開いて、奴は虚構を見つめる。
思っているよりヤバい、思考のループ状態だ。
「ローズを家に連れてくるとき、車の中で怒鳴っちまったんだよ。『ケイティのこともあるのに、何で俺たちに助けを求めなかったんだ』って。ローズが親父に殴られたからって連れ出したのは俺なのに」
「最低だろう、俺」と言いながら説明する奴の表情は完全に“無”だ。
「それは、お前があの娘のことを心配したから出た言葉だろ? きちんと話したら、きっとわかってくれるさ」
肩をすくめてそう返すと、奴はやっと、ニヤリと笑う。
「ああ、同じこと言われたよ。全然気にしてないってね」
思わず眉を動かした俺の顔を見て、小さく笑いはじめた奴に、少しホッとすると同時に、腹立たしさもこみ上げてくる。
仕方ないだろう、俺は大人げないんだ。
「大体、酒びたりで娘を殴る男や、女にフラれた腹いせに、その娘を階段からつき落とすような男と、その子たちを救急車を呼んで助けたり、自分の家に連れてくるようなお前と、何が同じだってんだ?」
そうアダムに返すと、奴は笑いをひっこめる。
そして少し、罰の悪そうな子供のような顔をした。
「言ったろ、お前のしたことは正しかったって。だから胸を張って、クソして大の字になって寝ろよ」
俺だって眠いんだから、そう加えると、さすがに苦笑される。
「やっぱり同じなんだよ、ダニエル」
そう言って、俺の目を見つめてくる奴の目は、やっぱりガラス玉のようだ。
「だって、俺が今こうして“俺”でいられるのは、あんたとエミリーが俺のことを受け入れてくれて、皆と違う変わった子供でも愛して今日まで育ててくれたからなんだ。他の親なら、とっくに匙を投げるような俺を」
ひゅ、と思わず変な息が漏れる。
こいつは、親である俺たちも、双子の弟のことも、他の皆のことも、絶対にファーストネームで呼ぶ。
唯一ニックネームで呼ぶのは、義理の妹のことだけだ。
まるで、自分と自分じゃない人間の区別をきちんとつけるようだと、いつも思う。
そうしていないと、相手と溶け合って自分がなくなるのを恐れるように。
「カイルはいつも、俺がヤバい方に行ったり、変な思考をしていたら、手をひいて俺を“戻して”くれる。それでも悪い方向に行きそうになると、ホープが俺を救ってくれる。『この子が傷つくようなことはしたくない』って。誰かひとりでも欠けたら、俺は多分、女を殴ったり、酒を飲んで暴れたり、最悪ヤクに手を出してるんじゃないかと思う」
「だから、俺の人生には、誰も欠けちゃダメなんだよ」と呟くこいつを見て、頭を殴られた気分になる。
そんな歳で、そんなことを考えられるような男が、父親の俺より遥かに頭がよくて優しいお前が、そんな人間になるわけないだろう。
そうさせてたまるもんか。たまらず大きく息を吐いた。
「お前の欠点って何だか知ってるか? アダム」
どうしていいかわからず頭をガシガシかきながら言うと、不思議そうな顔で見つめてくる。
そういう顔をすると、弟とそっくりそのままだ。
「頭が良すぎるところだよ。だから何でも大体のことはひとりで解決できちまう。今日だって、ケイティが病院に運ばれたことも、ローズが親父に殴られたのも、お前が全部事をおさめてから知らされた。お前がいなかったら、ケイティもローズも、今頃まだ色んなことで苦しんでたし、俺たちも助けるのが遅れたよ」
「俺はいつも、もっと頼ってくれてもいいくらいなんだ。お前だけじゃない、カイルもホープも、俺の子達は皆そうだ。頼りないのはわかるが、頼むから、もっと頼れよ」
両手を広げながら、必死で話す俺を見ながら、奴は微笑みながら耳を傾ける。
まったく、どっちが親なんだか。
それでもこいつは、俺のことを一度も馬鹿にしたような態度をとったことがない。それどころか、どこか尊敬している風に接してくる。
なんて人間のできた男なんだと、俺はいつも思っている。
「頼ってるよ。だから、ローズを家に連れてきたんだ。だって、あんたとエミリーなら、絶対に彼女を助けようとするだろ。絶対に見捨てないって思ったんだ」
そう静かに告げるアダムの声に、鼻の奥がツンとする。
ちくしょう、泣かせようとするなよ。
「なあ、ダニエル」
溜息混じりに俺を呼ぶ奴の声は、どこか濡れたように響く。
きっと、一番思考を占めていることを話すつもりだろう。
俺がここに来なければ、ひとりで延々と考え続けていたことを。
「ローズの親父の奴、ローズに向かって何て言ったと思う?」
そう問いかけてくるアダムに、静かに「わからない」と告げると、奴は眉と鼻を寄せ、くしゃくしゃの顔になる。
ガキの頃から変わらない、アダムが泣くのをこらえるときの顔だ。
「あいつ、『お前なんてこの世に生まれなきゃよかったんだ』って言ったんだよ。そしたら自分もこんなに苦しまなくてよかったって。あいつはローズの父親なのに」
そう言うアダムの声は、血を吐くような苦しさに満ちている。
「子供がいらないなら、セックスなんてしなけりゃよかったんだ。あいつがいなけりゃ、ローズが生まれてくる奇跡だって起きていないのに、馬鹿だからそんなこともわからないんだ。その上、あいつ、ローズが貯めてた金を盗んで酒を買ってやがった。あの娘が必死で生活するためにバイトしてた金を」
とうとうガラス玉から綺麗に涙の粒がこぼれたのを見て、俺はアダムを抱きしめた。
どうか教えてくれ。誰がこんな状態のこいつを放っておける?
俺の腕の中で静かに泣き続けるアダムにとって、この世界は、音も、光も、香りも、何もかもが刺激が強すぎる。
あまりにも疲れ果てたときは、音も光も遮断して眠り続ける。
不安を抱えるように丸くなり眠るアダムのそばには、いつだってカイルがいる。
たとえ、激しい喧嘩をした日だって。
「ダニエル、もう大丈夫だ」
しばらくして、すん、と鼻を鳴らし、ようやく聞こえるほどの声でアダムがそう言う。
「なんだよ、もっとハグさせろ」
そう言うと、本気で腕の中から逃げようとするのを感じて、笑いながら腕を解く。
離れた体温を惜しむ代わりに、頭をぐしゃぐしゃに撫でてやる。
「正直言うとな、俺はもっとお前に恨まれてると思ってた」
そう言いながら、アダムの頬をペチペチと叩くと、元々大きなガラス玉の瞳を更に大きくして、俺を見返す。
その目元は、まだ赤い。
「恨む? なんであんたを恨まなきゃいけないんだ?」
そう言う奴の口調は、心なしか俺に似ている気がする。
こいつが誰にも言うつもりがなかったことを俺に話したんだ。
俺も誰にも話すつもりがなかったことを、こいつに話すのがフェアってもんだろう。
「お前がホープと結ばれるのを邪魔したからだ。お前が9歳の頃からあの娘に夢中なのを知っていて、両親が死んだあの娘をひきとったのは俺だ」
そうしなけりゃ、今頃きっとプロムも二人で行けたろうに。
そう言いそうになるのを、なんとかこらえる。
ホープもずっと、こいつを憎からず思っているのを、俺は知っている。
「そんなの、あんたを憎む理由にならないよ、ダニエル」
そう言うアダムの表情は、驚くほどまっすぐだ。
こういう顔のときのこいつは、まるですべて見透かすように、瞳を光らせているように見える。
「あんたは身寄りのない子供を助けた。そうしなきゃ、その子供は生きてゆけないから。正しい行動だよ。本当に凄いと思う」
「それに、」とつけ加える声は、今までが嘘かのように力強い。
「それに、あんたがそうしたから、俺たちは家族になれた。恋愛関係なんていう、不確定で不安定な関係じゃなくて。俺にとって、それって凄い重要なことなんだよ。だから、自信持てよ」
偉そうにそう言うアダムの態度に、思わず吹き出す。
こいつはいつもそうだ。
誰よりも頭がよくて、誰よりも優しいから、たとえどんな小さなことでも誰かが何かを悩んでいるのに耐えられない。
「第一、俺たちの恋愛事情なんて、俺たちが勝手に悩んだりしてるだけなんだから、放っておけよ。ホルモンのせいなんだから、あんたにもどうにもできないって」
わざと顔をしかめてそう言うアダムに、思わず笑いながら首を振る。
「まったく、どっちが親なんだろうな」
そうこぼす俺に、奴はニヤリと笑い返す。どうやら調子は戻ったらしい。
「知らなかったのか? あんたもエミリーも、俺が育てたんだ」
そう言うアダムにヘッドロックをかけ、寝室へ連行する。
寝静まった皆を起こさないように、二人で笑いを押し殺しながら。
「ありがとう、ダニエル。多分、もう眠れるよ」
自分の部屋の前に着くと、そう言ったアダムはずっと穏やかだ。
これなら、安心していいだろう。
「何かあったら起こせよ」
人差し指を向け、釘を刺すようにそう言うと、奴は「もちろん。とびきり熱いキスでね」と応酬する。
「待ってるよ、ダーリン」そう言いながら扉を開いてやると、「お休み、ハニー」と笑いながら、アダムが扉を閉める。
「お休み、アダム」
祈りをこめながら、奴にそう返す俺の声色は、自分でも驚くほど優しく穏やかだった。
アダムが安らかな眠りに包まれるように。
この家で眠る子供たちの見る夢が、幸せなものであるように。
子供は起きているときだけでなく、眠っているときもそうであるべきだ。そうじゃないか?
しばらくアダムの部屋の前で佇む俺は、今頃ベッドで俺を眠りながら待っているであろう妻を、無性に抱きしめたかった。
My Son