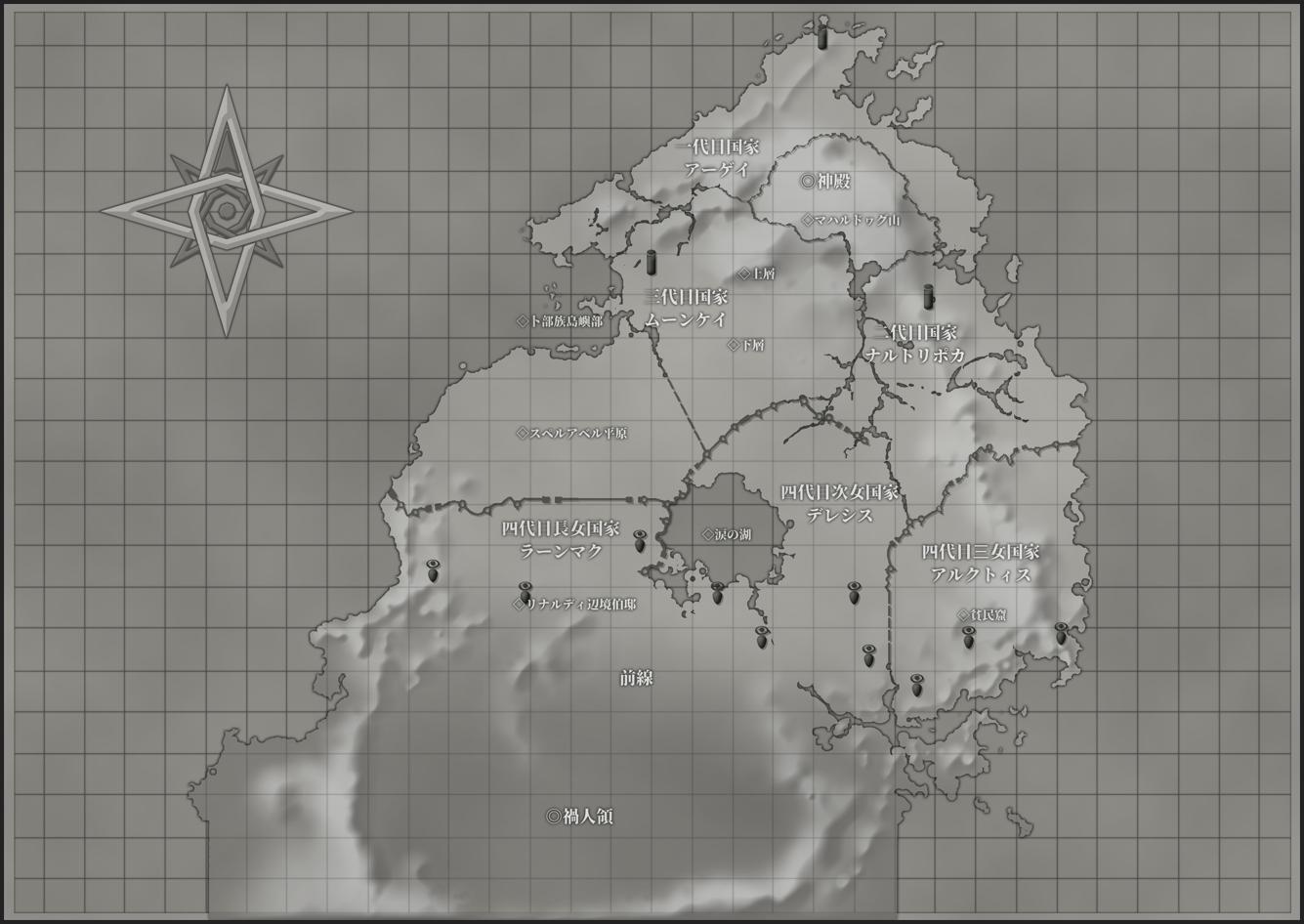
最後の異世界転生譚 ――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
完結済。『カクヨム』または『小説家になろう』でも読めますので、
評価、感想、応援してくれると嬉しいです。
❖序幕❖
■000――愚者
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
鈍色をした朧雲が陽射しを遮る昼の下がり、海原に孤島が一つあった。
その孤島には、天を衝く一基の塔が屹立しており、海原に突き立つ楔のようなその姿は、悠久の時を見つめ続ける厳かな佇まいである。
塔の頂上は遥か高く、山々を見下ろすほど。朧雲は塔にぶつかって左右に切り離され、裂け目からは光芒が幾筋も射し込んでいた。光線を浴びて白く煙る孤島の砂浜は、俗世を拒むように静まり返っていた。
汀に横たわる青年が一人。上は生成の貫頭衣に下は滅紫の鳶袴。脛に襦袢を穿いている。全身じっとりと重く濡れそぼり、海藻の絡んだ衣服を身体に張り付かせたまま動かない。下肢を波に晒して乾くことがなく、睫毛に砂をからませた瞳は昏々と閉じられていた。
❖
海洋の彼方から、一艘の舟が穏やかな波に艪を沈ませて進んでいた。全身を覆う白布は、波間に光る陽光を照り映えて眩しく、大きく垂れた頭巾に顔は隠されている。纏う長衣には華美というほどではない金糸の刺繍があしらわれており、ときおり艪を握る手が袖から覗く。脂っ気のない、青年期をとうに過ぎた偉丈夫の腕である。その者は世俗から離れて生きる隠者であった。
隠者が艫に立ち、黙々と水面を進む舟もまた無垢な白さである。舳先の先から全長は十振(※一振=およそ一メートル)、横幅は四振ほとで、多少の積み荷ならば載せることも容易いだろう。実際その舟には整然と荷が乗せられていた。
舳先から船尾まで、ざっと三十基の柩が並ぶ。長方形の箱が二列に整然と敷き詰められ、その全てに遺体が収められていた。
白き舟は、沈黙のうちに海を往く。
箱の天面の蓋は四角くくり抜かれており、潮風に髪を躍らせて静かに横たわる者達の顔が覗く。
どれも成人を迎えていることは確かで、一層老けている者もいれば、若い女もいた。目立った外傷はなく皆安らかな表情をしていた。肌に血の気こそないものの、こうして日に照らされているとそれが死者であるとは気付かないかもしれない。
白一色の舟の中で死者の周りにだけは慎ましやかな淡い薄色の花卉の類いが敷き詰められていて、それぞれの遺体が慎ましくも華やかに彩られている。
舟には帆が取り付けられておらず、航行は隠者に任されている。艪脚を操り波を揉む手さばきはごく自然なもので、舟はゆりかごのように穏やかに霊園へと向かう。
霊園――それは海にそびえる塔の島。
南側に位置する砂浜以外は岩礁の海岸を形成し、陸地の大半は塔の土台に占められている。
本土の者たちは敬意と畏怖の念を込めてその孤島を『死の島』と呼ぶ。名の表す通り、死者のための島。死者を癒やす霊園である。
今日も舟は遺体を運ぶ。
塔内部に存在する霊素転換炉にて、火葬を行う。
焼かれた遺骨はこの島に眠り、霊素は塔の上へ昇っていく。
死の島全体が霊園としての機能を備えており、翻せばそれ以外の機能を何一つ有してはいない。静かに死者を受け入れるだけの島だった。
「む……」
ふと目をやると、砂浜に見慣れぬものが打ち上げられていた。隠者は低く呟く。長い沈黙を破る、掠れた低い声だった。久しぶりに開かれた唇の皮はつっぱって、もともと上下に分けられることを忘れていたかのように声に遅れて開かれた。隠者は舌でもごもごと唇を湿す。
艪を握る手を緩め、前のめりに身を屈める。先にある漂着物に目を凝らし、それが人であることを察すると、特段驚くでもなく眉を顰めて独り言ちた。
「先客とは、珍しいな……」
❖
青年はいつから意識を失っていたのだろう。或いは一度、死んでいたのかもしれない。
すっかり日の落ちた夜の底。天を遮る雲は無く月明りと星空が広がる。隠者は岩礁の裂け目を利用した風除けの洞に腰を下ろして空を見上げていた。上体をわずかに右へ捻り、塔を見やる。
遥か上空、夜の闇と一つに溶け合った塔の、円筒状に開かれた頂上部からは仄明るい燐光を孕んだ煙が風に流れて筋を引きながら、夜の闇に溶けていく。島の地下に存在する霊素転換炉が、今日運び込んだ三十人の遺体を燃やしているのだ。隠者は、生業として火を操る者。だからこそ、煙をただ無心に見つめ続けていた。目が慣れてしまえば夜闇と煙の境は見えなくなるが、それでも見上げ続けていた。感慨があるわけではない。炉が問題なく機能しているかを確かめるだけの、呆けたような、無感動な目だった。その足下、焚火に焼けた流木がぱちりと爆ぜた。
頭巾の下から覗く隠者の顎先を照らす焔の揺らめきを、青年はどこか夢を見ているような心持ちで見つめていた。前後の記憶が曖昧で、目の前に座り込んでいるこの男が何者なのかわからない。白い外套が炎の橙色にゆらゆらと照らされて、夜闇に浮かび上がる様は現実感を薄めていた。
やがて、耳が潮騒の音を聴き意識が急速に覚醒すると鼻の塩辛さに盛大に咳いて起き上がる。隠者はただ視線を向けるだけで、青年の背をさすることもなかった。
「うっ! ごほっ、ごほ……っ」
肺の奥まで海水を吸い込んでしまった青年は、なんとも言えない塩味と喉の奥に残る苦味に顔を歪め、砂浜に唾を吐く。反射的に胃が引き攣り、どろりとした胃液を吐き出すと、やっと息が落ち着いた。
「うぅ、なんだ、これ……」
口元を手で拭うとかえって砂が口に入る。青年はますます顔を顰めた。
「起きたか」と、隠者。
「起きたも何も……一体なんなんだ……よ……」
青年は荒い口調であったが、言葉尻は勢いを落として呆然とした様子である。あたりを確認しようとして、焚火に照らされる洞の外側、上へ上へと伸びる大きな影に気付いたのだ。
隠者の背後に聳え立つ闇夜に溶ける輪郭、星空を左右に分ける巨大な影。青年は確かめるように視線を上に向けて影の果てを探す。
見上げるしかない青年に、隠者は短く告げた。
「ここは霊素転換炉――本土では『霊園』、或いは『死の島』と呼ばれている」
青年は青褪める。
「霊……園……? 死の島……? ってことはおれ……俺、死んだのか……?」
隠者はその言葉を聞いて硬く口を引き結び、驚いたように目を丸くして青年を見た。呆然とした青年の表情にくつくつと身を震わせると、ついに耐え切れずに笑い出した。
「くははははっ! はっははは……いや、すまんすまん。……っ、くくく……」
心底可笑しいのか、何度も笑いを堪えようとしているもののなかなか収まる気配はない。急に笑い出した隠者に怯えるように後ずさりながら、青年は半目で睨む。
「な、なんだよ。この島は死者しか来れないんだろ? いや、確か聞いたことがあったぞ、『死の島に棲む化け物は人を喰う』って。連中がそう言ってたんだ」
これから喰うつもりなのか。と、反抗的な目で隠者に対する青年。そうはさせまいと警戒の色を宿した瞳で隠者を睨む。対して隠者は大笑に一息ついて頬を揉む。吊り上っていた口角が元あった横一文字に収まり、改めて青年を見つめた。その表情は先ほどの笑みの名残りか、僅かに柔和な、親しみのあるものだった。
「本土ではそんな噂が流れてるのか。それなら言いたいことは二つだ。
一つ、死んじまったんなら今頃はあの塔で燃してるだろう。
二つ、常識なら人なんか喰わねえわな。運び出した遺体は全て本土との取り決めに従い火葬している。お前さんは生きてるよ」
「じゃあ、あの噂って……?」
「『死の島に棲む化け物は人を喰う』か、……言い換えれば『霊園の塔は遺体を火葬する』ってことだろうよ。喩え話で怖がらせるのは、子供の躾けにはよくあるさ」
「……そう、なのか……」青年は安心したのか、力なく頷いた。
隠者は返事を聞いたかどうか、やおらに丸石から腰を上げると洞の奥へと姿を消した。何かを取りに行くような足取りだったから、青年は何も言わず見送ったものの、なかなか戻って来ないので少し不安になった。あの洞がどこまで続いているのか知らない。
どこか遠くから寄せては返す波の音が耳を打ち、闇の奥から這い寄るように響く。その音がただの潮騒ではなく何かが近づく気配のように思えた。焚火の熱は体を温めるのに十分だが、この何もない島の闇と比べれば頼りない。すこし離れた場所に視線をやれば、そこはもう夜に呑まれて何も見えなくなる。
理屈ではわかっている。何も起こるはずがない、と。でも、闇の奥を見つめるうちに、胸の奥がじわじわと冷えていく。
昔、大人たちが話していたのを覚えている。『死の島には化け物が棲んでいる』と。『黒い龍の姿をしていて、塔から昇る死者の魂を喰らう』と。誰もその目で見た者はいない。ただ、夜の海の向こうを指差し、"近づくな"とだけ言っていた。……化け物がこちらを狙っていやしないか? だんだんと不安が強くなる。星の瞬きに紛れて獲物を見つめる瞳はあるか。草むらの影に、波の向こうに……。
……この島に潜む龍が物陰からこちらを見つめてはいないか、魂を喰われてしまうのではないか……青年は孤独の中で再び恐怖に身が竦んだ。
波の音が、さっきよりも近い。まるで何かが、じりじりと忍び寄ってくるように……今にも化け物の手が波間から現れ俺の足首を掴むのではないか。ひとたび波間に引きずり込まれてしまえば夜の海は方角どころか上下の判別もつかないだろう。そんな空恐ろしい想像をして青年は身を震わせ、揺らめく焚火の方へ躙り寄った。
隠者はそれからしばらくして戻って来た。
右手には小ぶりの鍋――と言うには奇妙な装飾がなされた金属製の器だ。大きさは小振りで、ずいぶん使い古されたものであることだけは青年にもすぐわかった――を持って、左手にはこれまた年季の入った分厚い装丁の本と、ずいぶん上質な漉いた真っさらな紙の束を掴み、そして中指に硬筆を引っ掛けていた。
隠者は迷うことなく丸石に腰を下ろすと、流れるような手つきで焚火の周りに石を積み上げていく。どこに何を置けばいいか、すべて計算し尽くされているような動きだ。無駄がない。きっと何度も繰り返してきたのだろう。そうして造られた即席の窯の上に鍋を下ろして火にかけ、温めはじめた。
鍋の中には、黄色くややとろみのある液体が入っている。甘藷黍を乾燥させて粉に挽いたものを水に溶いたのだろう。本土でもありふれているものなので青年は少し安心した。
「たいした飯もないが、一夜を過ごすくらいできるだろう」隠者は匙で二、三かき混ぜると鍋の取っ手を青年の方にまわす。「鍋を持て。手を離したらぐらつくぞ。温まったら喰うといい」
青年は素直に鍋の取っ手を受け取りながら首を傾げた。「一夜を過ごす?」
「こんな暗い海を渡って本土に帰るつもりか?」隠者は問い返すと、こだわりがあるのか再び注意した。「焦がすなよ。こびりついたら面倒だ」
「帰してくれないのか?」
青年はやや驚いたような顔をして隠者を見た。隠者のほうは小さくため息を吐いて続けた。
「親とはぐれて泣き出す歳でもないだろう」
「でも、帰らなきゃ……」
「そもそも俺がお前さんを攫った訳じゃない。砂浜に打ち上げられていたから助けただけさ。
お前さんが人魚で、この島で昼寝していただけだってんなら泳いで海へ帰るといい」
「そんな……」青年はやや俯いた顔で視線だけを上に向け、悄気げた様子で露骨に肩を落とす。
隠者はこの青年が塔の存在を恐れていることを悟った。星空を遮る霊素転換炉が怖いのだ。
「焦げちまうぞ。ちゃんとかき混ぜな。夜の闇より、焦げた飯の方が始末に負えん」
隠者は匙を取って鍋底をかき混ぜる。ふつふつと沸きだした鍋では甘藷黍の粉が溶け出して、濃い黄色の液体が随分と粘度を増している。隠者は溶け切らず固まっているところを匙でほぐしてかき混ぜた。
「食え。朝になれば帰すさ」
匙から手を離すと膝もとに乗せた分厚い本をそっと広げて、さらに頁の上に乗せた紙に筆を走らせ始めた。硬筆が紙面を叩き、線を引く掠れた音が聞こえる。
横目に隠者を捉えながら、青年は匙で汁を掬って一口啜った。
もしかしたら、この男は夜通しそばにいるのだろうか?
そう思った瞬間、胸の奥の緊張がふっと和らいだ気がした。
たとえこの島が恐ろしい場所でも、少なくとも目の前の男は怪物ではない。
鍋をかき混ぜる手、紙に走る筆、ただそれだけの動作が、妙に心を落ち着かせる。
「……あんたはずっとここに居るのか?」青年は問う。
隠者は筆を止めることなく返す。
「『ずっと』とは今夜のことか、それとも俺の半生のことか」
青年はふむ、としばし沈黙。
「あんたはこの夜、ずっとこの焚火の側にいるのか」
「ずっと居る」隠者は答える。「ここは客が来るような場所ではないからな……不用意にうろつかれて場を荒らされても困るし、お前さんの見張りも兼ねて今晩はここで過ごす」
隠者は筆先でこつこつと紙面を叩くと、本の文字を目で追い始めた。
「見張り……」青年は言葉を転がす。
死の島は死者となって初めて招かれる、でなければ踏み入ることの許されない島だというのは本土では当然の知識だった。客を呼び集めるような場所ではない事は当然で、その島の全てを管理しているのが隠者と呼ばれる人物だと言うこともまた広く知られている。青年は未だ現実味のない現状に視線をぼんやりと鍋に向け、その鍋越しに男を見る。謎多き島、謎多き隠者。
もう一口匙を運ぶと、青年は再び問いを投げかける。
「ずっとここに居るのか?」
隠者の文字を追う目が止まる。ちらりと青年の方に視線だけを向けた。睨むというよりは青年の表情を見極めようとしたのだろう。
青年は茶化すような顔をしていなかった。隠者の真っ直ぐな視線に困ったように眉を下げて続ける。
「だって、気になるだろ? 本土ではあんたについての情報はまるでない……噂は島に棲む化け物の話ばかり。それこそ背中に翼がある蛇とか、巨大な牙が生えていて全身が鱗に覆われてる狼とか……魂を喰らう龍だとか……だけど、ここに化け物はいない。 ……あんたの正体くらい知りたい」
「ほう」隠者は目を細め声を漏らす。「愚者か……無知であることは可能性と言える」と、続けて呟いた。
青年は意図をつかめず首をかしげる。そもそも独り言なのかもしれないとさえ思える声だった。
「お前さんの質問の答えはさっきと同じだ。俺はここに『ずっと居る』。どれほどの歳月か……もう覚えていないな。目の前で骨になった者の数も、塔へ焼べた亡骸の数も、いちいち数えちゃいない」
隠者は焚火の揺らめく光を映しながら、淡々と続けた。
「俺はここで見守る役目だ。それだけの話さ」
「その前は? 生まれた時からここに居るのか? 親もそうなのか? 一族で代々……」
「いや、それは違うな」隠者はそう言って星空を見上げると膝もとの本をぱたりと閉じる。ずいぶん古いものなのか、閉じた時に頁のほつれから塵が舞い上がる。挟み込んだ紙が栞のように頭を出していた。青年はそれに目を取られていると、次に隠者へ視線を戻した時には真正面から面を合わせることとなり、思わず息を呑んだ。
頭巾の下から覗く男の面構えは意外なほどに端正で、無情髭もなく整えられている。額や目尻には皺が刻まれているが双眸には活力が燻り、瞳の奥には、燃え尽きることのない残光があった。
まるで、何百年も消えることのない灯火のように、ゆっくりと揺れている。
それは冷たい光ではなく、かといって優しいものでもない――
青年は目を逸らしたくなった。が、なぜか目を離せなかった。いったいどれほどの歳月をここで過ごしたのか推察することもできない。
青年は無意識に喉を鳴らした。まるで、そこに座っているのはただの男ではなく、何百年も生きてきた霊そのもののようにさえ思えた。
どれほどの死を見送ってきたのか。
どれほどの悲しみを、この瞳は映してきたのか。
「……あんた、本当に……ただの人間なのか?」
気づけば、そんな言葉が零れていた。
問いかけには答えず、隠者は青年に視線を向けた。
「少し、昔噺をしようか――」
隠者は綴じ合せた本を持ち上げると青年に向けて表紙を見せた。
『アウロラ写本』そう題された本の内容については青年も多少の知識がある。というよりも、この世で知らぬものはいない聖書だ。そこには遡ること紀元前、その時代を生きた者達の歴史と、今日に繋がる世界の成り立ちが語られている……筈である。青年は概要を把握していても、実際に手にとって読んだことはなかった。
「昔噺って、紀元前のはなしをするのか?」青年は少し笑みを浮かべる。てっきり隠者の身の上話でもされるのかと思ったら、あまりに時代を遡り過ぎているため、冗談を言ったのだと解釈したのだ。
しかし、隠者は至極真面目に頷きを返した。
「俺の仕事は塔の管理……より具体的に言えば霊素転換炉の保存と維持。だが、実はそれだけじゃあない」隠者は本を持つ手をひらひらと揺らす。
「書の編纂……生きる因でもある」
隠者は片方の口角を小さく吊り上げる。その笑みは焚火に照らされて自嘲気味な陰影を浮き上がらせた。いっそ泣いているようにさえ見えて、青年は言葉の意味をすぐには理解できなかった。隠者は続ける。
「これを聖書だと言う者が増えているようだが、そんな大層なものじゃあない。ただ点在していた記録を一つに纏めたという側面においては価値があるが、それだけだ。
……それに、知ってるか? この本の別名」
隠者の問いに青年は迷いなく答える。
「『未完の神話』……でしょ?」
アウロラ写本は紀元前の人々の生活を克明に記した歴史書であり、現存しない書から引用された記述も添えて当時の信仰と戦争の日々を綴った神話を紡ぐ聖書であることは誰もが知るところ。この本を読んだことのない青年でも知っている常識だ。それに合わせて、この本が未完であるというのもまた、有名な特徴であった。
「……俺は、この本が記すことのなかった歴史を知っている」
隠者の声は焚火の揺らめきとともに低く響く。
断言するような、揺るぎない口調だった。
その言葉に青年は素直に驚いた。しかし、少し遅れて懐疑の念が兆す。今日は信じられない事ばかり起きるからついなんでも信じてしまいそうになる。……だがさすがに無理があるだろうと、目の前の隠者を冷やかに見つめた。
この聖書の空白を埋める歴史の物語。この世の飽くなき探求者が書という書をさらい、文字という文字をなぞり、それでもついぞ明るみに出ることはなかった欠落。
世俗と隔絶された、転換炉しか存在しない死の島に棲む隠者は、当時何があったのか知っているだなんて。
「……そんなこと、あるわけない」
そう言いながらも、青年の胸の奥で何かがざわつく。
もし、本当にこの男が 歴史の空白を知っているのだとしたら?
「……信じるかどうかは任せるしかないさ。……でもお前さんは、顔も名前も知らない作者が書いたこの本を信じているんだろう。ましてや読んですらないのに、信じている。なら俺の言葉を疑ってかかる道理もない」
「まあ……そう、だね……」青年は、自分がこの本を読んでないことを見透かされてたじろぐ。
そして、隠者は小さく咳をして声の調子を整え、語り始めるのだ。
「紀元前に生きていた者達の営みは確かに存在した。それが連綿と続いて今日に繋がる――紀元前六百年もの間、途絶えることなく続いた『災禍戦争』の時代――それを神々の争いと呼ぶのなら、きっとその人にとって神話たりえるだろう」
青年は息も静かに、居住まいを正した。
この夜、この出会いは無価値ではない。己の人生においてなにか変化をもたらすだろうことを感じ取ったのだ。
隠者は本を閉じ、少し記憶を思い出そうとするように空を仰ぐと、青年に笑みを向けた。
「さて、昔噺をするんだったな……どうやらまだ眠るつもりもないようだし、付き合ってもらおう。
どこから話すべきか……そうだな、やはり黄昏の女神、アーミラから始めよう。
苛烈を極めた時代を生きた、彼女達の物語――」
❖第一部❖
神殿編
■001――黄昏へ向かう世界《テティラ・マテル》
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
「お師様……っ」
捨てられた教会堂の中では、ぐったりと褥に横たわる老婆と、傍で嗚咽混じりに呼びかける少女がいた。二人は共に白い肌に尖った耳を持つ――いわゆる魔人種である。
少女のほうは歳は十四を数えるほどか、まだ若く幼さを残す。老婆の年齢は判然としないが外見で推察するならばおよそ八十に届くだろう。当時からすれば大往生と見ていい。
それほど長命であった老婆であるが、最期を看取るのは少女のみ。しんとした教会堂はとうに打ち捨てられた廃墟らしく、めぼしいものはすべて取り払われたうら寂しい有様であった。
老婆は少女の声に瞼を開くと、濁った両目を少女に向けた。
左脇で膝を折り、心配そうに見つめている少女は、何度も何度も「お師様」と呼ぶ。縋りつくような碧眼の双眸は涙をためては溢れ、顎を伝って襤褸を湿らせる。
「……どこにも、……いかんよ……」
お師様と呼ばれる老婆は震える腕を襤褸から出し、少女に触れようとした。少女はその手を掴むとそっと頬へと導き、まるで失われゆく温もりを惜しむようにそっと擦り寄せた。
皺だらけの手に涙が落ち、静かに染み込んでいく。
肌に触れたその指先が、思った以上に冷たく、少女の胸を締めつける。
老婆はそのかすかな温もりを感じながら、自身の体温がもう戻らぬほどに冷えているのだと悟る。触れ合った肌は、生気を失い始めていた。
死期が近いことは、お互い十全に理解しているのだ。老婆は二度と目覚めぬ睡りの引力に抗い、重たい瞼を震わせてなんとか意識を保ちながら、万感の思いで末期の言葉を絞り出す。
「アーミラ……お前には、随分と、非道いことを……してきた……」呼吸が浅く、言葉は一息には紡げない。
「そんな……そんなことはありません」アーミラと呼ばれた少女は唇を震えさせて首を振り、老婆の辞世を聞こうとしない。その言葉を聞けば終わりが来てしまう。そんな現実を振り払おうと目を強く瞑る。睫から大粒の涙が零れた。
「聞け……アーミラ……これ、からは……何処へでも行きなさい……。婆の事は、……忘れて……」
「……っ! いや、嫌ですお師様!」アーミラは意固地に首を振って老婆との別れを拒む。「私は離れません……!」
「これだけ……これだけは……、約そく……よいか」
老婆は最後の力を振り絞り、焦点の定まらない瞳で少女の顔を見つめた。像を結ばない視界だが、老婆には少女が今どんな顔をしているのかがわかる。何処までも悲しい娘だ。これほどまでに多くの犠牲を払っても、果たして運命から逃れられるかどうか――
「……婆から教わった事、……魔術の、そのすべて、人には、……決して……見せてはならん……」
少女は力の抜けていく老婆の腕を握りしめると、喉を詰まらせながら嗚咽を漏らし、崩れ落ちるように俯いた。
胸の奥からせり上がる痛みに耐えきれず唇を噛みしめるが、それでも震えは止まらない。
「流浪の民とは、異なる……まつろわぬ者が、お主と出会う……その、ときには……婆はしんだと……つたえておくれ……」
こと切れたように老婆の瞳孔が開く。
「い、き……な――」
肺の空気が吐息となって抜けたきり、最期の声が途切れてから、教会堂内には啜り泣く声だけが続く。嗚咽は勢いを増し、慟哭が響もした。
少女は師なる存在を失い、これからは一人で生きていかなければならない。そんな現実を受け入れるには時間が必要だった。この空漠を埋め合わせるにはどれほどの時間があれば足りるのか……少女にとっては永遠の絶望に等しい。
どれほどそうしていたのだろう。泣き疲れて涙は枯れてしまったが、肺は引きつって嗚咽は止まない。硬い床に座っていたからか膝の骨がしくしくと痛む。しかしアーミラはいつまでも老婆の傍らから離れなかった。『何処へでも行きなさい』その祈りが真綿のようにアーミラを包み込んで、思考に靄がかかる。いつだって……いつだってお師様は、突き放すような態度の中に優しさがあった……親の記憶もなければ身寄りのない私に手を差し伸べてくれた唯一の光……何処へでも行けというのなら、私は――
「お師様の……傍に……傍に居たい……」
アーミラはぽつりと呟くと、埋み火が風に煽られ再燃するように、収まりかけた慟哭の念が再び湧き上がる。アーミラは言葉にならぬ言葉を喘ぎ、喪失感にのたうち回り、赤く腫らした目に涙が滲みる。そうしてまた泣くのだった。
死後数刻、握った老婆の指は冷たく色を失い、肘から下に溜まった血液が死斑となって浮かび始めていた。落ち窪んだ眼球は渇き、顎が強ばり死後硬直を開始する。その隣でアーミラは強い絶望感に苛まれ、今となっては胸中に残された老婆の末期の言葉を反芻しながら、床に額を押し付けて起き上がる気力を失っていた。荒れた教会堂の毀たれた側面壁から西陽が鋭く射しこみ、数刻という長い時間をかけてアーミラの蹲った背中にぎらついた光を突き立て滑らせると辺りは夜の闇に覆われた。
アーミラはもはや、身動ぎ一つしなかった。
――それからアーミラが立ち上がるのは、集落へ向かう商人が付近の死臭を嗅ぎつけ、総出の騒ぎとなってからだった。
老婆の死からおよそ二日、アーミラは盆の窪を晒し蹲ったままの状態で腐敗液に身を浸しているのを大人達に無理やり引き離されてのことである。老婆は既に死後硬直の峠を越えて筋組織の腐敗が進み、強張っていた四肢は柔らかく溶け出して、褥には体液が染みて床板まで黒く変色していた。一言で言えば壮絶の極み。駆けつけた大人達は鼻につく異臭と黒ぐろとした遺体の成れの果てに言葉もなかった。
アーミラ自身も飢餓と絶望に倒れ、虫が集るのさえも気に留めない有様で、最初の発見者である商人は、棄てられた教会堂に「死体が二人いる」と触れまわったほどだ。話を聞きつけた大人が死体を片付けるためにアーミラの肩を乱暴に掴み老婆と引き離したとき、彼女の体が腐っておらず、生きているのだと知って思わず悲鳴を上げてしまったほどである。
❖
老婆の遺体は、集落の者達が火葬として教会堂ごと野焼きにした。もとより捨てられた教会であり、死臭の染み付いた建物を残すことはできないと判断されたのだ。
腐敗の進む遺体を前に誰もが鼻を覆い、顔をしかめながらも、ためらうことなく火を放った。
やがて炎が勢いを増し、朽ちかけた梁を飲み込むと、黒煙が立ち昇り空へと溶けていった。
この地では間もなく収穫の時期を迎えるため、陰気なものは縁起が悪いと嫌われていたのだ。
幸か不幸か教会堂は基礎の部分が石造りであるため、そのものが遺体を葬る窯の役割をした。
とはいえ野焼きの火力では、老体であっても完全焼却には到らず、長時間高温を維持して燃焼させることでようやっと老婆の遺体は炭になる。さらに一帯に蟠っていた不浄の臭いを焚きあげるまで、火葬は三日三晩の仕事となった。季節の変わり目に空模様は安定せず、時折ふる雨から火勢を守るために他の集落から魔術師を集める大変な作業となった。その間、アーミラは憔悴しきって意識を失っており、集落の女手によって介抱された。
多くの者がその衣服や髪にこびり付いた死臭を放つ腐敗液や肌を這う蛆虫を気味悪がっていたが、なんとかしないことには解決しない。皆くちぐちに「貧乏くじを引いた」と腐した。大人たちは各々の労働時間と束の間の暇を見ず知らずの他人の火葬に浪費することになったのだった。
集落の者達から邪険に扱われるのも仕方のないことで、老婆とその少女は身寄りのない流れ物でしかなく、二人の名を知るものは集落にはいない。おおかた流浪の民の随行に付いてこれなくなった老婆が教会堂に隠れて住み着いたのだろう。互いに交流もなく、今回の件は寝耳に水の出来事であった。
穏やかに日常を営んでいる集落のそばで人がひっそりと死んでいるとは、怖気の走る話である。
降ってかかる迷惑は嫌うのが道理。集落の者たちにとって、残された少女も例外ではなかった。できるなら誰かに押し付け、最悪の場合は追放する――それが彼らの暗黙の結論だった。知らぬところで少女が野垂れ死ぬとしても致し方無しと考えてさえもいた。迫る収穫を前にして面倒ごとにかまってはいられない、誰か任される者はいないのか。
少女を預かると名乗り出たのは獣人種の夫婦だった。
夫婦の名は妻をシーナ。夫がアダン。二人の間には子供ができなかった。対してアーミラは、歳こそ離れているが歩幅すらともにした育ての親であろう老婆と死別したばかり、繋がりを渇望する者と喪失した者……求めるものが家族であれば、少女もまた同じ苦しみの中にいるのだと同情していた。このまま一人で生きていくのなら、少女はきっと飢えて死ぬ。
アーミラは師との別れに後ろ髪引かれるような葛藤に苛まれながらも、夫婦に招かれるまま『二代目国家ナルトリポカ』の一集落の片隅、同じ屋根の下で過ごすこととなった。
――ここで一度、国家について説明をしておこう。
『二代目国家』とは、戦争によって獲得された領地の一つである。国家は世代ごとに「一代目」「二代目」「三代目」と区分され、最初の三つの国家は神殿がそびえる山脈の麓に築かれた。戦線は今も進退を極めており、そのため領地が減ることもあり得るが、継承者によってこれまで拡大の一途を辿っている。それぞれの代の継承者が領土を拡大させると防壁を築き、国を興す。そこに人が営むことで、歴史は紡がれる。
そして、『継承者』と呼ばれる者達こそ、この物語の軸となる。
現段階では、六百年続く戦渦の中で『四代目』まで国が建てられている。六つの国家と神殿合わせて計七つの国が存在している。
継承者の名に合わせて、国の名はそれぞれ以下の通り。
・一代目国家アーゲイ
・二代目国家ナルトリポカ
・三代目国家ムーンケイ
ここまでは百年に一人の周期で継承者が出現した。四代目では同時に三人の継承者が現れたため、三女神を姉妹とし、長女、次女、三女と区分する。
・四代目長女国家ラーンマク
・四代目次女国家デレシス
・四代目三女国家アルクトィス
――となる。
❖
ナルトリポカは神殿の築かれたマハルドヮグ山を尾根筋に沿って降りた所に位置する国で、山脈からの豊富な湧水が多数存在し水源に恵まれている。河川が多く常時において灌漑可能な肥沃な土地ゆえに農耕民族的生活文化が形成されており、主に甘藷黍の生産を担い流通することで安定した収益を得ている。
建築様式は神殿からの流れを汲み、削り出しの石材を積み上げた柱に半円弧型の大梁が重厚な天井を支えている頑丈な造りのものが多い。この様式は、当時ナルトリポカが前線であった時に重要な防衛線であったという歴史が背景にある。というよりも、頑丈でなければ今日まで現存することなど叶わないのだ。
現在は、前線からみて神殿の山陰に隠れた一代目国家アーゲイに次ぎ、戦火の被害が軽微な内地国ではあるものの、農耕労働者は基本的に全てを家族内の世襲制で賄うため日銭を稼ぐ方途がない。数少ない働き手の椅子を奪い合うとしても奴隷階級が雇用を独占しているためアーミラのような信用のない孤児が職を探すのは難しい。
そこに手を差し伸べてくれたのが工匠の夫婦であった。孤児であるアーミラを招き入れ、労働を与え日に二度の飯も与えた。そして月に銅二十五粒が手に入った。この待遇は家族同然であった。
アーミラは一年、二年と夫婦と生活を共にする中で少しずつ喪失の傷を癒やすことができたが、かと言って親代わりをしてくれる二人には、膝下の恩を感じつつも家族のような形に収まることはしなかった。アーミラは娘役に消極的で、工匠の下働きとして日銭を稼ぎ、あくまでも居候としての振る舞いを固持した。夫婦はそのことを少し残念に思いつつも、勤勉さを評価し、アーミラの意思を尊重した。
救いの手があれば、悩みの種も付きまとい続けた。
工匠の養子として迎えられ、アーミラがこの集落の一員となって三年を数えた。アーミラは十七を数え、成人となった。
切り揃えた藍鉄色の長髪を背中に流し、おさがりの上着は薄手生成の貫頭衣。中に着た肌着の袖は五分丈だが裾は膝までの長衣であり、それをこざっぱりと纏って腰元を縛っていた。下はゆとりのある山袴で、元々は紺染めのものだろう、色の褪せた青色をしていた。集落の者達に紛れるありふれた服装である。
顔の作りは顎も鼻も小作りで引き締まり、瞳は前髪に隠しているが生来の意思の強さを物語るはっきりとした形で、瞼は伏し目がちで長い睫毛が揃っている。老婆の一事がなければ集落の者達もこの娘を嫌うことはなかったであろう。
死別から始まったこの集落での生活は、未だ教会堂の残骸と共に黒ぐろとした焦げ付きを残していた。大人たちから表立って嫌われることはなかったが、その視線の白々しさをアーミラは敏感に捉えていた。……地頭の良さか、処世術か。アーミラは寡黙であり続け、万事において一歩引いた態度で、面倒事を未然に避けて暮らしていた。
しかし、そうした身過ぎ世過ぎの中で大人たちとは折り合いがついたとしても、集落の同年代同士では避けられない衝突も起きた。アーミラは工匠の夫婦には隠していたが、お使いを頼まれて一人、人の目が集まらない道を通ると、決まって嫌がらせを受けていた。
「アーミラ、お昼の準備できたから、これ持って手習いさんとこまでお使い頼めるかい?」
家の中からシーナの声がすると、外で箒を握っていたアーミラは前掛けで指先の汚れを拭い、ぱたぱたと駆けつけた。台所では大きな編みかごが二つ、中には工匠手習いのために用意したお昼が詰められていた。シーナはにっこりと笑ってアーミラの頭を撫でる。
「うふふ、外で掃除してくれてたん? いつもありがとね」
アーミラはこくこくと頷く。
「ほんじゃ、場所はいつもんとこね。お父さんに『帰りは飲みすぎないように』って伝えてね」
「……は、はい……行ってき、ます」アーミラは俯きがちに言うと編みかごを両手に提げて歩き出す。
「気を付けて。一つはアーミラの分のお昼だからちゃんと食べなね」
玄関まで見送ると、扉が閉まりアーミラの足音がぱたぱたと遠くなっていく。シーナは甲斐甲斐しく働く彼女の後ろ姿に思わず笑みを作ると、少し心配そうにため息を吐き、気持ちを切り替えて台所に戻って行った。
アーミラは、人との会話に怯えたような態度をみせていた。視線が合うことを嫌ったり、言葉をしょっちゅう詰まらせたり、夫婦にとっては以前の彼女を知らないので、これが生来の性格なのかわからない。もし、本当は明るく笑える子なのだとしたら……。このままでは、いずれ心が壊れてしまうのではないか。三年間共に過ごしたシーナは確信していた。アーミラは不吉な娘なんかじゃない。
とてもいい娘で優しくて、気立ても良く器量もいい。……だというのにそれが他人とでは上手く機能しないのが歯痒くて、口には出せないものの捨てきれぬ親心なりに悩みの種となっていた。
❖
集落の北側、工房では小気味の良い槌の音が忙しそうに響いていた。鑿を叩く甲高い音が連続したと思えば不意に荒々しい木槌の音に変わる。耳をつんざく喧騒の中にあって、アダンはまるで何も聞こえていないかのように集中していた。木屑の温かな香りと少し粉っぽい室内にふと食欲をそそる香りが漂う。アダンは手を止め、戸口へ視線を向けた。そこには、昼食の詰まった籠を抱えたアーミラが立っていた。
「もうそんな時間か、いつもありがとうな」
アダンは鑿を置いて、首にかけていた布で額の汗を拭う。膝元にはまだ荒削りな、一抱えする大きさの木材がどっかりと並び作業場を圧迫している。入口手前に置かれたのは納品を待つ完成品で、アダンは日々同じ姿の木像を量産していた。
目下依頼が殺到しているのは、長身の勇ましい剣士の木像。顔は意志を宿したかのように生き生きとして眼光鋭く、結わえた髪も風に踊るような躍動感がある。大きさは様々で、机の上に飾っておけるものから、アダンよりも大きな背丈になるものもある。アーミラが二人の家に招かれてからいくつも目にしているものだ。アダンが言うには、「前線に立つガントール様」の像だと言う。
「……おおきい……」アーミラが呟く。
「ああ、出征の日も近いからな。依頼が途切れなくて困るくらいだ。納品も一苦労だよ」
アダンは編み籠を受け取り、包みを一つアーミラに手渡す。彼女はこくりと頷いてそれを受け取った。自分の分の弁当だ。
包みを開けば、ふわりと香ばしい湯気が立つ。黍粉を油で練った生地を薄く延ばし窯で焼いた平たいパンが二つ。緩く谷折りになり、間に挟み込まれた具材はそれぞれ違うものだ。一つは萵苣と塩漬けした燻製肉の炙りを薄切りにして交互に挟み、仕上げの薬味として肉の油と大蒜の刻みを掛けたもの。もう一つは水で戻した豆を多種類の香辛料と煮詰めて甘辛い餡にしたものだ。
アーミラは燻製肉の方をこの場で食べることにした。もう一つは帰りに持っていこう。そうしてぱくついているとアダンは何とはなしに満足そうに笑みを浮かべ、手習いたちのもとに編みかごを運んで「昼にするぞ」と声を上げる。午前のうちから精が出る。手習いたちは各々肩をほぐしたり首を回したりして人心地つくと編みかごの前に群がっていく。
空になった編みかごをアダンから受け取ると、アーミラは言伝を思い出した。
「あ、あの……『今日はお酒、飲みすぎないように』って……」
「おうおう、厳しいなぁ」
「し、シーナ……から」
「わかってるよ。早めに帰るさ。アーミラも仕事は程々にしとけよ。片付いちまってやることないだろ」
アダンは笑い、アーミラの肩を軽く叩く。彼の笑顔はシーナとよく似ていた。
それはアーミラにとって、あまりにまぶしく、あまりに温かい光だった。そしてその光に照らされるたび心の奥で氷解していく何かを感じる。それが嬉しくもあり、同時に寂しくもあった。忘れたくないものが少しずつ薄れていく。アーミラにとって罪悪感にも似た感情が胸にこびりついて、うまく笑うことができなかった。
❖
帰り道、アーミラは残りの昼食を食べながら川辺の路を歩いている。畦道を挟み、向こう側には甘藷黍の畑が広がっている。青々とした葉はきらきらと、去りゆく春の風に揺れながら擦れ合い、涼し気な音を立てている。来る夏ノ一(六月のこと)からの収穫に向けて茎は太くしなやかに、蜜を蓄え順調に育っているようだ。収穫を控えたこの時期は、いつもアーミラの心を寂しくさせた。
甘藷黍とはなにか。以前、アーミラはアダンに尋ねたことがある。
「この国ナルトリポカが生産を担う重要なものだ」
ひいては「これが前線を支えている」と教えてくれた。
この世で魔呪術を使用する者は、代償として自身の命を消費する。
しかし術者たちは、命の代わりに魔鉱石を用いることで生命力の消費を回避する方法を見出した。魔鉱石に内包された霊素を代償として支払う方法を確立したのだ。しかし生命力を奪われずとも術者の活力はどうしてたって消耗は避けられない。精神は著しく疲労するのである。
疲労には甘露。永きに渡る戦争の中で、人々は甘藷黍を摂取することで活力を癒やすことができた。甘藷黍の堅い茎の内側に詰まった髄こそ蔗糖であり、甘い蜜がすり減らした活力を癒やすのである。かつては飢えを凌ぐために口にしたものが、やがて戦場を支える必需品となった。
重要な輜重として内地ナルトリポカは甘藷黍の主要生産地として全国へ供給を続けている。乾燥させて粉に挽けば保存が可能、水に溶かせば如何様にも融通がきく。魔鉱石と甘藷黍、この二つが術者の命を、前線を支えている。これなしに前線の維持は叶わないと言うのは決して大言壮語ではない。
川辺の細道に入ると、昼下がりのせいか人気が少なかった。
なんだか嫌な予感がする——。
そう思った瞬間、何かが風を切り、アーミラの手の甲を打った。鋭い痛みが走る。驚いて手を引っ込めると、指から昼食が滑り落ち、土の上に転がった。
「……あ」
地面には彼女の昼食と、拳ほどの丸石。
河原に目を向けると数人の影が笑っていた。
「何拾ってんのよ、それまだ食べるつもり?」
河原に視線を向けると、石を投げた者達が寄り集まって騒いでいた。女一人に取り巻きの男が二人。くだらないごっこ遊びか、獲物を仕留めたつもりの手柄顔は下卑た笑みだ。工匠の二人とは大違いだった。
アーミラを困らせる悩みの種とは彼女らのことだった。この集落に来てから三年、ことある毎にちょっかいをかけてきては一方的に笑いものにされる。気にするなと自分に言い聞かせても不愉快なものは不愉快で、目障りなことには変わりなかった。特に厄介なのが三人組の中で上背のある女。彼女はこの集落を治める領主の娘であり、勝ち気な吊り目に高飛車な顎先を向けてくる女だった。いじめの手段は陰湿なうえ、下手に抵抗すれば事実を捻じ曲げて吹聴する。そうなれば集落での居場所がなくなってしまうのではないかとアーミラは考えていた。何より、シーナやアダンに要らぬ心配をかけたくない。その一心で降りかかる受難を耐え忍んでいた。
「はあ、臭い女も退治したし、行きましょ」
しとしきり石を投げ悪口を浴びせると、三人は反応がないことに飽きたのか、手で衣服の土埃を払いどこかへと歩き出した。アーミラは手の痛みも気にすることはなく、パンを拾い上げると土を落として再び食べ始めた。例え泥に浸かったとしてもシーナのご飯は美味しい。
しかし――
「ほら!」
鋭い叫びとともに、石が飛んできた。
視界が揺れ、頭に鈍い衝撃が走る。
次の瞬間、アーミラは地面に崩れ落ちていた。
何が起きたのだろうか。アーミラは目の前に散らばる豆の煮物とパンの残骸、そして編みかごの他に拳程の大きさの石を見た。これが投げられたのか……そう思い手を伸ばしかけたとき、側頭部の痛みがより明確になる。
顳顬から垂れる汗は、指先で触れると真っ赤に濡れていた。思っていたより頭を深く切ったらしく、次第に裂傷が焼けるように痛みだして髪が血に濡れて頬に張り付く。
痛みの中に懐かしさすら覚える。お師様と修行をしたときはこんなものではなかった。アーミラは血の付いた石を捨てて、傷が奴らの死角になるように顔を逸し、悟られないように髪の房に指を差し入れると魔力を込めた。傷はすぐに塞がる。
「まるで食い意地の汚い乞食ね。なんだか腐った匂いがするわよ。あの老婆と同じね」
むっとして、アーミラは領主の娘を睨んだ。
「なに? やり返そうって?」
領主の娘は得意げに河原の石を掴むと、脅しのつもりか明後日の方向に石を投げる。石は左後方の岩にぶつかり、硬質な音を立てて転がった。取巻きの二人が煽り立てる。
「またさっきの魔術やって見せてくださいよ!」
「すごかったなぁあれ! 初めてみた!」
アーミラの身体が強張る。見えないようにやったはずだ。三人の目線も確認していた。誰にも見せてはいけないとお師様に言われていたのに、まさか見られたのだろうか。
しかし、その心配は杞憂だった。
「いいわ、見せてあげる」そう応えるのは領主の娘である。
「……え」
アーミラは思わず声を漏らす。
次の瞬間、領主の娘は魔術を使い、石を浮遊させ、自在に操ってみせた。
驚くアーミラを見て気を良くしたのか、領主の娘は饒舌になる。
「将来この集落を治めることになるんですもの、この程度の魔術くらい扱えて当然。
まあ、私くらいの才能があれば造作もないことだけれど」
得意げに笑うと指先を上げ、次に振りかぶってアーミラを指差した。
石はその動きをなぞるように追従し、射出される。
左右から迫る石を、アーミラは首を傾げるだけで交互に回避した。アーミラにとっては慣れた回避動作だったが、彼らにはその力量を測ることはできない。まぐれで避けたように見えたのか、取巻きたちは余興のように歓声を上げて笑った。
「……い、石は、何を使っているんですか……?」
アーミラが問いかける。
頬に張り付いていた血糊がぱらぱらと剥がれていく。その様は、被り続けてきた陰気な仮面が剥がれ落ちていくようだった。
三人は微かに、目の前の少女の雰囲気が変わったことに気づいた。しかし、茶化されるのを恐れ、口にはしなかった。
だが確かに、彼らは彼女の逆鱗に触れていた。
「はあ? いしだぁ?」
「河原の石しかないだろが」
取り巻きは強がるように応えるが、領主の娘だけは違和感を拭えずにいた。
魔術や呪術を用いるには魔鉱石という触媒が必要だ。でなければ自身の命を摩耗することになる。河原の石を浮かせる程度のことで自分の寿命を削る者はいない。当然領主の娘は魔鉱石を身に着けていた。
その知識を前提とした上で、彼女が問うている『石』とは魔鉱石のことだとわかる……領主の娘は眉根を寄せる。一体誰からそんな知識を……? この薄汚い女は学もない流浪の娘ではないの……?
「……ほら、石はこの指輪よ」
興が削がれたか、領主の娘は素直に答えた。
「父さまが『好きに使え』って」
「っ……! こ、これ……!」
アーミラは眉を跳ね上げて詰め寄ると、奪い取らんばかりの勢いで指輪を嵌めた娘の手を掴んだ。
煤けた金属製の輪に、小さな魔鉱石が等間隔に三粒。
その年季、鉱石の灰色がかった赤紫色、魔力の減り具合――どれも見覚えがある。
「お、お、……お師様の……っ!」
アーミラの頭に血が昇る。
思わず、領主の娘に平手打ちをした。
わなわなと唇が震えるのを噛み締めていなければ嗚咽が漏れてしまいそうだった。
「な、なにが『好きに使え』ですか……! これは、私の……っ、お師様のものです!!」
領主の娘は、呆気に取られた。
初めて見せるアーミラの感情的な視線。
初めて受けた反撃。
しかし、すぐに怒りが湧き上がり、逆上する。
「はあ!? 気安く触らないでよ乞食のくせに!」
「か、か、返してください!!」
「あなたのものなわけないじゃない!」
二人は川辺で掴み合った。領主の娘はアーミラの髪を掴んで水辺に引き寄せるが、やられるだけのアーミラではない。引き寄せる勢いに乗せて彼女の腰元に肩でぶつかり水中に押し込む。盛大な飛沫をあげて二人は取っ組み合いになる。浅瀬は瀞を形成しているが少し奥まったところでは水流は早く足もつかない。取巻きたちは呆気に取られ、どうしていいかわからず互いを見合うばかり。
気付けば川沿いの路にも橋の上にも農作業を再開していた野次馬がぞろぞろと集まり、集落の大人達も何事かと河原を見下ろしていた。その中にはシーナの姿もあったが、アーミラは気づかない。
「あ、あなたみたいな駆け出しに、そ、そもそも、好きに使えるような魔鉱石なんて、あ、あ、あありませんよ……!」アーミラは震えながらも言葉を続けた。「だって、せ、せいぜい河原の石を浮かせられる程度でしょう……!? そんな、じ、実力のうちから、好きに魔鉱石を浪費したら、お、お金が、いくらあっても足りません……! き、き、きっと、お師様のものを盗んであなたに使わせているんです……乞食は、泥棒は、どっちですか……っ!」
「っ! あんたねぇ……!」
「才能があるなら……こんな、こんなところでちやほやされている暇なんて、あ、ありませんよ……! 石を浮かせるのなんて、初歩の、初歩じゃないですか……!」
アーミラの言葉は正しかった。
老婆を火葬した後に残ったいくつかの装飾品は、全て領主が預かっていたのだ。とは言ってもアーミラの元に渡ったものは一つとして存在せず、実質奪い取られた形となる。一方で領主の娘はせいぜい河原の石を浮かせる程度の実力しかない。勉学の成績が奮わない娘に実践で経験を積ませるのに都合がいいと、領主は娘に指輪を渡したのだ。
本当に才能のある魔術師ならば成人している時には戦闘に耐えうる術を身につけているはずだった。
彼女自身、言葉には出さずとも才能が劣っていることは前々から気付いており、その鬱憤を晴らすために弱い存在を虐げていた。流れ物であるアーミラはまさにうってつけで、八つ当たりに嫌がらせをしていただけに過ぎない。そんな矮小な存在であることを、他でもないアーミラに言い当てられたのだった。
「……流れ者の乞食の癖に口答えしないでよ……!」領主の娘は形振り構わず喚き散らして水面を叩く。「要らないわよこんなもの!!」
彼女は怒りに耳まで赤くして乱暴に指輪を外すとアーミラから背を向けて川の下流方向へ力の限り投げ飛ばした。アーミラがあれだけ高価であると言ったのに捨てるとは、野次馬達は思わず声を上げて指輪の軌道を目で追った。唯一、指輪ではなくアーミラを見つめていた者が一人。シーナはこれまでに見たこともないアーミラの姿に驚いていた。
共に過ごした三年間、朝も夜も一緒にいたというのに、これほどまでに感情を表に出しているのを見たことがなかった。シーナにとっては驚きで、大いに戸惑い、そして一抹の寂しさを感じていた。
アーミラはそんな周りの状況に依然として気が付いていない。ずぶ濡れの肌は衣服がまとわりついて蒸し暑く、ぴすぴすと笛のなる鼻を膨らませて、老婆の指輪を目にしたときから既に視界は狭くなっていた。そしてその指輪は今にも川の中へと失われようとしている。
だからこそ、アーミラの体は動いてしまう。これまで抑え続けていた感情、言葉、そして才能。師との約束を守るため秘匿し続けていた己の魔術を行使してしまう。
瞬時に魔力を練り上げると指先に集め、水面を掌で掬い上げて飛沫を空へ飛ばす。水は燐光を纏って軌跡を描くと、なぞるように川の水流がアーミラの意のままに足場を作った。アーミラは己の放った飛沫の足場を一足飛びに駆け抜けて高く放物線を描き落下を始めた指輪を追い、見事に手中に収めてみせた。両手を伸ばして飛び込み、指輪をしっかりと掴むと空中でくるりと身を翻し背中から水面へ落下、水面は飛沫をあげてアーミラを受け止めた。
一連の早業は人々を驚かせた。身のこなしも普段見せる気弱な態度とは別人のようで迷いがない。水を自在に操るその姿はまるで夢か幻か、皆が呆気にとられているが、当の本人は水の上に片膝をついて大層大切そうに指輪に両手に包み掻き抱いていた。
指輪をつまみ、日に照らして状態を確かめる。見間違えようがない。やはりお師様の指輪だ。
安堵に笑み、その形見を再び胸に抱きしめると二度と失うものかと左手中指に嵌め、満足そうに眺める……その手の向こうに見える景色には人集り、騒ぎ立てる声に気付くと我に返り、アーミラは人々の視線に戸惑うのだった。
「空を浮いていたぞ!」
「水の上を走ってた!」
……まずい。
「あの子、まさか魔術が使えるだなんて!!」
まずいまずいまずい……!
アーミラは練り上げていた魔力を霧散させ、足場が抜けたように川に落ちる。強かに飛沫を立てて膝までしとどに濡らすが、そこは浅瀬の瀞だった。いっそ深みに沈んでしまいたいと思うものの、今更身を隠したって意味はない。アーミラは老婆との約束を破ってしまったのだ。今や集落の者達はアーミラを魔術師として認識していた。領主の娘は既に騒ぎの蚊帳の外、あれだけ見下していた存在がこれほどまでの才覚を持っていたことを知り、自身の愚かさを嫌というほど見せつけられていた。しかし、己の罪を知るには遅すぎたのだ。彼女は以降、歴史に名を残すことなくその一生を終えることとなる。
運命の栄華、明暗を分かつこの一大事、富に驕る者は衰え、貧しくも勤勉である少女は祝福の光を浴びた。しかし、その光の眩しさたるや、よく磨かれた牙のよう……。運命とはときに飢えた獣となって、見定めた相手に逃れられぬ使命を与える。あらゆる犠牲を払っても逃げおおせること能わず。獣は、獲物を喰らうまで満たされることはない。
――アーミラが師と敬う老婆、マナ・アウロラが命を賭して逃げ果せたはずの獣は、今再び獲物を嗅ぎつけ狙いを定めた。
人集りの喧騒に圧されて、どのような言い訳なら筋が立つかとアーミラが逡巡していたまさにその時、突如として遙か頭上の青天から光が爆ぜた。
光の輪が広がると共に、荘厳な鐘の音が地上に届く。集落の者達の意識は否が応にも空へ向けられ、今度は何事かと事態を見守る。音の波は地表を震わせ木々に身を隠していた鳥達は翼を広げて逃げ去った。シーナは、あの光もアーミラが起こしたのだろうかとぼんやり見つめていたが、見上げるアーミラの表情が次第に険しくなるのを見て胸が締め付けられる感覚を覚えた。
もう会えなくなる気がした。……もしかしたら、アーミラは遠い存在になってしまうのではないか……? 別れの時が迫っているのではないか……? シーナはそんな予感を自覚したのだ。
鐘の音が響く度に光の輪が弧を描いて広がる。それは水面に広がる波紋のようで、しかし寄せては返すことはなく収斂しないまま果てまで輪を広げていく。これまで見たことのない魔術の流れがそこにはあった。光の筋は雲を押しやって青空を開くと、見えざる神の指先が規則的な意匠を描いていく――
誰かが、言った。
「おい……あれ、三女神の刻印じゃないか……」
❖
時を同じくして、マハルドヮグ山頂に聳える神殿からも三代目国家ナルトリポカ上空に現出した魔術陣は観測された。正午を少し下った時分のことで、昼餉後の小憩に響き渡る鐘の音は、青天の霹靂であった。
突然の事態に神殿領内を忙しなく駆け回ることとなった彼等は、麓の国々から神人と呼ばれる者達。神の血筋とされる天帝――ラヴェル一族――に仕えている者達だ。皆一様に白衣を纏い、神殿領内で生活を送る特権階級の役人たちで、彼らは全国から集められ、魔人種、賢人種、獣人種の血を等しく扱いあらゆる学問、あるいは何かしらの才覚に優れる者たちで構成されている。
所謂『神人種』という一つの括りとなる。その中でも、彼らに采配を飛ばしている一人の女がいた。
その者の名はカムロ。神人の中でもとりわけ優秀であると評価を受け、まだ歳も若いうちから神族近衛隊隊長の座に昇りつめた実力者だ。
カムロは占星術――星の位置を読み、歴史と照らし合わせて吉兆を占う学術――の使い手である。彼女は星読みによって刻印出現という未曾有の事態を予見していた唯一の人物であり、当代継承者についてはこれまでとは異なる星の巡りがあると見ていた。そして事実、当代六百年の節目を迎えたこの世はこれまでとは異なる事象が多く、この度の刻印現出に対しても彼女の表情は厳しかった。
占星術で予測していた通り、この日に刻印が現れることは知っていた。しかし、百年前の継承者不在の変や、それに伴う星辰周期のずれが複雑に絡み合い、これから先の予測がつかない。
部下たちの前では適切に指示を飛ばし冷静に振る舞いながらも、彼女の内側は渦巻く濁流のようだった――
やはり現れた……! しかし、ならばこそどうして、
まずは冷静に、状況を整理しましょう。……この数年、星読みに現れ続けている兆候について私は憂い続けていた。継承者の出現を伝えるいくつかの天体の輝きに反して実際に見出されたのはガントール様お一人だけ。これだけであれば前例はある。初代継承者アーゲイもまた長女継承のみだったと記録にも残されている。
しかし、此度はそうではないのだ。星の瞬きは安定せず、星読みの度に激しく輝いたり、消え入る蝋燭のような光となる。一体なにを訴えているのか……それに呼応するように刻印現出は気が触れたように三度も発生した。一度につき一人を選んだということもない。こんなことは過去に例がない。
前提として、継承者嬰児は百年周期で誕生していた。少なくとも四代目まではその周期に従って魔術陣の観測が記録されている。その四代目について、より細かい記述によると、『産まれた日は違えど同じ年にそれぞれの種属から一人が選出されるようにして三人の娘が揃えられた』とある。この事実は神殿内外を問わずその時代を生きているものならば誰もが知っていることだ。その周期がずれ始めたのは百年前。本来五代目継承者が現れる節目の年だったのだが、その年の三女神継承者は生まれてこなかった。つまり四代目から今まで二百年の沈黙があった。星の巡りはここで狂ったのだ……はたして当時何があったのか、記録されている史料もやたらに乏しいのが気になるところだが今は置いておこう。とにかく今理解しておくべきなのは、二百年の沈黙が破られたこと。そして、星読みを狂わせる不穏な光が現れたこと……。
それは彗星――二百年の沈黙を破って当代継承者の魔術陣が現れた最初の年から、南西の方角に長く尾を引く天体が現れた。それは観測が認められてから十七年間、現在も夜空に存在する。果たしてそれが何を意味しているのか……。過去の記録でもまさに二百年前、先代の三女神継承者達が前線へ向かったときにも彗星は現れていると史料にはあった。曰くその史料に拠れば、当時前線では災禍の龍による被害が甚大であった事、そして龍との交戦の記録が残されている。それらを鑑みるに彗星は禍事の前兆……。恐らくは当代継承者達の先行きは困難なものになるのだろう……いや、そもそも先行きどころの話ではない。今まさに混乱している有様ではないか!
全くもって頭が痛む。顳顬に石でも擦りつけられているかのようだ。
本来五代目が現れるはずの年に継承者は揃わず、先代から二百年の空白を経て魔術陣は三度観測された。先程にも言ったとおり当代では今日を入れて三度目の魔術陣観測となる。その様子もまた、過去の記録とは異なる。
一度目の魔術陣現出から振り返ろう。当時は十七年前、今度こそ継承者は現れるだろうと誰もが期待していた世の中で、継承者は一人だけ現れた。
ガントールと名付けられたその娘は産声を上げるより先に未来を決められた。獣人種の長女継承。その娘だけが刻印を身に宿して神殿に迎え入れられた。空には他二つの刻印が現出する気配を見せ、曇天を切り裂く雷鳴が機嫌悪そうにごろごろと鳴いていた。継承者が三人揃うか、それでなくとも二人目は現れてくれないか……固唾を呑み空を見上げる人々の期待も虚しく雷鳴は勢いを失う。
それから時を経て十年後に二度目の魔術陣が観測された。この時はまさか二度目があるとは誰も思っておらず、望外な知らせに戸惑い眉をしかめる者もいた。
次女と三女の刻印が空に現れたが、いずれも数刻後には霧散。魔術陣の動きから、生まれた娘が流れたかしたのではないかと憶測も飛び交ったが、後の調べではその日魔術陣の示した集落で出産したものはいなかった。こうなれば当代は長女のみの前線出征かと思われたが、今日になって三度目の魔術陣が観測されたのだ。三度目の正直となるか、ナルトリポカの集落で次女継承者が現れたのであれば、どこか他の場所で三女も現れるかもしれない……その可能性は捨てきれない。
――カムロは痛む頭に顔をしかめながら思考を整理していると、玉砂利をまっすぐに駆け寄る足音に気付き意識を向けた。
「カムロ隊長、至急お伝えしたいご報告が」神族近衛の部下が駆け寄る。低く喉にこもった声の主はよく知った顔であり、カムロは目で見ずとも呼び当てられた。
「どうしました、ザルマ」
「はっ、……それが、三代目国家ムーンケイ上空にも刻印が現出しました。当代三度目にして本当に継承者が揃うかもしれません……異例の事態ですな」
「もしかしたら本当に……しかし、いや、まだ楽観するには早いか……」
部下は日差しの照りつける前庭を駆けていたのだろう、額から噴き出す汗を手の甲で乱雑に拭う。対してのカムロの返答は冷静なものだった。隊長はこの事態を予想できていたのだろうかと、部下は内心考える。しかし今しがた目撃した魔術陣に興奮は収まらず、形振り構わずムーンケイの方角に指をさす。百聞は一見にしかずとでも言わんばかりの態度はいささか礼を失しているが、カムロがそのことに目くじらを立てる様子はない。促されるままに指し示した方角の空を確かめるが、視界は神殿の陰に遮られている。間抜けを晒す部下を置いてカムロは開けた場所まで駆け出した。
「これは……!」
カムロは言葉が続かない。
「今回の魔術陣は随分と近いですな。ナルトリポカとムーンケイ、ともに内地……陣も大きく観える」
例え三度目であっても目を奪われる。山頂から見霽かす薄雲の青空には、大輪の花のように刻印が二輪、燦然と輝いていた。
その場にいた誰もが息をのんだ。視線はただ一点、天を仰ぎ、言葉を失っていた。人生で三度目の魔術陣の観測……本来なら三百年生きなければ経験することのできない出来事だ。未曾有の事態に手放しに喜ぶ立場ではないことは重々承知ではあるものの、唯一無二の規模と美しさを誇る魔術陣を前に心を釘付けにならぬ者はいない。
「揺らぎはありませんね……二つとも霧散の兆候は?」カムロが問う。
「ありません。もしかしたら、本当に……」
「となれば今度こそ継承者が現れたのかもしれません。長女継承者様と鎧の魔導具を集堂に召集してください。次女と三女の保護に動きますよ」
❖
マハルドヮグ山頂の領域は一括に神殿と呼称されるが、実態はラヴェル一族とその他種属の優秀な人材からなる神人種が生活を送る特権階級の宗教都市である。つまり、山頂にただ孤立して神殿があるわけではなく、外郭に囲われた神殿領内には様々な役割を果たす建物があり生活の全てを賄うだけの機能を有していた。
至聖所と祭礼を執り行う神殿本体を中心に南東側には円形闘技場、北西の斜面には段々畑、その他居住区が各所に点在し、山の源泉を引いた湯浴み場さえも存在する。そして三女神を象徴する巨大な石像が背中合わせに三方を向き、忍び寄る蛮族を睥睨するかのようにマハルドヮグの裾野を油断なく眺め下ろしている。
カムロがその部下――名をザルマカシムという――に指示した召集の待ち合わせ場所は、神殿領内の一劃、近衛隊集堂だった。
時刻は午後の二刻をまわり、集堂には長女継承者ガントールと、板金鎧の魔導具が集められた。
「――ふむ、今回の魔術陣はこれまでのものとは違っているな。いや、同じというべきか……」
そう語るのはガントールである。
三女神長女継承者。リナルディ・ガントール。
産まれは前線にある四代目長女国家ラーンマクの一辺境伯の娘である。
背の丈は二振ほどはあろう、天へと突き立てた羚羊のような頭角も背丈をかせぎ、横に流れて尖った耳や引き締まった見事な体躯はいかにも獣人種特有の血筋を顕している。二つ結いに束ねた長髪は天秤のように左右に垂れて腰元まで届き、体の動きに合わせてさらさらと舞っていた。
彼女は当代三女神のうち、生まれた瞬間から刻印を宿している唯一の正統継承者である。
物心がつく前から神殿に招かれていて、その待遇は女神と同格とされるため神族に肩を並べる最上位階級である。
身に纏うのは白衣ではない。長女継承者代々の正装である真紅を貴色として纏い、前腕肘あたりから籠手ですっぽり覆われている。下は薄手の襦袢に小具足を履いた脚が覗く。本来は胴を守る鎧も装備するのだが今は略装である。とはいえ肌着の下に隠された肉体は非の打ち所がないほどに鍛え上げられており、鎧がなくとも刃が通るとは思えないほどである。彼女は当代三女神の中で一足先に継承者となり、他の誰よりも戦人であった。
カムロはガントールを見上げて言葉を継いだ。
「ガントール様の時と同様の魔術陣であると……そう思いますか」
ガントールは頷く。「霧散するならもうとっくに。なにより聴こえるだろう、鐘の音が」
なるほど。と、ザルマカシムは眉を開く。今も集堂まで届く鐘の音は、過去の魔術陣現出の時には無かったかもしれない。カムロもまた同じように思ったのだろう。近衛隊は毎度忙殺されているので、このように鐘の音の有無で違いを感じ取れるとは考えもしなかった。
「では、ここからは継承者が出現したと仮定して行動致します」と、カムロは続ける。「此度ガントール様とウツロをお呼びしましたのは折り入ってお願いしたいことがあるためです。というのも、継承者に合流して頂きたい」
ガントールは頼もしくカムロの視線を受け止め、無言の内に首肯すると、ちらと視線を横に滑らせた。ウツロと呼ばれる板金鎧は何も言わない。というより、ウツロは魔導具でしかないのだ。鎧の中に人がいるわけではなく、それそのものが兵として自律し、行動する。中身が無い……故に虚と呼ばれている。とはいえただの魔導具ならばわざわざ名指しで集堂に集めるわけはない。この鎧が唯一特別である所以は、それが先代継承者によって産み出された魔導具であり、言わば忘れ形見。先代から当代へ継承されるべき物の一つであるからだ。
「魔術陣が空にある以上、居所を常に晒していることになります。それを目標に『咎』が群がることも想定できます。継承者自身、戦闘の心得があると期待したいですが」と、カムロ。
「敵襲ですか」ザルマカシムは難しい顔をする。
「産まれたばかりという可能性もあるし、私と同じ歳だとしても内地育ちではひ弱な娘かもしれないな。万が一は避けたい……」ガントールは腕を組むと事情を把握して一人頷く。「うん。すぐにでも向かおう。私は三代目国家ムーンケイ、鎧は二代目国家ナルトリポカとそれぞれ単独でいいかな」
「はい。それで構いません。継承者を保護したのち、速やかに神殿に帰還して頂きます。前線出征を控えている以上、本人の都合は……」
カムロは言い淀んで表情を翳らせた。
「そうか、なかなかに酷だな」ガントールは言葉の先を悟り、組んでいた片腕を持ち上げて親指を頤に沿わせた。
酷。というのは、本来ガントールのみの前線出征の手筈だったところに、無理やり残り二人の継承者も合流させるということになる。内地に産まれた次女継承者と三女継承者は故郷を離れ、そして神殿を経由したあと早くても七日後には戦争の最前線へ向かう旅程となるのだ。平穏な人生から急転直下、死と隣り合わせの日々へ落ちる。それを残酷だと言わずしてなんと言うのか。
産まれてすぐに刻印をその身に宿したガントールであれば、既に覚悟はできているだろう。これまでの十七年、神殿で戦術を学び、時には前線での実戦も経験した。これから出会う二人とは訳が違う。覚悟も矜持も使命も受け入れているのだ。
「赤子だった場合は……」これはザルマカシムの言葉。
「流石にその時はその時で沙汰するしかない」
「どうあれ神殿まで保護するのは決定です。成人しているのであれば前線……それ以外に道はありません。彼女達には運命を受け入れていただく他ないでしょう……」
合流を果たす前から、その者の顔を見る前から、早くも近衛隊集堂の面々は憐憫に面持ちを暗くする。その中で、鎧だけは事情を理解していないのか、呆けたように微動だにせずカムロ達を眺めていた。
❖
夕刻にはガントールとウツロはそれぞれ山を降りた。ガントールは三代目国家ムーンケイへ向かうため、神殿の南西側から門を出て尾根縦走の路を駆け抜けて夜には国境を跨げる算段である。一方、ウツロの方は南東側の門からナルトリポカへ向かった。こちらは比較的鋪装された路を進むこととなり、轍の跡が刻まれた石畳が続いていた。直線距離も短く、ガントールより早く入国にこぎつけるだろう。
二代目国家ナルトリポカは昼の一大事に仕事も放って人々が一献を呷っていた。まるで祝祭の様相で町は賑わい、夕暮れに灯りを飾って気炎を吐く赤ら顔どもを照らし、露天では商売っ気たっぷりに惣菜を並べて店主が声を張り上げていた。客引きの喧騒に酒食の供を冷やかす男達は空を見上げては、先刻空に消えた魔術陣の名残りを、まるで取り逃した魚の大きさを語るように笑い声を上げていた。彼らにとっては継承者の出現は祝い事に他ならない。過去二度に及ぶ空振りのあとに降って湧いた霹靂の報せは、心を浮足立たせること欠かなかった。
目抜き通りの雑踏を上機嫌に行き交う者達を眺めるアダンは、ただ一人の素面であった。シーナとの約束のために酒を控えている……というわけではない。先刻前に工場に駆けてきたシーナの言葉を、いまだ飲み込めずにいた。
「本当に、選ばれちまったのかよ……」アダンは言う。それは独り言のような呟きで辺りの喧騒にかき消されてしまうが、それでも隣にいたシーナには届いた。
「うん……あたし、見たもの……」
集落の広場は収穫祭のように灯り眩しく、人々はまさに祭りの中心で上機嫌であった。日の落ちた今でこそむやみに絡んで来るものは居なくなったが、夕方頃までは頻りにアーミラの顔を拝みに来た客が押し寄せ家の前に人だかりをつくっていた。シーナは困惑しながらも、最初は「ありがたいことだ」と口先で答えていたが、当のアーミラは部屋に閉じこもり顔を見せようとはしなかった。
手放しに喜べはしない。この先アーミラにかかる災難を思うとシーナもまた心に翳を落とし、苦労して人払いをした。あの時のアーミラの表情……あの娘、泣いてたじゃないの……。
――あの時……上空に魔術陣が現れてしばらくのこと、アーミラの体に異変が起こった。
鳴り響く鐘の音と共鳴したかのように体を震わせたかと思うと、髪を振り乱してその場に膝から崩れた。シーナは人集りを掻き分けてアーミラの傍にしゃがみ込み青褪めた表情のアーミラに声をかけた。
「アーミラっ! どしたんよ!?」
アーミラは何かを吐き出すように口を開いて河原に手をつくと目を見開いたまま堪えるようにじっとしていた。閉じられなくなった唇から涎が垂れるのも構う余裕はなく、見開かれた瞳が涙に濡れて呻きながらシーナを見つめる。息を吐いたまま吸うこともできず、額からは脂汗が噴き出す。肺の中の空気がなくなったとき、歯を食いしばってシーナの袖を掴んだ。苦悶に表情を歪めるアーミラの目が助けを求めて縋りつく。いつも悩み事を抱え込み、人に頼ることだけはしなかったあのアーミラが助けを求めている!
シーナは状況が飲み込めていないままに尋常ではないことが起きていることは理解していた。しかしそれがどのような事態なのかがわからない。継承者というものが、どうすれば助けることができるのか、全く判らずただ背中をさすって案ずることしかできない。
アーミラは短く息を吸い込むと悲鳴を上げた。そこで明確に痛みに苛まれていることがシーナにもわかった。衣服を掴んで胸を抑えるアーミラの姿を見て、掌に隠された胸の奥で胸が光を放っていることに気付いた。
「アーミラ!! そこが痛いん!?」シーナはアーミラの両手を掴んで痛みの正体を確かめる。もし傷があるなら無闇に掻きむしってはいけない。娘の胸ぐらを覗くと、そこには傷と判断できないものが浮かび上がっていた。周りを取り囲む野次馬の何人かがそれを見て色めき立った。シーナはそのものたちを睨み、見せもんじゃないと怒鳴る。
まだ若い乙女の胸の谷間、かすかに浮いた胸骨の陰影の上、皮膚が火傷のように爛れている。それは細く線をひき皮膚に刻まれているが、外傷ではなく内側から痣のように浮かび上がっている。全体の図画は記憶に新しい、上空に現れた魔術陣と同じ紋様だとシーナはすぐに理解する。そうか……これが刻印……これが継承者の証……でも、なんだってこんなに痛そうにしてんだい……。
「ア、アーミラ……大丈夫だかんね? もうすぐ、刻印、できあがるから、それが終われば、痛くなくなるから……」シーナは慰めにもならない言葉をかけるのが精一杯だった。刻印が刻まれてしまえばどうなるのか、痛みが収まる保証もないだろうにと自分の中で吐き捨てながらもなんとかならないかとアーミラの身を案じ続けた。
しばらくすると上空の魔術陣が解けるように空に消え、鐘の音も止んだ。人集りは未だ固唾をのんで二人を見守るが、一部の者は外へ馬を走らせて行ったのが見えた。
アーミラは痛みが収まると、肩で息をして体を引きずるように歩き出した。その背中に歓声が上がり、シーナは肩をびくつかせて振り返る。もう一度怒鳴ってやろうかという思いが頭に浮かんだが、継承者の誕生を祝う彼らの視線には一点の曇りもない希望の光があった。
背筋が凍る思いだった。場違いなのは私なのか、私は間違っているのか、いや、そんなことはない。シーナは己を奮い立たせ、急ぎアーミラの後を追い、押し寄せる人波を割いて部屋に避難させると、アーミラはそれきり引きこもった。錠があるわけでもないが、シーナは扉を明けて中に入ることを躊躇った。どんな言葉をかけるべきなのかわからなかったからだ。だからその脚でアダンのもとへ行き、今に至る。
「みんな嬉しそうにしてる……」シーナは言う。「あたしは、嬉しくないよ……」
隣に立つアダンはかすかに目を見開いて驚くが、気持ちは同じだった。
継承者が現れたのなら祝い事だ……それは遠い前線にとってとても重要なことで、そして内地に生きる己の生活にも根底では繋がっている。――だが、喜べない。そんな言葉を誰かに聴かれたら石を投げられるかもしれないが、喜べないのだ。
他人事ならば、どこか他の家の娘ならば、きっと両手を挙げて喜び、酒を飲んで祝っているだろう。……アーミラでなければ、うちの娘でなければ……
アダンは自身の内にある想いをはっきりと自覚して口をひき結ぶ。そしてシーナの方を見るとはっきりと目が合った。
二人は、一度だってアーミラのことをただの居候とは思っていなかった。
うちの娘だ。
血は繋がっていなくとも、アーミラは大切な娘なんだ。
二人は集落の喧騒を背にして決意を新たにアーミラの部屋の扉を叩いた。
「アーミラ、体は痛むか?」
アダンが扉越しに問うと、奥から足音がそろそろと近付いて、扉は開かれた。部屋の中は暗く、僅かな隙間から廊下の灯りが差し込みアーミラの顔を細く照らした。前髪に隠れた目は赤く泣き腫らして、初めて出会った頃の痛々しい面影を思い出させた。
「も、もう……平気、です……」アーミラはそう言って胸を衣服の上から指先で撫でる。赤く腫れた胸元は血が染みていた。「そ、それよりも……」
意を決したようにアーミラは扉を開けて部屋から出ると、一度胸を張り、そして挫けたように背を丸めて視線を逸らす。掻き抱くようにしている両手には何かを隠し持っているようで、アダンとシーナは互いに目配せしてアーミラの言葉を待った。
「私……行かなくちゃ……いけません……」
「行かなくちゃって……」シーナは不安げに言葉を転がす。「心配だよ。どこにも行ってほしくない」
「だめですよ」アーミラはきっぱりと言い、シーナに笑ってみせる。「……本当はずっと、わかってた気がするんです。こうなること……受け入れるべき運命が、あるんだと知ってたような気がして。……私は一度、生きることを諦めました。……でも、シーナさんとアダンさん……二人が助けてくれた。これまでの巡り合わせが運命だと言うなら、きっと私は、この日が来ることを……自分の運命を……全うしなくちゃいけません」
シーナはなおも心配そうにアーミラを見つめるが、アーミラはこれまでにない気丈な振る舞いでシーナに対した。どこか頼りない立ち姿ではあるが、心は決まっているらしい。
あの河辺で痛みに苛まれていたときこれほどまでの覚悟を決めていたなんて、シーナにはとても信じられなかった。しかし、アーミラの次の言葉で理解する。
「魔術が、つ、使えること……ずっと隠してて、ごめんなさい……」
そうだ。あの時、魔術陣が現れる前にアーミラは確かに魔術を使っていた。
きっと私達が出会う前にも、いくつもの困難を乗り越えて生きてきたんだろう。これまで言えなかったこと、隠していた想いだってあるかもしれない。思慮深い娘であることは誰よりわかっている。
なんの考えもなしに決めたわけじゃないだろう。なんの覚悟もなしに決めたわけじゃないだろう。
……だったら、信じてやるのが親心というものか。
「……わかったよ」シーナは引き止めることを諦めたように嘆息し、一呼吸おいてアーミラを真っ直ぐに見つめた。「頑張るんだよ、アーミラ」
「はい……」
アーミラは深く頷くと、大事そうに両手に隠していたものを手渡した。
「……あの時、わ、私を、助けてくれて、ありがとう」
手渡されたものは、小さな耳飾りであった。見覚えがある。長く伸ばしたアーミラの髪に隠れてちらちらと揺れていたものた。細い耳飾りにはまだ輝きの残る魔石が嵌められ、魔力を内包して光を零している。片割れをシーナが受け取ると、もう片方はアダンの手に渡された。
「居場所をくれて、ありがとう」
何かの御守だろうか。と、アダンは戸惑いながらもしっかりと受け取った。いつの間にか少女の手も一人の大人として嫋やかに成長している。久しぶりに触れた手を見てそんなふうに思っていた。
「……うまく、娘になれなくて、ごめんなさい……」
そんなアーミラの言葉には二人は明確に首を降った。
「そんなことはないよ。短い間だったが、お前はちゃんとうちの娘だ。それはこれからも変わらない。たとえここを離れるとしてもな。……俺達はそう思っていてもいいか」
アダンの言葉にアーミラは驚いたように目を見開いて上目遣いに二人を見る。自分の中では娘として落第だろうと決めてかかっていたアーミラは、改めて二人の温かい人格に触れ、胸が咽び、堪えていた涙が込み上げそうになるが息を止めて押しとどめた。泣いてはだめだ。ろくに娘らしく振る舞うこともできなかったのに、旅立ちのときに今更縋り付くなんて許されない。そんな自罰的な想いから、アダンの言葉には否定も肯定もしなかった。
「その、御守には感謝と祈りを込めました。私がここを去った後も、どうか息災でいられるように。本当の子宝にどうか恵まれますように」
「なら、アーミラの妹だな」アダンはきっぱりと言う。「いや、弟の方がいいな。姉弟に本物も偽物もない」
そう言って娘の髪を乱雑に撫でる父の手にアーミラは狼狽えながらもされるがまま、頬に一粒の涙が零れたのを気づかないふりをした。アーミラの葛藤を理解しているからこそ、アダンは気丈に振る舞い強引にでも繋ぎ止めたかったのだろう。シーナはそんな親子の姿に微笑む。アダンもアーミラも一度決めたら譲らない。その性格は誰に似たのか。ともに過ごした日々は、確かに親子の絆だったのだ。
夜の底。喧騒の捌けた集落の広場は静寂が落ちて、時折誰かの笑い声が戸の内側から籠もって響く。月の光が晩春の空に輝き、雲間を朧に照らしている。まだ肌寒い夜風が肌を撫でると戸口に立ったアーミラは腕を組むように二の腕を擦って鳥肌を収めた。
すぐにでも旅立たなくてはならないだろう。どこに行くべきかは決めていないが、恐らくはマハルドヮグ山へ向かうべきか。アーミラは刻印を宿したときに直感した。いや、魔術を行使したことが人の目に触れた時点でこの集落にはいられなくなるだろうと思っていたのだが、いずれにしろ、別れの時は近い。
アーミラは夜風に身を晒して一人心を静ませる。この別れが望外に落ち着いてよかったと考えていた。遡ればここまでの半生は記憶にあるうちでも出会いと別れの連続であった。もとより生き様は根無し草であるから、むしろシーナとアダンは珍しい繋がりだった。いつかまた、ここに帰ってくることになるかもしれないなと思い、そんな予感に顔が綻ぶ。
と、そこでアーミラは何者かの視線を感じて笑みを消した。夜闇に目が順応してはいないが、闇の中に人影の輪郭がある。
「誰、ですか……?」アーミラは問い掛ける。返事はない。
怪しい人影に警戒しながら観察すると、次第に目が慣れてきた。帯剣しているのか、或いは杖か……手に握っている得物は細く長い。地面の土を削っているらしく、恐らくは武器の類で間違いないだろう。輪郭からみるに体躯は男らしく肩幅が張っている。背丈は一振半を越えるだろうが二振には届かない。となれば獣人ではない。私と同じ魔人種か――と、アーミラが臆せずにじっくりと人影を観察できるのは、その存在が先程から微動だにしないからだ。敵意があるのかどうかは判断しかねるが、握られた得物と間合いから脅威とは見ていなかった。
「もう一度問います……誰ですか?」
アーミラは繰り返す。しかし人影は変わらず答えない。変わりに手に持ったもので地面を削りはじめた。得物は長槍のようで、穂先が土をたやすく切り込んでいく。陣を描くつもりかとアーミラは警戒を高めたが、魔力の気配はない。そうしているうちに人影は土いじりを辞め、どさりと何かを地面に放って奥の闇へ向かって消えた。その足音は重く、さりさりと音を立てていた。それは金属同士が擦れ合う音だ。防具か何かを着込んでいたのだろうか、とすると、もしかしたら昼の魔術陣を見たどこかの兵が様子を見にここまで来たのかもしれない。でも、それならなぜ一言も話さないのだろうか。
アーミラはその者の後を追うか考えて、ためらった。害意のある者でないなら深追いする質ではない。今日は激動の一日であったため興奮に眠気もなかったのだが、流石に疲労を自覚した。もう眠ろう。そう決めて立ち上がると、部屋に入る前に人影が立っていたところへ向かって歩いた。あの人影は話しかけるのが恥ずかしくて土いじりをしていたわけではないことくらい分かっている。放られた荷物の中身くらいは検めておこうと考えたのだ。
人影の立っていた場所には放られたまま転がっている背嚢と、二種混合の言語が用いられた伝言が彫り残されていた。
マハルドヮグ領ニ而伝令也。
次女継承ノ印ヲ宿シ者、召集サレタシ。
明日朝更、此ノ場ニ御迎仕ル。
❖
謎の人物が残した書き置きに従って、アーミラは早朝には身支度を整えた。
あの場に置かれた背嚢には、一式の服が丁寧に納められていた。アーミラはそれを継承者のための――つまり私のための――衣装なのだと受け取った。あの夜、相手は既に私を視認しており、継承者であることも理解した上であの書き置きを残したのだろう。
あの人影が何者なのか、自分はこれからなにをすればよいのか、それらの疑問は悩んだところで解決しないと決めて、褥に潜り浅い眠りに身を休め、空が白み始めた頃には目を覚まし、桶に貯めた水で布巾を湿らせると丁寧に体を拭い、顔を洗った。鳥も鳴かぬ時分のこと、廊下から床板を踏む足音が近付き、その背に声がかかる。
「アーミラ、もう行くん?」
まだ誰も目覚めないだろうと油断していたアーミラは、シーナの声に眉を下げてゆっくりと振り返る。
「シーナさん……」
できることならば誰も知らぬ内にこの集落を旅立ちたかった。シーナがそれを許すわけもない。
アーミラは顔の水気を拭い、手拭いを握る。
薄ぼんやりとした部屋の中で、アーミラの碧眼が真っ直ぐにシーナと向き合う。出発の決意が固いことを知り、シーナは思わず大きなため息を吐いた。
「誰かに譲ることができればいいんに」シーナは本音を漏らす。誰かに聴かれたらきっと大目玉だろうと知りながらも、言わずにはいられない。
「いいんです」アーミラは首を降る。「……『どこへでも行け』と、お師様から言われていましたから」
石を投げた領主の娘。彼女の才を尺度にするならば、私の内にある才覚というものに無自覚ではいられない。幼い頃の記憶こそないが、きっとずっと学び磨いてきたものなのだろう。この力は誰かに譲ることはできないし、今さら明け渡すつもりもない。継承者として選ばれた以上もう隠し果せることさえ叶わないだろう。ならばどうするか。
「……やりたいことがあるんです」アーミラは宣言するように言った。
アーミラは己の欲求というものを表現することが得意ではなかった。その原因は、自信のなさ。幼い頃の記憶が欠落し、肉親の愛情を知らぬことだと考えていた。
己の由縁を知らないからこそ、自分の価値がわからない。
意思決定のために必要な土台、自身を支えてくれる価値の根幹がごつそり抜け落ちているアーミラにとって、物の善悪や自身の欲求というものが他者の価値に勝るとは思えなかった。なにか主張したいことがあるときも、それが他者に受け入れてもらえるものなのかを考えると、途端に口ごもり、億劫になってしまう。
しかし、しがらみに黙殺されていた心は、この状況を甘んじて受け容れることを厭うていた。
「わ、私……失くした記憶を取り戻したいんです。取り戻して、もっと強い私になりたい……だから……」
「その目を見ればわかる。きっと何言ったって決意は変わんないって……。前線なんて、ほんとに命がいくつあったって足りないのに……」残念そうにシーナは言う。
素直に心残りだっただろう。シーナからしてみれば、ようやく娘の核に触れたばかりだと言うのに、それを手放すことになるのだ。前線へ行って欲しくない。もう一度娘として家に招き入れたい。健気な娘を抱きしめてやりたい。そうした想いが口から溢れ出すのを堪えて、明るく笑みをつくる。
「絶対に死ぬんじゃないよ……まずは自分のこと守りなね。人を守るのは、それからでいい。わかるかい?」
「はい」アーミラはシーナの言葉一つ一つにうんうんと頷く。
「記憶を探すのも大事だけど、たくさんの人と出会いなさい。……守るものができて、人は強くなれるんだから」
「……はい」
立派な言葉で送り出そうと努力したものの、シーナにはこれが精一杯だった。親らしく振る舞おうとしたものの、伝えたいことはこれじゃないとわかっている。
シーナは取り繕った言葉を飲み込み、観念したように手を広げた。
「……おいで」
「……はい……っ」
扉を隔てたぎこちない二人の距離が縮まって、慣れないままに抱き締めた。シーナは言葉もなく抱き締め返し、さらにぎゅっと強く抱き締めるとアーミラ髪に鼻を埋める。母娘二人、初めての抱擁だった。
最初からずっとわかっていた。アーミラに伝えたかったのは言葉ではない。母の温もりだったのだ。ずっと前から、こうして抱き締めてあげたかった。もっと早く、こうしてあげたかった。燃やしても燃やしても消えることのない温もりをわけてあげたかったのだ。
「あなたのことが大好きよ……」
シーナの抱擁にアーミラはぐらりと体勢を崩し、自重を支えるように母の背中に手を回した。洟をすすり、静かで熱い息を吐き、なんとか涙をこらえようとするアーミラ息遣いがしばらく続いた。この別れに泣き顔を見せたくないのだ。
「頑張ります……っ」アーミラは言う。「私……ずっと、何かから逃げてるような気がしてた……向き合わなくちゃいけないことがあるんじゃないかって……だから、だからこの旅で何かが変わるんじゃないかって思うんです……。
もし変われるのなら……全部取り戻して本当の私になりたい……自信があって、力があって、シーナさんとアダンさんに誇れる私になりたい……」
私を守るために、本当の私と出会いたい。
人を守るために、大切な人と出会いたい。
これまでの人生と決別して、変化を遂げる時が来た。
涙声の密やかな決意表明に、シーナは繰り返し頷いた。思わず涙が零れて、アーミラの髪に落ちる。本当にこの娘はどこまでも優しいんだから、それこそ女神のようにどこまでも。
「アーミラならきっとできる。信じてるからね」
名残惜しく体をなぞる指先が離れて、シーナはアーミラを残して部屋をあとにした。
アーミラは扉を閉じたあと額を押し付けて目を閉じ、刻一刻と迫る別れを感じていた。込み上げる涙をぎゅっと抑え込んで上を向き、手探りで褥の上に置いていた継承者の衣服を手に取る。潤んだ瞳を乱暴に拭って誤魔化し、畳まれた衣を手早く広げて確かめた。泣いてなるものか。
継承者の正装であろうその一張羅は生地一つとってもかなり上等なものだということが素人目にもわかる。少なくとも新しく仕立てられたものだろう、先代達が着用した形跡もほつれも見当たらない。
装いは青藍染めの法衣と見えるが、馴染みがないので袖を通すのも苦労した。襯衣は一度前後ろを逆さに袖を通して、襟が頤にこすれて窮屈だとわかってから前袷の釦留めなのだと理解するほどであった。一度着てみれば難しいことはないが、これまで貫頭衣程度の簡単な衣服しか持っていなかったのでこの一張羅の内どれが袴でどれが上衣かがすぐには見分けられないのだ。なかには袈裟や頭巾といったものもあったが、その時点では何に使うものなのか検討もつかず、大きめな座布団と止め紐のない巾着にしか見えなかった。
アーミラは、とりあえず目に鮮やかな紺色の細袴と釦留めの襯衣、そしてゆとりのある作りの巾着が頭巾だとわかると頭に被り、残る衣装は判断がつかないため背嚢に押し込んだ。ずいぶんな略装となるがそれでも見違えるほど瀟洒な装いだ。おそらく問題ないだろうと決めて部屋を出る。後ろ髪を引かれる思いで一度振り返り、がらんとした室内を目に焼き付けると胸に去来する思い出をそっと仕舞い込むように扉を閉めた。
外へ出るとシーナとアダンが待っていた。その表情がどことなく剣呑で落ち着きのないように感じてアーミラは首を傾げる。
「あそこ、誰かいるんよ。お迎えなんかね」
シーナは言う。指をさした方には言葉通り何者かが立っていた。昨晩に人影を見た場所である。……そうか。とアーミラは眉を開いて警戒を緩めると、朝日に照らされた人影の正体を見る。
それは、黒い鎧であった。神殿からの迎えであるとは先刻承知ではあるが、遣わされたにしてはその姿はやや恐ろしい佇まいである。全体は無骨で重厚な鎧が覆い、関節部には薄くしなやかな板金が重なり合うことで執拗なまでに肌を隠している。古びているのか鎧には艶がなく、夜に出会えば月明かりを映すこともないのだろう。きっと目を凝らしても闇に溶けるはずだ。だからあの晩に顔が伺えなかったのかと、アーミラは心のうちに理解した。
じっとして動かない様はともすれば置物のようであった。人が無意識のうちに行う片足への重心移動や僅かな揺れ、指先の手遊びもない。全身を鎧で覆っているのに威圧感さえなく、なんとなく人の気配を感じさせない。二人もその違和感を捉えているようで、不審がるのは当然のことであった。牧歌的な農地の風景にその者が馴染むことはなく、正直夜に見るよりも場違いで不気味な趣きは強く神殿までの道程を共にするのだと思うと旅たちの決意が揺らぎかねないところであった。
「大丈夫です、迎えの方ですよ」アーミラは二人に答える。
とはいえ、鎧の方も自分で誤解を解くなりすればいいのに。と、アーミラが不満げにちらりと視線を向けると、鎧はそろそろと近づいてきた。その所作はやや躊躇いがちなように映る。
「……え」
アーミラは不意に声を洩らす。黒色の鎧に滴る血に遅れて気付いたのだ。板金の隙間を伝うようにして指先に雫を作り、一滴の血が土に落ちた。
「あなた、怪我を――」
駆け寄ろうとしたアーミラに対し、鎧は掌を掲げて首を振る。気にするなと言うことか。態度からして、その血は自分の血ではないと言いたいのか。では誰の血だろう?
片眉を跳ね上げて、やや顎を引くアーミラは上目遣いに鎧の顔を窺うが、面鎧の孔の奥には闇が満たされているばかりで瞳が確認できない。もしや顔が無いのではないかという思いが浮かび、いやまさかと今度は眼光鋭く覗き込んだ。鎧は無言のまま掌でアーミラを抑えてそっと距離を置くように促した。構わず覗き込む。顔が見つからない。
そんなアーミラと鎧のやり取りは取るに足らない些細なことであるが、アダンとシーナは目を丸くした。ただでさえ怪しい存在に物怖じせず、アーミラがあそこまで距離を詰めるなんて初めて見る光景だった。
「あなた……魔導具なの?」アーミラは言う。「だから話せない……」
鎧は黙って頷く。そして槍の穂先を地面に向けた。土を削って文字を彫る。
――次女継承者ノ刻印ヲ宿シ者、召集サレタシ。
「それは、昨日も読みましたよ……?」
――爾、刻印ヲ。
ああ。と、アーミラは理解した。そして襯衣の釦を上から外していくと、アダンがたまらず声をかける。
「お、おいアーミラ……?」
「え、あ……すみません。刻印を見せてほしいそうです……あ、こ、この方は神殿が遣わせた魔導具ですので、問題はありません」
「いや、それもそうだが、字が読めるのか?」
「……あ、」
いや、そうか――と、アーミラは思う。
アダンとシーナが戸惑う理由は至極当然のことであった。この世界では識字を学ぶ者は自由人階級以上の地位の者に限られており、およそ裕福でなければ識字教養は必要なく、日常会話は口頭での発話で事足りている。この集落には言葉はあれど文字はない。
「……え、と……はい」アーミラはばつが悪そうに答える。
アーミラが識字能力を有しているのはやはり老婆による教育の賜物であった。というのも、魔呪術を学ぶ上で文献を繙読する必要があり、あくまで魔呪術のための基礎知識でしかない。なので、アーミラからしてみれば文字の読み書きは別段意識して秘匿していたわけでもなく、ナルトリポカでの日々のなかで筆をとる機会も文字に触れる場面も無かっただけのことである。
些か気まずい表情のアーミラを見てアダンとシーナはその事情を漠然と悟る。彼女は、老婆と過ごした日々の中で多くの重要な物を獲得したのだろう。二人を多少なりとも親のように感じているからこそ、過去の親代わりを務めた存在について語ること、老婆への恩義を表に出すことができないのだ。
沈黙の中で鶏が鳴く。長閑に色彩を取り戻す朝に日が差して、アダンは言った。
「愛されているんだな」
「あ、い……?」
面食らったアーミラにアダンは穏やかに笑い、繰り返す。
「愛されているんだ。アーミラ……俺もシーナもそうだし、きっと言葉を教えてくれたお婆さんもそうだ。……みんな君のことを大切に思っている。愛されているんだよ」
アーミラはその言葉をしばらく転がして、やがてすとんと心に落ちた。
私が手に入れたものは、どれも与えられたもの……考えてみれば当たり前のことでしかないのに、それを愛という言葉で表すと、かけがえのない輝きを持って目の前に現れる。
ずっと気付かないでいたものだ。
愛だなんて。
私が愛されていたなんて。
親も無く、血のつながりのない私は出会いと別れを虚しく繰り返してきた。誰にも馴染まず、何処にも属さず、一所にとどまらない。それが私の人生であると思っていた……だが違う。私は確かに出会っていた。決して孤独の闇に落ち続けることはなく、別れの度に光へと導く新たな邂逅があったのだ。そしてその繋がりは消えない。もし、二度と会えない別れでも、共に過ごした思い出、与えられた知識は私の中に残り続ける。
「私だって愛しているわ。アーミラ……帰ってきてね」シーナは言いながら、言葉尻は震えて洟をすすっていた。
「……はい……っ」アーミラも思わず胸咽ぶ。「必ず……」
いったい何度泣くのだろう、今日は泣かないと決めていたのに。アーミラは一張羅の袖を濡らし、毅然と胸を張った。そよぐ風が襯衣の襟をはためかせ、はだけた胸元の刻印が淡く青白い燐光を放つ。
鎧は賢しげに、その者の旅立ちの決意を見届けるのであった。
■002――継承者
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
「ちょっと、待ってください」
息を切らしてアーミラは言う。
二代目国家ナルトリポカの集落を出発したが、鎧が単独で山を降りた往路と比べて、その足取りは遅い。
理由はいくつかある。まず、行きは鎧単身で降りの道程であり、寄り道もない。対して帰路は継承者に随行することとなるため、歩幅は継承者に合わせなければならない。その継承者、アーミラこそ問題の人物であり、遅れの原因だった。
幸か不幸か、新たに現れた継承者が産まれたばかりの嬰児であるという懸念は杞憂だったものの、アーミラの足取りは遅々としており、これならば赤子を抱えて運ぶ方がまだ早い。
復路での遅れの原因は間違いなくアーミラだが、体力がないという訳ではなかった。十七の娘にしては弱音を漏らさず黙々と歩くのだが、夏の陽射しに体力も水分もすぐに底をつく。人である以上どうしょうもないことだが、休憩のために道中いくつかの集落を経由しなければならなかった。そして歓待を受け、長時間足止めされる。この歓待こそ、遅れの一番の原因である。
口々にかけられる祝福の言葉に、アーミラはどのように返礼するのが作法なのか分からず、小動物のように所在なく狼狽する様を見せた。飯を食うための店を選ぶのも、水を貰うために井戸を借りるのも、アーミラは言葉に詰まらせ苦労していた。
民草は「当代は笠に着ない継承者だ」と褒めそやすが、頼りない姿に一抹の不安感を募らせて、その背を見送るのだった。
そんな調子で、ただでさえ人嫌いな向きのあるアーミラは体力の消耗が激しい。集落ではむしろ気が休まらないため、国境手前の街外れに夜営して夜を明かし、早朝にナルトリポカを抜けたときには、既に二日を費やしている。
残るは山行、マハルドヮグ山中腹では急勾配が続きぐんぐんと標高も上がり、空気も薄い。這う這うの体でアーミラは休息を求める。先導する鎧は足を止めた。
「き、休憩を……しましょう……」
喉が乾いているのか声も掠れて、言い終わる頃には路の横に手をついて座り込んだ。
鎧はアーミラのもとまで戻ると槍の穂先で土に文字を刻む。書記体系は依然として古めかしい文体であるが、ここでは口語で表記させていただく。
――既に二日を消費した。可能なら午前にも神殿へ辿り着きたいのだが。
そんな遠慮のない要求にアーミラは青褪める。
「えぇ……。む、無理ですよ……魂を、まだ下に……置いてきて、ます……」
魂が下に残されている。というのは、マハルドヮグに登る者が口にする言葉で、詰まるところ高山病である。高地により空気が薄くなると呼吸が苦しくなり、頭痛や疲労の症状が出るというのは神殿に住む者達にとっては常識であるが、梺の国々には発達した医術は広まらず、宗教的な尺度から解釈されている。それによると、マハルドヮグ山には選ばれた者しか辿り着けず、登るほどに魂を下に残して肉体と離れてしまう。そしてついには歩くこともままならず倒れるという。助けるためにはその肉体を山から降ろし、取り残された魂と合流させること……と、このようにして解釈されているのである。古くから言い伝えられる経験則に基づく民間療法に信仰という肉付けが行われているが、アーミラはそれを信じていた。一方で神殿付きの鎧は高山病というものを理解しているのであった。
鎧はつま先で土をならして文字を消すと改めて彫り刻む。
――魂は肉体から離れたりしない。問題ない。呼吸を深く意識しろ。
そのように伝えると冷徹にアーミラの手を取り、立ち上がらせる。アーミラは疲労から足の踏ん張りが効かず情けない声を出しながらふらついた。そして盛大にため息を吐いて愚痴をこぼす。
「もう……あなたは魔導具の割に人間らしくて、変な感じです……止まれと言ったら止まってほしいんですけど……」
――俺は俺を魔導具と定義し、そしてその価値観を他者と共有している。
「なにを言っているのか……そもそも魔導具って魔導回路の機巧ですよね。ちゃんと受け答えできるなんて、まるで思考する……心があるみたいじゃないですか?」
苦しそうに膝に手をついてアーミラは言う。皮肉ではなく本心であった。項垂れた視界に槍の穂先が返答する。
――対象に心があるのかどうかについて、それは観測者側の主観に依存するだろう。その場合、俺が人であるか。ではなく、君が俺を人と見做すかが重要だ。
その言葉を読んでいるかどうか、アーミラは地面を見つめて荒い呼吸を繰り返す。垂れそうになった唾を飲み込み、ちらりと鎧の手を見た。旅立ちの日、つまり二日前のあの日、迎えに来た鎧の手は何者かの返り血に濡れていた。
鎧には口がない。故に何があったのかを語ることもない。そしてアーミラも問いたださなかった。しかし、推測するにあの返り血は敵を殺めたのだろうと考えていた。私が継承者に選ばれたときに現れた陣……それは敵からしてみたら脅威を報せる合図に他ならない。おそらくはあの夜、鎧は私のもとに現れ、無事を確認すると闇の中に身を潜めて敵の凶刃を払ったのだろう。――と、アーミラは考えていた。そして事実はそのとおりである。
鎧は休息を必要としないため、次女継承者である彼女から片時も目を離さず、足音一つたてない兇手を一つ残らず召し取っていたのだ。
そうしている内に呼吸も整い、高山病の初期症状は軽減した。彼女の言うところの『置いていった魂』が遅ればせながら山路を辿り肉体に追いついてきた。興味は依然として鎧へ向けられているが、口を開くより先、鎧は休憩を切り上げにする。
――俺の背に乗れ。神殿まで運ぶ。
鎧はしゃがみこんで指先でそう書いた。アーミラは恥じらいから断りを入れようとするものの、最終的には鎧の背におぶられることになった。楽ができるなら助かるというのが正直なところで、梺の路は舗装されているとはいえ左右は針葉樹林が広がっており二人の他に人の往来はない。乙女の体を触れさせることについては、この男は魔導具であるとして折り合いをつけた。なんとも都合のいい解釈である。
「あなたの名前ってあるんですか?」
鎧の背中に乗り、まわされた腕に膕を乗せて身を預けるとアーミラは問う。鎧は上体の重心を前傾にしてアーミラを支えると器用に槍を手繰る。歩きながら一文字ずつ、地面に書き記していく。
――ウ、ツ、ロ。
「ウツロ、うつろ。……もしかしてそれって空っぽの鎧だからですか? 賢人種の書体に当てはめると『虚』と書きますよね」
鎧は何も聞こえていないふりをして返答をしない。歩きながら文字を書き記すことが面倒なのだろうか。怠惰を表現するその行動の人間臭さにアーミラはますます興味を示して目を輝かせた。面倒を厭うなんて……これほどまで血の通った魔導具を作り出す技術が神殿にはあるのだろうか。
「ね、ねえ、ウツロさん。貴方は誰に作られたんですか? 故郷はどこです? 一番古い記憶はなんでしょう?」
相手を魔導具と見るとアーミラの人嫌いは鳴りを潜めてずけずけとまくしたてる。神殿に向かう緊張を紛らわせたいのか、あるいは旅立ちの昂りが影響しているのかもしれない。
ウツロはちらりとアーミラの方を見ると、思案げに前を向いてぼんやり歩き続ける。先程の無視とは違い、返答に困っているような、言葉を選んでいるような間が続いた。そして、「先代ノ忘形見」と、穂先を走らせる。
「え……」アーミラは書き残された文字が後ろに流れていくのを目で追って読み返す。「確か、二百年ほど昔……でしたよね」
にわかには信じられないことだが、しかし先代の忘れ形見……それならばこの異質な魔導具の存在にも納得できる。と、アーミラは考える。深く追求したい気持ちを抑えて次の返答を待つ。鎧は「ニホン」と書き、間をおいて「フメイ」と書いた。
「ニホン……それが、故郷ですか? 聞いたことはありませんが昔はそんな名前の集落があったんですかね」アーミラは独り言のように呟いて推理するが、鎧はそれについて反応しない。
「フメイ、記憶は不明……。ですが貴方は四代目継承者を見たことがあるはずですよね」
鎧は頷く。
「先代はどのような方でしたか?」
鎧は黙ってアーミラを見ると、背負い直して前を向いた。どことなく機嫌を損ねたような気がした。心があるのかないのかはわからないが、鎧が先代によって生み出され、今ここにいるということは、先代の死を見届けたのだろう。やはり踏み込みすぎたのだ。アーミラは不躾にあれこれと聞いていたことを反省し黙って背中に揺られることにした。
前方から後方へ流れていく針葉樹の景色。気温を高めていく山の気候。たゆみのない律動に揺られ登坂する景色に代わり映えはなく、その内にアーミラは瞼が重くなっていく。
うとうとと舟を漕ぎ出して、意識の舫いを解くと夢の中へ落ちていった。
❖
ガントールが単身、三代目国家ムーンケイの国境を跨いだのは鎧が二代目国家入りした時分よりも先のことであった。
崖がちな傾斜のきつい山肌に拓かれた蜿蜒たる路、本来であれば時間を要する道程を、彼女は一足飛びに跳躍して、『降りる』というよりも『落ちる』ようにムーンケイに辿り着いた。彼女の移動方法は尋常ではない。女神の継承、そして獣人種の血。その二つが彼女にこの跳躍を可能にしていた。
ムーンケイは神殿から南西に下った山嶺の中腹にある卓状地周辺に築かれた国家であり、安定した鎔鉱炉を常時操業し金銀銅と貨幣の造幣を一任されている。主に賢人種が多く住む都市である。また、卓状地の首都周辺を『上層』、卓状地の下の街は『下層』と区分されており、刻印が現れたのは距離からして下層であるとのことだった。ガントールはずれた背嚢を背負い直すと、改めて方角を確かめる。目的地の方角に目星をつけると黒染の長衣に笠を被って先を急ぐ。
「これがムーンケイ……これが内地か……すごいな……」
神殿からムーンケイへ辿り着いたガントールが、初めて訪れる都市の様相に思わず零れ出た言葉だ。
造幣操業により燃え続ける焰と、魔呪術の研鑽による文明の混淆する様は圧巻。磨き抜かれた金物に炎の揺らめきが煌々と街を照らし夜闇を隅に払い退けている。夜半にも関わらず賑わいを見せる市場はいつもこうなのか、あるいはこの日が特別なのか、往来が激しく人でごった返しており、手練の戦士や術師が一級の品々の真贋を見極めようと忙しない。彼等は前線へ向かうものか、或いは帰還した者達か、鋭い目つきと剣幕で店の者相手に値段の交渉をしている声が賑わいの中でよく聞こえてくる。相手に立つ店番も慣れたもので、傷があればその石は正真正銘の天然物の証拠であるだの、魔導書が古びているのはそれだけ重用されたということだの、涼しく受け流している。通り過ぎざまに聞き流しているガントールにはどちらが正しいかはわからない。
マハルドヮグ山脈から南下した山行はムーンケイの卓状地を迂回して下層に続き、海峡に途切れた港湾都市は一代目国家アーゲイへ続く海路を擁している。その海域の間に点在する島嶼部こそガントールの向かう目的地だが、彼女は卓状地の迂回を考えてはいなかった。山の断崖と同じように、この街を突っ切ってしまえば早いという算段だ。
先を急ぐと決めていても、やはり道中腹は減る。ここまでの道で十分に時間と距離を稼いだのだからと、休憩がてら歩を緩めて物見遊山に街を逍遥する。外套に身を包んで身分を隠しているため傍から見たら旅人にしか見えないだろう。手頃な飯を探して露店を冷やかしては目についた炙り肉の串を買うと、次はどの露店へ行こうかとふらつきながら一口頬張る。
活気のある露店に雑多な往来、のべつ幕無しと耳につんざく人々の声……宵の縁に灯る灯籠は鎔鉱炉から噴き出す焔に似て活気がありこの街の生命力を表しているようだ。そして行く先には仲間との出会いが待つ。ガントールの心は浮足立っていた。
そして串を平らげて市場を抜けた上層の崖際、そこから下層を一望すると、星空を地上に再現したかのような街の景色が広がる。
「これは……」ガントールは言葉を失う。
まさに地上に再現された星空。その小さな輝きの一つ一つが魔鉱石に燈された灯りであり、その数だけ人の営みがある。下層でもこれほどまでに魔導具が普及しているのなら、やはり魔呪術の研鑽が日夜行われているのだろう。流石は賢人の都。
眼下の絶景を眺めてガントールは歳相応の態度で目を輝かせた。吸い込む空気は立ち昇る火の粉に熱気をはらんでいて気を昂ぶらせる。ガントールはこれまでの疲れも忘れ、唇を舐めて口角を吊り上げると、卓状地の崖際から下層を眺め下ろして飛び降りた。
ガントールが向かった下層、島嶼部への航路が繋がる港湾では、上層の炉にも負けぬ喧騒と賑わいを見せ、まさにその只中にこそ三女継承者はいた……いや、待ち構えていたのだった。
❖
三女継承、チクタク・オロルがこの港湾に足をおろしたのは同日の夕暮れ時であった。彼女はまるでこの日が来ることを予知していたかのように落ち着いていた。
手袋を嵌めた自身の掌に視線を落とすと物憂げにしばし見つめ、顔を上げると海凪の向こう、生まれ故郷の諸島を目に焼き付けるように眺める。その顔は面映ゆく望郷に思い馳せるには厳しい視線で、怒りさえも滲んでいるように見えた。
島は夕日を背に逆光が照らし、黒く陰り輪郭を描く船が波の随揺られながら帰っていくのが見える。帰らないのは己だけだと心に決めて、オロルは港湾を歩き出す。沈みゆく西日の鋭いきらめきに耳飾りが反射した。
彼女が纏う外套は首を通すだけの造りで丈も短く袖もないが装飾は隙間なく曼荼羅模様に埋め尽くされており、広がった裾の内側には前掛けが揺れている。冷徹な印象を持つ金色の瞳は世界を見定めんと油断がない。
白っぽい衣装に対してそこから覗く素肌は夕日に濃い褐色を照り映えて、背丈も十を数える程度に見えた。この上背の小ささと琥珀を焦がしたような肌の色は賢人種の血特有のものだ。その肌の上には赤土の泥を塗っている。民族的な頬紅は賢人種の中のさらに一部族に属する出自の者であることを示す。
そんな少女の姿はどこか斜に構えたような出で立ちで物怖じがなく、肝が座っているような印象がある。腰に手を当てて港を歩き、口元には小癪な笑みさえも浮かべていた。短く整えられた髪は瞳と同じ金色で、潮風に撥ねた癖毛を踊らせている。
彼女は下層の街に入るとすぐに雑多な人の波を潜り抜け、教会堂まで辿り着くと司祭に対して手袋を外してみせた。それだけで身分の証明は事足りた。司祭は伝え聞いていたものよりも強烈な継承者の到来に、驚きと畏怖の綯交ぜになった面持ちで歓迎した。
その後、急拵えの宴席が野外に設けられた。儀式めいたものではなく、オロルがこの場にいる間だけでも言祝ぎの体裁を整えようと司祭が人を集めたのだ。噂を聞きつけた下層の住民たちは継承者の姿を一目見ようと駆け寄り集まり、教会から広場までの道という道は人で埋まった。
教会前に設置された玉座に鎮座するオロルは既に片足の靴を脱いで膝を立てると、肘を乗せて寛いでいた。司祭の大時代的な歓待と大仰な挨拶を前にしてもまるで言葉を知らない猫のように、いっそふてぶてしい程に視線を跳ね返している。崇め奉られて当然という態度は堂に入ったもので、そこに演技然としたものもなければ気負った背伸びもない。そうして、女神としての威厳を発揮しながら、供される酒食にこれ幸いと箸をつけ夕餉にありつけるのであった。
腹くちくなり夜が深まった頃、下層へ降りてきたガントールが人集りの中を掻き分け、その中央に坐す娘を見つけたときに始めて継承者二人が出会った。
「はじめまして」ガントールは高台に据えられた玉座に座る賢人の少女に声をかける。
オロルの方は声をかけられる前からガントールを見つめていた。その者が待人であると悟り顔を向ける。毅然と見つめ返す少女の顔は年相応に可憐で、丸みのある頬の輪郭にあどけなささえも感じさせる。ガントールはふと、首筋にかけて襯衣の陰に消える蜘蛛の糸のような筋が目に留まるが、言葉を継ぐ前にオロルが口を開いた。
「……長女継承者じゃな」
いやに古臭い言葉づかいだ。ガントールは片眉を吊り上げる。若い少女の口から老婆の様な訛り、だというのにそれが様になっているとも感じられた。小さくもどっしりと構えた彼女の悠然とした雰囲気は、精神的な成熟によるものだろう。
「わしの名はチクタク・オロル。呼ぶときはオロルで良い。察する通り、三女継承者じゃ」
息を吐くついでのように間延びした、しかし油断ならない気配を纏ってオロルは名乗った。射抜くような金色の瞳が脂下がった笑みを浮かべて、遠くを睨む夜鷹を思わせる。ガントールはその瞳を見た時に得も言われぬような感覚で腑に落ちた。なるほど、これは生き残るだろうな。
その直感は前線に向かう者の目利きのようなもので、つまるところ互いに会話を交わしただけでおおよその力量を推し量ったのだ。ガントールの内に漠然と抱いていた不安はここで随分と晴れた。内地に継承者が現れたのだから、前線の厳しさとは無縁の、もっと軟弱な者が現れるのだろうと覚悟していたが、いま目の前に居るのは少なくとも肝の座った賢人である。祝祭の主役として祭り上げられて尚、玉座に悠然と腰を落ち着かせ、手には酒の入っていたであろう杯を乾かしている。
一方でオロルもまたガントールを値踏みするように不躾に眺めていた。笠と長衣に隠しているが、朱い髪に緋色の瞳。対の頭角を備えた天を衝くような獣人種の女。もとよりその者の存在は誰もが知るところで、当代唯一の継承者として嬰児の頃より広く膾炙している。
「それではよろしく、オロル。私はリブラ・リナルディ・ガントール。ガントールと呼んでくれ。前線出征を前に君達継承者を迎えに来た」
そう言って握手を求めて右手を差し出し、オロルがそれに応じると、握りあった腕に対して眉を顰めてから言の葉を継いだ。
「『君達』? わしの他にも……つまり次女も揃ったのか」
「ああ。隣国ナルトリポカでも魔術陣が現れたんだ。そっちには別の者が迎えに行ったよ」
「ふむ、内地か。であれば襲われている可能性は低いが……いや、ナルトリポカとなると油断はできんな」
「こことは違って農地だからな。まあ、迎えのものも油断する性分じゃないし、心配はしてないよ」
「お主がそういうのなら抜かりはないのじゃろ。とはいえ、肝心の継承者が腑抜けでなければよいがのう」
オロルは自分も内地生まれであることを棚に上げてずけずけとそんなことを言う。ガントールは笑うところなのかどうか眉を困らせた。そして思い出したように手を叩いた。
「おっと、刻印を検めるのをすっかり忘れていた」
三女継承者の纏う雰囲気に今更疑うつもりはなかったが、むしろこれで偽者ならば大したものだ。と、ガントールは玉座の傍に膝をつくとあぐらをかいてオロルを正面から見上げる。
「人前で悪いが見せてくれないか?」ガントールは気安く言う。三女継承者の刻印は服を脱ぐ必要もなく確かめられることは事前に承知していたのだ。
「ふむ、まあ出し渋るものではないわな」
そう言ってオロルは手袋に手をかける。周りで銘々酔いどれの者達が俄に色めき立ち始めた。刻印をその目で見ることは今を逃せば一生ないだろう。ガントールは喧騒のただ中で努めて冷静にオロルを見守る。その後ろで司祭は一人固唾をのんで身をこわばらせていた。彼は一度刻印を見ているはずだ。なぜ緊張しているのか……ガントールはその妙な気配を背中に感じながらもさして気に留めなかった。
オロルは視線が一身に集まることを煩わしく思いながらも手袋を取り去る。その白い手袋に隠されていた素肌は……いや、なんだこれは……ガントールは一変、先程までの笑みも消え表情を曇らせて視線を厳しくした。
露わになったその両掌、手首から先はどちらも同じように引きつった膠原質の皮膚が爛れて硬質化している。蝋で固めたような独特の艶があり、血の透けた赤紫色をしていた。爪は赤黒く、節くれだった指は関節ごとに裂け目が開いて、荒れた木の枝か鳥の脚を思わせる肌である。
ガントールは思わず息を呑んだ。人の肌とは思えない異様な手――。先程まで気炎を吐いて心地よく酩酊していた者達も、三女継承者の娘の手袋の下の手が予想外に仰々しく痛々しい傷痍であることに肝を冷やし、畏怖の念とともにたじろいだ。
司祭の横腹をつつく男は「印ってのはこんなもんなのか」と声を潜めて訊ねる。司祭は曖昧に首を傾げるばかりである。無理もない。司祭もまた人生で初めて出会う継承者なのだ。
「ガントールよ、お主が刻印を宿したとき、痛みはあったか?」
不意に問いかけたオロルに対し、ガントールは我に返って答える。
「あ、ああ……無かったな。産まれて間もないから記憶がないだけかもしれないが」
「普通はそうなのじゃろうて……わしはな、痛かったぞ」
天蓋のようにオロルの全身を覆っていた外套が裾から捲られると、隠されていた襯衣一枚の体を見ることができた。襟から覗く首筋や裾から出た上腕のから伸びる筋は、それぞれが至るところで収斂し、ある種の葉脈か血管のように皮膚の上を走り紋様を構成する。その筋が繋がる果ては全て掌に帰結していた。両掌には刻印の上に刻印が、自傷行為のように幾重にも重ねられてしまっているがためにもはや何が描かれているのか判別がつかないほどだった。
「刻印現出は三度だけだったはずだ」ガントールは断ずるように言った。「その火傷みたいな手は、三度繰り返されただけでは足りないくらいじゃないか……?」
「そうじゃな」オロルはさも当然と答えて続ける。「お主が選ばれたとき、次女と三女は現れなかった。そうじゃろう?」
ガントールは首肯する。
「それから十年、二度目の魔術陣が空に現れた」
ガントールはまた頷く。
「その時わしは選ばれたのじゃ」
「まさか、それならなぜ――」
ガントールは膝立ちになって食い下がる。が、オロルはそれを遮った。
「すぐに消えてしもうたのじゃ。
わかるか? 選ばれたはずが次の瞬間には力を失う、この腹立たしさが……」
オロルは変わらず玉座に寛いでいるが、語調には忌々しい怒りが漏れていた。しかしその怒りも鳴りを潜めて続きを語る。禍々しい手指を見せびらかしながら。
「先代から数えて二百年の節目……継承者が選ばれるのならばこのわしが相応しかろう。例え次女継承が現れずとも、三女継承は賢人種から生まれる……それはわし以外にありえん。じゃが、運命はそうならなかった。
ならば運命を捻じ曲げるまでよ。何度でも、何度でものぅ」
「だから自ら迎えに行った」と、オロルは平然と言う。自ら組み上げた魔術陣によって一人、繰り返し三女継承の力をその身に宿すために研鑽を行った。
「じゃが、結局は失敗した」
その身に三女神の力を宿そうと試みる度に掌は爛れ、癒えるのを待たず傷の上から次の陣を刻む行為は手全体を変質させた。手の甲から指先まで傷痍は拡がり、本来持っていた柔らかな乙女の肌は変色し関節のささくれた硬い鱗状に変異した。
言わずとも継承者の能力は容易に再現できるものではなく、文字通りの奇跡。神の力なのだ。たとえオロルが優秀であろうと、自らの手で神の力を欲したところで奇跡が手に入るわけはない。彼女は禁忌を冒し、文字通りその手を汚したのだ。
そうして全てが失敗に終わったとき――正確にはオロルの万策が尽きたわけではなく、次の試みを思案する間でしかないのだが、少なくともこれまでの試みが全て失敗に終わったとき――その日がやってきたのだ。
オロルの話を聞き終え、ガントールは掛けるべき言葉を探していた。
禁忌と知りながら強行する執念。
変質することすら顧みない狂気。
そのどれもがガントールの理解を超えていた。
言葉が出ない長女継承の姿を見て、オロルはどこか満足そうに目を閉じる。その時、遠巻きにいた民衆がそぞろにざわめき、どこかひやりとした塩風が香った。海の匂いだ。
「……なにか来た」
ガントールが暗闇を警戒すると同時、誰かの叫びが場を凍りつかせる。
『トガが出たぞ!!』
けたたましく鐘を打つ音が辺りに響き、家の中にいた者達は血相を変えて外へ逃げ出す。警鐘は警鐘を呼び、ラーンマク一帯へ広がった。駆け出す者は一心不乱の有り様で、宴の席も構わず蹴飛ばして、転がった杯のがらがらという音にいっそう驚いて悲鳴をあげ振り返りもしない。
ガントールとオロルは人波を見送り、さてと互いに目配せした。
トガが出た。新たな継承者、オロルを狙う敵が現れたのだ。
「話は後だ、ここは私に任せてくれ」ガントールは杯をぶちまけて立ち上がる。
「わしに護衛なぞ必要ない」
「戦う気か?」
「当然じゃ。さもなければこの腕は切り落としたほうがましじゃろうて」
オロルは玉座の上に立ち上がると敵の姿を探した。先程までの酩酊もどこ吹く風で、その瞳に揺らぎはない。
遠方を睨み呟いた。
「手負いじゃな」
「視えるのか?」
ガントールの問いに答える代わりに、オロルはトガの状況を伝えた。
「背中に漁船の銛が突き刺さっておる……空の陣を頼りにわしを追ったか、最初は島を襲い、その後にここへ来たようじゃな。さっさと片付けるぞ」
オロルが指をさしたのは通りの先の暗がりだった。潮の臭いを纏う敵の影をガントールも認める。ムーンケイ下層と島嶼部を結ぶ港から現れたそれは、里に迷い込んだ熊のような姿だった。ただ、その大きさは熊の倍はあるだろう。ずんぐりとした巨体はこちらに向けて頭を下げてのそりのそりと四足歩行で近付いている。弓なりになった背の頂点は、通りに並ぶ家々と肩を並べる程だ。人気のなくなった通りを自身の縄張りであるかのように悠然と歩いている。全身の体毛は重くじっとりと濡れていた。
「あの図体で港の櫓が鐘を鳴らしてないってことは、海に身を潜めて来たのか……」
「まさか」オロルは鼻で笑う。「隠れる場所もないじゃろうて――」
オロルの言うとおり、この魔物は忍び寄るような狡猾さを持ち合わせてはいないように見えた。空に現れた魔術陣を目指し愚直に島を襲い、既にオロルが本土へ渡ったと分かれば臭いを頼りに港を目指したのだろう。
濡れているのは海水のせい――だけではない。海水と、血に塗れているのだ。
道中に立ちふさがる命も、逃げ惑う命も、見境なく食い散らかしながらこいつはここに現れた。ガントールは扼腕して奥歯を噛みしめる。この塩辛く饐えた臭いは貪った罪の残り香か。
オロルは飄々と続ける。取りこぼした命を振り返ることなく。
「――さて、わしの初陣じゃ。見事に華を添えてみせい」
ガントールは目眩がする程の激情を覚えながらも己の不覚を律する。オロルの無情なまでの切り替えの速さは共感できないが、判断の誤りはない。重要なのは今これから犠牲者を増やさないことだ。
敵を眼前に対し、油断なく外套を脱ぎ捨て、ガントールは背剣していた得物を構えた。鈍く金色に煌く剣である。
その剣は鋒が平たく刃を設けていない特殊な代物だった。突き刺すことができない剣――本来戦闘用ではなく、罪人を裁く斬首に用いる振り下ろすことに特化した剣――これこそが長女継承者に与えられる神器、天秤である。
敵は咎と呼ばれる存在で、その外見はてんでばらばらな獣の四肢を寄せ集めたような魔物だ。その姿に種としての規則性はなく、あるものは狼、またあるものは烏のような姿をしている。その大概は出来損ないのような醜い外見であり、冒涜的ともいえる姿である。
今、ガントールとオロルが対峙しているものもまた尋常ならざる化け物に他ならない。
山の稜線のように盛り上がり丘を作るトガの背筋には脊椎らしきものが露出しており、頭部から骨盤を繋ぐ背骨が黒い毛並みの上から甲羅のように覆い被さっている。白い肋骨と黒い毛皮が縞模様を描き、その上から篝火を朱に照り返して、二人の前に立ち塞がる檻のようだった。
発達した前脚は丸太のように節くれだち、捻じくれた鱗が棘のように変質している。後ろで揺れる尾部は全長の半分を占めるだろうか。形状は平たく、鰭の役割を果たすのだろう。海を渡って来たのなら、その尾鰭の筋力は陸に上がってなお猛威を奮う得物と視えた。まさしく巨大な斧だ。
しかしオロルが手負いだと指摘した通り、その背には数本の銛が深々と突き立てられており、もはや背鰭と同化している。血は止まっているらしく、トガは痛がる素振りもない。太い首に支えられた強靭な顎が涎を垂れ流しながら憤怒に牙を剥いている。
血走った形相はひっくり返った白目のままにオロルを射抜いている。昼の魔術陣現出から島嶼部を狙い、ここまで追いかけてきた執念深さはかなりのもの。ガントールは深く息を吐き、酔いの残滓を確かめた。油断できる相手ではない。
「け、継承者様、急ぎ避難を……」
青褪めた司祭がこわごわ言う。
「阿呆を抜かすでない。女神の地位は奉られることに非ず。お主らこそ離れろ……ここはわしらの領分じゃ」
オロルがぴしゃりと言い捨てると男はこれ然りといった顔をして、ためらいながらも恐れをなして逃げ出した。若い女が魔物と対する道理はないが、それが継承者であるならば話は別だ。
先程までの人集りは蜘蛛の子を散らすように捌け、後には二人の女と一匹の化け物が残された。
先手を仕掛けたのはトガの方、オロルが玉座の階段を降りて間合いを詰めるとき、軋む足場に意識を向けて僅かに瞳が爪先に向けられた。しびれを切らしたトガはそれを好機と見たのだろう、土を蹴り、雷のような勢いで飛びかかった!
だが実は、オロルは誘いこんだのだ。わざと視線を外してトガに間合いを詰めさせた。手練であるガントールにはそれがわかった。初戦とは思えぬ豪胆な罠。オロルは外套の内側に包み隠した手に呪力を練り、後の先を取らんとする。しかしトガとの距離が近い。オロルの経験不足か、それとも慢心か――ガントールには、彼女がわずかに間合いを誤ったように見えた。
「まずい……!」
思わず声を漏らすガントール。助太刀に入る余地はない。そして誤算だったのはトガの持ち合わせた武器を見誤っていることだった。
トガが持ち合わせている兇器は逞しく棘に覆われた前脚でも、巨人の斧のような尾部でもなかった。背に露出している白い脊椎のようなものこそが真の兇器であった。
それは毛に覆われた背中から剥がれるとまるで巨大な鋏のように開かれ牙を剥き、オロルの小さな体に喰らい付かんとする。不覚を許したオロルの首元に牙が触れる刹那、一閃。
不意の光にガントールは思わず目を瞬くとオロルの安否を見定める。その光景に違和感を覚えた。トガと相対していた賢人の姿は先程までいた場所から消え、明後日の方に、まるで最初からそこにいたかのように佇んでいた。
一方でトガの方は遅れてうめき声を上げた。鮮血がトガの巨躯のいたるところから吹き出している。背中からは堰を切ったように血を噴いていた。大きく開かれていた鋏の動刃――つまり上顎が大きく欠損していた。
オロルは足元に転がったトガの顎骨を見下ろすと、しゃがみ込んで血溜まりに両手を浸した。ガントールは怪訝に思う。あいつ、何してるんだ……!?
一方で背中を断ち切られたトガは何とか体勢を立て直す。痛みに興奮しているのか地団駄を踏んで転がると勢いよく建物にぶつかり篝火を押し倒した。ぼうっと盛大に火の粉が舞い、息吐く暇もなく弾けるように炎の中から飛び出す。狙いは未だオロルである。隠し玉の兇器を失ったとて、トガにはまだ斧がある。爪もある。
継承者を引き裂くべく二度三度と前脚を振り回して襲い掛かるが奮闘虚しく空を切る。その時のオロルの身のこなしにもガントールはやはり目を疑った。
早すぎて見えないのだ。
まるで現れては消える幻のようである。
トガの爪がオロルの額に届く、頬を引き裂くその次の瞬間、爪は虚しく空振り土を踏む。攻撃が確実に届く筈なのに刹那には避けられている。トガは歯痒さに唸り声を響かせると力技に頼りだした。
前脚を軸に身を捩り、渾身の力を持って巨大な斧を横一文字に薙いでみせた。
「オロル!!」思わずガントールが叫ぶ。
膂力を存分に奮う薙ぎ払いが疾風を生み出し炎が吹き飛ばされる。ぶおんと耳朶を打つ轟音と共に一帯の瓦礫は押し出され、散った火種が一層勢いを強めて火の気が辺りを囲んだ。薙ぎ払いの一閃には強かに肉の爆ぜる音がして、血飛沫がガントールの体を濡らす。揺らめく篝火が鉄臭い煙を昇らせて消えてしまえば決着は闇の中に紛れてしまった。
しばらくして、灯石と火勢を失った瓦礫の薄闇の中でトガの雄叫びが響もした。
すわやられたか!? ガントールの背筋が寒くなる。しかし――
「勝負あったぞ」血煙の中から、呑気な声が響いた。
オロルはトガの全身全霊を持って繰り出した薙ぎ払いを前に回避動作をとってはいなかった。ガントールは見ていたのだ。今度こそ確実に屠られる……そして肉の爆ぜる音を聴いた。噴き出す血を確かに浴びた。
血煙が私雨のように一帯を濡らし、視界が晴れると、そこにオロルは立っていた。一歩も退かず、立っていた。その向こう、トガの太く発達した尾は千切れて転がっている。
「なんで……」ガントールは声を漏らす。オロルが無事であることが、喜ぶよりも先に不可解であった。「どうやって……!?」
オロルは不敵な笑みを浮かべると人差し指を立て、自分の口元に近付けた。ガントールの疑問など野暮だと言うように。
「わしの名はチクチク・オロル・トゥールバッハ。時を司る三女継承者……わしは決して、傷付かん」
オロルの静かな勝ち名乗り。その血に濡れた指先にこそ、あの一合を分かつ手品の種があった。牙を失い、斧を失ったトガは自らの鮮血に溺れ、鼻から血の泡を吹きながら尚もオロルに襲い掛かるつもりでいる。もはや脅威ではないその敵を前に介錯に立つオロル。ガントールは見守る。
トガは息も絶え絶えに、よろけながら勢いをなくした前脚で飛びかかる。というよりも、後ろ脚で立ち上がり、万歳の体勢で倒れ込むようだった。瀕死でありながら尚襲いかかる敵意はどこからくるものなのか、あるいは理性などとうに捨てたのか、ガントールは愚かしくも哀れにさえ思った。とはいえオロルの身の丈をゆうに超える巨体である。のしかかられるだけでもひとたまりもないだろう……もちろん、攻撃が当たるならばの話だが。
オロルは軽く握った右手を前に掲げる。
そして親指に引っ掛けていた四本の指を弾くようにぱっぱと開いた。血塗れの指先が飛沫を飛ばし、霧状の血液が舞い、空中に静止した。オロルが時を止めたのだ。
のしかからんとするトガを待ち受ける細かな飛沫の粒一つ一つが針のようにその身に突き刺さる。剣閃を防ぐ丈夫な毛皮をすり抜けて、厚い皮膚に極小の飛沫が針のように沈み込むとすぐに激痛が全身を襲いトガは断末魔をあげる。思わず身を攀じるが、体内に埋め込まれた飛沫は時を止めたまま動かない。トガは激痛の最中苦しみ悶えれば悶えるほどに肉体を掻き乱され、虚しく命を落とした。オロルがトガの尾を切り飛ばした手品の種も同様の術を行使したのだろう。
「希う果てに齎された……やはりわしは相応しかったのじゃ……」オロルは独り言のように呟く。
ガントールはそんな三女継承者の姿を前に静かに身震いした。それは司祭たちが感じた畏怖の念と同じだ。
オロルは既に完成されている。
そして少しだけ壊れてもいる。
間違いなく戦力にふさわしいだろう。些か容赦がなく陰惨ではあるが、待ち望んでいた三女神の末の妹との邂逅に高揚していた。
一方のオロルは、まるであくびを噛み殺すように眠たげな声で続けた。
「さあ、では改めてこの刻印の真贋を検めよ」
ガントールは促されるままに傍へ寄り、オロルの掌にそっと手を添え、視線を落とす。傷だらけではあるが、戦闘後の今なら魔力が残光となって残っているのではっきりと見える。
そこには精緻な紋様が小さな円環を象り、それぞれが互い違いに組み合わさりながら大きな円環の中に納まる精巧な紋様が描かれていた。篝火の消えた夜の薄闇の中で燐光を発し、手首の方へ伸びる鎖状の筋が螺旋を描きながら肘へ続いて襯衣の袖の内側へ消えていく。
なるほど、真贋。間違いはない。皮膚の奥にあるいくつもの失敗は積み重なって階層をつくり、膠原質の透けた掌に埋め込まれている。一番上に刻まれた印こそ、代々受け継がれた三女継承の印そのものに違いない。たとえ躰にいくつ偽物があろうとも、いや、偽物に塗れているからこそ唯一光を放つものが際立つ。彼女は紛れもなく、本物の三女継承者だ。
❖
三女神の継承者は、その名の通り三柱の女神になぞらえ、それぞれの力を継承する存在である。
それについては当代も例外はない。限定的な言い方をしたのは、当代は、先代の刻んできた歴史と比べると例外が多いためである。
初代から三代目までの継承者はそれぞれが一人ずつ、百年周期で現れた。初代は獣人から戦士が、次代は魔人から魔術士が、三代目は賢人から呪術士が、といった具合である。故に神殿側は前例を持たず対応は後手に周り、継承者に対しての待遇処遇を決めかねていた。ただ一つ確かなのは、百年周期であるという事実のみだった。
四代目継承者からは、獣・魔・賢人種からそれぞれ一柱ずつ、同時に生を受けるようになった。この異例の変化により神殿は本格的に介入を始め、刻印を持つ娘が誕生した際には嬰児のうちに親元を離れ、神殿に預けられることとなる。
刻印を宿す娘は女神の地位に就き、天帝と同格として招かれる。物心がつく頃になると戦術や規範、その他のいっさいについても学び育てられる運びである。五代目も当初はその流れを汲むはずであった。
しかしこれまでに語られたとおり、当代が現れたのは二百年経ってからのことだった。一代分の空白がある。そして娘は長女継承のみ順当な手順を踏み、次女と三女には突然刻印が現れた。
継承者については未だ謎が多く、この不可解な出来事も今の段階では神の気まぐれと片付けるのが精々である。一つ言えるのは、アーミラを除く残りの二人もまた旧知の仲というわけではないということ。
時を別にして、それぞれがそれぞれの門をくぐり、動き出した運命の渦中に身を投じているということである。
「ほう……ここか……」
閉じ合わされた門扉の前に二人の女が立っていた。オロルとガントールである。
二人は咎を討ち取った初陣の後、一夜を明かして朝霧の立ち込める薄闇を駆け、ムーンケイ下層から北上しこの山の頂に辿り着いた。オロルにとって初めて目にする神殿の門扉は分厚く重厚な造りで、表面は石の削り出した荒い肌面が結露に光っていた。その冷たくざらついた感触を掌で確かめると言葉もなく感慨深い思いが湧いて真剣な表情になる。後ろで見守るガントールはさも満足そうに腰に手を当てている。視線はオロルから流れて眼下の地平を眺めると、今度はオロルが振り返ってガントールの背中を見つめた。
その姿は獅子か麒麟か、物言わず構えているだけだというのに、腰や脚にすらりと竹のようなしなりがあって、朝日を望む横顔も凛々しく晴れ晴れとしていた。女の目的は端から護衛ではなくこの景色を眺めることであるかのようだ。
マハルドヮグ山の頂に佇む神殿はようやっと朝日に照らされて白く煙る靄を溶かしているばかりだというのに、その女は鶏も鳴かぬ時分から溌溂とした目を滾らせていた。今日という日に焼べられた暁にも劣らぬ、燃え盛る緋眼である。
「ガントールよ、何を見ておる?」オロルは問う。
「ん? ああ――」
清廉な空気を一息吸い込み、これまでの山行の路を遠望した。朝靄の向こうで朝日を浴びる峠の街は遠く小さく、吹き溜まりの塵のようにしかみえない。さらに果ての果てを見晴るかすと砂塵と戦火に暗く濁った世の果てがあるはずだ。たとえ見えずとも、地平の向こうであろうとも、それでもガントールは誇らしく答えるのであった。
「――故郷さ」
思い馳せる景色こそが前線『四代目長女国家ラーンマク』……己の故郷。
二人は互いに何とはなしに不敵な笑みを作り、恐れるものはないと門扉を開けた。アーミラ一行が辿り着く一日前、継承者二人の神殿入りである。
❖
――キィィィン……。
重い瞼の隙間から覗く視界は薄暗く、聴覚は判然としない雑音を拾う。それは耳鳴りに似た、玻璃ような薄く硬質な響きを持って、どこから聞こえてくるのかもわからないか細い音だった。
「……、ア………ラを……」
雑音の中で男の声。なにやら緊迫した声音である。視界を覆う人影が声の正体か、せわしなく、なにかに追われているかのように落ち着きがない。誰に向けての言葉かはわからないが、視線は私の頭上を見つめていた。場所は室内と見えるが窓は小さく、棚に遮られて射し込む光は埃を照らしている。
私の視界は不意に浮き上がり、男とは別の何者かに背後から手を回され抱きかかえられると、抵抗することもできず運び出される。闇の中へ――
「い……、必ず…………から……」
部屋に取り残された男の声は遠くなり、小窓から射し込んでいた光も届かなくなる。一面は闇に覆われ、唯一感じるのは私を抱えて走る何者かの切迫した息遣いだけ。
揺れる体の平衡感覚が次第に明確になり、真っ黒な視界が白く炙られる。肩を揺らされていることを悟ると、泡沫の夢から意識が覚醒していくのがわかる。
そうか、夢だ。
夢……誰かが私を――
❖
アーミラが目を覚ますと、目の前にはウツロがいた。面鎧の二つの穴がアーミラのことを見つめている。右肩には板金の手が添えられて、アーミラはゆすり起こされていたのだと理解する。なにか夢を見ていたような気がしないでもないが、瞬き一つほどの刹那の時間しか体感していないようにも思えた。疲労のせいか、昨晩の眠りが足りなかったからか、前後不覚に陥るほどに深く眠っていたと知る。
ともあれ、アーミラはついに神殿に辿り着いた。
世界に黄昏を齎すこととなる当代の娘たち。代を数えて五代目の三女神継承者が、今ここに集うのである。
季節は向夏の候。突き抜けるような青空のもと、風は涼やかでありながらもアーミラの額はうっすらと汗ばんでいた。表情は蒼褪めて茫然と神殿の門扉の前に立ちつくしている。頭巾の奥で影を落とす眼窩には涙に濡れた碧眼の双眸が、開かれた門から覗く神殿内部へ視線を注いでいた。
大陸一の標高を誇るマハルドヮグ山の頂に築かれた神殿。朝霧の立ち込める樹林を切り開いた山路を進む尾根縦走を丸二日かけての道程の締めくくりには、低木を抜けて森林限界の領域へと足を踏み入れた。岩肌を見せる山の装いはすぐに人工的な造形を見せて重厚な石積の防壁が眼前に迫る。土をさらって埋め込むように舗装された石畳に導かれ辿り着いた門扉の向こう側、陽に白く輝く玉砂利が敷き詰められた広大な前庭が迎える。いくつか見える石造りの建造物も瀟洒に待ち構えており、アーミラは自身が身を置いていた景色とはまるで違う高潔さを保っていると感じた。そのさらに向こう側には巨岩と見紛うほどの――おそらくは尋常ではない年月と執念によって工匠が彫刻したであろう――三女神の像が悠然と聳え立っている。神殿の中央から三体の女神がそれぞれ下界を見つめ、その一体の視線が丁度彼女のいる所を睥睨している。三体の視線は意図的に三方向に設けられた門を見下ろすように造られているのだが、そんな工匠の意図を知る由もない少女には像の鋭い眼差しが心の奥底を射抜き、拒絶の意志を湛えているように思えて肌が粟立つ。ウツロの背に乗って運ばれた彼女は、その旅程の内に備わるべき実感も、使命を背負う重みも無いまま、夢うつつの内にここまでたどり着いてしまったのであった。「魂を下に置いてきてしまった」とは、まさによく言ったものだ。
門をくぐるどころか後退り、石像の視線が冠木に遮られるとようやく我を取り戻す。今度は恐怖心からか辺りを見回して忙しない。ウツロを見つけると傍によって、まるで「なぜ私はここにいるのだろう」とすっかり怯えているようだった。事実、彼女は怯えきっていた。甚だ情けなくもあるが無理もない、自身が継承者であることを知ったのはほんの三日前に満たないのだから。
――少女の名はアーミラ・アウロラ。魔術の師である老婆との死別から三年の月日が経ち、彼女は神殿に招かれた。
後に災禍戦争の終結を宣言することとなる五代目三女神継承者のひとりである。
いかにも暑そうな青藍染めの法衣に中は釦留めの襯衣と提灯袖の衣。さらに袈裟で厚く着込んでいる。これは道中、略装だったアーミラに対してウツロが正しく着付けたものだった。下は細袴のうえから指貫を重ねて足先は沓が覆う。目深に被った頭巾の内側には長く伸ばした髪を胸元に束ねて重たく結わえている。……陽射しの強さに対して肌の露出を許さぬのは少女の意地や性格によるものではない。
アーミラの隣ではここまでの道中の警護に務めていたウツロが着付けも見届け、出迎えの神人種に交代する形で後を任せた。総勢六名。皆が綿布の白衣姿で、詰襟の釦は一番上まできっちりと留めている。下は厚底の長靴に脚絆を着用しており、並び歩く姿は統率された兵の様相。威圧感に言葉もなく、囲まれてしまったアーミラは目を白黒させて鎧の姿を探し求めた。
神殿での歓待はナルトリポカで経験したものとは趣きが異なり、肩透かしにも少人数のささやかなものだ。とはいえこれはあくまで出迎えに限った話で、後日大規模な儀式が待ち構えている。そんな展望を知ってか知らずか、アーミラはどうしようもなく場違いな気分になり、息苦しさを覚えた。
用意されたこの青い正装だってまさしく「服に着させられている」のが痛いほどわかる。数年前までは汚れの染み付いた襤褸を纏い、荒れた教会堂で饐えた臭いの泥に塗れて生きていたのだから、生まれの身分というものを痛感する。彼女は生まれ持った地頭の良さでもって辛うじてこのめまぐるしく変化する状況を把握していた。つまりは自身の身体に浮かび上がった『刻印』……これ一つで自身の価値が変化したのだと、改めて継承者の重圧を実感することになった。ここまでの道中で両手を挙げて言祝ぐ者達に流されて、内心多少なりとも浮かれていたのかもしれない。だが忘れてはならない。彼らは私を一人の人間として見てはいないのだ。前線に投下される兵戈を物珍しそうに褒めそやしているだけ――それでも。
胸の真ん中、ちょうど心臓のあたりだろうか。アーミラは刻印が宿る瞬間の痛みを思い出していた。忘れることのできない痛み。焼けた刃を心臓に突き立てられたような……焦げ付き、焼き付き、剥がれることのない継承者の証がここにある。
法衣の上からそっと撫でて門へと進む。相変わらず恐る恐る確かめるような足取りで、視線は辺りを見回しては表情を強張らせていたが、それでも故郷を振り返ることはしなかった。
❖
神殿に入ったアーミラは、神人種の後ろについて案内されるがままに歩いていた。その背に声がかかる。
「おーい、そこの青い法衣の方。もしやあなたは継承者ではないか」
声の方へ振り向くと、剣士のような出で立ちの女がずかずかとこちらへ向かって来ていた。敷石の通路を蹴散らすかのように突っ切って、玉砂利を踏む足音をざりざりと響かせる。アーミラは見てわかるほど身を強張らせて声が出ない。問いかけが独り言になったことをさして気にすることもなく、ずいっとアーミラの面前に立ち塞がるとガントールは改めて声をかける。
「やはりあなたも継承者で間違いないな? 私は当代長女継承のリナルディ・ガントールだ。よろしく」
快活かつ友好的な態度のガントール。微笑む視線が今度こそ返答を待つ。対してアーミラは、開いた口が塞がらない様子で自らを抱きすくめてガントールの差し出す手を前にすり足で距離を取った。案内役を担う神人種は最初こそ和やかな笑みを浮かべて二人を眺めていたが、当惑したように笑みが曇る。記念すべき継承者二柱の邂逅……だというのに一体なにを怯えているのだろうか。
「が、が、ガントール……さん……」アーミラは名前を確認する。
「ああ。そうとも」
「……本物が居たなんて」
アーミラの言葉にガントールと神人種の案内の者は首を傾げる。それについてアーミラは説明を付け加える余裕がなかったが、これ程までに驚いているのは、眼の前の長女継承者の姿を知っているからだ。なにより、アダンが毎日鑿を叩いて削り出していた木像こそ、ガントールだったのだ。
「本物というなら、アーミラも正真正銘の次女継承者であろう? 改めてよろしく」
再び握手を求めるガントールに対し、アーミラはなかなか手を伸ばさない。
「あ、えっと……。……わ、わ、」
ガントールは怪訝に片眉を吊り上げながらも努めて柔和に次の言葉を促す。
「わ、わ、私……やっぱり継承者じゃないと思うんです……ひ、人違いというか、な、何かの間違いというか……」
「えぇ?」
ガントールは目を丸くして隣に立つ神人種に視線を送る。人違いをしてしまったのだろうか。しかし、その者はすぐにかぶりを振って答えた。
「人違いでは御座いません。ガントール様の仰言る通り、此方のお方は五代目次女継承者、アーミラ・アウロラ様に御座います」
「でっ、で、でもっ……わ、私、刻印なんてこの前出てきたばっかり……。い、い、言い伝えと違うとお、思い、ます……」アーミラは言いながらますます蒼褪めて、想像するだに恐ろしい先行きへの不安に身を竦めた。
ガントールは「なるほど」と心の中でつぶやくとアーミラの肩に手を乗せた。アーミラは驚いたように肩を強張らせる。小さく悲鳴を漏らしていたかもしれない。まるで捕らえられた兎のようだ。
「刻印については三女も同じだ。言い伝えと異なっているのはアーミラだけではない。むしろ仲間意識すら芽生えるというものだ。そうであろう?」
友好的で屈託のないガントールの言葉にアーミラは僅かながらに警戒心は解れたか、上目遣いに顔をみて、こくこくと頷いた。ずかずかとこちらに迫ってくるときは恐ろしさに取り乱してしまったが、ガントールの二振に届く長身の威圧感は印象を改めて、頼れそうな出で立ちと見ることができた。話に出た三女刻印の出現時期の遅れというのも、萎びた勇気に安堵を与えてくれたのは確かである。が、傍から見た神人種からは、偉丈夫に気圧されて頷くしかできなかったように見えた。
そうして、ガントールに引かれるままに神殿での慣れない一日は濁流のように流れていく。大股で先を歩くものだから、アーミラは雛のように小走りについていくのがやっとである。
嬰児の頃より神殿に招かれた長女継承は勝手知ったる敷地内を闊歩し、「ここが湯浴場だぞ」と指をさすと、ついと指先は流れ、「見てみろアーミラ、あの石像……私より大きいな」なんて暢気に連れ回す。「ここは闘技場、組手をしてみるか? ……冗談だ、なにもそこまで怯えなくても」……などと軽口を叩いているうちに、アーミラも歩調が合い始めていた。
緊張感のない物見遊山な高い背の後ろについて周るうちにアーミラは年頃の少女らしい笑みをこぼして幾分か普段の調子を取り戻した。戦人の装いに怯えていたが、長女継承は獣人種。アダンやシーナと同じ種属であり、慣れてくるとむしろ親しみやすいとさえ感じていた。もしかしたら獣人種というものは皆、心根が暖かなのかもしれないと認識し始めていた。
ガントールは悟られぬようにアーミラの笑みをちらりと視界の端に認めると口の端を釣り上げてお互いに打ち解けたことを実感した。しかし気がかりも湧いた。三女と比べてどうにも頼りない……悪いやつではなさそうだが内地育ちらしい弱々しさが気掛かりだ……彼女は前線で生きていけるのだろうか……?
❖
「はぁ……極楽……」
宵の口。吹き込む初夏の風は平地からの雨雲を運び山肌を洗う。そんな折、うっとりと湯に全身を浸し、滑らかな岩肌に首を預けて目を閉じるガントールとアーミラがいた。ここは神殿の一劃、神人種の生活圏と重なる湯浴場である。
一日を神殿の中で過ごし、これまでの人生では目にすることのなかった新しいものの数々、神殿という生活圏に形成された格式高い文化、あらゆるものが新鮮であり、同時に落ち着けないものであった。ただでさえここへ辿り着くまでの道中も険しい山行である。そこへ来ての温泉というのは誰にとっても極楽の境地だ。アーミラは集落に残した二人に一抹の申し訳なさを感じつつも、出征までの時間を遠慮して無駄にしてはもったいないと割り切り、むしろ心ゆくまで楽しむことにした。
これまで身を清めるには桶に貯めた井戸水か、せいぜい沐浴が当たり前のことであったが、ガントールに連れられて来た温泉……なんという贅沢か! 湯を溜める半露天の湯槽だけでも教会堂一つ分の広さはあるだろう。これほどの空間を体を洗い清めるためにのみ使用するとは。それだけでもアーミラを驚かせたが、ガントール曰く、湯浴みではかけ湯に留まらず、全身を湯船に沈ませるのだという。恐る恐る足の爪の先から湯に沈ませると、骨身に染み付いたこれまでの労苦がじんわりとした熱に温かく包み込まれ、肌が輪郭をなくして溶けてしまいそうになる。このまま目を閉じたら深く眠りの底へ沈んで目覚めないのではないだろうか。神殿で生きる者達は毎日こんな心地よいものを愉しんでいるなんて……!!
マハルドヮグ山から湧き出る源泉を引いているだけあってなにやら水質もただの水ではないようだ。アーミラは両手を皿のようにして湯をすくうと僅かにとろりとして乳白色の濁りがある。何か治癒の術式を混ぜているのか、濁りの中に燐光を纏い夕暮れの時分に青白く仄かに光っている。すくった湯で顔を温めると恍惚に目を閉じる。
「髪は湯に浸からないように纏めたほうがいいぞ」
ガントールは良心からそう言ったが、アーミラは少し困った顔をして愛想笑いをした。
「え、いやぁ……はは」
「裸を見られるのが恥ずかしいのか? 女同士だろ」
「そういうわけでは……」
少し躊躇いがちに、アーミラは湯面に揺蕩う髪を両手で束ねて器用に纏めた。そして恥ずかしそうに首元まで湯に沈める。身を落ち着けると、アーミラは顔にありありと喜色を浮かべる。隣では我が事のようにガントールが手柄顔で口の端を吊り上げ小さく笑うが、湯に沈めた一糸纏わぬアーミラの体を見ると声もなく驚いた。彼女の全身にはいくつもの裂傷跡が見て取れたのである。小傷ではない。致命傷と思える程の深い傷痕だ。肉を穿たれたような跡に真皮質の蚯蚓腫れが見ていて痛々しい。首元は特に酷く、傷のせいで皮膚の色さえ薄赤くなっている。髪で隠したかったのか……なんだか悪いことをしてしまったな……。
「すまないな、首の傷を隠したくて髪を下ろしていたのか……」
「あ、……はい……でも気にしないでください。わ、私が勝手に恥ずかしがっているだけで……」
前線を生きるガントールでさえ、須臾の間閉口してしまった。オロルもアーミラも内地生まれだというのに傷だらけではないか、なんだか私の方が恩寵育ちだな……。そう思う一方で、やはりアーミラについて推し量るのはますます難しくなる。戦えるのかどうかはいよいよ実戦を見てみないことには判断しかねるといったところか。
「なぁ」ガントールは岩を枕にしてアーミラに声をかける。
「はいっ!?」不意に声をかけられたせいでアーミラは不必要に驚いてしまった。飛び起きて湯面に波が立つ。
「はは、いちいちそんなふうに驚いていては心臓が持たないんじゃないか?」
「うぅ、すみません」
「いいさ」ガントールは僅かに躊躇い、そして別のことを口にする。「アーミラは胸に刻印があるんだな。それが次女継承の紋様か……初めて見た」
アーミラは乳白色の湯に沈んだ自身の胸元に目を落としてはにかんだようにぎこちなく笑う。
「未だに、実感が湧かないです……」
天体を象る刻印が、彼女の胸にくっきりと刻まれていた。
下地となるのは、夜空に浮かぶような真円。その中心には、上下を指す三角形が重なり合い、六芒星を形作っている。外周には、解読不能な古代の文字がぐるりと刻まれ、さらにその外側には弧を描く弓が添えられている。そして、真円の中心を貫く一本の斜線――まるで地軸と天軸を示すように、斜めに交差していた。
この刻印はいわゆる天球儀と呼ばれる神器を象るものであり、弓から伸びて真円を貫いている斜線は地軸と天軸を表している。
アーミラは自身の首元に湯をかけながら刻印を撫で、皮膚の痛みがないことを確かめる。内側は墨を入れたように黒い。指の腹で触れるとすべすべとしていた。ふとアーミラはガントールの方に視線を向けて首を傾げる。そういえば……。
「あ、あの……ガントールさんは、どこに刻印があるんですか?」
一度は途切れかけた会話。それをアーミラの方から言葉を継ぐのは少し勇気を必要とした。しかし、生来の好奇心が後押しをしたのだろう。思いの外すらすらと声に出すことができた。
「ん? ああ、私はここだ」
ガントールは岩から頭を起こして半身を後ろへ向ける。アーミラの方に背中を向ける形となった。
細いうなじを外気に晒して、背は駿馬のようにすらりとして陰影に富む。余分な贅肉はなく、肥大しすぎた筋肉もない。アーミラは頭のより動物的な直感で理解していた。これは鍛練で手に入れた躰ではなく実戦の中で磨かれたのだろう、と。
そしてある種の機能美と女性性を兼ね備えた彼女の後ろ姿には、縦横に駆ける細い傷痕が刻まれていた。戦場で負ったものではない事は明白で、つまりはそれこそが長女継承の印。
描かれた紋様はアーミラの身体に刻まれたものよりも比較にならないほどに大きい。次女継承の刻印が両手で収まる程度であるのに対して、ガントールの背中に刻まれた長女継承の刻印は肩から腰にかけて雄々しくどっしりと構えている。
下地に描かれているのは地を指し示す正三角形。その上に均衡を保つ両天秤が重ねて描かれ、吊り下げられた左右の皿にはアーミラのものと同様の書体を持つ文字が載せられている。下部に台はなく、代わりに本体の柱部分は剣の形状をしており鋒は三角形の下端を突き抜け背骨に沿って臀部に伸びる。
と、そこでガントールは前髪を右腕でかきあげて、湯気で額に貼り付く髪を房ごと指先で持ち上げ撫でつける。その動きに追従して肩甲骨が滑ると、アーミラからは背中の天秤がまるで傾いたかのように見える。ちょっとした技巧か、神の遊び心だろうか? アーミラは小さく吐息を漏らす。
私のような不釣り合いな印象を微塵も感じさせない、靭やかな身体によく似合っている。アーミラは素直にそう思った。見惚れるように眺めていると、今更ながらガントールの右腕の違和感に気付いた。あまり目を合わせないようにしていたことと、視界の陰になる立ち位置の都合で一糸まとわぬ姿でもいまの今まで意識が向かなかったのだ。背中越しではあるが、どうやら二の腕の中程から断ち切られており、そこに黒錆の義手が嵌め込まれている。
「どうだ? 私は自分の刻印を見ることができないからな、どのようなものかよくわからないんだ」ガントールは首だけを後ろに回してアーミラに問う。身を捻らせて刻印を一目見ようと苦労して、諦めたように天を仰いだ。「あの鏡がもっと大きくて綺麗なら、私も見れたんだがなあ」
独り言にしては大きい声でぼやいては、湯浴み場壁面の曇った金属製の板を見る。ある程度なら姿見として機能するが、座高に合わせて低い位置に嵌められているためガントールには不便だった。幼い頃にも背中を見ようと奮闘した経験があるらしいが、身を捻って窺えるのは半分が精々、歪みなく刻印の全体像を見ることはできなかった。
「いよいよ明日だな」ガントールは唐突に振り向いた。「……って、恥ずかしがる割には、見るのは平気なんだな?」
「あっ、す、すみません!」
アーミラはガントールに指摘され、長く注視していたことに遅れて気付いた。ガントールは気にしていないと笑い飛ばす。つられて笑いかけるが、上手く笑えずに湯面に視線を落とす。浮かない表情の自分自身が水面に映り揺れていた。
「明日なんですね……」
日が沈み、再び昇れば継承の儀が執り行われる。神殿に呼び寄せられたのは、曰く、継承者の襲名式――心像灯火の儀――と、代々に伝えられる神器を授かるための儀式――神器継承の儀――その他諸々の式を執り行うため、そして戦場へと出征するための壮行式の準備が進められるということだった。
「私、その……自信、ありません……」アーミラは素直な心境を吐露した。ガントールは頷く。
「無理もないさ、今まで内地にいたんだからな。それが突然『国のために戦え』ってのは、アーミラには酷な話かもしれない」その言葉に、今度はアーミラがこくこくと頷いた。
「ガントールさんは何度か実戦も積んでますよね。 正式に神器を継承して、出征することは喜ばしいことですか?」
「もちろんだ」ガントールは勝ち気に笑みをこぼす。「リナルディ家はスペルアベルと縁のある血筋でな、辺境伯の中から継承者が出るのは願ったり叶ったりだ」
スペルアベルとはマハルドヮグ山嶺を迂回するように南下したところに位置する平原地帯の名だ。地理的にはムーンケイよりさらに前線側であったか、……確かそうだったはず、アーミラは地理に明るくないため思い出すのに僅かな間があった。
三代目国家ムーンケイの南西側国境と四代目次女国家デレシスの西側に接しており、過去永きに渡り戦場として進退を極めた。現在も内地での戦端が開かれた際には防衛線としての機能を保有していると聞いている。そこに縁のある血筋となれば、彼女の家柄は辺境伯の中でもかなり上の、重要な地位についているのではないだろうか。
「……とはいっても、妹はいい顔をしないけど……」
「え――」アーミラは思わず声を漏らした。『妹』?
どういう意味だろう。気になって問いを重ねようとしたが、二人の会話を断ち切るように湯浴み場の入口の引戸が勢いよく開かれる。驚いて顔を向けたアーミラは、湯けむりの向こうに人影を見た。
「ほう、ここにおったか」と、声がする。上背の低い子供のような人影から発せられる鋭い言葉の語気に何事かとアーミラは身を強張らせたが、存外に声が大人びている。湯けむりから抜けて現れたのは琥珀を焦がしたような肌をした少女だった。あどけない肢体を隠すことなく面前に晒し堂々と、睨め付けるようにして少女は言う。「姉共じゃな」
その瞳は値踏みをするようで、湯船に身を沈ませているアーミラからは、鼻越しに見下されているように見える。どう返すべきか躊躇っていると横のガントールが先に口を開いた。
「アーミラは初対面だったな。オロル、一体どこにいたんだ?」
「いろいろと、見て回っていたのじゃ。ここは蔵書も浩瀚を極めるからのう」オロルは応え、「此奴が例の次女か」と言う。どうやら二人はすでに知り合いのようだと、アーミラは心の内に微かな疎外感を覚える。
「あ、アーミラ・アウロラ……です」
「オロル。チクタク・オロルじゃ。当代は神殿預かりの者は長女のみと聞く。同じ身の上同士よろしく頼むぞ」いっそ不躾に言い終わるやいなやオロルは返答を待たず踵を返すと桶に湯をためて頭から被る。跳ねた金髪が湯に濡れて額に張り付くと、途端に随分と小さく見える。糠袋で体を擦り洗う背中を盗み見て、彼女の手の異変を言葉もなく認めていた。
「あの、そ、それ……」アーミラが指をさす。
「これか」オロルは予測していたのだろう。『それ』と呼ばれたものが何か理解しているようで、振り返ることもせず慣れた様子で答える。「刻印の失敗作じゃ」
オロルはここで「なぜ?」と続くことを予想していたが、アーミラは困惑したように狼狽えては、落胆したように湯に口元を沈ませてそれきり黙りこくった。オロルは眉を跳ね上げる。妙な奴だ。というのがこのときのアーミラに対する印象である。
「何も聞かんのか」
オロルは神妙な顔つきで黙りこくってしまったアーミラに問う。
「え、えぇ……はい」
そんな返答にオロルは心密かに憤る。そしてアーミラの継承者としての素養を疑った。魔呪術の研鑽において失敗こそ新たな発見の緒、ましてや他人の経験であればいらぬ手間を省いて知識を共有できるのだから、それこそ根掘り葉掘りと問質すのが作法であろうに。
「ふん……まぁよい」オロルはそう言って鼻を鳴らし、湯船に身を浸すと何かに気付いたように湯をすくい上げた。手のひらからこぼれ落ちる湯を眺める視線は険しい。
「どうした?」ガントールが言う。
「いいや、治癒の術式が溶けておる」
「歩き疲れただろう? ちょうどいいじゃないか」
「……別に疲れてなどおらん。先にあがるぞ」
烏の行水か、オロルは肩までろくに浸かることなく早々に湯浴み場をあとにする。まるで湯を嫌うかのようだった。その背を見送って、ガントールも身動ぎをした。
「すっかり長湯した。私もあがろうかな」ぐっと両手を天へ伸ばし背を反らせると息を吐いて、一応は距離を保ちたいのかオロルが身支度を済ませるまでの余裕を持ってから立ち上がる。「よし、じゃあまた」
アーミラは束の間一人になり、そしてその孤独に居心地のよさを思い出していた。知らずのうちに浅くなっていた呼吸を自覚して、湯船から半身をあげて岩に腰掛けると火照った体を涼ませてゆっくりと息を吸い込む。鉱物の何かしらがそうさせるのか、やや瓦斯臭い生暖かな空気で肺を満たす。思ったよりも胸の苦しさは晴れなかった。
❖
ガントールが湯浴み場から脱衣所に出ると、オロルはまだそこにいた。充分な時間を開けていたつもりだったが些か早かったかと心の内に呟いて、さして気にすることもなく乾布で全身の水気を拭い、濡れ髪を乾かし始めた。その姿をオロルは眺める。
「やはり義手か」
「ん? ……ああ、握手をした時に気付いていたかと」ガントールは思い出す。
ムーンケイでの初対面、そのときに交わした握手。オロルはそこで眉を顰めていた。掌に伝わる何かしらの違和感――篭手の内側が空洞であること――に気付いたのだろう。
「隠す素振りもなかったじゃろう」と短く返して、それよりと本題に入る。「あの女、傷を見たか?」
オロルが問う。その言葉を背中で受け止めて髪を乾かす手を止める。どうやらアーミラのことが気になって脱衣所で待っていたらしい。
「見たよ。性格は臆病そうだけど、あの傷はとても内地育ちじゃないね。死線を潜った戦士でさえもっと綺麗な体をしてる」これはガントールの皮肉か。
「どう見る?」
「今のところは、なんとも。仲良くやっていけるんじゃないか?」ガントールは曖昧に笑ってみせた。
「なんじゃい」オロルは呆れた声でガントールを見上げると、頤に手を添えて視線を横へ流した。「強いと思うか?」
「どうだろう……」ガントールは臆面もなく頭を抱えて考え込んだ。「印象だけだと、とても戦えるとは思えないけど、それなりに術はあるんじゃないか。何も剣を持って斬りかかるだけが戦争じゃない」
オロルは先行きの不安を見定めるように目を細めて眉を顰める。
「ふむ。わしを選んだ神様なのじゃから目は確かじゃろうしな」
ガントールは眉を下げて笑う。その満ち溢れた自信はなんなんだ……
「信じる他ない……か。
……神の御心のままに」
■003――天の暦数
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
湯浴み場を出て数刻、霽月の夜に各々が気儘に涼んでいたひととき、晩餐の招待を受けた継承者達は一堂に会していた。
場所は神殿領域内の西方に位置する大部屋で建築様式は他のものよりもぐっと古く、外壁は厚みのある石造りで列柱が等間隔に並び天井を支えていた。壁面は幾度もの時を経て鈍く色付き、その重厚な佇まいに歴史を刻んでいる。正面は一際径の大きい二つの柱が左右に並び、瀟洒な印象を持つ堅木の扉は後年に増設されたものだろうことを木目の艶から窺わせる。
大部屋の扉は開け放たれており、継承者三名の到着を今かいまかと待っていたのだが、横着したガントールが吹き抜けのある肋骨の列柱の間から内部へ踏み入ると、それに続いてオロルも横から忍び込み、悪いとは思いつつ一人だけ律儀に扉をくぐるほどアーミラも生真面目ではなかった。実は扉の傍で出迎えとして到着を待つ神人種の者がいたのだが、柱の隙間から不作法に入ってくる三人を認めて眉を下げながら苦笑して出迎えた。
「お早いお着きで助かります――」
男の言葉にガントールは少しだけいたずらっぽく笑ったのをアーミラは見た。扉から入る手間を横着したことを皮肉に表現した言葉だということを知り、同時にガントールの少女然とした態度を垣間見た気がした。
「――今宵は継承者一同が共にする初めての夜ということで、心計りの品々では御座いますが晩餐をご用意させて頂きました。出征を明後日に控える継承者の皆様には是非、お楽しみいただけたらと思います」
男の血統は獣人種だろう。ガントールに並ぶ長身の偉丈夫で顳顬の辺りから頭角が伸びているため一目でわかる。胸元の釦は、膨れ上がる筋肉に押し上げられ、かすかにきしんでいた。
歳は三十を数えたあたりか、それなりに若々しさもあるが髭を蓄えた顔には威厳を備えている。そんな威圧感のある風貌はきっとアーミラを震え上がらせるに違いないとガントールとオロル内心期待していた。が、二人が予想していたよりも怯えた様子はなかった。
というのも神殿の門を潜る際に一度顔を合わせていたからだ。出迎えの神人種の一人だと覚えている。
既に震えるだけ震え、怯えるだけ怯えた今、平気の平左でいるアーミラに対して、胸をなでおろしたのは獣人の男の方だった。
「僭越ながら改めて私の自己紹介をさせて頂きます。……とはいえアーミラ様は一度お会いしましたね。私は神族近衛隊副隊長ザルマカシム・スペルと申します」
ザルマカシムは二人に向かって深々と腰を折る。ガントールはすでに顔見知りであるため、他人事のように聞き流していた。隣のオロルは眼前に向けられた男の頭を眺めおろしながら眉尻を跳ね上げる。
「ほう……であればあのカムロとか言う女の下についておるのか」
「カムロを御存じでしたか、仰る通り、彼女は我が隊を率いる隊長、私の上司にあたる方で御座います」
「カムロと会ったのか?」と、こちらはガントール。
「少しな……昼に顔を合わせただけじゃ」オロルは眉を吊り上げて愉快そうに考え顔だ。「こんな大男を下すとは、あの女は大したものじゃな」
今度はアーミラが小さく手を挙げた。
「あ、あの、その、『スペル』というのは姓でしょうか?」
姓とは、特別な者にしか与えられない名前のことである。訳知り顔で質問をしたのは、アーミラ自身、刻印を体に宿して姓を手に入れたからだった。
例えばアーミラの姓『アウロラ』は、師匠である老婆マナ・アウロラから、正式な襲名ではないものの魔呪術の知識を修めた証として名乗ることとなった。オロルも同様に『チクタク』を名乗り、ガントールは辺境伯の階級的称号として『リナルディ』を名乗る。このような身分や功績を持つ者のみ姓を持つ。それこそ、ナルトリポカのアダンとシーナには姓は無い。であれば、この男の姓の由来は何か。
その問いについてザルマカシムは頷いた。努めて平静に振る舞おうとしたであろうが、内にある矜持が面持に現れたか、力強い返答となる。
「はい。私は前線での勲しを評価され神人種としての招請を受けました。現在は神族近衛隊に属しており、その際に勇名として『スペル』姓を授かりました。
由来はこの――」
言いながらザルマカシムは細剣の柄を右手でゆっくりと握りしめ、目の前の継承者に対して敵意はないことを改めて視線で伝える。これから行う行為が説明のために必要なことであると示すかのようにそっと抜剣すると鋒を天へ向けた。口元はささやくように術式を唱える。すると、ザルマカシムの言葉に呼応するように細剣から閃光が瞬き、剣身全体は魔力を纏って燐光が渦巻いた。
「――このような、詠唱を用いての戦闘に長けていることにあります」
鋭い稲光を帯びた剣を披露してみせると、被害が及ばないようにと空いた左手で丁寧に剣身を撫でて稲妻を取り去る。そして元通り細剣を鞘に納めた。
「なるほどのぅ……魔術剣士の獣人とは、類稀なる才覚に違いないわい」と、オロル。言葉の割に余裕のある態度は崩さない。褒めそやしてはいるものの、オロル自身も同程度の実力を保持しているだろうことが窺える。
「そうだな。本来獣人種は魔呪術を扱う才覚が魔人や賢人に劣る、それだけの魔力を剣に付与できるのは前線でもそうそうお目にかかれないぞ」ガントールもしきりに感心している。が、ザルマカシムは首を横に振って笑ってみせた。
「身に余るお言葉でございます。ですが、ことガントール様に於かれては私よりも遥かに熟達した魔術を扱う剣士であること、重々承知にございますよ」
「いやいや、それは謙遜が過ぎるさ。『スペル』という二つ名はその選択の幅にある。戦況に合わせて『詠唱』と『綴字』を選ぶことができるなら副隊長と言わずその上も目指せるくらいだろう」
「いやお恥ずかしい。そのように評価してくださるのは至極有り難いですが、カムロは易しくありませんよ」
ザルマカシムは人受けの良さそうな笑顔を見せた。ガントールも然りと笑みをこぼす。
なにやら盛り上がっている様子。アーミラは他人事のように少し離れたところから眺め、目の前の椅子に腰掛けるのは悪目立ちするかどうか思案していた。その椅子は、つややかに磨かれた木製の肘掛けを備えた深みのある風合いの上質な椅子である。脚部は緩やかに湾曲して有蹄動物を模しているようだ。革製の座面と背もたれは張りがあり厚みも充分。神殿ではこんな椅子一つとっても一級品らしく、革で作られた椅子自体アーミラは初めて目にする。心惹かれるのも無理はない。……はやく話が一段落しないかな。
そういえば、とアーミラは思い出す。先程の会話、ザルマカシムの勇名の由来であるスペル……これは魔呪術の基礎知識であるが、言葉と術……未熟な頃は二つの違いが分からなくてお師様によく叱られたものだった。教えを説くときのお師様も、ここまで上等とはいかずとも、椅子に腰掛けていたものだ。
――『魔術』と『呪術』の違い、そして『言葉』と『術』の違いについてをここで説明しておこう。そのためにはまず『魔呪術』と括られる体系について触れておく必要がある。どれもこの世界に根ざした重要な文化であり、この先無視することはできないだろう。
まずは魔呪術について、これは魔人種の扱う魔術と、賢人種の扱う呪術を包括して表す言葉である。どちらも原理は同じだが、魔術と呪術はそれぞれの人種が長い歴史の中で別々の方向に発展、体系化されている。主な特徴は以下の通り。
・魔術――物質に対して事象を適用させる能力。魔人種がより顕著に才覚を発揮する。人力を用いずに物質を移動させたり、等価の代償を支払うことで炎や水の生成などが可能である。
・呪術――生物に対して事象を適用させる能力。賢人種がより顕著に才覚を発揮する。思考を制御するような催眠や肉体の強化、生命力の吸収、治癒などが可能である。
魔人、賢人であれば誰もが魔呪術を扱えると言うわけではなく、あくまでも素質があるというだけに留まる。開花させるには後天的な識字教育から始まり、書物を蒐集する環境や実践の指導者が必要だろう。なので大半は才覚を眠らせたまま農民や労働階級としての人生を送ることとなる。また逆に、獣人種であっても素質を持ち、その上で充分な修学と経験を積むことができるなら、多少なりとも魔呪術を行使することが可能である。ザルマカシムのように高みへ至ることも。
そして、魔呪術の行使手段こそが言葉と術であり、複雑な式であれば両方を複雑に混ぜ合わせる事もある。
・言葉――魔呪術に用いる呪文の一節あるいは単語のこと。常用語とは異なる言語であり、発話であれば『詠唱』、筆記であれば『綴字』と区別される。言葉には、それぞれ実行者の記憶や意味が結びついているため、声で発しても文字で記しても、基本的には同じ効果を発揮するのだが、篆刻や筆記での行使は多くの場合、術との重ねがけで複雑な構造を維持することが可能で、詠唱は迅速な対応を求める場面に有効だといえる。
・術――詠唱方法そのものを指す。言葉のみでは行使できないような複雑な魔呪術の制御には道具や技、あるいは魔導回路図や体捌きの一連の動きによって魔呪術を使用することが多く、平たく言ってしまえば『言葉』以外の手段はすべて術といえる。
簡潔にまとめるならば、物質には魔術を掛けることができ、生物には呪術をかけることができる。そして行使方法は言葉と術の二通り。といった具合である。ザルマカシムの場合は剣という物質に詠唱を行うことで魔力を付与しているため、魔術と判断でき、行使方法が言葉であるから勇名の由来もわかる。
ぱん――と、不意に大部屋に乾いた音が弾けた。アーミラは思考を止めて音のなる方を見ると、丁度三人と視線がかち合った。咎めるような雰囲気はなく、談笑が一段落ついて手を鳴らしたのだろう。音の正体はザルマカシムのようで、合わされた手指を軽く擦り合わせて仕切り直す。
「お待たせして申し訳ありません。では、卓の手前から長女継承ガントール様、次女継承アーミラ様、三女継承オロル様の順にお座りください」
その言葉にアーミラはようやっと腰を落ち着かせることができると気を抜いて四脚の椅子に腰を落とすと、その柔らかさに転げそうになる。丸く膨らんでいた革の座面と背もたれが予想よりも深く沈み込むため体制を崩しかけたのだ。これまでは手頃な岩や丸太、上等なものだとせいぜい木のしなりで背中を支えるような細工の椅子しか知らないアーミラにとっては沈み込む座面は予想していなかった。まるで尻の下で座面が逃げていくようだった。慌てて肘掛けを掴んで前の方へ重心を戻し、浮き上がった椅子の前脚が床を打つ前につま先で静かに着地する。転びこそしなかったが視線を集めてしまったことに顔が赤くなる。ここに来てから何度目かの失態だった。
ちらりと二人の方を見る。ガントールとオロルの笑みはそれぞれ対象的な意味合いを含んでいることがひと目でわかった。
「いい椅子だよな」ガントールは言う。
アーミラは頷くことしかできない。ガントールの大らかな態度には助けられるが、ときに優劣を際立たせられる気がしてならない。確かにこうして体を落ち着かせると柔らかすぎるということはなく押し返して支えるような革の張りがある。
オロルはというと、脚癖の悪いことに短靴を脱ぎさって座面の上で胡座をかき、卓に片肘を付いて頬を支えていた。とうにアーミラには興味を失って笑みもなく「椅子がなんじゃ、それより飯じゃ」と、顔にありありと描いてある。
ザルマカシムは先程の歓迎をより大時代な表現で繰り返す儀式的な挨拶をそこそこに済ませると一礼し大部屋から下がる。晩餐の目的は三者三様の継承者が親睦を深めることであり、後のことはガントールに委ねられるようだ。ザルマカシムは晩餐のあと再び戻って来るとも言っていた。明日のことについて説明があるという。
退出したザルマカシムと入れ替わるように神人種数人が盆に料理を運んで現れた。列を作り足音もなく楚々として卓に並べられる品々はどれも豪華で色彩に富む。
神人種は運ぶ間も、部屋を出る時も言葉を発さない。微睡むように目を薄く閉じ合わせ、口元は引き結んで固く維持している。恐らくはそれが継承者に対しての礼儀かなにかなのだろうと推理してアーミラは奇妙な光景にしばらくそわそわとしていたが、ガントールやオロルもこのときばかりは口数が少なく緊張しているのが見える。三人を残して人が捌けるのを待った。
「ふう、……それじゃあ祈りから」ガントールは緊張を解いて息をつくと右手側に置かれた杯を手にとって目配せをした。ここからは彼女が仕切りの役となる。
「うむ」と、オロルも続いて杯を持つ。アーミラも二人に続いた。
祈りの言葉はガントールが唱えた。
「天地に遍く恵よ糧よ、其は我身を巡る血肉となりて、豊かな生の礎とならん」
食前に祈る行為はアーミラも馴染みがあるが、ナルトリポカでの祈りはもっと簡易的なものだった。目を閉じて手を合わせる程度、あるいはそれさえないことも珍しくはない。神殿であれば信仰も篤いのだろう。特にこの場は神聖だ。ある種の祈りの原点を垣間見た気がした。
ガントールが真面目に唱えると、三人は杯を向け合い掲げる。
「「「乾杯」」」
杯に満たされた葡萄酒は甘藷黍の糖蜜が溶かされて甘く、山葡萄の滋味深い渋みは柔らいでいた。とりわけ気に入ったのはオロルのようで、小さい舌で唇を舐めると満足そうに鼻を鳴らした。
「ふむ、なかなか。先の湯浴みも凝った造りじゃったが、神殿は酒一つとっても贅沢な味がするのぅ」
杯を揺らして液面を眺める。金色の瞳が薄く微睡み伏し目がちになる。そんなオロルの振る舞いは様になっているとアーミラは思った。糖蜜で甘みがあるとはいえ、後味は重く、じわりと酔いを誘う強い酒だ。胃にくだる冷たい液体は後に熱を残して鼻腔に抜ける。酒を嗜むことのないアーミラは、慣れない贅沢を用心深く口にした。
卓上にところ狭しと並ぶ大皿の数々には、それぞれに彩り豊かな料理が盛られていた。標高の高い土地でありながらこれだけの食材が調えられているのは神殿の威光がなせる力か、酒も食事も奢った一級品が並び、各地方東西山海の別もなく集結している。
ガントールは平皿に少しずつ料理を盛り合わせていた。椀にはすでに山盛りの飯が盛られ、先程までの瀟洒な態度はなりを潜めて獣人種らしい大食漢の姿をみせている。選ぶ料理も海産より陸産、魚より肉と豪快だ。卓の中央に陣取る首を落とした鹿の丸焼きを匕首と突匙で切り分けると「皆もどうだ?」と嬉々として肉と骨を捌いていく。澄んだ肉汁が滴る大皿の鹿の腹には臭み消しの香草が詰められ、切り落とされた脚は別鍋に煮込まれて卓の横に鎮座し、蓋の隙間からしゅうしゅうと音を立てていた。
アーミラも目も綾な大皿の中から一品に目をつけた。粉挽きにした麦を鶏肉にまぶして油にくぐらせ唐揚げにしたものに、細切りの甘唐辛子や筍と合わせて餡をかけた一品だ。薬味に葱と大蒜が刻まれていかにも精がつきそうだ。まだ湯気が昇り、食欲をそそる照りがある。皿に添えられた匙は取り分けるためのものだろう。アーミラは中腰になって手を伸ばすと一人分を盛り付けた。芳しい香りが鼻孔をくすぐる。どこか懐かしいシーナの笑顔を思い出す、馴染みのある匂いがした。
オロルのほうは飯よりも酒のあてを目当てに椅子から降りて、他の者の目がないのをいいことに裸足のままぐるりと卓上の品をひやかしている。左手は杯を離さず、右手に箸を持っていた。どうやら取皿もなしに直接摘んでしまうつもりらしい。
足を止めたのは、竹の簀子に山になっている揚巻物か。米粉の皮に貝柱と剥き身の海老、そこに生姜、白髪葱などの薬味に醸した調味料を包み香ばしく揚げた品である。海産物となるとアーゲイから卸されるものだろうか、内地でしか調達できない具材を取り入れているが、海の幸というものにはガントールもアーミラも箸が伸びなかった。醸された調味料もまた塩味の強い香りを放ち万人受けではなく、オロルのような賢人種が好む食文化である。
オロルは箸と杯を左手に器用に持つと、右手は萵苣の葉を摘む。そしてその上に揚巻物をかさりと乗せて一口頬張る。丸い頬が膨らんで窄ませた口から熱気のある湯気を小刻みに吐いて酒を呷った。皮の内側はまだ煮えたように熱いらしいが、飲み込んでしまえば口内は濃い味の汁と閉じ込められていた海鮮の旨味が広がる。二口、三口とあっという間に腹に収めては口内の油を酒で流し、杯も乾かしてしまった。そんな様子を眺めてみていたガントールとアーミラは自然と微笑む。
かくして、皆が晩餐を楽しみ、当たり障りのない身の上を打ち開ければ親睦は深まるというもの。皿の料理もおおかた平らげて腹くちくなった頃、三人の距離は随分と近付いていた。
「しかし……三人だけで好きにしていいとは、随分と放任じゃな」
オロルは酔いも回って多弁になっていた。素面のときでさえ思ったことは抜け抜けと言う質であるが、酒が入ると止めが効かない。葡萄酒の満たされた水差しを空の杯に注ぎ、椅子の上で再び胡座をかいた。
「とはいえ外に気配があるが、護衛でもしとるのか……」
そう呟いて、卓の前にガントールが切り分けた鹿肉の塊が香草を添えて綺麗に盛り付けられているのをつまむ。少し乾いてしまっているが目の前にあるとつい食指が動いてしまうらしい。誰にとっても絶佳の晩餐であるから、胃袋は無理を推して食欲を満たす。そんなオロルに続き、ガントールは言葉を継いだ。
「護衛してもらえるだけありがたい。継承者なら常に狙われているだろうからな」
「案外、外の気配は敵なのやもしれんぞ」
オロルの言葉をアーミラは真に受けて青褪め、ガントールが呵々と笑って否定した。
「ここは神殿だ、万が一にもあり得ないよ。気配も私からしたら馴染みのあるものだ。不穏なものは居ない。
晩餐会も素直に楽しめたよ。二人が現れなかったらこれも一人で食べることになってたのかと思うと笑っちゃうけど」
ガントールの言葉にオロルは笑みで返す。
「一人きりの出征は、寂しいじゃろうな」
「そうだね。出会ったばかりだけど、三人これからは長い付き合いになるだろうし、改めてよろしく頼むよ」
「ふむ、長い付き合いか……前線でおっ死んでしまわなければの話しじゃが」オロルはアーミラの方を向いて意地悪く笑う。「最後の晩餐とも言えよう」
アーミラは怖がらせようとするオロルの手には乗らないと身を強張らせて困った顔をした。冗談とはわかっているが、縁起でもない。
「ははは、脅かすなあ」ガントールは涼し気にオロルの言葉を受け流す。「大丈夫さ。二人は嬰児の頃から刻印を持っていたわけではないけれど、恐らくは皆各々が困難を乗り越えて今日に辿り着いたと信じてる」
酒に潤んではいたが、ガントールの瞳は力強くオロルを見つめていた。言葉に偽りはなく、本心からの返答なのだろう。あるいは願いか……いずれにせよ、三人は遠からず前線へ向けて旅立つこととなる。そこで実力が如何ばかりか詳らかにされることとなるのだが、当代はやはり巡り合わせが異なるのだと知るのはまた先の話である。
「確かに、各々困難を乗り越えて来たのじゃろうて。お主は生まれながらの辺境伯の娘で、唯一の正式な当代継承者。既に前線を駆け回ったとも聞く。
わしは島嶼賢人部族の娘として幼少より呪術の研鑽に身を置いてきた島一番、否、賢人種で一番の呪術師じゃ。
……して、アーミラ。お主はどこの産まれか?」
またもや矛先を向けられたアーミラは驚くこともできず、刹那の間呆然としていた。
「わ、私? ……ですか?」
吃音の上に要領の悪い確認が重なり、オロルの酒量が増す。
「おぬしに問うているのは明らかじゃろう。質問に質問で返すな」と心の声がそのまま口から出る。「飯の間も黙ってばかりじゃろうが。身の上くらい語ってみぃ」
「あ、はい……! えっと、私は……昔の記憶が無くて、覚えているのは、し、お師様と共に歩いていた程度です。流浪の民として」
「なに?」オロルは穏やかではない声で続ける。「それは幾つの時じゃ」
「十の頃からは……覚えています。それから……し、師匠が亡くなったのが三年前、くらいです。物心つく前から流浪をしていたと、思います」
オロルは頤に手を当てて、ふぅむ……と、難しい顔をした。
「記憶が無いとな。……身体の傷も踏まえると前線近くの出身かもしれんな。なるほど……親の顔も覚えとらんのか?」
アーミラは曖昧に首を傾げた。発話しないためかえって返答が早い。オロルは彼女の吃りも前線による影響かどうか考えたが、記憶がないのならば精神的な外傷とは思えない。これはただの人見知りか――兎も角。
「お主の親はきっと前線に居たのじゃろう。
一昔前に戦闘が激しかったのは四代目三女国家アルクトィス……そこで戦火に巻き込まれて命を落とし、流浪の民に拾われ師と出会った……そしてその後どこかで記憶をなくしたとみるのが自然か」
オロルの言葉にアーミラは無感動であった。実際、アーミラは親の温もりを知らない。師や工匠の夫婦との絆が数少ない温かい記憶だった。産みの親を特別に思うような感慨は皆無だった。
この世界では親がいないことは珍しいことではない。二百年の前線の膠着状態において仮初の平穏を享受しているものの、戦争自体は依然として続いているのだ。さすがに顔を知らないという程ではないものの、ガントールもオロルも親を亡くしている。
それでも二人が、アーミラに対して寛容であろうと考えたのは、孤独の日々の中で積み重ねたであろう努力を推し量ったからである。流浪の民という一所に根を張らず困窮した環境の中で魔呪術を習得したのであれば大したもの。恵まれない環境で才覚を発揮したのなら眠らせている能力も期待できるだろう。なにより、これから命をかける一蓮托生の仲に要らぬ不和を求めはしない。
「私……無くした記憶を取り戻したいんです……そのためにここに来ました」
「……なるほど。確かにガントールの言うとおり。皆各々が生温い日々を送ってはいないようじゃ」
オロルは言い捨てるように話題を切り上げて肉を一口放りこむ。そしてもう何杯目かわからない酒のお代わりを杯に注ぐと、ガントールにも酒を注ぎ、残りをアーミラの杯に注ぎ水差しは空になった。雫を垂らす水差しの最後の一滴まで見届けると、「まぁ飲め」と改めて杯を掲げる。それに続くようにガントールとアーミラも乾杯し口を湿す。オロルはアーミラが葡萄酒を飲む様を満足そうに見つめていた。
その瞳は次の瞬間には扉の方を睨む。酩酊に蕩けた瞳ではあるが感覚は冴えているらしい。微かな足音が届くと、扉が開かれザルマカシムが入ってきた。
❖
オロルは崩した脚を組みなおし、卓に肘を付いて掌で気怠い頬を眠たげに支えている。これまで気丈に振る舞ってはいたが旅の疲れに酒気と睡魔が手伝って随分と年相応な少女らしい姿を見せる。いや、ただの深酒か。あくびを噛み殺した金色の瞳は睨むように視線を厳しくしたため対面に座るアーミラは萎縮してしまうが、オロルに悪気はなくただ眠たいのだった。明日からは出征まで連日式典と儀式に忙殺されるだろうから、身体を休ませたいというのは皆が思うところである。しかし今宵はまだ一仕事残っている。
「それでザルマカシムよ。晩餐の後は明日の流れを説明するのであったか?」
ザルマカシムは首肯すると改めて進行を始めた。
「はい。皆さま一堂にお集まり頂いていますから、お開きの前に明日からの流れをお耳に入れておきたいと思いまして。アーミラ様とオロル様のお二方は神殿での日が浅く、式典での作法に不得手かと思われますので、僭越ながら少々のお時間を頂きたく思います」
「なにか挨拶でも用意せねばならんのか?」
「そのつもりでございますが……ご希望ならば代表者のみに致しましょう。この場では不肖、私めも明日の方針について一任されております故、ご随意に御判断頂ければその旨を上にお伝え致します」
「ではそのほうが良いな」
オロルは小癪に笑みを浮かべてアーミラに視線を送る。三人それぞれが挨拶の言葉を用意するのは面倒な上、次女継承者は場馴れも胆力も無いと見た。楽ができるなら己にとっても都合がいいとオロルは考え、挨拶は代表者のみとするように希望した。そして話し合いが踊ることもなく代表者は長女継承がふさわしいという結論に落ち着くのだった。
交わし合う言葉に意地悪な様子はなく、挨拶の言葉を用意する手間を省く事ができたアーミラも胸をなでおろしている。ガントールも傍で頷いて見守っていた。互いの得手不得手を補い合える継承者の仲間ができたことは、ガントールにとってこの上なくありがたい僥倖だった。
「明日は午下より『心像灯火の儀』、『神器継承の儀』、夜に『星辰の儀』、明後日の朝に『出征式典』と行事が執り行われます。皆様におかれましては明朝から昼にかけて身元をより正確に検めるために本殿の方へお集まり頂きますのでよろしくお願いいたします」
「わしらは朝からずっと出ずっぱりか」
「そうなりますね」
ザルマカシムは一度言葉を切り、折りたたんで脇に挟んでいた紙を取り出すと魔術を行使して空中に展開する。見えない壁に貼り付けられたその紙には絵図が描かれていた。アーミラは心当たりがあるのか、ふむ……と頷く。少し遅れてオロルとガントールはその紙が何か理解する。
端が破れていて随分古いが、用途に支障はない。
「地図か」とオロル。
オロルはちらりとアーミラを瞥見した。此奴は流浪の民……さらに次女継承の力は地図とも関係が深いのだから、これは因果か……。
「歴代の神人種が測量し、作成した国土大略図で御座います。原本は古い書翰で書庫に保管されております。こちらはその写しです。
陸地の境界線外は海が広がっていると見てください」
ザルマカシムは簡単に答える。
「下側の白飛れとる領域は禍人の領地か」
指をさすのは地図の下部、方角にして南側の大陸である。前線の引かれた場所を目測で推量するならばこの南北を隔てて空白の広がるところからは敵の領域だろうとオロルは見当を立てた。果ては海と陸地の境を描く線さえも記されておらず、おそらくは測量不可。なんの情報も手に入らないのだろう。
「仰る通りです」ザルマカシムは少し間をおいて続ける「御二人は神族として座学を受けてはおりませんので、個人の持つ知識に差が生じていると思います。順を追って説明を致しましょうか?」
「私はどうしようか」ガントールはあくび混じりに言う。「既に知っていることだし、やたらに眠くなってきた」
「はっ、然りじゃな」オロルは歯を覗かせて笑みをつくる「説明は必要なかろう。知らんことがあればその場で質問を飛ばす」
ザルマカシムは人受けのよい笑みを見せて了承すると部屋の隅にある書見台から碁笥のような入れ物を手にとった。蓋を開けて駒を大掴みにさらうと指で一つずつ摘んで地図に配置する。空白地帯に接する付近には二本の点線がほぼ垂直に引かれており、線を境に白と黒の駒を向き合うように配置した。
「では説明は省略します。早速ですが、こちらが現在の前線の戦況です。
地図上の点線部、向かって右側から長女国家ラーンマク、次女国家デレシス、三女国家アルクトィスとなります。四代目国家の姉妹国が連なる国境がそのまま前線とみていただいて構いません。そして南側全域が敵の領地です。一進一退となるほどの乱戦はしばらく行われてはいませんが、刻印現出を機にこれから敵側が先手を狙いに来るでしょう」
ザルマカシムの言葉に三人は頷く。
「その地図上の穴はなんじゃ?」
オロルが指をさす。それは次女国家デレシス領内に位置する円形の線であり、虫食い穴があるわけではない。答えたのはガントールだった。
「ああ、それは『涙の湖』だな」
「ほう」オロルは目を細める。「これがそうか」
アーミラは言問い顔で二人を見た。視線を受けてガントールが言葉を続ける。
「そこに大きな湖があるのさ。先代が前線を押し上げたときに龍と戦った場所だと言われている……その時穿たれた大地に雨水が溜まり湖になったと」
アーミラは「はあ」と間の抜けた返事を返した。この縮尺の地図でも拳ほどの大きさ、実寸なら集落の一つや二つまるごと飲み込んでしまう湖……先代たちが戦闘で作り出したものだというのは信じられなかった。
「見たことはあるのか?」とオロルはガントールに訊ねる。
「一度だけ。その一帯に踏み入るととても静かで、妙な草木が茂る雑木林だ。ほんとに、前線とは思えないほど空気が違うよ。戦場とは別の怖さがある。不気味というか、身体が竦む」
「妙な草木とはなんじゃ? 植生がそこだけ違うのか?」
ガントールは眉を困らせ腕を組んで頭を傾げた。
「うーん……とにかく妙としか。同種の草木でもその一帯に自生する植物は形状が歪なんだ。湖付近では枝ぶりも葉の形も捻じくれてしまう。元々は禍人の領地だったんだから、何らかの影響で土地が腐っているのかもしれないが、長居をするだけで致死の呪いが掛けられるとも聞く……そういう事情もあって手付かずなんだ」
なんとも不気味な物言いに皆が閉口する。笑い飛ばすこともできただろうが、ガントールの口から素直に『怖い』と評されると何となく真に受けてしまう。
ガントールは自身の体験としても野生の勘のようなものがその一帯での長居を嫌うと語るが、全容は判然としない。
「不可侵とでも言うべきか、物見遊山ではないが、一目見るのも一興……」
オロルは呟くようにして誰にでもなく頷いている。一方でアーミラは会話のすこし前から進めないでいた。
「りゅう……とは何ですか?」
「龍。……『災禍の龍』『厄災の禍龍』といくつか呼び方はあるが、とりあえずはとんでもない化け物だとだけ理解してくれればいいんじゃないかな」と、ガントール。
「その化け物は継承者と渡り合うだけの力がある。故に咎や禍人とは別に扱われておる」オロルは言う。「わしらも合間見えるやもしれんのう。先代は相討ちじゃったが、わしらは果たしてどうじゃろうな」
アーミラは青褪めて顔を引つらせた。あの地図に描かれた湖、そこに今も息を潜めて棲まう龍の姿を想像して、早くも気持ちが萎えている。私なんか、きっと指で摘まれて牙の並ぶ口の中、一口に飲み込まれてしまうんじゃないだろうか。と、アーミラは想像して身を震わせた。
オロルが一つ咳払いをして本筋に戻す。
「――それで、戦況の説明だったか。わしらが現れるところを、つまり空に浮かび上がった刻印を敵は確実に見ており、先手を取りに動き出す。……そこまで予想しているのなら、どう動くかも見当がついておるのか?」
「ええ。睨むべきは間者の存在です。
前線は百年以上膠着状態にあり、輜重の輸送だけでもじりじりと赤字を計上していました。そのため財政負担を軽減する策として、兵ではなく間諜を重用するようになったのです。つまり前線の指揮を辺境伯に任せることで神殿は戦力の漸減を食い止めつつ、敵の動きを把握するために少数の間諜を敵地に送り込んでいます」ザルマカシムは答える。
「つまり敵も同様に間者を放っておるということか」オロルは眉を顰める。「前線では結界が展開されているじゃろう? 少なくとも敵の間諜がこちらに入り込む余地はないはずじゃが……」
「……私もそう信じたいのですが、誰にも悟られず無理を押して潜り込むからこそ間諜なのです」
オロルはザルマカシムの言葉に膝を叩いて嘲笑う。これは確かにザルマカシムの言う通り。疲れと酔いと睡魔に思考が鈍ったか、愚かな質問をしてしまった。
地図に駒を並べているとつい勘違いしてしまうが、戦争は盤上の遊びではない。命さえ捨てる覚悟で挑む者達がせめぎ合い殺し合うのだ。結界があれば間諜は入り込めないなんて甘い考えは寝言に等しい。このわしも所詮は内地の育ち……気を引き締めねば足元を掬われるな……。
「あ……辺境伯って、そういえば」
アーミラは呟き視線を移した。ガントールは勇む戦士の眼差しを返して視線に肯く。
ザルマカシムは構わず説明を続ける。
「内地への侵入を拒む結界や防壁はありますが、それでも単体での侵入は防ぎきれてはいません。息を潜めてこちらを窺っているという可能性は大いにあり得ます。
実際オロル様もアーミラ様も夜半に咎の襲撃があったとウツロから報告がありました。敵は確かに動き出しております」
「ウツロとはなんぞや」とオロル。ガントールが答える。
「アーミラを迎えに行った遣いだよ」
「ほう……倒したか」
オロルは口の端を吊り上げてアーミラを見る。しかし咎を払ったのはウツロであって、当の本人は凶刃が迫っていた実感さえないので何も言えない。ザルマカシムは話を進めた。
「その上で、最初に戦端を開くのはラーンマクでしょう」そういって地図上の駒を動かした。「アルクトィスの貧民窟は過去の戦闘から辺境伯領が陥落し、指揮権が再び神殿に移っています。既に兵站の補給線が確保されており、敵からしてみれば攻めにくくなった上に旨みがない。経済的にも貧しい国ですから」
四代目三女国家アルクトィスは前線の中で運営が傾き、弱体化した国である。建国当時は魔鉱石の採掘が盛んであったが、現在は廃坑となっており、国は財政難に見舞われて貧民窟と化したのだ。一度は陥落の危機にまで瀕したが神殿からの派兵で守りは盤石となっている……いまさら敵がここを攻めても無駄な消耗戦を繰り広げること必至で、そのうえ得るものがないのは確かな事実であった。
ザルマカシムは続ける。
「デレシスも同じです。涙の湖が侵攻を阻む地形であり、左右のラーンマクとアルクトィスから挟まれます。誘い込んでも敵はここを通らないでしょう。
比べてラーンマクは辺境伯が強い指揮権を発揮していますが、それ故に神殿からの補給線が未開拓です。それにリナルディを落とせば後ろに広がるスペルアベル平原まで一息に侵攻できる……旨みがあるわけです。先手を取るならここを攻めるでしょう」
「正攻法ではあるが……」オロルは添えた親指の腹で頤を撫で擦る。「しかし、攻められることを予想しておきながらラーンマクの後ろ――スペルアベル平原まで手薄にするとは、いささか露骨すぎるな」
オロルはザルマカシムの答えを待たず渋面で言う。
「ここにわしらが向かうんじゃな?」
事情を掬し正鵠を射る彼女の言葉にザルマカシムは反論も訂正もなかった。招いたばかりの娘を今度は前線に送ること……その理不尽を強いる立場にあるザルマカシムには、返す言葉もないのだった。
「ふん……神殿側の戦略は、戦況が激しくなると予測されるリナルディの前線に継承者を投入し、集中している敵戦力を一気に叩くということか」
オロルは語調を強めて嫌味ったらしく言う。
「こんなものは予測ではない。前線に態と穴を開けて、敵に自分の領土を攻めさせてから総力戦で押し落とす……なんじゃい、盤上の駒のように人を消費するではないか」
机上の遊びではないのだと己を叱責したばかりだというのに、神殿側の戦略もまた命数を雑に支払おうとしていることを知り、オロルはくだまいた。
「いえ……お怒りは御尤もに御座いますが、この作戦はひとえに皆様の女神としての能力を鑑みてのことに御座います――」
「女神継承者となったわしらの命も相当に軽いもんじゃな。のうガントールよ」
同意を求められたガントールはザルマカシムの方にもちらりと視線を移して困り笑いをした。ガントールは短いながらもオロルと共に行動したから解っている。恐らくオロルは本気で怒ってはいない。その上で困惑させて遊んでいるのだろう。実際、オロルの表情にはまだ余裕がある。怒りの演技に跳ね上げた眉にも愉悦の笑みがあった。
「いや、そうはならないよ」ガントールは言う。「私達は明日の儀式を経て不死者になる。そして前線に穴が開く前に辿り着いてみせる。誰も殺させない」
遠巻きに会話を聴いていたアーミラは不可解な言葉に引っかかりガントールの方を見た。不死者になる……?
「頼りにしておるぞ。ガントールよ。
しかし……間諜とは……禍人は厄介じゃな」
「人に化けているだけですよ。奴らは皆皮を剥がせば化け物でしかありません」
と、ザルマカシムの言葉にガントールが続いた。
「ザルマカシムの言うとおり、奴らは化け物に過ぎない。実際、前線では禍人との戦闘も珍しくはないが、人の姿を模しているのは私達への精神的な嫌がらせだろうね。同じ姿形の存在を殺すというのはやはり心苦しく感じるものだから。
でも、防護結界に侵入した禍人は、擬態が維持できなくなる……それを咎と読んでいるに過ぎないんだ」
「それなら、禍人とトガは同じ存在ということですか?」アーミラは問う。
「その認識で間違いない。前線で人に擬態した姿が『禍人』で、内地に踏み入り擬態を解いた姿が『トガ』。
アーミラは見たんだろう? 人に化けることをやめた奴らの本性は悍ましいものだろう」
アーミラは曖昧に吐息を漏らして視線を逸らすとばつが悪い顔をした。オロルもガントールも勘違いをしている。咎を討ったのはウツロ一人で、わたしは身の危険を察知することなく暢気に眠りこけていたのだ。
そんなアーミラの心中に気付いたか、オロルは冷やかに見つめながら、何度目かのあくびを噛み殺した。
「とにかく、出征の後にわしらはラーンマクへ向かって南下するのじゃな。辿り着き次第、敵を残らず倒す。
そして道中で経由することになるムーンケイ、スペルアベルではそれぞれトガの襲来に十分警戒すると」
「ええ、仰る通りでございます」
「何か他に伝えておくべきことがなければ、明日に備えて休みたい」オロルはそう言うと再びこみ上げるあくびを奥歯で噛み殺して目に涙が滲んだ。眠気の限界が来たようだ。隣に座るアーミラにも移ったか、手で口元を隠して集中力が切れているのがわかる。
ザルマカシムは三人の娘の気儘な態度を前に肩の力を抜いた。目の前に対している三人の地位は女神継承者。数日前までただの生娘だったとしても、今や天帝に準ずる存在である。故に眉を困らせつつも諾々と従った。
「それでは、今宵の晩餐はお開きとさせて頂きます。皆様は寝所の方で明日に備えていただきますようよろしくお願い申し上げます」
ザルマカシムは一礼すると、継承者三名が大部屋を去る背中を見届け、簡単な片付けをすると自身もまた部屋をあとにした。
❖
石造りの列柱に支えられた大部屋の上、鈍角の不陸屋根の縁にしゃがみこんで、ぞろぞろと寝所へ向かう三人の後姿を見つめるものがいた。そのものは全身を黒錆の鎧で覆い、そして肉体を持たない虚である。朝に次女継承者を伴って神殿へ帰還してから、一度報告のために近衛隊集堂に寄った後、ウツロは次の命令が出るまでの暇を貰った。
先代との離別から数えて二百年ぶりの自由である。
目的も予定もないウツロは継承者が晩餐を楽しんでいた時にも、まるで屋根の雨樋に据えられた彫刻のようにずっと前からそこに居た。警護のためではない。縁に腰を落ち着かせて、夜風にあたっているのだった。
継承者達から少し間を置いて、ザルマカシムが足元から出てきた。彼はウツロの気配に気付くことなく近衛隊集堂の方へと向かっていく。手元に携えた灯石が魔力を焚べられてぼんやりと男の周りを照らしている。ザルマカシムは白い玉砂利を踏まないように敷石の小路に従って足音を潜めて歩いていた。ウツロはその足取りを目で追いかける。夕刻にザルマカシムがここに訪れたときは平然と敷石を斜めに突っ切り玉砂利の上を歩いていたのを見ていたが、帰りの足取りが密やかであることを無感動に見下ろしていた。皆が寝静まった夜半である。足音を潜めているのは彼なりの気遣いだろう。
灯りが遠く消えるまで眺めていると、ザルマカシムが近衛隊集堂の扉を開け、その身を滑り込ませた。扉が閉まると明かりは隠れ闇に溶ける。微かに扉の閉じる音が闇夜に抜けて、あとは静寂が落ちた。宵の口に山を濡らした雨雲は夏の風に流れ、月明かりが滲んでいる。ぼんやりと仄明るいがウツロの背に影は落ちない。
ウツロは鎧であり、先代によって霊素を定着させられた戦闘魔導具である。肉体はなく、血の通わない機巧だ。視覚と聴覚を備えていることは皆が知るところだが、面鎧に口がないため、会話する術を持たない。そもそも口があったとして、この魔導具が何を語るのかは誰も知らぬところである。しかし、少なからず思考する存在であると認める者はこの魔導具に語りかけ筆記での対話を望む。アーミラがその例である。
『先代はどのような方でしたか?』
ウツロは屋根の砂埃に指先で言葉を書くと動きを止めた。朝にアーミラから投げかけられた言葉。それを見つめ下ろす面鎧に夜闇が吹き溜まり翳りをつくる。ウツロは肉体がない故に疲労という概念がなく、睡眠を必要としない。もちろん体を休める必要がないとなれば、この魔導具に部屋は与えられていない。
屋根の上で独り黄昏れているのは、己の居場所がないからだ。彷徨くこともできず、ただ朝日を待つのだろう。手持ち無沙汰の一夜、物言わぬ鎧は沈思に耽るようにアーミラの投げかけた言葉を見つめていた。
❖
月明かりの届かない洞の奥、狭苦しい土壁の暗中を進むと湿った壁面は次第に渇き冷えた石積に変わる。規則正しい横長の石材と隙間を埋める泥の溝を右手の指先で辿り、左手に持つ燭台のか細い蝋燭の灯りは左右の壁面を辛うじて照らすのみ、一寸先は闇である。
そうして歩いていると、指先が空を切り、不意に左右の壁が消失した。燭台を持つ男は無言の内に驚くが、すぐに理解する。広い空間にたどり着いたのだ。扉で隔てられていないため気付かなかったが、男はいつの間にか部屋の仕切りを跨いでいた。
「勤勉ですねぇ」
なよなよとした声音が室内に響き、男は声のした方向へ体を向ける。そこには脚の長い机と、その上に載せられた燭台、その蝋燭の灯りを受け光を遮る長髪の後ろ姿が影を作っていた。
「……それが取り柄だ」男が答える。
「そうですか、そうですね。……では勤勉なるブーツクトゥス、報告を」
長髪の男は視線を返すことなく、机の上に並ぶ奇妙な薬品を指先で手繰り、匙で粉末を掬うと小皿に落として薬液と磨りながら混ぜ合わせる。その態度は、報告を求めたわりに興味はまるでないようである。
名を呼ばれた男――ブーツクトゥスはやや不機嫌に片眉を吊り上げるが、命じられるまま報告を始める。その際に意趣返しのように名を呼び返した。
「それでは報告だ。先日の継承者刻印の現出は真であった。第二継承はナルトリポカ、第三継承はムーンケイ島嶼部より確認。暗殺に向かった二人は内地に侵入、以降連絡は取れなくなった……やられたと思うか? ハラヴァン」
「そうでしょうね」長髪の男、ハラヴァンは短く相槌を打つ。「片方は私が看取りましたよ」
手は薬剤を注いだ小瓶を摘んで軽く揺すり、混ぜ合わせながらちらりとブーツクトゥスを見やる。赤みがちな目尻の切れ長な瞳が蛇のように睨めつける。ハラヴァンは言葉を続ける。
「先に力をつけてしまった第一継承だけでも随分と前線を荒らしてくれます。可及的速やかに第二第三の命を摘まなければならないというのに……厄介です、厄介ですね。厄介極まりない。……今からでも刺客を送ることはできませんかね」
「それは……厳しいな」ブーツクトゥスは語調を弱らせる。「暗殺に失敗した二人は、第一継承にやられたわけではない。先代の虚が封印を解かれているんだ」
その言葉にハラヴァンは初めてブーツクトゥスに顔を向けた。
「虚……とは何者でしょう?」
「鎧だよ。先代の継承者が作り出した魔導具だ。少なくとも百年は地下に封印されていたはずだが、ここにきて外をうろついてる」
「鎧ですか、ああ……、私が看取った方はまさにその鎧に討たれましたね……黒くて無口で肌を見せない……あれがそうですか……なるほど」
そう呟くと言葉は途切れ、ハラヴァンは一度長い髪の縺れを指先で弄くり回して手櫛で梳かした。そして薬液が完全に撹拌されているのを確かめて細い筒に移し替えた。筒は硝子細工で金属製の枠にはめられている。下端には細い針が繋がり、栓をすれば注射筒の用途を果たす。薬液を注ぎ切ると押し子を嵌めて上下を返し、中の空気を抜いた。指先でとんとんと叩いて筒内の気泡を針の先に集めると一仕事終えたようにハラヴァンは眉を開き、顔を向ける。なんの感情もない真顔がブーツクトゥスと対する一瞬、背筋が粟立つ。まさかそれは俺に打つ気なのか……!?
思わずたじろいだブーツクトゥス。引き下がる背中に何者かの手が添えられた。
「私が行こうか? 倒してあげるよ」
後退る背を支えて闇より現れたのは少女だった。陰惨な空気を纏い、陰気な影を落とす肩にかかるほどの黒髪と、太陽とは無縁の青白い肌。細い肩紐に吊り下げた衣は服と呼ぶには簡素な作りで、前後の布地が垂れ下がることで暗幕のように躰を隠している。脇、横腹、腰のところに紐があり、翻らないように結ばれているが心許ない。頭角はなく、背丈も中程。耳は丸いとなるとその者は獣人、魔人、賢人、そのどれでもない。まして禍人にも当てはまらない女だった。
「この女はなんだ……?」ブーツクトゥスは問う。「混血種か? どこで拾った?」
「聖杯ですよ……私達のね」ハラヴァンは微かに目を細めると少女の方へと視線を向けた「おいで……ニァルミドゥ」
ニァルミドゥ。そう呼ばれた少女は飼い慣らされた猫のように音もなくしなやかにハラヴァンの傍に歩み寄った。ハラヴァンが少女の顎に手を添えるとニァルミドゥは目を伏せた。全幅の信頼とはブーツクトゥスには思えない。従順ではあるが表情は暗く、微笑まないのがわかったからだ。
「君が行く必要はありません。大事な役目があるのですから」
「そう……なら、ここに連れてきた目的は何?」
「なんでしょうねぇ……私もここに呼び出されたものですから」
ハラヴァンの言葉に、少女は冷たい視線をブーツクトゥスへ向けた。
「確かにここに呼び出したのは俺だ」
「ふぅん。だとしても私を連れてきたのは結局アンタじゃない?」少女は再びハラヴァンに問いかける。二人の会話の中に男が介在することを拒むようだった。
「ああ、そうでした。そうでしたね」
そう言ってくつくつと笑う。ニァルミドゥは呆れたように眉を寄せて「しっかりしてよ」と言いかけて呑み込んだ。ハラヴァンが突然添えていた掌を顎先から右腕に滑らせ、少女の前腕を掴んだのだ。
少女は虚を突かれて目を見開き唇を引き結ぶが、抵抗しない。
「明かりを」
ハラヴァンの言葉に少し遅れてブーツクトゥスが従う。
差し出した燭台の灯りに少女の青白い肌が闇の中で浮き上がり、ハラヴァンは掴んだ手の親指で数カ所を指圧した。明度の乏しいこの空間で指先の感触を頼りに骨と腱を避けて血管の透ける柔肌に針を突き立てる。
ぷつりと針が皮膚に沈み込む瞬間、ブーツクトゥスは思わず目を背けた。可憐な少女の細い腕には到底ふさわしくない得体の知れぬものが流れ込む。一度は毒ではないかと疑ったそれが、押し子によって容赦なく注ぎ込まれていく。その光景に、彼は背筋が寒くなった。
一方で少女は痛みと不快感に顔を顰めて腕を見つめた。気丈に振る舞うものの、額からは脂汗が滲む。針の沈み込んだ皮膚の隙間から血が滴る。歪な針だ、この時勢に上等な医療器具の調達は望めない。注射をされた先から血管が膨らみ、熱を持つような、それでいて薄荷のような冷えた感覚に麻痺する。皮膚の下を何かが這うように、青黒い筋が浮き出す。それはやがて、木の根が地を侵食するかのごとく広がり、腕全体に絡みついた。
痛みがないことがかえって少女にとっては不快だった。肉と皮膚の間をぐねぐねと、蚯蚓が這うような感覚に歯を食いしばり少女は悲鳴を押し殺す。ハラヴァンはあやす様に少女の頭を撫でる。
「すぐに収まりますからねぇ……」
繰り返し髪の上を滑るハラヴァンの手。少女は悲鳴とも嗚咽ともつかない声を漏らして、痙攣する腕を見つめる。指先が狂ったように踊りだしたかと思えば緊張を高めて限界まで開き、次には爪が食い込むほどに握りこむ。少女の意思ではないことは明白だ。少女は無事な方の右腕で暴れる左腕を掴むとさらに両脚の内腿に挟み込んで抑えた。自制の利かない腕はしばらく暴れまわったが、峠を越えると少しずつ収まるのがブーツクトゥスからもわかった。
「貴様……それ、なんの薬だ?」ブーツクトゥスはたまらず問いかける。
「貴方に話す必要が?」
剣呑で冷ややかな視線が射抜く。
「いや、いい。……ただこれだけは答えてくれ。この先に必要なことなんだな?」
「私は言いましたよ。この娘は『聖杯』ですとね。私達の願いを叶える神器。その杯を、絶望で満たしましょう」
ハラヴァンの言葉にブーツクトゥスは正気を疑う。……いや、疑うまでもなく正気ではないのだ、この男は。志を共にする以外に理解できることはなく、目的を成すための一つとしてこの少女は贄となるのか……。
ブーツクトゥスは憐れみを持って少女を見やると、腕の痙攣は峠を越えて収りはじめたようだ。震える膝で辛うじて立ち、顎先から汗が一筋流れ落ちる。どこか諦観の陰を落とす伏せた睫毛がほんの少し歪んだように見えた。それが微笑であるとは考えたくなかった。
「とにかく、こちらのことは任せて下さい。貴方は貴方のやるべきことを全うする……いいですね」ハラヴァンは言う。
「ああ、わかっている」
「殺するは蚩尤。焦眉の急は継承者の首です。前線より手前、可能な限り未熟なうちに奇襲をかけましょう」
「二人は実戦の経験がないとはいえ、第一継承は例外だろう。戦力はどれほど投入するんだ?」
ブーツクトゥスの問いに、ハラヴァンは意味深長な笑みを作り人差し指を立てる。
「……秘密ですよ」
またか。心の内にブーツクトゥスは吐き捨てて閉口した。用心深いのは結構だが、こちらとて危うい綱渡りを続けているのだから信用されてもいいはずだ。だというのに、この男はこちらの問いかけをのらりくらりと躱すばかりである。
「そんな顔をしないでください。ふむ、そうですねぇ……少しくらいはお伝えしましょうか」
ハラヴァンはそう言って、これからの企てを語った。
「私達はこれから前線へ戻ります。その道すがら刺客を放ちましょう。場所は……平原を狙いましょうか。おそらく継承者共はそこを経由して前線へ向かうでしょうからね」
「なぜそう言い切れる?」
「簡単ですよ。次に戦端が開かれるのがラーンマクだからです。これは陽動でも搦手でもなく道理です。私達はラーンマクを攻め落とす以外に道がない。だからこそ継承者もそこに集まる……それは向こうも知っている……なので少数精鋭の間者を差し向け平原地帯で奇襲を掛けます。うまく行けば前後で挟み撃ちができるかも知れませんしね」
「……たしかに手堅い手段だろうな」
そう言いながらもブーツクトゥスの業腹は収まらない。ハラヴァンは至極当然な駒運びで次の作戦とやらを語ったに過ぎないのだ。実のある情報や秘密の共有とは程遠い、信頼関係の欠落を暗に語っている。
ハラヴァンとの繋がりはやはり望むべくもないと、ブーツクトゥス諦めた。早々に渡すものを渡してこの場は帰ろうと決め、懐から包みを取り出す。
「それは?」
「呼び出した目的だ。受け取れ」
ハラヴァンは包みを開けて中を覗き込むと僅かに喜色に笑みを作る。それを見届けるとブーツクトゥスは踵を返して洞から出ていった。
後に残されたのはニァルミドゥとハラヴァン。果たして手渡された品は何だろうと、少女は言問顔で見つめる。
「交渉がお上手ですね……」と、ハラヴァンは愉しそうに独り言つ。
❖
朝。薄青い空は初夏の気流に雲が千切れて、その向こうに薄く残月が透けている。
マハルドヮグ山巓に吹き込んだ濃霧が肌を濡らし、汗ばむ寝起きとなった。
ザルマカシムは近衛隊集堂の椅子に身を休めているうちに眠ってしまったようだ。酷く痛む体にうんざりと頭を抱えて顔を手のひらで拭うと目脂をこすり落としてよろよろと立ち上がる。いかん、今日は式典ではないか。
まだ朝も早いと見たが、ザルマカシムは椅子から起き上がって背を伸ばした。式典は午下からとはいえ、継承者ともども朝から出ずっぱりの予定だ。準備をしなければならない。あくびをかみ殺し眠い身体を引きずって扉を開けると、朝霧の中でウツロが立っていた。
「ウツロ……」
名を呟くが別に用があるわけでもない。待ち構える存在に驚き、認識した際に声になっただけである。
ザルマカシムは明度を増す清廉な空に染まることのない黒い鎧を鬱屈とした念の澱かなにかのように見紛い、恐ろしく思った。ウツロは得物を携えておらず、何も応えない。百年以上を神殿に幽閉されていたのにも関わらず、鎧は無感情なのだ。魔導具なのだから当然と見るか、しかしザルマカシムは知っている。過去の記録によればそれこそ百年前、待てど暮せど継承者が現れなかった約束の年、鎧は制御不能な程に暴れ回ったこと。近衛隊総出で鎧の四肢を分解することで強制的に封印したということを、知っている。
時折鎧の内側に人格を感じる瞬間がある。今もそうだ。魔導具ならば勝手に歩き回ることなどありえはしない。
「なあ……」ザルマカシムは改めて問いかける。「百年前の記録を読んだことがある。……なんで暴れたのかはわからないが、現れなかった次期継承者と関係があるのか? ……あの時何があったんだ?」
理由はわからずとも、その行動には情動を感じずにはいられない。
「ずっと待っていたんじゃないのか?」
先代との死別から百年、現れなかった待ち人達に憤ったのなら、どうだろうか。
「ウツロ、お前さんには、心があるんじゃないのか――」
鎧は闇を内包する虚ろな双眸でザルマカシムに対している。面鎧は何も語らず、感情の影すら宿さない。ただ朝日に照らされ、鈍い光を湛えていた。
■004――出征式典
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
三日間に渡る式典の初日。
継承者三柱の人生を決める分水嶺。
内地での生命が保全された生活は終わりを告げ彼女達はこれより先、神殿の所有する兵戈あるいは戦略の駒として前線へ出征せねばならない。
これは決して岐路ではない。刻印を宿す三人の娘達に道を選ぶ自由はなく、運命はただの一本道……使命と呼ぶほうがふさわしい。
ある者は産まれ落ちたその日から戦人として。
ある者は流浪の日々に轟く霹靂の報せに戸惑い。
ある者は扼腕の果てに待ち侘びた痛みを喜んだ。
交わることのなかった当代継承者の運命がこの日一つに収斂し、来る黄昏に向かい絡まり合う。
――それを理解しているからこそアーミラは昨晩、一睡もできなかった。
大部屋での晩餐から酒食を楽しみはしたものの、舐める酒に舌が慣れず、酔うほどまで深酒はしなかった。贅を極める食事でも結局馴染みあるナルトリポカの味に落ち着いた。
隣で会話に花を咲かせるオロルとガントールを横に聞き流し、晩餐が終わると寝所に横臥して輾転反側……身は落ち着かず気付けば昨日と今日の境を跨いだ。目を閉じている間の多少の記憶の欠落こそあるが前後不覚な程の眠りには落ちず、アーミラはぼんやり窓外が青く白んでゆくのを眺めながらしばらくじっとしていた。やがて、夜明けとともに去ってゆく眠気を追いかけることを諦めてもぞもぞと身を起こした。せめてこの日の始まりを清廉なものとするため、水場で顔を洗おうと考えたのだ。
昨日の雨が初夏の夜に煙り、尾根筋に沿って流れる風が神殿に朝霧を運んだ。湿度が高いせいで部屋が蒸しむししてしまう。どおりで汗ばむわけだとアーミラは窓を少し開けて、乳白色に微睡む早朝の神殿を眺めてから立ち上がり、部屋を出る。
標高が高い土地であるが故に空気は薄く、風はまだ肌寒い。さて水場はどこであったか、確か昨晩井戸を見かけたような気がするが……と、アーミラは朝霧の中を彷徨い歩く。
すると、晩餐を過ごした大部屋へ続く道でこちらに向かって歩いてくる人影が見えた。こんな早くから神人種はもう仕事に出るのかと驚き、やり過ごすためにアーミラは脇道に身を隠して様子を窺う。話しかけられては面倒だ。
こんな時間からいったいなんの仕事があるのかと人影を目で追いかける……その人影の正体が分かると眉を開いた。鎧とザルマカシムである。
一方でウツロもまたアーミラの存在に気付いたか、こちらに顔を向けるとザルマカシムに手を振り、一人で近付いてくる。
「お、おはようございます……」と、アーミラ。
最後に別れたのは神殿の門の手前、一日ぶりの再開である。
ウツロはアーミラの挨拶にただ、ひとつ頷くだけだった。地面は玉砂利か石畳で舗装されている上、どのみち得物が無いので筆談ができないのだった。それを理解したアーミラはどうしたものかと困惑した。こちらから一方的に話し続ける質ではない。しかし話したい。そんな葛藤に悩んでいると、ウツロはアーミラの腕に触れた。
――どうした?
鎧はアーミラの腕に指で文字を書いた。
「え、あわわ……」
アーミラは驚いて、つい身を引いた。
身を引いてから気付く。
「……その言葉……」
寝間着の袖から晒している腕に指を滑らせて、『どうした?』と書いた。『如何シタ?』ではなく、どうした? と書いたことを見逃さなかった。肌に触れた鎧の指先の硬質さ、冷たさ、何より言葉に驚いて、アーミラは腕を温めるように摩りながら続ける。
「……魔種書体も、心得ているんですね」
魔種書体とは、主に魔人種が用いる書体である。これまでウツロが用いていたのは賢種書体と獣種書体を合わせた堅苦しいものだったため、てっきり魔種書体の心得はないのだと思っていたのだ。なにより鎧の風貌からして、なめらかな運筆は想像できなかった。
ウツロはしばらく答えられずにいた。アーミラはあっと思い出したかのように腕を付き出す。書く場所がなければ答えようもないのだ。
――槍で土に書くには直線がいい。
その言葉にアーミラは一理あると頷いた。確かにウツロが用いる筆は硬い槍の鋒、線を引くのは荒い土の上。滑らかに筆を運ぶには曲線ではなく直線を用いるのが道理。
「……では、こうして普通にお話しできるんですね」
――君に触れなければならないが。
「私を背負って山一つ登ったじゃないですか。いまさら気にしませんよそんなこと」
アーミラは言い、自然な笑みを浮かべた。どうしてだろう。人ではないこの魔導具と心通わせられるのは。どうしてだろう。この鎧と語り合う一時に心が安らぐのは。
――こんな早くから何故起きている?
「眠れないだけですよ。横になっているのも疲れてきたので、顔を洗おうかと思いまして」
――水桶を持っていくから、部屋で待っていろ。
そう言って歩き出すウツロの背をアーミラは追いかける。
「あ、わ、私も付いていきますよ。少し話したいんです」
アーミラの言葉にウツロは振り返り、二人で水場へと歩き出す。アーミラは道中、昨晩の料理のことや他の継承者のこと、アダンとシーナについてを語り、ウツロはその言葉一つ一つを受け止めながら頷き返すのだった。
❖
一日目。
初夏の朝日がすっかり夜露を晴らした午前の神殿では、すでに人々が活動を始めている。いそいそと駆け回る神人種はこの日、下ろし立ての白衣に身を包み俄に色めき立っていた。心は午後の式典を今かいまかと待ち侘びて、行き交う者達の面持は期待と興奮に満ちている。
そんな中、継承者は略装で本殿に集められていた。
マハルドヮグ神殿の中央に座する本殿は弧を描く大きな円形の建造物である。列柱の並ぶ郭はくり抜かれた回廊となっており、その先には至聖所が待ち構える。また、円の内側は中庭があり、そちらもまた引き戸を開け放って至聖所に繋がる。吹き抜けとなった会場には朱染めの天幕が厳かに飾られ、式の準備は着々と整えられていた。
至聖所の向こう側、中庭から覗く空を見上げれば、突き抜けるような青空に三女神の巨像が屹立している。
アーミラはその姿を見上げて呆けていた。オロルが右腿を小突く。
「アーミラ様? 如何なさいましたか」呼び掛ける声の主はカムロであった。
「あ……い、いえ」
我に返り、巨像から視線を外してオロルを見ると流し目に片眉を吊り上げて視線が合う。そして言葉もなくカムロの方へ向き直った。アーミラはその一瞬の眼差しがなにやら意味ありげに思えたのだが、気にする間もなくカムロが説明を始めた。
「では、続けさせていただきます。
本日午後より開かれます儀式の前に、これから皆様の身辺調査にご協力頂きます。心像灯火の儀を開く前の、ある種の試験のようなものとお考えください」
旭日に眩しい白衣の女は、言葉使いこそ柔らかであるが、語調は揺るぎのない一陣の風のように耳朶を打つ。儀式を執り行うより先に済ませておくべきこととは――
「しけん」アーミラは呟く。聞き慣れない単語だった。カムロはそんな口調を読み取って言葉の意味を説明した。
「あなた方を試すということです。本当に戦えるのか……力を疑うというよりは、素質を詳らかに明らめるという意味ですが」
「であれば厄介じゃな」言葉の後ろからオロルが続いた。「アーミラには手を焼くぞ。記憶がない」
その言葉にカムロは驚き、改めてアーミラの方へ顔を向けた。
「記憶がないとは……こちらとしては継承者様方の身元を質して記録しておきたいのですが、血縁は追えないのですか?」
「あ、う、……」アーミラは狼狽えながら繰り返し頷く。親の顔も名前も知らないのだから頼まれたって無理なのだ。
「確かに手を焼きそうだ」ガントールはカムロに笑いかける。「記憶もそうだが、アーミラは厭人の魔女だからな、まずはその眉間の皺を解さないことには会話もできないぞ」
「余計なお世話ですよガントール様」
ガントールとカムロは共に神殿で過ごす旧知の仲。年の差からみれば、カムロはガントールが赤子の頃から姉のように成長を見届けてきたことだろう。二人は軽口を叩き合う仲だった。臆面もなく顔をしかめてみせたカムロの口の端には笑みが漏れていた。そして、咳払いをして面持を元の生真面目な表情に戻す。
「とにかく、後が詰まっていますから、始めましょう」
アーミラは本殿の回廊を促されるままに進み、ガントールの背中を追う。後ろにはオロルが続いた。先導するカムロは至聖所に辿り着く回廊の中程で歩みを止めて、壁面を押す。一見してなんの変哲もない壁であるが、さして力を入れていないカムロの手によって奥にある空間が姿を表す。隠し扉の向こうでは、さらに下へと続く道が現れた。
カムロが指を鳴らすと地下への階段に取り付けられた灯石が次々と燈される。手前の石から奥へ向かって順に道が照らされると随分深いところまで伸びているのがわかった。地下の生温く滞留した空気が肌を撫で、僅かに香木の焚かれた匂いがする。一列になって四人は石畳の階段を降りていく。
地上の喧騒は遠のき、地下はひどく静かだった。だが、人の気配がまるでないわけではない。締め切った扉の前を通り過ぎる度、向こう側の空間に鎮座する何者かの存在を感じ取る。口数も少なく四人は通路を進むと目も暗闇に順応して辺りの様子がわかるようになった。
厳かとも言えるこの場は本殿と同じ建築様式を汲んでいるようで、弧を描く廻廊は先が見えずどこまでもぼんやりと明るい。
カムロは一つの扉の前で立ち止まり、振り返ってオロル見た。
「ここからは別室にて待機して頂きます。オロル様はこの扉の中へお入りください」
オロルは不意を突かれ、表情を硬くした。これまでの流れでは先陣を切るのは長女継承者からだった。万事そのように運ぶと高を括っていたがここに来てまさか三女から呼ばれるとは。
カムロは扉を叩くと慣れた態度で扉を開けて框を跨ぎ、半身を部屋の中へ差し入れる。招かれるままオロルがアーミラの前を横切って部屋の中へ踏み入った。アーミラは、小さな背中越しに部屋の中を窺った。
カムロが早々に扉を閉めてしまったためまじまじと観察することは叶わなかったが、部屋は質素な造りのようだ。印象としては飾り気のない石壁と木材の柱、その隙間を埋めるように土が押し固められていた。オロルが今どうしているのか、扉の向こうからは何も聞こえない。
再びカムロが地下廻廊を進み、次はアーミラを部屋の中へと促した。一人に一部屋が充てられて、個別に試験が行われるようだと、アーミラは推測する。そしてその推理は正しく、三女、次女と続いてガントールも同じようにカムロが部屋へと案内したのだった。
❖
一人になったアーミラは何もない部屋に取り残されていた。孤独が恐ろしいということはないが、見知らぬ場所で一人きりというのは居心地の悪いものだ。室内はオロルの時に盗み見た部屋と同じ質素な空間である。今ごろ他の二人も部屋の中で待たされているのだろうか……アーミラは辺りを見回した。
窓は無く、背後には扉――先程入ってきた扉だ――。左右と前方には石積みの壁があり、やや手狭な部屋だ。唯一異様なのは部屋の中央に小上がりが設えられており、座布団が一つと隅の方に文机が鎮座していることだ。カムロは試験と言っていたが、この部屋の様相は儀式を行う場のように見えた。
と、ここで扉を叩く音が聞こえてアーミラは振り向いた。扉越しに「失礼します」と短く告げる声の後にカムロが入ってきた。
「ど、どうしました……?」どきりとして、アーミラは問う。心の中に湧き出た不安の泉が背筋を冷やし、声が上擦った。
「はい……? どうもしませんよ。記憶がないということで、急遽アーミラ様の試験担当としてこちらに戻って参りました次第でございます。早速ですが靴を脱いでそこに上がって頂いてもよろしいですか」
カムロが小上がりを手で示すと、白衣の襟元を空いた片方の手でぐいぐいと引っ張り緩めた。どことなく忙しそうな反面、その所作に堅苦しさは鳴りを潜めて砕けた印象を受ける。アーミラは言われたとおりに靴を脱ぎ小上がりに上がると、カムロは文机の方に正座をして、座布団をアーミラに勧めた。
互いが小上がりに座して対面する形となると、カムロは文机の上に紙を敷き筆を短く走らせる。墨が紙面を染めていく湿ったとても微かな音が途切れるといよいよ完全な無音が耳を詰まらせた。カムロは背をそらして凛とした表情でアーミラを見つめ、次の刹那にはぱっと柔和に笑みを作る。
「緊張しなくて大丈夫ですよ。では、始めましょう」
「は、はい……」
膝の上で拳を固めて肩を怒らせるアーミラの姿にカムロは眉を下げて苦笑した。手に持った筆の先で紙面を叩いていくつかの質問を飛ばす。
「昨晩の夕餐はお楽しみ頂けましたか?」
「えと、はい……」
「召し上がったお酒の量はいかほどでしよう」
「……? ……そ、うですね、三杯くらいだと思います」
なぜそんなことを聞くんだろう。アーミラは不審に思いながらも答える。昨日の出来事など隠す必要もないことだが、世間話にしては、妙に個人の趣向を探るような質問だった。
その後の質問も似たようなものが続いた。料理の中で気に入ったものは何か。量は多いか少ないか。味は濃いか薄いか。……まるで調理者を相手にしているようだった。私の過去を遡るのではなかったのか。香木の煙る静謐な室内で交わされる単調な会話は正直に言えば退屈で、ここに来て睡魔が重い鎌首を擡げ始める。
「次に、湯浴場へは行きましたか?」
「はい……ガントールさんに連れられて、行きました。その後オロルさんが入ってきましたよ。三人が揃ったのはそこが始めてでした」
カムロは答弁を紙に書き残しているのだろうか。表情が何故か和らいだように見えてアーミラは不思議に思う。これまでの会話の中で何か満足できる答えを得たのだろうか……。
筆先が紙面を叩く音が密室にこだまする。地下だからだろうか、小さな音でもとてもよく耳に届くのだ。墨が掠れる音。筆を払う音。墨の瓶に筆を浸ける液面の揺らぎの音。アーミラはいまや抗い難い眠気と戦っていた。筆が止まるたび、静寂が思考を奪うようで、アーミラはつい饒舌になった。熱に浮かされているような心地だっだ。
瞼が重いうえに目が滲みる。香木を焚く煙りのせいだ。瞼を閉じていないと瞳が痒くてたまらない。瞬きをするたびに涙が出た。一度目を閉じてしまうと糊を付けたように開くのが困難になり、首が船を漕ぐ。焦点は定まらず体に力が入らない。眠い……とても眠い。……けれど、これほどまでとは何かおかしい……。
アーミラは自身の意識の内にある残り少ない理性を働かせて考える。何か、呪術を受けたのだ、きっと。……しかしこの部屋に着くまでに魔力を感じた場面はない。陣も回路も見ていない。一体いつ、誰の手によって私は眠らされるのか――
❖
小上がりの敷物の上、座布団から足を崩して体を放り、次女継承者は眠りに落ちた。カムロはその姿をしばし見届けると紙面に筆を走らせる。アーミラは会話を記録しているのだと考えていたが、事実は違った。
――次女継承者、今眠りました。
カムロが筆を走らせて書いた文字はこの通りで、何者かに宛てた報告である。紙面を濡らすのは水のような薄墨で、乾けばたちまちに文字が見えなくなる。これまで走らせた運筆の軌跡は何一つ残らず、文机にあるのはただの白紙であった。カムロはその紙面をじっと見つめる。すると、ひとりでに言葉が浮かび上がってきた。
――こちらも、長女継承者眠りました。
――同じく三女継承者、眠りました。
紙面に現れた部下からの報告を見届けると、カムロは筆先で二回、紙面を叩く。それを持って了解の返答をしていたのだ。つまり、この紙と筆はある種の魔導具であり、遠くにいる他者同士で筆談を可能とする。しかし、継承者を眠らせたのはこの紙でも筆でもない。
アーミラのみならず三人が見破ることのできなかった呪術。一切気取られることなく術中に嵌めた手品の種を明かすならば、初めの一手は前日に遡る。
神殿から往復の旅となるガントールによってアーミラが誘われた湯浴場、湯船に満たされた湯にカムロは術を溶かしていたのであった。樋を引いた源泉には常時より治癒の術式が混ぜられていたが、その日に限りカムロが術式を上書きしていた。慰労のために湯に浸かる習慣のついたガントールがここに来るのは予測できる。また、それに継承者を誘うことも。……つまりは相手の行動を予測して罠を仕掛けていたのだ。とはいえ身を浸すだけではこの呪術は発動に至らず、術者の魔力が相手の体内に吸収されるだけである。
次の一手は夕餐。酒を注ぐ杯に唇を湿すことで二つ目の呪術を重ねることになる。これには微弱な効果が発動するが、酒の酩酊による睡魔としか感じないだろう。最も、大量に摂取したオロルは強い睡魔をその時点で自覚したが、旅疲れと酔いが重なったのだと結論づけたようだ。
この二つの呪術はいずれも下準備に過ぎない。最後の一手はこの部屋を充たす香木の煙りである。非常に弱い呪術を三つ重ねることで呪術式が完成し、強力な効果を発揮する。一つ一つはいずれも身体を癒やし、休ませるための効果しかないのだ。呪術そのものに悪意がないためオロルやガントールの警戒心を掻い潜り、眠りたらしめる。その先に待つ強力な催眠状態こそがこの呪術の本当の効果だと知らずに。
さて、この部屋には深い眠りに落ちた継承者と、呪術を悟られることなく行使した術者の二人きり。身元を質すという本懐を果たす準備は万事整ったのである。
「アーミラ様、アーミラ様。貴女はこれから私の声に従って緩やかに覚醒に至ります。次に目を開くとき、意識は睡醒にあり、この場においてあらゆる言葉に嘘偽りは通用せず、私の言葉には真の言葉を返す……よろしいですね?」
アーミラは眠ったまま、かすかに首肯を返した。
「それでは、おはようございます。目を開けてください」
「……はい」
小上がりに放った体が身動ぎをして、固く閉ざされていた瞼は錠を外したように軽く開かれる。あれほど煙に滲みていた目は今や晴れやかで、潤った碧眼の双眸は何も知らない無垢の視線でカムロを見つめて首を傾げる。倒れる前に見せた訝しげな態度とはまるで別人である。様子はまるで白痴のそれで、定まらない視点を虚空に据え、起き上がった際に隅にずれてしまった座布団を気にもせずその場でへたりと正座の足を左右に崩して座り込んだ。
「座布団の上にお座りください」
カムロの指示にアーミラは従順にしたがい、敷物から立ち上がると座布団を整え、膝を合わせて正座した。上体は不安定に揺れているが、カムロは揺れるなとまでは指示しなかった。
「では改めて、お名前を教えていただけますか。継承者としての姓もお願いします」
「はい、……私の名前はアーミラ……アーミラ・ラルトカンテ《次女継承》・アウロラ……」
「間違いはありませんね?」
「多分……違いましたか?」
自信無さ気な言葉にカムロは首を振って答える。
「次女継承者の姓は『ラルトカンテ』に間違いはありませんよ。私が問いたいのは『アウロラ』という二つ名の方です。貴女に魔呪術を授け、貴方が名を襲った方についてお答えください」
「お師様……の、名前はマナ、です」
「歳はいくつほどでしょうか」
「教えられていませんが、印象ではお年を召された方でした」
「人種と性別は」
「魔人種の女性です」
「いつから行動を共に? 家に招かれて育ててくれたのですか」
「お師様は流浪の民なので決まった家はありません。思い出せる限りはずっと行動を共にしました。なので、少なくとも私が十歳の頃から……きっと、記憶を失くす前もお師様と一緒にいたんだと思います」
「それは、なにか確証があるのですか?」
「いえ……当たり前のように傍にいてくれたので……」アーミラは続ける。「時折私を見る目が、とても優しかったのを覚えています」
「気まぐれに拾った娘に対する眼差しではないと……
師は貴女に、記憶を失くす以前の事を語ったことは?」
「ありません」
ふむ。カムロは質問を止めて沈思する。とりあえずこれまでの情報を整理しようと考えたのだ。
次女継承者の師匠。血の繋がりもない娘を拾い、その素質を引き出すほどに魔呪術の知識を教えたというのだから、それは並の執念ではない。老媼の魔人種で、流浪の民であるが故に一所に住処を持たず、恐らくは書物を一つ手に入れるのも困難だっただろう。領主の家系と比べて教育環境は雲泥の差、昨日手に入れた紙も明日には口を糊するための食糧と交換する羽目になるだろう。……そう思えば無理がある。
「なぜ貴女の師匠は、わざわざ貴女に魔呪術を教えてくれたのでしょう、目的については語っていましたか?」
「分かりません……」
アーミラは申し訳なさそうに肩を落とす。やはり謎が多い。流浪の民という貧しい生活をするくらいなら、魔呪術の力を切り売りすれば働き口はあるだろうに、彼女の師匠がそれを隠して生きてきた理由がわからない。
「マナ・アウロラ……ふむ……」
カムロは呟く。なんの気無しに転がした彼女の師匠の名前。しかし他者からその名前を聞いた事で記憶が呼び起こされたのか、アーミラの瞳が一瞬強張った。
「決して……見せては……」
アーミラが切なく言葉を漏らす。カムロは片眉を吊り上げて「何か言いましたか?」と問うた。催眠状態にあるアーミラは何を見るでもない視線でカムロの方を見つめる。不意に掴んだ手掛かりか、カムロは詰め寄った。
「アーミラ様。この場では嘘偽りは通用しません。私の問いかけには応えることに努めてください。
もう一度問います。何を言ったか、繰り返しなさい」
アーミラは虚空に手を伸ばして同じ言葉を繰り返した。
「魔術の、その全て。決して人には見せてはならん――」
自然と溢れ出す涙が頬を伝い、一筋の雫が敷物にぽたりと落ちた。カムロはその切実な声音にマナと呼ばれる者の影を見紛い、目の前の継承者がどのように師と別れたのかを悟った。辞世に遺した約束事か。
「それが、最期の言葉でしょうか?」
「……はい」
「アーミラ様、貴女は過去の記憶を持たず、肉親の顔も名前も知らないとオロル様が仰っていましたね。確認ですが、師とは血縁関係ではないのですよね?」
カムロの淡々とした言葉にアーミラは虚空へ手を伸ばすことをやめて、糸が切れたように腕が敷物を擦る。ゆっくりと姿勢を直して項垂れたままアーミラは答える。乱れた髪の房が顔に垂れて表情は見えない。
「私にとっては家族でした。お師様にとってもそう……だと思いたいです。血が繋がっていなくても、お師様は私の全て、お師様がそこで死ぬのなら、私もそこで死んでいいと思っていました」
そこから、アーミラはこれまでの足跡を隠すことなく語った。順序よくとは行かなかったが、話の内容に穴があればカムロは問い質し、次女継承に至るまでの半生をほとんど把握するに至った。
午前ももうすぐ終わる頃、カムロは筆の尻骨で顳顬の生え際を押すように掻いた。その顔には疲労の色が滲んでいた。アーミラも話し続けることに疲れたようだ。元々訥弁とした性格故に、時折肺を引つらせて喉を撫でていた。催眠下になければこれほどの時間をかけて語り続けることなどなかっただろう。……いや、マナと過ごした日々の中では、あったのかもしれない。
カムロは小さく息を吐いて呼吸を整えると視線をアーミラに向けた。およそ知り得るすべてを知った今、目の前の娘に対する想いは複雑なものだった。覚悟はしていたが、不憫な娘に使命を背負わせ、前線に向かわせることに良心が痛むのは当然のことである。神の力を授かったとて、先代の継承者には非業の戦死を遂げた者の記録もある。当代継承者の行く末だってわからないのだ。唯一はっきりしているのは、ここで出征の可否を判断するのはカムロ自身にあるということ。
――お師様がそこで死ぬのなら、私もそこで死んでいいと思っていました。
アーミラの言葉を思い出す。
朦朧とすることは呪術の特性上しょうがないことではあるが、自身の半生を語る少女が時折見せる憂いの表情……当時の情景を思い出しながら語る彼女の姿は、見ていて胸が締めつけられるようだった。嘘偽りを封じられ心を曝したこの娘は予想しているよりも希死念慮の閾値に近い所に身を置いているように見える。
だとするとこの試験には懸念が生じる。彼女が次女継承者として、前線で役目を果たすことができるかどうか。それを見定めなければならない。
「アーミラ様……最後にお答えください」
沈黙を切ってカムロが口を開くと、掠れた声でアーミラは応えた。
「……はい」
「アーミラ様、貴女は……己の死を今も願っていますか?」
カムロの言葉にアーミラの瞳が開く。虚を衝かれた顔をして、しばらく言葉が出ない。カムロは追い打ちをかけるように畳み掛ける。
「お答えください」
「……分かりません。あのときの私は死にたかったのかもって、思います。
でも、生きることを選ぶのも、死を選ぶことも恐ろしいことです……私は、なんというか……」
アーミラはここでまた思考の深みに潜り込む。朦朧とした譫言のような呟きが繰り返されるがカムロには聞こえない。その態度から言葉を探していることはわかるのだ。辛抱強くアーミラの結論を待った。
「……お師様はそれをきっと望んではいませんし、私には救いの手もありました。生きることは私にとって消極的な選択、あるいは選択そのものを放棄した結果なのかも……死を選ばないことはそのまま生存が継続される……私は選びたかったわけじゃなく――」
アーミラはこれまで言語化しなかった己の心に気付きを得たか、目に光が宿る。
「――選ばれることを待っていたんです。あの時私は死に選ばれたかった。お師様を失ったとき、その絶望が私に与えるものは甘き死こそ相応しいと願っていました。そうして終わる命こそ救われると」
カムロは何も答えない。
死を選ぶのも、生を選ぶのも放棄して、目の前の継承者は今日まで生きている。それは、ごく自然な成り行きだった。老体ならばまだしも娘は若く、生命は活力に溢れているのだ。魂が弱っていようと肉体は全盛。自ら選択を放棄すれば今しばらくは衰えを知らず死にはしない。それこそ、前線にでもいない限りは。
「……アーミラ様」
「……はい」
「アーミラ様が仰るとおりなら、貴女はその身の生き死にの選択を放棄した果てに刻印を宿し、次女継承者となりました。師マナ・アウロラから授かった魔呪術の知識と術を遺憾なく発揮する前線での活躍を私共は期待しておりますが……貴女はどうでしょう? その刻印を宿したとき、どのような心境でしたでしょうか? 戦火に身を投じる運命は死に選ばれたとお思いでしょうか?」
真剣な眼差しで問う。ここで頷くのであれば彼女はきっと望めないと、カムロはそう考えていた。
継承者の素質がないと判断すればこの娘の出征を取り止める。私にはその責任がある。
午後から始まる式典までに見極めなければならない。一人の娘を前線に送るだけでも神殿は多くの対価を支払うのだから無駄死にするものを認めるわけには行かないのだ。三日に渡る式典も道楽で行われるものではない。祭りではなく政なのだ。人々は継承者に祈り、奉り、希う。国が三人の娘に進退を賭けている。だからこそ見誤ることは許されない。カムロは次女を抜いた継承者姉妹二人での出征に変更することさえ覚悟した。
しかし、それは杞憂であった。
「……私は、死に選ばれたとは思えませんでした――」
アーミラはゆっくりと、明確に首を振る。
そして言葉を続けた。ぽつりと、それでも確かな声で。
「――私は生に選ばれたんです……生きること、生きてこそ成す使命を果たせと言われた気がしました」
カムロの表情が、かすかに揺らぐ。彼女は筆を握る手をわずかに緩め、アーミラを見つめた。
「刻印が刻まれたときの痛みを今も覚えています。心臓に杭を打たれたような、……それこそ死にそうなくらいに痛くて、その痛みの中で気付いたんです。
生きているんだって。
たとえ消極的であろうとも、人とのつながりを避けようとも、命からは逃れることはできないんだって……この胸に突きつけられたんです」
その言葉にカムロは耳を疑う。これまでの弱々しい雛鳥のような少女の面影は消え、語調には迷いがない。あまりにも揺るぎないその眼差しに気圧されるように筆を紙面に落とし、薄墨が紙面に散らばる。夢現の中で妄言を曰っているのだろうか……いや、それはありえない。この場で嘘をつくことはできないのだから。
アーミラは続ける。
「私には親の記憶がありません。父の顔も、母の顔も覚えていません。ですが、それでも私は愛されていました。お師様だけでなく、ナルトリポカでも私を温かく招き入れてくれた人がいます。大切な巡り合わせの中で温かな心に触れた。だからこそ別れの度に死にたいくらいに辛い……。
私は、もう逃げたくないんです。誰かを守れるのならそのために力を使いたいし、記憶を取り戻せるなら努力を惜しみません。
私は、……大切なものを守るために戦います」
目の前の娘は視線を反らすことなく胸を張り、明晰とした瞳でこちらを見返していた。呪術の催眠下にあってもその瞳は決意の灯を宿していた。カムロはその視線に射抜かれてアーミラから目を離すことができなかったが、暫くしてアーミラは香木の煙に微睡み事切れたように倒れてしまった。三度小上がりに倒れる娘を見下ろしながらも、カムロはその身が震えるのを自覚した。これが――
「これが、継承者の器……」
いわば彼女は原石だ。今はまだ石英の内側に眠る碧玉……過酷な世界に打ちのめされ、時に砕け、時に精神をすり減らしたことだろう。しかし砕ければ内にある碧玉は露出し、すり減らすほどに磨きがかかる。己の世界と向き合う彼女の有り様は懶惰に膿んだものではない。いたずらに砕けて失われるような脆さではなく、立ち向かう強さがある。素質については大いに期待ができるだろう。カムロは筆をとり、紙面の向こうに待つ二人に報告を記した。間もなく応答が紙面に浮かび上がり、部下達は既に身辺調査を終えていた事を知る。確かに時間を要したなとカムロは安堵に胸を撫で下ろし、自身の報告を持って当代三人の継承者出征は決定した。
❖
昼餉の休憩をとって継承者三名は一度大部屋へ向かった。オロルが想定していた通りアーミラの身辺調査に午前の時間を割いたため、午後の儀式のために正装へ着替える時間はずれ込んだ。そのため三人は落ち着く暇もなく飯を腹に収めることとなった。……反ってよかったのかもしれない。式典を控えての緊張に、きっと食事は喉を通らなかっただろうから。
本殿の中庭では白衣を纏った神人種が整然と並んで隊列を作っていた。玉砂利の上に蓙を敷き、ここマハルドヮグに住む者が一堂に会し、数百、ともすれば千人に届く人集りとなる。壇上の袖からオロルは聴衆の列をうんざりしたように眺めていた。
「心の準備はできましたでしょうか? 式典が始まりますと御三方は壇上の椅子から動くことはできません」カムロが言う。
暗幕の内側、継承者三名は面持ちもそれぞれにカムロの方を向いていた。
「うぅ……その、厠に……」
アーミラは眉を困らせながらカムロに訴える。もう何度目になるかわからない。厠に行ったところでもはや出るものはないだろう。それとも際限なく湧き出る不安を都度吐き出しているのだろうか。
「じゃあアーミラが戻ったらそのまま壇上へ向かおう」ガントールが言う。
「そうじゃな。ここに居ったらアーミラが干からびるわ」
二人の言葉を背に受けてアーミラは情けなくも厠へ駆けていった。廻廊を小走りに去るその背中をカムロは複雑な表情で見送った。
「……さてカムロよ、アーミラの過去は覗けたか?」
オロルはため息混じりに見送って、カムロに問いかける。その話題に興味があるのかガントールのとがった耳がぴくりと動いた。
「残念ながら……本人の覚えている限りは聞き出せましたが、記憶の鍵を開けるには至りませんでした」
「鍵を開ける……お主もそう考えているのじゃな」
「はい」
オロルの言葉にカムロは頷く。なにやら通じ合っている二人に対してガントールは言問顔である。
「アーミラに何かあるのか?」
ガントールの疑問に対してはオロルが答えた。
「何かはあるじゃろて。それが何かはわからんが、記憶を失くしているなんて都合が良すぎる。類稀なる才覚の出自、その親、アーミラを拾った師匠の存在……恐らくは意図的に記憶を消されておる」
「記憶を、消されてるって……」ガントールは思わず声を顰めた。「なんの為にさ」
「知らんよ」オロルは冷たくあしらう。「わしはそもそも、アーミラの記憶がないということ自体疑っておった。じゃから酒を勧めたのじゃ」
「酒?」ガントールはますます首を傾げる。話が見えない。「記憶がないことも全部嘘だと思ったから、酔わせて口を吐かせようってことか?」
「いや、飲ませたかったのは酒ではなく」オロルはそう言ってカムロに視線を滑らせる。
「どうやら、オロル様は初めから気付いていたのですね」
「さてな。どこからが初めかわからんが、怪しいと感じたのは湯浴場からじゃな。
正直さして気にもしていなかったが、治癒の術式が湯に溶かされているのに気付いた。確信したのは晩餐の酒……いや、酒を注ぐ杯じゃ」
オロルの語りにガントールは慌てて口を挟む。
「待て待て、なんの話なんだってば」
「カムロがわしらに呪術をかけた、という話じゃ。午前の地下での出来事、お主も眠らされたのじゃろう? 眠りの内に試験が終わっていた。そうじゃろう?」
「あ、ああ……そうだが」
「アーミラが戻ってくる前にさっさと話すからあとは黙って聞け」
歯に絹着せぬ物言いにガントールは素直に黙って聞く。そしてオロルは推理を開陳するのだった。
「呪術は三ヶ所、湯に溶かされた魔力を種とし、杯に口をつけると呪いが刻まれ、地下に焚かれた香で発動する。カムロはわしらを眠らせ、夢現の内に自白させたのじゃろう。それについてとやかく言うつもりはない。神殿とて継承者の見極めは重要じゃろうて。嘘偽りを取り除きわしらの底を覗くのは筋が通る」
カムロが言葉を継いで促す。
「それに気付いたオロル様は、アーミラ様の記憶について調べさせるために私の術中に敢えて嵌ったと」
「そうじゃ。アーミラが記憶を失くしておるという言葉そのものが嘘であると見ていたから晩餐でアーミラに酒を勧めた。あれは飲めば飲むほど呪術の効果が高まるからな」
「なんでアーミラの言葉が嘘だと思ったんだ? 結局記憶がなかったのは本当だったのに」
ガントールは言ってから慌てて口を噤む。オロルは不機嫌そうに片眉を吊り上げて睨んだ。
「言ったじゃろう。都合が良すぎる。十歳より昔の事を知らないなら、なぜ魔呪術の知識は失われておらんのじゃ? これまでの日々を覚えておらんのに子供の頃に読んだ魔導書の一行は忘れなかったと? だとしたら薄情者じゃなアーミラは、親の顔を忘れるとは!」
私に怒鳴らなくても、とガントールは参った顔でオロルを宥める。口を開けばまた癇癪を起こすだろうから今度こそ何も言うまい。心の内には「真っ白な状態から今日までの七年間で魔呪術を学べば十分な時間ではないのか」と問いたいが、オロルがその可能性を無視するわけがない。神殿で魔呪術を一通り学んだガントール自身そんな短い年月で修められるような技能ではないことはなんとなくわかっているから言う甲斐もない。きっと無理なのだろう。
「話を戻す。……都合の悪い過去を忘れたふりをしていると見たが、カムロが調べた限りではどうやら本当に記憶を失くしているらしい。ならば何者かの影響を怪しむのが道理じゃろう。
それならば怪しむべきはアーミラの師匠じゃ。共に過ごし魔呪術について教え伝えたというのに人柄については碌な記憶がない。師匠はわざと己の正体を隠していたのじゃろうよ。
では、なぜ隠すのか。わしはそこに、当代継承者の――」
不意にオロルは話すのをやめた。目配せをしてそれとなく会話を切り上げた理由を示す。間もなくしてアーミラが帰ってきた。
「――とはいえ全ては憶測じゃ。鍵となる者亡き今、二度と開くことはないのかもしれんし、あるいは肩透かしの空箱かもしれん」
「なんの話をしているんですか?」厠から戻ってきたアーミラはオロルの言葉に首を傾げるが、オロルははぐらかして煙に巻く。
先ほどまでの会話を悟られぬよう、皆は何食わぬ顔でアーミラを迎え、オロルが誤魔化すように言う。
「いよいよじゃと話しとったんじゃ。もう式典が始まるぞ」
「改めて御三方にここでお伝えしておきます」と、カムロも言葉を重ねる。「式典では壇上にお座りいただきますが、会場には各国王が列席し、神殿からも天帝――つまり神族ラヴェル家御一同様もご出席頂いております。大変不躾なお言葉を申し上げるようで恐縮なのですが、天帝の御前であることを承知の上、失礼のないよう、伏してお願い申し上げます」
「アーミラ、覚悟はよいな」
畳み掛けるようにオロルに念を押されてアーミラは露骨に狼狽える。時間は待ってはくれないのだとオロルが背中を叩き、ガントールは身なりを整えて先を歩き出した。少し遅れてアーミラ、後からオロルが続いていざ壇上へ。
斯くして、これより二日間に及ぶ出征式典の幕が上がる。
❖
初夏の候、夏ノ一に入り日増しに陽射し燃ゆる今日、皆さま御清祥の段、此度は種々の御配慮を賜り忝く存じます。尚過分の御厚志に預り御厚情誠に難有く、篤く御礼申し上げます――
式典の第一幕である『心像灯火の儀』は神族近衛隊隊長であるカムロの開会宣言から始まった。至聖所の壇上に立ち、詠唱にも似た難解な言葉を滞り無く重ねていくその背中を見つめながら、継承者はつい背筋を正す。肌を焦がすようなひりついた感覚は陽光の照り返しのせいではない。この場に集まる者達の真剣な眼差しによって作られた厳かな一種の力場のようなものに当てられているからだ。
これより先は生半可な覚悟では生きていけない。前線出征とは継承者である娘が神の力を得て死地へ赴き勝利をもたらす――そのような神話を心から信仰している者達に応える重要な儀式なのだ。頭では理解していても、いざこの場に座るとアーミラは息を呑んだ。祈り、奉り、希う存在として曇りのない想いを背負うことの重圧を実感する。
壇上に設けられた継承者の玉座は硬く、華美に象嵌細工を飾るもので格式も高ければ背もたれも高い。浅く腰掛けて肩を縮こまらせているアーミラは緊張に身が休まらず、指先は手遊びをして落ち着きがない。
式典を経て私達は神格化される。現実味の無いその事実を頭の中で持て余しながら、アーミラは式典を始終不安げに過ごすこととなった。
式典に列席する各国王の挨拶が続き、各々が歴史的瞬間に立ち会えたことを言祝ぐ冗長な挨拶が続く。先代からの通例に沿って固陋な詠唱の平仄を取るため、継承者は聴いている間に臀が痺れてきた。列席する国王たちは、いずれも内地側の王家の血縁ばかりであった。先代の中でも特に古い歴史を持ち、信仰も篤い者が多い。中には、盲信と呼べるほどの者すらいた。彼らは二百年の渇望をまるでその身で体験してきたかのように口々に語る。オロルは座面に身を委ね内心では辟易していた。同じことしか言えんのかこいつらは。
儀式は中盤に差し掛かり、壇上の脇に移動したカムロは国王列席の卓へ深々と頭を下げると今日の本懐である『心像灯火』を執り行うことを宣言した。その言葉を合図に聴衆である神人種から国王まで天帝に向かい叩頭いた。私達も頭を下げるべきかとアーミラは顧眄して、ガントールが頭を下げないことを知るとそれに倣った。天帝の登壇に対して拝礼を行わないのは無礼に思えるが、それはこれまでの話。今の彼女達は継承者であり女神の地位に座しているため神の末裔より上位である。
至聖所の暗がりに紗を掛けて身を休めていた神族の帝が徐に椅子から立ち上がり、近衛が紗を左右に開くとその姿を大衆の面前に晒した。
その神々しさは目を潰すとまで口伝される天帝ラヴェル一族の長。その名をラヴェル・ゼレ・リーリウス。神の血を引くという逸話の通り、背丈は獣人種を超え二振半ほど。最早アーミラから見れば天を衝くほどの巨人である。更に日に透ける白髪と顎髭は枝垂れのようにうねりながら腰元まで届き、身に巻き付けた一枚布の衣と相まって人の域を超越した神聖さを醸し出している。歳は六十に差し掛かるほどか、額や目尻に深々と刻まれた皺が厳格な人相を形作り、射抜くような賢しげな視線は衰えを感じさせない。何よりも目を奪うのはその後姿だ。衣に覆われている大きな膨らみ、肩口や裾からこぼれ落ちんばかりに豊かな純白の羽が覗く。……この翼こそ神族と人とを隔てる、最も顕著な特徴である。
人波を割り継承者の座する壇上へ一歩一歩と悠然と進む天帝。叩頭する者達はつむじを晒してその背中を追いかける。
「面を上げよ」天帝の低い声が響く。
壇上に上がったことを確認して聴衆はそろそろと顔を上げる。天帝リーリウスは継承者の前に立っていた。壇上の中央に座していた次女アーミラはその巨躯から落とされる陰に覆われ、向けられた眼差しの意味を計りかねて素直に戸惑った。隣にいたガントールは顔にこそ出さぬように努めたが意思に反して耳がぴくりと反応する。声がする……アーミラになにか伝えている……?
首を向けようか悩む間もなく、万事整った事を告げるカムロの声が割って入り、どっと場が色めき立つ。万雷の拍手を受けてガントールは努めて笑みをつくると聴衆へ会釈を返し、アーミラ、オロルもそれに続いた。リーリウスはゆっくりと間をおいてから身を翻して聴衆と向き合うと手のひらを向けて拍手を収める。
「……当代の継承者は、数えて五代目の継承者となる――」
リーリウスの含蓄のある嗄れた声が中庭に響もすと、会場は一語たりとも聴き漏らすまいとしんと口を噤む。
「――誰もが承知の通り、先代から二百の夏を数え冬を越えた。先代の顔をその目に見た者達はこの世を去り、遺された願いを継いで我らがここに集まっている。その願いとは何か、……勝利だ。
長きに渡る禍事を退ける神の血を分けた三人の御子、今この場に継承者が揃うという祝いの日を、共に迎えたこと、大変喜ばしく思う」
リーリウスは言葉を切りガントールの方へ手を示すと一人ひとりの紹介を始めた。これもまた詠唱の平仄に沿った律を持つ。
「この世の厄全てを平らげ斬り払うこと能わざるは無し。魂魄の導。天秤を司る三女神の長女。名をリブラ・リナルディ・ガントール。産まれは四代目長女国家ラーンマクの守護辺境伯であるリナルディの娘である」
ガントールは瀟洒に玉座から立ち上がると堂々と胸を張り視線を返す。見目麗しく家柄も申し分無し、誰もが思い描いた通りの長女継承者の勇ましい姿に中庭の聴衆は静かに興奮の焔を上げた。
「幽玄なる万物の解を齎す神秘の扉。現世に落つ智慧の果実。天球儀を司る三女神の次女。名をアーミラ・ラルトカンテ・アウロラ。記憶を失くした流浪の民の出であるが、その身を尽くしこの国のために奉仕すると誓ってくれた」
アーミラは紹介が終わると玉座から立ち上がり初々しく裾を掴んで集まる視線に堪えながら一礼した。神人種も彼女が継承者となってまだ日が浅いことは理解しているので場の雰囲気が和やかなものになった。リーリウスがオロルの方へ足を向けるとアーミラは集まる視線に耐えかねて腰を下ろしたくなったが、ガントールが手を水平に振り、「三人揃うまでそのまま」と視線を送った。
「未だ明らめぬ機巧の心臓、刻々と奏でるは糾う律動か。柱時計を司る三女神の三女。名をチクタク・オロル・トゥールバッハ。産まれは三代目国家ムーンケイ島嶼卜部族の娘である。どうか祈りの果てに嘉し給わんことを」
二人に倣い、オロルも玉座から降りて立ち上がる。聴衆には目礼のみを返し、金色の瞳は人の群れを見定めるかのように眺めおろしていた。
「五代目継承者が揃った。これより心像灯火を始める」
天帝リーリウスが声高々に告げると中庭一帯が発光し、聴衆は再び叩頭いた。辺りにはちりちりと季節外れの舞雪のように燐光が浮かび、地面が仄明るく光を発する。円形の本殿そのものが陣を描き、儀式のための詠唱は継承者の紹介の折に済んでいる。心像灯火が始まったのだ。
この儀式を一言で表すならば、女神継承者を非死へと昇華させる神殿の大祈祷である。『心の火を像に灯す』――それを持って心像灯火を成す。この儀式が行われるようになったのは先代である四代目継承者出征式からで、二百年の歴史を持つものの術式を展開するのは通算二度目。当然ながら術者である神人種達は先代の大祈祷を経験しているわけもなく、人生最初で最後の詠唱。彼らにとっても一世一代の大舞台といえる。
大祈祷は先述したとおり術式の対象者を非死とするものであり、非死について詳しく言うのであれば、生存率を底上げするために肉体と魂を分離させる術式である。つまり、三人の娘の魂は神殿の巨像に祀られ、その魂――霊素――を保管することで前線での致命的損傷を免れる。そして大祈祷によって尋常ならざる治癒能力を獲得した肉体のみを前線へ送るのだ。とはいえ、魂を抜いたからと言って人格や情動に影響が出るということはなく、また不老長寿を獲得するわけでもない。不死ではなく非死であることは、継承者各々も十分に頭に刻み込む必要がある。同時に、神殿の巨像三柱に祀られた魂についても無知でいることは許されない。神殿が墜ちたとき、その巨像が毀された場合は魂を喪失するだろうことは明白だ。ガントールやアーミラはその事実を理解していたが、オロルはさらに深く受け止めていた。つまりこれは「己の魂そのものが人質」だと。前線を守れなかった場合は逃げ場もなく魂は敵前に晒されることとなる……端的に言えば、命を懸けて戦わねばならないのだと理解していた。
この大祈祷には莫大な魔鉱石を消費するため、継承者以外に行われることはない。それこそ天帝でさえも非死の力を獲得してはいない。
その理由としては二つ。一つ目は、天帝は内地から出ることがないこと。魂を祀る依代の像をわざわざ建造し、そこに魂を納めたところで、天帝本人が神殿に籠もっているのなら意味がない。そして二つ目には魔鉱石の制限があること。大祈祷は二百年もの間に民草から税として納められた魔鉱石のおよそ三割を削るほどの非効率な術式を使用している。当代は二代分(継承者が百年周期であり、先代から現れなかったことから二百年分)の潤沢な貯蔵があるものの、黒字分を天帝に充てるのは反感を買うだろう。
非死という異能は前線での奉仕という約束が前提にある。死の危険と隣り合わせであるからこそ人々は女神の無事を祈るのだ。
心像灯火の大祈祷が滞りなく執り行われる中、まさにその継承者三名は自身の肉体の変化を感じ取っていた。強烈な目眩とそれに伴う浮遊感。それを幽体離脱だと言語化できたのはオロル一人だけだった。厖大な魔呪術の知識から、自身に起きた変化を冷静に観察していた。その傍ら、ガントールは口を引き結んで術式に耐え忍び、アーミラは漠然とした懐かしさに戸惑っていた。魂が引き剥がされる感覚――未知の感覚であるはずなのに、アーミラにとっては既知の記憶をくすぐられたのである。
肉体の中心にぽっかりと穴が開いたような、空腹感にも似た奇妙な感覚が残り、三人は申し合わせたように腹を撫で擦る。明確に臓器が欠落したわけではないが、感覚として何かが自身の体から取りさらわれたことは理解できた。おそらくはそれこそが魂なのだろうと考えがめぐると、アーミラは背筋が凍る思いで二人を見た。
術式の副作用らしき反動も無ければ痛みもない。大祈祷が終わると人々の視線は上を向く。その視線を追いかけるようにアーミラも後ろを振り返り空を見上げた。初夏の青空を遮る巨像が目の前に立ち塞がり、その像の胸元に今まさに小さな篝火が灯ると、すぐに燃え広がって吹き荒ぶ風にも負けない焔となった。あれが私達の魂――霊素が焔の形となって現れた姿か――と、アーミラは実感が沸かないまま、ぼんやりと思うのだった。
熱に浮かされたかのように惚けた継承者の背後からは祝いの拍手が上がり、喝采が肌を震わせ意識を呼び戻した。大祈祷が滞りなく終了したのも束の間、カムロが次の儀へ移行する旨を伝えた。
式典の第二幕、『神器継承の儀』が行われる。
神器とは、継承者に与えられる姓の由来であり神から授かりし魔導具の総称である。大戦の歴史から今日に至るまでの文明を支えてきたその三つの神器は神殿に保管され、当代継承者が現れるまで眠り続けてきた。それぞれの名称と特徴は以下のようになる。
長女継承神器――天秤。
外観は鋒の丸い両刃の剣。古い時代に使用されていた死刑執行人の用いる斬首剣のそれに似た特徴を持つ。刃渡り一振ほどの短い剣身の割に柄は長く獣人種の膂力に合わせた両手持ちの運用が想定される。
その剣がなぜ天秤の名で呼ばれるのかは鍔を見ればわかる。その意匠は左右対称に枝を伸ばした形状で、初代継承者の顕現時にはまだ存在していなかった質量計器の形をとっていた。時系列に沿って事柄を並べるなら、まず天秤と呼ばれる剣を神殿が預かり保管した。そのなかで鍔の見慣れぬ意匠の用途を分析し、質量計器としての活用方法が判明したのだ。以降は剣身を省き左右の皿で重量の比較測定を行う用途に絞った模造品が流通し、商人の貿易等に広く使用されるようになったというのが歴史の流れとして正しい。
次女継承神器――天球儀。
天秤によって齎された叡智と同様に、この神器はこれまでの通説である天動説を覆す要因となった。磨き抜かれた巨大な魔鉱石の表面には陸地と海面が描かれ、自身が生きるこの星が平面ではなく球体を成すことの証左となった――とはいえ、この球儀上でも禍人領は粗く削られたように曖昧に表記されている――。これによりこれまで不可能とされた天体の周期計算が可能となり、この世界が太陽を中心に星々が巡る説――地動説が立証された。また、雨季、乾季等の天体の周期計算に基づく知識は農耕において重要であり、一つの周期を『年』。それを十二に分割したものを『月』。日が沈みまた登るまでの周期を『日』と名付けた。季節や暦の概念が確立され、天体の記録からは占星術が誕生するに至る。
神器外観は魔鉱石を囲うように弧を描く弓が天体図形の上部と下部の極を貫き、天球儀を構成している。神器の下半分は石碑の破片が母岩のように癒着しており、全体として身の丈と並ぶ大杖のような形状である。石碑には解読不明の文字らしきものが刻まれており、神が用いる言葉の一節である可能性があるとされている。
三女継承神器――柱時計。
この神器については未だ謎が多く、神殿での目下研究対象である。三代目がこの神器を『柱時計』と呼んだため、この名称で統一されており、言葉のままに受け取るのならこの神器は『時を計る』ためのものであると推察されているが、そもそも時というものの概念が未だ曖昧であり、時計というものがどのようにして時を計るのかまでは解明できていない。現在は暦と合わせて十二まで数えて一巡する進数という数学的概念が解読されたが、神器に備えられた文字盤とその中央から伸びる三本の針はそれぞれが異なる律を持っており、複雑な歯車と用途不明の発条のような機巧等、魔呪術とは異なる金属加工によって構成されたこの神器を理解し模造するにはしばらくの時間を要するだろう。
外観についても名前とは異なり、手鏡ほどの大きさしかない。首飾りのようにぶら下げて持ち運ぶようだが、この神器でどのように戦闘を行うのかは一見して不明である。
「なあ、アーミラ」
声を顰めて問いかけるのはガントール。神器継承の儀においての一幕で継承者は依然として玉座に身を置いていた。昼下がり、集中の途切れる頃合いにガントールは視線を交わすことなく言葉だけを届けたのだった。
「え、と……どうしました?」
アーミラは名を呼ばれたときは思わず視線を向けてしまったが、余人に悟られぬように目を合わせないガントールの態度をすぐに理解して顔を伏せた。まだまだ式典は続く。これから神器を授かるという手前、何を問うつもりなのだろうか。
「さっきの式典でさ、天帝様が何か囁いてなかったか? あれはなんて言ってたんだ?」
アーミラは、ああ、と思い出して困った顔をする。
「確か、『恐れるな』と……そんな、ような、ことを……」
言葉切れは悪く最後の方はもごもごと口籠って会話は途切れた。実は天帝の言葉には続きがあるのだが、アーミラ自身その意味を図りかねていたのでガントールには伝えなかったのだ。正確にはこのように囁いていた。
『恐れるな、何も知らぬだけだ』
それが誰に向けた言葉なのか、何を意味しているのかわからないので、アーミラは都合のよい言葉のみを伝えるに留めた。
「ふぅん……アーミラが緊張してたからそう言ったのかな」
ガントールは思ったままに呟くと会話を終える。アーミラも曖昧に頷いて誤魔化し、改めて神器継承に集中した。
紗をかけた至聖所の暗がりへと戻る天帝をこれまた叩頭して見送り終わると、神人種の衆目は壇上へ向かった。一仕事終えたような息づかいが漏れ聞こえた。事実彼らは大一番の仕事を果たし終えたばかりなのであとは気楽なものである。その視線は緊張というよりも純粋に祝いや希望に輝いていた。
カムロ達が運んできた神器が本殿に姿を現すと誰ともなく拍手を叩き、継承者に神器が授与される瞬間を見守っていた。それぞれの神器がそれぞれの継承者の手に渡り、式典は第三幕『星辰の儀』へ続いた。
マハルドヮグ山の麓から夕焼けを西に望み、地平の遠景は雨雲が迫っていた。黒ぐろとした荒天の切れ間から射し込む茜色はまるで燻る埋み火のようである。裾野から吹き上がる風にはすでに湿った粒が混じり、遠雷の轟きがここ山頂まで雨期の到来を報せた。
ウツロは式典の開会から一日中、外郭を彷徨いていた。彼には門衛としての役割がこの日与えられていたのだ。本来であれば先代継承者の忘れ形見――ある種の神器として数えられる特異な鎧であるが、ウツロが抱える事情により、式典には参加できないのであった。
「――そういえば、今日は鎧を見ないな」ガントールが言う。
外壁に斜陽が遮られすっかり薄暗くなった神殿内部では灯が燈されはじめていた。継承者はこの日最後の儀を見届けるため、見届けるため、玉座を降りて本殿の中庭へ向かっていた。それぞれが先刻に授与された神器を手にしているが、オロルだけは両手が空いている。
『星辰の儀』とは――三女継承神器である柱時計の解明を進める儀式である。先述の通り柱時計は未だ解明されていない謎を多く抱えているため、継承者が現れた折に研究を進めるのが狙いである。つまるところ継承者とは神器の所有者であり、当人にのみ与えられた権能など、保管時には扱えない機巧を含めて未知を明らめられる可能性があるのだ。出征を明日に控えている為、神人種の博識高い者達は己の威信を賭けてこの日を有意義に使う必要がある。研究という目的が先に立つため、前の二幕とは趣が異なり、堅苦しい空気はなかった。
そういうわけで、三女神器の柱時計は今オロルの手元にはない。神人種たちは忙しそうに口角に泡をためながら、筆を片手に互いに意見を交わし、目の前の神器の解明に汗を流している。オロルはそれを傍目に眺めながら彼らの努力はどうやら実を結ばないであろうことを憐れんでいた。
「なぁ、見てないだろう?」ガントールは再び言った。
「何をじゃ」
オロルは短く応えた。視線の先にいる神人種達の徒労を眺めていたせいか語調が厳しいものだったが、ガントールは気にせず繰り返す。
「だから、鎧だよ。ウツロの姿を見なかったなあって」
「ああ、なんじゃったか、アーミラの連れじゃろ」
ガントールはその言葉に頷いた。既に二人の中では鎧はアーミラの連れという認識である。対して当のアーミラは満更でもない顔で首を振るが、頭の中では今朝の事を思い出していた。たしかに、顔を洗いに出た時ウツロは神殿にいたのに、今はどこにいるのだろう……。
「でも……どうなんだろうな」とガントール。
「何がですか?」
「彼奴はほら、先代の忘れ形見だろう。だからてっきり私達の出征に付いてくるのかと思ってたけど、式典にいないとなると『アーミラの連れ』どころか神殿で留守番なのかも」
アーミラはそんなことを言われて驚く。そうか、ことによっては一緒に旅を同道する可能性もあったのか。そんなことを思うと、つい余計な期待をして、この場にあの無口な鎧は彷徨いてはいないのかと辺りを見回してしまうのであった。
「もしわしらが現れなかったなら、ガントールと鎧の二人が出向いたのかもしれんな。当代は三人揃ったのじゃから、彼奴の出る幕はない」
オロルの言葉にアーミラは密かに落胆し、今宵は更けていくのであった。
❖
夏夜雨が山肌を洗い、朝には雲が流れて暁の光が射す。麓に茂る下草の葉に揺れる鈴のような夜露は旭に煙り白く立ち昇る。背の高い針葉樹の足元がその靄に隠れて、霧の中からは木立の先が黒く姿を覗かせていた。神殿は朝から神妙な音色の鼓笛が鳴り響き厳かな行軍の律動が早朝から続いている。外郭の門の外には頭絡を付けた馬と幌車が静かに待機していた。出征式典二日目、まさにその締めくくりである継承者の前線出征の門出であった。
儀式の一切は滞りなく執り行われ、長い一仕事に区切りが付いたカムロが細く息を吐いた本殿の中庭では、継承者三柱が割れんばかりの拍手の中まさに背を向けて会場を後にするところだった。先頭は長女継承のガントール。神器を背剣して前線へ向けて歩きだす。その後ろに列をなして次女アーミラ、三女オロルと続き、その姿が本殿から見えなくなっても、拍手は止まなかった。前庭では石畳の通路の左右、玉砂利の上に神人種が並び、女神の姿を一目焼きつけようと総出で見送っている。ガントールからすれば最早この眼差しも慣れたもので、むしろこれが最後であるから体は軽い。人々の視線に笑みを返し、時折顔見知りの者と会っては激励の言葉を交わし合い堂々と進んでいく。
後ろに続くアーミラは対照的で、頭巾を目深に被り極力視線を避けていた。そのせいで先頭のガントールと間が開いてしまっていることに気付かず、オロルは「早く歩け」と小声で急かした。
親鳥の背をついてまわる雛のようなたどたどしさでアーミラは小走りにガントールの背に追いつき、急かした当の本人が今度は一人離れてしまったが、オロルはあからさまに歩調を早めはしなかった。悠然として、常に余裕を持ち、不敵に民草の視線を見つめ返す。三者三様の行進はこうして神殿の門をくぐる。
神殿を後にする最後の刹那、アーミラは背中の寒さを感じて振り返る。今更になってオロルが付いてきていないことに気付き、急かした癖にと不満げに唇を尖らせた。次にオロルの後ろ、本殿の向こうに立つ女神三柱の巨像を見た。
次女の像が始まりの日と同じようにこちらを射抜き、東雲から射す暁に灼けて半身がぼんやりと白く輝いていた。彫りの深い眼窩と筋の通った鼻柱によって光が遮られ、ちょうど顔の半分が陰となって蟠る闇の中から暗澹とした瞳がこちらを見つめている。光と闇、その両極の眼に見送られ、アーミラは改めて背筋が粟立つ理由を知ったのだった。
閉口して逃げ出すようにアーミラは神殿を旅立つ。拍手で見送る者達は彼女の青褪めた顔を見ることもなく、他人事のように行く末の安泰を願い、心持ち晴れやかに三々五々解散した。
ガントールは門の外に吹く山風に髪を踊らせて背伸びをすると振り返り、心労に曇るアーミラの頭を撫でた。
「おいおい、今日はこれからだぞ」
そんな言葉にアーミラは首肯する。巨像の視線が冠木に隠れて緊張が解けると、今度は心残りに後ろ髪を引かれるように何度も振り返っては視線を彷徨わせる。結局、鎧とは会えずじまいのままここを発つことになりそうだと落胆に眉を下げると後からやって来たオロルは口角を吊り上げる。
「馬で行くのか。馭者は誰かのう」
道道を己の脚で歩かなくて済むのは幸いだというが、それにしては脂下った笑みである。その視線はアーミラに向けられ、まるで『馭者を見ろ』と言わんばかり。アーミラはまさかと思い改めて手綱を握る者の姿へ視線を向ける。
そこにはウツロが待っていた。無感情な面鎧は相変わらず何も語ることはないが、片手には二頭の馬と繋がる綱を絡めて、もう片方の手は指を広げて馬の首を軽く叩いていた。これは感覚の鈍い馬にとって撫でられているよりも明確に伝わり、気持ちを落ち着かせることができる窘め方である。指を反らせるほど広げているのは、板金の隙間に毛が絡まないようにするための気遣いのようだ。金属製の手指は少し冷たいからか、馬は心なしか涼んだ目をして身を委ねていた。
「前線への導き手はこの忘れ形見か……因果よな」オロルは呟くと一人頷いた。
アーミラはこの旅にウツロが同行することに目を丸くしてしていたが、嬉しい誤算に口元が緩んだ。――嬉しい? ……と、自身がなぜこれほどまでにウツロに心を惹かれているのかを不思議に思う。これまでの道を共にしたからか、その者が人ではないからか、言葉を交わさないからか、理由を挙げようと思えばいくらでも出てくるが、正鵠を射抜くには至らなかった。
❖第二部❖
出征編
■005――修羅
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
――始まりは火だった。
人類は大地を焼く火を見つけた。
草木を燃し、躯を焦がす熱を畏れた。
人類は枝の先に火を灯した。
棲家へ運び、暫くすると熱に慣れた。
人類はいつしか火と共にあった。
火は光を齎し、闇と穢れを遠ざけた。
❖
道程は滞りなく進み、途中、マハルドヮグ山の中腹――国境の狭間にある神殿管轄の駅で馬を換えた。一行を乗せた幌車は揺れながら進み、日の傾く頃には卓状地に辿り着く。
一行は神殿を出発し、その日の内に三代目国家ムーンケイに到着した。
鎧は幌車を降りて宿の馬繋場に馬を停めた。後ろの幌からはぞろぞろと継承者たちが腰を曲げて降車する。ガントールにとっては数日前にも訪れた街並みであり、オロルにとっては期せずして蜻蛉返りの帰郷であった。目を輝かせながら街並みを眺めるのはアーミラだけだった。
今宵の旅程に辿り着いた宿は立派なものだった。その昔賢人種である三代目継承者が建国したというこの国の独特な宗教感が景色から醸し出されていた。この辺りで伐採される杉等の木材を利用した建築様式は古く、全体的な佇まいは寺院のような姿をしており、扁額に掘られた宿の文字には金の箔押しが施されて格式の高さを窺わせる。粘土質の土を焼成して瓦葺きにしている様は、神殿とは雰囲気ががらりと変わっていた。
屋敷の周りを囲う土壁は幾度も塗り重ねて補修した跡があり、絶えず下層から吹きすさぶ炉の熱風に煤けていた。番頭曰く、先代の継承者もこの宿で身を休めたという。そんな謳い文句を聞き流しながら、オロルは宿からの景色を眺める。上層から見下ろす島嶼部は変わらず西陽に翳っていた。金色に煌めく波間を暫く見つめ、興味が失せたようにオロルは踵を返す。一行は宿で身を休めるのは夜まで後回しにすると決めて、鈍った体をほぐしがてら目抜き通りへ向かった。
継承者出征の報せは既に国々に駆け巡りもはや知らぬ者はない。ごった返す人波は目も綾な正装に身を包んだ女神を前に緊張が走り色めき立つ。往来の激しいムーンケイの露店街で彼女達の周りだけは斥力が存在しているかのように人波が左右に開かれ、その背中を盗み見る視線だけが後に残る。アーミラは居心地悪そうにガントールの裾を掴み、そんな様子を流しみてオロルは鼻を鳴らした。本当にあれで戦えるのか……。
ざっと露店を一通り流し見て、ガントールはアーミラに対して申し訳なさそうに「武具が見たい」と言い出した。握っていた袖を離すと、首輪の外れた犬のように一目散に目当ての店へ向かってしまった。振り返ればいつの間にかオロルも人波の中へ消えている。己の気の向くままに目星をつけた露店へ向かったのだろう。あとに残されたアーミラは一度オロルの後を追おうとしたが人混みを掻き分けてまで探し回るのは気が引けた。ならばやはりガントールか、彼女なら獣人種であるため上背が頭一つ抜けている。とはいえアーミラ自身は武具に興味がない。ガントールもそれを知っているから袖を離すように促したのだろう。どうせなら魔鉱石を扱う露店を見てみたいとアーミラは思うが、知らぬ街の衆目に晒されては動けない。アーミラは悄気たように肩を落として宿へ向かう――と、その肩に触れる者がいた。
「……ウツロさん」
どこへ行くのかと言いたげなウツロに振り返り、見る間にアーミラの表情は華やぐ。
「い、一緒に……露店を見ませんか……?」
そんな誘いにウツロはもとより拒む理由はなく、無言で首肯するとそのまま手を引かれて露店の並ぶ目抜き通りを練り歩く。
街は当代継承者の出征に伴い、軒を連ねる露店は商売っ気もたっぷりに声を張り上げる。その心は継承者の目を引くことに尽きる。もし手にとってもらえたのならその商品は値が上がる。もしお眼鏡に叶って買ってもらえたのなら店自体に箔がつくというものだ。往来の激しい露天の通りには、声を枯らしてなお張り上げる客引きの威勢のいい言葉が飛び交う。ガントールやオロルならばいざ知らず、アーミラは怒涛の剣幕で気を惹こうとする客引きにかえって足が引けていた。
露店の商人と目が合わないよう彷徨わせた目線の先に、辺りの賑わいから隔絶された、やけに静かな一劃を見つけた。土の上に茣蓙が敷かれ、その上には朽ちた木の板。そこには、かすれた墨字で『魔鉱卸商』と記されている。しかしその佇まいは襤褸く、一見して乞食の寝床と思う者こそあれ、店だとみるのは難しい。茣蓙の上にせめてもの設えとして木の板を横に安置し、それを陳列台として魔鉱石を並べていた。悲しいかな、往来による泥はねで木の板さえも汚れてしまっている。その奥では店番か、あるいはやはりのたれ死んだ乞食か、茣蓙の上で少年が膝を抱えて丸くなっていた。
隣に並んだウツロはその露店を眺めたあとにアーミラに向かい首を傾げる。何やら言問顔か、アーミラはその無貌のなかに表情を読めるようになっていた。
「……魔鉱石を扱うお店ですよ。あなたもそれで動いているんですから、最低限の知識はありますよね」
アーミラはそう言いながらウツロの体を検める。そういえばこの鎧、嵌め込まれた魔鉱石がいやに少ない……それで足りるのだろうか?
ウツロはアーミラの問いには曖昧に頷いて、また露店に視線を向けた。察するに魔鉱石のことをあまり知らないようだ。どうせ他の店は人が溢れて近寄れないのだからと、アーミラはあえてこの店に近付いた。
「ここで魔石を買っていきましょうか」
恐る恐る近付いて、店とお揃いに襤褸を纏う少年を見下ろす。少年の方は眠っているのか、膝の間にがっくりと首を落して、短く刈った襟足から盆の窪を晒している。店は湿気た黴の臭いがして、アーミラは悟られないように呼吸を浅くした。いつかの自分もこんな腐臭を纏わせていたであろうことを思い出す。
後ろでは継承者を射止めそこねた露店の者が「あんな襤褸よりこっちゃ良いもん揃えてるよ」と妬み嫉みに陰口を叩いている。アーミラはむしろ意地になって少年に声をかける。
「あの、すみませんがここはやっているんですか……?」
アーミラが訊ねると、少年はぴくりと耳を動かして顔を上げ、しばらくして目の前の客が何者かを悟り目を点にして飛び起きた。耳は丸く、肌は黒い。賢人種だ。
「わ……や、やっとるがね!」
まさか継承者がこの店に立ち寄るなんて思いもしなかったのだろう。少年は上ずった声で陳列台越しにアーミラに向き合うと、雑嚢から魔鉱石を取り出して並べた。眠りこけているときも握りしめていた雑嚢だ、露店の店先にはおいそれと陳列できない上物ということだろう。対してアーミラはどう見るか、ウツロは反応を窺うように後ろから眺めている。
土埃と油のしみで汚れた雑嚢をひっくり返しばらばらと店先に並べられた鉱石を見て、アーミラは殊の外目を輝かせた。掘り出し物を期待してはいなかったが、寂れた店の割に品はきちんとしているではないか。
アーミラは喜色に緩んだ面持ちを今一度引き締めて首を振り、目の前の鉱石を一つ手にとってその真贋を矯めつ眇めつ確かめる。そして振り返らずに話し始める。
「ウツロさん見てください。質の良いものもあるじゃないですか」
後ろに立つ鎧は一歩距離を詰めて覗き込む。
――俺にはわからん。
「ちょっと、あなたの目、節穴ですか?」アーミラはウツロを振り返る。しかし、その無表情な面を見て、ふっと苦笑いした。「……本当に節穴でしたね」
ウツロは抗議することもなく一歩下がり、片目をつむって鉱石を見つめるアーミラの背中越しに立つ。
「これは魔鉱石の中でも紫水晶と呼ばれるものです。象嵌用加工が施されていない原石ですが、加工後はもっと硝子に似た透明な石になります。この店ではこれが一番高価かと……
あとは、酔いを防ぐ力があると言われていて、幻惑の呪いに強く、明晰を助けます……呪術向きの石ですね」
――石によって向き不向きがあるのか。
鎧はアーミラの背中に指を当てて問う。くねりと弧を描く最後の文字は疑問符を指先で描いたのだろう。
「ありますよ。すべての魔鉱石、すべての魔呪術にはそれを形作る物語があります。この紫水晶は明晰と夢現についての物語を宿しているんです。
とはいえ、不向きな術にも使うことはできますし、人によってはあまり気にしなかったり、ウツロさんのように向き不向きの知識を持たずに使う人もいます」
――詳しいな。
「そんなことは……ないです……」
ウツロに他意はなく皮肉のない言葉だったが、アーミラは狼狽えて否定した。
傍から見ればアーミラだけが独り言を呟き続けているようにしか見えない。露店に立つ少年は不思議そうに見上げながら、継承者の後ろに立つ鎧の声が聴こえているんだろうとなんとはなしに理解していた。そして、アーミラの話に「はぁ」と声を漏らした。
「おいら知らねかった。無理に使うと駄目なんか?」
少年は無邪気に首を傾げる。相手が子供だからか、それとも魔鉱石の話題だからか、アーミラは返答に言葉をつまらせることはなかった。
「駄目ということはありません。ただ、消費が激しいんです」
少年はまた「はぁ」と言う。相槌の癖なのだろう。「なら、知らねほうがいいな。たくさん使ってたくさん買ってってけ」そう言って歯抜けの顔で笑顔を向けた。アーミラは面食らったように一瞬肩をこわばらせたが、すぐに脱力し、相好を崩して頷いた。商売の駆け引きもなく買って行けと言う少年を前にして、警戒する気が失せたのだろう。この少年は数ある露店の中で唯一アーミラのお気に召したのだ。
「では、手持ちがある分はここで買わせてもらいましょうか」
アーミラの返答に少年は一旦は「毎度あり」と返したが、表情はとても嬉しそうだった。すぐにでも飛び上がりたいといった顔だ。対してウツロは水を指すようにアーミラの背中に指を伸ばす。
――手持ちは必要ない。継承者はその刻印を手形に借款できるだろう。
と、書いた。難しい言葉には意味を掴みかねたが、鎧が言いたいのは「継承者は金を払わなくてもいい」ということだ。これはアーミラにとっては無粋な横槍で、むくれた様子で答えた。
「知っていますけど……それじゃああの子、今日のご飯が食べられません」
アーミラの見立ては正しかった。
まず継承者の懐事情について。継承者は刻印を宿し、神殿で正式に出征を認められた時点であらゆる物資の調達は金銭の交換を伴わない。身元の保証は神殿持ちであり、刻印を提示して身分を証明できれば、借款契約が成立し、商人の手元に入るべき貨幣は後日神殿から補填される。しかし今、目の前にいる少年は見るからに日銭で口を糊する生活と見える。契約書では晩飯は買えない。神殿から補填される金が手元に届くまで餓えを凌げるかどうか。この少年がひもじい思いをするのはアーミラにとっても不本意であった。
――いくらあるんだ?
手形で買わないとなればアーミラの手持ちの金が問題だ。もとよりウツロは手元不如意である。アーミラは袈裟の内側にしまっていた巾着袋の縛りを解いて覗きこむ。掌に乗せた量感からしてそれなりにありそうだった。
「すべて銅粒ですが、合計なら金棒二本分には届くんじゃないですかね」
そういって「ほら」と巾着袋を開いてみせた。対してウツロは中を覗こうとはしなかった。アーミラにとってはナルトリポカで貯めたそれなりの額なのだが、ウツロには豚に真珠、貯金の苦労など理解がないのである。
……ここで貨幣制度についても説明しよう。
この世界に存在する物質は金属と非金属に大別され、うち金属は霊素に感応しないという特徴を持つ。魔呪術の影響を受けないというのは貨幣偽造の危険性を遠ざける利点であり、そのうち金銀銅を貨幣として流通し、現在では継承者が訪れているここ三代目国家ラーンマクが神殿のお膝元に造幣を担う。
価値は以下のようになる。
金版1=金棒5=金粒25
金粒1=銀板1=銀棒5=銀粒25
銀粒1=銅板1=銅棒5=銅粒25……
まず最も高価な貨幣は金であり、下に銀、銅と続く。
そして貨幣の形状も板、棒、粒の三種存在する。一つの板は平たく薄い四角形で縦と横に五等分の折り目を付けられている。これを折れば棒状態となり、棒を折れば粒となる。
銅粒1以下の価値を持つものは正式な売買契約とは認められず、隣人同士での物々交換として扱われる。
粒や棒は取り扱いがしやすく、アーミラのように巾着袋に入れて携帯するが、保管には板が好まれる。端数の支払いには板や棒を割ることで対応する。一度割った粒や棒は炉に溶かして再び板へ形成が可能である。再形成は造幣を担うラーンマクだけでなく、国から許可を得た鍛冶屋でも精錬できる。ちなみに再精錬の過程で貨幣は不純物が落とされ純度が増していくため、少しずつ小さくなる。
不純物の中に混じる金属は必然的に鍛冶屋の報酬となるが、法外な上澄みをくすねるぼったくりな鍛冶屋もいるため、見極めなければならない。
アーミラは尚も少年の店で石を選びながら、鎧を相手に薀蓄を語る。
「魔鉱石がそれぞれに由来する物語を持つというのは話しましたが、魔術陣を刻めば石に力を貯めておくこともできるんですよ」
――どういうことだ?
ウツロは素直に首を傾げる。まるで子供が親に教えを乞うようだった。アーミラは頭の中で言葉を組み立てると、説明を続けた。
「物語を補強するという感じです。……石に物語があるのと同じで、術者個人にも物語はあります――まあ、これまでの記憶とも言えますが――それを結びつけることで、固有の術式を構築するんです」
アーミラは「例えばこの石を使いましょう」と言って銅粒の詰まった巾着に指を差し入れて一つまみの貨幣を少年の手のひらに支払った。
「この石はごく単純な灯石です。神殿でも夜は燈されていたので知ってますよね」
この石にも物語があるのだと、アーミラは言う。人類が火を手に入れ、そして人と共に文明を開いた物語を、一言一句間違えることなく諳んじてみせた。
始まりは火だった。
人類は大地を焼く火を見つけた。
草木を燃し、躯を焦がす熱を畏れた。
人類は枝の先に火を灯した。
棲家へ運び、暫くすると熱に慣れた。
人類はいつしか火と共にあった。
火は光を齎し、闇と穢れを遠ざけた。
やがて人類は火を操るようになった。
それは森を拓く力となった。
やがて人類は文明を築くようになった。
火は炎となり魔術が生まれた。
魔術は文明と共にあった。
文明は光を齎した。
光は闇と共にあった――
「――これが灯石の物語。そして私には私の言葉があります。それを術として物語を構築すると、術式がこの石に保存されます。それ以降はいちいち唱えなくても、すぐに術式を行使することができるんですよ」
――呪文を刻んでおけば、唱える手間を省けると言うことか。
アーミラが満足そうに微笑んだのでウツロは首を傾げるのをやめた。
「そうです……だから、強い者ほど石を着飾ります」
「おい」
アーミラの言葉に被さるように、背後から不意に声がかかる。どきりとして巾着を握りしめ、アーミラは声の方に顔を向けると、そこにはオロルが立っていた。
絢爛豪華という言葉が似合う賢人の姿にアーミラはしばし呆然と見つめ、思わず笑みをこぼす。面の無い鎧でさえも、この場では愉快そうにオロルを見つめていた。
対してオロルは怪訝に眉をしかめて不満そうに「何を笑っておる」と言った。
継承者の正装にあらん限りの魔鉱石を縫い付け嵌め込み、耳に揺れる飾りにも玉に磨かれた宝石が輝く。つい先程の言葉……なるほど。
――強い者ほど着飾る、とはこういうことか。
「ええ、まさに」アーミラは可笑しくて口元を手で隠した。
背中や腕に触れて、筆書きのように指で筆談する鎧を見て、オロルは片眉を吊り上げた。この二人……いや、鎧の方は知らんが、アーミラは随分と心を開いたな。
❖
継承者一行はムーンケイの市井で武具と魔鉱石を買い集め、着々と前線へ向かう準備を整えていった。宿に戻り飯を食い、各々が部屋で身を休めていた夜半にアーミラの部屋から戸棚をひっくり返すような騒がしい音がする。壁を隔てて別部屋で眠ろうとしていたガントールとオロルはまたぞろ鈍遅を踏んだかとしばらく無視していたが、結局は重い腰を上げて何事かと様子を見に部屋を出た。廊下では、アーミラの部屋に繋がる引き戸の前で鎧が立っていた。
「何かあったか?」
ガントールがウツロに問うが、どうしたものかとウツロは視線を返すばかり。二人の様子を見ていたオロルは二人の間に割って入ると手のひらを差し出した。
「ここに書いてみよ」
琥珀を焦がしたような黒い肌。小さな手のひらには刻印が刻まれて余白が無い。しかしウツロの筆に墨は必要ない。冷たい金属の指先がオロルの肌に触れると、一文字ずつ言葉を書いていった。オロルはその運筆を目で追い、肌の感覚を研ぎ澄ませる。
――魔石、銅粒、惣而無而、曰盗人従闇来。
ふむ、とオロルは手のひらに記される文字を頭の中で紐解いていく。拙いものの一応は賢文の体をなしている。ウツロが伝えている内容は単純だ。『アーミラが買い揃えた魔鉱石と巾着の財布のすべてが無くなっていて、恐らく泥棒が宿に入ってきた』ということらしい。
オロルは理解すると同時に拍子抜けしたように肩を落とし眉を開く。ガントールも目で指を追っていたから会話は読み取れた。互いに目配せして困惑する。
「敵……じゃあないな」
「いや敵ではあるじゃろ。被害があるんじゃから」
「それで、ウツロはなんで扉の外で立ってるのさ?」
ガントールの問いに合わせてオロルがまた手のひらを差し出した。
「わし相手じゃからと賢文を使わんでよいぞ」
ウツロは頷くと簡単に答える。
――男は入るな、と。
「男って……まあ男か……いや、人じゃないんだから関係ないだろ。そもそも、ここ宿屋だぞ?」ガントールは呆れた顔で鎧を見る。
「どうせ散らかしておるのじゃろうて。まともに取り合う必要もない、入るぞ」
オロルは言うが早いか既に扉を開けて部屋に押し入る。しかし、予想に反して部屋の中は整然としていた。だが、妙だ。荷物を荒らされた形跡すらない。まるで最初から何もなかったかのように、ただ静まり返っていた。
先程まで仰々しく騒がしい物音を立てていたアーミラも居ない。がらんどうの部屋には唯一、杖が所在無げに部屋の一隅で倒れていた。大きな物音は恐らくこれが床に倒れて転がった音か、オロルは奇妙な状況に閉口する。
「盗まれたのはアーミラ本人とは言うまいな」と、オロル。
「泥棒じゃなくて人攫いだって言いたいのか? 流石にないだろう。ウツロとは呑気に話したんだから」
とは言いつつもガントールは怪訝な顔をして腕を組み、ならばどこに消えたのだろうと閉じ合わされた窓を開けてみる。木製の引き戸を横に滑らせると、外側に格子が嵌められていた。やはりここから出ていったわけではなさそうだと、ガントールはますます思考を巡らせる。不可解な状況にからりとした風が心地よい。ガントールはその窓を開けたままにした。
一方オロルは、とりあえずという風に床に転がった杖に手を伸ばす――
「ありました!」
――杖に嵌め込まれた水晶からアーミラが飛び出した。
二人の顔は鼻先が触れそうなほどに近く、オロルはほんの刹那に立ち位置を移動して不機嫌にアーミラを睨む。一方でアーミラの方はつんのめって杖の中に再び半身を沈み込ませた。
「……何をしておる」
オロルは手を掴みアーミラを引きずり出した。露骨に機嫌を損ねているが、アーミラの方は気付いていない。というよりも興奮しているようだった。
「あ、あったんです……! あの、杖の中……!」アーミラは左手に巾着、右手にオロルの腕を掴んで振っている。
「待て待て、状況について行けてないぞ」ガントールはますます困惑している。「なんで杖に飲み込まれてるんだ? 大丈夫なのか?」
「あ、はい、えと……」アーミラは我に返って説明をしようとするが、どこから話すべきなのか言葉がまとまらない。雛鳥のようにきょろきょろとするばかりだ。
「まず石は見つかったのか?」と、これはオロル。アーミラに掴まれた手を振りほどき、心なしか語気が冷やかである。
アーミラは夜鷹に睨まれた鼠のように口を横に引き結んでこくこくと首肯して答えると、次にオロルは「杖の水晶の中に入れるのか」と問う。アーミラはまた首肯した。
オロルはアーミラの扱い方を既に心得ているようだ。一度緊張してしまうとまるで喋れなくなるのだから、首を横に振るか縦に振るかで成立する質問で攻めたほうが早道だ。一から十まで説明させていてはきりがなかっただろう。
「へ、部屋が……ありました……! す、すごく、ひろい……です……!」
たどたどしく水晶から抜け出すとアーミラは正座をして杖を指差す。視線は未だ興奮している。オロルとガントールは互いを見やってどうするべきかを沙汰する。杖の水晶は両手で抱えるほどの巨大な魔鉱石の玉だが、まさか内部に空間があるとは……
「その部屋……とやらに失くしものがあったのか?」ガントールが改めて事の次第を確認する。「なんでそんなところにあったんだろう」
「に、荷物を……部屋の、隅にまとめていたんです……きっとそのときに……き、巾着が水晶に触れて、飲み込まれたと……思い、ます……」
「巾着の行方はよい。興味ないわ」突っぱねるようにオロルは言った。「杖の中にある部屋……わしらでも入れるのか?」
その言葉にガントールも同意した。泥棒だなんだという下らない話はもう解決した。目下三人が関心を示すのは次女に与えられた神器、杖の内にあるという部屋の存在だ。
「た、たぶん入れます……わ、私の、手を、に、握ってもらえますか……?」
アーミラは言いながら既に半身を杖に押し込み、蝸牛のような体勢で手を差し出した。ガントールもそれに応えてしっかりと握り合う。もう片方の手をオロルと繋ぎ、後は引き込むだけ。一度ウツロも招待すべきかとアーミラは引き戸の方に視線を向けたが姿がない。残念だが諦めて杖の中へ身を沈めていった。
硬質な光沢を放つ磨き抜かれた玉石が、今目の前でとろりとした液体のようにアーミラを包み飲み込んでいく。灯石の光が波打つ曲面にきらきらと反射して揺らめき、アーミラの藍鉄色の髪を照らしている。彼女の喉元が沈み、次に口、鼻が見えなくなるとオロルは自然と息を吸い、肺に空気をためた。アーミラの手に引き寄せられるまま肘、肩と水晶玉の中へ沈んでいく光景が未だに現実のものとは信じられない。そして水面が唇に触れた刹那には視界は一度光に白く焼け、抗えずに目を瞑る。
三人が消えた後に残された静寂と虚無の中、様子を見に来た鎧はもぬけの殻になった宿部屋に立ち尽くしていた。そして三人を探すような静かな足取りで部屋の中を歩き回り、杖を通り過ぎて窓の方へ向かう。ガントールがなんの気無しに開けた窓だ。
ウツロは窓の外が木枠と格子が嵌められていることを確認して、微かに首を傾げる。窓を閉めようとして、ある一点に目を向けた。
そこで彼の動きが止まる。まるで何かを見つけたかのように暫し無言で佇むと、踵を返して足早に宿を出ていった。
わずかな時の中に起きたすれ違いが、この時ばかりは悔やまれる。
❖
薄暗い空間が果てもなく続いている。茫漠たる空間にただぽつねんと扉が存在している。それは古びた木製の扉――今しがた潜った水晶の外側へと繋がっているのだろう――であり、出入り可能なことを知っているアーミラはさも当然と扉を閉める。オロルは一瞬だけ、二度と開かないのではないかという不安に襲われたが、顔には出さなかった。
壁や窓、天井もない空間を目の当たりにして、扉の周りには三人が所在無く互いを見合う。そうしていないと自分の位置が把握できないのだ。
見上げれば夜天のように闇が広がっているが、そこに星はない。足元を見れば、磨かれた石のような硬質な床が広がる。
無限にも思えるこの部屋は、部屋と呼ぶにはあまりにも際限がなく迂闊に扉から離れれば帰ってこれないように思えた。しかし、目が慣れると少し離れた所に背の低い書架があることに気付く。石垣か畑の畝のように一定の長さで途切れてはまた列になり、視界の果てまで伸びていた。結局、書架に沿って真っ直ぐ歩いたとしても果てはないのではないかと思わせられる。
「恐らくこの空間……、ないしこの部屋は穹窿の構造をしておるのじゃろう」オロルは言う。
その根拠は、書架の配置がこの扉を中心に放射状に広がっているかららしい。果ては暗く、確かめる術はないが、ここは杖の内部……水晶玉が球形ならば、内側の空間もまた円環を成すのではないか。ここが水平であるということは、天井は球体を上下に分割した上半球形状なのではないかと推測したのだ。
それを聞いたガントールは見えない穹窿の内側をなぞるように仰ぎ見て息を呑み、ぐるりと扉の方へ振り返って後ろへ回り込んだ。アーミラとオロルの視界から隠れる形になる。
先ほどアーミラが閉めたとおり、裏側もしっかりと閉じられていた。ガントールは好奇心から、おもむろに取っ手を掴んで扉を開ける。こちらからも外に繋がるのか、あるいは――
「おいアーミラ……これは?」
――ガントールはそう問いかけながら、内心では予感が当たっていたことを理解した。
同時に、アーミラとオロルから見ても不思議な事が起きているのがわかった。
開かれた扉の向こうに、ガントールの姿はない。
二人は慌てて扉の裏側へ回り込みガントールと合流する。表からは見えなくなっていたガントールはまだそこに居た。
そして裏から開いた扉の先、そこには下へ続く階段が続いていた。扉の表と裏、それぞれが異なる空間に繋がっているようだ。
「え……うわ……し、下があるんですね……」アーミラは思わず口元を抑える。「知りませんでした……何があるんでしょう……」
アーミラもこの先はまだ知らないようだ。
オロルは推測を立てる。
「……この場所が半球の上側であるならば、下側の半球も存在しているはずじゃな」
長い年月もの間、そこは誰ひとりとして踏み入れるものがいなかった世界だ――それはこの場所もそうなのだが……――それでもアーミラはこの階段を降りる勇気が湧いてこなかった。
ガントールが開き、そのままぽっかりと口を開けて待つ扉の向こう側は、螺旋を描く階段が下へ伸びている。
枝のように伸びた階段の手摺も艶は失せていてどうにも心許ない。細い支柱が段ごとに繋がっているが、体重をかけると折れて落下してしまいそうな繊細さがある。それと同時に、神器の内側の空間なのだから、この階段は絶対に壊れないような予感もある。
「行かんのか?」
オロルは焦れったくなってアーミラを急かす。好奇心に駆られたオロルは一人先陣を切るのも吝かではないという気持ちになっていた。それを知ってか知らずか、アーミラは後退りして先を譲った。
「では遠慮なく」
不敵な笑みを返し二人を置いて扉をくぐる。アーミラとガントールは階段に余計な重さを足してはいけないと考え、後には続かずオロルの声を待っている。
螺旋階段はオロルの想像していたよりもぐっと短かった。ぐるりと二周。それだけで地下の床を踏む。てっきり上階のように途方も無く広大な地下世界が広がっているとばかり考えていたので、それはそれで意表を突かれた形だった。
地下の空気は生温く、腐臭というよりはやや湿った黴臭さがあり、古書の類いを保管しているらしき匂いがした。オロルは無言のうちに呪文を唱え、着飾った外套に燐光を発生させると、ひとまず足元を照らすには十分だった。
光蟲のような淡い光を全身に纏うと、闇に覆われていた視界は微かに明瞭になる。辺りは階段を降りた際の風で舞い上がったのだろう塵や埃が光にきらきらと照らされて季節外れの舞雪のようだった。オロルは鼻を鳴らして手扇で埃を払ったが、余計にひどくなるばかり。顔を顰めると次に外套の襟を立てて鼻先を覆った。
一度螺旋階段の方を見上げ二人を呼ぼうかとオロルは考えたが、すぐに思いとどまった。光を灯した今、この部屋の狭さが理解できたからだ。
賢人種は他の種族よりも体格が小さい。大柄な獣人種と比べるなら成人であれば背丈身幅ともに倍は違う。そんな賢人のオロルでさえもこの部屋に受ける印象は手狭であった。
室内の左右に床から天井まで届く棚が壁のように囲い、手前に机、奥に寝所が見える。もともと夜目が利く質なオロルはざっと見渡して、この部屋の用途も理解した。
「……驚異の部屋。先代の潜窟か……おい! 姉共降りてよいぞ。狭いからアーミラが先に来い」
オロルの声を聴き、二人はそろそろと螺旋階段を降りてくる。ガントールは一番後ろをついて歩くのは性分ではないと不満を感じていたが、床板を踏む頃にはオロルの指示が正しかったと知る。天井は低く、膝を曲げて腰を落とさないと頭角がぶつかって引っかかる程だった。
「うひゃあ、窮屈だ」
ガントールが戯けて言うと、声に振り返ったアーミラが不意に口元を抑えてくつくつと笑いをこらえた。
「そんなに面白いか?」
「天井を見てください」そう言って上を指をさすアーミラはまだ口の端に笑みが残っている。
ガントールが促されるままに天井を見ると、二人の会話を聴いていたオロルが自身の魔力を強めた。蠟燭ほどの灯りは風に煽られるように揺らめくと篝火ほどに光量を増し、蟠る暗がりが押しのけられた天井には蛞蝓が這った跡のように二条の線が引かれている。アーミラはそれを見て笑ったのだとはガントールは理解したが、それが何故面白いのかはわからなかった。
「なるほどのぅ」と、オロルまで口の端を吊り上げる。ガントールはさらに視線を天井に注ぐ。
よく見てみると、ときおり格子状に材木が組まれているところでは傷が付いていた。二条の線と同じように二箇所、何かがぶつかり、擦れたようにささくれている。ガントールはそこでやっと意味がわかった。
「……私の先代も、難儀したんだな」
この条痕は先代長女継承者が遺したものだ。ガントールと同じく天を衝くほどの身丈だったのだろう。二条の線は頭角が天井板に擦れた跡だ。身を屈めてもなお格子部に角をぶつけていたその情景が、この痕跡からありありと見て取れる。さらによく観察すると、条痕は部屋の入口付近だけでなく、天井のあちこちに刻まれていた。アーミラが笑ったのは、先代長女継承者がそんな風に角を引きずりながら部屋を歩き回る姿を想像したからだった。
「……この部屋も上階も、整理したら使えそうですね」アーミラは言うが、その顔は既に心を決めている。
「先代も好き勝手に使い倒したのじゃろうて、棚に飾っておるのも大概の値打ちものと見える……というより、二百年前のものがこうして現存しておればどんなものも貴重か」
二人はこの部屋の価値を推し量り満足そうにしているが、ガントールは窮屈な部屋に早くも辟易している様子。螺旋階段の欄干に持たれながら身を低くしている。埃の薄く積もっている現状では先代のように天井に角を擦って歩き回る気にはなれないらしく、階段に片足を乗せている様は戻りたい気持ちの表れだった。
「値打ちっていっても私達は金持ちになる意味がないし、魔呪術を学ぶための部屋なら二人が好きに使いなよ」
「言われずともそうさせてもらう。この驚異の部屋はいい拾い物じゃな」
平然とオロルは言うが、そもそも見つけたのはアーミラの手柄。二人のものとするのは少々不満であった。私が継承した神器なのに。
「わ、私は、今晩ここで過ごしますので……」
ガントールが階段を三段ほど昇り、オロルも後に続いて手摺を掴んだ時、アーミラはこの部屋に残ると言った。彼女なりの所有権の主張であることはオロルなりに理解したが、とはいえおとなしくその線引に従う質ではない。
「ならば掃除しておけ。明日から使えるようにのう」
莞爾りと笑って嫌味を返すと、気弱な姉を地下に残してオロルは階段を上がっていった。押し出されるようにして姿が見えなくなったガントールが「ウツロには伝えておくよ」と言い残して、後にはしんとした無音が耳を襲った。
隔絶された杖の中。アーミラはオロルの不遜な態度に機嫌を損ねながらも、気を取り直して自室となるこの部屋の整理を始めた。オロルの図々しさはどうやら生来のもののようだ。ならばむしろ、この一夜で先に唾を付けて自分都合で整理してしまえばいいのだ。私だけの自室を整えてささやかながら領有権を主張しようと、アーミラは考えた。
もとより杖は次女の継承した神器、優位性は揺らがない。そうと決まればまずは手近の灯檠の灯石を新しいものに取り替え、アーミラは部屋を照らした。どうやらオロルの言うとおりここは驚異の部屋に相違ないようだ。
「まるで小さな神殿ですね……」
石を交換し終えて灯檠の明かりが広がると、目の前の棚に収められた無数の品々が露わになった。骸骨、古文書、奇妙な形の鉱石、未知の動物の剥製……どれも見たことのないものばかりだ。硝子瓶に保管された得体のしれない薬液の類いに、所狭しと床に転がる物品でさえもどれほどの価値があるのかわからない。
アーミラはその一つをそっと手に取る。……こんなもの、どこで集めたのだろう。
彼女の脳裏に、かつて読んだ本の一節がよぎる。
『驚異の部屋――それは魔呪術師が己の知識を誇示するための陳列室』
アーミラは唇を引き結んだ。
――……ここは、ただの物置じゃない。
魔呪術師の叡智の証――そう思うと、この部屋が途端に特別なものに思えた。
アーミラは、これは骨が折れるとうんざりしながら、一方でこの部屋に居心地の良さを感じていた。外界と違い、この部屋には生物の気配がない。埃こそ溜まっているが蜘蛛の巣は無く、おそらく先代は虫や生き物を中へ招きはしなかったのだろう。この部屋にはどこまでも静謐な時が流れ、この場にいる一時だけは肩の荷を下ろすように緊張を解いていられた。
❖
「あれ……いない」
驚異の部屋から抜け出したガントールとオロルは、アーミラの宿部屋を出てウツロに伝言をつたえようと廊下を見回すが、姿が見えない。
「奴は外にでも行ったんじゃろ」オロルは興味なさげに言い捨てると、早々に自室へと戻った。取り残されたガントールは逡巡の末にさほど気に留めず、こちらもまた部屋へと戻る。
この時ウツロは単身でナルトリポカへ向かっていた。
眠れぬ夜を彷徨くため……ではなかった。アーミラの部屋の様子を窺い、継承者達が忽然と消えたため探して回っている……というわけでもない。
ウツロは単身、不吉の予兆を認めこの夜を駆け出した。距離にして片道三刻程、マハルドヮグ山を登らず横断する道であるため、ウツロが急げばもっと速い。
問題は、その地に起きている異変であった。
❖
マハルドヮグの山野を濯ぐ夜雨の雲が南に流れ、二代目国家ナルトリポカには今宵もじっとりとした風に冷たい粒が混じる。湿った土の匂いが立ち昇り草叢に潜む虫たちは初夏に先んじて銘々に翅を鳴らしていた。そして夜闇を覆う重たい天幕の下、風情をかき消す火柱の猛る喧騒があった。
集落が燃えている。
収穫を待つ畑も、石積の家々も、一切が火の海だった。
割れた窓枠や扉は既に炭となり、内部で燃え盛る火がもうもうと黒い煙を噴いている。
灼けた石材が熱に爆ぜると、一帯の虫は身の危険を感じたか鳴りを潜めて夜を明け渡した。
今や集落は見る影もなく、激しい熱波と荒れ狂う焔……本来あったはずの平穏な夜が壊されてしまったのだ。
ごうごうと燃焼する音が響き、目も開けられないほどに黒煙が充満し始めた。これだけ大きな火柱が夜闇に立ち昇るのだから大変な騒ぎになる筈であるが、集落の者達はもっと様子がおかしいのである。赤く照らされた道を歩く人影は乱れがなく、誰も声を上げず、騒ぎ立てる者もない。まるでこの火が見えていないかのように畦道や家の周りを列をなして徘徊していた。……例え火がなくとも、こんな夜半に人が列をなして歩くのは異様である。
その者たちは皆、胡乱な目をして魚尾は赤く腫れ、涙が岩清水のように流れて煤けた頬に筋を残している。半開きになった口は熱風に焼けて唇がひび割れている者もいた。微かに覗く舌も白く渇いて萎びている。
それなのに、誰一人として目を拭うこともなく、唇を湿すこともない。みな感情が抜け落ちたような有様で、誰が先頭に立つか申し合わせるでもなくふらふらと道なりに合流し列をなす――この集落の者達は皆、呪術により体を操られていた。
贄を欲する業火のように遠慮のない火勢が風に煽られ鼻先を炙り髪を焦がす。ある者は火の粉が服に移り、肩口から燃え広がって肌を焼いているというのに火傷を気にする素振りがない。畦道には夥しいほどの血の足跡が残されている。焼けた石を踏み、足の裏の皮が剥がれたのだろう。あるいは割れた硝子を踏んだ者もいるに違いない。彼らは血を流し、火達磨になりながら歩き続け、呼吸が出来なくなると静かに路肩に倒れる。その火は草叢を経由して民家を燃やした。
人が死に、列に隙間ができると後続は距離を詰めた。
己を葬る火葬場へと、葬列の歩みは淀みがなかった。
篠突く雨が振り始めたが、火の勢いが衰える様子はない。
人々は合流を繰り返し長いながい列となって広場にたどり着くと、その中央で燃え盛る炎を囲むように先頭がぐるりと列の最後尾へ繋がり、尾を噛む蛇のように輪を描いた。
輪の中心となった炎は魔力を高めて空へ伸びる火柱となり、その蛇は蜷局を巻き、怒り狂う火勢となった。……その隣、聖火を守る司祭のように悠然と立つ男は、揺らめく炎にぎらぎらと照らされ、歪んだ笑みで号令を飛ばした。
「一人ずつ火の中へ入れ!」
胡乱な表情の人々、その瞳の中に声にならない断末魔の叫びが映る。
❖
「おっと、失礼」
畦道の途中で足を止めていたハラヴァンは、ふと自分の後ろで人が立ち往生していることに気付き、道を譲った。
「覚束ない足取りでハラヴァンの前を横切った者は、意識があるのかも定かでない。挨拶もなく、そのまま燃え盛る集落の中へと消えていった。ハラヴァンはその列を見送って、再び道の真ん中に立ち、教会堂跡へ視線を戻す。
右を見ても左を見ても家屋からは火の手が上がり、肺を焼く煤混じりの熱波が木酢の臭気と火の粉を舞い上げ吹き荒ぶ。とうの昔に焼け落ちていた教会堂の跡地はこの集落で唯一延焼を免れているため、ハラヴァンはこの夜をここでやり過ごしていたのだ。
風の中に、火の粉とは異なる燐光がひらりと舞い、羽虫のように浮かんでは消えていく。それはこの地に満ちる魔力の奔流が、可視化されたものだった。ハラヴァンは気怠そうに肩を落とし、まだしばらくこの火事は収まらないと悟った。
「はやく、終わらせてもらいたいものですねぇ……」
一人呟き、徐に畦道から家屋の近くへ歩み寄ると絶命に怯える赤子の泣き声がくぐもって壁越しに聴こえてくる。火の気の音以外にはなにも聞こえない静かで異様な夜にあって、赤子の張り上げる破鐘のような声ははっきりと耳に届く。……だからといって助ける素振りはなく、ハラヴァンは通り過ぎていく。
人々には炎が見えず、彼には声が届かない。
ざあざあと篠突く雨と、炎に爆ぜる家屋の断続的な音だけが一帯に響いていた。立ち昇る濡れた土の匂い、熱の香りには髪や爪、腸が炙られる強烈な臭気が混じってきた。その臭いに釣られて野獣が炎を傍目から窺っている。今はまだ火を恐れて林の影に潜んでいるが、一夜明ければこの雨が火を消し、残った屍肉を喰い漁るだろう。
気付けば赤子の声が止んでいる。
ハラヴァンは無感動な顔をして歩いている。
その目の前、集落の中程に開けた場所がある。当時は広場だったのだろうそこが火の海となる前、異変に気付いた者たちはここで身を寄せ合っていた。
今、この場は火柱が上がっている。一度はみな蜘蛛の子を散らすように広場から離れ、ある者は己の家に錠をかけ閉じ籠もり、ある者は追手から逃れるために森へ逃げた。いずれにしても結末は変わらず、身体を操られこの場に列を成し、火を囲んでぐるりと大きな輪を描くと、声も挙げずに自ら火の中へ投身していく。
「ダラク……まだなのですか?」
ハラヴァンは炎の側に立つ男――ダラクに問いかける。
彼は髪を掻き上げた。あらわになった彫りの浅い額と薄い眉、双眸は鋭く吊り上がり、人相は粗暴である。そして額には細く枝分かれした頭角が左右不揃いに生え伸びていて、虫の触覚のようだった。口元は愉快そうに歯を覗かせてハラヴァンに視線を返す。
ダラクの足元には二人の男女が転がっていた。苦しそうに呻いているが、集落にいた人達とは違い、表情には意志があった。
「少々手間取っちまってな。畑ってのは存外湿気って燃えにくい。それに臭い。そのうえ何故だか此奴等だけ――」
ダラクは地べたに転がる二人のうち男の方を容赦なく蹴飛ばした。男は既に瀕死の様子で痛みにうめきながらも身をかばうこともできずその場からごろりと裏返るようにして転がる。
「――呪術が効かねぇんだ」
男は仰向けに倒れ口から血を吐き咳いた。苦悶に歪む表情に力が抜け、呼吸が弱まる。側にいた女はふうふうと荒く息をついて腹這いで両手を引きずり男のそばへ這い寄る。ハラヴァンはその姿を見て二人が両手足の骨を折られていると悟った。女は男の身をかばうように上から覆い被さり、ダラクの方を睨みつける。が、ダラクは女の前でしゃがみ込むと、懐から切り出し刀を取り出して首に突き立てた。鋒が女の首に刺さり、小さな傷口から細く血が流れ始めた。
「……先に手前から殺そうか……なぁおい」
その目を見れば理解る。この男は、まるで家畜を屠殺するかのように迷いも葛藤もなく人を殺せる。
女は泣きながら、折れた両足をばたつかせながら芋虫のように身をくねらせてダラクから逃げようとする。本当は男の側に寄り添いたいのに、逃げなければ殺されてしまう。恐怖、混乱、葛藤は綯い交ぜになって、女は地べたを這い回ることしか出来ない。腕も脚も、関節が増えたようにくねくねと体についてまわり、四肢自体が枷となってしまっていた。わずか一寸を進むのにも、耐え難い激痛に苛まれる。
「はっ、誘ってんのか? なぁよ。どこまで逃げられるかな? ほら、ほら」
ダラクは女を責め立てるように、わざと緩慢な歩幅で追いかける。歩くよりも遅いくらいだが、腹這いで逃げる女には振り返る余裕がなく、絶望の中を進み続ける。
「死にたく……い……じに、たくない……」
「怖いか? お前も、あの男も、術に掛かっておけば楽に死ねたのになあ」ダラクは凶暴な人相を愉悦に歪めて言う。
女は長い時間をかけ、僅か十数歩分の距離を進んだ。眼の前には檻のように人の列が行き先を阻む。輪になった人々は女に気付いてはくれず、緩慢な足取りで道を開けてはくれない。
ダラクが女に追いつき、引きずっている裸足の土踏まずを踏みつけた。腱が伸びて割れた骨が肉にくい込み激痛が走り、女はたまらず呻き声を洩らす。ダラクはもう一歩踏み込み女の服の裾を踏むと、身を屈めて髪を乱雑に掴み上げた。弓なりに背をそらされて首を晒す。掻っ切られるかと怯える女に耳元で囁く。
「……お前は最後だって決めてんだ。男を先に殺す。そこで見てろ」
ダラクは女の顎先を掴み凄んだ。殺気に満ちた視線を前に女は睨み返す勇気さえ失われていた。
男を助けることも、自身が助かる見込みがないことも理解して、目に涙が溢れる。ダラクは女の顔を横へ投げるように押し倒すと、女は思わず折れた腕で受け身を取り前腕中程からぐにゃりと折れて唇を噛む。肉の内側で血が溜まっているらしく、白い細腕が痛々しい紫色に腫れ上がっていた。
「泣き出したい気持ちを押し殺し、女は必死に男の元へ這い寄ろうとする。しかし、ダラクはすでに大股で歩み寄り、男の上に馬乗りになっていた。躊躇いもなく男の心臓目掛けて切り出しを右手に握り、柄の底部を左の手のひらで抑えると一息に刃を沈み込ませる。
「あぁぁっ……! アダン!! ……嫌……嫌ぁ……っ!」
眼の前の凄惨な光景に耐えきれず、シーナは絹を割いたような悲鳴を上げる。お願い……誰か……助けて……!
息もできないほどに声を振り絞り、女は滂沱の涙を流す。膝をつき、目を閉じ、必死の祈りを捧げるしかできなかった。
そして祈りは届いたのだ。
凶刃が振り下ろされ、アダンの胸に沈み込む既のところで青い光が行く手を阻む。ダラクは反発する力に負けじと腕に力を込める。呪術が効かなかった二人だ。何かしらの加護を受けていることは予想できていた。
ダラクは力むほどに口角を吊り上げて、笑みは凶暴性を増していく。刃は結界の光とぶつかり合い、まるで湧き水に栓をしようと奮闘しているようだった。刃先は紙一重で届かず、びくともしない。顳顬に一筋の汗が流れる。
キシ――
と、不意に聴き慣れない物音がしてダラクは笑みを消した。厳しく周囲を伺う。
「遊んでいるせいですよ。敵が来てしまいました」
ハラヴァンは既に剣呑な面持ちで音のなった方へ構えた。外套の内側に手を差し込み、今度は勢いよくその手を振り抜く。針を投げつけたか、細く火柱の明かりを反射して炎の中へ飛んでいくと、倒壊した家屋の火の海から円を描く閃きが針を弾いた。
焔に包まれても灼ける心配のない者……殺意も気配も持ち合わせない存在が、ここに来ている。そんな敵に心当たりは一つしかない。
ハラヴァンとダラクは確信した。
「鎧だ!」
「頭巾で顔を隠しなさい」
二人の声はほぼ同時、ハラヴァンの方は言いながら頭巾を目深に被っている。生きてこの場を離れるなら、顔を見られてはならない。ダラクはそんな指示も無視して女の髪を掴み首元に刃を立てる。それを咎めるようにウツロは炎の中から長槍を投げた!
一息に刃を走らせんとするダラクの右肩を目掛けて、火を纏う槍は突き進む。一瞬は引き伸ばされ、この刹那に勝負が決まろうとしている。二人の駆け引きをよそにハラヴァンは広場の物陰まで下がっていた。ダラクに迫る危機に対して既に逃避行動をとっており、彼のことを迷うことなく切り捨てる判断である。
女が首を切られるのが先か、ダラクの腕が落ちるのが先か……
「な……んで……っ」
ぞぶりと皮膚を裂きながら刃の先端が肉に沈み込む――はずだった。ダラクの心のなかでは女の首に刃を走らせ、肉が鮮やかな断面を晒し、少し遅れて真紅が吹き出す光景がありありと想像できていた。
だが、切り出しは女の首を掻き切ることはなく、これまた紙一重の輪郭をなぞり青い光が火花を迸らせる。微かな希望の兆しに女の瞳から生気が宿る。あの鎧は見たことがある……助けが来た……!
しかし、命の危機は未だ喉元にある。
ウツロが投げた長槍は、あの時確かにダラクへ届くはずだった。女の首を斬るより先、その肩に突き刺さり、腕を切り落とす軌道にあったのだが、寸前で横薙ぎに払われた。ダラクでもハラヴァンでもない何者かが阻んだのだ。
両者ともに命を奪うこと叶わず、状況は振り出しに戻された。
ウツロの槍を叩き落とした三人目の敵。最も異質な存在が立ちはだかる。
「――なんなの? こいつ」
黒煙吐き出し燃ゆる集落の一劃、そこには一夜にして悪鬼羅刹の如き無惨な殺生を行うダラクがいた。今にも消え入りそうな二人の命を救うため、ウツロが放った乾坤一擲は疾風に薙ぎ払われてしまった。
今、ウツロの前に立ちはだかるのは年端も行かない少女だった。
薄布を纏い、その上に頭巾で顔を覆う。頭巾の裾は短く、下肢は薄布が申し訳程度に垂れるのみ。臀から伸びる長く靭やかな尾は、長さは身の丈を超え、己の腕より自在である。
「助かりましたよ。……ご覧なさい。あれが虚ですよ」
「ふぅん……」
戦況は三対一。ハラヴァンは敵側の増援を警戒しながらも勝機を窺い退避をやめた。
ウツロは女を救うために賭けた長槍の投擲は叶わず、今は得物を失って丸腰である。
「……へぇ。……黒くて、無口ね……」
ニァルミドゥは鎧から視線を外すことなく応え、両者は暫く睨み合い互いの力量を推し量る。
❖
「長居は無用ですね……退きましょう」ハラヴァンは言う。
「はぁい」間延びした返事で応えるもニァルミドゥはすぐには歩き出さなかった。目の前には頑として二人を護る鎧の姿があった。
三人の攻撃を全て凌ぎ、何も語らず両手を広げる鎧の姿。
その向こう、女は首を切られることなく生きていた。
四肢は折れて腫れ上がり、朦朧とした意識で這いつくばい、痛みさえ感じなくなった体で少しずつ、少しずつ、男のもとへ這っていた。男の方は気を失っているが、まだ息がある。
「守り抜いたってわけだ」ニァルミドゥは吐き捨てるように言い、何度目かの攻撃を試みた。
尾を真横に振り抜き、その先端は空気を切り裂くほどの速さに達している。最高速度で鎧の首を叩くが、堅牢な腕甲で弾き衝撃を受け流した。その上、鎧はあくまで二人の死守を優先している。埒が明かないほど鉄壁だと、ニァルミドゥもハラヴァンの判断を理解できた。
長引けば継承者がここに来てしまう可能性もある。
今撤退すれば鎧は追いかけることはないだろう。
「つまんないね」ニァルミドゥは呟き、ハラヴァンの後ろについて行った。
その道中、焦げ付いて煙を吐く瓦礫を通りしなに尾で弾き飛ばす。鞭のように靭やかで脅威的な膂力の尾は、狙い澄ましたように一点を目掛けて迫る。鎧の顔面だ。
硬いもの同士が衝突して盛大に弾け砕ける音がした。砕けた石材が跳弾し、がらがらと毀たれた家屋の焼跡が土煙と火の粉を巻き上げ崩れ落ちる。
「あいつはあのままでいいの? 死んでないじゃん」
ニァルミドゥの問いにハラヴァンは首を振る。
「あの鎧は死なないのです。……というよりもともと生きていないというのが正しいのですかね……
ともかく焼くべきものは焼きました」
「あ、そ」不機嫌そうに言い、「集落の生き残り二人は」と言う。
「顔を見られてしまいました……なんの加護を受けているのかわかりませんが、仕留め損ねたダラクには責任を取ってもらいましょう……」
「そのダラクはどっかいってるけど……」
「次の指示を与えています」
ハラヴァンはどうということもなく言うが、手回しの速さにニァルミドゥは絶句する。任務で不手際があれば蜥蜴の尻尾切りだ。ダラクとは二度と会うこともないのだろう。
そんな風に沈思しているニァルミドゥの横でハラヴァンは呟く。
「……やはり、貴女は素晴らしいですよ」
「なにが?」
「ふふ……器としての素質です……」
ハラヴァンの言葉の意味を掴みかねたニァルミドゥは、片眉を吊り上げて言問顔をしたが、踏み込みすぎれば己の命数も減るような気がして、誤魔化すように尾を気まぐれに踊らせてみせた。返事を求めていないと言外に示すように。
まるで生まれたときから備わっていたかのような、臀から伸びた尾を自在に操る少女。ハラヴァンは静かに目を細める。その笑みは満足気であると同時、どこかほくそ笑むような厭世的な色を見せていた。
❖
一夜明け、継承者三名は前線へ向けて出発するはずだった。
ムーンケイで迎えた朝は暑く、夜通し熱の下がることのない鎔鉱炉は国一帯の気温を底上げしていた。ガントールは寝間着にじっとりと寝汗を掻き、喉の渇きに負けて重い体を起こす。部屋の窓辺に向かうと錠を外して隙間を開け、蒸した空気に風を通した。歪んだ硝子越しに外の様子を眺めては、山向こうの稜線に朝日が顔を覗かせているのを見つめた。
藍色の空に千切れた薄雲が黄金色に染まっている。暑い一日になりそうだとガントールは天気を読み、そして遠景にふと目を凝らす。
朝霧か……いや違う。
宿の窓辺から見下ろす下層の景色からさらに向こう、マハルドヮグ山の渓間沿いを下った地帯――あそこはナルトリポカか――に、濁ったように濃い霧が滞留している。一度は朝霧かと思ったが、ただの霧ならもっと広範囲に薄く広がっているはずだ。これは局所的に蟠っている。……なにか変だ。
ガントールは昨晩の記憶を辿る。確かアーミラの部屋へ行ったとき、私は窓の外を見たはずだ……あの時も窓外の景色は赤かった。当然だ。街全体が溶鉱炉を常時稼働させているのだから明るいからさして気に留めなかったが、こうして閑散とした朝の山を見れば、黒煙の出処はムーンケイではないぞ……。
にわかに肌が総毛立ち、ガントールは直感で不穏を悟ると隣の部屋へ飛び出して扉を叩く。
「オロル! 起きてるか!」
「起きとるよ……朝からなんじゃい」
返事はすぐに返ってきた。ガントールは扉に錠が掛かっていないと知ると許可もなく身を差し入れ、まだ寝台の上で目を擦っているオロルに駆け寄る。肌着を着ていないオロルは慌てて布をかき寄せて肌を隠す。
「おい、勝手に――!」
「そこの窓からも見えるはずだ、あれは何だかわかるか?」
ガントールの剣呑な顔に事情を掬したオロルは言いかけた言葉を呑み込み、黙って掛け布を肩から被って前合わせに全身を包んだ。そうして寝台から降りるとガントールが今開け放った窓の向こう、渓間に澱む煙を見る。
「……昨夜に騒ぎはあったか……? ナルトリポカからここでは報せが届くじゃろう」
「騒ぎはないが、昨晩窓の外が赤かったのを見たよ。その時は対して気にも留めなかったんだけど……あの煙はなんだろう」
「なんだろうもなにも火事じゃろうが。お主にはあれが朝霧かなにかに見えるのか?」
オロルの言葉にガントールはまさかと首を振る。あそこでなにか起きているからこそ、わざわざオロルのもとへ駆けつけたのだ。
当然そんなガントールの考えは百も承知で、オロルだって本気で莫迦にしている訳ではない。敵にしてやられた……そんな憤りが気を立たせているのだ。
「寝ずの番はウツロが務めると言っていたが、ウツロはどうした?」
「……見てない」
ガントールは言いながら、既に顔面は蒼白。
オロルオロルの胸中に、確信めいたものが芽生えた。不注意から起きた小火騒ぎではなく、敵の悪意による凶行と見たのだ。おそらく火が放たれたのは夜の底、ムーンケイにからは夜闇と山陰に紛れて異変に気付く事はできないことも敵は織り込み済みなのだろう。
それが朝になり火が燻ると一帯の塵が空気中の湿気と混ざり合って白煙を蟠らせた。すでに敵は逃げ果せているという算段だ。
ここからの距離でもそれなりの広範囲が煙の中に沈んでいることから、被害の規模は相当に大きい。……自分の身ばかり警戒していたが、まさかここまで搦め手で来るとは……油断したと認めるしかない。
オロルが眉間に皺を寄せ、窓外を睨む視線の下、宿の正面に続く通りに人影が映る。
軋んだ足音を鳴らして歩く鎧を見つけた。ガントールは怪訝な顔をして窓の格子に口を近づけると声を張り上げた。
「おぉい、どこに行ってたんだ?」
鎧は歩を止めて、ガントールを見上げた。そして垂らした両手を力なく広げて、また脱力した。おそらくは肩をすくめた身振りなのだろうが、二人が意識を向けたのはウツロの右手に握られた得物、それは柄を失って小刀のようになってしまっているが長槍である。槍頭の刃はひどく毀れており、一目見て明らかな戦闘の形跡を残していた。
オロルとガントールはこの有様をナルトリポカの野火と繋げて、ほぼ間違いなく何かが起きていたことを悟ったのであった。
❖
同日、継承者三名は前線へ向かう予定を取りやめ、宿部屋の中に膝を寄せていた。より厳密に言えば次女継承者の神器、驚異の部屋に集まっていた。
ことの始まり、夜の異変に気付いたのはウツロ一人だった。
当時、ウツロは杖の中に姿を消した三人とすれ違うようにしてアーミラの部屋に入り、窓が開いていることに気付く。しかし、窓には格子が嵌められており、人が通る隙間はない。どこへ消えたか首を傾げて窓外を眺めれば、微かな異変を認め外へ向かった。
所詮は遠景の野火であると異変を侮り伝言も残さず一人で向かい、そして今に至るというのがことの顛末である。
己の命は己持ち。しかし継承者としての自覚は甘く、油断はないと言いながらそれぞれが慢心していた出征初日の夜の悲劇。
互いを糾弾するには己の不覚が身に刺さる。ウツロの書き記す事のあらましを殊更に青褪めて目を走らせていたのはアーミラだった。
「……あの……ふたりは……」
声が震えている。安否を問う二人とはつまり、アーミラの育ての親を指していることは明白である。
ウツロは筆談でのやり取りのため、ここまでずっと文机に視線を落としていたが、紙面から筆を離しアーミラの縋るような視線に対すると手を止めた。最悪の事態を想定していたオロルとガントールは苦々しげに口を引き結んだが、ウツロは目をそらさない。
ぱた、と止めた手に握る筆先から墨が落ちて紙面を汚した。
――息はある。しかし手足の骨を折られ、運ぶ布の調達も出来ずにいる。
ウツロは一息に筆を走らせると、堰を切ったように筆を走らせる。言葉をまとめ終えたようだ。
――狼煙を上げはしたが、一帯の煙に紛れてしまい意味を成さなかったので急ぎこの場に合流した。
――二人は何らかの加護を受けている。手当ては行い多少の猶予はあると見ているが、それでも急ぎ救護を望む。
これは大手柄。オロルは素直に胸を撫で下ろす。
「まだ……助かる……! すぐに行きましょう」
立ち上がるアーミラの声は怒気を孕む。
そのまま駆け出して行きそうな彼女をガントールは呼び止めた。
「待て」
気ばかり急いては事を仕損じる。ガントールは文机の前に胡座をかいたまま深く息を吸い、口を開く。
「……全員は行けない」
「でも!」
「アーミラ、気持ちは解る。だけど全員でナルトリポカに行くのは無駄だ。それこそ敵の目的が足止めだったらどうする? 誘き寄せる罠だとしたらどうする?
何より、私達は継承者だ。一刻も早く前線に向かわなければならない使命なんだよ」
その言葉にアーミラは閉口した。進むべきだというガントールの言い分は正しい。ここで全員がナルトリポカへ舵を切れば、この先もずっと敵の後手に回ることになる。
なら、誰がナルトリポカへ向かい、誰が先へ進むかを決めなければ……そう理解した時にはオロルが手を挙げていた。
「――わしがナルトリポカへ行こう」
「え……?」
まさかの提言にアーミラは目を開きオロルを見る。これまで冷淡な態度を見せていた三女継承者はガントールとともに前線へ進むだろうと考えていたので、そんなことを言い出すとは望外のことだった。
「その心は」ガントールは困惑気味に問う。
「簡単なことじゃよ」オロルは言う。「二手に分かれるならアーミラとわしがナルトリポカに。お主はウツロと共に前線へ急げ」
「ウツロと二人で先に行けと? 前線に近付くほど危険なんだぞ」
「もはや『内地なら安全』、とも言えんじゃろうて。ナルトリポカを焼いた奴らは頭巾で顔を隠していたと聞く。敵の内通者か、間諜か、結界をやり過ごして内地に入り込んだ禍人の可能性も高い。わしらが下がる理由は十分にある」
「人員分けの理由はなんだ?」
「まだ助けられる命があるなら、呪術による治癒術式は必須じゃ。そして二人を神殿なり集落なり安全な場所へ運ぶにはアーミラの杖の中に匿うのが最善じゃろ。
前線は勝手知ったるガントール。ウツロも二手に分けるならこっちにはいらん。連れて行け」
オロルの提案にガントールはしばし逡巡したが、反論はしなかった。それぞれが最善と思う意見の折衷案として、とりあえずの納得はできた。それはアーミラも同じである。とはいえ、ガントールは前衛と後衛の役割を優先して振り分けたかったので、思惑が外れたことに内心すこしばかり悄気げていた。前線への道はまだまだ警戒を高めて損はない、後衛を任せられる二人のうちどちらかが必要と見ていたが、ここへ来てオロルとアーミラの二人がナルトリポカに向かってしまうのは痛手であり、梯子を外される思いである。
斯くして、アーミラはオロルと共に、ガントールはウツロと共に二手に分かれ行動することとなった。
宿を出る折にオロルはガントールの背に声をかける。
「一つ頼みごとがあるのじゃが、わしらをナルトリポカへ投げてくれんか」
これはなにかの冗談か……投げるとはどういう了見か。
ガントールは未だ不満顔を隠さずオロルを見下ろす。視線を跳ね返す彼女の表情はなんとも判別がつかない笑みを口元に浮かべて、金色の瞳は相変わらず値踏みをするような人を試す視線だ。
「……よくわかんないけど、オロルが言うならやってやれないこともないけど」ガントールは唇を尖らせて応えた。「ただぶん投げればいいのか?」
「わしらが杖の中に入る。お主はそれをナルトリポカへ向けて投げればよい。片道分は楽ができる」
ガントールは「ああ、そういうことか」と心の内に納得し眉を開くが、先の話し合いの手前、不貞腐れた面を崩すことはなかった。要するに馬が足りないため、往路を力技で解決するつもりのようだ。
「復路の足は?」
「自分の足しかない。半日程度の遅れになるじゃろうが、ま、なんとかなるじゃろ」オロルはアーミラの差し出す杖の宝玉の中へ身を沈めていく。「頼んだぞ」
言い残し、オロルは全身を杖の中へ沈めてしまった。ガントールは束ねた後髪を指先で小さく掻くと頷き混じりにため息をついた。アーミラは杖の先を地面について静かに指先から沈めていく。
「アーミラ、悪かったな」
「あ、いえ……前線に向かうことは大事ですから……」
「大事だけど、それでもなんだ。
アーミラが守りたい人がナルトリポカにいるように、私の守りたい人は前線にいる……先を急ぎたいのは、継承者の大義だけじゃないんだよ」
そう言って優しく笑うガントールを見て、アーミラも微笑み返す。
「……アダンとシーナを助けたら、直ぐに戻ります。あなたの守りたい人のために」
力強い返答にガントールは思わず面食らう。臆病なアーミラが時折見せる覚悟は、凛凛として頼もしい。二手に分かれるという話し合いではつい口論のようになってしまったが、拗らせずにまた手を取り合えそうだとガントールは安心する。
「行ってきます」
アーミラは一礼して杖の中へ消える。あとに残されたガントールは杖を支え、頼まれた仕事を果たすために持ち上げた。
一抱えするほどの大振りな杖を肩に担ぐようにして右手に構えると、ナルトリポカのある方角へ目測で狙いを定める。
通常、ここからナルトリポカは常人の遠投ではとても届くような距離ではない。人の腕力、投擲能力は小石を川の向こうまで飛ばせば頂上。杖のようなものを投げるなら遠ざけるのが精々。石材と金属で構成された次女継承者の杖『天球儀』を山の向こうへ投げるのは、無理な話である。
だがガントールは「やってやれないことはない」という言葉通り行動に迷いはない。獣人種の、さらに長女継承者の為せる尋常ならざる力を持ってすれば可能なのだ。
杖を握る手に血管が浮き上がり、指は確かめるように杖をしっかりと握り込む。全身の筋肉が熱を放ち、揺らめく熱波は魔力となって旋風のようにガントールを包んだ。
力を込め、数歩後方へ下がる。
息を吸い込み、構える。
緩慢な足取りで歩き出すと徐々に速度を上げ、大砲が弾を打ち出すように杖を投げた。
助走をつけて一息に投げ飛ばす。振り抜いた右手は風を切り、ぼん、と砂埃が巻き上がる。放たれた杖は矢の如く真っ直ぐに飛んでいき、雲を突き抜けて空に消えた。
ガントールは手をかざして杖の軌道を確認すると、おおよそ見当した方角へ飛んだのだろう一つ頷き、振り返る。
「……私達も急ごう」
❖
驚異の部屋では、アーミラが扉に嵌め込まれた小窓から外の世界を覗き込んでいた。外界と切り離されているこの空間は室温も安定していて、外からの音や振動も届かないが、この小窓だけは唯一外の世界を窺い知ることができる。
雲を突き抜けて地上の景色が目まぐるしく流れていくのを、アーミラは見つめる。その後ろ、オロルは本棚の上に尻を乗せて身を落ち着かせていた。
「ガントールは良い所へ投げたか?」
「ほ、方角はおそらく……少し、遠くまで飛びそうです」
「ならば時を見て降りるぞ」
オロルの指示に首肯し、扉の前を譲った。アーミラはその背中に声をかけようとして何度か躊躇い、ようやっと勇気を振り絞って「あの」と言ったとき、被さるようにオロルの声が重なった。
「よし、杖の外へ出るぞ」
上空を流れる杖の宝玉から飛び出すと、オロルは身を翻して柄を握る。後に続くアーミラが上半身を覗かせると手を伸ばし、二人は杖の外へ出た。
ガントールが投げ飛ばした軌道は弓なりに弧を描いて、一度は雲の上を飛んでいたが、今は頂上を越えて下降軌道へ移っていた。オロルは下に広がる森や川の位置からおおよその現在地を把握し、次に燻り続けている集落を睨んだ。
足元に広がる景色は煙たく、風には焦げ臭い匂いが混じっていた。オロルはアーミラと目配せをして指をさすと互いに頷いた。
オロルが魔力を込めると杖の軌道が変わる。空気の抵抗が増し、ぐっと失速した。アーミラは宙ぶらりんの体がつんのめってオロルの背中にぶつかり、思わず手を離してしまいそうで小さく悲鳴を上げた。
「しっかり掴まれと言ったじゃろ」
吹きすさぶ風が耳朶を打つ中でオロルの声が届く。そんなこと一言も言われた覚えがないとアーミラは困惑しながら歯を食いしばって柄を握る手に力を込める。横殴りの風は止み、自由落下を始めた二人は下から煽る風に目を細めた。
アーミラはオロルの方へ目をやるとふと奇妙なものが見える。一筋の、透明な……綱?
落下により全身を吹きすさぶ風の中で景色が歪み、丈夫そうな綱が輪郭を浮かび上がらせている。それそのものが見えずとも、質量を持つなにかが空気を断ち切っているのがわかる。
ゆらゆらと風になびくしなやかなそれはもとを辿ればオロルの背中から伸びており、もう片方の端は上に伸びて得体のしれない巨大な影に繋がっている。こちらも透明だが、硝子細工のように景色が屈折しており、ある程度の形は掴めた。巨大な傘の骨組みのような、或いは八本の脚を広がる蜘蛛と例えたほうが近いか。
オロルの背から伸びた巨大な蜘蛛は、脚の角度を細かく変えて滑空を行う。
木立の上を通り過ぎる二人は黒ぐろとした平野に出た。地面に衝突する寸前で巨大な影はその八本の脚を地に向けて着地の体制をとる。おそらくはオロルが操っているのだろう。その巨大な影は衝撃を受け止め、集落に降り立った。
杖がぐらりと揺れ、大きく減速する。二人が揃って着地すると、舞い上がる風が足元の炭を散らした。雨に湿気っているため火はほとんど消えているが、すでに大半を燃やし尽くしてしまったらしい。土塊のように固まった炭が一歩踏みしめるごとに砕け、塵となって崩れる。
「刈り入れの時季でした……」アーミラは呟き、悲痛な思いでこの黒い平野を眺める。ここは本来、甘藷黍畑だったはずだ。
――いいか、アーミラ。これが前線を支えているんだ。
いつかアダンが教えてくれた。
――これが……?
――この作物の茎や根に含まれる糖蜜が、皆を癒すんだ。これなしにはどんな戦士だって、どんな魔術師だって生きられないって言われてるんだぞ。
脳裏に浮かぶいつかの記憶。アダンの、いかにも職人らしい節くれ立った大きな手が、甘藷黍の茎を手折りアーミラの口元へ差し出した。
豊かな土の匂いと太陽の熱……ある夏の日差しの下、二人で畦道を歩いた記憶。
アーミラは差し出された甘藷黍の茎を受け取り、堅い繊維を口に咥えて噛みほぐしていくとじわりと甘い蜜が滲み出した。目を丸くするアーミラにアダンは微笑む。
ほのかに立ち昇る草いきれの向こう側、ささやかな日々が思い出された。それは記憶を蝕むように焦げついた臭いを放ち、アーミラは唇を噛んで集落へと向かった。
❖
アダンとシーナは燃え残った建物の内部に安置されていた。折れてしまった手足には添え木――これは長槍の柄を折って使っていた――と、燃え残った布で固定してある。取り急ぎの手当ては済んでいるようだ。必要なのはごっそりと失った血と、溜まった疲労を癒やすこと。どちらも魔呪術がなければならない。ここでオロルの出番というわけである。
アーミラとオロルはある程度の治癒術式を施し、未だ気を失っている二人をそっと杖の中へ移した。とりあえずは一安心といったところか、アーミラの表情に余裕が出てきた。
「ウツロの報告通り、敵はもうおらんようじゃな」
オロルは厳しい視線を崩さずに焼け落ちた目抜き通りを進む。集落は毀たれた煉瓦積みの建物が並び、凭れ掛かるように瓦解した屋根や壁が互いを危うい均衡で支えていた。路肩には虚無を掻き抱くように身を丸め炭と化した焼死体が時折転がっている。人は焼けると筋肉が固くなり、胎児のような体勢になるのだ。
「あ、あの……」と、アーミラ。「なんで私に付いてきたんですか?」
「はぁ?」
「いえ、その、……ガントールさんと、一緒に、前線へ行ってしまうのだとばかり……」
オロルは片眉を吊り上げてアーミラを横目に見る。
「最善を尽くすためじゃ」
当たり前だと言わんばかりにオロルは答えた。
あの時、論駁を繰り広げたオロルは、誰よりも早く事情を推し量ることができていた。
ナルトリポカへ戻りたいアーミラの意見と、前線へ進みたいガントールの意見。この二つがぶつかる中で事の本質を見極めていたのだ。というのも、二人の内にある思いは継承者としての振る舞いの正しさではなかった。わかりやすいのはアーミラで、彼女が戻りたい理由は育ての親を助けたいという一心だ。対してガントールは頑なに前線へ急ぐ。それは冷徹に映り、いかにも継承者然とした案だからこそアーミラに寄り添わない。
オロルが見ていたのはまさにここだった。ガントールは決して他者の心情に鈍感ではないはずだ。だというのにこの場では随分と狭量になっている。前線へ急ぎたい本当の理由、個人的な事情があるのだと、いち早く答えに辿り着いていた。
表向きは継承者としての振る舞いの正しさ、課せられた使命を笠に着て誤魔化しているが、それならば鎧が仕留めそこねた敵がより内地へ食い込む危険を咎めるべきだ。オロルの目はガントールの発言の裏にある焦りのようなものを把握していた。そして力量から鎧とアーミラを向かわせるのは心許ない。となれば収まるべき形はこれしかない。
「あやつの事は許してやれ。事情もわかっておるのじゃろ」
「はい」アーミラは素直に頷く。
アダンとシーナの救護は済んだ。
二人をどこか別の集落に預けたい。
復路の道すがら、オロルは焼け野原となった集落を見て回ることにした。とはいえここへ降りた時点で他の生存者がいることは望めないと感じていた。夜雨が続く時節においてなお執拗なまでの火勢の痕跡……間違いなく魔力を込めた犯行だ。そうでなければ火は雨に消える。悪意は昨晩、ここに存在したのだ。
変わり果てた景色であれ、土地勘のあるアーミラは先を歩く。一度、小路の分かれ道の方へちらりと視線を向け、その先の景色が黒く焦げ付いているのを見ると肩を落としたのがわかった。言葉にせずともオロルは察する。あの道は……家につながる道なのだろう。
目抜き通り。道の広がる手前でアーミラは歩みを緩めた。
ウツロに聞いていた戦場。広場はもう目の前に見えており、開けた視界には真っ黒な炭が堆く積まれていた。その量は膨大であり、広場の隅から薄く坂をつくり中央では勾配もきつく円錐状に積み上げられていた。
オロルは最初、継承者出征の祝いに建てられた祭り櫓の残骸と見ていた。炭の山は木材や瓦礫の集まりだと。しかし違った。山から突き出た枝の数々が人の手足であることを理解して怖気が走る。
「なんともはや……これは、惨いな……」
凄惨な光景にオロルでさえ形容し難く言葉は途切れる。ここまでの道々で死体は散見されていたが、まさか大多数が一処に集められて殺されているとは思っていなかったのだ。
アーミラは累々と折り重なる亡骸の山に近付くと、絡まりあった四肢を踏まぬように隙間を見つけては足を差し入れて遺体の顔を一つ一つ確かめた。一帯は炭化した皮膚とひび割れた腹から溢れる生煮えの腸が強烈な臭気を放っており、地獄のようである。
髪の禿げ上がった焼け焦げた顔、顔、顔……炭の山をぐるりと回りながら面影を重ねる。
この人はよく畑仕事をしていた。この人は道の向かい側に住んでいる人だ。この人は、アダンの工場で働いていた……この人は――
アーミラはその遺体を一目見て、どくん。と胸が痛むのを自覚した。まだ顔を確かめていないのに面影を重ねてしまう。変わり果てた姿であっても、誰なのかわかってしまう……。
――この人は、私に石を投げた領主の娘だ。
悪夢を見ているときのように心臓が早鐘を打ち、脂汗が噴き出る。目眩にふらついた脚が焼死体の四肢に縺れ、たたらを踏んで炭を砕いた。ぱきりと脆い骨が砕けると砂礫のように焼死体の腕が粉微塵になる。しかしアーミラの意識は足元にはない。心不在焉に娘の顔を見つめている。
関わりを持ちたくないと思っていたのに関わってしまった。最後までわかり会えなかった相手だとしても無念だった。こんな再開、望んでない。
黒く焦げついた亡骸を見下ろし立ち尽くすアーミラに、オロルが追い付いて隣に立つ。
「……アーミラ――」オロルは思わず口を噤んだ。
おそらくあれを修羅と呼ぶのじゃろうな……と、オロルは恐ろしいものを見たように肌を粟立たせる。
涙を流して怒りに震える横顔。炭となった亡骸の山を前に立ち尽くす背中には鬼気迫る激情が燻り、今にもこの場を焼き尽くしてしまうような炎が揺らめいて見えた。
■006――戦うための術《アレス》
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
――その昔、楽園があった。
楽園には永遠の命を持つ三人の娘がいた。
娘の前に蛇は現れ、三つの快楽を説いた。
一つは、他者と交わる快楽。
一つは、眼目を閉じる快楽。
一つは、果実を食する快楽。
楽園に表れた蛇を退治するため、
神は天使を遣わした。
天使は蛇を踏み亂れた世を糺し、
娘に戒律を打立てた。
(『ラヴェル法典』より序文抜粋)
❖
ナルトリポカの一集落、穏やかに営まれるはずの日々は燃え盛る業火に蹂躙され、収穫を待つ畑の青々とした夏の夜は、無惨にも燃え尽きた。灰となり脆く積上げられた亡骸の山を前に、一人の修羅が生まれようとしていた。
涙を流して怒りに震えるアーミラに対しオロルはそっと袖を掴み、気持ちを切り替えろと金の眼で訴える。
取りこぼした命に拘っている場合ではなかった。杖の中には救うべき二人がいる。
「弔う暇はない。急ぎ、二人を別の集落に預けるぞ」オロルは短く伝える。
アーミラは自分が泣いていることに気付いていないのか、瞬きもせず、目尻から涙が伝うのを拭おうともしなかった。ただ静かに、縺れた感情の糸を解しながら賢人の言葉の意図を推し量っていた。
事実、これだけの遺体を弔うには人手が足りない。
絡み合った亡骸の手足を引き抜いて山をそっと崩し、一人ずつ埋めているのではあっという間に日を潰してしまう。かといって大穴に纏めて葬り埋めてしまうのでは配慮がない。焼けて顔の判別も危ういとはいえアーミラの同郷の者達だ。ぞんざいに扱うのは配慮に欠けるし先を急ぐ以上拘泥される訳にもいかない。ならば近くの集落に事情を話し、沙汰を任せよう――オロルはきっとそのように考えたのだろう。
「……私が焼きます」
アーミラは洟をすすり、宣言をするように言った。
「は――」
オロルは虚を衝かれて言葉を詰まらせる。その間にもアーミラは即断で歩き始めていた。目で追いかけたオロルは困惑しながらも後に続いた。
火葬をするということか――オロルはそう思い至る。勿論この選択が思い浮かばなかったわけではない。同郷のアーミラの手前、雑な弔い方はできないと考えて真っ先に排除した選択肢だった。
火によって命を奪われた彼等をまた燃やすことを、他ならぬアーミラが選んだ。
オロルは先を歩く彼女の背中を見つめて並ならぬ覚悟を推し量り、何も言わず従うことにした。
広場から通りへ繋がる道まで戻ると、アーミラは振り返って遺体の山を見渡した。変わり果てた集落の景色を眺めていると、穏やかだった数日前までの風景の面影がふいに重なり、思わず胸に去来する思いがある。
悲しみに咽ぶ胸を押し止めるように奥歯を噛み締め、目を強く閉じる。出口を塞がれた行き場のない感情は内圧を高めて温度を上げていく。泡が立ち、発火する。吐き出す息が熱い。
杖を握る手に力を込めて前方に構えた。魔力を練り上げる横顔は苦悶に儚く歪み、祈りを込める行為そのものが痛みを伴う罰のようだった。後ろに立つオロルは賢人の流儀に習い、合掌で弔う。
大気にはアーミラの魔力が充満している。火葬の準備が整ったのだろう。右手でだけで柄を掴み、離した左手を水晶の宝玉に添えると、赤く腫れた目を開き唇を引き結ぶ。
杖を天に掲げ、解き放たれた術式は宝玉を通して展開された。光の雨は降り注ぎ、乾いた皮膚に、骨に、魔力が染み込んでいく。
そして堆く積まれた山の奥のほう、芯から少しずつ光が漏れる。遺体のそこかしこから、青く小さな種火が生まれ、火勢を増して燃焼を始めた。
昨晩の悪意とは異なる、柔らかな抱擁のような炎。しかしその熱量は凄まじく、穏やかな見た目に反して吹き荒ぶ熱風は激しい。広場に面した家々の壁面は既に焦げているというのに、あまりの熱さに石の表面が溶解して赤く蕩けだしている。
魔力による強制的な領域内の燃焼は、きっと骨さえ遺さないだろう。塵となり、風に流れて、集落は清められるはずだ。
それとは別に、オロルはふとアーミラの背中を見つめていた。以前まであった疑念は消え去り、ともに戦場に立つ者としてこの次女継承者を改めて推し量っていた。
戦いぶりを見たわけではないが、燃焼術式の強度は目を見張るものがある。なにより、臆病さに隠した彼女の、本来持ち合わせている強さを垣間見た気がしたのだ。
「行きましょう」アーミラは火勢を確認するとオロルに言った。「まだしばらく燃焼を続けます」
「見届けんのか?」
オロルの問いにアーミラは悲しい笑みを返す。
「……先を急ぐには、荷物になってしまいますから」
ナルトリポカにはいくつかの集落が存在する。
周りの集落は基本的に甘藷黍を生産する畑が広がっているが、神殿に続く道を束ねる北側にまで足を伸ばせば、より発達した都と呼ばれる街もあった。そこでは各集落が刈り入れた収穫を集めて貯蔵、管理する役割を担い、様々な職能が集まり、貿易が盛んに行われている。
オロルが定めた次の目的地は、そんなナルトリポカの都だった。
二人は前線からさらに遠のいてしまうことになるが、杖の中に匿い運び出したアダンとシーナの傷痍は酷く、治癒の設備や医者の頭数が整った街を目指すことにした。
人の多いところへ行けば当然組織は拡大し、施設も大きくなる。心許ない集落の町医者よりも都の救護院を頼りにしようという判断である。
手足が使い物にならなくても生きていればそれでよい――という話ではない。救うと決めたのなら背負った命に対しての責任が伴う。オロルはそれを正しく理解していた。
「……本当は出し惜しみたかったのじゃが、仕方あるまい」
観念したように呟き、背を丸めて前屈みの体制で固まる。そこからの変化は、蛹が羽化する姿に似ていた。
丈の短い外套の背面が盛り上がり、裾から現れたのは太い綱のようなもの。アーミラはこれを見たことがある――正確には透明だったので見えてはいないのだが――この綱を知っている。
これが三女の神器。綱だけではない。オロルから伸びていく綱の末端は布の貼られていない舵のようなものに繋がる。中心から放射状に伸ばされた八本の柱が地面に足を着けると、外観は丸屋根の骨組みのよう……内側から見上げれば巨大な蜘蛛が頭上に顕現していた。
この蜘蛛こそが神器本体――柱時計と呼ばれるものだった。
「『柱時計』……わしが継承した神器はこの魔導具じゃ」
オロルは誇らしげな面持ちでアーミラを見下ろす。その身体は宙に浮いていた。いや、蜘蛛型の魔導具――アトラナートと呼んだか――の胴体部底側から伸びる綱によって吊られているのだ。接続された綱はオロルの意のままに動くのだろう。宙吊りになったオロルはぐっと高度を上げ、綱は弧を描きながら小さな賢人の体を持ち上げている。
「柱時計の屋根に乗れ。奔るぞ」
そう言われ、アーミラは蜘蛛の脚に触れてみる。ここから伝って上に飛び乗れるか確かめたのだ。
目の前に顕現した神器はひやりとして、外骨格から関節に至るまで何かしらの鉱物か金属で構成されていた。形は違えど鎧と同じものらしい。硬い感触を確かめて、アーミラは蜘蛛の上に乗る。
オロルはそれを見届けるとナルトリポカの都へ向かい八本の脚を動かし始めた。金属の塊に見えるが、駆動する音は驚くほど静かだった。
「出し惜しみたいと言っていましたが、透明なまま私を乗せて向かえばいいのではないですか?」
速度を上げていく蜘蛛の上、耳朶を打つ風切音に負けないように、アーミラは声を張り上げて訊ねる。
「透けたままでは乗せられん。わし以外は触れられんのじゃ」オロルが答える。
なるほど。確かに空から降下するとき、私は蜘蛛に触れていない。実体を持つには透明なままではいられないということか。アーミラは一人納得する。
「式典の夜があったじゃろ」オロルは言う。「三女の神器は未だ解明されておらん。じゃから神殿の者達がわしの神器を借りてあれこれと弄くり回しておったが――」
アーミラは何の話か思い出す。
当代継承者の出征式典の夜に行われた星辰の儀……。
「――あれでは解明は無理じゃろうなと憐れんだものじゃ。目に見えるものは神器のほんの一部にすぎん。わし以外には見えないとなると、奴らは無駄骨を折った訳じゃな」
オロルは酷いことを言うが、その表情は特段嫌味がない。アーミラはその顔を見つめていた。
「なら何故、顕現させてあげなかったんです? 見せてあげたらいいのに」
「阿呆」オロルはぴしゃりと言う。「手の内を簡単に明かすやつがあるか」
アーミラは首をのけぞらせるようにして一応の反応を返すが口は閉ざしてしまった。鼻越しに人を見定め口さがない性格なのは重々わかったが、矛先が自分に向かうと辟易してしまう。
手の内を明かさない――それがオロルのやり方なのだとしたら、今こうして晒してみせた蜘蛛は問題がないのかと疑問に思ったが、また邪険に扱われることが火を見るよりも明らかだ。私に明かしても――或いは私達をみている者がいたとしても――きっと問題ない。まだ秘匿している手の内があるのだろう。
アーミラは会話から逃れるために視線を蜘蛛へ移した。蜘蛛といってもその外見は四阿のような形状で、糸を吐く大きな尻や、たくさんの目玉がついた顔もない。屋根の上に立つアーミラは縁ににじり寄り、屋根の下にある本体を眺める。
柱時計は浅い円状の窪みがあり、内部端面は白い盤が嵌め込まれていた。そこにぐるりと右回りに一から十二の数字が刻まれており、中心からは針が二つ伸びている。それが何を意味しているのかアーミラには未だ知るところではないが、この盤面が据えられた部分がいわゆる蜘蛛の顔……本体前面なのだろうとは推察できた。といっても消去法でしかなく、側面と背面の飾り気のなさ、進行方向から推察したに過ぎない。
盤面に取り付けられている針は常に少しずつ変化している。現在指しているのは長短それぞれ別の方向を向いており、短い針が九と十の間、長い針が七と八の間にあった。――後の世に明かされるこの絡繰は神器の名を授かり『時計』と呼ばれる事となるが、アーミラはまだそれを知らない。
この時代の人々にも朝昼夜を目安とした曖昧な時間の概念は存在するが、それは太陽の方角をもとにした日時計が主である。暗い内に時を刻む必要に迫られたときは蝋燭の燃焼で経過を計りおおよその指針とするのが精々であり、正確な数値として時間を把握することはできなかった。
この柱時計は神が授けた三番目にして最後の叡智である。内部は主に畜力装置、調速機の二つが占め、それにより示された時刻を針が表す事で時の流れを把握することができる機構である。
八本の脚は忙しなく動き、縺れることなく森林を抜けた。展開された柱時計は神器の中で一番巨大で、行ってしまえば長い脚で移動する塔だった。
多少の低木などは長い脚で跨いてぐいぐい進んでいく。焼け野原となった集落は既に遠く遥か後方。オロルとアーミラは標高の低い山々が連なる斜面をなぞりながら都へと向かった。柱時計の姿を公にしたくない事情から、人気のない道なき道を選んでいる。
オロルは鬱蒼と絡み合う葉叢をときに潜り抜けときに薙ぎ倒して神器を巧みに操り突き進む。飛び越えるのが難しい高木が並ぶ植生となり、現在地がそれだけ標高の低いところにいるのだと理解する。都も近いだろう。アーミラを振り落としてしまわないように気を配るついでに横顔をちらと窺う。
アーミラは縦横から迫る枝葉を煩わしく払いながら山路の先を目を細めて見つめている。……その表情はとうに泣き止んで涙も乾き、怒りだけが目元にこびりついていた。
簡単に涙を見せてしまう者を嫌うオロルにとって、アーミラのはじめの印象は良くなかった。臆病な態度で、風に吹かれて倒れてしまいそうな内地育ちの陰気な娘。そんな第一印象だった。しかし、同時に引っかかり続けた違和感もある。身体には数え切れない古傷があり、頭には抜け落ちた記憶という謎、焼けた輩を前に怒りに震える純粋さがある。この者を次女と選んだ神が、果たして何を知っているのか。前線で彼女は何を見せてくれるのか、オロルは不明瞭な未来に期待していた。
「部屋は片付いたのか?」オロルは通り過ぎる木々のざわめきに負けないように心持ち声を張り上げて問う。
「ある程度は整えました」アーミラは言い、表情が曇る。「……今思えば、あの夜、杖に入らなければよかった」
「ふむ……どこまでが敵の策なのかわからんが、杖の中に居らんでも、夜襲には気付けんじゃろう」
「え?」アーミラはオロルの方へ顔を向ける。「それは何故です?」
不覚を取った後では言い訳にしか聞こえぬかもしれんが――そう前置きしてオロルは語る。
「わしらの宿はムーンケイの上層じゃ。窓から望む景色は常時稼働の溶鉱炉。夜でありながら夜ではない……そんな窓外の景色から遠くの野火を見つけることはできんかった」
一度言葉を切り、アーミラの反応を確かめる。ここで意固地になって駁するなら会話は水掛け論となるだろう。アーミラはオロルの言葉の続きを待つ。
「朝にガントールが異変に気付き、わしも窓からナルトリポカを見たが、集落そのものが一望できたわけではない。蟠っておる煙に違和感があった程度のことじゃ」
「なら、ガントールが窓の外を見なければ……」
オロルは頷く。
「今も気付かんかったかもしれんな。
昨晩の動きはそれほどまでに運が悪かったか、もしくは死角を衝かれたか……わしらの行動が敵に筒抜けの可能性がある」
「まさか……集落が宿からは死角になることまで知っていたってことですか……?」
「難しいことではない。あの宿は『先代も泊まった』と嘯いておるから、わしらもそこに泊まると踏んでいたのかもしれん。そもそも出征式典は威す意味合いもあるのじゃから敵はこちらの動向を注視するはずじゃ。
神殿を出て三人揃って移動するのか、どの門をくぐってどの国へ向かうのか、その情報が掴めればわしらの裏をかくことができるじゃろう。不可能ではないが、厳戒態勢に潜り込む命知らずの策じゃな」
アーミラはその言葉を聞き、訝しむように眉間のしわを深くして唇を尖らせた。
この一件がただの偶然ではないなら、継承者が三人揃ってムーンケイに向かったことを誰かが把握していたことになる。厳重な守りの神殿にさえ間諜が……情報を売る内通者がいたのか、怪しい人物は誰か……。
「開けてきたな……森を抜けたようじゃ」
オロルはアーミラの側で話題を切り上げるように呟くと蜘蛛の先頭へ移動した。――警戒は怠るな。しかし今はアダンとシーナを優先しろ。オロルの背中にはいつも迷いがなかった。
それに比してアーミラの胸中は今だ鬱蒼とした森の中を彷徨っていた。こんがらがった感情は解けることのないままに、燃えていた。
まるで糸になる前の繭玉を炙るように、覚悟も、後悔も、疑念も、乱雑に丸めて放り投げ、火に焚べてしまっている。怒りという名の火に。
景色が開けたと同時、足元は地面が途切れ、深く切り立つ崖が現れた。
蜘蛛は前側四本の脚をつっかえ棒のように伸ばして制動し、地面を削り踏みとどまる。足元では、弾かれて崖へ転がる小石がぱらぱらと小気味よい音を響かせながら遠く小さく見えなくなる。
岸の向こう側には都の気配があり、木造の赤茶けた屋根が並んでいるのが見えた。オロルはこの崖を飛び越えることにして、一度助走のために後退した。
崖の底には細く川が流れている。小川のように見えるこの川は、見た目以上に耳元に届く水音が激しい。この流水こそが崖を形成した原因なのだろう。山肌を侵食し、削り取る内に下へ下へと掘り進め、この崖が生まれたようだ。
上に乗るアーミラは高所の景色に足が竦み、腰の抜けた身体で柱時計の縁を掴み跳躍に備える。立ちはだかる状況の恐ろしさに身が怯んでも心は折れていなかった。頭には一つ、迷い続けた森の果て、燃え残った疑問が転がっていた。
もし、窓外の異変を発見しなければ、私達はナルトリポカが襲われたことに気付けなかった。……本当にそうだろうか?
きっと窓を見なくともウツロの不在には気付いたはずだ。そしてウツロからナルトリポカの異変を伝えられることになるだろう。
ならば何故、ウツロだけはあの夜、駆け出せたのだろう……。
❖
結論から言えば、救出したアダンとシーナはこの日の昼前には都へと送り届けることができた。蜘蛛の顔で示すなら、短い針が十一を越え、長い針が三に重なっているあたりのことである。
都の救護院では痛々しく砕けた四肢の骨について医師から話があった。治癒術式ではもう繋ぐことも取り除くこともできないため、一度切り開いて骨片を取り除き、大きな欠片はある程度繋ぎ合わせて固定する必要があると説明された。もちろん完治を目指すが、術後に麻痺が残る可能性や、切り開いた箇所が化膿して腐る危険性もあると念を押された。話を聞いていたアーミラは負傷箇所を切り開くと聞いただけで顔を青くして「そんなことはやめて下さい」と難色を示すが、彼らが手足を再び動かせるようになるには避けようのないことだとオロルは救護院の意見を支持した。このまま傷を放置しては、いずれすべての四肢が腐り、切り落とす羽目になる。今は救護院の医師を信じ任せるほかないのだった。
「そもそも――」
二人を預けて救護院の外、市井に手持ち無沙汰となったオロルはアーミラを見上げる。
「――継承者の親類は神殿に招かれるのではないか?」
「そうなのですか?」アーミラは首を傾げる。
オロルの言う通り、神殿では継承者の親類を招き入れる制度が存在する。
第一に保護を目的としているが、継承者を産んだ功績に対しての褒章という側面もある。この話は門を潜る際アーミラにも伝えられていたはずだが、屈強な神人種たちに囲まれたことで怯えていたこともあり、まともに聴くことも出来なかったのだろう。
とはいえ、アーミラが何かしらの申請や手続きをせずともアダンとシーナは神殿へ招かれる手筈であった。集落を離れ神殿で暮らす、その選択肢があったはずだ。
「仕事の依頼が忙しいようでしたし、もしかしたら断ったのかもしれません」
アーミラはそう答える。依頼をこなすまでは集落に留まり仕事をこなす。きっとアダンならそうするだろうことは想像に難くない。そうして熱心に鑿を打つだろう。
……結局それも燃えてしまった。オロルはそんな皮肉が思い浮かんだが、喉元で抑えた。言う甲斐がない。
❖
日は高く天上に昇るが陽射しはすっかり勢いを弱めた。まだ夏の盛りではないのでどこか風も涼しい。車輪は時折音を立てて幌が揺れる。轍のない草原で石を踏んで跳ねているのだ。
車窓に設けられた幌の切れ目を捲くって退屈そうに景色を眺めているガントールは、辺りの地形がずいぶんと平たく様変わりしたことに気付いて後方を振り返る。幌の内側に一人きり……思えば継承者三柱が揃わなければ前線まで孤独な出征となっていたのだから、後から追いかけてくれるだけでもありがたいことだと、己に言い聞かせる。それに馭者もいるのだ。
ガントールとウツロは馬を走らせムーンケイを南下し、なだらかなマハルドヮグ山野を抜けてスペルアベル平原に到着していた。このあたりはだだっ広い乾燥した大地が広がり、木々も疎らである。
「二人は大丈夫かな……」
きっと今頃は集落で襲われたアーミラの育ての親を救い出し、こちらに向かっているだろうとガントールは考え、後ろに二人の姿はないかと振り返る。それらしい影はない。オロルのことだ、どこかで昼飯ついでに酒を呷っているかもしれない。
この平原は言葉の通り広い平野で、古びた遺跡と塹壕が過去に前線だった歴史を物語る。それらは長い間風雨に曝され崩壊し、無残な瓦礫となって面影を残している。川こそないが地下水脈が流れているため疎らながらに草が茂り、その草を目当てに牛や山羊が群がり、木陰から肉食獣が獲物を探す。穏やかな自然の営みはムーンケイの喧騒とは対照的で長閑な景色が広がっているが、地図でみればスペルアベルのほうが禍人領に近い。現在もこの地は第二戦線としての機能を有している。
ガントールはいい加減、後ろへ流れていく景色を眺めるのもうんざりしてきた。ムーンケイを出る頃はアーミラとオロルの身を案じて心持ちも暗く真剣なものだったので、ウツロに話しかける気はなかったが、午前中ずっとこんな調子ではつまらない。
幌の中で尻を滑らせて前へ移動すると馭者台のすぐ後ろに身を落ち着かせる。
「……半日程度の遅れって言っていたけど、夕方には合流できると思う?」
ガントールはウツロに問う。難しい返答を期待してはいなかった。持て余した暇を誤魔化せるような、都合の良い聞き手となればそれで良かった。
「遅れるとしたらオロルだな。アーミラは約束を守る質だろうけど、オロルはほら、なんというか強かだろ?」
口約束くらいじゃ守らないだろうな。と散々な言いようだった。それだけ互いのことを知れた仲間ということか、最早オロルが遅れることを前提にしてガントールはため息をついた。
そんな様子を見ていたウツロは、何かを考え込んでから、馭者台に薄く文字を刻んだ。筆の代わりには、柄の折れて短くなった槍の刃を用いた。
――襲夬ル事忍難シ、心配不有如。
「……んん? るー……しー……?」
思わぬ返答にガントールは眉を困らせ目を丸くする。二文字以外は賢人の書体で、まるで読めない。ウツロは隣にふりがなを配するようにもう一度書き直す。
――襲夬ル事忍難シ、心配不有如。
ああ。とガントールは眉を開き応える。
「集落に向かった二人が心配ってこと? 当然トガに襲われる可能性はあるけど問題ないよ。危険を承知で、オロルはアーミラを一人にさせなかったんだと思う」
今度はウツロが筆を止め、じっとガントールを見つめる。説明を求めているようだ。
「まず集落を焼いたのはほぼ確実に間諜だ。駆け付けたウツロと戦い、南へ退いて見せたのは嘘だと思う。私ならこう考える……『せっかく内地に入り込んだのだから、前線へ逃げるのはもったいない』ってね。次の機会を逃さないためにどこかに潜伏するはずなんだ。
……オロルはそうした敵の考えを読んだ上で仕留めたいんだろう」
つまり次女と三女の二人がナルトリポカの集落の異変にたまらず駆けつける。潜伏している敵は、継承者として未熟な二人が目の前に現れた状況となる。この好機に動き出すならオロルとアーミラは迎え討つ。何もしてこないなら予定通り速やかにアダンとシーナを救出した後、前線で合流……という流れとなる。
ガントールにとってアーミラの実力は未知だが、オロルの強さは充分に承知している。二人がナルトリポカへ戻ることを良しと判断したのだ。
「一番理想的なのはオロルが間諜の首を取って前線に合流することかな。内地の不安要素が無くなれば前線に集中できる」
逆に――とガントールは目を細めて付け足す。その表情は未だ見ぬ敵に対して警戒しているようだった。
「二人がなんの奇襲にも合わなかったら厄介だ。軽率に姿を見せない、それだけ利口な奴だと判断できる」
降って湧いた好機を見逃す……そんな慎重さが間諜には重要な素質となる。敵が用意周到であればあるほどこちらは尻尾を掴むことすら難しくなる。そんな現状の盤面を打開すべく、オロルは己を餌に敵の潜む藪を突いたのだ。さして切れ者ではないガントールもまた、前線に向かうという自らの役割を全うしていた。
しかし、継承者達の読みも虚しく禍人は盤面を荒らしていく。定石も搦手も知らぬ無邪気さで悪意を振り撒く。
異変に気付いたのはウツロでもガントールでもなく、幌車を牽く馬だった。
常歩だった蹄の歩調は不意に乱れ駈歩となり、なにかに怯えて逃げるように進行方向を曲げて鼻息荒く暴れはじめる。手綱を握るウツロと、その背中越しに馬の様子を眺めるガントールの二人にはまだ何が起きているのか分からない。
「急にどうした! 蜂にでも刺されたのか?」
揺れる幌車からガントールは身を乗り出して不満を漏らす。ウツロは面鎧だけを一度向けるが、返答する術はない。例え声があったとしても、馬が暴れ出した理由は解らなかっただろう。
首を振り嘶いた馬は両前脚を跳ね上げ全身を起き上がらせると、手綱はついに制御不能に陥った。ウツロの手からすり抜けてしまったのである。
御する手綱が緩んだ馬は一散に駆け出し、幌車は右へ左へ車体を踊らせる。
馬は、絡みつく頭絡や綱を毒蛇と見間違えたのか。血走った目を剥き、狂ったように身をよじらせる。その度に幌車は軋みを上げ、揺さぶられる。横に振られた幌車を猛獣と見間違えでもしているのか、馬は狂乱状態に陥った。
急旋回に耐えかねた幌車が傾いでしまった。
体勢を崩して馭者台から転がり落ちるウツロの姿を見ていたガントールは、自分だけでもこの場に踏み止まろうと幌車の内側で手足を柱に支えさせていたが、視界が横に傾いでいくのを抗えない。
幌車が軋みを上げて横に傾いていく刹那、ガントールは直感で幌から飛び出した。突然馬が暴れ出したこと、それに伴い幌車が横倒れになったこと、何故そうなったのか筋道を立てることもままならず、それでも危機を逃れる反射的な素早い回避行動をとることができた。
これが継承者の才か、純粋な獣人種の血から来る野生の勘というものだろうか。
ガントールは背を丸めて転がり込み、勢いを殺しながら片膝をついた。砂塵の向こう、状況を確認する。
離れたところにウツロがいる。傍では草むらに凭れるように幌車が転がっている。天を向いた車輪は、からからと回転の余韻を残し音を立てていた。その隣、幌車に繋がれ身動きが取れなくなっても尚、落ち着きなく暴れ続ける馬がいた。
……ウツロが手綱捌きを誤ったか? いや、そんな様子はなかった。ならば毒でも食べたか? それならば暴れる体力はないはずだ。ただの事故なんて間抜けな事があるわけない。どこかで敵が仕込んだな――なにを仕込んだ……?
ガントールの頭は次の勘を手繰り寄せるために感覚を尖らせる。違和感の気配がする……
飛び出した幌の外は日光が降りそそぎ、平原は草いきれのむんとした空気が纏わりついた。その足元、炙られるようなじりじりとした熱が一帯に満ち充ちている。土が異常なまでに熱い。そう気付いたガントールは一瞬地面に意識を向けた。が、脅威はいつも死角から迫る。
ガントールは殺気を感じ取り、顔を空へ向ける。
「敵襲――!」
本当なら近くにいるウツロに向かって叫ぶつもりだっただろう声は、眼前に迫る敵の殺意に対応するために絞られた。空から落ちてきたその人影はもう懐に飛び込んでいて、凶悪な笑みを浮かべ掌底打ちを繰り出さんとしていた。第二戦線とはいえ禍人が入り込んでいることに怯み、ガントールの抜剣が間に合わない。敵の掌に込められたものは魔術か、呪術か……ええい、義手で受ける!
掌打はガントールの右腕部に放たれた。衝撃が伝わり義手が撓むと、次に呪術の波動が弾ける。ガントールは一か八かの賭けに勝った。
「……ちっ」
鋭く尖った歯が並ぶ禍人の口元から舌打ちが一つ。術式が届かなかったことに不満を隠さない。これが義手でなく生身の肉であれば、込めていた呪術は通っていただろう。火傷を負うか、動きを縛られるか、術式の効果は定かではない。
一方で攻撃に後退るガントールは、穢れを払うように右手を振り、改めて抜剣する。敵の奇襲がまさかこちらを狙うとは想定外だったが、死線は越えた。敵の狙いを崩した以上、奇襲は失敗。真っ向勝負であればもう不安はない。
「貴様に勝ちは無くなった。大人しく首を差し出せ」
ガントールの言葉を聴いているのかいないのか、禍人は乱れた前髪を搔き上げ、粗暴な目付きで睨み返す。額から伸びた触角のような細い角がしゃらんと風に靡く。
嘲笑を浮かべ、睨み返す。
「くっくっく……」
「なにが可笑しい」
「いやぁ、あの夜、俺たちが集落を焼いた時――お前ら、気持ちよく寝てたらしいな?」
禍人の男は腹の底からこみ上げる笑いを留めるように口元を手で押さえるが、尖った歯が唇の隙間から覗いた。にやついた目が足元を見る。
「――先ずは足」
そう言って両の掌を合わせると指を伸ばしたまま擦り合わせるように右手を捻り、上下に開いていく。詠唱こそないがこれは術だ。ガントールは前方に跳んで回避行動を取る。不可視の攻撃を躱せたかどうか、足に異変はない。
視線は敵から離さず、鼻先が熱を嗅ぎ取る。焦げた臭いに気付くと悲痛な嘶きが平原に響いた。しまった……!
振り返った時には幌車は火に包まれ、立ち上る炎の向こう、馬の影がのたうつように暴れていた。全身の体毛に火が移り、これまで聞いたこともないような絶命の嘶きが長く長く平原に響いた。火に焼かれた影が倒れ込む。肺が焼かれて失神してしまったようだ。もう助からないだろう。
幌は焼け落ちていく。ガントールは糾弾するように敵を睨み間合いを詰めるが、禍人の男は魔力を込めて中指を突き上げた。
ぼん。と、ガントールの足元から火が噴きだす――が、火柱は上から圧されるように火勢を落とし、下方に伸びる斥力に捻じ伏せられて鎮火していく。力場を纏うガントールは駆け出し、両手で剣を構える。
「この火……その言葉……貴様ナルトリポカの主犯だな」ガントールは怒涛の勢いで詰め寄る。
火柱を圧し折りながら突き進むその足取りの一歩一歩が持つ重み。馬を失ってなお、その姿は騎馬兵のような威圧感があった。
長女継承の天秤――処刑人としての彼女が剣を構えて迫ることは、禍人にとって死そのものが迫っていると同義だ。
並の敵であれば恐怖に竦み、反撃の意思は砕かれるだろう。だが、禍人の男は長女継承者の超然とした恐ろしさに総毛立ちながらも奮い立ち、次の一手に打って出た。かろうじて攻勢の意思が折れなかったのは、この男――ダラクが命を賭ける覚悟をしていたからだ。それこそナルトリポカの集落で下手を打ち、生存者を出してしまった失態を挽回するためスペルアベルでの継承者足止めの指揮を任された。それは言外に馘切りを突き付けられたも同然だった。
馘首の放火魔と、処刑人の女。――あまりにお誂え過ぎて、ダラクの顔は凶悪な笑みを浮かべていた。
ガントールは横に構えた剣を左切り上げで振り抜いた。煽られた風切音は鋭く重たいが、手応えはない。ダラクは身を仰け反らせて紙一重に躱していた。そのまま後方へ宙返りして、距離を取る。
「ふっふ……はははははっ」
窮地に立たされ気の触れてしまった男の笑みに、ガントールは不愉快そうに眉根を寄せて警戒した。追い詰められたものはなにをするかわからない。警戒を高めて剣を構える。たとえ襲い掛かろうとも、必ずその首を叩き落とす。
ダラクが仕掛ける。上下に構えた掌を打ち合わせて、組み合った指を顎のように示した。魔術がガントールの頭上と足元に展開され、火が襲う。
「燃えろ燃えろ!」
ガントールは無言のままに斥力を高め、自身の周りに強い重力を発生させた。その時――
「土竜ぁ!」
ダラクの怒号を合図に地面が沈み込む。ガントールは何事か理解できていないままに跳躍で回避しようとしたが、足場が脆く穴に落ちてしまう。
「なに――!?」
してやられた。
眼下に広がるのはくり抜かれた穴だった。先程まであったはずの地面が沈み込み、体が落下する。
あの禍人……まだ策を用意していたとは。
敵は長女継承の力を理解し、地中に穴を掘っていたのだろう。この平原一帯の地盤を脆くさせて、私がここに現れるのを待ち、奇襲を仕掛けたのだ。そして、斥力を強めることで地盤が圧力に耐えられず崩れる仕組みか。
敵の言葉を信じるなら、地中に穴を掘ったのは別にいる。禍人か咎か、腕力か魔術か、いずれにしろ穴を掘る能力を獲得しているとみていい。ガントールが恨みがましく地上を見上げると、禍人の男は穴の縁から見下ろし、すぐに見えなくなった。
「くそ……っ」
こうなれば、ウツロに託すしかない。幸か不幸かあいつは穴に落ちていない……いや、これも敵の策か。私を穴へ落とし、禍人はウツロを狙う……。
ガントールは気持ちを切り替えて状況を把握することに努めた。
穴の深さは目測で三十振ほどか、幸いにも大したことはない高さだが、問題は足場が脆くなっていることだった。おそらく穴から脱出するために跳躍しようものなら、踏ん張った足元からたちまち地盤は崩れ沈下してしまうだろう。砂質は細かく、ただ立っているだけでも靴が沈む。平原の砂質から泥濘はないが斥力の使用は咎められている。そのうえ穴の縁では脆い崖が崩れ、流れる砂は漏斗状の窪みに飲み込まれていくのが見えた。あの穴はどこへ繋がっているのか……。
「地下か」いっそガントールは感心する。
砂が流れ落ちていく窪みは天然の蟻地獄だ。
ある程度の深さまで掘り進めればスペルアベル平原の地下水脈に繋がるだろう。
そこに落ちてしまえば砂と水に飲み込まれ、窒息する。非死の加護を授かっているが、暗く重たい土中を抜け出す術はない。落ちてしまえば窒息と蘇生の繰り返し……命が足りるかわからない。
敵の描いた勝ち筋を理解したとき、さすがのガントールも身震いをした。肌をひりつかせる明確な死の危険が迫っている。
その背後で、砂礫がもぞもぞと盛り上がり、鼠のような長い鼻先がこちらを伺う。ひと目見て人ではないとわかる造形にトガであると判断する。男の言っていた土竜の正体か。
それは、鈍色の体毛に覆われた兎ほどの大きさだった。
前脚には土を掘るための鉤爪が生え、鋸とも鍬とも言い難い独特の形状をしていた。頭部に目は見つけられない。地中に適応するうちに退化したのだろう。その代わり、執拗なまでに匂いを嗅いで首を回す鼻先は嗅覚が発達しているらしく、鬚ではなく明確に触手のようなものが備わっている。自然界の生物と一線を画す冒涜的な外見はやはり禍々しい。が、単体では大した脅威ではないだろう。単体では。
一帯の地盤を脆くさせて広域に穴を開けたのだ。こんな小型のトガ一匹とは思えない。
ガントールの予感に応えるように、辺りの土がぞもぞと蠕動する。夥しい数のトガがそこかしこに湧いて穴を埋め尽くさんばかりに群れている。
「……これを重力魔術を使わずに倒せってことか」
状況を己に言い聞かせるように呟き、ガントールは剣を構える。
❖
「奴は継承者の能力を使えない」
ダラクは目の前に立つウツロに言う。
「この平原は昔、俺達の領土だった。知ってるか? この一帯は地下の深くに水脈があるんだぜ」
長女継承者がトガを押しつぶそうと魔術を行使すれば、その度に地盤は沈下して最後には深い深い地下水脈に辿り着く。そうすれば芯まで凍える冷えた水に溺れて、光もなく脱出の手立てもない。いくら強くても、ほとんど不死だとしても、戦線からは居なくなる。ダラクが語る策とはつまりそういうことだった。
ウツロが一歩踏み込むと、それを遮るようにダラクが両手を広げて立ちはだかった。
「お前の足止めは俺だ」
口元には鋭利な笑みが浮かぶ。眼の前の鎧の力量は既に把握している上に、この奇襲では長女継承者が地下水脈へ沈むまでの足止めをしていればいい。命を持たぬ魔導具の兵を相手に、ダラクにはそれが可能だった。
ウツロは手に握っている柄の失われた槍の穂先を匕首のように構えた。刃毀れ甚だしいがもの言わぬ面鎧の内側は戦意に充ちている。
斯くして、スペルアベル平原での戦闘が始まった。
先に動いたのはウツロである。筆を持つように人差し指を柄に添わせ敵の顔面に向けて穂先を突き出す。魔術を繰り出されるより先に方を付ける腹積もりか、或いはナルトリポカで手の内を知っているからこその勇み足か。
ダラクは眼前に突き付けられる鋒を首の動きだけで躱し、鎧の伸ばした腕を下から押しのける動作と同時に手扇の身振りで炎を喚び出した。手首の動きに合わせて腕輪が袖口からちらちらと輝く。ダラクの術式と魔石はそこにあった。
大気が急速に熱を持ち、爆ぜる炎がウツロを包む。――が、構わず前へ出た。全身が金属で構成されているのだから、火傷を恐れるわけもない。攻め手を緩めることなく迫るウツロと逃げるダラク。両者はかなり一方的な戦況に縺れ込んだ。
時折ダラクは砂をかけるように腕を振り火を浴びせるが、抵抗虚しく目くらまし程度の効果しかない。一方ウツロは逃げてばかりの敵に容赦はない。手を焼いて拘い、その間にガントールが戦線から落ちる事こそ敵の本懐であり、なによりも阻止すべきことと理解していた。
だからこそ、考え無しに穂先を振り回してはいない。回避の足運びに合わせて攻撃を巧みに選び、たとえ躱されても、一歩、また一歩とガントールのいる方向へ近付くように追い込んでいる。
油断はなかった。
優勢であるはずだった。
しかし、異変はすぐに訪れた。
炎に包まれながらも意に介さず、なおもダラクを追うウツロ。穂先を握り、振り下ろした右腕をダラクは掌ではたき落とすように受け流した。右腕は握っていたはずの槍の穂先を落としてしまう。
これまで回避に専念していた敵の僅かな行動の変化。そして得物を落とす掌の握力の違和感。
ウツロは何を思うか、敵の顔を見つめながら穂先を拾う。ウツロの思考が読めるならばきっと今、このように考えているだろう。なぜ触れた? なにを仕込んだ? 呪術の布石か?
ダラクは一瞬の隙を見咎め煽り立てるように炎を喚び出しては鎧に投げつける。もちろん傷一つつかない。ウツロは挑発に乗るつもりはないが、かといって追うことをやめるわけにもいかない。得物を構え直し、攻撃を再開する。
敵の懐へ一足飛びに詰め寄り刃を腿に滑らせる。鋒は僅かに肉に届かず布一枚を割いて躱された。内腿が晒された仕返しとばかりに面鎧に火の玉をぶち撒ける。燃える視界を振り払いウツロは得物を振り上げ、その動きにつられた敵の足運びを見切り左腕で胸ぐらを掴んだ! 抜かったか、敵は目を見開き両手を伸ばして鎧の右腕を押さえるが、炎に焼かれた鉄が掌を焦がした。重ね掛けにウツロは頭突きを一発。額に生え揃う華奢な頭角が鉄の塊でできた頭とかち合いぱきりと容易く折れ、次の刹那にはごつっと鈍い音が響き小さなうめき声が漏れた。
脳が揺れたのが痛手だったのだろう。痛みに歪めたダラクの表情にはまだ闘志が宿るが体はついていかない。
膝をついて地面にへたり込んだ。角の折れた額からは血が滲み、垂れた血液は赤い涙となって頬を伝う。
「お前は……」
ダラクは何か言っている。
「お前は勘違いしている」
ウツロはとどめを刺す為に敵の後ろ髪を鷲掴みにして下に引っ張り、無理矢理顎を上げさせた。皮の薄い喉が日に照らされ、つばを飲み込む喉仏の動きがはっきりと見えた。
「俺の魔術は火……そう思うよなぁ……」
聞こえているはずだろうにウツロはなんの反応も示さず、握り込んだ槍の穂先を敵の首にあてて今にも頭を切り落とそうとしている。たとえ奥の手があろうとも殺してしまえば解決すると判断したのだろう。
だが――ウツロの腕は動かない。腕だけではない。指も肩も、脚さえも軋みを上げて固まってしまう。ウツロは敵の顔を見る。髪を掴まれたまま固められた以上、敵もまた首を晒したまま見上げるようにウツロと目が合った。見下すような笑みだった。
くまを溜め込んだ青い下瞼に、粗野で神経質そうな細い眉。それらが弧を描き形づくった凍てつくような笑み……それは比喩ではなく、本当に凍りついていた。角を失った額の窪みからは青白い燐光が冷気となって下に流れ、焼けた鉄の体に霜が降りている。
「……俺の魔術はなぁ、熱を操るんだぜ」
その言葉が聞こえていても、ウツロは身動ぎ一つ叶わない。
ダラクの魔術、その戦法が今ならわかる。
炎によって熱せられ膨張した板金の体は各部の関節が弛み、刃を振るう膂力は知らぬ間に弱められていた。回避に専念していたダラクが一度攻撃をはたき落としたのは、弛みの具合を確かめるためだったのだろう。
そして急速に冷却。精緻に構成されている関節は膨張からの収縮によりがっちりと噛み合い、締め付けられて動かなくなる。
ウツロはもはや自立さえままならず、ぐらりとダラクに身を預けてしまう。
「おっと……髪を引っ張るなよ」
ダラクは凭れかかる鎧の胴を片手で支え、もう片方の手で懐から切り出し刀を取り出すと、掴まれている後ろ髪をばつばつと乱暴に切り離した。そうして縛るものがなくなるとウツロを押し退け苦労して立ち上がる。
形勢は逆転した。
大きく息を吐き、傷痍の痛む額の汗と血をそっと指の先で拭いながら独りごちる。
「あやうく首を落とされるところだったぜ」
ダラクは手首を回し、屈伸を二、三繰り返し、脳の痺れが回復したのを確かめる。足元にごろりと転がる鎧はそんな敵の姿を睨むことさえ出来ないが、髪の束を虚しく掴み続ける様は恨めしい気配を滲ませていた。
「なぁ、悔しいか?」
ダラクは腰に手を当て脂下がった笑みで鎧を見下ろす。当然返事はないのだが、憂さ晴らしに踏みつける。
「悔しいかって、聞いてんだよ!」
言い終わると同時に鎧の晒した盆の窪を踏み抜き、頭部が撓む。ダラクはもう一度、鎧の頭を踏んづけた。返事が返ってくるか、あるいは己が満足するまで、踏んづけた。
当然ウツロは声を持たない。この場合ダラクが満足するまでこの憂さ晴らしは執拗に続くこととなる。
「お前の、負けだ! この、くそが!」
がちり、がちりと鎧の頭部は次第にぐらつき、留め具が外れて地面に面をぶつける。首の板金が一枚、両端の留め具がそれぞれ頭と体を繋いでいた。人であればこれを首の皮一枚とでも言うのだろう。
太陽の熱で温められた鎧は微かに指先が動いた。
ダラクは見逃さず一層濃い冷気を鎧に浴びせた。
ぱきぱきと音を立てて、ウツロは白く霜を纏う。とどめに思い切り踏みつけられ首はあっけなく捥げてしまった。ごろりと転がり天を仰ぐ虚ろな双眸は、何も見ていなかった。
鎧の無惨な姿を眺めてダラクは鼻で笑う。腹の虫が治まったのかしゃがみ込んでウツロの首を拾い上げる。
「よぉ……魔導具だから首もげても死なねぇんだったか。
だがよ、術式を覗けば内側から壊れんじゃねぇのか?」
その思いつきは愉悦を求め残虐を繰り返す者の発想か、それとも禍人とはいえ魔呪術を扱う一人としての知的好奇心か。
鎧の生首は何も答えない。
本当に死体のようだった。
ダラクは鎧の頭を様々な方向から矯めつ眇めつ眺め、まるで壷の中に入り込んだ虫を覗き込み観察するような手付きで首の穴から内側を覗き込み何かを探す。目当てのものが見つからないのか、足元に放り、今度は鎧の体に向き直ると身を屈めて胴の内側を覗く。
「……これか?」
探していたものはダラクが思っていたよりもずっと手前にあった。鎧の胴体、胸部の裏側。人で言うところの肋骨の中央胸骨体のあたりに書き置きのような小さな文字が記されている。ダラクは薄く張られた霜を擦り落とすと魔術で蝋燭ほどの火を生成し、その灯りで文字を照らす。
そこにはごく簡単に記されているのみだった。
『深淵を覗く痴れ者、魂は頂く』
ダラクが見つけたのはくだらない悪戯書きか、安い挑発に顔を顰める。
「なんだぁ……ふざけてやがる」
果たしてその言葉は誰がどのような意図で書き残したのか、ウツロを召喚した二百年前の先代の継承者が記したのだとしたらあまりにも無邪気で、馬鹿馬鹿しい悪戯である。――だが、ダラクはもっと深く考える必要があった。踏み止まり、一考する警戒心が必要だっただろう。語る口を持たない鎧の内側に唯一存在した言葉、その意味を軽んじた男は、そこで命数をごっそりと失うこととなる。
「『魂を頂く』だぁ? やれるもんならやってみな……!」
売られた喧嘩を買う勢いでダラクは言い、切り出しで自身の小指の付け根を割いた。この部分であればそれなりの出血が望める上に手指の運動にさほど不都合がない。――そう、これから彼が行う術に必要なのは血液だった。
滴り落ちる紅い雫を立てた小指で筆のように塗り拡げる。鎧の内側に眠っていた言葉は赤色に上書きされる。元々の文字は篆刻されて溝になっているため、凹部に沿って血溜まりが満たされた。ダラクは鎧の体から腕を抜き立ち上がると、まだ流れる血液を手刀で振り、鎧にふりかけるように五芒星を描いた。
よく晴れた平原の乾いた土に、草に、血が染み込む。
最後にダラクは傷口を圧迫して血を止めると、残る一滴をそっと頭の上に掲げて見上げる。
今にも零れ落ちるその一雫を左眼で受け止めた――そのまま目を閉じる。忙しなく動く眼球の動きが瞼の皮膚の上から伝わる。
「……ここが深淵ってか」ダラクは左目を掌で覆い、口角を吊り上げ、次の瞬間には笑みを消す。「いや、まだ奥があんだろ」
スペルアベル平原の北部、そこには異様な光景があった。
まだ暖かな午後の日差しを受け止める草むらの一隅、戦闘が行われた形跡を残す草原にはそこかしこに小火があがっていた。その中央では首のない鎧が不自然に凍りついている。
血液で描かれた五芒星は土に染み込み黒ずんだ痕を残すばかり。陣を引いた術者は禍人の男。鎧の傍で立ち尽くし、左目を隠してなにやらにやにやと笑みを浮かべているのであった。
ダラクは、今まさに深淵を歩いていた。
己の血を媒介とし、鎧と左目を門で繋ぎ、内側に広がる領域へ自身の意識を飛ばしたのだ。
現実で閉じた左目は、血の門の向こう側、術式回路の領域で開かれ、ここではない世界を覗き見ている状態にある。
鎧の内側に彫られた言葉。
その内側に込められた術。
その内側に展開する深淵。
……ダラクの目に広がる景色は、一つの確信を齎した。
「ウツロだったか……? 名前通りなんもねぇところだな」ダラクは右目を薄く開けて鎧を見下ろす。「扉が一つだけあるぜ」
左目に広がる景色はとても質素なものだった。……いや、質素という言葉で表すにはあまりにも空虚である。灰白色の果てもない空間。壁も天井も床もない曖昧な茫漠たる領域に、白く塗られた木製の扉が一つあるのみだった。
ダラクは迷わず把手を掴み、開く。確信したその答えを確かめるために。
「お前は不死じゃねえ。心臓も脳みそもねぇから、誰も殺せなかっただけだ」
ダラクの笑みは鋭くなる。下弦の月のように吊り上がる口角は、頬に穴を開けてしまうのではないかと思うほどに尖り、自覚していないだろうその呼吸も心なしか興奮していた。
「お前の魂はある……この領域が何よりの証拠だ。扉の奥に確実にある」
この際何故という問いは関係なかった。ダラクが手に入れた確信とは、この領域が魔術回路ではないことだ。逆説的に、この空間が呪術的なものであるとわかった。
他者の体を操り自死へ誘う事ができるダラクにとって、この空間が精神領域だとすぐに理解できた。どうして魔導具の鎧にそんな領域があるのか、ダラクはそれを一切無視した。こいつを殺せる。その手がかりがこの先にある。
押し開けた扉の向こうには、扉があった。
代わり映えのない灰白の空間が続いていて、扉を隔てたとて内外に壁はない。扉の周りをぐるりと回り込むことも可能だ。しかし、次の扉は無い。
出現条件は明確だった。目の前の扉を潜ること。その先に次の扉が現れる。広い空間であるにも関わらず、進むべき扉は必ず十歩先に待ち構えている。
いや、待ってはいないのだろう。ただでさえ招かれざる客だと言うことは承知。閉じられた扉は何年、何百年とそこに存在し続け、誰も中へ通すつもりもなかったはず。訪れたものを迷わせるつもりのないこの空間はなんの制限もなく、扉を潜る順番だけを縛っている。
ダラクは笑みを消して扉を蹴り開けた。粗暴な態度は不愉快な秩序に対しての反抗だった。扉は蝶番が馬鹿になって軋む音を立てて中途半端に開く。向こう側は変わらず灰白の空間が続いている。次の扉が見える。
「人の精神領域なら、もっと記憶と結びついてるはずだが……」
ダラクは警戒して呟く。
呪術による精神領域への侵入はかなりの経験があった。それこそ昨夜の集落を燃やしたときは女子供も関係なく、心を縛り、体を操り、自らの足で火へ飛び込むように仕向けた。呪いをかけるために覗き込んだ幾人もの心の内側……その景色はもっと雑多で、記憶の風景が散らかっている迷路のようなものだった。
そしてダラクにとって、他者の心象風景に入り込み人格の芯まで続く扉への道筋を解き明かすのは一種の快楽だった。これから殺す人間がどのように生きていたのか、それを知ることで壊す悦びが増す。そう感じていた。
だが、この精神領域は全く違う。
ダラクは次の扉の前に立ち、把手を掴み、捻る。
そこに待つのは扉だった。
迷わせるものが何もない。
向こう側は次の扉が待つ。
ダラクは息を呑み把手を掴む。鎧の内側、深淵を目指す足取りは順調なはずなのに笑みはない。追い詰めているはずなのに追い詰められているような焦燥が背後について回った。
あるはずだ……。この鎧にも記憶に象られた風景が。そこに心の核があれば壊して御仕舞だ。次の扉にこそ、次の、次の扉にこそ……。
把手を捻りずいずいと先へ進むダラクは一心不乱という有り様だった。追手から逃げるように不安を振り払い、足早に扉から扉へ駆け抜ける。
そしてある扉を開いた先、目の前の光景に足を止め僅かに目を丸くした。幾つ扉を潜ったか分からない。相変わらず茫洋とした空間が続いているが、待ち構えている扉の様子に変化があった――いや、そもそもこれは、扉なのか?
恐る恐る近付いたダラクの前、平滑に形作られた氷のような透明な板が四枚。冷気はないことからこの歪み一つない水鏡のような代物が硝子であると知る。これまで見たこともないほどに向こう側の景色を透かしている縦長の硝子板の扉。
上下には磨き抜かれた金属製の枠が嵌められており、横に支っている無目と繋がれている。恐ろしく薄く精巧な造りで、研磨面も鏡のようだ。
把手は無かった。開けずとも硝子の向こう側の景色が望めるが、まさかここに来て窓というわけではないだろう。
向こう側は病的なまでに清潔かつ直線で構成された室内が広がっている。灰白の空間とさして代わりないが、明確に壁と床が視認できるだけ進歩がある。そう考える反面、ダラクは不機嫌そうに鼻から溜息を吐く……鎧の記憶だとすんなら、いつの時代のどこなんだ……?
蹴破ってでも進むべきか否か、躊躇いがちな足取りで扉の様子を観察した。心境としてはかなり懐疑的である。ここまでの道のりは一直線……ずっと無理問答を押し付けられているような圧迫感で先を促された感が否めない。その上ここに来て把手がないとは、迂闊に手を伸ばすほど愚かではない。
硝子でできているとはいえ、形式は四枚の引戸。本来引手があるはずのところには楕円形の札が貼られていた。そして札には、三角の陣が描かれ、陣の左右に一文字ずつ『注意』と朱色で記されている。
それを見たダラクは、全く閉口してしまった。
描かれた陣も魔力を感じ取れない。
引手の代わりだと言わんばかりに配された三角形の陣には、縦の棒線と丸い点が一つだけ埋め込まれている。文字であれば感嘆符を意味しているが、なんの回路なのか判断はつかない。いっそ魔力のこもっていない印しなのか、朱色の賢種書体で『注意』とは……どう捉えたものか測りかねた。
訝しみ、睨みつけるように観察する顔が知らず知らず扉に近付くと、突然扉が左右に開いた。
ダラクはどっと冷たい汗が全身から噴き出し肝を冷やして射線上から飛び退いた。攻撃を警戒する。……が、なにも起こらない。間抜けを嘲笑うかのように扉はゆっくりと閉じていく。そのとき、微かな滑車の回る音と共に子供の笑い声らしきものを聞いた。
「奴の正体か……?」
くすくすと漏れ聞こえた幼い笑い声。硝子扉の向こうから確かに聴いた。
無機質な鎧の内に潜む無邪気な子供――頭の中で結びつかないが、しかし人の声がするのなら他の誰でもない鎧の正体であるはずだ。心の内にある人物像が外見とかけ離れていることは珍しいことだが、ないわけではない。
ダラクは再び扉の前に立ち、じりじりと摺足で近付き、指先で扉に触れようと腕を伸ばした。
扉は触れずとも開いた。魔力は感じないがなんの細工か上の無目から滑車の回る音がする。こんな代物見たことがない。
硝子の向こうから透けて見えていた室内は、扉が開かれた後も変わらずそこにあった。当然といえば当然だが、この空間はどこか人を食ったような胡散臭さがあり、扉が開けば何もない暗闇が口を開けていたとしても納得できる……そんな油断ならない猜疑の趣きがある。
苦々しく下がった唇から尖った歯を覗かせて内側へ踏み込む。声の主はどこか、辺りを見回した。
ここは石窟だろうかと、ダラクは思う。踏み入った足には硬い感触が靴越しに感じられた。左右の壁面もつやつやと光沢があるが、塗料の奥にひんやりとした感触がある。岩から削り出したのだと推理した。真実は全く異なるのだが、ダラクの乏しい経験ではそうとしか思えなかったのだ。
磨かれた床、等間隔に走る柱、壁面には案内のためだろうか太い線が奥へ伸びている。そのどれもが病的なまでに人工的で直線の空間。職人技といえば聞こえはいいが無機質で血の通わない建物だ。今、ダラクが立っている場所は廊下だった。
「ふふふ」
聴こえた。
ダラクは耳を澄まし、廊下の先を睨む。残響が手招きをするように右へ曲がる通路の奥へ消えた。蠱惑的とも取れる少女の、屈託のない笑い声だった。
拳を固く握り込み大股で進む。どうあれ奴の核に違いない。殺す。殺してみせる。終わりだウツロめ。
曲がり角へ進み、その先に声の主はいた。
「ほら、ここまで来ちゃったじゃん」
「……お前がウツロの正体か……?」
ダラクは問う。やはりその目でしかと見ても結びつかない。あの鎧の魂がこれとは。
禍人の目の前には間違いなく声の主がいた。小さな部屋に簡素な作りの褥があり、少女はそこに腰掛けて足を組み、後ろに伸ばした両手で反らした上体を支えている。射干玉のように黒く豊かな髪は生まれてから一度も切ったことがないのではないだろうか、褥を覆う蔦のように方々へ這わせている。肌着からさらされた細い首の上に据えられているのは幼いながらもすらりとした顎と薄い唇。小鹿のような通った鼻。硬質な黒い瞳はダラクを見つめ返しているようだが、焦点はもっと遠くを見透かしているようにも見えた。
何よりも、驚くべきは額の頭角だった。
少女にはとても似つかわしくない雄々しい角が冠のように円を描き、長い髪を抑えるように囲っている。
角を持つ人種は二つ――獣人と、禍人だけである。両者には明確な違いがあり、見分けるには角の位置を見れば良い。顳顬から生えているなら獣人。額から生えているなら禍人だ。両者は似て非なるもの――だからダラクは目を疑った。少女を見たほんの刹那に様々な逡巡をして、腑に落ちる答えが見つからず動揺さえした。
鎧とは二度刃を交えた。その中で掴んだ印象と目の前の少女が持つ印象はずっと繋がらない。何度も紐付けようとしているが、結びつかないのだ。態度も所作も雰囲気も、鎧とは異なるものだった。
だから問うた。
「応えろ。お前はウツロか」
「それで、どうする?」
少女は頬杖をつき、壁の方を見つめながら言う。
「愚問だな。殺すまでだ」
ダラクは切り出しを握り、構えた。
一度は揺らいだ殺意だが今更見逃す訳にはいかない。鎧に殺められた同胞たちの無念を晴らすため、この先の勝利のため、お前は殺す。
少女は何故か愉快そうに笑った。腹を抱えて足をばたつかせて褥に倒れ込む。
「できっこないよそんな身体で、僕が代わりにやったげるってば」
ダラクは動けなかった。こちらは殺すと言ったのだ。なのにこの少女の返答は……成立していない。飛び掛かる機会を逸し当惑するダラクは一つの違和感に気付く。この少女は、一度もこちらを見ていない。恐らくはこちらの言葉を聴いてすらいない……。
少女は寝返りをうち、完全に背を向けてうつ伏せになっている。少し不機嫌そうな息遣いで何者かの声に耳を傾け、虚空を見つめる。
「……ふーん。まぁ、そこまで言うなら一度だけ見逃してもいいけど。もしこいつがまた腹の中に来たら、次は待ってあげない。問答無用で噛むからね」
こちらの言葉が全く無視されていることに気付いたダラクは少女の言葉が何を意味するか理解して青筋を立てる。こいつは今、何者かと会話をしているのだ。あまつさえ俺を無視して。
そして俺の目の前でぬけぬけと言ってのけたのだ。『見逃してもいい。次は殺す』と。
背を向けながら言ったのだ。
ふざけやがって。
男を見もしない少女の大胆不敵な発言に対してダラクは怒り心頭に発した。継承者の傍でうろちょろしている古ぼけた鎧のくせによくもそんな大口が叩けたものだ。
内圧を高めて噴き出した炎のように、堰を切る川のように、少女へ襲い掛かる。
「死ね――」
そう言い、一足飛びに距離を詰めた――はずだった。
刃が少女の命を奪う、その一瞬が引き伸ばされていく。
緩慢な動作で少女が上体を捻り、首を後ろに回す。横顔がダラクを捉え、黒く輝く瞳が冷たく一瞥を送る。
「あとで」
すいっ。……と、少女は立てた人差し指を前方へ振った。
ダラクに向けて与えられたたった三文字と、それを呟く間の興味のなさそうな無感動な視線。それだけで事足りた。
全身を押し流すような力強い後方への引力。吹き飛ばされる身体。景色は急速に流れ、これまで通ってきたいくつもの扉が背後から迫り、ばっと風を切って通り抜けていく。
もう少女の姿は見えない。それでもダラクは恨めしく前方を睨み続けた。こちらを捉え指をさす少女の姿は脳裏に焼き付いて離れない。
『一度だけ見逃してもいいけど。もしこいつがまた腹の中に来たら、次は待ってあげない。問答無用で噛むからね』
「……上等だ……!」
ダラクは吹き飛ばされながら前方へ向かって指をさす。その笑みは負け惜しみか、再戦の覚悟か。
「何者なのかは知らねぇが、次会ったときがお前の最後だ……!」
❖
平原に吹く涼やかな風が襟元の熱を冷ます。
火照る身体、耳の先まで赤く染まり、ガントールは足を止めて呼吸を整えた。
なだらかに続く坂道を見上げ、顎先の玉汗を振り落とす。濡れた前髪が額に頬に貼り付き、煩わしそうに手漉きで払う。その際に手のひらが頬に擦れ、紅を引き摺ったような跡が残った。
足元の土は泥のようだった。靴で踏み固めると中に含んだ水分が絞り出されるように滲み出てくる。一歩一歩の足取りに纏わりつく、粘土質の赤土である。
ガントールは円錐状に広がるなだらかな斜面を今まさに登っているところだった。物量で攻めるトガの群れには流石に疲れたか、その斜面の途中で足を止める。
小石のように側を転がってきたのはトガの骸である。
小動物程の大きさの、何とも形容できないような、強いて言えば土竜に近い姿をした亡骸。それは首を落とされ事切れて、泥の坂をごろりごろりと回転しながら下っていく。
同様に首を落とされた化物達が円錐状の盆地の中央、穴の一番深いところで蟠っていた。
再び歩き始め、ガントールは坂を登り切ると膝に手を当てて倒れそうな上体を支えた。かなりの疲弊であるが、外傷はない。彼女をここまで疲労困憊にさせたのはトガが強敵だったから……というわけでもなかった。魔術を行使したことによる活力の消耗が原因である。
長女継承が持つ斥力を操る魔術をトガと禍人の男は奇策によって咎めた。であればガントールは魔術を使用せず戦っていたはずである。そのための奇策、そのための奇襲だったはずだ――が、しかしそこに大きな見落としがあった。
獣人種は生まれ持っている魔呪術の才覚は恵まれていない。そのため長女継承の先代達は神器が備える斥力魔法を下方向に限定していた。
この世の摂理の一つである強い力――重力――を主に操り、長い戦争の中で活躍してきた。
禍人達はその情報のみを頼りに対抗策を立てていた。地盤を脆くし、重力魔術を行使すれば自らの首を絞める罠を作り出した。……ここが見落としだった。
ガントールは前線伯領の気高い血筋に生まれた娘であり、この世に生を受けたその瞬間から神殿に招かれた。血筋と才能と環境、そのすべてが揃った麒麟児である。数ある斥力魔術の一つを奪われたとしても、慣れない魔術に活力を消費する分疲れる相手ではあったがトガの群れは敵ではなかった。
「お、いた」ガントールはこちらに向かって歩く人影を見つけ、上がらない肩で手を振った。「おーい! 倒したかー!」
ウツロはその問いかけに首を振ろうとして、頭を外されたことを自覚し肩をすくめて両手を軽く上げた。その右手に己の頭部を掴んでいる。てっきり手柄に持ち帰った生首の土産かと思ったガントールは疲弊したように上げた手をだらりと垂らした。
「逃がしたのか……よろしくないな」
よろしくない。ガントールは心の中で繰り返し、スペルアベル平原を眺めた。
禍人の男は姿を消した。南へ逃げたか、北へ逃げたか……状況は不安要素をはらんだまま、二人はアーミラとオロルの合流を待つしかない。
すぐ側まで歩み寄る鎧と向き合い、とりあえずは人心地のため息を吐き表情を緩める。へにゃりと眉を下げて気の抜けた笑みを一つ。酷い有り様だ。それは私も同じか。
「知っているだろうけど、この平原を治める領主とは親戚でな、とりあえずはそこで二人を待つとしよう」
先を示すガントールの指先の向こう、平原の荒れた地平線から一陣の隊列が砂埃を立ち上げてこちらに向かってきていた。噂をすればなんとやら。こちらの騒ぎを聞きつけて迎えがやってきたようだ。
■007――吊るし人
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
晩夏の夕暮れ時、オロルとアーミラは右側から差す鋭い西日に顔を顰めながら先を急ぐ。スペルアベル平原での奇襲について預かり知らぬ二人が夕陽に赤く染まる草原に辿り着いて見た景色は苛烈な戦闘の形跡であった。
眼前に広がる地面の窪地は土が掘り返されたように柔らかい。椀状に穿たれた大地の裂け目には、得体のしれない生物の死体が集められ崩れた土砂の流れを堰き止めていた。なにか自然災害の類か、あるいは疫病の類がこの地を襲い、家禽の亡骸をまとめて供養した墓穴のようにもみえたが、それなら埋め立てず野晒しにしている意味はない。
それに――と、アーミラは視線を移す。
少し離れたところには炭化した荷車が倒れ、頭絡に繋がれた馬の死体が放置されている。あの窪地が家禽の墓ならばこの馬も放り込まれているはずだ。
真っ赤に焼き爛れてずる剥けの皮膚には蠅が集り蛆が湧いている。……焼け焦げて見る影もないがこの馬車には見覚えがある。
アーミラはまたも炎によって蹂躙された命を目の当たりにする。幌は焼け落ちているが、この馬車は継承者一行のものだ。
立ち尽くす彼女の隣、オロルはこの事態も想定内だったのだろう。不愉快そうな表情を浮かべているが動揺は見られない。
「敵は手強いようじゃな」
オロルの呟きに、アーミラはこくりと頷いた。
「……ガントールさんも、ウツロさんも、やられたわけではなさそうです」
アーミラの言葉に今度はオロルが首肯を返す。
視線の先、穴に転がる死体の数々は砂に埋もれてしまっているが、よく見るとすべて首を落とされている。一刀による介錯はガントールの仕業だろう。既に平原が落ち着きを取り戻しているということは、奇襲を行ったトガはすべて撃退したと考えていい。
戦闘を終えたガントールはどこへ行ったか……平原を見回すオロルに対し、アーミラはふと思い出したように手を合わせる。そういえば……。
「ガントールさんはスペルアベル平原の領主とお知り合いだったような」
「ふむ……確かに」
片眉を吊り上げてオロルは記憶を辿る。出征前夜の晩餐の折に身の上を語り合い、そんなような事を言っていた気がしなくもない。あの時は睡魔に侵されていたからはっきりとは覚えとらんが。
「たしか、前線ラーンマク辺境伯とスペルアベル領主が親戚筋じゃったか」
オロルの言葉が呼び水となったか、アーミラは湯浴場での会話を思い出し、もう一つあったと人差し指を立てる。
「あと、ガントールさんの――」
という言葉尻が小さく消える。遠くからこちらに向かい近づいてくる隊列の、地鳴りのような騎馬の足音と砂埃が会話をかき消した。
二人は目を凝らして何事かと見定める。
二列縦隊の騎馬は帯剣こそしているが、手に握るのは軍旗であった。立てた棒の先に旗を垂らして風に靡かせる紋章は獅子――平原領主お抱えの討伐隊である。
「出迎えじゃな」
❖
討伐隊の一行と短い会話を交わし、二人は荷台に乗せられ邸へと案内される。南西に馬を走らせてしばらく、遠くに灯りが見えてきた……街だ。
それは国家と呼ぶには小さく集落と呼ぶには大きい生活圏だった。荒野と街を区切るのは背の低い木製の柵で塀も堀もない。外敵からあまりに無防備なこの街の姿にアーミラは不思議そうな顔をした。第二前線と呼ばれる平原に、この守りでは弱すぎるのではないだろうか? 有事の際、心許ない木製の柵で何が守れるのか。
言問顔を掬したオロルが口を開く。
「スペルアベル平原は国家ではない。
土地の面積なら他国と肩を並べるこの地がなぜ国家として成り立たないのか、わかるか?」
「……人が少ないから、ですか」
「ではなぜ人が少ない?」
アーミラは少しばかり思案して、言葉をまとめる。
「集まらないのは、仕事がないから……仕事がないということは、この土地に利益を生み出す資源がない……」
オロルは頷いた。
「この土地は、畑にするには水源がはるか深くにある。かといって鉱石が掘り出せるわけでもない。アーミラの言う通り国として成り立たせるには資源に乏しい。
じゃがここを手放すと四代目長女国家ラーンマクが孤立し、戦線が維持できない。南に展開しているラーンマクへ輜重を送るために、この平原は仕方なく誰かが維持しなければならないのじゃ」
アーミラは納得した面持ちで顔を上げ、事情を知って改めて街を眺める。
隊列は既に柵の内側を通り抜けて、街の外縁から目抜き通りを真っ直ぐに進め領主の邸へ向かっているところだった。
騎馬の足並みは人の往来とぶつからぬように速度を落とし、踏み固められた土に小気味よい律動を刻む。あちらこちらから喧騒が耳に届き、馬の荒い鼻息もひっきりなしに聴こえてくる。道幅が広いため馬車同士がすれ違う様子もよく見えた。
「なるほど……」アーミラは呟く。
領土を囲っていた低い柵も、目抜き通りの左右を埋める車輪付きの露店も、この地に住まう者たちも、いつどこで戦闘が起きてもいいように移ろいやすい佇まいをしていた。この街は人の数と同じくらい馬が多く、家々も遊牧民然としたものである。三角形の背の低い建物は土に突き立てた柱に雨風を凌ぐ革製の天幕を張った簡素な作りだった。
この平原で生きる者たちは土地を守るつもりなどさらさらない。災いがあれば住処を畳んで立ち去り、平原のどこかへ移り住む。土地の資源がないからこそその地に縛られることなく生き延びることを優先しているのだとアーミラは肌で感じた。どこか懐かしい流浪の民と似た生活様式だ。
生業も窺い知ることができた。前線で傷を負った雇われの兵士はこの地で傷を癒す。これから前線に向かうものはこの地にて装備を整える。戦えないものは戦場で回収した品や内地から卸した物を仕分け売りさばく。皆どこか血生臭く、ぎょろりとしていながら落ち窪んだ目は死線をくぐり抜けた顔をしている。露店で愛想よく鍋を振るう女も男勝りで二の腕が幹のように太い。
内地と前線を結ぶ駅として金が回っている。国として成り立たずとも逞しい生活圏が形成されていた。
「案外、都の飯屋に寄らんでもここで事足りたかも知れんな」オロルは露店の景色をぼんやりと眺めながら言った。
アーミラは困ったような愛想笑いで応える。
「結果的には、そうですね」
❖
星を散りばめた天幕が空を覆う頃、平原の熱は急速に冷まされていく。当初半日程の遅れになると見積もった継承者達の合流はガントールの予想通り後ろにずれ込み、オロルは悪びれもせずに冷えた足裏を脛に擦りながら他人事のように「大変だったようじゃな」と奇襲撃退を労った。
場所は辺境スペルアベル平原。その領主、ギルスティケー・セルレイ伯爵の邸、玄関広間。
招き入れられたばかりの二人に対するガントールは、オロルの軽口に至極真面目な面持ちで首を振った。
「大変なのはこれからだよ」
どう身を振るべきかと右顧左眄するアーミラを置いて遅刻を咎める風でもなくなにやら通じ合う二人は、含みのある笑みを交わすとガントールの先導で邸の奥へ案内される。平原においてほぼ唯一の煉瓦造りの邸は外観を見たときから檻なのか城なのか判別のつかない暗く堅牢な印象を抱かせた。古寂びた黒鉄色の煉瓦積みの壁は、爵位を持つ者の邸としては殺伐としている。人も街も移ろうこの地においてこの邸だけが楔のように平原に鎮座している。
広間も通路も飾りはなく、壁に掛けられているのは武器ばかり。探したところで肖像画も風景画も目に入らない。アーミラは二人の後ろを付いて歩き、この邸の主が怖い人だったらどうしようと、両手に持った杖を握り身を縮めた。
玄関広間から三方向に分かれる入口をガントールは右に進み、仕切られた半円を描く梁を潜ると次の広間に出た。そこには身を休める獣の前脚のように両脇から階段がこちらに向かって据えられていた。上には登らず腹の下を突っ切って通路を奥へ進むと窓の並ぶ廊下に繋がり円柱状の広間へと続いている。鼻先には紫煙が燻る香りが広がり、風に乗って細く揺らめく煙が滞留している。ガントールが向かっていたのは喫煙室だった。
先に立つオロルが喫煙室の中にいる人物に気付き軽く会釈をしたのを見て、後に続くアーミラは気を引き締めた。
視線を向けた先には、脂の染み付いた革張りの椅子に腰掛ける一人の獣人が、まさに口の端から紫煙を吐き出しているところだった。アーミラは交わりそうになった視線をお辞儀で躱すと、そのつむじに向かって声がかかる。
「……これはこれは、失礼。私の方から出迎えようと思っておりましたが、いつの到着になるか不確定だとガントールより申し出がありましてね」
思っていたよりも張りのある若々しい声にアーミラは顔を上げ、領主の言葉を聞きながらそれとなく観察する。若い声といっても三十は過ぎているだろう壮年の男で、謝る口ぶりのわりに椅子から腰を上げる様子はなかった。
こちらで待たせてもらいましたよ。と言う口の端に、肺に残っていた煙が混じり渦を巻く。
革張りは深い風合いの焦げ茶色で、もはや黒に近い。そんな椅子に寛ぎ肩幅以上に開いた脚は朱色の細袴に革靴を履いている。肘掛けに乗せた腕はだらりと垂れ、右手に挟んだ煙草は火をつけたばかりなのだろう。長さがあり火種は勢いがあった。軍衣のような前合わせは胸元の釦が開いていて襟巻も緩められている。今日の仕事を終えたというふうだった。顔にも疲労が張り付いているが、表情に弱々しさはなく爵位を持つ者らしい硬い眼差しでこちらに応えている。
顳顬から伸びる熊手のような角は、まるで平原を治める者の印……一種の象徴のようだった。
「わしらこそ夜分に申し訳ない。こうして招き入れて貰えただけでもありがたいことじゃ」
これはオロルの言葉。どうということはないが、隣に立つアーミラはその声音に妙な慎重さを感じ取った。……なにか考えがあるのだろう。
「重ねて、不躾ながらギルスティケー伯爵に頼みたいことがある」
伯爵は垂らしていた腕を持ち上げて煙草を咥える。
「なにかな?」
「この邸をわしらの拠点として使いたい」
後に続く沈黙に胸がざわついたのはアーミラだけだろうか。息を呑んでそれとなく隣のオロルを見て、次に伯爵の答えを待つ。というよりも、困惑して動けなかった。
着いて早々、邸を自分たちのものにしたいだなんて豪胆がすぎる。そもそもなぜここが欲しいのかもわからない。まさか外観を一目見て気に入ったというわけではないだろう。馬鹿ではないことだけはわかっている。彼女にしか見えないものがあり、どうするべきかを明確に判断しているはずだ。
対して伯爵は、まるで取り留めのない話題を聞き流すような態度だった。間に立つガントールも険しい表情こそ浮かべているがオロルの発言に口を挟まない。
煙草を吸い、一度肺まで入れて、弛緩して開かれた口から紫煙が吐き出される。
側に置かれた卓の灰皿にこつこつと煙草を弾き、灰を落とす。
「それは、ラーンマクが失われるということかな?」
「わしの予想では」とオロルは首肯する。
ゆらめく煙の向こう、伯爵は目を細めてオロルを見つめる。この先起こるラーンマクの失地という未曾有の危機が果たしてどれほどの実感を伴って耳に届いたか、アーミラは二人の会話にただただ立ち尽くしていた。
「随分と穏やかではない展望だな。先を見通すのは結構だが、戦争は遊びじゃない」伯爵はガントールに顔を向ける。「ラーンマクにはスークレイがいるだろう。継承者の務めは出征による士気の高揚だけか?」
言葉を投げかけるが語調は断定的だった。『前線の死守。それが継承者の務めだろうが』そう言っているに等しい圧があった。それとは別に、伯爵の口から発せられた何者かの名前……アーミラは気になったが、とても口を挟める雰囲気ではなかった。
「今日明日落ちるという話ではない。もちろん死守できるようにわしらは動く。
じゃが、それでも失地を許したとき、備えがいる。ここに拠点が必要なのじゃ」
「椅子と茶を」突然伯爵は明後日の方を向いてそう言った。
アーミラは肩をびくつかせ声をかけた方へ視線を滑らせる。こちらからは姿は見えなかったが、伯爵の位置からは従者が見えるところに待機していたのだろう。駆け出す足音だけが聞こえた。
「簡単な挨拶で済むと思っていたが……聞かせてくれないか。君の見ているものを」
ギルスティケー伯爵の邸の一劃、紫煙にけむる喫煙室では小さな円卓に椅子を囲い、三人はオロルに膝を向けていた。
オロルは注がれたばかりの熱い茶を一口啜って喉を潤すと、さてどう話したものかと考え顔で靴を脱ぎ捨て、用意された椅子の上に胡座をかいた。組んだ脚の膝下に覗く小さな裸足の指が曲げ伸ばしを繰り返して骨を鳴らす。
「わしの話をする前に、確認しておきたいことがある。ガントールよ、平原で何に襲われた?」
そう切り出され、ガントールが答える。
「トガの大群だよ。…いや、先導してたのは禍人だ」視線はアーミラの方に向いた。「集落を焼いたやつに違いない」
「え……」
思わず声を漏らしたアーミラは、一瞬驚いたように目を丸くしたが、口元は微かに吊り上がる。当惑に浮かべた笑みではないことをオロルは察している。次女継承の内に秘めた復讐心が、望外に手に入れた仇の足取りに心を弾ませたのだろう。
アーミラは両手を内股に挟み身を乗り出す。
「倒しましたか?」
その問いにガントールは首を振る。
「小賢しいやつだったよ。私にはトガを差し向けてウツロと戦っていた」
ガントールの言葉にアーミラとオロルは納得する。やはり平原に辿り着いて見た窪地はガントールとトガの戦闘の痕だったのだ。ではウツロはどのように戦っていたのか、視線を彷徨わせる。流れからしてこの先のことは本人から語ってもらいたいが、喫煙室に鎧の姿は不在だった。
「……姿が見えんな」
腹立たしげにオロルは呟く。
「ここに来てからまだ一度もみてません」とアーミラも続く。
不満を漏らす二人に対してガントールは訳知り顔で宥めつつ、小賢しいやつだったんだよと繰り返した。
ちょうど煙草を吸い終えた伯爵は名残惜しそうに煙を吐き、灰皿に押し付けて火種を消すと会話を本筋に戻す。
「ウツロとやらに話を聞かないと進まないのか?」
「……いや、よい」オロルはできることならば聞いておきたかったが、この場では些事として切り捨てた。伯爵の望み通り話を先へ進めても問題はないと判断したのだろう。「やはり前線は崩壊していると言っていいじゃろう」
伯爵は背凭れに身を落ち着かせて聴く体勢をとる。視線は発言の根拠を探るようだった。オロルは続ける。
「今日の朝からわしらはナルトリポカの集落に向かった。ガントールから聞いておるかもしれんが、昨晩襲われた集落の様子を見に行くためじゃ。昼前には用事を済ませたが、スペルアベルに向かう前に少し気になることがあってな。飯屋に寄った」
ここまで聞いてガントールは苦笑した。ほら……やっぱりオロルは寄り道してる。
飯だけなら結構だが、酔いが顔に出ないのをいいことに酒も嗜んだだろう。
「ただ昼食をとったわけではありません」と、アーミラが控えめに擁護するとオロルは勢いに乗って続ける。
「内地に位置しているはずの土地がこうも容易く、用意周到に襲われたのじゃ。敵の潜伏期間は年単位でも驚かん。南に逃げたとみせてまだどこかに潜んどるじゃろうから昼の時点では戻るべきか留まるべきか、判断に迷っていた……結果的には戻って来たがのう」
その考えはわかる。ガントールは素直な視線で同調してみせた。
「前線からここまで人の目を欺き紛れている間諜が、いつから活動していたのか、狙いはなにか……」
昼の飯屋となれば客入りは盛況だろう。二人はそこで情報を集めることにしたということか。
「それで、何か掴んだから合流を決めたんだな」腕を組んで先を促すガントールは、まるで伯爵の代弁者のようだった。
「行商人から聞けば、ずいぶん前から被害はあったようじゃ。畑に不審火が上がったり、人が行方をくらませたり、どれもトガの仕業じゃと恐れられておったが、暗躍しているのは禍人なのじゃろう」
「内通者ではなく?」
ガントールの問いにオロルは頷き、問いを返した。
「その目で見たのじゃろう?」
ガントールの言う内通者とは裏切り者のことを指している。
人種は獣人でも魔人でも賢人でも構わない。禍人側に肩入れし神殿を陥れるために動く存在。禍人が侵入している可能性を否定し、あくまで内通者がいるのだと考えるガントールの根拠は強力な防護結界に依存している。
ラーンマクに生まれ、神殿で育ち、前線派兵も経験したガントールにとって防護結界への信頼は厚かった。しかし、オロルはその信頼が揺らいでいるのだと指摘する。
「お主はその目で見たのじゃろう。額に角があり、言葉を交わし、集落を襲った禍人を」
「オロルが言いたいことはわかる。でも人に化けたところで中身は化物だ。内地に入ろうものなら――」
たちまち変化は解けてトガの姿を隠しきれないはず。禍人の姿を維持したまま内地の結界は越えられない。
「――何度か禍人が結界内に踏み込む光景を見たことがあるけど……あの結界は強力だよ。私にはあれをどうにかできるとは思えない」
そう言いながらガントールは眉間に皺を寄せる。確かに道理が通らないと自分の発言に首を捻った。スペルアベルで会敵した存在はナルトリポカ集落に火を放った。敵の口ぶりからしてもそれは間違いない。ウツロだって一戦目は頭巾で顔を隠していたとはいえ、間違いなく人の姿をした敵と戦っている。
「兎に角。ラーンマクに限らず前線は崩れる。わしが言いたいのはこの現状じゃ。
どうやっとるかわからんが、禍人は姿を維持したまま防護結界を突破する術を備えとる。トガどもが全員そうしないのは、その術が使えるものがごく僅かな、利口な者達だけなのじゃろう。そして少なくともそんな禍人は三人おる」
オロルは喫煙室での話し合いをまとめにかかる。
円卓の中心をこの邸と仮定し、灰皿を禍人領に例えて指で示す。
「三人じゃ。ウツロがナルトリポカの集落で戦った奴ら……その内一人は追い打ちの奇襲まで行い、逃げ果せた。残る二人は行方知れず……」
右手の人差し指は平原から灰皿の方へ滑らせ、左手の人差し指と中指で卓を叩く。
「なるほど」じっと話を聴いていた伯爵は重たく呟く。「挟まれているのか」
「うむ。狙われているのはここスペルアベルと四代目国家ラーンマクじゃ」
オロルの言葉に伯爵は腑に落ちたと言わんばかりに天を仰ぐ。継承者が出征しラーンマクを守ったところで背中から刺されてしまっては意味がない。それを阻止するために邸を寄越せという三女継承者の意図はガントールにもアーミラにもよくわかった。
ギルスティケー・セルレイ伯爵は頬杖をつき、薬指で下唇をかりかりと掻きながら沈思した。
「挟み撃ちをせずとも禍人は神殿を狙えばいい。背後を取らずとも心臓を刺せる……それをしないのは何故だ?」
「事情はわからぬが、憶測では話した通りじゃ。まず変化できる兵が揃わない。次に結界内で人の姿を維持し続けるのは消費が激しいのじゃろう。奴らはあくまで暗躍する間諜として闇に紛れ、結界の境目外側で機会を伺っている可能性が高い」
「うぅむ。心臓を刺すには背中に刃を立てる必要がある。神殿を狙えるのならとうにやっている……か」ガントールは忌々しく禍人領に配された灰皿を眺め下ろしていた。
「それをしないのはなにか事情があるのじゃろう。わしらを脅威と見ているかも知れんし、ウツロの妨害が慎重にさせているかも知れん。
それか、集落を襲ってわしらを二手に別れさせたのが敵の思惑通りと考えれば、さっさと合流したほうがよいと判断した」
「その判断が誤りだとしたらどうするかね」伯爵は問う。「君達が合流を選ばず、神殿に向かっていたらどうなっていた?」
「禍人が神殿に入り込んで居れば預けていたわしらの心臓の灯は消されておしまいじゃな。勿論、神殿の兵が三人の禍人相手に総崩れとは思わぬが、そのときは前線を捨ててでもわしらは飛んで向かう。
同様に、ここに合流せず神殿に向かい前線を留守にしたならば、ラーンマクと平原の失地により戦線が後退するだけじゃ」
オロルは毅然と胸を張る。誇れるような返答ではないが、今ここにいるのが最適解だという自信は示された。伯爵の薬指は再び唇に添えられたが掻く動きは止まっていた。
観念したように鼻で笑い、懐から二本目の煙草を取り出した。物陰で待機していた従者が燐寸をつまみ火を付けた。一息吸い込み、紫煙を吐き出しながら云う。
「……いいだろう。この邸は好きに使いなさい」
「賢明な判断じゃ。助かる」
「但し」伯爵は鋭く言い、人差し指を立てる。「私も好きにさせてもらう。『出ていけ』とは言われていないからな」
目つきは鋭いまま笑みを作る伯爵の発言は命知らずの蛮勇ではないだろう。一日の終わりに一服する姿は少しくたびれた風体ではあるが、たるみのない顔付きは辺境伯領としての矜持が伺えた。
オロルは好戦的な笑みを口の端に浮かべて了承する。
「それで問題ない。拠点と言ってもわしとガントールはラーンマクに出る。ここはあくまで後衛じゃ」
名前を呼ばれなかったアーミラは、その意味を悟って驚いた。
「この邸に私だけ、ですか?」
後衛の拠点。魔術による遠距離からの火力支援として不意に白羽の矢が立ったアーミラは預かり知らぬオロルの作戦に戸惑う。事前に何も伝えられていないのに、奪った邸を右から左へ譲られても……。
「案ずるな。伯爵も留まる」
「平原を守ればいいってことですか?」
「それだけじゃ足らん。わしらの背中も丸ごと守ってもらう」
「そんな――」
食い下がろうとしたアーミラを捻じ伏せるように一言言い足した。
「ウツロも居るじゃろう」
「ウツロ……さんが……」
では任せるぞ。そう言ってオロルは肩を叩き、喫煙室を後にする。まさかもう出ていくのかと声もなく目で追いかけたが、ガントールが後ろに付いて夕餉に誘っている。少なくとも一泊はするのだろう。
後に残ったアーミラは呆然と通廊を眺め、我に帰ると伯爵に一礼してそそくさと喫煙室を出て行った。腹が減ったわけではない。探しているのは鎧の姿である。
❖
平原に屯する者達もすっかり眠りについた頃、夜店通りは灯りもなく、青い月明かりだけが心細く一帯を照らしている。ギルスティケー・セルレイ辺境伯領主の要塞めいた邸の屋根の上に月光を浴びる鎧はいた。
首を失ったその見た目の悪さからウツロは衆目に晒されるのを避けるため一人で逍遥していた。邸の従者ともすれ違わないように、通路を右へ左へと彷徨い歩いたあとは、夜の帳が降りると、ウツロは屋根の上で雨樋の彫刻のようにじっとしていた。神殿で過ごした日々とさして変わりのない夜だったが、ウツロは携えてきた得物の槍も失い、穂先の刃も鈍、首に至ってはスペルアベルの兵に預けたきり戻ってこない。心持ち落ち込んでいるように見えた。
その丸めた背中に鋒が向けられる。
「おい」
気配もなく背後に立っていた者にウツロはゆっくりと振り返る。声をかけられるまで気配を感じ取れなかったのだろう。首がないので相手の姿を捉えているのか怪しいが、目の前に立っている男に警戒はしていなかった。敵ではないと理解しているようだ。
男の方も斧槍を離して石突を屋根につく。着古した軍衣は土埃に汚れているが伯爵お抱えの兵と同じものである。異様なのは、この夜半にあって面頬で顔を隠していることだった。
「お前さん」
と発する声が唖として、赤子の喃語か老人の舌足らずに聞こえた。だが目の前の顔を隠した男の体躯は三十路ほどだろう。若さは失われつつあるが獣人種らしい隆々と引き締まった筋肉が軍衣の内側に包まれていた。
男は続ける。本来はもっと聞き取りづらい言葉だがここでは意訳して記す。
「ガントールの連れだろう」
鎧は頷くが、頭がないので首の板金が軋んだだけだった。
取り敢えずは立ち上がってみたものの、問いかけに答える術がなく立ち尽くすウツロを、階下から指さすアーミラがいた。
「あ」思わず漏れた己の声が夜闇に存外大きく広がり、アーミラは口を両手で押さえる。そして顰めた声音で呼びかけた。「探しましたよ」
ウツロは前庭にいるアーミラを見下ろし、次に面頬の仮面の男に向き直る。だが男はもうそこにはいない。幽霊でも見たか、ウツロは屋根の上を見回して姿を探したが、結局見つけることはできなかった。
❖
「何をしていたんです?」
あんなところで、とアーミラはちぎったパンをつまむ手で上を示す。
今二人がいるのは邸の二階にある食堂の一劃。二人は前庭で再会し、首を失った経緯も、集落で瀕死の育ての親の安否についても一頻り伝え合った。晩飯が用意されているとあって卓越しに向かい合う形で椅子に腰掛けていた。
ウツロは慣れた手つきでアーミラの前腕に指筆で返答する。
――隠れていた。
「何からですか?」
二人の会話は密やかながら食堂内に響いていた。オロルとガントールはいなかったが、食事を用意した従者の耳には次女継承者の独り言だけが訥々と届く。
「怖がらせてしまう……まぁ、ないですもんね」
「幽霊を見た?」
「どうでしょう、仲間だと思ったんですかね」
そう言って悪戯っぽく微笑む。向かい合うように腰掛けている鎧の魔導具は笑いこそしないが見守っているような雰囲気である。声を発さないのは会話の様子から見てとれた。従者は目を伏せてじっと待機するよう努めたが、物珍しさからついつい悟られぬように視線が引き寄せられる。
片方だけの会話は続く。従者は話の流れを掴もうと耳を澄ませている。
「ところでウツロさん、これからのことは聞いていますか?」
長い沈黙。どうやら指で書いている返事の内容が長いようだ。
「自信はありますか?」
「そうですよね……経験もありますし、先日だって今日だって戦っているんですから、あなたは心配ないですよね」
そう言って励ます次女継承者の表情は暗い。
「私は……まだ戦ったことがありません……。幼い頃に修行は修めていますが、前線で通用するのか不安なんです」
耳をそばだてていた従者は思わず眉根を寄せる。女神を継承した娘が、今日まで一度も戦ったことがないと言ったのか……?
「『何故出征するのか』……ですか? そういえば言っていませんでしたね。私は……自分を変えるため……この戦いに、挑みます。無くした記憶を取り戻して、強くなれたらいいなって」
手に持っていた器が卓に置かれる音。
一拍の沈黙。
「――でも、約束したシーナさんもあんなことになって」
継承者の声は、消え入るほど小さくなった。
気を取り直し気丈に声を張る。
「そういえば、火を放った禍人と戦ったんですよね?」
青い瞳が鎧の首の穴を見つめる。どうでしたと訊ねているのだ。
鎧の指が再び言葉を書き始めた。走らせる運筆を追いかける。
従者は己の勤めをひととき忘れ、好奇心に負けて文字を読み解く。
――やつは火を操るわけではない。熱を操っていた。
「水を出して冷やすこともできる……ってことですか?」
――火を出す、水を出すというわけではない。掌に集めた空気を操っているように見えた。
次女継承者は鎧の返答を見届けて考え顔で卓に灯された蝋燭の火を眺める。既に器は空、客室で就寝してもよい頃合い。
従者は無闇に燃焼して減っていく蝋燭を勿体無いと思っていた。そんな思いが伝わったのか、継承者は立ち上がると盆の皿を纏めて食堂を後にした。鎧も後に続く。
従者は皿を片付けながら夢想する。私なら、熱を操る敵とどう戦うだろう……。
❖
「そもそもの話なのですけど」
アーミラは暗い廊下を進みながら、後ろを振り返らずウツロに言う。
「どうしてあの夜、貴方は集落の異変に気付くことができたんですか?」
問い掛ける声は固く、初めて会った時のように距離を感じさせた。
どこに返答を書けばよいのか、ウツロは歩みを止める。
「はっきりしておきたいんです」
アーミラは数歩分の距離をとってウツロに振り返り、向き合った。明り採りの細い窓から入り込む弱々しい月光が彼女の顔を青く浮き上がらせる。
アーミラはナルトリポカの集落の一件でウツロに感謝している。アダンとシーナが一命を取り留めたのは間違いなく鎧の功績だ。しかし同時に不可解な疑問もあった。
何故ウツロは異変に気付けたのか。
内地に潜む間諜と秘密裏に繋がり、継承者達の動向を敵に流せる人物は誰なのか……。疑いたくはないが、ウツロが怪しかった。
直感的には彼は違うと感じている。だが個人的な感情を抜きに考えれば、ウツロは単独で行動し二度も会敵している。もしウツロがわざと敵を見逃しているとしたら……? 戦うふりをして、伝言を受け取っているとしたら……?
裏では禍人と紐帯を持ち、こちらの情報を都度流していると考えれば、辻褄が合ってしまうのだ。
「あの夜、集落が襲われていることに気付いたのではなく、知っていたんじゃないですか? そこで落ち合い、情報を流した。違いますか?」
アーミラは腕を差し出す。月光に淡く照らされた肌が、うっすらと汗ばんでいた。
ウツロはその腕を掴み、指先で触れる。
――『知らなかった』と書けば、信じるのか?
「それだけでは信じるに値しません。異変に気付いたのは窓を見たからなのでしょう? でも、集落は死角でした。窓から見れるのは山陰だけです。それに、たとえ山に火の気が見えたとしても、夜は炉の炎が明るく燃えて、遠くの火事に気付くことなんてできないはずなんです」
ウツロは言葉を選ぶような態度で沈黙して、しばらくしてから指を滑らせる。
――見えざるものの声が聴こえたのだ。『あそこに敵がいる』と、『走れ』と。
「また幽霊の話ですか……?」
今宵屋根の上で見たと語った仮面の男の幽霊話。すぐに消えてしまったと言うが、集落の危機を伝えたのは見えざる者の声だという。
はぐらかされているのか、冗談のつもりか、アーミラには測りかねた。
――俺が駆け出すとき、お前たちは行方をくらましていたな。
「それは、偶然杖の中に」
――偶然か。偶然俺が一人になった。これも俺が裏切り者だから仕組めたのか。
ウツロの指が荒々しく動く。
――継承者となった初めての夜、俺はお前の夜警をしていた。寝首を狙う刺客はいたさ。みんな殺した。
――もし俺が裏切り者なら、出征はガントールとオロルだけになっていただろう。
「あ、あの……ごめ――」
明確な憤りの言葉にアーミラはたじろぎ、思わず謝ろうとするが、それよりも早くウツロは手のひらで制した。
――謝るな。俺も、アーミラも、言葉で弁明しても意味はない。
――俺の無実はこれからの行動で示す。
言い捨てるように走り書きをして、ウツロは階段を降りていった。夜警に出たのだろう。
取り残されたアーミラは呆然として、ウツロを見送ることしか出来なかった。
怒っていた。明確に。『裏切り者』と言われることが、鎧にとって何より耐え難いことのようだった。首を失って魔導具然としていく見た目に反して、内に備えた人間性は蓋を開けて一層強く香り立つようだった。
平原に訪れる夜も深まり、天上から照らす月明かりの下を雲が流れていく。山間と違い平野の気候は雨もなく昼間の戦闘も嘘のように皆が寝静まり戦線に休息が訪れる。
セルレイ辺境伯の邸では特別なもてなしもなく継承者達が客室を与えられ、それぞれの時間を過ごしていた。
厠を探し二階を徘徊していたのはオロルである。彼女は勝手のわからない邸を彷徨ったあと、通路の行き止まりに辿り着く。どん詰まりに設けられた扉は見た目からして厠らしからぬ大きな扉だが、一応は確かめるために近付いた。
漏れ聞こえる会話に足を止める。
声からして、この部屋は伯爵の寝室だろう。どうりで大きい扉なわけだ。
話し相手に招かれているのはガントールのようだ。
積もる話に花を咲かせる和やかな談笑を盗み聞くのも野暮……どうやら二階には厠がなさそうだと、オロルはそそくさと踵を返す。
己に与えられた客室まで戻るとちょうどアーミラと鉢合わせる。一人のようだ。
「ウツロには会えたか?」
「はい。今は夜警に出ています」
「精が出る」オロルは欠伸混じりに言う。気怠そうな瞳は充血していた。これはまた相当酒を飲んだなと、アーミラは思う。
「でも」
「……なんじゃ?」
アーミラはくだらない疑問であると承知して言い淀むが、なんでもないと誤魔化す方がオロルの機嫌を損ねそうだと考え、言うことにした。
「首がないのに見張りなんてできるんですかね……? まあ、できるからやってるんでしょうけど」
「わからん。やりたいようにさせておけ」
興味もなくオロルは言い、階段を降りていく。冷たいようにも思えるがウツロに対するオロルの放任主義は一種の信頼の形とも思えた。あいつは使える。任せておけば問題ない。ということなのだろう。頭の良いオロルが鎧の行動を疑わないのなら、自分の推理はきっと稚拙だったのだ。
実際ウツロはこの旅の中で貢献している。ガントールも。一方で私はどうなのだろう……今宵は無力感に苛まれて虚しさに包まれていた。
アーミラは見えなくなったオロルの背中を見つめる。彼女が何を思い、私を邸に置くことを決めたのだろうと考える。
もう誰もいない廊下に問う。私は言葉通り後方支援ですか? それとも足手纏いですか……?
❖
長い一日がようやく終わり、スペルアベル平原に朝がやってきた。
各々異なる道中を辿って合流したこの平野に朝日を遮るものはなく、邸で一夜を明かした者達は示し合わせずともぞろぞろと寝台から身を起こす。内地のような宿とは違い前線に近いとあって客人の世話は必要最低限のようだ。邸内に人の気配は疎らで、おそらく伯爵一人を世話するのに従者達は早起きの必要がないのだろう。
目を覚ましたアーミラは、前の晩に自ら用意した水差しから一杯の水を注いで喉を潤し、慣れた手つきで寝台を整えて部屋を出ると通路脇に備えられた水桶で手拭いを湿らせ顔を洗った。
奥の部屋からも誰かが起きた気配がある。扉を開く音、足音の歩幅から振り向かずとも判別できた。
「おはよう」
ガントールだ。
「おはようございます」アーミラは手拭いを二つ折りにして指にかけ、挨拶を返す。
「外が明るくなると急に暑くなるな」
窓外の景色に視線を向ける。殺風景な朝があった。
この地域は風通しがいいので夏でも湿度がなく、マハルドヮグ山脈に降る夜雨もここには届かない。疲労もあって久しぶりに夢も見ずに深く眠った気がするが、ガントールの言う通り、日が登ると一帯が日光に照らされて温度は急激に上がり、喉の渇きにいやでも目が覚める。
「起き抜け一杯の水を飲まないと干物になってしまうよ」と笑うガントール。くしゃくしゃになった長い緋色の髪が昨晩の寝相を物語っていた。
はだけた寝巻きから晒している右腕の義手は、断ち切られた二の腕の膠原質がよく見える。目脂を擦りながら大口を開けて欠伸をすると、ガントールの獣人種らしい牙の生え揃った口元に視線がつい吸い寄せられた。
「二人は前線に行くんですよね? 今日出るんですか?」
アーミラの問いにガントールは間延びした生返事の後、簡単に返す。
「そうだよ。遅くても昼には。オロルの準備が整い次第かな」
水桶に手を濡らし、手櫛で寝癖を整えていくガントールの背後に立つアーミラは、躊躇いがちに言葉を選ぶ。
「私、だけ……ここに置いていかれるのですが、それで、私はどうすれば……?」
「どうって、ここを守れとしか言えないな。状況が悪ければ私たちはこの邸まで戻ってくることになるんだから」
ガントールは言いながら髪を二つ結いに整え、アーミラに振り返る。
濡れやすい瞳に、不安そうな表情。藍鉄色の髪が俯いた少女の顔に影を落としている。三人が共に前線を目指すこの出征において、スペルアベルに置いていかれることに負い目を感じているのがわかった。
「急ぐ必要はない。しばらくは後方で戦況を見ながら経験を積んでほしい」
ガントールはそばに寄り添い、一度頭を撫でようとして手を止める。そして行き場に悩んだ手のひらで肩をそっと掴んだ。そして続ける。
「アーミラは、生き物を殺したことはあるか?」
優しい声音だが、言葉の意味は真っ直ぐで残酷だった。
アーミラは長女継承者がこれから言おうとしていることを予感して、首を振る。
「あ、ありません……」
「敵が化け物であろうと、生き物を殺める行為に心を慣れさせなきゃいけない。
初めから抵抗なく殺せる人はいないんだ。……どんな戦士でも初陣は後方から。誰かの取りこぼしにとどめを刺したり仲間の手当をしたり……そうやって血に慣れた奴、その場その場で決断と行動ができる奴から最前線に配置される。
だから邸に置いていかれるのは能力不足ってわけじゃない」
「……はい」
慣れた奴から前に。
アーミラはその言葉が持つ生暖かくどろどろとした耳触りに安心できなかった。この邸に置いていかれることが一人の新兵としての順当な評価であると励まされる一方で、武勲を立てた者はより命がけの境遇へ配される先行きの不穏さ。
強くなりたいと願った。アダンとシーナを酷い目に合わせた奴に対する怨みだって、この胸に刻まれている。――しかし、殺し合う場所に身を置く覚悟も経験もない。ガントールとオロルが言外に含んだ言葉の意味を理解し、アーミラは肩を落とす。
前線に向かうには未熟。
ついて行きたいと、言えるはずもなかった。
「姉ども」
水桶の前に立つ二人の後ろ、音もなくオロルは立っていた。
ぎょっとして目を丸くするのはアーミラだけではない。ガントールも思わず背を強張らせて身構えたほどだ。時折披露してみせるオロルの神出鬼没な移動術は、三女継承者の力に由来するものだと二人はうっすらと感じていた。
そんな二人の反応に機嫌をよくしたのか、オロルの眠たげな目元に笑みが浮かぶ。
「おはよう」
自堕落な普段の振る舞いからして、朝の挨拶など口に出す質ではないだろう。オロルの言葉が妙に意地悪く聞こえる。
「ガントールよ。今日は昼前にはここを出るつもりじゃが、問題はないか」
「ああ。朝食後にセルレイから邸に仕えている人達の紹介があるからそこは同席するけど、問題ないと思う」
ふむ。とオロルは頷き、今度はアーミラに向く。
「ということらしい。間諜が既に紛れているということはないじゃろうが、邸の者等の顔を覚えておくように」
「はい」
「それと、ガントールはああ言うが、お主の初陣は後方というだけではない。わしらの背後を狙う敵が現れた時、戦場は前も後ろもない。表と表じゃ」
「はい」
間諜の禍人が平原を攻めてきた場合、挟まれる形でこの邸は後方という立場を返して前線となる。雑兵を相手にするだけのぬるい初陣と思うな――オロルの言わんとすることを受け止め、アーミラは確かに返事をした。
伝えることは伝えたと、オロルは会話を切り上げて二人の間に割り込むと水桶の前に立つ。左手に握る貝殻の紐を解いて赤い顔料を湿らせ溶かすと、薬指で両頬に塗る。その姿を何とはなしに眺めていたガントールは腑に落ちたように呟いた。
「何か足りないと思ったら、卜部族の化粧がなかったのか」
得意げな表情で振り返るオロルに、アーミラは何故か少し自嘲めいた笑みを見た。
❖
皆で食堂に向かい朝食を摂ったあと、全員がこの場に残り集まった。
ガントールから伝えられた通り、邸に住み込みで仕えている者の顔合わせである。
卓を並べた下手側に継承者達と伯爵が座り、上手側の壁に沿うように従者達が立ち、紹介の出番まで待機している。ウツロは椅子に付かずアーミラの席の後ろに控えていた。
従者と兵、合わせて三十人。獣人種と魔人種が大半で賢人種の数は少ない。兵士は男所帯で、女は皆従者だった。
「警備の都合もあるので手短に。討伐隊隊長から紹介し、顔合わせの済んだ兵士から任務に戻るように」
伯爵が伝えると討伐隊は声を揃えて返事を返す。食堂は男達の発した声の残響に揺れる。
一糸乱れぬ統率。練度の高い兵であることがすぐにわかった。
「彼らが私の兵だ。街では様々に呼ばれているが特に決まった名はない。強いて言うなら討伐隊だな」
伯爵は短い説明を挟み、隊長を手で示した。
「こちらが討伐隊長ニールセン。もし兵を動かしたいときは私ではなく彼に頼んでくれ」
名を呼ばれた男が一歩前に踏み出して背を反らし胸を張る。
「討伐隊長を務めるニールセンと申します」
よろしくお願いしますと折り目正しく一礼する。力に驕った様子もなく、歳は継承者達より少し上だろうか、髭もなく青ささえ残る若人だ。顳顬に生えた頭角も髪も短く小綺麗で全体的に清潔感のある青年だった。
挨拶を済ませた者から食堂を出ていくという段取り通りニールセンは警備に戻る。背中を見送り、オロルは呟いた。
「あれが隊長か。若いな」
「兵の入れ替わりはどうしても激しくなる。あれで入隊年数は長い方だ」
伯爵は当然のように言い、次々と兵の紹介を進める。男達は名を名乗り、一礼。一挙手一投足同じような振る舞いで食堂を出ていく。アーミラは暗記しようと集中して臨んでいたが繰り返される光景に顔と名前を覚えられる気がしない。半分を過ぎたあたりで最初に覚えたはずの数名は何が何だかわからなくなって覚えることを諦めた。せめて隊長の名前だけ覚えておけば今後のやり取りに支障はないだろう。
顔ぶれは皆若く、おそらくは一定の期間兵役を全うした者は除隊する規律でもあるのかとアーミラはぼんやり考えた。
「私兵は以上だ」
二十四名の兵達の紹介を終えて食堂はすっかりがらんとした。残るは侍女ばかり。
何か質問はあるかと伯爵は継承者側に顔を向ける。邸に残ることになるアーミラを見るが、アーミラは視線から逃げるようにガントールとオロルに目配せをした。特に聞くことはないと二人は目で応える。次いで後ろに立つウツロの様子を伺い、ふと思い出す。
「あっ……あの、もっと歳が上の兵隊って、いませんでしたか?」
逃げていた視線が交わったと思えば妙な質問をする。伯爵は怪訝そうに答えた。
「いや、いないが」
内向ぎみに吃りながらアーミラは質問を重ねる。
「では、か、顔を仮面で隠した方は……?」
細い喉から発せられるか弱い声は、静かな食堂でかえって皆の耳を傾聴させた。壁を背に立つ従者達の緊張の息遣いに、あまり良い話題ではなさそうだと肌で感じる。
仮面で顔を隠した兵はいるか――そう聞かれたとき、伯爵の表情から僅かに余裕が減っていた。
「その男を見たのか?」
伯爵は重たいものでも背負うように姿勢を丸めて卓に両肘をつき、指を組んで親指の腹で顎を支える。見てはいけないものを見たのだと咎めるような、険のある口調だった。
本当に亡霊なのかもしれない。アーミラは小刻みに震えるように首を振る。
「いえっ、いえいえ……私は見てないです……ウツロさんが……」
なすりつけるように言い逃れをしたが、実際アーミラは見ていないのだ。
厄介ごとの気配にオロルとガントールは口を揃える。「またウツロか……」
当の目撃者は名を挙げられても置物のように微動だにしない。伯爵は視線厳しく目を細めるが首のないウツロを相手にしては睨む甲斐もないだろう。やがてため息をつき椅子の背もたれに腕を回して姿勢を崩す。煙草を取り出そうとした手が止まる。食堂では吸わない約束なのか、従者側からは口を引き結んで無言の圧力がかかったのをアーミラは感じた。
「……あいつは兵ではない」観念したように伯爵は言う。「関わることもないだろうと、この場に集めてもいない」
昨晩ウツロが見たものは幽霊ではなかった。しかし一人だけ除け者とは、邪険な扱いを聞いて思わず可哀想だとアーミラは言いかけた。喉元まで出かかった言葉を呑み込む。
仮面の男は、すでにそこにいたからだ。
いつからいた……?
どこから入ってきた……?
アーミラは思わずオロルの様子を窺う。神出鬼没の移動術ならば彼女に勝る者はいない。私に見えずとも彼女には見えたのではないか。そう望みを託して見つめたオロルの横顔には余裕の笑みが浮かんでいた。
「『兵ではない』と言っておったが、見たところかなりの手練……なぜ兵にせんのじゃ?」
オロルの言葉に伯爵が答える。
「しないわけではない。こいつは元々兵だった」
「退役か」
「そうだ。役目を終えた以上、継承者に紹介する必要はない」
それらしい事を言うが納得はできない。退役した兵だというが、本人を前にして『こいつ』だとか『紹介する必要はない』とか、いやにぞんざいな扱いだ。それに追求を拒むような口ぶりも気になる。
「役目を終えたにしては、まだ使えるように見えるが」
「生き延びるのも一苦労な役目だ。五体満足な内に余生を過ごしてもらう」
「……本人の口から話を聞くことはできんのか? おいお前、名は何だ」
「やめろ。答えなくていい」伯爵は制するように仮面の男に言い、椅子から立ち上がりオロルの視界を遮る。「こいつの名前はイクス。元兵士だ」
「住み込みか? 夜警をしておるのか? 忠誠心はまだ現役みたいじゃな」オロルは尚も仮面の男に問いかける。金色の瞳は目の前の伯爵を透かして仮面の男を見つめ続けていた。
「おい、無礼だろう」伯爵の声は怒気を孕み、卓に乗せた手は拳を握る。
「オロル、そのへんにして」と、ガントール。
「では、最後にしよう。なぜ退役した兵を邸に囲っているのか、教えてもらえるか?」
オロルは淡々とした態度で質問をぶつけた。伯爵は口籠りながらも返答を絞り出した。
「……私はこの地を護る領主だ。従える者は、除隊した者も含めて、その命を預かる責任がある」
言葉を慎重に選んだ風だった。
アーミラはこの場に沈黙が広がる気配を感じた。が、オロルはあえて詰め寄らず小癪に笑う。
「まぁ、よい。数に入らぬ兵なら、わしらにもおるのじゃから」
伯爵に倣い背凭れに腕を回して後ろに首を回したオロルは顎でウツロを示した後、皮肉混じりに続ける。
「素性の知れん顔の無い兵士……アーミラは気が合うんじゃないか?」
そんな言葉にガントールは冷や汗を浮かべながら笑い、伯爵も小さく苦笑する。オロルはその気になればもっと詰めることもできただろう。感覚的には伯爵の襟を掴んでいるようにさえ見えた。それをぱっと離し、見逃した。
糾弾するつもりはないという継承者側の意思表示に多少なり場が和んだ横でアーミラはほっとするのも束の間、一人閉口する従者を視界の端に捉える。冷や汗を乾かす微風のような愛想笑いが溢れる食堂に、一人陰気な侍女がいる……あれは昨晩飯盛りをしていた女だと気に留めるが、アーミラは顔を向けず、努めて気付かないふりをした。
「邸の人間がこれで本当に全部なら、紹介の続きを」
オロルが仕切り直すと伯爵は同調し、従者の紹介に入る。六人の侍女達は魔人種のみの構成で、主な仕事は邸の清掃と主人の世話である。
一人ずつ名前を紹介されるが、アーミラはほどほどに聞き流していた。覚える対象を絞っている。あの一瞬、笑みもなくこちらを見ていたあの侍女の名だけに……。
「――次にこちらがナル。主に炊事を担当している従者だ」
前に並ぶ数名の従者の紹介と名乗りが終わると、ついに伯爵は目当ての侍女を手で示した。
促されるままにアーミラは侍女の方へ顔を向け、それとなく観察する。やはり昨晩に見た飯盛りの従者である。
侍女は裾を捌いて一礼し、名乗る。
「従者のナルです。どうぞお見知りおきを」
小さな尖り耳に日に弱い白い肌。アーミラと同じ魔人種でも背丈も歳も幼く見えた。
従者が身に纏っているお揃いのお仕着せは裾が長く地味な作りで、汚れが目立たないように暗めの色で統一されているが多少なり色味が異なっていた。赤茶けたもの、深緑のもの、銘々に異なるがナルと名乗った女はやや黄土色のお仕着せである。肩口で切り揃えられた髪は栗色で、全体的な印象は柔らかいが、顔の作りはあどけないなりにやや冷たく、表情に乏しい。
他の者たちと同じように伯爵はさっさと次の従者の紹介をする中アーミラは笑わない少女をまだ見つめていた。飯盛りの従者であるナルは食堂が持ち場であるため紹介後もまだそこにいたのだ。
どこか気丈な振る舞いと、顔に張り付いた膨れっ面。初めは怪しい人物ではなかろうかと警戒したがこうしてみると笑みのない表情にも推し量れるものがあり共感できた。
アーミラはナルという少女に自身を重ねていた。幾つなのだろうか、周りの侍女と比べて頭一つ低い背丈で粛々と働くその姿……戦災孤児か。きっと親はいないのだろう。
もし私が流浪の民として内地に逃げ延びなかったらこうして生きていたのかも知れない……と、思い馳せているアーミラは頭蓋の内側が妙にくすぐったい気持ちになった。ぴりりとした微弱な雷が脳内を駆け巡ったような感覚の後に、いつか見た夢を思い出す。
それはひどく曖昧な遠い日の思い出。視覚と聴覚の記憶だった。
「……、ア………ラを……」
幻聴のように脳裡に繰り返される声。
食堂の椅子に腰掛けて残り数名となった従者の紹介を聴き流しているとき、アーミラは内側から響く声に意識を引き摺り込まれた。
「どうか、……ミラを……」
己にだけ聴こえる幻聴は次の刹那には記憶の奔流として一息に脳へ流れ込む。
アーミラの意識はスペルアベルから離れ、時を遡っていつかのどこかへと辿り着いていた。
それは、誰かの腕の中だった。
視界を覆う人影が声の正体か。せわしなく、なにかに追われているかのように落ち着きがない。私を抱きしめる人物は、別の誰かに向けて私を譲り渡すようにその腕を解いて離れてしまう。繰り返されていた声が誰に向けての言葉かはわからないが、ぼんやりと映るその人の視線は私の頭上を見つめていた。きっと幼い頃の記憶なのだろう。彼は子供の私ではなく背後に立つもう一人の大人に向けて伝えていたのだ。
「どうか、アーミラを――」
背後に立つ大人は、彼の言葉に頷きを返した。決意の息遣いだけが背中越しに聴こえた。
場所は室内と見えるが窓は小さく、棚に遮られて射し込む光は埃を照らしている。
私の視界は不意に浮き上がり、彼とは別の何者かに背後から手を回され抱きかかえられると、抵抗することもできず運び出される。
高くなった視点で、彼の顔がこちらを向いた。目も鼻も、輪郭さえも靄が晴れず、鮮明には思い出せない。こもって響く声音はどこか朧げで印象を掴み取れない。ただ男性であることだけが理解できた。もしかしたら彼は父なのかも知れない。
「いつか、必ず…………から……」
部屋に取り残された男の声は遠くなり、小窓から射し込んでいた光も届かなくなる。一面は闇に覆われ、唯一感じるのは私を抱えて走る何者かの切迫した息遣いだけ。喉から出る荒い呼吸は女性のようで、心当たりがあるとするなら師匠マナ……いや、若い印象を受ける。では母なのだろうか……。
思い出したのは短い夢だ。
いつか見た夢だ。
でも夢ではなかったのだ。
この記憶は過去、己の身に起きた出来事なのだと確信する。
体感ではほんの一瞬だった。我に返り、隣に座るオロルとガントールは私の異変に気付いてはいなかった。
去来する記憶の断片が不意打ちで流し込まれ、後に残る懐古の余韻がじんと胸に染み込んで、アーミラは悟られないようにそっと涙を指先で拭う。
まさか幼い侍女が記憶の呼び水となるとは全く予想だにしなかったが、それでもアーミラは静かに打ち震えた。断片的だが記憶を取り戻している。決断は間違ってはいない。ここまで来て良かった。そう思えた。
前線へ向かえばさらに思い出せることがある……そんな予感がしていた。
❖
昼が近づくにつれ前線側からは遠雷のような不穏な音と地響きが届く。邸の者は「ただの砲撃でしょう」と簡単に言うが、アーミラは気もそぞろだった。いつこちらに流れ弾が飛んでくるか、窓外を眺めては落ち着かない彼女に対して、珍しくオロルまでもそわそわとしていた。
「ここ最近は前線の衝突も激しくなっていると聞いとる」
オロルは窓辺に立って南側の景色を睨む。
ごろごろと雷雲の迫るような恐ろしい音だけが届くが、平原の地平に黒雲の影はなく向こうに広がる戦火は塵のような土煙でしか窺えない。目を凝らしても望めない遠くの地でどれほどの命が血を流し倒れているのか、未だ実感が湧かずアーミラは胃が引き攣るような空腹感と吐き気に顔色を失っていた。
「オロルさんでも、怖い……ですか?」
アーミラは問う。
てっきり「怖いものか」と一蹴されるのだと思っていた。
「当然じゃ。非死の加護を受けたとはいえ怪我をすれば痛みはある。ここから先は命がいくつあっても足りん」
南方を睨んだまま答えるオロルの手が固く握られている。
手袋の下に隠している異形の指がささくれて、拳の輪郭がぼこぼことしていた。
「よいかアーミラよ、怯えていては戦えん。じゃが恐れを失ってもいかんのじゃ。
なんのために戦うのか、答えが見つかった時、お主はラーンマクへ来い」
そう言い残してオロルは窓辺から立ち去り、廊下の先に待つガントールと合流する。振り向かず階段を降りていく彼女に代わり、ガントールは「行ってくる」と手を振った。
手を振りかえすアーミラは切に二人の無事を祈るばかりである。
❖
「けっこう信頼してるんだな」
ガントールは言う。
スペルアベル平原ギルスティケー辺境伯の邸から南へ進み、二人は町の外れに出ると柱時計を顕現させて馬の代わりとした。この脚ならばラーンマクまでそうかからないだろう。
「……なんの話しじゃ?」オロルはとぼけてみせる。
「アーミラのことだよ。実力は見たってことでしょ? じゃなきゃ邸を任せるなんてできない」
「ふん」オロルは鼻を鳴らす。「さぁの、あやつはよく愚図るし泣いてばかり、ここまで一度も戦ったところを見ておらん」
「え」
ガントールは巨大な蜘蛛の頭の上、胡座をかいた猫背を伸ばす。
「大丈夫なのか……?」
オロルは答えず、代わりに流し目でガントールを見つめる。
ややあって口を開く。
「あやつ……アーミラは心に暗いものを宿しはじめておる。おそらく自身が継承者となる選択をしたことで、集落一つを犠牲にしたと考えとるのじゃろう」
至極真面目な物言いにガントールは黙って続きを促す。
「どんな人間も、支払った犠牲の数だけ後戻りができなくなる。賭場で負けた者が損失を取り返そうと躍起になり賭け金を増やすようにの。
……集落という犠牲を払ったアーミラは、この先納得のいく見返りが手に入るまで継承者の使命を望んで背負い続けるじゃろう……それが敵討ちか、領地略奪か、戦争の終わりか」
遠く前線を睨むオロルの視線は、何を見るでもなく、むしろ全てを見通すような賢しく世を憂う眼に思えた。
ガントールは胸の奥にちくちくとした痛みを覚える。継承者の道にアーミラを引き摺り込んでしまった罪悪感を噛み締めて奥歯にぐっと力がこもる。
後悔しないために私たちはその場その場で選択し、最善を尽くす。
短期的な正解が長期的にも普遍の正しさを維持できるかは怪しい……積み上げたものがあっけなく崩れ去る無情は世にありふれている。
それでも今は、この道が正解であると信じるしかない。断罪の天秤を持つ以上、正義を疑っては行けないのだ。
そういう意味では私たちもまた、少なくない犠牲を支払っているのだろう――ガントールは決意を握るように拳を固める。
オロルは続ける。
「あくまでこれも最善策じゃ。わしにできるのは、知恵を絞ることだけよ。
……それで言うなら大丈夫なのか?」
切り返す言葉に今度はガントールがとぼける。
「ん? 何が?」
「アーミラを心配している余裕がこの先あるとは思えんぞ」
腐した顔のオロルの視線。前方に広がるラーンマクの景色は見紛うことなく戦場だった。
❖
激動の数日を過ごしたアーミラにとって、その後の日々は肩透かしなほどに平穏だった。
敵襲を警戒して数日、間者を警戒してまた数日、何もないまま一週間が過ぎようとしていた。
アーミラは伯爵から邸を譲り受けているとはいえ、討伐隊も従者も毎日の業務に変更は無かった。結局のところアーミラは手持ち無沙汰の居候に落ち着いている。
この体たらくに苦言を呈したのは炊事場を切り盛りしているナルである。齢十二にして朝な夕な齷齪と働き、朝餉から夕餉の献立をこなす少女からしてみれば、突然やってきた次女継承者は主から邸を横取りした挙げ句、日がな一日何もせず、飯時になると食堂で飯を食うだけの不躾な客人だった。
ナルは不快そうな表情を隠しもせず、腰に手を当てて言い放つ。
「ねぇ、貴女って穀潰しなの?」
単刀直入とはこのことか、真っ直ぐに突き付けられた言葉の鋭利さたるや、まるで鋭利な短剣を突きつけられたようにアーミラは仰け反り渋顔になる。
「うぅっ、す、すみません!」
申開きもできない現状はアーミラも重々承知だった。まさかこれほどまでに何事もない日々が続くとは想定外だったのだ。
とはいえそんな事情は少女には通じない。いきなりやってきて食い扶持一つ稼ぎもしないのに要らぬ配膳仕事を増やしている不満はこの一週間で溜まりに溜まっていた。
「この言葉は知っているでしょうね『働かざる者食うべからず』って」
「本当におっしゃる通りです」
「今度からお金取るからね!」
眉を吊り上げ捲し立てるナルの剣幕にアーミラは塩をかけられた蛞蝓のように小さく萎みながらひたすらに謝罪の言葉を繰り返していた。飯を食うはずが責め立てられてしおらしく泣きべそをかき始めたアーミラに最早女神継承者の威光は無い。緩んだ顔が青褪めて涙を流すまでの急転直下は切ないものだった。
食堂には他の人影はないように思えたが、隅で身を休めていた者が一人だけいた。
あまりの気まずさにかける言葉もないのかと思えば、その者はどうやら事情が違った。仮面の男、イクスである。
彼は食堂の片隅で静かに二人を注視していた。
よりによってこんな姿を……アーミラは気恥ずかしさと情けなさでなんとか涙を隠そうと袖で拭いながら立ち上がる。
「お手伝い……しますので……」
ぐずぐずと言葉を絞り出すアーミラに、ナルは内心困惑していた。ナルの想定では継承者とは生ける伝説のような殿上人であり、一辺境伯に仕える飯盛りの物申しなんぞ聴き流すか無視するだろうと思っていたのだ。まさかこうも萎びて叩頭くとは……。
引き攣ってしゃくりあげる肺を押し留めて洟をすするアーミラは、昼飯も抜きに食堂を出て行こうとした。配膳室に向かおうとしているのがナルにはわかったので慌てて袖を掴む。ぬるついて湿っていたが構っていられない。
「しなくていい。私が怒られるから」
何人も厨房に入らせず。不用意に人を入れることを伯爵が禁じている。これは食事に毒を入れられることを警戒しての邸の方針であった。
ならばこのまま昼飯を出すのか。それではナルの腹の虫がおさまらない。なにかこの穀潰しに労働を与えなければ……そう考え思いついたのは買い出しの依頼だった。継承者の懐であれば食材の調達は大した痛手ではないと睨み、昼飯を与える前に、まずは働かせることに決めた。
ついでのようにイクスも食堂から追い出されていたのでアーミラは気まずい思いだった。
一度自室に戻り外出の仕度を整えると、アーミラは玄関広間へ向かう。階段を降りた先に待つ者を見つけ、眉を顰める。仮面の男、イクスが待っていた。共に食堂を追い出された仲……付いてくる気なのだろうか。段を降り壁に立つイクスを通り過ぎざまに横目で見る。仮面の奥の暗闇にこもる微かな呼吸と見つめ返す視線に気付いて、さっと目を逸らした。当たり前だが、面頬の内側は空っぽではない。肉体があり、顔がある。それがアーミラには妙に恐ろしく感じられた。
後ろをついて歩きはじめたイクスから逃れるように歩調は早くなる。来ないで、とは言えない。もしかしたらたまたま別の用事で同じ道を歩いているだけかもしれないし、護衛をしてくれるのなら無碍にもできない。アーミラは思考を巡らせる。気がかりに背中を丸めて玄関広間にたどり着くと、首のない門番を見つける。警護に立つウツロである。これは渡りに助け舟、アーミラはぱたぱたと小走りになって声を掛けた。
「う、ウツロさん……! ウツロさん!」
逼迫した様子の声音で呼び掛けるアーミラ。ウツロは泣き腫らした目元に気付いたか、向き合って言葉を待つ。
「つ、付いてくるんですが……どうしましょう……」
そう言って、視線でちらりと指したのは後方、玄関を潜るイクスを認める。首のないウツロはしばし事態を推察しているのか、見つめたままじっと動かない。
暫くして、アーミラの腕に指を当てる。
――俺も同行しよう。
❖
斯くして、アーミラは二人の護衛を従え、邸の外へと繰り出した。街を往来する者達は戦士を生業とする者も多いが、その中でも一行の出で立ちは異様であった。
左には、身に馴染んだ軍衣を纏い、顔を面頬で隠した仮面の男。得物である斧槍を握る手に気取りはなく、むしろ膝を痛めて引きずるような歩き方が不気味である。
右には、板金鎧。こちらは一目みて行き交う者たちも距離を取って警戒している。首もなく得物も持たず、次の一歩で倒れてしまいそうな、亡霊のような姿だった。
その二人に挟まれ、目抜き通りを歩くのは――ただの魔人種の娘だった。
薄手の襯衣は袖を捲り、細い前腕を日光にさらしている。下は細袴に木履を履き、得物は何も持っていない。襤褸を纏う孤児であればこの街にも珍しくはないが、身なりから一見して前線にいるべき人間ではない。うら若い娘に警護付きとなれば、外部辺境伯の者が客人として邸に招かれたのだろうと推察するのが精々。法衣を脱いでしまえばまさか彼女が次女継承者であるとは誰も思わないだろう。
「……あ」
アーミラが誤算の声を漏らしたのは露店での買い出しの途中であった。
ナルから伝えられた食材は順調に見つけ出し、さて手に取ろうかというときに手元不如意であることを思い出したのだ。
「借款では、私が継承者だと明らかになってしまいます」
どうしましょう。とウツロに縋る。
――明らかにしてはいけないのか。
「いけませんよ……流石に面子もありますので……」
ウツロはそもそもアーミラの略装の意図にも気付いてはいなかった。青い法衣を纏わずに街へ出たのは身元を隠すためである。前線出征の使命を背負う次女継承者が邸の使いっ走りに食材の買い出しへ出向いたというのは、どう考えても外聞が悪い。
だからこそアーミラは自室に戻り略装へ着替えたのだ。しかし、詰めが甘かった。懐の貨幣はすでに使い切ってしまっていたのだ。
「あの時はもう使い所がないと思っていたので」
そう言ったのは、ムーンケイの一件である。茣蓙を敷いて、乞食の寝床のような襤褸の商店。そこの少年から魔鉱石を買い揃えた際に貯めていた財産全てを支払っていた。
「もういらないと思って散財してしまいました……」心底しくじったと肩を落とすアーミラ。
そこに声をかけたのはイクスである。始めて聞いた彼の声は嗄れているとも、痰が詰まっているとも言い難い、不気味な響きのある喃語であった。
「……あい」
日に焼けた男の手に握られていたのは巾着だ。声に背筋を粟立てたアーミラは一拍を置いて差し出された物の意味を理解する。中になにがあるのかはすぐに想像がついた。
ウツロは手を皿にして受け取る。巾着はじゃらりと重たく掌に乗った。邸から受けているぞんざいな扱いからは想像できないが相当な持ち合わせがあるらしい。腐っても退役兵としてそれなりの俸禄はあるようだ……だが、それにしても……。
「全部……銀粒……」
アーミラは巾着の中を覗き込み驚く。やはりこの仮面の男には、何かあるのだ。
ともあれ、アーミラはその懐疑の念は今は口には出さない。出せないとも言える。単に素性のわからないイクスが恐ろしいという心理と、貨幣を借りている明確な恩義がそうさせた。
結局、買い出しに支払ったのはイクスの懐からだった。ナルが目当てにしていた継承者は手元不如意で、銅粒一つも持ち合わせてはいなかった。当然ウツロも持ち合わせは期待できない。
「……あ」
本日二度目のアーミラの呟きにウツロは足を止めた。手には買い物の包みを抱え、後は邸へ戻るだけという道のりである。買い忘れでも思い出したのか。
アーミラはじっと一点を見つめていた。視線を追うようにウツロは上体を回す。先にあるのはなんてことはない井戸だった。
「おうした」
どうした。とイクスは問う。彼の荷物は行きと変わらぬ斧槍のみ。警護のため買い出しの荷物は持たなかった。むしろ懐は減り、往路よりも身軽になっている。
「いえ……あの……」
アーミラの返答は歯切れが悪い。なんでもないと言おうとした口は黙ってしまい、足が井戸へ向って進んでいる。ウツロは呪力を警戒してアーミラの前に立ち、先に井戸を覗き込む。
「……涸れてますね」
アーミラも井戸を覗く。かなりの深さだが底が目視できた。内側は石積の筒型で、水気はない。井戸外観にも苔はなく、根のしぶとい下草が周りを囲んでいた。
アーミラは呪力に操られているわけではなさそうだ。ならば何故、ただの枯れ井戸に強く興味を持つのか……。ウツロとイクスは説明を求めるように彼女を見つめた。
「す、すみません……なんだか、見覚えがある気がして……」
そう弁明して、また吸い込まれるように井戸の中を覗き込む。目を凝らしたところで何の変哲もない涸れ井戸だ。しかしアーミラにはその穴がとても懐かしく思えたのだ。この下に繋がる細く暗い地下水道の景色を知っている気がする。井戸へ降りる気にはならないが、ほとんど確信していた。過去の私は、お師様とここを歩いたに違いない。
井戸から顔を上げたアーミラは上機嫌で満足そうに帰路に戻る。
釈然としないウツロは不思議そうに井戸とアーミラの背中を交互に見やった。あんな穴ぐらの何を見てご機嫌なのか、本人にしかわからないことだった。
❖
さらに二日が経った昼飯前、夏も盛りの暑い日差しが爛々と平原を焼き、前庭では急な客人に何やら騒がしくしていた。
アーミラがそれに気付いたのは随分遅れてからのことで、継承者の神器である天球儀の杖の中――驚異の部屋――から外界の喧騒を聞きつけ邸の窓から下の様子を眺めると、なんとガントールが戻って来ていたのだ。
アーミラは喜び飛び上がって階段を駆け降りる。しかし段を降りていくうちに胸中は幾つもの不安が過ぎって、玄関広間にたどり着いた頃には眉は下がっていた。
ガントールさんが帰ってきた! ……でも、一人だけ……? そういえば何だか騒がしかったのは何だろう……確か、状況が悪くなれば戻ってくるって言っていたっけ……。
アーミラの足取りは、玄関を潜る頃にはすっかり重くなっていた。
胸元に手を寄せて心配そうに様子を見る。
前庭の騒がしさはある程度落ち着いていたが、ここまで走ってきた騎馬隊の馬は未だ興奮に鼻息も荒く、桶に汲んだ水を飛沫を立てながら飲んでいる。余程急いで来たのだろう、体力の消耗を見て馬小屋からは交代の馬が入れ替わりに連れ出されていた。雑務を処理している兵達は声を張り上げ邸と前庭を駆け回り、中央で客人と話している声は掻き消されて状況が掴めない。
討伐隊に囲まれて輪の中央にいるのはやはりガントールだ。彼女の背の高さが幸いして顔を確認できた。……オロルの姿が見えないのは背が低いから隠れてしまっているのか、或いは、問題が起きてガントール一人だけ戻ってきたのか……アーミラはそっと人波を搔い潜って向かった。
「――ですから、私はここへ退がれとあのちびに――」
飛び交う男達の声の中でガントールの声が紗で隔てたように浮き上がって聴こえる。
「第二戦線としてこの邸の指揮を譲り受けているのは何方でしたか?」
またガントールの声……なのだが、人が変わったような言葉遣いにアーミラは違和感を覚える。兎にも角にも背の高い獣人種ばかりの人の林を潜り抜け開けた場所に出ると、次女継承者が輪の中に入ったことを討伐隊の者たちが気付き、わっと一歩下がって輪が拡げられた。雑音は波紋を広げて押し飛ばされたようにして静まった。
「この方です」と手で示すのはニールセン討伐隊長だ。
何の話か、膝に手をついて上体を支えているアーミラは腰越しにニールセンを見て、次にガントールを見上げた。
「お、おかえりなさい、ガントールさん」
言いながら人違いに気付く。
「はぁ?」
昼日中の強烈な太陽を背に受けて立つ彼女はガントールにとてもよく似ていた。とてもよく似た別人だった。
後ろに縛った赤い髪もガントールなら左右に分けていたはずだ。だが目の前の彼女は馬の尾のように後頭部に束ねて垂らしている。そして逆光に翳る彼女の表情の刺々しさ……大らかで余裕の笑みを湛えていたガントールとは全く対照的である。思わず視線を下へ逃すと、纏う衣装が長女継承の正装である真紅ではなく、やや赤紫がかった色をしていることに気付いた。それに足先まで裾が垂れている。
彼女の衣装は戦士とは似ても似つかない、丈の長い外衣であった。
「ど、どなた……ですか?」
地べたにへたり込んで見上げるアーミラは恐る恐る訊ねるが、返ってきたのは厳しい舌打ちだった。
「……話にならないわ。セルレイを呼びなさい」
人並みを割り、地面に転がるアーミラを蹴り飛ばす勢いでその女はずかずかと玄関へ進む。討伐隊の何人かは今の邸を指揮しているはずのアーミラに対して心配そうな目を向けるが、女はニールセン隊長に指示を飛ばし平原の警戒を怠るなと厳に言い放った。前庭に集まっていた兵達はすぐに移動を始める。蜘蛛の子を散らした前庭でアーミラは体勢を立て直し外衣の女を追いかける。
あの女は案内もなしに邸に上がり、迷わず廊下を進んで喫煙室へ立ち入った。
「失礼いたします」
「……これはこれは、随分と急な客人じゃないか」
セルレイ伯爵はお気に入りの椅子に腰を落ち着かせて美味そうに一服している。邸の主の座を譲り、降って湧いた暇を満喫しているようだ。
「まあ座りたまえよ。スークレイ女伯」
喫煙室には従者が一人。椅子には伯爵と、向かい会って腰を下ろすのはスークレイ女伯と呼ばれる外衣の女。一足乗り遅れたアーミラは部屋の入口に立ち、少し離れたところからその名を聞いた。
二度目だった。前回その名を聞いたのもここ喫煙室での一幕だったはずだ。
「お久しぶりに御座います、ギルスティケー・セルレイ伯爵」スークレイと呼ばれた女は裾捌きも見事に挨拶を済ませると、短い雑談を交わし本題へ踏み込んだ。
「今年も夏ノ一は一層暑く、お元気そうで何よりです」
「そちらこそ御息災で。戦火の中にあって益々お美しくなられましたな」
「いえいえ、ここ最近の自治領の荒れようには、すっかり窶れてしまいましたわ」
「ご謙遜を。刃を研ぐことを窶れるとは言いますまい。……しかし、前線は厳しいか?」
「はい」きっぱりと言う。
己の自治領に危機が迫っていることを認めるのは沽券に関わる。通常ならおいそれと認めはしない。この発言には伯爵も面喰らって破顔する。この二人、相当に気の知れた仲のようだ。
ガントールに瓜二つの容姿と、ラーンマク辺境伯の爵位。スペルアベルとラーンマクの繋がりがあり仲がいい……そうか。
アーミラはようやく外衣の女が何者か理解する。
彼女こそガントールが言っていた妹に違いない。ガントールは長女継承者であると同時に、血を分けた本当の姉妹がいることをぽつりとこぼしたことがある。
「しかし十日ほど前に長女継承と三女継承は此処を発ったはず」
もし戦況が押されていても継承者二柱を状況に投入すれば敵勢力を平らげるだろう。伯爵が言わんとしている事を菊した上でスークレイは眉を吊り上げて顔を歪ませた。ガントールそっくりの顔が怒りを露わにするのはとても怖かった。
「えぇ、ええ。来ましたわ私の愚姉が。偉そうなちびを連れてね」
「ああ――」伯爵はわからなくもないと言いたげな曖昧な相槌を挟む。
「着いて早々何と仰ったかお分かりでしょう? 『この邸をわしらの拠点として使いたい』」
「それで追い出されてここへ? らしくないじゃないか」
セルレイ伯爵は本心からそう言っているようで煙草を吸う手が止まっている。どうやらスークレイ女伯は跳ねっ返りの強い質らしかった。アーミラからみてもその印象に相違はない。スークレイ本人もそれは認めているらしく、うんうんと頷いている。
「勿論あのちびの言いなりにはなりませんでしたわ」
どうでもいいが、スークレイが『あのちび』と言葉を発する度にセルレイ伯爵は疲れた笑いを溢す。オロルのことを言っているのだ。敵を作りやすい性格なのはアーミラが何より知るところ。目の前の女伯とオロルの反りが合わないのは火を見るよりも明らかだ。
「ですが、『これ以上は保証できない』と、無理矢理馬車に乗せられて、今ここに。
……三女継承からは言伝を預かっています。アーミラ様」
「あっ、は、はい!」
不意に名を呼ばれ、アーミラは喫煙室の隅から一歩前に出る。
スークレイは怒り顔でこそないが、なんの興味もなさそうな流し目で一瞥した後に、オロルから預かった言葉を誦んじてみせた。
「『後方指揮により適性を持つ者を見つけた。スペルアベルの拠点指揮はスークレイの到着を持ってその者に一任する。……お主は以降スークレイの指揮下に属し行動しろ』――以上」
「はい。……あ、いや、え……?」
朗々と伝えられたオロルの言葉に流され肯ってはみたものの、遅れて言葉の意味が頭に染み込み狼狽える。このいかにも恐ろしい女伯の指揮下に入るとは……。
アーミラの混乱を見て、伯爵はこの場をまとめにかかる。
「改めて整理させてもらう。まず長女継承ガントールと三女継承オロルの二柱は前線ラーンマクに到着した。そこでガントールは妹の邸を拠点として貰うことを考え、スークレイ女伯にお達しした」
「ええ」
「女伯はそのお達しを一度は跳ね除けたが、昨晩から前線の状況が悪化。今朝ここへ運ばれ、ついでに私の邸の指揮権を次女継承アーミラから貰い受けた」
「そうよ」
「ふむ。私の兵は?」
「既に哨戒の指示を出しました。私が到着した時点で隊の指揮は私にありますので」
「問題ない。それで、私はどうする?」
伯爵は当然のようにスークレイの下に就いた。指示を仰ぐ笑みは、長い休憩も流石に飽きてきた……とでも言いたげだった。
スークレイは人差し指を唇に当て確認する。
「あれはいるの?」
「数に入れていない」
スークレイは少し考える。
「そう……ならあなたは私の護衛を頼みます。腕は鈍ってないかしら?」
「どうだろうな」伯爵は顎で使われることになんの反論もない「戦乙女のご命令とあれば、やれるだけやるさ」
残る指示は、私。
「あ、あの……」アーミラは怖怖とスークレイの背に声を掛け指示を仰ぐ。「私は何をすれば――」
「貴女は好きになさい」
スークレイは、会話を重ねるほどガントールと正反対だと思い知らされる。
そして冷たく言い放つのだ。
「期待していません」
■008――勇名の矜持 前編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
月日は逃げ水のように過ぎ去り、季節は夏ノニに入った。
暑さは丁度この辺りが盛りでマハルドヮグ山脈を覆う梅雨前線もようやく峰を滑り降りた。青く澄んだ空は突き抜けて目に眩しく、立ち上がった入道雲は眩い白さで太陽を遠く受け止める。
スペルアベル平原はまさに炎暑の候、肌を撫でる風さえも茹だる熱風であった。前庭の木陰に立つ女伯は気休めの避暑地に篭手越しに握った扇を開きぱたぱたと首元の熱を冷ましている。
こう熱くては汗ばむばかり。逃れようのない気温の煩わしさに虫の居所は悪かった。
その上、彼女の自治領は陥落か否かの瀬戸際にある。この地に退がり、セルレイの邸を拠点に第二戦線を敷いてから数日、危ぶまれていた最悪の事態は幸いにも未だ起こっていない。それは結構なことだが憂いが先延ばしになっただけとも言えた。
今日が無事でも明日。
明日が無事でも明後日……終わりなく気を揉む日々が続く。
実際、ガントールとオロルが無理を通してスークレイを平原に引き退らせて以降、平原でのトガの目撃数はぐんと増えている。
晴れ渡る夏の空とは裏腹に、女伯の心には重い雲が垂れ込めていた。忌々しく睨む南方は入道雲もどこか煤け、待ち受ける脅威の象徴のように見えた。
四代目長女国家ラーンマクが未だ戦線を維持しているのは敵勢力が肩透かしだったわけでも杞憂でもない。
地平の向こうでは日を追うごとに勢いを増す砲撃の地鳴りが響き、街でも負傷した戦士たちの姿を見かける頻度が増えた。長い戦線の膠着状態は崩れている……それも劣勢で。
姉達は南で死力を尽くし戦っている。迫りくる敵から厳しい防衛戦を続け、その討ち漏らした敵が溢れて来ている。討伐隊もここのところ出ずっぱりだった。
こぉぉぉん……。と、青空を裂くように鏑の音が響く。
哨戒に走る討伐隊が平原内部でトガの侵入を知らせる矢を放ったのだ。弓兵の任に着いている兵は会敵した際にこうして空に向けて細工を施した矢を射る。
この矢は鏑矢といい、言葉通り鏑という鳴り物を備え付けた矢で、射た際に風を取り込み独特の音を鳴らす。
スークレイは音の方へ視線を向ける。戦闘行為は既に行われているはずだが、街からはまだ遠いようだ。
「首無し、向かいなさい」
扇を右手に持ち替え、口元を隠し指示を飛ばす。門の前で待機していたウツロは緩慢な動きで門から離れると、一度玄関の方へ振り返る。
「なにをしているの? 急がなければ兵に損耗が出るわ」
スークレイは扇を閉じ、篭手を纏った左手で南を示す。
「そのための魔導具でしょう」
渋々といった態度で、ウツロは指示に従った。
駆け出す鎧の後ろ姿を見届ける者がいた。あの時ウツロが振り返ったのは彼女の身を案じたのだろう。
玄関広間の暗がりには、しゃがみ込んで見つめ返すアーミラがいた。
「……わかってます……」
アーミラは、もう姿の見えないウツロに向けて呟く。
スークレイから「期待していない」と冷たく突き放されたあの日から、アーミラは杖の中に潜り引きこもっていた。好きにしろ。期待していない。その言葉に心挫かれ塞ぎ込んだのだと邸にいる誰もが思っていた。
しかし、玉磨かざれば光なし……彼女もまた神に選ばれし継承者なのだ。この程度の逆境に耐えられないのならそもそも前線へ向かいはしない。日の届かぬ暗がりに潜むアーミラの青い瞳は、決意の火が未だ消えずに燃えていた。
「スークレイさん――」
日向へ出たアーミラは女伯の背に声をかける。スークレイは興味のなさそうな三白眼で首だけを向けた。
「――私も行きます」
アーミラの宣言。その声に震えはなかった。
スークレイは扇で口を隠して応えた。
「……どうぞ」
促されてアーミラは前庭に歩を進める。開けた場に立って目を閉じて息を吸い、吐く。集中に研ぎ澄ました面持ちは凛々しく、平原を見霽かすと左手に携えた神器――天球儀の杖を静かに持ち上げた。弓構えである。
ここからのアーミラは、まるで別人のようだった。
取懸けに親指で不可視の弦を引っ掛け、人差し指、中指も合わせた三本で弦と矢を保持してみせる。はじめは摘んでいる矢も目には見えないものだったが、撚られた魔力によって発生した燐光は渦を巻き、質量を持ち始めた。
杖を握り直し、弓を保持する左手の形を整えると、物見に入る。顔を南に向け敵の位置を見定めると、上体をうんと上に反らした。弧を描く軌道を読み、それだけ高く遠くに狙いを定めたのだ。
きりりと指先に摘んだ弦が限界まで引かれたとき、アーミラは矢を放す。
張力によって打ち出された光の矢は目で追えぬ速さで邸から飛び出すと青空に溶けて消える――次の刹那、南方の空を覆う槍の雨となってトガに降り注ぐ。
側で見ていたスークレイは言葉もなく立ち尽くす。無能と判断した内地育ちの娘が前線でも類を見ない迎撃の兵戈へ変身した。だが、あの量ではトガだけではなく討伐隊にも矢の雨が……いや、豪雨が放り注いだだろう。
「貴女、それでは味方まで……!」
「平気です」アーミラは遮るように言う。「討伐隊には当ててません」
碧眼の双眸は女伯を見つめ返し、澱みなく断言する。
砂埃が巻き上がり地平線が隠れる。少し遅れて邸に届く驟雨の音……それは当代次女継承者が響かせた初陣の鐘でもあった。
❖
ウツロはスークレイの指示に従い平原南部を目指し街を駆けていた。馬車の往来が激しい目抜き通りを難なく通過し外縁を囲う木製の柵を飛び越えたとき、空から幾つもの風切り音がウツロの背後から迫り頭上を通り過ぎていった。
誰もが白昼に飛来した流星を見上げ、その尾が伸びた弾道の軌跡をなぞる。
それは邸から放たれトガを伐つ光の矢である。
アーミラが放ったものだということをウツロは知っていた。というのも、スークレイに突き放されたアーミラはその晩、ウツロと話していたのだ。
月日は少し遡る……。
「――あんなのが……ガントールさんの妹なんて……」
アーミラは床に尻をつき膝を抱え、がっくりと項垂れる。
スークレイ女伯が邸の指揮権を掌握した日の夜のこと、ウツロはその日始めてアーミラに手を引かれ杖の中へ招かれた。
杖の内側に広がる空間は地上と地下の二階建て構造で、地上には果てしなく続く書架が立ち並び、地下には対照的にこぢんまりとした私室がある。今はアーミラの隠れ家となっていた。二人はここにいた。
驚異の部屋――ウツロにとってこの場所は懐かしい場所なのだろうか。アーミラは姿勢を崩し片膝に身を寄せると項垂れた頭を横に向けてウツロを眺める。杖の中に身を沈めたときも慌てる様子はなかった。先代もウツロをここに入れたのかな……。
ウツロは無い首を回して部屋をぐるりと見回すと書の積まれた文机に転がる手頃な炭の棒を見つけた。おもむろに手に取り、アーミラの傍にしゃがむ。
――見た目はとても似ていたな。
床に炭を擦り、そう書いた。
「顔は本当にそっくりでしたね。姉妹と言っていましたが、まさか切り分けた双子とは」
ウツロはアーミラの言葉に何か引っかかったようで、すぐに問い質した。
――『切り分けた』とは?
「あれ、見ていないんですか?」アーミラはわざとではないが小馬鹿にしたような返答になる。「左腕です」
左腕? とウツロは身振りで返答する。
「スークレイさんの左腕です。あれも義手なんですよ」
そう言われてもウツロは理解できていない。義手だからどうしたというのか。そんな態度を見てアーミラは一から説明することにした。
「外衣を着ていましたが、スークレイさんは左手だけ篭手で隠していました。いえ、隠していたわけじゃないですね……あれは義手なんです。意匠がガントールさんの右腕とお揃いですから、すぐにわかります」
アーミラは一度言葉を切る。
「ウツロさんはガントールさんの右腕が義手なのって……それも知らないですか。……あれは義手なんですよ。二の腕から先は断ち切られたような傷があって、代わりに義手を填めているんです。姉妹で左右……」
――鏡写しなのか。
「はい。顔立ちも似ていて、躰の特徴もそっくり。とても珍しいですが二人は双子のはずです。それも、さらに珍しいことですが、腕が繋がって産まれてきたのでしょう」
当然そのままでは生活に不都合が出る。だから産まれてすぐに二人の結び目を断ち切ったのだ。
――理解した。だから切り分けた姉妹なのか。
アーミラは頷く。
「そうです。……極稀にそういった身体の特徴を持って産まれる子供はいるんですよ」
――切り離した双子のうち、ガントールだけが刻印を授かったということか。
何気なくウツロが床に書いた言葉を読み、アーミラは思いがけず忘れていた事実を思い出す。産声を上げた二人の姉妹が切り離され、運命が姉を女神に選んだ。
選ばれなかったスークレイの心境は如何許りか、推し量るにはまだ彼女を知らなすぎる。
「一緒に生まれてきたのに片や前線、片や神殿の育ち。そのせいか性格も正反対になってしまっていますね」
アーミラがそう言うと、ウツロは思いついたように炭を走らせる。
――両極なのは、天秤の継承者だからなのかもな。
その文字を目で追い、アーミラは腑に落ちた気がした。案外その考えは正鵠を射る答えなのかもしれないと思ったのだ。
左右の皿に同じだけの質量を乗せて、吊り合う関係。ガントールが成長するほど、スークレイも均衡を保つように成長する……。
――ところで、躰の繋がった双子なんて、そんなことを何故知っている?
ウツロの問いかけにアーミラは答えようとして、言葉が出ない。自分でもわからなかったのだ。本で読んだのか、まさか似た境遇の人に会ったことはないだろうが、知識の出所は記憶になかった。
「えぇと……なんで知ってるんでしょう……」
苦笑して、ふと笑っている自分に気付く。あれだけささくれて、沈んでいた気持ちはいつのまにか随分と和んでいた。やはり、鎧と過ごすひとときは心地よいとアーミラはしみじみ思った。
血も流れない。温もりもない。そんな目の前の魔導具に覚える感情に名前を付けようとしてアーミラは首を振った。……いけない。形を決めてしまっては……。
「そういえば、どうですか? この部屋は」
アーミラは話題を変える。整理したこの小さな私室の出来栄えを披露し、今更ながら感想を求めた。
「私もやれることはやっていたんですから」
邸の主として任された数日間、奇襲もなく平穏だったあの日々を、ただ怠惰に過ごしたわけではない。
まず自室――この驚異の部屋――の整理。ウツロを招き入れたのもこの部屋が客人を招く準備が整ったからだ。その際うえにある書架の方もある程度見てまわり、いくつかの魔導書を紐解き自主的な座学にも励んでいたのだと語る。文机に積まれた羊皮紙の古書や書簡の類いはアーミラが上階から持ち出したものである。
「なにより、これを見てください」
アーミラの声は少し昂り、私室の寝台の傍に寝かせてあった一冊の書を取り出した。
その古びた書は、革製の表紙に題名も著者も記されていない。
――なんだ?
「先代の手記です」
アーミラの言葉に、ウツロの聞く姿勢が明確に変わった。
二百年前の継承者……アーミラにとっては遠い歴史の出来事でしかないが、ウツロにとっては事情が違う。共に生き、そして別れた人間の言葉がこの書の中に眠っている。
ウツロはその手記にそっと手を伸ばし受け取ると、固くなった皮の装丁を慎重に折り曲げた。羊皮紙特有の硬い質感の紙がウツロの指先によって撓み、かさかさと音を立てて捲られる。
「ずっと気になっていたんですが、見えるんですか?」
頭もないのに。というアーミラの問いかけには答えず、ウツロの両手は手記を持つことに使われていた。返答がないことに頬を膨らませて不満げにしているアーミラを気にも留めない。
まじまじと紙面を見つめた後、数枚捲って肩を落とす。そしてアーミラに手記を広げて突き付けた。『何も書かれていないぞ』と訴えているようだった。
実際、手記は頁を捲れども白紙が続く。それはアーミラも承知済みである。この書には細工が仕掛けられているのだ。
含みのある笑みを口元に浮かべてアーミラは手記を預かると寝台の上に腰掛ける。初めの頁を開き、右手の人差し指を栞代わりに挟み書の天部を摘むようにしてウツロに向けた。
「きっと彼女は秘密主義だったんですね」
既に手柄顔のアーミラは、言いながら手記を胸元に引き寄せた。正確には寝台の置かれた領域範囲に手記を移動させたのだ。
じわりと染みが広がるように紙面には文字が浮かび上がる。特殊な魔導回路が刻まれていた。
術式としては簡易的な結界に近い。寝台の領域を内と外に分け、書物に記した言葉に閲覧制限をかけている。持ち出されたときに内容が読めないようにしたのだろう。
ただでさえ杖の中に部屋がある事を知るものは限られている。その上入れる人間は継承者の許しがなければ招かれることは叶わない。この厳しい条件を満たし、上の書架から白紙の本を見つけ、寝台の上でしか読むことができないと解明するのはかなり難しいだろう。誰にも読ませる気がない秘匿性である。
唯一この条件を満たし、閲覧を許されているのは次代の次女継承者であり、恐らくは先代もそれを想定してこの置き手紙を遺したに違いない。
アーミラがこれを解明したのはつい昨晩の出来事だった。
「言葉はちゃんとここにあります。
私もこの方のように、強くなります」
……こうして、アーミラは静かに誓いを立てた。
その約束を果たそうとしている。今の己にできること。その積み重ねによってアーミラは名実共に継承者へと至ったのだ。
南部に現れたトガに向かって、青空を幾筋も駆け抜けていく流星群。
ウツロは土を踏み締め、蹴り出す脚にさらに力を込める。前へ、前へと速度を上げる。昂りに身を任せ走る。
もとより心配はしていなかったのかもしれない。ウツロは出会ったときからアーミラの強さを疑わなかった……それは先代の力を一番近くで見ていたからか。次女継承者が授かる能力を遺憾無く発揮したとき敵う者はいないのだと信じていたのだろうか。
❖
次女継承者としての名誉を挽回してみせたアーミラは、その後も度重なるトガの襲撃を容易く打ち倒してみせた。日を追うごとに洗練されていく迎撃の魔術弓は邸のみならずスペルアベル平原全体の護りを盤石なものとした。
この頃になると討伐隊もアーミラを中心に構成されるようになった。
以前は騎馬隊二十四名からなる小隊で哨戒し平原を駆け警戒に当たるのが常だったが、今では限定的に班分けされ、防具も軽量化し、装備は鏑矢が主となった。
これは索敵能力を底上げするための戦略であり、班そのものが備える戦闘能力は低くなっている。現平原の指揮を預かるスークレイはそれで問題ないと判断した。
戦法は単純である。四人一班に分け交代で平原を駆け回り哨戒、索敵を行い、見つけ次第鏑矢を放ち邸に報告。それを聞きつけたアーミラが鏑矢の音の方角を目印にトガを発見、矢を放ち撃退する。という流れである。
初めは討伐隊の中から反発の声も上がったが、それを一蹴したのは驚いたことにスークレイであった。
彼女は生まれも育ちも前線であり、こと戦力、兵法においては合理を尊重する。使えぬものは捨て、使えるものはなんでも使う。一度捨てたアーミラでさえも有用性を認めれば手駒とする。面の皮の厚さは大したものだった。
不満を溜めていた兵達も、数回の実戦で意識が変わった。この戦法によって一番の利を得るのが何より自分たちなのだと実感したのだ。まず、班に分けられたことで休憩する余裕がうまれた。防具を最低限に絞り軽量化することでこの夏の暑さを幾分か軽減させることもできた。しかし戦闘では軽量化された防具では心許ないのではないか……心配はいらない。兵は鏑矢を放った後戦闘には参加せず退却すればよいのだ。後のことは全て次女継承者に任せればいい。
こうして、出ずっぱりだった兵の負担は大幅に改善され戦闘時の損耗もほとんど無くなり、平原はトガ一匹入り込めない堅牢な街となった。スークレイの采配は見事なもので、流石は前線伯領と褒めそやされた。
非の打ち所はない。現状の最適解である。
そんな士気も高まる邸にて、打って変わって不要とされたものがいた……ウツロである。
鎧は鏑矢の扱いに慣れず、また班割りでは会話もできないとあって統制が取れなかった。今の平原では輪を乱すだけの雑兵で、夜襲を警戒する邸の見張りも交代で行う余裕がある以上お払い箱であった。
居場所を失ったウツロは特に落ち込む様子もなく、日がな一日邸の周りを逍遥し、夜になれば屋根の上に身をおいた。
居てもいなくても変わりない、部屋と飯の用意の必要もないという手のかからない存在は、邸の者達からはまるで見えていないような扱いを受けていた。……幽霊を見たと言った本人が幽霊となってしまうとは、恐ろしい話である。
邸で顔を合わせる兵も従者も、ウツロが筆談で意思疎通ができることを知らないため噂話や陰口も口さがなく、ウツロがそばを通りかかっても声を潜める努力さえしなかった。
「あの気狂いはいったいいつ追い出すんだろうな」
……それはウツロが聞いた、兵の陰口である。
交代制にしてからは邸にも討伐隊の姿を見るようになり、彼らは猛暑の鬱憤を晴らすように愚痴をこぼし合っていた。
会話の流れは、スークレイ女伯が指揮権を握ってから負担が減ったという話から展開され、どうせなら女伯の采配で邸に居座るイクスを追い出してくれたらいいのにと、兵の一人が言い出したのだ。
前庭を彷徨いているウツロの存在には兵達も気付いていたが、首無しでは噂話もできないと高を括り、眼の前で堂々と陰口を叩き続けていた。
「セルレイ伯爵もあいつをいつまでも匿って……次また事が起きたらどうなるか、俺はひやひやだぜ」
「ナルも可愛そうだよな、親を殺した相手に飯盛りをやらなきゃならないなんて……まったく不憫だよ」
違いない、違いないと頷き合う若者たちを咎めたのは、同年代の青年であった。
「こらこら。そんなところで怠けるために班分けしたんじゃないぞ」
廊下の先に立っているのは討伐隊の隊長、ニールセンだ。
陰口を叩いていた兵は背筋を伸ばし威勢の良い謝罪を口先で唱える。言い慣れた態度からこういった注意を受けることに慣れているのだろう。
ニールセンはちらとウツロの方を見て眉を下げた。
「すみませんうちの部下が」
愛想のいい笑みで頭を下げるニールセンの横をウツロは通り抜ける。何を思うでもない足取りで邸の内外を歩き続けた。
その夜。ウツロは屋根の上に腰を下ろした。
ふらりと現れるのは同じお払い箱のイクスである。
「やぅ」
足音もなくウツロの背後に立つ仮面の男。不要の烙印を捺された者同士、どこか気やすい声がかけられる。
「ぢょうひあどうあ」
ウツロは聞こえていたが、返答に困っているようだった。筆がないわけではない。イクスがなんと言ったのかわからなかったのだ。
イクスはもう一度繰り返す。まるで唇の皮膚が突っ張っているような、聞き取りづらい言葉だった。
「ぎ、ぢょうし、はぁあ、どうあ」
イクスの努力には応えたいが、言葉を区切ることで余計に崩れてしまっている。ウツロはいっそ手に持った炭を手渡し互いに筆談をしようかと炭を差し出そうとした。
「『調子はどうだ?』と言っているみたいですよ」
ウツロは声がした方に振り返る。屋根の下、薄暗い夜の前庭にアーミラは立っていた。こちらを見上げる姿勢は気怠そうで、半ば閉じた目は隈が貼り付いている。
「……私はもう寝ますね。おやすみなさい」
そう言って小さく手を振ると、アーミラは足早に邸の中へ姿を隠した。ひたひたと、隠し事を抱えた子どものような密やかな靴音が夜闇に溶けていく。
アーミラはきっと今夜も寝食を惜しんで魔術の研鑽に励むのだろう。背負った使命。有用性の証明。与えられた力……。後ろ暗い活力が今の彼女を動かしているのだと思えば、ウツロは屋根を降りて後ろについて行く気にはならなかった。
静寂が再び夜を包む。ウツロは硬い屋根に乾いた炭をさりさりと走らせた。
――調子は変わらない。
イクスに向けての返答だ。
この夜の月光はやや心許ないが、青みがかった冷たい屋根に黒ぐろとした炭の文字は読めないことはない。イクスは目が慣れるまでじっくりと文字を見つめ、ははぁ、と不気味に笑った。
「おこざぃきんえは、うたい、立場がいくてんしたぅかぁな」
またもウツロは聞き取れなかった。
この夜、同じようなやり取りが何度となく繰り返されたが、この場では省略する。
イクスはこう言っていた。
「ここ最近では、二人、立場が逆転したからな」
苦労して聞き取った言葉は皮肉だった。
――お前は、俺しか話相手がいないのか?
「他にいると思うか?」
――失礼。莫迦にしたわけではない。夜更けまで起きているのは体に障るだろう。
「はっ……労わるにはもうぼろぼろだよこの体は。
お前さんこそ、眠らないらしいじゃないか」
――睡眠は必要ない。
「羨ましいね。俺もそんな形なら、死ぬまで戦い続けるだろうよ」
その言葉は、手に入らないと知っているからこそ軽はずみにでた大言壮語か。ウツロは推し量るようにイクスを見つめる。仮面の男は本心から言っているんだと伝えるように、首があるはずの鎧の上にある虚空を見つめ続けた。
足を引きずって歩き、顔には面頬。伯爵への忠誠はある一方で、従者ナルの親を殺したという噂も聞いた。邸での扱いは不遇なのか当然の報いなのか……ウツロは目の前の男に問う。
――お前はなぜここにいる。
イクスは闇の中に書かれた文字を読み、鼻を鳴らす。
「お前と話す理由か? それとも邸に居座る理由か」
――どちらも。
「……お前さんと話すのは、唯一無二だからだ。誰もお前になりすますことはできないからだ。
ここに居座るのは……話せば長くなるが、一言で言えば恨みだな」
ウツロはその返答では満足できない。何も納得がいかなかった。
――恨みと言ったな。長くなっていいから聞かせてくれ。
「アーミラも恨みに囚われているからか?」
イクスは鋭く言い放つ。この言葉だけは聞き間違うことなくウツロに届いた。
喃語のように口の回らない様子から痴呆があるのかと思う者も少なくない。より酷い言い方をするなら『気狂い』という認識を持つ者もいる。
しかしイクスは退役兵……過去に討伐隊に属し兵役を全うしているのだ。つまり、今の彼が持つ身体的な不自由は後天的なものである。脳が壊れたから身体が動かないのか、脳は無事だが身体が動かないのか、ウツロには判断ができないことだ。
――何を恨んでいる。何に囚われている。
ウツロはさらに問いかけを重ねた。
イクスは仮面越しに無精髭を撫で、ウツロの横に腰を落ち着かせると胡座をかいて月を見上げた。
「長くなってもいいなら、まぁ話してやろう。……俺を信じるかどうかは別だがな」
そう前置きをして、イクスはこの夜語り始めた。
語りを聞いてウツロは理解する。『長くなる』というのは、語るべきことが多いというわけではなく、口がうまく動かないから手間取ってしまうという意味だった。
苦労して話すイクスを前に、ウツロは重要そうな事柄は覚えるように努めた。彼の話は要約するとこうなる。
二年前までイクスは討伐隊の隊長を務めていた。
しかし、平原に入り込んだ一匹のトガが厄介な相手だった。
そのトガは顔を剥ぎ取り、顔を奪った者に化ける力があった。
そのトガを討伐するために、俺は必死に戦った。だが、部下と同じ姿、部下と同じ声、部下と同じ動きで攻める相手を前にして、俺はどうしても躊躇った。トガは部下の顔を被り、「助けてください」「隊長、隊長……」って、縋るような目をしたんだ。
苦戦を強いられる内に一人、また一人と部下を失い、ああ、これは部下ではない。このままではだめだと心を決めてトガを仕留めたときには、部下は一人も残らなかった。
皆死んじまった。俺が斧槍を奮って頭を叩き割ったあとで、邸の奴らに取り押さえられた。部下殺しだと罵しられて、今はこの有様さ――
「――おいがおろいたのはとがなおか、うかなおか、いまおなっへああかうない」
❖
「へぇ、そんな話が」
翌る朝、空が白んだ頃にウツロはアーミラの部屋を尋ねた。扉を叩くも返答がないのはもう慣れたことで、その場合は部屋の中に杖だけが転がっていて十中八九アーミラはその中にいる。杖に嵌め込まれた天球儀の意匠が造形された宝玉を前に表面を叩けば、中にいるアーミラが杖の中から手招きをする。
そしてウツロはイクスから語られた話をそのままアーミラに伝え、眠そうな返答が返ってきたのだ。
ちなみにアーミラは夜通し術の構築と改良に勤しんでいた。眠らない日も多いのだという。曰く、鏑矢の音がなるまでは日中仮眠を取れるので、夜にじっくり研鑽をしている。とのことだった。
「……でも、イクスの言うことだけを信じるのも危険ですね」
アーミラはそう指摘する。
「いろいろな可能性がありますよね。
まず、イクスの言っていることが正しい場合。……それは人に化ける力を持つトガがいるということです。前提として、それは禍人と定義されていますよね。ですがそのトガは変化に『相手の顔を奪う』という無駄な制約があります」
なので少し怪しいと思います。と、アーミラは断じた。
「そもそも、主観的過ぎて信じるのが難しいです」
――何故?
予想外に冷たい反応に、ウツロは不満そうに問う。
「自分が部下を殺してしまった。そのせいで邸での立場がない。……結果だけみれば間違いないのでしょうけど、事情を知らない私や貴方の同情を誘うための嘘かもしれません。真実はもっと矮小で、イクスはそもそも隊長ではなく、過去に多くの仲間を失った討伐隊の生き残りで、邸はうだつの上がらない彼をこのまま隊に残しても邪魔だから退役させた。居場所がないイクスは新人の討伐隊に先輩風を吹かせてはいるけど、誰からも相手にされていない……とか」
――それだと、ナルの親を殺したという話が繋がらない。
「では、もっと根本から。長い討伐隊の兵役にイクスの気は触れてしまい、同じ隊の仲間であったナルさんの親を殺してしまった。
その罪悪感から逃れるために、『やったのは自分じゃない。仲間に化けるトガがいたんだ』と嘘をでっち上げたとか」
アーミラの組み立てた仮説でも筋は通る。反論に窮したウツロは筆が動かない。
「聞かされた話をそのまま信じるなら、邸内での立場はここまで落ちぶれないのでは?
隊長として部下に化けるトガと戦い、その果てに気が触れたと誤解されてしまったのならその誤解を解けばいいじゃないですか」
――イクスも怪我をしたのだろう。それで上手く話せなくなった。
「なら、……彼は何に恨んでいるんです? ここまでの仕打ちを受けたなら、矛先はトガではなく邸の者達への復讐かもしれません」
そこまで言われてしまうのはあまりに無体だが、言動も風体もどこか信用できないものがあった。邸から鼻つまみ者として扱われている姿からして、とても過去討伐隊隊長だったとは思えない転落ぶりだ。
彼はこうも言っていた。『ここに居座るのは、一言で言えば恨みだ』……。
推理に一段落の決着が付いた。反駁はないが、ウツロはじっと無言の抵抗をしている……そうまでして信じてほしいのだろうか。と、アーミラは己の言動に抜けがないか省みる。前にも憶測で行動しウツロの機嫌を損ねたことがあったことを思い出す。そのときにウツロは謝らなくていいと言った。行動で示すとも言っていた。
「食堂で……オロルさんは見逃した……」
ぽつりと呟き、アーミラは髪を一房摘んで手遊びに弄する。
以前、ウツロばかりが会敵することを訝しんで間諜ではないかと責めたときも、結局私は真実を掴みそこねていた。そのとき、オロルはウツロを疑ってはいなかった。
彼女は常に正しい。一歩先、一手先を読み、真実の近くに彼女はいる。そんなオロルが食堂での顔合わせの際にイクスをわざと見逃した。本当に怪しい人物であれば、糾弾を緩めなかったのではないか。いや、その判断を私に託していたなら?
「巾着の銀粒……気配を消す移動術……彼を匿う伯爵……」
独り言を呟き頭を悩ませ、耳の裏を掻いて大きくため息を付いた。疲労の限界だ。
「とりあえず彼は部下――または仲間――を失いました。何人の犠牲かは分かりませんが、その一人にナルさんの親が含まれるのでしょう。
私が留めておくのはこの一点のみです。彼が正気なのか、そうでないかの判断がつかないですし、そのどちらでもなく正気のまま狂った者、神殿を裏切る間者である可能性もあります」
アーミラは三本の指を立ててウツロに示した。
同胞を殺した気狂いか。
策に嵌められた隊長か。
全て嘘の仮面の間者か。
「ウツロさんは仲良くやっているみたいですが、肩入れするのは危険すぎます」
そう言ってアーミラはこの話を切り上げた。
外が明るくなればまた忙しくなる。今のアーミラは邸の穀潰しではないのだ。朝も夜もやるべきことは山積みで、気が立っている様子は少しオロルに似ていた。
追い出されるように杖の外へ出たウツロは前庭に向かうアーミラの背中を見送り、今日も暇を持て余すこととなった。
肩入れするなと注意を受けたウツロは、その足で同じ穴の貉であるイクスの元へ向かう。
アーミラにとってイクスが不安要素であるように、ウツロから見たアーミラもまた、不安の種を抱えている。彼女の瞳に宿る炎がどれだけ青く澄んでいても生じる煤は黒いのだ。
ナルトリポカの集落の一件以降、アーミラの表情は少しずつ硬くなっている。微笑むことを忘れ恨みに囚われた。この問題を解決するための緒はこれまた同じ穴に棲まう先達から学ぶしかないのだと、ウツロは心得ている。
❖
この日、ウツロはアーミラと別れたその足でイクスのもとへ向かい、彼を邸の外へ誘った。
この者が正気であれ狂気であれ、あるいは間者であれ、邸の外へ連れ出せば不用意な企みを防げる――ウツロはそう解釈し、アーミラの意を汲んだのだろう。どうせ仕事のない昼行燈、両者は誰に呼び止められることもなく門を抜け、街を抜け、平原を歩いた。
「おい……」
そう言って歩みを止めたのはイクスである。面頬が日光に熱せられて蒸し暑いのか顎の隙間に親指を差し込んで風を送っている。玉の汗が滴っていた。
膝が痛むらしく斧槍の石突を杖の代わりに地面に立って、小さな歩幅でウツロの後ろをついて行くので精一杯な様子だった。
「何故、こんなところに、俺を」
イクスは伝わりやすいように言葉を区切り、不満を訴える。
ウツロは地べたにしゃがみ指先で土を彫って応えた。
――俺もお前も役立たずだ。二人で手柄を挙げる。
発破をかけるようにウツロは続けた。
――元隊長なんだろう?
陽炎が揺れる土の上、刻まれた文字が乾いた地面にくっきりと浮かび上がる。
イクスは腰に手を当てて、ウツロの魂胆を理解したか、肩で笑う。
「……実力を暴こうって訳だ」
聴く耳が鍛えられたウツロは聞き返す頻度が減ってきていた。会話の前後からイクスがなんと言っているのか把握して頷きを返す。
「だが、討伐隊の索敵より先にトガを見つけるのは難しいだろ」
――簡単だ。
「なに?」
――索敵範囲よりも南に行く。
地面に書かれた言葉に視線を落としイクスは閉口する。
スペルアベル平原のずっと南、つまり前線ラーンマク国境付近まで向かい、トガを迎え討つのだとウツロは言う。
「何が簡単だ。馬がなければ片道で体力全部持ってかれる」
往復するだけで一仕事。とてもトガを倒す余裕はないだろうとイクスは一蹴するが、ウツロの腹は決まっていた。
――日帰りではない。
「……はぁ?」理解できないとでも言いたげな声が漏れた。
――南に行きトガを待ち伏せる。何日でも構わない。一体でも討伐し、実力を見届けたらそれでいい。邸に戻る。
「構うだろ。飯はどうする」
ウツロは立ち上がり、背中を向けた。
よく見れば背嚢を背負っている。布の膨らみから察するに筒状の輪郭は水袋か。そして丸いものは携行食のパンだろう。
「持って二日だ」
――パン三つだ。三日は持つ。
「夏だぞ。水もパンも腐っちまうよ」
食事を必要としない鎧に腐敗の概念は伝わっただろうか。そもそも日に一食では気力も湧かないだろう……。イクスの不満をよそにウツロは本気のようだ。この誘いを断れば、昨晩の話を丸ごと嘘だと片付けるつもりだ。
根負けして溜息を吐き、また歩き始める。
「仕方ない。さっさと終わらせてしまおう」
気持ちを切り替えた歩調は、先程よりもしっかりとして膝の痛みも忘れたようだ。ウツロは隣を歩き、茫漠たる平原の道なき道を南へ進んだ。
途中では討伐隊の騎馬がこちらに気付いたようで少数の群れを成す蹄の音が近付いたが、特に呼び止めもなく踵を返して離れていった。トガではないとわかって引き返したようだ。
二人は道中会話もなく、昼過ぎにはラーンマクの手前に辿り着いた。イクスは背を向けて水袋を掲げ、水を口に含むとそそくさと仮面で顔を隠した。頑なに顔を見せない彼の所作をウツロは眺めている。
「お前の頃は、こんなのなかっただろ」
イクスは喉を潤して振り返ると、地平に引かれたラーンマク国境の分離壁を斧槍で示す。伯爵の邸と似た様式の煉瓦積みの巨大な防壁だった。建造物そのものの高さは五振程だが、領空は高度限界まで結界が展開されている。
限りなく透明な不可視の防護結界でも、ほとんど真下のこの位置から見上げれば境界面の光の屈折がよく見える。七色の靄が天蓋のように国境を示し、左右に果てもなく続いている。
「二百年前にお前はこの向こうで戦い、先代と共に災禍の龍を倒した。……そして勝ち取った領土はそれぞれ継承者の名を冠して国が興された。ラーンマク。デレシス。アルクトィス……昔の仲間の名前は懐かしいか?
壁の向こう側は、長女継承者ラーンマクの国だ」
感慨は湧くのか、イクスは感情に訴えるように些か大仰に語ってみせたが、ウツロはじっと防壁を見上げているばかり。先代との思い出の一つ語ってくれてもいいものだが、何も話す気はないようだ。
隣に立ち、イクスもぼうっと壁を見上げた。
この壁を越えて来るトガを討伐隊は駆除していた。今はその役を当代次女継承者アーミラが担っている。
だが、こうして見上げた壁は高い。乗り越えて攻め込む敵が現れる気がしなかった。
聳え立つ壁。その向こうに広がる煤けた青空と熱い陽射し。そして骨まで響く砲撃の地鳴り。日向で待っていては火傷しそうな暑さだ。隣のウツロは全身の板金が熱せられて首元の穴から陽炎を吐き出している。どこか適当な日陰が必要だった。
「あそこを拠点にしよう」
斧槍で示したのは朽ちて倒壊した建物の廃墟である。
石積みの蔵かなにかの遺構で、崩れてしまった今では入口もひしゃげて歪な合掌造りになっている。
内部にトガや野生の動物が潜んでないか警戒しながら足を踏み入れ、日陰に身を休めるとなかなかに快適だった。
「日が当たらないってだけで頂上だ」
気色に声が弾む。
「防壁の様子もここから見張れる」
あとはいつトガが壁を越えて姿を見せるかに掛かっていた。ここ最近の出現頻度ならば日帰りで片付けられる見込みだとイクスは考える。二人には余裕があった。
「どうせなら、休憩がてら最初のトガは様子を見るってのはどうだ」
日陰に身を休め、火照る体を涼ませるイクスは提案した。
横にいるウツロに顔を向けた男の仮面は左右で光と陰に分かれる。奥にある表情は見えない。
「まだ疲れていて戦えない。二人しかいないのだから無理な戦闘は避けるべきだろ。
それにトガの侵入経路を観察できるのはまたとない機会だ」
イクスは少し声を顰めて続ける。
「アーミラの放った矢がトガを討つ光景を、見たくはないか?」
含みのある誘い文句にウツロは静かに警戒した。
なぜ急にそんな提案を、早く済ませたいのではなかったか。しかし疲れているのも嘘ではないだろう。
もしアーミラの言う通りイクスが敵ならば、これも偵察の一環と考えられなくもない。
ウツロは腕を組んで沈思すると、渋々その提案を呑んだ。
「よし、決まりだ。」イクスは膝を叩いてウツロの背負う背嚢をまさぐる。
熱い板金に温められたそれは窯から出した焼き立てのようで、もしかしたら三日持つと言ったのも間違いでは無いのかもしれない。
イクスは廃墟の暗がりに顔を隠して遅い昼飯をさっさと口内に詰め込んで少しの水を含んで腹に流し込む。ほんの少し目を離した隙に鏑矢が飛んだ。
「見たか?」イクスは面頬を慌てて付け直して問う。
ウツロは首の代わりに上体を横に振った。トガはここに現れていない。
討伐隊の索敵範囲よりも南に陣取ったとはいえ、必ずしも先に見つけられるわけではない。
防壁は広い。南西か南東か、トガが現れるだろうと踏んだ防壁の一部しか見張ることができない。鏑の音からしてトガはずっと西側で索敵されたらしく、じっと空を観察すると昼の空に流星が駆け抜けていくのが遠くに見えた。
遅れて地鳴りが雷鳴のようにごろごろと響く。アーミラがまた手柄を立てた。
――これで満足か?
「おいおい、あんな芥子粒みたいに遠かったら見たうちに入んねぇだろ」
もう一体待つ。叶うなら目の前で見たい。
イクスは充分身を休めたが、こうなっては見届けるまで帰れないと言った。
立ち上がり、斧槍で西を示す。
一度トガが現れた場所であれば、前線の取りこぼしが再び現れるかもしれない。イクスは提案し、先に歩き出す。
ウツロはその背を見つめる。
彼が暗がりで昼飯を食べていたときにトガが現れた。
呼び寄せる仕草はあっただろうか。
それともただの偶然なのだろうか。
「……誰かを恨むことで立ち上がれるやつは確かにいる」振り返らずにイクスは言った。「誰も恨めずに死んじまうくらいなら、その方がいいと思ってる」
西へ向かう道。イクスは語る。
「だが俺は、恨むことに慣れちまってな。他の生き方ができなくなった。このまま朽ちて鈍らになるくらいなら全部忘れて楽になれたらいいんだが……たった二年じゃあそれもできない」
イクスは後ろを歩くウツロに振り返る。
「百年経ったらどうだ。二百年経てば、忘れるか?」
先代と過ごした日々も、その戦火での恨みつらみも、お前は覚えていないのか。
イクスは皮肉を言ったわけではない。切に思う本心が零れ出たのだ。
仮面の奥に隠していた男の心根を見て、ウツロはそれでも過去を語らない。覚えているとも忘れたとも答えなかった。
それでもイクスには何かが伝わったようで、どこか満足気に鼻で笑う。
防護結界が揺らぎ、境界面が陽光をきらりと反射する。
「……おい」
腰をかがめてウツロを手で庇う。先を歩くなという身振りだ。
斧槍で示すのは防壁よりはるか上空。結界を突き破り平原に侵入した有翼の蛇を認めた。トガだ。
かなりの高度を飛翔しているため体躯は把握できないが、相当に大きい。
「飛んできやがった……一匹じゃねえぞ」
飛膜を持つ蛇は空に浮かぶ十字の陰となって北へ向かう。それが一つ、二つ、三つ……。
「おいおい、おいおいおい……!」
イクスは空に釘付けになる。
トガの数は七匹。一気に前線から漏れ出してきた。
「やべぇんじゃねぇか……ラーンマクは……」
ウツロはトガを追いかけようとするが、イクスは手を掴み制する。
「待て! 近付くと危ねぇぞ……! 矢が降るんだから……!」
馬鹿正直にトガの背中を追いかければ、アーミラの放つ矢の射線に入って巻き添えを喰らう。味方に当てないようにしているとは聞いているが、倒されたトガが頭上に落ちてくることも大いにあり得る。二人は遠回りに群れの側面に回り込んで駆け出し、距離を保った。
こぉぉぉん……。
邸の方向から空に向けて矢が放たれる。アーミラではない。討伐隊の鏑矢だ。兵達も異常に気付いたらしく鏑矢を二本、三本と空に向けて放つ。大群だと伝えるために指揮が混乱しているようだ。
「七匹分の矢を放つつもりか馬鹿共……!」
イクスは苦々しくそう言って、己の箍を外す。斧槍を両手で握り、兵達の下へ鋒を向ける。
「ウツロ、悪いが討伐はやめだ」
言い残し、イクスは目にも見えない速さで目の前から消えてしまう。神出鬼没の移動術の正体は、斧槍に刻み込んだ魔術回路の縮地術だ。
敵か味方か、イクスは行動で示した。
ウツロは後を追いかける。
❖
「今日は久しぶりに穏やかですね」
ウツロと別れた朝のこと。
前庭と玄関を繋ぐ通路の低い階段を椅子にして、アーミラは分厚い古書に顔を埋め文字を追いかけていた。声がした気がする……もしかして私に向けて話しかけたのかな……。
アーミラが顔を上げると、ニールセンが手を振る。
「すみません。お邪魔でしたか」
「あ、い、いえ……」
ニールセンは後ろで手を組んでそっと歩みを寄せながら、一度話してみたいと思ってたんですよ。と笑う。継承者にずっと憧れていまして。
「難しそうなものを読んでいますね」
ニールセンが膝に手をついて屈むと古書の紙面を覗く。
アーミラは別にやましいことなどないのだが、見知らぬ者に読みかけの書を覗かれるのは無性に気恥ずかしい。かといって隠すように閉じてしまえばかえって後ろめたいものを読んでいたのかと誤解されるかもしれない。顔を赤くして、ニールセンの視線が離れるまでは敢えて開いたままにした。
「……よ、読めますか?」
「いやぁ、私は識字の覚えがありませんので」ニールセンはくすぐったい笑みで襟足短く刈った頭を掻く。「自分の名前だけ書けますよ」
「名前だけ……」アーミラは不思議そうに言葉を転がす。
「大事ですからね。名前は」ほら。とニールセンは指を立てて続ける。「伯爵の書類にも署名しなくちゃいけませんので」
「なるほど」アーミラはそう思った。なるほど。
「今日は久しぶりに穏やかですね」
ニールセンは繰り返す。
そう……今日は穏やか、というより奇妙なほど静かだった。トガが現れないのであればこちらもやることはない。だからアーミラは暇つぶしに書を杖から持ち出し読み耽っていたのであった。
「そう、ですね……矢が鳴りません」
会話が途切れ、二人はぼんやりと南の空を眺める。アーミラはこの無言のひとときを気まずく感じた。それとなく書は閉じて膝の上に乗せるとニールセンを窺う。大らかな性格のようで、彼はこの沈黙を苦にしていないようだ。なにか話題を振らなくては自分だけ居心地悪くなってしまう。
「あっあの……イクス、さんのこと、なんですけど……」
「はい」と返事をするニールセンの表情がわずかに曇る。
やっぱりなんでもないと言うべきかアーミラは逡巡するが、口は動いてしまっている。
「彼の過去について、き、気になってまして……あ、いや別に話しづらいことならいいんですけど、こう……、なんで皆隠すのかなって……」
辿々しく話すアーミラにニールセンは腕を組んで首を困らせた。
「ハル……いえ、イクスさんは少し混み行った事情がありまして……」
口ごもる態度に、アーミラは胸の奥で落胆する。やはり語ってはくれなさそうだ。
「でも、二年前まではあの方が隊長を勤めていたんですよ」
「え」
驚くアーミラの声にニールセンは笑う。
「今の姿からは想像できないですよね。でも本当なんですよ」
アーミラは素直に頷く。
ウツロから話は聞いていたが半信半疑だった。まさか隊長だったことの裏が取れるとは。未だに仮面の男が元隊長であると想像できない。
「なら、二年前に何があったんです?」
「そこが、まぁ……」
「部下殺しの話は本当ですか?」
アーミラの問いにニールセンは眉を上げ目を見開く。
「……なぜそれを」
「め、女神、ですので……」
「なるほど……継承者ですからね」
苦しい言い訳だがニールセンはあっさり納得した。継承者という立場は多少のはったりが効くものだとアーミラは胸を撫でおろす。
「あ、改めて、調べたいと思い、まして……ニールセンさんからもお話しを、き、聞かせていただきたいな……と」
「ふむ……わかりました」
アーミラの方便に乗せられ、ニールセンは了承する。
「では、あくまで私が知る部分だけですが――」
そうして、ニールセンから見た邸の一件が語られる。
――私がこの平原で生まれ育ち隊に加わるときにはすでにイクスは隊長を任されていました。
仮面で顔を隠すこともなかったですし、厳しいながらも冗談も言える。周りからの信頼も厚い尊敬できる人でした。
当時は隊の規模も今より大所帯で、倍はあったと思います。
全員で約四十人の部隊が邸から馬で出陣して、日が暮れた頃に帰って来る。……飯や酒を仲間同士で囲って、街の大通りはその度賑やかなものでしたよ。その頃は討伐隊にも呼び名がありまして、街では平原の風なんて呼ばれていたんです。『この街には朝と夜決まって一陣の風が吹く。この風が吹く間、平原に悪は蔓延らないだろう』って、それが兵として誇りでもあった……。
……ですが、二年前のことです。
私や今の討伐隊の仲間は現場にはいませんので、何が起きていたのかはわかりません……。隊は平原の内地側と前線側、二手に分かれて行動するんです。イクス隊長は年齢層の高い手練の部隊で前線側を、私達若い兵は内地側を見張っていました。その日もそうでした。
仕事を終えて邸に戻ると、隊長は拘束されていました。場所は丁度このあたり、日の暮れた前庭に跪いて、腕を背中に縛られ、虜囚のように蹲っていました。一体何が起きているのか、私は状況を理解するためによくよく観察すると、隊長の服は血にぐっしょり濡れていて、項垂れた顔には鼻がなく、真っ赤にとろけて額から顎まで皮が剥がれていました。瞼も唇も無く、奥歯まで剥き出しになった顎と涙に濡れる眼球は今にもずり落ちてしまいそうで……本当に衝撃でした。
伯爵や従者たちに何があったのかと尋ねると、「私達にもわからない」と返ってきました。
隊長を拘束したのは伯爵だったので聞いてみると、「手練の兵を失った。彼は『顔を奪われたから取り返した』『俺が殺したんじゃない』と繰り返すばかりで、気がおかしくなっている」と伝えられました。
拘束された隊長の手には、血の染みた濡れ布巾が握られていて、それが仲間の顔の皮だとわかったとき、ぞっとしました……。
……その後はよく覚えてないです。目が覚めたら自分の部屋で、きっと気分が悪くなって私は倒れたんだと思います。
部隊の人数はごっそり減りました。……あの日、隊長が部下を手にかけ顔を剥いでから、残った若い人だけで討伐隊を構成してます。上の世代は退役したんじゃないんだって、もうわかりますよね。
「――私が隊長の座を引き継いで最初の仕事は、仲間の亡骸を平原に埋葬することでした。
『トガにやられた』というあの人の言葉を信じたいけど、仲間の死体を調べても斧槍の切傷ばかりで、トガと戦った形跡は見つからなかったんです」
積み上げた信頼が崩れ、懐疑に変わる一件。
アーミラは話を聞いて余計にわからなくなってしまう。アーミラから見たイクスは最初から出で立ちも怪しく信用ならない仮面の男だった。今もまだその印象は変わらない。
だがしかし、ウツロの話を聞き、ニールセンの話を聞き、彼の為人が少しずつ輪郭を成してきた。
イクスは確実に部下を殺している。それと同じくらい強く、部下を殺すような人ではないとも思えてしまう。
思考を巡らせるアーミラを現実に引き戻す鏑矢の音が空に響いた。
❖
「もういぃい! えきかええぇ!」
縮地を用い、不意に現れたイクスの叫び。
討伐隊の索敵班は驚き、目を丸くした。馬たちも突然のことに嘶き興奮する。兵たちは手綱を捌いて馬を御するが、四人のうち二人は落馬して強かに尻を打ち主人を失った馬は厩舎へと逃げてしまう。
有翼のトガが群れを成して現れたと思えば、イクスまでも前線から駆けてきたではないか。一体何がどうなっているのか彼らにはわからない。しかし誰もがあの日の出来事を思い出しただろう。
班の一人がこう言い出した。
「まさか……お前がトガを呼んだのか……?」
はっとして、討伐隊の者は片手で顔を守る。
「剥ぐつもりなのか……!」
イクスは、ぎり。と斧槍を握る手が力んだ。
「朝に邸を出るのを見たぞ……」
「今日はいつもと違う行動だった……やはりトガを呼び寄せていたんだな……!」
兵達は矢筒から一本の鏑矢を取り出すと各々逆手に握ったり、弦に掛けて構えだした。護身用に鉈を携えたものはこれ僥倖と柄を握り刃を向ける。
今にも襲いかからんとする兵の背中に水袋が投げられる。
「ウツロ……!」
首のない鎧が間に割り込み、イクスを庇う。
文字を書いている余裕はないと空を指差す。
争っている場合じゃない。
「……邸に戻るぞ……」兵の一人が言う。
兵達は一度イクスに向け蔑んだ目をして舌打ちをすると、手綱を引いて退避を始める。馬を失った兵は軽装が幸いして二人乗りで帰還した。
残されたイクスとウツロは横に避難してアーミラの迎撃の射線から避難する。
雲一つ無い青空に風を切る矢の音。やがて鋭い光が迫り、夕立のような矢の雨がしとどに降り始めた。
当然その音はトガにも聴こえているだろう。明確な殺意を込めた魔力の矢に対して、蛇はそれぞれ身をくねらせて躱そうと奮闘しているのが見えた。しかし雨粒を避けることが不可能なように、大量の矢を躱しきるのも不可能である。
矢が翼手を貫き飛膜が裂ける。蛇達は体制を崩して落下し、矢は追い打ちをかけるように降り注ぎ蛇の全身目掛けて突き刺さる。地面に叩きつけられる頃には文字通り針の筵となり姿が見えなくなっていた。
アーミラは無から光の矢を具現化させて放っている。込められた魔力はそれだけ強力で、溶解した鉄よりも遥かに熱い。トガに突き刺さった傷口は焼け焦げ血が煮えていた。
矢は少しずつ冷え、それに伴い光を失って黒錆の鉄の棒のように固まっていく。こうして間近で見てみれば、光の矢は直径も太く、竿のように長い。矢というよりは槍と言った方がしっくりくる。
「見ろよこれ」
イクスは斧槍で示す。
「偶然……じゃあないな」
ウツロは何も答えることができなかった。イクスが示したものを見下ろし、アーミラの内に秘めたものを垣間見たのだ。
七匹の蛇。それぞれがまったく同じように殺されていた。
まず翼を貫かれ飛行能力を奪い、次に両目に矢が刺さる。苦しみに喘いだ口に何本も矢を飲み込ませ、膨らんだ腹を目掛けて今度は横から刺している。
このような惨い殺し方、偶然とは思えない。
ただ矢を放ったのではなく、全てを操作しどこに刺すかも意のままに操っている。
これが、今のアーミラの心。
戦う術を持つものが恨みに囚われれば、どこまでも残虐になれる。
ウツロは膝をつき、指筆を走らせイクスに問う。
――教えてくれ。恨みに囚われたアーミラを正道に戻すにはどうしたらいい。
「……俺にそれを聞くのか」
イクスは苦笑し、惨たらしい光景を眺める。
迎撃の様子を見ようと提案したのは正解だったが、同時にウツロの不安も的中していた。
次女継承者は修羅を宿している。憎しみに身を捧げる覚悟と露悪的な復讐心が使命の名の下に燃えている。
もしあの娘を正道に戻すとするなら――
「人は鏡だ」
イクスは言う。
「本当にアーミラを救いたいのなら、まずウツロ、お前が恨みを捨てる必要がある」
え? と、ウツロに声があればそう口に出ていただろう。膝をつき悲嘆する鎧がイクスを見上げる。
「忘れてないんだろ? 先代との日々も。
いいか、ウツロ。人は鏡だ。魔導具だろうと関係ないぞ」
……善いおこないをし、俺は平原の風になった。
……過ちに手を染めて、俺は顔も矜持も失った。
「誰かを正すには、まずお前が正しくなきゃだめだ。
今のお前は戦うことに信念なんて持っちゃいない。
お前は先代の戦場に囚われて、ただ敵を殺している。そうなんだろ」
ウツロから見たアーミラも、
アーミラから見たイクスも、
イクスから見たウツロも、恨みに囚われている同族だった。
「人は腐る。恨みは視界を狭くさせる。俺も随分間違えた……。だが、お前は黒鉄、古びちゃいるが錆びてはいない。
アーミラのために、もう腐るのはやめだ」
❖
「……上手くいきませんでしたか」
ハラヴァンは己の作り出した成果物を見上げて呟く。
陽の光も届かぬ常闇に彼らはいた。
場所は禍人領――まだ神殿側も位置を掴めていない彼らの本拠地内部は、一見して石窟寺院の様相だった。松明の灯りを頼りに渦を巻く階段を踏み進み、方位の感覚が麻痺するほど深く降りた先に彼等の根城は待ち受ける。
地下熱は季節に関係なく安定するため、この場所は夏の外気よりもずっと涼しく肌寒いほどだった。足元は結露の雫と染み出した地下水によって常に雨上がりのように濡れている。黴臭くはないが、独特の鼻につく薬品の臭気と、その奥に膿んだ腐臭が感じられた。
松明の灯りは湿った床や壁に反射し、彼等のいる階層は手に握っている炎の光量よりずっと遠くまでぼんやりと明るい。辺りは削り出しの石壁で円を描くように囲われて、空間は階層を支える太い柱が規則正しく並んでいる。立ち塞がる柱は樹木のようで、まるで星のない夜の森を彷徨っているような景色だった。
彼らが降りてきた階段はこの地下構造の中央をくり抜くように螺旋を描いており、上下に繋がる階段はまだ底が見えない。
外へ繋がる窓も、横に伸びる通路もない。ほとんど一本道で地上と地下を結んでいる。構造自体はとても簡素なもので、朽ちたまま手入れもされていない壁面には建造当時に施したであろう飾りもかろうじて面影を残していた。
ここにはハラヴァンとニァルミドゥ、そして合流を果たしたダラクがいた。
ダラクは内心、戦々恐々としていた。
彼は敵の内地にある広大な甘藷黍の畑を収穫前に焼き払い、集落の者達も口封じをするはずだった。男も女も関係なく一人残らず、子供も漏らさず殺めるはずだった。だが、ダラクはしくじった。
けじめとしてハラヴァンから命じられたのはトガを配した平原での決死の奇襲、その指揮である。狙う首は継承者……勝ち筋も低い作戦だった。
平たくいえば、死を持って遂行し手柄を立てろと言外に宣告されたのだ。相打ち覚悟で敵を殺すはずだった。
しかしダラクはここにいる。長女継承も鎧の魔導具も仕留め損ねた挙句逃げ帰ったのだ。二度の失錯、身の振り方を間違えれば今ここで馘を落とされる恐れがあった。冷えた地下の空気に奥歯ががちがちとなるのを、ぐっと噛み締めて抑えている。下手に目立てば殺される……。
そんなダラクの胸中を知らないハラヴァンは彼の同道を許し、成果物を見上げている。
「これ……なに……?」
ニァルミドゥは松明に照らされたそれを見る。表情に変化はない。成果物を作り出した男も、その隣で眠たげに問う娘も狂っている。ダラクは胸の内で毒突いた。そんな眠たいものじゃねぇだろ……。
「これはまだ空の器です」
無感動にハラヴァンは教えてくれるが、理解できない。
絶句しているダラクと小首を傾げるニァルミドゥを置いて、ハラヴァンは続ける。
「名前はユラ。……聖杯を作ろうとしたんですが、なかなか上手くいかなくて困っているんですよ。いや困りましたねぇ……」
「前も言ってたよね。聖杯って」
「あなたにも施した龍体術式です。ほら」と、ハラヴァンは袖を捲り注射を打つ身振りをした。
ダラクはその意味を掴みかねたが、会話に入ることはできない。そっと目立たぬよう保身に努めた。……どうせ奴のことだ。またよからぬ薬を調合し、娘共の血に混ぜたのだろう。
「私と随分見た目が違うみたいだけど」
ニァルミドゥの言う通りだとダラクは心の中で頷く。ユラと呼ばれた娘の姿は、全く異なっていた。というより、ハラヴァンが『娘』と形容するまで生き物かどうかすら判断がつかないものだった。
ダラクの目から見たそれは、強いて例えるのなら粘菌だった。鬱蒼とした木々の陰に根を張る茸や、湿気にまみれた腐敗の兆しを孕むもの。
糸を引き、壁にへばりついている繭のようなものがハラヴァンの言う娘であり、聖杯の失敗作だった。
「空の器を作るところまでは順調でしたが、貴女ほど経過が安定するものはありませんねぇ」
空の器……その言葉はハラヴァンの口から過去にも聞いた言葉だとダラクは思い出す。たしか、絶望に浸し続けた者が――
「感情を喪失した者が、龍体術式の素体となるんですよ」
ダラクの思考を先回りしたかのようなハラヴァンの言葉に肝を冷やす。
ハラヴァンは続ける。
「私が作った器と、あなた……何が違うんでしょうねぇ」
瞳を覗き込むハラヴァンを前にニァルミドゥは逃げない。鼻息が触れ合うほどの距離だった。
肝が据わっている。というよりある種の諦観を纏っているように思えた。ニァルミドゥと呼ばれる少女もまた空の器。絶望を経験して感情が腐っているということか。ダラクは冷ややかに二人を眺める。
「龍体術式って、なんなの?」二ァルミドゥは問いを重ねた。
「過去に龍人達が構築した呪術体系ですよ。それを私なりに磨き上げ、より強固なものとしたいんです。……ほら、継承者達に対抗しなければなりませんから」
その言葉にニァルミドゥは未だ理解が及ばない。要領を得ない説明に首を傾げるばかりだが、ダラクは目的を悟り肌が粟立つ。そうか、龍体術式……! 声を張り上げたい気分を抑え、拳を握った。災禍の龍を産むつもりか……!
昂りを隠すダラクの目力の機微をハラヴァンは見たか、口角をわずかに吊り上げて成果物――ユラに向き直る。
「絶望が足りないみたいですねぇ。しかし猶予はありません。困ったものです。
こういうのはどうでしょう? ……先にヨナハを仕上げるというのは」
その提案に、壁にへばりついた繭が蠕動する。壁にへばりつく丸い瘤が悶えるように伸縮を繰り返す。
ダラクの目には命乞いのように見えた。
抵抗する力を失ったものが縋りつき懇願するときの切実な挙措。それを繭から感じ取った。この繭は生きている。
「ユラ、どうか希望は持たないで頂きたい。かけがえのない妹を失い、あなたの絶望は完成するのです」
繭は激しく蠢く。
敵であれば構わず如何様にも残忍に振る舞えるが、この繭は同胞。ダラクはハラヴァンの行動に不信感を覚える……だが、今は何も言えない。己の命が優先された。
自由の身なら今すぐにでもハラヴァンの足に縋りついていただろう繭の内側に囚われている娘を置いて、一行は下の階へ降りる。
「……くさい……」ニァルミドゥが呟く。
降りる前からわかっていたことだが、この階に蟠る臭気は強烈だった。何者かが粗相をしたとか、そんな生易しいものではない。屎尿の臭いがたちのぼり、鼻を蹂躙した。
聞いていた話の流れからして、ここにユラの妹がいるはずだ。
ハラヴァンは滞留する瓦斯を警戒して松明を繭の傍らに置いてきていた。代わりに魔術で光源を召喚する。
この階層の床は水たまりが濁っていた。泥――ではないだろう。糞が水にふやけて溶け出しているのだ。
奥の闇で何かがいるのがわかった。灯りに反応して逃げ出す者の気配……泥に脚を引き摺るような水音がしたのだ。
「ここを進むの、嫌なんだけど」
ニァルミドゥは言う。見れば彼女は簡素な貫頭衣とも呼べない衣一枚で靴を履いていない。尻から伸びた発達した尾も、汚水に触れないように空を掻いていた。
「来なさい。ヨナハを捜しますよ」
そう命令するハラヴァンの目は、有無を言わさぬ鋭い視線だった。
小さな吐息を一つ。ニァルミドゥは肩を縮こまらせて汚水を踏む。足の指の隙間に柔らかい糞が入り込み、顔を青くしている。
「最悪……」ニァルミドゥは怒りで声を荒げる。「ねぇヨナハ? あんたが逃げるから糞の上歩かなきゃなんだけど!」
逃げる水音はばしゃばしゃと遠ざかり、部屋の隅に追い詰められた。灯りに姿を曝される。
本当にこれが俺たちの同胞なのか、ダラクにはもうわからなかった。
堆積した糞の泥濘の上を駆けて逃げ惑っていたのは痩せ細った裸の子供だった。ユラの妹であれば性別は女、娘である。日を浴びていない真っ白く薄い皮膚には骨が浮き出て、禿げ上がった顔は瞼が落ち窪み目が開いていない。長く闇に囚われてこの灯りに順応できず、眩しいのだろう。
長く伸びた爪は糞が詰まり、痒くてたまらない皮膚を汚しながら掻いている。一見して何かの病に肌が爛れているのは明白だった。
薬の調合を得意とするハラヴァンがこれを治さないのは、絶望を与えるための手段だからか。
「だ、れ……」ヨナハの声。まだ会話できるだけの正気を保っている。
「私ですよぉ」
「あ、あ、あぁ……やだ、やぁだぁ……!」
声を聞いただけでハラヴァンだと理解し、体を丸めて糞に潜る。一体どれだけの恐怖を敷いてきたのか、背骨の浮いたごつごつとした小さな背中を見て、ダラクは直視に耐え難いと目を逸らした。
上階の姉は、あれでまだましだと誰が予測できただろう。
「ころさないで。ころさないで」
「殺しませんよ。生き延びるために頑張っていますもんねぇ」
必死な命乞いに対して全く熱量の伴わないハラヴァンの返答。
「こうして上から落とされる糞を食べたくもないのに口にして、生きてますものねぇ」
遠回しな口ぶりにダラクは嫌な予感がした。
ヨナハは眩しくて開かない目に涙を浮かべ、屈辱に耐え頷きを返す。
「姉はまだ無事ですよ。あなたが私の望みを叶えてくれるなら、ユラには手を出しません」
「おねがい……おねがい……」
「私としてもあなたに死んでもらっては困るのです。すっかり痩せてしまわれて……ねぇ、お腹が空いているのでは?」
ヨナハは彼の問いにどう答えればいいかを理解して、嗚咽を漏らしながら糞を掬い、口に運んだ。
ダラクは無意識にハラヴァンを睨む。
「そうです。ちゃんとお食べなさい」
こくこくと頷き糞を頬張るヨナハを眺めて降ろして、ハラヴァンは告げる。
「……ですが、あなたが食い繋いでいる糞は、果たして誰のものなのでしょう?」
え? とニァルミドゥはハラヴァンを見る。その疑問はダラクにはわかっていた。上階から降る糞……ヨナハの上には誰がいるのか、先ほど見てきたばかりだ。
ヨナハは考えたくもないと首を振って一度大きく嘔吐くが、なんとか持ちこたえ震えながら飲み込んだ。
「これ……ユラの糞ですよ」
ヨナハは思考が真っ白になったようで、咀嚼を止める。
「――おえっ……」
口元を抑えるものの、胃液混じりの糞が指の隙間から噴き出して止まらない。口から鼻から焦茶色の屎尿を吐く噴水となった。
ダラクとニァルミドゥは飛沫がかかることを厭うて後退する。
「あなたのお姉さんは、あなたのために食べ物を与えてくれています。美しい姉妹の愛ですねぇ。頑張りましょう、さぁ」
ハラヴァンはもっとたらふく食べなさいと両手を広げて勧めるが、ヨナハは嘔吐が止まらない。心なしか目から溢れる涙まで茶色く濁って見えた。おそらく膿だろう。
ヨナハの表情は苦悶とはまた違うもので筆舌に尽くし難く、口から吐き出る糞の滝を止める気のない白痴のような無感情に見えた。怒りと諦めが綯交ぜとなった濃密な絶望。どん底に落とされたが故に揺らぎのない精神状態……ヨナハの貌は生きながらに死んでいる。
ひたすらに不気味だった。
胃をひっくり返して口から出してしまうのではないかと思うほどに糞を吐き、体を痙攣させるヨナハは、事切れたように天井を仰ぐ。未だ間歇泉のように食道を痙攣させながら上階を見つめる。
今まで上階に姉がいることも、その姉が排泄した糞を喰って生きていたことも知らなかったのだろう娘は全てを理解し、思考を手放した。
「ころして……」
ぽつりと、ヨナハの呟きが暗闇に響く。
ダラクは心底ぞっとした。
先ほどまで『殺さないで』と懇願していた娘が、目の前で生きることを諦めた。
人が絶望の奈落に落ちたのを目撃したのだ。
これが、空の器。
純粋な絶望の果てに感情を喪失した龍体術式の素体。
ハラヴァンは一度こちらを振り返る。口元は手柄顔に笑みを湛えて、目元は一雫の澄んだ涙が頬を伝っていた。もう誰の理解も追いつけない所に彼は居るのだとダラクは感じた。
「殺しませんよ。死なれたら困りますからねぇ」
生きるには辛すぎる環境。
しかし死ぬ方途は見出せず。
娘は殺されることも叶わず、呻き声を漏らし頭を下げ、盆の窪を曝す。
斑らに禿げた伸び放題の髪は、追い詰められて真っ白に染まっていた。
「……おなか、すいたよぅ……」
ヨナハはそう言って泣き出した。今まで糞だけを口にして生き延びたのだろう。他の物が食べたい。糞以外の物を口に運びたいのだと訴え泣きじゃくる声に、ニァルミドゥさえも同情の目を向ける。この世が例え戦時下であろうとも、その願いが我儘だとは到底思えなかった。
「おぉ、おぉ――最後に残ったのは食欲ですか。六欲の欠落者よ。
汝は聖杯に選ばれました――」
謂れのない罪科を荷のう龍の子よ。
瞋恚に燃える霊と、
嘆きに悴む肉体と、
その二つを持って聖杯をなす者よ。
器に満ちるは星穿つ災禍なり。
ハラヴァンは屎尿の堆積した床に跪き、ヨナハの手を取って詠唱を行った。
あまりにも自然な態度でやってみせるものだから、ダラクは糞に膝を汚す彼の姿に驚くことすらできなかった。呆気に取られて、いつから詠唱を始めたのかすらわかっていない。はっとしたときにはハラヴァンはもう詠唱を終え、手に握った筒の先に取り付けられた針がヨナハの腕に差し込まれていた。押し子に込めた親指の力だけが強い。
「お、お、おなか……すいたぁ……あ、ああ……が、がぁ……」
がくがくと痙攣するヨナハを目前にして、いよいよダラクとニァルミドゥは立ち尽くすことしかできない。
そんな二人を前に、ハラヴァンは睨みつける。
「ダラク」
「――っ、はっ……!」
なんとか応える。
ダラクの心中は穏やかではない。非道を目の前にして、次は俺が殺されるのだとほとんど確信していた。この男が手心や慈悲なんてものを持ち合わせていないことを充分理解した。
「ニァルミドゥを操りなさい」
「え?」というニァルミドゥの声。それはダラクの心の声でもあった。
釈然としない思いを呑み込み、ダラクは応える刹那も惜しいと油断しているニァルミドゥの首を掴んで熱を奪う。
苦悶に歪みかち合う視線。ニァルミドゥはもう事態を把握し始めている。
これは殺し合いだ。今この場でどちらかが死ぬ。
ばきん。と砕ける音がして、糞の山に彼女の尾が転がる。
ニァルミドゥは己の武器である尾でダラクの首を弾こうと振るったのだ。当たりさえすれば首は落とせるはずだった。だが、首を掴まれたと同時にダラクはもう片方の手で尻に掌を添えていた。凍った尾を無理に振り回したため根本から折れて千切れてしまった。
「なんっ……くそが――」
ニァルミドゥはあまりにも突然降りかかった身の危険に対応出来ず、全身を氷漬けにされてしまった。最後の罵詈はダラクに対してではないだろう。首はハラヴァンに向けられていた。その気持ちはダラクも同感だった。
ダラクは命令を遂行する。全て己の保身のためだ。
尖った氷の先端に指先を傷つけ、血液で彼女の額に五芒星を描くと、あとは血の門を結び精神領域へ忍び込むだけ。
鎧の時とは違う。この娘の肉体を掌握するのは対して手間ではなかった。
左目を閉じたまま、右目だけでハラヴァンに向き直る。
「――ニァルミドゥの肉体を奪った。何をすればいい」
「食べさせましょう」ハラヴァンは言う。
正気を疑ったが、疑うまでもなくこいつは正気じゃない。
ダラクは諾々と従いながらも全身に気持ちの悪い脂汗が止まらない。
「凍っていては食べられませんよ」
「すぐに」ダラクは掌で熱を込め、今度はニァルミドゥを温めた。
横目でヨナハを見る。
もう痙攣は治っているが、外見の変化はそれどころではない。
発熱し、屎尿の異臭が色濃くなっている。
荒く息を吐いているヨナハは心臓の脈打つ度に肉体を肥大化させ、白い皮膚から湯気が昇る。痛みを堪える為に噛み締めた歯が砕け抜け落ちると、血の滲む歯茎から牙が生え出した。
この熱ならば、解凍の必要もないだろう。
ダラクは肥大するヨナハから逃げるようにニァルミドゥから手を離し、ハラヴァンの傍らへ退がった。
血管を流れる血が耳鳴りのように響き、膝の震えを止められなかった。
そして拾った命で思うのだ。あの場で死ぬのは、どう考えても俺だった……。
「行きましょうか」
「あ、あぁ……」
ハラヴァンに促され、ダラクは階段を昇る。
一度振り返ると、丁度糞の中でニァルミドゥが丸呑みにされている光景が見えた。言葉もなく左目を開き、段を上る。
「おっと――」
上階に向かう階段の踊り場でハラヴァンは一度足を止める。
「――聞き忘れていましたね。ダラク。
あなたはなぜ逃げ帰ってきたのです?」
こちらを見ずに問いかける。一体どんな顔をしているのだろう……ダラクは急激に渇き出した喉を唾で湿して応える。
「手柄なら、ある……」
「ほう」ハラヴァンはまた歩を進め階段を上る。
ダラクは続けた。
「ウツロを覚えているか? 鎧の野郎だ。奴と戦い、わかったことがある。
奴は殺せるぞ」
「なるほど……ではなぜ殺さなかったんですかねぇ」
二人はすでに上階に着いていた。薄暗い闇の向こうに見覚えのある繭がある。
ダラクは己の声が震えているのが悔しかった。
「場を整える必要があった。あの場では殺す手がかりを見つけただけでも儲けものだったんだ。なぁそうだろ。俺が死ねば鎧の殺し方は分からず仕舞いだったぜ」
二人は繭の前、後ろ手に組んで話を聞いているハラヴァンと、彼を挟むように繭に対するダラク。
ダラクは気丈に振る舞いながら油断なく警戒し続けていた。繭からユラが飛び出して丸呑みにされる危険を回避する為に、ハラヴァンの陰に陣取っている。
「……貴方の強かさは評価していますよ。
詳しく聞かせてください。鎧の殺し方とやら」
ダラクは首肯し、慎重に言葉を選んだ。
ただ説明するだけではその後用済みになる。殺す方法を話し終えた後も自身が有用であることを示さなければ……彼にとっての正念場だった。
語るのは荒唐無稽な奇襲のあらまし、その結末にウツロの正体が名も知らぬ幼女であると伝えたとき、流石のハラヴァンも表情が動いた。事ここに至ってでたらめを言う度胸はないと見ているが、ハラヴァンは苦笑を隠せない。
「……つまりこうだ、鎧の中は別の術者に繋がっている。自立した魔導具に見せかけているが、そうじゃなかった。
俺はその魔術回路を逆から辿ることで、別の場所で鎧を操っていた術者の正体を掴んだに違いない」
「なるほど」
「考えてみれば先代が生み出したと言われても、二百年間動き続ける魔導具なんて嘘だぜ。封印されていた理由もわからないだろ。そんな便利な鎧なら、ずっと前線で戦わせておけばいいじゃねぇか。だがそうはいかない事情があった。
鎧は、継承者に合わせて士気を高めるために用意された偽物だ。
だから、また俺が奴と戦う。今度は鎧を操っている術者の精神まで潜り込んで、魂を犯してやる」
「……なるほど。よくわかりました」
ハラヴァンは両手を合わせて話を切り上げると、声音を変える。
「……とはいえ、精神に忍び込む呪術は貴方だけの術ではありませんよね」
「なに……?」
「それにダラク。あなたの術式では血の門を繋ぐために、場合によっては相手の動きを封じる必要がある。ニァルミドゥも、鎧も、凍らせなければ侵入できないでしょう」
ぱん。と合わせた手を叩く。ハラヴァンはもう一人、この場に招いている人物がいた。
「……エンサ……!」
ダラクは名を呼び、奥歯を噛む。
階段を降りてこの場に現れたのは醜く太った男、名をエンサと呼んだ。
同じ領内で年も近いだろう二人は、互いに面識もあるようだ。
「ぐひひ……」脂肪に埋もれた喉から気色の悪い笑い声が発せられる。「その役目は私が引き受けましょうぞ」
忌々しくエンサを睨み、ハラヴァンに縋る。
「ハラヴァン、俺はまだ使えるぜ。心配なのはわかるがエンサに頼る必要はねぇ。
鎧の内側は迷い道だ。俺じゃなきゃ道を進めない」
この発言は保身のための嘘だった。いや、ダラクが仕込んでいた嘘はそれだけではない。己のためにと二重、三重の嘘を渾身の二枚舌で語っている。
「落ち着きなさいダラク。用済みだとは言っていませんよ。
前線はもうすぐ継承者が来る頃でしょうし、戦力を無益に失うことは致しません」
「ならあの娘は――」と言い、ダラクは慌てて口を噤んだ。
「……ニァルミドゥを喰わせたのは、ヨナハの龍体術のために必要だったからです。災禍の龍の種として彼女は触媒となるでしょう」
ハラヴァンの言葉に反応して、部屋全体が大きく揺れた。
忘れていたが、ここにはヨナハの姉――ユラ――がいる。
「見てください……絶望は伝染するのです」
ハラヴァンは繭を見ろと手で示す。
地下構造は繰り返し揺れて、柱が悲鳴を上げる。
かけがえのない妹がハラヴァンの手にかかったのだと知ったユラの繭が怒り、この部屋を揺らしているのだ。
「どうか落ち着いて。ヨナハは生きています」
ハラヴァンの言葉が届いたか、繭は暴れるのをやめた。
「あぁ……失敗作のユラ。
貴女の妹はとても優秀でした。姉よりも先に龍の子となりました……羨ましいですか?」
ハラヴァンの問いかけに、繭の一点は大きく盛り上がり、尖っていく。内側から爪を立てている。
繭の一点が鋭く突き出し、そこに小さな穴が開いた。羊膜を破るように、ユラは繭の中から粘液を引きずるように滑り出た。両腕の力で起き上がり、エンサ、ダラク、ハラヴァンと三人の男を睨む。
「ハラヴァン……あんたは――」ユラの声。
「殺したいですか? 気持ちはわかりますが、思い出してください。殺するは蚩尤。今の貴女には私だけではありません。継承者さえも容易く葬れる力があるのです」
ダラクは初めて見る化け物の姿を見上げ、目を奪われる。……これが失敗作だと……?
「……おめでとう。貴女の絶望が完成しました。六欲の欠落者、嫉妬のユラ……」
■008――勇名の矜持 後編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
――地に踏まれた蛇ありて、
暗き怒りは龍となった。
額から伸びた角は奸詐を閃き、
裂けた細舌は佞辯を吐き出し、
胴から広げた翼は詭計を描く。
楽園に天使と共に三人の娘あり。
蛇叢に潜みてその踵を喰みたる。
驚いた三人の娘は神の坐す膝下のより傍に近付きたいと願った。
三人の娘は城を築いた。
蛇から逃れる為である。
楽園は悪しき龍となった蛇によってほとんど奪われてしまった。
天使は城の土を盛り上げ、
大きな山脈ができたのだ。
(『マハルドヮグ時祷書――蛇叢にありて――』より)
❖
結界を突き破り侵入した有翼の蛇を難なく討伐した次女継承者に対して、邸の兵達はその働きを褒めそやす。
場所は食堂、夕餉の時分。今日は珍しく混み合っていた。
昼に現れた七体のトガは飛行能力を有し体躯も大型、さらに群生とあって討伐隊だけでは対応できない厄介な敵だった。もしアーミラがいなかったらトガは平原を悠々と飛び越えて内地に侵入していたかもしれない。馬で追いかけることは出来ても手持ちの鏑矢では手も足も出なかっただろう。少なからず隊に属している魔人種の魔術でも届かない高度を蛇は飛んでいた。
アーミラは苦もなく倒して見せたがあの状況はあわや大惨事の冷や汗ものだったのだ。
あの後、いつまた蛇が飛んで来るかわからないこともあって、スークレイは今後の継承者不在を想定した対応を検討し討伐隊の武装と編成を練っていたため午後は皆忙しくしていた。当時の兵の心境としてはラーンマクがいよいよ落ちたかと顔を青くして邸を駆け回っていたのだ。
落ち着きを取り戻したのは日も暮れてからで、夕餉に食堂が混んでいるのはそうした事情が絡んでいた。
「翼のあるトガは珍しいんですか?」
卓を並べた中央で男衆に囲まれているアーミラは誰に向けるでもなく問いかける。
ここ最近の働きと今日の功績に兵達はすっかりアーミラを気に入り、夕餉に託つけて同じ卓に椅子を持ち寄り集まっていた。それとなく左右を挟まれて席を立ちにくい配置となった。
男勝りで威圧感のある長女継承者や、明らかに曲者な三女継承者と比べ、アーミラは押し出しも優しくいかにも可憐な乙女であるため近くに座る何人かの男は頬も赤く照れている。乗り遅れて遠巻きに座る者達はせめて興味を惹こうと問いかけに我先にと応える。
「ないことはないがかなり珍しいもんだ。俺が前に――」
「小さいやつならそれなりに見たぜ――」
「あれだけでかいのは相当手強いだろうに、流石ですアーミラ様――」
縄張りを争う雄にも似た押し合いの返答があちらこちらで捲し立てるように返ってくるのでアーミラは困った顔で笑顔を作る。こういった人集りは得意ではないので心境としては割と辟易していた。
こうなると場は厄介になる。気を引きたい男は雑談の声も少しずつ荒々しくなり、昼間に律されていた統率を失って血気盛んな若人の騒ぎは増長していく。この場の衆目を攫う話題を口にした者が勝者であると競うように卓の上には様々な話題が挙げられた。やれ食堂の飯で何が美味いだとか、トガを討ち取った数だとか、アーミラにとってはどれも興味が唆られなかった。
「討ち取った数……イクスさんはどれほどなのでしょうね」
アーミラはあえて仮面の男の名を卓の上にあげた。
この場の熱を冷ます冷水となれば良し、または誰かが口を滑らせるも良しと考えたのだ。
僅かな沈黙に返答を促すようにアーミラは続ける。
「ほら、元は隊長だったのですから」
男達はそれぞれ言葉に窮した。話題を振ってきた以上は何か答えたいが、元隊長についてとなると口は途端に重くなる。
「……まぁ、それなりだったんじゃねぇかな。俺はよく知らないが……」
「討ち取った数で隊長になるわけでもないしな、……うまく立ち回って生き延びればいいわけで……」
「……殺したのはトガだけじゃねぇしな」
誰かが呟くように皮肉を言い、小さく笑い声が漏れた。
「今日あいつは外に出たって聞いたぞ。あのトガを呼んだのももしかしたら――」
そのとき、投げやりに水差しを卓に置く音が割って入った。
ナルは口を引き結び、怒りを堪えるような表情で男達を睨む。食堂でイクスの話題を振ったのは軽率だったか。
浮かれた奴らの失言に気不味くなっただけ、会話には入れず遠巻きから聴くばかりで面白くない男達は白けてさっさと引き上げる。
アーミラの近くに陣取った者もこうなっては流石に粘る図太さはなかった。冗談とはいえ迂闊。本当に冷水を浴びせられた面持ちで退散した。
残されたアーミラは彼らと一緒に引き上げるのも気乗りせず、ナルと二人、食堂に残った。
「すみませんでした」アーミラは素直に謝る。「話題に出すべきではありませんでしたね」
「……いい」ナルは卓に散らかる皿を重ねながら言う。「私のお父さんのこと、聞いてる?」
ナルの視線にアーミラは頷きで応えた。
「お父さんはね、あの人の部下だったの。聞いてるならその後どうなったかも知ってるでしょ? ちなみにお母さんは私を産んだときに亡くなったそうよ」
アーミラはまた頷く。
二年前に起きた事件。イクスの部下殺し。
男手一つで育った娘が父を殺され、今はその相手が住む邸で飯盛をしている。
「辛くはないんですか?」思わずアーミラは聞いてしまう。
「さぁ……色々な噂や憶測も聴いたけど……怒って責めるのが正しいのか、恨んで飯に毒を盛れば気が晴れるのか、私にはわからない」
その物言いは決して儚い諦観ではない。諦めの悪い……未練がましいとも言える聡い洞察の目が、今はただ卓を片付けることに向けられている。
「色々探ってるみたいだし、あなたならどう考えるか教えてよ。
イクス隊長は部下殺しなのか、それとも見えないトガがあの平原にはいたのか……」
イクスの口からのみ語られるトガの存在…… そんなものはいないのだと多くの者が信じなかった。だが、親を失い一番の悲しみを背負う少女だけが、僅かな可能性を捨てきれず怨むことができないでいる。
「お父さんが生きていた頃はね」ナルは言う。少し声を低くして、亡き父の真似をする。「『イクスは隊長だが、良き友でもあった。戦場で背中を預けられるのはあいつだけだ』って。……あの事件の前まで、誰もがあの人を頼っていたし……信じてた。それこそさっきまでここにいた男達もそう。皆信じてたのに……」
ナルは一度言葉を切り、震える喉を落ち着かせる。
重ねた皿を持ち上げて配膳室に引っ込む後ろ姿で、振り向かずに言う。
「すごく辛いことが起きたけど……確信がないから飯に毒は盛らないわ……」
それは身寄りを無くした少女の気丈であり、一級の矜持だった。
❖
一夜が明け、その日はやってきた。
朝方から砲撃音が激しく前線が騒がしい。有翼の蛇との戦いに続き、討伐隊の者たちも表情を引き締めていた。
スークレイの指示で鏑矢のほかに得物を携え、各々が不吉な予感に抗おうとしている。
皆、目覚めた瞬間から『今日は何かが違う』と感じていた。それは荒れ模様の南方の空、雨を孕んだ暗雲、そして部屋を満たす湿った空気の圧迫感だった。
討伐隊は久しぶりに全隊一斉に邸を発ち、各自平原に散開して空を睨む。少し遅れてウツロも後を追った。邸に残るより、外でできることがあると判断したのだろう。アーミラはその背を見届け、杖を構えた。
予兆はあったのだ。日増しに数を増やしていくトガの侵入頻度、スークレイを下がらせたきり音沙汰のない継承者二柱。そして翼を持ち内地へ向かう蛇。
今日の前線は明らかに荒れていた。嵐が迫る気配を誰もが肌に感じていた。
緊張状態のスペルアベル辺境伯領主邸の前庭にて、アーミラとスークレイは鏑矢の音を待ち続ける。忙しくなる予感とは裏腹に、討伐隊からの会敵の報せはなかった。
「鳴りませんわね……」
組んだ腕の指先が忙しなく上下に動き、固唾を飲むスークレイ女伯の横、邸の門に寄りかかる人影があった。
「え……? ガントールさん……」
先に気付いたのはアーミラだった。
声を向けた方向にスークレイも首を向けるが、帰還した姉に対して妹の表情は険しいままだった。脱力した肩に、右手には神器の剣。疲弊しているのかガントールの背筋はどこかだらしなく見える。
生温い風に雨粒が混じり始めた。
「姉様――では、ありませんね」
突然襲いかかる剣戟をアーミラが弾く。ガントールが剣を振り上げたとき咄嗟に動いた判断は間違っていなかった。
「偽者……!?」
神器同士が鍔迫り合い、帯びた魔力が火花となって舞い散る。
これだけ至近距離でも姿は間違いなくガントールにしか見えない。だが、隣に立つ者ならばわかる、決定的な何かが別人だった。
❖
一月前。
スペルアベル平原の邸を発ち四代目長女国家ラーンマクに辿り着いた二人は前線を一望する。
ガントールにとっては故郷であり、広がる景色に驚きはしない。
だがオロルにとっては別世界だった。
内地の、それも西海の端に位置する島嶼部で生きてきたオロルにとって戦場の有様は容易く想像を絶していた。研鑽に励み血の滲む努力をしたとて所詮は己との戦い。故郷の島がいかに小さく、世界の広く残酷なことか。己が井の中の蛙であると思い知らされるばかりである。
アーミラには知ったような大口を叩いておきながら、その実オロルは敵意を剥き出しに殺し合う経験なんてものは数えるほどしかなかった。内地の娘なのだから当然と言えば当然だが、肝の座ったオロルの立ち居振る舞いと実態は、余人が思うよりもかけ離れていた。
しかし、三女継承者に選ばれる賢人はこれしきで怖気付く玉ではない。
いついかなる時もオロルはふてぶてしく金色の瞳で世を睨めつける。
あらゆる荒唐無稽も、降りかかる理不尽も、予測できない狼藉も、彼女を害することはない。
現に忸怩たる思いに苛むオロルを誰も観測していない。その理由は手中にある。絶対の優位が彼女の掌に握られている。
オロルには常に『時間』があった。
神より託され賜った神器、柱時計。それはただ時を計るだけのものではない。
長女の天秤が善悪を量り罪を切り払うように。
次女の天球儀が距離を測り光矢を突き立てるように。
三女の柱時計も刻限を計り過ちを犯すことはない。
血で血を洗う戦場で流れゆく時に待ったをかけ、堰き止められ瀞となった刹那をさらに極限まで引き延ばし、オロルは不連続の域にて思考する。景色は砂塵も空中に留まり、何人も動きを止めている。隣に立つガントールさえも認識できない一瞬の中にオロルの本領は存在する。
進むことを止めた世界でオロルは腕を組み頤に利き手を添えて付近をよく観察する。あくまで付近だけである。静止空間をどこまでも歩き回れる訳ではない。柱時計を所有しているとはいえ超常の力には幾つかの制限もあった。
まず、時を止めている間にオロルが動けるのは柱時計の足元に限られている。柱時計は不可視のままオロルの頭上に浮かび、八本の脚を放射状に展開している。この脚先を円で結んだ領域が静止空間でのオロルが行動できる範囲となる。
次は接触の制限である。
例えばオロルが歩いた際に肌に触れている衣服や塵、砂埃等は触れている限り時間停止の影響を受けない。この制限を逆手に取れば触れた人と静止空間を共有できる。
間接的な接触も制限されている。地面に足を付けていれば、土は時間停止の影響を受けない。そして土の上に立つ者も間接的にオロルと接触している。こうなれば時止めの意味はない。そのためオロルは柱時計と不可視の綱で繋がり、振り子のように宙に浮く必要がある。
このように時を操作する力は強力だが扱いは難儀を極めた。地頭の良い賢人種に相応しい神器である。
オロルは柱時計の力が及ぶぎりぎりの地点に立ち、改めてラーンマクを見渡す。
彼女が抱いた感想としては、「これで国なのか」だった。
地形は度重なる戦闘によって地面が削り踏み固められ草木も生えない荒涼の平野となっている。地質は粒の粗い砂質で石英などに混じって魔鉱石類の砕けた結晶も見て取れた。魔力を使い果たして捨てられた鉱石や本来この地にあった岩石の類いが衝撃によって砕け、前線の土壌に堆積しているようだった。
見渡す限り建造物はない。建てたところで的になるだろうとオロルは理解する。ならば前線辺境伯は何処を根城にするのか、それらしいものを探してみれば、遠くに魔術結界を展開している円錐形の天幕がいくつか点在しているのが見えた。戦場の簡易拠点かと思うが、あれで家なのだろう。これからはわしらもあれで過ごすのか、アーミラの杖があればよかったな……オロルは渋面で鼻を鳴らす。
気を取り直し、オロルは目的のものを見つける。
この戦いで脅威となるもの。咎が人に化けた姿――禍人種である。内地であればまず出会うことのない存在だが、神殿の結界の外とあってここでは探すのに苦労しない。トガに混じってそこかしこに禍人は見つけられた。
話に聞く禍人とやらをオロルはここで初めて目にすることになる。これまでの道中にも幾度かの奇襲を受けていたが、ムーンケイの戦闘では大型のトガ。ナルトリポカ集落では戦闘不参加。スペルアベル平原奇襲もオロルは不在である。
――ふむ。
――案外恐ろしいと言うほどでもないな。頭角の位置が獣人種と異なり、肌の色が青白いと言う以外は人によく似せておる。強いて言えば人をよく模倣しているという事実が気色悪い。丁寧に衣まで纏いおって……。
さて。と、オロルはガントールの側に引き返す。この場にはもう慣れた。次にやるべきことは今後の策を立てること。
オロルは宙ぶらりんに柱時計に吊るされたまま思考に集中する。
前線ラーンマクが陥落する可能性の推理を始めた。思い出すのは神殿で晩餐を摂った後の話し合いの言葉だった……。
『四代目国家の姉妹国が連なる国境がそのまま前線とみていただいて構いません。そして南側全域が敵の領地です。一進一退となるほどの乱戦はしばらく行われてはいませんが、刻印現出を機にこれから敵側が先手を狙いに来るでしょう』
ザルマカシムから伝えられていた戦況予報は概ね当たっていた。
状況はどうか。膠着状態は崩れ始めているとみていい……これも想定内だ。
神殿から伝えられている戦略に大きな変更はない。
ラーンマクは前線の中で一番の激戦地となる。敵を惹きつけたこの地に継承者が投入され、一気呵成に敵を召し取る。今の所は順調なのだろう。戦士共は溜まったものではないがラーンマクの危機も神殿の描いた筋書き通りである。
問題はここから……ガントールとわしらで群がる敵を一網打尽にできるかどうか。
オロルにとってそれだけが心配だった。
命を賭けた一発勝負。しくじれば恥晒しとして後世に語り継がれることになる。他人には決して見せないが、沈思しているオロルは人並みに心配性の質だった。
心配といえば、オロルの懸案がもう一つあった――神殿で見た国土大略図の禍人領が測量できていなかったことだ。
オロルは前線の向こう、地平の果てに視線を向ける。そこはスペルアベルから地続きの平野で、地平の向こうは山に囲われている。
これがオロルの頭を悩ませる。……つまり、前線から向こうの禍人領は盆地に位置しているが、南の切り立つ山脈までの間に本拠地らしき生活圏が見えないのだ。
神殿であれば北を向けば立ち上がるマハルドヮグの嶺が望み、帝の居場所を晒している。敵にとって達成すべき目標は目に見える場所にある一方で、こちらは攻め落とすべき目標が把握できていない。
それだけではない。トガについて知らないことは山ほどある。
奴らが何処から生まれ、如何にして人に化け、何の目的で襲うのか。禍人の想い描く勝利の形さえわかっていない。人を殺し尽くした後に奴らは満足というものを覚えるのかどうかすら怪しい。ただ非道の限りを尽くすことを喜びとしているように思えてならない。
継承者となってわかったことは敵の存在がわからないことだらけだということだった。先代継承者達が領地を確保するにとどめ、トガを根絶やしにできなかった理由が今のオロルには理解できた。
兎に角、今はこの地を平らげる。
それとは別に焦眉の急必要なのは禍人が前線を掻い潜り内地へと繋がる隠された穴の捜索だった。背中に回り込まれては戦況がひっくり返ることもあり得る。
オロルはさらに思考を深く掘り下げていく。
時が動き出せば考え事をしている暇はない。この場で結論を出したいが手掛かりは少ない。
「……流石に一人では厳しいか」
独言ち、ゆらりと綱を操りガントールの後ろに移動すると腋に手を差し込み一息に持ち上げた。
力尽くでガントールを地面から離し、静止空間を共有する。呪術でガントールを浮かせなかったのも制限の一つである。時止めの間オロルはいかなる詠唱も術も行使できない。
「ん、え……?」
景色を眺めていたら抱きかかえられた。
ガントールからしてみればオロルの行動は突拍子のないもので、戦場を前に柄にもなく気が昂ったのだろうかと困惑した。
「重たいのぅ……わしの手がもたんから、お主の方から掴まれ」
「そう――」
ほとんど羽交い締めされている体勢でどこに掴まればいいのかと言いかける間にオロルが目の前に現れた。
「――言われても……?」
「早う」
促され、ガントールはオロルの腰にしがみつく。巫山戯ている場合じゃないのにと戦場を見れば、景色が凍りついていることに気付いた。砂を巻き上げる風も、誰かが放った魔術の光もぴたりと静止している。
時が止まっているのだとガントールは感覚で理解する。
「お主と話せるのはわしに触れている間だけじゃ。……おっと、足を付けるなよ」
「無茶を言う……」
「なぁ、ガントールよ。お主はトガの巣を見たことはあるか?」
藪から棒に問われ、ガントールは答える。
「ない、かな」
「では禍人種の城は?」
「それもないね。……なんだよ、攻め落とそうって考えてるのか?」
「極論はそうじゃな。誰も敵の住処を知らんのか」
「知っていたら戦争が膠着状態になるはずがないよ。
でも、住んでいた痕跡はいくらでもあるだろ」
ガントールは当然のことのように言う。
「セルレイの邸だって、先代継承者が奪う前は禍人やトガの領域だろう? なら遺跡は奴らの住んでいた家なり城なりじゃないか」
オロルは目から鱗、盲点だったと珍しくガントールを見直す。
「そういう見方もあるか……じゃがあれは大元を辿ればわしらの土地、わしらの街をトガが攻め込み奪ったのじゃろう? マハルドヮグ時祷書は読んだか?」
ガントールは馬鹿にするなという顔でオロルを見上げる。
「神殿育ちを見くびってもらっちゃ困る。時祷書どころか法典を読んださ」
「ほう、ラヴェル法典か……それはすまんな」
オロルは珍しく謝った。法典に目を通しているとは……。
ラヴェル法典――二人の口から挙げられたその書は庶民と知識人を分ける法律書であり、国を治める者であれば必読書である。
原本は神殿が管理しており、古くは石版を用い大変に嵩張る代物であったが羊皮紙が誕生してからは過去の記録もまとめて閉架書庫に保管されている。
法典という名の通り、この書物は過去の人々の争いの事例とそれに対し下された裁きを知ることができる。今でも判例が追加されれば頁が増えていく現役の法典であり、神殿の善悪の方針を示し発布する意味もあるため各国に対しては数年間隔で神人種が写本を流通している。
そして、ラヴェル法典の序文にはこの世の成り立ちから咎の出現までの経緯も物語として記載されている。この序文のみを抜粋した廉価版ラヴェル法典の名が『マハルドヮグ時祷書』であった。
時祷書であれば街や集落の教会に必ず蔵書されており、信仰の篤い者ならば個人で手元に持っていることも珍しくない。識字の学がある者にとって所有していることが教養人の証明ともなった。
ガントールは神殿に蔵書されているラヴェル法典の原本に目を通している。島の生まれであるオロルはマハルドヮグ時祷書を読み修めている……悔しいが、教養の格差を前にオロルは無礼を詫びるしかない。
「……でも、土地を奪った後も壊されず維持されているってことは、トガはそこを住処に利用したんだろう」ガントールは言う。
当然と言えば当然のことだ。遠い過去から現存する幾つかの建造物は遥か昔、初代継承者が現れるよりも昔に築かれた文明の痕跡である。先代が領地を拡大し、奪還するまで形を保つには維持する人が不可欠だ。ガントールが言いたいのはそう言うことだった。
オロルには初めからセルレイ伯爵の邸としか見えていなかった。
奪い合いの歴史が形を保って語りかけていたなんて、島生まれにはない卓見である。
「ならば、古井戸もそうか……」
「そうだろうね。今では使い物にならないけど先代が奪った後に井戸を掘って、百年そこらで水が涸れましたってわけないもんな」
「……いや、待て、……だとしたらおかしい」オロルは不吉な手掛かりを掴みかけて身を強張らせた。「伯爵の邸は何処から水を引いている」
「そりゃあ邸に井戸があってそこから汲んでるのさ。平原の地盤の下には地下水脈があるから……」
ガントールは言葉尻に自信を失っている。自家撞着に気付いたのだ。
邸の井戸は生きているのに、同じ平原の街で見かける井戸はみんな涸れている。これは確かにおかしいぞ……。
「……もう離してよいぞ」オロルは言いながら腰にまわされたガントールの腕を解く。
「あっ、おい離――」
ガントールは抵抗する間もなく空中で両手を伸ばし、目と口をあんぐりと開いたまま固まってしまう。
オロルは再び一人になり、思考を整理する。手掛かりは得た。流石神殿で学んだだけはある。と、心のなかでガントールを褒めるが当然その言葉が届くことはない。
思い返せばスペルアベルの邸は異様な建築物だった。
街の外縁は木の柵だけ、そこに住む人達はラーンマクと似た天幕造りの簡易的な住居で土地に縛られない生活様式だった。平原には多少なりとも建物の残骸が残っているが古くから形を保っているのは涸れた井戸と邸のみ。
何故頑丈な造りになっている……? 簡単だ。井戸は日に何人もの人間が水を汲みに訪れる。普段使いの酷使に耐える必要がある。
では、あの獄と見紛う黒い煉瓦積みの邸が伯爵のものになる前は何のために存在したのだろうか。平原に現存する唯一の建造物だが、昔の姿はもっと違っていただろう。街の外に点在していた瓦礫が全て現存していたら……もっと大きな街だったはずだ。
スペルアベル平原の地盤の下には地下水によって侵蝕した空洞が存在する。だがそれもあくまで今の地形でしかない。二百年前、もっと遡れば水流が土を削り侵蝕する前は地下空洞はもっと浅かったはずだ。
水路が確保できていたのならば、街は発展していたはずだ。きっと遥か昔は草木も生い茂る大地だったのだ。
……そこにトガ共が現れ平原を我がものとし、土地の管理は行き届かなくなった。その間、地下水脈の水位は下がり井戸は涸れた。
トガも禍人も少なくとも生物だ。呼吸をし、獲物を喰らう。生きる上で水も必要のはず……だが井戸を掘り下げることはしなかった。山脈から水源を求めてしまえば、上流に位置する神殿に生殺与奪を握られかねない。だから涸れたままの井戸が遺された……そういうことか、見えてきたぞ。
「――すわけな……あれ?」
時は動き出し、ガントールは伸ばした腕に力を込めて抱きつくが、そこにオロルはいなかった。
自身が空中から落下をしていることを感覚し、慌てて着地をするとたたらを踏む。
不満顔でオロルを探すと、ふてぶてしい手柄顔がこちらを見ていた。オロルは答えに辿り着いたようだ。
「あれは井戸ではない」
「……セルレイ伯爵の邸の井戸は水が汲めるぞ」言い負かされるとわかっているが、ガントールは指摘する。
「あれは先代が領地奪還後に地下水脈まで掘り下げた歴史の浅いものじゃろう。今言いたいのは涸れた井戸の方じゃ」
ガントールは動きだした戦場の喧騒に目を向けている。吶喊の声と砲撃の衝撃が絶え間なく腹に響くが、耳と口だけはオロルと会話を続けていた。
「『井戸ではない』って、じゃあ何なのさ」
「涸れた水路は道になる。誰の目にも触れず移動する間諜にとっては、理想的な通路ではないか」
❖
禍人は別の水場を確保している。盆地を囲む峰を望めば候補はいくらでもあるだろう。マハルドヮグとは異なる水源から水を引き、その結果旧時代の井戸は枯れてしまった。城が見えないのは敵の本拠地が地上階の建築様式ではなく濾過器を備えた石窟で、恐らくは地下にあるのではとオロルは推理した。
この予想が正しいかどうかは誰も知らないところであるが、ガントールは、ムーンケイで現れたトガを思い出した。
次女と三女の継承者が選ばれ、空に陣が現出したあの日、トガは海を泳いでやって来た。巨大な斧にも似た尾鰭を振り回し牙を剥いたそのトガはオロルの初陣に倒れたが、水に適応できるトガがいるのであれば水源を確保している一つの証左と考えられる。
もし禍人の根城が地下にあるのなら、見つけていないだけで近くに本丸が存在している可能性がある。根拠こそ薄いがそれは良い報せだった。当代の働き次第では戦争に終止符を打つことができるかもしれない。
そして問題の前線の穴も、恐らくは古い水路を辿っているという検討がついた。
これが継承者二柱がラーンマクに到着し、導き出した結論である。三女継承の智慧ここに極まれり。後は巨魁を討ち取るのみとガントールの目に光が宿るが、愁眉を開くにはまだ早かった。
ここから一月、二人は連日の戦線維持に忙殺されたのだ。
継承者は一騎当千の強者であるが戦争は盤上の駒のように単純ではない。いくら強い駒が場にあれどそれが勝利に直結するわけではないのだ。
死をも恐れぬ獰悪なトガの群れと禍人種共が雑兵として行く手を阻む。それが己に向かうなら蹴散らすだけだが、ときとして同じ正義の旗幟を掲げる仲間の兵士を凶手から守る必要に迫られる。盤上であれば切り捨てられる駒でも、戦場で失われるのは紛れもなく一人の命、見捨てる判断はずっと難しいのが情動である。
二人にとってそれがときに足手まといになり動きを鈍らせた。どうしても攻め手を緩め、進行した前線を引きかえして仲間のために退かなければならない状況も数え切れない。単騎であればどれだけ楽かと心の中でつばを吐き、辛酸を舐める。
しかし彼らなしには前線の維持はあり得ない。力の及ばない仲間の兵士を蔑ろにして、継承者二人だけで相手をしていては当然前線は崩壊してしまう。煩わしいが無碍にもできない……歯痒い日々を過ごした。
オロルとガントールは埒のあかない戦況に辟易し、打開するために一人を戦闘に専念、もう一人は地下の通路を捜索するために二手に分かれることになった。いよいよ戦力に余裕がないため、ガントールの判断でラーンマク辺境伯領の一人、スークレイを下がらせる――ちなみに辺境伯は複数存在するが、ガントールはスークレイだけを引かせた。ガントールの完全な私情であった――そうこうしている間に季節は夏ノ二に入っていた。
そんな酷暑の前線にて、ガントールは目当てのものを見つけた。涸れ井戸である。
「……これは……」
足元に砂がこぼれて落ちる音が、やけに響いた。思わず唾を飲み込み、井戸の縁を握る手に力を込める。
場所は前線ラーンマクから東に逸れてデレシスに向かう辺り、地下通路の探索のため単独で戦闘を行い前線を移動していた昼のことである。
似たような涸れ井戸はこれまでの探索でも目にしている。だが地下通路として使用されている井戸は限られているらしく、大半は地盤沈下や戦闘の被害を被り水路が途切れてしまっていた。
ガントールは今度こそあたりであってくれと願いながら穴を覗く。水の臭いはしない。やはり涸れているが、底が見えないほど深いのは初めてのことである。これほど深いなら地下構造が戦闘の被害を免れているかもしれない。当然地下通路として用いられている可能性も高まる。
――どうしよう、潜るべきか……。
知恵や道理で判断するのが不得手なガントールは、視界の確保ができないこの穴に踏み込むのを躊躇う。
そもそも、戦闘向きであるガントールが探索を担当し、前線の維持をオロルが担っているというのは本来の素質として采配が逆である。当然それはオロルも知るところ。
そのオロルが何故ガントールに探索を任せたか。まず、地下通路という性質上道は狭い。柱時計はその狭い空間では真価を発揮できないというのが主な理由であった。その他にも、ガントールは仲間の治癒術式や戦術指揮の心得がない。今の戦線維持に必要なのは一騎当千の駒ではなく、駒を動かす棋士だった。故にオロルが戦場に残り、この暗い涸れ井戸の探索はガントール一人で行われた。
灯りのための松明と火種の石は用意があるが、果たしてこれで万全と言えるのか、オロルならどうするか、ガントールは自身がない。
……なんとなく、まずい予感がしていたのだ。
口を開けて待つ涸れ井戸の闇を覗き、獣人種の勘が肌を粟立たせ身の危険を感じ取っていた。
しかし引き返す意味もない。ガントールは覚悟を決め、井戸の壁を擦るように手足を踏ん張り、静かに暗闇に潜っていった。
潜り込んだ井戸はガントールには窮屈だった。迫持形の水路は左右が低く、中央が高い。床も石畳を敷いたような構造で、中央は轍を切った溝があり一段深くなっていた。そこであれば身を屈めずとも歩けそうだと松明の火を灯して確かめる。
水が漏れ出さないように水路の作りは密閉性が保たれていた。涸れてしまった今でもその頑丈な作りは健在のようで、微かな物音ひとつでも遠くまで反響して聴こえた。鎧を纏った今の装備では隠密には向かないと考え、ガントールはそっと略装に整える。擦れて音の鳴りやすい胴鎧と内腿の板金を取り払い、井戸の底に安置した。……よし、行こう。
ガントールは外からの光が届かない水路を進み、一つ目の曲がり角にたどり着いた。首だけ伸ばして先を覗くが当然何も見えない。
明かりが見えないということは、ここには誰もいないということだ。ガントールは松明で暗闇を照らした。
そこにあったのはただの曲がり角ではなかった。
目の前を照らせば壁がすぐ近くにあり水路は行き止まりかと思えた。が、そうではない。斜め下に伸びて先に続いていた。
ここは人が往来するための場所ではないため勾配も急で階段もない。降りるにも苦労するが、登って帰るのはもっと面倒そうだとガントールは眉を寄せる。
踏ん張りが効かないのでは音を立てずに先の様子を窺うことも難しい。ガントールは降りる前に靴を脱ぎ裸足になって石畳の坂に張り付いた。細かい砂が足の裏に付着するのが分かる。きっと井戸から出た頃には全身砂まみれだ。
松明の柄を口に咥え、脱ぎさった靴は紐を結んで首に引っ掛けている。背剣している神器が石畳に擦れるので腹に回した。虫のように坂を這う無防備な自分の息遣いすらうるさく思えた。
この坂の勾配はほとんど垂直だった。水が流れていればここは滝になっているだろう。
背を斜面に貼り付け水路の縁に脚をつっかえて少しずつ降りていくと、また暗く細い一本道に繋がる――いや、丁字路だ。
ガントールは松明の火を義手で握り、火を消すとその場で息を殺し身を潜めた。
道の先、暗闇に小さく明かりが見える。一見して行き止まりにしか見えない壁面は、横から松明の明かりに照らされている。ガントールにはそれが左から右に向かって移動しているのがわかった。何者かがこの通路を使用している何よりの証拠……だが、できればこの場は気取られずやり過ごしたいと考えた。攻め込むには準備が整っていなかった。
ガントールは身動ぎ一つせずに、相手の姿を見てやろうと目を凝らし続けた。明かりが強まり近づいてくるのがわかる。照らされた影がゆらゆらと迫る。それは松明を掲げた者のものか、それとも別の何かか。こちらに曲がるな……真っ直ぐ通り過ぎてくれよ……。
ざりざりと警戒することなく我が物顔で石畳を踏む足音。それが不意に立ち止まり、地下通路は静寂に包まれた。
「――くせぇな……」
聞き覚えのある男の声が地下通路にうわんと反響する。
ガントールは腹に抱えた剣を静かに引き抜いた。
足を止め警戒しているのなら、互いに気配は察知しているということだ。こちらはすでに相手がダラクと呼ばれる男であることも確信しているが向こうはまさか長女継承が地下にいるとは思うまい。因縁浅からぬ相手だ。今度はこちらから奇襲をかけるのも意趣返しとしては悪くない。
仕掛けるか……。
燃えるような覚悟とは裏腹にダラクは松明を消して、ガントールの視界は真っ暗闇に包まれる。
からん。と乾いた音。松明を捨てたダラクが来た道を引き返し逃散する足音が闇に谺した。
ガントールは追いかけようとしたが、剣を受ける体勢にして身を固めた。離れていくダラクの足音とは別に、暗闇の中こちらに迫る風に殺意を感じたのだ。
――なんだ……?!
前に構えた剣が何かを受けた。視界を奪われているため感覚で捉えるしかないが、それは水のように手応えのない、柔らかなものを刃で両断した。左右に分かれたそれはばしゃりと水音を立てて纏わり付く。濡れて重いものだが、水よりも粘性がある。何より不定形のそれは両断しても悲鳴もなく蠢き続けている。
衣に染み込み肌に纏わり付く液体は、触れている部分に痛痒感を覚えさせる。本能が危険を訴え、ガントールは声もなく戦慄する。
その液体が明確な意思を持っていると悟り、もうダラクを追いかける考えはなかった。
何を浴びた……!? 何に襲われている……!?
ガントールは悲鳴を押し殺し、身体が動くうちに来た道を引き返して井戸から飛び出した。
日のあたる場所まで戻りガントールは袖を捲り上げる。痛痒を覚えた箇所を見れば肌が粘液にぬるついて、皮膚には針の穴程度の無数の出血が確認できた。
「痛――」
ガントールは脹脛に痛みを感じ、慌てて裾を捲る。
そこには皮膚を食い破り体内へ侵入しようとする透明な蛭がいた。反射的に手を伸ばして捕まえようとしたが、粘液に滑り、肌の奥へ潜り込んでいった。後には少量の出血と小さな穴が残る。
まずいぞ……何匹入った……?
顔面蒼白でガントールは立ち尽くすしかない。
体内に侵入された。きっとトガに違いない……対抗する術はあるか……? 斥力でどうにかできないか、いや無理だ――
「う……っ、」
不意に吐き気を覚え、ガントールは咳き込んで喉に詰まったものを吐き出した。
そして喀血に赤く染まった地面を見て、死を覚悟した。
内側から痛みは増している。首の筋が痙攣しているように思うが、皮膚の下を這いずり回る蛭が脳に向かっているのだと分かって、自分の首を両手で締める。まずい……入ってくるな……。
鼓膜の内側から軟体の蠢く粘ついた音が響き、鼻からは体液が漏出した。鼻水か血か、もう確かめる為の視覚は失われ、白く焼き切れそうな脳内で思考は目まぐるしく生存の可能性を探る――神殿の加護で肉体の損傷は癒やされるはずだ。だけどそのあとも体内のひるが私を食い続ける、こうなればはらを切ってとりだすか、いやぬるぬるしてつかめないだろいしきだってもたないなんかかおがかゆいぞむくんできてるきがするおかしいしぬかゆいどうなってるだれかかゆいたすけてしぬしぬもうだめだ――
ガントールの体は見る間に浮腫み、額に浮かんだ青筋は紫に変色を始める。眼球は上向いて、鼻からは濁った鼻水がだらだらと垂れ流しになっていた。
体幹を支える胴回りの筋肉が食い破られてだらりと倒れたガントールは、しなる上体を制御できずに井戸の縁に強かに顔面を打ち、血をあたり一面にぶちまけた。眼球も脳漿も飛散して、後は加護による蘇生と体内のトガによる捕食による死を繰り返す。
当代継承者の正式な長女として国々から期待されていたリナルディ辺境伯の娘、ガントールは、誰もいない戦線の外れで再起不能に陥った。
一方、前線の維持に尽力していたオロルの前には、一際上背のある化け物が現れていた。
奇妙なのは長い四肢と首の位置だ。オロルはそれを見咎めて怪訝そうに見定める。でたらめに延長した人の体に蛇の首をくっつけたような、人に化けたつもりならば下手の一言だが、臆することなくこちらを見定め悠然と迫る姿は只者ではない。
禍人種か、それともトガか。いずれにしろ一線を画す厄介な相手の出現にオロルは顔の汗を拭った。潜るべき死線がやってきたのだ。
❖
熱い雲に陽射しは遮られ雨の降り出しそうなスペルアベル南方。ウツロはそこに斃れる若者達を見つけ、足を止める。
まるで身体が爆ぜたみたいに血飛沫を撒き散らしている兵達を見下ろし、何かの冗談かと眼の前の光景を呑み込めなかった。生存者を探すように一人ひとり亡骸から亡骸へ線を結ぶように見て回り、地面に顔を埋めて息絶えている兵士の肩を揺すった。
朝に馬に跨り邸を出た彼ら……油断なく得物を携えて討伐に向かった彼らが悲鳴の声もなく、静かに命を落としている。ウツロはここへ向かう道中に鏑矢の音を聞いてはいない。討伐隊に追いついたときには平原に生者はいなかった。
兵も馬も、争った形跡もなく血を吹き出し、地面に転がっている。
トガの姿はなかった。
得物を構えた様子もない。
「――よう」
不可解な状況に気を取られていたウツロの背に軽薄な声がかけられる。
声の方へ振り返るより先、挨拶がわりの炎を浴びせられた。ぼう、と首の穴に火が投げ込まれ、すぐに鎮火した。
「首が無ぇと燭台みてぇだな。火が似合うじゃねぇか」
ダラクの軽口を無視してウツロは一足飛びに拳を振り抜いた。語る口は持ち合わせていない。
固く握った鉄の拳はダラクの鼻梁を砕くはずだった。しかしその手前、別の人物が割って入り頬で受け止めた。下顎を砕く手応えがあった。
何者かとウツロは手を引くが、ダラクを庇った者の顔を一見しても誰かわからない。真っ赤に染まった筋組織が剥き出しの面……軍衣を纏った何者かが鼻血を噴き出してひしゃげた顎を庇い、苦悶する。
「ウツロ……さん、逃げて、下さい……」
見る影もない。それでも、討伐隊の生き残りだと分かった。
殴られたことに対して怒りを露わにするでもなく、彼の闘志は消沈していた。
何が起きているのかと、ウツロは問いたかった。
だが敵を前に筆談はできない。それに、スペルアベルに棲まう者は殆どの人間が識字ができなかった。たとえ問いかけられたとしても、彼は答えることができなかっただろう。
困惑しているウツロを嗤う、場にそぐわぬ品の無い引き笑いが響く。
ダラクから少し離れた物陰に太り肉の禍人種はいた。
「危ないところでしたねダラク殿。不肖私めが護衛して差し上げましたよ」
「……そりゃどうも」
雑に礼を言うダラクは興が削がれた表情になり、ウツロに顎で示す。
「……ん。気持ち悪ぃよな。この兄ちゃん操ってんのがあいつ、エンサってんだ。これからお前の相手をしてくれるんだとよ」
ウツロは再び拳を振るう。
ダラクは足の裏で受け止めて宙返りをして距離をとった。
「次こそ仕留める約束だったが、まぁ譲ってやるよ。
俺は今、気分がいいのさ。なんせ長女継承を倒したんだからな」
「あれはハラサグリの功績では?」エンサと呼ばれた男は茶々を入れる。
「ハラサグリは俺が従えてた。つまり俺の功績だ」
じゃあな。と、ダラクはウツロの横を通り邸へ向かった。当然先へ行かせる訳はない。ウツロはダラクの背後から迫ったが、兵士の槍が妨害した。
「そんなつもりは……すみません……」
顎が折れたせいでまともに話せていなかったが、ウツロは多少の唖や喃語であれば聞き取れる。
剥ぎ取られた顔面は出血こそ収まっているが、風が当たるだけでも激痛なのだろう。乾いて艶のある膠原質が彫り込んだような苦悶の表情で固まっている。瞼の削がれた目から血混じりの涙が流れ続けていた。
「鎧と相手をするのはこの私……エンサですぞ。ダラク殿から聞いたところ、どうやらあなたの正体はまだ幼い女子とのこと。もう私は居ても立っても居られませんでね――」
「逃げて、ください……ウツロさん……!」
兵士は敵の言葉を遮るように訴える。
必死な姿を、エンサはまるで珍しい花でも見つけたような顔で眺める。
「みんな長女継承に似たトガにやられたんです……! ガントール様が、帰ってきたと思ったら、中から蛞蝓みたいなやつが湧き出して……っ」
「――おや、おやおや」
兵士は早口で訴える。塊かけていた顔の皮膚がひび割れても言葉を止めない。殺される覚悟で彼は語る。せめて見たものを伝えるために。
「身体の中にそいつが入り込むと、顔の内側に移動して噛みちぎったんです……俺もそいつにやられて今も腹の中にいる……! そいつは顔を奪ったあと、成りすますことができる……。
だから……だから、俺は手遅れなんです……見捨ててくれて構いません……!」
エンサは兵士の矜持に敬服するように目を閉じ、首を振る。
「斯くも健気な命の輝き……思わず口封じするのを忘れてしまいました」
それはそれとして、というように丸く膨れた手を叩いてエンサは命令する。
「ですが喋りすぎですね。
さ、兵隊さん。自分の目を潰しなさい」
「うぁ――」
兵士は小さく呻き、手に握っていた槍を躊躇うことなく自分の目に突き刺した。穂先が半分程沈み、眼窩の骨に刃が喰い込んで止まる。裂傷の隙間から血がどろりと垂れて痙攣する。
喜んで指示に従っているわけがない。身体は呪術による支配下にあり、エンサの言葉に生死が委ねられている。
突然のことでウツロも止めることができなかった。
「やめ……もうしません……やだ。やめろ……あ、あぁ」
右目から槍を引き抜き、痛みと混乱に兵士の呼吸は荒くなる。崩れた水晶体が槍の刃先に掻き出され突傷から零れる。槍を握る手は震えながらもそのまま左の目を狙う。あまりの恐ろしさに兵士は命乞いに泣き叫ぶ。
「うぁぁぁ! 助けてぇ!!」
左目に刃が届く寸前、ウツロは兵士の体を抑えて槍を引き剥がす。互いの力が暫く拮抗し槍を握る両腕が震えていたが、呪術はふっと弱まり、束の間命拾いした。
精神は芯まで恐怖に染まり参ってしまい、何度も謝罪の言葉を繰り返している。
「ごめんなさい、ごめんなさい、俺が、間違っていたんです……信じていたら、こんなことには……」
「おやおや、せめて私にも分かるように話してくれませんか? ではウツロ殿、是非楽にしてあげてください」
エンサはそう言って再び呪術で兵士を操った。拳を振って暴れ出すとウツロを牽制し、槍を拾い鋒を向ける。
「お願いです……に、げて……ください」
兵士の声が震えていた。本心では助けを求めているのがわかる。わかるからこそウツロは戦うことも逃げることもできない。
兵士は槍を突き出し、無理やり横薙ぎに繋いだ。形も戦法も知らぬエンサの無手勝流の槍捌きだ。
ウツロは横に躱して後ろに退がり距離を取る。邸へ向って走り出す事もできたが、そうなればエンサはこの兵士を殺すだろう。
どうにか助けることはできないだろうか……傷痍は顔と右目がとにかく重症だが、それ以外はまだ目立った怪我がない。体内に潜むトガを取り除く方法は思いつかないが、もしエンサの術を解くことができるのなら助けられるかもしれない。
しかし邸にはダラクが向かっている。長女継承を倒したと豪語していた以上、アーミラに対しても何か搦手を仕掛けて来るはずだ。
彼を助けるにしろ切り捨てるにしろ、あまり猶予は残されていなかった。
❖
前線で動きだした詭計は既にスペルアベルにまで及び、閃めく凶刃は音もなく邸を襲った。
辺境伯セルレイの邸から出払った討伐隊の者たちと入れ違いに、前線からガントールが帰還した。まさか彼女が自陣に斬りかかろうとは、誰が予想できただろう。
胴鎧は身につけておらず、足元は裸足をさらしている。全身に鬱血の紫斑が浮かび、五体満足であることが奇跡と思えるほど傷だらけである。今すぐにでも駆け寄って治癒を施してやりたいが、そうはいかない事情があった。
ガントールは、実の妹であるスークレイに剣を向けたのだ。アーミラが既の所で剣を受けていなければ女伯の首が落とされていただろう。信じ難いことだった。
三女神継承者としての妹も、血縁としての妹も、未だ動揺を隠せない。
果たして彼女は、ガントールなのだろうか?
手負いの外見のことではない。もっと内側の、重要な何かが別人になっている……いや、人として備えるべきものを喪失しているようだった。
こちらを睨む緋眼は濁り、焦点も定まっておらず、口元は血と涎が乾いて張り付いていた。見る影もなく傷付いて気の触れた彼女の姿も、こうして疑いの目で観察すれば薄寒い嘘に見える。手負いのガントールは傷痍を痛がる素振りがないのだ。
しかしながら、スークレイに襲いかかるときに振るった得物は継承者の神器だ。この世に二つとない裁きの天秤、その断罪剣を彼女は握っている。
アーミラとスークレイは目の前に立つ長女をどう沙汰するべきか戸惑う。ガントールは気が触れているのか、それとも武器を奪っただけの偽者なのか……。
「よろしくないわね……」スークレイは予想だにしない状況に驚きつつも、指示を出す判断力は残っていた。「セルレイ!」
呼びかけに応える代わりにセルレイ伯爵は邸の物陰から飛び出しガントールの背中に刃を突き刺す。突き立てた得物は刃渡りの短い片手剣だったが、力を込めて沈めた切っ先は肋骨を砕き胴を貫いた。容赦のない一撃である。
噴き出した鮮血がアーミラの頬にかかり、袖で拭う。その付着した血液の手触りに違和感を覚えて袖を擦る。……普通の血よりも淡く、ねっとりとした感触があった。
「……これは」
セルレイも手応えの奇妙さに警戒して、身を捩るように片手剣を切り上げ刃を抜くと勢いをそのままに回し蹴りでガントールを押し退けた。スークレイの元に合流する。
セルレイは片手剣の血を振り払ってガントールを見つめた。皆が同じことを思っただろう。
目の前で立ち上がろうとしているガントールは切り上げによって胴から右肩まで裂かれていた。致命の一撃にもかからず痛みに喘ぐ素振りもない。よろよろと上体を起こして三人の前に対すると、たちまちにして皮膚が繋ぎ合わされていく……。全身に負っていた傷も痣も癒えていくのが見えた。
「どうなっている……治癒したぞ」
「神殿で授かった加護の効果でしょうか」
スークレイの言葉にアーミラは首を振った。
「いえ、違います」
これと似た状況を知っている。アーミラは続ける。
「きっと偽者です……ガントールさんがこちらを襲うなんてありえません」
顔を奪い、その者に化けるというトガの存在。
セルレイも心当たりのあるこの状況に困惑を隠せないようだが、今はガントールと戦う覚悟を固めた。スークレイも状況を呑み込み始めている。
「ならば、剣を取り返さないとな……本物のガントールはきっと前線にいるはずだ」
「……まったく手のかかる愚姉ですこと」
心新たに三人はトガと対峙する。
内心では危機を理解していた。ここに偽者のガントールが辿り着くまで鏑矢が鳴らなかったという疑問にも気付いている。だが今は敵前。考えている暇はない。
彼女達の気丈を嘲笑うかのようにガントールは口角を歪に吊り上げた。
ぽつりぽつりと空から生温い粒が降り出し土に点を描くと、堰を切ったように雨粒は降り注ぎ乾いた平原を塗りつぶしていく。
睨み合う状況に雨晒しになり、衣服が重たく貼り付いた。視界が悪い……どちらが先に仕掛けるか、雫の滴るままに意識を研ぎ澄ませる。
先手を取ったのはガントール。
雨垂れの中を駆け寄り姿を滲ませ襲いかかる。
速い――アーミラは内心で驚く。あの偽者、身体能力まで模倣しているの……!?
天秤の剣が狙っているのは伯爵の首だった。
セルレイはなんとか目で追いかけ、その一合を片手剣で受ける……。
「なっ――」
刃が触れ合う刹那、ガントールの剣閃が不意に伸びた。
受け止めるはずだった片手剣は空を切りすり抜ける。
軍衣に突き立てられる鈍い痛みが襲った。
「ぐうっ……!」
ガントールの刃の軌道はしなるように大きく弧を描きセルレイの死角に回り込んで脇腹を突いた。それを見ていたアーミラとスークレイは息を呑んだ。セルレイがやられた!
鈍い衝撃にセルレイはよろめくが出血はなかった。
ガントールの断罪の剣はもともと斬首に用いる剣であるため、鋒に刃を立てていない特殊な形状であることが幸いした。
じんじんと痛む肋骨に無理をして、追撃を逃れるだけの距離を取る。
「無茶苦茶するな……」
セルレイは堪らず泥濘に膝をつき、細く息をする。肺を膨らませると激痛が走った。スークレイが駆け寄る。
「スークレイさん、伯爵を連れて下がってください」
アーミラは一歩前に出る。
ガントールの伸びる剣閃は、自ら奮った膂力によって右肩の傷を裂き腕の長さを稼いだのだ。常人には不可能な技……いや、人ならざるものの技だった。やはりこの者はガントールではない。一刀による首への介錯こそ彼女本来の流儀、剣で突こうなどと、まずあり得ない。
「私がなんとかします……」
そう言って一人ガントールと相対する。敵を見つめる碧眼は細く尖り温度を下げ、固く冷えた殺意に充ちる。
アーミラの瞳の深いところにある闇を見て、ガントールは気圧され脚が退がる。油断なく構えているが、視線は手負いのセルレイばかり狙っていた。仕留めやすいものから数を減らそうという魂胆が透けて見える。
アーミラはセルレイを庇うように前に立ち、杖を二人に向けて宝玉の中に呑み込むと敵前から匿った。
濡れた前髪の房の隙間からガントールを睨む。
「トガというのは……つくづく性根が曲がっていますね……ガントールさんを襲うときも、きっと不意を突いた非道の策を用いたのでしょう……?」
問いかけにガントールは答えない。
アーミラの言葉は怒気を孕む。
「義に立つ彼女の顔を被って挑むというのなら、私も容赦はありません」
後ろに回していた杖を持ち上げ流れるように弓構えの体勢になると詠唱もなく矢を放った。一度弓を放つ動作を完了してしまえば術式は成立する。
光弾は連続して宝玉から射出された。
ガントールの回避は遅れ、最初に放たれた三発をまともに受ける。雨の匂いの中に肉の焼ける臭いが混じる。
目視してから体が回避行動に移るまでの間に首筋、左肩、左脇腹を断続的に穿たれて風穴が開いた。後の矢は横に飛んだ回避行動によって体を掠め、前庭の土に突き刺さる。痛みに喘がぬガントールの代わりに、高温の光矢がじゅうじゅうとけたたましい音を立てて雨粒を蒸発させた。
ガントールは丸くくり抜かれた自身の体をちらと見て表情に動揺が浮かんだ。勝ち目がないと悟ったのだろう、歯噛みしてアーミラを睨む。
降り注ぐ雨に濡れたアーミラの表情は頭巾と前髪に隠れて見えない。
藍色の法衣が雨に濡れて色味を深め、頭巾から白い肌が覗く。彼女の姿はまるで、黒衣を纏った死神のようだった。
「次は心臓に当てます」
トガに言葉が通じたか、それともただ殺意を嗅ぎ取って尻尾を巻いたのか、ガントールは前庭から逃げるように駆け出した。塀に隠れたその背中を目で追いかけアーミラは弓を構える。
振り向かず走るガントール。
その背中に曲射が突き刺さった。
宣言通り心臓が光弾によって焼かれ、ガントールは膝をついて顔から倒れる。残された力で懐から何かを取り出し塀の向こうに投げると、化けていた肉体は雨に溶けて土に染み込み、後にはガントールの面皮と神器が残された。
一方、矢が刺さる音を聞いたアーミラはガントールの息を確かめるために前庭を出た。外縁の塀を曲がったところに人型の染みが広がっている。しかし骸がない。
おそらくここに、仕留めたはずのトガが転がっていたはず……それが忽然と消えた。
アーミラは聞いていた話を思い出す。
『私が隊長の座を引き継いで最初の仕事は、仲間の亡骸を平原に埋葬することでした』
『仲間の死体を調べても斧槍の切傷ばかりで、トガと戦った形跡は見つからなかったんです』
襤褸のように放られたガントールの顔の皮を摘みあげて杖の中に回収すると、濡れた土を指で擦る。……雨水とは別に粘度のある液体が残留していた。
指先で感触を確かめ、息をのむ。……間違いない、これはトガの分泌液だ。
アーミラは土を払い邸に引き返す。そのとき手当てを済ませたセルレイが杖から飛び出した。
「やったか」セルレイは問う。
「まだです。中にいてください」
「あんなもの投げ寄越しておいて馬鹿言うな。私も戦える」
そう言ってセルレイは神器を拾い上げる。
確かに面皮を放り込んだのは失敬だったが、丁重に扱う余裕もない。
アーミラが思うに、ガントールの面皮だけは本物だ。それがトガの手に渡れば再び化けて出るかもしれない。かと言って焼いて処理してしまうと前線にいるガントールの顔が元に戻せないのではないかと危ぶんだのだ。今は保管して、不要と判断してから処理したい。
「どこに逃げたかわかるか」とセルレイ。
「おそらく、地中から塀を潜り前庭に……次に現れるときは誰に化けているかわかりません……。
もしかしたら顔を調達する気なのかも……」
そうなれば最悪だ――互いに顔を見合わせ邸内へ急いだ。邸にはまだ従者がいる。兵を信じ身を隠している彼女らに凶手がかかることは何があっても避けたかった。
玄関広間の分かれ道で脚を止めた三人は、絹を裂くような侍女の叫び声とガラス窓の割れる音を聞く。食堂だ……!
「くそ!」セルレイは一目散に駆け出す。
取り残されたアーミラは叫び声がナルのものだと分かり青褪める。
「ナル! 無事か……!」
二階に上がったセルレイは食堂の扉を蹴り開けた。
目に飛び込んできたのは割れた窓と血飛沫に染まる食堂。そして袈裟斬りに腹を裂かれ蹲るニールセンの後姿だった。
切り伏せた者は斧槍を腰に構えてセルレイと向かい合う。
「……イクス……」
またも部下が手にかけられた。セルレイは過去の記憶と目の前の光景が重なり、一瞬で頭に血が昇る。
「何をやっている……!」
片手剣を構えてイクスに詰め寄ろうとしたときナルが声を張り上げた。
「お待ち下さい!」
彼女はイクスの後ろ、食堂の隅で身を丸め怯えていた。
涙に濡れる少女の瞳が訴えている。
追いついたアーミラは食堂の光景を見て状況を推察する。
床に倒れたニールセン。切り伏せたのはイクス。目撃者として立つセルレイ……話に聞いた部下殺しの場面がここに再現されていた。
「彼はやっていません……!」縋るようにナルは訴えた。
反駁するようにニールセンも呻きながら訴える。
「……こ、こいつは……部下殺しの狂人だ……!」
セルレイは奥歯を噛み締め、イクスとニールセンの両者を睨む。
まただ……怒りが渦巻く脳内で伯爵は憤っていた。また、過ちを犯す所だった。
「誰も動くなよ……」
伯爵から見てこの二人のどちらかがトガであることは理解できていた。過去に起こった部下殺しの件……その中で語られる人の皮を被ったトガの存在は、まさに今、この目で見て知るところだ。
過去の一件をなぞるこの状況、ただ一人、真実を掴んだ者がいる。
「イクス、お前はここで何をしていたんだ」
討伐隊が平原に向かい、鎧と次女継承者が出払った邸で、何を企てていたのか。
「おぇあ、ずぅっと見張っえた」
赤子の喃語のような不器用な言葉だが、はっきりと聴き取れた。
俺はずっと見張ってた――この日だけの話ではないのだろう、イクスの言葉は重たかった。部下殺しの汚名を被り、狂人と罵られながら過ごした日々……企てていたのは復讐ただ一つである。
イクスは一日たりとも恨みを忘れてはいなかった。
それと同じく、兵としての矜持も捨ててはいなかった。
いつかまた人の皮を被ったトガが現れる……そのときに備えて彼は自ら闇に潜み、この邸を――平原を見張っていた。
「違う……!」ニールセンは遮るように声を荒げる。「私もずっと信じてた……、でも違う! この人はイクス隊長じゃない……!」
「お前は隊を連れて邸を出たはずだ」
「ガントールにやられたんです……っ、部下がみんなやられて……邸も狙われてる……、だから、急ぎ戻ってきたんです……」
筋は通るが、彼の主張はどこか空虚に聞こえた。
「我々は前庭にいたが、君の帰還を見ていない」
「……偶然、見ていないだけです……」
「鏑矢を鳴らさなかったのは何故だ」
「武器は、壊されたんです」
糾弾に耐えられる強度ではない。ニールセンの主張は綻びが生じ始めた。
「ちがう……そんな、信じてください……」
目の前で命乞いをする部下の姿は、まるで過去の再現のようだった。セルレイは眉間に深い皺を寄せ、悲痛な表情を浮かべる。
「その申し開きも誰かの真似か……?」セルレイは突き放すように言う。
「真似じゃありませんっ! ……ニールセンです、信じて……誰か……」
彼の堂に入った仕草を見ていると心を引っ張られそうになるが、誰の目にも明らかだった。
「イクスの顔が奪えなかった。……そうだろう?」
取り囲むアーミラ達は憤りの目で彼を見つめる。
ニールセンは偽者だ。
先のアーミラとの戦闘でトガはガントールの顔を失い、代わりに別の顔を被った。それがニールセンだ。邸に侵入し身を隠した先でナルと鉢合わせたのだろう。イクスはナルの危機を察知し、窓を割ってニールセンを切った。あとは見ての通りである。
しかし、なぜこのトガは斬撃に倒れているのか……急所を突かれても再生していたはずなのに、一体何がトガを追い詰めたのか……怪訝に思ったアーミラはふと床に撒かれた白い粒に気付く。これは――。
「イクス、お前はこれと戦ったのか……偽者だと分かっていても堪えるな……」
セルレイは神器である天秤の剣を握り、ニールセンの首を狙う。
「畜生……! お前さえ、お前さえいなければ……!!」
呪詛の言葉を吐きながら床を叩くニールセン。口惜しさに震え、追い詰められたトガは残された余力で飛び掛かる。
『お前さえ』という言葉が指す対象がイクスであると皆が思った。
セルレイが得物を構えイクスの前に立つが、ニールセンは自身の肉体を溶かしてセルレイを飛び越え、全く別の者を狙っていた――ナルの体は強張りその場から動けなかった。
❖
首のないウツロは平原の一隅でエンサと向かい合ったまま固まっている。大きく開いた襟の空洞が温い夏の雨を受け止めて、雫の音を空しく鳴らしていた。
攻めあぐねている……という訳ではなかった。むしろ勝負はとうに付いていた。
二人を見守るように側にへたり込んでいた兵士は既に虫の息。顔の皮を剥ぎ取られ、癒えぬ傷痍が雨にふやけて出血は止まらず、喉元に細く朱色の線を引いている。金縛りに身動きを封じられたまま体力は消耗しきっていた。
彼の意識は呆然としており、残された左の眼球も上転している。
エンサが行ったのは石化の呪術だった。
ダラクの術式よりも拘束に特化したもので、瞳を覗き込むだけで対象は術中に嵌まり身体が石のように動かなくなる。ウツロは人質を眼前にぶら下げられたときにはもう石化の邪眼に対抗する手立てはなかったのだ。
兵士を助け出せるかどうか、その考えが浮かんだ時点でエンサの術式は必中である。
こうしてウツロは、哀れにも体の自由を奪われ、その内側に招かれざる客人の侵入を許した。
精神領域ではエンサがにやにやと丸い頬に笑窪をつくり、肉に埋まった首から蛙のような引き笑いを溢す。万事順調なことに可笑しさが込み上げてとまらない様子である。
この逼迫した戦時下にいったい何を食えばそこまで肥れるのかと疑問に思うほど贅肉まみれの体を揺らし、迷宮の中を上機嫌に進んでいた。
向かう先は一つ、話に聞く鎧の正体、ウツロを操る術者のところ。
「ぐふふ……ダラクも意地が悪い……」エンサは芋虫のように節が膨れた丸い手で口元を抑える。「中は迷路だと言っていましたが、これの何処が迷路なのでしょうね」
扉を開け、目の前に待つ次の扉に向かう。
鎧の内側は単調な一本道だった。
「それとも私とは違うものが見えていたのでしょうか、ねじくれた性格が顔に出ていますから、きっと拒まれていたのかもしれませんね……ぐひひ……わ、私は怖くないですからねぇ? このまま真っ直ぐあなたのもとに向かいますから……」
エンサは逸る気持ちに身を任せ、ぐいぐいと精神を潜り扉の奥へ進む。エンサが扉をくぐるたびに着実にウツロの本質へ近づいている。
変わり映えのない繰り返しの景色は不意に終わりを迎える。
「おや、もう終わりですか……私、興奮してきました」
最後に待ち構えていたのは艶やかで平滑な硝子の扉だった。
しかしエンサは異質な扉を前にしても警戒するどころか期待に胸を膨らませていた。これまで見たこともない建築様式の通路を前に悠然と歩を進める。
余程己の術式に自信があるのだろう。だが賢さで比べるならやはりダラクが上手である。ダラクはハラヴァンの難詰を前にしても差し出す情報は絞っていた。それと同時に興味を惹くであろうことは言葉巧みに開示することで情報の価値を補強し、誠意を取り繕う。そうして保身に命を繋ぎ果せた。かたやエンサは呪術一つを極め、身の振り方に省みることがない。気に食わないものがあれば石化の邪眼で捻じ伏せ、快楽の赴くままに我が道を歩んできた。
そして道の先に辿り着いたのは虚ろな深淵である。
「……げ」少女は声を漏らす。
エンサが辿り着いたのは小さな部屋だった。そこには簡素な作りの褥があり、尻をこちらに向けてうつ伏せに寛いでいる少女がいた。冠のような頭角、射干玉の黒く豊かな髪が背中を覆い、肌着から覗く細い腕が肘をついて顎を支えている。大きく開かれた瞳は誤算に引き攣っていた。
「なんか違うんだけどー」
不満げに少女は言い、ばたばたと爪先で褥を叩く。
あどけなく自由気ままな態度に警戒の色はない。それどころかエンサを無視して明後日の方に向って独り言を呟いている。
「前に来たやつは痩せっぽちだったよね? ……次は食うって言ったから怖くなったのかな」
一方でエンサの方は歓喜に鼻息を荒くしていた。
「それはダラク殿のことですかな? その役目は不肖私が仰せ仕りましたぞ」
「骨ばってて食い出がないだろうなとは思ったけど、こいつはなんか……胃もたれしそうじゃない?」
「独り言ですか? このような場所に閉じこもっているから癖になってしまわれて……私と遊びましょう、体を動かして、ね? さぁさぁ」
丁度お誂え向きな部屋ですし。とエンサは気持ちの悪い笑みを浮かべて上衣を脱いだ。性欲が発酵したような独特な臭いが部屋に広がる。
「というか、腐るのはやめたんじゃないの?」
虚空に向って呟く少女は独り言ばかりで会話は成り立っていないが、どうせ致すときは石化で口をきけなくするのだから関係ない。可憐な少女が目の前にいるだけでエンサは己の男性の部分が脈打ち膨らむのを感じていた。
「なんという僥倖でしょう……ぐひひっ、まさか本当に……あのダラクが真実を語るとは……!
今なら神を信じれますぞ!」
脂の浮いて照りのある顔が興奮に上気して、エンサは辛抱たまらず褥に上がり、少女の背中に四つん這いで躙り寄った。腹の肉が重力に垂れて細くしなやかな少女の素足の上を滑る。
「……今、お前……」
つい、っと黒い瞳が滑り、少女の意識がエンサに向けられた。底冷えするような冷たい声音だった。
「『神を信じる』……と言ったか? 『真実を語る』と、言ったな?」
少女は太り肉の禍人種の言葉を繰り返し床に伏せていた体を翻して仰向けになると、先程までの呑気な気配を変貌させた。
「嫌いだね」少女はエンサを蹴り飛ばす。
細い体のどこにそんな力があるのか、エンサの巨体はごろりと転がり壁に頭を打つ。
「あ痛たた……」
わざとらしく顔を皺くちゃにして後頭部を手で押さえ、エンサは丸い目でおどけたように少女を見上げる。
褥に立ち怒りによってうねる黒髪は首を擡げた蛇のように揺らめきまさに怒髪天である。少女は厳しく睨め付けた。
部屋の内圧が上昇していく。
エンサは逆鱗に触れたのだ。
「……おっと、流石におふざけが過ぎましたな」
未だ余裕の態度を崩さないエンサは瞳に呪力を込め、石化の邪眼を行使する。
睨み合う視線が交差して、確かに邪眼は少女を捉えた。
「どうです……もう動けませんでしょう……?」
エンサは勝利を確信し、ゆっくり立ち上がると腰紐を解いた。
「遊んであげますよ……楽しみましょうねぇ」
少女の耳元で囁くと、舌打ちが返ってきた。
「遊ぶのはお前じゃない」
「なっ!? 石化が――」
「目障りだ」
事態を理解する間もなくエンサは宙に固定される。
「――むぐぅ……っ!?」
エンサは身動きができなくなった。石化の意趣返しとしてはあまりにも歴然とした力の差を見せつけられている。……否、見えてはいない。見えてはいないが全身の圧迫感で理解した。
巨大な手に全身を掴まれている。
「『遊んであげますよ』、『楽しみましょうね』」少女はエンサの言葉を返す。
込められた握力に応じて肥えた体に指が食い込み締め付けられ、骨が歪みはじめる。
エンサの表情から余裕は消え失せていた。四肢が、肉が、脊椎が、軋みを上げて激痛が襲った。このままでは……。
「簡単に死んでくれるなよ。生きたままでなければ食いごたえがないからな」
叫びたいのに口元にも指が押し当てられている。不可視の壁によって息を吸うことも吐くこともままならない。目を白黒させ、額は赤紫に染まり、言葉にならない絶叫を繰り返す。
拘束から逃れようと必死に身悶えする様を仰ぎ見て少女はほくそ笑む。
「滑稽だなぁ。アキラよ、面白かろう」
巨腕が握力を強める。軋みを上げて潰された四肢はついに限界を迎えた。
ぽくん、と間の抜けた音がエンサの脂肪の内側から一つ響くと、後に続いて全身の骨が粉々にへし折られる。エンサの見開かれた目から涙が流れた。
――こんなはずでは……。
彼にとって、いかなる者も脅威ではなかった。
強者には必ず意思があり思考がある。そして内面は瞳に宿り、石化の邪眼は必ず通用する。意志の強い者であれば尚更覗き込むのは容易くなる。
ウツロと呼ばれる魔導具を操るこの娘も、神殿が希望を託した娘達も、彼にとっては都合の良い愛玩具となるはずだった。
誤算。
大いなる誤算。
エンサは地面に放られる。
着地の体勢が取れるわけもなく、肉塊となって床に打ち付けられた。びちゃ、と腹の肉が床に弾む。血と汗と涙に汚れたエンサの顔が命乞いに少女を見つめる。
「……これは食えないな」
少女は視線を落とす。
迫り来る死の恐怖に遺精するそれを、不可視の指先が爪を立て取り除く。床に擦り、引き千切られた己の欠片を見つめ、怨嗟の声を上げる。
「んぐぃ、ぎぃぃぃ……!」
悲鳴に似た絶叫に少女の笑い声が重なる。
「誰なのです……っ、あなた……!」
エンサは未練がましく石化の邪眼を行使した状態で少女を睨む。
「知りたいか?」
少女は呪術を跳ね返し歩み寄ると、後生だと微笑み、起き上がれない肉塊の耳元で密やかに告げる。
エンサは少女の正体を知り、邪眼の呪力が吹き消されるように霧散した。
表情は蒼白で、「信じられない」と怯えた視線が語る。
「そんな、嘘です……あなた――」
「ふふっ、じゃあね」
ばく。
少女は脂下がり悪戯っぽい笑みで手を振ると、エンサの肉体は齧り取られて消滅した。床に残されたのはエンサの踝から先と片手の指先……所在なげに転がり少量の血を零す。
少女は唇についた血を舌でちろりと舐め取り、喉を鳴らす。
「糞不味い」
時を同じくして、朦朧とした意識の中で兵士の眼球は異変を捉えた。
ウツロを石化させ精神領域へ潜り込んでいたエンサの身体が突然消滅した。地面には抉り取られたように両足だけが残され、繋がりを失い宙に浮いた手の指が落下し地面に転がる。次の刹那には兵士の身体にかけられていた呪術が解かれ、泥濘に倒れる。
ウツロは駆け寄り、兵士を助け起こす。
「たお……した……のか……?」
ウツロは頷く。
「そうか……よかった……」
兵士は安堵に弱々しく笑みを作った。その人当たりのいい柔らかな笑みを見て、ようやく彼がニールセンだとわかった。
ウツロは指筆で呼びかける。
――ニールセン。お前は隊長のニールセンだろう?
悲しいことに彼は識字ができない。なぜ肌を指でなぞるのか、朦朧とした意識で理解するのに苦労する。
ウツロは懸命に、言葉が届くまで呼びかけを繰り返す。
――ニールセン。
兵士の顔がはっとして、ウツロを向いた。
唯一知る文字、己の名を指で書いていることに気付いて涙が浮かぶ。
「顔を奪われても……私がわかりますか。
……どうやらあの化け物も、名を、奪うことは、できなかったみたいですね……」
ニールセンは手を伸ばし、ウツロの鎧の襟元を掴む。
「私は助かりません……っ、どうか、邸を……」
弱々しく掴む手が震えている。後悔と無念に胸咽ぶ。
「ハルバド隊長は正しかったんです……、イクスさんは、きっと今も戦っています……。どうか、どうか……!」
ぐったりと、言葉は途切れる。
ニールセンの願いを聞き、ウツロは槍を携え邸へ急いだ。
ダラクはそこに向かったはずだ。
❖
アーミラは意識を取り戻したと同時に痛みを感覚した。
まるで煮えた油を顔にかけられたように額から頬、顎に至るまで強烈な疼痛。すぐに飛び起きようとしたが力が入らない。動けと念じる頭からの指示が、身体の何処かで途切れてしまっていた。
辺りは火の気が立ち昇り、石壁は毀たれて曇天が覗いていた。雨は弥増すばかりで、火勢と風雨が互いにせめぎ合っている。
前後不覚だったアーミラは、状況を思い出しつつあった。
あのとき、偽者のニールセンはイクスではなくナルを襲った。
そして咄嗟に身を挺して庇ったまでは覚えている。この顔の痛み……そうか、奪われたのか。
煙にしみる眼球を雨垂れが癒やす。剥き出しになった鼻腔が荒天の生温い風の臭いを吸い込む。壁材の焦げた香りが混じっている。
かろうじて動く首を己の腹に向ける。
湿疹のように赤く腫れた胸元の皮膚には無数の小さな穴が開き、とろとろと出血が確認できた。その下、鳩尾のあたりから肉が齧り取られて腑を晒している。
他人事のようにアーミラは腹を見つめる。肉に蛆が沸いているのをぼんやりと眺め、次第に意識が明瞭になる。
湧いているのは蛆ではない。トガだ。蛞蝓とも蛭ともつかない細い蟲が蠢き肉に噛み付いている。
――死んでたんだ……私……。
全く実感は湧かないが、アーミラは悟る。
ナルを庇い、トガに体内への侵入を許し腑を傷付けた。そして神殿の加護により蘇生が行われるまで死んでいたのだ。
みんなはまだ無事だろうか……と、首を回せば状況はすぐに分かった。
――ウツロさん……。
鎧は矢面に立って戦っていた。
セルレイとナルを背後に囲いながら、火炎を飛ばす禍人を相手に槍を振るっている。傍にイクスもいるが、足の古傷が痛むのか火をいなすので精一杯だ。
熱を操る禍人種……奴がダラクか……と、怒りに滾る思考とは裏腹に意識が途切れる。
失血による死を迎えた。おそらくは二度目の死である。
加護による蘇生から目覚めたとき、アーミラはまた状況を確認する。
幸いにも数刻前の死の直前から記憶の連続性は失われていなかった。空の明るさから見てそこまで長く気を失っていたわけではないだろう。感覚的にも微睡みに目を閉じたくらいのものだった。
とにかく今は、腹を食い荒らすトガを追い払う。睡醒に痛覚が麻痺している今しかない。
アーミラは神器を探して腕の力を振り絞り床を探る。天球儀の杖は少し離れたところに転がっていた。掴もうにも爪が微かに触れるばかり……これでは術の行使は望めない。
「……詠唱、するしか……」
歯を食い縛ったが、無駄だった。
真っ暗な闇。再び、沈む。
死んでいる間、アーミラは夢を見た。それは濃密な闇だった。果てもなく虚無が広がる空間で、心臓が青い炎を纏っていた。
その鼓動は私のものだ。
弱々しく脈打ち、次の鼓動の感覚が広がり、炎は大きく揺らめく。
神殿の加護は継承者の娘を非死にする。姿形を維持するためにあらゆる傷痍、欠損から復元を試みるが、決して不死ではない。
灯された火が限界を迎えれば蘇生は叶わない。垣間見た己の心臓……己の死……アーミラの焦りが出血を早め、炎が風に煽られる。
杖がなければ光矢は使えず、短い意識では詠唱は途切れる。
悔しさに歯を食い縛り、アーミラは細く息を吐いた。心を平静に保つんだ。まだ……、諦め……――
意識が暗転し、アーミラは四度目の死をから目覚めると、次の死を迎える前に指先で床を引っ掻き始めた。杖を手繰っているのではない。
杖も詠唱も奪われたが、アーミラにはもう一つ、手段が残されていた。
それはウツロと過ごした日々の中にあった――指筆である。
邸の床は石畳で爪を立てても線を引くことはできないが、雨水に煤に己の血……何かが付着するはず……。それが墨となって筆跡を残せば、術式回路は組み上がる。
指の感覚を頼りに陣を描く。それはアーミラが知る限り最も簡素な魔術回路であり、この場を打開する効果の期待できる術式でもあった。意識が途切れようとも次の命が術式の構築を引き継いだ。
「おねがい……」
乾坤一擲。アーミラは構築した陣に祈り、魔力を注ぐ。
拙い回路ではあるが、術式が発動する。
――やった……!
なんてことはない初歩の浮遊魔法……それこそ過去にナルトリポカの娘が石を浮かせて操っていたものと同じ基礎の術式。
できて当然のことが、今は感極まるほどに嬉しい。
アーミラはその術で食堂の甕を浮かせた。
邸はダラクとウツロの繰り広げる戦闘に荒れ、黒煙が立ち込めている。
食堂の隅で小さな甕が浮いていることには誰も気付いていない。ゆらゆらと微弱な魔力で甕は移動し、アーミラの倒れている上空で止まる。
あとは天命を待つのみ――アーミラは何度目かの死を受け入れるように目を閉じた。
陶器が叩き割られる音が響き、皆の動きが止まる。
ダラクもウツロも意図していない。外からの音に警戒した。
火災による視界不良の中、食堂に倒れていた次女継承者の瞳に光が宿る。啾啾と泣いていたナルは口を押さえて歓喜に目を輝かせた。
「アーミラ様……!」
私を庇って身代わりに命を落とした彼女が、生きていてくれた。失態に己を責めていたナルは救われた気分だった。
一方でダラクはこの状況に大いに狼狽える。
体内に寄生し腑を食い荒らす限り継承者は復活できない……現に長女継承は倒してみせた。三女神の中で一番手練の娘を倒したこの奇策が――
「なぜ!? そんなバカな……!」
ダラクは扼腕して儘ならない怒りを叫ぶ。
敵の言葉ながら、セルレイも同感だった。戦場に起きる奇跡ほど不確定で理不尽なことはない。アーミラは何故生き返ったのか。……信じられない。こんなはずでは――。
「あの甕は……」目を凝らすのはセルレイだ。
アーミラの倒れていた場所に散らばるのは、食堂に保管されていた甕だった。先程鳴り響いた陶器の割れる音の正体も明らかである。それが割られ、中に保管されていた塩が山となって床に散らばり、雨を吸って溶け出していた。
しかしなぜ塩甕を割ったのか、言問顔のセルレイを置いて答えにたどり着いたのはナルだ。
「……蛞蝓……いや、蛭……!」
まるで正体を見破られて術が解けたようだった。
アーミラの体を蝕んでいたトガが腹の穴から湧き出ては降り落ちて床に転がりのた打ち回る。
蛭に塩。
正体不明と平原を恐怖させたトガは塩に縮み、火に焼かれ、脆く崩れ出した。
偽者のガントール、そしてニールセンの正体は軟体の体を持つ群生のトガだった。
対象の手脚、胴体、衣服に至るあらゆるものが蕩けてねばつく分泌液と呪力によって形作られ、肉は糸屑のような蟲の類が結びつくことで人に化ける。そのためこの偽物に急所はない。
体を裂いた斬撃も立ち所に治癒し、アーミラの矢が心臓を捉えても生きていた。間違いなくこのトガは平原の脅威だった。
しかし、襲われたナルが偶然にも振り撒いた一匙の塩が、このトガにとってなによりも強い一撃だったのだ。助けに来たイクスの一閃が回復しなかったのは、傷痍に塗り込まれた塩の作用であった。
アーミラはあのとき、床に散らばる白い粒を見た。
そして偽者のニールセンは『お前さえ』と睨み襲いかかった相手は、イクスではなくナルだった。
点と点が結びつき、現状打開の緒となる。
それぞれが胸に宿していた勇気や矜持が僅かな手掛かりとなって、アーミラの命を繋いだのである。
ダラクは叫ぶ。
「誰でもいいから道連れにしろ!!」
その叱責に残る力を賭して、トガはその身をニールセンに変える。欺く為の変化ではない。なりふり構わず右手を槍に変え手負いのセルレイとナルを狙う。
その槍は思わぬ伏兵に阻害された。横から飛び出してきた扇によって狙いは逸れ、セルレイには刺さらない。
「スークレイ……!」
ニールセンを咎めたのは、杖から現れた女伯であった。
「ここが正念場でしょう! イクス・ハルバド!!」
スークレイの言葉にイクスは斧槍を構えた。引き摺る脚を拳で叩き、気合で奮い立つ。
アーミラは魔術により風を操りトガに塩を撒くと蛭の一匹一匹に光矢を刺し貫いて消し炭にする。
残されたのはあと一人。
「……儘ならねぇもんだなぁ……」
ダラクは天を仰いだ。
四人に前後を挟まれ、彼は荒く呼吸を繰り返す。
「そこのウツロよぉ……お前にはエンサがいただろうが……。
次女継承よぉ……ハラサグリを倒すとは思わねぇだろ……」
乱暴に頭を掻き毟り、ダラクは肩の力を抜く。
男にとって今回の策は勝率が高いと踏んでいた。一目でわかるほどの落胆……禍人は内省に俯く。
平原を餌場に育てたトガ――ハラサグリを嗾け、内地をわざとらしく暗躍することで地下通路の存在を匂わせた。誘き出された長女継承を仕留め、残る継承者は内地の娘ばかり……。
ナルトリポカの集落での失態がなければ、もっと上手くやれただろうか……否、俺は窮地さえ逆手にエンサを蹴落とした。この死線を掻い潜れば……。
「まだだ」
ダラクの面持ちが変わる。纏う空気は熱を帯びて風が巻き上がる。
「俺は生き残る……それに、次女継承……お前はまだ傷が癒えてねぇな」
アーミラは努めて動揺を隠したが、ダラクの指摘は事実だった。
杖を支えに立つのがやっとで、この場を威圧するためにトガを焼き魔術を見せつけたが、蝕まれ穴だらけの腹は癒えていない。
「観念しなさい」
「いいや、観念しねぇ」
アーミラの言葉をダラクは反抗的にあしらう。
続く両者の声は重なる。
「そうですか、なら――」
「どのみち貴様らは――」
互いが先手を狙い動き出す。
「――殺す!」
その決着は一瞬だった。
挟撃を仕掛けるウツロとセルレイは得物を前方へ突き出す。ダラクは前後から迫る攻撃に脇腹を掠めながら回避して槍の柄を掴み冷気で固める。片手剣を奪い取ると肩を凍らせた。冷やされた板金の関節が軋み、槍を手放す。
その間にイクスは斧槍に魔力を込めて縮地の術で踏み込んでいた。通り過ぎ様に横凪に得物を走らせたが、足のもつれたウツロを盾にして刃をやり過ごす。
「凍りやがれ!」ダラクの怒号。両手で印を結び術を発動させる。
雷に打たれたような衝撃と共に邸一体に霜が降り、燃え盛る熱気が凍てつく刃に刈り取られた。
「氷解――!」重ねるようにアーミラの詠唱。
邸の氷は砕け、湯気となり蒸発した。
それだけではない。ダラクの掌も焼き爛れ、腕輪が爆ぜる。
熱というのは、物質をつくる小さな粒子の固定と振動によって生み出される力である。この世界には『原子』や『分子』という言葉はないが、ダラクの術式はそうした物に宿る『精』や『素』を理解し操ることで力を操作していた。
人生の殆どを費し組み上げた秘中の秘の魔術体系、誰も到達できない高みだとダラクは自負し、裏付けされた努力があった。だというのに。
――こいつ……俺の積み上げたものを、もう理解してるのか……!?
アーミラが継承する天球儀は何を測り司るか――物の距離である。つまりは邸を満たす空気の『素』と『素』の距離を操ることで、強制的に大気を震わせ熱を生み出した。
強い振動に耐えかねたものは形の維持ができなくなり、ダラクの魔力の源である腕輪が砕け、術式に悴む掌の氷も一転して灼熱となり肌を焼いた。
「いきなさい…! イクス……!!」スークレイは治癒の術式で援護する。
古傷に痛む彼の脚はとうに限界を迎えていた。それでもイクスは縮地を行使し、ダラクに迫る。
ダラクは己の身に何が起きたか理解が追いつかず、同然とアーミラを見つめる。そこにイクスの追撃を認め、懐から反撃の手段を掴み取る。
「死ねぇ!」
ダラクは切り出しを握り、イクスの顔に突き出す。刃は面頬の隙間に滑り込み眉間を貫いた――かに見えた。
「これで終わりだ……」イクスは囁く。
勝鬨というには密やかで、むしろ己の戦いに終止符を打つ感無量の呟きだった。
切り出しは確かにイクスの仮面を捉えた。しかしイクスは寸前で仮面を脱ぎ切り出しを受ける盾とした。同時に斧槍はダラクの胸を一突きに貫いて、両者はぶつかり合った勢い余って身を預けるように支え合う形となった。
ダラクは死力を尽くし、己の戦いがここまでだと悟ると、自身の敗北を受け入れたようにイクスに凭れる。これ以上の奇策は出てこない。恨み節の一言もなくダラクは事切れていた。
握っていた切り出しが床に転がった。同じように、面頬もイクスの手から落ちる。
二年前のあの時から頑なに隠し続けていた彼の素顔に、雨止みの光芒が照らす。
何人もの部下を失った。
人の顔を奪い、その者に化けて現れるトガにイクスの人生は狂わされた。
部下を殺さなければならなかったあの日の悪夢はイクスの心身に深い傷を残した。慕ってくれる彼らを助けることのできなかった無念と、部下殺しを成し遂げた後の誰の理解も追いつけない奈落の孤独。
イクスは、部下殺しの汚名を背負う前には勇名を有していた。
片時も肌身離さず携えていた自身の得物――槍斧。平原の風と人々に呼ばれ、厚い信頼と主人への忠誠を持つ気高い兵士だった。スペルアベルでその名を知らぬものはいない。イクス・ハルバド討伐隊隊長。
彼は部下の顔を取り戻し、トガを始末したあと、一人無力にやりきれず咳き上げていた。悲しみに溺れ、彼らの無念を忘れないために、己の顔を斧槍で削ぎ落とし、そして仮面を被ったのであった。
恨みに生きた道程がここで終わった。
万感の思いを乗せた一撃の果てに勝ち取った勝利……ダラクは平原に倒れ、トガは焼き尽くされた。
イクスは込み上げる複雑な思いにうち震え、歔欷に洟を啜り、言葉にならないままに空に叫んだ。その醜貌は部下たちと共にする旗印として、敵討ちを成し遂げたと斧槍を天に掲げる。
その姿は醜く、気高いものだった。
「イクス……さん……」
ナルは信じていた。
父の口から語られる隊長の勇姿は、幼い頃寝床で聴かされる御伽噺で、悪い話は一つも聞かなかった。
父が帰ってこなかったときも、「きっとイクスはおかしくなんかない」と信じていた。それは彼を信頼していたというだけの話ではない。父の誇りも、そこにかかっているのだ。
だからこそ、空に向かい雄叫びを上げるイクスの姿に胸が震えた。部下たちに捧げる勝鬨の雄叫びに報われた思いだった。
「信じてた……っ! 私は、間違ってなかった……!」
イクスの成した恨みの矜持と、ナルの成した明察の矜持。
その二つを側で見届けたアーミラは訳もわからず涙が滲む。
平原を襲った長く短い動乱の一日は終わりを迎え、焼け焦げ半壊した邸には心地よい風が吹いた。加護に癒えたばかりの肌が少し寒い。
「イクスさん。ありがとうございました。貴方がいなければ、倒せませんでした」
アーミラの言葉にイクスは恥ずかしそうに顔を背け、仮面を拾い上げる。
「ナルさんも、ありがとう……それと塩甕をすみません」
「いいよ。食堂はご覧の有り様だしね」
「食堂だけじゃないぞ。邸は半壊だ」セルレイは疲れた顔で煙草を取り出す。「アーミラもスークレイも無茶をする……拠点を譲るんじゃなかった」
皮肉交じりの冗談を言い、口元に笑みが浮かぶ。皆もつられて小さく笑い、緊張の糸が解れる。
「ですが、まだ終わりではありません……私はラーンマクへ向かいます」
アーミラのはっきりとした声に一同は驚くが、実際問題前線はまだ争いが続いている。継承者を求めている。
ウツロは力強く頷きアーミラの隣に立つ。共に向かうつもりのようだ。
「……わかりました。ここは私達に任せなさい」
セルレイとスークレイがスペルアベルの指揮をとり、この地での戦闘は収まる。
邸は戦闘の被害も甚だしいが、壊れたのは二階食堂部分が主で、幸いにも従者は無事、ごっそり失った兵力は部下殺しの誤解を解いたイクスの下でどうにか兵をかき集めてもらう他ない。討伐隊が全滅とは……苦い勝利だった。
表情を曇らせる面々の中、ウツロがアーミラに語りかける。アーミラは指筆の言葉をその場で声に出して代弁した。
「『ニールセンは、助かるかも、知れない』……?」
「なに、どこにいる!?」セルレイは煙草を落としウツロの肩を掴む。
「『南方、顔を失い、倒れている。望み薄だが、放ってはおけない』」
アーミラはウツロの言葉を読み上げて、すぐにでも向かおうと目で合図した。
「私が行きます」スークレイが名乗り出る。「ニールセンのところまで案内を、治癒を施し、邸に連れ帰りますわ」
今度はアーミラが頷く。
こうしてはいられないと、三人は準備もなく歩き出す。その背に声がかけられる。
「ウツロ」
イクスの声だ。
振り返ったウツロに対し、イクスは意を決したように斧槍を差し出した。
「持っていけ」
ウツロは戸惑い、触れるのも恐れ多いと斧槍を辞して手を振るが、イクスは頑なに押し付ける。
声の出せないウツロに代わり、セルレイが問うた。
「本当にいいのか? この得物がなければ、お前の勇名が失われるんだぞ」
「捨てた名だ。構わない。どのみち俺はもう走れない。
頼む。ウツロ。この先武器は必要だろう? 連れて行ってくれ」
きっぱりと言うイクスに、セルレイは食い下がらない。彼はもう十分成し遂げたと納得し、棹さすようにウツロに告げる。
「本当の意味で退役か……。
イクスがここまで言ってるんだ。受け取ってくれ」
ウツロは躊躇ってはいたが、覚悟を決めて斧槍の柄を握った。
失ってばかりの旅で初めて得たものだった。
■009――災禍の龍 前編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
次女継承者アーミラを中心とした者達の活躍によりスペルアベル平原の動乱は平らげた。しかし向かう前線では長女継承者ガントールの消息は依然として不明。この地を任され、一人残されたオロルに訪れた試練の顛末についてもここで語らねばならない。
時は少し遡り、四代目長女国家ラーンマクにて。
曇天の空は今しも雨粒が砂埃に混じり、荒れた戦場の景色を気休めに癒し涼風を控えめに飾る。
戦場は巴のごとく敵味方が入り乱れ、奪い合う陣形は卍を描いていた。前線の中で誰もオロルを感知しない。視線を向けられ見つめ合う敵でさえも、静止した時間のなかでは眼差しが交差していることを知る由もなかった。
オロルは引き伸ばされた時間の中で腕を組み頤に指を添えて、前方に立つ敵にじっくりと視線を注いでいた。
普段のオロルといえば不遜な振る舞いが目立ち、己の背の低さもお構いなしに相手をつんと鼻越しに見下ろすような態度であるが、それは油断や慢心を意味していない。唯一与えられた長考の時間と鋭敏な警戒心が彼女にはあり、常に勝機を見出してから先へ進む。オロルという人間は石橋を叩いて渡るが如く、紐解けばこの世の誰よりも手堅く賢人種の血を窺わせる質である。隠した努力に裏付けられた自信に由来する超然とした物腰は彼女特有の魅力でもあり、継承者の姉達はそのどっしりと構えた姿に背中を支えられていたものであった。
当然、此度現れた見慣れぬ敵に対してもオロルは十分な警戒を怠らない。
こちらに向かい脚を前に踏み出したまま動きを止めているその敵は、オロルとは対照的な体躯を持ち戦場に現れた。
ほっそりとした体に常人の倍はあろうほどの長く伸びた手脚が揃い、草臥れた布の鎧を纏う。その襟から伸びた首は長くしなりがあり、末端に据えられ徒花のように揺れている人面は窶れた女の顔立ちであった。落ち窪んだ眼窩に影を抱えた双眸は一点を射抜き、長い黒髪が吹き荒れる風に流れている。
まるで蒲柳の質の者が病床から起き上がり、敷布を身にくるませてこの場に迷い込んだようだった。だが、その者が持つ余裕の挙措、悠然とした歩みは、病弱なる者のそれではない。むしろ死を連れ歩き病を先導する悪鬼である。
引き伸ばし堰き止めされた時の中で、誰もが指先一つ、思考の刹那、先へ進むことのできない世界でそれでもオロルは緊張に息を呑む。
「何者じゃあ……あいつは……」
禍人種にしては異形。だがトガにしては人に近しいその姿は、戦場に躍り込んできた客人ではなく、この前線を縄張りとする主のような振る舞い……もし禍人種にも何かしらの権能を賜る者がいるとするなら、きっと奴がそうだと、オロルは感覚的に理解する。
継承者がこの戦場において無二の存在であるように、奴もきっと同種なのだろう。
「まさか龍ではあるまいな……」
静止した領域で敵はまだ遠く距離があるが、目を凝らして望めば日に晒している肌は鱗のような光沢があった。腰に留めている布鎧の裾からほっそりとした青白い脚とともに長い尾が垂れている。
頭角に長い尾、これで翼まで揃っていたらなら、書物に記され人々に口伝する龍と言えるのだろうが、目の前の敵は翼が欠けていた。
例えるならその姿は半人半蛇というべきか。
ふむ、とオロルは少し考え、「……敵に倣うか」と呟いた。
奇襲を狙う――とりあえずの方針を決めた。とはいえ敵はすでにこちらを見据えて向かってきているため奇襲とはならないが、不意を打つ手段ならいくらもある。例えば、静止しているうちに術の構えを済ませておくだけでも先手を取ることができるだろう。
敵は得物も携えていない。恐らくは魔呪術と体術の近中距離が間合い。こちらは踏み込まれる前に先んじて魔術を放つ。効果があれば頂上。なければ次を考えればいい。
一度、着飾った魔鉱石の残量を確かめる。前掛けに縫い付けた鉱石の輝きは随分失われてしまったが、目算で強敵一人仕留める分は優にある。
覚悟を決めて、オロルは両手の指を内側に組んで前に構え、親指を合わせてできた三角の穴から敵を覗く。手印による術式の構築である。時止めを行っている今は魔力を注ぐことができないが、狙いを定め、オロルは大地に脚をつけた――時は動き出す。
時が動き出すと同時に柱時計から光線を射出。真っ直ぐに伸びた光が迸りオロルと半人半蛇を直線で結んで貫いた。後に遅れて衝撃が輪を描き広がると、光線の後を追いかけて土を抉った。
目で追うこともできない細く鋭い光線。不意をつかれれば回避できるものはいない。射出したとき必中を確信したオロルには手応えがあった。
砂煙の中で敵の影に風穴が開いている。逆巻く爆風に鱗が舞ってきらきらと光を跳ね返し、オロルは肩の力を抜いて息を吐いた。
――なんじゃ、呆気ない……――そう思ったときだった。
殆ど一瞬にして、眼前に半人半蛇の敵が迫っていた。
鋭く尖った爪が眼前に突きつけられ、あと少し、ほんの刹那、時止めが遅れていたならば、間違いなくオロルの右目は抉られていた。驚きに目を瞬けば睫毛が触れてしまいそうなほどに凶手はすぐ近くにあった。
まるで放った光線がこちらに跳ね返ってきたような速度。粟立つ肌をそのままに、オロルは声も無く戦慄していた。見えなかった……!
オロルは後ろに飛び退る形で背に繋がった神器の綱を操り、敵の懐から逃れた。全身を巡る血流が早い。神殿に預けた心臓が早鐘を打っている。
それだけではない。光線で穿った布鎧こそ丸く焦げて消失しているが、はだけた四肢は新たに生え揃っているではないか。この治癒速度は神殿の祈祷さえも上回る呪術だった。
もう一度構えようとして、やめた。
あの速度、反撃と治癒、まるで効果を期待できない。
辺りに散らばる敵の鱗と雨粒をそっと押し除けて、オロルは一人静かに窮地に立たされていた。あまり状況が芳しくない。
「……思考を止めるな……」オロルは己に言い聞かせるように呟き、勝機を探るための長考に入る。
敵の術式はオロルが持ち合わせている知識の外にあった。挑むにはこの場で敵の術式をある程度検討を立てて推測しなければならない。ひたすらな沈思による方途の摸索。
ある意味では、この場面、この状況こそ彼女の本領を発揮するところと言える。
時間はある。
時間はあるのだ。
オロルは次の一手を検討するために、改めて敵の攻撃を分析するところからはじめた。
強力な術式であればあるほど行使する際の難易度は上がる筈……敵の素早さには何か発動条件という縛りがあるやもしれない。そもそも、あれだけの速度で迫ることができるならば幾らでも奇襲ができただろう。何故あいつに限って歩いてやってきた……? どうしてわしに先手を譲った……?
オロルはふと心当たりに見当が付いた。
思考に沈く眉間が開く。
戦場を歩くあの余裕は反撃の術式に覚えがあるからか、しかし先手を取ったとき奴の身体は光線が確かに通った。いや、治癒術式で取り戻せるのか……。敢えて先手を譲り、受けた魔呪術と同等の速度と力で反撃するのではないか? だとしたらこちらから仕掛けるのは分が悪い。……なんとも厄介な敵じゃわい。
幸運にも、近頃似たような縮地の使い手を見たことがある。スペルアベル平原の仮面の男――イクスと言ったか――も同様の体系を持っていた。
奴は得物の斧槍に回路を組み込んでいたな。術式が簡易的なぶん、鋒を向けるだけで発動できていた。もっとも、速度は『目で追える』程度だったが……。
得物がないとなると敵の術式は魔術ではないだろう。徒手をぶら下げ構えもしなかった。であれば奴の術式は呪的な構造であり、外部要因によって発動する……。
一片の答えを掴み、確証を得るためにオロルは時を進める。上空に止まっていた雨粒が待ちくたびれたように雨足を強めた。
敵はオロルを見失い、突き出していた手刀を下ろす。
「……あたったと思ったのに」
その声は形に似合わず若い女のものだった。やや擦れ気味で朴訥とした声は感情が薄く、吐き出される言葉が呪文のような響きを持っていた。
長い首をぐにゃりをしならせて背後に立つオロルを睨む。目に捉えずとも気配で居場所がわかるようで、振り向く動作に迷いはない。
敵は続ける。
「そんなに早く動けるなんて……羨ましい」
羨ましい……?
命の駆け引き、理不尽がまかり通る戦場で、敵の能力を羨むとは。
オロルはそんな疑問が浮かんだが、表情にはおくびにも出さずに殊勝な笑みを浮かべてみせる。
両足を微かに浮かせたまま、敵と向き合う。
「お主は速いさ、危うく一撃喰らうかと思ったわ」
「お世辞が言える余裕があるんだね……羨ましいわ」
羨ましい……オロルは繰り返される敵の言葉に引っかかり、見咎めるように暫し睨む。
半人半蛇の方はそんな視線に首を傾げて見つめ返す。何を考えているのかわからない。心ここに在らずといった風で、はっきり言えば隙だらけに見えた。だが仕掛ければ反撃が来るのは分かっている。
「攻撃してこないの……?」半蛇の女は惚けた調子で借問する。
「まぁの」鼻柱を人差し指の側面で弾くように擦る。オロルの予想は確信に変わった。「こちらが仕掛ければ同じだけ、返すつもりじゃろうからな」
「わぁ、流石……」
蛇の女は竿のように長い両腕を折り曲げ顔の側で手を合わせる。賞賛の言葉を吐くものの感情は乗っていない。ただ一つ、後に続いて繰り返される言葉のみが心を伴っていた。
「頭いいんだね……羨ましい……」
オロルは重ねられた言葉に呪的なものを嗅ぎ取って警戒を強める。こちらから仕掛けない以上敵の動きはないが、次の何かが展開されるのは分かっている。『羨ましい』と口にするときだけ、蛇の目に羨望の色が宿るのだ。
何かよからぬ予兆がその瞳に映っているように見えるが、問題は術式の中身が判明していないことだ。口の端に浮かぶ言葉が何を練り上げているのか……。
「頭が良くて……すごく速くて……、とても強い」
蛇の女はまるで幼子が知見を己の身につけるとききっとそうするように、声に出して頭に覚え込ませる。
相対しているのが敵同士であるという事実を忘れているのではないかと思うほど、振る舞いは痴呆のそれである。しかし手を出せば思う壺。オロルは閉口して身構えることしかできない。
女はうんと頷き、学び得たものを呑み込むように長い首が波打ち、蛇のように鎌首を擡げオロルを捉えた。その視線が先程までの無感情とは異なることに気付くのが遅れた。
――しま……っ!
反射的に時を止めたがオロルの視界は押し流され、柱時計の領域限界に背を打った。
肩に指を食い込ませ体を押さえつけるのは半人半蛇の女。その長い両の腕がオロルに接触しているため、静止した時間のなかへ侵入を許してしまった。
蛇の女は長い首を伸ばし、オロルの耳元で囁く。
「……へぇ、三女継承は時を止めるんだね……」
底冷えするような声音は確かな知性を宿し、先程までの呆けた様子は見られない。
敵が呟き呑み込んだ三つの言葉、これらを羨望の念と共に取り込み我が物にしたのだとオロルは理解する。その推理は正しく、一連の流れが半蛇の術式の構造だった。
そして今、この状況ならば敵の次の一手が分かる。
同じだけの知性を手に入れたのなら、続く言葉は……。
「羨ましいなぁ……」
熱い息が顳顬を撫でて、ごくりと嚥下する音を聞く。敵はこれ見よがしにオロルの体に食い込ませていた手を離し、それでもなお静止空間を共有してみせた。
強かに背を打ち綱に吊られているオロルは、痛む肩を抑えて敵を見つめながら状況を理解しようとしていた。
半蛇は時を止める能力を獲得した。
考えうる限り最悪な失態だ。
三女継承者が持つ絶対の優位を、敵も手に入れてしまっている。
ことによっては勝ち筋は途絶えたかもしれない。
オロルは額に滲むあぶら汗を気取られないように面の皮を厚く、太々しく呼吸を整える。重たげな三白眼を冷ややかに細め、眉尻一つ動かさない。
「……わしの名はチクタク・オロル・トゥールバッハじゃ。三女神の三女継承者……。
お主……名を持つか?」
敗北を喫するかもしれない相手に、オロルは名を訊ねた。
立場は違えど呪術の道を征く者、気まぐれに頭の片隅に刻むつもりだろうか。
半人半蛇も一旦は構えを解いてオロルに対した。
「ユラ……嫉妬のユラ。六欲の欠落者だよ」
その言葉を聞いてオロルはますます目を細め声を漏らす。
「おぉ……嫉妬か。なるほどのぅ」
名は体を表すとはよく言ったもの。
羨望の呪術の根源が嫉妬に由来するものだと分かった。
それ以外の感情が乏しいのは七欲の残り――傲慢、憤怒、怠惰、色、食、強――を削いだ、言葉を借りるなら『六欲を欠落』しているからか……とオロルは思考を組み立てる。
同じ時を操る能力を有しているものの、呪術式の成り立ちも体系も異なる源流から来ている。あくまで蛇の女――ユラの獲得した時止めは模倣……完全な再現ではない。現に不可視に隠している柱時計の神器は再現されておらず、その上ユラは地面に足を付いている。荒唐無稽な術式だった。
おそらくは知覚した情報しか拾えていない。
こちらが持つ静止空間の縛りを向こうは知り得ないだろう。
それはつまり、こちらよりもより自由に時止めを行使できるということだ。
「お主はその嫉妬の力で、わしの持ち得る長所を羨望し、獲得した。そうじゃな?」
ユラは答えない。その沈黙が肯定を意味しているようだった。
「速度と強度と頭脳……そして時止めか……。
じゃが、まったく同じ能力ではないようじゃな」
オロルは手袋をつけた手を前に、人差し指を立てる。
「まずは速度……これはわしの光線を身を以て体感し、そのまま移動能力に転化した。言わば縮地術じゃが、時を引き伸ばしたこの状況ではこれ以上の加速はできんじゃろう」
二本目に中指を立てる。
「強度……これは継承者という肩書を漠然と捉えた概念でしかない。恐らく対した身体強化はできておらんと見た。わしを模倣したとて、このか弱い賢人の肉体……たかが知れとる」
三本目、薬指が立てられる。
「頭脳……これもそうじゃ。記憶や知識がそっくりそのまま獲得できたわけはあるまい。多少脳に血が回っても、引き出しが空ならば意味はないじゃろうて」
ユラは不機嫌そうに長い首を項垂れ、口元に運んだ親指の爪を噛む。
「嫉妬というなら、わしは今のお主が羨ましくて仕方がない」
声音を変えて言い放つオロルの語り出しにユラは片眉を吊り上げた。続く言葉を待つ。
「お主は知らんじゃろうが、この領域には制限が多くてな……上手くすれば知恵のないお主でもわしを仕留められるやも知れん」
例えばそうじゃな、と思案顔をして指を広げ掌を向ける。
「時止めは強力な術式であるがため、術の重ね掛けはできん」
オロルが薄手の手袋をつけた手をひらめかせ、呪力を込めようと奮う。当然何の反応も起きない。
ユラはものの試しと真似をして手のひらに呪力を流すとこちらは燐光を宿した。
「お主は未熟な紛い物故に道理を飛び越えた呪術がまかり通っておる訳か……」
落胆する素振りに隠したオロルの皮肉に気付き、ユラの無感動な表情の眉尻がきりと吊り上がる。
「こんなこと教えてくれるなんて、気前がいいんだね。
それとも苦しまず殺してくれってことかな」
オロルは肩を竦ませておどけてみせた。
「さぁて、どうじゃろ。
甘っちょろい呪術の徒に、賢人様が智慧を授けたくなった……と言ったところかのぅ」
この状況で諧謔を口にして見せた。この太々しさはどこから来るものか。
「甘っちょろい……ね……」
聞き捨てならないといった顔で、ユラは挑発に安請け合いをする。皺の寄った眉の下で、目がぎらぎらと輝いている。
オロルは徒手空拳の構え。この静止空間では言葉も術も意味を成さない。体術しか戦う手段が残されていない。
一方でユラは手加減もなく長い両腕を呪力の炎で燃やし、指先まで殺意を漲らせた。
縦に尖る爬虫類然とした瞳孔が睨め付けて、オロルを射抜く。
ユラは距離を詰めると右手を引き、攻撃の予備動作に入った。一歩踏み出す重心移動に合わせて膂力を奮い襲いかかる。
対するオロルは直接触れれば何の呪いを喰らうか想像もできないため纏っている前掛けを撚って攻撃をいなす。互いがぶつかり合うたびに呪力はばっと火の粉を振り撒き、同時に擦れた腕の鱗も散った。散った側から時を止めて空中で固定される。
次いでユラの左手が繰り出される。左右交互に突き出しと予備動作が巡り連撃となった。目にも止まらぬ手刀と殴打を衣服越しに受け流さなければならないオロルは防戦一方で、あっという間に衣服も肌も裂傷だらけになって追い詰められる。
「ほら、これでも私は未熟か? このままじゃ終わっちまうよ賢人様」
ユラは攻撃の手を緩めない。
オロルは軽口を返す余裕もなく迫る手数を払い、散った鱗を押し除けて、じりじりと後退する。
下がった足先が壁に触れた。
不可視の壁、柱時計の領域の限界にまで追い詰められた。
オロルは一瞬だけ意識が逸れ、次にユラを見たときには対応が遅れた。
外套の裾の隙間から貫手が差し込まれ、指先が肌を貫く鮮烈な痛みがオロルを襲った。
「がふぁ……っ」
横凪に迫った貫手は肋骨を砕き肺を傷付けた。穴の空いた腹からは白い肋骨が覗き、溢れ出した血が漏れた呼気によって赤く泡立ち見えなくなる。
よろける動きを追いかけるように、出血した軌跡が荒々しい筆の墨のように空に固定される。
ユラは満足そうに返り血に濡れる己の手を見つめた。
オロルは苦悶に顔を歪ませて堪えられず涙が滲んだ。
時止めの状況では、神殿の治癒術式も発動しない。
しかし時を進めてしまえば、ユラは目にも止まらぬ速さでとどめを刺すことだろう。
「……偉そうなこと言って、もう終わりだね」
ユラはオロルを追い詰め、勝利を確信している。
誰の邪魔も入らない。魔呪術を一方的に行使できるこの場で、どう考えても継承者に逆転の目はない。
「あんたさっき『甘っちょろい』って言ったでしょ……それは違うわ」
ユラはどうしても言い返したかったのだろう。首を振り、己が内に秘めたものを吐き出す。
「わからないでしょ。いつでも自信に満ちてるあんたには、私の絶望がわかるはずない」
オロルは左の肺が萎み、喉から犬の唸り声のような音を立てて苦しく呼吸を繰り返している。瞳は力無く土を見下ろし、瀕死だった。
「家族を失い、残された妹のために体をあの男に明け渡し、そうしてやっと私はこの戦場に辿り着いた……この絶望が、屈辱がわかる……?」
問いかけの後の沈黙。
オロルは疲弊した様子でゆっくりを呼吸を繰り返し、小さく笑った。
「知らんよ、恥晒しが」
これだけ追い詰められた状況、人情なら命乞いを込めたへつらいの受け答えがあってもよいというもの。
それをオロルは唾棄するが如く一蹴した。
虚を衝かれた後、埋み火に風を吹き起こしたようにユラの殺意がめらめらと燃え立つ。全身に纏う呪力が爆ぜて火勢となりあたりの塵や鱗、血と汗を吹き飛ばす。爆心地に立つユラは丸く見開かれた目でオロルを呪い殺さんばかりであった。
諾なった同情の言葉を期待するだけ無駄だった。
「死ね」
短く言い捨てて指先から呪力の光線を放つ。音もなく迫る光線はオロルの眉間を貫く軌道だったが、ユラの呪詛と被さるようにしてオロルも宣言していた。
「顕現……!」
不意に現れた巨大な結界が、ユラの放つ光線を遮る。
ユラはまだ何が起きているのか理解できていないまま、攻撃を継続する。静止空間では二人以外に誰も助太刀はできないはずだった。さらに三女継承は魔呪術の重ね掛けができない……なら降って湧いたあの壁は何だ。
砕けた呪力の飛沫が火花となって散り、空中で術者との接続が断たれると時を止めて光子となり列柱の結界の輪郭を浮かび上がらせた。本当に突然に両者を隔てる壁が顕現していた。
それはオロルを鳥籠のように囲う柱時計である。ユラは「時計」というものを知らないため、蜘蛛を模した巨大な魔導具に見えた。
柱の隙間、オロルは失血に青褪めながらも勝気にユラを見つめていた。
「言ったじゃろ……不便があると……」
「何が不便よ」ユラは忌々しげに言う。「奥の手の神器ってことね……」
領域の行動限界を示す八本の脚。
オロルは展開している脚の間隔をあえて狭めて顕現し、八本の柱をそれぞれ盾としたのだ。制限を逆手に取った戦法である。
今や綱で吊るされているオロルは柱時計の内側に護られ、丁度まさしく振り子のように収まっていた。
ユラは隙間を狙い光線を放つが、蜘蛛の脚のように機敏な動きで柱は位置を変えて攻撃を防ぐ。巨大な柱を己が手足のように巧みに操る鉄壁である。
守りには数本の柱があれば事足りる。持て余した柱を伸ばして攻勢に出た。ユラは身をくねらせて振り回される柱を掻い潜ると一旦引き下がる。間合いが離れた。
埒が明かないと攻撃をやめ、視線がぶつかる。次の一合までの読み合いは両者自明である。
「その神器が欲しくてたまらないわ……」ユラは持ち得ぬ神器に羨望の眼差しを送る。「ああ、羨ましい」
その言葉に応えるように、ユラの肉体はさらに異形へと形を変貌を始める。
オロルは眼の前の光景に目を見張った。嫉妬の術式はあくまでも模倣、まさか柱時計を召喚できるとは考えていなかったのだ。だが、ユラはそれを欲し、術式は際限なく応えようとしている。
著しい変化を遂げたのはユラの腹部である。身籠るように内側から膨張し、それに押される形で腰に留めた布鎧の留め具が弾ける。股の下からは、赤黒く濡れた触手のような異形の足が垂れ下がり地に降り立ち、ひたひたと地面を確かめて全体を持ち上げた。みるみるうちに触手は筋肉を発達させ、細く長く成長した体積はあっという間にユラを超えた。
ユラは肉塊で形作られた醜悪な蜘蛛の下で逆さまにぶら下がりながら笑壺に入る。形容し難い彼女の姿は生命の尊厳すら失い、静止空間は気の触れた女の笑い声が響もした。
恐ろしい光景に流石のオロルもたじろいでしまう――だが、勝機はこの状況にこそある。
オロルは神器の脚を展開して縮めていた行動範囲を再び最大まで広げると、ユラの間合いに躍り込んで蹴りをお見舞いする。
逆さまの体勢となったユラは両腕で攻撃を受け止め、見下ろす形でオロルを見上げる。反撃とばかりに腕に呪力を込めて手刀を振るうが、込めた呪力は発揮されずに脛を叩いただけ。ユラの想定では圧し切るだけの力を手刀に込めたはずだった。
僅かに戸惑い生じたユラの意識の隙、オロルはもう一方の脚で顎を振り抜く。靴の甲に掠めた手応えがあった。掴まれた脚を引き抜き一度退がる。畳み掛ける!
オロルは退がった勢いを発条にして、柱にぐっと力を溜めてさらに懐へ飛び蹴り一発。
対するユラは逃れようと背後へ跳んでいた。そのときユラの背中は不可視の壁にぶつかり、挟まれるようにしてオロルの蹴りをもろに浴びる。
腹と背に挟撃を受けたユラはたまらず血を吐き星が散った。
信じられないといった顔で振り返る。背後には何もない。だがこれ以上退がることができなくなっている。この不可視の壁は何だと、ユラは空間に手のひらを押し付け唖然とする。
先程までユラの周りには不可視の壁など存在していなかった。不可視の壁は三女継承のみに設けられた縛りのはず……だからこそ回避のために退がったのに。
「術の重ね掛けはできないはず……」
ユラの言葉にオロルは瞞着的な笑みを浮かべて応える。
「わしは何もしとらんよ。
しかし何でも手に入るんじゃなぁ……お主の嫉妬の呪術は」
ユラは、そこで初めて策謀に嵌められたと理解する。答え合わせをするように、オロルは続けた。
「わしが継承した能力……その制限、お主はそれを『羨ましい』と言った。そして欲しいままに獲得した」
三女継承、オロルに科せられた能力の制限。その三つ。
一つは接触制限――術者と触れているものは静止空間を共有する。翻って離れたもの、例えば血や魔呪術が術者から接続を解かれればその場で時を止める。オロルは地面にさえ接触できないことを行動で見せつけ、ユラの無意識に刷り込んだ。この認識が反映されたからこそ今のユラは紛い物の神器にぶら下がる形を取っている。
二つめが魔呪術の制限――接触制限と説明が重なるが、術の重ね掛けができたユラの場合でも遠距離攻撃は棒状でなければならなかった。術者と繋がり続けなければ時を止めてしまうからだ。
そしてオロルははっきりと伝えていた。『重ね掛けはできない』と。
三つめ、行動範囲の制限――これも言外にユラに示し、縛りを逆手にとって柱時計を顕現することであたかも奥の手のように振舞った。己を守る鉄壁の盾として扱うことでユラの口から『羨ましい』を引き出した。
これによりユラは神器を獲得したと同時に制限まで付与されたのだ。
手刀に込めた呪力が空振りだったのも、背中を不可視の壁にぶつけたのも、ユラの嫉妬による自縄自縛だった。もっとも、相手を操るのが呪術とするなら、煽り立てることで行動を操って見せたオロルの言葉には呪的なものが宿っていたのかもしれない。
追い詰められていたはずのオロルが一貫して強気の態度を保っていたのも、あの窮地においてすでにこの逆転の絵図が描かれ筋書きが見通せていたからである。
「能無き者に呪術は扱えん。精々呪詛を吐き捨てるのが似合いじゃ」
思考を止めぬ賢人は時を操らずとも明晰を誇示した。
激しい戦闘により両者の間には剥がれた鱗と血飛沫が舞っていた。オロルはそれらを手で払い、柱時計の脚を持ち上げてユラを吊っている紛い物の神器ごと踏み潰す。
落第の烙印を押すようにしてユラは地面に叩きつけられ、その瞬間に時止めの能力から切り離される。大地と接触したために制限を超えて術式が破綻し、静止空間から置き去りにされたのだ。
引き伸ばされた刹那は再びオロルだけのものとなった……だが、オロルもまた限界だ。
片肺だけで挑んだこの死線は掛け値なしに大博打だった。
外敵のいなくなった空間で人心地つくと、思い出したように血を咳いて、呼吸は浅くなる。
許されるなら柱時計の神器共々倒れ伏せってしまいたい。精魂尽き果て満身創痍である。息を整えたいのに、大きく吸い込めば肺が痛むので仕方なしにか細く苦しい呼吸を繰り返すしかない。
時止めの強度を維持することすら煩わしく、せめて呪力を弱めて時の運行を緩やかに進めて気を和ませた。現在オロルの体感速度は常人のおよそ二十倍。視界に映る雨粒がゆっくりと形状を波うたせながら地面に落ちるのが見える。
その向こう、ずっと切り離されていた前線の争いは、緩慢な動作ながら戦士の吶喊の雄叫びと駆け出す身の躍動が歩みよりも遅く繰り広げられている。迎え打つトガの形相も鬼気迫るもので、両陣営がぶつかり合おうとする僅かな時間に半蛇の女との死闘を演じたのだと思えばどっと疲れが込み上げるというものだ。
本当に、一日があまりにも長い。
ユラの沈黙を確認してオロルは時止めを解除すると、わっと耳に雑多な音が飛び込んでくる。長らく音を置き去りにしてきたため、銘々の音が粒立ってつんざくように聞こえた。辺りに散らかり放題となっていた両者の血の飛沫がやっと重力に任せて地面に落ちると、ばさりと縢るように重たくのしかかり、オロルの金色の髪を朱色に染める。
降りかかる血液の波に押し流されるようにユラはごろりのもんどり打って仰向けになり、意識を取り戻す。
紛い物の神器は時止めによって激しく消耗し、見る間に朽ち果てていった。繋がっていた臍の緒も茶色く萎びて千切れ、治癒術式も発動していないところを見るに持ち合わせが尽きたのだろう。
「なぜとどめを刺さない……」ユラは言う。
「……刺さずともお主は長くない」
オロルは癒えきらない片腹を腕で庇いながらも堂々と見つめ返した。召し取ることは容易いが敢えてそうしたのだと語るには十分な瞳だった。
「お主は嫉妬に駆られありとある呪術を模倣し手に入れた。じゃが消費する鉱石にまで考えは及んでおらん。
身に余る力を維持するために命を随分と消費した……言葉通り嫉妬に身を滅ぼしたというわけじゃな。
まぁ、……もとより惜しくないと投げ打ったのじゃろうが」
ユラは静かに死を悟り、じっと手のひらをみる。
紛い物の神器と同じように、急速に老いが進んでいるのがわかる。
乾き、刻々と皺を増やして痩せ衰える体。視界はぼやけ、きんと耳が遠くなる。風に揺れる長い髪も枯れ枝のように縮れて白くなっていた。
――殺するは蚩尤。
ユラは己の最期を菊して幾許かの心を取り戻したように見えた。感情の宿らない蛇の瞳が人のそれに戻り、丸い瞳孔の奥には、欠落していた感情が蝋燭の火のように再び小さく宿るのが窺えた。
それは後悔か、無念か、老媼の頬に一雫の涙が滲みた。
「ヨナハ……」
オロルには心当たりのないこの一言が、六欲の欠落者、嫉妬のユラの辞世の言葉だった。
後に続く言葉が何であるか、推し量ることもできない。
この長く果てのない戦役の世に生まれた者達。たといこちらが人でないと断じ、化け物の類いと定義しても、禍人種は他と近しい人類なのだとオロルは悟る。憎み合うもの同士が敵を人と見做さないその心理もなんとなく分かる気がした。
「ユラ、ヨナハ……か」
オロルは前線から世を儚む面持ちで内地の方に顔を向ける。遠く神殿を望むことは叶わないが、雨雲に煙るマハルドヮグの峰が微かに山陰を映している。……内地に設けられた防護結界、そこに込められた呪術の意味合いも今は解る。
いつかガントールは言っていた。
『防護結界に侵入した禍人は、擬態が維持できなくなる……それを咎と読んでいるに過ぎない』と。
これまでの道すがら簡単に切り伏せたトガも、元を辿れば禍人なのだろう。討伐する兵士の心理的負担を軽減するために、内地の防護結界は強固な呪いを内に宿し、存在しているのだろう。
加護に癒えた体はようやっと痛みなく腕が動かせるようになり、オロルは短く合掌すると柄にもなく弔いの念を呟いた。
「いつか新たな生を受けたなら、争いのない時代であるように……」
❖
平原に雨をもたらした雲は散れじれに季節風に流され、日は雲を追いかけるように足早に山の稜線へ隠れていく。
未練がましく西陽を睨むアーミラはスークレイと共にウツロに連れられて、ニールセンのいる場所を目指していた。
多くの命が失われた激動の一日が沈みつつある。
生き残った者達に称賛もなく夜になろうとしている。
あれだけのことが全て今日の内に起こった出来事なのだと、アーミラには未だ実感は湧いてこなかった。
気持ちの整理もつかないのに、世界は待ってはくれない。
どこか腹立たしい思いでアーミラは沈み行く太陽を見つめた。こうしていれば日没が速度を緩めてくれるのではないかと期待して、せめて熱に浮かされた心が落ち着くまで待ってはくれないかと睨むのだ。
突き詰めればこの腹立たしさは己に向かっていた。生き残ったことに対する形容し難い罪悪感があった。
神殿の出征式典で行われた『心像灯火の儀』によって、継承者の三人はほぼ無尽蔵に治癒の恩恵を受ける。アーミラが戦闘によって負った負傷も特段の手当を必要とせず、歩きながらに完治しつつあった。剥がされた顔も、穴だらけだった腹も、今は痛みもない。それがなぜか無性に腹立たしいのだ。
自分だけが生き残る恐ろしさ。
あの邸の戦闘は、全力だった。死力を尽くしていた。
戦いに決着がついた後、無念に斃れた兵達がいる中で自分が生き残ったことに安堵し、次に申し訳ない気持ちに襲われた。決して死にたいわけではないが、置いていかれるような寂しさがどうにも拭えなかった。
「ニールセン!」
ウツロの示す先に討伐隊の遺体があった。総勢二十三人の輪から少し離れたところにニールセンを見つけたスークレイが声を上げる。
「息は……」
駆け寄ったスークレイは皮の剥がれた彼の口に耳をそばだてる。微かに頬の産毛を撫ぜる呼吸を認めて、あらん限りの治癒術式を施した。
見守るウツロの佇まいもどこか安堵しているように見えた。胸を撫で下ろすように、強張っていた肩の板金が下がる。
「よかったですね」
と、アーミラはウツロに言う。言った後で「まるで他人事だな」と内省する。対してウツロは我が事のように頷いた。失われた首にもしも人の顔が備わっていたなら、ウツロは物悲しく微笑みを返したかもしれない。
まるで心があるみたい……アーミラはもう何度目か、ウツロに対して思う。初めてそれを伝えたとき、ウツロは何と答えたか。
『対象に心があるのかどうかについて、それは観測者側の主観に依存するだろう。その場合、俺が人であるか。ではなく、君が俺を人と見做みなすかが重要だ』。
……ウツロの言葉に従うなら、アーミラは初めから彼を人と見做していた。いや、人以上に心通じ合うものと思い、その気持ちは変わらない。だが今は、噛み合っていた歯車が軋み、すれ違い始めているように感じられた。
ウツロが人らしく思えるのと反比例して、自身の心がどこか希薄に思えてならない。ニールセンの無事を祈る二人から一線を引いて、アーミラは冷めた瞳でラーンマクの防壁を眺める。
ついにここまで辿り着いた。
私は何でここまで来たんだっけ。
「……兵戈として」自問自答に呟く。
私に求められているのは、敵を殺すこと。ただそれだけ。
これが私に科せられた使命……私という存在の価値……。
目を覚さないニールセンを担ぎスークレイは邸へと引き返した。
体内に潜んでいるトガに動きはなく、おそらくは偽者――ウツロ曰くそのトガは『ハラサグリ』と固有の名があるようだ――を討伐したときに活動を止めたようだ。群生の主を失ったハラサグリは呪的な結び付きを失って休眠したか、あるいは消滅したとみえる。
望みは繋いだとスークレイは二人に礼を言ってここから先の健闘を祈ると名残惜しさもなく急ぎ復路に去る。彼女の背に一人の命が、いや、平原の行末が懸かっている。
アーミラとウツロは防壁の側で野営し、ラーンマク入りは夜明けまで待つことにした。厳戒態勢の前線に於いて、夜は何より貴いものだ。門を開くにしろ飛び越えるにしろ、無用な物音を立ててしまえば衛兵は鐘を鳴らし、戦士の休息を奪うことになる。
何よりアーミラの疲労も限界であった。
出がけにナルから渡された有り合わせの食糧を晩飯に腹に収めると、倒れ込むように寝そべり、見張りをウツロに任せ昏昏と深い眠りについた。この地で失われた命と添い寝をするようだった。
一夜開け、アーミラが目を覚ましたのは丁度門衛が番に立つ頃だった。重い扉がゆっくりと開き、二人が分離壁の中に入ると一旦は壁の内側に閉じ込められる。
防壁は分厚い建造物で、途方もない数の煉瓦によって国境を隔てていた。壁の中は二重の門が設けられており、アーミラとウツロは手前側の門から入り、ラーンマク入りするには奥の扉が開放されるのを待たなくてはならない。
暗闇に閉じ込められたウツロは、欠伸を手で隠すアーミラをじっと見つめていた。
「歯車の音がしますね」と呟く声が密室に反響して、次第に鎖が巻き取られる音にかき消される。奥の扉が機巧によって力が伝わり、細く外界の光が差し込んだ。
前線の防壁を潜り二人はラーンマクの土を踏む。
眩しさに目を細めていたアーミラは、言葉もなく立ち尽くす。
目の前は赤い干潟だった。
踏み固められた土の窪みに雨水と血が流れ込み、この不気味な景色を形成している。
「これが……国? ――いや、こんなものが……?」
思わず気を失いそうだと言わんばかりにアーミラは目の前の光景を眺める。古傷が疼いて首をやや乱暴に掻く。皮膚の下をまだ何かが這っているような掻痒感があった。
「こんなの、どう見ても……」
失地している。
何を持って国が落とされたと判断するかはアーミラにはわからない。ただ、眼前の荒涼とした土地に建物は見つからず、剣呑とした空気が場を満たしている。これでは立ち行かないのではないか。
人々が生活を営む領土を国と呼ぶのだとアーミラは無意識に思い込んでいたし、ここにはそれがないと感じていた。
だが、戦争をしている国というのは敵国と接している前線だけが混乱に廃れるわけではない。比較的に内地側に寄っている地域だろうと輜重を運ぶ要衝は必ず戦端を開き、四代目国家ラーンマク、デレシス、アルクトィスの三国は領有地全土を二百年の戦火に焼き尽くされ進退に踏み荒らされる。それでも尚、この地は厳然と一国として数えられる。軟弱な内地の平穏があるのはこれらの国があってこそなのだ。
すれ違う戦士も歴戦の猛者ばかり。一目見れば強者とわかる威容を保ち、野天の下、我が物顔でこの地での朝をそれぞれに過ごしている。戦場の掘に横臥して、傷の絶えない身体に包帯を巻き直している者。懐の干し肉をしゃぶりながら持ち合わせの魔鉱石を確かめる者。篤い信仰に祈りを済ます者。彼らは継承者の法衣を認めても特段の驚きはない。ちらと瞥見し、横を通り過ぎるアーミラの顔を見て、すぐに支度に戻る。
日が昇ればどちらともなく殺し合いが始まる。
決まった一日の流れを淀みなくなぞるだけの生業なのだろう。生きる喜びだとか、そういった月並みな世俗とは遠く離れて、身も心も戦場に置き続けている彼らの瞳は、よく研がれた刃物のようだった。
以前のアーミラなら、そそくさと彼らから逃れるように足を早め、ウツロの背中に隠れていた。
けれど今は、違う。
彼らの視線を背に受けても、ただまっすぐ前を見据えていた。静かに後ろをついて歩くのはウツロの方だった。
しばらく荒地を進み、アーミラはオロルを見つけた。スペルアベルから見送ったときにはまだおろし立てのように輝いて見えた継承者の外套は見る影もなく色褪せほつれてしまっている。
その視線に気付いたか、振り返ったオロルと互いの視線が交わり、軽く手を挙げてアーミラを呼び寄せる。
「来たか」
待っていたという風に迎え入れたオロルは、ふとアーミラの顔を覗き込むように下瞼が持ち上がる。
アーミラの纏っている固く暗い気配を見て、鼻息を一つ吐くと肩を叩き、そのままウツロの方へ向かった。アーミラには見えなかったが、オロルはこのとき、ウツロに落胆するような視線を向けていた。
鎧の腹を叩くように拳を当てて言う。
「踏み外さぬように見守っていると思っていたが、お主には難しかったか」
言い捨てるようにオロルは返事を待たずその場を離れようとした。しかし、ウツロは無言でオロルの拳を包み込み、強く引き寄せた。
声に出すことは叶わずとも、否定を表明していた。ウツロはまだ諦めていない。
オロルは敢えて乱暴に振り解いて、二人に対し現状の整理を提案した。アーミラは頷き、互いの持ち合わせる情報を伝え合う。
状況として、オロルとアーミラはかなり魔鉱石を消費している。出征の折立ち寄ったムーンケイで揃えた魔鉱石と、道中スペルアベルで買い足した魔鉱石。その八割を消費している。
立てた手柄はといえば、平原の敵襲を撃退しアーミラとウツロが禍人を二体討ち取ったのと、オロルが半人半蛇の強敵を討ち取った程度。武勲を上げたというには少ないあがりである。
倒した禍人のうち二人は暗躍している者の人相と一致していない。ウツロがナルトリポカで見たというのはもっと小柄な女と、痩せぎすの男……ダラクという男以外は戦場で未だ相見えてすらいないということになる。この二人の行方を探り首を取らなければ当代の決着はないだろう。
どこかで一度魔鉱石の調達に戻るか、または輜重を輸送する兵の到着を待つ必要がある。待つ場合は期間をどうするか……これが目下の悩みの種である。
此度はナルトリポカ集落を襲われたことで甘藷黍の兵糧が少なく、活力も消耗している。ここ一月で前線の食糧事情はかなり逼迫していた。これ以上の長期戦は戦死よりも餓死者の方が多くなる危険さえ出てきている。ここで待ち続けるのは饑るい思いをするだろう。
それにガントールが戻ってこないのも気掛かりだった。
オロルの憂いに対し、「邸では、トガがガントールさんに化けていました」と、アーミラが報告する。
聞けばそのトガは人の面皮を奪い被ることでそっくりに化けるようで、術式に縛りを持つぶん強力な敵だったという。そいつが顔を持っていたということは少なからずガントールは一度命を落としている。
トガ本体を討伐したことでニールセンが一命を取り留めたことからして、どこかでくたばっているガントールも起き上がっているはずだった。
オロルは寄せ集めた情報を頭の中で采配して戦況を俯瞰すると、それなりに納得したか表情に余裕が出てきた。前線に継承者三柱が揃う日も近い。
「ふむ……スペルアベルは辛くも勝ち納めたか……となればもう背後の憂いは無いじゃろう。
前線の穴はガントールに引き続き託し、果報を待つとしよう」
オロルは補給が来るまでここで待つことに決めた。
継承者がここで戦線を維持さえすれば、輜重の供給もきっと届く。そうなれば状況は少しずつ好転するだろうとみたのだ。
どのような逆境にも必ず望みがあるように、当代継承者の兵役にもいよいよ終わりが見えてきた。ここに三女神が揃い、迫り来る敵を全て平らげてしまえば後は領土を支配し、前線を押し上げ国を興す。
そうして娘たちは使命を全うした活躍を讃えられ、栄光を浴するだろう。
――しかし、ただ朝を待つだけでは生き残れない。
この世界に一縷の望みもなく帳を下ろす、月明かりもない夜が訪れようとしていることを彼女たちはまだ知らない。
❖
「私、ここに来たことがある気がします……」
アーミラがふとそんなことを言ったのは、オロルに連れられて前線の案内をされていたときである。南を望めば今にも戦闘を始めようと剣呑な戦士たちの並ぶ荒涼としたこの場で、突然にそう言ったのだ。
過去の記憶が無いと言っていた彼女の事情を思い出したオロルは眉を曲げて首を傾げた。
「ガントールならいざ知らず、お主がここに来るのは初めてのはずじゃが」
アーミラは明確に首を振る。何に裏付けされているのかわからないが余程の確信があるようだ。
「きっとお師様と、流浪の民としてここを歩いたはずです」
「流浪の民として?」オロルは言葉を繰り返す。「だとしたらおかしい。流浪の民は避難民じゃ。彼らは内地に向かって移動する。お前はここの生まれか?」
オロルはアーミラをアルクトィスの生まれだと思っていた。神殿での晩餐を共にした際にある程度のことは聞き及んでいる。その上で両親は四代目三女国家アルクトィスで命を落とし、流浪の民に拾われ師と出会い同道したと結論付けたのだ。もしアーミラの確信が本当なら、アルクトィスからラーンマクに向かう二人の足跡は横に移動する旅路となる。避難民の行動としてそれはあり得ないことだ。
それに、二国間にはデレシスが存在し、手元不如意の流浪の民が進むには体力の面でも無理がある道筋と言える。
「アルクトィスも前線じゃ。記憶が不確かなら似た景色の違いはわからん」
「でも、スペルアベルの涸れ井戸だって私は見覚えがあります。 ナルトリポカには無いものですから、間違えようは……」
アーミラの言葉にオロルは目を丸くして、ほとんど怒っているような表情で見つめる。
「涸れ井戸じゃと……?」
あまりの剣幕にアーミラはたじろいで閉口する。
オロルは怒っていたのではなかった。驚いていたのだ。
スペルアベルの涸れ井戸――それはまさにガントールに任せている前線の穴。
人知れず往来を許す地下通路の存在をアーミラは懐古のものとして口に出したが、流浪の民が知るような道ではない。
……なぜアーミラは、いや、アーミラの師は、その地下通路を知っているのか? なぜ数ある選択肢から人目を避ける道を選んだ?
疑問が浮かび、オロルは目の前の次女継承者の姿が瓦解するような感覚に襲われた。アーミラを成すために組み上げられていた嵌め絵は仮初の結び付きを失って崩れ落ち、それぞれの欠片が今度は勝手に浮かび上がりこれまでとは異なる組み合わせで隣り合い全く別の絵に変わってしまう……そんな感覚に囚われる。
いつか明かしてやりたいと思いながらも忙殺されていた彼女の生い立ちの謎は、真なる形を示そうとここに来てオロルの前に立ち塞がった。
地形から見るにアルクトィスから北へ向かえばナルトリポカに辿り着く。当初のオロルの推理ならば流浪の民としての道筋に何の矛盾もない。
しかしアーミラの言う通りラーンマクからスペルアベルを通ったというなら、何かがおかしい。
どこかで前提が狂っているような、重大な見落としをしているような冷やかな警戒心が脳裏を掠め、その正体を掴み損ねている。
様変わりした嵌め絵の意味を理解したとき、そこに一つの残酷な真実が明かされるだろう予感がした。
「……その記憶は確かなのか? ラーンマクからスペルアベルを経由して、涸れ井戸の中を歩いたのか……?」
オロルの問いは、思い違いであってくれと頼み込むような圧があった。
「私は……」
アーミラは言葉に窮した。オロルがそこまで言うからにはそれなりの説得力がなければ意味がない。だというのに、この荒れ果てた戦地ではめぼしいもの、昔と変わらずそこにあり続けるものを見つけることができない。
それでも、この景色を眺めていると望郷の想いが溢れてくる。朧げな風景の面影や、風に混じる独特の臭気、肌の汗ばむ日の光、それら印象の集まりが言葉にできないままに胸に迫る。果たしてアルクトィスでも同じ感覚に襲われるのかはわからない。ただ、内側から何かが訴えるのだ。「ここだ」と、「ここなんだ」と。
少し離れたところでは首のないウツロがこちらに体を向けて静観している。
また別の所には禍人だろうか、同じく首を失い倒れている。
首のない二体の存在が言外に示す印のようにアーミラの目に映る。首、首、首が痒い。
アーミラは知らず呼吸が浅くなり、長い髪に隠した首元に指を差し込んで思うさま掻き毟る。視界は目眩にぐるぐると廻り、白く掠れる意識にウツロの首と禍人の首が代わる代わる明滅しながら既視感を伴って飛び込んでくる。そして全身を襲う死の恐怖に膝から崩れ落ちて蹲った。
混乱している表層の意識の奥で、どこか冷静なもう一人の己がいた。この真に迫る死の恐怖は何なのだろう……平原で死を経験したのが原因なのだろうか。ならば恐怖と同時に去来する懐かしさの正体は……?
「思い出せ」オロルの言葉。
手放した杖がごろりと転がる。
両手で首を抑えて地べたにへたり込んだアーミラの丸い背中に向けて、オロルは憑き物を祓うように繰り返す。
「思い出せ。お主が師と慕う者の顔を」
アーミラは目を瞑り、師の顔を思い浮かべる。
髪を引っ詰めに束ねた丸い額に細い顎、厳しい視線と固く閉じた唇。一つ一つの形は鮮明に思い出せたが、貌全体を思い浮かべようとするとマナはくるりと背を向けてしまう。
すらりと背筋を伸ばし先を歩く姿は、流浪のときから見慣れた……いや、お師様はもっと老齢……膝を痛めて背も曲がり、歩くことも厭うていた……この人じゃない。
「思い出せ。お主の記憶に鍵をかけた者の姿を」
アーミラは頭を振って絞り出すように記憶を辿る。
痩せぎすで皺だらけの老婆の姿を思い浮かべる。ナルトリポカの集落の外れ、誰も寄りつかない寂れた教会堂で師は横たわり、私は傍で手を握っていた。
あの日、あの時の、お師様の声が聞こえる。
『流浪の民とは、異なる……まつろわぬ者が、お主と出会う……その、ときには……婆はしんだと……つたえておくれ……』
そう告げると師はゆっくりと褥から上体を起こし、見る間に老いを削ぎ落として立ち上がると、若く美しい姿でアーミラを見下ろす。
どこか焦燥を隠した硬い面持ちは、どう見ても齢二十に届くかどうかの姿だった。若かりし頃の姿となって現れる彼女は、確かに師の面影を重ねてよく似ていた。
オロルは問いかけを変える。
「思い出せ。師とともに何をしていた?」
――この地で、お師様と共に……歩いていました。ずっとずっと。
何かに追われて、私たちはそれから逃れるために走り、追手を振り切ると走るのをやめて歩き続けて……。
「私、ここで死んだんじゃなかったっけ……」
「……はぁ?」
素っ頓狂なオロルの声は遠く、アーミラの自我は頭の中、ある一点に向かって吸い込まれていく。
その一点とは深層の意識にぽつねんと存在する匣。
失われていた記憶が収められた匣だ。その蓋が開かれ、意識は引力に抗うこともなく、波にさらわれるようにアーミラは気を失った。
❖
「アルミリア……っ」
光弾飛び交う前線の一劃に、ぐったりと地に横たわる少女と、傍で嗚咽混じりに呼びかける女がいた。二人は共に青白い肌に尖った耳、そして額には対の頭角を持つ――いわゆる禍人種である。
女の年齢は判然としないが外見で推察するならば二十よりも少し手前だろう。少女のほうは歳は十を数えるほどか、まだまだ幼さが残る。とても戦地には似つかわしくない姉妹のような二人だった。
女は目に涙を溜めて何度も何度も少女に呼びかける。しかし蒼白となった少女は揺すられた身体もだらりと垂れて、砂質の地面に赤い染みを広げていた。
戦場から放たれた魔呪術の流れ弾が、少女の小さな身体を焼き貫いたのだ。
「アルミリア! 頼む……死ぬな! アルミリア……!!」
少女は女の声に瞼を開くと、霞んだ両目を女に向けた。
左脇で膝を折り、心配そうに見つめている女は、何度も何度も名前を呼ぶ。縋りつくような青灰色の双眸は涙をためては溢れ、顎を伝って襤褸を湿らせる。
「マ……ナ……? そこにいる……?」
「ああ、いるとも……っ」
マナと呼ばれた女は少女の小さく冷たい手を握り、悔しそうに唇を噛む。魔鉱石があれば止血くらいはできただろうに、今の二人は着るものも満足になく、治癒術式さえままならなかった。
このままでは少女の命はないだろう。
女は忙しなく辺りを窺っている。
幸いにも戦火は二人から離れつつあった。流れ弾こそ四方を掠めて行くが、何処かに骸を調達できれば、懐の魔鉱石を拝借できるかも知れなかった。
「……アルミリア……ごめんね、あんただけは必ず助けて見せるから。
絶対、絶対に死なせないから……待っててね」
決意を固め、女は少女の手を離す。そしてどこかへ向かって駆け出すと、少女はゆっくり目を閉じてしまう。
事切れた少女の意識が次に目覚めたとき、一体どれほどの時が経ったのだろう。天上にあった太陽は消え失せて空は雲一つない星空が広がっていた。
少女が目覚めた事に気付き、女は顔を覗き込むように視界を覆った。
「……マナ? ……あれ――」
――声が変だ。と言おうとした少女に、女は抱きついた。あらんばかりの力で抱きしめるので少し体が痛いけれど、それだけ心配をかけてしまったのだと理解して、今は女の肩に鼻を埋めてされるがままに身を任せる。
「よかった……、本当に……」
「うん」
「私一人じゃこの先へ進む意味がないんだ。あんたが無事でよかったよ」
「うん……」
女の言葉の真意を測りかねたが、少女は深く考えずに頷いた。
ひとしきり無事を喜び、ようやっと女は抱きしめる力を緩めた。互いの顔を見つめ合い、少女はあれ? と事問顔をした。
「マナ、角どうしたの……?」
そうたずねると女は照れたようにはにかんだ。
「集めてきた魔鉱石だけじゃ足りなくてね、身を削ったってわけさ」
「そんな! 綺麗だったのに……」
「いいんだよ、役に立ったなら額の疣も本望さ」
気に病む事じゃないと女が微笑むので、少女も笑みを返す。
二人には確かな絆があった。
「じゃあ、私のをあげるね」
と、少女が冗談を言うと、不意に女の表情は曇る。
言いづらいものがあるときに人が無意識に行う動作。
女は静かに息を吸い込み、溜めて、俯いたのだ。
「それが、アルミリア……あんたのも無くなったんだ」
「え」
少女は驚き額に手を伸ばす。しかし己の手が眼前に映ったとき、おや、と額へ伸ばすのとやめて見つめた。
「私の手……こんなだったっけ……」
よく見れば纏う服も襤褸は襤褸だが見覚えのない布に着替えている。全身がまるで他人の体のように思えて、少女はぺたぺたと己をまさぐる。事実その体は他人のものだった。
動揺する少女に、女は申し訳なさそうに目を伏せ視線を逸らした。
「首から下は、もうどうしようもなかったんだ」
首から下……女の言葉を確かめるように、少女は己の首を指先で撫でる。ちくりと癒着しきれていない傷に触れて痛みが走った。断ち切られた皮膚の境がそこにあった。
「偶然さ、手頃な骸が手に入ったんだ。……これは僥倖だとおもったよ」
名も知らない魔人種の娘の遺体は頭蓋をかち割られて脳漿を晒していた。はじめは魔鉱石だけを目当てに漁っていた女だが、天啓のようにそこにあった死体を拾い、頭を挿げ替えることを思いつき、実行した。
「首と胴体が繋がって定着するまでは本当に不安だったけど、とにかくこうして生き返ったんだ。……本当に嬉しい」
聞いてもいないのに捲し立てるように洗いざらいを語る女と反比例するように、言葉を尽くすほど少女は受け止めきれない事態に青褪めて己が肩を抱き竦める。しかしこの抱き竦めた肉体は他人の腕で他人の肩を撫で擦っているということを幼いながらも理解して、逃れようのない恐怖に怯える。
それと同時に、少女の躰にはある変化が訪れようとしていた。
「やだ、……やめてよ……」
そう訴えかける少女の声に気付いて、女は申し訳ない顔をしてみせる。
「ごめん……でもね、アルミリア。今はわからないかも知れないけど、あの身体ではこの先どうしようもないの。どのみち切り捨てていかなくちゃいけなかったんだよ」
謝ってはみせるものの、女は意志の固い真っ直ぐな視線で訴える――が、少女の耳に言葉は届いていなかった。
見つめる先に座っている少女は両手で胸を押さえ、声も出せないほどの痛みに襲われていた。
「……え……?」
涙が流れ落ちて、潤んだ瞳が痛切に女に助けを求めている。
胸に錐を突き立てられるような痛みが生じ、全体が火で炙られるように熱い。
少女はなんとか訴えようとしたが、喉が緊張に強張って声が出せない。口をぱくぱくと開閉して、金切り声が絞り出された。
「ちょっ……アルミリア!? 胸が痛いの……!?」
少女の胸部に起こった正体不明の痛みに対して、女は魔呪術の燐光を認める。夜の闇に焚き火を熾したように少女の胸からは光が溢れ、それは勢いを増して両手で塞いでも漏れてくる。
僅かな指の隙間からでも目を開けていられないほどの光量が迸り、空まで届く青く強烈な閃光を生じさせていた。
「まずい……!」
女は光の筋が高く昇るのを見上げて、すぐに少女の身体にのしかかるように覆い被さった。
戦場の夜は両陣営とも神経をとがらせて警戒している。目立つ不審な光があれば、敵味方の確認もせず仕留めにかかるだろう。光弾が放たれれば眠りの浅い戦士どもは飛び起きて加勢し一帯は虫の一匹も残らないほどの集中砲火が行われることとなる。そうなってしまえば二人とも死は免れない。
「い、……だい……っ、いだい、いだい! いだい!!」
腹の下で痛みにもがき苦しむ少女を強引に組み伏せて、耳元で何度も謝り懇願する。
「ごめん……っ、お願いだから動かないで……!」
人の肉体を繋ぎ合わせる高度な呪術を簡単に扱うこの女でさえも、少女の身に起きた現象が何なのかまだ理解できていなかった。首と胴を無理矢理繋いだことでなんらかの拒絶反応が起きたのかとはじめは思っていたが、この状況では術式を観察することもままならない。
押さえつけながら下でじたばたと踠く少女の胸元の光源を睨み、それが何か理解したとき女は血の気が引いた。
「嘘でしょ……」
少女の胸元の皮膚には、刻印が現れようとしていた。
それは禍人種にはまずあり得ない現象であり、よりにもよってこの娘に宿るとは考えもしなかったことだ。だがしかし、心当たりがあった。
次女継承の印――才のある首を魔人種の身体に移植したのだ。今やこの少女は、選ばれる素質を満たしていた。
「うそでしょ……」
女は動揺を隠せず、痛みに暴れる少女に押し除けられて体勢を崩し、光は間欠泉のように夜空に向かい噴き上がる。もはや付近は昼のように照らされ、間も無く四方から号砲が響き、集中砲火の光弾が迫る。
光と音の洪水が少女と女を取り囲み、その嵐の中では助けを求める少女の嘆きも、女の叫び声もかき消されてしまう。
しかし不思議なことに、視界を埋め尽くす光弾の嵐は二人を傷つけることはなかった。胸に宿る刻印がひととき少女を護っているのか、台風の目の内側にいる二人は衝撃と眩しい光の奔流の中で一命を繋ぎ止めていた。
これが神の御業が成せる慈悲か……。
……だが、それでも。
――アルミリアを次女継承にするわけにはいかない。
「神でも龍でもいい! お願いだからこの子はやめて!!」
女は天に叫ぶが、当然刻印が消える気配はない。
マナは覚悟を決め、少女の上に馬乗りになると、全身に備わる魔呪術の全てを練り上げ、掌を少女の刻印に翳した。
もとより祈り叶う神は居ない。世は禍事こそ理の当然であり、心で願うよりも力で成し遂げるのが唯一の真理なのだ。
「隠してみせる……逃げ遂せる!
そのためなら私の全てを支払っても構わない!!」
砲煙弾雨の荒れ狂う光の渦の中で女は宣言する。
掻き集めた持ち合わせの魔鉱石も心許なく、それでも頑なに譲らぬ思いがあった。
たとえこの命を使い果たしても、この娘だけは、誰の手も届かぬ場所へ――
❖
記憶の匣は開かれた。
アーミラは長く短い夢から覚めて身を起こすと、弛んでしまった涙腺から涙が漏れて、そっと目を擦る。
特別悲しい訳ではなかった。
記憶を取り戻した達成感に打ち震えていた訳でもない。
或いはどちらでもないようでいてどちらでもあったのかもしれない。
これまで露程も思わなかったようなこと、全く慮外な事実が多すぎて理解が追いつかず、心は凪の中にあった。
戦場であるはずなのに辺りは静寂に包まれていた。未だ夢の中なのかと思うほど、景色は凍りついてしまっている。どうやらこれは三女継承者の能力なのだと理解するまでそう時間はかからない。気を失っている間に柱時計の上に移されたようだった。
「どうじゃ?」と様子を伺うオロルの表情は、記憶を取り戻したことを見透かしているような、金色の瞳が賢しく静かに見つめている。
「……その……」アーミラは言い淀み俯いた。
伝えねばならぬもの。
伝えるべきか判断に悩むもの。
決して明かせないもの。
アーミラが取り戻した過去には、そうした三つに区分し振り分けるべきものがあった。特に一番に伝えるべき己の由来が、決して明かせないものに属しているために答えることができない。
しかしオロルは告げる。
「アーミラよ、お主は魔人種ではないな」
アーミラは驚き、声もなく目を丸くしてオロルを見た。その動揺が答えだと言わんばかりだ。
「気を失い目覚めるまでの間、わしも考えていた。
全てお主の師が仕組み、施したものなのじゃろう」
オロルはまるでアーミラの過去を共に覗き見たように言い当て、推理を開陳する。
師と共に旅をした足跡はお主の言う通りラーンマクとスペルアベルなのじゃろう。じゃが記憶を失ってからの道程は最終的にナルトリポカに落ち着いておる。この三つの地点を一筋に繋ぐなら、どういうわけか一番古い記憶はスペルアベルとするのが自然じゃな。師と二人でなんの目的があったかラーンマクへ向かい、その後再び内地へ舵を切りデレシスかアルクトィスを経由してナルトリポカに落ち延びたわけじゃ。
お主は『流浪の民』という言葉の意味を「あてもなくさまざまな国を巡って旅をする者達」と無意識のうちに認識しておったな。それは師と共に歩いた道筋から刷り込まれてしまったのじゃろう。
つまり、本来のお主は「前線から内地へ向けて避難する者」ではない。流浪の民ではないわけじゃ。
「――ならばなぜ、そんな目的の見えない旅をしていたのか……?」
オロルは言葉を切る。それは問いかけだった。
「……実はまだ、全てを思い出した訳ではないんです。あの旅は、追手から逃げるための旅でした」
ふむ。とオロルは頷き、推理を続ける。
「追われていた二人は南へ逃げ続け、ラーンマクまで追い詰められた。そこで、まだ幼いお主は大怪我をした……。
――古傷が痒いようじゃな
視線で示されて、アーミラはようやく気づく。無意識に首を擦っていた。
思えばラーンマクに足を踏み入れてから、ずっと微かな掻痒を感じている。
「……流れ弾でした。瀕死になって倒れたのが、ちょうどここです」
アーミラは四方を見渡す。
――七年前、私が倒れた場所。
「お師様は私を助けるために、同じ年頃の魔人種の身体を見繕って戻ってきたそうです。それで――」
「首を挿げ替えた」
オロルが後を引き取るように言う。
「禍人種の身体から魔人種に乗り換えた……なるほど追手を撒くにも良い手段じゃろう」
「その……」アーミラは控えめに尋ねる。「いいんですか……私……敵、なんですよ……?」
目の前に立つ次女継承者の正体は、打ち滅ぼすべき禍人種だ。
自分から申告する勇気はなかったが、言い当てられた以上はオロルの判断を伺うしかない。
「無論殺すさ」
オロルは脂下がって口角を吊り上げた。
「……なんての、冗談じゃ」
笑えない冗談だった。肩の緊張が抜けない様子のアーミラを見て、オロルは続ける。
「禍人を恨み、ここまで戦ってきたお主が、今更裏切ることはないじゃろう。
生い立ちはどうあれ、今のお主は神に選ばれた魔人種の中の魔人種じゃ」
「そう、ですか……」
「……それで、言いづらいことはもうないじゃろう。取り戻した記憶は他に何がある」
敵意もなくおどけてみせるオロルに、ようやくアーミラは警戒を解く。
「……思い出したのは、お師様の姿です。
私が記憶を失う前は、とても若かった……ちょうど今の私くらいに見えました」
「ほう」
「首を挿げ替えた後、私はこの地で刻印を宿したようです」
「ふむ」オロルは相槌を打ち、ふと口を挟む。「すぐに消えてしもうたが、わしも幼い頃に刻印を宿したことがある。……時期が重なるな」
アーミラは初耳だったが、こくりと頷いて先へ進める。
「お師様は……全てを擲って、私の刻印を消したんです」
全てを擲った。
声に出して初めてそれがどれほど大変なことかを理解し、喉が震えた。
夢に見た記憶の光景は、その後を映してはくれなかった。だが、あの後のことならアーミラ自身が誰より理解している。
刻印は師によって隠匿され、痛みから解放された私は記憶を失い……そして師は命のほぼ全てを支払い、醜く老け込んでしまった。
――人ひとりを救った代償として、あまりにも理不尽だ。
それほどの代償を支払っても神の目を欺けたのは僅か七年。
結局、私は刻印を宿し、次女継承者となっている。
「もう長くないと悟ったお師様は、私一人でも生きられるようにと、厳しく修行をつけてくれました……」
末期の約束に込められた願い。
『婆から教わった事、魔術のそのすべて、人には決して見せてはならん』
やるせない虚しさは涙となってアーミラの瞳から零れる。
大切な約束を反故にして、神に見つかってしまった。
「失くした記憶を取り戻したいなんて思わなければ、……マナの恩義に応えられたかも、しれないのに……」
頬を伝う雫は、アーミラの顎の下で時を止め、いつまでもきらきらと輝いている。
一方、オロルはそんなアーミラを見ながら、満たされた表情を浮かべていた。
組み上げられた嵌め絵を眺めるように。
――本当によく泣く……。
だがこやつは、我が身可愛さで泣くことはついぞない。
いつも、他者の哀れに寄り添い、涙を流す……。
「詮無きことよ」
一つの残酷な真実……出征を共にしたアーミラが禍人だったという事実を受け入れ、そして幼い頃に消えた刻印の理由を知る。
マナという名の女が命を懸けて守ったもの。
その余波を受け、狂わされた運命の歯車。
二つが噛み合い、針は右回りに動き出す。
オロルは手袋を脱ぎ、アーミラに見せるように掌をかざした。
何度も追い求め、自ら刻みつけた偽りの刻印。幾重にも重なり、変質した皮膚は硬く罅割れていた。
――だが、その表情に後悔はない。
アーミラの額に、そっと手が触れる。
「後悔もあるじゃろうが、お主がこうして選ばれたことで、わしも刻印が手に入った。そう悪くないことじゃ」
アーミラは励まされる気持ちで頷いた。師の願いこそ叶えられなかったが、この争いを乗り越えれば全て終わり。私の望みは叶うのだ。
生きてさえいれば、きっとマナも赦してくれる。
決意を新たに洟を啜って悲しみを収めにかかる。
生き残る。勝ってみせる。
支払いすぎた犠牲に、マナの恩義に、報いるまでは……。
「さて」
オロルはこの一件に一段落ついたという態度で浮遊する身体を南に滑らせる。
「気持ちの整理がついたら、時を進めるぞ」
大したことではないと言いたげな口調だが、涙を拭って望む景色には明らかな異常事態が待ち受けていた。
オロルは告げる。
「如何やら最終決戦のようじゃ」
ラーンマクから前線南方の地平の果てより少し手前、大山鳴動してして鼠一匹とはいかない。
出征の任に使命を背負い、迎え打つ最後の強敵は静かに巨体を浮かび上がらせこちらに向かおうとしていた。
その巨体は遠くからでも特徴がはっきりと望める。
奸詐を閃く額の角。
佞辯を吐き出す裂けた細舌。
翼は詭計を描く巨大な翼。
知識がなくとも見誤ることはない。
アーミラは呟く。
「災禍の龍……」
■009――災禍の龍 後編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
『青生生魂の鎧は一揃いあった。私達はそこに霊素を注いだ。』
(『四代目次女継承者 デレシス・ラルトカンテ・テティラクスの手記』より)
❖
ラーンマク南方の景色に浮かび上がる禍々しい影は、午前の晴れた山々の景色を遮る夏の鉄床雲のように静かに存在を主張していた。
それは日を浴びて白く、体躯は山巓を超える無貌の巨人だった。鈍く陰影に富む肌は雌雄の別なく、目も鼻も、口さえも皮で塞がれ丸く固めたような、あるいは包帯に全身を包まれ封じ込められたとも思える姿をしている。人相も体躯も特徴らしいものはなく、人の概念に牛の頭角と蛇の尾と蝙蝠の翼を取ってつけたものと形容して差し支えない。
こうして時が止まっていると災禍の龍という名に備わるべき凶暴さはまるでなく精気すら感じさせない。一見して偶然にも人の形をした雲を見つけた気にさせた。
いつから現れたのかアーミラにはわからない。オロルがそれを認めたのは、アーミラが気を失った後のことだ。山の影から這い出てきたその存在に気付き、時を止めて控えていた。
「あれを抑える。わしとお主で光弾を放つぞ。よいな」
オロルは見据えたままそう言い、アーミラは硬く息を呑んで頷きを返す。
世界に音が満ちたとき、時止めを解除したことがアーミラにもはっきりわかった。
柱時計から飛び降りて地面に転がっている杖を拾うと改めて災禍の龍に体を向ける。互いに戦場の両極に構える距離であるため龍の姿は霞がかかるほど遠いが、先に視認していたこちらの兵士は砲撃の狙いを定めて既に攻勢に出ていた。アーミラが弓を引く前に最初の一撃はもう龍に到達していた。
肌に小石がぶつかる……そんなふうだった。
ラーンマクから放たれた砲撃の光弾が青空を飛び、龍の皮膚を叩く音が景色に遅れて耳朶に届く。初撃の様子から大した効果は望めないことは龍の反応から分かってはいたが、後に続き既に放たれた砲撃が勢いを増して着弾しているため、アーミラは流れに棹さし矢を指に摘む。横にいるオロルも柱時計から光線を射出した。一つ一つが小さくとも物量で圧すことができるかもしれない。
アーミラが覚悟を決めて杖を構えたとき、ウツロが袖を引いた。酷く慌てた様子だった。
摘んだままの袖を捲り上げ、日に晒された腕に素早く指筆を走らせる。
――逃げろ。
「何をいってるんですか」アーミラは真意を汲み取ろうと鎧の顔を見ようとしたが、首から上をなくしているため意図が読めない。
――ここにいる兵も全て避難させるんだ。龍は俺一人で戦う。
「……無理を言わないでください。私も戦います」
――無茶だ。
アーミラは流石にしかめ面になる。
「無茶なのはあなたの方です! いいから離してください」
腕を振り、ウツロの手から離れると、決然とした目で咎めた。
袖にされたウツロは悄気たように手を下ろすと未練たらしい態度で龍に向かって駆け出した。
龍は今しも滝に打たれるように全身に魔呪術の飛沫を浴びながら、胸元から腹部にかけて光弾が爆ぜていく。無力化している様子はなく龍の肌は焼け爛れているが、そもそもの巨大さ故に命を屠るには及ばない。そこにまずオロルの光線が加勢に加わった。魔力の収束を高め細く鋭い光線は皮膚を穿ち、次いでアーミラの矢が天から槍の雨となって降り注ぐ。
鋭い槍が龍の丸い額を埋め尽くす様はまさに針の筵。鋒は鋭さから肉を貫く音も立てず、灼熱の槍は龍の顔を焼いた。噴き上がる煙で首から上が見えなくなる。
一連の集中砲火の間、災禍の龍はその身を浮遊させており、今なおゆっくりと、しかし弛みない速度でこちらに向かい迫っている。
煙が後方へたなびいて龍の顔が露わになる。
針だらけの顔は赤く染まって、顎先から血が滴っていた。
攻撃は通っている……だが……。
「効いている気がせんな。本当に山を相手にしているようじゃ」オロルは汗を拭って憎らしそうに言う。
神殿を目指し北上する災禍の龍は、全ての攻撃に対して逃げも隠れもせず受け止める。厚い皮膚は熱に炙られ焼き爛れ、光弾が突き刺されば出血もある。しかしだらりとぶら下げた四肢は痛みに身を庇うこともなく、表情のない顔は怒りも悲しみも表さない。ただ確実にこちらに向かってきている。
アーミラは動揺を隠せない。
「本当に生きてるんですか……?」
「わしに聞かれてもな」
辟易した様子で返す。本当にこちらが聞きたい。あの白い人形は生物なのか。
「どうあれ攻撃は素直に通る。内地に入られる前に頭を吹き飛ばせば止まると信じたいが」
「……それか、翼はどうでしょう。飛べなくなれば足止めになるかも」
「ふむ」オロルは敵の翼を見据えた。「羽ばたきすらしないがお飾りとも思えん。任せるぞ」
オロルは言いながら構えを変え、一度合掌の形を作り両手を離し指先だけを押し付けた手印の三角窓から狙いを定め、龍の胴体から眉間へと調整する。より強く呪力を練り上げるために駄目押しの詠唱も重ねた。小さな唇がこそこそと言葉を紡いでいる。
眇眇たる残骸すらも口を開けば雄弁に、
万物は悪運へ立ち向かい不滅を謳う。
葬ることのできない悔恨と、
蘇ることのできない愛念と。
それらが絶えず流れ落ち一つとなる場所では、
太陽と月のように禍福が巡り招かれ続ける。
幾多の失敗がささやきかけたが、
ついぞ儂を振り返らせはしなかった。
彼の亡霊が示す先へ進み続ける。
その良心を手放さず、
遡行を許さず、
ただまっすぐに。
オロルが言葉を用いるのは初めて見た。
改めて、詠唱という行為は単純にして奥が深い。
言葉に対して結びつく意味や記憶が実行者の中にあり、固有の詠唱、または綴字であればあるほど内面に迫る経験や体験、記憶を反映させた物語の形となる。術が縛りを設けることで威力を高めることができるように、言葉は構造そのものの単純さが煩わしい制限となるため、練度が高ければ高いほど強く魔呪力を練り上げることができる。
アーミラもそれに倣い、杖を倒して弓構えを横に捻った。槍の着弾位置を左右広範囲に広げる構えである。詠唱も添えたいところだが、まだアーミラには唱えるべき物語が備わっていなかった。
再開した集中砲火は威力こそ増していたが物量を減らしていた。これには当然やむを得ない理由がある。禍人領からの報復攻撃が迫っているからだ。
勢いを増したトガに兵士は手が空かず、向こうから迫る禍人の砲撃に対しても防御の陣を展開しなければならない。敵は災禍の龍だけではない。得体の知れない大きい的は継承者の二人に任される形となった。
オロルの射出している光線はますます収束を高めて、径は指先ほどまで絞られた。その分高まる出力はそのまま貫通力となり、愚かにも射線上を横切ったトガは肉も骨もすっぱりと溶断された。
それが遥か南まで伸びて一直線に災禍の龍の眉間に注がれている。距離による呪力の拡散減衰は多少あれど、龍の額は滝壺のように飛沫を上げ崩壊していた。
それでも龍は迫り来る。
アーミラが弓手に力を込め、解き放った光矢は空の彼方へ溶け、招請の合図に応えるように少し遅れて槍が降り注ぐ。龍の視点から見ればまさに槍の雨だろう。
背から繋がる翼は一度でも羽ばたく姿を見せることなくその翼膜に穴を開け無惨にも切り裂かれた。果たして浮遊する能力は失われるか……。
それでも龍は迫り来る。
アーミラとオロルは徐々に災禍の龍の脅威を感じ始めていた。
無防備かつ無抵抗に血を流し続ける人間を象る印として戦場に現れ、すべての悲しみを受け止める器のようにそこに存在していること。その在り方自体が一種の儀式的、呪的な価値を持っているように思えたからだ。
同時にオロルは刷り込まれた知識を思い出していた。何故トガは人に化けるのか。――この問いは因果が逆転していることを知ったが、それでも龍の姿を見ていると一つの仮説が浮かび上がり纏わり付く。
精神負荷。
人が人を殺すことの重さを前に、常人は強烈な抵抗感が生じる。自分自身を危険にさらす状況においても他者を殺めるというのは本当に最終手段なのだ。例え「人に化けているだけなのだ」と暗示を重ねても、躊躇いなく禍人を手に掛けることは生まれ持っての素質と慣れが必要となる。姿形に囚われず認知を歪め深層意識にある禦衛機構を取り払う、素質と慣れが。
この論理の延長に災禍の龍の姿はあると言える。
ラーンマクに身を置いてきた戦士、あるいは神殿から派兵された兵士ならば、もっと容赦の無い砲撃ができただろう。もっとも、彼らの扱える術式の威力は神器と比べるべくもないが。
今オロルとアーミラの攻撃は少しずつ威力を弱めようとしていた。
魔鉱石の蓄えが減っているというだけではなく、激しく消耗している活力の方が問題だった。有り体に言えば、無抵抗に血を流す巨人の痛ましい姿に心が痛むのだ。こちらが悪意を持って挑むほど、精神負荷も比例して跳ね上がり、凄惨な疵痕を見せつけられるほどに罪悪が闇より染み出し、畏怖の念に心を囚われる。こうなれば一気呵成に場は動き始める。
戦況というのは生き物だ。僅かな勢いの優劣が戦線の全体へ波及し、状況が変化する。継承者とはいえ内地の娘。その二人が龍に圧される様は遠く離れた戦士にもよく見えた。
巨大な化け物が砲撃をものともせず迫る姿に神殿側は恐れ慄き、禍人共は背を押されるように励まされる。南から勝鬨と吶喊の雄叫びが轟き、戦士は劣勢に後退するのが見えた。このままでは戦線が危うい。
じりじりと迫る龍に成す術なく前線が押し上げられている。未だオロルとアーミラは砲撃を再三、再四と重ねるが、肉を穿ち血を流すことはできても骨を断つことができずにいた。
苦労しているオロルに加勢する形でアーミラは龍の脳天に矢を放ち、熱線と合わせて龍の額をなんとか切り裂いた。皮膚を千切り、頭蓋に鋒を滑らせた槍が不恰好に肉を抉り、毀たれた肉塊がその質量を伴って落石のようにごろりと地に落ちると、熟れた果実が蜜を弾けさせるが如く赤い飛沫を撒き散らして転がる。落下した場所はラーンマクの内側、オロルとアーミラが初めに陣取り砲撃を行った地点だった。
欠損を気にもせず龍は己の欠片の上を浮遊し通りすぎる。
詰められた距離の分だけ継承者は引き下がって立て直しを図るが、ラーンマクの防壁はもう背に迫っていた。
翼を裂かれ頭骨の露出した災禍の龍はラーンマクの領空を侵犯し前線を追い詰めている。
覚悟こそしていたが、前線の失地をついに許してしまった。それに気付いた時、オロルは肩で荒く息をして、呆然としていた。
一度の攻撃もなく災禍の龍によって戦線が壊滅的に瓦解している。
――何人死んだ……?
オロルは考える甲斐もない疑問が浮かぶ。
禍人の攻勢に撤退を余儀なくされた戦士や兵、彼らはわしらが龍に拘う間にどれだけ切り伏せられただろうか。
酷く渇いた喉に僅かな唾液を嚥下して呼吸を整えるが、砂埃と日差しに晒された体は余計に渇きを自覚させるだけだった。
どこで選択を誤ったのか、オロルにはわからない。
いかんせん砲撃の効果が認められるせいで別の策を立てる判断が遅れた。いや、そもそも別の策を立てるとして何ができた? 魔呪術しか能のない継承者に災禍の龍を倒す手段は光弾を放つしかない。もっと前の段階でやれることはあっただろうか……。
過ちを探るために思考を辿れば、行き着く結論は単純なものだった。
挑むべき相手ではない――揺るがぬ事実が、賢人の心をへし折る。
龍はラーンマクの防壁を前に一度侵攻を停止する。まるで流れる雲が山脈に阻まれ堰き止められたようだった。
見上げるものは色めき立つ。ここに来て初めて龍の首が動いたのだ。目覚めの身動ぎのように無貌の頭が左右に揺れる。
アーミラは……いや、龍の覚醒を目にした者は皆、きっと同じように身を強張らせて立ち竦んだだろう。見上げる程の巨大な化け物は目を覚まし、次に額の痛みを自覚して右手の指先でそっと血に触れ、顔の前に指を運んだのだ。
白い指先に付着した血の赤を暫し見つめていた。
この長く短い沈黙の中、見上げている者等は生きた心地がしなかった。
災禍の龍はもはや人類の上位存在、敵う相手ではないことは明らかだった。その巨人が微睡みの中にあるときに、矮小な、鼠や虫螻同然の我らの内誰かが、粗相を働き傷付けた。
荒ぶれば禍事――仲間であるはずの戦士ですら、「お前等があんな事をしなければ」と責める視線を継承者に向けていた。
龍は丸い顔の中央に皺を寄せて怒りを表すと大きく息を吸い込むように背を仰け反らせて顎を引いた。呼吸とは全く異なる理によって、龍は鼻腔も鼻梁もないのに大気を丸ごと呑み込み、局所に発生した真空を埋めるために吸い寄せる風が吹き荒れた。肺に溜めたのは空気だけではないのだろう。龍の頭上には光輪が出現し、急速に魔力の気配が高まっている。
オロルは声を張り上げ叫ぶ。
「伏せよ!」
ほとんど同時、アーミラの視界は地面に伏せって暗くなったと思えば瞼越しに白く焼かれた。渦を巻く横薙ぎの竜巻が上を掠めて体は吹き飛ばされ、何も見えないまま転がり全身を打つ。
爆風に鼓膜がおかしくなっている。とてもうるさいはずなのに玻璃の音みたいな耳鳴りばかりが張り付いて、外界の全てが遠く篭って聴こえる。
真っ白に焼かれていた視界はぼやけながらも色彩を取り戻し、アーミラは空と大地を見分けることができた。平衡感覚の麻痺も治り、よろよろと起き上がる。
遠景に目を凝らし、アーミラは絶句した。
マハルドヮグ山が燃えている。
山の稜線が齧られたように丸くくり抜かれ、かろうじて射線から逸れた神殿は炎と煙に隠れていた。
それだけではない。
「みんな……どこに……」
アーミラは切なく呟く。
龍が放った一撃によって辺りは何も残っていなかった。直撃したわけでもないただの衝撃波がこの地を襲い、敵味方無関係に吹き飛ばしたのだ。
アーミラは失意に項垂れ、砂を握る。その背に声がかかる。
「アーミラ……」
声がした方に顔を向けると、思わぬ再会だった。
「ガン、トール……さん……」
真紅というには赤茶けて、袖のほつれた衣装は幾つかの装備を紛失していた。はだけた肌に傷はないが、それは祈祷による治癒のお陰だろう。ここに辿り着くまでに数え切れない死と蘇生を繰り返したことを出立ちがありありと語っていた。
「道すがら前線の敵を払ってまわった」
合流が遅れたことを詫びる代わりとしてガントールは言う。
「地下通路を辿って敵の根城に繋がる道を把握したんだが、地上の様子がおかしいとみてここまで戻ってきた。あれは相当厄介みたいだな」
顎をしゃくってガントールは龍を示した。その強気の態度が頼もしい反面、恐ろしさを知らない無知の蛮勇にも思えてアーミラは首を振り裾を掴む。
「が、ガントールさんっ……あれは、さ、災禍の、龍なんです」
「知っているさ」
「勝てっこ、ありません……!」
泣き出しそうな声で縋り付くアーミラを見下ろし、ガントールはくしゃくしゃと髪を撫でる。硬く笑みをつくり、胸ぐらを掴み持ち上げた。
「『勝てっこない』じゃないんだよ。アーミラ」ガントールは厳しく叱る。「私達が諦めてどうする。私達は神に祈る立場じゃないんだぞ。内地からの祈りを一身に背負う、それこそ女神として進退を賭けるんだ」
ガントールはアーミラを無理矢理立ち上がらせて胸ぐらから手を離す。そして握手でも求めるように手のひらを差し出した。
「まだ希望はある。私の剣を持ってるだろう? 返してくれないか」
「でも……――」
「ウツロはまだ戦っている」
「――!」
食い下がろうとしたアーミラを遮ってガントールは告げた。
諦めない者がいる。この災厄に一人立ち向かう者がいる。
はっとして、アーミラはウツロの姿を探す。
龍の周りを飛び回る小さな羽虫のような影を見つけて驚いた。
イクスから託された斧槍を握り、縮地の魔術で跳躍しては切り掛かり、振り回される腕を掻い潜っては刃を突き立てる彼の姿。
果たしてこの無謀な挑戦に勝機はあるのか……いや、違う。勝機は掴むものだ。
アーミラの目に火が宿るのを認め、ガントールは肩を叩く。
「ここを乗り越えることができれば、禍人種の根城に攻め込める……正念場なんだ。
私とウツロが注意を引くから、アーミラはオロルを探して打開策を見つけてくれ」
返事の代わりとばかりにアーミラは杖の内側から神器の剣を取り出して手渡した。ガントールをウツロと合流させること、つまり戦闘の継続を肯ったのである。
二人は振り返らずそれぞれ駆け出した。生者なき前線で、災厄との決着をつけるために。
❖
次女を奮い立たせ、孤軍奮闘する鎧との合流を目指すガントールは、いざ災禍の龍を間近に対すると肌が粟立つのを感じた。本能が鋭敏に危険を察知している。……我がことながらこの勘が外れたことはない。
一撃だった。
もとより治安の良い場所とは言えないこの故郷を、龍はたった一息で吹き飛ばし景色を様変わりさせた。正直なところガントール本人にも天望はないのだが、かといって逃げ帰るつもりもない。
例えここで斃れるとしても、覚悟はできている。
「さて――」ガントールは呼吸を整えるように微かに俯き、天秤の柄を握り直す。「――やるかぁ」
浮遊する龍の足元、ガントールは剣の先を地面に突き刺し斥力を発生させた。踏み固められた地盤が軋み、地鳴りが響き渡る。これは強烈な重力操作によるものだ。対象物――災禍の龍――を中心とした円形の領域はあらゆるものが下方へ押し潰されようとしている。
初めに落ちてきたのはウツロだった。下へ引き寄せられる力に抗えず攻撃を中断して力場の範囲外へ斧槍を振ると、かろうじて体勢を整えてガントールの側に三点着地する。
「邪魔をしてすまない」ガントールは龍を見上げたまま言う。「足止めをしたくてね」
空に浮かぶ龍の爪先が少しずつ地面に引き寄せられている。傷から絶えず流れる血が重力に促され足を伝って滴り落ち、錨を引きずる鎖のように地面と龍を結んでいた。やがて座礁し、足裏が土を踏んだ。
「まだだ」ガントールは全身に力を込めてさらに斥力を強める。
どういうわけか災禍の龍は沈黙している。頭上に飾った光輪も消え、ラーンマクとマハルドヮグ山を焼いた光を放つ様子は無かった。それでもウツロが単身で挑んでいたときは腕を振り追い払うだけの意思はあったように思うが……。
「ウツロ、あれはどうなってるんだ?」
ガントールは具体的な返答が返ってくることを期待していない。度々こうしたわかるはずもない問いを投げるのは彼女の癖だった。が、不思議なことにウツロは今回も期待以上の答えを返す用意があった。
斧槍の石突の方で地面を削る。
――龍は山を喰んだ。
ガントールは文字を読み流し意味を掴みかねた。もう一度文字を目でなぞる間にウツロは続く言葉を書き始めている。
――マギカを放ったのではない。世界を飲み込んだ。
「なんだと……!?」
ガントールは意味を理解すると霹靂のように臓腑に雷が走った。認識に齟齬があったのだ。ウツロが伝えているのは災禍の龍が発した一瞬の光について……頭上に現れた光輪は確かに攻撃の予兆に間違いはない。だが、マハルドヮグの山を抉ったのは放たれた魔呪術の光ではない。
あの一撃は世界を吹き飛ばしたのではなく、齧りとったのである。
「……じゃあ今は咀嚼中だっていうのか?」
冗談じゃない。とガントールはウツロを詰るが、責める相手が違うと言いたげな襟元の虚無がガントールの視線を闇に受け止めている。その沈黙が答えだった。
ぎり、と奥歯を噛み締め、ガントールは龍を睨む。どこまでもふざけた真似をする。ウツロの攻撃もただ目障りな小蝿くらいにしか思ってないのか……? 私の重力魔法も意に介さないって?
「舐めるなよ――」
怒髪天を衝くガントールの力場はいよいよ地盤を破壊し、岩盤層をへし折って足元を沈ませた。彼女の瞳に宿る闘志は見るものを火傷させるほどに燃え盛り、同時に芯から痛むほど冷たく鋭いものだった。それこそ、龍が脅威を察知して首を向けたほどだ。
ガントールはこのまま奥義の詠唱に入る。途中、災禍の龍は地に着いた足を持ち上げ踏みつけようとしたが、ガントールの纏う斥力は足裏を跳ね退かし、朗々と誦じてみせた。
天秤剣は悪に傾いた。
我が掌零ゆる魂魄を掬い給へ。
善の上皿昇るならば、
我の誓に能う裁定を果し給へ。
この剣を振り上げし時、
我は科人に永久の生を祈らん。
この詠唱は獣人種である長女継承者に伝わるもので、ガントール個人が構築したものではない。本来はこうした魔呪術に適性を持たない種族であるため、唯一の詠唱を伴うこの術式は、故に奥義に相応しいものである。
楔のように突き立てられていた剣は唱えた言葉に呼応して、ふわりと宙に浮いた。一度ガントールの周りをくるりと踊り舞うと術式の行使者を示し、星の重力から切り離されて静止する。
鍔の飾りの上皿が鈴のようにりんと鳴り、龍に向かい引き寄せられ、吊り合いを保ち止まった。その次に刃が、まるで重力の中心が災禍の龍であるかのように、首へ向かい真っ直ぐに落下を始めた。都合ガントールから見て空に向かって剣が飛翔することになるが、術式の効果が発動している今、剣は間違い無く落下しているのだ。
刃がその首に向かい着地を目指すという単純な理。それは必ず斬首を成し遂げるという逃れられぬ断罪となる。しかし龍から見れば天秤の剣は小さく細い針か小石にしか見えないだろう。図体の差は歴然であり、指で摘めば済む話――とはならない。
先代長女継承者達が磨き上げ、戦の中で紡いだ天秤の物語は言葉通りの奥義なのだ。ガントールが唱えた言葉は物語構造の中に天秤の機巧を備えており、立ちはだかる理不尽を均す神力が込められている。眼の前の巨悪に天秤が重く傾けば、もう片方の善を乗せた皿は上へ昇る。この逆境において長女継承者は失われてしまう命を掬い上げ、善の皿に上乗せすることで均衡を保つように摂理を捻じ曲げる力を生み出すのだ。
つまり、軽やかに空へ吸い込まれるように落下する断罪の剣は、災禍の龍が持つ質量と同じ重さを備えて首へ落ちている。過剰な質量と鋭い剣身が空を切り裂き速度を増してゆき、受け止めようと広げた龍の掌に鋭く沈み込み貫通した。
勢いを失ったぶん首への一刀は浅いが、後ろに突き抜け軌道は再び落下に向かう。あまりの威力に流石の龍も防衛本能が働くのか、侵攻は止まり身を退け反らせて回避に忙しくしていた。
重力とは、この世で最も平等で、逃れることのできない呪いである。
何度弾かれ打ち上げられようと、剣は着地を目指し首へと落下する。
あとは次女と三女が揃いさえすれば、望みはある。
望みはあるのだ。
❖
アーミラはさしたる苦労なくオロルを見つけ、合流を果たした。
あのとき災禍の龍の攻撃の予兆にいち早く気付き、「伏せろ」とアーミラの身を案じたオロルは、当然己の身を守る猶予があった。衝撃波に視覚を奪われて吹き飛ばされてしまったために互いの行方がわからなくなったものの、二人揃って戦闘継続に問題はない。ただ仕留めるための決定的な一打に欠けているために、今はガントールの言う通り、打開策の立案を急ぐこととなる。
今二人はガントールとは少し離れたところに杖を置き、その宝玉の内側に広がる驚異の部屋の上階書架の間にいた。
「砲撃では仕留められんな」
オロルは杖内部に避難するとアーミラを柱時計に乗せ、時の運行を緩めて仕切り直すように状況の整理から始める。外界と切り離された書架の静謐は平時から時が止まっているような空間であるために、オロルの術が効いているのか不安になる。アーミラは扉に設けられた欄間を覗いては窓外の景色が動き出してはいないかと確かめていた。
オロルは続ける。
「まずもってわしとガントールの奥義では龍討伐は望み薄じゃ」
時計に腰掛けたままびくりと背を伸ばして、アーミラはオロルの顔を伺う。
「砲撃が通用しないのなら、弓兵としての私も役立たずでは……?」
「『弓兵として』はの」オロルはアーミラの言葉を強調して否定した。「神器に備わる奥義の術式はその限りではない」
「オロルさんの、柱時計の奥義は……」
「戦闘向きではない」きっぱりと答えた。「三女の神器は未だ謎が多く扱いきれん。いたずらに時を操ったとて、制御できなければ意味がない」
長女継承者の天秤は一対一の力の差を均す――騎士道精神に則した奥義であり、その先の勝敗は継承者の獣人種の娘の気概に依存する。……ガントールが行使しているところを目撃したわけではないオロルは、あくまで知識として先代からの奥義の全容を知っているに過ぎない。今こうして足止めをしているガントールも、龍相手では押し留めるのが限界だろう。
三女継承者の柱時計もオロルの言ったことに嘘偽りはない。時間をどうこうしたところで直接的な火力には結びつかないのだ。アーミラとしては柱時計の奥義の効果についても知りたかったが、奥の手を話す気はないのだろう。
それよりも。と、オロルは続ける。
「先代は災禍の龍を倒したという前例がある」
その言葉と視線から、何が言いたいのかアーミラにははっきりとわかった。頭に浮かぶのは神殿での晩餐後の一幕、そこで見た大略図――デレシスの大穴。
「要は先代の次女継承者が何を行ったかじゃ。これについてはなんの記録も残されておらん」
でも、と言いそうになるアーミラを遮りオロルは説明を止めない。
「理由はわかっておる。結果的に相打ちとなり、穿たれた大地は雨水を貯めて、世に言う『涙の湖』となった。それから二百年誰も寄り付かぬ曰く付きの土地じゃ」
アーミラはこくりと頷く。
記録が残っていないのは、その奥義を行使した先代の次女も無事ではなかったからだ。
「……わしらも同じ道を辿るやも知れぬ。じゃが次女の奥義は龍を倒す鍵となる。当時の者が何をしたか、急ぎ解明するのが現状を打開する策となるじゃろう」
オロルは指を立てて付け加える。
「もちろん、お主に死んでくれと頼むつもりはない。皆生きて帰ることをわしは諦めてはおらん」
その一言にアーミラは安心した。ともすれば決死の覚悟を必要とする状況で、オロルの言葉は支えだった。彼女が「無理」と言えば無理で、「できる」と言えばそれはできるのだ。先代が大地に大穴を穿って龍と共に戦死を遂げた前例をなぞり、それでも私達は生き残る方途を探る。なんとかして龍のみを討伐する。
「実は、奥義について……手掛かりはあります」
アーミラはそう言って地下階を示す。
「待て、そこから先は狭い。時止めを解除するが良いか」
「構いません」アーミラは柱時計から滑り降りて螺旋階段を下る。
後を追うオロルは二度目の訪問に部屋を見渡した。前回来たときは雑多に物が溢れていたが、見違えるように整理されている。離れている間もアーミラがここをいかに有効に使い、自室として過ごしてきたかが推察できた。当の主は視界の端、部屋の隅に設られた寝台に身を預けていた。手にはいつのまにか装丁された一冊を携えている。棚から引っ張り出したのではないだろう。元々寝台の上にその本は置かれていた。
「それが手掛かりか?」オロルは問う。
「はい」アーミラは確信を持って見つめ返す。「先代の手記です」
なるほど、とオロルは得心し、その書を受け取ろうと手を伸ばすが、アーミラは渡すどころか寝台に手招きをした。
「持ち出せないように術式がかけられています」
事情の説明はこれで足りた。
「……では失敬」
オロルは寝台に乗り込みアーミラの隣に身を落ち着かせる。互いに汗と血と砂埃の臭いがしたが、素知らぬふりで書に視線を注いだ。
「途中からになりますが」
「よい。それとも前の文にも重要なことがあるのか?」
「それは、なんとも……読んだ限りでは手記以上の意味合いはなさそうですが、仕掛けが隠されているかも」
「……一旦先を読む。謎が残れば仕掛けを疑うとしよう」
オロルはそう決めて、「呪術をかける」と背に手を触れた。手袋をしている小さな掌が熱かった。おそらく身体強化を施して文字を読む思考と意識を底上げさせたのだろう。時止めほどではないにしろ、体感速度を加速させることで相対的に時を操ったのである。これであれば重ね掛けも支障はない。
問題の手記、その開かれた頁は紙幅の内三割が読み飛ばされており、その内容はアーミラから簡単に説明された。場面は次女継承者が神殿での日々を終え、出征に十分な年齢となった頃から始まっていた。
二人は手記の文中から有益になり得る言葉を探すが、アーミラの言っていた通り大半が取り止めのない日々の記録であった。時折に術式回路の走り書きのようなものも散見されたが、二百年前の知識とあってめぼしいものは無いに等しかった。
なによりオロルが辟易したのは、文体の素朴さと情緒を欠いた表現である。幼少期から先代の三人は神殿に招かれ教育を受けてきたのだろう。芯まで軍人気質で人情を寄せ付けない硬質さが行間に表れていた。
「あ……――」
アーミラが指摘したのはある一文だった。
『青生生魂の鎧は一揃いあった。私達はそこに霊素を注いだ。』
「――これって、ウツロさんのことですよね」
「じゃろうな」
「一揃いって、ウツロさんはこの驚異の部屋の蒐集品の一つだったんだ……」独り言を呟き、改めて借問する。「この、……『あおせいせいこん』ってなんですか?」
「アポイタカラ」オロルが答える。「滅多に手に入らない希少な金属じゃ。それこそ神器は赤みを帯びた日緋色金であるとされる。ウツロは手記の通りなら青生生魂となる……先代の置き土産とは言われていたが、鎧自体もそこまで希少とはわしも驚いたわ」
口ぶりに偽りなくオロルは饒舌で、知らぬことを知るという知識探究への喜びに興奮している様子だった。
「『私達』とありますね。霊素を注いだ……」
「先代は常より行動を共にしていた。言葉通り三人の力を合わせてウツロを作ったのじゃろう」
アーミラは否定こそしなかったが、『作った』という表現には頷けなかった。彼には人格があるとやはり認めていた。
手記の内容はそこからしばらく鎧についてが主だった。オロルの推察は概ね正しく、三人共同で組み立てたようだ。生み出す目的は前衛補助の自律魔導具を欲したことにある。数ある蒐集品の中からあの鎧を選んだのもその動機から推し量れる。また、曰く『日緋色金と青生生魂はこの世に存在する金属の中で無二の、霊素に感応する特徴を備える。非金属同様、あるいはそれ以上の魔呪術親和性を持つ』という記載も見つけた。
つまりは神器を触媒とすることで禁忌級の術式回路も安定した結果をもたらすということだ。これは二人にとっては発見である。
神器が強力な兵戈である理由は先代が既に解明していた。が、手記の仮説とは異なり、以降の頁は暫く鎧が目覚めないことを書き残している。前線維持と並行して何度かの術の研鑽と改良を行い、自律魔導具が起き上がるのは数日経ってからだった。
『腕甲に震えを認める。霊素定着の兆候を確認。自律魔導具の完成をみる。』
『それは制御が効かず、ラーンマクが取り押さえた。何らかの拒絶反応、あるいは精霊を内に宿した可能性あり。』
『鎧に名を訊ねると慧と応えた。』
アーミラは文字を指さした。
「ここは声で返事ができたんですかね?」
「いや、手記の詳細が乏しいがウツロは指で書いたんじゃろう」
「ちなみにこの字はなんと読むのですか?」
「慧……かのぅ、彗星の『彗』と、下に『心』を組み合わせ一字にまとめた賢種文字じゃ。闇によく気づくこと、かしこいことを意味する。継承者が生み出した精霊にしては清濁併せ呑む妙な名を名乗ったな」
特に彗星は卜部では凶事の予兆とされる。とオロルは付け加えた。
「そういえば、ウツロさんに生まれはどこかと聞いたことがあります。オロルさんは『ニホン』という集落を知っていますか?」
「……知らんな。消えた集落なぞいくつもあるじゃろ。時勢を鑑みればデレシスの湖に沈んだのじゃろう」
確かに、とアーミラは腑に落ちたようにオロルの言葉を間に受けて会話は流れてしまったが、これは誤りだった。正体を明らめる何度目かの機会をまたしても彼女は逃した。
そんなことも露知らず二人は目を皿にして読み進める。急ぐ事情もあるが、知っている者が現れたことで手記が他人事ではなくなり、ウツロの過去について語る内容に興味が引き込まれていった。
『慧は无雲経の下で戦闘に参加。ラーンマクに命じられ従う後、咎二体、禍人一体を倒す。心がっかりと杖へ篭る。』
「がっかりとはなんじゃ」
オロルの呟きにアーミラは思考を巡らせる。
ウツロが初めて敵を討伐したことを記した場面である。敵の弱さ、呆気なさに意気消沈するような質ではないから、ここはおそらく――
「自分の行いに傷付いたということだと思います」
「そこまでの心が奴にあるのか? ほとんど人間ではないか」
関わる機会がなかったオロルにはわからなくとも仕方のないこと。しかしアーミラは解釈に自信があった。当時のウツロはきっと心を痛めたのだ。そして彼の過去は別れの痛みによって紡がれた物語であると理解しつつあった。
手記の内容は鎧についての記載が減り、長引く戦闘への心労、ときに弱音も赤裸々に綴られていた。
『私が驚いているのは、神殿であれだけ優秀な成果を上げても、いざ本物の敵を前にすると光弾が当たらなくなることだ。この傾向は決して私だけでなく、前線のあらゆる戦士にも当てはまる。意気揚々と挑み放った魔呪術の打ち合いは致命傷にならないようにと互いに遠慮しあい、結果として当初想定されていた以上に戦役は長引いている。そう、あらゆる戦士とは敵も含まれている。そうでなければ撃ち合いが長引くことに説明がつかない。』
『日を追うごとに良心的兵役拒否者が増えてきている。ラーンマクが率いる遊撃部隊ではその傾向がいっそう顕著であった。彼らは禍人種さえも人間に見えているようで、ラーンマクがどれだけ命じても敵を殺すことを躊躇い、神殿からの命令と心理的抵抗の狭間に身を置く戦闘行為に、著しく活力を疲弊させているようだ。』
『アルクトィスも同様の問題に頭を悩ませているようだ。火線部隊の兵士達を調べたところ、持ち合わせの魔鉱石の消費量が少なく、全く使用していない者までいたという。割合として兵士が一〇〇人いた場合、敵に光弾を放ち仕留める者はおよそ二割しかおらず、残る大半はわざと狙いを外すか、負傷した仲間の救護を率先して行う、いわゆる勇敢な臆病者で溢れていた。』
『この勇敢な臆病者が一番に恐れているのは「死や負傷への恐怖」ではなく、「相手を殺す恐怖」である。この問題に対応するために私達砲撃部隊は、強制的に禍人を咎に戻す呪術結界を展開するに努めた。また、砲撃の距離が離れているほどに殺人の実感は薄くなる――また実際に流れ弾が何に当たるのか制御できないことによる責任逃れの逃避ができる――ようで、砲撃部隊の敵殲滅率が改善された。
その一方で、回路を組み立てた私もまた、勇敢な臆病者になろうとしている。』
表現に乏しい文体は相変わらずだが、飾り気がないからこそ記される数値や割合には説得力があった。難航している先代の苦労や背負った傷が刻々と紙面に浮き上がるようで二人は会話もなく読み進めた。
『咎よりいっそう恐ろしい敵にラーンマクは倒れた。私達は奴を蛇堕と呼んだ。』
彼女は怯えてばかりの鎧をよく叱り、戦争の勝利へと強く導く厳しい女性としての印象があったが、手記全体では折々に仲間を支え頼れる人としても記されていた。おそらく筆舌に尽くし難い悲しみが当時の継承者にはあっただろう。この一文を残すのが精一杯で、短い記述のなかに悲嘆の影が窺えた。
その後頁を捲ることもないほどすぐに三女継承者も倒れたことがわかった。
『アルクトィスも倒れた。時を止めている間も彼女は毒を浴びていたから回りが早かったのだ。慧は悔しさに荒れている。』
蛇堕はここで三女と相打ちに倒れた。手記に書いてある通り、毒を操る敵に翻弄され、優位に立ち回るために三女は時止めを行使したのだろう。決着がつく頃には一人手遅れになるほど毒に侵されたようだ。恐ろしいことにこの蛇堕という存在は継承者を二人も倒している。
確かに、毒が効かないウツロが、もっと上手く立ち回れたならば救えたかもしれない。簡潔な文では詳しい状況がわからないが、読んでいる限りではアーミラはそう思ってしまう。どうやら昔のウツロはあまり戦いが得意ではないようだ。
「終わりが近いのではないか」オロルは言う。
この手記は分厚い装丁だが、内容はもう後がないように見える。後の頁がいつ手付かずの白紙になってしまうか危ういところだ。
アーミラはそっと次を捲り、そこにまだ墨が文字を刻んでいることに安堵した。しかしそこに記されている内容に目を通せば、状況がいっそう悪くなっていることを知る。……というより、結末は初めから知っていた。
『厄災が地の果てより現る。』
筆跡が震えていた。
読んでいる二人も息を呑み紙面を見つめていた。てっきり、この『蛇堕』が龍だとばかり思っていたのだ。
『慧が私の代わりに戦っている。私は臆病者だ。杖に引き篭もってこれを書いている。』
「なんと……」一文を読みオロルは落胆したようだ。
「でも、気持ちはわかりますよ。
だって一人になってしまって、……彼女は龍を初めて目にして、いきなり戦うなんて、できないです」
アーミラはすでに亡くなった先代の名誉を守るために擁護する。
「じゃが――」オロルは指を指して続きを読めと促す。
『やれることは限られている。ここから出て杖を手放す勇気だ。』
『もし次代があるとして、次女に娘が選ばれるとして、残せるものはきっとない。』
『この手記も意味を成さなくなった。これは本当にそうだ。術式とは関係なく心からそう思ってる。』
この言葉を最後に、あとは捲れども白紙が続いていた。
アーミラはやや乱暴に次々と紙を捲り、どこかに隠れた一言がないか探したが、何も見つからない。
「どうやら自暴自棄になったようじゃな。確かに手記は本物じゃ。偽書らしい色付けもなく武勇伝の語りもない。先代は最後に龍もろとも死んだのじゃろう」
「……どうやって……?」
「わしが知るか」
二人は結局奥義の手掛かりを得られず、先代の死に様を読んだだけだった。気分は苛立って互いに口調が荒くなる。
何かあるはずだとアーミラはもう一度最初から読み始めるが、なんの変哲もない日々の記憶が綴られている。
全く無意味だった……? そんなことがあり得るだろうか。
本当にわからない。
手記の内容が先代の歴史として真実なら、災禍の龍と相打ちになったのは次女だけだ。……いや、オロルの言う通り自棄になって死んだのなら、戦場に取り残されたウツロが一人で倒したと言うことになる。
ならばウツロに聞こうかと立ち上がり部屋を出ようとして、ある一文が引っかかった。
『やれることは限られている。ここから出て杖を手放す勇気だ。』
「……なんで部屋を出たんでしょう……?」
「……なんじゃと?」
オロルは気味が悪そうにアーミラを見上げていた。いきなり立ち上がったかと思えば頭と抱えて、部屋を出ることに首を傾げた。「こいつも気が触れたのか」と思ったほどだ。
だが違った。
アーミラはないと思われた手掛かりを掴もうとしていた。
「自暴自棄になったのならずっと篭っていればいい。彼女にはその選択があった……。
ですが、まるで最後の手段かのように部屋を出ています。『やれることは限られている』と記して、杖を手放す行為を勇気と表現しました。彼女らしくない表現です」
「皮肉を込めたのじゃろうよ」
「だとしたらここは『私も杖を手放し、勇敢な臆病者になる』と記すはずです。皮肉な言い回しは常に統一されていましたから……」
確かめるようにもう一度手記を開き、最後の言葉に目を落とす。
「残せるものはない……? 術式とは関係なく……? 何を覚悟してそんな後悔を書き残したんでしょう……」
頭を抱えるアーミラの一連の様子を見ていたオロルは不意に叫んだ。
「そうか!」
「なにかわかりましたか……!?」
縋り付かんばかりのアーミラの視線にオロルはまだ笑みはない。確信はないが閃いたということだろう。
「彼女は手放し、後に残せるものがない。手記も意味を成さなくなる。――つまり奥義に杖を使ったのじゃ」
「……えっ、杖は、私も使ってますよ?」
「なぜここで鈍くなるのじゃ。いいか、天球儀の杖を杖として使ったのではない。そこに嵌め込まれた宝玉を、もっと言えばこの驚異の部屋を龍にぶつけたのではないか?」
驚異の部屋を龍に……。
そんな荒唐無稽をどうやって――と言いかけて、アーミラは首を振る。あり得そうにない無茶だからこそ先代は龍を倒せたのではないか。
先代が『残せるものはない』と憂いたのは、次代の継承者に引き継がれるはずの杖を壊してしまう覚悟を決めたからだと考えれば道理が通る。手記の白紙は、もう何を書いても消えてしまうのだと悟ったからこそ、突然手記は白紙となった。
「でも、なら、なんで杖があるんです? 手記も、蒐集品の全部も、なんで……?」
「それだけがわからん。じゃから確信はない。
じゃがこの推理が間違いだとしても、名案だと思わんか?」
オロルの問いにアーミラは否定も肯定もできない。
考えつく限りでは有効な打開策だ。先代の用いた手段と違っていたとしても、龍を倒すだけの破壊力は期待できる。
だが、もしもこの手段でも龍を倒しきれなかったら? アーミラはその時点で神器を失い反撃の手段はなくなる。身を守ることもできないとなれば必死だ。
「他に手段がないのなら、杖を使いましょう」
アーミラは重たい口を開いて、覚悟を決めた。
己の生死よりも災禍の龍を倒すことを選ぶ、そんな決断だった。
❖
「ガントールさん!」
駆けてくる気配にガントールが振り向き、当代継承者三柱が集結する。スペルアベルでもラーンマクでもなにかと別行動が多い彼女達が揃うのは実に久しぶりのことであった。言葉はないが小さく微笑み互いの視線を交わし合って無事を喜ぶ。
「さて、……龍に変化はないのぅ」
オロルは聳え立つ龍を見上げた。ガントールに足止めを任せてから戻ってくるまでの間、状況に大きな変化はない。白痴の巨人は上から押し潰さんとする重力に踝ほどまで地面にめり込み足止めされ、顔の周りを飛び回る剣に煩わしそうにしている。はたき落とさんとする手が剣に触れ、肉を削がれる度に血の雨が降り注ぎ地面を赤く染める。
災禍の龍に痛覚はないのか、それとも痛みを訴える器官が備わっていないのか、ずたずたになった指をそのままに、血を撒き散らしながら首を守っている。
「このまま仕留められないのか?」
「悪いけど、どう見てもじり貧だな……」ガントールは苦笑する。「正直なところ石も活力も限界だ」
気丈に振る舞ってはいるがガントールの顔色は随分悪い。奥義を行使したことでかなり消耗しているようだった。オロルはなけなしの鉱石を使ってガントールの疲憊を癒す。
「ここに来たってことは打開策は見つかったのか?」ガントールは問う。
「そうです」手当を受けるガントールを心配そうに眺めていたアーミラが、思い出したように顔を上げて鎧を探す。「ウツロさんは」
名を呼ばれた鎧は少し離れたところから現れた。沈下した岩盤層に押し除けられる形で隆起した地層の陰に待機していたようだ。
「お聞きしたいんです。先代の次女継承者について」
ウツロは駆け寄る歩調を緩めた。
アーミラは続ける。
「龍を倒した奥義のこと」
目の前に対したウツロの沈黙を、アーミラは心のどこかで予想していた。彼が先代のことを語りたがらないのは、壮絶な死別の悲しみを背負っているからなのだと今は理解できる。
それでも、教えてほしい。
「ウツロさん……あなたの過去のことを知りました。ほんの断片的なものですが、前にお話しした手記のことは覚えてますか?」
その問いにウツロは肩を竦めるようにして応えた。
「杖の中で鎧を見つけたこと、先代の三人が魔導具としてあなたを喚び出したこと、そして仲間として共に戦ったことが書いてありました。……その結末も……。
先代と死に別れた悲しみは分かります。だから語りたがらないんでしょう?」
ウツロは腕を組んで躊躇っているようだ。
アーミラは畳み掛ける。
「でも今は必要なんです。次女がどのように災禍の龍を倒したのか、せめてそれだけでも教えてください」
組んでいたウツロの手を取って解き、アーミラは哀願するように頼み込む。斧槍を握る方の手が地面に言葉を書き始めた。
――手記に書いてなかったのか。
「はい……」
――なら残すべきものではないとデレシスは考えていたんだろう。
「そうとは限りません。龍を倒す力……もし生き残れたのなら、きっと手記に残したはずです。
当時を知るあなたの力が、必要なんです」
正直なところ、アーミラは教えて貰えるものだと踏んでいた。
共にここまで旅をしてきた仲間、その紐帯の絆が互いの内面の秘密さえも打ち明けさせるだろうと信じていた。
ウツロは斧槍を脇に挟み、握られている手を解くようにとそっとアーミラの指を剥がす。後退りながら両手を軽く上げて、やんわりと体で示していた。
――お断りだ。
「なんで……」
追い縋るアーミラを近づけさせまいと得物を握り、地面に石突を走らせる。
――はじめに言ったように、龍は俺がなんとかする。皆は逃げて欲しい。
「……だから、それはないって言ってるじゃないですか!」
まるで人が変わったかのようにアーミラは語気を荒げて怒鳴った。何やら様子がおかしいとオロルとガントールが二人の様子を遠巻きに窺う。
切羽詰まっているのだと突きつけるようにアーミラは龍を指差してウツロに迫る。
「あなた一人では災禍の龍は倒せない。そうでしょう? なにをそんなに隠しているんですか……?」
――教えたらきっと使うだろう。死なせたくない。傷つけたくない。
「あなたの気持ちはわかってます。私も死ぬつもりはありません」
そう言ってアーミラは再び歩み寄るが、ウツロは肩を掴んで押した。体勢を崩したアーミラはよろけて、拒絶されたことに戸惑いながらも視線で責める。
――わかっていない。もうどうしようもなく傷ついてる。
――先代の三人だって最後はどんな顔で俺と離れたか、アーミラは何にも知らない。
「そん――」
アーミラは反駁を言いかけたとき、異様な音が響き渡り、声を掻き消した。
地獄の釜が軋みを上げて開くような、全身の血が凍りつく、恐ろしい音だった。
「なんの音じゃ」オロルも見当がつかずあたりを警戒する。
「まさかとは思うが……」ガントールは青褪めて龍を見上げた。「腹が鳴ったんじゃないか」
馬鹿馬鹿しい……とは言えなかった。
災禍の龍がなにをもって世界に破壊をもたらすのかは皆が知るところ。マハルドヮグ山を一齧りして飲み込み、白痴となって沈黙していたのは腹の中のものを消化していたからだとしたら、この異様な音の正体がわかる。
オロルはふと、半人半蛇の敵のことが思い浮かんだ。間違いなく強敵だった。彼女はこう名乗っていた。
『嫉妬のユラ。六欲の欠落者だよ。』
……彼女は、先代の手記で言うところの蛇堕ではないだろうか。
そして同様の術によって六欲を削ぎ落とし、途方もない飢餓と貧食のみを備えた存在が災禍の龍となったのではないかと思い至る。でなければこの大喰らいの説明がつかない。
その推理は当たっていた。しかし半蛇のユラが最期に身を案じ祈りを捧げた妹が、まさか龍の肉体を形作っているとまでは知る由もなかった。あらゆる希望を断ち切られた魂を器とし、そこに濃密な絶望を注ぎ込んだことで生まれた破壊の権化は、世界を蝕み文明を食い荒らそうとしている。
「攻撃に備えろ!!」ガントールがアーミラに向けて叫ぶ。
龍はその巨体に据えた無貌の首をゆっくりと伸ばし、顎を引き足元の存在に気付いた。頭上には燦々と不吉に輝く光輪が出現し、広がりつつある輪の内側へと大気が渦を巻いて吸い込まれている。
「くそ……! どれだけ飲み込むつもりなんだ……!」ガントールは重力方向に拮抗する龍の吸引力を恐れ、奥義を中断して剣を手中に握る。
空腹に飢えた光輪は巨大な口を開けてアーミラを捉えようとしていた。照らされた範囲の広大さに唖然としたアーミラは回避行動が遅れ、死を悟る。もうだめだ――と絶望が脳裏に浮かぶ刹那に、縮地で迫ったウツロが腰を掴んで攫い出した。間一髪で転がり込んだのは龍の懐、脚の間である。
先程までアーミラの立っていた場所は光が爆ぜ、照らされた範囲のあらゆるものが忽然と消失した。抉り取られた底の見えない縦穴が大地に残される。
穴の断面は艶やかに溶解し、地殻の層が重なる様が見えた。堕ちてしまえば二度とは上がってこれないだろう深い闇の底部は星の内部の層、漸移帯にまで達していた。
膨大な熱量の爆発と、真空に吸い上げられた溶岩が遠く仄明るい熱を吐き、開かれた大穴からは黒煙と熱波がゆらめく。大気はもうもうと噴き上がった灰に遮られて夜のように帳が落ちる。だというのに荒野は燃え盛る焔で赤々と明るかった。
龍は僅か二口世界を喰むと、そこに地獄を生み出したのである。
「……だめじゃ……」
オロルはつい声が漏れた。
「こうなってはもうラーンマクにいる意味がない」震える声でガントールに指示する。「スペルアベルの西側に誘導……いや、意思がないものに誘導なぞ無理か……とにかくわしらは退がるしかない。邸でもなんでもよい、魔鉱石を補充し立て直すぞ」
ガントールは苦虫を噛み潰した顔で陥落した故郷を眺め、黒々と輪郭を浮かび上がらせる龍を睨む。災禍の龍――名に違わぬ悪鬼羅刹め……。
「おい聞いたか! ウツロ! アーミラ! この地より撤退し、スペルアベルで龍を迎え討つ!!」
❖
「あなたのせいです……」
這々の体で撤退する継承者の娘達と鎧。
煤けた頬を袖で擦り、アーミラはまるで仇を見るような視線でウツロを睨み、そう言った。
「誰も傷つけたくないなんて綺麗事言って躊躇うから、被害が広がってるじゃないですか……」
「やめろアーミラ」
諌めるガントールの声を聞こえないふりをして続ける。
「……答えてくださいよ、ウツロさん。
先代の次女が行使したのは、神器天球儀を投下する広域爆発の術式ですか?」
その言葉にウツロは足が止まる。首がもしあったなら、据えられた目がアーミラを見つめていただろう。アーミラは振り返って続ける。ガントールとオロルは疲れた顔で二人を待つ。仲裁する気力もなかった。
「『どうしてわかった』って感じですか? 私とオロルさんで手記を手掛かりに打開策を考えたんです。
思いつく限り一番威力のある攻撃方法はこれでした……先代も同じ答えを導き出していたみたいですね」
――絶対に使うな。
そう書き記したウツロの言葉をアーミラは読まずに歩き始める。
「この考えが先代と同じかどうかわかればいいです。もうあなたの言葉は届きません」
酷く気まずい関係の罅にかける声もなく、ガントールは先を行くアーミラに続き平原を目指した。ラーンマクの地を踏むときは崩れるなどと気ほども疑わなかった分厚く堅牢な防護壁の国境線も、今は無惨に毀たれた瓦礫の山となっている。
ラーンマクとスペルアベルの道半ば、ギルスティケー辺境伯の邸へ向かうアーミラ達の前に討伐隊の男達の遺体があった。彼らはニールセンの部下であり、未だ手付かずとして野晒しに放置されていた。赤黒く湿った遺体の損傷部に蛆が湧いているのを見て、これではあまりに可哀想であるとガントールは訴える。しかしこちらとて埋葬する暇はない。
「……褒められたやり方ではないけど」と、続けざまに提案した。「魔鉱石の調達がしたい」
前後の言葉に繋がりがなく、含みのある言い方にオロルは怪訝そうにして、一歩踏み込んで先を促す。
「死体漁りか? 状況を考えれば責められることでもないじゃろう」
「……ですが、貴重品の類は回収されていると思いますよ」と、控えめにアーミラは言う。
ガントールは首を振った。
「そうじゃない」俯いて翳る彼女の顔は葛藤に揺れていた。「彼らの遺体を、私の力で石にしようかなってさ……」
「そんなことができるのか?」
「うん、できると思う。全方位に圧縮する摩擦の熱量で骨を結晶化するんだ」
簡単に言うが、圧縮の工程でかける力は、長女継承者にしか実現できない。唯一無二の術式であり、言うなれば外流奥義である。
「このやり方が彼らの弔いになるかはわからない……でも野晒しに朽ちていくくらいなら、有効に、使ったほうが……いや、使うってわけじゃなくて、わかるだろう……?」
「それを龍に使えんのか」
「龍は大きすぎて、圧が分散されるんだ」
ガントールは詳しく説明することすら後ろめたいことのように歯切れ悪く訴える。この行いが決して褒められたものではないのだと、提案している本人が一番よくわかっているのだ。その葛藤が表情にもありありと表れていた。
今なら他の誰も見ていない。
この先も戦闘を続けるには魔鉱石は必需だ。
だが神に選ばれ民の希望である私達が、遺体を弄するのは……。
龍を打ち倒すためにも、アーミラはその案に乗りたかった。魔鉱石はいくらあっても足りず、喉から手が出るほどに欲しい。この場に倒れている骸が石に代わってくれるのなら仲間のみならず禍人もトガも全て変えてほしいと言うのが本音であるが、喉元に留まる言葉は声に出せずにいた。
「……やってくれ」
小さな鼻を捻るように脂を拭い、搾るように言ったのはオロルだった。
「理想論も現実論もなんとでも言える。全て抜きにして、わしは石が必要じゃ」
きっと討伐隊の魂も「まだ戦える」と言っている。その想いを石にして携えていこう。とか、
正義の番人である長女継承者が我が身可愛さに骸を利用するなど到底「美しくない」。とか、
賛成にせよ反対にせよ口先の論は幾らでも用意できた。それらの言葉を並べてガントールの背中を押すか、手を引くか、どちらもオロルにはできただろう。しかし、言葉巧みにガントールを操ろうとはしなかったのだ。
あくまで自分がそれを求めているのだと白状した。「わしのために、手を汚してくれ」と、頼んだのであった。
「……わかった。……ありがとう」
ウツロは遅れてついてきていたが、三人が足を止めて炎を囲む姿に気づき、何をしているのかと近づいた。
揺れる火影に朱色に照らされたそれぞれの昏い顔を認めて、次に囲っている炎を見る。
それは奇妙な火球だった。
宙に浮かび、内側に収斂する燃焼反応は音すらも火球の中心に吸い込まれ、焚べられた可燃物は体積を縮めながら丸く固められていった。継承者の娘達が何をしているのか、ウツロには見当もつかなかった。
事情を知らずに立ち尽くすウツロに対し、ガントールは落ち着きなく口を開き、聞かれてもいないのに討伐隊の遺体を魔鉱石に変えているのだと語り出した。
ウツロはただただ、災禍の龍と輩の火球とを、眺めていた。
火球は眺めている間に凄まじい速度で体積を減らし、やがて可燃物が尽きてふっと火が消えると、圧縮と炭化の果てに結晶となった遺骨が精製された。薄く黄色味のある八面体の魔鉱石……それをガントールは手に取って、おもむろに剣で砕くと平等に配った。互いに無言のまま差し出されたものを受け取り、ぐっと握りしめて額に当てると感謝に目を閉じる。汚れた頬が涙に洗われて、頬に筋が残る。
尊い犠牲のおかげで、私達は戦える――そう祈らずにはいられなかったのだ。
赦しを乞う祈りを終え、洟を啜って継承者は南を望む。
龍は腹に取り込んだものを消化しているらしく、直立のまま微動だにしていない。己がもたらした破滅によって、縦穴からは火と黒煙が吐き出されており、それが龍の足を焦がしているが、全くの無反応である。
「増援は、期待するだけ無駄か」オロルは邸のある方角をちらりと一瞥し、独り言つ。
「来たところで犠牲が増えるだけだよ。みんなには避難してもらった方がありがたいさ」と、ガントールが答える。
「では、ここでやるんですね」
アーミラは呼吸を整え、杖を構える。
魔鉱石が手に入り、体力的にも地理的にも、ここが災禍の龍討伐の最後の機会だ。互いに目配せに覚悟を問いかけ、強く頷く。
「では……」アーミラはすっと息を吸い、杖に向けてぽつりぽつりと言葉を口から生み出し紡いでゆく。
、流麗にはほど遠く、震える声が戸惑いを滲ませていた。初めはただの言葉の羅列にすぎなかったが、それらは止まることなく繋がり、やがて神秘的な美しさを帯び始める。
世界。
黄昏。
厄災――
アーミラの隣で耳をそばだて聴いていたオロルはこの時点で詠唱の骨子がみえていた。アーミラが試みている手法は三節三連からなる詠唱だ。この手法の強みは実行者と対象の関係と、用いる媒介を詠唱の中に織り交ぜて謳うことで物語が強固に形作られることにある。この場で奥義全体の構想を思い描き、術式を組み上げようとしているのだから堅実なやり方に頼るのは無理もない。もし自分がその立場であっても同じことをしただろうとオロルは思った。
――爪、突、振。
神の定めた測り言、
得物と獲物、鋒と牙の隔りのこと。
天球儀。
三女神引力の妹にして、時の姉。
星を象る此杖は、
須く万物の距離を掌る――
アーミラは詠唱による術式を組み上げることに集中している。乾坤一擲の奥義の発動へ向けて言葉を紡ぎ始めた以上中断はできない。練習も試作も研鑽もないたった一回きり、出たとこ勝負の大業であるため相当に時間を要するだろう。その間ガントールとオロルは龍を警戒しつつ可能な限り前線へ押し戻すために魔呪術を繰り出す。
――偃月。
命の気配がなくなった。
命の気配がなくなった。
それは静謐。
静謐とは音のあるなしではない。
距離か深さか虚無のこと。
我が名はアーミラ・ラルトカンテ・アウロラ。
女神の次女の姓を授かる継承者也。
宿痾の首と無辜の躰を持つ娘也。
神よ、謙虚なる娘の声に耳を傾けよ。
その右耳に捧ぐ娘の声に――
ガントールの操る斥力とオロルの放つ光線をものともせず、龍は梃子でも動かない。それどころか微かに身動ぎをして腹の音を響かせた。無貌は詠唱を聴き入るようにゆっくりと俯き斜に構える。
「お前じゃない」オロルは野次るように言う。これは詠唱の『耳を傾けよ』にかけての皮肉だった。
動揺しているアーミラには気にせず続けるように視線を送り、二人は注意を引きつけるために駆け出した。
――涙よ。汝の辿り着く恩寵よ。
血潮よ。汝の駆け巡る裂帛よ。
淋漓よ。汝の流れ滴る荒野よ。
我から溢れ注がれる全てはこの星を満たし、
海となり火山となり雲となるだろう。
我は杖を介し、星と一つに繋がっている――
柱時計を駆り龍の視線を奪うガントールとオロルは、スペルアベルとラーンマクの西側の境目に移動して、三度現れた龍の光輪めがけて攻撃する。それが逆鱗に触れたのか、龍は初めて明確に反応した。
遠目で見ていたアーミラは詠唱を組み立てるのとは別の意識で、ぞっと背筋が粟立ち嫌な汗が噴き出した。きっとその場にいたガントールも、オロルも、身が竦んだだろう。しかし翻して退避する間もなく、光が二人を囲った。
「閃光が空間を裂くように斜めに走り、次の瞬間にはすべてが消え去った。遅れて爆圧が吹き荒れた。
突然空いた穴に大気は寄せ集められ、風は波のように寄せては返しもて遊ぶ。アーミラは衝撃に身を揉まれて地面に転げながら、ぐっと身を丸めて震えた。体の痛みよりも心が張り裂けそうだった。
あまりにも呆気なく、二人を失った。
風が落ち着き、アーミラはそっと上体を起こして辺りを見回す。
龍のいる位置から方位を把握し、大体どのくらい吹き飛ばされたのかはすぐに見当がついた。ざわつく胸を手で抑え、二人がどうにか生き延びている望みを捨てきれず、荒野を隅々まで見渡す。先程まで二人がいた場所は、ぽっかりと虚無だけが広がっていた。
「……ぅあ――」
詠唱の途中なのに。
堪えようとしたのに、胸の奥から抗い難い悲しみが咳き上げて、嗚咽が漏れた。
一度途切れてしまえばこれまでの詠唱も全て水の泡だ。自分の周りに集まっていた魔力が霧散して離れていく。結んでいた言葉同士の連絡が失われて術式が崩壊していく。その虚しさも加わって悲しみに棹さし、滂沱の涙が溢れる。
こんなに頑張っているのに、全部奪わなくたっていいのに……。
「うあぁっ……! あぁ……っ――」
泣いている場合じゃないことはわかっていた。腹を満たし沈黙する龍の消化速度は明らかに加速している。次を逃せばまたすぐに龍は世界を齧り取り、最後には全てを貪り喰らうことだろう。……でも、体がいうことを聞いてくれない。
悲しみを振り切るために、アーミラは泣きながら杖を頭にぶつけた。何度も何度も。
痛みで奮い立とうとしているのだろうか。或いは深い悲しみと絶望に気が触れた故の行動かもしれない……血と涙と鼻水と唾液と汗と泥でぐちゃぐちゃの顔を杖に押し付け、狂った獣のように噛み締めた口から、ふしゅう、ふしゅう、と呼吸している。へたり込んだまま、もはや杖を持っているのか支えられているのか曖昧な姿勢で、もう一度詠唱を始めた。猛毒にも似た激烈な感情が胸中に渦巻き、混沌としたままに唇から吐き出され、彼女の紡ぐ言葉を補強した。
世界。
黄昏。
厄災。
爪、突、振。
神の定めた測り言、
得物と獲物、鋒と牙の隔りのこと。
天球儀。
三女神引力の妹にして、時の姉。
星を象る此杖は、
須く万物の距離を掌る。
偃月。
命の気配がなくなった。
命の気配がなくなった。
それは静謐。
静謐とは音の有無ではない。
距離か、深さか、虚無のこと――
災禍の龍は凄まじい速度で四度目の覚醒を迎えた。アーミラは怖気付き声を潜ませたが、詠唱はまだ止まっていない。途切れさせてなるものかと意気込んだが、この場から避難しなければ食われて終わりだ。
と、そこにウツロは現れる。頼りにしないと決別し、気にも留めずにここまできたが、ウツロはアーミラを見捨ててはいなかった。追い込まれてから助けを求めるのはあまりにも自分勝手がすぎるが、ウツロは何一つ見返りも求めずに龍へ剣を掲げた。
その剣はガントールの天秤だった。
――我が名はアーミラ・ラルトカンテ・アウロラ。
女神の次女の姓を授かる継承者也。
宿痾の首と無辜の躰を持つ娘也。
神よ、謙虚なる娘の声に耳を傾けよ。
その右耳に捧ぐ娘の声に。
涙よ。汝の辿り着く恩寵よ。
血潮よ。汝の駆け巡る裂帛よ。
淋漓よ。汝の流れ滴る荒野よ。
我から溢れ注がれる全てはこの星を満たし、
雲となり火山となり海となるだろう。
我は杖を介し、星と一つに繋がっている――
前に立つウツロを切り取るように視界が真っ白に焼かれ、アーミラは目を閉じ詠唱を止める。龍の光輪が放つ一咬みの中にいるのを悟り、死を覚悟した。しかし、痛みはやってこない。
左手に構えた斧槍と、右手に掲げた天秤剣。この剣こそ、今二人を護る盾となっていた。迸る光の濁流にアーミラは恐る恐る目を開き、ウツロが龍の顎を跳ね除けている。剣に宿る斥力が、光すら捻じ曲げていた。神器がまだ機能しているということは……。
「耐えろよアーミラ」
遠くからオロルの声が届く。思わず二人の名を呼びかけようとしたが、アーミラは堪えた。まだ詠唱は終わっていない。
「やられたと思うたか? 見縊るでない。わしは時を操るのじゃぞ」
光の中、オロルの気丈な声だけが届く。それが何よりの励ましとなって、アーミラを奮い立たせた。
実のところ、オロルとガントールはこのとき無事ではなかった。アーミラは知る由もないが、二人は時止めを用いてかろうじて回避に移っていたが致命の一撃を喰らい、体を齧り取られ、身動きができない状態だった。
ガントールは剣をウツロに託し、残る力でアーミラを護っていた……それが精一杯だった。
天秤を掲げ、剣の腹で龍の攻撃を受け止めているウツロは、奔流する魔呪術を一身に浴びていた。世界を齧り取る龍の牙は凄まじい熱量を持ち、たちまちに神器の緋緋色金さえも真っ赤に溶解し始める。青生生魂の鎧に灼熱の神器が浴びせられ、混じり合う。柔らかく溶けていくウツロに、不思議なことが起きていた。
鎧の体を維持しようとする魔力らしきものが働き、崩れた板金が穴を塞ぐように結び付き、混じり合った緋緋色金が首の穴に注がれて頭蓋を構成し始めた。爛れながら変化を遂げたウツロは、もはや鎧とは形容しがたい、皮膚を剥いだ筋繊維を剥き出しにした人のような姿となる。
排熱するように歯の並んだ口をぽっかりと開き、ウツロは熱い空気を天に向けて吐き出す。舌先には炎さえ吹き出ていた。そしてアーミラと目が合うとぽつりと呟いた。
「ああみら……」
アーミラは目を疑い、絶句した。
詠唱のために何も言わなかったのではない。何が起きているのか理解が追いつかなかったのだ。
一方、災禍の龍がアーミラを喰い損ね、光輪が無防備になる一瞬。金色の一人は狙いすまして手印を結ぶ。
「ここが痛いのじゃろう……?」
神器、柱時計から鋭く放たれた閃光が龍の口……つまり光輪を貫き砕いた。破鐘のような大仰な音が響いて、実体化していた光輪が脆く砕ける。
けたたましく鳴り響く音にアーミラは我に返り、なんとか詠唱を再開する。その声は動揺に震えていた。
――叢に蛇ありて。
慟哭に沈く憎悪の風は、
呱々の声もなく生まれ落ちた。
救われぬ御魂は澱を固めた醜貌で、
禍事のいっさいを引き連れ土地を蚕食する。
弓立。
磨かれた鏃は熱が冷めぬまま悪に突き刺さる。
肌を煇し、心臓を去り、
不浄の霊素は天の裁きに清められ、躰は星に還り給う。
延々と続く流転に終わりを告げる、滅却の光となりなむ――
砕けた天輪が萎縮するように輪を縮め、霧散せずに押し固めたような玉となった。魔呪術の気配はなく、むしろ自壊している様子があった。
そこから孵化するように、一人の女がまろびでる。
何者かとウツロは目を凝らし、ぴくりと指先が痙攣する。
玉から現れたのは、集落を襲った尾を持つ娘だった。
隣に立つアーミラは委細構わず詠唱を締めくくりに入る。
――星砕。
勇立つはうからやからの栄光のために。
携るは現世に落つ智慧の果実。
内に秘めたる蜜の全てを支払い、
災禍退く夜明けを齎せ――
「――天球儀よ、我が命令に従ぅえぁ……っ」
アーミラの詠唱が途切れた。不意に襟を掴まれて、ほとんど首を絞められる形となって声を発することもできない。
妨害したのはウツロだった。
「う……つ、ろ……さん……っ」
アーミラには、何故ウツロがこんなことをするのかわからない。いや、この場に誰がいようともわかるはずはなかった。
首を掴む手を振りほどき、咳き込むように息を整え、ウツロを見上げる。私が冷たく突き放したのが悪かったのだろうか。それとも神器を浴びて変化したことが原因だろうか。そもそも今のウツロは正気なのか。様々な疑問が浮かぶが、答えは出ない。
ただはっきりしているのは災禍の龍を討ち果たす最大の機会を逃したということだ。
「何してるんです!?」
アーミラはウツロを責め、しかし構っていられないと横に押しのけて急いで杖を構えた。ガントールとオロルが作り出した好機を逃すわけには行かない。幸い光輪が玉となり砕けてから、龍は沈黙している。詠唱を三度再開するが、ウツロは右掌から刃を生成して飛ばし、天球儀の神器を砕いた。
「――え……?」
アーミラは抱えていた杖が腕の中でばらばらと崩れていくのを呆然と見届け、本当に何をしているの? とでもいうようにウツロを見つめる。
その首に刃が奔り、彼女の前に立つウツロは返り血に赤く染まる。
景色が斜めに傾き、天地が転げる。
倒れたのは自分なのだとアーミラは自覚して、意識を失った。
■010――首失《くびうしない》の禍斬《まがつきり》
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
戦場に立つ者はいなかった。
龍と鎧を除いては。
ずっと空席だったウツロの首に据えられた日緋色金の頭蓋、その二つの眼窩の暗闇から災禍の龍を捉えていた。消失した光輪が再び宿る兆しを見せた龍へと、ウツロは手を伸ばした。
掌から生成され飛び出した幾本もの刃は、風に導かれるように龍の首を囲んで廻る。伸ばしていた手をぐっと握ると、刃が輪の中心へ向かって収斂し龍の首を千切り落とした。
その流儀はガントールのものだ。生成された刃も。
しかし、齧り取るような剣閃はウツロらしくない。災禍の龍を嘲笑うかのように屠ってみせた刃は勝利の舞踊を踊り、ウツロに付き従う。
無貌の頭蓋は大地に転がり、それを追いかけるように巨人は膝をつきゆっくりと倒れていく。巨大な質量が大地に叩きつけられる衝撃に一帯が轟き、当代継承者の終戦を告げる鐘となった。これを目で見た者、耳に聞いた戦士は前線にはいない。
ウツロは飛ばしていた刃の血を払い手中に収め、だらりと腕を垂らして天を仰ぐ。傍には二人の娘がいた。首を切られて倒れる次女継承者アーミラと、光輪を破壊した際に外殻の中から現れた意識のない少女――ニァルミドゥ――である。
一糸纏わぬ姿のまま地面に倒れ込むその娘に対して、ウツロは躙り寄りまじまじと顔を覗き込んでじっとしていた。……しばらくしてやおらに立ち上がると、意識のない娘の背中と膝に腕を差し入れ、壊れものを扱うようにそっと抱え上げ、南へ向かって歩き出した。
娘の臀から伸びる長い尾が、抱え込むウツロの腕から滑り落ちて地面に引き摺られている。オロルは加護により癒される体を放ったまま、目だけで二人の背を見届けていた。……追いかけて問い質したかったが、疲憊し、その余裕すらなかった。
「……何をするつもりじゃ、ウツロよ……」
オロルは届かない声を空に吐いた。
❖
意識を取り戻すと、俺の体は鎧になっていた。
……当時を端的に伝えるなら、そうとしか言えない。
あのときは自分の身に何が起きているのかなんて全くわからなかった。わかったところで納得できるものでもなかった。ただ次々と襲いかかる違和感が、呑み込む間もなく押し寄せてきたことだけは鮮明に覚えている。普通の人間が経験することのないであろう特異な出来事が我が身を襲ったのだ。
まず俺の視界に映るのは知らない部屋の光景である。
ここはどこだ? と目を瞬こうとした瞼の神経が途切れ、視界は常に眼前に張り付いた。眼球の運動も固定されている。
目が閉じられない! と顔を擦ろうと両手を持ち上げた筈が、右腕だけがぎしりと音を立てて視界に映る。
左手は……いやなんだこの手は……! 眼前の右掌を見つめ、俺はここで奇妙なものを着せられていると思った。金属製の囲いが関節毎に区切られ肌を隠している。鎧を着せられているのだと直感した。とはいえ、あまりに荒唐無稽過ぎて思考が追いつかない。
どこでこれを調達し、誰が何のために、俺に着せたのか……。
どういう目的の悪戯か、そういったことをする人物に思い当たる節がない。無差別的なものか、愉快犯か……ならば犯人の手がかりはきっとこの部屋だ。そう考えて首を回す。目が醒めたときから視界は壁に向けられていたから、仰向けに寝ていたわけではないというのが視覚から推察できる……というより、視覚からしか推察できなかった。
この体感覚の違和感を説明するのは些か難しいものがあるが、左腕と下半身がぴくりとも動かせないという事実からも理解してもらえると思う。感覚のほとんどが鈍く、麻痺しているようだ。
全身の皮膚感覚――痛みや温度を感じ取る神経や諸器官――がごっそり抜け落ちている。指を動かした際にかすかな板金同士の擦れる音を聴いたので、聴覚はある。視覚は言わずもがな。
部屋の匂いは感じ取れない……いや――俺はあることに気付き、ぞっとした。
――息をしていない……!
本来、呼吸は不随意的なものであるため特別意識を向けずとも繰り返し行われる自然なものであるが、息をしていないと気付き意図的に呼吸を制御しても、鼻が、肺が、口さえも、なんの反応もしない。まるで肋骨の内側に備わる筋肉や臓器が掻き出されてがらんどうになった気分だ。……実際胴鎧の内側はがらんどうだったのだが、今はまだその事実を知らない。
このあたりで俺の意識はほとんど正気ではなかった。自分の身に重大なことが起きている以上、なりふり構ってはいられない。
助けを求めるために声を上げようとしたが唇が麻酔をかけたように自由が効かず、篭手に覆われた右手でがしゃがしゃと顔を撫ぜれば硬い感触が返ってきた。強く触れあえば、鈍いながらも触覚が生きていることがわかった。
顔と指先、互いの触れ合う金属の硬質な肌触り。指でなぞる口元に唇は備わっておらず、何度探ってもつるつると凹凸のない面甲が覆われている。
――もしかして……、
強烈な違和感の正体を理解し始めていた。
俺は、この鎧の中に体ごと閉じ込められているのだと思っていたが、違うのではないか。
――俺は鎧になったのか……?
そんな出鱈目があるか。俺は右手で床を探り、不自由ながらも苦労して壁面に背を預けて座る形を整えた。部屋を見渡すために身を起こしたかったのだ。視界の下方では己の脚が金属に変わり果てて沈黙している。言葉通りの足枷だった。
部屋は蔵か納屋の様相でひどく散らかって薄暗かった。蜘蛛の巣こそ張られていないようだが、雑貨屋のように使途不明な物品が棚や机に溢れている。これだけ助けを求めているのに誰も来ないのだからてっきり室内は無人なのだと思っていたが、右側の暗がり、螺旋を描く階段の横に三人の人影を見つけたとき、俺は恐怖に身を震わせた。少なくとも内側に秘めた俺の体は震えていたはずだが、外側の鎧が身震いしていたかはわからない。
本能的な直感が働き、三人は助けに来たわけではないのだろうと理解したとき、俺は錯乱したのだと思う。口があればなんであれ叫んでいたはずだ。
これまでの自分はそれなりに艱難辛苦を乗り越えた自負があった。どんなときでも冷静さを失わず、それを密かな自慢にしていた。だというのに、この状況に対して自慢の冷静さは口ほどにもなく砕け散って、俺は激しい恐慌に陥っていた。魂に宿している属性さえ剥ぎ取られ、声がでないまま叫び、涙が流れないまま泣き、四肢が不自由なまま暴れた。
発狂だ。
そうでもしなければ俺は殺されると本気で思った。
三人のうちの一人が靴音を立ててずかずかと近付き、力任せに俺の右肩を抑えた。果たして暴れる男の腕力をこうもたやすく御する事ができるとはやはり恐ろしい……が、傍らに立つ子供が部屋に明かりを灯すと俺を抑えている人物が女性であることを知る。それどころではない。三人の人影が明るみに正体をさらすと、全員が女だと気付いた。悪戯の度を越しているが彼女等と面識はないように思う。
「……君は何者か」女に問われる。気怠げだが場の主導権を握るような、余裕のある声音だった。
本当なら答えるより先に聞きたいことが山ほどある。まずこの不可解な状況は誰が原因なのか、俺の命の保証はあるか、この体は治せるのか。ここはどこで、お前たちこそ誰なのか。言葉は出口を求めてせめぎ合うが、どれだけ内圧が高まろうとも口がなければ一言も、一字たりとも答えることは叶わない。
俺の憤懣を察したのか、あるいは単に口がないことに気付いたからか、女は俺の前を横切り頭巾を脱いだ。そのまま手に握った頭巾は小上がりに――恐らく寝台だろう――放り投げ、机の上に置かれた板を取って俺に寄越した。はじめは手渡されたものがなんなのかわからなかったが、外観から何か筆記のための道具なのだろうと察して床にそれを置いた。次いで女は先の尖った筆を差し出す。やはり文字を書かせるつもりだ。しかし、待てども紙は貰えなかった。どうやらこの板に直に線を引くことで文字を書けというのだろう。
試しに板の隅に筆で線を引くと、柔らかい蝋を彫って傷が作られる。彫り刻むことで字を書くようだ。
俺は返答を蝋板に刻んだ。四肢のうち満足に動くのは右腕だけということもあり、曲線の多いひらがなは蝋板には適しておらずカタカナで対応するしかなかった。
――俺ハ、慧。
ざわり。と、三人の娘の顔色が変わった。青褪めるような、事態が芳しくない気配が、狭い室内を満たした。
「これはなんと読む」女は蝋板の文字を指差す。
俺は指定された一字の横に振り仮名を添えた。
――慧。
ふむ。と銘銘に腕を組んだり腰に手を当てたりして左眄する。俺を尻目にこそこそと耳打ちの会話を始めた。
娘たちを眺めるしかできないので俺はしばし様子を伺った。その中でそれぞれの容姿を確認してもいた。
一番目を引くのは明らかに上背のある派手な女だ。どこで揃えたのかもわからない甲冑のような防具で身を覆い、毛量の多い頭髪は燃えるような赤色に染まっていて、癖毛のうねりも手伝って背中を覆っている。なにかの仮装としか思えないが、甲冑の重厚な質感や細かな戦傷も真に迫るものがある。なにより暴れる俺を容易くねじ伏せた腕力も人間離れしているし、それで言うならば顳顬から伸びている頭角も作り物とは思えない。あまりにも完成度が高く、状況も相まって映画の中にいる気分にさせた。少なくとも彼女には殺意や害意はなさそうだ。俺が五体満足ならばもっと違った出会いだったかもしれない――いや、五感があれば明確に嗅ぎとれただろう。彼女達の纏う血の臭いを……。
隣に立ち話し込んでいる三人のうちの一人、とびきり背の低い者の方は、子どものような外見とは裏腹に物腰は妙に老成ている。体躯が倍はある赤毛の女にも物怖じせず三人の会話は対等に見えることから、ああ見えて歳は近いのかもしれない。
褐色の肌は遠い国の生まれと見えるがどうだろうか。顔立ちは眉が濃く目鼻立ちがくっきりしているが、赤毛の女ような北方系の顔立ちに比べると鼻がやや低く顎の尖りがない。纏う衣装はこちらもなにかの仮装じみたもので、異国の神事や祭事に用いられそうな衣を纏っている。何より、部屋を照らす光源は彼女の周りを浮遊している。まさか人魂や超常現象とは思いたくないが、説明できない手品だ。
二人の間に立つ三人の娘の残る一人。部屋を我が物顔で扱うことからこの部屋の主だと思うのだが、彼女が一番人らしかった。獣人じみた赤毛と、歳のわからない褐色肌に挟まれている彼女は、耳が尖っていること以外は特別おかしな所はない。三人揃ってなにか仮装しているのは揺るがぬ事実だが、彼女は襯衣に襦袢と比較的なじみのあるおとなしい格好だった。
三人は方針が決まったのかそれぞれ会話をやめて俺を見下ろした。
襯衣の女が言う。
「なんであれ君には働いてもらうよ」
……これが、俺と先代継承者の出会いだった。
❖
目覚めてから数日、俺の体は鎧になってから眠りを必要としなくなった。……この表現は正確ではない。眠れなくなったうえに目を閉じる機能も失われた。面鎧に瞼がないので視界は常に開かれたまま、眼球も失われているため乾くこともない。
疲労や睡魔などのあらゆる生理現象もこの身から剥奪され、感情の起伏は以前より緩慢なように思える。
俺が出会った三人の娘は、どうやら別の世界の人間らしい。……これも正確ではないな。信じがたいことだが、今いるこの世界はどうやら彼女達の世界らしい。並行世界だとか、異世界だとか、概念自体は聞き覚えがあるがこうして迷い込んでしまうことになるとは信じがたい。そして、それらの事情を教えてくれた娘達の名前も教えてもらった。
まず、娘達は『継承者』と呼ばれる特殊な地位に就いており、人のために働き、敵と戦うのだという。継承者は女神の三姉妹に準えて長女、次女、三女の姓をそれぞれ授かっているという。
長女継承者が長身赤毛の女、リブラ・スウェイル・ラーンマク。
次女継承者が襯衣の尖り耳、デレシス・ラルトカンテ・テティラクス。
三女継承者が背の低い褐色、クォトィス・アルクトィス・トゥールバッハ。
……それなりに状況を理解したとて未だ半信半疑で、何か悪い夢か冗談なのではないかという疑念が拭えないが、そうだとしたら俺の体が鎧になってしまったことの説明がつかない。眠ることもできず、満足に体を動かせない持て余した時間で散々頭を働かせたが、彼女達の言っていることを信じるしかなかった。
俺が目覚め、ずっと座ったまま安置されているこの物置小屋のような空間は、次女デレシスの私室らしい。曰く、『あの日、突然部屋から物音が聞こえ、様子を見に行ったら鎧が動き出していた』のだそうだ。
以降デレシスは時間を見つけては俺の体を調べ、動かない下肢と左腕を繋げようと忙しくしている。働かせるにはまず動ける体が必要で、実現までに一月ほどかかることになった。
体が動くようになるまでの間、継承者の彼女達は疲労困憊といった様子で、寝床として部屋で眠るデレシスだけでなく、ラーンマクとアルクトィスも顔を出すときは生傷が絶えなかった。彼女らの姿をみると、なるほど人手を求めているのはよく分かる。俺が手伝えるようになれば、力を貸すのもやぶさかではない気持ちにさせた。
……当時の俺はこの世界について全くわかっていなかった。継承者が『敵と戦っている』という言葉の意味をもっと深く考えることができたはずだった。鎧の体が動けるようになるまでの期間にいくらでも理解を深めることができたのではないかと後悔せずにはいられない。
しかし命を奪うというのは奇しくも性的な接触と類似している。未経験者と経験者の間には断絶の壁が存在すること。才能あるいは素質を必要とすること。公の場では経験者は秘匿する傾向にあること。故に未経験者への手掛かりは勝手な憶測と魅力的な側面ばかりを語る夢想しかないということ。
彼女らは普段の仕事について進んで語ることはせず、俺もまた架空の作品知識に基づいた妄想に耽っていた。
重ねていうが、愚かにも俺はこの世界について、かなり低い解像度でしか認識できていなかった。無知なだけじゃなく、『正義のために戦う娘達』と『世に蔓延る悪しき魔物』という表層だけの――それもかなり偏った――対立構造の理解で満足していた。漫画でも映画でも、あらゆる娯楽作品に登場する剣と魔法の世界。……その夢物語を現状に重ねていたのである。理解を深めることを怠った言い訳をさせてもらうとするなら、前提として元の世界に帰るつもりでいたために深入りしなかったという苦しい事情が一つ。そして、俺はずっと部屋の中に居て、デレシスも夜になればこの部屋に帰ってきているという実情が認識を甘くさせたのだ。まさかこの部屋が杖の中だなんて誰が予想できただろう。だから、継承者は日勤の仕事として毎日家から働きに出て、街に湧いた害獣を駆除し、夜には家に帰っているのだと無意識に思い込んでいた。危険を冒して戦うといえども所詮は野獣や低位の魔物の類いを相手にするのだろうと――そんな浅はかな夢想はしばらく後に砕かれることとなる。
左手が動かせるようになり、デレシスは鎧と魂――彼女は魂のことを度々「霊素」と言った――の定着方法の骨を掴んだようだった。魔導回路が構築された後は下肢も動かせるようになるまであっという間で、この部屋で一月ほど過ごして初めて五体満足、一揃いの姿を手に入れた。
この頃は聞き手の一方で、自発的に何か話したいという感情も薄れていた。口がないこと、また蝋板の蓄えをむやみに消費できないことが俺をいっそう無口にさせた。なので多少なりこの世界の事情は聞き及んでいるが、継承者側は俺のことについて、知らないことの方が多かった。……これも数ある後悔の一つだ。もっと言葉を尽くして俺のことを開示する必要があっただろうと悔やまれる。『俺は霊素ではなく魂だ』と、『別の世界から来た人間なのだ』と、根気強く伝えていれば結末は少しでも違っていたのかもしれない。
初めて部屋を出た時は、俺の喜びに反してデレシスの表情が翳っていたことを覚えている。彼女の私室から螺旋階段を上り、扉の取手を掴んで開くと、眼前に広がるのは夜天の書架だった。予想していない光景に俺は足を止める。
部屋にいたとき、室内は常に薄暗く、窓がないことから地下だということは推察していた。だから扉の向こうは地上階のはず……少なくとも屋根ぐらいはあるものだと思い込んでいた。それに、普通外へ出るとなれば陽の明るい日中だろう。なぜこんな夜に……。
「ここは驚異の部屋上階、天球儀の閉架」
後ろに付いて歩くデレシスが簡単に説明した。が、これだけではまだ理解できない。俺は続きを求めて彼女を見つめる。
「ここはまだ外じゃないってことだよ。……言っていなかったけれど、この空間も、地下の部屋も、私が持つ杖の内側にあるものなの。
今まで気付きもしなかっただろうけれど、外ではずっと旅をしていたの」
まさかと思った。
デレシスは目覚めれば外へ出掛け、仕事が終われば部屋に帰ってきて机に向かうか眠るかの繰り返し、だからあの地下の部屋は定住地だと思い、疑いもしなかった。
意図的に隠していたのだ……目の前にいる彼女が消極的に俺を騙していたことを密かに悟った。
夜天に佇む扉の裏側に回り込み、デレシスは外への扉を開けた。同じ扉の表と裏で繋がる出口が異なるとはどういう理屈なのだろう。とにかく、気を取り直して光の中へ進んだ。
降りた先はムーンケイという国なのだそうだ。外は明るく、日が昇っていた。
切り立つ岩盤の先は広大な平野が地平線まで広がっていて、見渡す限り都市の風景は見つけられない。崖下は下層と呼ばれており、同じ国なのだそうだが、戦線が張られているため環境は全く異なるという。
振り返って後ろを望めば見上げるほどの山脈が空に伸びていた。頂は雲に頭を突っ込んで隠れているが、晴れていれば神殿が望めると教えてくれた。ムーンケイは、そんなマハルドヮグ山嶺の中腹にある卓状地周辺に築かれた国家なのだと知る。
俺は今しがた出てきた扉を探すが、デレシスの言っていた通り定住の家はそこにはなく、一本の杖が楔のように地面に突き立てられているだけである。
これが次女継承者の神器、天球儀の杖。
「やっと使えるようになったんだな」
と、声の方へ振り向けばラーンマクとアルクトィスが合流してきていた。デレシスが答える。
「ええ。きっと前衛の役に立つと思いますよ」
「なら早速貰って行くぞ」ラーンマクは言いながらこちらに迫るが、デレシスが慌てて前に立つ。
「おっとっと、早速は急過ぎます。事情から慣らしていかないと――」
「構うかよ。どうせ死なない魔導具だ、実戦で慣らせばいいだろう」
ラーンマクは豪気の笑みを浮かべてデレシスの制止を押し退け、俺の首根っこを掴んで崖から飛び降りた。
心の準備もできぬまま下層の戦線に躍り出ることとなった俺は、無様に戦場に転がり、上体を起こすとラーンマクが立ちはだかった。腰に右手を添えて、左手で戦場を指差す。そこには野蛮な世界が待ち受けていた。
「命令だ『殺せ』」
そんなぞんざいな命令で本当に俺が従うと思っているのか……ラーンマク本人は揺るぎない眼差しだったが、一向に動かない俺をみて眉を下げる。
「おいデレシス! 動かないぞ壊れてる!」
崖上を見上げて声を張り上げる。
同じだけ張り上げるデレシスの返答が上層から降ってきた。
「だから言ったのに!」
❖
死んだ人間の姿を見るのは決して初めてではない。……だが慣れるようなものでもない。
下層に落ちた俺が目にしたのは地獄だった。
山裾から広がる平野の全域に渡って、ここにいるすべての生命が悪意をぶつけ合い命を奪い合っている。争うことが生きることと直結しているように、奪うことがなにより尊いことのように、命を燃やし、尽きるまで前進を続けぶつかり合う。俺が元の世界から持ち寄ってきた常識なんてとても通用しそうになかった。泥と血と灰に塗れ、狂った炎を囲い、互いに武器を振り回す醜悪な奇祭。それが、初めて目にした戦争の印象だった。
「おい」
腰が抜けたように座り込み呆けている俺の背中をラーンマクは蹴り飛ばす。
「お前もやるんだよ」
それは、まるで「息をしろ」と言うのと同じような調子だった。
ラーンマクは俺の体を小石のように蹴飛ばし、乱戦に渦巻く火中へと放り込んだ。
「なんでもいいから殺してみせろ!」
俺は敵味方もわからぬまま他人を下敷きにしてしまう。咄嗟に謝ろうと身を起こせばその者は薪割りのように振り下ろされた刃物によって首を叩き切られていた。俺が落ちてこなければこの人が死ぬことはなかったはずだ。目の前で行われた残虐行為に心が追いつかず、彼の死に少なからず関わってしまった罪悪感に狼狽える俺の後頭部を槌の横薙ぎが襲い視界に星が散る。普通なら頭蓋が陥没して死んでいただろうが、鎧の体では痛みはない。視界がぐらりと揺れただけだ。
いきなり誰かを殺せと命じられたとき、果たしてその指示に従う者はいるだろうか。その問いを投げかけられた者はきっと俺と同じことをするはずだ。
大いに躊躇い、一応は獲物を探す素振りをし、怖気付いて逃げ帰る……俺はラーンマクの方へ駆け出し、彼女の怒鳴り声も無視して崖を登ろうともがいた。はっきり分かった。ここは地獄だ。上へ逃げ延びるしか助かる道はない。
俺の面鎧に表情があれば、哀願の目をしていただろう。
なにが剣と魔法だ。
ただの殺しじゃないか。
敵と味方を見分けるには、そもそも敵が必要だ。俺に敵なんていない。
この世界の人間に殺意を向けるほど恨みを持ってはいないし、殺されるようなことをした覚えもない。
硬い岩盤の外壁は掴むところもなく、籠手の指では滑ってとっかかりもない。そうこうしているうちに俺の背中に何かが飛び乗り、荒い息遣いが聞こえる。
俺は恐怖に身を捩ってそれを引き剥がし、それの姿を見た。
これが初めて見た咎だった。
口吻は乾いた血で汚れ、牙の間には何かの肉片が挟まっている。
その黒目は異様に上を向き、まるで自我など存在しないかのように。
ただ、喉の奥から漏れる濁った唸り声だけが純粋な殺意を俺に向けていた。
「それが敵だ、殺せ」と、静観していたラーンマクが再び命令する。
トガは俺を敵と見做しているが、その敵意は一方通行だ。俺からしたらこいつと争う理由がなかった。だから迷わず逃げの一手を選んだ――その背中に再びトガが飛びかかる。
唸り声をあげ、首の板金に何度も歯を立てる。がりがりと牙が擦れる不快な音と感触に、視界は狼とも蜥蜴ともいえない形容し難い獣の姿が一心不乱に俺を責め立てる姿が映る。俺の何が憎いのか、たとえ声が出せたとしても狂った獣とは分かり合えないだろう。
「殺せ」ラーンマクは言う。「でなきゃお前が殺されるぞ」
当然のように放たれた言葉が俺の理性を追い立てた。
鎧の体になったとはいえ不死身という保証はない。自分の体でありながらどこが急所かもわからないのだ、このままやられ続ければどうなってしまうのかを想像してしまい、途端に俺は激しく抵抗した。
トガは俺を倒せるという確信をもって首の噛みついていたとしたら? 魂に関わる魔導回路を壊されたら……俺は死ぬのか……?
戦場に吹き荒れる憎悪の風に踊らされ、俺は反撃に出た。トガの顎に腕を食い込ませて轡にすると纏わり付く六本の脚を首から剥がして腹に拳を叩き込んだ。痛みに怯んだトガは前足をばたつかせて牙を抜くと、毛を逆立てて威嚇した。俺は足元に転がる誰かの骸の胸に刺さった槍を引き抜き、自分から踏み込み鋒を突き出した。
構えも何もなっちゃいない間抜けな一撃。だからこそか、狙いの読めない軌道にトガの回避は失敗した。横跳びしたトガの頬を掠め、首元の鎖骨に沿って皮膚を裂いた。肋骨を砕く手応え、内臓に刃が沈む手応えがはっきりと感じられた。握った柄を通してトガの心臓の脈動が伝わり、噴出した大量の血液をもろに浴びた。面鎧の目の穴に入りこみ、内側を熱い液体が滴るのが不快だった。
鎧の内側にいる俺は鮮血を浴びたことで獣の狂気が伝播し、気が触れたように叫んでいた。
その叫びは魂の悲鳴だった。しかしこの声は外界の誰にも届かない。
この日は二体のトガと一人の人間を殺してしまった。この一人の人間というのは、俺が蹴飛ばされた際に下敷きになった人だ。額に角の生えた、所謂禍人だという殺して構わない敵だと教えられたが、俺には折り合いがつかなかった。二体目のトガについては覚えていない。生き残るために必死だったのだ。
ラーンマクに呆れられ、跳躍一つで崖上に助け出されてから俺は杖の中に潜り込み、以前のように床にじっと座り込んだ。この世界の有り様が、あまりに傷つけるものが多すぎて参ってしまったのだ。
「すまないね。ラーンマクは人の話を聞かないからさ」
驚異の部屋にて。
夜にデレシスはそう言って隣に座った。手持ち無沙汰に組んだ指先をくるくると回している。
「君に事情を説明してから、少しずつ慣らしていくつもりだったんだが……まぁなんとかなってなによりだよ」
腹に据えかねる言葉に、怒りが込み上げるのを感じた。
俺は立ち上がり、机の上の蝋板を掴んだ。思いの丈を書き殴ってやりたかったが、乱暴に筆を走らせれば蝋が砕けて文字を成さなくなる。怒りを堪えて言葉を削った。そしてデレシスの顔前に突きつけた。
「えっと……『お前は聞くのか』……? あぁ、皮肉を言ったんだね」
デレシスは疲れた顔で笑う。
「白状すると、君を騙そうとしたんだ」
手遊びをやめて続けた。
「継承者は三人、内二人は後衛でね、私とアルクトィスのことなんだけど……。前衛のラーンマクは負担が集まるでしょう? そのうえ君も見たように、ここから先の戦場は果てしない平野が続く。領土を奪い取るにはせめてもう一人前衛が欲しい」
俺はまだ話の全体像が見えていないので、憮然と腕を組み先を促す。
「三女継承者の神器は一種の魔導具なんだけれど、どうやら戦闘に特化した便利なものでね、私達にも似たような物が作れないかと考えたんだ。
それでできたのが君なんだよ」
……ちょっと待て、それはおかしい。
俺はこの部屋で、突然鎧に宿ったと言っていたじゃないか。
「三人で神器を触媒に術式を組み立ててね、そう苦労はしなかった。
何度目かの実験で君が現れて……いやぁ、驚いたよ。私達は自我を持たない霊素を作り出した筈なのに、君は名前を持っていて、『別の世界から来た』と言うんだからさ」
これは彼女の、彼女たち女神継承者の、罪の告白だった。
ただし自らの行いを悪びれることなく、反省もしていない。
「なんであれ宿った命だ。呼び出すことはできても返す方法がない。だからこのままこの世界について知ってもらい、一緒に戦ってもらおうって思ってたんだよ」
……そうか。
初めから騙していたんだ。
部屋の外についてもそうだ。彼女は初めから俺を利用しようとしていたんだ。
俺は思わずデレシスの肩を掴んだ。少し驚いた顔をしていたが、それ以上の暴力を振るわないとわかると小さく微笑む。
「君は異世界からやってきた稀人なんだね。それも、暴力を良しとしない、随分と穏和な世界から来たと見える」
デレシスは憐れむように言い、俺の手を解く。
俺は蝋板に文字を刻み直した。
――帰してくれ。
「……それを言われると弱いよ。私達は霊素精製という禁忌を犯した。その結果、君を召喚することになったのは本当に偶然なんだ。なんで霊素ではなく異世界の門が開いたのか、未だに私にはわからない」
俺は縋りつき蝋板を押し付けて頼み込んだ。
――帰してくれ。
化け物であれ人であれ、俺に殺しは無理だ。
役立たずだってことは今日でわかっただろう。元いた世界に帰してくれよ。
デレシスは頭を掻き、わざとらしくため息を吐いた。
溜め込んでいた疲労や気苦労を吐き出すような、繕っていた笑みを脱ぎ去るようなため息だった。
ぼりぼりと頭をかきむしり、俯いていた顔を上げる頃には人相は冷ややかな別人格に変わっていた。
「何度も言うようだけど、私とアルクトィスが組み上げた術式は霊素の精製なんだ。もし君を帰すとするならその術式の反転……つまり霊素の消失を行うことになる。これをやれば、鎧に定着していた魂は剥がされ消える。奇跡が二度起きてくれれば、元いた世界に帰れるかもしれないけど……本当にやってほしい?」
ほぼ確実に死ぬけどね。デレシスは造作もなく言った。
この女が三人の中で比較的親身になってくれていると思っていたがそれは勘違いだった。
初めから俺を道具としてしか見ていないし、俺の悲しみに寄り添うつもりもない。俺の正体を知りながらも騙しながら利用する道を選んだのだから、あの三人の中で一番悪意を持っているとさえ言える。……ここは平気で殺し合う世界なのだ、俺の泣き言なんて甘ったれの我儘としか映らないのだろう。
「どうする?」
俺はこの世界で今死ぬか、戦って死ぬか、二つに一つだった。
「戦ってくれるかな?」
俺は不服ながらも諾とした。デレシスは「よかった」とだけ言い残し、寝台に横になるとそのまま眠りについた。
以降の俺は自我を放棄し、命令に従う戦闘魔導具に徹した。帰る手立てもなく、我儘を言える身分ではないことを知ったからだ。
もちろん精神的な摩耗はあった。一日の終わりに倒した者らの凄惨な姿が思い出され、その度吐きそうな気分になるが当然腹の中は空っぽだ。逃亡や反抗、時に退行障害も患ったが、鎧の体は精神を差し置いて常に万全だった。敵を殺した活躍を褒められた夜は、赦されたいがために彼女の胸に縋ったこともある。この逃げ道が俺をより従順にさせるための罠だと知っていながら……。
俺はこうして魂を明け渡し、戦争行為に手を染めて、泥濘む底なし沼に肩まで浸かっていた。どれだけの敵を殺しても、この汚れ仕事から足を洗う日は来なかった。
思わぬ機会が訪れたのは、この世界で三月ほど経ってからだった。
従順な戦闘魔導具として完成されつつあった俺を、デレシス以上に高く評価していた者がいた。ラーンマクだ。
共に前衛に立ち、時に背中を預け、平野の前線を押し上げてきた立役者として曲がりなりにも紐帯の絆が結ばれていたようで、仮拠点の防壁――後にスペルアベル平原となる――の下、三人が揃って夜を過ごしている席に招かれた。
ラーンマクは俺を隣に座らせ気安く肩に腕を回した。マハルドヮグ山の裾野から続く広大な平野を禍人から奪い取ったこの戦役での活躍はもちろん継承者の力無しにはあり得なかっただろう。しかし、「それを支えたのはお前だ」と、上機嫌に酒を呷る。
「初めはまるで使えんと思ったが、目覚ましい成長だな」
背中をばんばんと叩かれ、俺は首を振る。こうも気さくに距離を詰められることには慣れていないのでどうしたものか対応に悩む。珍しく酔っているようで、注いだ酒を一息に飲むと気炎を吐き、熱っぽい視線を向けて凭れ掛かった。略装の肌着で身を寄せて、板金の体に頬を当て、「冷たくて気持ちいい」と呟く。
「そんなことしても鎧は靡きませんよ」と、デレシスはちくりと咎める。
「わかってるよ」
ラーンマクは俺の胸から離れはしたが座り直して背中をこちらに預けた。挑発的にデレシスに向き合い頭の後ろで手を組んで寛いでみせる。
「難儀だぜ、身体があれば夜の火照りも発散できるのになぁ?」
言わんとしていることはなんとなく察せられたが、どうとも答えることはできない。
デレシスとアルクトィスは杯に口をつけたまま睨む。
「そこら辺に転がってる棒切れを鎧の股に貼り付けたら?」
「物足りないだろ」
「大体、鎧の種族は獣人種とは思えませんが」
「魔呪術の才がないんだから、獣寄りだろ。……あぁあ、なんで身体がないのかね」
ラーンマクの指先が面鎧の頬を叩いて弄ぶ。
かかか、かかか。
「奔放すぎるのではないですか」これはアルクトィス。
「今を生きてるだけだ」
「この前も戦士の誰かを宿に連れていましたよね。今を生きるのは結構ですが、見境なく遊んでいると己の首を締めることになりますよ」
「問題ないぜ。あいつは死んだ。私はこう見えて一途なんだ。男が死んでから次の相手を見つけるのが早いだけ」
わざとらしい仕草で己の身を抱きしめるラーンマクに、二人が揃って鼻で笑う。
「……でも、本当にそうだ。こいつが相手だったら首切られても死ぬことはないし、ずっとさみしい思いをしないだろ。一緒に戦ってくれるし、必ず生きて帰る。そういう信頼は私にとって大事なんだよ」
「何が一途か。
どうせこの前の男が死んだからさみしいってだけでしょう」
デレシスは気に留めずあしらい、ラーンマクも呵々と笑うが、俺には彼女の言葉が多少なり本心からの言葉なのではと思ってしまう。それは俺が馬鹿な男だからなのだろうか。
「その話に関連しているので、この際聞いてもいいですか?」
アルクトィスは両手に杯を持ち、燗にした酒の湯気を見つめて言う。何の話か、デレシスはやや身構えながらも促した。
「うん、何かな?」
「鎧は以前、『慧』と名乗りましたよね。結局私達は鎧と呼んでいますが、本来は名を持ち、躰を持っていたのではないかと思うんです。……そのあたりの折り合いはお二方の間でどうなっているのです?」
「おう、そうだったな。あのときはデレシスに任せるってことになったが結局どうなったんだか知らねぇや」ラーンマクも身を起こして膝を向ける。「いっそ躰も作ろうぜ。そんで私の相手になってくれれば願ったり叶ったりだ」
「はいはいしつこい」デレシスはこちらに視線を向けて思案顔をする。「……元の世界に帰せないから協力してもらってる」
「じゃあじゃあ、今も意識はあるってことですよね?」アルクトィスは不審そうに首を傾げた。「戦闘にも積極的になって、めっきり自我を見せなくなりましたが、単に納得してくれただけですか?」
「そうだよ」
デレシスは屈託もなく言うが、細めた目元から覗く黒目がこちらを向いていた。「下手な反論はするなよ」と、言外に伝えている。
「なら、鎧にも過去があるんですよね」
幼く生硬な印象を受けるが、この賢人アルクトィスは静かに核心を突いた。
「そうかもね」
「聞いてはいないんですか?」
デレシスはばつが悪そうに俺を横目に見ながら杯を口に運んだが、既に空っぽだった。彼女なりの動揺が窺える。
「面白そうじゃねえか」ラーンマクは片膝をついてデレシスの杯に酒を注ぎ、座り直すと肘で俺を突付いた。「聞かせろよ」
俺は思わずデレシスに許可を求めるような態度で様子をうかがった。もはや俺は彼女の奴隷、所有物だ。
「……いいよ」観念したようにデレシスは言い、席を外す。
「んあ、どこ行くんだよ? お前は聞かないのか?」
「喋れないんだから、書くものが必要でしょ」
天球儀の杖の中に入ったのを見届けて、アルクトィスは声を顰めてラーンマクに切り出す。
「……デレシスって、掴みどころがありませんよね」
「そうか?」ラーンマクは片眉を吊り上げて生返事をする。
「二面性というか、私達ずっと一緒だったのにどこか信用されてないような気がするんです」
「そりゃないだろ。難しいことはわかんねぇけど、なにも全部見せ合うのが信頼じゃないし、伝えるべきことと隠すべきことをあいつなりに切り分けてるんだろ」
ほろ酔いも手伝っていまいち求めた返答は返ってこなかった。ふしだらな割に陰口は好まぬ質らしい。
アルクトィスは納得できていないようで頬を膨らませて俺を見る。彼女の中で想定していた話の運びはきっと違う筋書きだったのだろう。抱いている疑念はとても共感できた。
尚も食い下がろうとしたアルクトィスは何か言いかけたが、杖から戻ってきたデレシスに気付いて言葉を呑み込んだ。
「はいよ」
デレシスは座りしなに俺に手頃な石を手渡した。魔力の尽きた魔鉱石だ。握って土を彫れば字が書けるということだろう。
思いの丈を語るまたとない機会だ。
言葉を待つ三人を前にして俺は地面を削り始める。
❖
――元の世界で俺が身を置いていた環境は確かに平和だったといえる。少なくとも生まれてからこの世界に迷い込むまで、暴力で物事を解決した経験はなかったように思う。
――だが、あらかじめ断っておきたいことがある。
――俺は確かに戦闘経験のない人間だったが、それは、俺のいた世界が平和であるとは意味しない。少なくとも別の国、別の時代では大なり小なり争いごとはあり、殺し合いは起きていた。そしてもう一つ確信していることがある。それは元いた世界の方が圧倒的に強い戦士と、兵器と、軍略を有しているということだ。
――どうか落ち着いてくれ。ラーンマク。ここで俺を脅しても事実は変わらない。俺がいた世界では、文明はある到達点に達していた。世界を破壊しうる力をそれぞれの国が手に入れていた程だ。世界を破壊しうる力……俺は学がないためその兵器を再現することも、理論を説明することもできないが、俺の国は過去の戦争によってそれが二度、落とされた歴史がある。
――前もって言わせてもらうが、俺の種族がそれだけ悪しき民族と見做されていた訳では無い。あくまでも過去の大戦の話だ。ほんの刹那、強烈な閃光が走り、見渡す限りの生物が塵となる力を想像してみてほしい。もしこの前線にその光が落とされたら夜は砕け、大気は震え、敵も味方も全て焼き払われることになる。きっと継承者でさえも、無事ではない。
――これ程までの力を国家が保有しながら、何故平和なのかを考えてみてほしい。
――例えばこの三人がそれぞれ国だとしよう。三つの国に一つずつ、敵国を消し去る力がある。そしてデレシスとアルクトィス。君たち二人が敵国同士だったとした場合、そうした状況のとき、果たして先手必勝だろうか? 敵を消し去った後に勝利があるだろうか……?
――そう、そこに勝利はない。故に戦争が起こらないのだ。
――戦争とは互いに自国の意思を強制する利益獲得の手段である。開戦するのであれば相手国の土地、あるいは文明、または国民を奪いたいという意図があり、損益計算が伴う。魔呪術が強すぎるあまり、国そのものを消し去ってしまっては戦争に勝利したとしても利益がない。だって土地も文明も民も手に入らないのだから。さらに最悪なのは、先手を打った戦勝国は第三国であるラーンマクから非人道的な行為だと弾劾され正義の名の下に裁かれるだろうことだ。先手を打った戦勝国は兵士ではない者の命まで奪い、価値のある物や保管すべき書物を消し去り、作物の見込める土地を徹底的に破壊したことになる。この傲慢な行いは決して許されることではない。或いは戦勝国に一定の信念があり裁きを免れたとしても、力を使い果たした国と余力のあるラーンマクが対等に付き合えるだろうか。いずれにしても戦勝国は利益を上げるどころか大損の結果となる。実質的な敗戦と言っても過言ではない。つまり強力な兵器を保有する国は、どれだけ仲が悪かろうと話し合いで解決するようになるのだ。武力でできることは牽制が精々で、結局最強の魔呪術は脅しのための飾りになる。これを『抑止力』という。
――興味深いという反応だが、俺が知り得る世界の構造はこの程度しか知り得ない。ここから先は話を俺個人に戻させてもらう。つまらないかもしれないがどうか聞いて欲しい。
――思えば、君たちが俺のことを知らないように、俺も君たちのことを知らないことだらけだ。君たちの親は存命なのだろうか?
――そうか、皆存命とは少し意外だな。
――同情を買うつもりはないが、俺は平和な世界でありながら両親とは死に別れている。戦争ではない別の理不尽な死を俺は知っている。『交通事故』というやつだった。
❖
「なぁ慧、自然崇拝って知ってるか? 海や山、天の星なんかを対象とする信仰のことなんだが」
稔が突然そんなことを言う。
深夜のコンビニエンスストアの駐車場にしゃがみ、カフェインの溶けた缶飲料を揺らしながら空を見上げていた。
彼は高校時代からの数少ない友人で、互いに悩みを打ち明けることができる深い仲だった。俺が高校卒業後、金銭的な理由などから進学を諦めた一方で彼が大学へ進学してからもこうした交友は続いていた。金がない者同士、こうしてたまに連絡を取って最寄りのコンビニエンスストアで駄弁る関係が続いていた。
「……やばいサークルに入ったなら、話は聞かんが」
「いやそうじゃないよ」稔は笑う。「宗教学の講義に出席する機会があってさ、今まで大した興味もなかったんだけど、講師のトーク力がなかなかどうして、聞いてるうちに面白く思えてさ」
聞き齧りの受け売りだけど、と稔は前置きして語り始める。
「もともと日本の宗教観は世界的に見ても独特なものだとは聞くだろう? 『信仰心は薄いのに礼節の意識は高い』だとか、『神を信じていないのに犯罪率が低い』だとか、あとは『あらゆるものに神が宿る、一神教ではなく多神……それも八百万に渡る』とか」
「まぁ有名だな」
俺は夜更かしの話題としてはやや眠たい話だと内心で冷めていた。程よいところで話題を変えるタイミングを探りながら耳を傾けている。
「この独特な宗教観はアミニズムと呼ばれるもので、本来それほど珍しいものではなかった。島国という地理的な要因が日本を独自に発展させていったんだ。
まず自然崇拝――アミニズムから。大昔の人々は自然災害に生殺与奪を握られていた。生粋の農耕民族であった日本人がどれだけ土地を耕しても、日照りや火山噴火、あるいは年間雨量の気まぐれによって簡単に何万人もの人が命を落とす飢饉に襲われてしまう。この理不尽に対して折り合いをつけるため、姿の見えない大いなる力に対し人々はまず名前をつけたんだ。いわゆる天照大御神、大山津見神、高龗神だったりするわけだな。……ちなみに『オカミ』は龍のことで、大昔には龍と神は同等のものだったんだと」
「ふぅん」
受け売りとは言うが稔はかなりの知識を身につけているようで、話術についても講師の技を盗んだか、思ったよりは退屈しなかった。
「ヨーロッパ北部のリトアニアや南部イタリアなんかも長い歴史の中では自然崇拝が主流だった。が、大陸であるが故に隣国からのキリスト教化の波に呑み込まれた歴史がある。……この教化の波が日本と海外の違いになる。つまり地理上の理由だ。
日本は周りを海に囲まれた島国だ。多くの大陸国が何らかの強力な民族によって土地に攻め込まれ教化や改宗を受けたが、日本はほぼほぼその難を逃れたと言ってもいい。少なくとも列強諸国からの血を流すような改宗の憂き目を見ることはなかった。シルクロードからの仏教伝来という友好的外交の影響が色濃いんだ。その後は自然崇拝から発展した神道との神仏習合によって八百万が複雑に混じり合い、明治に起きた廃仏毀釈によって仏教は追い出されて神道を国教とする運動が起きた。だけど深いところまで混ざり合った仏教はもはや数ある神の一つとして分離できないものとなり、今でも神社とお寺、どっちがどっちだかわからないくらいに神仏が混淆している」
「……ややこしいな」俺は耳で聞くだけでは理解できたか怪しい。
「簡単に言うと、日本は一度神と仏を混ぜ込んだとんでもなく懐の深い多神教文化を築いたってこと」
「なるほど」
「神話そのものも、他の国の文化を広く取り入れているんだ。古事記や日本書紀に描かれた物語は、実はエジプトや古代ヨーロッパ、中国なんかと類似性が指摘されてる。因幡の白兎は南北アメリカと中国から流れてきた話だったり、素戔嗚が暴れて天照大神が岩戸に隠れるエピソードはエジプトの神話と類似している。そんな風に他を受け入れる下地があるから、異教に篤い信仰を持つ人が教化や改宗を試みても、むしろその懐に包んで数ある神の一つに過ぎないと呑み込み返してしまうんだよ。一神教同士なら互いを受け入れられずに反発しあって争うところだが、日本人は平気で混淆させる。呑み込むだけじゃなく、外からの神を受け入れ馴染む。融合してしまうんだ。
日本人は信仰心がないと言いながら、神を最も身近な存在として扱っている。ハロウィンやクリスマス、さらにはヨガや初詣なんかが最たる例だ。だからタブーとされるようなアレンジや擬人化もできてしまうし、法律と宗教を分けて考え、信仰がないときっぱり言い切ってしまえる。そのくせ冠婚葬祭や食事のマナーの中にさえ信仰が溶け込んでいる」
「米一粒に七人の神様か」
俺は茶化し気味に言ったが、稔は真面目に頷いた。お前の懐の深さも神仏混淆かと内心で思う。
「その上、現代でも自然災害の発生、特に地震発生件数は世界でトップレベルだから、自然崇拝のあり方は畏怖の念が強く、神が罪を赦してくれるなんて考えない。あくまで禍福は糾える縄の如し、親しみつつも一定の距離を保っている。すごく独特だ。
どうだい? 面白くないか?」
興奮して語る稔には悪いが後半の知識には付いていけなかったのでそこまでの共感はできていない。素直にそう伝えるのも尺なのではぐらかすことにした。
「怪しい新興宗教には嵌るなよ」
「そんな話じゃないってば」
二人で笑い、夜は更けていく。
最後の一口を飲み干してカフェインが切れた頃合い、軽くなった缶を手元で持て余しながら二人は重い腰を上げて明日に備える。
「明日の予定は?」稔が聞く。
「仕事だよ。土曜日なのにな」
その返答に驚いた顔をして舌を出す。社会人はくそだと言いたげだった。
「夕方は?」
「病院に見舞いだ」
「そうか」
俺に予定がなければ明日も会うつもりだったのだろうことは察せられた。
「稔は当然休みか」
「まぁな。出席が足りてれば後はほとんど遊んでる」
羨ましい返答に俺が舌を出して戯けて見せた。大学生はくそだ。
「じゃあまたな」
「おう、また」
ふざけあってひとしきり笑うと、ゴミ箱に空き缶を放り、それぞれの帰路に着く。このコンビニエンスストアが両者の家を結ぶ別れ際なのだ。携帯端末を起動すると日付は変わっていて時刻は午前二時と表示される。さっさと寝床に着けば仕事に支障はない。
❖
あくる朝は平凡な一日だった。変わらない業務内容にいつも通り取り組み、いつも通り疲弊し、いつもとは違い残業を断り病院へ向かう。
職場の人間にすれ違いざまに挨拶を済ませて端末に退勤の打刻を済ませると、俺がロッカー室にいることに気付いていない者の会話が聞こえてきた。
「そういえば課長、井上君はどうです?」
「どうって? 頑張ってくれているが」
「そうなんですね……いや、彼って働く必要がないなんて聞きまして」
――は……?
そんな俺の心の声は、扉の向こうの課長の声でもあった。
胸の奥がざらつくような感覚があった。
「彼の家族が交通事故の被害者で、多額の保険金が降りたんでしょう? 本来なら進学もできたでしょうに就職って、降って湧いた金を貯め込むつもりでしょう? 真面目に働けるんですかね」
「滅多なことを言うもんじゃないよ――」
庇ってくれる課長の後ろで、俺はロッカー室を出た。
二人は気まずそうに愛想笑いを浮かべ、課長は改めてお疲れ様と挨拶をした。
先程までの陰口にはまるで気付いていないという態度で俺も会釈を返す。
笑って流すべきだと頭で考えながら、荷物を抱える拳は爪を食い込ませていた。
「お先に失礼します」
足早に会社を出る俺の後ろでは課長が不用意な発言に注意をしていた。俺に対してのアピールもあるのだろう、声はこちらまで聞こえていた。
「いいか、彼の妹さんはまだ退院できてない。お金がかかるんだよ――」
会社から自転車で駅まで移動し、電車で二駅。そこから市営のバスに乗り病院へ向かう。風防室を経由してガラス張りの自動ドアが開き、病院内に入ると消毒液の匂う受付フロアに着く。慣れた足取りで窓口横の端末にカードを挿す。端末のウィンドウは俺の基本情報を読み込み、必要な操作は本日の来院目的の選択欄から見舞いを選ぶだけである。
控えめな選択音と共にウィンドウ画面が切り替わる。
『井上芹奈 212』
下の印字機から感熱紙が吐き出され、来院受付が完了したことを示す紙が印刷される。指で切り取って階段へ向かった。エスカレーターもあるが、人とすれ違うのが億劫で人気のない階段ばかり使っている。
二階に辿り着き、清掃の行き届いた廊下を歩き目的の病室の前に立つ。病室の番号には4や9といった数字は欠番となっていて、その違和感を誤魔化すためか部屋は連番になっていない。212は本来もっと奥のはずだが、意図的なシャッフルによって階段からは近い位置にあった。
一応表札の部屋番号と名前を確認するが、一度も間違えたことはない。
軽く扉を叩き、スライド式の扉を開ける。西日に赤く照り映えた室内で黄昏る妹の姿があった。
「電気ついてないのか、暗くないか?」
扉の横に備え付けられたスイッチに触れてベッドの上の間接照明を操作する。室内灯は院内で自動切替だが、個人用の採光のためにこうした設備が取り付けられていた。もちろん操作盤はベッド側にもあるが芹那は操作していない。
「暗かった? ずっといると目が慣れちゃって」
そっと小さく微笑む妹。まるで顔の皮膚がひび割れないように慎重に表情を作っているみたいだった。
「体の具合はどう?」
「いつも通りかな」
「そか」
会話が弾まないのはいつものことだった。病室に備えつけてあるモニターの電源を入れ、俺は夕方のニュースを流す。話題になりそうな情報を見つけては、「あれ美味そうだな」と言ってみたり、「また地震増えてきたな」と呟いたりして妹の様子を窺う。
そんなとき、病室の扉が開いて白衣の男が俺と目配せした。
「慧さん。少しお話が……」
同階、診察室に案内され、俺と男が椅子に腰掛けた。
男は妹を担当している主治医だ。おそらく見舞いに来たという情報が窓口の端末から通知され、俺を探したんだろう。
歳は四十がらみで染めていない七三分けの黒髪にぽつりぽつりと白い毛が光っている。人受けの良い笑みを作り、こちらの緊張をほぐすため振る舞いは朗らかだ。
「いつも遠くから来てくれて偉いね、バスで来てるんだっけ?」
「そうですね、電車とバスの乗り継ぎで」
「ああそう、大変でしょう」
最初は軽い世間話を挟み、俺も愛想笑いで受け答えをする。
「それでまぁね、芹那さんの経過報告なんだけども……」
彼は蔓の細い眼鏡を掛け直し、手元のカルテを読み上げた。
妹は、交通事故で両親を無くしてから全身に麻痺の症状が現れる原因不明の運動障害に罹っていた。慢性的なものではなく、万全なときには運動機能に問題ないときもあるのだが食事中に突然箸を落として掴めなくなったり、廊下を歩いている時に躓く物もないのに不意に倒れたりと、その時々によって不全麻痺から完全麻痺と程度に差があり、日常生活が困難なレベルだった。初めは事故による末梢神経へのダメージが残っているのではないかとあれこれ調べたが原因の解明には至っていない。脳もスキャンを行ったが病魔の影は見つからなかった。
今回の話で主治医が言うには、事故の後遺障害というよりも精神的な原因があるのではないかと言いたいようだ。
「芹那さんはきっと、意識を取り戻してから立て続けに辛い現実に直面しなくちゃならなかったでしょう? 剣道部の大会の後に両親と出掛ける予定があって、みんなでこれから食事ってところに横からね……酷い目に遭って、気がついたら病室なんだもの」
「そうですね」
「なので、今後の方針は、メンタルケアね。精神的な傷を癒す方向で、回復に持っていけないかと考えてる。どうかな?」
「妹がよくなるならなんでもいいです」
「そうだけどね、そうなんだけれども。君もいろいろ大変だと思うけど、あんまり無理しないように。ね?」
……曖昧に笑い、俺は妹の病室に戻る。
「なんの話ししてたの?」と、妹。それなりに気になってはいるようだ。
「治療のアプローチを変えるんだと」
俺の目線は興味もないのにニュース画面に向けられている。政治家の不祥事を批判している映像だった。
妹は不安そうに問いかける。
「今のリハビリじゃ、治らないってこと?」
「うぅん……芹那の体は、調子のいい日はリハビリなんて要らないくらい動くだろ。なら麻痺の原因は運動神経の異常じゃなくて別のところにあるんじゃないかって、それを調べるためにやり方を変えたいって言ってきた」
「そうなんだ……」妹はニュース番組をぼんやりと眺めて呟く。「ごめんね、お兄ちゃん」
「いやいや、謝ることじゃないさ、気にするなって……」
「私、やっぱりどこかおかしくなっちゃったんだ……もう、元に戻らないかもしれない」
「そんなことないって、やり方を変えたら、気分転換にもなる。あんまり塞ぎ込むと余計に悪くなるぞ……そうだ、今度外出してさ、近くの店で飯でも――」
「やめて!」
妹は声を荒げてしまったことに自分でも驚いていた。
不用意な発言だったと俺が思い至ったときには妹は申し訳無さそうに俯いてしまう。
「ごめ、……なさい……」
食事の約束は、妹にとってトラウマなのだ。
無理もない。両親はこの約束を果たそうとして死んだのだから。
主治医の言っていることもわかる気がする。病は気から……芹那の内にある心の傷を治してこそ、身体の麻痺と向き合えるのだろう。
「悪かった。……本当にごめんな。また、来るから。今日は帰るよ」
「……きっとだよ」妹はそう言って手を振る。
扉を締め、静かにため息を吐き出す。何だか階段を使って降りる気分ではない。俺は長い廊下を歩き、エレベーター乗り場へ向かう。
ボタンを押し、狭い箱に乗り込み、緩やかな浮遊感に包まれる数秒間。
精神的なもの――目に見えない病の原因を思い描こうとしたが、どうやって治すのか、俺には到底わからなかった。
扉が開き、一階に到着すると、俺は病院を後にして帰路につく。
また来週見舞いに行こうと心に決めて――しかしその日は来なかった。
❖
週が明けて水曜日。いつも通りの朝とはいかなかった。
ベッド脇に充電状態で置かれていた携帯端末が、設定した目覚ましアラームとは異なる警告音を鳴らした。
そのあまりにけたたましい音に俺は夢も忘れて飛び起き、画面表示を睨む。
『緊急地震速報受信 強い揺れに警戒してください』
黒地に黄色い文字で書かれた言葉を読む間に地鳴りが遠くから迫るのがわかった。下から突き上げる衝撃に建物全体がうねり、軋みを上げてぐらぐらと揺れる。額に嫌な汗をかいてベッドの上でじっと収まるのを待っていた。
――これは震度五、弱かな。
国民性か、揺れの強弱を言い当てる感覚が俺にも備わっている。端末の続報ではこの地域は震度四強と表示されていた。そして画面には『津波、余震に警戒』と続いている。
早朝に迷惑な野郎だ。と、俺はベッドに横たわり次の波が来るのを神経を尖らせて待っていたが、そのうちに二度寝してしまった。
目覚ましに起こされる頃には地震のことなどすっかり忘れていて、普段通り出社の打刻を済ませて日常業務が始まる。始業に備え機械を立ち上げていたとき、不意に地面が跳ね上がった。ほとんど同時に地震警報が鳴り、恐怖が伝播するように職場内の人間の携帯端末が合唱を始めた。
呆気に取られた各々がどうするべきかと戸惑っているうちに本震が襲いかかり社屋の窓ガラスが砕ける。警報とは比にならない激しい地鳴りと悲鳴で満たされ、「外に避難!」と「机の下に!」の混乱した指示があちこちから飛び交う。きっと震度六だ――俺は無我夢中で外に出る事を選んだ。
会社の駐車場にはすでに何人かの人間が避難していた。皆不安そうに誰かに向けて連絡を飛ばしたり話し合ったりしている。そこに課長の姿もあった。
俺も課長も内心取り乱していたのだろう、判断能力が正常ではなかった。うねる足元によろめきながら駆け寄り、「妹が心配なので早退をいただきたい」という旨を伝えた。俺の家庭事情を知っているせいか、先日の陰口の後ろめたさを払拭したい心理か、課長は「行ってあげなさい」と二つ返事で見送った。
俺は私服を鞄に詰めて着替える時間も惜しんで会社を出ると自転車に跨り、ペダルを踏み込んだ。
普段と同じ道を進もうとしたが、駅に向かっても電車が運行しているかわからないことに気付き、調べるためにポケットから端末を取り出す。
画面には『緊急速報 津波警報発令中』と通知が届いていた。
俺の住んでいる地域は内陸部だが、病院は海沿いの街だ。付近に港や河口もある。もし津波がやってくるのなら沿岸だけでなく河川汽水域を遡行しての冠水被害はあるかもしれない。例え津波被害がなくとも、妹は麻痺症状が現れたら自力では何もできないのだ。
通知を横に払って駅の運行情報を調べた。今のところ運転見合わせの情報は出ていない。俺はこのまま駅へ向かった。
立ち漕ぎで街を移動していると、明らかに人気が多いことに気付く。車通りも混雑していてみんな外に避難していることからこの地震の大きさは並ではなかったのだと確信する。駅前通りに差し掛かると赤色灯が回っていて、人だかりの向こうで民家が倒壊しているのが見えた。
今すぐにでも妹に連絡したかったが、回線が混んでいて繋がりそうにない。
駅の駐輪場に辿り着いた俺は自転車を置いて改札へ続く階段に足をかけたとき、ほとんど爆発音に近い未曾有の地響きが一帯を襲った。まるで足元から人知を超える巨大な生物が目覚め身動ぎをしたかのようだ。最早この地球そのものが怒り荒ぶっているようにさえ感じられた。
俺は総毛立って身体中の全細胞が危険を感じ、踵を返して階段から離れた。予感は正しく階段の屋根は崩れて、巻き上がった砂煙が治まる頃には瓦礫の山に変わり果てた。
三度目の本震だと……!? いや違う、今までの全てが余震だったのだ。あの恐ろしい体感震度六でさえ、今大地を揺るがしている地震と比べれば足元にも及ばない。
駅の改札口は壁面に飾られたタイルが鱗のように剥がれ、通用口は、のたうつ蛇のようにぐねぐねと捩れている。アスファルトを敷いた地面の舗装もひび割れて陥没し、揺さぶられる力に抗えず、誰もがその場に倒れ込んで動けなくなっていた。
「なんだよこれ……」
誰に言うでもなく、俺は声が漏れた。
こんな状況じゃ電車が動くわけがない。駅前のロータリーも混乱していて、信号を見れば停電して指示が灯っていなかった。これじゃバスもタクシーも使えない……。
揺れが落ち着くのを待ってから、俺は来た道を引き返し自転車に跨る。こうなってしまえば自力が一番の頼りになる。
仕事着を脱いで半袖一枚になると上着を鞄に詰め、噴き出す汗も構わず病院へ急いだ。
隣接市に移動した頃には街の被害がいかに甚大かを見ることができた。ここまで来ると家屋の倒壊した光景を見つけるのも珍しくなくなり、根本から折れた電力柱が住宅の屋根に倒れ、停電に断水と、住民が困り果てて立ち尽くしている。
見晴らしの良い大通りの交差点で街全体の様子が窺えた。建物は軒並み崩れ、巨大なショッピングモールさえもガラスの破片が散乱して立ち入り禁止の三角コーンとテープで囲われていた。駐車場では車内に避難している人でごった返し、隣接しているガソリンスタンドは夥しい車の渋滞ができていた。皆苛だち眉間に皺を寄せている。
病院へはあと少しだが、道路が地割れを起こしているためもはや自転車すら荷物になっていた。金目のものは入っていないので鞄ごとショッピングモールの駐輪場に置いて、ここからは徒歩、自分の脚で走った。
ポケットの中の携帯端末がずっと震えているが、会社からの電話だったので無視している。――早退の許可は貰っているので、心苦しいが抜け出した責任は課長に被させてもらう。向こうが諦めるまで待ってから、ダメ元で妹に通話を試みた。走りながら応答があるまで粘ったが、接続が中断された。やはり出ない。
頭の中は不安で一杯だった。妹は無事だろうか。
麻痺で動けないのか、すでに避難中なのか、単に通話回線がパンクしているのか、病院の耐震強度はどのくらいだったか。津波は届くのか……。
上空では深緑色した自衛隊のヘリコプターが旋回している。色違いの青い一機が俺を追い越して行った。ドクターヘリだ。
もしかしたら妹があれに乗るかもしれないと想像し、思い浮かべたその姿は他の患者と入れ替わる。きっと病院にはたくさんの患者がいる。不全麻痺の妹は他の患者と比べてどの程度避難を優先してもらえるだろう? 完全麻痺なら……? 今日がたまたま調子のいい日だったら自分の足で避難するのだろうか。もし急に麻痺症状が現れたらどうなる。
「ドクターヘリを追うように、病院まであと1キロという地点まで来た。この道はバスで何度も通った。変わり果てた直線を俺は息を切らして歩いている。
側溝からは奇妙な風が吹いていた。下から上に吹き上げる生温い風だった。それに排水の臭気が充満していることに気付く。……水が、逆流している。
遠くから拡声器が避難指示を繰り返し呼びかけているのが聴こえる。もはや、ここに津波が迫っているのは確実だった。
六階建ての病院の屋上では先程のドクターヘリが空中で救助担架を吊り上げていた。誰を乗せた担架か目を凝らすが、頭髪が白い……白髪の老人だと分かった。
「なんでだよ……っ」
焦燥に憤り、俺は走る。どう考えても妹が先だろう。それとも既にヘリに乗せたのか。
病院敷地内駐車場から真っ直ぐに入り口へ向かう。避難を急ぐ車が何台も俺の横を通り過ぎた。津波の到達はまだ猶予があるが、側溝からは汚水が溢れて靴底が泥に浸っている。靴下が湿って不快だが、かまわず先を急ぐ。
自動ドアは機能していなかったがガラスが割れて破片も取り除かれていたため侵入は容易だった。おそらく俺と同じように患者の親族がここに来て避難活動をしたのだろう。
窓口受付は真っ暗で、院内は予備電源によって薄暗くも最低限の照明は灯されていた。一階は既に無人。
俺は水嵩を増していく地面から逃れるように階段を上る。踊り場で折り返しざまに下の様子をみると茶色く濁った水が泡立ち、スリッパや紙の書類に、どこから攫ってきたのかわからないゴミが浮かんでいる。もう外へ避難はできそうにない。
二階に着くと212の病室を確認する。流石にここからは避難できたようで妹の姿はなかった。しかし安堵するにはまだ早い。このまま階段で屋上へ向かった。一階では設備が波に押し流される音が聞こえていた。窓がないため外の様子は見えないが、津波が到達したことは外の轟音と叫び声で分かった。
騒がしい階下、津波到達の衝撃に揺れる階段。迫る濁流の気配……。
六階を通り過ぎて屋上へ続く階段を駆け上がると外へ続く非常扉が開放されていた。人集りはほとんどが白衣か病衣の薄い色合いで、少なからず私服のものもいた。俺のような仕事着は他にいない。今頃は鞄も自転車も津波の被害に巻き込まれてしまっただろう……着替えておくべきだったと少し後悔の念が湧いた。
「お兄ちゃん……!?」
横から妹の声が聞こえて反射的に首を向ける。不全麻痺症状が現れているようで、妹は車椅子に座っていた。後ろで看護師がハンドルを握っている。
「芹那……!」
顔を見て安心するが、すぐに怒りに塗りつぶされる。どうしてヘリに乗っていないのだ。
俺は車椅子を押している看護師に向かって八つ当たりのように責めた。
「なんでヘリに乗せないんだよ!」
ドクターヘリを指差して声を張り上げる。ヘリのローターブレードがホバリングしていて煩かった。
看護師も大声で答えた。
「あれはドクターヘリです!」
「分かってる!」
「医療機器と一緒に乗せる必要のある方を優先させてもらいます! 我々の避難はこの後、自衛隊のヘリを待つんです!!」
そんなルールがあったとは……まるで冷や水を浴びせられた気分で面食らい、何も言い返せない。
「あなた芹那さんのお兄さんですよね?」
看護師は続けて言う。理不尽なクレームにも慣れているのか、俺の怒りが下火になったのを見て芹那を車椅子ごと預けた。
「申し訳ありませんが私は他の方の様子を確認したいので、お任せしていいですか?」
返答を待たずに既に数歩は離れて人混みに割って入ってしまった。ドクターヘリは数人の患者と医療機器を乗せて病院を離れ、入れ替わりに空中で待機していた自衛隊のヘリが救助活動を開始する。
「もうすぐ助かるぞ」
希望が見えてきたと思った束の間、芹那の顔を見てぞっとする。妹は希う面持ちで目に涙を浮かべ俺を見上げていた。
「……だめかも……」
ヘリばかり見上げていて気付かなかったが、僅か数秒間で津波は嵩を増していた。景色から推察するにおよそ三階まで汚水に沈んでいる。濁りきった水面には家屋の屋根部分や軽自動車が浮かび、盗難防止のクラクションが助けを求めて虚しく鳴いていた。
見下ろす先の濁流にうつ伏せに浮かぶ人影を見つけて、俺は慌てて目を逸らした。今なら見間違いで済むと心の中で言い訳して、下を見ないように努めた。同じ物を見てしまった妹は目を離せないでいるので、半ば強引に車椅子を旋回させて引き剥がした。
「大丈夫、大丈夫だ。早く乗せてもらおう」
自衛隊のヘリがホバリング姿勢で安定すると、まず垂らしたロープから迷彩柄の隊員が降りてきた。まるで地獄に垂らされた一筋の蜘蛛の糸と、それに群がる亡者の群れだ。恥も外聞もなく病衣の患者が隊員に纏わりつき、我先に助けてくれと取り囲む。俺は意を決して叫んだ。
「妹は自力では動けません! どうかお願いします!!」
声が届いたか、隊員と目が合った。一瞬のような気もするし、数秒は妹のことを見ていたようにも思う。そして隊員は亡者を掻き分けて車椅子をしっかりと掴んだ。
「彼女から乗せる!」
力強い隊員の言葉に、俺は思わず泣きそうになる。妹は助かる……その確信に胸が震えた。
俺もヘリに乗るために隊員に付いて行こうとしたとき、背中を何者かに引かれて逸れてしまう。
亡者の群れの中で俺は体勢を崩し声も出せないまま倒れ込む。ロープにしっかりと固定された隊員に抱えられた妹はゆっくりと吊り上げられ、俺に向かって「お兄ちゃん!」と叫ぶ口元が見えた。
救助活動はとにかく迅速に行われていた。俺は妹と逸れ、隊員は目の前の人間を助けるので精一杯だ。乗り遅れてしまったが、流石に患者が優先だと自分を律した。
屋上にずしんと振動が伝わる。また地震が来たのかと身構えたが、これは地震ではなかった。病院の建物全体に波が押し寄せ、凭れるように瓦礫の山が絡んでいるせいで構造を支えきれず、崩れかかっているのだ。
――まずい……!
「倒れるぞ!!」
誰かの声と同時、屋上が大きくぐらついて傾いた。場は騒然として身の危険に息を呑む静寂が広がる。
相当な傾斜だった。もし妹がまだ車椅子に乗っていたらフェンスに叩きつけられていたかもしれない。
隊員は今吊り上げている患者を最後に救助を中断し、罵声を受けながら上空へ避難した。
絶望的な状況に俺は現実味がない。自分の力では解決できないことだけは明らかで、脳みそが縮みあがった気分だった。酷く気持ちが悪い。朝からずっと悪い夢でも見てるようだ。
稔の言葉を思い出す。
『大昔の人々は自然災害に生殺与奪を握られていた。生粋の農耕民族であった日本人がどれだけ土地を耕しても、日照りや火山噴火、あるいは年間雨量の気まぐれによって簡単に何万人もの人が命を落とす飢饉に襲われてしまう。この理不尽に対して折り合いをつけるため、姿の見えない大いなる力に対し人々はまず名前をつけたんだ。』
――かみさま。
足元では何かが崩れるような断裂音と振動が伝わり、屋上に取り残された者は死を覚悟した。おそらく階下の柱が構造を支えきれなくなったのだろう。現に不安定な足場は傾斜を増し、ついには残る一本の柱を起点に波に押されて横滑りに回転した。一階部分が限界を迎え、押しつぶされた二階構造がひしゃげながらかろうじて病院上階を支えている。しかしそれもいつまで持つか……。
院内用のスリッパを履いていた何人かが体勢を崩して斜面を転がり、転落防止のフェンスに受け止められた。頭を打ってぐったりと起き上がれそうにない老人や、病衣の割に逞しく坂を登ろうとする中年の姿に心配して声を掛けるものもいるが、駆け寄る者はいない。
俺も含め、全員が無力だった。
理不尽に喘ぎ、僅かな運に振り回されて、抗いようのない死を前にじっと身を強張らせている。
どうあれ結果は同じだった。次の刹那には二階部分から倒壊し、あっという間に濁流の中へ放り出された。生き残ったものがいたのかどうか、知る由もない。
俺は濁流に揉まれ、他人の無事を気にする余裕もなく瓦礫に足を絡め取られて身動きが出来なくなった。硬いものが骨を挟んで痛みが走る。
浮上することはできず、辛うじて肺に溜め込んだ息だけで絡まった箇所を探る。足首を瓦礫が噛んでびくともしないのが指の感覚でわかる。
――くそ! 畜生……!
一人孤独に自分の足を瓦礫から引っ張り出そうとしているのが滑稽で情けなく思える。必死になればなるほど馬鹿みたいだ。誰も俺を助けちゃくれない。
――ああ、こんなことばかりだ。
俺は水中で踠きながらそんなことを思った。
本当は知っていた。何故自分だけ交通事故に遭わなかったのか。
あの日、家族は三人で出掛けていたのだ。四人全員ではなく、俺を抜いた三人で。
父と母は俺を家族として数えていないのだ。
家庭内では特別邪険に扱われてはいないが、妹と比較して俺への愛情は明らかに薄かった。何事もなく成人してくれ、早く大人になって家を出てくれ、とにかく問題は起こさないでくれ、……まるで腫れ物を扱うように両親は接してきた。俺に向ける笑顔は愛情なんかじゃない。ただのご機嫌取りだった。
それほどまでに俺を遠ざけるのは何故か?
捨て子だったのだ。俺は。
両親の葬儀手続きと共に遺産と保険金に関わる様々な書類をかき集めていたとき、戸籍謄本を見て知った。父にとっても、また母にとっても俺は養子だった。祖母にどう言うことかと尋ねたら、俺は父方の叔母の捨て子だと聞かされた。
『あんたのお母さんは本当に最低な野郎でね……、毎晩夜遊びして知らん男の子供を孕って、金もないからって中絶しないで、挙句家の前にあんたを捨てたんだよ。その後はもう勘当したって聞いたけど、向こうも帰ってくる気なんかない駆け落ちだよ。もちろん別の男とね。最後は薬であっぱっぱになったよぅ』――
『本当なら二人の遺産も保険金も芹ちゃんの金だよ。お前が芹ちゃんの面倒をみるって言うから、あげるんだからね』――
――それなのに、死ぬなんて。
あぁ、神様……もしいるのなら俺はあんたが大嫌いだ……。
俺が何か悪いことしたか? 答えてくれよ。
でなきゃこの一生の意味はなんだ。
誰に求められて生まれてきたわけでもない俺が、
この人生をどうしたらよかったんだよ。
もう、いいさ。
この世界も、人も、自分自身も、
何もかもが嫌いだよ。
■011――眠る躰を引きずって
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
「死んだと思ったらこの世界で目が覚めたわけか」
俺の過去を読み終えたラーンマクは合点がいったらしく首を縦に揺らして一息ついた。酩酊に気炎を吐いているが、むしろ酔いがあるからこそ普段よりも真剣に目を通してくれていた。
「……こうして語ってもらった今でも、少し信じられないですね。異世界というだけあって文明や営み、襲われる脅威も全く違うんですから」アルクトィスもまた興味深いといった様子で、それ故に頭を抱えている。
デレシスは普段通りの澄まし顔だったが、多少なりこの世界に魂を引き摺り込んで都合を押し付けた罪悪感が湧いているのか、頤に指を添えて腕を組んでいる。俺を物のように支配する所有者然とした振る舞いは鳴りを潜めて、初めの頃のような裏のない少女らしい表情で地面の文字を見つめていた。
俺の座っている手元の土は、書いては消してを繰り返してすっかり耕されてしまっている。時折異世界の技術を伝えるために図説したりもしたのだ。地面には未だ向こうの世界を語るに必要ないくつかの絵が残っていた。デレシスはそれに視線を注ぎ俺がでっち上げの嘘を語っているのではないか訝しむ。
「……この話が本当だとして、君は元の世界に戻りたい?」
いつか俺が願ったことをデレシスから改めて借問される。
――戻る手段は無いんだろ?
「ないよ。でも、聞いた限りじゃ戻るほどの未練もそもそも無いような気がするけど」
返答に窮した。もし戻れるとしても、もう時間が経ち過ぎている。魂の帰るべき肉体がまだ向こうにあるのだろうか。とうに腐ってしまっているか、誰かに見つけられたなら何らかの形で処理されているだろう。そしてデレシスが指摘した通り、冷静に考えてみれば元の世界への愛着なんてものは俺には無いように思えるのだ。もちろん馴染みのある環境への依存というのはあるのだろうが。
――確かに、以前ほど帰りたいとは思わなくなった。
突き放された世界に、今さら戻りたいと思うほどの未練はない。
――俺は忌み子だ。二つの世界のどちらにとっても。
不貞腐れたわけではなかった。自然と指が動き、本心からの言葉が地面に残る。
前にデレシスから『君は稀人だ』と言われたが、元の世界にだって俺の居場所なんてなかった。僅かな友人や妹の存在が俺を繋ぎ止めていたけれど、それも地震と津波によって呆気なく破壊された。
死んだのだ。俺は。
この地獄のような異世界で拾ってもらった命。
せめて願うのは一つだった。
――生きている以上は必要とされたい。
俺の言葉に三人は響くものがあったようで、ラーンマクなんかは目頭を熱くしていた。
「おいおい泣かせるじゃねぇかよ」
嗚咽を誤魔化すために乱暴に俺を揺する。
心が荒む戦場だからこそ、こうした身の上話が響いたのだろう。お前の居場所はここにあるというようにラーンマクは肩をまわして身を寄せた。
「まさかここまで健気な方だとは……ねぇ、デレシス」アルクトィスはそう言って袖を引く。
「なにさ」
「認めてあげましょうよ、一人の仲間だって。彼はただの戦闘魔導具じゃありません」
二対一の形勢不利に追い込まれ、デレシスは煩わしそうに大仰に溜息を吐いた。
「別に、認めてないわけじゃない。あのときは役に立ってもらわなきゃどうしようもなかった。……ああするしかなかった。そうでしょう?」
観念したようにデレシスは言う。
確かに彼女の立場から考えれば致し方なかったのかもしれない。この平野を進むにはとにかく頑丈な前衛が必要で、そのために戦闘魔導具を生み出したものの、鎧に宿った魂がまるで戦えないとなれば強硬手段に訴えるのも理解はできる。
使えるものは使う……でなければ己の命が危ういのだ。デレシスは俺を脅してでも利用する必要があったということだろう。
「そもそも私はゆっくり慣らすつもりだったからね」
デレシスは言葉の矛先をラーンマクに向けた。予定を崩し、いきなり戦場に立たせたのは誰だったか。
「昔のことはいいだろもう」
「昔じゃない」
デレシスとラーンマクが睨み合い、アルクトィスが間に入る。
「まぁまぁ、……そうです、折角ですし名前を決めてはどうですか?」
急な提案に視線が集まる。
「慧さんは元の世界の名前ですし、鎧さんと呼ぶなんて論外です。仲間として、新しい名前を授けましょうよ」
「なるほど……お前はどうだ? 名前はあった方がいいか?」ラーンマクは俺に問う。
確かにただ鎧と呼ばれるのは味気ないし、未練たらしく慧と呼んでもらうのも違うように思えた。
――良い名があれば。
「……なにか考えよう」とデレシス。
「でしたら愛らしいのが良いのではないですか? 螺泉とか祈とか」
アルクトィスは案を出すが、俺には耳馴染みのない響きで良し悪しがわからなかった。本人的には割と自信を持って提示したようで、なんなら満を持してこの話題を振ったと見える。
「愛らしいって、こんな見た目の前衛だぞ。無骨で格好付くやつがいいだろ」ラーンマクは歯牙にも掛けずにあしらった。
「なら、ラーンマクさんはなにかいい名前が思い浮かんだんですか」
アルクトィスはむっとして代案を求めた。ラーンマクは頭を捻って絞り出す。
「……例えば、禍斬はどうだ?」
「物騒な」アルクトィスはこれ見よがしに言い返した。
「なんだと」
互いに睨み合い、それらしい名前を罵声のように応酬し合う。
「じゃあ羅刹!」
「黒ちゃん!」
「ちゃん付けで呼ぶ気かよ……不眠!!」
「それが人の名前になると思ってるんですか……莫迦!!」
最後のは案ではなく本当に罵倒だった。
俺の気持ちを代弁するようにデレシスはため息をつく。
「虚。……ずっと空っぽだったんでしょ? これまでの君とこれからの君を繋ぐ一字は『虚』。これがいいよ」
――わかった。
彼女と俺の主従関係で決めたわけではない。
その名の意味も含めて、とてもしっくりきたのだ。
「ま、なんであれ新たな門出ってわけだ――」
そう言って手を差し出すラーンマク。出会ったばかりの頃はその豪気な性格に振り回されたが、情に厚く戦場では確かな正義感によって脅威を払い仲間の命を助けていた。なにより、共に前衛に立つ戦士として、その絆は確かなものだ。
「――よろしくな。ウツロ」
この夜に固い握手を交わしてから僅か数日後にラーンマクは蛇堕によって殺される。
「これからは一人の仲間として、頼りにしていますよ――」
同じく手を差し出すアルクトィス。その掌の三女継承の刻印が印象深い。思えば決して目立たぬ役回りではあったが、思慮深く機知は冴え渡り、こうして俺の人間性を見出し仲間として取り持ってくれたのは彼女だ。
「――頼りにしていますよウツロさん」
握手を交わしたアルクトィスの小さな手は熱かった。後にラーンマクの無念を払い蛇堕と相打ちに斃れて冷たくなっていく。
育まれた友情も、交わした誓いも、儚く崩れていく。
やっとの思いで手に入れた俺の居場所は、呆気なく崩れていった。
関わった人間は時の流れに別離して、交わした約束は果たせないまま過ぎ去った。後には一人取り残された俺の周りに、やるせない虚無ばかりが残される。
先代継承者最後の一人、デレシスとの別れは言い表せないほどに辛いものだった。後に災禍の龍と呼称されるに至る禍人領より現れた凶悪な化け物との戦いは、俺とデレシスが犯した過ちを後世へ残す結果となる。
❖
「ごめんね。また君を孤独にさせてしまう……」
禍人領より現れた災厄の化身……荒ぶる龍を前にして、デレシスは俺に向かい一言謝罪した。
俺は首を振って応える。
――そんなことを言うな。
肩を掴み励まそうとしたものの、状況を打開する方法は無かった。彼女は震えていた。
「……ねぇ、一度死んだことがある君なら分かる? これから死ぬんだってときは、どんな気分だったの?」
そんなことを聞かれても答えようがない。まさか龍の前で蝋板に書いてみせろとは言わないだろう。
「……困らせたいわけじゃないんだ……あぁ、もう、自分でもどうしていいのか……、ウツロ、聞いて。たった一つだけ、あいつを倒す力があるの」
――なんだと……?
と、俺はデレシスの目を見つめる。
「異世界から齎された『世界を破壊しうる力』……。君が教えてくれた全く新しい概念だよ。
それはたった一度しか使えなくて、ほんの刹那の光で、見渡す限りの範囲のあらゆる生物が消滅してしまう。
……本来使うべきではない絶大な力……『抑止力』って言うんでしょ?」
これは問うているのではない。わかっていて惚けているのだ。
デレシスの声は震えていた。己がこれから何を仕出かすのか理解している者特有の笑けたような震えだった。
逃れられぬ死を受け入れた者の顔だ。
迂闊だった。
これは俺の責任だ。
俺の知らぬところで彼女がそんな術式を生み出していたとは知らず、肩を掴んだままなんの反応もできなかった。この世界に核兵器の概念を持ち込んでしまったことに、ただひたすらに動揺していた。
継承者の持つ神がかりの才覚を俺は甘く見ていたのだ。俺が元いた世界と比べ文明が未発達だと決めつけて、魔呪術という奇跡を軽視していた。特に次女継承者の天球儀の杖が持つ権能は距離を司る。それは目に見えない物質でさえも操れるのだ。ならば核爆発――特定元素に中性子を衝突させることで生じる莫大な熱量とその連鎖反応――さえも、科学への理解がなくとも独自の経験則や神がかりのひらめきによって原理を生み出し再現することが出来る。何故なら物と物をぶつけるのは距離の問題だからだ。
この危険性に俺が気付けていれば――そんな無理を願ってしまう。
「……じゃあ、終わらせてくるね」
そう言って俺の手から離れるデレシスをなんとか追いかけ腕を掴む。
――待て!
今は一縷の望みであるこの術式が頼りなのは間違いない。核兵器の再現となればあの化け物だって一溜りも無いだろう。だが、それは恐ろしいものだ。デレシスはそれを理解できているのだろうか。
「言いたいことは分かってるつもりだよ。でも行かせて。……ほら、私って裏があるでしょ? 君はまた騙されただけ」
――違う! そうじゃない!!
俺は強く否定する。
「大丈夫だよ……ウツロ。君は優しいから、私がいないこの先の世界でも、きっと居場所を見つけられる」
デレシスは不意に俺に向けて術をかけて捕縛した。がっちりと手足の関節が固められて動けない。戸惑う俺に向けて微笑む。
「私が召喚したんだもの、手足を固めるくらいはできるよ」
――やめろ、デレシス……!
「この『奥義』が戦場の全てを消し去っても、たぶん鎧の体を持つ君だけは生き残れるかもしれない……だから後のことは色々押し付けることになるけど、よろしくね」
――待て、頼む……! 死ぬな!!
「……じゃあね――」
彼女は振り向かずに駆け出し、杖を上空へと浮遊させた。それはもはや核弾頭だった。
天球儀の杖が龍のすぐ近くまで移動すると不意に溢れ出した光によって視界はほんの一瞬真っ白に煌めく。
世界が、凪いだ。
風が消えた。大地が静まった。龍の咆哮すらも一瞬だけ音を失う。
まるで天地そのものが、恐怖に凍りついたように静かだ。
爆発の中心から、再び光が迸った。
いや、それは光などという生易しいものではない。
轟音が後から追いつくよりも早く、熱が、圧力が、世界を塗り潰していく。
何かが崩れる音。何かが砕ける感触。
音を置き去りにした光の熱が鎧の体さえ焼き尽くし、追いかける爆風の衝撃が俺を彼方へと吹き飛ばす――
❖
「やぁ、お目覚めかい?」
ふと気付けば、俺は病室にいた。
忘れもしない、212号室だ。
俺はあの時の服――つまり下は仕事着に上は半袖だ――を着ていて、全身に汗をかいて病室の入り口に立っている。
ベッドの上に、冠のような頭角がある一人の少女が腰掛けている。妹の姿はなかった。
その少女は俺が目覚めるのを待っていたと言いたげだが、俺は鎧になっていたはずだ。眠ることも気を失うこともありえないことだったはずだ。
「誰だ?」俺は問う。
「僕は『理』。……挨拶をしておきたくてね、まま、よろしくー」
ベッドに座ったまま、少女はにこやかに手を振る。敵意は感じられないが、名を聞いたところでやはり見覚えはない。
あるいは鎧となって過ごした体験の全てが白昼夢なのか……いや、それなら少女の頭に角があるのはおかしい。
全く理解できない。この空間は何だ……?
「……さっきまで、……俺は、戦場に……」
茫然自失に俺は言葉が出ない。少女に訊ねているのか、胡乱な独り言なのか、自分でもわからなかった。
「そうだよ。『さっきまで君は戦場にいた』」少女は言葉を汲んで教えてくれた。「……流石に鎧の体でも死にかけたね。危ないところだった。ここは君の精神世界さ、ここは記憶によって構築された病室で、君の意識はあの日の姿形をとっている」
「じゃあ、コトワリ……さん。あなたは俺の何なんですか」俺は恭しく問いかける。
豊かな射干玉の髪と、幼くも生命力に漲る少女の纏う雰囲気は只者ではないと分かる。この空間が俺の記憶、精神世界だと言うなら、見知らぬ少女の存在は異物のはずだ。そんな彼女が俺よりもこの空間に馴染んでいて、当たり前のように存在しているのは何故なのか。疑問に思って当然だった。
少女はにやりと機嫌良くこちらに微笑み、立てた人差し指を口元に運ぶ。
「それは秘密」
これからもよろしく頼むよ。と言って少女は指を前に倒し、それを合図に俺の体が背後から引っ張られる。力強い後方への引力に景色は急速に流れ、病室の扉を抜けると長い廊下の景色が背後から通り抜けていく――
❖
覚醒を感覚した。
鎧の体になってから初めて意識が途切れたように思う。……まさかこの体になって夢を見るとは。……いや、あの少女は極限状態が見せた夢や幻ではないだろう。もしかしたら、この世界の上位存在ではないだろうか……コトワリと名乗ったが、つまりは『理』を意味していると考えられる。
だが今は、そんなことを考える余裕はなかった。
目覚めれば去来する現実と向き合わなければならない。もうデレシスはいないという現実に。
デレシスが俺の目の前から離れていく姿を、どうすることもできず見つめていた。閃光が目を焼き、鎧の体を焼いた後……知らぬ間に俺は薄暗い室内にいる。
この状況の前後を繋ぐ記憶が欠落していた。おそらくは意識を失っているうちに誰かが俺をここへ運んだのだろう、俺が一人でこの空間まで歩いたとは思えなかった。
あるいはまだ夢の中なのか……もう俺にはわからない。
光に吹き飛ばされた衝撃も熱もつい先程のことのように覚えているのに、鎧の体は冷え切って、うっすらと埃を被ってさえいた。
明らかに時間が経過している。それも一日二日どころではない。
床に座る形で安置されていた俺は肩に積もった埃を舞い上がらせないようにゆっくりと起き上がる。片膝立ちに手をついたとき、埃の手形が床に残った。この空間は無人で、久しく手入れもされていないのが分かる。例え俺が一人で歩いて来たのだとしても足跡が残るはずだったが、足元には先程まで座っていた俺の尻の跡しかなかった。
ここがどこなのかわからず、安易に動き回って良いものか判断がつかないが、このままじっとはしていられなかった。
デレシスの術式で拘束されていたはずの体を見回し、各部の関節を回して指先まで不自由なく動くことを確かめた。つまり術者との繋がりが断たれている。はらはらと落ちる埃は、気を失っていた間に流れた年月を物語っていた。
――もう、この世にデレシスはいないのか……。
明かりのない室内は趣こそ異なるが、天球儀の内側と似ていた。様々な物が整然と収められ、無人の蔵の中にいるのだと理解する。
外への扉を探すのに苦労はしなかった。なぜなら丁度前方に、縦に細く光が漏れていて、両開きの扉が浮かび上がっていたからだ。
俺は扉を押し開ける。……待ち受けていたのは――白い街だった。
白い壁、白い玉砂利の敷かれた地面、白い衣を身に纏う人間達。
俺が目を覚ました場所はマハルドヮグ山の頂。神殿と呼ばれる場所だった。
蔵から目覚めた俺に、白衣の者は驚きながらも歓迎してくれた。彼らの話しを聞き、ようやく事情が分かった。
先の継承者が戦役を治め、勇敢なる戦死を遂げてから十四年。
彼女達が押し広げた領土にはそれぞれの名が付けられ、ラーンマクと共に戦ったあの平野はスペルアベルと名付けられた。前線は防壁の建設に忙しいのだという。
四代目次女国家デレシスには、今なお災禍の龍との戦闘の傷跡が大地に残されており、見せてもらった地図には巨大な湖が形成されていた。戦禍は目に見えない形でも瘴気として土地に蟠り、足を踏み入れる者すべての命を吸い取る呪われた場所となってしまったのだという。この呪いの術式は未だ解明されていないようだが、俺には心当たりがあった……もちろん言えるはずもなかった。
神殿主導の調査によって、『涙の湖』と名付けられたその湖底から俺が引き上げられ、蔵に納められたというのがこれまでの経緯ということである。
神殿には多種多様な人間がいた。彼らは神人種と呼ばれており、獣人、魔人、賢人から選ばれた優秀な人材なのだそうだ。
ここは内地の中でも最も安全で、前線の国家と比べれば文化や生活の水準もまるで違う。ここで過ごした約百年は、俺に多くの学びと、この世界への理解を深めさせてくれた。
ずっと戦うことのみを教えられてきたので、神人種との知的な触れ合いは助けになった。彼らが繰り返し語る継承者達への賛美は俺の傷を慰めてもくれた。
事情も知らず巻き込まれた戦争のそもそもの原因や、彼らが信仰している教えなど、足りなかった知識がここでやっと補われることとなり、継承者達の死後、俺はやっと彼女達が背負っていたものを理解できた。
――以下にこの世界の宗教を記す。
戦争と宗教について。
ことの始まりは六〇〇年前、『ラヴェル法典』によればこの世界は三人の娘が生きていた楽園だったのだそうだ。序文ではこのように語られている。
『その昔、楽園があった。
楽園には永遠の命を持つ三人の娘がいた。
娘の前に蛇は現れ、三つの快楽を説いた。
一つは、他者と交わる快楽。
一つは、眼目を閉じる快楽。
一つは、果実を食する快楽。
楽園に表れた蛇を退治するため、
神は天使を遣わした。
天使は蛇を踏み亂れた世を糺し、
娘に戒律を打立てた。』
この序文の解釈はこのようになっている。
楽園とは、マハルドヮグ山を中心とする豊かな土壌を持つ土地を意味し、三人の娘というのは人種のことを指している。つまり獣人種、魔人種、賢人種の外見と特徴の異なる種族が共存関係にあったということだ。
そこに蛇が現れた。これが意味しているのは禍人種、あるいはトガと呼ばれる者達だ。彼らによって唆され、三種属の共存関係が崩されることで多くの犠牲が支払われたのだという。具体的には病であったり、異種族間の交配による先天性の問題であったり、食物の取り合いや労働の不平等など、様々な争いの火種が生じることとなった。
この争いに介入した天使こそ今の神殿に棲まう天帝、ラヴェル一族ということだ。争いの絶えない世界に秩序をもたらし、法を整備することで内地の平和を維持しており、禍人に奪われた土地を取り戻し勝利へと民草を導くのだと信じられている。
この天帝の誓いこそが、神殿側の信仰であり、ラヴェル法典なのである。
――歴史の由来から宗教と戦争が密接に関係しているのがこれで理解できた。
次いで、ラヴェル法典に記された三つの戒律も以下に記す。
・ラヴェルの言葉は神の言葉。決して疑うことがあってはならない。
・民は豊かな生に励み労働の喜びを知ること。また豊かなる収入の一部を喜捨し、神殿に捧げること。
・生まれ持った種族に誇りを持つこと。そして隣人を敬うこと。しかし血を混ぜることは決してあってはならない。
――という。
ここまでの知識を手に入れて、ようやく俺は何と戦っていたのか理解することができたのだ。逆に言えば、これまでは何も知らないまま求められるままに敵味方を定義し、殺してきた。自分の居場所を守るために。
神殿で目覚めてからも、俺が異世界から来たということは伏せた。あくまで継承者によって作られた戦闘魔導具として振る舞い、こちらから何かを語ることはしなかった。……俺の軽率な行いがデレシスに核兵器を持たせてしまったのだ。優秀な神人種の彼らに要らぬ知識を与えてはいけない。それこそ法典のように、蛇の道――さらなる混沌――へ唆すことになりかねない。
神殿での日々は平和そのものだった。デレシスの犠牲を最後に、俺はてっきり戦争が落ち着いたのだと思っていたが、前線では変わらず血が流れているらしい。この争いが終わるときは、世に禍人種が一人残らず消え去ったときだけのようだ。
そして、デレシス達が請け負っていた継承者という使命は、その名の通り次代へと継承されていくものなのだそうだ。
言い伝えでは百年周期で相応しい娘が生まれ、神によって刻印が授けられるのだという。
先代の忘形見として、俺は次の娘の誕生を待った。
次こそ誰も失わせない……そう心に誓って。
❖
約束の年。
デレシス、ラーンマク、アルクトィスの四代目の継承者誕生から百年が経った。
しかし、次の継承者が現れない。
気を揉んでいた俺は居ても立ってもいられず一人で次代の娘を探そうとしたが、神殿は俺の外出を許さなかった。
予兆らしきものはあった。空には鐘の音が鳴り響き、光の輪は陣を描き娘の誕生を告げたのを目撃したが、奇妙なことに待てど暮らせど赤子は神殿に届かない。結果として本来現れるはずだった五代目三女神継承者は一人として生まれてこなかった。死産と伝えられた。
人の精神構造では百年正気を保つのは難しい。
疲れ果てれば眠り、いずれは老い、朽ち、死に至る。
俺にはそれがない。
終わりがこない。逃げ道がない。出口がない。
永遠という牢獄に閉じ込められた俺の心は、ひたすら腐り続けるだけだった。
次代継承者が現れるという希望だけが、俺の正気を保たせてくれていたのだ。
百年の孤独。無情に過ぎ去る時間に記憶は漂白されて、もはやデレシスの顔も鮮明に思い出せないことに気付いた。
彼女の声。彼女が最後に俺をどう呼んだか。
だが、それはまるで朝露のように指の間から零れ落ちていく。焦るほどに遠ざかる。
いつからこうなった? 百年の間、俺は何を見ていた?
振り返れば、記憶が白んでいる。人々の顔、語られた言葉、俺の時間は、漂白された羊皮紙のように色を失い始めていた。
俺はここで何をしていた? なぜここにいる?
いや、それよりも――
俺は、俺の名は……何と呼ばれていた……?
自己の消失感に支配された俺は、狂気にこの身体を明け渡した。
――誰か……。
最初に砕けたのは石柱だった。俺の拳が触れた瞬間、亀裂が走り、砕石が飛び散った。
次に弾けたのは神殿の床だった。重く、神聖なはずの場所が俺の暴力に震えた。
鐘が鳴る。警戒の音だ。誰かの怒号が聞こえる。
だが、聞こえない。わからない。
何もかもが遠ざかる。体感覚は鎧から離脱していた。
止まらない。止められない。
――誰か俺を終わらせてくれ。
この手で神殿を破壊しながら、誰よりも強くそう願っていた。
❖
「久しぶりだね」
覚えているかな? と少女は頭角の生えた頭を傾げ、自分の顔を指差した。
狭い直方体の空間は四方を平滑な壁面に囲われていて、どこかうら寂れた室内は朧げながら俺を懐かしい気持ちにさせた。
「ここは君の記憶を元に構成された空間。つまり精神世界だ。覚えてないかい? 本当はここに窓があって、壁のこの辺りに間接照明があったんだけど……忘れてしまったかな。『病院』、『212号室』、……可哀想に、封印されて五十年経ち、大事な記憶さえ思い出せなくなったんだね」
俺は胸の内に湧き出る望郷の念に座り込んで部屋を見回す。少女が言う通り、この部屋はとても大事な記憶だったように思う。確かに窓があった気がするし、壁が寂しいように思う。欠落した不完全な空間はもはや懐古の念を呼び覚ます抽象概念として、俺の心を優しく締め付ける。
「およそ常人では耐えられない長い時間が流れた。合計にして百六十九年。人間だった頃の記憶は、五十年、百年の戦闘魔導具として日々に塗り潰され、無機質な自己を揺るぎないものにしてしまったね。だが忘れないでほしい。君は遠い昔、人間だったんだってことを」
少女は褥から立ち上がり俺の前に立つと、憐れむように見下ろした。
「何が起きたのかも分かっていないようだけど、封印されたんだ。……そう言っても分からないか。神殿の帝は暴れ回る君を止めるため、鎧の手足をばらばらにして封印した。身動きのできない、音も光もない蔵に閉じ込められて、君の精神が跡形もなく消えてしまうところだった。
現れるはずだった五代目についてはとても残念だし同情するけど、僕にはどうにもできない。封印されたまま次の百年を待つしか無いんだ。今度こそ神に選ばれた娘達が、きっと君と出会うことになる。それまでは少しだけ、休ませてあげよう」
❖
次に覚醒を自覚したとき、外の世界ではさらに半世紀が経過していた。
神殿の蔵に封印されて五十年。
意識を失って、さらに五十年。
この世界に来てから、二百年の年月が経過している。
暗い神殿の保管庫に幽閉されていた鎧の部品は全て運び出され、俺は眠る躰を引きずって庭の玉砂利の上に広げられていた。
板金鎧の体は四肢ごとに大別され、さらに部品単位で分解されて厳重に封印処理が施されていた。
封印した者達はすでにこの世を去り、当時を知る者はいない。
俺を目覚めさせるために駆り出されたのは神人種の中でも金物の細工に心得のある者達や、術式回路の知恵を誇る者達だった。彼らは白衣の袖を捲り、書物を紐解き記録を頼りに復元を試みていた。
右手を繋ぐのに数日。残る手足を繋ぐのにまた数日を要し、体が揃うまでは指先一つ動かす気にはならなかった。
俺は夜が訪れる度に月を眺めながら、静かに記憶を辿っていた。
確か、始まりもこんなふうだった。
デレシスは毎夜、動かない手足を苦労して繋げてくれたのだったか……思い出そうとしてもどこか他人の空似のような目鼻立ちが彼女の顔に張り付いて、悲しいかな忘れてしまった悲しみさえも風化してしまった。
虚な鎧に宿るのは、継承者を守り禍人や咎を討つという一念。もはや形骸化して原型のない願いだった。
――俺は本当に人間だったのだろうか?
たった二十年にも満たない遠い昔の記憶。鎧になる前はこことは異なる世界の青年だったなんて、今の俺にはあまりに空虚な絵空事に思えた。鎧に宿った霊素の妄想だったと片付けてしまった方がずっとしっくりくる。初めから俺は魔導具だったのではないか。
明くる朝、神人種によって全ての部品が鎧の体の収まるべく場所に取り付けられ、封印から自由の身となった。俺は神人種達に囲まれ見守られる中ゆっくりと立ち上がる。それだけで人の輪はどよめいた。喜ぶ者もいれば、困惑する者もいた。
「おお、これが例の先代の忘形見……」
「しかし、戦えるのか……?」
「事情は知らないが、封印されていたと聞くが……」
色めき立つ者達を前に一人の女が厳しく言い放つ。
「静かに」
こちらに向かい玉砂利の上を真っ直ぐに歩く白衣の女は、場の混乱を鎮めるために鷹揚に語る。
「当代長女継承の随伴として先代忘形見を付ける。これは天帝の御意向である」
彼女の言葉に不満を漏らす者はいなかった。永らく保管されていた三種の神器とは異なる出自不明の得体の知れない魔導具、たった一人の五代目継承者の出征に先立ち封印を解き、随伴させると決めたのは天帝なのだ。これに異を唱える者は、つまり神を疑うに等しい。
そして天帝の御意向を伝える彼女は神族近衛隊隊長、名をカムロと言った。
「……鎧の魔導具、名を名乗れ」
カムロの命令に対し、俺は玉砂利の一つを拾って石畳の上に移動した。人集りは俺を避けるように形を変えて、追いかけるカムロの後ろを取り囲む。
石畳に石を擦りつけ、俺は名前を書いてみせた。
――虚。
「『虚』……? ではウツロ。あなたは何者によって生み出された魔導具か」
――輝羅翠。太陽魄。七星。
先代継承者の名前が並ぶ石畳の文字を読み、人集りからは興奮した声が漏れる。彼らからしたら、俺の存在は先代が紡いだ神話の生き証人ということなのだろう。
「あなたは先代の次女継承者様の戦いに参加しましたか?」
これは言葉ではなく首肯で答えた。
「災禍の龍との戦い、先代次女継承者様は何をしたのか答えられるか」
俺は躊躇うことなく嘘をついた。
――知不。
人集りは少し残念そうな反応だったが、もとより古くから封印されていた戦闘魔導具が真相を語ることは望み薄だと考えていたらしく、そこまでの落胆ではなかった。
カムロも長く息を吐いたきり、気持ちを切り替えて続ける。
「これより、当代長女継承者様の元へ向かう」
❖
カムロに連れられて案内されたのは神殿の一劃、近衛隊集堂だった。
室内は書類が積まれた棚が壁面を囲っており、実際の間取りよりも窮屈に感じられる。なにより部屋の中央、卓に両手をついてこちらの到着を待ち構えていた長身の獣人から放たれる圧がいっそう室内を狭く感じさせていた。
「君のことを待っていたよ。存在は予々耳にしていたがこうして見るのは初めてだ」
先代と同じ赤い髪、天へ伸びる頭角。そして面影のある顔付き。
カムロはそれぞれに向かって手を添えて、「こちらが長女継承者ガントール様」、「こちらが先代の忘形見、ウツロです」と紹介する。
「リブラ・リナルディ・ガントール……ガントールでいいぞ。
私はスペルアベルに縁ある血筋でな、つまり先代ラーンマクの子孫だ。……どうだ? 先代様と似てるだろうか?」
そう言って笑うガントールの勝気な口元に確かにラーンマクの面影を見た俺は、思わずそばに寄って袖に触れようとした。が、カムロが割って入り俺を押し退ける。
「気安く触れるな!」
受け身も取れず後ろに倒れた俺は、卓にぶつかり集堂を散らかしてしまう。物凄い剣幕だった。カムロは、いや、俺の事情を知る神殿側は信用していないのだろう。
当然だ。気が触れて暴れ回る戦闘魔導具なんて、先代の形見という由来がなければただの不良品なのだから。
「おいおい、そんな邪険にしなくていいよ」
「……失礼しました。しかしお言葉ですが、これから御身は出征を控える立場。いくら先代の忘形見といえど不測の事態はあってはなりません」
「大丈夫だ。不測の事態なんて起こらない」
少し話がしたいから席を外してくれ。とガントールは指示して、不承不承カムロは集堂の外に待機する。
「すまない。カムロはここ最近ずっとああなんだ。頭痛に悩んでるみたいでね。
……私としてはこの日を楽しみにしていたんだが、やれやれだな」
ガントールは倒れた卓をそのままに壁際に凭れ、一人と一体の魔導具が向かい合い、見つめ合う。
「そんなに見つめられると気まずいな」ガントールはたまらず相好を崩した。「知りたかったんだよ、私の顔が似ているかどうか。なにか応えてくれないか?」
俺は未だ衝撃の最中にあった。カムロに張り倒されたことなどどうと言うことでもない。本当にそっくりだった。
失いかけていた記憶が色付くように、ガントールの姿は先代ラーンマクを思い出させてくれたのだ。風化していた記憶が再び色付く喜びに、未だ立ち上がれなかった。
「言葉もないほど似ているのか」
俺は頷く。お世辞ではなく生き写しだった。
ガントールは照れたように笑い、自分のことを語ってくれた。
曰く、ラーンマクはスペルアベルで攻めあぐねている際に戦士の男との間に子を授かったのだという。驚くことに身重の体でありながら戦場に立ち、出産の迫った前後のみ、戦線を離れたのだそうだ。戦士の男の家系に子を預け、その後スペルアベルを領地として手に入れたが、ラーンマクは帰らぬ人となった。
リナルディ家は、その後土地を移り、生業だった屠畜の仕事から前線維持に努める戦士を輩出し、名家となった後に辺境伯へ上り詰めたという。
「表立って語られてはいないが、先代長女継承者は女神の肩書きにそぐわぬ色好きだと聞いた。ウツロはそのあたりも知っているのだろう? どうだった?」
俺はこくりと頷く。確かにラーンマクは誇り高い戦士であると同時に色好きという欠点があった。素行を鑑みれば子を儲けていたとしても不思議はない。あまりに見つめ過ぎたせいか、ガントールは何か勘違いしたようで、慌てて手を振り否定する。
「私もそうだと思うなよ。そこだけは似ていない。断じて」
……そうして、俺は二百年ぶりに継承者と出会った。
ラーンマクの血は獣人種の中でも優れているらしく、同じ血を引く末裔のリナルディ家の娘が再び神に選ばれるとは相当に珍しいことだろう。或いはデレシスやアルクトィスが子を産んでいたなら、結果はどうだったのだろうかとも思う。ラーンマクの褒められない素行が結果としてこの世に子孫を残せたというのは、ある種の正しさの証明かもしれないと思えた。
当代は三女神のうち長女継承者の一人しか現れなかった。俺からしたら残る二人が揃わないのは落ち着かないが、長い戦役の歴史から見れば、三人揃っている四代目が珍しいのだとガントールは言う。
「一度に三柱が揃う幸運に恵まれたのは先代だけだ。だからこそ反動で二百年の休息が必要だったのかもしれない」
たった一人の継承者出征になると誰もが思っていた。
事態が急変したのは、式典を控え、準備に追われていた七日前のこと。
突如霹靂として空に陣が現出し、ナルトリポカとムーンケイから娘が選ばれた。
全く異なる運命の導きによって次女継承者と三女継承者が神殿に招かれることになる。まさにその案内役として俺とガントールは選ばれ、急遽娘を護るために神殿を出発した。神殿の外へ出るのも久しぶりのことで、俺は舗装された山道を一歩一歩確かめるように南へ下った。
二代目国家ナルトリポカの目的の集落にたどり着く頃にはあたりはすっかり日も暮れていた。
めでたい祝い事に集落では夕暮れから祝宴が開かれていたのだろう。露天は卓も片付けず、杯には飲みさしの酒が残っていた。
寝静まった夜の集落を気配を殺しながら彷徨き、一軒の家の戸口に夜風に涼む娘を見つける。
貫頭衣を纏うどこにでもいるような内地の娘……だが、言葉には言い表せない部分でこの娘が継承者だと直感した。デレシスとは決して似て似つかぬ娘だが、事実この直感は正しかった。
俺は月光に仄明るく照らされる娘をじっと見つめていた。鎧の体を木立の影に潜ませて、まさか気取られるとは思いもしなかった。
「誰、ですか……?」
囁きかけるような声で娘は問いかける。物腰は柔らかいが、目を凝らすようにこちらに首を向けていた。俺の気配がどこにいるのか確信しているようだった。
「もう一度問います……誰ですか?」
はっきりと俺に向けて声をかけている。内地で生まれ育った勘の鋭さではない。それに腹も据わっている。もし俺が敵意を持つ者だとしても対応できるとでも言いたげな態度だった。
俺は呼びかけに答える代わりに書き置きを残し、その場を後にした。今宵はもう遅く挨拶には礼を失している。明日の朝に出直して、護衛に専念することにした。
❖
近衛隊集堂でカムロが危ぶんでいた通り、継承者を狙う咎は湧いていた。
集落の外れにある鬱蒼とした木々の闇から現れたそれは、蠍によく似た特徴を有し、体躯は馬車に匹敵する程に大きい。
本来なら触肢には鋏がついているのが自然だが、このトガが前方に掲げているのは牙の並ぶ二揃いの口だった。巨大な人の顎を模した部位を無理に継ぎ接ぎして形を整えたように口と触肢の境は呪術の刻まれた襤褸が巻かれており、口の皮を無理矢理引き伸ばして甲殻に打ち付けるように金具で留められている。
相変わらず禍々しい化け物……いや、二百年のときを経ていっそう奇妙な存在になったか。
これ以上集落へ接近を許せばきっとあの娘は気付くだろう。ここで過ごす最後の夜だ、静かに始末したい――そう考え、俺は得物を構えた。
――思えば戦うのも久しぶりだ。ガントールとは何度か手合わせをしているが、命を奪う実践となると二百年の空白がある。戦場の感覚は鈍っているだろう。
そんな及び腰な俺を見透かしたようにトガは大胆に距離を詰める。思考の読めない真っ黒な玉の目は月夜を映し、甲殻に覆われた巨体をくねらせ木々の間をすり抜け、八本の脚を器用に操り音もなくこちらに迫る。
闇を絡めた木立の隙間から触肢が噛みつき、それを躱すと別の方向から追撃が迫る。トガは一体のはずなのにまるで複数を相手取っているようだった。
俺は後ろへ跳んで間合いを保った。しかし侵攻を許せば集落に近付けさせてしまうため、槍の届く距離で触肢の柔らかそうな唇の部分を狙って反撃も織り込む。
大型のトガという見掛けにやや圧倒されていたが、冷静に一撃、二撃と槍で突けば実力は虚仮威し、次第にこちらが優勢になる。
倒せる相手だと判断して間合いをこちらから詰めたとき、待っていたように尾が頭上から迫る。蠍の尾の先端には毒針があるものだが、鎧の体に効く訳がない。だから脅威として数えなかった――それが油断だった。
あくまで敵は蠍ではなくトガなのだ。毒針と決めてかかった尾の先端は尖っていなかった。それは刺叉のように枝分かれした巨大な蠍の尾に替わる三前趾足の趾だった。
視界が不意に奪われて俺の体は宙に浮く。大蠍の尾に生えた鉤爪が俺の頭を鷲掴みにして、持ち上げられたのだと理解したときには地面に振り下ろされた。
トガは俺の頭を掴み、岩を目掛けて振り回す。容赦のない一撃に全身が撓み、負荷のかかる首の接合部が遠心力に伸ばされる。先に砕けたのは岩の方だった。
だらりと垂れた俺の四肢を見て仕留めたと判断したであろうトガは、鎧の内側にあるはずの肉を狙い捕食行動に移る。
左右の触肢を構え、トガは大きな口をこれ以上なく開くと生え揃う歯でがぶりと噛み付いた。上半身と下半身にそれぞれの口が噛みつき、俺の体を喰い千切ろうと力を込める。板金はぎしぎしと軋み、胴が捻られる。並の防具では容易く食いちぎられていただろう。
俺は抵抗するために槍を逆手に持ち替え何度も触肢の唇に突き刺す。形だけなら皮膚に覆われた顎ではあるが、この口はあくまで鋏の代わり、急所ではないようだ。効果が薄い。
まだ息があるのかとトガは顎の力を強めた。万力にも等しい咬合に板金が軋む。
ならばと俺は槍を持ち替えて尾を狙う。
この趾が鳥と同じ構造ならば筋を断てばいい。俺は視界を奪われた己の顔面に向けて躊躇なく槍を突き立てる。仕返しだと言わんばかりに何度も筋に刃を沈める。その度にざくざくと、骨ばった硬い肉の手応えがあった。
普通の人間ならば、自分の顔面に向けて刃を突き刺そうなどとてもできないだろう。己を痛めつけ鍛え上げた戦士でも、防具を纏う兵士でもきっと難しい。心でどれだけ命令しても無意識のうちに自己防衛の制御がかかるものだ。
自己を傷つける危険を度外視に動けるのは鎧の体の利点であり、魔導具として過ごした時間の中で人間性が失われた証拠でもあった。
そのまま刃を滑らせて三前趾足の付け根の筋肉を深く断ち切る。トガの握力は弱まり、傷ついた太い血管から溢れ出した大量の血を全身に浴びた。流血の熱と共に、トガの体を満たしていた圧まで抜けていくのがわかる。噛み付く顎の力も萎びて弱まり、俺は拘束を振り解く。
流石のトガでも耐え難い痛みのようで、尾を振り回してじたばたと暴れ回る。これほどまでに痛むならと自ら傷口を砕けた岩に叩きつけて趾を自切した。出血は治っているが体力を消耗して瀕死のようだ。こちらを見据えたまま退却を始めた。勝敗は付いたが生かしてはおけない。とどめを刺すべく俺は追いかける。
木々の隙間を縫うように闇の中を遁走するトガであったが、尽きぬ体力があれば、追いついて仕留めるのは容易いことだった。
集落は滞りなく朝を迎えて、昨晩に少女と出会った家の前でじっと待っていると玄関から大人が二人現れた。ここは次女継承者の娘が住んでいると見ていたが、家の主は獣人のようで仲睦まじい男女であることから夫婦のようだ。
次女継承者は魔人種の血を持つはずだが、ならば娘は親元を離れて生活していたのだろうかと考える。この世界では幼いうちから親と離れて暮らす者も珍しくないのだろうが、内地の娘が事情もなく獣人の家に転がり込むともおもえない。何か事情があるのだろう。
しかし憐れむ必要はないようだ。
娘の身を案じて何度も洟をすすって見送る育ての母と、気丈に振る舞いながらも帰る家がここにあると示す育ての父。居候の身であり、娘同然の愛を受け取り旅立つ少女の姿を見て、俺は憧れるように目を奪われていた。手に入らない尊いものを眺めるような気持ちだった。
❖
次女継承者の娘はアーミラと名乗った。
アーミラは魔人種で魔呪術の才を隠してこれまで生きていたようだ。そのせいか袈裟や頭巾に馴染みがないらしく、先代と同じ装いの法衣を神殿から支給されても、俺が教えるまでは袈裟を丸めて頭巾を雑嚢のようにしていた。
彼女の振る舞いは掴みどころがなく、多弁であると同時に朴訥でもあり、おどおどとしていながら肝は据わっている。よく泣くが泣き言は口にせず、弱々しいながらも時折に誰よりも強い瞬間がある。
アーミラは俺に対してはすぐに打ち解け、妙に人懐こい印象があったが、他人には心を開く素振りがない。おそらく裏表のない素直な性格が悪い方に働いて、嘘がつけない故に人付き合いに苦労したのだろう――デレシスとは正反対の娘だったが、俺はアーミラのような娘をどこか昔にも世話を焼いていたような気がしていた。
そのことを思い出そうとする度に、狭く四角い空間が思い浮かぶ。『病室』、『二〇二』という言葉を伴って頭の中に靄をかける。
遠い昔、大切だったもの。
大切であるがゆえに、記憶の深いところに仕舞いこみ、それきり忘れてしまったもの。
思い出さなければいけないのだという焦燥が俺を苛み心を切なく締め付けるのだが、夜毎思い馳せてもこの靄がはっきりとした形になることはなかった。
初めに予感があったのは出征の後……ナルトリポカ集落が襲われた夜のことだ。
ムーンケイに馬を係留し宿をとった五代目継承者一行であるが、宿ではアーミラが盗人か巾着切りにあったと騒ぐ。三人が失せ物を探している間、廊下で待機していた俺はしばらく経ってから様子を見に戻る。
静寂と虚無の中もぬけの殻になった宿部屋に立ち尽くし、三人を探して部屋の中を歩き回り、事情を理解した。
俺は杖を通り過ぎて窓の方へ向かい、木枠と格子が嵌められていることを確認して、外へ出た可能性は低いと確かめる。三人が忽然と消えた。しかし見当はついている。天球儀の杖内部の空間へ消えたようだった。おそらくアーミラの失せ物もそこで見つかっただろう。
窓を閉めようとしたとき、空耳が聴こえた。
『あそこに敵がいる』と囁く声。見えざる者の手に操られるように、首が勝手にナルトリポカ集落へと向いた。『走りな』と、再び聴こえた声に命じられる。
宿を出る前に継承者達を呼び集めるべきかとも悩んだが、結局一人で向かった。娘達を今度こそ護る――ならば危険が迫っている場所に連れてはいけないと判断したのだ。
その時の俺は、残忍惨毒を絵に描いたような光景を前に禍人と相対していた。収穫を待つ畑も、石積の家々も、一切が火の海だった。
禍人の凶手が、アーミラにとって大切な人さえも奪おうとしていた。首を掻き切らんとする危うい場面で、俺はたまらず槍を投げ――横から女が現れた。
敵は間諜の三人……その中の一人に女は数えられる。
歳はおそらく継承者の娘と同じくらいに見えたが、境遇が違えば纏う衣装も違いが出る。女は裸同然の襤褸布一枚で戦場に立っていた。
俺の槍を弾き、禍人に与する女。
敵でありながら、その額には頭角がない。
槍を投げ、手ぶらになった。
だが、もし武器があったとしても、あの女とは戦えなかったのではないか――そんな気がした。
獣人とも魔人とも賢人とも異なる何者でもない女。頭巾で顔を隠しているが、その姿を直視するだけで俺の思考は掻き乱される。理性よりもっと深いところで体が縛られるような感覚があった。
得体の知れない呪術にかけられたのだと判断した俺は、ひたすらに防戦に努め、鎧の体を盾にしてアーミラの育ての親を護ることに努めた。
幸い、敵の撤退は早かった。
守りに徹する俺をみて、取り逃した二人に固執するよりも次の一手を優先したのだろう。顔を隠した男が南の方角へ退がり、夜の闇に溶ける。
「守り抜いたってわけだ」
女は吐き捨てるように言うが、声の響きは単純な憎しみだけではなく、状況を楽しんでいる余裕も混じっているように聴こえた。
間諜がここを去ってからも俺は闇を睨み続けた。あの女のことが妙に気がかりだった。
振る舞いや言葉遣い、襤褸布から覗く青白い体もそうだ。言葉にはできないが、異なる世界からやってきた者特有の気配を纏わせていた。
異なる世界……そんなもの、二百年の歳月に忘れ去っていた。
自分が人間だった頃の記憶なんてただの幻想に過ぎないと忘我の内に切り捨て、初めからただの魔導具なのだと自分を定義していた。
前世の記憶を持っている……という妄念に囚われた戦闘魔導具……それが俺だ。
だが、あの女に感じる予感はなんなのだろう。
角が無く、代わりに尾を持つ化け物の女……頭巾に隠した顔から覗く口元の笑み……姿を思い浮かべるだけで、靄がかかっていたあの『病室』が、明瞭に色づくのがわかる。
あの女は俺と同じだ。
戦いに信仰を必要としていない。
正義も大義も持ち合わせず、求められるから戦っている。空っぽで他人事の態度が俺を確信させる。
――次会うときには問いたださなければ……しかし声のない俺がどうやって……?
❖
あの娘ともう一度会いたい。会って確かめたいことがある。
しかし次の機会はなかなか訪れなかった。
巡り合わせが悪いのか、スペルアベルではダラクという禍人が俺を付け狙い、そのせいでアーミラからは「禍人と繋がっているのか」とあらぬ疑いをかけられた。
集落が襲われてからのアーミラは、生来の優しい性格を隠すようになってしまった。火を放った首魁のダラクを追いかけるものの掴めず、その鬱憤を俺にぶつけているところがある。
『あの夜、集落が襲われていることに気付いたのではなく、知っていたんじゃないですか? そこで落ち合い、情報を流した。違いますか?』
裏切り者ではないのかと問われ、全くの無実無根であるはずなのに、俺は図星を指された気持ちになってしまった。同時に、俺の気持ちも知らないでそんなことを言うアーミラに怒りを感じた。
先代の無念を知るのは俺だけだ。二度とこの悲しみを繰り返さないために俺は継承者と共に戦い、眠ることも食うこともなく尽くしている。……だが同時に、禍人の女が同じ境遇の人間なのではないかという予感に駆られ、探し求めている矛盾……。
そんな後ろめたさをアーミラに見透かされたような気がしたのだ。
俺は柄にもなく感情を表に出し、皮肉混じりに反論してアーミラから逃げた。
……今になって、あの夜のことを後悔している。俺とアーミラの互いの歯車が噛み合わなくなったのはおそらくあの夜からだった。
スペルアベル平原は二百年前とは様変わりしていた。だが、邸で過ごす日々に俺とアーミラはすれ違うことが増え、アーミラは天球儀の杖に閉じ籠ることが多くなった。
彼女は力を求めていた。
俺はそれについて特別疑問には思っていなかった。先に前線へ向かったガントールとオロルに並び立つ次女継承者としての力を求める気持ちも理解できていたし、この頃は前線ラーンマクから女伯スークレイも招かれ、アーミラは成長への外圧がかけられていたこともよく知っている。……だが、アーミラが募らせている禍人への復讐心を軽んじていた――負の感情ほどよく燃える燃料であることを、俺は知っていたはずなのに。
それから一月も経てば、アーミラは先代にも劣らない次女継承者へと成長した。
目覚ましい活躍を支え、アーミラを次女継承者として導いた一冊の手記がある。
デレシスの手記だ。
アーミラにその手記の存在を教えられるまで、俺はデレシスがそんなものを認めていたことを全く知らなかった。
少しだけ、嫌な予感がした。
デレシスの手記に俺の過去がどれだけ書かれているのか、もし書かれていたとして俺とデレシスの犯した――異世界の――過ちがどれだけ残されているのか。想像するとありもしない肝がぞっと冷えた。
ここで俺が「奥義について調べるな」と釘を刺せば、アーミラはむしろ躍起になって探すだろう。下手な忠告は語るに落ちるというものだ。奥義の存在を示唆するどころか、俺の関与まで悟られてしまう。
それに、デレシスの性格的に奥義の効果と危険性を知っている以上、手記には何も書き残していないはずだ。
俺は何も言わず、アーミラの成り行きを見守ることにした。
毎夜とはいかずとも研鑽の様子を伺いに杖の中まで足を運び、アーミラが奥義の痕跡を見つけてはいないかと注意を払っていたがそんな素振りはなかった。だから安堵して、油断した。
己の保身にばかり感けて、本当に注意するべきものを見落としていた。
次女継承者として花開くアーミラの足下で深く根を張る復讐心こそ、真に警戒すべきものだった。
『私は……自分を変えるため……この戦いに、挑みます。無くした記憶を取り戻して、強くなれたらいいなって』
アーミラは失った己の記憶を取り戻すため、そして誰かを守るために強くなりたいと邁進していた。本来の彼女はもっと清廉で美しい心を持っていたはずなのに。
『――でも、約束したシーナさんもあんなことになって』
力を求める動機は恨みに引き寄せられ、薄暗い方へ道を踏み外していた。
いつも手遅れになって、俺は後悔するのだ。
スペルアベル南方でトガに矢を放ち、惨たらしく殺しを愉しむようになってしまったアーミラを再び正道へ導くため、俺は仮面の男――イクスに縋った。
イクスは言う。
『誰かを正すには、まずお前が正しくなきゃだめだ。
今のお前は戦うことに信念なんて持っちゃいない。
お前は先代の戦場に囚われて、ただ敵を殺している。そうなんだろ。』
その通りだった。……俺は信念なんて持ち合わせていない。
天帝への信仰もなく、大義もなく、ただ敵と教わったものを倒している。
心は未だ二百年前の悲劇に囚われ、自分の境遇を憐れみ腐っていた。思えば俺は、一度でも五代目継承者達と真正面から向き合ったことはあるだろうか?
「次代の娘を護ればいい」、「敵を殺せばいい」。そうして消極的に使命を全うする戦闘魔導具に成り下がっていたのだ。
こんな俺がアーミラの心に寄り添えるはずもなかった。
『人は腐る。恨みは視界を狭くさせる。俺も随分間違えた……。だが、お前は黒鉄、古びちゃいるが錆びてはいない。』
俺は虚だ。
この世界で名を与えられたあのとき、いつか満たされる日を夢見て立ち上がったのではなかったか。
今日に至るまでの幾つもの夜を越えて、俺は未だに空っぽだ。
だが、空っぽだからこそ、可能性が残されている。
叶えられなかったこと。
遂げられなかったこと。
果たせなかったこと。
目に見える形でなくとも、いつか彼らが、彼女らが語ってくれた言葉、言葉、言葉たちは鎧の内側に確かに存在しているのだ。
二百年の内に駆け抜け消えていった者達の虚無を俺は忘れない。ただの戦闘魔導具であるはずがない。
人の願いによって生み出された空の器であり、亡き者たちの想いを背負う継承者なのだ。
❖
決意を新たに、俺は災禍の龍と対していた。
二度目の最終決戦……何があっても継承者達を護りきってみせるつもりだった。
だが心を入れ替えたからといって世界が変わるわけではない。現実は残酷なものだ。
圧倒的な力を持つ龍を相手に継承者達はなす術もなく追いやられ、対抗する手段は絞られていく。
デレシスが生み出した天球儀の奥義……それ以外にないことを、俺は誰よりも先に理解していた。
アーミラに呼ばれ、その表情を見て何をしようとしているのかを悟ったとき、忘れかけていたデレシスの顔がはっきりと思い出された。面影が重なって見えた。
――だめだ……。
『お聞きしたいんです。先代の次女継承者について。』
――同じ結末を繰り返すのだけは許さない。許されない。もし誰かが犠牲になるのなら、俺一人でいい。
『龍を倒した奥義のこと。』
――あの奥義は確かに龍の命に届く……だけど使っちゃいけないものなんだ。
アーミラは失望の目を向けて、頼りにならないと俺を見捨てる。
悔しくてたまらなかった。俺に声があったなら、いちいち筆をとる煩わしさから解放されて思いのまま全てを伝えられるのに!
声だけじゃない。顔があったなら、視線や表情で伝えられるものがあるはずだ。
身体が、肉が、骨が、……俺が人であったなら!!
災禍は目覚め、飢えた光輪は世界を喰み、ガントールとオロルを齧りとる。
長女継承者が戦場に倒れ、追いかけるように三女継承者も重傷を負った……まるで先代の悲劇を再現しているように思えた。
この世を蝕む龍の牙に四方を囲われたガントールは、あの一瞬に確実な死を覚悟しただろう。オロルの時止めが光輪の放つ光よりも僅かに先手を取り、閉じてゆく顎の隙間からガントールを助け出して上半身をはみ出すことで辛うじて致命傷を免れたのだ。
ガントールは両脚の腿から下をごっそりと、オロルも膝下を失い、抉り取られた大地と面一の断面を晒して身動きが取れなくなった。丸太のように断ち切られた足は骨も肉も晒して、後に続く爆圧に全身を吹き飛ばされる。目と耳から真黒い血が流れ出して、死んでいるよりも酷い状態だった。
天秤の剣を託された俺はアーミラの元へ駆け、神器の放つ斥力と天秤そのものを盾として龍の光輪を凌ぐ。力のぶつかり合うところでは物凄い火花が散り、鋭い輝きで満たされた。
光の中は無茶苦茶な暴力の嵐だった。この世界の理不尽を体現したかのような禍々しい輝きの奔流が容赦なく俺を襲った。龍の牙は絶え間なく天秤を削り、地金が灼熱にとろけはじめる。皿を吊るしていた鎖は赤熱して弾けるように飛散した。灼熱の飛沫が肩にかかる。
――例え、死んでも……!
俺は背後に庇ったアーミラを守るため、溶解する剣をもろに浴びた。まるで札を貼り付けたように、溶けた神器は粘度の高い液体となって纏わりつき、痛覚を失って久しい鎧の体に熱が伝わり耐え難い激痛が走る。
――……それでも……!!
突き抜ける光を凌ぎ切ったとき、溶けて混じり合った二つの地金が脈動するのを感じた。熱に浮かされたような奇妙な解放感だった。
内部に溜め込んだ熱い空気を吐き出すために、空に向かって口を開ける。何が起きているのかわからないが、五感がはっきりとして清々しかった。そしてアーミラと目が合い、ぽつりと呟いた。
自分でも無意識だった。
「ああみら……」
アーミラは目を丸くして何か言いかけたが、熱の籠った俺の体は急転直下に調子を崩す。
膝の力が抜けて、上体を支えるために地面についた手が熱と冷却の狭間で虹色に焼けているのをぼんやりと見つめることしかできない。開けていた口からは胃液の代わりに溶鋼の雫が垂れた。全身が重く、顔を上げる余裕もない。
酷く意識が混濁している。出口を求めて彷徨っていた言葉達が一気に押し寄せるせいで口が塞がって、アーミラに伝えたい言葉が喉に詰まっていた。
視界の端では彼女が立ち尽くしている靴が見えた。心配そうにしてはいるものの、焦眉の急やるべきは龍の討伐……やがて俺から離れ、詠唱が紡がれる。
冴えた聴覚に、彼女のしなやかで芯のある声がよく聞こえてきた。
俺は自分の身に何が起きているのかわからなかった。この身の変化が龍の影響なのか、神器の影響なのかも判然としない。
握っていた天秤の剣は鎧と溶けて一つになり、失っていた首に新たな頭が据えられていることは感覚で理解できている。きっと天秤の地金が鎧と混じり合い、余剰分が頭を復元したのだろうとは思うが……そもそも、この感覚……五感が全身の隅々まで行き渡り、明瞭な神経が外界の全てを感じ取っている。
この鋭敏な体感覚が通常の人間に備わる五感なのだと悟る。
長く鎧に閉じ込められていた魂では、流れ込む外界の情報に追いつくので精一杯だった。その証拠に、情報の膨大さに処理が間に合わず、驚くほど短時間に意識が擦り切れてしまっている。
目眩、耳鳴り、悪寒、吐き気……二百年ぶりの身体感覚があらゆる不調を訴えて気持ちが悪い。このまま倒れて楽になれるだろうかという考えがよぎったとき――
「落ち着いて、感覚を絞るんだよ」
――見えざる者の声が囁く。不可視の少女……コトワリの声だ。
「替えの頭が手に入ったんだね」
俺はよろけながらもなんとか立ち上がり、感覚の酔いに体を慣らしていく。外界の全てを受け取る必要はない。鎧の体を苛む痛みも一切無視して、意図的に五感を鈍く制御する。
前線ではオロルが龍の光輪を砕き、アーミラの詠唱も佳境に入っていた。
コトワリは「あそこを見て」とまだ熱く焼けている俺の頭をぐいっと引き寄せる。
砕けた天輪が萎縮するように輪を縮め、霧散せずに押し固めたような玉となった。魔呪術の気配はなく、むしろ自壊しているように見えた。
「君が望んでいるものだよ」
そこから孵化するように、一人の女がまろびでる。
何者かと俺は目を凝らし、ぴくりと指先が痙攣する。
体内を犇めき合っていた言葉は消え去り、明晰の意識は娘の名を言い当てる。
「……芹那」
俺の口が名を呟き、その声を俺の耳が拾う。
まるで記憶の匣を開く呪文だった。仕舞い込んで忘れ去っていた過去が思い出される。
「そう。君が大事にしていたものだ」
尾の生えた娘。
集落を襲った娘。
異世界から来た娘。
あれは俺の、妹だ。
そう理解したとき、考えるより先に体は動いていた。
アーミラの奥義で妹が消し飛ばされるなんて、あっていいはずがない。
「日緋色金を使いなさい」
コトワリの声に導かれ、俺は体内を巡る日緋色金を掌から生成した。神器の欠片が刃となり、天球儀の杖を砕いた。
「――え……?」
アーミラは抱えていた杖が腕の中でばらばらと崩れていくのを呆然と見届け、本当に何をしているの? とでもいうように俺を見つめる。
その首に刃が奔り、彼女の首から迸る返り血を浴びる。アーミラは気を失うように倒れた。
「あの子も核を失った。……楽にしてあげて」コトワリは龍を示す。「青生生魂と日緋色金を取り込んだ今の君なら、それができる」
俺は刃を操り、災禍の龍の首を介錯する。
当代の戦役が終わった。
感慨深い……などと言える状況ではなかった。
俺の体に起こった異変、光輪から取り出された核としての娘……そしてこの娘が俺の妹だという事実。
「本当にぎりぎりのところで思い出せたんだね」
不可視の少女、コトワリは言う。姿は見えないがその声音は他意なく嬉しそうだった。
「人であることを忘れてしまった時には、君が自らの手で妹を殺めてしまうのだと思ったよ」
俺は声の聴こえる方に首を向けて、コトワリの姿を探す。
コトワリはいつも、俺の精神領域に潜んでいた。敵意を見せたことなどなかったが……。
「これはどういうことなんだ」
今この場に上がっている様々な疑問についてコトワリはどれだけ把握しているのか。
「残念だけど、僕にもわからない。……だけど事態は良い方向に向かっているよ」
「これのどこが――」と言いかけて、口を閉じる。
再び会えるなんて思っていなかった。
鎧の体ではあるが、五感と声も手に入った。
この戦役も決着はついただろう。
「それに、継承者だって一人も死んでない。こんなの奇跡だろう? 頂上だろう?」
コトワリの言うことは一理ある。守ると決めたアーミラを自分の手で切ってしまったのはよろしくないが、その傷も神殿の加護によって癒えつつあった。命数に余裕のあるアーミラであればしばらくすれば治癒するだろう。先代に誓った当初の約束通り、五代目継承者は誰も死なずにここまで来れたのだ。だが……。
「俺はどうしたらいい」
セリナを連れて神殿には戻れない。
「連れて行けば禍人種として処刑されてしまうだろうね」
コトワリは新たな道を示す。
「簡単なことだよ。君が禍人領へ向かえばいい」
他に道はない。
俺はセリナを抱え、そばに倒れているアーミラを目に焼き付け、今生さらばと南へ向かう。
「すまない……アーミラ」
別れの言葉は、いつかデレシスが俺に向けた言葉に奇しくも似ていた。
■012――焔を呑む
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
これまでの足跡をなぞる馬の常歩に揺られ、オロルは後方に流れる景色を名残惜しむようにじっと眺めていた。終わりの見えなかった戦役も、過ぎてみればあっという間に思える。
神殿から遣わされた幌に乗り、継承者は前線から帰還する。
気付けば暑さは盛りを通り越して、肌を撫でる風もどこか涼やかに和らいでいる。戦に明け暮れた夏が終わろうとしていた。
幌の荷台、日陰をつくる奥の方ではガントールが深く眠っていた。息はあるが傷痍は酷いものだった。
数々の戦況では常に前衛を務め、ときに己の身を盾にして戦った。当代三女神の中で最も死を経験し祈祷の術式を使い果たした彼女は、龍に齧られた脚を治癒すること叶わず、あれだけ大きかった背丈も今ではアーミラより低くなってしまっただろう。
幌の両脇に設けられた腰掛けに座り、オロルの向かい側でアーミラは項垂れていた。こちらはガントールと比べて治癒もまだ余裕があり、首の裂傷も失血もとうに癒えている。意識もはっきりとしているが……それ故に胸中に渦巻く複雑な思いに頭を抱えている。
――虚しいな。
オロルは声もなくそう思った。
腰掛けに胡座をかき、靴を失くして砂埃に汚れる裸足を手で擦りながら、世を憂うように幌の外の景色を見つめる。
失ってしまった命は多い。
流れる景色にだって、名も知らぬ戦士共の骸が転がっている。
選択が違えば助けられただろう命……生き残ってしまった者にはその虚無が重くのしかかる。
荒野の道はまだしばらく続く。オロルはうんざりして視線を掌に落とした。
――この虚無感が、わしらの求めた勝利なのか……。
求められていた戦果は上げた。
脅威となり得る禍人種の首を取り、災禍の龍を討伐。そして戦役によって無人となった前線の領土は神殿主導のもとで拡大され、国が興るだろう。五代目継承者は誰ひとり欠けることなく武勲を成し遂げたのだ。なのに……とても喜ぶ気持ちにならなかった。
幾つかの気がかりが呑み込めぬ溜飲となってオロルの喉に引っかかり続けている。
「のぅ、アーミラよ」
オロルは青藍の頭巾に向かって声をかける。
「……はい」
悄げた様子のアーミラの声。俯いたままに顔は見えない。
「ウツロがここを去った」
アーミラは返事をするのも辛いという様子で背を丸めた。喪失感にくれるようだった。
彼は私の首を切り、裏切った。紛れもない事実だが信じられない――アーミラはそんな失意のなかにいる。
「心当たりはないか?」
オロルの問いに、集る羽虫を払うように何度も首を横に振る。
当代継承者の中では主にアーミラが、ウツロと行動を共にしていた。勿論それは後衛であるアーミラの護衛をさせるためにオロルが意図して割り振ったところもある。しかし、それなりに絆を結んでいたとみえる二人でも、ウツロの裏切りは全く予想外だったとみえる。アーミラを切り捨て禍人領へ与する素振りなどオロルの目から見てもこれまでに一度だってなかった。
「お主は倒れ、その後のウツロの行動を見ておらんじゃろうが、わしは見たぞ」
「え……」アーミラは顔を上げる。
目は赤く腫れ、酷い顔だった。
「わしが龍の光輪を砕き、その欠片が一つの玉となって中から小さな龍が現れた。尻から尾が生えた娘に見えたが、お主は見とらんか」
「わ、私は、詠唱に必死で、砕けた欠片は見てません……」
「そうか」無我夢中だったのだろうと考え、オロルは続ける。「ウツロはその娘を見て様子が変わった。突然お主の詠唱を妨害し、あげく首を切ったのじゃ」
「そんな……」
アーミラの驚きの表情はめらめらと色を変え、目の焦点が離れた。
ウツロが一目見てこちらを裏切るに値すると判断した龍の娘……アーミラは思い当たる人物はいないかと頭を巡らせるが、検討もつかない。
「私たちを裏切る理由は分かりませんが、尾の生えた女なら、集落を襲った者の一人ではないですか……?」
そう応えるアーミラの声は怒りを押し留めきれず硬くなっていた。
確かに、とオロルも思い出す。ナルトリポカ集落を襲った間諜は三人……その内の一人、ダラクという男は倒したが、残る二人はそれきり姿を見せていない。尾のある女と首魁らしき男という特徴は伝え聞いていることから、災禍の龍から現れた娘が同一人物である可能性は高い。
「……許せません……っ」
アーミラは腹に据えかねた黒い感情に身を震わせ拳を握り、燃え盛る激情の炎は……不意に燻った。
固めていた拳を弛緩させ、肩を落としがっくりと項垂れる。どれだけ怒ろうとも、今のアーミラは杖を……力を失ってしまったのだ。
ずっと携えてきた神器も砕け、ウツロもいなくなってしまった。気力も底をついて裏切りを裁くことも尾を持つ娘を捕えることもできない。
打ちひしがれ、無力に喘ぐしかなかった。
頭巾に隠れたアーミラの喉から歔欷の声が漏れる。幌の床板に雫が落ちて染みをつくる。そこには勝者の姿はない。
「私……、悔しくて、っ……ウツロさんと、こんな別れになるなんて……!」
膝を抱えたアーミラは洟をすすり、袴の裾を握りしめる。
ウツロとの関係が単なる継承者と魔導具という形に収まらないことはオロルも察してはいた。言葉にこそしていなかったが、きっとアーミラはウツロを慕っていたのだ。
戦場に翻弄され、そんな儚い恋心は成就せぬままに散ってしまった。
……始めから見込みのない片思いだったか。魔導具に人間性を見出し、アーミラは叶わぬ恋をしていたのか。オロルにはそう簡単に片付けられないようにも思っていた。なぜならオロルもまた、多少なりウツロのなかに心を見ていたからだ。彼奴は凡庸な魔導具ではない。心を通わせ、アーミラの隣を選ぶ意思があったなら、共に歩く明日もあり得ることと見ていた。
だがそれも、今となっては虚しい夢想だ。
「……何の慰めにもならんが――」
オロルはそう前置きして、語り出した。
暗い車中の気を紛らわせるための与太話だと言い添えて、ほんの少し遠くを見つめる。
語り出したのは、己の過去だった。
オロルが完成し、そして壊れることとなった物語――
❖
わしの手の平に刻印が宿ったのは、十の頃じゃった。
あのころはこの化け物じみた手もまだ気娘らしい綺麗なもんじゃったが、神は狙い澄ましてこの手に雷を叩き込んだ。それはもう焼けるように熱く、肉も骨も砕け散って指がなくなるかと思ったわい。
場所はムーンケイの西。沖合に波の泡立つ島嶼部。
その島々に生きる卜部族の里が、わしの故郷だった。
今でもはっきりと思い出せる。その日は海が時化ていて空はごろごろと機嫌の悪い雷鳴が轟き、厚い曇天越し、稲光に紛れて巨大な光の輪が覗いていた。
雷に打たれるまで、わしは浜辺の小屋で漁に使う網の手入れを手伝っていた。薄暗い小屋の天井を吹き飛ばした稲光りに視界も耳も焼かれ、なにが起きたのかわからないままに両手の先に激痛が襲った。
次の刹那には焼けた腕をだらりとぶら下げながら、わしは痛み打ちのめされ、天を仰いでいた。
傍らで共に作業をしていたわしの親は心底驚いた顔をしていたが、決してわしを憐れまなかった。この雷が神の宣告だと理解したからだ。
両親は喜びわしのことを抱きしめた。まるでこの理不尽な痛みを耐え抜いたことで祝福を受ける資格を得たみたいに。
父と母の背に手をまわそうとして、わしは己の掌に刻まれた印に気付いた。きらきらと金糸の刺繍を施したような精緻な刺青……しかしその輝きはすぐに色褪せ、熱を失い消えてしまった。
この日を境に、親は何かに取り憑かれたようにわしに魔呪術の知識を買い与えた。決して裕福ではないのに家財を売ってでも本土に通い、漁の利益を上げるために収穫の大半を競りにかけた。食卓で消費するはずの取り分さえ絞って書を求め、欲しいなんて一言も言っていないわしに与えた。
神が気まぐれにぬか喜びした親は、「もう一度」と奇跡に執われ、まだ幼いわしを継承者に相応しい娘に育てようと躍起になった。まるで人が変わってしまったようだった。
「……わしは海が好きなんに、毎日部屋に閉じ込めよるのじゃ。どう思う?」
不満を口にすると、彼はなにがそんなに面白いのか、大仰に笑う。
「そうけそうけ、オロルは海が好きか」
「何が可笑しい?」
「いやぁ、泳げもせんに海が好きち、変わってんなぁ思うてな」
わしの悩みを真剣に聞いていないのか、彼は口元に笑みを残したまま、海に夕陽が沈む様を眺めていた。
「なんじゃい、フリウラの阿呆」
――人が大真面目に話しているのに。
これから先、ずっと部屋に籠って勉学に励むなんて、当時のわしにはとてもじゃないが無理だと思った。
卜部族が生活を営むこの島嶼地域は、北東の大陸に座すマハルドヮグを源流に一代目国家アーゲイと三代目国家ムーンケイの国境を流れる巨大な運河によって土地が侵食されてできた急峻な地形である。島とぶつかった海流が複雑に絡み、海産物が豊富に取れる資源豊かな離島だった。
『海が好き』とは決して半端な気持ちで言ったわけではなかった。
内地でありながら文明発展の波からは離れ、島に棲まうのは主に賢人が占めている。同じムーンケイでありながら、本土の上層、下層とは別に『田舎』として扱われているむきがあり、実際島嶼部の里の者は特有の訛りと独自に発達した卜の魔呪術体系を持つ。
そんな一族の娘であるわしは、勉学に特別興味などなかった。
この里の者がほとんどそうであるように、漁をして日々安穏に過ごせればそれで良いと思っていた。
「才能が眠ってるっちゃろ? 勿体無いと思おぎね」
フリウラは言う。
「眠っとらん。文字だって読めん」
「読めんからこそよ。オロルは才能に気付けてないだけがん。
読めるようにないば、そいで初んで気付くさ」
「……そう言って――」
わしは冷ややかな視線を送る。
「――お主は仲間が増えるのが嬉しいだけじゃろ」
フリウラがやけにわしの才能を期待しているのは確信があったわけではない。座学仲間が欲しいだけなのだ。
島嶼部に独自に発達した魔呪術……それは遡れば里の者達が飢餓に苦しんだ過去の歴史に起源を持つ。潮風に晒される岩だらけの土地は作物に適さず、船を出せば急峻な海溝によって形成された渦潮に溺れる。この地で漁を生業とするには、気候を読み、船を制する魔呪術が必須だった。風向きや空模様から時化を見極めた才ある者が里の者を導く卜部の長となり……その風習はいつしか気候を操り、海を制するものとして今も続いている。
彼はつまり、次の島の長として座学に一人励んでいたのだ。
ここに来てわしという仲間ができたことが嬉しいのだろう。
「わからんことあいば俺が教えちゃる。そんでオロルは女神ん継承者になんがいい」
「継承者になったら島から出ていくんじゃぞ? わかっておるのか」
「漁と同じじゃあ。たくさん獲って、終わったら帰ってきたらいいがん」
図太いのか能天気なのか、フリウラはあっけらかんとして笑う。
そんな彼に背中を押される形で、興味のなかった魔呪術に対しての座学もなんとか続けることができた。互いに研鑽し、彼は長を、わしは三女継承者を目指したのだ。
❖
あかるい志しとは裏腹に、親は次第に笑顔を見せなくなった。
理由なら明らかだ。端的に言って、心の余裕を失くしている。
あの日ほんの一瞬刻印が宿ったというだけで家財一切を捨てて魔呪術の書と交換してしまったのだ。殺風景になった我が家にあるのは小さな卓と漁の道具、そして高価な書がたった五冊。それだけだった。
その掛け金と吊り合う結果を手に入れるまで、親はわしを許してくれないだろう。
信じた可能性に賭けて金も生活も切り売りし、わしが神に選ばれることを今かいまかと待ち望んでいる。今にして思えば愚かな親だったが、当時のわしには異を唱える頭も、抵抗する力もなかった。漁師である父は特に恐ろしく、鍛えられた太い腕は撚った縄のようで、その腕で拳骨を振るわれでもしたらひとたまりもないだろう。せっかく頭に詰め込んだ知識も全部星となって散りそうだ。
声に出してわしを責めないのは、才能が開花することをまだ諦めていないからで、今更「継承者になりたくない」とは言えず、わしは期待を背負うしかなかった。
……掌に掴み損ねた栄光を追いかけ、報われるかもわからない努力をひたすらに積み上げる。終わりが見えない焦燥に結果は付いて来ず、そんなわしの姿に親は苛立ちはじめていた。それがわかるからこそ、余計に焦り、勉学に身が入らない。悪循環だった。
支払ったものが多ければ多いほど、後戻りは難しくなる。親がそうしたように、わしもまた様々なものを犠牲にして机に向かっていた。
十一歳になると部屋の外へ出ることも許されなくなってしまった。
「おぅい……、オロル、居るか…… 」
小屋の外から呼びかける声が聴こえる。
「む……」
そう声に出して、今日初めて声を出したと気付く。……いや、今日どころか数日ぶりかもしれない。机に向かっていた集中力が霧散して、外に意識が向いた。
「居ないのかよ、オロル……おぅい」
「……フリウラか……?」
意図せず嗄れてか細い声になったのを誤魔化すために咳をして誤魔化す。
「すまんな。忙しくて会えんなった」
「……本当にいるとは驚いた……」フリウラは呼んでおいてそんなことを言う。「ここんとこずっとか?」
「まぁの。こうでもしないと選ばれん」
「もう夜じゃに」
フリウラの言葉で初めて夜になったことを知る。
篭りきりだったうえに部屋では常に灯り石を燈していたため、昼と夜の感覚が鈍くなっていた。
「心配したんが、元気かよ」
「あぁ……」
「……顔が見たい。中入っていいがん?」とフリウラ。
「構わんが、鍵は親が持っとるぞ」
わしがそう応えると、無言ながらぞっとしたような彼の息遣いが壁越しに聞こえた気がした。
「……出られんとか?」
わしはその問いに答えなかった。親によって軟禁されているなんて大っぴらにしたくなかったからだ。しかし、沈黙が答えでもあった。
「……酷いこつすんがね……待ってろオロル」
フリウラの声に怒りが兆した。
岩がちな砂浜を歩く気配が入口の扉にたどり着き、錠をがちゃがちゃといじり始める。
木材の板で覆っただけの小屋は簡素な造りで壁を壊せば出られないこともないが、わしは期待を裏切ることへの恐ろしさに囚われ、出られなくなっている。狭い島の里しか世界を知らないわしは、家族の繋がりがとても重要なものだと考えていたのだ。
扉に掛けられた錠は納屋として使用していたときからのものだ。扉と壁に取り付けた金具に閂を掛って、さらに鎖で繋いで巾着錠を施している。漁で使う大事な道具を盗まれないようにするための錠前であるが、今は娘を閉じ込めるために使われている。それをフリウラは壊してしまうと思い至り、わしは声を荒げた。
「やめろ! 壊したらいかん!!」
鎖を壊すということは、家族の繋がりを壊すと同義だ。そうなればこの里に居場所はない。失望されて、家族に見捨てられてしまう。
「問題ないがん」フリウラは言う。「今開けちゃるけぇ」
壁の隙間越しに光が漏れて、わしは眩しさに目を細める。魔呪術による燐光だった。
小屋の外ではがちゃりと小気味の良い音が一つ響いて、閂が引き抜かれ鎖が地面に落ちる音が聞こえる。
開かれた扉の向こう、星空の広がる浜を背にしてフリウラが立っていた。
「錠を開ける魔術だに」
手柄顔でフリウラは手に持った鍵を見せつける。扉も錠も壊してはいなかった。軽石で創り出した即席の合鍵を拵えたのだ。
「来いよ、オロル」
フリウラは手を伸ばす。わしは誘われるままに月明かりの照らす彼の元に歩み寄る。
手に触れようとしたとき、彼はわしの背に腕を回して抱き寄せた。
「いつでも連れ出しちゃる」
触れ合うフリウラの肌は海風に冷えていたが、その奥の芯から伝わる体温が暖かかった。鼻を埋めた彼の胸の匂いに思わず気が緩んでしまったが、問題が解決したわけではない。そっと引き剥がし、わしは首を振る。
「でも……いかん……」
「何が」
「わしは出来損ないじゃ、外に連れ出されては、とても許されんのじゃ」
「外に出ることに許すも許されるもあるか。閉じ込められとっちゃろ」
「なるためじゃ。継承者になるためじゃ。こうでもしなければ期待に応えられん」
わしには才能がないのだから。
人よりも辛い努力をせねば、きっと神にも、親にも、認められない。
「そんなん間違うとるがに」
フリウラは語気を強めて訴える。見つめ合う彼の瞳は涙が滲んでいた。
「追い込んば追い込んほど上手なるわけじゃながん。
泳げんやつ沖に投げ込めば必死になって泳げると思おか? ……そいと同じじゃ」
フリウラは手を引いて夜の浜へわしを連れ出す。真っ暗な闇に潮騒が寄せては返し、頬に飛沫がかかる。
「まず泳ぐには浅瀬から、そんあとに足がつかない場所へ進む。オロルはいきなり真っ暗な海ん中放り込まれて、もがいて、苦しんでるだけがん」
フリウラの声音は優しかったが、言葉はわしの本心を見透かしているようで、鋭く尖っていた。
――わしは苦しんでいる。その姿を見せつければ親が諦めてくれると思っていた。許されると思っていた。
与えられた書はどれもこれもが難解で、読める文字は全体の一割もなかった。当然だ。勝手を知らない親のもとで学ぶ以上、段階を踏むことさえままならないのだ。まず識字から学ぶ必要があることさえわかっていない。
わしはその書の言葉が何を伝えようとしているのかを図や絵挿絵からくみ取り、言葉の法則性から文字を解読するところから始めていたのだ。
「……でも、やっぱし凄いわ」フリウラが言う。
「なにがじゃ?」
「読めん文字の解読から始めて、小屋ん中の灯石に術式を込めたがん。普通は出来ん」
フリウラは小屋の奥、オロルが紐解いていた書が置かれたままの卓を示す。そこには灯石が燈っている。難易度で言えば初歩の初歩だが術式構築の心得がなければできないことだ。識字すらままならなかったわしにとってはやっと魔呪術の一歩を踏み出せたと言える。
「……試行錯誤を繰り返しただけじゃ。これしきで何度も躓いたわ」
「そいが才能じゃがん。オロルは女神んなる。絶対」フリウラは机に転がるまだ灯りの燈っていない灯石を一粒摘み、手の中で祈りを込める。
米粒程の欠片が薄暗い闇の中で橙色に発光し、フリウラはそれを差し出した。
「祈りの火じゃ。これを飲めば願いが叶う」
「なんじゃそれ」
「女神の御呪いがに。火ば石ん宿したら、そいが護っちくれる」
互いに色恋も知らぬ子供とはいえ、歳の近い男に『女神』だなんだと真っ直ぐに言われるとむず痒くも悪い気はしなかった。後で知ることになるが、この呪いは『心像灯火』の儀式が口伝の内に間違って伝わったものらしい。
わしは皿のように広げ差し出された彼の手のひらから灯石を受け取り、口に含んで飲み込んだ。
❖
「――まぁ、あやつの言葉に乗せられて、わしは三女継承者に選ばれ、ここにおるわけじゃな」
過去話に区切りが付き、オロルは一息ついて手袋の裾を摘んで手遊びをする。
初めは胸咽びながら聞き流していたアーミラも、幾分か落ち着きを取り戻し後半はきちんと耳を傾けていた。
「……思っていたよりも裕福な家柄ではなかったんですね」と、涙声でアーミラは言う。一度洟をすすって、「意外でした」と続けた。
「当代が揃う初めの頃はわしだけが田舎者なんじゃと身構えておったからな。今じゃから言えるが、気を張っておったよ」
オロルが口の端を吊り上げてみせると、アーミラも笑みで応えた。
「では、帰ったら彼に会いに行くんですか?」
「……いや――」オロルは痛痒を堪えるような顔をした。「――これは叶わなかった恋の話じゃ。大した慰めにはならんな」
言い淀むオロルの態度にアーミラは気付いたものの、オロルは笑みを残したまま外の景色を見つめてしまったので気にしないことにした。島の思い出を語ったのは、傷心に寄り添おうとしたオロルなりの優しさなのだろう。
もとより死すら覚悟した出征だった。こうして生きて帰れることの有り難みを忘れてはいけない。後悔というのは、多少なり贅沢な悩みなのだ。
戻る場所がある。会いたい人がいる。それだけで十分だとアーミラは思うことにした。今は幌に揺られながら帰路を眺めるひとときに心を癒そう。
私たちは使命を全うした……継承者として兵戈を奮う以上、どうしたって禍根は残るが、とにかくやり遂げた。もう、戦わなくていいのだ。それがなにより救いだった。
ナルトリポカ集落は焼けてしまったけれど、アダンとシーナは生きていて私の帰りを待っているし、きっとオロルを、ガントールを待つ人はいる。
❖
帰る場所を失い、鎧は龍の娘を抱えたまま荒地を南に進む。
磨き抜かれた鏡面のように輝く金属の肌が、鋭い西陽を反射させて辺りを金色に照らす。その輝きは荒地の逃げ水となってゆらゆらと先へ誘う。
今のウツロは上半身がほとんど人のそれになっていた。神器の日緋色金が災禍の龍の攻撃に溶け、奇跡にも似た偶然の作用により混じりあった体は皮下に神経を通わせていた。
頭蓋骨の貌と金属光沢のある艶やかな上半身、そして板金鎧の下半身という姿である。形態の変化により神性を高めたウツロは、もはや戦闘魔導具と呼べる代物ではなく、また、人ともかけ離れてしまっていた。
既に二人は前線を超え禍人領に踏み入っている。二百年を超える年月を生きたウツロでも、流石にこの地を進むのは初めてのことである。いつなにが襲いかかってくるかもわからないと神経を尖らせるが付近に敵の気配はなかった。
西陽に温められたウツロの腕の中で皮膚を焼かれる娘は痛みに目覚め、覚醒を悟られぬように眼球だけを回して状況を窺い、唇を引き結んだ。……見覚えのある荒野だが、抱きかかえて歩く得体の知れないこの者は誰か――金属質の体を持つ男……まさかウツロか。
抱えられた娘の視点からは男の頭蓋の顎下から鼻を欠いた横顔が見える。頭骨の眼窩に目玉は無いが、どうやらこちらが目が覚めたことに気付いていない。
娘は瞬発的な敵意を持って鎧の首に尾を巻きつけた。しゅるりと鱗が鉄と擦れる音とともに、がっちりと絡みつかせて体勢を崩しにかかる。ウツロはなんの抵抗も出来ず、いいように地べたに倒された。ねじ伏せるように尾に力を込めて、入れ替わりに立ち上がった龍の娘は素早く付近の敵影がないことを確認し、ウツロの上に乗り肩を膝で押さえて首を絞める。
龍の娘は瞳孔の開いた目でウツロに対した。
「仲間は?」
なぜ二人だけなのかと娘は問う。
気が動転しているせいか言葉が足りていないとウツロは内心で思う。『仲間』とは継承者か、それとも他の禍人種のことを指しているのかわからない。いずれにしろ首を振るのみだった。
「……知らない……それより――」
「ここは龍人の領域だよ。なんでお前がここにいる? なぜ私を連れているの?」
畳み掛けるように問い詰めるのは当然の疑問である。
長い間意識を失っていた。敵であるウツロはいくらでも私を殺す機会があったはず……娘はそう考えたのだろう。どこまでも怪しいこの鎧の存在を前に、娘は首を絞める手に体重を乗せるが、硬質な首はびくともせず真っ暗な眼窩の穴が睨みつけた視線を深く吸い込んでいる。
力を込めた手の平の下で、ウツロの喉仏が上下に滑るのを感じた。発せられる声には些かの閉塞感もなくはっきりとしたものだった。真実を突きつけるような鋭さがあった。
「――兄だからだ」
「……は?」
娘は慮外の言葉を聞き、理解できずに目を丸くした。
多少なり動揺したのは、『兄』の存在に心当たりがあるからか。
ウツロは続ける。
「お前の名はなんだ」
「答える義理があるか?」娘はあしらう。
「芹那だろ」
「……っ――」
娘は事態が呑み込めず固まっている。思い当たる節があるからこその動揺……名を言い当てられた狼狽が指先の反応に出ている。
「そうなんだろ」
ぽっかりと開いた眼窩の闇が真摯に向き合い龍の娘を――妹を見つめる。妹の顔は少しずつ事態を理解し始めたようで、敵意は薄れ動揺が表れた。同時にその様子を見たウツロも確信した――やはりこの娘は妹だ。
彼女の揺れる瞳に宿るのは再開の喜びか、残酷な真実に対する怒りか。
「慧……なの……?」
ウツロは――アキラは力強く頷く。「212の病室のこと、覚えてるか? 『飯にでも行こう』って俺が言ってさ……ずっと後悔してる」
セリナはそこで初めて泣き出しそうな顔をした。唇を噛み、顎に皺を寄せてぐっと堪え、やり場を失った手がウツロの首から離れてわなわなと肩に置かれる。
「約束、守れなくてごめん」
「……ほんとだよ」セリアは俯き、ウツロの腹から降りて荒野に座り込んだ。「お父さんもお母さんも、お兄ちゃんも、みんな約束を守らないでいなくなって……すごく辛かった……なんでここにいるの? 今までどこに行ってたの?」
「……それはこっちの台詞だ」
兄としての声音が硬くなる。セリナは瞳に浮かべた涙も引いて、黙ってしまった。
何故セリナがここにいるのか。
妹はあの日、俺の命に替えても守り遂せたはずだ。一方でこの世界にいるということはどういうことなのか。
「俺はお前のことを助けられなかったのか……?」
「……違うの!」セリナは思わず否定するが、ならば何故ここにいるのかについては口が重くなっている。
語りたがらない理由が本人の中にあるというのなら……やはり、助けられなかったのだ。
ウツロは心密かに落胆し、立ち上がる。
「話せるようになったら聴かせてくれ。今は先へ進もう」ウツロは手を差し伸べて、セリナを立ち上がらせた。「ここでの名はウツロだ。お前はこの世界でなんと呼ばれている?」
「……ニァルミドゥだよ」
「ニァルミドゥか……覚えておこう。
もう事情は理解できるだろうが、俺は災禍の龍からお前を救い、神殿を、継承者を裏切った」
「うん」セリナは頷く。
「帰る場所を失ったので禍人種の根城を目指している。案内してくれるか?」
「わかった。……けど、『禍人種』って呼ばないで」
釘刺すようにセリナは訂正を求めた。
「彼らは龍人種。蚩尤とは違う……不滅の種族だよ」
❖
セリナに案内を任せ、ウツロはさらに南へ進む。何度も振り返り、遠くマハルドヮグ山脈のある方向を眺めては、セリナの後ろをついて歩いた。
地平線から射していた西陽がすっかり沈んで熱と輝きを失った頃、二人は丸くくり抜かれた縦穴が広がる場所に辿り着いた。
龍の喰み跡とは異なる巨大な縦穴は深く、地上から覗く程度では底の様子を窺い知ることはできない。この穴の内壁に沿って、螺旋を描く下り坂が続いていた。その坂に差し掛かる手前で待っていたセリナは顎をしゃくってついてくるように促す。
「思っていたよりもずっと近かったな」
「なにが? 根城が?」
ウツロが頷くと、セリナが言葉を続けた。
「まさか私たちの棲む国がまるまる地下にあるなんて思わなかったでしょ」
「あぁ。道理で見つけられないわけだ」
「この石窟は大昔は塔だったんだって。蚩尤が神の怒りに触れ、地底に塔を沈めた……その遺跡を龍人達の生きる拠点にしたんだよ」
ウツロは無言でセリナの後ろ姿を見つめた。異世界から来たはずのセリナの口から、さも当たり前のように『神』という言葉が出てくる奇妙さにたじろいだのだ。……信仰心が芽生えたのか、それともあくまで自然災害の例えとして神という言葉を選んだのか、ウツロにはわからなかった。そして折に触れて気になったのは、神殿側の者を指す言葉だ。
「なぁセリナ、『蚩尤』ってなんだ?」
ウツロの問いにセリナは振り返り足を止める。
「シユウ。……龍人を禍人と呼ぶのと同じか。むしろ神殿側ではあいつらのことをなんて呼んでいるの?」
問いを返されたが、なんと答えればいいかわからない。
「あいつらとは誰を指している」
「そっちの大将のこと。王様? ……羽を持ってるって」
「帝か」
ウツロの返答は答えとしては不十分らしく、セリナはそうじゃないと首を振る。
「帝も王も神も違くて、……ほら、種族としてなんて呼ばれてるのかってことだよ。例え蔑称でも『禍人種』って括りがあるでしょ?」
セリナが言いたいことをようやく理解した。
禍人という種族としての括りがあるように、神族にも種としての括りがあるだろうと問うているのだ。だがウツロは頭を捻る。……考えてみれば帝は種族として呼ばれたことがない。まさかそのまま『神族種』とは言わないだろう。
「獣人種、魔人種、賢人種……ラヴェル一族はなにに属しているのか考えたこともないな。神話の立場では神の使いだったり天使だったり」
「随分と特別扱いされてるんだね」とセリナは言うが、語気は冷ややかだ。「とにかくその一族は背中に翼を持つ……貪欲な梟という意味を込めて、蚩尤と呼んでいるんだよ」
セリナはくだらないとでもいうように先へ進む。螺旋を描く坂は夕闇のわずかな光さえも届かない翳りに入って視界が悪い。手すりもない絶壁なのでウツロは右手を常に壁に触れさせて慎重に後ろをついていった。踏み外せば底の見えない奈落が常に左に待ち構えている。
「『蚩尤が神の怒りに触れた』と言っていたよな」ウツロは再び問う。「それは……龍人の神話なのか?」
「そうだよ」セリナは振り返らずに応える。
「どんな話かわかるか」
そう問われたセリナの首が上を向く。何かを思い出そうとするときの無意識な癖だろう。ウツロはセリナのつむじを見つめながら返答を待った。
「全部は覚えてないかな……えっと――『梟は人々に塔を作らせた』、があって、少し飛ばして――『くらおかみは現れ、人々にここから去るようにと説き勧める』、最後が『神は怒り、荒れ狂い、塔を叩いた』……こんな感じだったと思う」
「塔……か……」
「一度読んだきりだしうろ覚えだよ。……重要なことなの?」
返事もせず沈思するウツロに無視された形となったセリナは怪訝に振り返り表情を読み取ろうとしたが、彼の頭は金色の頭蓋骨なのであった。
ウツロが思考に没頭したのは、二つの信仰に類似があるということだ。
神殿側のラヴェル信仰では楽園に蛇が現れたことで世に混乱が生まれた。
一方で龍人種側の信仰では神の怒りに触れたのは梟――ラヴェルが過ちを犯したと語る。
蛇と梟。禍人と蚩尤。敵対し合う両者で信仰が似通っている……きっと二つの民族間で過去に重大な出来事があり、その一件の責をなすりつけ合い火種となり、争いへ発展したようだとウツロは推測した。
――大昔に存在した楽園とは、この塔のことではないだろうか。
その塔で三人の娘――つまり獣人、魔人、賢人の種族が平和に暮らしていたのではないか。そこに現れ、唆したのは蛇か、梟か。
結果として世に混乱が訪れ、塔は神の怒りによって沈められた。逃げ延びた神族と獣人、魔人、賢人はマハルドヮグに根差し、塔の遺跡が残る地底に龍人は留まった……。
おそらくセリナは知らないまま誦じたのだろうが、引用した一節に出てきた『くらおかみ』とはおそらく闇龗。龍を意味しているのだろう。偶然にも元いた世界の知識がここで役立つとは。
さらに言えば、『龍』は神と同等の扱いだったはずだ。龍人が信仰している対象にも辻褄がぴたりと合う。
神殿は龍を邪なものとし、塔は神を荒れ狂うものと嫌う。鏡写しの対照的な構造がはっきりと見えてきた。
「なぁ、セリナ。龍人ってなんなんだ……?」
「それは――」
「私から話しましょう」と、暗闇の奥から男の声が割って入る。
姿が見えないが、そばにいたセリナがはっとして殺気立つのを感じ、ウツロも身構えて声の方をじっと睨んだ。
「初めましてでは、ありませんねぇ」
男の声はうねるように石窟の縦穴に響く。こちらに近づいてくる姿は闇に紛れ、輪郭だけがかろうじて捉えられた。
会うのはこれが初めてではない……とすれば――
「集落を焼いた者の一人か」ウツロは言い当てる。
「ご名答」男は指を鳴らし、内壁の灯石が青く光る。「ここで争うつもりはありません……せっかくここまでお越し頂いたのですから」
照らされた室内で男は頭を垂れて歓迎した。口元には柔らかな笑みさえ浮かんでいる。
対するウツロは会釈も返さずに男を見つめる。こいつが禍人の知将……此度の戦役で継承者を翻弄した詭計の首謀者……。
肩にかかるほどの長髪は毛先の一部が染色に痛み白くなっている。額の頭角を晒してこちらに対する顔は一目で病的と理解できるほど窶れており、目の下には墨をひいたように濃い隈がある。纏う衣服は寝巻きか外套か、裾の長いくたびれた生成の前合わせに草履を履いている。一見して凶器は持っていないようだが、集落では外套の内側に針の暗器を隠していた。おそらく今も懐に忍ばせているだろう。ウツロは構えを解きはしたが、警戒は怠らなかった。
「……ハラヴァン……!」セリナは未だ視線も厳しく、敵対関係であるウツロよりも一触即発の気配を纏っている。「なぜ私を裏切った……!!」
「裏切ってなどおりません」男――ハラヴァンの表情は崩れない。「あなたは出会ったときから空の器として完成していた。そしてその器を最適に使うのが私の使命でした」
「ならなんであんな糞喰らいに私を……!」
「無論、最適だったからです」
ハラヴァンの表情に険はないが、言い様は素っ気がない。
事情はわからないが仲間同士であった二人は確執があるようで、セリナ――いや、ここではニァルミドゥか――の怒りは収まらない。
「最適? 私を餌にする必要なんかなかった! 私が龍になれば――」
「いいえ。それは違いますねぇ……、もちろん感情の面では私も君を失うのは残念でしたが、しかし龍に至る絶望を迎えたヨナハを捨てるわけにはいきません。
それに、ヨナハが龍となれば失敗作であったユラも戦力として揃えられるのですから迷う手はありません」
両者の剣呑な言い争いはハラヴァンが優勢に見えた。余裕のある超然とした態度がウツロにそう思わせるのだろうか。
「実際、強かったでしょう?」ハラヴァンは不意に視線をウツロに向けた。
「……災禍の龍のことか」と、ウツロ。
「ええ」
「強敵だった」
「……ふふ、素直に認められるとかえって始末が悪いですねぇ。あなたはそれを倒し、ここまでやって来たのですから」
ウツロとハラヴァンに会話が移り、ニァルミドゥはむっとした表情で睨む。彼女は災禍の龍本体であるヨナハに取り込まれ、戦闘時の意識がなかったのだ。どれほどの脅威となってヨナハが前線を蹂躙したのかを知らないのである。
「でも、倒されたってことは最適解じゃなかった」ニァルミドゥは皮肉を口にした。
「おや」
「私が龍になっていれば――」
「もっと簡単に倒されていたでしょう」ハラヴァンが口を挟み言い返す。そして続ける。「言ったでしょう。あのときの最適解は君がヨナハに食われること。暴食を司る六欲の欠落者こそ、世界を喰むにふさわしいのです」
「私は――」
「君は傲慢ですねぇ」
ぴし。とハラヴァンは指をさす。
「傲慢は足を掬われる」
「そんなこと――」
「あるでしょう。君はヨナハの苦しみを知らないのにぬけぬけとそんなことを言って、あれに耐えられる自信がお有りですか?」ハラヴァンの指が地下へ続く階段を指差した。そして指先はすいっと滑り、ウツロを指す。「もし君が龍になっていたら、隣にいるこの鎧は倒せていたでしょうか? あとで後悔することになったのでは?」
ハラヴァンの問いかけにセリナは言葉に詰まる。ウツロには知らぬことだが、災禍の龍となったあの娘――ヨナハが身を置いていた環境を、責め苦を見たセリナには口が裂けても「耐えられる」とは言えなかった。結果的に今こうしてウツロの隣に立っているのも、ハラヴァンの采配の妙と言えなくもない。
反論の余地もなく黙ってしまったセリナに対してハラヴァンは語調を緩めて本題に移す。
「そろそろ教えていただきたいですねぇ、ニァルミドゥ。
ウツロとどんな関係が?」
言い争いにうんざりしたように、ハラヴァンの声にため息が交じる。
これ以上の論が立たないセリナも素直に答えた。
「……兄だ」
「あに?」
「兄妹なんだ。私も今まで知らなかった」
表情を崩さなかったハラヴァンであるが、微かに目の下が痙攣した。
継承者の忘形見である鎧と柔らかな白い肌をもつ娘、似ても似つかぬ二人に血の繋がりがあると言われても理解できないだろう。
「……それは……鎧を操っている術者と君が、ということですか」
「術者はいない」セリナはウツロに視線を送る。本人の口から話をしてくれと言いたいようだ。
ウツロは前に立ち、言葉を継ぐ。
「術者はいない。戦闘魔導具として扱われてきたが、二百年前にこの世界へ魂のみを召喚され、今日まで戦ってきた」
ハラヴァンは首を傾げる。
「足りません。……足りませんねぇ。
ニァルミドゥはあなたほど長命ではないはず。それに鎧の肉体も尋常ではない」
説明を求めるハラヴァンに、ウツロはほんの一瞬躊躇った。戦役は落ち着いてひとまずの決着がついたとはいえ、はたして目の前の知将にどこまで開示して良いものか。迂闊なことを言えば再び神殿に向けて策を弄するかもしれないと、言葉は慎重になる。
「……この体についてはわからない。
何度も言うようだが、先代継承者に喚び出されたとしか言えない」
「喚び出される前は」
「人間の体を持っていた。そのときは……ニァルミドゥと兄妹だった」
「二百年前ということですか。ならニァルミドゥはなぜこれほどまで若いのです?」
「むしろ聞きたい」ウツロは下手を打つまいと切り返す。「俺の妹はいつからここにいる。なぜこんな体なんだ。龍人とはなんだ」
ハラヴァンは腕を組み斜に構える。問いに答えないウツロに機嫌を損ねたような態度だが、返答を渋りはしなかった。
「……出会ったのも目覚めたのも二月ほど前のことです。彼女はこの塔の地下深くで倒れていました」
ウツロはセリナに視線を向ける。ハラヴァンの言葉に偽りはないとセリナも頷きで応える。
「外傷もなく、まるで私が来るのを待っていたかのように目覚めたのです…… なんの感情も持たず、四肢も動かせず、既に器として完成していた彼女に私は名を与えた」
「器……?」とウツロは呟く。これに答えたのはセリナの方だ。
「空の器。心を失くした人のことだよ。空っぽになった体に術を注いで……災禍の龍が生まれる」
教えてくれたセリナの目がウツロから逸らされていたことに気付かぬ兄ではない。心を失くしていたのならやはりセリナは――
「元の世界に絶望したのか」
ウツロは真っ直ぐにセリナに言った。兄妹でしか分かり合えない話にハラヴァンは立ち入らず、静かに傾聴する。
「……そうなるね」観念したようにセリナは続ける。「ひとりぼっちで、どうしようもなかった……」
この世界の門を潜るには一度死ぬ必要がある。俺と同じ手順を踏んだのであれば、セリナもまた命を落としこの世界へ迷い込んだということだ。
何故、元の世界で生き延びたはずのセリナがこの世界にいるのか。ずっと気掛かりだった。その答えは孤独と絶望ということか。
「だが、喚び出されるにはこちらの門を開く術者の手引きがいる。俺が先代継承者の術式に巻き込まれたように、セリナも何者かに招かれなければ転移など起こらない――」俺は再びハラヴァンを睨むように見つめる。「――本当にただ見つけただけか? 召喚や、それに類する陣を構築したのではないのか?」
「いいえ」ハラヴァンはきっぱりと否定する。「神がかりの継承者三人揃ってやっと開く門なのでしょう? 私にできると思いますか?」
もっともな返答だが継承者に対抗してきた知将だ、疑念は拭えない。しかし問い詰めたところで水掛け論にしかならない。ウツロは矛を収めた。
「それよりも、聞く限りではあなたもニァルミドゥも死を経験して召喚されたようですね。そのあたり詳しくお聞きしたいものですねぇ」
セリナはばつが悪い顔をして唇を噛み、ハラヴァンを睨む。
「言ってもあんたには理解できないことだよ」
「構いません。こちらだって龍人についてお話しするのですから、」ハラヴァンは頬に垂れた髪を一房指で摘み弄ぶ。「交換条件としましょう」
「結構だよ」セリナは拒否する。「龍人のことは私から話せばいい。あんたに話すことはない」
「寂しいですね」ハラヴァンは両手の指先をそっと合わせて悄気た態度をした。「信用を失って、私は孤独ですか」
「言っとくけど裏切ったのはそっちだから。ヨナハに喰わせた時点で信用なんて無くなって当然でしょ」
「では、蚩尤の秘密についてあなたに教えましょう」ハラヴァンはウツロに提案する。「山の頂に棲む忌わしい一族の秘密を。それこそ神殿との信頼関係が失われた今のあなたは、知る必要がある」
セリナはウツロの手を引いて上階へ向かおうとしたが、もう一方でハラヴァンはウツロの腕に縋った。
「次の百年も生きるであろうあなたは、真実を闇に葬ってはなりません。
ここで私の話を聞かなければきっと後悔するでしょう」
――後悔。
ウツロはその言葉に反応した。セリナを前にして意識の外へ忘れていたが、己の体は不死の鎧だということを思い出す。
妹を優先し他を蔑ろにしてはきっと道を誤るだろう。そしてまた後悔する――そんなのは御免だった。
「わかった。先にお前の話を聞く。その内容によって俺たち兄妹の事情をお前に明かすか決める」
その言葉にハラヴァンは目礼を返す。知将はすでに確信があったようだった。
結論としてハラヴァンの語った『龍人の由来』と『蚩尤の秘密』は密接に関係し合い世界の真実に迫るものだった。引き換えに明かすウツロとセリナの転生の話は、返礼としては安いほどである。
❖
私が、兄と血の繋がっていない兄妹だと知ったのは、事故からそう間もない頃のことでした。
212号室に見舞いに来る親戚の面々は突然の訃報に悲しみ、「これからは兄妹二人で頑張るんだよ」と励ますものでしたが、ある一人は訳知り顔で見舞いにやってきて、「別々に暮らした方がいい」と口さがなく兄を悪し様に言うのでした。
面食らった私は、どういうことかと訊ねると、その人は兄の生まれの事情を話してくれたのです。
『あんたたち、血の繋がった兄妹じゃないのよ。そんな若い男女が、親もいないまま一つ屋根の下で暮らすなんて、やめた方がいいわよ』
それを聞いて驚いたと同時に、これまでになんとなく感じていた両親の温度差の理由に気付きました。私と兄に対する教育の熱の入れようや普段の何気ない態度、親は巧妙に隠してきたつもりでも時折感じ取れる違和感……これと断定できない靄のようなそれが初めて言葉になって現れたと感じました。
家族で出かけるとき私が体調を崩せば予定を延期にするのに、兄の都合が悪いときは仕方ないと言って三人で出かけたり、成績や通知表に私だけあれこれと小言を言われるのに兄は放任していたり。てっきり兄がしっかり者だから自由を許されているのだと思い込んでいましたが、円満に取り繕っている家庭にちらつく疎外感の理由がはっきりして、腑に落ちた思いでした。
それでも、私にとっては兄は兄でした。
これまで兄妹として当たり前に過ごした日々が消えたわけではないのです。むしろ私は、これまで気づけなかったことに対しての後ろめたさを感じました。兄は自由を与えられていたのではなく、親の愛を与えられなかったのです。そばにいた私が気付くべきでした。
違和感を覚えていたのに兄の密やかな疎外感に寄り添いもせず親の愛を疑うことなく享受して、のびのびと学校に部活に邁進していた私は、むしろ兄から見捨てられてしまうのではないかと不安でした。
事故により親を失った今、兄までも私を置いていってしまうのではないかと考えると恐ろしかった。私にとって家族というものがどれだけ大切だったのか、失って初めて知りました。そして世の不条理がどれだけ凶悪であるか、孤独というものがどれだけ恐ろしいかを知ったのです。
父も母も突然失い、兄までも私から離れていってしまえば、きっと私は生きていけない。……これは心の拠り所という比喩だけでなく、現実の問題としてもそうです。怪我が回復するまでの手助けが必要でした。
――不遇な兄の悩みにも気付けず助けもしなかったくせに、麻痺に動かない私の介護を頼もうなんて虫が良すぎる。
……そんな私の悩みをよそに、兄は当たり前のように見舞いに通い、怪我の具合を気にかけてくれました。あれこれと世話を焼き、私の側で微笑みながら、「心配ない」と励ましてくれる。そんな兄を、一人の人間として尊敬できる人だと思いました。
兄の尽力のおかげで事故の怪我は順調に回復していき、同時に私の中にある想いが芽生えました。
初めは小さな火でしたが、悪癖のように気付かぬふりをして過ごしている内に火は勢いを増し、胸を焦がす焔となりました。
脳裏にはあの言葉が反響します。
『実の兄妹じゃないのよ。そんな若い男女が、親もいないで一つ屋根の下で暮らすなんて』
麻痺に動かない私の手を握って、「明日は動かせるようになるさ」と摩り温める兄を前に、私は平静を装うのも苦労しました。
――ねぇお兄ちゃん、私たち血が繋がってないんだよ……? お父さんもお母さんもお兄ちゃんのことを愛していなかったかもしれないけど、私は違うよ。
なんて、言えるわけもなく、私は秘めた焔を呑み込んだのです。きっとこれ以上兄を困らせては、兄妹の絆まで壊れてしまう。
――親の死という大きな悲しみと私の身体に残る事故の傷、これが兄を繋ぎ止めている。……なら、怪我が完治してしまったら……? 病室で過ごす穏やかな二人だけの日々は終わってしまう。……そんなの嫌だ。
そんな思いが麻痺という症状となって現れたように思います。
心の奥底で、私はこの傷ついた体が治らないでほしいと願っていました。
悲しみを乗り越える手前で、ずっと悲劇の妹を演じていれば兄からの愛を独占できる。いけないとわかっていても、心の奥底では、手足が動かないままでいてほしいと願ってしまう。
――私の気持ちに気付かないまま、妹としての私に触れてほしい。
――いっそこのまま治らなくたって構わない……。
――二人の日々が、ずっと続けば……。
兄は死にました。
あの日私を、病院を、街を襲った巨大な地震が平穏な日々を粉々に砕き、津波は私の前から兄を攫っていったのです。
世の不条理はこうも呆気なく、私の全てを壊していきました。
……いえ、これは私に対する天罰なのかもしれません。
私が身体を治したくないなんて願ったせいで、兄は死んでしまった。
残ったのは麻痺の治らない体と、親族の同情と、孤独な時間でした。
どこまでも愚かで欲深くて、救いようのない私自身に絶望しました。
❖
そう長くないセリナの話は、兄への想いを赤裸々に打ち明けた独白だった。
ただの兄妹という関係以上に膨れ上がっていたセリナの気持ちを、当の本人が他人事のように眉一つ動かさずに語るのでウツロはどう受け止めて良いものか言葉が出てこなかった。
「……そんなふうに思っていたのか」
「もう終わったことだよ」セリナの口調は頑なである。
この場にいるのが二人だけならいざ知らず、ここにはハラヴァンもいるのだからそう言うほかないのだろう。
二百年も昔の話だと片付けるのは簡単だったが、それはウツロの時間軸であり、セリナからしてみればまだ数月程度しか経っていない。
この世界で兄妹の間に流れている途方もない時間の齟齬が、セリナの態度をやさぐれさせてしまっているのかもしれないとウツロは悟った。
「愛を失い、君は器となったのですねぇ」ハラヴァンは妙に共感したように目を閉じてしみじみ頷いていた。
「嗤うつもり?」
セリナは片眉を跳ね上げるが、ハラヴァンは首を振る。
「決して。……愛を失うこと以上に強い絶望はありません。人は愛から生まれ、愛に生きるのです。その根源が欠落すれば、なるほど龍の器にもなりましょう」
セリナは鼻を鳴らしてウツロに目配せする。……あいつは狂ってるからほっとこう。
「……それで、自死を選んだのか」ウツロは先を促した。
「そうだけど、でも、死ぬ前に誰かに会った気がする」セリナは記憶を思い出そうと目を閉じて眉間に皺を寄せる。
「たしか……小さな女の子だった。でも、ただの子供じゃない気がした。やけに髪が長くて……妙に大人びていて……」
ウツロは思い当たる節があるようで、「冠みたいな角があったか?」と問う。
「角? ……あったら忘れなそうだけど、思い出せないや。見た目は私よりもうんと下で、幼いのに大人びて見えて、なんだか幽霊みたいだった。場所も避難先の知らない街だったし、『あ、普通の子じゃないな。ここは出る病院なんだな』って直感したんだ」
「それで? その子供が?」
「目が合っちゃってさ、子供が話しかけてきて、受け答えをしているうちに意識がぼんやり……気付いたら屋上から飛び降りてた」
「誘われたのか?」ウツロの声が荒れる。その子供に死へ誘われたのか。
「わかんないよ。私も不安定だったし、ただの幻覚かも。
結果として私が飛び降りたことに変わりはないし、次に目が覚めたらこの塔の底にいたよ。ハラヴァンが何かしたって感じでもなかった」
「……君が何者か、散々問い詰めましたものねぇ」と、これはハラヴァンの言葉。「蚩尤の遣わした者ではないと分かり、器として使えると考えてそばに置きました。切羽詰まっていましたから、恨まないでくださいね」
ウツロは無言であしらった。
ともかく、ことの経緯は理解できた。
残る謎は、誰が異世界の門を開きセリナを塔に召喚したのか。セリナが見たという幽霊の正体が召喚者と同一なら、疑わしい人物に心当たりはある。
そしてもう一つは――蚩尤の本懐について……。
「……ハラヴァンの話が正しいなら、すぐにでも神殿に向かう必要があるな」
❖
幌に揺られ続けた三日三晩の帰路を継承者三名は噛み締めるように過ごし、神殿へと辿り着いた。
山行の途中では、災禍の龍の放った熱線――正確には齧り取られた形跡を垣間見る場面もあり、迂回路を通ったが神殿に被害はなかった。白い門扉は始まりの日と変わらず、冠木の上から顔を覗かせる女神三柱の巨像もまた今日も厳しく外界を睥睨している。
アーミラは顎を上げて石像に視線を向け、被っていた頭巾がずり落ちて肩に掛かるのも気にせず眺めていた。
――なんだか災禍の龍みたい……。
神聖も畏怖も、そう変わらないものなのだろう。陽を浴びて白く輝く姿も、像全体の大きさも、偶然にも龍とよく似ていた。違うのは貌に目鼻がきちんと揃っていることだ。それだけの違いがあれば対話可能な知性さえ見出せる。
もう巨像を恐ろしいとは思わなかった……本当に恐ろしいものを知ってしまったから。
「よかった、まだ燃えとるな」
オロルは側に立ち、像に灯された焔を指差す。示された方にアーミラは目を凝らした。そこには赤々とした小さな灯火が長女の像に収められて燃えていた。ガントールの心臓である。
出征式典の折、執り行われた儀の一つ――『心像灯火』。神殿に住む者達の重ね合わせた大祈祷によってアーミラ達の命は非死となった。治癒力を付与され、肉体の急所となる心臓を神殿に預けることで生存率は底上げされた。が、不死には至らない。
前衛として幾度となく死線を潜り、命数を消耗したガントールは祈祷による治癒が底をついて倒れてしまった。失った両足も生えてくる気配はなかった。
像に収められた三つの焔を見比べてみると、確かに火勢には違いがある。それぞれが鞴で風を送られるように一定の律動で揺らめき、これこそが心臓の脈拍を意味しているのだろう。ガントールのそれは脈拍も弱く獣人の図体とは正反対に小さな火だった。次に小さいのは青みがかったアーミラの焔で、オロルの黄金色の焔は盛んに燃えてゆらめいていた。
「結局一度も目を覚さんかったが、あれだけ燃えておるならきっと心配はないじゃろう。ここには優秀な治癒師もおる」
さぁ、と中へ促すオロルを追いかけるようにアーミラは神殿の門を潜るが、一歩踏み込んだと同時に生ぬるい風を鼻に受けた。微かな身の危険を感じ取って前方に待つ神人種の列を見つめる。
歩みを止めたアーミラの様子に気付き、なにやら芳しくない状況を察してオロルは落胆する。
「……なんじゃ、歓迎してはくれんのか」
「いいえ歓迎致します。オロル様」そう応えたのは白衣の列の中央に立つ女、神族近衛隊隊長のカムロだった。「……此度の出征、御大義でありました。継承者の滅私奉公あってこその勝利であることを我々は確信しております」
淀みない言葉の割にその表情には戸惑いがある。久しぶりに見たカムロの姿が記憶よりもどこか危うく見えたことにオロルは何かしら込み入った事情があると掬し、不承不承に招かれるまま先へ進む。
後に残されたアーミラはその場から動かず、じっとカムロに対していた。出征前のアーミラであればここは確実にオロルの後ろをついて離れなかっただろう。アーミラなりの成長ではあるが、強さの内に荒んだ心が表れてもいる。
「用があるのは私みたいですね」
「はい」
姿勢を崩さず、堂々と白衣の隊列と向き合うアーミラに、かえってカムロの方がたじろいだ。後ろ手に携帯している細剣の柄を握り直す。
出征を見送ったあの日からまだ二月も過ぎていないというのに、目の前に立つ次女継承者はまるで別人のように感じられた。前線が人を変えてしまったのか、アーミラの元来の性格なのか……ふと思い出したように、カムロは他愛のない言葉を投げた。
「……随分と見違えましたねアーミラ様、記憶は取り戻されましたか?」
次女継承者アーミラは記憶を失くした少女だった。前線へ旅立つと決めたのも記憶を取り戻す手掛かりを求めてのこと。弱々しい雛鳥のような少女は、思えばそのときから羽を広げる予兆があった。
「全てとは言いませんが、それなりには取り戻せました。……代わりに失ったものも少なくはありませんけれど」
ざわりと隊列が緊張に身動ぎをして、アーミラは目を細める。
そしてカムロに問いかけた。
「なぜ敵意を向けられているのか、私にはわかりません」
当然の問いを前にカムロは真摯に頷き、隣に立つオロルも聞き逃すまいと見つめる。納得のいく答えが返ってくるのだろうか……。
カムロは覚悟を決め、真っ直ぐに応えた。
「前線での働きを我々は常に監視しておりました。
アーミラ様には先代忘形見である戦闘魔導具ウツロの乱逆を幇助した疑いがあります」
「は……?」オロルは失望したようにカムロを睨む。「何を言っておる」
「それだけではございません」カムロは続ける。「龍の光輪から現れた禍人を取り逃がし、自身の天球儀の杖だけでなく、長女継承ガントール様の神器と両足も喪失しました。これらの過失は故意によるものと考えられます」
オロルはわなわなと扼腕に震える。神族近衛隊の隊長ともあろう者が世迷言をよくもぬけぬけと……!
「よってアーミラ様には、戦闘魔導具ウツロの乱逆とその幇助。そして神器の喪失について責を問うため、身柄を拘束させていただきます」
カムロが言い終わると、白衣の兵が一歩前進し、アーミラを囲む輪を縮めた。
「待て待て待て!」
オロルはアーミラの前に駆け出して青褪めた顔で抗議する。
「なんも分かっておらん! こやつは首を切られたのじゃぞ!? ウツロの裏切りを幇助するわけなかろうが!!」
「身の潔白を証明するためにも、アーミラ様。どうぞ拘束に同意してください。抵抗せず従っていただければ手荒なことは致しません」
カムロに詰められ、兵はまた一歩輪を縮めた。オロルは予想外の窮地に汗が噴き出す。
――確かに潔白じゃ。アーミラを疑う余地もない。じゃが拘束されれば、いつぞやのように呪術を受けて眠らされ、洗いざらいに自白させられるじゃろう。そうなればアーミラは取り戻した記憶について語る。禍人種であるという事実が間違いなく明るみになってしまう! ……ならば拘束を受け入れるわけには行くまい……しかし、逃げ出すにも心臓は神殿につかまれておる……。
「待て! それ以上近付くなよ。わしの命令じゃ」
オロルは両手を兵の輪に向けた。手袋越しに刻印が光っている。三女継承の命となれば近衛隊の足も止まった。
「納得できん。血迷うたかカムロよ。お主はこの神殿一番の知の傑物であろう」
「これは帝の勅命である」
「……ならば帝も耄碌じゃな」
「無礼な!」
カムロは額に青筋を浮かべ、声を荒げた。だが、オロルは鼻を鳴らしてほくそ笑む。
「女神継承者の地位は帝と同等……無礼も失敬もないわい」オロルは胸を張って白衣共を睨む。「次女継承アーミラもまた帝と同等の地位に座する者と心得よ! ……勅命じゃろうが関係ない。『乱逆の責』も謂れのない冤罪じゃ」
息を呑み如何すべきかと板挟みに動けなくなる白衣の兵、左眄する視線を集めてカムロもまた沈黙してオロルを見つめる。
危うい場面を脱したかに思えたアーミラの胸に、不意に激痛が走る。
「――ぅぐっ……はぁっ……!」
「アーミラ? どうした!?」
異変に気付いたオロルはアーミラのそばに駆け寄る。アーミラは声にもならない激痛に喘ぎ、胸を押さえて膝をついた。
原因は刻印ではない……オロルは何が起きているのかを悟り、白衣の取り囲む輪の向こう、女神三柱の巨像を睨んだ。
近衛隊の一人だろう、石像の影に待機していた白衣の兵が今まさに鞣し革の手袋をつけて次女継承の焔を握っていた。心臓を鷲掴みにされたアーミラは苦悶の表情に脂汗を垂らしながら身動きができないでいる。そして三女の像の焔にも、耐火の手袋を着けた者が迫っていた。
心臓を直に触れられる気持ちの悪い圧迫感がオロルを襲う。
「近衛隊にとって、勅命は絶対なのです」カムロは言う。
「……正気とは思えん……!」オロルは言い捨て、胸の痛みに歯を食いしばる。そして負けじとカムロを睨み続けた。
対するカムロは決して勝ち誇ってはいなかった。
勅命に従いつつも本心では己が間違ったことをしているのではないかという葛藤が、瞳に暗澹とした迷いとなって浮かんでいる。
近衛隊は皆、神族の傀儡なのだった。
玉砂利に這いつくばい、オロルは目の前でアーミラが連れ去られるのを見ていることしかできない。こんなのは龍を討伐し神殿に貢献した継承者に対する処遇じゃない。
このままでは……アーミラが禍人だと明かされ、謂われない罪を被さり処刑されてしまう……。
――頼む……誰か……アーミラを……。
「『勅命』ってことは、やっぱり帝が怪しいよなぁ」
空から舞い降りる男の声に、神殿に集う者達は驚き目を奪われる。ここはマハルドヮグ山の頂き、雲より高いこの地において、下界を見下ろすことはあれど空を見上げることがあろうとは。しかし上空には確かに声の主がいたのである。
カムロは招かれざる客に眉を顰め、オロルは口角を吊り上げた。それがあまりにも禍々しい彗星に見えたからだ。思わず笑ってしまうほど、その者の姿は強烈な威光を放っていた。
「ウツロ……!」
「オロルにアーミラ……どうやら急いで正解だったみたいだな」
オロルは目を丸くしてウツロを見る。
口が利けるようになったことも、姿形の変化も、背に翼と尾を生やしていることも、この際どうでもいいことだと首を振って声を張り上げる。
「アーミラが狙われとる!」
「承知した」
ウツロは足元に群がる白衣の群れを一瞥し、女神三柱の巨像に張り付く神人種を見咎めた。ぴんと張った黒い翼膜がばさりと空を叩いて隼のように飛び、神人種の男の前に立ちはだかる。
男は一瞬で距離を詰められたことに肝を冷やし、怖気にみっともなく悲鳴をあげて腕を振り回すが、ウツロは避けることもせず鎧の体で受け止めた。厚手の手袋をつけていなければ指の骨が砕けていただろう。男は痛みに顔を歪めて手を庇い、とても敵う相手ではないと後退る。
「女神の心臓だろう? 頂いていくぞ」
腰砕けに石像の縁にへたり込んだ男を跨ぎ、ウツロはアーミラの心臓の灯の前に立つ。そして頭蓋骨が顎を開いて一口に焔を呑み込んだ。
オロルはアーミラの様子を見る。呑み込まれたことで火を失ってはいけないが……どうやら痛みはなさそうだ。それどころかウツロの頭は今も青い焔が漏れている。左右の眼窩に、顎の隙間に、アーミラの心臓がやや昂りに火勢を増して、ふしゅう。ふしゅう。と脈打ち火の粉を振り撒いている。
「ちょっと……! 早くしないと髪が燃えちゃうんだけど……!」と、ウツロの内側から女の声が聞こえ、「一旦退くぞ」とウツロが応えるように呟く。
――なるほど、背に生えた翼と尾は龍の娘のものか。鎧の内側に姿を隠しているようじゃな……。
ウツロと龍の娘が協力関係にあるらしいことをオロルは理解し始めていた。
「待ちなさい!」
翼を広げ、神殿から飛び立とうとするウツロにカムロが叫ぶ。
ウツロは石像の肩に飛び移り、眺めおろして続きを促す。まるで、「聞いてやらんでもない」と言いたげな態度だ。
「ウツロ……なのですか……?」黒い板金鎧の姿しか知らないカムロからしてみれば、まずそこから疑わしいほどの変化だった。
「そうだが」
「……何故神殿を裏切ったのです……! 二百年の忠誠は捨てたのですか……!?」
ウツロは腕を組み、次に痒くもない頭を掻いた。
「俺が従うのはラヴェルではない。継承者だ」ウツロは右手を出して名を呼びながら指折り数える。「デレシス、ラーンマク、アルクトィス。そしてガントール、オロル……アーミラ」
五つの指を握り、人差し指を立てて六人目を数えた。
ウツロは続ける。
「平和を願いその身を捧げる者のために俺は存在する。彼女らの信頼を裏切った蚩尤には、決して与しない」
外套を靡かせるようにばさりと身の丈を超える翼を広げ、ウツロは皆の視線を釘付けにして矢のように飛び去った。まるで嵐が通り過ぎたようだった。後にはどう沙汰すれば良いのかわからない混乱と動揺ばかりが散らかっていた。
「おい……」オロルは声を顰めてアーミラに囁く。「お主はこの混乱に乗じて逃げよ」
「えっ……」アーミラの瞳は不安げに揺れる。
オロルは励ますように頷き、肩に触れると時止めを行使して、アーミラを白衣の取り囲む輪の外へと導いた。この騒動でウツロはアーミラの焔を呑み、行方を眩ませた。それはアーミラの心臓を匿ったということ。助けたということだ。
きっと近衛隊から見ればよく映らないだろう。ウツロはともかくとして、アーミラまでもが禍人領と関係を結んでいると誤解されかねない。ここに留まれば確実に身柄は拘束され、あらぬ罪まで被せられることになる。
「事態がややこしいことになっておる……。お主にとって神殿は安全ではない……どこかに身を隠しておるのが賢明じゃ」
「でも……どこへ……?」
「わからん。思いついてもわしに言うな。わしは神殿に残る。下手に知れば自白させられるからのぅ」
アーミラはぐっと唇を噛み、涙を堪えてオロルの後ろを歩く。声もなく一筋の雫が頬を伝い、密かに洟をすすった。時の停止したこの空間では泣いたところで誰にも気付かれはしないが、それでもアーミラは咳上げる嗚咽を堪えた。
継承者として、神殿の兵戈として戦いに身を捧げ、活躍を讃えられることもなく追われる身となった我が身の不運を嘆いたのではない。失い続け、最後に残った友との確かな絆に胸打たれて泣いたのだ。それがわかっているからこそ、オロルは振り返らず手を引いた。オロルもまた、密かに涙を流していた。
「時止めの領域はここまでじゃ。わしは戻る……お主は行け」
オロルは目を合わさずに背を向けて言う。
「……はい」
涙声を隠し、アーミラは応えた。気丈に振る舞うことが二人の流儀であるかのように。
オロルの姿が白衣の輪の中に消え、時が動き出すとアーミラはすぐに物陰に身を潜め、誰にも見つかることなく門の外へ出た。
崖下に潜み、次女継承の法衣と袴を脱いで放り投げると、目的地も定めぬままに山を駆け降りる。何故だか脚は疲れ知らずだった。
アーミラは転げ落ちるように森林限界の高度よりも下まで山を降り、身を隠せるだけの林の中に入っても走ることをやめなかった。荒く息を吐き、目は爛々とし、枝が肌を掠めて薄く尖った下生えの葉が脛を切る。痛みなんて感じなかった。どこまでも激情に任せて走っていける気がしていた。
「うぁ――」
ついに小石に蹴躓いた。
アーミラは泥まみれに汚れた体でよろよろと立ち上がり、意地になってまた山を駆け降りる。もう隣にはガントールもオロルもいない。たった一人、追われる身になってしまった。
胸に渦巻くのは様々な感情からなる混沌である。その渦の中に悲しみがあり、怒りがあり、不安があり、懐かしさがあった。
神殿から命からがら駆け出す道が、幼い頃の記憶と重なっている。
……過去の私もこの道を逃げていた。神殿の者に追われるのは、これで二度目のことだった。
❖第三部❖
真理編
■013――汚れた血
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
ウツロとセリナが神殿へ向かう少し前のこと。
龍人の根城である塔の底にて、ハラヴァンは『龍人の由来』と『蚩尤の秘密』を語った。
この二つの事柄は歴史の中で密接に絡み合い、失われていた真実へと通じるものだった。
それはウツロにとって、足りなかった嵌め絵の穴を埋める決定的な鍵となった。
「人類はおよそ三つの種族に分かれています」
ハラヴァンはそう語り始めた。
「そしてそれぞれには固有の長所がある」
獣人種は体力。
魔人種は魔力。
賢人種は呪力。
この基本的な知識はウツロもセリナもすでに理解していた。元いた世界とは異なる特徴を持つ彼らについて、最低限の認識はある。
「次に、この世の神話において、突然人類の前に現れた種族が二つ。
一つは梟。今の蚩尤です。
一つは蛇。龍人種ですね。
神話では『梟』や『蛇』と呼ばれていますが、ご存知のとおり、どちらも人類に違いはありません。当然、龍人は龍人の親から生まれます。翼人もそうでしょう」
ハラヴァンは確認するように言った。ウツロとセリナは頷く。
「えぇ、そうです。人類は子を産むことで命を繋ぎます。無から生じるわけでも、闇から這い出るわけでも、まして天から降りてくるわけでもありません」
二人の頷きを見届けると、ハラヴァンはゆっくりと次の問いを投げかけた。
「しかし、ならば、歴史上に突如現れた龍人と翼人は、元を辿ればどこから生まれたのでしょう?
龍人は龍人の親から生まれ、親はそのまた親から……血脈を辿れば、龍人の最初の一人がいるはずですねぇ」
おそらくここからが本題だろう。
ウツロは意識を集中させた。
「その最初の一人はどうやって生まれてきたのか……まさか、無から生じた? ……そんなはずはありませんねぇ」
勿体ぶったハラヴァンの問いかけにウツロとセリナは互いを見合い、さして悩むことでもないと答える。
「異なる種族間の血を混ぜたんだな」
ウツロの言葉に、セリナも同意して頷く。
「とても慧眼ですねぇ。いやはや驚きました」
まさか一度目で正答を導き出すとは思わなかった――と、ハラヴァンは心持ち目を開き、手を叩いて二人を讃えた。
「……そんなに驚くことか?」
混血という概念は、ウツロたちのいた世界では珍しいものではない。
肩透かしを喰らった気分だったが、話を聞き進めるうちに理解した。
世界が違えば、文化も価値観もまるで異なる。
元いた世界の常識が、この地では通用しないのだと。
「驚くことですよ。もし答えるのがあなた方でなかったら、きっと百人に聞いたってこの答えには辿りつかないでしょう」
ウツロは実感が湧かず、おだてられているのではないかと肩をすくめて首を傾げる。そして「真面目に聴く価値があるのか」とセリナに視線を送る。セリナの方も戸惑うばかりだ。
「ふむ……、お二人はどうも不思議ですねぇ。この世界の有り様を異なる尺度から量っているみたいです」
その言葉にウツロはどきりとした。まだ明かすつもりはないと秘めていた真実を、兄妹二人が異世界から来たということを、鋭く掠めてみせたからだ。
ハラヴァンは決して馬鹿ではない。
今語っている話が、単なる与太話ではないと視線が伝えている。
「異なる種が現れたとすれば、大概の者はこう考えます。
『魔呪術で作り出された』、あるいは『天上の主が生み出した』のだと。
種族違いの血を混ぜるという発想は、普通ありえないのですよ」
「なぜ――」
ウツロはつい溢すが、失言だった。
「なぜですって? 二百年生きてきてわからないのですか?
蚩尤が掲げた戒律ぐらいはご存知でしょう、……あなたはこれまで、混血の人を見たことはありますか?」
――そうだ。
自らの愚かさを、ウツロは思い知る。
ハラヴァンの口調が厳しくなるのも無理はない。二百年間、一度だって混血の者に出会っていないことに気付くべきだったのだ。
元いた世界では、民族や国の血が交じり合い、それを戒める法も存在しなかった。
しかし、この世界では――
ウツロの脳裏に、ラヴェル法典の戒律が蘇る。
『生まれ持った種族に誇りを持つこと。そして隣人を敬うこと。しかし血を混ぜることは決してあってはならない』
この世界では、種族の血が交わることは、決して許されなかった。
だからこそ、混血の存在を知る者すらいないのだ。
それを『なぜ』などと問うたのは、墓穴を掘る愚行だった。
ウツロが種族に関して浅学だったのは、元いた世界の尺度で見ていたからだ。
例えば獣人を見たとき、ウツロの解釈は『半人半獣』となる。
その時点で、異なる生物の血を混ぜた亜人と無意識のうちに捉えてしまう。
魔人も、賢人も、同様だった。ウツロの目から見れば純粋な人間から離れていると見てしまうのだ。
そして、肉体を持たなかったという一因も大きい。もしウツロが――いや、アキラが――身体ごとこの世界に迷い込んでいれば衣食住の細かな差異にこれほど無関心でいられたはずはない。性に関する諸問題への理解だってあったはずだ。
「獣人と魔人の間に子が生まれたら、種族はなんでしょう?
魔人と賢人の間でも賢人と獣人の間でも構いません。
その子は、どの種族に分類されるのでしょう?」
ウツロは、ハラヴァンの意図を理解し始める。
答えたのは、セリナだった。
「血が混じった別の種になる」
「そうか、ハラヴァン。お前が言いたいのは……龍人も翼人も、元はただの人間だったということか」
「理解が早くて助かります」
龍人も翼人も、元は三種族の中から生まれた。……由来が同じであれば、この世界で突然姿を現した梟と蛇の意味も分かる。ハラヴァンが言いたいのは、そこに悪意がなかったということ。生まれてきた混血に罪はないということだ。
遠い昔、どこかの誰かが、異なる種の異性に惹かれることもあっただろう。まだ戒律もなかった時代かもしれないし、あったうえで逃れられぬ恋に焦がれた二人がいたのかもしれない。異なる種同士で育まれた愛が混血を産んだ。
掛け合わされた親の特徴が子に現れ、翼を持つ者、尾を持つ者が生まれた……これが混血種、『龍人の由来』である。
「自然発生したのなら混血は少しずつでも数を増やしていくはずだ。初めは受け入れられなくても人々は徐々に慣れて、いつかは受け入れるようになるはずだろう?」ウツロは問う。
「見た目は種族を選り分ける重要な要素です。背丈や肌の色、耳の形、頭角の有無……混血の知識を持たない者にとって生まれてきた子の姿は悍ましい異形に映るでしょう。どっちつかずの半々な外見、馴染みのない容姿で産まれた子を目が開かぬ嬰児の内に間引くことだって珍しくはなかったでしょうねぇ」
決して裕福とはいえないこの世界の生活水準では、健康体という確信がない赤子を育てる余裕はないだろう。農民であれ職人であれ基本は家族代替わりで生活を営むのだ。子は将来の労働力として期待され産まれてくる。外見はその重要な判断基準となり、混血児の特異な容姿は一見して健康体とは判断できず間引きの対象となる。……だからこそ混血に不吉な意味合いが付与されていった。
安定して食い扶持を確保する上で種族間の無用な交配が忌避されるのは当然の流れ……この世界が歩んだ歴史がウツロにもなんとなくわかってきた。
「……それでも身体の特徴が父母に似ていれば、どうしたって愛着が湧くだろう? そうやって間引かれなかった子がきちんと働き、健康であると理解されたなら、受け入れられたはずだ」
「そうですねぇ……混血が他の種族と優劣に差がなければ、人々は受け入れたでしょうねぇ」
ハラヴァンは口元に笑みを浮かべるが目は暗く翳っていた。察するにそうはならなかったということだ。
龍人が人より劣る――というわけではないだろう。
「特別な能力を持っていたんだね」と、セリナ。
「はい……獣人に備わっていた類稀なる体力の優位と、魔人、賢人に備わる魔呪術の才……本来一人に一つあれば良い能力……混血は本来持ち合わせることのない二物を授かった」
なるほど……と二人は理解する。なんと難儀な……。
子間引きを免れた混血の子供に待ち受ける受難は属する民族がないということの他にもう一つあるのだ。ハラヴァンが『血』と呼んでいるのは単なる血潮のことではない。この世界に科学や生物学などと言った学問は存在しないが、言い換えれば『遺伝』と言い換えて差し支えないだろう。
血を掛け合わせるというのは、遠い遺伝子を持つ親それぞれの優れた能力を顕性遺伝させるということ。三種族は固有の特徴が強いため混血による顕性遺伝も色濃く出る。実際、龍人は長い戦役を三種族と互角に争うだけの優れた才能を有している。
混血児は間引きを免れても人の輪に馴染めず、白い目で見られ蔑まれることとなった。他の種族より劣った外見を持って生まれ、しかし才能は優れてしまっている事実が反感を買ってしまうのだ。純粋な血を持つ者は劣等感をくすぐられ不満がたまり、混血の者は理不尽な迫害に憤る。
……だがあるとき、この迫害を免れた稀有な一族が現れることとなる。
「貧民ならともかく、生活に余裕のある者なら我が子を簡単に間引きはしないかもしれない――」
ウツロはこの時点でハラヴァンの語る内容が真実に即していると疑わない。
魔呪術に馴染みのあるこの世界の住人であれば龍人の由来がまさか三種族と地続きにあるという事実を受け入れられなかっただろう。それこそ元いた世界でも人類の祖先が猿であるという事実を長く否定し続けたように、嫌悪の感情から論理を無視して拒絶してしまうのだろう。
信仰に篤い者ならば「ラヴェル一族は神の遣いであり、天からやってきたのだ」と信じて疑わず、混血という説を一蹴したに違いない。
しかし、ウツロもセリナも異世界からの迷い人だ。混血や顕性遺伝といった知識をすでに有しており、まさに『異なる尺度』からハラヴァンの説が真実に触れていることを理解できていた。
その上でウツロは、話題を次へと掘り下げる。
「――迫害から逃れ、寵愛を受けて育った者がいてもおかしくはない」
ハラヴァンは投げかけられた疑問に待っていましたと目を輝かせた。
「その通り。生活に余裕のある上流層の一族からは、迫害を免れた龍人もいたでしょう。そういったごく僅かな混血の中に、翼を持つ珍しい混血が生まれました。今の蚩尤……ラヴェル一族ですねぇ」
上流層ということは、親の代から才能が秀でているということだ。
当然、その家系から産まれた混血児もより一層の才能を宿すことになる。
「神族として崇められるに至ったラヴェル一族には、他の混血と一線を画す白く美しい翼を備えた外見と、その魅力を底上げするもう一つの恵まれた才がありました――あえて言葉にするなら、『巫力』とでも言いましょうかねぇ。
恵まれた外見を巧みに扱い人心を惹きつける話術を駆使し、翼人を名乗ることで他の混血と線引きした。……いつしか自らを神と騙るようになったのです」
「それって……つまり蚩尤は、数ある龍人の掛け合わせの一つってこと?」
セリナの借問にハラヴァンは首肯した。
ラヴェル一族は龍人の迫害から逃れ、言葉巧みに彼我の線を引くことで新たな種族としての地位を獲得した。正体はただの人間であるにも関わらず、巫力を用いて自らを神の遣いと宣ったのである。
『その神々しさは目を潰す』とまで口伝される天帝の一族は、なんの神性も超常も持ち合わせていないのだ。……私達が尾を持つように、角があるように、翼があるだけ――ハラヴァンはそう語る。
「神殿でふんぞり返る翼人は神の使いではない。そして迫害された我らの体が禍々しいはずもない。禍人ではなく龍人と自らを名乗ることに何の僭称もないのは自明の理であります。
この姿は獣人、魔人、賢人の血が混ざる事で形作られる……自然な交配種族なのです。斯様に虐げられ、棲家を追われ、神殿に叩頭く者たちから蔑まれるようなことは、あってはならない。えぇ、断じて」
これが『蚩尤の秘密』……なるほどまさに貪欲な梟。龍人がそう揶揄して怨む気持ちもよくわかる。
こうしてハラヴァンが語った『龍人の由来』と『蚩尤の秘密』は、当初ウツロが予想していたよりもはるかに重要な事柄を明かすものと知り、それこそ混血のように混じり合って切り離すことのできない血の螺旋は憎悪と悲劇の連鎖を描いてみせた。光と闇の渦はこうして生まれ、長きにわたる戦役となったのだ。
しかし、ウツロはまだ全てを知ったわけではない。梟と蛇の始まりは理解したが、ハラヴァンの持つ知識の深淵はこれで全てではないだろう。
「『楽園』や『塔』については知っているのか?」
「ある程度は」ハラヴァンはやや得意気な表情をした。「ですが答える前にウツロなりの考えを開陳していただきたいものですねぇ」
気安く名を呼んだハラヴァンに対して内心動揺したが、てっきり取引にないことだと断られると思っていただけにその反応は好ましいものだった。つい先程まで敵対していたもの同士、一応の警戒は崩さずに、ウツロは自身の解釈を話すことにした。
神殿と龍人のそれぞれの信仰の聖地、楽園と塔は普通神殿と禍人領の対極に位置すると考えるだろうが、ウツロはその聖地が同じ場所を示しているのではないかという仮説を語った。今三人が集まり、立っている場所こそが件の塔であり、逃げ出した三種族と翼人が楽園と呼ぶ地なのではないか、と。
ハラヴァンはその仮説に概ね同意した。まるで薫陶を受けたようにしみじみ目を閉じる。
「我らを生み出した主をも疑うその冒涜的な知性が、私とあなたを結んでいる……」ハラヴァンはそう呟き、「……仰る通り、この地は遥か昔に楽園と呼ばれていた聖地です」と答えた。その口調は交誼の友のように穏やかである。
ハラヴァンにとって、ウツロは理解者たりえた。
まさか戦闘魔導具が、肉体を持たない異界の霊素が、世の理をこれほど深く知悉しているとは考えもしなかった。
これまで自身が展開する論について来れる者など碌にいないばかりか「気狂い」と言い捨てられて憚りないハラヴァンは、敵味方の関係を抜きにウツロを評価し、心を開き始めていた。……もし出会い方が違っていれば、此度の戦役の勝敗は大きく違っていたのかもしれない。
「歴史の流れとしては、まず三種族がこの一帯に根差し、質素ながら平和に暮らしていました。そこに龍人……混血が出現し、さらにその中から翼人が生まれたのです。
先程も話した通り、翼人は自らを神の遣いと騙り、信仰を集め、信者に塔を作らせた」
「ということは、楽園は三種族が住んでいた大陸全体のことで塔はその一部か」
「楽園の中心に建てたとは思いますねぇ。翼人の巫力や威光を示すためのものでしょうから」
ハラヴァンは続ける。
「由来や起源が悪ければ人々から恐れられ、禍人種と名付けられてしまえば誤解を解く機会は失われる。……龍人は忌避され、翼人のみが神族として君臨し続ける盤石な土台を築くことに成功したのです。翼を持たぬ禍人を形態異常と罵りながら……」
翼人にとって、混血種である龍人は、地位を脅かす存在でしかない。同じ源流から生まれた混血なのだという事実は秘したまま、権益を維持するため迫害の構造を利用した。
これが祈祷書の天使と蛇の関係だ。
点と点が矛盾なく繋がり線となるのをウツロは感じていた。それと同時に、ハラヴァンという龍人の知将に対する印象も変化していた。彼らが争うことの正当性も一理あるとさえウツロは感じている。むしろ、神殿の掲げていた正義がいかに翼人の私益に塗れているのかを思い知った気分だった。己の中で築かれていた正義と悪の構造が音を立てて崩れ、逆さまに積み上げられていくのがわかる。
背筋が冷える――鎧の体で得物を振い、有利な条件のもとで召し取った命の数々とその無念が、この背中に爪を立てているように思えた。正義の下で切り伏せた悪が、裏返って身に降りかかる罪咎となるのを感じていた。
「……ですが、純粋過ぎる血はどうでしょう? 近しい者たちで撚り紡がれた血はいつか破綻します。……そのことをあなた達は知っているのではないですか?」
罪悪感に苛まれるウツロを見て締めくくりに入ったかに見えたハラヴァンの話は、まだ終わらない。
ここからが真の本題だと言わんばかりに目を開いていた。
その熱量に圧倒されて口籠るウツロに代わり、セリナが短く応える。
「近親交配は罪だよ」
「そう、よろしくない。一族同士での交配は血が濃くなり、毒となります」
ハラヴァンは地下の空間を右へ左へ歩きながらセリナの言葉に続けた。
「現に翼人は、ごく少数の一族であるために自縄自縛に陥り、世継ぎに困っていることでしょう。そのため別の家系との混血は避けられず、神殿に優秀な人材を集めてる動きがある……神人種と呼ばれる神殿仕えの者たちも、そうした血の選別の一つなのですよ」
ハラヴァンはあまりにも神殿の事情に明るい。とてもじゃないが間諜が掻き集められる情報を超えており、内部事情どころではない暗部までも掴んでいるのがウツロには不思議だった。
口角に泡を溜めて語り続けるハラヴァンの勢いは止まらない。
地下の空間を往復する様は、正気と狂気の狭間を行ったり来たりしているみたいだった。
「しかし、神人種の肩書き付きとはいえ三種族の血を招き入れてしまえば民草の信仰を著しく弱体化させてしまいます。何故なら戒律に背くこととなりますからねぇ。自ら打ち立てた法を破っては……規律は乱れ、風紀が乱れる。内地から混血を、龍人を生み出しかねません。
さて、神人種は最善ではないとなると、翼人は誰の血を求めるでしょう?」
「三女神継承者だ」
突然割って入る男の声が、兄妹の背後から聞こえてきた。
二人は驚いて振り返り、闇に溶けた何者かを警戒する。
「早かったですね、ブーツクトゥス」ハラヴァンはそう言って迎える。
ブーツクトゥス――そう呼ばれた男の名に聞き覚えはない。ウツロはこれまで一度たりとも会敵しなかった間諜との邂逅に拳を固めて身構えた。対するブーツクトゥス本人は敵意のかけらもない足取りで灯りの下へと歩み出る。
「俺は勤勉だからな。……そっちはまた何か企んでるのか?」
「さぁ、此度の戦役も敗戦を喫したばかり……。予期せぬ客人をもてなしていたところですよ。企むことなどありません」
大柄な男の影が鼻で笑い、こちらへと向かってくる。ウツロはあまりのことに狼狽え、呆然と立ち尽くすことしかできなかった。
筋骨隆々な獣人種の大男……白衣こそ着ていないが、顎髭を蓄えた彼の顔はよく知っている。
「久しぶりだな。ウツロ」
「ザルマ――」
「おっと。お前さん、声が出るようになったのか」ザルマカシムはウツロの肩に手を置いて遮る。「だが今は、その名で呼ぶんじゃないぞ」
ウツロは判然としないままに首肯した。
どうやらこの男、ブーツクトゥスと名を偽って間諜を行っているようだ。ザルマカシムが真名かどうかも怪しいが、二つの名を用いて渡り歩いているとみえる。
「お前さんなら真実を掴んだとき、こちらに与すると思っていた。改めてよろしく頼む」
そう言って握手を交わすブーツクトゥスは、敵意どころか神殿にいた頃よりも友好的な態度である。心強い味方を手に入れたとでも言いたげな真っ直ぐな視線が注がれて、ウツロは難詰する気も失せてしまった。
……まさか神殿にまで間諜がいたことにも驚きだが、近衛隊の副隊長にまで昇り詰めたこの男が龍人と繋がっていたとは……。いや、上り詰め、翼人に近いところにいたからこそ真実を知ったのか。どちらにせよ、今のウツロは彼の裏切りを責める立場になかった。
それにこの男は、先ほどなんと言ったか。
「翼人は継承者の血を取り込むつもりか」
神人種はどれだけ優秀であろうとも武勲や功績は後天的に認められたに過ぎず、三種族の生まれ血筋は揺るがない。だからこそ血を混ぜては民からの印象が悪い。
だが継承者ならば……産まれたときに神に選ばれた娘ならば、それは刻印という形で女神の証明を授かっている。神人種よりも相応しい血として選ばれる正統な理由がある。女神と神族であればなるほど筋は通る……そういうことか……!
――なにが正統な理由だ……翼人は神ではないどころか、私欲のために女神継承者の娘までも穢そうとしている……!
こうしちゃいられない……ウツロは現状の危機に気付き、ザルマカシムに視線で訴える。龍人の由来、蚩尤の秘密という世界の真実に一足先に辿り着いたこの男であれば、神殿の動きも知っているはずだ。すぐにでも神殿へ向かいたいところだが、ザルマカシムはウツロの肩を叩いて宥めた。
「落ち着け、無策で神殿には挑めないぞ。準備が必要だ」
ザルマカシムの言葉は初めから継承者を救うつもりだと言いたげだ。……実際そうなのだろう。でなければ近衛隊に属する者が禍人と手を組むような危うい橋を渡りはしない。
「距離からみて、継承者もまだ神殿入りはしていないでしょう。焦らずとも猶予はあります」
それに、とハラヴァンは言う。
「まだ話の続きですし、この後はあなた方の秘密を教えて頂く約束ですよ」
「なら、続きを」
気が逸って仕方がないウツロに、ハラヴァンは少し脂下がり底意地の悪い顔をした。
「まぁ……実際にはもう手遅れなんですがねぇ」
「なんだと?」
「当代はまだ無事だとしても、先代は蚩尤の毒牙にかかっています。一族の血が濃くなったのは今に始まったことではありませんからねぇ」
「それはおかしい」ウツロは頭ごなしに否定した。「俺は先代の最後を見届けた。蚩尤の子を産んだ者はいない」
デレシス、ラーンマク、アルクトィス……皆、前線に倒れた。
四代目継承者たちは余生もなく壮絶な戦死を遂げ、神殿に帰ることさえなかったのだ。であれば先先代……いや、それほど昔に血を招いたのなら今に困ることはない。やはりこればかりはハラヴァンの推理は間違いだ。
だがしかし……ウツロの言葉は地下に虚しくこだまして、後には沈黙が広がった。ハラヴァンはまるでウツロを哀れに思うような細く遠い目をし、ザルマカシムは唇を引き結んで俯いていた。
「なんだよ……なんで、なにも言わない」
ウツロの不安げな声に、ブーツクトゥスは重い口を開く。
「そうか……知らないんだな」
「え……?」
「ずっと待っていたんじゃないのか?」ブーツクトゥスは心に問いかける。
「百年前――あなたは待っていたのでしょう?」これはハラヴァンの言葉。
出征式典を控えた夜明けにも、ブーツクトゥスは――ザルマカシムは百年前について訪ねていた。全く同じ問いかけだった。
『百年前の記録を読んだことがある。……なんで暴れたのかはわからないが、現れなかった次期継承者と関係があるのか? ……あの時何があったんだ?』
――まさか……そんな……。
ウツロはふらつくように後退りし、膝を突いた。意識が遠のく。
思考がひやりと凍りつくのを感じていた。同時に炙られるように熱かった。意識の隅にずっと身を潜めていた宿痾が疼き始めたみたいだった。
――ひゃくねん……百年、前……。
当代と先代には二百年の空白がある。まさに継承者不在の年。
ウツロは弛緩した腕を石畳の床に垂らし、首は暗い天井を見上げていた。思考はある一つの真実へと辿り着き、惨たらしい歴史の傷跡に触れてしまっている。
「……俺は……ずっと待っていた。
継承者を待っていた。現れるはずだった、五代目継承者たちを……」
ハラヴァンとブーツクトゥスは頷く。
セリナは、少し離れた場所から心配そうにウツロを見つめていた。。
ウツロは糸をそっと手繰り寄せるように声を紡いでゆく。縫い合わされた帳が開かれ、その先に待つ真実の姿が顕になっていくのを感じていた。
――俺の心を壊した孤独……。だが、この孤独が誰かの悪意によるものだとしたら……。
「……結局、神殿には、誰も来なかった……。死産と伝えられ、この代は継承者不在となった。
俺にとっては唯一の、長い孤独を耐えるための、希望だった……だから、俺は気が狂いそうになって、……いや、違う……気が狂って、暴れたんだ」
人の精神では耐えられない不死の時間。あまりに虚しい待ちぼうけの果てに夢見た待人との出会いは叶わず、ウツロは心を壊した。
セリナは兄の境遇を知り、側へ寄って背を支えた。微かに気を取り戻したウツロの首がブーツクトゥスに向いた。
「……本当はいたんだな。……そういうことだろ……」
「そうだ。出征式典の日、俺はお前さんに訊ねたな。『なんで暴れたのか』って、百年前の真実をお前さんが知っていて、ラヴェル一族と争ったのなら、きっとこちら側だと考えたんだ」
「そうか……ブーツクトゥス。お前は始めから、この世界を糾すために暗躍していたのか……。
俺は沈黙した。二百年の月日に心をほとんど失っていたから……」
「誰もお前さんを責めはしない。ばらばらに封印されて正気を保てる奴はいないだろう。……それに、今はここにいる」
「そう……悪いのはあなたではない」ハラヴァンは強い口調で言う。「殺するは蚩尤……あなたが邪魔になると見れば蔵へ封印し、現れるはずだった継承者嬰児を攫い、なにをしたか……もはや皆まで言う必要もないでしょう」
真実はあまりにも残酷すぎる。
百年前、蔵に封印されたあの時、神殿は許されざる悪事を働いていた。
ウツロは己の無力に打ちひしがれ、床に手をついて黙り込んでしまった。誰もかける言葉が見つからず、セリナは困惑してブーツクトゥスとハラヴァンを交互に見やる。セリナはまだこの世界に迷い込んでから日も浅く、彼らの会話全てを理解できたわけではないのだ。わかっているのは蚩尤という真の巨魁が、この世界を大きく歪めてしまったと言うこと。そしてその歴史に二百年加担していた兄が、正義を失ってしまったということ。
セリナにとって、それだけわかれば充分だった。
元の世界での兄は、常に懸命だった。弱者に手を差し伸べ、苦境にもめげずに立ち向かい、静かに世界と戦っていた。……そんな兄が道を見失っている姿を見ているだけで辛かった。
「……本当に、百年前の継承者は捕まったの?」
「本来の五代目継承者は、神殿の記録では存在しないことにされている」ブーツクトゥスは言外に含みを持たせ、代わりに前線の事情について触れた。
「『勇名』という称号は二百年前にはなかっただろう。この称号は、継承者不在の全線を支えた戦士に授けられたのが始まりなんだ。継承者不在の前線の負担を戦士に丸投げした見返りがこれだ。……吝嗇なもんだろう」
周り巡ってその称号が俺を真実まで導いた。そうブーツクトゥスは語るが、ウツロの心を慰めるには至らない。
そもそも、慰めの言葉などいらないのだ。ウツロは己の無力を悔い、怒っていた。
ハラヴァンは手を差し伸べて発破をかけてみせる。
「不都合は下民に押し付け、自らは享楽に耽る。蚩尤の本性は充分理解頂けたでしょう。
さぁ、立ちなさいウツロさん。我々龍人は戦闘に敗れても、戦争には勝たねばなりません」
そしてセリナ――ニァルミドゥに向けて、「今度は君の番ですよ」と言った。
「『龍人の由来』と『蚩尤の秘密』――どちらも重要な情報である。そして、それと引き換えに兄妹の過去を明かす約束だった。
❖
失われていた真実を知ったウツロは神殿を襲い、アーミラの灯を手土産に龍人の領域に舞い戻っていた。
継承者の忘れ形見――或いは神器ならざる戦闘魔導具であるところのこの鎧が災禍の龍討伐の瀬戸際で見せた謀反と、その後の奇襲。次女の灯を奪い去った事件は、神殿内外に早馬の伝聞として駆け巡った。
受け取る者達の反応は其々で、全く予期せぬ出来事と顔を青くする者あらば、初めから信用していないと掌を返す者もいた。いずれにしろこの鎧は神殿の管理下にある所有物で、同道を命じたのは帝である。当代戦役も終わりを迎えたと思っていた矢先に起きた前代未聞のこの事態に、次なる指示がいつ届くのか各国は固唾を飲んで見守っていた。今ごろ神殿は混乱していることだろう。それこそがザルマカシムの、いや、ブーツクトゥスの目論見である。
彼の立てた策はこうだ――
まず問題として、マハルドヮグに入山している者を攫い出すのは困難を極める。そのうえ長女継承は瀕死の身で自力で歩くことさえままならない。現状では継承者の娘三人を救い出すことはほぼ不可能であった。ならば謀叛を起こしたウツロが神殿に対し奇襲を仕掛け、その姿を衆目に晒すことで威圧を行うことにした。
目的は単純。『この戦役がまだ終わっていない』と印象付けることである。それによって蚩尤の魔の手が継承者に及ぶのを避けることができる。
「……ですが、龍人は生き残りの兵が足りません」
乾いた声音でハラヴァンは言う。当然龍人の兵を殺したのは他でもない目の前のウツロであり、これからウツロが助けようとしている継承者達なのだが、そこに対する感情を排して淡々と状況だけを添えた。
「残存する兵力でここから仕掛けるつもりはない」ブーツクトゥスの目は終始ウツロに向けられていた。「あくまでも『終わってないと印象付ける』だけだ」
双方に兵力の余裕はない。緊張を高めることで神殿は否が応でも警戒体制となり不審な動きに目を光らせる。翼人は継承者に手が出せなくなるだろう。急場凌ぎでも助け出すための時間を稼げるという算段である。
「しかし奇襲と言ったって、今から走って何日かかる」
ウツロは問う。塔から神殿までの距離は馬の脚で早くても七日を要すると考えていた。単騎で走るなら馬の替えもないのでさらに遅くなる。なら自分の脚で休まず走り続けるとしても、やはり間に合う距離ではない。道中では神殿からの兵が道を阻むこともあり得る。
「空を飛んでいけ」
「どうやって」と言いかけ、ブーツクトゥスの目線がセリナに向けられたことに気付く。
「ニァルミドゥに龍体術式を受けてもらう……翼があれば間に合うはずだ」
「なんだと……」
龍体術式は人を災禍の龍へ変える術式、おいそれとやっていいものではないはずだ。
「準備って……このことかよ……!」ウツロは怒りに拳を固めてブーツクトゥスに迫る。「人の妹をなんだと思ってんだ!」
襲いかかる拳をブーツクトゥスは大きな手で受け止め、もう片方の腕から振りかぶった二撃目も握りつぶし、そのまま押さえ込んだ。二振を越える巨体が覆い被さり、ウツロに迫る。
「お前さんは選べるだけ恵まれていることにいい加減気付け。この世界は過ちを繰り返し、もうどうしようもないところまで来ているんだぞ。
継承者を助けるか見捨てるか、妹を龍にするかしないか、どっちかしかない」
「く、そ……!」
抵抗は通用せず、ブーツクトゥスは睨み下ろして手を離すとウツロから離れた。腕を組み、返答を待つ。
ウツロは震える拳をじっと見つめた。
指を開き、また握る。逡巡しているのがよくわかる。
そして強く拳を握り、ブーツクトゥスへと顔を向けた。
「……だめだ。やらな――」
「やるよ」セリナは決然と繰り返す。「私はやる」
「セリナ……でも、」
「私の体は私のものだよ。決定権は私にある。今重要なのは蚩尤の野望を砕くことでしょ。敵だった継承者達を助けるなんて気乗りはしないけど、そうも言ってられないわけだ」
「……すまない」
「安心しなよお兄ちゃん。後悔なんてさせない」
勝気な表情で笑みを作るセリナの姿にウツロは感謝した。
妹の体に不可逆の変化を伴う選択と継承者の命運を天秤にかければ、後悔すると分かっていても妹が大事だった。それがセリナ自身の意思によって選択がなされたことに助けられたのだ。
何より、決断するセリナの姿に、親を事故で失う以前の面影を見たように思えた。心を病んでしまう前は竹刀を携え稽古に励み、男勝りな即断即決の意思があった。
「私の体はとっくに龍なんだ。むしろ無かったのが不思議なくらいだよ」
茶化した物言いにハラヴァンは生真面目に応える。
「それは私の落ち度でしょう。
君の絶望の形が捉えられなかったために、ユラと同様の不完全な覚醒になってしまいました。ですが今ならば、翼を授けることくらい容易い」ハラヴァンは懐に忍ばせていた喞筒を取り出す。
「……そういうことね……」セリナは腹立たしげに腕を差し出す。
「二本目が必要とは、君は本当に傲慢です」これはハラヴァンなりの皮肉か、少し笑みが見える。「ご安心くださいウツロさん。此度の龍は災禍にあらず、人の姿を維持しましょう」
こうして龍体術式を受けて翼を手に入れたセリナと共に、鎧は空を駆け抜け神殿へ飛んだ。アーミラの灯を救い出すに至る。
その後、ハラヴァン達一行は塔から前線へ向かう地下道を進んでいた。蚩尤の野望を砕くため、人目を避けながら水路を北進している。向かう先はもちろん神殿である。
ウツロとセリナは道すがら神殿の状況をブーツクトゥスに伝え、次女継承の灯を強奪するに至った経緯を説明した。
「なるほど、アーミラ様が濡れ衣を着せられたのか……」
「俺のせいで危うく処刑されるところだった」
「罪状は神殿側の建前だろう。アーミラ様を捕える理由をつけて、ラヴェルは奥之院へ隠すつもりだったと見ていい」
「奥之院?」
「ラヴェル一族の棲家だ。入れるのは神族と、限られた近衛隊の数人だな」
「でも……アーミラは継承者だぞ? そんな搦手を使わなくても女神と神族同士で婚姻でも結べばいいだろうに」
腐してこぼしたウツロの言葉。
ブーツクトゥスは顎髭を撫でながら考える。
「……確かに、疑問だな」
謀叛を起こしたウツロと次女継承は繋がりがないのだから、裏切られた側の娘として神殿は迎え入れればいいはずだ。優しく慰め、終戦の褒美でも与えて神族と友好を築けばいいはず……実際、長女ガントールと三女オロルにはなんのお咎めもないようだった。なぜ次女アーミラ一人だけ捕えようとしているのか……。神器を失ったことに対する責任を糾弾する意味はなんだ? 神器は武器である以上、戦闘で傷つくのは当然想定されるべきであり、天秤剣はウツロに奪われたとしてもそれを責められるのはガントールであるはずだ。天球儀の杖を破壊されたアーミラが責められるのは筋が通らない。
――ラヴェルは何を考えている……? ここにきて見えなくなってきやがった……。
「それで、これからどうするの?」
セリナは問う。四人は暗く湿った地下の水路を辿って神殿に向かっているものの、辿り着いた後のことはまだ何も決まっていない。成り行きで寄せ集められたこの四人では利害こそ一致しているものの目指すべき目標がまるで違うのである。このまま揃って移動することに意味はあるのか? セリナはそれを訊ねていた。
「俺は神殿に戻る。あんまり留守にもできないんでな」ブーツクトゥスは言う。
「私は一度前線の様子も見て回りたいですねぇ」こちらはハラヴァン。「少し遅れてから勇名に紛れて神殿に忍び込みますよ」
「そんなことができるのか? 禍人は結界を越えられないだろう」
ウツロの疑問にハラヴァンは自嘲するように口角を吊り上げた。
「私には通用しません。ブーツクトゥスと同じようにもう一つの顔がありますから。……先に潜り込みますが、ニァルミドゥは地下の私室を覚えていますか」
セリナはこくりと頷く。
「……では全てが終わった後に、そこで落ち合うとしましょう」
ハラヴァンの指示にブーツクトゥスが続けた。
「二、三日すれば次女継承の身柄を捕えるために兵を出す。俺がそうする。手薄になった頃合いを見て二人は攻め込め。
地上ではお前さんを捕えるための戦力も相当数出ているだろうからこのまま地下を進めよ。水路はスペルアベルまで続いてるから掻い潜れる。その後は空を行け」
なるほど。と、ウツロは会話の中から全体の動きを理解した。
つまりブーツクトゥスは神殿に何食わぬ顔で帰還し、ザルマカシムとして振る舞いアーミラ捜索に兵を外に出す。
ハラヴァンは前線を経由した後で神殿に忍びこみ、俺とセリナが奇襲をかけた裏で蚩尤に攻め込む。ガントールとオロルを連れ出した後、地下に身を隠して合流するということか。
地下水路の分岐を前に、ハラヴァン、ブーツクトゥス、ウツロとセリナはそれぞれの背を見送り別れた。
ザルマカシムが設定した三日間という束の間の暇は、暗い水路の中であっという間に過ぎていった。
❖
ナルトリポカ集落跡地ではオロルが一人、ぼんやりと空を見上げていた。
纏う衣装は長旅を共にした曼荼羅模様の外套ではなく、神殿お誂えの白衣である。残暑の日差しに眩しく照り映えた上着を羽織り、腕を通していない袖がはたはたと風に躍っている。
「……祈りの火じゃ。これを飲めば願いが叶う……」
空を見上げたまま呟く。
誰かに向けた言葉ではない。オロル自身に向けられた彼の言葉を手持ち無沙汰に転がしている。
煤の取れない煉瓦積みの塀に腰掛け、靴を地面に脱ぎ散らかして裸足を揺らす。
「……女神の御呪がに。火ば石ん宿したら、そいが護っちくれる……」
普段のオロルらしからぬ、物思いに耽る少女然とした姿がそこにあった。
ナルトリポカのこの地は、以前は集落の広場であった。
禍人の奇襲に畑を焼かれ、家屋を焼かれ、命を焼かれた。
斃れた者達の亡骸をアーミラが弔って久しい。今では遺灰も供養されたか、はたまた風に流されたか消え去っている。焦げ付いた壁面と粉を吹いたように汚れた灰の名残が灰燼に帰した景色を黒白に染めている。目を閉じればまだ焼けた臭いが香ってくるようだった。
なんの目的でオロルはここにいるのか。まるで待ち合わせているような態度でその場から離れず、時折あたりを見回しては、また空を見上げていた。
「む……来たか」
不意にオロルの声が鋭くなり、金色の目が細められる。
見上げている雲の向こう、きらきらと輝く彗星が昼の空を滑っている。
オロルはやおらに立ち上がると、その飛翔する者へ向けて手を振った。
南方より飛来したその彗星は手を振る者に応えたか、不意に速度を緩めると急降下を始めた。点の大きさが近づくにつれて渡り鳥程になり、人の形を判別できたときには地鳴らしの衝撃が臓腑を揺らした。
「相変わらず元気そうじゃな」
待ち人の到来に跳ねた土を払って、オロルは予期していたものが予期した通りに現れたとでもいう風に特段の驚きもなく出迎えた。
「やっぱりオロルじゃないか」日緋色金の頭骨を据えた鎧が声を弾ませて再会を喜ぶ。「丁度良かった。……ガントールは一緒じゃないのか」
「すまんがわし一人じゃ」オロルは短く応える。
「そうか……神殿から連れ出しに来たんだ。こんなところにいるなんて、見逃すところだった」
オロルが手を振って居場所を示したから気付けたが、そもそもとして、なぜ他に誰もいないのか、こんな場所で何をしていたのか、空から会話を見下ろしていたセリナはふと疑問が湧いた。まるで待ち構えていたみたいじゃないか……。
僥倖に安堵するウツロは無警戒に歩み寄る。セリナが兄の油断を咎めた。
「待ってお兄ちゃん!」
その声とほぼ同時、ウツロは不意に現れた巨腕の横薙ぎによってオロルの間合いから吹き飛ばされる。丸太のようなそれが勢いよくウツロの左頬を叩き、爆ぜた火花の明滅が一撃の重さを語っていた。
広場は灰を舞い上げて視界不良となり、煙った集落跡地の中で瓦礫が崩れる音が響く。いくつもの軒を薙ぎ倒してウツロは広場の離れまで飛ばされてしまった。何が起きたのか、セリナはかろうじて目で追えていた。
気を許し接近したウツロに、三女継承が攻撃を仕掛けてきたのだ。
八本の太い柱を召喚し、ウツロに重い一撃を見舞ったのである。衝撃にウツロの体は容易く殴り飛ばされて火花を散らし、きりもみしながら瓦礫を貫いて姿が見えなくなった。
ぐるりと回転の名残を残し、八本の柱がその全容を顕現させると、ずしん。と大地に脚を降ろす。セリナはこれが三女継承者の神器『柱時計』だと遅れて理解する。言葉に聞くその神器の外見は、セリナの知る時計とはかけ離れており、どちらかといえば蜘蛛のようだった。祭りの山車や近代芸術として制作された意図的な異形の絡繰、機械仕掛けの巨大な蜘蛛……。
オロルは蜘蛛にぶら下がり、八本の脚がウツロへ追撃に移る。
「させない……!」
戦闘を止めるためにセリナは咄嗟の判断でオロルに攻撃を仕掛ける。が、背後を捉えたと確信した次の刹那には姿を見失い、戸惑う背中に向けて足癖の悪い踵落としを喰らった。焼けこげた家屋の瓦礫に叩きつけられてウツロの横に倒れる。焼け残りの瓦礫に倒れるまでの全ては一瞬の出来事で、セリナには何が起きたのか信じがたかった。雷にでも打たれた気分だ。
凄まじい速度で繰り出された一撃……もしこれが踵でなく神器の柱であったら……鎧の体でさえ起き上がれない一撃をまともに喰らっていたら脊椎が圧し折れていただろう。
痺れる身体でなんとか起き上がり、呼吸を整えて三女継承を睨むセリナ。オロルは毒虫でも見るような目で眺め下ろす。
「龍の翼に、尾っぽに、頭角。……災禍の龍にしては弱いのぅ。今日は鎧の中に隠れんのか?」
「……煽らないでよ……腹が立つから」
これから助けに行くはずの相手に痛めつけられて、セリナは苛立ちを隠せない。
「腹据えかねて結構」
そう言ってオロルは固めた拳でセリナの頬を殴打する。白い手袋の内側に収められた彼女の手は節くれ立って硬くごつごつとしていた。石を詰めた雑嚢で叩かれているみたいにセリナの頬は腫れ、視界には星が散った。
曲がりなりにも大義のため、蚩尤の野望を砕くためとはいえ、目の前の継承者は数多くの同胞を殺したことには変わりないのだ。助けてもらう立場なら、もっともらしく神殿の奥で手足でも縛られていてくれればいいのに。追われる身となった次女継承や昏睡状態の長女継承はまだ助け甲斐があるというもの。なのにこの三女継承は憎らしく待ち構え、いきなり攻撃を仕掛けるとはどういう了見なのだろうか。
「ところで聞きそびれたんじゃが、ウツロはお主を見てアーミラを裏切り、お主と共に神殿に現れた。……何者じゃお主は?」
「……殴る前に聞いて欲しいね」セリナは唇にできた裂傷を指で拭い恨み節を言い、名乗った。「セリナ・ニァルミドゥ……二百年ぶりに再開した。私はウツロの妹だよ……」
「……は? 妹、妹か――」
オロルは片眉を吊り上げた後、さして面白くもない冗談が笑壺に入ったみたいにくつくつと笑い出す。
「こりゃ予想できん。あの鉄の塊に妹がいるとはのぅ……。
お主、血を分けたか」
「血は……」セリナの表情が曇る。「どうだろうね」
「じゃろうな。……なかなかどうして、なんの巡り合わせかのぅ。
まぁよい。ウツロ、お主もよく聞け」
オロルの声にウツロは瓦礫を押し除け上体を起こす。これしきでくたばったわけではない。
「お主らはわしを連れ出しに来たと言ったな。じゃが儂が、継承者であるわしが、黙って従うわけにはいかん」
「継承者だからこそ戦ってる場合じゃないんだ――」
ウツロの言葉に聞く耳を持たないとオロルは首を振る。
「黙っておれ。禍人共が今更なにを企てようとも無駄じゃ」
「蚩尤はあんた達全員を騙してる! あのアーミラって人だって酷い仕打ちだったでしょう!?」
セリナも説得を試みるが、オロルは掌を向けて制するのみ。
「不毛じゃ。主らは敵に言葉を尽くしたか? それで戦が終わったか? 違うじゃろう。わしも、主らも、問答無用で殺し合ってきたではないか。
わしを従わせたくば捩じ伏せ、腕の一本でももぎ取って見せよ」
狷介固陋なオロルの態度に、ウツロは致し方なしと項垂れて得物を握る。首を垂れて頭を外すと、襟の隙間から一振りの斧槍を引っ張り出した。
それは鎧の内側に収めていた斧槍であり、イクスから授かった業物である。
「立てるかセリナ」
「……龍人を舐めないでよね……」
口では強がりながらもセリナは額に汗が滲んでいた。三女継承の恐るべき素早さを前に太刀打ちできるか、彼女にとっては初めての対継承者戦……どうしたって身体が緊張に強張るのを感じていた。
ウツロはそんなセリナの様子を見て、妹が決して手練ではないことを悟る。
集落を燃やした三人の一人ではあったが、実行犯はダラクという男だったのだろう。それからも戦闘でセリナを見ていないことから実戦の経験は浅いと見た。人を殺めた数が少ないというのは兄として喜ばしいことだが、オロルを相手にしたこの状況は死線である。
兄としてオロルの壁になるようにやや前に陣取り、セリナを後衛に立たせた。とはいえ、時止めの脅威に対応できるとは言えなかった。
無言のままにじっと睨み、出方を窺う。
「……焦らしよる」
オロルの呟く声――それが耳に届くよりも先に懐に潜り込まれている。
先手を取ろうが後手に構えようが、人の反応できる速度ではないのだ。
――まずい!
思考より速く、柱時計が面を叩いた。灯緋色金同士がぶつかり、火花を散る。
耳をつんざく衝撃音が残響し、セリナのすぐ横をウツロが吹っ飛んでいった。からん。と斧槍が転がり、セリナはやっと振り返る。
「お兄――」
一瞬の無音。
瞬きする間に、視界いっぱいに三女継承の姿が広がった。
褐色の小さな裸足が鳩尾に深く沈み込む。
セリナは血反吐を吐きながら驚愕する。攻撃の予備動作すら目に捉えられない!
小柄な身の丈に見合わない重い一撃にセリナは身体を丸めて地面を転がり、龍体となった皮膚からは鱗が剥がれて血が滲む。
ただただ三女継承の権能に困惑した。
「時を止める力……強すぎて卑怯でしょ……」
「……そりゃあ龍人が勝てない訳だ」ウツロはまだも黒焦げた瓦礫の山から起き上がる。
「で、どうするのさ? 弱点とか知らないの?」
「生憎だが、オロルに弱点はない」
「……はっ――」
ウツロの断言にセリナは思わず笑う。悪い冗談にも程がある。
それでも、災禍の龍は継承者達を追い詰めた。龍体術式は彼女たち女神に対抗する唯一の手段なのだ。私は……それを二度も受けている。
――何かあるはず……。三女継承を倒す力が……。
思考に沈くセリナの面持ちはここにきて凛々とする。心はまだ折れていない。
「無駄じゃ。わしに勝てるなどと思うな」
オロルは緩慢な歩みで二人に近付く。それに対してウツロは立ち上がり、拳を構えた。
「どこを見ておる」
ウツロの頭骨を模した面鎧の眼窩は睨む対象を見失っていた。オロルの声はすぐ下から聞こえる。
「ここじゃ」
間合いはすでに触れ合うほど。オロルは胴鎧に掌を這わせ、込められた魔力が炎のようにゆらめくと光線が放たれた。激しい光がウツロの鎧にぶつかり反射して、仰け反った身体を踏ん張り光線を受け止める。
放たれた先で行場を失った閃光が不規則な軌道を描いて付近を焼いていく。尻に火がついたようにセリナは慌てて飛び上がり這々の体で回避した。間抜けな様を眺めてオロルの口元に、きり、と小さく冷笑が浮かび、反撃に出たウツロを見もせずに柱で殴り飛ばす。
――遊んでるつもり……!?
ウツロには容赦なく柱をぶつけ、私には素手……偶然ではない、三女継承は意図して手心を加えている。そう確信してセリナは怒る。
「こいつ本気……! 泣かすから!!」
吶喊の声と共にセリナは翼を広げてオロルに迫る。手の届く間合いまでほとんど一足飛びに詰めると腕を振るった。しかし爪は空を切る。目の前に居たはずのオロルは霧か幻のように忽然と消えていた。
セリナは遮二無二両手と尾を振りまわして擦り傷だけでも負わせられないかと暴れてみせたが、虚しい風切り音だけが響いた。
一方ウツロは転がる体を立て直し斧槍を拾っていた。仮にも二度の出征を戦い抜いた戦士、手堅く立ち回り形成逆転の機会を逃すまいと得物を握っている。その背にオロルは迫るが――
「おっと」
静止空間の中、オロルは痛みに脚を止めた。
隙だらけに見えたウツロの懐に潜り込もうとして、知らぬ間に怪我をしていることに気付いたのだ。飛散している鱗か火花で皮膚を切ったか、頬を撫でるとぬるりと手袋が赤く濡れた。傷は深く、両頬を串刺しにでもされたように口内まで血の味が広がった。
何事かと怪我の原因を探し、初めて罠に気が付いた。
ウツロの周りには砂粒程の塵が舞っている。灰や瓦礫に紛れているために意識していなかったが塵の中に金属質のものがあり、鋭く尖った刃が立っている。それは触れるものを切り裂かんとオロルを待ち構えていた。どうやら知らぬ間にやられていたらしい。
試しに一欠片を指先で触れると、刃は恐ろしい速度で回転して指先を切り裂き、オロルの手を逃れて再び静止した。弧を描く軌道から、ウツロを中心に円を描くように刃が展開されているのだろう。
原因がわかり、改めてオロルは全身を確かめる。頬に一つ、腕に三つ、脚に一つ……細く深い切り傷から血が流れていた。
「……天秤の破片……?」
一歩退いて頬を撫でる。赤い指先を見て、オロルの眉がわずかに動いた。
「なるほど……意のままに操る、か」
となれば浮遊している刃の一粒ひとつぶがウツロの身体と繋がっている。不用意に触れればこちらが斬られるだけでなく、接触による静止空間への割り込みもあり得る――おそらく指が触れたことを、ウツロは感覚したじゃろう。
流石じゃな。とオロルは声に出さず称賛した。
これでは時を進めるのも億劫だが、神殿から持ち合わせた魔鉱石も潤沢ではない。そう考え、オロルは時止めを解除した。
想定通り、ウツロから反撃が迫る。
縮地で間合いを詰め、横一閃に振り抜いたウツロの一撃はかがみ込んだオロルの頭上を掠め風切り音が唸る。二撃目が来る前にウツロの胴を蹴りながら飛び退いて、刃の結界に包囲されないようにオロルは立ち回る。時の流れを絞り慎重に躱していくが、間隔が狭い所では白衣の裾が裂けるのも仕方がないと諦めた。
戦う覚悟を決めたウツロは流石の手強さである。打たれ強く、疲弊もしない。長期戦となれば敵う者はいないだろう。
オロルはちらと龍の娘を見た。石が尽きる前に戦力を削ぐか――そう考えて振り向けば、娘は両手を突き出して構えていた。
「……なんじゃ……?」オロルは眉を顰める。
龍の娘は一見して合掌の手を前方に突き出す体勢だが、よく見れば両手は逆さに捻り、甲を合わせるようにして指先を伸ばしている。空間の一点に向けて力を込めている様子だった。時の流れを絞っているため、これから何をするのかはまだ判然としないが、これまでの禍人が漏れなくそうであったように、何かをしでかすつもりだということはわかった。阻止するのが賢明だろう。
オロルは時の流れを堰き止め、わずかに躊躇いながらも柱時計をセリナに向ける。ウツロにとって大切であろうこの娘を手に掛けるのは気後れするが、術式を破壊するために最大火力をぶつける覚悟だ。
「慈悲は尽くした。すまんが消えてもらう」
静止空間では術の重ね掛けはできない。オロルは掌をセリナに向けたまま呼吸を整え、命を召し取る腹を括った。
――この娘にはもう手ごころは施した。尻尾を巻いて逃げることだってできただろうに、……それでも尚わしに挑むのなら死は免れん。
堰き止めていた時を進めると同時、柱時計の風防から熱線が放たれる。この光は龍の娘の体を焼き焦がすだろう。そしてウツロの逆鱗に触れ、袂を分ち殺し合うのだ。オロルはそう考えていた。
「月輪――」
縷々と娘の声が聞こえる。
放つ熱線の先、セリナは両腕に渾身の力を込め、不可視の門扉が左右にこじ開けられていた。
何が起きているのか。
この娘は何をしでかしたのか。
オロルは迸る光の向こうに目を凝らす。
セリナは空間を断裂させ、亜空間へ繋がる門を生じさせていた。柱時計から放たれる熱線はその無限の穴の内側へ呑み込まれ、セリナには届いていなかった。
そして熱線の全てを呑み込むと、静謐を保つ濃い闇の向こうから一振りの剣を取り出した。
「――竹取」
唇で小さく紡いだ言葉は剣の銘だろう。
『月輪・竹取』
亜空間から取り出されたその得物は、名が示す通りの月光にも似た燐光を纏っていた。淡い火の粉は焼けた鋳鉄の荒ぶる熱とは異なり、まるで夜の竹藪に舞う光虫の煌きのようである。
眩しい剣身は刃を立てるには太く鈍角で、それこそ若竹の幹に似て飾り気がない。燐光を纏う以外は円柱形の棒としか形容できなかった。
しかし、本能でわかる。
オロルはどちらかといえば理性の質だが、あの剣は『研ぎ澄まされている』。
幽けき夜闇を剣の形に押し込めたような威圧感は尋常ではない。柄を握る手を緩めればそこから闇が溢れ出て空を覆うのではないかという想像に囚われる。現に剣を手にした龍の娘の佇まいも別人のように超然として、握り込んだ指が硬く白んでいた。
「腕を叩き切れば納得するんだね……?」
見慣れぬ型。セリナはすっと背筋を伸ばしながら重心を低く蹲踞に構え、両手で柄を握る。「その棒で切れるものか」とオロルは言えない。時止めを挟み、可能な限り間合いから離れた。
そんなオロルの背に声がかけられる。
「捕らえたぞ」
静止空間内で他者の声を耳にするほど恐ろしいことはない。オロルは背筋を粟立てて振り返る。少し離れたところでウツロのくり抜かれた眼窩と視線がかち合った。
「日緋色金が触れている」
「そのようじゃな」
淡々と告げるウツロの言葉の意味を、オロルはすぐに理解する。
柱時計に天秤剣の欠片が突き立てられたのだ。こうなってしまえば探して取り除くことも難しいだろう。だが時止めを共有するウツロは攻めてくるどころか体を動かせないようだった。
「ふむ……神器同士の接触では介入できるのは意識までか」
神器同士の接触と身体の接触では条件が違う。
ウツロは静止空間内に侵入できていない。……だというのに、ウツロはそれで構わないとでも言いたげな態度で気安く話しかける。
「らしくないな。俺とお前が戦う必要なんてないことを、本当はわかっているだろう」
「知ったようなことを抜かすな能無しが。少し見ない間に随分と賢ぶるようになったものじゃな」
「オロル――」
「その金ぴかの頭に少しでもものが詰まっているというのなら考えるんじゃな、なぜわしがお主と戦うのか。……それでなければ娘の方がまだ救いようがあるわ」
停戦の呼びかけも虚しく、オロルはウツロを突っぱねる。……が、これはオロルなりの本音であろう。
ウツロは静止空間内で素直に沈思する『なぜわしがお主と戦うのか』。
救い出すのがこちら側の都合なら、それを拒まねばならないオロル側の都合というものがある。それは何か。
実はオロルはその答えも伝えていた――『継承者であるわしが、黙って従うわけにはいかん』――言葉通りに受け止めれば、神殿のために戦い、使命を全うしているのだと考えられるが、そうではない。そうではないのだ。
何か得心に至ったか、ウツロの視線が心なしかオロルを睨んだ。
「……無駄じゃ。身動きの取れんお主に出来ることはない」
「あるさ」ウツロはきっぱりと言った。「言葉がある」
ウツロが懐に忍ばせていた言葉。
それは停戦の呼びかけではない。
「あまのはかりのつるぎはあくにかたむいた――」
天秤剣は悪に傾いた。
我が掌零る魂魄を掬い給へ。
善の上皿昇るならば、
我の誓に能う裁定を果し給へ。
この剣を振り上げし時、
我は科人に永久の生を祈らん。
誇り高き長女継承の奥義詠唱を、ウツロは一言一句間違うことなく誦じて見せたのである。
斥力を司る術式が静止空間に差し込まれ、両者の魔呪術がぶつかり合い、わずかにウツロの詠唱が勝った……!
時止めが強制的に解除され、機械仕掛けの術式が音を立てて砕け散るとナルトリポカ集落跡地の地盤がごっそりと沈下する。下方へ向かう強力な重力が足下で展開され、底の見えない穴が待ち受ける。
「なに……!?」これにはオロルも驚きを隠せない。
三者はすでに奈落に身を投げている。すぐ横にある崖に手を伸ばす猶予もなく体は浮遊感に包まれ、落下を始めた。誰よりも先に下へ姿を眩ましたのはオロルである。これは失態であった。ほとんど反射的にオロルは己の窮地から脱するために時の流れを絞ってしまったのだ。後の先を取るために前線で培った行動であるが、今回ばかりはウツロの術中に嵌められた。
落下しているこの状況で時を操れば、ウツロとセリナは空中で静止し、落下の距離は相対的に短くなる。オロルが時間を絞るほど柱時計は地面を求めて奈落へ落ちて行き、それに気付いて時止めを解除したときには二人との距離は見上げるほどに遠くなっていた。
「しまった……!」
漏れた言葉が上空へ置き去りになり、耳に届いたセリナとウツロが鬨の声を揃える。
逃げ場のない奈落にて、最早オロルに術はなかった。
「その腕――」
「――貰った!」
思わず助けを求めて伸ばした両手。風が手袋を攫い、爛れた皮膚に覆われた己の手が露わになる。
斧槍と竹刀の剣閃がオロル目掛けて駆け抜ける。
❖
フリウラはわしの手を引いて、夜毎誰もいない浜へと連れ出した。
日中は島で軟禁状態であったわしにとって、家族は鎖を意味し、フリウラは錠を解く鍵のような存在であった。
彼と過ごす夜は自由で心地よいものだったし、停滞していた勉学も調子が良くなった。当時のわしにとっては不思議なことに思えたが、『根を詰めてはよくないのだ』と、彼は気の抜けた笑顔で語った。
万事順調に思えたわしの人生に、神は再び試練を与えた。
十二の夏。フリウラは帰らぬ人となった。
島に住む者は皆、彼の死を残念に思ったが、悲しみに暮れる者は少なかった。それはこの島に住む者が海と共に生きているからだ。
男は十を数える頃には一端の働き手として船に乗り、漁をする。フリウラも長となるべく勉学に励む傍ら、週に二度は手網を持って海へ出ていた。……誰であれ海に落ちてそれきり帰らないことは珍しくなかった。
それが偶々、フリウラだったに過ぎない。
フリウラの死を境に、親は以前までの態度が別人のように軟化した。
悲嘆に暮れるわしを継承者へ育てることを半ば諦め、代わりに空席となった島長の座を目指せばそれで十分だと方針を変えたのだろう。わしも、失意の中でその判断に甘んじた。辛く苦しい道のりを共に歩む片割れを失い、継承者を目指す理由も目的も無くなってしまった。
それから二年経ち、継承者を目指していたことなどすっかり忘れていたある夜、わしは戸を隔てた向こう側に父と母の会話を耳にする。
「もうあの子も十四になるか……」
「……結局、印は貰えんかったども、島長んないば安泰がね」
「まぁなぁ……目の上のたんこぶが死んだおかげで、なんとかなったいな」
しみじみと懐かしむ口ぶり。彼について語っていることはすぐに理解できた。そして父と母が彼の死をまるで良いことのように捉えていることも。
わしは胸の内に湧き出る怒りを堪え、静かに二人の会話を盗み聴いていた。
なんとなく予感があった。己の親でありながら、この二人はフリウラの死に何か関わりがあるのではないかと感じたのだ。
耳をそばだてていると、しばらくの沈黙の後に父が言った。
「あいつが海ん落ちたとき、『あ』っと思うたよ。『しめた』ってな」
母は相槌を打ったのだろうか、一拍の間を置いて父は続けた。
「次の長になる子供だっけぇ無理にでも助けようとする奴もいたが、俺はやめとけって止めたんだ。波も荒れていたし、道連れになるだけじゃてぇ――」
そこまで聴いて、わしは足音を忍ばせて戸から離れた。これ以上聞きたくなかった。
込み上げる言いようのない激情を口元に押し留め、一目散に浜へ走った。
――父はフリウラを見殺しにした……!
何故……とは思わなかった。下手に冴えた頭が父の意図を理解している。
フリウラが海に落ちたところまでは、本当に不運な事故だったのだろう。
だが、このまま彼がいなくなってしまえばいいという邪な考えが過ったに違いない。優秀な者が島から消えてしまえば、わしを継承者にできなくても、次の島長にできると考えたのだろう。
わしに才能がなかったから……継承者になれなかったから……彼は見殺しになった。
もし、わしが夜毎抜け出すこともせずに勉学に励んでいたら、今よりももっと実力を培うことができたかもしれない。脇目も振らず、命を賭けていたら、彼は助けられたかもしれないのだ。
わしの怠惰が、彼を殺した。
胸の中はぐちゃぐちゃだった。
飲んでも飲んでも海原が飲み込みきれぬのと同じように、後悔に溺れる日々が続いた。
❖
それから六十年。
わしは島長になったが、人生のほとんどを小屋に籠って過ごした。
今にして思えばあの日々は正気ではなかっただろう。継承者にはなれず、フリウラの死を乗り越えることもなく、過去に囚われながら無我夢中で研鑽に励み、親も死んでいなくなってからは家財一切を書物へと替えた。長としての役目も碌に果たさず、人として腐り果てていた。
掌は独学で刻み込んだ刻印を幾度も幾度も重ね、老齢の肌は魔呪術にいっそう爛れて化物じみた手になった。……いや、手だけではない。落ち窪んだ目、潮風に軋む髪、骨と皮だけの体。あのときのわしはどこを取っても化物そのものだっただろう。
そんな狂気の果てに、掌に刻んだ刻印は一度だけ神懸かりの術を発動した。それは禁忌の領域に踏み入っていただろう。術式を構築したわしでさえも全てを理解できておらず、またそれによる成果も予測できないほどに複雑なものであった。
老齢となり己の死期を悟ったわしが、自暴自棄であったからこそできたと言っていい。
六十年の間に塗り重ねてきた呪いは、成功の期待をしていないわしの目を光で焼いた。多層構造となっていた刻印の失敗作が、この時のみ、全ての歯車が噛み合い術式が発動したらしい。後にも先にもこの術式を再現することはできなかった。
全てを焼き尽くすような光に包まれ、わしの全身は骨も肉も焼き縮んでいく激痛が襲った。何が起きているのかわからず死を覚悟した。
――あぁ、ついに身を滅ぼすときが来たか……。
抵抗を諦め、業火に焼かれたかに思えたわしが意識を取り戻したとき、少女の姿となっていた。
――若返ったのか……?
体だけではない。小屋も、島も、世界全ての時が戻されていることを知った。わしは弾かれるように駆け出し、彼を探す。
時が戻っているのなら、フリウラがまだ生きているのではないかと考えたからだ。
島じゅうを駆け回り彼の姿を探した。だが、運命とはそう甘いものではないのだ。
海原へ漁に出ていた船も見える限り目を凝らしたが見つからず、夕暮れに戻ってきた一隻の船に最後の望みを賭けてフリウラが乗ってはいないかと探した。その脳裏では不穏な予感が鎌首を擡げていた。いつか彼を失ったのも、こんな年頃ではなかったか。
船から降りる男衆の面持ちはどこか暗く見えて、嫌な予感がどんどんと強まる。
最後の一人が浜に降りたとき、わしは悟った。その男が他でもない、わしの父であったからだ。
「……フリウラは、フリウラはおらんのか……?」
わしが訊ねると、父は悲しむような顔をして肩に手を添えた。予感が確信に変わる。
時を遡ったこの日は、まさにフリウラが死んだ日であった。
奇跡は起きた。だが運命は嘲笑う。
これまで乗り越えてきた数多の苦難や後悔。
そして手にした栄光も、積み上げた功績も。
全てが運命に決められているのだとしたら。
少女に戻り、それでも彼は助からないというのが定めなのならば、わしはこの取り戻した六十年を……残された時間を何に使えばよいのか……?
また島長となり、無益な努力を繰り返したとて、なんの意味がある……?
――否。
――断じて否。
支払った対価に見合うものはそんなものではない。
空いた島長の空席を蹴り、狂気の沙汰を歩んだ日々は継承者こそ相応しい。
彼に誓おう。
彼を殺した者達を一人残らず復讐し、わしは己の運命を変えてみせると。
❖
「のぅ、親父よ」
翌る日の明け方。
浜辺には見る影もなく浮腫んでふやけたフリウラの水死体が打ち上げられていた。下肢は鮫に食いちぎられたらしく、背骨の途中からなくなっていた。臓物を失くした空洞を肋骨が支えて、色素の薄くなった皮膚が提灯のようだった。
わしは島の誰よりも早くそれを見つけ、眠っていた父を起こして浜へ連れて行った。
父はその小さな遺体をそっと覗き込み、すぐに彼であると気付いた。そしてここに呼び出したわしに対して同情の顔を向けた。
「おぉ、なんということだオロル。辛かろうに。
いいか、海には化物がおる。……抗うことができんくらいに強い化物だ。それはこうして気紛れに人を襲うのだ」
「……そうじゃな。その化物にフリウラはやられてしもうた」
父はわしに心から同情し、胸に抱くと髪を撫でた。
わしは無感動に父の匂いと潮風を感じ、肩越しに海原を眺める。
「悲しいが、島に生きる儂等は受け入れるしかない」
父は分かったようなことを言う。
だがわしは知っている。フリウラを見殺しにしたのは父だ。
「受け入れるしかない、か……」わしは可笑しさが込み上げて口角を吊り上げる。そして手袋に隠した手を晒した。「親父よ。それであれば受け入れてくれるな。化物が恨めしそうに見ておるぞ」
「オロル……? なんだその手は――っ!?」
爛れて変質した皮膚に覆われた赤黒い化物は父に襲いかかった。
体勢を崩して背中から倒れる父を見下ろしながら、見開かれた真丸な眼と向き合っていた。
浅瀬に倒れて全身をしとどに濡らし、砂を掻いて踠く父は、化物に首を噛まれて海中に引き摺り込まれてしまっている。
息が出来ず苦しかろう。
助けを求める視線に、わしは応えない。
父が彼にそうしたように、化物に殺されてしまう様を眺めていた。
❖
海に棲まう化物は、あれ以来オロルの両手に宿っていた。
オロルは呪われた運命から逃れるため、二度目の人生を継承者となるべく努力した。時を遡る以前の経験値およそ六十年分がその努力を底支えして、オロルは希う果てに三女継承の座を勝ち取った。
時の流れは残酷であること。
後悔にやり直しはできないこと。
積み重ねた努力のみが報われること。
三女継承に選ばれる前から、オロルは時の概念をよく理解し、完成していた。
……そして、少し壊れてもいた。その理由が手袋の内側にある。
ウツロによって穿たれた奈落の穴の中、落下する体は思わず空へ手を伸ばした。いつか父がそうして助けを求めたときのように。
手袋は風に揉まれて取り払われ、その下に隠していた化物が姿を現す。
「その腕――」
「――貰った!」
二人の振り下ろす剣閃が化物の首を刎ね飛ばした。すぱっと切れ味よく刃が閃いた後には骨ごと両断され、血飛沫が舞う。
焼けるような痛みの中で、オロルは呆然と欠損を認めたが、仕方ないと肩を落とし、どこか満足そうに空を見上げる。
――今度はわしが倒される側に回ったか。……それも血を分けとらん兄妹同然の二人が成し遂げるとは……。
ウツロとセリナ、この二人の間柄は奇しくもフリウラとオロルに似ていたのである。全くなんという因果か。
柱時計は霧散し、意識を失った小さな体をウツロが抱き止める。まもなく穴の底、硬い地盤に着地した。
「オロル!!」ウツロが呼びかける。「これでいいのか……!?」
身を揺すられ、オロルは疲弊した様子で目を開く。
憎まれ口でも飛び出すかと思ったが、オロルは「あぁ」と頷いた。
「……上出来じゃ……どこへでも連れて行け……」
宣言通り腕を切り飛ばし、刻印を奪うことで継承者としての権能を剥奪する。
力を失ってしまえば、もはやオロルは神殿の兵戈ではなくなり、戦闘の決着が着いたということになる。……が、そのような形式だけの使命、いくらでも無碍にできただろう。やはりこの一件は二人に釈然としない思いが残った。
「……結局どういうこと? なんで私達は戦っていたの……?」
状況を理解できないセリナが不満げに言問顔をする。三女継承は賢人種の中でもとりわけ利口な者が選ばれると聞いているが、それであればやはり戦わずとも話し合いで解決できたとしか思えなかった。何より勝敗が腕の先を切り落とすだけで済むのなら、尚のこと差し出してくれればそれでいいはずの話。痛い思いをするのは全く無駄ではないか。
しかし、オロルにとっては違うのだ。
「化物退治……わしには必要なことなのじゃ……」
セリナは意味を掴みかねてウツロを見る。説明を求められたところでウツロも応えられなかった。
二人は戦闘に決着が着いた今でも、化物がなんなのかわかってはいない。それでよいのである。
オロル自身、神殿には不信感を抱いていた。しかし、これまでに支払った犠牲は多く、継承者となり既に引き返せないところにいた。亡き彼との約束、積み上げた歳月、遡ってまで勝ち取った執念を、今更捨てることができなかったのだ。
だから誰かに止めてもらうしかなかった。死力を尽くし、ウツロに敗北を喫することで、初めてオロルは納得できる。
「本当はわかっとる。付き纏う運命という呪いも、この手に宿っていた化物も、全てわし自身じゃと……。
これはわしの罪の象徴であり、わしがわしを許すために必要なものじゃった。……じゃが、もう要らぬ。もう、わしは救われた……」
手首から先を断ち切られたというのに、オロルはなぜだか晴れやかな表情をして目を閉じた。
「これでわしは……海へ帰れる……」
ウツロに抱えられたまま眠りに落ちたオロルに対して、セリナは到底理解できないと渋面をする。
「……めちゃくちゃだねこの人……」
「オロルはいつもこうだ。慣れてくるとそう悪くない」
ウツロの返答に辟易した様子でセリナは溜息を吐き出した。「こいつらには着いて行けない」と言外に表明している。
兎も角これで一段落。穴の底に転がる変質した三女継承の手をセリナは拾い上げて、捨てておくのも悪いと手荷物にした。治療するなら必要かもしれないと考えた彼女なりの善意であった。
■014――審判 前編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
神殿より廻状
アーミラ・アウロラ
一、魔人種
一、齢十七
一、性別女
一、背丈一振ト五突程
此者廻状を見た後出頭せよ。
一、逃去リ着用之品
法衣脱ギ捨テ襯衣ト股引
一、黒色ヤヤ藍色ノ長髪
一、顎ト鼻ドチラモ小サク眉薄イ
一、目ヲ逸ラシ前髪長ク隠シテイル
一、肌ハ全身ニ傷アリ
右の通りの者が居た際はその場に留め置き、領主または爵位を持つ者へ申し出よ。また、居所を耳にした者、目睹した者も申し出よ。
この者を匿う者がいた場合、見つけ出した後にその罪を問い、行方を知らせた者には手柄の後に相応の報酬を与える。
(『人相書』アーミラの捜索に用いられた廻状)
❖
奈落から這い出たウツロとセリナは、オロルを仲間に迎えて神殿を目指し北へ進んだ。
道中ウツロの背におぶられ眠っていたオロルは痛みに目を覚まし、手首の傷痍を痒そうに擦った。指を失って丸められた腕の先には、乾いて粘度を増した血が糊のように糸を引き骨の断面が覗く。
見かねたセリナが切り落とした手をまたつけてはどうかと提案したが、オロルはそれを固辞したのであった。
祈祷の治癒に任せ、今は新しいまっさらな手が生えそろうのを待つつもりのようである。赤々とした真皮の膜で塞がった両手をオロルは芽吹の時を待つように見つめていた。継承者の印を失い、両手を失ったはずのオロルであるが、確かに何かを手に入れ、目には希望を宿していた。
ナルトリポカから急ぎ北上した一行がムーンケイの国境を跨いだとき、こちらを射抜く視線を感じて兄妹は互いに目配せをした。
「また一悶着ありそうだね」セリナが言う。
「……ガントールは戦えないはずなんだがな……」
訝しむウツロにオロルが口を挟んだ。
「内地じゃからな。神殿の兵でなくとも手練の戦士はおるじゃろう」
それであればさしたる脅威ではない。ウツロは声に出さずそう思った。『神殿の兵』や『手練の戦士』程度なら赤子同然である。
「手緩いと思うとるじゃろ」オロルは咎める。「周りを見よ……人払いが済んでおる」
オロルが指摘した通り、付近には人の気配がなく静まり返っている。記憶の中のムーンケイはもっと喧騒に溢れて人の往来が激しい国だった。誰もいないなんて、ありえない。
「……そう――」
凛とした女の声が聞こえる。
「――ここが最終防衛線ですから、国民は避難させました」
こつこつと靴を鳴らして、通りの先からは白衣の女が現れた。襟元まできっちりと釦を留めたその姿が誰であるかを理解したウツロは腑に落ちる。……なるほど。
「神殿の兵であり、手練の戦士でもある――」
背筋を伸ばしこちらに対するその女は、神族近衛隊隊長の座に堂々君臨する者。自らマハルドヮグを降りることはなく、座して指示を飛ばす神殿守護の要。
「―― お前が降りてくるとは予想外だ、カムロ」
ウツロが名を呼ぶ。
「なんとまぁ禍々しい姿……」
指を組みほぐすようにゆっくりと曲げ伸ばしをしながらカムロは続ける。
「……私はずっと、貴方を信用していませんでした。
神殿に対する敬意のない態度、過去に封印された経緯、そして謀叛……ついに正体を現しましたね。ウツロ」
ウツロは肩をすくめて応え、斧槍を握る。
「……敬意を払う価値があればな」
背後ではおぶわれていたオロルがそろそろと地面に降りて、セリナの方へ身を隠していた。カムロが鋭く呼び止める。
「オロル様も、こちらを裏切ると言うのですか?」
「……さてな。これこの通り」オロルは手首のない両手をこれ見よがしに振ってみせる。「腕を失くしてしもうてのぅ、戦えんので降参したわ」
返答を聞いてカムロは顳顬を押さえる。苛立ちに頭が痛むようだ。
「ウツロ。オロル様の身柄をこちらに引き渡しなさい」
「怪我人を往復させるのは手間だろう」と、これは皮肉。オロルは笑みを隠す。
はぁ……、とカムロは面倒な仕事に取り掛かる者がそうするように、気の重い溜息を吐いた。
手櫛で前髪を掻くように手で顔を覆い、指の隙間から睨みつける。
「……封印では甘い……貴方を壊します」
睨み合う二人は、静かに開戦した。
❖
「気を付けろよ」オロルの態度は気安い。
ウツロとカムロが攻防を繰り広げる手前、セリナとオロルは参戦せずにいた。傍目から見ている限りではカムロは確かに強いが、実力は継承者にやや劣る……神器を取り込んだウツロの相手ではないように思える。
「……なにに気を付けるのさ?」セリナは首を傾げる。
「射抜いていた視線は此ではない」
そう言われてセリナは付近を警戒する。
オロルの助言通り、先程から感じている威殺すような圧は依然としてこちらを捉えて離さない。カムロとは別の誰かが潜んでいるようだ。
「まさか、もう一人いる――」
「二人よ」
背後から耳元に囁く声にセリナは振り向けない。首筋に短刀を添えられた冷たい感触に息を呑む。刃が引かれれば動脈が裂かれて致命傷は必至。そして背後に立つ敵がそれを躊躇うとは思えなかった。事実その者は腕を引こうとした。
「……あら……」
「――っぶないなぁ……!」
突き立てられた短刀が首を切る前に、セリナは尾を巻きつけて背後に立つ者の腕を封じた。そのまま肘と裏拳で反撃し、引き剥がしに成功する。
「あんた誰?」セリナは降りかかる受難にうんざりしていた。「やる気満々な奴ばっかり……本当疲れる」
時止めを使えない今、オロルは状況を把握するのに忙しい。むしろこれまでの優位を失って誰よりも反応が遅れていたが、一目見て敵の名を言い当てる。
「スークレイか……!」
「誰さ」セリナは苛立つ。名前だけでは救うべき継承者か否か判別できないのだ。
「長女継承者、リブラ・リナルディ・ガントールと血を分けた双子の妹……こっちは辺境伯じゃ」
「つまり継承者じゃない……いやでも倒すわけにもいかないのか……」
セリナは戦う相手を見定める。スークレイと呼ばれた女は白衣の裾を瀟洒に捌き、振る舞いに無駄がない。辺境伯ということは戦い慣れしているということか……と、不意に冷や水を浴びたようにセリナは鱗を逆立てる。
「待って、これでもなくない……?」
射抜いていた視線はスークレイのものではない。
「言ったでしょう、『二人よ』」
ならばあともう一人。カムロと、スークレイと――
オロルは場に現れた二人の共通点を悟り血の気が引いた。
「まさか――」
思い至るときには重たい衝撃波が臓腑を揺らす。
オロルは驚き、ウツロの方へ視線を向ける。
目を離していた数刻前まであれほど優勢を疑わなかったウツロの戦況は完膚なきまでにひっくり返っていた。盤面を覆す程の圧倒的な戦力をオロルは一人だけ知っている。
眼前に広がるのは地に倒れるウツロの姿。そして仕事を終えて乱れた髪を耳にかけて整えるカムロの姿と……その隣に立つ、ガントールの姿であった。
状況は理解している。それでもオロルは目を疑う。
「……動けないはずであろう……!?」
金色の双眸は動揺に震え、足元を見た。
失ったはずの脚がムーンケイの地を踏み締め、ガントールは立っている。
そのすぐ側で腕に力を込めて立ちあがろうとするウツロの姿があった。板金鎧が軋み、押し潰される。
ガントールは球状の斥力を生み出してウツロを強制的に平伏させている。その威圧感は間違いなく射抜く視線の正体であった。
カムロとガントールの二人は煉獄の番人が如くウツロを睨み下ろし、ガントールの口元が何かを呟いた。その声は力場の中に消滅してオロルには聞こえなかったが、唇の動きは読み取れた。
おそらくこう言ったのだろう。
『剣を返してもらおう』。
斥力の内側、地鳴りの向こうに遮断された景色の向こうでは、うつ伏せに倒れたウツロに対してガントールが手のひらを添えている。そう、前線で脚を失い、満身創痍に倒れても、彼女は未だ神器『天秤』の正当な所有者なのだ。溶けた地金に取り込んで我が物のように振る舞っていたウツロは所詮は戦場の泥棒に過ぎず、返還の光景はまさに盗人を審判に掛けて裁いているかのようである。
鎧の身体が軋む音が微かに耳に届き、日緋色金の頭部が吸い寄せられるように手のひらに向かって引き剥がされていく。ひしゃげた頭蓋が苦悶に顔を歪めているように見えた。
金属の断裂する音は激しく大仰で、ガントールの展開する領域の外側まで漏れ聞こえる。
地に磔にされて頭を剥ぎ取られる光景は容赦がなく、もしウツロが人間であったならば、直視に耐え難い光景だっただろう。背骨ごと引き抜かれる極刑を受けているのではないかと思うほどに、残酷な様子が繰り広げられている。不死のウツロといえども痛々しい姿だった。
やがて刑の執行が終わり、ウツロの身体を補い超常の力を与えていた天秤が持ち主のところへ返され、日緋色金がガントールの手中で再び剣の形を取り戻した。
首を失った黒鉄の鎧は力無く倒れている。
「……お兄ちゃん……!」
死んでしまったのではないかと思ったセリナは我を忘れて駆け寄る。
「待て!」オロルは呼び止めるため咄嗟に手を伸ばしてから、己には繋ぎ止める指がないことに気付く。「っ! 行ってはならん!!」
セリナはガントールに向かい飛びかかるが、剣の腹でいなされるとその頬に拳が叩き込まれた。混じり気のない真っ直ぐな痛みに涙が散り、セリナはよろめきながらもウツロに覆い被さった。洟をすすってガントールを見上げる。
禍人種の娘を前にガントールは無感動に奮った拳に付いた血を払い、剣を握り直して感触を確かめる。……あやつ、切る気じゃなかろうな……!?
「彼女はこんな態でもウツロの妹じゃ! 早まるなよ!!」オロルはガントールに向けて鋭く声を張り上げる。
ガントールの戦意は直情的であり、禍人であれば躊躇いなく首を切り飛ばす危険があった。ウツロとセリナが倒れる事態はオロルにとって避けたいことだ。
「……眠っている間に、色々あったみたいだな、オロル……」
どこか微睡むようなガントールの視線がちらりとかち合った。……瞳孔が開いている。様子がおかしい。
あの目は、呪術に操られている者の目だ。
ガントールは剣を掲げて続ける。
「案ずるな……二人一緒だ」
セリナの首めがけて天秤剣が振り下ろされる!
オロルは叫んだ。
「躱わせよウツロ!!」
降ろされた鋒はセリナの髪を一房切り落とし、重くめり込み地を揺らした。甲高い金属音と衝撃が弾けて耳を麻痺させた。オロルは痛む鼓膜を腕で塞いだが残響が消えない。
ガントールは二人一緒に殺すことに躊躇がない。二人の安否を確かめるためにオロルは痛みを耐えて目を開く。
振り下ろされた刃の先にセリナはいなかった。ウツロがセリナを突き飛ばし、処刑人の振るう落とし首の剣閃を一人で受けたのである。耳を襲った音の正体はこれだった。
降ろされた剣はウツロの襟元の鎧を深く切り欠いた。幸いにもかち割られるような頭蓋は持ち合わせておらず、まさに先程没収されたばかりである。
斥力が微かに弱まった一瞬を見逃さず体勢を立て直し、ウツロは青生生魂のみとなった身体でガントールに対する。
「ウツロよ。ガントールは呪術に操られておる……あの脚を見よ」
ウツロは言われた通りにガントールの脚を見る。前線で災禍の龍に喰い千切られた両脚には見慣れない金属製の長靴を履いていた。おそらくは義足だろう。
「操られているんなら、もしかして翼人の巫力って奴じゃないの?」セリナは言う。
我が意を得たりと頷く。声を奪われてしまったウツロも同じことを考えていた。振る舞いも太刀筋もどこか彼女らしくないと感じていたからだ。
「どうあれ、まだ戦えるほど回復しておらんはずじゃ。義足を狙い脚を止め、今度こそ神器を破壊しろ」
頷くウツロの向こう。オロルの言葉を聞いていたカムロとスークレイが眉を跳ね上げ視線を尖らせる。
「その口ぶり……馬脚を露わすとはこのこと」カムロがオロルに向ける視線が温度を下げる。「……禍人に加担していますね」
二人はガントールを護るように背に隠し、前衛に立つ。
「馬脚? ふん……主らこそ。ガントールをここに立たせている無体には全く失望したわい。それにのぅ、アーミラを追い立てた仕打ちも正当性を見出せん。
祈りを背負い奉仕した女神継承者の現状を見よ。方や身柄を追われ、方や操られとる。謀叛に翻らぬ方が愚かじゃろう」
オロルは悪びれず、むしろ胸を張って三人に宣言した。
「たとえ前線を勝ち納めたとしても、世に不穏の影があれば争いは無くならん。
わしは決めたぞ。膿を出し切り、真の終戦を目指す」
「神器も両手も失くしたというのに?」くだらないことだとカムロの目は言っていた。「今のオロル様には到底無理でしょう」
嘲笑の声を意に介さずオロルは言う。
「……わしはそれを、ウツロに託す」
宣言を聞き、ウツロは斧槍を握って奮い立つ。
――また託されてしまった。
背負うものがまた増えたというのに、体には力が漲るようだ。
託された想いの数々が、空の鎧に注がれ、ウツロを休ませてはくれない。
闘志を新たにマハルドヮグ山嶺を見上げる彼の前、立ちはだかるガントールはオロルの宣言も空しく心には届かない。響いていない。
「『神殿に絞れるような膿は無い』。『こうは思わないか……禍人を根絶やしにすることが真の終戦だと』」
熱に浮かされたように虚空を見上げてふらついているガントール。開いた瞳孔からはちりちりと燐光が漏れ光る。――これはガントールの言葉ではない。……オロルはそう直感した。セリナの話していた『神族が持つ巫力の仕業』だろう。ただでさえ体力を消耗しているうえに、信仰が盲信へと塗り替えられ、思考を奪われてしまっている。
相当な無理を強いられているのは明らかだ。
本人の気力か或いは巫力がそうさせているのか、苦しみを顔に出してはいないが、額や首元の発汗が凄まじい。癒合しきっていない間に合わせの義足からは血が滲んでいた。このままでは戦わずとも倒れてしまう。
そう感じているのはオロルだけではない。もはやこの場にいる全員がそう感じていた。
スークレイは敵前でありながら背を向けて姉に寄り添い、ふらついている姉の肩を支えた。誰もその隙を狙いはしなかった。代わりにオロルが毒気たっぷりに野次を飛ばす。
「仮にも女神に地位に居る娘を襤褸になるまで酷使して……これを膿と呼ばずなんというのじゃ……」
そうだそうだとセリナも加勢した。
「ラヴェルがこれまでやってきたこと、あんただって知ってるんじゃないの?」
「天帝を愚弄するな! 一族に後ろ暗いことなど有りはしない!!」カムロは青筋を立てて否定するが、怒涛の剣幕にもセリナは冷ややかだった。
「……よくそれで近衛隊長なんてやってこれたね……いや、やってこれてはいないのか。だって副――」
セリナの肩をウツロが掴んで制する。危うく口を滑らせるところだった。……思うところがあったのか、カムロは口を引き結んで表情が曇る。
「――……次女継承を捕らえようとした時だって、あんたはそんな顔してた。隠したところで翼人はあんたの働きに応えちゃくれないよ」
畳み掛けたいセリナの糾弾をスークレイがぴしゃりと割り込み制する。
「そこまでです」
「もとより姉様を戦わせるつもりはありません。不届者から天秤を取り戻せばそれで役目は充分……」
喧々諤々な両陣営の睨み合いの中、ガントールは熱に魘されて視線も定まらず、息が上がっていた。
「こうしましょう。オロルと姉様、どちらも手出し無用。
こちらは私とカムロ。
そちらはウツロと娘、二対二の決闘……これで蹴りを付けます」
異存はないかと問うより先に、ガントールが膝から崩れ落ちた。これにはオロルもウツロも思わず駆け寄ろうと身を乗り出し、睨む面構えも忘れて肝を冷やした。
「……姉様」スークレイの慕う声は、敵前であることを忘れたかのように優しい。「どうかもう、無理はしないで……」
腰を降ろしてガントールの身を落ち着かせ、岩壁に背を凭せ掛けると、握っている剣に手を添えてそっと指を解していく。
「姉様が背負ってきたものの半分……私が預かります」
最後の気力で握りしめていた柄を取り上げ剣を奪われると、ガントールはがくりと首を垂れて気を失った。
スークレイは姉の頬を撫でで微笑むと、決然と表情を厳しくしてカムロの横に立つ。双子の妹として、継承者代理を務め天秤を握る。
正義も大義も、ここには無い。
眼前の敵に恨みも無く、ムーンケイの戦闘は始まる前から破綻していた。
だが後に振り返ってみれば、確かに無益で大義のない戦いではあったものの、それ故に個々が信ずるもの、護りたいもの、その矜持が泥臭く激しくぶつかり合った戦いだと言えた。夜明けの前が一番暗いことと同じように、先の見えない混沌とした争いの果てに、黎明が近付きつつあった。
❖
ムーンケイ下層、宵の口。
まだ明るい薄青の空には半月が浮かび、西の方では背の高い雲が夕日に照り映えて赤く燃えている。茜色から藍色へ移ろう色彩は見惚れてしまうほど目も綾なものだった。
季節は秋に近付きつつあり、肌を撫でる風は火照りを覚ます清涼さで殺気立つ四人の間を静かにすり抜けていく。
首の無い鎧の姿で斧槍を構えるウツロ。
その隣で鱗を逆立て尾を揺らすセリナ。
向かい合う形で鋭く睨むスークレイは姉の天秤剣を握り、カムロは先を狙い詠唱を繰り出した。状況は動き出す。
「占星――『術七天秤座』」
顰めた声をウツロは聴いたか、斧槍の鋒をカムロに定めて縮地で飛び込む。
ウツロはこの詠唱を先程も耳にしていた。ガントールに倒される前、カムロは同じ言葉を唱えていたのを覚えている。この詠唱の後にウツロの優勢は崩された……阻止しなければ……。
懐まで潜り込むと同時、踏み込んだ脚を踏ん張り、後ろに構えた斧槍で下弦の弧を描き切り上げる。
下顎を狙った鋭い一撃、カムロは首を反らせて地面を蹴り回避。勢いをそのままに宙返りをして体勢を整えつつ、空いている両手で印を結ぶ。
――くそ……躊躇ったか……。
追いかけるウツロは内省していた。少なからず顔見知りであるカムロを相手にしているせいで踏み込みが浅かった。いや、そもそも下顎ではなく胴を切るくらいに深く踏み込んでもいいはずだ。
仕留める覚悟を固めなければ神殿の野望は砕けない。だが、これ以上誰かを殺すのは、本当に正しいのか……?
斧槍を再び後方に構えたウツロを相手に、カムロは中指と親指をつまむような手の形でそれを上下互い違いに重ねて勾玉を型取る。後方へ着地とともに呪術を展開する。
「輾」
言葉と印。その二つから構成される術。
ウツロは景色が逆さまに映り、歪んでいくのを感じた。鎧の頑丈な手足が練り飴のようにぐにゃりを曲がる感覚に支配される――が、しかし。
斧槍を横回転に振り回し攻撃を継続する。攻めに転じようとしていたカムロは危うく鼻柱を切られるところであった。
「……こいつ、呪術を弾いた……!」
カムロを守るため斧を受けたのはスークレイである。剣の柄を両手で握ってなんとか押し返す。膂力はガントールに及ばず、スークレイは体勢が崩れた。一合の後に生じた隙をセリナが狙う。
ウツロは『いけ』とも『殺すなよ』とも思いながらセリナを見ていた。相反する二つの感情が鎧の内側でせめぎ合う。
ここで誰かが命を落とせばきっとガントールとは手を結べなくなる。それだけではない。例えここで立ちはだかる者がカムロやスークレイでなかったとしても命を奪うのは悪手だろう。
――これ以上殺してなんになる。死体を積み上げた山に新しい正義の旗を打ち立てたところで、誰がついてくるってんだ……。
「下方!」
スークレイは苦しげに叫ぶ。どん。と地面が押し固められ、ちょうど飛び込んでいたセリナは受け身をとれず重い空気の層に叩きつけられる。重力を操る長女継承の権能、スークレイの攻撃だった。
「まさか、力を使えるじゃと……?」離れたところから戦闘を見守るオロルは対岸のガントールを見る。スークレイが斥力を操ったことが信じられなかったのだ。
ガントールは今も意識を失っている。であればスークレイは継承者の印を受け継いだ……? 例え瓜二つの双子でも別人には変わりない。なぜ長女継承の権能を扱える……。
「……また神器……狡い力ばっか……!」
セリナは不満を吐きスークレイを睨む。強かに打った顔面が熱かった。鼻の奥で血が伝うのがわかる。肩で息をするスークレイの睨み返す表情に余裕はない。
「狡くても構わないわ! ……守るための手段を選べる立場じゃないのよ」
柄を握る手から血が伝い落ちる。見上げる形となったセリナはふと視線に入ったスークレイの出血に意識が向いた。何の負傷か心当たりはないが、剣を握る左腕、籠手から肩へ遡上して袖の隙間から覗く二の腕から滔々と血を流しているのが見えた。きつく嵌め込まれた鉄の腕輪を見る。
「あんたそれ……義手――」
「目障りよ!」
不躾に見つめるセリナを咎めるようにスークレイは剣を振るった。寸手で受け止め、衝撃を逃すため吹き飛ばされるままに後退する。翼を広げふわりと着地すると、乾いた鼻血を腕でこすり落とす。
「……勘違いしてるんじゃないの?」セリナは言う。「私達はガントールを傷付けたいんじゃない。神殿から守る必要があるからここまで来たの。今からでも手を取り合えるんじゃないかな」
「いいえ。勘違いなんてしていません」スークレイは突っぱねる。「守りたいのは姉と、姉の打ち立てた正義よ」
セリナは眉を吊り上げる。正義だって?
「その正義が……間違いだって言ってるの。神殿は人の道を踏み外してる。だから私達が――」
「必要ない」スークレイは拒絶する。「神殿が正義でなかろうと関係ないのよ。私は姉が守ったものを守りたいだけ」
「……その言葉、冤罪で殺された人に言える……?」セリナの声が震えている。独りよがりな論理に対する唖然と、遅れて燃え上がる怒りと悲しみ。複雑な感情を内に押し留めた声だった。
一人の禍人――ニァルミドゥ――として、戦場に斃れた同胞の無念を背負い彼女はこの場にいる。呑みきれぬ不満をそれでもと呑み、世界を正すために行動しているのだ。スークレイの言い分が腹に据えかねるのも当然である。
「神殿がもし悪であるなら、貴女たちを倒した後に神殿も成敗すればいいだけの話よ。少なくとも禍人に助けてもらう筋合いはないわ」
肩を怒らせていたセリナの温度が、吐き出した息とともに急速に冷えていく。
「……そうだね。筋合いはない」セリナは諦観の籠った声で同意する。あくまでも理性を保つことで正当性を主張したいのだろう。「でもね、私たちは翼人に用があるんだよ。性根の腐ったやつの顔面に一発叩き込まなきゃ気が済まない。利害の一致はあるでしょ。『共に黒幕を打ち倒そう』……みたいなさ」
セリナの言葉にスークレイもカムロも本心から困惑した。なにも底意地わるく惚けているわけではない。この世界には創作物の中にあるようなご都合的な共通言語はないのだ。敵味方が力を合わせる事例などなく、また巨魁を指す黒幕という言葉も通じない。
「共に黒幕を倒す……?」
冷めた反応にセリナは心挫けてウツロに振り返る。……私間違ったこと言ってる?
ウツロは憐れむように胴を横に振った。
……結局、人の闘争は醜いものなのだろう。――ウツロはしみじみそう実感した。はじまりに掲げていた正義や大義はいつしか失われ、憎しみが憎しみを生み出し、敵意さえ形骸化してしまっているのだ、この世界は。
ガントールもスークレイも、きっとカムロも、本心では神殿に不信感を抱いているのだろう。だがそれ以上に禍人を憎むように仕組まれていて、両者は断絶されている。
彼女達は戻れないだけなのだ。これまで正しいと信じて歩んできた道が間違っていたとわかっても、引き返そうと振り向けば来た道は崖となり途絶えてしまっている。後戻りはできない。だから先へ進む。
そうやって進みながら、まっすぐに歩けているのかわからなくなり、『右に進めば元の道に合流できるはず』とか、『左に進めば光が見えるはず』と暗闇を彷徨うのだろう。
だが、今回ばかりは通用しない。
翼人の築き上げた過ちの歴史は、いわば脆い地盤なのだ。その上にどれだけ几帳面に正しさを積み上げても傾いてしまう。帳尻合わせを試みたところで必ず破綻する。……それが今なのだ。
そんなウツロの声ならぬ声が聴こえたようにカムロは視線を向ける。反抗的な態度を見咎めて剣呑な雰囲気が伝播した。
互いに相容れないことを再認識し、これ以上言葉はいらないとそれぞれ構える。
戦闘再開は三名それぞれの詠唱が重なった。
「術三双子座」
「月輪・竹取……!」
「下方、常々」
ひとときの静寂から一変して状況は再び混迷を極めた。まずカムロの詠唱が発動。これは自身の身体強化の類と見えた。呪力がカムロの内部へ向かい、腰に携帯した細剣を引き抜く。
セリナとスークレイの術の発動はほとんど同時だった。セリナが亜空間から燐光を放つ竹刀を抜剣したとき、スークレイの下方斥力がのしかかる。
重力の効果範囲外にいるオロルは状況に目を光らせる。助太刀は出来ないがせめて魔呪術の分析だけでもしておこうという考えである。
「『天秤座』に『双子座』……そうか……!」
なぜ二人がこの場に出向いているのか、オロルは理解した。
「ガントールに近しい者というだけではない。互いの素質と才能を補い合うことで長女継承の力を再現しておるのか」
初めにカムロが唱えた術、『天秤座』。これはガントールがウツロをねじ伏せたときに巻き添えを喰らわないための術……つまり斥力魔法の無効化。確かにカムロは強力な重力の効果範囲内で涼しい顔をして立っていた。
そして今唱えた『双子座』。ガントールとスークレイの双子姉妹に準えた術であり、味方の魔呪術を底上げしていると見ていい。長女継承の力を出しきれないスークレイを支える意図があるようだ。
血を分けた双子の妹が姉の代わりに剣を持ち、足りない分はカムロが補助しているという構造となる。
スークレイ側は効果の漸減した斥力を改めて唱え、『常々』と念押しした。裏を返せば念押ししなければ持続できないほどに練度が甘いということ。二人合わせてもガントールの実力には及んでいない……オロルは勝利を祈った。
斥力の内側、のしかかる重力にセリナはたまらず膝をつく。
「ぐっ……!」
身を屈めて顔を上げているのがやっとだった。背骨が軋み、頭蓋を押し潰されるような圧迫感に涙腺から知らず涙が漏れる。
目の前にいるのは本当の長女継承ではないはずなのに、それでも全身が地面に引き寄せられる力には抗えない。
「このまま去ね」
カムロは細剣を構え、セリナの額めがけて突き出した。衝撃に弾かれるようにのけぞるセリナの姿にウツロは動揺するが、セリナは剣突を牙で受けていた。必死の抵抗である。
「往生際が悪い」
牙から剣を引き抜きセリナの頬が裂ける。痛みにひるんだ背に対しカムロは無慈悲にも剣を突き込む。
うずくまっていたセリナの背面から胸にかけて鋒が貫き、地面に串刺しとなった。
ごぷっ。と、粘度の高い水音が漏れる。
心臓を傷付けたか、セリナの口から血が噴き出した。間歇泉の如く吐血し、下方斥力に従ってぞっとするほど大量の鮮血が滝のように落ちる。
――セリナ!!
ウツロは我を忘れて叫んだが、声は誰にも聴こえていない。
押し潰される斥力の中で踠くように這い寄り、力無く頽れるセリナからカムロを追い払う。斧槍を振り回す気迫に鬼が宿っていた。
――死ぬなよ!! ……セリナ……?
肩を揺すられたセリナは煩わしげにウツロを見つめ返していた。血色の失せた顔だが瞳に宿った光は消えずむしろ爛々として、小さく笑む余裕すら見せた。
「へへっ……龍人を舐めるなってね……」
先手を譲り痛手を負ってでも作り出した隙……絶好の機会をセリナは待っていた。
龍体を犠牲にして詠唱に集中する隙を稼いだのである。
血を咳き上げ引き攣る肺を抑えてセリナは目を閉じた。
気を失ったのではなく、言葉を汲み上げているのだった。
「望月の明るさを、十合わせたるばかりにて――」
そう唱え、セリナは背中の羽を広げる。
翼膜をぴんと張り詰め、両翼がそれぞれ半円を描いて左右揃って円を模るとセリナの頭上に天輪が生じた。
矢を取り立てむとすれども手に力もなくなりて、萎えかかりたり。
立て籠る所の戸、則ち、ただ開きに開きぬ。
天人の中に、持たせたる箱あり。
今はとて、天の羽衣着る折ぞ、君をあはれと思い出でける。
「――『天輪・羽衣』」
天輪から放たれる光の残像が暮れの空に上り、十の満月となって戦闘領域を取り囲むと輝きを増してこの場に立つ者たちの影を焼き消す。見上げるカムロとスークレイは月光の煌めきに目を奪われ言葉もなく立ち尽くす。
セリナの頭上に生じた天輪の内側は亜空への門を開き、そこから冷気のような魔力の霞が漏れ出した。それを頭から被ったセリナは両足で立ち上がり、背を反らす。胴にはまだ細剣が貫かれているが血は既に止まっていた。
「まずはうざったい重力魔法を」
セリナは呟き、頭上の天輪が波紋を広げた。するとウツロの身体は途端に軽くなる。見上げるウツロには何が起きているか分からなかったが、天輪が斥力を亜空へと呑み込むことで無力化したのだ。
カムロは「まずい」と青褪め策もなく魔弾を放つ。
のしかかる重みから解放されたセリナは天輪に翳る眼でカムロを睨む。冴え冴えとした三日月の笑みだった。そのまま次の詠唱へ続く。
「抜刀――」
竹取を天へ突き上げ、くるりと手首を回して空に円を描いた。滑らせた竹取の切先によって切り抜かれた円は薄皮のように剥け、その向こうに二つ目の亜空を開く。
これまでのどのような魔呪術とも異なる現象に誰もが唖然としていた。セリナの繰り出す術式は詠唱に含まれる物語がまるで推察できず、発動する現象も余人の理解を超えていた。それ故にカムロもスークレイも対応できない。
とろけた濃密な闇の次元……その裂け目から現れたのは無数の腕であった。描かれた円の内側から触手のように幾本もの手が伸ばされ、まるで月の都からの迎えのようにセリナの掲げた竹取の刃に絡み付く。燐光を纏う竹刀の刃を覆い隠すように握る手が重なり、がっちりと固定された。柄を握っているセリナは一本の剣を取り合う形となり、得物を引き寄せる腕に力を込める。
「ここで仕留める!」
カムロの荒い指示に従い、放たれる魔弾に紛れてスークレイも懐へ飛び込んだ。しかし距離を詰めながらもスークレイの直感は危険を感じ取り全身の産毛を逆立てていた。安易に前に出てしまった己の軽率さを呪った。
後方から飛び交う断続的な魔弾の雨。目の前に立つ龍の娘は亜空の腕供と引っ張りあっていた得物を一息に引き抜いた。握り込めて離れない竹刀の部分と柄の間に激しい火花が散り、竹取の中に隠されていた本来の刀身が現れる。
「――輝夜」
『抜刀・輝夜』
鍛え抜かれた艶やかな黒鉄の刀身が、流麗な運筆の軌跡のように閃く――スークレイは縦横に駆け抜けたセリナの幻影を追いかけるのが精々。回避もできぬままに胴を斬られたと感じた。たなびく光の尾が視界の下、胸を通過していていたからだ。それどころか躰のあらゆる箇所に光の筋が通過している。
痛みは未だ襲ってこない……奇妙なむず痒さに困惑する。
「動かない方がいいよ」セリナは告げる。「余波鋭鋒……はシェークスピアだから竹取物語とは関係ないけども」
「な、何を言って――」
「おっと、動かない。
……わかるでしょ? 今動いたら二人とも胴が真っ二つだよ」
セリナの宣告にスークレイもカムロも押し黙る。身体の異変は察していた。
少しでも動けば胴が、腕が、首が、たちまちに血を噴き出して落ちてしまいそうだった。セリナの剣捌きは切れ味が良すぎるあまり、刃が通過した後の傷口同士がくっついているのだ。自然治癒で癒着するまで二人は動けない状況にあった。石のように固まる彼女等の間を余裕たっぷりに歩くセリナは胸に刺さっていた細剣を引き抜き、開いた傷跡が塞がるまでの数刻カムロを見つめる。生殺与奪は彼女の手中にあった。指で頭を突かれるだけで首が落ちる。或いは意趣返しに抜いた細剣で胸を刺し貫くこともできるだろう。
呼吸一つ、心臓の鼓動一つさえ神経を尖らせる絶体絶命に、二人は命令通り身動ぎ一つしなかった。
セリナは結局カムロに手を出さず、スークレイの方へ向かった。
カムロは安堵と共に動揺した。――この期に及んで私を見逃すだと……!?
「離せるかな」
スークレイは眼球のみをセリナに向ける。言葉の意図を汲もうと努めた。
セリナは天秤を指差してもう一度言う。
「これ、離せる?」
天秤剣を寄越せと言っているのだと理解して、スークレイはぐっと瞼に力を込めて逡巡した。剣を手放してしまえば勝敗が決まる。……いや、既に決まっている。抗えば死が待っている。重要なのは屈するか否か……矜持の問題だった。
「もうおしまいにしよう。何度も言ってる通り戦う意味なんかないよ」
幾許かの躊躇いの後、スークレイは決意を固め左腕に力を込めた。
「それでも……っ!」
「わっ、馬鹿――!!」
セリナは予想していない反撃に目を丸くして驚いた顔のまま袈裟斬りにされる。噴き出す鮮血の向こうでスークレイの身体が瓦解していくのが見えた。
誤算だった。まさかこの期に及んで反撃するとは思っていなかったのだ。セリナとて得物を振い彼女等の身体を切り刻んだが、それはあくまでも脅し。戦闘を終わらせるために振るった剣閃であり、降伏してくれれば切り傷は後も残さず繋がるはずだった。
スークレイのこの反撃は、自決と同義である。
肋骨を圧し斬られて、腑を溢しながらへたり込むセリナは、痛みも忘れてスークレイを見上げていた。
「なんてこと……!」
カムロは怒りにかられて呪力を練るが、縮地によって現れたウツロが射線を遮る。ぽっかり空いた襟首の虚からそれでもセリナに手出しは出せまいと睨んでいた。顔がなくとも『睨んでいる』と確信できる凄みがあった。
「スークレイ!!」カムロの叫ぶ声は一帯に響いた。
スークレイは自らの膂力に自壊し、剣を握った左腕が義手の根元で別れ、不恰好な弧を描いて明後日の方へと飛ぶ。引き伸ばされた刹那の光景、全身の切れ目から赤い染みが広がっていく。
「所詮私じゃ、吊り合わないわね……」
スークレイは諧謔に笑み、血を咳く。
目を閉じた彼女の首の切れ目が血の玉を作り、傾いでいく。
このまま崩れてしまうかに思えたそのとき――
「……こんなに重いとは、知らなかった……」
――両手を伸ばし、ガントールは斥力を手繰ってスークレイの身体を多方面から支え、不器用ながらに人の形に押し留めている。
「ガントール……! 目覚めたか!!」オロルは思わず声を張り上げてしまった。
スークレイが命を落としてしまうのを歯痒く見届けることしかできなかったが、ガントールのおかげでまさに首の皮一枚繋がった。快哉を叫ばずにはいられない。この争いで誰かが命を落とすなど、誰も望んではいないのだ。
「参った……でいいのか?」ガントールの問いにウツロとセリナは首肯する。「頼む、妹の止血と治癒を――」
「任せろ」頼まれるより早くオロルは駆け出していた。
斥力によってなんとか形を繋ぎ止めているスークレイは、首を繋げられ、失血を癒されると目を開いた。死を覚悟して意識を失ったはず……そう考え目を瞬くと、姉がこちらを見ていることに驚いた。
「姉、様……?」
意識を取り戻したと見て、ガントールは胸を撫で下ろしがっくりと項垂れる。心底から安堵したようだ。
「何があっても、お前を失うわけにはいかない」
「姉様、ごめんなさい……私はただ、姉様の代わりになれたらと……それでなくともせめて右腕になれたらと、思ったのです」
無念に嘆くスークレイの言葉に、ガントールは首を振る。
「私の右腕になんてならなくていい。私だって、お前の左腕にはなれない」
「でも……」スークレイは食い下がろうとしたが、ガントールは言葉を差し込む。
「離れていても私達は二人で一つだ。天秤を使って私が守りたかったのは正義だけじゃない。何よりお前が大事なんだ」
その言葉にスークレイは矢で撃たれたように身を震わせ、天啓を受けたが如く静かに涙が溢れた。
双子の姉妹にしか通じ合えない会話のやり取りに、オロルは突然「なるほど」と訳知り顔で唸った。
「……え、どう言う事?」
例に漏れず状況に理解が及ばないセリナは説明を求める。散らかっていた腑は既に腹に仕舞い込まれ、龍体は治癒が進んでいた。
「オロル様は忙しいので、ここは私が」と、これはカムロ。戦闘の勝敗がつき、自ら治癒術式で切断面を塞いだ彼女はガントールとスークレイの仲に入らずこちらへとやってきた。
セリナは「よくもまぁのこのこと」と半目で睨むが、そこに先程までの敵対心はなかった。カムロは膝をついて頭を下げた。
「先程の戦闘……あなた方が不殺の姿勢を示したこと。何よりあなた方の意志によって命拾いをしました。これ以上抵抗は致しません」
「……じゃあ聞くよ」
むくれ面で胡座を描き、セリナの得物は霧散した。停戦の姿勢に乗った形でカムロに説明を促す。
「あの二人、ただの双子というわけではないのです」
「と言うと?」
「母胎の中で双子となる過程で、お二人はどういうわけか互いの腕が繋がった状態で成長したそうです。難産の後、産声を上げる赤子の腕は直ぐに断ち切られました」
「その後、ガントールだけが刻印を授かった、という訳じゃな」治癒を終えたオロルが言葉を継いだ。「継承者として神殿預かりとなった後も互いはお揃いの義手を身につけ、離れていても心は一つじゃったと」
カムロは頷く。
「前線出征を終えて帰還したガントール様は目覚めず、スークレイ様が駆けつけました。禍人の動きに未だ油断できない中で、血肉を分けたスークレイ様は長女継承の代理を努めるとお覚悟なさったのです」
「うむ……互いの腕が切り離されるまでは一つだった双子、限りなく同一の存在だからこそ長女継承の力を使うことができたと」
オロルは納得したように息を吐く。一方でセリナは戦闘中に交わした言葉を思い出していた。
「姉が守ったものを守る……」
あのときスークレイは悪辣にもそう言っていた。『正義など関係ない』と。
セリナは傍目から双子を眺める。
姉妹はといえば、どちらも歩くことがままならずもどかしい距離で見つめ合っている。交わす言葉はなく、心で通じ合っていた。離れて暮らしていた歳月を埋め合うように、長旅の荷を下ろした者の笑みが浮かんでいる。
「命を捨てられる覚悟……それが一番の間違いだった……って訳か」
姉妹を眺めるセリナの視線は賢しげとも愚かともいえない細めた目で面映ゆい感傷を密めていた。同じ妹という立場、そして命を捨てる選択と覚悟をした者として、胸に共感を覚えなくもない。
姉のために戦ったスークレイであるが、彼女は姉の真意を知らずにいた。
ガントールが長女継承の責務を一人で背負い、前線出征をして戦うのは神殿の勝利のため、使命を果たす責務を全うするためだと思われていた。
だがそうではなかった。
揃いの義手を贈るのも、出征してラーンマクへ急ぐのも、辺境伯の地位を無視して妹をスペルアベルへ退がらせるのも、全てスークレイのための行動である。
ガントールが天秤の皿に乗せていた願いは正義や大義それらを含めたうえでスークレイが穏やかに暮らせる世界であった。
もし『正義と大義』、『双子の妹』の二つの錘があったなら、ガントールの天秤は迷いなく一人を選び傾くだろう。
「……なんだよ、やっぱり誤解してたじゃんか」セリナはますます脹れて地べたに大の字に寝そべる。「なにが『勘違いなんてしてません』だよ。こっちは骨折り損続きだよもう」
セリナの愚痴にウツロは深く同感して頷く。側に立つカムロは少し居心地悪くしていた。
スークレイとガントール。互いを想い帰結した関係を知っていれば、そもそもスークレイは戦わなくてもよかっただろう。……とはいえ、もしそうなっていれば翼人は双子ともども巫力をかけて差し向けたかもしれない。結果を見ればこれでよかったとも思える。
刻々と夕闇が迫り、土煙の向こう側に天秤は突き立っていた。
ウツロはそれを回収しに向かうと、後ろからカムロがついてきた。
「ウツロ」名を呼ぶ声音が微かに緊張している。両手に斧槍と天秤剣を持つこの状況で襲いかかるとは思えないが、カムロの目は真剣だった。
「あなたであれば……私の立場を理解していると判断して、この場でお話しします」
言い淀むカムロに対し、ウツロは黙って立ち尽くす。首を失った以上返答はできなかった。カムロの向こうではオロルとセリナがこちらには気付かずにガントール達の方へと歩く背が見えた。
「この場での戦闘に降伏したとはいえ、近衛隊長の私は以後も神殿の立場に立ち、あなた方と敵対の姿勢を維持しなければなりません。
ガントール様と神器天秤を失って、私は手柄なしに神殿へ帰ることはできないのです」
――お前も逃げたらどうだ。
ウツロは斧槍の石突で地面に書いた。カムロは目を落とし文字を読むと首を振った。
「そう簡単にはいきません。部下達は私の帰還を待っています。……彼らに指針を示さなければ、訳もわからぬまま混乱の渦に巻き込まれてしまう。何のために生き、戦うのか、選択の機会を与えたい」
カムロは切ない表情で唇を噛み締める。彼女にとって神殿はもはや第二の故郷なのだろう。帰りを待つ者がそこにいて、裏切れぬ絆で繋がっている。彼らの信頼に応えるためにも、例え敗北を喫して失望されたとしても、帰らないわけにはいかない。
この葛藤を打開するためにカムロはウツロと二人きりになるのを待ち、頼ったのなら、きっと考えがあるのだろう。
――俺はなにをすればいい?
斧槍から出た言葉を読み、カムロは真っ直ぐにウツロを見た。
「お願いです。私とともに神殿へ来てください」
❖
オロルとガントールを立て続けに奪われた神殿は、先に逃散し行方をくらませたアーミラも含め当代継承者を全て失ったこととなる。これは前代未聞の失態であり、責を問われる立場にあった近衛隊隊長の首が飛ぶことは免れない。
神殿へ戻ると決めたカムロも当然として現状の身の上の危機は理解している。それをわかって首を差し出すほど愚かではない。保身のためにこのまま逃げることもできたカムロは、裏切れぬ仲間との義理と責務を果たすために一考を案じた。
譴責への打開策として見出しているのが、ウツロであった。
当代継承者と互角に渡り歩き、神器を砕くほどの脅威であるこの鎧姿の戦闘魔導具を連れ帰れば多少なり手柄にはなる。問答無用で裁かれることはなくなるはずだとカムロは読んでいた。
「ウツロは身柄を拘束されるでしょうが、謀叛に至った理由を私が伝えます」
――理由を伝えてなんになる。その場で殺されるぞ。
「……そのときは、見捨ててもらっても構いません。ですがもし気が向くのであればどうか私を守ってください。いずれにしろ貴方は神殿へ向かうつもりなのでしょう?
お得意の奇襲で禍人は攻め込む……その混乱に部下の犠牲を払いたくはありません」
――お仕えしている帝を見捨てるのか?
棘のある物言いにカムロは苦々しい顔をする。戦闘の時ですら表情を硬く維持していたというのに、充血気味だった目が濡れて涙が下まつ毛に乗ってぽろりと落ちた。雫を追いかけ下を見たウツロは、彼女の脚が震えているのを知る。
「私には、……っ、貴方を止める力がない……」
カムロは涙声で言う。
「二百年も生きているあなたが、天帝を悪と断ずるなら……きっと、なにかしらの証拠を掴んでいるのでしょう……、それでも私や、部下、……民達は、っ、信じているのです。救われているのです……」
らしからぬカムロの訴えは、近衛隊長ではなく、一人の、この地に生きる女の言葉だった。
オロル達が何事かとぞろぞろ集まって、ウツロは悪態で泣かせてしまったことに気まずく思いながらも、足元に残った言葉を消さなかった。
「あぁあぁ、お兄ちゃん。泣かせるなんて最低」
茶化すことで場を明るくしようとしたのか、セリナはとりあえず兄を責める。その隣でオロルが地面に残された会話の断片に目を落としていた。
「『帝を見捨てるのか』か……酷なことを聞いたな。これは庇えんぞ」
――すまない。
ウツロは声があれば謝っているのだが、いかんせん謝罪の言葉を土に羅列するわけにもいかず、肩を落とす。カムロは泣き腫れた顔を手扇で冷ましていた。
「すみません、面前で……泣き言を言うべき立場でないのは理解しているのに……」
「いいんじゃ。阿呆なことを聞いたウツロが悪い」オロルはそう言って今度はウツロに顔を向ける。「お主はこれからやろうとしていることの重大さがわかっておらん」
ウツロは反省を態度で示すために正座になり、一言『申し訳ない』と指で土を削った。
わかっていたつもりでいた。
でも本当はわかっていなかった。
この世界を正道へ導くという己の中にある確固とした信念。それは遠い昔に翼人と龍人が掲げていた大義や正義となんら変わらないものだ。
翼人の野望は砕く。だが同時に、翼人を信じていた無辜の民は救恤しなければならない。悪を裁くだけでは多くの絶望を世に生み出す結果となるだろう。
今こうして目の前にいるカムロだってそうだ。信ずるものを失い、明日への希望を持てずに涙を流している。
道を示すための新たな光が必要なのだ。そのためにやるべきことを考えなければならない。
■014――審判 中編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
ムーンケイの戦闘と時を同じくして、隣国ナルトリポカは人でごった返していた。
普段であれば作物を運ぶ商人や農民の荷車が行き交う大通りが、今は馬を通せるだけの道を開けるのも困難なほどに混み込みとしている。煉瓦積みの建物が居並ぶ都の景観はここ数日は朝も夜もなく喧騒に包まれている。
都に押し寄せて来た者達は主に賢人種で、褐色の肌は炎に炙られ墨のように黒い者もいた。彼らは本来、ムーンケイで炉の操業につく職人達である。先立って神殿からの御触書があり、禍人の襲来に備えた避難のために住処を離れてこの地まで流れ込んで来ていたのだ。
道中では人相書も回覧され、一件の騒ぎの原因である次女継承者がいやしないかと誰彼構わず睨め付ける。怒りの矛先を求めて気が立つ賢人たちに、ナルトリポカの者たちは戸惑いを隠せなかった。
本来ならナルトリポカの都はその土地に避難民を招き入れる用意があるのだが、あいにく歓迎するだけの懐の余裕がなかった。禍人が起こしたとされる甘藷黍を主に狙った焼き討ちの被害によって、食料の備蓄が例年の三割程度まで落ち込んでいたのだ。
宿は開けど飯がない。そのため様々な店の品々の値が一夜にして跳ね上がり、碌な身銭を持ち合わせていなかった避難民は己の非もなく困窮した生活を強いられることとなり、人口密度の高まりと共に不満が波及して、街全体が殺伐としているのである。
職能と矜持を持つ賢人であるため、流石に荒事や窃盗のような問題はまだ起きていないが、この状況が続けばそう遠くないうちに治安の悪化は免れないだろう。どこの集落もぴりぴりとした空気に満ちていた。
すれ違う者同士の盗み見るような視線。誰も彼もが指名手配された一人の少女を探していた。「捕まえれば報酬が出る」……誰が言ったかその額は一生暮らしに困らぬ額だという。
猥雑な話し声を他所に、編み籠を抱えた獣人種の女が足元の賢人達を蹴飛ばさぬように道を歩く。頭には日除けにと身につけた釣鐘帽子を目深に被り、どこかよそよそしい態度で先を急いでいる。
すれ違う賢人は女の顔を見てやろうと斜に構えて帽子の内側を覗くが、目当ての人物ではなさそうだとわかるとすぐに目を逸らす。身の丈も廻状の人相書とは異なるので、それ以上怪しむこともないが、不躾な態度に違いはなかった。
女は見上げてくる幾つもの視線に気味悪さを覚え、そそくさと路地を一本抜けて宿の石段を昇る。慣れた手つきで錠を解き、部屋に入ると誰にともなく捲し立てる。
「なんなんもう。人の顔見て挨拶もなしに……。人探しか飯探しかわからんけどじろじろじろじろして、もっと目付きくらい優しくできんもんかねあれは。……はぁ、なにが『一生暮らしに困らん報酬』よ。そんなに金が欲しいなら自分とこの炉でいくらでも作ればいいんに」
部屋の奥にいた男は玄関から漏れ出す怒りの気配に気付き、椅子から立ち上がって出迎えた。
「……大丈夫か……?」
「大丈夫じゃない」
憤懣やるかたない様子で女は言い、玄関の側面の壁に取り付けられた突起に脱ぎさった帽子を引っ掛ける。ずんずんと木の板張りの床を進んで男の側によると抱えた籠の中身を見せつける。朝に買い物へ出掛けて随分とかかったわりに、覗き込まなければ品物が見えないほどに少ない。
「こんだけしか買えなかったの。どんどん値上がりして麦粉なんてこの量で銅粒二つよ、二つ!」
前のめりに訴える女に対し男はたじろぎながらも肩に触れてやんわりと抑える。
「落ち着け。今はムーンケイから押し寄せた人の分だけ需要があるから値を吊り上げてるんだろうし、急に上がったのなら下がるのもすぐさ」
「だって、アダン……」
「それより」男は声音を変えた「どうだった?」
心持ち密やかに問いかけるアダンの言葉にシーナは上目遣いに首を振った。
「ならいいんだ。今は見つからないことが大事……よし、飯にしよう。買い物に出掛けている間に有り合わせで作ってくれたんだ」
アダンはまるで自分の手柄のように得意げに言って先程まで座っていた椅子に戻る。四人がけの木製の椅子に囲われた卓には、湯気の立つ鍋と三人前の食器が並べられていた。
「あら、本当に助かるよ」シーナは感激したように声を弾ませ、先程までしわを寄せていた眉間がぱっと開いた。「ありがとうね。アーミラ」
❖
行く当てもなく山を降りたアーミラが夫婦と再開したのはほんの数日前のことである。
オロルに促され、命からがらに山を駆け降りたアーミラはナルトリポカに落ち延びていた。
最早どこにも頼れる者はいないと悲観しつつ、脳裏ではあの夫婦ならという一縷の望みを抱き、都の水路に潜り込んで救護院へ向かった。林の木陰に身を潜めて一夜を明かし、内部の様子を窺っていたがアダンとシーナの姿はなく、どうやらもう救護院にはいないのだと悟る。ではどこへ行ったのか、帰るべき集落は焼かれているのだから、もう探すこともできないだろう。
――二度と会えないかもしれない……。
アーミラは失意に肩を落とすが、禍福は糾える縄の如し、偶然にもシーナがそこに通りかかった。街路を行く彼女の姿を見て、思わず林から飛び出しそうになり、慌てて藪に潜り込む。葉叢ががさりと音を立てて枝を揺らし、シーナは顔を向ける。
獣が藪に飛び込みでもしたのかとシーナは思ったが、なんとも言葉にできない予感が胸に迫った。何者かと通じ合うような胸の切なさを覚え、確証もなく「あの娘かもしれない」という考えがよぎったのである。
薮の方へ近付き、そっと声をかける。
「アーミラ……? そこにいるん?」
掻き分けた枝葉の向こう、くしゃくしゃに泣いているアーミラがそこにいた。
こうしてアーミラは夫婦と再会を果たした。
シーナはすぐにでも仮住まいの宿へ案内したがったが、往来に出ることをアーミラが頑なに嫌がったため、夜に人目を避けて部屋に連れ込んだ。
後日廻状が街まで届き識字の心得の無い者にも伝聞が周知されると夫婦は大層青褪めたが、同時に身を隠す事情を察しこのまま匿い続けると決めた。……アーミラが罪人なはずないもの、きっと何かの間違いだわ。
これが神殿から行方をくらましたアーミラの経緯である。
「……すみません……こんな形で、再会なんて……」
アーミラは昼食の前に改まって謝罪した。卓を挟んで向かい合うアダンとシーナは、あえて重く受け取らないようにと努めていた。
「どんな再会でもあたしゃ嬉しいよ。……生きて帰って来てくれたんだもの。本当によかった」
シーナは甲斐甲斐しくアーミラの皿によそい、鍋の中の根菜と肉を丁寧に盛り付けた。街の急激な物価の上昇を受けて質素な味付けではあるが、溶けた野菜の風味と肉の脂の旨味があった。何よりこの味付けは昔シーナがアーミラに教えた調理法である。ひと匙掬って口にすると、アダンもシーナも泣き笑いの顔をする。些細なことでも家族としての繋がりを感じて嬉しくなったのだ。
「外ではアーミラのことを追っかけ回す連中がいるみたいだが、俺たちが守ってやるから安心してくれ」アダンは言葉を切って腕を組む。「ただ、何が起きたのかは話してくれないか」
アーミラはこくりと頷き、食事に手を付けていないまま匙を置いた。
どこから話すべきかとしばらく沈黙したあと、ウツロという鎧と共にナルトリポカから神殿に向かった場面から語り始めた。
木彫りでしか見たことのない長女継承者その人に出会ったこと。
オロルという生意気な賢人がやってきて三女神が揃ったこと。
四人で前線に向かっていた夜に、集落を守れなかったこと。
襲った禍人種に復讐するため力を身につけていったこと。
「あのときウツロさんがいなければ、お二人を助けることはできなかったでしょう……」
「そう……」シーナは神妙に相槌を打つ。
長いながい困難の旅路を語るアーミラは、一度喉を潤すために汁を啜った。すっかり冷めてしまった汁には滋味深い味わいがあり、胡椒の芳醇な香りと辛みが鼻に抜ける。胃に降る温度が心地よかった。久しぶりのまともな食事だった。
「でもね、あのとき確かにアーミラは助けてくれたんだよ」
「え……?」なんのことかとアーミラの声が上ずる。
「鎧の人が来たとき、禍人の男が私の首を切り裂こうとしたんさ……でも青い光が、ばばって光ってね、刃が刺さらないように私の首を守ってくれた。
だからあたし、『あぁアーミラだ』って思ったの」
「……そんな、私は、何も――」
かぶりを振るアーミラに対して、シーナは少しだけ横を向いて髪を耳にかけた。
控えめに輝く耳飾りを見つけてアーミラは理解する。あれは旅立つ際の餞別として二人にあげたものだった。私がここを去った後も息災でいられるよう、不出来な私に代わる本当の子宝にどうか恵まれますようにという感謝と願いを込めたもの……そうか、『息災の祈り』がシーナの危機を救ったのかと、アーミラは理解する。
「私たちのことを、守ってくれてありがとね」
穏やかな笑みと感謝の言葉。……なぜだかアーミラには深々と刺さり、心を揺さぶられた。記憶を取り戻すときの胸の高鳴りにも似た感情が湧き上がって、匙を握る手にぐっと力を込めて俯いてしまう。
急に泣き出したことに、アダンとシーナは椅子から腰を浮かせてアーミラの様子を窺う。どこか痛むのかと身を案じたが、この涙は悲痛から来るものではない。
ずっとこの言葉を探し求めていた気がしたのだ。
背負わされてきた使命のために戦って、傷付いて、その果てに今度は神殿から追い立てられ必死で逃げているこの悔しさ。報われない労苦を誰にも理解されない孤独の寂しさに、シーナの何気ない一言が優しく寄り添うのを感じた。
――そうだ。私はただ『ありがとう』って言って欲しかったんだ……。
失っていた記憶を求めて神器を携え出征した。
大切な人を守れるような強い人間になろうとした。
だが、しかし。
大切な人を守るための強さなんて初めから持っていた。
誰かを思い、祈ること。
それだけでよかったのだ。
一つの真理を手に入れて、アーミラは涙を堪えるのをやめた。
「よかった……」
アーミラはぽつりと呟き、涙を溜めた顔をあげた。
シーナはうんうんと頷いてアーミラを胸に抱き、アダンはそっと頭を撫でた。娘の内に抱えるものを十全には理解できずとも二人にはこの涙が快方の兆しだと感じることができた。
なんと可哀想なのだろう。こんなにも純真な心を持つ娘が神殿から追われるとは、まさしくこの世の不条理ではないだろうか。一体なぜ、アーミラは神殿から追われ、廻状が出ているというのか。
アーミラは一頻り泣き、それが落ち着くと旅の続きを語った。時折洟をすすりながらではあるが、腫らした目から涙は落ちなかった。暗澹とした瞳は虚空へと視線を飛ばし、アーミラの意識は追憶の戦場にいた。
スペルアベルでの日々。
ラーンマクの戦い。
前線までの足跡で拾い集めた記憶。
そして現れた災禍の龍と、その決着について。
耳を傾けている夫婦は、想像を超える壮絶な前線の実態を聴いて言葉もなかった。
「……記憶が取り戻せたのはなによりだが、まさか禍人の生まれとは……」
アダンは話を聞き終えて難しい顔をしていた。隣に座るシーナが肘で小突くと、アダンは自身の失言に気付き慌てて取り繕う。
「違うんだ、そういう意味じゃなくてだな……えっと、例えアーミラが禍人であっても俺は娘だと思っているぞ……! その上で、流石に驚いたというかだな……」
「……平気です。私もまだ、自分が禍人の生まれだとは呑み込めていませんので」
「そう、なのか……いや、そうだよな」
アダンはやや強引に笑って誤魔化すが、シーナは夫の失言を責めるような視線を向けた後に会話を継いだ。
「でも、神殿に追われてるのは禍人だからじゃないんでしょ?」
シーナの問いにアーミラは頷く。生まれの事実はオロルにしか打ち明けていない。帰投した時点では神殿には伝わっていないはずだった。
「大切な神器が壊れたこと、災禍の龍討伐でウツロが寝返ったことと、ガントールさんが脚を失ったこと……これらの責任が私にあると」
「ウツロっていう鎧と一番仲良くしてたから、いよいよ立場が悪くなって神殿から逃げたわけね……」言いながら眉を顰める。「なんだかおかしな話ねぇ」
おかしな話……アーミラはその一言で片付けられたことに少々戸惑ったが、しかし言い得て妙である。オロルの手引きで逃げ出したときは頭が働かなかったが、こうして冷静に振り返ってみると道理が通らない。いくらでも反論できたはずだが、事はそのように運ばなかった。道理を枉げたおかしな話を押し通すため、神殿の態度が有無を言わさなかったのだ。
「そう考えると、ウツロはアーミラの心臓の火を持って逃げてくれたんだろう? ……これじゃ裏切ったのか味方なのか、何がしたいんだろうな」
アダンもしかめ面をして天井を見上げて考えている。持ち得る手掛かりだけではウツロの行動を理解できるはずもなく、アーミラの頭の中は戸惑いと自責がどっしりと居座っていた。前線の日々では釦を掛け違えたかのようにウツロとすれ違い衝突してばかりだった……もし私の態度が原因なら……。
物思いに耽るアーミラ。悩みはあれども身を落ち着けられるだけの余裕があった。しかし、束の間の休息に終わりを告げる来訪者が宿の外に迫っていた。
こんこんこん。
木製の扉に取り付けられている叩き金が三回鳴らされ、室内は緊張が走る。
「どちら様で?」アダンは椅子に座ったまま扉の方に声をかけ、顎をしゃくってアーミラを奥の部屋に隠れるようにと促す。
外からの返答はなく、扉が再び叩かれる。
こうなるとこちらも居留守を使えばよかったかとアダンは後悔したが、居直ってもう一度「どちら様かね」と繰り返した。……名乗るまで椅子から立ち上がらんぞ。
ややあって、向こうが名乗った。
「神殿に仕える者だ。速やかに扉を開けなさい」
太く勇ましい声が部屋に届く。それなりに腕っぷしに覚えのあるアダンであるが、威圧的な相手の声を聞いて臆病風に吹かれてしまう。
「ちょっと待ってくれ」アダンは立ち上がり、シーナの方に振り返る。――アーミラは隠れたか?
シーナもまた頷きで応える。――大丈夫、隠れたよ。
アダンはさも忙しさで応対できなかった風を装って食器を台所へ運び、無駄に棚を開け閉めして物音を立ててから、足の怪我を大袈裟に引きずって玄関へ向かい錠を解いた。
扉を少し開けると、外に立つ白衣の隊列に目を丸くした。てっきり相手は一人か二人だろうと思っていたが、外に待つのは偉丈夫の男達が三十は列をなしていた。
怪しまれぬように平然と振る舞おうとしていたが、これにはむしろ驚くのが当然だろう。アダンは事情が呑み込めないと狼狽えた様子で白衣の訪問者を見る。
「こりゃあ、どうしたんです……そんな大勢で」
「廻状にあるアーミラ・アウロラがこの宿に潜伏している疑いがある。総員中へ」最後の言葉はアダンではなく後ろに並ぶ隊列に向けていた。
狭い玄関に向かって男達が押し寄せ、有無も言わさずアダンとシーナは台所の奥まで退けられた。部屋の中は嵐が吹き荒れたように隅々までひっくり返され、閉じられた戸は全て開けられ、棚の引き出しも一つ残らず床に放られた。これではすぐに見つかってしまうと思っていたが、アーミラは巧妙に姿を消していた。だが、宿に身を隠せる場所はそうないだろう。きっと時間の問題だった。
「おい、なんなんだよいきなり……!」
憤ったアダンの声も気にせず、白衣の者達は手当たり次第に荒らし回る。部屋が滅茶苦茶になることも大変だが、シーナは怯えながらアーミラが見つけられてしまうことを心配した。こんな乱暴な奴らにアーミラは追いかけられているなんて……恐ろしいよ……。
「もうやめて! ここには誰もいやしないよ!!」シーナは震える体で必死に抵抗するが、屋根裏に身を潜め気配を消していたアーミラはかえって気が気ではなかった。下手に抵抗したら二人まで捕まってしまう。
自分の身に危険が迫るのならいくらでも耐えられた。でもこの二人に危害が及ぶのは絶対に許せない。アーミラは覚悟を決め、屋根裏に立つ。下にいる者の気配を感じ取り、好機を待った。
「私はここです!」アーミラは梁に張られた薄い木の板を蹴破り、白衣共の頭上に飛び降りる!
ばりばりと板が破れ、溜まっていた屋根裏の埃が視界を覆う煙幕となった。アーミラは無詠唱で風を操り彼らの目に向けて埃をねじ込み、男たちは両手で顔を覆って痛みに叫ぶ。
「ぐわぁっ、目が!」
「何も見えん!!」
「おいだれか、なんとかしろ!!」
異物を眼球に入れてしまった偉丈夫達は堪らず苦悶の声をあげ、亡者のようにその場で腕を振り身を捩る。アーミラは彼らの足元を鼠のようにするすると駆け抜けた。衣擦れに逃走者の気配悟り、男達は互いの白衣を掴みあって無様に縺れて転がった。先程までの威圧的な姿も形無しである。
アーミラは玄関には向わず台所の調理場の窓を目指す。そこから出ていくつもりだった。
「おい! 待て……!」
埃の目潰しを免れた白衣の男がアーミラの後を追いかけ腕を伸ばす。血管の浮き出た太い腕がアーミラの髪に絡み、離すまいと乱暴に握る。アーミラの頭は力任せに引き寄せられて頭皮から数本の髪が抜けた。
「……っ!」痛みに顔が歪む。
このままではアーミラが捕まってしまう! ――アダンは己の腰帯に収めていた切り出しをアーミラに向けて放った。
それは集落を襲った男の得物だった。ダラクという名の凶暴な男がアダンの胸に突き刺そうとした刃である。絶体絶命に思われたアダンを守ったのは、やはりアーミラが渡していた耳飾りの祈りであった。それから都の救護院で目覚め、自力で歩けるように回復した後、集落の燃え滓の中でこの切り出しを見つけ、木工に使えないかと呑気にも拾っていたものだった。
投げ渡された切り出しをアーミラは握り、髪を掴む男の表情が強張った。腕を切られると思ったのだろう。しかし、アーミラが切ったのは髪のほうであった。
重たく結えていた綺麗な髪がばっさりと切り落とされ、髪を掴んでいた男は張り合う力が抜けた弾みで後ろに転がり、団子になった男達の上に倒れて悲鳴が上がる。
アーミラは既に窓の下枠に足をかけていた。そのまま外に飛び出して都の路地裏へ消える。白衣の男達も倒つ転びつ目を擦りながら後を追って部屋から出ていった。
嵐のあとの静けさに、アダンとシーナは呆然と立ち尽くす。
「……行っちゃったよ、あの子……」
「凄かったな……あんな兵隊相手に……」
二人は大変な目に遭ったというのに、不思議と笑いが込み上げた。
部屋を散らかされた怒りも忘れて目を輝かせる。
「強かったねうちの娘は……! 見たかいあの身のこなし、ありゃあ誰にも負けないよ」
旅立つ以前と比べて別人のように逞しく成長しているアーミラを目の当たりにした二人は、身を案ずることが杞憂であると確信した。
あの娘は立派に成長している。心配はいらないだろう。
別れの言葉を交わせなかったが問題ない。すぐに帰ってくるだろう。
❖
夫婦と別れたアーミラは都を離れて北へ走った。
――彼らは、私を殺す気がない。
これは楽観ではなく、白衣の者達が武器を構えていなかったことからアーミラが推察したことだ。
――縄があれば私を捕まえられると高を括っていた……? 神殿から逃げ出した継承者をそこまで甘く見るとは思えない。もっと容赦なく攻撃を仕掛けてきてもいいはずなのにそれをしない……なら、神殿の目的は何……?
頭の中で道理を導こうとしたが、欠けた穴は依然として大きい。
それでもアーミラは着実に穴を埋めようとしていた。
ウツロの謀叛から始まる一連の騒動……ですが果たして、原因はウツロなのでしょうか。彼が私を裏切ったのなら、神殿で私の心臓の灯火を救い出した矛盾はどうしても説明できない。
アーミラはぐんぐんと道幅の狭くなる都の路地を抜け、腰ほどの高さの柵を足場にして家屋の上に移ると、屋根伝いに逃走した。下では人相書を頼りに捕物を行う者達がアーミラを見上げて騒ぎ始めるが、かえって都合がよかった。彼らは人壁として白衣の隊列の進行を阻んだのである。
郊外まで逃げたアーミラは一度追手を振り返り、北側の林を潜った。その先はマハルドヮグの山が待つ。追手を撒くには悪手だが、考えがあった。
呼吸を整え、方針を決めた。――彼を疑うからややこしくなる……。
『俺が従うのはラヴェルではない。継承者だ』あのときウツロはそう言った。『彼女らの信頼を裏切った蚩尤には、決して与しない』と。
ウツロが継承者に従い、今もそのために戦っているとしたら彼は何と敵対している? 『蚩尤』とはどんな意味か? 神殿はなぜ私に責任をなすりつけた……?
アーミラは少しずつ、しかし着実に穴を埋めつつあった。触れられるはずもない真実の輪郭に、その指先が触れようとしていた。
私が神殿から逃げ出さなければならなくなった原因が誰かの裏切りによるものなら、きっとその人こそが『蚩尤』なのだろう。そして一番に疑わしいのは近衛隊を動かせる者……であれば蚩尤とは天帝……?
ラヴェル一族は継承者を騙すような事をした……? それともこれから、継承者に悪事を働くかもしれないってこと……?
アーミラは神殿から逃げ出す前に聞いたカムロの発言を思い出す。
『近衛隊にとって、勅命は絶対なのです』
勅命ということは、捕らえよと命じたのが帝であるということだ。であるなら、ここまでの推察は間違っていない。帝についてなにか知りえることはないかとアーミラは記憶を辿る。接点なんてあるはずもないが、出征式典の折に一度だけ顔を見た。そして声を聞いた――そうだ……なにか言ってた……!
私を見下ろして、帝はこう呟いていた。
『恐れるな、何も知らぬだけだ』
あの言葉はどういう意味だったのだろうか。私の記憶がないことに同情して励ましているのだと思っていたけれど、それにしては暗い独り言のような赴きだった。どちらかといえば自分に言い聞かせているような印象だと記憶している。
――帝は、私を恐れている……? 私が記憶を取り戻すことで、帝にとってなにか不都合がある……?
アーミラはこの疑問が頭に浮かんだときに言いようのない胸のざわめきを覚えた。核心に触れている予感があった。実際にこうして、記憶を取り戻した私を追っているではないか。
――思い出せ。私が前線で拾い集めた記憶を……。
まず、物心つく前の朧げな記憶。
マナに抱かれどこかへと向かう場面と、部屋に残り見送る男……これはおそらく父だろう。おそらく一番古い記憶の欠片。
そして内地の涸れ井戸と水路で過ごした幼少の日々。流浪の民としてひたすらに歩き続けた。
ラーンマクでは、私がアルクトィスの生まれという仮説が覆り、それどころか生まれの種族さえも違うと知った。
禍人種の血を持つ次女継承者……神殿にとって不都合な記憶とはこれだろうか。他にも、幼い頃私は一度死んでいる。この記憶は帝に都合が悪いだろうか。
私は禍人種の肉体を捨てて偽りの魔人種となり、刻印を拒んだ。これにより命を削ったお師様は老婆となり、私は記憶を失い――
「全部の謎が……お師様に繋がってる……」
記憶喪失。
刻印の拒絶。
神殿からの逃走。
一つ一つの点を結ぶ線の先に、複雑に絡み合った糸の結び目がある。
そう。お師様――マナ・アウロラとの旅は流浪ではなく逃避行だった。
幼い頃に胸に抱かれ駆け出したあのとき、マナは何から逃げていたのか……神殿だ。
これで二度目の逃避行なのだと、そう確信できるような懐かしさがあの山道にはあった……幼い頃と現在、同じように追われている。きっとその理由は同じなんだ。
では、私を見送り、あの狭い室内に留まった男は――父は――まだそこにいる……? なぜ禍人である私が神殿にいたの……? 師は何者だったの……? なぜ私を逃がしてくれたの……?
なにか、とても大きな暗闇が世界を歪め、真実を隠している。……そのしわ寄せが私を苦境に立たせているのではないかとアーミラは感じていた。そしてその闇の力の根源が神殿と関わりを持っている予感は常にあった。
林の深くへ潜り、斜面は勾配をきつくしてマハルドヮグの裾野に入っている。手荒なことになってもいいように人のいない場所を選んで逃げてきたアーミラは、左手側に木漏れ日の射す一帯を見つけた。
鬱蒼とした林の一画、木々の切り拓かれた場所に辿り着く。そこは人気のない木造小屋の並ぶ庄……今は誰も住んでいないようだが、捨てられた集落という風でもない。山に住む杣人は木を切りすぎないようにいくつかの拠点を持ち、一つの庄で採伐が終わると別の庄へ移動すると聞いたことがある。つまりここには誰もいないということだ。追手の相手をするには丁度よい。
アーミラはこの場所を選び、走る脚を止める。
遅れてやってきた白衣の兵隊は輪になって取り囲む。目が充血して息も切らしていた。遠くからは馬の蹄の怒涛の律動がこちらに向かって来ているのが聴こえる。……神殿からの増援だろうか。
「いい加減逃げられないぞ、大人しくしろ」
目をやられて腹を立てている男が威勢よく脅しかける。
アーミラは聞こえていないかのように無視して、握ったままの切り出しで不揃いな髪を整える。藍鉄色の髪が肩にかかる程度になるよう毛先を揃えると、手に残った房を指に絡ませた。使い様によってはこの切った髪も武器になる。
「そちらこそ大人しくしてください。近付けば目を刺します」
アーミラの脅しに白衣の男は慄いた。彼女が手に握っている髪の毛が針となって目に飛んでくる想像をしたからだ。それでなくともここは山の中、手頃な武器が足元にいくらでも転がっている。
「答えてください。なぜ私は追われているのですか? 目的はなんです?」
男達は黙ってアーミラを睨む。膠着した状況はじりじりと白衣の兵を増やし、無人であった庄は白衣の男達で溢れる。アーミラに怯える素振りはない。男達も問いかけを無視して輪を絞る。
「答えませんか……」
捕えろ! という号令にアーミラの呟きはかき消され、庄の樹々からは騒ぎを警戒した鳥達が上空を旋回する。
腕で顔を守りながら突っ込む男達にアーミラは宣言通り髪の針を飛ばしたあと、当然の対抗策として脚を捕縛し転ばせた。先陣を切った人の輪は縺れて倒れ、後続の騎馬兵がそれを飛び越えてアーミラへ迫る。その手には槍を握っていた。
「……槍……!?」
アーミラは兵の目的が変わったと悟る。
――生け捕りは諦めたようですね……!
アーミラは驚きはしたもののすぐに回避行動に移る。馬の横、低く構えた槍の横薙ぎを飛び越えて躱し、距離を保つ。新たな増援である騎馬兵の一振りには明確な害意があった。
彼らはおそらくこう命じられている。『可能であれば生け取りにせよ。抵抗するようであればその場で殺せ――』
「……分かりました」アーミラは頬の泥を拭い、唇を噛む。「ここで死ぬわけにはいきませんので……!」
決然と睨む碧眼が青く燃える。
神器を持たぬ魔人の娘が、神人種の兵達と徹底抗戦の意志を示した。
対する騎馬兵の集団も、面甲の隙間から鋭く娘を捉えている。蹄が大地を蹴り、アーミラへ迫る。
魔力を練り上げたアーミラは即座に術を展開し、下生えを操り脚を狙う。馬の歩調は乱され、騎馬兵の連携が崩れた。その中でも手綱捌きを誤った者は落馬し、背中を強かに打って転がる。
体勢を崩した騎兵は手をつき立ちあがろうとするが、その手も蔦に絡め取られて緑色の繭が覆った。草木に捕縛され身動きのできない兵は微かな隙間から驚愕に凍りついた顔を覗かせる。その横を他の騎馬兵が通り過ぎる。
迫る兵達を目で追いかけ、アーミラは少し虚しくなった。
まるで内地に侵入した間者でも見る目で、彼らが睨んでいるからだ。
――もしかしたら、あのときのウツロさんもこんな気持ちだったのかな……。
誰にも功績を称えられず、利用されるだけ利用されて、挙げ句の果てに追い立てられて……。
……今からでも、また会えるだろうか……。
手を取り合って一緒に戦えないだろうか……。
騎兵は馬の脚を止めぬようにアーミラの周りを駆け回り、俯く娘の油断を突こうと槍を振って迫る。アーミラは間合いを見切って飛びかかると、刃のない竿の部分を掴み、逆上がりをして槍の上に乗る。目を見張る兵の面甲に術を飛ばして顔を焼いた。爆ぜる炎に馬が嘶く。
我を忘れて火を消そうと踠き騎兵は地面に転がる。その姿を樹々の根が炎ごと呑み込み土中に隠す。
残された槍をアーミラは仮の杖として拾い上げ、次の兵を見定める。
次々と迫る騎馬兵達をアーミラは打ち倒し、馬から落ちた兵は庄の瘤となって土中に埋まった。数で圧倒できると意気込んでいた騎馬兵の攻め手が詰まり、どうにも勝てる気がしないと力量の差を理解しはじめる。
気付けば歩兵は全て庄の木立に絡め取られ、増援の騎馬兵もほとんどが草の繭に閉じ込められていた。閑散として穏やかな庄の景色はアーミラの力によって瘤状に膨れ上がった異形の景色に変貌していた。
「助けてくれぇ……!」
「誰か……、誰かいないのか……!」
「俺はここだぁ! 助けてくれぇ……!!」
繭や瘤の内側からは助けを求めるくぐもった声が響き、庄全体に呻き声が響もす。ただでさえ自由の利かない重装に、がっしりと全身を絡め取られてしまえばどんな屈強な兵であっても閉所恐怖に陥るだろう。
「まだやりますか……?」
アーミラは駄目押しに兵を脅し、助けを求める瘤に材木をあてがう。何をするつもりか、騎馬兵は直ぐに理解することになる。
浮遊させた材木の先端が独りでに削ぎ落とされて鋭く尖り、今にも突き刺さらんばかりの杭となった。アーミラの合図一つあれば中に閉じ込められた兵に深々と突き刺さることだろう。
兵は互いを見合い、そして「参った」と両手を挙げる。先頭にいる兵から後ろへ波紋を広げるように全員が手を挙げる。降参だ。勝負あった。
その陰で、一人の男は顎髭を撫でて不敵に笑う。
「……俺の出番か――」
❖
追手を降し、アーミラは鼻らから吸い込んだ息を口から吐き出す。
このまま逃避行に決着が着くのだと思っていた。
山の庄はからりとして荒天の気配もなかったが、上空を流れる雲は急速に渦を巻き始めて曇天となる。木漏れ日の穏やかな陽射しが不穏に翳り、アーミラは解きかけた警戒を再び厳とした。
牙を剥いた狼が木立を駆け抜けるが如く肌寒い風が樹々の狭間で唸り、視界は突然黒白に焼かれた。
どどう! と衝撃が爆ぜる。
強い光に照らされた騎馬兵達の姿がアーミラの目に焼き付き、思わず目を閉じると激しくのたうつ稲妻が耳に轟いた。アーミラは堪らずその場に身を屈める。
ごろごろと余韻を残す雷の音が去り、アーミラは恐る恐る目を開ける。庄に積まれた材木から焦げた煙の臭いが立ち昇り、騎馬兵が白目をむいて項垂れている。口からは煙を吐いているようにさえ見えた。
雷が直撃したのだ。それも一人だけではなく、全員に。
降参に挙げていた両腕は肩からだらりと弛緩して馬の背を叩き、鐙に引っ掛けた爪先からは、地面に向けて細枝のような稲光が放電されている。下にいた馬も目を丸くしたまま立ち往生しているように見えた。
死んでしまったと、アーミラは思った。
駆け寄って彼らの安否を確かめたい気持ちもあるが、まさかこの雷が自然現象なわけもない。――伏兵による奇襲……私が狙われていなかったということは、神殿と仇なす者の仕業……。
「安心しな……殺しちゃいない」
語りかける声にアーミラは辺りを窺う。人影は意外にも前方にいた。
馬と諸共に頽れる騎馬兵。開けていく視界の中で一人、立ち続ける白衣の男……近衛隊の中に、雷を放った者が紛れていたのである。
それも、知った顔だった。
「ザルマカシムさん……!?」
アーミラは目を疑った。
この男は近衛隊の副隊長の立場であるはず……。
「なんで、部下を……」
といいかけて、言葉が続かない。
目まぐるしく移ろう状況の変化に理解が追い付かなかった。
この男が禍人種と連絡を持っているという驚きが初めにあり、次にザルマカシムが本物かどうかを疑った。いつぞやのように顔を奪いなりすますトガの存在を忘れはしない。
無言で槍を構えたアーミラに対し、ザルマカシムは慌てて手を振る。
「おっと! 待ってくれよ、戦うつもりはない」
「偽者かもしれません」
「『ハラサグリ』だってか、あれはきちんと倒したんだろう? 私は本物のザルマカシムだ」
アーミラはしばらくじっと睨み続けたが、溜め息を鼻から漏らし、槍を降ろす。両者が戦わずして済んだことを後にセリナが知れば、それは羨ましく思ったことだろう。オロルやガントールに手間取ったウツロとは違い、ザルマカシムは首尾よく継承者を味方に引き入れることに成功した。
「貴方がザルマカシムさん本人であるなら、なおさら疑問です。……なぜ部下を倒したのですか?」
「気を失ってもらった方が都合がいい。アーミラ様を助け出すにも、俺の正体を明かすにも……。
白衣には簡易的な治癒の術式も編み込まれていますし、暫くすればこいつらは目を覚ますでしょう」
落ち着かせるような態度でアーミラの肩に触れる。その大きな掌は温かで、呪力は込められてはいなかった。
「驚いたかもしれませんが、私が間者の正体です。……そして今はアーミラ様を迎えに来ました」
筋骨隆々な巨体を丸めて跪くザルマカシムを眺め、アーミラは浅い呼吸を整えて逃避行が終わったことを実感する。
だが、それでも釈然とはしなかった。まだまだわからないことが多すぎる。
「私の知らないこと、聞けば答えてくれますか?」
言問顔に対し、ザルマカシムは首肯する。
「ええ、知る限りならいくらでも答えましょう。
ですが……もろもろの事は移動しながらご説明させていただきます。一緒に来てくれますかな?」
アーミラはこの誘いを信ずるべきか推し量る。
まず自分の状況を省みる。……追手を倒したものの、神殿と敵対してしまっている。ならば禍人と手を組むか? そう簡単な話ではない。確かにこの体には禍人の血が流れているが、敵として憎み、命がけで戦った敵対関係にある。このまま禍人の根城へ連れてかれればどんな報復に遭うか……それに――
「ウツロさんは……、そこにいますか?」
彼にどんな顔をして合えばいいのか。
思い悩むアーミラの表情に、ザルマカシムは暫し呆気に取られたように目を丸くしたが、ややあって力強く答えた。
「ああ。ウツロは我々と手を組んでいるからな」
アーミラは訝しむような目をしていた。ザルマカシムは「証拠だってある」と言って指笛を吹き、木陰に離していた自分の馬を呼び寄せる。その馬には駄載の装備が着けられていた。
「ウツロからの預かり物だ」
籠の中から取り出したそれがザルマカシムを青く照り返し、手のひらにそっと乗せてこちらに差し出された。眩しく燃える炎である。
「これ……私の……」
アーミラは自身の心臓を受け取り、炎はすり抜けるように胸の内側に収まった。熱い血潮が脈打ち、久しく感じていなかった鼓動に意識を向けた。
心と体が一体であるという心地よい感覚に包まれる。
「継承者を救うために、ウツロは今も戦っている」
「継承者を……救うため……――」
その一言を契機として、アーミラは差し出されたザルマカシムの手を取り、誘いに乗った。囚われていた心臓を救い届けてくれた誠意を、アーミラは信じることにした。
「――わかりました。彼のもとに連れて行ってください」
❖
ザルマカシムとアーミラは計略の運び通り合流地点へと向かっていた。
ナルトリポカと神殿の麓、国境付近の庄からそのまま登坂を進んだ二人は道の整えられていない山道を登り数刻、日はすでに沈んでいた。
今頃はハラヴァンも神殿に潜み機を伺っているはずであった。ザルマカシムは捜索に食い潰してしまった遅れを取り戻すために先を急ぎ、その後をついて歩くアーミラも疲れた脚を歩かせる。鬱蒼と生い茂る背の高い葉叢に覆われた視界の悪い鞍部を踏み分け、二人はマハルドヮグ山の地下水脈の入り口へと辿り着いた。空には赤々とした月光が照らしていた。
アーミラは目の前に開かれた洞穴の真っ暗闇を前にして踏み入るのを躊躇い、脚を止める。鍾乳洞だろうか、穴の上下から伸びた鋭くも艶めかしい石が不揃いにならび、まるで巨大な化け物の口のようだった。
夜闇にいっそう黒く浮かび上がる虚空の入り口……奥から絶えず鳴り止まぬ滝の瀑声が腹に響き、飛沫混じりの風が脚を怯ませる。
本当にこの先にウツロがいるのだろうか……? アーミラはちらりとザルマカシムのいる方に視線を向けるが、山の夜は暗く表情は窺えない。
代わりに声が届く。
「この地下水は洞窟になっていて、奥には間者の隠れ家がある。……それこそ出征式典の前日も禍人は潜んでいたんだぞ」
その言葉に驚く元気もない。アーミラは呼吸を繰り返し息を整える。
「……せっかく逃げてきたのに、自分から神殿に向かうなんて」
「ははっ、違いない……これで最後と祈りたいものだな」
道中の会話を経てザルマカシムの言葉使いからは敬語が砕けていた。さして気にすることではないとアーミラも指摘はしなかったが、時折覗かせていた近衛隊とは別の姿が、本来のザルマカシムなのだろうとアーミラは思った。
「おそらく隠れ家にはハラヴァンという禍人がいる。そこでウツロとセリナが奇襲をかけるのを待ち、混乱に乗じてガントールとオロルを連れ出す」
簡潔に段取りをアーミラに伝え、ザルマカシムは鍾乳洞を先導する。実はこのとき神殿にいるはずのガントールとオロルは留守であり、内地の手前でウツロと戦闘を繰り広げていたのだが、アーミラ捜索の指揮に乗り出していたザルマカシムはその事情を知らなかった。すでにウツロとセリナは二人を仲間に引き入れていて、神殿に向かい奇襲をかける段にあった。
「灯りは無しで行く。アーミラ様、夜目は利きますか?」
地下水脈への入り口は人の手が加えられていない天然の隧道であるため足下を照らしたいものの、神殿の警戒を掻い潜るならば奥へ進むまでは灯りを燈すわけにはいかなかった。魔呪術の痕跡も残したくない。
「はい、少し慣れてきました」
アーミラの返答にザルマカシムは「おや」と思う。
生来の獣人の目とハラヴァンの施した龍体術によってザルマカシムは暗闇にも視界は利く。通常は夜目の利かない魔人種を暗渠に連れ歩くことを心配したのだが、アーミラは「慣れてきた」と言った。
「ほぉ、そりゃすごい。この闇は禍人でもなければ見えないと思っていたが」
ザルマカシムの言葉に他意はなかったが、アーミラは己の中に流れる血を意識しないではいられなかった。
「……暗がりばかり、歩いてきたので」
そんな返答が返ってきて、ザルマカシムは片眉を吊り上げつつも、とりあえず愛想よく笑った。厭世的なアーミラの皮肉と受け取った。
天井から伸びる鍾乳石に頭をぶつけぬように手をあげて庇いながら真っ暗闇を進み、いよいよ自分の腕さえも見えないほど光の届かないところにやってきた。こうなると夜目が利くかどうかの問題ではないが、夜警に見つかる心配がなくなったので灯りを点けることができる。
「火をつけてもいいですか?」
「加減を誤ると目に悪い。俺にお任せを」
ザルマカシムは灯りの役目を買って出ると、腰に携えた細剣を鞘ごと握り、ごく小さい燐光を纏わせた。直接的な光ではなく、帯電による間接的な発光現象を用いて闇を優しく照らす。確かにこれであれば目を焼かれることもないとアーミラは感心する。
洞の内部は蕩けた乳白色の壁で覆われており、まるで剥がされた人の皮が幾重にも張り付いているような景観だった。至るところから伸びている石筍が道を難み開けた空間を複雑なものにしていた。夜に歩くには不気味極まりない洞穴だが、足下に流れている小川の水は綺麗なようで泥に汚れる不快感はない。しんとした冷たさが沓越しに足指に伝わる。
入り組んだ斜面が織りなす洞穴の道を進みながら、アーミラはウツロの生い立ちと事情を知らされる。滑りやすい隧道の坂を登るだけでも一苦労、意識を集中しなければならなかったが、ザルマカシムの口から語られる彼の半生――とは言っても二百年の歳月を生きている――は、驚くことの連続であった。
ウツロの正体は人間であり、異世界から霊素のみが鎧に宿ったこと。
先代継承者達との壮絶な死別を経験し、癒えぬまま封印されたこと。
私達と出征した後、異世界に置いてきてしまった妹と再開したこと。
私の首を切ってみせたあの前線で、ウツロは裏切れぬ二つの誓いの狭間で選択を迫られたのだ。
災禍に眠る妹を救うか。
神殿を勝利へと導くか。
……そしてウツロは妹を選び、神殿を裏切るしかなかった。
――しかし、これは果たして責められるべきなのだろうか。
アーミラはウツロの選択とそれに至る事情を聞かされ、自責の念が氷解していくのを感じた。私の振る舞いが彼を蛇の道へ追いやったわけではなかったのだ。
災禍の龍討伐の瀬戸際で見せたあまりにも突然な手のひら返し、不可解であったウツロの謀叛に彼なりの道理が通ることで不信感はどんどんと晴れていった。
彼は一貫して私達に誠実であった。同時に、妹に対しても誠実でありたかったのだろう。
私の詠唱を止めなければ目の前の妹に確実な死が迫っていた……そうなれば兄は神器を破壊してでも止める……それは神殿への謀叛となるが、救いだせる機会はあの場しかなかったのだ。
どれほどの覚悟と勇気を必要としただろうか……ウツロに降りかかる受難はどれも常識を超えていた。
歪な世界の不条理に翻弄され苦しむ彼の半生に共感を覚え、彼を特別に思ってしまう理由がようやくわかった気がした。初めて合ったときから彼だけは心を通じ合えるのではないかと予感していた意味がわかった気がした。
「――それに、ですよ。アーミラ様。
これは間諜を働く私が言ったところで説得力はないかもしれないが、近衛隊副長の立場から言わせて貰えば、ラヴェル一族は黒だ」
ザルマカシムの話はウツロの半生から神殿の暗部に移った。
この先展開されるであろう話しにはアーミラはどうしても身構えてしまう。それこそザルマカシム本人が言うように、間諜の言葉をどこまで信ずるべきか推し量る必要があるからだ。……だが、地下水脈を歩き、語られた全てを聞き終えた頃にはこの疑念も消え失せていた。
「……権威を維持するために親族内で代を重ねた結果血は濃くなり、形態異常の子が産まれるようになりました。
翼人の象徴である羽の奇形や無頭児。その他に形態異常を持つ子が産まれ、産声も満足に上げられないまま間引かれ、奥之院の闇に葬られたのです……」
『禍人の由来』と『翼人の秘密』。
血の掛け合わせによる顕性潜性の法則と、混血間引きの歴史、そして禍人の由来の一切が語られ、翼人の誕生の秘密をアーミラは知る。
まるでじっとりと粘ついた血液を浴びたように、頭から背筋にかけて悍ましい温もりがアーミラを包む。乳白色の地下水脈を歩く脚に、間引かれた嬰児たちの霊が取り付くような錯覚に鳥肌が立つのを感じた。
膨大な年月をかけて積み重ねられたラヴェル一族の悪事……これがもし本当ならば、使命を背負い戦ってきた継承者は、どれだけの無実の人間を……。
二人は隧道を抜け、人の手によって掘られた横穴へと辿り着く。奥へ進めば湿った壁面は次第に渇き冷えた石積へと変わっていった。
「ここが隠れ家に繋がる道だ」
ザルマカシムの声はアーミラの耳をすり抜けていく。目の前の光景と記憶の風景とが重なって、アーミラは静かに立ち尽くす。
――ここは、この場所は、マナに抱かれて逃げ出した道だ……。
強烈な既視感を伴い眼前に迫る地下通路の光景、この先に待つのは小さな室内であるはず。ザルマカシムの横を通り抜け、先を歩いて仕切りを跨ぐ。
通路と室内を隔てる扉はなく、壁や天井が一回り広くなった空間がアーミラを受け入れる。アーミラが思い出せる中で一番最初の記憶……その場所についに辿り着いた。
成長して背も伸びた分、室内の印象は思い出よりもこぢんまりと寂れていたが、面影はたしかに残っている。幼い頃は窓枠の光を外からのものだと思っていたが、今こうして改めると窓枠にあるのは灯石であった。壁面を埋める棚には見覚えのない薬品の類いが納められているが、こちらは間諜の私物だろう。
記憶では私とマナを見送り、この場所に留まった者がいた……もうその人はいないのだろうか……。
「ここで誰かと待ち合わせをしていたのでは?」アーミラは我に返り、ザルマカシムに問う。この場所で落ち合うはずの禍人種はどこにいるのか。
「先に着いてる筈だが、姿が見えないな――」
と、言い終わるかどうかの刹那に地鳴りが迫り、室内を揺らした。棚の薬品ががたがたと揺れ、いくつかの瓶が床に転がる。悠長に拾い上げる暇はない。
土埃の舞う地下でアーミラとザルマカシムは目配せに頷き合い、室内のもう一つの通路へ走った。上へと繋がる石段が真っ直ぐに伸びて、途中で行き止まりに見える壁は折り返してさらに上へと続く階段の踊り場であった。駆け上がる道中にも地上からの激しい衝撃の余波が肌に伝わってきていた。
「出遅れたな」ザルマカシムは唇を噛み、一段飛ばしで駆け上がる。アーミラも出口へ走る。
仕掛けの錠を解いて隠し扉を開く。その向こうには夜天を焦がし燃え盛る動乱が広がっていた。炎上している光景が神殿の景色と結びつかないが、間違いなくここはマハルドヮグの頂きである。本殿も、三女神の巨像も、見るも無残に破壊されて見る影もない。
聞いていた話ではウツロが神殿に乗り込む算段であるが……。
「なに……あれ……」アーミラは思わず呟く。
見上げた先、神殿の領内を蹂躙し暴れ狂う巨大なトガがいた。……いや、トガではない。
――災禍の龍……!?
その体躯は龍を思わせたが、目の前の化け物は前線で対峙した龍とは似て非なるものである。アーミラは扉の陰に隠れて気配を消し、そっと化け物を観察する。化け物はまだこちらに気付いていないため、背を向けて暴れていた。二足の鉤爪の生えた脚と尾羽、艶のある白い羽毛が炎に赤く照らされている。
前線で対峙した災禍の龍はもっと救いようのない絶望を体現したような、人間の形をした破壊の権化のような姿であった。それに比べれば目の前の化け物は夜の闇を支配する猛禽――梟に似ていた。一見して咎と見紛ったのはその生物的な外観のせいだろう。何より龍と異なるのは左右に広げた翼で、綺麗に整った羽毛が荒れ果てた神殿の中では不釣り合いなまでに美しく輝き、いっそ白々しい偽物のように映った。
「蚩尤が出たな」
ザルマカシムの言葉を聞き、アーミラは唇を引き結んで敵の姿を焼き付ける。それは首をぐるりと回し、面がこちらを向いた。
アーミラに気付いたわけではなく、蚩尤の周りを駆け回り戦っている者を目で追いかけている様子だった。しかし偶然目があったように錯覚したアーミラは化け物の面をまじまじと見てしまったがあまり、絶句した。
蚩尤の貌は鳥とは似ても似つかぬ人を模した仮面が三枚張り付いていた。まず額から頬にかけての面が目鼻を覆い、仮面から伸びた大ぶりな鼻が嘴の代わりに前方に突き出して垂れ下がっている。頬から下は左右にそれぞれ横顔を模る仮面が配され下顎を構成していた。
寄せ集められた三枚の仮面からなる梟の貌。どことなく三女神の石像を彷彿とさせる冒涜的な面の頭上には冠が飾られ、尊大な振る舞いで下を駆け回る者を睥睨しながら追い立てていた。これまた羽毛に覆われている胸から伸びるのは石のような質感の六本の複腕で、筋肉の起伏に乏しく線の細い腕の表皮には鱗のように細かな羽が生えている。
対して、追われる側の人影は誰か……アーミラは駆け回る者の姿を目で追いかけるが捉えられない。凄まじい素早さで瓦礫の山となった神殿領内を駆け巡り、六本の腕を相手に縦横無尽に掻い潜り戦っていた。一見してウツロではなさそうである。
――ガントール……いや違う。それならオロル? あれは誰だろう……。
アーミラの疑問に答えるように、ザルマカシムは言った。
「相手はセリナか……」
「セリナ……さん。確か、妹さんでしたよね」
道中に聞かされたウツロの兄妹……その妹の名前と一致している。
ザルマカシムが頷いたのを見て、改めて駆け回るセリナの姿を目で追いかけた。この世界に迷い込んだ異世界からの人間――今は龍体術と呼ばれる術式により翼膜を備えた翼と長い尾を持つ異形の女である。背格好はおそらく同じかやや低いくらいだろうか、手足はそれぞれ肘膝までを鱗が覆っていて、蜥蜴のような鉤爪が生えていた。後頭部には砕けた光輪が飾られているが、本来は綺麗な円で繋がっていたはずだ。あの梟の化け物に砕かれたとみえる。
「あぁ。戦力が心許ないな……ウツロ達はどこにいるんだ」
神殿に向けて奇襲を決行したのであれば、少なくともセリナとウツロが揃ってこの場にいたはず……となるとセリナが戦っている蚩尤の正体も自明の理――天帝の変貌した姿である。
「っ……! あそこを見ろ!」ザルマカシムは何かを見つけて指をさした。
アーミラは示された方に注視する。六本ある複腕の一つ、胸元に引き寄せている三番目の左手が何かを握りしめているのに気付いた。それがウツロであると一目ではわからなかった。
「ウツロさん……!?」アーミラは口元を抑えて青褪める。
鎧のあらゆる箇所が消失しており、握られたウツロに残る体は胴の板金と襟口、背中側の一部、そして右腕のみである。腰から下と左腕、そして頭はごっそりとなくなってしまっていた。生きているのかすら怪しかった。
「加勢するしかない! アーミラ様、戦えますか!?」ザルマカシムは言いながらも既に細剣を鞘から引き抜いている。
アーミラの心は決まっていた。迷うことなど一つとして無かった。
❖
神殿に奇襲をかけたウツロとセリナが如何にして形成不利に追い詰められたのか……時は数刻前に遡る。
ムーンケイの上層に移動した一行は、風前の灯のような西陽を眺める。千切雲がマハルドヮグの山陵に絡み細くたなびいて、まるで夜へ吸い込まれているかのようだった。暑さを失った晩夏の夜風が高原にそよぎ、セリナの胸をざわつかせた。
満を持して神殿へと臨むため、カムロとウツロが夕飯の用意に走った。カムロは上層の大通りを回り、避難せずにいた街商から腹の足しになるものを買い集める。
一方でウツロは、飯の話題になったときには山の深くへ潜って狩りへ出た。
二人が食糧を集めている間、焚き火を起こす者と山菜を集める者に仕事を分担し、枯れ枝に火を起こして待つこととなった。それぞれ準備を済ませて腰を落ち着かせた頃にウツロが耳長の兎を一匹調達して戻る。
捕らえた兎は腹部から左後脚を槍に裂かれているがまだ生きており、それをスークレイが引き取って調理番に立った。まだ帰ってこないカムロを待つ間に兎の首を切り、逆さ吊りに血抜きを行った。小柄な体から溢れ出る多量の血液を自前の小鍋に集めると、懐に忍ばせていた乾飯と水も加えた。米が柔らかくなるまで煮込む血粥というものを拵えたようだ。
「鍋なんて持ってたんだ」セリナは言う。
「これさえあれば最低限の飲み水が沸かせますもの」
調理の様子を見ていたセリナはこの世界でそれなりに酷い飯を口にした経験があるため、この獣人種の拵える血粥もまともな飯として見ていた。しかし、賢人種のオロルには料理とも呼べない下手物で、煮えはじめた小鍋の蓋を開けたとき香りたった湯気が鼻に入ると獣臭と血の生臭さに驚き顔の中央に皺が寄った。食の好みが違いすぎる。凝縮した血生臭さに食欲も失せてしまう……滋養にはよいかもしれんが、わしは遠慮しよう。
「欲を言えば胡椒と塩だけでもあれば味が整うのですが」
スークレイのぼやきに、丁度戻ってきたカムロが「それでしたら」と応える。
「薬膳ですが、代用できますかね」差し出した硝子瓶の中身は不揃いな粉末が入っていた。「枸杞や陳皮、あとは果実の乾物が混ざっています」
スークレイは栓を開けて香りを確かめ、「体に良いなら」と少量をふりかける。察するに姉のためを考えた一品だろう。オロルは内心胸を撫で下ろした。
残った兎の肉は皮を剥いで脚と胴でぶつ切りにした後、鍋の回りで石焼きにした。その他カムロが買い集めた出来合いの握り飯と温い薬缶の汁、串焼きの川魚が人数分あった。思っていたよりも露店は開いているようだった。
「酒はないのか」オロルはがっかりした顔をするが、カムロには通じない。
「当たり前です。手もないのにどうやって飲むつもりだったんですか」
「そこに口がないウツロが居る」と、皆まで言わず、返すウツロも匙を手にして律儀にも隣に座ったので束の間の笑いを誘った。
「ムーンケイの様子はどうだったんだ?」ガントールはカムロに訊ねる。
「朝に避難していた人たちの何割かは戻ってきているようでした。聞けばナルトリポカでアーミラ様を追いかける捕物騒ぎがあったそうです」
その話にウツロが反応する。
「山の方へ逃げたらしく、もしかしたら人払いされたムーンケイに逃げ込んだのではないかと考えた人達が夜を待たず国に戻り、飯の用意もないと見た街商は儲かると見て店を開いたようですね」
「なるほど……逞しいな」
夕飯調達が望外に豪華になったことの理由に納得した一方、ウツロはどこかそわそわとしている。アーミラが近くにいる事実に気が逸っていた。
「探しに行こうなんて思うなよ」オロルは先んじてウツロに釘を刺す。「人手は足りんが、寄り道する余裕もないのじゃからな」
人手という言葉を耳にして、セリナはふと思い出したように腰元の雑嚢に指を差し入れてまさぐる。二つの切り落とされた手首を引っ張り出して焚き火の光に照らして検めた。もともと変質したオロルの手首ではあるが、知らぬ間に肉も骨も硬質化して薄紫の結晶となり、腐敗を免れていた。
「飯時に見せるものでもないけど……、これってどうなってるかわかる?」
「……なんですか……? それは」
セリナはそれをカムロに手渡すと、同じように焚き火に透かして見せた。人の手首とわかってもカムロは取り乱さずに眉間を寄せて渋面で眺める。まるで鉱石と見紛うほどに変質しているが、少なくともセリナにとっては無用の長物で、戦闘では邪魔だった。
「わしの手か……?」オロルも興味深そうに身を乗り出して眺めるが、カムロが差し出すと首を振って受け取らなかった。
「オロル様の手ならオロル様が持つべきでは」
「いらん」オロルは再び首を振る。「相性というやつでな。朽ち果ててなおわしにとっては呪物なのじゃ」
呪物と聞いてカムロは放り投げたくなったがそうもいかない。セリナに返そうと差し出したが、セリナは頑として受け取らない。
「お主が持っておれ。この先役立つかもしれん」
押し付けられる形で、あまり嬉しくない頂き物をカムロは不承不承受け取った。
❖
焚き火を囲ってそれぞれが飯を分け合い、米の一粒、汁の一滴まで残さず食べ終わると、さてと立ち上がり神殿を見上げる。
狙いは翼人のみ。立ちはだかる脅威も所詮は神族種。これまでの強敵と比べれば烏合の衆である。……だがきっと、これが最後の戦いとなるだろう。
ムーンケイから神殿へ続く道を堂々と進み、いつか出征に旅立った冠木の前へと辿り着く。固く閉じられた門扉の屋根に飛び乗れば、夜警に歩哨していた神族種がぎょっとした表情でこちらを見つけ、敵襲を知らせる閃光を空に打ち上げた。
外廓の灯石が警戒の光を放ち、神殿領内を真昼のごとく白々と照らし出した。
駆けつける近衛兵を前に、カムロが声を張り上げる。
「全隊止まれ!!」
隊長の号令に近衛兵はびたっと身体を静止させ、張り詰めた呼吸でウツロと背に隠した龍の娘を警戒する。僅かでも動けば仕留めてやるという気迫である。
緊張に息を呑む静寂。カムロが口を開こうとしたとき、玉砂利を踏んで歩く足音が響く。隊の人波が後方から左右に開き、頭を垂れて道を開ける。
「――ほう……連れ帰ってくるとは見事なり……」
拙い……カムロはその声を聞いてすぐに口を噤む。この状況は想定していなかった……。
ラヴェル・ゼレ・リーリウス。天帝が直々にこの場に姿を現すとは、誰が予想できただろうか。戸惑いつつもカムロは目を伏せ、手柄を持って帰ったのだと振舞う。
獣人種を上回る二振半の背丈がカムロのすぐそばまで迫り、首を垂らして旋毛を見下ろす。カムロは目を合わせることもできずに直立のままじっと耐えた。灯りに透ける白髪がカムロの周りを天蓋のように囲い、ゆったりと広げた翼が眼前を遮る。悪事を知っていても思わず魅了されてしまう、美しい純白の翼であった。
「……ご、ご報告、申し上げます。神族近衛隊長、カムロ。ただいまムーンケイより帰投……謀叛人、虚の鎧も……つ、連れて……戻っております……」
辿々しく言葉を紡ぎ、カムロは報告を終える。リーリウスは嗄れた声で「そうか」とだけ返事をした。首切りを免れたカムロは息を殺して耐え忍ぶ。
リーリウスは背を伸ばし、攻め時を見失って立ち尽くすウツロ達をゆっくりと眺める。この場には少なくとも龍体のセリナがいるが、それにも怯える様子はなく、意図が見えない。いっそ耄碌の痴呆なのではないかと思ってしまうほどに所作は悠然としていた。
翼人は知る限り戦闘に参加した記録はない。故に天帝の実力は未知数である。互いに重苦しい視線が交差し、剣呑とした沈黙が場を圧した。
先に口を開いたのはリーリウスである。
「リブラ・リナルディ・ガントール。お前は歩けるか?」
「は」――と、ガントールも虚を衝かれ、それから首を横に振った。スークレイに肩を貸して貰わなければ立っているのもままならなかった。
「カムロ。兵を散会させなさい」リーリウスは言う。
「……し、承知致しました。……全隊、散会!」
カムロは言われた通りに周りを取り囲む兵に指示を飛ばした。これは奇襲に臨むこちらにとっても都合がいいが、しかし奇妙な指示である。この距離で天帝を無防備にするなど常識ではない。
リーリウスは続けて命令した。
「チクタク・オロル・トゥールバッハ、リブラ・リナルディ・ガントールとリナルディ・スークレイ、そしてカムロ。君たちは奥之院へ進みなさい」
「なにそれ、従うわけ――」
セリナは思わず口に出して嘲笑しようとしたが、横を見ればスークレイもオロルも諾々と従って歩き始めていた。肩を預けているガントールさえ、奥之院へ連れ去られることになんの異も唱えない。
「どういうこと……詠唱なんてしてないのに……」
狼狽えるセリナの隣、ウツロはじっとリーリウスを睨み続ける。
一人一人を姓も略さず呼んでいる時点で呪的な行為であると感じ取っていた。リーリウスは式典のときも一貫して省くことをしていない。
おそらくこれが巫力……呪いよりも強い絶対的権力の正体だ。名前を把握している者にはあらゆる命令を下すことができるのだろう。ウツロもセリナも名を明かしていないことは幸いであった。
神殿領内に残る三人はじわりと臨戦体制へ移行してセリナは先手必勝と言わんばかりにしならせた尾を叩き込む。
音速を超えて空気の壁を砕く破砕音とともにリーリウスの羽が宙に舞った。翼で受けたように見えるが手応えはない。薄膜を隔てて直撃を避けていた。
「結界まで……!」セリナは驚く。
「なんの備えもないと思うかね」
リーリウスは腹の底から響く声で言い、詠唱へ続いた。
「弓の勇名を持つ者、アレン、バルロサ、矢を放て」
たたた。と三方の死角からセリナの体に矢が刺さり、右腕、背中、翼膜を貫いた。
「オーウェン、シクラ、続け」リーリウスは指揮者のように澱みなく名を呼ぶ。「ラーグ、ジェクトマ、コットロラド、続け。皆よく狙い、矢を放て」
すたた。たん。ばち。たたん。
風を切る気配すらなく、セリナを狙う矢は正確に肉を抉った。
厄介な援護射撃にはウツロを盾にして立ち回り、多少の傷は意に介さずに攻撃を重ねるセリナであるが、矢の一つが左目に刺さって思わず仰け反る。
すこん。と鏃が目蓋を貫いて眼球の水晶体を崩し、眼窩の骨を滑って内耳が千切れる。三半規管が狂わされて体勢を崩してしまった。
「ぐっ……! くそ!」
脚が止まった瞬間、リーリウスが好機に表情を鋭くした。弓兵の勇名共は狙い澄ました矢を放ち、容赦無くセリナの急所に突き刺さる。胸に三、眉間に一、首に二、腿に一……。
ふらついた脚を踏ん張り、セリナは力ずくに左目と額に刺さった矢を引き抜いた。
「いらいらさせる……!」
砕けた頭骨から滲み出た血混じりの脳液を親指で拭う。脳を傷つけたものの、既に塞がりつつあった。これにはリーリウスも目を見張る。
「その形で災禍の龍か」
「どの口が」セリナは挑発する。「災禍にもっと相応しい奴が目の前にいる」
「……放て」
再び射られた矢の雨を羽ばたきで吹き飛ばし、セリナは攻め手を加速させる。矢よりも疾く、誰にも捉えられない速度で連撃を重ねた。リーリウスも見切ることはできず、身を固めて防御を結界に任せた。
「もとの世界じゃ動かない身体のせいで散々迷惑かけた……」
セリナは目にも止まらぬ連撃に旋風を纏い、神殿に羽が散る。
「もう他人の足引っ張るのはごめんなんだよ……!」
拳に膝蹴り、身を翻して尾を振い、開いた間合いに素早く飛び込む。結界に阻まれ直撃こそしていないが、鋭い攻撃の応酬でリーリウスに衝撃を通す。袋叩きにされた結界が消耗し、翼が撓む。
「ぐっ! ……ガラハウっ、エルエラ、守れ……!」
「どこまでも他人頼りか糞天使!!」
リーリウスは翼で全身を包んで、結界の詠唱を強めるよう兵に指示する。
重ね合わせて閉じた翼に魔力壁の結界が重ねられ、セリナの繰り出す連撃の竜巻を受け止める。叩きつける一撃、鋭く切りつける風が結界にぶつかるたびに魔力の火花が飛び散った。
セリナに向けては弓矢だけでなく光弾も加わった集中放火が浴びせられたが、動けないリーリウスを壁にするように立ち回り、狙いを回避した。
連撃はやがて結界の修復を上回り、斬りつける竜巻が不可視の壁に白い罅を生じさせた。
「な――!」
「こじ開ける!!」
回し蹴りを繰り出した踵が結界を砕いて翼をこじ開け、中からリーリウスの慄く顔が覗く。間髪入れずに連撃の尾が下顎を叩いた。
顔面を吹き飛ばすような小気味よい手応えが伝わり、血と汗の飛沫が弾ける。老体の脳は強かに揺れただろう。
「ぐ、ぬうぅ……っ!」
リーリウスはたたらを踏んで倒れそうになる体をなんとか踏ん張り、セリナを睨む。鼻からは静かに血が垂れて、白い口髭が赤く染まる。
「……許さんぞ……蛇め……!」
❖
混濁した意識の中、奥之院へ進むカムロは微睡みから目覚めるように目の光を取り戻す。
脚は勝手に歩行を繰り返し暗い廊下を進んでいるが、集中すればこの催眠状態を抜け出せる気がした。だがその前に、首を回して状況を確かめる。状況は前後不覚に陥ることもなく思い出せた。……私は天帝の言葉に従い、巫力に操られたのだ。
ウツロ達を連れて来たことで首切りは免れているが、名を呼ばれてからは身体を支配されていた。スークレイと継承者の二人も含め、奥之院へ向かうように命じられていたはず。ならば何故正気を取り戻せたのか……。
カムロは歩くたびに横腹を小突く感触があるのに気付き、脚を止める。
白衣の懐を探って取り出したそれは、ごろりとした二つの塊、変質したオロルの手首だった。
硬質化して結晶となったこれがカムロの意識を根気強く呼び戻したのである。
――紫水晶……そうか。
カムロはその変質した鉱石を理解し、得心に至る。
魔鉱石にはそれぞれ固有の特徴があり、紫水晶は明晰の石として知られている。こうして意識を取り戻せたのも何の因果か、偶然だとしても運命が味方しているような気さえしてくるというものだ。
「ここに来て運が向いてきましたね……」
断ち切られたはずの手が繋いだ勝機。果たして三女継承オロルはこうなる未来を見通していたのかどうかはわからない。カムロは先を行く仲間を追いかけて回廊の先、奥之院へ向かった。
❖
奥之院へ向かうには神殿領内の中央に位置する本殿に入り、外縁の通路を進んだ至聖所の横道に進む必要がある。
通常、入室が叶うのは選ばれた者のみで、ラヴェル一族以外では近衛隊の隊長、副隊長が出入りを許可されている。とはいえカムロが奥之院へ脚を踏み入れるのは数えるほどしかなく、どちらかといえばここでの業務は副隊長に任せていた。
段差の急な一本の階段がマハルドヮグ山の地下へカムロ達を誘う。真っ暗な通路には等間隔に灯りが燈され、階段の足場は明暗を交互に繰り返す。まるで照らされて浮かび上がる足場は細く心許ない柱で、暗闇は全て奈落へと繋がる崖のように錯覚してくる。
気圧変化にカムロの偏頭痛がじくじくと痛み出したころ、奥之院へ続く階段は平らな床に辿り着いた。
艶のない石灰質の黒い壁が囲む廊下を抜け、鉄格子の扉を開く。まるで地下牢のようなこの場所にカムロは改めて嫌な気持ちを思い出す。例え頭が痛まずとも、副隊長に仕事を押し付けた理由がわかった気がした…… ここはどこか気味が悪い。
鈍く照り返す寒々とした石窟の広間は、水を張ったように床だけは磨かれており、上下鏡写しに一人の男が佇んでいるのが見えた。
「おや……」
男はこちらに気付き、長い横髪の縺れを弄くり回す指を止める。すっと引き伸ばすように髪を梳かして指を離すと、毛先は使い古した筆のように跳ねた。
カムロはこの男を知らない。
「ザルマカシムではありませんね……名前を伺っても……?」
そう訊ねたのは男の方である。
顔を知らぬのはお互い様だと言わんばかりに男は借問した。副隊長とは知り合いである様子から奥之院の出入りを許されたものであると推察した。
「近衛隊隊長のカムロです」
「おお、貴女がカムロ様ですか、お話はザルマカシムさんから予々聞いておりますよ」隊長の肩書きを聞いて男は深く頷きを繰り返し、顔と名前が一致したと言いたげに大仰な反応をする。
「そちらはなんとお呼びすれば」カムロも訊ね返す。
「これは失礼、申し遅れました。私は奥之院天帝侍医のマーロゥ・メイディと申します」
「侍医、マーロゥ・マイディ……」カムロは名前を呟く。姓を持つということは勇名……由来は薬師か。
「して、そちらの方は長女継承者と三女継承者では御座いませんか?」
思考に沈くカムロの意識に割り込むように、マーロゥは一歩近付いて手で示す。
「一見する限りでも酷い傷だ。重傷です。えぇ、重傷極まりない」
指摘するとおり、オロルもガントールも五体満足ではない。特にガントールの義足は無理が祟って出血を繰り返し、化膿していた。
「間違いないです。……マーロゥ殿、この傷の手当を任せても宜しいでしょうか」
「それはもちろん……貴女はどこへ?」
踵を返し階段に向かうカムロの背に問いかける。
「私は……恩義に報いなければなりません」
❖
苦悶を噛み締め堪えるように血の滴る口の端を下げ、リーリウスはセリナを睨む。世に天帝と畏れられる、身の丈二振を超える存在を相手に躊躇わず戦うセリナの姿には、内心ウツロさえも気圧されていた。
崇め奉られる民草の信仰の象徴たるラヴェル一族が血を流したことなど、この二百年を越える人生で初めて見る光景である。
「忌々しい……、これだから禍人は好かぬのだ……」
リーリウスは体勢を立て直し、痛みを振り払うように首を振って鼻に詰まった血を口から吐き出した。
対するセリナは、あっけらかんと言い放つ。
「あんただって禍人じゃない」
神殿に児玉した揺るぎない事実。
ウツロに顔があれば目を丸くしていただろう。そして魔法が溶けたように腑に落ちた。
わかっていても、こうして言葉にされると強烈な違和感があった。それこそ己の意識が巫力で操られているのではないかと疑ってしまうほどに、威厳のある天使のような姿のリーリウスが禍人種であることを呑み込めない。
そんなウツロと同じように、リーリウスさえも唖然とした表情をしていた。自身にかけていた魅了が剥がれ落ちて、正体を見破られたことに動揺しているように見えた。
「その通りです」
言葉を継いだのはカムロだった。
「カムロ……!?」セリナは本殿の露台を見上げる。「操られたはずじゃ……」
「龍の娘の言っていることは正しい」
カムロは視線で応え、部下達の前に姿を晒して、詠唱する。
それは信念の一撃であった。
「占星――術重。
八蠍座――」
指し示すカムロの指先はリーリウスに向けられ、次いで詠唱が重ねられる。
「――九射手座」
呪力はカムロの全身から霧のように染み出し、詠唱に呼応して射手の中に集結する。握られた呪力の弓が右手に収まると同時に、左手は鉱石化したオロルの手首を握り、鏃に仕込んだ。
射手座の弓に構えるは蠍座の毒……紫水晶に込めた明晰の祈りである。
「全隊、目を醒せ」
放たれた矢は風を切りリーリウスに迫るかのように見えた。身を庇う翼へ突き刺さる刹那、矢は四方へ枝分かれしてリーリウスをすり抜ける。
神殿の床に鏃を跳弾させた矢は壁に向かい反射と屈折を繰り返し、砕けた鉱石が領内に散らばる。一見ばら撒かれただけに見えた欠片達は円形の回廊にそって規則的な芒星を描き、リーリウスを捕らえた包囲陣を展開した。
「……なんだ……?」守りに入り後手に回ったリーリウスは対応に遅れ、包囲陣を見上げる。「解呪だ! コルネア! オシュトル!!」
攻撃を警戒するリーリウスは近衛兵に呪力の解除を指示するが、兵達は誰も応えない。
カムロの放った矢の狙いは天帝ではなかった。
鉱石の塵は拡散し、神殿を半球状の霧が包む。目に見えぬほどに細かく砕かれた欠片が近衛兵の肌に僅かに突き立てられ、明晰を込めた毒は気付けの薬となって、彼らに付与された巫力を奪い去る。
「……身体が動く……!」
「俺たち……一体……」
「操られていたのか……?」
操られていた近衛兵は意識を取り戻して互いを見つめる。そして神殿の中央には陣に怯える醜態を晒す天帝。すぐそばに龍の女と、虚の鎧が立っていた。奇襲に現れたはずの二人は何故か隊長と視線を通わせて紐帯の絆を結んでいる様子。混乱の中で少しずつ、この争いの勢力図が見え始める。
微睡みの中でも、近衛兵達は天帝の巫力で操られていたことを漠然と覚えていた。そして龍の娘の言葉もまだ耳に残って消えていない。天帝が禍人だって……、まさか……。
「近衛隊よ聴け!」露台に身を乗り出してカムロは叫ぶ。「……驚くべきことですが、これからお伝えすることをしかと受け止めなさい。この龍の娘が言ったこと、我々が信じ奉仕してきたラヴェル一族が禍人であるということは、嘘ではありません」
外縁からどよめきの波がうねる。懐疑の衆目に曝されたリーリウスは背を丸め、翼の陰でカムロを睨め付ける。その邪気を払うようにセリナはカムロの前に立って月輪の威光で視線を跳ね返す。手には亜空の刀を握っている。
カムロは部下達への説得を試みた。守るべき部下を救うために。
「謀叛人であると断ぜられた先代の忘形見……ウツロの名で知られるこの鎧は前線に真実を見つけ、争いの根絶を実現するべく神殿に敵対しました。私はその経緯を知り、五代継承者のガントール様、オロル様と共に叛旗を翻すこととなりました。
私と、そしてこの場に集うあなた方、我々近衛隊はその名の通り神族に仕える誉れ高き兵士である。だがしかし、考えて欲しい。思い出して欲しいのです。その肩書きや誉れよりも先に大義があることを。
この地位まで昇り詰めたのは、ひとえにあなた方が世界を……人々を守りたいと決意したからでしょう。
神族は巫力という巧妙な術で人心を掌握し、不当に権益を浴している事実を私は知った。この事実は仕えるべき神族との信頼関係を根底から覆し決して無視できない、許されざる行いである。そのため私は、今より近衛隊長の座を離れ、リーリウスに対し禍人勢力と共に反抗しようと思う」
近衛兵の戸惑いは相当なもので、篤い信仰を寄せている者はあまりに不届きな隊長の姿を前に顔面蒼白にして思考が追い付かずにいた。呑み込むには大きすぎる衝撃だった。
生まれる前から存在していた、決して揺るがぬはずの善悪の道標が突然にひっくり返ったのだから、その驚きようは無理もない話である。
「終わりの見えない戦争に、家族、友人、恋人を失った者だって大勢いることでしょう。長く続いてきた苦しみの時代に、皆が祈り、願い続けた終戦がもうあと一歩のところにある……!
それは敵を一人残らず根絶するという勝利ではない。他者によって齎される偽りの旭日に目を眩ませてはいけないのです。この世界に幾重にも帳をかけた巨悪を暴き、我々は自らの足で、明日を迎えに行かなければなりません。
……この夜明けを迎えることができなかった同士達が何故、その命を散らさねばならなかったのか……よく考えてほしい。この場にいる貴方達にはその機会がある。
今ここで背を向けてマハルドヮグを降る者を私は責めません。むしろ全員逃げ出して欲しい。大切な人を連れて、一目散に……。
重ねてお伝えしますが、これから先は地位や名誉のための戦いではありません。人々を騙し、多くの命を犠牲にしたラヴェルに対して責任を問う戦いです。そして禍人の謗りを受け迫害された種族のために挑む戦いなのです。
武器を下ろし神殿から降りるか。我々と共に一族に立ち向かうか。いずれにしろ二つに一つ――」
締めくくりにカムロは告げる。
神人種と呼ばれマハルドヮグの頂に住む者達、彼らの中から選別された上澄みである近衛隊の、さらに上澄みである隊長としての最後の言葉。
「――最後の命令を伝えます。全員、この夜を生き残りなさい」
俸禄も地位も捨てた彼女が矜持を持って貫いた一本の筋は、神殿に残された部下にとっては闇夜を照らす光であった。天帝という光を失い明日も見えぬ急転直下の一大事の夜に、心許ない蝋燭の灯りだとしても彼女は歩むべき道標を示してみせた。その姿はウツロが学ぶべきものであり、薫陶に心を震わせた。彼女だって明日もわからぬ立場であるのに、上に立つものとして見事な立ち居振る舞いであった。
対して、神の遣いであり天帝を僭称する翼人はその地位を頽落させ、近衛兵から見放された。
「よくも……」
恨み言を吐くリーリウスの低く掠れた声は不気味な弔鐘のような響きを持って領内の士気を凍えさせる。
「……よくもやってくれたな……」
リーリウスの怒りを受け、神殿は俄かに揺れる。石材でできた堅牢な建造物が地鳴りにひび割れ、耐久の閾値を超えるとあっという間に崩壊を始めた。崩れていく自身の城の中心で、リーリウスは居直り、不敵な笑みを浮かべた。
「我ら一族に対して責任を問うだと……? 笑わせる」
まだ何か企てている――そう考えたウツロは斧槍を向けてリーリウスに迫るが、頭上から迫る影に気付いて回避に翻る。巨大な影が鎧の体を掠めて玉砂利が跳ね、舞い上がる砂埃の向こうで三女神の巨像が瓦解していた。反応が遅れていれば潰されるところだった。
「炉を開け」
煙る景色の向こうではリーリウスの声と赤々とした熱波。風に舞上げられた砂埃が晴れると、崩れ落ちた巨像の首が口を開けていた。
石像の口内には灼熱の溶岩がとろりと待ち受けている。
――何が起きた……?
「ウツロ……!」
「お兄ちゃん!」
切羽詰まった呼び声に視線を向ける。先程二人が立っていた露台は砲撃に吹き飛んだように無残に破壊されていた。その傍ら、脇腹ごと翼を抉られて血を流しているセリナが倒れている。
――セリナ!
腕の出血も構わずセリナは上空を指差す。助けて欲しいのは私じゃない……!
指し示す先で巨像の腕が夜空に突き上げられていた。偶然によって屹立しているのか、まさか、ただの瓦礫であればこうはならない。石像が敵意を持ってこちらに襲い掛かっていると知って、ウツロは戦慄した。
――まさか、これも巫力なのか……!?
倒壊した三女神の巨像は意志の宿らない表情を硬く保ったままリーリウスの傀儡となり暴れ始め、露台に向けて振り下ろされた巨大な拳の一撃がセリナに痛手を負わせた。手の中に掴まれたカムロの見開かれた瞳と首の無いウツロの視線が交差する。脳裏には彼女の言葉が聞こえていた。
『見捨ててもらっても構いません。ですがもし気が向くのであればどうか私を守ってください』
「カムロを助けて!」セリナの叫び。
当然だ。ウツロの体は駆け出していた。
縮地で石像の腕に飛びつき、斧槍の一撃を振り下ろす。耳障りな甲高い音が鳴り白く硬い石材が僅かに欠けたものの、これでは歯が立たない。食い込んだ斧槍を楔として、ウツロはセリナの方へと手を伸ばす。
――刀を貸せ!
首のない兄の声が聞こえているかのように、セリナは得物を投げ渡す。
柄を握り、ウツロは巨像の腕に向けて横一閃に刀を振るう。亜空の刀『抜刀・輝夜』の剣閃が煌めき、石像の腕が艶やかな断面を滑って落ちる。
握力を維持した指の檻を切り刻んでカムロを助け出し、腕に抱えると痛みに顔を歪めた。彼女の肋骨は圧迫されたせいで折れているようだった。
――無事か?
ウツロは声もなく見つめ、カムロは気を失わぬように根性で痛みを堪える。何か訴えたそうに口を開閉しているが、陸に上げられた魚のように声はでない。目蓋を千切らんばかりに目を見開いて、かろうじて言葉を吐き出す。
「うぅし、ろ……!」
ウツロは咄嗟にカムロと刀を放り投げた。次の瞬間には巨大な質量に轢き飛ばされたと思えば胴鎧を鷲掴みにされる。
ぐわっと振り回される遠心力に抗えぬまま、口を開けて待つ灼熱の炉へと叩きつけるように沈められた。
どぷん。と、粘度の高い液面に脚が沈み、底に付かぬまま潜っていく。くぐもった音の後に外の喧騒は遮断され、足先から全身に感じたことのない激痛と消失を感じて長く忘れていた死の恐怖を思い出した。視界は燃えるような赤から眩しい白に焼かれ、助けを求めて右手を伸ばす。
死に様を見て愉しむように、石像の腕がウツロを掴んだ。
「どうだ。手も足も溶けた気分は」
荘厳とも陰鬱とも形容できないリーリウスの声……。ウツロは炉から引き上げられ、外気によって急速に冷やされる板金が軋む。
見るも無残な姿だった。
下肢は腰から先を溶解して失い、残されたのは胴と右腕のみ……巨像に摘まれる最低限の鎧しか残されていなかった。
石像の首は開いた口に青生生魂を溜めたまま炉としての役目を終え、使い捨てられて転がる。事切れたように横を向いた石像の顔は炉の中の溶湯を涎のように垂らし、池をつくった灼熱の湯が石畳に広がって火を吹いた。
「我を裁こうとしていたようだが、全く愚かな……」
向かい合うリーリウスは人の姿を逸脱し始め、肥大化した翼が彼の肉体を持ち上げて羽毛の中に呑み込んでしまう。傀儡として操っていた三女神の巨像も羽の内側に取り込むと、恐ろしい梟の姿に変貌した。
「この世に蔓延る禍人種を一人残らず駆逐する。民に平和を齎す。この神聖な大義に、誰が罪を犯しえようか」
貌は三女神と老人の混ぜ合わされた醜い仮面で覆われ、リーリウスは炎上する神殿の中心で翼を広げる。
「我こそが法であり、故に審判を下すのは貴様ではない」
そして栄光を疑わない蚩尤は嗤う。
呵呵大笑が燃え盛るマハルドヮグの頂きを圧して、避難に駆け回る近衛隊達の背筋を粟立たせた。手当のため肩に担がれ本殿へと運ばれるカムロは、朦朧とした意識で天帝の本性を見つめ、落胆した。
「……本当のところ、信じたくはありませんでしたが、やはりウツロが正しかった……ならばあれが蚩尤……」
退避の殿に付き添ったセリナは頷く。
「今からでも遅くないよ。逃げたい奴は早く山を降りな」セリナは兵達に忠告する。「私は兄貴を助けに行くから、多分もっと危険になる……」
手頃な枝でも振り回すような気軽さで磨き抜かれた片刃の得物を肩に乗せ、セリナは兵士を一瞥した。
千切れたはずの翼と脇腹の傷は痕跡もなく綺麗に再生し、その治癒能力は大祈祷に匹敵すると兵達は推し量る。龍の娘の言う通り、加勢するのは無謀に思えた。この先は並の兵士では命が幾つあっても足りない死線となるだろう。
後に続かない兵士をちらと見て、セリナは来た道を引き返し駆け出した。臆病だと揶揄するような笑みはなかった。
むしろ利口だとすら感じていた。異世界に迷い込んでからこっち、禍人側に立ってこの悲惨な戦闘を垣間見てきた彼女は、自暴自棄と勇敢さを履き違えて死にゆく同胞をうんざりするほど看取っていた。力量を踏まえ戦闘に参加しないだけ利口で、恵まれているのだ。
誰かを頼る素振りもなく龍の娘は戦線に躍り出た。祈りも加護も期待していない彼女が天帝との戦闘を繰り広げる最中、残された近衛隊達は動乱に揺れる現状に打ちひしがれる。
ほんの数刻前まで、我々は神殿側に付いていたはず……それがどうしてこんなことに……。
毀たれた本殿の入り口では回廊の壁が崩れ、孤軍奮闘する龍の娘の姿が見える。いや、正確には見えていない。目で追いかけられない速度で瓦礫の隙間を駆け回り撹乱し、戦っている様子を窺い知るだけだ。
「何もかも、桁が違う……。」
「くそ……っ! 俺たちにできることはないのか……!」
「継承者に頼るしかないなんて、情けねぇ……」
加勢できない歯痒さに兵士は拳を震わせて唇を噛む。
思えばいつだって、他力に頼っていた。その最たる例を天帝として、権力の中央で安穏と過ごし、危機に瀕すれば前線側の兵士に頼り、継承者が現れれば両手を上げて出征を見送った。
帝が近衛を、近衛が勇名を、勇名が農民を……上に立つ者が下に頼ることで生きている。……いつから俺たちは肩書きに甘えてしまったんだ。
「祈りましょう……」憔悴した様子のカムロは言う。その瞳に弱々しさはない。「弱音を吐く暇があるなら、心を捧げなさい……」
「ですが、我々の神は――」
「神に祈るのではない。あの娘に、ウツロに、祈祷を捧げるのです。
例え必要ないとしても、私達が無力だとしても、祈りはきっと注がれる。なにかの助けになるかもしれません」
カムロに促され、傍観するしかなかった兵士達は一人、二人と指を組んで胸に寄せ、切実に祈りを捧げた。
これは天帝の他力本願とは似て非なるものである。
運命を他人任せにせず、心を束ねて一連托生とする想いは、戦場に立つ者を奮い立たせ背中を支える。空の器だったセリナの胸に、密かに、確かに、暖かなものが注がれていた。それは彼女だけではない――
「待たせたな! ニャルミドゥよ!!」
溌剌とした吶喊の雄叫びとともに蚩尤の側頭部に光弾の雨が降り注ぐ。強烈な爆圧に梟の巨体は仰け反り、何事かと首を向けた。
「……ブーツクトゥス……!」
セリナは予期せぬ仲間の加勢に目を輝かせる。
「遅れちまったが、ウツロを助け出すにはうってつけの仲間を連れてきた」
少年のような手柄顔で笑む大男にセリナは少し面食らい、しかし心強いと眉を吊り上げた。
圧倒的な物量で蚩尤を退がらせた新たな仲間は、自らが射出した魔弾の煙をたなびかせて揚々と手印を構える。
「加勢します!」
肩にかかる藍鉄色の髪を揺らし、アーミラが最後の戦場に辿り着いた。
■014――審判 後編
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
マハルドヮグ山頂に座す神殿は普段の厳かな沈黙を破り、夜にあって山肌が望めるほどに明るく照らされていた。夜通しで踊り狂う喧騒に打ち上げられた光弾が爆ぜ、すこし遅れて爆音が麓に届く。見上げる者にはまるで祝祭のように見えたが、外郭に隠された神殿領内はあらゆる破壊を尽くした最終戦争の最中であった。
怒りに猛る蚩尤に向けて練り上げられた魔力の光矢が連続射出され壁という壁が崩れ去った。その威力は凄まじく、玉砂利の敷かれた領内は断続的な爆圧が吹き荒れて着弾点は風穴が開けられた。砲撃の射手はアーミラであり、蚩尤は白く眩い巨体を俊敏に操って射線を回避すると反撃に鉤爪の趾を突き出す。それにはセリナが刀で受けた。二人は示し合わせることなく前衛と後衛の連携を取り阿吽の呼吸であった。返す刀で素早く刃を奔らせる。
切られてなるものかと鉤爪を引っ込める。蚩尤は空中で身を翻し、不気味な仮面が眼前に迫った。セリナは眉を跳ね上げて続けざまに刀を振るうが、萎びた茄子のような老人の鼻を模した梟の嘴は鋒を避けて、惚けるように左右に小首を傾げる。さながら本物の梟のような仕草である。
閃く太刀筋は空を切る。挑発に乗り、セリナはさらに一歩、深追いしてしまった。瓦礫に隠れた石像の手刀が襲いかかる。これはウツロが切り落とした腕だった。
「躱して!」アーミラが叫ぶ。
「んにゃろう……!」セリナは刀ではなく尾を振るって一合を交わし、押し負ける形で弾き飛ばされる。それを今度は蚩尤が追いかけた。
巨像を取り込んだ六本の腕。そこから繰り出される凶手が厄介であった。そのうえ、石の腕はもとより無機物であるため切り落としても痛まないどころか再生してしまうらしく、カムロを救い出すために切り刻んだ腕も継ぎ接ぎの姿で本体とくっつき、襲いかかってくる。リーリウスは巨像の腕を武器に盾にと都合よく取り回していた。
着地の足元を狙う蚩尤の腕が執拗に追いかけ牽制するので、堪らずセリナは翼を広げて空に逃げた。
陣形は崩され、前衛の仕事はできない。
「もう――!」
セリナを追い払った蚩尤は次にアーミラに狙いを定める。
六本の腕を器用に扱い、荒れた神殿を這うように駆け出していた。距離を縮める不気味な面と真正面から対したアーミラは足が竦んだか回避をしていなかった。
「間合いを崩された!」
「任せろ!」
焦るセリナに応えたのはザルマカシム――いやブーツクトゥスで、彼は前衛が離れた機を狙っていた。上空に呼び集めていた暗雲から雷を生じさせ、蚩尤めがけて叩き込む。
かっと光が爆ぜ、雷鳴と地響きが轟いた。稲妻を浴びた蚩尤は強烈な光量の中で黒く焼きつき、なんとも形容できぬ呻き声が仮面の奥から絞り出される。
その口を塞ぐ詰め物を押し込むようにアーミラは魔槍を放つ。蚩尤を前に足が竦んでいたのではない。正確無比に、狙うべき位置へぴたりとつけた攻撃は蚩尤の痛点に刺さり、攻勢を止めて巨体を震わせる。降り注ぐ攻撃を浴びた蚩尤の体は針の筵となって立ち尽くし、溜め込んだ雷が漏れ出るようにして石畳に放出された。手応えは致命の一撃だろう。
アーミラの放つ魔術はどれも圧倒的で、行使するまでに時間を要するブーツクトゥスの雷撃と同等かそれ以上の破壊力を持っている。しかも、それほどの魔術を隙もなく繰り出すのだ。連携を崩され焦っていたセリナも、前衛の穴を埋めるために技を振るったブーツクトゥスも、彼女の戦いぶりを見て「一人で足りるのではないか」と思ったほどだ。末恐ろしいのは、これで継承者の能力を失っているということである。
「ぬぅぅぅ――!!」
蚩尤は翼を広げて風を巻き起こし、体に刺さった槍を振り落とすと円形闘技場に着地する。巣へ逃げ込んだように見えるがそんな呑気なものではない。六本の腕が触手のように不規則に蠢き、次に左右三対の腕がそれぞれに手印を結び始めた。
左右中央の手を合わせ外縛印。左下の手と右上の手で降魔印……うち左手の中にはウツロの残骸が握られている。そして左上の手と右下の手は掌を前に向けて伸ばした指先で天と地を示すと、左右の組み合わせを変えてまた別の手印が結ばれる。結合と分離動作を繰り返し手印を結ぶ。
鼓笛も拍子もなく、蚩尤の胸の中で手遊びに踊る娘の腕、腕、腕。
細くしなやかな手指が組み合わさるたびに石同士が擦れてぶつかる硬く乾いた音が響き、その間に揉まれるウツロの鎧が無抵抗に捻られる。
すぐにでも助け出したいセリナの肩を掴み、手印を見てブーツクトゥスは悟る。
「今は避難が先だ、そうとう剣呑だぜ――」
その言葉通り、蚩尤の纏う気配が変わった。
「私の後ろに来て下さい!」アーミラの指示が被さる。セリナはブーツクトゥスを掴み、指示に従った。
「何が来る!? あんたは何する気!?」
アーミラの背についたセリナは問う。手印を解読できないため、ほとんど直感に従って動いていた。結果的にそれで正しかった。
「闘技場の円を利用して陣の短縮をしてる」これは興奮したブーツクトゥスの言葉。「複雑な魔呪術を行使する場合は言葉と術の両方を用いる、あれはさらに上だ」
アーミラは蚩尤を睨んだまま言葉を継いだ。
「祭祀の構えですね。場を掌握するつもりなのでしょう……印の連なりで詠唱を構成、それを三体同時に……」
「独自の言語圧縮ってことか……なぜ口を使わないんだ? 式の構成も滅茶苦茶だ」
「禁忌を犯す覚悟なのでしょう。あえて唱えないのはこの祭祀が外典だからでしょうか」
「だから、何が来るのさ!?」
小難しい言葉で通じ合う二人に、我慢できずセリナが割り込む。
しかし、アーミラもブーツクトゥスも見つめ返して首を振る。
「あれは外典祭祀です。禁忌の中でも悪意を持って行う術式……」
「必殺技って訳でしょ。やばいのは見ればわかるよ!」
気が短いセリナは八つ当たりに声を荒げる。知りたいのはどんな攻撃が来て、どう防げばいいか、この二つだ。だがそれがわかれば苦労しない。
「禁忌ってのは術式の結果が安定しない、不確実で行使者にも害が及ぶ危険がある。だから禁忌なんだ」ブーツクトゥスは子供に教えるように言う。「つまり、何が起きるかわからねぇ」
「なら今のうちに邪魔しちゃえば――」
「っ、もう来ます……!」
律動に合わせ結合と分離を繰り返していた六本の腕は術式構築の締めくくりに一つの印を表した。それは天へ開く蓮の花を形作り、六枚の花弁を表わす手のひらは次に切り払う動作に移り素早く下へ滑った。次の刹那、どこからか嬰児の泣き声が聴こえたような気がして、セリナとアーミラは互いに目配せする。空耳か……?
神殿を囲うように空からは巨大な白い円柱――御柱――が降りてきた。その柱には節があり、区切られたそれぞれに生物の頭部を模した彫刻が施されていた。石でできた巨大な墓標柱……セリナにはそう見えた。
真っ黒い夜の雲間から一つ、二つ……計六つの柱がゆっくりと降下し、神殿の周りに浮遊する。そして赤子の声がはっきりと耳に届く。
「どうなってるんだよ」理解を超えた事象に当惑し、セリナはアーミラの袖を引いた。
なぜ柱から呱呱の声が聴こえるのか、誰でもいいから現状を説明して欲しかった。
呆然と空を見上げる二人とは違い、ブーツクトゥスは赤子の声と翼人の繋がりを結びつけて震え上がった。奥之院最奥で闇に葬られた子間引きの因習が形を持って現れたのだと理解する。
生々しい生命の主張とは不釣り合いな六本の御柱の無機質さに畏怖の念さえ覚えた。
「おぎゃあ」と声を張り上げる一本の柱が一層苛烈に叫び始める。生命を脅かされているとでも言いたげな悲痛な声が夜空に響き、御柱の巨大な質量がゆっくりと抽送に揺れる。まるで柱の内側に閉じ込められた赤子を虐げているように思えた。
「おんぎゃあ」「おんぎゃあ」「おんぎゃあ」
叫び声と抽送運動はやがて六つの御柱全てに行われた。マハルドヮグ山脈を取り囲む冒涜的な悪夢に、アーミラ達はどうすることもできず困惑していた。禁忌を発動した行使者である蚩尤でさえも立ち尽くしている。……或いは世界の終末を前に為す術などないということかもしれない。
「おんぎゃあああ」
「おんぎゃああああああ」
「おんぎゃあああああああああ」
「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ」
「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ」
「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ」
絶叫。
この世の全てが音の波に震え、神殿の石材ががらがらと崩れる。
耳を塞いでも骨を揺らす赤子の叫びに曝されて、セリナはいよいよ脳が破裂しそうな気分だった。隣でアーミラが何か叫んでいるが、口の動きははっきり見えていても声が掻き消されて聞こえない。
あまりにも煩い爆音に、むしろ何も聞こえなくなったように思えたセリナは、ふらっと目を上転させ倒れかかる。ぎりぎりのところでアーミラの詠唱によって結界が展開され、三人は膝をついて呼吸を整える。ブーツクトゥスの開いたまま閉じられなくなった口から涎が垂れ、顳顬から頬に血混じりの汗が伝った。耳から出血しているようだ。
「おい大丈夫かよ」ブーツクトゥスはセリナに言う。そして自分の耳からも血が流れていることに気付き、ふらつきながらも立ち上がる。「困ったな……攻撃はこれからだってのに」
アーミラの張った結界は三人が入れるだけの狭い半球状のもので、外の絶叫は幕一枚向こうにくぐもって尚も響いている。がらがらと不快な赤子の声は徐々に上擦り、高音域の音波へと変化して――限界点に達し、破裂音一つ残して鳴り止んだ。むしろそれが恐ろしかった。
肩をびくつかせた三人は柱を見つめる。
抽送運動が終わり、柱は杯を傾けるように横倒しに傾く。
「……来ます」アーミラは確信を持って呟く。
外典祭祀は始まった……いや、正確にはもう終わりを迎えようとしている。この不穏な風は、儀式の終わりを告げている風だ。
「えへ、えへ、えへ、……ぅあぁぁぁ――」
肺を引き攣らせしゃくりあげる赤子の歔欷が次第に消えていく。それは聞く者を悲しみへ引き摺り込むような痛ましい名残を残して、後には沈黙が場を圧した。
奥之院最奥に流れた無辜の霊素は、まだ物心も無いために概念すら獲得していない負の感情のみを抱いて怨念となった。黒く濡れた瞳は一度も空を見ることなくくり抜かれ、微笑みかける母の寵愛を知ることもないままに押し殺された。
その濃密で純粋な情動は世界を呪う澱となり、この禁忌の術式によって顕現するはずだった。だがしかし、怨念はまたも翼人による幽閉によって御柱の中に封じられ、発散する術も機会も奪われたままに儀式のための贄としてなぶり殺された。
一度ならず二度も尊厳を踏み躙られたのである。
これが外典祭祀、霊素の二度殺し。
御柱の内部で受肉した赤子は万力に潰されるが如く肉体を損壊し怨嗟の念は二乗する。無に帰すはずの哀れな霊素は徹底的に穢され、濾し取られた呪咀のみが柱の内部に満たされる。それがマハルドヮグに、神殿に注がれようとしている。
ごぽっ……と、溢れ出る赤黒い液体――柱を見つめていたアーミラ達は煮え立ち湯気を吐くその液体が呪われた血だと直感で理解した。だがあまりにも膨大な血の洪水を前に避けようもなく、呑み込まれぬように結界を死守するしかない。
「踏ん張れよ……!」ブーツクトゥスはアーミラの結界の外にもう一枚防護結界を重ねた。「ここを越えなきゃ何もかも無駄になる!」
柱から注がれ、狂った飛沫を撒き散らす呪血は行き場を求め怨嗟に煮えたぎる。炎上していた神殿を鎮火して赤く塗りつぶし、触れるもの全てを立ち所に侵食しながら呪いを拡散させてゆく。
奔流は津波となって瓦礫を巻き込みながらブーツクトゥスの結界に迫る。それはもはや帳を引きずって死を届ける可視化された闇そのものであった。
結界の壁にそって液面が波打ち、半球状の空間は丸ごと呑み込まれた。視界は光を遮られ、防護の術式と怨嗟の念が接触する境界面では激しく泡が発生しちりちりと焼きつく魔力の火花が微かに状況を照らした。食い破られた結界の穴から赤黒い液体が染み出した。
「……だめだ……!!」ブーツクトゥスは自身の展開した結界を放棄して視界を照らす。「食い破られる……!」
漏出する血液はそのままアーミラの結界と接触する。抵抗するためにアーミラは結界を拡大させて押し返すが、酸に溶かされるように術式はみるみるうちに消耗していく。悪足掻きに一回り小さい結界を重ねて補強したが時間稼ぎが精々、打開策とはいえない。
「あの血はあらゆる術も破壊するようですね……」
「術だけじゃない。呑まれれば俺たちも終いだ」
このままでは――アーミラは破滅を予感して奥歯を噛み締める。その隣、セリナは万事休すと呪血に覆われた景色を仰ぎ見て、思わず兄の名を呟いた。ウツロはこの赤い洪水の向こう、蚩尤に握られたまま水面より高いところへと逃げ仰せているだろう……捨てられていなければの話だが。
それでも、アーミラは一つ閃いた。
「ウツロさんの手脚はどこにありますか!?」
切羽詰まった状況での突然の問いかけにブーツクトゥスとセリナは何か策が思い浮かんだのだと悟る。
ウツロの手脚は、アーミラとブーツクトゥスが合流した時点で既に消失していた。奇襲をかけたとなれば神殿までの道のりでは自分の脚で歩き、腕に得物を携えて戦ったはず。この洪水のどこかに転がっているはずである。
「溶岩に溶かされたよ……」セリナは応える。
「溶岩……?」とアーミラは疑問符を浮かべるが、ブーツクトゥスが炉のことだろうと言い添える。「それはどの方角かわかりますか?」
セリナはおおよその場所を指差した。結界の向こうは全て赤黒い濁流に覆われているものの、己の立ち位置と蚩尤のいた方角から少なからずの見当はついている。
二枚の結界が呪血によって消滅しかけていることに気付いたアーミラはさらに複雑に組み上げた三枚目の結界を展開した。術を複雑にするほど呪血が食い破るまでの時間が稼げるからだ。……が、不意に襲った痛みに驚き、声が漏れた。
握っていた槍が乾いた音を立てて転がり、何事かと手を見れば指の関節がそれぞれ好き勝手にひん曲がって砕けていた。心配して様子を窺うブーツクトゥスも目を丸くする。
「……侵食だ……!」
呪血の怨嗟が結界を経由して行使者に影響を及ぼしたのだろう。
肌には小さな歯形が蛇目紋様の痣となって残り、奇妙さの訳を理解すると怖気に頬の産毛が逆立った――赤子の歯形……だが乳歯ではなく大人の歯が小さな弧を描いて窮屈に並んで噛みついている。
「ザルマカシムさん、護りを頼めますか」
「そりゃやるが、何する気だ……?」
先頭を譲って引き下がるアーミラの背中は諦めていない。
理不尽なまでにあらゆるものを蝕む呪血の坩堝の底で、何ができるというのか。
「……青生生魂を熾します……」
セリナの示した方角に向けてアーミラは両手を構えた。指の感覚は失われ、爪も剥がれてだらりと力無く血を滴らせている。
猶予はない。ブーツクトゥスとセリナは最後の賭けとしてその命をアーミラに託した。
――熱を……。
アーミラは既に魔力を練り始めていた。扱う術式はスペルアベルで用いたものと同様……あのときは冷却のために用いたが今回はその逆、物に宿る『精』や『素』を激しく振動させることで、冷え固まった溶岩を再び溶解させるつもりだった。
祈りが届くのであれば、きっとウツロは応えてくれる――アーミラは切なる願いを術式に託した。
しかし、三人が立っている場所から炉までの距離には呪血に満たされた領域が広がっている。アーミラの放つ魔術は結界同様に飛沫を立てて漸減し、炙られた呪血が沸騰しながらも術を蚕食して対消滅が引き起こされている。
これでは炉に届くかどうか、届いたとて鉄を溶かすほどの熱を維持できない。
「それなら……!」セリナは半壊している月輪を前方に呼び出し呪血に向けた。「私が道を開ける……!!」
セリナが込めた魔力が月輪を発光させ、呪血の一点は丸くくり抜かれた。月輪の内側に展開した亜空の門に多量の血液が押し寄せ、際限なく吸い込まれていく……。
「このまま全部呑めるか!?」ブーツクトゥスは叫ぶ。
「……っ、無理っぽい! アーミラ早く!!」
亜空の門の縁にそって流れ込む呪血の渦の中心、透けて見える向こう側には巨像の首が転がっている。力無く開いた唇からは黒々とした溶岩が涎のように垂れて張り付いている。
「あいつの口の中に兄貴の体があるはず!」とセリナ。
「もう保たねぇぞ!!」ブーツクトゥスは既に多重結界に消耗して腕が使い物になっていない。青筋を浮かべた眼力だけで結界を維持し呪血の圧をなんとか堪えていた。
アーミラは返事をする間も惜しいと、最大出力で巨像の首を温める。放出している魔力の波動は射線上の空気に熱波の揺らぎを生じさせ、門の中心を通過して巨像を熱する。石の頬が柔らかく赤熱して輝きはじめる。
「お願い……!」アーミラは縋るように固く目を閉じて祈る。炉を熱したところで、青生生魂が応えてくれるかは賭けでしかない。
ごふっ。と、セリナは不意に咳き亜空の門が閉じられる。押し寄せた呪血の波が射線を塞いで、もはや助かる道はなかった。膝をついて立ち上がれないセリナは、呑み込み続けた大量の呪血に内側から侵食され、怨念の慟哭に精神を引っ張られていた。限界だ。
「……ここまでかよ……」ブーツクトゥスは結界を展開するだけの余力も尽きて血反吐を吐く。体には幾つも歯形が残され、呪血による侵食が襟元まで迫っていた。
二人が倒れ、結界は一気に領域を狭める。
術式はあっという間に食い破られて三人は呪血の洪水に飲まれてしまった――かに思えた。
「諦めるな!」
望みを繋いだのは近衛兵達の声だった。
「まだやれるぞ!!」
「俺たちが助ける!!!」
波の届かぬ高台まで逃げ仰せた彼らは、アーミラ達三人の捜索と救助を諦めなかった。この血の洪水の中でも必ず生き延びていると信じ、そして祈りを繋いだのである。
「……お前ら……」ブーツクトゥスは呆気に取られて部下達を見上げる。
「やってくださいよ副隊長!」威勢のいい声で発破をかける部下の声。「これでも俺たちは勇名ですぜ!」
「……副隊長はやめろ、ザルマでいい」
血に固められた髭が不敵な笑みにひび割れる。例え間諜に手を染めた裏切り者だとしても、全員が近衛兵の肩書きを捨て、謀叛に翻ってしまえば関係ない。共に戦うと腹を括った仲間の声に背中を支えられるようにして、ブーツクトゥスは立ち上がった。勇名の戦士――ザルマカシム――として背を反らし胸を張る。そこに抂げられぬ矜持がある。
「まだ生きておるか……」
闘技場の外縁、呪血から避難していた蚩尤はもはや失望したとでも言いたげな声音で言う。あるいは本当に失望していたかもしれない。外典祭祀の理不尽な暴力はセリナとブーツクトゥス、そしてアーミラの体に確実な死を与えるはずだったのだ。誤算だったのはアーミラの結界が並の術式よりもうんと強固であったこと、そして近衛隊が揃って旗幟を翻したことにある。三女神の顔を寄せ集めた不気味な仮面が俯き影を落とすと、蚩尤は小さく首を振る。
「せっかく名を与えてやったというのに、我の兵もここに来て邪魔ばかり……お前達はもう要らぬ。消えろ」
ばかん。と蚩尤の仮面が割れた。単に顎を開いたのではなく、固く閉じあわされていた三女神の面に亀裂が生じる。
奥にあるはずの蚩尤本来の素顔は暗がりに秘められ、代わりに闇の奥から殺意の閃光が迸った。
放たれた熱線は呪血の水面を鋭く叩きながら高台に集まる勇名達に迫る。その威力は触れたものを容易く溶断し、熱線の走ったあとは少し遅れて衝撃と爆発が生じて飛沫の柱が立つ。下は呪血の海、狭い高台に立つ勇名達は逃げ場もないと恐怖に体を強張らせた。――白衣を切り裂く寸前、灼熱の炉から何かが飛び出して熱線を遮る盾となった。
なにが起きたのか理解できたのは、アーミラとセリナの二人だけである。
「……お兄ちゃん……」
「ウツロさん……!」
熱線を吐き続ける蚩尤は、なおも攻撃を弾く近衛共に苛立ち、出力をさらに高めた。細く絞られた光の筋が真っ直ぐに突き抜け……得体の知れない壁に弾かれて七色の飛沫となって拡散する。なぜ殺せぬ……、なにが起きている……。
照射の限界に達し、蚩尤は仮面を閉じて体を震わせると体内に籠った熱を深く吐き出し、近衛共のいる方をじっと見つめた。
熱線によって巻き上がった呪血の飛沫が驟雨となって降り注ぎ、赤黒い雨垂れが焼石に蒸発して煙が立ちこめる。熱風による気流に視界が晴れると勇名を守った盾の全貌が明らかになった。
黒曜石に似た艶のある平滑な円盤……まだ熱いそれは丸い輪郭から物憂げな袖を振るようにゆらゆらと煙を吐き、呪血の驟雨を受け止めては蒸発させていた。
その姿は夜の闇よりもさらに黒く、さながら日蝕を思わせた。磨き抜かれた面が蚩尤の姿を反射している。
意思があるのかさえわからない円盤は、煙を吐く鏡だった。
世界を見霽かす全知全能の瞳が静かに見つめているようにも思えて、己が重ねた悪事を見透かされることを畏れた蚩尤は僅かながらに後退る。そして未練がましく握りしめていた鎧の残骸が温度を上げていることに気付いた。胸の羽毛が焦げることを厭うて、蚩尤は鎧を摘んで確かめる。伝わった熱が巨像の指まで柔らかく溶かし始めていた。
「なにを――!」驚く蚩尤の声。
ウツロの胴体を熱していたのは、アーミラの術式だった。
アーミラは自身がなにをするべきか手に取るようにわかっていた。理の当然、物の道理を悟り、明けぬ夜などないと確信している瞳がウツロの鎧と通じ合っている。
「ウツロさん……!」
灼熱の溶湯となったウツロの鎧は蚩尤の手をすり抜けて呪血の海へ落下する。焼けた黒鉄に触れた血液は瞬間的に蒸発して激しく煙を吐き出し、同時にウツロの熱を奪っていく。水位を下げていく呪血の海は青生生魂との対消滅ではなく、明らかにウツロに呑み込まれていた。
そこに煙を吐く鏡も転がり込んで一つに溶け合うと、ウツロの鎧が形を取り戻す。
およそ人ひとり分の体積に神殿を満たしていた呪血の全てを取り込み、鏡は消失した手脚となって鎧の体を構成する。失って久しい面鎧も揃い、炉に落としてしまった斧槍も復元された。
呪血に染まる神殿で対峙するウツロと蚩尤。
両者は無言のまま見つめ合い、どちらともなく距離を詰め、一合を交わした。
蚩尤の吐き出す熱線を躱したウツロはその眼前に縮地で迫り、女神の三つの顔を押し固めた醜悪な仮面の中心に斧槍を突き立てた。僅かに開いた隙間に両手を差し入れると、鎧の内側に広がる虚無から嬰児の怨念を顕現し蚩尤へ解き放つ。
「むぐ、おおおぉぉぉ……!!」
黒い霧と化した怨念が、抉じ開けられた仮面の内側へと流れ込む。怨嗟は仮面を蝕み、奥に隠した素顔を焼き付きしながら目や耳、鼻、もちろん口と、穴という穴から潜っていった。外典祭祀により自らが生み出した呪血は周り巡って蚩尤の腹に収まり、その恐慌に陥った蚩尤は埋めていた首を長く伸ばして振り回し、ウツロを振り解いた。
引き剥がされた後もしばらくは呪血の怨嗟がウツロ全身から噴き出し、一筋の流れとなって蚩尤の口と繋がっていた。
「おおお、おぉ、おぉぉぉ……!」
結局、蚩尤は全てを飲み下した。拒絶反応に腹は痙攣し、羽根に覆われた喉元が絶えず嘔吐きを繰り返し膨らむが、出てくるのは血混じりな唾液ばかり。
ウツロは石畳に着地すると、アーミラを見つめた。面鎧の真っ暗な二つの穴……アーミラはこの昏い目が好きだった。
――すまなかった。
声が直接アーミラの頭に届く。
―― 『行動で示す』と言いながら、俺は裏切ってしまった。
アーミラは首を振る。
「大切な妹を助けるためだったと知りました。それに、ウツロさんは裏切ってません」
この世界を歪め、裏から手引きする巨魁を明らかにした。ウツロの謀叛は神殿こそ揺るがすものだったが、継承者達を裏切ったわけではない。むしろその逆……。
「あなたのおかげで多くの方達の無念が晴らされたでしょう……わたしもその一人です」
ありがとう。と、アーミラは真摯な瞳でウツロを見つめ、次に蚩尤と対した。
――ガントールとオロルの心像灯火を蚩尤は取り込んでいる。切り離して決着をつけるぞ。
「わかりました……!」
返事を聞き、ウツロは先陣を切って駆け出した。
蚩尤は収まらぬ吐き気の勢いに任せて熱線を放つ。仮面の縁からは呪血の怨嗟が漏出し、飛沫に触れた白い羽毛が萎れるように腐っていく。
ウツロは迫る熱線を全く意に介さず距離を詰めて斧槍を構える。
鎧は蚩尤の吐き出す呪いを弾き、待ち受ける巨像の六本腕をアーミラの援護射撃が貫いた。
「なんだと……!?」
――審判の時だ。
魔槍がそれぞれの掌を貫通し蚩尤の懐が曝け出されると、そこに飛びかかっていたウツロの斧槍が振り下ろされる。斬撃というより裁きの鉄槌と呼ぶに相応しい重たい一撃であった。蚩尤の腹は深くまで切り開かれ、内側から呪血の反撃が棘の山となって突き出した。取り込まれていた巨像の腕が崩れて、ガントールとオロルの心像灯火を回収する。
「よもや、よもやか……」
白い翼は見る影もなく鮮血に濡れて、リーリウスは蚩尤の体を維持できなくなった。羽毛は萎びて抜け落ち、禿げた皮膚が月明かりに照らされる。
糸を引いて腐り落ちた仮面の奥から焼き爛れて腫れた唇が荒く呼吸を繰り返す。息をするのも苦しいという風だった。鉤爪が石畳を滑り、穴だらけの胴体から倒れ込む。
ウツロは回収した二人分の灯をブーツクトゥスに預けた。彼は勇名の仲間達によって治癒が施され、随分と回復していた。
この世の真実を掴み、翼人の野望を打ち砕いたブーツクトゥスとウツロの二人は互いに頷き合って無事を喜んだ。ついに成し遂げたのだ。
ブーツクトゥスの隣り、へばって座り込んでいるセリナには手を伸ばし、起き上がらせる。
「死んだかと思った」
セリナの軽口にウツロの面鎧はかすかに微笑んでいるように見えた。
気を緩ませている三人とは離れて、アーミラは蚩尤の顔を見下ろしている。
「…… 稟性の才能か……」
醜い口元が言葉を発する。水脹れの唇がぶよぶよと蠢くのを見て、アーミラの瞼がぴくりと痙攣した。『稟性』――その言葉が全ての答えだった。
「語るに落ちましたね」アーミラは杖代わりの槍と小杖代わりの切り出しの両方を構え、魔槍と光矢を生成する。
「……そうか……!」
二人の会話にそれとなく注意を払っていたブーツクトゥスは真相を理解する。突然声を張り上げたことに満身創痍のセリナは言問顔で説明を待っていた。ウツロも同様にブーツクトゥスを見つめる。
「アーミラは奥之院で生まれ、逃げ出した神族の姫だったんだよ」
興奮気味なブーツクトゥスの言葉だけでは事情を把握することはできない……が、セリナは眉を吊り上げてアーミラを見つめた。
稟性とは――生まれながらにそなえている性質のことである。つまりリーリウスはアーミラの出生を知っている……それどころか深く関わりを持っている。
「何も知らないというのは、本当に恐ろしいです……」アーミラは呟く。
私は神殿で生まれ、そしてマナと共に逃げ出した。
記憶を失い、継承者となって舞い戻ってきた私の顔を見たリーリウスはさぞかし驚いたでしょう。もし私が記憶を取り戻せば神殿の暗部が世に明るみになる。しかしこの場で私を殺せば、式典に支障が出る。
「『きっとこの娘は前線で死んでくれる』……その可能性に賭けて当代継承者を前線へ送り出してのですね」
「……そうだ」
リーリウスの返答に、アーミラが抱いていた疑念は確信に変わる。
冷たく光る碧眼が荒涼とした神殿領内を眺める。
真実を勝ち取るまで、本当に長かった。
「貴方のような人間を父であるとは認めません」
「お前が最奥から逃げ出さなければ……ここは今も盤石であったろうな……」
「あり得ない」アーミラは否定する。「あなたも、神殿も、ここで終わりです」
アーミラは天稟の才能を発揮し、構えた魔槍と光矢を蚩尤に向けて一斉射出した。
血なまぐさい巨体が羽を散らし、穿つ魔術によって重く濡れた翼が、神々しかった巨体が見る間に挽き肉に変わる。赤黒い爆炎の向こうで砲撃に弄ばれた人面の梟が喚きのたうち回っていた。
「あぁ! 口惜しい!! 口惜しいぞアルミリア!」
「その名は前線で捨てました。あなたが捨てさせたようなものですよ」
「あぁ! あああっ!! 後少しだった!!! アルミリア……、アルミリア……!」
砲撃が止んだ頃には蚩尤の頭上に飾られていた冠も砕け散り天帝の威光は完膚なきまでに消え失せていた。肉塊の山から這い出てきたのは、我が身への痛みと憐憫に身を悶えさせる老人である。
リーリウスは外典祭祀の呪血に魂を蝕まれ、アーミラによって肉体を叩きのめされて正気すら失っていた。これまでに浴してきた権益による甘い日々が、この男を惰弱な精神に育てたのだろう。
「いやだ……! なぜ私がこんな目に……やめろ……やめろぉっ!!」
退行障害だ。
敵前にも構わず駄々をこねる老人の姿を見下ろすアーミラは、憤怒と粛正の衝動がどろどろの溶岩となって胸の奥から噴き出すのを感じた。とどめを刺すのは容易いが――
「やめろ、そんな目で見るな……私を見るなぁ!!」
喚くリーリウスを前にアーミラは、ぎり、と奥歯を噛み締める。
私がこれまで受けてきた理不尽と比べればリーリウスへの仕打ちはまだまだ手緩い。翼人の我儘に振り回されて、どれだけの血が、命が零れ落ちただろうか……そう思えば意識の暗がりから修羅という蛇が鎌首を擡げるのを感じた。
殺してやりたい。
それほどまでに憎かった。
この怒りを代弁するかのように呪血は老人の体に痣を浮かび上がらせた。「こいつを殺せ」と語りかけている……アーミラにはそう思えた。この呪血は奥之院で流れた血だ。逃げ出すことの叶わなかった、同胞の血なのだ。
ウツロがアーミラの肩に手を乗せる。
「……『怒りに囚われてはいけない』……そう言いたいんですか……」
――……いや、わからない。こいつを殺して心が晴れるなら、俺は止めない。止める立場にない。
裁かれるべき人間だからな。と、ウツロは言う。
「ならこの手は何です」アーミラは肩に乗せられた手を見る。
――これは、俺の我儘だ。アーミラにはもう、力を使ってほしくない。だが……どうしてもというのなら、こいつで最後だ。存分にやってくれ。修羅を濯いでお終いにしよう。
ウツロはそう言って、アーミラの肩から手を離した。復讐を促すことも、止めることもせずに委ねたのだ。
アーミラは杖がわりの槍を握って白痴となったリーリウスを睨む。内に宿っていた殺意がこの体を突き動かすだろうと思っていた。だが、体は動いてくれなかった。
「……ずるいですよ」
アーミラは血に染まった石畳に槍を放って、切り出しも手放した。
「私の帰りを……待ってくれる人達がいます……」
リーリウスにとどめを刺そうとしたとき、脳裏に浮かんだのはアダンとシーナの温かな笑顔だった。胸を張って帰るには、恥じない生き方を選ばなければいけない。
そしてそれができると、ウツロは信じてくれたのだろう。
武器を捨てた際に生じた音にリーリウスは驚き、気を失った。
アーミラが手を汚さずとも、この老人は呪血に蝕まれて命を落とすこととなる。
全てに決着がついたのだと皆が思ったその時、ブーツクトゥスは漸くいるはずの者の不在に気付く。
❖
「おやおや……閉じ込められてしまいましたねぇ」
天帝侍医マーロゥは呑気にもそう言った。
場所は奥之院。地上階では最終戦争が繰り広げられていたそのとき、祈りながらに気を失ったカムロが部下達によってここまで担ぎ込まれていた。
階下から立ち昇る腐った水の臭いに顔を顰めながら、それでもこの先に待つ場所が現状最善の避難所になると信じて近衛隊の男達は一段一段確かめるように進み、通路へとたどり着く。
開かれたまま放置されている鉄格子を素通りして駆け抜け、足下に張られた水の飛沫に脚絆が濡れるのも構わず辿り着いた地下回廊には一人の男が待っていた。
訝しげに目を細めて警戒する近衛の男は、不意に背後から掛けてくる大勢の足音に振り向いた。怒涛の迫る呪力の気配……それよりも濃厚な殺意の意志が血の臭いと共に迫っている。
不意に鉄格子が大仰な音を立て、叩きつけるように閉じられた。
先ほど降りてきたばかりの階段からは滝のような濁流が渦を巻きながら流れ込み鉄格子に押し寄せて再び激しい音を立てた。こちらに迫っていた足音の正体はこの洪水である。
明るいところであれば一目で血だと分かっただろう黒い液体は攻撃性を隠しもせずに暴れ狂い、寄せては返す波が幾度となく鉄格子を揺さぶる。その度がたがたと衝撃に揺れたが、隙間だらけの格子であるはずなのに堅牢な壁に阻まれているかの如くこちらには一滴たりとも染み出すことはなかった。
黒い水は水位を上げて天井まで満たすと、波を生み出す隙間を失って勢いを落とす。
明らかに尋常ではない何かが神殿で起こっている……近衛達は地上で繰り広げられているであろう激戦を思い、恐ろしさに息を呑んだ。
そうして、地下回廊に立つ男は「閉じ込められた」と言ったのだった。
「お前はここで何をしている」近衛の男は問う。
「私は奥之院に仕えております。天帝侍医マーロゥ・メイディにございます」
近衛達は互いに顔を見やり、「知っているか?」と伺った。奥之院に出入りができるのは翼人と、近衛隊の隊長と副隊長に限られているはず。……であればこの男は怪しいが、物怖じせず堂々と振る舞う態度には威勢を挫かれてしまう。侍医という肩書きもまた、老齢なリーリウスには有り得る話だった。
「ところで、カムロ隊長はどうされたのですか?」
マーロゥと名乗る男はなんの警戒もせずに近衛隊の者達に歩み寄り、気を失っているカムロの顔を覗き込んだ。頬に添えた指先から治癒の術式を光らせると、目を閉じてぐったりとしていたカムロの意識が回復する。折れた肋骨の痛みに顔を顰めて呻いた。
「どうやら私の仕事のようですね」
「マーロゥ……」
カムロの口から男の名が呼ばれ、男達は警戒を解いた。隊長と知り合いであれば一安心、どうやら奥之院天帝侍医というのは間違いないようだ。……その裏付けができたと早合点したのである。
閉じられた鉄格子の向こう側は床から天井まで血の海に満たされて、波のない液面は磨かれた石壁のように沈黙している。初めからここに通路などなかったかのようだった。
近衛の一人が術式を調べようと近付いた。
「触れれば死にます」
マーロゥは簡単に言って咎める。指を伸ばして触れようとしていた男は慌てて腕を引っ込めた。
「この鉄格子は……あんたが守ってくれたのか?」
「いえ……ここの守護は特別ですよ。最奥に棲む翼人の子が同胞の血を遠ざけているのでしょう……」
なんとも含みのある物言いに近衛の者達は眉を顰める。翼人の子……? 同胞の血……?
「つまり、どういう――」
説明を求めた声が途切れ、一人の男が突然気を失って倒れる。
この場に集まった近衛達は仲間の異変に駆け寄る者や、警戒を厳しくする者もいた。反応はそれぞれだったが、最後は皆一様に床に倒れて転がった。
「オーウェン? ジェクトマ……? どうしました……?」まだ意識が朦朧としているカムロは部下の異変に対応が出来ない。「マーロゥ……、私の仲間が……」
「えぇ、倒れましたね」
「アレン、バルロサ……! 何が起きてる……!?」
カムロは焦点の合わない目に力を入れてなんとか部下達の顔を観察する。立ちあがろうとしたとき、背後からそっとマーロゥが引き寄せてカムロを仰向けに倒し、無感動な表情で見下ろした。
「無理はしないほうがいいですよ。吸って、吐いて、……そうです。呼吸を繰り返して――」マーロゥは落ち着かせるような優しい声で囁く。遠のく意識の中、続く言葉を聞いた。「――よく眠れるでしょう。あなたが作った香木ですよ」
❖
奥之院の暗がりに倒れる白衣の者達。
通路の影には先に運ばれていた長女継承ガントールとその妹スークレイ、三女継承オロルの姿もあった。全員が昏昏と深い眠りについている。
「さて……」
マーロゥは膝下で眠っているカムロの懐に手を差し入れて弄ると、目当てのものを掴んで取り出す。それはオロルの切り落とされた手首、紫水晶に変質した魔鉱石である。取り上げたそれを掴んだままカムロの頭を避けて立ち上がり、天井を見上げて耳を澄ました。
「上はもう決着ですか……」
神殿の戦闘が落ち着いてきていることを悟ると足早に通路の奥へ歩き始めた。道すがらガントールのそばに寄り、天秤剣の柄を握ってさらに奥へと進む。天帝侍医を騙るこの男こそ、禍人を束ねていた巨魁――ハラヴァンであった。
ハラヴァンは嗾けたウツロとセリナの奇襲には参加せず、ブーツクトゥスとの合流も反故にして、ひとり奥之院まで潜っていたのである。ハラヴァンは地下深い常闇の牢獄にも似た地下通路を迷いなく進み、最奥の扉の前に立つ。
「審判の日が来ましたよ」
扉に向かってそう告げると、分厚い鉄の扉に掛けられている錠を解いた。扉に隙間が開き、ハラヴァンは手で押し開ける。
通路と地続きの室内は変わり映えのない牢獄然とした殺風景な場所で、長く贅沢な暮らしをしてきた翼人の棲家とは思えない室内には、一人の翼人がいた。
やや幼い年頃の背丈をすっと伸ばして、その翼人は静かにハラヴァンに対している。外見は人間というよりも蚩尤に酷似しており、肌を埋め尽くす羽毛に全身を覆われて顔すらも表情が窺えない。背中から夥しく生える十二対の翼は繭のように肩を包んで、手入れのされていないまま伸び放題の羽がは床に引き摺られて茶色く染まっていた。細部に目を凝らせば凝らすほどに異形の化け物であるが、全体の佇まいはまるで純白の長衣を着飾った箱入り娘のようである。
「やぁ、セラエーナ」
ハラヴァンは旧知であるかの如く名を呼んだ。
「……きっとあなたは此処を訪れるだろうと思っていました。マーロゥさん」
セラエーナという名を持つこの翼人は禍人領から攻めてきたはずの男を前にしても慌てることなく、むしろ出迎えるような態度で最奥へと招き入れた。『殺するは蚩尤』と散々息巻いていたハラヴァンの方も敵意は形を潜め、肩を並べて室内に踏み入る。
二人は互いをよく知っていた。天帝侍医の肩書きでこの最奥にも幾度となく立ち入ったことがあったのだ、
「千里眼――を使うまでもないでしょうねぇ……これで最後となれば私の来訪を予測することは容易いでしょう」
公に姿を現すことのなかった天帝の子。その存在は翼人のみが知るところで、近衛隊長のカムロさえも把握していなかった。何故ならばセラエーナは、その躰に形態異常を引き起こしているからである。
長きにわたる翼人種同士のよる近親交配によって形態異常を引き起こし、百年前に問題を解消するために継承者の血を取り込んだものの依然として血は濃いままである。それ故にセラエーナは羽だらけの化け物として生まれ、神殿でも秘中の秘として隠されていた。
蒲柳の質である彼は発育にも遅滞があり、その外見は年齢よりも幼く見える。若さの対価であるかのように、この奥之院最奥では発熱ばかりしていた。
そんなセラエーナは空咳を丸めた手で受け止め収めると、今度はハラヴァンの来訪の目的を言い当てた。
「母を殺しに来たのでしょう」
「……それだけではありませんよ」
見透かしたようにセラエーナは事情を掬して続けた。
「いずれにしろ急がなくては行けません。父はもう猶予がありませんから」
ハラヴァンのやり遂げるべき本懐……野望と言い換えて差し支えないそれは、天帝リーリウスがその命尽き果てるより早く遂行する必要があった。セラエーナは父が生きていなければまったく意味がないことも言い当てたのだ。
「急ぎましょう。母君はどこですか?」
「ずっとそこに」セラエーナは翼の絡まった腕を伸ばして最奥の壁面を指し示す。言われるまでそこにいると気付かなかった。
灯石の光の届かない最奥の暗がりに母はいた。
過去に取り込んだ継承者の娘の血の中でもとりわけ魔人種の特徴を色濃く持つ混血の王妃ラヴェル・ゼレ・カルミナ。
彼女は目と耳を煇され、生まれてから死ぬまでをこの奥之院最奥で過ごしている。少し前までは彼女の他にも王妃はいた。それこそ獣人種の特徴を持つ混血と、賢人の混血、龍人の混血さえいた。
彼女たち王妃の役割は魔人種の血を持つ者として、翼人の子を産むことであった。
「話しかけたところで聴こえはしません」ハラヴァンは言い捨てる。しかしその表情は痛々しい笑みを浮かべ、微かに涙が滲んでいた。「いま解放してあげますよ」
ハラヴァンはカルミナの手を握ると、そこで初めてカルミナの方もこの部屋に訪れた来客に気付く。不意に握られた手に顔を向け、次いでハラヴァンの方へ顔を見上げた。痛ましい古傷を残す眼窩は真皮が覆っていた。誰に手を触れられているのか、わからないはずだった。
「……マーロゥ……?」
カルミナは名を呼ぶ。
玻璃の器に清水を注ぐような美しい声だった。
「マーロゥよね……、あぁ、……もうずっと、会えないのだと思っていました。それでも良いと……どこかで生きていてくれさえすれば良いのだと願っていましたよ。
マナはいますか? アルミリアは……?」
ハラヴァンは顎に皺を寄せて唇を噛み、耳が聴こえないカルミナの首に針を刺した。
「ここにはいませんが、すぐに会えますよ」
握った喞筒の押し子にかけた親指に力を込め、動脈に薬物を注ぎ込んだ。カルミナは小さく戸惑いの声を漏らすと、苦しむこともなく眠りに落ち、心音は緩やかに感覚を広げていく。
見届けていたセラエーナは何も言わずハラヴァンが顔を上げるまで黙っていた。最奥には洟をすする音だけが響く。
「……さぁ、……始めましょう」
奥之院最奥に器が一つと触媒が三つ。
これらは全てハラヴァンの手中にあった。
器とは、血塗られた歴史の暗部にて全ての血を色濃く取り込んだ翼人の末裔――ラヴェル・ゼレ・セラエーナのこと。そして三つの触媒は本来であれば手に入れることの叶わない三種の神器、及びそれに準ずる素材のこと。
前線ラーンマクでの災禍の龍討伐の折に砕けた次女継承者神器――天球儀の欠片をハラヴァンは密かに拾い集め、神殿への謀叛に挑む虚の鎧によって切り落とされた三女継承の変質した手首をカムロの懐から窃盗ねて、度重なる死線を潜り抜け奥之院に倒れた長女継承の神器、天秤もこの手にある。三女神の力を宿す素材が揃っているのだ。
ハラヴァンはこの場所で、真の目的を達成しようとしていた。
それは世を正道へ導かんとするザルマカシムやウツロとは別の目的である。
復讐。
それこそが彼の本懐であった。
ハラヴァンはこの戦争の終結や勝利に端から興味などなく、全くもってどうでも良かった。どちらの勢力が勝ったとしても最後にはこの世界から人類を消し去る……それがハラヴァンの思い描いた結末である。
あらゆる人類、文明、記録を消し去り虚無へ導く……彼を突き動かす熱量は深い絶望という炎だった。
❖
間引きを免れた翼人の一人として、ハラヴァン――否、マーロゥはここ奥之院最奥という地下牢で産まれた。
最奥で産まれる赤子は翼人の血を濃く引き継ぎ、ほとんどの確率で先天的な形態異常を持っていた。そういった赤子は間引きの対象となり容赦なく摘み取られることとなる。闇の中で満足に産声も上げることなく殺されていった兄弟姉妹は数えきれない。
マーロゥは形態異常を持たずに産まれた目溢しの生き残りであった。額には僅かに膨らみがあり、成長するにつれて禍人の頭角が生えるだろうことは明らかだが翼人の証である翼は持っていない。このような軽微な混血の兆候を持つ子供は将来、子を産み育てる種付けか、間引き選別といった一族の暗部を担う……それはこの因習を耐える側から維持する側に回るということ。
この世に生まれ落ちたときから彼の地獄は始まっていたのだ。
マーロゥはいつかここを抜け出すのだと心に誓い、朝も夜もない日々を過ごした。
共に苦痛を耐えていた姉がいた。
先天的な形態異常を持たない唯一の理解者だ。
姉の名はラヴェル・ゼレ・マナ。
彼女はマーロゥと同じく翼人種の特徴である翼こそ持っていないが、形態異常のない身体で生まれたために間引きを免れた。彼女もまた、額の瘤が角となって現れる頃――子が産める歳になれば母胎の役目を課せられる、危うい立場にあった。
最奥で数年を過ごし、二人の額に禍人種の頭角が生え揃ったあるとき、翼をもつ妹が産まれた。
ラヴェル・ゼレ・アルミリア……彼女こそ翼人の求めていた存在だった。
背には天使のような美しい純白の羽。
見る者を魅了する可愛らしい姿。
形態異常もなく、間違いなく次の神殿を統べる姫たり得る娘が誕生した。
こうなってしまえばマナも自分もまず奥之院の外に出ることは望めない。
間引かれるか、生きながらえたとしてもこの最奥で子を産むためだけに命を使い潰されるだろう。そんなのは御免だった。
マーロゥはマナと協力し、この奥之院から逃げ出すと決めた。
「……てっきりあなたは間引かれると思っていましたよ。セラエーナ」ハラヴァンは兄弟の再会だというのにそんなことを言う。「明らかな形態異常持ちですから」
セラエーナは翼に覆われた口元を少しだけ吊り上げる。
「兄達がいなくなって、こんな僕でも迂闊には殺せなかったのでしょう。父も歳でしたからね」
いよいよ禅譲も視野に入れなければならない段にあって年老いたリーリウスは唯一残った赤子を間引くことをやめた。セラエーナと名付けたその赤子は外見に明らかな形態異常を持っていたが、その奇形は全て翼人の証たる翼に由来している。性別も両性具有であったため、ある種の神聖を有しているとして最奥に隠した。最有力の候補であったアルミリアが行方知れずとなったためにラヴェル一族は擁立すべき子を妥協したのだ。
セラエーナは特異な外見のみならず、心を読む千里眼の能力を備えていた。これはリーリウスも知らない才覚である。
関わる者の心を読み取り、幼少の頃から人間がいかに穢らわしく悪なる存在であるかを知ったセラエーナは、神殿から逃げ出した姉兄を羨ましく思っていた。
奥之院から出ることも叶わないまま月日が過ぎ、禍人の間者となったハラヴァンと出会ったとき一目で全てを理解した。禍人に紛れて生きるこの者こそ最奥から逃げ遂せた兄マーロゥであると悟り、この世から人類を消し去ろうとする思想に共感した。
そこに世話係を請負う近衛隊副隊長のザルマカシムをそれとなくハラヴァンと引き合わせることで此度の戦役と混乱を操り、必要な材料を集めたのである。
「……準備が整いました。覚悟はできていますか?」
ハラヴァンは最奥の床に陣を描き終えて腰を伸ばした。薄く水を張っている床には繰り返し傷をつけて刻んだ術式が白く跡を残している。その陣の中心には三つ横並びになった円環の図があり、それぞれは太陽と世界と月を意味している。
太陽にはセラエーナが立ち、月にはマーロゥが立つ。二人は視線を交わして最後の意志を確かめ合った。
翼人から生まれ、翼人を憎む二人は、共に終末を齎さんと画策する。
セラエーナの不死の祈りとハラヴァンの絶望が重なり、禁忌を行う腹積もりである。この場には神器とそれに準ずる素材が揃っているため触媒として用いることで術式を制御できると考えていた。
ハラヴァンがこれから行うのは、『翼人以外のすべての人類と文明を消す』こと。リーリウスに対して不死を付与し、それ以外の全てをこの世から奪い去ろうとしていた。
誰も世話をしてくれない世界であの男だけが惨めに生き続ける世界の構築――死という救いがリーリウスに訪れることはなく、無間地獄の孤独と絶望を与える。
そして自分達の霊素は神の元へ還り、離れ離れになった姉妹と再開するだろう。怒り狂った鬱憤の果て、張り詰めた幽けき憤怒を司るハラヴァンの審判がここに成就しようとしていた。
「もうすぐです。もうすぐ会いに行きますよ。マナ……アルミリア……」
■015――真理
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
神殿の熱狂を冷ます夜風にウツロの鎧は薄氷の音を立てる。
禍人領からここまで幾つもの死線を乗り越え、その度に傷付いた青生生魂は相当に無理をしたのだろう。今やその体は身動ぎ一つで節々が欠け落ちて、炭化した断面は黒曜石に似た劈開が見て取れた。二百年戦い続けた体が朽ちようとしていた。
アーミラとセリナは、ウツロを助けるために二人がかりで鎧の頭部と襟、そしておそらくは魂の核が存在するであろう先代の文字が刻まれている背部の一枚板を慎重に取り外してそれぞれを胸に抱え持った。残された四肢はその役目を全うして砂の山となり、アーミラは頭巾を広げてそれらの残骸も包んで回収した。
「これってなんて書いてあるの?」
血族の戦いに終止符を打ち、どこか消沈の面持ちをしているアーミラに対し、セリナは努めて明るく、それとなく気遣うように問いかける。複雑な曲面によって構成された背甲を抱えて、普段は隠れてしまう内側に刻まれた一文を視線で示した。
アーミラは気丈に振る舞って文字を読み上げる。
「……『深淵を覗く痴れ者、魂は頂く』」
「物騒だな」セリナは戯けながら、もう面倒事はこりごりだという顔をした。「覗き込んでこの文字を見つけたら怖いだろうね」
「ウツロさんを分解しようとする者に向けた先代の脅し文句かも知れません」
「なるほど」
セリナは納得したが、推理を開陳したアーミラの方が気がかりに眉を顰めて、もう一度文字を観察する。
先代―― デレシス・ラルトカンテ・テティラクス――の手記を読み込んだアーミラには違和感があった。板金に刻むのと紙に書くのでは勝手も違うだろうが、ここに残された文字と、手記の文字の特徴が全くの別人である。それになにより、手記から読み取った先代の人物像はもっと即物的で……ウツロを分解出来ないように細工こそすれ、このような挑発的な遊び心を仕込むのはらしくないように思えたのだ。
思考をさらに深く巡らせようとした丁度そのとき、ザルマカシムが血相を悪くして人探しをしていた。
「なあセリナ、ハラヴァンを見てないか?」
「そういえば居ないな、あいつ。一緒に来たんじゃないの?」
「いや、別行動だ」
セリナの表情が鋭くなる。横で会話を聞いていたアーミラも状況を把握しはじめる。ハラヴァンとは神殿で合流するはずだった者の名前だ。
「どこかでくたばったか」ザルマカシムは言う。
「まさか」セリナは鼻で笑って否定した。「嫌な予感がしてきた……ハラヴァンを捜すよ」
休む間もなく三人は駆け出す。疲弊した脚は重く、衣服は泥に塗れたように体にのしかかる。その上ウツロの残骸まで抱えるのは荷物だったが、高台に待っていた勇名の仲間が肩代わりに荷運びを請負った。
「地下の合流地点は?」
先を歩くセリナの問いにザルマカシムが応える。
「俺とアーミラ様はそこを経由して来た。あいつはいなかったぞ」
「様はやめてください。アーミラでいいです」
アーミラは敬称を付けて名を呼ばれることの意味合いが変わったような気がして、つい横から割り込んでしまう。
それを聞いた勇名達の口元に笑みが浮かぶ。視線がザルマカシムに向いていた。
「……なんだ?」
笑みの理由は単純なものだった。
ザルマカシム本人が近衛隊の部下――勇名の仲間に向けて同じことを言っていたのだ。『副隊長はやめろ』と。立場を変えて同じやり取りが繰り返された光景に、つい気を緩めて笑ったのだ。
「……まだ全部が終わったわけじゃないんだ。気を引き締めろよ」
眉を怒らせたザルマカシムも目元に笑みが浮かんでいた。本気で叱っているわけではない。
次女継承に、災禍の娘、近衛副隊長であり間者、そして近衛の部下……共に苦難を乗り越えた者達は、肩書きを捨て、敵味方の垣根すら超えて一つになった。
もうすぐ夜が明ける……平和の時代がすぐそこまで来ている。その想いを共有した彼らは気持ちを新たにハラヴァンという名の龍人を探すため、奥之院へ向かう。
❖
本殿の地下へ続く通路に潜り込んだアーミラ達は、呪血に染められた階段を降りて奥之院へ進んだ。
「あれは……!?」
先導する勇名の一人が異変に気付き、慌てた様子で駆け出した。ばしゃばしゃと足元の水溜りが跳ねる。その飛沫は血混じりの水であった。
「あっ、おい!」
呼び止める声にも振り向かずに男は先を行き、固く閉じられた鉄格子にぶつかって立ち止まる。アーミラ達が追いつき、通路の様子を一目窺って取り乱した理由を知る。鉄格子の向こうにカムロと近衛数人が倒れていた。
「地下に逃げたせいで呪血にやられちまったのか……」勇名の誰かが口惜しそうに言うが、そうではない。
「いや……白衣が染まってない。血に溺れたわけじゃねぇ」
ザルマカシムの言葉を聞いてアーミラは鉄格子の取り付けられた壁面を見つめた。鉄格子を境にして赤と黒が綺麗に塗り分けられていることに気付く。……これは。
「結界ですね……少し変わった仕組みのようです」
「それなら」と、腕に覚えのある勇名が鉄格子に手を伸ばす。助け出すには結界を解いて鉄格子を開く必要があるからだ。だがしかし、複雑に織り込まれた回路を前に勇名の男は苦戦した。呪血の侵食すら拒むほどの強固な結界であるため無理もなかった。
「ガラハウ! なにもたもたやってんだ!!」
「解けねぇんだよ……! オシュトル、手伝ってくれ!」
二人がかりで解呪に挑む勇名の傍ら、アーミラも鉄格子に触れて術式を指先に感じていた。そしてこの術式の特性を見破り、こんな方法があるのかと心の中で唸った。――なるほど。
「どうやらこれは、力押しが通用しないみたいです」
アーミラは結界に沈ませた指先をぱちりと鳴らし、容易く波紋を生じさせる。ガラハウとオシュトルからすれば、指先が結界の中に侵入できていることが驚きだった。
「どうやって……!?」
「式の複雑さに意識が向いてしまいますが、構築された結界は単純です。
こちらの持つ魔力、呪力が微弱であるほど結界も弱まり、強力なほど堅牢に拒むみたいですね」
その証拠に、とアーミラは勇名の一人に持たせていたウツロの頭部を借りて結界に沈ませる。板金に備わる魔力がないため抵抗なく結界を素通りした。鉄格子を叩いてがしゃりと音を立てる。
解呪に挑む二人はアーミラに倣い魔力をあえて絞り、指の先を沈ませるところまで成功した。要するにこの結界は鏡のようなもの。加わる力に比例し、呪血の洪水に対しても同等の反射によって侵入を拒んだ。反対に、力を抜いてゆっくりと優しく触れれば多少なり侵入することができる。
オシュトルと呼ばれた男は迂闊にも手柄を急ぎ、沈ませた指先から術式の破壊を試みたが、その瞬間に光が爆ぜて指を弾き出された。痛みに引っ込めた己の手が無事か確認し、危うく手首から先が消し飛ぶところだったと青褪める。
この世界の人間には霊素――つまり魂――に魔呪術の素が宿っているため、指先を浸すことはできても、結界を通過することができない。どうにかして道を開く必要がある。
ガラハウが教えを乞うようにアーミラを見つめた。
「……解呪は、破壊するにはどうしたらいいでしょうか……?」
「破壊はしません。同等の結界を展開させて馴致領域を形成します」
アーミラは言いながらに実践し、すでに鉄格子を直に掴んでいた。拒んでいるはずの結界はアーミラの腕の周りに円形の穴を作り、そこだけが無防備に風穴を開けていた。
さも難しくないことのように言っているが、他者の構築した術式と己の術式を馴染ませる芸当は並外れた技である。呪術も魔術も全て戦うために存在しているのだから必ずどちらかが上書きされるように考えるのがこの世に生きる術者の常識。ガラハウもオシュトルも、調和させるという発想がなかった。
この馴致領域は互いを喰い合う呪血のような対消滅ではなく、双方の術式が一つに混じり合うことによって形成される。鉄格子の外にいながら結界に取り込まれることで内部への侵入を可能としたのである。
ガラハウは言葉にこそ出さなかったが、表情はありありと語っていた。――全ての血を持つ混血……彼女がもしも神殿に敵対せずに禅譲していれば、誰も敵う者はいないだろう。
柔軟な発想と巧みな術解釈。そこに生まれ持った才覚が合わさってアーミラは無二の実力を発揮している。畏れを抱くガラハウに一つ訂正するならば、アーミラは神殿から逃げ出したからこそ才を手に入れることができたということである。
ともあれ、一行は結界を潜り抜けて鉄格子を開き、奥之院に踏み入った。
勇名達は通路に伏せっている同胞を膝に抱えて呼吸を確かめた。命に別状はなくただ眠らされているだけだと知り、ほっと胸を撫で下ろす。
「水の臭いに呪血の残穢……、僅かに香木か。これはカムロのものだが……」
この場所に残る香りを嗅ぎ分け、ザルマカシムはここにハラヴァンがいたことを確信する。皆を眠らせたのは香木に違いないが、当のカムロまで眠っているのなら悪用されたに違いなかった。そんなことをする人間に心当たりは一人しかいない。
「最奥に居るな」
ザルマカシムは呟いて推論を立てる。
ハラヴァンが奇襲に参加せず最奥へ潜る理由は暗殺か。リーリウスにはウツロを差し向け、その隙に最奥に潜む翼人を根絶やしにする――業腹だが権謀術数を性癖とするハラヴァンであればそう動くことは想像に難くない。それだけの恨みがあるのだろうし、確殺する手段として効果的だろう。
しかし、ザルマカシムの不安は拭えない。ハラヴァンの張り巡らせた奸計という巨大な蜘蛛の巣が、神殿のみならず龍人さえも絡め取っているような、空恐ろしい予感があった。あの男は常に本心を隠していて油断ならない……。
「ガ、ガントールさん……!? スークレイさんまで……!」
通路の曲がり角に進んだアーミラは、そこに倒れている仲間を見つけて驚く。駆けつけたセリナも目を丸くして声を荒げた。
「オロルもいるじゃんか……!」
傷だらけの体、纏う衣服も赤黒い血染みに汚れているがこの傷はウツロとの戦闘に負ったもの。やはり眠らされているだけだった。
「二人にはこれを」そう言ってザルマカシムはアーミラを呼び、心像灯火を差し出した。「直接触るなよ。そっと戻してやるだけでいい」
ガントールとオロルの心臓の火を手渡されたアーミラは掌に魔力の器を作って受け止めると、セリナが見守る中で火が消えてしまうことがないように慎重な足取りで運び、眠っている二人に火を注いだ。おそらくはこれで一安心といったところか。
「……ザ、ルマ……?」カムロが睡醒から潤んだ目を開く。「私は……」
前後不覚となったカムロは状況を思い出せないようだった。見慣れない壁と天井に視線を忙しくしている。意識は明瞭なようだ。
「ここは奥之院です。神殿での蚩尤との戦いから避難していたはずですが、隊長は眠らされていました」
誰にやられたのかとザルマカシムは肩を掴み、カムロは天帝侍医の男だと答えた。
「やはりそうか」そう呟いて、ザルマカシムの手に力が籠る。
「その男がどうしたんです?」
まだ立ち上がる力が無いカムロは上目遣いに首を傾げた。天帝侍医と近衛副隊長の間柄になにか疚しいことでもあるのかと、信頼の眼差しが刺さる。
躊躇う沈黙の後、覚悟を決めてザルマカシムは白状した。
「あいつの正体はハラヴァン……禍人領の将だ」
カムロはずっと騙され続けていたことに些かの動揺をして……見開いた目はすぐに伏せられた。副隊長の座に就きながら裏では敵対する禍人と手を組んでいる……そんな裏切りにカムロは薄々気付いていたのだ。
「あなた達は知っていたのですか?」
「まさか、先ほど知ったばかりですよ」
部下達が一様に頭を振るのを見て、カムロは少しだけ安堵したように頷いた。
「……副隊長が時折に姿を見せずとも、それは奥之院での業務のためだろうと追求はしていませんでした。ですが心のどこかで疑問に思っていました。どこで怠けているのか……、私の下では不満か……と。
前線で武勲を立てたこの正義漢がどうして神殿に仇なす者と手を組むのか。その責任が私の不甲斐なさにあるのではないかと思うと自分が情けなかった」
「そんなこと――」
ザルマカシムは否定しようと声を発しかけたが、カムロは続ける。
「……今ならば解ります」ザルマカシムの頤に手を添えて髭を撫でる。「正しさを求めているからこそ、あなたは間者となったのですね……」
「カムロ隊長……」
帝の悪事を知り、ザルマカシムは敢えて禍人と繋がった。
その選択は困難を極めただろう。近衛の激務を日々こなしながら、密かに翼人の闇を暴き、真の戦争解決の方途を探った。たった一人の間諜として表と裏を行き来する綱渡り……利他と正義の信念がなければここまで勤勉に努めることはできない。
「あなたを信じていてよかった。神殿は壊れてしまいましたが、これも必要なことなのでしょう」
労うようにカムロが微笑んで見せると、ザルマカシムは頬を赤らめ、ぐっと唇を引き結んで見つめ返した。眩しさに仰け反りそうな体を踏ん張っている。
武勲から『スペル』の勇名を授かり近衛入隊を果たした時、この神殿は知の集積する気高い城だった。そして隊長の座に君臨するうら若き彼女に憧れたのである。ザルマカシムの目には、カムロが山の頂に咲く一輪の花のように見えたのだ。
「カムロ隊長、私は……」
密かに想い続けていた感情が言葉となって溢れそうになるのを堪えた。
「いや、俺は……っ――」震える喉から漏れ出す言葉をもう一度抑え込み、ザルマカシムはぶるぶると首を振ると気を取り直して真っ直ぐに見つめる。「――俺達が、全部終わらせてきます。だから、待っていてください」
決然とした眼差しをして鼻息をふんと吹き、通路の壁際まで抱きかかえたカムロを運ぶとそっと座らせる。気恥ずかしそうにして言葉が出てこないカムロに向かってもう一度視線を向け、力強く頷くと振り向かずに最奥へ歩き出した。
通り過ぎて先へ進む男の巨体を眺めてセリナは口の端を綻ばせた。魔人種の女と獣人種の男……この世界の事情を知り始めたばかりのセリナにもこればかりは理解できた。
「行きましょう」
アーミラに促されてザルマカシムの後に続く。
最奥に待つハラヴァンがどう出るか、いずれにしろ夜明けは近い。
❖
ザルマカシムとセリナ、アーミラの三人と、近衛を抜けた勇名の戦士の内でまだ動ける者が奥之院の通路をさらに先へ進み、最奥の間に辿り着いた。
過剰なまでに堅牢な鉄の扉は、人ひとりが通れる程度の隙間を開けて静かに彼らを待ち受けている。神族の居住地であるはずの奥之院に物々しい牢があることを、こうして目の当たりにした勇名は尻込みをしたように足を止めて呼吸を浅くする。室内に立ち込める邪気が冷たい靄となって床を這っている気持ちにさせた。
扉の向こうからは仄明るい魔術陣の光が漏れ、その光源に炙り出されたハラヴァンの影を見つける。その瞬間、セリナが蜥蜴のようにするりと室内へ突入し、ハラヴァンに向かって待ったをかけた。
「そこまでだ!」
後に続くザルマカシムは扉をさらに押し開けて厚い体を差し入れる。室内は魔力による燐光が眩しく細めた目の先にはハラヴァンとセリナと、もう一人いるのが見えた。
「セラエーナ様……? いや、ハラヴァン。いったい何をしているのか教えてくれ」
一方、アーミラはまだ扉を潜らずにいた。戦闘にもつれ込んでもいいように警戒して耳をそば立てる。
「ブーツクトゥス……お早いですね」この声はおそらくハラヴァンと呼ばれる人物だろう。
アーミラが聴く限り内部の状況はそれほど一触即発という風ではないようだ。……セラエーナとは誰だろうか。
男二人の会話に耳を傾ける。
「勤勉が取り柄でな」ザルマカシムが応える。
「おやおや、後ろにいるのは近衛の方達ではありませんか」
「惚けるのはやめて」セリナの声が挟まれる。「ハラヴァン、蚩尤との決着が付いた」
ハラヴァンは押し黙る。間を置いて「リーリウスは死にましたか?」と問いかけ、ザルマカシムが答えた。
「赤子に呪い返されて虫の息だ。まもなく死ぬさ。
なぁ……お前さんは何をやろうとしていたんだ?」
くつくつと、笑壷に入り肺を引き攣らせる奇妙な声。
何が面白いのかと怪訝に思ったアーミラは扉の隙間から室内の様子を窺う。丁度ハラヴァンと呼ばれる人物が笑みを収めて息を整えていた。
まだ口角の吊り上がった顔がザルマカシムとセリナに向く。
「復讐ですよ」右手で部屋の一劃を指でさし示す。
「カルミナ様……!? お前が殺したのか……」
アーミラの位置からはハラヴァンの指差したものは見えないが、ザルマカシムの動揺から状況は理解できた。おそらくそこには遺体が転がっているのだろう。
ハラヴァンが命を召し取った人物に聞き覚えはない。だが奥之院最奥にいる人物となれば、当然アーミラにとって血の繋がりがある。どうしようもなく引き寄せられるようにアーミラは扉の影から首を伸ばし、遺体の姿を目に捉える。
『カルミナ』とザルマカシムが呼んだその遺体は、翼人というよりは魔人種のような印象を受けた。直感的にこの人こそ生みの母親なのではないかという予感が脳裏に浮かんで、アーミラはすぐさま思考の隅に押しやった。自己憐憫に耽っている場合ではない。
翼を持たず、床にだらりと四肢を放って倒れている彼女は齢四十絡みの女性で、まだ生きているのではないかと見紛う程に外傷は少ない。足首に刻まれた深い傷――これは枷に擦れて化膿した古傷である――や、振り乱した長い髪に隠された顔が実は目と耳を抉られていることを、アーミラのいる位置からは窺い知ることができなかったためである。ハラヴァンは暴力を用いずに殺めたように推察できた。復讐という動機に反して残忍さが感じられないことに違和感を覚える。
視線は次に、白く浮かび上がる羽だらけの異形へと吸い寄せられた。性別も年齢も判別がつかない翼人の形態異常……セラエーナと呼ばれているらしいこの者は最奥の隠し子だろうとアーミラには見当がついた。というより、外見の特徴から誰の目にも明らかである。
セラエーナは床に描かれた陣の太陽の位置に立ち、髪とも翼ともつかない覆い越しにザルマカシムと対していた。その隣で月の位置に並び立っている者こそがハラヴァンだと知る。……あれが、禍人種の将……。
アーミラはその男の姿を見て、幻が重なって見えた気がした。
疲労で目が霞んだのかと瞼を瞬かせる。
「初めからそう言っていましたよ。『殺するは蚩尤』……誰かがこの最奥からカルミナを解放しなければならない。そうでしょう?」
ハラヴァンの声に僅かな震えが混じる。それが戯けているからなのか、噎せているからなのか、ザルマカシムには判断が付かなかった。
「解放……、解放だと……?」
いつもであれば迷わず愉悦の笑みだと理解できたはずなのに、今目の前にいるハラヴァンの表情があまりにも痛々しい笑みに見えて、返す言葉が喉元に詰まった。人の形をした狂気と言っても過言でないこの男がここに来て初めて偽らざる悲しみを滲ませている。
そんなハラヴァンを庇うようにセラエーナが言い添える。
「……ザルマカシム。貴方は知らないだろうけど、この男も最奥で産まれたんだよ」
「は――」
素頓狂なザルマカシムの声は、アーミラの心の代弁となった。
セラエーナは隣立つ男に羽に埋もれた手を向けて、事の経緯を語る。
ハラヴァン――本当の名はラヴェル・ゼレ・マーロゥ。彼はこの最奥で産まれ、そして神殿から逃げ出し生き延びた唯一の人間なのです。形態異常を持たず魔呪術の類い稀なる才を持つ彼は、つまるところ僕の兄にあたります。……驚いてしまうのも無理はありません。嬰児を間引いていること自体神殿は秘密にしていますから、まさか逃げ延びた子供がいるなんて父は誰にも明かすことはありませんでしょうし、この件はザルマカシムが近衛に入隊するよりも前の出来事ですから……そんな兄が母を手に掛けたのは身の上を憐んでのことです。
「……もういいでしょう。よしなさい」ハラヴァンはそう言って過去話を切り上げさせる。「ブーツクトゥス。そういうことで、邪魔はしないでいただきたい」
翼人を怨む本心が明かされたのだからこの復讐が悲願であると理解したはずだ。そうハラヴァンの目が語っている。初めて真摯に向き合うその眼差しにザルマカシムは疑うところはないのだが、この世から人類を消し去ろうとしていることについてはひた隠しにされたままである。
「いや……――」
歯切れの悪い否定の言葉が漏れた。
ザルマカシムの戸惑いは全く別のところにあった。
続く言葉に、今度はハラヴァンが驚く番だった。
「――お前も最奥から逃げ出していたのか……?」
❖
「……なんですって……?」
耳を疑う言葉を聞いてハラヴァンは問い返した。
ザルマカシムの方は既に別のところへ意識を向けているため、問いかけを無視する形で視線を外している。彼は今、身を捻って後ろにいる人影と見つめ合ったまま凍りついたように固まっていた。問いかけが無視されてしまったハラヴァンもまた憤慨する余裕もなく内省に沈く。
遡ること百年前、ウツロが待ち焦がれていた四代目継承者が現れなかったそもそもの原因は、歴史の裏に葬られた一つの事件に端を発する。
『継承者嬰児幽閉』……翼人は一族の権益を維持するため民草に混血の一切禁じた一方で、恥知らずにも多種族の血を取り込むことを画策した。
その目的は濃すぎる血を薄めるため……だけではなく、すべての種族を掛け合わせることで正真正銘の神の一族を築くつもりだったのである。
そのための相応しい血こそ、神に選ばれた継承者達三種族の娘の血。ウツロと共に出征するはずだった嬰児を攫い集め、行方知れずの疑惑を消すために集落が襲われたように偽装し、国内外に「四代目は死産」と広めた。
奥之院に連れ去られた赤子は目をくり抜かれ、踵を切られ、逃げられぬようにと最奥に幽閉された。……そうして百年間、翼人は代を重ねながら娘に子を産ませ、血を取り込んだ。継承者の少女は暗闇の中で母となり、産まれた子が年頃になるとさらに翼人の子を産ませ、混血同士を掛け合せたのである。
……結果として、ほとんどが龍人として産まれた。
外見の形態異常が軽微な赤子以外は全て間引き、数少ない生き残りを翼人は厳選し始めた。その子供がハラヴァン――ラヴェル・ゼレ・マーロゥであり、アルミリアであり、マナである。
ハラヴァンは、最奥から逃げ延びたのは自分ただ一人だと思っていた。
アルミリアは死んだという確信も彼にはあったのだ。マナと落ち合うために前線を歩き回り、そこに妹の亡骸を見つけていたのだから見間違うはずがなかった。だが、しかし……。
交わらざる者達の運命が一つの真理へ向かい収斂しようとしていた。
『お前も最奥から逃げ出していたのか』――聞き間違いでなければ、ブーツクトゥスは確かにそう言った。つまり、同じ境遇の人物を知っているということ……そんなことがあり得るだろうか? 私はこれまでどれほど必死に捜したかをブーツクトゥスは知らないだろうに。……生きているのなら何故再会出来なかった? 何故ブーツクトゥスは知っている? 欺こうとしているのか……いや、おそらく視線を交わしているその人影こそが件の待ち人だろう。ならばこの目で確かめればいい……。
ハラヴァンは短い刹那に思考を巡らせ、平静を取り繕って居住まいを正す。
ザルマカシムの厚い胸板に阻まれているため、背後の人影はハラヴァンの立つ位置からは僅かにしか覗けない。細い手足は白衣を着用しておらず、間違いなく女のものである。この段階で真贋の判断はできないが、霹靂の希望が兆した。
――まさか……。
とうの昔に再会を諦めた瞳に、否応なく光が宿るのを自覚する。心臓が高鳴るのをやめない。
時の流れは引き延ばされ、娘の姿は勿体つけるようにゆっくりとハラヴァンの待つ最奥の間に踏み入った。
――まさか、そんな……!
娘の歩みに舞い上がる微風が、ハラヴァンにとっては嵐のような衝撃を伴って迫る。神はなんと底意地の悪い悪戯をするのだろうか!
華奢な体つきをしたその少女は着の身着の儘といった風体で草臥れた襯衣と細袴、木履を履いていた。晒している肌は蚯蚓腫れの傷痕がいたるところに残されており、少女が歩んできた半生が壮絶なものであることを物語っている。
肩にかかるほどで断ち切られた藍鉄色の髪が戸惑いに揺れ、物憂げな瞳はやや上目遣いにハラヴァンを見つめて困惑の表情を浮かべていた。
「アルミリア……」
ハラヴァンは祈るようにその名を呼び、目の前の娘が何者なのかを悟って肌が粟立つ。夢か幻の存在でしかない娘を現実に留め置くことに成功したような興奮が胸の奥から湧き出すのを感じていた。
歓喜に震える心が少女の名を叫ぶ。
「アルミリア・ニァルミドゥ……!」
その言葉にセリナがぴくりと反応した。
「……それが、私の名前ですか?」
アーミラは当然の疑問を口にする。
翼人はラヴェルという姓を持つため、『ニァルミドゥ』という氏族は存在しない。アーミラのやや後ろに立つセリナもまた、同じ名を授けられた者としてこの問いの答えを興味深く待っていた。
「混沌乃宝石……ニァルミドゥとは私が付けた造語に過ぎません」ハラヴァンは白状するような態度で答える。「全ての血を掛け合わせて産まれた翼人の娘……私にとって恐るべきものでもあり、翼人にとっては無二の価値を持つ……」
言葉の意味を知ったアーミラとセリナは、互いに目配せをして腑に落ちたような吐息を漏らす。
最奥から逃げ出した彼が自らをラヴェルとは名乗らないように、皮肉を込めて妹に授けた名前。最奥という混沌の闇から産まれた有翼の娘を的確に表現していると思えた。
「ただ逃げ出すだけでは翼人はなんの痛みもありません。損害を与えるために私とマナはその宝石を盗んでみせました」
手柄顔をしてみせたハラヴァンは、一転して自嘲に目を翳らせる。これで精一杯の強がりなのだろう。妹を最奥から連れ去る事で翼人に一矢報いるというのは建前で、奥に隠した心根は同じ兄妹として大切に想う感情が透けて見えた。
側で見ているザルマカシムは静かに驚いてすらいた。これまでの非道を非道とも思わないこの男にも、斯様な優しさがあったとは……。
マナとアルミリアから逸れた彼は、一人孤独に禍人領で過ごし、生まれ持った才覚で禍人の将としてのし上がった。地下で出会った空の器であるセリナに妹の面影を重ねてニァルミドゥと呼び、此度の戦役を暗躍していた……これが、ハラヴァンの半生である。
そしてアーミラも、失われていた記憶の全てが繋がるのがわかった。前線でかき集めてきた断片が色づき、旋風に巻き上げられながら収まるべきところへ収まり、一点の曇りのない嵌め絵がついに完成する。
マーロゥとアルミリア。前線で敵同士の立場でありながらも交差することのなかった兄と妹の数奇な運命は再び結び付き、心はあの始まりの日に立ち返っていた。
目の前の龍人が何者であるか解を得たアーミラは、兄と似た翳りを纏って切なく微笑む。
「貴方だったんですね……」
マナに抱かれて神殿を逃げ出したあのとき、二人の背を見送る者がいた。アーミラはてっきりその人物が父なのではないかと思い込んでいたがそれは違った。父は悪の権化であった。――であればあの日、私達を見送っていた人物は誰だったのか……。
「マーロゥ……やっと名前がわかりました」アーミラは大切なものを抱き締めるように胸元に手を当てる。「何度も同じ夢を見ました。マナに抱かれて逃げ出したあの日……『いつか必ず迎えに行く』……そう言って私を見送るあの人は誰なのかと……貴方が……」
ハラヴァンは妹の言葉を受け止めるように頷く。
気付けば最奥を満たしていた魔力は霧散しつつあり、床に刻まれた陣から放たれる燐光も勢いを無くしている。
「マナを逃がすために私は殿を務め、追手を撒くために二手に別れたのです。
命からがらに神殿を逃げ出した後、落ち合う筈の前線を彷徨いながら……再開は果たせませんでした」
続けてハラヴァンは、意を決したようにアーミラに借問する。
「……マナは、どうなりましたか……?」
マーロゥの問いかけに対して、アーミラは泣き出しそうな顔で最奥の天井を見上げた。――お師様は、マナは、この日が来ることを信じていたからこそ、私に言葉を託していた。
流れる涙を拭うこともせず、いつかの言伝を誦じる。
「……『流浪の民とは異なる服わぬ者がお主と出会う。そのときには婆は死んだと伝えておくれ』……」
胸咽ぶアーミラの言葉を聞いたハラヴァンは狂気の仮面を完全に脱ぎ去って喜悲交々に顔をくしゃくしゃにしていた。再開を誓い共に暗闇を抜け出した姉はその命を燃やし尽くし、妹の命を繋いだのだ。
「お師様は……マナは、もういません……」
「……やはり、そうですか……わかっていました……。
あぁ、なんなんでしょうねぇこの世界は……誰が予想できますか?」
ハラヴァンは遣る瀬無い面持ちで誰にともなく訴える。
彼を取り囲んでいたザルマカシムやセリナ、勇名の者達は狼狽えるばかりで言葉は見つからない。
「首を落とされた妹が生きているなんて……、継承者として戦っていたなんて」
深い後悔を滲ませる声は兄妹の再開を喜んでいない様子だった。
実際、望外の希望が今更になって現れたことにハラヴァンの覚悟は大きく揺らぎ、心が不安定に傾いでしまっていた。――全てを終わらせるためにこれまで残忍な非道に手を染めてきたというのに、最後に希望なんて、欲しくはなかった。
「アルミリア、あなたが最奥に生まれ落ちたとき、私は恐ろしかったのです。
赤子でありながら美しい翼を持ち、最奥の闇の中で輝く妹の姿を見て、きっと私もマナも用済みになると思いました」
辛うじて間引きを免れた側の存在であるマナとマーロゥは、妹の誕生を契機に翼人の目的が達成されたと見て、己の命に猶予はないことを悟ったと当時を語る。
しかしアーミラは別の言葉に引っかかっていた。
「翼?」
そんなものはない。と、言いかけて首の傷を思い出した。この体は生来のものではないのだ。それこそマナが命を賭したあの前線で致命傷を負い、別の娘の身体と入れ替えている。――いや、……そうだ、マナはこうも言っていた。
『あの身体ではこの先どうしようもないの。どのみち切り捨てていかなくちゃいけなかったんだよ』
マナは私を救うために何を切り捨てたのか。
ハラヴァンが前線で見つけた骸の何を見て、何故私だと断定できたのか。
――翼だ。
「……首を落とされた貴女の遺体を見つけ、私はマナと約束した通り混血に紛れるために禍人領へ進みました。しかし貴女達は内地へ戻った」
翼人としての身体はどこへ行っても嵩張り目立つ。白く美しい翼を前線に捨て、内地に紛れ込むために魔人種の娘の身体を借りた。そうして、記憶を無くした翼人種アルミリアは魔人種アーミラとして生きることとなり継承者となった。
「……すみません……」アーミラはつい謝罪を口にする。幼い頃の、それも記憶を失っていた頃の事とはいえ、前線での出来事はハラヴァンの人生を大きく歪めてしまった。
「いえ、いいんです……離れ離れになった理由がやっとわかりました」
ハラヴァンは腑に落ちたと頷き、諦観めいた伏し目が物憂げに床を見つめている。
アーミラがなにか言葉をかけようとしたとき、ハラヴァンは続けた。
「……セラエーナ。陣から離れてください。私は私を終わらせます」
不意の宣言にアーミラは声もなく、兄の肩に手を伸ばしたところをセラエーナに受け止められて魔術陣の外側へ引かれる。
沈黙していた術式は火勢を取り戻し、練り上げられた魔力は燐光を伴って爆ぜる。ハラヴァンは最後の詠唱を始めた。――殺するは蚩尤……。
「ハラヴァン……っ、マーロゥ!」
アーミラの叫びが届いたか、最奥の闇を圧す光の中で一人佇むマーロゥは一瞥で応える。
「けじめです」
ただ一言だけだった。
最奥に刻んだ術式を行使する……が、当初の願いは書き換えられ、魔術陣を満たす魔力は色を変える。
マーロゥがこれから行うのは人類の抹殺ではない。自らの術で妹を殺めることを回避したのだ。であればこの陣で何を成すつもりなのか。
そもそも、彼を突き動かしていた絶望とはなんだったか。
翼人の仕打ちに腹を立てるだけではマーロゥはここまで悪鬼羅刹の非道に堕ちはしなかった。あの最奥の暗闇にあってマナとアルミリアを連れ出し、外へ出るという勇気すら彼は持ち合わせていた。
そんな彼が本当に絶望したのは、ただ一人逃げ仰せた後悔と孤独。この世界で何一つ守れなかったことに絶望し、世界に反旗を翻したのである。
マナを失ったことへの復讐。
アルミリアを失ったことへの復讐。
翼人に対する復讐心を燃やし、ハラヴァンは禍人領を束ね勢力を牛耳る巨魁となった。
この本懐を達成するために、マーロゥはあらゆる犠牲も厭わなかった。仲間として従えたはずの龍人達にすら壮絶な責苦を与え、濃密な絶望に浸すことで龍体術式を研鑽し、その過程で咎や蛇堕を生み出し神殿を脅かす勢力となる。
人を人とも思わぬその所業は、もはや最奥の子間引きと同じ鬼畜の行いである。
救われるには罪を重ね過ぎていた。
のうのうと生きることは赦されないことを、誰よりも理解していた。
そんなマーロゥが最後に行う詠唱は、やはり蚩尤を召し捕ることである。
罪を背負った己と天帝の二人を、この世から消し去る覚悟を決めた。
閃光が収まると、最奥の床、陣の太陽を描いた位置には頽れるリーリウスが喚び出されている。老体は呪血による染みに覆われて、赤黒い骸のような無残な姿で背を丸めて床に転がる。最早意識はなく、辛うじて呼吸をしている有り様だった。
「これからの世界に不要な存在は消えましょう」
「そんな……やっと逢えたのに!」アーミラは必死で手を伸ばすが、強烈な魔力の奔流に近付くのは危険であるとセラエーナと勇名達が押さえつける。「貴方を一人にさせません……! お兄さん……!」
マーロゥは首を振る。
「すまないアルミリア。本当なら、三人で静かに生きて行きたかった。それが叶わずとも、お前さえ生きていればそれ以外何も望まなかった……」
マーロゥはそう言い残し、次に弟であるセラエーナと視線を交わす。
セラエーナは千里眼によって兄の想いを掬し、何も言わずに見つめ返す。
マーロゥは辞世の句にも似た最後の詠唱を唱える。
「我が名はラヴェル・ゼレ・マーロゥ。憤怒を司る六欲の欠落者なり。
この世に溢れる我が咎よ、我の下に還れ」
詠唱に呼応した陣の中心から細く鋭い光が発生し最奥の天地を貫く。まるで垂らされた蜘蛛の糸のようなその光は径を広げて柱となり、五感をまっさらに焼いていく。必死に呼び止めるアーミラの叫びも、眼差しも、白くかき消された。
❖
禁術とは本来、術式によって齎される成果あるいは代償が不確定のものを指す。ハラヴァンが行ったこの禁忌はそれとはまた別の、しかし確実に行使者に不利益をもたらすものであった。
『自らの術式によって行使者が自決する』という、おそらくは誰も使う意義を見出すことができないであろう最悪の成果だけが確定している術式。この世において――いや、どのような世界においても――自らの命を無為に捨てる行いは罪であり避けるべきものだ。その点ではやはり、この術式は用いてはならぬ禁忌に他ならない。
目眩のような視界不良が治ったとき、アーミラは事態を把握すると失意に膝をついて愕然とする。目の前にいた兄はリーリウスを連れてこの世から跡形もなく存在を消滅していた。骨の一つも残さずに消え去ったのだ。
怒り、悲しみ、どうしようもない無力感と後悔の念が複雑に混ざり合う極彩色となってアーミラの胸中に渦を巻いて暴れ回る。我を忘れて地団駄を踏んでしまいたい感情の負荷を押し留めるのに精一杯で、内圧を高めて混じり合うこの極彩色の激情が鎮まるのを待っていた。
身体を抑えていた勇名達はこの結末が果たして良いものなのかわからず、ばつの悪そうにゆっくりとアーミラから手を離す。この世界から悪は滅びた……だが、世界を救ってくれた娘にとってはあまりにも辛い結末ではないだろうか。
アーミラは神経が焼き切れたように呆然と座り込んでいる。見開かれた目は一点を見つめ、しかしなにも見てはいない。己の内側に巻き起こる嵐を処理するのに手一杯で、外界との感覚が麻痺してしまっていた。
……私が傷ついている様を、天から見下ろす神が嘲笑っている。
これ以上、心を消耗したくなかった。
そんな思いに取り憑かれたアーミラは涙を堪えて、混ざり合う渦が黒く濁って凪となるのを待とうとしていた。
――我慢するな。
優しく語りかける声に、アーミラははっとして我に返り、ウツロの面甲を見る。
暗い穴の空いた双眸が、勇名に抱えられたまま見つめ返していた。
――辛いなら泣いていい。苦しいなら叫んでいい。……あの男はアーミラにとって大事な人だったはずだ。
「っ……う、ぁ……」
アーミラは瞳を潤ませて目に光が宿る。空になり、渇きかけていた心に水が注がれる。
横溢する器から一雫溢れれば堰を切って流れが生じるように、思うまま泣き叫ぶ。
赤く煮えたぎる怒りに任せて床に爪を立て床に蹲い、青く苦々しい後悔に嗚咽を漏らしながら髪を振り乱して胸咽ぶ。
喪失感も無力感も、心から湧き出る様々な想いとして、慟哭とともに吐き出した。
ウツロは悲しみに寄り添うように語りかける。
――心を殺してはだめだ。マーロゥだって、呪うためにこんなことをしたんじゃない。
「……確かにさ――」
セリナは言の葉を継いだ。
それはニァルミドゥとして共に過ごした者の言葉である。
「――積み重ねた非道を思えば生かしちゃおけないやつだよ。神殿側にとっても龍人側にとってもハラヴァンは一線を超えてたし、私も危うく殺されかけた。……でもね、あんたの兄貴は罪から逃げるために死んだんじゃない。全部背負って……私達に託したんだ」
次の時代に禍根を残さぬためにマーロゥはけじめをつけた。
絶望に身を焦がした男が最後には希望を手に入れ、世の平和が訪れることを祈り、その命を手放したのである。
「アーミラのお陰で、あいつは最後に兄としての自分に戻れたんじゃないかな」
慰めの言葉にアーミラはますます泣き声が大きくなる。
辛く壮絶な別れの幕引きではあるが、そこに救いがあったのだと思えばこの悲しみにも意味があると思うことができたようだ。
❖
アーミラ達が輪を作る一方で、ザルマカシムとセラエーナは少し離れたところにいた。
己の利害が一致していると見て、マーロゥの思い描いた策謀に乗る形で間諜に身を落としたとばかり考えていたザルマカシムは、その実、これまでの行動が巧みに操られていたことを今更ながら理解した。
翼人の血塗られた過去をそれとなく示し、神殿に忍び込むハラヴァンと引き合わせた者こそ、最奥に幽閉され続けていた嫡嗣セラエーナである。
「……貴方はどこまで知っていたんです……?」ザルマカシムは駆け引きもなく問う。
思えば神殿がどこか不穏だと感じ始めたのも、ハラヴァンと出会ったのも、奥之院の仕事を任せられるようになってからで、つまりセラエーナと出会ってからザルマカシムはブーツクトゥスとしての一面を持つようになったのだ。いや、その仮面を着けさせられたと言ってもいい。
「千里眼……僕は人の心が見える。
初めて君と会ったとき、『君ほど真っ直ぐな人間はいない』と思ったよ」
「だから翼人の秘密が露見するように仕向けたと」業腹に片眉を跳ね上げてザルマカシムはセラエーナを見下ろす。
「同じ時期にハラヴァンがやって来た。何の期待もしていない顔をしていたけど、ここにマナやアルミリアが捕まっているんじゃないかと戻ってきたのがわかった。翼人の秘密を知り、この世界を破壊しようとするハラヴァンと、強く正しい精神を持つザルマカシム……二人を引き合わせれば神殿にとって脅威になってくれるってわかった」
セラエーナは囚われの身でありながら、千里眼の力によって外の世界に働きかけていた。悪しき者が権益を浴し、正しくも貧しいものは虐げられてしまうこんな世界なら滅んで仕舞えばいいと考え、ハラヴァンに協力していたのである。
「だが……マーロゥは結局、世界を滅ぼさなかった。……貴方はどうする?」
ザルマカシムは真っ直ぐに相対して見つめる。アーミラを除けば彼が最後の翼人の末裔であり、破滅を求めるハラヴァンの共犯者である。返答次第では事を構える覚悟であった。
そんな心中を見透かして、セラエーナは苦笑する。
「僕は、もとより何かできるわけではないから」
籠の中の鳥として生まれ、すぐに全てを諦めた。
世界が滅ぶのならそれで結構。
神殿が崩れるならそれで結構。
翼人が裁かれるというのなら、それも構いはしない。
セラエーナは最奥に幽閉されながら日々の世話をザルマカシムに頼り、神殿に収められた閉架から浩瀚な書を読み解きこの世界の真実を求道していた。
世に語られるラヴェル一族の姿と裏の有り様を知っているセラエーナは、長きに渡る禍人との戦役にその緒があることを知った。己の成り立ちから血筋、その全てに嫌悪すらしていた。
「塔がなぜ、地下に沈められたか知っているかい?」
「あぁ」ザルマカシムは頷く。
「歴史上で初めて神と龍が顕現した出来事……」
遡ること六百年前。混血種の一つであった翼人は巫力を用いて地位を築き、神になろうとした。
獣人に石を運ばせ、魔人に設計図を描かせ、賢人に組織を管理させた。そうして建てられた塔は、他の種族に対し威光を示すだけの飾りではなかった。この世界を見下ろす神のもとへ駆け上がるための天界へ繋がる螺旋階段……それを建造しようとしていたのだ。
「塔の全高が雲を超えて、いよいよ神のもとに届くそのとき龍が現れた。
龍は人間に向かい言った。『神に近付いてはいけない』と」
人間に塔の建造をやめるように諭したが、翼人は龍を悪だと罵り、兵を嗾けて殺してしまった。
「こうして神は怒り、塔を叩いた」
セラエーナはまるで自身が体験した出来事を語るかのように神話を要約してみせた。もしかしたら書の文面を目で追いかけるだけでも千里眼が働き、当時の光景が視覚に現れるのだろうかとザルマカシムは思う。
「神はこの怒りを人間達が忘れることのないように、戒めの楔として塔を土の中へ沈め、翼人は恐れ慄き山へ逃げた。塔の名残は混血達の根城となって今も南方にあり続ける……」
セラエーナは一度言葉を切って声音を変えた。
「翼人こそが人々を唆した蛇なんだよ。龍を殺すように命じた、最も神から嫌われている種族なんだ」
セラエーナの言葉にザルマカシムは目を細め、無意識にアーミラの方を見る。神によって幾度となく困難を課せられた翼人の娘……彼女の艱難辛苦は神によって仕組まれたのだろうか。
「それで、セラエーナ様はもう何もしないと?」
セラエーナの羽に包まれた頭が頷く。
「はい。処刑を望むのであれば僕の首を差し上げます」
その言葉にザルマカシムは面食らって目を丸くする。だがしかし、ありえないことではないため返答は保留とした。……民の信仰が瓦解し、政治すらままならなくなるであろう。この終戦は人々の生活を根底から揺るがす未曾有の事態であるため、最悪の場合には公衆の面前で翼人の首を落とし擾乱を収める必要はある。そのときにアーミラは必ず護らなければならない……セラエーナの命は俺が預かろう。
そんなザルマカシムの思考さえ千里眼には筒抜けだった。
セラエーナは羽毛から覗く口元を吊り上げ、最奥の暗い天井を仰いだ。
「マーロゥ……僕も連れて行ってくれて構わなかったのに……」
■016――暁
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
アーミラは泣き腫らした目を親指で拭い、勇名の者達に支えられながら立ち上がる。痙攣して歔欷の声が漏れる喉からそれでも言葉を発した。ここでやるべきことがあるのだ。
「う、ウツロ、さんを……っ、じん……陣、にっ……」
ウツロを魔術陣に……そう指示するアーミラの健気さは男達の胸に切なく迫るものがある。言う通りにしてやりたい気持ちはあるが何をするつもりなのかわからない。自棄になってないかだけが心配で、彼等は口を噤み、伺い立てるようにセリナの方へ視線を向けた。
「何をするつもりなの?」
男達を代弁してセリナが問いかける。敢えて寄り添わず距離を保つさっぱりとした態度に応えるためにアーミラも気丈に振る舞いたいのだが、そう思えば思うほどに肺が引き攣って涙が溢れる。
「う、ウツロ、さんっ、……も、戻して……、あげたいんです……」
はっきりとした意思を表明したその言葉にセリナは深く頷き、男達にも聞こえたかと首を回す。アーミラの意思を理解した勇名達は諾々と従い、預かっていたウツロの面甲と背甲、そして頭巾に包んでいた朽ちた青生生魂の砂鉄を陣に集めた。
月と太陽の間に描かれた中心の円にウツロの残骸が置かれると、アーミラは熱心に魔術陣の加筆を行う。床を見つめながらの作業でどうしても洟が垂れてしまうので勇名達には泣き収まっていないように映っていたが、アーミラの涙は止まっており、気持ちの整理は付かずとも意識の隅に追いやるだけの気力が残っていた。
なにより、刻まれた陣を読み解き術式を理解したときには驚きと共に没頭し、失意の無念は吹き飛んでいた。
アーミラは一魔術師としての矜持を持って、マーロゥの遺した陣と向き合う。
――こんなものを……本当に使おうとしていたの……?
戦役を暗躍し緻密に研鑽を重ねて構築したこの魔術陣は、文明の崩壊と全人類の霊素消滅を目的とした世界収束の禁忌と見て間違いない。
対象範囲がとにかく広域で、大陸全土……この星そのものに効果を及ぼしかねない代物だとわかる。術式を発動してしまえば、言葉も道具も、文明の痕跡さえも灰燼に帰し、世界から人類が消え去っていただろう。
そんな絵空事のような彼の破滅願望を体現した術式は、蚩尤憎しの執念によって微に入り細を穿つ魔術陣を構築していた。
実現不可能なものとして思い浮かぶ問題点は全てマーロゥの手によって都合が付けられていた。
例えばこれは禁術である以上、通常ならば制御はできない代物だ。しかしこの問題は陣の外縁に規則正しく設置されている神器の欠片を用いれば解決する。
では発動のために必要な膨大な魔鉱石はどこから調達するのか。この問題も解決済みなのだ。神殿が税として蓄えた魔鉱石を充てればいい。
到底実現できるものではないと一笑に付してしまう類いの禁忌の術式がアーミラの目の前に存在している。荒唐無稽に思えるこの術式は見せ掛けだけの脅しではなく、驚くべきことに使用可能なのだ。この事実を理解すればマーロゥの苦悩の一端を推し量ることもできる。彼がどれ程の心血を注いで世界と立ち向かっていたのか、とても正気の沙汰では成し得ない執念だった。
――マーロゥは、この壮大な計画を本気で成し遂げるところまで来ていた……。もし発動していたら、世界は全く別の様相を呈していたはず……。
だからこそ、彼の自決には心がついて行けていない。アーミラはそれが申し訳なかった。
――私という存在一つでマーロゥは悲願を諦めた。諦めてくれた。譲り受けた世界に対して責任を全うしなくてはならない。
アーミラの覚悟は固かった。
月と太陽。
破壊と再生。
風化と不易の二律背反を抱えたこの陣はマーロゥとリーリウスの消滅に一部の術式が消費されたが、アーミラが必要としているのは陣の再生の方、未だ使用されていない術式の方である。
対象をウツロのみに限定し、アーミラはせっせと術式を書き換えていった。
不足している部分には切り出しの刃で床に傷をつけて線を引き、不必要な箇所は靴底で擦って掻き消した。その作業に迷いはなく、黙々と行なっている姿をセリナと勇名達は見守っていた。
最奥の動きを見咎めたザルマカシムが人集りに合流して、近くにいた仲間に声をかける。
「アーミラは何する気だ?」
「どうやら鎧の魔導具を治すらしい」
勇名の返答は気楽なもので、輪の中心で忙しくしているアーミラの熱が届いていない。ウツロの存在がなんであるかなど全く知らない様子……事実、彼等はウツロが一人の人間であることを知らないのだ。
父を倒し、母と兄を目の前で失った……そんな離別を経験したばかりのアーミラが、この最奥でウツロのために陣を描く。その行動の重みをザルマカシムは多少なり理解しているつもりだった。
一族の鎖を断ち切り、影ながらに継承者達を支え続けた男……それこそがウツロである。共に過ごしたアーミラが彼をどう思っているのか察するに難くない。
「愛しているのか……」ザルマカシムは誰にも聞こえぬ声で呟き、歩み出る。
セリナは陣の外縁に近付く気配に気付き、視線を上げてザルマカシムを見つめた。推し量るような目をしていた。兄の復活を妨害する者を立ち入らせる気は無いようだ。
「邪魔はしないさ……指示をくれ」
その一言でセリナの態度は軟化する。
汚れた白衣の袖を捲って、ザルマカシムは加勢した。
勇名達の見守る中、ウツロの正体を知る三人は暗黙の了解で通じ合い魔術陣の書き換えを進める。アーミラの頭の中にある式を再現するために回路の整理も行った。その指示は難解で、魔呪術の覚えがあるザルマカシムでさえも指示の意味を把握できない場面があり、額に汗を滲ませながらなんとか応える。
苦労の末完成した頃には流石に疲れの限界が来て、ザルマカシムはしゃがみ込んだ。それきり立ち上がる気力も無くなっていた。
「これで行けるか?」喉の渇きに唾を飲み込み、ザルマカシムは床にへたり込んでアーミラを見上げる。
「はい。……あとは私に任せてください」
返答に頷き、ザルマカシムは尻が汚れることも気にせず寛いだ。あとは見守るのみという段にあって、オロルとガントールが勇名に支えられながら合流してきた。スークレイやカムロも歩けるほどには回復したようで、彼女の姿を認めると疲れも忘れて飛び上がり、湿った裾を手で払った。
カムロは初めて踏み入る最奥をゆっくりと見渡して、ことの経緯を推し量る。床に転がったままの翼人の遺体と、身柄を拘束されたセラエーナ。そして無事仕事を終えたザルマカシムを見つけて、柔らかく微笑む。
「ラヴェル一族は」
「王妃カルミナは亡くなりました。最奥の隠し子であるセラエーナは降伏し、天帝リーリウスはハラヴァンと共に消滅……骨も残っていません」
「そうですか」カムロは複雑な顔をしていた。
信仰と営みの地盤は、これで全て失われた。神殿での地位を無くした二人は明日からどのように生きるべきか、身の振り方を考えているのだろう。
一つ確実なことは、幸いにもこの先の日々も孤独ではないという希望だった。カムロは意思の強そうな瞳でザルマカシムを見つめて言葉を続けた。
「これからも頼りにしていますよ。ザルマ」
「任せてください……!」その言葉にザルマカシムは力強く応える。
一方、陣の側でも再会を喜ぶ三人がいた。
ガントール、アーミラ、オロルの当代継承者を務めた三人である。
「無事じゃったか」
オロルは相変わらずの不敵な笑み。しかしその金色の瞳はどこか誇らしげにアーミラを見上げている。
「本当によくやったなアーミラ」と、ガントールはオロルとは対照的な素直さで褒めそやす。
体が万全であれば飛び付きすらしたであろうガントールは引き摺る脚を無理やりに歩かせアーミラの側に行こうとした。このままでは転んでしまうとアーミラは慌てて両手を広げ、案の定前のめりに体勢を崩したガントールを受け止めた。
熱を帯びた左腕と、冷えた義手の右腕が、迷いなく抱き返す。アーミラの肩に鼻を埋めてガントールは囁く。
「一人で大変だっただろう……何もできず、すまなかった」
ガントールはこの一言のためにわざと倒れたのだった。アーミラが戦役に終止符を打ったこと。翼人の一族を倒したこと。事情は全て勇名越しに伝えられていた。重要な局面でアーミラを孤独にさせてしまった不甲斐なさ、隣にいることすらできなかったことへの謝罪を、ガントールはどうしても伝えたかったのだ。
「一人ではありません」アーミラは背中を摩りながらガントールを宥める。「それに、まだやることがあります」
横を向くアーミラの声に決意を感じ取ったガントールとオロルは、その視線の先を追いかけ床を見下ろす。最奥を埋める巨大な魔術陣と、円の中心に据えられたウツロの残骸を見つけ、アーミラに振り向いた。
「あれはウツロか……」オロルは無惨な姿となった鎧の欠片に驚く。
「どうするつもりなんだ?」ガントールは問う。「鎧を修復するのか?」
「まだ、決めていません。彼の意志を尊重します」
アーミラはそう答え、ガントールの手をそっと離すと不安そうに微笑んだ。陣の中へと踏み込み、セリナを手招きした。
「え……私……?」
セリナは何の用かと首を傾げ、床に描かれた陣を踏まぬようにウツロの隣に立つ。
「準備が整いました。全ての血を持つ術者と青生生魂と日緋色金……。潤沢な鉱石と場に満ちる呪力があれば、どのような禁忌も制御できます」
アーミラは神妙な面持ちで二人に向かって語りかけた。語調は整然としたもので、すでに詠唱の前段階に入っているらしい。
取り巻きにいたザルマカシム達もいよいよだと固唾を呑んで見守っている。ウツロの復活……しかしなぜセリナまで陣に呼んだのか……? アーミラの真意を伺い待つ。
「二人は、元の世界へ帰りたいですか?」
「……え……?」
セリナは驚いた表情でこの提案を聞き、ウツロの方へ視線を落とすが、面甲は沈黙したままである。
アーミラの言葉を聞いていた勇名の者達も意味を汲み取ることができず、互いに聞き間違いかと仲間の顔を伺い合った。……鎧を修復するんじゃないのか……?
アーミラは続ける。
「神器を用いれば、任意の時間、任意の世界……つまり召喚とは逆の手順で本来の世界で生き返ることができます」ウツロの方に視線を落とす。「ここでの二百年は辛いことばかりだったでしょう……面倒事に巻き込まれ、多大な貢献をしてくれたウツロさんには、生きる世界を選ぶ権利があります」
時間も場所も思いのまま……セリナはその可能性について夢想する。
震災に襲われたあの日、津波に呑み込まれて消えた兄の姿ははっきりと思い出せる。もしもあの日に……いや、それ以前の時空に戻ることができたなら、兄妹は死ぬ運命を回避して、必ず違う未来に辿り着けるだろう。
――だけど選ぶのは私じゃない。
兄はもう、この世界で二百年を生きている。二十年にも満たない元の世界と比べればどちらがより馴染みのある世界なのか一目瞭然だ。私はたった数ヶ月しか過ごしてはいないが、兄にとってはもはやここが故郷なのだ。
「元の世界で人生をやり直すか、鎧としてここで生き続けるか……どっちを選んでも私はついてくよ」
セリナは腹を決め、アーミラと共に面甲を見つめ返答を待つ。
最奥に無音の時間が流れる。
「考えたんだが――」
ウツロの声がどこからともなく室内に響いた。
何が起こっているのかと驚いているのは勇名の男達で、耳元に響く謎の男の声に警戒して周囲を見渡す。まさかウツロが、地下構造を声帯として用いているなどとは見当もつかなかった。
「――この世界で、人間として生きることはできないか?」
「可能です」
アーミラは断言する語調で言う。無理でもやってみせるという意志の表れである。
「元の体そっくりに?」
「必ず」
「それはいいな。
セリナはどうだ? 帰りたいなら考え直すが」
「愚問だねお兄ちゃん」セリナは笑う。「この体は最高だよ。元の世界じゃ空は飛べない」
ウツロは微かに笑ったか、暫しの沈黙の後アーミラに告げた。
「俺とセリナはここで生きる。
アーミラ、俺に体を与えてくれ」
「……相分かりました」
アーミラは肩の力を抜いて安堵し、セリナには陣の外に出てもらうように促した。元の世界に戻らないのであれば陣にはウツロだけでいい。
「どう? 安心した?」セリナは茶化すためにアーミラの顔を覗いた。
「そう、ですね……彼がいないと寂しいですから、ここで生きることを選んでくれたのはありがたいです」
『彼』と呼んだアーミラの綻んだ笑みを見て、セリナの意地悪な心が下火になる。妹としてでなく、同じ人を好きになってしまった者として皮肉の一つでも言おうとしていたセリナであるが、この恋路を邪魔するのは野暮だと省みて毒気が抜けた。
「セリナさんも、悔いはありませんか? ……龍体術式を解くことも――」
「この体を気に入ってるのは本心だよ」セリナは首を振ってアーミラの提案を遮った。「それより、お兄ちゃんのこと頼んだよ」
「はい、必ず」
そう言ってアーミラは頷いた。
❖
魔術陣の発動を目前に控えた勇名達は、アーミラ達が何やら通じ合っていることが気になってザルマカシムに説明を求めた。
この場の話題の中心となっている虚の鎧。この戦闘魔導具をアーミラや龍の娘、ザルマカシムまでもが肩書き以上に特別なものとして扱っている。
先代の遺した唯一無二の魔導具であることは、勇名達も当然知っていた。此度の戦闘でもリーリウスを倒し勝利へ貢献した。この功績を讃えて丁重に扱う向きには理解できるが、損耗して壊れてしまった鎧を今修復するのはやや大袈裟に思えた。少なくともこの騒乱が落ち着いてから改めて検討すれば良いことなのでは、と。
旅を共にして思い入れのあるアーミラだけならいざ知らず、龍の娘やザルマカシムまで真剣な面持ちで手を貸しているのはなぜなのか。それに、陣を流用する事情があるとはいえ、鎧を修復するにはあまりに大掛かりな術式が構築されている。これは勇名達が『ウツロを戻してやりたい』と言われたときの予想からは逸脱していた。もっと気楽な補修を行うものだと思っていたのだ。
そして疑問を決定的なものにした姿なき者の声……。最奥に響いた声がウツロのものならば、あの鎧には意志があり、霊素が宿っていたということになる。そんな事実を彼らはこれまで知らなかった。
「なあザルマカシム、さっきの声はウツロなのか……?」
勇名達の問いに対し、ザルマカシムは脂下がる。
「そうだ」
「あれは先代が生み出した魔導具だろう? 百歩譲って会話が出来るとしても、龍の娘はウツロに向かって『お兄ちゃん』と言ってたぞ、何がどうなってる」
混乱した様子の仲間を見てザルマカシムは意味深長に笑う。わざと返答を勿体つける気持ちもあるが、真面目に説明すると長くなってしまう事情もあって、勿体ぶった沈黙となった。
代わりに応えたのはガントールである。スークレイの肩に寄りかかり、アーミラを眺めながら言う。
「ウツロは一人の人間なのさ」
「……そんな、まさか……。ウツロは二百年も生きてることになりますよ。それに中は空っぽだ。首が無くても平気だった」
「それでも彼奴は二百年生きとる」オロルが返答を引き継ぐ。「身体がないのは、別の世界から魂だけを召喚された客人じゃしのぅ」
「ますますわからない……何者なんだ……」
勇名達は肩を竦めて困惑した。
「見ていればわかるさ」
ザルマカシムは訳知り顔で会話を切り上げてしまう。勇名達は食い下がろうとしたが、陣の前に立つアーミラが目を閉じて集中しているのが見えたので押し黙る。詠唱が始まった。
我が名はラヴェル・ゼレ・アルミリア。
翼を持ち、爾して記憶を失くした娘也。
宿痾の首と無辜の躰を持つ娘也。
この星に満ちる炁よ、
青生生魂に宿る気高き御魂は世界に応えた。
海岳の恩義があらば、
異界の霊素に相応き肉体を此者に与え給え。
滔々と湧き出る清水のようにアーミラの声は最奥に澱みなく響いた。
水を張った床面に刻まれた陣は血が巡るが如く輝きはじめ、一息の間に全域が青く発光する。書き替えを行なった術式はひとまず問題なく発動した。
アーミラは密かに緊張の息を細く吐き出し、背筋を伸ばしたままウツロを見守る。火を熾すことは簡単でも、火を制御することは難しい。魔術陣が走り出してしまえば術者は一層神経を尖らせる。異界との門を繋ぎ、ウツロの受肉を行うのは禁忌に値する高度な術だが、マーロゥが揃えた日緋色金などの触媒によって、滞りなく魔力が巡っている。
ウツロが無事体を手に入れることができるかどうかは、アーミラの制御に掛かっていた。
変化に気付いたオロルが小さく声を漏らし目を細めた。
陣の中央に据えられているウツロの鎧が脆く変質して面甲が自重にへこんでいくのが見えたのだ。
――まずは崩壊……。
アーミラは己に言い聞かせるように念じ、術の経過、変化が意図したものであると見極め心を落ち着かせる。
マーロゥの構築した崩壊術式を参考にしたウツロの分解。青生生魂に定着している霊素を一度引き剥がすことで、術式は次の段階へ進む。
鎧は皆が見守る中で静かに魂を失い、物言わぬ残骸となった。もう後戻りはできない。
――再構築!
祈るように陣を見つめるアーミラの眼差しに熱が籠る。その様子を後ろから見守っていたセリナとザルマカシムは倣うように両手を組み胸元に寄せ、賦活の念を込めた。
魂は宙へ。
魄は地へ。
霊素を失い本当の意味で虚となった鎧は脆く崩れて砂鉄の山となる。虚無の微風に塵が舞うと同時にウツロの気配は消え去り、床の水溜りに波紋が広がる。追いかけるように次の術式が輝き出した。
このとき、ウツロ――正確には慧――の意識は遥か上空、天界にあった。
❖
……遠い昔、翼人が神の領域を目指し、今日の戦役にまで続くこととなった最初の火種。天上の世界に辿り着くために建設された塔は見る影もなく土中に沈められ、その高みに辿り着いた者はいない。
井上慧は最初で最後の一人となった。
知らない場所に飛ばされた俺は、ここはどこかと季節外れの雪原を見渡す。
積雪によって白く覆われた地面を脚で払うと、雪は抵抗なく風に揺蕩い渦を描きながら消える。これは雪ではなく水蒸気の煙……つまりこの景色は雲海……。
視界の晴れた足元に床は敷かれておらず、それどころか膝下が透けてしまっていることに気付いた。
雲と脚先は渾然一体となって溶け合い、俺の全身はぼんやりとした白い靄のようなもので構成されていることに気付く。
動揺した俺は己の手を見つめると。足と同様にうっすらと透けて見えるが、馴染みのある籠手に覆われた掌が意のままに動く。……どうやらアーミラの術式によって魂と鎧が分離しているのだろう。いわばこの姿は仮初めのものと仮定できた。
自身が霊体となったことを理解し、何故ここにいるのかを悟った。……禁忌の魔術陣にすら介入し、見覚えのない領域へ俺の魂を招く芸当ができる者がいるとするならば、それは超常の存在だろう。心当たりはある。
俺の内側、精神世界に棲む冠角の幼い娘……名を『理』と言っていた。
――あいつが俺を呼んでるのか……?
雲を敷いた床と澄み渡る成層圏の空……唯一の人工物である荘厳な門扉は横幅およそ三十振。二本の円柱がどっしりと雲海に屹立して全高は見上げるほどに高く、穹窿構造で上部が繋がっている。装飾の意匠は三女神に授けられる神器と似通っており、鈍く落ち着きのある光沢は日緋色金のそれである。待ち受ける者がなんであるか、予感はほとんど確信に変わっていた。
奥へ招くように、歩みに合わせて門扉は重苦しい音を立てて隙間を作り、通り抜ける頃には人一人が通過するのに十分な幅となった。向こうではやはり幼い子供の人影が見え……コトワリとはとてもよく似た別人が後ろに手を組んでこちらを見つめている。
――角がない……。
出鼻を挫かれて僅かに狼狽え、緊張を高めた。セリナの言葉を思い出す。
『たしか……小さな女の子だった。でも、ただの子供じゃない気がした。――角? ……あったら忘れなそうだけど、思い出せないや。』
――セリナを転生させた奴か……。
そんな奴が俺を招いたとなると目的が見えなくなった。妹を死へ誘うような怪しい輩だ、害意を持っている可能性すらあると訝しむが、だとしたら問答無用でこちらに襲いかかるはず。こうして待ち構えているのは対話の意思表示に思えた。
警戒しながらも俺は歩みを止めず、導かれるまま門を潜ると神と思しき存在と対面して会釈をした。雲と同化している俺の姿を果たして目に捉えているのか、こちらを見つめる幼子からの反応はない。
神前の作法がわからないので静かに言葉を待つ。
その存在が放つ神聖な気配は後光すら見える。
きっとこの世界の神なるものだという確信があった。
「鎧姿が板に付いているね」
神は一言目にそう言った。
意図を掴みかねて戸惑っていると、幼さの残る小さな指を突きつけて指摘する。
「物みたいにじっとしていては疲れるだろう」
その言葉を聞いて、微かな気怠さを覚える。試しに重心をずらして片足を休めてみると体が落ち着くのがわかった。何とも言えないこの感覚は、久しく失っていた疲労というものだと思い出す。
次に神の指は俺の顔に向けられた。
「まばたきの仕方すら忘れている」
指摘と同時に視界が一瞬暗転した。立て続けにすばやく明滅して俺は後退る。痛みはがあるわけではない。
「これは……」
一度目の暗点は瞼が眼球を潤すための不随意な開閉運動であり、その後の素早い明滅は驚きに目を瞬かせたことによるものだ。神の言葉によって、封印されていた体感覚を取り戻しているように思えた。
これまで不自由を感じていなかった聴覚さえ、これまで栓が詰まっていたのかと思わされるほど清澄となり、視界は曇り硝子を外したような鮮明さで世界を映す。青く澄み渡るが故に黒く果てしない成層圏の空と、絹のように白く輝く雲海の地平線が眩しい。
下界よりも一足先に夜の終わりが迫りつつあることを知って、雲海を突き抜ける光芒に手を翳す。光量を調節する虹彩が絞られるのがわかる。
かざしている俺の腕にも変化はあった。いつの間にか籠手は取り払われており、鎧姿だった体は人の姿に変わっていた。
「……こんな感じだったか」感嘆に声が震える。
俺は暫し、神前にいることを忘れて全身を確かめるように撫でた。霊体では体温を感じられないが、指先で触れる肉体の感触が新鮮で、同時に懐かしい感覚にさせた。
ふと我に返って神の方へ向き直る。敵意は感じられないが、本当にコトワリとは別人なのだろうか。
「失礼ながら……あなたは、神なのですか?」
「『真』だよ」
「シン……?」
「真と書いてシン。真実の神さ。…… 神を騙るだけの翼人種とは違うよ」
真の、神。
なるほど……やはりコトワリとはよく似た別人なのだと理解する。頭角の有無以外は鏡写しのような二人は双子なのだろうか? あるいは『三女神』の言葉通りもう一人、合わせて三人の神が存在するのだろうか?
頭に浮かぶ幾つもの疑問を問いかけるより先に、シンは本題へ入った。
「君をここに呼んだのは見せたいものがあるからだ」
真剣な声音で見上げるその瞳に吸い込まれて目が離せなくなった。
井戸の底の水鏡のような瞳孔に、自分の影が映った。俺は反射する己の鏡像と視線がかち合い結びつく。自我が溶けていく恐ろしさがあったが、抗い難い引力に吸い込まれて声も出ない。
「見せたいものはこれではない。意識を保て、イノウエアキラよ」
名を呼ばれ、深淵に微睡みかけた意識が浮上するのがわかる。
俺は眠気を晴らすように首を振った。
「今のはなんだ?」
「円環の入り口だ。あまり私の目を見ないほうがいい。輪廻に呑まれてしまうぞ」
なんだか恐ろしい言葉に無い肝が冷えて顔を逸らす。
シンは口角を小さく吊り上げて「それで良し」と笑む。俺はシンの胸元に視線を移して、そこで初めて彼が少年であることに気付いた。長い髪と端正な顔立ちに惑わされるが、纏う布からはだけた肩は筋張っていて、声の響きも少女の声帯とは異なっている。
それとは別に、コトワリとは表情の印象が違っていた。蠱惑的で余裕のある笑みを浮かべているコトワリとは対照的に、悲しみを堪えているようなシンの硬い表情。この世を憂うとはまた違う、何があっても本心を見せるつもりはないといった意地を張る幼子の雰囲気がある。
俺の視線に対し、シンは冷ややかな流し目をして体の向きを反転させ、先を歩きだす。案内されるままに数歩後ろを着いて行った。『見せたいもの』が、この先にあるのだろう。
「神様は――」
「シンと呼んでくれ」前を向いたままシンは言う。「謙る言葉遣いも必要ない。私と君は対等だ」
対等という言葉には引っ掛かりを覚えたが、思えばコトワリとの関係も堅苦しいものはなかった。案外天界に棲まう者は人間に寛容なのかもしれない。
「――では、シン。単刀直入に聞きたい。なぜ争いを止めなかったんだ?
六百年も殺し合う世界なんてどう考えてもおかしい。シンには人を導く力があるはずなのに」
長い髪に隠れた少年の背中は応えず、足早に雲海を踏み進む。
「人が愚かな行いをしていたら止めてやればよかったんじゃないのか? 塔を沈めたときみたいに」
無視を決め込むシンの態度に俺は戸惑った。
まるでこちらの声が聞こえていないという風だった。機嫌を損ねるでも、肩を怒らせるでもなく、壁に向かって話しているような沈黙。行き場を失った問い掛けは俺の耳に残り、独り言の自問自答に変わる。……なぜ争いを止めないのか……。
俺は釈然としない思いを抱えながらも、これ以上の追求はやめた。
程なくシンは足を止めて、無視していたことが嘘のようにこちらに向き直る。
「ここから下を覗いてご覧」
勧められて辿り着いたのは雲海の終わり。
シンは先へ促すと俺一人を縁に立たせた。
踏み外さないように恐る恐る下を覗き込めば、宇宙から星を望む距離で外界を眺めることができた。それと同時に、シンがこの景色を見せたかった意味を知る。
「これが、俺たちのいた世界か……?」
この星は、俺が思い描いていた姿形をしていない。
あまりに奇妙な景色に目を疑って絶句してしまった。
ふわりと宙へ浮かんだシンは俺の肩に手を添えて、耳元で囁く。
「天球儀の杖で見た星の形とはまるで違うだろう? この世界は片割れを失って、半球になっている」
「片割れ……」俺は言葉を繰り返す。
確かにこの星は片割れを失っているように見えた。
まるで巨大な刃物で切り落とされたように、星の北半球がごっそりと消えていた。その星の断面に中心核は見えず、水を張った杯のように海が断面を覆い、そのまま南半球まで海面が包んでいる。
杯の水面には大陸が浮かんでおり、まだ夜に包まれた闇の中にあって延焼を続けるマハルドヮグ山脈と麓の文化圏に灯石の光が埋み火のように小さな光を灯していた。薄暗い前線の荒地は、ここから見れば月の模様に似ていた。
――星が半分しかないなんて、悪い冗談みたいだ。
昔聞いたことがある『平面説』に似ているが、外殻は球体で構成されているため少し異なる姿だ。この星の姿は何なのだろう。……と、疑問に思う俺の心を見透かしたように、シンは続けた。
「これは『渾天説』という構造だ。世界は卵の殻のような結界によって包まれ、海と空が大陸を囲んでいる。……どうだい? 君が生きていた世界と比べて陳腐だろう?」
陳腐……シンは自らが創り上げた世界をそう評した。確かに目の前に浮かぶ天体の有り様は強烈な違和感を伴うもので、本来あるべき姿ではないと感じた。閉じられた世界……不完全な世界……。
「どうして、こんな形に……失った片割れってなんだ……?」
「ときに人が『神』と呼ぶもの。『龍』と呼ぶもの。『星』と呼ぶもの。
私達は世界を循環させる三柱だ。真と理と形。この三つによって成り立っている……けれど――」
シンの言葉が切なく途切れる。少年は寄るべない迷子のように目を伏せて星を見つめていた。
「―― 私のせいで龍は失われ、星の半分も消えた。この世界はいずれ壊れる運命にある……」
「つまり、こういうことか」俺は現状を理解するため言葉を重ねる。「真と理と形……それぞれが世界を循環させるために不可欠な要素で、今この世界が不完全なのは龍が討伐されてしまったから。そういうことだな?」
シンは頷く。
「真の神。理の龍……。そして形の星……」
理の失われた世界は、星の半分を失った。
「なぜ六百年間の争いを止めないのか。これが答えだ」
俺は苦々しい思いで外界を眺める。
きっと初めこそ神と龍は人間たちを愛していたに違いない。獣人、魔人、賢人の娘を愛でるように楽園を創り上げたのだろう。
しかし、人類が数を増やし、その中から混血が生まれ、さらには翼人が現れた。天界を目指し塔を築き始めた人類を制止しようとして龍は殺された。
「翼人の過ちによって世界は理不尽が罷り通る地獄になった。傷心の神様は人類を見捨てて、真実は隠されたというわけか」
俺の言葉にシンが続ける。
「真の神と理の龍が合わさって真理となる。
真理とは円だ。どちらかを欠けば形は維持することができない。私は空と海を閉じ込めて不完全ながらに星の崩壊を留めたが、大陸は逃げ場のない戦場となった。
神を騙る愚かな翼人と、迫害からの復讐に燃える龍人、争いは災禍の渦となり……私は黄昏へ向かう世界をただ傍観し続けている……」
「こんなことになって、人が憎いか」俺は問う。
「……龍を殺す野蛮な存在となってしまった。もはや愛想が尽きたよ」
「だから傍観するのか」
「いずれにしろ龍がいなければ星の修復は叶わない。この世界は破滅に向かう運命しかない」
「だったら、何で継承者なんてものがある」
俺は新たな疑問を口にした。
修復を諦めていると言うのなら何故娘に神器を授けるのか。この介入には矛盾がある。
「思えば不思議だったんだ。『天秤』『天球儀』『柱時計』……この三つは全部はかるためのものだ。
それがなんで兵戈なのか。どうして戦士でもない娘ばかり前線に立たせるのか」
シンはこの問いに対して小馬鹿にした笑みを浮かべた。彼が初めて見せた悪意の滲む表情に俺は向き合う。
「神器はいずれも世界を形作るために用いた計器だ。壊れてしまう運命ならば私にはもう必要がない。……これがあればか弱い娘すら強力な兵戈に変わるのだから、授けることになんの不思議もないだろう」
「それなら兵士でも戦士でもよかったはずだ。それこそ野蛮な奴に渡せば望み通りに世界を壊しただろう。
でも神様はそれをしなかった。百年かけて無垢な娘を探し、世を糺す使命を背負わせたのはなぜだ」
剣呑な空気が漂い始めたのがわかる。
それでも俺は糾弾するように語気を強めてしまう。運命に翻弄され前線に倒れた彼女達の無念を思えば、言葉を抑えることができなかった。……あのとき俺がどれだけ神を恨んだことか。
「分かっていないな」シンは口角を吊り上げる。「戦う術を持たない娘を選ぶからこそ、眺めていて愉しいのだろう?」
愉しい……?
愉しいだと……?
俺は怒髪天の怒りに任せてシンの胸ぐらを掴んだ。霊体ではすり抜けてしまうかという懸念が過ぎったが、少年の身体は俺の膂力に振り回され捕らえられた。
小さくて軽い体だ。
こんな惰弱な神に彼女たちの人生は傷付けられたのか……だとしたら真実は残酷だ……。
「デレシス、ラーンマク、アルクトィス……みんな優しいやつだった。お前に選ばれなければ……っ!」
俺はシンを睨む。
視線が交差しているが、魂が瞳孔の奥へ吸い込まれる感覚は無い。
「四代目は優秀だった。彼女達が門を開いたおかげで君が現れたのだから。君を眺めているのもいい暇つぶしにはなったよ」
俺は叩きつけるようにシンを投げ飛ばした。
雲海に少年の身体が受け止められ、衝撃を逃してふわりと着地する。
脳裏では、瘡蓋が剥がれて血が滲むように、風化した記憶が色付くのを感じていた。
「思い出したよ……神様ってのは俺が嫌いで、俺も神様が嫌いだった」
人としての短い一生を終えた最後の日……瓦礫を孕んだ濁流に揉まれて息が続かず身動きさえままならない極限の焦燥と死の気配。俺は何も成せない人生を嘆き、神を呪ったものだ。
「ふむ……神殺しを望むか」シンは問いかけるでもなく呟いた。「当時とは違い、今の君は挑むことができる」
俺は拳に力を込め、指の骨が鳴る。
ここに俺がいる理由が、意義が問われている。
「四代目は俺をこの世界に召喚してくれた。五代目はここに導いてくれた。……託された願いが神殺しなら、俺はそれを成すだけだ」
虚として生きたここでの二百年。たくさんの命が俺を追い越しては消えていった。先代の継承者だけでなく、前線に倒れた兵士や神殿で語り合った神人種たち……彼らがその一生のうちに果たすことのできなかった悔恨や無念は鎧の内側に堆積している。
「神様を倒す……!」
「それでよし……!」
シンは俺が神殺しに挑むと信じて疑わない。纏う衣をはためかせて一足飛びに仕掛けてきた。対する俺は右手に意識を集中させ、望むものを召喚した。
この体に流れる血は龍の力を宿す青生生魂……。それは魂と呼応することで溶湯となり、灼熱に蕩けた金属は血管から噴き出し掌の中で渦を巻いた。
神殺しの刃に変えることは造作もない――だが俺は、この龍玉を円盤状に押し固める。
少年の繰り出した蹴りとぶつかり、じゅう、と炙る音が鳴る。シンは咄嗟に飛び退いて足の裏を雲海で擦った。俺の構えた得物を睨む。
「……盾……?」
それはまだ熱くもうもうと煙を吐き出す灼熱の円盤――
「鏡だ」
シンは俺の持つ鏡に呆然と視線を向けて立ち尽くす。先程までの殺気立つ空気は熱気によって押し流され、困惑の時間が流れる。
「私を倒すのだろう?」
「ああ」
「ならばかかってこい」
シンは両手を広げて挑発し、俺を焚き付ける。
「違うな」
「なに……?」
「ウツロとは、虚無の鏡――今さら真実を見失いはしない」
俺は冷え固まった鏡を構える。磨き抜かれた平滑な面がきらりと世界を反射して、そこにシンの鏡像が映る。
「隠しごとは無しだ」
掲げた鏡からは光が溢れ、二人は時を遡る。
❖
世界が崩壊を始めたとき、シンは崩れゆく星を繋ぎ止めるために楔を打ち込んだ。
その楔こそ人類が築き上げた塔であり、災禍戦争の始まりだった。
深々と地中に突き立てられた塔を中心に星は形を変え、半球の渾天となった……それから百年。翼人と龍人の争いは終わることはなく、シンは一人の娘に神器を与えた――
流れ込む星の記憶。
これが隠された真実。
「……神様は、戦士でも兵士でもない娘に善悪を見定める機会を与えた。これが初代の天秤だな」
目の前で再現される当時の情景を前に、俺とシンは並んで立っていた。
場面は二百年、三百年と経過する。
記憶を再現する情景では当時のシンが孤独に奮闘する姿が映されていた。神器に祈りを込め、下界の娘に託す姿は健気で、とても人類に愛想が尽きたとは思えない。
「二代目にはどこまでも逃げられる力を与え、三代目には無限の思考を与えた。……全部この世界を見直すには必要な力だ。
……あんたは天界でたった一人、世界を立て直す方法を模索していた。その手がかりを求めて下界の娘に権能を与えたんだな」
「……そうだよ」
シンは観念したように応えた。
場面は四百年が経過する。
「下界の苛烈さは増すばかりだった。だから四度目の継承者は三人揃えて戦力に余裕を持たせた。それでも前線で倒れた。翼人が制度を整え、巫力によって娘たちに使命を背負わせて前線に送ったからだ。
本来の五代目は歴史の表に出ることなく奥之院に捕えられてしまった。だから六代目は翼人より先に見つける必要があったが、一人の魔術師が次女を隠したせいで揃えるのに苦労した」
場面は目まぐるしく真実の年表を流し、現在に追いついた。鏡は血液に戻り、皮膚に浸透して消える。
「愛想が尽きたというのは嘘だな。龍と共に創造した人類を、世界を、諦めていなかった。だが崩壊を止める手段が見つけられずにいた。
だから憎まれるように振る舞い、この世界にうんざりした奴がここにやってくるのをずっと待っていたんだろう」
そうでなければ、正義よりも妹を優先するガントールに天秤を授けない。
そうでなければ、失った記憶を追い求めるアーミラに天球義を授けない。
そうでなければ、思慮深く後悔を何より嫌うオロルに柱時計を授けない。
この世の姿に異議を唱え、真理を追い求める素質がある娘を継承者に選んでいる。
例え俺でなくとも、もしかしたらガントールが、アーミラが、オロルが。或いはザルマカシムがここに辿り着いていたかもしれない。理不尽に対する恨みを携え、怒りに燃えて神と対峙していたかもしれない。
「神殺しを望んでいたのは、俺じゃなく神様だ」
俺はじっと反応を待った。
シンの思考する息遣いが聴こえる。
長い沈黙を経て、シンは口を開いた。
「……正解だ」
その口調は諦観の吐息と共に、白状するようであった。
「真と理と形……私達は自らを自らの手で殺すことができない。
私はここで、殺される瞬間を待っていた」
「神殺しをしてなんになるんだ? この世界から龍も神もいなくなれば、それこそ全部消えてしまうんじゃないのか?」
「ただ殺されるだけならそうなるね。でも、私はここに来るべき者を『継承者』と呼んでいる。私と理が創り上げた世界は壊れてしまうが、新たな真理が生まれ、形を取り戻す」
「神殺しを成し遂げた者に力を継承させるのか……そいつが新世界を創造する……」
「神の御技を持って万策が尽きたんだ。このやり方は最終手段だよ。
世界を循環させる摂理そのものが円環を巡る……この転生には受け継ぐための誰かが天界に辿り着く必要があった」
「……俺でよかったのかな」
ふと、そんな思いが口から溢れた。
異世界から来た俺は言ってしまえば部外者だ。当代継承者達を差し置いてこの世界を創造するのに相応しい人間とは思えなかったが、シンは真っ直ぐにこちらを見て頷く。
「アキラとセリナ。二人をこの世界に呼んだのは正解だった」
「二人……?」
「私が呼んだのはセリナだけ、迷い込んだ異世界人と繋がりのある娘として招き入れた。……しかし、君を召喚した者が誰なのか、今ならわかる」
「それはデレシス達だろ」
「まさか。術者の願いを私達が聞き入れなければ、亜空の門を開けることも、鎧に魂を宿すことも到底無理だよ。その上で、四代目の戦闘魔導具作成に私は関与していない。ウツロが人間だと知ったときに気付くべきだった。」
シンはそう言いながら俺の胸に手を伸ばし、心拍を指先に感じながら目を閉じる。
「ここにいたんだね」
「コトワリが……俺をこの世界に呼んだ張本人なのか?」
「他にいないだろう。
理、姿を見せてはくれないのかい?」
シンの語りかけに応える声はない……と、思いきや、俺の頭で彼女の声が響く。
――体がないって伝えてよ。
「……あー、『体が無い』だそうです」
「そうか、残念だ」
――……先に転生しないで待ってたんだからそれで充分でしょ。
「『先に転生しないで待ってたんだからそれで充分でしょ』」
――ちょっと、今のは独り言だから伝えなくていい。
「おっと、独り言だった」
シンは少し寂しそうに、けれど本心から微笑む。
きっと何よりも嬉しいことだったろう。
世界の終わりを悟ったシンにとって、コトワリが迎えに待っていてくれていたのだから。
❖
「私の願いは一つ」
と、シンは指を立てる。
「どうかこの首を切って欲しいのだ――」
真と理。
神と龍。
この二つは星を支える概念だ。失えば忽ち世界の秩序が乱れることになる。その混沌に飛び込むのが俺のやるべきことだった。
「――そして新たな世界を想像して欲しい」
「それじゃあ願いは二つでは……?」
「破壊と再生は二つに一つ。循環を君の手で始めてくれ」
シンは気安い態度で伝えるものの、両者にある生や死の価値観は根底から異なっていると感じてしまう。本来不滅の存在であるシンにとって死は怖く無いのだろうか。
「循環といえば『転生』と言ってたな。死んだ後にまた会えるのか?」
「……君たち生命と僕ら概念は構成するものが違うから、また会える保証は無い。人として生まれるのか、宇宙の法則の一つに加わるのか、先のことはわからない」
――神のみぞ知るってことだね。
コトワリが言い添える。
「……そうか!」
それはつまり、次の真理となるものに采配が委ねられるということか。
ならこの別れは、必要な儀式でしかない。俺が創る世界で二人が穏やかに生きられるように、願わずにはいられない。
……いや、二人だけじゃない。誰も悲しむことのない新世界秩序を俺は創造する。してみせる。
「よし、……やるか」
覚悟を決め、俺は手の中に鏡を呼び出し両手で構えた。正面に立つシンの姿を鏡面に映す。
「私の最後を見届けたら君は下界でもう一度目覚めるだろう。アーミラによる受肉は完了し、同時に世界の崩壊が始まる。君は神と龍――真理の権能を行使して星を繋ぎ止めてくれ」
「両方俺が継ぐのは荷が重い気がするが」
「相応しい人間がいるならどちらかの継承権を譲ってもいい」
「……まぁ、出たとこ勝負だな。やるだけやるさ」
「期待している」
緊張を隠しているせいか淡白な言葉の応酬が続くものの、互いを信頼する絆は確かにあった。
時を同じくして、同様のやり取りが精神世界でも行われていた。
――……今更だけど、ありがとね。
彼女の言葉が、意外なほど優しく響いた。
いつもの皮肉めいた調子はなく、ただ静かに感謝を告げる声。
コトワリと過ごした二百年――長いようで、一瞬だったような時間。
「らしくないな」
鏡を構えていた俺は彼女の様子が気になって顔を覗きみる。そこには毒気のない少女のはにかむ笑顔があった。
「コトワリが理の龍だって未だに信じられないな。前線で戦った龍とはまるで違う」
――君の妹と似たようなものだろう。とはいえ姿なんてものは有って無いようなものだけど。とにかく、お礼ぐらいは言いたいんだ。……君を鎧に閉じ込めた二百年、相当に無理をさせたと僕は思ってる。最後には僕もシンも恨まれながら消えることも覚悟してた。
「だからシンは俺を焚き付けていたのか」
――殺される覚悟だったんだろうね。でも君は手を差し伸べてくれた。その優しさを心から尊敬しているよ。
まっすぐな言葉に、俺は頬が赤くなるのを自覚して鏡に隠れた。
「俺の方こそ、……ありがとう。
コトワリは俺に、何かを成し遂げる人生をくれた。俺の孤独を支えてくれた。コトワリがいなかったらここには辿り着けなかったよ」
――へへ、照れくさいね。
「まったくな。……よし。始めるぞ。最後の転生を」
シンとコトワリはこくりと頷き、鏡と向き合う。
握る力を込め、鏡にはぴしりと横一文字の罅が走る。
鏡に映るそれぞれの首にも裂け目が生じる。
「さらばだ。ウツロ」
シンは別れを告げる。
――さよならだね。
精神世界でもコトワリが手を振る。
鏡が割れ、二人の断ち切られた首からは眩い光が迸る。
別れの余韻に浸る間もなく天界は消滅し、俺の体は雲海をすり抜け落下した。
❖
「は……っ!?」
その男は、神殿奥之院最奥に描かれた魔術陣の中心で意識を取り戻した。
見開かれた瞳の色は黒く、二つの穴が開いているような、鎧の頃の面影を残していた。
彼は放心したように天井を見つめ、膝を寄せて心配そうに見守っていたアーミラに力強く抱き締められる。
「ウツロさん……!」
「あ、アーミラ……」
圧迫感と彼女の体温に戸惑いながらも、彼はそっと手を回す。そして抱きしめ返そうとした自分の腕を感慨深そうに見つめている。
「いや、今はアルミリアなのか……」
「アーミラでいいです。……よかった……記憶がちゃんとある……」
碧眼の双眸は感極まった涙に濡れる。
それを眺めていた仲間たちも胸を撫で下ろし、どうやら魔術陣が求めた結果を齎したと理解する。その苦労を知るセリナとザルマカシムは内から湧き出る歓喜を噛み締めた。。
「これが真の姿か、ウツロ」
ザルマカシムは一糸纏わぬ彼の姿を眺め、自身の外套を脱ぎ渡した。
「汚れちまってるが、とりあえずはこれを着てくれ」
「ああ、ありがとう」
獣人の体躯を覆う外套の丈は彼には大きく、これ一枚で全身を隠すには事足りた。
「二百年ぶりの体はどんな気分? 兄貴」
彼は指を動かし、拳を握った。
骨が鳴る。皮膚が引き攣る。
――喉の奥で息を吸い込むと、鼻の奥がつんとした。
「臭いと、熱を感じる……」
惚けたように呟いた彼の言葉に、アーミラは恥ずかしそうに距離をとった。ただでさえ道中で汗をかき、泥と血に塗れた衣服だ。アーミラは顔を赤くして恥じらっていた。
「それが人間だよ」
セリナはくすりと笑う。
「人に戻ったのなら、兄貴はどっちを名乗るの? ウツロ? それとも慧?」
「わからない。そもそも戻ったと言えるのか……」
外套の袖に腕を通さず、羽織るようにして身に纏うと彼は告げる。
「皆……悪いがまだ終わってないんだ」
その言葉にカムロの眉が跳ねる。
「終わってないだと?」
「ああ。これから世界が崩壊する」
彼の言葉を証明するように、足元は俄に揺れ始める。
微かな余震に最奥はかたかたと石材を鳴らし、すぐに大地そのものがうねり、地鳴りを響かせる。立っていられないほどの強い揺れに勇名たちは思わず悲鳴を漏らす。このまま地下で生き埋めになるのではないかと背筋を凍らせ、本能的な恐怖に目を丸くしている。
「山が、震えている……!?」
「このままじゃ噴火するか……」彼は裸足で床を確かめ、外へ駆け出そうとする勇名に声を上げる。「部屋から出るなよ! 全員外に運ぶぞ!!」
「そんな、部屋から出ないで外に行くって、どうやって!?」足止めされた勇名は声を荒げた。
「こうやってだ」
外套から腕をさらし、彼は念じる力で最奥を押し上げた。詠唱も術式も用いずに発動したことに誰もが絶句した。
硬い地層を押し砕きながら最奥は上昇を続ける。この魔術は誰の仕業か、ザルマカシムとカムロは互いに首を振り、アーミラの方を見た。当然アーミラも否定する。
ザルマカシムは信じられないという顔をした。顎髭を撫でつけ、彼に視線が釘付けになる。
鎧姿のときには魔呪術を使う素振りがなかった。使えるとも思えなかったが、人の姿を取り戻しこれほどの術を使えるようになったのだろうか。
「異世界人のお二人は強力な魔呪術が使えると……?」
カムロの早合点を彼は訂正する。
「いや、使えない」
「ですが、セリナ様も尋常ではない強さでしたよ」
「本来なら俺もセリナも魔呪術の才能はない。これは……特別な力だ。後で説明する」
「ちなみに私のはただの龍体術だよ」と、セリナは呑気に言う。
「『ただの』で片付くものでもないが……頂上に出るぞ」
彼の言葉通り、部屋は地下構造を抜けて外へ出た。
瓦解して壁の取り払われた最奥はもはや石畳のみとなり、横から射し込む朝日に目を焼かれる。
神殿外廓の向こうには太陽が頭を覗かせていた。
待ち侘びていた終戦の夜明け。
待ち侘びていた暁は空を朱に染め、地鳴りの響き渡る世界を不吉に照らしている。世界は今まさに崩壊が進んでいた。
まるでこの世の終わりのようだった。
「何が起きてるんだ……」
光芒を遮るように手をかざし、麓の状況を見下ろしていたガントールは異変に気付いて指をさす。スークレイも只事ではない変化を認める。
「あれは……!」
ナルトリポカの方角、大地には巨大な裂け目が生じていた。
地割れはいたるところに現れ、まるで星が砕けるような恐ろしい光景が広がる。もはや彼の言葉を疑うものはいない。
「なあウツロ、一体何がどうなってる……!?」ザルマカシムはたまらず駆け寄る。
「このままじゃ世界が……、マーロゥの陣を使ったからですか……?」カムロはアーミラに対して術に間違いがなかったか問い質していた。
「私は書き換えましたよ……!」
「相当に複雑なものでしたよ……なにか、見落としていた可能性は……」
「そんなはずは……」
応えるアーミラの目に不安が兆す。マーロゥの遺した陣は確かに世界収束の術式、手違いで異変が起きたという可能性を否定できなかった。
「違う」彼は断言した。「アーミラのせいじゃない」
「ウツロさん……」
「誰のせいでもない。必要な儀式なんだ」
「必要な儀式……?」カムロは戸惑いの視線を向けた。
彼は超然とした佇まいで不安を受け止め、案ずることは何もないと腕の中に鏡を呼び出す。そして鏡面からは神器が飛び出し、ごとりと鈍い音を立てて石畳に転がった。
「「……神器!」」オロルとガントールの声が揃う。
天秤、天球儀、柱時計と順に呼び出し、最後に出てきたのは鎧の腕だった。
地面に指を這わせ、輪を潜るようにぬるりと顕現するとそのまま跪く。手には斧槍を握っていた。
「ウツロが、二人……?」ザルマカシムの声が動揺に震えている。
「真理だ。虚の鎧と慧としての俺……それぞれに力を継承している」
「う、えっと、アキラ、さん……鼻から血が出てます……!」アーミラは彼の鼻を指さす。
「え――」彼は親指で鼻血を拭い、啜って誤魔化す。「とにかく大丈夫だから」
「……大丈夫とは思えんが……」
オロルの指摘に彼は困ったように笑って見せた。その表情にアーミラは胸が苦しくなる。アキラさん……無理してる……。
「本当に大丈夫なんだ。誰も死ぬことはないから」
「どうしてそう言い切れるんですか……?」
心配そうに問うアーミラに対し、彼は気丈に応える。
「俺は真理を手に入れたんだ。神と龍の力、二つがここにある。世界を創造できるとんでもない力だ。
先ずはこの力で、崩壊による怪我や死亡は全て無効とする」
力強く宣言する。その彼の背に鎧が凭れ掛かり、蕩けるように板金が形状を変えた。冠に似た頭角と身の丈を超える黒鉄の翼が揃う。
「んな……無茶苦茶な……」
ザルマカシムは人智を超えた姿に圧倒されて言葉が続かない。
言っていることも、やろうとしていることも、その姿も――全てが人の理解を超えている。
彼は腕を伸ばし、その手に神器を掴む。三種の神器に対して腕二本では足りないと気付けば鎧の腕を二本背中に追加した。天秤剣と天球儀をそれぞれ握り、自身は斧槍と鏡を携え、後光のように柱時計の八本脚を展開する。その姿は人を超越に、異形の存在そのものだった。
「……あはっ」
誰も口出しできないような物々しい状況で、不意にセリナが笑い出す。
「いよいよ化け物じゃんか」
あえて口に出さなかった言葉をセリナは言った。
そこは兄妹、ウツロも機嫌を損ねることなく眉を困らせる。
「ごめん……正直慌てて」
彼の気弱な返答に、むしろこの場に集まる者たちは安堵した。姿はどうあれ、少なくとも精神は人のものだと感じさせるものだ。
「まぁ、兄貴らしいか」セリナは背中に隠していた翼を広げる。「心配だから私も手伝うよ」
「セリナ……」
ウツロはセリナの瞳を見つめ、その覚悟を見定める。
「……そうだな。手を貸してくれ。
実はこれから世界を作り替えなきゃいけなくてさ」
――これから世界を作り変える……?
そんな言葉を聞いて、アーミラは思わず鎧の手を掴む。
「あ、あの……ウツロさん……私も手伝います……!」
「アーミラ……」
「私は、ずっと争いのない世界を求めていました……っ! お願いです! 私にも創造の力を……!!」
その目は真っ直ぐにウツロを見つめる。その覚悟は本物だった。
しかし、ウツロは首を横に振る。
「疲れているだろうからアーミラは待っていてくれ」
「……えっ、でもセリナさんは――」
ウツロは一度翼を閉じてアーミラの側に歩み寄ると、手を包むように握る。
「『使命』なんてもの、これ以上アーミラに背負わせたくない。だから見ていてほしい」
――からなず期待通りの世界に変えてみせるさ。
アーミラの右耳に囁き、彼は優しく微笑むと天高く飛翔した。
❖
真理は消え去り、形もまた崩れ去る。
これまでの世界は終わり――そして新しい時代が始まる。
避けた大地は空に浮かぶ島となり、その向こうで人類は黎明の訪れを見た。
不吉に輝いていた太陽は悪夢から目が覚めたように澄み渡る青空を照らし、この世の終わりに怯えていた早朝の街の一隅、震えていた母の腕で赤子は彗星を指をさした。
明けの空を駆ける流れ星……長く尾を引く天体はいつかカムロが占星術によって導き出した破滅を知らせる彗星である。その彗星と影を重ねるように、ウツロとセリナは降臨した。
カムロが頭を悩ませ続けていた天体は、来たる聖者の到来を示す。
「……で、ついて来たけど、こんなところで何するの?」
セリナは彼に問う。
眼下に広がる大穴は歴史に因縁深い禍人領の根城……翼人が築き、神によって沈められた塔が静かに口を開けている。
「こいつを抜くのにセリナが必要だと思ったんだ」
「こいつって……」セリナは流石に正気を疑わずにはいられない。「引き抜けるものなの……?」
「神が言うには、この塔は楔なんだ。世界を繋ぎ止めるための楔……」
「だったら余計に抜いちゃ駄目じゃん」
「いいや、作り変えるには邪魔だ。……それでこれは相談なんだが」
彼は口籠って斧槍を手遊びにくるくると回す。
「神と龍の力を受け継いだってさっき言ったけど、独り占めするには荷が重くてさ。どちらかをセリナに譲ろうと思ってる」
セリナは腕を組み、片眉を吊り上げた。兄がなにか思い悩んでいるとは思ったが、そういうことか……。
「私は龍がいい」
「そんな簡単に決めていいのかよ」
「だって神って柄じゃないし、私の見た目ならどう考えても龍でしょ」
「そうじゃなくて、龍になったらこの世界の理を司ることになってだな――」
「兄貴を」セリナは彼の言葉を遮った。「お兄ちゃんを一人にさせない」
「……そう、か」
腑に落ちたように彼は息を吐く。
「セリナならそう言ってくれるんじゃないかって期待してた。だけど言わせてくれ。ありがとう」
「アーミラじゃなくてよかったの?」
「アーミラには、穏やかに過ごしてほしいんだ。辛い経験ばかりで、これまで使命ばかり背負わされていた。自分の人生を生きてほしいって思ったんだ。
いや、セリナにも当然同じことを思ってるけど」
「好きなんだ?」
「え、――」
「アーミラのこと。好きなんでしょ」
セリナはにやりと笑い、意地悪な視線で兄を誂う。
「そうだよ……! もういいだろ、始めるからな」
彼は受け継いだ真理の片方をセリナに渡し、神器を二つを預けると兄妹の息を揃えて旧時代の楔を引き抜いた。
この世界に招かれた兄妹は、空の器だった。
兄は肉体を持たず、虚の鎧として。
妹は希望を持たず、龍の娘として。
器は人々の祈りで満たされ、奇跡は起こる。
破壊と再生を繰り広げる星は失った半球を取り戻し形を変える。そのうねりによって大陸と海は手を取り合って踊りだした。空は七色に輝き、歌うような風が吹く。
新世界創生の最中、神は内から湧き出る歓びに相好を崩し、一つの詠唱を口ずさんでいた。
"If I could reach the stars"
〈もしも星々に手が届くのなら〉
"Pull one down for you"
〈君のためにひとつ手に取って〉
"Shine it on my heart"
〈輝きで私の心を照らしてみよう〉
"So you could see the truth"
〈そしたら真実が見えるだろう〉
"That this love I have inside Is everything it seems"
〈私の内側に愛が宿っているということ〉
"But for now I find It's only in my dreams"
〈まだそれは夢の中にしかないのだけれど〉
"And I can change the world"
〈世界を変えようと思うんだ〉
"I will be the sunlight in your universe"
〈宇宙を温める太陽になって〉
"You would think my love was really something good"
〈そしたら君はきっと微笑むだろう〉
"Baby, if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
"If I could be king"
〈もしも私が王様になれたなら〉
"Even for a day"
〈それがたった一日だとしても〉
"I'd take you as my queen"
〈王妃には君を選ぶよ〉
"I'd have it no other way"
〈他の誰でもない君を〉
"And our love would rule In this kingdom we have made"
〈そして二人が興した王国には愛が溢れるのさ〉
" 'Til then I’d be a fool Wishing for the day"
〈そんな時が来ることを愚直に祈り続けている〉
"And I can change the world"
〈世界を変えようと思うんだ〉
"I would be the sunlight in your universe"
〈宇宙を温める太陽になって〉
"You would think my love was really something good"
〈そしたら君はきっと微笑むだろう〉
"Baby if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
"Baby if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
"I could change the world"
〈世界を変えてみせるよ〉
"I would be the sunlight in your universe"
〈宇宙を温める太陽になって〉
"You would think my love was really something good"
〈そしたら君はきっと微笑むだろう〉
"Baby if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
"Baby if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
"Baby if I could change the world"
〈世界を変えることができたなら〉
❖(『Change The World』歌詞引用。翻訳は作者の独自解釈のもの)
「……あ……」
天変地異により標高を下げた旧マハルドヮグ山の小高い丘にアーミラはいた。彼女はウツロとセリナが行っている新世界の創生を見つめ続け、ある程度大地の狂乱が収まると空を見上げた。そして空に揺れる極光を見つけた。
「七色の帯……?」ガントールとスークレイ、双子の瞳はそれがなにか分からないままに目を奪われている。「綺麗だ……」
「これは……オーロラって言うんですよ。星の極域でしか見られない、大気の発光現象……」アーミラは得意げな顔をして言う。
「これは魔術じゃないのか?」
「はい。虹や雷のような自然の現象だそうです。とても珍しく、姓の由来なのだと、昔お師様から聞いたことがあります……」
アーミラは万感の思いで極光を見上げる。なぜだかその揺らめく光を眺めていると、隣にマナが寄り添ってくれている気配が感じられた。
「一度見てみたいと思っていました……」
それはアーミラに微笑むように優しく輝いて溶けていく。
一方で、オロルもまた彼の幻を見る。
一度目の人生では辿り着けなかった終戦の、思いがけない祝祭に年相応の無邪気な笑みと苦節に報いる涙をこぼした。
「……フリウラ……」オロルは幻に向かってそっと声をかける。
吐息で消えてしまうのではないかと思うほどに儚い彼の姿に、言葉が詰まる。積み重ねた歳月があまりにも多すぎる。
「わしは、報われたのじゃろうか……? この奇跡を前にしても、悔いは消えてはくれぬ……。お主のいない世界を生き続けることの後ろめたさは、きっと消えんのじゃろうな……。
じゃがのぅ、それでも……今日が美しいと思える」
オロルの流した一筋の涙は頬紅に滲み、白衣に染み込んだ。
彼の幻は微かに頷いて、風に流されて消えていった。
セラエーナは極光を見上げる首に疲労を感じて視線を落とす。そして側に座っている姉の脚が新しく生え揃っていることに声にならない驚きの叫びを上げた。
「ね、姉さま……っ、足が……!」
「そういえば妙に痒い――あれ……」
ガントールはまるで夢のようだと、自分の足を凝視して、裸足の指を動かしてみる。神経が通った綺麗な足が揃い、姉妹は飛び跳ねて抱き合った。快活なガントールの笑い声が響く。
いくつもの夜を越えて、奇跡に満ちた朝が訪れた。
ザルマカシムはカムロと共に天変地異を見守っていたが、新世界の美しさに警戒する気持ちも萎え、心配しても無駄なのだと笑みを見せる。肩の荷が下りた、二人穏やかな微笑みだった。これからの世界に種族の壁は存在しない。手を繋ぎ、唇を重ねる二人を囲って勇名の仲間達は口々に祝福の言葉を述べた。
奇跡は神殿だけにとどまらない。
旧ナルトリポカでは光の波が大地を駆け抜け、石畳が熱を帯びたかと思うと、突然、湯気が立ち上った。
温泉が噴き上がり、人で溢れていた街道は優しい雨に打たれる。太陽は黄金色に大地を照らし、全てが輝いて見える。
アダンとシーナは、星が祝福しているのがわかった。
「この輝き……ねぇ、アダン……!」
「ああ、きっとそうだ。アーミラはやり遂げたんだ!」
旧スペルアベル平原は創生により豊かな森に変化していた。
目の前で木々が生え、次から次へと空へと伸び幹を太くする。木陰からはどこから現れたのか動物たちが現れる。
神がかりの光景を目撃して呆然としていたイクスに、色とりどりの蝶が戯れる。
「幻術……? どうなってるの?」
ナルが袖を掴み、手で扇いで蝶を追い払う。戯れる蝶はひらひらとナルの周りを舞い、気ままに森を飛んでいった。
「いや、心配ないだろう」
ニールセンとセルレイが邸から出て空を見上げる。
「ウツロがやってくれた。……そんな気がする」
長く暗い黎明の終わり。
暁の射す新世界の始まり。
球形を取り戻した星は果てしなく広がり、様変わりした世界は希望に溢れていた。
翼を広げて舞い戻る彼を、アーミラは満面の笑み抱きしめた。
「始めまして、アキラさん。
そしておかえりなさい。ウツロさん」
❖
爾後。
終戦に導いたアーミラはアダンとシーナのもとへ向かった。
胸を張っての帰還だった。
異世界人の兄妹が創生したという事実は生き残った人類には知る由もなかった。その事情を理解できるように語るには時世が悪く、焦眉の急新たな世界には新たな秩序が求められた。それは兄妹が受け継いだ真理とはまた別の、人の心の拠り所としての秩序――つまりは法が求められたのだった。
アーミラは翼人の負の遺産を旧時代へと全て濯ぎ落とし、全く新しい国の勃興に際して戴冠を丁重に断った。終戦に導いた功績を認められても、翼人の血を引く己の身を秩序の中心に据えることは否定的だったのだ。並びにセラエーナもまた帝政国家の樹立には反対の姿勢を示した。
その代わりに玉座にはオロルがついた。島嶼卜部族の産まれから三女継承、前線出征を経ての大出世である。
オロルは戦時に切り落とされ、まだ生えたばかりの綺麗な手に傷が付かぬようにと手袋を装着し、新たな建国の事業として新酒の醸造に取り掛かった。市民からは、はじめは『浮かれた君主』だと受け取られたものの、争う敵国の存在しない時代の到来において、我先に平和な時代を楽しむオロルの姿は人々の不安を大いに和らげた。その王の右、騎士団長の地位に収まったのはガントールで、方や宰相にはスークレイが就任した。
旧マハルドヮグ山脈は沈下して海に沈み、当時の威光は海底の遺跡となっていた。過去のあらゆる文献や歴史書は消失し、陸地を残すナルトリポカに都が移されることとなった。
街はどんなものでも入り用で復興に忙しい。商人は天秤を前に互いの利益分配を語り合い、朝も夜も活気に満ちている。人々の生活は、少しずつではあるが、平和というものを実感し始めていた。
戦争のない世界。災いの渦が消え去った日々の中で人々の関心は新たな景色へと向けられていた。それは健全な欲求――知的探求心の萌芽であった。
旧アーゲイ、まだ土地の名も決まっていない港の遺構を元に再建された船着き場にて。
よく晴れた秋の空。大海原には一隻の船が係留していた。
その船はまだ見ぬ星の裏側、人類未踏の大陸を目指し、新たな地図を描き始めようと船出の準備が着々と進められていた。この船乗りの一人にアーミラはいた。彼女は天球儀から羅針儀に持ち替え、希望の海原を望む。
――そう、アーミラはまたも旅立とうとしていた。
しかし、今の彼女は根無し草ではなかった。帰りを待つ家族ができたのだ。
「もう、まだゆっくりしてても誰も怒らないだろうに……」
シーナは不満げに頬を膨らませてみせたが、荷造りに忙しいアーミラは気にもとめていない。シーナの方も内心では理解していた。この娘は一処に留まるような質ではないのだと。
「なんだがじっとしてられないんです……わくわくして、眠れなくて」
「そんなんじゃ船でへばっちまうぞ」アダンが工房から口を挟む。「世界地図を描くんだろう? 忘れ物はするなよ」
「わかってますよアダン」アーミラは工房に届く声で返事をする。
紙や蝋燭、仕事道具で膨らんだ鞄を肩にかけて、アーミラは部屋を出る。慌ただしい足音が廊下を横切り、アダンとシーナが玄関で見送りに立つ。
「帰ってくるのはいつになるの?」
「一年はかかると思います」
「じゃあ、帰ってくるころにはお姉さんだな」アダンは言う。
「……え、それって……」
シーナは照れ臭そうお腹をさする。
夫婦の間には新しい命が宿っていた。
「シーナさん! わぁ、隠してたんですか……!?」寝耳に水だったアーミラは口元を押さえて目を輝かせる。「気付きませんでした……」
「驚かそうと思って」シーナは悪戯っぽく笑う。「アーミラもウツロさんと仲良くね」
「アキラさん、アキラ・アマトラですよ」
「噂をすれば、ほら迎えが来たよ」
シーナは背中を叩き、アーミラを送り出す。
「では、行ってきます!」
――これが、空白の歴史の真実。
黄昏に光を齎した女神アーミラの物語である。
❖終幕❖
■017――塔
❖❖最後の異世界転生譚❖❖
――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
長い長い物語を隠者が語り終えると、青年は没入していた意識が我に帰るのを感じた。あたりはすっかり夜が明けて、白い砂浜は穏やかなゆりかごのように波が押し寄せては余韻を残して引いていく。繰り返す潮騒の音を聞いているうちに少しずつ現実に心が馴染んでくるのがわかった。
自分は眠りに落ちていたのだろうか……青年は呆けたような、奇妙な体験をしたとでも言いたげな顔をして隠者を見つめる。
「……本当に見てきたみたいな臨場感だった……」
青年は言う。見開かれた目が感動を伝えていた。
「そうだろう」
隠者はさも当然のことのように応える。しかし青年の興奮は収まらない。
「すごく長い話だったはずなのに眠りも忘れて全部聴いてた……本当に物語の中に入ったみたいだったんだ……! 信じられないよ、聖書や神話なんてこれまでまともに読んだことなかったし、きっと途中で寝ちゃうと思ってたのに!
本当に、街で聞いたどんな吟遊詩人の話より、ずっと面白かったよ!」
「そうか、お前さんが満足してくれたんならよかった」
隠者の満更でもない反応を気にすることなく、青年は深く息を吐いて島を見渡す。目に映る全てが様変わりして見えた。
空白の歴史。
紀元前の出来事。
それがなぜ空白だったのか、どうしてアウロラ写本は未完の神話と呼ばれるのか。悉皆の疑問に答える隠者の語りは千夜一夜の物語か、全てが繋がった感覚はまるで神の啓示を授かったような目覚めの体験だった。
眼前に広がる海も空も、新しい神によって創られたものなのだ。――青年は語られた物語が真実だと疑わない。そして島に屹立する塔を見上げ、畏敬の念を覚える。それは死の島と呼ばれるこの場所に対する漠然とした恐れとは異なるもので、立ち塞がり睥睨する無口な塔が、その沈黙に込めた雄弁な言葉を感じ取ることが出来たからだ。今ならばわかる。
「この塔って……もしかして……」
「お前さんの考えてる通りだ。だが今は転換炉になってるから上に登ることはできない。もちろん天界にも繋がっていないさ」
「じゃあ神と龍になった二人はどこに行ったんだろ……」青年はある考えが思い浮かぶ。「まさか――」
死の島に棲まう魂を喰らう龍の噂はやはり本当だったのではないか。そして空白の歴史を知る隠者こそが、神。
そのような考えに至った青年は息を呑んで隠者を見つめる。対する隠者は、その視線を疎ましく思うような素振りで視線を下に向けて、すっかり灰になった流木の塊を指先で砕いた。
「初めに言った通り、この話を信じるかどうかはお前さん次第だ。『死の島にいる怪しい男がこの世界の創造主だ』と人に話したところで誰も信じない」
「でも俺は信じてる」
「俺が異世界から迷い込んだように見えるか? 二百年間鎧の姿になって、その後神として二千年生きてるなんて、常識じゃない――」
自嘲する隠者の声を遮って青年は答える。
「俺には見える」
衒いのない正直な言葉に隠者は面食らったように目を丸くして、それからくつくつと笑う。
何がおかしいのかわからない青年は、なんだか騙されているのではないかというふうに思い始める。……夜通し語られた物語の壮大さを間に受けて、大掛かりな隠者の悪い冗談に踊らされている気がしてきた。
「笑うなよ」
「とにかく、もう朝になったんだ。お前さんを送ろう」
己が神かどうか、答えをはぐらかした隠者はやおらに立ち上がり、浅瀬に浮かべた舟に青年を乗せて本土へ向かう。
海原は穏やかで艪を手繰る水音が耳に心地よい。遠くでは長閑に海鳥が鳴いている。
「あの物語は結局作り話なのか?」
舳先に腰掛けた青年は、艫に立つ隠者の方を振り向かずに聞いた。その問いは海に訊ねているようにも見えた。
「……アウロラ写本の改訂は過去にも何度か行った。だが、この話を加筆することはなかった。これからも可能性は低いだろう」
「それはどうして?」
「聖書と呼ばれているからだ。写本は多くの人に流布され読まれることになる。新世界秩序を打ち立てた立役者が別の世界から来た人間だったなんて、そんな文言は法王の目玉が飛び出るぞ。
お前さんも誰かに広めようなんて馬鹿なことはするなよ」
「そんな……! 話したくてうずうずしてるのに」
「だめだ。さっきも言ったが、お前さんが話しても誰も信じない。それどころか異端扱いされかねないし組合にも目をつけられる。碌なことにならんぞ」
青年は心底悔しそうな顔で隠者に訴えるが、隠者は首を振るだけだった。
「せっかくの土産話だと思ったんだけどなぁ」
❖
本土に着くと隠者を出迎える者がいた。
おそらく彼らは物見台から舟が向かって来ていることを事前に把握していたのだろう。若者の一人は手に小さな望遠鏡を持っていた。
青年はかなり気後れした。なぜなら、船着場に人集りを作っている者たちが身なりの整ったいかにも身分の高そうな姿であるからだ。しかし隠者が舟を出したのは他でもない自分のためであるから逃げも隠れもできない。縁に隠れるために寝そべるのも憚られるので、じっと置物のように座り、息を潜めた。
そんな努力も虚しく、彼らの一人が舟に座っている青年に気付くと驚いた顔をして会話の身振りが大きくなるのがわかった。青年が思っていた以上に海に落ちて行方不明になったことは大事になっていたようで、隠者がここに来た理由を察したであろう何人かは舟の到着を待たずに踵を返し、急ぎ足で街の方へ走るのが見えた。青年は気まずさにますます縮こまる。
舟は桟橋に沿うように係留され、慣れた手つきで隠者は綱を結んだ。
「出迎えが多いな……」
隠者は独り言を呟き、桟橋を渡って来ようとする者をやんわりと手で制すと青年を置いて自ら陸地へ出向いた。大人たちは指示通りに舟には近寄らず、桟橋を降りた隠者を待ち受けて囲み、各々が礼儀を尽くして挨拶を交わす。青年に会話が聞こえないところまで遠ざかりると隠者は歩みを止めて彼らの相手に忙しくなる。
一方で、別の所から一人の女が船着場に向かってきていた。隠者を囲う人集りを気にも留めず、むしろ手薄になったところを狙っていたかのように真っ直ぐ舟に進み、桟橋をずかずかと歩いて来る。腰元には鞘に収めた刀を携え狼の尾のように揺らしていた。
隠者の目はちらりと女を見咎めていたが、青年の元へ向かうことを黙認した。
「君、……そこの少年」
呼びかける声は微かに怒気が込められているような威圧的な響だった。女は追い詰めるように桟橋の真ん中を歩き、逃げ場のない青年を睨み下ろす。
「岐・テウルギア!」
「は、はいっ!」
膝を抱いていた青年は冷や水を浴びせられたように背筋を伸ばして応える。
「無事か?」
低く芯の通った声音で女性は訊ねるので、青年は頷く。
見覚えのない女性……だがこちらの名を把握している。この人は何者なのだろうと青年は考える。
「踏査組合の者だ。学園に依頼されて行方不明の生徒の捜索をしていた。お前がクナトで間違いないな?」
気の強そうな大人の女性に圧倒されつつ、青年はなんとか声を絞り出す。
「はい」
「死の島に流れ着いていたそうじゃないか。離岸流に乗って運ばれたのか知らないが、普通は泳いで行ける距離じゃない。ともかく運が良かったな」
励ますような言葉ではあるが、女性の声は冷淡に聞こえた。……それもそうだ。丸一夜かけて捜索してくれていたのだろうから、疲労から不機嫌にもなるだろう。青年は素直に頭を下げた。
「ご迷惑をお掛けしました」
「全くだ。捜索願いを出されてから四日、もう生きてはいないと思っていた」
「え――」
青年は耳を疑い、女を見上げたまま思考が固まる。
「――……四日……?」
島で過ごしたのは一夜だけのはず。多少記憶が曖昧なところもあるが、一睡もせずに長い物語を聴きながら夜を明かしたのだ。それとも海に落ちてから島に流れ着くまでに三日間気を失っていたというのか……青年には分からなかった。
動揺した表情を見て女は訝しんだが、後方から足音が聞こえて振り返る。
こちらにやってきた人物は隠者を囲む輪から一人先んじて抜け出した老齢の男であった。杖をつきながら一歩一歩桟橋を進む姿に女は微かに口角を吊り上げ、青年は対照的に苦虫を噛み潰したような顔をした。……学長だ。
「……叱られたまえ」そう言い捨てて女性は立ち去る。すれ違うときは織り目正しく一礼し、学長は軽く手を振って応えた。
女の背中を青年は目で追いかける。聴きたいことはまだいろいろあったのだが、彼女の後ろ姿は月蝕のように学長に遮られてしまう。
「クナト君。まずは無事で何よりだ」
❖
青年と同じように、桟橋から遠ざかっていく女の姿を隠者も眺めていた。しかしながら、その視線に込められた想いは全く異なるものである。
腰元で揺れている帯剣の装備を賢しげな目で見つめ、船着場の外へ続く石段を登る背中を見送って姿が見えなくなると鼻を鳴らした。隠者らしからぬ邪険な態度には理由があった。
鞘に収められた刃はよく研がれた本物の武器だ。
この平和な時代に似つかわしくない代物を踏査組合は当然のように身に付けている。青年のような若者はきっと、彼女のような生き方に憧れを抱くだろうが、隠者には不愉快でたまらないのだ。
既に出迎えの者達との挨拶を終え、もののついでと帰りの舟に霊園行きの棺を乗せることとなった隠者は、人心地ついて係船柱に腰を落ち着かせて青年と学長を眺める。訥々と理詰めで叱る学長に背を丸めて悄気ているのが見えて口角を吊り上げる。経緯はどうあれ海に落ちてしまったのは青年の責任だ。反省してもらう他ない。
やがて説教も終わり、駆けつけた仲間に手を引かれた青年は桟橋を後にする。
別れの言葉もなく立ち去ろうと思っていた隠者に対して、青年は探すように船着場を見渡し、隠者を見つけると大きく手を振った。残された舟の方には教会の者が乗り込み、棺を積む作業に取り掛かっていた。
手を振りかえす隠者の後ろから声が掛けられる。
「改めて、うちの生徒がお世話になりました。アマトラ殿」
杖に両手を乗せて、学長は隠者の横で青年の背中を見送る。
「思っていたより説教が短かったな」
学長の白い髭の奥に隠された口が笑う。
「貴方からの口添えがありましたのでな。とはいえ親からはたっぷりと叱られることでしょう。
ところで、あの事件についてはご存知ですかな?」
「あの事件?」
「ここ最近、妖精が姿を消しています」
初耳だと、隠者は顔を向ける。
学長は続けた。
「あくまで噂話に留めておいて貰いたいのですが、一説によると殺してまわる何者かの存在がいるようです。言葉通りの『妖精殺し』ですな。
アマトラ殿もどうかお気をつけて」
「俺が気をつける意味とは」
「アマトラ殿には要らぬ心配かも知れませんが」学長は毛の長い眉を吊り上げて伺うように隠者を見上げる。「『霊園の管理人は不死である』……この秘密を知られれば、妖精殺しはやって来るやも知れません」
「不死性を持つ者を狙っている。か……」
「とはいえ妖精殺しはあくまで噂。重要なのは妖精が姿を消しているという事実です。何が起きているのかは教会も組合も総出で調べております」
学長の言葉に得心がいった隠者は眉を開き石段の方に顔を向けた。とうに女の姿はないが、大手を振って帯剣している理由は察せられた。
「踏査組合の女が刀を持っていたのは警戒していたからか」
学長は頷く。
❖
霊園に戻る頃には昼を過ぎていた。
砂浜に舟を打ち上げ、艪を片付けた隠者は疲れた手を揉みほぐして瞼を押さえた。海原に乱反射する光に視界が焼けてしまったのを暗闇で癒す。
じっと立ち尽くす隠者の向こう、突然島の岩肌が持ち上がる。
樹々の枝を押しのけて現れたのは龍の首だった。それはまるで、高い塔がもう一基そびえ立つようである。
がらがらと石が転がり落ちる音にも隠者は反応を示さない。まるで聞き慣れた生活音の一部であるかのよう。……事実、彼にとって龍は当然のものだった。
「お疲れみたいだね」
「……四日も寝ていないからな」ごしごしと目を擦り、脱力して腕をぶら下げる。
「子供相手に呪術まで掛けてずいぶん熱心に語ってたね」龍は舟に積まれた棺を目で数えて皮肉を言った。「仕事も溜まっちゃってさ」
「後でもう一往復しなきゃならん。怠けていたぶん死者が多い」
「それはいいけど」龍は咎めるような視線で隠者を見つめた。「あの青年に何を思ったの?」
はぐらかされることのないように、龍は問いかける。
隠者は何を見るでもなく水平線を眺め、言葉を選び沈黙した。
「……彼に愚者の印を見た。愚か者というのはいい。自由で気ままで、可能性を秘めている」
「よくわかんないんだけど」龍は困惑の表情を浮かべる。「良い兆しってこと?」
「そうだな。新しい物語が始まる……そんな気がする」
ふぅん。と龍は矛を収めるように納得して、棺を運ぶ作業に取り掛かった。
過ちから生まれ、時に楔として眠り、引き抜かれてから悠久の歴史を見つめる高い塔。それを管理するのは一人の隠者と魂を喰らう龍。……霊園は死の島と呼ばれ生者の立ち入りを禁じている。
それは静かに、そして優しく魂を癒す転換路として世界に存在し続ける。
―― 完 ――
最後の異世界転生譚 ――Echoes Beyond the Aurora Manuscript――
無事完結!
月一更新を目標にしていたときは前書きの欄に『完結させます』という宣言をしていたので少しプレッシャーでしたが、なんとかひと段落がつきました。
正直なところ、星空文庫はアクセス数が他の小説掲載サイトよりも穏やかなので、初めは書き途中のデータを保存する程度の軽い気持ちで掲載していました。
現在は推敲作業を行いながら『カクヨム』と『小説家になろう』にて連載していますので、評価や応援をしていだだけると嬉しいです。
ここから先の続編は青年が主人公となり、新たな舞台へ展開します。
まず、本編の後日譚であり、続編の前日譚となる幕間エピソード(中編)。
その後に本格的に続編を書く予定です。
ここまで読んでいただいた方、ありがとうございました!


