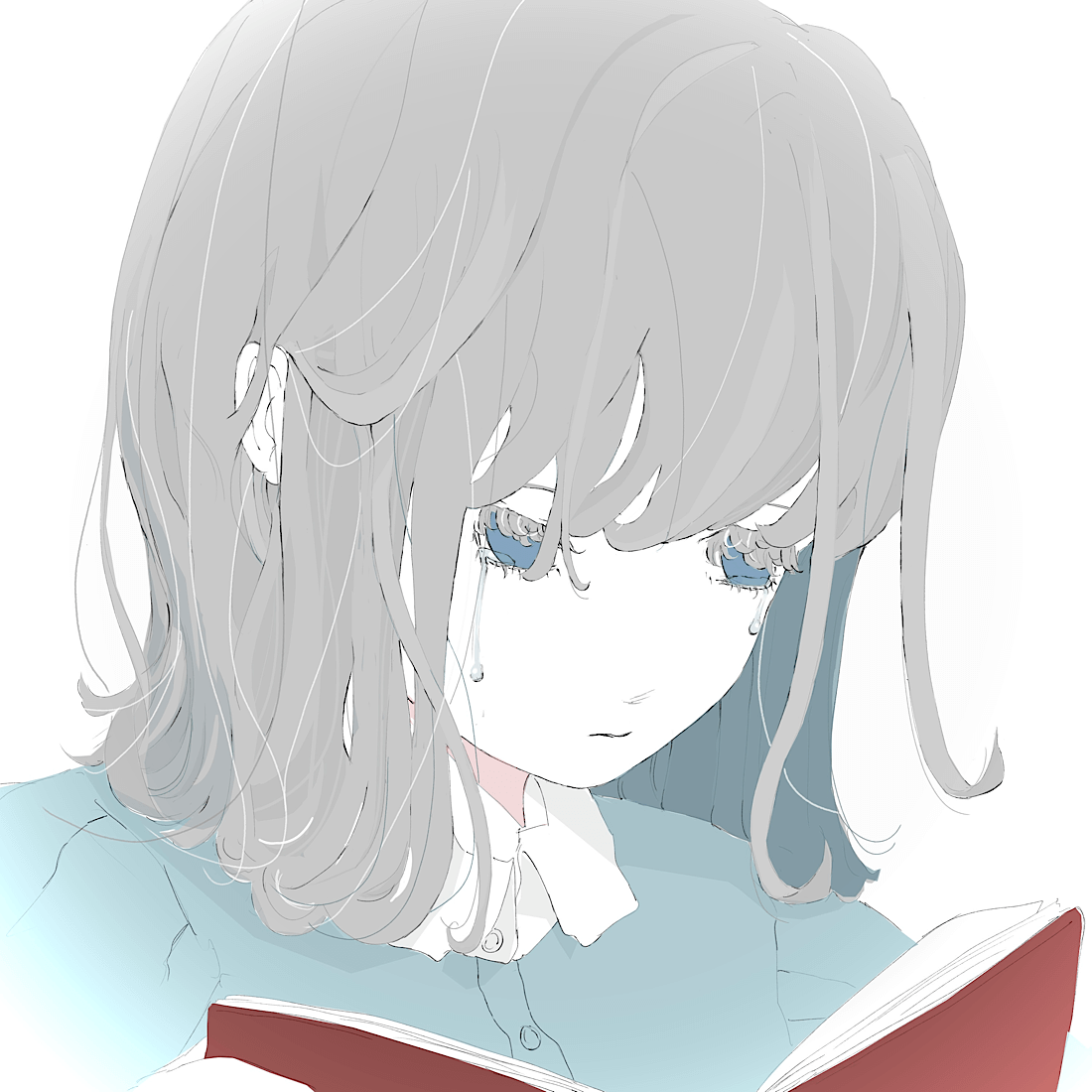
重なり合うプシュケーの塔
スマホで縦読みしやすいように、改行多めにしています。
※表紙変えました。
ノーコピーライトガール(NCG)さんからお借りしました。
【第一部】プロローグ 流れ出す生命
五メートル先から放たれた二十二口径の金属の塊。
その塊は少女の頭部を通り抜ける際に、何億、何兆という組織を破壊した。
それにより彼女は笑うことも、泣くことも、僕に語り掛けることも、たった今不可能となった。
撃ち抜かれたその小さな頭から、明確な意味を持ち|生命は流れ出て行く。
あの日から一年間。背だって伸びたし、たくさん笑うようになっていた。そうだ……この子は今朝。初潮を迎えたばかりだった。
手を伸ばしても届かない……どうしてこんなことになってしまったのだろう。
引き金を引いた男は、何やら一言呟いて何処かへ行ってしまった。僕ももうこれ以上は、何も考えられなくなって来ていた。
少女と共に暮らした家は、すぐ隣で巨大な炎に包まれていた。その炎が僕の元まで延び、いっそのこと焼き殺してくれればよかった。
【第一部】一章 北の灯台

僕は、国の最北端にある岬の灯台で管理人をしている。
船舶の誘導だけでなく、一応監視としての業務もあるが、もう十年以上、所属不明の船がこの灯台から観測されることもないので、言ってしまえば、かなり楽な仕事だった。また、灯台の足元には小さな家が付いており、そこが僕の住居となっている。
監視をする時間は決められていて、それ以外の時間は好きにしていいことになっているが、近くには誰も住んでいないため、人と話す機会は街に買い出しに下りた時くらいのものだ。
僕には友人と呼べる相手はいないが、特に不便を感じたこともない。野菜を育てたり、岬から森へ自転車で下ったり、灯台から見える景色をスケッチしたりして暮らしている。毎回同じ絵になってしまうが、不思議と何度描いても飽きないものなのだ。
森には動物もいるが狩をしたことはない。肉が食べたい時は街で買って来ている。僕はそんな、風のない日の海のような、どこまでも穏やかな生活を送っていた。
【第一部】二章 出会い
その夜は、大雪が降っていた。
国の最北端といってもこの国自体雪国ではないので、雪が降ることは珍しい。そんな急な大雪おかげで灯台から見える景色もいつもとは大きく異なり、僕は何だか少しだけわくわくしていた。
久しぶりに付けたストーブで暖まりながら海の様子を確認していた時、大粒の雪が降りしきる向こう。小舟が一瞬、見えた気がした。
「えっ」と思わず声が出た。まさか……
もう十年以上こんなことはなかったのに。僕は照明の角度をそちらの方に向け目を凝らしたが、やはり間違いではなかった。
この極寒の中、小舟はこちらに向かって来ていた。僕は傍に置いてあったライフル銃とランタンを手にとり、厚手のムートンコートを着ると外に出た。
浜の近くまで下って行き、確認すると、小舟は既に着岸していた。僕は足音を殺しながら相手に悟られない距離まで近づき、岩陰に隠れて様子を伺った。しかし見る限り着岸したというより、漂着したという表現の方が近いのかもしれない。止まっている場所も、角度も、あまり適切とはいえないからだ。
無人の小舟がどこかから流れて来ただけなんだろうか? そうであれば僕としては面倒がなくてありがたい。
僕は、しばらくその場から小舟の様子を見ていたが、誰も降りてくる気配がないので、ゆっくりと近付き、ランタンの光を向けた。
するとそこに見えたのは、小舟の上で気絶している子供の姿で、駆け寄ってみるとそれは、およそ十歳の少女であった。
一体どこから……
どのくらいの時間、こんな状態で……
事情は分からないが、このままでは死んでしまう。僕は少女をおぶると灯台下の家まで走った。
部屋に入ると、彼女の濡れたコートを脱がせ、タオルで髪の毛や手などを拭き、暖炉の近くに寝かせ毛布で包んだ。
手は氷のように冷たく、血の気が引き顔は白くなっているが、脈はまだ打っている。どうか間に合ってくれと、あとは願うしかなかった。
【第一部】三章 涙
少女が目を覚ましたのは翌日の朝だった。
僕は眠らずに彼女の様子を見ていた。朝になり陽が昇るころには、彼女の顔は赤みを取り戻し、僕もウトウトし始めていた。
彼女は目を覚ますと、ここが何処なのか把握しようと目だけをキョロキョロと動かした。そして、ソファに座っている僕の存在に気がつく。
「体の具合はどうだい?」と僕は尋ねる。
「頭が……ボンヤリします」と少女は答えた。
「ちゃんと手は動く?」と尋ねると彼女は、腕を少し浮かせ、手を握ったり開いたりしてみせた。
「大丈夫そうだね。じゃあひとまず水を飲んで、少し何か食べよう」と僕は言う。
しかし彼女は、今は何も食べたくないと言うので、じゃあせめて水は飲まないとダメだと僕は言った。今彼女の体はおそらく、水分をかなり失っているはずだった。僕は、この家にある一番大きなグラスに水を注いで彼女に手渡した。
彼女は黙って受け取ると、一口だけ飲み込んだ。すると、身体が反応するように大きなグラスに入った水をゴクゴクとあっという間に飲み干してしまった。
僕は、まだ要るかと尋ねたが返事がなかった。最初、無視されたのかと思ったが、そうではなく、返事をすることが出来なかったようだ。彼女は、深々と泣いていた。まるで今飲んだ水がそのまま目から溢れるように、とめどなく涙は流れ続けた。
無理もないだろう。よほどな事情があったことくらい、僕にだって察しがつく。あんなにも寒い夜に、一寸先も見えない暗い海を、子供一人で漂うなんて、並大抵の事態ではない。
「水はまだいっぱいあるから好きなだけ泣いたらいいよ」と伝え、顔を拭くためのタオルを手渡した。
僕は彼女が落ち着くまで一度、表に出ていようと思い立ち上がったが、彼女が僕のシャツの裾を掴んでいることに気がつき、隣に座り直した。
——それからしばらく、僕は待った。
そして、少し落ち着いてきた様子の彼女を見て、迷ったが……思い切って訳を聞くことにした。
「ねえ、もし嫌じゃなければ何があったのか話してくれないか? 一人で抱え込むよりは良いんじゃないか?」
そう言うと、彼女は一瞬考えるような様子を見せたが、海を漂うこととなったその経緯を話し始めた。
==========
彼女の話では。ここから北に二十キロメートルほどの地点に、彼女の故郷の小さな島国があるとのことだった。漁業が盛んな国で、湊町はいつも賑わい皆平和に暮らしていたという。
しかし突然、ある一人の男の体に異変が起きた。
体から水分が無くなったみたいに、男の体はカラカラになり、目は霞み、数日後には歩くのもやっとになった。
そして、十日後にその男は死んだ。
気がつけば、彼と暮らしていた家族や仕事仲間にも同じ症状が現れ始めていた。
みるみる内にその病気は国中に広がっていき、気がつけば疫病と呼ばれるようになった。既に国民の三割以上が感染し、その一割以上の人間が亡くなっていた。
感染の広がるスピードは凄まじく、あまり医療の発達していない少女の国では特効薬もない。症状の出た者はただ死を待つばかりだった。
そして、少女の両親もまたその疫病に感染し、助かる見込みがなかったという。
島から出ることは条約により禁止されていたが、少女の母親は、まだ感染していないこの子を国から逃がそうと、彼女を小舟に乗せ、海に出させた。
しかし、運悪く数時間後には大雪が降り出し、気を失っている内にここに流れ着き、僕に発見された。
という事だそうだ……
==========
「……なるほど、そういうことだったのか」
僕もここより二十キロメートル程北に、小さな島国があることは知っていたが、あまり詳しくは分からなかった。それ程の事態なら、僕の耳に入っててもおかしくはないと思うのだが。
「すぐに出て行きますから」と、ふいに少女は言った。
その言葉に、僕は少々面食らう。
「どうして? 感染を気にしてるならもう手遅れだよ。昨晩君を散々看病したし、君の体を暖めるために、換気だって最低限しかしてなかったんだ。それに、君は感染していないから、お母さんが逃してくれたんだろ?」
「だけど、今発症していないだけかもしれません」
「そうか。まあ僕はほとんど人に会わない生活をしているから、誰かに移す危険もないし、もし君が感染してたとしても、死ぬのは僕だけだ」
そう伝えると彼女は、驚いている様でもあり、戸惑っている様でもあった。
「とにかく、それなら尚更今はここにいて欲しい。君が安全と分かるまでは、僕も国の見張り人として君を、街に行かせるわけにはいかないんだ」
それを聞いた彼女は何も言わなかったが、僕の顔から目をそらした。僕は続けて言う。
「だからひとまず、十日くらいはここにいてくれないか? 君のことは国には黙っておくよ。その後は好きにしていいから。出て行きたかったらそれでいいし、ここに居たければ、しばらく居てもいいから」
「……分かりました」と少女は俯いたまま答えた。
僕は、彼女の隣から立ち上がる。
「外を散歩しに行こうと思うんだけど、君も行く?」
「今はいいです」と、彼女は言った。
僕は家から出ると岬の先端の方まで歩いて行き、朝の潮風に当たりながら考えた。
急に大雪が降ったり、かと思えば十年ぶりに舟が観測され、そこにはなんと少女が乗っていたりと……今までの静かな日々は、この日のための序章だったのだろうか。
足元には、昨晩降った場違いな雪が積もっていたが、朝の日差しと、この島本来の気候により、既に多くは溶け始めていた。
【第一部】四章 朝食(トマトとチーズのサンドイッチ)
———五分ほど潮風にあたり、僕は家に戻ることにした。
部屋に入ると、少女は変わらぬ様子でベッドに腰掛けていた。さっき渡したタオルはテーブルに畳んで置かれている。
僕は、クロワッサンとサンドイッチの入ったバスケットをテーブルに置き、彼女の飲み干したグラスに再び水を注いだ。
「無理して食べなくていいけど、出来れば少しでも食べた方がいいよ。トマトとチーズは食べれる?」
彼女は「大丈夫です」と答えた。
僕は、クロワッサンとサンドイッチを一つずつ、自分の皿に取り食べ始めた。彼女も戸惑ってはいたみたいだが、サンドイッチを一つ、自分の皿に取った。
強い子だ。と僕は思った。それはきっとこの子にとって生涯の糧となるだろう。
それからしばらく僕は喋ることなく、黙々と食べていたが彼女はやはりあまり食べられなかったようで、一口だけかじり、後は皿の上に残し、それを何も言わずに見つめていた。
「いいよ、それはとっておくから、夜にまた食べよう」と、僕は言った。
彼女はまだ、サンドイッチを見つめたままであったが、その目には再び涙が溜まっていた。
「ごめんなさい、あまり気にしないで下さい」
と、彼女はそう言ったが、この状況で気にしないのは正直難しい。
その言葉の半分は、気にしないで欲しいというものであり、もう半分は、気にして欲しいというものでもあるように思えた。僕は何も言わずにもう一度、タオルを差し出した。
この年齢で両親を失ってしまうということが、どんな気持ちなのか僕には分からないけれど、この経験にどういう意味を持たせるのかは、この子がこれから自分で決めることが出来る。
ただ、今辛いのは仕方ない。そればかりはもう少し、時間が過ぎるのを待つしかない。美味しいサンドイッチも、美しい海も、僕という存在も、悲しみに暮れる今の少女にとってはあまりにも力不足だった。
「大変だったね。辛いだろうけど、必ず少しずつ楽になっていくよ。僕も母親が亡くなった時は辛かった。いや、君の両親はまだ亡くなったわけじゃないから、余計辛いかもしれないね。とにかく、今辛くても少しずつ良くなっていくよ」
「……ありがとう。もう少し寝てても良いですか?」
「うん。好きなだけ寝たら良いよ」
それから彼女は、ベッドに窓の方を向いて転がった。
僕は、彼女の残したサンドイッチを冷蔵庫にしまい、お皿とグラスを洗うことにした。洗いながら背中では、彼女の啜り泣く音がずっと聴こえていた。
あの子の国と、何かしらの連絡を取る手段でもあればいいのだが、連絡船なんて出ていないから手紙は出せない。もちろん舟で乗り込むわけにもいかない。
彼女の母親があの子を逃がしたというのなら、その気持ちを汲んでとにかく今は、ここで僕が面倒を見るしかないのだろうか。
【第一部】五章 あなたの命はあと十日です
次の日。僕は少女に、街に買い出しに行ってくると言って家を出ようとした。
すると彼女は「私のことを報告しないと、あなたは捕まっちゃうんじゃないの?」と言った。
だから僕は「んん、どうだろう。大丈夫だと思うよ」と小さく笑って答えた。
彼女がそれを見てどう思ったかは分からないが、僕は返答を待たず家を出た。
だけど本当は、僕は平気ではなかった。街に行くつもりなどなかったし、今足りないものなど得に何もない。僕はひとまず、考えを整理する時間が欲しかったのだ。彼女の前では強がったものの、自分が死ぬかもしれないという事実に、少なからず恐怖を感じていた。
僕は森に向かうことにした。森を抜けた先にはストーンサークルがあり、僕は考え事をしたい時には時々、そこを訪れることにしているので、ひとまずそこを目指すこととした。
森の中を歩きながら「死」と「違反」という2つの言葉が頭から離れず、そのイメージは最初感じたときよりも、明らかに大きくなり始めていた。
彼女は僕に、報告しないと捕まっちゃうんではないかと言った。その通りだ。
あの灯台で観測したこと、あの岬で起きた出来事など、全てを報告する義務が僕にはある。嘘をついたり、事実を隠したりすれば僕は捕まる。職を解雇されるだけではない。捕まって城の牢に入れられてしまう。
ただ城の役人も、ここ十年何もない状況に、深い詮索をわざわざいれてくることもないだろうし、定期的に監視記録を取りに来る使いの者に少女を見られなければ、存在がバレることもないだろう。もし見られても、親戚の子を預かっていると言えばそれで済むだろう。
やはり恐ろしいのは、彼女が本当に感染していないかどうかという事だ。そして、今もう既に僕に感染していないかということだ。今ならまだ、城に報告し彼女を引き取ってもらえば、彼女が感染していたとしても僕は助かるかもしれない。
しかし彼女は不法入国で、しかも疫病を持ち込んだ可能性があると知られれば、おそらく国に強制的に送り返されることになるだろう。それはあまりにも不憫だ。
だけど、僕にどうしろと言うのだ。僕はファンタジーの勇者ではないし、賢者でもない……ただの灯台の管理人だ。モンスターとも、病魔とも、戦うことは出来ない。
さっきまで少女の前で強がっていた自分が、別人のように思えた。
———気がつくと既に森を抜け、ストーンサークルのある広場に出ていた。あまりに集中していたので、自分がどの辺りを歩いているのか、全く把握していなかった。
ひとまず石の上に腰を下ろした。ここにも雪は降ったようだが、既に石の上の雪は溶けてしまったようだ。芝生にはまだ少し残っている。
僕は、今日までの何もない自分の生活が、とても特別なものだったのだと思い知った。
友人はいないし、もちろん結婚だってしていない。だけど僕は、日々の生活に満足していた。幸せだった。そう。ちゃんと幸せだった。
もし、心を病んでいる人に対して、何か特効薬のようなモノがあるのだとしたら、それは「あなたの命はあと十日日です」と伝えることだろう。
そして僕は、少しの間途方に暮れる。
十分後。諦めて少女の待つ家へと引き返すことにした。
【第一部】六章 目を潰した話
ストーンサークルを後にした僕は、森を抜け海岸へ向かうことにした。あの子に街に行くと言ってしまったため、今帰るとあまりに早くなってしまうからだ。
———海岸に着くと、一人の老婆が海の方に向かい椅子に座り、膝に抱えた何かを撫でていた。
あまりこの辺りで誰かを見かけることがないので不思議に思い、僕はしばらく背後から眺めていた。
すると、老婆はなんと、振り返らないまま「あそこの灯台の人かい?」と、僕に声をかけた。
僕は驚き、一瞬体が震えた。
そんなに近くに立っていたわけじゃない。足音が聞こえる距離とは思えない。なのに、老婆は僕の存在に気付いていた。
「そうです。すみません。何も言わず背後に立ってしまって」
「聞こえずらいからもう少し近くに来てくれないかい?」
「はい。しかし僕は今体調を崩していまして、あなたの近くに行くと、迷惑をかけてしまうかもしれない」
しかし老婆は「お前は何の病にもかかっていないから大丈夫だ」と言った。
なぜ老婆がそう断言したのか分からないが、僕は袖で、口と鼻を覆いながら老婆に近付いた。
そして老婆の前に回り込み、声をかけようとしたが、老婆が膝に抱えているモノを見て一瞬、息が止まった。
それは、人間のしゃれこうべだった。
「驚かして悪かったね。これはあまり気にしないでおくれ」
老婆が言うには、そのしゃれこうべは若い内になくなった、ある青年だという。
生前。その青年には友人がおらず、いつも孤独だったそうだ。しかしこの老婆だけには心を開いており、何気ない身の上話をよく交わし合ったと、そう話してくれた。
また、その老婆は目をつむっていたので僕は「失礼ですが、目が見えないのですか?」と訪ねると、この青年が死んだ日に自分で目を潰したと言った。
薬を使って失明させ、その後取り出したと。だけどそれから、本当の事と、偽りの事の見分けがつくようになったという。
「だから安心しなさい。お前は病気ではないし、お前の判断は間違ってはいない。それからね……」
そして老婆は、その瞳のないまぶたを閉じたまま、ゆっくりと顔を上げ、こちらを向いた。
「いずれ、あの子はお前の命を救うことになるよ」
「えっ……⁉︎」
僕は、驚いて尋ねずにはいられなかった。
「あなたはあの少女について何か、知っているのですか?」
「もちろん知っているよ。ただね。『知っている』とはとても難しい言葉だね。多くの場合それは『ただ表面をなぞる』や『都合よく解釈する』といった意味として使われてしまう。
それは他人を見るときだけでなく、自分自身を見るときにも当てはまるだろう。しかしあの少女の場合は少し違う。彼女が『どういう目的で生まれ』『どういう信念を持っているのか』私は確かに知っている。
だけど例えば、どんな食べ物が好きだとか、どんな家庭で育ったのかは知らない。私が少女について知っていることは、そういう類の事だけさ」
僕にはその具体的な意味は分からなかったが、老婆の話す言葉には妙な説得力があり、「お前の判断は間違っていない」という言葉は、確かに僕の心を軽くした。
この感覚こそ、老婆の言う「都合よく解釈する」ということかもしれないが、今の僕にとっては、それで十分だった。
「ありがとうございます」と礼を言って、僕は森に引き返そうとした。すると老婆は最後にこんなことを言った。
「帰りの道で、中心が白く花弁が水色の花が咲いているはずだから、それを摘んで帰るといい」
僕は「分かりました」と言い、再び森の中へと足を踏み入れた。
【第二部】七章 母からもらった本
老婆としばらく話をしたおかげで、もう家に戻っても不自然ではない時間となっていた。
まだ陽が沈むほどの時間ではないが、傾きかけている時間だった。
帰り道、確かに老婆の言った「中心が白く花弁が水色の花」があったので、一輪摘んだ。僕は、この森にこんな花が咲いていたこと、今まで気が付かなかった。
———灯台までたどり着く頃には、もう夕暮れ時になり、海はオレンジ色に染まっていた。
家の扉の前に立つと、今朝この中で交わした少女との会話が、自分の妄想だったのではないかという気がした。
ふと。少女がこの中にもう既にいないような気さえしたのだ。
扉を開けると、少女はやはり居なかった。だけど不思議と、逃げ出したとも思えなかった。
どこに行ったんだろうと思い、灯台を上ったが見張り台にはいない。そこから海岸を見下ろすと、昨晩彼女が乗ってきた小舟のところにいた。
僕は見張り台から降りて、彼女を迎えに行った。
浜辺に続く道を降りている途中で、彼女は僕に気付く。
手には一冊の本を持っていた。
僕から聞いたわけではないが彼女は「お母さんからもらった本で、舟に置いたままだったので取りに来ただけなんです」と説明した。
僕は「そう。陽が沈むと寒くなるから、家に戻ろう」と言った。
———家に戻り、少しだけこれからのことを彼女と話すことにした。
まず、城の使いが来た時には、隠れてもらうこと。好きに出歩いてもいいが、一先ず人には近付かないことなど、全て了承してくれた。
そして、もし助けが必要なら遠慮なく言ってほしい。例えば何か欲しいものがあれば僕が街で買って来るし、この家にある物は好きに使ってくれていい。自分の家と思って構わない。
だけどその分家のことを手伝って欲しい。もちろん君に出来ることでいいから。
それからしばらくして、君が感染していないことが分かれば、後は君の好きにしていい。もちろんここに居なくてもいいし、居てもいい。
僕は君の保護をしたわけじゃなく、あくまでも経緯によって、一緒に住んでいるだけだから。僕のことは対等に見てほしいと、そう伝えた。
彼女は「わかりました。それで大丈夫です」と言った。そして「ごめんなさい」と謝った。
僕は「謝ることは何もないよ」と言ったが、彼女は何やら気まずそうだったので、「良かったら明日この周りを案内するけど」と提案した。
しかし彼女は、「きっとすぐ出て行きますから、大丈夫です」と言った。
そして窓辺に生けてある花に気付き、「この花はどうしたんですか?」と僕に訪ねた。
「さっき森で摘んで来たんだけど、この花知ってるの?」と僕は答える。
「故郷にはよく咲いている花なんです」
どうやら、彼女の母親が部屋の窓辺にいつも飾っていた花らしい。その島にしか咲かない花だと母親から聞いていたそうで、どうしてここにあるんだろう。と少女は驚いていた。
確かに僕も、あの森はよく通るが、こんな花はやはり見たことはなかった。
あの老婆は、本当に何者だったのだろうか……
【第一部】八章 生きていてはいけない人間
———少女との共同生活が始まって二週間が経った。
彼女は本当によく働いた。しかもかなり要領が良かった。
庭の野菜への水やり、洗濯、掃除、僕は簡単に説明をしただけだったが、僕が見張りの為に灯台に登り、夕方降りた時には全て器用に済ませていた。
食事の支度は最初は僕がやっていたが。二週間が経過し、彼女が安全だと分かってからは、お願いするようにもなった。
彼女はまだ、空中を見つめボンヤリする瞬間があった。
よく働くのは、考える時間を作りたくないからだろう。
自分が彼女の立場であれば、同じようなことが出来るだろうか。本当に強い子だと思う。
だから僕はなるべく彼女に話しかけるようにした。
しかしもちろん故郷のことや、両親のことを聞くわけにはいかないので、この国の美味しい食べ物の話や、僕が絵の資材を買うために通っている画材屋の話、そして、三年前までここで共に暮らしていた恋人の話もした。
僕の話を聞く時の彼女は、やはりボンヤリしていて、左から右にただ通り抜けているようにも見えた。
だけどどうやら、恋人の話をしている時だけは興味を持ってくれているようだったので、僕はなるべくその話をするようにした。
———そんなある日。森から出てきた彼女は、首から血を流す一匹のハクビシンを右手に掴んでいた。
「どうしたの? それ」
「晩ご飯になるかと思って」
「そっか。ありがとう。今日は野菜しかなかったから助かったよ。だけど、狩りが出来るなんてすごいね。どこでそんなこと覚えたの?」
「父に教わりました」
「へぇ。変わったことを教えるもんだね」と言うと、彼女は暗い顔になった。
「父が動物を狩る理由は、食べるためではなく甚振るためでした」
「甚振るため?」
「はい。父はよく私を狩りに連れていきました。最初のうちはまだ普通だったと思います。だけど段々とおかしくなっていきました。
捕えた動物を、色々なやり方で殺すようになったんです。
お母さんが言うには『お父さんは仕事で疲れてしまい正気ではなくなった』と言ってたけど、父をいつも近くで見ていた私には、それは違うように思えました。
父はいつも正気でした。正気のまま、楽しんでそういうことをしていました。
私は、父が死んでしまったことは良い事だと思っています。生きていてはいけない人間というものが、この世界にはいると思うんです。
父は、いや。あの人はそういう人だったと思います」
【第一部】九章 絵の描き方
———少女との共同生活が始まって一か月が経った。
僕は、久しぶりに絵を描いていた。
あの子がここに来てからというもの、何だかバタバタしていて、絵を描くことをすっかり忘れてしまっていた。
今日は、家の窓から見えるすぐそこの丘に行き、そこから見た灯台とその周りの景色を写生していている。
描いている間に集中力が途切れることもある。
大体いつも一時間くらいは集中出来るのだが、今日は十分も持たずに、絵とは違うことを考え始めていることに気がついた。
それはやはり、少女のことだった。
僕は、あの子のように大変な苦難を経験したことはない。
ごく普通の家庭で、ごく普通に育てられた。
十八歳までは故郷の街にある神学校に通った。
僕はあまり神とか信仰に対して興味を持つことは出来なかったけど、親切な友人もいたおかげで、学校生活自体は楽しめていたように思う。
両親は、卒業後は神父になってほしいと考えているようだったけど、僕にはずっと、誰にも話していない小さな夢……というほどでもないけど、ボンヤリとした願望のようなものがあった。
それは「海の近くに住んで、暮らしてみたい」というものだ。
そんな時に、灯台の管理人の仕事に空きがあることを街で聞き、僕は思い切って父親に相談した。
人里から離れた場所であるため心配はされたが、父親は「お前は自分にとっての幸福が何なのかよく分かっている。それは何よりも重要なことだ」と言って、賛成してくれた。
人が焚火の炎を見ていると心が安らぐように、僕は海を見ているだけで、自分の心が満たされることを知っていた。
そして灯台の灯は、僕にとっては焚火の炎だった。
僕は、理解ある両親のもとで育てられたことが、何よりも今の生活の基盤となっていることを知った。
特に父親はいつも、僕のことを一人の自立した人間として扱ってくれた。
神学校ではそんなことは教わらないはずなので、父の元々持つ気質かもしれないが、父はそういった理念を持っていた。
そして僕は、そのおかげで自分の道を自由に選べたのだと思う。
———そんなことを考えているうちに、少女が家から出てきて、こちらに向かって歩いてきた。
こちらまで来ると、僕の隣に座り、スケッチブックを覗き込んだ。
隣で誰かに見られながら絵を描くというのは何年ぶりのことだろうか……
「見てて楽しい?」と尋ねると、彼女はコクンと頷いた。「自分で描いたことはないの?」
「少しだけ」
「良かったら描いてみるかい?」
そう尋ねると、満更でもない様子を見せたので、僕は色えんぴつのセットと、新品のスケッチブックを渡した。
「そのスケッチブックはあげるよ。色えんぴつは僕の机のひきだしにいつもあるから、好きな時に好きに使っていいから」
と言うと少女は「ありがとう」と言い、少しだけ笑った。
それは、この子がここに来てからの間、僕が切に願っていることだった。
そうか。この子は笑うとこんな顔になるのか。
僕はこのスケッチブックと色えんぴつが、今までで一番役に立ったような気がした。
人は一度、大きな闇に食べられたとしても、ちゃんと這い出ることが出来る。
這い出ることの出来ない多くの人はきっと、その闇の渦中にいる「可哀想な私」を見て欲しい。そんな「不幸な私」のことを特別扱いをして欲しいと、きっとそう願っているのだろう。
病みを手放すというのは、とても勇気のいることだからだ。
僕は以前この子の言った。「生きていてはいけない人間もいる」という言葉に心の闇を感じていたが、その感覚は間違っていたのかもしれない。
実はそれは、この子の強さであり、真っ直ぐに生き抜こうとする生命力の一部なのかもしれない。
今そんな風に、僕の中での解釈が変わった瞬間だった。
今目の前にいる少女は、スケッチブックをその小さな左手で支え、もう一方の手にえんぴつを持ち、灯台の輪郭を一生懸命に描いていた。
この子がどんな絵を描くのか、僕は知りたかった。
風が吹いて、足元の草を揺らす。
春が、もうすぐそこに訪れていた。
【第一部】十章 本棚の上の本
———少女との共同生活が始まって三か月が経った。
少女は、初めの頃に比べれば本当に元気になった。
ご飯もちゃんと食べてくれるし、今では当たり前のように自分から色々と話すようにもなってくれた。
今日は午前中から、街に一人で買い物に行っている。僕は留守番だ。
僕は少女が出て行ってすぐ部屋の掃除を始めた。
あの子が来てから、そういえばまだ本格的な掃除をしていないことに気がついたのだ。
やはり、二人で暮らすようになって、部屋が汚れるスピードも少し早くなっていた。
まず出しっ放しになっている本は全て本棚に戻した。といってもあの子は自分で読んだ本はちゃんと自分でしまうから、片付けていない本は全て僕が読んだものだった。
あの子は自分の家でも、こんなにきちんとしていたのだろうか。
それから扉と窓を開け放して、床をホウキではき、ソファやベッドなどを叩いてホコリを外に出した。
夢中になって掃除をしていると、僕は本棚にぶつかってしまい、その衝撃で僕の頭の上に本が落ちた。
拾い上げるとそれは、いつか少女が舟に取りに戻った、あの母親からもらったという本だった。
本棚に戻そうと思い見上げる。すると、不思議なことに気がついた。
ぶつかった衝撃で本が落ちるのは分かる。だけど一番上の段でも、僕の顔と同じ高さの本棚である。
じゃあなぜ僕の頭の上に当たったのか……?
考えられる場所は《《本棚の上しかない》》。
本棚の上は僕の身長よりも少し高い位置なので、そこに置いていたのであれば、頭の上に当たった事の説明も付く。
だけどどうして、あの子はわざわざ本棚の上に本を置いたのだろう?
あの子の身長で考えると、椅子に上って背伸びをしてやっと届くくらいではないだろうか。
まあ。考えても仕方がないので、ひとまず掃除を終わらせることとした。
——–それから一時間ほどで掃除は終わってしまった。
大きな家でもないから当たり前なのだが、面倒だと思っていても取り掛かってみるといつも予想していたよりも早く終わってしまう。
あの子が帰ってくるまで、まだ時間があるだろうから、せっかくなので僕は先ほどの、あの子の本を読みながら待つことにした。
—–—数時間後。
僕は夕食の準備をしながら少女の帰りを待っていた。
彼女はただいまと言いながら部屋へ入って来る。
僕は振り返らずに、おかえりと背中で返事をした。
彼女は少しその様子を気にしているようではあったが、街で自分のキャンバス立てを買ってきたことを楽しそうに話した。
そして僕に、絵の描き方を教えて欲しいと言った。
僕はまた背中を向けたまま、いいよと答えた。
彼女はやはり、僕の様子がおかしいことに気付き、それから喋るのを控えた。
僕は黙ったまま食卓に白身魚の塩焼き、ポトフ、バタールのスライスを並べた。
僕たちは向かい合って座ったが、僕は自分一人で食べるかのように、小さくいただきますと言った。
彼女も同じくらいの声で寂しく、いただきますと言った。
カチャカチャという食器の立てる音。
風が窓を揺らす音。
波が砕ける音。
最近はいつも、僕たちは何か話をしながらご飯を食べていたから、こういった音がいつも側で鳴っていることを忘れていたような気がする。
少女の顔を一瞥する。そこには初めて彼女を見た時のような暗い顔があった。
僕は、自分がとても悪いことをしている気分になってしまい「ごめん、少し頭が痛くて。明日また外に絵を描きに行こう。そのキャンバス立てを使って描いてみよう」と言った。
彼女は「ううん。今日は私が洗い物をするからゆっくり休んで」と言った。
一瞬、目の前の少女が、かつてここで共に暮らしていた、恋人の顔と重なって見えた気がした。
僕も、ありがとうと答えた。
【第一部】十一章 城の使い
——–少女との共同生活が始まって半年が経った。
今日は、城から使いの者が監視記録を取りに来る日だ。
僕は少女に「悪いけどその時だけ、ベッドの下に隠れていてくれるかい?」とお願いし、彼女は了承した。
使いの人間は稀に時間よりも早く来ることもあるので、外はうろつかず家の中で過ごした。
僕はコーヒーを、彼女はミルクコーヒーを飲みながら時間が来るまでノンビリ過ごした。
——–いつも通りの時間になると、車がこちらに向かって来る音が聞こえた。
僕は彼女に目配せをし、彼女は素早くベッドの下に潜り込んだ。
車が家の前で止まる。エンジンを切る音が聞こえ、扉がノックされた。
「はい、今開けます」と、僕は扉を開けた。
そこにはいつもの男が立っていた。
ヒョロリとした線の細い体格。メガネをかけ、支給された城の制服と、肩掛け鞄を斜めに下げた彼は、いかにも城の使いが似合う男である。
「こんにちは。監視記録を受け取りに来ました」と男は言う。
僕はいつも通り今日までの記録を男に手渡した。
「特に変わったことはありませんでしたか?」
「ええ、特に何も」
「承知しました」と言いながら男は、監視記録をパラパラとめくり、簡単に目を通しているようだった。
いつもなら、そのまますんなり帰るはずなのだが、男は口を開いた。
「そういえば、先ほど裏の浜辺で小舟を見かけたのですが、あれはあなたのものでしょうか? 前回来たときにはなかったように思うのですが」
しまった……舟を隠すのをすっかり忘れてしまっていた。
「そうです。いつもは入り江の先の洞窟に止めているのですが、昨日あれで釣りに行っていたもので」
「そうですか、では一度近くで確認したいので、案内してもらえますか? 何か変化があった場合には確認しなくてはいけない事となっていまして」
「分かりました」と言い、僕は男と家を出て、舟のある浜辺の方へ歩き出した。
——–おそらく少女の手がかりとなるようなものは、何も残っていない筈だ。
しかし……浜辺の方へ下れば下るほど、僕の心臓の音はどんどん大きくなり、まるで頭の中で鳴っているようだった。
小舟の元へ着くと、男は舟に上がり中を調べ始めた。
そして時々、手に持っていた用紙に何かを書き込んでいる。
僕も近づいて、何かマズいものが落ちていないか覗き込んだが、見る限り舟の中は空っぽだった。
そして男は小舟から降りると、僕の前に立ち、用紙に目を落としたままこう尋ねた。
「しかしこの辺りでは見ない作りの舟ですね。どこから持って来たのですか?」
僕はひとまず、確認の取れないような言い訳を答えなければならないと思い「すみません。これは確か、随分前に友人から譲り受けたものなので、元々どこで作られたものかは、僕にも分からないのです」と答えた。
男は僕の話を聞きながら用紙にまた何かを記入していたが、納得した様子で、ペンと用紙を鞄にしまった。
そして「ではもう大丈夫です。舟が傷んでいるようなので沖にでる際は気をつけて使った方がいいでしょう」と言った。
そして僕と男は再び浜辺から、灯台の方へと上り始めた。
——–家の前に着くと男は「ではまた」と言い車に乗り込んだ。
僕はホッと胸を撫で下ろす。しかし男は最後に、こんな言葉を口にする。
「お忙しいところすみませんでした。ベッドの下のご友人にもそうお伝え下さい。では」
そして、森の中へと消えて行った。
僕はその場で立ち尽くし、男の車が小さくなるのをただ見ていた。
【第一部】十ニ章 油断
僕は訳がわからないまま家に戻った。
見ると、テーブルの上には飲みかけのコーヒーとミルクコーヒーがそのままになっていた。この二つのカップを見て男は、他に人が居ると勘づいたのか?
しかしどうしてベッドの下だと分かったんだろう……くそ、僕は城の使いを甘く見ていたようだ。
僕はベッドの方に向かい「もう大丈夫だよ」と声をかけた。
少女はのそのそとベッドの下から這い出てきて、大丈夫だったかと尋ねたので、問題ないよと言った。そして、悪いけどもう少し家にいてくれるかいと言って僕は一度外に出た。
僕は家の前をゆっくりと歩きながら考えた。
今までこの岬では何もトラブルはなかったので、何かを隠すようなことは一切無かった。嘘を答えたのは今回が初めてだった。
あの男は僕の僅かな動揺と、部屋の様子の違いで何かを見抜いたというのか。あの男は、城の使いに専任されるだけの人物だったということか……とは言うものの、こうなった以上どうすればいい。
あの男は僕を疑っているだろう。城に何か報告をされるかもしれない。そうすれば次は、衛兵を引き連れて来て、本格的な調査と尋問が行われるかもしれない。
そうなれば僕は終わりだ。少女だって不法入国だしタダじゃ済まない。これ以上ここに居るのは危険ということか。どうすれば…………
僕は不意に、あの日のしゃれこうべを抱えた老婆のことを思い出す。あの人なら、この状況に何かしらの助言を与えてくれるような気がした。
——僕はもう一度、あの老婆のいた海岸を目指し森の中へと入って行った。そして足早に森を抜け海岸に着いた。
そこには、あの日と同じように、海に向かい、椅子に座る老婆の後ろ姿があった。
【第一部】十三章 助言
「こんにちは」と僕は声をかけた。
老婆は振り返ることなく「また来てくれたのかい」と答えた。
僕は老婆の前に回り込んだ。老婆は相変わらず膝にしゃれこうべを抱え、目を閉じたまま波打ち際の辺りに顔を向けていた。
「すみません。また少し困った事態になってしまいました」
「そうかい。だけど困難とは起こる時にはひっきりなしに起こるものだから、受け入れるしかないよ」
そして老婆は手招きをした。僕は老婆のすぐ近くまで行くと、持っていなさいと羅針盤を手渡された。
「これは?」と僕は尋ねる。
「この問題はお前が考えるよりも、まだ大きいものになって行く。それを持っていた方がいい」
僕は、分かりましたといい羅針盤をポケットにしまった。
「この世界には、二種類の人間がいる。分かるかい?」と老婆は言う。
「二種類ですか……いえ、どうでしょう。わかりません」
「それはね。親に愛された者と、愛されなかった者だよ。この二者の間にはとても大きな隔たりが出来てしまう。お前さんは一目見てすぐ分かったよ。よい両親に恵まれたんだね。
だけど残念ながら、そうではない者も居る。きっと私たちが想像する以上にその数は多いだろうし、またその深淵の深さは、よほど勇気のある者でないと覗き込むことは出来ない。
勇気とは、『自身には価値があると思える』ということだよ。そして、その感覚を最初に教えてくれるのは両親だ。
分かるかい? だから愛されなかった者は危険なんだ。誰かを傷つけることで、己の存在を誇示しようとするからだよ」
僕は、老婆の言うことの意味が感覚的にとてもよく理解出来た。老婆は続ける。
「お前さんは、もう既にそういった問題の渦中に身を置いている。愛情を知っているお前さんには、この問題を乗り越える為の知恵と素質がある。
だけど簡単じゃないよ。気を抜かずにしっかりと、目の前の状況を切り抜けていかなければ、未来は全く違うものになってしまう。
私に出来ることはこんな風に助言を与えることくらいだ。全てはお前さんにかかっている」
「ありがとうございます。分かりました。僕が今日こちらに来た理由はですね。やはりあの少女のことなのですが、今日は城の使いが灯台に監視記録を取りに来る日でした。
ついさっきのことなのですが、その城の使いの男に、どうやら僕が少女を匿っていることがバレてしまったようなのです」
僕はそこで少し言葉を区切ったが、老婆は何も答えようとしなかったので続けた。
「その使いの男はですね、最後去るときに、ベッドの下に少女を匿っていることを見抜いているような発言をして帰りました。なぜ男にそれがバレてしまったのか、僕には全く不思議なのです」
「そうかい……私が思う以上にもう事は進んでいるのかもしれないね。いいかい? 落ち着いて聞きなさい。その男はマズい。とても危険だ。
しかも頭も良いだろう。とにかく逃げなさい。決して冷静に話し合おうなどと考えてはいけない。
どうしてその男が、少女の存在を見抜いたかよりも、なぜその事を最後にお前さんにわざわざもらして行ったのかを考えてみなさい」
「なぜ……ですか?」
確かにそうだ。なぜ最後にわざわざそれを僕に教えるような言葉を残して行ったのだろう。
まさか……僕に行動を起こさせるためか。
揺さぶりをかけて、例えば僕が逃げる準備を始めるとか、少女と何か決定的な話をするとか、そういった行動を誘発させて、証拠を掴もうとしているのか。
だとしたら男はまだ、灯台の近くに潜んでいる⁉
老婆が、口を開いた。
「もう戻った方がいい。今すぐに。走って戻りなさい」
【第一部】十四章 推理
僕は老婆にお礼を述べると、すぐに駆け出し、森を全力で走り抜けた。
———岬に着くとやはり不安通り、家の前にはあの城の使いの男の車が停まっていた。
マズい。既に家の中にいるのか。
僕はあがった息を整えながら、一歩ずつゆっくりと家に近付いていく。
扉の前に立ち深呼吸をする。
平常心だ。いつも通り扉を開けるんだ。
僕は扉を開ける。先ほどの城の使いの男が、椅子に腰掛け、玄関口の方を向き足を組んだ姿勢で待っていた。
しかし少女の姿はどこにもない。なぜだ……どこへ消えたんだ。
「何をしているんですか? 人の家で」僕は言った。
「確認し忘れたことがあって戻ったのですが、留守のようなので勝手に上がらせてもらいました」と男は答える。
「そうですか。確認とは何でしょうか?」
僕はそう答えたが、少女が見当たらないことがただひたすらに気掛かりで、男の言葉が頭に入って来ない。何なんだ……この男は……一体どこまで分かっていて、どうしようというのだ。
「いえ、大したことじゃないのですが、さっきね、このテーブルにコーヒーカップが二つ。しかも飲みかけのコーヒーと、ミルクコーヒーがあったのが気になりまして。どなたかが来ていたのかなと……思ったんです」
男は僕を見透かすように、血の通わない声でそう言った。僕が返答に詰まっていると男は続けた。
「それともあなた、コーヒーを飲んでる途中で飽きてしまって、それでミルクコーヒーを淹れたんですか? しかも新しいカップで。幾分変わった飲み方だとは思いますがねえ」
「よく分かりません。何が言いたいのですか?」と僕は答える。
男は、ふぅと溜息をついた。
「質問を質問で返すということは、何か答えにくい事があり焦っているのでしょうね。それと、疲れるんですよね。会話が成り立たない相手と話すのは」
「それはすみません。あなたが来る少し前まで来客がいたんです。だからカップが二つあるというだけです」
「そうですか。来客とは誰ですか?」
「なぜあなたにそこまで……」
僕が喋り終わるよりも先に、男は手慣れた素早い動きで、腰の拳銃を引き抜くと、僕の顔に銃口を向けた。
「ちょ! 何ですか急に!」僕は思わず両手を顔の前にかざした。
「さっき言いましたよね? 成り立たない会話は嫌いだと」
「いや、だからって……」
ズドンッ! という破裂音が狭い家の中に響き、放たれた銃弾は僕の顔の少し左辺りを通り、後方の壁に穴を空けた。
「あなた、死にたいんですか? 質問に答えろと言っているだろうが……まずこれに答えて下さい。死にたいんですか?」
「し……しに、死にたくありません」僕は震える声でそう答えた。高い音で耳鳴りがしている。
「そう。それで良いのです。まあどうせあなたは、後は捕まるだけですので教えてもいいでしょう」
男は眼鏡を外すと、テーブルの上に置き、目頭を右手の人差し指と親指で軽く揉みほぐした。
「消去方のようなものですよ。私は浜辺にある小舟を見つけた時点で、ある仮説を立てていました。ここに何者かが流れ着いて、あなたが何らかの理由でかくまっていると。
そして、私が来る時間帯に外をうろつくのは危ない。この辺りは外に隠れるといっても森か海岸沿いくらしかありません。
しかし森は私がここに来る途中に通るから危険だ。海岸沿いは見通しが良いし、小舟を確認しに降りる時に私に見つかるかもしれない。尤も、あなたは小舟の存在自体を忘れていたようですが。
灯台の上の監視台の鍵は、私も合鍵を持っているから危ない。だとしたら安全に隠れられる場所は家の中だと思ったわけです。私は玄関先に立つだけでいつも中までは入りませんからね。
そしてあなたが扉を開けた時、テーブルの上に二つのコーヒーカップが見えた。あなたは本当に詰めが甘い」
男はため息をついた。
「そして、こんな物の少ない狭い家の中に、人間が隠れられるとしたらベッドの下くらいのものです。
これが私の推理です。そして私の揺さぶりにも、あなたは素直に応じてくれた。焦って何処かに駆けて行く様を見て確信したのです。
さぁもう良いでしょう。全て白状して下さい。どちらにしてもあなたはもう、終わりなんですから。ハハ」
と、使いの男は幸せそうに笑った。
【第一部】十五章 試練
「ちょっと待って下さい。確かに僕は嘘をついた。だけど、いつまでも黙ってるつもりではなかったんです。落ち着いたら報告するつもりでした」
男は一言、だまれと言った。そして、拳銃を構えたまま縄を取り出し、僕に両手を前に出すように指示する。
僕は黙って両手を前に出し、男は慣れた手つきで縛った。
「しかし、お前ほどの間抜けを私は他に見たことがない。こんな誰もいない岬の管理人を引き受け、安い報酬を受け取り、所帯を持つこともなく、いつも一人でニヤニヤと暮らしている。
自分が惨めだと気づくこともなく、街の人間とも関わろうとしない。城の人間がお前のことをどう呼んでいるか知ってるのか? 灯台の管理人だなんて、誰も言ってない。『北のおとり』って言われてるんだよ。
北側から攻められた時にここは真っ先に狙われるからな。お前が連絡をよこし、殺されている間に、我々は城を防衛する準備が出来るってわけだ。
知ってるか? 北から攻め入られた時、灯台の管理人の生命を守るための作は何も立てられていないんだ。
要はお前は、国に正式に認められた捨て駒なんだよ。死んでもいいやつをここにつかせるんだ。実際そうだろう。お前が死んだところで誰が困る? ええ? 誰も困らないだろう。
寂しい人生だったな。もうお前が城の地下から解放されることはない。明日から死ぬまで、湿った牢屋で暮らすことになるだろう」
使いの男は、そのように僕を散々罵ると、唾をぺっと床に吐いた。
僕の家の床に。
「チッ、ここは嫌いだ。潮風が喉に張り付いて気持ちりい」
さっきまでとはまるで別人のように、言葉遣いや顔つきまで変わってしまった男に、僕は更に狂気を感じた。それはまるで、人間の持つ醜さそのものであるように思えた。
しかし、僕の脳裏ではやはり、少女はどこに行ったのだろうという疑問だけが、ずっと残っていた。
男が来る前に逃げたのだろうか。
無事だろうか……
男は僕の両手を縛った縄の先を持ち、僕に玄関の扉を開けて出るように指示した。僕は言われた通り、男の前を歩き扉を開ける。
外はもう夕暮れだった。きれいな夕焼けが目の前に広がっていた。僕はここでの生活が好きだった。
いつも優しい何かで満たされていた。それがたった今失われたのだと思うと、心が真っ暗になった気がした。
だけどこうなったのも当然だ。僕のとった選択は違法だ、国の決まりに背く行為だったのだから。
だけど仕方ないだろう。あの状況で少女のことを国に引き渡していたらあの子は、長い拘束と尋問を受けることになり、最後には国へ送り返されることになるだろう。それはあまりに不憫だ。あの子の母親の努力だって無駄になってしまう。
僕が考え込んでいると、男は僕の背中を力任せに蹴飛ばした。
僕は草の上に倒れ込み、両手が使えないせいで、地面で鼻を打った。鼻の奥に、あの嫌な鉄の感覚が広がっていく。
「言われた通りに歩くことも出来んのか。なんならここで殺してやろうか?」
男は腰の拳銃を引き抜き、倒れている僕に向ける。
「や、やめて下さい!」と僕は恐怖のあまり丸くなる。
その時だった。
ガァンッ! という低く鈍い、金属で何かを殴るような音が、鳴り響いた。
僕が慌てて顔を上げると、目のとんだ男がまさに倒れる瞬間だった。
倒れた男の背後には、しっかりと両手でフライパンを握る少女が立っていた。
【第一部】十六章 逃亡
僕は声も出せず、鼻の痛みと共にその場でへたり込んでいた。殴られた男もまた、草の上で丸まり低い唸り声を上げている。
すると、少女はフライパンを振り上げ、倒れている男にもう一撃くらわせようとした。
「おいやめろ!」と僕は彼女に怒鳴った。「もうそれは捨てるんだ」
彼女はこちらを一瞥すると、無表情にフライパンを地面に投げ捨てた。僕はほっとする。
「隠れてたのか?」
彼女はこくんと頷く。
「そうか……とにかく、ひとまず逃げよう。もうここには居られない。分かるね?」
彼女はもう一度頷いた。
そして僕は、男の手にあった拳銃を奪い取ると海に投げ捨てた。それから家の中に戻り、金を入れた袋とランタンだけ取ると、すぐに浜へと向かった。
——–小舟の場所へ着くと、僕は縛られた手のまま、小舟を沖の方へ押し出し、少女と共に乗り込んだ。
舟に乗り込んですぐ、彼女は僕の手の縄をほどこうとしてくれたが、上手くいかない。手が震えているようだ。
僕はその震える手を見つめながら言う。
「驚いたよ。あんな事するなんて」
「ああするしかないと思ったから」
「うん……そうだね。ありがとう。助かったよ。僕があいつを甘く見ていたのが悪かった。本当にすまない」
そして彼女が縄を解くことに成功すると、僕はポケットから、老婆にもらった羅針盤を取り出し彼女に手渡した。
それで方角を見ていてくれと彼女にお願いし、僕は舟を漕ぎ始めた。
何度か振り返ったが、浜辺に男の姿は見えなかった。
あの男は大丈夫だったろうか。死ぬことはないだろうがやはり気がかりだった。
ふと見ると、オールを漕ぐ僕の手もまた、震えていた。
【第一部】十七章 満月の夜に彼女が死んだ理由
満月が昇っていた。その光が水面で真っ直ぐに揺れながら道を作っている。小舟はその道に沿うようにして、ある場所に向かっている。
僕たちが居た灯台の灯りは、もうとうに見えなくなってしまい、少女は少し前から、隣で眠っている。
僕は一体、こんなところで何をしているのだろう……という感覚が不意にやって来たが、それはこの子だって同じだろう。
いや、この子はもうずっと前からそんな気持ちなのかもしれない。まだ十歳なのに、本当に壮絶な人生だと思うよ。
大人をフライパンで殴ることが出来るだなんて、普通の生活をしてた十歳の子が、そんなこと出来るだろうか。
多分、普通じゃなかったんだろう……この子について僕が知っていることなんて、ほんの一部に過ぎないのだろうから。
もしあの時僕が止めなかったら、あの男を殺すつもりだったのだろうか……複雑な気分だ。助けられたのは事実だけど、この子はあまりにも気を張りすぎているように思える。
気がつくと僕は無意識に、眠っている少女の背中をゆっくりトントンと、子供を寝かしつける母親のように、手を一定のリズムで動かしていた。
僕はふと思う。そういえば、三年前。彼女が亡くなった夜も、こんな、満月の夜だった。
——–結婚したら女の子が欲しいと、彼女はよく話していた。彼女がまだ生きているうちにこの子が灯台に流れ着いていたら、ある意味で僕たちは家族のようになれたのかもしれない。いや、そうじゃなくても、きっと僕たちは結婚していただろうし、子供だって作ったかもしれない。
僕と彼女は、とても似ていた。表面的な好き嫌いはもちろん異なっていたが、根本的な部分が本当によく似ていた。
人は誰であれ、仮面をかぶって生きている。長い時間を生きる途中で、当たり前のように「他人に見せる自分」と「他人には見せない自分」が作られてゆく。
僕は初めて彼女と話した時、彼女の付けていた仮面に、今までにない居心地の良さを感じた。
運命の人に出会うと、本当の自分をさらけ出せると言う。それは半分は正しいが、半分は間違っている。
人は、他人の仮面を見た時に、その人がどういう理由でその仮面を付けたのか直感的に判断する。その感覚が正しいのか間違っているのかとは関係なく、ただ、そのようにして人の印象というものは、一人一人の中で勝手に、都合よく作られていく。
だから僕が、彼女の仮面に対して居心地の良さを感じたのも、ある意味僕の、都合の良い解釈だったのかもしれない。
だけど、それでも僕は彼女の仮面を見た時に、仮面の下の彼女が無意識に恐れている何かと、無意識に抱いている願望が、僕の抱えているものと同じものであると感じた。その仮面を選んだ事情が、手に取るように伝わって来る気がした。
それは、分かりやすくいうと恥ずかしいのだが、人から嫌われたくない。いや、自分が人から嫌われるような人間だと、認めたくない。
人から愛されなければ「私」は幸せになれない。だから、人から愛させるような特別な人間でありたい。そんな思いであったと思う。
そういった人がつける、いわゆる「良い人」の仮面であった。
今の僕はそうではないが、当時の僕はまさにそんは人間だった。そして、彼女もまた僕と同じ仮面を付けていた。
そして最も大切なことは、仮面の下の素顔だけが、その人ではないということである。「仮面」もまた、同じくらい、もしくはある場面においては「素顔」以上に重要な意味を持ち、生活に理由をもたらしている。
つまり僕は、彼女の「素顔」も「仮面」も、どちらも同じくらい愛していた。なぜならそれは表裏一体で、それ以上分けることの出来ない最小単位だったからだ。
——–僕達は知り合ってから、すぐに付き合ったわけではなかった。知人を交えて会うことはあったが、初めて二人だけで会ったのは、出会ってから約二か月が経った時だった。
僕は彼女に対しやはり好意を持っていたし、どこか似たような人間性を感じていたこともあり、あまり人には話さないことも話した。
その時彼女に話したのは、僕が何年も持ち歩いているある青春小説の話だった。彼女はその小説は知っているが読んだことはないと言った。
僕は彼女に勧めるつもりなどは全くなく、ただその小説が自分にとってとても大切なものであるという話をしたかっただけだった。
そういう、自分の内面を晒すような話をしたいと、相手にそう思わせる雰囲気が、彼女にはあった。僕はそれに甘えたかったのだと思う。
彼女は一度も口を挟まずに、わざとらしく笑みを作ることもなく、静かに僕の話を最後まで聞いてくれた。
そして、また後日会った時、彼女の鞄の中に、僕の話したその小説がチラリと見えた。
僕がどうしたのかと尋ねると、図書館で借りたのだと言った。
僕の話を聞いて、読みたいと思ったのか、それとも僕のことを知りたいと思ってくれたのか、それは分からないけれど、少なくとも彼女はわざわざ図書館に行きその本を借りた。
そしてそれを僕に言うこともなく、僕の知らないところで、ただ読んでいた。
それが、僕が彼女を好きになった理由だった。
その日のうちに僕は彼女に告白をし、その半年後には僕たちは一緒に住み始めた。
そう、あの灯台下の家で。
それから彼女が死ぬまでの五年間。僕たちは一度も喧嘩をしなかった。
時々どちらかが不機嫌になることはあったが、そんな時は、そうでない方が訳を聞き、知らずに傷つけてしまっていたことについて謝る。それだけ。
僕も彼女も自分の都合で勝手に不機嫌になったり、相手に当たったりする人間ではないので、そういう時は何かしらのすれ違いが起きている時だった。
それはただそれだけのことであり、僕たちにとっては、喧嘩する理由にはなり得なかった。
——それから。これは、信じられないことなんだけど僕は、なぜ彼女が死んだのか覚えていない。
本当に全く覚えていないんだ。
もしかしたら、もう一人の「仮面」をつけた僕、もしくは「素顔」の僕が、その出来事に蓋をしてしまったのかもしれない。僕が眠ったり、絵を描いたりしている間にそっと、僕にバレないように。
それから僕は友人に会うことを止め、街に行くことも最低限となり、あの灯台で隠居生活を送るようになった。
そうして「良い人」であるための仮面は、僕には必要なくなった。
——–今。隣で眠っているこの子は、初めて会った時からその仮面は付けていなかった。
僕は「生きていてはいけない人間もいる」と言った、この子の言葉を思い出し「僕もそう思うよ」と一人呟いた。
眠っている少女の目から涙が伝った。母親の夢でも見ているのだろうか。
【第一部】十八章 花の名前
翌朝。少女が目覚めるよりも前に、僕は目的地近くの入り江に着岸していた。そこは、あの灯台から数十キロメートル離れた、国の北西辺りの海岸だった。僕が目指しているのは、祖父の別荘である。
祖父はもう亡くなっているので、正確には今は父の所有となっているが、父はもう何年もそこを使っていないから、空き家同然となっている筈だった。
少女は具合悪そうに目を覚ます。そりゃそうだ。こんなグラグラと揺れる小舟の上で熟睡など出来るわけない。
僕が「大丈夫?」と尋ねると、彼女は「吐きそう」と答えた。
「ひとまずもう岸には着いたから、少し休もう」
「夜通しずっと、漕いでたの?」
「うん。なるべく暗いうちに着いておきたかったから」
「ありがとう」と彼女は言う。
それから彼女の気分が落ち着くまで少しの間、僕たちは入り江近くの洞窟で休憩をした。それから、今度こそこの小舟が発見されてはマズいので、僕は彼女と一緒に小舟を洞窟の奥まで運んだ。
それから僕たちは、祖父の別荘へ向けて歩き始めた。
その道すがら、花を見つけると彼女は「ヒメジョオン、ノヂシャ、キュウリグサ、オオイヌノフグリ」と、おそらく花の名前であろう言葉を口にしていた。
「詳しいね」と僕が言うと、「お母さんに教わったから」と彼女は言った。
——二十分も歩かない内に僕たちは、目的地である祖父の別荘に着いた。僕は一睡もしていないし、彼女だって寝たと言っても疲れは取れていないだろうから、二人とも、もう疲労困憊だった。
別荘の中は案の定埃まみれで、木の湿った匂いがした。僕達は今からここを掃除する気力など当然残っておらず、ひとまず自分たちが寝転がれるスペースだけを簡単に掃除をして、そこに倒れ込んだ。
「やっと眠れる」
「ありがとう。お疲れ様……私たち大丈夫かな」
「大丈夫だよ。何とかなるさ」
「もう、犯罪者ってことかな? 二人とも」
「そうだね。多分……そういうことになるね」
そこで、少しの間沈黙が流れる。
そのまま眠っても良かったのかもしれないが、僕はこの子が心配だったし、何か声をかけるべきだと思い「起きたら、掃除しような」と言ってみる。
彼女は「前の家より広いね」と答える。
「確かにね……」と僕はほとんど無意識に答え、そのまま、深い眠りの底へと落ちて行った。
【第一部】十九章 告白
目を覚ますと外は既に暗くなっていた。どれくらい眠ったのだろうか。
少女は先に起きて、窓から入り込む外灯の明かりで本を読んでいた。その本は、母親からもらったというあの本だった。
「起きてたんだ? 寝れた?」
「……私も今起きたばかり」
そう答えた彼女は、何やら元気がないように見えた。
—–—僕たちはひとまず、街まで食料を買いに行くことにした。子供の頃、この別荘に遊びに来た時の記憶がまだ残っていたので、おおよその場所は覚えていた。
夜道を歩いていると、彼女はやはり言葉数が少なかった。やはりこの一連のドタバタで疲れてしまったのかとも思ったが、寝る前はもう少し元気だったし、僕には起きてから様子が変わったように思えた。
「どうかした?」と僕が訪ねると、少し沈黙したあと、緊張した様子で彼女は「謝らなきゃいけないことがある」と切り出した。
「本当に……取り返しのつかない嘘をついてしまいました。もっと早く言うべきだったんだけど、怖くて、ずっと言い出せなくて……」
僕はその言葉で、彼女が何を言い出すのか検討はついたが、黙って聞くことにした。そして彼女は、先ほど読んでいたあの本を僕に手渡し、上ずりそうな声で話し始める。
「私が……その。つまり……私が、疫病の流行っている島から来たという話は……嘘なんです」
僕は「知ってたよ」と答える。
彼女は驚いて、時が止まったようにまん丸い目のまま、僕の顔を見つめている。
「前、部屋の掃除をしてる時に偶然、この本が本棚の上から落ちて来たんだ。時間があったから読ませてもらった。そしたら、君が話した疫病の島の話が全くそのまま、この小説の中に書かれていた。君はそのストーリーを、自分に当てはめて僕に話したんだろ?」
彼女は何も言わず、いや、何も言えず強張った表情のまま僕を見ている。僕は続ける。
「そりゃ驚いたし、ショックだったけど、きっと君はこの話をすれば、僕が君を追い出すと思ったんじゃないか? そして僕から離れようと思った。まあその気持ちは分かるよ。急に見知らぬ人を信用する方が難しいさ。
でも君は、その後にいつだって逃げ出す機会はあった筈なのに、逃げ出さずに僕との生活を選んでくれた。それに何らかの事情で、夜中に海を漂っていたことは事実なんだし、大変な事態だったということには変わりないんだ。だから別に、最初についた嘘なんてことは対した問題じゃない。気にすることないよ」
「ごめんなさい。本当に……私が初めから嘘なんてつかなければ、きっとこんなことにはなっていなかったのにと思うと、私があなたの生活を奪ってしまったような気がして」
そう言うと、彼女は泣き出した。
「いいって。ほら、今度の家だってそう悪くないよ。前よりも広いんだし、海からだってそう遠くないよ。だからあんまり変わらないよ」
「ありがとう。私はあの時……海を漂っていた時、恐怖でいっぱいだった。意識もほとんどなかったけど、多分このまま死んじゃうんだろうって、揺れる舟の上で考えていたんです。だけど、あの灯台の、オレンジ色の灯りが見えた時、一瞬暖かいモノが心に生まれた気がしたんです。
だけどやっぱり気は失ってしまって。次に気が付いた時は、あなたがそこにいました。暖かい暖炉と、おいしそうなスープの香りがしたことも覚えています。だから私は『あぁ、まだ生きているんだ』って分かったんです。
その時は生きているという事実だけで辛かったけど、今はもう辛くないです。こうしていられることは。あなたのおかげです」
「そっか。今生きてて良かったと思えるならそれが一番だね。良かったよ」
少女は涙を拭うと、短く深呼吸をした。
「少し長くなるかもしれないけど、本当のことを聞いてくれますか? 私がどうして夜の海を漂っていたのかを」
彼女のその言葉によって、鈍い音と共に重い扉の鍵が外された。そんな感じがした。
「うん。聞かせてほしい」と僕は答える。
【第一部】二十章 夜を駆ける
少女の家は父親、母親、そして彼女の三人で暮らしていたという。
彼女の父親は国の役人で、故郷では名の知れた人物だったそうだ。しかし彼には裏の顔があった。それは日常的に母親に対し暴力をふるうという一面であった。
母親は「あの人がいないと私たちは貧乏になってしまうから」と言って別れようとはしなかったそうだ。しかしそれは単なる理由付けであり、本当は母親はただ父親に依存しているだけだった。暴力を振るう時もあれば「すまなかった。もう二度と手はあげないから」という父親をいつも許し、そして翻弄されていた。
少女の故郷には争いごとも無く、平和な国ではあったが、国の役人として働いていた父親は、いつも国民の不満の吐口にされ、その度に困ったような笑顔を浮かべていたという。
——–そしてあの日。酷く酔った父親が帰って来た。
母親はふらついている父親を介抱しようとしていたが、父親は家に入るなり「なぜ俺の帰る時間に部屋が暖まっていないんだ!」と怒鳴り散らし、母親の顔をぶった。
少女もその音で目を覚まし、扉の隙間からその様子を覗いていた。
母親が「ごめんなさい」と謝ると父親は「いいからまず水を持って来い」と言った。
しかし母親は、殴られた恐怖で手が震えており、水を用意するのに手間取っていると父親は再び怒り、母親を張り倒した。そして転がった母親の腹を蹴り始めた。何度も何度も蹴り続けた。三発、四発、五発、どんどんと音は大きくなっていく。
少女は、このままでは母親が死んでしまうと思い、飛び出して父親の背中に飛び付いた。
父親は「お前も俺が嫌なんだろう!」と大きな声をあげ、少女を振り払うと、側にあった椅子を掴み、少女の目の前で振り上げた。
その時だった。後ろから母親が父親に体当たりをした。
父親の手にあった椅子は、床に落ちて大きな音をたてた。そして、父親の脇腹から血が流れ始めた。母親は、父親の脇腹から包丁を抜くと、今度は背中に力一杯突き立てた。そしてついに父親は床に倒れ込んだ。
母親は少女の元へ這って行くと、抱き寄せ、そして「ごめんなさい、ごめんなさい」と何度も繰り返した。「お母さんにもっと勇気があれば、こんなことにはならなかった。もっとはやく逃げるべきだった」
そして少女はそこで、母親からある秘密を打ち明けられた。
実は父親と母親は夫婦ではなく、不倫関係であったというのだった。父親には他に本来の家庭があるのだと。そして国の役人である父親は、不倫が表沙汰になってしまうことを避けるために、少女の出生を国に申し出ていないとのことだった。
つまり、《《少女は隠し子ということだった》》。
状況が状況なだけに、少女には十分に理解が追いつかなかったが、ただ。母親の言いたいことはこうだった。
「私は今この人を殺したことによって犯罪者となった。この先、犯罪者の娘として生きていくことはあなたにとって、大きな足かせになってしまうだろう。だけどあなたの存在は、この国には知られていない。だから今逃げなさい。もう会うことは出来ないけど、世界には、あなたのことを大切にしてくれる良い人が、たくさんいるから大丈夫」と。
少女は当然それを拒否した。嫌だと言った。どこに逃げればいいのか、一人でどうすればいいのか、何も分からないと。
そうごねる少女の手を引いて、母親は、裏口から家を飛び出した。人気のない暗い路地を、少女の手を力強く握り駆け抜けた。その手には、空気に触れて固まりつつある、父親の血液が付いていた。
——–島の南にある入り江に着くと母親は、海水で少女の手に付いた血をよく洗った。
そこには小舟が一艘あり、あれは父親の舟だと母親は少女に教えた。少女が生まれる前。まだ父親が優しく暴力も振るわなかった頃は、舟でよく沖に出ていたのだと、昔聞かされたことを少女は思い出した。
「まだ使えるはずだから、あれに乗って南に向かって。しばらくすると灯台の灯りが見えるから、そこを目指して進みなさい。そこの人達がきっと、助けてくれるから」と、そう言った。
少女はずっと泣いていた。「そんなこと出来ない!」と言った。
すると母親は、少女の頬を強くぶち「言う通りにしなさい!」と怒鳴った。
少女が母親にぶたれたのは、この時が最初で最後だった。
そして「またすぐに会えるから」と言った。少女には、その言葉が本当でない事は分かったが、受け取るしかなかった。
少女はほとんど強制的に舟へ押し込まれ、海へと流された。泳いで岸に戻ることも出来たが、母親をこれ以上困らせることも出来ず、ただ言う通りにするしかなかった。小さくなっていく母親を見ながら、少女はずっと泣いていた。
そして、家を飛び出すとき、母親に着さされたコートのポケットには、疫病に侵され一つの島国が崩壊するまでを書いた、一冊の小説本が入っていた。
【第一部】二十一章 深緑色の傘
光の裏には闇があるというが、ある場合には、闇を隠すために闇を使うこともある。少女の告白はそんな人生の不条理を感じさせるものだった。ただ偶然。そこに生まれ落ちただけの命に、なぜそんな厳しい現実が用意されてなくてはいけないのだろうか。
この別荘に逃げて来て一週間が経過し、大掃除も終わり、あらかた必要な物は揃えることが出来ていた。そして僕は、これからのことを考えていた。
あの子の故郷が疫病の島でないということが確定し、あの子の母親は、まだ生きていることが分かった。しかしおそらく今はもう捕まってしまっているだろう。例えば僕が父親のフリをして、あの子を連れて、面会に行くことは出来るのかもしれない。けれども、城の役人を殺害したとなれば、母親はもう牢屋から出ることは出来ないだろうし、悪ければ死刑もある。
あの子は、どのくらいまで理解しているのだろうか……
分からないが、これから殺されてしまうかもしれない母親に会うことは、余計辛いのではないだろうか。きっとあの子は、僕が想像する以上に色々なことを理解し、そして受け入れようとしているのかもしれない。
「ただいま」
スケッチブックを抱えた少女が、外から帰ってくる。
僕はあまりに考え込んでいたので、つい返事するのを忘れてしまう。
「帰ったぞ!」と、彼女は僕の近くでもう一度、大きな声で言った。
「わっ! お、おかえり」と僕はびっくりして答える。
「どうかした?」
「いやいや、どうもしないよ。なに、今日は何を描いてきたの?」
彼女は僕の質問には答えず、握りしめた右手をこちらに差し出した。僕は彼女の顔をちらりと見やり、何かを手渡そうとしていることを理解する。僕は彼女の握りしめた手の下に、両手で水をすくうような形の手を差し出す。彼女が手を開くと、僕の手のひらに落ちてきた物はクルミだった。
「クルミかあ。どうしたのこれ?」
「いっぱい落ちてる場所見つけたんだ。これで、何か美味しいもの作れる?」
「そうだね。なんだろう、サラダにも使えるし、あと、鶏肉とかキノコとかと一緒に料理してもいけると思う」
「それ、食べたい」
「よし。じゃあ、食材を買いに行こうか」
というわけで僕たちは、街の市場まで晩御飯の材料その他諸々を、買いに行くことにした。
——–僕たちは祖父の別荘を出ると、海とは反対方向にある街の方へと歩き出した。
その道中、水路を泳いでいる鴨を見つけると少女は、不意に「ねえ。馬が泳いでるところ見たことある?」と聞いてきた。
「ないかな。馬って泳げるの?」と僕は聞き返す。
「泳げるよ。私一度だけ見たことがあって、ブルブルと鼻を鳴らしながら器用に泳ぐんだよ。なんかね、城で飼ってる馬が逃げ出して、近くの池に落っこちたんだって。私急いで友達を呼びに行ったんだけど、友達と戻った時にはもう引き上げられて、体を拭かれてるところだった」
「そうか、そりゃあ惜しかったね。でも馬が無事でよかったじゃないか」
「うん、そうだね」
と、こんな具合に僕たちは特に中身のない会話を交わしながら歩いた。しかし、まだ慣れない新居から街への順路。無意識で辿り着くことは出来ない。
「ここ曲がるんだったよね?」と、僕が言い。
「もう一つ先だよ」と彼女が答える。
「あ、そうだそうだ」と互いに確認しながら進まなければならなかった。その感覚は同時に、僕たちに新生活という新鮮な空気を、取り入れてもくれていた。
それにしても、僕は早く仕事を見つけなければいけない。まだしばらくは大丈夫だけど、この子も思ったよりも元気そうだから、あとはお金さえ安定させられれば、ひとまずはそれなりに何とか暮らしていけるだろう。
——–街に着くと、それほど人で賑わっていたわけではないが、通りにはたくさんの店が軒を連ねていた。服屋、酒屋、雑貨屋、食べもの屋、宝石屋など。灯台の方にあった街よりもこちらの方が、少し大きい街のようだ。少女はその中でも、傘屋に興味をそそられたようだった。店先には売り物の傘が、色とりどりに並んでいた。
彼女は美しい深緑色の傘を手に取り「広げてもいいかな?」と僕に尋ねる。
「ゆっくりね」と僕は答える。
ばっと広げた傘はとても大きく、彼女の体はすっぽりと包まれた。
「それなら全く濡れずに歩けそうだ」と僕は言う。
「この傘があれば、雨の日だって待ち遠しくなるね」そう言いながら彼女は、クルクルと回った。
僕は彼女のそんな姿を、出来ることなら彼女の母親にも見せてやりたいと思った。命がけで我が子を海に流した母親の判断が正しかったのかは分からないが、少なくとも彼女は、賭けに勝ったと考えて良いだろう。いまこうして、あなたの娘は元気なのだから。
少女は傘を閉じると、元の場所に置き「行こっか」と言った。
——–その後、僕たちは通りを抜け市場で食材を買い、家に帰る道中で、彼女の言ったクルミの落ちている場所に寄って、いくつかのクルミを拾って帰り、晩御飯にはクルミを使った何品かの料理を作って食べた。
サラダは予想通りの味に作れたが、その他は何とも微妙な仕上がりだった。彼女は満足そうだった。
【第一部】二十二章 朝焼け
––––この別荘に越して来て、もう半年が経っていた。
夜明け頃、僕は体を揺らされて目を覚ました。
目の前には少女が立っていて、その背後の窓から小さな朝焼けの空が見えた。今、一体何時なんだ?
「どうしたの?」と僕は尋ねた。
「……血が出た」
「え、血って、どうして?」と聞くと、彼女は黙り込んでしまった。
ああ。なるほど……僕は、その様子で察した。
「こういうのは初めて?」と聞くと、彼女は頷いた。
「そっか。それはね、君くらいの年齢になるとみんな起こることなんだ。聞いたことはある?」
「ある……」
「そっか、とにかくそれは当たり前のことで、君がある意味健康な証でもあり、大人になった一つの証でもあり、んん何ていうか、あえて心配するようなことじゃないんだ。だけどこれから月に一回くらいはあるはずだから」
「……シーツを汚しちゃった」
「大丈夫だよ。シーツはどうする? 自分で洗うかい?」と言うと彼女は頷いた。
「体調が悪くなったら、すぐに言うんだよ」と言うと、彼女は分かったと言って、自分のベッドの方に戻った。
僕はもう一度横になり目を閉じた。彼女がばたばたとシーツをはぎ取り、外に持って行く音が聞こえる。まだ陽も上りきらない朝焼けの中に、血のついたシーツを抱えて、溶けて行く少女の様子を僕は想像する。そして、ふと気がつくと僕の顔は緩んでいた。何となく、あの子の成長が嬉しいと感じたのだと思う。たった一年ほど一緒に過ごしただけだけど、父親のような気分になっていたのかもしれない。
僕は二度寝は止めることにして、あの子が洗濯を終えて戻って来るまでに、朝ごはんを作ることにした。
この国では、初潮を迎えた女の子には、ハチミツを食べさせるのが一つの文化としてある。しかし彼女は、外の国の子だし、こういうときの女の子の心理が、僕にはよく分からないので、特別なことはやめておくことにした。僕はいつも通り、パンにスライスしたトマトとチーズを挟み、トースターで焼いた。それと、タマネギとキノコを使った簡単なスープを作った。
––––二十分が経ち、ちょうど朝食が出来上がる頃、シーツを干し終えた彼女が戻って来たので「朝ご飯食べれる?」と聞くと、食べれるというので僕たちは食卓を挟み、椅子に座った。
「いただきまーす!」と言うと同時くらいに、外で何やら物音がした。
「……なんだろう。聞こえた?」と僕は彼女に聞く。
「うん。何か落ちるような音」
音の距離は近かった。玄関のすぐ向こうに何かがいるのか?
「ちょっと待ってて」と僕は彼女にそう伝え、扉の方まで進む。
取手に手をかけ、ゆっくりと、ほんの少しだけ扉を開き覗いてみると、そこから見えたのは山羊だった。わずかな隙間なので顔と前足くらいしか見えなかったが、山羊がすぐそこに横たわっていた。
「なんで山羊が?」少なくとも人間じゃなかったことで僕はホッとして、扉を全開にする。
しかしその瞬間。僕の背筋は一瞬で凍り付くことになる。
山羊の下半身が無いのである。
「なっ、なんなんだ……」
【第一部】二十三章 骨髄
「なっ、なんなんだ……」
腹より下は、何か鋭利なもので切断されたように、すっかりなくなっていた。切断面には骨の髄が見え、生臭い血の匂いが漂っている。しかもまだ意識があるようで、山羊の虚ろな目は、わずかに動いていた。
僕は嫌な予感がして、急いで扉を閉め鍵をかける。
「何だったの?」と少女は心配そうに僕に尋ねるが、僕はほとんど過呼吸のようになっており、すぐには答えられなかった。
「はぁ、はぁ、山羊だよ。死にかけの山羊だ」
「山羊? 私がさっきシーツを干した時には何も……」
「嫌な予感がするよ」
「きっとあの男だよ! あなたのことを撃とうとしたあの、使いの男」
「僕もあの男のことはよぎった。だけど、なぜこんな猟奇的なまねを? 僕らを捕まえるつもりなら普通、衛兵を連れてやってくるはずだ」
「ううん。私には、あいつがまともな人間には見えなかった。多分もっとどろどろしたものに覆われてて、自分が人とは違う特別な存在だと思い込んでいるような、きっとそんな奴だ」
なぜ彼女がそこまで、あの男の人間性について見抜けたのか、僕には分からなかったが、そういえばあの老婆も、男が危険であるという話をしていたことを、僕は思い出す。
「じゃあ例えば、今はすぐ近くに潜んでて、僕たちが怖がってるのを楽しんでいる。そんな感じのことかな?」
「そんな感じだと思う」
「そうか……」
しかし男の拳銃は、あの時海に投げ捨ててきた。城の正式な職務として僕たちを追いかけているわけじゃないなら、新たな銃も支給されることはない。おそらく奴は今銃は持っていないはずだ。
だけど、どうすればいい。まるでケージに入れられた実験動物の気分だ。落ち着かない。動くことが危険でもあり、ここに立て篭もることもまた危険に思えた。
僕は全ての窓に鍵がかかっていることを確かめ、カーテンを閉めた。そして彼女の手を引いて階段の下まで連れていく。
「ひとまず様子を伺おう。今すぐは動かない方がいいと思う。僕は二階で武器になりそうな物を探してくるから、君はここで待ってて。ここなら扉かも窓からも離れてるから。もし何か異変があれば、大きな声で教えて」
「分かった」と彼女は言う。
さっきの切断された山羊を見せられて分かった。きっと彼女の言う通りだ。相手はまともじゃない。こっちだって覚悟を決めなくてはいけないということか。
——–僕は階段を上がると、まだほとんど踏み入れてなかった、かつて父が書斎として使っていた部屋に入った。
そして父が使っていた机の前に立つ。今はこの父の別荘を、勝手に使わせてもらっている訳だが、それでもやはり、人の机の引き出しを勝手に開けるのには抵抗があり、今まで開けたことはなかった。
一段目を開けてみると、中身のないペンケースといくつかのクリップがあるだけだった。次は二段目を開けてみる。空だった。続いて三段目。中にはよく分からない書類が数枚入っているだけだった。
最後に四段目。他の引き出しよりも多少、高さが設けられている引き出しだ。開けると、中には大きな四角い缶が入っていた。
僕はそれを手に取ると、机の上に置いた。蓋を開けると、中には日焼けした地図、コンパス、帽子、懐中電灯、そしてダガーナイフが入っていた。
「武器……あった」と思わず声が出た。
それは刃渡り約二十センチ以上はある本格的な両刃作りで、多少古びてはいるが、重量感のあるナイフだった。これなら十分に人を殺すことが出来るだろう。
一緒に入っていたホルダーにそのナイフを納め、腰に装着した。
しかし、いざ武器が見つかってしまうと、それはそれで戸惑ってしまう。確かに今、僕たちが追い詰められていることも、あの使いの男が危険であることも事実だろう。
だけど、僕にこのナイフで人を殺すことなんて出来るだろうか。例えばどうしようもなく追い詰められ、少女の命に関わるような事態となれば、アイツにこの刃を、突き立てることが出来るのだろうか。そう、例えば少女の母親のように。
その時だった。
「大変! 降りて来て!」と少女の呼ぶ声が下から聞こえた。
僕は父の書斎を飛び出し、階段を駆け下りる。
焦げくさい臭いと共に、立ち上がる大きな炎が僕の目に飛び込んできた。
「なっ⁉」
家の玄関辺りから火をつけられ、少しずつ燃え広がっているようだった。
「もうダメだよ! 逃げるしかないよ!」と少女は言う。
確かに家の中に水気のものはないから、消火することは不可能だ。いくら奴が外で待ち構えているとはいえ、僕たちに残された選択肢は、家から飛び出すという一択だけだった。
しかし奴はおそらく、入り口を燃やすことによって、僕たちを窓から逃げさせようとしているのだろう。いま二人で窓から飛び出せば奴の思う壺だ。
「いいかい? よく聞いて。僕は今からそこの窓から飛び出して、男を引きつける。君は三十秒数えてから出てくるんだ。向こうの壁と床の角に顔を近づけて浅く呼吸をするんだよ。これくらいの火ならまだしばらく大丈夫だから」
少女は涙目になっていたが、泣かないよう我慢しているようだった。
「分かった。無事でね。後でね」と少女は答える。
「うん。後で小舟のところで会おう」
僕は窓から飛び出した。
——–やはりそこには、松明を手に持った、あの使いの男が立っていた。
「おや。まだそんなに燃えていないのに、もう飛び出すのですね」と男は楽しそうに笑っている。
それはまさに、自分の趣味を楽しむ人間の顔であった。
その顔を見た瞬間。僕は自分の心が冷たくなっていくのを感じた。
あの子を守るためには、僕はこいつを殺さなくてはいけない。
そう。話が通じるような相手ではない。
僕は、腰のナイフに右手を添えた。
【第一部】二十四章 おまもりのうた
僕は右手で、腰につけたホルダーの留め具を外し、ナイフを抜き取ると、それを男に向かって構えた。
「そんなものを出して。人を殺したこともないくせに、お前に何が出来るというんだ」と、使いの男はあざ笑うように言った。
「残念だけど、ここには僕しかいないよ」
「嘘をつくな。お前だけがどうしてこここにいる? しかもこんな時間に——」
使いの男が喋り終わる前に、僕は思い切り地面を蹴り、奴の腹に向かって突進する。使いの男は反射的に横に跳び避けた。
ナイフは使いの男の太もも辺りをかすめ、ズボンとその中の肉を、少しだけ裂いたようだった。
「このバカが!」と、奴は僕を睨む。
「今ので分かったろう。僕は本気だ」
僕はもう一度、ナイフを両手でしっかりと握り、正面に構えると、突進する体制に入る。足に力を入れようとした瞬間、奴は持っていた松明を僕の顔目掛け投げつけた。
僕は反射的に両腕で顔をガードする。視界が塞がれ、一瞬腕に凄まじい熱が伝わるが、松明は僕の腕に弾かれ背後に飛んで行った。
しかし、次の瞬間。
僕の視界に映ったのは、五メートルほど先でライフル銃を構える、奴の姿だった。
あれは。あのライフル銃はそう、灯台の監視台に置いてあった物だ。
そうか、どうして僕は気付かなかったんだろう。いつもあんなに身近に、銃が置いてあったことに…………
「私の勝ちだ。惜しかったな」
けたたましい音と共に二発の銃弾が放たれ、僕の太ももと腹に命中した。痛みは無かった。何かが自分の体を通り抜けていった。それから力の抜けるような感覚があり、僕はそのまま地面に倒れ込んだ。
音を聞いたのか、それとももう三十秒経ったのか分からないが、少女が窓から出てくる。
そして、もうろうとする意識の中で、彼女の悲鳴が聞こえ、僕のもとへ駆け寄って来るのが分かった。
「そんな……」
彼女はしゃがみ込んで、僕の撃たれた傷の具合を見ているようだったが、くるりと向きを変え、僕を背中に隠すようにして男の方を向いた。
僕は、少女の背中に向けて声を放つ。
「おい逃げろ。早く。何やってんだ」
しかし少女は、背中を向けたまま答えない。
男は、銃に新しい弾を込めながら言った。
「そのガキを逃すわけがないだろう。一体、誰の頭をぶん殴ったと思ってるんだ? いいか、お前らは二人ともここで死ぬんだ。それはもう決まっている事だ」
僕は、力を振り絞って腕を動かし、少女の背中を強く叩いた。
「逃げろってんだ! ばかやろう!」
しかし彼女は、振り返ると僕の首に抱きついた。
そして「ありがとう」と、耳元で囁いた。
それから彼女は立ち上がり、男を真っ直ぐに見つめ、言い放つ。
「だから私はあの時、お前に止めをさしておこうと思ったんだ。お前がどんな危険な人間か分かってた。お母さんをいつも殴ってたあのクズと同じ匂いがしたんだ。撃つなら撃てばいい。私にはもうどこにも行く所なんてない。
だけどお前みたいにはならない。お前はずっとそんな風に、その銃口をあらゆる人に向けながら生きて行くんだ。誰にも愛されないってことを、言い訳にしながら」
男の目は本気になっていた。もはや、子供を見る目ではなくなっている。
「言いたいことはそれだけか?」と言い、少女の顔へ銃口を向ける。
しかし彼女の目は、もう涙目ではないし、怯えているようでもなかった。ただ冷たい瞳がそこにあった。いや……だけどおかしい。僕から彼女の顔が見える筈はないのに、背中越しでもそのガラス玉のような瞳を、僕は確かに見ることが出来た。
「ううん。そっか、きっと大変だったんだね。同情してあげるよ。お母さんには愛されなかったの? 私のお母さんは私を愛してくれたよ。それを知らずに大人になるのは大変なことなんだね。可哀想だから同情してあげる。辛かったんだね」と言って彼女は笑った。「これで満足?」
いつも冷静だった男の姿はもう無い。男は怒りにまかせその勢いのまま引き金を引く。またしても、けたたましい破裂音が鳴り響いた。
それは、運命の糸が断ち切られる音なのか、それとも紡がれる音なのか……少女の体は文字通り貫かれる。二十二口径の金属の塊が、彼女の頭部を通り抜ける際に、何億、何兆という組織を破壊する。それにより、彼女は笑うことも、泣くことも、僕に語り掛けることも、たった今不可能となった。
倒れた彼女の後頭部が僕の目に映り込んだ。その小さな頭から血の池ができ、広がっていった。少女のもとに近づきたいが体が動かない。
「ちょうど弾切れか。胸くその悪いガキが」
奴がそう言ったのを覚えている。その言葉の記憶を最後に、僕はそのまま意識を失った。
すぐ隣では、僕たちの家が燃えていた。
【第一部】二十五章 パレード
真っ暗な画面の中には、線香花火のような、小さな火花がぱちぱちと散っている。やがてその火花から色々なものが形成され、しばらくすると弾け、また新たなイメージが創られる。それが何度も繰り返されていく。
雪の降りしきる海。
少女を運ぶ小舟。
それを照らす灯台の灯り。
名も知らない白い花。
暗い瞳。
嘘を隠した、母の本。
絵を描く小さな手。
フライパンを握る頼もしい手。
笑ったときの顔。
そして、火花は少女の形で留まり、僕に語りかける。
——–「私は昔、故郷の街で一度だけ、パレードを見たことがあった。お母さんが私の七歳の誕生日の時に、連れて行ってくれたんだ。夏の涼しい夕方だった。年に一度の大きなパレードで、外の国から観に来ている人もいたから、すごく賑わってた。私は背が小さいからあまりちゃんと見えなくて、半べそをかいてた。
そしたら、前で見てた二人組の男女が私に気付いて、前で見なよって譲ってくれたんだ。お母さんはその人達にお礼を言って、私を連れて前に出た。そのおかげで私はパレードをちゃんと見ることが出来たんだ。
—–—パレードが終わった後、私とお母さんは、場所を譲ってくれたその二人と一緒に、レストランへ夜ご飯を食べに行った。
二人は、ここから二十キロメートルほど南の、ある国から、観光にやって来てたそうで、今日は泊まって明日の夕方頃に帰るって言ってた。今はその国の一番北にある、灯台下の家に二人で住んでいるそうで、男の人の方が、『僕たちは今年の冬には結婚するんです』って言った。女の人も嬉しそうだったけど、私はその人から何か、影のようなものを感じた。
その後、私がトイレで手を洗っていると、その女の人が入って来た。私を見つけるなり目の前まで来てしゃがみ込むと、私の顔を見つめ言った。
『もし良かったら、まだ誰にも話していない秘密の話を、聞いてくれない?』って。
私が頷くと、その女の人はこんな事を話し始めた。
『実は私は、あの人とは結婚出来ないんだ。どうしてかって言うと、私はもうすぐあの人の心臓になるの。あの人の心臓は海に住む悪い菌にやられてしまって、もうかなり弱ってる。だから私は昨日、城の病院まで行って来たの。
そこで心臓を移植するための手続きをして来たんだ。だからつまり、私が死んだ時は他の人のために、どうぞこの心臓を使って下さいってこと』
当時七歳の私には、その話は半分くらいしか理解出来なかったけど、その女の人の目が、何ていうかあまりにも真っ暗で、先の見えない洞窟のようで、私はその引力にひかれて、目を、意識を、そらすことが出来なかった。
その女の人は話を続ける。
『彼は、お医者さんの話では、冬まではもたないから、多分あと二ヶ月もしないうちに倒れて病院に運ばれてしまう。私はその時にすぐ死ねるように、ある薬を持ち歩いてるんだ。もちろん。心臓には害を残さないものだけど。そうすれば、私の心臓を使ってもらえるでしょ?
私はもう。あの人がいない世界では、生きて行く気になれなくて。わがままだとは思うけど、嫌なんだ。どうしても。だから文字通り私は、あの人の中で生きて行くことを選ぼうと思った。それが、私にとって一番良い選択なんだ。あの人にとってはきっと違うだろうけど……あなたはまだ七歳だったかな? 意味分からないよね。ごめんね。怖い話をしちゃって』
そこまで話すと、女の人は泣き出したので、私が泣かないでと言うと、その人は私を抱きしめた。私はそのまま動かないことにした。
そしてその人が泣き止むと、私達は席へと戻った。
席に戻ると、女の人は何事もなったかのように、穏やかな表情で振る舞っていた。その二人の様子を見ていると、それはもう既に夫婦のように思えた。二人は本当によく似ていたから。
——–この話は、もう結構前の事だけど、私はあの岬であなたに助けられた時からずっと、記憶のどこかで何か引っかかってる気がしてた。それであなたが、亡くなった恋人の話をしてくれた時に、パチンッて綺麗に繋がった。やっと思い出すことが出来たんだ。
だからお母さんはあの時『そこの人達が助けてくれる』って、私に言ったんだって分かった。
暗い顔をしてた私に、いつも話しかけてくれてありがとう。疫病にかかってるかもしれないのに、受け入れてくれてありがとう。嘘をついたこと、許してくれてありがとう。絵の描き方を教えてくれて、いつも美味しい料理を作ってくれて、本当にありがとう。
色々あったけど今思えば私は、不幸なんかじゃなかったと思う。スケッチブックをくれた時は、本当は飛び上がりたい気分だった。私も、あなたの体の一部になれたら良かった。それじゃあ、ばいばい」
そしてその少女の形をしたものは、またぱちぱちと火花をちらしながら消えていった。ついに画面は真っ暗になり、深い静寂が訪れる。
そこにはもう、生命と呼べそうなものは、何も残っていなかった。
「重なり合うプシュケーの塔」
【第一部】 完
【第二部】二十六章 森の教会

——–目を覚ますと、知らない天井がそこにあった。体の痛みを感じた。だから僕は、自分がまだ生きているということを知った。
周りを見渡すと、そこは六畳ほどの大きさの部屋で、ベッドの他には、薬の瓶などが置かれた棚、四角い窓、その窓にひっ付ける形で置かれた机と椅子。そして木の扉があった。
上体を起こそうとしたが、うまく力が入らない。体はぼろぼろで、心は他の場所に置き忘れて来たように空っぽだった。
扉が開き人が入ってくる。見るとそれは、いつか浜辺で会った、膝にしゃれこうべを抱えた、あの盲目の老婆であった。老婆は何も言わずに窓を開け放し、手に持っていたグラスと薬を、ベッド脇のテーブルに置いた。そして、椅子に腰掛け、僕の方に顔を向けた。もちろん、目は閉じたまま。
僕の気のせいだろうか、老婆はあの浜辺で会った時よりも若返ったように見えた。あの時は八十歳は過ぎたご老人だった気がするが、今はどう見ても六十代くらいに見えた。老婆ではなく、老婦人と言った方が良いのかもしれない。
「目が覚めましたか? 陽の光が眩しいでしょう。すぐ慣れますよ。ここは、もう誰も訪れることのなくなった、忘れられた教会です。かつては人で賑わっていたし、私もここの修道女だったけど、今はただ、ここが朽ちないように守りながら暮しているだけです。
ここにはもうずっと誰も来ていないし、もし来たいと思う方がいたとしても、辿り着くことは出来ない筈です。それは道が複雑だからという理由ではなく、望まない人にとっては見つけようがないという意味です。
だから、|プシュケー《魂》を休めるにはどこよりも適した場所です。まだ休んでいなさい。あなたはしばらく休んだ方がいい」
そう言うと老婦人は、僕の左手を取り両手で包んだ。暖かく柔らかい老婦人の手には、混じり気のない慈しみがあった。その手は、僕の精神にのしかかる何かを、ゆっくりと退かせようとしてくれている。その何かは僕の内側で、胸の辺りから徐々にスライドして、左肩、左膝、左の手の平へ、そして、老婦人の手へと移って行く。
途端、悲しみが胸に広がり、涙がぽろぽろと出てきた。空っぽだった僕の心が、痛みを取り戻したことが分かった。
呼吸が、胸が、息苦しい。痛い…………。
老婦人は手を離し「今は、泣けるだけ泣きなさい。その方がいいでしょう」と見える筈のない眼差しを向け、言った。
「私はもう少しやることがあるから、あなたは落ち着いたらそこの水を飲んで、まだ少しゆっくりしていて下さい。もし歩けそうなら、この辺りを散歩するのも良いかもしれませんね。この辺りは空気が澄んでいますから」
そして、最初部屋に入って来た時よりも重い足取りで、老婦人は部屋を出て行った。僕の枕は既に、濡れてぐしゃぐしゃになっていた。
頬が冷たいので僕は上体を起こしてみることにした。目が回るような感覚が訪れる。僕はどのくらい眠っていたのだろう。その回転が落ち着くまでしばらく、僕は目を閉じて待った。
それからゆっくりと目を開き、ぼやけた視界で窓の外を見ると、どこかの森のようだった。老婦人が窓を開けて行ってくれたおかげで、初春の新鮮な空気が部屋に流れ込んできた。
僕は、近くにある机の角を掴んで、腕の力を使い無理やり立ち上がる。机のすぐ横には杖が置かれていた。きっとあの老婦人が僕のために置いてくれているのだろう。僕は杖をつきながら歩き、部屋の扉を開けた。
すると目の前に、美しい、教会堂内部の景観が開かれた。
【第二部】二十八章 暗い瞳の青年
天井には花紋様の装飾が施され、カラフルなステンドグラスには、様々な物語が陽の光を通して七色に輝いている。柱頭には、ごつごつとした個性的な彫刻。そして祭壇には白い布がかけられ、その向こうの壁に、聖体を安置している証の赤いランプが灯っていた。
僕は杖をつきながら身廊を歩き、誰もいない会衆席へ座る。あの老婦人がいつも掃除をしているおかげだろう。席には埃一つなかった。
それからしばらく、僕はぼんやりと教会内部の様子を眺めていた。ふと壁に目をやると、所々から細い光が差し込んでいた。
近付いて見てみると、壁にはガラス玉がいくつか埋め込まれており、そのガラス玉を通して入り込む光だと分かった。
やがて外から老婦人が戻って来る。老婦人はこちらまで歩いてくると、僕の隣に腰掛けた。
「三十年ほど前。いえ。実際の時間で言うと五十年前です。まだ私もあなたくらいの歳の頃のことです。この周りにも人が住んでいて、多くの人がこの教会を必要としていました。
——–ある日の昼下がり、一人の青年が訪ねてきました。それはそれは深淵のような暗い瞳の青年でした。初めて見る顔で、身なりからしてもおそらく旅人だろうと私は思いました。長い紺色のローブを着込み、あちらこちら泥が跳ねて汚れていて、顔つきからしてまだおそらく二十代の中頃くらいだろうという感じでした。
私が『なんの御用でしょう?』と尋ねると彼は、『もし水があれば、分けては頂けませんか?』と言いました。
私は教会の裏手にある井戸まで青年を案内し、『ここの井戸水であれば好きなだけ飲んで構いません』と言いました。彼はお礼を述べ、井戸水を汲み上げて飲み始めました。それも、ごくごくと凄い勢いで大量の水を飲んだのです。
もしかしたら数日、何も飲み食いをしていなかったのかもしれないと思い、私は『パンはいかがですか? 時間があるようでしたら、その着ているものも洗って差し上げますが』と提案しました。しかし彼は『ありがとう。だけど、今は時間がないからお気持ちだけ受け取らせて下さい』と丁重に断りました。
それから私たちはまた教会の正面へ回り込みました。
『どうかお気をつけて。そして困った時はまたいつでも、この教会を訪ねて下さい』と私は彼に別れの言葉を告げました。
すると彼は、鞄から綺麗な青色の輝く石を取り出すと、こちらに差し出し『これは、旅の途中に出会った商人から譲り受けた、マラムという宝石です。これを売れば、一年分ほどの生活の糧となるはずです。親切にして頂いたお礼です。受け取って下さい』と言いました。
私は『これはしかし、私のした行いを遥かに超える対価です』と言いました。
彼は『そんなことはありません。あなたは僕だけでなく、ここに訪れる全ての人へ分け隔てなく慈悲の心を向けてきたのでしょう。これでは足りないくらいです。それに僕は罪を犯した身の人間です。このような物を持ち歩くのは、あまり似合いません』と言いました。
私は、青年の言うその罪というものが、何なのか分かりませんが、その暗い瞳からは何か深い部分で入り混じった、混沌のような心情が伺えました。
『ありがとうございます。では、この石はこの教会のために使わせて頂きます』と言い、私はそのマラムという宝石を受け取りました。
彼は力なく笑い『もし時間があれば、僕はあなたに、その罪を打ち明けていたと思います。またこの国に来ることが出来たら、ここを必ず訪ねたいと思います』と言い、森の中へと消えて行きました。
それから一年後、彼は本当にまた、この教会を訪れてくれたのです。
『お久しぶりです』と彼が現れた時は、私はまるで夢のように思いました。何となく、彼にはもう二度と会えないような気がしていたものですから。
それから彼はほとんど毎日、この教会に訪れてお祈りをして帰るようになりました。彼がここに通ってくれている間は、私は彼と色々な話をしました。彼は両親の話や仕事の話など、たくさんのことを私に話してくれました。
私も同じくらい、特に楽しくもない身の上話を、たくさんしたことと思います。気がつくと私は毎日、彼が来ることを楽しみにするようになっていました。
そして彼の瞳はもう、初めて会った時のような暗い瞳ではなくなっていました。そうですね。それは、海のような……そんな、優しい瞳でした。きっとそれがあの人の、本来の色だったのだと思います」
——–老婦人は、光の失ったその目を閉じたまま微笑んでいた。
「ごめんなさいね。長話になりました。もうとても昔の話です。ただあなたの瞳が、その時の青年の瞳とよく似ているのです」
そう言うと老婦人は、僕の顔を覗き込んだ。もちろん、まぶたは閉じたままで。
「今は確かに暗いけれど、また必ず元のような優しい瞳に戻るでしょう。さぁ、では行きましょうか。少し歩きますが、ゆっくり行きましょう」と老婦人は言う。
僕は頷く。
【第二部】二十八章 故郷の花
僕たちは教会を出ると、森へ入り坂道を上っていく。老婦人は、やはりあの浜辺で会った時よりも若返っているようで、山を上るその足取りも軽かった。
だけど、ゆっくりしか歩けない僕を気づかい、合わせて歩いてくれているようだった。この人が白杖も無しに、山道を上ることが出来ることに対し、僕は特に疑問は持たなかった。この人の実体はきっと、あの浜辺に座る老婆なのだから。
山道を登っていくにつれ、道端にちらほらと花を見かけるようになった。その花は、かつて僕が灯台近くの森で老婆に言われ摘んで帰ったあの中心が白く、花弁が水色の花。そう、少女の故郷の花だった。
山道を上れば上るほど、その花が道を占める割合は増えて行く。そして、足元のほとんどがその花で覆われて、踏まずに歩くのが困難になってきたころ、やっと森を抜け、開けた場所へと出た。
——–そこは、一面その花で覆い尽くされた高台の丘であった。向こうには海も見える。
「さぁ、もうそこです」と老婦人は、その丘の中心の方を指差した。
僕は、後ろを付いて歩く。既に花は、踏まなければ一歩も進めないまでになっていた。僕はなるべく、老婦人が踏んだ花の上を歩く。そして、丘の中心へと到着する。
そこには、木で作られた墓標となる十字架があった。まるで故人を慰めるかのように、その墓を中心に、花はぎっしりと咲き誇っていた。いや、そうではなく、この墓が花を咲かせているのかもしれない。
老婦人は墓の少し手前で止まり、僕を振り返る。
僕は老婦人に深く頭を下げ、墓の前まで歩み寄る。
少女の頭に手を添えるように、そっと、十字架の天辺へと手を置いた。
しかし何も感じなかった。当たり前だ。それは……ただの冷たい木である。
僕は目をつむる。風が吹き、花は揺れる。長い間眠っていた気もするが、この体にも、少女との記憶は残っているようだった。
この十字架の下に、彼女が横たわっているのだと思うと、胸が締め付けられた。腹の弾痕が、熱を持ちうずき出す。
結局、この子を守ることの出来なかった自分が情けなかった。むしろ守られたのは僕の方だった。
重い扉が開かれ、心に抑えつけていた思いが、言葉となり流れ出る。
「僕はどうすれば良かったんだろう。初めて君を助けた夜に、やはりすぐ城に報告するべきだったのかな。それで故郷に送り返されるくらいなら、それなら、あの灯台で時間を使いながら、少しずつ生き方を見つけて行く方が良いように思ったんだ。
だけどね。だけど……今だから、正直に言うと、君が来てくれたことが、僕は嬉しかったんだ。恋人が亡くなってからはずっと一人で暮してた。それは穏やかで自由な生活だった。一人でも幸せだからという理由で、僕は人と関わることを避けていたように思う。
それが間違いだったとは、別に思ってないんだ。だけどね、君が来てからの方が、ずっと楽しかった。多分僕は、本当は誰かと話がしたかったんだと思う。一人じゃなく、誰かと空間を分け合って、下らないことでも報告し合って、そして、誰かの為にサンドイッチを焼くような生活を、僕は望んでいたんだ。望むことは怖いことだと知っていたから、僕は望まなかったんだ。今はもう、君とお喋りが出来ないから、つまらないね。
僕が君の父親の代わりになれたかどうかは、分からないけど、いや、正直そんなことはどうだっていいんだ。ただ僕は。君が少しずつ元気になってくれてたことが、本当に嬉しかった。だって、良い人間が苦労するばかりの世界じゃ辛いだろ? きっとそんな筈はないって、もっと『世界』は、一人一人のために存在していて良いものなんだ。
そしてその『世界』を見つけることが君の旅であり、僕の旅でもあったんだ。だから君は僕の中に、抱えきれないくらいの多くの意味を残してくれたよ。それは今までだけじゃなくて、これからもまだ僕の『世界』の中で増えていくんだ。きっと君のお母さんにとってもそうなんだよ。君が関わった人全てに、君はそんな風にこれからも、ここに咲くこの花達のように、凛とした姿を見せてくれる。
今はこの陽だまりの中で、ただ、静かに休んでいてほしい。いつも、僕の手を引いてくれていたんだから。今度来るときは、あの傘をあの市場で買って持ってくるよ。いつものサンドイッチも持ってくるから。ここで食べたらおいしいだろうねきっと。それじゃあまたね。またすぐ来るから、それまで」
あの日、あの岬で。僕たちが絵を描いていた時のような、一度会ったことのあるような、懐かしい風が海の方から吹き抜けた。
冷たい木の上に生ぬるい涙が落ち、染み込んで行った。
【第二部】二十九章 海のような瞳
僕が少女の墓の前で膝をついていると。後ろで見守ってくれていた老婦人が、僕の肩にそっと手を置いた。
「あなたのせいじゃない。もともとその子は……私の思念が生み出したものだった。きっとあなたと出会えて幸せだったと思う」
そして、肩に置かれたその手は、瑞々しい若い女性の手であることに気づき、僕は振り返る。
《《そこには更に若返った老婦人、いや、女性の姿があった。》》
おそらく僕とほとんど同じくらいの年齢で、今まで閉じていた目は開かれ、初めて見るその人の瞳がそこにあった。それはもちろん、あの老婆が若返った姿ではあるが、この墓の下に眠っている少女の、成長した姿でもあるように思えた。
「その少女のことについて、私から少し、お話してもよろしいでしょうか?」と、女性は僕に尋ねる。
「……はい。お願いします」と、僕は答える。
「教会の壁に埋め込まれていたガラス玉を見ましたか? あれは、もう五十年も前の話になりますが、あの教会で襲撃事件がありました。
やはり教会などは、他の過激な集団から狙われることもあるのです。
先ほど私がお話したあの青年ですが、その時、あの教会にお祈りに来ており、その銃撃に巻き込まれ死んでしまいました。壁に埋め込まれたガラス玉は、その時に空いてしまった穴を塞ぐために、後で子供たちがはめ込んでくれたものです。
あれも、運命だったと言うのでしょうか。いえ、ただ無残だったとしか言えません。私は悲しみに暮れ、自分の無力さを憎みました。私は人間にとって最も大切なことは、罪を許す心だと真っ直ぐに信じていました。しかし、あの青年が殺された時に気付いたのです。
私は平和主義者でも博愛主義者でもなく、ただ問題に立ち向かう勇気のない臆病者であったと。現実はいとも簡単に、私の大切なものを奪っていきました。
そして、その痛みと向き合わざる得ない状況に立たされた私は考えました。何日もまともに眠れず、必死に救いを探し続けました。救いなどありはしないことは、きっと気付いていたのです。
しかし、その気づきを受け入れることは、私にとっては死よりも恐ろしく、真っ暗で、どんな魑魅魍魎が潜んでいるか分からない闇の中へと、身一つで飛び込むような、そんな恐怖と絶望がありました。本当に私は愚かでした。既に地獄だったのに。私の立っているところは、まぎれもない地の底だったのに、救いだなんて笑える話です。
私は修道女を辞めることを決意し、その事を長上に伝えました。長上は残念そうに『こんな時だからこそ、今はここに留まるべきだ』と言いました。私を本当に心配してくれていたことは分かりましたが、私は、お世話になりましたとだけ言い、教会を出て行きました。
私はそのまま青年の墓まで行き、墓から骨壺を取り出すと、壺を布袋で包みました。その様子を、長上と一人の修道女が見ていましたが、何も言わないので、私も何も言わず、その壺を胸の前に抱えて立ち去りました。
私は家に着くと、テーブルの上に、持ち帰った骨壺を置き布を解きました。そしてその横に、空の瓶を置き、教会から持ってきた、神を宿すと言われるいくつかの品々を瓶に詰めました。
その品々とは、『子宮への回帰』と呼ばれる儀式で使うものです。私は、このように願いました。
『強かで、悪魔に対して武器を向けることが出来、愛する人を守るための強い意思と勇気を持った新しい命』
それが産み落とされますように。私の命と引き換えでも構いませんから。
それから私は、あらかじめ用意してあった薬を使い目を潰しました。
そして、使えなくなった二つのそれらを取り出し、一つを骨壷の中へ、もう一つを瓶の中へ入れました。そのようにした理由は、二つの思念に「目」を持たせる必要があったからです。
そして瓶は海へと流し、壺は家で保管しました。
本来は『子宮への回帰』は、そういった風に行うものではないのですが、ただ、私のその強い思念……いや、そんな綺麗なものではなく、渇望と言った方がいいでしょう。
私の渇望の一つはこの地に。もう一つは海を漂いました。
やがて、その二つの「目」は、あなたのプシュケー、そして少女のプシュケーを、それぞれに見つけました。
あなたのプシュケーは青年の遺骨の方へ、その少女のプシュケーは海を漂う瓶の方へ、それぞれに惹かれ、結びつき、宿りました」
そこまで話すと、話を一度区切るように、女性は目を閉じて静かに深呼吸をした。
そして、僕が瞬きをしている間に、既に女性は幼い少女へと姿を変えていた。
その少女は、「少女」の墓の方を見下ろした。自身の無念を受け継いで散った少女のことを、考えているようだった。
「だけど別に、この少女の半分がわたしで、あなたの半分があの青年だとか、そういうことではないんだ。あなたはあなただし、この子はこの子。ただ、始まりのきっかけがそうだったというだけの事なの。
だけどやっぱりその子の中には、私があの時あの人を守れなかったことの無念が、きっと強く影響してたから、だからこの子は、あんなにも強かったし、自分よりもあなたの命を守ったんだと思う」と少女は言った。
しかし、彼女は何かに気付いたように、少しの間黙り込み、こう言い直した。
「ううん。ごめん違うね。この子があなたを守ったのは、あなたがこの子に、ちゃんと愛情を注いだからだね。きっとこの子が、今まで経験したことのないくらいの愛情だったんじゃないかな。だからだね」
「……ありがとう」と僕は言う。
その少女の顔は、僕が共に過ごした少女と、どことなく似ていた。それは多分、同じ使命を抱えたもう一つの姿であるからだと思う。だけどあの少女よりもか弱く、無邪気でまだ何も知らない、どこにでもいるような、健康な少女の姿だった。
「君はあの青年の事を、海のような優しい瞳だったと言ったけど、君も、同じ目をしているよ」と僕は言った。
少女は「あなたもだよ」と、言って笑った。それから「あのね。あんまり悲しまないで。きっとこの子は、またいつかどこかで、あなたの事を思い出して、それで、再会するための旅に出る筈だから」と言った。
「それは、どういうこと?」と僕は尋ねる。
しかし少女は何も言わず、くるりと回転し僕に背を向けると、一面の花の中を、森の方へと歩いて行った。そして向こうの方から「じゃあね! 幸運を!」と言い手を振った。そして森の中へと姿を消してしまった。
一人残された僕は、少女の墓を振り返りもう一度見つめる。
僕が知っている、これまでの少女の勇敢な姿や、普通の子供らしい姿を、僕は恐れることなく、今やっと鮮明に思い返すことが出来た。
そしてそれは、僕の胸を暖かく満たしてくれた。
「僕も、やるべきことをやらなくちゃね」と、少女の墓に向かって言った。
【第二部】 三十章 再び灯台へ
——–僕はその日の夜には、必要なものを鞄に詰め込んでいた。
まだ傷が完治したわけではなかったが、いつまでもここにいるわけにもいかないし、不思議と痛みはほとんど無かった。
家は燃えてしまい、僕の手元にはダガーナイフとコンパスしかなかったが、僕が寝かされていた教会の小部屋の壁には、ランタンと薄手の黒のローブが掛かっていた。
そのローブはおそらく、神父が着るものであると思うが、シンプルな作りであまり聖職者ぽくなく、他に着るものもないので、着ていくことにした。
そして、机の上には「これがマラムです。きっと何かの役に立つから持って行って下さい」という置き書きと共に、ほんのりと青みがかった、約二十カラット程の重さの、透き通る石が置かれていた。
僕はその宝石を手頃な大きさの布で包み込み、鞄にしまった。そして最後にランタンを手に持ち、部屋を出た。
教会正面の入口まで進み扉を開いた。一歩踏み出し、教会の扉を閉め、お世話になったその教会を見上げる。
そして、この中に居たであろう、あの人の|プシュケー《魂》にお礼を言う。マッチを擦ってランタンに火を灯し、僕は夜の森へと足を踏み入れた。
——–あの教会は老婦人が言ったように、もう長年誰も訪れていない、人々から忘れ去られた場所だったようだ。またもう一度行きたいと願っても、辿り着けるかどうかすら分からない。
おそらく銃撃事件があった辺りから誰も訪れなくなり、少しずつ廃れてゆき、あの人は周囲の森ごと、教会を隠してしまっていたのだろう。もうこれ以上、悪意に教会を汚されないように。
森を抜けるのは簡単だった。道が手にとるように分かった。それはやはりこの森自体が、あの人の意識の一部だからだろうと思う。僕に、道を示してくれているように思えた。そしてなんと、五分と歩かない内に森を抜けることが出来た。
目の前には海岸……ではなく、最北端の岬だった。目の前に灯台がある。
「どうして……」と僕は思わず呟いた。
僕は、半年前にこの灯台を逃げ出し、父の別荘のある、北西の地方に居た筈だった。そしてその家の前で、あの使いの男に撃たれたのだ。あそこからこの岬まで、随分離れている筈なのに。
僕は振り返り、今自分が出てきたばかりの森を見つめた。森はただ静まり返り、岬からの潮風を受けた葉が、微かに揺れていた。
きっと、この森に再び入り、来た道を引き返したとしても、もう二度と、あの「森の教会」へ、たどり着くことは出来ないのだろう。
……いや、もしくは。まだ僕はあの老婦人の内側に留まっているのかもしれない。
今朝、教会で目を覚ましてからは、説明のつかない不思議なことばかりが起こってしまっている。僕はひとまず考えることを止め、灯台下の家の方まで歩き始めた。
———家には灯りが灯っていなかったが、僕は扉の前に立ちゆっくりと丁寧に、三回ノックをした。
それは、使いの男が来る時にいつもするノックと同じやり方であることに、自分でやってみて気付いた。その気付きは僕を嫌な気分にさせた。長年あの男のノック音を聞いていたので、その音とリズムが、頭に染み付いているようだった。
やはり返事は返って来ない。誰もいないようだ。新たな管理人が居てもおかしくはないのだが。僕は扉のドアノブに手をかけ、ゆっくりと回し、前方に力をかけた。部屋の中に月明かりが入り込み、部屋の様子が少し見える。とても懐かしい匂いがした。
電気をつけ、部屋の様子をじっくり見渡した。その様子は、驚くほどそのままであった。
僕たちがここを飛び出したあの日から、何も変わっていないように見える。半年もの間、誰もここを訪れなかったのだろうか。いや……というよりも、正直僕には、あの日から一日も時間が進んでいないように見えた。
「ただいま」と僕は小さく呟く。
するとそこに。ベッドに腰掛け本を読む少女の影が見えた。また、中央のテーブルでシチューを啜る少女が見えた。中身のない話で盛り上がる少女と、僕の姿まで見えた。
ここではまだ、あの日の僕と、あの日の少女が暮らしているようだった。
今ここで、その二人の様子を見ているこの「僕」は、きっと既に別人なのだろう。一度死んだようなものなのだから。
僕は「お邪魔します」と言い直し、部屋へ足を踏み入れ、扉を閉めた。
僕はベッドに横になり、部屋の中をボンヤリと見渡した。
それから一度目を閉じてみる。
すると、部屋の中にはやはり二人の気配があった。
目を閉じ、ゆっくりと呼吸をし、頭を空っぽにする。意識を、内ではなく外に集中させるよう務めた。
少女が動く気配や小さな物音が、少しずつ、より鮮やかで立体的な音に聴こえてくる。
まるで僕の心臓や血管、脳の細胞までもが、この空間に存在していた少女の情報を、可能な限り正しく、そして純粋に捉えようと努めているように思えた。
これは、いつのことだろう……?
少女は、何をしているのだろうか?
(それは。暖かい日差しが窓から差し込む正午前。少女はどうやら絵を描いているようだった。すぐそこの椅子に座り、ソファの方に向かい何かを描いていた。とても真剣に、何かを観察しながら描いているようだ。
少し描くとスケッチブックから鉛筆を放し、前方の何かを眺める。そしてまた少し描く。時々、消しゴムで修正をした。そして、その上をまた薄くササッと鉛筆でなぞっている。
しかし突然、焦ったように、クルッと体を半回転させ、ソファではなく机の方へと向き、スケッチブックを閉じると、急いで引き出しに閉まってしまった)
———僕はそこで目を開ける。
少女はその時、何を描いていたのだろう?
僕はベッドから起き上がると、机の前に行き引き出しを開けた。するとそこには、少女の使っていたスケッチブックが一冊入っていた。
そうか。あの時急いで飛び出したから、ここで使ってたスケッチブックは、ここに置いたままだったんだ。
僕はそのスケッチブックを取り出し、開いてみる。花の絵、海の絵、野菜の絵、蝶の絵など、いろいろな絵が描かれていた。見たところ、どうやら風景よりも、物や虫など、近くにある物を見て、細かく描く方が得意なようだった。
それは僕とは逆だった。僕はどちらかというと風景を描く時の方が自然と、あまり何も考えずに描くことが出来る。何かを観察して細かく描くのは苦手である。
だからそうだな。まず、あの子に花を描いてもらい、僕がその後ろの木々や丘などを描けば、バランスの取れた良い絵になるんじゃないかな。多分、僕たちが共に過ごした時間も、そんな風に成り立っていたんだと思う。しかし本当に、こんなにたくさんの絵を描いていたなんて。
スケッチブックはめくってもめくっても、また次の絵があった。このスケッチブックの中にはあの子がここで暮らした日々と、命と、ささやかな幸福が感じられた。
ページが、永遠に終わらなければ良いと思ったが、とうとう最後のページとなった。そして、最後のページをめくる。
そこに描かれていたのは、「眠っている僕の顔」だった。
目の横にあるホクロや鼻の形など、とても上手に描けていた。髪の毛も上手だった。耳も、まつ毛も、とても上手だ。上手なだけではなく、他の絵よりも明らかに丁寧に描かれていた。
きっと時間をかけて少しずつ、僕が寝ている間に描いていたんだろう。僕に見せるつもりだったのだろうか。間に合ったのだろうか。この絵は完成品で、僕が見て良かったのだろうか。
部屋にいる少女の気配に尋ねてみようと一瞬思ったが、やめた。結果は分かっているし余計悲しくなるだけだ。既に、僕と彼女は違う世界にいるのだから。
それは亡霊とかではなく、何と言えばいいのか分からないが、ただ確かに「命を持った気配」がそこで暮らしていた。僕はスケッチブックを鞄の中にしまい、もう一度ベッドへ転がり目を閉じた。
———今、目を開けば、目の前で少女が、僕の寝顔を描いているところかもしれない。だとしたら今は、目を開けてはいけないな。
そんなことを考えながら、僕は鉛のように重い体を、泥の中へ沈み込ませ、深い眠りについた。
【第二部】三十一章 真相
———朝になり、窓から陽が差し込んでいた。
頭はかなりぼんやりとしている。あまりに疲れていたので、自分でも信じられない程深い眠りについていたようだ。
まるで二十四時間一度も目覚めることなく、ぐっすりと眠ったような感覚だった。まだ上手く焦点が合わないが、部屋の中を眺めてみる。すると、昨晩見た時とは、部屋の様子がまるで違っていた。
昨晩は確かに、僕と少女が住んでいた部屋そのものだった。僕が記憶している限りでは、間違いなくそうだった。
それに何よりも「少女と自分」の気配が消えていた。昨日眠りに就く直前まで、くっきりと感じていたそれは、跡形もなく消滅していた。
僕は一度目をこすり、感覚ではなく、そこにある物質的なものを一つずつ見ていくことにした。家具の配置は、さほど変わってはいなかったが、部屋の中心に置かれている長方形のテーブルは、僕が以前使っていた物とは違うし、部屋の角に置いている冷蔵庫も、一回り大きいサイズのものに変わっていた。ソファもベッドも、やはり全く別物に変わっていた。
僕はベッドから起き上がり、テーブルの上を見てみる。するとそこに、監視記録の束と、多分、城の使いに向け書かれた一枚の書置きがあった。そこには「連絡を差し上げた通り、一カ月分の監視記録です。お持ち帰り下さい」と書かれていた。
やはりこの灯台にも、既に新しい管理人が就いているようだ。しかし、どうやらメモから察するに、今はここを空けていて、城の使いが取りに来た時の為に、ここにこの監視記録を置いて何処かに出掛けている。という感じだろうと思う。
その時だった。
コン、コン、コン
と扉を誰かがノックする音が聞こえた。慌てて窓の方を見ると、使いの男が着る城の制服が見えた。
まずい! と思ったが。
「こんにちはー」と扉の向こうから声がした。
しかしその声は、僕の想像したあの男の声とは違った。おそらくもっと若い、二十代の男の声だ。
「い、今開けます」と言い、僕はゆっくり扉を開いた。そこに立っていたのはやはり、あの眼鏡の使いの男ではなく、初めて見る若い青年であった。
「ごめんなさい。もしかして、まだ休まれていましたか?」と、その青年は、焦った様子の僕を見て言った。
「いや。申し訳ない……」と僕は恥ずかしい気持ちと、あの使いの男でなかったことの安堵の気持ちで、少し混乱していた。
「ええと、初めてですよね? お会いするの。新しくここの担当になった者です」と、その若い青年は言った。
「あ、ああそうか。すまない。すっかり寝過ぎてしまったようで」と僕は答える。
だけど、新しい担当だって? こんなタイミングで。
「じゃあ、前の担当の眼鏡の男は、別の地区の担当になったのかい?」と僕は尋ねる。
すると、若い使いの青年は、なにやら深刻な表情になった。
「あなた……ご存知ないんですか?」と若い使いは、何か事情を含んだ言い方をした。
「ああ、すまない。教えてくれないか」と僕は素直に答える。
「あの男はいま、指名手配中です」と彼は言ったが、僕にはよく理解が出来なかった。
「指名手配って、どうして?」
「あなたは、あの男から何か異常さのようなものは感じませんでしたか?」と若い使いの青年は言う。
あの男が異常なことは、今の僕は誰よりも身に染みて分かっている。けれどこの青年が、僕たちに起こった一連の出来事を知っているとは思えなかった。
「いや、分からない」と僕は答える。
「そうですか……いえね。僕も城に勤め始めたばかりの時、あの男から研修を受けている期間もあったもので、本当に驚いたのですが」と青年は言い、鞄から二枚綴りの紙を取り出した。「あなたも城に仕える人間なので、一応、お知らせしておく必要があるのですが、結論から言いますとあのメガネの男は現在、殺人容疑で指名手配中となっています」
「殺人容疑だって⁉︎」
なぜ……? 僕や少女との間で起こった事件のことを、城側が知っているとはやはり思えなかった。
「詳しく教えてくれないか?」と僕は尋ねる。
若い使いの青年は手に持った用紙に目を落とし、あのメガネの元使いの男が、指名手配となるまでの経緯を話し始めた。
「つい先月の話ですが、夕方頃、私たちは仕事を終えて帰ろうとしていました。そこに突然、女性が一人、城の保安課に駆け込んで来ました。そして、人殺しを見たと言うのです。
彼女は主婦で、国の北西に位置する山村から来たと言いました。その場所はあのメガネの男が担当している地区でもあり、まさにその日は、そこに記録の回収に向かっている日でしたから、我々は彼に話に参加してもらおうと思い、帰りを待ちました。
そしてしばらくして、仕事を終え帰ってきた彼に、その女性の待機する部屋へ行くように指示しました。彼は『分かりました』と素直に、急な申し出にも応じました。
部屋の中には、保安課の窓口で話を受けた中年の男性と、その女性が待機していました。しかし、部屋に入って来た彼の顔を見るなり、その女性は静かに震え出し、俯いたかと思うと『すみませんが、お手洗いをお借りして良いですか?』と言いました。そして足早に部屋から出ると、課内の別の者に、『あの眼鏡の男が犯人です』と耳打ちしたのです」
僕には正直まだ、正確に理解が出来ていなかった。どういうことだ? つまり、僕たち以外にも被害者がいるということか? 青年は話を続ける。
「私たちも本当に驚きました。なんせ影の薄い人物でしたし、礼儀正しく丁寧な言葉を使う男でした。だから最初はきっと人違いだと思ったのです。眼鏡をかけた細身の男なんて結構いますから。
だけど、その保安課の中年男性が、念のため事情は伝えずに、『仕事終わりのところ申し訳ないが、事情聴取をさせてもらってもいいか? 今日、あの地区に行っていた者にはやっておくように言われてね』と言うと、メガネの男は『構わないが私も今戻ったばかりで、急に連れ回されてるんだ。先にトイレくらい行かせてはもらえないか?』と言ったんです。鞄を置いて行くことを条件とし、保安課の中年男性はそれを了承しました。
それから、トイレから帰ってくるのを待っていたのですが、彼はいつまで経ってもトイレからは戻りませんでした。それが我々が見た、彼の最後の姿でした。そしてその後、置き去られた鞄からは拳銃が発見されました。
後日、駆け込んできた女性の言った現場を捜索したところ、死体が発見されたのです。殺された人物はその山村に住む、貧しい家庭の主でした。そして、死体から出てきた銃弾が、あの男の鞄にあった拳銃に込められていたものと一致しました。その女性の証言や、彼がそのタイミングで行方をくらましたことなども含め、我々はあの男を指名手配とし、捜査に踏み切ることとなりました」
僕は激しいめまいに襲われ、椅子から床に倒れこんでしまう。
「大丈夫ですか!」と若い使いの青年は、駆け寄る。
つまりアイツは、そもそも常習的な殺人犯だったということなのか?
殺されたのは少女だけではなく、他にもいるということか。
確かに、城の制服を着ていれば、疑われることもないだろう。だから何かしらの理由をつけて、人目のつかないところに連れて行くことも容易だったんだ。
「大丈夫。ありがとう」と僕は答える。
僕はあの日、男に拳銃を突きつけられ連行されそうになった時の事を思い出す。あのまま連れて行かれていたら僕は、森の中で殺されていたのかもしれない。確かに今考えれば、僕に不審なところがあったのに、衛兵も引き連れずに単独で引き返して来たことは、おかしいことであった。
少女はあの時本当に、僕を救ってくれていたんだ。
それにあの時、僕があの子を止めず、あの場でちゃんと殺してれば……そう思わずにはいられなかった。悔しくて仕方がない。
あの男を憎めばいいのか、自分の無能さを憎めばいいのか、あの子のように、いやせめてあの老婆の言った通り初めから、あの男の危険性を見抜くことが出来ていれば。
「だ、大丈夫ですか?」と若い使いの青年は僕に、心配そうに尋ねた。
「ああ。だ、大丈夫だよ。いつも、顔を合わせていた相手だったから、少し驚いてしまって」と、僕は何とか声が震えないよう、気をつけながら答える。
「分かります。私も初め聞いたときはショックでした」
「だけど指名手配中って、あの男の行方に関する手がかりは、何か掴めているの?」
「いや、私も保安課の人間ではないのでそこまでは。私が知っていることはあの男の生まれ故郷くらいです。先程も言いましたが、私が城に勤め始めたばかりの頃、担当する地区が近かったこともあって、あの男に研修をしてもらっていたんです。
その時に故郷のことを一度だけ聞いたのですが、意外な場所の出身だったので、何となく記憶に残っていたのです」と若い使いの青年は答える。
「そうか。ちなみにその生まれ故郷っていうのは、どこなんだい?」と僕は、興味本位の質問であるかのようなニュアンスで尋ねる。
「国の『南西にある農村』です。比較的、貧困層の国民が集まる村で、おそらくこの国に数ある集落の中でも、かなり貧しい方の地域と言えるでしょう。あの男はどちらかというと、街出身者のような雰囲気があったので、私としては意外だったのです。洋服もわりといつも、高価そうなものを着ていましたし、だからこそ印象に残って覚えていたのです」と、青年は教えてくれた。
「そうか。確かに意外だね」
「はい。しかしどうやら収穫はなかったようです。先月、既に城の保安課から数名、捜査に向かいましたが、行方の手掛かりとなるようなものはなかったようです」と、若い使いの青年は答える。
それはそうと、何やら彼は、さっきから僕のことを少し不思議な様子で眺めているように見えた。
すると「すみません。一つ、お尋ねしてよろしいでしょうか?」と僕に言った。
「あ、うん。何?」と僕は返す。
「どうして、黒いローブを着ているのですか? まるで教会の神父のようだ」と、彼は言った。
「ああ、いや、深い理由はないんだけど、悪いデザインじゃないから、着てるだけなんだ。変かな?」と、僕は適当に答える。
「いえ、変ではないですが、珍しい格好だったもので気になっただけです……ああそれで、今日は私は、監視記録を受け取りに来たのですが」と、若い使いの青年は言う。
僕は、テーブルに置いていた、一か月分の監視記録の事を思い出す。
「はい。ではこれを」と言い、僕は書置きの紙は省いて、監視記録の束を彼に渡した。
「……あれ? しかしそういえば。本日はここに居られないから、記録だけを取ってくるようにと、言伝を受けていたのですが」と若い使いの青年は言う。
「ああ、すまない。予定が変わってね」と僕は答える。そうか。どうやら彼も、担当地区が変わって初めての訪問なので、僕が既に、ここの管理人じゃない事には気付いていないようだ。
「そうでしたか。承知しました。では、そろそろ失礼したいと思います」と言うと、彼は丁寧に頭を下げ、部屋を出て行った。
僕は「ありがとう。それじゃあまた」と言い、扉を閉めた。
扉の向こうで車のエンジンがかかる音が聞こえ、若い使いの青年は去っていった。
次回、彼が来た時には、また違う人間が管理人をしているわけだから、きっと驚くだろうな。僕は少し申し訳ない気持ちになった。
しかし、これで次に行くところが決まったわけだ。「南西の農村」か。
———僕はその時、閉めた玄関の扉の辺りに何か違和感を感じた。しかし、何によってもたらされている違和感なのか分からなかった。だけどどうしても、何かが引っかかる。何年も見続けたこの風景が、よそよそしく感じられた。
久しぶりに見たからだろうか?
しばらく考えてみたものの、答えは見つかりそうにないので、僕はあきらめてベッドへ腰かけた。そしてあの日、ここを、少女と共に飛び出した日の事を、何となく思い出していた。
あの日僕が扉を開くと、そこの食卓の椅子に、使いの男が足を組んで座っていた。玄関から入ってきた僕は、まず少女が部屋のどこにも見当たらない状況に焦る。
そして使いの男は、僕を徐々に追い詰めるように、いやらしい言い方で僕に質問を投げかけてくる。僕は彼の質問に対応しきれず、ついには拳銃を抜かれ、発砲されてしまう。
放たれた銃弾は、僕の顔の少し左辺りを通り、後方の壁に穴を開けた。
つまり、この位置から見ると、玄関の扉の右上辺りだ。僕はベッドに座ったまま目を細め、その辺りにあるはずの穴を探してみた。しかし上手く見つけることが出来ずに、再びベッドから立ち上がり、玄関の前まで歩いた。
そう。僕はこの辺りに立っていた。
そして使いの男は、部屋の中心に置いてある、そこの食卓の椅子に座ったまま、僕に対して発砲した。間違いない。
「だからこの辺りに、弾痕があるはず」と、僕はそう呟きながら、玄関の扉の周りの壁一面をくまなく探す。
しかしそれでも、あるはずの穴は見つからなかった。
そうか。僕がさっき感じた違和感というのは、これが原因だったのか。
あの日、使いの男が空けた筈の壁の穴は、どこにも残っていなかった。
【第二部】三十二章「ある少年」
その少年は、国の西部に位置するある貧しい村の、貧しい夫婦の一人息子として生まれた。
物静かなその子供は、わがままの言わない、手のかからない子供だったという。しかし生まれつき目が悪く、五歳の時には眼鏡を掛けることとなった。
少年の両親は、少年の成長と共に少しずつ仲が悪くなっていった。少年が十歳の時には、二人の関係はただの同居人と化しており、また父親には愛人がいたため、家を空けることも多かった。母親はその事実を知りながら、それについて何も言わなかったという。それは気を使っていたからではなく、ただどうでも良かったのだ。自分の生活費を稼いでくれさえいれば、それで。
そしてその年の内に、少年の両親は離婚することとなり、少年は母親のもとに引き取られた。
少年の母親は、よく別れた父親の愚痴をこぼした。特に酒の入っている時には酷く、夜が明けるまで延々と「あの男がどれだけ器の小さい男であるか」という話を、我が子である少年に聞かせるのであった。
母親は働いてはいなかったが、少年は生まれつき頭がとても良かったため、同じ村に住む子供達に勉強を教えることで、いくらかの生活費を稼いでいた。また、別れた父親からの養育費もあったので、生活は辛うじで何とかなっていた。
——–ある日少年は、少し離れた街に住む子供の家までアルバイトに行った。そこは裕福な家庭であったため、同じ村の子供に教えるよりも、良い報酬をもらえるからだった。
そこの家で少年は、ふんわりとしたいい香りのする洋服を身にまとう、その家の子の母親に美味しいケーキをご馳走された。「遠くからわざわざありがとうね」と、その母親は、少年を労った。
その帰りに乗ったバスの中で、少年は偶然にも、約三年ぶりに父親と再会することとなる。
その時少年は十三歳だった。父親と少年は途中下車し、二人でステーキハウスに入った。
痩せた少年を見た父親は、母親がちゃんとした食事を作っていないのではないかと、我が子の普段の食生活について心配をしたようだった。事実そうであったが、少年はあまり気にしていなかった。母親の手料理を特に美味しいと思ったことはないし、お腹が減りすぎて倒れる程でもなかったからだ。
しかし大きなステーキを目の前にした少年は興奮し、あっという間に平らげてしまった。父親もその姿を見て安心した。
そして、「また時々こうして食べに来よう」と少年に約束した。
その時に少年は、はっきりとした理由は分からないが、きっと離婚の原因は母の方にあったのだろうと感じ、以後そう思うようになった。
そして同時に、母親が自分に対して無関心であることにも気付いてしまった。
バス停の前で別れる時、少年は父親にこんなことを尋ねた。
「父さんは、もし夜中に電話が鳴ったら迷惑だよね?」と。
「相談したいことがあるなら、いつでも掛けてくればいいさ」と父親は答えた。
「ありがとう。それじゃあ」と言って少年はバスに乗り込み、父親と別れた。
——–その日の深夜二時、父親の家の電話が鳴った。ベルの音で目が覚めた父親は、息子が別れ際に言っていたことを思い出し、受話器を取った。
「もしもし。どうした?」
しかしその電話は息子からではなく、城の保安課からであり、内容は、たった今先妻が焼死体で発見されたとのことだった。
しかも椅子に手足を縛りつけられた状態で、ガソリンをかけられ、そのまま椅子ごと燃やされたとのことだった。
「一緒に住んでいた筈の息子さんがどこにもいないのですが、心当たりはありませんか?」と聞かれた父親は「いえ、分かりません」と答え、受話器を置いた。
【第二部】三十三章 「南西の村。男の故郷へ」
僕はあの若い使いの青年から聞いた、使いの男の故郷へと来ていた。
城からの長距離バスに乗り、約七時間の移動だった。バスは山の裾を沿うようにして、南方面へと回り込む。そして平野へ出ると更に南へと下った。そこから二つの町を通り過ぎ、まだ南へと向かう。後方の町が辛うじで見えているくらいの所で、今度はバスは西へと進路を変えた。
その方面へ進むにつれ、土地は緩やかに、標高の低い方へと下がって行っているようで、じめじめとした湿地帯のような雰囲気の地域へと、少しづ変わっていった。しばらく走ると小さな林が現れ、その林を通り抜けたところに、その農村はあった。
家屋のほとんどがレンガ造りで、屋根には必ず煙突がついており、水路に沿うような形で家々が連なっていた。その途中には水車小屋もあり、水路を流れる水がその水車を回していた。
また民家ばかりではなく、洋菓子店や、コーヒーショップ、パン屋や、手作りの家具を売っている店などもあるようだった。貧困層と聞いていたが、決して廃れているわけではなく、昔ながらの雰囲気の残る、美しい村であった。
僕はかつての、使いの男が生まれ、幼少期を過ごしたという家の住所を目指して歩いた。村の入り口からは少し離れており、なだらかではあるが、坂道を上っていかなくてはならなかった。その坂道の途中には、白いガマズミの花がいくつか咲いていた。
坂道を上って行った先にも、いくつかの家々が集合している場所があり、その中の一軒に、使いの男の生まれたという家はあった。それは周りの家々と特に変わりない、レンガ造りの、古い小さな家だった。
僕がその家を見上げている時だった。
「珍しいな。こんな村に神父さんがやってくるとは」と背後から声がした。振り返るとそこに、八十代くらいに見える老爺が立っていた。「この家に何か御用でしょうか? お若い神父殿」
「いえ、僕は神父ではないのです。旅をしていまして、ただこの格好が楽なので着ているだけです」
「そうでしたか。で、何か御用で?」
「実はある行方不明の男を探しているのですが、この家が、その男の生まれた家だと聞いたもので、訪ねたのですが」
「ええ、そうでしょうね。先月だったか、城の者も兵達を何人か連れてやって来て、二日間ほど何やらごそごそと、調べて帰って行きました」
あの若い使いの青年の言ったことは、どうやら本当だったようだ。
「僕も、この家の中を見たいのですが、中に入ることは出来るのでしょうか?」と僕は老爺に尋ねる。
「ええ、まあ今は誰も住んではいませんから、構わないとは思いますが、あなたも城の方なのですか?」
「ええ一応。城の中で働いているわけではないので制服は着ていませんが、城に使えてる身ではあります」
しかしそれは正確ではない。もう昔のことだ。
「そうでしたか。では、鍵は開いている筈なので、まあ構わないでしょう」
そう言うと、老爺はその家の扉を開いた。
「まぁ先月の捜査で、もともとあった物はほとんど持って行かれたようですが」と、老爺は言った。
確かに、中はほとんど物がない状態で、綺麗に片付けられていた。扉を開けるとすぐに十畳程のダイニングキッチンだった。部屋の左側にシンクと調理台があり、中心には、家族が食卓を囲めるような大きなテーブルがあり、その周りに三つの古びた木製の椅子が設置してあった。そして、右側の壁には別の部屋へと続く扉、奥の壁には窓があり、裏庭の向こうに樫の木が見えた。僕は家を開けてくれた老爺に尋ねる。
「すみません、おじいさん。あなたはこの村にもう長いこと住んでいるのですか?」
「ああ、わしはこの村から出た事がないからの。ずっと前から住んでいるよ。それは気が遠くなるほど長いさ」
「そうですか。では、この家に住んでいた一家のことは何かご存知ですか?」
「もちろん知っているさ。ここの家では色々と奇妙な事件があったからの。この村に長く住んでいる数名が知っている話じゃ。捜査に来ていた城の者達にも、教えてやろうと思ったんじゃがの、『じいさん。あっちへ行っててくれ』と、若い兵にあしらわれてしまったよ」と言い、老爺はほっほっほと、実に老人らしく笑った。
「そうでしたか。まあ、城の兵と言っても色んな人間がおりますからね」と言い僕は笑った。「もし今お時間があれば、その事件の事や、この家に住んでた人物のことを、僕に詳しく教えてはくれませんか? 私、下の店でコーヒーと、何か菓子を買って来ますので」と、僕は老爺に提案した。
「ああええですとも。婆さんが亡くなってからはわしも毎日暇じゃからな。あんたみたいな若い者と話すだけでも、ええ脳の運動になる」と、老爺は快諾してくれた。
「本当ですか! 助かります」と言い、僕は老爺に頭を下げる。「では、少しここで待っててもらえますか? 下の店で何か買ってきます」
「そうか。それなら洋菓子店の南瓜のロールケーキが、この村では名物じゃ。せっかくこの村に来たんなら、それを買って来なされ」と老爺は言った。
——–僕は早速、さっき上がって来たガマズミの咲く坂道を下って行く。
そして洋菓子店で老爺の言った南瓜のロールケーキを注文した。その時に、カウンターにいたお姉さんが「旅の方ですか?」と、僕に尋ねた。
「旅という訳ではないのですが、少し用があって」
「そうでしたか。いえ、うちの南瓜のロールケーキ。大抵外から来た人しか買っていかないんですよ。この村の人はあまり買わないんです。名物って多分、そういうものなんですよね。私は、この店のメニューでも一番美味しいと思ってるんですけどね。だから売れ残るのが分かってても、必ず毎日一つは作るようにしているんです。好きだから」と言った。
僕は彼女のそのこだわりに、好意を持つことが出来た。
「見た目も綺麗だし、本当に美味しそうです。南瓜のロールケーキなんて、僕も初めてなので、楽しみです」と、僕は正直に感想を言った。そう。このロールケーキはお世辞抜きに美味しそうだった。
「ありがとう神父さん。この村にまた来ることがあったら、その時はまた、ここに来てくれたら嬉しい」と彼女は言った。
「また来る時があれば、必ず立ち寄らせてもらいます」と、僕はあえて、神父ではないと訂正するのは止めて、そう答えた。決して面倒だったからではなく、何となくその会話の流れというか、雰囲気を壊してしまうのに抵抗があったのだ。
僕は洋菓子店を出ると、今度はコーヒーショップに寄り、僕よりも少し年上(おそらく三十代後半くらい)の愛想の良い男性の店員から、コーヒーを二つ買った。それから再び坂道を上り、老爺の待つ家へ戻った。
——–扉を開けると老爺は、窓際に立ち、裏庭の向こうに見える、樫の木をボンヤリと眺めていた。
僕はその背中に「さあ座って下さい。コーヒーでも飲みながら話しましょう」と声をかけたが、老爺は窓の外を眺めたまま、まだぼんやりしていた。
僕はその様子をあまり気にせず、買って来たロールケーキとコーヒーをテーブルに並べ始める。そうしている内に、老爺は静かに口を開いた。
「あんたに聞かれて、いま色々と思い出しとったところじゃ。あれは本当に不思議な事件じゃった。悲しめばええのかどうかも分からん。今思い出してみても、やはりやり場のない気持ちになるの」と言うと、こちらを振り返り椅子に座った。
そして、老人特有の男女関係なく持ち合わせる、無邪気な微笑みを浮かべた。
「いやあ、この南瓜のロールケーキを食べるのは実に久しぶりじゃ。絶品なのは知っておるが、この村に住んでおると、意外と買わんもんでな」と老爺は言った。
「南瓜のロールケーキは、毎日必ず一つは作るそうですよ。よそ者の僕が言うのも変ですが、たまに買ってみるのも良いと思います。あのお店のお姉さんも喜ぶと思います」と僕は答える。
「そうじゃな。それも良いかもしれんな」と言い老爺はコーヒーをすすった。「さて、ではどこから話そうかの」
【第二部】 三十四章「南瓜のロールケーキと、三つの不可解な事件」
「もともとこの家には、三人家族が住んでおった。若い夫婦が二人で農業を営んでおり、可愛い男の子が一人おった。その子は事件当時は確か六歳じゃったと思う。
ワシもまだそのころは五十代じゃった。何度か立ち話くらいはしたことはあるが、ここの夫婦は二人ともいつもにこにこして、誰に対しても親切で優しい人達じゃった。
じゃからここの子も、伸び伸びと健康に育っておったのじゃろうな。村の誰もこの家庭の悪口を言う者はおらんかったじゃろう」
老爺は当時のことを、かなり鮮明に覚えているようだった。
「それで、その事件というのは、何だったのですか?」と僕は尋ねる。
「神父さんは、いや神父さんじゃなかったの。お若い方。あなたはここの村の入り口から、村には入らず反対の方に坂を下って行くと、沼地があることを知っておるか?
そこの沼は危ないのでな、昔からこの村の者は皆、近づかないようにしておったし、子供たちにもきつく言っておったんじゃ。後で見に行くといい。今は柵が立てられている筈だし、それ以上入らなければ大丈夫じゃろうから」と、老爺は僕に言った。
「分かりました。後で行ってみます。それで、その沼が何かこの家に起こった事件と関係があるのでしょうか?」
「その沼に落ちて亡くなったんじゃ。この家のお子さんがな」
老爺の顔に刻まれた深いしわが、その事件の悲しみを、より深く訴えているように僕には感じられた。
「そうだったんですか……」
しかしだとしたらこの家が、あの使いの男の生まれた家だという情報は偽だということなのだろうか?
「その亡くなった子以外には、この家には子供はいなかったのですよね?」
「ああ。ここの夫婦の子供は確かにその子だけじゃった。しかしな、不思議な事件はまだ続くんじゃ。
その子が沼で亡くなっているところを発見されてから、つい二週間ほど経った日の夜じゃった。子を失った悲しみから寝付けなくなっていたここの奥さんは、夜な夜な家を出て、村を散歩することがあったそうじゃ。
その日の夜。奥さんが家の玄関を開けると、目の前の道に、見知らぬ少年が倒れておった。身体は痩せこけ、体中擦り傷だらけで、意識もなかったという。奥さんは旦那をすぐに起こしに行き、状況を伝えた。
それから二人はその子を抱いて城へと向かった。もう村の診療所は当然閉まっておったし、そんな瀕死状態の子を診療所で何とか出来るとも思えんしの。バスがまだ走っておる時間じゃったのが幸いじゃった。
城下町の病院で少年はすぐに治療を受け、翌日の昼には目を覚ました。重度の栄養失調と疲労による気絶だったそうじゃ。
訳を聞くと、少年は、この国の西部にある村に住んでおったそうじゃが、それは誰も聞いたことのない村じゃった。
そして少年は両親に虐待を受けており、三十キロメートル以上離れたこの村まで、自力で歩いて逃げて来たとのことじゃった。村を発見したことで安心し、この家の前で倒れてしまい、そのまま気を失っていたと、少年は夫婦にそう話した。
それから、心優しいその夫婦は、その少年のことを不憫に思い、養子として引き取り、この家で一緒に暮らすようになった。幼い子を失ってしまっていた喪失感が、その少年を引き取る要因となったかどうか、わしには分からんが、まあ気の毒なくらい気の優しい夫婦じゃったから、そう決断したこともまた、自然なことじゃったのかもしれんな」
そこで老爺は、ぬるくなり始めたコーヒーを一口飲み、喉を潤した。それから、皿の上の美しい橙色のロールケーキを、フォークで四等分にし、その一つを口に入れた。僕もその様子を見ながらコーヒーを一口飲んだ。コーヒーは冷めたせいで少し酸味が際立っていた。
ロールケーキを飲み込んだ老爺を見て、僕は質問をした。
「なるほど。それで今はもう、その養子となったお子さんと共に、ここの夫婦はどこか別の所に、引っ越されたのですか?」
「いや、違う。ここの家族に起こった不可思議な事件は、まだ最後に最も謎と言える出来事があったんじゃ」
「それは、一体何ですか?」
「ある日突然いなくなったんじゃ。家族三人とも。家の中は全てそのままの状態で、神隠しにでもあったかのように、三人の人間だけがある日突然、パッと居なくなったんじゃ。そう……あれは確か、その少年がここの家に引き取られてから、五年が経ったくらいのことじゃ」
「何ですって……? それは、事件にはならなかったのですか?」
「そうじゃな。家族全員が居なくなったもんじゃから、特にだれも城に通報する者はおらんかったのかもしれん。村の者達も夜逃げか何かと思った。特に家の中も荒らされたりしておった訳ではないから、きっと何か事情があって、夜のうちに出て行ったのだろうということで、私たちは特に何もしなかったんじゃ」
「なるほど。そうだったのですね。もうここの家に関する事件というのは、これで全てですか?」
「ああ、ワシの知っていることは、これで全てじゃ」
「すみません。ちなみにその養子となった少年とは、おじいさんは当時、話されたことはありますか?」
「ああ、何度かある」
「どんな子供でしたか?」
「とても礼儀正しい。頭の良さそうな子じゃった。線が細く、いつも眼鏡をかけておったな」
「なるほど……そういうことでしたか」と言い、僕も南瓜のロールケーキを四等分し、一つを口に入れた。
「丁寧に説明して頂いて、ありがとうございます。それと、本当に絶品ですね。このケーキ。この後の用が無ければ、お土産に持って帰りたいくらいです」
「また時間のある時に、いつでもゆっくり来たらええ。城で働くのは大変じゃろうから、たまにこういう貧しい村に来て、休養しなされ」と言い老爺は微笑んだ。
その微笑みは、この村の美しさや、物理的ではない豊かさが確かに根付いていることの、象徴であるように思えた。
「今抱えている問題が終われば、また来たいと思います」と僕は言った。
【第二部】三十五章 「沼の底」
僕は村から出ると、坂道を下って行った。
その方面には人家などは全く見当たらず、放置されたおかげで伸び伸びと育った背の高い雑草が生い茂っていた。かろうじで道のように思える場所を歩いて進み、坂を下り終えると、老爺の言っていた沼地へと辿り着いた。
足元はぬかるみ、ガマやイグサがそこら中に生え、中にはモウセンゴケのような奇妙な植物もあった。所々にある水溜りを踏まないよう進んで行った先に、ぼろぼろの掘建て小屋があった。
何の用途でここに建てられたのかは分からないが、長年放ってられたその小屋は斜めに傾いており、この緩い地面に、少しずつ沈んで行っているようにも見えた。
そして、その掘建て小屋の向こうに、直径十数メートルほどの沼があった。柵で周囲を覆われているところを見る限り、おそらくここが老爺の言っていた、三十年前にあの家の子供が落ちて亡くなった沼だろう。
しかしそれは、僕が予想していたよりも遥かに小さな沼だった。水は濁っているせいで水深は分からない。
僕は目を閉じ、あの日浜辺で会った老婆の言葉を思い出していた。
「目を潰すことによって色々なものが、見えるようになった」という、その意味を考える。
そして、ここで命を落としてしまった幼い子供のことを想像する。
どの辺りから落ちたのか?
一人でここに来ていたのか?
なぜこんなところにいたのか?
そして死ぬ間際に何を見たのか?
僕は意識を集中し、浮かんでは消える様々な映像を追いかけた。何か少しでも真実の手掛かりになるような光景を見られることを願い、目まぐるしく回り続けるフィルムの中から、真実と感じられるものだけを選定して行く。
「よし」
僕はローブを脱ぐと、その辺りの木の枝に掛けた。そして肌着の上から、村で買って来た雨具を身につけ長靴を履いた。沼へと足を踏み入れていく。
—–—数時間後。僕はもう一度村に戻り、先ほどの老爺のもとへ向かった。
そして事情を説明し、数名の村人と道具を集めてもらうようにお願いした。
老爺は僕の格好を見て「うちの浴室を使っていいから、一度シャワーを浴びなさい」と言ってくれた。僕は老爺の親切を受け取り、シャワーを浴びることにした。
シャワーを浴び終え、再び黒いローブに着替え外に出ると、老爺と五人の中年の男達が道具を持って集まってくれていた。
僕は「みなさんありがとうございます。こんなよそ者の話を信用して頂いて感謝しています」と言い、再び沼地へと向かった。
沼に着くと、僕は五人の男達にある程度の場所を指差して、「その辺りです」と教えた。
水深は深いところで七メートル程だった。底には大きなドラム缶が沈んでおり、その中に、二名の遺体が押し込まれていた。
そして、浮かび上がらないよう隙間に、大量の石や土を詰めて蓋がされていた。
沼の底に沈められていたこの親切な夫婦は今やっと、二十五年ぶりに陽の下に出ることとなった。これで、少しでもこの二人のプシュケーが報われてくれることを、僕は願った。
引き上げを手伝ってくれた男の一人が、僕のもとにやってきてお礼を言った。
「ありがとう神父さん。俺はこの旦那とは若い頃、よく飲み交わした仲だったんだ。奥さんもよく気のきく利口な人だった。ありがとうな」
「はい……発見することが出来て良かったです」
僕の隣で、その引き上げを見守っていた老爺が、静かに涙を流していることに気が付いた。
その涙はまっすぐ頬を伝うことはなく、何層にも刻まれた老爺のしわに沿って、斜めに進んだり、広がったりしていた。
「なぜ、罪のない人達が、こんな目に遭うのじゃろうか?」と老爺は言った。「あんたはどう思う? 何かの大きな道筋の途中には、必ず残酷な側面がなければいけない理由でもあるんじゃろうか?」
「分かりません。ただその『残酷な側面』というものに、僕自身、何度か遭遇したことがありました。その時に身を挺して僕を守り、死んでしまった少女がいました。
また、僕の為に心臓を捧げ、何も言わず去った人がいました。悲しみを伝えるために、自らの光を切り取った人もいます。彼女たちの行動は全て、おじいさんの言うその『残酷な側面』への抵抗であったと思うのです。
彼女たちの抵抗があったおかげで、僕は今こうして生きているし、ここにいます。
僕は、彼女たちの意思を引き継いでいるつもりです。そして今度は、僕が立ち向かう番だと思っています。そうするべき理由は、『残酷な側面』は逃れられない絶対的なものではないからです。
数ある可能性(過去や未来)の中に僕たちは生きていて、その中には、大切な存在があるべき姿で存在している軸がある筈です。そこに着地するために、僕は今、抵抗を続けています」
と、そう発した言葉が、僕だけの言葉ではないことは明らかだった。
それはあの老婆や、少女や、恋人や、少女の母親や、五十年前に教会で亡くなった青年も、今もどこかに存在する、「それぞれの世界から集められた思い」達の言葉であり、希望であった。
「そうか。あんたの言う事もよく分かる。あるべき姿を取り戻すことが出来れば、それは多くの人にとって、きっと幸福な世界となるじゃろうな」と、老爺は言った。
【第二部】三十六章 「犬と、髭を蓄えた主人(ある少年)」
深夜。故郷の村を飛び出した少年は、国道に沿い、南に向かって歩いていた。
その国道は国の北部から南部にかけて、国全土をほとんど縦断するような形で、何百キロメートルと敷かれた大きな道路であった。
少年に、どこか行く当てがあった訳ではないが、なるべく、自分の事を誰も知らない方へ行かなければ、という思いがあった。
深夜とはいえ数分に一度車は横切って行く。少年は、車のヘッドライトが届かない程度に道路から距離を空け、足場の悪い、見渡す限りの砂利道を歩いた。
それから数時間。夜が明けるまでに、少年は二十キロメートル程の道のりを歩いた。陽が昇り、辺りの様子が分かり始めたころ、運よく道路わきに建てられた休憩所と、併設された食料品店を見つけた。
少年は食料品店の正面まで歩いたが、朝早いため開店前であった。店の裏手に回り込むとそこには、犬小屋と、雨風に晒されて劣化した、三人掛けの長いソファがあった。
そのソファはおそらく勝手に廃棄されたものだろう。犬小屋の中には、肥満気味の中型犬がいた。
少年にはその犬の種類は分からなかったが、本来茶色かったであろう体毛は、砂埃をまとい白みがかっており、ぼさぼさに乱れた毛の中に、二つのつぶらな瞳と、乾いてひび割れた鼻先が見えた。犬は少年の存在に気がつき一度顔を上げたが、興味が無かったようで、またすぐに顔を伏せてしまった。
疲れ果てていた少年は、そのぼろぼろのソファに寝そべり、明け方の空を見上げた。すぐに強烈な睡魔が訪れ、気がつくと目をつむっていた。
少年が目を覚ますと、すでに太陽は真上にあった。体には薄いタオルケットがかけられており、空だった犬の皿には、残飯が入れられていた。
少年はソファから起き上がると、店の正面へと回り込んだ。店はすでに開店しているようだったので、少年は扉を開け中へと入っていく。
店内の様子は昔ながらの、国道沿いには数多く点在するような、よくある小さな食料品店であった。会計のカウンターには、五十代半ば程の髭を蓄えた中年の男性が、椅子に座り何かの雑誌を読んでいた。
彼は、入店してきた少年に気がつき顔を上げたが、裏で寝ていた少年であることを確認すると、またすぐに雑誌に目を落とした。少年はそれを見て、犬と同じ反応だなと思った。
少年は店内を歩き、肉や魚の缶詰を数種類、水を二本、クラッカーを二袋をかごに入れ、カウンターへ向かった。店主の男は読んでいた雑誌をカウンターの影に置き、立ち上がると、かごの中の商品を袋に詰め始めた。
「お前。いつからあそこで寝ていたんだ?」
「今朝です」
「そうか。まあ構わないが、あまりあんなところで寝るのは体によくないぞ。変な菌でも吸い込んだらどうする?」
「すみません。あまりに疲れていたもので、気がつくと寝入っていました」
「どこから来たかは知らないが、まだしばらく歩くのか? 夜まで待つなら俺が車で送ってやることも出来るんだぞ」
「いえ。せっかくですが結構です。ただ一つ聞きたいのですが、ここから一番近い村か町はどこでしょうか?」
「ここからだと、南に十キロほどのところに小さな農村がある。ただ、道路沿いに行くなら、回り込まなければならないからな。歩く距離で考えればそれ以上になるだろう。湿地帯を抜ければ近道になるが、まああまり安全な道ではないから、そこは通らない方がいいだろう」
「分かりました。ありがとうございます」
「本当にいいのか? 車なら三十分とかからない。別に俺は構わないんだぞ」と店主はもう一度、少年に尋ねた。
「はい。歩くのは苦じゃないんです。そのくらいの距離なら、大丈夫です」
「そうか。分かった。気を付けろよ」と言い、店主はカウンターの端に置いてあったクーラーケースからソーダを一本取り出し、商品を詰めた紙袋の中へ追加した。「これはおまけだ。どんな訳かは聞かないが、頑張れよ」と言い、少年へ紙袋を手渡した。
「ありがとうございます」と少年は言い、会計を済ませ店を出た。
少年は、店の裏へ再び回り込むと、犬小屋の前で、店で買った肉の缶詰を開けた。
犬はのそのそと小屋から出てくると、嬉しそうに口を開け舌を出した、そして、その肉が自分の皿の中に移されるのを大人しく待った。
しかし少年は、その様子を眺めながら「お前がいちいち吠えない犬で、今朝は助かったよ」と言い、その肉を自分で食べ始めた。
缶詰の中身が半分を過ぎた辺りから、犬は少年に対し吠え始めたが、少年は顔色一つ変えることなく全てを平らげた。
そして食べ終わった空の缶詰を、犬の皿の横に置き、その場を去った。
——夕方。店の主人は商品棚の整理をしながら、「あの少年は今、どの辺りを歩いているのか?」と考えていた。
あまり混むような店ではないため、こんな風に何かをぼんやりと考える時間が、ここの主人にはよくあった。
そしてその対象として、「旅する謎の少年」の存在は、あまりにも都合が良かった。
それから彼は、犬に夕飯をやろうと思い、裏口から外に出た。そして犬の皿の隣に置かれた空の缶詰を見るなり、犬に向かってこう言った。
「お前。いいものもらったな」
【第二部】三十七章「学者の住む館へ」
僕は、沼地から村に戻ると、老爺に教えてもらった、村の裏山にあるという、図書館へと向かっていた。
老爺と話をした家のある住宅地を、更に奥に抜けて行くと、緑地へと突き当たった。その一か所に、奥へ進んでいけるように林道が設けられており、なだらかな上りの斜面に、一直線にずっと上の方まで、木の板と丸太で組まれた階段があった。
二人で並んで歩けるくらいの幅の階段である。僕はその階段を上っていく。
正直失礼ながら、こんな小さな村に図書館があるとは思わなかった。老爺が言うには正確には図書館ではなく、数年前まである学者が住んでいた、小さな館であるという事だった。
そこには、ちょっとした図書館並みの量の書物があって、村人は図書館と呼び、定期的に訪れ利用しているとのことだった。
木の階段をしばらく上って行くと、今度は足元は石の階段へと変わった。一人分ほどの幅しかない狭い通路で、左側は急斜面となっており、落ちないように、鉄のパイプと細い針金で作られたフェンスが、その急斜面に沿って立てられていた。
フェンス越しに下の方を見ると、先ほどまで僕がいた住宅地や、村の入り口。また沼地の方までも、見下ろすことが出来た。思ったよりもかなり上って来ていたようだ。
進行方向に視線を戻し上の方を見上げると、木々の向こうに館が見えた。もうすぐだ。石段はすぐに急斜面の方からは離れて行き、館の方へと続いて行った。そしてその館をぐるりと一周するような経路で回りながら上り、やっと館正面の門へと辿り着いた。
そこもまた、地面を石で固められた敷地となっていた。この大きな緑地の一部が、その学者と呼ばれる人の、住む土地となっているようだ。館自体は、そこそこの大きさだった。下の村にある家屋に比べれば倍以上の大きさであるが、図書館と呼ぶにはかなり小さいだろう。
おそらく十五分くらいは上って来たが、こんな不便なところに館を作るなんてきっと、変わった人物なのだろう……が、しかし。最北端の灯台下に住み、一人で野菜を作ったり、絵を描いたりしていた自分も、まあ対して変わりはないのかもしれないと思い、先入観を持つことは、あまり意味のないことなのかもしれない。と思い直した。
門は開きっ放しになっており、フランス落としの先が、地面に付けられた落とし受けに入った状態で、錆びてしまっていた。きっともう何年もこの門は、この状態のままなのだろう。
僕は門を通ると、館の扉の前まで歩いた。そこには看板が立てられており、「午前九時から午後六時まで、鍵は開けていますので、ご自由にお入り下さい」と書かれていた。僕は扉を開け中に入っていく。
玄関スペースは、正方形の空間となっており、左右にそれぞれ一つずつ、隣の部屋へ入るための扉があった。正面の左には、おそらくキッチンへと続く、扉のない入口があり、右には二階へ続く階段があった。
僕は「ごめんください」と、声を出してみた。
数秒経ってから「はーい」と女性の声が、上階から聞こえてきた。
そして降りて来たのはなんと、背の高い美しい女性であった。艶のある長い黒髪は、彼女を大人っぽく見せていたが、おそらく僕よりも若いだろう。
「なんでしょうか?」と女性は僕に尋ねる。
「ここに来れば、色々な書物を読ませて頂けると伺ったのですが、あなたはこの館の持ち主の方ですか?」
「はい。元は父が建てた家ですが、三年前に亡くなったので、今はそういうことになりますね」
「そうでしたか。ええと、利用方法などがあれば教えて頂きたいのですが」
「決まりは特にありませんよ。別にただの家ですから。あえて言うなら、本を丁寧に扱って頂くことですかね。あとは好きに読んで頂いて構いませんよ」と言って、彼女は微笑んだ。
僕は何となく、村人達があんなにも大変な坂を上ってまで、定期的にここを訪れる理由が分かった気がした。高齢の人が多い村だし、こういった若く美しい女性は、街の方に行けば珍しくはないが、ここでは貴重なのだろう。
「分かりました。歴史書はどこにあるでしょうか?」と僕は尋ねる。
彼女は、左の部屋を指さし「そっちが歴史、地理、語学などです」と言い、今度は右の部屋を指さし「そっちが宗教、哲学、社会科学、文学などです。私は二階に居ますので、何か分からないことがあればまたお呼び下さい」と言い、二階の部屋へと奥へと戻っていった。
僕は左の部屋の扉を開ける。中は十畳ほどの広さで、部屋の四方八方に本棚があり、様々な書物が隙間なく、本棚に詰め込まれていた。
ある程度の間隔で「歴史、地理、語学」と書いたプレートが差し込まれている。さっきの女性は、本は丁寧に扱って下さいと言っていたが、ここにある本の大半は既に、色あせていたり、角がすり減っていたりしていて、綺麗な状態の本の方が少なかった。
僕は歴史のジャンルの辺りから、比較的新しそうな物を選んで引き抜いた。隙間なく詰められているせいで、引き抜くのにそれなりの力が必要だった。同じ場所にもう一度この本を入れられる自信が、僕にはなかった。
部屋に一つだけ置いてある椅子に座り、僕はその本を開く。七年前に発行された本で、様々な国内の事件の記録が記されている本であった。
目次を開き、年代別に書かれた色々な事件を目で追っていく。
三十年前。あの家の幼児が亡くなり、使いの男が養子として引き取られた年と、同じ年に起こった事件を探す。
【役場、立てこもり事件】
【南西部農村児童、沼地溺死事件】
【少年誘拐、物干し竿吊り晒し事件】
【村八分民家放火、女性焼死事件】
【路面バス毒物散布事件】
ここにある記録では、同年に五つの事件記録が記載されていた。
その中の「村八分民家放火、女性焼死事件」と言う事件は、「南西部農村児童、沼地溺死事件」の、ほんの一週間前に起こっており、またその事件現場もここから、近い村だということが分かった。
歩いて移動できない距離ではない。もしかしたらその村こそが、使いの男の本当の、生まれ故郷かもしれない。僕はその事件について書かれた頁をめくる。
【○〇年〇月○日 深夜一時十七分。
西部の村の村民より「家が燃えている」との通報が保安課にされた。城は現場近くの交番所へ連絡し、消火活動を要請。
それと同時に五名の衛兵を、すぐに現場へ向かわせた。駆け付けた衛兵と共に消火活動を実施。一時五十二分に鎮火。
屋内にて、椅子に手足を縄で縛り付けられた女性の焼死体を発見。後の調査で火元はそこからであったことが判明。
また、同居していた十三歳の息子が消息不明となる。
保安課は当初、金銭がなくなっていたことから強盗、放火殺人、また誘拐事件として取り扱った。しかし、外部の人間が侵入した形跡はなく、村人の証言でも不審な人物などの情報はなく、消息不明となった息子が、何らかの形で関わっている可能性があるものとして、捜査の方向を転換していったが、現在でも有力な情報は掴めておらず、迷宮入りとなった。
また、村人の証言から判明したことは、事件のあった家庭は、事件の起こる三年前に夫婦が離婚しており、母子家庭であったという。
そして、焼死体で発見された、その家庭の母親は村人に対して素行が悪く、そのせいで息子もろとも、村八分状態にあったという。
しかし息子の方は、生まれながらに頭脳明晰であり、一部の村民からは家庭に招かれ、勉学の指導を頼まれることも度々あったという。
某少年が最後に目撃されたのは、事件の三日前。同村の十五歳の少年のもとへ訪れ、勉学の指導を行った際に、その家庭の母親が、少年が帰る際、玄関で挨拶を交わしたのが最後であった】
僕は本を閉じ、膝の上に置いた。
この行方不明の少年が、使いの男である可能性は高いと思う。
この村で殺された夫婦同様に、使いの男はそこを去る時に、両親となった人物を殺す傾向があるのかもしれない。もちろん断定は出来ないが調べてみる価値はある筈だ。
この放火事件のあった村からこの村まで、休憩を入れたとしても、徒歩で一日半もあれば辿り着くことは出来る。
そしてあの沼で、あの幼児が水死体で発見されるまで五、六日。それから更に、あの家の前で衰弱した状態で発見されるまで二週間あった(と老爺は言っていた)が、その間はどこに身を置いていたのだろう?
分からないが、一度この放火事件のあった村に行ってみれば、何か分かるかもしれない。
と、その時。
「お探しの本はありましたか?」と、後ろから声がした。
振り返ると、先ほどの、館の美しい女性が、扉のところから顔だけをひょこっと覗かせていた。
「はい。ありました。それにしても、本当にすごい数の本ですね。確かに村の人達から図書館と呼ばれる理由も分かります」
「父の趣味のようなものです。父は物理学者だったのですが、その他にも色々なことに興味があって、とにかく四六時中本を読んでいるような人でしたから」。そう言いながら、彼女は部屋の中へと一歩足を踏み入れた。「私も幼い頃から本を読むという事には慣れていましたが、父ほど何かに熱中する程でもないし、ここの書物は私には持て余すものばかりだったので、ここを開放することにしたのです」
「なるほど。そういう経緯だったのですね。しかし……お父さんが物理学者だったのに、物理学の本は置いていないのですね」
「いえ、科学系の本は全て二階に置いています。主に量子力学の専門書ばかりですが、あまりそういう本を求めて来る人はいませんし、主に私が読んでいるので、基本的に二階に置いているのです」
「お若いのに、変わった生活をされているのですね。下の村に下りて行くことはあるのですか?」
「もちろんあります。父は本当に典型的な学者タイプの人間だったもので、基本的には、他人を避けて生きるような人間でした。だからこんな、秘境のようなところに家を建ててしまいましたが、私はそれほどでもありません。この村の人達は暖かいし、食べ物だって美味しいものばかりです」
僕は、彼女を最初見た時、正直この村の人にしては、少し異質だなという印象を受けたが、どうやらそうでも無いようだ。話をすればする程、この村の人達の持つ寛容な精神が、彼女の中にもちゃんとあることを、僕は感じた。
「本当に、僕もこの村は良いところだと思います。多分僕は、どちらかと言うと、あなたのお父さんのように、他人との接触を避けるような人間だと思います。だから……この村にいると、少しばかり自信を無くしてしまうのです」
「面白い神父さんです」と言い、彼女は笑った。「私の父は、いくら人から孤立していても、全く自信を失わない人間でした。だけどあなたは、自分でそのように感じてしまう時点で、きっと、人との繋がりが自分にとって必要であると分かっているのだと思います」
「それは確かに、そうかもしれませんね」と言い、僕も笑った。
「だけど、ここにこの村以外の人が来るなんて、本当に久しぶりの事ですよ。それに神父さんが来たのは、初めてのことかもしれません。北の、国道沿いにある教会から来られたのですか?」と彼女は言った。
「いえ、僕は神父では…………」あり、ま………………
その時。何かが頭の中で弾ける音がした。
「〇Δ×〇?」
「〇Δ×〇**!?」
「だ……じょ……で……」
「ど............さい………………」
な。にが オ こた ?
こ こは ボク ハなニモの
ロウふ じん、
もりノきょ、うかい。
しょウじョのか。はカ。ハ、ドコニあル……
「……か? 聞こ……か?」
「………………」
「どうな……ま……たか⁉」
「………………」
「見えていますか?! 瞬きをして下さい!」
「……す」
「え! 聞こえますか?!」
「き……えま、す」
「私が見えていますね?!」
「み、え……ます」
気がつくと、彼女の顔がすぐ目の前にあった。僕は椅子から落ちて、地面に尻もちをついていた。倒れないように彼女が反射的に、肩を支えてくれたのだと理解する。
「す、すみません! ごめんなさい」と言い、僕は彼女から急いで離れ、立ち上がり、椅子に座った。
「驚きました。今医者を呼びますね」と彼女は言う。
「い、いえ! 大丈夫。もう大丈夫です」と僕は答え、彼女の目をしっかり見て、小さく笑ってみせる。
「だけど……あなた、目を開けたまま急に倒れて、しばらくその状態だったのですよ」と、彼女は言った。
「え、でもしばらくって言っても、一瞬でしょ?」
「一瞬ではないです。二、三分はありました。脈や呼吸が正常だったから躊躇いましたが、もう電話をかけるところでした」
「そんなに? すみません。だけど、もう本当に大丈夫なので」
「以前も、こんな風になったことがあるのですか?」と、彼女は心配そうに尋ねる。
「いえ、初めてですね。だけど別に、体がどこか悪いわけではないのです。ただ、何というか、フラッシュバック……に、近いことなのかもしれません。いや、んん。正確には違うと思うのですが、上手く説明が出来ません。ただ、もう大丈夫ということは確実に言えます」と言い、僕はもう一度彼女の目を見て、大丈夫だという顔をみせた。
「……そうですか」と彼女は、僕の言葉をひとまず、受け入れてくれたようだった。
「ところであの、さっき、国道沿いの教会と言いましたか? 僕が倒れる直前に。そこは、ここから近いのでしょうか?」
「え、ええ。まあ近いですよ。北から城に向かう方面のバスに乗っていけば、すぐです」
「もしかしてそこは、広い荒地の中に、農園のように等間隔に植樹された木々があって、その中心にある教会のことですか?」と僕は尋ねる。
「そうですね。確かそんな感じだったと思います。私も、曖昧な記憶ではありますが」と彼女は答えたが、やはりまだ心配そうな顔をしていた。
「すみません。急に倒れてしまって。もう本当に大丈夫なので」と僕は言う。
「しかし、ちゃんと休まれていくべきです。帰りは長い坂道になりますし、もし途中で倒れでもしたら大怪我に繋がります。二階にソファがありますから、そこで横になっていって下さい」
「しかし……」と僕は断ろうとしたが、彼女は言葉を遮った。
「今日はもうバスはありませんよ。どちらにしても今日は、この村に泊まって行くしかないのですから。それなら、ここで一晩泊まって、明日の朝に坂を下った方が良いと思います」と彼女は真剣な眼差しで言った。「夜御飯は二人分用意するのも、そう変わりませんから」
「では、あなたの迷惑にならないなら」
僕は彼女に半ば押し切られる形ではあったが、彼女の提案をありがたく受けることにした。
【第二部】三十八章 ミサンガ(ある少年)
その小さな男の子は左手の手首に、緑色と水色のビーズを交互に五つ、藁で編み込んで繋げた腕輪をしていた。
それはつい昨日、誕生日で六歳を迎えた男の子の為に、母親が作ってやった物だった。
それを大変気に入った男の子は、広場に集まった近所の仲間達に、ちょうど自慢しているところだった。
周りの友達はみな「きれいー」「いいなあ」と羨ましがっていた。男の子は誇らしげな気分で、仲間たちの中心に立っていた。
しかしそこに、ガキ大将の太った九歳の少年が、弟分を連れてやってきた。
「貸せよ」
と一言言うとガキ大将は、腕輪を付けた男の子の方へ、右手を差し出した。
男の子は抵抗することなく、黙って左腕からその腕輪を外すと、ガキ大将に手渡した。さっきまで騒いでいた周りの子供達も、何も言えず、すっかり大人しくなってしまっていた。
ガキ大将は、男の子から奪った腕輪を、自分の左腕に巻き付けた。
「ふうん。お前の母ちゃんが作ったのか?」
「そうだよ。きれいだろ」
「おいこれ、マッチで燃やしてみようぜ」と言い、ガキ大将は笑った。そして「お前、家からマッチ取って来いよ」と、横にいた弟分に指示を出し、弟分は住宅地の方へとすぐに走って行った。
「やめてよ。おねがい」と男の子は、ガキ大将に言った。
「やめない。お前貧乏なくせに、こんな生意気なもん付けてるからいけねえんだ」
「もうつけないよ。もうつけないから、返しておくれよ」
しかしガキ大将は「うるさい」と言い、それから男の子が何を言おうと、無視を決め込んでしまった。
そうしている内に、マッチを持った弟分が戻って来てしまった。そして弟分は、ガキ大将にマッチを渡した。
「おい、みんな見てろよ」と言い、その太ったガキ大将は、左腕から腕輪を取り外すと、みんなの前でマッチを擦ってみせ、火の付いたマッチを、腕輪に近づけていった。
女の子が一人「ねえ、やめようよ」と言ったが、ガキ大将は構わず、その藁の腕輪に、火を付けた。
「お願い! やめて!」と、男の子はついに泣き出し、ガキ大将の腕にしがみついた。
しかし力の強いガキ大将は、男の子を左手で押さえ、火の付いた腕輪を持った右手を、天高くつき上げた。
そして「止めてほしいか?」と意地悪く、改めて男の子の方を見下ろして言った。男の子は必死に頷いた。
「止めてほしかったら、俺の言うことを聞くか?」とガキ大将は言った。その間にも男の子の大切な腕輪は、みるみる燃えていっている。
「聞く! 聞くから!」と男の子は必死に答えた。
「よし」と言いガキ大将は、燃えている腕輪の火を吹き消した。
しかし、小さな腕輪だったので、もう既に半分が真っ黒に焦げてしまっていた。男の子はその腕輪を見て、もっと悲しい気持ちになった。だけどそれでも、母からもらった、大切な誕生日の品であるために、その焼け焦げた腕輪を返して欲しかった。
「……返してよ」
「そうだな。じゃあ、沼地にあるあのぼろ小屋の中に、鉄砲の弾があるって、親父が言ってたの聞いたんだ。それを取ってきたら、この腕輪と交換してやる」とガキ大将は言った。
村の外にある沼地というのは、危ないので近寄ってはいけないと、子供達はみな、大人からきつく言われている場所であったが、男の子は、涙を拭き「分かった」と答えた。
ガキ大将とその弟分、そして男の子は、三人で村を出て、沼地の方へと続く坂道を下って行った。
——–坂を下り終え沼地に着くと、ガキ大将は「ここからは、お前ひとりで行ってこい」と、男の子に命じた。
幼い男の子は、数十メートル先にある掘っ立て小屋を目指して、歩き出した。沼地の水たまりは、あちこち無数に点在しているので、よく用心して歩かなければならなかった。大人なら、うっかりはまってしまっても膝くらいまでだが、まだ六歳の子供にとっては相当な深さであった。
男の子は数メートル進んで、泥に一度足を取られた。半べそをかき、振り返ってみたが、いじめっ子達はこちらを睨みながら腕を組んで、仁王立ちしている。
許してくれる訳がないことは明白だった。そっちに戻ってぶたれるよりは、まだ、黙って前に進む方がいいと思い、男の子は少しずつ小屋に近づいて行った。
そして男の子は、どうにか掘っ立て小屋の前まで辿り着くことが出来た。ガキ大将の方を振り返ると彼は「早く中に入れ!」と、遠くから叫んだ。
男の子は、自分のおでこ程の高さの取っ手を掴み、前方に力をかけた。ギギギィという、きしむ音と共に扉は開いた。中を覗き込んでみる。
するとそこには、眼鏡をかけた少年が、具合悪そうに、むしろ(藁で出来た敷物)の上に寝転がっていた。
少年の周りには、缶詰の空や、クラッカーを空けた袋、水の入っていたペットボトルなどが散乱していた。
少年の向こうの壁際には、右から、大きなドラム缶が一つ。その隣に、積まれた土のうが三つ。更にその隣には、クワやシャベルなど、様々な農具が入れられた木箱があった。
その少年は最初は、開く扉の方を睨むように見ていたが、入って来たのが幼い子供であることに気が付くと、強張った表情を緩めた。
「おにいちゃん……だれ? ここはおにいちゃんのお家なの?」と男の子はその少年に尋ねた。少年は、まだ十三歳であったが、六歳の男の子からすれば、遥かに大人であった。
「そんな事より君こそ、こんな危ない所に一人でどうしたんだい?」と少年は、男の子に尋ねた。
「ここに、てっぽうのタマがあるから、とってこいって言われたんだ」と男の子は答えた。
「そっか。だけどここには、鉄砲の弾はないんだよ」と、言いながら少年は上体を起こした。「どうしてそんな物が要るんだい?」
「もってかえらないと、ウデワを返してもらえないんだ。もう焼かれちゃったんだけど……」
「腕輪? 腕輪って、腕に付ける腕輪のこと?」と言って、少年は分かりやすく、左手の手首を右手で掴んで、空中に持ち上げて見せた。
「そうだよ。お母さんが作ってくれたんだけど、とられて燃やされちゃったんだ、それでもいいから、ぼくは返してほしいんだ。だからぼくはてっぽうのタマがいるんだ」と男の子は言った。
少年はその説明でやっと、ある程度の状況を予想することが出来た。
そして、ちょうどその時「おい。何ちんたらしてんだよ」とガキ大将と、その弟分が小屋の中へと入って来た。
二人は、小屋の中にいる少年を見るなり、驚き、少しだけ飛び上がった。
「お前なんだ! こんなところで何してるんだ⁉」と太ったガキ大将は少年に向け怒鳴った。
まだ六歳の男の子よりも、九歳のガキ大将の方が、こんな沼地の暗い掘っ立て小屋に、少年が一人で生活している。ということの異常さに、やはり恐怖を感じたようであった。
「そっか。こいつが、君の腕輪を燃やしたってことかな?」と、少年は男の子に向かって言った。
男の子は、こくんと頷いた。
【第二部】三十九章 「誰かと食べる夕食。量子力学の話」
気がつけば外はもう、夕暮れ時となっていた。それから僕は二階のソファまで案内され、そこに座った。
「では、これから晩ご飯を作りますので、待っていて下さい」と言う彼女は、何やら張り切って見えた。鼻歌を歌いながら、階段を下りて行った。
僕は、晩ご飯が出来るまでの間、二階の窓から外をボンヤリと眺めていた。山の中腹に建てただけあって、景色が良かった。眼下に広がる村の灯りや、遠くの方には国道沿いに連なる道路灯の光までも見えた。
部屋の中に視線を戻してみると、彼女の言った通り、化学系の書物ばかりが置いてある本棚があり、本の背表紙は、僕にはやはり、難解なタイトルばかりであった。
その隣には研究者が使うような、引き出しがたくさん付いた大きな机があった。あの机も、彼女の父親が使っていたものなのだろうか。
——–数十分後、彼女が晩ご飯をトレーに乗せて階段を上がって来た。
晩ごはんは、焼きナスと、茶碗蒸し。それから、鶏肉とカシューナッツを甘辛いタレで炒めたものだった。
それらは僕にとって、目が眩む程の輝きを放っていた。
「やばい。これは……何と美味しそうな」と僕は言った。
そういえばここ数日は、移動しながら何かを食べたり、即席のものを食べたりしていたので、ちゃんとした食事をとっていなかったことを思いだした。
「神父さん。ちょっと顔色悪そうだったので、栄養のあるものを作りましたから」と言う彼女は、とても得意げだった。
料理の味は、言うまでもなく絶品だった。
僕だって料理は好きで、以前は毎日のように作っていたが、何というか、どれも僕が作るものよりも品があった。特に盛り付けのセンスや皿のチョイスなどは彼女の圧勝だった。
僕は料理を頂いている間多分十回以上は「美味い、美味しい」と言っただろう。その度に彼女も目を細めて笑っていた。
晩ご飯を食べ終わった後は、彼女は、量子力学の魅力について熱く語ってくれた。
それから基礎的な話などをしてくれた。僕には理解出来ないと思ったが、彼女の説明がとても上手だったため、何となく理解することが出来、専門的な話にも関わらず、楽しく聞くことが出来た。最初だけは…………
彼女が覚醒したのは、僕が話の導入をある程度、理解してしまったからかもしれないし、単に夜中だったからかもしれない。
彼女ははっきり言って、驚くほどお喋りだった。会話のうち九割は僕は相槌を打っていたように思う。嵐のように喋り続ける彼女に、僕はただ圧倒されていた。
そして夜中の十二時をまわると、彼女は「それじゃあ!」と言って、寝室へ帰って行った。
彼女が研究者である父親の血を受け継いでいることを、僕はとことん思い知らされた。
ものすごいエネルギーだった。彼女の父親が、内に引きこもるタイプの変人だったとしたら、きっと彼女は、前面に押し出していくタイプの、変人なのかもしれない。
「美しい料理上手な女性」という印象の上に、圧倒的な存在感のあるキャラクターが上書きされてしまった。
——–急に静かになった部屋の中で、僕はしばらく呆然としていた。どっと疲れた気もしたが、それだけではない不思議な感覚もあった。
正直。少女が死んでしまってから、僕は底辺をうろついていたが、それを行動することで紛らわせていた。
だけど先程の彼女のパワーが、その底辺にいる僕に、別世界の光を見せてくれたのかもしれない。
彼女の目に映る世界はきっと、僕の見ている世界とは想像もつかないほどに遠く、輝いているのだ。
あの沼地で見かけた、沈みかけの掘っ立て小屋のように、僕の足元はずぶずぶと、毎日少しづつ沈んでいっている。そんな気がしていた。
それについて、今は仕方ないと思い受け入れていた。だけど、それは少しづつ慢性化し、確実に僕を捉えようとしていた。そして僕はやはり、この沼地からはもう抜け出せないのだと、思い込みかけていた。
だけど彼女が、自分の好きな話を一生懸命に話す姿を見て理解した。
僕は沼地から抜け出せないのではなく。沼地に留まることを望んでいるのだと。
僕は自分の事を、可哀想な被害者だと思いたいのだ。そうして不幸を背負い、暗い顔をして歩きたかったのだ。そうすれば、誰かが、優しく声をかけてくれるかもしれないから。
そんな風な時間あることは自然なことなのかもしれないし、あってもいいのかもしれない。だけどずっと留まってはいけない。絶対に。
だからそろそろ進む方向を変えよう。それは少女から学んだことじゃないか。闇から抜け出すには、病みを手放してそれ以外の選択肢を選ぶことだと。
そして僕は、彼女が貸してくれた来客用の寝間着に着替え、ローブをハンガーにかけた。それから電気を消し、ソファに横になった。
寝転がった頭のすぐ横に、読書灯があることに気付き、そのスイッチを押した。小さな暖色の灯りが手元だけを照らし出した。
僕は鞄から少女のスケッチブックを取り出して、また一枚目から順番にめくって、見てみることにした。
一枚一枚、絵を見て行くだけで、自然と心が癒されていく気がする。
初めて少女にスケッチブックをあげた日のことを、僕は思い出していた。まだ彼女が岬に流れ着いてから、一ヶ月ほどしか経っていない時だった。
僕が近くの丘から、灯台とその周りの景色を描いているとあの子は家から出てきて、黙ってこちらまで歩いて来て、黙って隣に座り、黙って僕の描く絵を眺めていた。自分から描いてみたいとも言わずに、ただ黙って。
そして僕がスケッチブックをあげると言うと、笑った。それが、初めて僕の前で見せた笑顔だった。
僕はスケッチブックの最後のページをめくった。恥ずかしいが、僕の寝顔が描かれているページだ。
しかし、何だろう。気のせいかもしれないが、このページだけ少し、前見た時よりも描き足されている気がする。
鼻の辺りか? 前はもう少しボンヤリと描かれていた気がするが、少し鼻の縁がはっきりとしたように思えた。が、確信を持って思える程の変化ではなかった。僕はスケッチブックを閉じて鞄にしまった。
読書灯を消し、仰向けになると目をつむった。
そして僕は、使いの男にライフル銃を向けられて、腹と太ももを撃たれた時のことを思い出した。
そして否応なく、少女が目の前で撃たれる場面もまた再生されてしまう。心に広がりそうになる絶望を振り払い、歯を食いしばった。
それから僕は、シャツの下に手を滑り込ませ腹を指で触ってみる。次に、ズボンの中に手を入れ、左の太ももを触る。
「……そんな気がした」と僕は呟いた。
僕は寝返りをうって横向きになった。すぐに睡魔がやってくる。
僕がその日最後に思い出したことは、焼きナスの香ばしい醤油の味の事だった。
【第二部】四十章 「掘っ立て小屋(ある少年)」
少年は黙ってその場に立ち上がった。他の三人の子供達もまた、何も言わず少年の様子をうかがっていた。
「おい。お前」と少年は、ガキ大将のほうに顔を向け言った。そして、先に入って来ていた幼い男の子を指さした。「その子が言ってたぞ。『くそブタ野郎に、鉄砲の弾を取って来るよう言われたんだ』って」
ガキ大将は「お前許さねぇ」と言い、男の子の方へと詰め寄った。
「ぼくそんなこと言ってないよ!」と、男の子は言った。
「嘘つくな! お前あいつに助けてもらおうとしたんだろう!」と、隣にいた弟分も口を挟んだ。
「してないよ! てっぽうのたまがあるか聞いてただけだよ」
「うるせえ! あいつ、俺がお前の腕輪を燃やしたこと知ってたじゃねぇか!」と、ガキ大将は男の子に向かい拳を振り上げた。
「やめて!」と男の子は、両手で頭を塞いだ。
しかしその時だった。
「おい」
ガキ大将は後ろから声をかけられた。
振り向くと、少年が大きなシャベルを持って、すぐ後ろに立っていた。いつの間にか向こうの壁際から取って来ていたようだ。
少年は振りかぶると、ガキ大将の脇腹を、その巨大なシャベルの硬い鋼鉄の部分で力任せにぶん殴った。
ガキ大将は横に吹っ飛び、床の上にうつ伏せで倒れ込んだ。そして、殴られた左の脇腹を押さえながら「うっうっう」と、しゃくり上げ始めた。
「ごめんな。嘘をついちゃって」と少年は、壁際に追い詰められていた男の子に謝った。そして「小屋の裏にロープがあるから、それを取ってきてくれるかい? その間に僕が君の腕輪は取り返しておくから」と言った。
男の子も突然のことに戸惑ってはいたが「わ、わかった」と言って小屋を出て行った。
それから少年は、横で震えているガキ大将の弟分の方を向いた。弟分はビクッと一瞬体を震わせた。
「おいお前。向こうから土のうを取ってこい。言うこと聞かないと、お前もこれで殴るぞ」と弟分に言った。
弟分は言われたとおりに、土のうの積まれた壁際まで走って行った。しかし、一つ十キログラムはあるであろう土のうを、まだ十歳にも満たない子供が持つのは大変だった。しかしそれでも、殴られたくないという恐怖だけで彼は、重たい土のうを持ち上げた。
「それを扉の前に置いて、開かないようにしろ」と少年は言った。
弟分は、必死に入口までそれを運ぶと、ドスンッと下に土のうを落とした。
「もう一つ持ってこい」と少年は言った。
その時、こっそり起き上がろうとするガキ大将に気がつき、少年はさっき殴った脇腹と同じ個所を、シャベルでもう一度殴った。
「ぎゃああああ!」
ガキ大将の叫び声が小屋の中に響いた。
「じっとしていないと殺すぞ」
何とかもう一つの土のうを、持ってきた弟分に少年は「このブタの上に置け」と、倒れているガキ大将を指さして言った。
「でも……」
少年はシャベルを振り上げて「置け!」と、怒鳴った。
ついに弟分は泣きだした。そして力がないために、ゆっくりと土のうを下ろすことは出来ずに、倒れているガキ大将のふくらはぎの辺りに、土のうを落下させた。再びガキ大将の悲痛な叫びが小屋の中に響いた。
その時扉の方から、かたかたという音が聞こえてきた。どうやら男の子が、外から開けようとしているみたいだった。
「ロープなかったよー」という声が外から聞こえた。
「そっか。無かったか」と少年は答える。「今ね、腕輪を返してもらえるように言って、もう二度と君をいじめないように、話してるところだから、ちょっとそこで待っててくれるかい?」
「わかったー」と、男の子は言った。
少年は、倒れているガキ大将の背中に跨った。足には土のうが乗せられているため、力自慢のガキ大将でも、もうさすがに身動きが取れなかった。弟分は、すぐ横で立ったまま震えながら泣いていた。
「おい」
少年はガキ大将の耳元に顔を近づけて囁いた。それからシャベルの先を、倒れているガキ大将の顔の前に持って行った。
「これからお前の体を、足の先から順々に切り刻んでいく。このシャベルの先端を見てみろ。太い木の根も断ち切れるように、先は薄くなっている。見えるか? この先を、まずはお前の足の指の関節に置き、僕が上から踏みつける。簡単に指は吹っ飛ぶだろう。
それから少しづつ、ゆっくりと。体の上の方に向かって、シャベルの刺し込む位置を上げて行き、僕は何度もシャベルを踏みつけていく。そうしてお前の体を少しずつちょん切って行く。どの辺りまで生きてられるか分からないけど、一度こういうことをやってみたかったんだよ」と言い、弟分の方に顔を向けた。「おい。こいつの靴と靴下を脱がせろ」
弟分は「ごめんよ、ごめんよ」と言いながら、ガキ大将の靴と靴下を脱がせ、素足にした。
少年は立ち上がると、シャベルの先を、ガキ大将の足の指の関節部分に置き、鋼鉄部分の上側に足を乗せた。
「いいか。いくぞ」
「や、ややめ……止めて、ゆ、ゆ、ゆるして、うっ、く、ください」
弟分は。少年の腕にしがみ付いた。顔をどろどろにさせて泣いていた。
「い、いいいとこも、あるやつ、なんです。どうか、うぅぅゆるして」と、言葉にならない言葉で言った。
少年は、ガキ大将の方はどうしているだろうと思い、顔を覗き込んだ。すると彼は唇をかたかたと震わせながら、発作の状態のようになっていた。
激しい運動をした時の犬のように、凄い速さで息を吐き出していた。どうやら黙っていたのではなく、声すら発せない状態になっているようだった。
「お前、家は村のどの辺りだ?」と少年は、まだ少しは喋れそうな、弟分の方に尋ねた。
「む、村の、水車ごやの、向かいの、あか、い。やねの家です」
「このブタの家は?」と、ガキ大将を指さして言った。
「ぼくいえっのと、となりです」
「お前ら。僕がもしここにいることを誰かに喋ったら、すぐに殺しに行くからな。お前達だけじゃなくて、お前らの、お母さんやお父さん、兄弟も皆殺しだ。お前らが言わなくても、もし何かでそんな噂が立ち僕の耳に入れば、それでも同じだ。絶対に殺してやる。いいな?」と少年は言った。
弟分は、震えながら分かりましたと言い、ガキ大将は倒れたまま、何度も首を縦に振った。
「明日から毎日、あの子にここに来てもらうことにする」と、小屋の外で待っている男の子の方を指さして言った。「その時に、お前らが余計なことを喋ってないかも聞くことにする。もし何かの誤解で僕に伝わったとしても同じ事だ。言い訳もさせない。そこにある鎌や、シャベルを持って、すぐに家に押しかけるからな」
「も、もう、だれも……い、いじめないよ」と、やっと喋ったのは、ガキ大将だった。
「……そうだ。あの子の腕輪はどこにある? 出せ」と少年は言った。
「こ、ここにあります」と横から弟分が言い、少年の元まで駆け寄ると、手渡した。
少年は、ガキ大将の背中から立ち上がると「それ、どかせ」と弟分に言い。ガキ大将のふくらはぎに乗っている土のうを指さした。弟分はヘロヘロになりながらも、なんとか土のうを持ち上げ、床に落とした。
「早く立て」と少年は、ガキ大将のおでこを、足の先で突っつき、立ち上がらせた。
「これからそこの扉を開ける。お前らは何も言わず真っすぐに、村の方へ帰れ。あの子と目を合わせるな。顔も向けるな。いまお前らの顔は恐怖で満ちている。そんな顔を見せるな。あの子に顔が見えないように反対を向いて、直ちに沼地を抜けていけ」と少年は言った。それから、扉前に置いていた土のうを持ち上げ、扉前から除けた。
——–扉を開くと男の子は、小屋前で板切れに座って、地面の泥を枝でかき回して遊んでいた。
「ほら、腕輪だよ」と少年は、男の子に手渡した。
「うわあ! やった!」と男の子は喜んだ。
少年は、小屋の中の二人の方を振り返り「早く帰れ」と、目と顔の動きで合図した。ガキ大将はすぐに走り出した、弟分もそのすぐ後ろに引っ付いて行った。
沼地を走って行くガキ大将の体は左に曲がっていた。シャベルで二度も殴られた左の脇腹は、恐ろしく腫れ上がっており、体を真っ直ぐすることが出来なかったのだ。
「ありがとう」と言い、男の子は腕輪を受け取った。そして振り返って、そそくさと帰って行くいじめっ子二人の背中を見た。「おにいちゃんは、あのふたりを、ひとりでやっつけたの?」
「そうだよ。悪い奴らはこらしめないとね。君のことを二度といじめないように、ちゃんと言っておいたからね」と言い、男の子の頭を撫でた。
「おにいちゃんすごいね! あいつ、ちからもちだから、村のみんながこわがってるのにさ」と男の子は、ヒーローを見るような目で、少年を見ていた。
「ところで、お兄ちゃんのお願いを、良かったら聞いてくれないか? 今とっても困ってるんだ」
「うん。うでわをとりかえしてくれたお礼をしなくちゃね。お母さんも、しんせつな人のおねがいはきいてあげなさいって、いつも言うんだ」
「ありがとう」と言い、少年は膝を曲げ、男の子と同じ顔の高さまで下がった。「実はね、僕も君と同じように、自分の村でいじめられてたんだ。それでここまで必死に逃げて来て隠れていたんだよ。だから、僕の事を村の誰にも、言わないでほしいんだ。大人に知られちゃうと、僕は自分の村にまた返されてしまう。そしたらまたいじめられてしまうんだ。わかる?」
「うん。わかった。じゃあだれにもいわないよ」
「ありがとう。君はとっても賢いね。じゃあ約束だ。指切りしよう」
少年は男の子と、小指を繋ぐと、指切りげんまんの歌を歌った。
「それから、もう一つお願いがあるんだ。これはさっきより少し難しいかもしれないけど、聞いてくれるかい?」と少年は言った。
「もちろんだよ! なんでも言って!」
あの強靭なガキ大将を撃退し、自分の大切な物を取りかえしてくれたヒーローからお願い事をされることは、この幼い男の子には誇りのように思えた。そして子供と言うものは、こういった非日常的な隠し事というものが大好きであると、少年は知っていた。
「あのね、僕はまだしばらくはここに居なきゃいけないんだ。だけど、そろそろ食べ物や飲み物が無くなって来たんだ。だからね。少しでいいから、毎日こっそり、ここにパンとお水を、運んで来てくれないかい? これは君にしか頼めない、秘密の指令なんだよ」
「そんなのらくしょうだよ! ちっともむずかしくないよ。だってぼくの家には、いつだってパンがいっぱいおいてるんだ。お母さんが毎日やくからね」と男の子は言った。
「そうなんだ! 君は本当に頼もしいね! だけどね、さっきも言ったけど決して、ばれてはいけないよ。そうだな。君はいつもパンをいくつ食べるの?」
「うーん。ふたつかな。いつもおなじパンだし、あきちゃったんだ」
「そっか。それじゃあ明日から、三つ取って来て、一個と半分を僕にくれないかい?」
「うん。いいよ!」
「よし、決まりだ!」と言い少年は男の子の両肩に手を置き、にっこりと笑った。「だけどいいね。必ず三つだよ。四つや五つ取って来ては絶対にダメだよ。僕がここにいることは、決して君以外の誰にも知られちゃいけないからね。頼めるかな?」
男の子の顔を真っ直ぐに見つめて言った。
「うん! まかせてよ」
「よし。じゃあもう一度指切りをしよう」と言い、少年と男の子は、再び小指を繋ぎ、指切りげんまんを一緒に歌った。
それから少年は最後にもう一つ、男の子に質問をした。
「ところで、君のお家は村のどこにあるの?」
【第二部】四十一章 「『僕』という波」
僕は、村人達から図書館と呼ばれる館を後にすると、村まで続く緑地の坂道を下っていた。
昨日、陽が傾きかけた時間にこの坂を上った時とは、やはりその景色から感じる印象も違った。高台から朝一番で見下ろす村の様子や、国道を走る車の様子はとても眩しかった。太陽から受けた光を反射しているのではなく、それ自体が内側から淡い光りを放つ、発光体のように見えた。
僕は、昨日館の女性が話してくれた量子力学の話をふと思い出す。
この光る光子だけでなく、この世界の全てはミクロの物質で出来ているそうだ。風も木々も、人間も。
しかしどうして、僕と同じように、脳や心臓や二百以上の骨からなるこの物体は、世界中に存在しているのに、なぜ僕は、あの「館の女性」ではなく「僕」なのだろうか?
この肉体の持つ全機能を扱う権限をなぜ、「僕」だけが与えられたのだろうか? 例えば僕は「少女」であっても、「老婆」であっても、仮にあの「使いの男」であったとしても、物体として持つべき機能は変わりはない筈なのに。
光子の波を決して観測出来ないように「僕」という存在もまた、この肉体を通す以外の方法で、観測することは出来ないのだろうか。
では、この「肉体」が粒子だとするなら、観測することのできない「僕」は波のようなものなのだろうか。
まあ……今はあまり深く考えても仕方ない。
僕はひとまず、西部にある女性が焼き殺された事件のあった村を目指しつつ、その道中にある、国道沿いの教会を、次の目的地とした。
そういえば、今朝館を出る際に、あの館の女性は僕に謝った。
「昨晩は少し喋り過ぎました。久しぶりのお客さんで、つい嬉しかったもので」とのことだった。
「いえ、僕も最近はずっと一人で旅をしてたので、とても楽しかったです。あなたの言う通り、僕には誰かとの繋がりが必要なようです」
「私もそのようです」と言い彼女は笑った。それから「坂を下る時は、よく気をつけて下さい」とも。
僕は、手料理が美味しかった事と、泊めてくれた事の礼を言って、彼女に別れを告げた。
——–坂道を下り終え緑地を抜けると、再び村の住宅地へと辿り着いた。
村は、朝の支度を終えてバス停に向かう人や、自分のお店の開店準備をしている人などがおり、村の一日が始まろうとしていた。
僕は長い間、集落には住んでいなかった為、朝のこういった光景を見ること自体が、とても久しぶりだった。
そう多分、まだ十代の時。故郷の街に両親と共に住んでいて、神学校に通っていた頃は、毎朝こんな光景を見ていた筈だった。
それは間違いなく、僕の記憶の中にあるものだ。それなのに、灯台で過ごした恋人との五年間のこと。それから少女と過ごした一年と少しのこと。その辺りの出来事が少しづつ、不明瞭になりつつある気がしていた。
それは、僕の中で変わってきているのではなく、そうではなくて……「僕」以外の全てが、それを否定しているように思えるのだ。
その時だった。
先日話を聞かせてもらったあの老爺の姿が、行きかう人達の向こうに見えた。
その隣には大柄な中年の男性がおり、老爺は僕の方を指さして、その男性に何か説明しているような様子だった。それからその大柄の男性は老爺に頭を下げると、こちらに向かって歩いてきた。老爺は僕の方にも顔を向け、右手を上げてにっこりと笑った。僕も同じように右手を上げて笑った。それから老爺は自分の家の方へと、歩いて行ったようだった。
そして気が付くと、大柄な男は僕の目の前に到着していた。
「よう。あんたが昨日、沼地の遺体を見つけてくれたんだってな」と男は言った。
「え、ええまあ。そうですが」
「そうか。いやな、さっきの爺さんから聞いたんだが、あんたこの男を探しているんだろう?」と、その大柄な男は手に持った一枚の紙を差し出した。
それは驚くことに、あの使いの男の指名手配書だった。
僕はあの老爺には、僕が探している人物は、『城の使いの男だった人物』だという情報は、一言も喋っていない。ただ、ここに住んでいたかもしれない男を探しに来たんです。と伝えただけだった筈だ。
「はい。まさにこの男です。しかしどうしてあなたは分かったのですか? この男がこの村から消えて、もう二十五年程立っている筈ですし、この指名手配書だって、そんなに流通しているわけではない。少なくともこの村では見かけませんでした。なのにあなたはどうしてこの手配書の男と、この家に住んでいた少年が同一人物だと分かったのですか?」と僕は少し、興奮気味になってしまった。
「すまん。ここであまり詳しいことを話すのはあれだ。何というか、気が引ける。近くに知り合いの酒場がある。今の時間はもちろん閉まってて誰もいねぇから、そこで話すのはどうだ? 嫌なら別の場所でもいいが」と男は言った。
「いえ、そこで構いませんよ。行きましょう」と僕はすぐに承知した。
「すまねぇな、神父さん。じゃあ向こうだ」と言って男は、色々な商店が並んでいる、下の地区の方へと歩き出した。僕は男の背中に付いて行く。
「きっと、あんたの役に立てると思うんだよ。俺にも少しばかり事情があってな」と男は歩きながら言った。
「そうですか。事情ですか」
すると男は、歩くスピードを緩め、僕の側に寄って来て、耳元で囁いた。
「先月、城の兵達が捜査に来た時には、手を貸すことが出来なかったんだが、あんたになら話せそうなことなんだ」
「は、はあ……分かりました」と言うしかなかった。
決して悪そうな人には…………まあ正直ちょっと見えるのだが、案外こういう人は信頼出来たりもするし、あの老爺の知り合いなのだから、大丈夫だろう。
関係のない事なのだが、僕はふとある事が気になり、聞いてみることにした。
「あの、ぼ……いや、私はやはり神父に見えるでしょうか?」
「あ? ああ見えるぜ。もちろんだ」
「それは、この黒いローブのせいでしょうか?」
「まあそうかもしれんが、聖職者の格好をしていても、全く神父に見えない奴もいる。しかしあんたはばっちりそう見える。そのローブを着ていなくたって、きっと俺はあんたに、神父か何かか? と聞いていたと思うぜ」と男は言った。
「そうですか……」
やはり僕は、誰から見ても神父のようだった。
「おら、着いたぜ」と言い、男は立ち止った。
見上げるとそれは、この村の他の家屋と比べてみてもいくらか年期が入った、ノスタルジックな雰囲気のある酒場であった。建物自体はやはりレンガ造りで、煙突があった。それがこの村の建築物であることの証でもあるようだった。
「今の時間は誰もいねえ。店主もな。開けてくるからちょっとここで待っててくれ」と言い、男は店の裏手に回って行った。
そういえば、さっき男の後ろを歩いている時も思ったが、彼の体は少し、左に傾いているようだった。
【第二部】四十二章 「悪人の方が、正しくて強い(ある少年)」
少年は、樫の木の陰に隠れ、味のしない手作りパンをかじっていた。
視線の先にはある民家の窓があり、夕暮れの闇も深くなり始めた頃、やっとその家にも灯りが灯った。
母親は、せかせかと夕食の準備を進め、父親は帰ってきたばかりだったので、子供にまとわりつかれていた。
父親は、息子を抱き上げると、適当な効果音を口で発しながら、空中で振り回した。息子はキャッキャと喜びの奇声を上げている。
逆さになったりもするせいで、頬はピンク色に染まっていたが、まるで、そこは初めから、ピンク色であることの方が正しいことのように、その子には似合っていたし、愛くるしかった。
窓の外の少年は、樫の木の陰からその様子を眺めながら、長い溜息をついた。
——その日、男の子が少年の元を訪れたのは三度目だった。
昨日と一昨日は昼の時間に。約束通り三つのパンと水を持って。
二人は掘っ立て小屋近くの雨林の中を、歩きながら話をしていた。
「あの太っちょは、君のこともういじめてこなくなったかい?」と、少年はガキ大将のことを尋ねた。
「うん。あれからいちども見ていないんだ。みんなよろこんでるよ。だってあいつ、ひとの物すぐとりあげるし、すぐたたくんだ」
「そっか、悪い奴だね。家で大人しくしてるのかな」
「そうだとおもうよ。もうずっと家にいてほしいよ」
「もう、腕輪はしてないのかい?」
「うん、はんぶんこげちゃったからね。へやのひきだしにしまってるんだ。あいつにもやされたって言ったら、お母さんはおこってた。だけどまた新しいのをいま、つくってくれてるんだ」
「そっか、よかったね」
「ねえ。お兄ちゃんは、いじめられて逃げてきたって言ってたけど、いったいだれからいじめられてたの? あいつをやっつけれるくらい強いのにさ」
「お母さんだよ。君の家みたいに、優しいお母さんやお父さんばかりじゃないんだよ。というかお父さんはもう、途中から出て行って居なかったけどね」
「そうなんだ。おとながこどもをたたくのはよくないよね。でもどうして、お母さんは、お兄ちゃんをたたくの? なにかわるいことしたの?」
「いいや。していないさ。そんなものだよ大人なんて。いや、人間なんてそんなものさ」
「そっか。じゃあ、お兄ちゃんもうちに来ればいいじゃないか! そうしなよ!」と、男の子は名案が思いついたように、大きな声をあげた。
「いいね。君の家に行けば、もう叩かれなくて済むのかな。君はお父さんやお母さんに、一度も叩かれたことないの?」
「いちどだけお母さんにたたかれたことはあるよ。でもおかあさんは泣いてたから、ぼくはちゃんとはんせいしたんだ」
「泣いてたって、どうしてお母さんは泣いていたんだい?」
「ぼくがとびだして、バスにひかれそうになったんだ。それをとおくから見てたんだけど、お母さんは走ってきて、ぼくをたたいたんだ。そのあとで泣きだしたんだ。お父さんは、『お母さんの手の方がいたかったんだぞ』って言ったけど、ぼくのほっぺだってそのあとずっと、ひりひりしてたよ」
「そっか。だけどきっと、お母さんの手は痛くなかったと思うよ。大人はよくそんな適当なことを言って、大人の方が正しくて、子供は間違っていると、そう思わせるように仕向けるんだよ」
「そうなのかな。よく分からないや」
「…………」
しばらく話ながら歩いている内に、雨林を小さく一周して、また掘っ立て小屋のある沼地の方に出て来ていた。
「見て!」と男の子は、頭上の何かを指さして叫んだ。見上げると、すぐそこにアテモヤの実がなっていた。
男の子は手を伸ばして跳び上がったが、少しだけ届かないようだった。
少年は、男の子の背後に回り、後ろから両脇を抱えて持ち上げた。男の子は手を伸ばして、アテモヤの実をもぎ取った。
「取れた!」と、男の子は嬉しそうに言った。
「この辺りは水たまりがたくさんあって危ないから、向こうまで僕が運んであげよう」と少年は言った。
それから男の子を抱えたまま、足元に気を付けながら、沼を回り込むように歩き出した。
「お兄ちゃんは、いつまでここにいるの?」
「そろそろ、どこかに行こうと思っているよ」
「なら、やっぱりうちに来ればいじゃないか! ぼくがお父さんに言ってあげるよ」
「そっか……じゃあ、そうさせてもらおうかな」
掘っ立て小屋の前まで辿り着くと、少年は数メートル先の沼の方に身体を向けた。そしてまだ、男の子を腕に抱えたままで言った。
「今日もちゃんと来てくれてありがとう。最後に君に一つ。この世界の真理について教えてあげる」
「しんり?」
「そう、真理。『本当の事』『偽りのない事』『変わることのない定理』ってこと」
「……ていり? よくわからない」
「つまりね」と言いながら、少年は沼に向かって速足で歩き出した。「正義の味方よりも、悪人の方が、強くて正しいんだよ」
そして駆け出すと、その勢いのまま男の子を放り投げた。
化け物が餌を飲み込むような鈍い音と共に、男の子は着水する。そして、沼の底の方へ沈み込んだ。
数秒後、浮き上がってきた男の子は必死に手足を動かし、何かを叫んでいた。しかし、そうすればそうするほど沼の水を飲み込んでしまい、パニックへと陥っていった。
男の子はまだ学校にも通っていないし、泳げる筈はなかった。その叫び声は、まだ声変わりのしていない声帯。いつものあの、あどけない声が出るはずの場所から発せられる、高く、耳を塞ぎたくなるような、鋭い音だった。
男の子は、数分間もがき続けたが、やがて自分の力ではどうすることも出来ない事態だと体が頭に伝え始めた。水はたっぷり飲んでしまったし、空気だってどんどん無くなっている。体は重たくなるばかりだった。
そして、その死の隙間から、水辺に立つ少年の顔が途切れ途切れに映りこんだ。だけど、あの優しかったお兄さんの顔には、暗い影が落ちていて、よく見えなかった。
どうしてだろう……。
よく見えないな……。
お母さん……。
お、かあ……さ…………。
少年は、男の子が完全に沈んでしまった事を確認すると、掘っ立て小屋の中に入って行った。
そしてまた、味のしないパンをかじった。男の子はもう居ないため、今日は三つとも食べれるな。と少年は考えた。
【第二部】四十三章 「酒場にて。壁にかかった地図」
酒場は、奥に木製の長いバーカウンターがあり、カウンターの向こうの棚には様々な種類のウイスキーが置いていた。
そしてその横の壁には、黒と茶のグラデーションのボディの、アコースティックギターがかかっている。
ホールの方は木の丸テーブルが五つと、それぞれに木の椅子が五つ、または四つ置かれていた。それほど広い酒場ではないが、この村の大きさにはちょうど良い広さに思えた。
ホールの壁には大きな古びた地図が貼り付けてあった。それはこの国の地図であったが、本当に古びているわけではなく、あえてクラシックなデザインで作られてた、インテリア用を目的とした地図のようだった。
僕は、近くに寄ってその地図を眺めてみた。本来の地図の用途として作られているわけではないので、見辛く、土地の名前さえ、ところどころ文字が擦れて読めなかった。とてもよく出来ている。
縦長の楕円形の島の中心には、大きな城が記されていて、その周りに様々な街や村の名前が書かれていた。
僕は、今自分が訪れている南西の村を探してみる……あった。そこにこの村の名前がちゃんと記されていた。それから僕は視線を上げていき、最北端から一番近い街を探すことにした。
その街は、僕が灯台に住んでいた頃にいつも買い物で利用していた街だ。自転車で坂道を下っていた頃が懐かしい。あの画材屋の店主は元気にしているだろうか。
しかし、いくら探してみても、僕が知っている街の名前が見つからなかった。おそらくこの辺りであろうという場所には、ちゃんと街が記されていた。しかし名前が違っていた。
「おう、コーヒーだ。ここに置いておくぜ」と言い、大柄の男はバーカウンターにコーヒーを置いた。
「ありがとうございます。いいんですか? 勝手に出してしまって」
「いいさ。この店のマスターは、おれの兄弟みてえなもんだからな。ガキの頃から家が隣でつるんでた仲だ」と言い、男はカウンターの椅子に腰かけた。そして「さあ、神父さんも忙しいだろう。話を始めようじゃないか」と言い、自分の隣の椅子を引いた。
僕は、カウンターの方まで歩いて行き、彼の隣に座った。
「まずは俺からも礼を言いたい。あの行方不明の夫婦を発見してくれて、ありがとうな。残念な結果だったが、それでも、ずっとあんな沼の底にいるよりはいい。誰にも供養されることないってのは、あまりに不憫だからな」と言い、男はコーヒーを啜った。
「あなたは、あの夫婦と、生前は交流があったのですか? と言っても、もう何年も前のことでしょうけど」と僕は男に尋ねる。
「そうだな。俺はガキの頃この村では嫌われ者だった。まあそれは俺が悪いんだがな。ほとんどの家の子供を泣かしてたからな。だけどな、当時からその夫婦だけは、他の子供達と同じように、俺にも優しく接してくれていた。俺の親はかなり厳しかったから、その家の子供が羨ましくて、ついいじめちまってた。
本当にろくでもねえガキだと自分で思うぜ。もし今、俺のガキがそんなことしやがったら、ぶん殴って謝らしに行かせるだろうな」
この男が反省していることは、良いことなのかもしれないが、きっと当時いじめられた人間の中には、今でもこの男の事を死んでほしいくらいに思っている人もいるだろう。いじめとは、また暴力とは、大抵そういうものだ。
そして何故かこういう男の方が、家庭を持つのも早かったりする。
「それで、本題に入りたいのですが、城の者には話せなかった話というのは、なんでしょうか?」と僕は尋ねる。
「ああ。それはな、あんたこの男を探しているんだろう?」と言い、使いの男の指名手配書を、カウンターの上に出した。「偶然のことだがな、つい先日、北方面から城の方に向かうバスに乗った時、バスの中にこの指名手配書があった。俺は一目見てすぐに気がついた。ガキの頃、近所に住んでいたあいつだってな」
「なぜすぐに分かったのですか?」
「あれはなあ。俺がまだ十歳にも満たない、ほんのガキの頃だ。沼地の掘っ立て小屋で、俺はこの男に殺されかけた。その時に見たあの冷たい獣の目を、俺は忘れることが出来ねえ。
確かに俺は村の子供達に暴力をふるっていたし、物を取り上げて壊したりもしてた最低なガキだった。だけど、それはよくある悪ガキの範疇だったと思うんだ。
しかしあいつは、まるっきり別の生き物のようだった。目立ちたいとか、強さを見せたいとか、そんなありきたりな欲求はなかった。人間の持つ善悪感情なんて微塵も入っていない機械のようだった。
あいつは俺をシャベルで殴り倒し、そして細切れにして殺すと言った。しかし、俺の仲間が謝って止めてくれたお蔭で、殺されずに済んだが、あの時殺されなかったのは多分、殺すことによって仕事が増えるのが面倒だと思ったからだろう。
俺を殺せばその仲間も殺さなければいけなくなるし、死体を隠すのも大変だ。後の作業や効率のことを考えて止めただけの事だ。分かるか?
例えば料理を作れば、皿やスプンを洗うのが面倒だ。しかし出来た物を買って来たなら、食べた後に容器を捨てるだけだから楽だ。と思うことはあるだろう? あいつにとって人を殺すってことはその程度の違いなんだ。
俺に、本当に殺されるかもしれない恐怖を味合わせて、絶対に喋れないような精神状態にするくらいの方が楽だったんだ。奴にとっては全て単なる作業なんだよ」
「そうでしょうね。僕もその男のことはある程度知っていますから、あなたの言う事はよく分かります」
「そうか、あんたもきっと大変だったんだろうな。それで、ここからが本当にあんたに話したいことなんだが、俺は表向きは林業の仕事をしている。しかしな、裏ではまあ、何というか少し言いにくい仕事もしているんだ。
城の連中に言えなかったのはその為なんだが、あんたが内密にしてくれるなら、奴に関する重要な情報を教える。それは、今現在の奴の居場所が分かるかもしれないほどの情報だ」
「秘密は守ります。教えて下さい」と僕は答えた。
【第二部】四十四章 「空いてしまった部屋(ある少年)」
「いつも、暗くなる前には必ず帰ってくる息子が帰って来ない」
両親はその日のうちに、城にそう連絡を入れた。それからすぐに、夫婦は村人達にも事情を話した。
村人は皆一丸となり、男の子の捜索に当たった。村からすぐ近い沼地も当然捜索範囲となった。しかし、男の子はその時まだ沼の底に沈んでいるため、その日の内に見つかる事はなかった。
男の子が見つかったのは三日後の、昼過ぎだった。村人の一人が今一度沼地の方に向かったところ、沼の水面に巨人の様に膨れ上がった男の子の姿があった。時間が経ち、腐敗ガスが発生したことにより膨れ上がり、浮き上がったのだ。
この時に少年は、人間の体はただ沈めるだけでは浮いてきてしまう。ということを学び、次の時は何かに詰めてから沈めなければと考えた。
発見した村人はすぐに村の男数人に伝え、その子の両親には知られないように気を付けながら、男の子の遺体を沼から引き上げた。
そしてその日の夜。両親は息子の死を告げられることとなる。村民達は集まり、広場で男の子の火葬が執り行われた。
城の兵達が沼地を訪れ捜索に当たっている間。少年はしばらくは、雨林の奥にある岩場に身を潜めていた。雨水を飲んだり、葉についた露を集めて飲んだりしていたため、水分を確保することは出来たが、食べ物が無いため、体は痩せ細りあばら骨がくっきりと浮き出てしまっていた。しかしそれもまた、目的達成の確率を上げる為の彼の考えの一つでもあった。
数日後、沼地の捜索をしていた兵達も引き上げたため、少年は再び小屋へと戻った。
あとは、なるべく体力を使わないよう動かず、時が経つのをじっと待つだけだった。栄養不足でぼんやりとする頭で、少年は反省していた。
つい突発的に母親を殺してしまったことで、こんなに苦労する羽目になってしまうとは……ある程度の金があれば、しばらくは何とかなっただろうが、予想以上に母親が所持していた金額は少なかった。
アル中で毎日酒を買っていたせいだ。そう思うと少年は、やはり母親のことが憎らしくなった。その半分は自分が働いたアルバイトの給料でもあったのだ。
少年は小屋の中でうつ伏せになり、暗闇に目を凝らしていた。その時農具が置いてある木箱と土のうの間に、未開封の缶詰が転がっている事に気がついた。
少年は跳び起きて缶詰を拾いに行った。拾い上げてみるとそれは小魚の缶詰めだった。少年は、もう一週間は何も食べていなかったので、今すぐ開けてしまいたい衝動に駆られたが、その感情を何とか飲み込んだ。そして、それをいつ食べるべきか考えてみた。
男の子が発見されてから既に十日が経っている。そろそろ両親にとっても、最初の衝撃が終息し始め、現実の事として重くのしかかって来ている頃だった。
もちろん少年自身、あとどれくらい食べずに過ごせば自分が死んでしまうのか、正確に分かる訳ではないので、少し余裕を持って行動するべきでもあった。少年は結局、我慢出来ずその日の内に缶詰を食べてしまう。
そしてその翌日に、完成された満身創痍の身体を引きずって夜の村に侵入し、そしてあの家族の住む家の前の道に倒れ込んだ。
村の中で、そんな時間に外に出ているのは、酒場の方で騒いでいる男達か、不眠症となったその家の母親だけだった。
そして少年の思惑通り、その子の母親に最初に発見されることとなった。
その時少年は、ひとまずのやる事をやり終えた達成感からなのか分からないが、本当に気を失ってしまっていた。
——翌日、病室のベッドで目覚めた彼は、自分を城下町の病院まで運んでくれた、優しい二人の大人とやっと対面することとなる。
そこで、様々な嘘の物語を並べ立て、自分がいかに悲惨な境遇であるかということを話した。そして「もし家に返されたら、またお母さんに殴られてしまう」と頭を抱えて見せた。
「それなら、ひとまずはうちに来ればいい」と最初に言ったのは、意外にも父親の方だった。「どうするべきかは、それからゆっくり考えよう。今……空いてしまった部屋がある。あの家にこのまま私たち二人だけで暮らしていては、潰れそうなんだ」
「ありがとう。本当にありがとう。僕はあなた達のような、優しい両親のもとに生まれたかった」
と少年は言った。
【第二部】四十五章 「酒場にて。いじめとは」
「分かった。あんたは信用出来るから話そう。誰にも言わないでくれよ」と男は言い、左の眉の辺りを小指で掻いた。
「俺はな、ある小さな組織に参加してる。それは密航者。つまり国外逃亡者の手助けをする為の組織だ。と言っても別に悪人に手を貸すわけじゃない。未だに政治的迫害を受けたり、内戦があったりしても、なかなか母国から逃げ出せない人ってのがいる訳だ。
まあこの国だって、俺たちの親父が子供の時はまだ帝国だったわけだからな。兵役から逃げて来た者もいる。俺たちはそういう人達を水面下で引き入れたり、出したりしているんだ。まあ当然違法だがな」
「なるほど、その活動は具体的にどういったことをしているのですか?」
「具体的には、まずうちの頭は、小さいが貿易会社の代表をしている。だから、逃亡の際に貨物船の中で安全に隠れられる場所を用意することが出来るんだ。例えばよく冷凍庫や、密閉される貨物の中に忍びこみ、渡り切る前に死んじまう人がいる。
そうならないよう、渡り切るまでの数時間、快適とは言えないが、少なくとも安全に居られる場所を作り、提供するんだ。そして、ここからがあんたの聞きたいところだと思うんだが……」
男はそこで一度言葉を区切り、残っていたコーヒーを一気に飲み干した。
「この指名手配中の男だ」と言って、彼はテーブルに置いてある指名手配書の写真を指さし、トントンと二回、その上を人差し指の先で叩いた。「こいつによく似た男がつい先日、俺達の組織のことを探っていたと、ある村の酒場の店主から聞いたのさ」
「つまり……?」
「国外に逃亡するための手段を探してるってことだな。まあ当然だろうな。正当なやり方では、どこの港からも出ることは出来ないだろうし、この国に留まっていれば自由が効かない。まだそこまで自分の顔が知れ渡っていない今のうちに、裏の手段を使って逃げ切るつもりなんだろう」
「なるほど。それで、その目撃したある村とは、どこの村なのですか?」
「ああ。しかし……本当にいいのか? これを聞いて俺たちに関わっちまうと、あんたまで罪に問われるかもしれないんだぞ」
「ええ、構いません。その程度の覚悟はずっと前から出来ていますから」
「そうか分かった。その村はここから近い。三十キロほど北の、山間にひっそりと佇む村だ。かなり小さい村で、大抵の地図には載っていないし、そこに村があること自体ほとんどの人間は知らない。人々から忘れ去られた村だ」
それはまさに、僕が昨日館で読んだ本に記載されていた、女性の焼死事件があった村であった。男は話を続ける。
「この農村だって、国全体から見れば貧しい集落だろう。しかし、その山村はもっと貧しい。まるで時代がある時から止まってしまっているような村だ、聞いた話では、村のすぐ近くには、かつて戦争中に強制労働をさせられていた捕虜達の、強制収容所の廃墟もあるって話だ」
「なるほど。そういうことでしたか。しかしなぜあなたはそんな情報を、リスクを取ってまで僕に教えようと?」
「俺はな神父さん。俺だけだったんだ。当時から奴の恐ろしさを知っていたのは。まあ正確にはもう一人いたんだが。最初は、確かに俺は震え上がっていたさ。なんせ殺されかけたからな。だがあの家の子供が沼で発見された時、奴の仕業だと俺はすぐに思った。しかしな、誰も俺の言うことなんて信じちゃくれないだろう? 俺は横柄で乱暴で、みんなから避けられていたからな。
それに引き換えあいつは要領が良かった。この村の人間にはないような品の良さがあり、いつも控えめだった。例え俺が『あいつがあの家の子を殺したんだ!』と訴えていたとしても、みんな相手にしなかっただろう。だからな、俺はこうしてあんたのところに来たんだ。二十五年前にあの一家が行方不明になってからずっと、嫌な予感がしていたんだ。
そしてなぜか今になって、村の外から急に現れた神父が、夫婦の遺体の位置を言い当てたって話を聞いてな。そりゃあ腰を抜かすほど驚いたさ。あんたがどういう事情を抱えているか知らないが、俺もこのわだかまりを何とかしたいんだ」
「そうですか。事情はよく分かりました」と言い、僕も残っていたカップのコーヒーを飲み干した。「しかしあなたは、その掘建て小屋の件以降、村の子供達をいじめるのは止めたってことですか?」
「そうだな。まあ時々八つ当たりみたいなことはしてたと思うが、もう常習的に誰かをいじめるってことは無かった筈だ。そういう気持ちはすっかり無くなっちまってたんだろうな」
「だとしたらその点については彼は、いい結果を残しましたね。だってその出来事がなければ、次の日からも引き続き、あなたは村の子達を殴っていた訳でしょう? それもきっと数年に渡って。一方的に殴られる側に立ってみて、恐怖からなのか、良心からなのか分かりませんが、少なくとも行為は止まった。という事なんですから」と言い、僕は男に向け微笑んでみせた。
男は不意をつかれたように、何も言わずに顔の筋肉を硬らせていた。僕は続ける。
「あなたは先ほど自分で、自分がしてたいじめ行為は『よくある悪ガキの範疇だった』と言いましたけど、それをいじめた側の人間が言ってしまうのは、あまりに滑稽だと思いますね。あなたはきっと反省しているのでしょうが、誰かを理不尽に殴って傷つけたという事実は消えない訳ですから。特にやられた側にとってはね」
そう言ったのは、「僕」の中の他の誰かであるような気がした。この感じは以前にも、沼地で老爺と話した時にあった覚えがある。
「…………ああ、全くな。その通りだ」と男は答えた。
「あ、いえ。まあでも僕には関係のないことです。生意気なことを言ってしまい申し訳ありません。僕はただ、この男に復讐がしたいだけです」と言って僕は、指名手配書の顔を指さした。「その結果、今後この男によって殺されるかもしれない人の命が助かると思えば、やる価値は十分にあると思います。それだけです」
「ああ。そうだな。俺も協力させてもらう」
「ありがとうございます。助かります」
それから僕達は、今後の作戦を練ることにした。
【第二部】四十六章 「見捨てられた村」
——その眼鏡を掛けた男は、数日の間ある宿屋に宿泊していた。
そこは、強い風が吹けば今にも崩れそうな、木造の古い戸建てだった。二階の窓際の椅子に腰掛け、ウイスキーをちびちびと飲んでいた。
窓の外には、崩れて絶壁になった山の斜面があり、男のいる部屋の窓から見れば、それはただの巨大な壁にしか見えなかった。その壁を眺めながら男は頭の中で、少年時代に起きた様々なことを回想していた。
故郷の家を母親ごと燃やし、夜中に逃げ出したこと。そして南西の村に辿り着き、沼地の小屋に身を隠し、その後、ある家庭の養子になるまでのこと。
そして今彼は三十年ぶりに、自分の故郷の村へと帰って来ていた。そこは国内のほとんどの人に認知されていない、国家からも見放された村だった。
廃鉱山の隙間に、隠れるように存在するその村は、太陽の光が差し込む時間も限られており、いつも曇りの日ように薄暗かった。
村の中には、痩せた木々が点々と生えていたが、なぜかそれはいつも枯れていた。その為、そこには四季という概念もなく、冬のような、乾いた雰囲気が一年中漂っていた。
しかし、だからと言って雪が降るということもない。ただそのような状態が、いつも、いつまでも、ずっと昔から続いているだけであった。
数少ない村人は、この男がかつてここに住んでいた人間であるとは、誰も気が付かなかった。なぜならここの村の者は成人すると、皆外に出て行ってしまうからであった。
当時から残っている人間は既に死んでしまっているか、高齢の老人なので、三十年も前の、当時まだ少年だった人間のことを覚えている者などいないだろう。
それにこんな僻地に、男の指名手配書が届くわけもなく、彼にとっては身を隠す場所としてとても都合が良かった。
——朝から何やら、トラックの走り回る音が何処かから聞こえていたため、元使いの男は予定よりも早く、目を覚ましていた。
彼は今夜この村の酒場で。ある裏組織の「主導者」と呼ばれる人物と会う約束をしていた。
その男がおそらく、その組織の頭ということだろう。そして、その主導者と呼ばれる男に事情を話し、彼の承認が下りれば、本日の深夜〇時に出港する貨物船に、乗せてもらえるという話だった。
その船は、遥か千三百キロメートル西にある大陸に向かう船ということだった。
男は、この村に隠れている数日の間に着々と逃げる為の準備を整え、昨日ついに、必要な物を全て揃えてしまっていた。
日持ちのする食料や、隠していた財産、新たな名前の入った身分証明書、そして拳銃までも。
常習的に殺人を繰り返していた彼は、いずれ自分のミスによりこういった状況に陥ってしまうリスクを承知していた。
だから、数年掛けて、裏のルートを予め確保していたのだ。そして迅速に、集められるものから順に集めて回った。
その一部は、彼が城の内部にいた人間だったからこそ可能な事もあった。
つまり「城の使い」という国の業務に携わる職を選んだ理由は、初めからいざという時、すぐに国外に逃げられるようにしておく為の予防線だった。
それほどまでに、「人を殺す」という行為は、彼の人生には特別であり必須だった。
彼が標的とする人間はなぜか貧困者がばかりだった。だからこの国では、地方での消息不明事件が多かったのかもしれない。
なぜ貧困者ばかりなのか? それは彼自身が幼いころからずっと、貧乏な生活に苦しんで育ったことに何か関係があるのかもしれないが、答えは解らない。
この男自身が、そのことについて口を開く事は永遠にないだろう。
元使いの男は、窓を開けグラスを傾けると、底の方に少しだけ残っていたウイスキーの残りを捨てた。そしてベッドに横になった。
酒場で、主導者と会う約束の時間まで、まだしばらくあるため、仮眠しておくことにした。
——二時間後。
彼は目を覚ましすぐに異変に気がついた。いや逆だ。異変を察知したことで目を覚ました。
下の階の受付の辺りで、何やら話し声が聞こえた。
元使いの男は、ベッドから音を立てないように慎重に起き上がると、今度は床に寝そべり、そして耳を押し当てる。
聞こえてくる声の一つは、この宿の主人である老人の声だが、あと二つ、聞き慣れない若い男の声が聞こえた。
「この上の部屋にいるのですね?」
「ええ、数日前からずっと泊まっています」
「そうですか。今は?」
「二時間ほど前から物音が聞こえなくなりました。おそらく眠っているかと」
「なるほど。現在、他に宿泊している人は?」
「おりません。あの男一人だけです。いやあわしもね、絶対に訳ありだと思っておったんですわ」
「ええ。ご協力ありがとうございます。このことはくれぐれも、内密でお願いしますよ」
「ええ分かっていますとも」
「城の兵達だ……」と、元使いの男は呟いた。
なぜだ? あの老人が報告を入れたのか? いや、こんな村の老人が私の素性に気がつく筈がない。ではなぜ?
しかし、そんな事を考えている暇などなかった。
二名の足音は受付から階段の方に進み、一段ずつ上り始めたのだ。
元使いの男は、逃亡用に準備していた鞄から拳銃を取り出し、ズボンの右ポケットに差し込んだ。そして、窓辺に置いてあったウイスキーの瓶で、窓ガラスを叩き割ると、鞄を外に放り出した。
重量感のある物が落下した音が辺りに響いた。
その音を聞いた廊下にいる二人の内、一人は外の方へ駆けて行く。もう一人はそのまま部屋のドアの前までやって来た。
そして慎重にドアを開け、中へ侵入して来る。
しかし、部屋の中には誰の姿もなかった。どこに行ったのだろうか。
クローゼットの中か?
ベッドの下か?
それとも既に窓から飛び降りてしまったか?
いや、そうでは無かった。男は、その開かれた扉と壁の間に潜んでいた。
元使いの男は、侵入して来た男の後頭部を、至近距離から撃ち抜いた。
血が部屋の中に飛び散り、入って来た男は即死する。
元使いの男は次に、窓からスタンドライトを投げ捨てた。しかし今度は、先程鞄を落とした位置とは少し違う方向に。
そしてすぐさま外を覗くと、案の定もう一人の男は、最初に落とされた鞄の位置に立っており、今投げたばかりのスタンドライトの方に顔を向けていた。
元使いの男は、その一瞬の隙をつき、二階から彼に向けて三発の銃弾を発射した。一発は肩に、一発は胸の辺りに命中。一発は外れてしまった。その男も、そのままその場に倒れてしまう。
元使いの男は、コートを着ると階段を駆け降りて行った。受付を通るとき、宿屋の主人の爺さんを撃つことも考えたが、もうこの国に帰ってくることはないだろうし、弾がもったいないので止めた。
宿屋の主人は、カウンターの下にしゃがみ込んで震えていたが、男はその前を素通りして行った。数日分の宿代は、置いていかずに。
宿屋を出ると、先程投げ捨てた鞄を回収する。隣には瀕死状態の男が転がっており、拾い上げた鞄には、彼の血が点々と散っていた。
それを見た元使いの男は舌打ちをし、そのままの足で酒場の方に向かった。
待ち合わせ時間にはまだ早かったが、こうなってしまった以上仕方がない。彼は、この張り詰めた数日の中でかなり疲弊しているようだった。
そして、それも今夜には解消されるのだという気持ちから焦ってもいた。一刻も早く主導者と会い、密航の為の約束を取り付けたかった。
その為の口実も何日もかけて捏造し、頭に叩き込んでいた。後は許可をもらい、今夜〇時発の貨物船に飛び乗り、この国から去ることが出来れば彼の完全勝利だ。
逸る気持ちを抑えきれず、彼は額に汗をかき口元には不気味な笑みが浮かんでいた。
あと一息だ……あと一息だ……あと一息だ……
あと一息で私の勝ちだ!
彼は、酒場に向けて全力で駆けて行った。
【第二部】四十七章 「人間たち」
元使いの男が酒場に着くと、時間はまだ二十一時半であった。待ち合わせ時間は二十二時半だったので、一時間早かった。
カウンターには、年配の太ったマスターがいた。頭の天辺が禿げており、その周りを囲うように白髪が生えていた。
彼はいつも、真っ赤なシャツの上から、デニム生地のエプロンを着るというスタイルで店に立っていた。それは彼なりの、こだわりなのかもしれない。
そして彼もまた、密航者たちを支援する裏組織の一員であった。
彼は主に、組織の存在を世間に知られないようにしながら、密航を望む者がいれば組織のことを水面下で伝え、組織内部の人間と繋ぐ役割を担当している。つまり窓口のようなものだ。
先日、元使いの男が密航の件について相談を持ち掛けたのも、このマスターたった。
つまり南西の村の大柄の男に、「指名手配中の犯人に似た男が来た」という連絡を入れたのも彼だった。
こんな僻地の村に住んでいたとしても、彼にはこの組織の情報網があるため、国内で起きた事件の大半は把握していた。だから男の顔にピンと来たのだった。
そして、間違えて犯罪者を逃亡させる手助けをしてしまわない為にも、特にそういった情報は、把握しておく必要があった。
元使いの男は走って来たため、息が完全に上がってしまっていた。しかしそのままカウンターの方まで進み、マスターに耳打ちした。
「すまない。はぁはぁ……事情が悪くなってしまい、早く着いてしまった。今から主導者に会うことは出来ないか?」
「あんた大丈夫か? おや? それより、さっき若い者を二人向かわせたんだぞ。そいつらから聞かなかったか?」
「何だって……? 若い者を二人?」
彼は、自分が重大なミスを犯してしまったことに気がつく。
「ああ、ついさっきあんたの泊まっていた宿に向かわせた。すれ違ったのかもな」
「いや。ふぅ。すまない。見かけなかった」
「まあいい。待ち合わせの場所が変わったんだ。今夜の船で密航する人数が、十人を越えちまってな。その事情で待ち合わせ場所は、ここじゃなくなったんだ」
そう。彼が先ほど宿屋で殺した二人は、城の兵などではなく、待ち合わせ場所が変更になったことを伝えに来た、組織の下っ端の者達だった。
格好を見れば兵でないことは一目瞭然だった。しかし彼は、視界に映り込んだ瞬間にはもう引き金をひいてしまっていた。
やはり彼の考えた通りで、こんな僻地の村にそんな情報が届くことはなかったし、宿屋の主人も、彼が密航希望者であるという話を聞いただけであって、指名手配中の男だと言うことは更々知らなかったのである。
冷静に考えれば、彼なら十分に分かったことなのだが、飲酒後の寝起きであったし、何よりも彼はここ最近の逃亡生活に疲れ、とても過敏になっていた。
「村を出て、山間部を更に奥の方に行くと、収容所の廃墟がある。知っているか? 今は俺達が、隠れ家として使ってもいる場所だ」とマスターは言った。
「ああ、知っている。そこに向かえば、主導者に会わせてもらえるのか?」
元使いの男もようやく息が整って来て、普通に喋れるようになっていた。
「その通りだ。まあ少し早いが大丈夫だろう」と言い、マスターは紙に何か簡単なメモを書き男に手渡した。「敷地に入ったら、ここの棟に向かい地下に行ってくれ。主導者はそこに居る」
「分かった」と言い、元使いの男はそのメモをコートのポケットに入れ、急ぎ足で酒場を出た。
マスターは男が店から出たことを確認すると、すぐにカウンター内の電話からどこかにダイヤルを回した。
「奴は予定よりも早く来た。おそらく十分程でそっちに着くだろう。ああ、ああ。すまないが、急いでいる様子であまり観察出来なかった。大きな鞄を持っていた。銃については分からない、ああ。……健闘を祈る」
——元使いの男はそのまま、まっすぐに収容所跡地へと向かった。
彼はやはりその場所をよく知っていた。戦時中に利用されていた場所なので、当然、彼が昔ここに住んでいた時から、廃墟としてそこにあったからだ。
当時、子供達は、怖がりながらも面白半分に近づいたりしていたが、大人達は戦争に被っている世代も居たため、そこの恐ろしさをよく知っていた。
だからこそ、出来れば別の土地に移り住みたいと、そう考える人間も多くいた。
村の木々が決して色付かないことや、いつも冬のように冷たい風が吹いていることも、そんな悪夢のような場所が、すぐ側にあることの呪いではないかと、外の者からは噂されることもあった。
元使いの男は、寂れた山間の道を奥へと進んで行った。狭かった道幅は少しずつ広がっていき、最後には開けた場所に出た。
周囲の岩壁は、先程よりも更に高くそびえ立っており、外からは完全に見えないようになっている。
そこに、強制収容所はあった。
元使いの男が少年時代に見た時よりも、三十年分古くなり、その分不気味にも見えた。
高さ六メートル程の橙色の塀は、煉瓦と煉瓦を、モルタルで接着させて積み上げたもので、収容所の九つの棟をぐるりと囲い込む形で繋がっている。
その塀の周囲の全長は百八十九メートルだと、子供の頃に村の老人に聞いたことを彼は思い出した。
塀の途中には、大きな鉄の門が付いており、その上に収容所の名前の書いた鉄のプレートが付いていた。どうやらそこが正面入り口のようだった。
元使いの男は、鉄門の前まで歩いた。鉄門もプレートもやはり既に錆びており、劣化した箇所が所々剥がれ落ちている。閂が引き抜かれている事を確認し、手で押すと、案外軽い力で扉は開いた。
中に入ると、舗装された土の道が真っ直ぐに延びており、一番向こうにはおよそ長さ四十メートルはある、横長の煉瓦造り三階建ての建物があった。あれがおそらく、当時の軍人たちが使用していた建物だろう。
そして、そこに行くまでの道の両脇には合計九つの棟があり、右側に五棟、左側に四棟。
全て二階建てのコンクリート造であったが、色が塗られていない上に、窓も正面に一つと、向こう側の壁面に一つあるだけだった。
屋根も真っ平なので、遠くから見るとそれは、のっぺりとした灰色の巨大な箱のようだった。
手前右の棟を見てみると、壁面の上の方に「G」のアルファベットが書かれていた。手前左の棟には「D」のアルファベットが書かれている。
彼は、酒場のマスターにもらったメモを、コートのポケットから取り出して確認した。
【正面から入り、一番右奥の屋上にタンクがある棟の地下一階へ向え】
アルファベットが、どういう並びになっているのかは分からないが、彼はメモの通り、屋上にタンクが設置されている、右奥の棟を目指して歩き出した。
左右の棟を確認しながら歩いて行くと、どうやら左側の列は奥から「A」「B」「C」「D」と順番に並んでいるようだった。
右側の列は、奥から見ていくと、まず何も書かれていない棟が二つあり、その次から手前に向かい「E」「F」「G」となっていた。
彼は右奥の、屋上にタンクのある棟までたどり着くと、正面の扉の前まで進んだ。
すると、扉は半開きに状態となっていた。
今まで通り過ぎてきた棟は、どれも全て扉はしっかりと閉まっていたが、この棟だけが唯一開いている。
既に主導者が、中にいるとの事だったので、別に不思議なことではないが、もしかすると今夜密航する他の志願者達も、この中に既に数名居るのかもしれない。
そうだとするなら、あまり気が進まなかった。その人達の中に、彼の顔を指名手配書で見た者がいると困るからだ。
しかしまあ、もしばれたとしても、お互いに身ばれしては不味い立場なので、その場で騒がれることもないだろう。とも考えることは出来た。
何よりも重要なことは、今夜中に船に乗り、大陸に渡るということだった。それさえ達成してしまえば、仮にここで誰かに気付かれてしまっても、逃げ切ることは容易い。
それに今更引き返して、別の作戦を考える程の余裕はもう彼には無かった。元使いの男は、その半開きとなった扉から中に入って行く。
中の様子は、やはり想像した通りで、一面コンクリートの壁だった。
最初の部屋の正面にいきなり、階段があった。右から地下に降りることが出来、左から二階に上ることが出来るようだった。
左に顔を向けると、そこには扉のない入口があり、向こうの部屋を覗いてみると、何かを操作するであろう機械類が置いてあった。
右側の壁には扉があり、開けてみると、そこはポンプ室だった。おそらく、ここから屋上のタンクに水を送り、そしてそこから、重力で各部屋へ水を供給する仕組みだろう。
しかしもちろん今は、この収容所自体に、電気が供給されていないため、ポンプが動くこともないのだろう。
蛇口はひねれば水が出るかもしれないが、屋上のタンクには、何十年も前の腐った水が溜まっているのかもしれない。
元使いの男は、正面右側の階段から地下に降りて行った。十五段降ってしまうと、防音室のような分厚い鉄の扉があり、半開きの状態となっていた。
その扉の取っ手は、室内を密閉出来るよう特殊な作りとなっていた。
彼はその半開きの状態の扉を手で押して、中へと入って行く。
部屋の奥には男が一人、木の椅子に腰掛け、膝に置いた本を読んでいた。
部屋自体は八畳ほどの広さとなっており、天井の蛍光灯と、彼の座る椅子以外は全く何もなかった。それ以外は、本当に全く何も置いていない、ただのコンクリート打ちっぱなしの空間となっていた。
そこが、何の為に作られた部屋なのかまるで分からなかったが、不気味な空間であることは間違いない。
そして床の端をよく見ると、水が通るような細い溝が壁際に付いていた。
「すまないが、そこの扉を閉めてもらえるかな?」
椅子に座った男は、本に目を落としたまま言った。
元使いの男は言われた通りに扉を引く。ガチャリと、最後まで閉まりきった音が部屋の中に響いた。
「あなたが主導者か? すまないが予定より少し早く着いてしまった。今から話をさせてもらうことは可能か?」と、元使いの男は尋ねた。
しかし主導者は本に目を落としたまま、何も言わなかった。
元使いの男は、今彼の機嫌を損ねてしまってはいけないと考えた。
「いや、すまない。もし都合が悪いなら出直そう」と言い、引き返そうと扉に手をかけたその時。
「お前はそんな風に……」と主導者は呟いた。
「今、何と?」
「お前はそんな風に、その銃口をあらゆる人に向けながら生きて行くんだ」と言い、主導者は顔をあげた「誰にも愛されないってことを、言い訳にしながら」
「何を…………言っているんだ?」
その主導者と呼ばれる人物は、意外にも元使いの男よりも一回り程も若い青年であった。彼は神父のような黒いローブを身にまとっていた。
青年は膝の本を閉じると、元使いの男を真っ直ぐに見つめて言った。
「これはある少女が、死の間際、ある男に向けて言い放った言葉です。格好良いと思いませんか?」
【第二部】四十八章 「主導者」
僕はバスに乗り、南西の村で会った大柄の男と共に、北の山間の村に向かい国道を走っていた。
男は隣で寝てしまっている。沼地で夫婦が発見されたことで、昨晩はあまり眠れなかったそうだ。
その村に着くまでまだ三十分はかかるようだから、僕は、少女のスケッチブックをもう一度開いて見てみることにした。
昨晩。山の館で見たばかりだったが、どうも無性に気になるのだ。
最後のページを開いてみる。昨日と変わりはないだろうか。
そこには相変わらず、僕の寝顔の絵があった。昨晩見た時は、鼻の辺りに何か違和感というか、変化のようなものを感じていた。
そう例えば。ついさっき誰かが一度消して描き直したような感じがしたのだ。
このスケッチブックは、あの北の灯台の家の引き出しから持って来てからは、ずっと僕が鞄に入れて持ち歩いているので、そんな事を誰も出来る筈がないことは分かっている。
しかし、今度は上唇の辺りに変化の跡を感じた。昨日よりも、もう少し自信を持ってそう思える。
やはりこの絵は、日を経るごとに少しづつ描きかえられていっているのかもしれない。
少女は、なるべく正確に僕の顔を描きだそうと、今もどこかでこの絵を描き続けているのだろうか?
だとしたら、それはどこなのだろうか?
いや……それこそもっとありえない事だな。
「あんたの子供が描いてくれたのか?」と、いつの間にか目を覚ましていた男が、隣から言った。
「い、いえ。これは何でもないんです」と言い、僕はスケッチブックを慌てて鞄にしまった。
「上手だな。あんたの特徴をよく捉えている」
「そ、そうですか……? この子に絵を教えたのは一応僕なんですが、この絵は僕が眠っている間に、こっそり描いていたようです」
「そうか。この件が片付いたら、無事にあんたも、その子の所に帰ってやれるといいな」と男は言った。
「ええ。そうですね」
会話も途切れてしまい、僕は窓の外に目をやった。すると、ずっと荒野ばかりだった風景の中に、補給場と食料品店が併設されている場所が現れた。
車が十台くらいは停められる広さの敷地で、食料品店の中には、カウンターのポールに繋がれた白い大きな犬が、退屈そうに居眠りをしていた。
そういえば最近は、犬が外に繋がれているのも、あまり見かけなくなったなと僕は思った。
それからまたしばらく走ると、右側の風景だけが、等間隔に植樹された農園のような土地の雰囲気へと変わっていった。
それが何の木なのかは分からないけれど、ただ等間隔に、大きな木が植え付けられ並んでいるだけである。
森や林とも呼べない。人工的な木の羅列である。
きっと昨日、館の彼女が言った、国道沿いの教会もすぐ近い筈だ。そう思うと僕は、落ち着かない気分になった。
自分の心臓の鼓動が早くなっていることに気がつく。
そして、木々の切れ目に、奥の方へと真っすぐに続く道が見え、その道の一番向こうに、小さな教会が見えた。
その瞬間また、僕の中で何かが弾けた。
また昨日と同じように、気を失ってしまう。
ただ昨日と違ったのは、まだ少しだけ意識があるということだった。
(僕は真っ暗な空間の中で。宙に浮いていた。もしかしたら、宇宙に身一つで放り出されたのかもしれない。と僕は本気で思った。
その恐怖から、一瞬、心が引き裂かれそうになり、思わず目を瞑ってしまう。
しかしすぐに肌に風を感じ、目を開いてみるとそこはもう教会の中だった。
そして目の前には黒いローブ姿の僕がいた。初めて自分の目で見たが、確かにそれは神父に見えた。
その僕は祭壇の前に立ち、聖書に目を落として祈りの言葉を呟いていた。僕の後ろには会衆席があって、三十人くらいの人達がそこで同じように聖書を見ながら、祈りの言葉を読んでいた。
「そうか。やはり僕は……初めから、神父だったんだ」と僕は呟いた。
目の前で聖書を読んでいる僕ではなく
《《この「僕」が呟いた。》》
「だけどこれ以上は、正直あまり思い出したくない。大体の事情は分かったから、ここから出してくれないか? 僕は今、それどころじゃない。やらなきゃいけない事があるんだよ」
と僕は、この映像を見せている誰かに向かって喋りかけた。
すると。目の前の映像は泡のように画面の端の方から、ブクブクと消えて行った)
——「おい。着いたぞ」という声で、僕は目を覚ました。
目の前に男の強面があった。
「は、はい」
僕は、まだ理解しきれていない頭で返事をした。
「大丈夫か? 降りるぞ」と言い、彼はバスを降りて行った。
僕もその後ろに付いて、バスを降りた。
バスから降りた僕達は、国道と垂直に延びる土の道を進んでいく。その道は二つの大きな山と山の間に向かって、真っ直ぐに伸びていた。
僕はてっきり山間の村と聞いた時には、森林に囲まれた村だと思っていた。
しかしその両脇にそびえる山は、禿げ上がった廃鉱山であった。
所々に木が生えている個所はあるようだが、どれも枯れ木ばかりで、それは余計にその山全体を寂しい雰囲気に見せているように思えた。
奥に進んでいくに連れ、深い谷へと入り込んで行った。硬い鉱山の斜面は、近くで見ると、ほとんど垂直なため、それは岩の壁の様だった。
僕はその迫力に、めまいさえ感じていた。
それから更に二十分程歩き、僕たちが村に到着した時には、もう昼下がりくらいの時間となっていた。
そこは周りを巨大な壁で囲まれた、異様な雰囲気の漂う村だった。太陽の光さえまともに射し込まないので、全体的に暗い。
例えば「この世の果て」というタイトルの絵画があるとするなら、多分こんな感じだろう。と僕は思った。
南西の農村から、距離としてはそんなに離れてもいない筈だが、気温もかなり低いように感じた。
乾いた風が、山と山の間を通り、この村に吹き付けているようだ。薄手のローブで歩くには、少し寒い。
「よし。まず酒場のマスターに会いに行こう」と大柄の男は言い、歩き出した。僕は彼の後ろに付いて行く。「既に、これから向かうという連絡は入れてあるから、待っているはずだ」
歩いていても人の姿は見かけなかった。民家は確かにあるが、人の気配と言うものをそもそも感じなかった。
こんな村で酒場を経営するこ自体が、そもそも可能なのだろうか? と僕は疑問を抱いた。
「人が、全く見当たらないですね」と僕は、前を歩く男に言った。
「ああ、そうだな。この村に住んでいるのは老人ばかりだからな。大抵は家に籠っているんだろうな」と彼は答えた。
程なくして僕たちは酒場に着いた。
中に入ると、客は誰もおらず、カウンターの中には、赤いシャツの上からデニムのエプロンを着た太った白髪の男性が、椅子に腰かけて新聞を読んでいた。
「やあ、調子はどうだ?」と、僕と一緒に来た大柄の男は言った。
「ああ、最高に決まってるだろう!」と、その白髪の男性は答えた。それから僕の方を一瞥して「この人が、俺たちの救世主か?」と言った。
「救世主? いや、主導者さ。俺たちを導いてくれるんだ」と、大柄の男は言った。
僕はマスターに、丁寧に頭を下げた。
【第二部】四十九章 「強制収容所 廃墟」
「最後にもう一度聞くが、本当にいいのかい?」
赤いシャツを着たマスターは、トラックの運転席から窓を開け、外にいる僕にそう言った。
「はい。そのくらいのリスクは取らないと、奴に勝つのは難しいと思います」
「そうか……」
大柄の男は、空になった最後のポリタンクをトラックの荷台に乗せると、僕の隣まで歩いて来た。
「これで準備は整った。村から、三度の往復で済んだのは良かった。もう時間もあまりないしな」と言い、彼は腕の時計を見た。
「では、わしは酒場に戻る」と言い、マスターはキーを回して、トラックのエンジンをかけた。「酒場へ着いたら、若い二人を奴の泊まっている宿屋に向かわせ、二十二時半にここに行くように伝えさせる。それでいいな?」
「ああ、それでいい。何かトラブルがあったら俺にすぐに電話してくれ」と、大柄の男は言った。
「分かった。じゃあ、また後でな神父さん」とマスターは僕に言った。「全て終わったら、俺の店で酒でも飲もう」
「いいですね。そうしましょう」
マスターは運転席の窓を閉めると、僕達に片手を上げて、収容所の敷地を出て行った。
大柄の男はしばらく、トラックが去っていく後ろ姿をボンヤリと眺めていたが、何やら申し訳なさそうに口を開いた。
「本当に、すまないな……肝心な所を任せちまって。俺だって奴のことは何とかしなきゃならんと、思っていたんだがな」
「いえ、あなたには家族もいますし。僕はもう失うものなんてないし、その為にここまで来ましたから」
「そうか。それと、今朝はすまなかったな」
「今朝? 何がですか?」
「バスの中で、あんたがスケッチブックを見てた時、俺はてっきりあんたの娘が描いたんだと思ってな……」
「ああそんな、構いませんよ。全く気にしていませんから。それに、娘ではないですけど、娘くらいの歳の子が描いてくれたものなんです。
その子と一年程、一緒に暮らしている時があったんです」
「そうか。その子は養子か何かだったのか?」
「そお……ですね。周りから見れば養子だったと思います。だけど、凄くしっかりした子だったし、僕も対等な立場で接していたんで、養子だなんて、一度も思ったことはなかったですね。それに、その子も密航だったんです」
「そうなのか⁉ よく見つからず無事に渡れたもんだな」
「はい。だって僕がそこの見張り人だったんですから」
「ほう。つまりどういうことだ?」
「今はこんな格好ですけど、元々僕は北の灯台の管理人だったんです。そこに、ある時その少女が小舟で流れ着いたんです。
話を聞いたら、色々と訳ありだったので、そのまま引き取ったんです。
だから何というか、もしかしたら今あなた達がやっている活動と、少し似ているかもしれませんね。僕がやったこともやはり、違法なことでしたし」
「そうか、いや! なるほどな。俺は立派だと思うぞ。普通ならびびっちまって、なかなか出来ることじゃない」
「いやそんな」と僕は言葉を濁した。立派だったのは僕ではなく、あの子の方だ。「でもきっと、あなた達がやっていることも、実際に多くの人の命を救っているのですよね。
未だ国家や法律では、救いきれない事態があることは事実ですし。違法かもしれませんが、それこそ立派なことだと思います」
「ああ、もちろん俺達もそういう信念のもと集まった仲間達だ。だから当然、密航者から金銭を受け取る訳じゃない。あくまでも非営利組織だ。それに、国家なんていつ狂うか分かったもんじゃない。ここを見てみろ」
彼は両手を広げた。「こんな建物が、俺の親父がガキの頃にはまだ、実際に使われていたんだぞ。想像も出来ねえさ」
僕にも想像出来なかった。もしその時代に生まれていたとしたら、僕はこの事についてどんな風に思っていたのだろうか。
また、当時の人達はこの施設の実態を知っていて、それが正しいことだと思っていたのだろうか。
正義とは? 強さとは?
僕たちは歴史を塗り替えながらも、他者と共存し、誰かを攻撃しなくても自分達の価値を見いだせれるような生き物に、なって行っているのだろうか。
同じ平坦な道の上を、誰のことも憎むことなく、何かと比べて卑下することなく、ただ純粋に歩いて行けるようになるのだろうか。
こんな場所に来ると、自分はどんなに平和な時代に生まれたのだろうと、そう思わざるを得なかった。それは本当に良いことだ。
もしも今不意に長い夢から覚めて、頭上から爆弾が降ってきたとしても、僕は何の文句も言えないまま、ばらばらになって死ぬのだろう。
そういう時代が確かにあった。
その事を僕は知らないのだから。
僕はこれから人を殺そうというのに、どうしてこんな事を考えているのだろうか。
「どうした? 大丈夫か?」と、大柄の男は、僕に声をかけた。
「すみません。大丈夫です。僕も今回の件でもしこの国に居られなくなった時には、密航をお願いするかもしれません」
「もちろんだ。いつでも言ってくれ」と彼は言った。それは頼もしい親父の顔に見えた。
「では、そろそろ行きます」と僕は言った。
「ああ。気を付けろよ。あんたなら大丈夫だ。必ず奴に勝てる」と言い、僕の顔を真っすぐに見た。「それでもし嫌じゃなければその後で、あんたの事情を俺に教えてくれないか? きっと、さっき話した少女は、もういないのだろう?」
「…………お見通しみたいですね。僕の顔に書いてますか?」
「ああ。ばっちり書いてある。だからこそあんたは勝って、戻って来なくちゃいけねえ。いいか? 必ず戻って来るんだ」
「はい。必ず」
僕は男に右手を上げる。男も右手を上げ返す。
——そして僕は、屋上にタンクの付いたその棟の中へと入り、地下へと続く階段を十五段降りて行く。
地下室に入ると、扉は開けた状態にして、部屋の奥にある、さっき置いておいた木の椅子に腰掛け、鞄の中から本を取り出す。
奴が来るまではゆっくり本でも読んでおこう。
本のタイトルは「疫病に沈む島」
いつか少女が僕から逃げる為に、嘘のネタとして使った本だ。
これは、あの山の図書館から持って来た物だ。少女が持っていた物じゃない。偶然あの館で見つけて借りてきた。
そうか……この本を返却する為にも、僕は生きて帰らなきゃならないんだ。さっき彼に渡しておくべきだったかもな。
——直に、誰かが建物に入ってくる足音が聞こえた。
そしてその足音は、左右の部屋を一度覗いてから、この地下室にゆっくりと近づいて来た。
僕は、小説がいいところだったので、顔をあげるのが面倒だった。しかし、その誰かは部屋に入って来た。
だから、本が面白くてもそれを置いて、相手をしなくてはいけない。
「すまないが、そこの扉を閉めてくれるかな?」と、僕は声を掛けた。
「あなたが主導者か? すまないが予定より少し早く着いてしまった。今から話をさせてもらうことは可能か?」とそいつは言った。
初めて見た奴の顔は、あの運命の銃声が鳴り響いた瞬間から、憎み続けてきた男の顔そのものだった。
そう気づいた瞬間。自分の中での激しい怒りと、それを制御しようとする意思が、喉の少し下辺りで均衡しているような感覚があった。
【第二部】五十章「踏みにじる」
「これは、ある少女がある男に言った言葉だ。その後すぐ、その男に撃たれてしまったけどね」と僕は言った。
「何を言っているんだ? その小説の話か?」
と、元使いの男は膝に置いてある小説のことを言った。
「物語じゃない。実際に起こったことだ。だけど、その少女の言ったことは本当のことだった。どこの世界でも、その男は人を殺してばかりだったんだからな」
「よく分からないが。しかし、裏組織の頭が、こんな若い神父だったとはな」
「ああ。じゃあ、まず銃をこちらに渡してくれ。危険物を持ったまま乗船することは出来ない」
僕は右手を差し出した。
「私は銃など持ってはいない」と奴はしらを切った。
「残念だけど、お前の情報はこちらもよく把握している」と僕は答える。しかし。
「いや、本当に持っていないんだ」と、元使いの男は、あくまで嘘を通そうとしているようだ。よほど銃を手放したくはないのだろう。
「そうか、分かった」と言い、僕は足を組み直した。
「今から約三十年前に、ある村で放火殺人事件があった。現場は、ここに来る途中に通るあの村だ。
その時にその家の家主であった女性は殺されている。そして、そのすぐ数日後には、国道を三十キロ程南に走った所に位置する、湿地帯の沼で、幼児の水死体が見つかる。
更にその事件の約二週間後には、その沼のすぐ付近にある農村で、十三歳の少年が衰弱した状態で、道端に倒れているところを発見され、その村のある夫婦に保護される、それから……」
「もういい」と奴は不意に、僕の言葉を遮った。「お前、何者なんだ?」
「さあな」
「なぜ、城の正式な記録にすら残っていないことまで知っている?」
「そんな事お前が知る必要はない。僕が言いたいのは、お前の様な人間が、得体のしれない犯罪組織の密航船に乗ろうって時に、銃を携帯しない筈がないだろうって話だ」僕は再び、右手を奴の方に差し出した。「さあ、出せ」
「…………」
「出せないのなら、お前を船に乗せるわけにはいかないぞ。他の民間人もいる訳だからな」
元使いの男は、深い溜息をつき、ズボンの右ポケットから銃を取り出した。
「さあ、こっちへ」と僕は促す。
奴はしぶしぶ僕に銃を手渡し、僕はそれを受け取った。
「では、まだいくつか質問したいことがある」と僕は言う。
「なんだ? これで今夜の貨物船に乗れる筈じゃないのか?」と、奴は怪訝そうな顔で言った。
「誰がそんなことを言った? 銃を渡すのは最低条件だ」
「そうか……では、なんだ?」
僕は、膝に乗せていた拳銃を奴の顔に向けて構えた。
「なぜ、あの村の子供を殺したんだ?」
「お、おい。どういうつもりだ⁉ 質問には答える。しかし、なぜ銃を向ける必要があるんだ」
元使いの男は、銃を向けられたことにより、初めて動揺した様子を見せた。
「質問を質問で返すんじゃない」と僕は、かつて自分が言われた言葉を、奴に言い返した。「お前は今僕に、質問出来る立場じゃないだろう」
「分かった。答えよう。しかし、あの村の子供とは、どの子のことなんだ?」
「さっき話した、南西の村の男の子のことだ。お前が沼で殺したんだろう」
「ああ。あれか」と奴は言った。
「なぜだ? あの子をわざわざ殺さずとも、あの夫婦ならお前のことを引き取ってくれたんじゃないのか?」と僕はもう一度、正確な部分を尋ねた。
「それは分からないだろう。引き取ってもらえない可能性だってあった。なんせ貧乏人の家庭だったしな。私は少しでも有利な方を選んだだけだ」
「……有利な方?」
「人間は、精神にダメージを受けた時にはそれを他の何かで補償しようと考える。それに、たとえ内側の強烈な闇と向き合っている時でも、目の前で緊急性のある事態が起これば対応しなければならない。
それによって一時的だとしても、その闇から目を逸らすことが出来る。そういった状況を作り、私自身がそういった存在になれば、引き取ってもらえる可能性は、そっちの方が高いだろう? 少し考えればわかることだ」
と奴は、自分は戦略的に考えた上で当然の振る舞いをしただけ。という風な話し方をした。
「そうか、納得した。しかし、よくそんな事が平然と答えられるな。僕は今どういうつもりでお前と対面しているか分かってるのか?」
僕は椅子から立ち上がり奴に近づいた。そして奴の眉間の数センチメートル手前で銃を構えた。
僕の手はかたかたと震え始めていた。怒りなのか、人を殺す前の恐れなのか、自分でも分からなかった。
「ああ。分かっているとも」と奴は冷静に答えた。「だから私も今必死に、この状況をどう切り抜けるべきかを、考えているんだよ。はっきり言って、お前が誰かなんて私は知らんし、知っていても同じことだ」
僕の手が震えている事を見て、また、威圧的に一歩近づいた事によって、普通の人間なら、撃たれるかもしれないと余計恐怖するだろう。
しかしこの男の場合は違った。僕にまだ、引き金を引く心の準備が無いということを、読み取ったように見えた。
「お前は、死ぬのが怖くないのか? お前にとって痛みとはなんだ?」
と、僕は奴に尋ねる。手の震えは止まらない。
「怖いさ。怖いに決まっているだろう。私が幼い頃、親に虐待を受けていたと語ったこと。まるっきり全て嘘だと思っているのか?
母は私を毎日殴っていた。父だってそんな状況を知っていながら、私を置いて出て行ったのだ。それならばせめて、私を連れて行けば良かったのではないかと、子供心に思ったさ。離婚は良かったとしてもな。
だがな、新しい女との生活には、私は邪魔だったということだ。ただそれだけの理由だ。だから私は結局毎日、母には殴られていたんだ。ひどい時には、酒の瓶で殴られ何日も痛みが残ることもあったさ。
その時の恐怖があるからこそ、私は他人に恐怖を与えるやり方をよく承知しているんだよ」
「そうか。だか、だからと言って、お前のやったことは事実として消えないし、僕はお前を許すつもりはない」
「ならば早く撃てばいいじゃないか」
奴は、いとも簡単にそう言った。それは僕の今の心中を、完璧に見透かして言ったような、最も的確な言葉だった。
「…………」
僕はただ震えるだけで、何も答えられなくなってしまった。
指一本動かせば全ての決着がつけられる。それなのに……僕には、それが出来なかった。ついには涙まで出て来てしまった。
僕は自分の事を過信していたようだ。この男なら、何の躊躇いもなく殺す事が出来ると思い込んでいた。しかしそれは、都合のいい妄想の中の自分を、通して見ていたのかもしれない。
拳銃を握る右手の震えはどんどん大きくなり、照準は、奴の眉間に上手く定まらなくもなって来ていた。
そして奴が、そんな隙だらけの僕を見逃す訳はなく、素早く頭を避けると同時に、僕の手から拳銃を奪い取ってしまった。
僕は、涙で視界が滲んでいたせいで、反応する事も出来なかった。元使いの男は、僕の鼻と口の間辺りに銃口を向けた。
「人を殺すという能力は、選ばれた者にしか与えられない。人類の歴史を見ればそれが分かる。
いつの時代も非道な者が権力を握る。そして勝ち残り、歴史は塗り替えられて行ったのだ。そしてそれは正しい。なぜなら私達も皆、先住民を|蹂躙し、生き残った人間達の子孫なのだからな」
僕の涙はようやく止まり、頬で乾いて透明な筋となっていた。目は赤く充血し、鼻も詰まってしまっていた。
そんな状態で、この世で最も憎んでいた相手から説教を受けるだなんて、なんて情けない姿だろうか。
あの子に……呆れられてしまうな。
「では最後に教えておこう。私は幼い頃親に虐待など受けてはいない。まるっきりの嘘だ。母親は確かによく酒を飲んで潰れてはいた。しかしただそれだけだった」と奴は言った。
「なんだと?」
胸が急激に締め付けられるような気がした。絶望が心に広がって行くのが分かった。
かつて北の岬で、この男をフライパンで殴り殺そうとした少女の手を止めた時のことを僕は思い出した。
僕はまたも、同じ失敗を繰り返してしまったのだ。そのせいで少女を失ったというのに、どうして僕はこうも、いや、どうしてこんなにも、だめな人間なのだろうか。
「お前はさっき、私が虐待を受けていたと言った時、『それでもお前を許さない』と言ったな。しかし動揺した。口ではそう言いながらも、確かに動揺を見せた。
私はそれを見逃さなかった。だから私が勝ったのだ。これで分かっただろう。悪はいつも正しく強い」と言い、奴は拳銃の撃鉄を親指で起こした。「では死ね」
「お前はここで溺れ死ぬ」
「……なんだと?」奴は、引き金を引こうとした指を止めてそう言った。
「《《僕を今撃てば、お前はここで溺れ死ぬ》》って言ったんだ」
「おかしくなったのか?」
「…………」
「答えろ!」
奴は怒鳴り声を上げた。
「最初からお前の勝ちなどない。お前がこの部屋に入って扉を閉めた時点で、あるのは僕の勝ちか、引き分けのどちらかだ」
「どういう意味だ?」
今度は奴の手の方が震え始めた。それは先ほどの僕の様な、プレッシャーと恐怖から来る震えではなく、苛立ちから来る震えだった。
「僕はお前と対等に向き合った時、心理戦で勝てないことは分かっていた。だから、決して負けない状況をあらかじめ作っておいたんだ」
その時だった。
天井の方から水が流れるような音が聞こえ、天井と壁の隙間から水が吹き出して来た。
「この部屋はかつて、収容人達の拷問に使用されていた部屋だ」と僕は言った。
【第二部】五十一章「光」
天井と壁の隙間から、もの凄い轟音と共に水が噴き出して来ていた。この八畳ほどの、一面コンクリートの部屋に。
「この棟は、その為に作られたんだ。唯一屋上に水のタンクがあるのはその為だ。僕たちはさっき村から三往復もして、屋上のタンクに水を張っておいたんだ。
電気が通っていなくてもバルブさえ開ければ、水は重力で落ちてくる。そして、この部屋が天井まで満たされるまで、水は止まらない」
「今すぐここから出せ!」と、元使いの男は拳銃の先を僕の眉間に、強く押し付けた。
「さっきお前は、死ぬことは怖いと言ったな。僕の気持ちを話そう。僕は死ぬことは怖くない。なぜなら既に一度、お前に殺されたからだ。その時、死というものが何なのか感覚的に分かった。撃たれたって大した痛みはなかったしな」
「小説の読み過ぎで頭がおかしくなったのか? ならすぐに死なない箇所を撃ってやろうか?」
「やってみろよ」
「なっ⁉」
「人を殺すことは躊躇わないが、自分の命が掛かるとなるとさすがにそう簡単にはいかないみたいだな。
僕が今最も恐れていることは、お前を生かしたまま、死んでしまうことだけだ。それだけが怖い。こんな気持ち、お前には理解出来ないだろう」
男の持った拳銃の先は、さっきよりも大きく震えていた。表情にも余裕がなく、歯を思い切り食いしばっているようにも見えた。
「お前のような男が追い込まれ、焦り、絶望に向かっている様子が見れて、僕は今とても幸福だ」と言い。男に笑って見せた。
その時。
バァン! という破裂音がした。奴は、僕の左腿を撃ち抜いたのだ。
「くうぅっっ!」と僕は声を上げ、思わず身体を斜め左に傾ける。
「おい! 大人しくそこの扉を開けろ。どうやる? 外の仲間に連絡を入れろ!」
奴は拳銃の先を、撃った僕の左腿の傷口に押しつけてねじった。
「うううっっ!」と僕は更に唸り声を上げる。
「はぁはぁ……お前は終わりなんだ。諦めるんだ」
水位は、膝の辺りまで上がって来ていた。
奴はついに僕の胸ぐらを掴むと、自分の方まで引き寄せ、銃口を僕の左のこめかみに押し当てた。そして顔を、僕の目の前まで近づけた。
「おい。よく聞け。最後だ。外に仲間が居るんだろう? でなければ、あのタイミングで水が急に出て来る筈がない。
どうやって外に合図を送っているのか知らんが、今すぐ排水させろ。そして扉を開けるんだ。
そうすれば、私も今回は諦めて大人しく帰ろうじゃないか。しかし断れば今すぐ、その足りない頭を撃ち抜いてやる。いいか? 最後の選択だ」
「…………」
「…………」
天井から轟音と共に吹き出してくる水。
それは確実に、僕とこの男の命を捕らえるための意思を持っていた。
僕は奴の質問に答える。
「……分かった。後ろの椅子のところに鞄が置いてあるだろう? あの中に無線が入っている。それを通して、今までの会話を聞いていたんだ」と僕は奴に胸ぐらを掴まれた体制のまま、右手で後ろを指さした。
奴は僕から目を逸らし、僕の背後の、椅子の上の鞄を見た。もう水面が、あとほんの数センチメートルの所まで迫って来ている。
「しかし、鞄はもう水に浸かってしまう。そうすれば無線は壊れるし、外とも完全に連絡が取れなくなる。それに僕は一度バルブを開いたら、排出しないまま最後まで落としきって欲しいって頼んでいるんだ」
奴は僕を右に投げ飛ばすと、太股の辺りまで上がった水をかき分けながら、鞄の方まで進んで行った。投げ飛ばされた僕は水中に倒れ込んでしまう。
そして奴は、ぎりぎり水面が達する前に、椅子の上の鞄を持ち上げた。
鞄を開けると、水に濡れないように胸の前に抱え、無線を探し始めた。そして、必要のない物を次々に水の中へと放り出していった。僕のノート、小説、財布、マラム(森の教会から持って来ていた宝石)、そして、少女の形見であるスケッチブックまでも。
しかし鞄からすべての物を放り出しても、奴の求めている物は結局出てこなかった。当たり前だ。
「そんなもの。あるはずないだろう」
僕は既に、男のすぐ背後まで歩み寄っていた。
男が振り返るよりも早く、僕は腰に付けていたダガーナイフで奴の首の後ろ、頸椎の辺りを、思い切り力を込めて突き刺した。
父の部屋の引き出しから取ってきた刃渡り二十センチのナイフは、綺麗に首の皮と筋肉を引き裂き、深く刺さりこんだ。
そして僕はナイフを引き抜く。
男は手に持っていた拳銃を水の中に落とす。そしてこちらを振り返り、首の後ろを手で押さえた。
「な……だと」
頸椎を刺せば即死する筈なのだが、こいつは本当に人間じゃないのかもしれない。いや、その方が納得出来るような気もした。
「殺してやる!」と奴は僕の首を両手で掴んだ。
僕は構わず、今度はガラ空きになった腹部にナイフを突き立てる。
引き抜いてもう一度突き立てる。
もう一度。もう一度……
奴の腹部から血が止めどなく流れ出し、周りの水に溶けていく。僕の首を掴んでいた手から徐々に力が抜けていき、ついに男は水の中に倒れ込んだ。
浮かぶ男の体から黒い血が流れ出ていたが、水と混ざると徐々に薄まっていき、体から離れた場所で、それはピンク色になっていた。
【第二部】五十二章「冷たい水の中で」
僕は、腰の辺りまで上がって来ている水をかき分けて、水面に浮かぶスケッチブックを取りに行った。
スケッチブックに、奴の血が付いてしまうのが嫌だった。運よくそっち方には、血は流れて行ってなかった。濡れてページはくっ付いてしまっていたが、それくらいは仕方ない。
水は相変わらず、もの凄い勢いで噴き出して来ていた。一度バルブを開いたらもう排水しないで欲しと言った話は、本当の事だった。
だから僕にだってもう、この部屋から抜け出す術は無かった。
溺れ死ぬのは苦しいと聞いたことがある。それならば、まだ足が付いている今のうちに、このナイフで僕も、自分の頸椎を刺してしまった方が良いのかもしれない。
上手くやれば即死出来るかもしれない。
しかし……いや、考えても仕方ない。どうしようもない。どうしようもないさ。
水位はもう、胸の辺りまで上がって来ていた。僕はスケッチブックをローブの中に無理やりねじ込んだ。
そして顔を真下に向け、首の後ろが上に向くような体制になる。それから両手でナイフを握りしめ、その手を前方斜め上に真っすぐ伸ばした。
後はその状態を保ったまま、肘を勢いよく曲げれば頸椎にナイフが突き刺さる。
僕は最後の微調整を終えると、目を瞑り深呼吸を何度か繰り返した。
きっと戦時中には、こんな風に敵軍に追い込まれた人々の中には、自決をした人も多く居たのだろう。この収容所でも、そんな事があったのかもしれない。
さあ、今度こそ僕は本当に死ぬ。それでいい。目的は達成したのだから。
しかしその時。突然、天井から噴き出していた水が止まった。
しばらく轟音が鳴り響いていた部屋の中が急に静かになり、僕には耳鳴りだけが残った。
そして今度は足元が、ある方向に引っ張られ始めた。それは床の壁際に付いている側溝の方だった。
そう、水が排出を始めたということだ。
きっと、外に居る大柄の男が僕との約束を破り、水を抜き始めたのだろう。彼は確かにそういう男なのかもしれない。
いや、僕だって彼の立場なら同じことをしていたと思う。ついさっきまで普通に話していた相手が、すぐそこで溺れ死ぬのを何もせず待っているなんて、そうそう出来る事じゃない。
僕が奴と戦っている間、彼だって心の中で戦っていたんだ。
——程なくして、胸まであった水は全て抜けきってしまう。
部屋の中には椅子と、鞄から放り出されたいくつかの荷物と、元使いの男の遺体と、持ち主の居なくなった逃走用の大きな鞄。そして僕が居た。もちろんどれも全てずぶ濡れの状態だ。
部屋の扉が開き、外で待機していた大柄の男が入って来た。彼は息を切らし、汗をかき、僕と同じくらい、全身ずぶ濡れの状態となっていた。
手には薪割り用の斧を持っていたが、彼は部屋の様子を見て僕が勝ったことを把握したようで、それを捨てると僕の方まで駆けて来た。
「おい! 足が血まみれじゃねえか」
僕も、撃たれた足を随分長い間水に浸していたので、血がかなり流れ出てしまっていた。命が繋がれ緊張が解けたせいで、僕の体はようやく血液を多量に失っている事に気がついたようだった。
気が……遠退いて…………く。
「くそ!」と言い、彼は僕を抱えると階段を駆け上がり始めた。
僕は意識を失う途中で気がついた。彼は水のバルブを開いてからすぐに、あの斧を村まで走って取りに帰っていたんだ。それはつまり、やはり途中で水を抜き、もしもの時は、自分があの男を殺すという決意だったのだろう。
痛みもなく、その上どうしてか体全体がぽかぽかと暖かいような感じさえした。
スケッチブックを胸のところに挟んでいたせいかもしれないが、僕は少女と、灯台近くの丘で一緒に絵を描いている夢を見た。
風が吹いて、足元の草を揺らす。
春が、もうすぐそこに訪れていた。
【第二部】五十三章 「健康な女の子と、宝石のような朝食」
僕は、右側から聞こえる、風で窓がカタカタと揺れる音で目を覚ました。
そこは、全く見たこともない部屋で、僕は柔らかいベッドに寝かされていた。その部屋からは、何処かの人の家庭の慣れない匂いがする。それは尊くも感じられた。
どこだろうかと思い、窓枠を手で掴み引っ張って少しだけ上体を起こす。外を眺めてみると、並んでいる家々に見覚えがあった。
どれも煉瓦造りで煙突の付いている家だった。ああ分かった。ここはきっと南西の農村だ。僕は窓枠手を放し、またベッドに仰向けになった。
いや、そうか。だんだんと頭がはっきりしてきた。
僕はあの収容所の地下室であいつを殺して、そのあと、そうだ。あの大柄の男が水を止めてくれて、部屋に入って来た辺りまで覚えている。
じゃあ僕は助けられて、生き延びられたということか……僕は左手をそっと動かして、自分の左の太股辺りを触ってみた。すると、太股全体が包帯でぐるぐる巻にされていた。
真ん中の辺りを親指の先で軽く押してみる。その瞬間、予想を遥かに超える激痛が走った。
「わあぁぁっ!!」
僕は思わず叫んでしまい、ベッドから転げ落ちてそうになる。痛い……なんて痛さだ。脳天まで響くような痛さだった。僕は間違いなく生きているようだ。
ガチャリと、扉の取手が回される音がした。
少しだけ扉が開き、誰かがこちらを覗いているようだ。隙間から目と前髪だけが見えていた。それは多分小さな女の子だった。僕は先ほどの激痛で、涙目になっており恥ずかしかったが、その隙間から覗く目に挨拶をした。
「こんにちは」
しかし、その目は何も反応を見せなかった。というか僕からは、目と前髪しか見えないので、反応しているかどうかも分からない。
その目は何も言わず僕を数秒見つめてから、突然ふっとそこからいなくなり、階段を勢いよく駆け降りていく音が聞こえた。
「とうちゃーん! 起きたみたいだよ!」
という声が下の階から聞こえてきた。なるほど。さっきの子は、あの大柄な男の娘さんだったのか。
今度は重い体重を乗せた足音が、木の階段を軋ませながら上って来た。部屋の扉が開かれる。入って来たのはやはりあの大柄な男だった。
腕には六歳くらいの女の子を抱えていた。
「よう。目を覚ましたか。安心したよ」と彼は言い、椅子に腰を下した。「記憶はしっかりしてるか?」
「ええ多分。あなたがあの部屋に入って来た辺りまでは覚えています」
「そうだな。俺が飛び込んだ時、既に意識が朦朧となっている様子だったからな。そこまで覚えていれば、きっと大丈夫だな」
「ここは、あなたの家ですか?」と僕は部屋の中を見渡す。
「ああそうだ。ああいう事情だったもんで、あんたを病院に連れて行く事が出来なかったんだ。ただ俺たちの仲間の中には医者もいるからな。ここに呼んで、あんたを治療してもらった」
「そうだったんですね。ありがとうございます」
彼の膝に抱えられた女の子はさっきから、お父さんのあご髭の辺りを指先で触って遊んでいた。
「その子、おいくつなんですか?」と僕は尋ねる。
「六歳だ」
彼女はまた僕の方を見つめている。
「やあ、こんにちは」と僕はもう一度言った。
しかし彼女は父親に抱きついて胸元に顔を埋めてしまった。
「おい。お前に言っているんだぞ」と、彼は目線を下に向けて言った。
「ごんにぢわ」と彼女は、父親の胸に顔を埋めたまま言った。
僕は笑う。
「それで僕は、どれくらい眠っていたのですか?」と彼に尋ねる。
「そうだな」と彼は部屋の壁に掛かった時計を見上げた。「三十時間ってとこだな」
少し安心した。もっと何日も経過しているのだと思っていた。
「腹が減っただろう? 何か食べれそうか?」と、彼は尋ねる。
「え、ええ。食べれると思います。良いのですか? そんな何から何まで」
「当たり前だろう。気にするな。足が良くなるまでは、ここでゆっくりしてればいい」と言い、彼は娘を床に降ろすと立ち上がった。「ちょうど朝飯が出来るところだ。少し待っていてくれ」
「はい。すみません」
そして彼は部屋を出ると、階段を下りて行った。
部屋の中には僕と、その六歳の女の子だけが残された。彼女は窓辺に置いてあった大きな貝殻を手に取って、くるくると回して色んな角度から眺めていた。それからこちらに駆け寄ってくると、僕の足を指さした。
「あし……」
「え? うん。足だよ」
「あし。だいじょうぶ?」と彼女は言った。
「え、ああ。大丈夫だよ」
「さっきすごい声だしてたねえ」と彼女は言う。
「うん。うっかり傷口を触っちゃったんだよ。君だって傷をつい触っちゃうことはあるだろう?」
「うん。でも私はそんなに大きな声出さないよ」
「そうだよね。僕も初めてだよ」
「前なんか、かさぶたをはがしてから三十分もずっとペタペタしてたけど、ぜんぜん痛くなかったよ」
「そんな事してたら、バイ菌が入っちゃうかもしれないよ。瘡蓋は剥がさない方が良いんだよ」
「だって見てるとはがしたくなるんだもん。はがしちゃいけないなら、もっとはがしたくならないような見た目にならなくちゃ」と彼女は言った。
それは確かにその通りだなと納得してしまった。自分の体の一部を治している最中なのに、自分で剥がしたくなるのは。自然の摂理に反しているような気もする。
「その貝殻はどうしたんだい? 大きいね」と僕は、彼女が持っていた大きな貝殻の事を言った。
「きたのかいがんに行ったときにとって来たんだ」と彼女は言った。
「北の海岸って、一番北の、灯台のある方の?」
「そうだよ。私がよんさいの時だったけど、みんなであそびに行ったんだ。大きなまちがあって、すてきなおようふくのお店もいっぱいあったのに、お父ちゃんは何もかってくれなかった」
「そっか。きっとその時はまだ、君が小さくて着れる物が無かったんじゃないかな?」
「そうなのかなあ。でもお父ちゃんはつりざおのお店に一時間もいたから、さいごにはお母ちゃんがおこったんだよ」
「そうなんだ。そりゃあ怒られちゃうよね」
その時。コン、コン、と扉をノックする音が聞こえた。
「はい」と僕は答える
美味しそうな香りと共に、朝ご飯を載せたトレーを手に奥さんが入って来た。彼女は背の低い素朴な女性だった。
「たくさんありますけど、無理せず、食べれるだけで良いですからね」と言い、テーブルにトレーを置いた。
「ありがとうございます」と僕はお礼を言う。
「多分、全部食べれると思います」
「それは良かったです」と言い彼女は笑った。
「うちの人、あんな図体で少食なんです」
「うそ。本当ですか?」
「はい。元々あまり食べなくても太りやすい体質なんですよね……」
「はああ、なるほど。それはそれは……」
「なので、ぜひ好きなだけ食べて下さい。まだ下におかわりもありますから」と言い、彼女は娘を見た。「こら、あんまりはしゃいじゃダメよ」
「ぜんぜんはしゃいでないよ。ねえー?」と女の子は僕に言った。
「ねえー」と僕も返した。
奥さんは、娘に良かったわねと言うと、部屋を出て行った。
ベッドから上体を起こそうと思い腹筋に力を入れた。太股の傷が少し痛んだが、何とか起き上がることが出来た。
トレーの上のメニューを見てみると、アスパラガスの蒸し焼き、豚の角煮、長ねぎの味噌汁、卵焼き、そして白米だった。
アスパラガスは上に、白ごまと鰹節が降りかけられており、味噌汁には底に鮭の切り身も入っていた。卵焼きは、お店で出るようなツルッとしたものでなく、もう少し硬そうな、表面に焼き目のついた卵焼きだった。僕はこっちの方が好みだ。
「す、すごい……」と思わず唾を飲み込む。それらは僕にとって、どんな高価な宝石よりも輝いて見えた。
「お母さんは、いつもこんなにすごい料理を作るの?」と僕は女の子に尋ねた。
「うん。でもそのお肉はたまにしか作らないかな。おきゃくさんだからきっとはりきったんだよ」と、少女は豚の角煮の事を言った。
「いや、それにしても。手を付けるのが勿体ないくらいすごいよ。これは」
「ふうん。おじちゃんおもしろいねえ」と女の子は言った。
まあ、この子からしたら僕だって当然おじちゃんだろう。
それから僕は一口一口噛みしめながら、その料理を味わって食べた。
その間女の子は、窓辺に来る二匹の猫の話や、お父さんが寝るときには怪獣のようないびきを立てる話。山の上の館にはお化けが出るという話(僕が一晩泊まったと言ったら驚いていた)などをしてくれた。
そしてそのうちにお父さんがやってきて「そろそろ休ませてやりなさい」と抱えられて行ってしまった。
——僕は、一人になった部屋の中で窓の外を眺め、ボンヤリとしていた。
全て終わったんだな…………
しかし僕は、今まで感じることのなかった大きな「何か」が、頭上で手を開き、僕を摘み上げようとしている事に気がついた。
もう一か所。行かなければいけない場所があることを僕は思い出し、急いで支度を始めた。
【第二部】五十四章「大柄の優男」
僕はその日の夜。すぐに出発することに決めた。
僕を助けてくれた大柄の男は、足が治るまでゆっくりしていた方がいいと言ってくれたのだが。
「すみません。実はあまり時間がないんです」
それは、確かなことではなかった。
「どういうことか分からんが、遠慮しているわけじゃないみたいだな」と彼は事情を汲んでくれた。
「はい。早くしないと、まずい気がするんです。うまく説明が出来ませんが」
「そうか、分かった。それなら俺が、そこまで車で送ろう。しかしこんな時間でも、入ることが出来るのか?」
「ええ、きっと大丈夫です」
僕は彼の車の助手席に乗り、二十一時頃、彼の家を出発し、南西の村を後にした。
——国道に出ると、車は北に向かって走り始める。道路灯の光が、アスファルトを橙色に照らしていた。
「素敵な奥さんと、娘さんですね」と僕は言った。
「ああ。あいつのお蔭で俺は、まともな生き方が出来るようになった。そうでなければ、今頃どうなってたかも分からねえ。いくら感謝してもしきれねえさ」
「そうですか……」
「あんたは結婚は、今まで一度もしなかったのか?」
「そうなる予定の相手もいたのですが、亡くなってしまいました」
「そうか……それは気の毒だな。病気だったのか?」
「病気なのは僕の方でした。心臓が悪かったんです。彼女は僕の為に心臓だけを残して、逝ってしまいました」
「色々と事情があったようだな。最愛の人に救われて、自分だけ生き残るということも辛いな」
「そうですね。僕は彼女に救われたわけですが。多分彼女は、僕に申し訳ないことをしたと思っている筈です。だけど僕には感謝の気持ちしかありません。
僕は彼女が亡くなってからも、彼女の事は忘れないまま、だけどまた新しい自分の生活を組み立てて、幸せに暮らすことが出来ていました。
もし仮に、どこかで彼女がその様子を見ていたとしてもきっと、寂しいなんて思わずに、素直にそのことを喜んでくれていたと思います。だから。そうあって欲しいのです」
「そうか。だが、『きっと彼女は申し訳ないことをしたと思っている』そんな風にお前さんが考えていることも、その彼女は知っていたんじゃないのか?」
「…………」
「だから、相手を心配して申し訳ないと思っているのは、お前だって同じだろう」
「そうかもしれません」
「じゃあ、お互い様だな」と言い彼は、ガハハと笑った。
しばらく走ると、右手にはまた植樹された農園のような木々が見えてきた。それが見えてくれば、教会はもうすぐそこだった。
「もうこの辺りで大丈夫です」と僕は彼に言う。
「お、そうか」と言い、彼は教会が正面に見える道のすぐ前まで行き、車を停めた。
僕は車のドアを開けて外に出る。夜の冷たい風が体に吹き付けた。
「本当に、何から何までありがとうございました」と僕は、運転席に座る大柄の優しい男に言った。
「こっちこそ、いくら礼を言っても足りないくらいだ。長年抱えてきた気持ちの悪いものが、すっかり取れた気分だ。あんたほど勇敢な男はなかなか居るもんじゃない。誇りを持ってくれ」
「そんな……あ、奥さんにもお礼を言っておいて下さい。娘さんには、館にはお化けなんていないから、一度遊びに行っておいでと」
「ああ分かった。じゃあ気を付けてな」と彼は、別れの意味を込め左手を上げた。「じゃあな、灯台の管理人さん」
そして車は、国道を来た方に向かい走って行ってしまった。僕は相変わらず黒いローブを着ていたが、彼は僕の事を最後にそう呼んだ。
僕は彼からもらった杖を突きながら、教会の方まで歩いて行く。教会まで真っ直ぐに延びるその道を歩いていると、帰るべき場所に帰って来たような、妙に落ち着いた気持ちになって行った。
正面の大きな扉の前まで着いたが、教会の灯りは消えて真っ暗になっていた。当然鍵は掛かっているし、中から音は聞こえない。教会の周りにもやはり、誰の気配もなかった。
僕が困っていると、突然。教会の中の灯りが点いた。
カチャ。と、目の前の扉の鍵が開けられる音がした。そして、内側からゆっくりと扉は開き、少しずつ中の光が、外の暗闇に広がって行く。
そこに立っていたのは、かつて森の教会で僕を助け看病してくれた、あの老婦人。いや、その若い時の姿の彼女だった。
「神父様。おかえりなさい」と彼女は言った。
【第二部】五十五章 「プシュケー」
「あなたは……」
「神父様。おかえりなさい」と、|修道女の彼女は言った。「さあ、中へどうぞ。寒かったでしょう」
僕は彼女に招かれ、教会へと足を踏み入れる。しかしすぐに、内部を見て足が止まった。いや、体全体が止まった。
「これは……」
天井には花紋様の装飾が施され、カラフルなステンドグラスには、様々な物語が光を受け輝いていた。柱頭には、ごつごつとした個性的な彫刻。そして祭壇には白い布がかけられ、その向こうの壁に、聖体を安置している証の赤いランプが灯っていた。
僕は、杖をつきながら身廊を歩いて行く。席には埃一つなかった。ふと壁に目をやると、壁にはガラス玉がいくつか埋め込まれていた。
そう。そこはまさに、僕が使いの男に撃たれ、その後目を覚ました場所。
あの「森の教会」そのものだった。
「ちゃんとした説明もなくて、ごめんなさい」と、修道女は後ろから言った。「もう、ある程度は気付いているかもしれませんが、あの『森の教会』のモデルとなった、本来の教会はここです」
「モデル……ですか? つまり、どういう事でしょうか?」
「『森の教会』は実在しない場所です。教会だけでなく、あの森全体が、私自身の意識の内側にだけ存在する世界でした。
つまり。あの少女のお墓のあった高台の丘も、たくさんの花達も、少女のお墓さえも、全てが実体のないものです」と彼女は説明した。
あの時と同じように、海のような優しく深い瞳がそこにあった。今はもう、彼女自身に切り取られてしまったその瞳は、僕が生まれた海でもあるのだ。
「そうですか……だけど、そんな気はしていました。僕も旅を続けながら、色んな可能性を考えてはいましたが、きっとあの場所を転換点として、何かが大きく変わってしまったのだろうと。そう感じていました。
だけど、この教会は本物なのでしょう? 不思議な感覚ですが、僕はここに入った時から、妙に落ち着いた気分なのです」
「もちろん。あなたがもう何年も、毎日のように通っている場所ですからね」
「では、あなたもここの修道女なのですか?」
「いえ。かつてはそうでしたが、今はもう違います。この姿も、五十年も前の姿ですから。好きな時の姿を選べるのなら、あなたと同じくらいの年齢で現れたいと、思ったもので」と言い、彼女は微笑んだ。
僕もそれに応えるように微笑んだ。彼女は続ける。
「あの時。つまり、あの使いの男に撃たれてしまった時。《《あなたは少女と共に、確かに絶命してしまいました》》。
だから、それから後の世界は、あなたが元居た世界とは違う軸にある世界です。
きっと様々な差異を見つける内に、どこかでそう気付くことはあったかもしれませんね。
この世界のあなたは神学校を卒業した後に、そのまま神父となる道を選びました。その肉体に『あなた』のプシュケーが降り立ったのです。
今は、元の宿り主だった『神父として生きてきたあなた』の意識というものは、ほとんど眠ってしまっています。あなたの意識の方が強かった為、あなたが上に来ているからです。
しかしです。しかし、目的に辿り着いてしまったあなたは、間もなくその肉体を離れなければならない事となるでしょう。そして今度こそ。本当に|プシュケー《魂》そのものとなり、時間を経て、また別の何かに向かう事となります」
「はい。その事も、今朝目覚めてから感じるようになっていました」僕は、自分の手の平を見た。
やはりこの体は僕であり、正確な「僕」ではなかった。
「人の太股に穴を空けてしまいました……きっと目覚めた時に、彼は驚くでしょうね。悪いことをしてしまいました」
「きっと、分かってくれますよ。あなたなんですから」と彼女は、優しく笑った。
「そうだ。これを」と言って、僕は鞄からマラムを取り出した。「これは『森の教会』であなたからもらった物です。お返しします」
彼女はそれを見て、何やら思い付いたようで、わざとらしく真面目な表情を作り背筋を伸ばした。
「これはしかし、私のした行いの対価を遥かに超えています」と彼女は言った。
「え、それって……」僕は躊躇ったが、彼女に付き合うことにした。「いえ。私は罪を犯した身の人間です。このような物はあまり似合いません」
「完璧です!」と言って、彼女は膝を叩いて笑っていた。「よく覚えていましたね!」
これは、面白いのだろうか……?
やはり五十年前の人の感性は、少し違うのかもしれない。だけど、今はあんなにも賢者のような風格の漂う老婆も、やはり若い頃はこんな風に朗らかな人だったのだな。
「その宝石は、後に目覚める彼の為に書置きと共に、置いて行ってあげてはどうですか? 目覚めた時に、大怪我をしているだけでは可哀想ですから」
「なるほど。確かに良い考えですね。しかし、良いのですか?」
「はい。私が持っていても仕方ありません。使い道がありませんから」と言い、彼女は両手を差し出した。
「そうか。そうです……よね? では、お言葉に甘えて。そうさせて頂きたいと思います。ありがとうございます」と言い、僕は頭を下げた。
「では、ここから先。もう少し別の聞きたい事もあるかと思いますが、私の役割はここまでです」と言い、彼女は教会の奥にある小さな扉の方を指さした。「あちらへ。寒くはありません」
僕の記憶が正しければ、その扉の向こうは、ベッドや薬の棚などが置いてある小部屋になっている筈だ。僕が目を覚ましたあの部屋だ。寒くはないって、どういうことだろう。
「分かりました」と言い、僕は彼女の後ろに付いて行く。
教会の中に、僕一人分の足音が響いていた。
扉の前まで辿り着くと、彼女は僕の方を振り返った。
「……あなたの事は永遠に忘れません。どうかまた、もし何処かでお会いする事があれば、その時は。また仲良くして下さい」
「こちらこそ。あなたが助けてくれたから、僕はここまで来ることが出来たのです。またぜひ何処かで」
そして僕と彼女は抱き合った。彼女は優しい母親のような暖かさを湛えていた。僕は一瞬そのまま寝落ちしてしまいそうになる。
彼女は僕から離れると「では、あなたの幸運を願って」と言った。扉の取手に手をかけてゆっくりと回し、扉を開いた。
そこには、夜の海岸が広がっていた。
頭上には、絵に描いたような真ん丸な月が浮かんでいる。
僕は一歩踏み出して扉をくぐった。そこは、僕が初めて老婆と出会ったあの、北の灯台近くの海岸であった。
そして波打ち際には、椅子に座り、膝に乗せた何かを撫でながら、海の方を眺める老婆の後姿があった。
僕は慌てて後ろを振り返るが、既に扉も教会も無くなっており、ただ暗い夜の森が目の前に広がっていた。
僕は再び海の方に向き直り、老婆の元まで歩いて行く。
「お久しぶりです」
「おかえり。大変な旅だったねえ」と老婆は言った。
【第二部】最終章 「希望」
「おかえり。大変な旅だったねえ」と老婆は、僕に背を向けたまま言った。
「お久しぶりです。こちらで会うのは初めてですね」
老婆は椅子に座り、足元には小さなランタンを置いていた。
横に立つと、彼女はやはり目を瞑ったまま、斜め下の方に顔を向けて、膝に抱えた青年のしゃれこうべ……ではなく、まるまると太った。白黒模様のはちわれ猫を撫でていた。
猫は顔を上げて僕の事を一瞥したが、特に興味は沸かなかったようで、また老婆の膝に顔を伏せて、うつらうつらし始めた。
「その子は、おばあさんが以前から飼っていた猫ですか?」と僕は尋ねた。
「そうさ。はて? 初めてじゃったかな見たのは」
「そうですね。僕の知っているおばあさんはいつも、しゃれこうべを抱えていました」
「ほほほ。そうかい。私は猫の方がいいねえ。この子はぐうたら猫じゃから、急にどこかに走って行ってしまうことも無いしの。
海と猫や、月と猫というのは、昔から仲良しじゃ。じゃからこの子も安らいでおる。それにあの青年の遺骨なら、ちゃんと家に保管して、毎朝拝んでおるよ」と言い老婆は、はちわれ猫の背中を頭からお尻の方に、柔らかく撫でた。
僕はなぜだか分からないが、その太った白黒模様のはちわれ猫を、少女が抱きかかえてどこかに運んでいる様子が脳裏に浮かんだ。
何故だかは分からない。だけどそんな様子が、あの子にはとても似合うような気がしたのだ。そもそも僕は、あの子が猫を好きなのかすら知らないのだけれど。
「あの。僕にはまだ、いくつか分からない事があります」
「ああ。少女の事。そしてあの邪悪な男が、どうなったか。ということかい?」
「そうです」
「まずあの男だが、安心しなさい。お前さんが元居た方の世界でも亡くなっておるよ。二つの世界は違うものだが、それはお互いに干渉し合い、影響を及ぼし合っている。
些細な違いが生じることはよくあるが、『あちらでは生きている人間が、こちらでは死んでいる』というような、根本から揺るがしてしまうような差が生まれることは、まずない。
だから、お前さんがあの男を殺した時に、あちらの世界でも、何らかの切っ掛けにより亡くなった筈じゃ。あとは、その邪悪なプシュケーがどうなるかは、神のみぞ知る。というところじゃな。
浄化され、また新たな入れ物に入れられるのか。それとも完全に消滅させられるのか。そこまでは私には分からんが、大切なことは、ひとまずの区切りを、お前さんはきちんと付ける事が出来た。という事じゃな。
どんなに用心していても、邪悪なプシュケーはまた何処かで生まれる。悲しいが、それを完全に防ぐことは出来んのじゃ。またそれは、白黒はっきり分けられるようなものでもない。
『邪悪』はあらゆるものの裏側、側面、時には表にも。可能性として常に存在しておる。ただ多くの人間が、それを選んでしまわないようにしながら、日常を過ごしておる。それは歴史であり、文化であり、教育でもある。
身近に居る人を大切にしながらも、自分の時間軸を見失わず歩む事が出来れば、それを選ぶ必要がないことも、感覚的に分かるようになっていく。それが多くの人間の生きる意味となれば、きっと歴史というものは、良い方向に向かうじゃろう」
そう話す老婆の横顔に、瑞々しい瞳が見えた。その瞼をめくったとしても、もう何も無いことは分かっている。今、目の前に居る彼女には、失われた物質的な瞳ではなく、真理を見ることの出来る。内なる瞳が新たに開かれているのだ。
老婆の話は、よく理解することが出来た。あの使いの男が、僕の元居た世界の方でも死んでいるという理由もよく分かった。
しかし……そうだと言うならやはり、もう一つの疑問が生まれてしまうことになる。
「では、どうして僕は、こちら側の世界の、この『神父である僕』は、なぜこうして生きているのでしょうか? あちら側の『灯台の管理人である僕』はあの時に死んだというのに」
「《《それはね。私がまだ、ここに生きているからだよ》》」と老婆は言った。
「少女の墓の前で話したことは覚えているかい? 私はかつて、眼球を取り出し『子宮への回帰』の儀式を行った。
その時の私の強い無念から生まれた『大切な人を守れる強い存在として生まれ変わりたい』という願いが、青年の遺骨と、海に流した瓶の中には込められていた。
そしてその引力に惹かれた二つのプシュケーがおった。それが、お前さんとあの少女じゃった。その話は覚えておるかな?」
「はい。覚えています」
「つまりお前さんは、私の『強い思念(眼球と、愛する者の遺骨)』に、合流するような形がきっかけでこの世界に誕生した。それが何を意味するのか? つまり。
《《お前さんのプシュケーの中には、僅かながら私のプシュケーの一部が内在しておる》》。
その為に、肉体が滅びてしまってもなお、世界から完全に切り離されることは無かったのじゃ。
とは言うものの、元の肉体は機能を停止してしまった。じゃからもう一方の世界線へと移り、こちら側のお前さんの肉体に、降り立ったということじゃ。そしてまた、こちら側の私の意識と結びつく事となった」
「なるほど……頭が混乱しそうですが、しかし。その感覚は確かに以前からありました。つまり、誰かの意識が内在しているという感覚です。自分の口から発せられたものの、自分の考えた発言ではないように感じることが、時々ありましたもので」
僕は、老婆が話してくれたことと、僕の身に起こった数々の不思議を、頭の中で整理しようと努めた。
「ええとつまり。あなたの行った儀式の力によって、僕は肉体が滅んでもなお、継続した意識を持ったまま、並行するもう一つの世界。つまりこちらへと移動した……ということですね?」
「ああ。その通りじゃ。本当はね、そのままお前さんのプシュケーを解放し、逝かすことも出来たのじゃが、まずお前さんに、あの子の墓を見せてから決めようと私は思った。
すまんね。勝手なことをしてしまって。しかし、私の思った通りお前さんは立ち上がり、あの男と戦う道を選んだ。じゃから私はそのまま繋がりを維持させ、お前さんの行方を見守ることに決めたのじゃ」
「そう、だったのですね……」
「お前さんは目的を達成した。既に私との結びつきも解消しておる。そして今、眠っている『神父としてのお前』が目覚めようとしている。もう間もなく、今度こそ本当に、世界との別れが訪れる事じゃろう」
「はい。本望です。正直もうとても疲れてしまいました。ここ数か月は、自分であり自分でないような感覚が、いつもありました。死というものが何なのか、僕には分かりませんが、今はそうなることが自然であると感じています」
僕は自分が、あとどれくらいで消えてしまうか分からないが、最後にどんな事を思い出せばいいのだろう。何を考えるべきなのだろうか。死後の世界というものが、もしあるとするのなら少女は僕を、覚えてくれているだろうか。
いや。待て…………
待てよ。
僕が死なずにこちらの世界に来ることが出来たのは、老婆の行った儀式によって、その思念に結び付いたことが要因。
ということなら……
「もしかして少女もこの世界のどこかに? 僕と同じように、来ているのでしょうか?」
「ああ。もちろんだよ」と言い、老婆は笑った。「本当は、分かっていたんじゃないのかい?」
「…………」
僕は何も答えられなかった。
目を背けていた最も恐ろしい感情が、涙を流し始めたからだ。
その感情のことを僕たちは「希望」と呼ぶ。
少女が生きているかもしれない。その希望を持つことが、僕にはずっと……何よりも恐ろしかった。
「いいんだよ。希望を持つということは、『希望を失ってしまう可能性』をも同時に持つということ。それほど勇気の必要な事はない。皆そうやって生きている。だけどね」と言い、老婆は僕が肩に提げている鞄を指さした「あの子が存在している証明は既に、その中にある」
僕は鞄を開き、中から少女のスケッチブックを取り出した。使いの男との対決の時に、濡れてぼろぼろになってしまい、絵は滲んで原型を留めていなかった。
しかし唯一、何事もなかったかのように、影響を受けていないページがあった。
「こっちに貸してごらん」と老婆は言った。僕はそれを手渡す。
老婆は「すまないね」と言うと膝の上のはちわれ猫を、砂浜に下ろした。猫は椅子の足で爪を研ぎ始めた。
老婆はスケッチブックの最後のページを開き、表を空に向けて膝の上に置いた。
砂浜の砂を片手でひとすくいすると、握り込み、その拳を絵の上に持っていく。そして指を細かく動かして、その絵の上に少しずつさらさらと砂を落とし始めた。
砂の落ちたところの絵は当然、隠れて見えなくなっていく。
僕は固唾を飲んで、その様子を見ていた。砂は一定のペースで、老婆の手から、スケッチブックへと落ちて行き、僕の寝顔を、砂の下に埋もらせて行く。
最後に残った唇と顎の辺りにも砂をかけると、ついに、そのページに描かれていた線の全てが見えなくなった。
老婆はその砂まみれになったスケッチブックを、ゆっくり持ち上げるとくるっと九十度回転させ、表面を僕の方へ向けた。砂は全て表面から滑り落ちて行く。
すると不思議なことに、描かれていた僕の似顔絵はすっかり消えてしまっていた。
「どうじゃ。手品みたいじゃろう」と言い、老婆はほっほっほと笑った。
「これは、どういう事でしょうか?」
「このスケッチブックは、この世界では異質な物じゃ。この世界の物質を触れさせれば、このように、一時的に消えてしまう。別に砂じゃなくても良いんじゃ。ほれ、これを持って」と、老婆は足元に置いているランタンを僕に手渡した。「スケッチブックを照らしておるんじゃよ」
僕は老婆の持つ、そのまっさらになったページにランタンの灯りを近づけた。
「さあでは、ゆっくりと見ようじゃないか」と老婆は言い、スケッチブックのページを眺めている。
すると。スケッチブックの表面に、再び黒い線がすらすらと蘇って行くのである。
まるで透明な手が絵を描き出して行くように。少しずつ、少しずつ、丁寧に。絵はまた元の状態へ戻ろうとしていた。
「これは、あの少女が実際に描いたその軌道を、正確に再現してくれているんだよ。これこそが、あの少女が今もまだどこかに生きている証拠と言える。
そしてお前さんの事を思い出そうと、記憶の世界を探し回っている。それはまるで風に漂う草の切れ端を掴み取って行くような途方もない作業かもしれんが、それでも思い出さなければいけないという、使命感なのか、愛なのか、その両方なのか。
少女は毎日。切れ端を見つけるその度。スケッチブックに描き足しているのじゃ。そうすればいずれ真実に辿り着くことが出来ると、信じておるんじゃな」
その時。ぽたっと、スケッチブックの表面に水滴が落ちた。雨か? と思ったが雨は降っていない。そして線の軌道は止まった。
どうやら、今のところはここまで描けている。ということだそうだ。
「あの子には、僕との記憶がなくなってしまっているのですか?」
「ああ。お前さんは死ぬ時にまだ、強い目的を持っておった。なんせ、大切な人が目の前で撃ち殺されたわけじゃからな。じゃからこちら側の肉体に移っても、元の持ち主の上に位置することとなった。
しかし少女は違った。一足先に死んでしまった彼女は、お前さんを守り抜いたことで、一つの使命を全うしたと感じながら、あの場を離れた。お前さんが死んでしまったことを知らんかった訳じゃ」
「するとつまり。僕とは逆のような状態に在るということですか?」
「そうなる。こちら側に元々いた少女の意識の下に、わずかに存在する程度に息を潜めているじゃろう。しかしね。あの少女のプシュケーに内在していた私の一部も、私は既に開放しておる。
つまり、あの子が望みさえすればいつでも肉体を離れ、旅立つことが出来る筈じゃ。そうしないのは、余程。お前さんにもう一度。一目だけでも。会いたいという事じゃろうな」と言い、老婆は満面の笑顔を見せた。「ほっほっほ。良かったのう」
「ずっと会いたかったのは……僕の方ですよ」
人の体なのに関わらず、僕は頭が痛くなる程に涙が止まらなくなっていた。
その時ようやく、少しづつ、体に力が入らなくなって来た。
力の入れ方が分からない。コントロールが出来ない。つまりそれは、「感覚」が遠ざかって行く感覚だった。
「すみません。そろそろかもしれません……瞼が、重くなってきました」
「ええ。ゆっくり休むといいよ。お前さんは本当によく頑張ったね。もう聞きたいことは全て聞けたかい?」
「はい。もう何も……心残りは」
僕は立っていることが出来なくなり、砂浜に寝そべった。
「この……砂浜は、暖かい…………の、ですね」
「そうだよ」という老婆の声が聞こえ、はちわれ猫が、倒れている僕の顔の前にやって来る。そして、鼻に鼻を押し当ててきた。
しかし僕にはもうその感触を、感じることは出来なかった。
さざ波の音が、少しずつ遠ざかって行く。
最後。僕の頭に浮かんだのは。
あの灯台の暖かい光。
そして岬を吹き抜ける。春風の感触だった。
エピローグ「少女」

歩き出すためにはまず、最初の一歩を踏み出さなきゃいけない。
それが右足なのか、左足なのかはあまり大切じゃなくて、とにかくあれこれ考えずに、一歩踏み出すことは大切なのだ。
部屋を掃除する時だって、洗濯物を干す時だって、朝ご飯を作る時だって必ず、最初はまずどちらの足でもいいので、前に踏み出さなきゃいけない。
それが例えば右足なら、次は左足を踏み出せばいいって分かるし、それが反対だったとしても同じことである。
——私は桟橋から足を垂らして、海の水をぱしゃぱしゃと、足先で散らしていた。
最近どうも、ぼんやりする事が多い気がする。
「落ちないでねー」と、洗濯物を干しているお母さんが向こうの方から、私に声をかけた。
私は海面から足を上げ立ち上がると、桟橋を駆けて行く。お母さんの背中を通り越し、家の中へ入る。
二階に上がり自分の部屋へ入ると、机の引き出しからスケッチブックを取り出した。
最後のページに、私は存在するはずの無い記憶を頼りに、心の中にぼんやりと浮かぶ誰かの顔を、何日もかけて少しずつ描き足していっている。
何となく、今なら描けそうだな。という気持ちが訪れると、こうしてすぐに、取り掛かるようにしている。
「これは、とても大切なことなんだ」と海の向こうから声が聞こえる……気が、するのだ。
少しずつ少しずつ。現像液に浸したフィルムが景色を写し出すように、だけどそれよりも、もっと。もっと。ゆっくりとしたスピードで、私の中のイメージを、正確にスケッチブックに描き写していく。
輪郭、目元、鼻すじ、髪の毛。数ヶ月かけてそこまでは描けていた。多分眠っている男の人の顔だった。
そうだな、口元はどんなかな? こんな感じかな? 私は新たに口元を描こうとしていた。頭に浮かんだイメージを、なるべく忘れない内に。
「うん。そうそう。確かこんなだった」と私は無意識にそう小さく呟いた。「フフ、確かこんなだったって。私こんな人……知らないのに」
ぽたぽたと、スケッチブックの上には水滴が落ち始めた。
「いけない!」と私は、絵が滲んでしまってはいけないので、すぐに離れた。
そう。この絵を描いていると、いつもどうしてか胸が締めつけられるような気持になる。だけどそれでも、この絵を完成させることが、私にとってはとても大切なことに思える。
また取り掛かろうと思ったけど、どうやら今日はここまでみたいだ。今はこれ以上描けそうにない。
もう一度、その男の人の顔を眺めてみる。
どうして……この人の顔は、こんなにも優しいんだろう。
「ご飯よー! 降りてきてー」とお母さんが、一階から私を呼んだ。
「すぐ行く!」と私は返した。
スケッチブックをまた引き出しに仕舞うと、私は階段を降りていく。
食卓の上には、焼いたトマトとチーズのサンドイッチ。きのことタマネギのスープ。クルミを使ったサラダが並んでいた。
「あれ、なんか今日の献立、いつもと少し違わない?」と私はお母さんに尋ねる。
「そうかな」と、お母さんはあまり関心無さそうに答える。「ぼーっとしてないで早く食べてよ。今日は忙しいんだから」
「うん……」
私はサンドイッチを一口かじる。何か懐かしい匂いがした。
「お母さん」
「何?」
「お母さんは、南にある大きな国に行ったことある?」
「あるよ。もうずっと前だけど」
「私もその時いた?」
「いないわよ。あなたが生まれるずっと前のことだもん。まだ、お父さんと離れる前だったし」
「そっか……ねえ、その国の地図ってある?」
「確か、お父さんが使ってた部屋の机の引き出しにあったと思う」
「ちょっと見てくる!」と言い私は立ち上がると、食卓を離れ階段を駆け上がって行く。
「ちょっと! 後にしなさいよ」とお母さんは後ろから言った。
私は二階へ上がると、かつてのお父さん(と呼びたくはないけど)の部屋に入り、机の一番上の広い引き出しを開けた。
そこには確かに地図があった。
この小さな島国の全景と、下の方には見切れる形で、海の向こう二十キロメートルほど南に位置する、ここよりも遥かに大きな島国の北部が少し、写り込んでいた。
私はその最北端の岬に注目する。そこに灯台があることが記されていた。
「ちょっと。いい加減にしなさいよ」と、不機嫌になったお母さんが、一階から上がってきた。「何してるの? 最近少し変よあんた」
「ごめん……」
「ごめんじゃなくて、どうしたの? 何でも言ってみなさいな。お母さんはあんたが嘘つくなんて思ってないんだから」
「私にもまだよく分からないんだけど、ここに行った事がある気がするの」と、地図にある岬の灯台を指差す。「なにか大事なことを忘れてる気がして、ここに行けば何か思い出せるかもしれない」
「ここに? そんな訳ないと思うけど」お母さんは頬に右手を当てた姿勢で、その地図上の灯台を眺めていた。「そっか。じゃあ一度行って、自分で確かめてみればいいじゃない。そこまで行くお金くらいなら、お母さんが出してあげるから」
「ホント⁉ いいの?」
「いいわよ。行ってきなさいよ。ここで悩んでても仕方ないんだから。よく気をつけて行くのよ」
「ありがとう。私、お母さんにはいつも助けられてばかりだね」
「な、何言ってるの急に? いいから下でご飯食べるよ」
私たちは再び、食べかけのサンドイッチの置いてある、一階の食卓まで戻った。
「ねぇ、お母さん。その国ってどんなところだった?」
「んー、もう随分前だからね。とにかくすごく大きな城があって、その周りにたくさんの街や村があって、それでその間を蜘蛛の巣みたいに、バスが何本もあっちこっち行ったり来たりしてて、それを使ってみんな定期的に、その城に入ったり出たりしながら暮らしてたな。
城を中心にみんなの生活が回っているような、そんな感じがした」と、言うとお母さんはスープを一口すすった。「うん。まあ、いいところだったと思うよ」
「そっか。じゃあご飯食べたら準備して行ってくる」と私は言う。
「うん。ホントに気をつけてよ。それでまた物語の続きが分かったら、お母さんにも教えて」とお母さんは微笑む。「冒険が始まるのかな?」
「どうかな。楽しい冒険だったらいいな」と私は答えた。
重なり合うプシュケーの塔


