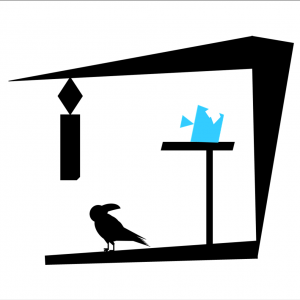踏切屋
『踏切屋』で、僕は一人の老人と出会った。故郷でめぐる短くも暑い夏の思い出は、僕をまた一つ強くする。
僕は数年ぶりに帰ってきた故郷で、馴染みのある弁当屋に向かうために自転車を漕いでいたが、建物の老朽化によって通行止めとなった裏道が通れなくなっていた。仕方なく別の道を通って向かおうとしたが、そのまま戻るのも時間がかかると思い、同じ方向の別の道を進むことにした。日差しが首筋にささり、汗で服がぴったりと張り付いて気持ち悪い。さっさと弁当屋で効いているクーラーの元に行きたいものだと道を急いだ。
しかし、漕いでも漕いでも弁当屋にはたどり着かず、いくつかの分岐点はどれも行き止まりであった。陽炎が見える中、あと一本の道が違えば今汗を流しながら通ってきた道を戻らなければならないと思うと、今までいい子にしてたので神様お願いしますと祈りたい気分だった。
「あーあ、行き止まりか。嫌だなー戻りたくないなー」
最後の道も日陰ではあったが行き止まりだった。久しぶりに帰ってきたのはいいが、今まで知らなった道もあったんだと感慨深さはあるが、この炎天下の中で行うもんじゃないと天を仰ぐ。お腹もすいてるし、さっさと弁当屋に行くかと自転車を漕ぐ足に力を入れた。少し日陰で涼んだためか頭が冴えていて、黒く古びた家が立ち並ぶこの道の途中に木彫りの看板があるのに気がついた。片面しか彫っていなかったみたいなので行くときには気がつかなったようで『踏切屋』と看板には書かれていた。踏切屋?踏切ってあの電車の踏切なのかなと想像するが、何でそんなものが売っているのか不思議だ。ガラスの窓から中を覗こうと、自転車に前のめりになりながら様子を伺った。薄い遮光カーテンが掛かっており、網戸にしているために風で靡いている。チラチラと暗い部屋の中に淡い色の白熱球が見えたが細部まではハッキリとは見えず、前のめりなっていたためにバランスを崩しかけて「うぉぁっと!」と声が出てしまった。その声に反応した誰かが店の中からこちらに向かってくる。ドアを開けたのは年老いた男性であり、僕のことを見てこいつは誰だろうと言わんばかりの顔だったが、田舎特有のやけに近い距離で話しかけてきた。
「おー兄やん、こんなところで何しとるんや。うちの店に何かようあるんか?まぁあるんやったら、そこに自転車でも停めときな。ほとんど人なんて来ないさかい、気にせんでええで」
「あ、はい。わかりました」
断れる雰囲気ではなく、その場に自転車を止めて『踏切屋』に入らせてもらうことにした。踏切屋と書いてあるものだからてっきり踏切が置いてあるのだと思っていたが、置いていたのは写真ばかりであった。その写真も電車は一つも写っておらず、駅や線路、それも見た目にわかる古びたものばかりだった。写真は一枚一枚が額縁に飾られており、店の至る所に飾られていた。店なんだよなと僕は思っていたが、値札がついてあるものは一つもない。レジっぽいものも無い。正直な印象は、昭和か大正時代から残っている古びた家の居間に、勝手に上がらせてもらっている雰囲気が正しい。さっきの男性は家の奥に入っていったと思うと、グラスに氷の入った麦茶を持ってきてくださった。
「兄やん、外暑かったやろー。こんなもんしかないけど、茶でも飲んで涼んできな」
「ありがとうございます」
冷えた麦茶は美味しかった。炎天下で自転車を漕ぎ、体中のエネルギーはすでに放出されてスポンジのようにスカスカになっていたため、自分の体に麦茶が染みこんでいくのは当然だった。
「おー兄やん。いい飲みっぷりやな!」
男性は豪快に笑い、僕は節操が無い行動だったと思って少し恥ずかしかった。男性はお茶をもう一杯下さったので、それを飲み干した後に改めて店内を見渡したが、やはり何かの店のような印象は無かった。
「ここ、踏切屋って書いてあったんですけど、何をしている店なんですか?」
「あー、あの看板なぁ。カミさんがここで昔マッサージやっててな、踏んでほぐすマッサージやったんやけど、それがよぉ効いてなぁ。コリとかを体から切り離してくれるちゅう評判がたったから、踏むと切るをもじって踏切屋って命名したんや。目には留まるやろ」
「はい、てっきり電車の踏切かと思っていました」
男性は近くにあった写真を取ってきて僕に見せた。その写真には鉄が錆び、混凝土がひび割れて緑にほとんど飲まれてしまっている、人が何年も通っていないであろう駅が写っていた。写真を飾っている額縁はよくみると年代物であり、綺麗に手入れはされているが、所々傷がついており、ガラスも劣化して若干白くなっていた。
「この写真、写ってんのどこかわかるか?」
「いいえ、廃線のような気がしますがそれ以上は…」
「廃線は正解や。この駅はな、むかーし俺が使ってた駅なんよ。まぁ随分さびれた町やったから何年も前に廃線となってしまってな。それがなんか、こう、上手くは言えんのやけど…まぁ寂しかったんやろうな」
男性は写真に視線を落として話を続ける。
「廃線になったって話聞いた時はちょうどカミさんが危ない時やってな、そんなことどうでも良かったんや。その後、一人なって踏切屋もできやんし、看板も片づけてしまおうと思たんよ。けどなぁ、近所の電車好きの子が今の兄やんみたいに勘違いして入ってきたことあったなぁってな。やから、せっかくやし電車に関係することでもしよかって思ったときに、さっきの話に戻るんやけど廃線の話も思い出して、これいいやんってそれで写真をな、撮りだしたんよ」
「じゃあ、お店はもうされていないんですか?」
「そうやなぁ。別に店ってわけじゃないから、たまに昔の友達とか来て話題に上がるぐらいやな」
残念だった。電車はあまり乗っていなかったのもあり、詳しくは無かったがそれでも目の前の男性の写真には何か引き付けられるものがあった。もし、店として販売しているのなら写真を買っていきたいぐらいで、僕は目の前に置かれた写真を手に取った。
「なんや、兄やん写真買いたいんか?」
見透かされていたみたいで、僕は慌てて写真を机の上に戻した。
「あ、いや、ま、そ、そうなんですけど…」
男性は歯茎が見えるほど豪快に笑い、僕の背中をドンドンと叩く。老人とは思えない力強さで、背中がしばらくヒリヒリした。
「ええよ、ええよ!他に気に入った写真あるか?」
「いえいえ、そんな。今お金そんなに無いんです」
「金なんかええよ!どうせこの先、長ないから持てるだけ持って帰ってもええぞ!」
僕は男性の圧におされ気味で一瞬たじろいだが、男性のお言葉に甘えることにした。
「じ、じゃあ、あの写真もいいでしょうか」
僕は振り子がついている時計のそばにある写真の近くの方向を手で示した。
「お、あれ持って行くか!あれ、この持ってきた写真に写ってる路線の、終点の写真やな。名前はなんやったかなぁ、忘れてもうたわ。でも兄やんよぉわかってるやんか。よし、持って行きな。あ、大きい鞄持ってないんか。ちょっと待っとき、袋持ってくるわ」
男性が袋を持ってくる間、僕はその写真を眺めていた。駅名はもうとっくに掠れてしまって読めなくなっている、名も分からない駅。街中ではまず見ることのない狐が写っており、写真の主役となっている。カメラ目線で写る瞳も黒曜石に光り輝いて綺麗だ。また全体的にさっきの写真よりも緑は増えておらず、まだ駅の原型も留めていた。丁度、緑と半分半分ぐらいだろうか、その絶妙な自然と人工物の融和が印象に残った。写真が撮られたのはずっと前だろう。この風景が二度と見られないのかと思ったらそれは非常にもったいない気がした。同じ路線とは知らなかったが、これも何かのご縁、一緒に頂くことにしたのだ。
「ほい!額縁は使うかもしれんから、写真だけやで」
男性は額縁から手慣れた手つきで写真を取りだした。写真自体はまだそれほど劣化しておらず、写真そのもののエネルギーが鮮明となり、僕は圧倒されかけた。しかし、男性が袋と一緒に持ってきた麻模様の布が写真を包んだことにより、そのエネルギーを遮った。
「ありがとうございます。突然来てしまったのに、何から何まですみませんでした」
「気にせんでええ。ただの老人のお節介や、ま、わしも久しぶりにこんなに人と話して楽しかったわ。また暇やったら来てええで!」
「また、写真を見に来ます。お体を大切にしてください」
また歯茎が見えるぐらいに笑いながら、老人は僕を見送った。自転車のかごには頂いた写真が入っており、僕は漕ぎながら写真を部屋のどこに飾ろうかと考えすぎてしまい、そのままお弁当を買うのを忘れてしまった。
数日後、僕は再び踏切屋に来ていた。あの男性にお礼のお菓子と、包んでいた布を返却しようと思ってきたのだ。しかし、あの古びた家の前には黒い喪服姿の人々が並んでいた。僕はどうすればいいか分からなくなり、しばらく立ち尽くしていた。僕の存在に気がついた一人の女性がこちらに駆けよってきて言った
「もしかして、あなた最近ここのおじいちゃんと話した人?」
「は、はい。そうです」
「ここの人、私のおじいちゃんなんだけど、今朝急に倒れてそのまま亡くなったの。あなたの話は聞いたわ。あの難しい人が、すごく楽しく話すことができたって喜んでた。最近おじいちゃんずっと暗いままだった。でも、あなたの話をしていると本当に明るくなっていた。きっと、最後にあなたは思い出をおじいちゃんにくれたのね。ありがとう。もし、良かったらあなたもおじいちゃんに手を合わせてくれないかな?」
僕は踏切屋に入り、男性の遺影に向き合った。その遺影は彼が貰った写真が入っていたものと全く同じ種類だった。僕が貰った写真の額縁はもっと年季が入っていたから、全く同じものではないだろう。けど、遺影に使われていた写真は、あの豪快に笑う人と同じ人とは思えないほど険しい顔になっていた。現実味が無いのは当たり前で僕は何も言えず、ただ手を合わせた。
自転車を押して歩いていると、後ろで何人かで踏切屋の看板を家の中に入れていた。あの男性の思いも、こうして片づけられていくのかと思うと、”寂しかったんやろな”と言った男性の気持ちがわかる気がした。
何年か経ち、僕は電車で初めて来た街で自転車を漕いでいた。初めて通る道ばかりだが、自転車を漕ぐ足が早くなる。僕の住んでいた町と似たような雰囲気の街だった。色んな所を探索したくて町中を駆け回り、そして案の定、また僕は行き止まりに入ってしまった。
「行き止まりか。でも、まぁいいや。来た道を戻ろうか」
こういった街をめぐると僕はどうしてもあの踏切屋を思い出した。あの男性は店の名前の由来をコリを踏んで切り離すと言った。そして、踏切から電車に繋げて写真を撮り続けた。今も家の中にはあの写真が飾られており、今度の新しい額縁は僕が自分で彫ってみた。不格好だけど、なぜが写真と上手く合わさっていたからそのままにしている。
僕は数年たって、踏切屋にはもう一つの意味があるんじゃないかなと思う。それは踏み切る本来の意味。思い切って何かをすること。あの男性を見ているとそれが一番あっていると感じたのだ。
踏切で僕は止まった。あらゆるものが立ち止まる中、カタンコトンカタンコトンと電車が通りすぎ、ツクツクボウシの声が僕の耳を流れていく。僕は水筒に入れていた冷えた麦茶を飲む。それは、それはいい飲みっぷりで、あの男性の豪快な笑い声が聞こえた気がした。
踏切屋