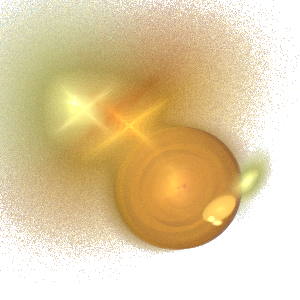雑音
「音がね、聞こえないの……」
月が厚い雲に隠された蒸し暑い晩夏の夜のことでした。コンビニでお菓子を買った帰りに、暗くひっそりとした林の横の道を歩いていると、向こうから歩いてきた人が私の行く手を阻むようにして前に立ちはだかりました。そして小さいながらもよく通る声で、囁くようにそう言ったのです。若い女性の声でしたが、私にはその声を今までに聞いた憶えはありませんでした。
知らない女性に、突然前を立ち塞がられて話し掛けられた――たったそれだけでも私が驚いたのは言うまでもありませんが、私は暗い中にうっすらと見える彼女の姿を見て、その驚きを重ねました。彼女は、何一つとして身に付けていなかったのです。暗闇でも分かるほどの白い肌を露わにして、夜道を歩いていたのです。
いくらじめじめとした暑さが残る夜だからといって、一糸まとわぬ姿で外を出歩くことは、少なくとも私の中の常識では考えられません。それが若い女性なら、尚更のことです。
今まで私が生きてきた中で、道の横から現れた変質者の男性にその汚いものを見せつけられたことはありましたが、女性が変質者となって現れたということは一度もありませんでした。ですから私はその女性が目の前に現れたということに、大変に驚いたのです。
「音が、聞こえない……。聞こえないの」
彼女はそう呟きながら、驚きのあまり立ちすくんでいる私の顔を、まるで細かく観察するかのようにして、左から右から上から下からと覗き込んできました。それは奇妙な踊りのようでもありました。
これは普通ではありません。この女は、気の触れてしまった変質者に違いない、そしてただの変質者じゃない、何をされるか分かったものじゃない。私は全身に恐怖がじわじわと広がっていくのを感じて、走ってその場から逃げ出そうとしました。
ですが、私の身体は言うことを全く聞かなかったのです。何故かは分かりません。金縛りに遭ったときのように、身体中が固まってしまったのです。
誰かに助けを求めようと声を出そうにも、口が開きません。喉も動きません。彼女から顔を背けることもできません。目すら閉じることもできなかったのです。
私にはただ、視界いっぱいにまで大きく映った彼女の白い顔がゆらゆらと揺れているのを、冷たい恐怖に縛られて心臓をばくばくとさせながら黙ってじっと見ていることしか許されませんでした。
「ねえ……、音が聞こえない……。聞こえない……」
彼女の声と顔には、だんだんと鬼気迫る様子が見て取れました。どこか何かに追われて余裕を失っているような気がしたのです。
それを裏付けるように、初めはのろのろとしていた彼女の動きが忙しくなり、息遣いも聞こえるほど荒くなるなど、明らかに確かな焦りに囚われているのが感じられました。
彼女の様子がその異常さを増していることに気付いて、私は次第に命の危機を覚えました。正常な心を失った人間は、行動様式が読めないものです。目の前の彼女は何をするかも予期できません。予期できないものは、同時に危険でもあります。つまり彼女の存在は、危険そのものだったのです。
ですから、突然彼女が私に襲い掛かるとしても全く不思議ではありませんでした。またそうではなく、彼女が自分自身を傷付けるような行為に出ることも有り得るでしょう。
いずれにしても彼女が何をするか分からない状態で、私の心は安堵することなどなかったのです。“運を天に任す”とはよく言いますが、この時ほどその言葉を強く実感したことはありませんでした。
「聞こえない……、聞こえない、聞こえない……」
暗い小道に私と彼女は二人きり、他に誰も通り掛かる気配はありません。周りは林に囲まれており住宅もありませんでしたから、襲われている私に誰かが気が付いてくれることも期待できませんでした。
私は身体が動かせないまま、彼女の踊りを見せつけられていました。あるいは、その踊りは“呪い”だったのかも知れません。彼女が得体の知れない怨みを踊りに乗せて、私を呪ったのです。そうであれば、私が身体を動かせないことも説明が付きます。
しかしその踊りによって私は呪われたのかどうかなど、その時の私にはどうでもいいことでした。
私は動けない。そして目の前の狂った女に、私は捕らえられている。その状況から逃れられなければ、私は助かることができない。動けない私は、このまま彼女に殺されてしまうまで自由にはなれないのかも知れない。
もはや、絶望的でした。彼女は焦りこそ見せていましたが、一向に私から離れる様子もなく、小声で呟きながら、執拗に私の顔を舐め回すように見つめ続けていました。それはいつまでも続くかのように思えました。
しかし突然、彼女は顔をぴたりと止まらせ、辺りに響くほどの大きな叫び声を上げたのです。
「ああ! 雑音が……、雑音が、私から音を……。雑音が、雑音が……!」
すると彼女は、視界の中から崩れるように消えていきました。同時に、動かせなかった私の身体が自由を取り戻したのです。
私は動かせることを確かめるように手の平を閉じたり開いたりしたあと、彼女を見ました。彼女は地面へうつ伏せに倒れて、耳を塞ぎながら言葉にもならない呻き声を上げていました。
そんな彼女の様子に、何故か私は哀れみを抱いたのです。普通ならそんな感情は、今まで自分を恐怖に陥れていた相手に対して抱くことはないはずです。しかし私は呻きながら苦しがる彼女を見て、不可解にも同情の念を覚えていました。
ああ、倒れている彼女が可哀想、手を差し伸べてあげなきゃ。そう思ったときでした。どこからか「にゃあ」と猫の鳴き声のような音が聞こえ、同時に稲妻のように鋭い、閃きにも似た感覚が頭の中を走ったのです。
彼女を助けてはいけない。逃げるには、今しかない。
私ははっと気付いて、正気を取り戻しました。明らかに、私は何かに惑わされていたのです。惑わされて、私を捕らえていた彼女を助けよう、などと考えてしまったのです。
私はコンビニで買ったお菓子の入った袋を持つと、急いで走り出しました。彼女が後ろで何かを言っている声が聞こえましたが、私はそれに構うことはありませんでした。
悪夢のような出来事から解放されて、私は空を見上げました。空を覆っていた黒い雲はいつの間にか晴れて消え、大きな白い満月が明るく輝いていました。
雑音