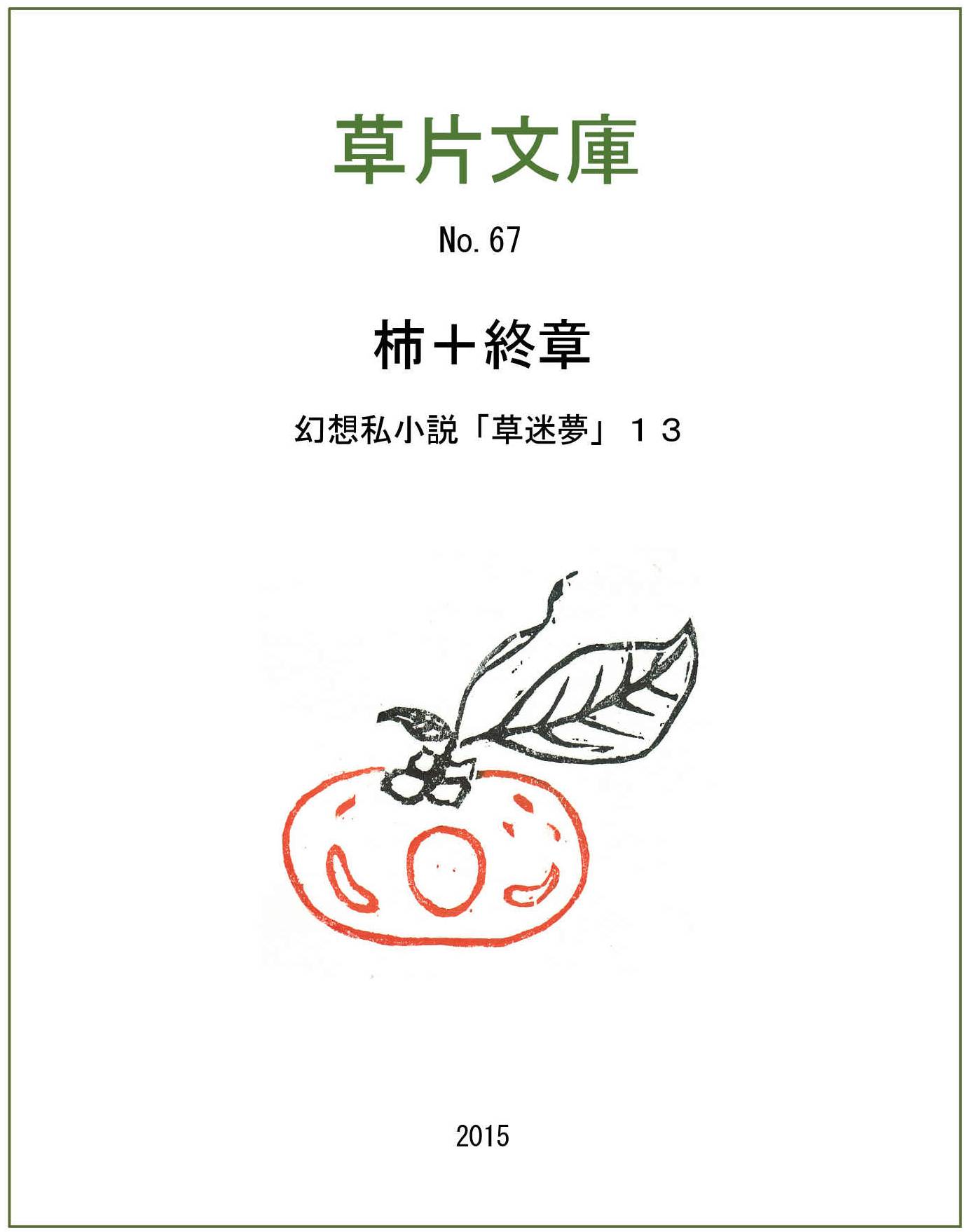
柿ー幻想私小説最終章
蒟蒻の精となった吾をくっつけた蝿のやつ、我家の庭の柿の木の実に止まりおった。
吾はべたべたする蝿の足から何とか離れて、柿の実の上にくっついた。いつもだと人間になっているのにならない。どうしてだろう。あ、柿の実に穴があいた。吾が吸い込まれる。柿の実の中を皮に向かって動いていくと、我が家のベランダが見える。
どうやら吾は柿の精になったようだ。
庭の渋柿はとても古い木だ。この団地が造成された頃のものだろうから、六十年以上は経っているのだろう。なかなか味のある形をしていて、猫たちの格好の遊び場になっていた。
今、真ん中あたりの枝の先にぶらさがっているようだ。両隣には少し黄色くなってきた兄弟がいる。片方は妹で、片方は弟のようだ、名前はあるわけがない。つけろというのなら、柿子と柿男かね。芸がないことだ。
軽子が洗濯物を干しにベランダに出てきた。なんだか知らない子猫がベランダでうろちょろ、ちょろちょろしている。三匹もいる。いつの間にか拾ってきたようだ。みんな真っ黒じゃないか。
洗濯物は自分のものだけのようで、吾のはない。
軽子が猫を呼んでいる。
「うろちゃん、ちょろちゃん、ちょろちょろちゃん」
そのまんまじゃないか。芸がない。どこで拾ってきたのだろう。
美町がベランダに出てきた。泊まりにきているようだ。パジャマのままじゃないか。還暦にもなって若いころのままだ。うちに来ると一日中パジャマだ。おや、森根も顔をだして「うろ、ちょろ、ちょろちょろ、こっちこい」なんて言っている。
あいつも昔のままだ。猫ばっかりかまって、人間と話ができなくなっちまった。どうするんだ。
三匹の子猫がこっちにかけてくる。ベランダから柿の木に移ってきて、大騒ぎしている。
あ、柿を一つおっことした。
「おい、舐めるな」
吾が入っている柿の実を一匹が舐めた。くすぐったい、笑っちまう。
可愛い顔してるじゃないか。黄色い眼の黒猫だ。
もう一度舐めるなと言ったら、聞こえたようで、三匹とも我の入っている柿の実の前にきて枝に座った。
一匹が吾の入っている柿の実を前足でたたいた。いて。
ぷらぷらゆれて、船酔いしそうだ。
軽子がそれを見ていたようで、森根に言った。
「そろそろ柿とってちょうだい、あの猫たち柿が好きなのよ、かじっちゃうといけないから」
「うん」
背が高いので、物をとるときは昔から使われる。
「今年はなににするの」
「そうね、樽柿か、干し柿」
「柿漬けは作らないの」
「どうしよう、いい大根が手にはいらないとね」
柿漬けは渋柿をつぶして、それに大根を漬けたもので、とてもみずみずしくておいしい。
吾は大きな声を上げた。
「樽柿がいい」
渋柿に酒をかけビニール袋に入れておくと、甘くなるのだ。酒に浸ってみたい。
「酒にしろ」
「あれ、お父さんの声みたい」
美町が空の上を見る。カラスが一羽「酒」と叫んでいる。
「では、酒漬けにするかな」
軽子が言っている。
子猫たちは幹をつたって庭に降り、じゃれあっている。
森根が脚立をもってきて柿をとりはじめた。高いところは、それ用のはさみでちょんぎる。吾は森根の手が届くあたりにぶらさがっている。
隣にぶら下がっている柿男と柿子がとられた。森根の手が伸びてきて吾の入っている柿が引っ張られた。やっぱりくすぐったい。笑っちまう。
「なんだか、この柿笑っているみたい」
森根が吾を無造作にザルに放り投げおった。
ザルの中の柿男と柿女にぶつかった。
「すまん、森根のやつ乱暴だ」
謝ったのだが、柿男と柿女は知らん顔だ。渋柿って奴は愛想がない。
ザルが運ばれて、居間の丸テーブルの上にごろごろとだされてしまった。我の入った柿がころがって、テーブルの端から落ちそうになった。
「おっとっと、笑い柿がおっこちる」
といいながら、森根が捕まえて、柿たちの真ん中にいれられた。また、隣に柿男と柿子がいた。
「何、それ笑い柿って」
「採るとき、なんだか笑っているようだったんだ、ここに虫食いがあったので覚えていたんだ」
美町が吾の入っている柿を持ち上げた。
「ほんとだ、間抜けな面」
全く、余計なお世話だ、自分の面を鏡で見ろ。
のっけられたテーブルは結婚当時、軽子が見つけてきたもので、横浜元町の家具である。その頃は家具類を横浜家具に統一していた。あたりを見渡すと、大きなテレビが目に入った。昔からテレビは大きめの新しいものを買うことにしていて、ビクターのブラウン管のものも当時は大きかった。そのあとはパイオニアのプラズマにした。43インチで液晶がはやり始めていたが、プラズマの方が好きだった。その後、8Kがでるまでがまんをした。眼鏡なしでみることのできる立体の映像は魅力だ。
針鼠の置物がテレビの周りにもあふれている。美町が生まれた年に吾はヨーロッパに行ったが、ドイツで見つけたものが初めてだ。そのときには針鼠を集めるというつもりはなかったが、家に持って帰り、じっくり見ていると、かわいらしいく、鼠年であることもあり、集めたくなった。ヨーロッパに行ったら是非針鼠を探して買ってこようと夢を膨らませた。日本に針鼠は住んでおらず、置物などほとんどない頃である。吾が二十七の時であった。それ以来、針鼠の置物を必ず買いもとめ、軽子も、子供たちも外国に行くと針鼠を買ってくる。本箱にいっぱいになり、いろいろなところに溢れでている。
庭園水晶も居間に飾られている。ずい分集めたものだ。最初森根が誕生祝いに買ってくれ、それ以来凝ってしまった。ガーデンクオーツを覗いていると、未知の庭、
未知の海の底、他の星を見ているようで楽しい。
「今年はたくさん採れたよ」
森根の声に軽子が二階から降りてきた。
「ほんとね、干し柿もつくりましょう」
大きなビニール袋が用意され、日本酒がその中に振りかけられた。軽子の手が柿を持ってへたのところに酒をぬると、袋の中に入れていく。吾もそうしてもらいたいね。
軽子、吾をなににしてくれるのかね、樽柿にしてくれよ。
ホワイトリカーをお尻のあたりにたっぷり塗られて、ビニール袋の中で酒のサウナだ。これで甘くなる。想像するだけでも嬉しい。
柿子は樽柿に持っていかれた。なに、柿男も樽柿か。
俺はなんだ、選ばれない。なぜだ。軽子が言っている。
「樽柿にするのは元気なのにしましょう、あとは干すのよ」
なに、干し柿。俺の年を知っているのか、八十八歳の干し柿かよ。おい軽子。
バカ、皮を剥くな。八十七歳の軽子の手が包丁を動かして、皮を剥いていきやがる。とうとう皮をむかれた。すっぱだかだ。
「美町はどうした、ほら助けろ」
「この柿よれよれね、干してもだめかもね」
なんてことを言いやがるんだ、このすんだらぼったらひとりもん。
森根のやつが、柿のへたに紐をくくりやがった。紐の片側にもう一つの柿を結ぶ。とうとうベランダに吊るされちまった。相手の柿がこっちを見て笑ってら。やっぱり爺さんだ。つまんねえ。
周りを見ると、干し柿に選ばれた柿が整然と竿に掛かっている。
たった八つか。後は樽柿か、なんということだ。運が悪いな吾は。軽子がいじめているんじゃないか。
庭の眺めはいいが、秋の日差しといったって、熱いったらありゃしない。
ほら、蠅がきた。吾を運んできたやつではなさそうだ。
止まって、俺をなめてやがる。目がぎょろっとして、分厚い口を突き出して、汚い顔だね。映画の蠅男の方がまだましだ。
「やい、糞ばえ、舐めるな」
「うるさい、おまんまはしゃべるな」
蠅には聞こえるらしい。
「きれいな干し柿になるんだから、おまえの唾などばい菌だ、まずくなる」
「ばかいえ、蠅がたかってやっと一人前の干し柿だぞ」
「いいから、どっかいけ」
あ、糞をしやがった。ひでえ蠅だ。表面に黒い点ができちまうじゃないか。ああ、熱い。
じわじわと水分がなくなる。からだがねっとりしてくる。あまったるくなる。三日たった。天気が続くのはいいが、熱くてたまらん、拷問だ。
と思っていたら、雨がぽつりときた。
その後は、ずーっと雨だ。蠅もこない。
体がなんだかぐずっている。喘息になりそうだ。湿気が高くて、気圧が低いとすぐ喘息だ。
軽子がベランダにでてきた。
「あら、干し柿が黴てる」
そうだろ、緑色の斑点がついているのを知っているんだ。なんとかしろ。
軽子が霧吹きを持ってきて、我のはいっている柿に液体を吹きかけた。
お、アルコールだ。
しみるねえ、いい匂いだ。飲みたいねえ。
青かびが死んでいく。いい気持ちだ。だが、風がつよいね、おや、どんどん強くなるじゃないか。何だ、台風じゃないか。すごいね、遅い台風だね。
と言っていると、風が急にやんだ。台風の目に入ったようだ。朝になりゃあいい天気のはずだ。
そう思っていると、朝日がさしてきた。
また、小蠅がきた。
ところが、吾がはいっている柿にはたからない。隣の柿にたかっている小蠅に言ってやった。
「やい、小蠅、怖くてこれないんだろ」
小蠅は赤い目をこっちに向けた。
「黴が生えた奴なんて食えるか」
と、のたまわった。
「アルコールで消毒してあるんだ」
そう言ってやると。
「そりゃまずくなる、自然がいいんだ」
いいやがった。
しゃくに障る奴だ。
こうして、また、毎日秋晴れが続いた。
自分が入った柿はしわしわになっていく。
森根がベランダにでてきた。
「だいぶ干されたよ」
下から軽子の声が聞こえる。
「おいしそうなのもってらっしゃい」
森根の手がつるしてある干し柿を竿からはずした。だけど、吾の入っている柿はおいていっちまった。相棒とともにぶらーんとぶらさがったままだ。
「かあさん、一つとても汚れてたから、吊るしたままにした」
「いつか食べればいいでしょう」
それからは長かった。全く忘れられていた。秋も深まってきた。食べ物がなくなったと見えて、蠅がよくたかるようになった。
すると、守宮がやってきた。吾がはいっている柿にくる蠅をねらって、いくつもの守宮がきて、蠅をなめとっていく。いっぺんに八匹の守宮がきて、大きな金蝿をねらって、飛びあがってきた。なんと、大きな金蝿をとらえたのは、今年生まれた若い守宮だった。
年寄り守宮は「若いもんの目はいいね、年とるとだめだよ」とぼやいている。
「人間の世界と同じだね」
吾が言うと、守宮たちがそれをききつけて、こんなことを言った。
「聞いたことがある声だぜ」
すると、他の守宮が「そうだな、ここの主人に似てるな」と言いおった。
「あの、偏屈男か」
「ああ、マニアックな奴だが、だけど、おいらたちには親切だったじゃないか」
「そうだったな、あいつは、動物にはもてるが、人間にはもてそうもなかったな」
「そうだそうだ、あいつの奥さんなんか苦労してたろ」
「ああ、子供たちも苦労してたよ」
「あの主人、ぜんぜん成長しなかったものな」
「そんな男もいるさ、だから動物にもてたのさ」
八匹の守宮がうなずいている。
よけいなお世話だ。
やがて蝿もこなくなるほど寒くなった。軽子達は吾を全く食べる気がないようである。ベランダにでてきても、無視してやがる。いや忘れているんだ。目も悪くなっているんだ。
木枯らしが吹き始めた。寒いじゃないか。
もう吾がはいっている柿は黒く小さく縮んで、柿にすら見えない。汚い黒い蝿の糞の塊だ。
雪が降ってきた。凍っちまったじゃないか。
新しい柿の実が固まったならシャーベットだが、この真っ黒の干し柿が凍ってもなんと言ったらいいかわからないものだ。柿糞シャーベットだ。
クリスマスらしいな。下でケーキの話をしている。
あっと言う間に正月だ、やだねえ、それにしても寒いねえ。いつまで我慢すりゃいいんだ。
眠くなった。冬眠だ。
どのくらいたったかわからないが、美町の声で目が覚めた。
「お父さんの庭の浦島草が目をだしたよ、孔雀羊歯もきれい、寒葵の花咲いている」
そう、結構珍しい浦島草があるんだ。真っ赤なやつや真っ黒なのを園芸屋から買った。結構高かったんだ。
「手入れしなくても元気ね」
軽子の声である。
「寒葵の写真撮ったよ」
森根の声だ。相変わらずカメラをいじくっているのか。
「寒葵、お父さんずいぶん集めたね」
「天南星も集めたわね」
軽子が言っている。
「今年も、あの白天南章咲くでしょう、すーっとしてきれいね、あの白い天南章」
「みんなお父さんのお気に入りだったわよね」
美町が言っている。
「赤や黒の蝮草も咲きそう」
森根がカメラを蝮草に向けている。
それにしても、どのくらい寝ていたのだろうか。もう春のようだ。
森根の手が多摩の寒葵の葉っぱをよけた。そこには、みたこともないような、大きな花が咲いていた。しかも朱色である。
「これ、珍しいね」
美町がのぞき込んでいる。
「もしかすると、庭のどこかの寒葵と混じったのかもね」
森根が他の寒葵を指さした。
鬼寒葵や外国のキウイ葵など地植えにしたものが立派に茂っている。
「おやじが作った新種かもね」
それをきいたとたん、吾は干し柿から落っこち、多摩の寒葵の朱色の花の真ん中に吸い込まれた。吾は寒葵の精になったようだ。
「あ、あそこに干し柿二つ吊るしっぱなしだ」
森根の声が聞こえた。
「でも、真っ黒で喰えないね」
近くにキセル貝がよってきた。吾がはいっている寒葵の花の真ん中に潜り込んだ。
なにしに来たのだろう
思っていることがわかったようだ。
「どうして入ったんだろうな、わかんないね、こう、運命っていうか、自然と引かれて、中に入っちまった。自然ってこういうもんなんだ」
キセル貝は哲学者だ。吾の考えていることがわかったようだ。
「哲学者ってなんだ、これが哲学なら、人間以外はみんな哲学者だ」
「その通りであろう」
寒葵の精になった吾はキセル貝の殻にくっついた。
キセル貝はのろのろと、寒葵の花から離れ、塀の石の脇にやってきた。
そのとたん、鶯がおりてきて、キセル貝をくわえると、とびあがった。
どこにいくのだろう。吾は寒葵の精になって運ばれている。空から見る我が家の屋根はだいぶ傷んできた。そろそろ塗らなきゃダメだよ。
夢はまだ覚めない。
終章-浦島草
南平の我が家で、吾は寒葵の精になり、キセル貝にとりついた。鶯がキセル貝をくわえ、こんな遠くに飛んできた。ここでぽとりと落としたのである。
厚木の南毛利の雑木林であった。夢が続いている。夢は自由でいい、どこにでもいけるし、なんでも出来る。死んだ猫たちにも会える。こんなに長い夢は始めてみた。
夢というやつはほとんど見なかったが、時折あった。しかし、人に話すほど立派なものではない。軽子は夢を良く見る。いろんな飛び方で空を楽しんでいるそうな。ぴょおおん、ぴょおおんと孤を描くように飛び跳ねたり、手足をばたばたさせて空中を遊泳したり、すーうううとすべるように飛んでいったり。羨ましいことである。
頭に手をやる。寒葵の精から抜け出て、人に戻っている。不可思議なことだ。つるりと光り輝いてしまった吾の頭の毛が黒々とふさふさとしている。夢とはよいものじゃ。空を見れば入道雲がわいている。八月八日の誕生日、八十八歳のはずが、どうも三十ちょっと手前のようであるな。
二歳のときになぜか喘息になり、子供の時分からからだと折り合うのに苦労してきたが、三十手前の頃、よい薬を処方され、発作を起こす怖さからのがれることができた。とても元気が出てきた時分だ。さらに還暦の頃すばらしい予防薬ができた。
それにしても暑い。せみの声に覆いつくされ、夏の太陽ともみあっているような蒸し熱い日である。八月八日は立秋だ。小高い丘の麓を覆っている雑木林は黒っぽく熱そうに静まりかえっている。その前で吾は何をしようとしているのだろう。自分で自分を眺めている。
薄暗い林の中をのぞき見る。林の中は背丈の高い下草で被われており、道らしきものは見当たらない。子供の頃よく探検に来た南毛利の丘の麓である。
そんなときだ。林の中からぬうっと吾を見上げたものがいる。
間抜け面などと、思ったこと自体が失礼であったのだろうと思うが、しかたがない。
汝は何だ。声を出さずに問うが、人ではないことをすでに把握していたことになる。
「けけ」
そやつは鳴いた、いや言った。
穴熊のやつだ。またでてきた。穴熊が狢といわれていたんだ。要するに、狢のやつ、また吾にいたずらするつもりか。狢はグニャグニャ這うように、羊歯の中をすすんでいく。
狢の手足が動いていない。ただすべっていく。やはり妖怪か。どうもすでにとらわれているようだ。吾は羊歯を掻き分け狢の後を追っている。無責任な言い方だが仕方がない。
次第に自分の意思がはっきりとしてきて、狢の行くほうに行きたいと思うようになってきた。いまでは、行き着くところへの興味が吾を突き動かし、早足にしている。おおなんと、ひんやりしてきたことか。
奥に行くにしたがって、羊歯が大きくなって、自分の背丈ほどにもなってきた。もしやもすると、吾が小さくなってきたのだろうか。や、そうじゃない。周りの木の太さはさほど変わりがないところを見ると、羊歯そのものが大きくなっていることは確かだ。いや羊歯ばかりではない。キクやセリ科と思われる名も知らない雑草たちも私の頭を覆うほど成長している。
とうとう、草の中をすべっていった狢を見失った。
足元からはぼんやりと乳色の霞が漂ってきた。振り向くと、さほど歩いたと思われないのに、入って来た林への入口が霞んで見える。そういえば生き物たちの声がしなくてあまりにも静かだ。林の中を歩けば必ず往生する蜘蛛の巣がない。
見上げると、木々の間から見ることの出来る空は青くない、どちらかというと紫にどんよりとしている。日の光が腐ってしまったようだ。
さあ歩かなければ。
全く疲れていない。夢の中でそんなこと心配することもあるまい。
どのくらい歩いたか分からないが、そそりたつ一本のブナの木に行き当たった。回りの木々よりひと回り大きく、根はごつごつと地上にはい出して生きもののようにうねっている。ブナの木を見上げると枝の上に狢が腰掛け見下ろしている。
「けけ」
鳴いた。
声をかけるべきか、どうすべきか、自分としては優柔不断だ。
「向こうだよ」
狢が言ったような気がした。
ブナの木を迂回してさらに林の中に進むと。急に空気が土臭くなった。羊歯におおわれていた下草が大きな笠をゆらんゆらんと揺する浦島草の群落になった。どの株にも花がついている。
小学生のころ南毛利で浦島草を採って庭に植えた。この花に出会ったことから、奇妙なもの、気味の悪いものに興味を持ち、みながきれいと言うものに魅力を感じなくなったのだ。「浦島草綺譚」という幻想小説を二十四、五のときに書いて、七十のときに、浦島草の短編を数篇加えて、自費出版した。
それにしても、ここの浦島草はとても背が高く大きい。花が目の高さにまでくるものまである。濃紫色の壷のような花の中から長い一本の蔓のようなひげが出ており、そのひげがやぶれた笠のような葉に絡みつきふらふらと揺れ動く様は、笠をさしてこの世に迷いでたものに似ている。子供の頃はお化けの花だと騒いだものである。
歩いていくと、吾の通った後では浦島草の花が折れて、下を向いてしまっている。頚骨を折った首の様だ。この花の根には大きな薯が出来ているはずである。花の様子から毒があると思い込んでいたことがあったが、大した毒ではなく、薬としても用いられているようだ。
随分大きな群落である。どこまで続くのだろうか。足が痛くならないのでともかく歩いていく。夢よ覚めるな。
前方の木立の陰に鳥居らしき物が見えて来た。歩を早めて木々の間を抜けると、古い社のある苔におおわれた広場にでた。自分で書いた小説のストーリーとちょっと似ている。それでこの夢を見ているのだろうか。浦島草神社と鳥居に書いてある。
神社入り口に小さな浦島草が生えている。いや、姫浦島草のようだ。見ると神社境内一面に姫浦島草が咲き乱れている。
姫浦島草はかわいらしい女の子のようだ。ちょこちょこと歩き出しそうだ。そういえばミミズクにも似ている。
そう思ってみていると、一つの姫浦島草が靄につつまれ、紫色のワンピースを着た丸顔をしたおかっぱ頭の女児になった。大きなかわいらしい黒い目で私を見ている。少女が微笑んだ。
他の姫浦島草がまた女の子になった。やっぱりおかっぱ頭の女の子だ。次から次へと、姫浦島草はおかっぱの女の子にかわり、境内一面に女の子が立って吾を見ている。
女の子の中から狢が顔をだした。
「きょきょ」と鳴いた。
少女たちが一斉に吾に向かって言った。
「いきましょ」
姫浦島草の女の子たちは歩き出した。吾も女の子に囲まれて歩いた。
浦島草神社にくると、女の子たちは社の扉を開けた。
女の子たちの可愛い手が吾の背を押した。吾は社の中に押し込まれ、社の扉が閉められた。
「さよなら」
女の子たちは浦島草神社を取り囲むと、また姫浦島草になって揺れている。
浦島草神社の中では薄明かりの中に真っ白な浦島草がいた。ご神体だ。私は白い浦島草に拍手をうった。
白い浦島草は白いべろをべろーんと伸ばすと、吾のおでこにぐりぐりと穴を開けた。
吾の頭の中からにょきにょきと浦島草が芽吹き、大きな浦島草となった。みるみるうちに紅い花が咲いた。白い浦島草が白いべろを紅い浦島草になった吾に絡みつけてきた。
紅い浦島草はべろを神社の窓からべろーんと伸ばした。吾は浦島草の精となり、べろの先にくっついて浦島草神社から外に出た。
姫浦島草の中で油を売っていた狢の尾っぽに赤い浦島草のべろが触れた。
「きょきょ」と狢が振り返った。
その時、浦島草の精となった吾は狢のしっぽに取り付いた。
びっくりした狢は浦島草の森の中を駆けずり回った。
ふわっと眩暈がする。狢は尾っぽを振り回し、吾を空中に弾き飛ばした。
浦島草の精となった吾は林の中でふらふらと彷徨った。
アナグマが歩いている。吾はやつの鼻先に浮かんだ。
「おいアナグマ、いや狢、吾はどこへいくんだ」
「けけー」
狢がつぶらな目で吾をみると、わかるだろうという顔をした。
夢が覚めないねえ。いやまてよ、これは覚めない夢なのか、死んだのか。猫の玉も言ってたじゃないか、これからいつでも会えるって。楽しみだねえ。浦島草の次にはなにの精になるのだろうね。
「草片に決まっているだろ、あんたの大好きな」
狢はこちらを振り返りもせず言った。
そうか、茸になるのか、この夢は覚めないでほしいねえ。
狢がけけと笑って手を合わせた。
「覚めないよ、ご愁傷さま」
幻想私小説 完
柿ー幻想私小説最終章
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


