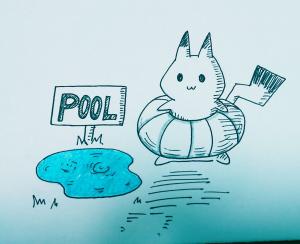岩躑躅
記憶

温かな雨が頬を濡らす感覚に、薄目を開ける。しかし、頭上に見えるのは雨雲ではなく目元を赤く腫らした若い女の顔だった。眼前の光景に戸惑う自分に対し、女は赤い目を丸くして口元を両手で覆った。そのまま自分が上体を起こすと、女は驚きを隠せないまま側から後ずさりし、声をかけようとした瞬間あわてて部屋の外へと走り出て行ってしまった。随分と長く眠っていたような気がする。十畳ほどの部屋には、四方の隅に自分の横たわっていた寝台と、文机と、小さな棚が置かれるのみで、剥き出しの壁を頭上のランプが煌々と照らしていた。眠る前のことが僅かも思い出されない。今突然に世界が始まり、自分が生まれたかのような唐突さがある。唯一明らかなのは、向かいの障子戸を透かして差し込む光が認められないことから今が昼間でないことぐらいであった。
(それに、あの女はいったい…)
どこか儚げな可憐な花が頭に思い浮かんだ。伸びて鬱陶しい髪をかき上げようとし、自分の節くれだった指と骨に皮を纏ったような腕を見て愕然とした。同時に異様な寒気が全身を駆け巡り、足が泥に沈み込むような言い知れぬ不安に襲われる。恐る恐る全身をまさぐって、次に自分の顔を確かめたくなった。鏡か水の張った盆でもないかと顔を映すものを探すうちに、ふと自分の名前すら思い出せないことに気づいた。気を動転させていても不思議ではないのだが、いまだ夢から覚めないのか自我がはっきりしない。
寝台の上でもぞもぞと動いていると、遠くから何者かが走ってくる音が聞こえ、襖が勢いよく開いた。見知らぬ男が息を切らしていた。どたどたとした足音から想像するより小柄な男だ。かなり白髪の混じる頭に対して、小さな眼は油断ならぬ鋭い光を放っている。呼吸の乱れからして余程あわてて走って来たのだろう。男の後ろには目を赤く腫らしたままの女が立っていた。立ち尽くしているといった方が適当かもしれない。男はそのまま数歩駆け寄ってきて片膝をつき、震えの混じる声で言った。
「…よくぞ戻られました、殿。」
(待て、俺はそのように呼ばれる身分なのか)
居心地の悪さを感じながら、初対面の相手にどう返すべきか迷った。しかし、どう答えても男の鋭い眼光の前では見透かされると思い、正直に話すことにした。
「私はいったいどれ程の間眠っていたのだ。」
「昨日で丁度三年、ですから今夜は三年と一日となります。しかし、本当に、よくぞご無事で…」
今度はこちらが驚く番だった。三年、一千日近くも自分は眠って、いや生死を彷徨っていたのか。次にどうやって三年もの間眠ったまま生きてこられたのかを知りたくなったが、死人同然の自分がいかなる処置を受けていたのか尋ねるのも愉快なものではないだろう。ただ少し俯いて、
「すまない、一つ言わなければならないのが、どうやらすっかり前後のことを忘れてしまったようなのだ。」
と呟くだけにした。
(あの方がお目覚めになったのはこの上なく喜ばしいことではあるけれど、まさかあんな状態だとは)
妙はぴんと水の張った釣瓶を井戸の淵に下ろし、小さく息を吐(つ)いた。母屋の方を見やる。屋根の上には朝の、冷たく澄み切った空が広がっていた。妙は歩きながらここ数日、つまり香登が目覚めてからのことを思い出していた。本当は記憶えを失っていることが気になっているわけではないと分かっていた。二度と目覚めぬかもしれないと、覚悟もあるつもりだったのだ。それより心の中で引っかかっているのは、自分や弥七の口から自らの身の上を説明された後の香登の歪んだ表情だった。その後も生気の感じられない香登の様子を目にする度に、胸の奥が透明の茨に締めつけられるのに耐え、行き場のない感情の奔流を堰き止めなければならなかった。幼いころから慕い、叶わぬ淡い期待を振り払おうとした義兄はいまや遠くに霞んでしまったのだ。
(それでも今は、姉上のためにもお力にならなくては)
廊下を渡っていくと、庭の方から何かを落としたような物音が聞こえた。縁側に出てみると地面に延びていた肢体がゆっくりと起き上がるところだった。
革の鞘から分厚い刀身を抜き出す。おそらく自分とともにしばらく眠っていたであろう鋼の塊は鈍い光を放って目を覚ました。
(重いな)
軽く一振りしてみて思った。それにしても奇妙な形だ。肉厚の刀身と柄と十字に交差した鍔、さらに真っすぐに伸びる両刃を持つ刀は珍しいだろう。
(少なくとも目を覚ましてから俺はそんな刀を他に見たことがない。)
などと呟いてみても、心の底に蟠る渣滓が取り除かれることはない。
男は弥七、女の方は妙。名を訊くのは勇気の要る仕事だった。混乱する自分に対し、二人は喜んだのも束の間、ひどく心を痛めるであろうことは想像するに難しくなかったからだ。それから実にたくさんの昔話を聞いた。それらは弥七の口からも、妙の口からも同じ程度語られた。しかし、語り口や表情からは、このことに対して二人の間で微妙な感情の違いが存在するのが伝わってきた。それが立場に因るものなのか、はたまた別の理由故なのかを判断するにはあまりにも自分は無知だったが。
それから、ある部屋の前に連れていかれた。妙が襖戸を開けると、中に様々な武具が並べられているのが目に入った。
「私はやはり武人だったようだな。」
「はい、先ほど申し上げた通り、三年前のその日まで明科(あかしな)様、木次様とともに日ノ本中を駆け巡っていらっしゃったのです。」
遠い昔、自分と二人の戦友は長い内乱の後、疲弊した国土に上陸した兵寇を押し戻そうと東へ西へ奔走していたのだ。部屋の中へと入る。半歩後ろに弥七が立ち、さらに後ろで妙が灯りつける。武具に施された装飾が淡くぼうっと拡がる光を反射して煌めいた。中でも金色の花々を咲き乱れさせる壺が、武具たちの隅に佇んでいるのに目を奪われた。床の間に飾るにはやや小ぶりで、昼間ここを見渡しても特に目に留まることはないだろう代物だ。しかし、惜しいことに近づいてみると、壺には激しく割れた後で修復したような痛々しい罅が何筋も走っていた。
部屋の中央にはおそらくもう一人の自分が身に着けていたであろう刀と鎧が鎮座している。その隣には一対の刀。その持ち主は三年前ともに戦い、斃れた二人の友だった。
「お二方とも、刀を持ち帰ることしかできませんでした。」
妙の声は震えていて、あの涙に濡れた赤い目を暗闇で想像した。
三年前のその日、敵の策謀に足を取られて一気に形勢が逆転し、味方の多くが命を落とし、多くが散り散りになり、わずかに残った者がこの辺境の島に逃れたのだった。
(俺は何もかも知らないんだ。)
目の前の、顔も思い出せない死者と背後の弥七と妙の重苦しい気配に押しつぶされそうだった。
自分のかつての姿を断片的にでも視認してからでも、記憶は呼び戻されることはなかったし、すぐにもう一人の自分を受け入れることは出来なかった。ただ一つ部屋を出た後重い足取りで理解したのは、これから何かとてつもなく大きな荷を背負わなければならないということだった。
それから数日の間、正直なところ誰とも顔を会わせる気分にはなれなかった。それでも部屋の内に籠もっていれば必ず誰かしらが顔を出しに来る。
それは妙や弥七のときもあれば他の小間使いのときもあった、二人はあれから何事もなかったように、突き放すようでも腫れ物に触るようでもなく接していたが、それは逆に気分を落ち着かなくさせるのだ。二人の心は読めなかった。いや、あれこれ想像することはできた。しかし想像はいつも良くない方向へと導かれ、今の自分の情けなさに煩悶し、自らの生を否定する結果に辿りつくのは分かっていた。臆病な想像は心中でぐるぐると螺旋を描いていた。
(いっそまた眠りに落ちて全て忘れ去ってしまえたら良いものだが。もしくはそのまま今度は目を覚まさずに…)
そんなことは実際的にも、また自分の勇気の不足からもできないだろう。仮にそれらを無視したとしても二人の顔が頭に浮かんだら誰が安心して眠れようか。
囚われ人

骨ばった白い手が柄を握りこむ。奇妙な刀は重心の位置がやや柄の方へ寄っており、重い刀身でもなんとか扱えそうな代物に見えた。一つ息を吸い込むと微かに甘い芳香が混じっている。前に倒れそうなくらいで自然に足が出て、強く一歩目を蹴った。敵の姿は見えない。しかし数歩先に確かに敵は居て、それを斬るのだ。自分にとってはほとんど完璧な挙動だったが、長く己の足で地を踏みしめなかった代償は大きかった。空を切った刀は鈍い音をたてて地面に落ち、恥ずかしい具合に尻もちをつくことになった。周囲に人の目がなかったのは幸いか。
(体の弱り方を甘く見ていたみたいだな。)
「本当にお身体は大丈夫なのですか。」
「ああ、まったく問題ない。」
広い縁側に腰を下ろし、熱い茶を啜った。
「躓くところを見られていないのは良かったが、体はすっかり鈍ってしまったみたいだな。」
顔を綻ばせて言うと、
「三年も外をお歩きになっていないのですから。無理はよくありませんよ。」
と妙の健康的な血色の口元に微小が浮かんだ。ここ数日そういう表情を見ていなかったから、まじまじと顔を覗き込んでしまうところだった。髪は大人らしく結ってそれが馴染んでいるのに、どこか幼い雰囲気を持っている。さらに最近はそこに微かな憂鬱が混じり、自分はそれに触れるのを恐れていた。それでも今日の彼女の柔らかい雰囲気に接して、三年前の自分でしかないもう一人の自分はかつて彼女にとってどのような存在だったのかが気になった。
「三年前の私はどんな人物だったんだ。」
妙の口が開く前に言葉を付け加えた。
「妙にはどう見えていたのか、という意味だぞ。」
妙は吐き出しかけていた言葉を飲み込み、やや間をおいて
「わたしにとっては…兄上のように感じていました。」
と小さく答えてそのまま顔を横へ逸らした。目線を追うと、縁側の端で風変わりな刀が板戸に立て掛けられていた。そこに立て掛けるなら普通の太刀の方が良いと思った。直線的で幾何学的な輪郭は周りから浮いているように見えるのだ。
「いえ、実際に血は繋がっていないものの義兄上でした。」
「義兄上?」
思わず口にしてしまってから後悔した。
「姉上もあのとき命を落としたのです。」
そう言ってすぐさま妙は自分の方へ向き直った。吸い込まれそうな深い色の瞳に貧弱な男の姿が映っている。
「今思い出せなくとも、これまで義兄上は多くの、この國の民を救われました。そしてそれは私も同じです。…だからこそ、これからは姉上のためにもお力になりたいのです。」
妙の目は過去を見つめているのではなかった。そこには揺るぎない現在が映っているのだった。
(妙は思っていたより強い。だが俺はかつての頼もしい彼女の兄、香登ではない。)
妙の姉の話は自分の肩の荷を何倍にも重くした。自分が過去になくしてきたものを数え上げるのはひどい苦痛だった。その痛みは肉が切り裂かれるようなものというより、身体の隅々まで回った毒でじわじわと蝕まれるのに近い。しかし今の自分が鼠なら毒蛇より獅子(ライオン)の餌食となるのを選ぶだろう。何も知らずに目覚めた自分は悼むのを許されるのか分からなかった。
妙がその場を離れてもしばらく座ったままでいた。ふと見上げると澄み切った空に、胡麻粒のような鳥が十数羽、魚鱗の陣形を組んで横切るのが見えた。鳥たちが何処へ向かうのかが気になり、それを見届けたくなった。
次の瞬間には立ち上がって走り出していた。何度も躓きそうになりながら門を出る。背中に誰かの声が掛けられたようだが、耳には入らず、頭上の鳥雲をひたすら追いかけ続けた。すぐに息が上がって足がいうことを聞かなくなるが憑りつかれたかのように空を見上げて前へ進もうとする。急勾配の坂を幾つか上り下りして林の中に突っ込む。そこを抜けると一気に視界が開けた。それだけではなく、地面は数歩先で途切れていた。潮風が頬を撫でる。鳥の群れは早くも地平に向かって消えていった。足を踏み外すぎりぎりまで進んで下を覗くと、まさに断崖絶壁の形容がふさわしい様相だった。足元では割れてしぶきを上げる波がこの瞬間にも崖下の岩塊を削っているところであった。翼の無い自分は地を歩かなくては進めないというのに、切り立った崖は無情だった。自分を突き動かした熱が徐々に冷めて、へなへなと座り込む。海の匂いに混じる芳香に気づいて辺りを見回すと、そこかしこに躑躅の花が咲いていた。鼻腔に流れ込んでくる甘い香気は先ほどより濃密だった。多くを忘れていたが、なぜかはっきりと覚えていることも少なくなかった。今もその淡紅の花弁を躑躅のそれだとすぐにわかったのもその一つと言えた。
結局、何からも流れることなどできないのだ。自分はこの島に根を張り、この奇跡的に賜った生を受け入れることしかできないのだと、ぼんやりと頭の片隅で悟った。まだ疼痛は消えなかったが、海に背を向け躑躅の花の咲き乱れる中をゆっくりと引き返した。
帰還

人はなかなか変われないものだ。一度思い切って事を進めても、後で心の内に迷いが出てきて、気が付けば決意が固まるのと揺らぐのが繰り返されて蹣跚としているのは珍しくない。躑躅の濃厚な香気を肺に満たした後も、あの夜が来るまで何度も自分の芯が揺らぐのを感じたのだ。それでも、折れることはなかったのは単なる幸運ではなかろう。
あの夜、暗闇のなかで一人置く奥歯を噛み締めて震えこらえようとしていたのを覚えている。鼓膜には敵の蛮声と傷つき倒れた者の呻きがこびりつき、鼻は血の匂いをはっきりと憶えていた。奴らはとうとうこの島まで辿り着いたのだった。しかし、自分にとっては三年前死闘を繰り広げた相手と刀を交えるのは初めてだった。震えが収まったとき、両手の拳は爪が掌に食い込むくらい握りしめられていた。戦うと決めたのは自分だったが、現に敵を前に離れてここに隠れた自分がいるのだ。落ち着いたところで灯りを点すと、目の前には久々に見るあの武具宝飾品があった。
戦うと決めたとき、はじめ弥七と妙は身を案じて止めようとした。それでもその意志が固いことを知ると無理はしなかった。むしろ、ふたりの表情が少し明るくなったようでもあった。それは安堵するようであり、また懐旧に顔を綻ばせるようにも見える。その様子に、目覚めてから今に至るまで、何か大きな誤解をしていたのではないかと疑うようになった。同時に彼らの本心を疑って何も知らずに目覚めた自分を疎んじているという可能性をわずかでも想像してしまったことを恥じたのだ。
眼前の二振りの刀は何も語らない。ただ静かにそこに在るだけで、決して遠い日々を思い出させてくれるわけではないが、無言でこちらを責め立てることもない。ただただ沈黙を続けるのだ。屋敷の中、この部屋だけは夜の静寂に包まれている。温かい雨の降る夜の、冷たい静けさに似ていた。
足元の重い刀を持ち上げる。
(ただ逃げるならこんな重い刀は置いていくだろう。戦い続ける理由に、今右手に握られた刀以外に何が要るというのだ。)
弥七と妙、そのたわずかな手勢はじりじりと追い込まれていた。弥七は唇を噛んだ。敵の数は多くはなかったが、少数精鋭というところなのか、香登に剣術の腕を認められ刃を深紅に染め上げてきた弥七にとっても手練ればかりという感覚であった。
(しかし、殿と逸れるとは何という不覚なのだ!)
弥七は早まる心を抑え、周囲を警戒しつつ屋敷へと歩を進めた。一旦退いて態勢を立て直すのだ。地の利はこちらにある。弥七の後ろを数人の息を押し殺した気配が続く。こちらも同様に戦場での立ち回りを心得ている者たちであり、物音はたてず、風が移動するのみである。弥七は三年前を思い出していた。あの夜も、こちらは分散させられ、その後合流したときには香登は眠りに落ちていた。側には一人、寸分違わず急所を貫かれた屍が転がっていた。気づけば眠ったままの香登を負って駆け続けていた。首元に感じる息だけが弥七の平静を保つのに貢献した。胸騒ぎが収まらない。今夜はあの夜に似すぎている。妙もおそらく同じ心持なのだろう。
弥七は足を止めて刀を構えなおした。またしても不覚というよりは、敵が一枚上手だったということか。どちらにせよ、弥七たちは透明な網に捕らえられた魚だった。姿は見えなくとも、各方位木々の奥にはこちらへ狩人の獰猛な牙が向けられているのだ。弥七が覚悟を決めたとき、前方の木々が重なった向こうで何かが一瞬光った。
それはまるで白い風が刃の隙間を通り抜けていくようだった。その風は鎧を切り裂き、肉を貫いた。香登はほとんど鎧を身に着けず、白い袖と月明かりに照らされた白皙の長身はしなやかに舞う。十字の鍔の刀は次々と斬撃を寄せ付けぬ厚い鎖の襦袢を破っていた。今こそと弥七たちも一瞬の敵の怯みを見逃すことはなかった。香登を視界の端に捉えて剣を振るいながら、弥七は疲れが消えうせ、力がいくらでも漲るのを感じた。
(殿は今度こそ戻られたのだ。)
暗殺者のほとんどを片付けたが、退くものを深追いすることはなかった。それは、この島、また香登のあるがままの姿を彼らの主に知らせるためであったが、島から生きて戻った者が一人もいない方が与える衝撃は大きくなるか。弥七が武器を納めると、数歩先でこちらに背を向けている香登が口を開いた。
「残念ながら三年前のことはまだ判然としないが、俺は俺として生きようと思う。」
そこで振り返ると、二人に目が合った。
「これからも、お供いたします。」
弥七はすぐさま力強い口調で言ったが、なかなか顔を上げようとしなかった。妙は妙でこみ上げてくるものを必死におさえようとしている様子で、
(また泣かれても困るな)
と思わず頬が緩んだ。
甘い香りが鼻をくすぐって、冬枯れの木々の間に躑躅の花が顔を出しているのに気付いた。長い冬もきっともうじき終わりを迎えるだろう。
岩躑躅