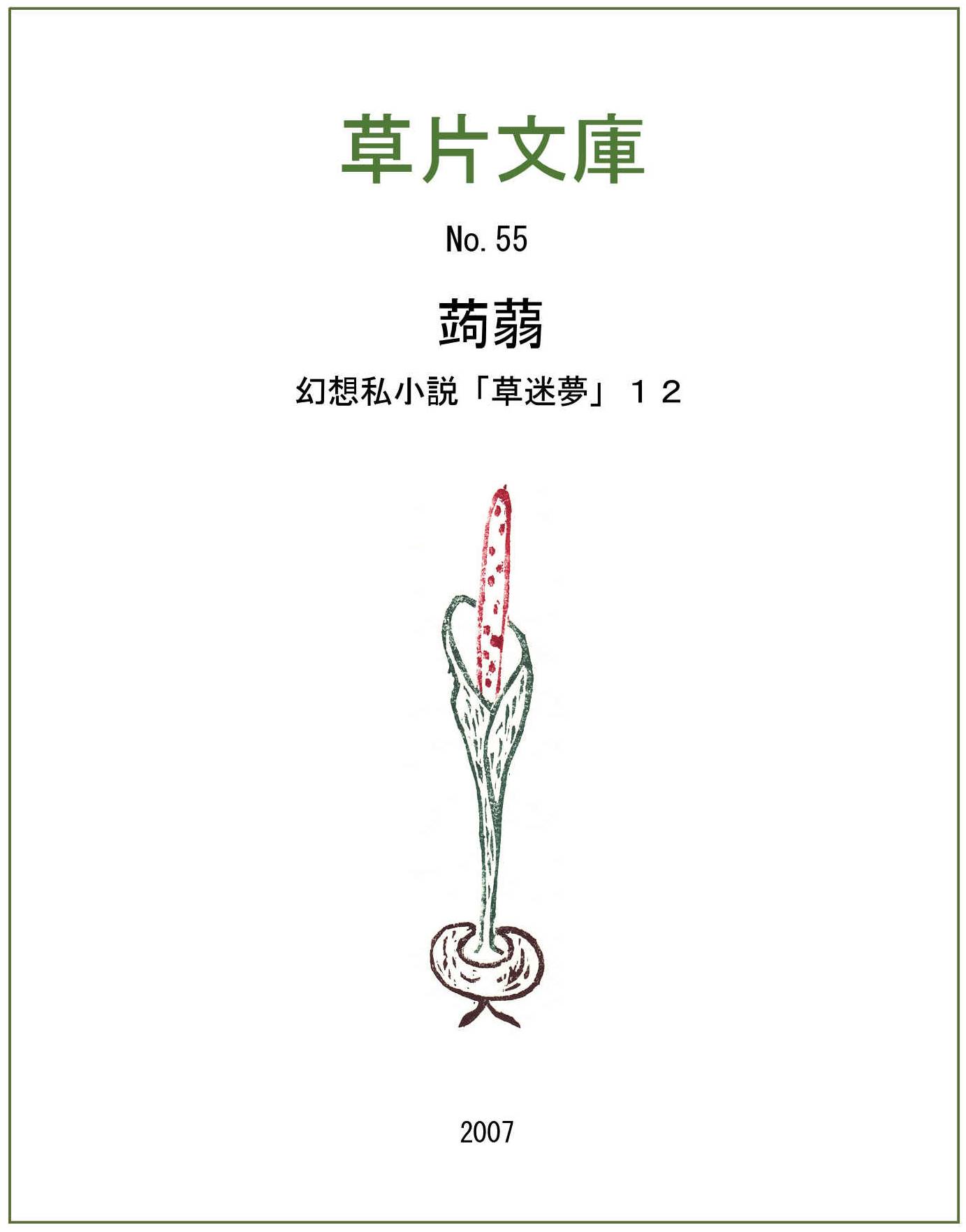
蒟蒻(こんにゃく)-幻想私小説12
ポーの大鴉が大きな桃の実をもいで、桃源郷を出ようとし。結界が張ってあって、でることができない。黒い大きなタツノオトシゴが桃をもどせば出られると言った。大鴉は桃を返した。その際、ちょっと突っついて汁を吸った。桃の精になっていた吾は大鴉の嘴の脇にくっついた。意地汚い大鴉だが、そのおかげで桃源郷を無事に出ることができた。大鴉は桃を食べ損ね無性に腹が減った。飛びながら涎をたらした。吾は涎に絡みとられ、地上に落下し目を回した。
夕日が山の陰に沈みかけている。町並みが薄暗いシルエットに浮かび上がってきた。
吾は名古屋の公務員住宅のある町にいた。下駄履きで砂利道を歩いている自分に気がついた。幼稚園から小学三年まで住んでいたところだ。
電信柱に明かりがともり、蝙蝠がパタパタと飛び始めた。
おでんの匂いがどこぞから漂ってくる。
角を曲がると、大久保さんの家の塀の前におでんの屋台が出ていた。まだ始まっていないらしく、腰の曲がった白髪ぼさぼさの爺さんが準備をしている。
通り過ぎようとすると、じいさんが顔を上げた。誰かに似ている。
「お一ついかがで」
煮ているおでんの蓋を取った。いい匂いがますます強くなった。
じいさんが椅子を屋台の前に置いた。
ズボンのポケットに手を突っ込むと千円札が手に触れた。
「へい、なににします」
「蒟蒻と大根を」
辛子が脇に盛られた皿に、汁が浸みて薄茶色になった大根と蒟蒻が形良くならんででてきた。大根を一口かじる。旨い。
「どちらからいらしたので」
「東京の日野市です」
「ほう、ずいぶん遠いところからおいでなすった」
夢の中でいきなり来たのだとも答えられない。
「酒はいかがで、遠いところから見えた客へのおもてなしで、どうぞサービスで」
蒟蒻を食べていると、湯飲み茶椀に入れられた酒が差し出された。
「これはすいません」
恐縮して、いっぱい飲むと、辛口で、ほどよい酒の香りが口の中に広がった。
「お客さん、蒟蒻の花をご存知ですかな」
「一度、咲かせたことがありますよ、いや二度ですね」
「そりゃあ珍しい」
「近くに住んでいる人が蒟蒻玉をくれたんですよ、鉢に植えといたら勝手に花が咲きました。息子が五歳ほどの時で、息子の背丈まではいきませんでしたが、大きな花でした」
「嫌らしい花でしょうに、赤黒くて、それに嫌な匂い」
「ええ、蠅がたかっていました」
「どの位の大きさの蒟蒻玉だったかね」
「あまり大きくなかったのですよ、十センチなかったのじゃないかな」
「それは珍しい、ふつうは五年ほど経って、かなり大きくならないと咲かないし、いや、五年経ったって咲かない方が多いのですがね」
「二度目は、生協で買った蒟蒻玉で、最初の年は葉っぱだけだったのですが、次の年は、白い棒状のものがでてきて、だんだんと延びると紫色に変わり、大きな花になりました。二週間ほどで成長し、その後すぐに枯れてしまいました」
「花を見ただけで、蒟蒻を喰わんかったんかね」
「ええ、天南星のたぐいの草を庭に植えてたので」
「ああ、浦島草、姫浦島草、蝮草、緑蝮、雪持草、中国の白天南星に、赤天南星てなぐあいかね」
「まさに、それすべて庭にありました。まるで知ってるみたいだ」
「好きなやつぁあ、そんなもんさね」
そんなことを言いながら、おでん屋の主人はたのみもしないのに新たに蒟蒻を吾の前に置いた。
「へい、サービスでさ」
吾は蒟蒻を食べた。ずいぶん旨い、今まで、こんなに旨い蒟蒻は食べたことがない。それを察したようにおでん屋の主人が、
「そりゃあね、この蒟蒻は他の蒟蒻とは違いましてね、蒟蒻にもいろいろあるんですよ、改良品種がね、ところが、この蒟蒻は江ノ島にしか生えない蒟蒻で、江ノ島蒟蒻というんだが、それが絶えちまった。何せ江ノ島は観光化されちまって、蒟蒻がつくれない。残念がっていたら、同じ蒟蒻が外国にあった。お客さん知らないかい」
そんな話を聞いたこともない。夢の中の話だから仕方がない。
「フランスにあったんだ、モンサンミッシェル」
その島なら知っている。島が家になっているような、世界遺産になっている、何でも高価なオムレツで有名な店があるという話である。
「いえね、お客さん、あそこは江ノ島そっくりなんで、フランスの江ノ島なんていうやつがいる」
「そこに、蒟蒻があるってわけ」
「そうなんで、そこから取り寄せた蒟蒻玉を使ったおでんたあ、世界でここだけでしか食えないんでさ」
確かにそうであろう。フランス語で蒟蒻はなんていうんだ。だいたいおでんはなんというのだろう。
「蒟蒻はLes arum enracinentっていうんでさ、おでんはね、ポトフの仲間だ。だけんどお客さん、何だっていいじゃないの、旨きゃあさあ」
確かにそうである。
おでん屋の爺さんが、また蒟蒻を吾の皿においた。酒までだしてくれた。
「千円しかもっていないから」
と言うと、おでん屋の爺さんはおったまげたという顔をした。
「ちょって見せてくれよ」
吾はポケットからくしゃくしゃの千円札を出した。
「ひょー、本物だ、いつでたんだ」
「これしかない」
「あんたさん、千円で家一軒度どころか、別荘も一緒に買えちまう」
いったい、いつの時期なのだ、不思議に思って、いや、これは夢だったということを思い出した。
「お釣りだってありゃしない」
「それあげます」
吾がそう言うと、おでん屋の爺さんは、またびっくりした。
「そんな、それじゃ、毎日おでんを食べにきてくれや」
ということで、その日は、江ノ島蒟蒻、卵、それもキウイの卵、イタリア製ちくわ、ドイツ製はんぺんで、日本酒を五合ほど飲んでいつの間にか家に戻った。
次の日も家を出ると、知らない間に駅の近くにきていた。そこで、また、おでんの屋台があった。
「へい、いらっしゃい、今日はまた、違った蒟蒻を食ってくれや、昨日あんなにもらったんで、珍しい大蒟蒻を買うことができた」
そういって、おでん屋のおやじは煮こんだ赤黒い蒟蒻を私の目の前においた。
「こいつには、ビールがいい、どうかね、ベルギーのビール、白ビールがいいよ、ちょっと酸味があるけどね」
ということで、白ビールが私の前におかれた。
蒟蒻は大変おいしいが、
「どうだい、旨いだろう」
「うん、でもどのように違うのか、わからなくてね」
「そうかね、どれも儂のおでんの汁だから同じ味になるかもしれんね、代々使っているおでんのだし汁だよ、もう百五十年になるよ」
やけに歴史のあるおでん汁である。
「蒟蒻、うまそうだな、いい匂いだな」
知らないお客さんが隣に座った。
「へい、どうぞ」
じいさんが大蒟蒻を皿に載せ、隣に座った客の前にだした。
「匂いが違うよ」
客がじいさんにいった。相当いい鼻をしている。
「へえ、大蒟蒻は値が張りますが、いいですか」
「いくら」
「一円」
「そんなにもってない、今度稼いでからにする」
客は立ち上がろうとした。
ポケットに手を入れると、また千円札があった。吾はそれをじいさんに渡した
「みんなにおごってあげてください」
「あれ、また千円も、それじゃもらいすぎだ、昨日もらったので、十分」
と言いながら、隣の客に座るように言った。
「このお客さんからだよ」
じいさんは新たに大蒟蒻おでんを皿に載せ客の前に置いた。
「オー、いい匂いだ、ごちそうになります」
隣の客が吾の方をみた。吾も客の顔を見た。
真っ白い猫が椅子に腰掛け、ヒゲをぴんとのばしてお辞儀をした。
「白じゃないか」
本質的にはとても甘えったれの吾の家の白猫である。
「二度目でございます、また、お世話になります」
殊勝なことを言って、髭をふるわせながらおでんを食べている。
「ビールはどうだい」
「へ、いただきます」
「この猫にもビールを頼む」
「へい、お客さんのお知り合いで」
「うん、うちの猫だった。アレルギーがあって、早く老衰になっちまった」
「へえ、南平の家は居心地がよかったです、おかげでハッピーに死ねました」
「そりゃよかった」
吾は白にビールをついでやった。
「あたいも、大蒟蒻食べたい」
隣に、女のお客さんがすわった。爺さんが吾にきいた。
「みんなに、おごっちまっていいですかい」
「いいよ」
じいさんは隣に座った女の客に大蒟蒻をだした。
「おーおいしい」
女の客は蒟蒻にかぶりついた。
「ビールはいかがですか」
吾はその客にもビールをすすめた。
「あら、すてき」
女の客はじいさんからコップをもらって、吾の前にさしだした。
「ありがとう」とその客はぐーっと飲み干した。
「うまい」
吾はもういっぱいビールをついでぐっと飲むと、その客を見た。
「黒じゃないか」
うちにいた黒い猫である。無口な猫だった。これも老衰だった。
「大山以来です、ご無沙汰してます」
黒が黄色い目で吾をみた。
「姉サン、久しぶり」
そう言ったのは、隣にすわっている白である。黒は外飼の猫だったのが我が家の一員になり、白は野良だったが、かわいがられていたようで人なつっこく、どうしても我が家にはいりたがった。いれてやったが、その前からいた黒に頭があがらず、こそこそしていた。
大蒟蒻のおでんをおかわりし、ベルギービールをやりとりして、昔話に花を咲かせた。
白の隣に若い人が座った。
「白兄ちゃん、久しぶり」
僕はその客をみると、また驚いた。
「腎じゃないか、高尾山以来だね」
「お世話になりました」
腎は、本当は斜め前の家のおばあさんの猫で、お孫さんが子猫の時につれてきたやつある。しかし我家の白になついちまって、一緒についてくると我が家に住み着くようになってしまった。背中の下のほうに二つの大きな黒丸がある。腎臓のあるあたりだ。それで腎臓という名になった。元気な猫で、いつも外で遊んで土にまみれて帰ってくる。
「この猫にも大蒟蒻をだしてくれますか」
じいさんに頼んだ。
「猫の知り合いが多い人だね、猫がこんなにたくさん来たことはないよ」
そういいながら、大蒟蒻のおでんをみんなの前にならべた。
「腎、なにしてたんだ」
吾がきくと、「モグラや赤鼠の手伝いをしていました」
「おまえはずいぶん捕まえたからな」
「うん、だから、ここでは、彼らを養ってるんだ」
「それはいい」
夢の中ではいなくなった動物たちと会える。楽しいことである。そういえば、前の夢にもすでに猫たちは登場している。何回でも会えるのは嬉しい。
腎にもビールをついだ。
「みんなどこにすんでいるんだい」
そうきくと、「高尾山」と答えた。
そうか、高尾山に墓があるからかと思った。そのとたん、みんな消えてしまった。
次の日も家を出ると、神社の入り口に屋台がでていた。
おでん屋である。
「へい、いらっしゃい、今日は蒟蒻ないよ」」
おでん屋の前には蒟蒻の花が咲いた植木鉢が何十もおいてある。やな匂いがしてくる。金蝿が飛んでいる。
「たくさん花を咲かせましたね」
「ああ、蒟蒻のやつ勝手に咲いちまった、だから今日は蒟蒻がない」
じいさんはしょうがないという顔をした。
「それで、なにがあるの」
吾は煮立っているおでんをのぞき込んだ。紅い蒟蒻がある。
「あの紅いのは蒟蒻でしょう」
「いや、ちがうんだ、これを食べると大変よ」
「どうなるの」
「蒟蒻になる」
「こいつは、こんやく玉からつくったもんでな」
「こんやく玉ってなに」
「雄の蒟蒻と雌の蒟蒻が一緒になる約束をすると、その間に玉ができる。それがこんやく玉だ」
「雌と雄の蒟蒻がこんやくすればみんなこんやく玉をつくるじゃないの」
「蒟蒻は雄も雌もないが、ほんのときどき、雄と雌の蒟蒻が生まれる。それがこんやくするので、なかなか採れない」
立て続けにじいさんが説明してくれたが、何言っているのだか分からない。
「食べてみるかい」
夢の中なかならかまわないだろうと思い、
「食べたい」と言った。
「でも、蒟蒻になると、もうおでん屋には来れないよ」
「そうだなあ、でも食べたい」
いいはったらじいさんが大きな虎猫になった。
「なんだ、山椒じゃないか」
吾の家に出入りしていた大きな山椒魚みたいな野良猫で、名前を山椒とつけたやつだ。顔が大きく、ともかくよく食べ、水をよく飲んだ。首のところの出来物が破裂し、しばらく調子が悪かったが、それも回復して元気になった。しかしいつの間にかいなくなった。腎が怖がって家出をしたことがある。
「いや、ご無沙汰をしておりやした。今はこの世でおでん屋をやってます」
「どこにいっちゃったの」
「いや、除草剤を撒いた草地で遊んでたら、気分が悪くなって、神社の社の下で成仏したってわけで」
そういいながら、山椒はこんやく玉からつくった紅いこんやくおでんを僕の前においた。一口で食べられるほどちいさい。
「食べたら、蒟蒻になるけど、これ以上おいしい蒟蒻はありませんねえ、先に言っておきますが、ご機嫌よう」
吾はその紅い蒟蒻を口に入れた。
なんと言っていいかわからない香りが鼻に昇ってきた。うまい、それはうまい、表現ができない。
と、目の前がぼやけてきた。
周りが蒟蒻の花である。どうやら、蒟蒻の花の一つに入り込んだようだ。
蠅がやってきた。吾は蠅にくっついた。
蠅は蒟蒻の花から離れるとおでん屋の屋台の脇にとまった。おでんがお湯につかっている。匂いだけはかぐことができる。
また、あの猫たちがおでんを食べにきている。
今日は蒟蒻がないので、つみれを食べている。
吾もそうすればよかったのかな。
蠅が飛び上がった。
蒟蒻の精になった吾は、蠅にくっついている蒟蒻の花粉のなかにいる。
蝿のやつこれからどこに行くのだろう。
夢がなかなかさめない。
蒟蒻(こんにゃく)-幻想私小説12
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


