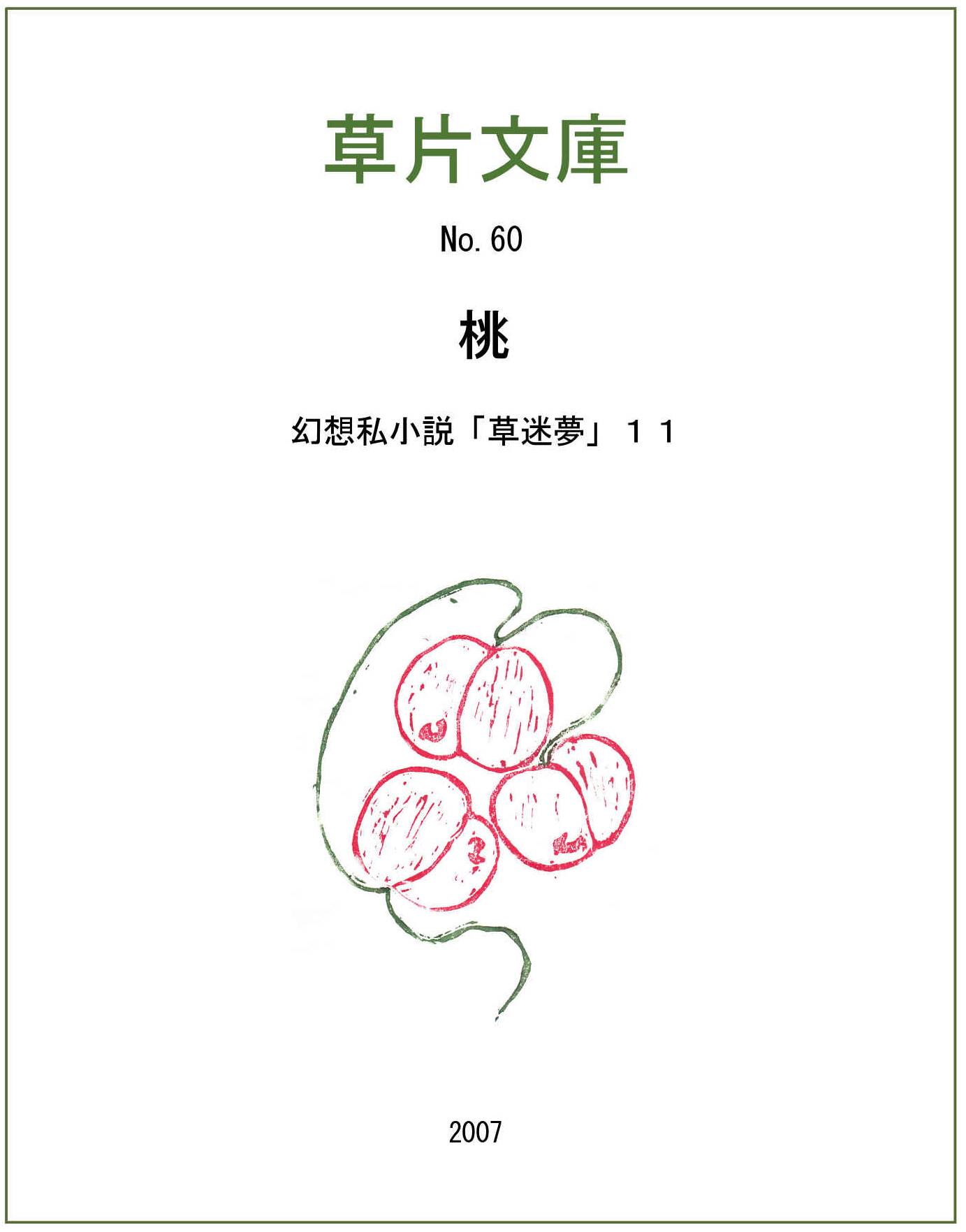
桃 - 幻想私小説11
桃畑の水溜りが干上がり、中にいたタマミジンコは休眠してしまった。タマミジンコにくっついていた光苔の精となった吾は桃の香りを嗅いでいた。
桃はなぜか危ない。香りと、柔らかく水の滴る熟し方、これが複雑な感覚を人間に与えることは確かなようだ。少なくとも、桃を男と捉えることはあるまい。たくさんの文芸作品に登場し、それは、まさに女性でしかない。しかも大人の。
桃そのものをタイトルとした本は久世光彦のものがある。腐る手前の桃を人間の感覚に持ち込んだ匂いまで感じさせる小説ではある。映画もある。新しいものではあるがフィメールと題された現代のオムニバス映画の中の一作は、桃から強烈な若いエロティシズムを生み出している。
自分が桃の季節に生まれただけではなく、山梨の祖父母の住む桃の木のたくさんある家で生まれ、少し物心ついたときには、その家で桃を食べ過ぎて、喘息を起こした。
今でこそ流通の手段が発達したこともあり、おいしい桃を食べることができるが、昔は気の抜けた桃を掴まされることも多くあった。
入道雲がわきあがる暑い日に、白いコットンズボンに、茶色の半そでシャツを着て桃畑を歩いている。なっている桃は水蜜のようだがどれもずい分大きい。
一本の木の下に来たときに、それはそれは大きな桃が、ぷらんぷらんと揺れているのが眼にはいった。細かな金色の毛に覆われていて、ふっくらと美味しそうだ。その桃からはとても強い香りが漂ってくる。食べたいものだ。立ち止まって手を伸ばそうとすると、金毛の桃がさらに激しく揺れた。
なんだろう。と見ていると、桃の皮がちょっとはじけて、白いタツノオトシゴが顔をだした。香港で薬膳のスープにするために買ったタツノオトシゴだ。結局食べずにシャーレに入れて飾ってある。
タツノオトシゴは吾を認めると、ウインクをして桃の中に引っ込んだ。一番うまそうな桃の中にもぐりこんでいるとは大変なやつである。夢なのだから桃の中に何がいようがかまわないが、食べたかった桃の中にいることはなかろうに。
あきらめて、てくてく行くと、さっきのふっくらとした桃とは程遠い、小さな扁平な桃のなる木が目につくようになった。扁桃である。桃の原種に近い。オランダ、アムステルダムのコンビニで売っていた。水気たっぷりの桃ではないが、ちょっと黄桃に似て、身が固くなかなか甘くておいしかった。種はぎざぎざしている小さなものである。
手のとどくところにある扁桃に手を伸ばすと、扁桃がゆれて、また中からタツノオトシゴが顔をだした。邪魔するのが好きなタツノオトシゴだ。癪に障るからタツノオトシゴごと実を取ろうと手を伸ばした。そのとたん、その桃はタツノオトシゴを乗せて空中に舞い上がった。
見る間に空に上ると、消えていった。なんてこった。
てくてくいくと、普通の桃のなる木の畑になった。今度こそ一ついただこうと、桃色に熟した桃を採ろうと手を伸ばすと、ぱっと場面がかわって、幹の径が五メーターにもなろうとする大きな桃の木の下にいた。周りの景色は、霞がかかったように、もやっている。
桃源郷だ。
とすれば、仙人がいるやも知れぬと、周りをみると。また、白いタツノオトシゴだ。
今度は吾とほとんど同じ背の高さで、桃の木に寄りかかってゆらゆらと揺れている。
おっと、目があってしまった。タツノオトシゴがまたウインクをしやがった。
「おほほほほ」とタツノオトシゴが笑った。
雌だ。
そう思ったとたん、タツノオトシゴの頭の角が大きく伸びて、怖い顔になり、
「ふん」と横を向いた。
どうしたのかいと声をかけてみた。
「雌ではない」と返事が返ってきた。
「そりゃ失礼、おほほほと笑ったので雌かと思ったのだよ」と謝った。
「あたいはー女―」と返事があった。
そうか、雌といったので気を悪くしたのか。日本では動物に雌雄の字を当てはめるが人間に用いることはない。女男である。英語では人間にもフィメイル、メイルを当てはめることが多い。
失礼とお辞儀をすると、機嫌が直ったのか、巻いている尾を伸び縮みさせて、ぴょんぴょんと飛んでよって来た。吾を見るとピンク色に変わった。
「あたいは桃タツよ」
なんだろうこいつは、なれなれしい口調になった。
その雌は「いくよ」と答えると、いきなり吾の肩に首を乗っけて、尾を吾の胴体に巻きつけてきた。タツノオトシゴの顔が自分の顔の隣にある。奇妙な気持ちになる。だが重さを感じない。
「いいじゃないさ」とタツノオトシゴはますます顎を擦り付けてきた。
考えていることをみんな読んでしまわれるようだ。
「そうさ、気持ち悪いんだろう。そのうち慣れるわさ。人間は自分たちの顔が気持ち悪くないとでも思ってんだから、やになるわね。目玉が前にあってさ」
人間のほうが他の動物にとっちゃ気持ちの悪い格好をしているのだろう。それにしても好き勝手なことを言っている。
「で、どこにいくんだい」
タツノオトシゴは尖った口先を右手の山の上に向けた。
「何があるんだい」
「行ってみりゃわかるわよ」
「どうして桃の林にタツノオトシゴが住んでいるんだ」
「いけないかしら」
私が無言でいると。
「人間は自分勝手に似合うものと似合わないものを決めているわね、あたいからみると、人間ほどひどいアンバランスな生き物いないわよ、二本足でよろよろ歩いて、あんた真っ裸になってごらんよ、まあみっともないのだよ、それにくらべりゃ、タツノオトシゴなんか、ぴしっとしてるもんさね。
それにね、やっと今頃になって、人間は子供を産むことの重要性を知ったようじゃないか、なんだい、あの育面パパなんてことばは、タツノオトシゴなんて、男が子供を育てるのは当たり前さ」
それは確かにそうである。私もそれは知っている。
「それで、桃の話に戻るが、あんたは、海の中で暮らしたことがあるの、海中には美しいものが五万とある。緑の藻の揺れる中、五色の水母が舞を舞い、あの美しい海牛が漂う。磯巾着が華麗な触手を長くのばし、きらきら光る魚たちがその間を泳ぐ、宝石より貴重な珊瑚が花を咲かせ、そこに我々はゆったりと泳いでいく。その様を想像してみなさいよ、桃の実の脇にタツノオトシゴが優雅に腰掛けていてなにが合わないの」
私はシャッポを脱いだ。
「おっしゃる通りです」
「素直だね、男は素直じゃなきゃ」
ピンクのタツノオトシゴは、私に巻き付いて、歩いていく方向を示した。
桃畑にはいろいろな桃が植わっていたが、すべての木に実がたわわ。
「食べたいでしょう」
自分に巻き付いていたタツノオトシゴが熟れた桃に口をつっこんだ。
私は立ち止まって、タツノオトシゴが桃の汁を吸うのを待った。
みずみずしい桃の匂いがあたりに漂ってきた。
「どう、一つもぎ取って食べてみたら、これ水蜜よ」
私はその桃をとり、皮をはいだ。熟れている桃の皮のはすーっとむけた。そのあとかぶりついた。
「うまい」
「そうでしょう、それでいいのさね、正直がいい、先に行きましょう」
やけに広い桃畑だ、行けども行けども果てしなく桃の木が並んでいて、おいしそうな実がなっている。
「どこまで歩きゃあいいのかな」
吾がつぶやくと、巻き付いているピンクのタツノオトシゴが耳元で「歩いていきゃあ、道は開けるものよ」と囁いた。
それで、なにも考えずに歩いていると、一本の大きな桃の木の枝の中から声がかかった。
「ねえ、ピンクのタツノオトシゴが巻き付いているあんた、アルバイトしない」
上を見ると、いろいろな藻をまとったような、きらびやかな真っ赤なタツノオトシゴが、枝に腰掛け見下ろしている。
吾に巻き付いているピンクのタツノオトシゴが返事をした。
「ハナタツのお姉さんなにやってるの」
「いやね、この木の桃をジュウスにしなければならないのだけど、面倒ね」
「どうして、ジュウスにするの」
「桃の神が飲みたいって言うのよ」
「自分でやりゃあいいのに」
「ほんとにね、どう、その男に手伝ってもらっちゃいけない」
ハナタツが僕に巻き付いているピンクのタツノオトシゴにきく。なぜ僕にきかないのだろう。
「いいわよ、手伝ってあげる」
勝手に答えている。まあ仕方がないか、僕はその桃の木の桃をもぐと、ハナタツが差し出したジューサーにいれ、一つ一つ搾った。搾った汁はこれもハナタツが差し出した一升瓶につめた。
その木に生っていた桃すべてをジュウスにすると、ハナタツは、「はい、お駄賃」と桃の葉っぱを八枚僕にくれた。
桃の葉っぱの表面には帽子をかぶった黒いタツノオトシゴが印刷されている。1000桃とかいてあり、どうやらタツノオトシゴの紙幣のようだ。
「よかったね、それで、あたいに、帽子をかってよ」
巻きついているピンクのタツノオトシゴは吾にねだるのであった。
「いいよ」と歩いていくと、桃の木の下で、黄色のタツノオトシゴがいろいろな帽子を売っていた。
「どーお、一つ買っていかない」
売っている帽子は色が違うが形はみな同じ三角錐だ。
「あたい、あのピンクのが欲しい、あんたは茶色だよね」
そういうものだから、ピンクの帽子を取って「いくら」ときくと「1000桃よ」と黄色のタツノオトシゴは口を伸ばした。だから、もらった桃の葉っぱを差し出すと、むしゃむしゃと食っちまった。
「この茶色のももらう」
もう一枚桃の葉っぱを渡すと、やっぱり、食っちまった。
「そのお金はおいしいのよ、海草からとった染料で印刷してあってね、そういう価値があるの、味付け紙幣よ」
「金本位制じゃないんだね」
「そう、だからお金じゃなくて、お海草」
なるほどと思い、ピンクの帽子をピンクのタツノオトシゴにかぶせてやり、茶色の帽子を吾がかぶった。
さらに歩いていくと、桃の実に小さなタツノオトシゴが群がってくっつき、口を桃の実に差し込んで吸っていた。
そばでは青い大きなタツノオトシゴが空中に浮かんで、お腹の袋を揺らしている。
中から、何匹もの子どもが飛び出すと、桃の実にとっついて、口を実に刺した。
「ここはお産の場所で、幼稚園」
ピンクのタツノオトシゴが説明してくれた。
「たくさん食えよ、食って大きくなれ」
青いタツノオトシゴがドスの効いた声を上げた。
経験から、桃の食いすぎは喘息になることを言おうと思ったが、気にし過ぎるのも喘息にしちまう可能性があるのでやめた。親があれこれ気にし過ぎると、子どもが神経質になっちまう。喘息は母原病の一つだ。でも一言言ってしまった。
「食べ過ぎないようにね」
タツノオトシゴの子供たちが一斉に僕を見て、
「あんたみたいに、無鉄砲じゃないからな」
と大人びたことを言ったので、ちょっと鼻白んだ。
「こどもはかわいくなくちゃ」
そう呟くと、大きな桃が吾の頭に飛んできた。
「あっちいけ」
どうやら嫌われたらしい。
「あんた、ぜんぜん成長していないね」
巻き付いているピンクのタツノオトシゴにも言われてしまった。確かにそうだ。それで歩き始めた。
「桃源郷の仙人に会いたいのだがねえ」
吾が尋ねると、
ピンクのタツノオトシゴは、
「ともかく、歩かなきゃ」
きびしく指示した。言われるままに、桃畑をひたすら歩いた。
「それで、桃の仙人に会ってどうするの」
きかれたが、ここを歩いているのがなぜだかわからない夢の中で、そんな目的など答えられるはずはない。
「ちょっと休んで桃をたべようか」
ピンクのタツノオトシゴの指示で、立ち止まったところ、高野のフルーツパーラーで腰掛けていた。
テーブルの上に一つ数千円もする岡山の白桃がころっとおいてある。
目の前にはピンクのタツノオトシゴが腰掛けている。
「さあ、食べましょう」
ピンクのタツノオトシゴは器用に口で桃を剥くとかぶりついた。僕も爪の先で桃の皮を剥ぐとかぶりついた。じゅうと白い汁が滴り落ち、口いっぱいに桃の香りが充満した。
「うまい」
「そりゃあ、岡山の白い桃だもの」
ピンクのタツノオトシゴはもう食べ終わっている。しかも、食べた後の種を磨いて、彫刻刀で何か彫っている。
「なにを彫ってるの」
「高校の記章」
「どこの高校」ときくと、「南平高校」という。出来上がった桃の種を見せてくれたが、カンアオイの花が上手に彫られていた。
「さあ、行こう」
ピンクのタツノオトシゴが言うので立ち上がると、また桃畑を歩いていた。目の前に大きな山がある。高尾山に似ている。
「仙人はあそこにいるのかい」
吾が山を見上げると、ピンクのタツノオトシゴはうなずいた。
「山のてっぺんに大きな桃の木があって、そこに仙人がいる」
ピンクのタツノオトシゴは、いきなり僕から離れて宙に浮いた。
「あの一本道を登っていくといいわよ、ばいばい」
いきなりそう言うと、これもいつの間にか現れた緑のタツノオトシゴを追いかけて飛んでいってしまった。あっけない幕切れである。首の周りが寒くなった。そういえばほっぺたにも風が当たって寒い。
急にさみしくなった。
それで、ともかく山の道をとぼとぼと歩いていって、山のてっぺんにたどり着いた。
大きな桃の木である。相撲取りのようにでぶった木である。でも筋肉だ。
見上げると、黒いタツノオトシゴが枝に尾をまきつけて、ぶらんぶらんとゆれている。ずい分でっかいやつだ。
これが桃の仙人だろう。
「仙人さん、これが食べると不老不死になる桃ですか」
吾はその木に一つだけ生っている、西瓜のように大きな桃の実を指差した。
黒いタツノオトシゴはぎょろっとした目を吾に向けた。
「わしゃ、仙人じゃない、この実を食して、仙人になろうかどうか迷っているんじゃ、不老不死というのは覚悟がいるものだからなあ、死なないのは苦しいものよ、よほどの覚悟ななければ、仙人などにはなれぬわ」
確かにそうであろう、黒い大きなタツノオトシゴはこんなことも言った。
「おたくは、もう死なないから食べても大丈夫だが、注意して食べないと、桃の実に飲み込まれるから気をつけてな」
どんな意味かわからないが、夢の中のことである。
「それじゃ、もらってしまっていいですか」
尋ねると、黒いタツノオトシゴは頷いた。
それで枝にぶら下がっている桃の実を両手で抱えてねじって採った。
桃の皮を剥がそうと試みたが、なかなか爪が立たない。硬い皮である。
「桃が嫌がっているな、無理するな」
黒いタツノオトシゴが気にしている。しかし、ここまで来て、この実を食べないわけにはいかないだろう。
人差し指で思い切り桃の表面をつついた。そのとたん、指がずぼっと中に入り、桃の汁が顔に垂れてきた。
桃の中に入った指がどんどん吸い込まれていく。手が吸い込まれ、あっと言う間に、自分は桃の実の中に入ってしまった。からだ中に桃の汁が浸み込んでくる。
「言ったこっちゃない」
黒いタツノオトシゴがつぶやくと、吾の入った桃の実を元のところに釣り下げた。
黒いタツノオトシゴが実に向かってささやいた。
「どうだ、あの男はうまかったか」
桃の実が横に揺れた。
「さもありなん」
そう言うと黒いタツノオトシゴは目を閉じ瞑想をはじめた。
桃の実の中にいると、薄い皮を通して、柔らかな日の光が当たる。ぽかぽかと眠くなってきた。
こっくりこっくりしていると、いつの間にか、桃の木の畑の中を、桃の実の中に入って空を飛んでいる。
ピンクのタツノオトシゴと緑色のタツノオトシゴが桃の木の枝に腰掛けてよりそっている。
ピンクのタツノオトシゴが飛んでいる桃の実に気がついて、緑のタツノオトシゴに言っている。
「見て、あたいの前彼が桃の精になっちゃったみたい」
ポーの大鴉が吾の入っている桃の実を咥えて飛んでいるのだ。
桃の香りに包まれて、桃源郷の上を飛んでいるのである。とても幸せな気分だ。
桃 - 幻想私小説11
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


