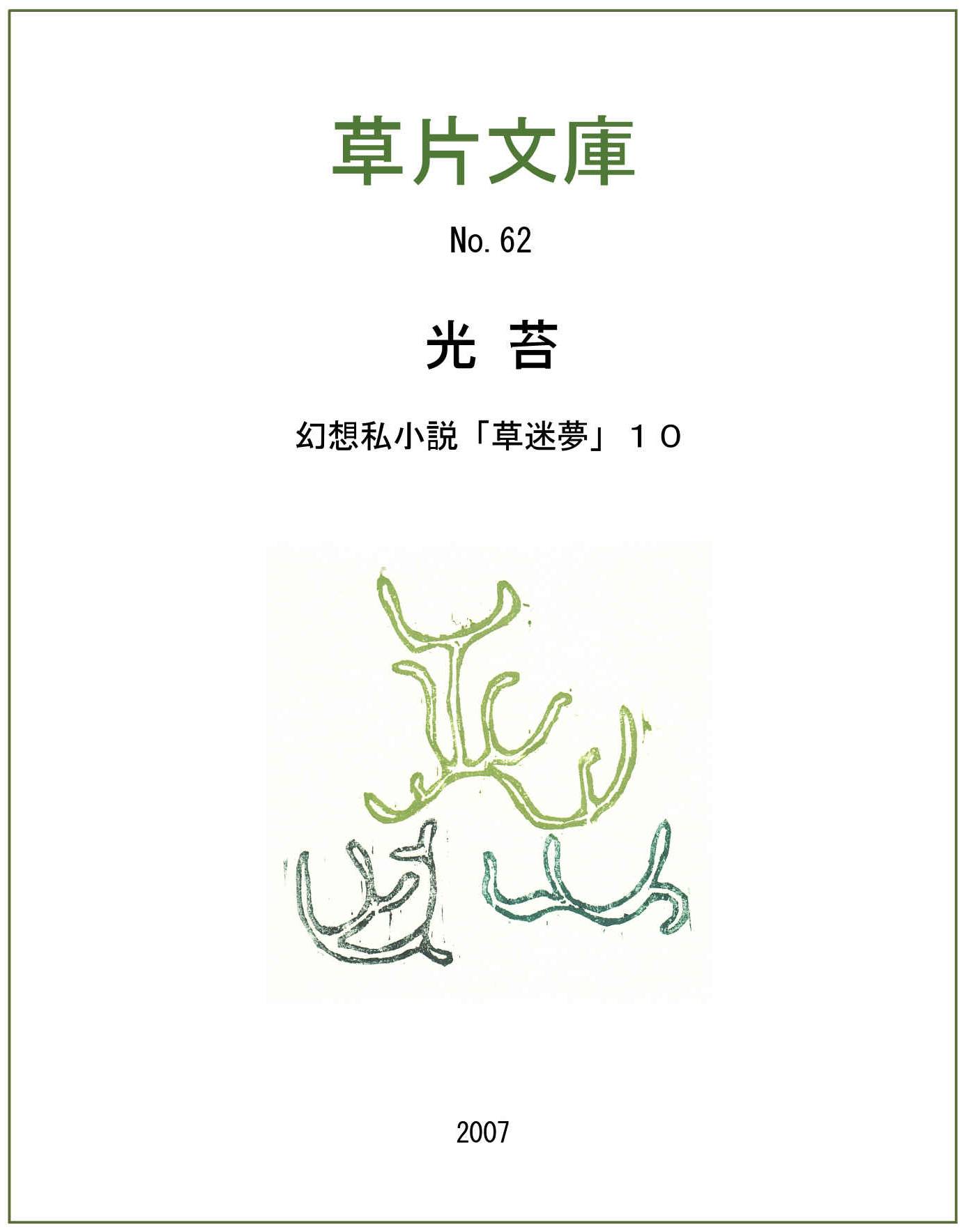
光苔-幻想私小説10
庭の山牛蒡が枯れてしまった。亀虫が大発生したからだ。山牛蒡の精となった吾はどこいくあてもなく空気の中を漂っていると、山の中腹から熱い水蒸気が噴出し、吾を吹き飛ばした。
ふっと気が付くと、温泉に浸かっている。岩の間から湯がゆっくりと流れている。透明の湯はかすかに硫黄の匂いがする。いい気持ちだ。
湯殿の戸が開いた。
やはり夢なのだ、ぞろぞろと入ってきて、ちゃぽんと、湯の中に入ってきたのは、タマミジンコたちだ。わさわさと、吾の周りに浮かんでいる。半透明の体の中が透けて見える。
タマミジンコの腕が吾の腕に触れた。
タマミジンコが振り向いて微笑んだ。
甲殻類のタマミジンコの腕は硬いと思っていたら、女性の肌のように柔らかいものであった。
一匹のタマミジンコがかえる泳ぎを始めると、他のミジンコたちも泳ぎ始めた。
「あなたもどう」
タマミジンコに誘われたが、どうもその気にならない。そろそろ上がろうか、と思っていると、タマミジンコたちが吾を囲んだ。
よってたかって吾の頭を抑えると、湯の中に沈められてしまった。湯の中ではタマミジンコたちの下半身が透けて見える。背中の卵がもぞもぞ動いている。
湯の中に横になって、水面をみていると、タマミジンコたちが、優雅に背泳ぎで泳ぎだした。卵が泳ぎと同期して動いている。きれいなもんだ。心臓がときとき動いているのもリズミカルだ。
そのとき、ざぶんと音がして、また、誰か湯に入ってきたようだ。湯の中に沈んだまま見ていると、今までとは違った世界が見えてくる。飛び込んできたのはケンミジンコだ。
「出てって」
大きな声が聞こえたと思ったら、ケンミジンコはそそくさと出ていった。
「あほなのね、あのケンミジンコ」
と声が聞こえた。
「女湯よここは」
そうか、確かに、タマミジンコたちは皆卵を持っている。女たちだったのだ。しかし、ここは男湯だと思ったが。
「人間はみな女なの、ミジンコの世界ではね。人間はみな女々しいもの、私たちタマミジンコは女、ケンミジンコは男よ」
女々しいというのは差別語で、人間の世界では使えません。
「ははは、女々しいというのは、女をたたえる言葉なのよ、ミジンコの世界では。女の強さはやわらかさ、寛容さを意味するの、そしてデリケート」
ところ変われば、品変わる。言葉の意味は人間の世界でも時代と、場所と、個人とみな違う。もしかすると、タマミジンコの言っていることは正しいかもしれない。
女性は強いのだというのは人間ばかりではなく、地上の生命全て同じはずだ。子供を産める仕組みをからだにもっている女が弱いはずはない。子孫を残すことが生物の宿命なのだ。女が主役だ。
温泉の底に沈んだまま水面を見ていると、また誰かが入ってきた。
「あら、久しぶり」
タマミジンコたちが声を上げている。
「いつまでもきれいね」
にゅうと水面から水中に突き出されたのは、半透明の伸びた足だ。中は透き通って、なんにもない。やがて体が見えてきた。核が真ん中にあり、足が何本も突き出されている。アメーバじゃないか。アメーバも女か。
「永久の命ね、若いわけね」
タマミジンコたちはアメーバを取り囲んで、褒め称えているのだ。
アメーバは吾の腹の上に足をすえると、こそこそと動かしたものだから、こそばゆく、どうしても笑ってしまった。
アメーバはそれを聞くと、タマミジンコが言ったことに笑ったと勘違いしたようだ。 腹の上をちくちくと刺し、まったく気分が悪くなった。しばらくすると、アメーバがしんなりしてきた。お湯につかり、気分がよくなったと見える。腹をつっつくのを、やめると、水面に浮上し、くねり始めた。
それをみていると、なかなかの色っぽさがアメーバに備わっていることがわかってきた。なにせ、その柔らかさといったら、他の生き物に比べられらないだろう。
タマミジンコたちが吾を水面に引き上げた。もっとお湯の中が見たいのに。
「海に行かない」
タマミジンコがささやいた。折角の誘いを断ったら悪いだろう。吾はうなずいた。
タマミジンコたちは脱衣場にいくと、タオルにくるまった。丸っこくて可愛いし、なんだかこれも色っぽい。多摩美人子だ。
タマミジンコたちは様々な模様の和服をきれいに着こなした。見る間に人形(ひとかた)になり、優雅な歩きで女湯を後にした。吾も茶色のシャツに茶色のズボンをはいて後についた。タマミジンコたちは下駄をはき、白い足をのぞかせてからころと歩いていく。ミジンコに足などないはずなのに、吾の目にはそう映ったのはなぜだろう。
野原の一本道をしばらくいくと、海が見えてきた。
タマミジンコが振り向くと、浅虫よと教えてくれた。
浅虫温泉は青森の有名な温泉どころであったが、近年寂れて目立たない。そこがいいのかもしれない。夕日が海のかなたに沈むのをながめた記憶がある。タマミジンコたちは一軒のつぶれた宿に入っていった。むかしは立派だったのであろうが、何年も放ってあったと見え、庭は荒れ放題である。
蜘蛛の巣の張った玄関に靴を履いたまま上がり、砂っぽい廊下を歩いていくと、湯の印がみえてきた。
暖簾をくぐり、タマミジンコたちは脱衣場に入っていく。棚の上の竹で編んだ脱衣籠がいくつか使われている。もう誰か来ているようだ。
人形になっていたタマミジンコたちが着物を脱ぎ始めた。ミジンコといえど女性である。後ろを向いていると、タミジンコたちが寄ってきた。
「入ろう」
見るともうタマミジンコの形に戻っていて安心した。洋服を脱ぐと、ガラス戸を開け中に入った。ミジンコたちがついてくる。湯はとうとうと湧き出している。湯殿は石造りで、茶色く変色しているが、なんとなく懐かしい。湯の中に何人か入っている。
覗いてみると水母のようだ。刺されると痛い。躊躇していると、ぽんとタマミジンコに背中を押され、ぼちゃりと湯の中におちた。何のつもりか知らないが。タマミジンコが湯に入ってくると、吾の頭を押さえつけた。乱暴だなと思いながら、吾は湯殿の底に沈んでしまった。
湯の中から見ていると、タマミジンコたちがポチャリポチャリと湯の中に落ちてきて、卵を入れたからだを湯に浮かせた。アンドンクラゲ、クシクラゲ、カツオノエボシ、ミズクラゲ、クラゲたちがタマミジンコのそばによってきた。
「久しぶりね」
ミジンコと水母は知り合いのようだ。真水のミジンコもたまに海に行って泳いだりしているらしい。水母にしても、湖での生活を楽しんだりすることがあるという。
「どうして人をつれてきたの」
「人間だけど大丈夫、頭が破裂してるから」
「ほほ、面白い」
水母たちの足が吾のからだをくすぐった。たまったもんじゃない。笑うのをこらえていると、カツオノエボシがお湯の中に沈んできて、吾に向かってにこっと笑った。
「我慢しなくていいのよ、笑いなさいな」
とうとうこらえきれなくなって笑ってしまった。するとクラゲたちが吾の笑っている口の周りに集まってきて、ふわふわと裾をまくった。パンツのようだ。ちょっと恥ずかしい。そして、水母たちの足は脇の下やら、足の底、鼻の中やらにはいってきて、こちょこちょやるものだから、くすぐったくて、がはがは涙を流しながら笑ってしまった。
「この人間おいしいわよ」
クラゲたちは裾をふわふわさせて吾にくっついてくる。
「こいつらなにやってるのだい」
水母のスカートの脇からミジンコに声をかけた。
「笑いを食べているのよ」
タマミジンコが教えてくれた。クラゲは笑いを食べるのだそうだ。獏が夢を食べるということは聞いたことがあるが、クラゲが笑いを食べるというのは知らなかった。
「私たちも食べるのよ、でもくすぐってでてきた笑いは食べないの」
「人間だけではないのよ笑うのは」
「猫だって、犬だって、クツワムシだって、くつくつくつ、あら冗談。でもクツワムシでも笑うのよ、それをそおっといただくの、とても甘いのよ」
そういうもんかと、見ていると、また誰か入ってきたようだ。
「ほほ、だじゃれよ、くつくつくつ」
「あーら、遠くからよく来たわね」
タマミジンコたちが水面に顔をだした。湯の中から見ていると楽しい。
湯の中にとてつもなく大きなものが入ってきた。
マンボウだ
「いい湯ね」
マンボウの眼が吾を見た。
「おや人間がいるのね」
「食べてはだめよ」
「おいしそうね」
「マンボウは人間が好物なのよ」
マンボウの口が近寄ってきた。こりゃ大変だ、喰われそうだ。おちょぼ口といってもかなり大きく、ぎざぎざと歯が生えている。目の前に迫ってくる。動こうとしたけれど、タマミジンコたちが吾の上に乗っかって押さえつけている。大怖い、と思っていると、マンボウが大きな声でがははと笑った。
それをタマミジンコが口を開けて食べた。マンボウの笑いはミジンコの口から吸い込まれ、ミルクのように白くなって腸にはいっていった。
タマミジンコとマンボウのいたずらであることがわかった。
「私たちはみんなプランクトン、こうやって楽しんで笑いを食べてのんびり生きてるの」
マンボウがそう説明してくれた。
プランクトンとは浮遊生物である。魚の生まれたての子供も、クラゲも、ミジンコも、おおきなマンボウ、そして植物である珪藻もみなプランクトンなのだ。種など関係ない集まりだ。のんびりと水の中に浮かんでいる生き物たち。吾もそうなりたいものだ。
わいわいがやがやと温泉の中で彼女たちは話を楽しんでいる。温泉の底から上を見上げると、ふわりふわりと浮き沈みしているミジンコの背の中の卵がごそごそ動いているのが見える。もうすぐ孵りそうだ。
ツボワムシの集団がチョコチョコとお湯の中に入ってきた。ツボワムシは我の周りをくるくる回り、ピョコピョコ踊って剽軽だ。
ついつい、笑ってしまった。
ツボワムシはそれを吸い込んだ。
しゃべり方が男である。
タマミジンコが「そうよ、ツボワムシは男」
「いっしょでいいのかい」
と聞くと、「この湯は混浴よ」と答えた。
また、ツボワムシがくるっと回って、ぴょこりと飛び上がった。面白くてまた笑ってしまった。
ツボワムシはまた吾の笑いを食ってしまった。
「自分で作って、自分で食べるのはなかなかうまいなあ」
ツボワムシがいうと、ミジンコたちが言った。
「子供にも食べさせて」
「いいぞ」
ツボワムシはそう言うと、再び何とも剽軽な動きでくるくる回るものだから、吾は大笑い。
すると、赤ちゃんミジンコがうようよ母ミジンコの背中からでてきて、吾の周りに浮いてきて、笑いを食べた。
「おいちい、おいちい」
赤ちゃんミジンコの声が聞こえる。
ツボワムシがたくさん風呂に入ってきた。みんなそろって奇妙な踊りを始めたものだから、おかしくておかくして笑いが止まらない。ツボワムシ、ツボワムシと変な踊り方だ。滑稽な生きものだ。タマミジンコの赤ん坊が吾の周りに集まって、笑いを吸い込んでいく。
「食べ過ぎないようにね」
タマミジンコの母親たちが注意をしている。ミジンコの子どもたちは生まれたときの倍ほどの大きさになった。
「次の温泉に行きましょ」
タマミジンコの親たちが湯船からあがった。吾も二匹のミジンコに抱えあげられ、湯から出された。子どもたちもぴょこぴょこと湯から上がった。
「またねえ」湯の中に残っているツボワムシと水母とマンボウが手を振った。
タマミジンコたちは湯上りタオルで子どもたちのからだをふいている。
吾もふいて服を着た。
タマミジンコたちは人形(ひとがた)にならず、そのままの形で和服を着て、子どものミジンコを背中に背負った。一匹のミジンコに数匹の子どもがくっついている。ねんねこに子どもが何人か入ったような格好だ。
玄関から外に出ると、海が見渡せた。
夕日が沈もうとしている。
いきなりタマミジンコたちが駆け出した。
「電車が出る時間よ」
吾も後を走る。駅では蒸気機関車が蒸気を吐いていた。
客車の開いている窓から、ミジンコたちは電車の中になだれ込んだ。吾もミジンコに押されて中に入った。
汽笛が鳴った。
蒸気機関車はしゅぽしゅっぽといいながら動き出した。
「どこにいくの」と聞くと、一匹のタマミジンコが振り向いた。髪をお下げにした丸顔のミジンコだ。
「作並温泉よ」
宮城の作並温泉には一度行ったことがある。広瀬川上流のなかなか風情のある宿だった。入った露天風呂に二匹の蛇がからんでいて、ポチャンと湯に落ちて泳いだりしていた。たまたま一人で湯に浸かっているときである。ちょっと危険なような、なにか、嬉しいような、良い思い出である。風呂の脇から下の川を覗くと、清んだきれいな水がゆったりと流れていた。
「そのお宿ではないの」タマミジンコが首を横に振った。
別の宿に行くようだ。
汽車が駅に着くと、ボンネットバスがまっていた。ぞろぞろとみんな乗った。一時間も走ると、山際に止まった。
脇に古いお寺がある。
ミジンコたちはバスから降り、がやがやとお堂の中に入っていった。
お堂には大きな木彫りの弁天様がまつってある。ミジンコたちは弁天様を小突くと、どかしてしまった。
穴がぽっかりとあき、ミジンコたちは階段を下に降りていく。吾も後についた。最後のミジンコが上を見上げると、弁天おもどり、と声をかけた。
穴が閉まり、急に暗くなった。弁天様がまたもとの位置にもどったようだ。
中は岩を繰りぬいた風呂であった。壁が緑色に光っている。岩の壁には一面に光苔が覆っている。光苔は原始的な苔で光苔科光苔属の一種類しかない珍しいものだ。
タマミジンコたちは子どもを降ろすと、着物を脱いだ。吾もそうした。
タマミジンコたちが湯の中にぷかぷかと浮いた。子どものミジンコたちも、騒がずに静に浮いている。
タマミジンコたちは光苔に照らし出されて緑色に輝きながら目を閉じている。
ぷかりぷかり、のんびりと湯に浸かっていると、眠くなる。
赤ちゃんミジンコはいつの間にか大人のミジンコの大きさになっている。
吾の頬にタマミジンコがくっついた。頭の後ろにもくっついた。
そのうち、ぐーぐ、がーがー、すーすーと音が聞こえてきた。タマミジンコたちがいびきをかいて寝ちまった。
頬にくっついているタマミジンコが目を開けた。
「光苔の光を浴びると眠くなって、目が覚めると、悪いところが直っているのよ」
「病気を治すのだね」
「そう、あなたもそうしてもらいなさい」
そう言ってそのタマミジンコも、再びうっつらうっつらしはじめた。
自分も眠くなり、いつの間にか寝てしまった。
どのくらい経ったのだろう、声がする。目があいた。
タマミジンコの子どもが母親に言っている。
「あの人いなくなっちゃった」
「あの人はね、光苔の胞子になって飛んでいくんだよ」
タマミジンコの親子はまた目を閉じた。
吾は今、岩の天井の光苔の中から、タマミジンコたちが岩風呂の水面にぷかぷか浮かびながら寝ているのを見ている。一匹のタマミジンコがくしゃみをした。その拍子に胞子が飛び出し、母親のタマミジンコの頭にくっついた。
「お母さん光苔の胞子が落ちてきたよ」
「食べちゃってちょうだい」
こうして、光苔の精となった吾は子どものミジンコに食われ気絶した。
光苔-幻想私小説10
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


