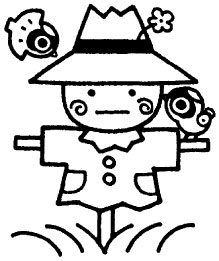彼氏が料理を作るわけ
昼過ぎに啓斗から電話があった。
「今から行くから」
それだけ言うと、すぐに切られた。――素っ気無い電話。
ほとんどの土曜の夜は一緒に過ごす。電話が来て、啓斗がわたしのマンションにやってくる。今みたいに。もしくは、わたしが押しかける。今日は土曜日。いつもとなんら変わらない。
声の雰囲気が違ってたような気がする。気のせいかもしれない。そうに違いない。心にやましいところがあるから、そんなふうに聞こえただけだ……
二十六歳から付き合い始めてもうすぐ二年、奴が来るからって、ドキドキするような時期はとうに過ぎている。多分、これはストレス性の動悸である。
三日前の水曜日。良いワインが手に入ったと、啓斗からメールがあった。わたしは仕事帰りにチーズと、フランスパンと、サラダと、さきいかと、カップラーメンを買って啓斗のマンションに行った。
シャルドネの何とかという白ワインと、ブルゴーニュのなんたらかんたらという畑で作った赤ワインだそうだ。わたしにはよく分からない。啓斗はその畑の歴史や、ブドウの品種についての薀蓄を語り始めたが、それを遮り、とりあえず乾杯と、勝手にオープナーで白ワインのコルクを抜く。これがなかなか口当たりもよく、クイクイいってしまう。瞬く間に一本空けてしまい、次は赤ワイン。少々渋みがきついのだが、チーズとあわせるとこれはこれでよい。それを飲み終わり、さきいかをつまみに焼酎をロックで飲み始めたあたりから、記憶が怪しくなってくる。
啓斗は酒豪で、酒癖はよいし、とにかく強い。乱れるということがない。
わたしはというと、父親も母親も共に酒乱の家系。どちらの親類の新年会に参加しても、毎年大荒れである。特に母親のからみ酒は目を覆いたくなる代物で、身内の間でも母にはあまり酒を勧めないのが暗黙の了解になっている。
悲しいかなわたしの酒癖は母親似らしい。さらに、記憶がなくなるから始末が悪い。まったく忘れてしまえば、すべてを闇に葬れるのだが、ときたま、暴れている自分の姿がフラッシュバックする。部長のハゲ頭にヘッドロックをしているシーンはわたしのトラウマだ。ただ、誰もそのことに触れないし、わたしも確かめられないでいる。単なる夢であって欲しいと、切に願っている。
先日は、三杯目の焼酎を作ったところまでで、以降の記憶がない。酒癖が悪いことは重々承知しているので、気をつけてはいるのだが、たまにしでかしてしまう。
朝、ベッドから二日酔いの頭をもたげると、啓斗の姿はすでになかった。奴のほうが出勤時間が早いので先に出かけたらしい。
泊まってしまうのは日常茶飯事で、着替えも置いてある。鍵も持っている。一緒に起きようと心がけてはいるのだが、六割くらいの確立で失敗する。なので、啓斗が一人で出ていってしまったこと自体は、気に病むほどのことではない。
しかし、朝の啓斗の表情を確認できなかったのは失敗だった。それによって、何かやってしまったのか、何もなかったのか、おおよその見当は付けられたのに。少なくとも、怒っているのかどうかくらいは確かめておくべきだった。
その後、啓斗から電話はなかった。こっちも、まぁ、そのままにしておいた。そして、先ほどの電話だ。もうすぐ奴はやってくる。はぁー。気が重い……
午後四時過ぎにわたしのマンションのチャイムが鳴った。ドアを開けるとそこには汗まみれの啓斗が立っている。
「よぉっっ」わたしはさり気なく言った。
左肩にいつものショルダーバック、右手にスーパーの袋をさげている。九月に入ったとはいえ、このところの残暑は半端ではない。顔を真っ赤にした啓斗が、熱風と共に押し寄せてきた。
啓斗は身長が百八十センチ、ずうたいがでかい。見ているだけで暑苦しくなる。高校、大学とラクビー部で主将を務めていたらしいが、見た目のわりに性格は温厚である。ただし、気に入らないことがあったり、緊張したりすると何も喋らなくなる。喧嘩になったときも、最終的には、「男の癖にウジウジすんな!」という、わたしの逆切れで終わることが多い。
「まっ、熱いねぇ。入りなさいな」普段わたしはどんな話し方してたっけ?
啓斗はドアの前で突っ立ってる、持っている袋を覗き込む。「ん? なんじゃこりゃ!」
ちなみに言っておくが、わたしは料理を作らない。作れないのではない、作らないのだ! 才能がないのではない、必要がないのだ! みたいなことを今まで散々言ってきたが、最近ではどうでもよくなってきている。
母にはそんなことだから貰い手がないんだと言われる。別にまだまだあせる年でもあるまい、料理上手の男を見つけるからいいよ、なんてうそぶいていたが、来月に誕生日をひかえ、やや自信を失いかけている。
まぁ、そんなことはどうでもよいのだ――
だから、啓斗が来たときは、外に食べに行くか、弁当を買ってくるか、デリバリーを頼むかの三択になる。啓斗は二歳年下なのだが、もちろん料理を作れるような才覚は持ち合わせていない。ただ、意外に気が利く。だから、スーパーの袋を見たときに、当然弁当を買ってきたのだと、疑いもしなかった。
今日はハンバーグ弁当の気分かなぁ、なんて覗いてみると、中には玉ねぎやら、キュウリ。肉? どうすんじゃ、これ?
「約束どおり、料理作るからな!」
突然、何てことを言い出すのだ。わたしは動揺する。もちろん、約束なんて覚えているわけがない。
啓斗は靴を脱ぐと、目の前にあるキッチンに向かった。指揮者が指揮台に向かうときのような表情をしている。どんよりとした空気が漂っている。ん?
わたしの部屋は1LDKの賃貸マンションで、入口を入ったところが、六畳のダイニング・キッチンになっている。その奥に八畳の部屋がある。キッチンは入口の並びにあるので、奥の部屋に背を向ける形で料理をするようになる。
啓斗は「できるまで、そっちの部屋で待ってて」と言い放つと、わたしをダイニング・キッチンから追い出した。普段なら啓斗の言葉なんぞに従うことはないのだが、今回はとりあえず様子を見る。
啓斗はわたしに背を向けると、黙々と作業を始める。料理など作ったことはないと言っていたのは本当らしい。手際が悪い。呆然とキッチンの前に立ち尽くし、やっと何かを始めたかと思うと、そのままの形でしばらく固まっている。少し動くと、またすぐに止まる。接続の悪いインターネットの動画サイトを見ているようで、イライラする。
「こうやって、啓斗の後姿ずっと見てることって、ないよね。隣にいたり、向かいあってたり、一緒に寝てることはあるけどさ。何かちょっと新鮮だよ」
やることもないので、冷蔵庫にビールを取りに行きながら、探りを入れてみる―― が、黙殺される。
機嫌が良いのか悪いのかさえ把握できない。状況はかんばしくない。いや、最悪に近い。
――約束っていったいなんなのだろう。
これには三つのパターンが考えられる。
今度、俺が料理作ってやるよ、という見返りを求めない一方的な約束。わたしがすでに何かをしてあげていて、そのお返しとして、約束を履行しているパターン。もう一つが、俺は約束を守るのだから、お前も約束守れよな! 的なパターン。
どう考えても、啓斗の雰囲気からして、第三のパターンにしか思えない。というか、確信をもって言える。この気配は、確実にわたしが何かすることを求めている。
わたしは戦々恐々としながら、怯える子羊のように、ビールを片手にテレビを観ていた。
テレビを観ながら、横目でチラチラと啓斗の様子を伺う。
こうやって、男がわたしのために必死に何かをしている姿を、ビールを飲みながら眺めるのも悪くない。なんて、悠長なことを考え始める。わたしは酒が入ると、気が大きくなる。何でもよくなってしまう。これが失敗の元凶だ。男が料理中の女を後ろから羽交い絞めにしたり、裸エプロンなんてものに憧れる気持ちも、なんとなく分かるような気がしてきた。
「イテッ」
啓斗が左手の中指を押さえている。どうやら指を切ったらしい。
「大丈夫か? 見せてごらん」
啓斗は素直にわたしの元へやってくる。
見ると、それほど深い傷ではないが、指先から血が流れている。絨毯に、今にも血が滴り落ちそうだった。わたしは思わず、その指を口の中に入れ、傷口を吸った。啓斗の血の味がした。鉄っぽい臭いがして、なんだか啓斗を食べてるみたいで、恥ずかしい。
啓斗の身体の一部を、わたしの内臓が消化・吸収し、やがて全身の細胞に拡散して、わたしの身体の一部となるのだ、なんて想像していたら、少し興奮した。強く傷を吸ったら、啓斗が顔を歪めた。
わたしは絆創膏を啓斗の指先に巻いてやった。ついでに啓斗の唇にキスをした。このまま押し倒してしまおうかと思ったが、キッチンで何かがグツグツと音をたてている。とりあえず料理っぽい、いい匂いがしてきて、お腹がグーッと鳴った。二本目のビールのプルトップを開け、「飯まだかぁー!」いっちょう気合を入れてやった。
わたしは”Sっ気”が強いのかもしれない。血を見ると興奮するし、痛みに耐えてる男の顔もなかなか良い。悪いことに、啓斗もどちらかというと”S”だ。ときどき変なことを言い出したり、してきたりする。当然、わたしはその倍返しで応酬する。それがお互いの抑止力となり、おかげでノーマルな関係を維持できている。
ちょっと前の話になるが、啓斗がベッドの中で、あろうことか突然とんでもないことを言い出したことがある。わたしにはそんな趣味はないし、痔になるのも嫌なので、もちろんキッパリ断った。
もしかすると、今回の約束も、そういった類の話だったような気がする。ん? なんか、入れるとか入れないとか、ケツがどうだとか、言ってたような気がする。んん?? なんか、そんな約束してたような気がする――
なんてこったぁ…… こりゃぁ、本気でまずいぞ。
料理が出来上がったらしい。啓斗がダイニングのテーブルに皿を並べている。
「どうぞ」
待ちかねていた。飲みかけのビールを片手に、テーブルに座る。
「スパゲッティーにすき焼きとは変わった組み合わせだねえ」
「これ、肉じゃがのつもりだったんだけどな」
「肉じゃがって、ジャガイモ入ってないじゃん」
「ごめん、買い忘れちゃって……」
「……」
とりあえず、シャンパンで乾杯する。これって、けっこう高いやつじゃなかったっけ?
スパゲッティーは多分、ボロネーゼとかミートソースとかいわれているものを、意識したのだと思われる。端的にいえば、ひき肉を大量のケチャップで炒めただけの代物だ。啓斗の認識では、ミートソースというのはそういうものなのだろう。まぁ、わたしもどこが違うのかよく分からないが……
食べてみる。これがなかなか美味しい。甘めのケチャップの味と、芳ばしい(多分、本当に焦がしてしまったのだろうが)香り。スパゲッティーはアルデンテからほど遠く、クッタリと茹で上がっていたが、これはこれで哀愁が漂うなんともいえないクッタリ加減である。ミートソースとナポリタン・スパゲッティーのいいとこ取りをしたようで、まったく美味い。
肉じゃがはジャガイモは入っていないが、肉は金に糸目をつけなかったのだろう。最上級黒毛和牛の霜降り肉が使われている。味付けはやや薄めだが、すき焼きと思えば十分いける。というか、こんないい肉を使っていて、まずいわけがない。本当は溶き卵につけて食べたいくらいだったが、肉じゃがだと言い張る啓斗の手前、それは我慢しておいた。
「うーん。オヌシなかなかやるのう。美味しいよ」
啓斗は、恥ずかしそうにうつむいている。
「約束は守ってもらうよ」
やっぱりきましたかぁ。分かったよ。覚悟はできてるよ。
啓斗は立ち上がると、おもむろに自分のバックを持ってくる。バックを開き、中から何かを取り出そうとしている。
まっ、まさか、道具を使うこととは―― ごっ、ごめん、そこまでは心の準備ができていない。想定の範囲を超えている。これはまずことになった。ロープとか蝋燭とか、まさかあんなことまではさすがにないだろう。このアパート壁が薄いから、変なことすると隣の人に聞こえちゃう。そういえば、昔、おばさんに嫌味っぽいこと言われたことがある。でも、約束したなら多少のことは我慢しないといけないのか? どうするかぁ? どうする、どうするんだ、わたし!
啓斗はカバンから、思いのほか小さな箱を取り出す。中身を見せられる。
あまりにも唐突で、一瞬、意味が把握できなかった。
こんなのでグリグリされたら相当に痛いぞ! というのが、悲しいかな、わたしの最初の印象だった。
――中にはゴツゴツとした、ダイヤの指輪が入っていた。
彼氏が料理を作るわけ
読んでいただきありがとうございます。