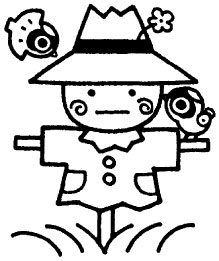雨が降る月曜日の朝に
――不快な音色が聞こえる。
地獄の世界へと引き込もうとするこのしらべ。やすやすと屈するわけにはいかない。勝ち目のない勝負であることは承知している。しかし、最後のときがくるまで、抗い続ける。そう、啓斗は心に誓った。
啓斗は手を伸ばし、指先の感覚だけで辺りを探った。――何も見えない。いや、見てはいけない。瞳を開けてはならないのだ!
指先に意識を集中し、啓斗は探り続けた。指先に何かが当たる。――これは? いや違う。こんな形ではなかったはずだ!
さらに奥へと手を進めた。冷たく硬質のものを指先に感じた。滑らかな球形の物体。その頂に扁平な突起物がある。
――こっ、これだ! 啓斗はその突起物を球体に埋没させた。とたんに音は止み、静寂が訪れる。どこからか雨の音がした。その音が静寂をいっそう深く際立たせる。暗く深い海の底へ、啓斗はゆっくりと沈んでいく。
啓斗の遥か下から咆哮が聞こえる。戦いはまだ終わっていない。簡単に逃げおおせるはずがない。静寂を引き裂くかん高い声が、地の底から響きわたる……
「啓斗、そろそろ起きなさい!」
一階のキッチンで母親が叫んでいる。
「もぅちぇぇーっ」とりあえず、啓斗も低く吠えて応酬する。
母親の声の調子からして、緊急度はレベル2、まだ慌てる必要はない。啓斗は再び布団の中に潜り込んだ。それと同時に、電子音が鳴り響く。「チェッ、またかよ」目覚まし時計の上についてるボタンを手探りで探し、憎しみをこめて叩き潰す。ボタンを押すと五分後に再びベルが鳴る仕組みだ。
雨の音だけが残っていた。布団から顔を出し、わずかに目を開ける。薄暗い部屋。窓ガラスを無数の水滴が覆っていた。その向こうには、その重みで世界を押しつぶしてしまいそうな暗雲。「ハァーぁ」雲よりも重たいため息をつく。「――月曜日かぁ」啓斗は布団の中の世界に舞い戻り、最後の抵抗を試みる。
その後、二回ほど目覚ましの奴をやっつけた。五分間のなんと短いことか。時間の流れは一定でないと、アインシュタイン君は言っていたが、なるほど、彼の言い分にも理があるなどと寝ぼけているうちに、レベル4の母親の声が聞こえた。
「啓斗! もぅ、いい加減にしなさい!」
抵抗もここまでと、投降を覚悟する。
ゆっくりと布団から頭をもたげる。重い。重みに耐えられず、もう一度布団に崩れ落ちる。昨日も雨だったので、一日中ゲームをしていた。深夜までやっていたので、目がチカチカする。こめかみから後頭部にかけて、鈍い痛みが走った。
何事でも、一日専念して取り組むと、それなりの充実感を得ることができるが、ことゲームにおいては、なぜその充実感が得られないのだろう。レベルを五つも上げたのに、疲労感と虚無感しか残らないのは、なぜだろう。そうと知りながら、自分が一日中ゲームを続けてしまうのは、なぜなのだろう。うつぶしたまま啓斗が考えていると、目覚まし時計が電子音を鳴らし始める。
「お前もよく働くねぇ」
啓斗は時計の頭を力いっぱい叩きつけると、その勢いで、布団から起き上がった。
窓の外にはまだ雨が降っていた。いかにも陰湿な降りかたである。シトシト、ジトジト、ベタベタ……
「ハァーぁ、月曜日かぁ……」
啓斗は洗面所に向かい、これ以上ない程簡単に顔を洗い、それ以上簡単に歯を磨いた。一階のダイニングに向かう。いつもは日当たりがよく、朝日が眩しいほどだが、今日はあまりの暗さに蛍光灯がついていた。その青白い光が、羽音のような雑音が、陰気な雰囲気をより強く演出している。
母親はカウンター越しにあるキッチンに立ち、シンクの中の食器を洗っていた。
「朝の挨拶ぐらいちゃんとしなさいよ! まったく!」
天気の悪い日は、母親の機嫌も悪い。ピリピリとした電気のようなものが含まれている。不用意に触れると甚大な被害をこうむる。
「……ぉはょぅ……」啓斗はどうにか声を絞り出す。やけに陰気なくぐもった声になってしまう。
キッチンにいる母親は、聞こえなかったのか、食器を洗い続けていた。
「おはようございます! 今日は六月二十八日月曜日、梅雨前線どまんなかー」
テレビではやたらに元気なアナウンサーが、傘をさしながら中継をしていた。どうしてこんな日にあんな笑顔で大きな声が出せるんだろう。啓斗は信じられないという顔で、テレビを見つめた。
「朝ごはんは?」
「ん? 時間ないからいらない」
「朝ごはん食べるくらいの時間の余裕持って起きなさいって、いつも言ってるでしょ! 朝ごはん食べないからいつもそんなぼうっとした顔してるのよ。だいたい、来週からテストでしょ! ちゃんと勉強してるの?」
憂鬱な雨の月曜日の朝に、このテンションで攻められるのは非常に辛い。辛い、つらい、ツライ…… 体が床の下に沈んでいく……。
だいたい、自分の顔がぼうっとしているのは、朝ごはんのせいではなく、半分はあんな顔の亭主を選んでしまったあなたのせいなんだと、そして残りの半分は、まさしくあなた自身のせいなんだと、反発する気もおきなかった。
「野菜ジュースだけでも飲んでいきなさい」
母親は啓斗の前に、ジョッキ一杯の濁った暗褐色の液体を差し出した。トマトとニンジンをベースに、セロリやらアセロラやら青汁やらがブレンドされている。いわば母親の愛情たっぷりジュースだ。ちなみに、これを拒否する権利は啓斗にはない。それは繰り返し実証済みで、拒絶したらどんなことになるか十分承知している。啓斗は黙って、それの処理に取りかかった。
「今日の血液型競技会、最下位はAB型でした」
啓斗は半分くらい飲んだジュースを噴き出しそうになる。
テレビで血液型占いをやっていた。まさしく啓斗はAB型、何でこんな憂鬱な気分の日に、朝から最下位とか言われなきゃいけないんだ!
「今日は、考えたことが裏目に出ちゃう日。恋人と喧嘩したり友達に裏切られたりしそう。気をつけてくださいね。ラッキーアイテムはピンクのハンカチでぇーす」
だいたい、公共の電波で、占いとか流すの反則だと思う。雑誌ならそのページを見なければすむけれど、テレビだとそうはいかない。つけっぱなしにしていると、気が付いたときには占いが始まっている。こっちが望んでもいないのに、勝手に運勢占って、今日はついてないよとか言うのって、余計なお世話だ!
啓斗は腹立たしい気持ちをぶつけるようにテレビのチャンネルを変えた。
「ごめんなさい。今日、運勢が最悪なのはおうし座の方でぇーす!」
今度はジュースが本当に鼻から出た。青汁の臭いが鼻腔全体に広がる。
言うまでもないが、啓斗はおうし座だ。
「おうし座の人は注意力が散漫になしそう。犬に噛まれたり、穴に落ちたり、落下物に当たったりしそうだから、周りの状況には十分注意してくださいね。幸運を呼ぶ食事は『豚キムチ納豆チャーハン』ですよ」
「……さ、最悪だぁ。だいたい豚キムチ納豆チャーハンってなんだよ。そんなもんどこ行ったら喰えるんだよ!」
ひとしきりテレビに突っ込みを入れた後、時計を見るともう家を出なければいけない時間になっていた。
「母さん、ハンカチどこ?」
「啓斗がハンカチ持っていくなんて珍しいわね。いつもの引き出しのところにあるよ」
啓斗は引き出しを開け、綺麗に畳まれた家族全員のハンカチの中から、母親の物であろうピンクのハンカチを取り出すと、乱暴に制服のポケットに突っ込んだ。
「行ってきます」
玄関の扉を開けると、まだ雨は降り続いていた。傘を差し、雨空を見上げる。一歩踏み出したとたん、あれ? 独特の浮遊感に見舞われた。
「玄関のところ、水道工事で穴掘ってあるから気をつけてね」
啓斗は母の声を、斜め四十五度に傾きながら聞いた。
何で今頃言うかなぁ! 完全に手遅れ――、とひとりごちながら、啓斗は穴に落ちていく。
穴といっても五十センチほどの深さ、倒れずにはすんだが、学生服の膝と肘は泥だらけになっていた。
ちょっと待てよ、着替えてる時間ないんだけど。
啓斗は悪態をつきつつ、穴から這い出る。靴箱にあった、靴磨き用のボロタオルで大まかに泥を拭き取り、諦めて学校に向かった。
確か穴に落ちるようなこと占いで言ってたよなぁ、当たってるじゃん! やばいなぁ……
真っ黒な雲で覆われた空を見る。落下物っていったって、いったいどうやって気をつければいいんだ。傘なんて差してたら、上から何か落ちてきたって、見えないよな。
一瞬、傘を差すのをやめようかと思った。雨の中、テレビの占いを気にして濡れながら歩く自分の姿を想像する。そのくらいならば落下物に当たって死んだほうがましだと思うだけの、少しばかりの良識は残っていた。
この雨ならさすがに犬は大丈夫だろう、そう思った矢先に、黄色のレインコートを着た犬が、リードをグイグイ引っ張り、お揃いの黄色のレインコートを着たオヤジを、まるでお供のように従えて前からやってきた。
何もこんな雨の日に、こんな時間に、よりによってこんなコースで散歩なんてしなくたっていいだろう。一本道で迂回できる道はない。啓斗が固まっていると、オヤジを従え前からゆっくりと近づいてくる。
突如として雷鳴がとどろき、雨が激しく降り始めた。ややうつむき加減に歩く犬の目は、レインコートのフードに隠され、見ることができない。
口もとに牙がむき出しになっていた。チロチロとうごめく赤く濡れた舌。
啓斗は道の片隅により、通り過ぎるのを固唾を呑んで見守った。
犬は自分のことを嫌っていたり、恐れていたりする人間が、本能的に分かるという。このただならぬ啓斗の気配を感じ取ったのかもしれない。
すれ違いざま、フードの下の目と、啓斗の目が合った。啓斗は感じた。
――野獣の目だ。
「ウーッ、ワン」
吠えたかと思うと、啓斗に飛びかかろうとする。驚いた啓斗は三十センチ飛び上がり、水溜りに足を突っ込んでしまった。
「コラ! やめなさい。どうもすみません」
飼い主のオヤジはリードを引きながら、水溜りに足を突っ込んだまま恐怖に固まっている啓斗に軽く会釈する。しかし、その口もとに微かな嘲笑が浮かんでいた。
「おはよう」
突然声をかけられ、再び啓斗は飛び上がる。同じクラスの佐竹が後から追いついてきたのだ。
「何そんなびっくりしてるんだよ」
「いや、何でもない」
「それにしても、今すれ違ったチワワ可愛かったなぁ。あんなレインコート着てチョコチョコ歩いてたら、抱きしめたくなるよなぁ」
「そっ、そうか? よく見てなかったから気が付かなかった……」
佐竹は目を細め、値踏みするように啓斗を見た。
「――嘘つけぇ」
啓斗は背中にゾクリとしたものを感じた。
「見てたのか?」
「ああ、しっかりな。でも心配するな。このことは誰にも言わへんから」
何で急に関西弁ぽくなるんだ! 目じりと口もとが笑ってる。鼻を含めた顔を構成するパーツ全てが笑いを堪えている。絶対に嘘だ!
一瞬、啓斗に殺意が芽生えた。この道には啓斗と佐竹しかおらず、他に目撃者はいない。啓斗の頭は、父親から譲り受けた十年落ちのマッキントッシュ並みのスピードで計算した。
もし、殺人を犯すなら、完全犯罪をしなければならない。啓斗は周りを見回した。まずい。こんな路地では密室を作ることができない。しかも、徒歩での通学途中である。はやぶさ三号を使った、時刻表トリックでアリバイを作ることも不可能だ。せめて、小学五年のときに作った氷のナイフだけでもカバンの中に入っていたなら……
――最悪だぁ。
啓斗は殺人計画をあきらめ、ポケットの中のピンクのハンカチを強く握り締めた――
どうにか教室までたどり着くことができた。これで、少なくとも教室内にいるあいだは、犬に噛まれたり、落下物に当たる危険は少ないだろう。
「おはよう。朝から雨降りさんですね」
境沼詩織が啓斗の机の前に立っている。口を尖らせ、目をパチクリさせながら啓斗のことを見つめている。タコのまねでもしているのかと思ったが、どうやら違うらしい。
身長百五十三センチ、目が大きくクリッとしている。笑うとえくぼができて、髪型はツインテール、子供料金で電車に乗ったとしても、誰にも咎められないだろう。
信じられないことにゴールデン・ウイーク前、詩織のほうから啓斗を映画に誘ってきたのだ。詩織は啓斗のことを世界一のイケメンだと思い込んでいる。ナメクジや芋虫、タランチュラからコモド・ドラゴンまで可愛いという彼女の美的センスはあなどれない。
映画の題名は『魔法プリンセス・くるくるパラりん』。周りの幼稚園児と一緒になって、「キャー、危ない! 逃げてぇー」とスクリーンに向かって叫ぶ詩織。
帰りに寄ったファミレスで、「くるくるパラりん、詩織のことを大好きになぁーれ!」魔法プリンセスのまねをした詩織が、パフェについてきた長いスプーンを振り回し、啓斗に向けたとき。
――可愛い!
啓斗は本当に魔法にかかってしまった……
占いで恋人と喧嘩するかもって、言ってたよなぁ――恋人かぁ…… 恋人の定義ってなんだろうと啓斗は考える。手はつないだことはあるが、キスや、ましてやあんなことやそんなことは恐れ多く、まだ一歩たりとも近づけないこの関係は、恋人といえるのだろうか?
そんな想像だけで顔を赤らめる、思いのほか純情な啓斗であった。
教室の端では、佐竹が数人のグループで話をしていた。再び、啓斗に殺意が芽生えてくる。
教室であれば密室を作ることができる。三時間目は体育なので、教室から人がいなくなるチャンスもあるはずだ。水滴の滴る窓を見つめる。教室にはかなりの数の窓があった。これを全部閉めて、鍵をかけるのはけっこう面倒くさそうだ。――心が折れそうになる。そして、廊下に出る扉を見て絶句する。
――かっ、鍵が付いていない! これでは密室は作れない!
失望による虚脱状態のまま後ろの扉を振り返ると、その横に置いてある掃除器具を入れるロッカーが目に入った。ロッカーには鍵が付いていた。幸いにしてロッカーの扉は歪んでいるので、上部にわずかな隙間がある。佐竹をロッカーの中で殺して、鍵を閉め、隙間から鍵を中に入れれば完全な密室殺人が出来上がる。啓斗は自分の立てた完璧な計画に、にんまりとほくそ笑むのであった。
――問題は、ロッカーの中にどうやって佐竹を誘い出すのかと、狭いロッカーの中でいかにして佐竹を殺すかだ。
自分のアリバイを作るために、体調が悪いと言って保健室へ行き、保健室の掛け時計を十分進め、その他の学校中の全ての時計を十分遅らせるという、時計を使ったトリックを考案している最中、みんなの爆笑の声で啓斗は我に返った。
そちらを向くと、佐竹の周りで話を聞いていた生徒たちが、腹を抱えて笑っていた。啓斗と目が合うと、全員いっせいにそらす。啓斗は視線の端に佐竹の唇が『チワワ』と動くのを、確かに捉えた。それに合わせて、全員がいっせいに笑い出す。
……手遅れであった。
口封じのための『清掃器具ロッカー密室殺人事件』は時機を逸してしまった。
佐竹は話し上手だ。小さな話を、何倍にも膨らませ、臨場感たっぷりに面白おかしく話すその技術は相当なものだ。クラスの女子まで、佐竹の話の輪に加わり始めた。一段とグループの輪が広がる。
……最悪だ。
啓斗はうなだれる。その手に、祈るようにピンクのハンカチを握り締めながら……
啓斗の横に、何か言いたげにモジモジしながら詩織が立っていた。
「ん? どうした」
「…………」
モジモジしている姿もけっこう可愛いな、なんて思いながら啓斗は頬を赤く染める。
「……今日、啓斗くんのためにお弁当作ってきたんだょ。食べてくれる?」
「――うっっおおぉっ」
啓斗が夢にまで見ていた手作り弁当だ。テンションは一気に上がる。これぞ恋人の証と言っても決して過言ではない。
生まれて初めて母親以外の人からもらう手作り弁当。一瞬、目頭が熱くなる。しかし、このくらいのことで、男子たるもの涙を見せるわけにはいかない。下唇をグッと噛みしめ、啓斗は耐えに耐えるのであった――
◇◇◇◇◇
その頃、地上四十八万キロの上空、月軌道(約三十八万キロ)の外側に、秒速十三キロで地球に向かう直径一メートル五十センチの隕石があった。
地球到達時刻は本日午後六時五十四分。このスピードで大気圏に突入した場合、燃え尽きずに三十センチほどの固体が、地表にまで達すると思われる。その場合、深さ二メートル、幅七メートルのクレーターを地表に形成させる。
隕石は音もなく、まるで何かの意思を持っているかのように、地球上のある一点を目指し、宇宙空間を猛スピードで進んでいた。
◇◇◇◇◇
昼休みになると、佐竹の噂話はすでに沈静化していた。そもそも、啓斗のキャラクターははじめから『ちょっと頼りない奴』であり、その『ちょっと頼りない奴』がチワワに驚いたからといって、それほど意外性があるわけでもなかったようだ。佐竹がどんなに脚色し、面白く語ったとしても、話の賞味期限は半日で過ぎてしまった。もう誰も、啓斗のことを盗み見るような人間はいなかった。あまりにも速い沈静化に、啓斗自身なんだか物足りない気さえしていた。
そんなことはどうでもいい。待ちに待った昼休みである。詩織と密かに校舎の屋上で待ち合わせをした。朝からの雨はどうにかやんでいたが、空は相変わらず重苦しい雲に覆われていた。屋上のコンクリートも渇いておらず、雨上がりの湿気に包まれている。こんな日に屋上に出てくるような奴はいないらしく、屋上にいるのは二人きりだった。
「今日のモーニング・スタジオ見てたら、おうし座の幸運を呼ぶ食べ物をやってたんだぁ。啓斗くんおうし座だよね?」
「もしかして、豚キムチ納豆チャーハン?」
「啓斗くんも見てたんだぁ。昨日のご飯の残りでチャーハンが丁度あってね、キムチと納豆があったから、啓斗くんのために作ってきたんだよ」
啓斗はそこはかとなく不安を感じた。その不安は悪い予感へと姿を変え、啓斗のテンションを少しずつ押し下げていく。
二人は貯水槽のわきの、コンクリートが段になっているところに座っている。
「はい、これが啓斗くんのお弁当ね。詩織はお母さんが作ってくれたのがあるから」
詩織は啓斗に弁当箱を渡すと、膝の上にハンカチを敷き、自分の弁当箱の蓋を開けた。卵焼きに、鳥のから揚げ、たこさんウインナーまで入った、典型的な美味しそうな弁当だ。
啓斗は渡された弁当箱の蓋に手をかけた。にっ、臭いがぁー! 予感は確信へ変わる。これはやばい!
恐る恐る蓋を開けた。封印された魔物が飛び出すように、閉じ込められていた臭気が襲いかかってきた。
梅雨の時期、昨日の残り物のチャーハンというだけで、リスキーな雰囲気が漂う。そのチャーハンの中にキムチと納豆が無造作に混ぜ込まれている。しかも、炒めなおされてはおらず、ただ混ぜてあるだけだ。キムチの汁がチャーハンをぐちゃぐちゃの赤色に染め、納豆と混ぜられた米粒の一つ一つが粘々としていた。蓋には納豆が三粒ついており、弁当箱との間で長い糸を引いていた。
「このチャーハンは詩織が作ったの?」
「ううん。昨日の昼にお母さんが作ったやつ」
詩織は無邪気に笑いながら言う。
――うっぅっっ……!
母親が作ったチャーハンにキムチと納豆混ぜたのって、詩織が作った弁当ってことになるのだろうか?
啓斗は下唇を強く強く噛みしめた。
しかも、チャーハンは昨日の夜ではなく、昼の残りらしい……
「どうぞ。召し上がれ」
詩織は啓斗のことを見つめ、微笑んでいる。多分、詩織には悪気はないのだと思う。そう信じたい。
――詩織は啓斗のことをじっと見つめている。パチクリ、パチクリ、パチクリ……
「どうぞ、どうぞ」
啓斗は窮地に立たされていた。絶体絶命のピンチ。勇気を出して箸を握るが、その箸を動かすことができない。額に玉のような汗が浮かぶ。
「食べないのぉ」
「いや、もうすぐ食べる」
「早く、早くぅ」
「うん……」
「……」
「…………」
「詩織がせっかく啓斗くんのために作ってきたのに食べてくれないんですね。もう知らない、知らない!」
詩織は自分の弁当を丁寧にわきに置くと、金網のフェンスに向かって駆け出していく。
啓斗は慌ててその後を追いかける。
「ごめんよ。ちょっと待ってよ」
「詩織はもう死んでやるんだからぁ!」
詩織は金網をよじ登ろうとしている。啓斗は慌ててそれをとめようと、詩織の腕をつかんだ。
――ガブリ。
啓斗の腕に詩織が噛みついた…………
どうにかさっき座っていた貯水槽のわきまで詩織を連れ戻してくる。噛まれたところに歯の形の痕がくっきりとついていた。薄っすらと血まで滲んでいる。
詩織は隣で両手で顔を押さえ泣いていた。ん? 本当に泣いてるよね?
「ごめん、何か食べるのがもったいないかなぁなんて…… 詩織、愛してました。いただきまぁす」
啓斗は遺言を言うように言葉をはくと、覚悟を決めて、弁当を一塊口に入れた。想像以上の衝撃が、口腔全体に広がる。えーいと、勢いで三分の一ほどかき込んだが、苦しい。たまらずに一呼吸おく。キムチの辛味と酸味が口の中に広がる。この酸味は、キムチのものだけでないのかもしれない。やけにすっぱい。
悶絶し、意識が遠くなり始めた。このまま意識を失うことができたなら、どんなに幸せだろう。口の中全体に広がる粘々感。内臓全体が拒絶している。
内臓の反乱など力ずくで鎮圧する。強引に咀嚼した。しゃにむに嚥下する。安堵の吐息を漏らす。フー。いけない! 息が、臭いに犯されている。
――弁当はまだ半分残っている。
ここからは、消耗戦である。一気に攻撃を仕掛けるような体力はもう残っていない。ゲリラ的な攻撃を散発し、一進一退の攻防を繰り返した。最後の納豆の一粒を完食し、勝利の丘に星条旗を突き立てるような気分で、弁当箱の中へ箸をしまう。何事も中途半端な啓斗にとって、久しぶりに感じる達成感だった。
啓斗は詩織のほうを向き、拳に親指をグッと突き立て、笑顔を作った。
「美味しかったよ」
弁当を作ってもらった者の、当然のマナーである。犬歯の間でキムチのカスがオレンジ色に輝いていた。上唇と下唇が触れ合うたびに、糸を引くような粘り気を感じる。
「本当に? よかった」
詩織は顔を覆っていた手をどけ、微笑を返す。
詩織の頬には一筋の涙の跡がついていた。啓斗は一瞬でもこの純心無垢な彼女のことを疑ってしまったことを深く後悔した。
「さあ、これで涙を拭いて」
啓斗はポケットの中にあったピンクのハンカチを詩織に差し出す。
「ありがとう」
詩織は受け取ると、涙の跡を拭いた。
安心すると、噛まれた痕が鈍く疼き始めた。
「ごめんね。大丈夫かにゃぁ?」
「まあな。そういえば詩織の苗字、境沼(サカイヌマ)だよな。苗字の中にイヌって入ってるじゃん。これで犬に噛まれるってのと、恋人と喧嘩するっていうの、二つともクリアだな」
思わず恋人などと言ってしまい、啓斗は頬を赤らめる。詩織もうつむき、はにかんでいる。
「でも、詩織の苗字にイヌが入ってるからって、それはずいぶん強引ではないですか?」
「そうかなぁ、まぁ、気持ちの問題だし、いいんじゃないかなぁ。それに詩織、動物にたとえると、猫とか狐とかに比べたら、一番犬っぽくね。そういうことでいいよ」
「プーっ、詩織は犬じゃありません! うさぎたんですぅ!」
詩織は頬を膨らませて、啓斗のことを見つめている。もちろん目をパチクリさせることは忘れていない。
――可愛い!!
啓斗は目を奪われたまま動けない……
◇◇◇◇◇
上空三十万キロ、月軌道の内側に入り、依然として秒速十三キロのスピードでばく進する隕石。啓斗が弁当の最後の一口を飲み込んだ丁度そのとき、異変が起きた。何かと接触したのである。それは一メートルほどの鉄板のようなもので、よく見ると十三という数字がどうにか読み取れた。まさしくアポロ十三号が事故を起こしたときに飛散した、金属片の一部であった。
この衝突によって、隕石の軌道にほんのわずかなズレが生じた――
◇◇◇◇◇
「ん、ん! こっ、これは! ケロケロ大将ではないですか」
詩織はピンクのハンカチを広げると、とんでもないお宝を発見したように言った。
多分何かの景品でもらったものなのだろう。ハンカチにはカエルの形をしたキャラクターが印刷されていた。
「詩織は、ケロケロ大将が昔からだいだい大好きなんですよ!」
「ピョコタン、ピョコタン、ピョコタン――」
詩織は両手のひらを耳の上に開いて、ジャンプを始める。最初、呪いの踊りでもはじめたのかと思ったが、どうやらケロケロ大将のまねをして跳ねているようだ。それにしても、手を耳の形にかざすのはウサギのまねだろう、と思ったが、そういった細かいデテールはさほど問題ではないらしい。
先ほどまでの暗い雲に亀裂が生じ、その間から光の束が差し込んできた。さながらスポットライトのように、跳ね続ける詩織を照らしだす。こんじきに輝く光の中、詩織はウサギだかカエルだかのまねをし続ける。
「ピョコタン、ピョコタン、ピョコタン――」
もちろんこれは、詩織が口で言っている。
啓斗はその姿を瞬きもせず見つめていた。
――かっ、可愛い!!
そのジャンプには、本当に呪いの効力があるのかもしれない……
放課後、部活が終わって校門を出ると、そこで詩織が待っていた。
「こんな時間まで、どうした?」
「……一緒に帰ろうと思って待ってたんだよ」
恥ずかしそうに笑う詩織。授業が終わって、三時間以上過ぎていた。先ほどまでの雲は完全に消え去り、今にも沈みそうな赤く染まった太陽が、詩織を茜色に染めていた。学校は高台に建てられている。そこから見える家々の屋根、少し遠くに見える駅前のビルディング群、その向こうに見える突き出した半島と海、全てが輝くオレンジ色の世界に包まれていた。
「帰ろうか」
詩織は啓斗に手を差し出す。啓斗はその手をつかむと、一緒に坂を下り始めた。夕日は詩織と啓斗を燃え立つような赤に染め、地平の向こうに沈んでいく。
「何か気持ちのいい天気だね」
「このところ雨とか曇りばっかりだったからな。久しぶりに太陽みたよ」
「太陽さぁーん。明日も出ておいでねぇー」
詩織は大きな声で叫んだ。太陽は完全に沈み、世界を包む茜色は、より濃く、深く暮れていく。
「啓斗、聞いてもいい?」
「なに?」
「チャーハンとピラフってどこが違うの?」
「知らないけど、同じようなもんじゃねーか」
「本当に? よかったぁ」
「なんで?」
「今日のお弁当のチャーハン、ニチスイの冷凍ピラフってやつなの。お母さん作るの上手なんだ。クラスの佐代子に言ったら、ピラフとチャーハンは違うって言うの。一緒だよね!?」
「多分な」
「あー、よかった」
チャーハンは炊いた飯を具材と炒めたものだが、ピラフは洋風の炊き込みご飯だ。
――別ものである。
そんなことは、詩織と手を繋ぎながら歩いている啓斗にとって、どうでもよいことだった。
前から、ドーベルマンを連れたオヤジが近づいてきていることも、その首輪の留め金がゆるんでいることも、ビルの看板がユラユラ揺れていることも、五階のマンションの窓際で、今まさに大きな鉢植えに水をやろうとしている主婦がいることも、詩織の手のぬくもりだけに集中している啓斗にとってはどうでもよいことだった。
「あ!」
「あぁ! ……」
「見たぁ?」
「うん」
「すごい大きな流れ星だったね。それに長かった。頭の上から、スーって海の向こうまで流れていったよ」
「そうだな、こんな大きな流れ星見たの初めてだよ」
「何かお願い事した?」
「まぁな」
「何、なに?」
「詩織は?」
「わたしは、これからもずーっと、ずーっと、啓斗くんと一緒にいられますようにって、お願いした」
「啓斗くんは?」
「えっ? まぁ……、俺もそんな感じ……かな……」
「本当に! 二人で同じお願いしたなら、きっと叶うよね」
詩織は笑っている。
流れ星を見た瞬間、思わず明日の血液競技会で一位になることを願ってしまった。このことは、決して誰にも言わないでおこう。啓斗は固く心に誓うのであった――
完
雨が降る月曜日の朝に
読んでいただきありがとうございました。