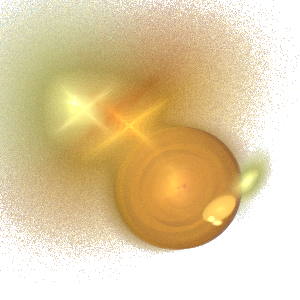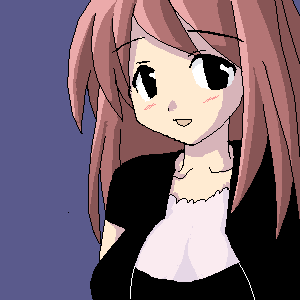
姉貴
「青木の奴、頭おかしいぜ、絶対」
高校のカフェテリアで昼の食事をとっていると、吉田が呆れたような顔をして言った。僕は今まで目にしたことのない吉田の表情を見て、箸を止めた。
「何かあったの?」
「あいつと日曜にカラオケに行ったんだけど、その時何か変な話されて。気味悪いわ」
「へえ。どんな話?」
「山本、この話、お前にだから言うんだぜ。絶対秘密だ。ましてや俺が言っていたなんて言うんじゃねえよ。他言無用だからな」
家に帰ってきたらさ、姉貴が、俺の姉貴がさ、二人になってたんだよ。信じられないかも知れないけど、本当の話なんだよ。俺だって信じられないから、マジで驚いた。
まず帰ってきて、何か食うもんはないかと居間に行ったらさ、姉貴がいたんだ。まあそりゃおかしいことじゃない。その日は姉貴は大学が休みで、バイトもなかったからな。そんな日はいつも姉貴は居間でテレビを見てるか、ネットをしてるかどっちかなんだけどさ。
でも何だか、姉貴の様子がおかしい。俺の目の前で、ソファーに横たわりながらハナクソをほじってやがったんだ。ガリガリとね。もちろんそんな音は実際はしなかったんだけど、そういう音が聞こえるほど激しいハナクソのほじり方だった。
いつもは人の前で、家族の前でさえもハナクソをほじるようなみっともないことをする人間じゃないんだ、姉貴は。何て言うのかな、どっちかと言うと、自分が高潔でありたいタイプ。だから、姉貴がハナクソをほじる光景が俺には信じられなかった。
もしかするとテレビに集中していて俺がいることに気付いていないのかも知れない、と俺は思った。だから俺は声を掛けたんだ。「姉貴、ただいま」って。
そしたら姉貴は、何て言ったと思う?「お前、うるせえよ、バーカ」って。あの姉貴がだよ。「お前、うるせえよ、バーカ」って言ったんだよ。姉貴は、そんな暴言吐いたこともないんだ。いつもの姉貴は、優しいとまでは言えないけど、さっきも言ったように高潔でありたいタイプ。だから直接的な暴言は吐くことがない。暴言すら吐くこともない。例えばこういう場合、いつもの姉貴なら、「ちょっと静かにして」とでも言うはずだったんだろう。でも今聞いたのは、直接的な暴言だ。
そんな姉貴の返事を聞いて、俺は心が冷える思いがした。何があったんだろう、これはいつもの姉貴じゃない、ってね。きっと俺がいない間に何かあったんだろう、彼氏か友達と酷い喧嘩でもして、今までになく不機嫌なのかも知れない。こういう場合は、関わらないのが一番だ。触らぬ神に祟り無し。それで、俺は二階の自分の部屋へ戻った。
階段を上っている途中、丁度階段を降りてくる姉貴に会ったんだ。俺と目が合うと、「トモくん、おかえり」って笑顔で俺に声を掛けた。あれ? あれ? 何かがおかしい。姉貴、さっき居間にいたよな。居間で俺に「うるせえよ」って言ったよな? ん? 俺は全く困惑したね。
決して幻覚なんかじゃない。目の前には、笑顔の姉貴がいる。居間には、不機嫌な姉貴がいた。どちらも同じ服装だった。ということは、俺が階段を昇ろうとする間に、不機嫌な姉貴は二階へ行って、笑顔で俺を迎えてくれた? いや、無理だ。物理的に、無理な話なんだよ。あり得ない。
「あれ、姉貴、さっき、居間にいなかった?」って、俺はもちろん訊いた。誰もがこんな状況に遭遇したら、言うようにね。それに対する姉貴の答えは、ノーだった。
「居間になんかいないよ。今までずっと二階で本を読んでいたんだから。ああ、そうだ。井伏鱒二の山椒魚、トモくんの本棚から勝手に借りたけど、ごめんね」
姉貴はとろけるような笑顔でそう言ったんだ。いや、別に勝手に本を借りてもいいんだけどさ、というかね、姉貴が本を読むなんて珍しいことだったから、俺は少しびっくりした。それに俺の呼び方だよ。トモくん、だなんて姉貴はこれまで一度もそんな風に俺を呼んだことはないんだよ。俺のことを呼ぶときは、トモ、って呼んでたんだけどさ。それが、トモくん、だよ。異常だよ、これは。
ていうかね、そもそも姉貴は居間にいなかったと言っている。じゃあ居間にいた姉貴は何なんだ? あの不機嫌な姉貴こそ、俺の見た幻覚なんじゃないかと思って、俺は確かめに居間に戻ったんだ。
そしたら、やっぱり姉貴はいた。相変わらずソファーに横たわっていたんだけど、何だか部屋が煙臭い。姉貴を見たら、今度は煙草を吸っていたんだ。煙草だ。姉貴はまだ十九歳なんだぜ? それがむくむくと白い煙を上げながら、煙草を吸っていたんだ。ハナクソ然り、俺は姉貴が煙草を吸う光景を見たことがない。隠れて吸っていたのかも知れないが、俺には姉貴が堂々と煙草を吸うなんて信じられなかったんだ。
これは……これは、姉貴じゃない。俺の姉貴は、人前でハナクソをほじることもないし、うるせえよ、なんて言わないし、もちろん煙草も吸わない。この目の前にいる人間は、姉貴じゃない。外見は姉貴そのものだけど、中身は全く違う人間だ。いや人間じゃないのかも知れない。姉貴そっくりに化けた、妖怪かも知れない。すると何だ、妖怪がこの家に紛れ込んだということなのか。俺は怖くなって、本当の姉貴であろう姉貴の所へ戻ったんだ。
姉貴は、玄関にいた。掃除機を回して、掃除をしていたんだ。普段の姉貴は、わざわざそんな面倒くさいことなんてしない。それが今は、鼻歌を歌いながら楽しそうに掃除をしていたんだよ。
やっぱり、こちらの姉貴も何か違う。訝しげに姉貴の様子を見ていると、姉貴が俺に気付いたようで、掃除機を止めてこちらに笑顔を向けた。
「姉貴が掃除だなんて、何だか珍しいな。槍でも降ってくるんじゃないの」
「やだあ、トモくん。あたしだって、掃除くらいするよ」
いや、この姉貴も、何だかおかしい。普段の姉貴なら、俺の嫌味に対して嫌味で返すはずだ。それが今はどうだ、さっきと同じとろけるような笑顔で、嫌味の一つも感じられない返事を返したんだ。あり得ないよ。
狼狽する俺に追い打ちを掛けるかのように、姉貴は言った。
「あっ、そうだ、トモくん。この前トモくんが買ったゲームあるでしょ? 何だっけ、何とかハンターとかいうやつ。あたしもやってみたいなあ。後で一緒にやろうよ」
もう、俺はダメだと思ったね。この目の前で笑顔を惜しげもなく振りまいている人間も、本当の姉貴じゃない。姉貴は俺の買ったゲームになんか興味も持たないはずなんだ。ゲームなんて、馬鹿馬鹿しい。そう公言する人間だったんだよ。だから目の前のこいつも、妖怪だ。姉貴に化けた、妖怪だ。
俺はその笑顔の妖怪に返事をせずに、自分の部屋へと向かった。去ろうとする俺に、妖怪が後ろから言ってきた。「あっ、トモくん、部屋で待っててね。掃除が終わったら、行くから」
やめてくれ、来ないでくれ、来るな。お前も姉貴じゃない。お前は妖怪だ。姉貴はいない。まだ家に帰ってきていないんだ。家にいるのは、俺と、二匹の妖怪だ。妖怪なら、早く消えてくれ。消えてくれ。
俺はそう願いながら、部屋に篭もった。幸い、あの笑顔の妖怪が来ることはなかったんだ。ああ良かった、と俺は思って、そろそろ夕食の時間だから居間へ戻ると、俺はびっくりした。あの妖怪、姉貴に化けた妖怪たちが、二人揃って座っていたんだ。両親は両親で、何も不思議がる様子もなく、妖怪たちと一緒に座っていた。
「あっ、トモくん、ご飯できてるよ」
「おせえんだよ、お前。メシが冷めるだろ」
姉貴に化けた妖怪が二人、それぞれ俺を見てそう言った。その時、俺は理解した。理解できなかったけど、理解せざるを得なかったんだよ。
姉貴は、分裂してしまったんだ。
「そんな話だよ。山本、お前も訳が解らないだろ? 青木の奴、本当に頭がどうかしちゃったのかも知れないな」
青木からの話を伝え終えた吉田は、ため息をついた後に一気にコーヒー牛乳を飲み干した。一気に喋ったものだから、喉が渇いたのだろう。
「いや、意外と事実なのかも知れないよ」
僕は半笑いをして、そう言った。
姉貴