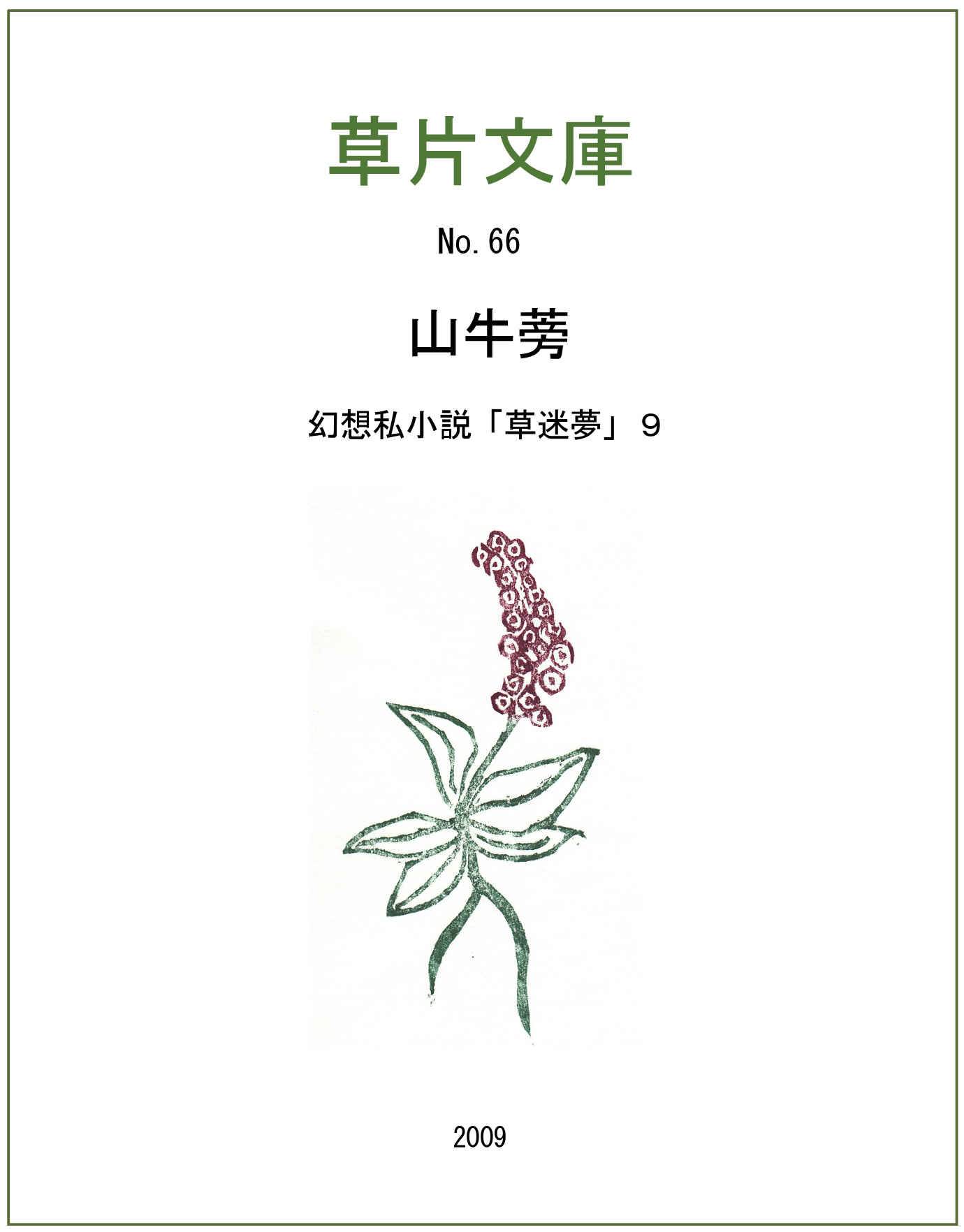
山牛蒡(やまごぼう)-幻想私小説9
多摩動物園の裏の林の中、緑色の冬虫夏草が顔をだした。冬虫夏草の精となった吾はエジプトから南平にもどっていたのである。
気が付くと、白い帽子をかぶって、ステッチワークの革製リュックを肩に掛け、神社の脇を歩いている。このリュックはハンガリーに半年間滞在した時にもとめたものである。
雨が降りそうである。
南平の駅から我が家に行く途中で、もう家が見える。
山牛蒡の赤紫の実が、神社の脇のフェンスからとびだしていて、吾の白い帽子にぶつかった。実の赤紫色の汁が帽子のつばのところを染めた。
家についたら洗わなければいけないなと思いながら歩いていると、雨が降り出した。
ボコボコと音がして、雨が道路に跳ね返っている。目の前の道がみる間に紫色にそまっていく。
頭にもポコポコと当たる。
雨じゃない、山牛蒡の実が空から降ってきている。
見上げると、なんと山牛蒡が天高くそびえ、空を覆い、赤紫の実をおとしている。
子どもの頃、山牛蒡の赤い実を葡萄に見立てて遊んだり、布を染めてみたり、楽しんだものである。
我が家の狭い庭にも柿の木の根本から大きな山牛蒡が自然に生え、よい景観をつくっていた。ヤマゴボウ科の多年草で、それにしても、こんなに大きく育つとは思っていなかった。
頭に何かが触れた。見上げるとミズの葉だ。秋田からもってきたものだ。ミズも大きくなり、自分に覆いかぶさっている。
いや違いそうだ。自分が小さくなっているのだ。我が家の山牛蒡の下にいるようだ。
これは夢なんだ。
ミズの葉の陰に大きな目玉が浮いている。
目玉がひょいと動いた。よく見ると大きな金色の亀虫が触手を動かしてこちらを見ている。
金色亀虫に手を振った。
金色亀虫も右手をあげた。
「やあ」
金色亀虫は顔を出し、にじり寄ってきた。
「ここの主人じゃないか、ちいちゃくなったな」
吾はうなずいた。どこぞであった亀虫か。
「冬は天井の脇からみていた」
「なにをだい」
「みんなだ、白い猫をこねくりまわし、ぬいぐるみをひっぱたき、ウイスキーを食らって、絨毯の上で寝ちまって、よだれをたらして」
「のぞきみだ」
「へへ」
「住居無断侵入罪だ」
金色亀虫の口元がふにゃりと笑った。
「お宅らが、俺の住居に家を建てたんだ。住居侵入罪だ」
金色亀虫も理屈が通っている。そりゃこちらが悪い。肯いてやると、
「おたがいさまさ」と手を上げた。
なかなかよくわかった亀虫だ。
「これから、養老の滝まで行くのだが一緒に来ないか」
金色亀虫に誘われた。
養老の滝は岐阜にある。養老鉄道を使って一度いったことがある。岐阜の大垣から三重の桑名まで一両の電車が一時間に一本ほど走る。
「養老の滝になにしに行くのだ」
「不老不死のお水をちょうだいにさ」
死なないからだをもったら大変だろう。世の中飽きたときにどうするのだろう。
金色亀虫は人間の気持ちを読み取れるらしい。
「養老の滝の不老不死の水はからだの死をなくすのではなくて、からだの悪いところをよくしてくれるのさ」
この金色亀虫はどこか悪いのだろうか。
金色亀虫がお尻をあげた。臭いにおいが放出されるときのポーズだ。軽子の育った秋田じゃ姉子虫と呼ばれ大いに嫌われている。その匂いを思い出していると、
「心配するない、それがでなくなったのだ、亀虫は臭くなきゃね」
と、金色亀虫はウインクした。どうしてそうなったのか気になったが、いろいろ亀虫にも訳があるのだろう。根掘り葉掘り聞かれるのもいやかもしれない。
しかし、金色亀虫のほうから年取って出なくなったんだと理由を言った。もう十八年も生きているのだそうだ。
養老の滝まで行くのには相当時間がかかる。
「歩いていくわけではないだろうね」
「空気のトンネルさ」
そう言って、金色亀虫は羽を広げ、空中に舞いあがった。
山牛蒡の隙間から見上げていると、金色亀虫は空中停止をして、前足の先、すなわち手首より先をパタパタさせて吾を見ている。
吾にもそうやれといっているようだ。両腕を脇につけて手首を軽く上下させてみた。からだが浮いて持ち上がった。もう少し早く動かすと、あっという間に空中停止している金色亀虫の横にならんだ。
「できるじゃないか」
なかなか面白い。手をパタパタするとどんどん上に行き、我が家が小さくなっていく。どこまでいくのかな。
山牛蒡のわきの大きな柿の木の上でホバリングしている金色亀虫が手招きしている。下りて来いの合図だ。
手の動きをとめると、すーっと落ちてあっと言う間に金色亀虫の横にきた。
そこでまた手を動かす。ホバリングだ。近くでみると亀虫の目玉もなかなかかわいいものだ。
「前に進むにはどうやるんだい」
金色亀虫が手を前にだしてぱたぱたさせた。手の位置で進む方向が決まるのか。簡単な運転技術だ。同じようにすると前に進んだ。左手を右手より前に出してパタパタさせると左に曲がった。
勢いに乗って、家の周りをぐるぐる回ってみた。トヨに葉っぱがいっぱいつまっている。雨が降ると、じゃあじゃあと落ちてくるところだ。掃除をしたいところだが、手を止めると落ちてしまう。
金色亀虫の奴が笑っている。吾が手を前に出し、パタパタさせるのが滑稽なのだ。
「人間はみっともない格好をしているのだな」
人間が格好良いとはちっとも思わないが、亀虫だって、怪獣のような顔をしているではないか。
金色亀虫が上空に上がっていく。吾もそれについていく。
町が小さく見えるほどになると、金色亀虫は前に進み出した。亀虫の後ろについていくので、つい忘れて、
「臭いもの出すなよ」
と言ったら、金色亀虫が振りって、顔を赤くして踏ん張った。
「でねえな、ケケ」
よかった。
金色亀虫は前へ進んでいく。
眼下に湖が見えてきた。
諏訪湖だ。早いな。
中津川だ
と見る間に、金の鯱が見えてきた。
「名古屋城じゃないか」
「今日は時間がかかったな」
「リニアモーターカーより早いじゃないか」
昔、名古屋城の北側に練兵場が草原として広がっていた頃のことである。幼稚園から小学校三年まで、父親の仕事の関係で名古屋にいた。北区の公務員住宅にいたのである。そのころは草ぼうぼうの練兵場で日暮れまで遊んだ。蛇の死骸に驚いたり、セスナ機からまかれる宣伝のビラを走り回って拾い集めた。空を見上げると遙か上にいるセスナから赤や青の紙がまかれるのは楽しかった。
公務員住宅ではイタチがよくでた。飼っていた鶏の卵を盗みにくるのだ。練兵場のいずこかに住んでいたのだろう。練兵場は今では名城公園として整備されてしまった。
おやと前を見ると金色亀虫がいない。下から、オーイと呼ぶ声がする。
「ここだここだ」
名古屋城の屋根から声が聞こえてくる。手を止めて降りていくと金の鯱の上で金色亀虫が手を振っている。金色亀虫は口を突き出して鯱をなめている。亀虫は植物に口を差し入れて汁を吸って生きているのだが、金の鯱を舐めてどうするのだ。
近づいていくと、金色亀虫は舐めているのではなく、口吻を差し入れて吸っているのだ。金を吸っている。
「旨いかい」
金色亀虫は口を鯱からはずした。
「たいした金じゃないな、秋田県の山奥にある洞穴の天然の金は旨い」
よく見ると金の鯱に小さな穴がぽつぽつとあいている。
「この小さな穴はなんだろう」
「俺の仲間がここで金を吸って、一息ついてから養老の滝にいくからな」
金色亀虫はまた上空に浮かんだ。吾も浮かんだ。
桑名の上空を通ると、すべからくなにごともなく、養老鉄道の養老駅についた。養老駅のホームの天井には無数の瓢箪がつるしてある。
金色亀虫は瓢箪の一つに止まると揺らした。瓢箪が隣りの瓢箪にぶつかって、あっという間にすべての瓢箪が揺れだした。瓢箪同士でカチカチとぶつかり合うと、それぞれの瓢箪から、いろいろな顔をした亀虫が顔をだした。種類がたくさんある。
「待たせたな」
集まった何百もの亀虫たちはどいつも年寄りの爺さんたちだった。八月八日の日に、年取った亀虫が集まって、養老の滝にいくのだという。早く着いた亀虫は駅に吊るされている何百もの瓢箪の中でこの日を待つのだそうだ。
吾を連れてきた金色亀虫が瓢箪からはいでた亀虫たちをつれて、空に舞い上がった。空中で亀虫たちがふらりふらりと踊りだした。
亀虫たちはゆったりと、舞い踊りながら、養老の滝をめざした。吾もあとにつく。
林の中をゆらりゆらりと亀虫たちは楽しげに踊る。
時間をかけて養老の滝の上にでた。
何百もの亀虫たちは、滝つぼの上空で、尻から金の粉を霧のように放出した。
金粉はあたり一面に舞って、きらきらと空気の中を落ちていき、養老の滝の水面に浮かんだ。
滝つぼが金の粉で覆われると、水面から亀たちが顔を出し、亀虫に手招きをした。
金色亀虫が亀の甲羅に取り付いた。吾も亀の背中に取り付いた。
亀虫を乗せた亀は養老の滝の滝つぼに沈んでいく。吾はどうなるのかとちょっと心配だったが、水の中に入っても何にも変わりがない。
水中は青緑にすんでおり、まわりがきれいに見渡せる。山女たちがこちらをちらっと見る。
滝壺の底は金色に光っている。なんだと見ると金色に輝くドームである。亀はドームの入り口で亀虫たちをおろし、急いで滝つぼの表面にもどった。息継ぎがひつようなのだ。亀たちは甲羅に水面に浮かんでいた金の粉をつけ、再びドームの入口に来た。山女たちがよっていくと、亀の甲羅から金をはがした。山女はドームの菌のはがれたところに行くと、金をはりつけた。亀と山女が養老の滝の金のドームをまもっているようだ。
一匹の亀が入り口を開け、亀虫たちに中に入るよう促した。金色亀虫の後について吾もドームの中に入った。
ドームの中の大広間では、亀たちが酒を飲んで騒いでいた。亀虫たちはその脇を通り、奥の部屋に案内された。
部屋の中に入って驚いた。部屋の周りには、赤紫に熟した実のなった大きな山牛蒡の鉢が何十とおかれている。部屋の中央に木のテーブルがあり、その周りの椅子に金色亀虫たちが腰掛け、亀が大きな封印された甕を机の上に運んできた。
亀は甕の封印をはがし蓋を開けた。あたり一面に酒の匂いが満ちた。
「これが養老の滝の酒だ」
吾を案内した金色亀虫が言った。
亀は用意されたグラスに葡萄色の酒を注ぎ、亀虫たちに配った。
金色亀虫が吾に言った。
「山牛蒡でつくった酒だ」
亀虫たちは一気に山牛蒡の酒を飲み干した。亀がまた酒をそそぎ、亀虫たちは礼をして酒を口に運んだ。
やがて、一匹の亀が吾にも赤紫のきれいな色をした酒の入ったグラスを持ってきた。
礼を言うとともに、ちょっと飲んでみた。古代米でつくったような、しかし、甘みより酸味の強い、不思議な酒だった。
亀虫たちはグラスを持って、空中に舞い上がり、ふらりふらりと踊りはじめた。やがて、亀虫たちは葡萄色にかわっていく。金色亀虫も紫金色になった。
色が変わった亀虫たちは鉢植えの山牛蒡に舞い降りた。
吾を案内した金色亀虫も山牛蒡の葉の上から吾に向かって言った。
「娘になったのよ」
年寄り金亀虫が若くなって、しかも性転換しちまったのだ。
吾は、山牛蒡の酒を飲み干した。
そのとたんだった。目の前がとろけだし、頭の中がもやもやとしてきた。
はっと気がつき、目がはっきりすると、目の前で亀虫たちがお尻をあげて、吾に向かって卵を生み出しているところだった。
白い卵が目の前にくっついた。
吾は山牛蒡の中にいるようだ。そう、山牛蒡の精になったのである。
目の前で亀虫の卵がはじけた。亀虫の幼虫が口を開け、吾にかぶりついた。吾は気を失ってしまった。
山牛蒡(やまごぼう)-幻想私小説9
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


