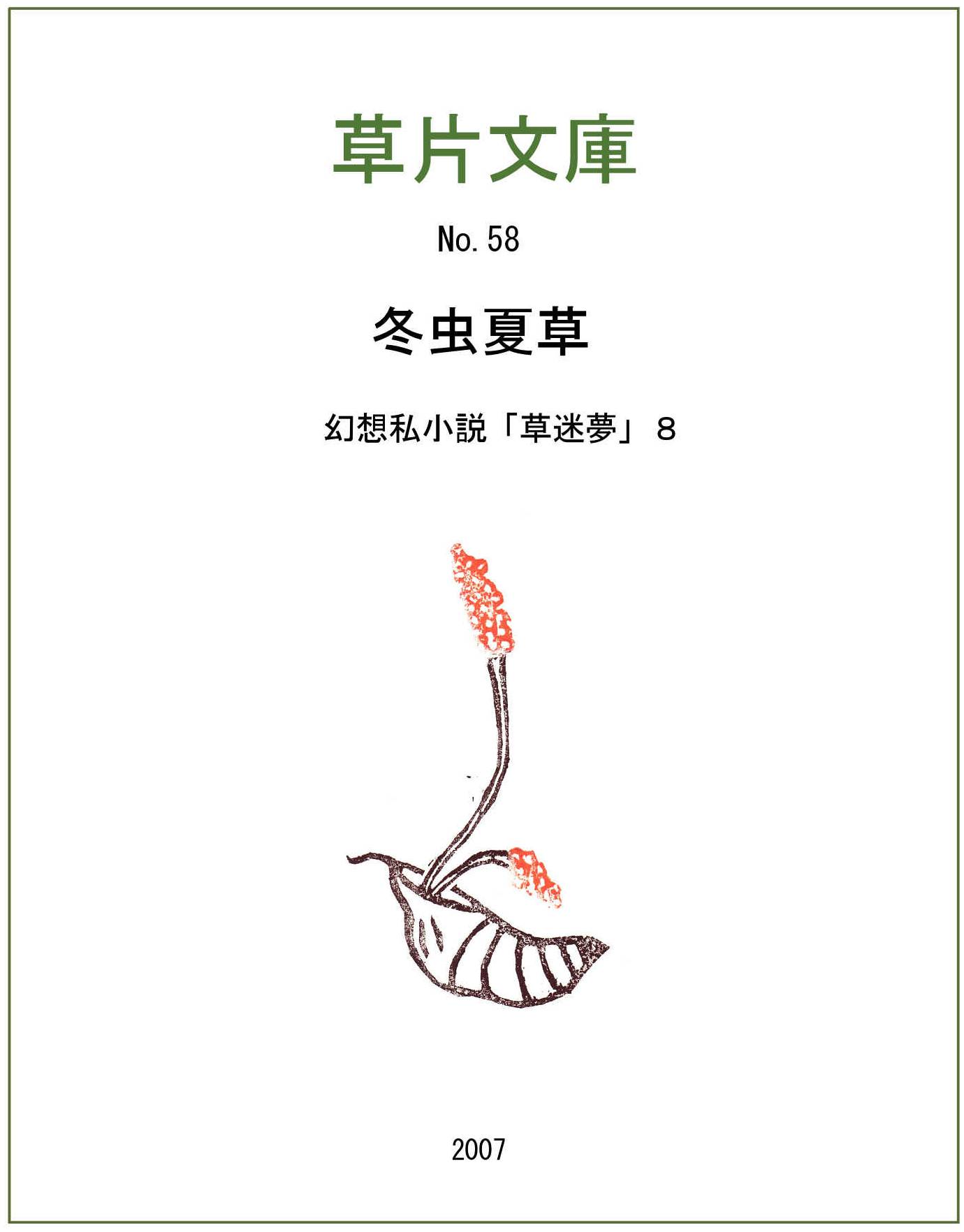
冬虫夏草-幻想私小説8
無花果の精となり、雪女の子どもに背負われて地球に帰りついた吾は振り落とされて意識がなくなり、気が付くと海の見えるところにいた。
夕日が海に沈もうとしている。
パリの街のような急な登り坂を歩いている。むかし、子供たちが小さい頃から成人式をむかえる頃まで、日野南平の丘の上に住んでいた。そこもこのように急な道を上がっていかなければならなかった。しかし、歩いている道の周りに立つ家々は別荘風で南平の住宅地とは違う。坂を歩きながら海が見下ろせる。
吾は茶色の革靴に茶色のスーツを着て、ベージュのシャツに濃いグリーンに小さな鹿の顔が刺繍してあるネクタイを締めている。一九九二年ハンガリーに半年滞在したときにもとめたネクタイで、ずいぶん長い間つかっていたが、七十になる頃、ほころびがひどくなり捨ててしまった。手には茶色の革のカバンをもっている。
道の頂上に出ると、小さいな木造の壁土作り二階建ての家に行き着いた。木の門を開けて中に入ると、野草の植えてある庭が眼に入り、玄関は昔ながらの格子戸で、門灯は南平の我が家のものと同じような、白く丸いガラスであった。
ポケットを探るとキーフォルダが手に当り、いくつかある鍵の中からそれらしいものを選び鍵穴にさし込むと鍵が開いた。
玄関を開けると、小さいながらまとまった土間があり、靴を脱いで上がると、二十畳ほどの広さの部屋であった。客間兼居間といったところだろう。床は一枚板が張られ、黒光りしている。向側がガラス戸になっていて、広い庭が見える。壁はすべて板張りだ。右と左に扉がある。一角にはシングルモルトと壽屋の角瓶が並んでいる棚がしつらえてある。
右の戸を開けると、狭い廊下を挟んで、トイレと風呂場、反対側は寝室になっていた。風呂場は掛け流しの温泉のようで桧でできた湯殿からきれいな湯があふれている。
寝室にはベッドがしつらえてあった。左の戸を開けると小奇麗な台所になっていた。
二階がある。上がってみる。二階に上がる階段の脇の木枠に縁取られたガラス窓から海が見える。小さな漁船がゆっくりと走っている。
二階は大きな一部屋で、ぐるりが壁一面の本棚になっていて、渋澤龍彦、中井英夫、種村季弘、塚原邦雄、須永朝彦、平井呈一、薔薇十字社の本、桃源社の本、古沢岩美などの本が整然と並んでいる。吾が集めた本だ。
それに、自費出版をした本が並んでいる。六十六で退職したが、その二年前より、小説、寓話、ライトバース、絵本と自分で書いたものを本にした。もう二十冊にもなるだろう。愛知の半田市にある一粒書房からだしたものだ。みな三方を染めたきれいな本だ。装丁もすべて自分で考えたのだが、とても良い出版社で自分の思ったとおりの本を作ってくれた。究極の道楽だと思う。
吾は部屋の中央に置かれている木製のデスクにカバンを置いた。
一階にもどり、寝室の脇の納戸に行くと洋服類が吊るされており、そこで浴衣に着かえた。
そこへ玄関の呼び鈴がなった。
玄関にでてみると、割烹着を着た若い女性が、大きな皿と小鉢を差し出している。
「頼まれていた料理をお届けに来ました」
近くの小料理屋の女将さんだそうだ。頼んだ覚えはないがと不思議な顔をしていると、女将さんは愛想よく、
「もう代金はいただいてます、またご贔屓に」
そう言って、皿を吾にわたすと帰ってしまった。
皿の上には金目の刺身がのり、小鉢には烏賊と大根の煮付けが入っていた。これは大変なご馳走だ。なんだかわからないが、客間の茶卓の上にのせた。
風呂に入ってくるか。
湯に浸かり、窓を開けてみると、そこからも海が見えた。遠くに大きな船が通る。少し温めの気持ちのよい湯だ。あまり長湯をするほうではない。すぐに上がると、客間にいった。
ウイスキーの棚の下の戸をあけると、小さな冷蔵庫になっていた。角のハイボールをつくり、刺身の前に座った。
庭に面したガラス戸を開けると、庭と海が見渡せる。あまり広くない庭には数種類の寒葵と蝮草など、地味な野草が植えられている。
夕日は海から少し顔を出しているだけである。
金目の刺身は脂がのっていて旨い。
「こりゃ、お味はどうですかな」
いきなり庭のほうから、はげ頭をなぜながら少し腰の曲がった老人が入ってきた。ちょっとびっくりした。
「どなたで」
ちょっと一人の楽しみをそがれ、不満であった。しかも玄関ではなく、庭から直接入るというのは、失礼なやつである。
「失礼しましたな、ちょっと出ものがあったんで、久しぶりにもってきたのですが」
何の話だろう。老人は開いたガラス戸の脇に腰掛けると、かかえていた風呂敷包みを解いた。
中から、本が一冊でてきた。
「これですが」
手渡された本は見慣れたものだ。渋澤龍彦氏の妖人奇人館の限定版である。しかし、本を取り出してみて驚いた。蛇皮装の五部本である。四十部本はもっているが、五部本はまず市場には出てこないし、でてきてもとても買えるような値段ではあるまい。
素性のわからない老人に手渡されて面食らっていると、老人は自分がせどり屋であり、今までいかにすごい本を掘り出したかを語った。せどり屋は古本屋などで見つけた本を、別の古本屋にもっていって、その差額をこずかいにしている連中だ。本の価値を知っている人間とも言える。
「この本を買えとおっしゃるのですか、とてもそのようなお金がないが」
「いえいえ、物々交換ということで」
そういわれても、もっている本に交換できるような価値のあるものがあるかどうかわからない」
「いえね、あそこに生えているものが欲しいので」
「なんでしょう」
庭には寒葵の仲間と、天南章の仲間、それに地味な野草しかない。土地と取り替えるえることができるほどの海老根の話は聞いたことがあるが、とてもこの庭には珍しい植物などないはずだ。
「ちょっとごらんになって」
老人が立ち上がったので、サンダルを履いて庭に出た。老人が庭の端の石の後ろを指差した。そこには真っ赤な細長い頭をもった冬虫夏草が生えていた。
「ふふふ」
老人が笑ったのかと思い、顔を見たのだが、老人は真顔で冬虫夏草を見ている。
「冬虫夏草が笑ったのでな」
老人は吾の顔を見返して言った。
不思議なこともあるものだ、冬虫夏草が笑うのか、何に対して笑ったのか。
「みつかっちまった、と笑ったのですよ」
老人はこれと限定版と取り替えたいということである。
「これは何に生えた冬虫夏草ですか」
老人は掘ってみないとわからないという。どうぞ掘ってくれというと、老人は嬉しそうに、小さなシャベルをポケットから出して掘り始めた。丁寧に掘っている。出てきたのは団子虫だ。団子虫の頭から赤い茸が伸びている。
「まだ持っていないものでした、これはありがたい」
冬虫夏草の収集家らしい。冬虫夏草は虫や虫の幼虫に寄生し、夏や初秋に胞子嚢をつける茸の一種だ。中国、台湾では薬として高価なものである。
「もらっていきます」
吾が肯くと、老人はポケットから取り出した瓶に冬虫夏草を丁寧に入れた。
「ふふふ」
冬虫夏草がまた笑ったようだ。今度はなぜ笑ったのだろう。老人は答えなかった。
「どうです、ウイスキーしかないのですが」
「いや、捕ったやつを、すぐに飼育室に入れたいので、これで帰ります、どうもありがとうございましたな」
こちらこそ、あの五部本が手に入るとは夢のようである。
「また、なにかあったらどうぞ」と見送った。
老人は、ニコニコと、さもうれしくて仕方がないといったような表情をして、庭から出て行った。
吾は狐につままれた気持ちで家のなかにもどった。
本はきちんとおいてある。夢ではなさそうだ。
しかし、どうしてあの老人は庭に冬虫夏草が生えているのを知っていたのだろう。
蛇皮装の限定版を手にとって見た。限定版をたくさん買えるような立場にはないが、一冊だけ蛇革装の本を持っている。シュールな絵で知られる古沢岩美画伯が一九六〇年に名刺代わりにと出版した画集IWAMI FURUSAWAを、二十部ほど特別装丁版に仕立て、そのうち十部が蛇皮装の私家版である。その一番である。
澁澤氏の妖人奇人館は一九七一年二月に桃源社より発行され、装丁を変えて一九七八年五月にもでている。限定版は一九七一年の六月に桃源社からだされたものである。
もらった特装限定版を二階にもっていくと、すでにもっていた限定版の隣が開けてあり、収まるべくして、そこに収めた。夢はすごい。
階下におり、再び金目の刺身と、烏賊の煮つけを楽しんだ。暗くなった海に浮かぶ船の光が輝いて見える。後片付けをすると、二階に上がり、特装版を開きじっくりと手触りと眼触りを楽しんだ。
次の日も、茶色の服を着て、家に帰るところから始まった。夢なのだなあ。家に帰りつくと、また、玄関の呼び鈴が押され、料理屋の女将さんが皿をかかえていた。今日は橙色のかなりミニのワンピースで、ふっくらとした白い足がかわいらしい。すこしお腹がでているようだが。
「今日は、真鯛の刺身と、蛸の煮付けですの、御代はいただいています」
皿が差し出された。
「どうも、しかし、誰がこれを」
「あら、ご存じなかったのかしら。海の際に住んでいる、針山さんご夫妻よ」
「針山さんを知らないのですが、どなたでしょう」
「あらいやだ、昨日来たでしょう、せどりやの」
「ああ、あのおじいさん」
「でもどうして、ご馳走を届けてくれるのかわからないのですが」
「あら、この家の庭は冬虫夏草が生えるので有名なのですのよ。針山さん冬虫夏草が大好きなの、きっとまた変わったのが生えていたのね」
そう言っておかみさんは帰っていった。私の料理屋にもよってくださいねと言っていたが、ぜひ行って見よう。
ビールを飲みながら、鯛の刺身、蛸の煮付け、海と庭を眺めながら楽しんでいると、またあの老人が来た。
「これは、また、お邪魔いたしますです」
「ああ、どうぞ、昨日は大層な限定版をいただいてしまって、恐縮をしております」
「いえ、こちらこそ、あの冬虫夏草は奇妙でとても面白い」
「しかし、あの限定版ほどの価値があるものなのでしょうか」
「それはもちろん、それ以上かもしれませんな」
「それに、料理屋から料理まで届けていただいてすみません」
「いや、私のほうこそ世話になります」
「どうぞ、ビールでも」
針山さんに上がるようにすすめたが、
「いただきたい冬虫夏草がありまして、あちらです」
すぐにも見たいようである。吾も下駄をはいて庭にでた。
針山さんが指差した。昨日とは反対側の石の陰に、青い膨らんだ丸い冬虫夏草が伸びていた。
「ふふ」
また笑い声が聞こえた。
「いただきますが」
「どうぞどうぞ」
針山さんが、さなスコップで丁寧に掘っていくと、小さな蛇からでた冬虫夏草であった。
「これは珍しい、世界で初めてでしょうな、蛇の冬虫夏草は」
針山さんは大事そうに瓶にしまうと、それはそれは嬉しそうな顔をした。
「この本をどうぞ納めてくだされ」
針山さんはかなり大きな包みを吾に押し付けた
「そんな、このようなものいただかなくても、昨日いただいた本は本当に珍しい本で、欲しいものでした。どうぞ冬虫夏草を好きなだけお持ちくさい。ご馳走までいただいて、なんとお礼をいっていいか」
「いえ、こちらこそ、それでは」
針山さんは、瓶をいだいてそそくさと帰ってしまった。
いただいた包みをもって家の中に入り、刺身をつまみながら中のものを取り出した。厚手の帖につつまれた、洋風の本が4冊でてきた。
食べるのをやめて、本を畳の上に並べた。ほんのり紫がかった一冊を開くと、三方金、皮装の幻想博物館がでてきた。中井英夫の幻想譚である。悪夢の骨牌、人外境通信、真珠母の匣である。この4冊はそれぞれ短編幻想小説集である。すべてをまとめて、とらんぷ譚として出版されてもいる。それらすべて、サイン本を集めた。平凡社から出た本で、知っている限り、どこからも限定版は出ていない。吾に甲斐性があれば限定版を出したいものだと思っていた本である。
開けてみると、四冊すべてに、元の本に挿絵を入れていた立石修二氏の銅版画が一葉はいった、すばらしい本である。
大変なものである。とりあえず二階にもっていき、テーブルの上に並べた。本当に夢がかなうのが夢なのだなあ。そのうち針山さんの家にお礼に行かなくては。
その夜は中井英夫氏の4部作を眺め、ほとんど徹夜だった。
次の日も、茶色の背広を着て坂を家に向かって歩いている。今日はあの料理屋に寄ってみよう。坂の途中から横道に入り、ちょいといくと、角に行灯のおいてある小料理屋があった。のれんに「溶子」とある。変わった名前であまり小料理屋のような感じではない。
戸をあけると六、七人座れるカウンターと、二つの腰掛が用意されているテーブルが一つある。小さな店だ。敷居をまたぐと、カウンターの中で煮物をしていた女将が振り向いた。
「あら、いらっしゃい」
と顔一杯に笑みが広がった。
「今日はここで召し上がりますの」
「はい、何かつくってください」
カウンターに腰掛けた。
「今日は鯨が入ったの、さしみと焼いたの出しましょうね」
頼んでいないビールが一本カウンターにおかれ、すっきりとした硝子のグラスがでてきた。
「このビールしかないの」
女将が申し訳なさそうに言った。
よく磨かれた薄手のグラスは、驚いたことにバカラのようだ。バカラでこのように薄手のものをつくっていたとは知らなかった。
女将がグラスを眺めている吾を見た。
「フランスにいったときのよ」
茶色のビール瓶に楕円形のラベルが張ってあり、水母の絵が描いてある。
「うちのビールよ」
女将の手が伸び、ビールをグラスに注いだ。
一口飲む。ホップの利いたさっぱりした味だが、甘みも苦味もしっかりしており、うまい。
鯨のさしみが篠焼きの皿に無造作に乗せられてでてきた。さすが哺乳類で、鯨の刺身は魚の刺身とは違う力強さが感じられる。鯨は魚ではないと強調しているようで、食べる前から想像力をかきたてる。もう一つはあぶった鯨で、やはり篠焼きの丸皿にのっている。
一口いれると、とろけるように鯨の匂いが広がった。鯨の匂いをいやだという人がいるが、とんでもない話で、この匂いがなかったら鯨ではない。いい味である。
「おいしい」
「ありがとう」
女将が減ったビールを足してくれた。
「後になったけど、お通し」
茶色に煮た野菜が小鉢に出てきた。
「針山さんにいただいたのを今煮ていたの、食べてみて」
箸でつまむと、ちょっと土筆の佃煮のように見える。口に入れると、動物くささが鼻についたが、なかなか乙な味だ。
「冬虫夏草よ」
なかなか、食べられるものではない。
「珍しいね」
「針山さん栽培しているのよ、毎日いただいているの、からだのためにいいのよ」
鯨をあぶったものを口に入れた。それも舌にじわっと味のしみる、美味いものであった。
ビールはすでに三本飲んだ。
「お茶漬けどう」
「もらおうかな」
すぐに、軽い梅茶漬けと、自分のところで漬けたという胡瓜の漬物がでた。うまかった。
代金を払うと、女将が、
「これもってって」
と、袋に入ったものをくれた。なんだろうと中を覗くと本であった。
「本なの、私が持っていてもしょうがないから、あげますわ」
本好きなのを知ってだろう、遠慮しないことにした。
「どうもありがとう、ビールも鯨もおいしかった、おやすみなさい」
「またいらしてね」
このようにして、家に帰った。
着替えをして、紙袋を開けてみた。濃紺の絣(かすり)のような布でできた帖につつまれた本であった。帖に本の題名は書いていない。開けてみると、白っぽい装丁の本で、表紙にはカラスウリの葉の絵が配置され、三匹の守宮がバランスよくカラスウリの葉やつるにつかまっている。きれいな橙色のカラスウリの実が一つ表紙の左下に画かれている。真ん中より少しうえのほうにタイトルの押された薄い皮が張られている。家守奇譚とある。梨木果歩氏の小説で、この本もぜひとも限定版で読んでみたいと思っていたものである。
手にとって見ると、普通の本と少し違う。よく見ると、表紙は木でできていた。裏書きのところを読んでみると、表紙は百日紅をもちい、本文紙は楮の生すきとある。限定八十の私家版であった。中を開くと、所々に、どのように処理をしてあるのかわからないが、それぞれの話に出てくる植物の押し花が紙に組み込まれている。紙を漉く時にいれるしかない。
今夜もこの本を読んで夜更かしとなるのだろう。それにしても、このような本が出ているとは思ってもいなかった。なぜ、あの女将がもっていたのだろう。
次の日も同じように茶色のスーツを着て坂道を上がっていた。今日はいったん帰って、針山さんを尋ねお礼を言おう。
家に戻り、コットンズボンにポロシャツに着替え、庭で冬虫夏草を探してみた。針山さんの土産にするためである。庭の真ん中あたりに植えてある万両の下に、黄色っぽい頭を持った冬虫夏草らしきものが数本固まって生えていた。スコップを持ってくると、針山さんがやっていたように周りからゆっくりと大きく掘り進めた。やがて、冬虫夏草が生えているらしい昆虫の背中が見えてきた。どうやら、大き目の螻蛄(おけら)らしい。背中から白いきのこが数本生えており、先に黄色の胞子を付けている。
ガラス瓶はないので、あいた牛乳瓶にそっといれた。
冬虫夏草を持ち、小料理屋「溶子」にいって、女将に刺身をたのみ、針山さんの家を教えてもらい出かけた。
針山さんの家は海の砂浜に続くような場所にあり、コテージ風のしゃれたものだった。ベランダから砂浜に下りられるようだ。
ノッカーをたたくと、針山さんの奥さんらしき人が顔を出した。
「はい、あ、ちょっとお待ちください、主人を呼びますから」
奥から針山さんが顔を出した。
「おや、いらっしゃい、よく来られましたな、どうぞお入りください」
針山さんは嬉しそうに手招きをした。
中に入ると、簡素ながらも、しゃれた部屋で、布製のソファーに座るように勧められた。
「家内です」
針山さんは小太りのかわいらしい白髪の奥さんを紹介してくれた。
「溶子の女将に刺身を作ってもらってきたので、どうぞ、飛び魚だそうです」
奥さんに手渡した。
「おや、ごちそうですこと、ありがとうございます、ビールをお持ちしますわね」
「それがいい」
「この冬虫夏草をみつけたので、もってきたのですが、どうでしょう」
針山さんは牛乳瓶を手にとると眼を輝かせた。
「こりゃすごい、螻蛄ですな、また珍しい、世界で一度確認されているが、誰も本物を見たことがないのです。ありがたいことです」
針山さんは隣の部屋に来るように手招きをした。その部屋は温室になっており、無数の冬虫夏草が盆栽のように鉢植えになって並んでいた。
「この温室の中では、冬虫夏草は枯れません」
針山さんはその仕掛けは教えてくれなかった。大事な秘密なのだろう。
螻蛄の冬虫夏草を植木鉢に植えて、居間に戻ると、ビールと刺身が用意してあった。
奥さんも一緒に、刺身をつまみビールを飲んだ。ビールは溶子で飲んだものと同じである。
このあたりは、冬虫夏草がでやすいところで、特に吾の家の庭にはよく生えるそうである。冬虫夏草は茸の部分である子実体ができるのに時間がかかり、普通のところでそう見かけるものではない。日野の家にいる頃には、ほんのたまに、丘陵の木の下に生えているのを見ただけであった。
針山さんが冬虫夏草に興味をもったのは、ここに移り住んでからだそうだ。よく見かけたので採ってきて、たまたま他の植物のために改良した温室に入れておいたところ、枯れることなくいつまでもそのままであったことが集めるきっかけになったという。
せどりのために、全国の本屋を回るとき、ついでに林の中を探してくるということである。
話しこんでいると、あっという間に時間が過ぎた。
「溶子さんがまたフランスに行くそうでしてな、歓送会を私どもの家でやりますのじゃが、いらしてください」
「それは、よろこんで、溶子さんがいないときは、刺身が食べられませんね」
「そうですな」
その日もわかれしなに、大変な限定版をもらってしまった。この本も特装本にしたら見事だろうと思っていたものである。渋澤龍彦氏の手帳シリーズで、やはり桃源社から出ている。黒悪魔の手帳、毒薬の手帳、秘密結社の手帳である。渋澤龍彦氏の本の中ではじめて読んだのは毒薬の手帳である。大学生の時代、高い本であったが、古本屋で無理して買った覚えがある。A5版の本で、黒に近いような緑色の箱にはいっており、本自体も濃い緑色で、小口も全て緑色である。黒悪魔の手帳は黒、秘密結社の手帳は、最初早川書房から新書として出されていたが、後に、他のものと同じ箱入りの単行本として桃源社から出版された。赤の装丁である。
家に戻り、開けてみると、まさに、それぞれの色に染められた皮装の、よく手になじむすばらしい本であった。皮装の表面には本の色にあわせ、大きくはないが質のよい黒ダイヤ、エメラルド、ルビーが目立たないが埋め込まれ、本を開くと、見開きに、野中ユリ氏のそれぞれの本に合わせた銅版画がはいっている。野中氏の銅版画は珍しい。裏書には、私家版、八十部とあり、いただいた本はその中の、全て8番であった。
次の日も、帰りに小料理屋、溶子によった。店の中にはなにもなく、なぜか、お腹がせり出している女将さんがなにやら片付けをしている。
「あら、今晩は、針山の奥さん喜んでいたわよ、お客さんは珍しいものね」
「あの特装本どうもありがとうございました。あんな貴重なものもらっていいものかどうか」
「いいのよ、それより、今日はやっていないのよ、これからしばらく、お休みなの、私、フランスまでいってくるの。今日たつのよ、針山さんが歓送会してくれるというの、あなたも聞いていますでしょう」
「今日なのですか」そういえばいつと言うことを聞き忘れた。
「そう、夜の八時に針山さんのところにいくの」
「今日ということは聞いていないのですが」
「大丈夫よ、針山さんのところに来てくださいな、それにこの本も持っていってくださいな」
また、本を手渡された。女将は片付けに忙しそうなので、礼を言い、針山さんのところで会う約束をして家に戻ることにした。
家に戻り包みを開けると、渋澤龍彦氏の幻想博物誌の皮装版がでてきた。私家版である。もともと、池田満寿夫氏の装丁で、それだけでもすばらしい本であったものだ。皮装版の表紙をめくると、なくなったはずの池田万寿夫氏の版画入りであった。不思議なことだ。しかしすばらしい。
しばらく感激にしたっていたが、針山さんのうちに行くまでには少し間がある。庭に出て、冬虫夏草を探してみた。庭にはなかったが、玄関の脇に生えているのを見つけた。紫色の子実体を持ち、ひょろひょろと長い柄がついている。ちょっと固い土で掘ってみたがなかなか動物が現れない。やがてでてきたのはカタツムリだった。カタツムリから生えた冬虫夏草は珍しいのではないだろうか。おらないように牛乳瓶に入れた。
八時に近いがまだ薄明るい。針山さんのお宅に行くと、波の音が近くに聞こえ、少し涼しい風が吹いてきている。
溶子さんはもう来ていた。ふわっとした、白っぽいドレスを着て、とても小料理屋の女将には見えない。どこかの女王のようだ。
「よく来てくださいましたな」
針山夫妻もよろこんでくれた。
カタツムリの冬虫夏草を渡すと、針山さんはことのほか喜んで、そそくさと温室にもっていった。
テーブルには刺身のほかに、肉料理が珍しく並んでいた。ビールはいつもの地ビールである。
「フランスへはどのくらい行くのです」
女将は首を傾げた。
「さあ、どうかしら、一月くらいか、一年か、波任せだから」
溶子の女将さんは、ニコニコしながらビールを飲んでいる。
フランスのどこへ行くのか聞いたりしたが、その時次第と、とてものんびりした旅のようなことを言っている。
「針山さんは、どこか外国旅行へいったことがありますか」
居間に戻ってきた針山さんに聞いた。
「エジプトにいたのですが」
エジプトには我々も家族で旅行したことがある。長男の森根が小学に上がる前、美町が中学に入ったときではなかっただろうか。仕事仲間の勧めで、エジプトに十日ほど遊んだ。家族にとっては初めての海外旅行がエジプトであり、印象深かったようだ。中東がまだもめていなかったときで、しかもエジプトには案内してくれる人がいて、全てついてきてくださったので、本当に気楽で安心な旅であった。ピラミッド、スフインクスはあまりにも有名だが、やはりその場にいくとその感激、驚きはすごいものであった。森根のリュックに入っていたおもちゃの剣が、空港の検査にひっかかり、検査員同士でやり取りしていた後に、許されてリュックに戻された。そのとき、小さい森根がショックランとエジプト語でお礼を言っていたのが印象的であった。
そんな話を、針山さん夫妻は興味深そうに聞いていた。
だいぶ夜も更けてきた。
溶子さんがベランダに出ると、「そろそろ行こうかしら」と言った
針山夫妻もベランダに出て、みんなで海岸のほうに歩いていった。
波打ち際に女将が立つと、針山夫妻が、
「気をつけて、土産話をたのみますぞ」
手を振った。どこにいくのだろう。
溶子さんが着ているものをするりと脱いだ。ふっくらとした白いおしりが波打ち際に浮かびあがった。振り返ってにこりと笑うと、
「いってきます」
海の中に入った。夢だ。
針山さんがびっくりしている吾を、抱えるようにして波打ち際につれてきてくれた。 海の中では行灯水母が、ゆったりとゆれている。
行灯水母は一本の足を高く上げた。
「きゅ、おほほ」
足元から海の中に次々と小さな行灯水母がでてきた。
「うまれましたな」
針山さん夫婦が眼を細めている。
行灯水母は、小さな水母をともなって沖に漂っていく。
「いってらっしゃい」
針山さん夫婦がまた声をかけた。
「溶子さん、やっと子供ができたのですよ、毎日冬虫夏草を食べたから」
「さあ、家に入りましょう」
針山さんの奥さんが、家に戻っていく。吾も後をついた。
「自由でいいわねえー」
針山さんの奥さんが言った。
「そうだなあ」
旦那さんも相槌をうった。
家に戻ると、
「さあ、もう一杯いかが」
針山さんの奥さんが水母の絵のついたビールをついでくれた。
「この水母、彼女なのよ」
針山さんの奥さんが言った。
針山さんがテーブルの上に、吾が持ってきたカタツムリの冬虫夏草を植えた鉢を置いた。
「これはすばらしいものですな、ありがとうございます。それと、我々大変お世話になり、可愛がられ、感謝しているのです、特にこいつは三年もの間大切にされましてな」
はて、何の話だったのだろうと考えていると、シューと聞きなれた声が聞こえ、目の前にいた針山さん夫婦が消えた。
と思ったのであるが、テーブルの上の冬虫夏草の鉢の脇に二匹の針鼠が吾を見上げていた。
ヌトとトトだったんだ。エジプトに行ったときに、階段ピラミッドの下にたわしが落ちていた、と森根が拾ってきたものがある。まだとってあるが、干からびた針鼠であった。海外旅行をすると必ず針鼠のクラフトを買って来た。家族が行くたびにかってくるのでいろいろな国の針鼠が飾り棚いっぱいになっている。家族の趣味になってしまった。あるとき、エジプトから撮影のために許可をえてもってきた針鼠を二匹もらった。それを大事に飼った。トトは年をとっていたようで、一年と生きなかったが、ヌトは三年以上生きて、老衰で死んだ。
「会いたかったなあ、ヌトとトト」
そう言ったとたん、吾の目の前に、大きなヌトとトトの鼻が突き出された。
「こちらこそ大事にしていただいて」
ヌトとトトのつぶらな眼が吾を見ている。
「これからエジプトに行きません」
ヌトとトトの後について、冬虫夏草の温室にはいった。
温室には真っ赤なドアがあった。ドアが開くと温かい風が吹き出して来た。ヌトとトトの後をついて、外にでると、満天の星空にむかってピラミッドが聳え立っていた。
階段ピラミッドの下であった。
ヌトとトトが大きな昆虫に挨拶をしている。スカラベだ。
スカラベは吾を見ると、
「わたしゃ糞の虫、あんたは本の虫、お互い虫だぜ」
にたりと嗤い、
「こちらにこいや」
と手招きをした。
ヌトとトトとともに、スカラベの後をついていくと、階段ピラミッドの端にある大きな石のところにやってきた。スカラベは後ろ足を石にかけるとよいしょと押して、どかしてしまった。
穴がぽっかりと開いた。
「こっちさね」
スカラベの手招きで穴に入っていくと、朱に塗りたくられた石室に出た。
石棺の上には、一冊の皮の本が置いてある。
スカラベが説明するには、世界で一つの猫革の本で、砂漠の冬虫夏草のことが書いてあるのだということだった。
ヌトとトトが本をひょいと開いた。
そこから、ひょろりと緑色のキノコが胞子を散らしながら生えてきた。
「ほっつっほ、本の冬虫夏草だ、猫の皮から出てきたのさ」
ヌトはうれしそうに鼻をつけた。
とたんに、緑色の胞子がとんで、私はその胞子の中に閉じ込められた。
ヌトとトトが手を振っている。
吾は冬虫夏草の精になり、胞子にのって、ピラミッドの中を漂った。
やがて、ピラミッドから外に出て、砂漠の上に舞い出ると、太陽の暑い赤い光に吾の頭はボーっとなり、気を失ってしまったのである。
冬虫夏草-幻想私小説8
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


