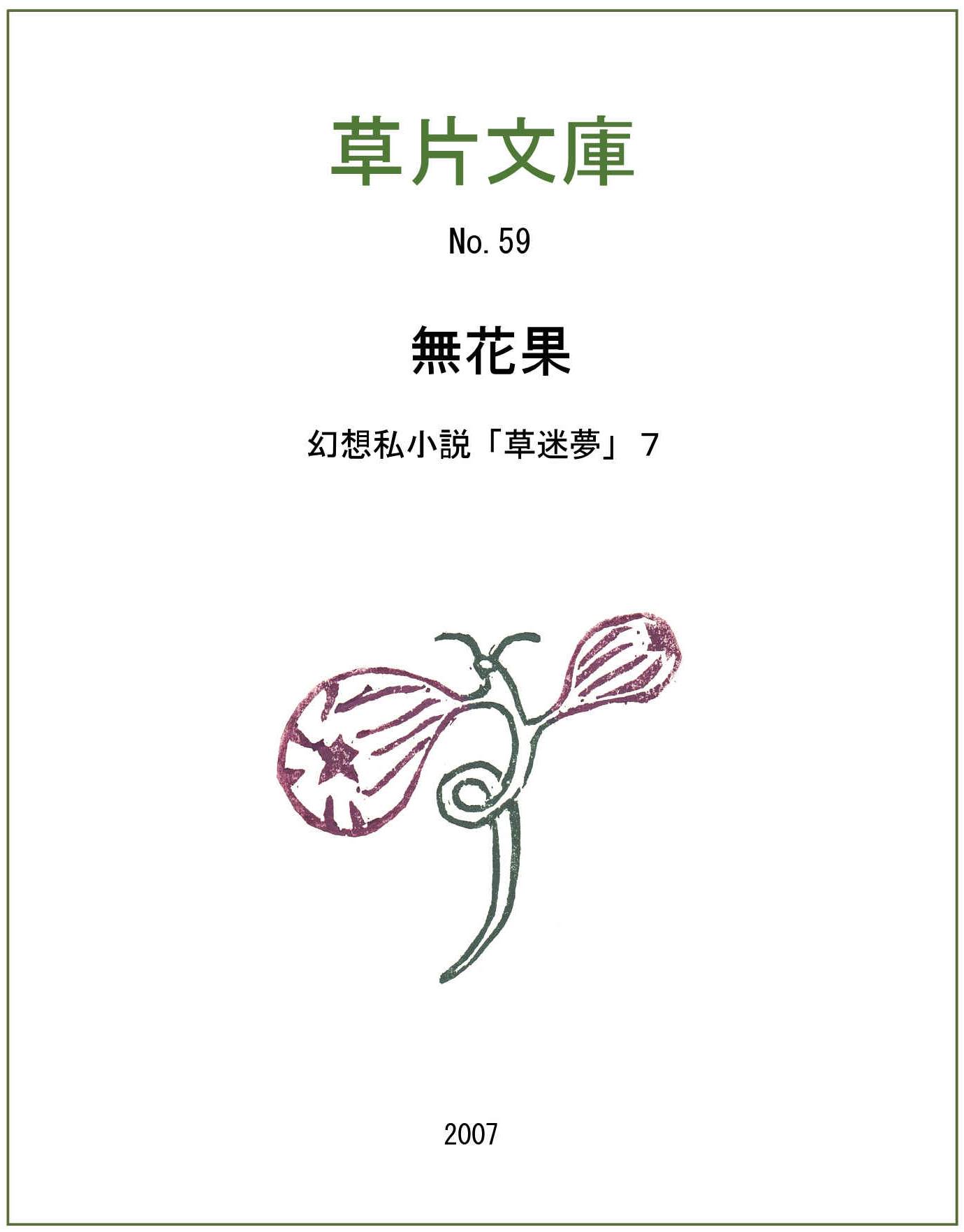
無花果-幻想私小説7
夢のお話し。縦書きでお読みください。
茶色になり、かさかさになった雀瓜の実が、風が吹いた拍子に、寒空に放り出された。ずい分長い間、雀瓜の中で眠ってしまったが、今目が覚めた。
なんだか寒い。雪が降ってきた。雀瓜の精になった吾は雪にぶつかると、再び意識がなくなってしまった。
雀瓜が芽生え、つるが伸びて行き、青い葉を繁らせた。熱い風が頬にあたり、吾は夏の日差しの下にいた。空にはシュウクリイムのような白い雲が青い空にふわりと浮いている。今ではこのような夏の空を見ることができない。なぜか夕立もあまりこなくなった。地球全体の気候が変わりつつある。
白いコットンズボンに茶色のティーシャツをきている。おそらく40歳半ばの頃だろう。何ももたず草原に続く丘の上の一本道を歩いている。遠くに家が一軒見える。
道の脇の草原にはクローバに混じって、蛇苺が赤い実を付けている。
だいぶ歩いた。遠くに見えていた家がかなり近くになった。暑い日ざしだ。
後ろのほうから、ブーンと何匹かの蜂が吾を追い越して家に向かって飛んでいった。
家は木造の簡素なつくりで、洋風でもあり和風でもあり、昭和初期の一般の家とでもいったらいいのだろうか。だいぶ古びていて倒れそうである。
家の隣には大きな木があった。見ると無花果がなっている。無花果の木としてはかなり大きい。たくさんの蜂がその木に向かって飛んでくる。さっき吾を追い越した蜂もその木の周りを飛びまわっている。
家の前には草花がかわいらしく植えられている。家に近づくと、少女が玄関の戸をぎしぎしいわせ、開けて出てきた。
「おじいちゃん、見えたわよ」
吾に気がつくと、少女は家の中に声をかけた。
戸を開けて白髪の老人がでてきた。
吾を待っていた様子だが、こちらとしては全く知らない人たちである。
無花果の木には大きなおいしそうな実が鈴なりになっている。実の先は紫に熟し、いかにも甘みの強そうな無花果だ。飛びまわっている蜂は実の中にもぐりこんでいく。 そういえば無花果は虫媒花で蜂がそれを引き受けている。
「いらっしゃい、待っていましたのじゃ」
茶色の紋付袴をきた老人である。白髪を後ろ手に縛り、手には杖をもっていた。よく童話に出てくるような老人だ。
細面の皺の寄った柔和な顔に笑みを浮かべている。
やはり吾は待たれていたようだ。理由は後でわかるのだろう。
吾は老人と少女に向かって頭を下げた。
「こんにちは、おいしそうな無花果ですね」
老人は笑った。
「やはり人間じゃな、確かにこの無花果の実は旨いのですよ」
老人は少女に促した。
「アンジール、家の中にご案内しなさい」
アンジールと呼ばれた少女は吾に家の中に入るように手招きした。
夢の中ではどのようなことも起こる。
吾は少女の後について、家の中に入った。
家の中は質素なつくりで、木の床に木製のテーブルといくつかの椅子があるだけである。飾り気のないカップボードには白い食器と、きれいに磨かれている透明なグラス類が数個おいてある。
老人は椅子を勧めてくれた。
「遠い道をよく来なすった」
アンジールが水を満たしたコップをテーブルの上に置いた。
「無花果のつゆですの」
吾は遠慮なく飲んだ。喉にしみとおる。からだがスーッときれいになっていくような透明感のある味の水であった。
「夢の中の出来事で、雀瓜の精になって雪に叩かれて気を失ったのですが、いつの間にやら一本道を歩いていました。そのまま歩いてきたら、ここにたどり着いたわけです、待たれていたようですが、吾は自分の役目を知らぬのです」
老人は笑顔で頷いた。何が嬉しいのだろうか。
「そうです。あなたは知らない。でもここに来ることで、もう役目は果された。ここに来るように組み込まれた宇宙の遺伝子によるものなのですよ」
老人の口から遺伝子という言葉が出たことにひたすら驚いた。
「あなたは宇宙がよこした者なのだろう、生き物がこの世の中にできて、人もその中にあったが、別の宇宙を作って瘤のように宇宙から飛び出してしまった。きれいだった宇宙にでこぼこをつくってしまった。その原因はわしなのじゃ。わしがもっとしっかりとしてればよかったのだが」
「しかし、人間は決して悪くはならなかったようじゃ、そなたを見たので、少し救われた。きっと宇宙がそれをわしに教えるため、あなたを使わされたのですよ。ありがたいことだ」
「アンジール、どうじゃろう、外のほうが気持ちがいいかもしれんな」
「そうですわね、おじいちゃん」
老人は椅子から立ち上がると、吾を促して外に出た。
アンジールがテーブルと椅子を二つ、無花果の木の脇にしつらえた。
「どうぞ、すわってください」
アンジールが飲みかけの無花果のつゆを運んできた。
吾は何かの力で、この老人に何かを伝えにきたようだ。その役目もすでに終わっているように感じる。
「そうですのじゃ、そなたの役目は終わったのです、今度はわしのほうからあなたに、本当のことを教えなければならん。それを聴いてくださるのもあなたの役目なのです。長い長い話じゃが、ほんのさわりを聞いてくださらんか」
吾はうなずいた。無花果の木には蜂が群れ飛んでいて、頭の上でぶんぶんいっている。ちょっと怖い感じもあった。それを察し、老人は蜂が刺すようなことをしないと教えてくれた。
無花果の香はすばらしく、甘そうな蜜が実の先から染み出しているのをみるとエジプトを思い出した。エジプトに行ったとき、カイロからアレキサンドリアまで車を使い、高速道路でいった。高速道路といっても砂漠のようなところを通っている割れ目だらけの舗装道路で、家畜が横切ったりしている。我々を載せた車がかなりの勢いで走っているとき、案内をしてくれた斉藤さんが、車を止めさせた。
道端に無花果売りが出ていたのである。彼は何箱も買ったが、我々はそのおすそ分けをいただいた。その甘くておいしかったこと。無花果は好きな果物であったが、あのような甘く味のある無花果を食べたのは初めてだった。
老人はそれを察した。
「エジプトの無花果はここから持ち逃げされたものから生えたものなので美味かったでしょうな。この木の無花果は食すことはできないが、他の場所に食してよい無花果の木がある。すぐに採りに行かせます」
「アンジール」
老人が家の中にもどっていた少女を呼んだ。
赤い上着を羽織ったアンジールは家から出てくると宙に舞い、老人の脇に降りたった。ティンカーベルか。
少女が空を飛んだが、夢の世界はなんでも起こる。
「アンジール、この方に、無花果の酒、無花果の料理を用意してくれんか」
「はい」
アンジールは笑窪を寄せて会釈をすると、すうーっと空に舞い上がり、無花果の木の天辺に向かって飛んでいった。アンジールが木の天辺に生っている無花果の実を細い指でぽんとたたくと、あちこちの無花果の実から緑色の上着を着た妖精たちががやがやと顔を出した。
「お願いね」
アンジールは妖精たちに頼みごとをすると、我々の前に降りてきた。
「ありがとう、アンジール」
老人が声をかけると、アンジールはまた会釈をして小屋の中に入っていった。
緑色の上着を着た妖精たちが手に手に、いろいろな料理を携えて降りてきた。
それはテーブルに乗せ切れず、周りの石の上にも置かれた。
「皆ご苦労さんであったな、ありがとう」
「いいえ、楽しかった」
緑の上着の妖精たちはお互いじゃれあいながら宙に浮き、もといた無花果の実の中に消えていった。
「それでは召し上がりながら私の話をきいてはくれまいか」
そう言いながら、老人は私のグラスに無花果酒を注いだ。
コクのある甘い酒だ。
テーブルの上に湯気が立っている白い無花果がある。
「これは無花果の珍しい食し方ですのじゃ。無花果に白い味噌を塗って、焼いたものです」
「味噌は日本の食べ物です」
「そうでしたな、日本から来られたのですな。人間の世界はいろいろな国に分かれているからのう。このわしの着ている衣装も日本のものですな。今日はもてなしにこの格好をせよと達しがきたのじゃ。今日の朝までは自分のままだったがな、しかし、このわしの格好と、あなたのはずいぶん違いますな」
「それは百年以上前の日本人の侍の格好です、今でも着る人はいますが」
「そうだったか、宇宙とて全て分かっているわけではないのでな、すまなかったな」
老人も無花果の酒を飲んだ。
そのとき、一本道を一人の老女が早足で歩いてきて我々を見つけて声をかけてきた。
「宴会かえ、わたちも仲間に入れてくれや」
「スラッグばあさん、いいとき来なすったな。なあ、アンジールもう一つ椅子を持ってきておくれ、なんなら、もう一つもってきて、グルヌイユばあさんも呼んでおくれ、今日は大事なお客人だ」
スラッグばあさんは老人から無花果酒をついでもらい、ちびりとなめた。
「美味く熟れたな、この無花果酒は」
「アダムとイブが去った次の年の無花果からつくった酒だから熟しておるだろう」
グルヌイユと呼ばれる老婆もやってきて、しわくちゃな顔で吾を見た。
「これがお客人かえ、アダムとイブの子孫かい」
「そうだよグルヌイユばあさん」
「あまり悪くなっていないようだね」
「わしも安心してね」
会話を聞いていても吾にはまったく理解ができなかった。難しい話になりそうだ。
老人は吾に向かって頭を下げた。
「おどろかんでくだされ、我々の本当の姿になりますのでな」
そのとたん、彼らは蛇と、蛞蝓と、蛙になった。
蛇の老人が話すのにはこのようなことだった。
この木は禁断の果実の木と呼ばれており、人間の世界では林檎の木にすりかわってしまっているとのことだ。アダムとイブの話である。アダムの食べたのは林檎ではなく、無花果だそうだ。アダムもイブも蛇にだまされて林檎を食べた後は羞恥心ができ、からだを隠すようになったという俗説があり、その時からだを隠すのに無花果の葉を用いたことになっておる。本当は無花果の実を食べたのである。
蛇は話をしながら、いきどうっていた。
「アダムとイブはくわせもんでな、他の動物たちは言いつけを守って、禁断の果実を食べようとはしなかったが、アダムとイブはいじきたなくて、うまそうな無花果を食べるために私を騙しおった。
あのごじんたちは、蛙と蛞蝓に悪いことを吹き込んでわしをおとしいれたのじゃよ。
わしはその頃、蛞蝓や蛙とも仲がよく、我々三人でこの無花果の木を守っていた。ある時、アダムがグルヌイユを、イブがスラッグを口車に乗せて、この家から誘い出し、グルヌイユを氷河に、スラッグを溶岩に閉じ込めてしまったのだ。
二人が帰ってこなかったのでわしは一人で無花果の木を守っておったのだが、アダムとイブが米で造った旨い酒をもってきたのだ。わしはついふらふらと、その酒を飲んでしまった。ほろ酔いで二人を待っていたのだが、なかなか帰ってこない。アダムとイブは次から次へと酒を持ってくる。酒好きのわしは意志が弱かったのじゃな、全部飲んでしまって、寝てしまったのだよ。その間にアダムとイブは無花果をみんな食っちまった。この木はまだ小さくて、たった八つしか実がなっておらなかった。ところが、次の年は十六個と、その次は三二個となり、アダムとイブは毎年独り占めして無花果を食べたのだよ。
それが百年続き、火山が爆発して溶岩が溶け、閉じ込められていたスラッグが出てきて、氷河が溶けてグルヌイユが出てきて、戻ってきた。やっとわしを起して、無花果の木から実を採られてしまったことがわかった。
この無花果の実を食べると、言葉をもつようになる。アダムもイブも人間ではなく、最後の類人猿だったのだ。最初の原始人と言ったほうがよいかもしれない。無花果を食した二人が生んだ子どもが人間になったのだ。しかも、無花果を食べ羞恥心をなくしたアダムとイブはのべつ幕無しに交尾を繰り返し、子どもをたくさん作ったのだ。アダムとイブの子どもたちはいろいろな言葉をもち、その言葉を悪用することを覚えていったのだ。
人間の世界ができてくると、だますために言葉を使うようになった。人間の世界では言葉が真実を伝えなくなった。違いますかな」
老人は吾を見た。その通りである。頷くしか他にない。
「嘘を言うことができる世界をつくっちまった。それもこれも、意志の弱いわしのせいなんだ。禁酒がなかなかできなくてのう。
さぞかし、言葉を持った人間がいる世界は悪くなったことだろうと、この禁断の無花果を守りながら考えておったのだ。しかし宇宙の時間は無限じゃ、言葉を持った悪知恵のある生き物はいつか自分から滅びる。
無花果を食べて羞恥心がめばえたのではなく、もともとあった羞恥心がなくなったのだ。無花果を食べすぎ、腹の具合の悪くなったアダムとイブは無花果の葉を持って用足しに行くところを見られたのじゃ。無花果には便秘や整腸の効果もある。その様子が葉っぱであそこを隠したという言い伝えになっただけなのじゃ」
なんとも、神話もいいかげんなものだ。
蛇の老人は人間である吾に、人間がつくられる最初の出来事の本当のことを伝えられたことをとても喜んで、これは宇宙が許してくれた証だと涙を流した。
無花果の料理は多岐にわたり、十分楽しませてもらった。
吾は知らずして大事な役割をになっていたのだなあと思う。
蛇の老人、蛞蝓と蛙のおばあさんたちが言うには、人間が言葉をもって、もっとひどいずるがしこい動物になっていると思っていたが、そうでもないということを吾を見て悟ったということだ。どうしてだと聞いたところ、宇宙が使わした吾は全人間の最も平均的な人間だからだそうである。平均的人間というレッテルを宇宙からもらって、なんとなく喜ばしい。
そうこうしているうちに、夜になり、蛞蝓と蛙は自分のすむ家に帰っていった。
星が夜空を覆い尽くした。蛇の老人は一つの方向を指差すと
「あそこにある小さな光が太陽じゃ、地球はその周りにある」
と言った。
そうか、ここは地球ではないのだ、人間が生まれた場所なんだ。我々の感覚でどのくらい遠いところにあるのかわからない。いや、隣り合わせにあるところなのかもしれない。
その時、ぽこっと音がした。
そちらを見ると、禁断の無花果の木で、熟れて蜜のような汁が光っている実の一つから、一つ目の妖精が首を出している。ノールウェーに行ったときに買った一つ目の妖精の顔である。ちょっと離れたところの実から丸い顔が出た。北海道の笛を持ったコロボックルだ。
「禁断の無花果の木は妖精たちが生まれる木でな。妖精は人間たちの子供の枕元に一晩立つと、また、もどってくる。言葉を持った生き物を産ませてしまったからには、その後のケアーが必要なのだよ。人間性を養わないと、人間は悪い方向にいってしまう。いつか滅びるにしても、宇宙のほかの生命の迷惑にならないようにしなければならないからな」
ティンカーベルが空に舞っていく所だ。妖精には性がないそうだ、男と女の葛藤がない世界の生き物なのだそうだ。毎日、夜空の中で、妖精たちが地球に向かって飛び立つ様は、花火が空に向かってはじけるような美しさがあるそうである。
その時間が近づいていると老人が言った
その瞬間には音がなかった。
宙に無花果の実から舞いでた妖精たちが思い思いの振りをしながら空に静かに舞い上がったと思ったら、空中に花火が炸裂したような色とりどりの光の爆発とともに、流れ星のように地球のほうに流れていった。
音のない光のショウが終わると、妖精の赤い上着を着たアンジールが吾の前に来て、無花果のお酒を勧めてくれた。細い白い指でかかえられたクリスタルのボトルから透明の酒がグラスに注がれた。吾がグラスを持ち上げ、一口飲むと、アンジールが微笑み、大きな蛇がありがとうと日本語で言うのが聞こえた。
その後は、禁断の木の天辺の実の中から、吾は首を出して地球を眺めていた。隣の実からアンジールが微笑んでささやいた。
無花果の精になったのよ。
こうして吾は無花果の中に閉じ込められた。
見たこともないトロールが、隣の無花果から生れた。吾の入っている無花果からも、白装束の女の子が生れた。雪女の子どもだ。雪女もここで生れるようだ。雪女の子どもが空に舞いあがると、吾も一緒に舞いあがった。無花果の精となった吾を背負った雪女の子どもは乳白色の光を放ち地球に向かって飛んでいった。
これで地球に帰ることができる。
無花果-幻想私小説7
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


