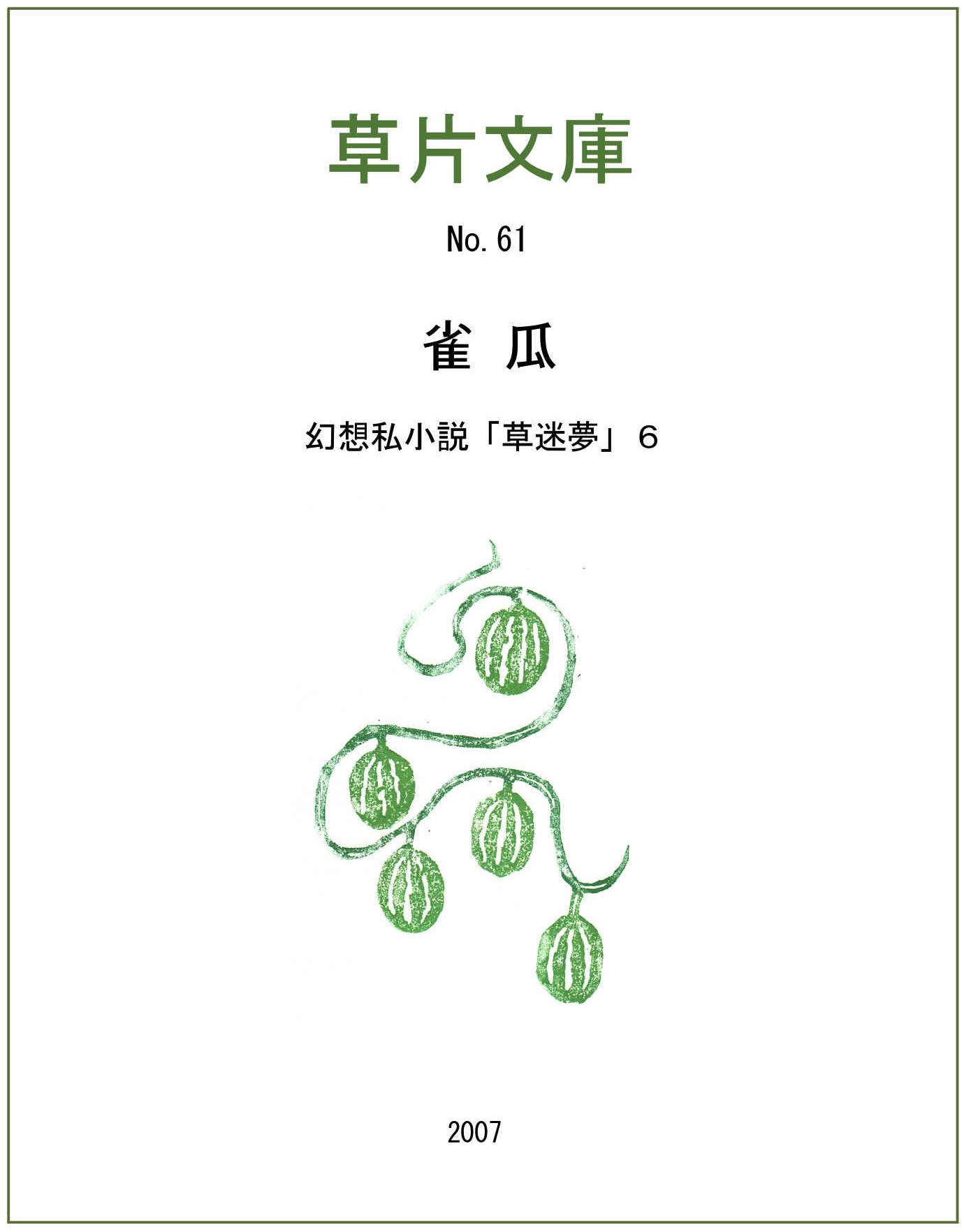
雀瓜 - 幻想私小説6
霜柱の精となり、吾が入った氷は、溶けたのがとても遅かった。溶けたにもかかわらず、冬眠してしまっていた吾は、気が付いた時は夏も終わり、秋の初めであった。
垣根に這い上がった雀瓜が緑色の実をたくさんつけている。
縁側の障子を開け、夕日に映える雀瓜を見たら、なぜか酒が飲みたくなった。
日本酒を飲むことはほとんどなかったが、頂き物の酒がある。そういえば、もらった鮭とばもあった。
雀瓜は好きな植物で、白い五弁のちいさな星型の花が咲く。雀瓜の仲間に烏瓜がある。どちらかというと、真っ赤な大きな烏瓜の実のほうが一般に知られている。ただ、烏瓜の夜咲く大きなレースの白い花の見事さは、知る人ぞ知るで、あまりしられていない。レースの花を押し花にして、額に入れて飾ってあるのだけれど、これ何と聞かれることがある。烏瓜の花を知る人は少ないが、雀瓜の花を知っている人はもっと少ないだろう。雀瓜はウリ科スズメウリ属の植物で、可憐な縞の入った緑色の実を見ると、誰でも好きになるだろう。大きさや形は雀の卵に似ているかもしれない。ただ赤くはならない。沖縄の倍ほどもある大きさの沖縄雀瓜は白い筋の模様の入った真っ赤の実になる。
今日は軽子がいないようで、おそらく友達と温泉にでも行っているのだろう。一人の気ままな夕食だ。豆腐でも買って、もらったもので楽しもう。
頭もかなり薄くなって、若い頃は穿いたことのない茶色のジーンズを無理に穿いているのだから、七十になった頃だ。
いつもはもっぱらシングルモルトか、角瓶の炭酸わりだ。ずいぶん長く角瓶を愛用しているものだ。五十年以上だろう。五十になってから痛風をわずらい、ビールが主だった晩酌が、ウイスキー中心になった。ハイボールである。
角瓶もいろいろ変わったものだ。それを全部とっておいたのだから物好きといえばもの好きだ。本棚にずらりと並べてある。二〇〇〇年だったと思うがクリスマスの時期に女性向きの赤い角瓶がでた。その後、色のついた角瓶は出ていない。壽屋には茶色の瓶の角瓶を出してくれといっているのに、いまだにだしてくれない。
トーフィと豆腐屋のラッパの音がした。このあたりには三河屋という豆腐屋が車で売りに来る。いつも絹ごし豆腐と、柚子豆腐、揚げだし、玉蒟蒻を買う。今日もそれをもらって、冷蔵庫から新しく出た恵比寿ビールをとりだした。
食卓の上に買ってきたものを並べ、まずはビールを開けた。それから日本酒。
ふと見ると、
雀瓜ががさがさと動いた。太った守宮(やもり)が雀瓜の上に一匹いる。
雀瓜たちがいっせいに守宮のほうを向いたようだ。
太った守宮が首をたれた。
「ククククッツ」
雀瓜たちが笑った。
遠いのであまり聞こえてこない。聞き耳を立てたくなる。
新しくでた恵比寿の黒ビールは前のものよりきめ細かく、やわらかいが、しっかりとしていてうまい。揚げ出し豆腐を温めて、鰹節をかけた上に、醤油はヒゲタの玄蕃蔵。
「笑うなよ」
守宮が言っている。
雀瓜がまたいっせいに守宮を見た。
「家出なんてするなよ、戻りな」
雀瓜が諭している。
「怖いんだ」
太った守宮は首を垂れている。
「自分で選んだのだろう」
「うん」
身の上話のようだが、あまり聞いてはいけないようだ。聞き耳を立てるのはやめにしよう。
庭の柿の木に目をやると、画眉鳥が薄茶のお腹を膨らませて止まっている。こいつらは中国からもってこられて、逃げたか放されたかしたものが繁殖し、東京のいたるところで、ころころといい声を張りあげている。中国では鳴き声を楽しむために飼うようだ。はじめて聞いたときには、なんといい声だと思って、近くの木に止まっているのを見つけたときには感激した。写真をとって鳥に詳しい友人に名前を聞いたものである。ところが、毎日毎日聞いていると、日本にはあわないやつらだと思うようになってしまった。彼らのせいではないのだが、ウグイスのような奥ゆかしさのある鳴き方ではなく、いい声だろいい声だろという押し付けがましさを感じてしまう。それでいつぞや、毎日鳴かないでくれといったら、そのようにしてくれている。頭のいいやつらだ。太っちょで、鈍感で、可愛らしくはある。
どうも守宮をみているようだ。そうだ、こいつは虫を食べる鳥だった。獲物をとるために鳴いていないだけなのかもしれない。
画眉鳥が飛んだ。危ないと思った瞬間、守宮にむかって雀瓜たちが寄り集まり、とり囲んでしまった。
画眉鳥は面食らって、雀瓜を一個飲み込んでしまって、咳き込んでいる。
「ククククッツ」
雀瓜たちが笑っている。
画眉鳥は食いっぱぐれて飛び去っていった。
よかったと胸をなでおろした。雀瓜が元のようにぶらんとぶら下がると、その中から守宮が眼に涙を浮かべて顔をだした。
「おお怖かった」
「家に帰るのも怖いし、ここにいようかな」
「だめだよ、お帰り」
雀瓜たちは冷たく言っている。
守宮はよろよろと、生垣を歩いて後ろの家に入っていった。
「怖がりの癖に、あんな怖い女と一緒にいるなんてね」
雀瓜のささやきは小さくなっていった。
庭の草木たちがなにやらささやいているのを聞きながら酒にした。
北海道の知人が農場を開拓し、無農薬の野菜類を作ったり、鮭や鳥や貝類の燻製を作って生活をしている。その知人が送ってくれた鮭とばは少し塩辛いが、味があり、酒の肴にはもってこいである。酒は東京の酒蔵で名入りで造ってもらっている所沢小手指の飲み屋のだ。佐藤水産という酒だが、その店はもともと魚屋で、道楽で始めたいっぱい飲み屋が、魚のうまさと主人の料理上手というか人柄からか常連が集まり、魚屋よりそちらのほうがさかんになってしまったところだ。さっぱりとした口当たりの、うまい酒だ。
コップに盛った酒をちびりちびりと飲んでいると、パタと目の前に守宮が落ちてきてひっくり返った。真っ赤な腹の守宮とは珍しいと思ったら、真っ赤な腹をした井守である。井守が天井にいるのはおかしいと見上げると、天井にもう一匹ついている。
そいつは、ちょろちょろと壁を伝わって降りてくると、ひっくりかえっている井守の鼻先を突っついた。そいつは井守ではなく守宮だった。
「あんた、ばかね」
そう守宮に言われた井守は、もそりと起き上がると、恥ずかしそうに吾を見た。
「お酒の匂いにつられて、落ちちまうんだから」
吾の手にはコップ酒がある。確かに鮭とばを肴に酒を飲んでいる。
守宮が吾を見上げた。
「すみませんね、こいつにちょっとお相伴させていただけませんでしょうかね」
井守の亭主と守宮のかみさんていう夫婦なのか。なかなか亭主思いだ。
言った後、守宮は恥ずかしそうにもじもじしている。
確かに恥ずかしい一言ではあった。いくら惚れた亭主のためであってもなかなかいえないだろう。
「亭主じゃないんです」
人の心も読む守宮か。
「じゃあ、これから結婚するのかい」
と余計なことを聞いたのは、いつもの自分ではない。酒を飲んでいたからかもしれないが、なんだかそのような具合になった。
「私の亭主は隣の家に住んでいるんです」
「守宮か」
「そうです」
「見つかったら大変じゃないか」
「いいんです、あの人、餌にと捕ってきた蟷螂に惚れちまって、今一緒にいるんです。今に食べられちゃうというのに、だまされやすいんです。それでもいいというのです」
「そんなもんか」
雀瓜に助けられたのはどこの守宮なのだろう。蟷螂に惚れたやつだとすると、蟷螂の怖さを知ったようである。そろそろ戻るのじゃないかな。
井守にコップを用意して、冷えた佐藤水産をついでやった。
井守は赤ら顔の男に変身し、身をかがめ、お辞儀をしながらコップを受けとると、うまそうに飲んだ。
もう一つのコップを守宮に渡そうとすると、守宮は悲しそうに見上げるではないか。
悪いことをしたかと、とまどっていると、井守が首を横に振った。
「すんません、こいつは、化けられないんで」
「どうして」
「守宮は天井を這うのはうまいのですが、一人で化けるほど器用ではないんで」
「それじゃ、どうやって酒をついでやったらいい」
「今手助けしますんで」
井守男は守宮を手のひらに乗せると、尾っぽをつかんでぶら下げて、振り回した。
「おいおい、乱暴な、眼を回すし、尾っぽが千切れたらどうする」
本当に心配になったとき、くるくる回されていた守宮が、ふっと女になった。
女になった守宮は床に落ちると、キャット悲鳴を上げて座敷の隅に這っていってうずくまった。
井守の親父も吾も目を丸くした。
守宮女は素っ裸だった。
「ほら、まじないを言い間違いやがった、人間になるだけじゃだめといったじゃないか、人間の世界にいくといわなきゃ、人間は皮が弱いから着物を着るんだよ」
小柄でやせた女の背骨が浮いて見えている。
「すみません」
丸く平べったい顔をした女が恥ずかしそうにこちらを向いた。
われも仰天してちょっととまどったが、台所においておいたエプロンを急いでもってきた。
女のほうを見ないようにしてエプロンを渡してやった。エプロンをつけてこちらを向いた女はもっとなまめかしいものになってしまった。
これはいかんと思い、自分の部屋にいって、とりあえず、吾のティーシャツと半ズボンをもってきてやった。女は急いでそれをつけた。
ぶかぶかのティーシャツと半ズボンをつけた女は、井守男の隣に座り、白い顔を吾のように向けた。
守宮女に酒をついでやった。
「お騒がせして、すみません」
といいながら、うまそうに酒を飲んだ。井守より酒が好きそうだし強そうだ。
「うちに棲んでいるのかい」
守宮はここに住んで三十三代目だという。この家を建てたのが二〇〇二年だから、家ができたときにきた守宮の子孫なのだ。
「棲みごこちはいいのかい」
守宮の女はうなずいて、兄弟もここにいたかったんだが、残るのは一軒に一人という慣例にそって散り散りになっていったそうだ。長女のこの女守宮が後を継いだそうだ。しかし、親夫婦、その親夫婦、またその親夫婦、数え切れないほどこの家のどこかにいて、まだ最初にここに来たじいさまが三十三歳で家のもっとも虫のたくさん来る西側の軒にいるそうだ。吾の部屋の窓に出てくる太った守宮ではないだろうか。その連れ合いは、白い猫に遊ばれて若くして死んだという。うちの猫の白のやつだ。
守宮の女は玄関の軒に住んでいるのだそうだ。あの玄関の電灯は、厚木の実家についていたものをはずしてつけた。厚木の実家はもうないが、昭和の終戦直後に建てられたものなので、玄関灯は優に百歳を超えている。
それにしてもなぜ井守と出会ったのだろう。
守宮はまた心を読んだようだ。
「この人、人に飼われていたのだけれど逃げ出して、ガマガエルについてこの家にやってきたのです」
庭にある睡蓮鉢に時々ガマガエルが浸かっていることがある。いつぞやはホテイアオイを入れておいたらホテイアオイの間にガマガエルが顔を出して考え事をしていた。
井守に聞いてみた。
「あそこにいたヒメダカが一匹もいなくなったが、お前が食ったのか」
井守ははっとして、正座をすると深々と頭を下げた。
「そうなのか、気にするな」
井守に酒を注ぎ足してやった。
「足を崩してくれ」
井守男は、すんませんといいながら、胡坐をかいた。守宮女も頭を下げた。
「ほんとにこの役立たずがご迷惑ばかりかけてすみません、この人、あのヒメダカをみんな食べちまって、お腹すかして、たまたま塀の蔦の上を通りかかった私を餌だと思って食いついてきたんです。ばかって、水の中に叩き落としたら、ばちゃばちゃしておぼれそうになるじゃありませんか。井守がおぼれてどうするのと引っ張ってやったら、腹へって死にそうだっていうので、蜘蛛を捕まえると口の中に押し込んでやったんです。そしたら蜘蛛は初めて食べた、うまいうまい、狩の仕方教えてください、と涙ぐんじゃって。でも私そういうの弱くて、かわいそうと思ったので、蜘蛛の捕り方を教えてあげたのよ。そうしたら、今度は一緒に住んでくれって。ちょうどあほな亭主が蟷螂に熱を上げて出てっちまったから、一緒に棲んでるんです」
「あの玄関の軒でかい」
「ええ、でもこの人おっこっちゃうので、いつもはトヨの中にいるの、あそこは水もたまるし」
玄関のトヨはよく木の葉でつまり水が外に溢れ出て落ちる。なるほどと納得できた。
守宮女にももう一杯ついでやった。女はうまそうに飲む。鮭とばはどうかとすすめたが、ちょっとつまんだだけで、食べなかったので無理にはすすめなかった。少し血色がよくなって可愛いところもある顔である。
井守男のほうはおとなしく飲んでいる。
男のほうにも鮭とばを勧めたがやはり好みではないようだ。何か出してやろうかと考えたが、豆腐はどうかと勧めてみた。
「うまいです、おいしいです」
彼らは醤油も付けずに食べた。
「これは豆からつくるんだ」
「植物がこんなにおいしくなるんですか」
守宮女は目を丸くしている。
守宮たちはどいつも人の心を読めるのだろうか。
「守宮はみんな読むんです。強弱はあるけど。最初のじい様はもっとも人感がよくて、ここの人たちなら追い払わないと感じて棲むことにしたそうです。ただみんな猫好きでそれが困ると言っていました」
正直な守宮だ。
「ほほほ」
守宮女が口をすぼめた。
コップが空になったので一杯についでやった。
守宮女はいっきに半分ほど飲むと、ペロッと舌を出した。
なんとも不思議な顔なものだ。守宮のはずだが人の形、しかも女だ。
「そろそろ、私どもも帰りますわ」
井守のほうも丸い顔をとろっとさせて、メダカのことをまだ詫びている。
その時、大きな声がして、守宮が駆け込んできた。その後をおなかの大きな蟷螂が追いかけてきた。
「お助けを」
井守男が逃げてきた守宮を捕まえるとぶら下げて、さっきと同じように振り回した。ぎゃあという声とともに守宮が男になった。
蟷螂は自分でくるりと回って、和服を着た妊婦姿になった。口元がちょっときつそうだが、それは大そうな美人で、長い黒髪が腰まで伸びて、背中をやわらかく覆っている。
蟷螂女はちょっと疲れたように、テーブルの脇に横すわりになった。妊婦とはいえなかなか粋なお姉さんといったいでたちだ。逃げ腰であった守宮男は引き寄せられるように蟷螂女の隣にすわってしまった。怖いけれど離れられないと守宮男の眼は言っていた。
守宮女がつぶやいた。
「馬鹿な亭主」
「逃げられ女房」
蟷螂女もまけじと言うので、こりゃ大変と思い、まあ酒でも飲んで、と吾はコップを二つ持ってきた。
蟷螂女は何もいわないうちから、手を伸ばしコップを取った。守宮男にもすすめてやった。ともあれ、これ以上喧嘩がひどくならないようにと、佐藤水産をついだ。守宮男はちょっと口を付けてコップを下においたが、蟷螂女はクククイーッツと空けてしまった。いい飲みっぷり。またついでやると、
「すみませんねエーと甘え声を出した」
鮭とばを勧めると、蟷螂女はきゅきゅと食べてしまった。
「おいしい鮭とばだこと」
通な蟷螂だ。
また、酒をクイイイッツと空けた。面倒なのでほっといたら、自分でついでクイッツと飲んだ。
「お腹の子達が栄養をほしがるの」
「馬鹿な亭主も食べたいんでしょ」
先に来た守宮女は横目で蟷螂女を見ながら、井守男に寄りかかった。帰るつもりが帰れなくなったようだ。
そういえば、お腹の子供たちというのは卵のことを言っているのだろうか。人の心を読むことができる守宮女が言うには、この蟷螂女の八代前のおばあさんがネズミだそうで、卵ではなく子供を産むそうだ。
日がだいぶ傾いてきた。
二本目の佐藤水産をもってきた。ついでに豆腐の残りと鰹節をもってきて、皆に勧めた。
守宮女が家出した守宮男に、もうこの家に来ないでくれといっている。守宮男は少し未練がましくうなずいている。蟷螂女が嬉しさを隠せなくて、目じりを下げている。井守男は難しいことはわかりませんと言っている。
そこそこ酒がまわってきて、蟷螂女は妙な目つきで守宮男をみるようになった。
守宮女は豆腐を食べながら井守男に言った。
「そろそろ始まるよ、わたしは見たくないのよねえ」
井守男は何を言われているのかわからないようだ。
蟷螂女の眼が据わってきた。横すわりになっている蟷螂女の手がのばされた。袂から出た両手が守宮男の顔をかかえた。人間は口をどこまで大きく開くことができるのか知らなかった。顔中口になったかのように大きく口を開けた蟷螂女は守宮男の頭にかじりついた。
吾は夢中で叫んでいた。
「その格好でやってくれるな」
その声で、蟷螂女と守宮男は蟷螂と守宮にもどっていた。蟷螂の口は守宮の頭をくわえている。
蟷螂はずるずると守宮を引きずると庭に出た。ムシャリムシャリと守宮を食べちまった。
「しかたないの」
蟷螂のおなかがクイッツとくびれると、頭が守宮のこどもの蟷螂がぞろぞろとでてきた。おかしい、蟷螂は卵を産むはずだ。
蟷螂の子どもの頭は守宮だった。だからか。
「うまれたわ」
蟷螂女が言ったとき、ばさばさと音がした。
また画眉鳥だ。あっという間に蟷螂の子供を何匹もくわえてもっていってしまった。蟷螂はあわてて一匹を自分の腹の下に隠した。また別の画眉鳥が滑空してきて、蟷螂本人もくわえて飛んでいってしまった。
蟷螂の腹の下にいた一匹の小さな守宮蟷螂が空を見上げている。
守宮女があわてて守宮になると子供の守宮を抱えあげた。
「わたしが育てます」
井守男もうなずいた。井守に戻っている。
守宮女と井守男は深々と頭を下げると、子どもを連れて帰っていった。
ドラマが終わったなあと、佐藤水産を飲んでいると、ぽこっと音がして、庭の雀瓜がわれ、中から白い煙がたちこめた。煙は漂いながら部屋に入ってくると、吾の周りを取り巻いた。
からだが宙に浮き、白い煙に溶け込むように分散し、雀瓜の中に吸い込まれた。
こうして吾は雀瓜の精になった。久しぶりの日本酒を飲んだせいだろう、とてつもなく眠くなった。意識がもうろうとしてきた。夢の中で眠るのもいいもんだ。
雀瓜 - 幻想私小説6
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


