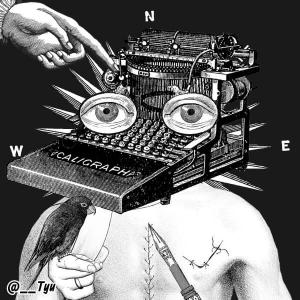芽
小説家を目指し、上京してきたのは十年前。悪戦苦闘しながら書いた小説は結局何の賞も取れず、ただ都会の波に逆らい続けるには、その波に逆らうだけの度胸や強さは持ちえず、最悪波に逆らう魚群となればよいものの、余計なプライドと小説家は一匹狼だという謎の固定概念に囚われた一匹の小さな魚でしかない私は、そのまま都会と言う波に淘汰された。いつからか私の綴る文章は世界をも震撼させるものから、売れようとするために民衆にも理解されやすいであろう量産型且つ安物の芸術へとなり下がってしまった。足りない脳みそでできる限りの知恵を振り絞ったほうがよかったのかもしれないが、言い訳を聞いてくれ。私のようなものが書く小説とは、結局のところ良くて一流の補欠程度のものしかないのであれば、数打ちゃ当たる戦法も悪くないものだとそう予想していた。なぜなら「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」ということわざが存在しているのだから、二流小説家のカバン持ちをする私程度の小説家はそうするしかないと、半分期待半分絶望していた。しかし結果は言わずもがな撃ってきた玉という玉は、さよならホームランよろしく、全く予期せぬ方向へと飛んで行った。
小説の効率どうこう起承転結云々脳内で緊急会議をしている間、私はせめて脳内にいる上司たちに有益な情報を提供しようと、勉強と自分の想像力向上を称して傑作と駄作の境界線を漂っているB級映画並びに小説を網羅しつつ、タバコと酒を片手に、クオリティは並の半減でしかないものを一心不乱に書きなぐる日々を過ごしていた。もちろんそんな安物の芸術など売れるはずもなく、バイトとバイトと、バイトとを繰り返す日々になっていた。時には全く執筆せず、時には何晩も机の前にしがみ続けたまの執筆活動は、どうせだめだと、いやきっと次こそは、の大乱闘。憎むは次から次に浮かぶアイディアだが、それは天才がアイディアらをろ過した過程で出たゴミでしかなく、悪くはないがなどとよく腕を組まれていた。きっと天才も同情してこれならいいよと差し入れいてくれたに違いない。もし天才たちが私に変な同情を与えずにいたら、きっと私はすぐに区切りをつけて真っ当な社会人になっていたのは明白である。
揺れる電車の中から見える景色は、上京する時、ここに帰ってくれるときは雪景色ではなく、満開の桜がきっと祝福してくれるものだと思っていた。だが、今では右往左往する自分の心を紛らすために電車の窓から見える桜を見るほかなかった。これからいいことあるって、と全く煩わしいことを今にも言われそうなくらい、満開だ。今日の電車はよく揺れる。
無駄に過ごした十年は何にもならず、先生と呼べる存在でもない私は、両側から現実というの名の壁に押しつぶされそうになった。昭和の小説家にあこがれ着物で日常生活を過ごしていたせいかもしくはTPOにあう格好をしていないからか、ほかに乗車している人からの視線が痛い。特効薬であったはずの桜ももう見えず、洞窟の中を走る電車はこれから地獄へ向かう火車にも思えたが、あながち間違いではなかった。
電車から降りるや否や、目に余る桜と安堵感を与えてくれる心地の良い風に包まれたかつての故郷に私は、砂糖を入れすぎた珈琲かのような不快感に溺れた。息が詰まる、本当に水の中に溺れたみたいだ。水中に溺れたときはまずは冷静にならないといけないのだが、私は至極冷静であり、私は冷静に考えてもここではうまく呼吸ができないという結論に至った。小説家たるものいくら現代社会からの地位、名誉、その他社会で生きる上で不必要かつ実力を象徴として見せびらかすもの等剥奪上等精神であろうとも、奇人扱いされるのは私も中途半端に人であるゆえに、羞恥心が巡り回り理性で蓋を落としている。いっそのこと全部吹っ切れて暴れて叫ぼうとも思ったが、人間を失格になれず、かといって社会人には適応できず、両者一択であるなら、ベクトルから落とされた不良品である私はその欲望を宥めるほかなかった。
この世には大きく分けて三種類の人間がいる。使うものか使われるものか、そしてそれを逸脱した者か。天才と呼ばれる人間は逸脱したものに含まれており、同時に人間の出来損ないもまた、ここに含まれている。人間の出来損ないも一歩間違えたら天才なのだ。何が天才と出来損ないを決めるか、それは至極単純であり、それは努力の一言としか言いようがない。私が出来損ないであるのは、きっと才能はそれなりにあったのだろうが、努力する才能に欠けていたのであったと思う。だがしかし私はこう言いたい。天才と呼ばれる人たちは「そのもの」の才能があったわけではない、むしろ一般常識的な言葉を借りるとするならば、普通、平均的な才能であったのが天才の幼少期の大半を占めるであろう。もちろん天才の中でも幼少期から類いまれなる才能があった者もいるであろうが、共通して言えるのが「努力の天才」であると思う。思うというか、まぎれもない事実だ。
何が言いたいのかと言うと、ここには使う人間と使われる人間しかいない町だということであり、私は私もそのうちの一人か一人ではないかを試しに町を出たのだった。ここに夢破れて帰ってくるということは、私のなりたくなかったそのうちの一人だということを決定づけてしまう。しかし、この10年で唯一学んだことは、私も結局才能足りず一人目立つスイミーにはなれなかったということであり、なれるのはせいぜいスイミーを引き立たせる魚群のうちの一匹なのだということだった。
駅西口から降り、独りスーツケースを引きずっていると、初めて原始人を見たかのような物珍しさに人たちは寄ってくる。それもそうだ、この駅に降りるのは都会から帰省した天才かそれ以外かの二択に別れる。
商店街の佐藤、旧姓谷原は名前の通り佐藤と結婚し、エプロンには血が斑点のようにおしゃれな殺人鬼みたいな恰好でありながら、何が面白いのか人に死肉を売りつけている。その隣の花屋はたしか高校の時に学校一の美少女こと井の中の蛙の河合さんが、売れ残りの花共々いつ枯れるかわからない日々を暮らしていた。10年という月日は薬で夢を見せられていたかのような錯覚に陥り、あたかも私はこの魚群の一部であったように、町に飲み込まれていく。その時皆口をそろえて、先生様のお帰りだなと言われる度に、頭から氷水をバケツごとぶっかけられるような感覚に見舞われ、声を掛けられる度胸に空いた穴に、飛行機に乗る時なら追加料金をぼられるほど重量オーバーな私のスーツケース同様、詰め込まれていく。その隣、その隣と、店舗と言う監房に縛られた懐かしくも悲しい魚たちが、少しでも町と言う一つの魚群を大きくさせようと、占い師よろしく血液型占いよろしく誰にでも当てはまるお世辞と言うお世辞を豪速球で投げてくる。だが私は一つ当てがあった。この混ぜるな危険の闇鍋に突っ込まれたことも気づかない仔魚たちで形成された町の中にも、唯一と言ってもいいほど、人間が生息している。
私には一人の相棒がいた。彼はこの街には珍しいほど努力家で、勤勉で、誠実で、分け隔てなく優しく、人類の卑屈の総本山とも言える私とは正反対でありながら、正反対だからこそ馬が合うものがあった。しかしそれ故に喧嘩することも多々あり、殴り合いにまで発展した時もあった。その度に私はその事を根強く気にし気にかけるのだが、そうか、あいつはこんなこと気にしてないな、と気楽に翌朝いつものように声かけることもできた。私はそんな彼を愛しているが、私が愛しているということは、向こうは愛していないのかというと、そこだけは合致しているのかもしれないしそうではないのかもしれない、私が勝手にそう思っているのだけかもしれないが、大して気にしたことはない。
そんな彼だが俳優になることを夢見て、高校卒業と同時に私と共に荒波に突っ込んでいったいわば戦友なのだ。
互いに夢と希望を持ち、何も疑わぬ信念で努力をしていたことが懐かしい。彼とは8年共に人生を共有した。期限切れのコンビニ弁当と安酒をたばこでふかした8年、いずれどっちも有名になって居酒屋で語り明かそうと、二人で悠久の夜を過ごした8年。彼は、彼も夢破れ2年前に帰ってきている。しかし私は信じている。彼もきっと帰ってきたときは今まさに私が受けた洗練を受け、同じ感覚に陥ったに違いないと。彼と私の唯一の共通点は夢に愚直であったことであると思い出し、それに浸り溺れ、縋るように彼に連絡をした。彼なら私の体に纏わりついた凝固した同情の念を溶かして、私の冷め切った熱意を燃え上がらせる男だと確信している。
私たちは約2年ぶりの再会だというのに、かつて我々が大都会に多くの夢と希望を見て語り合った居酒屋オゴセで飲んでいた。その店の内装は昔からボロボロで壁にヒビがあり、帰ってくる頃にはそのヒビが店を一周して真っ二つに割れるものばかりだと思っていたが、行く前と何ら変わらずそのヒビは、いや店はまるで私の帰りを待っていたかのように、堪えていた。
店長は昭和のザ・頑固おやじで我々が煙草という紙幣を燃やす悪魔と仲良くなる前からその毒害を吹いていたが、今ではすっかり衰え堕ち、愛孫のために無駄に長生きをするためか、年金を貪ろうとするためか、もしくは店を継いでくれない息子へのあてつけか、ともかく煙草をやめていて、あまつさえ手前は昔餓鬼の前で毒害を吹きかけやがったのにあたかも昔から嫌いです風を装って嫌悪しているらしい。そのため私が店内で煙草を出した瞬間、隣のテーブルに座っていた鬼達磨に叱られた。店長さんたばこお嫌いなんですって、私は別に構わないけどと、自分が嫌いなのに意思を他人に丸投げし他人の代弁者を装った上、受動喫煙のような悪意のない悪意が店内を漂っていた。そういえばあの頃は鬼妻からの現実逃避した老けた男どもの楽園かのように思えたが、今では鬼か達磨かその両方か、飯を味わうためか毒を吐くための舌かわからないが、視認できない副流煙を吐くものが大半を占める店に成り下がった。毒を以て毒を制すとはよく言ったものだととても感心した。
いくら祖母の家に住んでいるとはいえ仕事しなくてはならないと、相棒が仕事を紹介してくれた。町はずれにある工場で、そこの工場長はいい人だからお前でも大丈夫だと背中を叩かれた。呑みの席であったため私もつい余裕とばかり思っていたが、いざ電話がかかってきた時は謎の緊迫感により心臓から耳の毛細血管まで血が通ってることを再確認した。その瞬間脈拍が戦闘態勢だとばかりに己を鼓舞し始めたが、視覚は敵を捕らえられず脳が混乱し、それにより数兆あるといわれる細胞の中のミトコンドリアまでが我々の敵はいったいどこにいるのかと混乱し戦慄し、震えあがっているのがよく分かった。
私は本能的に仕事が嫌いなのだと、いや人間が嫌いなのだと、何兆とある細胞の1つ1つが私に呼びかけ、それに呼応するように震えた。大腸から小腸、胃に食道はそれまで甘受していたのを拒絶し始める。私が関わったことのない人間は、動物が本来持ち合わせていた闘争本能と敵に対する拒絶反応が、雌親の排卵期のように、凶暴で最凶で最悪な結果をもたらしてしまう。しかし私たち人間は理性と本能の生き物であり、それをしようにもそうさせない理性を持ち合わせていたことから、私はその敵を殺すこともできず、かといって逃げる場所もなく、ただただ迫りくる死を受け入れるしかなかった。
電話が鳴り終わる。結局電話に出ることができなかった。一仕事終えたかのような汗の量。私は少しばかりの安堵の後、私に落胆した。なにより私が私に落胆したという事実に落胆した。
常日頃から、いや、昔から自分に他人に期待しない生き方をしてきたつもりだったがいい年にもなって無職な私に何を自分に期待したのかと。むしろ絶望が平常だった私が、ほんの少しでも人生に希望を抱いてしまったことに焦燥感がふつふつと沸いてきたが、今さら人生なんてと煙草に火をつけた。
一介の小説家として、そのことをとりあえず綴り始めた。かつてはなんでもネタにしてやろうとなんにでも飛び込んでいたが、それは安全な場所から指令する過去の自分によるものである。
「前向き。経験値を稼げ。すべてはネタになる」そんな指令を受けていた。しかし現在と数秒先の未来の自分は命令違反を起こし、決して任務を達成したことはない。そもそもメンタルはそこまで強くないのに最初にガテン系物の小説を書こうとした日からうまくいくはずがなかったのだ。
しかし書いている最中に思うのはいつも前向きなことばかりだ。
もしかしたら売れてるのかもしれない、そして天才呼ばわりされるのかもしれない。しかし、そう天才にこだわり、何某賞にこだわり、そんなものは天才ではない。でも売れたら…。その永劫回帰だ。厚かましいことに「売れない」という選択肢は頭の中に入っていない。
かき集めた情報の中の一つに、「負けると思って挑む馬鹿はいない」という言葉を脳内から引っ張り出した。数ある名言から都合の良いやつをいくつかピックアップし、それは私の向き合うべき現実からの脱却を助長した。カーネルサンダースのようにいつかきっと理解される、ゴッホやニーチェのように真の天才とは死んでから評価される、そんなことばかり考えている。
実際それはそれで楽しい。しかしいざ現実に向き合うと決して裕福な家庭に生まれず、父親と母親は離婚し、祖母の家に居候するニートだ。それに幼少の時はたまに会う父からは「お前は母親に洗脳されている」と言われ、父親の所から帰ってきた時には母親から「洗脳されなかった?」と言われ、幼いながらに傷ついていた。そしてその心の傷からか、両親ともに信用しなくなり、代わりに祖母に依存するようになった。だが、祖母も祖母で幼い日に父―私の曽祖父にあたる―を亡くし、父親からの愛が欠如している人間だ。なにより尽くしたがりで、私がやらなくても良いと言ったことまで執拗に世話を焼いてくる。それに知能が低い。しかしそれは戦後中学校に通えない家庭もそこまで珍しくはなく上に、当時不治の病である日本脳炎にかかったからである。祖母の病は奇跡的に治ったがその後遺症により、―娘である私の母親曰く―大人であっても子供のような振る舞いをすることがあったそうだ。そのせいか知的好奇心はそれなりにあると思う私と比べて、知識に差がある。そんな生活にうんざりするも、一人で暮らすには私はあまりに弱く、かといって一緒に住む友達もいない。結局私は何かと理由をつけて寄生し、それでいて自分を正当化することにしか才能がない社会的弱者なのだ。
作品を書き終えた後に残る謎の自信とは、綿毛のように軽く柔く、何の役にも立たない自伝を綴ったところで何にも得られないのは分かっていても、それも私を包んでくれる。非常に不快だ。
それなりには読める内容でしかない、私の拙い文章で整列された話など、文学が崩壊しない限り認められることは無いと思う。確信を持てず、思う、で済ませてしまうから変な期待をしているのであろう。
もしかしたら、可能性が、そんな言葉が頭を渦巻く。通り過ぎては、ダメだ、無理だ、いやしかし、その三拍子揃って仲良く歩いてきやがる。追い越し車線は犯罪だろうに。死に晒せ。プライドを捨てろ。殺せ。己は醜いアヒルの子に出ている何にでもない虫だ。才能が開花する夢を見た、何度も見た。夢物語に過ぎない。悲観がまた私を呼んでいる。今度は脳に直接送り込んでくる、間者のように。
いかにして、どうしても、私は抗い続けるのだろうか。折れても気にしない雑草になれたら良かった。それでも根強く、心強くなれたら。ただ悪戯に作品を死なせ、愛せず、自慰紛いのものにしか成り下がらない。2人揃ってのものだと言うのに、ただ絵にも出来ず、作品にならず、苦痛が故に眠らされているのであるならばいっその事苦から解放されるべきなのだろうか。自問自答を繰り広げたところで、それが何になるというのだ。ただ、作品を死なせ、またこの話か、飽き飽きだ。
孤独だ、こんな孤独があってたまるか。私だけが正常なのか、私以外が正常なのか。正常とは何か、多数決か。排他的に不貞腐れた精神の生温い泥沼の中に死ぬまで浸からなくてはならないのか。大学出がなんだ、中卒出がなんだ。与えられたものしか出来ない探求心を失った思考放棄人と、与えられたものも出来ない知識放棄人、そう言いたいのか。どこに出ようと何をしていようと人生を己で考えることができないであれば等しい沼だ。社会というものはあらかじめ人のためにあるものではなく、偶発的に生まれた副産物であり、適応云々ではない。思考をする動物がなぜ効率的ではない方向に進もうとするのだと吠えたてたいのだが、それこそ思考をする生物であるという裏付けになるのだということに気づき、ならばいっそ思考停止になる方が余程マシである。
あてのない怒り、何に対して怒り、何に対して宣戦布告しているのか。己だけが良いという上級国民か、多分そうだろうな。世界は変わらないが、見方は変わる。それは全く以て都合の良い資本家の手先である。人類はいかれている。金がなんだ、金はなんだ。しかし結局私もそこに依存するしかないのは承知であり、私はそのことについて怒り心頭なのかもしれない。社会の在り方について怒っているのかもしれない。全人類が各々幸せのためにと尽力すればたったの半世紀で世界の在り方は変わるというのは確信している。しかし、日本という、国という排他的な空間でそれを我の物だとテリトリーを強調しているならば、いかに地球のためと言おうと利益という最も恐ろしい毒に毒されてしまって何も始まらない。宇宙という人類が考えている以上の広さを持つこの世界の中で、たった地球ぽっちの中の一国を主張するのはあまりにも滑稽で、それはアリがここは俺のエリアだと巣をコンクリートの隙間に作り始めるのと同じくらい規模の小さい話である。我々人類はそれに税金をかけるだろうか?不法侵入だといって捕まえるのだろうか?はたまたアリだからとほっとくであろうか。後者であろう。
自己顕示欲、己という個人を称賛させるなんとも言葉も見つからぬ酷い欲である。
それぞれ理に適っている三大欲求、それに比べなんだ自己顕示欲や自己承認欲というものは。人間が二足歩行をした産物が脳の発達というのならば、これらの欲を造り上げた脳は失敗作である。
死にたくはない。が、生きたくはない。
太宰治のように絶望している訳でもない、ただ、このまま生きていても何も無いように思えてしまうのだ。いやむしろ、上司から叱責され、同僚から異端の目で見られ、憩いの場であるはずの家では社会的ステータスと常識の被害者となった祖母から、それを盾に私に愛と偽った口撃をしてくるのだ。しかし、そんな事があろうと過去の記憶からか楽しい思い出が共存している。それによりありもしない未来に希望を抱いてしまう。いつか、きっと。人間が神を造り上げた時のように、私も輝かしい未来を妄想し、創り上げる。
…いつ私はこの悪夢から目を覚ますのだろうか。自暴自棄するには微妙に強く、社会で生きるにはあまりにも弱い。いつだってそうだ。人間は社会の中で生き、社会によって殺されるのだ。他動物を殺すのは少数の人間と大多数の他動物であるが、人間を殺すのは大多数の人間と少数の他動物。それが人の所業か、またはた悪魔の所業か。
嘘を嘘と見抜けない人は、本音と建前に翻弄され、建前を理解せず、それを本音と受け取ってしまう。よく言えば純粋なのが、いや、純粋なのが悪なのがいけないのか、もしくは俗に言う大人になりきれていないのか、私は本音と建前はよく分からず本音で話して損することが多かったがそれはともかく、建前だらけの世界となった日本では生きていくにはとても辛く、腹を割って話すのは親友同士の出来事でしかなく、各々がその蛇の卵のような柔い殻に篭もり、その薄皮1枚だけで人間を判断してしまうようになった。私の生き方はそれを断固として反対し、昔から蔑まれて生きてきたのと、幼い時母から相手の目を見て話すよう教えこまれたせいで、表情ひとつで相手の感情を大抵理解してしまう。それが真実か否かともかく、その薄皮1枚の確信までは届かなくともその裏にあるものが分かってしまう。それがわたしの思い込みであると信じたいのだが、気が利くねという相手から発せられた言葉を取るに、嫌でも私はこの社会の常識とは戯れられないようだ。
鈍感な人が羨ましい。何も察しずに馬鹿みたいに犬の如くしっぽを振り回しているのだろう。本人がほかの犬も可愛いとも言ってると知らずに。
犬はそれで幸せなのだ。犬になりたい。馬鹿なコーギーにでもなりたい。ただ無限の愛を感じ、悠久のときを過ごし、死んでも愛される犬になりたかった。忘れ去られるのではなく、その飼い主に強烈な、人生を変えかねないほどの悲哀を、浴びせたかった。
遅めの朝食をとっている時だった。泣きつかれた夜を越した朝というものは、恋人にフられたものと中々に等しいものがあり、元々埋まっていない胸の穴の存在すら忘却の彼方へとおいやった。とかく、私は気分が良い。それがたとえ一時の愉悦であろうとも、それを甘受するにはあまりにも条件が整いすぎていた。ベランダから差し込む木漏れ日、木々が靡く音にそれを靡かせる風、鳥の囀りにどこからか聞こえる笑い声。夢ではないか、そう思い強く頬を抓ったがどうにも夢ではない。
小さい時は朝食はパンとミルクと決まっていて、それも母がマーガリンといちごジャムをふんだんに塗りたくったパンが大好きであった。そして中学に入り、大人に見られたいという思春期の顕著な欲望から、ミルクと砂糖多めのコーヒーだけにした。もちろん食べ盛りの中学生が朝食にコーヒー一杯なぞ足りるわけもなく、優しい母はいつもお握りを余分に持たせてくれた。それも高校に入る頃には朝食を取らないようになった。しかし、今日日滅多にない素晴らしい日に、若い時を思い出して朝食をとろうとやかんを沸かした。
待っている間、何気なくつけたテレビからは声と効果音とが流れ、寝起きの頭で最近出た若い小説家が芥川賞を取ったというニュースがやっているのを朧げに感じ取った。最初、他人事のようにただへーと耽っていたが、次第に動悸が早くなり、それと同時に悔しさやら怒りやらそれらが混ざった、確実に悪い感情が沸騰し鳴り響くやかんのように、わいてきた。
どうやら私よりも6つも若い女性小説家が、今の若者の流行であるものを取り入れた小説を書いた作品がノミネートされたらしい。それを確信するべく、スマホのない私が唯一インターネットを使える手段であり、長年私の執筆活動を共にしてくれたパソコンの前に座り、その小説のタイトルを打ち込み、真っ先に通販サイトのレビューを見た。レビュー欄をスクロールしても星4や星5ばかりで、どうせ読者は最近読み始めた文学弱者なのだろうと蔑んだ。しかし、名もなき小説家であるからにはぜひ読んでから圧倒的な非難をしてやろうと意気込み、ダウンロード版を買って、はっとした。
私は一体何をしたのだろうと。冷静に考えて、私は無職で社会的弱者で、戸籍にしか生きていない死者であるにも関わらず何様なのだと、そう誰かに言われた気がした。
「…。」
思考が無になった。朝の清々しい気分も、今まで拭えなかった本たちも、その悲しみも私が造り上げた虚像なのではないかと。それはきっと昔からわかっていて、ただ自己責任という重りを付けられるほどの覚悟がなくて、ただ逃げていただけなのではないかと。
涙も流れない。ただただあったのは私という20幾年小説に費やした無駄な男が、台所に立っていただけである。
溜息をつき、コーヒーを注ぐ。とりあえずさっきダウンロードした本を読もうと、椅子に座った。
天才を見た。彼女はまさしく天才であった、自他ともに認める。彼女は何も欲しず、欲張らず、目的や目標もなく天才としていた。二流とは言え小説家をしている私ではあるが、あまりの凄さに呆気をとられてしまった。どうその凄さを表現しようにも、とてもじゃないが私では文で魅せることは出来ない。天才を肌で感じ、耳で見、目で驚く。私なんて言うのは彼女の本の前では喜怒哀楽が激しく廻り回る壊れた歯車がいいところだ。
人と比べたところでどうしようもない、あなたは特別な一人で比べられない。幼い日にそう母に言われたことを思い出した。
先ほどの悪い感情というのは、誰にあてたわけでもない、自分に対するものであったことに気づく。嫉妬でもない、畏怖でもない、渇望でもない。
焦り。
焦燥感と絶望感が混ざり合い、しかしそのどうしようもない感情のはけ口はなく、ただただ怖かった。
そしてそれは決して私は天才ではないと決定づけた。
いつか私も、私もきっとできるはずだと、そう思い込んでいた一本の柱が崩れた。所詮、私は天才に憧れた凡人なのだ。
どうしようもない葛藤と、ぶつけようのない怒りが胸の中暴れまわり、私はひたすら文を綴る。それしか私にはない。どうかそれだけは私から奪わないでほしい。怖い。私から私を奪わないでくれ。
縋るように、何も書くことのない原稿用紙には文字にならない文字が散りばめられていく。
「お父さん、この本面白かった」
「なんだ見つけちゃったのか。お前が二十歳になったら渡そうと思ってたんだがな」
「そうなの?」
「そうさ、それはお父さんの親友が書いた本でな、もう随分前に亡くなったんだが今でも彼より面白い本を書く人はいないと、お父さんは思う」
「ふーん。でもこの本さ、なんか中途半端な終わり方してるね、続きとかないの?」
「ふふ、その続きはいつか分かるさ。なんならお前が書いてもいいんだぞ」
「よくわかんないけど、私書いてみるね」
男の娘は、部屋に戻るや否や机に座り自由帳に文を綴りだした。まだ中学生にも満たない幼い子が一生懸命に文を綴る様を見守る父は、ただただ涙を流し、かつて遂げられなかった自分の思いを娘に託すのだった。
芽
初めてこのサイトで投稿するので、変なところがあれば教えてくださると助かります。