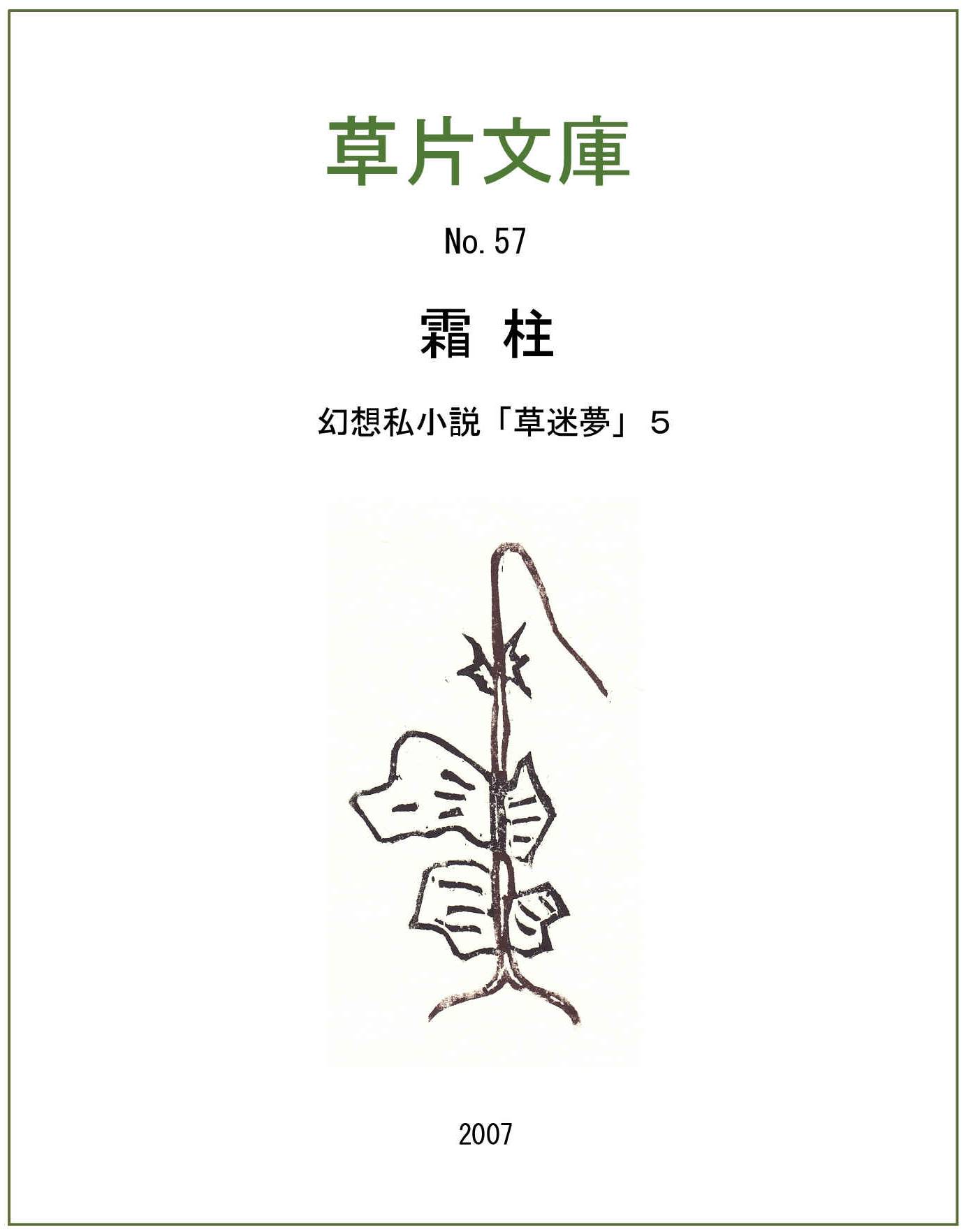
霜柱-幻想私小説5
不思議な夢の物語
蛇苺の精となった吾はなにも気がつかず、どこまでも漂っていったようである。
ふと吾にかえると、窓から朝日が差し込んでいる。どこだろう。
ガラス窓の外を見ると、木々の枝に雪が積もっている。どうも雪国の林の中の一軒家にいるようだ。
雪の積もった木の枝を茶色の動物がちょろちょろと動き回っている。栗鼠のようだ。だが、よく顔を見ると、人に似ている。耳と口は栗鼠のままだが、黒い色をした鼻の形は人のものだ。目は面フクロウのように前面にあり、睫毛が長い。
人面栗鼠がこっちを見た。
「おいでよ」
窓を開けると冷たい空気がなだれこんできた。一番近い木の枝の上を見ると、人面栗鼠が二本足で立って万歳をしている。
吾が見ると、人面栗鼠が枝の雪を丸めてなげつけた。そいつが吾のおでこにぶつかった。
他の枝にいる人面栗鼠たちは二本足で立ちあがり、手をたたいて喜んだ。
「いてえな」
吾は窓を閉め、おでこをさすった。小さな雪の塊がこんなに痛いとは思わなかった。 ひどいやつらだ。
椅子に座って、おでこをなでていると、がさっと音がした。
沢山の人面栗鼠が窓枠に取り付いて、部屋の中を覗き込んでいる。
「きょきょきょ」
人面栗鼠たちは尾っぽを立てて笑った。
おでこがまだ痛む。
吾はベージュのトックリセーターを着て、別珍のズボンをはいている。どうも二十代のはじめの頃らしい。ここはどこだかわからないが、長野か北海道のようだ。家の中はガスストーブがつけられていて、程よく温まっている。
人面栗鼠たちを無視して、湯につかりにいった。温泉が引かれている。温泉つきの家には暮らしてみたいと思っていたが、夢はこんなこともかなえてくれるのである。
このような家には住んだことがないが、なぜだか中のことはよくわかっている。
風呂場は三畳ほどで、個人の家としてはとても広い。すべて白いタイル張りで、大きくはないがやはりタイル張りの楕円形の湯殿がしつらえてあった。かけ流しである。
タイルの壁から突き出した白い蛇口から、少し茶色がかった透明な湯が湯殿に静かに流れ落ちている。天井は高く、木の枠取りの真ん中から、白くて丸い電気が吊るされている。薄緑色に塗られた窓の木枠は、外側に雪がこびりついて、そこから見える青い空が花模様に切り取られている。
天然の石で作られた風呂をイメージしていたのでちょっと残念だが、明治大正の和洋折衷の家にしつらえられた、モダーンな雰囲気をもつ、好ましい造りではある。
窓から入る雪の反射した光がきれいで、電灯をつける必要もなく、湯に浸かった。
あまりの静けさに、ぴちゃっぴちゃと自分の立てる湯の音がやけに高く聞こえる。
すると、いきなり窓が塞がれ暗くなった。
何が起きたのかと窓をみると、窓いっぱいに大きな目が張り付いている。と思ったのは瞬間であった。例の人面栗鼠たちが窓の木枠に何匹も腰掛けているのが見えた。後ろを向いているので立てられた尾っぽが並んでいてかわいらしい。
彼らはしばらく腰掛けていると、きょきょきょと鳴きながら離れていった。
また、明るくなった。
ゆっくり湯につかっていると眠くなる。
ふっと吾に返ると窓から見える空が雲で覆われ、雪が降っている。さっきまで青空だったのに。
風呂から上がると、喉の渇きを覚えた。キッチンにはやけに大きなアメリカ製の冷蔵庫がある。最近日本の冷蔵庫も大きくなった。にもかかわらず、むしろ電気は食わず、収納率も良くなった。ここはなぜ米国製だろうと思いながら開けた。
だだっ広い中には何もない。しかし、幸いにもドア側の物入れにサイダーが一本あった。栗鼠温泉サイダーとある。
サイダーで喉を潤すと、居間に行き、テレビをつけた。テレビでは天気予報をやっている。暖冬で雪が降ってもすぐ溶けるというアナウンスであった。
確かに外を見るともう青空に戻っている。それでも冬である。雪の積もった木々が、重そうに枝をたらしている。
庭に出てみるか。
玄関に回り下駄を履いて外に出た。庭にはかなりの雪が積もっているが、土が顔を出しているところもある。寒い地方の住宅のありようで、塀はない。というより、周りには家がなく、林や山が見えるだけである。
生えている植物たちの名前はわからないが、茶色く枯れた茎の根元に氷の柱をくっつけた植物がたくさん生えている。氷の柱が日に輝いてとてもきれいだ。
「きょきょ、霜柱だ」
ふっと振り返ると、人面栗鼠がちょっと離れたところからこちらを見ている。
霜柱は紫蘇科の植物で、白い小さな花が列を成して咲くのだが、なかなかきれいである。確かに色は違うが紫蘇と花のつき方が良く似ている。花は秋に咲くのだが、冬になり、氷が張るような寒さの日には、枯れた茎の吸い上げた水が、茎の裂け目から噴出し、凍り付いて奇麗な氷の芸術品を作る。それで霜柱と呼ばれるようだ。
なるほどと思いながら霜柱をみていると、人面栗鼠がやってきて霜柱を氷ごと引き抜くとなめ始めた。
「ここの霜柱は甘いんだ」
まねをして霜柱をとり、氷の部分をなめてみた。かなり甘い。ただ甘いだけではなく、なめた後、周りの景色がしんなりと、やわらかく見えるようになる。景色が甘くなるという言い方が許されるならその通りである。なにやらの成分がはいっているのだろうか。
「ここの霜柱だけなんだ」
林の中から、人面栗鼠がたくさん集まってきた。
「食事の時間なんだ」
それぞれ一本の霜柱引っこ抜くとなめはじめた。旨そうになめている。一本なめると、また林の中に走っていく。彼らは木の上に上り、雪の積もった枝の中に消えていった。
部屋に戻ると、やけにおでこがひりひりしている。朝、人面栗鼠に雪をぶつけられたところだ。鏡を見ると真ん中が赤くなっている。
鏡に窓の枠から覗いている人面栗鼠が映っている。振り返ると人面栗鼠が何匹も窓から吾を見て笑っていた。
しょうの無いやつらだ。窓に向かって歩いていくと、人面栗鼠がワーッと言いながら窓枠から落ち、雪の中をころがっていった。いたずら坊主たちめ。
居間に行き、テレビをつけた。また天気予報をやっている。日本人ほど天気予報の好きな国民はいないそうである。
雪が再び舞いだした。
何もすることがなく、眠くなってきた。ソファーで横になるとすぐ寝てしまった。
夢の中の夢はただ雪の降る山並みをどこかの山の頂上から眺めているだけのものである。ゆっくりと落ちてくる雪がすでに積もり積もった木々に覆いかぶさっていく。
遠くで啄木鳥(きつつき)が木をたたいているようだ。山の下のほうから聞こえてくる。いや、冬に啄木鳥が木をたたくことはない。音はだんだんと近くなってくる。
ふっと気がつくと夜になっている。ずいぶん寝てしまったようだ。とんとんとんと夢の続きの音がする。玄関だ。
電気をつけなければ、あわてて立ち上がり、スイッチを探した。居間の明かりをつけ、玄関にいそいだ。照明のスイッチを押すと同時に、音もなく玄関が開いた。
鍵はかけたはずなのだが。
外は暗いが玄関灯に照らされて雪の世界が見渡せる。雪は降っていない。しかも、寒さが感じられず、玄関の前の雪はむしろ溶けて水溜りになっているようだ。
玄関灯の明かりの中に女が現れた。
白い布に包まれた大きな荷物を持っている。
「はい」と遅まきながら返事をした。からだ中に鳥肌がたっている。気分的に怖い。
女性は白いスラックスに白いタートルネックのセーターを着た小柄な人だった。白い丸い顔の半分が長い髪の毛で隠れている。女性は大きな片目を私に向け微笑んだ。
「夜分すみません」
白いコートを着た女は、玄関に入ってくると、大きな包みを前に突き出した。
「お願いがあるのですの」
女性は持っているものの布をとった。真っ白な大きな卵であった。西瓜くらいある。
「冷蔵庫にいれておいてくださいませんこと」
女性が少し首をかしげて吾を見上げた。
どうしてと聞く前に女性が言うには、冷やしておかなければいけないけれども、それができないということである。冷蔵庫でも壊れたのかと思い、吾は頷いて、その卵を受け取とった。手にずっしりと重い。
「明日取りに来きます、くれぐれもよろしく」
女性はそう言うと去っていった。
そういえば名前も住んでいる所も言っていかなかった。
玄関が開いているままであった。そこから人面栗鼠がひょこっと顔を出した。
「卵をたのまれたんだな」
玄関の中に入ってきた。
吾はうなずいて玄関の戸を閉めた。
人面栗鼠は吾の持っている卵の上に飛び乗った。
なれなれしいやつだ。
振り落とすと、卵を冷蔵庫に入れた。ずいぶん大きい卵だ。ダチョウの卵だってこんなに大きくない。
人面栗鼠は床から、冷蔵庫を見上げている。そういえば玄関を閉めてしまったから、帰れないのだ。
「どうだ、明日山にいかんか」
人面栗鼠は言葉の使い方を知らないようだ、目上の人にそんな言葉遣いはないだろうと思っていると、人面栗鼠が笑った。
「若造、俺は百八だぞ、お前は八十八だろうが」
この人面栗鼠は二十歳も年上なんだ。
「今の若いのは口のきき方も知らん」
同じ言葉を返されてしまった。反省をしなければと思い、
「はい、行きます」
と返事をしてしまった。
「よし、面白いところに連れて行ってやる」
人面栗鼠が玄関に向かったので、戸を開けて外まで見送りに出た。
「では明日な」
人面栗鼠は雪が溶けてできた水溜りをひょいひょい飛び越えて、林のほうに走っていった。
何か食べるものを探さなければと思い冷蔵庫を覗くと、大きな卵があるだけで、何もない。これは困った。野菜かごを覗くと、バナナと林檎があった。今日の夕食はこれだ。果物が夕食とはからだに良いが、チンパンジーになった気分だね。ビールとチーズでもあればいいのに。
空のはずの冷蔵庫を覗くのは意味がない、と思いながら開けるのは、無駄を知りつつやる人間のあほさ加減なんだろう。
また、大きな卵が目に入った。何の卵なんだ。おや、冷蔵庫のドアのポケットに、ロックフォールチーズがあるじゃないか。なんだ、多摩ビールがある。夢は何でもかなうのか。おお、クラッカーまである。
夕食はこれで決まった。居間のテーブルにそれらを運ぶと、テレビをつけた。Xファイルをやっている。アメリカのSFテレビドラマだ。アメリカのSF映画は大人を相手につくるからいいが、日本のSF映画ときたら、SF自ら大人用ではないと決めてかかっているようなところがあって、とても稚拙だ。
テレビを見ながら、ビールを飲み、チーズを食べ、至福のときをすごし、さて、あまり眠くないなと思って、テーブルの脇を見ると数冊の本がおいてある。
梨木果歩氏の家守綺譚、渋澤龍彦氏の唐草物語、藤枝静男氏の田神有楽、久世光彦氏の1934年冬―乱歩。単行本でそれもみな初版帯付、梨木氏以外の本にはサインがある。なんだ、吾の本箱にあるやつじゃないか。
まあいいや、家守綺譚をもう一度読み直そう。
本を持ってベッドに入った。
そして、いつか眠りについていた。
朝日が差してきた。今日も天気がいい。天気予報が言っていた通り、かなりの温かさになるようだ。それも何日か続くようだ。
玄関を開けると、庭から立ちの上る湯気が顔に流れてきた。庭に出てみると、土が暖められて、霜柱にも氷がない。これでは人面栗鼠も食べ物がなくて困るだろう。
玄関に戻ると、牛乳二本とコッペパン、それにバターがおいてある。卵をよろしくお願いします。よろしかったらどうぞと、達筆な字で書かれた紙が添えてあった。
昨日の女性のようだ。どこに住んでいる人なのか、ありがたいことである。飲むものも食べるものも冷蔵庫にはない。だが、卵は今日とりに来ると言っていたはずだが。
ミルクを温めて、カップにたっぷりそそぎ、テーブルについた。ミルクから湯気が立ち上っている。暖かいミルクは朝一番、目がさっぱりする。一口飲んだ。
口の中に入ったミルクが舌の上で跳ねた。暖めたのになぜか冷たい。
冷たいミルクが喉を通って、胃に落ちていく。ミルクはとろっとしていて、冷たいけれどもほっとする味である。湯気が立っているのにどうして冷たいのだろうか。冷たいのにお腹は飲むたびに暖まっていく。おいしい。おや、牛乳アレルギーだったのにどうしたことだ。パンはできたてのように暖かく、バターをつけて食べたとき、匂いと頬で感じる味がお互いを高めあって、今までに経験したことのない朝食となった。
この満足感は夢が覚めても残っているに違いない。
テレビをつけた。また天気予報をやっている。ずいぶん暖かくなる。これだとなだれが起こる危険がある。
玄関から声が聞こえる。
「行きましょ」
人面栗鼠が迎えに来たようだ。やけに丁寧な話しぶりだ。学校に行くときに友達を誘う小学生のような言い方に、これもまたほっとした。
人面栗鼠は自分から玄関を開けて入ってきた。
「朝食べた?」
肯くと、人面栗鼠はにこやかになった。
[おいしかったでしょ」
また肯くと、満足そうになった。
外に出ると、人面栗鼠たちがうじゃうじゃと飛び跳ねていた。
「たくさんいるんだなあ」
独り言を言うと、
「人間ほどじゃないさ、世界でこれだけだ」
そう言い返された。確かにそういえばそうだ。
「どこにいくの」
「ついといで」
人面栗鼠は林の中に入っていく。
吾もついていく。
「ほら」
人面栗鼠が蕗の薹をとり、ニコニコと抱えてもってきた。
「うまいんだ」
人面栗鼠たちは蕗の薹を探し始めた。
みんなそれぞれ一つずつ見つけると、両手に抱えていっせいに齧りだした。食べるのは霜柱だけでは無いようである。
「今年は蕗の薹がやけに早く顔を出したな」
人面栗鼠が齧りながら私に向かってそう言った。
食べ終わると、また歩き出した。
「どこにいくの」
もう一度聞いた。
「地獄谷だ」
温泉が沸くような所には必ずといっていいほど地獄と名のつく場所がある。そのようなところは蒸気が噴出し、硫黄の匂いが満ちていて、岩は噴出した硫黄で黄色っぽく染まっている。だがそこに何しにいくのだろう。
「遠いのかい」
「ほんの八つ目の山だよ」
かなりあるじゃないか。
林の道を抜けると大きな山の麓に出た。
「最初の山だよ」
人面栗鼠たちは一列になって登りだした。しんがりをいく人面栗鼠が吾の担当らしい。例の百八歳の人面栗鼠である。
「ずいぶん長生きなのですね」
「俺が一番若いんだ、先頭を行くお頭は日本ができたときに生まれたんだ」
「日本が生まれたときというのは千四百年ほど前でしたね」
「そりゃ日本書紀だな、日本が生まれたのは46億年前に地球ができて、その後何億年かたち、海と陸ができた時、日本の卵が産み落とされのだ」
では何歳なのだろうか、人面栗鼠は答えなかったが、その理論でいくと何十億歳となってしまう。
人面栗鼠たちは歩きながら植物の芽をちぎって食べていた。意外と食べ物が多い。
杉の木がまばらに生えている山を登りきると、尾根づたいに次の山が見えてきた。木はさらにまばらになり、草原が多くなってきた。雪はちらほら見えるのみで、ほとんどない。
吾はおでこが痛くなってきた。人面栗鼠に雪をぶつけられたところだ。おでこをさすった。少し盛り上がってきた。
百八歳の人面栗鼠は吾をみた。
「きょきょきょ」
その声で、みな歩くのをやめ、戻ってくると、吾の周りに集まった。
なんだろうと思っていると、ぷちっという音がして、目の上に白っぽいものが見えた。さわってみると、硬いものがおでこから突き出ている。
「きょきょきょ」
人面栗鼠たちが手をたたいた。その音が山に響き、木々が一瞬ゆれたようだ。
吾のおでこに角が生えてきたのだ。
先頭を歩いていた人面栗鼠のお頭が始めて吾の前に来て、お辞儀をして、急に飛び上がった。宙に浮かぶと、どんどんと上昇し、見下げて尾をふった。それを合図にみんな、宙に浮かぶと尾っぽを回し、空に向かって上昇していく。変な生きものだ。
おでこの角がむずがゆくなってきた。もそもそと角が動く。
宙に舞った人面栗鼠を見上げていると、おでこの角が回転し始め、その勢いで吾も宙に浮かんだ。人面栗鼠は山の頂に向かって上昇していく。吾もおいかけた。眼下には雪がちらほら残った林が見える。
八つ目の山まで飛んだ。たいした時間はかからなかった。地獄谷のある山である。 石でできているのは確かだが、空の上から見ると全て黒く、想像していたようなごつごつした石ではなく丸みを帯びた、ヘンリー・ムーアの彫刻のような石である。石の隙間から蒸気が立ち上っているのは想像通りであるが、熱くもなく、硫黄の匂いもしない。音もしていない。
人面栗鼠たちは大きな卵のような形をした黒石の脇に降り立った。吾も引きずられて降りた。
黒石の真ん中に大きな穴があいており、人面栗鼠たちはその中に入っていく。
穴の中は白光が満ちており、奥に進むにつれ、明かりがだんだん弱くなっていく。
人面栗鼠たちは一列で奥に進み、前をいく人面栗鼠の姿が見えなくなると、吾はいきなり水の中に落ちた。水の中を人面栗鼠が歩いている。可愛い尾っぽがピコピコと動くのを見ながらついていくと階段があり、自然と水から上がることになった。あたりは靄っていて、周りの様子が判然としない。
人面栗鼠たちがかたまった。そばに行くと、人面栗鼠は白い花の咲いた霜柱をしゃぶっていた。花の時期と氷の出来る時期は違うはずだが。
百八歳の人面栗鼠が霜柱をもってきた。
「ここが地獄谷さ、これは地獄谷の霜柱さ」
花が咲いているが根元には氷が張り付いている。
「食べなさい」
吾は言われるままに、霜柱の根元を口に入れた。
霜柱の氷が口の中で溶け、甘みが舌を刺激した。そのとたん、花火をあげたように周りが明るくなった。見渡すと黒い石の床があまりにも広く広がり、周りにそそり立つ黒い石の柱が空高くそびえている。これが地獄谷の全貌である。床のところどころに花の咲く霜柱が生え、その根もとにはきらきら光る氷が光っている。
からだが宙に浮きはじめた。人面栗鼠も上向きになったまま空中を漂いはじめた。
「試練じゃ」
百八歳の人面栗鼠が私にささやいた。
この広い広い洞窟の、黒い石の柱の間を行ったりきたり、ゆらりゆらりと彷徨っている。夢の中でまた夢を見て、光にあふれた地獄谷に浮かんでいた。人面栗鼠たちは目をパッチリと開けて、ぐっと歯を食いしばっている。
からだの重さも、心の重さも、どのような重さもない状態がどのように頼りなく心細いかわからなかった。初めは心地よさを感じていたが、だんだんと寂しく、怖く、恐ろしくなってくる。重石が何もなくなった状態であった。きっとからだがなくなり、魂だけになるとこのように心細くなるのだろう。何かによりどころを求めたくなる。しかしまったくつかまるところも何もない。落ちるのか上がるのか誰もわからない状態である。身体は魂の支えなのだ。
それだから地獄谷なのだろう。
「きょきょ、そうだよ、成長したな」
人面栗鼠たちは時々ここに来て、霜柱の氷をなめ、地獄谷の試練を受けることで、肉体のありがたさを感じているのだそうだ。
吾のおでこの角は白く尖って、立派になってきた。
時間がどのくらい過ぎたのかわからないが、霜柱の効果が消えてきたようで、気がつくと、薄暗い黒い岩の上で人面栗鼠とともにぼーっとしていた。
人面栗鼠のお頭が「帰ろう」と言って水の中に入った。みんなも入っていく。吾も後について水に入った。
水を上がり、入口の光が見えてきた。
外に出ると、吾が暮らしている家の庭だった。夕日が山間に隠れようとしている。
人面栗鼠たちが手を振って、林のほうに歩いて行った。
なんとなく別れが心細かった。不思議な経験をしたものだ。玄関に再びパンとミルクが置いてある。家に入るとどっと疲れがでた。風呂に入り、パンを食べ暖めたミルクを飲んだ。ミルクの味は朝飲んだときと同じで、飲んだ瞬間、元気が出た。
テレビをつけると、また天気予報をやっていた。天気が急に変わったようである。今夜から寒くなり大雪の警報がでていた。
眠くなった。
夜中のことである。また、とんとんと音が聞こえる。もしやと思い、ベッドから出て、玄関の明かりを点けた。玄関がするすると開いて、昨夜の女性が白い布を片手に顔を出した。外は吹雪いている。雪が玄関の前に厚く積もっている。
「どうもありがとうございました」
「いえ、ミルクとパンをありがとうございました。ミルクはとてもおいしかった」
女性は一瞬顔を赤くした。
吾は冷蔵庫から卵を取り出し、玄関にもってでた。女性は卵を受け取ると、白い布にくるんだ。
「一緒に来ていただけませんの」
どこへ、と聞き返す前に、はい、と返事をしていた。
下駄をはいた。パジャマのままだが。
女性は玄関をでると、吹雪く雪の中を歩き始めた。女性が歩くと、斜めに降ってくる雪が女性の周りをよけ、積もった雪も脇に飛び散り、女性の行く道が遠くまで作られていく。自分も真っ暗な中を、長い黒髪の揺れる女性の後姿を見ながら、歩いていった。
林の中に入ると、薄明かりの中からたくさんの目が我々を見ている。
人面栗鼠だ。
「きょきょ」
懐かしい声が聞こえる。
積もった雪で重さに耐えかねた木々の枝はしなだれ、女性が通ることで巻き起こる風で揺れた。
林の中の一角にある広場に出た。
女性は広場の切り株の前に立った。風が渦巻き始めた。竜巻になり、雪が巻き込まれ、雪の柱となって空に向かって立ち昇った。ぽっかりと開いた大きな竜巻の眼の中に我々は入った。
女性は切り株の上に布から取り出した卵をおいた。女性がこちらを振り向いた。黒髪がからんだ白い顔には赤い目が光っている。冷たい顔だがきれいだ。
女性が手招きをした。凍りつくほど寒い。吾が卵の前に立つと、おでこの角が回りだした。吾は卵に向かって頭を突き出していた。角は卵に突き刺さり、吾の脳が流れでている。脳はどんどん卵の中に吸い取られていく。
卵が割れると、中から真っ白な子供が這い出て来た。子供は女性ににじり寄っていく。女性は着ているものを脱ぐと杉の木よりも大きくなり、真っ白な肌で子供を受け止め、乳房を与えた。ほとばしる乳は吾にも降り注いた。口に入ったその乳は、朝飲んだミルクだ。
人面栗鼠がささやいた。雪女だ、ピュミャルゴだ、日本をつくった雪女なんだ、何千年に一度の子どもの誕生なんだ。
人面栗鼠がいっせいにいなくなった。
雪女は子供を抱きかかえ、赤い目で吾を見下ろすと微笑んだ。あけた口から牙が覗いている。脳を吸い取られ空っぽになった吾は雪女に咥えられ、噛み砕かれた。
雪女が再び微笑んだ。
そこには大きな霜柱が生え、吾は霜柱の精となった。
霜柱の根元の氷に閉じ込められている。
吹雪がやみ、暖かくなったとき、氷が溶け、その蒸気の中に、閉じ込められた霜柱の精になった吾は、宙に舞いでることになるのだろう。
雪女は赤子とともにいずこかへきえていった。
霜柱-幻想私小説5


