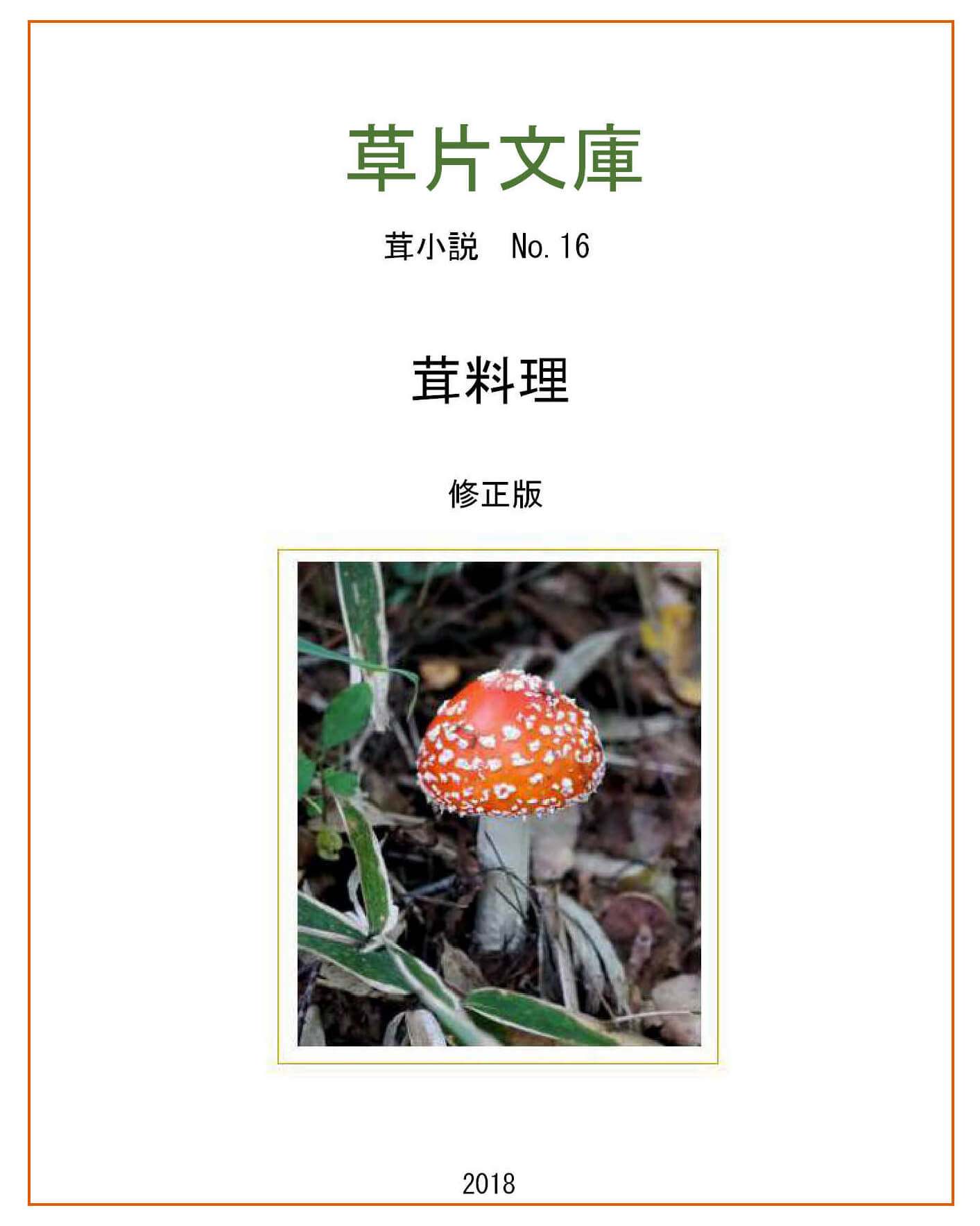
茸料理
茸児童小説です。
暑い日が続いたある日のこと。
自転車の前に何かが飛んできて、車輪がその上に乗り上げた。
買い物帰りの母親が、あわてて自転車を止めた。後ろを見ると、真っ赤な茸が二つに割れている。茸を轢いてしまった。でもどうして茸が飛んできたの。
母親は頭と胴体になった茸を自転車の籠に入れて家に帰った。
買った夕飯の材料と一緒に、二つになった茸も台所に運ばれていった。
母親はもうすぐ帰ってくる小学三年生の女の子のために、お三時のプリンを作りはじめた。
今日の夕飯はピーマンと豚肉を炒めたものだから簡単だ。
二つになった赤い茸は台所の調理場の脇に放置されている。
子供が帰ってきた。
「おかえり」
母親が声をかけると、女の子が台所に入ってきて茸をみつけた。
「あ、真っ赤な茸、今日食べるの」
母親は赤い茸を思い出した。
「違うの、自転車で轢いたの」
「どこで」
「マーケットを出て少しのところ」
「へー、誰か買って落としたのかな」
「野菜売場にはこんな茸売ってなかったよ」
「じゃーどうしてあるの」
「さー、飛んできたのよ」
「名前なんていうのかな」
「わからないな、でも毒茸よ」
「そうだね、まっ赤だもんね」
夜、その家の主人が帰ってきて、頭と柄が離れた赤い茸をみつけた。
「どうしたんだい」
「自転車で轢いちゃったの」
「この茸は山に生えているやつじゃないかなー」
「この町に山なんてないじゃないの」
「そうだな」
話はそれで終わってしまった。
その日の真夜中、台所でゴソゴソと音がするのに気がついた女の子が、ベッドから抜け出ると、台所の戸を少し開けて中を覗いた。
テーブルに置かれたままになっていた赤い茸の周りに、真っ白な茸が集まっている。
そのうち白い茸たちは頭を垂れて、滴を垂らし始めた。
茸たちが泣いている。
一つの白い茸が少し前にでた。
「紅(べに)天狗(てんぐ)茸(たけ)の姫様、おいたわしや、なにも車に飛び込んで自殺しなくてもよいものを」
他の一つが言った。
「我々白鶴(しろつる)茸(たけ)の若様が、熱で萎びてしまわれたのを悲観して、自殺などをなさるとは、おいたわしや」
女の子は、戸を開けると、テーブルの前に立った。
白い茸たちはあわてて逃げようとしたが、女の子がみんな捕まえて、笊(ざる)に放り込んだ。
女の子は、電気釜の蓋を開けると、残っていたご飯から、ご飯粒をいくつか摘まみだし、赤い茸の柄の付け根があったところに張り付けると、胴体を繋ぎ合わせた。
すると、赤い茸はぴょこんと飛び上がって、生き返った。
笊に入れられた白鶴茸たちは、わーっと歓声を上げた。
女の子は、笊の中に向かって、
「萎びた茸をつれてらっしゃい」
と言った。それを聞いた白鶴茸は笊からやっとこと這い出ると、テーブルの上立ち上がった。
「姫様よかったですな、この人間のお嬢ちゃんに感謝しましょう」
「あい、ありがとうございます」
赤い茸が女の子に向かってお辞儀をした。
白鶴茸たちは
「今、若君を連れてきますで、よろしくお願いします」
と、テーブルから飛び降りると、一列になって少し開いていた窓から外にでちまった。
女の子は赤い茸に
「あんた、食べられるの」
と聞いたのだが、赤い茸は
「毒があります」
と申し訳なさそうに答えた。
「みんなどこから来たの」
「微笑み公園から」
微笑み公園とは町が作った公園で、小さな池と、ちょっとした林がある。
「どうして死にたかったの」
「彼が萎びてしまいました、私も死のうと思って」
「ばっかみたい、ロミオとジュリエットじゃあるまいし、茸の恋愛ってそんなものなの、もっとドライかと思った」
赤い茸は小学生の女の子が、ませた言い方をしたので、どう答えたらいいのか分からなくて、もっと赤くなった。
そこに、萎びた白鶴茸を皆でかついで、皆が戻って来た。
テーブルの上に萎びた茸をのせると、生き返った赤い茸は涙を流して言った。
「これがあたしの許嫁です、治してくださいますか」
女の子は、システムキッチンの戸棚を開けると、ボウルを取り出し、水を入れ、塩を一つまみ入れた。
そこへ、萎びた茸を放り込んだ。
萎びた白鶴茸はふーっと、あっという間にふっくらとした若い茸になった。
赤い茸は
「若様」と駆け寄ると、自分も塩水の中に入った。
やがて、白い茸と赤い茸は、ボウルの中で寄り添って、眠ってしまった。
女の子も、もう眠くなり、自分の部屋に戻るとベッドの中に入ったので、それ以降のことは知らなかった。
明くる朝、母親が、
「赤い茸がなくなってるわ」
と気がついた。
女の子が答えた。
「帰っていったわ」
「そう、捨てたのね」
母親はそう答えると、朝食の用意を始めた。
「今日は夜何をたべたい」
「私ハンバーグ」
女の子がそう言ったところに、父親が起きてきた。
「今日は飯いらんよ、同僚と飲んでくる」
「そう、それじゃ、今日はハンバーグね」
母親は出来上がった目玉焼きと、味噌汁を父親の前に置いた。
女の子の前には、目玉焼きとトースト、それに梨を置いた。
こうして、女の子と父親はそれぞれ出かけていった。
夕方、母親は自転車で買い物に行った。ハンバーグの材料を買って家に戻ると、女の子はもう学校から帰っていた。
「早いのね」
「うん、誰も遊ぶ子いなかったから、まっすぐ帰ってきた」
「どうして」
「みんな塾なんだって」
「塾に行きたいの」
「いや、行きたくない」
「そう」
母親はハンバーグを作り始めた。
その夜、女の子が自分の部屋で寝ていると、何かが胸の上に乗っかってきた。
女の子が眼を開けると、黒い茸が上にいた。
「あ、こりゃ、失礼を致しました、白鶴茸に聞きましたのじゃ、病を治すお方だとうかがいまして、参りました」
「どうしたの」
女の子は黒い茸を掴むとベッドの脇において、自分も起き上がった。
「はい、わが一族の長老様が萎びてしまわれました、治していただけないでしょうか」
「どこから来たの」
「はい、隣の町のお山にございます」
女の子は、きっと、足高山だろうと思った。小学校でいつも遠足に行くところだ。ずいぶん遠いところから来たもんだ。
「そう、連れていらっしゃい」
すぐに、たくさんの黒い茸にかつがれた、萎びた赤い茸がやってきた。
「我々の女王様でございます」
女の子は萎びた赤い茸をもって、キッチンに行くと、ボウルに入れて、その上からオリーブ油をかけた。黒い茸たちもついてきて、ボウルの周りに集まった。
萎びた赤い茸は、ぷつぷつと小さな空気の泡をオリーブ油の中に放ちながら、だんだんと膨らんできた。とうとう、パンパンに張った綺麗な赤い茸がボウルの上に立ち上がった。
黒い茸たちはひれ伏して
「女王様、生き返られましたな、この方が治してくれました」
赤い茸は、
「ありがとう、このお礼は必ずします」
と言って、黒い茸たちと帰っていった。
全く真夜中なのに人騒がせな、女の子はちょっと怒っていたが、すぐ眠くなって、自分の部屋に戻ってベッドに入ってしまった。
あくる朝、キッチンで母親が首をかしげていた。
「オリーブオイルを何に使ったんでしょう、私も忘れっぽくなったわね」
そういいながら、マッシュルームを冷蔵庫から取り出すと、スライスにして、塩を振り、オリーブオイルに浸けた。
女の子と父親の前には、マッシュルームサラダが出された。
その夜も、女の子のところに茸たちが現れた。たくさんの頭と胴を切り離された網笠茸がケーキの箱にいれられて、仲間たちに運ばれて来た。
「踏まれて、たくさんの同胞がばらばらにされました。直してくださると聞き、捨てられていたケーキの箱にいれて連れてきました」
網笠茸たちは頭を下げた。
「お前たちは食べられるの」
女の子が聞いた。
「それは、もう美味しい茸でございます」
「そう、それじゃおいで」
女の子は網笠茸をキッチンに連れて行き、大き目のボウルに水をいれ、ちょっと食塩水を入れた。
「ここに入れなさい」
女の子に言われるとおり、ばらばらになった網笠茸を、運んで入れた。すると、見る見るうちに頭と胴がくっつきみずみずしくなった。
「おおすばらしい」
仲間の網笠茸が賞賛のことばを贈ったところ、女の子は言った。
「お前たちもお入り」
仲間の網笠茸も慶んで、その中に入った。
すると、女の子はボウルの上に鍋の蓋をのせてしまった。
そこで眠くなった女の子は自分の部屋に戻って、ベッドに入ってしまった。
あくる朝、母親がキッチンにいくと、「何でここにボウルがでているの」と言いながらボウルの上の鍋の蓋をとった。
「網笠茸があるわ、どうしたのだっけ、忘れっぽくなっているわ」
そういって、網笠茸をボウルから取り出して、もう一度水で洗うと、スライスにした。玉子を溶いてかき混ぜると、網笠茸のスライスを入れて、スクランブルドエッグをつくった。
女の子と父親の前に茸入りのスクランブルドエッグとパン、またはご飯をおいた。
「この茸入り卵、とても旨いな」
父親が賞賛した。
「そりゃあ、網笠茸が自分で言ってたもの、美味しい茸だって」
女の子もそういって、口に入れた。
「本当、おいしい、また来ないかな」
母親と父親は顔を見合わせて、首をかしげたのである。
茸料理


