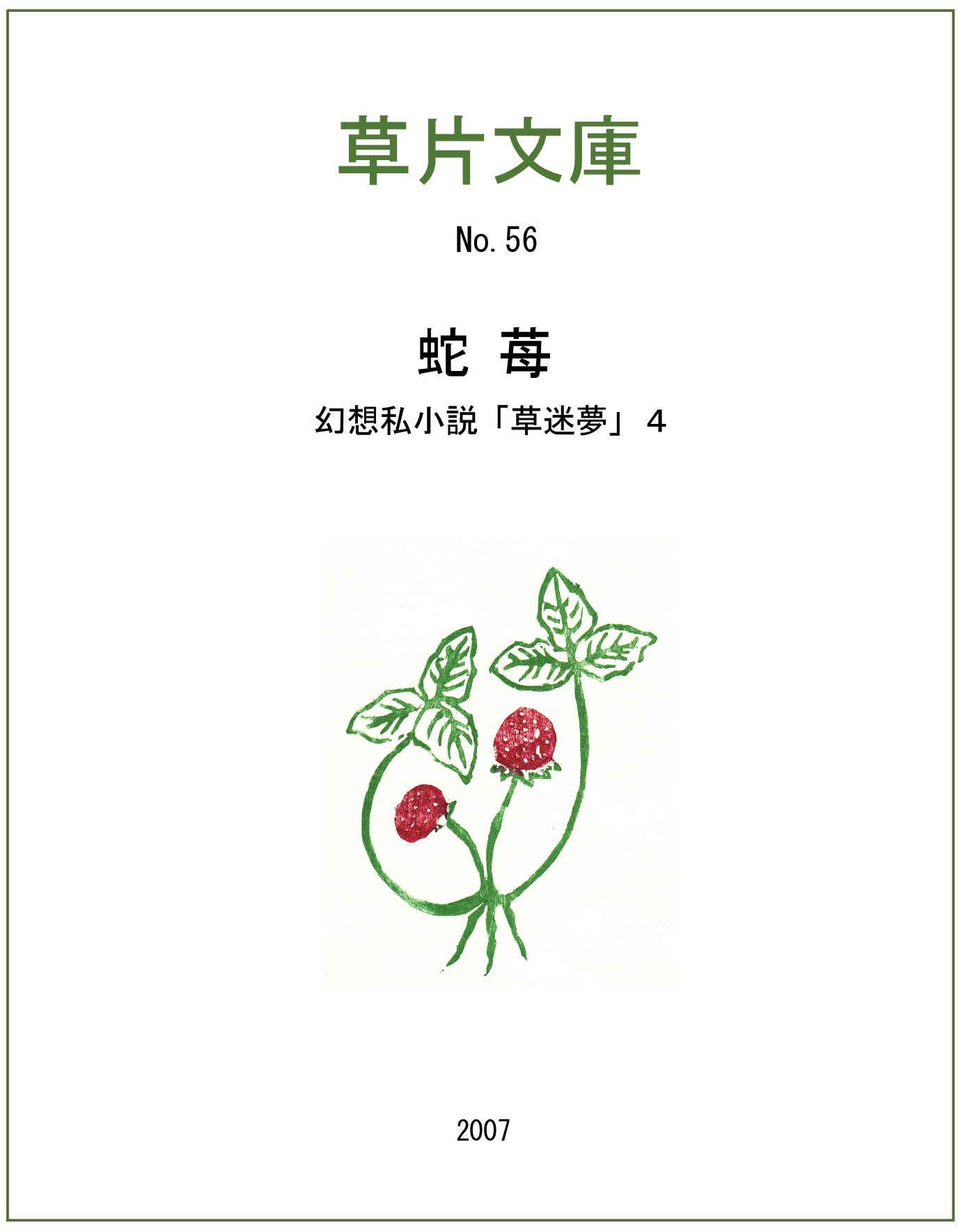
蛇苺-幻想私小説4
泥棒ガラスがカアと鳴いた。そのとたん、柘榴の精となって吾が入っている柘榴の実が地上に落っこちた。柘榴が赤くはじけ、吾は田んぼの畦(あぜ)道にいた。こうして吾は蛇苺の赤い実が点々と続く田んぼの道を歩いている。
黒いズボンに、白のシャツ。学生鞄をもち、まさに高校に行く出立(ででたち)ちだ。田んぼの中にザリガニ(ザリガニ)が掘ったたくさんの穴が見える。
前のほうから赤い自転車がやってきた。狭い道をすり違うのは無理だろうと、立ち止まると、自転車も目の前に止まった。
自転車ではないじゃないか、大きなはさみを振り上げているザリガニだ、亜米利加ザリガニ。
「亜米利加ザリガニではない」
ザリガニはむくれている。
「大山ザリガニだ」
そのような種類は知らないが、新種だろうか。
「もともといるんだ、みな知らないが」
そうか、そりゃ悪かった、日本ザリガニより大きかったので、亜米利加ザリガニだと思ったのだ。
「しかたがないが、単純で、目の悪いやつだ、自転車とも間違えるとはな」
確かにそうだ。高校生の時には目はよかったのだが。
大山ザリガニは畦道の蛇苺の赤い実をはさみで器用に切ると口に運んだ。
菜食主義なんだ。
「いけないか」
挑戦的なやつだなあ。
蛇苺は毒苺とも呼ばれる。食べられないものと思っていたが、毒ではないようだ。
蛇苺は好きな野草である。南平の最初の吾の家に植えてみたりもしたがつかなかった。日当たりがよく、程よく乾燥していないといけないようだ。今の家は玄関の周り に蛇苺がはびこり、赤い実をたくさんつけて、とてもいい風景になっている。
「これは、藪蛇苺」
蛇苺は薔薇科蛇苺属だそうだ。
「藪蛇苺のほうが蛇苺より大きくて美味しいんだ」
大山ザリガニは大粒の一つをちょん切ると吾の目の前に差し出した。
「喰え」
なんとも命令口調だが、癖なのだろう。本当は親切なんだ。
受け取って口に入れてみると、少し酸っぱいが、苺の匂いがするわけでもなく、旨くもなんともない。
「繊細さに欠けるやつだ」
大山ザリガニはもう一つ採ると自分の口に入れて、
「花言葉は、可憐、なのだ」
と言った。
それでどうしたのだ、可憐なものを喰っちまうなんてひどいじゃないか。ちょっと挑戦的になってやった。
大山ザリガニはうなだれた。
可愛そうなことを言ったかもしれない。
「可憐なものしか喰えんのだよ」
大山ザリガニは、
「学校に行こう」
とはさみを振った。一緒に高校に行くつもりらしい。それもいいかと、歩き始めた。歩きながら大山ザリガニは家出のこと、恋人に振られたことや、将来の設計がたたないことなど、いろいろなことを話してくれた。吾に話したとてどうしようもないのだが。
厚木の高校は、実家から歩いて二十分ほどのところにあった。校舎の手前にはちょっときつい坂道があり、桜の木が植わっていた。青々と茂った桜の枝が垂れ下がり、陽の光を遮断してくれている。築何十年もたつ古い校舎は、我々が卒業した昭和四十二年の後に壊され、新しい建物になった。新しい建物になってからは全く来たことがない。しかし大山ザリガニとともに坂道を登りきると、現れたのは、懐かしい古いままの木造の校舎だった。
「木の校舎はいいものだなあ」
大山ザリガニは先頭だって校舎の中に入っていく。吾もついて入った。
中は薄暗かったが、最後の学園祭にだれぞやが壁に描いた色彩画が目に入った。上手いものである。取り壊すと決まっていたので、壁に絵を書くことが許可されたのだ。
校舎の中は誰もおらず、壊される寸前のようだ。
大山ザリガニと廊下を歩いていくと、トイレの隣にある生物部の部室についた。
生物部の部室にはベニヤでできた蟹が無様な格好で釣り下がっている。手足を動かすことができるものだ。吾が作ったものである。生物部の蟹斑で蟹を調べていたのだ。
どこぞやの高校の生物部からザリガニの調査を頼まれたこともある。高校生活の思い出といえばすべて生物部しかないといってもいいくらいだ。
感慨にふけっていると、大山ザリガニが校庭に出ようと誘った。
ザリガニとともに校舎から出ると、広い校庭の西側に、大山がそびえている。大山には雨降(あふ)り(阿夫利)神社があり、農耕民にとっての信仰の対象だったそうだ。
「どうだ、大山に行こう」
大山ザリガニは、自分の生まれ故郷だという大山に吾を連れて行くことにしたようだ。
ところが、大山ザリガニは吾を生物部の部室に連れ戻した。大山ザリガニははさみで床を持ち上げた。覗くと暗い穴があり、周りはタバコの吸殻だらけである。生物部のやつらはここに吸ったタバコをすてていたのだ。けしからん。吾は大学に入ってからタバコをはじめたから高校の頃は吸っていない。誰が吸っていたか想像がつく。
大山ザリガニはその穴の中に身を躍らした。真っ暗な穴の中になんと勇気のあるやつだ。しかたがない、吾もその中に飛び込んだ。
真っ暗な中を落ちていく気分はあまりいいものではないが、怖くはなく、楽しい思いすらあった。なんだか、ジェットコースターや宙返りロケットに乗っているようだ。
足元から明かりがさし込むと、ひょいと大山の麓にでた。
「あたいたちが掘った穴なんだ」
そうか、ザリガニが掘った穴は全国に通じているのだな。でもなぜ言葉遣いが変わったのだろう。
道端にはクローバに混じって、蛇苺が黄色い花を咲かせ、ところどころに赤い大きな実をつけている。
大山ザリガニが実をとって食べるのではないかと思ったが、まったく気にかけずに、一軒の立派な門構えの家に入っていった。
古い瓦葺の民家で、表札は山(やま)蝦(えび)とある。この大山ザリガニが飼われていた家なのかもしれないと乏しい想像力を働かせた。
玄関の脇に赤い自転車が立てかけてある。大山ザリガニと見間違えた自転車そっくりだ。
大山ザリガニは自転車の脇を通り玄関の前に進んだ。吾も後につく。
大山ザリガニが玄関脇の柱をよじ登るとブザーを押して、どたっとおちた。そう言ってくれれば吾が押したのに。
中からは、あい、という女性の声が聞こえ、玄関の戸ががらがらと開けられた。
老婆が顔を出した。老婆は大山ザリガニが玄関の前ではさみを広げているのを見ると、おおーと言うなり、大きな手を広げて、大山ザリガニを抱き上げた。
「久しぶりだねえ、お前、どうしておじゃった」
どこの言葉ともいえないおかしな言葉遣いをする老婆だ。変な気分になったが、この大山ザリガニはやはり飼われていたようだ。
吾はどうしてよいかわからず、ただ立っていたのだが、老婆が気づいた。
「おまえさまはこの子の友達かえ」
大山ザリガニはなんとも言わぬので、どう思っているかわからないけれども、ともかくここまで一緒に来たのだからそうであろう。うなずいた。
「おはいんなさい」
老婆は手招きをした。
大山ザリガニも吾に向かって手招きをした。
玄関をあがり、奥の部屋に入ると、床の間の脇で、もっと年取った老婆が若草色の紋付を着て籐椅子に腰掛けていた。
その老婆は大山ザリガニを見ると、涙を浮かべた。
「舞ではないかえ、よく戻ってきたの」
年取った老婆は立ち上がることはしなかったが、やはり手を広げた。その拍子に袖についている赤い向かい蝦の丸い紋が目に入った。
みんなに可愛がられていたザリガニなのだなあ。
大山ザリガニは老婆について、さらに奥に行く。
吾もついていこうとすると、若草色の紋付をきた老婆が、
「お友達は、ここでまたんしゃれ」
大きく手を広げた。
立っているのもおかしいと思い、畳の上に胡坐をかいた。
若草色の紋付の老婆が手をたたいた。
何事かと思っていると、障子が開いて、若い二人の女性がテーブルを運んできた。
すぐ後ろから、別の女性がお茶と和菓子を載せた皿を吾の前に置いた。若草色のぎゅうひ餡に蛇苺がいくつかあしらってある。つくりものの蛇苺だろうか、とてもよくできている。
「召し上がれな、舞がおせわになったようじゃ、ありがとうさん」
あの大山ザリガニは舞という名のようだ。
おかしな成り行きではあるが、ここまで来て、遠慮するのもおかしいので、いただくことにした。和菓子をつまみ、そこで楊枝が添えられているのに気がついたが、もう遅い、かじってしまった。ふーっと草の匂いとともに、すっぱいような餡(あん)の味が口に広がった。奇妙といえば奇妙な味で、かじったところを見ると若草色の餡がはいっている。
「我が家で作りましたのじゃ、蓬(よもぎ)の餡に蛇苺をあしらった舞の好物でな、いかがかな」
「いや大変、珍しい、おいしいお菓子です」
「それはよござんした、お茶も召し上がれ」
お茶を一口飲むと、苦味のある、舌がしびれるような味がした。
「それはな、破れ傘のお茶でな、少しばかりドクダミや、センブリなどがまじっているのじゃ、薬茶でな」
舌ばかりではなく、頭もしびれているようだ。周りが暗くなっていく。
時間の感覚がない。また、襖が開けられ、今度は最初の老婆がお膳を運んできた。
「今日は、舞が戻ったお祝いじゃて、どうぞゆっくりしていってください」
食卓に皿が並べられていく。
四人分が用意された。
大山ザリガニはどこに行ったのだろう。
若草色の紋付の老婆が吾の隣に座った。老婆の前に最初の老婆が座った。そこへ、洋装の若い女性が襖を開けてはいってきた。目を合わすと、ちょっとばかり首を傾け、
「おまたせしました」
と静かに吾の前に座った。
紋付の老婆が吾のほうに向かって頭をたれた。
「家出しておった舞を連れ戻してくださってありがとうさんでした」
「舞ですの」
大きな黒目勝ちの目が吾をとらえた。しびれている頭の中に、和菓子の甘い、すっぱい、奇妙な味が広がっていった。
「ここまでお供していただいてありがとうございました、祖母と母ですの」
舞が紹介してくれたが、なんだか頭がこんがらがっている。
「ほほ、私大山ザリガニですの」
「雄、いや男のザリガニだと思っていたもので」
と言うのが精一杯であったが、このような美人がザリガニとは。
「あそこでお会いして、高校に行って、ここに帰る気持ちになったのですわ。私もあの高校を卒業したのです、大昔に、高校の校庭で見た大山の素敵だったこと、もう一度我が家に帰って、子供を産むことにしたのです」
子どもを産むとはどういうことなのだろうか。
「でも、大山蛇苺の青い実を食べないと、子供は産めないの」
どうしてなのだろうか。
「明日、大山の山頂近くの湧き水の周りにはえている大山蛇苺の青い実を採ってきてくださらないかしら」
吾は考えることもなく、舞の目を見ながらうなずいていた。
「今日は、大山の豆腐をごちそうしますわ、いろいろな豆腐をお召上りください」 舞の声が遠くで聞こえている。大山の麓は豆腐が美味しいのだ。
若い女性が豆腐をもって部屋に入ってきた。
目の前に出された豆腐は少し黄身がかった、みかけはそのへんの豆腐と変わりのないものである。
「どうぞ」
醤油はどこかと見たのだがない。ともかく箸をとって、豆腐を口にいれた。口に入れるとすうーっと溶けるように口の中を覆い、舌だけではなく、上顎の粘膜にも豆腐の味が染み渡った。
「いや、おいしい」
隣に座る舞のおばあさんもザリガニなのか、その隣のお母さんもザリガニなのか、まあいいか。混乱することは考えないにこしたことはない。
「舞さん」
「なんですの」
「どうしてザリガニなのです」
「人はみな生れる前は何かだったのです、本当の姿がザリガニなのです。あなたはなになのかしら」
「いや、おはずかしいのですが、知りません」
どうせ碌なものでないのだろう。舞さんは今私が考えたことが分かったようだ。
「偉い学者さんが蚤だったり、偉い政治家がO157だったりします」
碌なものでという生き物は無いのだろう。失礼した。
「それを知っている人は、ある時決断をすれば、祖先に戻ることができるのです、私はそれを知って、祖先に戻ったのです。それが家出ということです。でも、あることで人間に戻ることにしたのです。人間に戻るには人間に私を認めてもらわなければなりません。あなたが、なにごともなかったように大山ザリガニの私と話をしてくださった。それは稀な機会なのです。感謝いたしますわ」
「子供を産むということはどういうことです」
「大山ザリガニとして何百の卵を産むか、人間として一人の子供を産むかの選択です。もう人間にもどりました。しかし、ほっておくと、お腹の中の子は泡になってしまいます。人間の子供として産むためには大山蛇苺の実を食べなければいけないのです」
「それで、私にその実をとってくるようにたのまれたのですね」
「何も関係のないあなたにお願いするなどというのは、厚かましいのですが、ご迷惑を承知でお願いしました。その実を食べるまではこの家から出ることができません。今の私は大山には行けないのです」
吾はうなずいた。八十八年生きてきて、大して人の役にたったと思えないし、夢の中とはいえ、このようなことで役に立てば嬉しいものである。
緑がかった豆腐がでてきた。枝豆をすり込んだ豆腐は食べたことがあるが。
「このお豆腐はユキノシタですの」
舞さんが説明してくれた。
「一口食べると、今度は蕗と山葵(わさび)のような香りがした。少しばかり、なぜかクロッカスを思い出した」
紫色の液体がガラスの容器に入れられて運ばれてきた。
「姫浦島草のお酒」
マイさんがリキュールグラスについでくれた。紫色に輝いている。
一口飲む。強い。六十度ほどはあるだろう。ラガブーリンが海草くさい、ヨードくさいとすれば、この酒はウイスキーよりもっととろっとしていて、それで口の中に残らず、刺激は頭の中に長くとどまり、香りは甘い草の匂い、辛口であった。うまい。高校生の格好をして飲んでいていいのだろうか。つい手酌で杯を重ねてしまう。
豆腐がまた出てきた。赤い豆腐である。これは想像できた。
「藪蛇苺でしょう」
「そうですの、私の名前もそれからとったのです」
「舞さんの名前ですか」
「ええ、ほんとうは山蝦苺(まい)ですの」
苺という漢字をまいと読むとは知らなかった。母の字は毎からきたようで、毎は元気で生産する女性の形から作られた字だそうである。よく増える植物であることからそれに草冠がついたのが苺。
蛇苺の豆腐も旨いものであった。頭の痺れが浦島草の酒と、豆腐の甘みで強くなり、苺さんの顔が見えなくなっていく。
気がついたときには朝日を浴びて、大山の石段の入り口に立っていた。大山には長い長い石段がある。昨日のことはよく覚えており、自分の役割も理解していた。
夢なのだ。
高校の時には大山によく来たものだ。高校の担任の先生が大山を案内する先導師だった。
石段の脇に立ち並ぶみやげ物屋はまだ朝早いため開いていない。ぽちぽちと上っていくと、最後のみやげ物屋のところに来た。それより上は杉林に囲まれる。
その店だけは開いており、野草を売っていた。寒葵、マムシ草の芽生え、鳴子ゆり、見慣れた草がきれいに置かれている。どうも野草だけではなく、料理も出すようで、木野子料理とかいてある。朝の木野子粥をどうぞとかいてもある。朝の食事はまだだが、と思い立ち止まってのぞいていると、奥から黒い前掛けをつけた色白の女性がにこにこと笑顔で出てきた。
どうも食べないわけには行かないだろう。ついでに道を聞くのも良い。
吾は木のテーブルの前にある杉の切り株に腰掛けた。
「朝の木野子粥を」
「はあい」
おかみさんは明るい声を上げて奥にもどっていった。
ほどなく、おかみさんが笑窪をよせて、小型の鉄鍋をもってきた。鍋から湯気がたって、おいしそうな匂いがしている。
おかゆだ。おかみさんが吾の前に置いた。どこかでみたことのある箸が添えられている。これは、昔ニューオルリンズに行ったときに、骨董屋で買った箸だ。鹿の角でできている奈良のものだ。きっと亜米利加の人が奈良に観光に行って買ったのだろう。どのような経緯でニューオルリンズの骨董屋に流れたのか分からないが、何かの縁かと思い買ってしまったのだ。亜米利加から日本土産を亜米利加土産として買ってきたというわけだ。でもなぜそれがここに。いや、夢だから不思議はないか。
おかみさんの顔を見ると、小さな細い目でまたにこっとした。どこかで会ったようだ。かわいらしい。
付け添えに土筆の佃煮が添えられている。箸をとって、かゆの中をみると、網笠茸が何本もはいっている。旨そうだ。
「お好みでしょう」‐
たしかに、網笠茸の粥は初めてだが、これは旨い。
「ところでおかみさん、大山蛇苺はご存知ですか」
「知っていますよ、山蝦さんに頼まれたのでしょう」
ザリガニ一族のことを知っているようだ。
「どの路をいけばよいのでしょう」
「山頂まで行かず、黒石のところで、わき道にそれて、そこを登っていくと、湧水のところにでます。その湧き水の脇にはたくさんの大山蛇苺があるのよ」
土筆の佃煮もうまいし、これは偶然にしてもついていた。
女将がお茶をもってきた。
香りのよいお茶である。
「これは裏の茶畑でとれたものよ」
さて、出かけようと立ち上がったとき、そうだ勘定をしなければとポケットを探ったが、高校生のときにほとんど小遣いなどもっていなかったことを思い出した。これはしまったと、反対側のポケットを探っていると、女将がにこにこと首を横に振った。
「御代はいいのよ、それより、湧水のところまで案内しましょうか」
「あれもこれもみんな助かることばかりです」
恐縮して頭を下げた。
「ほほ、いいのよ、恩返し」
山蝦さんと相当親しい仲なのだろ。おかみさんは前掛けをはずして前を歩き始めた。
石段の脇に蛇苺の黄色い花が咲いている。ところどころに赤い実をつけている。
「この蛇苺は大山蛇苺ではないのですね」
「これは藪蛇苺、大山蛇苺は雄(お)蛇(へび)苺(いちご)の仲間で、実はつけないの。だけど、数年に一度、一つだけ青い実がなるのよ。見つかるといいのだけど」
だいぶ登ると、黒っぽい石碑が立っていて、そこからわき道があった。石碑に、くちわな泉、とある。なんだろうと見ているとおかみさんが説明してくれた。
「蛇のことをくちわなと言うんです。だから蛇苺もくちなわいちごとも呼ばれるのですよ。蛇がたくさんいた泉がこの先にあります。その周りに大山蛇苺があるのです」
おかみさんについてしばらく歩くと、きれいな水の湧き出る小さな泉の脇にでた。
「ほら」
泉は背の低い羊歯に囲まれているが、日の当る一角に蛇苺が群生していた。花はまったく咲いていない。
周りを見ていたおかみさんが嬉しそうにあったと声を上げた。
「ほら」
おかみさんの指差すところを見ると、蛇苺の中に、ぽつんとたった一つ、青い実がついていた。
「よかった」
おかみさんは自分のことのようにほっとした顔をして吾を見た。
「ありがとうございました。こんなところまで案内していただいて」
礼をいうと、おかみさんは懐から小さなガラズ瓶をとり出して渡してくれた。蛇苺の青い実をそれに入れなさいということだろう。
ますます恐縮して受け取ると、青い実をとって瓶に入れた。これで大山ザリガニの苺さんは子供が産めることになる。よかったよかった。
ほっとしていると、女将が吾を見上げて、またにこっと笑うと、すうーと目の前からいなくなった。
あれと思って足元を見ると、真っ黒な猫が黄色い目をして見上げている。
「うちの黒じゃないか」
黒い猫が「うん」とうなずいた。
昔飼っていた猫で、静かに寝てばかりいた猫である。若い頃近くの家で外飼いされていたようで首輪をつけて歩いていた。三毛猫のたまが我が家にいた頃である。たまが死んで、その黒猫が我が家の一員になり、その後、引っ越しても一緒に来て、家の猫の統領になった。ほとんど鳴かない猫で、グニャンとか、ウーンとか言うだけのかわいい猫であった。何をされても嫌がらない猫で、森根などは黒を襟巻きにしたりしたがそのままであった。長生きをして、十六歳で老衰で死んだ。一時、猫の白と一緒の時期があったが、白は一生黒には頭が上がらなかった。
「黒、会いたかったんだ」
手を伸ばして黒の頭をなでると、昔のように鼻を擦り付けてきた。
思わず手に持っていた大山蛇苺の青い実の入ったガラス瓶を取り落とした。
あっと叫んだとき、吾の目の前に大きな黒の口があった。
黒が吾をくわえた、と言うより、青い実の入ったガラス瓶を銜えた。
どうやら吾は大山蛇苺の青い実の中に入ってしまったのだ。蛇苺の精になったのだ。
黒がガラス瓶を咥え歩き出した。
そうか、黒、大山ザリガニの苺さんにこの実を届けてくれるのか。
石段を降りていくのが瓶の揺れでからだに伝わってくる。石段の脇に生えている草草が動いていく。時折、蛇苺の赤い実が見える。
しばらく揺られていくと、黒の歩みが止まった。玄関がガラガラと開けられる音がして、
「あら、木野子粥のクロさん」
と、苺さんの声が聞こえた。
「大山蛇苺をたのまれましたのよ」
黒は人間の形に戻っているようだ。吾の目の前にはおかみさんの指がある。瓶がつままれているのだ。今度は苺さんの指につままれているようだ。
「嬉しい、これで子どもが産めるわ、あの方はどうなさったの」
「私のご主人だった人は蛇苺の精になりました」
「あら、この青い実の中にいるのかしら」
「きっとそうね」
舞さんが私の入っている瓶を覗き込んだ。大きな黒い瞳が吾の目の前を覆った。銀杏のような目に変わった。黒が覗き込んでいるのだ。
黒は人間になると色の白い、落ち着いた美人なんだなあと感慨にしたっていると、ガラス越しにちらっと苺さんの顔が近づいてくるのが見えた。やがて、細い指が吾の取り付いた大山蛇苺の青い実をつまみ上げた。
苺さんの唇が近づいてくると、舌の上にのせられ、白い歯の間にきゅとはさまれた。青い実がじゅっと青い汁を飛ばし、苺さんの口の中に入っていった。蛇苺の精となった吾は反対のほうに弾き飛ばされ、外に飛び出し気を失ったのである。
蛇苺-幻想私小説4
私家版幻想私小説集「草迷夢、2018、279p、一粒書房」所収
絵、版画、写真:著者


