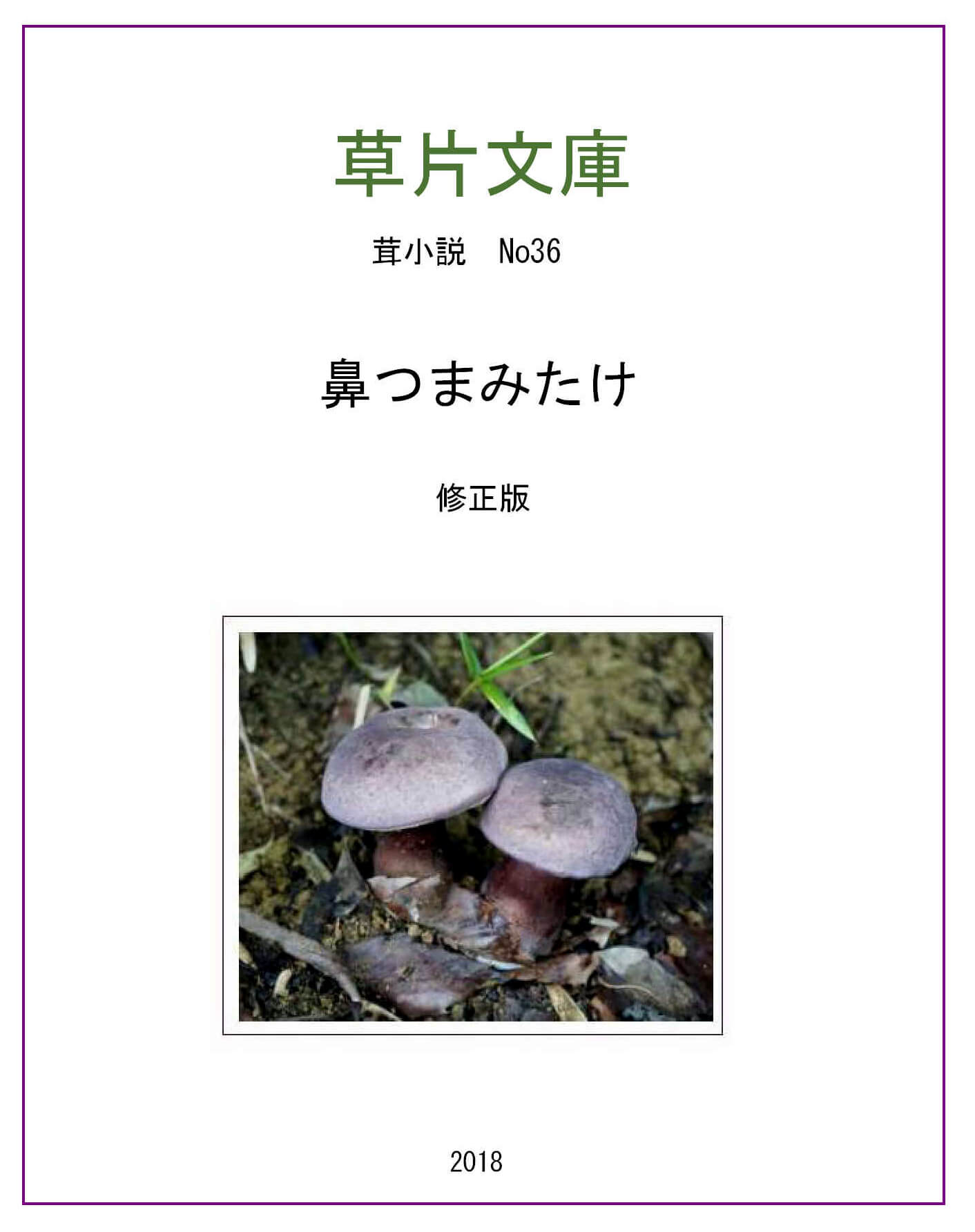
鼻つまみ茸
茸の小咄、児童小説、縦書きでお読みください。
信州の山奥に生えていた松茸と椎茸が旅にでた。
「松茸の兄さん、どこへいくかい」
「そうさな、あったかいところにでもいくか」
「それじゃあ、伊豆か静岡か」
「いいや、もっと遠くよ、琉球だ」
「ありゃ、遠いね、歩けるかね」
「そこが腕次第さね、いや足次第だ」
ということで、松茸と椎茸が、沖縄に向かって歩きだした。
慣れない山道をころころ転がったり、ぴょんぴょん飛び跳ねたり、こりゃすごい旅になった。
「兄さん、大変だね、動くってえのは、ただ生えているのは楽でいいね」
「そりゃ、そうだ、ただ生えていりゃ、やがて萎びて土の中に溶けちまうか、鼠に食われて、糞になって土に溶け込むか、人に踏まれてぐちゃぐちゃになって、土まみれになるか」
「へえ、なにしても、土に溶け込んじゃうんで」
「そうさな、だが、旅にでてみねえ、きっと、天国みたいなところに行き着くさ」
「天国ってえのは、なんです」
「きっと、いつまでも生えていて、毎日毎日胞子を飛ばすことができるところだ」
「胞子ってなんです」
「おれたちゃ、まだ若いが、もう少したつと、胞子ができて、それを空にばら撒くんだ、そんときゃあ、気持がいいんだそうだ」
「胞子、そいつはなんで」
「松茸のこどもよ」
「そいじゃ、松茸の兄いは、女なんで」
「なんだそりゃ、いいか、動物は女が子供を産む、でも、精子っていうやつがなきゃあ子どもにならねえ、そいつをを作ってばら撒くのは男だ、茸はみんな胞子をばらまく」
「それじゃ、茸はみんな男で」
「いや、茸は男も女もねえ」
「へえ、それじゃ、松茸の姉さんと呼んでもいいわけで」
「そりゃあこまる、おめえ、人間はな自分が女とおもったら女なんだ、男と思ったら男なんだ、自己認識ってやつだ、性のアイデンティティー」
「兄貴は難しいこと知ってるね」
「だからな、人間がそうなら、おいらたちだって、自分で男と思えば男なのよ、俺は男だ」
「ふー、さすがは兄貴だ、よく考えているな」
てな、会話をしながら、山を越え、谷を越え、してまいりますが、なかなか信州、長野をでることができない。
「おい、椎茸、今どっちに行っている」
「へえ、お天道様が上る方に転がっていやす」
「おー、そりゃ間違いだ、琉球は日の沈む方に行かなきゃいかん」
ともう、日が暮れてきた。しかし、夜が大好きの茸たちでございます。むしろ元気になって、山の中を飛び跳ねていく。
夜になると、動物がでてくるようになる。茸の大好きな虫などがしょろ、しょろとでてきて、食いつこうとする。
「し、っし」
松茸と椎茸は虫を払いながら進んでいく。
しかし、とうとう椎茸に、黒っぽい虫が食いついちまった。
「いてて」
すると、松茸が椎茸に体当たり、虫を弾き飛ばした。
「兄さん、ありがとよ」
「気をつけねえと、ぼろぼろになっちまうぞ」
「うん」
また二つは転がったり、飛び跳ねたりして進んでいく。
今度は松茸に虫が食いついた。するとどこからか鼠が現れて、松茸の虫に食いつく。
「助かったよ、鼠の兄さん」
「あたしゃ、女だよ」
「あ、すいませんな、あっしらには目がないんで、足音だけで見てますんで」
「なんだえ、あたしの足音は雄なのかい」
「へえ、ちょっと似てたので」
「これでも女だよ、もう三歳になるがね」
鼠の三歳はかなりの高齢だ。すなわち婆あ。
「鼠のお婆さんか、ここはどこなのかね」
「お婆さんはないだろ、ここは高尾山だ」
「高尾は静岡でござんしょうか」
「はは、馬鹿お言いではないよ、東京だよ」
「え、東京、やっぱり、反対に歩いちまった」
「どこにいくんだい」
「琉球」
「ほ、琉球とな、そりゃあちょっと大変だねえ」
「あとどのくらいだかわかりやすか」
「わかるわきゃあないさね、途中で死んじまうくらい遠いんだ」
「そうなんですかい、そりゃあこまった」
「兄貴、どうだろう、この高尾山で暮らすのは、鼠のねえさん、ここは暖かいんだろう」
「冬はかなり寒いよ」
「雪は降りやすかい」
「そうだねえ、ちょっとは降るけど多かあないよ、おまえさんたちどこから来たんだい」
「へえ、信州で」
「ずいぶん寒いところからきたね、そこよりは暖かいさね」
「ところで、鼠の姉さん、このあたりに赤松は生えていませんかねえ」
「赤松なら、この先のところに何本か生えていたね」
「そいつぁあありがたい」
「なんだい、椎茸も赤松がいいのかい」
「へえ、子どものころから松茸の兄いと赤松で育ちやした」
「そうかい」
「赤松はまっすぐいきゃあいいですかね」
「そうだが、途中にゃ茸虫がうようよいるから、食われないようにね」
「恐ろしいね」
「それじゃ、気をつけなよ」
鼠の姉さんは食べ物を探しにいっちまった。
「だがよ、赤松があるようでよかったな」
「そうだよ、兄貴、出かけてこの方、なにも食っていない、腹減ったなあ」
「ああ」
茸たちは転がりながら、赤松の木の生えているところに向かいました。
上の方から、松茸の兄貴になにかが飛び掛かった。
「いて」
そいつは松茸の頭に食いついた。
「ちぇ、こいつは血をもっていねえじゃねえか」
落ちてきたのは蛭。
松茸の兄貴は頭をふると、蛭を払い落とした。
「まったく、気色悪い」
「だいじょうぶかい、兄貴」
「何ともないが、頭の吸われたところが気持わりい」
「ふーん」
すると、今度は、子分の椎茸が底をかじらた。
「あ、茸虫だ」
松茸が飛び上がると、子分に食いついている茸虫を潰した。
「おー、痛かった」
椎茸の根本が少し齧られちまった。
「あぶないやね、急ごうや」
松茸と椎茸は飛び跳ねて、林の中を飛んでいく。
赤松の木は八本はえている。
松茸がさて、どの木にとりつこうかと、品定めをしていると、赤松の木が「あんたらどこからきた」と聞いてきた。
「信州は諏訪でございます」
松茸の兄貴は気取って言った。
「遠くからきたね、俺たちにくっつきたいのかい」
「ええ、ええ、もう腹減って」
「養分をやらんでもないが、もう、あんたらの仲間がたくさんくっついて大変なのさ」
松の木が言い終わらないうちに、根本からぽこぽこぽこぽこと松茸が顔を出した。
「おう、おまえさんがた、どこに行く途中で」
「いやさ、それが、琉球に行こうと思っていたら反対にきちまった」
「ふーん、ちょっとだけ休むならいいが、俺たちの仲間はたくさんいるんで、赤松が参っちまうといけねえ」
「そりゃ道理で、それじゃ、ちょっと休ませていただきやす」
松茸と椎茸は赤松の根の一本にとりつくと、ちょっとばかり養分を吸った。
「うまい、松だねえ」
「そうだろう、そんじょそこらの松じゃねえ、天狗のしょんべんで育ったんだ」
「天狗てなあ、おっかねえやつだろうに」
「おっかなくはないさ、からえばりしてんだ、ほんとはな、あの団扇がなきゃ、なにもできないのさ」
「団扇ってのはなんでい」
「何でもやっちまう団扇で、ひと振りすると、みんな吹き飛ばすってすごいものだ」
「へー、天狗はそいつをみんな持ってるのかい」
「高尾山の天狗は八人、みんなもっている。なぜかその八人がこの根本でつれしょんをするので、旨い赤松になったのさ」
「ふーん、天狗のしょんべんか」
「そうだ」
「会いてえもんだ」
「会ってどうするんだ」
「ちょっとお願い事をするんだ」
「高尾山の頂上の神社の天辺であたりを眺めているか、大山まで遊びにいってるかだ」
「なんだい、その大山ってのは」
東京の隣の神奈川の奥にある山で、高尾山とは続いているのさ、そこに、亜不利神社ってのがあって、その神さんにお習い事に行くのさ。天狗の団扇だって、そこの神さんにもらって、使い方を教えてもらってんだ」
「ふーん、高尾山の頂上に行くのには時間がかかるかい」
「そうさな、一時もありゃあいいだろう」
松茸と椎茸は礼を言うと飛び跳ねて頂上に向かった。頂上の神社では人間がうようよしいる。
見つかったら大変なことだ。茸虫どころではない。踏みつぶされるのは避けることができるが、みつかって追いかけられたらたまったもじゃない。高尾山で松茸と椎茸が落ちていたと新聞にでるにちがいない。子供たちだったらもっと大変だ、いじくられてぼろぼろになってしまうのは目に見えている。
松茸と椎茸はもう少しで頂上というところで、枯れ葉の中に身を隠した。
やがて人間の匂いと足音はなくなり、あたりは暗くなってきた。松茸と椎茸はもそもそと起き出すと頂上にやってきた。空では星がきれいに瞬いてそよそよそ風が吹いている。茸は社の天辺を見た。
おお、天狗が一人止まっている。
「おーい天狗さんよ」
茸は動物のような声を出すことはできないが、動物植物と意思疎通ができる。傘を上下に揺すると相手に気持が通じちまう。もちろん人間には聞こえない。きっと、天狗にもわかると松茸は思った。
あにはからんや、天狗がはてという様子で下を見た。
天狗の目は千里眼だ。
「なんだ、松茸じゃないか、椎茸もいっしょか、赤松にしょんべんかけるなといいにきたのか」
「とんでもない、天狗様のしょんべんは、赤松にはとてもよいようで、じゃんじゃんおねがいします」
「それじゃ、なんだ」
「あっちらは、旅している茸で、ちょっと、天狗様にご挨拶をと思いやして、へい」
「ただ、挨拶だけか」
「いや、噂に聞く天狗様の団扇の力を見てみてえと、お願いに参りやした」
「そうやたらとは、団扇を打ちおろすことはできん、二人はどこから来たのか」
「へえ、信州でございます」
「ほう、信州とな、ずいぶん遠くから来たものだ、わざわざきたわけか」
「へえ」
「とすれば、むげに断ることはできぬな、今日はこれから、天狗の会合に出かけねばならぬ、明日の夜に、ここで団扇を振って見せてしんぜよう」
「はい、ありがとうございます、明日また参ります」
ということで、二つの茸はもう一度枯れ葉の中に隠れ、日の照る間はじーっとしていた。
「兄貴は嘘がうまいね、でもなんで団扇なんで」
「あの団扇を俺たちに振り下ろしてくれりゃあ、あっというまに琉球に行き着くのさ」
「ああ、そうか」
椎茸はうなずいたが、
「ちょうどよくそこまで飛んでいくことができるかな」
と疑問をなげかけます。
「いやな、天狗にゃそんなに力がないだろう、だけんど、途中までだって楽だろうに」
「そうだな、ほんとに兄貴は頭がいいや」
と夜を待っておりました。
夜になると、また、高尾山の天辺の神社にいった。昨日と同じように、神社の屋根の上に天狗が腰掛けている。
「天狗さん、天狗さん、昨日はありがとうございました」
「おお、きたか」
天狗は地面に飛び降りてきた。
「して、お主らはどこに行きたいのだ」
「いちばん遠いところにいきたいと思っておりますで、暖かいところに行きたいと思ってやす」
そう言いますと、天狗は、神社境内の中の石の上に乗れと申します。
二つの茸は石の上に乗りました。
天狗は「一番遠き暑きところに参れ」
と声をあげますと、団扇をふりおろした。
ところが最初は生暖かい風が茸たちのわきを通り過ぎただけ。
「むむ、ちょっと、失敗したな、もう一度やるからまっておれ」
天狗は再び団扇を力一杯振りおろした
二つの茸は、コロンと転がって、石の上から落ちちまった。
驚いた松茸は「もう琉球に着いたのか」と椎茸に声をかける。
しかし、椎茸が「いや、まだ、高尾山だ、ほら、星の位置がかわっていませんぜ」
と立ち上がった。
「どうも、エネルギーが足りないようじゃ、明日にでも見せてしんぜよう」
「へえ、それまで待っておりやす」
「お前たち、あの八本の赤松にもどるのか」
「いえ、あそこには持ち主がございます」
「そうか、反対側に赤松が二本あるがそこにいきなさい、あの松には茸がついておらん」
「へえ、その赤松は天狗様のしょんべんで育ったのでございますか」
「いや、そこは、われわれの便所じゃ、大きい方のな」
「その赤松は天狗様のうんこで育ったわけで」
「まあそうじゃ」
「しょんべんより、もっと育っているかもしれねえ、是非、そこによらせていただきやす」
天狗に道を教わり、二つの茸は二本の赤松のところにやってきた。
ずいぶん大きな赤松である。向かい合って立っている松の間に太い根っこが絡み合って、大きな祠ができている。それが天狗の便所のようだ。
松茸と椎茸は、松の根に入り込み、養分をいただくことにした。
松茸の兄貴が椎茸につぶやいた。
「なかなか旨いが、あっちの八本の赤松の方が旨かったな」
「たしかに、こちらはちょっと何かが濃すぎるようで」
「うん、なんか濃いな、おや、体が大きくなっていくような気がする」
「俺の体も大きくなっていくようだ」
松茸と椎茸はネズミほどの大きさから子猫ほどになってしまった。
「大変だ、大きくなっちまうと、ますます、琉球まですっ飛ばしてもらうのはむずかしくなるな」
そうこうしているうちに、天狗が鼻を高くして、団扇にエネルギーを蓄え、
「琉球でもどこへでもとばしてしんぜよう」とやってきのです。
そこで、天狗は二つの茸を見ると驚いた。
「なんと、大きくなったのう」
「へえ、天狗様のうんこは栄養たっぷりのようでございやす」
「ふーむ、この団扇だいぶ古くなっておるでな、おまえたちのように大きなものが飛んでくれるかどうか、わからんのお」
そう言って天狗は二つの茸に向かって団扇を振りおろした。
大風がわきあがると、ぐあーっと茸にぶつかったが、茸は松の根に深く入り込んでしまっていて全く動くことがでない。
「こりゃ、だめじゃな」
そう言って、もう一回団扇を振りおろした。
強い風が大きな松茸と椎茸に当たると、茸がぐらっと揺れた。
そのとたん、鼻が腐るほどの強いうんちの匂いが茸から流れ出てきてしまった。その臭いは人間が嗅ぐと気絶するほどのすさまじいものだ。八百年も便所にたまっていた臭いが、茸を煙突にして外にでてしまわけである。
それはそれはそれは臭いもので、松茸と椎茸は気絶してしまった。
「ふーむ、もっとエネルギーを貯めねばだめのようだ、大山の雨降り神社に行って、新しい団扇を手に入れて来よう。十年ほど待たねばならぬであろな、お前たちはそれまでここに生えているように」
天狗はそう言い終えて神社に戻って行ってしまった。
気がついた松茸と椎茸はこれは大変と、松の根っこから降りようとしたのですが、離れることができません。
「あいついっちまったよ、おれたちゃ、天狗の便所の煙突になっちまったようだ」
「そうよ、兄貴、十年しないと天狗はやってこねえ」
「ああ、それまで、こうやって、臭い匂いを外に吐き出さなきゃならねえのだなあ、松茸の高貴な臭いがなんてこった」
ということで、二つ大きくなった茸は天狗の便所の煙突になってずーっと生えていなければならなくなった。
それでも、十年、何事もなく松茸と椎茸は赤松の根元でくらしいた。
やっとこ天狗がやってきた。
「ほれ、新しい団扇だ、みごとだろう」
天狗は赤い団扇を見せびらかした。本当は団扇が弱っていたのではなく、天狗の勉強が足りなかったのだ。十年間大山で修行をしてきたわけだ。
「さて、琉球にとばしてつかわす」
天狗は得意げに団扇を振り下ろした。
団扇からかぜは出てこなかったが、松茸と椎茸はふわっと、空中に浮いた。これが本当の天狗の団扇の力でした。風が出てはいけないのです。
「さあ、琉球にいきなさい」
天狗は宙に浮かんだ茸を団扇で静にあおいだ。
そのとたん、松茸と椎茸は琉球まで飛んでいった。
ようよう、琉球の小さな島の一つに生えていた蘇鉄の根元に降りたつことができたのです。
松茸と椎茸はその根っこにとりつくと、
「ここは暖かいなあ、赤松の味とはちがうが、これもいけるな」
とつぶやいた。
二つの茸は暖かい琉球で傘を開いた。
胞子がたくさん放たれたた。
「兄貴、胞子を出すと、気持が良くなるな」
「おおそうだな、人間の男も精をだすとき気持ちよくなるということだ」
「やっぱりおれたちゃ男だな」
「ああ、胞子をうんとこだそうじゃないか」
胞子は島中に広がり、やがて、松茸と椎茸がたくさん生えました。
人間が松茸と椎茸を見つけた。喜んだ人間が採ろうとしたのですが、余りにも臭くてやめてしまった。
琉球の小島の松茸と椎茸は鼻つまみ茸と呼ばれ、人間に食べられることなく、島一杯に子孫をふやし続けたのでした。
鼻つまみ茸


