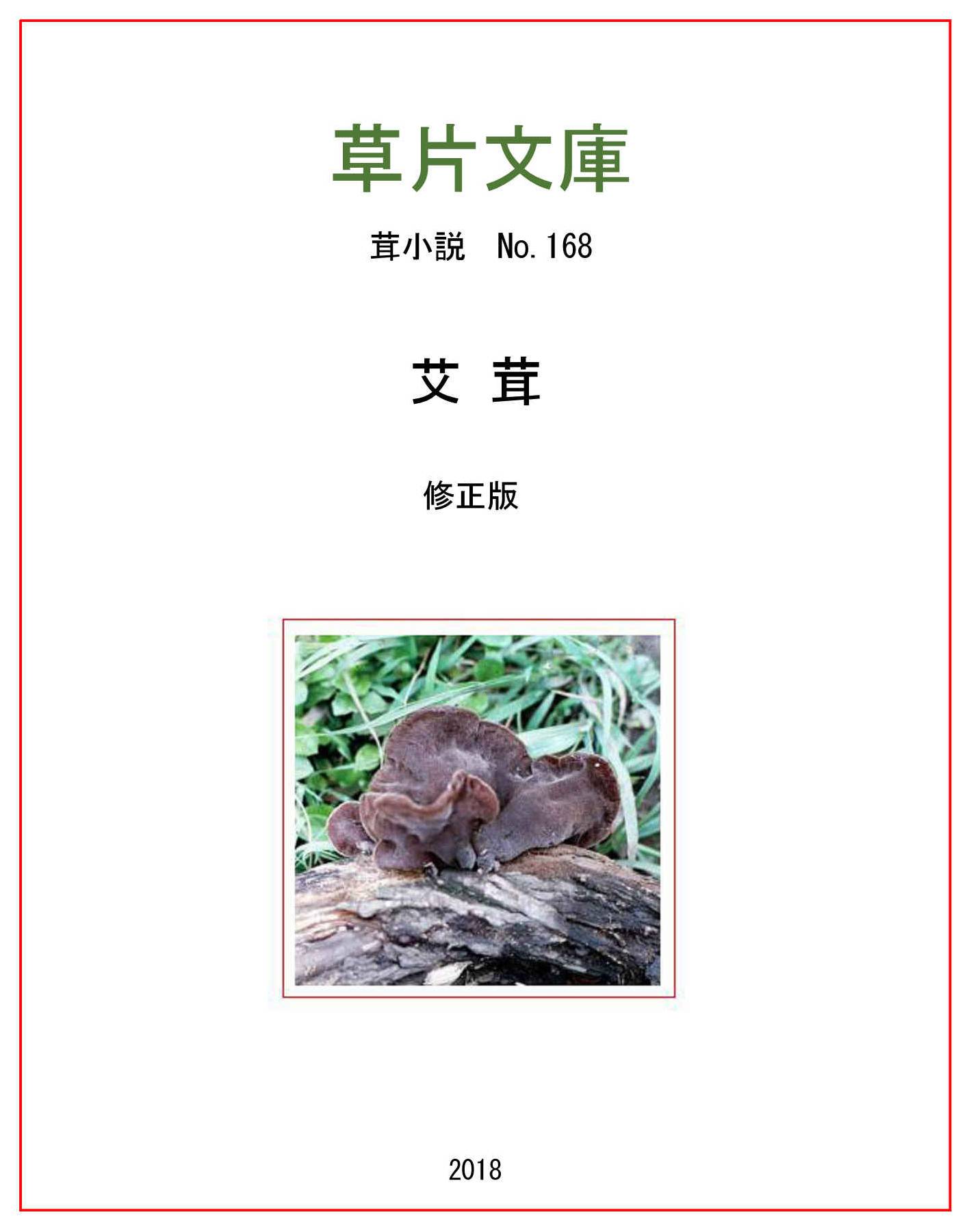
艾茸
「不思議なこともあるもんじゃ」
秋田の山奥に住む艾(もぐさ)爺さんが独り言をつぶやく。
降ろした籠からはみ出しそうになっている山盛りの緑色の茸をみつめている。
艾爺さんは山菜や茸のことを誰よりもよく知っている。茸ときたら知らないものはない。秋になると村人たちは採った茸をもって鑑定を頼みにくる。大学のどえらい生物の先生ですら聞いてくる。それだけじゃない。こういう茸を採ってきてほしいと頼むと必ず取ってくる。
それほどの爺さんが私の研究室に電話をくれた。不思議な茸をみつけた、一度見てほしいとのことであった。
私は茸の研究者で、南米の茸の分類をやっている。南米の茸は探検に行けばたくさんの新種の茸にぶつかる。日本でもまだまだ新種がたくさん見つかるが、それなのになぜ南米の茸の研究を始めたかというと、近年神の茸として有名になったしびれ茸の仲間に興味をもったからである。アステカ文化では神の茸として大事にされ、今ではマジックマッシュルームという名前で呼ばれている茸である。その種の茸に含まれる化学物質が脳に働くことはすでに知られており、食べるのは社会的にも問題があるが、向精神薬として役立つものとして、大事な茸である。毒といわれる多くの茸は脳に作用する様々な成分が含まれているものである。
さらに、アマゾンなどには日本にはない奇妙な形の茸があるから面白い。日本にはない色彩のおかしな形の茸などを見つけるとメディアが取り上げてくれる。正直言って地味な分類に毎日を費やしていると、そういったことが一つの励みになる。日本には茸のまじめな研究者がたくさんいる。素人でも玄人はだしの茸マニアが多い。そのような中で、自分は違うところで茸を調べたいという気持ちが強かったのである。
艾爺さんとは、日本の茸を研究している友人を介して一度会ったことがあった。何年か前、友人が艾爺さんと茸を採りに山に入ったとき、私もさそわれついて行った。茸採取のあと、艾爺さんの家で囲炉裏を囲んで酒盛りになり、なんだか気が合って、茸の面白さを語った。名刺を渡したきり、その後彼のことは忘れていた。
そんな艾爺さんが私に連絡してきた。ちょっと驚いた。よほど珍しい日本離れした茸に遭遇したのだろうと思った。
艾爺さんは本名を山田正太郎というが、村中の人たち、いや近隣の町中の人たちが艾爺さんと呼んでいる。爺さんは膝頭の脇の三里や、親指と人差し指の間の合谷、上腕の三里に毎日点灸をしている。自分で採ったヨモギを艾に仕立てて、自給自足で灸をすえているが、ある日山道を歩いているときにいつもとは違った、白っぽいヨモギをみつけた。それが色の白い、香りのよい艾になり、火をつけると穏やかな熱さになる気持ちのよいものであった。それを聞きつけた艾を作っている会社が、そのヨモギをもらって新たな艾を作り出した。そのヨモギもヨモギの亜種として登録され、発見者として爺さんの名前が残り、艾の名前も正太郎艾として売り出された。そのようなことから、艾爺さんと呼ばれるようになったのである。
電話をもらって二日後、秋田にでかけた。艾爺さんの家を訪ねるのは二度目になる。正太郎さんは七十を過ぎたはずである。
山間の中腹にある艾爺さんの家に行くには、一日四本しかないバスに乗り、山の中腹を走る県道を一時間ほど行かなければならない。幸い艾爺さんの家の近くにバス停がある。
バス停をおり、声をかけ、開いている玄関をのぞいた。艾爺さんは土間で、その日採った食茸を土間で選り分けているところであった。日に焼けた深いしわのよった顔を私のほうに向けた。前にあったときとまったく変わらない。元気そうだ。
その脇に大きな背負子が置いてあり、その中に茸がいっぱい入っていた。電話で言っていた茸のようだ。茸の種類が分からない。
「ありゃ、先生、すんませんのう、こんなところまで呼び出してしまって、それですのじゃ、とってきて三日になりますのう、変わらんですわ」
艾爺さんの太い指が茸を指示した。
とても鮮やかな少し薄めの青緑の茸で、南米などでも見たことがない。海外の茸図鑑でも見たことがない。
「珍しい茸ですね」
「そうなんですわ、まあ上がってくだされ」
爺さんは茸が入った籠を持つと、土間から居間に上がった。黒光りがした板の間に囲炉裏が掘ってあり、大きな五徳の上に薬缶がのっていて、口から湯気が立ち上っている。自在鉤は使っていないが、昔ながらの寒い地方の農家の家の中の景色である。前に来た時にもこの炉端で酒を飲んで茸の話をした。
私は囲炉裏の縁にある座布団の上に胡坐をかいた。
脇に茸の入った籠を置いて、お茶の用意を始めた艾爺さんは、
「不思議なことがあるもんじゃ」と籠を指さして、「中の青い茸をとってみてくだされ」と言った。老人は緑色を青と言う。昔の人にとって緑色は青色の範疇だったのであるが、この茸の色は青っぽくも見える。その中から一つ手にとってじっくりと見た。形はよくあるマツタケ型で大きさもマツタケ並みであるが傘がかなり広い。襞を含めすべてが薄青緑で、かすかにハーブのような匂いがする。茸の匂いではない。日本に緑色の茸はないわけではなく、数種類あるが、どれも小さな茸である。これは大きいし、茸としてかなりの重さがある。
艾爺さんはお茶を両手に抱えるように持つと、「いつもの山に行ったときですわ」と話し始めた。
「その日は舞茸でもと思って、山に向かったのですわ、そこに茸の木がありましてな」
茸の木とは茸の採取人しかしらない舞茸の生える水楢の木のことである。
艾爺さんの小さな目が、本当に信じてもらえるかなといった様子で私を見た。
「水楢の木の裏に行きますとな、当然あるはずの舞茸が生えていなかったんですわ」
「今年は茸のできはいいんじゃないですか」
「そうなんでな、だかんら、熊かなんかが喰っちまったかと思ったんだが、あいつら食い散らかすから、舞茸のかけらがたくさんあるはずじゃが、なかったな、生えた様子がまったくなかった。他の茸はぽちぽち生えてるんだよ」
「どんなところなんです」
「とりたてて珍しいところじゃねえよ、南向きの急斜面で、水楢、ブナ、クルミ、楓、入り込んでいてな、このあたりとも同じだ」
艾爺さんは茶を飲んで一息入れた。
「それでな、もっと奥山に行くことにしたんじゃ、この年になるとあまり遠出はしたくないがな、いつもいく場所までここから二時間、そこはさらに二時間ほど行かねばなんねえ、若い頃はよく行ったが、この年になったで、ずい分行ってねえ、ところが、そこに行ったらこの青い茸がたんとありましてな」
「ずい分重かったでしょう」
「帰るのに四時間だから、昼前に家にもどれねえからな、しかたねえな、いつもは五時に家を出て、往復四時間、だからゆっくり茸採りをして帰っても、十時ごろには家に帰れる、昼飯はいつもうちで食うんだ、朝出るときは水を飲むだけで、朝飯用に握り飯を三つ持っていくんだ、途中で二つ喰って、一つは残しておくんだ。なんかあったときに食べるためにさ、昨日は帰りの途中で残りの握り飯を食ったよ、重いのを担いで歩いたから腹がへってな」
艾爺さんは籠の中の緑色の茸を一つとると傘をちょっとかじった。
「最後の握り飯を食うとき、この青い茸を喰らおうと思ったんだがな、おらの感じじゃ、生で喰える茸だと思う。だけんど、何しろ初めての茸だし、おかしな生え方してたもんで、食わんじゃった。それでともかく先生に連絡したんですよ、なんの茸かわかりますでしょうか」
私は首を横に振った。
「珍しい、緑色の茸は若草茸というのがあって、子供の頃は緑色をしていますが、こんなに大きくないですね、そいつはちょっとした毒がある。他にも萌黄茸というのがありますが、これも若いとき頭が緑色で、食べられます、だがどちらも形が違いますね」
「先生のやっている、外国にはありませんかね」
「知らないですね、南米でも見たことがない、それに、外国の茸の図鑑でも見たことがありませんね」
「わしゃ、理由はわからねえが、マツタケに近い種類じゃないかと思うんだがね」
「確かに、形は似ていますね、詳しく調べますのでいくつかもらっていいですか」
確実に新しい種類の茸である。艾爺さんが、茸爺さんと呼ばれるようになるかもしれない。新種なら山田さんの名前も入るだろう。私は緑色の茸をしまう準備をはじめた。小型のクールボックスを持ってきている。できるだけ新鮮なものを持って帰りたい。保存用の袋に一つ入れたところで、それを見ていた艾爺さんが、
「先生、明日、その茸の採れるところにいってもええが、どうしなさる」と言った。
「まだ生えているんですか」
「仰山ありますわ、ただ、ここから四時間歩かにゃならんですがね、それに二泊しなきゃならんね、今日泊まって、明日採りに行って、その日は町へのバスがないので戻ることはできないだろうから、帰るのは明後日になるね」
いつでも山に入れるような恰好はしてきている。幸いこの週は研究室に詰めなければならないような仕事はない。
「それはありがたい、駅の近くの宿をとりますよ」
新鮮な茸を持って帰るに越したことはない。袋に一つ入れた茸をクーラーボックスに入れて終わりにした。
「いんや、ここでよきゃあ、部屋はありますで、どうぞ」
ということで艾爺さんの家に泊まることにした。
夕飯は艾爺さんの作った茸の料理である。贅沢なものである。囲炉裏の脇のちゃぶ台の上に、茸の煮しめ、茸の天麩羅、酢の物など数品が載っている。なかなか見栄えもいい。
艾爺さんは料理の腕も大したものである。
「喰ってくだされ」
ビールをついでくれた。
うまい、天然舞茸の天麩羅など絶品だ。
それから緑の茸を採った時の話の続きになった。
「それでな、山奥には原始林に近い林がありましてな。古い古いブナの木があって、必ず舞茸がとれるところでしたな、だがな、そこまでいかなくても、それなりの舞茸が採れるんで、あまりいかんでしたがな。さっき話したように、若い頃ですわみつけたのは、近くで茸がだめなときに、茸を求めてあっちこっち歩いて、高い山に登って行くと、急な斜面に、立派な水楢の木が何本か生えていてな、中でも太い水楢の根元に、あたったね、そこの塊だけで、三十キロほどだったかね、そういった場所ですわ。そのときゃ若かったから背負子にいっぱい入れて持って帰ったね、まだ培養舞茸ができていないときで、大もうけさね、だけど近場で十分採れれば、行くことはしなかったね。そこへは三度か四度ほど行ったっきりさ」
「それで、今回はそこにいかれたのですね」
「ああ、そうですじゃ、ずいぶん久しぶりだし、おらも年だから覚えているかどうか自信がなかったが、体が覚えておった、なんとなく来たことがあるような景色をたどって登っていくと行き着きましたな、不思議なんですわ、水楢はそれは見事な大木になっていましてな、まえに来た頃、すでに大きな老木だったのに、もっと太く大きくなり、枝には青々とした葉が覆っていましたわ、まるで若返ったように、きれいな若木のような枝葉でした。若くなったなーと思わず声をかけちまいました、本当はそうじゃなかったのですがな」
艾爺さんはお湯割りの焼酎を一口飲んだ。私は爺さんの作った茸の煮しめをつまみ、ビールを飲んだ。
「水楢の実をしっちょるでしょう、大きな木のくせにずいぶんちっこいどんぐりがなりおる。わしは木の下を見たときに、おかしいなと思ったんですわ、ちっちゃなどんぐりがあたり一面落ちている。そうですわ、秋ももう半ば、このあたりは今は寒いんですわ、それなのに、枝は青い色だ。今頃は青いというものはありゃせんわい、それで、わしは木の根元に行ったんじゃ、それで見上げますとな、枝に何か青い実のようなものがたくさんぶら下がっている。その木はおそらく三十メートルもあるものでな、てっぺんは枝に覆われていて見えない。一番低いところの枝にしても3、4メートルも上にあるので、わしの目ではぶら下がっているものがはっきり見えない。青色であることはわかる。葉っぱの集まっている先にぶら下がっている。ということは、本来なら実がなるところにそいつがついているようだったんだ。どんぐりが落ちてからそこにできたような感じじゃったな」
「何がなっていたのですか」
そんなことはないだろうと、緑の茸を想像しながら艾爺さんに聞いた。
「あの茸じゃよ」
「それはだけどありえない、茸がぶら下がっていたわけですか、しかもたくさん」
艾爺さんは大きくうなずいた。
「それでな、わしは落ちていた長い枯枝を振り回したらな、ボロボロ落ちてきましたんじゃ、それがあの籠の中の青い茸じゃ」
確かにあの茸の石突にごみのようなものはついていない。土から生えていたのならもっと汚れている。落ち葉から生えたにしても、茶色っぽい落ち葉の破片がついている。そういった様子はない。
「上のほうの枝にもなっているようだったし、まだまだたくさんあったよ」
「明日行ってみるとそれを見ることができるのですね」
「んだ、不思議だがなあ」
木から茸がぶら下がるなどという現象は今まで報告されたことがない。錯覚ということも慣れた艾爺さんのことだからないだろう。いくら考えても分からないが、明日行ってみればわかるだろう。
次の日は良く晴れた。風はあまりなかったが、冷たい空気が顔を包んだ。朝五時というとまだ薄暗い。艾爺さんは慣れた様子で、私の分まで朝食の握り飯を作ってわたしてくれた。
「寒くねえですか、先生」
「大丈夫です、防寒の用意は十分にしてきました」
今は軽くて暖かい新素材のダウン風ジャケットがある。靴にしても折りたためる長靴が開発されていてもってきている。
といってもやはり外は寒い、襟を立ててマフラーを巻く。
「歩いてりゃあ、すぐ暑くなりますで」
爺さんは、必要なものを身にまとうと、さっさと山道に入っていく。家に鍵などかけたりしない。
「いつぞやあ、茸採りから帰ってきたら、猿っこが家の廊下の隅で丸くなってましてな、まるで猫みてえに、寒い日だったから、入口の戸を押し開けて入ったんだろう、かわいそうなんで、そのままにしておいたら、次の日、いつの間にかいなくなっていたな」
もう七十を過ぎているはずの爺さんの足の運びはまだ四十代だ、さっさと暗い山の中の道を平気で歩いていく。私のほうがついていくのに苦しい。
しばらく歩くと少し明るくなってきた。日の出まではまだ時間があるが、山の中が見やすくなってきた。足元にはいろいろな茸の顔が見える。私でも名前のわからない茸がある。菌学者はやることがたくさん残っていて幸せだ、自分の名前を付けることができる新種の茸を研究生活の中で十や二十は見つけることができるだろう。
「さすが、茸の先生だのう、素人の連中を連れてくると、一時間も歩かんうちにわしについてこられなくなる、もうすぐ、いつも舞茸をとるところにでるのでな」
艾爺さんはそれでも歩く速度をかえなかった。追いかけるのが大変だ。
その場所は確かに舞茸などが出やすいところであった。少し日が差し込み、大きな水楢が何本もあった。水楢があれば舞茸が必ずあるというものではない。しかし、艾爺さんの茸の木に行ってみると、舞茸の子供が顔を出していた。
「あと、一週間だな、かなり大きくなるだろうよ」
艾爺さんは笑った。
「あと、二時間歩くが、先生大丈夫かね」
私は頷いた。その頃は日も昇り、あたりは気持ちのいい明るさが満ちていた。
艾爺さんは黙々と歩いた。途中に滑子が群れていた朽木を見つけたが、それを採ろうとしなかった。帰りにもし余裕があったら採ると言った。私に茸のなる木をはやく見せたいようだ。
「ほら、猿がいる」
山の木の上に動くものがいた。何頭いるかわからないがかなりの数だ、私にはわからないが、爺さんには認識できるようだ。かなりの山奥である。そういえば原始林に近いと言っていた。
その斜面は山の尾根に出たところで突然目の前に現れた。
「あそこにある大きな水楢なんだ、だけんど青くないな」
彼の目にはその木がもうわかるようだ。我々は斜面を下り、反対側の山の斜面に入り、林の中を歩いた。道はない。獣道らしきところを艾爺さんは自分の庭のように歩いていく。
だんだん近づくにつれて、唸るような音が聞こえてきた。人間が苦しんでいるような声に聞こえる。
「あの音はなんでしょう、なにかの動物が苦しんでいるような声だが」
「おらもわからんですな、初めて聞きます、このあたりには猿も熊もいますけんど、あんな苦しそうな声は聞いたことがないの」
「病気の熊でもいるのでしょうか」
「わからんな」
林の中を歩いていくと、その声が高くなっていく。
「ありゃ、枝が青くなくなっちょる」
私の目にも大きな老木が見えてきた。地衣類でもくっついているのだろうか。緑っぽい色をしている。枝の先に残っている葉はむしろ黄色い。だけど緑色の茸がなっている様子は見られない。
艾爺さんが早足になった。
「あっ」
爺さんが老木の周りを指さした。緑色の茸がごろごろごろごろ、ころがっている。
「みんな落ちちまったようだ」
その時、水楢の老木が軋んで、苦しそうな声というか音をたてた。若い頃喘息があった私は、吐く息ができず、ぜいぜいと苦し思いをしたときを思い出していた。
近づくと幹に付いている青っぽいものが明らかになった。
「ああ、なんじゃあれは、大きなクラゲがついちょるな、しかも青っぽいやつだ」
艾爺さんが大きな声を出した。
水楢の幹にあふれんばかりの薄緑の木耳がくっついている。しかも一つの茸は手の平より大きい。木の幹にぺらぺらと何重にも重なっている。
「な、なんだ」
艾爺さんが後ろに下がった。私も後ろに下がった。水楢の老木が揺れ始めたのだ。それに、水楢の木が苦しそうに唸り始めた。みしみしと音がする。
すると、幹についていたたくさんの薄青緑の木耳が幹に吸い込まれていく。やがて、幹からすべての木耳が消えた。
水楢の老木が大きく膨らんで、息を吐いた。はーっと、幹から白い蒸気のようなものが吐き出したのである。あたかもため息だ。その途端、枝の先から緑色の茸がでてきて、ブランブランとつり下がった。艾爺さんの言うとおり、水楢の枝に緑色の茸がなった。
「木耳が吸い込まれちまったら、青い茸がなりおった」
ところが、また、水楢の木が幹をよじった。
根元から薄緑の木耳が這い上がり始めたのである。どこから現れたのかと思って下を見ると、落ちていた緑の茸がぬるっと木耳に変わると、ぞろぞろと、水楢の老木に這い上がっていく。
「先生、ありゃなんだ、水楢が木耳に襲われているんじゃねえか」
「そのようです」
水楢の木は太い幹をよじって、木耳を振るい落そうとしているような振る舞いをしている。年取った水楢は枯れたくないのだ、木耳を吸い込んで、枝から茸にして外に放り出そうとしているのだ。
周りに落ちていた緑色の茸がすべて木耳になった。ぞろぞろと水楢の幹に這い上がり攻撃をしている。水楢は苦しそうに幹をひねる。木耳は上のほうに這い上がっていく。しかも木耳は途中で二つになり、大きくなりながら、幹をあがっていく。増えているのだ。
「こ、こりゃ、妖怪じゃ、木耳の妖怪じゃ」
そう言った艾爺さんに、木耳が一つ這い上がってきた。
「や、やめれ」
足にくっついた木耳を艾爺さんが払おうとしたが落ちない。私はそいつを持って思い切り引っ張った。爺さんのズボンが破れ、木耳をとることができた。手の中で薄緑の木耳がくにゃくにゃ動いている。
「先生、遠くへ投げれ、はやく」
私はその声であわてて木耳を林の中に放り投げた。
「妖怪じゃ妖怪じゃ、茸の妖怪じゃ、先生、逃げれ」
彼の声で、あわてて道を戻り始めたとき、水楢の木が「ぎゃー」という声とともに、悶えながら、崩れ落ち始めた。
我々は走って逃げた。
黒くなった水楢の木はバーンという音とともに崩れ落ち、あたりに土埃が立ち込めた。
我々が反対の山の稜線にたどりついたときには、斜面に緑色の煙が立ち込めていた。
「あの、化け物木耳のやつらは、胞子を飛ばしやがった、これからも古い水楢の木がねらわれちまう。
俺の茸の木が死んだ。木耳にすべてを吸い取られちまって」
艾爺さんは手を合わせ涙を流した。思わず私も手を合わせた。
それから、艾爺さんは黙ったままだった。我々はせっせと家に戻った。
家にたどり着くと、爺さんはなぜか急いで居間に上がって、「やっぱりだあな」と大きな声を上げて私のほうを向いた。
「先生、お湯を沸かすだ」
彼はそういうと、土間におりて、大きな鍋に水をくむと、流しの脇のガスコンロに載せ火をつけた。
私は居間に上がって、籠に入れっぱなしになっていた緑の茸を見た。どっさりと詰まっている緑の茸が透き通り崩れだしている。木耳に変わろうとしている。
それで艾爺さんがあわてたのである。
私は籠を抱えて、土間に下りた。かごの中の緑の茸が木耳の形になり、ぴくぴくと動き始めた。
「先生もうすぐ湧くが、間にあわねえ、もう入れちまおう」
艾爺さんの声で、私はあわてて、ガスコンロの上の大きな鍋の上で、籠を傾けた。手を入れて掻き出そうとすると、「あぶねえ、手をいれちゃいけね」
艾爺さんの声が飛んできた。
あわてて手をどけて、籠を逆さまにした。まだ湯は煮立っていない。茸は木耳に変わりながら、大なべの中でぽちゃぽちゃ蠢めいている。
お湯がぶつぶついってきたとき、青緑の茸が木耳に変化し、熱いためであろう、飛び上がろうと押し合いへし合いを始めた。一つの木耳が大きく飛び跳ね湯から飛び出ると土間に落ちた。そいつはぞろぞろと動いて、艾爺さんを目指した。私は、おいてあった丸太でそいつをつぶした。そのとたん「ぎゃあ」という声がでた。
湯が煮立ってくると、鍋の中の木耳たちが「ぎゃあ、ぎゃあ」と騒ぎだした。
「おっそろしい茸だで、化けもんちゃ」
私は目が信じられなかった。
「あの大木を殺しちまうくらいだから、よほどの時を経て、妖怪になっちまったにちげえねえ」
艾爺さんの言うことを否定できるかというと、今の自分には出来ない。目の前で茸が変化して木耳に変って動いている。しかし、後になってこの出来事をどう思うであろう。誰に話しても笑われるだけだろう。
鍋の中の木耳は赤くなって動かなくなった。
死んだのだろうか。
赤い木耳は、やがて黒っぽい、普通の木耳の姿になってしまった。どうやら、退治できたようである。鍋の中で木耳が煮立っている。
それを見つめていた艾爺さんが私に言った。
「先生、どうかね、この妖怪キクラゲを喰ってみるかね」
私が返事を返す前に、艾爺さんは酢味噌を作り始めた。
「あの水楢の供養だわさ、わしゃ喰ってやろうと思う」
そう言って、木耳をすべて酢味噌和えにしてしまった。朝作ったおにぎりを取り出し、酒まで出してきた。
「通夜だ、あの水楢の」
私ももらったおにぎりを取り出した。
もう昼をだいぶ過ぎている。
艾爺さんは「このやろう」というと、酢味噌に和えた木耳を箸で持ち上げると、口にいれた。
「お、うめえよ、先生」
私も箸で木耳をつまんだ。どこといって今まで食べたことのある木耳と味に違いは感じられなかった。ただ、今の今まで、ぎゃあぎゃあと蠢いた木耳である。美味しいと頭では感じられなかった。
「先生、水楢の木は木耳を退治しようとして、青い木耳を幹から吸い込んで青い茸に変えて枝に咲かし、下に落としていたんだ、それでエネルギーを使い果たしたんだね、がんばったんだよ」
私は頷いた。
「もうなくなっちまったから、青い茸には名前が付けられないが、つけるとすりゃあ、どんじ、かね」
「なんです、それ」
「どんぐりじゃなくて、ドン茸」
ちょっとすっきりしないと思ったのだろう、艾爺さんは苦笑いをして、「名前なんか付けなくてもいいか」と言って、箸で木耳をつまんだ。
「みんな食ってやる」
爺さんは酒を飲みながら、木耳をせっせと口に運んだ。
私は思い出した。
アイスボックスに緑の茸が一つ入っているはずである。それも木耳に変わっているのだろうか。研究室に帰ってから開けようと思う。もし中に入っているとすると、木耳に変っていようとなかろうと、茸に名前を付けることができるかもしれない。その時は、艾爺さんの思い出として、和名は艾茸にしようと思う。色もちょうどヨモギのような色である。
妖怪木耳の酢の物はまだ半分ほど残っている。私も箸で摘みあげると口に入れた。気持ちが落ち着いたのであろう、コリコリしていて確かに美味いものであった。
艾茸


