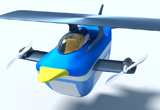タイプライター ――先輩後輩と、カチャリと音を立てる骨董品と。
――カタリ、カタカタ、カタタカタ……
人気のない、休日のミドルスクール。
放送室のドアの前。
室内から漏れ聞こえる、リズミカルな打鍵音。
ドアの前、ノックをしようと手を動かしかけたルーナは、微かに聞こえるその音に、そっと手を止める。
調子よさそう、あと少しかな。
書き上げるとき、センパイはいつもこんな音。
気付かないままに表情を変えながら、軽くコンコンと目の前のドアをノックして。ルーナは返事を待たずに、元気よくそのドアを開ける。
――カチャリ、カタタ、カタリ、カタカタ。
ドアの向こうには、いつものように、機械式のタイプライターを打つアウローラ。漏れ聞こえていた微かな音は、はっきりとした音となって、笑顔のルーナの耳に届く。
「こんにちは、センパイ! 調子、どうですか?」
そう明るく話しかけながら、ルーナは壁ぎわの折りたたみ椅子を「んしょ」っと両手で運んで、アウローラのすぐ隣に、自分の席を作る。
「もう少しね」
アウローラのやや低い、落ち着いた声。うーん、いつもながらクールでイイ声と思いながら、ルーナは自分が準備した椅子にちょこんと座る。
カタタと鳴りながら動く、古めかしい機械を眺め。
白い紙に打たれていく文字を目で追って。
印刷された文章をのぞき込もうとして……
「……ジロジロと見ない、いつも言ってると思うけど」
アウローラが、クールな表情はそのまま、手も動かしたままで。そっと横目でルーナを流し見る。それを見て、てへへと視線を逸らせるルーナ。そんな彼女の様子を視界の片隅に入れながら、アウローラは変わらずタイプライターの上で、手を動かし続ける。
打鍵するたびに左に動くローラー。チーンという音にアウローラは、慣れた手つきで改行レバーを掴み、ローラーを右側へと押し戻す。再び鳴りだすカチャリ、カタリという打鍵音。その音と共に打ち込まれていく文字。
その様子を耳で聴きながらルーナは、さてどう取りつくろうかと言葉を探すように、そのままあさっての方へと視線を泳がせる。
放送室の隣、ガラス越しに見えるスタジオ。月に数回、スクールバンドやコーラスクラブがレコーディングをするのに使う、がらんとした広い部屋。放送室には、ほんのりと間借りするように座る、普段通りに静かなアウローラと、今はちょっと静かなルーナ。
――ガチャカチャリ、カタリ、カタリ、カタリカタリと。規則正しい打鍵音と共に、静かに時間が流れていく。
◇
都会から離れた小さな離島にある、たった一つの中等学校。その学校にある、放送新聞部という部員数が6人のささやかな部。そこには、今となってはめずらしい、一つの機械がある。
――小型の機械式タイプライター。テコの原理を使って直接活字を紙に押し当てて印刷する、とても懐かしい印刷機械。
今となっては骨董品とも言えるその機械には、どこか懐古的な魅力があるのだろう。便利な個人端末を利用せず、この不便な機械を使って文章を書こうとするような部員が、たいてい一人はいる。
今は最上位学年となったアウローラもその一人。放送新聞部に入った直後に、そのタイプライターのこじんまりとした姿形を見てかわいいと触れてみて。いつのまにか虜になって。その時から今までずっと、使い続けている。
◇
全く、これで何度目かしらね。アウローラは隣に座るルーナに気付かれないよう、そっと様子をうかがう。……まったく、どうしていつも推敲前の文章を見たがるのか、それさえ無ければ良い子なのに。大人しくなったルーナを横目に、アウローラはリズミカルにタイプライターを打ち続ける。
「――ハイ、センパイ! 今回のお話、どんな内容ですか!」
ようやく言葉を見つけたのだろう、あらぬ場所から視線を戻して、なぜか挙手をしてから質問をするルーナ。そんな後輩の様子を少しだけ微笑ましく思いながら、表情はそのまま、アウローラは手を動かし続ける。
「掲載されたのを見れば?」
そっけなく答えるアウローラ。ルーナの少し不満げな様子を察しながらも手を止めずに、テンポ良く文章を打ち込んでいく。
思えば自分もそうだった、隣に座るかわいい後輩をちらりと見て、アウローラは思い出す。入部直後、タイプライターで打ち込む先輩を見て、憧れて、頑張って練習したことを。
……で、気が付いたらこの子じゃないと筆が進まなくなっていたと。そんなことまで思い出して、笑みがこぼれそうになるのをこらえる。
カーソルも無ければ挿入もできない。少し間違えただけでホワイトだ位置合わせだと、面倒なことこの上ない。本当、時代遅れで不便な道具よねと、自分でも思いながら。
それでも、この子じゃないと浮かばない文章があるのも確かで。――この深く沈み込むような文字盤と、活字を押し当てるときのカチャリという音には、きっと言葉をあふれさせるような魔法がかかっている。
そんなことを思いながら、アウローラは文章を打ち続けた。
◇
――カタカタ、タタタ、カチャリ、カタカタ。
そっけない返事もいつものこと。
ルーナの視線はアウローラの白い指先を追い。
――チーン、カタカタ、ガッチャン、カタリ。
隣にいるのはいつものこと。
アウローラは視界の隅に、ちょこちょこと表情を動かすルーナをおさめて。
やがて、文章を全て打ち終えたのだろう、アウローラは手を止めて、タイプライターから原稿を取り出す。
あとは、この原稿を顧問の先生に提出すれば、今日はおしまい。先生が推敲するのを待って清書しないといけないけど、それはまた今度と、アウローラは集中を緩めて、大きな吐息をほっと一つ。
「じゃあ、ちょっと行ってくるわね」
いつものように、職員室に行こうと席を立つアウローラ。あなたはどうするのと、無言でそっと視線を向けるアウローラに、今日はここでおとなしく待ってますと、軽く手を振るルーナ。
そんなルーナに、アウローラは一つうなずいて。
歩きながら、背中のルーナに軽く手を振って。
やがて、ドアの向こうに姿を消して。
小さな足音もすぐに聞こえなくなって。
――行きましたな。
しばらくして、アウローラが立ち去ったと確信したルーナは、独りつぶやいた。
◇
今まで何をしても、未完成の草稿を見せてくれなかったアウローラ。隣に座って覗き込もうとしては叱られ、真正面から手を合わせて、頭を下げて頼んでみても断られ、とにかく何をしても、アウローラは未完成の原稿をルーナに見せようとしなかった。
だが、ルーナは知ってしまったのだ。――アウローラは先生に出す原稿を打つ前に、「原稿の原稿」ともいうべき下書きを書くことを。そして、清書をする時には必ず、その下書きを机の引き出しの中に、お守りのように忍ばせているという事実を。
――ふっふっふ。つまりこの引き出しの中には、大量に赤ペンがはいった草稿が入っているはずナノダ!
そう心の中でつぶやいて。グフフと心の中で欲望の笑いをあげながら引き出しを引いて。目的のブツを手にしたその時。
「……ルゥーナァーさぁーんー?」
いつのまにか音もなく放送室の入口に立っていたアウローラ。その声にルーナは、鼓動を跳ね上げながら、反射的に立ち上がってしまうのでした。
◇
速足でツカツカと歩いてくるアウローラ。
じりりとあとずさり、壁に背を預けるルーナ。
なおも無言で近づいてくるアウローラに、ルーナは部屋のふちにまで追い詰められて。
それでも必死に逃げ道を探して。迫り来るアウローラの横をすり抜けようとするルーナ。その目の前に、勢いよく差し出されるアウローラの白い腕。
手のひらで壁を叩くようにふさがれる行く手。
鳴り響くドンという音。
その音にルーナは驚き、身体をこわばらせる。
そんなルーナの、気が付けばまるで両手で守るようにしっかりと抱きしめられた草稿に、正面から手を伸ばすアウローラ。
「ふぇっ! ……っと、ちょ、ちょっと、センパイ!」
その勢いに押され、バランスを崩して。背中を壁にあずけて、身体を沈み込ませて、それでもなんとか制止の声を上げようとするルーナ。
そんなルーナにアウローラは、焦ったような声を投げつける。
「このハレンチさんめ! いいから返す!」
そのまま尻もちをつくルーナの耳に入ってきた、予想外の言葉。その言葉に、ルーナは真っ白になる。
いやアナタ、さっきから超アグレッシブですよ?
ワタシ、タジタジですよ?
ナニカ、リフジンナコト、イワレタヨ?
……そんな釈然としない戸惑いのなか、なんだかよくわからないままに時間が過ぎて。
「まったく、油断も隙もない。――おかげで埃まみれになったじゃない」
気が付けば、あれだけしっかり抱え込んでいた草稿はアウローラの手に渡り。
立ち上がって、しわくしゃになったその草稿を小さく折りたたんでポケットの中に入れるアウローラ。その様子を見ながら、ちょっと放心状態から抜けきれないままに、ルーナは思う。
ソウネ、ユダンシテタヨ、ワタシ。
◇
すぐに戻ってくるからと言い残して、再び放送室を出るアウローラ。
まだまだポカンとしながら、大人しく椅子に座ってアウローラを見送るルーナ。少しして、今度は本当に原稿を渡しにセンセイの所に行ったらしいと察して、アア、バレテタンダと小一時間。
しばらくして、再び戻ってきたアウローラは、いつものように練習しよっかと、普段どおりにルーナに話しかける。
そうして、今度はルーナがタイプライターの前に座る。
普段は騒がしいルーナも、打ち始めはいつも静かで。
いつものように静かなアウローラに見守られて、ゆっくりと指を動かし始めて。
――カチャリ、カチャリ、……、…………、ガチャ、カチャリ……
たどたどしい、どこか初々しさを感じる打鍵音が、放送室に流れ始めた。
◇
「センパイの方が、よほど『はしたない』とオモイマス」
しばらくして。ようやくいつもの調子を取り戻したルーナは、先刻の騒動を思いだしながら、あえて軽い口調でそんなことを言う。
とっさに何のことかわからなかったのだろう、軽く首を傾げるアウローラ。ルーナも別に答えを求めての発言ではなかったのか、返事を待たずに、少し疑問に思ったことを聞いてみる。
「なんで見もしない下書きを、引き出しの中に入れておくんですか?」
「えっ? 下書きは、いつでも見れるようにするのが普通じゃない?」
「……センパイが下書きを見ながら打つところ、ワタシ、見たことないですけど」
「ええ、見せた覚えもないわね」
うん、ワカンナイ。質問に答えているようで矛盾しているその答えに、ルーナは理解をあきらめ、再び目の前のタイプライターに意識を向ける。
まあでも、あんな流れるように文章が出てくるのかも今の自分には謎で。それを知りたいから、自分も打てるようになればわかるかもと、今もこうやって練習しているのだけれど。
だからきっと、いつか知ることができるだろう。ルーナはそう思いながら。それでも、ついさっきの騒動を思いだして、思う。
――うん、あれはもう、あの時のセンパイはとっても「ふらち」でした、と。
壁ドンされて、押し倒されて。
胸に抱えてたはずの原稿を奪われた。
うん、間違いなくそんな流れだった。
思いだせる範囲の感触を思いだして、頬に熱を感じて……
――カチャリ、ガチャン! ……カチャリ、カチャリ。
思わず力がはいったのだろう、タイプライターからひときわ大きな音が鳴るのが聞こえて。思わず隣のアウローラの様子を確認して。その視線が変わらず自分の指先にあって、表情を見られていないことを確認して。
少しだけホッとして。
少しだけ寂しく思いながら。
ルーナは、そっと心を整える。
◇
私も初めの頃はこうやって教わってたっけ。
真剣に、真面目に入力を続けるルーナを見ながら、アウローラは思う。
私が先輩に教わったように。
ルーナが私に教わって。
きっと次の誰かもルーナから教わって。
学年が上がれば、私は卒業して、この子は残る。
そして、この子は受け継がれて。
そうやって、いつまでもこの子は使われ続けるのだろう、と。
◇
……きっと、ぜったい、センパイは誤解してると思う。けどまあ、それも良いかと、ルーナは思う。
センパイが卒業するまで、まだまだ時間もある。
センパイが「アグレッシブ」で「はしたない」ことも、ヨクワカッタ。
だからダイジョウブ、次はアワテナイ。ワタシはもっと上手くやれる。
そんなことを考えながら、ルーナは文字盤を打ち続ける。
――ガチャン、ガチャガチャ、カチャリ、カチャ……
そうして今日も、二人だけの放送室に、タイプライターの音がしばらくの間、鳴り続けた。
タイプライター ――先輩後輩と、カチャリと音を立てる骨董品と。
本作品は、「小説家になろう」からの転載です。
https://ncode.syosetu.com/n3321gv/