
くゆる朝灯
朝灯のかいじゅう 序章
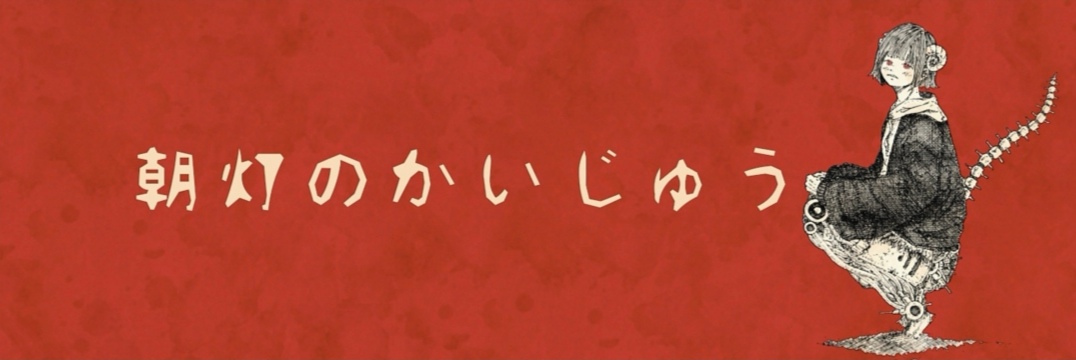
小さな梟は朝灯の周りを飛び廻る。
ぐるんぐるんと毎日忙しく飛び廻る。
昨晩だって小さく光りながら、西の空を飛んでいた。
朝灯はちょうど腹を空かせていたところである。
梟を見るや否やぶるぶると身を震わせて、一瞬間に弾けてそれを食らった。
梟はシャボン玉のように四散して、たちまち朝灯に呑まれゆく。
朝灯はぐんぐん膨れあがった。
鯨の群は逃げ惑う。
あちらこちらへ尾をなびかせて逃げ惑う。
それがてんでんばらばらに飛び回るものだから、たちまちぶつかり合って千切れゆく。
海鼠のような残骸を、朝灯は次々むさぼった。
そうして、ひと息ぼうっと火を吐く。
朝灯はぐんぐん膨れあがった。
目についたものを見境なくごくりごくりと呑み込んで、朝灯は真っ赤に燃え盛る。
この街を、この星をまるごと呑み込んで、僕らの知っていた景色はきっと焦げてなくなる。
そうして、いよいよ朝灯は腹を満たした。
すると今度はぎゅんと小さくなって、弱々しく光りながらうずくまる。
やがて光を失い、朝灯のかいじゅうは白くなって死んだ。
遥か数百億年後の話である。
くゆる朝灯


