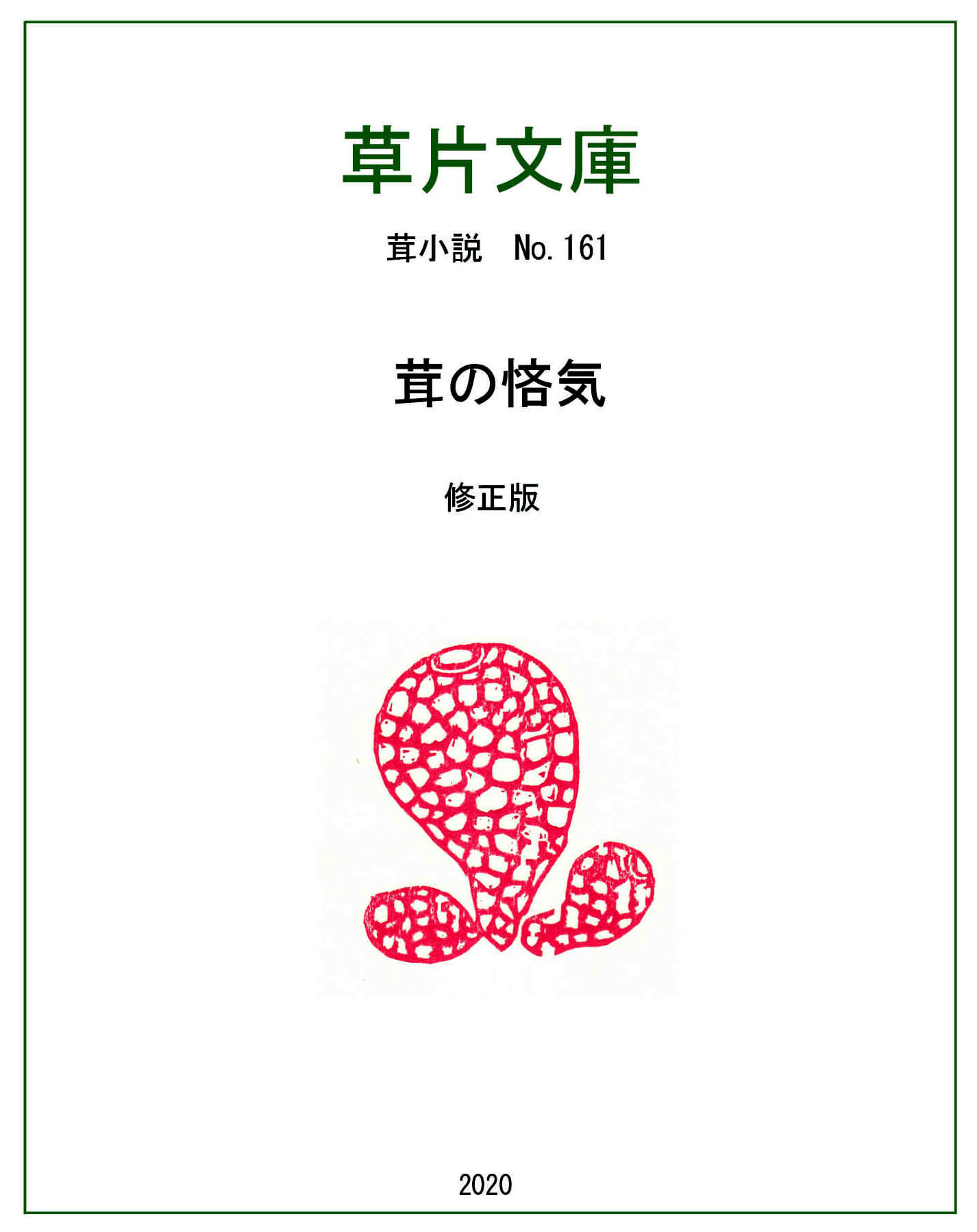
茸の悋気―茸書店物語7
茸のファンがジー、縦書きでお読みください。
昨日は珍しく、寄席に足を運んだ。本来はDVDで楽しむだけなのだが、新宿の紀伊国屋ホールに、雲助が出たからだ。NHKに日本の話芸という、落語や講談を聞かせる番組がある。再放送が土曜日の朝四時半という早い時間に始まるが、二時か三時に起きてしまう自分にとって、とてもありがたい番組である。そこで雲助の木乃伊取りという演目を聞いた。話も表情もうまい。生で見たいと思わせるものだった。紀伊国屋での演目は古典落語の悋気の火の玉である。本妻が妾を嫉妬し、五寸釘を藁人形に打ち込むが、妾もそれを知って同じことをした結果、効果が現われ、どちらも同じ日に死んでしまう。しかし、死んだ後も、本宅と妾宅から陰火、すなわち火の玉が飛んで、途中でぶつかり、火花を散らす。陰火は幽霊の出るときに飛ぶ火の玉、それで,火事になるとあぶないと、主人が二人の幽霊に謝るという話である。なかなかよかった。
若い頃、古典落語全集を持っていたが、今思うと惜しいことに、棚に入りきらなくなり、古本屋に売ってしまった。もう改めて買うことは無いだろう。
朝、新聞を開くと、語るというコーナーに柳家小三治の落語人生の文章が眼にはいった。もう五回目である。今まで気が付かなかった。小三治が影響を受けた落語家の話である。彼は上手いと思う一人で、筆頭にあげたい位の落語家である。上手というのは、いくら流暢でも機械のようにしゃべるのではそういえない。、話をする人間の個性が上手さを引き出すのであるから、機械では絶対にできない。落語は耳で聞くものというのは確かであって、ラジオから聞こえる落語も確かに面白い。しかし、DVDが出来て、身振り手振り、表情が加わって、面白さは倍増した。さらに寄席に行けば、落語家だけではない観客の反応、その場の匂いが、それにさらに刺激を加えてくれる。ノンバーバルコミュニケーションの重要性ということである。それはなにも落語に限ったことではない。
今日は、天気もいいし、久しぶりに神田に出る気になった。持っていた落語全集がなつかしくなって、ちょっと本の背でも見てみようという気になったのだ。
神保町駅の岩波ホールの出口を出て、御茶ノ水とは反対の九段下方面に少し歩くと、演劇や映画専門の古本屋、矢口書店がある。のぞいてみた。いくつか落語の本が並んでいる。自分の持っていた古典落語全集もあった。十数冊だったと思うが、全部で五千円の値が付いている。ずいぶん安くなったものだ。落語全集に限ったことではないが、単行本はなかなか売れないようだ。古本の世界で顔を利かせているのは、漫画本である。
ついでに、古本屋がたくさん入っているビルに入る。ここも久しぶりだ。昔はここで時間を潰したものだ、中野書店が何階か占めていて、いい本をたくさん置いていた。個性的な本屋もあった。成人向けの本を扱う本屋、子供の本屋、科学の本屋が入っていた。鳥海書房の図鑑類はすばらしいものがある。エレベーターを待っていたのだが、なかなかこないので、一階の中野書店の古書部をちょっとのぞいて出た。十一時半だ。ランチョンには空いているうちにと、いつも早めに行く。
ランチョンではハンバーグにライスをたのんだ。この店の定番メニューだ。ハンバーグそのものもだが、かかっているソースが美味しい。今日はさっとそれを食べて、草片書店に行くことにする。次の語草片叢書が出ているはずである。
紅天狗茸の描かれている扉を開けると、笑子さんがデスクに座っていた。私を認めると、立ち上がって「いらっしゃいませ」と声をかけてくれた。
「出てますよ、先生」
出てますよは「語草片叢書」のことだが、なぜ先生と呼ばれたのか分からなかった。
いつもの、茸の地方紙のところにいくと、語草片叢書、第七集として「茸の悋気」がでていた。
茸が嫉妬する話だろう。面白いタイトルをつけるものだと、手に取った。それにしてもここのところ、悋気ずいている。
筆者は千葉在住の人のようだ。
笑子さんが「先生、千葉には茸の愛好家がたくさんいるのですよ、そこに、愛好家の会報があると思うのですけど、房総の茸って言うのがあるでしょう、それに、県の博物館などで、茸関連の展示会や、説明会がたくさん開かれているのですよ、今も、千葉県立中央博物館では、きのこワンダーランドといって、展示をしています。もちろん科学的な部分と、その博物館で集めている、西欧の昔の茸の本が展示されていますわ」
なかなか面白そうだ。
私は「茸の悋気」をデスクに持っていった。表紙の絵は、紅天狗茸と天狗茸、それに真っ黒な天狗茸が描いてある。
「ありがとうございます、先生」
笑子さんが受け取って袋に入れようとしたとき、気になったのでちょっと言った。
「あの、先生と呼ばれるような者ではないのですけどね」
「あーら、昔、エッセイでいろいろな賞をとっていらっしゃいますね、お名前をうかがって、ネットで引いたらずい分出てきました、旅のエッセイの一人者でいらっしゃる」
確かに、昔はそんな賞もずい分もらった。しかし、それだといって、生活の足しになるわけではないし、本を出してくれるようなところもそんなに無かった。出版した単行本は十数冊である。雑誌の編集長ならば、たくさんの著書があるはずだが、数からいえば少ないほうだろう。ただ、彼女が言ったように、その本の半分以上が、地方のものが多いが、賞をいただいている。ただ旅を正直に書いただけなのであるが。
「おはずかしい」
「茸の話は書かれなかったのですね」
「ええ、全くありませんね、今思うと惜しいことをしました。いいテーマですね」
「はい、いつか書いてください」
「もう、年ですから」
「書くのに年は関係ありませんわ」
確かにそうだが、それが活字になるかどうかの問題である。
「茸の面白い本はありますか」
最近、茸の本にかなり興味をもってきた。
「新しい本で、奇妙な菌類、という本があります、白水貴という若い方が書いたものですけど、今までにない、不思議な茸が紹介されています」
ということで、専門書のところにあった、NHK出版のその本も買った。
「またおいでください」
笑子さんの声に送られて草片書店をでた。
地下鉄の電車の中で奇妙な菌類を開いた。口絵に珍しい茸や綺麗な茸の写真が載っていて見ているだけで楽しい。かなり専門的な本であるが、分かりやすく書いてある。その中でも茸が花に化けるという項目があった。生きている植物に寄生している菌で、菌が誘導して、その花とは違う花を作らせてしまう。作られた花は他の植物の花と似ていて、その花に行くはずの昆虫が間違って飛来し、花粉ではなく、菌の生殖細胞をくっつけて、飛んでいく。昆虫は他の贋の花に止まって、配偶子を菌の作った菌糸に渡し、胞子をつくる。とんでもない仕掛けをすることで、自分の子孫を残す菌である。要するに、昆虫をだまして、自分の配偶子を運ばせてしまうのである。外国にいるらしい。
分からないところは読み飛ばしていくと、いつの間にか自分の降りる駅に着いてしまった。面白い本である。
語草片叢書は夜、寝ながら読むとしよう。著者は千葉の茸の同好会に所属している人のようだ。
「茸の悋気」
千葉は海に面している歴史のある地域である。海の幸が豊富であることは誰もが知るところであるが、渓谷もあり、山の幸も豊富である。もともと、椎や樫の木が生えており、里山ではいろいろな茸がとれる。
どういうわけか、今でも茸の好きな人が多く、県の博物館では茸の古い図鑑を集めているし、茸の研究の部門もあり、毎年大きな茸展を開いている。茸の観察会なども秋にはよく行なわれている。
私自身は茸のことをよく知るわけではないが、興味はあるので、一つの茸同好会に入っている。しかし、周りの会員のように、極端なマニアではない。ではなぜ、茸の同好会に入っているかというと理由がある。
私のもう一つの趣味として、古い文献や本には大いに興味を持っており、古い文字を解読して楽しんでいる。大学時代、古代文字の研究室にいたことがあり、卒業研究に平安時代の文献を取り上げたことから、辞書など片手に少しは読むことが出来る。
私の家が大昔、大きな醤油屋であったところから蔵がある。しかしこれも随分昔に廃業している。蔵はその時点で書庫として使われることになったようで、預かり物らしい書物類が無造作に棚に置かれている。その中に、茸の書かれたものがいくつかあり、それを読み解く楽しみから、そのためには、本当の茸のことを知らなければならないと思い、同好会に入ったわけである。
最近蔵の中から見つけた一冊の本が、万葉仮名で書かれた茸の本であった。万葉仮名は平安時代には使われており、ひらがなの元になったわけなので、この本が平安時代のものだとすれば、とても貴重なものである。書の題名は「君草妣楽香田里」とあった。漢字そのものに意味がないとすると「くさびらかたり」となるのだろう。それで、これは面白いと思い、大学に残った知人に見てもらうと首をひねった。本の紙が新しいというのである。平安時代のものであれば文化財として大変なものになるが、紙は江戸時代のもののようで、江戸時代の物好きが昔のもののように書いたのではないかということである。さらに、草片という言葉は平安時代には無いと指摘された。その言葉が出てくるのは室町だそうである。確かに、狂言のくさびらや独りまつたけなどの演目は鎌倉時代に作られたものである。
それにしても、このようなものが書けるということはかなりの知識人だったろうという。むしろ書いた人を特定すると、江戸時代のとんでもない人であることが判るかも知れない、と知人は言っていた。
ともあれ、私はその本を、こつこつと読み解いてみた。内容は、茸の世界が面白く書かれており、その中の一つの話を今の言葉に置き換えて、さらに私の注釈も加えながらここに紹介したい。
昔昔の話である。
草片の森と呼ばれる、緑豊かな山の中に、赤いべべを着た女童(めのわらわ)が、女官に付き添われ、遊びに来た。宮中のお姫様のようである。草片の森には様々な生きものが生活をしていた。その中心は茸である。その頃、茸は禽獣であった。草でも、木でもなかった。
禽獣とは動物のことである。草は話が出来なかったが、禽獣は吠え、鳴き、話すことができる。茸は草のように動きは遅いが、話が出来た。それで、人は茸を禽獣と思っていた。しかも、ヒトの友として存在していた。
「あの赤い茸とお話がしたい」
女童は孔雀羊歯の脇に生えている赤い若い茸を指差した。おそらく、紅天狗茸の子供であろう。
「姫様、あの赤い茸ですね」
女官が赤い茸に近寄ると、
「姫君が話をなさりたいとおっしゃっておる、よかったのう」
そう言って、赤い茸の傘に人差し指をのせた。子供の頭をなでて、可愛がるのを、茸に対しては指を傘にのせるのである。
女童がそばにくると、女官と同じように、赤い傘に人差し指をのせた。
「かわゆいのう」
女童が赤い茸に話しかけた。
「ありがとうございます」
孔雀羊歯の下の赤い茸は傘に女童の指がのったものだから、茎中しびれていた。気持ちがいいのである。
それを蕨の陰から見ていた赤い茸は、「私の赤のほうが綺麗だろうに、なぜ指をのせてくれぬ」そう、隣に生えていた黄色い茸に言った。この赤い茸は紅茸の子供で、紅天狗茸より少し年上のようだ。
黄色い茸は、小金茸の子供で、よくわからず頷きはしたが、ちょっと、傘を揺すっただけだった。何しろ、いきなりいわれたのもあるが、この黄色い茸も紅天狗茸のほうが綺麗だと思ったのだ。紅茸はかなり自意識の強い雌茸だなと思ったのだ。黄色い茸は、赤い茸より後に生えたことから、まだ若い雄の茸である。もちろん紅天狗茸は雌である。
草片の森の茸には雄と雌があったのである。
女童は立ち上がって、「もう少し歩きたいのう」と、女官を連れて、森の道を奥に向かって歩いて行ってしまった。
その森には、このようにして、ときどき人間が入ってきて、茸に話しかけるのである。
もちろん、ヒトだけではない、様々な禽獣が森の中を歩いていた。
女童が立ち去ると、蜥蜴がやってきた。茸たちはこの蜥蜴も好きである。ときどき、二本足で立ち上がると、傘の上に顎を乗せて、うっつらうっつらするのである。そのような時、傘にのっている顎が、茸たちをしびれさせる。
蕨の下の紅茸のそばにやってきた。
「蜥蜴の兄さん、顎を乗せておくれや」
紅茸が声をかける。
「どうかな」
蜥蜴は二本足で立ち上がると、手を紅茸の傘にかけた。
「ちと硬いのう」
顎を乗せるには調度いい硬さがあったのだ。雄の蜥蜴は紅茸の隣にいる黄色い小金茸を横目で見て、通り過ぎた。雄の蜥蜴は雌の茸の傘で居眠りをする。
蜥蜴は孔雀羊歯の脇の赤い茸のところにやってきた。紅天狗茸だ。
蕨の紅茸が見ていると、蜥蜴は立ち上がって、紅天狗茸の傘に顎を乗せた。
「何さ、あの蜥蜴、茸の良さをわかってない、とんちきだ」
紅茸がそういうのを、小金茸がおやまあ、というふりで聞いていた。
蜥蜴がしばらくそうしていると、紅天狗茸の傘が小刻みに震えた。あまりの気持ちのよさに、からだが我慢しきれなくなって震えたのだ。その震えが、蜥蜴にとってたまらなく心地よいのである。
しばらくすると、蜥蜴は青い尾っぽを揺らしながら、紅天狗茸から離れていった。
紅天狗茸は気持が良かったと見えて、すーすーと寝息を立てている。そこへ、雌の赤座頭虫と雄の赤座頭虫が仲良く、下草の間を歩いて来た。ゆっくりゆっくり、長く折れそうな前足を前に突き出し、確認をしながらやってくる。
座頭虫の旦那は寝ている紅天狗茸の子供を見ると
「かわゆいの」と前足の一本を、傘の上にかけようとした。
「おやめよ、おまえさん、寝ているじゃないか」
「そうだな、目が覚めてから、可愛がってやろうかね」
「そうおしよ、ほら、蕨の下にも赤い茸がいるよ、こっちを見ている」
おかみさんの座頭虫が紅茸の子供に気がついた。
「いってみるか」
夫婦の座頭虫が紅茸の子供に近づいて来た。ゆっくりゆっくりと、時間がかかる。紅茸の子供は、早く来ないかと、いらいらしている。
「おや、黄色い雄の茸もいるよ、小金茸じゃないか」
おかみさんの座頭虫が小金茸の傘の上に細い足をのせた。
座頭虫の細い足が傘の上にのると、茸にとって、これまた気持ちが良いのである。小金茸の子供は大喜びで、傘を震わせた。
それじゃあ、俺もと、座頭虫の旦那が長い前足を持ち上げたとき、
「あーあ、気持ちよかった」という可愛い声が聞こえた。
孔雀羊歯の脇の紅天狗茸が目覚めたのだ。
それに気がついた座頭虫は、あわてて振り上げた前足を、土の上に降ろすと、ささささと紅天狗茸のところに走っていった。座頭虫はとても早く走ることもできる。人間の目にはとまらないほどである。
紅天狗茸の傘に座頭虫の旦那が足を軽く乗せた。この細い足で傘をつつかれると、茸は失神してしまうほど気持が良くなるのだ。
「あれー」紅天狗茸の子供は気持が良くて、もう何もわからなくなってしまった。
それを見ていた紅茸のこどもは、
「きーーい」
と、ぶるぶる傘を震わせた。怒るとぶるぶると傘が動く。
それを見ていた、座頭虫のおかみさんがびっくりして、
「おー、こわ」と、小金茸から離れてしまった。それでも、小金茸のぼおやはとても気持ちがよかった。
こうして、その日は終わった。
茸たちは一晩経つと大人になる。
次の朝になると、孔雀羊歯の脇の赤い紅天狗茸は背が高くなり、羊歯よりも上に頭をだし、妖艶さがでてきた。蕨の脇の赤い紅茸は、背はあまり伸びなかったが、傘が横に伸び、大きな茸になった。その脇の黄色の小金茸は、これまた立派な背の高い青年になった。
青く輝く雄の蜥蜴がやってくると、「紅茸さんも、大きくなったね、いい子だ」と、蕨の脇を通り越すと、孔雀羊歯の脇にいった。
蜥蜴は「おー、こりゃすごい迫力だねえ」と紅天狗茸を見上げた。もう、背が高いので、顎を傘にのせることは出来ない。
「お上がんなさいな」
紅天狗茸が声をかけると、青く輝く蜥蜴は傘の上によじ登った。紅天狗茸は傘の白いぼちぼちで蜥蜴の腹をくすぐった。
「ほー、たまらんね」
気持ちの良くなった蜥蜴は紅天狗茸の傘の上で、しばらく日を浴びた。
それを見ていた紅茸は、「全く、あの蜥蜴は本当の茸を知らないやつよ」とそっぽを向いた。
ふと隣の黄色い茸を見ると、ずい分立派になった。
「おや、なかなかの美男子になったね」
それを聞くと、雄の小金茸は恥ずかしそうに俯いた。とってもうぶな雄の茸だ。
それを見た紅茸は、ぽっとさらに赤くなった。どうも小金茸に懸想したようだ。
「どうだい、あたしと付き合わないかい」
紅茸が小金茸に声をかけたのだが、小金茸はまだもじもじしている。
そこに、座頭虫の夫婦がやってきた。
「茸がみんな大きくなって、立派だね」
座頭虫のおかみさんが、小金茸の傘の上に二本の前足を両方とものせると、からだをゆすった。小金茸の傘が前後に揺れた。小金茸は気持が良くなり、傘を少しばかり開いた。これで、小金茸はやっと男になった。
座頭虫の旦那は「紅茸も大人になってきたのう」と言いながら、紅茸の脇を通り越して、孔雀羊歯のところに行った。すっくと立っている紅天狗茸の傘の上では青く輝く蜥蜴が寝ている。
「おいおい、そろそろ起きて、飯でも食いに行きな」
座頭虫の旦那は、傘の上で日の光を浴びていた蜥蜴を前足で揺すった。
「おー、座頭虫の旦那も、紅天狗茸がお気に入りかい」
蜥蜴は、目をこすりながら紅天狗茸を降りると、「紅天狗の姉さん、それじゃ、また」と食事にでかけた。
「座頭虫の旦那さん、お願いしますよ」
紅天狗茸がしなを作った。
座頭虫の旦那は両方の前足を傘にかけると、からだを揺すった。紅天狗茸が前後に揺れて、「あー」という、紅天狗茸のため息が聞こえた。紅天狗茸の傘が少し開く。ますます妖艶な茸になった。
それを見ていた、紅茸は「ちくしょう」と、紅天狗茸を、遠くからだが睨みつけた。
それを聞いた、座頭虫のおかみさんが「怖い茸だね」と小金茸の傘から前足をおろすと、すたこらと、その場から旦那のいる紅天狗茸のほうに逃げていってしまった。
紅茸は小金茸にむかって、「なんだい、紅天狗茸より、あたしの傘の方が立派だろう、そう思わないかい」と、赤く広がった大きな傘を広げた。
確かに、立派な傘だと思ったから小金茸は、うんうんと頷いた。
「そう思うだろ、あんたはいい男になったね」
紅茸は小金茸にますます好意を強くした。
座頭虫のおかみさんは「あんた、いくよ」と、紅天狗茸を揺すっていた旦那を連れて、食事をしに行ってしまった。
気持が良くて傘を開いていた紅天狗茸が目を開けると、蕨の脇の小金茸が眼にはいった。
小金茸も紅天狗茸が自分を見ていることに気がついた。
小金茸は「紅天狗茸のねえさん、きれいだね」と思わず声を上げた。ちょっとそう思ったからそういっただけなのだが。
「お前様も、素敵でござんす」と紅天狗茸が応じたものだから、小金茸は紅天狗茸のとりこになっちまった。
さて、紅茸の心中は大変なことになっていた。
あの紅天狗茸のやつ、生意気に、なんとかしちまいたいと思っていたのだが、手だてが無い。
そう思って、紅茸がうじうじしている時、草片の森に、また女童が女官を連れて遊びに来た。
「おとついの赤い茸がこんなに大きくなった」
「そうですね、姫様、お話し相手になさいますか」
「うん、それにあの黄色い茸も」
女童は蕨の脇からすっくと立っていた小金茸も指差した。
「はいはい、帰りに連れて行きましょう」
この世では、人間たちの間では、綺麗な茸を自宅に採って帰ると、鉢に植え、萎れるまで、お話を楽しむということをしていた。その習慣はやがて、茸があまりにも可愛らしいので、食べてしまいたくなり、人間は茸と話をし終わると食べるようになった。そのようなことから、今の人間は茸を食べるものと間違った認識を持つようになったのである。
「あら嬉しいね、黄色い茸のお兄さんと一緒に、連れて行かれるのよ」
紅天狗茸が小金茸に言った。人間に話し相手に連れて行かれるのは大変名誉なことだったのだ。小金茸も喜んだ。
紅天狗茸は小金茸と傘を震わせて、気持ちを通わせた。相思相愛になったのだ。
紅茸は振られた上に、紅天狗茸と小金茸が人間に選ばれたことに怒った。特に恋の相手の小金茸を持って行ってしまうとは何てことだろう、何か言い手がないか、考え続けた。
そこに、斑猫(ハンミョウ)がやってきた。青と赤の綺麗な虫だ。虫の癖に虫を食べる。
斑猫は紅茸の脇を通ると、そそくさと食事を探しに歩いて行ってしまった。
「挨拶ぐらいしろ」
いらいらしていた、紅茸は斑猫に八つ当たりした。
そこへ、豆斑猫がやってきた。豆斑猫は斑猫の親戚だが、色は地味な黒っぽい虫である。ただ、触るとかぶれる毒をもっている。
紅茸の性格はずい分捻じ曲がっていたものだから、変なことを思いついた。
「豆斑猫のだんな、孔雀羊歯の脇の紅天狗茸がこんなことを言ってましたよ、斑猫は綺麗なのに、豆斑猫はなんて地味でつまらない、なんてね、わたしゃそうは思いませんよ、黒くて男らしいと思ってますよ」
それを聞いた豆斑猫は、その話を真に受けた。
「けしからん茸だ」
「そうですよ、あいつに、毒を注入しておやりなさいな」
ちょっとばかり怒った豆斑猫は、紅天狗茸の幹に毒を注入した。
紅茸はこれで小金茸を独り占めできると思ったのだ。
女童と女官が戻ってきた。
「それじゃ、この赤い茸とあの黄色い茸を話し相手に連れて行きましょう」
「採っておくれ」
「はい、お姫様」
女官が手を伸ばした。採ろうと紅天狗茸に触れると、手にぶつぶつができた。
豆斑猫の毒はカンタリジンといって皮膚にできものをつくる。
「姫様、この茸は毒があります、話し相手にはできませぬぞ」
「綺麗なのじゃがな」
女童は残念そうである。
「また、明日、別の茸をさがしましょうね」
女童と女官は去っていった。
紅茸はざまー見ろと笑った。
ところが、紅天狗茸は小金茸に「私がこんなになってしまったので、お前さんまでも人間の話し相手になれなんだ、すみません」
あのしゃんとしていた紅天狗茸が急にしおらしくなってしまったのを見て、小金茸は「いえいえ、姉さんが悪いのじゃない、これから一緒に胞子を飛ばそうではありませんか」と言った。
一緒に胞子を飛ばすと言うことは、二人でいつまでも暮らそうということである。
紅天狗茸と小金茸は、傘を膨らませ、ひだの間から、胞子を空に撒き散らした。胞子を撒く時、茸は恍惚になる。
それを見ていた、紅茸はますます怒り狂い、とうとう、胞子を飛ばすことなく萎れてしまったのである。
このようにして、紅茸の悋気が、紅天狗茸を毒茸にしてしまった。
しかし、紅天狗茸の毒は違うものにかわっていき、人の心に影響を与えるものになった。この話を知ってか知らないかは分からないが、あるところでは、毒をもつにもかかわらず、紅天狗茸が幸福の象徴として考えられているのである。
これを読み終わって、大変面白い話しが伝わっているものだと、感心したと同時に、この原本を見せてもらいたくなった。
また、草片書房に電話をすると、笑子さんが親切にも電話番号を教えてくれた。
私が電話をかけると、筆者は「お見せしてもかまいませんが、遠くまで大変ですよ」と、千葉の家に行く方法を教えてくれた。著者は野田さんと言った。三日後に会う約束をした。
東京駅から総武線快速に乗り、津田沼で降りてタクシーで野田さんの家に行くと、古い門構えで、中は広大と言っていいほどの庭であった。いくつもの古い蔵がある。
背の高い男性が玄関に出て来た。白いひげをはやしている。それが野田さんだった。
「遠いところまで良くいらっしゃいました、どうぞ、お入りください」
立派な邸宅である。黒光りした廊下を行くと、しゃれた客間に通された。
「すばらしいお家ですね」
「いや、古いだけですけど、先祖が頑張ったお陰です」
野田さんは謙虚である。古いソファーに私は腰掛けた。
彼は書庫から、一冊の古びた和書をとりだし、私の目の前に置いた。茸の悋気の文章が入っている原本のようである。
私はそれを手にとって、中を開いた。確かに万葉仮名で書かれたものである。
しかし、私はふと、奇妙なことに気付いた。墨の色がどこか新しいような気がするのである。古い本を開いた時の匂いが無い。墨のかすかな匂いがしたようである。数百年前の本であるなら、墨の匂いはしない。古書の匂いがする。
どこか、腑に落ちない面持ちでいると、野田さんの顔が笑っている。
私は思い切って言った「紙は確かに江戸時代のもののようですけど、墨が匂います」
そこまで言うと、「先生には嘘はつけませんね」と彼は口を開いた。
「草片書房の笑子さんから、文筆家であることをうかがっています、だから、すぐ分かってしまうだろうとは思っていたのですが、こんなに早く分かってしまうと思いませんでした」
「野田さんが書かれたものですね」
「その通りです、全くの創作です、笑子さんが、それでよいと言ったので書かせてもらいました、茸が好きであることは確かです、それに、万葉仮名も少しは分かるので、このような遊びをしてしまいました、すみません」
野田さんが頭を下げた。
「いや、謝っていただこうなんて思っておりません、とても面白い創作でした、サインをお願いしたいと思って、持って来ました」
茸の悋気の小冊子をバックから出した。
「サインですか、字が下手で、恥ずかしいのですが」
そういうのを押し切って、サインをもらった。
それから、しばらく、野田さんの祖先のことや、千葉の茸の話しをして、おいとまをした。わざわざ千葉まで行った甲斐があった。
いい一日にだった。
茸の悋気―茸書店物語7


