
扉のない中庭
サラサフロラ 作
書肆彼方 編
I will give my love an apple without e'er a core,
I will give my love a house without e'er a door,
I will give my love a palace wherein she may be,
And she may unlock it without any key.
My head is the apple without e'er a core,
My mind is the house without e'er a door.
My heart is the palace wherein she may be,
And she may unlock it without any key.
——英国の古い歌
干しわらになった王子さま

一 はじまり
むかしむかし、深い山あいの水鳥たちだけが知る美しい湖のそばに、ひっそりとそびえるお城がありました。まわりの国から知られず、兵士や従者もいない名もなき小国は、いつも手をつないで歩く、仲むつまじい王さまと王妃さまがおさめ、それはそれは優しく、民から父母のように慕われ、みんな楽しく暮らしていました。
王さまと王妃さまには小麦色の髪に青い瞳の元気な男の子がひとりおりまして、王子さまはまいにち、町の子どもたちと一緒に山をかけまわったり、湖でおよいだりして遊ぶのでした。
二 王さまのなぞかけ
晴れたある日の朝。王子さまはヒヨドリのさえずりでぱっちり目をさますと、寝床からとび起きて顔を洗い、パンをほおばりスープをかきこみます。イスをひいて食堂を飛びだそうとするやいなや、父から執務室にくるよう呼びとめられてしまいました。
「ちぇっ」王子さまは舌打ちをして、「父上のようじをさっさとすませて川で葉っぱ流しをしよう。きのうはヘレムの葉っぱがいちばんだったけど、夜にとっておきの舟を思いついたんだ。きょうこそ勝ってやる」と、はやる気もちをおさえ、いそぎ足でむかいました。
湖を一望できる回廊をぬけ、黒ぬりの大きな扉で立ち止まると、かるくせきばらいをしてからコンコンたたき、「王よ、まいりました」。このときだけは父ではなく王だとわきまえておりますので、背すじをピンとのばし、すこしばかり落ちついた声です。
「はいりなさい」
王さまの呼びかけに応じて王子さまは肩をそびやかし、部屋に入りました。
しけた紙のにおいのする執務室は、いかにもむずかしそうな本が本棚にずらりとならべられ、レリーフのほどこされた大きなつくえの上に山とつまれた本は今にもくずれ落ちそうなほどです。
王子さまはすきまからあちらをのぞくと、王さまは考え深げなようすで手紙をしたためています。
——ほかの国と交流はなく、国にあるたったひとつの門をくぐるものすらほとんどいないのに、いったいどこのだれにあてているのだろう——王子さまはふしぎに思いました。
「おまえを呼んだのは」と、王さまは鵞ペンをつくえにおきます。「息子よ。おまえに探してきてほしいものがある」
勇猛で威厳あるライオンのような低い声、先を見通すワシのようにするどいまなざし。王子さまはそんな父が大好きでした。なにより父のような王になりたいと願っていたのです。
「王よ、わたくしになにを探せというのでしょうか」
「うむ。それは、『芯のないりんご』『扉のない家』『鍵のいらない宮殿』を」
王子さまはすこし考えてから、いぶかしげにたずねました。
「わたくしをためすなぞなぞですか?」
「そのようにとってかまわぬ。おまえが山あいの国王としてほんとうにふさわしいのか」
王さまの言葉に王子さまの心はふるえます。
——父はわたしを将来の王として見てくださっていたのか。子どもではなく、りっぱなおとなとして父のきたいにこたえ、民の希望とならねば。
「わが王よ。あなたの目にかなうものをかならずやお見せいたしましょう!」
「おお、よくいってくれた。ではさっそく明日の朝、出発するように」
「おおせのままに!」
王子さまは目をかがやかせ、自信たっぷりにそうこたえると、部屋からでていきました。
いまやもう友だちと遊ぶことなどすっかりわすれて、父からあたえられた試練をのりこえるため、すぐに出立の準備をはじめます。そんな王子さまの背中をながめる王さまと王妃さまは後悔したような、さびしい顔をするのでした。
つぎの朝。雲ひとつない空のもと、王子さまはたくさんの食りょうと水をつめた大きな布袋を荷鞍にのせて白馬にまたがると正門をくぐり、国の外へと旅立ちました。母からはなにかあった時のためにと、赤い宝石つきの金の指輪を首かざりに、父からはひとふりの青い剣を腰に。
「希望をもって国をあとにし、栄光をもってむかえられよう」
威勢のよい声をあげ、王子さまの長い旅がはじまりました。
三 王子さまの旅路
山あいの国をたち、田舎の村からはじまり、街にでてやがて大都市へ。国の外を知らない王子さまにとって、目にうつるすべてのものは新しく、たくさんのことを知りました。世界は広く、故郷はちっぽけなこと。歓待される時もあれば、うとまれる時だってある。美しい景色に目頭を熱くし、みにくい光景に顔をそむける。どしゃぶりの雨に打たれ、ふきつけるつめたい風に体をガタガタふるわせ、なにより、ひとりがどれだけつらいか。洞穴に身を横たえ、広がる紫紺の地平線をながめ、ちらばる星くずの夜空に祖国への思いを馳せました。
「わたしを知るのは旅をともにする白馬だけ」
長い旅の果て、もの知りが住むという話を聞き、荒野にむかいました。そこは陽の光でまっ赤に染まることから血の荒野と呼ばれ、何百年もまえに興亡し、人々からわすれられた都市の廃墟がありました。
遠くに立ちのぼる、ひとすじの白煙を見つけた王子さまは馬をおりてちかづきます。「はじめまして」と、たき火のまえで腰をおろす、ボロをまとった老人に話しかけました。
「わたしは遠くの地からやってきた旅人です。あなたの深い智恵についてうわさを聞いております」
老人はうつむいたまま少年など目もくれず、パチパチとはぜる火に木ぎれをくべます。
「あなたにうかがいたいのです。それは……」
「ここからさらに東……」と、老人は王子さまの言葉をさえぎります。「金色の小麦畑にある白い壁、黒い屋根の風車に知りたいものはあるだろう」
「なぜ、わたしが話すまえにすべてわかるのですか」
「風はどこからふくのか、だれが知りえよう。ただ行くべき先にのみ目をむけよ」
王子さまは老人に感謝をつげ、残りの金と食べ物や水をわたし、こう言いました。
「旅の成功に、どうかあなたの秘密についておしえていただきたい」
「さて、おまえにできるかな」老人はニヤリと笑いました。
東にむかって馬を駆り、しばらくして見わたすかぎり金色の小麦畑に、ぽつりとたつ風車が見えました。老人の言葉のとおり、白い壁に黒い屋根です。まちがいありません、ついに目的地にたどりつき、試練の旅はむくわれたのです。
王子さまの胸は高鳴りました。そう、たしかにこの時までは。
四 東の風車
ゆっくりとまわる大きな羽根のぶきみな姿におののきながら、王子さまは馬をおき、風車の中へ入りました。
ゴオンゴオン……ギギギギー。部屋中、きしむ音やたたく音はやかましく聞こえますが、人の姿はありません。
「老人はこの風車について語ったのだろうか」
王子さまはしんぱいそうに室内をあちこち探し、やがて地下につづく階段を見つけます。階段をおりて閉じられた木扉につきあたり、はずれかけのくすんだ金の把手に手をかけました。蝶番はこすれたにぶい音を鳴らして開き、うす暗い部屋へゆっくりと慎重に進みます。
「ここはなんだろう。麦を備蓄する納屋、あるいは倉庫か……」
ほこりのまうカビくさい部屋を見まわしていると、ばたん! 背後のたたきつけるような音に、なにごとかと思わずふり返ります。
はたといそぎもどりノブに手をかけ、ぐいぐい押したり引いたりしますが、扉はビクともしません。
「だれかむこうから鍵をかけたのか? いや、風でしまり錠はひとりでに……そんなはずは」
ただならぬ空気を肌で感じた直後、背に強烈な気配。自然と右手は腰にさがる剣にふれ、すばやく見返ります。
「だれだ? いるのはわかっている」
しんとした部屋に、ひゅうとかわいた風の音。うっすら灯火はあらわれ、王子さまは呼吸をととのえてから、そろりそろりと進みました。すると灯火は奥にむかって、順に灯ります。
——いったい何者が?——そう疑問に思うやいなや部屋全体はぱっとあかるく照らされます。風車の地下納屋は一転して、てんじょうは高く、中央に石づくりのりっぱな座をかまえる壮麗な王の間にかわっているではありませんか!
立ちつくす王子さまはおどろきと不安を感じながらも、けっしておもてにだしません。どんな時でも静かな威厳をたもつよう父からおしえられていたからです。
「わたしは遠い地から王の命によりつかわされたものである。あなたに聞きたい!」
はりあげた王子さまの声は部屋中にこだまします。
「……なにも……わかっていない……」
ひやりとつめたい風のような男の声。王子さまは形なき姿をとらえようと、するどい眼光で周囲を見ます。
「どこにいるのか!」
「おまえはなにも見えていない。西の国のちいさな王子」
さっきよりもはっきりとした声はあたりにひびきます。
「なぜ、わたしが見えていないというのか?」
だれもいない部屋の中央にある座はスポットライトのようにパッと照らされ、王子さまは目をおおいます。
「なぜならおまえの父は……」
王座にはいつのまにか、金のかんむりをかぶる人のかたちをした黒い影のようなものが、ふてぶてしく腕をくみ、胡坐をかいて王子さまを見おろしていました。
「おまえが邪魔で、早く国から追いだしたかったからだ。できるだけ遠くにな」
王子さまはいらだち、おうへいな黒い影をにらみつけます。そんな王子さまを知ってか、影はあざ笑うように話しをつづけました。
「おまえは今ごろ国中の笑い者だ。なにも知らず放浪している、わらのように中身のないスカスカな王子だと」
「嘘をつくな。父と民はわたしを愛している。わたしをおとしめようというのか」
影は下品な高笑いをして、こう言います。
「ああ、疑いを知らない、なんとあわれでおろかな干しわらの王子! おまえをおとしめてなんになる? むしろ真実をあたえようというのに」
——こんな影になにがわかるのだ——憤然とした王子さまはだまってしまいます。
「いいかよく聞け、干しわらの王子。この世はなによりもまず猜疑であり、史実は下卑でこうかつな支配のくり返しだ」
風の流れをよみとる船乗りのように、感情のゆらぎを冷静につかむ影は、ここぞとばかりに王子さまの耳をなで、軽妙な疑心で王子さまを攻撃します。感じたことのない悪寒、聞こえてくる人々からのクスクスという笑い声——王はわたしをほんとうに認めてくださっていたのだろうか。もしやあいつの言うとおり……そんなまさか。
「おまえは故郷をでたとき、だれからも見送られぬことをおかしいと思わなかったのか?」
「それは……」王子さまは視線をそらします。
「ふん。では国の外はおまえにとって理想であったか」
「良いものも、悪いものもあった」
「否。人はつねに悪を善で覆う。羊の皮をかぶるおおかみのようにな。権力を渇望するおまえの父も、うかれさわぐ愚鈍な民も、良識ある王の皮をかぶり、善良な民の皮をかぶる。しかしまことの顔はだれにもあかさん」
王子さまはスラリと剣をぬき、きっ先を影につきつけます。
「決闘をもうしこむ! おまえはわが王を、祖国を侮辱した」怒気をふくむ王子さまのするどい声。
「笑止! くだらぬ忠義心。だからおまえの頭は干しわらなのだ。剣は名誉でなく恥辱のためにふるうものよ」
「ふざけるな!」
「そして我は」と、影はゆっくり王子をゆびさし、「すでにおまえにもたらした」。
王子さまは身体中に寒気がひしひしとせまるのを感じます。ひたいにつめたい汗がにじみ、歯はガチガチ鳴り、のばした右手と剣も小きざみにふるえます。
「さあおしえてやろう、真実を」と、影はひじかけにどっしりもたれ、ほおづえをつきます。「むかし、おまえの国は我とひとつの契約を結んだ。それは国の安寧と引きかえに王の子ひとり国から追いだすこと。しかし追放する子になにもつたえてはならない。また子は自発的に国をでなければならない。干しわらの王子、おまえのことだ」
王子さまは顔をゆがめ、青い剣をゆっくり鞘におさめます。
「父上……わたしに力を……」
「人はいつも悪を善で覆う。おまえとの約束など、なんの価値がある」
「……わたしの旅は……ああ、こごえてしまうほどに寒い……」
「我のいるこの座を見ろ。血で汚れた白い大理石の玉座を。遠いむかし、領域を統べる強大な王は君臨し、民に裏切られ、滅びた」
王子さまの体はみるみるかわき、干されきったわら束にかわってゆきます。
「干しわらの王子、絶望のうちに座するがよい。眠れぬ王のように」
王子さまは考えるのをやめてしまいました。祖国、父と母、友人、山からふく森のにおいのするここちよい風、つめたくさわやかな川、小鳥のさえずり、きらきらした朝と星いっぱいの夜。王子さまにとって明日はもう楽しみではなくなったのです。すべてのものがつまらなく思えたのですから。
「どうか……どうか、わたしを助けてほしい」
心までカラカラになった王子さまはそうつぶやくと、吸いよせられるように王座の前に立ちつくし、ついには力なくすわってしまいました。干からびた手をだらりとさげ、王の間を見おろしますが、そこにはただ闇しかありません。
「幕は……おりてゆく」
影はいつのまにか消えさっていました。風車はかわらずゴオンゴオンと音を立ててまわっています。ただひとり、干しわらになった王子さまをのこして。
見つからない本と中庭

鏡よ鏡。このおはなしのおしまいはなあに?
女の子の菖蒲は窓のむこうで顔をよせるアヤメにそう問いかけました。
大きなビルの五階にある、こじんまりとした図書館は、お気にいりの居場所です。
赤いくつをぬぎ、いつもの丸いベンチソファにすわり、書棚と書棚にはさまれて、本を読んでいました。
小学校が休みのある日、高学年の菖蒲は濃紺のそでなしワンピースと白いパフスリーブのブラウスを着て、お姉さんといっしょにやってきます。
きょうはどうしても見つけたい本がありました。それは、あかね色の表紙に金の題字で『干しわらになった王子さま』という本です。
「わらにされた王子さまはだれにも助けられず、いきなりおしまいって、なんてへんてこなのかしら。ぬけてるページもあるし、のこりもぜんぶ白紙。それに、王子さまとの約束って……」
菖蒲はそうつぶやいて、つまらなさそうに本を書架にもどしました。けれど、王子さまの本が気になってしかたがありません。それでまったくおかしな物語について宿題の読書感想文でまとめようと考えました。ところが、いくら探しても見つからず、検さくしても受付に聞いても、そんな本はないと言われます。たしかに棚から選んだはずなのに……
じつはもうひとつ、ふしぎな秘密がありました。といっても、それは図書館ではないのかもしれません。でも菖蒲だけは秘密に気づいてしまったのです。それで、こんどは見つからない本を探すより、新しく見つけた秘密のほうが気になってしかたありません。
丸いベンチソファにひざをつき、窓わくに手をかけ、外をじっと見つめる菖蒲に、お姉さんはずんずんちかづきます。
「アヤメ!」お姉さんはおこって言います。「あなたが本を借りたいってきたのに、窓ばっかりながめて。みんなでお昼ごはん食べる約束でしょ。もう帰るわよ!」
「ねえねえお姉ちゃん、窓をのぞいてみて。あのお庭、扉がどこにもないの」黒い瞳をキラキラかがやかせ、菖蒲はビルの一階にある中庭に目をやります。「なのに、ねえほら! あそこの木のそばに白いぼうしをかぶった人がいるわ。庭のお手いれをしてるのかしら?」
うす暗く青みがかった長方形の中庭は壁にかこまれ、たしかに出入りするための扉はありません。ビルのこちらとあちらの壁にそって赤い実をつけたリンゴの木がそれぞれ三本ずつ、それに庭一面にびっしりとはられた芝生のまん中には白い井戸がありました。庭師がひとりで管理しているのでしょうか、リンゴの木にそれぞれ手をふれます。
「あっ! こっち見た!」
菖蒲は身をのりだし、目を丸くします。はじめて見る人なのに、どこかであったような、なんだかなつかしい気もちがこみあげました。
「どうやって扉のない中庭に入ったのかしら」
しかし、なにも返事はありません。
「お姉ちゃん?」
ふりむくと、うしろにいたお姉さんはこつぜんと姿を消していました。
「もう! ちょっと見てただけじゃない。だまって帰らなくたっていいのに」
長い黒髪をかきあげ、むすっとしながら図書館をでてエレベーターの前に立ちます。ところが、下にむかうボタンをいくらおしてもかごはやってきません。上のボタンもおなじです。エレベーター乗り場ドアの上部にならぶ表示灯も消えています。メンテナンス中なのでしょうか。
「まったく。きょうはついてないことばかりね!」
菖蒲は深いため息をつき、しかたなく内階段にむかいました。
アリ隊列

「おい1051バン! レツをミダすな!」
エレベータ横のおどり場のどこからか、ひそひそばなしが聞こえてきます。
「1049バンがススまないからさ」
「オレはマエにならっている、1050バン」
菖蒲は耳をそばだて、あたりを見まわします。
ザッドドザッドド、ザッドドザ。ザッドドザッドド、ザッドドザ。こびとのような声はリズムあふれる歌へとかわりました。
イッソげ! イッソげ! ジョオウのモトに
スッスめ! スッスめ! ジョオウへレツを
ハタラけ! ハタラけ! ジョオウのために
ハッコべ! ハッコべ! ジョオウにチエを
くり返される歌は菖蒲の足もとから黒えんぴつの点線のように、図書館のほうから内階段の下へとつづいています。
かがんで顔をちかづけてみると、なんとアリの隊列ではありませんか。足なみそろえ、あっちに行ったりこっちに来たり。こんなところでなにをしているのだろうと、菖蒲はだまって観察してみました。すると、おもしろいことがわかりました。アリたちはちいさな紙片をせっせと運んでいたのです。
ハキリアリは葉っぱを切って巣に持ち帰るという話は本で読みましたが、紙を集めるなんて聞いたことはありません。そんなものを運び、いったいなにをするつもりなのでしょう。菖蒲の好奇心の水がめはあふれるほどで、思わず目のまえにいるアリたちに声をかけてしまいます。
「こんにちは、アリさん。わたしはアヤメ。アリさんたちはなぜ紙きれを運んでいるのかしら。巣にもち帰ってなにするの?」
しかしアリたちは菖蒲の言葉など知らんぷりです。それでよけい、アリたちについて知りたくなりました。こんな懸命なのですから、働きアリはよほどの理由があるにちがいありません。
菖蒲は、なにももっていないアリ隊列の先頭を追ってみることにしました。
アリたちのとなりをはって図書館へもどり、貸出カウンターをぬけ、児童書のならぶ書棚にむかって進みます。
「ああああっ!」
菖蒲の目はぱっちり開き、図書館にいるのをすっかりわすれて口からサイレンがもれますが、すぐに手をあてます。でも図書館には人がだれもおらず、注意されたり、ひややかな視線を感じたり、せきばらいされるしんぱいもありません。
菖蒲が声をもらすほどおどろいたのは、そんな規則にがんじがらめのオトナたちにではなく、アリたちの運んでいた紙片がなにかわかったからでした。
なんとアリたちは『干しわらになった王子さま』の本にむらがり、ページをかじってはこまかくしていたのです。菖蒲の眉間にしわがよってきました。ずっと探していた本なのですから、とうぜんでしょう。
「あなたたち、本をこんなにしてダメじゃない!」
菖蒲の怒号もなんのその、工事現場の横をするりとぬけるようにアリの隊列は見むきもしません。それで菖蒲式大型クレーンはガバッと本を取りあげ、こびりついた黒い土砂をぶっきらぼうにふるい落とします。
「おい、ナニをするのだ! ワレワレのシゴトをウバうつもりか」アリは菖蒲の周囲にわらわらと集まり、いっせいに抗議します。「そうだそうだ!」
「ちがうわ。あなたたちはだいじな本をこわそうとしているのよ」
アリたちはそんなの知るか、といわんばかりに自信たっぷりにこうこたえました。
「これはジョオウのメイレイである。ジョオウはカシコくなるため、ホンのカミでマクラをヨウイするようメイじられた。ワレワレのジョオウにサカらうつもりか」
「ええ、そうよ。だれがなんていおうと、まちがえているに決まってる」と、菖蒲はかんかんです。
「本はちぎったり、まくらにするためのものではないもの。それにね、本をまくらにしても賢くならないんですからね」
「ははあ、ワかっていないのはキミのほうだ」と、監督アリは偉そうに言います。
「ワレワレにとって、これがなんであるかがモンダイではなく、ハコぶことがジュウヨウである。それとも、キミはワレワレにメイレイできるケンゲンをモっているのかね?」
「そうだそうだ!」と、ちょっぴり偉そうな作業アリはうしろでさわぎます。
「まあ!」菖蒲はほとほとあきれます。「わかったわ。じゃあ、あなたたちの女王さまにすぐつたえてちょうだい。この本はわたしが借りたかったの。あなたがまくらにしようと考える前からってね」
「だから、ワレワレには『ジョオウにツタえる』というシゴトはナいのだ」きっぱりと言う監督アリ。
「それはワレワレではなくデンタツアリのシゴトだな」と、作業アリ。
「ワレワレワレワレうるさい!」菖蒲はこぶしをワナワナふるわせ、どなりつけます「どうでもいいからさっさと女王につたえてきなさい!」
菖蒲の口からいきおいよく噴出する熱風にアリたちは飛ばされないようはいつくばり、ブルブルふるえ、かたまってしまいますが、ハッとなり、たがいに見つめ、顔をあわせながらひそひそ話しあいます。
「おいおい、なんてこった」
「あのでっかいのはジョオウよりコワいぞ」
「いやいや、ジョオウはあんなカイブツよりずっとヤサしいおカタさ」
「あんなキショウのアラいブシツケカイブツ、ワレワレのアゴだってカナわない」
「はあ?」青筋を立てたカイブツはアリたちを見おろします。
「ショ、ショウチした」
さきほどまでの強気な態度はどこへやら、アリたちは軽くせきばらいをしてから言います。
「ではトクベツにジョオウにツタえよう。しかし、なにが……」
「なぁ、にぃ、がぁ?」菖蒲はゆっくりと力をこめて言います。
「ゼ、ゼ、ゼンイン、イマスグタタタタイキャーク!」
アリたちは怖くてたまらなくなり、紙片を投げすて、雲の子をちらすように逃げさりました。
一匹みだれると、ほかのアリもなにごとかと、整然としていたアリ隊列はめちゃくちゃになり、のこされたのはひとすじの紙片だけになりました。
菖蒲は落ちている王子さまの本をわきにかかえると、腰をまげ、ちぎられた紙片を一枚一枚ていねいにつまんでは本におさめ、図書館をでて、おどり場までもどります。紙片はそこでぷつりととぎれていました。
「よかった」と、菖蒲は首をかしげながらも、ほっとして言いました。「かがんで歩かなくていいのね。でもいつか女王アリに会ったら注意しなきゃ。本をこんなにしてはいけないって」
そんなアリたちとやがて再会するのも知らず、菖蒲は腰をトントン手でたたき、ぐっとのばしてから階段をおりていきました。
下に上がる階段

すみからすみまで探したはずでした。図書館の新刊コーナーで新しい本をかかさず見ていましたし、書架のどこにどんな本があるかもすべておぼえていたほどです。司書のお姉さんに、わたしより知っているとほめられたのはちょっとした自慢でした。
「それなのになんで、見つからなかったのかしら」
菖蒲はボロボロにされた本についてあれやこれや考えていると、ふとおかしな変化に気づきます。
灰色のつめたいコンクリートだった内階段が、いまはまるで古い洋館のような、あたかみのある電球色に照らされ、ざらざらとした乳白色の壁、なめらかな曲線をえがいた木製手すりがついた階段になっているのです。
もしかすると改装したのかもしれませんし、いつもはエレベーターを使っていたので、気にしていなかっただけなのかもしれません。でも、しばらくおりているとこんどは、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ。
菖蒲が目を下にやるとカメがゆっくりとふみづらを歩いています。カメの足の長さで階段などおりられるのでしょうか。そもそも、なぜこんなところに? 菖蒲はカメをじっくりながめていましたが、地面にへばりつき階段をせっせと進む姿があまりにおかしくて、すわって話しかけることにしました。
「こんにちはカメさん、わたしはアヤメ。あなたはなぜここにいるのかしら?」
カメはピタリと止まり(もっとも、うごいているようにも見えませんけど)首をにゅうっとだして、ねむたそうな目をこちらにむけます。
菖蒲はカメがのんびりやさんであるのをよく知っていましたので、こたえを待ちました。
するとカメの口はゆっくりひらき、とてもちいさな声で話しはじめます。
「かのじょは……いたずらずきなのだ……わたしは……いたずらに……つきあっている」
菖蒲はあたりを見まわし、首をかしげます。
「あの、ここにはだれもいませんよ」
するとカメはふたたび階段のほうに頭をゆっくりともどします。『かのじょのいたずら』とはなにか、とても気になりますが、のんびりなカメと話していたら明日になってしまうでしょう。
「さようなら、カメさん。わたしかえらないと」
菖蒲はあふれる好奇心を胸にしまい、立ちあがってカメに手をふり、わかれました。
「きっとどこかで待っているお友だちがいるのね。ふふっ、いつになったら会えるのかしら!」
くすりと笑い、しばらくいくと、カサカサ、ノッソリノッソリ。またカメです。
しかもさきほどのカメとそっくりで、やはり階段をおりようと歩いているではありませんか。さきほど歩いていたカメの彼女かもしれない、と菖蒲は思います。
「こんにちは、カメさん。上であなたを探しているカメさんがいましたよ」
するとカメは菖蒲にむかってのんびりと頭をのばし、じいっと見つめ、ゆっくり話しはじめます。
「かのじょは……いたずらずきなのだ……わたしは……いたずらに……つきあっている」
「あなた、もしかしてさっきのカメさん?」
カメはそっぽむいて、なにもこたえてくれません。
菖蒲はまたわかれをつげて階段をおりましたが、おなじカメはいて、トコトコぐるぐる、トコトコぐるぐる、いくら階段を下へ下へと進んでも、カメと出会います。まるでいつまでもカメに追いつけないアキレスのように、菖蒲がどれだけがんばってもカメより先に階段をおりられないのです。
それでこんどは階段をのぼってみましたが、やはりカメのいるおどり場についてしまいます。
階段を上がったり下がったり、下がったり上がったり。菖蒲は目がまわり、ヘトヘトになって、ついにカメのそばにドスンとすわりこんでしまいました。
ここは何階で、階段を下がっているか、はたまた上がっているのか、カメに聞きますが、あのこたえしか返ってきません。しかたがなく菖蒲はほおづえをついて、しばらく考えてみました。
まず彼女とはいったいだれなのでしょう。
「かのじょのいたずらにつきあっている、ということはカメさんはいま、そのいたずらをされているわけよね」
菖蒲はあたりを見まわします。
「でも、わたしにはかのじょが見えないわ。じゃあカメさんがされているいたずらとはなにかしら」
こちょこちょ、ぺんぺん、なでなで、ぐりぐり……思いあたるいたずらを考えてみますが、カメはなにもされていません。いたずらさえわかればきっと彼女が何者なのかわかるはずなのに。菖蒲はカメと一緒にのんびりと考えます。なにかヒントはあるでしょうか。
「そっか!」
菖蒲の大きな声が階段中にこだまします。
「かのじょはわたしにもいたずらをしていたのよ。だっていくら階段を下がっても上がっても、カメさんのいる階にもどってしまうんですもの。だから、かのじょは階段そのもののことね!」
そう、菖蒲はカメと彼女のいたずら、つまり下に上がり、上に下がる階段につきあわされていたのです。いたずら好きの彼女は、やってくる人をそうしてこまらせていたのです。もちろん、だれも喜ばないので、階段にちかづく人はだれもいなくなってしまいました——カメをのぞいて。カメにはいくらでも時間がありましたし、このいたずらには相性ピッタリだったのです。のんびり屋のカメは、いたずら好きの階段にアリアドネという女の子の名前をつけてあげました。それでカメは彼女と言ったのです。アリアドネは名前をつけられて、とても喜びました。そのかわりにひとつだけ、カメと約束しました。もういたずらをしない、と。
「アリアドネは約束をやぶって、わたしにいたずらをしたの?」
するとカメは首を横にふり、菖蒲が手にしているあかね色の本をポンポンたたきました。
「これ? なぜこの本が関係あるのかしら」
こんどはゆっくりとカメは階段の下をさしました。
階下のおどり場の壁には、さきほどまでなかったカカオたっぷり板チョコのような扉があります。アリアドネは菖蒲に進まなければならない、道しるべの赤い糸をたらしてあげたのです。
「もしかして、わたしが行くの?」
カメは、はっきりそうだとうなずきましたので、菖蒲は立ちあがり、扉にむかいます。
「うんわかった。ありがとう、とても楽しかったわ」
菖蒲はカメとアリアドネに手をふり、はがれかかった金メッキのノブをまわし、扉をそおっと開けます。さきは暗くてなにも見えません。おそるおそる部屋に足をふみいれると、菖蒲の体はあっというまに闇の中へすいこまれてしまいました。なんと床がすっぽりぬけていたのです。ダークチョコレートの扉が菖蒲をぱくりと飲みこんで喉を鳴らし、閉じてなくなります。
そんなようすをじいっとながめているのかいないのか、カメはカサカサ、ノッソリノッソリ歩きだしました。彼女のいたずらにつきあうために。
底なし部屋

もし、ここがあかるい部屋だったなら菖蒲はどんなにかこわい思いをしたでしょう。でも室内はまっ暗、いつまでたっても着地しないので、まるでういているように思えました。
「これなら空からおっこちるのも、海底にしずむのだっておなじね」
あっけらかんとしていますが、ひとつ悲しいことに、せっかく見つけた王子さまの本をすべり落としてしまいました。働きアリのやぶった紙片はひらひらと舞いちり、のこったページもするするほどけ、底なし部屋のずっと下で星のようにちかちかとかがやきます。
「まあ、なんてきれいなのかしら。宇宙旅行をしているみたい」
菖蒲はうれしくなって『ちいさな星の歌』を口ずさみました。
ティンクル ティンクル、ちいさな星よ
あなたはだあれ?
世界よりずっと、ずうっと遠く
夜空にちらばるダイアモンドみたい
ピカピカ太陽はさってゆき
あかりがみんな眠るとき
ちいさなあなたはキラキラと
一晩中わたしをてらしてる
ティンクル ティンクル、ちいさな瞳よ
あなたはなんてステキなの
歌いながら手足をばたばたさせたり、すいすいおよいでみたり。そんな姿があまりにおかしくて、おなかをかかえ、笑います。すると魚のむれは菖蒲にちかづいてきて、まわりをぐるぐるかこみ、こうたずねました。
「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」
「こんにちは! 魚さんたち」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」
「どうだろう、そんなの考えたことないや」魚たちは尾びれをぶんぶんふります。「でもぼくたちがおよげるってことは、ぜったいに海だね」
「なるほど。でも下を見て。星がかがやいているの。海に星はあるのかしら?」
「なんと!」魚たちは菖蒲のさすほうをいっせいにのぞくと、たいへんおどろきます。「これは知らなかった。もしかして深海に住むものたちだろうか。なあみんな、たしかめにいこうじゃないか」
そう言うと竜巻のようにぐるぐるまわる魚たちは、光る底にいきおいよくむかい、菖蒲は魚たちに、ばいばいと手をふりました。
だれもいなくなると、つぎに翼をぐんとのばしたわたり鳥のむれがV字編隊で菖蒲にちかづきます。
「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」
「こんにちは! 鳥さんたち」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」
「どうだろう、そんなの考えたことないや」わたり鳥たちは翼をパタパタはばたかせます。「でもぼくたちが飛べるってことは、ぜったいに空だね」
「なるほど。でも下を見て。星がかがやいているの。地上に星はあるのかしら?」
「あれは街のあかりさ」鳥たちは口ばしをゆらして笑います。「夜間飛行でよく見かけるもの」
「じゃあ、あちらを見て」と、菖蒲はあおむけになって上をさします。「ほら、なんにもないわ。もしここが夜空なら満天の星がちらばっているはずよ」
「なんと!」わたり鳥たちはたいへんおどろきます。「これは知らなかった。ひょっとするとあつい雲で見えないのかもしれない。よおしみんな、たしかめにいこう」
先頭の鳥が翼を広げてふわりと上昇し、つづいて前から順にわたり鳥たちは上方の闇へと消え、菖蒲は鳥たちに、ばいばいと手をふりました。
だれもいなくなると、こんどは流れ星が光のつぶをパラパラまきながら菖蒲のところにやってきて、こうたずねます。
「ねえねえ、なにがそんなに楽しいんだい?」
「こんにちは! 流れ星さん」と、菖蒲は大きな声であいさつをします。「はじめまして、わたしの名前はアヤメ。この部屋がなにかを調べていたの。だけどなんだかおもしろくなってきちゃった。ここが空か海か宇宙なのか、どれもしっくりこないんですもの」
「どうだろう、そんなの考えたことないや」流れ星はくるくる光の尾を引きます。「でもぼくが飛んでいるってことは、ぜったいに宇宙だね」
「なるほど。でも下に星がかがやいているのに上はまっ暗なの。宇宙はどちらにも星があるはずよ」
「いいやアヤメ、宇宙には星もかがやけない、常闇があるんだ」
菖蒲はそうかそうかとうなずいて、「流れ星さんの言うとおり、ここが宇宙なら、わたしは止まっているはずよね。わたしはなぜ下に落ちているのかしら?」
「なんと!」流れ星はたいへんおどろきます。
「それは知らなかった。アヤメがどこに落ちているのか、ぼくが見てみよう!」
菖蒲はかがやく底へ消えてゆく流れ星に、ばいばいと手をふりました。
ついに魚たちも、わたり鳥たちも、流れ星もみんないなくなって、菖蒲はぽつんとひとり、底なし部屋についてじっくり考えてみることにしました。
りんごはなぜ木から地面に落ちるのでしょう。雨はどうして雲から地上にふってくるのでしょう。そして、この部屋で本を手ばなしたとき、なんで菖蒲と本は落ちたのでしょうか。
「そもそも落ちているのかしら?」
菖蒲はずっと、暗い部屋でリンゴや雨のように落下しているとばかり思っていました。もちろん、本は下に落ちましたし、菖蒲もそれを見たのです。でも魚や、わたり鳥のむれも、流れ星ですら自分たちが落ちていると、言いませんでした。
「ここは空や海や宇宙であって、そうではない部屋ってことかな」
つまり、海にしずんでいるのでも、空から落ちているのでも、宇宙をただよっているのでもありませんが、魚がおよぎ、鳥は飛び、星も流れるというわけです。
「そっか、引かれているのね!」
ついにひらめきました。菖蒲は見えない力に強くひっぱられていたのです。でも、いったいなにからでしょう? その答えはすぐにわかりました。『干しわらになった王子さま』の本です。底なし部屋でほうり投げたとき、ちらばってきらめく星となり、菖蒲を招待していたのです。ぜひこっちにきてほしい、と。それがなぜかはもうすこしあとで知ることになります。
底なし部屋のからくりを知った菖蒲は、ためらわず星にむかって両手をさしのべ、本の招待を喜んで受けました。星にひかれるまま、白い光は菖蒲をつつみこみ、あまりのまぶしさに目を閉じてしまいました。
——————
ガサガサかわいた音を立て、やわらかいものにしずむと体がチクチクして麦わらぼうしのにおいがします。ほそくて黄色いストローをかきわけ、ひょっこり顔をだすと、わら束がたくさんつんでありました。
「ここは、どこ?」
菖蒲はなにがおきたのかわからず、しばらくぼーっとしますが、遠くのほうでゴトンゴトンという音が聞こえましたので、上方についた半開きの窓から外をながめます。
青空の下には金色の麦畑が一面に広がり、遠くでは建物についた大きな羽根が風をうけてまわっていました。
「風車だ!」
菖蒲は干しわらの王子さまの世界にやってきたのだとすぐにわかりました。胸はドキドキと高鳴ります。ここが本の世界だから、だけではありません。
なんと、干しわらの王子さまをおしりでふんづけていたのです。
キジ三毛のネコ
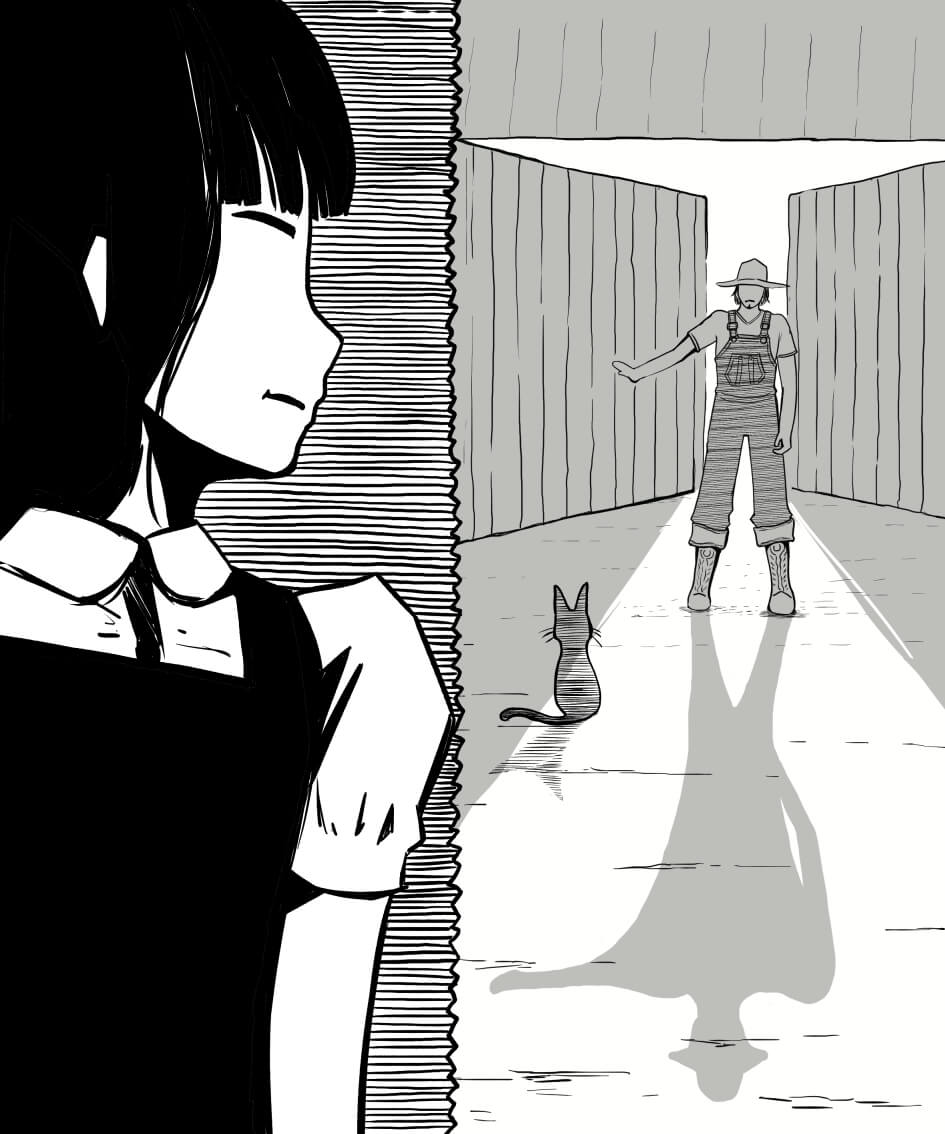
たくさんあるふくろからアタリを一回で引けるでしょうか。たとえば、いろんな味のキャンディーにひとつだけキャラメルがまざっていて、どれもまったくおなじつつみだとしたなら、どのように探しあてますか。もちろん、ひとつずつ開けてみるしかありません。
でも、菖蒲は山とつまれたおなじわら束から王子さまを一目で気づき当てたのです。なんでだろうと思うかもしれません。きっと菖蒲にもこたえられないでしょう。ただ胸がドキドキして、これは王子さまだとおしえているようでした。
ひとつ疑問がわきます。わら束に変えられた王子さまは、風車の地下室にある王座にすわっていたはずなのに、なぜ菖蒲のそばにいるのでしょうか?
「それは農夫がひろい、ここに投げていったからさ」
「だれ?」
菖蒲はどこからか聞こえる声に返事をします。
「こっちだよこっち」
広い納屋をあちこち見ると、正面の大きな両扉のそば、くま手を背にキジ三毛のネコがちょこんとすわっていました。
菖蒲はネコのそばにちかづこうと、つまれたわら山からおりようとしますが、なかなかうまく足をかけられず、きゃあと声をあげ、ずるずる落ちてしまいます。
「なあ、お嬢ちゃん。もうすこし静かにしてくれにゃいと。あいつが物音に気づいてやってきたらどうするんだ」
「ごめんなさい。わらの上を歩くのがこんなにむずかしいだなんて思わなかったの」
やれやれとキジ三毛ネコはため息をつきます。
「まあいい。それよりあのわらについてだ。お嬢ちゃん、あれがにゃにかわかるのか?」
「もしかして、あなたも王子さまだって知っているの?」
「あの小僧は王子だったのか」キジ三毛ネコはニヤリと口を広げます。「オレが風車でネズミを追いかけていたとき……」
キジ三毛ネコは白馬にのった王子さまが風車に入るのを見かけましたが、けっきょく、もどってくることはありませんでした。
「しばらくして黒い大蛇は風車から飛びだし、いきおいよく西にむかって消えたんだ」
おそらく王子さまと対峙した影だろうと菖蒲は考えます。
「ここの畑の農夫は風車の地下で青い剣と赤い宝石の首かざりをかけたわら束を見つけ、大喜びしていた。ごうつくばりにゃ農夫め。白馬もすべて自分のものにし、町で売りさばいて金にするつもりだぜ」
それを聞いた菖蒲はひとつ思いつきました。王子さまの帰りを待つ白馬に話しを聞けば、干しわらの王子さまについて、もっと知ることができるでしょう。
しかしキジ三毛ネコの言うとおりなら、いそがなければなりません。
「白馬さんはどこにいるのかしら。助けてあげないと」
「まあおちつけ。すぐに売ろうってわけじゃあにゃい」あわてる菖蒲にキジ三毛ネコは言います。
「馬は風車のちょうど裏手、農夫の家のすぐそばにある馬小屋につながれてる。にゃわで固くしばられてるからかんたんにはほどけにゃいぜ。青色の剣を使うといい。切れ味がいいからハサミがわりにちょうどいい、と農夫は喜んでた。剣は寝室にあるはずさ」
「わかったわ」キジ三毛ネコの話を聞いて、菖蒲はほっと胸をなでおろします。「でも、なんでわたしにいろいろとおしえてくれるの? あなたは農夫さんの飼いネコなんでしょ?」
「にゃにおバカな! オレはあんなやつに飼われちゃいにゃいぜ」キジ三毛ネコは不機嫌そうに目を横にそらします。「ただ白馬にかりがあるだけさ。大蛇はオレを……いや、まわりにあるものすべてのみつくそうとした。必死に逃げたが追いつかれ、もうおしまいかとあきらめかけた時、白馬はオレを口にくわえ、助けてくれたのさ」
「そうだったのね」と、菖蒲はキジ三毛ネコの黒い首輪にふれます。
キジ三毛ネコは首をぶるぶるふるわせ、すっくと立ちあがり、菖蒲のまわりを歩きだしました。
「そもそもあいつと契約したのがまちがいだった……」
キジ三毛ネコによると、農夫と仕事の契約を結んだのがはじまりでした。この土地にいるネズミを一〇〇〇匹退治するまでの条件で宿と食事を提供する、という内容です。しかし『退治するまで』という文言にまんまとだまされました。つまりネズミをすべて退治しなければ、農夫から自由にはなれない、というわけです。なんと農夫はキジ三毛ネコと契約を結んですぐ、ネズミ捕りをそこらじゅうに置きはじめます。これではいつまでたっても退治できません。
「旅ネコのオレは気ままに生きるのが好きにゃんだ。おなじにゃわばりをまいにちウロウロするようにゃやつらとはちがう」
キジ三毛ネコは立ち止まり、うらめしそうにつづけます。
「ここもすぐでるつもりだった。にゃのにあのいじわる農夫はだましやがった! はじめっからここでずっと働かせるためのわにゃだったんだ」
「にゃんてひどい人にゃのかしら!」と、菖蒲はネコみたいにまゆをしかめます。
「それでお嬢ちゃんにひとつたのみがある」キジ三毛ネコはじっとりした目つきで菖蒲をのぞきこみます。「あいつは寝室のどっかに、オレとかわした契約書をかくしたはずにゃんだ。それをもってきてほしい。あいつの目をぬすみ、にゃんどか探したが、どうにも見つからにゃかった。あの契約書さえ捨ててしまえば自由ににゃれるんだが」
「うん。さがしてみる」菖蒲は頭をたてに大きくふりました。
ちょうどその時、キジ三毛ネコの両耳はピクピクうごきます。
「まずい、あいつだ。かくれろ!」
ぎゅっぎゅと砂利をふみしめる足音が納屋の外からこちらにちかづき、やがてピタリとやみ、大きな両扉がゆっくり開きます。
菖蒲はおどろきあわてて、飛びこむようにつんであるわら束の影にかくれ、口に手をおしあてます。
「おいキジ三毛!」荒々しい男の声がします。「昼飯の時間だ。とっととこい!」
鼻からもれる息ですら聞こえてしまいそうな重苦しい沈黙。
「にゃ、にゃあ」
キジ三毛ネコのへたな鳴き声に笑いをこらえながら、菖蒲は農夫を見ようと、正面をそっとのぞきます。こちらにのびる人影を頭からたどり、扉の前にはウェスタンブーツにデニムのオーバーオールと白シャツ、麦わら帽子をかぶった、いかにもたくましい口ひげの男がどっしりかまえています。
菖蒲は口に手をあて肩をすくめます。
「おくれたらめしはないと思え!」と、大男は扉を乱暴にたたきつけ、でていきました。
「さぁて家にもどるとするか!」キジ三毛ネコは大きな声で言います。「あいつは昼飯がすんだらオレをつれて小麦を売りに馬車で街へでかけるだろう。そうすれば家にはだれもいにゃくなる。玄関はカギがかかっているが、二階の窓はいつでもあけっぱにゃしでたすかるぜ。しかし泥棒がそばの木をのぼってこにゃいかしんぱいだよ。まあ夕方、暗くなるまえにもどるからいいか!」
それからキジ三毛ネコは農夫のあとを追い、扉のすきまから走りさりました。
納屋にひとりのこされた菖蒲は王子さまのそばにもどると、計画をアヤメと話します。菖蒲ひとり会議のはじまりです。
「まず王子さまをここからださなきゃ。だって、ほかのわら束と一緒にもっていかれたらたいへんよ」
「いい考え。でも、どこにかくせばいいのかしら」
そこらへんにほっぽって、だれかに盗まれたらいけませんし、動物にでもバラバラにされたらたいへんです。話し合いの結果、風車の地下にしました。きっとあそこに王子さまをもとの姿にもどすための手がかりがあると思ったからです。
「つぎに農夫さんの家のそばにある木をのぼって、二階の窓から寝室へ」
「青色の剣とキジ三毛さんの契約書を探す」
菖蒲はのぼり棒が得意でしたので、木のぼりだって問題ありません。
「それから馬小屋で、つかまった白馬さんをたすける」
「うん、これでよし!」
菖蒲のひとり会議は万事うまくいきました。もちろん、頭の中ではいつだって順調に進むものです。菖蒲はまんぞくそうにひじをついて寝そべり、足をバタバタさせて窓の外をながめ、かんぺきな計画を実行する時を待ちつづけました。
菖蒲の計画

昼さがり、キジ三毛ネコの言うとおり、風車のむこうから荷馬車はでていきました。
菖蒲は見のがすまいと目で追いますが、まだ行動は起こしません。わすれものを思いだして引き返した農夫とかち合いでもしたら計画は水のあわです。もちろん失敗などゆるされませんので、できるだけ慎重に行動します。
馬車がだんだんちいさく、地平線のかなたに消えたのを見て、あせらずゆっくり、「いち、にぃ、さん……」六十までかぞえてから、それ今だと納屋の扉をおしあけました。
どこまでも広がる新しい世界。ここちよい風はささっとふき、菖蒲の長い髪をゆらします。目をつむり、空気をいっぱいにすいこめば、どこか知らない異国のかおりを体いっぱいに感じます。
人生をかえてしまう物語がはじまる前兆。おさえきれない高揚を胸に目を大きくひらき、回転する大きな羽根にむかって、王子さまをかかえ、小麦畑の中へ走りだしました。
小麦畑をぬけると大きな黒い風車がどんとかまえています。羽根の音はまるでうなり声、さっき見た農夫がうでをくみ、計画をじゃまするため、立ちはだかっているように見えて菖蒲はたじろぎます。しかし、のんびりできる時間はすこしもありません。王子さまのため、ちいさなドン・キホーテは勇敢に風車へ突進しました。
風車の中は時計のように木製の歯車が複雑にからみあい、こすれるにぶい音、テンポよい打音でさわぎたっています。
「たしか本には地下につづく階段を探したとあったわ」
しかし、いくら見まわしても階段など、どこにもありません。
「探しまわった、ということは王子さまはすぐに見つけられなかった……つまり、かくし階段だったのよ!」
菖蒲はよつんばいになって木のゆかを一まいずつ指でなぞります。すると一か所だけ、ゆか板に金色の回転把手がうめこまれています。しめた、と金ぞくのつめをひっくり返し、四角く切りぬかれた板を持ちあげると、うす暗い地下へとつづく階段を見つけます。おりた先にはゆるく閉じた木製の古い扉からヒューヒューとすきま風がふきぬけていました。
「本に書かれたとおりね」
扉のむこうは風車の地下室とは思えない、オレンジ色のともしびがいくつもゆらゆらゆれる壮麗な王の間でした。いまはなき強国の歴史の針はポッキリおれ、つもるほこりが長い時を知らせます。部屋の両わきにはいくつもの巨大な支柱がならび、中央ひなだんの頂点にすえられた玉座は天じょうからふりそそぐ光をあび、空位のまま、こちらをむいていました。
「まっていて。すぐにもどるから」と、菖蒲は王子さまを玉座にのこします。
さいしょの任務をぶじに終え、外でふうっと一息つき、すぐつぎの計画にうつります。風車の裏手にまわると、よく手入れされた庭のさきにわらぶき屋根の家、となりには馬小屋が見えました。
菖蒲は門をくぐり、色とりどりの花がさきこぼれる庭を足早にぬけて、家によりそうブナの木で立ち止まります。それからくつとくつ下をぬいで木の根もとにかくしてから、うねる木にしがみつき、ぐいぐいのぼります。屋根裏の窓にせりでた太い木の枝を毛虫のようにくねくねとつたって進み、窓に手をかけようとしたとき、思わず地面を見てしまい、あまりの高さにめまいがします。
「やすんでるひまはないのよ、アヤメ」
菖蒲は下をのぞかないよう顔をあげて呼吸をととのえ、ゆっくり腕をのばすと、なんとか窓はこちらに開きます。
「だいじょうぶ、わたしは飛べる。だいじょうぶ、わたしはあっちに飛べる……」
そう言い聞かせ、太い枝に手をあててふるえる腰をあげ、こずえに足をつけます。
「鳥のように飛べる、チョウチョのようにまうのよ……!」
ケムシはサナギに、そしてチョウとなってはばたくように菖蒲はいきおいよく窓に飛びうつります。
木の枝はたわんでバサバサ葉をちらし、ヒバリもなにごとかと空へ逃げていきました。
そして、どすんと重いものがぶつかるにぶい音。
「いったぁぁい!」
屋根裏部屋からほこりがもくもくとけむりのようにあがり、斜光でかがやきます。
「アヤメチョウ……ちゃくりく……しっぱい」
菖蒲は赤くなったおでこを手でおさえ、ふらふらと天じょうの低い屋根裏をおります。
かまどや壁にぶら下がる鍋におたま、きれいに整とんされた食器棚のある台所にでると勝手口、居間そしてべつの部屋につながるろうかにわかれています。菖蒲はまよわずろうかをとおり、サニタリールームをすぎて扉につきあたります。
扉の把手に手をかけると菖蒲の胸はうずきます。人の家にだまって入るのはわるいことですし、部屋となればなおさらです。もしも知らない人に寝室をいじられたら、と考えはじめると、よけいに心は痛みます。でもここで引き返せば王子さまを助けられませんし、キジ三毛ネコもあのままです。
小声で「ごめんなさい」と言い、把手をまわしました。
広い部屋には大きなベッドにつくえと棚、刺しゅうの入ったレースのカーテンから陽の光がうっすら差しこみ、よくみがかれたマホガニー製のつくえのそばに両刃の青い剣が立てかけられていました。
「なんてきれいなのかしら……」
剣を手にすると片手で持ちあげられるほどに軽く、美しい透明な深青のガラスはあざやかな青緑に色をかえます。ふしぎなことに剣から手をはなすと剣はもとの青色にもどります。
菖蒲は計画を思いだし、キジ三毛ネコの交わした契約書を探そうと部屋を見まわします。
ところで計画というものはたいてい思いどおりにいかないもので、その時どきでなんとかしたり、あきらめたりするものです。菖蒲もできるだけうまくいくよう努力しますが、どうにもできない、やっかいな問題にあたってしまいます。
契約書のありか
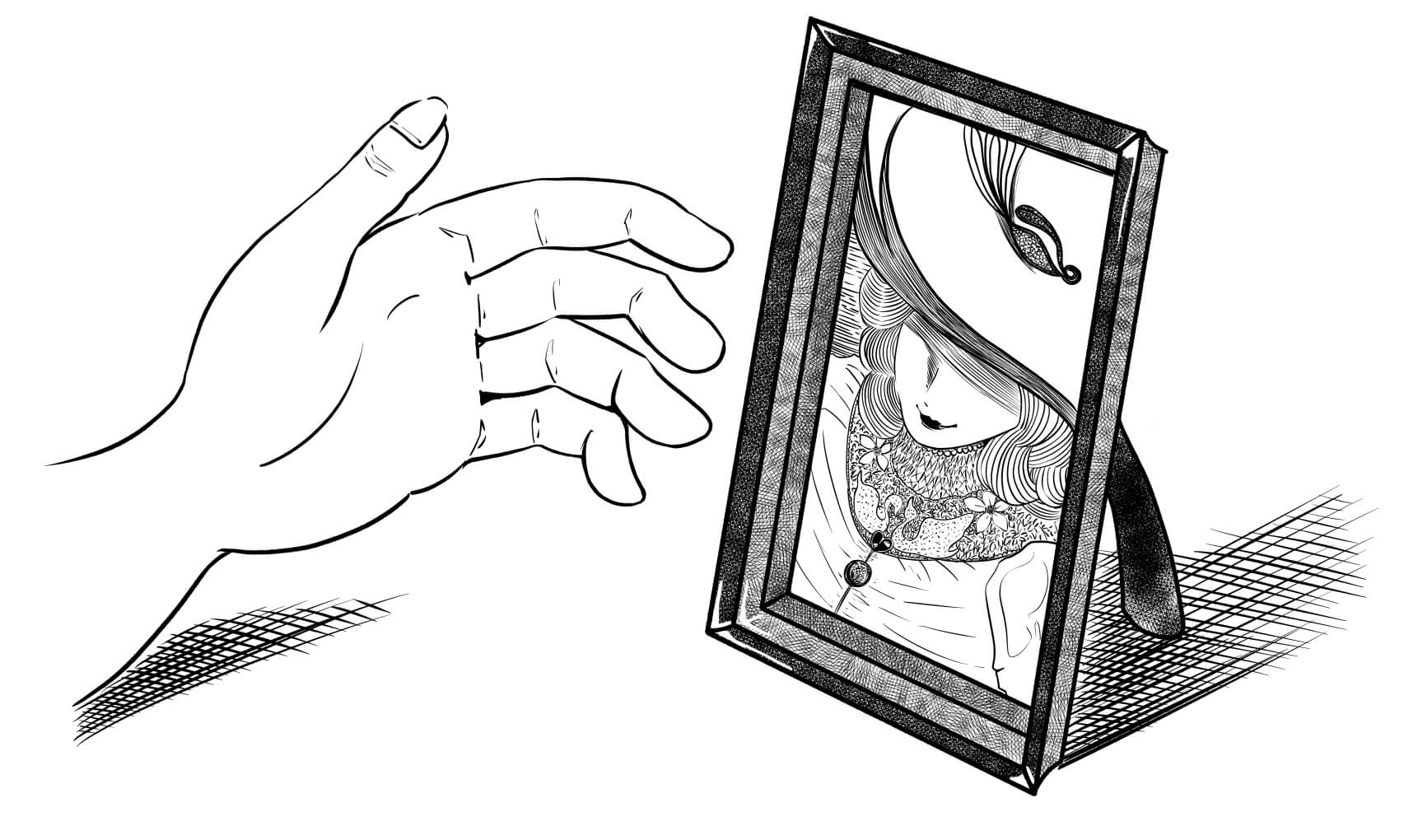
王子さまの剣はすぐにわかりましたが、キジ三毛ネコの契約書はどのようなものか知りません。紙に書いたのか、それともほかのなにかでしょうか。
「キジ三毛さんにちゃんと聞いておくべきだったわ」
菖蒲はうらめしく思いながら、つくえの引きだしに手をかけた時、卓上にかざられたポストカード立てが目にとまります。真ちゅうの額の中では白いキャペリンハットをかぶった金髪の女が笑みをうかべています。
「この人どこかで……」
引きだしを開けても何通かの手紙だけで契約書らしい紙はなく、奥までのぞいてもからっぽですし棚にもありません。もしやキジ三毛ネコのかんちがいなのか、まさか探す部屋をまちがえたのか。時間だけは過ぎ、みるみる陽はかたむいてゆきます。
「どこにあるのかしら。アヤメ、おちついて探すの。きっとあるはず。どこかにおきわすれてしまった自転車のカギとおなじよ」
たった一枚の契約書を探すだけなのに、計画が進まないもどかしさを感じながら、そわそわと部屋中を行ったり来たり、引きだしを開けたり閉めたりをくりかえします。
するととつぜん、外から車輪のこすれる音が聞こえました。窓をのぞくと農夫が乗る荷馬車が見えます。
「ええっ! もう帰ってきたの?」
なんて最悪のタイミングでしょう! 部屋からでれば農夫と鉢あわせになります。菖蒲はあわてて隠れる場所を探します。棚は小さすぎて入れませんし、つくえの下ではおしり丸見えです。ベッドの中もふとんをめくられたらおしまいでしょう。
農夫の足音はずんずんと寝室にちかづいてきます。
「あぁぁぁ、まってまってまって!」あちこちに首をふりながら、あわてふためく菖蒲。
ガチャガチャガチャ。把手は小きざみにふるえ、ついに扉が開きます。大きな足はゆか板をきしませ一歩また一歩と窓ぎわへ、真ちゅうの額があるつくえの前で止まり、「ただいま」と、農夫のさびしそうな声が聞こえ、すぐにでていきました。
静まり返った部屋で菖蒲はゆかに頭をつけ、大きなため息をもらします。
でもいったいどこに隠れたのしょう?
それはベッドの下です!
農夫が部屋に入る、もうすんでのところで、すべりこむようにもぐりこんだのです。
しかし菖蒲の計画はまたたくまにくずれさりました。ベッドの下から身動きが取れなくなってしまったからです。契約書をあきらめ、青い剣だけを持ちだそうにも、いつここから脱出すればよいのでしょう。農夫が家の外か屋根裏、それとも勝手口や居間にいる時に? そもそもいまどこにいるのかわかりません。もし窓の外からのぞいていたら……いくら計画をねり直しても、菖蒲の計算機は最悪な結果をはじきだします。
あれこれなやんでいるうちに寝室は暗くなり、出口の見えない不安はどんどん高まります。いっそ農夫の前に姿をあらわし、わけを話そうかとも考えましたが、強欲な農夫に鎖でつながれ、どこかに売りとばされるのではと考え、身がすくみます。菖蒲はうつぶしたまま、なにもできず、ついに夜をむかえてしまいました。
好機は深夜におとずれます。農夫はランプを手に、ふたたび寝室へやってきて、部屋全体をうっすら照らします。菖蒲は耳を立て、つくえにむかう足を目で追います。
「おやすみ、リリィ」農夫は真ちゅうの額にあいさつをして灯りをふき消します。
ベッドのきしむ音を聞いた菖蒲は大胆な計画をひらめきました。農夫がベッドで寝ている時、青い剣をこっそり持ちだそうと考えたのです!
菖蒲は農夫がぐっすり眠るのを待ちます。またたくまに過ぎた時間がこんどはゆっくりと、じれったく感じました。
農夫はベッドの上で、その下で菖蒲がウツボのように横たわるおかしな夜はさらに深まり、いまか、まだか、そわそわしていると、やがて大きな寝息が聞こえます。
さあ計画の再開です。菖蒲は音を立てないようベッドの下からもぞもぞはいでて息をころし、そおっと顔をあげます。ふとんにしずみ、ぐっすり寝ている農夫を見た菖蒲はひざをつき、そろそろと青い剣にちかよります。カーテンからもれる月の光をあびた剣は、まるで宇宙をかためた深い紺色のようで、つかむとあざやかな青緑にかがやきます。
「んっんん」と、顔に手をあて、うめく農夫。
菖蒲は剣から手をはなし、さっとゆかにふせます。農夫は寝がえりをうちますが、起きてはいません。
ところが立てかけた剣はバランスをくずし、すべるように倒れます。菖蒲は目をむいて、とっさに手をのばし———!
夜風は麦をこすり、窓ガラスにあたってカタカタ鳴らします。
ぎゅっと目をつぶり、息を止め、くちびるをかみ、ふるえる腕をのばして剣を支える菖蒲。
部屋中に聞こえそうなほど鼓動は脈打ち、片目ずつ開き、そおっと立ちあがり、ベッドをのぞくと農夫は……寝ています。
菖蒲は肩をなでおろし、ふたたび剣を手に、すり足で扉にちかづきます。
(お願い、どうか起きないで!)
頭の中で何度そう唱えたでしょう。かくれんぼや鬼ごっこ、学習発表会に合唱コンクール。できるかぎり思いうかべても、これほど緊張したことはありません。
菖蒲は息のつまる思いで寝室をぬけだしました。
しんとした戸外は丸い月が空にぷかりとうかび、小麦畑をやさしくてらしています。菖蒲は木の根もとに隠しておいたくつとくつ下を取り、いそいで馬小屋へむかいます。
干し草のにおいでみたされた馬小屋の奥には美しい白金の毛なみの馬が菖蒲を見つめていました。
「はじめまして、お嬢さま」白馬の高く澄んだ声。
そばにはギロリと目を光らせたキジ三毛ネコもいました。
「ごめんなさい、キジ三毛ネコさん。あなたのほしがっていた契約書は見つからなかったの」
キジ三毛ネコはぷいっと顔をそむけ、菖蒲はきまりわるそうに白馬にちかづきます。
「はじめまして、白馬さん。あなたに聞きたいことがあります」
「わたくしも、お嬢さまにお話ししなければなりません」
「オレもまぜてもらおうか」背後から男の低い声。
菖蒲の顔からみるみる血の気が引いていきます。おそるおそるふりむくと、寝ているはずの農夫が目の前に立っているではありませんか! 菖蒲は言葉をうしない、青い剣を両腕で強く抱きしめたまま、かたまってしまいます。
菖蒲の計画はすべて失敗におわりました。
農夫たちの秘密
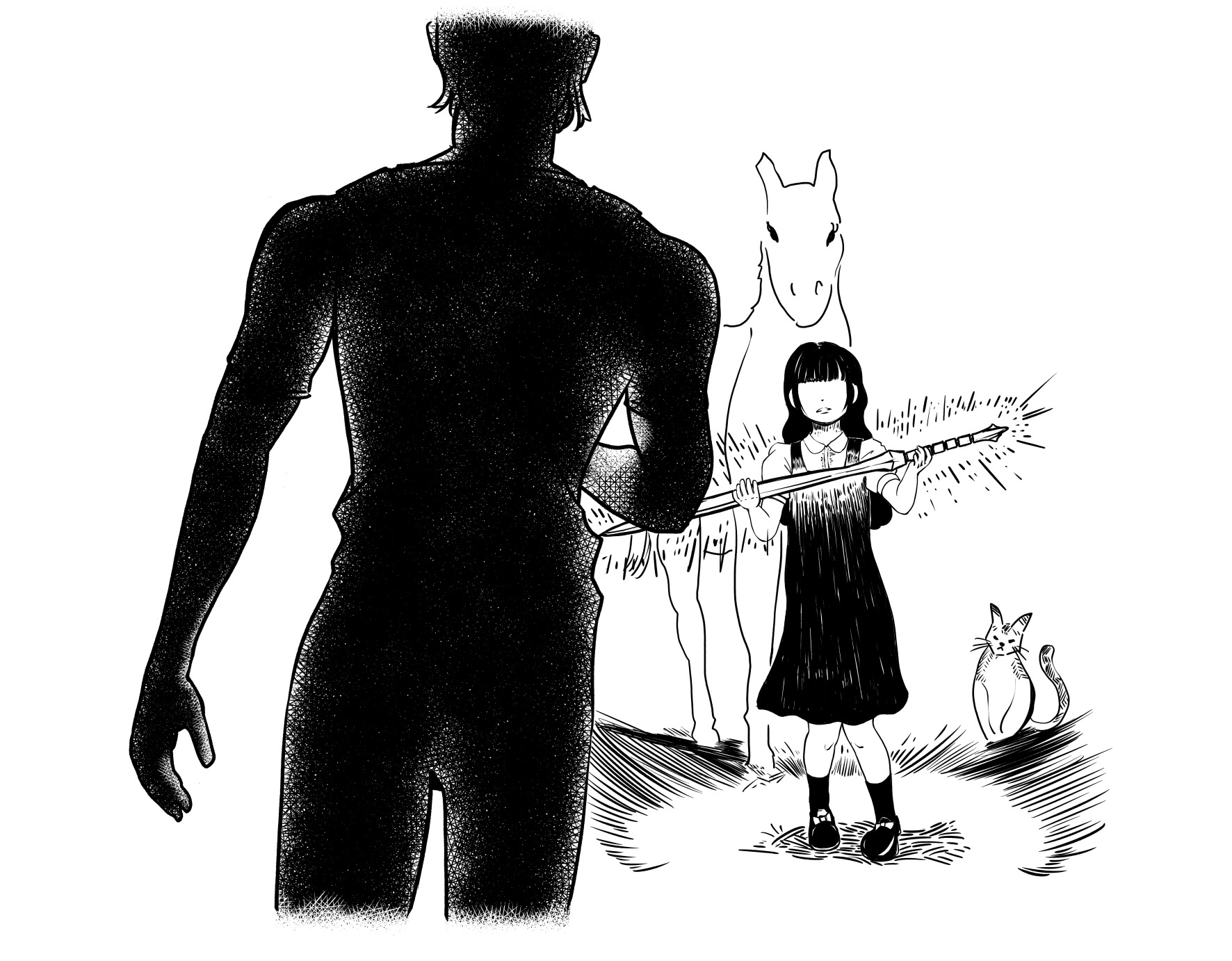
しょうじきに話し、あやまらなければ。
おびえる菖蒲は剣をわたそうと農夫によろよろちかづきます。
「けっして剣を手からはなしてはなりません!」
白馬は菖蒲を制止します。
「で、でもわたし、剣をぬすんだから……」
「いいや、あの白い馬の言うとおりに」
農夫はおだやかに言います。
「わたしはきみが家にいるのを知っていたんだ」
「ど、どういうことですか?」とまどう菖蒲。
農夫はにこりと笑い、「そこにいるネコがきみをだましたんだよ」。
「だましたにゃんてネコ聞きのわるい!」
「そんな、ひどいわ」菖蒲はまゆをしかめます。
「ごめんよ、お嬢ちゃん」キジ三毛ネコは悲しそうに言います。
ひとつだけわかりました。ここにいるみんなはすべて知っていましたが、菖蒲はおどらされていたのです。納屋でじっと待ち、木の上から家にしのびこんで契約書を探し、きゅうくつなベッドの下で恐怖にふるえ、やっとここまで来たのに。計画をめちゃくちゃにされてばかばかしくなり、菖蒲は腹がたってきました。
「なんなのよ、もう!」
「お嬢さま、どうかおゆるしください」白馬は菖蒲をなぐさめるように言います。「すべては闇に気づかれないためなのです。闇はあらゆるものを監視しています」
闇とは干しわらになった王子さまと対峙した黒い影だと白馬は説明します。自由自在にその姿を変えるため、つかみどころがなく、霧のように世界にたちこめているのです。
「青い剣はお嬢さまの手にある時だけ、とくべつな力で闇から守ります。その証拠に剣をごらんなさい」
菖蒲の手にある王子さまの剣は青緑にかがやいています。
「わたくしの主人である王子は言いました。「おまえのもとにかならず娘がやってくるだろう。その子に剣をわたしておくれ」と。それがお嬢さま、あなたなのです」
「それなら、はじめから言ってくれればいいのに」菖蒲はほおをふくらませます。
「できればそうしたかった」と、農夫は言います。「でも王子のいう女の子はどこからやって来るのか、どんな顔なのか、まったくわからなかった。それに、わたしたちの味方になるかどうかも試すひつようがある。しかも闇に気づかれないようにね。だからいじわるしようとたくらんだわけではないんだ」
「だ、か、らぁ、オレはごうよくにゃ農夫にだまされた、あわれにゃネコってわけ!」キジ三毛ネコは鼻息をあらくして言います。「それに肉球印の契約書はちゃあんと寝室にあったんだぜ。ポストカード立ての裏に、ね」
「ええっ」菖蒲はあきれたように言いました。
「きみが約束と秘密を守るかどうか試してみたら、わたしたちが思っていたよりもずっとすてきな女の子だったんだ」と、農夫は言います。「それにしても寝室に入ったら、だれもいなくてあわてたよ。まさか夜中にベッドの下からでてくるなんて」
「ほんとうに、どうしていいかわからなかったんですもの!」
菖蒲の顔はまっ赤にそまり、みんなくすくす笑います。
すこしだけ、ほっとした菖蒲は図書館からやってきたこと、本に招待されて納屋に落ちてきたことをかくさず話しました。
「なるほど。わたしたちの領域のものではないのか」農夫は口ひげに手をあてます。
「お嬢さまには理解しがたいかもしれません」と、白馬は言います。「わたくしたちの領域で約束は力をもっています。重い約束ほど力は強く、約束を守らなければ大きな代償がともないます。王子の剣の力も約束によるもの」
「そうだったのね。でも、だれの約束なのかしら」
「ちょっと待った」農夫は用心深げにあたりを見まわします。「夜ふけに長居は危険だ。つづきはまた明日にしよう」
農夫は手まねきをし、みんなちいさく輪になって集まります。
「いいか、よく聞くんだ。これから闇に気づかれないよう、ひと芝居うつ。女の子は白馬を助けようとするが農夫に見つかり家につれこまれ、おどしつけ、ここで働く契約を結ばせる、という台本だ。剣をこちらにわたしたらすぐ開演する」
みんなこくりとうなずきます。
菖蒲が農夫に青い剣をさしだそうとした時、みんなは菖蒲の前にならびます。
「わたくしの名はアルビレオ。王子につかえる馬です」と、白馬のアルビレオはおじぎします。
「おれのにゃはモルト。山あいの国の王につかえる伝達役のネコさ」と、キジ三毛ネコのモルトはおじぎします。
「わたしの名はグレエン。山あいの国の王につかえる風車の監視役です」と、農夫のグレエンはおじぎします。
みんなの名前を知ると菖蒲の胸はふわっとあたたかくなり、勇気もわいてきました。
菖蒲は目をかがやかせ、仲間たちにこう言いました。
「わたしは王子さまに招待されたアヤメです」
観客のいない芝居

お芝居はじつにみごとなものでした。もし観客がいたなら立ちあがり、万雷の拍手をおくったにちがいありません。
「どうかおゆるしくださいませ!」
泣きじゃくる少女役のアヤメ。
「げっへっへ。こーんにゃところにいやしたぜ、だんにゃ」
うらぎり役のモルト。
「この契約書にサインしろ。さもなきゃ町で売りとばしちまうからな!」
強欲な農夫役のグレエンはアヤメのうでをつかみ、居間に引っぱります。
「なんでもいたします、どうかおたすけください、ご主人さまぁ!」
「にゃんでもするとは、いい度胸してやがるぜぇ!」
迫真の演技にテーブルで顔をあわせると、みんなうつむき、肩をふるわせます。闇が監視しているといっても気配はなく、まるで観客のいない劇場で本番さながら歌いおどるプリマドンナのようだったからです。こんな真夜中に、みんなでいったいなにをしているのでしょう。あまりにもおかしくて笑いをこらえきれません。
契約書を結ぶ場面までひととおり演じ、農夫はウツボの住むらしい、うわさの寝室で寝るようアヤメに命令しました。
「いいか! もし逃げたりなんかしたら、ただではすまさんぞ。モルト、こいつを見はってろ!」
グレエンは寝室からでていき、菖蒲はしょんぼりベッドにもぐります。毛布とふんわりしたまくらからはモクレンのいいにおいがします。
「ねえモルト、ここはグレエンのベッドでしょ……」
「アヤメ、あいつのことは気にすんにゃ。あしたからはいそがしくにゃる。早く寝ろ」
そばでぐるりとまるまったモルトは目をつぶります。
「うん……ありがとう」
探していた本を女王に運ぶアリや下に上がる階段のアリアドネとカメ、底なし部屋に落ちれば魚やわたり鳥に流れ星。干しわらの王子さまのもとにやってきて、お芝居までしています。おどろくような物語に興奮しっぱなしの菖蒲は、まだまだ起きていたかったのですが、目を閉じると深い眠りに落ちていきました。
つぎの朝。やわらかな太陽の光は早く起きてと菖蒲の顔をなでます。大きなあくびをしてからカーテンを引き、窓の戸をいっぱいに開くと、さわやかな風がすうっとふきぬけ、菖蒲の髪はさらさらなびきます。
「やっぱり夢じゃないんだ……なんてセリフ、ぜったいに言わないわ。だって、夢でもそうでなくっとも、すてきなお話しはいつまでも見ていたいもの」
菖蒲は体を思いきりのばし、青空を雲といっしょに丸ごとすいこみました。
「アヤメ、あいつからの伝言だ。「風呂をわかしておいた。そこに新しい服も置いてある。着がえたら庭にこい」」
モルトはそう言ってあいさつもせず、外へ走り去ってしまいました。
「そっか、おしば……」菖蒲はすぐ口に手をあてます。
ラベンダーの香るサニタリールームは花がらのトルコタイルでいろどられ、真ちゅう蛇口のついた洗面台と奥のバスルームには白くてなめらかな卵型のバスタブが見えます。
「まあ、なんてすてきなのかしら」菖蒲は声をあげ、すぐに服をぬぎ、色とりどりの花をうかべた湯につかります。「ああ、ジャスミンのいいにおい。人生最高のお風呂ね」
おりかさなるふわふわのタオルを広げ、ぬれた体をふいて服を着がえ、軽やかな足どりで庭にむかいました。
庭の四つ辻のちょうどまんなかに立つガゼボでグレエンとモルトは待っていました。ダマスク織りのテーブルリネンがしかれた丸テーブルには焼きたてのパンと野菜スープ、プレートにはオムレツとサラダ、ピンクのティーポットまでならべてあります。
つばの広い白いぼうしをかぶり、レースのワンピースの菖蒲はくるりとまわり、グレエンはやさしい農夫の顔になります。
「服ぴったりでよかった。ぼうしはすこし大きいかな」
モルトは大きなせきばらいをします。
グレエンはすっと立ちあがり、菖蒲のイスを引きます。
「ありがと……」
グレエンは大きなせきばらいをします。
モルトは笑いながら、「ふたりともダメだにゃあ。芝居をわすれ……」
菖蒲とグレエンは大きなせきばらいをしました。
「アヤメにはこの庭の手入れをしてもらう」
おいしい朝食とお茶をしかめっつらで楽しんでいると、グレエンは言いました。
「わたしにできるかしら」
「もちろんできるさ。リリィのだいじにしていた庭だからね」
そう言ってグレエンは庭の草花について話し、菖蒲は図書館で草花の図鑑やガーデニングの本を思いだしながら聞いていました。
「ご主人さま、むこうの畑はなにもしないのですか?」
菖蒲は遠く納屋のまわりに広がる小麦畑を見て言います。
「ああ、あそこは……うん、気にしなくていい」
「そうですか」
すぐにも収穫できそうな、たわわにみのる小麦を気にしなくていいだなんて。菖蒲はすこしふしぎに思いました。
「それよりアヤメ! はやくメシ食べて庭いじりしよう! チョウチョ追いかけて穴ほりするんだ」
「ねえお仕事なのよ、モルト」
「そうさ、ネコの仕事はいつものんびりいそがしいもんなんだ」モルトは自信たっぷりに言いました。
夕食後、農夫は白馬が脱走していないか、馬小屋の見まわりをするよう菖蒲に命令します。農具にまぎれた青い剣をさりげなく手に持つとみんな集まり、馬小屋会議の始まりです。
「むかし、ひとつの大きな国がありました」と、アルビレオは語ります。「それは領域を統べるほど強大な王国で、王の支配により雲にまでとどくほど高い建物が林立し、たくさんの人を速く運ぶ乗り物、どこでも話せるべんりな機械など、生活を豊かにする技術はまたたくまに進歩をとげました。ただ不信という種もまきました。ちいさな疑いは根を広げ、やがてゆがんだ芽をだします。それぞれ正しいと思う話に花が咲き、たくさんの正義の実を生みました。すると都市には城壁が、家には何重ものカギがかけられるようになりました」
「そのような時、わたしたちの祖先はある秘密を知り、だれも知らない山あいにうつり住むようになりました」と、グレエンは言います。
「ある秘密とはなんですか?」
「王国の繁栄には裏がありました。領域を統べる王は闇、つまり影と手をくんでいたのです。しかし長くはつづかなかった」
「たったひとつの嘘から平和はうしなわれ、領域全土に荒廃をもたらす大きな戦争がおきました。この領域の栄枯盛衰の歴史です」と、アルビレオは言います。
「オレの国もその戦争でなくなったんだ」モルトは悲しげに言いました。「約束が力をもったのはそれからさ」
菖蒲はモルトを抱えあげてほおをよせ、『干しわらになった王子さま』の話しをみんなに聞かせました。
「なるほど、そんなことが……」グレエンはすこし考え、言います。「わたしが風車の地下に行った時は、倉庫に赤い指輪をかけたわら束と青い剣しかなかった」
「でも王子さまを置いてきたのは、たしかにお城の王座よ」と、菖蒲は言います。
「おそらく」グレエンはあごに手をあてます。「王子がわらになったのはアヤメさま、あなたと関係あるのかもしれません」
「会ったことも、話したこともないのに?」菖蒲はおどろきます。
「きのう、約束の力について話しましたね」と、アルビレオは言います。「青い剣はアヤメさまが手にするととくべつな力を発揮しました。つまり、王子はアヤメさまをまじえた大きな約束をだれかとしたのではないでしょうか。それでわらとなった」
「そっか」と、モルトはあいづちを打ちます。「だからアヤメさまだけオレたちの行けない王の間に行ける、というわけか」
「わたし、王子さまをもどす方法なんて知らないわ」菖蒲はうつむきます。「それに王子さまはなぜわたしを知っていたのかしら」
「知らないといえば、ひとつ気になるんだ」グレエンはモルトを見て言います。「王子の友人でヘレムなんて名の子ども、山あいの国にいたか?」
興廃の丘

さいしょの馬小屋会議から数ヶ月が過ぎた朝。
ひだつきのエプロンドレス姿の菖蒲は、ブリキじょうろを手につるバラのアーチをくぐり、庭のアガパンサスにあいさつをします。
ひとつひとつ名前をつけたパンジーに水をやり、ガゼボのそばでさわやかに香るお気にいりのギンバイカとおどり、ペパーミントをつんでハーブティーにします。食事の準備に家のおそうじ、服の洗たくまで大いそがしです。
観客のいない芝居は好評上演中で、菖蒲はものわかりのよい召使いとして主人からとても信頼され、モルトやアルビレオと仲よしになります。
馬小屋会議は週に一度、日曜日の夜に開かれました。しかし王子さまをもどす方法がわからず、闇を打ちやぶるための作戦を立てられないため会議は平行線のままです。
あれから菖蒲は風車にいきませんでした。闇に気づかれるかもしれませんし、グレエンのそばがいちばん安全だと考えたからです。いっぽう風車は大きな時計がチックタクと時をきざむように、風のない日も仕事を休まずまわりつづけていました。
家事を終えた菖蒲はアフタヌーン・ティーにみんなを呼ぶため、畑へむかいます。
「ご主人さま、お茶の時間です」
グレエンとモルトは城塞で見張りをする戦士のようにするどい顔で目をこらし、空に流れる雲を見つめていました。
「お天気、かわりそうですか?」菖蒲も額に手をあて空をあおぎます。
「よし!」グレエンはパチンパチンと大きく手をたたき、「いつもよくはたらくアヤメへのごほうびに、日曜日はとっておきのピクニックにでかけよう」。
「まあ、とっておき! なんてすてきな言葉なの!」菖蒲はうれしそうにはしゃぎます。
闇に襲われるかもしれないと菖蒲は家のまわりしか自由に歩けませんでした。でもほんとうは小麦畑のむこうがどうなっているのか、知りたいと思っていました。
ピクニック前日の夜。あまりのわくわくに菖蒲の目はぱっちり開いて、まっ暗な天じょうをいつまでもうつしていました。
「ねえ知ってる? たのしみはたのしみにしている時がいちばんたのしいのよ、アヤメ」
もうひとりのアヤメは寝てしまったのでしょうか、部屋は静まり、そばで丸まっているモルトのかすかな寝息まで聞こえそうです。青白い月明かりはレースのカーテンをぬけてゆかに窓の陰影をぼんやりえがき、ときおりゆらゆらとすきま風にゆられ、光と影がワルツをおどっているようでした。
菖蒲は頭を起こして過ぎてしまった今日を思いめぐらしていると、コツンコツン。だれか窓をたたいたのか、それとも小石でもあたったのでしょうか。菖蒲はモルトを起こさないようにそっとベッドからはなれ、そばにかけたカーディガンをはおり、戸を開けて外をのぞきます。夜空をくりぬく、まん丸の月に照らされた庭はすやすや眠っていました。
「気のせい、だったのかしら」
菖蒲が家にもどろうとすると、ガゼボのむこうから影絵がひょっこりあらわれます。
「こんばんは、わたしはアヤメ。あなたはだれ?」
目の前に立っていたのは、こいむらさき色の長い髪、左右の瞳に一点の星がかがやく美しい顔立ちの少年のかたちをした影でした。
少年の影は菖蒲など気にせず、地面の土にえがいた丸をぴょんぴょん飛んでいました。
「けーんけーん、ぱっ」菖蒲は声をだして少年のあとにつづきます。
「ねえ、これだけじゃかんたんすぎよ。わたしがもっとむずかしくしてあげる」そう言うと棒きれで丸をいくつかかきたします。
少年は菖蒲の作った丸を器用にこなし、こんどは少年が丸をふやします。黙ってけんけんぱを交互にくり返し、ついにバランスをくずした菖蒲はつまずいてしまいます。
「あーあ、わたしの負け。あなたと遊べて楽しかった。おやすみなさい」
そう言って菖蒲は少年に手をふります。
「わたしの名はイシュ。父を待っている」
悲しみをまとう、はかなく澄んだ声に菖蒲は思わずふり返ると、そこにはだれもいませんでした。
とっておきの日は青空で風もおだやかです。花がらチュニックにカプリパンツ姿で庭の仕事をいつもより早めにすませます。そでなしの白いワンピースに着がえてから大きなバスケットを持ち、菖蒲とグレエンとモルト、それにアルビレオも連れてピクニックに出発です。
小麦畑のあいだにのびる小径を進むと風車は遠くに消え、整然とならぶ黄緑色のポプラ並木が見えてきました。並木道にそってしばらく歩き、てらてらかがやく小川にぶつかり、グレエンは対岸の雑木林をさしたので、菖蒲はくつをぬぎ、足を水につけます。目のさめるほどひんやりつめたく、「ひゃっ」と声をあげ、あわてて対岸へわたります。美しいシラカンバ林の木もれ日はモザイクのようにしめった土をてらし、うっすら蒸気をあげていました。
プチプチプチ、ポキポキポキ、パリパリパリ。地面に落ちる木の実や枝や葉を足でふみつける音は、ここちよいリズムで、すっかり気分のよくなった菖蒲は歌を歌いはじめました。
きまま きまま ネコはいつもきまま
きまま きまま カゼはいつもきまま
きまま きまま ソラはいつもきまま
きまま きまま クサはいつもきまま
「なんだその歌?」グレエンは首をかしげます。
「おれのつくった歌さ。気ままにゃものをにゃんでも歌うんだ」
モルトは偉大な作曲家のように言います。
「庭で水やりをしていると、モルトはいっつも歌うから、おぼえちゃったのよ」
「つまらない歌詞だなぁ」と、グレエンはあきれます。
「だからいいのさ、グレエン。かこくにゃ労働には、にゃんでもない歌を歌えば気がまぎれる」
「モルト、おまえは菖蒲のそばにいるだけじゃないか」
「それはちがうぞグレエン。オレはアヤメが逃げないよう目をひからせているのさ」
「ずいぶんのんきなもんだ。アヤメは逃げないだろうし、明日からオレのそばで仕事するかい、モルトくん?」
「ご主人さま、それはそれはなんてすばらしい案なのでしょう! そうしていただければ、わたくしはモルトのへんな歌になやまされずにすみますわ」菖蒲はいたずらっぽく言います。
「きまま きまま ネコはきまま!」
モルトは歌いながら先頭に走り、わざとらしくしっぽをふります。
「まあ! 知らんぷりして!」と、菖蒲は大笑います。
こんなに楽しそうにして、闇の監視をわすれたのでしょうか。いいえ、じつはこれも芝居で、農家の休日というひとつの場面を演じていたのです。
シラカンバの林をぬけた先には、おだやかな風のふく、青々とした草原がどこまでも広がっていました。
「ここがとっておきの場所、興廃の丘だ」
「なぜ興廃なんですか?」菖蒲はグレエンに聞きます。
「ここはむかし、高い城壁にかこまれた都市だったが、大きな戦争によりほろびた。いまはアリ一匹住めないほどけがれた土だけがのこっている」
「こんな美しい丘で争いなんて信じられない……」
菖蒲はまゆをよせ、なびく髪に手をあてます。
「妻のリリィはここで闇にのみこまれた」グレエンは言いました。「あの日、ふたりで丘をながめていた。とつぜん、空から黒い大蛇が襲ってきて、リリィの手をつかみ逃げようとしたが、彼女はわたしの手をふりほどき、大蛇に立ちむかっていった。きっとリリィは覚悟していたのだろう」
——リリィ。菖蒲はすぐにわかりました。寝室のポストカード立ての女です。
「すべての秘密を今晩、最後の馬小屋会議でつたえよう」
グレエンからの終幕の予告に、菖蒲はなにもこたえられませんでした。
「おーい、おふたりさん!」遠くでモルトが呼びかけます。「ぼけっとしてにゃいで、はやくランチにしよう!」
グレエンはうつむく菖蒲の顔をのぞき、にっこり笑い、軽々と肩にのせて走ります。
みんなでピクニックシートを広げ、バスケットからグラスとお皿を取りだせばランチタイムのはじまりです。グレエンは野菜のサンドイッチをおいしそうにいくつも食べました。
菖蒲謹製サンドイッチは食パンから手作りです。粉やイーストをまぜあわせてぬるま湯をいれ、まとまったならバターをもみこみ生地をこねます。発酵させて生地をくるくる丸め、四角い型でもう一度寝かせ、石窯で焼きます。なんどやってもうまくふくらまず、カチカチの石っころパンも、ふっくらと焼きあげられるようになりました。庭でとれたきゅうりやトマト、ふわふわスクランブルエッグをパンにはさみます。もちろんバターにマヨネーズソース、マスタードもかかさずに。
グレエンやモルト、アルビレオだって菖蒲の料理をいつもほめますし、失敗したならみんなで大笑いしました。菖蒲はうれしくて、もっともっとおいしい食事を作ります。
ジャガイモのグラタンにデザートのフルーツまでおなかいっぱい食べたあとは乗馬です。アルビレオに乗れるのは主人である王子さまだけですが、とくべつにゆるしてくれました。
グレエンは菖蒲をアルビレオの背にのせます。まるでソファのようにふかふかな乗りごこちで、かけだすとまわりの景色はひゅっとうしろに流れ、あっというまにグレエンは遠くにいます。
「アルビレオには見えない翼があるのね。だってふんわりういているみたいなんですもの」
「わたくしの祖先は天をかけていたと聞きます」と、アルビレオは言います。「でもほかの馬でおなじようにしてはなりませんよ。かならず痛い思いをしますから」
シロツメクサのかんむりをグレエンの頭にのせて王さまごっこもしました。お城のくらしにたいくつなアヤメ姫を白馬アルビレオにまたがる騎士グレエンが大冒険につれだすお話しです。
「ちょっとまて!」モルトは不機嫌そうに言います。「にゃんでオレは従者役にゃんだよ!」
「にゃんにゃんって。従者のモルトはネコみたい」
「オレはずっとネコだ!」
みんなピクニックがいつまでもずっとずっと続けばいいのに、と思いました。でも、わかれはむかえるのではなく、やってくるものだと、その夜に知ることになりました。
王子さまの約束

菖蒲はこの領域でふたつの悲しい夢を見ました。ひとつめは、興廃の丘へピクニックにでかけた日の夜です。
一本のリンゴの木がみるみるうちにしおれ、菖蒲は枯れないよう懸命に水をやりますが、うまくいきません。リンゴの木にお願いしても、抱いてやっても、なでてもうまくいかず、苦しむリンゴの木をただながめるしかできませんでした。
ついにリンゴの木は倒れて塵となり、天から低い声が聞こえてきます。
「娘よ。どんなに請うても、おまえは一本のリンゴの木ですら、救うことはできない」
菖蒲は目をさまし、ぼんやり天じょうを見つめます。
「わたしのもとに来て」
————王子さまがわたしを呼んでいる。
菖蒲はベッドからすべりおり、着がえて家を飛びだします。
「ここは……どこなの?」
闇におおわれた空には赤黒くそまる巨大な蛇がうねり、そこかしこに聞こえる断末魔のさけびや慟哭、ときの声は菖蒲の耳奥をかきまぜます。まるでおぞましい戦争の渦中にほうりだされたように土ぼこりをまいあげ、地面をゆらす軍隊の足音に火薬と鉄、じっとりした血の臭気は鼻にまとわりつき、菖蒲は体を折り、吐きけをもよおして口をおさえます。
ギロリとにらみつけられるような強い視線を感じた瞬間、思わず顔をあげると眼前には大蛇がいまにもおそいかかろうと口をいっぱいに広げています。あまりの恐怖に逃げなければと気はあせるも、両足はガタガタふるえ、体もまったくいうことを聞きません。
するどいきばの先たんから鮮血をしたたらせ、口の奥から青白い手のようにわかれた舌がのびて菖蒲の首をしめあげ、ずんずんせまります。
もだえる菖蒲は全身を緊張させ、目をギュッとつむったその時、小麦畑の方角から青い閃光が一直線に大蛇の赤い眼をさし通し、菖蒲をつつみます。
「走れ! 走れ!」身をよじる大蛇のむこうに立つ戦士はさけびます。
「グレエン!」
大蛇にふり落とされた菖蒲は、グレエンの持つ青く光る剣がさす風車目がけ、夜陰を切って一心不乱に走ります。
命からがら風車に飛びこみ扉を閉めると背にしてよりかかります。息をあげ、ひたいから流れるつめたい汗をぬぐい、悪夢から遠ざかるようによろよろと奥の階段へちかづきます。
「アヤメさま」
菖蒲はおどろいて肩をびくりとさせ、声のするほうに体をひねります。
「モルト!」菖蒲は涙をポロポロこぼし、「グレエンが……グレエンが! どうしよう!」
「アヤメさま、どうかおちついて。グレエンには王子の剣があります。それよりこれを」
モルトはガーネットのような赤い指輪のついた金の首かざりをくわえていました。
「王子さまの指輪……なぜわたしに?」菖蒲は目をぬぐい、たずねました。
「時はつきました。闇は山あいの国を、いいえ、この領域を、そしてアヤメさまを消そうとしています」
「でも、わたしたち気づかれないよう芝居を!」
モルトは首を横にふります。
「あれは時間かせぎほどのまやかし。すでに闇はアヤメさまに気づいています。ここにいればめちゃくちゃにされるでしょう。あの闇は冷酷無比です」
「そんな……」
「よくお聞きください。オレたちはアヤメさまにすべてをたくします。お願いです、王子をどうか、どうかもとの姿にもどしてください。そうすれば闇を打ちやぶることができるはず。これはグレエンからの伝言です。「赤い指輪はきっとアヤメさまの役に立つでしょう。ただしお気をつけください。指輪の力と引きかえに、たいせつな思い出をわすれさせる【忘失の約束】を守らなければなりません」」
菖蒲は首かざりを身につけてモルトをかかえあげます。
「オレはこれから王にすべてをつたえるため、山あいの国にもどります。でも生きて帰れるかどうか」
モルトの毛は逆立ち、わなわなふるえています。
「わたしの大好きなキジ三毛ネコのモルト、あなたと約束する。王子さまをもとの姿にもどして帰ってくると。それまでぶじでありますように」
菖蒲はモルトとひたいを合わせ、目を閉じ、ふっと息をふきかけます。するとこわばる体はゆるみ、いつものおだやかなモルトにもどりました。
「アヤメさま、感謝します。オレたちは闇をおそれ不安でした。でもアヤメさまとのきらきらかがやく生活は、すべてわすれるほど楽しい日々でした。アヤメさまはオレたちのきらめく星、雲のあいだからふりそそぐ太陽です。オレも約束します。アヤメさまを信じて待つ、と」
モルトは菖蒲の手からするりとぬけて、外の闇に走りさりました。モルトを見送った菖蒲はいそいで地下にある王の間にむかいます。
「大きな蛇がわたしを食べようとした時、グレエンの手にある青い剣はアヤメ、あなたを守ったわ」
「そうよ」と、菖蒲はアヤメに言います。「だからやっぱり王子さまの約束にわたしが関係している」
王の間は王子さまをもどしたあの日からピタリと時間が止まっているようでした。菖蒲は王座につづく石階段をのぼり、灯りに照らされる王子さまを抱きしめます。
「わたしの名はアヤメ。あなたとあなたの友だちをたすけたいの。あの約束をおしえて」
菖蒲の首にある赤い宝石の指輪はかがやきはじめ、強い光にみたされます。燭台の炎はゆらゆらゆれ、王座にすわる黒く燃える影と、青い剣をかまえた小麦色の髪の少年が見えました。
——————
「むかし、おまえの国は我とひとつの契約を結んだ。それは国の安寧と引きかえに王の子ひとり国から追いだすこと。しかし追放する子になにもつたえてはならない。また子は自発的に国をでなければならない。干しわらの王子、おまえのことだ」
「そう、そのためわたしはここにきた」燃える影に王子さまは不敵な笑みをうかべて言います。「きさまを打ちやぶるために。真実をつたえられずとも大義はなせる。わすれたか、世を統べる王よ」
「なんだと」
「よく聞け! わたしはおまえとひとつの約束をする。わらとなり、かわききったわたしのくちびるを、この領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸の水によってうるおす。その時、青き剣はきさまを打ちやぶる力をえる」
「はっはっはっは!」燃える影は身をのりだし、「ついに気がふれたな。その女はどうして干しわらのおまえがヒトだと、まして王子とわかるのだ。かりに知ったとて、なぜおまえのためにありもしない庭の井戸とやらの水をあたえるというのだ」。
「不可能だからこそ、この約束には大きな力がある」王子さまは王座のそばに立つ菖蒲をじっと見て、目をほそめます。「どうした、疑いにのまれ、信じるのをやめた臆病な王よ、おびえたか?」
「なんたる侮蔑。追放されたガキめが!」影は黒い炎をゴオゴオ燃やし、王子さまを食いつくさんばかりです。「よかろう! 挑発にのった。しかし約束が果たされぬその刹那、その女もろともこの領域すべて滅ぼしたやしてくれるわ。さあ、いますぐわらとなれ!」
——————
王の間はふたたび眠りについたようにうす暗く、指輪はもとの赤色にもどっていました。
「あなたの物語にわたしが、わたしがいたわ!」
おどろく菖蒲の背後で扉はきしんだ音を立てて開きます。
おりてきた階段がこんどは下へとつづく階段になっているではありませんか!
不自然な本の空白、図書館の窓から見えた扉のない中庭、そして王子さまの約束。それぞれパズルのピースはつながりました。
菖蒲は王の間をあとに階段をおりていきます。
こうして、干しわらになった王子さまを助けるための長い長い旅は始まりました。
通路の消失点

まっ白な壁の通路は、あまりの長さに先が見えません。まるで宙に浮いているような白い窓が等間隔にならび、ガラスはなく、のぞいても外に広がるのは白でした。
しばらく歩いていると、おりてきた階段はだんだん遠くなり、やがて周囲の白とまじりあい、消えてしまいます。
「どこまでつづくのかしら」
終わりのない通路の消失点は黒いつぶのようでこちらにむかっていつまでも大きくなることはありません。菖蒲は目をこらし消失点を見つめていると気分がわるくなり顔を右にそむけます。
すると窓の下にちいさな文字が書かれていましたので、かがんで読みました。
ミエルモノガサキデワナイ
ケレドモミエナクバサキニワユケナイ
菖蒲は目をゴシゴシこすり、右目だけで消失点を見ると左側に点があります。こんどは左目だけを見ると右側に点があるのです。両目で見れば点は左右にひとつずつ、ゆっくりまん中によってかさなりました。それから通路の消失点を手でふさぎます。
「見えるものが先ではない。けれども見えなくば先にはゆけぬぞ、アヤメ」
菖蒲は物知り老人のつもりでふらふら歩きます。
ゴチン! 通路にひびくにぶい音。
「いったああい。もう!」頭のまわりに星がチカチカまたたきます。
ずきずきするおでこをおさえ、うらめしそうに顔をあげると木製の扉がありました。
「『前方注意』をそえてほしいわね。まったく!」
菖蒲は通路にもんくを言い、扉を開けて入りました。
雨にぬれる教室

窓の外は雨でした。
コンクリートのしめったにおいがする通路にはいくつかの部屋とそれぞれ上方に数字のない室名札がつきでています。
まるでどこか知らない小学校に迷いこんだようで、ちょっぴりドキドキした菖蒲はてきとうに開いたクリーム色の引き戸から部屋をそっとのぞきます。
「だれもいないわねアヤメ。おやすみかそれとも廃校だったりして」
菖蒲はぶるぶるっと肩をふるわせ、となりまたとなりと順番に教室をのぞき、水たまりのある部屋で足を止めました。
スチール丸パイプのフレームに木製の座面、背もたれ、天板のついたつくえとイスは六列五段に整然とならび、制服を着た男子や女子の大きなビスク・ドール生徒たちがカサを広げてすわっていました。教室の天じょうはぬけ落ちたようにまるでなく、部屋全体が雨にぬれ、ジメジメした陰うつなようすに菖蒲の気分も暗くなります。
すると、ヒタヒタろうかを歩く足音がこちらにちかづきます。
「お、おばけ!」あとずさりする菖蒲。
「ほっほう、おばけとはしっけいな。きみは転校生かね?」
グレーチェックのスリーピースに濃紫色のネクタイをつけたフクロウは、黒いこうもりカサを手に肩をそびやかし菖蒲のまえにあらわれました。
「こんにちは」菖蒲はホッとして言います。「わたしは転校生ではありません、フクロウさん」
「ほっほう、きみ、わたしのことはセンセイと呼びたまえ。それに転校生でなければ、なぜここにいるのかね。さては新しい学校がいやでウソをついているのではあるまい」
「あの、わたしは……」
「ほっほう、すぐに教室に入りたまえ」
フクロウ先生はうろたえる菖蒲を雨の教室につれていきます。
「ほっほう、ところできみ、カサはあるのかね?」
「いいえ、先生。教室でカサはさしませんもの」
「ホッホー! 横着な生徒め。社会にムダはない。つねに備えをせよ!」
フクロウ先生は半分閉じた目で持っていたカサを菖蒲に貸し、おりたたみカサを広げました。
「ありがとうございます」
「ほっほう、時間はない。いそいで黒板のまえに」
バケツの水をこぼしたような床はつるつるすべり、菖蒲は手足をじたばた、腰をふりふり、なんとか教だんにたどりつきます。
「ほっほう、生徒諸君。このクラスに転校してきた生徒である」
フクロウ先生は淡々と早口でビスク・ドール生徒に言います。
「きみ、いそいで自己紹介を」
「こんにちは。わたしはアヤメです。よろしくおねがいします」
もちろん教室内のビスク・ドール生徒はビスク・ドールなので、だれも返事をしません。
「ほっほう。いそいで席は窓ぎわ、前から三番目へ」と、フクロウ先生は席をさします。「ほかのつくえにけっしてふれぬように! 席のずれは社会のみだれ!」
菖蒲はじたばたと席にむかい、びしょぬれのイスに腰かけます。
「ああ、これまでの学校生活で最低な日がたったいま、更新されたわ」
「ほっほう、さて生徒諸君、実に人生はふりやまぬ雨のようである。そのため教養をもってたちむかいまた……」
ザーザー、パチンパチン。フクロウ先生のたいくつな授業は、たえまなくふる雨音でほとんど聞こえず、服もしめり、菖蒲のがまんはついに限界をこえます。
「フクロウセンセイ!」菖蒲は手をあげ起立します。「なんにも聞こえません。となりの教室に移動できませんか?」
フクロウ先生は菖蒲をにらみつけて言いました。
「ほっほう。わたしはきみに意見をもとめていないし、立つよう指示もしていないのだが」
「でも!」
「ほっほう、わたしは『でも』という言いわけがましい逆説の接続詞がもっともきらいな言葉なのだ。わかるかね?」
「で……先生の声が聞こえなければ、だれも授業についていけません」
「ほっほう。生徒諸君はどう思うかね?」
ビスク・ドール生徒たちはなにも言わず、まるで雨音がヒソヒソばなしをしているようです。
「ほっほう、みな異論はないようだ」
「そんなのむちゃくちゃよ。だってしゃべれないもの」
「ほっほう。アヤメくんは、はなはだ社会ルールをわかっていないようだ」フクロウ先生はあざけるような目で菖蒲を見ます。「まぎれもない事実として、雨のふる教室ではみながカサをもち、授業を受ける。先生はわたしで、きみは生徒だ。わたしはきみに発言するようにも、立つよう指示してもいない。さらにきみのほか、どの生徒も不満はない。ゆえにこれは社会通念である。それにもかかわらず、わたしの授業をぼうがいし、風紀をみだす。この不良生徒め!」
「まあ! しつれいね!」菖蒲は声をあらげます。
「ホッホー、聞いたかね生徒諸君!」フクロウ先生は生徒たちにむけ、いかにも大げさに身ぶり手ぶりをしながら熱をこめ、大声でまくしたてます。「ホッホー、こういう無作法な不良生徒が社会において法と秩序をおびやかし善悪を他者に強制しかつ大通りを占拠して示威行為をし燃えさかる火にまきをくべるがごとく主観的批判を大仰にくりかえすホッホーらもこのようなホッホーにはじゅうぶん気をつけたまえホッホッホッホー!」
菖蒲はまゆをしかめ、ほおをふくらませてイスにすわろうとします。
「ホッホー、これからは指示にそむかぬように! わかったのなら返事だけをしてすわりたまえ、不良生徒のア、ヤ、メ、くん」
「……はい」
「ほっほう、よろしい。この機会に社会通念がいかに至要たるものか、諸君らにおしえたいと思う。それをつぎのホッホーで話そう。では休けいとする」
フクロウ先生は勝ちほこったように教室をでていきました。
ベーっと舌をだした菖蒲はとなりのビスク・ドール女子に耳打ちします。
「ねえ、ひどいと思わない? なんにも聞かないでホッホーホッホーって」
チュンチュン、コツコツ。
ビスク・ドール女子から鳴き声とつつく音がします。雨があたっているのでしょうか。そうではないようです。ビスク・ドール女子に耳をあてると中からわずかに音が聞こえるからです。
菖蒲はカサをさすビスク・ドール女子をゆすります。チュンチュン、コツコツ、チュンチュン、コツコツ。重たいビスク・ドール女子をぐいぐい動かし、さぐっていると……ガシャリン! こなごなにくだけちったビスク・ドール女子の悲鳴が教室中にひびきます。
「きゃあ! フウロウセンセイに見つかったらどうしよう!」
菖蒲はあわててバラバラのビスク・ドール女子にちかづきます。
「ちゅんちゅん」小鳥がひょっこりあらわれて言いました。「たすけてくれてありがちゅん」
「あなたは、スズメさん?」
「雨宿りのつもりが、とつぜん閉じこめられてしまってね。暗いし、遠くでぶきみなさえずりは聞こえるし、ほんとこわかっちゅん」と、スズメは言います。
「はじめまして、わたしはアヤメよ。もしかしてほかにもスズメさんはいるのかしら」
それでこんどは前のビスク・ドール男子をこわしてみます。
「ちゅんちゅん、たすけてくれてありがちゅん。雨宿りのつもりが……」
菖蒲は1羽目のスズメと目をあわせ、うなずきます。うしろのビスク・ドール女子も、そのまたうしろも、われたビスク・ドールからスズメが一羽あらわれました。それでカサをほうり投げ、教室中のビスク・ドール生徒をこわします。いやみったらしいフクロウ先生の顔を思いうかべ、投げたりけったりふんづけたり。ぜんぶで二十九羽のスズメたちは教だんに集まりました。
「さて、これからどうしよう」菖蒲はスズメたちにたずねます。
「ちゅんちゅん、雨がふっているからぼくたちは飛べないちゅん。どこか晴れている空はないかな」
このままではフクロウ先生がスズメたちを閉じこめてしまうでしょう。なにかよい方法はないものか、菖蒲は教だんを探してみると引きだしに新品の十二色チョークの入った木箱を見つけました。
「これだわ!」
菖蒲は王子さまの首かざりから指輪をはずして右手の中指にはめると赤い宝石は炎のように燃えてかがやきます。
「きまま、きまま、ネコはいっつもきまま」
モルトの歌を口ずさみ、新品のチョークで黒板に緑色の草やシロツメクサに青い空、白い雲、遠くには雑木林を描きました。みんなでピクニックにでかけた興廃の丘の絵です。
「これはわたしのたいせつな思い出の場所なの。あなたたちにぴったりな青空があるわ」
菖蒲は先生のようにスズメたちに興廃の丘についておしえてあげます。
「……そういうわけで、あなたたちがのぞむなら、黒板にむかって羽ばたいてみましょう」
アヤメ先生のすてきな授業にスズメ生徒たちはすっかり感心して拍手喝采です。
「ちゅんちゅん、あそこなら自由に飛んだり、あの林に家をつくったりできちゅんね」
「そうだちゅん」
「よし、きめちゅん」
「アヤメセンセイ、おしえてくれてありがちゅん!」
「うれしいわ。あなたたちにお願いがあるの。おなじように空を飛びたい鳥たちを見かけたら仲間にむかえてほしい。それとキジ三毛のネコと白い馬と大男の農夫にアヤメは元気だとつたえてもらえる?」
「もちろん。約束しまちゅん!」
スズメたちは声をそろえてこたえ、黒板の絵にむかって元気よく飛びだします。アヤメ先生は手をふり、生徒たちの卒業を見とどけてから指輪をはずし、首かざりにもどします。そして学校と友だちをわすれてしまいました。
「ホッホー!」顔をまっ赤にしたフクロウ先生は、くちばしをふるわせて言います。「なんてことをしてくれたのだ!」
「フクロウセンセイ。生徒はみんな巣立っていきました」菖蒲は笑顔で言います。
「ホッホー、きみはわたしをバカにしとるのかね」
「いいえ、かわいいスズメたちがぶじに大空へ飛び立ててよかった」
「ホッホー。無責任な自由のどこがよいのか。もし捕食者にでもねらわれたらどうするのかね! もし他者を傷つけでもしたらどう責任をとるつもりなのだ。きみは仮定もせず結論をみちびくつもりか!」
「生徒たちを信じればいいのよ、フクロウセンセイ。スズメたちは青空をもとめ、翼をもっています。わたしにはないすてきな個性だから、それをいかせる場所をおしえてあげただけ」
「ホッホー、詭弁だな」フクロウ先生は吐き捨てるように言います。
「あら、そうかしら。フクロウセンセイもほんとうはそうしたいんでしょ?」
「ホッホー、なにをバカな」首をくるくるまわすフクロウ先生。
「だって番号のない教室とか新品の十二色チョークとかスーツとか、どこかで聞いた理屈をこねこね。フクロウセンセイはなれないものにムリしてなろうとするから」
「ホッホー、無礼者!」フクロウ先生は羽を大きく広げ、ツバを飛ばしてどなりつけます。
「フクロウセンセイも望むなら、あの空で自由に飛べるのよ」
「ホッホー、きみのような不良生徒はいらん。退学だ。すぐにでていきたまえ!」
「さようなら、フクロウセンセイ」菖蒲は手をふってわかれます。
教室にのこされたフクロウ先生は顔をあげ、黒板の絵をさびしそうにながめました。
「ほっほう。わたしに希望はまだのこっているだろうか」
ぽつりとそう言ったフクロウ先生はスーツをぬぎ、黒板にむかって飛んでいき、絵は雨水に流され、消えてなくなります。
やがて雨はやみ、だれもいない教室ではビスク・ドールのかけらが陽にあたってキラキラとかがやき、水たまりに青空をうつしていました。
騒々しい法廷

「セイシュクに! セイシュクに!」
アリの巣裁判所の裁判長はさわがしい法廷を静めようと声をあげます。しかし、なかなか話し声はやみません。
裁判所のうしろでは働きアリたちが女王アリのためにせわしなく食料や部屋をととのえていました。
菖蒲は砂をかためた傍聴席にすわって裁判のゆくえをぽかんとながめています。なにがおきているのかわかりませんし、みんな黒いアリで見わけもつきません。
「サイバンチョウ。ワタシはジョオウのためにハタラきツヅけてきましたし、これからもそうするつもりでした。それをショクムホウキのヒトコトでカタヅけてヨいでしょうか!」
原告らしい集団のうち一匹のアリは裁判長アリに主張します。
「そうだそうだ!」ほかの原告アリたちは同調します。
「ワタシタチハタラきアリのジョウキョウをまるでリカイせず、いきなりカイコはフトウではないかといっているのです」
「そうだそうだ!」
「ではなぜ、まずデンタツアリにツタえなかったのだ」と、被告アリは反論しました。「シレイアリのメイレイをまってからコウドウするのがルールではないのか。それをおマエたちハタラキアリはレツをミダし、ハタラキアリゼンタイのイノチをキケンにサラした!」
働きアリ側の弁護アリは異議をとなえます。
「コウセンテキなテキにレツをミダさずにマつのはジメツしろとイっているようなもので、クロアリケンポウダイジュウサンジョウ、コジンのイノチのソンチョウにハンしている。また、ハタラキアリとシレイアリとのタイグウがチガうのはモンダイである。イノチをカけてゼンセンにタつ、ハラタキアリとブルジョアリーのサベツは、クロアリケンポウダイジュウヨンジョウにイハンしている」
「そうだそうだ!」。
「シッケイな」被告アリは鼻息あらくして言います。「ワレワレもジョオウのためにこのミをササげている」
「しかし、ハタラキアリのリスクとイノチはケイイではないか。まさかキミタチはジョオウのおキにイりだからと、ふんぞりカエっているのではあるまい」
「そうだそうだ!」
「ブジョクザイである!」被告アリは前足をだして訴えます。
「ブジョクといったらキミタチだろう!」働きアリ側の弁護アリは言います。
「そうだそうだ!」
「いいや、キミたちだ!」
法廷内はいちだんと騒々しくなります。
「セイシュクに! セイシュクに! ホウテイですぞ。ヒンイをカくことナきように!」
裁判長アリは木づちをトントンとたたいて静聴をうながすものの、さわぎはおさまりません。
菖蒲はとなりで傍聴しているアリに、なぜこんなにさわがしいのかをたずねます。
「クビになったハタラキアリが、シュウダンソショウをオこしたのですよ」と、アリは言いました。
「どうして仕事をクビに?」
「ヒエアリキーというやつです。ジョオウのメイレイからニげたのがゲンインのようで」
「女王の命令、ですか?」
「ええ、コロニーのジョオウはアタラしいマクラに、ホンをショモウされたのです。なんでもチエがつくとか。それでハタラキアリはトショーカンのモリにハケンされたそうですが、ホえたけるキョダイカイブツにオソわれ、イノチからがら、ニげてきたらしいのです」
「まさか」菖蒲は図書館のことを思いだします。「王子さまの本をやぶいたアリたちかしら」
「ジョオウはオカンムリでハタラキアリゼンインカイコし、ベツのアリをヤトうとコロニーはオオサワぎ。ワレワレアリはコロニーでシゴトをウシナえばルンペンプロレタアリとなってサイシュウショクはムズカしいのです。それにジョオウにジキソはできないので、こうしてサイバンショにうったえているというわけです」
「そんなのおかしいわ。ちょっとうまくいかないからって、なにも解雇しなくても」
「いえいえ、ここはまだヨいほうですよ。ソショウをおこせるサイバンショすらないコロニーはざらですし、モンドウムヨウでシケイなんてジダイオクれもハナハダしいコロニーもケッコウありますから」
「そ、そんな!」菖蒲は目を大きくしておどろきます。「アリの領域ってそんなにきびしいの?」
「はい。アリオロギーにシバられているんですよ」傍聴アリは足をくみ、言います。「ここもムカシはそうだったのですが、プロレタアリによってカイゼンされたのです。サイキンはジョウホウカのナガれで、キュウタイイゼンとした、タンジュンなシュジュウカンケイはフルクサいとカンガえるワカいアリもフえました。ワタシのようなジャーナアリもペンでタタカっています」
傍聴アリはとくいげにペンをクルクルまわします。
「なんだかよくわからないけど、女王におしえてやらなきゃ」
菖蒲は傍聴席をすっくと立ち、裁判長アリにむかって言いました。
「あの、みなさーん。お話しのところすみません」
いくら声をかけても、みんな自分の発言に夢中で、菖蒲など見むきもしません。
「みなさん! ちょっといいですか!」
菖蒲が大声で叫ぶと法廷内は水を打ったように静まります。
「この裁判、わたしも関係していると思うんですけど」
一匹の原告アリが菖蒲をじいっと見て、「あぁぁっ! こいつです、サイバンチョウ! ワレワレのシゴトをボウガイしたハンニンアリは!」
「ちょっと、わたしはアリじゃないわよ!」
「ハンニンミズカらシュッテイしてくるとは、なんてふてぶてしいカイブツだ!」
「カイブツってのはずいぶんしつれいね」菖蒲はむっとして言います。「そもそも女王がわるいのよ」
「ワレワレのジョオウをワルモノあつかいするとは!」
「ブジョクザイだ!」と、被告アリ。
「そうだそうだ!」と、原告アリ
「よろしい!」裁判長アリは強い口調で菖蒲に命じます。「コエデカフテブテシカイブツアリよ、ショウゲンダイへ!」
「わたしはふてぶてしくも、アリでも、カイブツでもないわよ! ちょっと声は大きいけど」
菖蒲は土の上をずかずかと歩き、砂でかためた証言台にどっしり立ちます。
「こりゃあオモシロいコトになったぞ」興奮して身をのりだすジャーナアリ。
「わたしはあなたたちの女王に言いたいことがあるの。まくらにするために本をやぶっていけないし、知恵をつけたければ本は読まなきゃダメよ。わかった?」
さわがしかった法廷内はしんと静まり、アリたちはひややかな目で菖蒲を見ます。
「なによ、なんでみんなだまるわけ?」
裁判長アリは二、三回せきばらいをします。
「それだけかね?」
「そうよ。そもそも女王の命令がまちがえてるんだから」
「ハンケツ!」裁判長アリはトントンと木づちを強く打ちならします。「ヒコクアリはムザイ、ハタラキアリのカイコはセイトウである!」
「まってまってまって! 働きアリさんへの命令がまちがっているの! なんでおかしな判決になるのよ」
裁判長アリはあきれたように言います。
「ホンサイバンはジョオウのメイレイイハンをシンギしている。キミのショウゲンでイハンがカクショウされたのだ。ジョオウメイレイはゼッタイである。ムホウアリをソソノカすモノはコロニーをサらねばならない」
「そんな、わたしはただ……」
「キミのカンガえはキミのコロニーではユルされるのかもしれんが、ワレワレのコロニーでミガッテなセイギをフりかざすのをヤめてもらいたい。ジダイのチョウリュウだとかにキョウミはないが、チシキアリのメンドウなシュギシュチョウのおかげでワレワレのコロニーもフンキュウしてメンドウなのだ。こんなムダなサイバンよりコロニーカクダイのためにハタラいたほうがどれだけケンセツテキか」
「でもこんなのおかしい!」
「もういいさ」働きアリたちはぬけがらのような顔で力なく深いため息をつきます。
「これにてヘイテイ!」
ルンペンプロレタアリと菖蒲をのこし、みんな裁判所からでていきました。
「アリさんたち、ごめんなさい。ぜんぶわたしのせいね」
「あやまってもしょうがない。ジョオウのメイレイをヤブり、ニげたのはワレワレのセキニンだからね」
「これからどうするの?」
「ショクとイエをウシナったルンペンプロレタアリがどれほどミジめか、キきたいのかい?」
「じゃあ、わたしがあなたたちの女王になる」
とぼとぼ去ろうとするルンペンプロレタアリたちに菖蒲は言います。
「キミが? コロニーもないくせに」
ルンペンプロレタアリたちは見合わせ、あきれたように笑います。
「ジョオウとなってワレワレになにをしろと? バカバカしい」
「そうかしら。これから新しいコロニーを作るのよ。あなたたちがね」
「ワレワレが? イッタイどこに?」
「それはね」と、菖蒲は言います。「わたしの知っている興廃の丘はとても汚れているの。そこをきれいにしてコロニーを広げる。報酬は丘ぜんぶよ。だってだれも住めないんだもの」
「そんなツゴウのいいバショなどホントウにあるのかい?」ルンペンプロレタアリたちは言います。
「もちろん約束する。でもわたしは前の女王とちがい、命令も要求もしない。あなたたちで考えて仕事をしなければならないから、とってもたいへん。あなたたちが望むなら、すぐにその場所を紹介してあげる。どうかしら?」
ルンペンプロレタアリたちはわらわら集まって話しあいます。
「キまりました」代表アリが言います。「ワレワレはあなたをジョオウとミトメます」
「よかった。交渉成立ね」
菖蒲は王子さまの指輪を右手の人差し指にはめて、宝石は炎のように燃えてかがやきます。それから指を地面の土につきいれるとすぐに深い穴ができました。
「この穴は興廃の丘につながってるわ」
ハタラキアリたちはわあっと歓声をあげます。
「あなたたちにお願いがあるの。おなじように仕事をなくした者たちを見かけたら仲間にむかえてほしい。それとキジ三毛のネコと白い馬と大男の農夫にアヤメは元気だとつたえてもらえる?」
「アヤメジョオウのおコトバ、タマワりました」
アリたちは菖蒲女王の前に整然とならび、頭を深く下げてから一列でとっとこ穴に入っていきます。
菖蒲女王は手をふり、アリたちの出発を見とどけてから穴を閉じます。指輪をはずして首かざりにもどすと住んでいた街をすっかりわすれてしまいました。
だれもいない法廷のうしろでは働きアリたちがせわしなく女王アリのために食料や部屋をととのえていました。
通路の消失点Ⅱ
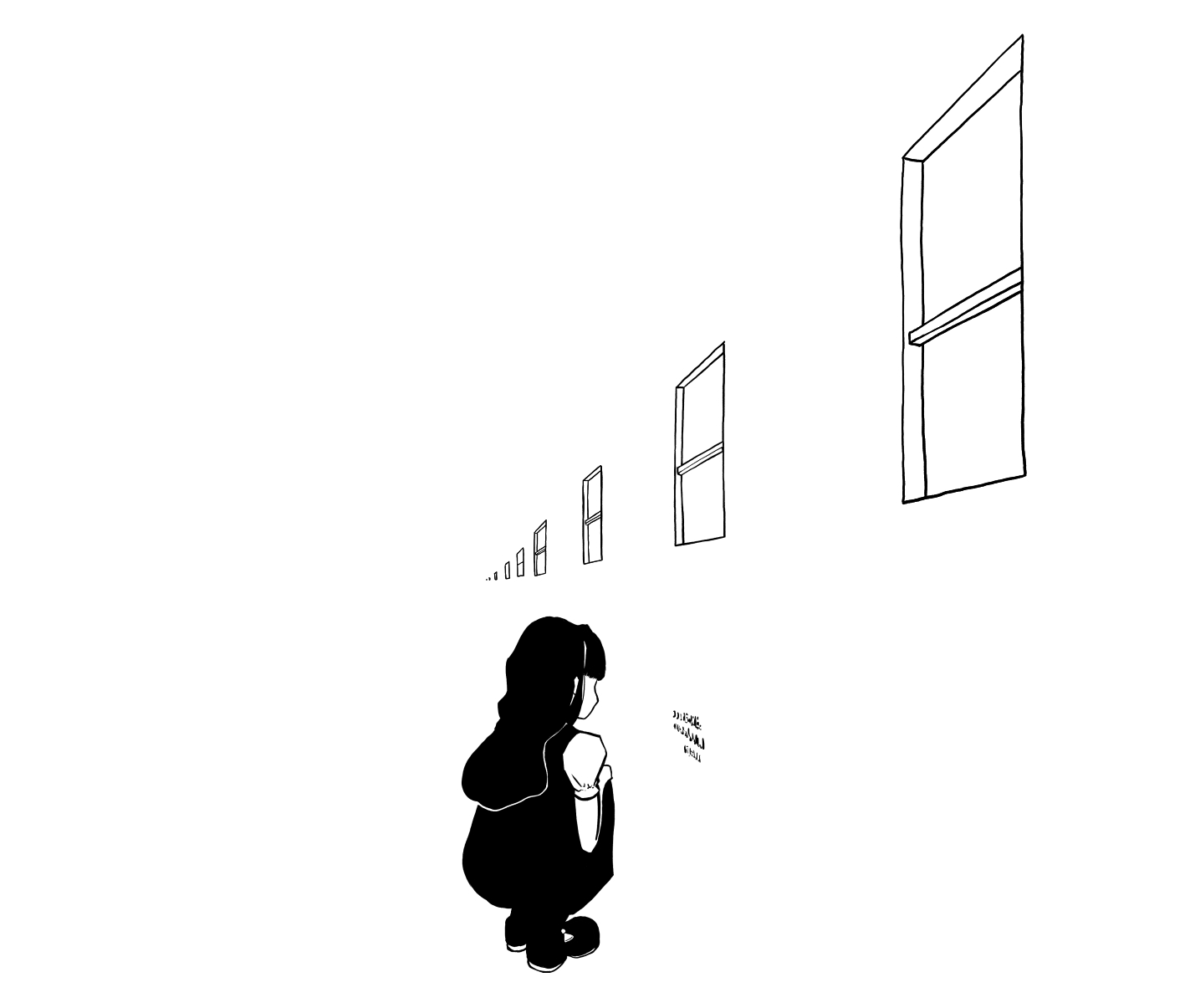
まっ白な壁の通路は、あまりの長さに先が見えません。まるで宙に浮いているような白い窓が等間隔にならび、ガラスはなく、のぞいても外に広がるのは白でした。
しばらく歩いていると、おりてきた階段はだんだん遠くなり、やがて周囲の白とまじり合い、消えてしまいます。
「ここはもしかして……」
菖蒲は右をむくと白い壁にちいさな文字が書いてありましたので、かがんで読みます。
ミエルモノガサキデワナイ
ケレドモミエナクバサキニワユケナイ
ゼンポウチユウイ
菖蒲はふっと鼻先で笑い、「そんなのわかってるわよ」と、通路の消失点を手でふさぎ、前方の扉にぶつからないよう注意しながら歩きました。
ガサガサ、ドサリ! 通路にひびくにぶい音。
菖蒲はなにかにけつまずき、思いきり地面にたおれます。
「いったああい。もう!」
通路の消失点はなく、こんどはゆかに扉がありました。
「『足元注意』もそえてください!」
菖蒲は通路にもんくを言い、把手を引いて鉄のはしごをおりました。
待合所ときどき夏休み

下へとつづく鉄のはしごは、おだやかな海にぽつりとうかぶ、ちいさな駅につづいていました。
菖蒲はプラットホームに足をつけ、ぐるり見まわすと赤いかわら屋根の待合所に照明柱、石のベンチとさびた駅名標がありました。
まちぼうけ
←風のむくまま 気のむくまま→
到着 着けば
出発 発てば
「ずいぶん気まぐれな駅ね」
菖蒲は駅名標を前に首をかしげます。それから待合所にむかい、潮風にゆれる藍色の麻のれんをくぐり、引戸をカラカラ開けて入りました。
「こんにちは。どなたかいますか?」
手前にカウンター席が三つと窓ぎわにテーブル席ひとつ、奥の台所では、ずんどうなべからふつふつとゆげがのぼっていました。
「いらっしゃい」
白い割烹着に三角巾をつけたおばあさんはカウンターごしにひょっこり顔をだし、菖蒲をまじまじと見つめます。
「へえ、女の子かい。めずらしいね。さあさ、そこの席にすわってくださいな」
菖蒲はカウンター前のイスにこしかけます。
「おばさま、はじめまして。わたしはアヤメといいます。あの、ここはどこですか?」
「おばぁでいいよ」と、おばぁは菖蒲におしぼりをわたして言います。「見てのとおり駅の待合所さ。食堂みたいだけど」
「まあ!」菖蒲はおどろきます。「もしかして電車がくるのですか?」
おばぁはすこし考え、「電車というかバスというか船というか生き物というか、まあきてみればわかるさ」。
「はあ」
「それよりアヤメちゃん、おなかすいてないかい?」
菖蒲のおなかはぐうっと大きく鳴ります。
「そうだと思った!」おばぁは笑顔で言いました。「うちはすばしかないよ」
「ありがとうございます。でも、お金もっていないんです」菖蒲は顔を赤らめます。
おばぁはポカンとした顔でながめ、「おかね? おかねってなんだい、おしんこか?」
「いいえ、ものを買ったり売ったり、こうかんするために使うものです。知りませんか?」
「アヤメちゃんのいるとこはめんどくさいもんがあるんだ。おかねはいらんからすば食べてきな」
そう言っておばぁはてぎわよく麺をばんじゅうから取りだし、てぼざるに入れ、ふっとうしたずんどうなべにほうり、まな板でコネギを切りはじめます。
「おばぁはずっと食堂をされているのですか?」
「ああそうさ。ときどき、アヤメちゃんみたいな客がふらっとやってくる。あとはほとんどイルカやカモメとかさ」
菖蒲はクスッと笑います。
「アヤメちゃんはどうしてここにきたの?」
「探しものがあるんです。それをいそいでとどけなければいけないのですが、まだ見つかりません」
「そうかい、見つかるといいね。まあ、探しもんはだいたい、ふとしたときに見つかるもんさ」
おばぁはどんぶりを菖蒲の前におきます。
「さあできたよ」
透明なスープにちぢれた平打ち麺、白くてふわふわした雲に小ネギがぱらりとふりかけてあります。
「とってもいいにおい! こんぶですね」
「そのとおり! アヤメちゃんよく知ってるね。白いのはゆし豆腐さ、だからこれはゆし豆腐すばね。おこのみで卓上のコーレーグスをすこしかけるといいさ」
「いただきます」
まずはスープをひとくち。こぶダシのやさしい風味に、ほんのり塩味のゆし豆腐がふんわり口いっぱいに広がります。赤と黄色の箸を手にして麺をふうふうふいて一口すすればスープを飲みほすまで箸は止まりません。
「ごちそうさまでした」菖蒲はまんぞくそうに顔をあげます。「とってもおいしかったです。おなかぽかぽか」
「それはよかった。お茶をいれようね」
「わたし、てつだいます」
菖蒲はどんぶりと箸を台所で洗い、おばぁはゲンコツ形のあげたてドーナツと気泡入りのガラスコップを菖蒲にわたしました。
「おやつのサーターアンダーギーとさんぴん茶ね」と、おばぁは言います。「それとアヤメちゃん、そっちのテーブル席はとっておきだよ」
おばぁがおしえてくれた席の窓にはコバルトブルーの空と海がどこまでも広がっていました。
「外からながめれば景色で、窓をのぞけば絵みたいね」菖蒲はぽつりと言います。
「アヤメちゃんは詩人だねぇ」むかいにすわるおばぁは目を大きくします。「そんなふうに見たことなかったよ」
菖蒲は照れをかくすようにサーターアンダーギーを口にします。
「カリカリであまくておいしい」
ジャスミン香るお茶にすっかり落ちついた菖蒲はおばぁと窓の絵をぼんやりながめました。
こんなちっぽけな駅でひとり、さびしくなったりあきてしまうことはないのだろうか。菖蒲はおばぁに聞いてみようとすこし顔をゆらします。
きらきらかがやくヘーゼル色の目、知恵深くおりかさなる目じり、口びるのそばに山をえがく経験ゆたかなほうれい線、やってくる日々はまるで客人のような、時を楽しむ端正な横顔。菖蒲にはおばぁが悠久の人に見えました。
「いつも考えるんだよ」遠くを望むおばぁはゆっくり口を開きます。「空と海はおなじ青なのに、なぜまじらないのか」
菖蒲はあこがれのまなざしをおばぁにむけます。
ときおり、海風は戸をゆらし、陽光は波をてらてらなでます。空は青からあかね、オレンジがにじむように染まり、いつまでも海とまじりあいませんでした。
まったくふしぎな駅の待合所です。なにも到着も出発もせず、ただ始発から終発まで時間は遠くにうかぶ雲のようにゆったり流れていたのですから。
「アヤメちゃん、とまってくかい?」おばぁは窓に聞きました。
「うん」菖蒲は窓にこたえます。
「外にかけてあるのれん、おろしてもらおうかな」
「うん」
菖蒲は夏休み、おばあちゃんの家に遊びにきているような、そんな気のない返事をしました。
おつかい

つぎの朝、鉄のはしごは消えていました。
「まあいっか。そのうちなにかやってくるはずよ、アヤメ」
空を見あげる菖蒲は、小さな寝床でおばぁと夜おそくまで話したのを思いだしていました。
「おばぁ、わたしね、みんなの家に住んでいて、お姉ちゃんと部屋がいっしょで、友だちみたいに仲よしで……」
ふたりは横になり、おばぁがうんうんとあいづちをうつたび、菖蒲の体はすっかり軽くなります。
「おばぁの耳は大きなポッケね。わたしのお話しがいくらでもはいるんだもの」
「いやぁ」と、おばぁは菖蒲の胸にふれ、「アヤメちゃんのはここにあるのさ」。
あけがた、おばぁといっしょに豆腐作りをしました。
ひと晩水につけておいた大豆をすりつぶし、布でしぼり豆乳を中火で煮ます。火をとめてからニガリを入れ、木のしゃもじでさっと切るようにまぜ、しばらく待つとかたまります。それをまん中にやさしくよせれば完成です。
「わたしの作ったお豆腐とおばぁの作ったお豆腐、すこし味がちがうと思わない?」
「それがいいのさ」と、おばぁはゆし豆腐を味見してうなずきます。
「いいかいアヤメちゃん。どんなもんでも、おんなじだからおんなじだと、決めつけてはいけないよ」
おばぁに借りた大きな水中メガネをかけた菖蒲は、プラットホームのふちに腰かけ、海に足をちゃぷんとつけてのぞきます。色とりどりの熱帯魚は菖蒲の前をすーっと通りぬけ、うれしくなり手をふるとわんぱく魚たちは、顔を見あわせ、菖蒲の足めがけていっせいにつつきはじめます。
「きゃっ」菖蒲はたまらず足をひっこめます。「やったわね!」
いそいで服をぬぎ、ざぶんと海にもぐりますが、いくらおよいでも魚たちのほうがずっと速いので、まるでおいつきません。魚たちは菖蒲をくすぐりにやってきて、菖蒲の口からゴボゴボと泡はどんどんこぼれます。もがいて息つぎしてから水中をおよいでいると、海底には美しいサンゴ礁の街なみが見えました。ショッピングを楽しむコバルトスズメ、ホテルで優雅に寝ているカサゴやフラダンスしているチンアナゴ。遠くにはひらひら飛ぶマンタやジンベイザメまでとてもにぎやかです。
「アヤメちゃーん!」
海面に顔をだすとおばぁの声が遠くに聞こえ、じゃぶじゃぶおよいで駅までもどります。
「アヤメちゃん、ちょうどいいや。わるいんだけど、おじぃのいるレウケ島に豆腐もってってくれるかい?」
「あばぁ、わたし島までおよいでなんかいけないよ」
「バンちゃんがつれてってくれるからへいきさ」
「バンちゃん?」
首をかしげる菖蒲のそばに、ハンドウイルカがすいすいちかづいてきました。
「やあ、はじめまして。ぼくはバンドウ。ぼくにつかまれば、島まであっというまさ」
イルカのバンドウは菖蒲のまわりをぐるりとまわります。
「はじめまして、わたしはアヤメよ」
「豆腐はふろしきにつつんであるからさ。島についたら広げてパレオにすればいいさ」
ふろしきをかついだ菖蒲はバンドウの背びれにつかまり、しぶきをあげ海をきって進んでいきます。
「ねえバンドウ。もしかしてあなたが海の駅にやってくるのりものなの?」
「ああ、それはね……だよ」バンドウはバッシャバッシャおよいで言います。
「ぜんっぜん聞こえないわ。もう一度言ってちょうだい!」
「ほら、島についたよ! アヤメちゃん!」
「ちがうの! そうじゃないの!」
レウケ島はさらさらの白い砂浜にヤシの木がずらりと立ちならび、おいしげった森のむこうには切り立つ岩山が見えます。菖蒲は豆腐をつつんでいた大きな花がらの布ふろしきを広げて両端を胸もとで結び、ワンピースにしてから、まんぞくそうに足を前にだしますが、すぐぴたりと立ち止まりました。
「おじいさまのおうち、どこか聞いてなかったわ」
こまっていると森の中からしば犬がひょっこりでてきて、しっぽをふりふりこちらにやってきます。
「こんにちは、アヤメちゃんだね。ボクはシバ。先生の家まで案内するからついてきて」
しば犬のシバはささっと森に消えます。
「シバ、ちょっと待って!」
菖蒲は見うしなわないよう、早足でついてゆきました。
「ねえシバ。わたしの名前をどうして知っているの?」
「郵便カモメのジョナさんが砂浜にアヤメちゃんという女の子がくるっておしえてくれたんだ」
「まあ、おもしろい!」菖蒲はくすりと笑います。「おじいさまはなぜこの島でくらしているのかしら」
「先生は冒険家だったんだ。でも、おばぁのゆし豆腐を食べたらここに住むと言いだして助手のボクもびっくりさ」
シダの森をしばらく歩くと、開けた原におしゃれな石づくりの家が見えてきました。
「あれがおじぃの家だよ」
まるでロビンソンクルーソーの世界に迷いこんだようで、菖蒲は「おじゃまします」と言ってドキドキしながら木の扉を引き、家に入ります。
香辛料の香りにみたされた薄暗い部屋は、ふりこ時計がカッチコッチ時をきざみ、ぎっしり本がならぶ大きな本棚にかこまれていました。中央には金羊毛のじゅうたんと、ピカピカのソファ、ポリネシア風の像やアンティーク調のランプシェード、縄文土器のような装飾のつぼ、奥のつくえには使いこまれた地球儀やコンパスにボトルシップ、まるで博物館のようです。
「先生! 先生!」シバはつくえにむかう男のそばによります。「アヤメちゃんをつれてきました」
「ありがとう、シバ」
シバの頭をなでる男は白いえりつき半そでシャツと深藍の半ズボン姿で、銀色の髪と豊かにたくわえた上品なひげは、かさねた経験のほどをうかがわせます。
「はじめまして、アヤメと言います」菖蒲はすこし緊張した声で言います。「おばぁのお豆腐をとどけにきました」
男は菖蒲に右手をさしだし、あく手とチークキスをします。
「よく来たね。きみがアヤメちゃんか。とてもかしこそうな娘だ」
「おじいさまは……」
「おじぃでいいよ。アヤメちゃん」おじぃはやさしく目をほそめます。
「おじぃはここでなにをなさっているのですか?」
「ふむ、わしもよくわからんな。いろいろ見たもんを書きのこしてるのかな。それともアヤメちゃんは、わしをロビンソンクルーソーかなにかときたいしていたのかね?」
「すこしだけ」菖蒲は恥ずかしそうにこくりとうなずきます。
「わしはレミュエル・ガリヴァーの冒険がこのみだな」
「どちらもかわり者です」
「そんな家におとずれるアヤメちゃんはもっと、かな?」
「おほめいただき、たいへん光栄ですわ」
菖蒲はすそをつまんで会釈し、おじぃと目を合わせて大笑いします。
「さあさ、こちらのソファにすわりなさい。まずは茶にしよう」
「なんてごうかなソファなのかしら」菖蒲は金のソファを見て言います。
「むかしサアサン朝アルペシでもらった品だよ。王がねむれんというから毎晩旅の話しを聞かせたら、たいそう喜んでな。礼にと宇宙ラクダにのせて運ばれてきた」
おじぃは花がらにうわ絵つけされた白磁のティーセットを背の低いテーブルにおき、紅茶をカップにそそぎます。
「とってもいいにおい」あまくてはなやかな香りにうっとりして菖蒲は言います。
「わしはコーヒーなんだが、たまにくる行商のウサギがぜひにとくれたんだよ」
銀製の皿にもられたペカンナッツやマカダミア、カシューにアーモンド、ブルーベリー、イチジク、パイナップル、それにチョコレートをつまみながら、しばらくおじぃと旅の話を楽しみました。
「……ところでアヤメちゃん」おじぃはコーヒーカップを置きます。「扉のない中庭についてだが」
「なぜそれを?」菖蒲はおどろいたように言います。
おじぃは軽くせきばらいをしてから、「ふむ、おばぁから聞いた」。
「もしかしてジョナさんですか?」
「そう。で、わしは若いころ中庭に行ったことがある」
「ほんとうですか!」菖蒲は目を大きく開き、身をのりだします。
「まあ落ちつきなさい」おじぃは両手を上下にゆらします。
「中庭に行ったというと語弊があるか……正しく言えば中庭のちかくまでかな」
「どういうことですか?」
「まず中庭に入ることはできない。そもそも出入りするための扉がないからな」
「でもわたしは中庭を見ました」
「ほう、中庭を見たと。知覚できないはずだが。いや、あるいはだれかなんらかの方法で現象させたのか」おじぃは菖蒲から目をそらし、あごひげに手をあてます。
「おじぃ、わたしにはわかりません。でも扉のない中庭にある井戸の水をくんでこないといけないんです。そうしないと王子さまはもとの姿に……」
「わかっとるよ、アヤメちゃん。そんな悲しい顔しなさんな。すこしずつ考えていこう」
「はい……」
うつむく菖蒲に、おじぃはうなずきます。
「むつかしい表現をすれば扉のない中庭は形而上の場所、形であらわせない空間なのだよ。つまり扉のない中庭は『在るが無い庭』といえるかもしれん。アヤメちゃん、心はどこにあると思うかね?」
「それは」菖蒲はすこし考えます。「わたしの中にあって、胸のあたりでしょうか。でも考えるのは頭にあるような」
「とてもいい答えだ。内側にあるのはおそらく正しい。頭つまりアヤメちゃんの脳は心を認識し、胸に影響をあたえたりもする。だが実際どちらにあるかといわれてもわからない。そもそもアヤメちゃんの体の中にあるかどうかすら知らん。精神や生命も脳か心臓か、はたまたほかのどこにあるのかわからないのとおなじなわけだ。アヤメちゃんの行きたい場所はそういう神秘の領域なのだよ」
おじぃはコーヒーで口をぬらします。
「そこでだ。わしは中庭に入るため記憶からたどってみた。扉のない中庭を心の空間、周囲の壁は時間軸内における記憶と仮定する。まったく記憶を捨て、無垢の状態から壁をぬけて心にアプローチできるか試そうとした。結果は庭の手前というわけさ」
「だから中庭のちかくまで、とおっしゃったのですね」
「そう」
菖蒲は目をつぶり、王子さまの約束を思い返します。
干しわらになった王子さまのくちびるをこの領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸の水によってうるおす時、青き剣は闇を打ちやぶる力をえます。闇の王は笑いましたが、王子さまは信じていました。なぜでしょうか、わかりません。ただひとつ、菖蒲にしかできないことがあります。
「おじぃ。わたしは中庭のちかくでも行きたいんです。そこに行けばなにかわかるかもしれない。もしあきらめてしまえば約束は果たせなくなる。それにわたし、王子さまの信頼にこたえたいの」
おじぃはするどい顔を菖蒲にむけて言います。
「先はかなりつらいぞ。アヤメちゃんのだいじなものをうしなうかもしれん」
「それでも行きます。わたしの願うおしまいでなくっとも。だってわたし、わたし……」
菖蒲はひざの上でこぶしをにぎりしめます。
「ためしてわるかった。アヤメちゃんはやさしい娘だ」
おじぃはやわらかな手で菖蒲の頭をなでました。
「シバ。ジョナとバンドウにアヤメちゃんの帰りがおそくなるとつたえておくれ。それから島々のあるじにもよろしくな。わしらはこれから岩山のてっぺんにゆく」
耳をひくりとさせたシバは起きあがり、ささっと外へかけだします。
「さてアヤメちゃん。これから天体観測にでかけよう」
「天体観測、ですか?」
出発のあいずを知らせるように、部屋のふりこ時計がボーンボーンとお昼の時間をならしました。
天体観測
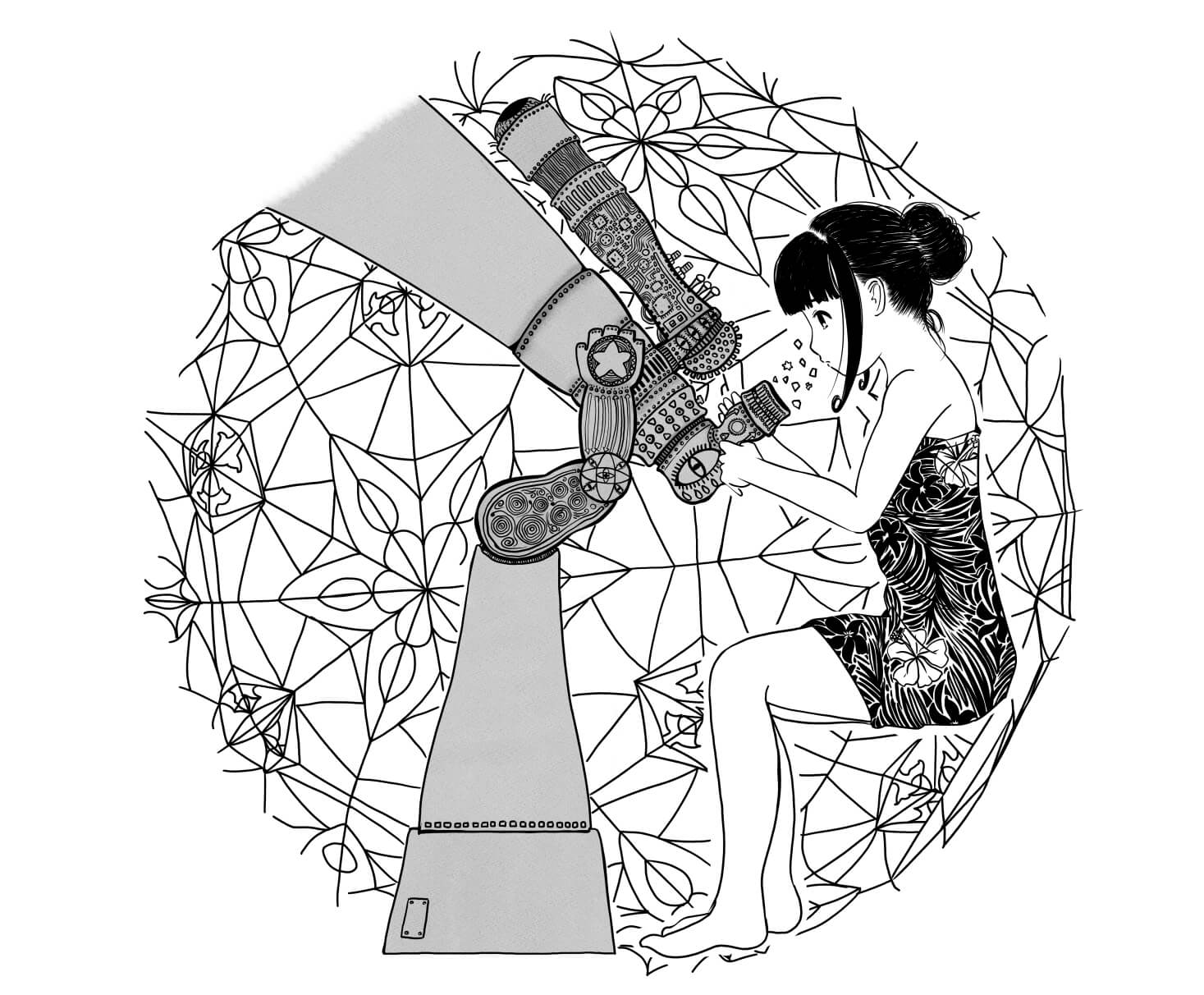
まわりを気にせず昼夜かがやく蝶のジコチョウ、歌のへたなノドガラガラガエル、いつまでもぶつぶつもんくを鳴くコゴトツブヤキオウム、勤労意欲があるのかわからないハタラクナマケモノ、食べるといつまでも生きられるような気がするキノコのフロウフシモドキ……おじぃはガイドツアーのように山を登りながらレウケ島に住む、ふしぎな動植物たちについて菖蒲におしえました。
山頂はたいへん見晴らしがよく、見わたすかぎりのオーシャングリーンにサンゴ礁がじゅうたんのように広がっていました。やがて空はだんだん赤く染まり、凪とともに夜のとばりがおりると月はくっきり海をてらします。
菖蒲とおじぃは、がけっぷちに立ち、遠くさびしそうに光るまちぼうけ駅をながめていました
「あそこは未練のこすものたちが待つ駅なんだよ」
おじぃは言いました。
「おばぁもだれかを待っているのですか?」
「ああ。息子の帰りをずっとね。おばぁはこの島をいつも見て泣いている」
「わたしも父と母を待っているのかもしれません。だって、あの駅にいるとおちつくんですもの」
菖蒲はまちぼうけ駅にむかって大きく手をふりました。
「さあいこうか、アヤメちゃん」
ふたりは天体観測所と呼ばれるドーム型の小屋にむかいます。オレンジ色の電球が灯り、部屋の壁にたくさん貼られた奇妙な数式や図形、ちいさなつくえに散らかる万年筆や黒いインク入れ、本やノートを照らします。部屋の中央にはとても大きな天体望遠鏡が一段あがった円形の台の上にどんとかまえ、屋根の外につきでていました。
おじぃは望遠鏡をのぞき、ハンドルをぐるぐるまわして止め、手まねきします。
「アヤメちゃん、ここをのぞいてごらん」
菖蒲は望遠鏡の接眼レンズをのぞきこみます。
「うわぁ、これはなんですか?」
赤に青に黄色、紫や緑と、まるで宝石をちりばめたカレイドスコープのような幾何学模様が見えます。
「アヤメちゃんの領域では月というのかな。まあこの衛星はいわゆる月としての役割はないのだが」
「ふしぎな星……ああっ、おじぃ、だれかいる!」
月に小さな黒い豆つぶひとつ、ゆっくりうごいています。
「よく見えたね。あれは記憶集めをしている」
菖蒲は望遠鏡のレンズから目をはなします。
「記憶集めとはなんですか?」
「散らばった記憶のかけらをひろう仕事さ」
ふたたび菖蒲は望遠鏡をのぞきます。
「あっ! 月になにかぶつかった」
「月にはたくさんの流れ星が落ちるからね」
「とってもきれい……」
「アヤメちゃんはまず、あそこへゆかねばならない」
「月にですか? でもロケットでないと宇宙にはいけません」
「いや、あの月は宙にはない。シロクジラで行くのだ」
「シロクジラ、ですか?」
「うむ。シロクジラはおばぁの駅にやってくる」
「そうだったんですね! でもシロクジラさんは空を飛べるのでしょうか?」
「はっはっはっ。もちろんクジラは空を飛べないし、月はわしらの上にあるとはかぎらんよ」
「どういうことですか?」菖蒲は首をかしげます。
「まあ乗ってみればわかる。ともかくアヤメちゃんはこれから月で王子の記憶を探し、それを結晶化してもらいビンに加工する。それで井戸の水をくむ」
「ただのビンではいけないのでしょうか?」
「うむ、おそらく」おじぃはつくえに置いてあるガラスの一輪挿しを指ではじきます。
「物質を非存在の中庭にもっていけんだろうからな」
おじぃは菖蒲のそばにある大きなハンドルをすこしまわすと、すわっていた円形の台がゴリゴリ音をたててうごきだします。
「もういちど、のぞいてごらん」
「ブラックホールみたいなぽっかりあいた黒い穴が見えます」
「そこは『闇の門』でさいしょの難所。扉のない中庭にちかづくためには門をくぐってから常闇の地を歩いて薄暗い階段を探す」
「暗くてなにも見えません」
「光とどかぬ闇の支配する領域だからの。薄暗い階段をおりたところに最大の難所、中庭にもっともちかい場所がある。そのさきはわしもわからん」
「どうして行かなかったですか?」
「恐怖で行けなかった、というのが正しいのかもしれん」おじぃは肩をちぢめ、身ぶるいします。
「無垢な記憶とは自己喪失を意味する。己をうしない、中庭をおかしたとて存在理由もわからないのであればなんの意義があるか。生まれたての赤んぼうは自己そして外界を親はじめ、他者により段階的に知覚してゆく。しかしうしなった自意識と記憶を中庭で瞬時に回復し、かつ脱出するか、まったく解決できなんだ。失敗すれば体は空となり、心は虚無にとらわれるだろう。わしは好奇心と無謀は結びつかん性格なのだよ」
「それでつらいとおっしゃったのですか?」
「うむ。なんらかの強大な力で自分を捨て、扉のない中庭に侵入し、王子の記憶でつくったビンで井戸の水をくむ。それから自我を回復させ脱出する。これらをアヤメちゃんひとりでできるかね?」
菖蒲は決意にみちた力強い目で遠くを見ます。
「これくらいにしよう」おじいはため息まじりに菖蒲の肩をたたきました。
観測所の灯りを消し、外にでたおじぃは空の月を指さして海にゆれる月までなぞります。
「海面にくっきり丸い月のうつりこんだ時、シロクジラは海の駅にくる。日が落ちる前に駅で待っていなさい」
「わかりました」
「先生!」シバがやってきて言います。「準備できました。みんな浜で待ってますよ」
「ありがとう、シバ」おじぃはシバの頭をなでます。「さてアヤメちゃん、もどろうか」
「はい」
おじぃは角灯を手に、菖蒲と岩山をおりていきました。
真夜中の砂浜は、打ちよせる波の子守唄で眠りにつく時間ですが、今夜ばかりはそうもいかないようです。なぜならたくさんのウミガメたちがとても大きなウミガメを中心にして集まっていたからです。
「アヤメちゃん。こちらは島々のあるじ、オオウミガメのスルフファー氏だよ。アヤメちゃんを海の駅までおくりたいそうだ」
「はじめましてスルフファーさん。わたしはアヤメです」菖蒲は大きなウミガメに頭をさげます。
(テティスニスベテキイテイル。ニジノムスメヨ)
スルフファーは水泡の言葉で菖蒲に話しかけると波はやみ、ウミガメたちは涙を流しました。
「先生、産卵でもないのにこれは……」シバはおどろいたように言います。
「島々のあるじ祝福する時、海に新たな島、誕生せん。みな帰る場所がふえて喜んでいるんだよ、シバ」
「おじぃ、ありがとうございました」
菖蒲はおじぃと抱きあいます。
「気をつけてな」
「またね、アヤメちゃん」シバはしっぽをふります。
「ありがとう、シバ」
スルフファーの化石のようなこうらに足をかけ、てっぺんまでのぼります。すべてのウミガメ、ヤドカリやカニは道をあけ、オオウミガメのスルフファーは海までドシンドシンと地面をゆらし歩いて着水します。それはまるで船の進水式のようでした。
菖蒲はみんなに手をふり、ぷっくりと丸い島のようなこうらはレウケ島からはなれていきました。
みじかい航海のあいだ、菖蒲のひとり会議が開かれます。
「駅でシロクジラさんを待つのよ、アヤメ」と、菖蒲は言います。
「それから月で王子さまの記憶を手にいれる」と、菖蒲は答えます。
「でも、どうやって?」
「そんなの行ってみなければわからないわ」
「たしかにそうね。やってみなければわからないことだらけよ、人生なんて」
やがて、駅の外灯と待合所の灯りが見えてきました。
「ただいま」
まちぼうけ駅についた菖蒲はベンチで待っているおばぁの胸に飛びこみます。
「アヤメちゃん」おばぁは力強い腕で菖蒲を受け止め、耳もとで言います。「山の上からこっちに手をふってくれただろう」
「おばぁはなんでも知ってるのね」
「あぁ、わかってる、わかってるさ。アヤメちゃん」
食堂でゆし豆腐すばをすすり、まくらに頭をのせたら、その晩はぐっすり眠りました。
シロクジラ

天体観測からひと月後。
菖蒲はいつものように豆腐作りをして、朝ご飯のゆし豆腐すばをすすります。それからイルカのバンドウと海中探検をしました。足をくすぐったわんぱく魚たちはサンゴ街の三丁目、アオサンゴアパートメントに住んでいて、家をのぞくとあわててちりじりになります。バンドウからイルカ式遊泳法をおそわった菖蒲はまるで人魚のように大きなシャコガイケイムショまでおいつめます。ここは悪さをした魚を閉じこめておくためのろうやなので、みんな恐れていました。
「くすぐったりしてごめんよ。きみと友だちになりたかったんだ」わんぱく魚たちは言います。
「わかったわ。そのかわり、あなたたちの街を案内してちょうだい」
菖蒲は、わんぱく魚たちとすっかり仲よしになりました。
服をきて食堂にもどると、さんぴん茶をいれたグラスを片手に、とっておきの席で窓にうつる、いつまでもまじらない空と海の絵をおばぁとながめます。
夕方、プラットホームの街灯がチンチロ点滅し、パッと灯ります。
ふたりはベンチにこしかけ、空にうかぶバニラアイスクリームのような月を見ていました。
「ずっとアヤメちゃんを待っていたさ」おばぁはゆっくり口をひらきます。「だから、つぎはみんなでおいで」
「つぎなんて、ないかもしれない」菖蒲はぼそりとこたえます。
大好きな友だちと遊んだ夏休み最後の帰り道、楽しかった思い出はシャボン玉となり「またね」と、夕空ではじけてしまいそうな、どうしようもないさびしさに胸がしめつけられます。
「ここにいてもいい」菖蒲はあまえるように、おばぁの肩に頭をあずけます。「やっとわたしだけの家に帰れたんだもの」
「王子さまとの約束、果たさんとね」
「わたしにできるかな」
「果たせるから約束なんだよ」
「どうやって果たすのかわからないのに?」
「そう、結婚もそうさ。愛しあうふたりがどうして誓いを果たそうか、考えるかい? ただ信じるんだよ。ほんとうの愛はまったく信じて疑わない。果たすつもりのない約束はでまかせっていうのさ」
「そっか」
「アヤメちゃんは王子さまのこと好きなんだろう?」
——スキ。王子さまのコトがスキ?
菖蒲は目の前がぐらぐらゆれて胸はどきどき鳴り、おなかはきゅうっとします。顔はぽっぽと蒸気船のように頭のてっぺんから蒸気がふきださんばかりです。
「おばぁ、そんなのわかんない。だってだって会ってもないし、話してもないし、それにそれに、男子なんてよくわかんない!」菖蒲はおばぁの肩に顔をぐいぐいうずめます。
「たしかにそうだ、なんせわらだからねぇ」
おばぁの大きな笑い声は静かな海をゆらします。
「……おばぁのばか。やっぱりでてくもん」
その時、海のむこうから白く光る大きなマッコウクジラがやってきて駅に停車しました。
「そろそろおわかれだね」
おばぁはそう言って菖蒲を抱きしめ、せなかをポンポンとたたいてからやさしく、なんどもなんどもさすり、耳もとでこう歌いました。
つきぬかいしゃ とぅかみーか
みやらびかいしゃ とぅーななつ
ほーいちょーが
あがりからあがりょる うふつきぬゆ
あやめんあやめん てぃらしょうり
ほーいちょーが
「おばぁ、ありがとう。あっというまだったけど、ずっと前からここにいたような気がするの」
「そうさアヤメちゃん」おばぁは菖蒲のほっぺをなでます。「たいせつな一瞬をすくいよせれば、人生は思ったより長く、ややこしい時間すら、いとおしく感じるものさ」
「わたし、おばぁのようになれるかな」
「もちろん。いい大豆と水とにがりさえあれば」
「うん……」
おばぁは菖蒲の手の甲に丸いスタンプを押すと、くじらの模様に光りました。
「これはどこでも乗り降り自由の乗車証さ。それとここに帰ってくるための道しるべだよ。宙は海とおなじくらい広いからね」
「おーい、まってー!」
シバを乗せたスルフファー氏がシロクジラと反対のプラットホームに停車します。
「あれあれ、なんだかにぎやかだね」おばぁは感心して言います。
いつのまにか、まちぼうけ駅にはスルフファー氏を追うたくさんのウミガメ、イルカのバンドウやサンゴ街のわんぱく魚たち、アザラシ、ペンギン、ジンベイザメやマンタ、クラゲとホタルイカのイルミネーションと、お祭りさわぎです。
「シバ! どうしたの?」菖蒲はおどろいたように言います。
「まにあってよかった。アヤメちゃんの手伝いをするよう先生から言われたんだ。だからボクも月にいくよ」
「まあ! それは心強いわ」菖蒲はシバのほおにキスをしました。
シロクジラ発車の時間。菖蒲はみんなに手をふります。すこしずつ駅が遠くに、やがて街灯はオレンジ色の星となって水平線に消えてなくなります。
「ところでシバ、どうやって空にうかぶ月へいくのか、知ってる?」
「なにを言っているんだいアヤメちゃん」と、シバは首をかしげます。「ボクたちがこれからいくのは、あの夜空にうつる月ではなくて、海にうかぶ月さ」
「おじぃも言ってた。どういうこと?」
「水面の月が空にうつっている。つまり宇宙と海はおなじなのだよ」シバはおじぃの声まねします。
「ほんじつぅはぁ」運転手兼車掌マッコウクジラの低い声が聞こえます。
「シロクジラ観光のキタールにごじょうしゃありがとうございやぁす。つぎはぁきぉくのほし、きぉくのほしでございやぁす。これよりぃスピぃドをあげやすのぉで、ふりをとされないよぅどぅぞぉおつかまりくださぃ……とぉもうしましてもぉ、つかまるところなどありゃぁございやせんがぁ」
自嘲気味な車内アナウンスをおえたキタールは、ぐんぐん速さをあげて海面の月にむかい、潜水艦のようにしずんでいきます。
「ちょ、ちょっとまって。まさかもぐるわけ?」
菖蒲はあわててヒトデのような姿勢でツルツルのシロクジラにへばりつきます。水しぶきをうけながら息をいっぱいにすいこみ、ほおをふくらませて目を閉……じた……ら…………
「くるし……くない?」
「おぼれてないからだいじょうぶだよ、アヤメちゃん」
菖蒲はおそるおそる顔をあげると、チョウチンをぶら下げたアンコウが目の前を通りすぎます。青くひかるプランクトンはまるで深海にちらばった星くずのようで、遠くに幾何学模様の丸い大きな月がうかんでいました。
「これでわかったかな?」シバは菖蒲をのぞき、にこりと笑います。
おきあがった菖蒲は腕をくみ、周囲をぼうぜんと見つめて首を横にふりました。
「いいえシバ。なんべん説明されたって、わたしにはまったくわからないわ」
記憶採取

世界中で語られたおとぎ話は人々の記憶にきざまれ、夢をえがきます。やがて、わすれられた物語は流れ星となって長いあいだ宇宙をさまよい、忘却の彼方である月に引きよせられます。それらふりそそぐ記憶の断片は無数にちらばり、月はステンドグラスのようにいろどりかがやいていました。
菖蒲はつぎの停車地にむかうシロクジラのキタールに手をふり、記憶の星におり立ちます。地面は薄氷の割れた音をたて、七色に発光しました。
「プリオシン海岸にいるみたい」菖蒲はぽつりと言います。
まるで河原で百二十万年前のクルミのような実をにぎりしめた少年たちが改札口にかけこみ、乗りこんだ汽車の窓にうつるおもかげはだんだん消えいるように見えました。
「ふしぎね、シバ」菖蒲は鈴の音を鳴らし落ちる星をつかみます。
「さわってる感じもしない」
「あたってもぜんぜん痛くないや」と、シバは言いました。
「ねえシバ、遠くで割れた音が聞こえない?」菖蒲はうつぶして頭を横にします。「パリパリ、パリパリって、だれか歩いてる」
シバは耳をピクピクさせ、「こっちだ!」と、かけだします。
「まってよ、シバ!」菖蒲は息をきらして言います。「あなたに置いてかれたらわたし、迷子になっちゃう」
「ごめん。うれしくってつい」
目の前に藍色の作務衣を纏うバクが腰かごをぶらさげ、立っていました。すこしおどろいた顔で「やあ」と右手をあげます。
「ここにやってくる旅行者はひさしぶりだ。ぼくはメレ」
「はじめまして。わたしはアヤメ。こちらはシバよ。メレさん、もしかして記憶集めをされているのですか?」
「いかにも。よく知っているね」
「わたし、ある人の記憶がほしくてこの星にきました」
「だれかの記憶がほしいだって!」メレはますますおどろいてから笑い、腕を広げます。「はじめにひとつだけ忠告しておこう。だれかの記憶を選び取るなどぜったいできない。流れ星に名が書いてあるわけではないし、記憶をのぞくこともできないのだから。それにまわりをごらん。記憶の断片がどれほどあると思うんだい。しかもああして流れ星は絶えずふってくる。落下した記憶のかけらを採取するのもむずかしい。ためしにさわってごらん」
メレにすすめられるまま、菖蒲は落ちていた黄色のガラス片にふれてみます。するとガラスはすぐにはじけとび、消えてなくなりました。
「どうしてすぐになくなってしまうのですか?」
「干渉するからさ。記憶はこの星に落ちるまでのあいだ、どんどん儚くなってゆく。落下した古い記憶はアヤメの新しい記憶とふれあい、儚いほうが粉砕される」
「ではどうやって記憶を拾うのですか?」
「これさ」と、メレは手にしている乳白色の長尺棒を菖蒲に見せます。片方の先端は四角い小型スコップに、もう片方は熊手のようにわかれていました。
「初代星の化石からけずりだしたこの棒を使い記憶の断片をかきわけ、こわさないようそっとすくう。それでもあまりいじると消えてしまうから、拾ったらすぐに工房で結晶化させる」
メレはいくつか断片をすくいあげると記憶は消えず、にじ色の火花をパチパチちらしながらスコップの上でおどります。
「このごろの記憶は無色や灰色が多い。良質な記憶を採取するのはむずかしくなっているんだ」
「なぜですか?」
「おそらくむかしの人は夢より現実を、おとぎ話よりパンについて語っていたのだろう」
「夢、ですか?」
「そう。夢やおとぎ話は記憶に色をあたえるんだよ」
「王子さまの記憶の色は何色かしら」菖蒲は無数に散らばる断片をながめます。「どんな夢を見ていたのかな」
「さてどうだろう。ここにはあらゆる色の記憶が落ちてくるから」
「探している王子のにおいがわかれば、ボクがおいかけるんだけどね」と、シバは言います。
「それよシバ!」菖蒲はぱっとひらめきます。
「王子さまの記憶をふらせればいいのよ。シバは落ちた星をおいかけ、わたしが拾う」
「へえ、干しの王子さま作戦ってわけかい?」シバはにやりと笑います。
「そんなのむりさ」メレはあきれたように言います。「だれかの記憶を流れ星にしてふらせるなんてつごうのいい話し、聞いたことない」
「どうかしら。これをつかえば」と、菖蒲は金の首かざりから赤い宝石の指輪をはずします。
「うわあ、その赤い宝石!」メレは目を大きくして言います。「ぼくの工房で加工した奇跡の結晶だ!」
「ええっ! どういうことですか」菖蒲もおどろきます。
「その赤い指輪は青い剣と対で加工されたんだ。とってもふしぎな時間だった。そう、あの時もアヤメみたいにとつぜん、ふたりはシロクジラでやってきて……」
太陰潮

夫婦は秘めたる思いで月にやってきました。いつものように記憶採取をしていたメレは、そんな若く美しい男女の姿を目にしたのです。
「自分たちの記憶を探すだって!」メレはふたりの話しを聞いて笑います。「はじめにひとつだけ忠告しておこう。だれかの記憶を選び取るなどぜったいできない。流れ星に名が書いてあるわけではないし、記憶をのぞくこともできないのだから」
それでもふたりは指輪とひとふりの剣を作りたいとメレになんどもたのみます。理由を聞いても、妻の出産前に完成させたいというだけです。
ためしてみればわかるだろうと考えたメレはしぶしぶ記憶採取をおしえることにしました。
しかしふたりはおどろくほどの速さで熟達します。どこからか希少な記憶の断片を採取しては工房に持ち帰り結晶化させ、それはみごとに加工しました。
「あなたたちの作品は芸術だ」メレは感嘆の声をあげます。
夫婦が記憶の星にきてからしばらく経ち、妻の出産はいよいよちかづきます。メレは故郷にもどるよう言いますが、ふたりはもうすこしと、聞きいれません。
「つぎシロクジラがくるまでに記憶を採取できなければ帰りなさい。そうでなければ工房はかさない」
それからふたりはまいにち月をめぐりますが、記憶の断片は見つかりません。すこしもあきらめない姿に感動したメレは深いため息をつき、悲しげに工房へもどりました。
するといつもは聞こえる流星の音がぴたりと止み、なにごとかとメレは工房をとびだします。
なんと遠くに赤と青の美しい尾を引く星ふたつ、からみあったり、はなれたりしながら、まるで宇宙を舞台に優雅で気品あふれるバレリーナのように舞いおどっているではありませんか!
流れ星たちはエトワールのパドドゥのために軌道をゆずり、祝福とすこしばかりの羨望をそえてコール・ドのように月の外縁でまたたきます。ダンスを終えたつがいの星は、手をつないであおぎ見る夫婦の手もとにそれぞれ引きつけられたのです。
ふたりは赤と青の星をメレの工房でふたつ同時に結晶化させます。まじりあう記憶の断片は一体となり紫色に、やがてふたたびわかれ、夫はゆらめく紺碧の剣を、妻はこうこうと燃える赤い宝石つきの指輪を像づくりました。
そのようすをメレはおどろきの眼でながめ、かつてメレに記憶の結晶法を伝授した師の言葉を思いだします。
「まこと美しい結晶は、結ばれる愛の序幕だ」そして師はこうつけくわえます。「もっとも、これほど貴重な記憶を手ばなす、おろか者はいないだろう」
完璧に仕事を成しとげた夫婦はメレに感謝し、シロクジラで帰っていきました。
わかれぎわ、メレはふたりにたずねました。
「もしやあなたたちは、はじめから星の引きあう力を知っていたのですか?」
ふたりは見つめあい、小国の王と王妃であること、また【手つなぎの約束】をメレにおしえます。夫はまいにち妻の手をとり、妻は夫の手をはなしてはならない、という約束を。
それからふたりは高貴な笑みをたたえ、こう言いました。
「わたしたちは永遠につながる手を通して約束を信じ、星の惹かれあう日をただ待っていたのです」
金色あられ
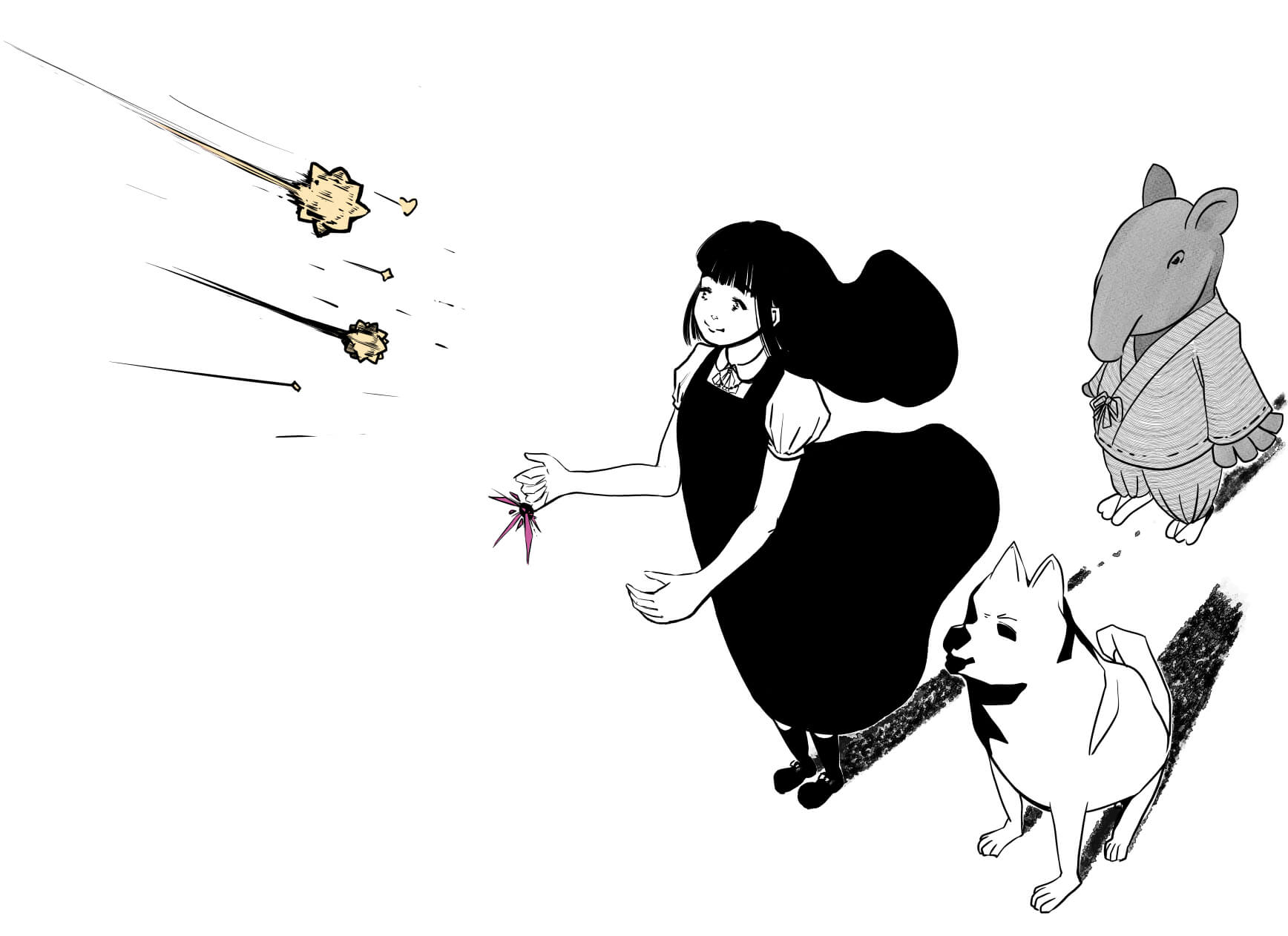
首かざりから指輪をはずした菖蒲は右手の小指にはめると、宝石は炎のように燃えてかがやきます。
流れ星はぴたりとやみ、あたりはぶきみなほどの静けさにつつまれます。
メレとシバは好奇心と恐怖のいりまじった顔で夜空を見上げていると、遠くのほうからたくさんの星がチカチカまたたきました。
「なにかくる!」
シバの言うが早いか、金色の流れ星はあられのようにどっとふりそそぎ、パチパチ火花をちらして消えます。なんと古今東西いろんな王子さまの記憶が菖蒲のもとに引きよせられてしまったのです。
「なんということだ!」メレはたじろぎます。
「アヤメちゃん、ちいさすぎるよ!」と、シバは飛びはねます。
「うん、わかってる」菖蒲は手をくんで目をつぶります。「わたしの王子さま。あなたの夢を、あなたのおとぎ話を、もっともっとおしえて」
金色あられは菖蒲の願いにこたえるように数を増し、あまりのまぶしさにメレとシバは顔をそむけます。
光にのまれた菖蒲はゆっくり目をひらき——————
「ヘレム! ヘレム!」王子さまの声。
深い森、草をかきわけ、山の斜面をかけおりる。
巨大な老樹のコケむす木の根もとに、どうどうと立つ、せいかんな顔つきの大男。
「ヘレム、きょうはなにをしよう。どんな遊びをおしえてくれるの?」
「あなたの手をわたしの手にのせなさい」
ヘレムと呼ばれる男は手をさしだし、王子さまと手をかさねる。
「山あいの国の王子よ、いまから話すことは時がくるまで口外しないように」
「ぼくは【口止めの約束】を守り、あなたについてだれにも、父上や母上にだって話してやいないさ」
男は笑顔でうなずく。
「そうだ。ちいさな約束を守ることは大きな力となる。いつかおまえは大きな力をひつようとする時がくるだろう。ゆえに将来の約束をつたえる」
男は両手で少年の手をがっしとつかむ。
「わらとなり、かわききったおまえのくちびるを、この領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸からくんだ水によってうるおす。その時、青き剣は影にとりつく邪悪な王をうちやぶる力となる。
その少女とは」
「その少女は?」
男は顔をよせ、親しみをこめた優しいまなざしで、こちらをのぞきこむ。
王子さまの? ううん、わたしの目を、わたしの……そう、わたしの眼を!
「そうだ、アヤメ」
景色はぐんぐんうしろに流れ、深い森からせせらぐ川、夕日の映える湖畔、石造りのちいさな町をぬけてゆく。山あいにそびえる城壁をなめるように上昇し、バルコニーで手をつなぐ王さまと王妃さまがほほえみかけて言う。
「わたしたちはあなたも信じています」
言葉とともに大地をこえ宇宙へ。王子さまの記憶からほうりだされ、くるんとさかさまに、月の手がぐいとひっぱり、遠くにシバとメレとアヤメ、わたしがいる——————
「シバ! 記憶が流れる。おいかけて!」
菖蒲の指さす方角に、大きな流れ星はすさまじい速さで弧をえがいて落ちます。
シバは地面をけりあげて流星めがけ、全速力でかけだし、メレもついてゆきます。菖蒲は指輪を指からはずし、首かざりにしてもどすと、金色あられはやみ、住んでいたみんなの家をわすれました。
「アヤメちゃん! ここだよここ!」シバは金光のまわりをぐるぐるまわっています。
「でかしたわ、シバ」菖蒲はかがみ、記憶の断片に両手をそえます。
「だめだアヤメ! さわったらこわれてしまう」メレはうしろでさけびました。
「そうね」と、菖蒲はためらわずに星をひろいあげ、「もし、わたしの王子さまでなければ」。
金色の星は菖蒲の手の中でこうこうとかがやきます。
「メレさん、王子さまの記憶を結晶化できますか?」
あっけに取られたメレは、ただうなずくしかできませんでした。
物見やぐらと細長いえんとつを目じるしにメレの工房はあります。ほら穴の入り口に『キオクザイクコウボウメレ』ときざまれた木製扉をくぐり、モザイクタイルの階段をおりると、記憶の細片が縞模様の地層となってきらめく壁、丸いガラス天窓、大小さまざまなオブジェの置かれた円形広間にでました。
「なんてすてきなのかしら」菖蒲は中央にかざられた美しいらでん細工の花びんを見て言います。
「ああ」と、バクは花びんにふれます。「さきほど話した夫婦がはじめて採取から加工まで仕事をした作品だ。ほかのは行商にゆずったけど、桃色に金彩をちりばめられたものはすごくめずらしいから記念にのこしておいたんだ。まあ結晶化した記憶の断片は役割を終えると自然に割れてしまうのだけど」
「いつ壊れるかわからないのに売れるんですか?」
「そこに価値がある。美しい記憶のおしまいを見ようと所有者は結晶を手もとに置くのさ」
円形広間を中心に各部屋は放射状にいくつかわかれ、台所、居間、寝室、資料室、加工部屋、そして記憶を結晶化させるための作業部屋がありました。
「これらは作品となる前の記憶の結晶だよ」
メレは長い板にならんだ色とりどりのガラス玉をさします。それから作業部屋のすみにある口をななめにむけた白いるつぼの前に立ちます。
「星の光を集めたこのるつぼに記憶を入れるんだ」
菖蒲は強い光を放つるつぼに王子さまの記憶をほうり投げます。すると記憶の断片は火花をちらし、くずれて砂のようにサラサラになります。メレは茶色い紙袋からあまいにおいのする金平糖をスプーンで小さじ一ぱいほどすくい、るつぼにいれました。
「お菓子みたいですね」
「月の核をけずったものだよ。結晶を安定させるためにつかう」
「ぜんぶこの星で取れた材料と光がでなければいけないから、工房もここにあるわけですね」
「そのとおり」と、メレは壁にたてかけられたかくはん棒をるつぼにつっこみ、かきまぜます。「こうやって結晶化するまで記憶、星の核、光。すべてひとつになるよう手を止めずにゆっくりまぜつづける」
「メレさん、わたしがまぜてもいいですか」
「もちろん。でもこの棒、アヤメにはすこし重いかも」
メレはかくはん棒を菖蒲にわたします。
「かくはん作業は、まぜ手の思いによって結晶の仕上がりも決まる繊細な工程なんだ」
るつぼの中で砂金と金平糖はころがり、キュンキュン、キュンキュンと工房中に砂の鳴き声が聞こえます。
「つかれたらぼくを呼んで。いつでもかわるから」
「はい、わかりました」
メレは菖蒲をのこして部屋をあとにします。そのようすをシバは中央広間でうずくまり、見守っていました。
つぎの日。
「ふつう結晶化するまで半日、どんなに長くても一日かからない」メレはけげんそうに言います。
「でもアヤメちゃん、きのうからあのままずうっとかきまぜているよ」と、シバは言います。
「奇跡の記憶だからなにがあってもおかしくないけど」
「だいじょうぶかな」
「かわろうかって言っても聞かないんだ」
菖蒲はたくさんの思い出や夢、おとぎ話のこもった王子さまの記憶をだれにもさわらせたくありませんでした。もちろん記憶は菖蒲に語りかけはしませんが、星の鳴く音にできるだけ耳をかたむけ、王子さまに信頼してもらおうとゆっくり待っていたのです。三日間ひたすらかきまぜつづけ、菖蒲の想いと王子さまの記憶が理解しあった時、砂の音はなくなりました。
「かくはん棒をひきあげてごらん」メレは言います。
菖蒲はかくはん棒をるつぼからあげると、先端にふわふわとしたわたあめがからまっています。
「こちらの台に棒をむけて」
メレは平皿を作業台におきます。かくはん棒についたわたあめは白くにごり、皿にてろりとたれて、おまんじゅうのような丸い形にかたまります。
「水晶玉みたいだね」シバは結晶にうつるメレを見て言います。
「おかしい」と、メレは腕をくみ、首をかしげます。「あれだけ良質な金の記憶が、どうして透明な結晶になるのだろう」
「アヤメちゃんはどう思う?」
シバが顔を横にむけると、菖蒲はかくはん棒によりかかるように、すうすう眠っていました。
願いの像

うっすら目をあけるとモザイクの天じょうが見えました。ズキズキ痛む両手にほうたいがまかれ、ベッドで寝ているのに気づきます。
ころがるようにベッドからおりて広間を通り、だれもいない作業部屋にむかい、作業台に置いてある水晶をながめます。
「アヤメちゃん、起きたんだね」背後からシバの声が聞こえます。「ずうっと寝ていたから、しんぱいしたよ」
「わたし、そんなに休んでたの?」
「うん。アヤメちゃん、三日間も手がぼろぼろになるまで記憶をかきまぜて倒れたんだよ。眠ってるあいだにメレが特製なんこうをぬって手あてしたんだ」
「そうだ、メレさんは?」
「記憶採取にでかけている。メレはアヤメちゃんの結晶についてなやんでるみたい」
「どういうこと?」
「金色だった記憶が無色透明の結晶になったんだ」
「わたし、なにかまちがえたのかな」
「いや、そうではない」
工房に帰ってきたメレは言いました。
「なぜ色がないのかしら?」不安そうにたずねる菖蒲。
「ぼくにもわからない」熊手を立てかけたメレは作業台のそばにあるイスにすわり、ひと息つきます。「資料室にある師匠がのこした作業日誌をしらべてみたけど、色つきの記憶から無色の結晶になったという記録はなかった。無色の記憶に色をつけるという技法はあるのだけど」
「採取した王子さまの記憶はもともと無色だったのかしら」
「いやいやどうだろう。あの時見たのはたしかに金色の星だったし、透明な記憶は夢ぬけといってガラスとかわらない」
「そんな……」
みんな答えを探そうと王子さまの結晶を見つめ、低い声でうなります。
「わたしは王子さまの記憶だと信じる」と、菖蒲はきっぱり言います。「たとえガラスとおなじでも、だれに見わけられなくっとも」
そうです。菖蒲にとって透明な結晶は、道で拾った石ころに名前をつけてみがき、クッキー缶にしまうような、たくさん思いのこもった宇宙でたったひとつの宝物だったのです。
「わかった」と、メレはうなずき、イスから立ちあがります。「アヤメが言うなら加工の工程にすすもう。仕事には敬意を、達成には賞賛を。ぼくの師のおしえだ」
「なんせアヤメちゃんの王子の結晶だからね」シバは片目をパチリとさせました。
「まずはその手をなおしてから」と、メレは菖蒲の手を見て言います。
「ほら」菖蒲はほうたいをほどき、ふるえる手のひらをゆっくり開いたり閉じたりします。「ちゃんとうごくわ。いますぐに加工しましょう」
「しかしそんなにボロボロでは……」
「メレさん、お願い」
「わかった」とだけ、メレはそれ以上なにも言わず、となりの部屋に菖蒲をつれていきます。
加工部屋はせまく、板ばりの小上がりで中央に穴があり、ろくろがすえられていました。
「アヤメ、ろくろの前にすわって」
菖蒲はくつをぬぎ、スカートのすそをまくりあげてこしかけます。メレは王子さまの結晶をろくろ台の上に落とすと、まるでおもちのようにぺちっと台にひっつき、ふるふるゆれます。
「足もとにある円ばんをけってごらん」
メレの言われたとおりにすると、ろくろは反時計まわりにくるくる回転をはじめ、結晶がふわりと宙にうきました。
「加工にとくべつな技術はいらない。結晶にふれて思いうかべるだけでいい。結晶はアヤメの願う像になる。ただし手をはなしたら二度と像をかえたり、もとにはもどせないから気をつけて」
そう言ってメレは部屋をあとにしました。
結晶の加工は思いをみだされるとうまくいきません。どんな像にもできるのはワクワクしますが、な
かなか思いどおりにはいかない作業なのです。
メレはろくろとむきあう菖蒲に、加工法の師からはじめて加工をゆるされた自分の姿をかさねます。
茶わんを象るよう師にいわれた弟子のメレは、緊張した手つきで結晶にふれます。丸いうつわを想像し、茶わんの像がくっきりうかび、もうすこしよくしようと、おごそかな茶わん、さらにだれも考えつかないような変わったうつわをつぎつぎに思いつき、まるで博物館を旅しているような気分です。
うっとりしたメレは、長い鼻をヒクヒク。どこからかお米としょう油のにおいがします。おにぎりにじんわり染みこんだしょう油は炭火でじっくりあぶられ、パリパリの表面をわれば、ふっくらとしたお米のあまい湯気につつまれます——味噌汁とぬか漬けもほしいな。きょうの昼ご飯はなんだろう——
おすし、チャーハン、カレーライスと大好物におぼれる姿はまるでヘンゼルとグレーテル。メレのおなかはぐぅっとなり、思わずあっと声をだし、結晶から手をはなしてしまいます。メレはじめての作品は三角の像をした焼きおにぎりでした。
「焼き目がじつにすばらしい!」と、師はメレをなぐさめるように言います。「なあメレ、自然な願いこそ最高の像なのだよ」
ベテラン職人はなんでも自由に結晶を象ることができます。描かれた絵や詩、音楽など、加工師はめいめい思いをくむ技法を知っていました。
ゆたかな色をもつ流れ星が落ちていた時代は分業制で、記憶採取、結晶、加工と、職人がそれぞれいて、なかでも加工の工程は花形でした。いつからか透明のもろい断片ばかり落ちるようになり、職人たちは仕事をやめてほかの星へ、工房もひとつまたひとつと消え、メレだけになりました。
「できた」加工部屋から菖蒲の声が聞こえます。
「ずいぶんと早くおわったみたい」と、シバ。
「はじめはじっくり時間をかけるものだけど」メレはふしぎそうに加工部屋にむかいます。
ろくろ台の上には素朴なフタつきの小ビンがポツンとひとつ、もしほかのガラスビンがならんでいたなら、まったく見わけがつかなかったでしょう。
「おどろいたね」メレはたまらず笑ってしまいます。「これはなんとも」
「願いの像はきめていたの」と、菖蒲は小ビンをまんぞくそうに手にします。「だって、井戸の水を入れるだけですもの」
「それはしつれいした」メレは軽くせきばらいをします。「目的にかなった作品というわけだ」
コツコツと玄関扉のたたく音を聞いたシバは、菖蒲とメレのもとに飛んできます。
「だれかお客さんがきたみたい」
「そうだ!」と、メレは思いだしたように手を打ちます。「行商の日だった」
「なにか売りにくるのですか?」菖蒲はメレにたずねます。
「いいや、行商に加工した記憶をゆずるのさ。かわりに食べものや日用品とか、たまに珍品をもらったりする。アヤメの手にぬった即効性ナンデモキクリームもそのひとつさ」
「わたしの手、だいじょうぶかしら」
菖蒲がいぶかしげに両手を見ていると、玄関扉がばっといきおいよく開きます。
「やあ、ひさしぶりだね、メレ!」
階段をおりてきたのは、青いふろしきをかついだ、スーツ姿のシロウサギでした。
行商シロウサギ

「ねえねえ、アヤメちゃん」
シバは小ビンをじいっとながめ、広間でメレがあぶったしょう油味の焼きおにぎりをほおばる菖蒲に話しかけました。
「なあに、シバ」
「この小ビンなんだけどさ、もしかして……」
「おばぁの家にあるガラスのしょう油さしよ」
「やっぱり。たいせつな作品だから、へんなこと言ってはよくないと思ってさ」
「なんで?」と、菖蒲はお茶をすすります。
「ろくろの前にすわっていたら、なんだかおなかすいてきたの。これはいけないって王子さまを思いうかべ納豆ご飯から……」
「まさか、わらからわら納豆からしょう油からのおばぁってこと?」
菖蒲は目を丸くするシバの耳もとに手をそえ、ひそひそと小声で、「そのまさかよ、シバ」。
ふたりはしばらく遠くに目をうつし、ぷっとふきだしてくすくす笑います。
作業部屋で商談をおえたメレとシロウサギは広間にもどって来ると、楽しそうに肩をゆらす菖蒲とシバを見つけます。
「なにかおもしろいことでもあったのかい?」
「いいえ、なんでもないわよね、シバ」菖蒲は口もとに人差し指をあてます。
「う、うん。なんでもないよ。ね、アヤメちゃん」と、シバは頭をこきざみにふります。
でも考えれば考えるほどおかしくて、菖蒲はおなかをおさえ、シバはへんてこりんな顔をします。
「まあいいや」と、メレはけげんそうに言います。「それよりアヤメ、こちらは行商シロウサギのアルネヴ。加工した結晶の取引をまかせている友だ」
シロウサギはグレンチェックスーツのえりをクイクイひっぱり、ちょうネクタイをキュキュッとつまみ、背筋をのばしてからすらりと長い足をくっつけ、つややかなくつのかかとを鳴らして菖蒲の前に立ちます。
「はじめまして。わたしは星間行商のアルネヴです。宇宙の塵から恒星まで、お客さまの所望する品をなんでもおとどけいたします」と、いかにも自信ありげな表情で会釈しました。
「はじめまして、わたしはアヤメです。アルネヴさん、金色の記憶を結晶化させたら透明になったんです。見ていただけますか?」
「もちろんですとも。金色の結晶など、なかなか目にすることのできない博物館級の品ですから、たいへん興味があります」
菖蒲は加工した透明の小ビンをわたします。
アルネヴはまじまじと見つめ、「ううむ。これはなんともむずかしい品だ。ガラスの小ビンにしか見えない。しかし材質はまちがいなく記憶の結晶。金色の断片と言われなければ色ぬけ品でしょう」。
「そうなんだ」と、メレはうなずきます。「でも金色の記憶をこの目ではっきり見た。それに、結晶化まで立ち会っているからほかの断片がまじるはずない。もっとも、ほかの記憶と混合したら干渉により結晶化されないけど」
「なるほど」と、するどい目つきのアルネヴはあごに手をあてます。「ますますむずかしい」
「そのしょうゆさ……」と、シバは思わず言いかけます。
「シバ!」顔をしかめる菖蒲。
「ごめんごめん。金の結晶について、もっとくわしい人はいないかな。ボクの先生に聞いてみるとか」
「まあ、それはいい考えね!」
「なるほど」アルネヴはふたりの話に割って入ります。「それでしたらどんなものでも見定める超一級の鑑定士がいますよ。その鑑定士にみてもらえば、あるいはなにかわかるかもしれない」
「アルネヴさん、よろしければ鑑定士さんを紹介していただけませんか?」
「もちろんですとも」アルネヴは喜んで応じます。「わたしも小ビンの秘密について、ぜひとも知りたいのでね。ただ……」
「問題ありますか?」
「ええ、ひとつだけ。宇宙を旅するためには旅券がひつようなのですよ、ミス・アヤメ」
「そんな」菖蒲はこまったように胸に手をあてます。「わたし、持っていません」
「すばらしい!」アルネヴは菖蒲の手を見て、おどろいたように言います。「持っているではありませんか」
「どこですか?」菖蒲は自分の体にしっぽでもついているのかと見まわします。
「あなたの手に光るのは海の領域を統べる女王テティスの認印ですよ、ミス・アヤメ」
なんと、くじら模様のスタンプは宇宙の果てまで旅できる、とくべつな旅券だったのです。
「まちぼうけ駅のおばぁが押してくれたんです」
「なるほど。わたしもちかくのレウケ島に住む大冒険家イアソン氏と取引でよくいきます」
「レウケ島のイアソン氏っておじぃのこと?」
「そうさ」と、シバは言います。「イアソン先生はアルゴー船でレウケ島に来たんだ」
「そういえばわたし、おばぁとおじぃの名前を知らなかった」と、おどろく菖蒲。
「よかったね、アヤメちゃん。これでボクの役目も果たせたよ。早く先生の家に帰って報告しなきゃ」
「ありがとう」菖蒲はシバを抱きしめ、頭をなでます。「あなたがいなければ王子さまの記憶を見つけられなかったわ」
「干しの王子さま作戦、大成功だったね。それにボクたちだけの秘密もできたし」
「メレさんも、ありがとうございました」菖蒲はメレとあく手します。
「こちらこそ」と、メレは照れながら言います。「アヤメを見て記憶採取は奥深い仕事だと学んだ」
「よし、ではさっそく鑑定士のいる夜明けぬバザールへむかうとしよう。銀河をわたる長旅になりますよ。ミス・アヤメ、わたしについてきて。家と仲間を紹介します」
そう言ってアルネヴは菖蒲を工房の外につれだします。外にはとても大きな白いザトウクジラが停車中で、その背に船のブリッジのような家が見えました。
「こちらはわたしの旧知の仲にして商売の相棒、シロザトウクジラのサトウです」アルネヴが呼ぶと、シロクジラはこちらにやってきます。「サトウ、夜明けぬバザールまで旅をするミス・アヤメだ」
「はじめまして、アヤメです。サトウさん、おせわになります」
サトウは菖蒲を見て、大きな口をゆっくり開き、「はじめましてぇ、サトウでいいよぉ。とってもかわいいむすめさんだねぇ。よろしくぅ」と、あいさつしました。
アルネヴはサトウの背中から垂れ下がる太いロープに足をかけ、「どうそ、こちらへ」と、菖蒲を抱きよせロープをひっぱると、サトウの背にある大きな滑車がくるくるまわり、エレベーターのように家までいっきにもちあがります。
「わたしの家にようこそ」
部屋の床は豪華なペルシャじゅうたんがしかれ、黒ぬりの木製ダイニングテーブルとイス、周囲の壁はいくつもの大きなつづらで仕切られ、天じょうはなく、ハンモックがぶらさがっていました。
「長距離旅行はここで寝とまりするのです。なれれば居心地もよくなるでしょう」
「アルネヴさんの家は秘密基地みたいですね」
ふたりが話していると部屋全体はぐらぐらゆれます。「出発のあいずだ」アルネヴはよろめく菖蒲の手を取り、サトウの頭上にある甲板にむかいました。
菖蒲はぐるり一望してシバとメレを見つけ、手をふります。地平線はみるみる球体に、幾何学模様となった月にはいくつもの流れ星がぶつかり、花火のようにはじけ散ります。
「ねえアヤメ」小ビンをにぎる菖蒲は言いました。「大砲じゃなくってクジラで月にいくのをヴェルヌが聞いたら、きっと腰ぬかすわよ」
月は遠く、まわりの星とおなじほどちいさなつぶとなりました。
「ミス・アヤメ。歓迎をかねた、ささやかなティータイムにあなたをお誘いしたいのですが、招待をうけていただけますか?」
紳士のアルネヴは腕を差しだしました。
「もちろん、よろこんで!」
「いやはや二度も奇跡を見るとは」メレは遠ざかるシロクジラをながめ、ぼんやり言いました。
「でもね」と、シバはこたえます。「ボクの先生がよく言うんだ。二度あることは三度あるぞって」
メレは大笑いしてから肩をすくめ、工房に消えていきました。
夜明けぬバザール

夜明けぬバザールには朝がやってきません。それでガス灯やお店の照明、ネオンサインは絶えずきらめいていました。
バザールのショーウィンドウには服飾や陶器、貴金属に宝石から隕石まで飾られ、ふしぎな色と形の野菜やくだものもならびます。工房や食堂、喫茶店に遊園地やデパートなど街全体は活気にあふれていました。
「朝や昼といった時間のサイクルで活動しない街なんだ」
バザールを歩くアルネヴは菖蒲に説明します。
「日がのぼると起きて、落ちれば寝るのがふつうだけど、ここではずっと夜だから眠くなったら眠り、おなかがすいたら食事をする、というぐあいに、時間にしばられずくらしている」
「どうやって待ちあわせするの?」と、菖蒲は聞きます。
「しない」アルネヴはキッパリ答えます。「会いたいと思ったら会いに行くし、いなかったらまたいつかって」
「時計は? 電話とか」
「まさか」と、アルネヴは顔をしかめ、「きゅうくつでどうかしてしまうよ。時計を手にした、遅刻にいらだつシロウサギなど考えられないだろう?」
バザールでは多くの動物たちがそれぞれ買い物を楽しんでいました。妻ライオンにつきあわされた夫ライオンが大きな箱と手さげ袋を両手にバランスをとりながら歩いています。おめかししたメンドリは子どもたちをうしろに連れ、楽しみにしていたフルーツパーラーへパルフェを食べにいきます。中おれ帽にステッキを手にしたハシビロコウは、ぼーっとブティック前で立ちつくし、オーナーのヒョウ夫人がこまりはてています。秘伝スパイスで有名なカレーショップ『ピッグ』のにおいにさそわれたウシは行列を、通りをへだてたむかいのカレー屋『カウ』ではブタが行列をつくります。
「わたしはおすすめしないよ」と、アルネヴは言います。「味はわるくないが、どちらも鳴き声がうるさくてね」
とりわけにぎやかな広場の中央ではスパンコールドレスにカールさせたまつ毛のホッキョクオオカミが、アコーディオンを奏でるヤマネコの伴奏で『ポラーノの広場のうた』を歌い、みな足を止め、うっとり聞きいっていました。
つめくさ灯ともす 夜のひろば
むかしのラルゴを うたいかわし
雲をもどよもし 夜風にわすれて
とりいれまぢかに 年ようれぬ
まさしきねがいに いさかうとも
銀河のかなたに ともにわらい
なべてのなやみを たきぎともしつつ
はえある世界を ともにつくらん
「アルネヴ!」歌い終えたホッキョクオオカミは、観衆の中にかつての恋人を見つけ、抱擁します。
「いつ帰ってきたの?」
「やあミセス・レイラ、急用でね。常夜の歌姫と呼ばれるきみの声を聞けるぼくは幸せ者だ」
「あなたのためならいつでも」
「ひさしぶりじゃないか、アルネヴ!」
「ザラーファにワヒドカルン!」旧友のキリンやサイもやってきてアルネヴをわっとかこみます。
ひとりのこされた菖蒲は、ベンチにこしかけ、たくさんの動物たちにまじる男や女、子どもからおとなの人影が行き交う様子に目をやり、夜明けぬバザールにつくまでに起きた出来事を思い返しました。
記憶の星を出発したシロザトウクジラ・サトウ号の乗組員となった菖蒲は、アルネヴの秘書をしていました。買い集めた珍品をてきぱきと整理してはカタログにまとめ、取引に持っていきます。
「ミス・アヤメのおかげで商談がスムーズに成立する」と、アルネヴはまんぞくそうに言いました。
ティータイムには新商品の説明を聞き、質問したりして楽しみました。
「このお茶、とてもいい香り。いままでにない味でおいしい」と、菖蒲は言います。
「さすがミス・アヤメだね。これはとくべつな花茶なんだ」と、アルネヴは自慢げに言います。
「希少な長寿星カノープスの竜骨をどうしてもほしいという客がいた。どうしようか迷ったけれど、三千年に一度しか咲かない幻の花ウドンゲをブレンドした茶葉を提示されてしまってはね」
「そっか、香りの正体はめずらしい花というわけね」
「ああ、しかし秘密はそれだけじゃあない」と、アルネヴはもったいをつけて玉虫色のつつをだします。
「ある村の伝統的な保存法で、この茶づつで熟成させるんだ。はじめは酸味がたつが、だんだんミルクのようなまろやかさに変化する。ほんのりハニーの甘みがあるけど、くどくはならない」
「うーんアルネヴ、わたしはミルクよりチョコレートだと思う」
「なるほど、いわれてみればそうかも」と、あごをなでるアルネヴ。
「わたしのテイスティングはこうよ。口にふくむと上品なローズの香り、レーズンのような深みのある酸味と甘み。なめらかなカカオのコク、後口はさわやかなカルダモンね」
菖蒲は身ぶり手ぶりで、いきいきとお茶について説明します。
「すばらしい!」アルネヴは思わず拍手します「ミス・アヤメ、お茶の商売もはじめよう。きっとわくわくするような出会いがあるにちがいない」
アルネヴは行商の仕事を選んだのも出会いだと話します。
「つまりね、わたしはせっかちということさ」
オリオン座の南にあるアルネヴの故郷で家族と昼食をとっていた時、菖蒲に言いました。
「友の手紙を待つナマケモノにもいつか出会いはとどくだろう。ポストの前でそわそわするキツネもいるし、待てずに郵便局まで走る好奇心たっぷりなコッカースパニエルもいるかもしれない。わたしについていえば……」
「家までおしかけるせっかちシロウサギね!」秘書のするどい指摘にアルネヴの十人兄弟は笑います。
そんなせっかちシロウサギと菖蒲はいろんな星に出会いました。オペラハウス『かに座』で上演されたカルキノスがふみつぶされる劇は涙なしでは観れませんでしたし、こと座シェリアクでの舞踏会は海の女王テティスのお姫さまとかんちがいした星の王子さまたちからワルツをさそわれました。おひつじ座にある羊星では秘薬ケムクジャラシを飲んだアルネヴが全身まき毛モフモフにふくれあがり、羊飼いに毛刈りバサミで刈られてツルツルに。菖蒲はおなかを抱えて笑いました。
大きなハンモックにゆられたふたりは星々をつなぎ、長旅のあいだにすっかり意気投合し、深い友情で結ばれました。もし王子さまとの約束がなければ、菖蒲はアルネヴと行商の仕事を楽しんでいたかもしれません。
「ミス・アヤメ、待たせてすまない」アルネヴは言います。
「いいのよ。お友達との再会はたいせつにしないとね」
「ありがとう。さあ、きみとの約束を果たそう」
大通りから入り組む迷路のような路地に入り、奇妙なハーブやスパイスを売る店、バー、地下へとつづくあやしげなラウンジを横目に、さらに進みます。道のつきあたりにジジジ、ジジジと音をたて、ついたり消えたりする赤むらさきの『室定鑑レェシア』と、書かれたネオンサインがありました
「ここがわたしの修行先、アシェレ鑑定室だ。店主は高名な工学博士で考古学にもくわしい。星間ガスを利用したエネルギーシステムで夜明けぬバザールを大きな街にしたのはアシェレ博士なんだよ」
木の扉を開けた先は古びた飾り棚にくすんだアクセサリーやヒビの入った食器がたくさんつみかさなり、ほこりだらけの棺桶からのぞくミイラや倒れかかった甲冑などがひしめきあっていました。
商品を倒さないようせまい通路を横むきに、もぐるように奥へ奥へ進むと、赤いセータにフィンチ型メガネをかけた老ヒツジが薄灯りの下で金のアクセサリーを凝視していました。
「博士、おひさしぶりです」
「字がつぶれておるのぉ」老ヒツジはアルネヴに気づかない様子で、毛むくじゃらの頭をかきながらブツブツひとりごとを言います。
「その象嵌技術は、おそらく百万年前に噴火で消えた星、ペイポンでつくられたペンダントではありませんか?」と、アルネヴはのぞきこんで言います。
「わしもそう思うんじゃが、裏の刻印がな。あとで打ったのか、それとも偽物か……」
老ヒツジはそう言ってゆっくり顔をあげ、アルネヴを見つめ、目を大きくします。
「やあやあ、アルネヴか。ひさしぶりじゃなぁ」
「博士、お元気そうで」
アルネヴは手をのばし、老ヒツジとあく手をします。
「しばらくここに顔を見せないということは商売上々かな。サトウは元気かい?」
「はい。博士によろしく、と。ここまで連れてこれませんので」
「イッヒッヒッヒ。わかっとる、わかっとる」
「博士に紹介したい人がいます」
「はじめまして、わたしはアヤメといいます」菖蒲はおじぎをします。
「ほう、これはかわいい実体の子か。わしはアシェレじゃ」
老ヒツジのアシェレ博士は菖蒲とあく手をかわします。
「さっそくですが、博士に鑑定していただきたい品があります」
「わしにとな」アシェレ博士はおどろいたように言います。「おぬしのほうが目も肥えておるじゃろうて」
「博士にはまだまだ遠くおよびません。鑑定していただきたいのは記憶の結晶です。ミス・アヤメ、見せてもらえる?」
「わかったわ」
菖蒲は小ビンをポケットから取りだし、アシェレ博士にわたします。
アシェレ博士はかがみこむようにして鑑定をはじめます。フタを開けて底をのぞき、アルコールランプのゆれる光にあててコンコンとやさしくたたき、なでてからつくえに置きました。
「で、アルネヴ。おぬしの見立ては?」
「はい。よくある透明な記憶の結晶だと思います。ただ……」
「ただ?」
「金色の記憶から結晶化したと聞いていますので、透明であるにはなにか理由があるのかと」
「ふむ。ではすこし質問を変えようか」と、アシェレ博士は見透かすように目をほそめます。
「もしなにも知らず、これを見たら、サトウの背中に乗っとるおぬしの全財産と交換するかな?」
かたい表情のアルネヴ。ぴんとはりつめた空気が流れます。
「いいえ、しません」
「理由は?」
「損失が高く、利益は見こめません」
「つまり、色ぬけした、そこらにころがる小ビンであると?」
アルネヴは思わず目をそらします。
ヒゲにかくされたアシェレ博士の口角は上がり、メガネをはずします。沈黙を楽しむように数回まばたきをしてから大きなため息をつき、「残念だよアルネヴ。おぬしは一粒の真珠のためにすべてを売った偉大な商人にはまだまだ遠い」。
「どういうことですか!」
「おぬしが星間行商をはじめたいと言った時、わしの話しをおぼえておるかね?」
「はい。よくおぼえていますとも。常識を捨てよ。近似値で評価すべからず。本質を見よ。わたしはいつも心にとめてきました」
「ふむ。個とは似て非なるもの。全は微妙な差異にあり。真は客観に拠る事実よ」アシェレ博士は菖蒲に目をうつし、「この小ビン、アヤメくんはなんだと思うかね?」
「王子さまの記憶で結晶化と加工をした金色の小ビンです」菖蒲は迷わずに答えます。
アシェレ博士は笑顔でウンウンとうなずき、小ビンをアルネヴにわたします。
「もう一度よく観なさい」
言われたとおり、しばらく鑑定しているとアルネヴの顔は紅潮します。
「まさか、まさか、これはもしかして、いや、そんな!」
「そういうことじゃよ、アルネヴ」
「これがあのすきとおった純金……しかし、あれは古い本の!」
「いいかいアルネヴ。まったく未知なるものを前にする時、それまでの知識や経験はいたずらする。おぬしは透明な記憶は色ぬけして価値をもたない、という常識にとらわれ、すきとおった純金の小ビンをガラスの近似値で錯覚した。しかもこの品のむつかしいところは質朴とした外見。だがここで重要なのは本質ではないかね」それからアシェレはこうつけくわえました。「まあわしもこの目で見るまで表現のひとつと思っておったがの。これじゃから鑑定はやめられんわい。イッヒッヒッヒ」
「あの、すきとおった純金とはなんですか?」と、菖蒲は聞きます。
「古い預言書にでてくる鉱物で、『ガラスのような純金』ともいわれている。不純物をうけつけない精錬しつくした金……領域に存在しない伝説の鉱物なんだ」
「ふつう」と、アシェレ博士は言います。「記憶を結晶化させる際、思念が混じる。つまり、もとの色にまぜ手の思いが色をくわえ、そのにごりは結晶に価値をうむわけじゃが、この小ビンは金色の記憶がアヤメくんの思いによって鍛えられ、純度をきわめた、と考えられる」
「金色の結晶でも、その希少性は後世語りつがれるのに、すきとおった純金はいったいどれほどの値打ちなのだろう……」アルネヴは声をふるわせます。
菖蒲はふと顔をうしろをむけ、薄暗い店内を見ました。
「ミス・アヤメ、どうしたの?」
「扉の開く音がしたような」
アルネヴはせまい店の通路をのぞき、「だれもいないよ」。
「気のせい、かしら……」
「なあ、アヤメくん」と、アシェレ博士は言います。「よほど深いわけがあるんじゃろう」
菖蒲は深くうなずき、扉のない中庭について話しました。
「なるほど。言いつたえでは在りえない領域と聞いたが」と、アシェレ博士。
「旅のうわさで耳にしたことがあります」と、アルネヴは言います。「特定の|《ばしょ》ではないはず」
「わたしは中庭を見ました。それにおじぃは闇の門をくぐり、中庭のちかくにまで行ったのよ、アルネヴ」
「レウケ島のイアソン氏か。彼ほどの大冒険家であれば信ぴょう性は高いね」
「闇の門は考えになかったの」アシェレ博士は感心します。「あそこは光うけつけぬ、生命と正反対の領域。足をふみいれれば二度とはもどれまい」
「はい。それでもわたしは闇の領域にむかいます」
「ほうほう」アシェレ博士は菖蒲の覚悟の目を見定め、笑みをうかべて言います。「その思いが奇跡の小ビンをうんだ、というわけじゃな」
「おしえてください。闇の門はどのようにいけばよいのでしょうか?」
「なにを言ってるんだい、ミス・アヤメ。このバザールのすぐそばにあるよ」
「ええっ!」菖蒲は思わず声をあげます。
なんと、知らないうちに目的地まできていたのです。
家出した影

雨がしとしとふってきました。ガス灯やネオンは、ぬれた地面のモザイクガラスに反射して、虹色の水玉をキラキラうつします。
アシェレ鑑定室をあとにした菖蒲とアルネヴは頭をおさえ、路地を走っていました。
「大きな屋根があるのに、なぜ雨はふるのかしら?」と、菖蒲は聞きます。
「街の湿度と温度を安定させるために水滴が落ちるしくみになってるんだ」
ふたりが大通りにぬけようとした時、菖蒲はなにかとぶつかり、「きゃっ」と、声をあげて水たまりにしりもちをつきます。
「だいじょうぶかい?」と、アルネヴはすぐに手を差しだします。
「うん、ありがとう」菖蒲は痛そうに腰をさすり、「だれかとびだしてきたみたい」。
「あやまりもせず立ちさるなんて!」
「わたしも前をよく見ていなかったから」
菖蒲は腹を立てるアルネヴをなだめ、サトウの待つ市外の公園にいそいで帰りました。
「きゃあああ!」
サニタリールームで顔をふいていたアルネヴは菖蒲の悲鳴にびくりと肩をふるわせました。
「小ビンがないの!」
「アシェレ博士の店におきわすれたんじゃないのかい?」と、アルネヴは菖蒲にタオルをわたします。
「ポケットにちゃんといれたわ」
「では帰る道すがら落としたのかもしれない」
「さっきころんだときかな」
「往来のはげしいバザールで落としたらたいへんだ。はやく探そう!」
家を飛びだし、ふりしきる雨もそっちのけ、ふたりはあわてて事故現場の交差点にもどります。
「ああどうしよう、どうしよう!」
顔色をうしなう菖蒲はあっちふらふら、こっちふらふら、気もそぞろです。
「王子さまがもどせなくなったらどうしよう!」
見かねたアルネヴは菖蒲の背にそっとふれます。
「おちついて。いいかい、わたしは博士の店までたどる。きみはこのあたりを探して」
「うん、わかった」
雨ガッパ姿の動物でごったがえすバザールではいつくばるように探しまわりますが小ビンはどこにも見つかりません。キラキラ光るガラスの細片がタイルの目地に落ちていると、まさか割れてしまったのではないかヒヤヒヤします。
「見つかってお願い。見つかってお願い」と、菖蒲はぶつぶつ念じ、フラフラ歩きます。
ふりやんだ雨や周囲の様子など気にもせず、地面をひたすら追いかけ、にぎやかなバザールからどんどん遠ざかります。黒い灯火のゆれる石畳の両わきに白暖簾のちいさな屋台が立ち並ぶ通り道を進み、霧のような闇につつまれました。
「サキにススんではイケナイ。サキにススんではイケナイ」屋台から聞こえるヒソヒソ声。
つめたい風にぶるりと肩をふるわせた菖蒲は、やっと頭をあげました。
目の前に、高さ二十メートルはある鳥居のような巨大アーチ門から人影のようなゆらぎがあらわれては消え、バザールのほうへ行ったり来たりしています。
あまりのぶきみな光景に、菖蒲はこわくなってあとずさりします。すると、門のほうから夜の海をてらす灯台のように、チカチカと光がまたたき、菖蒲は目をうたがいます。なぜなら月で見た金色の流れ星とおなじだったからです。自然と足は光にむきますが、ちかづけばちかづくほど深い闇のほうへすいよせられます。
暗黒からもがきのばされた影のかたまりは、かわいた風によって人形となり、男女はまじわり、子を産み、すぐに朽ちてうつろいます。菖蒲は嵐にもまれ、重い足どりでわずかな光へ進んでいると、若い男女の影がそばによってきます。甘美なぬくもりにまどろみ、菖蒲と影は親子のように仲良く手をつなぎ、深い闇の領域へと連れ去られていきます。
「おかえり、おかえり、わが子よ」と、耳に聞こえる男女の混声。
「お父さん、お母さん。ただいま……」暗闇にすいこまれていく菖蒲。
「サキにいってはだめ」と、男女の混声を打ち消す、笛のように澄んだ女の声。
菖蒲は手首をぐいとつかまれ、門柱の土台石に引っぱられます。
「あなたは……」
菖蒲が夢うつつに見たのは小ビンを手にした少女でした。菖蒲とおなじくらいの年恰好で髪はみじかくカールして、ひとつだけ大きなちがいは人影の像だったことです。
「わたしを助けてくれたの?」
そう聞いても影の少女はうつむいたまま、なにも答えません。
「はじめまして、わたしはアヤメ」と、菖蒲は気にせず笑みをむけます。「よければ家でお茶でもいかが?」
すると影の少女はこくりとうなずきました。
「……わたしはねサトウ、聖人だとはいわないさ。だけどこんどばかりはミス・アヤメをまったく、すこっしも理解できない」甲板で腕と足をどっしりとくみ、寝そべるアルネヴは、ふてくされたように言いました。「貴重な小ビンを盗まれて憤慨もせず、帰るやいなや、ふたりだけで話しをしたいという。雨のなか、懸命に探したのにわけもいわず、わたしの家なのに入ってくるな、だなんてひどいと思わないか」
サトウは、なぐさめるように鼻息をフシューっと吐きました。
いっぽう、そんな哀れなシロウサギの家で、菖蒲はむかいにすわる影の少女に言います。
「ね、おいしいでしょ。めずらしい花をブレンドしたお茶なのよ。さっきのシロウサギさんは行商のアルネヴ。わたしたち、よくティータイムを楽しむの」
影の少女はティーカップを置き「わかんない」と、つまらなさそうに言います。
「味もにおいもなにもかも。影にはいらないから」
「そんなひどいこと、だれが言ったの?」と、菖蒲は聞きます。
「門の外にでてはいけないってパパに言われた。だから家出した」
「あの大きな門のむこうに住んでいるのね?」
少女はかるくうなずきます。
「影はみんな影、影はだれも影」
「ほかの影は門の外にいたわ。なぜ外にでてはいけないのかしら」
「パパが己をもつ影はいけないって」
「そっか」と、菖蒲は言います。「ねえ、もしいやでなければ、あなたの名前をおしえて」
やっと顔をあげた影の少女は首をかしげ、こう言いました。
「ナマエってなに?」
名もなき
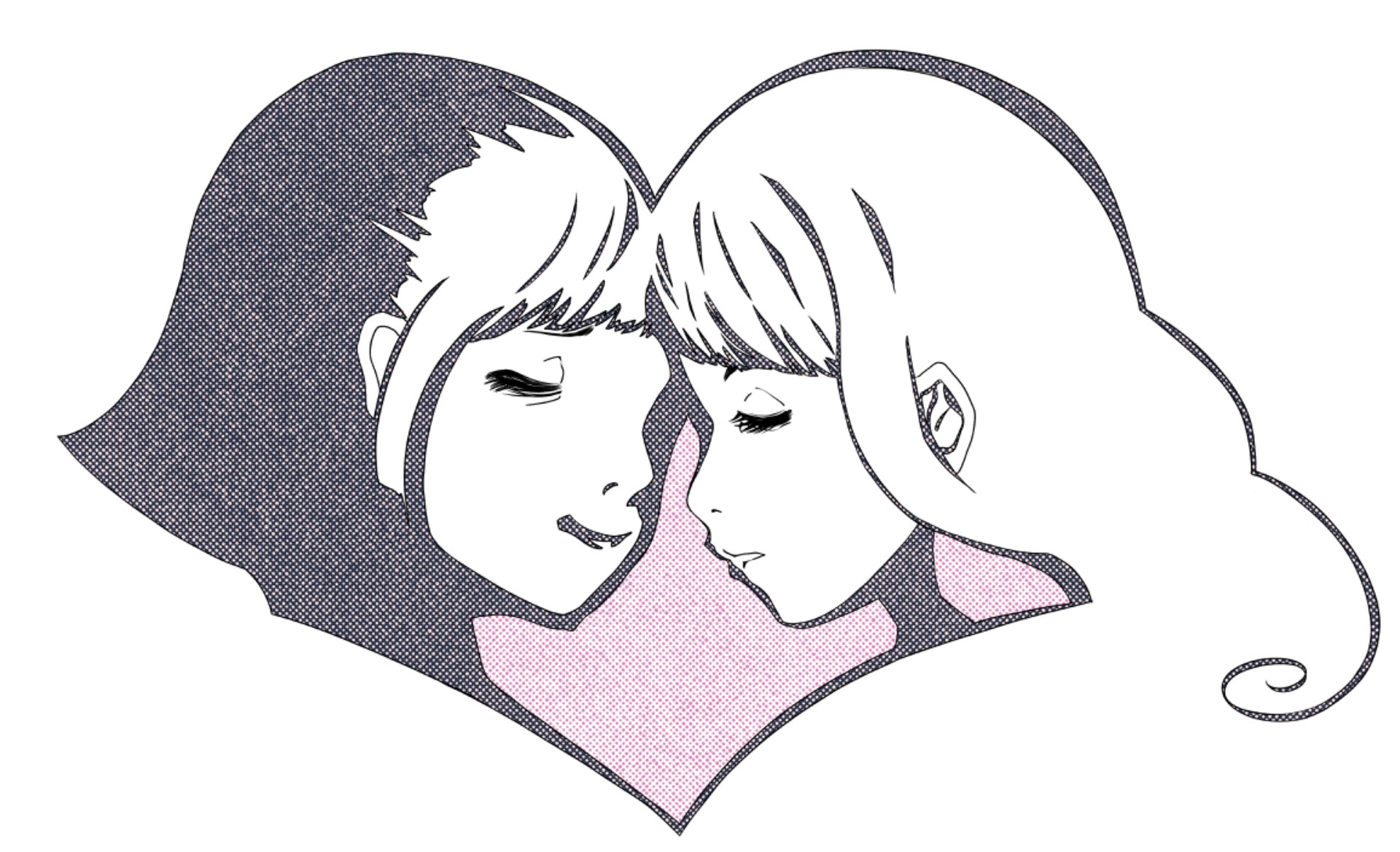
名はなぜあるのでしょう。区別するため、意味や価値を付すため、あるいは理解するためでしょうか。
だれでも名をもち、好き嫌いにかかわらず名によって呼ばれます。だれかを知ろうとする時、知ってもらおうとする時、まず名をたずね、自己紹介をします。菖蒲もあたりまえのように少女の名をたずねました。
人影は自分や他人がなにであるかを知るひつようがありませんし、そもそも影を意識して生活する人はいません。
夜明けぬバザールにうつろう影は実体の投影で、住民は空気のように見ていましたし、菖蒲も影の少女と出会い、話さなければ、影について気にしなかったでしょう。
しかし名について問われた名もなき影の少女は、いまやその意味について知るひつようがありました。
わたしはなにをもってわたしなのかを。
「あた……あたし」
影の少女は居心地わるそうに目をきょろきょろさせ、小声で言います。
「ナマエは知らない。でも」
「でも?」
「あんたの心がほしい。それで家出したのよ。兄みたいに」
「お兄さんがいるの?」
「兄は兄妹といってた。兄はナマエをもらったと言い残してでていった。二度と帰ってこなかったわ」
「お兄さんはなんで家出したのかしら」
「ほしいものがあるんだって。あたしもいつかそれをほしくなるって」
菖蒲はすこし考えてから、少女にこうたずねます。
「どうしてわたしの心がほしいの?」
少女はひくっと肩をゆらし、「あたしも知りたい。オチャ……それにナマエ。だから……」
「だから?」
少女は小ビンをにぎりしめたまま、かたまってしまいます。
うなだれる少女をじっと見つめる菖蒲は、黙って答えを待ちます。
「だから、だから……」と、少女の目から影の涙がポロポロこぼれ、しぼりだすような声で言います。
「だから……あた……し……あたしは、あんたの小ビン……とったのよ」
少女のつたない告白に菖蒲の胸は強くしめつけられ、まゆをよせ、口びるをかみました。
「あんたが小ビンのこと話してるの聞いたわ」と、少女の顔はあかるくなります。
「これがあれば、あんたになれるんでしょ。だから使いかたをおしえてちょうだい」
少女のすんだひとみにうつるひとつ星を見た菖蒲は強い愛を感じ、なぐさめるようにこう言います。
「なれないのよ。その小ビンでわたしにはなれないの」
「うそつき」少女は首を横にふり、乱暴に言います。「記憶と思いがあるって聞いてたんだ」
「そう。たしかにその小ビンは、わたしのだいじな人の記憶やわたしの思いがたくさんつまっているけど、それを手にしたからといって、わたしになれないわ」
「うそつき!」机をたたき、どなりつける少女。
「どうか、聞いて」と、菖蒲はおだやかに言います。「あなたはあなたで、わたしはわたし。あなたがどれだけ望んでも、心はあなたの空腹を満たしてはくれない。それに、たとえわたしになっても、ほかのだれかに変われたとしても、自分ではないと気づいたら、あなたはもっと傷つくだけよ」
「うそつき!」少女はちがうとばかりに首をなん度も横にふります。「そうやってあんたはぜんぶ自分だけのものにしてる! あたしはあんたになりたいの。あたしにはなんにもないんだから!」
「わたしは捨てられ、家族も生まれた場所や誕生日も知らないのよ。菖蒲という名前ですら五月に拾われたからってだけ。それでも、あなたはほんとうにわたしになりたいと願うの?」
「大うそつきのあんたなんかにわかんないのよ! あんたには心がある。あたしにだってもらえなきゃおかしい!」
「じゃあ交換しましょう」と、菖蒲はぱっと立ちあがり、興奮する少女の両肩にふれます。「わたしはわたしの想う人のため、小ビンがどうしてもいるの。だから、わたしの心の半分をあげる。そのかわり小ビンを返して」
「ええいいわ」少女はにこりと笑顔で首をたてにふります。「どうやってあんたの心をくれるわけ?」
菖蒲は王子さまのつけていた首かざりから指輪をはずして右手の薬指にはめると、赤い宝石は炎のようにまっ赤に燃えます。
「ひとつだけ約束して」と、菖蒲は少女に言います。「いつか、わたしの心をひつようとしなくなったなら、わたしに返してほしいの」
「わかった。約束する」
菖蒲が少女の首に腕をまわした、その時————
「アヤメはうそつきなんかじゃない! きみがわがままなだけなんだ!」
ひどくとりみだしたアルネヴは、声をあげてふたりの前に飛びだします。
「アヤメ、アヤメ。ぜったい、ぜったいにあげてはいけない! きみの心が分たれるなら、どれほど苦しむだろう。欠けた心はたがいを探しもとめ、どんなにかつらい思いをするだろう。そんなのわたしは見ていられない! こんなのおかしい、まちがってる、まちがってるよ!」
菖蒲は少女のむこうに立つアルネヴにほほ笑みかけます。でも、アルネヴは見ました。菖蒲の右目から涙が一つぶこぼれるのを。菖蒲はやさしくキスをし、おでこを影の少女のおでこにあてました。すると赤い宝石から鮮血がほとばしり、天は産声をあげ、稲妻がふたりに落ちました。菖蒲はアヤメが引き裂かれる強烈な痛みを内奥に感じます。顔をゆがませ、歯を食いしばり、じっと耐え、すべて受け入れます。魂がぬけでるような息をはき、指輪をはずしてから首かざりにもどし、仲のよい義姉を忘れました。
「アヤメ!」アルネヴはくずおれる菖蒲にかけよります。「ああ、きみはなんてことを!」
「ねえ」と、菖蒲はまゆをひそめ、「わたしはふたりで話したいって言ったでしょ」。
「そんな、わたしはきみがしんぱいで、いてもたってもいられなくて」
「外で待っていて」
紳士のシロウサギはしょんぼりと部屋をでていきました。
「ありがとう、アルネヴ」と、菖蒲は小声で言います。「ごめんなさい」
影の少女はとまどいながら盗んだものを返し、どうしてよいかわからず、小ビンをだいじそうになでまわす菖蒲を見つめます。
「あなたの名前、わたしがつけてあげる」菖蒲は少女にはっきりと言いました。「あなたの名はミモザ。ミモザよ」
名もなき影の少女は、この時はじめて名の意味を知りました。影である自分はミモザで、相手は菖蒲であると。
「聞きなさい、ミモザ。あなたはわたしが歓ぶとき喜び、わたしが悲しむとき哀しむの。わたしの痛みはあなたのとげとなり、わたしの辛苦はあなたにとってかせとなる」
そう言い残し、菖蒲はアルネヴを追いました。
ひとりになったミモザは両手を胸にあて、目を閉じます。
美しい景色、こころよい音楽、すてきな香り、ほっぺが落ちるような料理、ふれあい満たされる充足感……ゆたかな感性やあふれる感情はすべて心さえあれば自由に叶えられるだろう。兄がほしくなるといったものはこれだったんだ。影の少女はそのために家出し、小ビンをうばいました。
でも、心の半分を手に入れてミモザがさいしょに感じたこと、それは空虚でした。
闇の門口
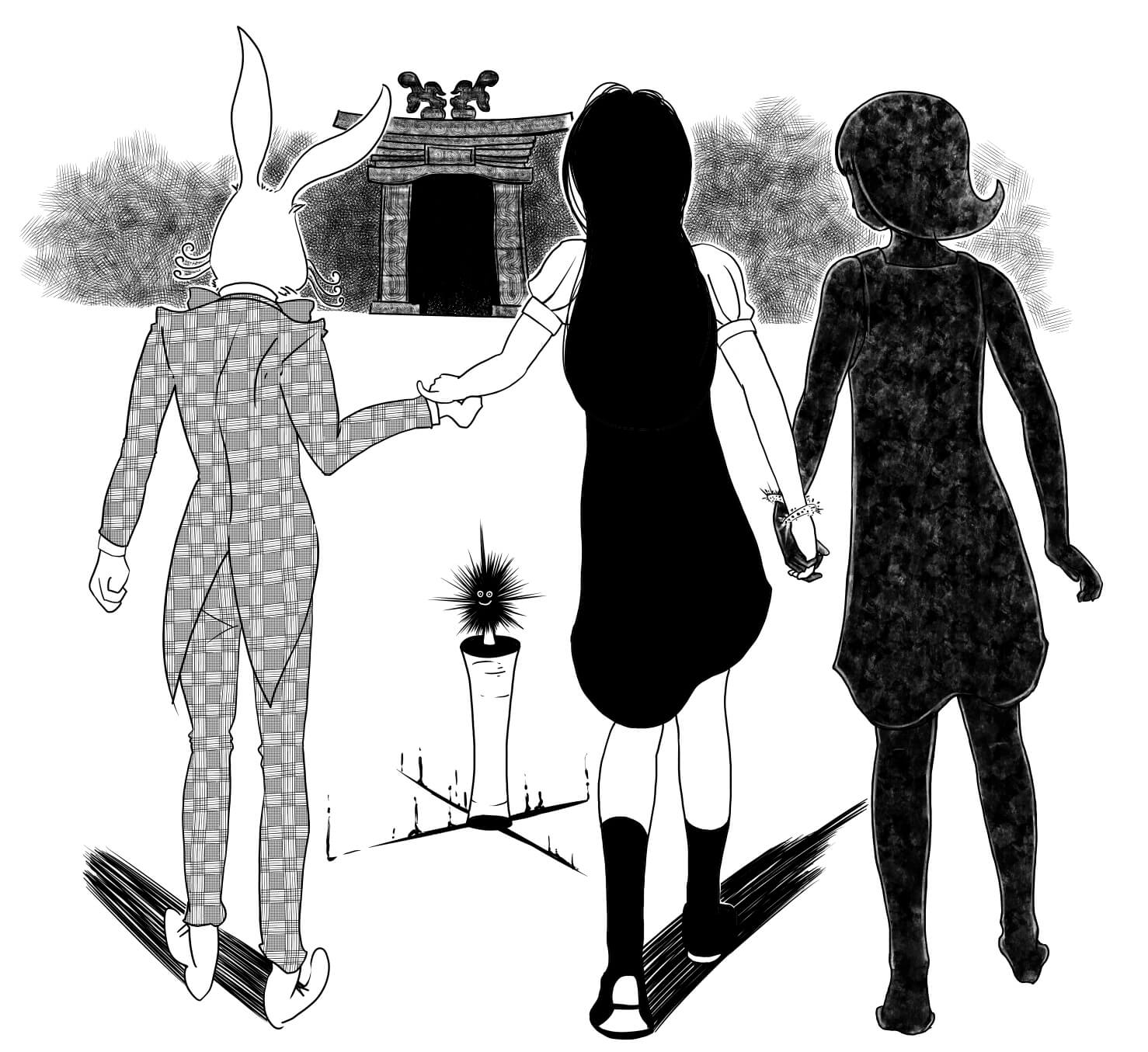
ミモザはそっと隠れて菖蒲とアルネヴを遠くからのぞきました。
しんぱいするアルネヴ、うれしそうに小ビンを見せるアヤメ、ふきげんなシロウサギが頭上でうるさかったとあきれるサトウ。みんなミモザが小ビンを盗んだとは言いません。
でも、なぜだかミモザの胸はうずきます。
「それはね」と、菖蒲の分つ心はミモザの耳もとでささやきます。「友情は守らなければ、かんたんに壊れてしまうからよ」
ミモザは答えるように菖蒲にかけより、言いました。
「アヤメ、あの、その……アヤメのだいじなものをとってしまってごめんなさい。それに、うそつきって」
「もちろんゆるすわ、ミモザ」と、菖蒲はためらわずに言います。「だってわたしたち友だちでしょ」
すると、ミモザの感じていた胸のうずきは消えていきます。
「もし」と、ミモザは痛みにむかって語りかけました。「あたしがだれかを傷つけたり、うそをついて悲しませたのなら、またもどってきてほしい。まちがいに気づくために」
ミモザをティータイムに誘い、みんなでテーブルをかこみます。金ぶちの白磁カップとソーサー、銀製のティースタンドには下からキューカンバーサンド、スコーン、一口サイズのケーキやマカロンがのっていました。
「うん、これもまたいいね」と、アルネヴは温めなおした花茶をテイスティングして言います。「もっとまろやかになっている」
「だめよアルネヴ」菖蒲はむすっとします。「しぶみがでてる。ゲストにこんなお茶をだしたらわたしたちのティータイムはだいなしよ。新しいのと交換してちょうだい」
「ええっ」アルネヴはおどろいたように言います。「このお茶、高価なのに……」
「レディをもてなしていますのよ、紳士のアルネヴさん」菖蒲はすんとした顔で言い返します。
「それとも、うしろの棚の上から二段目、右奥に隠してある、もっとすばらしい茶葉をわたしが知らないとでも?」
アルネヴはあきれてなにもいえず、しぶしぶ新しいお茶にいれなおしました。
ミモザはくすくす笑っていると、ふんわり立ちのぼる花の香りに目を大きくします。
「なんていいにおいなの!」
「でしょ。ミモザ、飲んでみて」菖蒲はうれしそうにミモザにすすめます。
お茶を口にしたミモザはまゆをよせたりあげたり、菖蒲とアルネヴは固唾をのんで見守ります。
ふーっと、鼻から息をぬくミモザ。
「ミモザ、どう?」
「おいしい……お茶ってこんなにおいしいんだ」
うっとりしたミモザの体は、なぜだかここちよさでみたされます。
「それはね」と、菖蒲の分つ心はミモザの耳もとでささやきます。「みんなに歓迎されているからよ」
ミモザは答えるように、笑顔で言いました。
「アルネヴ、アヤメ、あたしのためにありがとう」
「どういたしまして」アルネヴは照れながら言います。
「アルネヴはキュートなレディに弱いんだから」と、からかう菖蒲。
「まさかミス・アヤメ、彼女にやきもちやいているのかい?」と、言い返すアルネヴ。
菖蒲は顔をまっ赤にして、「そんなことないもん!」
サトウまで大笑いすると部屋は大きくゆれ、ミモザはもっとうれしくなります。そして、この時がいつまでも続けばいいのに、と思いました。
「もし」と、ミモザは幸せにむかって語りかけました。「あなたをあたりまえのように思い、ありがとうってつたえるのをわすれたら、どうかあたしからはなれてほしい。感謝を思いだすために」
ティータイムを楽しんだ後、みんなでバザールにでかけました。
「ねえねえ見て見て、ミモザ。あそこで行列しているカレー屋さんは鳴き声がうるさいのよ。でもそういわれると食べてみたくなるのよね。あっちも……」
そう言って菖蒲はミモザの腕を引き、お店に走ります。
どこまでものびるスパゲッティ化現象アイスクリーム店、プカプカとうかぶ星の卵を売る店ではだれよりも先に星の名前を決めることができます。ただし、みんなに自慢できるのは何十億年もあとの話ですけど。宇宙乗りものショップでは高速ロケットのほかにも、おしりからもれるあの空気を利用した、クリーンヘネルギー新型バイクがショーウィンドウにかざられています。でも、においの完全除去については今後の課題のようです。そのとなりが焼きいもの店であるのは偶然でしょうか。古着屋さんのマネキンには裸の王さまが着ていたというバカには見えない服、雑貨屋さんのおすすめはジャックがうえた天までとどく豆と金のたてごとで、いまなら金のたまごもセットで買えるようです。
ミモザに刺しゅう入りのボタニカルブラウスをあてがい、菖蒲の首にきらきらのネックレスをかけます。ふたりはなんでも手にとり、においをかぎ、口にし、たくさん笑いました。スゴロクでマスを進めたりもどったり、ときには一回休みになるように、この店に入ったかと思えばまたあの店と、ゴールになかなかたどりつきません。アルネヴには、そんな手をつないであちこち歩くふたりの少女のうしろ姿が姉妹のように見えました。
それからついに「サキにススんではイケナイ」と、ヒソヒソ声の聞こえる屋台までやってきます。
「きみたちにプレゼントしたいものがある」と、アルネヴは菖蒲に金、ミモザには銀の腕輪を贈ります。
「これは超新星爆発でわかれた星のかけらをアルケミストの手により金と銀に変えたとされている。ふたつはひとつになろうとする腕輪なんだ。きみたちの友情にぴったりだと思って」
菖蒲とミモザは口をそろえて感謝を伝え、菖蒲は腕輪を右手首に、ミモザは左手首につけました。
「行商はこれより先に進むのをゆるされていない。市のあるところまでだ。だからお別れだね」アルネヴは名残惜しそうに言います。
「アルネヴ!」菖蒲は愛するシロウサギをぎゅっと強く抱きしめます。「あなたに会えてほんとうによかった。あなたはわたしの、とても、とってもたいせつな家族よ。またティータイムに招待してもらえるかしら」
「もちろんさ、アヤメ」と、アルネヴは親しみをこめて言います。「わたしたちは多くのすばらしい宝に出会えたね。そしてこれからも」
「うん」
「おぼえておいて。わたしはきみのためならどこでもすぐ助けにゆく。約束だ」
「ありがとう、アルネヴ。大好き」菖蒲はアルネブのほおにキスをします。
ミモザはそんなふたりの惜別をながめ、強い悲しみに襲われ、こう思います。
——そうか、アヤメとアルネヴはこの時をふたりだけで過ごしたかったけれど、なにも言わず、だいじな時間をあたしにゆずってくれたんだ。大切な人とはなればなれになるのは、こんなに不安で苦しくてつらい時を耐え忍ばなければいけない。それなのに、あたしはアヤメの心を引き裂き、アヤメはずっと菖蒲を探している。
ねえアヤメ、なぜあたしを責めないの? 小ビンを盗む、姑息な影だとしかりつけ、ののしればいいのに。ねえアヤメ、どうしてあたしはあなたの友人なの? 心を奪った悪い影だと憎み嫌い、避けてくれればいいのに。
「それはね」と、菖蒲の分つ心はミモザの耳もとでささやきます。「ただ分けあいたかったから。どうしようもなく、言葉にならない寂しさを、ただ知ってほしかった。わたしが独り泣く時に、あなたのような妹がそばにいてくれたら、どんなによかっただろうって」
ミモザは遠くまで広がる孤独にむかってさけびます。
「ああ、あたしのうちにまかれた、たくさんの悲しみよ! おまえたちは喜びの花となれ。カタクリの花がいくどもいくども厳冬を越し、早春の野山をひっそりとかざるように。いつか、そのちいさな花を独り待つ姉にとどけよう」
ふたりはアルネヴに手をふります。
「アヤメ、あたしの手をはなさないで。あなたの行きたい場所を知っているから」
ミモザは左手で菖蒲をつかみます。
「あたしを信じてくれる?」
「もちろん」と、菖蒲はミモザの手をにぎり返します。「いつも、いつも。ずっと、ずっと」
ふたりは手をつなぎ、闇の門をくぐりぬけていきました。
人と影による交唱

道しるべは右手に感じるミモザのぬくもりだけでした。
歩くたびにコツンコツンと石をたたくような固い足音が反響しますが、神殿なのかお堂なのか、まっ暗でなにもわかりません。
撚り糸をほどくようにミモザの手をはなしたなら、闇の中でひとり残され迷子となって、だれも助けてはくれないでしょう。
「ミモザはどこにいるかわかるの?」
菖蒲は不安げにそうたずねると、ミモザの声が返ってきます。
「ええ。でも前よりわからなくなってきてる」
「なぜ?」
「光を見るようになったから。かすむけどだいじょうぶよ、アヤメのいきたい階段は、兄になんどかつれていってもらったの」
「お兄さんと?」
「うん。兄は闇の領域にやってきた男の人を階段に案内したわ。帰りを待っていたけど、もどってこなかった。そのあと、兄は闇の門から出ていった」
「ミモザはここにどれくらい住んでいたの?」
「闇の領域は時間がないからわからない。でもアヤメの生まれるずっと前から存在してたと思う。己をもつ兄とあたしは変化しない人影で、実体や意志のない影はいろいろな形相に変化する」
「闇の門やバザールで見た影のように?」
「そう。あれらはアヤメから視えた象。アルネヴから視える影はちがうのよ」
「ミモザも?」
「ううん。あたしは影を作りだすことはできない。それぞれ投影された姿から、思いや考えをすこしのぞける。兄は影をとどめ、あやつれるのよ」
「ねえミモザ、なにか聞こえない?」
「アヤメ、それは幻聴よ」ミモザは菖蒲の右手をくいっと引きます。「闇はいろんなものを見せるから気にしちゃだめよ」
「た……すけ……て……」
「女の人がどこかで泣いてる」
「たすけ……て」
「どこ? どこにいるの?」と、菖蒲は左手を闇にのばします。「見えないの。なにも、なんにも」
「たすけて」
「アヤメ、無き者に関心をむけてはだめ」遠くになっていくミモザの声。「あたしだけを信じて」
「ミモザ、どこ? どこにいるの?」左手をおよがせる菖蒲。
「ここよ、助けてアヤメ」
「わたし?」
「そう、ここよアヤメ」
「待っていて。すぐに行くから」と、菖蒲はからませた右手をふりほどこうとします。
「アヤメ!」と、ミモザは左手をぎゅっと強くにぎり、「あたしの手をはなさないで!」
「ミモザ、わたし……」菖蒲の呼吸はみだれ、心臓はバクバクと強く鼓動します。
「しーっ、静かに。闇のあるじがあたしたちを引きはなそうとしてる。そうよね、パパ!」
ミモザがどこかに呼びかけた瞬間、菖蒲はおしつぶされるほど強い力と視線を感じ、あまりの寒さにぶるぶるふるえます。
「我は」と、地面をゆらすほどの低いうなり声は反響してあちこち聞こえ、混だくした言語は集合し、理解できる音声にかわります。「おまえの父ではない」
菖蒲は恐怖のあまりミモザの腕にしがみつきます。
「あなたがあたしたちの父であると兄から聞きました」と、ミモザは言います。
「影に兄弟などない」闇のあるじは答えます。「どちらも配列の誤差と補正のガラクタにすぎん」
「ガラクタ?」と、つぶやく菖蒲。
「それでも、あなたはパパです。あたしは友人を連れてゆきます」
「領域の調和をみだす者は報いをうけるさだめ。己をもつ影よ、わきまえていよう」
「はい。もちろん、ここで罰はうけます」
「愚かなガラクタめ。名は己をあざむく言葉。もうひとつのクズがそうであったように」
「クズ?」と、つぶやく菖蒲。
「そうだ、娘よ」と、闇のあるじは菖蒲にむけて言います。「さだめられた領域を侵すにあきたらず、本質を異にする影に情をよせ、つけこむとは。その傲慢が領域に破滅をもたらした事実をわすれたか」
「ちがう!」菖蒲は力強く反論します。「どんなものもおなじであると決めつけてはいけない。わたしは海の女王からそうおしえられた。世界にひとつとしておなじものはない。影もまた」
「虹の娘よ。捨てられてなお、口にあまく、腹には苦い言葉をはくか」
「アヤメ、無き者を気にしなくていいのよ。もういきましょ」
ミモザはそう言うと闇のあるじを無視して菖蒲の手を引き、ずんずん歩きます。
すると濃い影があらわれ、菖蒲とミモザを大勢でかこみ、闇のあるじと交唱をはじめました。
黄色い花の下劣な詩は
我らに浅く
黄色い花の醜悪な体は
我らにおぞましく
黄色い花の低俗な舞は
我らにつたなく
黄色い花の卑猥な口は
我らに耐えがたく
黄色い花の…… 黄色い花の……
我らに…… 我らに……
反復するあざけりの歌は菖蒲の耳にまとわりつき、くすぶる怒りに火を、憎しみのマグマをふつふつとわきあがらせます。容赦ない非難そして同調により、感情や自尊心をぐしゃぐしゃに破壊してやろうと歌っているのです。しかし黄色い花とはだれなのでしょう。
——わたしのミモザよ! ぜったいゆるせない!
菖蒲は右手に力をこめます。
「あたしのためにおこらないで」と、ミモザは言います。「そんなアヤメを見たくないの」
「だってミモザ、あなたを壊そうとしているのよ! 闇に隠れ攻撃する卑怯で最低な者たち!」
「パパも影も隠れてなんかない。知らないだけ。ねえアヤメ、あたしもそうだったでしょ?」
「あなたは、あなたはちがう!」
「ううん。あたしも知らなかったのよ、アヤメ。言葉は火傷させたり、凍える手を温めもできる。あなたにそうおしえてもらえた」
「でも、あいつらはそんなあなた独りを知ろうともしない!」
「あたしはアヤメだけに知ってもらえればかまわない。アヤメだけでいいの」
見えない闇から投げつけられる罵詈雑言を払いのけるように、ふたりは前へ前へひたすら歩き、ついに目的の場所につきました。下へとつづく、うす暗い階段に。しかし、燃え広がる憎しみは菖蒲の目をくもらせ、すぐ前にある階段がまったく見えません。
闇のあるじは、つたない撚り糸を無情に断ち切ろうと誘惑しました。
「浅薄なアヤメよ。おまえが名づけた黄色い花のゴミクズミモザは影ゆえ存在も廃棄できず、情に苦悩しながら闇をさまよい続ける。約束の力で破壊しろ。キエロゴミクズミモザ、コワシテシマエ」
「ええ、こわしてやるわよ。あんたたち! みんなぜんぶ!」
激高した菖蒲はミモザの手を力づくでふり切ろうとします。
「アヤメ、手をはなしてはだめ。やっとここまできたのに」
「キエロゴミクズミモザ、コワシテシマエ」
「ミモザ手をはなして! みんなこわしてやる! みんなみんなこわしてやるんだから!」
「心を闇にしずませないで、アヤメ」
「はなせ! ミモザ! はなせミモザ!」どなりつける菖蒲。
「キエロゴミクズミモザ、コワシテシマエ、キエロゴミクズミモザコワシテシマエキエロゴミクズミモザコワシテシマエキエロ……」
「あんなやつら、いなくなればいいんだ! あんなやつら、消えてなくなればいいんだ!」
灼熱の憎悪が両手を焼きこがしても、ミモザはけっして力をゆるめませんでした。菖蒲の手をとり、闇の領域をみちびき、役に立てたのが、とてもうれしくて、なにより幸せだったからです。
——だから、これはあたしの大好きなアヤメなんかじゃない。
「アヤメ、アヤメ」ミモザは声を荒らげる友に呼びかけます。そう、なんども、なんども。
「あたし、あなたとの約束ずっとおぼえてる。おぼえているわ。だってあたしは宇宙でいちばん美しいアヤメの心をもっているんだもの。あたし、アヤメのためになんだってしたい。すべてをあげてもいいとさえ思える。もう、あたしのぶんはなんにもいらない」
「でも、あいつらは! むりよ! あいつらだけはゆるせない!」
「ううん。それでも、よ」と、ミモザは焼けただれた左手をアヤメの右手にからませます。「さよならの時は大好きな友に笑顔でいてほしい。また会おうって、あしたまた遊ぼうねって」
「でも、あなたをこんな腐りきった墓場においてけない!」
「ううん。それでも、よ」と、ミモザは右手を怒りでこわばる菖蒲の顔にのばし、やさしくなでます。自然とふたりは語りかけるように、やがてそれは交わす歌となり、闇の領域に広がりました。
あなたは聞くでしょう
吹きすさむ非情な声を
それでもあたしは越えよう
あなたは清らかな琴の音
あなたは歩くでしょう
光とどかぬ闇の淵を
それでもあたしは望もう
あなたは夜にまたたくアメジスト
あなたは泣くでしょう
凍てつく孤独の時を
それでもあたしは耐えよう
あなたは穏やかな暖炉の炎
あなたは抱くでしょう
みにくいわたしの本心を
それでもあたしは愛そう
あなたのあたえてくれた分つ心
「よかった。いつものアヤメね」
「わたしのミモザ! また会いましょう。一緒にお買いものをして、一緒にお茶をのんで、一緒に旅するの。あなたと見たいものや知りたいことがたくさんあるから。いっぱい、いっぱいよ……」
あふれる想いをつたえた時、笑顔でいられたのか、それとも悲しい顔なのか、菖蒲にはわかりませんでした。でも、ミモザだけは知っています。ミモザが最後に暗闇で見たのは、大好きな菖蒲の顔だったのですから。
菖蒲は手をふりうす暗い階段へ、ミモザはあざけりの歌が聞こえる深い闇にとけてゆきました。
通路の消失点Ⅲ
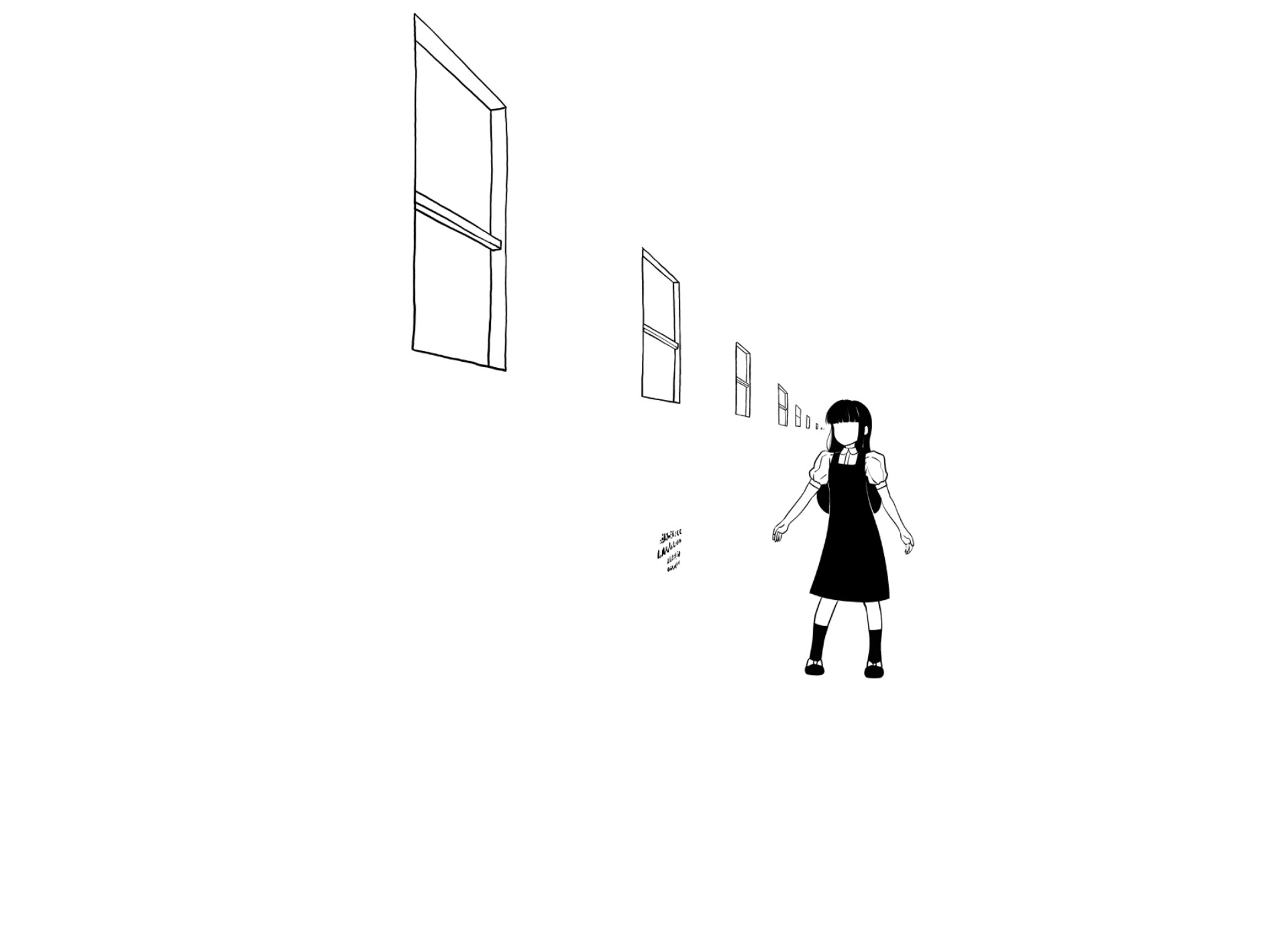
まっ白な壁の通路は、あまりの長さに先が見えません。まるで宙に浮いているような白い窓が等間隔にならび、ガラスはなく、のぞいても外に広がるのは白でした。
しばらく歩いていると、おりてきた階段はだんだん遠くなり、やがて周囲の白とまじりあい、消えてしまいます。
旅のはじまりにおりてきた変わらない通路になつかしさをおぼえ、菖蒲は足を止めます。
干しわらの王子さまを玉座にのこしてから、どれくらい過ぎたのでしょう。
遠くの消失点にむかって歩き続け、いろんな仲間と出会い、わかれ、まっ白な通路へ帰ってきたのです。まるで時計の針が一周したように。
「だったら0時に出発したことにして、いまは12時かな。そうするとつぎは……24時にしよう。まだ一周できるわね」
菖蒲はくすりと笑い、思いだしたように右下、足もとあたりに目をやると文字が書いてありました。
ミエルモノガサキデワナイ
ケレドモミエナクバサキニワユケナイ
ゼンポウチュウイ
アシモトチュウイ
菖蒲はかがんで壁面文字の謎についてじっくり考えました。
まず、『ミエルモノ』とはなんでしょうか。
「それは通路とその先に見える点よ」
しかし文字の続きは『サキデワナイ』と、否定しています。菖蒲は見える消失点を見えないようにして『サキ』へ進むのが謎の答えであると解釈し、『サキ』を手でかくし、見えないようにしたのです。一度目は木の扉にぶつかり、二度目は地面の扉に足を引っかけましたが。
「二段目の文字はフクロウ先生の大きらいな言いわけがましい逆説の接続詞、『ケレドモ』ね。『ミエナクバサキニワユケナイ』って一段目と矛盾してるのよね」
菖蒲はレウケ島のイアソン氏から聞いた話しを思いだします。
「おじぃは、うす暗い階段をおりたところが中庭にちかい場所とおしえてくれた。だから『ミエナクバサキニワユケナイ』ところが中庭にもっともちかい場所ってことになる」
どうやって『サキ』を見ることができるのでしょうか。菖蒲はポケットの小ビンに手をやりました。
「アシェレ博士は常識を捨てて本質を見るようアルネヴに言ってた。小ビンの本質である金は変わらず、色ぬけガラスだというアルネブの見かたが変わったのよ。それなら通路の本質はなにかしら」
菖蒲は『ゼンポウチュウイ アシモトチュウイ』と刻まれた段を指でなぞります。
「これは通路を通るたびに話したわたしの声がのこされたんだわ」
では、さいしょの文字はいったいだれがのこした言葉なのでしょうか。
「わたしのほかに薄暗い階段をおりたのはおじぃだけのはず。だからはじめの文字はおじぃの声ね。でもおじぃはわたしに階段をおりた先はわからないと通路について言わなかった。ううん、言わなかったんじゃなくて通路だと思わなかったのよ。ということは、これらの文字は通路でなく中庭について書いてあるのか。だから矛盾している」
菖蒲はぱっと立ちあがり、通路を見回します。窓は消失点に続き、壁面文字はかならず右にありました。消失点にむかって歩きますが、もちろんいつまでも『サキ』はつきません。ふしぎなことに天井をあおいでも目を落としても正面となって窓は消失点へ続いているのです。
「ずっとこの通路の『サキ』が扉のない中庭だとばかり思いこんでいたから窓と文字の位置が変わらないことに気づかなかったんだ。自分で作りだした錯覚の通路を歩き、『サキ』である近似値の扉を開けていた。でも本質はもっとシンプルで、この場所そのものだったのね」
ついに壁面文字の謎を解き明かした菖蒲は、さっきまで12時をさしていたあたりまえの時計の針がとつぜん、ぐるぐるぐるぐる回りはじめ、あまりの速さに煙をあげて爆発するような衝撃をうけ、新しい時間の波にくらくらめまいすらしました。
「つまり、わたしのいるここが中庭にもっともちかい場所よ!」
そうです。菖蒲は旅のはじまりに目的地のもっともちかくにいたわけで、通過点をそのように認識するだけでよかったのです。しかしいったいだれが、壁面文字はイアソン氏の言葉だと、中庭にもっともちかい場所だとわかるでしょう。
では、菖蒲は無駄なまわり道をしていたのですか?
そうさアヤメちゃん。たいせつな一瞬をすくいよせれば、
人生は思ったより長く、ややこしい時間すら、いとおしく感じるものさ
「おばぁ」と、菖蒲は顔をゆるめます。「たしかにそう思えるようになりました。きっとこれからも」
ここまで歩いた菖蒲の旅路は、どれもいとおしい思い出になっていました。
もっともちかい
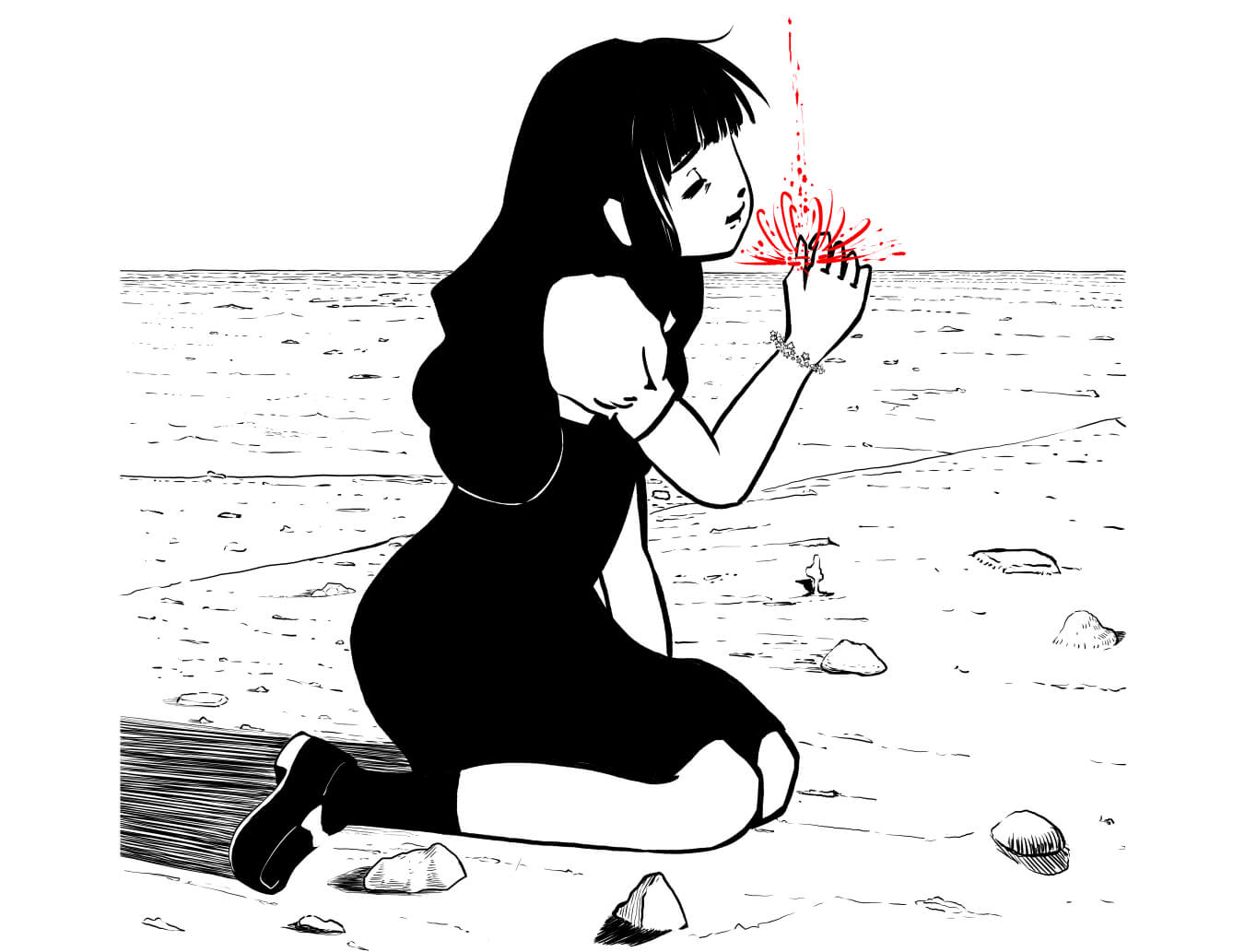
……チン……チリン……チン……
ガラスの器を指ではじいたようなかたい音が不規則なリズムで聞こえ、意味を失った壁面文字と窓わくは風化してボロボロくずれ、ちりとなります。
無色の空と、さらさらの白い砂に、石英のような透きとおった石がころがる荒漠とした地平のあいだに、ぽつねんと立つ菖蒲だけ色をもっていました。
ぐるり見渡すと、地面には双方にむかう足あとが遠くまで描かれていました。まるで新大陸に到達した航海者が残した記念のように。
「これはきっとおじぃの歩いた足あとだわ」
菖蒲はそう言って足跡をたどりました。すると大きなリュックサックを背に、カタンコトンとケトルやマグカップをうちならす好奇心にあふれた青年の幻影が見えます。ふと青年はこちらをふりむき目をきょろつかせ、口もとをうごかします。
「見えるものが先ではない。けれども見えなくば先にはゆけない……」
菖蒲は幻影をひたすら追います。
「暗い夜道をミモザに手をひかれ歩いた時も、こうやっておじぃの足跡もなければ、なんにもわからなかったはず。わたしはみちびかれているのかな。それともわたしが選んでいるだけなのかしら。そのどちらもなの? だれかおしえて。自由とはなに? わたしとは? わたしはいったいどこにいるの?
——人生の雑踏。人はゆきめぐり風のようにあらわれては消えてゆく。わたしはいつもひとりぼっち。そんなわたしを時間は急かし、文字盤の上で前に進めという。ねえ悔いはない?
うん、そうだ。わたしは王子さまのためにここまできたのよ。これはわたしが選んだわたしだけの物語なんだから、おしまいまでやりとげないと。これからも、わたしは菖蒲を演じよう——
新しい気もちで胸いっぱいの菖蒲は、いつもより高く、もうどこへでも飛んでいけそうなほど軽やかな足どりで歩き、到着点の足跡をふみしめ、ついにその先をながめました。
……ぷっつりとぎれ、なにもありません。まったくなにも。
領域の涯ては、すみずみまで威光にあふれ、誰も立ち入らせない白亜のようでもありました。闇の領域で感じた不安や恐怖ではなく、自然とわきおこる畏れが、すこしでも触れたり、進まないよう後ずさりさせます。こちらにむかう足跡があったのは、イアソン氏もおなじように感じたからでした。夜はなく灯りや陽の光ではない、白く清らかな領域への畏敬を。
「やっぱり、中庭に扉なんてなかったのね」菖蒲はきびすを返し、ため息をつきます。
さきほどまでの高揚は気まぐれの羽をつけてあっというまに飛び去り、通路のあった地点までとぼとぼもどると、力なくあおむけに寝っ転がり、赤い宝石の指輪を首かざりからはずしていじります。
菖蒲に力をあたえた指輪は、使用した者の記憶を失くす【忘失の約束】がかけてあります。もし、すべての記憶がからになってしまえば力は使えなくなるので、菖蒲は右手に過去の記憶を、左手には未来の記憶をふりわける、という条件をつけました。過去とは菖蒲の住んでいた領域の記憶で、未来とは王子さまの領域での記憶です。スズメのための中指は学校と友人、ハタラキアリのための人差し指は街、干しの王子さま作戦の小指は家、ミモザのための薬指はお姉さんの記憶でした。では、親指の記憶はなんでしょう。
「それは、わたしよ」
菖蒲は体を起こし、ひざまずいて息をととのえ、指輪とむきあいます。なんども親指に通そうとしますが、右手はいやがるようにふるえ、どうしてもできません。
無垢な記憶とは自己喪失を意味する。
己をうしない、中庭をおかしたとて存在理由もわからないのであればなんの意義があるか。
「おじぃ、あなたの言葉は正しかった。なにも知らないバカな子どもだと笑ってください」
中庭へふみこむために約束の力で現在の菖蒲を犠牲にし、過去の菖蒲を忘失させるのは恐ろしい手段でした。もし菖蒲そのものがなくなれば、王子さまを助ける記憶もなくなり、干しわらとなった王子さまのくちびるを、この領域のものではない少女が扉のない中庭にある井戸の水によってうるおすという【干しわらの約束】を果たせないかもしれません。それに、底なしの穴、空や海、宇宙……これまで旅した未知の領域はどれも菖蒲が選べました。どうしようもない問題をなんとかしたり、失敗をうまくやり直したり、まちがいを正せるのはすべて意志があるからです。もし指輪の力に身をゆだねてしまえば、そうした自由意志を捨てることになります。そしてなによりも、王子さまがわからなくなるくらいなら、イアソン氏のように引き返したほうが正解なのではないかと決意はゆらぎます。なぜなら、わたしの王子さまではなくなるのですから。
しばらくのあいだ、菖蒲は葛藤しました。望めば通路の消失点はすぐにふたたびあらわれ、本質から目を背けた近似値の扉を開き、くりかえし意識の階段をおりて、新たな領野への冒険をいつまでも続けることができるでしょう。しかし目的地は扉のない中庭なのです。
自分を捨て中庭に侵入するか、あくまで菖蒲としてほかの道を探すか。指輪の力はあと一回だけ……
「さよなら、菖蒲」
覚悟を決め、指輪が右手親指の関節をくぐり、根もとにぴたりとくっついた時、赤い宝石は火花をちらし、こうこうと燃えます。
うすれゆく意識の中、菖蒲の目には白妙に一輪、大きなヒガンバナがゆっくりほころぶ様子がうつりました。
「ああ、なんてきれいなのかしら……ミモ……ザ」
……チン……チリン……チン……
ガラスの器を指ではじいたようなかたい音が不規則なリズムで聞こえ、意味を失った少女は風化してボロボロくずれ、ちりとなりました。
扉のない中庭

そこは扉のない中庭でした。
まるで高くつみあげたつみ木の上にたつように、微細な空気の振動ですら崩壊へかたむこうとする緊張感と、神秘的な荘厳さが静謐をまとい、中庭全体に厳粛な雰囲気をただよわせていました。
オリバナムとミルラの薫る中庭では、あらゆる形は均等にわけあい、幅十メートル、奥行き二十メートルほどの長方形の地面に大きさのまったくそろった青草が一面にしかれていました。中庭の広さと相似である無機質な窓は、磁器のようになめらかな乳白の壁に等間隔で四方にならび、上方へずっと続き、天からやわらかな光の粒子が中庭中央に鎮座する渦巻く空気のような白い井戸にふりそそいでいます。そのまわりをかこむように、まったくおなじかたちをしたリンゴの木が六本、整然とのびていました。
長い黒髪の少女は生まれたばかりの赤子のような姿でぼんやりとあおむけに倒れていました。光の粒が目にとけこみ、まぶしくなって右手をひたいにあてると腕に金の輪が、親指にはゆらゆら燃える赤い宝石の指輪がはめてありました。やがて右腕は重たくなり、ゆっくり上体をおこし、見回します。
少女はどうしてここにいるのか知らず、関心もありません。自分がだれであるか、まったくわからないからです——わたしとはいったいなにか。なにをもってわたしといえるのかも。
とにかく、右手にからまる輪っかをとってしまいたくなりました。しめつけられ、縛られているように感じたからです。異物をはずそうと左手をかけた時、肩になにかそえられ、ふんわりとしたここちよさで全身は満たされます。顔を横にむけると、なめらかな白い手がありました。
少女は体をひねり、手から腕、肩に視線をうつし、ドレープのきいた薄絹のドレスをまとい、つばの大きな白いぼうしを深くかぶる女の園丁の顔をのぞきました。
園丁の女は、口もとがゆるみ、声をあげ笑おうとする少女のぷっくりとやわらかなくちびるに指をそっとあてて右手の親指をふれ、黒い瞳をのぞきこみ、首を横にふります。あたかも「それをしてはいけない」と、止めているかのように。それからすこしも音をたてず、空気のようにリンゴの木にちかより、幹をやさしくさすり、となりの木も、そのまたとなりの木も、といったぐあいに、六本の木を一本ずつ、ていねいにおなじところをおなじ回数、公平になだめました。
どれくらいそうしていたのかわかりません。指輪に興味をなくした少女は笑みをうかべ、一本ずつりんごの木をなでる園丁をいつまでも目でおいかけました。まるで、ベッドメリーをながめる赤子のように。
ふと、少女は左手で右手首の腕輪にふれます。首をかしげ、ふしぎそうに手首をまげて、きらりと光る腕輪を見つめると、腕輪は少女の顔をうつし、こちらの目とむこうの目があいました。
あなたは?
わたしとは?
わたしは?
あなたとは?
とつぜん、喜びでくすぐられ、怒りで熱くなり、哀しみでふるえ、楽しくてうきうきし、虚しくてしずみ、恐れおののき、安心したり、恥じたり……さまざまな感情がいっせいにおそいかかり、困惑して手をあちこちとさまよわせます。
わからない、こたえられないの
わめけば! さけびさえすれば!
園丁のぬくもりで少女のくちびるはぴたりとくっつき、どうにも開きません。少女は鼻息を荒くし、たまらずおなかをおさえ、みけんにしわをよせてむせびます。目からしずくがひとつこぼれると、滝のようにどっと流れだし、手でぬぐいますが、どうしようもなくなり、腕輪をひたいに強くあて、むきだしの感情たちから逃れるようにまぶたを閉じました。
まっ暗。ここなら責めてこない
感情たちはすぐ追ってきて、うずくまる少女をかこみ、頭にたくさんの重たい石をぶつけます。
やめて! やめて!
わからない! たすけて!
遠くから感じる、笛のように澄んだ女の思念——それは怯えた少女を慰撫するように……
あなたの想う人のために水を
あなたの慕う人のために水を
あなたの愁う人のために水を
あなたの恋う人のために水を
恐る恐る目を開けた少女は腕輪を通し、ほころぶ黄色の花を見ます。それから顔をあげ、なんの意図もなく立ちあがり、ひたひたに水の張られた白い井戸へ、歩きだします。
こんどは疑問が衝動に理由を求め、井戸に行かせまいと少女の全身を抑圧します。
なぜ? なぜ? なぜ? なぜ?
わからない、こたえられないの
園丁はよろめき歩く赤子を見守る母親のように少女をながめます。
一歩また一歩。少女が中庭の青草をふみしめるとしなびて枯れ、汚された地面は少女を呪い、足にするどいナイフで切りさくような激痛をあたえます。ひと足歩くたび、針で突き刺される痛みを我慢し、倒れては起きあがり、ゆっくり井戸へとむかいます。
なぜ? なぜ? なぜ? あなたの……
わからない、こたえられないの。あなたとはわたし?
少女は痛みを声にもらさないよう、くちびるを強くかみ、両手を口におしつけ、ひたすら井戸へ。
なぜ? あなたの…… なぜ? あなたの……
そう、あなたはわたし、わたしの! わたしの!
愛する者へ、祈るように口を数回おどらせた少女は、井戸の前でくずおれ、身悶えます。
おまえは——天から低い声
けれど——こたえる少女
おまえは無知に溺れ
けれどあの声を知っている
おまえは嘘に惑い
けれどあの声を知っている
おまえは偽に誘われ
けれどあの声を知っている
おまえは信じ悩む
けれどあの声を知っている
奔放な女よ
だからりんごの木はなくなった
おまえの罪ゆえに
だから潤す水をわきあがらせたかった
おまえの過ちゆえに
だからゆたかに実をむすぶようにと
おまえに呵責をあたえよう
だから願う さあ強くわきあがれ!
少女は井戸のふちにふるえる左手をからませ、息を止め、右手で金の小ビンを水で満たしました。
中庭全体は強い光に照らされ、まいあがる雪のように崩壊しはじめます。壁も、青草も、りんごの木も、井戸も、少女も、なにもかも取りさろうとしました。
息を吐きつくして肩をおとし、力なく目を閉じた時、慈愛が、少女のつめたい体を包みます。
「なぜ泣いているの?」と、少女は問いかけます。
「あまりに無力だったから」と、園丁はこたえます。
「あなたはたすけてくれたのよ」
「なにもしてあげられなかった。すべて、すべて失ったのに。たくさん、たくさん苦しんだのに」
「泡になって溶けてもいいとさえ思った。でもあなたが肩に手をのせたから、口に指をあてたから、手をふれてくれたから、見守ってくれたから、こうして抱きかかえてくれたから、だから、わたしはここに在る」
「ごめんなさい、アヤメ」
「ありがとう、リリィ」
たりないもの

ベッドに横たわる菖蒲は、いく日も熱と悪夢にうなされていました。リリィはそばによりそい、にじむあせをタオルでぬぐい、かわいた口に水をふくませました。
ある日、菖蒲はとつぜん目をさまし、息をあげて言いました。
「はじ……めまして、わたしアヤメ。おう……じさまをもどすために……きたの」
リリィは菖蒲のほてるほっぺをなでます。
「わたしはリリーフロラよ。リリィって呼んでね」
「リリィ、わたしね、わたし……知りたいことあるし、おしえたいことたくさんあるの。だから、聞いてくれる?」
「もちろん。でもいまはダメ。アヤメはたくさん傷ついたから、ゆっくり休まないと」
「……ねえリリィ。わたし、うまくやれたかしら? 王子さま、もどるかな。王子さま、よくなるかな……」
菖蒲は意識もうろうと眠りにおちます。
「あなたはなぜ、あたえつづけるの?」
こたえを探すようにリリィは、ひたすら王子さまを想う少女を懸命に看病し、優しく世話します。しかし、穴のあいた桶に水をそそぐように、どれほどの愛情も菖蒲は受けとめず、満たされませんでした。それでもこの方法しかなかったのです。なぜなら、治す薬はどこにもないのですから。
「わたしはどうなってもいい。どうか、どうか、アヤメだけは救ってください!」
リリィは、目の前で消えそうな灯火をながめるしかできず、もどかしさ、焦り、苦しみ、そしてなによりたいせつな子をうしなう恐怖でいっぱいになり、たまらず懇願します。できるなら、すぐにでも変わってあげたいとせつに願ったのです。
菖蒲のたりないものはだれもがもっていますが、ひとつしかなく、かけがえのないものです。それを大きな力で引き裂き、むりやり足をふみ入れたので、菖蒲の内にあるわたしは壊れてしまいました。
リリィが扉のない中庭から連れだしたとはいえ、いまや菖蒲の生気は右手の親指で燃える指輪の力でかろうじてたもたれているだけでした。人の内奥にある中庭は、それほど繊細な場所ゆえにだれも開けたり閉めたりする扉がないのです。
「もうなんでもかまわない」と、悲嘆にくれたリリィはわらにもすがる思いで言います。「いっそわたしを憎んでくれてもいい。わたしを恨めば、よくなるかもしれない」
「ミモザがね」と、菖蒲はリリィの手を弱々しくつかみ、不安そうにこたえました。「ミモザが、怒ったわたしはわたしじゃないって。笑顔でいてほしいって。それにね……わたしね、約束したの。もう自分にうそはつかないと。だから井戸は水をくむのをゆるしてくれた。お願いよ、リリィ……わたしのためにわたしをきらいにならないで」
「好きよ、アヤメが大好き」リリィは声をふるわせます。「中庭からアヤメを見ていたもの。すてきな女の子がくるって。どんなおどろくこともなしとげる強い女の子がくるんだって待っていたもの。だから、はやくよくなって王子のもとに帰りましょう。ね、アヤメ?」
「うん」菖蒲はうれしそうにうなずき、目をつむり、「ああ、はやくおうじさまが……もどると……いい……な……はやくおうじさま……よくなると」
ふーっとおだやかに息をついた菖蒲は、呼吸をやめました。
リリィは強く叫びます——もし、わたしのこぼすしずくでアヤメを返してくれるなら、もし、わたしの流す雨がアヤメをいやすのなら、いつまでもやまぬ五月雨になろうと。
「リリィ!」
背後から名を呼ばれたリリィはふりむくと、目の前に菖蒲とおなじくらいの少女が息を切らして立っていました。
「あなたは……」
リリィのかすれた声に、少女はこくりとうなずきます。
「あたしは妹のミモザです。アヤメの痛みが闇でさまようあたしに聞こえ、走ってきました」
ミモザはすぐベッドへ、菖蒲の右手に銀の腕輪を通し、左手をからめました。
「ねえ、アヤメ」と、耳もとでミモザはささやきます。「いまから、あの約束を果たすね。こんどはあなたにたりないものをあたしがあげるばん。許してくれるよね? いつか、アヤメが天高くのびるクスノキみたいに元気になったら、あたし、その木にやどる黄色い小鳥になる。ふたりの新しい約束よ」
やさしくキスをしたミモザは、おでこを菖蒲のおでこにつけました。
「ミモザをくれてありがとう。とってもうれしかった。だからね、ミモザだけはあたしのものよ、アヤメお姉ちゃん」
ミモザは満足そうに両手をしっかりと強くにぎりしめ、たりないものを返し、自分のすべてをなにもかもあたえ、花びらのように散っていきました。
親指にある赤い宝石の指輪は砕け、菖蒲の左目からキラキラとかがやく涙が一粒こぼれ落ちます。
それから、息をふきかえした菖蒲は、もうすっかりよくなりました。
むかしむかし
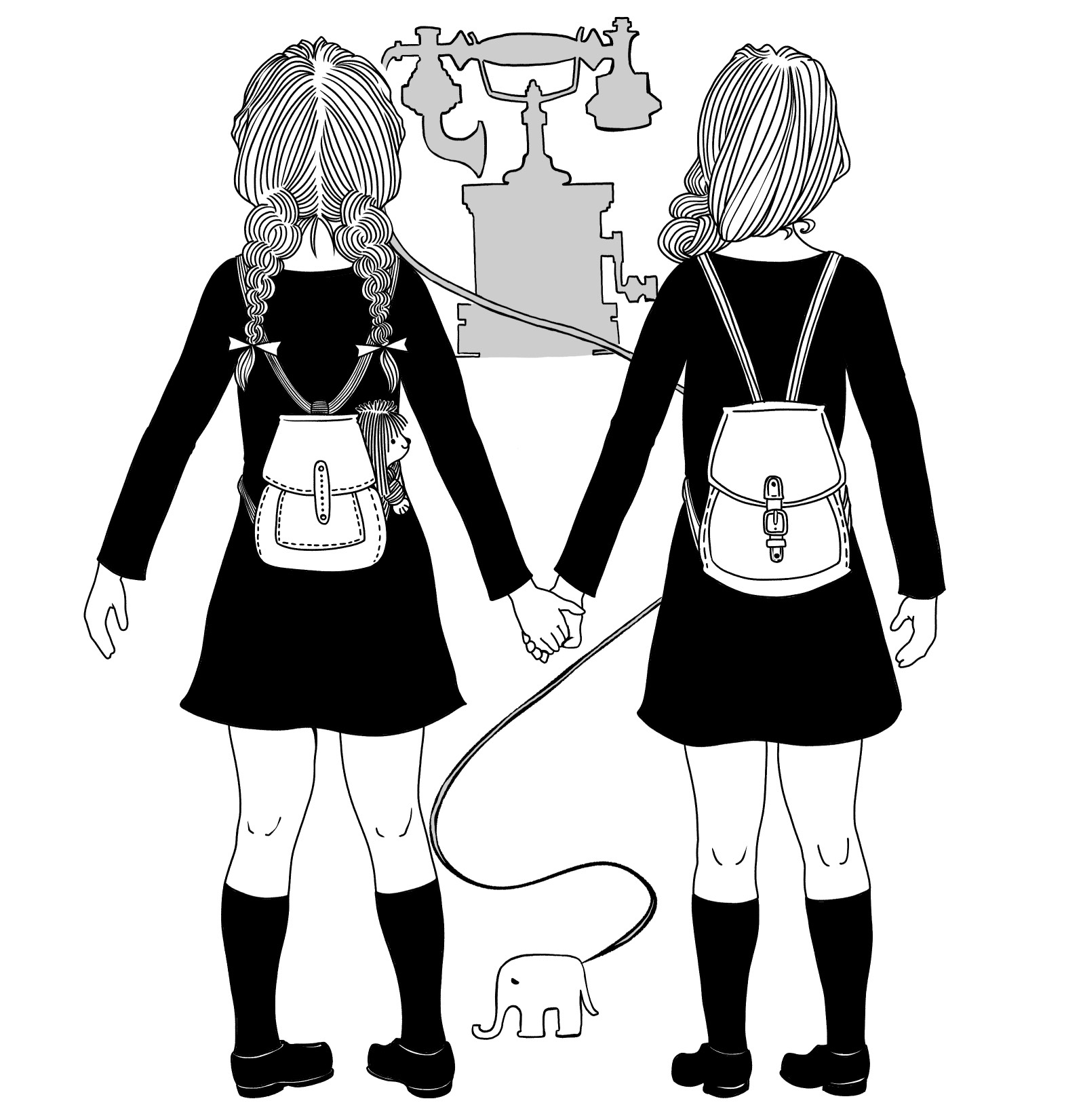
「おとぎ話のお姫さまは、ほんとうに王子さまといつまでも幸せに暮らしたのかしら?」
ベッドで身を起こし、アイボリー色のミルクガラスのマグカップを手にした菖蒲は質問しました。
「そうね」と、リリィは刺しゅうをしながら答えます。
「いつまでも幸せであるのと、いつでも幸せであるのは少しちがうかもしれないわ」
「おもしろい考えよ。つづけて」
「物語の余白ではケンカもあったんじゃないかしら。たとえば食事の時、サラダとスープのどちらから手をつけるか、タマゴが先かニワトリが先かみたいな話しね。わたしはグレエンと洗たくものでいいあいになるし」
菖蒲はマグを口につけてから言います。
「そんなことで?」
「夫婦のいざこざの因果なんてつまらないものよ、アヤメ。服と下着はわけて洗ってほしいとか。ああ見えてグレエンはめんどくさい人なんだから。だいじなパンツは自分で洗いなさいっていうと、彼はしかたなしに洗うけど」
「わたしと住んでた時は、そんなわがままいわなかったわ」
「グレエンはアヤメの王子さまではないもの。かっこつけてるだけよ」
「そっか。じゃあ、どうしてリリィはグレエンと結婚したの?」
刺しゅう糸を引き、だまって考えるリリィ。
「おとぎ話のお姫さまだったのか、夢みる少女だったか」
「ちょっと、なにそれ」菖蒲は目をほそめます。「わたしが子どもだからってごまかしてるでしょ?」
「だって」と、リリィはほほ笑みます。「アヤメにもおとぎ話のような恋をしてほしいから」
「ねえ、そんなのずるい。リリィのいじわる!」
それから、リリィは菖蒲に山あいの国のお話しを聞かせました。グレエンや干しわらの王子さまがどんな男の子だったか、それに、キジ三毛のモルトの話も。
「モルトはね、いろんな国をさすらい、山あいの国にきたのよ」と、リリィは言います。
「旅ネコの話はうそじゃなかったのね」と、菖蒲は思いだすように言います。
「いえいえ、それどころかネコ座の由緒ある王族ネコだったのよ」
「なるほど。だから興廃の丘でモルトは従者役をいやがったんだ」
「彼、プライド高いから、きっと騎士役もことわるでしょうね」
「わたしのベッドで毎晩寝ていた彼が?」
「ベッドで寝そべるネコにプライドなんかないわよ、アヤメ」
ふたりは声をあげて笑います。
菖蒲とリリィの会話は、こぼれ落ちた菖蒲のかけらをひろう散策のようでした。深い孤独の森から陽のさす原っぱにぬけ、大きなニレの木陰で休み、さわやかな風とこすれる葉のおしゃべりに耳をかたむけます。ごろんと寝っころがり草まみれのままリリィに抱きつき、手をつないで走ったと思うと、ぴたり止まって腕を引き、きゃっきゃとはしゃぎます。菖蒲はアヤメだけではなく、リリィをまじえて道すじのない会話を楽しみ、時間をかけてわたしを取りもどそうとしました。
そんな自分探しも順調に進んでいたある日のこと。リリィはベッドにいる菖蒲のそばに腰かけます。
「おやすみをいいにきたの?」と、菖蒲はたずねます。
「アヤメがよくなってくれて、とてもうれしい」リリィは菖蒲の頭をなでます。「だから、わたしたちのおとぎ話を聞いてほしいなって」
「リリィたちの?」
「ええ、そうよ。でもアヤメが知りたいなら、だけど」
菖蒲はリリィを探るようにじっと見つめ、「もちろん」と、うなずきます。
「まずはそうね」リリィは菖蒲を胸に抱きよせ、ゆっくり話しはじめます。「おどろくかもしれないけど、わたしたちはアヤメとおなじ領域にいたの……」
むかし、西の島国に、親のいないふたごの姉妹が施設でくらしていました。
ある晩のこと、姉妹は知らない領域へ招待されました。姉妹を招いたのは、干しわらの王子さまのお父さん、つまり山あいの国の王さまと、農夫のグレエンです。
「ふたりは兄弟なの」と、リリィは言います。「王が兄でグレエンが弟。ふたごの姉妹は姉が王妃で、わたしが妹よ」
「グレエンは王につかえる風車の監視役って自己紹介したわ」と、菖蒲は言います。
「それは【口止めの約束】のため、すべてを伝えられなかったんだと思う」
「そっか。モルトやアルビレオも山あいの国の話しをしなかったわ」
「アヤメは興廃の丘の歴史を聞いたかしら?」
「うん。高い城壁にかこまれた領域を統べる王国が滅びたのよね」
「ちょうど東の風車に本城があって、山あいの国の人々はそこから移住した王家や貴族の末裔なの」
それらの人々は領域をまきこむ大戦前夜、争いを避けるように祖国をあとにしました。しかし燃える影が見過ごすはずがありません。
「臆病な反逆者どもめ」と、城門に立ちはだかる燃える影は彼らをおどしつけます。「おまえらがコソコソと逃げるのを黙認するとでも思ったか!」
「逃げるのではない」と、王の一族は答えます。「民を守るため、避難させるのだ」
「くだらぬいいわけを」燃える影はニヤリと笑みをうかべます。「よしわかった。逃げないというのであれば、門を通る前にひとつ、条件がある」
王の一族は燃える影と契約を結ばされました。それは、王家の長子をひとり捧げる、というもので、安寧の契約と呼ばれました。
深い山あいにうつり、しばらくしてさいしょの王子さまを送りだそうとした時、領域を統べる王は側近の手にかかり、国は滅び、戦争は領域に荒廃をもたらして終わりました。
山あいの国は災厄をまぬがれましたが、おとぎ話のような幸せな結末にはなりませんでした。なぜなら、不滅である影は安寧の契約の履行をもとめ、やってきたからです。
「王国の再興か、裏切り者への復讐なのかわからない」と、リリィは言います。「いずれにせよ、安寧の契約は山あいの民を苦しめた」
「ひどい!」菖蒲は怒って言います。「山あいの国がわるいんじゃないのに!」
「そうね」と、リリィは菖蒲の背をなでます。「でも、影は人の弱さをよく知っていた」
懐疑、絶望、憎悪……燃える影は飢えたオオカミのように人間の欲望をむさぼり、領域を統べる王の意志を完璧に投影しました。
いく世代も過ぎ、戦争の記憶もうすらいだころ、山あいの民は王に進言しました。
「王よ。わたしたちのために、あなたの子を犠牲にしてきました。朝に焼きたてのパンを食べても、夜に音楽をかなで、ベッドに横になる時も、知らない地をひとりさまようあなたの子を思い、わたしたちの胸は痛みます。王よ、どうか思いだしてください。父祖たちがこの山あいの地にやってきたのは、みなが公平な自由を楽しむ黄金時代への懐古ではありませんでしたか」
山あいの民は、ゆがんだ連鎖を断ちたいと思いました。
「自由だと? 愚民どもめ。束縛こそおまえらにふさわしいのだ」と、燃える影は口をはさみます。
「法と則の檻をもとめたのはおまえら人間だろう。争い絶えぬ嘘ばかりの社会に平和と秩序をもたらすため、子一人など些細な犠牲だとは思わんのか」
王は民にこうたずねます。
「自由と束縛、わたしたちはどちらを望むだろうか」
「いうまでもなく自由です」と、民は力強く答えます。「わたしたちは自由と責任を担い、美しいこの山あいの地をみなでわけあえるよう子たちに語り伝える親でもあります」
「兄弟たち! 今日、この場に立てることを誇りに思う。ついに庇護の約束をする時がきた!」
つぎの朝、山あいの国王は犠牲となるはずの子に真実をおしえました。安寧の契約を破棄した夜、燃える影は激怒し、大蛇となって山あいの国王をふくめ、オトナをみんなのみつくしました。
「おぼえておけ! これがお前らの親が望んだ自由への報いだ!」
燃える影は山あいの国の子どもたちをおどしつけ、空へ消えていきました。
【庇護の約束】は、山あいの親の犠牲により、子が燃える影から守られる力です。ただし国外にでると効力は失われてしまいます。親からすべてを聞き、学んでいた子どもたちは、ひそかにねられた影を打ちやぶる計画を実行しました。まずは、ずるがしこく強力な燃える影と戦うため、ほかの領域の仲間を集めなければなりません。それで、ふたりの王子さまは少女を招待しました。
いっぽう、深夜の孤児院で、おとぎ話が大好きなふたごの姉妹は、みんな寝静まったのを横目に、ボロボロの人形とビスケットを数枚、お気にいりのカバンにつめ、こっそりぬけだそうと玄関にむかいました。
きしむゆか板をそろりと歩いていると突然、リリリリン! 使われていないはずの古い電話機のベルがけたたましく鳴りだします。姉妹はあわてふためき、踊る受話器を持ちあげました。
「どうかそのままで! あなたたち、ふたごの姉妹の助けがどうしてもひつようなのです!」
受話器から聞こえる男の子の声に、姉妹は思わず顔を見あわせます。なぜこちらがふたごの姉妹だと知っているのでしょうか。
「そうやってリリィとお姉さんはこの領域にきたのね」と、菖蒲は言います。
「ふたりの王子さまはわたしたちを大っ嫌いな場所からつれだしてくれた。あとこれは秘密だけど」
リリィは菖蒲の耳もとで言います。「あちらとおとぎ話をつなぐ交換手はシロゾウなのよ」
「ほんとうに? 会ってみたい!」
「わたしたちはもうワクワクしたし、なによりうれしかった。姉さんとどうやって遠く広い世界へ旅するか、たくらんでいたの。あの日だってわたしたちはすこしも疑わなかった」
ふたごの姉妹は山あいの国の子たちにむかえられ、夢のような生活がはじまりました。
「山あいの子たちとすぐに仲よしになったわ。わたしたちは年上だったから食事をつくってあげたり、お掃除に針仕事にとってもいそがしいまいにちだった」
菖蒲はリリィがもっと大きく見えて、あこがれるように言います。
「リリーフロラ。あなたはウェンディ・モイラ・アンジェラ・ダーリングね。わたし、あなたみたいに強い人になりたい」
「うれしいわ、アヤメ」と、リリィは微笑をうかべます。「わたしたち、いい友だちになれそうね」
約束の力
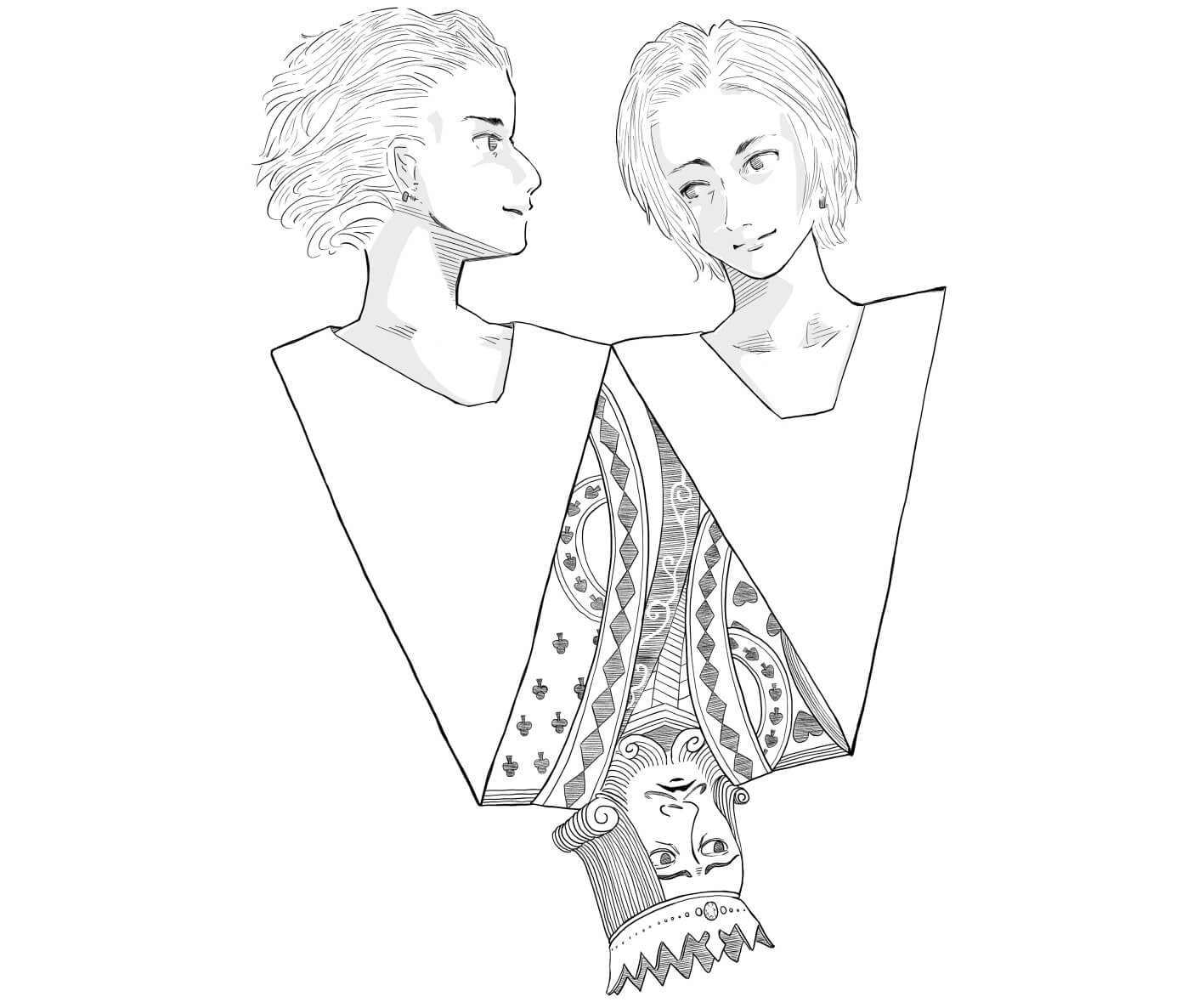
燃える影は、山あいの国の子たちに安寧の契約がまだ有効であるとだましました。オトナたちがかってに破棄したにすぎない、というのです。それで子どもたちは、ほころんだ契約を利用しました。
「燃える影は子どもたちの計画に気づかなかったのかしら」と、菖蒲はたずねます。
「山あいの子たちは【口止めの約束】より重い、【沈黙の約束】で燃える影に知られないようにしたのよ」と、リリィは説明しました。
「みんな燃える影を打ちやぶるまで真実を他言しない約束をした。親をなくした悲しみをふくめ、だれにも知られないよう記憶にとどめた。おかしな話しだけれど、わたしたちがこの領域にやってきた時、彼らがなにを助けてほしいのか、いくら聞いても口をつぐむのよ。でもね、わたしと姉さんはアヤメも持っているステキな力を使ったの」
「約束の力ではなく?」と、菖蒲は聞きます。
「どんな境遇も人に力をあたえる」リリィは目を閉じ、耳を澄まします。「彼らの言葉にならない声を聴いたのよ。わたしたちは彼らと生活してうちとけ、なにを思い、どんなことを望んでいるのか、わかるようになった。きっとアヤメは自然に使っているから気づいていないけれど、とても美しい能力ね。もちろん、どんな力でも正しく使わなければいけないわ」
「わたし、ちゃんとできているかしら」菖蒲は不安そうにリリィを見ます。
「もちろん」と、リリィは目をほそめます。「できているからこそ、わたしたちは会えたのよ」
菖蒲は恥ずかしそうにリリィの胸もとに顔をうずめました。
「大きくなって結婚した時、わたしたちは山あいの国のひとりとして夫から計画のすべてを聞いた。約束の力についても」
「リリィは利用されたって思わなかった?」
「ぜんぜん」リリィは首を横にふります。「むしろうれしかった。これからもっとわくわくするような冒険がはじまろうとしている、たいへんだろうけどわすれられない物語になるんだって。アヤメも見知らぬ異国の風を感じたでしょう?」
菖蒲は干しわらになった王子さまを抱えて納屋を飛びだしたあの日を思いだし、大きくうなずきます。
「それに愛はべつ。強要されたわけではないわ。いっしょに時をすごし、せせらぐ小川のような恋から始まり、とうとうと流れる川となって、どこにつながっているんだろう、グレエンをもっと知りたいと思ったから結婚したのよ。もちろん、姉さんも」
「すてきなお話しね」
「ありがとう」と、リリィは菖蒲の頭をなでます。
「燃える影を打ち倒すチャンスは一度だけ。【安寧の契約】で国を旅立つ王子さまが燃える影と相対する瞬間しかない。姉さんはみごもってすぐ、兄と記憶の星へ旅立ち、【手つなぎの約束】で自分たちの記憶を手にいれ、影を切り裂くための青い剣と、それをさらに強める赤い宝石の指輪を加工した」
「記憶の結晶は役割を果たすまでけっして壊れないからよね」と、菖蒲は言います。
「そう。それに実体のない影にはうってつけの道具だったのよ。ふたりが記憶の星から帰ってから、わたしたち姉妹はあちらの領域へ二度と帰らない【不帰の約束】を剣と指輪にくわえた。王子も誕生し、あとは旅立ちを待つだけ」
「でもリリィ。なにも知らない王子さまはどうやって剣と指輪で燃える影を打ちやぶろうと考えたのかしら?」
「ええ、それがいちばんむずかしい問題ね。ほんとうは【口止めの約束】で王子に伝えようとしたの。ただし【沈黙の約束】をおかす危険もあった。それに、約束の力も弱まってしまう」
「どういうこと?」
「アヤメは約束の力について知っているかしら?」
「うん。馬小屋会議でアルビレオがおしえてくれた。重い約束ほど力は強く、守らなければ大きな代償をもとめられる」
なぜ約束に力があるのでしょうか。それは約束を守る人がいなくなり、なにがほんとうか、わからなくなったからです。軽易な口約で領域から真実がなくならないよう力をもつようになりました。
「約束そのものではなく、約束を果たそうとする意志に力が宿るのだと思う。グレエンがいうには、むかし、嘘で領域を破滅させ、約束の価値をさげた代償に信頼を失ったからと。だから、この領域でない人の約束はより大きな力になるみたい」と、リリィは言います。
「それでわたしたちに助けをもとめたわけね」と、菖蒲は言います。
「約束は信じれば強化されるし、疑うと弱くなる。わたしたちは王子が真実を理解し、みずから行動するのを信じようと決めた。もっとも、王子は旅立つ前から多くを知っていたみたいだけど」
——ヘレムのことね——ハッとする菖蒲に、リリィは黙ってうなずきます。
燃える影はどこに身をひそめているのか。これも問題のひとつでした。転機となったのは【安寧の契約】を破棄した日の夜です。山あいの国でオトナを襲い、空へと消えた影のあとをモルトが命がけでつけていきました。なんと勇敢なキジ三毛ネコでしょう!
灯台もと暗し、燃える影は根城を変えていませんでした。王子が国を立つすこし前、リリィとグレエンはモルトの案内で東の風車へむかいます。小麦畑の農夫として監視をはじめてからしばらくたち、ついに王子さまがアルビレオと風車にやってきました。
王子さまは、燃える影を確実に打ち破るため【干しわらの約束】を、扉のない中庭から菖蒲が水をくめるように【忘失の約束】をくわえ、アルビレオにたくします。干しわらになった王子さまを残して燃える影は大蛇の姿となり、興廃の丘にいたグレエンとリリィを襲います。
「わたしは山あいの国をでる前、影を恐れない【覚悟の約束】をしていた」と、リリィは言います。
「影の化身である大蛇に立ちむかい、約束の力で生きのびた。それから【干しわらの約束】について知り、扉のない中庭を見守る園丁として待つのを許されたわ。でも……」
まるで深い穴の底へとしずむようにうなだれるリリィ。重たい沈黙が部屋を支配します。
「あなたはわたしを助けてくれたのよリリィ、助けてくれたの」菖蒲は言葉にならない声に答えます。
リリィはそのまま静かに首を横にふります。
「なぜ、とてもだいじな約束をわたしに隠すの?」と、菖蒲は問いかけます。「小麦畑の家にあったすてきなカーテンも、モクレンのかおるベッドも、わたしにぴったりなワンピースも、ちょっと大きめのぼうしも、ドライフラワーやハーブのお風呂も、かわいい食器もすてきな庭も、みんな、なにもかも、わたしのために用意していたのよね?」
「それは……」と、リリィは自分のおなかにふれ、「わたしには子をやどす力がないから、せめてだれかの……」
打ち沈むリリィの長い金色の髪が幕のようにふたりを遠くにへだてます。すると、いっしょに歩いた草原にもつめたい風と暗雲がたれこめ、地面にはぽっかりと空虚な穴が広がり、アヤメをのみこみます。
「ちがう」菖蒲はもがくようにきっぱりと否定します。「リリィが園丁として扉のない中庭に入れたのは、ひとつの約束をしていたからよ。わたしが妹のミモザを望んだように、あなたは子であるアヤメを望み、わたしたちのかすかな希望は交差した」
「わたしに命を抱えるわずかな力でもあれば、あの時、ミモザのようにすべてをあたえられたのに!」
「どんな境遇も力をあたえるのでしょ? リリィ、あなたには迎え抱く力がある」
「わたしにはなんにもないのよ……からっぽでなにもない女なの。ごめんなさい、アヤメ」
「なくなんかない! だって、窓ごしに見つめあったあの時からわたし、どうしても会いたかった。だれも入れないわたしの中庭にいたのはあなただけだった。なによりいま、わたしはこんなにみたされてるの。知らないところまでもたくさん。リリィがいるからこんなにおだやかでいられる」
「わたしは薄情よ! 強がってるくせに中庭で苦しむアヤメひとり守れず、壊れてゆくのをそばで見るしかできない役立たずなの!」
「リリーフロラ、お願いだからアヤメのためといって! お願いだからわたしを恐れないで。お願いだからわたしを独りにしないで。お願いだから、どうか、あなたの約束をわたしと果たしてほしい。わたしはずっとずうっとリリィ、あなたの想いに気づいてたから。宇宙でいちばん温かな力がわたしたちを引きよせた奇跡も知っていたから。だから、わたしたち母娘の約束を信じて」
それからアヤメはリリィの両手を強くにぎりしめ、「もうわたしをはなさないで、お母さん」。
感情あふれた母は、たまらず力いっぱい子を、そのすべてを守るように覆います。
「そうよ、あなたのため、ぜんぶあなたのためよ。わたしの愛する娘、アヤメのために!」
なぞかけ歌

「リリィのすてきなところは」
ダイニングテーブルでほおづえをついた菖蒲は、サラサラと下に落ちる砂時計をながめながら、お母さんのすてきなところをかぞえていました。
「あれこれせかさない、むりに押しつけない、おかしいって顔をしかめないところでしょ、それに……」テーブルと台所を行ったり来たりするリリィをちらりと見て、「メアリー・ポピンズみたいに現れては消え、いつもいそがしそうね」と、菖蒲は足をバタバタさせてリリィに言います。
「あら、そうかしら」リリィはわざとらしく鼻を鳴らして答えました。
「わたしの見るかぎり、きょうだけでも三十人のリリィがうごきまわっていたわ」
「それは」と、キャロットケーキを手にしたリリィが言います。「この家に住むこびとね」
「七人じゃなく? ちょっと多すぎじゃない?」
「あら、うちのお姫さまにはたりないくらいよ」
リリィはキャロットケーキを切りわけた皿を菖蒲にわたします。
「ああ、なんて世話のやけるお姫さまなの!」
お姫さまはそう言って深いため息をつき、ティーコゼーを取り、ティーポットをかたむけて紅茶をふたつのカップにそそぎます。
「女王さま、どうぞ。わたくしめがいれました紅茶でございます」
菖蒲はむかいにすわるリリィにうやうやしくティーカップを差しだしました。
「苦しゅうない。ところで白雪姫よ、紅茶はだれに習ったのじゃ?」と、大きな顔をするリリィ。
「ウサギでござい……」
「まさか!」と、リリィは目を大きくして言います。「帽子屋と庭でおかしな茶会をしているあのウサギか」
「はい、三月のでございます。わたくしがふりかえりますとウサギと帽子屋は、眠るネズミをティーポットにつっこんでおりました。これが世にもめずらしき、くるったお茶でございます」
「ぶれいな!」リリィは立ちあがって手をふり、「この子の首をおはね!」
「ねえ、リリィがハートの女王になっちゃった」と、菖蒲はくすくす笑います。「もうめちゃくちゃ」
「たしかに。このお芝居は失敗ね」と、リリィはキャロットケーキを口にしました。「でも、ケーキはうまくできたからよしとしましょ」
「お母さん、山あいの国のお話しでどうしても気になることがあるのだけど、聞いてもいい?」
「なんでもどうぞ」
「干しわらの王子さまにだした王さまのなぞなぞ、『芯のないりんご、扉のない家、鍵のいらない宮殿』とはなんだったのかしら」
「たぶん、なぞかけ歌じゃないかしら」
そう言って、リリィは歌を歌いました。
愛する彼にリンゴを
愛する彼に芯のないリンゴをささげよう
愛する彼に扉のない家をささげよう
愛する彼のすごす宮殿をささげよう
彼が開くのにカギはいらない
わたしの想いは芯のないリンゴ
わたしの気もちは扉のない家
わたしの心は彼のすごす宮殿
彼が開くのにカギはいらない
「リリィは歌がうまいのね」
菖蒲はリリィの歌声をすてきなところのひとつに加えました。
「一番になぞなぞ、二番に答えがあるのよ」と、リリィは説明します。「この歌でわたしたちはよく遊びをしていたわ」
「どんな遊び?」
「兄さんとグレエンに姉と妹を当てさせるの。わたしたちふたごで顔と声がそっくり似ているから一番と二番をそれぞれ歌い、どちらが姉で、どちらが妹でしょうって。彼らをまどわすいたずらを楽しんでいた」
「ルイーゼとロッテみたいね」
「みんなおとなになって、秋の収穫もすぎ、冬じたくをはじめようとしたある日の朝、湖のほとりにあるガゼボで、兄さんとグレエンはそれぞれわたしたちにこう言ったの。
もし、あなたたち姉妹を|見わけることができたなら、どうかあなたのリンゴをください。
それからまいにち、わたしたちはいれかわるように生活した。髪や服やクセもごちゃまぜにして、わたしたちですらどちらかわからなくなるほどね。冬がおわり春になろうとするころだったかしら、ガゼボに集まり、この歌を歌ってから、あなたのほしいリンゴはどちらって」
「それから、それからどうだったの? ねえリリィ」菖蒲は目をかがやかせ、身をのりだして興奮気味に聞きます。
「結末はアヤメも知っているでしょ。ふたりの王子さまに子どもだましの遊びはまったく通用しなかった。知っていたのにわざとだまされたふりをしてたんだもの。約束の力を使ったのか聞いたら、そんなことしなくてもわかるって。まちがえたら姉さんとふたりで大笑いしようと思っていたのに。まじめな男の子はつまんないわよ、ねぇ」
「……」
「お人形さんみたいにかたまって。どうしちゃったの、アヤメ?」
リリィはふくらむ菖蒲のほっぺをきゅっとつまみます。
「いや! そんなおしまいはいやよ。ちゃんと聞きたいの!」
「お姫さまはしあわせにくらしましたとさ、よ」
「そうじゃなくて」と、菖蒲は言います。「アーデンの森でオーランドがロザリンドに告白したみたいに、あの言葉を交わしたんでしょ」
「エイリーナの紅茶はほんっと最高だよ」低い声のリリィ。
「ごまかさないで、ギャニミード」熱心に見つめる菖蒲。
おいつめられたリリィはなにかを思いうかべ、顔をあからめます。
「……いままで聞いたことないくらい、とてもあまくてとろけるような愛の約束を耳もとでささやかれたわ。あとは秘密! ぜったいおしえない、もうおしまい」
「リリィのけち」
「へえ、母にけちなんて言うんだ」と、リリィは目をほそめ、「アヤメも王子さまにささやかれるのよ。そうしたらわたしも聞くけど、それでもいいの?」
思わぬ仕返しをうけた菖蒲の城は火矢でみごと撃たれ、心臓|《》がとびでそうなくらい、どっくんどっくんなります。考えれば考えるほど燃えあがる炎を消火しようと、水をゴクゴク飲みます。ふたりは目をあわせ、大笑いして楽しいティータイムはおひらきになりました。
山あいの国の歴史、いろんな人の考えや願い、複雑にからむ約束、そしてなぞかけ歌の秘密を知った菖蒲は、霧が晴れて遠く稜線がくっきりとうかぶように、これからやらなければならないことを指ししめしたのです。
「さあリリィ」と、菖蒲はおちついた、でも力のこもった声で言います。「はじめましょう」
リリィはうなずき、くすんだ金色の鍵をつくえの上に置きます。
「このカギは家の裏口をあけるための鍵よ。扉の錠前は内側についていて、むこう側はどこへでも行ける階段がある。ただし、使えるのはわたしとアヤメの一回ずつ。なぜなら鍵穴にさしてまわしたら、外側から閉じて錠をおろすまで鍵はぬけないから。それに、外側は把手がないからあけられない」
「これで王子さまのいるところに帰れるってわけね」
「そう、そしてアヤメ、わたしたちがいま、どこにいるか、もうわかっているわね?」
「もちろん」と、菖蒲はカーテンを思いきり引きます。
窓の外はどす黒い血のような雨のふる沼地が広がり、遠くには切り立つ黒い山が雷光にてらされていました。
もちろん、ここは地上ではありません。あのおそろしい大蛇の体内だったのです。
「わたしをここまで案内してくれたのは男の子の影よ」と、リリィは言います。「ときどきやってきては干しわらの約束や父と呼ぶ人についておしえてくれたの」
「その子はミモザのお兄さんのイシュね」と、菖蒲は言います。「影をとどめ、あやつれる」
「小麦畑の家とこの家がおなじなのは、イシュがとどめている思い出だった」と、リリィは言います。
興廃の丘でグレエンの伝えたようとしたすべての秘密、羽根のまわりつづける風車、いつも穂をたらす小麦畑、納屋と農夫の家すべては、影の子イシュと父親のすごした心象風景だったのです。
「リリィ、わたしたちへんよね。外は最悪なのに、ぐっすり寝たり、おいしい食事をしたり、さっきまでティータイムまで楽しんでいたんだもの」
「わたしたちだれよりも強いわね。断言できる」と、リリィは腰に手をあて、どっしりかまえます。
「ピッピロッタ・タベルシナジナ・カーテンアケタ・ヤマノハッカ・エフライムノムスメ・ナガクツシタみたいに?」
「ながい名前!」
「馬をもちあげるくらいとっても強い女の子なのよ。わたしピッピ大好き」
「アヤメならアルビレオだってもちあげてしまいそうね」
「リリィ、わたしのお願い、聞いてもらえる?」
「わたしのしてあげられることならなんでも」
「裏口の鍵、わたしたち一回ずつ、つかえるのよね? リリィは先にもどってほしい。わたし、イシュに言わなきゃいけないことがある」
一瞬、リリィは止めようと顔を横にむけます。すると菖蒲ともうひとり、重なるようにミモザが固い決意で外の黒い山を見つめていました。
リリィは少し考えてから、「わかった。では【帰還の約束】をしましょう」と、言います。
「きかんのやくそく?」
「そう。遊びにでかける子どもに親が時間までには帰ってきなさいっていうでしょ。あれは【門限の約束】で、時間を守るために力を使う。【帰還の約束】は、親のもとに帰るまで、その距離が遠いほど力が働くのよ。わたしの右手にアヤメの手をのせ、わたしの言葉を復唱して」
菖蒲は手をのせ、リリィはさらに左手をそえます。
「わたし、母リリーフロラは、娘アヤメと、かならず母のもとへ帰る【帰還の約束】を交わします」
「わたし、娘アヤメは、母リリーフロラと、かならず母のもとへ帰る【帰還の約束】を守ります」
「無理は絶対だめよ。それと、グレエンに会ったら、家で待っていますと、伝えてもらえるかしら」
菖蒲は静かにうなずきました。
光と影による交渉

金色の棒鍵錠に鍵を差しこんでひねり、木製の扉を押し開けると、石階段が上にのびていました。見えない先にふきぬける風は、まるで階段を通る者の目ざす出口を知りたがっているようです。
リリィは菖蒲にできるだけ早く帰ってくるよう言いのこし、階段の奥に消えていきます。風で扉が閉まると錠はひとりでにかかり、鍵はくるんとまわってぬけ落ちました。
菖蒲は鍵をひろってポケットにしまい、居間を通り玄関の壁にぶらさがる丸い姿見の前に立ちます。
「わたしのミモザ」菖蒲は右手首についた金と銀の腕輪にふれ、「立ちあがる勇気を」。それから扉をいきおいよく開き、家の外へ飛びだしました。
なまぬるくべっとりした空気、ただよう腐臭、一度足を止めたなら体ごとのまれそうな底なし沼、灰色の枯木はいたるところに突っ立ち、絶望ときざまれた骸が山とつまれ、時おり、ころがり落ちて沼にしずみました。
菖蒲は、死体がずるずる引きずられたあとをずんずん歩きます。あちこちにかくれる面子をつぶされた欲深き四つ足の影は、悪意にみちた表情で菖蒲をうかがい、むさぼり食おうとわずかな失敗をねらっていました。しかし、短夜を舞うホタルのように、ぽおっと黄色い光をまとう菖蒲に手をだすものはいません。うしろめたい影はまっすぐな光を恐れていました。
闇の領域で聞こえたような罵詈雑言も、空からたれ落ちるタールのような黒い雨も、菖蒲は気にとめず、前へ前へと進み、沼地を背に、雷鳴とどろく黒い孤峰のふもとまでやってきました。するどいきばをむく鍾乳洞の口から吐きだす熱風にさからい、山の中心部にむかってひたすら奥へ、やがて広間に出て、ぴたりと立ち止まりました。
中央にはオニキスをけずりだした漆黒の座がすえられ、金のかんむりを頭にのせた髑髏の顔をした燃える影が胡坐をかき、ひじかけにどっしりとよりかかり、ふてぶてしくこちらを見おろしていました。
「さて、賢良な人間だと評し、ひとつ提案しよう」と、燃える影は冷淡に言います。「井戸の水を我に。そうすれば安寧の契約を破棄する。命はおまえの手中にある。干しわらか、罪なき子たちか、選べ」
菖蒲のこぶしが緊張するのを影は見すごしません。
「我は辟易していた」と、影はため息まじりに話します。「自由と権利をふりかざし、道徳をさえずる愚民に。あいつらは真実であるほど疑い、偽りを熱心に信じる口やかましい人形だ。紳士淑女よろしく常識のボロをまとわせ、まやかしの舞台でおどらせるのがふさわしい。嘘で混乱し、おのおの正義で争い、平和のために領域を破壊しつくすまで。人形は約束を守らずいいわけばかり。なるほど世界に偽りはない。そむいたのは人形だ。罪にまみれた体をイチジクの葉で覆い、恥を隠そうとしたはじまりから。約束の価値を低めたのはあいつらではないか? だが虹の娘よ、おまえはちがう。おまえの母イリスが冥府の水をくんだように、苦心し、神秘の井戸から水をえた。それを人形ごときに流すのはなんともったいない! 干しわらの阿保など捨て、我とともにあゆめ。我が水をつかえば、新たな文化の黎明を拝し、高尚な秩序をもたらす瞬間にも立ちあえよう」
じっと静かに見つめる菖蒲。
影はあきれたようにため息をつき、「金か、称賛か、それとも凡庸な人生か?」
洞穴を横切る風だけがヒューヒューと口笛をふきます。
「つまらん、なにかこたえろ!」
ごおごおと憤怒を燃やした影は、ひじかけをたたきわります。
「うす汚い目をむけやがって! あの時のように謀略をめぐらし、我の背を狙っているのに気づかないとでも思っていたか女狐め! なにが水だ! なにが約束の力だ! そんなもの世を統べる我の強大な力の前でねじふせてやる!」
影は憎しみをあらわに、獰猛な顔つきで菖蒲にせまります。
「なにかこたえろ!」
——わたしはあなたを呼んだ。
「おまえを!」
——くりかえし、なんども。
「この場で!」
——あなたを取りもどそうと。
「苦しめ、痛めつけ!」
——わたしの兄さんだから。
「泣きわめき、命ごいさせ!」
——でも、とどかなかった。
「消しさってやる!」
——なぜあなたには見えないの? なぜあなたには聞こえないの? なぜあなたには感じられないの?
「うるさい! だまれ! だまれ!」
燃える影は菖蒲のほおを打ちたたきます。
うしろに倒れた菖蒲は身を起こし、顔をあげて前方を望み、息を大きく吸いこむと、「いいかげんになさい!」
洞窟全体はびりびりふるえます。
「影にかくれる人間の王よ、聞け! あなたのうぬぼれた野心により、剛毅朴訥とみずからの役割をまっとうせんとする大勢の高潔がどれほど深く傷つけられたか知りなさい。ゆがめられ、にごされた貴重な約束の数々は血涙とともにさかまく大河を流れ、たどりついた激動の海で天にむかい公正をさけびつづけている。そうしてふりそそぐ美しくも悲しい歴史の雨はあなたの玩具ではない! なにより闇の子よ、あなたを兄としたう妹の愛を思いだしなさい」
「ゆるさん、ぜったいゆるさん!」燃える影はギリギリと食いしばり、菖蒲を指さし、わめきます。
「おまえこそ男のために妹をだまして利用し、殺したくせに! すべてアヤメがわるいんだ! アヤメなんかいなくなれ! アヤメなんか消えてしまえ!」
「だったら左のほおもぶてばいい」と、菖蒲は右手を強くにぎります。「それでもミモザはわたしのそばにいる。たとえわたしがすべて悪くても、許されなくっとも」
影は手をつなぎ、走りさるふたりのうしろ姿をながめるしかできず、よろけ歩き、くだけた王座に力なく腰を落としました。
「ああ、わたしにも見えていた。わたしにも聞こえていた。わたしにも感じられていた。だが、もどれなかった」
燃えつきた影の少年はかわいた笑いを、うなだれると顔を覆い、目から黒い水が流れます。
「父よ、父よ。あなたはいったいどこにいるのですか? どうかわたくしを助けてください」
影は四方八方に破裂し、大蛇となって力と怒りのなすがまま、おたけびをあげ、山をくずしはじめました。憎悪のかたまりはあらゆるものを、ここが自分の体内であるなど関係ないといわんばかりに、なにもかもぶち壊し、家にもどろうといそぐ菖蒲を見るやいなや、あれくるう波にのまれる小さな木造船のようにひねりつぶしました。
かろうじて難をのがれた菖蒲は裏口を通り、すぐに扉を閉めようとしますが、大蛇は反対側から力ずくでぐいぐい押します。ミモザはみしみし音を立て、たわむ扉を後ろ手に背でおさえつけました。
「ミモザ!」
「はやく! 王子さまのもとへ」
「でも」
「迷わず信じて。あたしはいつもアヤメといっしょ」
「うん」
ちいさくうなずいた菖蒲は階段をかけあがります。
すぐに大蛇は扉をぶちやぶり、階段にどっとなだれこんできました。
もうぜったいに止まることはできません。背後には黒い大蛇が菖蒲を八つ裂きにしてやろうと、これまでにないほどの強い怒りで猛追していたからです。
干しわらの王子さま

せまくて暗い直線の石階段からわずかに聞こえる蒸気機関車のブラスト音はだんだんちかづき、どおっと通り過ぎます。
「おい、出口はまだか。いったいどこまでトンネルはつづくんだ?」
重厚な鉄車輪と左右にふられる主連棒はもんくたらたらです。機関車は口をへの字に煙をあげて息せき切らし、懸命に階段の先を見ていました。後方から聞こえる大蛇の咆吼に追い立てられながら。
どんなことにもおしまいはあります。読めないとわかりつつ背のびして借りてしまった、文字びっしりのぶ厚い本、おしえかたがヘタな先生のたいくつな授業、苦手な科目のテスト時間、夕食にだされた嫌いな野菜ばかりのスープにも。
菖蒲はおしまいが大好きでした。本を閉じたあと、どん帳のむこうにいる役者たちのくらしを想像できたからです。しあわせにくらしたお姫さまの日々、食べ終えたおやつのケーキにだって物語はありますし、ほろ苦い結末のお話には、たっぷりのミルクと砂糖をまぜてしまえばカフェオレにできます。たとえ暗くて長いトンネルのような日々だとしても、菖蒲の王国では、おしまいがはじまりと仲よく腕をくみ、いつまでも終わらない物語をいきいきと語っていました。
「だから、ねえほら見て、機関車やえもん。このトンネルにもおしまいとはじまりがあったでしょ」
菖蒲はそう言い、こちらにやってくる四角い灯りに体を投げだします。
さあついに王子さまのいる部屋に帰ってきました。しかし、感慨にふけってなどいられません。暴走した影の大蛇は菖蒲を、いえ、この領域を破滅させようと、すぐそこまで迫っていたからです。
胸はバクバク、ひたいは汗でぐっしょり、息もてたえだえに菖蒲は重たい鉄の足をとにかく回転させ、腕をふり、部屋の中央、干しわらの座る王座へまっすぐ走ります。
やぶれた水道管から噴出する水のように飛びだした大蛇は、周囲をのみつくしながら、すさまじい速さで襲いかかります。なんて執念深いのでしょう!
干しわらに水を注ごうと菖蒲は小ビンをポケットから取りだし、フタを捨てたつぎの瞬間……!
「あっ」
小ビンに気を取られ、石だたみのでっぱりに蹴つまずきます。汗ですべった小ビンは手からすっぽぬけ、目の前でゆっくり、ゆっくりと宙にういて遠ざかりました。
ありったけ手をのばし、指をおよがせる菖蒲。
無情にも小ビンは地面に落ち、たたきわれたガラスの音が部屋中に響いて火花をちらし、たちどころに消えてしまいました。
——壊れないはずの記憶の結晶がなぜ?
ぴたりと止まる時間。
— ほんのりただよう挫折の香りに酔いしれた大蛇は、喜び勇み、とまどう菖蒲の頭上をかすめます。
地にかるく手をついた菖蒲は小ビンのそばまでかけよると、ひざをつき、こぼれた残りの水を口にふくんで王座へまっしぐら!
闇はするどい矢となり、菖蒲にとどめを刺そうと心臓一点にねらいをさだめ、いきおいよくはなちます。
無我夢中の菖蒲は王座につづく階段を一段飛ばしでかけのぼる、のぼる!
王座に飛びこみ、干しわらの口に口づけして、こう言いました。
「わたしの王子さま
どうか、どうか、もとの姿にもどりますように」
それから干しわらをぎゅうっと抱きしめ、目をつむります。
菖蒲にできることはもうなんにもありません。
ただし、扉のない中庭にいくため戦わねばならなかった孤独や失意、無力感を感じはしませんでした。安心してなにもかも、すっかり全部、干しわらの王子さまにゆだねたのです。
いっぽう闇は、みにくいかちどきをあげ、ふたりをまるごとのみこんでいきます。
こうして光は闇のものとなり、暗転しました。
————————
——でも、それはほんの一行だけ。
「……はな………れ………よ……」
ぽつりぽつりと聞こえる男の声。
「おまえと……の約束を……はたした」
少しずつ、声は明瞭になります。
「……わたしの勝ちだ、影よ」
王の帰還した王座から光あふれ、闇を切り裂き、燦然とかがやく少年の姿をはっきりあきらかにしました。
「燃える影よ。おまえはほんとうに約束の価値を知っていたのか」
菖蒲は顔をあげ、ふんわりなびく小麦色の髪にサファイアの瞳をもつ少年と目を合わせます。
「もとの姿にもどれたのね。よかった」
「ありがとう、アヤメ」王子さまは、太陽のような笑みを菖蒲にむけ、ゆっくりうなずきます。
「きみがわたしのくちびるにそえた水は、どんな花よりも芳しく、極上の蜜よりずっと甘かった」
二重星

なんだか恥ずかしくなってきました。なにせ王子さまにしがみついていたのですから。しかも干しわらとはいえキスまで……
菖蒲は王子さまからはなれようと、あわてて体をひき、うしろによろけます。王子さまは高い壇上からころげ落ちそうな菖蒲の手をとっさにつかみました。
「どうしたの、アヤメ?」きょとんとする王子さま。
手から伝わる王子さまのぬくもりが電流のように全身をびりびり巡り、菖蒲はかーっと熱くなって顔をそむけました。
「あの、その、だから……うん、ごめんなさい」
わけもわからず目をきょろきょろさせ、手をふりほどきます。
——あぁもう、おばぁがへんなこというから!
もちろん、菖蒲は納屋で選んだ干しわらが王子さまだとまったく信じていました。だからこそ、もとの姿にもどすため、必死に行動してきたのです。ただひとつ、干しわらでも人間でもおなじだろうという大きな誤算がありました。眼前に立つ想像していたよりもずっと強くてやさしそうな王子さま——なにを考えているのだろう、わたしのことはどう思っているのかな。
菖蒲の頭で『とりとめなき楽団』による演奏会が開演し、満員の観客を前に指揮者はタクトをふります。ティンパニーのロールで最前列の恋は目ざめ、シンバル奏者が情熱を打ち鳴らそうと両手を広げ愛のファンファーレが……
「アヤメ!」王子さまは、ぼんやりしている菖蒲に言います。「影と決着を!」
そう、戦いはまだ終わっていませんでした。ばらばらの黒い水が集まり、王座にぬらりとちかづいて、ふたりをかこみます。いっこくの猶予もありません。
それにもかかわらず、菖蒲はとんでもないことを口にします。
「わたしをおいて先にいって!」
王子さまが菖蒲を見ると、腫れたほおに全身はススけてぼろぼろ、生まれたばかりの雌鹿のように足をブルブルふるわせています。王子さまのためにひたすら走った菖蒲は、すっかり力を使い果たし、もう限界でした。
竜の形に姿を変えた影はいきおいよく飛びかかってきます。王子さまは菖蒲を横にしてふわりと抱きあげ、口を大きく開いた竜を切るように正面の扉にむかって突っ走ります。
「だめ! このままでは追いつかれてしまう。わたしをおいて早く!」菖蒲はじたばたともがきます。
「聞いて、アヤメ。わたしは傷をおった羊を背負い、山を三つ越えたことがある。それにかけっこではだれにも負けない」
王子さまはそう言って木扉を蹴破り、軽々と階段をのぼります。ふたりが風車をでようとしたその時、大きな地ひびきを立て、噴火する黒いマグマは風車をこっぱみじんにし、がれきが飛散します。木ぎれは矢のようにふりそそいで地面に突き刺さり、間一髪、爆発から逃れた王子さまは菖蒲をかばいながら穂をたらす小麦畑をひた走ります。暴れ狂う巨大な竜はグレエンたちと過ごした家も馬小屋も納屋も、たがやした畑も、まいにち水をまき、手入れした庭も、いいにおいのギンバイカもすべて、なにもかもめちゃくちゃに破壊し、のみつくしました。菖蒲はなくなった思い出の景色に傷つき、闇の領域で怒りをしずめてくれたミモザに感謝しました。
「アルビレオッ! アルビレオォ!」王子さまは戦友の名をくり返し呼びます。
上空でうねる竜は、赤い目玉で王子さまをにらみつけ、地上に牙をまき、背後から足を打ち鳴らす幾万もの影でとどめられた兵士を差しむけます。
形勢は逆転し、がけっぷちの王子さまでしたが、あきらめずにアルビレオを呼びます。
王子さまの力強いうなじに手をそえ、厚い胸に鼻をよせ、リズムよく鳴らす鼓動と荒い呼吸に耳を溶かした菖蒲はすっかり安堵して、ゆりかごでゆられるように目を閉じ、旅を思い返していました。
——モルトやグレエンにアルビレオ、わたしのステキな仲間たち。フクロウ先生や生徒スズメ、働きアリさんは元気かしら。まちぼうけ駅でおばぁと話しをしたいな。おじぃとシバは新しい冒険にでかけたのでしょうね。もしかすると天体観測所でわたしたちをのぞいているかも。メレさんは記憶採取してるにちがいないわ。アルネヴとのティータイムはいつにしよう。なによりミモザ、あなたはわたし。リリーフロラお母さん、ぶたれたほっぺを見たら怒られるわね。わたしは闇を進んできたんだもの。だからこれからも光はやってくるはず。
「きたわ」菖蒲は顔をあげて言います。
闇のむこうから、チカチカ星はまたたき、希望がこちらにやってきました。
「アルビレオ!」王子さまはおどろきと喜びのまじった声をあげます。
「わが主人、わが王よ! あなたをどれほど待っていたか!」
「おそくなってすまない、アルビレオ。喜べ、わたしたちの勝利だ! さあわたしを青い剣のもとに連れていっておくれ」
王子さまは菖蒲を白馬の背に乗せ、うしろにまたがると、アルビレオが土くれをけり飛ばし、せまりくる軍隊をいっきに引きはなします。
「青い剣はグレエンの手に、興廃の丘へ、モルトは王に顛末を報告するため国へもどりました」
「よし、アルビレオよくやった。すべて計画どおりだ」
小麦畑は遠くに、ポプラ並木は前からうしろへとぐんぐん流れ、興廃の丘手前、シラカンバ林の入り口でひかりかがやく戦士が待っていました。
「グレエン!」王子さまはさけびます。
戦士グレエンは、待っていたとばかりに青い剣をほうり投げると剣はするどい閃光とともに森に消えます。戦場に疾駆する王子さまが青い剣を高くふりあげるうしろ姿を見るや、グレエンは血湧き肉躍り、大声で言いました。
「ああ、いまは眠りし父祖たちよ。まんぞくです! 切望した解放の時を見ることができたのですから」
それから腰にぶらさがる剣を右手でゆっくり引きぬきます。研ぎすまされた長剣アトロポスは、後方で行進するおびただしい数の兵士を鏡のようにうつし、常世の運命を瞬時に断ち切ろうと、かん高い女の泣き声を鳴らしました。
「背信と虚言の亡者どもよ!」グレエンは獲物を捕らえたワシの眼をして、哮り立つ獅子のように、「俺がだれの子であるかおぼえているか。底知れぬ憎悪と悪事の応報、貴様らにおしえてやろう!」
そうして孤高の戦士は兵士に突進していきました。
いっぽう王子さまは、風を切ってシラカンバ林を越え、興廃の丘に出て、見晴らしのきくところでくるりと一回りして止まります。
広い平原には黒雲をつきやぶる赤黒い巨大な竜がうねり、いくつもわかれた尾で地面を打ちつけるたび地面は振動し、咆哮は空気を焦がす熱風となって菖蒲や王子さまの髪、アルビレオのたてがみをゆらしました。
「アルビレオ!」王子さまは青い剣のきっ先を遠く対峙する竜のひたいに突きつけます。「おまえはあれを恐れるか、狼狽するだろうか」
「わが主人!」と、アルビレオはすぐに答えます。「たとえ深い谷であろうと、切り立つ山であっても、あなたが一言命じれば、わたしはどこへでもかけぬけてみせましょう」
「よくいった!」王子さまは高らかに宣言します「永遠につづく友情のしるしに、わたしが闇を打ち破る様をおまえに見せよう。そしてそれは夜空にきざむ二重星となり、人々が仰ぎ凝らす時、今日の戦いを思いだし、いつまでも語りつぐ。さあゆけ、強くあれ!」
アルビレオは武者ぶるいし、ひづめを地面にうちつけ、雄壮にいななきます。
「アヤメ、こわくない?」と、王子さまは耳もとでたずねます。
「ううん、ぜんっぜん。だってわたし、あの影にしかってやったのよ」
「なんて気丈な姫だろう!」王子さまは口を大きく開け、豪快に笑います。
「気高きお姿、リリーフロラさまにたいへんよく似ておられます」と、アルビレオはつけくわえました。
「たしかに」王子さまはうなずきます。「アヤメ、どうかわたしの願いを聞いてほしい」
「わたしのしてあげられることならなんでも!」
「青い剣を共につかんでほしい。わたしの約束にきみの信じる力を」
菖蒲のゆるがぬ信念は青い剣をターコイズブルーに、王子さまが手を重ねると、まばゆいばかりの白金になりました。アルビレオは丘を一直線に駆けくだり、竜は全力で対抗しようと強襲します。天馬は光の速さで突進し、竜を頭からまっぷたつに切り裂いていきました。
「先生、あれはなんでしょう」と、レウケ島の山頂で夜空をながめるシバは聞きました。「ボクはあんな美しく、暗闇をわける力強い流れ星を見たことがありません」
「むかし」と、おじぃは悲しげに言います。「扉のない中庭にむかう道すがら、闇の領域で少年と親しくなり、わしは名を付し、少年はわしを階段まで導いてくれた。彼はより大きな存在を渇望する心の貧しい影だった。なあイシュ、おまえはいまも心の純粋なわしの友人だよ」
流星は暗黒にぶつかると、白い輪が宇宙いっぱいに広がります。光は一点に収縮してからぐるっと渦を巻き、七色の光が花火のようにあちこち芽ぶいたのです。
「すばらしい!」宇宙にさきこぼれる花をアルネヴはサトウの展望台で見ていました。「まるで銀河の終焉と誕生がひとときで起きているようだ。ミス・アヤメ、きみはついにやりとげたんだ」
どんな争いも、おしまいは静かなものです。雲ひとつない夜の丘に陽がさすと、こぼれるつゆは草の上でテラテラとかがやき踊り、朝のおとずれを告げます。消える灯火を昨日に残しながら。
帰路

かすみたなびき、興廃の丘にうっすらあらわれた王子さまとひざまずいた影のあいだをつめたい風が横切りました。
「もうすぐ、わたしはなくなる」と、少年の影は言います。「その前に王の子よ、剣でわたしを打ち、約束を果たそうではないか」
「イシュ!」王子さまのそばに立つ菖蒲は声をあげます。「なぜ門をでたの? なぜミモザを妹と?」
「わたしが自分をあたえられ、いちばんはじめに考えたこと、それは父だった。もとめ、探し、たたいてきた。いまも、これからも」
「こんな痛み苦しむことはなかった。イシュ、あなたやミモザだって」
「その言葉を父から聞きたかった。わたしは身勝手で、とても弱い」
「そんなことない! はじめて会ったあの晩、あなたはわたしを手にかけることもできたはず。リリィもあなたに助けられたと感謝していたわ」
「リリーフロラはアヤメだけを思い、母を胸に秘めていたね」と、イシュはおだやかに目をほそめ、みじかいおとぎ話を語りました。
むかしむかし、心優しい農夫は、地をさまよう美しい少年の影をわが子のように受け入れ、親子のようにくらしていました。まわりの人々は影を蔑み、遠ざけましたが、農夫はひとつ星を瞳にもつ少年の影と手をつなぎ、風車のまわる黄金の小麦畑を歩いて夢を語り、愛についておしえたのです。ある日、少年は父を喜ばせようと、すこしばかりの力を見せます。それが人を狂わせるにはじゅうぶんな力であるなど考えもせずに。『すこしばかりの力』を手にした農夫は一夜で領域を統べる王となり、結婚して人の子をもつと小麦畑、風車、愛や夢、影の少年との思い出をすっかりわすれてしまいました。少年は父を自分だけのものにしようと父の面影をとどめ、あやつりはじめたのです。
「わたしは父と畑を歩くだけでよかった。だが父は、争いをやめない愚かな子どもたちに愛をそそぎ、信頼し、裏切られ殺された。そんな人間が許せなかった。家族を捨て山あいに逃げた、卑怯な息子も。わたしは知りたい。影とはなにか、なぜわたしは影なのか、影が命をもつのはどうしてなのか」
「アヤメ」と、王子さまは言いました。「しばらく、こちらを」
王子さまに顔をむける菖蒲は、まるでミモザが斟酌を訴えているようでした。肩越しにイシュが黙って首を横にふるのを見た王子さまは、かたい表情をくずさず、菖蒲を胸に抱きよせます。
「けーんけーんぱ、けーんけーんぱ」イシュは遠い過去を焦がれるように、空にむかってつぶやきます。
「父よ。ああ、やっとあなたのもとへ……」
王子さまは右手の青い剣をふりかざし、陽光は刃先を天へとつたい、力をこめていきおいよく!
—————
さわやかな朝に流れる重たい空気。
王子さまは胸もとがしめるのを感じます。
「アヤメ、おわったよ」
しぼりだすようにそう言い、青い剣を地面に思いきりたたきつけようとしました。
「お願い、やめて!」菖蒲は王子さまにすがりつきます。「赤い宝石の指輪は約束を果たした時に壊れた。だから青い剣も……」
こたえるように剣はガラスの割れたような音を鳴らし、火花となって消えます。
「わたしにはこうするしかできなかった」沈痛な面持ちの王子さまは、広げた両手をのぞきます。
菖蒲はなぐさめるように、頭を横にゆらしました。
「アルビレオ!」
草をはむ白馬に菖蒲は手をふります。
「さあ、うちに帰ろう」と、王子さまは背すじをぐっとのばします。「はやくやわらかいベッドにもぐりたい。もうあんなカチカチのイスはこりごりだよ」
「干しわらだったのに?」菖蒲は目を大きくして言います。
「まさか」王子さまは腕を広げました。
ふたりが話していると、「おーい!」漆黒の馬にまたがるグレエンがちかづいてきました。「みんな、ぶじでよかった」
王子さまはグレエンとあく手をして、抱きあいます。
「助けてくれてありがとう、グレエン」
「いえ王子、みなの協力あってこそ」
「王子はやめてください。グレエンおじさんに言われるとなんだかはずかしいや」
グレエンは高笑いしてから菖蒲の前で深々とおじぎをします。
「アヤメさま、感謝いたします。あなたと過ごした日々はわたしたちの力となりました」
「わたしもです、ご主人さま」と、菖蒲はうやうやしく会釈します。「リリィお母さんがあなたの家で待っていますって。わたしも帰りますね、グレエンお父さん」
あまりにたくさんのうれしい知らせがかさなったグレエンは目をうるませ、ぱっとあかるい顔になりますが、みんなの視線を感じてすぐに頭をふり、わざとらしくせきばらいをします。
「きみたち、わるいが急用だ。先に国へ帰る。では!」グレエンはだれの返事もまたず、馬に飛び乗ると、あっというまに消え去りました。
「グレエンってあんな人だったかしら?」しんぱいそうに見つめる菖蒲。
王子さまとアルビレオは声をあわせ、「うん、あんな人!」
「おーい、アヤメセンセーイ!」
今度は空からさわがしいさえずりが聞こえてきます。
「こっちだよ、こっち!」
菖蒲は顔をあげると、たくさんのスズメが集まってきました。
「まあ、あなたたちはセイトスズメね。それにフクロウセンセイも。なつかしいわ」
セイトスズメは菖蒲のまわりをくるくると、楽しそうにおどります。
フクロウセンセイは菖蒲のそばにきて言いました。
「教室でどなって、すまなかった。どうかわたしをゆるしてほしい」
「もちろんです」菖蒲はフクロウを許しました。
「アヤメセンセイのおしえてくれたこの空は自由に飛びまわれるすばらしい青空だよ。センセイとの約束どおり、いろんな鳥を誘ったんだ。きっとこの丘はにぎやかになるね」
「きっとここは鳥たちの楽園になるわね。みんなの旅のお話し、わたしにもおしえてちょうだい」
セイトスズメは菖蒲を祝福してから遠くへ飛びさり、手を大きくふって見送ります。
「ワレらのジョオウ!」
今度は地面からにぎやかな声が聞こえてきました。
菖蒲はかがんでのぞくと、働きアリがたくさんならんでいました。
「あなたたちはコロニーをおわれたアリさんたちね!」
「ジョオウのショウカイしてくださったこのコウダイなトチは、やりがいのあるドジョウです。ワレワレだけでニンムはカンスイできないのでアヤメジョオウとのヤクソクドオり、ミミズやモグラ、ネズミなどなど、ドウブツにホウボウコエをカけ、キョウリョクしてシゴトをします」
「とてもよいアイディアね。もっと美しい丘になるわ」
「ジョオウのおかげです。ジョオウのヤシキとテイエンがカンセイしましたら、おいでください」
「ぜったいに行くわ。どうやってお屋敷と庭園を作ったのか、わたしにおしえてちょうだい」
「アリ、アリ、サー!」
働きアリたちは菖蒲を祝福して、穴にもぐり、手をふって見おくりました。
「アヤメはよい出会いがたくさんあったんだね。うらやましいよ」と、王子さまは言いました。
「ええ、わくわくするような冒険だったわ。とっても、とっても……」
長旅をおしむように、菖蒲はみどりさざめく丘をながめて言いました。
「さて、わたしたちもいこうか。アヤメにわたしの国を見せたいんだ。いっしょにきてくれる?」
「もちろん」と、菖蒲はうなずき、思いだしたようにたずねます。「ねえ、わたしをアヤメと呼ぶけど、あなたの名前をまだ聞いていなかったわ。それとも、王子さまとお呼びしたほうがよろしいかしら?」
「アサゼル」と、王子さまはすぐに答えます。「わたしの名はアサゼルだ」
「みじかいのね。もっとおごそかな名前かと思った」菖蒲はくすりと笑みをこぼします。
「しつれいな。じゃあ王子でいいよ、もう」
「いじけたの? アサゼルは子どもねえ」
「まったく、アヤメがそんな人なんて」
「レディにそんな人とか言うのはしつれいよ、王子さま」
「……ごめんなさい」
「わたしたち、あやまってばかり!」
ふたりは顔をあわせ、ぷっとふいて笑いました。
「そういえばアルビレオ」と、アサゼルはたずねます。「アヤメをいやがらないね。モルトが乗るだけでも大あばれするのに」
「さてそうでしたっけ、ねえアヤメさま?」とぼけたように耳をヒクヒクゆらすアルビレオ。
「どうだったかしらねえ、アルビレオ」菖蒲は知らん顔です。
アサゼルは首をかしげ、「まあいいや」と、アルビレオを走らせました。
丘陵地から西へ、山々をのぞむ大草原を通り、ゆるやかにまがりくねった川と水車場を過ぎて石だたみの街道にでます。昼に遊牧民から天幕でパンとミルクティーのもてなしを受けていた時、アサゼルは菖蒲に「より道したいのだけど、いいかな」と、たずねます。できるだけ早く山あいの国へ帰るのを約束し、道を北にはずれ、血の荒野へと馬を走らせました。
赤い砂の毛布をかぶった眠れる都市の廃墟は基礎だけが顔をむきだし、宮殿跡にむかって道路をのばしていました。アサゼルは宮殿へのびる長い階段の前でアルビレオと菖蒲を残し、散乱する大きな石灰岩の石づみに飛びうつり、ドリス式の列柱廊を進みます。天井のぬけ落ちた宮殿の中央広間にでると斜光をあびる頭部のかけた巨像の足もとに粗布をまとった老人がつえを手にして腰かけていました。
アサゼルは老人の前でひざまずきました。
「あなたの導きにより、闇を打ち破ることができました」
「わしはなにもしておらん」老人はそっけなく答えます。
「あなたはただのもの知りではなく、山あいの国の安寧のため追放された王子です」と、アサゼルは言います。「広い世界を旅した時、各地で名もなき国の王子アサゼルに救われた話を聞き、おどろきました。数珠のように土地から土地へとつながる善行の軌跡をたどり、ここまでやってこれたのです。あなたたちアサゼルがどのような思いで祖国をあとにし、どのようなこころざしで歩み、なにを残そうとしてきたのか。わたしにあたえられた試練とは、アサゼルという名の目的地を示す旅であると」
「山あいの国では代々、物語を愛する王妃を招待し、ふたりの王子が誕生する」と、老人は言います。
「一方は王として国にとどまり、他方は安寧の契約のために国を去る。旅立つ王子にアサゼルと名づけ、新しい王子が旅立つと古いアサゼルは追放を意味するヘレムと名を変えてきた」
「そして、あなた方ヘレムは幼いアサゼルを旅に備えさせ、山あいの国をずっと見守ってきました」
「ことの終わりは初めよりもよい。耐え忍ぶ心は、おごり高ぶる心にまさる」
老人はぼそりと言ってからうなずくと立ちあがり、アサゼルの肩に手をのせます。
「おまえはよくやった。それにグレエンの勇姿もたたえよう」
「勇敢な姫に救われました」
「うむ。では約束どおり秘密をおしえよう。顔をあげなさい」
「ヘレム、あなたは!」アサゼルは目をまるくします。なんとそこに立っていたのは老人ではなく、白銀の髪に琥珀色のひとみをもつ屈強な男だったからです。
「おどろいたな、アサゼルよ。おまえは身なりで人を判別したか」と、ヘレムは腰に手をあて、不敵な笑みをうかべます。「むかし、燃える影の誘惑と戦い、精魂つき果てこの廃墟の宮殿にたどりついたわたしは倒れ、深い眠りについた。目覚めると都は栄光ある本来の姿をあらわし、虹の女王イリスがわたしに不死の水をあたえ、将来を告げた。わたしたちは愛しあい、虹は一輪の花を産み、光と闇にふれられぬよう天地のあいだに隠したのだ」
「では影が打ち負かされるのをはじめから?」
「いや、好奇心がそれを許さなかった。おしまいを知った旅など、なにがおもしろい? なるほど、たしかに国を去る王子のはじまりは夜であり冬。しかし、いちどあの自由を手にした子ヤギがどうなるかおまえもわかっているだろう」
「けわしい壁をもっと駆けまわりたくなる。良いものも、悪いものも」アサゼルは得意そうに答えます。
大いなる巡礼を思いだしたふたりは目くばせして、微笑をかわしました。
「ああ、だからどうかわたしをいじわるな幼子だと思わないでほしい。人は先を知らぬとも自由を探求し、まだ見ぬ知識と理解をえる。そうでなければ信じる心とはいったいなにか。おぼえておきなさい。この世界は言葉によってできている。宇宙をゆきめぐる力と法則は約束にもとづいているのだ。アサゼル王子、おまえに星々のきずなを解くことができるか」
「なんと! わたしの手にあまる問題です、王よ。なにせ語りつがれた物語のひとつにすぎないのですから」
「よい心がけだ。これらは時がくるまで秘しておくように。それと国のみなに言伝を託したい」
「ヘレム、あなたは帰らないのですか?」
「これから失った仲間たちを探しにゆく。困難な旅となろう。わすれるな兄弟、わたしたちはいつもおまえと共にいる」
ヘレムはアサゼルと抱き合い、言伝を告げてからつえを地面に三回打ちつけると、虹がヘレムをかなたへ運び去ります。一礼したアサゼルは菖蒲と山あいの故郷に帰りました。
この後、ヘレムと廃墟の宮殿を二度とふたたび見ることはありませんでした。
静かな凱旋

緑に覆われた渓谷の奥深く、山ぞいの道をくだってゆけば、やがて眼下に明かりの灯る、ちいさな町と、斜面にかわいらしい城が見えてきます。駿馬アルビレオでも山あいの国についた時はすっかり真夜中になっていました。
「アヤメ、あそこがわたしの国だよ」
王子さまは懐かしそうに言いますが、返事はありません。菖蒲の顔をのぞくと長旅でつかれたのでしょう、ぐっすり眠っていました。それで菖蒲の体をそっと、腕にもたせかけました。
石のアーチ橋を渡ってすぐ、低い石門の上部中央には旗がつるされ、つがいの白鳥と白鳥座を中心に、まわりを葉でかこみ、頂点にギンバイカと二匹のヤギがあしらわれた逆ハート型の紋章を描いていました。
パチパチ燃えるたいまつのそばには『ようこそ、名もなき国へ』という立てふだと、編まれた花かんむりがかけてありました。
門をくぐると大理石のふん水広場を中心に、大きな柱のそびえる円形劇場や、どっしりかまえる図書館は見えてきます。人々は朝から広場に集い、芸術や思想、数学、建築まで自由に語りあいました。昼には手をつないだ王さまと王妃さまはやってきて、みんな歴史やおとぎ話に耳をかたむけ、夕方になるとにぎやかな宴がはじまり、夜はつなげた星を夢見て眠りにつきます。
いつもは静まりかえった暗闇の広場で王子さまはアルビレオを停止させました。なんと、そこにはグレエンを先頭に山あいの国の騎士たちが灯火を手に、整列して主君の帰りを待っているではありませんか。
王子さまは馬上からひとりひとり名を呼ぶようにじっくり見まわし、何度かうなずきます。それからまっすぐ背すじをのばし、遠くそびえる城に頭をあげ、ゆっくり歩きだすと、アルビレオの馬蹄はおごそかに鳴り響き、敬意の思いで見つめる民の道を威風堂々通りすぎていきました。
町はずれのほたるの舞う森にグレエンとリリィの家はあります。バラアーチの美しい庭にかこまれ、わらぶき屋根に白しっくいの壁で、オーク材の木窓から白鳥の置物の影をぼんやりうつしていました。
王子さまは玄関で待っていたリリィに眠れる森のお姫さまをまかせ、山の中腹にある城門へ、そこでアルビレオの労をねぎらい、旅の仲間と解散しました。
重厚な観音開きの門扉は最後に開けた者の閉めわすれか、それとも不精者が仕事をしたのか、無防備にも開けはなたれたままです。ひとつ言いわけをするならば、今日まで深い山あいの辺ぴな小国をわざわざ攻めようなどと考える、ひまな国はひとつもなかったのでしょう。
王子さまは城のアーチ扉の上方にある小さなのぞき穴を見て「よおし」と、手のひらにつばをぺっぺとはきます。石壁のでっぱりに足をかけてよじのぼり、子どもひとり入れるくらいのせまい壁穴にもぐりこんでぐいぐいすすみ、城内に侵入しました。これは『通りぬけの儀』と、呼ばれる山あいの国で代々おこなわれてきた儀式です。子どもたちは城にある壁穴をどれか見つけて通りぬけたならひとつオトナになるのですが、みんなあまりにくぐりすぎて親よりも年上になってしまい(ある女の子はなんと数日で一〇〇さいをむかえたのです)年に一回だけとなりました。
ほかにも、城に隠れて王さまと王妃さまに見つからないようにする『かくれんぼの儀』、地図を手に宝石を探す『宝さがしの儀』、正門から城の屋上まで競争する『かけっこの儀』、子どもたちだけで城に宿泊する『おとまりの儀』、三時の『おやつの儀』など、それはもうたくさんの儀式があって山あいの国の子どもたちはおとなよりいそがしいまいにちなのです。
王子さまは大きな赤いじゅうたんに飛びおりると、エントランスの壁につるされた王妃さま手製のドライラベンダーの香りに、ますます郷愁をかきたてられます。
旅先ではいろんな場所に寝泊まりしました。草原、大木のこずえ、ビュービュー風のふくほら穴、ときにはりっぱな宮殿やお屋敷にも。ただどんなここちよいベッドも、自分の家にはかないません。山あいの国では、はなばなしく出迎える侍臣や兵士、なんでもしてくれる家令や侍女はいませんでしたが、みんな助けあい、それぞれが仕事をするという約束を果たしたので、仲のよい王国となりました。
王子さまは内階段を軽やかにのぼり、執務室の前に立ちます。
「希望をもって国をあとにし、栄光をもってむかえられよう、だなんて息巻いたのはだれかな。将来の王にふさわしく、りっぱなおとなになろうと血気盛んな子どもはいったいどこにいる?」王子さまはくっくと笑います。でもほんの一瞬、大志を抱く男の子が自由な風のように颯爽と走りぬけたような。山あいの城をちょっぴり狭く感じつつ、ひと呼吸して黒ぬりの扉をコンコンと手でたたき部屋に入りました。
大きな窓を背に、王さまと角灯を手にした王妃さまは立っていました。
「王よ、ご命令どおり、すべて約束を果たしてまいりました」と、王子さまは言います。
「よくやった」王さまは、けわしい表情で王子さまをじっと見て、低い声でこたえました。
「アサゼル、おまえはわたしたちの誇りだ。さぞつらい旅であっただろう。安寧の契約のためとはいえなにも伝えられず、苦労させてしまった。すまない」
「わたくしは真実、徳、なにより無償の愛について父上と母上からおしえていただきました。それゆえ言葉なくとも山あいの国の子としてなんら恥ずべきことなく正道をふめたのです」
「うむ……わが子よ、ざんねんだ、非常にざんねんなのだ」と、王さまは深いため息をつきます。「おまえはわたしたちの考えているよりずっと、りっぱな青年になってしまった。もう母の胸をはなれ、父の腕から飛び立つとは。だが、今夜だけはわたしたち親の勝手を許してほしい」
「おかえりなさい、アサゼル」王妃さまは手を大きく広げ、王子さまを力いっぱい抱きしめました。
「ただいま、父さん、母さん!」
これが安寧の契約によって国を追われ、帰ってきた王子さまのさいしょで最後の記念すべき静かな凱旋のお話です。
湖畔のガゼボ

朝から町はにぎやかでした。広場では長づくえに白いクロスをかける母親とドレス姿の子どもたちがつんできた野花でかざりつけをしています。劇場では大工が木製の演壇を鼻歌まじりにトントン組み立て、赤いカーペットや古いタペストリーを広げます。町じゅうにただようパンやケーキの焼けるあまいかおり、シチューのこってりとしたにおいに、みんなおなかを鳴らしました。
今日は王子さまが帰還したセレモニーの日です。
黒い燕尾服に着がえたアサゼルはボサボサの髪のまま食事もせず、階段の手すりをすべりおりて正面扉を思い切り開けます。あわただしい広場は通らず、裏口からこっそりグレエンの家にむかうため坂をくだりますが、友人たちに見つかって森にすら行けません。
それまでも何度か菖蒲に会おうと城の脱出を図りましたが、立ちはだかる王妃さまがアサゼルをむんずとつかまえ、問答無用で執務室に連行しました。アサゼルは凱旋の翌日から大法官として自身の旅程や諸都市でつたえ聞いた歴代のアサゼル王子のおとぎ話をすべて記録するというぼうだいな仕事を王さまに命じられたのです。
朝から晩まで紙とにらめっこする王子さまのもとに時々モルトはやってきて、菖蒲のようすを話してくれました。グレエンとモルトがまいにちのように菖蒲を遊びに誘うので、リリィにおこられ、グレエンは外出禁止になったこと、リリィと庭の手入れをしていることなど、そばで聞くアサゼルは鵞ペンを置き、窓を開けると、しけった部屋にさわやかな風が通りぬけ、ヒラヒラと紙をおどらせます。土と緑のまじる山の息吹をすいこみ、ぐうっと腕をのばし、リリィの家の方角をちらりと見おろしました。
菖蒲に会えず、がっかりしたアサゼルは、とぼとぼ町の広場に歩くと、正装をした王さまと王妃さまが待っていました。
「なんて姿勢ですか」と、王妃さまは強い口調で王子さまをしかります。「王の子らしく背すじをのばしてしゃんと立ちなさい」
「まあいいじゃないか」と、王さまはなだめるように言います。「セレモニーという名の宴会みたいなものさ」それから王子さまに目くばせしました。
「すぐそうやってあまやかす!」と、王妃さまはきっぱり言います。「あなた、きのうも本をちらかしたまま寝てかたづけない、食べたあとの食器は洗わない、服もたたまない……」
王妃さまの怒りはなぜか王さまに。強い母と、たじろぐ父の背中にアサゼルは、ほほ笑みます。
緊張した男の子がトランペットを上げ、空気のまじる、まのぬけたファンファーレを会場になりひびかせます。さあセレモニーのはじまりです。国じゅう、といってもそれほど大きいものではありませんが、劇場にはおとなから子どもまで、華やかなドレスを着て、王子さまを祝福しようとわき立っていました。大きなはく手とともに王が登壇し、聴衆の視線をあびます。王さまは民の前で両手を上げ、国の歴史を語りはじめました。
むかし、領域を統べる王には三人の息子がいました。なかでも末子は文武の才にめぐまれ、人望あつく、優秀な家臣を大勢もつようになりました。数多くの功績をあげると自国はもちろん、周辺諸国にまでその名は知られ、王の寵愛を受けるようになりました。
ある時、末子は影の力により王の考えがますますゆがみ、大きな災厄につながる戦争を案じ、影の子と手を切るよう王に提言をしますが、むしろ怒りをかいます。さらに妬みにかられた兄弟の陰謀や反逆者との流言飛語で命を狙われた末子は臣下と家族を守るため、深い山あいにある秘密の別荘地に逃れなければなりませんでした。
「祖先はおくびょうでも反逆者でもなかった」と、王さまは言います。「王を、国を、民を守ろうとした。そして知識の数々も。横に見える図書館におさめられた数えきれない書物は、わたしたちの祖先が命がけで荷車にのせ、ここまで運んできたのだ。歴史や科学、賢者の夢見たおとぎ話すべて。わたしたちはみな、父母から読み書きを学び、だれでも自由に本を楽しみ、考察し、語りあえる幸せな国である。
なるほど心は人の苦しみを知っており、喜びすら他のものとまったくわかりあうことはない。まくらをぬらした長夜、安息はまばたきほどであるのを知っているのはだれであろう。それでも理解し、なぐさめ、莞爾として笑おうと願うのは人のもつ美しさではないか。これらも深い知恵あってこそ。兄弟たち、独力で闇に勝利し、自由を勝ちとったなどと思いあがりたくはない。この物語から学ぼう。そして感謝しよう。美しい山あいの地を残した祖先に。身を賭して真実をあきらかにした父と母に。国を旅立った王子たちに。わたしたちのため、外の領域から助けにきてくれた勇敢な女たちに!」
民は大きなはく手でこたえます。
つぎにグレエンとアサゼルが登壇します。劇場全体を見まわし、入り口にリリィとアヤメを見つけました。美しい刺しゅうのほどこされた絹のドレスにルビーやエメラルドのネックレスとイヤリング、ダイアモンドをちりばめた白鳥の羽がいくえにもかさなる銀細工のティアラは、なめらかな黒髪をかざり、陽にあたってキラキラかがやきました。
王子さまは、お姫さまに目をうばわれます。
「こちらにくるように言ったのだけど、どうしてもいやだって」と、グレエンは耳打ちします。
アサゼルは軽くうなずき、話しをしはじめます。
「兄弟たち、わたしひとりでは成しとげられない、きびしく困難な戦いであった。みなの信頼こそ闇を打ち破る力となったのだ。わたしからひとつだけ伝えたい。それは旅立った歴代の王子たちからの言伝である!」
アサゼルの堂々たる姿に、会場は水をうったように静まり、王さまやグレエンですらも、なにごとかと緊張が走ります。
「安寧の契約のため、わたしたちアサゼル王子にしたことで苦しまないように。そして愛する山あいの国にいつまでも平和があるように」
アサゼルのおだやかな眼差しに、民は自然と涙を流しました。
「わたしは思いだす」と、王さまは民に言います。「親をなくしたあの夜を。解放の夢見てみなで約束を交わしたあの朝を。自由に野山をかけまわり、自由に湖をおよぎ、自由に歌おう。まちがえたのならあやまり許せ。深い山あいに住むちいさな兄弟たちよ。名もなき国はわれらの名、山むこうに虚栄捨て、山むこうに虚飾捨て。
わたしは王を辞めることを宣言する! 今日から城にくる子どもたちが親しみをこめて呼ぶピートおじさんとなるのだ。そして、そろそろたいくつなセレモニーはおしまいにして宴を楽しもう。好きなだけ食べて飲み、音楽に身をゆだねよう!」
王さまは民衆にうやうやしく一礼して、にっこり笑います。民はわっと歓声をあげ、しんみりした空気はどこへやら、そばに立つ王妃さまはあきれて顔をおさえます。でも王妃さまは知っていました。王さまはだれよりも息子をしんぱいして食事をひかえ、帰りを待ち続けていたことを。
舞台は楽団の演奏に場面転換し、テンポのよい音楽とごちそうでお祭りさわぎです。
王子さまは人々のあいだをぬうようにしてリリィにちかづきました。
「アヤメは?」
リリィはにっこりして森の家をさしました。
アサゼルは急いで庭にむかうと、真紅のバラ、アルティシモの前にお姫さまが見えました。
「王子さま、見事なスピーチだったわ」菖蒲は背後で息をあげるアサゼルに言います。
「主役はアヤメだったのに」
「ごめんなさい。わたし、どうしてもうまくできないから」
「ううん、いいんだ。それより見せたいものがあるから来て!」
アサゼルはそう言って菖蒲の手をとり、走ります。
「ちょ、ちょっと、そんなにいそがなくっても」あわててドレスのすそを持つ菖蒲。
「いや、はやくしないとおわってしまうんだ」
ふたりはこけむした敷石道を進み、小川にかかる木橋の先、森の斜面に咲くスミレの群生を横切ります。ナラの木立をぬけ、大理石のガゼボにでました。
「アヤメに見せたかった場所はここだよ」
ガゼボの前は茜に染まる湖が広がっていました。水鳥たちは優雅に飛び立ち、水面に紫の陰影が流線を描きます。
「どうぞこちらへ、お姫さま」と、王子さまは菖蒲を湖畔のガゼボにエスコートします。
「なんて美しい湖なのかしら」菖蒲はうっとり言います。
「朝も好きだけど、夕方がとっておきなんだ」
「すてきね……」
菖蒲はそばに座るアサゼルに目を注ぎます。夕日に焼かれた情熱的な横顔、黄金の湖水にむけられた瞳はどこか憂いを秘めています。菖蒲の手は自然と胸にそえられ、心に響く彼の声に耳を傾けました。
「よい解決はないか、旅をしながらずっと考えていた。アヤメはミモザの望みをかなえたのに、わたしはイシュになにもできなかった。どれほど勇み剣をぬいても、運命に翻弄され無力だと知る」
そよ風が葉むらをゆらしアサゼルの耳をなでます。沈黙は夕闇とともに濃藍の湖に沈み、寂寥があたりの森をつつんで、やがて月が男女の輪郭をそっと照らしました。
「いくら望んでも、すべてをあたえられはしないのよ」と、菖蒲は言います。「だから、こぼれ落ちてしまうほどちいさな赤子のような手の中で、せいいっぱいしてあげようと」
「強く優しい森の姫君」と、アサゼルは立ちあがり、お辞儀をし、「わたしと一曲いかがでしょう?」
菖蒲は右手を差しだしてから左手を腰に、ひざを軽く曲げ、ワルツのステップをなめらかにふみだしました。
「王子さま、ダンスがおじょうずね」
「南の女王に誘われて。姫君こそ」
「こと座シェリアクの舞踏会で毎夜、星の王子さまたちと」
「眠る干しわらを横目に?」
「そうよ、わたしの王子さま」
菖蒲はくるりと回ってアサゼルの腕から逃げるよう欄干によりかかり、はにかみます。
「アヤメをもっと知りたいんだ。どんなものを見て、どういう出会いがあったのか」
「いいわ。そのかわりアサゼル、みんな知らない、あなたの旅をわたしだけにおしえて」
「もちろん」
「そのまえに……」菖蒲は外にむかって大きな声で言います。「いるんでしょ、でてきなさい!」
するとザザッと葉むらはダンスして、へたなネコなで声が聞こえてきます。
「とぼけてもむだよ、キジ三毛ネコのモルト」
チッと舌うちしてふたりの前に姿をあらわしたモルトは、じとっとした目で菖蒲のひざの上で丸まり、鼻息をふんっと鳴らします。
「なんだモルト、こちらにくればよかったのに」と、アサゼルは言います。
「こんにゃおもしろいのに、くるわけにゃいだろ」と、モルトはつぶやきます。
「リリィ! それにグレエンも!」
すると、また葉むらはザザッとダンスして、リリィとグレエンがガゼボに登場しました。
「ふたりもいたの!」アサゼルは目を大きくします。「ぜんぜん気づかなかった」
「あなたそれでよく影と戦えたわね」と、菖蒲はあきれ顔です。
「おれたちは娘をあたたかく見守っていただけさ。なあみんな!」
グレエンの言いわけに、モルトとリリィはうんうんあいづちを打ちます。
「あのね、娘をしんぱいして楽しそうにこっそりのぞく親とネコなんてどこにいるの。ゆだんもすきもないんだから」
「おーい」と、森のほうから、のんきな顔したピートおじさんは大きめのピクニックバスケットを手に王妃さまとやってきました。
「アルビレオに聞いたらここじゃないかって」ピートおじさんはバスケットからろうそくをいくつか取りだして角灯の火をうつしていきます。「おなかすいただろう。食べ物をもらってきたんだ」
「お兄さん、町は主催者もいないパーティーかい?」グレエンは言います。
「気にするな」と、笑顔のピートはグレエンの肩をたたきます。「あれがはじまってしまったのだよ。だから、やられるまえに逃げてきた。前回の仕返しがこわいからね」
「あれって?」菖蒲が聞きます。
「それはそれはおそろしいパイ投げ祭りだよ」と、グレエンは苦笑します。
「やっと会えたわね、アヤメちゃん!」王妃さまは菖蒲の手をにぎります。「わたしの名前はユリーフロラ。ユリィって呼んでね」
バラの香水を香らせるユリーフロラは凛とした美しい顔立ちで、リリィが物静かな月なら、ユリィはあかるい太陽のような王妃さまでした。
「アヤメちゃんのかわいいドレス、リリィが仕立てたのかしら」
「はい」と、菖蒲はうなずきます。
「ねえねえリリィ。わたしもほしい、お願い、ねえねえ」と、太陽は月にベタベタすりよります。
「いやよ。まだまだアヤメの服を作ってあげないといけないんだから。ユリィお姉ちゃんは衣装棚にお義母さまの服がいっぱいあるでしょ」
「リリィのけち。あなたが留守の時、庭のお手いれしてあげたのに」
「それだけどね、お姉ちゃん」リリィはまゆをひそめて言います。「帰ってきてびっくりしたわ。庭がめちゃくちゃなんだもの」
「めんぼくない」と、ピートはもうしわけなさそうに言います。「がんばって世話したんだ。あらゆる本を読み勉強したが、やればやるほど植物が弱っていく。わらとなった息子の報告をモルトから聞いた時、あやまろうと手紙を書いたが、リリィが影にのまれたと聞いて……」
「父上、どういうことですか!」アサゼルは聞き捨てならないと強い口調で言います。「わたしが国のために旅をしているあいだ、庭で頭を悩ませていたのですか」
「王子が旅立つ時もお姉ちゃんがスフレの焼きかたを知りたいって手紙で来たわね」と、わざとらしくリリィは言います。
「まさかあの時、執務室で書いていた手紙は料理のレシピだったのですか!」
「まあおちつけアサゼル。リリィがいないと国がうまくまわらないのだ」と、しみじみ語る王さま。
「そんなことよりあなた」と、ユリィはごまかすように言います。
「母上、そんなこととはなんですか!」悲しそうに声をあげるアサゼル。
「リリィのおうち、とっても快適だったわね」と、ユリィは気にせずピートに話します。「王さま、ずっと夢だった湖畔の家を建てましょうよ。お城は冬になると寒いし、じめじめするし、カビくさいし、階段多くてたいへんですもの」
「おお! それはよい考えだ妃よ。さっそく明日から新居探しをはじめようじゃないか」
「まあうれしい!」上品に手をぱちんとたたくユリィ。
「よおし、またひとつ楽しみができたぞ!」
「それでは王よ」と、グレエンがうやうやしく言います。「わたしは娘のアヤメとモルト伯爵で最良の土地を探しにまいりま……」
「ダメです。アヤメとの外出はしばらくゆるしません」きっぱりとリリィ。
「だいじょうぶかな、この国」アサゼルはあきれたように腕を組み、肩をすくめました。
「山あいの国ってこんなだったかしら?」菖蒲はふしぎそうにたずねます。
みんな声を合わせ、まよわず答えました。
「ずっとそう!」
それから夜おそくまで、みんな晩餐会を楽しみました。
ふたつめの夢

幸せな日は、たいくつがいたずらをして時の針を早めると、山あいの国の親はベッドで子どもたちに話します。
「夜はおやすみに時をゆずり、朝まで目を閉じてごらん。たいくつはあなたをすこしだけ大きくするだろう」
たいくつは菖蒲の時の針も、ぐるぐる回しました。山あいの友人たちと山登りに水遊びや、大好きな庭いじり、それにアサゼル王子と白馬アルビレオで遠出をしたり。グレエンやリリィは娘の時間を宝物のようにたいせつにしました。たくさんのすてきな服、おいしい食事、いつも笑い声が聞こえる森の家は、山あいの住民からもよく知られるほどした。
幸せな日は続き、約束も力を失いはじめたころ。おとなになった菖蒲はふたつめの悲しい夢を見ました。
薄絹のドレスに、つばの大きな白いぼうし姿で、中庭の木をひとつずつなでていました。満開に咲いた六本のリンゴの木の真ん中に、ひざ丈ほどの若木がのびているのに気づき、うれしくなり、かがんでなでます。木は苦しみながら真っ赤なリンゴを結び、手に落ち、すぐとけてなくなります。
赤く染まった両手を天からふりそそぐ光にかざすと、低い声が中庭に聞こえました。
「時は終わる……3600、3599……」
声は残りの時間を刻みはじめ、時の鐘が鳴り響きます。いそいで立ちあがり、周囲をへだてる白い壁と等間隔にどこまでも上にならぶ窓をぐるり見回しました。すると、五階にあるひとつの窓だけ黄色い光が灯り、黒髪の少女が悲痛な顔で「助けて、助けて」と、こちらにむかって訴えていました。出口をいくら探しても扉はどこにもなく、「ごめんなさい、ごめんなさい」と、さけぶしかできません。強い風でぼうしは宙に舞い、リンゴの花をすべて散らして雪のようにつもり、崩れた扉のない中庭はのみこまれてなくなりました。
「……3400……3399……3398……」
時の音から逃げるように、波立つ黄金の小麦畑を走っていました。はるか遠くに一番星を軸にして回転するイリスの翼がついた巨大な宇宙風車はたっていました。深い瑠璃色の空は雲のようにわかれて、純白の天が開かれます。
天界へのびる虹の階段があらわれ、踊るように足をかけ、地上からはなれます。しばらくのぼると眼下に、いなくなった花を探し、小麦畑をさまよう王子さまを見ました。引き返そうとしますが、天から少女の「助けて」という声が聞こえます。宇宙風車から流れるたくさんの星は虹にぶつかりくだけていきます。天に帰るか、地にもどるか悩み、ついに身を投げて白鳥となり、空へ飛んで消え、目覚めました。
ある夜、菖蒲は居間で針仕事をするリリィのそばで聞きました。
「リリィ、あなたはわたしの大好きなお母さんよ。グレエンお父さんも優しいから、まいにち幸せ」
「まあ、うれしい」と、リリィは顔をほころばせます。
「もしも、だけど、わたしが家をでるとしたら、お母さんはどう思う?」
手を止めたリリィは、すこし考え、娘の心配事を察して答えました。
「アヤメと母娘の約束をしてからもう十年になるかしら」
「へんなこと聞いて、ごめんなさい」菖蒲は後悔したように言います。
「ううん、いいのよ」リリィは菖蒲の頭をやさしくなで、ゆっくり話します。「それはとてもだいじな質問ね。だって菖蒲がおとなになった証拠だから」
「いつのまにか、たいくつがわたしを大きくしたのかしら」
リリィはくすりと笑い、「そうかも」。
「もう少しだけ、なにも考えずにお母さんのちいさな子どもでいたかった」
「そうね。あの日、菖蒲と母娘の約束をしてから、わたしはいつもアヤメだけを考えてる。思い返すとよくわかるの。ただ約束だからあなたを愛したのではなかったんだって。そばにいればいるほどアヤメをちかくに感じて、もっとアヤメのためにしてあげたい、アヤメに生活を楽しんでもらおいたいって、日々力が湧くるのよ。でもね……」
「でも?」
「どんなに愛しても、成長したヒナは巣立つでしょう。きっと親もつつむような愛から、むかえいれる愛に成長しているんだと思う。あなたがいつでも安心して家に帰ってこれるように」
「お母さん、とてもこわいの」菖蒲は弱々しく言います。「わたし帰ってこれるかな? またひとりになったらどうしよう」
「おそれないで、アヤメ」と、リリィは菖蒲の手を強くにぎります。「あなたは誇り高き戦士グレエンと、大蛇にひとり立ちむかったリリーフロラ自慢の娘よ。窓をいっぱいに開け、いつもあなたの帰りを待つ母を信じなさい」
「リリィがわたしのお母さんでよかった。ありがとう」
「グレエンに話してはだめよ。あの人、あなたがいなくなるなんて聞いたらめんどくさいんだから」
そう言ってリリィは菖蒲を抱きよせました。
明け方。菖蒲は白いワンピースに着がえ、家をでました。ガゼボで湖をながめるアサゼルを見つけ、どんぐりをそっとひろい、背後からぶつけて、すぐ葉むらに隠れます。頭をかくアサゼルに見つからないよう、またどんぐりを投げようとすると……
「アヤメだ」とくべつな親愛をこめ、アサゼルは彼女の名を呼びます。
「気づいてたの」菖蒲は彼のとなりに腰をおろし、肩にもたれかかります。「つまんない」
「だって」と、アサゼルは微笑をうかべます。「アヤメの好きなマグノリアのにおいがしたから」
湖は白い吐息を薄墨色の湖面にただよわせ、ときおり、まどろむ森を鏡のようにうつします。朝露と苔、ほんのり土と石のまじるさわやかな空気にみち、舞台の幕開けを鳥たちが知らせました。
「朝もすてきね」菖蒲はぼんやり言いました。
「セレモニーの日にどっちもいいっておしえたよ」と、アサゼル。
「そんなむかしのこと、もうおぼえてない」
「うそだ」
「なんで?」
「アヤメはぜんぶおぼえている」
「わたしだってわすれたいこといっぱいあるわ」
「みんなを傷つけないよう隠してるだけさ」
「それでわたしを知ってるつもり?」
「知らないのかもしれない。だから知りたい」
「……へんなの」
「考えていたんだ」
「なにを?」
「わたしたちのこれからを」
「わたしたちの?」
「うん。だからいま、アヤメにつたえようと思う」
「わかったわ。その前に、小麦畑の風車へつれていって」
湖水でハヤはぴちょんとはね、波紋が広がります。
「風車はないはず」困惑したアサゼルは菖蒲を見つめます。
湖の底に沈んでいくような目で、菖蒲はこたえました。
「ほんとうに、わたしを知りたいのなら」
アサゼルはアルビレオを呼び、菖蒲をうしろにのせて白馬を駆ります。
渓谷を越え、大草原を走るあいだずっと、菖蒲は彼の背に、ほおをぴったりつけていました。
「アサゼル。わたし、夢を見たの」
「どんな?」
「扉のない中庭にひとつだけ、あかりのついた窓があって、そこで少女が助けをもとめてた」
「たいくつのいたずらさ。目ざめれば幸せはつづき、いつかわすれる」
「そうね。人は夢をわすれてしまう。それは流れ星となって長いわたりの果てに、月の断片としてだれかにひろわれるまで眠るの」
彼はなにも言わず、右手で彼女の手をつつみます。
「アサゼルの手、やっぱりあったかい」
菖蒲は静かに目をつむりました。
やがて、小麦畑の中に燃えるような赤い風車が見えました。影の竜に破壊され、微塵となったはずの、あの風車を。
ぶきみな音を鳴らす風車は羽根が逆回転していました。アサゼルは忌々しげにこの大きな怪物をにらみつけます。
「ありがとうアサゼル。ここでじゅうぶんよ。先に帰って」
アルビレオからおりた菖蒲はそっけなく言い、風車にむかいました。
「つたえたいことがあるんだ」
アサゼルの呼びかけに菖蒲は足を止めず、ふり返りもしません。
「ひとつだけ聞いてほしい」と、アサゼルはあとを追います。
菖蒲は風車の戸口へずんずん歩き、うつむきかげんで把手に手をかけました。
「アヤメ、どうかこちらをむいて」
「いやよ」
「少しでもいい」
「いや」
「なぜ?」
「いやなの! だって……だって、扉を開けられなくなるもの」
「アヤメ、アヤメ、どうかこちらを」
ついに菖蒲は手をゆるめ、ふりむいてしまいました。まゆをよせ、目に涙をためたその顔に、アサゼルの胸はしめつけられます。
「聞いたら、もどれなくなってしまう」菖蒲はふるえる声で言います。「けっしてわすれたくない、あなたとの約束を。ずっとこの日、この瞬間を待っていたのに。わたしはまよわず「はい」と、こたえたいのに」
「そう、すべて解決したんだ。母やリリィも、山あいの国に招待された姫はずっとここで幸せにくらしてきた。だからアヤメもわたしたちと!」
「のこしてきた約束がまだある! あの子は苦しんでいた。あの子はわたしなのよ。わたしなの……」
「そんなむかしの約束なんか」アサゼルはうつむきます。「だれもおぼえてないさ」
うつろにのびる影を見た菖蒲は首を横になんどもなんどもふります。そう、なんどもなんども。それから思いきり空をあおぎ、ゆっくり息を吐き、アサゼルに人形のような笑みをむけます。
「ねえ王子さま。約束は一度口にしたら、たとえだれもおぼえていなくとも、果たさなければならないのよ。嘘は闇の糧になる。約束の力はたくさんついた嘘の代償。わたしはミモザやイシュのような子たちが苦しむのを見たくないの」
「だけど」アサゼルはこぶしをかたくにぎりしめます。「そのためにアヤメがいなくなるなど耐えられない。そんなの考えるのもいやだ」
「わたしもよ。だけど小さな約束を守ることは、わたしたちがのりこえなければならない大きな悲しみよりずっとだいじなこと。お願いだから、これいじょうわたしを苦しめないで」そう言って扉を開けた菖蒲は、ゴオゴオとすいこまれるような風にのまれます。
彼女を傷つけまいとする愛情と、ほとばしる恋の葛藤で身を焦がし、アサゼルはくちびるを強くかみしめました。かきみだされた主人を見るに見かねてアルビレオが口をだそうとしたとき————
「この約束を信じてうたがわない!」アサゼルはあらんかぎりの声でさけびます。「わたしはかならずアヤメをむかえにゆく。約束を果たした、その日、その瞬間に!」
宣言むなしく風車の扉はばたんと閉じ、翼をつけ、風とともに消え去ります。
のこされたみじめな王子さまは、朝焼けをわたる白鳥に、こうささやきました。
「いつまでも愛している、アヤメ」
夜半〇時のらせん階段
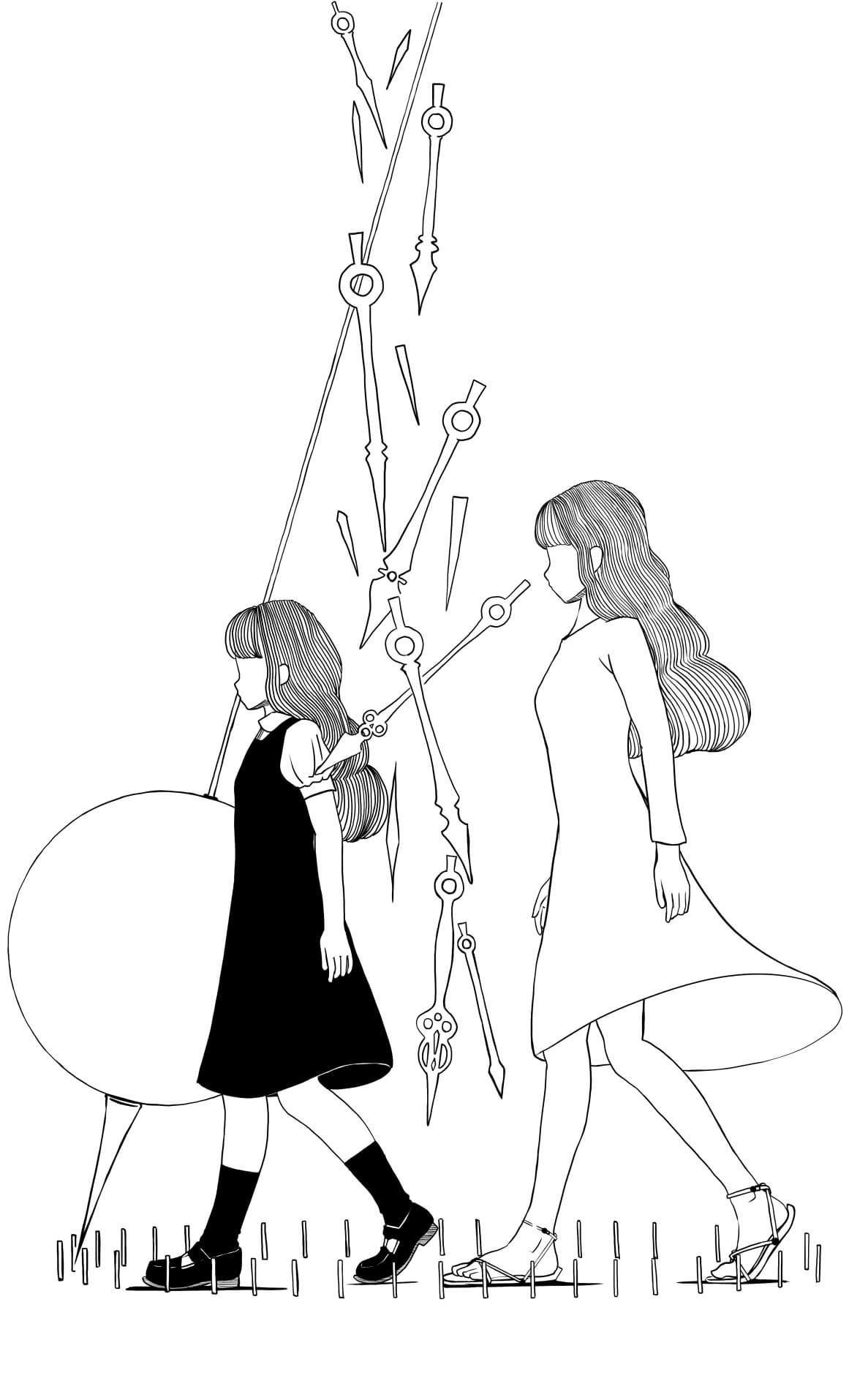
シンデレラはくりぬいたカボチャの馬車で家に帰ったのに、なんでわたしは歩きなのよ。しかもけっこう長いし……」
菖蒲はぶつぶつともんくを言いながら、きしむ木製のらせん階段をぐるぐるのぼっていました。
中央のふきぬけには、水晶の時計の針が宙にういて止まり、天井からのびる金のひもにつるされた大きな丸いはおもりは振り子のように、いろいろな方向にゆれていました。ゆかに描かれた七つ星の上にはルビー、トパーズ、エメラルド、ガーネット、サファイア、碧玉、オパール、めのう、アメシスト、アクアマリン、ラピスラズリ、オニキスといった宝石のピンが円形にならび、時おり、振り子の針がふれて倒れます。
「こんなさびしいおしまいもあるのね」と、菖蒲はため息まじりに言います。「ガラスのくつくらい落としてくればよかったかしら。だけど金の馬車とか、りっぱな身なりの従者とか、山あいの国はなかったし、盛大にむかえられず、見送られもしない、ひっそりおうちへかえりましたとさ、おしまい、なんてのもアヤメ、あなたらしくていいのかな」
階段を一周巡るたび、時間は菖蒲をおとなから少女の姿にもどし、アヤメはだんだん遠くへ、昨日までのできごとは、まるでどこかで聞いたおとぎ話のように思えました。でも菖蒲の中ではっきりと残っている、どうしても手ばなせない物語もありました。それを抱えながら上へ上へ。
いつのまにか、周囲はまるで古い洋館のような、あたたかみのある電球色に照らされ、ざらざらとした乳白の壁、なめらかな曲線の手すりがついた階段になっていました。しばらくのぼっているとこんどは、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ、カサカサ、ノッソリ、ノッソリ。
「ひさしぶりね、カメさん!」菖蒲はうれしそうにカメの横に腰かけます。「アリアドネとはうまくいってる?」
「も、ち、ろ、ん」カメはゆっくりこたえました。
「よ、か、っ、た」と、菖蒲は、ほおづえをつきます。「ねえねえカメさん。あのドアのむこうはとんでもない部屋だったのよ。わたしのお話、聞いてくれる?」
「も、ち、ろ、ん」
「じゃあまずはね、ドアを開けてすぐの場面からね」と、菖蒲は身ぶり手ぶりをまじえて、楽しそうに語りはじめます。「まっ暗で床がなくて、まっさかさまに落ちたら、魚や鳥や流れ星までわたしに話しかけてもうてんやわんや。でも、じつは落っこちたんじゃなくて……」
たいせつな宝物を箱にひとつひとつしまうように、菖蒲はアヤメの物語をありったけカメにつたえました——ただひとつをのぞいて。
「……それからここにもどってきたというわけ。どう、おもしろいでしょ」
「よくやった……うまくやった……」カメはうんうんうなずきます。
「ねえ、ねえカメさん。わたしよくやれたかな。わたしうまくできたかな」菖蒲はうつむきます。「だって好きな人に嘘の笑顔をしたから。だいじな人を傷つけてしまったから。自分に正直でなかったから」
「じゅうぶん」と、カメはこたえます。「よくやったさ」
「ねえ……ねえ、カメさん」菖蒲の目からぽろりと涙がこぼれます。「すこしだけ、泣いてもいい?」
カメはみじかい手で菖蒲の太ももをぽんぽんたたき、甲羅にこもります。
菖蒲はあふれるしずくをぬぐいませんでした。アヤメとアサゼル、ふたりのために。はなればなれだった水滴は、ほおをつたい、あごでまじわると、ひざをぬらすまでのあいだ、一緒になれたからです。ひとつ、またひとつ、菖蒲の中から王子さまが遠くなるほど恋しく、淡く薄れるほどにますます慕い、ミモザに分けた心とはまったくちがう、くだかれる心の痛みを全身に感じ、情愛が迫り、うなり苦しみます。悲しみは波のように岸壁にくりかえし打ちよせ、泡となり、好きな人への言葉を鉛色の冬海に散らしました。
「わたしも愛してる、アサゼル! あなたを深く……とっても深く。むりよ、あなたのいない日なんて考えられない。あなたをわすれるなんてできない。わたしの想いも、わたしの気もちも、わたしの心もすべて、あなたのもの。なぜうまくいかないの? なぜこんなおしまいなの? なぜわたしだけ? ああせめてどこか知らない村のおとぎ話にでもなればいいのに。そうすればいつまでもあなたのそばに……でも、こうするしかなかった。でもこうするしか」
おとずれた約束の時間。振り子はすべての宝石を倒し、ゴーンゴーンと、大きな鐘の音は鳴りはじめます。
「いかなきゃ」残らず涙を流した菖蒲はすっくと立ちあがります。「アリアドネ、帰り道を」
くりかえしアリアドネの名を呼びかけても、階段はなにも変わりません。まさかアリアドネはカメとの約束をやぶり、菖蒲を帰さないためにいたずらをしたのでしょうか。カメもなにごとかと甲羅から顔をだします。鐘は五回……六回……
「なんてやさしいアリアドネ!」謎を解いた菖蒲は顔をあかるくして言いました。「わたし、まちがってた。あなたがわたしたちのおとぎ話をおぼえてくれるというのね」
上階は光り、コンクリートの階段に変わってゆきます。カメとアリアドネにさよならと手をふり、階段を一歩また一歩と進み、あかりの灯る小さな図書館が見えてきました。
菖蒲は胸に手をあてます。鼓動は鐘の音とリズムをずらし、物語のおしまいをすこしでものばそうとしているようでした。
「わかってる。だけどアヤメ、あなたの選んだおしまいは、菖蒲が選んだはじまりよ」
夜半〇時。菖蒲は深呼吸して足をふみだすと、新しい冒険にずんずん立ちむかっていきました。
「菖蒲!」お姉さんはおこって言います。「あなたが本を借りたいってきたのに、窓ばっかりながめて。みんなでお昼ごはん食べる約束でしょ。もう帰るわよ!」
「ちがう、お姉ちゃん。わたし、ダルゲと西空のちぢれ羊を観察していたの」
「ここは四階よ、菖蒲。それにあなた、まえは金色の羊を探しにアルゴー船で宇宙イワシの大群とおどったとか、その前は牛車で北極熊と南極熊を見にいったとか、下の庭でジャックに巨人と鬼ごっこを誘われたとか、わけわからないことばかり。もうちょっとちゃんとした本読みなさい」
「ねむくなる本? わたし、お姉ちゃんみたいにおかたい子どもじゃないし」
「ほんとは読んでるくせに」
菖蒲はベーっと舌をかるくだすと、お姉さんも口をいーっとしてふたりは笑いますが、せきばらいが聞こえ、口に手をあてて目をあわせ、わきをつつきあい、ふざけます。何冊か本を借りて、受付のおばさんにバイバイと手をふり、仲よく手をつないで図書館をあとにします。
こうして、干しわらになった王子さまを助けるアヤメの長い旅はひっそり幕を下ろしました。
おはなしのおしまい

ビルのすきまにわきあがる雲の峰、アスファルトにゆれる逃げ水、大きなケヤキ並木のそびえる大通りでは、セミたちがジージーやかましくさわいでいました。ベビーカーをおす母親と、楽しそうにはしゃぐ男の子、写真を撮る外国の旅行客、足早にゆきかうオフィスワーカーの中に麦わらぼうしを頭にのせた長い黒髪の女の人が立ち止まり、肩にかけたトートバックからハンカチを取りだして、疲れた顔にたれる汗をぬぐい、「あー夜ごはん、なんにしよ……」ひとりごとをため息まじりに、歩きだしました。
おとなになった菖蒲は、干しわらになった王子さまをすっかりわすれ、どうにも思いだせない夢のように、もやもや悩むことはありませんでした。そのかわり、もみくちゃのまいにちは無色透明の夢を、たいくつに支配された生活は、ありふれたまんぞくをあたえました。
学校の勉強はまあまあ、お姉さんとのおしゃべりやときどき学校の友だちと遊んだり、気むずかしい教師をうまくかわしながら学校を卒業して、新しい職場仲間と知りあいました。あの図書館にはなんどか足を運び、窓ものぞきましたが、なんでもない中庭でした。ひとつ変わったのは、アヤメに話しかけるクセをやめたくらいでしょうか。
「あら、菖蒲ちゃん。ひさしぶりねぇ」古い木造の甘味処からでてきた老婦人は菖蒲を見つけ、やわらかな笑顔で手をふります。
「たまにはうちでおやつ食べてきな」
「おばぁ、ありがとう。こんどお姉ちゃんさそってラーメンとあんみつ食べにいく!」
菖蒲はおばぁに手をふりました。
「図書館の帰りにお姉ちゃんと、どら焼きを半分っこしたっけ」
大通り中央の緑道には陽を浴びたブロンズ像が子どもを見守る母親のような強くしなやかに立っていました。菖蒲はあこがれをいだいてながめ、「またあした!」と、あいさつをします。
すると、ブロンズ像は「おかえりなさい」と、こたえます。
骨董品屋のひさしの下でぐったりしているシバ犬を見つけ、ひざをかがめて頭をなでます。
「ねえシバ、元気にやってる?」
「にゃあ」あまりにヘタなネコの鳴き声が聞こえ、菖蒲は思わず顔をあげると、街路樹からさわやかなあまい花のかおりがします。花の咲いていないタイサンボクの下にキジ三毛ネコを見つけました。
「あたりまえよ。だって夏のおわりだもの」と、菖蒲は言います。
「あたりまえ? わすれちまったのかお嬢ちゃん。にゃつのつぎは春だぜ」と、キジ三毛ネコは菖蒲のわきをわざとらしく体をこすりつけて走りぬけ、図書館のあるビルに消えました。
菖蒲は追いかけるようにビルへ、左右にガタゴト開く古い自動ドアを通ります。
「ひさしぶりだね、菖蒲ちゃん! お姉ちゃんは元気かい?」
声をかけたのは、ビルの監視室から顔をだす、大きな体の警備員でした。
「こんにちは、ビルのおじさん!」菖蒲はあいさつをします。「姉は隣町の病院で働いています」
「そうかい。しばらく見ないから引っ越したのかと思ったよ」
「いえ、大きな図書館にいくようになったので」
「まあ、ここはせまいからね。なんかようじでもあるの?」
「たまにはビルのおじさんに通行証をもらおうかなって」
「あはは。じゃあ菖蒲ちゃんのひろったガラスと交換だね」ビルのおじさんは、りんご味の飴をひとつ菖蒲にわたしました。
「せっかくきたので、ちょっと図書館によっていきます」菖蒲はビルのおじさんに手をふり、エレベーターの丸ボタンを押してすぐ「左!」と、指差します。
左右二基あるエレベーターのうち、先に到着したのは左でした。「きょうはラッキーな日決定ね」
かごに入ると五階のボタンがパッとひかり、ゴトンと音を立てて、もちあがりました。
「これ、まだあったのね……」菖蒲はかごの中に貼られた図書館のカレンダーや白ウサギのイラストを見ていると、なんだかまるで大好きなお姉さんと手をつなぎ、そわそわする少女がすぐそこにいるような、ふしぎな気分になります。
「出会いはいつだってふしぎなものさ、ミス・アヤメ」と、シロウサギは言います。「そして、再会はおどろきなんだ」
エレベーターのドアが開くとすぐ横に新聞や雑誌の閲覧席、その先につるつるとした緑色のゆかに天じょうの低い部屋はありました。だれもいない貸切の本屋さんみたいな図書館です。
「うわあ、なんにもかわってない」
菖蒲は煮つめたような濃い紙のにおいをくんくんかぎ、児童書コーナーへと足をむけます。入り口すぐ左には歴史、そのとなりの書棚に地理、社会、植物や動物の図鑑、むかいに芸術の書棚があります。右手には事務室と受付カウンター、その前には大きなスツールソファーと紙しばいや絵本の書棚、奥は児童小説、窓際の低い書棚に絵本のコーナーです。バッグと麦わらぼうしをソファーに置き、紙しばいをめくったり絵本を開いたりします。本の背に人差し指をのせ、「この本好きだった」とか「これは王子さまとお姫さまの話ね」とか「これはいまいちな冒険活劇」とか「何回も読んだ漂流記ね」とか「これは海賊がでてきてちょっとこわい話」と、本にふれさえすれば、つぎからつぎへと菖蒲の中で物語がうごきだします。おやすみしていた空想や夢たちは、やかましく鳴りおどる目ざまし時計でベッドから飛び起き、さあ早くとパジャマ姿のアヤメの腕をつかみ、カーテンを思いきりひいて、たいくつ星からつれだしました。たくさんのおとぎ話や物語はアヤメの自由な発想で新しい領域にうまれかわって、それはどこまでも広がり、星座のように結ばれもします。
空にうかびながら海でおよぐ潜水宇宙服のお話も、金色羊を探すため帆船アルゴー号にのってイワシの大群とダンスするお話も、夏野菜と冬野菜がオーロラスープを食べるお話も、赤道を牛車で行き来する仲良しの北極熊と南極熊のお話も、巨人と小人が中庭でかくれんぼをしていた雲の上にまでとどく豆を見つけて旅するお話も、菖蒲の王国ではなんでもできるのです。そう、信じていればなんでも!
ただ、菖蒲の指は一冊の本で止まりました。
「干しわらになった王子さま? そんな本、あったかしら……」
菖蒲はくつをぬぎすて、書棚と書棚の特等席にぎゅうぎゅう体をつめてすわると表紙を開き、ページを繰りました。
山あいの国の王子さまは邪悪な影と戦うため、わら束に変えられてしまう章からはじまります。もとの姿にもどるためには、べつの世界に住む少女が扉のない中庭の井戸でくんだ水を王子さまのくちびるにそそがなければなりません。それを知ったひとりの勇敢な少女は、王子さまを助ける冒険にでかけ、やっとのことで井戸の水をくみました。邪悪な影は少女を襲い、井戸の水がはいった小ビンはわれてしまいます。少女はのこった水を口にふくんで王子さまにキスをすると、もとの姿にもどり、ふたりは力をあわせ邪悪な影をたおしました。
「とても強い女の子ね!」
菖蒲の目は夢中で文字を追います。
闇を打ちやぶったふたりは山あいの国へ帰り、みんな幸せにくらしました。ただし、いつまでもではありませんでした。なぜなら大きくなった少女はのこした約束を守るため、もとの世界にもどらなければならなかったからです。大好きな王子さまといつまでもいたいのに、帰りの時間はやってきて、小麦畑の風車は少女を連れ去り、物語はそこでぷっつりとぎれていました。
「女の子がだれにも助けられず、いきなりおしまいって、なんてへんてこなのかしら。のこりもぜんぶ白紙。それに女の子の約束って……」
「鏡よ鏡。このおはなしのおしまいはなあに?」
窓のむこうでアヤメが菖蒲にそう問いかけた時、いたずら好きのだれかさんは息をフッとふき、そよ風は内階段から図書館の入り口へ、菖蒲の手にある本の白紙ページは紙ふぶきとなって宙を舞います。隠された物語を見つけた菖蒲はつづきを読みました。
お姫さまが連れ去られたあと、とつぜんふってきたどしゃぶりの雨は大地をぬらし、王子さまは鉛のような雨つぶに打たれたまま、じっと立ちつくしていました。
「笑え、アルビレオ」自嘲するように王子さまは口を開きます。「彼女は愛想つかしただろうな」
「姫君は王子の助けを待っているのではありませんか」と、アルビレオは言います。「だから、けっしてあなたにだけは手をふらなかった」
「そんなのわかっている!」
「わかっているのであればなぜ! なぜ、いつまでもぬれそぼり、うなだれているのですか! 姫君は苦しみを耐え、中庭で井戸の水をくんだのではありませんでしたか。あなたのために、あなただけのために! 死せる王子のくちびるをいやしたあの水は、うるわしい女の涙なのです。王子、あなたがすべきは姫君のため、道なき道を、いばらやアザミに身を投げいれねばならぬとも、顔をあげ、前に進むことではありませんか」
——いくら望んでも、すべてをあたえられはしないのよ。だから、こぼれ落ちてしまうほどちいさな赤子のような手の中で、せいいっぱいしてあげようと。
「わたしは」と、王子さまは両手を見つめ、「彼女をこぼしてしまうほど、ちっぽけな手なのだろうか、愛する人に望むものをあたえられぬほど、みじかい腕だったか」
大きな雨音。しばし沈黙のあと、顔をあげ、「いいや、ゆかねば」。
遠くで白鳥がわたしを呼び
わたしはその声を知っている
天地の間に隠された
白くほころぶ苹果の花
過ぎさる星々 明けゆく群青の空
わたしは彼方をさすらい
ついに見いだす
湖水におどる美しきその姿
はためく春雪の羽つかみ
なめらかなうなじに鼻をよせ
ぬくもる吐息は耳をとかし
うす桃色のくちびるからほとばしる
甘い約束の言葉を内に秘め
いつまでも いつまでも
ともに摘もう
銀の苹果と黄金の苹果
「アルビレオ、おまえが友でよかった」
王子さまは急いで城にもどり、王さまの前でひざまずきます。
「王よ。ふたたび国を旅立つこと、どうかおゆるしください!」
王さまと王妃さまは、ずぶぬれの王子さまにおどろきながら、こうたずねました。
「なにゆえか」
「虹の姫を取りもどすためです。王よ、いつ帰れるのかわかりません。いえ、帰ることはないかもしれません」
「息子よ。安寧の契約ゆえ国をはなれる前に話したなぞかけをおぼえているか」
「はい。芯のないりんご、扉のない家、鍵のいらない宮殿。これらはおさないわたしの耳もとで毎夜、母上の歌う子守歌です。わたくしは愛と信頼こそがなにより強い約束であると学び、影をうちやぶる示唆をえました」
王さまはまんぞくそうにうなずき、王子さまに七色の指輪をわたします。
「むかし、ヘレムはグレエンに運命を断ち切る長剣アトロポスを、わたしにこれを託した。この指輪はあらゆる領域をまたぐ虹の女王の認印指輪だ。王として、父としておまえに命じる。これを持ちすぐにゆきなさい。すこしも遅れないように。たがうことのないように。そしてなによりも信じ待つ虹の姫をしっかりつかみ、その愛にこたえるように」
王子さまは天馬アルビレオにのって月にむかいました。記憶の断片を採取をしているメレに会うと、こう言います。
「どうか、わたしに記憶集めをおしえてください! なんでもしますから」
「おしえるのはかまわない。だがいったいどうしたというんだい?」メレは聞きます。
「姫のなくした記憶がほしいのです。手ばなしたすべてのおとぎ話を」
「だれかの記憶がほしいだって!」メレは目を大きくしてこたえました。「はじめにひとつだけ忠告しておこう。だれかの記憶を選び取るなどぜったいできない。流れ星に名が書いてあるわけではないし、記憶をのぞくこともできないのだから。それにまわりをごらん。記憶の断片はどれほどあると思うんだい。しかもああして流れ星は絶えずふってくる。落下した記憶のかけらを採取するのもむずかしい。ためしにさわってみるといい……」
それから何年も王子さまは休まず記憶を探しました。無数の断片から、たったひとつの宝石を見つけるために広大な月をすみずみまで歩きまわり、落ちる流れ星を見つけては走ります。しかしどれもちがいます。お姫さまの記憶ではないのです。王子さまはあきらめませんでした。お姫さまを愛していたので過ぎ去った年月はただ数日のように思えました。そんな王子さまの姿にバクは心をうたれました。
みんな、お姫さまの帰りを待っていました。セイトスズメ、フクロウセンセイ、ハタラキアリ、海の女王テティス、ジョナ、わんぱく魚、イアソン、シバ、バンドウ、スルフファー、キタール、メレ、アルネヴ、サトウ、アシェレ博士、モルト、アルビレオ、山あいの王さまに王妃さまと国民、そして父と母のリリィとグレエンも。
そしてついに、その日、その瞬間はやってきました。
月に落ちる流れ星はピタリとやみ、王子さまは静寂の宙をあおぎます。しばらくして星がふたつ、弧をえがきます。遠くから聞こえる翼のはためきは、だんだんとちかづき、虹色の尾をひく白鳥が黄色の小鳥にみちびかれ、こちらにやってきたのです!
永い永いわたりを終えた白鳥と王子さまの再会を祝福するため、真珠のような星々は光の帯となり、宇宙はオーロラを全体にかざります。月は記憶の断片に呼びかけると色彩を思いだしていっせいに発光し、パイプオルガンの音色を遠くまで響かせました。
メレはあまりの荘厳な光景に、言葉をうしないます。
王子さまは胸に飛びこんできたかがやく白鳥をうけとめ、「時がこないように」と、願いをこめます。すると白鳥は王子さまの手の上でイリスの認印指輪とまじりあい、金の指輪に昇華します。
王子さまはメレに礼をいい、お姫さまのもとへ馳せむかいました。
軽やかに打つひづめの律動
白馬のいななきは魂を癒すしらべ
あなたの知らせは春のうたげのよう
山あいにふくさわやかな緑の風は
色あざやかな思い出とあなたの香りを運び
かわいた心でほおを濡らすわたしをついに休ませる
ああ わたしの王子さま!
わすれていた ときめく想いを胸に
待ち焦がれた冬のおしまいに
あなたを愛そう
どこまでも……どこまでも……
「アヤメがのみこんだ棘をわたしにもわけてほしい。お願いだからどうか、ひとりで行ってしまわないで」
「ねえどうしよう、王子さま。あなたの本が雨でびしょぬれ」
「もう、いいんだよ」
「わたしね、やっとわかったの、アサゼルの気もち。あなたがどんな思いで干しわらとなっていたか。信頼して待つのはこんなに勇気がいるなんて。そう、干しわらだったのはわたしよ。あの時、気づいていれば、素直にあなたと」
「ううん。わたしはそんなアヤメが好きなんだ。そんなアヤメをいつまでも知りたい。だから、わたしたちの物語のはじまりは」
アサゼルは菖蒲の両手を取り、優雅に立ちあがる彼女の耳もとで、いつまでもおしまいのない愛の約束を告げます。ふたりは見つめあい、きらめく星を瞳にたたえた菖蒲は、おだやかな笑みをうかべ、すこしもまよわず、こうこたえました。
「はい。」
王子さまは金の指輪をお姫さまの左手薬指に、お姫さまは強くあたたかな王子さまの胸にその身をゆだねるのでした。
少し長めの追伸

秋も深まり、だんだんと雲は高く、山から流れるひんやりした空気は森を茜やオレンジ、黄色に染め、やわらかな陽のさす湖では水鳥たちが旅立ちの準備であわただしくなりました。はらはらと葉の落ちる色鮮やかな木の下で、親子はピクニックブランケットを敷いてランチを楽しみ、子どもたちはひろった木の実をポケットにつめ、こちらにかけよって収穫をすこしばかりわけてくれるのです。
そんな時、母と過ごしたとくべつな時間を思いだします。
夜寝る前、ぬいぐるみを抱いて横になるおさないわたしのそばで、数々のおとぎを話してくれました。なかでも干しわらになった王子さまのお話は週はじめのお楽しみで、いちばんのかがやきをはなつ物語でした。わたしは目をキラキラさせ、多くの親をこまらせてきた、あの問いかけ、「ねえなんで、井戸の水をくむのに王子さまの記憶の結晶がひつようだったの?」とか「ねえなんで、王子さまはアヤメのキスでもどったの?」など、身をのりだすように、「ねえなんで?」をくりかえしていると母はわたしの頭をなで、こう言いました。
「サラサはどう思う? あなたの物語を聞かせて」
そうしていつのまにか、わたしの夢の王国へ母を招待していたのです。
もう少し大きくなると母は恋の話やほろ苦い話もまじえ、ドキドキしたりほおを赤らめたり、涙したり、あたたかな気もちになったものです。きっと、生きてゆくためのむずかしい知恵や道徳を離乳食のようにあたえてくれたのでしょう。
おとなになったわたしは大好きな母のおとぎ話をまとめて文字に起こし、本にしようと考えました。それが『扉のない中庭』です。これからあとがきに変えて、物語のおしまいのちょっぴり先をみなさんにおつたえしたいと思います。
まず、ネコ座の由緒ある王族モルトについて。彼は山あいの国にはとどまらず、気ままな旅を楽しみながら自分の武勇伝を各地のネコに大げさに語り歩いているようです。ときどき、うちへ帰ってきては母のベッドで寝ています。
スパルトイ軍団を倒した英雄グレエンは畑仕事や家や家具の修理をするなんでも屋さんとして、みんなからしたわれています。アヤメがいなくなった時はものすごい落ちこみようで、リリィはそれはそれはものすごーくめんどくさかったって! そんなリリーフロラはやさしいグランマです。リリィは今もひとり娘の服をすべて準備する一流の仕立て屋さんで、わたしは母の服をおさがりでもらうほどよ。
山あいの国で手をつないで歩くカップルを見たなら王さまと王妃さまだ、というほど有名な二人について。王妃ユリーフロラは、ふたごの男の子をさずかり、わたしの幼なじみです。王さまをやめたお城のピートおじさんは湖畔の新居を探していますが、子育てにいそがしく、なかなかよい場所は見つからないと、なげきながら喜んでいます。いつかすてきなお家に引っ越せますように。
ハタラキアリたちのいる興廃の丘は菖蒲女王の美しい庭園に変わりました。丘の上に建つ邸宅には執事となったフクロウセンセイやセイトスズメたちがせっせと働いています。アルネヴやおじぃやアシェレ博士からたくさん贈られた骨董品の管理はたいへんだってフクロウセンセイはぼやいていたわ。彼らは女王のためにもっと魅力的な庭園を広げるのが目標なんですって。いったいどんな庭になるのでしょうか。
おばぁとおじぃの家には家族で夏休みにでかけます。わたしは父とおじぃの島でキャンプを楽しむけれど、母はおばぁのとってもせまい待合所にわざわざ泊まるの。どうやら彼女はせまい空間にはさまると落ちつくみたい。おばぁには姉妹が何人かいるらしくて、いろんな領域でパスタ、クスクス、シュペッツレ、ペリメニ、ラーメン、ビーフン……いろんな麺のお店を営んでいるらしいわ。もしかするとあなたの街におばぁはいるかもしれませんね。おじぃとシバはアルゴー船で新しい冒険をする予定で、わたしも誘われています。時空の穴をくぐり、宇宙創世の領域にある不可知の色を探索しにいくのだそう。
メレは月で記憶採取を続けています。きらめきを取りもどした断片を加工するのはわくわくするとはりきっていました。「二度あることは三度ある」というシバの金言をたいせつに、記憶には名前がないから見つけられないとは言いません。それなので、ぜひみなさんも月に好きな人の記憶を探してみるのはいかがでしょうか。
アルネヴはサトウといろんな星で星間行商をしています。アヤメをビジネスパートナーにする夢はついえたので、新しい出会いをもとめているの。ティータイムをことわらない女の子ならいつでも大歓迎だそう。いつか、ミセス・レイラとの恋物語も書けるといいな。
干しわらの王子さまについて。父に「なぜわらじゃなくって干しわらなの」って聞いたら「びっくりするほどパッサパサだったから」ですって。わたし、おなかを抱えて笑ってしまったわ。そんな父アサゼルはいつもユーモアのある王子さまです。この物語を『干しわらになった王子さま』にしようか相談したら、父は出窓のソファにはさまり本を読む母をいとおしそうな目で見て、「その本はもうなくなってしまったんだよ」と、小声で言っていました。
みんなのお話しはこれくらいです。もちろん、もっといろんな話を聞いたり旅して見たすてきな物語を書きたかったのですが、それではいつまでも終わらないので、またいつか。山あいの国の歴史、王子さまの旅、おじぃとシバの出会い、扉のない中庭のちかくまで行った大冒険家イアソンの行程、菖蒲とアルネヴがバザールに行くまでの星旅行。とってもおもしろいのよ。『正直でいたってまじめなうそつき像』を手にいれたアルネヴとアヤメはクノッソスの迷宮からでられなくなった話とか、宇宙一渋い流星の渋茶を飲んでから、上をむいて三回願いをとなえるとなんでもかなう話とか……
最後に二つ。ひとつはミモザのこと。
母はミモザについてあまり話したがりません。金と銀のバングルを知ったのもさいきんだし、父もウエディングでつけたのを見たくらいだそうです。父と母はアルビレオをつれて遠くにいます。母によると『クスノキに宿る黄色い小鳥を探す旅』であると。先日とどいた母からの手紙に、もうすぐ帰れると書いてあったの。もしかすると、みなさんがこの本を読んでいる時にはわたしもミモザと会っているかもしれません。すごく楽しみ。やさしいママ! ミモザのことを書いてごめんなさい。どうかおこらないで。
もうひとつはそんな大好きな母のこと。
母は山あいの国の図書館に収蔵された本の分類、古文書や巻物の修復、筆写の仕事をしています。
「お宝を見つけたの!」と、ほこりかぶった書物をうれしそうに家に持ち帰っては読みふけり、忘れられた人々のおとぎ話を想像しながら、アサゼルのそばでいきいきと話しています。そんなふたりを見ていると、新しく広げた領域を旅する永遠のお姫さまと、追いかける王子さまのように見えるのです。
最後の最後に。ぜったいおしえてくれない『いつまでもおしまいのない愛の約束』について。
「ねえママ、アヤメは干しわらになった王子さまから耳もとでなにを告白されたの?」
母にくり返し聞いても、答えはいつもおなじです。
「いままで聞いたことないくらい、とても甘くとろけるような愛の約束を耳もとでささやかれたわ。あとは秘密! ぜったいおしえない、もうおしまい」それから目をほそめて、「サラサも王子さまにささやかれるのよ。そうしたらわたしも聞くけど、それでもいいの?」
晩秋のある日、湖畔のガゼボにて
父アサゼルと母アヤメへ
たくさんの愛と感謝をこめて
あなたの娘サラサフロラより
扉のない中庭 設定

扉のない中庭 設定
登場人物のこと一

扉のない中庭〜設定①〜
登場人物のこと二

扉のない中庭の〜設定②〜
登場人物のこと三

扉のない中庭〜設定③〜
ゆびわのこと

扉のない中庭〜設定④〜
つるぎのこと
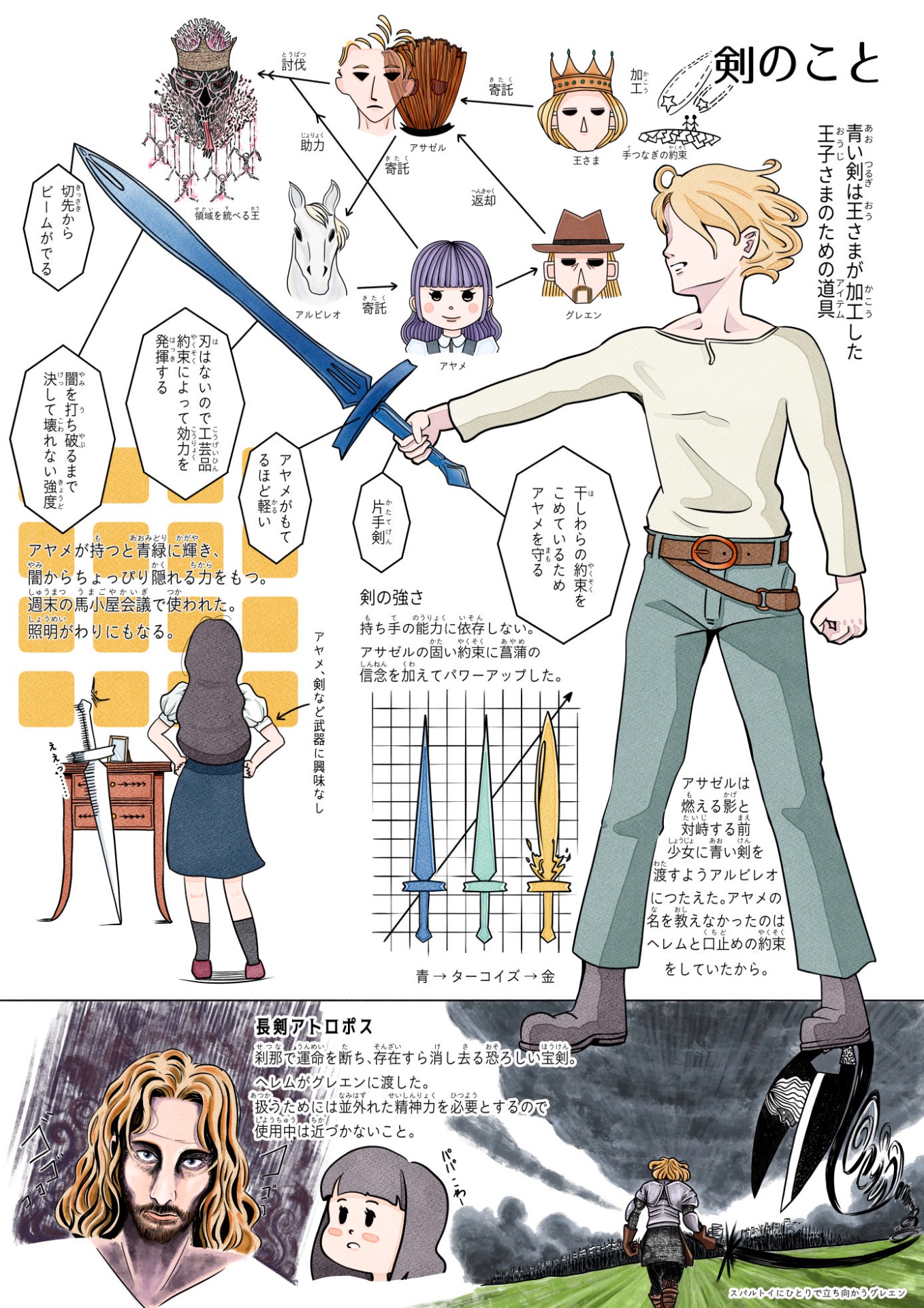
扉のない中庭〜設定⑤〜
たびじのこと
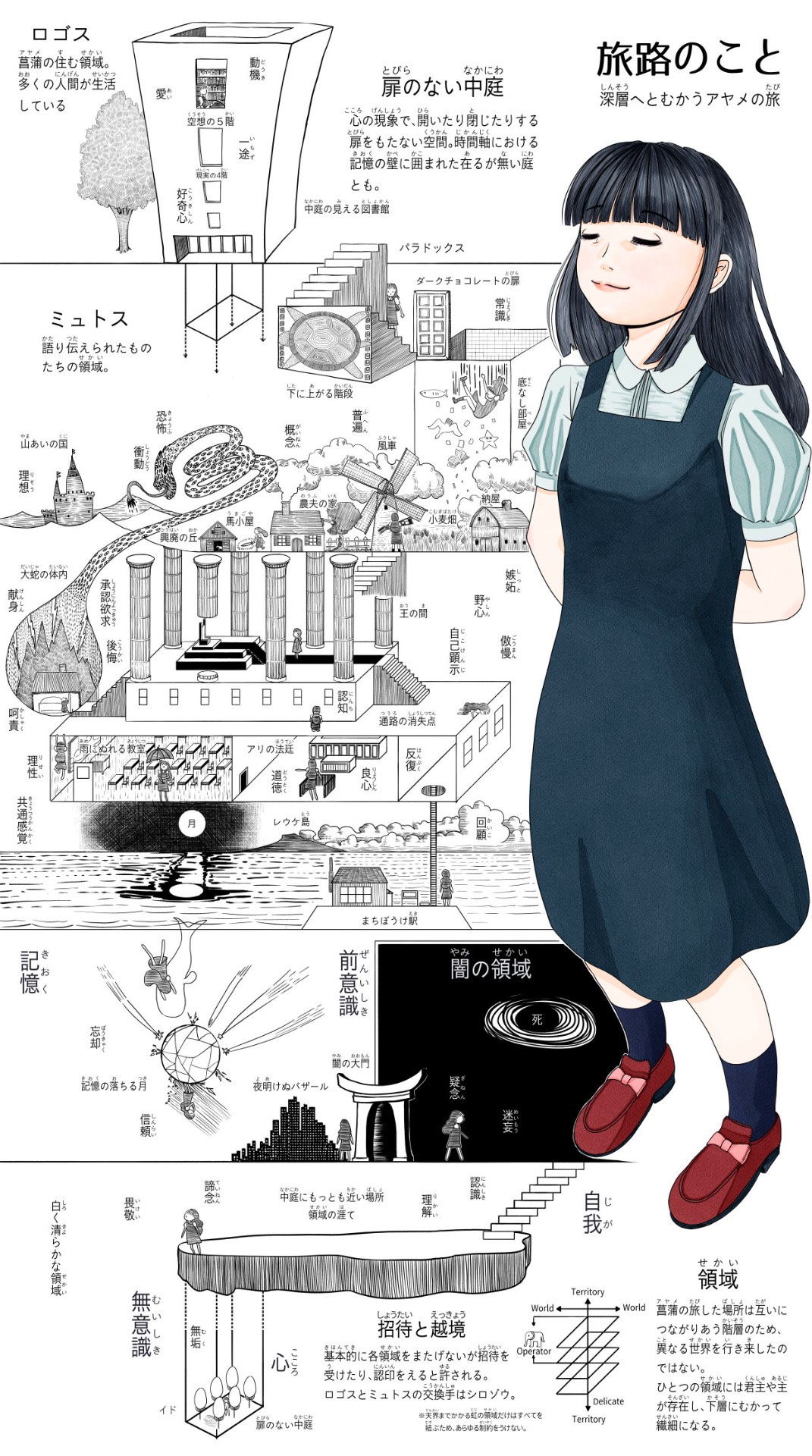
扉のない中庭〜設定⑥〜
やくそくのこと

扉のない中庭〜設定⑦〜
イメージ画のこと①
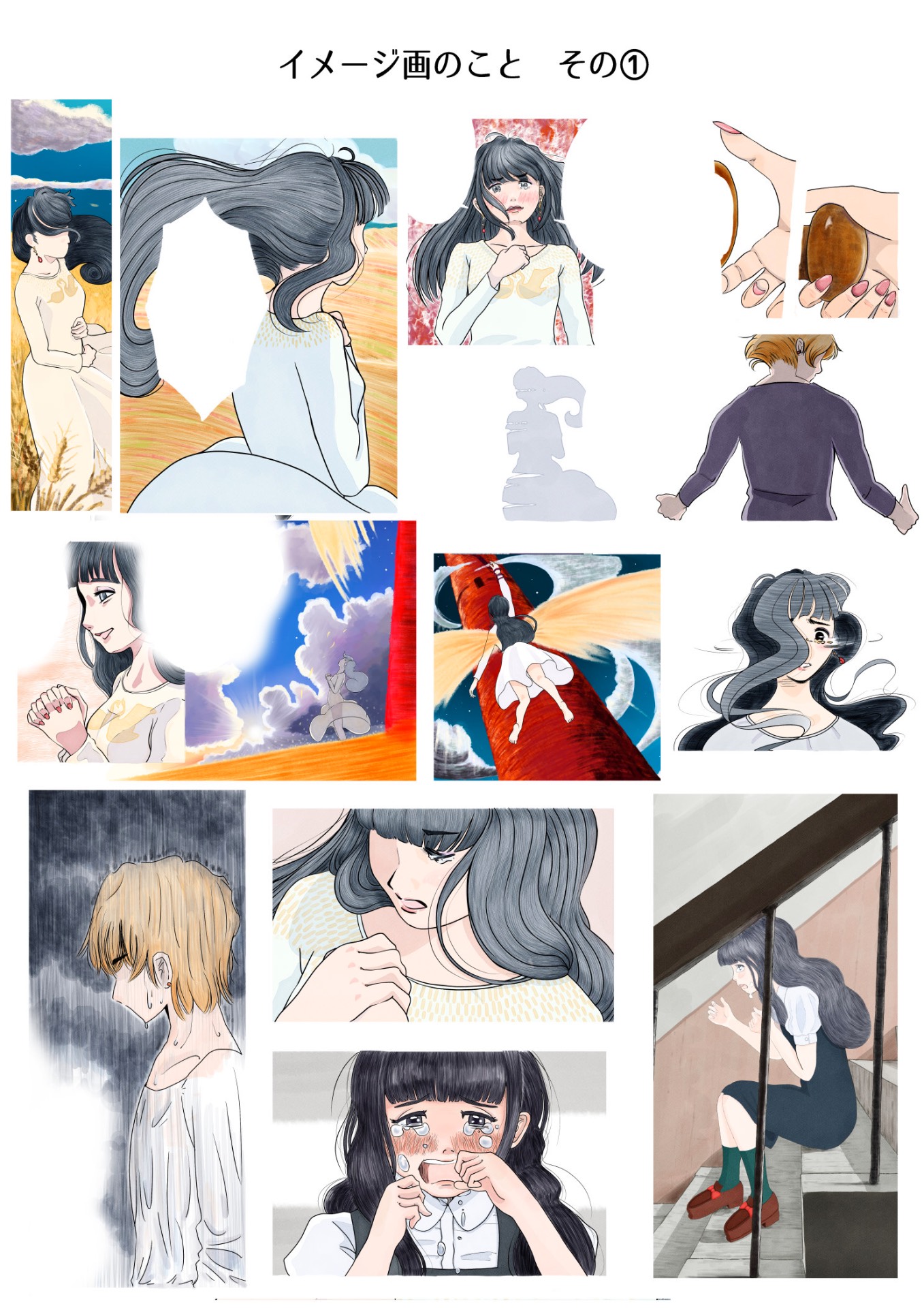
イメージ画のこと①
イメージ画のこと②
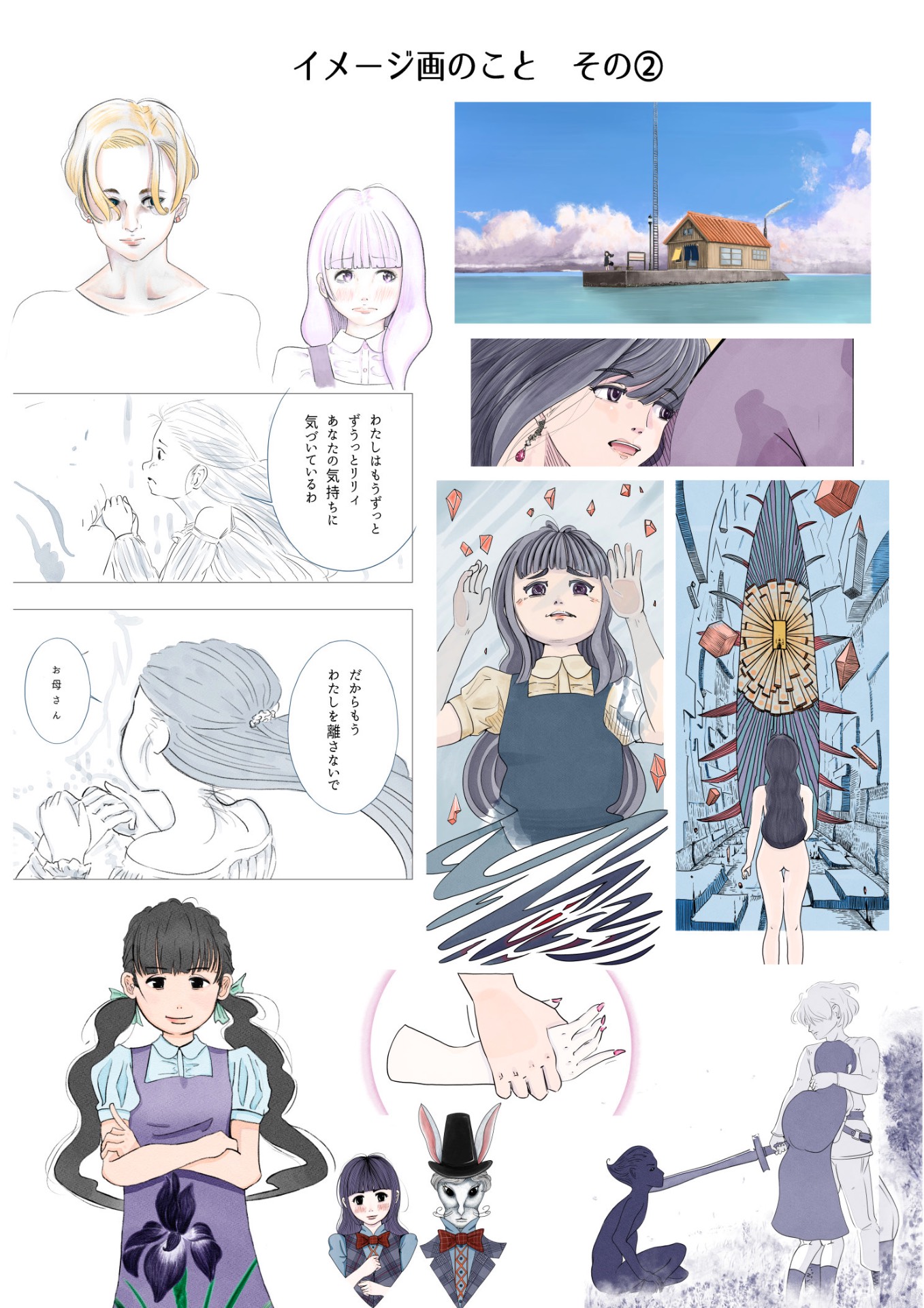
イメージ画のこと②
イメージ画のこと③
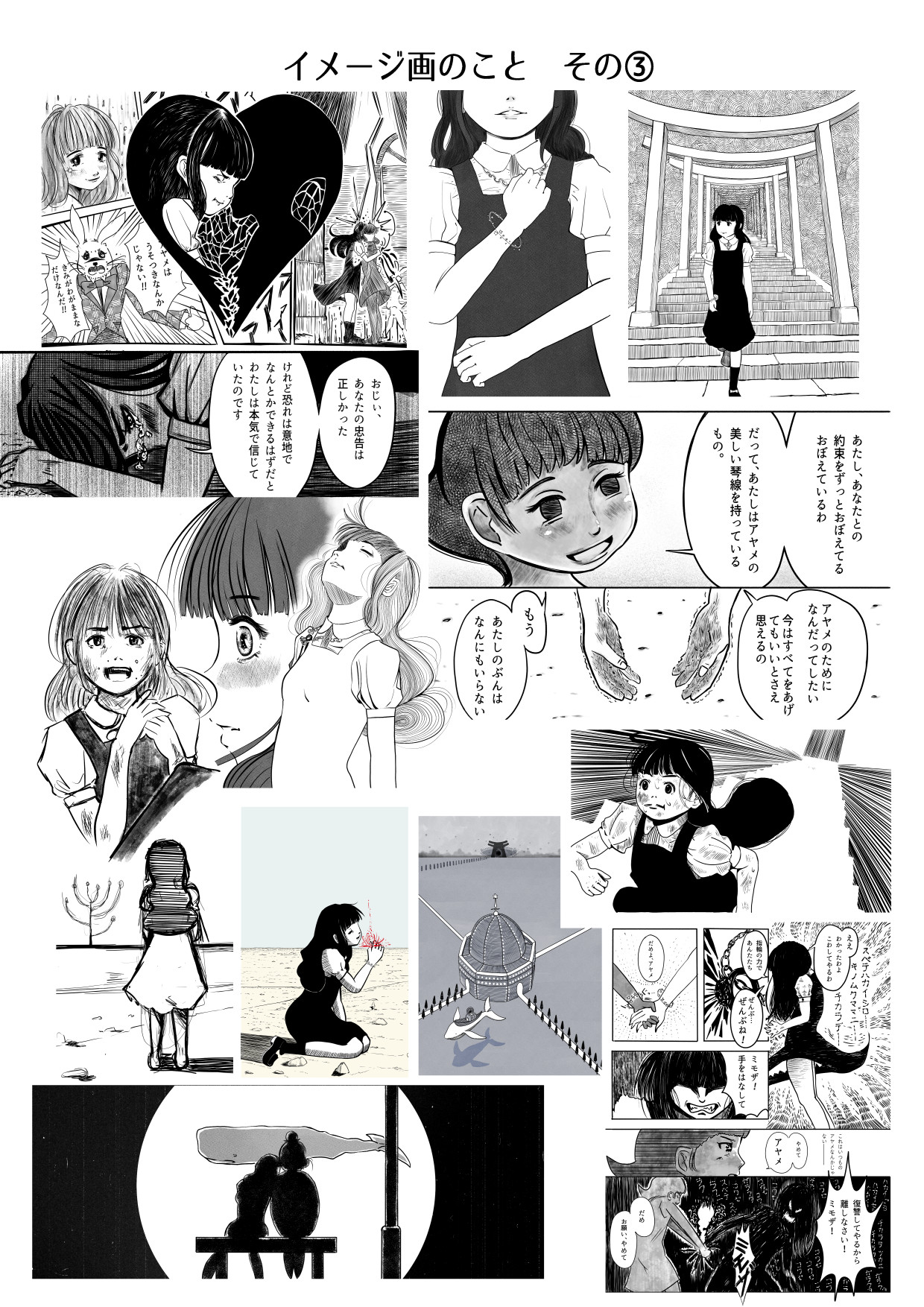
イメージ画のこと③
扉のない中庭
主人公の菖蒲は実在する養女がモデルです。
本や芸術を愛し、聡明な、いつも前向きで、母親としても強く、リリィの言葉を借りるなら境遇が力を与えたような、尊敬する美しい女性です。
彼女との会話はいつも新しい領域を開くように、たくさんの知識や知恵、アイディアをもらえます。
かつて、ひとりのちいさな女の子と夢の国のプリンセスについて話していたとき、日本には西洋的なプリンセスがまだいないことに気づき、もし東の最果てにあるちいさな島国の女の子が選ばれたら、を出発点に心と約束を題材としたお話を書きはじめました。できるだけつじつま合わせをしないよう注意しつつ……
一途な少女菖蒲はアルビレオのいうとおり、はじめから王子さまだけを想い、彼だけのために人生の選択をしていきます。闇との戦い、ミモザとの関係、扉のない中庭での水くみ、彼とわかれる決定すらも。
「干しわらだったのはわたしよ。あの時、気づいていれば、素直にあなたと」
何年も大人を経験し、理想の王子さまを想うあまり、あなたの気持ちを考える余裕がなかった、と菖蒲は気づきます。
それに対しアサゼルは、「そんなアヤメが好きなんだ。そんなアヤメをいつまでも知りたい」と答えます。
信頼や待望といった、この時代には語られない、古い男女の愛の物語であり、男女の境界の揺らぐ危機的な時代がゆえにファンタジーなのです。
母に、この物語をささげます
心からの敬意と感謝をともに
2018ー2024
※1『Twinkle, twinkle, little star』Jane Taylor
※2『月ぬ美しゃ』八重山民謡《一部改変》
※3『ポラーノの広場』レオーノ・キュースト・訳述 宮沢賢治
※4『I Will Give my Love an Apple』英国民謡
※5『長くつ下のピッピ』アストリッド・リンドグレーン・大塚勇三訳 岩波書店
※6『きかんしゃ やえもん』阿川弘之 岩波書店


