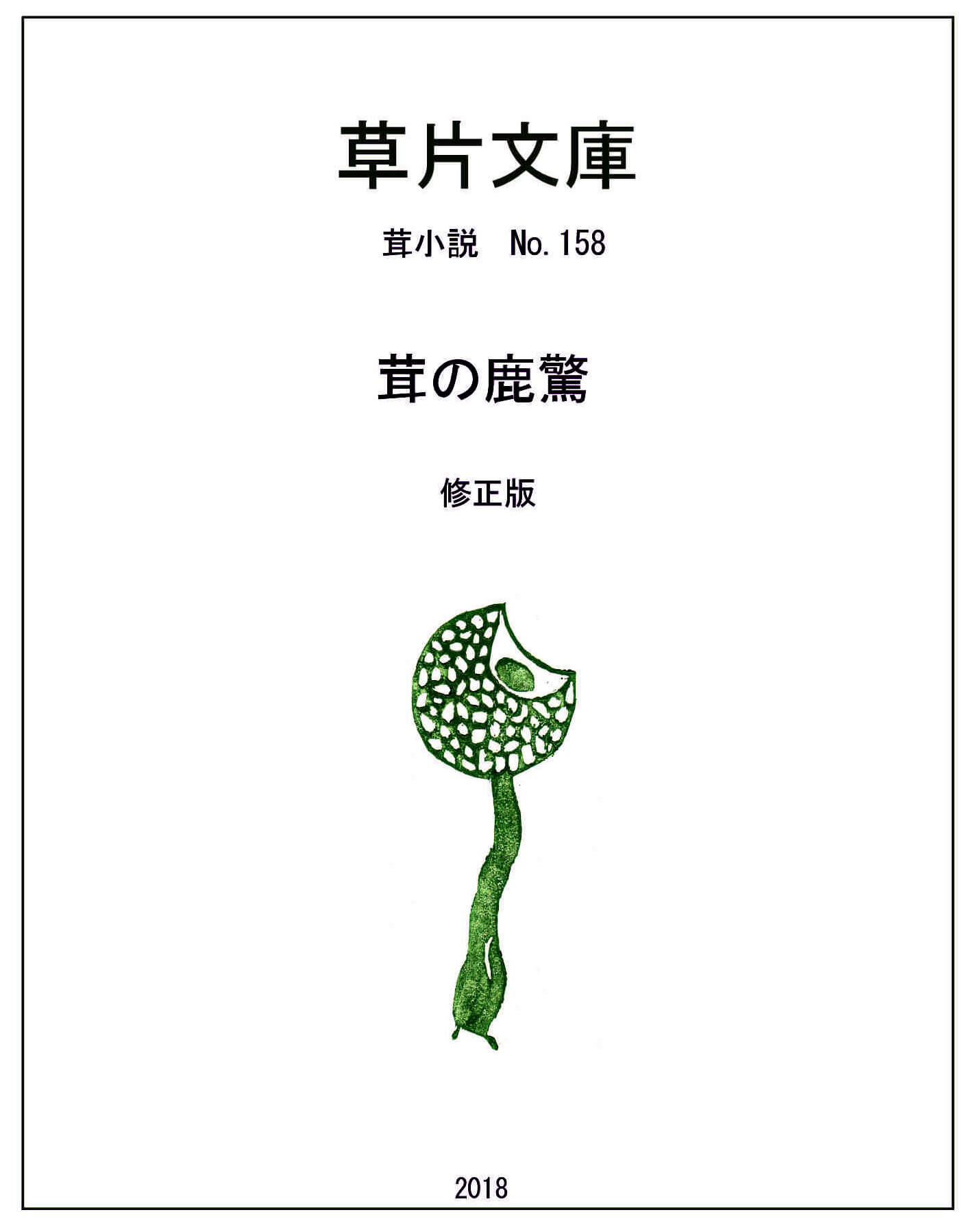
茸の鹿脅(かかし)-茸書店の物語5
茸の不思議物語です。縦書きでお読みください。
昨夜、遅くまで同級生と飲んでしまった。起きたのは八時である。若い人にとって八時に起きるのは当たり前かもしれないが、いつも二時や三時に目が覚めてしまう私にとっては、しばらくぶりの朝寝坊である。
充分寝たにしても、たくさん飲んだ次の朝は必ずしもすっきりしていない。ヨーグルトを飲んで朝食はおしまい。うだうだしているうちに、十時になってしまった。さて、何をしようか、昼飯はどうしようなどと考えていると、十一時になる。
カレンダーに目がいくと、今日は八日であることに気がついた。語草片が出る日だ。神田の草片書店に買いに行こう思い立った。まずランチョンによってからだ。
ランチョンでは軽くと思ってオムレツを食べた。
ランチョンをでて、草片書店の木の扉を押すと、中にオンナ性客が二人、中央のテーブルで図鑑を見ている。奥のデスクには珍しく店主と妹がいる。
地方誌のコーナーにいくと、第五集が出ていた。表紙の絵は私でも知っているスッポン茸である。虻が青緑の粘液に覆われた頭に取り付いている。この茸の類は臭い匂いで蝿などを呼び寄せ、粘液に混じった胞子を虫に付着させる。それで胞子が運ばれるという仕組みを持っている。
本のタイトルは茸の鹿驚とある。どのような意味なのだろうか。
ともかく、本を持ってデスクにいった。主人の笑子さんが、あいそよく「いつもありがとうございます」と受け取った。
「お恥ずかしいのですが、このタイトルなんと読むのですか」
笑子さんが答えようとしたその前に、妹の泣子さんが「それ、かかしって読むのです」と笑顔で教えてくれた。
「鹿が驚くで、案山子ですか」
「ええ、今ではほとんど使いませんね」
「鹿がそんなに出たんですかね、想像できませんね、案山子は鳥のためと思ってました」
「そのころ鹿が田んぼに水を飲みに来てたのかもね」
泣子さんがそう言うと、お姉さんが本を私に渡しながら、
「いい加減なことを言っちゃだめよ、なにかに書いてあったの」と言った。
「へへ、知らない」
妹はそう言って笑っている。まあ田んぼの水を鹿が飲みに来ることは無いだろう。本当の語源は分からない。
今日は他の本屋に行く気がないので、草片書店の棚を隈なく見て回った。最近は茸ガールとか言って、茸に興味のあるオンナの子が増えているようだ。そのせいか、しゃれたイラストや可愛らしいイラストの茸の本がある。猫から茸が生えている奇妙な本もある。それを見ていたら、泣子さんがそばにきた。
「その本は今一番人気のあるイラストレーターですよ、ヒグチユウコさん」。そう言って自分から本を広げて見せてくれた。色も綺麗だし、面白い絵だ。
「イマジネーションが広がりますね」
「そうでしょう、言葉の世界も面白いけど、絵だとぱっと、頭に入ってきて、刺激しますものね」
泣子さんはなかなか言葉の表現がうまい。だけど、やっぱり、購入まではいかない。昔ながらの素朴の絵のついているこの語草片のシリーズのようなものの方に手が伸びてしまう。年をとった証拠だろう。いや能力の幅の狭さか。
「それじゃ、また来ます」
「ありがとうございました」彼オンナ達の声を後ろに聞いて、私は外に出た。
神保町駅に行くまでの間にある山田書店の一階をちょっとのぞいた。写真集などに混じっていい本がゾッキででていることもある。二階は高価な浮世絵や限定版である。とても手が出るようなものではないので二階に行くことはあまり無いのだが、その日は、何気なく上がってしまった。日本の菌類図譜がガラスケースの中においてあった。たまたま開かれていたところが、スッポン茸である。昔の日本人がこの茸を食べるわけはないが、奇妙な茸ということと、形があたかも男根のようで、面白いので絵の材料になったのであろう。
家に帰り、図鑑「日本のきのこ」でスッポン茸を調べた後、インターネットで検索してみた。いくつかのサイトがあるが、必ず学名の意味が書いてある。まず姿から男根というラテン名がつけられていて、さらに恥を知らないという言葉が続く。おそらく、地上に堂々と立っているのでそのような名前になったのだろう。そればかりか、スッポン茸はぶよぶよした丸い卵のようなものから突き出しているので、それが陰嚢に似ていると書いてあるものもある。そのような形になったのは茸自身の責任ではない。それでもそのまま和名にしないで、スッポンの頭のようだということでつけられたのは日本らしい。
それでは海外でどのように言われているのか知りたくなり、またコンピューターをいじくった。英語ではstinkhorn で臭い角だが、hornはスラングとして、硬くなった一物のような意味がある。フランス語はSatyre puantで神話の半人半獣のサティロスの匂いということになるようだ。サティロスは野や山の精で、好色だというから、やっぱり男のもののイメージなのだろう。イタリア語ではSatrioneでフランスと同様である。さて、スペイン語のFalo hediondoは男根と臭いがくっついて、なんだかすさまじい。
こうみていくと、どの国の名前も学名に近いが、スッポン茸という日本の言葉が一番おとなしい言い方であることがわかった。
科学者は正直だから学名を見た目のままにしたに違いない。調べたら、名付けたのは動物分類の父である、スウェーデンの分類学者、大リンネのようだ。一方、恥の文化の中にいる日本の科学者はスッポンにしたのだ。
きのこの語源・方言辞典(奥沢著、山と渓谷社、1998)には和名の命名者、梅村とある。誰だろう。おくゆかしい。しかしスッポンの頭も男根に見立てられることが多い。
さて、そんな下知識を得たのだが、第五集、茸の鹿驚を紐解いてみよう。書いたのは神奈川の伊勢原に住んでいる人で秋山さんと言った。大山の案内人、先導師の家に生まれた人である。大山には阿夫利神社があり、信仰の対象として、昔から全国の人々が訪れた。大山講と呼ばれるが、その人たちが泊まる宿坊があり、そこに先導師がいて、その案内のもと大山に詣でた。
茸の鹿驚
大山は修験者たちの修行の場でもあったし、大山にある阿夫利神社は雨降り神社で、米作りには大事な雨を降らせてくれる神が祀られている。そんな信仰の場でもあったのだが、ここに紹介する言い伝えは神代のことである。
神代のこと、大山にはいろいろな原獣や原鳥が住んでいて、麓に下りてきてはヒトが作る米や野菜を喰らってしまっていた。将来鼠になるムルや兎になるミルなどの小さな獣は、ヒトは簡単に追い払うことができた。しかし、鹿や猪、それに熊の原獣たちはそう簡単にはいかなかった。それだけではない、面倒なのは、原鳥たちだった。大山の木々に住んでいた原鳥たちは、空から、実った米や豆をついばみにやってきて、根こそぎ喰ってしまった。特に将来雀になるジャヌは集団でやってきて米をみな食ってしまう。
何とかしないとヒトが亡びる、大山を取り囲む村々の長が集まり対策を考えた。
「ジャヌを追い払うのに何かいい方策はないものか」
「ジャヌは耳が良い、人の足音を遠くから聞きとり、我々が追い払うために家を出た足音でさえ聞こえてしまい、すぐ逃げてしまう」
「そうとわかっているが、我々がずーっと、田の脇で立っているわけにはいかぬ」
そのころのヒトはまだ数が少なかったのだ。
一人の長がいいことを思いついた。
「ジャヌはヒトが動いているのを嫌う、ちらちら光るものを考えよう」
そこで、白い布を細く切って、畑の脇に立てた棒に吊るした。風になびくと、白くちらちらと動いて、ジャヌは驚いた。とうとう大山に住むジャヌは一羽も飛んでこなかった。
次に、大山の中から将来鹿になるカカチが何頭も現われ、せっかく育った実のなる木の幹を食ってしまい、実のなり方が少なくなった。
ヒトはこれにもまいった。
「カカチは臆病のはずじゃ、ちょっとの音でも、逃げていくだろうよ」
長の一人が言った。
そのころ、日本列島に住むヒトは獣や鳥を喰らうことを知らなかった。だから、鉄砲などというものもない。大きな音をだすとなると、木を叩くしかないと思っていた。拍子木みたいなものである。
村のヒトたちは、実のなる木の脇に立って、木を叩いた。すると、耳がいいから、カカチは木のそばにヒトがいることを知ることができたのだ。だから寄ってこなかった。
しかし、それだけでは、人がいつも立っていなければならない。拍子木がなくとも来たら追い払えばいいのである。
ある村のオトコが木をいくつか吊るしておくと、かぜにゆられて音が出ることに気がついた。そこで、田に棒を立て、その先に、木を吊るした。すると、カチカチという音がでた。それで、チカカはなかなか大山から出ることが出来なくなった。
しかし、風がない時には、堂々と出てきて、実のなる木の樹皮をかじって、木を弱らせてしまった。
「いつも、音を出しておかねばだめだろう、何かいい方法はないか」
それを聞いた水車番の男が、
「水はいつでも流れているでよ」
と言った。
長はそれで気がついた。
「水が溜まると、カタンと音を出すものををつくればよい」
水車番のオトコは、水車から出る水を、竹の筒で受けてみた、だんだん重くなる。それで筒の真ん中より少し後ろを持っていたのだが、重さで前が傾いて水が流れた。いくらか流れ出ると、後ろに残っている水の重さで元に戻った。後ろに石でも置いておけばカタンと音がする。
そう思った水車番のオトコは、チカカおどしを作ることができた。今のシシおどしの原型である。
あちこちに水路があったので、その水を引いて、チカカおどしを動かした。
どこからも、カタンカタンという音が聞こえるようになった。
これで、大山からチカカはでてこなくなった。
しかし、大山にはまだまだいろいろな獣や、鳥が住んでいた。鳥のジャヌはこなくなったが、将来鴉になる、真っ黒な鳥、マクロはジャヌの何倍もの大きさで、田んぼに来て稲を食い荒らし、果物畑に来て、なった桃、林檎、柿の実を平気で喰らった。
「マクロは、チカカおどしの音もジャヌおどしの布も何も効かぬ、何かよい方法はないものかの」
また、大山の麓の長たちが集まった。
「棒で追い払うと、よく覚えていてしばらくは来ぬが、ヒトがいないとすぐ戻ってくる」
「マクロの怖いものは、ヒト以外にはないのであろうな」
「それでは、ヒトの形をしているものを、田畑に置いておいたらどうでしょうな」
「それがいい、ヒトガタをつくり、着物を着せて、立たせておこう」
「まずはやってみましょうかい」
ということで、オンナとコドモが、モミ藁を使って、ヒトガタをつくった。それを田んぼに置いてみた。
ところが、マクロは平気でやってきて、モミ藁の上に止まっている。
「まったく効きませんな」
「それでは、着物を着せてみましょうぞ」
その長の声で、オンナたちは布で着物をつくり、モミ藁のヒトガタに着せた。
ところが、それでもマクロはヒトガタの上に止まり、着物を嘴で引き裂いて、巣の材料に持っていってしまったりした。
「もみ藁のヒトガタは効きませんな」
「マクロは鼻はよく利くのですかい」
「鳥の仲間は鼻馬鹿といいますぞ」
「匂いを嗅ぐことはできないとすると、モミ藁のヒトガタは、モミ藁だからだめなのではないのですな」
「もっと似たものじゃないといかんのだろう」
ある長がそういったので、みんなそれを試してみようということになった。村の樵の一人が木を上手に彫る。その男にオトコのヒトガタとオンナのヒトガタをつくらした。色まで施して、ヒトそっくりに作った。
それを、田畑に置いてみたところ、マクロは、オトコのヒトガタのところには来なかったが、オンナのヒトガタがいるところにはやってきてしまった。
きっと、田畑はオトコが耕しているからだろう。
「オトコのヒトガタが利くようですぞ、マクロは目がいいのですな」
「だが、大山の麓のすべての田畑に、木彫りのヒトガタをつくるのはむりじゃな」
「どうじゃろう、からだ全部ではなく、一部分でためしてみよう」
そこで、樵のオトコは、オトコの首と、胴体と、手と足を上手に作った。
それを、田畑に置いたところ、首と手のところにマクロはこなかった。
「それでも、首と手の木彫りを作るのは大変だ、しかし、少しずつ作ってもらおうではないか」
ということで、マクロを追っ払うための対策が打ち出されたのだが、何十年かかっても、ヒトガタはすべての田畑に行き渡ることはないだろう。
ヒトガタの首と手を樵のオトコは一生懸命作ったが、なかなかはかどるものではない。
その時代、ヒトは米や野菜や果物を作っていたが、自然の恵みも重要な食料だった。春は山菜、秋は木の実、茸である。どの家でもみな、オンナが山菜や茸を採りに山に入った。オトコは米を作り、畑を耕していた。
ある秋の日、茸採りのオンナが大山の林の中に入った。いろいろな茸が生えていて、ヒトにとって、自然の恵みの最も栄養のある大事なものであった。
占地や滑子、そこには食べられるいろいろな茸が生えている。いつも背負い籠一杯に茸を採って帰る。
その日、大山の奥で、せっせと茸を採っていたオンナの背負い籠が茸であふれんばかりになった。
オンナは「どして、こんな旨いものが大山に生えているのに、獣や鳥は食わんのじゃろう」と独り言を言った。
籠をいっぱいにしたオンナは家に戻る道を歩き始めた。
マクロやジャヌ、それにチカカがオンナが呟いていたことを聞きつけた。
オトコどもが田畑に変なものを置くので、行きづらくなった鳥や獣は、仕返しにオンナを脅してやろうと思った。
たくさんのジャヌがオンナの周りを飛び回って糞をした。
いきなり、糞が降ってきたのでオンナはびっくりして駆け出した。駆けても駆けても追いかけてきて、今度はたくさんのマクロがオンナを突いて、着ているものを剥ぎ取った。
裸にされたオンナは大声を上げながら、茸の入った籠をしょったまま、林の中に入り込み逃げ回った。茸がどんどんこぼれてて落ちていく。
チカカが角でオンナの尻を突っついた。驚いたオンナは、背負っていた籠の中の茸をすべて落としてしまった。
オンナはちょっと日差しの少ない薄暗い林に逃げ込んだ。食べられる茸は多くないので、こういうところはあまり入ることはない。すると、マクロ、ジャヌやチカカはその林の前まで追いかけてくると、ぴたりと止まり、林の中に入ってこようとしなかった。
裸にされてしまったオンナはちょっぴり寒くて震えていた。木の陰から見ていると、マクロ、ジャヌやチカカは、くるりと向きを変えて戻り始めた。
林の中で、マクロ、ジャヌ、チカカはオンナの落とした茸を食ってみた。オンナがなぜこんなに旨いものを喰わぬかと、ぶつぶつ言っていたのを覚えていたのだ。
大山の鳥と獣は、「旨い」と、落ちていた茸をみんな食ってしまった。それだけでなく、生えていた茸もみな食ってしまった。それで、生えている茸を探しに他の林に行ってしまったのである。
そんなことがあってから、鳥や獣も大山の中で茸を食べるようになった。それで、里に出てくる回数は減ったという。しかし、まだまだ、ジャヌ、マクロ、チカカは田畑に出てきては稲や野菜を食ってしまった。
暗い林の中で裸のまま籠を背負って震えていたオンナは、鳥と獣が行ってしまったことを知り、安堵した。
だが、なぜこの林に入ってこなかったのか不思議に思った。
落ち着いてくると、その林の中から、異様な匂いが漂ってきた。臭いのである。人糞と何かが混じったような臭い匂いである。
その頃ののヒトは人糞は貴重なものだった。畑にまく肥料になったからだ。それが江戸時代の野菜作りの基本になり、そのシステムがあることによって、江戸の町が綺麗に保たれたのである。サイクルの原点がここにあった。
それで、臭いことは臭いが、オンナは気にしなかった。肥溜めの匂になれていたからである。獣たちはこの匂いが嫌で入ってこなかったのかもしれないと思った。
林の中を行くと、草原に出て驚いた。そこには見たこともないような、茸がにょきにょき生えていた。
それは、なんだかオトコ物によく似ていた。先の膨らんだところに黒緑色の液が付いていて、それが臭いようである。陽物のように立った根元には丸い柔らかそうな玉があった。それまでオトコのものとよく似ていた。
その茸の先に蝿や虻の原虫、アジとハジがたかっている。オンナはこの虫たちも始めてみる生き物だった。
オンナはしげしげとその茸を見た。
喰えるだろうか、そう思ってちょっと茸に触れてみた。意外としっかりとしている。洗ったら食えそうにも思えた。折角採った茸はジャヌやマクロに追いかけられて、全部落としてしまった。籠の中は空である。オンナはこの茸を採って帰ることにした。その茸の群の中に入ると、アジとハジが一斉に空中に舞いだした。ぶんぶん、ぶんぶん、うるさいくらいである。オンナは手で払いながら、茸を籠の中に放り込んだ。
やがて一物のような茸で籠がいっぱいになったオンナは家に向かった。
アジとハジが後をくっついてきた。
それから、アジとハジは里に住むようになって、家の周りをぶんぶん五月蝿く飛ぶようになり、困ったことに、肥溜めの周りを飛んで、肥をくむ時に邪魔になった。
家に戻ったオンナは畑から帰っていたオトコに茸を見せた。
「喰えるじゃろうか」
「やな匂いじゃな、だが、幹のところは旨そうだ」
オトコはその茸を一本手に採ると、水で洗ってみた。頭のところの緑色の汁はきれいに流れてしまった。それでもオトコは茸の頭と玉を千切り、口に入れてみた。
「歯ざわりはいいし、旨いよ」
それで、たくさん採れたので、ちょっと離れた家にも配った。
隣の家では、家族がみな腹を下していて、もらった茸を食べることができなかった。いつものように、干しておいて後で食おうと、畑に持っていった。まだ鳥と獣を追い払うヒトガタをもらっていなかったので、畑にはマクロが数羽、野菜を突いていた。マクロたちはヒトが来たのであわてて空に舞いあがった。
隣の家のオトコがその茸を畑の脇の切り株に乗せた。
すると、空に居たマクロは、目を白黒させて、大山に帰って行ってしまった。
隣のオトコは不思議に思って、茸をもらった家に行って、その出来事を伝えた。
茸を採ってきたオンナが、
「そういえば、ジャヌもマクロもチカカも、この茸の生えていた林には入ってこなんだな」
と言った。
それを聞いたオトコは、その茸を持って、長のところに行った。
「おお、臭い茸だ、それにオトコの一物そっくりだ」
長は驚いた。オトコは連れのオンナが山で遭遇した話と、隣の家のオトコがこの茸がマクロを追い払ったことを伝えた。
「ふーむ、まるで金玉っこだな、この茸は、きっと、オトコのヒトガタになるな、これを取ってきて、田畑においておくと、マクロばかりではなくジャヌやチカカが近寄らんかも知れぬな、鳥は鼻馬鹿だが、チカカなどの獣はこの形や匂いはいやじゃろう」
そう言って、次の日にオトコも総出で、この茸、金玉っこを採りに行った。
みな、田畑の脇に石を置き、その上に金玉っこをのせた。すると、ジャヌやマクロ、それにチカカも全く来なくなったという。鳥もいやな匂いを感じて避けたようだ。
ヒトは金玉っこの幹のところを食べ、頭の粘々のついたところと、根元の袋を、田畑の脇に置くようになったということである。
神代が終わるまで、金玉っこは田畑を守り、しかも旨い茸として大事にされたということである。
神代が終わった日本では、ヒトが人間になると、ヒトガタは案山子、または鹿驚という名前になり、鳥獣を追い払うものとなったが、しばらくの間、金玉っこ、すなわちスッポン茸は、鹿驚として使われていたということである。
おかしな話である。著者に会ってみたいものだ。
大山には何度か登ったことがある。あの石段を一番上まで登るのは大変なことだが、ロープウェーがある。かなり昔からあったようであるが、一端途絶え復活したようだ。私は利用したことが今までなはい。しかし大山の登り口である伊勢原には何度も行った。あのあたりは丹沢などとのつながりがあり、旅の雑誌には何度も取り上げたからだ。
私は著者の電話番号を草片書店に問い合わせ、連絡をとった。いつでも来てくださいとのことだった。
それで、次の日に、新宿から小田急線で伊勢原の駅に行った。そこからバスに乗り、大山の登り口で降りると、電話を掛けた。迎えの車をよこしてくれるということだった。
バス停で待っていると、数分後に一台のワゴン車が来て、運転手が降りてきた。
「井原さんでしょうか」
と尋ねられたので、はいと返事をすると、「車でお連れします、社長は店でお待ちしております」と言う。
車には「大山豆腐、元祖篠田」とあった。大山は豆腐が有名である。秋山さんは豆腐屋さんだったのだ。
連れて行かれたのは、大きな農家風の豆腐専門の食事処だった。
迎えてくれたのは赤ら顔の恰幅のいい人で、おそらく五十代だろう。
「よくいらっしゃいました。笑子さんからは聞いております」
と、愛想がいい。
「すみません、こんなにお忙しいお仕事をしていると思っていなかったので」
「昔は大山の先導だったのですが、宿も営んでいまして、今は先導の仕事がなくなり、豆腐屋を始めたというところです。家内の実家です。今では私がとりしきっています」
「そうでしたか、大山は何度か来たことがあるのですよ」
「ええ存じてます、先生の雑誌には何度も載せていただきました」
私は覚えていないが、記事ばかりではなく宣伝もたくさん載せているようだ。
「うちの、豆腐と湯葉の料理は一品ですので、是非召し上がりながらお話をさせていただきたいものです」
願ったりかなったりのことである。
そこでの話は、大山の茸の話であった。どの山でもそうだが、山の恵として茸は重宝されたようで、豆腐と茸の組み合わせは絶妙だということである。実際に、美味しい豆腐と椎茸の料理を堪能した。
この語草片の話は、確かにそのような記載のある古文書があるようだ。しかし、かなり、この秋山さんの脚色が大きいいのだろう。
「あの、語草片叢書は楽しいですね」
秋山さんは豆腐と茸の相性を調べているということだが、調べる必要が無いということが最近分かったとのことであった。
「どうしてですか」
と私が尋ねると、
「どんな茸でも豆腐にあうのですよ、豆腐の腐はくさらす、くさらすのは菌類、仲が悪いはずが無いでしょう」
面白かった。この秋山さんも茸が大好きな、それに文学が大好きな人なのである。
大山の豆腐料理はまた食べに来よう。
茸の鹿脅(かかし)-茸書店の物語5


