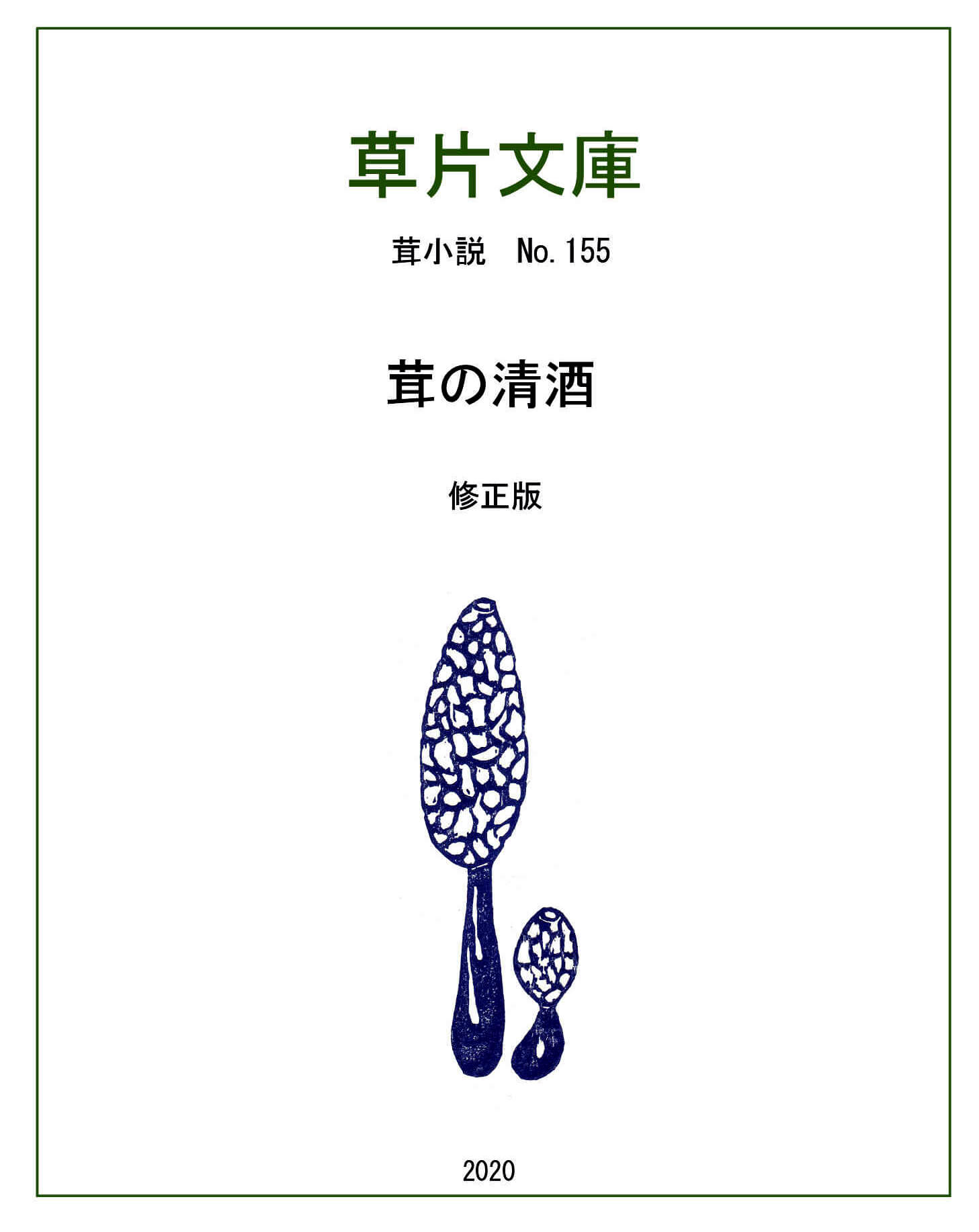
茸の清酒(きよき)ー茸の書店物語3
茸の本屋の幻想小説 縦書きでお読みください。
神田ランチョンでミートスパゲッディを食べた。年寄りにはかなり量が多い。それに、味はよいのだが、この店にしては自分には甘味が強い。やっぱりビールを一杯飲んでしまった。
その後、草片書店に寄った。今日は御茶ノ水の順天堂医院で、薬をもらって、その後、直接ランチョンに寄ったのだ。月に一度、血圧、痛風、高脂血漿、喘息、アレルギーの薬をもらう。
草片書店にはいつもの金髪の女性はいなかったが、もう少し小柄な、やはり黒い装束に身を固めた女性が、デスクに座っている。私が入ると顔を上げて「いらっしゃいませ」と声をかけた。髪は黒くおかっぱ風にしているが、丸顔で大きな目をしていて、店主とよく似ている。姉妹か親戚か。
私はいつものように、デスク近くの地方の出版物が置いてあるところにいった。前回来たときには一月後に語草片が出るということだった。三週間ほどしか経っていないから、まだ出ていないだろうと思って眺めていると、あった。第三集、茸の清酒、語草片叢書、と書いたものが置いてある。
冊子の表紙は重々しい黒い茸が描いてある。何の茸か知らない。
デスクにそれを持っていって差し出すと、「ありがとうございます」と店番の女性が手を差し伸べた。「三百円です」
「まだ出ていないと思ったらありました、出版が早まったのですね」
そう言って、お金を渡した。
「いえ、いつも通りだと思いますが」
「いつもいらっしゃる店主の方が前回来たときに、一月後とおっしゃっていたもので」
「すみません、あの子、いいかげんですから、この冊子は月に一冊、八日にでる予定です,前回は出るのが遅れていたかもしれません」
そういえば、今日は8日である。
「あの方が店主ではないのですか」
「ええ、私です、あの子は私の妹です、妹の方が大人びて見えるものだから、誰もがそう思ってらっしゃるようです」
彼女は笑いながら、包んだ冊子を渡してくれた。話をすると、この人のほうが落ち着いていて年上だということがわかる。なかなか魅力のある姉妹である。
「いつも買っていただいて、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします」
彼女は店の名刺も渡してくれた。草片笑子とある。
「伊原菜鶴です」
私も名乗った。
「くさびらしょうこです、妹はりゅうこといいます、ただ、泣子と書きます。親が出生届の時に漢字を間違えたものだから、いやがってます」
また彼女は笑った。確かに、泣子じゃ本人はつらいだろう、いじめられたに違いない。そう思ってそんなことを聞くと、笑子さんは笑いながら首を横に振った。
「あの子は逆で、皆をいじめていました、何せ、泣きまねもうまいし、口が達者だから」
それを聞いて笑ってしまった。
「間違えて付けたとはどういうことでしょう」
「生まれたとき、小さくて、ころっとしていたので、粒子にしたのですけど、戸籍届けに泣の字を書いてしまったようです、父親はおっちょこちょいですね、妹も父親に似ています」
粒子にしたって、つぶつぶと言われそうだ。
「茸がお好きなのですか」
「ええ、まあ、好きですけど、この店に入るまで、特に強い興味を持っていたわけではありません」
「ものを書く方にみえますが、お名前もさいかくと、戯作者風ですが」
笑子さんの言うとおり、私は旅行作家でもあり、旅行雑誌の編集長をやっていた人間である。もう引退したが、時々、文を頼まれることがある。
「ええ、旅行に関する雑誌をやっていました、名前はおやじの趣味が日本画で、なぜか菜の花と鶴が好きなのでそんな名前をつけられちまいました」
彼女は笑窪を寄せて笑った。
「それでは旅行にはよく行かれるのでしょうね」
「もう引退して、あまり行きませんけど」
「日本には茸のよく採れるところがありますけど、いろいろ行かれたのでしょうね」
「茸を意識して旅をしたことはないのですけど、茸料理はいろいろなところで食べました、それに、地酒を楽しみましたので、今度のこの本は面白そうです」
「書いたのは兵庫の方で、京都にも近いし松茸の採れるところです」
「そうですね、帰って読むのが楽しみです」
そんな会話をして、反対の棚の前を通って出口に向かう時、茸図鑑類や専門書のコーナーに、「キノコやカビの研究」という箱入、四六版の古めかしい本が眼に留まった。棚から下ろしてみると、少国民理科の研究叢書とある。素朴な茸の絵が描かれている。少年少女用である。
箱からだしてみると、本の表紙にも綺麗な茸の絵がある。奥付を見ると、昭和十七年の本で印東弘玄いう大学の先生が書いている。戦前の本で紙はざらざら、それがなんともいえないい手触りだ。二千円の値札が貼ってある。
笑子さんが近寄って来た。
「その本珍しいですよ、当時一円五十銭もしています、今に換算すると五,六千円です。カラー印刷があるからでしょう、お金持ちの子供しか見ることができませんね」
確かにそうだろう、と思いながら、「これください」笑子さんにその本を渡していた。彼女はなかなか商売上手である。だが私の好みの本であることは間違いない。
家に戻った。語草片叢書の表紙にある黒い茸も名前を知らない。図鑑を引っ張ってきて調べると、黒皮とある。ネットで調べたら、岐阜の中津川の保健所がだしている「きのこウオーキング」という、キノコ採りの人のためにだした小冊子の抜粋がのっていた。奥付を見てあっと思った。、あの「茸の亡魂」を書いた宿の主人が関わっている。この小冊子には毒キノコの見分け方だけではなく、食べられる茸の写真があり、それぞれのレシピが書いてある。
黒皮は苦味がちょっぴり利いて、日本酒にあう、日本の男の味だとあった。面白い表現である。黒皮は栽培されていないので、東京ではなかなか手に入らない。そのためだろう、全く知らなかった。
茸の清酒の作者を見ると、兵庫の谷川の人のようだ。丹波市の谷川は福知山線の谷川駅で、丹波竜の骨がでるところである。一度行ったことがあるが、大阪からかなりかかる。
「茸の清酒」
酒は最初誰が創り出したのか、ちょっと考えれば想像がつく。果物や穀物が発酵すれば酒になる。自然界には発酵させる酵母菌は五万と存在する。果実や穀物が放って置かれると、温度や光の状態によって自然にアルコール分を生じさせる。ということは、自然にできて溜まっていた酒を動物や人間が見つけたというのが本当だろう。すなわち、酒を創り出したのは自然である。
そもそも、葡萄酒などは葡萄に付いている菌を利用して、ただ踏み潰して作る。ずい分昔の話になるが、子供のころにビューティフルピープルという、野生動物の映画があったが、木になったまま実が自然発酵して、それを食べた象やヒヒが酔っ払ってふらふらする場面が記憶に残っている。
猿が最初に酒を作ったのだと主張するものもある。猿が木の実を木の穴に集め、それが発酵して酒になったものを猿酒という。
日本の米で作った酒の起源ははっきりしていないが、かなり古いらしい。しかし、米作が行なわれるようになってからとすると、米が大陸から持ちこまれた弥生時代以降と考えるのが妥当なのだろう。ただ、米や穀物は果汁があるわけではないので、果物と違って、でんぷん質を糖分にしないと発酵はしにくい。辞書には、噛み酒というものがあったことが書かれている。口の中に焚いた米を入れ噛んで吐き出し、それが発酵することで酒になるという、動物の口の中の消化酵素により糖分を分解し、自然の菌により発酵させるというものである。巫女さんに噛み酒をさせることで、祭祀の一つにもしていたようである。
この地方には、酒にまつわる変わった話が伝わっている。茸が酒を飲みたい、または、茸が酒になりたいというものである。
このあたりには、赤松の林がいたるところで見られる。赤松といえば松茸である。もともと丹波のあたりは松茸の産地としても名高い。これから書くことは、神代の時代から伝わる話であり、御伽噺のようなものでもある。子供のころ祖父から聞いたことである。祖父は大酒飲みであった。
赤松の林の落ち葉の中で、松茸同士が話をしていた。
「今年はちょっとばかり、湿り気が足りないような」
「そうじゃ、あまりからだが大きくならんようだ」
「だが、香りは良くなりそうな」
「ああ、よい匂いになりおったわい」
「これで、一雨くれば、かなり大きくなれるの」
そんな話をしていると、ポツリと雨が落ちてきた。
「おお、雨か、それはよい、久しいことじゃな」
そこへ白い猿たちが山から山葡萄をどっさり採ってきた。
白猿たちはてんでに、赤松の根がごつごつと地上に這い出し、絡み合っていい具合に凹みを作っているところに山葡萄を詰め始めた。子猿たちも、われもわれもと、山葡萄を根の凹みに入れた。
松茸たちが落ち葉から少しばかり顔を出して白猿たちを見ている。
「猿のやつら、今度は葡萄を採ってきおったの」
少し前のことになるが、白猿たちは猿梨の実を採ってきて、同じように松の木の根が作った凹みに詰め込んだのだ。
「猿梨のときは、噛んでほき出していましたな」
「ああ、そうでした、今度は手で葡萄を潰しているだけじゃの」
白猿たちは凹みに入れた山葡萄を指で潰していた。指が赤紫になっている。
「またあの匂いが漂うのですな」
「ああ、かなりよい匂いのものだが、猿梨の実がどうなったんだえ」
「あれは猿の水と言っての、薬のたぐいと聞くが、一度飲んで癖になると止められぬものだというがのう、それはそれは旨い飲み物だという」
猿梨のときは実を凹みに吐き出してから、数日経ったころに、白猿たちが松茸の森におりてきた。赤松の根の凹みからいい香りがただよって、赤松林が甘ったるい匂に包まれてしまった。その香りは風に乗り、奥山に住む猿たちが嗅ぎとったにちがいない。赤松林に降りてきた白猿たちは松の根元に群がると、かわるがわる口を突き出し中のものを吸った。白猿の顔がさらに赤くなる。子猿達の顔も赤くなる。。
一匹の白猿が二本足で立ち上がると、両手を掲げて松林の中で踊り始めた。やがて、周りの猿も踊りだし、一晩中騒いで、朝になると山奥に帰っていった。
「全く騒々しかったの」
松茸はにぎやかなのが得意ではなさそうだ。
「だが、楽しそうではありますな」
「あの猿梨の実が変わった飲み物てえのは、美味いだけではなさそうだの、見も心も軽くなっていたようじゃ」
「だがな、わしたち松茸の香りにはかなわぬわな」
「そうじゃわしらは茸の王だからな」
そんな会話を、松茸からちょっと離れた落ち葉の中で聞いている茸たちがいた。
真っ黒な茸である。
「松茸のやつら、自分達が茸の王だといっておる」
「まあ、言わせておけ、あの匂いは、人間しか好まぬ」
「そうだ、あれは、商人の茸だ、我々黒い茸は武士だ、ぐっと抑えて時を待つ」
「何のときだ」
「わしらの旨さが分かる時だ」
そう言っているところに、人間が赤松林に入ってきて、松茸を根こそぎ引っこ抜いていった。黒い茸には眼もくれない。
「ほら、松茸は人間の好みなんだ」
人間がいなくなると、黒い茸の一つが歩き出した。
「おぬし、動けるようになったのか」
「おお、白猿の残していった猿梨で作った水を飲みたいと思ったら、ほれ動くようになった、おぬしらも思ってみろ」
他の黒い茸も「猿の水を飲みたい」と念じた。するとみなぴょこりと飛び上がった。
黒い茸たちは落ち葉から顔を出すと、ぴょこぴょこと、赤松の根のところに飛んでいった。
「おお、いい匂いだ」と残っていた猿梨が変った飲み物に頭を浸した。
「沁みるな、ふむ、いい気持ちになる」
黒い茸は傘を上げると、ぶるりと身震いをして、枯葉の上で舞いだした。
一つが歌い始める「水は飲め飲め飲むならば、日の本一のこの水を」。
この歌は今の福岡、越前黒田の歌で、黒田節という。黒田の武士が好み、酒の席で歌った歌で、メロディーは雅楽の越天楽だと、岩波の広辞苑にはある。しかし、どうやら、この黒い茸が最初に歌ったものらしい。ただ、酒ではなくてまだ水であった。
歌い終わると、黒い茸たちは枯葉のなかにもぐりこんだ。
猿梨のときはそんなことがあった。
今度は山葡萄である。人間が採り残した松茸と新たに生えた松茸が、山葡萄が猿の水になり、匂いが漂ってくるのを待っていた。
もちろん、枯葉に隠れて黒い茸も楽しみにしていた。
「山葡萄が猿の水になるのは、いつごろだろう」
「あと数日だ、猿たちは心得ておるから、匂いがただよえば、すぐさま山奥から降りてくる」
「なぜ山奥の自分の住処で酒を作らないのだ」
「猿の水は寒すぎるとなかなか出来ぬ、暖かさがいるのだ、猿達の棲んでいる山奥は涼しいからうまくできぬのだろう」
などと話しながら黒い茸は猿の水が香ってくるのを待った。
それから数日たったとき、黒い茸は山葡萄が匂いを放ち始めたのを嗅ぎ取った。
「猿梨とは違った匂いだな」
「ああ、山葡萄の匂いのほうが強いな」
「確かに、なんだか旨そうだ」
黒い茸たちは猿梨の酒のときのように、動き出したくなってきた。
さらに二日ほど経ってからである、山奥から白猿達がひょこひょこと飛び跳ねながら、楽しそうにやってきた。きっと美味しい山葡萄の水が飲めると期待してきたのだろう。
松の木の根元に来ると、白猿たちは山葡萄をつめた凹みに指を突っ込んだ。それを舐めて、満足そうに頷いている。
白猿たちは口を伸ばして山葡萄の水を飲み始めた。交代でしばらく飲んでいると、猿たちはふらふらとなり、顔が赤くなった。またしても踊りだし、またどんちゃん騒ぎである。とうとう一睡もしないで騒ぎまくり、朝日が山間から顔をだすころ、やっと山奥にもどっていった。どいつもこいつもよろよろ、枝に飛び損ねて落っこちたりしている。
それを見ていた黒い茸はぴょこりと、枯葉の下から飛び出した。残った山葡萄の水に頭を浸した。黒い傘が鮮明な黒になる。
「ほほう、酸っぱくて渋いが、旨いものだな」
「確かに、猿梨より渋い」
「渋いのは我々と同じだ」
黒い茸は山葡萄の猿の水を堪能して、また枯葉にもぐりこんだ。
「我々茸はあのような水にはならんのかな」
「うむ、実の物と違い、すっぱみが足りんのじゃないか」
「それに甘味も少ないかもしれん」
赤松の根元でそれを見ていた松茸たちが話している。
「黒い茸が酒を飲んでおる、わしらは動けんのにどうしてやつらは動けるのだ」
「何、一つぐらい特技がないとな、やつらは我々のように旨い茸じゃないからな」
そんな時、白猿の子供たちが手ぶらで赤松の林にやってきた。遊びにきたようだ。どの生きものも子供は親の真似をするものだ。
白猿の子供たちは顔を出したばかりの松茸を引っこ抜くと、親が猿梨のときにやっていたように、噛み砕いて、赤松の根っこの凹みに入れた。
「子猿たちが、茸で猿の水を作ろうとしておりますぞ」
黒い茸は茸の猿の水はどうなるか興味しんしんである。
子猿たちは松茸をみんな採ってしまうと、噛み砕いて凹みに入れ、ひとしきり、松の木に登って遊んでいたが、やがて山奥に帰っていった。
そうして数日がたった。
凹みの中の噛み砕かれた松茸から、松茸の強い匂いがしてきた。
「人間ならいい匂いというのでしょうな」
「ああ、だけど、我々には松茸の匂い、としか表現の仕様がないですな、旨そうでも、なんでもない」
「ただの茸の体臭だ」
「上手いことを言うじゃないか」
赤松の根っこの凹みから、白い毛の様なものが生えてきた。
「なんですかなあれは」
「ありゃ、黴じゃないか、我々のお仲間だ」
「松茸は猿の水にはなれなかったのだな」
「黴がでてきたのなら、だめだな」
そこへ、子猿たちがやってきた。黴が生えているのを見ると、しょんべんを引っ掛けて、山に帰って行ってしまった。
「松茸のやつら、ざまをみろ」
黒い茸たちは、松茸の悪口を言うと、落ち葉の中でうとうと始めた。
人間がやってきて松茸を探した。松茸は子猿がみんな採ってしまったのであまり生えていなかった。そのためだろう黒い茸も引っこ抜かれた。
「こんな真っ黒な茸、喰えねえべ」
「そうかもな、松茸を採りにくると、いつもこいつらがいるんだ」
「食えるかどうかわからんけど、まあ、採っちまったから、持ってかえるべ」
こうして、黒い茸は松茸と一緒に一軒の農家に持っていかれた。
その晩、松茸は人間に食われたが、黒い茸は籠の中に放って置かれた。
「おれたちゃ、喰ってもらえねえようだ、逃げ出そうじゃないか」
夜中に黒い茸たちはごそごそと籠から這い出して、家の外に出た。何しろ、動くことができるようになったのだ。
赤松の林に帰ろうと、黒い茸が歩いていくと田んぼに出た。田んぼには稲が黄色くなって穂を垂れている。
「こりゃなんだ」
黒い茸は林にはない稲を見た。物知りの黒い茸が、
「こりゃ、米といって、人間が食べるために作っているんだ」と言った。
「それじゃ、猿の水が出来るのじゃないか」
黒い茸は猿の水が大いに気に入ったようだ。
「白猿に教えてやろうじゃないか」
「それがいい、それで、わしらもお相伴に預かろう」
ということで、赤松の林に帰った黒い茸は、林に遊びにきた子猿に、
「里に行くと稲という猿の水になりそうなものが生えている、お父ちゃんたちに教えてやれや」と声をかけた。
子猿は茸に話しかけられて、びっくりしたようだったが、子供は柔軟だ。
「黒い茸が、里に猿の水になる稲っていうのがあるって言ってた」と親猿に教えた。
白猿もよほど猿の水が好きである。
「そうか、坊主、よく聞いてきた、その茸に、里まで案内させよう」
ということで、真夜中、山奥から出てきた白猿たちは、松林でうだうだしていた黒い茸たちに里まで案内させた。
里に下りてくると、満月の明かりで、稲穂が金色に光っている。
「なるほどな、この稲の種を猿の水にしてみるか」
白猿は隣の畑に顔を出していた土器(かわらけ)を掘り出すと、田の水で洗って、畑の隅に半分ほど埋めた。猿たちは米を口に入れるとくちゃくちゃ噛んで、壷の中に吐き出した。
「三日経ったら、見に来ることにしよう」
白猿たちは黒い茸とともに山に帰った。
ところが、黒い茸は三日待つことに我慢が出来なくなった。二日目の夜中、様子を見ようじゃないかと、畑にやってきて埋めた土器の中を覗いた。
ぷーんと、旨そうな猿の水の匂いがする。猿梨や山葡萄とは違って、もっと甘そうである。黒い茸たちは頭を中に浸した。甘みの強いとても旨い猿の水だ。たっぷり吸った黒い茸たちは、「酒をのめのめ飲むならば」と酔っ払って歌いだし、とうとう、その場で寝てしまった。
早起きの百姓が田で一仕事終えて、朝飯に返ろうと畑を通ると、隅に土器の壷があり、覗くと米が入った水がある。いい匂いがする。こりゃなんだと、舐めてみると、これがとてつもなく旨い。人間はまだ猿の水というものを知らなかったのだ。
周りを見ると、真っ黒な茸がころがっている。はて何故茸があるんだ、と百姓は籠に黒い茸をいれ、壷を抱えて家に戻った。
百姓のひい爺さん、爺さん、父親がその壷の中の水の匂いをかいで「旨そうだなあ」と、器をもってきた。なぜかその壷の中の液体は下のほうに米粒が見えるが、上の方は透き通っていた。ひい爺さんがそれですくって一口飲むと、
「うめえ、朝飯に、みんなでこれ飲むべ」
とうなった。それで、朝飯に碗に入れた米の汁を飲んだ。
「その黒い茸も焼いて食おう」、
爺さんが言ったので、かみさんたちは黒い茸を焼いて、塩と一緒に出した。
父親がちょっとかじると、
「お、乙な味だ、こりゃ米の汁とあう、なんともいい苦味だ」
そういったものだから、ひい爺さん、爺さん、父親、百姓みなで、食べて飲んだ。朝からみんな気持ちよくなってきた。
「この茸は、松茸の生えるところにあるやつだべ、こんなに旨いものとは知らなかったな、こんどは、こいつも採って食うべえ」
百姓たちは猿の水とともにこの黒い茸を食べた。
「だが、どうやって、この汁ができたんかの」
「誰がつくったか調べてみろや」
ひい爺さんがそういったので、百姓は次の日朝早く、まだ暗いうちに田に行った。すると、畑の中に白猿がたくさんいる。酒が出来ていると思って、山から出てきたのだ。しかし、壷がなくなってしまっているので、また土器を掘り出して、米を口に含んで噛むと、その中にほき出していた。
猿はみんなして、何度も繰り返し、その器をみなで持ち上げると、山に帰っていった。なくなっちまうとまずいと思った猿たちは、壷を持って帰ることにしたのである。
それを見ていた百姓は、家に戻ると見たままを言った。
頭の回る父親は、「炊いた米でもいいんだべ、土器に入れて、しばらくおいておいてみべえ」と百姓に言った。
このあたりは縄文人が住んでいたという。それで、土器はたくさん転がっていた。百姓は畑にうずまっている土器を掘り出して家に持ってくると洗った。かみさんに、炊いた飯を噛んで入れるように言った。かみさんは言われるように炊いた米を二三度くちゃくちゃかむと土器のなかにほきだした。
三日すると、甘く美味そうな香りがただよってきた。その時百姓は稲刈りが忙しくて、壷を放ったままにしておいた。
稲刈りが一段落した百姓たちは、家にもどると、土間においておいた壷に気がついた。
爺さまが覗くといい香がして、澄み通ったきれいな水が溜まっていた。
「できたんか」
爺さまが器で米の水をすくうと一口飲んだ。
「なんと、うめえ水だ」
稲刈りが終わった百姓の家では、その夜は米の水を飲み、みな良い気持ちになって寝てしまったのである、。
こうして、米が美味くて、体が温まり、気持ちの良くなる水に変ることが知れ渡ることになった。その造り方は、百姓の家から隣の家に、また隣の家に、と村中に伝わり、その村では家々で、米の水をつくるようになった。
作り方は、そこここに埋まっていた壷を掘り出すことから始まった。壷は酉(とり)と呼ばれていた。百姓たちは米からできた水を酉の水と呼んだ。秋の祭には必ず酉の水をつくり、赤松林から黒い茸を採ってきて焼いて食べた。
しばらくすると、その地をとある武将が治めることになった。なかなかできた武将で、ますます安心に暮らすことのできる村となった。
安寧をもたらした武将に、百姓たちは、この村をますます栄えさせてくださいますようにと、酉の水と黒い茸を献じた。武将は酉の水を飲み、大いに喜んだ。文にも長けていた武将は、酉の水であるがゆえに、水を酉の左側にくっつけ、酒という字を作りだした。三水は水を現すもので、そのままでも酒の意味もある。栄える水ということで、酒をさけと呼んだといわれている。
清んだ酒は、上澄み、清酒(きよき)といって神にささげ、みき、神酒とした。
武将は黒い茸のその苦味を好み、酒には必ずこの茸を食した。侍の茸として珍重し、皮の厚い重々しい黒い茸ということで、黒皮と呼んだ。
それが、この地方に伝わっている、茸の清酒の話であった。この地には旨い清酒がある。白猿から教わったとされるが、そこに黒い茸、黒皮がこのように関わっていたのである。
私はこれを読んで、谷川に行って筆者と話をしてみたくなった。連絡先がわからないので、草片書店に電話を入れた。
「咋日、語草片叢書をいただいた井原です」
電話に出たのは、笑子さんだ。
「昨日はありがとうございました」
私を覚えていてくれた。作者のことを尋ねると、
「高校の生物の先生で、丹波竜の骨の発掘をしている方のようです。一方で、茸の写真を撮ったり、伝承を調べたりもしておられます」
そう言って、電話番号を教えてくれた。
電話をかけ、会う約束をして、数日後その筆者に会った。
筆者は四十半ばのまだ若い男の先生で、伊丹さんと言った。生徒と一緒に恐竜の骨探しや、茸探しなどをしているとのことだった。
彼は車で地蔵さんに連れて行ってくれた。地蔵と言っても四辻の角に立っているような小さなものではなく、大きな社で、中には首の無い地蔵さんが何体かおいてあった。首なし地蔵と呼ばれ、首より上のことに関して願いがかなうということで有名である。頭の病気回復祈願、頭が良くなりますように、すなわち受験合格祈願、など願い事をする人がたくさん訪れる。
平家の落人がここで首を跳ねられたそうで、その供養の地蔵さんだそうだ。
車から降りて地蔵の脇に来ると、彼は「あの酒造りと、黒皮の話は、この地蔵と関係がありそうなのです、あの話は古い郷土史の中に、さらに昔々の話しとして書かれていたのを僕がちょっと脚色をしましたけど、まとめました。あの中の武将はもしかしたら、平家の落人の首を跳ねた、このあたりを治めていた武将なのかもしれません。あまり書き残されたものも無いので、はっきりはいえません」
その話を聞きながら、首の無い地蔵さんを見ていたら、なぜか地蔵さんたちに顔が生え、猿の作った酒を飲みながら、黒皮を焼いて食べている情景が浮かんできた。
「黒皮はお好きですか」
高校の先生が聞いて来た。
「お恥ずかしいのですが、まだ食べたことはありません」
「この地方は松茸が採れることをご存知ですね」
私は頷いた。
「と言うことは、黒皮もたくさん採れます、今日はどこかでお泊りですか」
「泊まるつもりで来ましたが、大阪にでも出て泊まります」
「良かったら、うちにお泊まりください」
「そんな厚かましいことはできません」
「いや、ちょうど採ったばかりの黒皮もありますし、本物のお神酒もあります」
ずい分遠慮したのだが、結局泊まらせていただくことにした。
車で連れて行ってくれた彼の家は山の中のちょっとした神社だった。彼の家は代々神主を務めており、彼は神主さんでもあるということであった。
神社の裏の自宅には住み込みの老夫婦がいて、食事の用意からすべてをやってくれているということである。
テーブルの上に運ばれてきたのは、近くの谷川で獲れた山女の串焼き、自然の山葵を添えた猪のステーキ、それに、焼いてちょと塩を振った黒皮である。
「黒皮をちょっと食べてみてください」
私は黒皮を口に運んだ、ちょっぴり苦味があるが、なんと深みの味がある茸だ。酒が欲しくなる。
「酒を早くたのむよ」
彼が奥に声をかけると、巫女の装束の若い娘が白い徳利を持って現われた。
「おいでませ」
彼女は、私の脇に座ると酒をついでくれた。
「あ、すみません」
一口飲んだ。すっきりとした、ちょっと甘めのある酒で、おそらく昔からの酒なのであろう。
「黒皮とあう酒ですね」
「昔から伝えられている、ほんとうのお神酒です」
「あそこに書いてあったものですね」
「はい、この巫女がこの酒を仕込んでいます」
うりざね顔の白い顔をした彼女の赤い唇が小さく開けられ、微笑んだ。白い歯が綺麗に並んでいる。この娘が米を噛んでほき出して造った酒ということなのだろうか。
娘はまた酒をついでくれた。その酒を飲みながら、黒皮を食べた。何度も何度も同じように酒を飲み、黒皮を食べた。そのたびに「旨い茸だ」と口に出していた。何度酒を注がれたかわからなくなった。
巫女の首がすーっとなくなったと思ったら、どうなったかわからない。
あくる朝、眼を覚ますと、枕元に巫女が座って私の顔を覗いている。周りを見回すと、広い畳の間の真ん中で、私は布団に寝かされていた。
「お目覚めですね、神主様に、駅まで送るように言われております、神主様はもうお出かけになられました。よろしくとのことでございます」
巫女は「ご用意が出来ましたら、お送りします、あちらでお待ちしております」
そう言って、その場を去った。
玄関に行くと、老人が待っていた。
「先生から、駅に行くようにといわれていますで、ぼろ車ですみませんが」
と軽トラックに案内された。
車が神社から出るとき、賽銭箱のところに白い動物がいるのが見えた。犬ではないようだが、猿?と思って振り返ったのだが、鳥居の陰で見えなくなった。
「今日の朝採ってきた黒皮です、これを差し上げるようにとのことで」
私は駅で土産を渡され、帰路についた。時計を見た。もう昼に近い。昨日のことが定かに思い出せない。
夕方マンションに帰りついた私は、しばらくボーっとしていて、朝食も昼食も食べていないことに気がついた。急に腹が減って、近くの食事処に食べに行った。
テーブルの上にはもらった黒皮が置いてある。あわてて冷蔵庫に入れ、明日食べようと思い立った。友人を呼ぼう。黒皮で一杯やろうと決めた。。昨日の夢のような話を誰かにしたくなったのもある。
その後、谷川の伊丹先生にお礼のために電話を何度かしたのであるが、とうとう通じなかった。今でも、あの巫女さんの白い顔を思い出すが、本当にあったことなのだろうか。こんなに記憶が曖昧になったのははじめてのことである。
今度草片書店に行った時に聞いてみよう。
茸の清酒(きよき)ー茸の書店物語3


