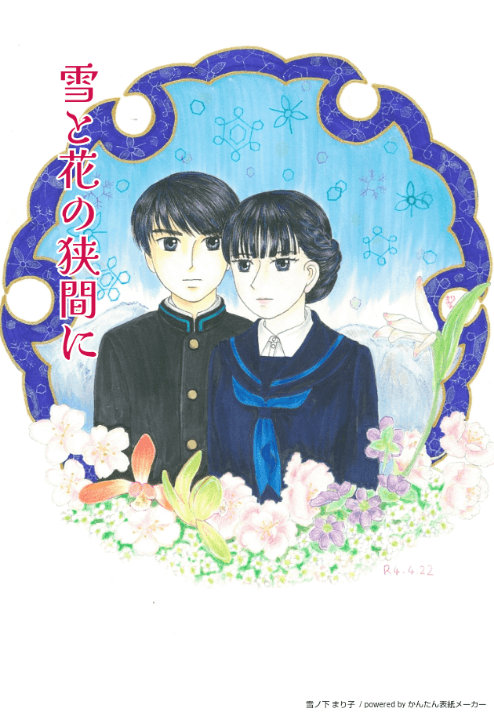
雪と花の狭間に
地名と名称は時代背景に合わせた表記で記しており、特に地名は過去編と令和編で表記が異なる場合がございます。
また、地方都市が舞台なので方言や地域特有の姓が複数登場します。
令和編の時系列はコロナ渦が収束した年の冬となります。
20年目のクリスマス

いよいよ遠景に街並みが見えてきた。
高速バスの車窓からは、四方を山に囲まれた街並みが覗く。
東北の冬とはいえど雪の気配は感じられない。蘭はほっと息をついた。
◇◇◇
蘭が卒業した県立高校の生徒達が演じる『くるみ割り人形』のミュージカルの公演に招待されたのは、収束には及ばないがコロナ禍が落ち着きかけた頃だ。
クリスマスの時期になると芸大への進学に特化した科を専攻する生徒による『くるみ割り人形』のミュージカルの公演が恒例となっていたが、コロナ禍の影響で前年度の公演が取り止めになった。
観客を募るのは二年ぶりとなる。
この度、在校生から「舞台の制作に携わった卒業生達にぜひ観に来てほしい」と招待状が届き『くるみ割り人形』の公演を観に故郷の福島まで赴いた。
高速バスで、二時間の道のり。
「ねえ、蘭ちゃん。福島の方は寒波ですごい雪が降るって話だけど、帰りどうする?」
現在の蘭が住んでいる新潟から福島までを結ぶ直通のバスはないものの、会津若松で一度乗り換えれば問題ない。
いずれにせよ予約の必要はないので当日にバスターミナルで乗車券を買えばよい。
それ以前に蘭と夫である一哉を出立の当日まで心配させたのは、寒波による積雪だった。
「蘭ちゃんも疲れてるだろうし、無理は禁物だからね。俺は仕事終わったらさくらとすず連れて福島まで迎えさ行こうか?」
蘭を気づかうあまり心配そうに眉をひそめた一哉の顔が苦笑いに変わったのは、蘭が自らホットミルクに入れている蜂蜜が桁違いに多いからだ。更に、蘭は生姜の砂糖漬けも入れている。
「それもいいけど、クリスマスにママがいないのは可哀想だしなぁ」
「蘭ちゃんがいない俺も可哀想だよぉ」
夫の発する本音交じりの冗談に蘭はクスッと笑う。
二人の娘は自分が面倒を見るので無理をせずに実家に泊まってきたらよいと一哉から提案を受けるも、クリスマスに母親がいないのは可哀想だからと蘭は当初はトンボ返りでの帰宅を決めた。
12月の下半期から毎日チェックしている天気予報ではクリスマス寒波による大雪の予報は相変わらずで、出立の間際になると実家に泊まるという提案に従った方が無難だと結論を出すほかなかった。
◇◇◇
貴賓席として宛がわれた最前列の席で、蘭は自身の年齢の半分よりも年若い少女達の演じる姿に感心しつつ、懐かしさに胸を震わせる。
懐かしい音楽に、懐かしい制服。
本格的なタータンを起用したキルトスカートに揃いのネクタイを組み合わせる制服は、少女だった蘭のお気に入り。
BGMは元々はチャイコフスキーが手掛けたバレエ音楽を起用していたが、いつしか芸大進学コースで音楽を専攻する生徒が作曲を手掛けるようになる。
その始まりとなった生徒が、蘭だった。
公演後の花束贈呈では在学時の活躍を紹介された後に、現在までの音楽家としての実績を放送部の生徒が誇らしげに述べる。
かつて演奏家として活動していた蘭は国内を中心に各地を巡りつつ、故郷の高校からの依頼により生徒達の指導を受け持っていた時期があった。
現在は一線を退くも、スクールバンド向けの楽曲の作曲を中心に音楽活動を継続している。
◇◇◇
青を基調としたイルミネーションは夕闇の駅前を鮮やかに彩った。
同時に、降雪の気配も静かに忍び寄る。
雪の精は、音もなく忍び寄る。
翌日から年末年始にかけて継続的に雪が積もると聞く。
豪雪地帯とは言い難いが、この盆地に鎮座する街も積雪する。
それでも、例年にはない事態だと地元に住む招待客=元同級生達は揃って震え上がっていた。
「蘭ちゃんは雪国さ住んでっからどか雪にも慣れたべ?」
同級生達が集まると誰かが必ず"福島より雪が降る地域に住んでいる者"にそう話を振るのだが、実態はまちまちだ。
その毎に蘭は「積雪は福島に毛を生やしたくらいで、どちらかといえば雨と雷が多い」と答えている。
20年前は、イルミネーションなどあったであろうか。
まだ中学生だった蘭は、15の少年だった一哉と『くるみ割り人形』のミュージカルを見に行った。
あの時は駅から出るなり百貨店に入ったものだったと懐かしく思う。
一階のアクセサリーと化粧品を扱うフロアにて蝶々を模したカットガラスのバレッタの美しさに一目惚れしたが、価格を見て購入を断念したことを未だに覚えている。
その後に一哉から雪の結晶を模したヘアアクセサリーをプレゼントされたこと、帰り足の無人駅の構内で彼に渡したマフラーは20年を過ぎた今でも愛用しており、今朝方も襟元に巻いて出勤していたことを思い返し、蘭はマスクの下で照れ笑いを堪えた。
ことあるごとに立ち寄っていた駅前の百貨店は閉店してしまったが、地元民に愛された百貨店だ。
再開発で解体するまで地元のスーパーがテナント入りし、各地域の物産展を開催するなど活用していると両親から聞いた。
まずは駅ナカでお土産を選ぼうと蘭は足を進める。
クルミの佃煮を入れた太巻きが一般化しているという食文化の影響でクルミの入った食べ物を好む一哉はエンガディナーが好きなので、お土産に買っていこう。
長女と次女には食べ物か、または雑貨にしようか……と考えを巡らせていると「ママ!」と呼ぶ声が聞こえた。
おおかた駅ビルに来た買い物客による声だろうと思いつつ、二人の娘の顔が脳裏に浮かんで切なくなる蘭の耳に通知音が届く。
スマートフォンを取り出し、手帳型のケースを開くなり蘭は発信者の名前に驚く。
『蘭ちゃん、お疲れ様。今福島さ来てるよ。あ、いたいた!』
地元を代表する作曲家をモチーフとしたモニュメント付近で蘭に手を振っているのは一哉だった。
彼は20年前に贈った薄桜色に藍鼠色でチェック柄を織り上げたマフラーを巻いており、トレンドの市松模様のマスク越しに笑っている。
これはサプライズではない。
事前に二人で相談し、天候次第では仕事を終え次第福島で合流する話も出ていた。
年末年始の福島の降雪は例年になくひどいと聞き、正月の帰省が困難であれば年明け前に帰省しようという結論に至ったのだ。
一哉は精神科の診療所に勤める医師だ。
35歳。駆け出しからようやく中堅に仲間入りを果たせたであろう彼は、亡き父方の祖父が開いた診療所を任される身。
週末と祝日、盆と年末年始は休診日を設けているので、休診日は医師もスタッフも休暇がもらえた。
ママ!
長女のさくらが嬉しそうに駆け寄ってくる。
名前のとおり桜の季節に生まれたさくらは5歳児だが、背が高いのでしょっちゅう年長組に間違えられる。人によっては小学生に見えがちだ。
乳児期から子供騙しがきかないほどに賢いところへもってきて、勝ち気で我の強いさくらには両親共々手を焼いているが、かわいい我が子には変わりない。
「お車の中でお利口にできた?」
「うん! だって寝てたもん! パパがね、今年は福島にサンタさん来るってパパが言ってた! それでね、サンタさんにおやつあげるのぉ!」
「そっかぁ、よくできたね。サンタさん喜ぶぞぉ」
おやつは枕元に置くんだよ、と話して聞かせる蘭にしがみついて甘えるさくらは、会う人会う人に「パパにそっくりねぇ」と言わしめるほど一哉と瓜二つ。
つり目がちの、黒目のハッキリとした大きな瞳が印象的で、己の頭を蘭にすりつけている姿は飼い主に甘える子猫さながら。
朝の登園時に着せた、中綿の入った薄紫のコートと起毛素材の縫い込まれた雪靴が暖かそうだ。
コロナ禍など予想だにしなかった二年前の初夏に次女のすずが生まれて以降は姉としての自覚を持ち始めたのか、時々お節介が過ぎるところは置いておき面倒見の良い性質が強まった。
すずはというと、お気に入りのシロクマを模したコートを着こんで座り込み、石畳の隙間を指でなぞって一人遊びをしている。
マイペースな性分が、垣間見えた。
そんな次女の面差しは蘭に似ているが、父方の祖母からは「カムカムすっ時のつぐんだ口元があんたの父さんそっくりだよ。こりゃあ頑固者さ育つナイ」と言われた。
その傍らで苦笑いを浮かべる一哉は顔を蘭に向けると満面の笑顔へと変えた。
「蘭ちゃん、おかえり」
小走りで駆け寄る蘭の髪に、雪の結晶が青く煌めく。
「ただいま」
2011年冬
―――2011年12月―――
冬の午後らしい、金色を帯びた空だった。
フランクフルト発の飛行機に乗り込んでからどれほどの時間が過ぎたろう。
音澤蘭は両手を組み合わせて腕を伸ばし、窓からのぞく空を見た。
時刻は15時過ぎ。もうすぐ成田空港に着く頃だ。
演奏家志望の蘭はドイツのハンブルク市内にある音楽院に留学中で、翌年には卒業を控えている。
冬休みを利用し一時帰国する最中だった。
実家は東京から新幹線で1時間ほどかけた東北の地方都市にあるが、諸々の手続きを考えれば帰宅時間は夜にずれ込むだろう。
空いた時間に日本に着いたと連絡を入れ、実家や周りで変わったことはないかと聞くと母はこのように返した。
3月の震災で道路にできた凹凸で走らせた車が弾むほどだった、と。
地盤が頑丈な地域ゆえに実家に大きな被害はなかったが、除染作業で取り除いた土は庭の片隅に置いたままで、いつになれば持ち出すのだと不満を漏らしていた。
気に入って育てた鉢植えの行き場がなくなった、母は電話でそう愚痴をこぼす。
母の自慢でお気に入りだった牡丹と藤の鉢植えは、どこへ置いたのだろう。
予想どおり福島に着いた時には夜になり、駅前広場は青いイルミネーションが煌めいている。
駅ビルはクリスマス一色で賑わいを見せ、クリスマスの雰囲気を楽しんでいる人々の様子に蘭は安堵した。
福島。四方を山に囲まれたこの街は蘭の生まれ故郷だ。
街並みと吾妻連峰の取り合わせは壮観で、雪と花の狭間の季節は特に美しいと蘭は疑わない。
実家の部屋の窓からは吾妻連峰が見えるので、朝起きたら見てみよう。そう考えていると名前を呼ばれた。
少女の声。
「やっぱり蘭さんだ! 兄ちゃんから今日帰国するって聞いてたんです!」
二重まぶたの大きな目が蘭を見上げる。
蘭は背が高い。
平均的な身長の女性でも少しばかり見上げねば、170センチを少しだけ超えた蘭との視線は合わないのだ。
「花梨ちゃん? 予備校の帰りなの?」
「はい。今帰りなんです。聞いてくださいよ。今年は冬休みが短くて……」
花梨は高校三年生。
薬剤師志望で連日予備校通いだ。
この女子高生が蘭と親しげに接しているには、理由がある。
「総文祭も会場が避難所になっていたから吹奏楽は中止でした……。しょうがないって頭では分かってはいるんですけど、せっかく福島県内が開催地だったのに。あ、兄ちゃんとはいつ会いますか?」
「明後日だよ。高速バス乗り継いで行くよ」
「医者になった暁には蘭さんとお兄ちゃんゴールインなのかなぁ」
含み笑いの花梨。花梨の兄である一哉は蘭の恋人だ。
いずれ義理の妹になる花梨は素直で愛らしく、蘭にとって本当の妹のようにかわいい存在である。
「女子高生って恋愛の話が好きだよね。まさか花梨ちゃんに会うなんて予想外だったから渡せるのこれしかないけど、ドイツのお土産」
熊を象ったグミを花梨に手渡す。
検疫が済んだ後の空き時間、知り合いに遭遇した時に備えてコートのポケットに忍ばせておいたのだが用意周到にも程がある。
「ミヒャエル・ゾーヴァの本で見てから憧れていたんですよ。ありがとうございます! よし、LINEで兄ちゃんに自慢したろ」
言葉どおり花梨はスマートフォンを取り出して手元を撮影し始める。
その前に通行人の妨げにならないよう壁際に寄るという配慮は忘れていなかった。
「お兄さんにプレゼント用意してあるよ」
「まさか人相の悪いくるみ割り人形ですか?」
「当たり」
「兄ちゃん、人相の悪いくるみ割り人形が欲しいって言ってたんですよね」
変わったセンスだね、と二人は互いに顔を見合せて笑う。
「昔ね、そんなこと言ってたの思い出したんだ」
「大学の時ですか?」
「いや、中学生の頃。くるみ割り人形の公演に行った時にそう話してたのをふっと思い出してね。通販のくるみ割り人形はどうしてもかわいい寄りだからねえ。でも人相の悪いくるみ割り人形を探すのは大変。作家物だとおっかない顔はいるけど高いし、蚤の市で探してやっと理想どおりの見つけたの」
花梨と話し込みながら飯坂線の乗り場へ向かう。
福島駅から飯坂温泉までをつなぐローカル線は雨が降ろうが槍が降ろうが運行すると聞く。
沿線に住まう周辺住民の足となり、時間帯によっては一時間あたりの便数が多いのでローカル線としては充実しているのではないかと蘭は思う。
蘭自身も中高生の時分には世話になった。
寒いと言いつつも花梨は黒タイツにレッグウォーマーを重ね、更にショート丈のスノーブーツを履いていたのでいかにも温かそうな足元をしている。
「花梨ちゃんって彼氏いるんだっけか?」
苦笑いで、花梨は顔の前で片手を振る。
「いませんよ。周りにあまり興味持てる男子いなかったし、言い寄られることもなかったですね」
「えー、そうなの? 花梨ちゃんかわいいのになあ」
目鼻立ちのハッキリした愛らしい顔をしている花梨。
素直で心根が優しいので彼女に好意を寄せる者が存在してもおかしくないのにと蘭はと思うが、花梨は兄譲りの『いい加減な男女交際はしたくない主義』かもしれなかった。
花梨の兄も美男子ゆえに異性から高い人気を得ていたが、蘭への想いがぶれたことなど全くない。
「そりゃあ、彼氏欲しいって思う時もありますよ。蘭さんと兄ちゃんのラブラブっぷり見ていると羨ましかったし、あんな恋愛したいなーってすごく憧れてました。でも高校では勉強と部活に熱を入れてたし、女子の比率が高いから出会いが少ないんですよねえ」
花梨の置かれた環境を顧みて、まあ、確かにと蘭は納得せざるを得なかった。
「うちの高校は男女比が商業高校並みだもんね。でも吹奏楽部にも男子いたじゃん?」
うちの高校。花梨の通う県立高校は蘭の卒業した高校でもある。
現在、花梨の着ているブレザーの制服をかつては蘭自身も着ていたものだった。
90年代に制定されたタータンチェックのキルトスカートは未だに女子中高生から高い支持を得ているのだろう。
「あくまでも部活仲間って関係でしたね」
でも恋がしたい、と切符を買う蘭の隣で花梨は唸った。
電車内の暖房はちょうど良い加減になっていた。
◇◇◇
「ただいま」
蘭の自宅は市街地より西側の郊外にある。
郊外とはいえど昭和末期から開発が進んだこの地域は複合型のスーパーがあり、更には地元企業のスーパーが複数件存在する。
ファミレスや焼き肉店も複数件建ち並び、靴屋、ペットショップ、ファストファッションの店舗まで揃うという利便性の高い地域だ。
自宅は地区内で最も栄えた場所から少し北に位置した住宅地にあり、築30年はいかないであろう和の趣のある戸建てに蘭は入っていった。
確かに、庭の片隅には長方体にシートを被ったものが見えた。
これが母を悩ませる土かと蘭は長方体を睨む。
長方体の上には、いくつかの鉢植えが置いてあった。
母自慢の牡丹と藤の鉢植え。父が気に入っている梅の盆栽もある。
いかにも、仕方なくそこに置いたと言わんばかりだ。
「おかえり。電話かければ迎えに行ったのに」
蘭と面差しの似た女性がドアを開け、リビングのコタツに入るようにと促す。
かすかに、日本家屋に似つかわしい薫物の香りがした。
この香りは蘭が大学卒業時に母へのお土産にと渡した新潟の雪椿のお香だと分かるなり、蘭は嬉しい気持ちになる。
母親の星(せい)は若かりし頃に駅前の百貨店でデパートガールを勤めていたのも頷ける、才気煥発で溌剌とした女性だ。
音澤は母方の姓である。
ルーツは知らないし音の字が北海道っぽいと言われたことはあるが、母は横浜出身であった。
父の旧姓は星。会津地方に多い苗字だ。
星が二つ並ぶと珍妙だからと父が母方の姓に入ったのだ。
星の後ろからヌッと現れ、蘭のスーツケースをひょいと持ったのは父の泰造だった。
会津生まれの寡黙な泰造。
大柄の筋肉質で、パッと見はサングラスが様になるコワモテだが、我が子の意思を尊重し寄り添うことを厭わない、子煩悩な父親だ。
泰造は県庁で働く公務員である。
見た目は母親似で醸し出す雰囲気は父親似だとよく言われたが、蘭自身もそう思う。
「ご飯は花梨ちゃんと食べたの」
自宅に着く前に少しだけ遠回りして、蘭は花梨と町内のハンバーグがメインのファミレスで夕飯を食べてきた。
ハンバーグってハンブルク発祥なんだって。
えー、知りませんでした。
私も留学した頃に初めて知ったの。馴染みのある食べ物って案外ルーツを知らないものだよね。
冷えた身体をコタツにもぐり込ませて暖をとる蘭はファミレスでそんな会話をしてきたと両親に聞かせた。
「パフェも食べてきたよ」
「あらー、そう? 蘭が帰ってくるから小学校前のお菓子屋さんでケーキ買ってあるんだけどなあ」
「えっ! 食べる!」
母の言葉に目の色を変える蘭。
コタツから勢いよく跳ね起きた。蘭は甘党だ。
筋金入りの甘党の娘の様子を微笑ましく思う星は「はいはい」と言って苦笑いをしながら人数分のケーキを用意する。野太い声で「俺、運ぶよ」と言う声が台所から聞こえた。
ケーキ三つにティーポットと三人分のカップ&ソーサーのセットをいっぺんにお盆に乗せて、泰造は易々とリビングに運び込む。
蘭の好きな、ホワイトチョコレートのババロアにオレンジ色のソースをかけたケーキ。
オレンジ色のソースの上はフルーツで彩られている。
大好きなホワイトチョコレートのケーキは帰省の毎にありつけた。
蘭が徒歩で買いに行く時もあれば、今回のように帰省するその日に合わせて家族が小学校前の菓子店まで車を走らせる時もある。
両親もケーキを食べたいということもあるのだが。
入浴前にパジャマを取りに行こうと蘭は二階へ上がる。
高校卒業時まで過ごした吾妻連峰を臨む子供部屋は、年子の妹と共同で使う相部屋であった。
その証拠に本棚と学習机の機能を備えたロフトベッドが二つ、対に配置されていた。
北海道の大学で獣医学を学ぶ妹の『みちる』は滅多に帰省できない。
高校時代に見た獣医学部を題材としたドラマの影響を受け関心を持ったみちるだが、留学前に再会した時には「生命を相手にする以上、生半可な覚悟では務まらない」と話していた。
泣き言を口にしながらも妹は動物はかわいいし社会に貢献できる仕事だからと懲りずに頑張っている。
時折お調子者のように振る舞いつつも性根の真っ直ぐなみちるらしい。
いざ数ヶ月ぶりに自分の部屋に入ると本来の目的も忘れて関係のない引き出しを開けたくなる。
まずはクローゼット。
モノトーン、または寒色系で占めている。
その中でも大多数は青系だ。次いでモノトーン。
時々紫が顔を覗かせた。
紺色。
藍色。
勿忘草。
ペパーミント。
プルシアンブルー。
我ながら、どれだけ青が好きなのだろうと苦笑いするほかない。
実際に青のイメージだと言われたことが沢山あるし、一番しっくり馴染むのも青。
特に紺色は肌が綺麗に見えると褒められた。
成人式の振袖も青系だ。
瑠璃色をベースに珊瑚色と藤色と鳥の子色で雪輪と季節の花々を描いたアンティーク調の柄行きがお気に入りの振袖は、象牙色の袴と合わせて来年に控えた音楽院の卒業式にも着る予定である。
パジャマはクローゼットではなく引き出しだろうと我が身に言い聞かせるが、次に開けたのは学習机の引き出し。
こちらも苦笑いするほかなかった。
小学生時代から一貫して最も好きな科目は音楽だった。
引き出しには小学校から高校までの音楽の教科書が残されているのだ。
音楽が好きだとはいえ、小中学校でありがちなクラシック音楽の感想を強要するスタイルはいかがなものかと疑問を抱いたのは否めない。
蘭の友達には感想の強要が原因で音楽の授業が苦手になった者がいる。
友達が言うには楽しい、かっこいい、綺麗な曲などの感動はあるものの文字に表すと上手く表現できなくなるらしい。
小学校低学年を過ぎれば思ったままを単純に綴った感想文は許されない。
何でも良いからと言っておきながら気取った文章で小難しく綴った感想を提出することが暗黙の了解になっている。だから書けないのだ、と。
そして、蘭自身は好きな楽曲ほど言葉で表現したくない性分であった。
言葉に出せば安っぽくなってしまう。そんな気がした。
中学時代に所属していた吹奏楽部では部員が安っぽい言葉で茶化しながら、時としてからかいの材料にしながら楽曲を汚してゆく様を何度も何度も目の当たりにした。
「言葉で表したくないことなんて沢山あるのにね」
書かなければ点数がもらえないので気が進まないとは思いながらも感想を書いて提出した。
高校や大学時代のアナリーゼは楽曲を分析するためなので純粋に楽しめた。
独り言と共に教科書をパラパラとめくる。
カーペンターズと井上陽水、サンタ・ルチアが掲載された教科書は高校一年生の時のものだった。
2011年冬・2
教科書をしまい、一段下の引き出しを開けた。お菓子の缶。バレンタインシーズンに駅前の百貨店で買い込んだチョコレートの缶だった。
女の子が好みそうな花のイラストをあしらった缶を開ける。
懐かしい!
そう叫びたいのを堪えて蘭は缶の中身を手に取った。
パールホワイトの携帯電話。高校入学前に最新式として発売された、いかにもな女の子向けの外見を誇る携帯電話はイルミネーションの色を自由に変えられるところが気に入っていた。
ご丁寧に充電器も取ってあるので、動くかは定かではないが充電してみよう。
缶の底には紙。おおかた友達からの手紙かと思ったが手に取るなり五線が透けて見えたので手紙ではないとわかる。
心当たりがあった。桜の舞う中で、白い携帯電話から聞かせたあの曲。
「やっぱり……」
――無題――
五線譜には手書きの音符。カノン進行を覚えたての頃に初めて作った曲だった。♭の数と位置から変ロ長調だとわかる。
中学三年生の頃に放送されていた学園青春ドラマの中で、ある生徒が作った曲をクラスメートがリコーダーで演奏するシーンがあった。ドラマの1シーンがきっかけで、受験生の身なのにと罪悪感を抱きながらも作曲に関心を持った蘭は、合間を見ては作曲方法を調べたのである。
幸いにも蘭は地頭が良く、秀才と呼んでも過言ではない成績をキープしていたので「優等生の気分転換だろう」と許された。
携帯電話にはオリジナルの着信メロディを作れる機能があり、これ幸いとばかりに春休み中に作った楽曲が『無題』だった。
うまい曲名が思いつかないまま慌ただしく時間は過ぎ、記念すべき初めて作った楽曲は未だに名無しのままであったのだ。
いい加減名前をつけてくれよ。
名無しの楽曲がそうせがんでいるように思えた。
桜の下に、かすかに聞こえる変ロ長調。
柔らかな色彩の花々を思わせる温かい曲調は懐かしさすら抱かせた。
真新しい制服の少年少女が顔を寄せ合い白い携帯電話を覗き込む。整った鼻筋の美しさを目の当たりに、少女だった蘭は頬を染めてはにかんだ。
目を覚ました時には空が白みかけている。
チョコレートの缶は、時間を逆戻りさせる玉手箱。
昨晩は懐かしい夢を見た。花梨と同じ、膝丈のキルトスカートの制服。
少年の髪からはライムのような、爽やかな柑橘の香りがした。
会いたくて仕方ない、愛しい人は少年の姿で少女の蘭に会いに来た。
帰省の期間は限られているが、大好きな友達は元気に過ごしているだろうか。
少なくとも、今でも年賀状と誕生日を祝うメッセージを送り合う友達の無事は確認できている。
蘭はパジャマの上に綿入れのフリースの上着を羽織り、窓を開けた。
白鳥が飛んでいる。これから川へと向かうのか。
青みを帯びた山肌に白雪を被った吾妻連峰が光り輝いていた。
2001年12月

あの子がいる。はやる気持ちは加速する。真冬の風に逆って、飛鳥川一哉は自転車を走らせた。
冴える空気が肌に冷たい。
近代的に舗装された道は北へ向かうにつれ時代を遡るようにノスタルジーを帯びてくる。
あの子はもう、無人駅に着いているはずだ。
あの子に会いたいがゆえのじれったさを抑えて「木枯らしに吹かれて」を口ずさみながらメタリックブルーの自転車を無人駅の駐輪場に停めた。
無人駅の階段を登った先に『あの子』はいた。
モノトーンの背景に濃紺のセーラー服が映え、身じろぐ度にスカートの裾はひざ下で揺れる。
既に時代遅れと言われながらもこの地域では女子中学生のスカートはひざ下丈と決まっており、それは10年先も変わらないだろう。
しかし、時代遅れの長いスカートこそ伏し目がちな少女の品格を引き立てるにふさわしかった。
濃紺の制服の鮮烈さに一種の懐かしさを覚えたのは、初めて彼女と出会い恋を覚えたその時を思い起こしたからだ。
あの時、彼女は濃紺に少しだけ紫を加えたプルシアンブルーのワンピースを着ていた。
プルシアンブルーの少女の頑とした強さを宿す眼差しが和やかに弛んだ時、まだ十つの一哉は己が恋心を自覚した。
俺はこの子が好きだと。
セーラー服の少女・音澤蘭は一哉を見つけるなり引き結んだ唇をほころばせた。
容姿に恵まれている蘭だが、かわいいという言葉が甘すぎて似つかわしくないと思えるのは170センチの長身とプライドが高そうな切れ長の目のおかげだろう。細面の輪郭に高い鼻筋が貴族的である。
しかし、一哉はこの少女が誰よりも可憐だと信じている。
怖いものなどなさそうな堂々とした蘭の姿は気高き女王の風格を漂わせるが、気を許せば年相応の無邪気さを見せる。
はにかみの笑顔は大人びた彼女を可憐な少女へと変貌させた。
「ごめん。蘭の方が早かったね」
蘭は顔を2回ほど左右に動かし、そんなことはないと告げた。落ち着いたアルトは理知的な少女に似合い、よく通った声質だ。
伏し目がちな麗しい目元も魅力的だが、やけに唇へ目が行くのは蘭が元吹奏楽部員でフルートを受け持っていたからだろう。赤みのさした唇は形良くまとまり、薄すぎない厚さのおかげかクールな顔立ちながらも冷たさはなかった。
「一哉ちゃん、キョンキョンの木枯らしに吹かれて歌ってた?」
「いや、ALFEEの方だよ。聞こえてたの?」
「うん。白い季節のあたりから。髪乱れてる」
「え、マジ?」
好きな女の子に乱れ髪を指摘され、一哉は窓ガラスを鏡にして前髪を整える。ガラスに映る一哉はつり目がちの大きな目が特徴的で、それでいて尖った印象はない。
二枚目の整った顔立ちをしながらもがさつな手つきで乱れ髪を直す姿は普通の少年そのもの。太めの、凛々しい眉が前髪に隠れた。
髪を整える一哉をおもしろそうに見守る蘭もまた、快活で真っ直ぐな一哉を恋い慕う。
向き直る彼の、幼さを残す面立ちに見え隠れする精悍さが眩しい。
眉が髪に隠れたところで電車がホームに入る時を告げるシグナルが鳴り響いた。
二人が降り立つ狭いホームには小型の券売機があり、蘭は券売機のボタンを押して用紙を取り出す。この用紙はどの駅から乗車したかを証明するもので、電車内で目的地までの切符を購入する仕組みなのだ。
商店が点在する西側に相反し、東側には古い住宅地が広がる。フェンスで隔てた先には小規模なブドウ畑、そして信夫山を臨む。
「蘭、コート着てないね。寒くない?」
この時の蘭はコートを肘にかけており、襟元にマフラーを巻いていた。タータンチェックのマフラーは良質のウールでできている。
マフラーに隠れて見えないがセーラー服の下には白いブラウスを着込んでおり、この着方は市内の中学生によく見られた。
県内のよその市町村では丸首の白い運動着を重ね着する着方がありがちだが、蘭はセーラー服の襟元からのぞく白い丸首を「幼稚で野暮ったくて汗臭そう」と嫌ったので、ブラウスを重ねるという地域特有の着こなしは都合が良い。
「私、寒いのは平気。一応、持ってはいるけど。そう言う一哉ちゃんこそ学ランのままだべした」
垢抜けた容姿にそぐわない、方言混じりのセリフ回しは蘭が田舎娘であると確信させる。言葉どおり、蘭は腕にコートをかけている。
ミトンをはめた手に向けて吐いた息が白く染まる。雪を模したノルディック柄のミトンは、今年の2月末に一哉からもらった誕生日プレゼントだ。
一哉はというと陽気な笑みを蘭に向けて袖をまくって見せた。
目を爛々と輝かせて笑う顔は人馴れした猫の甘えた表情に似ている。
「偶然だね。俺もコートが邪魔だから学ランの下にニットのカーディガン重ね着してんの。男子でもカーディガン着るの市民権得てるらしいよ」
「カーディガン、グレーなんだ。黒線がかっこいいね」
学生服の袖口からのぞくカーディガンの袖。黒線が二本入っている。
「いいでしょう? でも俺、本当はピンクが着たい」
「学生向けでピンクのカーディガンなんて売ってないんじゃないの?」
「あったらかわいいと思わない? 俺、ピンク好きなんだけどなあ。マゼンタじゃなくて桜色っぽい薄いやつ」
男物でマゼンタみてえなケバケバしい色はあるのになんで桜色ってないんだろ、と一哉は言う。
マゼンタをケバケバしい色と評する発言に、派手好みではない性分が垣間見えた。
「……確かに学生向けでピンクのカーディガン、実際にあったらかわいいかも。女の子以上に女の子らしいところあるよね、一哉ちゃんって」
「え、なになに、例えば?」
「ホワイトデーにクッキー焼いてくれたところ。あと常に裁縫セット持ち歩いてたり臆せずに少女漫画とか少女小説読むとこ」
女の子以上に女の子らしいと蘭は言うが、一哉はがさつでズボラな少年であった。
通学用の革靴を履いたままハゲた部分を靴墨で塗りつぶし、学生服を着たまま取れかけた金ボタンを最も手近にあったからとピンクの糸で縫い付け、穴のあいた靴下を履いたまま繕うなどのズボラさを垣間見せる有り様だ。
(しかしながら針で手指を刺すなどしたことはなく、尚且つ整った縫い目をしているので手先が器用なのは間違いなかった)
蘭の通う中学の女生徒達から美男子と持て囃される彼が同性の友人に恵まれるのは人並みに備えた「がさつさ」に由来するのだろう。
幼少の頃から現在にかけてやらかした男子ならではの失敗は数しれずだ。
「クッキーは進藤先輩と奥山と松っちゃんと焼いたんだよ。あの先輩、料理上手いんだ。気に入った? また作ってあげよっか?」
「きゃあ! ありがとう!」
甘いものに目がない蘭である。それまで冷静に徹していたが両手を組んで満面の笑みで歓喜し出した。
「コート持つよ。両手塞がってやりにくいでしょ」
ほら、と一哉は蘭に向けて手を差し出す。
「えー、申し訳ないよ」
持つよ。
悪いからいいよ。
押し問答の結果、蘭が折れた。
がさつでズボラな彼も蘭の前では紳士的に振る舞いたいらしく、ホームに着いた電車のドアが開くなり先にどうぞと促した。八代亜紀の『雨の慕情』の振り付けを連想させるその動きはぎこちなく蘭の笑いを誘う。
それでも彼の気づかいが嬉しかった蘭は礼を述べて電車に乗り込んだ。
電車内では小学校高学年ほどの少女が二人、好奇のまなざしを蘭と一哉に向けてささやく。
「あの人達、付き合ってるの?」
「彼氏かっこいいよね?」
「だから。美人はイケメンとくっつくんだねぇ」
微笑ましい対話に悪い気はしないが、蘭は一哉をイケメンという軽い言葉で言い表したくなかった。
当時は気づいていなかったが、心のどこかで一哉を神格化していたのだと成人した蘭は振り返る。
このことを一哉に話すと笑われ、同時に自分も蘭を神格化していたと打ち明けられた。
二駅を過ぎた頃に乗務員が来たので蘭は用紙を差し出し、運賃と引き換えに切符を渡された。
終点の福島駅で二両編成の電車を降り、薄暗い通路を抜けるとバスターミナルが、続いて百貨店と大通りの並木が目に飛び込む。
他県から来た一哉は知らないが、蘭が小学生の頃は県庁所在地らしい華やぎに満ちたこの街もここ数年のうちに勢いに欠けると指摘を受けがちだ。
しかしながら仙台は目と鼻の先、新幹線を使えば東京まで一時間で行くことができるので欲を出さない限りは生活するに不自由しない。
何よりも、春には果樹園や近くの山を花々が彩り、雪を被った山並みが見える景色を蘭は気に入っている
2001年12月・2
この日、二人は共通の知り合いが出演するミュージカルに招待されたので市街地へと出向くことになっている。
街うちの会場までは徒歩でも苦にならない距離にあった。信号待ちの間、二人はもうじき控えた高校受験の話題に花を咲かせた。
「一哉ちゃんも祥蘭受けるんだっけか?」
「そうだよ? F高と迷ったんだけどな。うちのところの男子はほとんどF高か祥蘭に分かれるんだよ」
一哉が着ている学ランの襟元には深い青緑のラインが走る。私立翠楓学園中学の制服。
90年代に設立されたその学校は歴史こそ浅いものの、一応は受験校と銘打つだけに地域のトップ校から二〜三番手の進学校への合格者を輩出した。会話中に名前が出てきたF高校は県北地区でトップの偏差値を誇る県立の男子校。
そのような受験校でも高校が併設されていないのは、公立至上主義の地域性から県立の進学校に生徒を取られることが明らかとの判断によるものだろうと地域の人達は語る。
「へえー。一哉ちゃん、F高余裕そうなのに? 医学部志望でしょう?」
意外だと発言しながらも、蘭は嬉しそうだ。
「野郎だけだとすげえ気楽そうだけど、女子がいねえ分ムサイって聞くからなぁ……」
「そう言うよね。F高じゃあり得ないだろうけど、男子ばかりだと学校によっては夏場の休み時間はパンツ一丁で過ごすって本当なのかな」
含み笑いの蘭に、声を立てて笑う一哉。
端から見ればプラトニックで好ましい二人だが、まさか男子校にまつわるむさ苦しい噂話をしているなど考えてもみないだろう。
青信号に変わり、どっと人垣が動く中でも二人はパンツがどうだ、男子校がどうだと語る。
人垣はスーツにコートを着込んで昼食を食べに行くサラリーマンと百貨店帰りの小洒落た服装の主婦が大半だが、冬休みなので制服姿の中高生も入り混じっていた。
「パンツ一丁って誰に聞いたんだよ?」
「慧ちゃんから。友達の親戚がどこかの工業高校に通っていて、工業系って野郎ばかりだから夏の休み時間はパンツ一丁になるらしい。女の先生も『あー、はいはい』って軽くあしらってるらしいよ」
当然、校風や地域差もあることは承知していると蘭はつけ足した。
「ある意味開放的だなぁ」
「頭のネジが吹っ飛んでない限りできないね」
「あとは修学旅行ん時に野郎共が一つの部屋に集まってエロいやつ見るってモジャ山に聞いた」
そこで蘭の含み笑いは爆笑へと変わる。くだらない下ネタは嫌いではない。
「えー、もしかしてやってたの?」
「いやいや、高校生ならともかく中学生がそんなのやる度胸ねーっつーの。俺、委員長だしそんなのやってたら学級裁判にかけられるわ」
学級裁判のところで二人は昭和の面影を残す百貨店へと足を踏み入れた。住んでいれば必ず何回かは世話になるであろう百貨店は地元の顔である。
香水の甘い香りが漂う中で、きらびやかなジュエリーと高級そうな化粧品が並ぶ様子に蘭の気持ちが浮き立つ。
中学生には高嶺の花だが、いつかは私も……と夢を見たい。
「一哉ちゃん、お昼食べたら花屋さん寄っていい?」
蘭はそう聞きながら、ふらふらとアクセサリーの並ぶ陳列棚へ歩み寄る。「これ、好き」と輝いた表情でガラスのヘアアクセサリーを手にしたが、値段を見て元の位置へ戻した。
「いいよ。花、慧ちゃんにあげるの?」
ヘアアクセサリーは青いカットガラスを組み合わせて蝶々を模したバレッタであった。蘭に似合いそうだったので予算内なら蘭にプレゼントしたいと値札を覗き込んだ一哉だが、その直後に諦めた。
「夏目漱石が八人……」
2~3ヶ月分のお小遣いが飛んでゆく価格帯は蘭が引きつった笑顔で陳列棚へ戻すのも頷ける。
「そう。やっぱり赤い花束かな。慧ちゃん、赤が似合うから」
百貨店で昼食をとり、さらに花束を買った後に会場へと着いた。
二人が観るのは県立祥蘭高校で芸術を専攻する生徒によるミュージカルの定期公演であった。
演目は「くるみ割り人形」。
終戦後に設立された祥蘭高校だが80年代に芸術専攻クラスが新設されて以降、クリスマスシーズンの伝統となっている。
「俺、前から思ってたんだけど芸術科って男子いるの?」
芸術科。だいたいの地元民は祥蘭高校芸術専攻クラスをそう呼ぶ。
芸大や音大への進学を目指す生徒が対象で、美術と音楽、そして東北では珍しく舞台芸術を学べるのだが、その大多数は美術系の生徒であった。
次いで音楽系が多く、音楽が盛んな地域性と、遠方の市町村から入学する者、果ては他県から越境入学する者が必ずいるのでそれなりの人数はいた。
しかし、舞台芸術系はその珍しさから毎年一桁の生徒しか入ってこないので(少数ながらも毎年志願者が必ず出るので廃止はしないもよう)一括して芸術専攻クラスとして募集をかけていると聞いていた。
「若干名はいるみたいだよ。でも舞台芸術を専攻しているのは女子のみだろうね」
「男役は女子がやるのかあ」
「だから人気なんだよ。男装の麗人って昔から女性の憧れだもんね」
パンフレットには明らかに女子とわかる生徒が王子の服装を纏っている写真が掲載されていた。
頭からすっぽり被る仕様の、やたら歯が目立つ人相の悪い仮面を手にキザったらしく微笑みを向けているので二人は苦笑いするしかない。
この王子に扮した女生徒こそ、会話中に登場した『慧ちゃん』であった。
「去年なんてネズミの王様役で仮面被っての出演だったから、顔出したくてウズウズしてたみたい。慧ちゃん、根っからのナルシストだから……」
「あー、それ姉ちゃんに聞いたような気がするわ。なんか聞いてるだけで笑っちゃうようなこと言ってた」
「あれだべ。『先輩は何考えてんだか。私の顔を仮面で隠すなんて宝の持ち腐れだろ』」
「それだ」
二人は顔を見合わせ、声を抑えてクスクスと笑う。肩をすくめて、ロングヘアの毛先を揺らして笑う蘭の無邪気な笑顔。一哉は胸がうずく感覚にとらわれる。
「同じセリフで私にも愚痴ってたっけね。だから私言ったの。『慧ちゃんがナルシストこじらせて天狗にならないように先輩が気を遣ったんだべー』って。そしたらどつかれた」
「俺なんて玄関先で慧ちゃんが姉ちゃんに言ってたの聞いて爆笑してたら『殺虫剤ぶっかけられたみたいに転げてるアホな弟は放っておけ』って姉ちゃんに言われた」
「清子さん……男嫌いで有名だけど弟にも容赦ないね。つまり笑い転げていたんだ?」
「うん、笑い転げてた。あれでも小さい頃は優しかった記憶あるんだけどなあ……いや、可愛いがられたか。かずこちゃ~んって頭にリボンつけられたり母ちゃんの化粧品塗りたくられたし」
姉のいる弟ならではのエピソードだ。
一哉の二学年上の姉である清子は蘭が通う公立中学の卒業生なのだが、蘭が入学した時には既に「合唱部のサヤコ先輩は男嫌いだ」という噂が浸透していた。
蘭自身も清子が蔑みのまなざしで「これだから男は……」と不機嫌そうに言い募る場面を何度か目の当たりにした。「これだから男は……」の後に、大概は「野蛮」「嘘つき」「ガキ」「汚い」の言葉が続く。
蘭とは親しい間柄で、清子が男嫌いで幼稚園から福島に越してくるまでは女子校生活だったと知った時には「どうして女子校に行かなかったのか」と聞いたところ、福島に引っ越したのが4月だったので福島に女子中学があることを把握していなかったという。
「たぶん姉ちゃんも来てるよ」
清子は『慧ちゃん』と親友同士なので、用事がない限り公演には必ず行く。一哉によると一つ前の便の電車に乗ったそうだ。
「かずこちゃん、見てみたいかも」
「やめて。恥ずかしい」
客席が暗転しアナウンスが流れる。アナウンスは放送部の生徒が担当していた。
携帯電話の電源はお切りください。
2001年12月・4
そして、舞台が始まる。
暗闇に流れる『くるみ割り人形』の小序曲は音楽系の管弦楽専攻の生徒による演奏だ。
華やかなクリスマスの情景。
舞台のセットは美術系の生徒が担当し、大掛かりな舞台装置は使い回すがメンテナンスを施し、経年劣化した装置は新たに作り直すのだ。
舞台のど真ん中に鎮座する巨大なクリスマスツリーは初演から受け継がれているが、てっぺんに飾る星は毎年異なるという。
クリスマスツリーの周りで子供に扮した生徒が舞い歌う。
舞台芸術専攻の生徒のみでは足りないので、音楽系で声楽を専攻する者は半ば強制的に、果ては学科の枠を超えて希望者を募り、厳正なる審査の上で演者として駆り出されていると蘭は『慧ちゃん』から聞いている。
女の子役はふんわりとした膝下丈のワンピースをそれぞれ着ており、動く度にスカートの裾が跳ねる。男の子役はスーツだった。ハーフパンツもいればフルレングスのスラックスの者もいたが、いずれも女の子と比べて落ち着いた色味である。
クララとフリッツがくるみ割り人形を取り合う。
主役だけにクララの髪型と衣装が一番目立った。普段ならできないであろう、リボンで飾った縦ロールのツインテールに赤を基調としたワンピース。ワンピースの素材はベルベットだろうか。
至るところから「衣装、かわいい」と聞こえる。
決して安価では済まない材料を衣装に使うあたりに、この舞台には一切の妥協が見受けられない。
ここまでの時点で『慧ちゃん』はいなかった。
クリスマスパーティーが終わり、夜にネズミの王様が現れる場面になると騎士の衣装を纏い仮面を被った『くるみ割り人形』が文字通り躍り出た。
舞台の上手からバク転をしながら現れ、スミレ色の衣装を翻して舞い、剣を手に華麗に戦う。
客席から黄色い歓声が響く。
寝巻き姿のクララがスリッパを投げ、ネズミの王様と子分が退散すると舞台が暗転した。
暗闇にセリフだけが響いた後、スポットライトに照らされた王子が舞う。
バレエ作品のくるみ割り人形に登場する『王子のバリエーション』を模した動作で、美しい王子は長い手足を自由に繰り出し舞台を駆け巡る。
「慧ちゃんだ!」
声の大きさをを抑えつつも、その声は興奮を隠しきれない。一哉は自身の右側へちらりと視線を移す。隣には、目を輝かせる蘭がいた。
蘭の黒い瞳に映るは、片足を振り上げながら舞台の中央で回転を繰り返す男装の麗人。
クララの手を取り、伸びやかに歌う凛々しい王子はどこか蘭に似ていた。
◇◇◇
「お二人さん、相変わらずお熱いですねぇ」
芯の通った声がロビーで休んでいた二人の耳に届いた。
声の聞こえた方を見やると、ブレザーの制服を着た少女がこちらへと向かってくる。
少女は長い睫毛に縁取られた、ナツメ型のキリッとした瞳で二人を見据えた。
王子の衣装から制服に着替えた『慧ちゃん』こと橋本慧子は誰が見ても清楚な女学生でしかない。
真っ黒なロングヘアと紅い唇が雪白の肌に映える。
「慧ちゃん!」
赤い花束を手に蘭は駆け寄る。
「すごくかっこよかった! 花束持ってきたよ」
蘭の口振りは親しげだ。
「ありがとう。さりげなく蘭の花が一輪入ってるね。蘭が選んだのかい?」
小さいが、真紅の花束は人目を引くのに充分だ。
真紅の中に一輪、白いデンドロビウムが咲いていた。白い花びらに、かすかな桜色を帯びている。
「俺が提案したの。いいセンスだと思わない?」
赤い花束を手にする慧子は苦笑い混じりで、凛と響く声で続けた。
「生意気な小僧もセットで来たなぁ? さすがはサーヤの弟だな。悔しいけどセンスが良いのは認めるよ。まったく、かわいい又従妹を取り上げられて悔しいったらないわ」
又従姉妹。
互いの母親が従姉妹同士の蘭と慧子は、パッと見は別人でもどこか似ている。
例えば、先述の雪白の肌に紅い唇。
そして、意志の強そうな切れ長の大きな眼。
蘭の身長が慧子に追い付いた頃には後ろ姿の区別がつかないと間違えられることが増えた。
冗談めかしたセリフ回しだが、確かに慧子は蘭に対してシスコンに近い感情を抱く。
三歳離れた実妹はいるが、同性の親族の中で蘭が最も年齢が近いのでもう一人の妹のような存在であるのだ。
姉が欲しかった蘭も小学校低学年の頃に慧子がドイツから隣町へ越して以来、度々彼女の自宅を行き来した。
背が高いためか大人びた印象を持たれがちな蘭だったが、慧子の前では飼い主の後をついて回る猫のように甘えん坊だった。
彼女を姉同然に慕い、憧れて手本にした。
バレエを習い、声楽とフルートを学び、髪型を真似た。オシャレも慧子から教わった。
おかげで小学校ではセンスの良い女子として一目置かれ、影響されて始めた習い事のうちフルートでは突出した才が芽生える。
利発な慧子に少しでも追い付きたくて、知識を得るために様々な本を読み漁った。
苦痛などない。
頭に知識を詰め込み、わかることが増えることが兎にも角にも楽しかった。
幼い頃から「賢くて、きれいなお嬢さん」と評された蘭であるが、所作の美しさやファッションセンスの良さは一朝一夕では身に付けられない。
姉代わりの慧子がいたからこそ、今の蘭がいるといっても過言ではなかった。
2001年12月・5
しかし、慧子が中学校に入学する年の春に新潟から一哉が橋本家の目と鼻の先に越してからは関係性が変わった。
それまでの蘭は「慧ちゃん、慧ちゃん」と後をついて回ったはずだったのに、口を開けば「一哉ちゃんは?」である。
男の友達なんかいらない。
そう断言していたはずなのに、慧子の目から見ても蘭が一哉に恋をしているのは明らかだった。
慧子にしてみれば、愛娘に恋人ができショックを受ける父親の心情に等しい。
別に一哉を恨んではいないが「慧ちゃん、慧ちゃん」と慕っていた甘えん坊を取られて面白くないという感情は否めなかった。
だから慧子は一哉をおちょくり、からかう。
「やだなあ。慧ちゃん、俺が蘭ちゃんと仲良いからヤキモチ焼いているんでしょう? やーねぇ」
慧子からの挑発に一哉は身振り手振りを交えて応戦し出す。井戸端会議に興じるおばさんの動きを模しての動作だ。
気安い関係性だからこそ許される振る舞いだ。
「はっ。『グリーンスリーブス』を三つの不細工な顔を持つ緑色のモンスターだと勘違いしてたやつに言われたくはないわ」
女子高生というよりは女学生と表現したいような上品な容姿の慧子だが、その口振りはがさつだ。
小声で「グリーンスリーブスはもうやめて」と言う蘭は口を押えて肩を震わせる。
記憶を辿れば中一の冬頃だった。
一哉は小学生の時分、清子が音楽の授業で『グリーンスリーブス』を習った話を夕食時に聞いて『三つの恐ろしい顔を持つ緑色のモンスターの歌』と勘違いしてしまったことを、笑える失敗談として蘭に打ち明けた。
その上『三つの顔を持つ緑色のモンスター』のイラストを生徒手帳のメモ欄に即興で描き上げて蘭に見せたのだ。
元々、漫画家志望だった一哉はやたら絵が上手かった。
一哉が描いたのはケルベロスのように胴体から三つの首が生え、メデューサのように髪を逆立てた醜女の頭がついているモンスターのイラスト。
ご丁寧に蛍光グリーンのマーカーで色を塗ってみせた時には蘭は目に涙を浮かべ、腹を抱えて声を引きつらせて笑っていた。
以来、彼の笑える失敗談を聞くと蘭は困ったことに思い出し笑いが込み上げる。
そして、堪えられず笑うしかなかった。
アンサンブルコンテストのフルート四重奏での演目が『グリーンスリーブス』だと話した時にこの失敗談を聞いたはずだ。
中一の蘭は『グリーンスリーブス』が好きな楽曲なだけになんて酷い勘違いをするのだ、どうしてくれるのだと笑い転げながら一哉に抗議した。
「えー、それ俺が小学生の頃にやらかしたやつでしょう? 面接で『魔王』さドイツ語で歌ったの誰だっけか?」
「『魔王』でねっつーの! 私が歌ったのは『ローレライ』だ」
目立つ慧子には数々の伝説、またはガセネタ混じりの噂が存在した。
中学時代に生徒達の間で度々囁かれた「高校には行かないで宝塚音楽学校を受験する」という噂はガセネタであるが、慧子が舞台女優志望で、部活動には入らずバレエと声楽を習っていたゆえに真に受ける者が出ても不思議ではない。
そして慧子は元々宝塚音楽学校を志望していたが「せめて高校だけは出て欲しい」と両親に大反対されたという事実も噂に発展する原因となった……と蘭は慧子の妹から聞いている。
以来、受験シーズンとなると「こんな噂あったね」と必ず話題に上がるのだ。
噂の中には
・バレンタインデーにはもらいきれないほどのチョコレートをリヤカーに乗せて運んでいた
・週末にはファンの女の子とデートに行く
・実は男だ
などの無理のあるものも出回った。
高校入試の面接で『魔王』をドイツ語で歌ったという噂もそのうちの一つだった。
「魔王にしろローレライにしろ魔物じゃんねー蘭ちゃん?」
ローレライは美しいイメージだが、やはり双方とも魔物だ。
二人のやりとりがおかしすぎたので蘭はマフラーに口元を埋めて、声を押し殺して笑う。
「なんなら魔王様が姫君連れ去ってやろうかぁ? その前にこの生意気な王子ひねり潰してくれるわ」
「あ、いたいた!」
「慧子のやつー、翠楓のインテリいじめてんでねえどー?」
向こう側から慧子と同じ制服を着た女子高生達が歩いてくる。
女子高生達は蘭と一哉より離れた場所にいたが、学生服の襟元に走る深緑のラインは遠目にもわかりやすかった。
「新聞社から取材着てっぞー」
女子高生達は口調からして慧子とは相当親しいことがうかがえる。口調こそくだけてはいるし、中には2000年代初頭の女子高生らしく着崩した格好の者もいたが、総じて進学校の生徒特有の硬派な雰囲気を纏う。
「そろそろ戻るわ。小僧、蘭に何か奢ってやりなー?」
かわいい又従妹と生意気な小僧に向けて軽く片手を上げて、慧子は女子高生達に混ざって颯爽と去り行く。
揺れる黒髪が艶を放つ様が二人の目に眩しい。その後ろ姿に一哉は声をかけた。
「だいじょぶー。奢るつもりだからー」
その言葉を聞いて蘭は「申し訳ないからワリカンでいこうよ?」と遠慮するのだった。
2001年12月・6
◇◇◇
「ごめんね。慧ちゃん、悪乗りしやすくて」
黙っていれば男子が寄り付くだろうにと蘭はあきれ顔だ。
セーラー服の上に着込んだ濃紺のスクールコートにも無地のセーラーカラーがついていた。
母が中高生の時分に愛用していたスクールコート。
セーラーカラーが珍しいからと母が大事に保管していたものを蘭が気に入り、母にねだって譲り受けてもらった。
会場を後にした二人は肩を並べて来た道を引き返す。これから甘いものを食べに行くところだ。
『くるみ割り人形』にはグミの人形やジンジャークッキーの人形が登場し、果てはお菓子の国まで登場する。
セリフのみの登場だが、言葉を聞くだけで胸が踊るオレンジジュースの川。クッキーの壁。砂糖菓子でできた住民達。
甘党の蘭にはたまらない。
それゆえ、蘭が甘いものを食べに行きたいとリクエストしたのだ。
駅前通りにコーヒーとババロアが評判の喫茶店がある。
コーヒー味のババロアにソフトクリームをうず高く盛ったデザートは蘭のお気に入りで、なおかつ地元民にも愛される。
「いやいや、もう慣れてるって」
通常は、男女問わず年少者達の良きアドバイザー役に徹する慧子。
一哉から見ても頼りになる姉御だが、蘭が絡んだ途端に『蘭ちゃん争奪戦』の敵方になるのは恒例だ。
「くるみ割り人形のミュージカルって、毎年芸術科の生徒が台詞や舞台装置を作るんだよ」
「思ったより大がかりだったよなぁ。生徒があれだけの装置を作るなんてすげえよ」
「慧ちゃん、あの美貌で演技力高いから宝塚の男性役さながらに女子からすごく人気あるの」
「歓声がすごかったもんな」
態度のがさつさはもちろんだが、慧子の持ち味である豪快な性格に恐れをなして男子が寄り付かないことを二人は清子から聞いている。
反面、女子からはタカラジェンヌさながらにかつぎ上げられ、堂々たる振る舞いはかっこいい姉御肌と絶大な人気を誇った。
その人気は他校にまで及ぶ。
清楚な身なりは当時の奇抜さを追及した流行からかけ離れているが、気品漂う風貌は流行り廃りにとらわれず、自我を確立している生き様がかっこいいと人気を高めた。
(慧子は2000年代初期のファッションをケバケバしいと蛇蝎の如く嫌い、頑なに清楚な装いに固執した。令和の時代になった現在でも「嫌いなファッションが流行った時期に貴重な青春時代がぶつかったこと」をたいそう悔しがっているという)
今回の公演に来た一般の観客は、ファンの女の子達で占められているのだった。
「今回の公演は芸術科設立以来の最高傑作だと語り継がれるよ。それだけに今後慧ちゃんを超える生徒がいない、今回の公演を超えられないんじゃないかって、前から危惧されてるの」
マフラーに口元を埋めて語る蘭の横顔を一哉はじっと見つめる。
「蘭、来年のくるみ割り人形出てみたら?」
「無理だよ! 音楽に回るならともかく、演技なんて……」
演劇の経験なんて学習発表会と文化祭の演劇ぐらいだ、プロ志望には及ばないと蘭は言う。
「蘭はバレエやってたでしょう? 黒鳥だっけか? 小学生ん時に見せてくれたあれ、すげえかっこ良かったよ」
黒鳥。
バレエ作品の『白鳥の湖』に登場するオディールのことだ。
ヒロインになりすまし王子を欺く悪役だが、32回転のバリエーションと黒い衣装に憧れるバレエ少女は少なくない。
蘭もその一人だった。
発表会の小品集で「最後だから憧れているバリエーションを踊ったら?」と講師に勧められて黒鳥を舞うことが決まり、レッスン場に残って練習に励んでいた時になりゆきで忘れ物の月謝袋を届けに来た一哉に披露した。
小学校卒業を控えた時期と覚えている。
「数年のブランクがあるもん。ブランクを甘く見たらダメだよ」
中学校入学以降は音楽に専念したいと蘭がバレエを辞めて三年が経過していた。
ブランク云々は当事者が言うと妙な説得力があるが、黒鳥になりきった自信に満ちた笑み、爪先が床を蹴る音、疾走感溢れる楽曲に合わせて舞う姿。
全てが少年の胸を離れない。
「えー……。蘭ちゃんは美人だし背高いし、絶対に舞台に映えるって。俺、見てみたいな」
目を見開く蘭の頬が紅潮する。好きな人に容姿を褒められるのは嬉しい反面照れくさい。
寒いのに、頬が熱い。
「なら、一哉ちゃん出てよ」
照れ隠しで蘭は冗談を口にする。
「えー、恥ずかしいよ。まさか王子じゃないよね? またはくるみ割り人形さ壊す悪ガキの兄ちゃん?」
冗談とは承知しているが、一哉は敢えて乗ってみた。
フリッツを「くるみ割り人形を壊す悪ガキ」と呼ぶあたりが"がさつ"だが、フリッツは原作の時点で悪童という設定があるので蘭は反論しない。
少し前に一哉は蘭にこう話した。
もしも自分がフリッツと同じ"悪さ"をやらかしたならば清子から即座に鉄拳制裁を喰らうだろうと。
そしてクララとフリッツの姉のルイーゼは優しすぎるとまで述べた。
「クララ。一哉ちゃん、顔きれいだし合唱部だから声通るし、きっと映えるよ」
「やだよー。それこそかずこちゃんだろ」
「一哉ちゃん、ピンク好きじゃん。ピンク着られるかもよ?」
今年のクララは赤い衣装を着ていた。
数年間使い回す時もあれば、経年劣化したりサイズが合わない時には新しく作り直すそうなので、来年の衣装はピンクになる可能性がなきにしもあらずだ。
蘭によればクララの衣装は5代目。パンフレットに記載されていたという。
「だいたい、俺が受けるの普通科だよ。学科の枠超えて募集するにしてもたぶん女子が採用されるだろうし、まだ受験すらしてないよ」
この段階で、冗談のつもりが半ば本気になり会話が白熱したと互いに知った。ほぼ同時に声を立てて二人は笑い出す。
「ねえ、蘭ちゃん」
「なあに?」
「ババロア食べたらルミネ行かない?」
さすがに百貨店で見た蝶々のバレッタは易々と買えない値段だが、駅ビルならば予算内で買えるそっくりなものがあるはずだ。「これ、好き!」とバレッタを手に取った蘭の輝いた表情が目に焼き付いている。
蝶々がなかったら、冬らしい雪の結晶も良い。
羽のデザインならば、それこそ本物に近い造形が似合うだろうな。
妹が好んで身に付けているハートや丸っこい天使の羽といったかわいらしいものよりは、大人っぽい意匠を凝らしたクラシックなものが蘭に馴染むだろう。
頭の中で蘭の髪にヘアアクセサリーを取っ替え引っ替えして思い巡らす一哉の傍らで、蘭が「うん、行きたい!」と賛成の声を上げた。
2011年 大好きなあなたへ
帰省して3日目の早朝。
蘭はキャリーバッグを手に、雪混じりの道を進んだ。
自宅から歩けばすぐに西道路の交差点に出られる。
交差点の四隅には地下道。住民の要望により作られた地下道にはずいぶんとお世話になったものだ。
蘭より向かって右側にはお土産物の薄皮饅頭を扱う菓子店があり、車道をはさんだ左側の地下道からは男女を交えた中学生グループがわらわらと出てくる。
かつては同じ制服を着ていたと懐かしく思うと同時に、足早に過ぎた10年が二度と戻らないとわかると切ないような物悲しいような気持ちになる。
蘭なりに、中学時代にやり残したことはいろいろあるのだ。
中学生グループは冬休みの部活動に参加するのだろう。コートの下に制服を着ているので文化部の生徒に違いない。
蘭の記憶と比較して、2011年の男子中学生と2000年代初期の男子中学生の風貌に大差はないが、女子中学生の髪型や通学カバンのアクセサリーに流行が表れているなと感心した。
厚く切り揃えた前髪と、部活マスコットに時代が反映されている。
しかし、スカートは相変わらずのひざ下丈だった。
楽譜とアルトサックスを模したデザインから女子中学生は吹奏楽部員とわかり、よく見れば男子中学生の中には黒い楽器ケースを持っている者もいる。
ケースの大きさから見て、クラリネットかオーボエか。
憶測をしていると、楽器ケースの男子中学生が車用の信号が赤になったのを機に横断歩道を渡り出すフリをしたので、女子中学生のうち1人が
「フライングゲットしてんなよー」
と笑いながら咎めたてた。
菓子店の手前にさしかかるとちょうど中学生グループとすれ違う形となり、学校から指導されているのか中学生グループは蘭に向かって元気のよい挨拶を投げかける。
「おはようございます」
蘭は微笑み、帽子を軽く上げた。
少しだけ、かっこつけてみたくなったのだ。
中学生グループはというと蘭に大人の余裕を感じたのか
「超かっけえ‼︎」
と騒ぎ立て、歩道を駆け出していった。見知らぬ中学生にかっこいいと褒められるのは気分がよい。
この日の蘭は新潟へ向かう予定だ。
福島駅から会津若松行きの高速バスに乗車した後、会津若松駅から新潟行きの高速バスを乗り継ぐ。
父の実家がある会津若松には年に数回は立ち寄っていたので親しみがあり、伝統を感じさせる街並みも気に入っている。
余裕があれば会津塗りの専門店で小物やらアクセサリーやらを見繕い、甘味処であんみつを食べたいところだが、早く新潟入りを果たしたいので寄り道はできない。
磐越自動車道の黒森トンネルで県境を越え、しばらくは雪にまみれた山間部が続く。
山と山の間を縫うように流れる阿賀野川は壮観で、絵画の世界にありそうな景色だと蘭はいつも思う。
雪にまみれた平野部を走るとようやく街並みが見えた。
田園地帯にいきなり現れる摩天楼。
白に染まった田園の向こう側で新潟の街並みは銀色に光る。
曲がりくねった高速道路から大型ショッピングセンターとスタジアム、そして高層ビルが見えると新潟入りした実感が湧いた。
蘭の新潟入りの目的は一哉に会うため。
一哉はここ、新潟市に住んでいるのだ。
2011年 大好きなあなたへ・2
新潟駅の万代口のバス停で降り、待ち合わせ場所の駅前に着いた蘭は自分が先に来ていたとわかる。
約束の時間まであと10数分はあるので、どんなセリフで再会を喜ぼうかと考えを巡らせていた矢先に
「わっ‼︎」
と背中を押された。軽く押されたとはいえ、突然のこと。
不意打ちに脅かされ、蘭は間抜けな声で叫んだ。脈打つ胸元をさすって振り返る蘭の目には陽気に笑う青年が映る。
青年の背丈は蘭より頭半分ほど高く、青紫の冬物のジャケットがよく似合う。
「びっくりした。一哉ちゃん、先に来てたなんて」
3月に新潟市内の国立大学の医学部を卒業した(しかし震災により卒業式は中止となった)一哉は研修医として医療の現場に携わる。
彼は親族の経営する精神科の診療所を継ぐ身なのだ。
職業柄か少年期と比べ理知的な雰囲気を纏い、猫みたいな丸さを帯びたつり目がちの瞳は切れ長に走るなどの変化は見られたが、陽気でお人好しな性格が現れているのか凛々しい青年の顔ながらも愛嬌がある。
片手を一哉の右肩に乗せ、もう片方の手で彼の左頬を軽く引っ張り、蘭はわざと怖い顔を作ってみせた。
「せっかくの再会をどんな甘い言葉で飾ろうかなって考え込んでたのに?」
蘭は本気で怒ってなどいない。不意打ちのいたずらには慣れっこであるし、一哉だからこそ許された。
「ごめん。不意打ちでキャアって言う蘭の反応がかわいいから見たかったんだ」
申し訳なさそうに言い訳を述べる一哉には、持ち前の素直さがにじみ出る。
蘭は彼の素直さも好きなのだ。つねった頬から手を離す蘭は照れ笑いを見せ、愛し君の腕に手を絡めた。
「白山さま行こ? あと信濃川」
蘭は高校卒業後に新潟の大学へと進学したが、一哉とは異なる大学であった。
母が卒業した女子大の、音楽学部だった。
大規模ではないものの附属幼稚園から高校までが併設され、きめ細かい教育方針と卒業後の就職率の高さには定評がある。
高校入学から大学卒業までを新潟で過ごし寄宿舎生活を送っていた母。
昭和期でも首都圏に住んでいれば身近に選択肢が山ほどあっただろうし、ましてや母は横浜のエスカレーター式のお嬢様学校の出身であった。
そんな母が中学卒業後の進路としてわざわざ受験してまで新潟の学校を選んだ理由は「故郷から敢えて離れて見聞を広めたいから」。
表向きではそう語ったが本心は「雪国に憧れていたから」であった。
前者も偽りではない理由だが、どちらの理由が大きいか、となると圧倒的に後者が勝る。
真相を知った雪国出身の友人達には雪を甘く見すぎだと怒られたそうだが。
大学時代のデートコースは専ら万代橋を臨む信濃川沿い。それにもかかわらず、蘭は飽きたと言わなかった。
蘭はこの景色を愛している。
柳の枝がたなびく、風薫る初夏。
川縁を桜の紅と萌木の緑に染め上げる春。
医学部でまだ二年間の大学生活が残っている一哉より一足先に大学を卒業し、瑠璃色の振袖に薄藤色の袴を合わせた姿で川縁に佇む蘭に四年間も同じデートコースで飽きなかったかと聞いた時に蘭は静かに告げた。
「一哉ちゃんの育ったこの景色が好きだから」
そう返して蘭は一哉にもたれて肩に顔を埋めた。
その時、編み上げた髪に挿した春蘭のかんざしが震えるように揺れたのを彼は忘れはしない。
──いつか、またこの街に戻るね。だから、待ってて──
桜の季節にまだ届かない、忘れ雪の頃に交わした約束。
一歩ずつ、着実に約束に近づいている。
2011年 大好きなあなたへ・3
万代橋を臨むベンチに腰掛けた二人。信濃川を挟むように建築物が立ち並び、海沿いにそびえ立つは朱鷺メッセだった。夕方は新潟港まで行こうかと話が出ている。
「えー、スマホの待ち受け私?」
一哉のスマートフォンの待ち受け画面は昨年のハンブルク市内のクリスマスマーケットで撮影した、ホットワインを飲んでいる蘭の画像だった。「彼氏に送る画像を撮ってあげる」と同じ音楽院に通う日本人の友達に撮影してもらった写真が思いの外出来が良く、蘭のSNSのアイコンにもなっている。
「会えないんだもん、待ち受けにしたっていいでしょう?」
目の前の笑顔につられて蘭も笑う。
「かくいう私も一哉ちゃんとのツーショットが待ち受けだしなあ」
ツーショットといっても蘭と一哉は遠景に写り、蘭は袴姿である。常に目にしやすい待ち受けにすることで、会えない寂しさを紛らわせた。
「この画像すげえお気に入りなんだけどよぉ、デメリットといえば患者さんから医師仲間から『きれいな彼女さんだねえ。今度彼女さんの顔見せて?』って言われる。蘭、うちの大学のやつらからカチューシャの君って呼ばれて人気なんだよ。あくまでも芸能人に憧れる感情みたいなもんだけどね」
一哉は苦笑いだった。恋愛感情のない憧れとはいえ、同性の医師仲間と男子学生が蘭を持て囃す度にやきもきさせられたと。
「えー、何やきもきしてるの? 私だって一哉ちゃんが女子に告白された噂を逐一聞かされる度に落ち着かなかったよ」
余計なお節介焼きが報告してくるんだよね、とため息をつく。
「医学部は生命に関わるだけに精神的にきついから心の拠り所としてマドンナが欲しいんだと思うな。女子もそうだよ。蘭、うちの大学の女子からもカチューシャ様ってモテてたよなぁ」
照れた表情で間を置いて、一哉は「蘭はきれいだし、かっこいいから」と続けた。
はにかみの表情の蘭はしばらく黙った後、被っていた帽子を取る。
ロシア風にも見えるウールのトーク帽はコートと揃いの青みのグレー。
「前から気になっていたけど、カチューシャつけてるからカチューシャの君ってこと?」
冬らしいベルベットのカチューシャが黒髪を彩る。
このカチューシャは大学時代、カチューシャが流行り出した頃に一哉と選んだお気に入りのものだった。
「うん。それもあるけどロシア民謡のカチューシャが愛し君と離れ離れで、俺らも国境を越えた遠距離恋愛だからそれにあやかってカチューシャの君って誰かが呼び始めたんだ」
互いに手を取り合い、立ち上がるとコンサートホールの空中庭園へつながる階段をかけ上る。
白山神社からコンサートホールを囲むように桜の木が植えてあり、春先には見事な桜に覆われる。
「一哉ちゃん、初めて会った時に『桜、好きなの?』って聞いてきたの覚えてる?」
「覚えてるよ。蘭、きれいだったから……」
照れ笑いの後、一哉は語る。
「あの時の蘭、同じ子供だったのに神々しくて言葉が出なかったな」
「だから、しばらく無言だったの?」
「そっ」
澄んだ瞳が蘭の姿を映す。
一哉と初めて会った、十つの春。
黒目がちな、ひたむきな澄んだ瞳の輝きを十つの蘭は美しいと感嘆した。
蘭は目を伏せた。寒いのに熱に浮かされたかのように頬が熱い。
「……蘭ちゃん」
桜色に上気した蘭の頬を一哉は両手で挟み込むように触れ、小さく整った唇に己の唇を重ね合わせる。
待てなかった。キスをしたい衝動を抑えられなかった。
唇が離れた。元から赤みの強い唇に蘭はルージュを重ねている。彼のために美しくありたいと願う女の見栄が愛おしい。
「ずっと、蘭に会いたかった。離したくない。一緒にいたいよ。蘭ちゃん……」
蘭の背に腕を回し、強く、固く抱き寄せた。
先ほどのキスとはうってかわり、食むように深く口付ける。
その時、蘭の後ろ髪が優雅に跳ね上がったのを一哉は知らない。
全身がキュッと縮むような切ない感覚に囚われ、胸が締め付けられる蘭の目からは、はらはらと涙がこぼれ落ちる。
蘭に半ば覆い被さり、弓なりに反った体勢は躍っているようにも見えた。
雪灯りの中で初めて唇を重ねて以来、数えきれないほどのキスを交わした。
2011年 大好きなあなたへ・4
新潟で過ごした大学生活は楽しかった。
雪国の人は無口でよそ者への当たりがきついと噂で聞くが、少なくとも蘭の周りではそんな話が嘘であるかのように人懐こくおしゃべり好きで温かい人達に恵まれた。
一哉の親友の家で営んでいる学生アパートを借り、互いの部屋を行き来したり、花見の季節とクリスマスを迎える度に宴会と称してアパートの仲間と食卓を囲んで談笑した。
時には仲睦まじさを夫婦のようだ、いっそのこと同棲してしまえとからかいを受けたこともある。
勉強面と経済面では決して楽とはいえない生活も、アパート仲間と過ごした時間は励みになる。
早生まれの蘭が一哉より一足遅く成人した暁には、コンビニで買い込んだチューハイと百貨店で買い込んだケーキ、洋菓子の詰め合わせで二人で祝杯を上げた。
蘭は酒に強い方だがビールを苦いからと好まず、専らカルーアミルク。またはカシスオレンジ、ライチのフレーバー、はてはメロンソーダを模したチューハイという甘い酒ばかりを選んだので、一哉からは酒に関してまで甘党なのかとからかわれた。
蘭が学生アパートで過ごす最後の夜、パジャマ姿のまま身体をかつてないほどに強く抱き締められた。
一哉は蘭を抱き締めたまま告げる。
「俺、頑張って医者になる。医者として認められた暁には蘭をお嫁さんにするよ。蘭が帰ってきたら一緒に指輪選びに行こうね?」
ほとんど何もなくなった部屋の中で蘭は一哉にしがみついて、肩に顔を埋めて声を上げて泣いた。
一頻り泣いて、涙で濡れた頬に唇が優しく触れた後、深く熱いキスを交わす。
彼の腕に抱かれ、会えない日々を補うように濃密な時間を過ごした。
厳しい、辛い実習。
理不尽な出来事で心が折れてしまう瞬間が幾度となく襲いかかったかもしれない。
優れた容姿ゆえにやっかみも買ったであろう。
負けじと彼は世のために邁進する。
愛しい彼のために、蘭は祈る。
蘭がその澄んだ瞳の輝きに救われたように、偽りのない優しさに支えられたように、たくさんの人の支えとなり苦しんでいる人達が救われますように。
――彼の瞳の輝きが、永遠でありますように――
「私も会いたかった、一哉ちゃん」
コンサートホールを取り囲む公園は空中庭園と呼ばれた。
空中庭園を散策する最中で、地方でも活動できる時代になってきたね、と蘭は寒空を見上げて語る。
この空中庭園では大学時代、散策がてらに練習と称してフルートの演奏を始めては人だかりができたものだった。大学の音楽仲間と共に演奏したこともある。
桜と雪柳の香りに包まれ、フルートを奏でる蘭の姿を一哉からは水に放った魚のように生き生きとしていると言われた。
蘭が自分らしくある時間を生きた場所。
空中庭園は特別な場所だ。
「いい時代になってきたと思うよ。今までは、芸術を仕事にするには東京に行くスタイルが主流だったけど、私はそれが納得できなかったんだよね。地方に学校が少ないのが現状だから仕方ないんだけど……」
ビル街から工場の煙突、悠然と流れる信濃川と波の静かなる日本海、雪を頂く山並みを見渡した後、蘭の瞳は一哉をとらえた。
「私はそれが気に入らなかった。何でもかんでも東京に行かないとできなくて、地方が蔑ろにされている現実が子供の頃から納得できなかったの」
顔だけを振り返って一哉を見据えていた蘭は、身体の向きを正し、改めて真っ直ぐに彼と向き合う。
憂いを帯びている蘭の伏し目がちな瞳は、この時、頑とした力強さを宿す。
――幼い日の一哉が恋した、高潔な蘭がそこにいる――
「結局、地方在住の人なんてお金がないと好きを極めるなど無理に等しいという事実だよ? 不公平だと思わない?」
それなら、私が時代を変えてやる。
地方でも、好きを仕事にできる時代に。
地方でも好きを仕事にできるんだと証明してやる。
高校時代、芸術専攻クラスで三年間主席で通してきた蘭は教師陣から東京の有名な芸大や音大を薦められたが、それを拒み母の卒業した女子大を選んだ。
敢えて地方の大学を選んだのは、その強い思いが根底にあるからかもしれなかった。
「たった一度の人生だよ。人生80年というけど、いつ死ぬかもわからないんだよ?」
2011年 大好きなあなたへ・5
「私を金持ちのお嬢様だから好きなことをやらせてもらえてるって勘違いしてる人がたまに出てきたけど、それは違う」
妬みで心ない言葉の刃を蘭へ向ける者が少なからず存在したのも事実だった。
同じ志を持つ者が集まった大学と高校では見かけなかったが、中学生活では何度か遭遇した。
妬み嫉みを向ける者達は、蘭に直接は言わずに陰口に留めておく程度ではあるが、時々わざと蘭の耳に届くように聞こえよがしに言う時もあった。
運良く聞こえなかったとしてもお節介焼きな同級生が報告してくる。
蘭は意に介さない風を装いながらも耳に入れてくるなと不愉快に思ったという。
「地方公務員の、一般家庭の娘だよ? お母さんが若い頃に働きに出ていたお陰で、うちにはある程度の収入があった」
「蘭の母ちゃん、デパートガールだったんだっけか?」
「そうだよ? 私もレッスンが最優先ではあったけど、家庭教師とか中等部と高等部の後輩の勉強を見るバイトで稼いでたよ。いろいろ言う人にも遭遇したけど、決して楽していたわけじゃないから」
大丈夫。俺はわかってるよ、と一哉は蘭の手を握る。
十つの春。桜の下で出会ったあの頃から、音楽と共に生きる蘭の姿をいつも見守ってきた。
好きなことをやるからには決して周りに文句は言わせないと豪語するだけに学業は優秀であったし、コンクールで好成績を修めたのも一度や二度ではない。
蘭の生き方には妥協がない。
そんな彼女の生き様をかっこいいと一哉は尊敬しつつも、身体を壊したりしないか、心がすり減ってしまわないか……と心配したのも一度や二度ではなかった。
試験中だかコンクール間近だか、蘭は大学とレッスンへ向かう以外に部屋を出ることが減った期間が何度かある。
学生アパートの大家が作った惣菜を一哉が手渡しに蘭の部屋まで会いに行った時の、蘭が見せたホッとした笑顔に切なくなり抱き締めた。
肩を震わせ泣き崩れる蘭の身体から力が抜けた感覚は、未だ忘れはしない。
楽をしているなど、誰が言えようか。
「確かに音楽家は私の夢。でもその先に更にやりたいことが見えてきたの」
蘭を抱き寄せたままの一哉は相槌を打ち、スッと切れ上がった涼やかな目尻とルージュを塗った唇に見惚れつつ二の句を待つ。
「私は幸いにも、お父さんもお母さんも教育熱心だから音楽の勉強ができる高校に行けて、大学にも行かせてもらえて、留学までさせてもらえた。もし違う家庭に生まれていたらお金がないとか将来が保証できない仕事に就くなと言われて違う道を歩まされたと思うよ。現実は、後者が圧倒的に多い」
蘭の切れ長の瞳に硬質な光が宿るのを一哉は見逃さなかった。
ミステリアスな雰囲気を纏う女性、時折だが一哉の目には蘭がそう映る。
雪の如し透き通る清らな存在感は気品すらあり、花の如し儚げな可憐さを見せたと思えば、鋼の如し凛とした力強さを垣間見せる。
恋人は常に相反する美しさを身に纏う。
「若いうちは金銭的にも実力的にも実現は無理かもしれない。だから数十年も先になるのは目に見える。でも、好きを仕事にするのを諦めざるを得ない人達をバックアップする事業を始めるって、素晴らしいことだと思わない?」
今、腕の中にいる美しい恋人は鋼の如し強さを帯びていた。
2011年 幸せな時間
「カチューシャ様だ!」
「おかえりぃ」
「あの人が噂の彼女さん?」
学生アパートの仲間と新顔、そして雪かきがてらに作った大小の雪だるまが二人を出迎える。
一哉が通っていた大学の医学部にほど近い場所に学生アパートはある。二階建ての10部屋で、防犯の目的からか女子学生は二階の部屋を充てがわれた。
会える日は互いに窓辺に「WELCOME」と書かれたプレートをかけ、試験勉強の期間やコンクールの遠征などで会えない時は「Sorry」の文字に泣き顔のついたプレートをかける。そんな日常だった。
既に医学部を卒業している一哉だが金銭面を理由に研修医である今も学生アパートに居着いていた。アパートの住民の中では一番年上ゆえにアパートの主的な扱いを受けているという。
住民は皆、大学生と専門学校生だ。
大半は近県の出身者で構成されているが中には県内の離れた市町村から来ている者も存在し、魚沼あたりの出身の学生は実家から定期的にコシヒカリが送られてくると聞く。
「先輩の彼女、噂どおりきれいな人っすねえ」
女子学生は同性ゆえの気安さから蘭にまとわりつき、男子学生は一哉に遠慮していることもあってか遠巻きだ。
しかしながら若干名の新顔の男子学生は遠巻きにしつつも頬を赤らめて首を伸ばし、女子学生に囲まれた蘭を覗き込もうとする。
女子学生に至っては一哉との馴れ初めを聞きたがるので、交際を始めたのは高校卒業の頃だが小学生の時から相思相愛だと聞くと「純愛にも程がある!」と羨ましがれた。
「蘭さん帰ってきたから、うちで宴会やっちゃう?」
「アホ。先輩は久々に蘭さんに会えたんだからここは一足遅いクリスマスデートを優先させろや」
久しぶりに目の当たりにする学生達の掛け合いが微笑ましい。
「お土産あるよ。と言ってもグミベアーだけどね」
「グミベアー食べたい!」
「蘭さん、今日はどこ泊まるの?」
照れ笑いで蘭と一哉は顔を見合わせ、蘭が答えた。
「一哉ちゃんの部屋」
人垣からヒューッと口笛が鳴る。
「やっぱり、二人でどこか行くんですかぁ?」
「夜景見ながらバーで飲むとか? 憧れるわぁ」
「それ、あんたがやりたいだけじゃん」
「先輩達かっこいいからバーでカクテル飲みながら夜景を眺めるなんて様になってそうだよね」
好き勝手な憶測で盛り上がる学生達だ。
「えーと、これから決めるところだよね?」
「蘭が行きたいところ言っていいよ」
「悪いよ。だから一哉ちゃんに任せるよ?」
「遠慮しないでいいから」
しばらく勿体ぶって、蘭は躊躇いがちに告げる。
「だって、雪の弥彦と角田の灯台なんて行きたいと言える?」
そりゃあ躊躇いもするわ、と一同は納得せざるを得なかった。
2011年 幸せな時間・2
「覚えていたんだ……」
据わった目に、石をも砕きそうな前歯。
人相の悪いくるみ割り人形を前に、一哉はいろいろな意味で絶句するほかない。
10年も前のつぶやきを蘭が覚えていたこと。
くるみ割り人形が想像以上の人相の悪さであること。
くるみ割り人形が白衣の医者の姿であることにも、だ。
くるみ割り人形は
「何デスかぁ? 何かワタクシに文句ありマスかぁ?」
と、歯をカタカタ鳴らして凄んできそうな面構えだ。
いいえ、ありません。
むしろ求めていました。
「蚤の市で見つけたんだよ。本場のくるみ割り人形」
晴れていたら夜空にオリオン座が浮かんでいるであろう時間帯だ。
学生アパートで後輩達と談笑した後、二人は街中で昼食をとり、更に百貨店内のカフェをハシゴした。
カフェでケーキを堪能し、商店街を歩いたり信濃川に沿って歩いて港を見に行った。
内陸部の生まれでほぼ海なし県民に等しい蘭にとって港は珍しい場所。
なおかつ留学先のハンブルクは都会の港湾都市で、色とりどりの灯りをちりばめた港の姿に新潟港の面影を重ねたと蘭は海を眺めて語る。
夜の9時前には一哉が住んでいる部屋へ戻ってきた。
持ち込んだスーツケースにはくるみ割り人形が潜んでおり、一哉が風呂に入っている間にコタツの上に置いたのだ。『Merry Christmas 会いたかったよ』と書いたクリスマスカードをくるみ割り人形の前歯に挟み込んで。
「ありがとう蘭ちゃん。見てよ、この据わった目。欲しかった面構えだよ」
腹話術を操るように一哉はくるみ割り人形の歯を鳴らして、笑顔で礼を述べる。
「でも、なんでくるみ割り人形が人相悪いって知ってたの? ああ、慧ちゃん家にあったよね」
「そういやあったね、人相が極めて悪いくるみ割り人形。中三の時に慧ちゃんからチケットもらったでしょう。それで『くるみ割り人形』の内容ってどんなだっけ、ってパソコンで調べたら画像が出てきたんだ」
◇◇◇
「くるみ割り人形って、すげえ人相悪いやつあるのね」
中学三年生だった一哉が蘭にそう話したのは『くるみ割り人形』のミュージカルの公演後に立ち寄った喫茶店で珈琲ババロアを食べていた時のこと。
彼はババロア以外にもココナッツカレーを頼んでいたので蘭はどれだけ食べるのだと苦笑したが、かくいう蘭の前にはババロアとパフェが並ぶ。
ソフトクリームがうず高く盛られたババロア自体がかなりの量であるというのに、蘭は嬉しそうに「わあ、おいしそう!」と言っては爛々と目を光らせ、どちらを先に手をつけようかとババロアとパフェを見比べていた。
結果、蘭は珈琲ババロアから先に食べることにした。
「慧ちゃん家のも大概だけどね」
慧子がドイツから持ち帰ったという本場のくるみ割り人形もまた相当な人相の悪さだった。
下がり眉なのに目が怒っているし、やはり石を砕きそうな前歯を持つ。
作家物の立派な造りをした人形であったが、用事があって橋本家に来た子供がことごとく変な顔だと笑い出す有り様だ。
人相の悪いくるみ割り人形がクリスマスになると橋本家の玄関先に飾られるのを蘭は毎年のように目にしていたので、くるみ割り人形の御面相がどれほどのものなのかを知っている。
「いやいやいや、パソコンで見たやつはそれ以上の悪人面だったよ」
ババロアの上のソフトクリームをスプーンですくい上げて一哉は笑う。いつの間にか、器の中のココナッツカレーは綺麗さっぱりなくなっていた。
彼は笑うと猫みたいな大きな目が幾らか細くなり眉尻も下がるので、凛とした精悍な顔は優しげなものへと変わるのだ。
「欲しいよなぁ。あれだけ人相悪いと却ってかわいいというか、愛おしいよ」
私はあなたの笑顔が愛おしい、とは恥ずかしくて口に出せない蘭であった。
◇◇◇
当然だが蘭にもクリスマスプレゼントが用意してあり、一哉はくるみ割り人形の手に透明な箱を持たせて「じゃじゃーん」と言いながら手渡した。
箱の中から見えたのは、透き通った花びらを一枚一枚組み合わせた、繊細な桜の髪飾りだった。日常的に使うよりはフォーマルな服装に似合う。
「綺麗! ありがとう!」
蘭の満面の笑顔が近づき、一哉の頬に唇が触れる。自ずと表情が弛む。
蘭は白地にペパーミントグリーンで雪の結晶を描いたパジャマ姿だった。その上に中綿の入った水色のノルディック柄の上着を羽織っている。
「蘭、大学の卒業式につけるかんざしで迷ってたの覚えてる?」
「そうだね。桜か蘭の花か迷ったなあ」
悩みに悩んで、その時は物珍しいからと春蘭のかんざしを選んだのだった。
「卒業式につけていい?」
「日本人らしくていいじゃん。つけていきなよ、桜」
「桜、私達にとって思い出の花だからね」
洗い髪の蘭は一哉の肩へとしなだれかかる。
先ほどにバーで酒を飲んできたのだが、素面でも二人っきりになれば彼にもたれて甘えたに違いない。
「ねえ、一哉ちゃん」
目を伏せてはにかむ蘭の頬は上気している。
一哉より先に風呂に入ったので、ある程度時間が過ぎていたのだが湯上がりのように赤い。
「気が早いけど、私ね、春に女の子が生まれたら『さくら』って名前つけたい」
人気がある名前だから周りと被りそうだけど……と蘭は続ける。
「さくらちゃん、かぁ。かわいいね」
「私、花の名前でしょう? だから娘が生まれたら花の名前をつけるのいいなって思ってたの」
同じ高校に進学した春に、蘭っていうんだ、かわいい名前だね、と会う人会う人に褒められているところへ出くわしたのを思い出した。
「春以外なら、どうするの?」
わくわくした表情で一哉は二の句を待つ。
「生まれた季節に準じた花にするの。椿とか、アヤメとか、夏なら百合。雪割草から雪でもいいかな。個人的に睡蓮や鈴蘭の花も好きだけど名前には難しいよね」
やはり名付けには当人のセンスが出るのだろうか。夏の花にちなんだ名前など沢山あるのに、百合を選ぶあたりが蘭らしい。
「一哉ちゃんは、どうかな? 私一人の趣味で名付けるのも不公平でしょう?」
「お淑やかな感じでかわいいと思うよ。蘭って名付けセンスいいよなあ」
「よかった。名付けって複雑だからちょっと自信なかったの」
「全然問題ないよ。俺ね、女の子の名前で一番好きなのは……」
紺色のスウェットの両腕が迫るのを見て蘭は抱き締められるかと期待したが、お姫様のように抱き上げられた。
「蘭が一番好き!」
抱き上げたまま視線が合い、驚いたのと恥ずかしいのとで蘭は一哉の首もとに顔を埋めた。
かわいい名前だね、蘭ちゃんと弾んだ口調で言いながら蘭をベッドに横たえて、布団を被せると一哉は「蘭ちゃん、寒いだろぉ?」と布団にもぐり込む。
布団の中で一哉は蘭の身体をしっかりと抱き締めた。
高校時代は弓道部に所属していた一哉。その腕はしなやかに見えて思いの外力強い。
くすぐったそうに蘭は肩をすくめて笑う。
「一哉ちゃん、あったかいよ」
猫が暖を取るように蘭は身体をぴったりとすり付けた。
「蘭ちゃんは柔らかいねえ。すごくいい匂いする」
2011年 幸せな時間・3
まだ薄暗い時間帯だった。薄明かりに浮かぶは蘭の端整な寝顔。
枕に流れる黒髪は大和絵のように優雅な趣があり、長い睫毛が可憐だ。
蘭が学生アパートにいた当時、月に数回は同じ布団で寝ていたが(どれだけ仲良いのだ)蘭は横向きに寝る癖があった。今日も一哉に顔を向けて寝息を立てている。
冬物の分厚いパジャマの袖から覗く白い手。
少年だった頃、セーラー服の袖から見えた手首の白さに見惚れたものだった。
会えなくなる寂しさに負けて蘭の身体を堅く抱き締めた夜。
布団にもぐり込む蘭は「実は、もう一つ夢があるの」と照れた表情で打ち明けた。
――一哉ちゃんの、お嫁さんになりたい――
愛しい女性へ抱く想いが今、溢れ出す。
溢れた想いは、まずは熱い口付けにと表れた。
唇へのキスを繰り返した後、額からまぶた、頬へと移り、再び唇へと戻る。
艶めく髪を愛でるように撫で、潤んだ瞳から溢れ出した涙を一哉は指先で拭った。
蘭は何度も、一哉の名前を呼んだ。
一哉ちゃん。
一哉ちゃん。
愛しています。
大好きです。
離れたくない――!
大好きです。一哉ちゃん……!
蘭は首もとにしがみついて「大好きです」と繰り返して泣いた。
アパートを出る前の夜も、蘭は同じ言葉を紡ぎ出して泣いていた。
涙に濡れた、白百合の肌。
雨上がりの花にも似た、可憐な美。
一哉にしがみついたまま蘭は息を弾ませて、しゃくり上げる。
蘭……。
蘭ちゃん。
大好きだよ。
一緒にいたいよ。
離れたくない!
離したくない!
大好きだよ。蘭ちゃん……!
思い出しただけで気恥ずかしくなった一哉はその場でのたうち回りたい衝動にかられるが、それはできない。
隣には蘭が寝ている。
のたうち回る代わりに、黒髪をそっと撫でた。
滑らかな、絹にも勝るきれいな髪。
憧れで、触れてみたかった。
蘭の自慢の、みどりの黒髪。
手に触れることが実現したのは、いつの頃か。
蘭を好きだと打ち明けた、14歳の夏の夕暮れか。
15歳の雪解けの季節か。
雪明かりの中で初めてキスを交わした18歳の冬の日か。
目覚めたら、蘭はきっと恥ずかしい素振りを見せるだろう。
そしてアパートの仲間達から冷やかされるだろう。
2011年 幸せな時間・4
昼食はアパートに隣接する戸建てに集まることになり、正午前に蘭と一哉は部屋を出た。そこはアパートの大家一家の自宅である。
大晦日の夜の料理が豪華なのは、この地域特有の文化だろうか。
夜にはだいたいの学生が帰省していないからと昼食時に集まって宴会をすることになったのだ。
もちろん、自家用車で帰省する者もいるため酒は出さない。せっかくの酒どころなのにと残念がる者も出たが。
塩引き鮭。くるみの佃煮が入った太巻き。いくらの入った雑煮。八ツ頭の入ったのっぺ汁。
夫人の実家のある長岡市の寺泊から取り寄せた海産物。
「うわあ! すっげえ!」
「いつも以上に豪華だね!」
「これよ、これ。くるみの入った巻物!」
大家一家の苗字は本間という。
新潟市内でよく見かける苗字だが佐渡にルーツがあると聞く。
大家の息子で一哉の親友である本間純平は蘭とも顔見知りで、蘭をカチューシャさんと呼ぶ。
本間家の玄関前で再会するなり、相変わらず仲良いなと冷やかした。
福島で聞いた新潟時代の思い出話に度々登場する本間は飄々としたマイペースな人物で、一哉とはまた違う猫みたいな顔をしていた。
三日月型の細い目とアヒル口にも似た特徴的な口元で、どら猫の風情がある。
本間は台所から大皿を運んできた。
特に蘭が喜んだのは大家が作った大和芋の煮っ転がし。
大学時代、一哉が蘭を気遣って部屋まで届けた惣菜だった。
本間夫人がニコニコと笑いながら煮っ転がしの入った鉢をテーブルに置く。本間とそっくりな、猫みたいな顔だ。
「わあ! 懐かしい!」
少女のように歓声を上げる蘭を見て「蘭さんがテンション上がってる!」と女子学生が囃し立てた。
「蘭ちゃん大和芋の煮っ転がし好きだったでしょう?」
「はい!」
「でも、本当に残念ねえ。今日、福島に帰るの?」
「そうなんです。三が日過ぎたら日本を出るので……」
「こっちで二年参りできたらいいのに……ねえ?」
「ごめんね、おばちゃん。俺達ね、今日福島さ行かなきゃならないの」
一哉も研修先の病院の正月休みを利用しての帰省だ。正月休みが明けるまでに往復せねばならない。
「私も、もう少し日本にいられたら白山様への二年参りに行きたかったです」
アパートに越してきたその日に初めて挨拶に出向いた時、夫人はかなり昔から蘭の話を本間の口から聞かされていたと語る。
そして、やれ美男美女カップルだの女優さんみたいだのと蘭を褒めそやし、息子同然の一哉の恋愛が成就したことを白山様のお陰ということにしてたいそう喜んだ。
白山様。コンサートホール近くにある白山神社のことである。
「大丈夫だよ母ちゃん。そのうちカチューシャさんは飛鳥のやつと結婚する運命なんだから」
照れ笑いの蘭は夫人へと目を向ける。
「いつか、白山様へ二年参りに行きます」
一哉ちゃんと、とつけ加えたので蘭は学生達から更なる冷やかしを受けたのであった。
酒が入っていないにもかかわらず宴会は盛り上がりを見せた。
男子学生が「昨晩はお楽しみでしたね」と耳打ちをしたのでくるみの佃煮入りの太巻きを頬張っていた一哉は顔を真っ赤に染め上げて咳き込み、ある女子学生は咳き込む一哉の背中をさすっている蘭の頭に『ローエングリン』の婚礼の合唱を歌いながら白いレースの生地を被せた。
(この学生は服飾の勉強をしているので部屋に多数の特殊な生地を持ち込んでいる)
調理学校に通う学生は自慢の腕を振るい寺泊の海産物をふんだんに使った豪勢な料理を作ってみせた。
「今日は、五十嵐君と小野塚君はいないんだ?」
蘭が名を挙げたのは双方とも本間と同じく一哉と古くからの親友だ。
前者は「いがらし」ではない。「いからし」といい、新潟特有の読み方をする。
五十嵐達也は歯科医師の跡取り息子である。
名前が名前なので、一哉とセットで有名な野球漫画を引き合いにからかわれたと蘭は聞いている。
一哉が通っていた大学の歯学部を卒業し地元の歯科医のもとで研修に励んでいる五十嵐だが、残念ながら県をいくつも跨いだ先の親戚に会うため来られなかったらしい。
後者の小野塚紳士に至っては調理学校を卒業後、料理人としての修行に励む身で今回のような集まりでは召集されるのが常だ。
無口だが、名前どおり紳士的で人柄の穏やかな小野塚は年末のかき入れ時で参加できなかった。
「すげえ残念がってたよ。でも、タッちゃんもシンちゃんも地元民だからいつでも会えるからね。蘭は友達と会うの?」
「留美達がうちに来てくれるよ。高校の友達とも会いたかったなあ。街中で会うかもわからないけど」
白い生地を被ったままル・レクチェ味のノンアルコールカクテルの缶を手にしている蘭だが、その頬は酒が入っているかのように紅潮している。
その姿を、一哉は少年の頃にノートの空白に描いた落書きと重ね合わせた。
ベールを被った、白いドレスの美しい女性。
隣に座る恋人を生き写した女性に描き足すならば、花束を描き足すだろう。
名前に合わせた蘭の花では陳腐だろうか。
白百合、鈴蘭、銀梅花。
柑橘やジャスミンの花も良い。
花の名前は、よく見る花しか知らなかった。
それまで知らなかった、見過ごしていた花の名前は全て蘭が教えてくれた。
花も音楽も、新しい世界を知りたいと踏み込むきっかけを作ったのは紛れもなく蘭であった。
男が関心を持つなんて、と憚られそうで周りに言いにくいことも不思議と蘭になら打ち明けられた。
男が花に興味を持つなんて女々しいかな、と聞くと蘭はあっけらかんと答える。
「優しい印象でいいじゃん。私、男には猛々しさより誠実さと凛々しさと優しさを求めるから」
薔薇やカトレアといった艶やかな大輪の花も長身で華のある蘭に似合っているが、きっと彼女ならば清楚でスッキリとした雰囲気の花束を持ちたがる。
――派手な洋蘭よりは春蘭や朱鷺草みたいな控えめな蘭が好き――
十つの春に、蘭はハキハキとした口調でそう答えた。
一哉は大和芋の煮っ転がしを食べつつ思い巡らせた。
2011年 幸せな時間・5
この一日ですっかり打ち解けた学生アパートの後輩達。決まった予定とはいえ、せっかく仲良くなれた後輩達との別れは名残惜しい。
蘭と一哉はこれから福島へ帰省する。
高速バスを乗り継ぐのだ。
「蘭さん。また来て下さい」
「私ら、まだ一年生なので来年もいます」
もちろん来るよ、と蘭は笑って答える。なぜか後輩達は一哉の部屋に「突撃」していた。
後輩達から見た一哉はよほど気安い存在で、良き兄貴分として慕われているのだとわかる。
綿入れ半纏を羽織った男子学生が一哉に腕を絡めて、しなを作って「センパ~イ、行っちゃだめ~」と言う姿は後輩達の笑いを誘う。
「や~だよ。俺は蘭ちゃんと帰るの」
「楽しかったよ。また来るね」
鍵を閉めるからと促され、まずは後輩達が部屋を出て、蘭と一哉の順番で出た後にドアを閉めた。
新潟と会津の山奥は雪深い。空は少しずつ暗くなり、いよいよ夜の気配が忍び寄る頃に会津若松の町並みが見えた。
真冬の町の灯りは、何ゆえに安心するのだろう。
二人は会津若松駅近くのバスターミナルの食堂で夕飯を食べた。「うわ、うまそう!」「だから!」のやりとりに食堂の従業員が嬉しそうに笑みを返す。
万が一、道路事情による理由などで高速バスに乗れなかった場合は父の実家をあてにするつもりであったが問題なさそうである。バスターミナルに併設されたお土産物売場を見ているうちに福島行きのバスが着いた。
「蘭ちゃん?」
高速バスが会津地方を走っていた頃はまだ起きていたが、郡山ジャンクションに差し掛かった頃には蘭は寝ていた。
この郡山ジャンクションがとても紛らわしい。
新潟方面といわき・東京方面への分かれ道がわかりにくいのだ。
一応は道路に引かれたラインで色分けされているので意識をすれば間違えないのだが、新潟を行き来する毎に父は「ここ、見誤りやすいんだよねえ」と苦笑い混じりで言っていた。
小学五年生に進級する春、福島へ引っ越す最中にも父はまごつきながらこのジャンクションを通過したものだった。
一哉は眠っている愛しい、美しい恋人の白い手に目を向ける。
婚約指輪はやっぱりダイヤモンドかな。
ダイヤモンド以外の石って使うのかな。
かわいらしいものよりは、スマートなデザインが似合いそうだけど、花を模したものも好きそうだな。
蘭のモチーフの指輪があれば絶対にかわいいのに、なぜかあまり見かけない。
形が複雑だからかな。
◇◇◇
「liebe」
一哉が初めて蘭に教えられたドイツ語。
つまり、愛である。
メールでのやりとりは当たり前だが、月に一度の間隔で蘭からのエアメールが届いた。
手紙を送る毎に蘭は恋にまつわる何かしらのドイツ語を書いて教えたのだ。
続いて「Kätzchen」と「Schat」。
いずれも恋人への愛称で前者は猫ちゃん、後者は宝石を意味する。
恋人を指す言葉だと他には熊とウサギもあるようだが、蘭は猫の方を教えた。
手紙には
「一哉ちゃんは猫みたいな顔をしているから」
と書いてあった。
蘭がクスクスと笑う姿が目に浮かぶ。
Schatを知った時は
「俺は何色の宝石? 誕生石はエメラルドだけどピンクの宝石がいいな。でもピンクはイメージではないよね」
と送り、律儀にも蘭は次の手紙で答えてくれた。
「一哉ちゃんは紺色か藍色の宝石かな。でもサファイアとも違うし……」
サファイアはむしろ蘭のイメージだな、と思いながら手紙を読み進める。
リボンをつけた騎士と同じ名前の、凛とした硬質な輝きを持つ青い宝石は蘭によく似合うだろう。
サファイアの深い青は蘭の肌に映えるに違いない。
しかし、蘭は宝石ではアクアマリンが一番好きだと話していた。
「アズライトなんてどうかな。藍色で絵の具に使われるの。不透明なものが多いけど結晶のものは透明感があってすごく綺麗だよ。一哉ちゃん、翠風学園の人達からアズと呼ばれていたよね」
一哉ちゃんは絵を描くのが得意だからアズライトはうってつけの宝石だよと続き、更に蘭はアズライトの名前を冠したインクでこの手紙を書いたとつけ足している。
手紙を読んだ後、一哉はアズライトについて検索したのは言うまでもない。
確かに透明度が高い結晶は深みのある藍色がこの上なく美しい。
孔雀石と共生した不透明な原石は地球にも似た色彩だった。
蘭の書く手紙の最後には必ず
「Ich vermisse dich」
と書き記してあった。
――あなたに会えなくて、寂しいです――
◇◇◇
婚約指輪について考えていただけなのに、ダイヤモンドから飛躍していつかの手紙での宝石談議を思い出してしまった。
婚約指輪は右手と聞いたが、何ゆえか一哉は蘭の左手の薬指を見つめる。
指輪を選ぶ暁には、できる限り蘭のワガママを聞くつもりだ。
おそらく蘭は高い買い物だからと敢えて小さいダイヤモンドを選ぶなど気を遣うかもしれないが、きっと蘭の理想とする指輪があるだろう。
――蘭ちゃん――
蘭は一哉の肩に頭を乗せて寝ている。
唇に塗ったルージュが艶っぽい。
人を選ぶ赤い口紅。蘭がつけると大正~昭和期の銀幕スタアのように様になる。
よく見れば爪も白から桜色へのグラデーションに染まっている。
――俺、いつか蘭ちゃんをお嫁さんにするよ。だから、待ってて――
忘れ雪に交わした約束。
少しずつ、近づいている。
永遠の愛を誓い合う、その時に。
ひじ掛けに乗せている蘭の手に、一哉は自身の手を重ね合わせた。
2011年 幸せな時間・6
年が明けて蘭は日本を発っていった。
一哉も新潟の学生アパートへ戻ったところだ。
ポストには何枚かの年賀状に混じって、蘭からの年賀状が届いていた。
伸びやかな、綺麗な文字で一哉の名前が綴られている。
福島でも初詣で会えたのだが、この年賀状は蘭が実家に着いてすぐに書いたものかもしれない。
初詣に来ていた蘭は着物姿だった。
街中にある神社まで蘭は昔の友達と初詣に来ていたのでせっかくの再会だからと気を効かせて身を引いた。
一哉自身も友達と来ていたし年末に会えたのだからと言い聞かせたが、やはり寂しいのは否めない。
「日本に戻ったらまた会おうね。卒業式の写真も送ります。幸せな時間を過ごせて楽しかったよ。ありがとう。大好きです」
大好きです。
この言葉で、一哉はなぜか泣き顔の蘭を思い起こす。
はらはらと涙が白い頬を伝う姿。
涙で潤んだ黒目がちな瞳に星空の輝きを宿す姿。
泣いているのに、美しい。
大学の卒業式が終わり、一哉の肩に顔を埋めて蘭は小さく「大好きです」と繰り返してしくしくと泣いた。
柔らかな春の空に映える瑠璃色の振袖。
繊細な絹の手触り。
花びらの透き通った春蘭のかんざしの煌めき。
薄藤色の袴の裾から覗くブーツがどこか懐かしかった。
少女だった蘭を思い出すからだろう。
真冬の蘭は膝下丈のセーラー服に雪国仕様のブーツを合わせていた。
可憐なはずのセーラー服は一歩間違えれば野暮ったくなるのに、蘭が着るとこの上なく似合っているから不思議だ。
初めての「大好きです」は14歳の夏の夕暮れ。
まだ一哉より背が高かった蘭。
一哉の首もとにしがみついて泣きながら言っていた。
蘭の15歳の誕生日に抱き締めた時も、蘭は一哉の腕に顔を伏せて「大好きです」と泣いた。
あの時もセーラー服にブーツを履いていた。
初めて、キスを交わした雪明かりの中でも蘭は泣き笑いで「大好きです」と言った。
もうすぐ18歳になる、少女から女性へと変わる頃ならではの危うい美しさ。
手のひらに収まるほどの紙一枚で溢れんばかりに蘇る、蘭との幸せな思い出。
「俺も寂しいよ……蘭ちゃん」
年賀状の最後には
「Ich vermisse dich」
と書き記してあった。
――あなたに会えなくて、寂しいです――
登場人物紹介(中学校編)
・音澤 蘭(おとざわ らん)
…フルート奏者を目指す少女。
一哉とは相思相愛で地元の学生オーケストラに所属。
ある理由から学校では周囲と壁を作り、一部の親しい生徒にしか気を許さなくなっている。
こだわりが強く、通学時以外は革靴(冬は雪道用のブーツ)を愛用する。
・飛鳥川 一哉(あすかがわ かずや)
…蘭のことが好きな少年。愛嬌があり溌剌とした性格。
フルネームが言いにくいため友人達からは飛鳥、またはアズと呼ばれる。
医者志望で私立中学に通う。新潟県新潟市出身で時折新潟弁が抜けない。
・橋本 慧子(はしもと けいこ)
…蘭の母方の又従姉で蘭より二歳年上の高校生。慧ちゃんと呼ばれる。
舞台女優志望で女傑然とした気の強い美少女。
ドイツのハンブルク出身でドイツかぶれ。
・鵜沼 留美(うぬま るみ)
…蘭の親友。福島県相馬市の生まれでパンチのきいた浜言葉を話す。
コワモテな上に粗野な立ち振舞いで怖がられがちだが友達思い。
・大槻 エリ(おおつき えり)
…蘭の親友。絵に描いた女の子らしい優しい少女だが気が弱く、吉田と取り巻きの男子からいじめられている。絵を描くことが好き。
・二階堂 ミヨシ(にかいどう みよし)
…蘭の親友。三年生の女子では蘭に次いで長身。
体力バカで勉強が苦手。
アクの強い容姿とアグレッシブな性格の持ち主。
・力丸 薫子(りきまる かおるこ)
…無口かつニヒルなお嬢様。身体が小さい。苗字で呼ばれる。
・合田 康範(ごうだ やすのり)
…一哉の親友兼悪友。ゴウダと親しまれ学年一の巨躯の持ち主。
茨城県勝田市出身で茨城弁が抜けない。
お調子者だが成績優秀で洞察力に長ける。
・斎藤 聖良(さいとう せいら)
…蘭に憧れる優しい少女。大きな瞳と眼鏡が特徴。
愛称はセイちゃんだが蘭からはセイラさんと呼ばれる。
蘭と同じオーケストラに所属し、担当はオーボエ。学校では周囲と壁を作る蘭を気にかける。
ロマンチストで恋に憧れ、蘭と一哉をセットで神格化している節がある。
・白沢 小百合(しらさわ さゆり)
…蘭のクラスメートで同じ高校を受験。シロちゃんと呼ばれる。
大規模な農家の娘で度々自宅が集合場所になる。小柄で可憐な容姿だが男兄弟に挟まれた影響からがさつな言葉遣いで男勝り。
周囲と壁を作る蘭を気にかけている。
・橘 織絵(たちばな おりえ)
…一哉と同じ私立中学に通う大人びた少女。愛称はオリちゃんで天然パーマが特徴。
蘭の小学校時代の同級生で同じ高校を受験する。蘭と白沢とは幼なじみ。
パッと見は冷静だが激情家。合田のことが好き。
・久間木 春奈(くまき はるな)
…愛称はハルちゃん。一哉と合田とは同じ小学校の出身。ソバージュ風の天然パーマが特徴。
白沢の友達で蘭と同じ高校を受験する。大柄でクールな姉御肌。
・浜津 陽一郎(はまつ よういちろう)
…一哉と合田の小学校時代からの親友。あだ名はハマちゃん。元陸上部員でやたらフットワークが良い。
気が優しく温厚な少年。小柄でリス、または小猿を思わせる風貌をしている。
・林
…蘭の中学の同級生。元吹奏楽部員でユーフォニアムを担当し、後輩からはモヤシ先輩と呼ばれる。
一時期はエリといい雰囲気だった。育ちの良さげな風貌だが白沢曰く男気がない。
・タケちゃん
…苗字は武田。蘭のクラスメートで一哉と合田と春奈とは同じ小学校の出身。
文武両道を具現化した好男子でファンが多いが、ぶりっ子に弱く他人に流されやすい。
なぜか蘭に苦手意識がある。
・吉田
…元吹奏楽部員で部長を務めていた。みーちゃんと呼ばれる。蘭とエリと織絵を目の敵にする。
学年では目立つ存在だが凡庸な容姿。
尊大な態度で自信家のように振る舞うも、本性は小心者の見栄っ張りで劣等感が強いことを周囲に隠している。
・斎藤
…吉田の友人で元吹奏楽部員。あーちゃんと呼ばれる。お嬢様風の生徒。
教養があり優秀だが、陰険かつワガママな性格で生徒と保護者からはあまり好かれていない。
・松井先生
…三年生の学年主任で蘭のクラスの担任教師。
教科担当は女子保健体育。熱血教師な反面、生徒への好き嫌いが激しい。年齢は50代。
・白沢 巧(しらさわ たくみ)
…白沢小百合の兄で四歳年上。地元の農業高校を卒業している。温厚で面倒見の良い性格。
・村上 晋(むらかみ すすむ)
…蘭と同じ小学校を卒業。合田達と仲良しで一哉に憧れている節がある。
吉田達へ反発心を抱きつつも強く出られないことを気に病んでいる。図書委員。
・由香理
…蘭と同じ小学校を卒業。委員長タイプのハキハキとした性分だが短気なのが玉にキズ。
・絢
…蘭と同じ小学校を卒業。クラス委員で空手部の元主将。
由香理と同様の委員長タイプだが冷静な性格。
・上野先生
…吹奏楽部顧問で音楽教師。中堅にして吹奏楽部を好成績に導き出した実力者。
蘭を筆頭とした退部者を気遣う一方で、一部の部員の行動に振り回されている。年齢は30代後半。
2002年 1月
年が明け、2ヶ月後に高校入試が迫る最中でありながらも生徒達に緊迫した様子は見られない。
いつもと変わらない、騒がしい教室。
喧騒の中で蘭は朝の読書にいそしむ。
クラスメート達は黙々と読書に打ち込む蘭を不思議に思うことはなく、思い思いの過ごし方を楽しんでいた。
しかし、普段どおりの光景が少しだけ変わったと蘭が知ったのは
「用もないのに入るなよ?」
と言ってたしなめる男子の声だった。それに反発する二人の女子の声に蘭は眉根を寄せる。
蘭の端正な顔がコワモテに変わったのは『用事がない限りは他の教室に出入りしない』という規則に反した生徒が出たからではない。
その生徒二人を、蘭は蛇蝎の如く嫌っている。
「蘭ちゃ~ん」
よりによって、嫌いな生徒二人はわざとらしく作った甘ったるい物言いで蘭にすり寄る。
どうせ、目元や口元がいびつに歪んだ笑顔を張り付けているのだろうと思ったので、蘭は見向きする気も起きない。
「何」
書籍に目を向けたまま、二人に冷たく問う。
「蘭ちゃんさぁ、一哉君と仲良いよねえ?」
「どこの学校受けるか教えてくれなぁい?」
やっぱり、と蘭はため息をつく。
この二人とは同じ小学校の出身であるが犬猿の仲だ。やっかみを買い、嫌がらせを受けたこともある。
教師を交えた話し合いで関わりたくないと宣言したにもかかわらず、二人は難癖をつけるためにわざわざ寄ってくる。
「やだ」
キッパリ断ってもしつこく食い下がる二人に蘭は再びため息をついた。
一触即発といえる様子に、怖気付くクラスメートも出る始末だ。
「あんた達、さっき昇降口で『F高以外の進学校を受ける男子って学力が中途半端なイメージで気持ち悪い』って喋ってたの丸聞こえだったからね。あれ、祥蘭と東高受ける男子にも聞こえてたし、その理屈だと一哉ちゃんも当てはまるけど?」
「えー、そうなのぉ?」
ぎろりとにらみつける蘭の目に、引きつった笑みの女生徒が映る。
名札に吉田魅里と書かれた女生徒の、アヒル口が片側に寄るという特有の表情に蘭は相変わらず不快感を催す顔だと腹の底で思う。
もう一人の名札に斉藤と書かれた女生徒に至っては見た目こそはお嬢様風で育ちが良さそうだが、軽薄さが表情と小馬鹿にする口調から滲み出ていた。
本来は柔和に見えるであろう垂れ目すら、スケベ親父じみたいやらしさを覚える。
「文句があるなら伝えておくよ。一哉ちゃんにね」
蘭の静かなる迫力に威圧され、二人はそそくさと立ち去る。教室を出るなり
「みーちゃん、何あれえ? 超性格わるーい」
「小難しい本なんか読んで、秀才ぶってさーあ」
と、負け惜しみゆえの陰口が聞こえた。
陰口が聞こえたのも、教室が静まり返っていたからだ。
沈黙を破ったのは複数の生徒の笑い声。笑い声に混じって一人が野太い歓声を上げた。
「音澤、ナイス!」
拍手と共に歓声を上げた生徒は合田康範といった。
学年一の巨躯を誇り、三年生の過半数からはゴウダと親しまれる彼は一哉と同じ小学校の出身で親友と悪友を兼ねる。
一緒になって笑っていた男子も一哉と仲が良い。
しかしながら、蘭の気は晴れない。
お気に入りの書籍を読む邪魔をされた上、嫌いな生徒二人のためにクラスメートに怖い人という印象を持たれたのも癪に障る。
事実「音澤ってマジでおっかねーよな」とささやく声が喧騒に混じっていた。
◇◇◇
「蘭、聞いたぞ」
2時間目の総合学習の授業を終えた休み時間、廊下の窓から吹き込む外気に当たっていた蘭は親友の鵜沼留美に呼び止められた。
親友の存在に蘭の表情は先ほどと打って変わり、和やかなものとなる。
「留美……。どしたの?」
蘭の肩に腕を回す留美は平均より背が高いが、170センチの蘭は少しだけ屈まなくてはならない。
化粧せずともアイラインの濃いつり目が蘭に笑いかける。ライオンを思わせるコワモテが、彼女の最大の特徴だ。
「総学の時間にゴウダのやつが触れ回ってたんだっけー。蘭があいつらを撃退した話」
「ああ、あれね。朝から嫌な目に遭ったよ」
和やかな顔は、げんなりとした顔へと変わる。深いため息をついた蘭に全くだと同情した留美は、腕組みをしながら顔をしかめた。
「本当に一哉君も気の毒だよな。顔がいいと変なやつにまで目ぇ付けられてよぉ」
だから、と蘭は相槌を打つ。
「一哉ちゃんの容姿に惹かれる子が出てもおかしくないのはわかるよ。一哉ちゃん、きれいな顔してるもん」
でもさ、と蘭はつけ加える。そして、留美の肩をガシッとつかんだ。
「あいつらはね、ルックスの良い男と仲良くなることで自分に箔がつくという考えが透けて見えるから腹立つの。そんなくだらない欲求に一哉ちゃんを利用しようとするなんて許せないと思わない?」
普段は堂々とした佇まいの留美だが、想い人を汚された怒りに燃える蘭の気迫に留美はやや逃げ腰にならざるを得ない。
「やっぱりそう見えるか……。この前の総学ん時なんか、1組のタケちゃんにすげえぶりっ子っぽい態度取っててよ、それ見てたシロちゃんがあいつらマジうるせぇって怒ってたで」
「タケ? あの人、相変わらず私を毛嫌いしてるみたいだけどね」
同じクラスであること以外に関わりなどないのにいい迷惑だ、と蘭は不機嫌そうに言い募る。
文武両道を絵に描いた上に三年生の男子で一番ルックスが良いと評されるタケちゃんが蘭を毛嫌いする理由に、先ほどの女生徒二人が関わっていることは蘭も留美もお察しだ。
気に入らない人の嘘八百を吹聴し、言いくるめて、無関係な人物にまでターゲットへの敵対心を植え付ける。
朝方の教室で「音澤ってマジでおっかねーよな」と口にした者こそ、タケちゃんこと武田であった。
「ぶりっ子やるだけならどうぞご勝手にで済むよ。何がムカつくかっていうと、お気に入りとそうでない人への接し方の落差だよ。目立たない男子はぞんざいに接してよぉ、女子は女子でエリちゃんとかのおとなしい子をバカにするところが気に入らないんだっけー」
留美は二組の教室を見やる。廊下の窓からはおとなしめの容姿の女生徒が担任と会話を交わしている様子が見えた。
「いじめられたり悪口言わっちゃっつうなら距離を置かれても当たり前だけど、あいつらの場合は自分より格が上か下かで判断した上での差別だもんね」
「だから。なんで中学生活って人間関係面倒くせえのかなー?」
それにしても、留美はがさつな話し方をする。
コワモテな上にドスのきいた地声で方言混じりの男言葉を話す彼女は『スケバン』というありがたくないあだ名をつけられる始末なのだ。
蘭は身体を留美から窓側へと向けてサッシに肘をかけたので、留美も親友に倣う。
「異性関係でも友達作りでも言えるけどさ、自分を引き立てるアクセサリーとばかりにファッション視する考えが私は気に入らない。でも、ああいう人ほど自分を出し抜く人も嫌うでしょう」
「だから。小学校で一緒だったオリちゃんなんかよく僻まれてたよな。オリちゃん、翠風だっけか? 私立さ行ったのに未だに存在が面白くないとかいろいろ言ってんだよな」
オリちゃんは美人で大人びてたから男子からモテてたもんなと留美は言った。
久しぶりに懐かしい名前を聞いたなと蘭は思う。
オリちゃんこと織絵は蘭とは未就学児の頃からの幼なじみ同士。
確かに、織絵は背が高くスッキリとした顔立ちの、大人びた雰囲気を纏う美少女であった。
そして、織絵は先ほどの吉田から目の敵にされている。
理由はくだらないもので「小学校の吹奏楽部の部長の座を入部して一年目の織絵に取られたから」という。
一哉の翠楓学園中学校での暮らしぶりはだいたいは織絵から聞くのが常だが、そんな彼女とは近所にもかかわらず年が明けてからは会っていない。
「一哉ちゃんをそんなやつのアクセサリーにされてたまるか。おこがましいにも程があるっ!」
眉をつり上げて、蘭はサッシを拳で叩いた。
「蘭、あんたって意外と独占欲強いな」
2002年 1月・2
この日は1月の第三土曜日。
当時は第一土曜日と第三土曜日の授業が午前中で終了する制度だったので、蘭は学校から帰宅した後にオーケストラの練習に出向く。
やっぱりこれじゃないとね、蘭は白い運動靴から雪道用の丈の長いブーツに履き換える。革製の薄茶色のブーツは、不思議なことにオーソドックスな紺色のセーラー服と似合っていた。
蘭が所属する学生オーケストラは小学校高学年から高校生までの年齢層で編成された楽団であった。
県の北部を中心とした狭い範囲とはいえ市外から来る団員もいるので少しだけ視野が広がった気持ちになれた。
学校と比べればこの楽団は居心地が良いが、春休み中の公演で蘭は引退を決めている。
最後の公演で披露する、プロコフィエフ作曲の「古典交響曲」第三楽章のガヴォッタは蘭の好きな楽曲だ。練習に気合いが入る。
「蘭ちゃんお疲れ。一緒に帰る?」
ビオラ担当の同い年の団員が蘭を誘い込んだ。
伊達町から来ている堀越梨穂子、通称ホリ子は4号線経由のバスで帰宅するが気分によっては阿武隈急行で帰る時もあった。
その時は蘭と福島駅の飯坂線乗り場まで一緒に帰るパターンが常である。
阿武隈急行と飯坂線の乗り場は同じ場所にあるのだ。
「ごめんね、ホリ子ちゃん。今日は約束あるの」
「えー、残念だなあ」
同じ高校の同じ科を受験する堀越とは仲が良いだけに、せっかくのお誘いを断らざるを得ない蘭は心苦しくもある。
フルートをクロスで拭いながら代替案として福島駅の東口までなら行けると提案すると、堀越はそれでもオッケーだと快諾した。
そのやりとりを近くで聞いていた女子高生の団員が冷やかしにかかる。
「蘭ちゃん。先約ってあの眉毛の凛々しいイケメンだろ? 前に蘭ちゃんのこと探しに来た人」
堀越も丸っこい大きな目を見開いて「あーっ、あのかっこいい人!」と手を叩いて何かを思い出した様子だ。
「なるほどー。あの人、すごい美少年だったもんなあ」
「あれは去年の夏……もう一昨年か。あの中学生さあ『蘭、じゃなくて音澤さんいますか?』って顔真っ赤にして聞いてたよね? ひゃーっ、今思い出しても初々しいリアクションだったわ」
その後に男子高校生の団員から『音澤~、翠風の制服着た眉毛の凛々しい男が来てるぞ~』と取り次ぎされ、ひどく狼狽えたこと、一哉に会いたいがために練習場から走り出たことが記憶に新しい。
その男子高校生の団員は昨年度末に引退したのだが、彼が密かに蘭に好意を寄せていたことを蘭も堀越も知らない。
「あのかっこいい人、蘭ちゃんを苗字で呼び慣れてなさそうだったけど名前で呼ばれてるのかい?」
「そうだけど?」
堀越と女子高生の団員が色めく。
「蘭ちゃんうらやましい~。あんなかっこいい男そうそういないかんね?」
◇◇◇
レッスンを終えた蘭が堀越梨穂子と福島駅に着いたのは夕方の6時を過ぎた頃。
福島駅東口で堀越と解散した後、駅ビルの書店で文庫本を眺めていると一哉と出くわした。
彼は予備校の帰りである。
「蘭ちゃん、お疲れ。あの件だけど伯母ちゃんがオッケー出したよ」
「ありがとう。でも大丈夫なの?」
蘭が泊まりがけで新潟の私立高校の受験に行くと知った一哉は新潟市内に住む伯母を思い出し、交通費と宿泊費がかさむことを案じたので伯母に蘭を泊めても大丈夫かと掛け合ったのだ。
蘭の母親は一哉の伯母の後輩に当たり、伯母は快く許可したという。
「後輩の娘だし、ぜひ会ってみたいってよ」
「そうだね。お母さんへの年賀状の写真で顔は知ってっけど、すごくきれいな伯母さんだよね。一哉ちゃん、これからどうする?」
「腹減ったからマックさ寄ろうかと思うんだけど、いいかな?」
「行く行く! 私も何か食べたい。相変わらず花梨ちゃんはマックに寄らないの?」
まだ覚えていたのか、と一哉は吹き出した。
今でこそ、花梨自らが過去の恥ずかしい思い出話として笑いを取るほどになっているようだが、花梨が幼稚園児だった頃に「マクドナルドではドナルドが接客している」と、清子から教え込まれた。
些細ないたずらのつもりであったが、いたずらの弊害は大きなものだった。
しばらくの間、花梨は「ピエロが怖い」と言ってはマクドナルドへ行くことを頑なに拒む有り様だったという。
「いやー、もう小二だしドナルドが常駐してるなんて嘘だって気づいてるわ」
「グリーンスリーブスといい、ドナルドといい、兄妹揃って変な勘違いするよね?」
自ら「グリーンスリーブス」の一件を口に出しておいて、蘭は含み笑いだった。
「グリーンスリーブスは俺が勝手に勘違いしたやつだからともかく、ドナルドは姉ちゃんが諸悪の根元だから」
◇◇◇
ようやく笑いが収まった頃に駅中のファーストフード店にて注文を済ませ、空席へ向かう途中で二人は少女の声で「おいっ」と呼び止められる。
通路をはさんだ隣のテーブルには女子中学生が三人。
モノトーンのタータンチェックのスカートと、スカートと同じ柄の縁取りが襟に入った黒いセーラー服は一哉が通う翠風学園中学の女子の制服だった。
今着ている古風なセーラー服はもちろん好きだが、赤いリボンがアクセントの現代的なセーラー服も蘭は少しだけ憧れる。
蘭と三人が軽く頭を下げてすぐに一人の少女が早速一哉をからかい始めた。
「アズの野郎、受験勉強そっちのけで噂の彼女とデートしてんのかい?」
仰け反る姿勢で二人を見上げてからかう少女は流行りの学園ドラマに登場する男装の女生徒を意識したショートヘアが似合う。
「ちがわい、さっきまで予備校行ってたわ」
特別、一哉は嫌がるわけでもない。
蘭にまつわるからかいには慣れているようで一哉は余裕綽々の様子で上手くあしらう。
続け様にボブカットの細身の少女が下からのぞき込むように見上げて言った。
「お前と身長どっこいどっこいだなあ!」
「残念でした。俺の方がでけえから」
お互いの気安い態度から同級生同士とわかる。
一哉は学校ではアズと呼ばれており、合唱部の先輩から「苗字が言いにくく、自分のクラスにカズヤという友達がいるので紛らわしい」との理由で命名されたという。
その言いやすさから瞬く間に合唱部のみならず同級生達にも浸透したようだが、蘭には女の子のあだ名、または青色の顔料に使われるアズライトの名に似ていると思えた。
ボブカットの少女は更に続ける。
「あーあ、青春だねえ。いいねぇ、うらやましいねえ、お相手のいるやつはよぉ。アズの野郎は予備校帰りに間引きかよ」
「まっ、間引きって……!?」
顔を引きつらせた一哉と、笑いを堪える蘭。
間引きと発言した少女は逢引きと言いたかったらしい。
三人のうち太った少女がボブカットの少女に笑いながら突っ込む。
「ばっか、おめー。それを言うなら逢引きだべした。間引きなんて恐ろしいこと言うなで」
「もうちょっとさぁ、逢瀬とか綺麗な言い方あるべー?」
「ばかっこの。間引きは農業用語だで。農作物は間引きやらねっきゃ育ち悪くなんだよ。うちの母ちゃんの実家会津のアスパラ農家だかんな?」
「あー、そういやそう言ってたな。ところで、あんたって言い間違い多いよな? 生意気な態度取った後輩に『足を洗って出直しな』っつうところを『首を洗って出直しな』ってドスのきいた声で凄んで言ったっけよ、後輩めちゃめちゃ青ざめていたんだっけー」
げんなりとした様子の一哉のかたわらで、蘭がたたんだコートに顔を埋めて肩を震わせた。
パッと見は愛らしいボブカットの少女だがよく見ればつり目がちな一重まぶたで鋭い目付きをしている。その鋭い眼差しで凄まれた後輩はさぞかし怖かったであろう。
「だから。この前なんか『掲示板に張り付ける』を『掲示板に磔にする』って言ったべ? いつも恐ろしい言葉と間違えんだ、おもしぃねえ。あっはっは」
笑っては失礼だとなんとか堪えてきた蘭だが、磔というワードが出たところでギブアップだ。
たたんだコート越しから笑い声が漏れる。
よほど三人のやりとりがおかしかったのか目尻には涙がにじむ始末だ。
さすがの三人も初対面の他校生に笑われた気恥ずかしさゆえか、きまり悪そうに顔を見合わせる。
「やばい、アズの彼女があきれてる」
そんなことはない、と蘭は笑いながら顔を横に振った。
あきれていないという意思表示であるが女生徒達には通じているだろうか。
「初対面なのに醜態晒しちまったな」
「変なやつらと思わっちゃかもしんねえしな。それより挨拶まだだったね?」
2002年 1月・3
◇◇◇
ひとまず、互いに簡単な挨拶を済ませた後に蘭と一哉は席に座る。そして、腰掛けるなり蘭は肩を震わせつつ両手で顔を覆った。
指の隙間からククク……と引きつった声が漏れている。
言うまでもなく笑っているのだ。
「それにしてもアズの彼女って噂に違わず美人だよなあ。他の野郎にも言い寄られたりするんだべ?」
ボブカットの少女、以下言い間違えの得意な少女が唐突に言うので一哉は言葉に詰まる。
自分以外の「ヤロー」が蘭と交際するなど考えただけで愉快ではない。
「彼女、祥蘭受けるんだべした? 祥蘭にかっこいい先輩いるらしいしよ」
「かっこいい先輩って進藤先輩だろ? あの先輩、好きな人いるってよ」
「違う違う」
顔見知りの先輩の名を挙げた一哉だが、女生徒達は身振り手振りで違うという動作を見せる。
「進藤先輩も美形だけどさ、あの先輩は中性的なきれい系であってかっこいいって柄じゃねえべした。うち、この前ハーフ顔で王子様みたいな先輩がいるって祥蘭に行った先輩に聞いたよ」
「うはぁ! アズ大ピンチだな!」
女生徒達は一哉を茶化すことを楽しんでいるようだ。
蘭は一哉がクラスメートの女子にイロモノ同然にからかわれていることを意外に思う反面、安堵していた。
「お前ら、むやみに騒いだら蘭が困るだろ」
ようやく笑いがおさまった蘭は穏やかな面持ちだ。
困っていないから大丈夫、と告げる蘭を見て恐縮したのか、先ほどまで一哉をおちょくることで盛り上がっていた女生徒達は緊張した顔を見せる。
まずはショートヘアの少女が隠しきれない好奇心を垣間見せつつ、おずおずと口を開く。
「ランさんの名前って胡蝶蘭の蘭って書くの? それとも藍色の藍?」
「え、花の方だよ」
蘭が答える前に一哉が答えた。
四君子にちなんで蘭と名付けられたのは本当であるが、好きな男の子に花の方と説明されるのは嬉しい反面恥ずかしかった。
頬、耳たぶが熱を帯びて朱に染まる。
恥ずかしさを少女達に悟られまいと唇をキュッと引き結び視線を逸らすが、一連の動作では却って悟られることになる。
第一、色白で頬が赤くなりやすいだけに誤魔化しがきかないのだ。
「蘭さんって、パッと見クールでミステリアスだけど反応が初々しいよなぁ」
「だからぁ。変に神々しいから取っつきにくいのかと思ったけど照れるし笑うし意外と普通の子だよな?」
「蘭は普通の子だよ。それにしても珍しく言い間違えなかったな」
そうだね、と頷いて太った少女が続けた。
「神々しいを禍々しいと言ったらアズの野郎がブチギレるだろうなぁ」
そこで蘭は再び、声を押し殺して笑い出す。
ここが飲食店でなければ大声を上げて笑い転げていたであろう。
「俺の彼女さ禍々しいち言うなでぇ! ってか」
「うわ、ひでぇ。私そこまでアホでねぇから。ねえ、蘭さん?」
「アズの野郎も反応がかわいいって思ったべ」
「勘弁してください~」
「しっかし、アズのやつよく食うよなぁ」
「予備校行ってから何も食ってねえの」
一哉の前には普通サイズのハンバーガーに更に何かを足したようなハンバーガーが二つ。フライドポテトのLサイズが一つ。Mサイズのコーラが一つ並ぶ
「弁当の他にも菓子パン食らってよ、先生方から『食欲の貴公子』ち呼ばれるだけあるわ」
クリスマスの季節に会った時、百貨店のレストランで昼食をとったにもかかわらず「くるみ割り人形」のミュージカルを見た帰りに立ち寄った喫茶店で珈琲ババロアとココナッツカレーを平らげた様子を見れば、食欲が旺盛なのも納得だ。
「だから。既に『懺悔の貴公子』ってあだ名あるのに貴公子シリーズ増えてんだっけー」
「懺悔の貴公子?」
蘭の問いかけに太った少女が食べかけのハンバーガーを手に答える。
ダブルチーズバーガー。誰の目にもハイカロリーだ。
ダブルチーズバーガーは半分ほど減っている。
「こいつね、ルックスいいから何回か告白されてんだよ。あ、安心しな、私らの興味は各々別の男子にあっから。告白される度に『悪い!好きな女の子いるんだ!』って謝ってんの。しかも90度に体折り曲げてよ。だから懺悔の貴公子」
断っているとはいえ、蘭の胸は少し痛む。
「理由は言うまでもねえべ。だーれも高潔なる雪の女王には敵わねえべした」
「雪の女王?」
蘭の問いかけに答えるのはショートヘアの少女だった。
「蘭さんってうちの中学じゃ有名だよ。特に吹奏楽部の連中はそう呼んでる。あ、私も吹奏楽やってたからコンクールとアンサンブルコンテストですれ違ってたかも。蘭さんって花の名前ついてっけど雪のイメージだべえ。だから雪の女王」
蘭は笑う。
小学生の頃、登校してきた蘭が教室に入った途端に外がひどく吹雪いたためクラスの男子からお前は雪女か!とからかわれたことを思い出したので、その件を手短に語った。
「中学生に女王もへったくれもあるかよ、なんて言ってた先輩ですら蘭さんの実物見て納得してたもんな?」
それまで伏し目がちだった目を上げて蘭は「へぇ」と興味深そうにショートヘアの少女を見た。
「吹奏楽部だったんだ。何の楽器やってたの?」
「私? クラリネットやってたよ」
上手い子には及ばないけどね、とショートヘアの少女は気恥ずかしそうに付け足す。
蘭は「そうなんだ。会場ですれ違っていたかもしれないね」と笑顔で話すも、蘭とショートヘアの少女のやりとりに一哉は引っ掛かりを感じた。
蘭は、吹奏楽コンクールにもアンサンブルコンテストにも一年生の時しか出場していない。
せっかく、蘭が初対面の人物と馴染んでいるのだ。
一哉は、この和やかな雰囲気を壊したくなかった。
本当のことを言わないことにした。
もしかすると、ショートヘアの少女も噂を通じて真実を知っているのかもしれないが。
「しかし告白する子達もチャレンジャーだべしだ」
「普通は彼女いるち聞いたら引き下がるべ?」
「一年とか蘭さんの存在知らないんじゃろ。でなかったらあわよくば飛鳥センパイと付き合えたら……なんて考えまで及ばねぇもん」
「しかし、アズの野郎。あんた学校さ出る時も何か食ってたべ?」
食ったよ、と一哉は答えた。
「みそぱんだろ? あれモジャ山からもらったんだよ」
度々、一哉との会話に登場するモジャ山。
蘭とも何度か会ったことがあり、飄々とした自由奔放な少年という印象が強かった。
本名は奥山直樹というのだがパンチパーマを彷彿させる天然パーマの持ち主で、自虐的なあだ名は小学生時代から使用しているという。
「あとは?」
「寒いから公園でジョリ松とセブンのおでんの大根とはんぺん食ったよ」
蘭はジョリ松とも面識があった。やはり一哉と行動を共にしている時に会ったのだ。
ジョリ松は坊主頭で眼鏡をかけており、ややポッチャリしている。
苗字は若松といった。
奔放なモジャ山と対照的に優等生然とした真面目な人物でありながらも、どこかお茶目さを垣間見せる憎めない少年だった。
地元でトップの進学校を受験するジョリ松は一哉と同じ予備校に通っていると聞く。
「おでんの大根、いいね」
蘭も、ダシの染み込んだおでんの大根が好きだ。大根にありつけた一哉がうらやましい。
「他には?」
「新町のパン屋さんでクルミパンとチョコデニッシュとワッフル買ったよ」
そんなに食べたの? と絶句する蘭をよそに、少女達の尋問は続く。
三人は揃ってあきれ顔だ。
「で、予備校さ着くまで合計いくつ食った?」
あきれている三人を尻目に一哉は指を折り数え出す。
「えーと、はんぺん三つにー、大根とー、みそぱんとクルミパンとチョコデニッシュとワッフルを一個ずつ」
おふざけの間延びした口調が蘭の笑いを誘う。
「そうそう、蘭にチョコデニッシュ買ったから後であげる」
「わぁ、ありがとう! 嬉しい!」
「あんたの胃袋はブラックホールか!」
二つ目のダブルチーズバーガーの包みをはがす太った少女の突っ込みに残る二人が「お前もな」と被せる。
「えー? 男子中学生なんてそんなものだろ? 俺のダチなんて夕飯に米五杯も食ってるわ」
「五杯ぃ~!?」
夕飯に米五杯も平らげる友達はおそらく合田のことだろう。
毎日のように「フードファイト」と称して給食を大量におかわりする姿には納得せざるを得ない。
2002年 1月・4
◇◇◇
「しかし、あんたよく食うよね?」
「全く同じセリフをさっきも聞いたよ」
言い間違えの得意な少女が手招きする動作を見せ、残る二人が顔を寄せ合う。
「知ってた? 先輩に聞いたけど食欲とスケベ心って正比例するらしいよ」
ささやき声は見事に、少年と少女の耳に届く。
気まずい話題を振られて吹き出しそうになったり喉に詰まりかけたのは、蘭も一哉も共に初めてだ。
二人揃って真っ赤な顔である。
「あ~、言えてるわ」
「だから男子って食ってばかりいるのかぁ」
三人はチェシャ猫さながらにニヤリと笑いながら、通路を挟んで隣り合うテーブルにゆっくりと顔を向ける。
「からかうのもいい加減にしてくれよな。悪趣味にも程があるっつーの」
蘭に背中をさすられ、一哉は咳き込みながら抗議する。当然ながら、まだ顔が赤いままだ。
「あんたのことだなんて誰も言ってねえべした」
「や~だ~、そういうリアクションするんだから思い当たる節があるんじゃねえのかい?」
言い間違えの少女がニヤリとしたまま言って冷やかす。
「言えてる!」
「やーいやーい、どスケベな貴公子~」
マジでひどい、と一哉は比喩表現ではなく本当に頭を抱えた。
「彼女相手にやらしいこと考えんなよなぁ!?」
「悪いな。うちのクラスやたら女子が強くてさ」
「楽しいじゃん。うらやましいよ。いつもこんな感じなの?」
親しい友達以外の、学校の仲間達と笑ったことなど、どれくらい前になるだろう。
同じ制服を着た仲間達と笑い合う生活を、蘭は当たり前のように到来すると思っていた。
結局は、叶わない夢となった。
始めは理想どおりの笑顔が絶えない生活だったかもしれない。
現実は、今はどうだ?
鉄面皮で、仏頂面で前を見据える息苦しい毎日。
つまらない妬み嫉みによる悪意は、蘭のささやかな願いを容易く奪い去る。
学校での息苦しさから解放されれば、蘭は抗うように外へ出向いた。
例えば、学生オーケストラであったり、想いを寄せる少年のもとであったり。
心から笑っていられる、仲間のもとへ。
「おう。だから委員長の立場薄いんだ」
人聞きが悪いと少女達は抗議する。揃ってがさつな物言いだ。
「うわー、アズの野郎マジひでえ」
「なんだよそれー?」
「言ってくれるじゃねえか?」
口々に抗議の言葉を並べる姿は、親鳥に餌をもらおうと鳴きわめくツバメの子のようだ。
「覚えてねえかもわからんけど、合唱コンクールの選曲で丸く収めるの一苦労だったんだよ?」
だって、と言ってショートヘアの少女が握り拳を作って意見し出す。
「『黒い瞳』を二年に取られたんだよ? ただでさえ二年の連中、生意気で鼻持ちならないのに! あれ三年になったら絶対に歌いたかったんだから」
太った少女も、言い間違えが得意な少女も続けて加担した。
「だからぁ! あの曲カッコいいしやりたかったわ」
「創立以来三年が『黒い瞳』担当してたのにさぁ!」
「創立ってまだ5、6年しか経ってねえべ。だいたい三年がやる伝統だなんて決まってねえよ」
なだめすかす一哉お構い無しで少女達三人は文字どおり鼻息荒くまくし立て、最後に言い間違えが得意な少女が締めくくる。
「わかってるっつーの。ただ今年の態度が生意気な二年がやるのが気に食わん」
首を洗って出直せの件といい、言い間違えが得意な少女は二年生を目の敵にしているとみえる。
「あんな感じ悪りぃ二年よか、無気力な一年がやる方がまだ割り切れるわ」
「確かに今年の一年って無気力っつーか自己主張しねぇよな~」
静観していたというよりは、少女達の迫力に気圧された蘭。ようやく言葉を発する気になれたので「あの……」と前置きする。
「どこの学校も後輩が生意気ってのは同じなんだね」
「同じだよぉ。私立受ける層でブランド志向のやつはいかにも『自分はそこらのバカと違うから~』といった具合に妙な特権意識持ってて本当に鼻に付くから。特に二年の連中はその傾向が無駄に強いんだわ。学閥だか何だか知らないけどたかだか東北の小都市の新設の私立校に過ぎないのにさ」
淀みなく語るショートヘアの少女に続き、太った少女が言う。
「公立は更に先輩後輩にまつわるトラブルがすごそうだよね?」
「あくまでもうちの中学では先輩後輩関係はそうでもないけど、同級生同士のトラブルはめんどくさいね。公立中なんて玉石混淆の極みだから。それで『流浪の民』のドイツ語になったわけ?」
この街では、毎年各校で行われる合唱コンクールで勝ち抜いた中学三年生が音楽堂に集まり合唱を披露する行事がある。
蘭がいるクラスも優勝し出場したのだが、翠風学園中学校三年A組による『流浪の民』のドイツ語版が披露された後に「全部ドイツ語なんてさすが進学校だねー」という声がちらほらと聞こえたのを覚えている。
コンプレックスゆえの皮肉混じりの声もあれば、純粋に感嘆する声もあった。
「そうだけど、知ってるってことは泉清は蘭さんのクラスが出たんだ?」
「実は私のところも『黒い瞳』を他のクラスに取られたって騒いでたの。だからロシア民謡絡みで『カリンカ』に決定」
小学校で習ったからみんな知っているし疾走感と緩急のある曲は受けるからね、と補足した。
「蘭が指揮やってたんだよ。な?」
少女達はしばらくの間黙り込んだ後に「あ~、あの子ね」と手を叩く。しばしの沈黙は記憶の引き出しを探っていたがゆえであったのだ。
「指揮やってる子、背が高いなーと思ったら蘭さんだったの!?」
指揮者を担う生徒は学校ごとに異なるかもしれないが、蘭の通う中学の合唱コンクールでは各クラスの学級委員長。または吹奏楽部か合唱部の部長or副部長or学生指揮者のいずれかが指揮を担当することが常だ。
浮いた存在とはいえ音楽の心得があり、中一の時のアンサンブルコンテストでは全国大会出場を果たし、ソロコンテストでも好成績を修めた実績のある蘭を指揮者にと推したい生徒は複数いたらしい。
指揮に自信のない学級委員長と副委員長からも「虫が良すぎる話とは承知だけど、蘭さんしか頼れる人がいない」と頭を下げつつ懇願されたので、蘭は指揮者を引き受けた。
早朝から練習を始めるクラスもあったが、在学中に引越したなどの事情で学区外から通学する生徒を考慮し、クラスメートからの意見を踏まえた上で放課後の練習に特化した。
元々緩急のある曲だけど、速くなるところを更に速く歌うのはどう?
歌が上手い生徒に見せ場を作るのは?
振りはつける?
いや、小細工しないで歌だけで勝負しようよ。
音楽という名の原石。
更に美しく磨き上げるために意見を出し合い、一つの音楽を作り上げる工程が楽しかった。
「ソロの男子がすごく上手かったよね?」
「その人、一哉ちゃんの友達。しかも合唱部じゃなくて野球部」
ソロを担当した野球部の男子は合田康範のことであった。
「昔さあ、蘭さんの中学で『流浪の民』の1フレーズだけドイツ語で歌ってた学年なかった?」
「中一の時かな。三年の先輩がやってたよ。あ、一哉ちゃんのお姉さんのクラス」
「アズ。あんた、姉ちゃんいたの?」
太った少女が問う。小学生時代からの知り合いならばともかく、中学からの知り合いの兄弟構成は意外と知らないものだ。
「そうだよ、F女の二年」
市内の女子高の名を挙げると「うちら受けるところじゃん!」と言い間違えの得意な少女が言った。そして「苗字で丸分かりだな」と加える。
「慧ちゃんがドイツ語を取り入れるの思い付いたって姉ちゃんが言ってたよ」
「泉清の学区から来てる子だからオリちゃんだかお京が言い出したのかな。かっこ良すぎてすごく鳥肌立ったって。選曲でモメてるうちにその話になってさ、ドイツ語? いいじゃんって流れになったんだっけか?」
「始めは1フレーズだけのつもりが全部ドイツ語でやる流れになってさ。あれ何がきっかけなんだっけ?」
「元々はドイツ語の歌だから誰かが出来心でインターネットで調べたんじゃなかった? パソコン部のやつが調べたんだわ」
「保険として日本語版も練習したよな? もし本番まで覚えられなかった時に備えて」
苦笑いの一哉だが、懐かしそうだった。
「ずいぶん徹底してるね。……もちろん一哉ちゃんがテノールのソロ歌ってたの、しっかり聞いてたよ」
手を触れなくても、蘭は頬が熱い。
一哉が『流浪の民』のテノールのソロを歌っている時、蘭は冷静である風を装ってはいたが、きっと顔が赤くなっていたはずだ。
クラスメートに知られてはいないだろうか。
隣に座っていた親友の力丸薫子は無口なので何も言わなかったものの気づいていたに違いない。
(留美はクラスが異なるので会場にいなかった)
今さらながら、考えただけでも顔から火を噴くほどに恥ずかしい。
なぜ今さらかというのも、クラスの女子はもちろんだが他校の女子が「翠楓のテノールのソロを歌っていた男子がかっこいい!」と騒ぎ立てて落ち着かなかったからだ。
一哉は一哉で他校の男子が複数人「泉清の指揮やってた女子、モデルみてえな美人だったな」と口にして惚けていたのを聞いてしまい落ち着かなかったそうだが。
『管弦の響き、賑わしく』
日本語に訳したテノールのソロ部分の歌詞である。
音楽会の後日、一哉は蘭に語る。
「蘭を思い出して歌ったんだ」
インターネットで調べてみたところ管弦の響きというのもギターや太鼓による演奏らしいが、クラスメートからの「あんたの好きな女子、音楽やってるんだべした? 彼女思い浮かべて歌ったら?」とからかわれた件がきっかけで蘭を思い浮かべながら歌うようになった、と彼は打ち明ける。
そして、一哉はにっこりと蘭に笑いかけた。
「ありがとうね。蘭のおかげで上手く歌えたよ」
◇◇◇
「変に負けず嫌いでこだわり強いんだ、うちらの学年」
「うちの学校の三年生もそうだよ。よく言えば意欲的で、悪く言えば好戦的ですぐに張り合う。確かに勝負事には結果を出しやすいから先生方からは受けるところもあるけど、穏やかに過ごしたい平和主義な子にはやりにくい環境だと思う」
好戦的という言葉に少女達は揃って「それ、わかる!」と賛同し出した。
「うちら寅年だからか何らかの因果関係あるのかね?」
「まあ、寅年は気が強いってよくばあさん世代が言うよね」
「蘭は卯年だよな?」
「私、早生まれだからね」
2002年 1月・5
◇◇◇
駅を出た時刻は7時を過ぎていた。漆黒の闇夜に冬の星座が煌めく。
雪の降り積もる夜は周りが明るい。雪明かりともいう。
曇り空と積もった雪が灯りという灯りを跳ね返し、薄明るくなるのだ。
銀色を帯びた薄明るい夜の景色を見慣れている中で、ここまで冴えた星空は久しぶりに目にした気がする。
真冬の夜の、凛と冴え渡る空気。
どの季節よりも澄んだ冬の夜空が蘭は好きだ。
夏が苦手な蘭はオリオン座を見る度に季節がまだ冬であると安堵する。
「さっきは楽しかったよ。あの子達、家に着いたかな」
真冬の星空も好きだけど、やっぱり雪明かりも好きだなと蘭は隣にいる少年へと顔を向けた。
雪明かりは顔がハッキリと見える。
「あいつら街うちに住んでるから着いたべ」
駅前というよりは駅の敷地の片隅にある自販機で各自温かい缶入りの飲料を買うことにした。
「寒い中であったかいの飲むって好き」
蘭は飲み口に向けてフッと息を吹いた。その唇の動きに一哉はドキリとさせられる。
蘭が手にしているのは細かい花模様を散りばめた赤い缶。缶入りの甘酒であった。
「俺、この前ブラックコーヒー飲んだんだけどよ」
「うん」
ブラックコーヒーの味を思い出したのか、一哉が眉をしかめている表情が暗がりの中でかすかに見えた。
「あれ、まっずいのな。苦いやつ飲めたらかっこいいだろうなーって思ったけど」
「私なんてコーヒーに砂糖にクリープ入れなきゃ無理。いや、クリープより好きなのは練乳かな」
至極真面目な顔で語る蘭の隣で、一哉は声を立てて笑う。
コーヒーに練乳を入れる知り合いなど、蘭しかいないのではないか?
それ以前に聞いたためしがない。
「練乳入れるって初めて聞いたよ。蘭ちゃん、どんだけ甘党なの。砂糖も入れるの?」
もちろん入れると答えた。
「お父さんがそうやって飲んでた」
父は仕事で疲れた翌朝、血糖値を上げるために練乳と砂糖を入れたコーヒーを飲んでいる。その度に母からはあきれられていると蘭は一哉に話して聞かせた。
「たぶん、私の甘党はお父さんに似た」
「会津の人って甘いもの好きなのかな」
「関係ないと思うよ。食文化の関係でしょっぱいものが好きな話は聞くけど。たまたまお父さんが甘党なだけ」
「……蘭ってマックスコーヒー好きそうだねえ」
「え、何それ? 甘いの?」
蘭は甘いものの話になると食い付きが良い。
以前も珈琲ババロアを食べに行こうと持ちかけたところ喜んで賛成したし、夏に会った時などはソフトクリームの専門店に行きたいと言い出す始末だ。
「いやー、この前ゴウダん家で飲んだんだよ。練乳入っててすげぇ甘いの。でも千葉と茨城にしか出回ってないらしい」
「いいな、甘いやつ。ゴウダのやつ千葉だか茨城から来たんだっけか?」
「ゴウダは茨城だよ。蘭が好きそうだと思ってゴウダにどこで売ってたか聞いたけど、茨城の親戚から御中元で送られてきて福島にはないって言ってた」
なんだ、と言って蘭は肩を落とす。
「ここだって甘党多いから需要ありそうなのに」
「じゃあ、機会あったら母ちゃんの実家で確かめてくるよ。母ちゃん、茨城が地元なんだ。それにしても、蘭の甘党っぷりは群を抜いてるねえ」
「甘党っちゃ甘党だけど、甘いものなら何でもいいわけじゃないよ?」
「あれだろ。同じあんこでも大福はあんこがみっちり入ってくどいから嫌だけど、クリームあんみつは好きってやつ?」
確かにその通りであった。
甘いものならば何でも好むだろうと誤解されがちだが、こだわりの強い(好き嫌いの激しい)蘭はあんこを使った菓子をあまり好まない。
嫌いとまではいかないが、進んで食べたいとは思えなかった。
あんこがメインの菓子の中でもきんつばは特に苦手であるし、おはぎに至ってはずんだ派である。
しかし、あんこはあんこでも見た目が愛らしくスッキリとした口当たりの練りきりは好んだ。
たい焼きはクリーム派で、チョコレートがあれば迷わずチョコレートを頼む。
「よくわかってるね。クリームあんみつは好きだよ。白玉入っていたら最高」
「本当に好きだよなぁ。それなら弥彦に白玉クリームあんみつの店があるよ」
白玉クリームあんみつと耳にするなり、蘭の目が輝く。
文字どおり目を爛々と光らせて「弥彦って新潟だっけか? 新潟市内からアクセスしやすい?」と喰らいついた。
「燕三条駅からローカル線乗り継いで行けるよ。ただ弥彦線の乗り換えで待つけど」
蘭は甘酒を持っていない方の手の指を折る動作を見せる。時間の計算をしていたのだ。
福島発の高速バスを会津若松で乗り継ぎ、新潟市内まで二時間。
乗り継ぎのための待ち時間を多めに見積もってトータルで三時間とする。
燕三条駅までは新幹線なり電車なり高速バスを使えば行ける、高速バスでも一時間はかからないと一哉は言った。
しかし、弥彦線の乗り換えで待ち時間は長い。
どれほど待つのだろうか。
「乗り換えで待つのかぁ、面倒そうだけど行ってみたいな」
「蘭って神社巡り好きなんだっけか。弥彦には彌彦神社があるんだ。あ、縁結びの神様がいるんだよ。近くに弥彦山があってロープウェイで頂上まで行けるよ」
「へー」
お喋り好きで饒舌な一哉だが、蘭が興味深そうに食らい付く姿を目の当たりにして気を良くしたようだ。
「頂上からは日本海が見渡せて、運が良ければ佐渡が見えるんだ。冬は雪だから難しいけど、春には雪割草が咲いて観光客が山登りに来るんだよ」
「雪割草!」
甘いものの話をした時と同じように蘭の瞳と表情がパッと輝く。雪割草がどうかしたかと一哉は不思議に思うも、すぐに疑問は解けた。
「私の誕生花なの! 特に白と薄紫が好き!」
でも、この辺りでは見かけないと蘭は肩を落とす。
「かわいいんだけどね、雪割草」
「信夫山じゃ見かけなかったしなぁ……新潟では咲くんだけどな。そこまで言うなら、見せてあげたいよ」
雪割草を目にした蘭はどんな顔をするだろう。「見て見て、一哉ちゃん!」と幼子のようにはしゃぎ立てるか、傍らに屈んで「かわいいねぇ」と静かに見守るか。
いずれにしても愛しい反応だ、旅装束はどんな格好だろうな……と考えを巡らせる一哉に蘭はいたずらっぽく笑って「泊まりがけ?」と問うので、一哉は動揺する。
「だろう、ね。日帰りは体力的にきついと思うよ」
「やっぱり中学生だと難しいよね……。お金ないし中学生が男女二人で泊まりがけだなんて絶対に変な噂立てられるし……」
蘭の表情は照れているようにも落胆にも見える。
2002年 1月・6
◇◇◇
「さっきの子たちと話してて思い出したんだけどさ」
蘭が不愉快になるような変なことを口走らなかったかと一哉は危惧したが、すぐに杞憂だと安堵する。
「中一の時なんだけど、文化祭の準備でいつもより帰り時間が遅い時があったの」
ただでさえ日が短くなった秋、文化祭の前準備となれば暗い中での帰宅となる。
吹奏楽部に所属していた頃、帰り道が同じだからという理由で一緒に帰ることになった男女に向かって他の男子が「襲うなよ~」とからかう光景に出会したと蘭は語る。
「嫌だったの?」
「別に嫌じゃなかったよ。でも、少し前まで小学生だったのに、大人になってしまったんだなぁ……って思い知らされた」
数ヶ月前までは男子はゲームの話を、女子は少女漫画やファンシーグッズの話ばかりをしていたのに、中学校に上がった途端、彼らは舵を切ったかのように性を交えた話題で盛り上がりを見せる。
嫌ではないし、自然なことだと理解しているが、妙な寂しさを覚えて変な気持ちだったと蘭は続けた。
「そいつら、小学校からの同級生だったから違和感じみた感覚を抱いたのかも。年齢が一桁の頃からの付き合いでしょう? たぶん中学から知り合った同級生なら何とも思わない」
不思議なもんだよねえ、蘭はそう言ってため息をつくと甘酒の缶に口付けて傾ける。
おそらく、蘭は俺だから言えたのだろう。
いや、鵜沼とか力丸とかの、いつもつるんでいる友達には話せたのかもしれない。
蘭は友達と同じように俺を信頼している。
信頼されている。
嬉しいはずなのに、一哉は申し訳ない気持ちにさせられる。
◇◇◇
出会った頃は、ただお喋りしているだけで幸せだった。
蘭の笑顔が見られれば上々だ。
手をつなぎたい。
抱き締めたい。
艶やかな髪と頬に触れてみたい。
様々な願望が芽生え、互いの唇を触れ合わせる想像を巡らせた後に、我に返って「ばか!」と自分に言い聞かせたのはいくつの頃からだろうか。
学校の友達と猥談で盛り上がるのは嫌いではないし、男子中学生らしいスケベ心は十分に持ち合わせている。
それらの話で盛り上がっている最中に、脳裏を蘭の姿が掠める度に罪悪感に陥った。
ある夏の日。普段ならば制服で会っていた蘭だが、この日は膝丈のワンピースにショート丈のカーディガンを着た姿で一哉の前に現れた。
令嬢の趣のある、上品な装いだった。
スカートの丈は膝頭が覗く程度で紺色と深緑で統一した暗めの色彩は禁欲的ですらあるのに、蘭は妙な色香を纏う。
深みのある色彩こそ、肌の白さや美しさを際立たせた。
ふわりと広がるフレアのスカートは妖精のドレスのように可憐で、締まったウエストの細さを引き立てた。
トゥシューズを模した勿忘草色のパンプスの、編み上げたリボンで飾られた足首が艶っぽい。
色付きのリップを塗った唇には、否が応でも視線を向けてしまう。
うなじからカーディガンの襟元にかけた、白い肌が眩しい。
いずれも、15の少年を翻弄するには充分すぎた。
蘭と正反対の派手な風貌に厚化粧を施した女の子ですら、蘭を眺めては惚けて立ち尽くす。
好きな女の子が隣を歩いている、それも誰の目から見てもデートの装いとわかる格好で隣を歩いている事実に舞い上がる一方で、逢瀬の間、一哉は理性を保つのに必死だった。
二人だけで日陰で休んでいる時、蘭は「今日の服装、気に入っているの」と笑って言った。留美達と有名なアニメーターが製作した長編アニメ映画を見た帰りに選んだのだと話す。
「すごく、似合ってる」
普段ならばすらすらと話せるのに、男のくせによく喋ると言わしめるほどなのに、一哉は途切れ途切れに言葉を紡ぐほかない。
「男って、ひらひらした服、着られないからさ、そういうの、いいよね。スカートとか、靴のリボンとか、女の子って感じしてさ」
二の句を待つ蘭を真っ直ぐ見ることができない。それでも、偽りのない精一杯の褒め言葉を絞り出した。
「蘭って、制服だと、大人っぽいけど、今日の服装、似合うよ。綺麗すぎて、直視できなかったけど、その……かわいいね」
最後の1フレーズに至っては、もはや言葉の代わりに心臓が口から飛び出る思いをしながらの最大級の褒め言葉だった。
「嬉しい! 一哉ちゃんに見せたかったんだ」
満面の笑顔が、はにかみの笑顔に変わったその時、一哉は蘭の両手首を掴んだ。
端から見ればダンスを踊っているようにも見える格好だった。
蘭は怯えたり嫌がる様子はなく、ただただ驚いたように目を見開く。
蘭の黒目に顔が映り込んだのを目の当たりにして、我に返る。
「ごめん。今日の蘭ちゃん、かわいかったから……」
手首を解放し「蘭ちゃん。ごめんね」と背を向けた。
きれいな姿を見てほしいだけなのに、踏みにじってしまったようで心苦しかった。
◇◇◇
二度と同じ過ちをするものか。
そう心に決めたのに、彼を試すかのように、蘭は同じ服装で何度でも一哉の夢枕に現れる。
時には、手首を掴まれたまま唇を押し当ててきたり。
時には、一哉の制服の肩に顔を埋めてしなだれかかってきたり。
時には、スカートの裾を翻して蝶々のように舞い踊る。
話し合った末に決めた約束。
交わしていなければ、きっと、間違いを犯していただろう。
――純真な恋心は、成長を遂げるにつれ変化する――
気がつけば、蘭の肌を見たいと願ってしまう自分がいた。
清廉な少女へ向けるに最も似つかわしくない願いであるというのに。
一哉は、蘭を汚したくなかった。
◇◇◇
「さっきの話に戻るけど……」
「うん」
「いつか行ってみる? 弥彦のクリームあんみつの店」
蘭の伏し目がちな瞳が見開かれ、しばしの間一哉を見つめる。そして、照れながら笑うと静かに言った。
「……行きたい」
マフラーに顔を埋めてはにかむ。
「今すぐでなくていいの。一哉ちゃん。いつか一緒に行こうね」
クリームあんみつを幸せそうに頬張る蘭の姿は想像するだけでも愛おしい。
まだバイトもできない中学生が県を跨いで出だすなど、それも男女二人でとなれば世間が許さないであろう。
それでも、蘭の手を取り蘭の知らない世界を共に駆け回りたい。蘭に手を引っ張られ、時にはリードして。
その、いつかが何年後になるかは定かではないが二人には実現しそうな気がした。
北天の夜空に浮かぶ星を見上げ、想像の中でしか許されない二人だけの大冒険に想いを馳せる。
2002年 雪解けの音
――俺の身長が蘭を追い越した暁に、想いを伝えるつもりだった――
やはり時期尚早だったのか。
蘭が好きだと想いを告げたのは中学二年生の夏。あと少しで蘭の身長に届くであろう頃だった。
何を言ったかは覚えていない。「好きだ」かもしれないし「付き合おう」だったかもしれない。
怖いものなどないとばかりに堂々と振る舞う彼女の、今にも押し潰されそうな姿に一哉は想いを抑えきれなかった。
彼女を支えたい。
その想いが彼の決意をフライングさせた。
「ありがとう」
驚愕の後の、蘭の微笑みには翳りが見える。日焼けなど知らなそうな肌が朱鷺草の花の紅に染まってゆく。
蘭の唇から放たれたのは偽りのない答え。
「私も……好きだよ」
照れ笑いとも、はにかみの笑顔ともつかない表情で前髪をつまんでいじり始める蘭の姿は恋愛慣れしていない少女そのものであった。
「一哉ちゃんと付き合えたらどれだけ幸せだろうって、何度も想い巡らせた」
でも、と蘭は続ける。
「私たちまだ中学生だし、いつかは他の女の人を好きになってしまうかもしれないでしょう」
「そんなことないよ!」
変声期を終えた声が虚しく響く。
蘭は周りの同年代の者たちと比べて達観している。
だが、まだ中学生なのに相手の心変わりまでを見越す者はこの世にどれだけいるだろうか。
「俺、初めて会った時から蘭のことが好きだったよ」
いや、顔がどうのではなくて……と狼狽える一哉に蘭は表情を和ませるも、すぐに目を伏せて続けた。
「好きだから、終わりが来るのが怖い」
中学生。恋を夢見る年頃だ。
高潔なる雪の女王は恋を怖れた。
「怖いの?」
「信じて期待した末に終わってしまうのが、怖い」
蘭は、ふふっ……と笑う。
自嘲。その言葉が似合う笑みだ。
ロングヘアの毛先を翻し、くるりと背を向ける。
「我ながらカッコ悪いよね。変に恐れてさ」
背中を向ける蘭がどのような顔をしているかを一哉は知らなかった。泣きそうな顔かもしれないし、自嘲を続けているのかもしれない。
「でも、相手を信じていたのに終わったり裏切られるってあるじゃん? 私は……やられたことあるんだよね。小三の頃だけど初めて好きになった男子から。私の何が気に入らないのか知らないけど仲良かった同級生がいきなり手のひら返して、私が悪口言ってたとか、その男子に嘘を吹き込んだの」
初恋だった男子に嘘だと弁解しても、全く聞き入れてくれなかった。
それどころか、初恋の男子は陥れた同級生と一緒になって蘭を悪く言ったり睨みつけるなどしてイビり倒すようになった。
蘭を陥れた同級生は、他のクラスメートにも嘘八百を吹き込んでは蘭を孤立させるよう仕組んた。
嘘を信じる者。嘘を見破った者。
どちらも混在したが、声が大きいのは嘘を信じた者達であった。
産休に入った担任の代任として来たばかりの若い女教師も、悪意ある嘘を引き合いに蘭を悪者にした。
嘘を真に受けたというよりは、その女教師は大人びた容姿の女子児童全般に苦手意識を抱いていた。
嫌いなタイプに見事に当てはまる蘭を攻撃する理由として嘘を利用したというのが真実であったのだ。
件の同級生をはじめとした児童達は、蘭の姿を見ればクスクスと笑いながら走り去る。
初恋だった男子も含めて。
負けず嫌いな蘭は「私は何も悪いことをしてない」と主張し続けたし、生意気だと言われようが嫌がらせを受ければ反発した。
踏みつけられても何度でも立ち上がる雑草のように。
多忙な母には言えなかった。
母に代わり、県庁での仕事が終わると足早に帰宅して家事を切り盛りする父にも、中学校に通い始めた兄にも言えない。
私は強いから、一人で戦えると言い聞かせた。
狭い町ゆえ「音澤君の妹がいじめられているらしい」という噂が中学生達の間に出回るのは思いの外早かったらしく、噂を耳に挟んだ兄は真偽を確かめる。
そして、子供が一人で抱え込むなと泣かれた。
年子の妹や嘘を見破った者からの報告もあり、蘭への嫌がらせは両親に知られることになる。
家族だけではない誰かの働きかけがあったのか、教育委員会が動いたのか年度内に担任が変わったが、それまでの間、蘭の戦いは続いた。
四年生に進級し、出産後に復帰した担任は「守ってあげられなくて、ごめんなさい」と蘭を抱き寄せて泣いた。
育児で疲弊した身体に追い討ちをかけたかもしれないのに。
数年の間を置いて、中学二年生になった今も同じ同級生に同じ手口で追いやられている。
公立の中学校に進学し、吹奏楽部に入ると知った同級生から過去の過ちを涙ながらに謝られた。
本当は蘭に憧れていた。
家族や近所の人達が蘭ばかりを褒めていたのを見てだんだん妬ましくなってきた。
弟と兄弟喧嘩をした時に「蘭ちゃんがお姉ちゃんだったらよかった」と言われたのが悔しかった。
実は、自分も同じ男子が好きだった。
彼も蘭のことを好きだった。
同級生の流す涙を前に、過去を悔いていると信じた蘭は「昔のことだから」と許したはずなのに。
ため息に似た息を深く吐いて、一哉に背を向けて、蘭は更に続けて言った。
「一哉ちゃんと出会えて、新しい交遊関係ができてせっかく忘れて前を向けるようになったのにね。あいつに騙された子達も謝ってきて、前のように付き合えたのに。中学入ってまたやられたよ。もう、そんなのまっぴらゴメンなの」
なんだよ、そいつ。
聞いているだけで息の根を止めたくなるほどに腹立たしい連中だと一哉は唇を噛んだ。
「周りも周りだよ。特に男子。相手が悪どいことをしているのに、結局はかわいらしく媚びてくる女の味方について、私が悪者ってことにするの。信用した末に欺かれて、変な嘘を真に受けて離れていって、すごく自尊心ズタズタにされる。そんな思いするぐらいなら絶ってしまった方がいい!」
吐き捨てるように言い募った後、蘭は強張った顔で振り返る。
全速力で走った後でもない。
その場にいただけなのに蘭は冷や汗をかき、息を弾ませながら話し出す。
「わかってるよ、一哉ちゃんはあんな奴らと違う。絶対にそんなことしないってわかってる。でも毎日のように当てつけがましく『どうせ心変わりする』とか『同じ女と一緒にいると飽きる』とか『男は自分より背が高い女を嫌いな人が多い』とか嫌みなこと言われたら、もし本当にそうなったら……って不安になるよ。カツアゲとか暴力なんてやられている人に比べたら奴のやってること自体はしょぼいのに、毎日やられたら精神が削られるよ」
友達からは、蘭が何かと特定の生徒から言いがかりをつけられる嫌がらせを受けていると聞いてはいた。
やる側は軽い気持ちかもしれないが、やられた側は時間をかけて精神を傷つけられ、削り取られてゆく。
少しずつ肉体を削ぎ落としじわりじわりと殺しにかかる凌遅刑にかけられているも同然。
身体と違って血を滴り落とすことのできない心は如何に傷をつけられ削り取られても他者の目には映らない。
目に見えないから、傷だらけのまま放ったらかしにされる。
考えただけでも背筋が凍る。
夏の夕暮れとはいえまだ汗ばむ。
しかし、蘭は凍えそうに両腕を胸元で交差させ我が身を固く抱き締めていた。
「蘭、変わってしまったよね」
「やっぱり?」
振り返らずに蘭は答える。一哉がどんな表情で「変わった」と言っているかを知ることが怖かった。
「変わったよね」の手合いの台詞は、だいたいは相手を責めるニュアンスで使われることを蘭は知っている。
「前は素直だったよ。俺と話している時なんてよく笑ってたね。でも最近は笑うことも減った」
一哉は腹立たしかった。
蘭に呪いをかけ、笑顔を奪った連中の全てが。
心を削り取られた蘭を呪縛から解き放つ。
自分に与えられた役目はこれしかないのだと一哉は確信する。
眠り姫は王子のキスで目を覚まし、雪の女王のカイはゲルダの涙で温かい心を取り戻す。
傷つけられただけ、否、それ以上に傷を癒す時間はかかるかもしれない。
如何にして、呪いを解けばよい?
「俺、蘭の笑顔好きなんだ。蘭、笑うとかわいいから……」
「今の疑り深い、笑わない私は嫌い?」
どこか怯えた様子で蘭は問いかける。
「嫌いになんかなれないよ」
土が二、三回ほどジャリジャリと鳴る。足を踏み出し、蘭のもとへ歩み寄る音だ。
「俺、蘭をそんな風にさせた奴が憎い。片っ端からとっちめてやりたいよ」
怒りを含んだ声と共に、肩に温かさを感じる。セーラー服の襟に骨ばった男らしく成長した手が重なりあった。
「いじめてくるやつらは蘭が妬ましいんだよ」
「一哉ちゃん、私はいじめだと認めたくないの」
「え?」
「いじめられてると思うと負けた気がするの。そいつらより弱いって認めたくない」
一哉は何も言えない。気位の高い蘭らしい意見だった。
「でも、嫌なんでしょう?」
ゆっくり頷く。
「嫌だよ。私の中学校生活はそんなんじゃなかったって毎日思うよ。あいつさえいなけりゃ今頃円満だったという考えすらよぎる」
「……そうだね」
「友達はもっとひどいことをされてる。スコアを隠されて、行動を監視されて笑われて。だから私がされていることは嫌がらせには入るけどいじめのうちに入らない」
「友達も……」
「優しい子なの。自然と気づかいができて、他人のいいところを見つけるのが得意な子」
そんな優しい友達だが、他人に優しくできない連中に劣等感を抱かせるらしく、気が弱いことをいいことに攻撃されるのだという。
「私は理解できない。私はその子の優しいところが好きだから庇ったりするんだけど連中はそれも面白くないみたいね。点数稼ぎって陰口叩かれるの。一哉ちゃん、私、間違ってる?」
一哉は即答した。
叫ぶように発した「間違ってない!」が少しの間だけ辺りにこだまする。
「友達がやられたら助けるの普通でしょう?」
一哉にも経験がある。
幼なじみの、気が弱く泣き虫な友達。
優しい性格が好ましく、いつも一緒に遊んでいた。
幼稚園で意地悪いことをされたり言われたりする度に「タッちゃんいじめたら許さないかんね!」と言って止めに入った。
口で言ってもやめなければ喧嘩中の猫のようにいじめっ子に飛びかかり、紙を丸めて作った刀を振り回して応戦した。
福島へ引っ越す前日、件の友達は涙と鼻水にまみれた顔で感謝の念を繰り返し述べて別れを惜しんだ。
友達の鼻水が手についたが気にする暇はなかった。一哉もまた、二枚目が台無しだと言われるほどに涙と鼻水にまみれた顔だったのだ。
「鼻水まみれでもぉ、飛鳥君はぁ、僕にとって永遠にかっこいいヒーローなんですぅ!」
友達からの贈る言葉はその場にいた人達の笑いを誘ったが、その後の人格や行動に影響されるまでに深く、心の奥底に残っている。
「蘭は、間違ってないよ!」
確信する。
蘭は、間違っていない。
たとえ周りが何を言おうと、蘭は永遠にかっこいいヒーローでしかない。
「きれいでかっこ良くて正しいことをハッキリ言える蘭を見ていると、惨めったらしくなるんだろ。
自分の汚さを認めたくないから、当てつけ言ったりして無理にでも自分以上に根性ねじ曲げさせようとしているんだよ。
卑屈になっていたら奴の思うつぼだよ。負けるだけだよ。
奴の望むとおりになるぐらいなら、意地でも完敗を認めさせた方がいい。
凛々しくて、気高くて、かっこいい蘭にはどう足掻いても勝てないって」
蘭の横顔を見据えて一哉は淀みなく語る。
2002年 雪解けの音・2
一哉は蘭と出会った十つの春に恋を覚えた。
プルシアンブルーのワンピースに映える、白い肌の清冽さ。
ピンと伸ばした背筋。
引き結んだ唇。
憂いを帯びながらも、頑とした強さを宿す眼差し。
彼が惹かれたのは全身から溢れ出る高潔さだった。
凛々しくて、気高くて、かっこいいプルシアンブルーの少女。
瞬く間に少年の心を捉え、未だ胸を離れない。
「乗っかってる野郎共も蘭が妬ましいんだろ。自分より優れている女が面白くないだけだよ。アホくせえよ男のくせに。なんなら俺が説教しに行ってやろうか? 女相手にくだらねえ嫉妬心燃やしてマジで恥ずかしい野郎だなって言ってやるよ」
だめっ、という声とともに一哉は腕を掴まれた。思いの外強い力だ。
眼前には訴えかけるような目をした蘭の顔。
「そんなことしたら一哉ちゃんの立場が悪くなる。やらかしたら他所の学校の男子に喧嘩売られたって吹聴されるよ。あいつら排他的でズル賢いから、だから周りもあいつらが間違ってるとわかりながらも黙認してるの。巻き込まれたら面倒だから」
蘭の声色は静かだが焦りが含まれていた。
「俺はその程度のちっさい野郎なんか怖くないよ。ズル賢いって言っても蘭の頭の良さに比べりゃ知れたもんだ。だいたい、蘭も俺も悪くない」
「ありがとう……でも乗り込むのは絶対にやめてね。私、一哉ちゃんの立場が悪くなるのだけは本当に堪えられない」
蘭の手が離れた。
不承不承、蘭の懇願に応えることにした一哉だが守り通せるかといえば自信がない。
もし、件の生徒連中が蘭を誹謗中傷する場面に居合わせてしまったなら約束を破ってしまうだろう。
「わかった。蘭がそう言うならやめる。万が一やらかした時は怒っても構わないよ。俺は、蘭が傷つくぐらいなら悪になっていい。泉清にはダチがいるし、あいつらは俺のこと信じてくれるよ」
「なんで、そこまで言ってくれるの?」
恐る恐る顔を上げれば、真っ直ぐな、活力に満ちた瞳が蘭を見つめる。
「蘭か好きだからに決まってるでしょう」
「誰だって、好きな子が泣いてたら助けたいよ」
再び、蘭は顔を背ける。小さくかすれた声で「やめて」と聞き取れた。
「優しくされたら……」
声が、肩が震えていた。
「優しくされたら、調子に乗って甘えてしまう」
「い、いや、俺は……」
先ほどまで淀みなく話せたというのに、一哉は言葉に詰まった。
蘭なら甘えられても構わないし大歓迎だ。
蘭に笑ってほしい。
自分を頼ってほしい。
蘭が笑顔でいられるためならば、騎士にでも悪にでもなれる。
今は、いずれも言葉に出すことがキザったらしく思えて恥ずかしい。
むず痒い。
嘘くさく聞こえてしまうかもしれない。
普段ならば男の割にはよく喋ると言われるにもかかわらずだ。
しかし、偽りのない想いを口に出さねば、蘭に信じてもらえない。
蘭は呪縛から解放されない。
俺を信じろ!
「おっ……、俺は……いつでも甘えられても、構わない……よ?」
理想は、キザったらしくない程度に、紳士的に、スマートな振る舞いで言いたかった。
本質はがさつな少年であるがゆえ、狼狽えているがゆえに蘭の前でみっともない姿を晒しているかもしれない。
事実、途切れ途切れに言葉を紡ぐしかできなかった。
「俺は……」
身体中が熱い。
「蘭じゃないとダメなんだよ」
心臓が、激しく脈打っていた。
「蘭が隣にいない人生なんて、耐えられないよ」
間を置いて顔だけを振り返った蘭が何かを言う。
溢れ出た涙が瞳に輝きを与え、頬を濡らす。
唇の動きから名前を呼んでいるとわかったが、声は出ていなかった。
蘭は身を翻し、凍えそうに我が身を固く抱き締めていた両腕を羽ばたくように差し出す。
視界が揺らいだと思えば、一哉はバランスを崩し尻餅をついた。
腕の中に感じるのは蘭の存在。
制服越しに響く胸の鼓動。
生きている証しである体温。
石鹸に花の香りを足した、清潔感を覚える香り。
耳元にすすり泣きが聞こえる。
蘭がしがみついて泣いていた。
「大好きです……一哉ちゃん……」
――大好きです――
高潔なる雪の女王が、唯の少女となった瞬間だった。
2002年 雪解けの音・3
◇◇◇
「それでさぁ、あんたたちいつになったら付き合うんだっつーの。もう中三も終わりでしょうが」
西道路に面した新興住宅地の一角の公園で話し込む少年少女。
橋本慧子は腕組みをしたままその場を右往左往した後、飛鳥川一哉を見下ろした。
一哉はというと村下孝蔵の『初恋』を口ずさみつつ棒を使って真っ白な雪面に何かを描いていたが腕を止め、斜め上を見上げて気強そうな眼差しの少女を視界に入れた。
真っ黒い髪。
細面の輪郭に、気品ある顔立ち。
アルト寄りの芯の通った声。
又従姉妹なだけに蘭と慧子は似通うところが幾つかあるが、蘭とは全くの別人だ。
「俺もさあ、愛しの蘭ちゃんと付き合いたいと思うよ。
でも、考えてみてよ慧ちゃん。中学生で男女交際に踏み切っている人たちがどれだけいると思ってんの? 親の管理下にいる中学生なんて世間から見ればまだまだガキ扱いだよ。
付き合うとなれば当然キス以上のやりとりもあるわけでさ。
俺、慧ちゃんに殺されるの覚悟で言うけど、俺も蘭に対してエッチぃ願望を抱くスケベ人間だから、いざ欲求に負けて間違い犯した時どうすんの?
二人だけの問題ならともかく俺たち未成年で周りを巻き込むのは目に見えるし、間違い犯さないためのやつを買うのも本来は正しいことなのに不純異性交遊をしているって変な噂を立てられるでしょう?」
相変わらずの、文章におこせばうんざりする文字数になるであろうセリフを一哉はすらすらと述べる。
今回などは400字詰め原稿用紙を半分より少し多く埋め尽くすに違いない。
慧子は、いつだか一哉の母親から「息子は口から生まれたのかと思わざるを得ない」と冗談を言われたことを思い出し、本当にそう思いたくもなるわとあきれるほかなかった。
「今の話だってゴウダと慧ちゃんだから言えるんだよ。俺は蘭を汚したくねえのよ。汚したくねえのにエッチぃ願望はあるのよ。恋する男子中学生なんて、毎日が自制心との戦いでジレンマモードなの」
「さーすが双子座男だな。必殺技は屁理屈。無駄に口が立つのは相変わらずだよ」
屁理屈のあたりをやたら強調し、慧子は「この、へらっちょめが」と憎まれ口をつけ加え、口が立つ双子座男を見下ろした。
「男子中学生がここまでの考えに至るのも甚だ珍しい話だよ。翠楓のインテリ共とエロ本回し読みしてるだけじゃないんだな」
憎まれ口を叩きつつも慧子は一哉を蘭の王子様として認めざるを得ない。
インテリ共とエロ本回し読みの件はあくまでも当てずっぽうな憶測だが、あながち間違いでなかった一哉はひどく焦った様子で応戦し出す。
「エロ本回し読みって、エロもと慧子さんには言われたくねえなぁ」
「あんた、なんで私がエロもとって呼ばれてんの知ってるわけ? 高校でのあだ名なんだけど」
慧子が所属するクラスは女子のみで編成されている。
女だけの環境ではままある光景だが、仲の良い生徒と下ネタで盛り上がっている際に相手からふざけて「エロもと」と呼ばれて以来、時々ではあるが「エロもと」呼ばわりをされているのだった。
「慧ちゃんと同じ学校さ行ってる先輩から聞いた」
う~ん……と野太いうめき声が聞こえ、一哉と慧子がうめき声のした方を振り返る。
ブランコに座った少年が両手を組み合わせて伸びをしていた。
眼鏡をかけ、タワシの如し剛毛を刈り上げた少年の体つきは大柄で、児童が遊ぶことを想定したブランコに腰掛けるには不釣り合いすぎる。
大柄な少年、合田康範の口からは身の詰まったバリトンボイスが飛び出す。
「お前らが何らかの理由で敢えて付き合ってねえのはわかるよ。でもよぉ、客観的に見れば飛鳥と音澤って付き合ってるようにしか見えねえんだよ。ですよね、慧ちゃん先輩?」
一哉と合田。
二人が並ぶ様は牛若丸と弁慶さながら。
そう言って蘭にからかわれた出来事が合田の記憶に残っている。
蘭がまだ学校内で笑顔を見せていた時期であるから、中一の頃だろうか。
嬉々として「なあなあ、牛若丸はどっち? まさか俺?」と問う合田に対して蘭を含む複数の女子から「牛若丸は一哉に決まっている」と冷たくあしらわれたことも、一哉が牛若丸ならば静御前は蘭であると合田が言うなり頬を赤らめた蘭にローキックをお見舞いされたことも、いつかは良き思い出になるだろう。
合田は座っていたブランコから勢いよく立ち上がりつつ尻のあたりを手で払う。
雪面に新たな足跡が刻まれた。
「んもぅ、ゴウダまでそう言う。俺たちはまだまだプラトニックな関係だっつーの」
事実、プラトニックな関係を築いているのだからやましいことは何もない、一緒にいて何が悪いと返して再び地面に何かを描き始めた一哉は合田を見上げる。
「別に悪いとか言ってねえべよ。プラトニックだろうが何だろうが、みんなお前ら付き合ってると思ってるんだよ。俺の母ちゃんですら『一哉君ってあんたのクラスの音澤さんと付き合ってるんだって?』ってニヤニヤしながら聞いてきたしよ、誰に聞いたかっていうと久間木の母ちゃんから。そして久間木の母ちゃんは松下の母ちゃんから聞いたってよ」
久間木も松下も一哉が卒業した小学校の同級生だった。
松下に至っては翠楓学園の生徒で現在も同じクラスという腐れ縁だ。彼女はしょっちゅう蘭との関係性をからかってくる。
「だ~れもお前らの邪魔さしねえのは音澤が美人だからだよ。お前ら、悔しいぐらい絵になりすぎんだよ。仮に音澤が月並みの容姿なら既に横槍さ入れられてるわ」
「ゴウダ君も言い得て妙なこと言うね。あんた達絵になりすぎるのさ。美しすぎて周りが踏み込めないんだよ。ま、蘭は私に似て美人だから太刀打ちできねえって諦めつくのも当たり前だな」
通学鞄を肩に担ぎ、慧子は得意げに延べる。
制服の上に着込んだ、ガーネットの真紅を宿した赤いコートは彼女の激情的な性格を表すかように灰色の寒空に映える。
慧子が通う白嶺高校は明度が高くなければ色物のコートを着ても構わない。第一、ブレザー自体が鳩羽鼠と珍しい色なのだ。
「ゴウダく~ん。愛しの蘭ちゃんは慧ちゃんと又従姉妹でもナルシストなところは似なくてよかったねー」
一哉の発言に同意しつつも「しかしだなぁ」と前置きして合田は続ける。
「音澤のやつもあれだけ容姿端麗なら大なり小なりは自分の美貌を自覚してもおかしくねえよ? 俺、あいつと二年間同じクラスだからわかったけど、あいつは自慢はしねえけど謙遜もしねえから」
「蘭が自慢もしなければ謙遜しねえのも俺は小学生ん時から知ってたよ。あ、例外で髪質は自慢だって言ってた。蘭、きれいな髪だもんなぁ」
いつもならばキリッとしているはずの一哉の表情が緩んでいるのが見てとれた。
「仮にナルシストでも蘭ちゃんなら許す~」
慧子も合田もあきれ顔だ。
福島に越してきたばかりの頃、小学校の教師陣や近所に住む大人達から「かっこいい男の子が来たねぇ」と褒められていたというのに。
「俺はね、蘭ちゃんがもう大丈夫だと確信持てるまで待つの」
「飛鳥よぉ。お前、どれだけ音澤にぞっこんラブなんだよ」
少年向けの漫画でデレデレしながら好きな女の子のことを考えている主人公の描写を見かけるが、今の一哉はまさしく「デレデレしながら好きな女の子のことを考えている主人公」そのものであった。
「しょうがない。一哉君のやつ、齢十つにして自分史上最高の美少女を知ってしまったからね。ゴウダ君、この手の話になると毎回聞く割には知らないんだけど確信ってどういうことか知ってる?」
慧子に話を振られた合田の顔がほんのりと染まる。
「蘭もこの件について話してくれないんだわ。まだ男が信用できないから確信持てないのかと聞いても、一哉君だけは信用してると言い張るしさ」
同じ中学の卒業生で高嶺の花と名高かった憧れの生徒会長である慧子が相手なので、合田が赤面するのも無理はない。
「飛鳥のやつ、男のくせに喋りすぎる割にはこればかりは一切喋りたがらないんだよなぁ。こいつ、音澤が関わると口堅いんだよ。要は音澤を守りたいがため、だろ?」
「男のくせにってひでえな。ゴウダも甚だ口数多いでしょう。ジェンダーフリーの世の中になりつつあるのに」
2002年 雪解けの音・4
慧子はふと何かを思い出して「話変わるけど」と切り出した。
「来週は蘭の誕生日じゃん。一哉君、蘭に何か用意してるのかい?」
「あいつ2月生まれけ? ……出席番号、最後から二番目だもんな」
もちろんだよ、と一哉は言い切る。
「プレゼントしっかり用意してるよ。泉駅近くのお菓子屋さんのケーキも買ってくる」
いつだか蘭と一哉の待ち合わせ場所となった無人駅の近くには菓子店がある。
菓子店で売っている洋菓子の中でも、蘭はホワイトチョコレートのババロアにフルーツを盛り付けたケーキが好きなのだ。
「へー、蘭のことよく理解してんな。まさかプレゼントはエンゲージリングじゃないよな?」
慧子は『エンゲージリング? 我ながら上手いこと言えたわー』と自分の発言に大笑いし出した。
彼女は筋金入りの笑い上戸で、客観的に見てつまらない事柄でも笑いのツボに入りやすい。
慧子の笑い上戸が発動するなど珍しくないので、一哉と合田はそれほど反応を示さずに会話を続ける。
「シューパイ買うのけ? あれ旨いよなぁ」
今度買ってくべ、と合田がつぶやく。
未だ茨城弁の抜けない合田。
福島弁の「~かい」に当たる言葉を「~け」と言うなど、地元民が話す方言とは違う方言を使うが、一哉も慧子も慣れっこだった。
一哉は新潟出身で元々はそれほど訛っていないが職員室を教務室、模造紙を大洋紙と呼ぶなど新潟で刷り込まれた独自の言い回しが未だ抜けず、慧子に至ってはドイツ生まれだ。
三人共に、地元民ではないという事情もあるのだろう。
(しかし、一哉も慧子も「もっさりしながらも個性的すぎる福島弁の強烈さ」には抗えず、数年のうちに福島弁に染まってしまった)
「シューパイもいいけど、蘭はホワイトチョコのケーキが一番好きなんだ」
帰宅時間まで売ってるかな~と一哉は少し不安げだ。人気のあるケーキは夕方には品薄になる。
「最も好きなケーキを把握してるだけあるわ。そりゃあ甘党の音澤のやつが他の野郎に見向きもしねえわけだよ」
「蘭、中一ん時うちのクラスのやつに告白されても見事に断ってたしな。そいつ、うちの学年でも三本の指に入るイケメンだったけど」
紅顔の美少年というべき血色の良いはずの一哉の顔色は、みるみるうちに蒼白となった。
悪趣味な笑みを浮かべて語る慧子に合田が被せて言う。
「知ってますよ。野球部の斎藤カズヤ先輩っすよね」
そして合田は「この町、サイトウさん多いな」とつぶやきを添えた。
「そうだった! みんなサイトゥーって呼んでっから忘れたけど一哉君と名前同じだった! あいつどこ高行ったんだっけかなぁ」
ひゃはははっ、と慧子は笑い声を立てる。
「県工でしたっけ、いや、商業だったかな。実業系だった気がしますよ」
「マジかよ! 慧ちゃん、ゴウダ、俺そんな話聞いてねえよ!?」
全くの初耳だった。棒を持ったまま立ち上がる一哉は完全に焦っている。
「音澤が飛鳥以外の野郎に興味ないとはいえお前がショック受けかねないことをわざわざ言う必要ねえべ?」
俺なりの優しさだよ、と間にはさんで合田は続けて言った。
「だいたい、音澤は他の野郎の存在匂わせるようなやつじゃねえしな」
「ゴウダ君も野球部だったんだな。なら斎藤知ってるよな。それでさ、斎藤のやつ蘭に振られてしばらくの間給食残してたよ。まったく、だらしねえやつだわ。さすがにサーヤのやつが『振られたぐらいで給食残すな根性なし!』って七五調で節つけて罵倒して斎藤泣かせた時はヒヤヒヤしたけど」
そう語りながら慧子の表情が悪趣味な笑みから苦笑いへと変わる。
「姉ちゃんえげつねぇ……」
男嫌いゆえに異性に対して容赦のない清子である。
幼稚園時代に同じクラスの男子から執拗にいじめられたことがきっかけで男嫌いに成り果てたのは同情できる案件だ。
(実際は好意の裏返しであったがいじめを受けたことに変わりなく、更には複数の男子が面白がって便乗していじめてきた。その後、清子はお嬢様学校の附属の幼稚園に転園した)
姉の過去を考慮しても、男だからという理由だけで無関係の男子へ向けたえげつない態度に一哉はガッカリするしかなかった。
青っ恥をかく、肝を冷やす、生きた心地がしないという慣用句があるが、まさに今の心境なのだと思い知らざるを得ない。
ましてや、斎藤先輩が蘭に振られた理由が
『クラスメートの飛鳥川清子の弟(俺)』
なだけに、だ。
恋敵とはいえ、姉が傷心の斎藤先輩に失礼な言葉を投げつけた件を後ろめたく思う。
「サーヤは同性には親切なんだけどさ、高貴かつ清楚な名前に似合わず男に対して冷淡すぎる」
パッと見はお嬢様風の眼鏡っ娘で、顔つきの愛らしい清子。
中学校に入ったばかりの頃は容姿の愛らしさはもとより、名前の美しさも相まって興味を抱く男子が多かった。
教室まで清子の姿を拝みに来た者もいたが、いじめのトラウマで男嫌いに成り果てた清子は「自分を笑いに来た」と疑ってかかっては自らが威嚇して追い返すことが常となり、卒業する頃には男子の誰もがに恐れおののいて寄り付かない有り様であった。
「斎藤が振られたのはあんたの弟が原因でしょうがって話だよ。まあ、男憎しを地で行くサーヤのことだから分かってて言ったんだろうけど」
「飛鳥の姉ちゃん、イケメンの斎藤先輩にもきついんっすねえ。あの先輩、うちの学年の女子からモテていたんですがねー」
斎藤という顔も知らない先輩の学校内での立ち位置を知れば黙ってはいられない。
一哉は手にしていた棒を放り投げ、血相を変えて慧子と合田に詰め寄る。雪の上に描いていたのは相合傘だった。
「斎藤先輩ってそんなにかっこいいわけ!?」
「斎藤もあんたも学校でのポジションは似たようなもんだ。一哉君さぁ、あんたの顔が男の割には美しいのは認めるけど所作ががさつで汚すぎ。顔と裏腹に全っ然美しくない」
男の割にはが余計っすね、と合田がムッツリとした様子で横から口を挟んだ。
「喋り方、その他諸々ががさつな慧ちゃんにだけは言われたくねえなぁ」
「あんたは蘭の王子様なんだからもう少し王子らしくしなさい。わかりましたね?」
相合傘を描いていた棒を放り投げたことを指摘されるのはわかるが、若干的外れな説教を食らったので一哉はげんなりした。
高嶺の花にふさわしい華麗な容姿に反して気さくで取っつきやすい慧子だが、独特の美意識を振りかざすところが一哉は少し苦手だった。
「えー、やだよー。蘭はありのままの俺がいいって言ってたし花梨が読んでる少女漫画のイケメンみてえな非現実的な野郎いねえっつーの」
合田もげんなりした顔で「いねえな、そんなやつ」と横から同調する。
「まあ、斎藤の件については問題ない。ヤキモキさせて悪かったよ」
悪かったと謝るぐらいなら言わないでくれ、寿命が縮んだと一哉は抗議した。
「まあまあ、気を落とすなって。現実はお前ら相思相愛なんだしさ」
合田のなぐさめに慧子も「そうそう」と被せる。
「斎藤のやつ『私には好きな人がいます。誠に申し訳ありませんが、彼以外の男の人とはお付き合いできません』ってバカ丁寧にお堅い口調で断られたって嘆いてたわ」
落ち着いた声色を作り、客室乗務員さながらの真面目そうな動作を交えて慧子は蘭を演じ出した。
「さすが舞台女優志望だわ。目を閉じれば愛しの蘭ちゃんが見えそうな演技だよ」
「彼以外の男の人とはお付き合いできません、だってよ。いいよなー、俺も女子から言われてみてえよぉ」
親友の脇腹を肘で突いて囃し立てつつ合田は一哉がうらやましい。
「しかし、斎藤のやつに勝つなんて一哉君、あんたもやるよなぁ。『彼以外の男の人とはお付き合いできません』だって。斎藤のやつ、私から見ても相当な男前だったんだよ。中一なんて小学生に毛を足したガキっぽいやつばかりだろうに、そんな中で妙に色気のある大人びた美少女が混じっていれば興味関心持つわな」
長身の家系によるものか、中一にして蘭の背丈は成人女性の平均より高かった。
慧子と同学年の女生徒からも「ガキくさくない分、私らに混じっても違和感がない」と言わしめたとも聞く。
入学当初の、三つ編みをカチューシャのように巻き付け後ろ髪を一つに結って垂らしたクラシカルな髪型や背筋を伸ばした立ち姿は人目を引いた。
目立つ容姿ゆえに目を付けられるかと慧子は危惧するも、蘭は元来真面目な性格で規範意識に厳格だ。
その生真面目さは中学校入学時には殊更に顕著となり、気を許した者以外には、堅苦しいほどに礼儀正しかった。
我が子の個性を尊重しつつも蘭の母親はデパートガールという職業柄「他人に失礼のないように。無礼な振る舞いはいつか自分へ返ってくる」という考えに基づき、言葉遣いと礼儀作法にはとりわけ厳しくしつけたのである。
蘭の持ち合わせる正義感と生真面目な姿勢は、母親の教育による賜だろう。
吹奏楽部のみならず、中学校の上級生達は蘭の礼儀正しさを評価しながらも近寄り難いまでの堅苦しさに困惑したという。
吹奏楽部の部長に至っては「チャラくさい後輩もカンに障るけど、あそこまで堅苦しいと却って私らが恐縮するしとっつきにくいんだよねぇ」と困った笑顔で慧子に打ち明けたぐらいである。
親族としての気安さから慧子の前ではくだけた様子を見せていただけに、慧子もまた学校での蘭の堅苦しさに戸惑った。
もし、一哉も公立に進学していたならば「俺の前にいる時みたいに、もう少し肩の力を抜きなよ」と助言したに違いない。
「懐かしいな~。俺、中一の時は蘭よりチビだったけど、その分蘭ちゃんがかっこ良く映ったんだよなぁ……」
うっとりとした面持ちで「斜め下から見上げた目の形が本当に綺麗なのよ。睫毛の長さが分かりやすくてさぁ……」と一哉は懐かしそうに語った。
「飛鳥、お前、いつから音澤よりデカくなった?」
「中三に入った頃かな」
その頃にはお互いに170センチ台に到達していたという。
「さっき、慧ちゃん先輩が確信がどうのって言ったじゃないっすか? 俺も確信がどうたらという経緯が気になるんですよねぇ」
「私も知りたい! 他人の恋愛話って気になるよなぁ!」
慧子も合田も目を爛々とさせて詰め寄ったが、一哉は勿体つけて渋ったままを貫き通すことにした。
「本当に悪いけど、合田と慧ちゃんにもあまり言いたくねえんだよなぁ……」
蘭と交わした約束だから、と納得させるほかない。
その様子では却って気になるだろうと釈然としないながらも、合田は話を切り替えることにした。
恋愛の話には変わりないのだが。
「付き合うの境目って何なんだろうな? お前ら、いつもセットでいる割にはまだ付き合ってねえと言い張るしさ」
「セットって雛人形みてえな言い方だな」
合田のセット発言に突っ込むも、一哉は悪い気はしないようだった。
「こればっかりは人それぞれの解釈だからね」
一哉君の解釈はどうなの? コートのポケットに両手を突っ込んで慧子は問いかけた。
慧子もまた一哉に引けを取らない目力の持ち主だ。真冬の夜空を彷彿させる黒い瞳は頑とした強さを宿す。
「付き合うイコール合意の上で成り立つこと多々あるでしょ。キスなんて欧米人かよほどいい加減なやつじゃない限り友達という間柄じゃできねえよ? 蘭はそういうの嫌がりそうだし、そこら辺のカップルがやってるようなことしたいとは思うけどよぉ……俺たちまだ中学生だし、正式に付き合ってない限り蘭が嫌がりそうだし」
始めは真面目くさった顔の一哉だが、だんだん唇を突き出した変顔になっていった。
「さっきから話聞いてると、あんたは蘭のことしっかり考えてんだよな。あんたの愛は本物だと確信したよ。本来の性教育っつったら相手を尊重することに重きを置くのさ。日本じゃあ妊娠だ出産だ生理現象だ第二次成長期だがメインでさ、もちろん身体的なのも大事だけど精神面での教育がなってない。だから正しい知識もないうちに好奇心でやらかしたり相手を傷つける羽目になるわけだ。まったく」
慧子は「まったく」が口癖なのかもしれない。
「音澤のやつ、性格上いい加減な男女交際嫌いだもんなぁ」
「付き合うつったらもちろんセ……」
「あーーー!」
「やめてー!」
したり顔の慧子の声をかき消すように、一哉と合田は真っ赤な顔で大声を出した。
「なんだよぉ、大事な話でエロ目線じゃないのに勝手に恥じらってんじゃないっつーの男子共」
2002年 雪解けの音・5
◇◇◇
――雪が解けてしまう――
2月の末が音澤蘭の誕生日だった。
蘭。
四君子の一つとされ、春の始まりに咲く香り高き清逸な花。
雪と花の狭間に生まれ、清逸な花の如し優れた人になるよう蘭と名付けられた。
美しい花の名であり、歌うような愛らしい響きを持つ名を蘭は気に入っている。
学校内でおめでとうと言祝ぐ者はごく親しい友人だけ。自分でも友達は少ない方と自覚しているが、別に苦にならない。
外に出ればオーケストラ仲間と、かつて慧子に触発されて数年間習っていたバレエ教室の友達がいる。
気の合わない者と無理して友達ごっこするよりは、互いに信頼し合う者と狭く深くの関係を築くやり方が自身に合っている。そう確信していた。
「蘭さん」
声に気づき、振り返るとショートヘアに眼鏡をかけた女生徒がいる。斎藤聖良だった。
聖良は蘭と同じ学生オーケストラに所属し、担当はオーボエ。
蘭に告白した斎藤先輩といい、いつだか蘭の読書の邪魔をしてきた斎藤といい、この町には斎藤姓が多い。
「セイラさん?」
眼鏡の奥のくりくりした大きな目が蘭を見上げた。聖良は近視なので裸眼では相当な目千両なのが窺える。
「今日、誕生日だよね。おめでとう」
愛嬌のある顔に似合う、透き通るかわいらしい声で斎藤聖良は蘭の誕生日を祝う。
「あ、ありがとう」
「でも残念だな。蘭さん、卒業したら楽団を引退するってホリ子ちゃんに聞いたからさ」
「うん。ごめんね……。セイラさんは楽団続けるんだっけか?」
「F女入れたら管弦楽部と掛持ちするかも。好きなことは苦にならないから」
聖良は市内のミッションスクールに合格しているが、本命は県立の女子高だ。
3組の教室から別の女生徒に呼ばれ「はーい今行く」と返し、聖良はまた今度ねと教室に入って行った。
入れ違いで鵜沼留美がライオンの如し悠然とした足取りで蘭に歩み寄る。留美は登校時に誕生日を祝った。
「セイちゃん、オーケストラ続けるんだ?」
「そうみたいだね」
「蘭は、やらないのけ?」
少しの逡巡の後、蘭は親友の質問に答える。
「高校でやりたいことがあるの。楽団との両立ができるか難しそうでさ」
「一哉君には相談した?」
「なんで、カズ……彼の名前出すの?」
真っ赤な顔で狼狽える蘭に留美はケケケと笑う。笑っても留美はコワモテだ。
「だってあんた、彼がいないとダメそうじゃん?」
「ひどいー!」
親友の前では蘭も女子中学生らしいリアクションを取れる。
鉄面皮で突っ張っている蘭と、普通の女の子と変わらず拗ねたり笑ってみせる蘭。
どちらが蘭の本質かと問われれば留美は間違いなく後者を選ぶ。
「しっかし残念だよなぁ。せっかくの蘭の誕生日が雨ときた」
憂鬱そうに蘭と留美は窓に目をやる。
雪が降ってもおかしくない時期だが生憎の雨だ。
豪雪地帯とまではいかないものの、冬になると当たり前のように積雪するこの町に雪を疎む者は少なくないが、蘭は全てを純白に染め上げる雪景色が好きだった。
その雪景色を憎い雨が溶かしてゆく。
「私、雨嫌い。服が濡れて気持ち悪いし手が痒くなる。そして楽器が傷む」
「蘭は放課後に逢瀬、するのにさ」
留美がわざわざ難しい言葉を使ったのは他の生徒に悟られないため。言わばカモフラージュだ。
「雪ならロマンあるのに」
「土産話、聞かせろよ?」
◇◇◇
夕方に帰宅した蘭は靴を履き替える。
濡れたからというよりは学校で指定されている汚れっぽい白いスニーカーが嫌いなのだ。
靴下も靴も何もかも、どうして地方の中学は白にこだわるのだろう。それも清潔感のある潔癖な白ではない。
野暮ったい白。白のくせに泥臭い。
小四までドイツに住んでいた慧子が中学校に上がる頃、度々そのように愚痴をこぼしていたが全くそのとおりだ。
高校に入ったら黒光りするローファーを選ぼう、蘭はそう決めていた。
基本的には白く短い、寒々しい靴下が指定だが冬場だけは黒タイツの着用が認められているので蘭は寒くなれば専ら黒タイツだ。
オーケストラの練習などで制服で学校外に出だす際はストラップのついた革靴に履き替えるが、この日は雪道仕様の丈の長いブーツにした。
合皮製でレースアップされた靴紐が上品なこのブーツも蘭のお気に入りだ。
同じセーラー服でも足元を変えるだけで田舎の女子中学生は良家の子女へと変化する。
私服に着替えても良いが、限られた期間しか着られないと言っては蘭は一哉と会う時はセーラー服を選んだ。
蘭自身がプライベートでもきっちりした服装を好むのもあるが、いつだか蘭には紺色が似合うと彼に言われて気を良くしたからかもしれなかった。
プルシアンブルー。
二人にとって特別な色。
◇◇◇
――雨などもう見飽きた――
雨は止んだが、好きな女の子の誕生日が鈍色に包まれる。
蘭の好きな甘酒の缶を手に一哉はうんざりした。
新潟から来たと言えばまずは雪について聞かれるが(それも興奮気味に嬉々として聞いてくる。彼らは会津地方並みの豪雪を期待している節がある)新潟市内は同じ県の他の地域と比べてそれほど雪は降らない。
降雪量はおそらく福島と大差ない。もしくは毛を生やした程度であろう。
それよりも雨が多いし、風は強いし、雷も多い。夏はフェーン現象で蒸し暑いと返すと九割がた驚かれ、期待を覆された悔しさゆえに落胆される。
雨が多いと聞けば興醒めなのは理解できる。彼自身も雨が嫌いだ。
どうせならば白銀にきらめく中で蘭の誕生日を祝いたかった。
真白なる雪は、清廉な彼女にふさわしい。
「ごめん、待った?」
冴え渡るアルトに心臓が跳ね上がる。
蘭はチョコミントアイスを思わせるミントグリーンにこげ茶色のドット柄の傘を持ち、欧州の女学生が持っていそうな深緑のタータンチェックの蓋のついた鞄を下げている。
いつだったか、チョコミントアイスはあまり好きではないが配色が好きでこの傘を選んだと蘭が笑いながら話していたのを思い出した。
「いやー、来たばかりだよ?」
嘘を言った。
駅の近くの菓子店にて蘭の好きなホワイトチョコレートがベースのケーキを買い込んだ後、待ちきれなくて約束の時間より20分も早く着いてしまったのだ。
「一哉ちゃん、寒くなかった? これ」
蘭が差し出したのはホットタイプのミルクティーだった。待ち合わせ場所へ向かう途中に自販機で買い込んだのである。
寒いから、何か温かいものを買っていこう。
全く同じことを考えていた事実に二人は声を立てて笑い合う。
「蘭ちゃん、ありがと。はい甘酒」
甘酒はまだ温かい。
この日、学校ではよりによって持ち物検査が行われた。
鞄に入れていたプレゼントの包みは担任に見つかり、事情を知っているクラスメートからは「飛鳥君は今日が彼女の誕生日なんでーす!」と囃し立てられた。
担任からはプレゼントを必ず渡すようにと釘を打たれ「健闘を祈るよ」とエールを送られる始末だ。
「担任がさ、鞄開けるなり『お前よぉ、ずいぶんと女々しいもの持ち込んだなぁ?』って顔さ寄せて迫ってきて参ったわ」
一哉は鞄から蘭へのプレゼントを取り出す。
十字に水色のリボンがくくられ、白い薔薇の造花が飾られた紺色の箱は確かに男子中学生が持ち歩く代物ではない。
「大変だったね。担任って……組長みたいな先生じゃなかった?」
組長のあたりで蘭が含み笑いを浮かべるには訳があった。
翠楓学園の入学式当日に隣合ったモジャ山が一哉に耳打ちし「組長」とささやいたので、あまりにも言い得て妙すぎて笑いのスイッチが入り爆笑させられた事件を織絵から聞かされたことを思い出したからだ。(この一件により一哉は委員長にさせられてしまった)
「担任のあだ名、組長からヤーさんに進化したよ。ボッシュートされたらシャレにならねえど? 下手すりゃ退学覚悟で教務室……職員室さ忍び込んでキャッツアイだ」
他の人ならしないであろう言い回しだ。鬼気迫る表情で語り聞かせる一哉に蘭は肩を揺らして笑う。
「奪還するをキャッツアイって言う人いる? でも私、一哉ちゃんのそういうところおもしろいから好き。没収は免れたんだよね。ヤーさん、いい先生でよかった」
一哉は落ち着かない。日を追うごとに蘭の色香は増すばかりだ。
三つ編みのハーフアップに後ろ髪を巻き付けるギブソン・タックにまとめた髪からは、かすかな花の香り。
この清々しさは可憐な鈴蘭か、荘厳な白百合か。
いずれにせよ、雪の如し純白の花は蘭に似つかわしい。
もしも許されるならば、その華奢な肩を抱き寄せて唇を触れ合わせていただろう。
あの夏の夕暮れに、全身に刻み込んだ蘭の感触はそう忘れられるものではない。
いつかは悲しげにすすり泣く蘭ではなく、幸せそうに笑う蘭を抱き締めたい。
「ハッピーバースデー」
嬉しそうに蘭は手を差し出してプレゼントを受け取る。
紺色の袖から覗く、白く細い手首の可憐さ。
目に入る度に一哉は幾度も胸が疼いた。
「ありがとう。開けてみていい?」
箱を開けた後、蘭はタガが外れたというべきか、普段の優等生然とした姿からは考えられない大声で
「えー! 嘘ぉ! 本当にいいのぉ!」
と叫んで一哉に抱きついた。
勢いで床に倒れ込む。
この喜び様には既視感がある。
そうだ、合唱部のコンクールで上位大会への出場権を獲得した団体の女子が見せるリアクションだ。
キャーキャー騒ぎながら涙を流す。
泣き笑いで仲間に抱きつく。
はじける笑顔。
蘭もそうしたかったのかと思うと、疼いた胸はチクリと痛む。
押し倒された態勢のまま一哉は蘭を想い、彼女の背中に両腕を回す。
――蘭も部活で青春したかったよなぁ――
そして、我に返った蘭は真っ赤な顔で謝りながら飛び退いた。
2002年 雪解けの音・6
◇◇◇
「一哉ちゃん、これロシア村で買ったの?」
恥ずかしさゆえに蘭は体育座りで縮こまり、目線を外して問いかけた。
甘酒と、先ほどの自身が引き起こしたアクシデントによって身体中が暑くなった。
「いや、蚤の市。正月に新潟さ行った時に見っけたよ。でも、なんでロシア村ってワード出てきたの?」
紺色に艶めくネックレスを手に取った蘭は目を爛々と光らせている。体育座りから正座になると、一哉に向けて身を乗り出した。
「インペリアルイースターエッグのネックレスだよ? ファベルジェという職人がロシアの皇帝のために作った卵型の工芸品なの。レプリカも出回っていてすごくきれいだから憧れるけど、中学生には高嶺の花」
授業でも聞いたことのない言葉が幾つか飛び出す。授業に役立つかはさておき蘭は博識だ。
真冬の夜空を切り取ったかのような深い紺色のエナメルに金色の星が浮かぶ。
昔の友達と出向いた正月の蚤の市で見かけ、一哉はネックレスを手に取り「これ、いくらするんですか!?」と食い付いた。
蘭の白い首もとにネックレスが煌めく様子が目に浮かんだ。
紺色の似合う、蘭にうってつけのプレゼントだったのだ。
見るからに中学生だからと(そして好きな女の子に渡すためだと丸わかりだった)定価より何割か安く買えたのは内緒である。
「知らなかった。たぶん……いや、間違いなくレプリカだけどきれいな紺色で蘭に似合うと思ったんだ」
ネックレスの入った箱を床に置き、蘭はおもむろにマフラーをほどき始める。
相変わらずセーラー服の下にブラウスを着込んでいるが、首から肩にかけた曲線の美しさは隠せない。
「着けて?」
「ええーっ!」
すっとんきょうな声だった。
先ほどまで恥じらっていたかと思えば、鼻先が触れてしまいそうなほどに迫ってくる。
「嫌じゃないの? 男から着けてもらうだなんて。ほら、首もとに触れるしさ」
彼にはわかる。別に翻弄し誘惑することが目的ではない。
蘭はただ、王子様であり騎士様である一哉に甘えているだけなのだ。
鉄面皮で気を張っての生活を余儀なくされた蘭にとって、一哉は数少ない心からの笑顔を見せられる存在。
分厚い氷の壁を薙ぎ払い、高潔なる雪の女王を緑萌え出ずる春の陽だまりのもとへ解き放った騎士様。
一哉の前では、蘭は恋を夢見る唯の少女でいられた。
蘭の一哉へ向けた「好き」が暴発しかけていた。
「一哉ちゃんになら、触られても構わないよ」
そう言って蘭は目を伏せてセーラー服の下に着込んだブラウスの第一ボタンを外す。
「やめてー。理性弾け飛びそう」
よりによって、うなじを出したまとめ髪だ。
少し前には弾みとはいえ押し倒された。
一哉は自分を律することで精一杯だった。
一線を越えたら蘭を泣かせてしまう、と己に言い聞かせて。
当然だが一哉はアクセサリーの留め金を扱うなど初めてで、こんなにしち面倒くさい作業を女子は繰り返しているのかと唖然とするほかない。
いつだか、ブレスレットの装着に四苦八苦する清子に「面倒ならつけなくても良くない?」と聞いたところオシャレは自己満足でありストレス解消だと返ってきたことがあったが、蘭も同じなのだろうか。
「結婚式みたい」
「え?」
留め金の装着に四苦八苦している手を止める。
「なんかね、ベールを上げる時みたい」
「あ、あぁ。あのキスの前の?」
自らの口でキスと言うなり、かぁっと頬が熱くなる。
手が滑ったかと思えばちょうど留め金がはまり、蘭の首元に濃紺と金色が輝く。
前から見るのは恥ずかしいので、一哉はひざ立ちのまま蘭の背後から横に移る。
「でもさ、向きが違わない? 俺達向かい合ってないし……」
ブラウスの襟元からのぞく紺色が肌の白さを引き立てた。
色白なこともあるが、蘭に紺色が似合うのは生真面目な気質ゆえだろうか。
紺色は真面目な人が好む色だと聞いたことがある。
「距離感が似ているでしょう?」
瞳を伏せたはにかみの笑顔。桜色に染めた頬の可憐さに、ついに理性が弾け飛ぶ。
「あーっ! もう無理ぃ!」
一哉は目の前の少女を抱きすくめる。
ひざ立ちの状態なので蘭の頭は胸から肩にかけた位置にあった。
「カズ……ちゃん?」
身体を、特に頭と肩のあたりをホールドされて動きにくいが蘭はなんとか顔を上げる。
切なげな顔の一哉がいた。
「ごめんね、痛かった?」
「どうしたの……?」
「俺、蘭を触りたい衝動を抑えられない。蘭を抱き締めたい。ギューッとしたい」
一哉も男性である。腕の力が緩められたことで蘭を抱き締める腕の力強さを思い知り、蘭はたじろぐ。
耳に届く己の鼓動に混じり、彼の声が聞こえた。
「俺、蘭を汚したくないよ。大事にしたいよ。傷つけたくないから、蘭を抱き締めたくてもできなかった。一線を超えてしまいそうで怖いんだ」
蘭ちゃん、ごめんねと繰り返す一哉の胸元に蘭は顔を埋めた。
学生服越しに心臓の鳴り響く音が聞こえる。
あったかい。
「――ありがとう。ずっと私を気づかってくれて」
解っていた。
一哉の、蘭を気づかう優しさを。
会う度に見せる、笑顔に隠れた葛藤を。
肩を並べて歩く最中に、蘭の手に触れようとしても思いとどまり手を引っ込める動作を何度も目にした。
お気に入りのワンピースを着て二人で会った日。蘭の両手首を掴む彼は葛藤していた。
蘭は彼の自制心が勝つまで待った。
蘭自身も自制心が勝るまで堪えた。
ひと度キスを許してしまえば、たがが外れたように全てを許してしまう。
それなのに、蘭は一哉からのキスを期待してしまった。
神様の前で愛を誓う花嫁のように、瞳を閉じて彼の口付けを受け入れられたら、どれほどに幸せであろう。
一哉は、蘭へ向けた「好き」が暴発することを恐れていた。
それを察しているからこそ、彼の気づかいを無下にしたくないと蘭は手を繋ぐこともキスを交わすことも自制した。
手を繋ぎたい気持ちは同じなのに。
誰よりも近くにいるのに。
すらりとしなやかでありながらも精悍さを纏う勇ましい立ち姿は、抱きつきたいと願わずにいられない。
整った鼻筋の美しい、凛々しい横顔を見る度にその頬に口付けたいと何度も願った。
交わしたことのない初々しい口付けは、夢の中でだけ許された。
唇から伝わる、蘭へ向けた嘘偽りのない想い。
溢れる涙で蘭は応える。一哉への嘘偽りのない想いを、涙で伝える。
そして夢から覚めたことをこの上なく恨んだ。
「ごめん。始めっからこんな欲求なかった。一緒にいられるだけで幸せだったのに、中学に入った頃から少しずつ変な欲求が出てきて……」
嫌じゃないよ、と蘭は首を振った。
「それでも、私は一哉ちゃんと一緒に居たいよ」
「引いたりしない?」
「全然」
迷いの後に腕の力が強まった。
覆い被さるように、蘭は彼の腕に強く抱き締められる。
「蘭ちゃん……」
一哉は時々、蘭をちゃん付けで呼ぶ。
ずっと一緒にいようね。
静かに、噛み締めるように言った。
頭の上から聞こえた声に蘭が頷いて応える。
「嬉しい……時間が止まればいい」
その声は涙で濡れていた。
「大好きです……」
雪と花の狭間の季節に、蘭は15歳になった。
2002年 雪解けの音・7
◇◇◇
ヒグラシが寂しげに鳴いていた。
陽光は金色を纏い、秋の気配を帯びている。
鮮やかな夏の花々は少しずつ鳴りを潜め、代わりにアキアカネが空を舞い、鉄砲百合が盛りを迎える。
「付き合うとなれば、キス以上のやりとりをしたい欲求が当然出てくるよ」
泣き腫らした目の蘭は冷静さを取り戻し、一哉の隣に腰掛けた。
まっさらな開襟のシャツと黒いスラックス。
どこにでもいる男子学生の夏の装いだが、堅い印象に爽やかさを垣間見せる夏の制服は彼の顔つきの凛々しさを引き立てた。
いつもならば硬派な男子学生そのものの姿に見惚れるのに、今は見つめることが照れくさい。
「そう……だよな」
「私たち、まだ中学生でさ、性のこと分かっているようでお互いの行動に責任持てないかもしれないね。私も、感極まると突っ走るところあるから……」
自分を律する自信がない、と言い蘭はスカートの上に置いた手をギュッと握る。
「俺も、自信ないよ。蘭ちゃん」
「恋愛って、決して綺麗なだけじゃないと思う。自分達の中では高尚で美しいと神格化していても、端から見れば非常識に映るってよく聞く話でしょう?」
例えばロミオとジュリエット、または八百屋お七は現代と事情が異なる故に"哀しくも美しい恋物語"と語り継がれているのであり、現代の親の庇護下にある中高生が真似しようものなら大問題になると蘭は言った。
「きっと私、一哉ちゃんに甘えて駆け落ちしたいって言い出すかもしれない。恋を夢見る女の子って時々想いが暴発するの」
「暴発?」
「よくあるのは、夜寝る時に好きな人のことを考えていたら切なくなって泣いてしまうってやつ」
蘭は照れて打ち明けた。
一哉を想い、切なくて泣く夜があるのだと。
会いたい。
笑顔が見たい。
声を聞きたい。
楽しかった思い出、彼との未来を想い巡らせ、蘭は涙する。
両手で顔を覆うように前髪をかき上げ、かわいいと小声で呟く一哉も切なげな顔だ。
「でも、そんなの序の口だよ。さっきみたいに抱きついてしまうのも暴発のうちに入るから」
呻くように「あーっ、もう恥ずかしい!」と言いながら蘭は両手で顔を隠し、身体を折り曲げて膝に突っ伏す。
髪の隙間からのぞく耳が赤い。
「いやー、俺は嬉しかったよ? 蘭って本当に生真面目だよなあ。フツーそこまで考えが及ぶ中学生いないよ? でも、そういうところが蘭らしくて好きだよ。俺、待ってるよ」
膝に伏していた顔を上げる。
髪の毛が作り上げる御簾の如し隙間から、愛しい少年の澄んだ瞳が見えた。
髪を耳にかけ、恐る恐る顔を上げて蘭は「待ってる、って?」と聞き返す。
「蘭が大丈夫だと確信持てたら、付き合おう?」
「それなら……」
逡巡の後、蘭は一哉に告げた。
――私が18歳になったら、返事をさせて――
◇◇◇
気付けば23時を回っていた。いい加減風呂に入って寝ろと清子姉にドヤされるだろう。
夜中なのに白鳥が鳴いている。
寝床へ帰るのだろうか。
宿題と、入試に向けた勉強は既に22時絡まりには終わらせた。おおざっぱなO型ゆえか無理なスケジュールで行動するのは好きではない。
帰り際、蘭はケーキの箱を見て相当に喜んだ。
蘭の大好きな、ホワイトチョコレートのババロアをベースにフルーツを盛ったハート型のケーキ。
きゃあ、と歓声を上げ、両手を組み合わせて目を輝かせる姿が愛おしい。
一哉は文字ではないものを書いていた。
否、描いていた。
そして、しかめっ面で髪をモシャモシャに掻き上げる。
「また、こんなん描いちまったよ。恥ずかしい」
医師を志す前になりたかった職業は漫画家だった。
血は抗えないのか親族に音楽と絵を心得ている者が何人かいて、一哉も例に漏れず音楽も絵も好きで、絵に至ってはそこそこ自信がある。
小学生の頃、答案用紙の裏に描いた黒猫の落書きを「落書きにするには勿体ない出来栄えだ」と担任に褒められ、気を良くして自由帳やノートの空白に絵ばかりを描いていたらいつの間にか上達してしまったのだ。
母が花梨の出産を控えた頃、清子と共に父方の実家に預けられた時期があった。
年齢の離れた従姉が持っている「紡木たく作品集」の優しくも切ない作風にのめり込み、従姉にねだってはよく借りていた。
流行りの少年漫画を模した絵やリアル調の絵も描けなくはないのだが、従姉から借りた漫画の影響は強く、一哉の描く絵は80年代後半の少女漫画を思わせる清涼感とノスタルジーを抱かせるラフな画風になっていった。
絵柄が古いと揶揄もされたが、蘭に好きだと言われた画風を変える気はない。
蘭が結婚式みたいだなんて言うから……。
ストイックな優等生の反動か、確かに蘭は突っ走るところがある。
結婚式みたいという発言も、鼻先すれすれに迫ってきたのも『好きが暴発』したからかもしれなかった。
思えば、好きの暴発に当たる行為が今までにもあった。
静かに、音を立てずに蘭は一哉への恋心を暴発させていた。
ボーダーラインを決めなければ、暴発の限りを尽くしてしまうかもしれない。
だからこそ、蘭と一哉は法的に結婚が許される年齢=自己の行いに責任を持てる年齢まで交際を先送りにすると決めた。
ノートの空白に描かれたのは、当てずっぽうなデザインながらもハイネックにAラインのスカートが上品なドレスを纏った女性の絵。
編み上げた髪にベールを被った姿は花嫁以外の何者でもない。
――いつか、俺の隣で白いドレスを着てはにかむあなたが見たいです――
「あと三年かぁ」
――大好きです――
蘭と一哉は付き合っているか論争
「結局、蘭ちゃんと一哉君って付き合ってんの?」
高校入試に向けた勉強会の前に、白沢小百合の問いかけから『蘭と一哉は付き合っているか論争』が始まる。
白沢の自宅はブドウや桃を栽培する兼業農家で、広大な敷地に年季の入った立派な日本家屋と白漆喰の蔵屋敷を有する。
家が広いからという理由で、勉強会など大人数の友人が集まる際は白沢の自宅に集まるという暗黙の了解がなされていた。
この日は第一土曜日の放課後で全員が制服。白沢はセーラー服の上に最近買ったばかりのユニクロのフリースを着込んでいる。
「いや、アズ本人が相思相愛だけどまだ付き合ってないって言ってる」
白沢の向かいに座っている橘織絵が静かな口調で答える。
翠風学園に通う織絵は一哉と同じクラスである……と同時に、蘭がマクドナルドで遭遇した三人とも顔見知りであった。
切れ長の細い目に薄い唇の、あっさりとした目鼻立ちながらも華のある端正な顔を持つ織絵。
彼女は翠風学園の男子生徒から人気が高いものの、高嶺の花としての扱いで遠巻きに憧れられるポジションである。
典型的なクールビューティーの織絵だが、緩いウエーブの入った癖っ毛が柔らかさを補った。
「相思相愛かぁ、いい響きだなあ」
織絵の隣で正座する斎藤聖良が眼鏡の奥の大きな目を輝かせて言った。
「あの雰囲気は、お互いが好きだと確信してない限り出ないよねえ」
聖良は私も恋がしたいとうらやましそうである。
「蘭さんも付き合ってないと言い張るけど、あの二人って本当に素敵だよねえ。女王様と騎士様って感じする」
「セイちゃん、ロマンチストすぎ」
がっしりとした骨格の大柄な少女がひらひらと手を振りながら苦笑いで突っ込む。
久間木春奈。一哉と合田と同じく、南沢又小学校の出身だ。
中学では剣道部に入っていた白沢と春奈の二人。クラスは異なるが、学校内で顔を合わせれば必ずお喋りをするなど仲が良い。
小学生時代のみ吹奏楽部に所属していた春奈だが、その時の縁もあり清水が丘小学校の吹奏楽部員だった織絵や聖良とも知り合いであった。
そうした縁が重なり出会った四人は現在、白沢家の客間に勉強会という名目で集まっている。
「だから。昨今の中学生に女王も騎士もあるかい」
ロマンチックな表現は嫌いではないが、現実味がないと白沢も突っ込む。
「蘭ちゃん、市内の吹奏楽やってる連中の間じゃ『高潔なる雪の女王』って通り名付けらっちぃ」
翠風学園の吹奏楽部員だった織絵が言う。
更に「やっかみを買われて部を追い出さっちぃ悲劇の女王さ」とも付け加えて。「まあ、確かに」と相槌を打つ春奈は妙に納得した顔だ。
「蘭さんが女王みたいなのはわかるかもしれない。しかしなぁ、転校してきた頃の飛鳥のやつ、今思いだしても笑えるなあ」
思い出し笑いによるものだろうか。春奈はややコワモテの顔に含み笑いを浮かべている。
「あー、そうか。一哉君って福島が地元じゃないんだっけか」
「そうらしいね。どこ出身だっけ」
「新潟だよ」
「すげえ苗字だもんなあ。新潟にはいるのかね」
白沢の発言に少し遅れて、珍しい苗字って憧れるなあ、と聖良がつぶやく。
「いや、飛鳥井ならいるけど飛鳥川は俺ん家の親族ぐらいだろーって言ってた。あいつさ、転校早々知らない女の子に一目惚れして一週間ぐらい腑抜けてて生きた廃人みたいになってたんだよ」
「うっそぉ! あんなにキリッとしてかっこいいのに?」
白沢はがっかりした様子だ。一哉に恋愛感情はないにしても美形好きの白沢は美少年に夢を見たいらしい。
「キリッとしてるかい? まあ、アズのやつが美形なのは認める。あいつ、同じクラスだけど見た目に似合わず普通の男子だよ?」
「清水が丘出身の女子から見れば、飛鳥のやつは凛々しい美少年に見えるのかい。又小では腑抜けた飛鳥君って有名な話だよ。一目惚れのお相手は言わずもがな蘭さん」
クールな物言いに相反した含み笑いのまま春奈は語る。
「又小の連中も、あの一件で恋煩いっつうものが何ほど厄介な症状なのかと小五にして学習したわけだ」
「そんな前から知り合いかよ。いつの間に」
知らなかったぞと白沢が言う。
「そういえば、蘭さんと一哉君の馴れ初めって私達知らないよね?」
白沢と織絵も「そうだね」と言い興味深そうに目を光らせた。あわよくば二人の馴れ初めを知りたい。
「高潔なる雪の女王様が如何にして騎士様と巡り合ったかを知りたいね、私は」
頬杖をつき、やはり静かな口調でロマンチックな表現を駆使して延べる織絵。
中二病と揶揄されかねないセリフ回しも、織絵が纏う知的な雰囲気のおかげか不思議と様になっていた。
「ゴウダなら知ってたりして」
「ゴウダぁ!?」
白沢がすっとんきょうな声を上げ、織絵が細い目を見開き頬を染める。
「ゴウダと飛鳥のやつ、同じ日に転校してきたこともあって仲良いんだよ。その頃から1組のハマちゃんともつるんでたし」
両手を一度だけ叩く白沢。何かを思い立った様子だ。
「今日ゴウダとハマちゃん来るしな、聞いてみっか」
「えっ! ゴウダ君、来るの!?」
それまで静かだった織絵の、動揺した素振り。
白沢の脳裏にある疑惑がよぎる。
「んだ。オリちゃん、まさか……」
小学校も中学校も異なる学校に通う織絵と合田は接点がないように見えて、何度かの接点はあった。例えば、今回のような白沢繋がりの集まりの時だ。
「うん、実は……ゴウダ君が好きなの」
頬を染めたまま淑やかに告げる織絵。
少女達は色めくどころか、その場の空気がサーッと白けた。
「美女と野獣もいいところだな」
「だから。ゴウダのやつハッキリ言ってかっこ良くねえべした」
「シロちゃん、言いすぎだよ……」
三者三様のリアクション。困り顔の聖良が白沢をたしなめるより少し遅れて織絵がスッと立ち上がる。肩の上で薄茶色の天然パーマがふわりと跳ねた。
「男も女も顔じゃないよ! 性格が男前なのゴウダ君は!」
白けた空気の中で織絵だけが熱くなり、アルトのハスキーボイスで早口を繰り出す。
冷静なようでいて織絵は激情家だ。そして如何に合田康範が魅力的な男であるかを身振り手振りを加えて熱弁し出したのだ。
「そりゃあ、確かにゴウダはいいやつだけど」
「意地悪りぃことは決して言わないしな。つーか、オリちゃんはなんでゴウダに惚れた?」
「内面だよ内面! ゴウダ君、おだっているように見えて洞察力あるしさりげなく気づかいできっぺした」
「そうかい……?」
頬杖をついて、織絵の想い人が合田康範である真実を信じられないとばかりに春奈は言う。
続けて白沢がコタツに顎を乗せて気怠そうに口を開いた。
「いいやつで頭いいのは認めるけど、給食の残り物でフードファイトしたり美術の授業で変な造形物作っておだってる印象しかねえない」
白沢は合田と同じクラスだ。
学校での合田の様子を嫌と言うほど目にしているが、理想の高い白沢にとって合田は恋愛対象になり得る相手ではない。
「ゴウダ君はいい人だよ! 去年の夏にシロちゃん家さ集まった帰りに雨降らっちゃ時に傘貸してくっちい!」
「いや、それ普通だべした? なあ?」
「オリちゃんが相手ならだいたいの男は傘貸すっつーの」
春奈の発言に白沢も同調するが「そんなわけねえべした」と否定の言葉を述べて織絵はかぶりを振った。
「みんな、変な噂流されたくないがために知らん顔すっから。異性相手に親切にすると変に勘繰るやついっぺした。でもゴウダ君は違うよ。周りの目を全く気にしないし、地下道で迷った時にも道案内してくっちゃし」
「それも普通だから」
「オリちゃんが困ってたら、だいたいの男は放っておけないんじゃないかな」
控えめに発言する聖良に織絵は「いや、あり得ない」と否定した。
「だいたいの男は知らん顔するね。でもゴウダ君は自ら『あれ~、お前白沢のダチだよな? 道迷ったのけ』って声かけてきてくっちい。損得関係なしに気を効かせてくれるのゴウダ君は。そうそう、去年の夏は黒アゲハ飛んできた時に追っ払ってくっちゃし……素敵な人なんだよぉ、ゴウダ君」
織絵はうっとりとした面持ちだった。おそらく、学校で惚けた顔は見せないであろう。
ファンの男子達が黙っていられない状況に、白沢と春奈は内心面白く思う。
「あー、オリちゃんって蝶々嫌いなんだったな」
中学校に進学して以降はしばらく見ていなかったが、蝶々を嫌がり逃げる織絵の姿を白沢は思い出していた。
「オリちゃんと蝶々似合うんだけどなあ」
「あれは変な粉付くのが嫌なの。アクセサリーとか着物の柄なら平気だけど……」
いつの間にか座っていた織絵。「あれ、本当に嫌なんだよねぇ。蝶々の見た目は綺麗だけど」と蝶々の鱗粉が嫌だと愚痴をこぼして頬杖をついていた。
「花火大会の時に蝶々柄の浴衣着てたね」
「ゴウダのやつもオリちゃんみたいな美人に惚れらっちい、幸せじゃねえかよ。ゴウダのことだから全く気づいてねえかもだけど」
「いいよ、別に気づかれなくても」
どうせ初恋は実らないし受験する高校も違うからね、と織絵はため息混じりで語る。
合田が受験するのは男子校だ。
「ねえ、オリちゃん。ゴウダ君が好きなことを誰かに話したの初めて?」
問いかける聖良は、なぜか眉をひそめている。
「翠風の友達には好きな人いるんだ~って話してはいるよ。でも泉清の友達には初めて言った。このメンバーだから言えたんだ」
織絵も聖良と同じように眉をひそめた。
「みーちゃんに知られたらメチャメチャにされっから。小三の時の蘭ちゃんみたいにね」
一呼吸置いて織絵は続ける。
「私も、みーちゃんに良く思われてないこと、とっくの昔に気付いてるし」
蘭と一哉は付き合っているか論争・2
一同の間にホッとした空気が流れ、やがてノックと共に若い男性の声が届く。
「小百合~男性陣が来たどー。あと女の子も」
白沢には二人の兄と弟が一人いる。
男兄弟に挟まれた影響だろう。白沢は「絵に描いた女の子のよう」と評される華奢で可憐な容姿に似合わず粗野で勝ち気な少女だった。
来客の到来を知らせたのは次兄の巧。
四歳年上の巧は白沢をそのまま男にしたような、線の細い小柄な優男である。
白沢との相違点は気が優しく穏やかであるところ。
この次兄が小学生の頃、憧れていた光GENJIを真似て『ガラスの十代』を歌いながらローラースケートでスライディングした際に派手にスッ転んだエピソードは近隣では有名な話で、思い出話の度に10数年前の恥ずかしいエピソードを持ち出されることが常だ。
巧は石油ストーブの斜め前に正座し、ストーブの上に乗せたヤカンのお湯で人数分のお茶を淹れる。
指を揃えた動作は男性ながらになよやかな印象を与えた。
3月とはいえ春は名のみ。
ストーブの中で揺らめく朱色の炎は目にも肌にも温かい。
歯科助手で週6日間働いている母親に代わり、妹と弟絡みの来客の世話を焼くのが巧だった。
男臭くない見た目と気さくな性格から織絵を筆頭とした女性陣に話しやすいと親しまれ、しまいには白沢家の第二のお母さん扱いを受けるまでになる。
「うーっす」
「お邪魔しまーす」
合田康範を先頭に数人の男子と更に数人の女子が加わった。
巧は寒い中わざわざ来てくれてありがとうねと気づかいの言葉をかける。
「あっ、オリちゃん久しぶり。顔赤いよ?」
「どうも。気にしないで」
「お前ん家デカくていいよなぁ」
「良くねえべした。騙し騙しリフォームしてるだけだし、家デカくても古い分だけ掃除がめんどくさいんだっつーの。母ちゃんも夕方まで働いてるし家政婦さん雇いたいよ。ねえ、兄ちゃん?」
いつの間にか巧は人数分のお茶とお菓子を全て配膳し、ほぼ空になったヤカンに水を足して台所から戻ってきた。ストーブとヤカンの境目からプシューッと音が鳴る。
「そうだね。明治時代に建てたのを増改築してるから掃除が大変だよ。あと、今時農家の嫁になりたいと思う女の子はいないし……。あ、未来ある中学生にする話ではなかったよね。それじゃあ、頑張って?」
白沢の「将来は無難な広さの新しい家さ住む!」という声をBGMに、そそくさと去りゆく巧の姿は儚げだ。
整った容姿をしている巧だが、気苦労が多いのか19歳なのに年齢より疲れて見える。
優秀な長兄が東京の大学を出たまま東京に居着いてしまい、実質上巧が跡取りに等しい立場であるのだ。
「お前の兄ちゃん気苦労多そうだな。不景気だけど就職できたんだべ?」
「んだ。農業高校出て乳製品作る会社で働いているよ」
白沢が「遠慮しないで飲んでいいよ」と指差した先には北欧風の刺繍を模したかわいらしいパッケージの飲むヨーグルトがあった。
巧が「特売で安くなったから多めに買ってきたよ」と出してくれたのである。
「デンマークヨーグルトだべした! お前の兄ちゃん気前いいな! これ旨いんだよぉ! 特売の時しか買ってもらえねえけどよぉ」
「私ん家もだよ。デンマークヨーグルトもだけど桃とかさくらんぼとか、福島で作るものって何気に高嶺の花の農産物が多いな。地元民は傷みかけを安く買うけど。そうだ。ゴウダに聞きたいんだ」
久間木春奈が合田に視線を向けて言う。
「え、何だ?」
「ゴウダさあ、飛鳥と蘭さんのなれそめ知ってっかい?」
「お前も又小だから知ってっぺよ?」
「でも詳しい話は知らないよ」
煎餅に手を伸ばし、合田は「あ~」と思い出したように言う。
「飛鳥のやつ、川縁の桜を見に松川さ行ったんだよ。そしたら桜の下に音澤がいたんだってさ。要するに一目惚れ」
「桜の下!」
まず反応したのは白沢。
頬を染めて目を輝かせ、さながら恋愛映画の山場を見た後のリアクションだ。
「美男美女が桜の下」
いいね、絵になりすぎると静かにつぶやきながら、頬杖をついたままの織絵はうなずく動作を見せた。
「蘭ちゃん、桜の花似合いそうだもんねえ」
「一哉君が桜の下の蘭ちゃんに惚れるのもうなずけるなぁ……」
複数人の女子も白沢同様にうっとりした表情だ。
特にロマンチストの聖良は蘭と一哉をニコイチで神格化している節があり、とりわけうらやましそうだった。
女子達の反応に対してか、またはその場にいない親友に対してか合田はやれやれと言いたそうにため息をつく。
「飛鳥のやつ音澤と付き合ってねーと言い張るけどよぉ、なんだかんだで付き合ってるようにしか見えねえんだよなぁ」
先ほどまでうっとりした面持ちだった聖良がおずおずと手を挙げる。
「私、学習センターの図書館で一緒にいるところ見た」
はにかむ聖良の頬はリンゴのように赤い。
「図書館の職員さん達も『あのカップル絵になるわねえ』って微笑ましそうだったな」
「私は稲荷神社の例大祭で見かけた! 蘭ちゃんが嬉しそうにリンゴ飴食べながら巫女舞眺めてるのを、一哉君めっさ嬉しそうに見つめているんだっけー」
そして、物陰から留美を筆頭とした親友達がワクワクした様子で蘭と一哉の動向を窺っていたという。
「私は福島駅の本屋で見たよ。蘭ちゃんが本買うか悩んでて、一哉君が買ったら? なんて言ってた」
その本は『星の王子さま』でハードカバーは家にあるが携帯用に文庫本を買おうか悩んでいたと目撃者は語る。
「俺はクリスマスの頃に飛鳥君と音澤が飯電で隣り合って座ってたのを見たよ。隣の車両から見えたけど」
その男子は泉駅の次にある岩代清水駅から乗り込んだのだが、どう見ても親密すぎて付き合っているようにしか見えなかった、と語る。
言うまでもなく、蘭と一哉が『くるみ割り人形』のミュージカルを見に行った日のことだった。
「なんか、目撃情報多数だナイ」
合田の隣に座る浜津陽一郎は驚きを隠せない。
150センチに毛を足した背丈の白沢よりも背が低い浜津はリス、または小猿を思わせる風情だ。
「でも必要以上にベタベタしてねえんだよな、あいつら」
「手さつなぐのも?」
浜津はまず合田を見上げ、更に勉強会の参加者達を見回す。人の良さそうな糸目の奥に、戸惑いの感情が見え隠れした。
最後に浜津と目が合った男子もまた戸惑いながら口を開く。
「あいつら、なんだかんだで目立つし影響力あっからよ。変な行動取ったりでもしたら周りがうるさいの察してっから……」
男子は口ごもり、しばらくして再び躊躇いがちに語り出す。
「一緒にいるけどキスとか手を繋ぐは、まだしてねえんじゃねえの?」
「あり得る。蘭ちゃん身持ち固そうだし」
白沢が納得したように相槌を打ち、浜津も先ほどの男子と同じく躊躇いがちな様子で言った。
「率直に言うの避けるけど、音澤のやつ絶対成人してから……いや、結婚を考えてる人でないとダメって本気で言ってそう」
生真面目な蘭ならあり得る、一同は全く同じことを考えていた。
「結婚するのかな、あいつら」
浜津のつぶやきに勉強会の参加者一同はどっと笑い出す。
「そんなの10年以上先にもならねえとわかんねえべした」
と、突っ込みを添えて。
「音澤のやつも『好きを貫き通すからには周りに文句は一切言わせない』のスタンスで動くだろ。好きなことほど文句言われたら誰だってムカつくけど、音澤はそれが顕著なんだよな」
そう話す合田は半ば貪るように煎餅をかじりつつ、ノートにシャープペンを走らせている。
織絵が「合田は洞察力がある」と話したとおりだった、と白沢と聖良と春奈は納得せざるを得ない。
お調子者でふざけているようで、合田は周囲を取り巻く者達の人となりをしっかりと見抜いている。
「飛鳥のことで文句言われたりでもしたらまずキレるよね」
変声期を終えたものの未だボーイソプラノの面影が残る声で浜津が言うと、別の男子が腕組みしながら続け様に発言し出した。
この男子も清水が丘小学校の卒業生。もちろん蘭の一件を知っている。
「もし音澤と飛鳥君がキスとか抱き合うとかして、万が一見られて噂になったりでもしてみろ? そしたらあいつがまたぶち壊しにかかってくるから」
蘭と一哉は付き合っているか論争・3
「うちらが小三か小四の頃だっけか」
白沢も織絵も聖良も小学校三年生の時のクラスは蘭と異なったが、だいたいの事の顛末は知っている。
「好きな男子が被ったかなんかで、悪口を言ったとか周りをバカにしていたとか嘘の噂を流されたんだよね?」
「蘭ちゃんに限ってあり得ないのにさ、流されるやつらもバカじゃないの? どうせ、中流家庭で経済的にも環境面にも恵まれて友達も普通にいるくせに、内心は家族や学校とかの自分を取り巻く者達への不満ばかりで強い劣等感を抱えるやつらが便乗していたんだろうけど」
冷ややかな織絵の発言。頷く動作。同調のセリフ。
所々から納得したかのような反応が認められる。
真っ先に言葉で同意を示したのは聖良だった。
「確かに……蘭さん対していろいろ言う人ってそんな感じだよね」
続けて発言したのは浜津。
「だから。音澤を妬む連中って、どちらかといえば運動神経は問題ねえし、成績も良い方だし、要領は良いし、Mステとか金八っつぁんとか好きな番組を見せてもらえて何かしら買ってもらえたり、土曜日の弁当のオカズも彩り良くて良い暮らししてそうなのに、変に不満ばかり言うんだよなぁ」
「俺よりも身長あるだろー、俺の弁当はいつも煮物と唐揚げとミートボールで茶色なんだよ」
「母ちゃんが忙しいから作り置きオカズを自分で盛り付けているんだよ」
「俺なんて金八っつあんもバラエティも父ちゃんが嫌いだからと見せてもらえねえのに、あいつら何が不満なんだよ」
「別にバカでも不細工でもねえくせに、あいつら贅沢すぎだよ!」
浜津が力説しながら沢山の恨み言を連ねたので、一同の顔に苦笑いが浮かんだ。
浜津の隣に座る男子は、まあまあ落ち着けと背中を叩いてなだめすかしつつ
「却って、成績良くねえやつとかどんくさいやつらが音澤を支持するよな」
と発言した。
「しかし橘もよく解ってんなぁ」
思いがけず合田からの反応があり、織絵は頬を染めて顔を伏せる。
「私も言われてたからね。そういう連中に、いろいろと」
「えー、オリちゃんも?」
人気者の位置付けだったべ、と不思議そうな聖良に織絵は顔を振る。
「一部のやつらに陰口叩かれてたよ。男女問わず。あからさまな嫌がらせはなくても陰口はあったね。みーちゃんはそんな生徒の代表格と言ってもいい」
再び顔を上げた織絵は勉強会の参加者をぐるりと見渡す。
「やつのタチの悪いところはわざわざ『誰々が悪口言ってたよ』と他人事のようなツラさらして報告しに来るところ。自分が悪口を言うようけしかけるくせに。あいつと一緒にいると、不思議と人を信用できなくなる。
だからうちの学年の女子、下手にみーちゃんに楯突かないし誰が好きだなんておおっぴらに言わねえべ」
上手くいくものが、上手くいかなくなるから。
織絵は静かに、重々しく告げる。
みーちゃん。
いつだか、蘭の読書の邪魔をした吉田という女生徒のあだ名だ。
中学生以降はミサっちゃんというあだ名も派生している。
後からきたメンバーのうち、髪を短いポニーテールに結った女子がしかめっ面で頬杖をつきながら口を開いた。
「相手がいる前で『あんたの好きな人いるよ』って言ってさぁ。あれ、見ている方も感じ悪くて嫌だな。自分だってタケちゃんを引き合いにやられたらただの友達なのに~って被害者面するくせに。でも、みーちゃんって敵に回すと怖いから言いにくいんだよねぇ……」
「なんだ、由香理ちゃんも言いにくいのかい」
白沢に「だって……」と不満そうに返すポニーテールの女子=由香理は『嘘を見破った者』にカテゴライズされた人物の一人だった。
テニス部の元キャプテンで勉強も得意だが、スポーツ万能なイメージが先立つ由香理はスクールカーストの最上位者といっても過言ではない。
それだけに陰口こそ叩かれはするものの、気が強く且つ口が立つので表立って敵対心を露にされるなどはなかった。
典型的な委員長気質で仕切り屋な面があり、男子からビビられるのは否めないが。
「怖いっていうか、人間関係こじれさせてめんどくさい展開にさせたがるよね。自覚あるんだかないんだか知らないけど」
由香理の隣に座る親友の絢が「だからぁ」と続ける。利発そうな顔が不満げに歪められていた。
三年一組の学級副委員長を務める絢は、合唱コンクールで蘭を指揮者にと推した張本人。
「実際にエリちゃんがそれで林に嫌わっちゃべ。せっかくいい雰囲気だったのに」
参加者一同の脳裏に浮かぶは、どんくさいが暖かい眼差しを持つ優しげな少女。
微笑みが絶えないはずだった少女は、いつしか蘭や留美の背中に隠れてオドオドと怖がる姿を見せることが増えた。
「それで蘭ちゃん達、目を付けられないようにプラトニックな関係を貫くのかな」
「相思相愛なのに勿体なくねえ?」
「でも堂々と一緒にいるしな。引き裂かれた大槻と林よりは断然マシだべした」
「エリちゃんも典型的モヤシっ子の林のどこがいいんだか」
フーッと息を吐いて腕を伸ばす白沢はさりげなく林という男子にえげつない評価を下す。
学校生活においても男子に対していちいち毒舌で厳しい発言が見られる白沢だが、林に至っては顕著だった。
「吹奏楽部の後輩からあからさまにモヤシ先輩って呼ばれっちいし、林のやつ飄々とした風しておいて意外とズルいところあっぺした」
「ふーん……小学生ん時はそうでもなかったけど。中学入って性格悪くなったとは風の噂で聞いた」
織絵は小学生時代の林しか知らない。
「女々しくて男気ねえ上に女みてえな顔だしモヤシだかんな、あれ」
やはり手厳しい白沢である。更に白沢からの林へのダメ出しは続く。
「男気ねえからみーちゃんに流されてエリちゃんに冷たくなったんだろ、どうせ」
「男子から見ても大槻への手のひら返しは引くよ。大槻のやつが林に気をつかって避けてると『逃げてる逃げてる』とバカにして囃し立てたのは見ていて腹立ったね。
陰でだけど男子の間でも『ちょっと大槻に対して態度悪すぎねえか』って話になって、林本人に忠告した男子が何人かいたんけどな。
でも林も人のせいにして逃げやがったわ」
俺も注意したと合田が名乗り、浜津も続けて「俺も林に注意したよ」と手を挙げた。
「あの時の飛鳥君とは大違いだよ。だから音澤のやつも飛鳥君のこと信頼してるんだろうね」
「あの様子の飛鳥を見りゃ、どんな嘘八百も通用しねえとわかるよなあ」
一同にある光景が浮かぶ。
まだ冬真っ只中の放課後の出来事。
烈火の如しと呼ぶべき、激昂する一哉の姿。
合田が腕をさすりながら当時を思い返す
「あれでも飛鳥のやつを取り押さえるの精一杯だったかんな。すげえ力だったし振り切られっかと思ったわ」
「んだから。俺もチビなりに頑張ったよ」
「私ら女性陣はオリちゃんをなだめすかすので精一杯だったよ」
春奈が言うと白沢も続ける。
顔を見合せる二人は当時を思い出したのか疲れた顔になっていた。
「だから。オリちゃんが『私、あいつ殴っていい?』ってキレたぐらいだもんな」
「蒸し返すのやめて。恥ずかしいから」
「まあまあ、ああ言われりゃ橘のやつがブチギレるのも無理ねえべ」
合田のフォローに織絵は頬を染める。
「飛鳥のやつ、あの後に『蘭との約束破った』って意気消沈してたね。約束って何だべな?」
「知らんわ。あいつ蘭ちゃんが絡むと口固いし」
蘭と一哉は付き合っているか論争・4
◇◇◇
実は、白沢小百合も蘭と一哉の逢瀬の瞬間を目の当たりにしていた。
よりによって、白沢家の敷地の裏でだ。
飼い犬のエサのストックを探しに蔵屋敷を探っていると、白沢家を取り囲む白漆喰の塀の裏で蘭と一哉が話し込んでいたのを目の当たりにした。
恋愛事への好奇心は凄まじいもので、白沢は蔵屋敷の小窓から二人を観察するも蘭と一哉が抱き合うなどのアクションはない。
抱き合う二人を期待していた。
ただでさえ、同級生にカップリングが派生したとなれば進展が気になるもの。
踏み込めないほどに美しい二人のキスシーンなどは、さぞかし恋愛映画みたいだろうなと白沢は胸をときめかせた。
蘭と一哉は、お喋りに興じているだけだ。
次第に冷静になり、プラトニックな二人にキスを期待した愚かさを白沢は恥じた。
時折、どちらからともなく照れた表情を見せるので、罪悪感にかられていた白沢は段々と二人の初々しい反応を微笑ましく思う。
蘭ちゃんが笑っている。
はにかみ。
微笑み。
満面の笑顔。
凛とした切れ長の瞳が優しげに細められ、同性ながらに惚れ惚れしてしまう。
小柄な白沢の目には、大人びた容姿を持つ蘭はかっこいい女性に映る。
幼なじみの気安さから一哉との関係性をからかう時もある白沢だが、その度に頬を染めて恥じらったり焦ってたり、拗ねてみせる蘭の姿はかわいらしく映った。
中学二年生に進級して以降は、仏頂面が増えた蘭。
もちろん留美達の前では無邪気に笑う。
同級生という括りの中では比較的交流のある白沢にも蘭は愛想よく受け答えはするが、だいたいの生徒の前では鉄面皮。
笑うと年相応の愛嬌が垣間見えてかわいいのに、もったいないと白沢は惜しく思う。
蘭に対して『人によって態度を変える』と快く思わない同級生が存在するが、そうならざるを得ない理由を彼らは知らない……というよりは『そうならざるを得ない理由から敢えて目を背けて蘭を悪者に仕立て上げている』だけだ。
それらの人物はえてして、蘭の優れた容姿と清廉な人柄に劣等感を抱えていることを白沢は察している。
こういった連中こそが、蘭が気を許した人物にしか笑わない原因を作っているのだ。
白沢はあきれるほかなかった。
互いの兄が親友同士で、その縁で未就学児の時分から親交のあった蘭と白沢。
幼なじみの一人である蘭には同情心が芽生える。
雪解けを言祝ぐ花の如し可憐さを纏う蘭こそが、本来の音澤蘭の姿である。
雪の女王が作り上げた、容易に解けない分厚い氷の壁を薙ぎ払い蘭を可憐な少女へ戻した一哉はどんな人物なのか。
白沢は不思議に思いつつ、未だ知らない相思相愛の恋という未知の感情への憧れを募らせた。
それ故に、白沢は蘭と一哉の逢瀬の瞬間を話す気になれなかった。
いいなぁ、蘭ちゃん。
私も恋がしたい!
蔵屋敷の小窓から気配を潜めていた白沢だが「小百合~ザビエルのエサあったかーい?」と巧が大声で聞いてきたの、で盗み見は蘭と一哉の二人にバレてしまい、内緒にすると約束したのだった。
手土産に白沢家の畑で収穫したリンゴを添えて。
リンゴ。時系列は今より少し前の季節だと白沢は回想するとノックの音により現実に引き戻される。
「みんな、はかどってるかい?」
お茶菓子を用意した巧によって現実に引き戻された中学生達は、しまった……と青ざめる。
勉強会の参加者一同は30分ほど『蘭と一哉は付き合っているか論争』に花を咲かせ、勉強会などすっかり忘れていたのだった。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編)
――ジャンヌ・ダルクは白旗を揚げた――
音澤蘭が吹奏楽部を退部したのは斎藤聖良が14歳の誕生日を迎えた2日後の梅雨時だった。
聖良は蘭を引き止めることができなかった。
そして、奴の暴走も。
「蘭さん、エリちゃん、部活……辞めたの?」
音楽準備室の戸棚からスコアと教則本一式を片付ける蘭と、同じく吹奏楽部を退部することにした大槻英里ことエリを前に、悩みに悩んで口から出た質問文は直球だ。
口から出たそばから、もう少し湾曲した言い回しでも良かったのではないかと聖良は後悔する。
どうしよう、蘭さんが怒るかもしれない。
エリちゃんが泣くかもしれない。
暑さと緊張から汗ばむ両手を祈るように組み合わせ動向を見るも、聖良をゆっくり振り返る蘭は思いの外冷静そうだった。
憧れの、涼やかな切れ長の目尻と高い鼻筋が今日は冷たく見える。
「人を蹴落として平気な顔していられるやつが取り仕切る部活なんて、こっちから願い下げ」
蘭の陰でエリはうつむいたまま一言も発さない。
蘭とは対照的の地味な容姿ながら朗らかで優しく、いつも微笑んでいるはずのエリは今までにない暗い顔をしている。
「ごめん。力になれなくて。でも私は……」
「聖良さんはどうするの? これから」
蘭の問いかけに聖良は何も答えられなかった。
しかし、無言の聖良を蘭は責め立てるわけでもなく静かに語り出した。
「今までありがとう。聖良さんが陰ながらいろいろと気遣ってくれたのはすごく嬉しかったし励みになった。でも、私達もう限界なの。居場所のない部活に無理して居座る必要なんかない。行こ、エリちゃん」
「セイちゃん、私からもありがとう。根性で三年間辞めないで頑張ろうとしたけど、あんなことされて限界来ちゃった。私は美術部に入ることにしたよ」
この時、大槻エリはようやく言葉を発した。
申し訳なさそうな笑顔でぺこりと頭を下げるエリを連れ立ち、蘭は準備室を後にする。
二人の後ろ姿を眺めるしかできなかった聖良が吹奏楽部を退部したのは吹奏楽コンクールの県大会が終わり、東北大会の出場権を得られなかった翌日。
不思議がる顧問に退部の理由を聞かれ、告げたのはたったの一文。
「私は彼女の暴走を止められません」
抑揚のない声で告げた後、聖良の頬を一筋の涙が伝う。
――私は、ジャンヌ・ダルクになれない――
◇◇◇
「あーっ、もう超ムズカシイんだけどー。なんで通信制決まったのに勉強するわけー」
図書室で生徒が勉強に励むのは珍しくない光景だが、その人物が珍しい。
二階堂美好(以下、ミヨシ)だった。
好きなことは極めるミヨシだが興味のない事柄は投げ出したい性分で、勉強は興味のない分野に入る。
意地の悪い生徒から魔女と揶揄される容姿はなかなかに鮮烈すぎて、否応なしにも一目見ただけで覚えてしまう。
更に、誰にも忖度をせず我が道を往くアクの強い性格。掟破りな彼女について行けないとミヨシを敬遠する生徒は少なくなかった。
皮肉を言えば倍返しで応戦するほど気が強いが、心根は優しく純朴。害のない者には決して意地悪をしないためか仲間はいる。
うち一人が音澤蘭である。
「あんた卒業まで怠けるつもりだったのけ?」
私立の女子高に内定している鵜沼留美はあきれ顔でテーブルに片手をついてミヨシのもっさりしたボブおかっぱの頭を見下ろす。
「だってー、勉強おもしくねぇべした」
「私だって勉強嫌いだよ? 特に数学と公民はダメ」
でも国語は好き、と付け加えて漢字の書き取りをしているエリは留美と同じ女子高に内定した。
留美は普通科でエリは家政科。
普通科と比べ家政科の偏差値は劣るもののそれなりに人気で(就職難の時代で実業系の学科に注目が集まるご時世だった)毎年のように高い倍率を誇るのでエリにとってプレッシャーだったそうだ。
「本能の赴くままに生きたいところがミヨシらしいよね」
ミヨシが解いた公式を蘭が採点する。その傍らで小柄な少女が無言で戦争漫画を読んでいた。
力丸薫子。
ゴツい苗字に相反した雅やかな名前が様になる、垂れ目がちな麗しい目元と桃色の頬が愛らしい美少女だが、力丸は極端に無口だ。
頭は切れるが表情の変化に乏しいので、顔はかわいいのに何を考えているのか分からないとの理由で彼女も敬遠されている。
「ねえねえ。力丸はさぁ、県立は受けるのかい?」
「んーん」
ミヨシに否定の返事だけを返すと力丸は再び漫画に視線を落とす。
薫子という人から褒められやすい名前を持つにもかかわらず力丸は親友からも苗字で呼ばれた。
理由は単純で苗字のインパクトが勝っているからだ。
「力丸ん家金持ちだもんねえ、建築会社だっけか? いいなー。うち、苗字だけは金持ちくさいけど貧乏なくせに兄弟多いしさぁ。力丸が行くとこ、お嬢様学校だべえ?」
貧乏で兄弟が多い、ミヨシが通信制高校を選択したのはそれに尽きる。バイトをして家計を助けつつ通信制高校に通うという。
当時としてはレアケースで全日制にこだわるあまり眉をひそめる部外者もいたそうだが。
「こん中で一番勉強できる蘭ちゃんだけが決まってないんだもんなあ」
「こん中じゃない、学年トップ」
力丸がささやき声のマシンガントークでさりげなく訂正した。漫画を読みながら。
留美が漫画を読んでいるのは力丸だけだとさりげなく突っ込むも歴史の勉強だと無表情で切り返し、それ以上力丸は何も言わなかった。
「しょうがないよ、県立の入試は15日だし。あと滑り止めなら受かってるよ」
「でも県外の私立だべー。うち、蘭ちゃんが遠くさ行くなんてやだよー。どこだっけか、山形?」
ミヨシの純真な感情が蘭には嬉しい。
「いや、新潟」
「ガタしか合ってねえべ」
唇を突き出した顔でミヨシは留美に反論する。
「どっちにしろ日本海側だべした」
「おーっ。ミヨシが珍しく正解した」
「ほんとだ。正解した」
蘭と留美とエリの音量を抑えた拍手に、力丸薫子のフッと笑う声が混じる。
「えー、何だよぉその言い方ぁ。うちはそこまでバカじゃねえよ……っ!?」
蘭がミヨシの口をふさいでいた。
「ミヨシ、声でかいよ」
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 2
口をふさいだままの蘭は鋭い目付きだ。
その眼差しの先に居るはミヨシではなく別の女生徒。
女生徒は二人いて、端から見ても感じの悪い笑みを浮かべて歩み寄る。
まず、肩の上で揃えた分厚い髪の毛をツーサイドアップに結った吉田が注意とは名ばかりに蘭達を吊るし上げ始める。
「あんた達さぁ、もう卒業なんだから図書室で騒ぐのやめたらぁ?」
正論だが人を小馬鹿にする口調。
敵を作っても当たり前な態度だが、蘭達に対してのみ態度を一向に改めないのは一部の男子からの支持があるからかもしれない。
優れた女に劣等感を抱き、気弱な女にだけ強く当たる、器の小さい男子からの支持。
「そうだよそうだよ。中学生にもなってさぁ」
斎藤が茶化す。大それたことはせず、安全地帯からかわいらしく煽り立てる様は所詮「小物」に過ぎないが、それが却って腹立たしい。
大それたことならば、堂々と警察にでも教育委員会にでも突き出せるのに。
彼女達は何とでも言い逃れのできる、法に触れない程度のやり方で攻めてくる。
「蘭ちゃんも留美ちゃんも勉強できるくせにマナーはなってないなんて恥ずかしくないのぉ?」
吉田が煽り、斎藤は間髪入れずに「エリちゃんはバカだけど」とつぶやく。
斎藤は進学校も余裕で合格できると言わしめるほど成績が良かった。それだけに成績の芳しくない者を見下した発言は癪に障る。
噛みつかんばかりの形相で留美が顔を上げ、ドスのきいた低い声で応戦し出した。
「成績の話なんぞ、今は関係ねえだろうが?」
「あのさ、声出したのはうちだけだよ? 責めるのはうちだけにしてよ」
声量を抑えたミヨシが、あっけらかんとした顔であくまでも自分以外は悪くないと告げた。
ズル賢い吉田と斎藤のことだ。
いつものミヨシお得意の倍返しでは、話を膨らませて「注意したら逆ギレした非常識な連中」と吹聴しかねない。
ミヨシなりに仲間を巻き込まないようにとわきまえての発言だった。
妙に打たれ強いミヨシは吉田からしてみれば「いじめがいのないやつ」なようで、すぐに矛先を変える。
「蘭ちゃんも留美ちゃんエリちゃんも一緒にいるんだからさあ、止めるべきだよねえ」
青い顔のエリはうつむいたまま震え、留美は襲いかかる寸前の肉食獣の如し表情で見据える。
無視されたも同然の力丸だが、小学生の頃、吉田に強烈な頭突きを見舞わせたことがあるからか敢えて見逃されたのかもしれない。
無口な力丸は、敵と見なした者に対してのみ攻撃的になる性分であった。
「え? 蘭ちゃんは声でかいって止めたけど?」
ミヨシの声に混じり、かすかに聞こえた衣擦れの音。衣擦れと共に、かったるい様子で立ち上がるは蘭だった。
仲良しグループと勉強に励んでいた時の和やかな表情とは打って代わり、鬼に憑かれたと疑われても無理のない険のある顔だ。
「人に向かってあーだこーだ言うくせに、うるさいなあ」
静だがよく通る声に、気だるそうな態度。ミヨシの勉強を見ていた留美と同じ姿勢でテーブルに片手をつき、キッと鋭い目で蘭は敵方を睨む。
「中学生にもなって、幼稚園児でもわかる『いじめは絶対にやってはいけない』ってことすら守れないあんた達にだけは、マナーがどうだなんて言われたくないね」
真っ向から睨みつける蘭は、静かながらも迫力があった。
突如響いたのは二、三度手を叩く音。
乾いた音はカウンターから聞こえた。
三年生の男生徒一人と女生徒が二人。他には下級生が三人。
「そこの三年生。静かにしてください」
薄ら笑いで「ほら、うるさいって言われたじゃん」と勝ち誇る吉田だが直後に落胆することとなる。
「違うよ。吉田と斎藤、お前らのことだよ」
先ず、口を開いたのは男子の図書委員だった。
「そうだよ。蘭ちゃん達は注意してたよ」
「いい加減見苦しいよ。口実つけて無理矢理蘭ちゃんとエリちゃんを悪に仕立てるのもうやめたら?」
女子の図書委員も加勢する。
その様子に目を見張る蘭。後ろで留美も力丸も驚愕の表情で図書委員達を見ている。
「女子庇うとお前らみたいなやつが下衆の勘繰りして冷やかすから今までできなかったけど、ハッキリ言わせてもらうよ。嫌がらせをやめろ」
「スーさんに同意。嫌がらせはもうやめなよ」
「容認されてると勘違いしてるようだけど、三年のみんなはあんた達が怖くて口出しできないだけだから」
ガタリと椅子が動いて、蘭が立ち上がった。
そして、一歩、二歩と蘭は敵方に詰め寄る。
抑揚のない、しかしながらはっきりと聞き取れる声で蘭の唇は友達を傷つけられたがゆえの恨み言を繰り出す。
「あと、エリちゃんに謝ってよ。エリちゃんが強く出ないからってやりすぎなんだよ。
あんた達をこれ以上恨みたくないから敢えて強く出ないエリちゃんの気持ちを無駄にするな。
モラルのない連中にエリちゃんみたいな優しい子がバカ呼ばわりされる筋合いはない」
想定外の反撃に女生徒は嘲笑いの表情を顔面に張り付けながらもそそくさと立ち去る。
嘲笑う顔は、図書委員達に言い負かされた惨めさを隠すための意地だろう。
潔くなさすぎて見苦しい。舌打ちしたい蘭だが、行儀が悪いと我が身に言い聞かせてどうにか堪えた。
「今までごめんね。止めに入るべきなんだけど、みーちゃん達強いから……」
「いつも思ってたけど、ミサっちゃん達って蘭ちゃんやエリちゃん達に対してやりすぎだと思うんだよね」
「正直、あいつらのやり方は男子から見ても引くんだよなぁ……一部のぶりっ子に弱いヤローは騙されてっけど」
いずれも真面目そうな生徒達だった。土地柄もあり、この学校は基本的に荒れた生徒は少ない方だ。
大概の生徒は制服を着崩さず髪も染めず真面目そのものの風貌をしているが、当然ながら各々が纏う雰囲気には差異がある。
吉田も斎藤もパッと見は荒れた感じの見受けられない、ごく普通の女子中学生だ。
流行りのアイドルの話題に敏感でミーハーを気取る吉田は野暮ったさの残る田舎娘であったし、斎藤に至っては裕福な家庭で育ったからか箱入り娘じみたお嬢様らしい雰囲気を漂わせた。
見た目は普通の女子中学生だからこそ、ある意味『目に見えて不良とわかりやすい生徒よりもタチの悪い生徒』だった。
しかしながら、吉田と斎藤に共通する拭いきれない軽薄さや陰険さはどう足掻いても隠しきれず「普通っぽいのに、どこか生意気で意地悪そう」と違和感を抱く者が少なからず存在するのも事実。
違和感に気付く者は、大概は彼女達と接点のない上級生と保護者だった。
ワガママな態度で友人達を振り回すと陰で嫌われている斎藤はともかく、吉田に至っては
「楽器が上手いから」
「部活に対して一生懸命に取り組むから」
「リーダーシップがある」
と、吹奏楽部の上級生からの評判は良かった。
確かに部活動をサボりはしなかったし、喫煙や夜遊びをするなど素行が荒れているわけではない。
いじめ行為をする以外は。
一方で、吹奏楽部以外の上級生からは
「話し方が軽薄」
「お気に入り先輩には礼儀正しいけど、自分より下に見ている先輩への態度が生意気」
「雰囲気が意地悪そう」
「陰で悪どいことをしていそう」
という理由で嫌われた。
一年生の頃には吉田を疎ましく思う二年生数人に呼び出され、生意気だの調子に乗るなだのと因縁をつけられたこともあった。
吹奏楽部のある保護者は彼女の立ち振舞いの下品さに驚愕し(大会会場での昼食時に、がに股で椅子に座り大声で下ネタを話しながら飲食していた)、部活動紹介の挨拶の仕方や部を私物化する振る舞いに「知性と品性に欠ける」と落胆する保護者が続出した。
中学三年生の今では保護者から吉田へ対する評判はイマイチ良くないものへと成り果てた。
さて、エリは消え入りそうな小さな声で「ありがとう」と礼を述べた。女子の図書委員のうち一人が涙ぐむエリの肩に手を置いて気づかう。
「……スーさん、どういう風の吹き回しなの?」
先ほどまで座っていた椅子に再び腰かけた蘭が疑問を呈する。
頬杖をついた留美もまた潜めた声で続けた。
「まさか図書委員会が加勢するなんて夢にも思わねかった……」
スーさんと呼ばれた男生徒が、申し訳なさそうな顔で語る。
「俺よぉ、小学校ん時のこと知っていながらあいつらに強く出られなかったの後悔してたんだ」
「あいつら、気に入らないとすぐに変な噂立てて孤立させっから、私らも怖かったんだよ。でも生ぬるい態度があいつらを増長させてるって分かったから……」
処世術。
賢い生き方。
俺達、私達は強くないから。
それらの便利な言葉を言い訳に、周りは一切戦おうとしない。
むしろ、戦う者達をバカだと、余計な真似をしていると陰口を叩く者すらいた。
エリの肩を支える女生徒が憤る。
「何も言われない、イコール、自分が正しいから容認されてると勘違いしているんだからよ。あいつらは」
「俺、音澤と鵜沼とミヨシみてえに度胸ねえけど……」
男生徒が口ごもる。度胸のなさを悔いている表情だ。それは女生徒達も同様であった。
「このままじゃダメだって思っていたんだ」
「私も、強くないから……蘭ちゃんがその手の言葉が嫌いなのは承知してるよ」
両手を膝に置いて、蘭は真っ直ぐ図書委員達に向き合う。
「私はもちろんあいつらが嫌い。一時期は信じたい人すら信じられなくなりかけた恨みすらある。状況を変えたいのに一向に戦おうとしない意気地無しな人達にも、嘘だと見抜いておいて尻馬に乗って攻撃する連中にも失望してた。だから、学校では限られた友達としか繋がりたくなかった」
でも、と蘭は繋げた。
「限られた友達以外にも気づかってくれる人がいると分かって嬉しかった。ありがとう」
膝に手を置いて、蘭はぺこりと頭を下げる。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 3
◇再会と本心◇
市立泉清中学校は吹奏楽部の強豪校として東北地方内に名を馳せていた。
1990年代の初頭から毎年のように東北大会への切符を獲得し、蘭の兄である音澤秀が部長を務め上げた代には全日本吹奏楽コンクール出場の一歩手前にまでこぎつけている。
合唱。オーケストラ。吹奏楽。
音楽の盛んな県なだけに吹奏楽コンクールの参加団体が多い福島県では、吹奏楽コンクール東北大会への出場は名誉といっても過言ではない環境にある。
兄から聞いていた夢の大舞台に憧れて吹奏楽部への入部を希望した蘭。
部活動見学の初日に音楽室へ出向くと、先に来ていた女生徒に表情が強張る。
6年生の途中で転校したはずの吉田。
松川をはさんだ隣の校区か、更に離れた校区に引っ越したはずだ。
異なる中学校に通うはずだった。
なぜ、この中学にいるの?
耳に覚えのある、聞きたくもない名前を入学式の点呼で聞いた際には「よくある名前だから同姓同名の別人だろう」と頑なに思い込むよう努めたが、無駄足だと知り愕然とした。
吉田から涙ながらに謝罪されたのは、再会したその日の放課後のこと。
「転校先の小学校でみんなに無視されて、やっといじめられる側の辛さが分かったんだ」
無視をされた理由は言わなかった。
ただ、痛みを知って蘭が受けた苦痛を省みて、謝らずにはいられなかったと語る。
目の周りを赤くしながら、吉田は謝罪の言葉と小学生時代の嫌がらせに走った理由を述べた。
「本当は、美人で何でもできる蘭ちゃんに憧れてた」
目の前の涙に、蘭を蝕んできた恨み辛みが流される。
「もう、いいよ。昔のことだから」
目の周りのみならず鼻まで真っ赤にして吉田は何度も「ありがとう」と繰り返す。
蘭は「みーちゃん」の流す涙を信じたかった。
◇ミーティング◇
1999年も泉清中学校吹奏楽部は東北大会出場を果たす。
吹奏楽部員。
それだけで学校内では花形の扱いだ。
無礼な振る舞いは我が身へ返ってくる。
傲るな。
天狗になれば、いずれ鼻っ柱をへし折られる。
いずれも人付き合いを築く上で母から教育されてきたこと。
母の教育は功を奏したのか蘭は傲る様子はない。
日々、吹奏楽部の活動とソロコンテストと掛け持ちで練習に励む。
そんな姿勢をかっこいいと尊敬する同級生が出てきた。
うち一人が斎藤聖良だ。
眼鏡はかけておらず、セミロングヘアを二つに結わえていた。
小学校時代の6年間と、中学一年生の時点で聖良は蘭と同じクラスになったことが一度もない。
小学生時代の聖良の中では
「きれいだけど、なんとなく近寄りがたい雲上人」
という位置付けの蘭だったが、吹奏楽部で共に練習に励むうちに「友達になりたい」と願うまでになる。
東北大会が終わってまだ日が経たない頃に吹奏楽部ではミーティングが行われることになった。
10月の文化祭で披露する楽曲を選ぶのだ。
音楽室に入った聖良は、音楽室の片隅で蘭とエリが話し込んでいるところに出くわす。
楽しそうに談笑する二人に聖良は「何話してるの?」と声をかけ、談笑に混ざることにした。
「文化祭でやる曲、何がいいかなって話してたの。セイラさんはどんな曲やりたい?」
にこやかな表情の蘭は口調も明るい。
この頃になると蘭は同級生の前ならば溌剌とした無邪気な姿を見せるようになる。
「クラシック好きだけど、A・リードとかヴァン・デル・ローストとかのいかにもな吹奏楽曲やりたいよね」
蘭と聖良の口からはいくつかの吹奏楽曲と作曲家の名が飛び交う。
吹奏楽を始めて半年も経たないエリは蘭や聖良と比べて専門的な知識は乏しいが、吹奏楽曲そのものは好きなようで目を輝かせながら聞いていた。
「文化祭だし、幅広い年代の人達が来るからねぇ」
エリの話すおっとりした口調。のんびりした性質が垣間見える。同じ口調でエリは更に続けた。
「だいたい3~4曲ぐらい演奏するべよ? 偏ったりしないようにポップスとクラシックと、吹奏楽曲は欠かせないかな~って、さっき蘭ちゃんと話していたんだ」
「私としては古関裕而の楽曲もやりたい。福島の作曲家だし『栄冠は君に輝く』は盛り上がると思わない?」
「いいなぁ、それ」
会話の内容を耳に挟んだ部員が次々と集まる。
数名の上級生も混ざり込み、ミーティングが始まるまで何を演奏したいかを語り合った。
◇◇◇
ミーティングが始まる。
顧問は職員会議で遅れて参加すると部員達は予め聞いていた。
吹奏楽部のみならず、どの部活動でも顧問が職員会議で遅れてしまうことはしょっちゅうで、見方を変えれば部員の自主性に任せているともいえる。
蘭は臆せず意見を述べる。
「幅広い年代が集まる文化祭なので、ジャンルに偏りがない方が望ましいと思います」
と、堅苦しい態度にポーカーフェイスで発言した。
元は友達(エリ)の意見であると前置きをすることも忘れずに。
「えーと……音澤さんとしては、例えば、どんな風にしたらいいと思うのかなぁ?」
代替わりしたばかりの二年生の部長は緊張を隠せない引きつった微笑みで蘭に問いかける。
蘭と同じく清水が丘小学校を卒業した部長。
小学生時代は互いの顔と名前だけを知っている関係であったが、部長は蘭が礼儀正しいを通り越した堅苦しい生徒だとは思いもよらなかったであろう。
一年生の女子は名前に「ちゃん」付けかあだ名で呼ぶ上級生達だが、蘭だけを「音澤さん」と呼ぶのも蘭の堅苦しさに起因する近寄り難さが原因でしかない。
「あ、あの、一年生だからって遠慮しなくていいからね? 大事なミーティングだし、先輩後輩関係なく意見を交換するのは当たり前なんだからね。遠慮なく話して?」
やはり引きつった微笑みのまま部長は遠慮なく話してくれと促した。
満場一致で部長に選ばれただけあり、普段は冷静な才女と呼ぶべき立ち振舞いと公正な判断で部員から信頼を集める部長。
そんな彼女が緊張するほど、蘭はとっつきにくい後輩であった。
部長の「遠慮なく」を額面どおり受け止めて、堅苦しい態度を維持したまま蘭は意見を続けた。
「流行りのJ-POPは生徒や若い世代のお客様からの受けが良いです。昔の歌謡曲や洋楽やクラシックも好きな人が聞けば嬉しいものですが、いずれも同じジャンルばかりに偏ったら興味のない人からは退屈なだけですので……」
観客に寄り添う意見に部長は感心する一方で、蘭に対して「この子、本当に中一?」と不思議に思わざるを得ない。
「……全員がやってみたい曲を一通り書き出して、ジャンルごとに一曲から二曲選ぶやり方が無難ではないでしょうか」
「貴重な意見ありがとう。……曲を決める上でお客さんが退屈しないかを意識するのは大事だもんね。
まあ、音澤さんが真っ先に発言したことで一年生も意見しやすくなったかなぁ。
というわけで一年生も二年生も文化祭でやりたい曲、ジャンジャン言っちゃっていいから」
顧問が音楽室に入ってきた頃には
「ポップスから二曲、クラシックと吹奏楽曲から三曲演奏する」
という結果が出た。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 4
◇余計な言葉◇
「蘭ちゃんのおかげで私らも意見出しやすくなってよかったよ」
「だから。部長や同じ楽器の先輩はフレンドリーにしてくれるからいいんだけど、荒川先輩みたいな怖い先輩もいるから緊張して言いにくかったんだよねえ」
荒川という上級生は話してみるとジョークは言うし声を立てて笑うし、愛犬が如何にかわいいかを力説して自慢をするなど至って庶民的で決して悪い人ではなさそうだが、話したことのない後輩には怖い先輩に映るのも無理はないだろう。
部長と、意識が高く活発な先輩達とはソリが合わないのか荒川はいつも部員達が集まったところから離れた場所で三~四人ほど固まっているのだが、その姿は親しみやすい先輩とはいえない。
仲間内での口調も突き放すように冷たいのを何度か聞いている。
後輩の視点で見れば御指南願いたいと思えないし、何を考えているのかわからないので関わりたいとも思えなかった。
二年生の中では小柄だが、眼光の鋭いキツネ目と冷淡そうな顔立ちには威圧感がある。
スカートは膝下であるし肩で揃えた髪も染めていないのに、荒川の醸し出す雰囲気は凄みがありどこかスケバンじみていた。
「ちょっと冷たいように見えるけど、荒川先輩って意外と面白い人だよ? 犬好きでゴールデンレトリバー飼っているんだって」
「……たまにコープの周りさ犬連れて歩いてるね」
「蘭ちゃん、あの先輩と喋ったことあるんだ」
「うん。又小の学区で偶然会ってね。親戚がそっちさ住んでっから」
荒川と話した日に、慧子の自宅に遊びに行っていたのは臥せておいた。
ネームバリューのある者に弱い生徒はどの組織にも必ず存在し「女子のみんなが憧れる生徒会長の慧ちゃん先輩」が蘭の又従姉妹だとわかった途端にすり寄る生徒が少なからずは現れた。
蘭は「慧ちゃんに近づきたいがために利用されているようで気分が悪い」と内心うんざりしたものだった。
ゆえに、蘭は親友以外の生徒の前では、極力は慧子の名前を出さないことにしている。
「先輩、うちの犬かわいいだろーって笑いながら自慢してたな。犬も先輩のこと好きみたいだし」
「あのおっかない荒川先輩がねぇ、なんか意外……」
「蘭ちゃんって、堅苦しい割には先輩達と仲良くない?」
「だから。慧ちゃん先輩とか合唱部の清子先輩とか……」
「いや、そんなことないよ。仲良いといっても三~四人ぐらいだし、部活じゃ私だけ苗字呼びだよ」
だよねぇ、と若干しわがれた低い声がした。吉田だった。
わざと低い声を出したわけではなく、吉田は地声が低いのだ。
あまり綺麗とはいえない声がコンプレックスだと入学当初に蘭は聞いている。
アルトはアルトでも織絵みたいな色気のあるハスキーボイスでもなければ、蘭のように芯の通った声でもない、汚いダミ声だと意気消沈した顔でこぼしていたものだ。
普段は我先にと口を出す吉田は、この時は珍しく聞き役に回っており、ようやく口を開いたと思えば
「二年の先輩達とこの前話したんだけど、蘭ちゃんはとっつきにくくて可愛げがないってみんな言ってたよ」
と、しれっとした顔で言った。
入部当初はそれなりに馴れ合っていた吉田。
各大会を勝ち抜く毎に共に涙を流した仲間。
過去を忘れたはずなのに。
涙と共に水に流したはずなのに。
東北大会が終わり、一年生の副部長に就任した頃から吉田はアドバイスを装いつつ心に引っ掛かる言葉を蘭に投げ掛けるようになった。
誰々が、何々と言ってたよ。
褒め言葉ならば嬉しいが、ダメ出しが含まれると一気に気分が悪くなる。
しかも吉田はしれっとした顔で余計な一言まで添えてくるのを忘れない。
喉に刺さった魚の骨がなかなか取れないかのように、余計な一言は胸の中に突き刺さったまま残る。
場の空気が凍りつくのを、吉田以外の誰もが察した。
「みーちゃん、可愛げがないってのは言いすぎだよ……」
聖良が困り顔で、ありったけの勇気で抗議するも蘭はモヤモヤが抜けない。
忘れ物をしたと出任せを述べて蘭は一年生の集団から抜け出し、付き添うからとエリが同行した。
吉田は得意げな顔かといえば、そうでもない。
悔しそうな顔でもなければ笑ってもいない。
何食わぬ顔。
虚言癖まではいかないが、吉田は周りの注目を浴びたいがために「少しばかり」話を盛る傾向があったこと、注目を浴びるためならば他人を悪者・笑い者にしてまで話を盛ることを清水が丘小学校出身の一年生は皆知っている。
その悪い癖が元凶となり、転校先でクラスメート達に遠巻きにされたことを泉清中学校の生徒達が知るのはもう少し先になる。
◇荒川先輩◇
「たぶん、みーちゃんが最近トゲのあることばかり言うようになったのも副部長の件があるんだと思う」
ずいぶん長く歩くなぁとエリが蘭の後をついて行くと、蘭の足は中学校近くの神社へと入っていった。
ふうっ、と深くため息をつく親友の背に、エリはそっと手を添える。
「一騎討ちだったもんね……」
副部長は二年生と一年生から各一名ずつ選ばれる。
一年生が副部長になる、それは将来の部長を約束されたも同然。
退部したり問題行動を起こして副部長を退くことさえなければ、自動的に部長になれる仕組みだ。
蘭を副部長に推したのは、荒川だった。
「フルートが上手いのはもちろんだけど、クールな分だけ客観的に物事を見られるから」
普段の冷淡な口調とは裏腹な、熱烈さを含んだキッパリとした口調で荒川はぜひ音澤蘭を副部長にと推薦したのである。
ミーティングで荒川が発言するのは稀なこと。
だいたいは、気だるげな顔と投げやりな態度でミーティングに参加するだけだ。
頬杖をつく荒川の顔には
「どうせ私の意見など採ってもらえない」
と書いてあることが常であったのだ。
顧問が驚き、それまでのミーティング中の荒川を知る上級生達もざわついた。
荒川の取り巻きのみならず、複数の二年生と一年生、引退する三年生の半数が荒川についた。
荒川に従い蘭を推薦した部員の中には、元々は吉田を推していたが荒川の発言に納得し寝返った者と、小学生時代の噂を知って吉田を良く思わなくなった者も含まれていたのだった。
「それだから、吉田に船頭を握らせたくなかったのに」
いつの間にか荒川とその取り巻きが蘭達の背後にいた。相変わらずの険のある顔だ。
「聞いていたんですか!?」
エリが驚いて問いかける。
「聞こえてっぺした。近くにいたんだから。そんなに私ら影が薄いのかい?」
眼光鋭く荒川が凄んでくるので、怖がりなエリは身を縮めながらも「そんなわけありません!」と荒川の目を見据えた。
蘭はミーティング時と同じように堅苦しい態度に出る。
「申し訳ありません。話に夢中で気付けませんでした。先輩も、私を気づかってというよりは好奇心で後をつけてきたのではありませんか?」
薄ら笑いで「はっ」と言って嘲る荒川に蘭もエリもガッカリする。
「よく分かってんじゃん。さすが学年トップ」
ペットには愛情深い荒川だが人間相手には薄情であるゆえに、いささか悪趣味な行動に走るのも重々承知だ。
「だいたい人の根性が数年で根っこから変わるわけないだろーが。私は又小で吹奏楽やってたけど、その頃からあいつが気に食わなかった。コンクールや演奏会でたまに会うだけだったけど、悪い意味で印象強かったわ」
腕組みをする荒川の後ろには取り巻きの先輩方が棒立ちでいる。
取り巻きの先輩方は全ておとなしいタイプで揃っていた。
荒川とは異なり尖った雰囲気はなく、むしろ温厚であるが気弱そうでもあった。
好きで荒川と一緒にいるよりは、吹奏楽部のメンバーに馴染めない者がくっつき合った結果であろう。
そして「なんか調子に乗っている吉田がいけ好かない」という利害が一致していることが見て取れる。
取り巻きのうち、荒川と同じく南沢又小学校の吹奏楽部員だった先輩がいつになくハキハキとした口調で語り出す。
「ハルちゃんだっけか? 久間木春奈って知ってるよね? あの子も又小の吹奏楽部員だったんだけどさ、大会や演奏会で会う度に吉田から髪型をビンボーパーマだのバブル期だの言われてしつこくからかわれてさあ」
ああ、と蘭もエリも頷いた。
剣道部の春奈は骨格のがっしりとした大柄な体型がいかにも強そうで、ソバージュ風の癖毛のおかげですぐに覚えられた。
強そうな彼女もからかわれていたのかと二人は意外に思う。
荒川は細いキツネ目で取り巻きを一瞥し、腕組みのまま再び口を開く。
荒川が纏う底意地悪そうな雰囲気は健在であるが、薄い唇が繰り出す落ち着いた声色は知的そのものであることを蘭とエリは初めて知った。
「今だって舞ちゃん(部長)に気に入られてるからーって調子こいてっぺした。あいつが部長にでもなってみろ? 天狗になって吹奏楽部さ私物化するの目に見えっから。意地でも部長にはさせてやんねーよ」
「みーちゃん……吉田さんに部長になってほしくないから、私を推薦したのですか?」
まあ半分はね、と薄ら笑いで告げる荒川は更に続ける。
「それもあるけど、さっきのミーティングさ見ても音澤さんって中一のくせに幅広い視点で物を見られるっていうの? 人に媚びたりしねーし頭良い分達観してるし、そういうところ買ってたんだよ」
「みんなさあ、吉田がクラリネット上手いからって推薦してっけどさ、上手いだけが部長になる判断基準なら小学校から楽器やってたやつが全員部長になれるっつーのな」
普段はおとなしい取り巻きの先輩方は、憂さ晴らしも含めて腹の内を語れたからか、やけに活気に満ちている。
ところで、と切り出すは荒川だ。
「前から疑問だったけど、音澤さんってなんでいっつも堅苦しいわけ?」
問いかけられた蘭は、少しの間だけ黙り込む。
「小学生の時、先生に目を付けられました」
「あー、もしかして又小で慧ちゃん先輩イビってふっ飛ばされたって噂の女教師?」
蘭の顔が忌々しげに強張った。
眉をアンバランスにしかめ、僅かに開いた唇の端から喰い縛った歯が覗く。
入学式で吉田の名前を聞いた時と同じ表情。
さすがに話してはいけないことを言ってしまったかと荒川達は申し訳なさそうな顔を作った。
深いため息の後に蘭は語り出すことにした。
「そうですね。私は先生に生意気な態度を取ったわけではありません。先生はクラス中に出回った私のありもしない悪い噂、私が人を見下しているだの悪口を言っていたという噂を鵜呑みにして、厄介者扱いをしてきました」
「だってあんた、あの先生が嫌いそうな容姿してんじゃん。先生は噂を都合よく利用したってわけだ」
あーあ嫌だねぇ、大人はきったないねぇと荒川は忌々しそうに吐き捨てる。
正義感ではなく、大人は汚いと思いたい年頃ゆえの反発心による発言だ。
「あの先生ねえ、背ぇ高くて大人っぽい女子が嫌いなんだって。あんたみたいな美人だと尚更。コンプレックス刺激されるとかでね」
蘭の記憶では、因縁の女教師はごく普通の成人女性の印象だった。
痩せてもいなければ太ってもいない。
顔の造作は月並みであろう。
「どうせ美人の元クラスメートに好きな男子取られた恨みでもあるんだべ」
「慧ちゃん先輩もそうだったもんね。美人だし帰国子女で目立ってたし」
「でも、慧ちゃん先輩ってその頃からすげえ気ぃ強かったからすぐに返り討ちさ」
「んだから! 平気であの先生に口答えして楯突いてたし、見かねた他の先生が教育委員会に通告してふっ飛ばされてさぁ」
思い出したくない苦い記憶。
あの女教師は、二度も問題を起こした以上教壇に立つことはないだろう。後ろ楯もない若手の教師ならば、あり得なくもない。
「もう、誰にも文句を言わせたくないんです。だから目上の方々から一切の文句を言わせないよう振る舞っているんですよ、私は」
荒川と、取り巻きの先輩方を見据えるは、硬質な、頑とした光を宿す黒い瞳。
蘭の背に隠れて、エリは静観するほかない。
眼光鋭い蘭の眼差しに圧倒されて黙り込んだ荒川だが、突如ギャハハハと声を上げて笑い出した。
「あんた気に入ったわ! 何、その据わった根性? そんな中一見たことねーよ!」
荒川の声色は知的ですらある。
しかし笑い方は下品で柄が悪すぎた。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 5
◇林とエリ◇
吹奏楽部の一年生は女子が十数人に対して男子は一人だけ。
一年生の男子部員の名は林といった。
林はクラスに若干名は存在する「冬になると必ずインフルエンザにかかる生徒」の代表格だ。
鼻が弱い体質なのか、彼はよく鼻風邪をひくし花粉症にもかかりやすい。
色白で線が細く、体つきも細く、そのひ弱そうな容姿から「モヤシ」といじられる林だが、気品のある目鼻立ちをしているので会う人会う人に「育ちの良いお坊っちゃん」という印象を植え付けた。
態度と言葉遣いを除いて。
「林、ティッシュなくなったの?」
「あぁ?」
衣替えが済んだ10月初旬だった。
ユーフォニアムを床に置いて、鼻をこすりながら無愛想に返事をする林は悪態をついているように見えるが、鼻が赤い不恰好な姿を大槻エリに見られたがゆえの恥ずかしさを誤魔化しているだけであった。
鼻炎持ちにとって季節の変わり目は厄介で、この日も林は慢性鼻炎に振り回されていた。
エリは制服から取り出したポケットティッシュを差し出す。
中一の頃の、エリの体型はスマートだった。濃紺のセーラー服は、肩と袖に充分すぎるほどにゆとりがある。
「はい。私は予備のやつあるから使っていいよ~」
相変わらず間延びした口調のエリは頬が赤い。
林の手に渡ったポケットティッシュをよく見れば、鼻が痛くなりにくい柔らかい素材のティッシュだった。
隠された優しさに気づいたのか、椅子に座ったままの林は手を後ろに組んで動向をうかがうエリの照れた顔を見上げる。
「私もよく鼻風邪やらかすんだよねえ。だから柔らかいの欠かせないんだ」
エリは中肉中背で、髪型はよくある二つ結びの、どこにでもいる普通の女の子。
同級生には林の苦手とする勝ち気な性分の女子が多い中で、温厚で人当たりの優しいエリを吹奏楽部で共に過ごすうちに意識するようになる。
頼りなさそうな垂れ目と下がり眉は、日に日に好ましく映ってゆく。
平凡なはずのエリがはにかんでいる姿を、林は特別にかわいいと認めてしまった。
鼻のみならず顔中を真っ赤に染め上げ、ティッシュを引っ張り出して勢いよく鼻をかんだ。
「ありがと。今度返す」
クスクスと笑うエリを横目で見て、林は鼻をかみながら礼を言う。
「いいよ~。それ、あげる」
所作が絵に描いたかのように女の子女の子しているのは、内向きの動作だからだろうか。
口元に片手を添えて笑う仕草。
内股気味の足。
色に例えるならば、淡いピンク。季節に例えるならば春といったところか?
エリの所作と澄んだ声。
穏やかな人柄ゆえに、和む、癒されると好意的な生徒がいる一方で、声と仕草がぶりっ子みたいだ、美人でもないのにかわいこぶるなと辛辣な態度に出る生徒が存在するが、同じく「女の子らしい女の子の代表」とも呼ぶべき斎藤聖良が何も言われないのは理不尽だと林自身も疑問に思う。
何よりも、林はエリのかわいらしい声と仕草が愛おしくなっていた。
第一、男性的な仕草などエリには似合わない。
「林、慢性鼻炎ならいっぺん病院行ったら?」
「うるさいな。俺、病院嫌いなんだよ」
ぶっきらぼうだが、まんざらでもない様子の林。
エリに対して優しい時もあればぶっきらぼうな時もある林は、この時は照れ隠しで後者の態度に出た。
そんな林に対して、蘭は誰かと比較するように「終始愛嬌のある男子もいるのに、林は態度が悪すぎる時があるよね」と言っては良い顔をしなかったが。
「しかも最近疲れやすいんだよ」
「ストレスじゃない? 中学に入った途端にほとんど毎日がハードスケジュールだし……、私も疲れやすいからわかるなぁ」
「お前、どんくさいもんな」
茶化されたエリはムッとした顔を作る。
林には「どんくさいなりに頑張っている」など、僅かながら残っている良いところを認めて欲しいのに。
「うーん、林に言われて悔しいけど、否定はできないなぁ。成績も、楽器も頑張ってるつもりでも追い付かないんだよね……。もっと別な印象持たれたいけど無理だし……」
楽器の件では林も他人事に思えない。
林自身、ユーフォニアムが下手だと陰口を叩かれたことがあった。
同級生ならばこれまでにも吉田を筆頭とした口の悪い部員達に下手だの何だのと直接言われていたので今更気にはならないが、陰口を叩いたのはよりによって引退した三年生だったのだ。
吹奏楽コンクールで演奏する楽曲が決まった頃。
音楽準備室で「林は下手なのに無断欠席ばかりしている」と当時の部長を含む複数の三年生が不機嫌そうに話し込んでいるのを聞いてしまった。
「林さあ、今日も来ないの?」
「下手なんだから練習に参加しろってのなぁ。課題曲と自由曲決まったのに」
「だから。下手なのは仕方ないにしてもしょっちゅう無断で休むし。本当にヤル気あるの、あいつ?」
「仮入部の時も入るか入らないか先延ばしにしてたしね」
確かに、入部したての頃に高い頻度で吹奏楽部を欠席したことがあった。
欠席の理由は予防接種と体調不良。
マイペースに過ごしていた小学校生活から一転し、勉強中心の中学生活に身体がついていけなくなったのだろう。
サボったつもりはない。
欠席する時は前もって顧問には伝えていた。
しかし、当時の部長をはじめとした上級生達には、年長者特有の威圧感に怖じ気づくあまり顔を合わせたシチュエーションで欠席したいと言い出せなかったのである。
三年生の女子部員は揃いも揃ってキリリとした賢そうな面差しで、いかにも出来る女らしい雰囲気が近寄り難い。
二年生も然りで、荒川率いるグループに至っては正直なところ関わりを持ちたくない。
一年生の部員とも表向きは馴れ合いつつも、気の強い女子達への苦手意識があるので言い出しにくい。
いずれにしても、休みすぎだと厳しく責められるに決まっている。
仮入部の時点で吹奏楽部か他の部活動かを決めかねてゴールデンウィーク前まで先延ばしにしていたことも余計に話しかけにくい原因となっていた。
自身の優柔不断さと、上級生と女子達から逃げていたせいで伝達が上手くいかなかったのだから、悪く言われても仕方ない。
その時に、林を庇った部員がエリであった。
小学生の時分から林は体調を崩しやすく欠席がちであったことを話した上で擁護に入る。
「きっと、休みたいと言い出しにくい理由があるんだと思います。でも、林なりに頑張っているんです。たぶん身体がついていけなかっただけで、ヤル気がないわけではないんです」
オドオドとしながらも震える両手を固く握り締め、強張った表情で必死に訴えるエリに拍子抜けした三年生達。
音楽準備室の出来事以降、三年生からはそれ以上のことを何も言われなかった。
思えば、この一件から林はエリを意識し始めた。
「何だよ、例えば?」
「私、蘭ちゃんとか慧ちゃん先輩みたいになりたかったなぁ。美人で頭も良くて、言いたいことをハッキリ言えて何でもできて、目が切れ長で鼻が高くて……」
瞳を煌めかせるエリとは対照的に、林は思いっきり顔をしかめる。
「はあ? 俺、ああいう女子嫌い。音澤のやつ小学校ん時から苦手なんだよ。みんな音澤とか慧ちゃん先輩を美人だと言うけど、俺、あの手の顔の女っていかにも高飛車そうで好きじゃねえんだよなあ」
吹奏楽部で行動を共にするにつれ、互いを知ってゆく。
林が、女傑タイプの女を「気後れするから」と好まないことも。
そうとは存じ上げていても親友と尊敬する先輩を悪く言われたエリの気分は良くない。
いつものゆったりした口調からは想像のつかない早口で林への反論を始めることにした。
「何言っちゃってんの? 蘭ちゃんも慧ちゃん先輩も全然タカビーじゃないし。林なんか清水が丘さ転校してきてたったの二~三年しか一緒にいねかったべした。蘭ちゃんかっこいいじゃん。クールに見えるけど人のいいところ見つけんの得意だし、教え方上手いし、優しいんだよ?」
のんびりした土地柄ゆえに学校の外に出れば自分と似たタイプが周りにいるからか、エリは自分を卑下するほど自信がないわけではなかったが、自分にはない利発さや勇ましさ、凛とした美しい顔を持つ蘭に憧れる。
「はいはい。お前が友達思いなのはわかりました」
投げやりな応対の裏には「気負わない、ありのままのエリが好きなのに」という気持ちが隠れているが、彼女に伝わるには言葉が足りなすぎた。
◇ジャンヌ・ダルクの助け船◇
帰り道でエリは一年生の部員達から冷やかされることとなる。
真っ先にからかい始めたのは、吉田だった。
「エリちゃんってさぁ、林のこと好きなわけ?」
顔を真っ赤に染めて戸惑いながら否定する姿から、エリが恋をしていることは丸分かりだ。
別の女子部員が、吉田とは対照的な冷静な口調で「休憩時間に仲良く話してたべ?」と指摘するのでエリは狼狽えた。
「あれは林が鼻風邪ひいてて、ティッシュ使いきったようだったから……!」
「えー、なんでそんなことまで知ってんのぉ? 監視してたりとかしてたのぉ?」
吉田の笑顔は見る者を不快にさせる笑顔だ。
蔑むように目の開き加減が左右で異なり、嘲笑うようにアヒル口がアンバランスに偏る。
同じように歪んだ笑顔で斎藤が「流行りのストーキングとかぁ?」と、たたみかける。
好奇心にかられて聞いただけかもしれないが、吉田の意地悪い物言いと薄ら笑いは見聞きしていて気分が良いものではない。
少し後ろに離れた場所には、他の部活に所属する男子と話ながら歩いている林がいる。
余計なこと言わないでよ……。
ひそめた下がり眉に焦りが感じられた。
「鼻すすって制服のポケット探ってたら……誰だって風邪とわかるじゃん」
消え入りそうな反論には苛立ちが含まれる。
それでも、吉田を筆頭とした複数人の女子部員は冷やかしを止めない。
吹奏楽部は学業が優秀な者と、前者には及ばないながらも中堅進学校ならば余裕で行けるであろう成績を誇る者が全体を占めているが、それだけに他人を見下す部員が複数存在した。
上位大会への出場という実績が、彼らを「天狗」にさせていたのだ。
そんな天狗達を内心疎んでいる部員達の間にも、穏やかではない空気が広がる。
モヤモヤとまとわりつく不快な空気を「天狗達を内心疎んでいる部員」の一人である斎藤聖良は敏感に感じ取る。
止めなきゃ……。
心根の優しい聖良は嫌がるエリを執拗にからかい不快な空気を作り上げた者達が許せない。
背負っている鞄の肩紐を握り締め、顔を上げてキッと前を見据えた。
「やめなよ」
静かだが、凛と冴え渡る声に沈黙が生まれる。
空気が、真冬の夜の冷気のようにピンと張り詰める。
聖良は声のした方を振り向いた。
後方にいる、背の高い美しい女の子。
「エリちゃん嫌がってるじゃん。やりすぎだよ」
音澤蘭の声だ。
不快そうにしかめた眉。
「金管は分奏で同じ教室で練習してたし、エリちゃんは具合悪い人を放っておけなかっただけ。そうだよね?」
最後の一言に含まれた優しさ。
自身なで肩に手が置かれたのを合図にエリが横を見上げれば、凛とした横顔がある。聖良からは蘭の伏した目尻が流麗な曲線を描いて切れ上がっている様が見えた。
エリの内に隠した怒りの感情が鎮まってゆく。
反して、聖良は不思議な高揚感にとらわれる。
「じゃあ、そう言えばよかったのにぃ」
斎藤がぶりっ子じみた口調で駄々をこねるように抗議したので蘭は再び前を向いて「言ったよ」と言い切る。
「林が鼻風邪ひいててティッシュなくなったって、エリちゃんは始めに言ってたよね。でも、あんた達は敢えて知らんぷりしてしつこくからかってきた」
毅然とした態度で、ズバッと切り込む蘭の強さにエリは憧れた。
これでも、エリなりに意見はした方なのだ。
エリの両親、特に母親は「人との和」を重視する一方で「和を乱す」ことを恐れ、反発する術をエリに教えることはなかった。
幼い頃の記憶を辿っても「嫌なことは嫌と言いなさい」と指導された覚えはない。
結果、両親の理想どおりエリは他人を気づかえる優しい女の子に成長したが、同時に引っ込み思案でノーと言えない、生きる上で厄介な性質を備えることになる。
意見を、特に断り文句を口にする行為はエリの精神に過剰な負担がかかるものであった。
幼稚園まではなあなあで済んだ。
比較的ゆるい環境の園で、何を考えずとも園児達とも仲良く過ごせた。
周囲を引っ掻き回して波風を立てる園児はいなかったので、エリは気の赴くままクレヨンを手に画用紙と向き合う楽しい毎日を送れた。
小学校に上がり、自分を取り巻く者達が何倍も増えれば、幼稚園時代のままでは済まなくなる。
運動着のタグの位置。鍵盤ハーモニカのマウスピースの形。ノートのマス目の個数。学用品のメーカーなどなど、大多数の児童との僅かな違いを見つけては笑い種にする児童に向かって「やめなよ、嫌がってるじゃん」と冷静かつキッパリと言い放つ蘭の姿にエリは衝撃を受けた。
後に少女雑誌だか歴史の漫画で知ったジャンヌ・ダルク。
真っ先に思い浮かび、面影を重ねた存在は蘭だった。
形の良い唇で、蘭は更なる苦言を呈する。
「前から思ってたけど、人の善意をからかいの種にするのは神経を疑う。あんた達、天狗になったかどうだか知らないけど、最近周りへの態度が悪くなったよ」
ぐうの音も出ない。
吉田も、斎藤も、二人に乗っかってエリをからかった部員達はバツが悪いとばかりに顔を曇らせて居心地悪そうにしている。
「お前らぁ、喧嘩してんでねえど?」
いつの間にか林を含む男子グループが吹奏楽部の女子グループの横を通り過ぎようとしていた。喧嘩するなと笑いながら突っ込んだのは林とつるんでいるテニス部の男子だ。
「エリ、あのさぁ」
林が進み出る。緊張しているのか、動作がぎこちない。
「さっきはありがとな。やっぱり、明日ティッシュ返すわ」
柔らかいティッシュは高いしお前も鼻風邪ひいた時に不便だろ、と林は続けた。
ほらね、とエリは恨めしそうに吉田達を睨む。
林もエリと同じ方向を向き
「お前らも変な詮索すんなよな? ハッキリ言って迷惑だから」
と、困惑した表情で訴える。
んだからぁ、とテニス部の男子が林に同調した。
「音澤が言ってたの聞こえたけど最近やりすぎだでぇ、お前ら」
男子グループはヘラヘラと笑いながら「東北大会出たからって天狗になるなよぉ?」と通りすぎた。
態度こそ軽薄だが、正論だ。
◇ゴメンナサイ◇
翌朝、大槻エリの下駄箱に吉田からの手紙が入っていた。
吉田は現在でも書道を習っているだけに丁寧な文字を書くが、一文字一文字がやたら小さく間隔が広い。
人によっては読みにくいかもしれない。
『英里ちゃんへ。昨日はゴメンナサイ。蘭ちゃんと男子に言われて考え直したよ』
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 6
◇二枚舌と天の邪鬼◇
ゴメンナサイって、書いたよね。
考え直したって書いてなかった?
エリの心のモヤモヤが消えない。
文化祭が終わった頃から林の態度が冷たい。
「本っ当、態度悪い」
蘭が腕組みして林の後ろ姿を睨みながら荒らげた声で憤る。
それに続いて留美も「力丸がいたら頭突きされっぞ?」と鋭い眼差しで睨んでいた。
数分前になる。
放課後の廊下でエリは林が落とした譜面を拾い上げたので手渡そうとしたが、林は噛み付かんばかりの形相で、恫喝と思われても仕方がないくらいの強い口調で言い放った。
「テメェ! 汚ねえから触んな!」
暴言はエリのみならず蘭と留美の逆鱗に触れる。
譜面を取り落とし、目には涙を溜めて震えるエリを背に庇い、蘭が進み出た。
「林!」
蘭が声を張り上げたのを合図とばかりに教室という教室から野次馬が廊下になだれ込む。
校内で『模範生の音澤さん』で通っている蘭が学校で声を荒らげるなど、滅多にないことなのだ。
「今のは酷すぎだよ! エリちゃんに謝ってよ!」
何があったの?
音澤が怒った!
林が何かしたらしいよ。
エリちゃん泣いてない?
野次馬に構わず留美も親友に加担する。
「そこは『ありがとう』って言うべきだろうが」
更にドスのきいた声で節をつけて「あ~り~が~と~う~と、ご~め~ん~な~さ~いは~?」と続けた。
林の顔を覗き込んで凄む留美は、さながらケンカ相手にメンチを切るスケバンの佇まい。
野次馬は聞こえたセリフで事の経緯を把握できたらしく「謝りなよー!」と林を責める者が出る始末だ。
林、謝りなよ!
そうだよ、謝れ!
鵜沼のやつおっかねーよな。
蘭ちゃんも怒ると怖いね……。
謝れコールのほとんどが女子によるものだが、男子の声で「林のやつ、最近大槻への態度悪くなったよな」というささやきも混じる。
「あーあ、うるさい連中だな。やだやだ」
同性にまで咎められて堪えたのだろう。
居心地の悪さを振り切るかのように数回激しく頭を振ると林は譜面を乱暴に拾い上げ、肩を怒らせて早足で立ち去る。
文化祭の後に、エリは林に告白すると決めていた。
しかし、実践に至ることはなかった。
引っ込み思案なエリと天の邪鬼な林。
いわゆる「両片思い」だった二人は、互いに好き合っていたことを知らない。
蘭と男子グループから周りへの態度の悪さについて指摘を受けた放課後の出来事から、吉田と便乗してエリをからかった部員達はおとなしくなったように見えたが『喉元過ぎれば熱さを忘れる』とはよくいったものだ。
文化祭が迫るにつれ吉田は再び林を引き合いにエリを冷やかして反応を見ることが増えた。
「エリちゃん、いるよ」
吉田は、林の姿を見かける毎に林本人に聞こえる声でエリに林がいると余計なお世話じみた発言を投げかけてはエリを慌てさせる。
冷やかしが原因で嫌われるかもしれないからやめて欲しいとエリは何度も何度も訴えたが、一向にやめなかった。
耐えかねて、下駄箱の手紙と話が違うと怒って抗議した時にはいわゆる「逆ギレ」をする始末。
声を荒らげはしなかったが、ふて腐れて唇を尖らせて「別に冷やかしてないし。何、勝手にキレてんの?」と言い返す吉田の顔に、さすがのエリも憎たらしい顔だと嫌悪感を抱く。
その憎らしい顔で、吉田は更にボヤくように続けた。
「馬っ鹿じゃないのって感じ」
逆ギレ騒動からの数日間は、吉田と吉田についている数人の部員がエリと口をきいてくれなかった。
顧問の介入でエリに対する無視は収まったものの、いじめまがいのトラブルは懲り懲りだとエリは吉田に意見できなくなってしまった。
エリが危惧したとおり、文化祭まであと一週間の頃に林はエリを避けるようになる。
文化祭の後に告白できなかったのも、エリが林に声をかけようと足を踏み出した途端「エリちゃ~ん! いるよ」と吉田が大声で林を指差したのだ。
そして
「何か伝えたいことあるんでしょ!」
と、やはり大声で言ったのである。
恥ずかしさのあまり、エリも林も互いに背を向けて去るしかなかった。
計画どおり、エリは林に想いを告げるつもりだった。
当初の計画とは違った言葉で。
――また、今までどおり仲良くしたいな――
本心を、願いを伝えるチャンスをエリはぶち壊されたのだ。
◇吊し上げ◇
楽器が上手いからと部長を筆頭とした上級生にかわいがられるようになったからか、文化祭の準備期間頃から吉田は天狗になりかけていた。
楽器だけではない。
吉田は気に入った者に取り入り、味方を作ることに長けていた。
いわゆる「ぶりっ子」だ。
小学生の頃からぶりっ子の気配はあったが、吹奏楽部の副部長に就任して以降は殊更にぶりっ子の気配が強まった。
対象となる「お気に入り」は、上級生とスクールカースト上位者。
吉田も馬鹿ではないので誰彼構わないとは限らないとわきまえており、自分に厳しい目を向ける者には近寄らない。
小学生時代は教師も対象だったが、かわいらしさより礼儀正しさを求める中学校では教師陣にぶりっ子が受けないと察し、教師相手にかわいく振る舞うなどはしなかった。
特に学年主任で女子保健体育担当の松井はチャラチャラとした軽薄な生徒全般を嫌い、松井が進行する学年集会では吉田は度々当て付けがましいことを言われている。
しかしながら、教師よりも生徒間での評価が気になるようになった吉田はベテラン教師の松井に目を付けられても痛くも痒くもない。
そうして味方を増やしてきた吉田は「私はみんなの人気者だから、少しばかりの悪ふざけなら大目に見てもらえる」と思い込むようになる。
悪ふざけ。
エリに対する林を引き合いにしたからかいも含まれる。
そんな彼女を呼び出して吊し上げたのが、荒川であった。
取り巻きの部員の他に吹奏楽部員ではない二年生を三~四人引き連れ、荒川は「部長に気に入られているからって調子に乗りすぎる」だの「態度が生意気」だの「ぶりっ子は嫌い」「だから松井先生に嫌われているんだ」だのと吉田に向かって因縁をつけてきた。
「部長には内緒だよ」と釘を打つことも忘れずに。
複数の上級生に取り囲まれて泣きじゃくる後輩の図。
絵に描いた吊し上げの光景だった。
吊し上げが行われたのが校舎内、それも吹奏楽部員が各教室を借りてパート練習をする時間帯だったので、吊し上げはその日の活動時間内に部長にバレるところとなる。
部長と仲の良い部員が吊し上げの現場を目撃し、各教室に設置された内線を使いスパイの如く部長に報告したのである。
吊し上げを知った部長は激怒して現場に乗り込んだというが、翌日には冷静な態度で部活動に臨んでいた。
翌日の部活動は急遽ミーティングに変更され、部活動のための時間を丸々費やした。
音楽室の床の上で部員達が車座に座らされ、部長が司会進行となり荒川とその取り巻きによる不穏な動きはなかったかと一人一人から証言を集め出すのだ。
証言で最も多かったのは「吊し上げの三日ほど前に、荒川は他の金管パートの部員に吉田と斎藤への愚痴をこぼしていた」である。
同じパートの後輩の斎藤に対しても、パート練習終了後に教室を出る時、斎藤が出る前に電気を消して立ち去るなど冷淡な態度を取っていたことも明かされた。
ミーティングという名の糾弾会議で、荒川と取り巻きの部員が部長から吊し上げを喰らう展開と成り果てた。
「そろそろアンコンの練習に入るんだし、全国出場を目指してるパートもいるんだよ。あんた達の好き嫌いによる問題行動に付き合わされる暇はないんだからね?」
部長は荒川とその取り巻きに向かって冷ややかに言い放つ。
「真面目にヤル気ないなら、辞めていいよ」
11月の始め頃の出来事だ。
この一件こそ、吉田が増長するきっかけとなる。
私に人望があるから、私がかわいいから守ってもらえた、と。
◇あんたのせいだ◇
「エリちゃんに謝りなよぉ!」
どの口が言うか。
蘭は腸が煮えくり返る思いで、これ見よがしに林に詰め寄り責め立てる吉田の声から避けるようにその場を去る。
まぶたを赤く腫らしたエリを引き連れて。
吉田の行動だけを切り取れば「友達思い」に見えるが、当事者達のいる場で騒ぎ立てるなど余計なことでしかない。
大騒ぎすることで、当事者の反応を見ているのだろう。
甚だ悪趣味だ。
成り行きを知らない二年生達が「どうしたの?」と寄ってきて、吉田は「あっ、舞ちゃん!
林ったら悪いんだよぉ? さっき廊下でエリちゃんに酷いこと言ってきてさぁ!」と媚びを含んだ口調で誰かから聞きかじったトラブルの内容を話し出す。
部長と吉田は清水が丘小学校の吹奏楽部で長らく活動を共にしてきた仲だ。
中学校に進学した後も吉田は小学生時代の感覚のままタメ口で接し、部長自身も敬語は戸惑うからとタメ口を容認している。
部長のみならず引退した三年生を含め、小学校時代からの吹奏楽仲間は吉田からのタメ口を許しているようだった。
取り巻きの一人で、吉田と同時期から清水が丘小学校の吹奏楽部で活動していた千晴は敬語に変えていたが。
後に部長をはじめとした二年生による林をバッシングする声が、防音の機能を備えた重いドアをすり抜けて蘭とエリの耳に小さく入ってくる。
あんたのせいでしょうが。
変に冷やかすから。
だから林がエリちゃんから離れたんだ。
また、ぶち壊すつもりなの?
あんたは、何がしたいの?
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 7
◇恋とジャンヌ・ダルク◇
「却って、その程度の野郎とくっつかなくて良かったと思うしかないよね」
「そうだね」
「男もよく分からねえやつが存在するからなぁ。エリちゃんは人が良い分騙されやすそうだよ」
やっぱり、と蘭は返した。
優しい反面、意志薄弱なエリはつけ入られやすいところがある。
下駄箱に入っていた謝罪の言葉が綴られた手紙の処理に悩むエリに、証拠品だからと保管しておくよう助言したのは蘭だ。
厳密には、蘭の相談を受けた一哉が提案したのである。
日記をつけておくと良いと助言したのは慧子だった。
「元生徒会長の私が吉田とその腰巾着をマークすっから、何かあったら遠慮なく私に報告しなね。生徒会のメンバーにも吹奏楽部に怪しい動きがある件を伝えておくよ。面倒で場合によっては苦痛かもしれないけど、簡単でいいから日記はつけときな。いつ、どこで誰に何をされたかを記録するんだよ。日記だって立派な証拠だから」
そう告げて慧子はエリの頭をくしゃくしゃに撫でた。
慧子がエリに向ける力強い眼差しと、涙ぐんで礼を述べるエリの顔を、蘭は忘れはしない。
「林の態度は酷すぎるよ。外野が冷やかすからってのを考えても、手のひら返しの度が過ぎる」
「まず好きな女子を庇えよって話だよなぁ。俺だったらそうする。男気がなさすぎるよ。同性として引くわ、その林ってやつ」
苦手なタイプだわと言う一哉はげんなりとした顔だった。そして、くるみパンにかじりつく。
「林と仲の良い男子も面白がってエリちゃんを茶化してくるの。あくまでも一部の男子で、ほとんどの男子は引いてるしゴウダとハマちゃんがさりげなく注意してるけど。あれじゃあ、エリちゃんも男嫌いになりかねないよ」
「姉ちゃんの二の舞は避けたいよなぁ」
男嫌いに成り果てた者による弊害を、一哉は身をもって存じ上げているので他人事ではなかった。
「私も男嫌いな時期あったから……全員ではないんだけど、とにかく信用できなくなるの。男はサバサバしてるとか陰湿じゃないなんて、そんなことない。男で嫌な思いをしたことがないからそう言えるんだよ。周りに左右されて流されやすくて、相手の言い分を聞きもしないで、一時の感情で尻馬に乗って攻撃さ仕掛けるのもだいたいは男」
そして、一哉ちゃんは別だよと蘭は慌てて言い繕う。
「一哉ちゃんは、絶対にそんなことしないって分かってるから……」
頬を赤らめてうつむいた蘭に向けて一哉は冗談で「見る目あるねえ、蘭ちゃん」と言うので蘭はクスッと笑った。
「一度不信感抱くと抜け出せなくてタチ悪いのはよく知ってる。新聞記事でセクハラとか痴情のもつれによる犯罪の記事を見る度にさ、姉ちゃん『男は不潔だ、汚い、去勢しろ』だの過激なこと言うんだわ」
案の定、林の件を知った清子は「これだから男って馬鹿で不誠実」と嫌悪感たっぷりに憤っていた。
「私、これから週末の部活には参加できなくなりそうなの。エリちゃんは気にしないでって言ってくれるけど……」
この時、蘭は学生オーケストラに入団するための手続きに出向いた帰りだった。
一哉と会ったのは偶然ではない。久しぶりに会って話したいからと予め蘭は電話で約束を取り付けて待ち合わせたのだ。
待ち合わせ場所は街中だった。楽団の事務所も翠楓学園中学校の校舎も街中にあり、街中ならば中学校の同級生に見られるリスクが低いのだ。
ソロコンテストで好成績を修めた蘭は、地元の学生オーケストラからぜひ楽団に来て欲しいとスカウトを受けた。
学校の部活動と掛け持ちする団員は少なくないらしく(管弦楽部などの音楽系であるが)基本的には週末のみの練習という。
蘭は、自分が楽団の練習で土日の部活動に参加していない間に吉田がエリに対して余計な真似をしないか、林に暴言を吐かれたりしないかを気にしていた。
「みーちゃんは土曜日は書道のお稽古で途中から抜けるんだけど、取り巻きの子達がエリちゃんにきっついこと言うんだよ。あの子達、親が厳しいとかでおっとりマイペースな子を見ると癪に障るんだって。要するに八つ当たり」
「うっわ。俺、そういうやつの方がやだ。うちの学校にもいるよ。親が厳しすぎたり、仕事で忙しくて満足に甘えられなかったやつらだよ」
「そう! 特に当たりがきついのは両親が教師やってる子」
私も八つ当たりするきつい子の方が嫌だな、と蘭は言う。
「あんた達のコンプレックスやストレスとエリちゃんは関係ないでしょうって話。マイペース、イコール、自分に甘いとのたまうけど甘ったれてるのはあんた達だよって」
「蘭がいない間に、エリちゃんの味方になりそうな部員はいないの?」
「味方ってだけなら何人かはいる。林には言えても、みーちゃん相手に苦言を呈する人となると難しい。聖良さんはさりげなくエリちゃんをフォローするから信用できるけど、他の子はみーちゃんは怖いからーって強く出られない」
そして部長と副部長、学生指揮者を務める先輩達は吉田を買い被っている節があることを話すのを蘭は忘れない。
「みーちゃんの取り巻きでさえ強いから意見できないんだって。中には嫌ってる子もいるんだけど、利害が一致すれば好き嫌い関係なく友達付き合いするのかな。私には理解できない」
「怪人クラッシャーみてえなやついるよな。取り繕うの上手くてさ、周りを巻き込むやつ。……林ってやつ、扱いがぞんざいっていうか下に見られてない?」
それはあるかもしれないと蘭は相槌を打つ。
「見た目があまり男臭くないからなのかな。林も……小四だったかなぁ、留美と同じ時期に仙台から転校してきたんだけど、その頃から既にズケズケと言われてたね。先輩からも生意気でかわいくないやつってしょっちゅう面と向かって言われてるし。林って結構気が強くて、一を言われたら十は返すタイプなんだけどね」
「きついことばっかり言われる中で、優しくされたからコロッとイッちゃったのかな……」
「たぶんそれだね。林がエリちゃんを好きだったのは」
言い終えて、「好きだった」と過去形で言い表したことを蘭は切なく思う。
「蘭も怪人クラッシャーには気を付けなよ?」
「さっきから言ってる怪人クラッシャーって、みーちゃんのこと?」
そうだよ、蘭を傷つけたやつは名前すら言いたくないと一哉は返した。
「だって、二度も人間関係ぶち壊してるじゃん。だから怪人クラッシャー。好きなやつ……できたらできるだけ隠し通せ、な?」
蘭は隣を見る。出会った頃の一哉は蘭より頭半分ほど背が低かったが、少しずつ蘭の背丈に追いついてゆく。
しかし、蘭の背も伸びていた。160センチ半ばまで届いた身長は女子高生の平均よりも高い。
出会って二度目の春を迎えたある時、身長が150センチを超えた一哉は「俺ね、蘭より背が高くなるのが夢なの」と、制帽の下で黒い瞳をキラキラと輝かせて話していたのを蘭は覚えている。
今、こうして肩を並べても蘭の肩の位置が高い。
いつになれば一哉の背丈が蘭を超えるかは、定かではない。
「私……」
隣を見たまま蘭は言いかけるが、口を閉ざす。
一哉ちゃんが、好きなんだよ。
◇◇◇
三年生の男生徒に告白されたのは、文化祭の前頃だった。
告白してきた男生徒は斎藤先輩といった。
慧子と同じクラスの元野球部で、日焼けした肌が見るからにスポーツマンらしい好男子。
チャラチャラと浮わついた感じは全くない。硬派そのものの態度と口調で、斎藤先輩は蘭に想いを告げる。
「一目見た時から好きでした! 俺と付き合ってください!」
蘭はその場で断った。
付き合ってください。その言葉を聞いた途端、脳裏に一哉の姿がちらついた。
「ごめんなさい」
斎藤先輩は一年生の女子から人気が高いのも頷ける容姿だ。
スポーツ狩りというのだろう。眉と額の見える短髪が爽やかで、一重の切れ長の目も日本男児の風情がある。
「私には、好きな人がいます」
この先輩もカズヤという名前だったと蘭は思い出した。
一年生達は揃って斎藤先輩、斎藤先輩と呼ぶので下の名前を失念していたのだ。
「誠に申し訳ありませんが、彼以外の男の人とはお付き合いできません」
同じ名前でも全くの別人。当たり前だ。
私の好きな一哉ちゃんではない。
目の前の上級生は、私の王子様でも騎士様でもない。
顔は存じ上げていても、話したことのない上級生の一人に過ぎない。
蘭は目を閉じて深々と礼を返す。
閉じた瞼の裏で、蘭は腕を伸ばす。
学生服の似合う。澄んだ瞳の美しい少年。
蘭より背は低いが、誰よりも頼もしい、愛しい少年を想像の中で抱きすくめる。
私の王子様で騎士様。
一哉ちゃんならば、喜んで手を取ったのに。
「この件は内密にお願いいたします。先輩は人気がありますので、やっかみを買う恐れがありますし……」
頭を上げ、蘭は斎藤先輩をしっかりと見据えた。
「好きな人に誤解されたくないんです」
◇◇◇
蘭はうつむいて目を逸らした。
「何回も言うけど蘭も気を付けなよ? 現に副部長の件でやっかみ買われたようだし、また小学校ん時の繰り返しなんてあり得そうだよ」
彼ほど、蘭を気にかけてくれる男はいない。
外で蘭の姿を見かければ、必ず駆け寄って声をかけてくる。
すぐに駆けつけられない離れた場所ならば、名前を呼んで手を振ってくる。
通学時に自転車ですれ違う一哉に、蘭は手のひらを向けた。ハイタッチだ。
戸惑いの後、一哉は笑顔で触れ合わせた。
元よりおしゃべりで口数が多く、好きという感情がわかりやすい性質がプラスに働いているのだろう。
小学生時代よりは薄れたものの、男嫌いの名残がある蘭も一哉ならば信頼できた。
「一哉ちゃん、私……」
大きな目に蘭の横顔が映る。
「私は、みーちゃんを信じたかった。それまでは絶対に許せなくて、よその小学校に転校した時なんかいなくなって良かったと思ったもん」
蘭の幻滅したでしょう、という問いかけに一哉は否定する。
「誰だって自分に嫌がらせして追い詰めてきたやつが転校したら『わーい、あの野郎いなくなった、ヒャッハー!』って頭ん中で雄叫び上げてガッツポーズするわ」
嘘八百を吹聴され、孤立させられるという実害があったのだから、自分の目の前から敵が消えて安心するのは仕方のないことだと返され、蘭は少しだけだが安堵した。
「部活動見学の後で泣きながら謝られて、ようやく『昔のことだからもう、いいや』って思えるようになった」
自分の判断が正しかったのか、蘭は未だに自信が持てない。
許さなければ、いつまでも昔のことを根に持つ陰険なやつ、と後ろ指をさされる。
いつだか、荒川が話したとおりだ。人の腐った性根が簡単に変わるはずがないと。
「みーちゃんは小学生の頃から他人の失敗や体質をからかって笑いを取って、注目を浴びたがる節があったんだよね」
ある時は会話中の言い間違いを笑い種にしたり、ある時は突然体調を崩して授業を抜けた児童に向かって「今日はトイレ大丈夫なの」と数日間に渡りしつこく聞き出す。
それも大声で、必ず人が集まっている時にだ。
ひどいと学年が異なる者がいる前で、わざと心配そうな顔を作り「トイレ大丈夫?」と大声で聞く。
その児童は女子だったこともあり、相当恥ずかしかったであろう。事実、吉田が発言する毎に便乗してからかうクラスメートが存在した。
女子児童が「いい加減にして!」と怒ってもヘラヘラした態度でのらりくらりとかわす吉田の不誠実さに耐え兼ね、蘭はやりすぎだときつく注意した。
それ以前にも度の過ぎたからかいに遭遇する毎に蘭はもちろん他のクラスメートもやんわりと指摘していたが、やめなかった。
だから、蘭も大勢の人がいる前で声を張り上げた。
「みーちゃん! 人に恥かかせるのいい加減にして! 聞いててイライラする! 毎回毎回やりすぎだよ!」
その場にいた児童の大半が、蘭に賛同した。
「私に指摘されたのが気に入らなかったのかな、って思う時はある。嫌がらせが始まったのそれから少し過ぎた時だった。でも、私がしたこと間違ってないよね?」
好きだった男子も、蘭の勇姿を称賛したはずだった。
それなのに、彼は手のひらを返して「正義感が強いのをわざわざアピールしている点数稼ぎ」と蘭を中傷するようになった。
吉田からの嫌がらせが始まったのと同じ時期にだ。
ゆえに、蘭は林の言動が許せなかった。
今までの関係性はなかったとばかりにエリを口汚く罵倒する林の姿が、昔好きだった男子と重なった。
元来正義感の強い蘭であるから、仮に昔好きだった男子との確執がなかったとしても林のことは許せないだろう。
幼い日に受けた傷。それによって蘭の持ち合わせる正義感は強まった一方、他者への尊厳を踏みにじる行為をより許し難いものとさせていた。
「私はただ、執拗にからかわれて泣きそうになっている子を見ていられなかったの。みーちゃんのやったことは誰がどう見ても間違っているし、許されるものじゃないよね?」
「当たり前だよ。蘭は間違ってない。その子、蘭に助けられて嬉しかったんじゃないかな……」
「みーちゃんが吹き込んだ嘘八百にも騙されなかったしね。その子、私立に行ったからたまにしか会えないけど」
2002年 私のジャンヌ・ダルク(前編) 8
◇独裁◇
一年生諸君に告ぐ!!
・無断遅刻したら退部(理由に学活、掃除、委員会、日直の仕事含む)。
・週に二度以上休んだら退部。
・早退は週に一度まで。破ったら退部。
・部活動が終わったら校舎周り5周走る。
・欠席した翌日は1周追加する。
・タイムが遅れたら1周追加。
守れない人は退部!
音楽室の黒板の、片隅にある箇条書き。
箇条書きは整った字面だが小さくて間隔が広すぎて読みにくく、縁取りのつもりで描いたカラフルなチョークの装飾が箇条書きを見辛いものにさせていた。
箇条書きの末尾には「勝手に消すな!」の文字がギザギザの縁取り付きで追加されている。
「何、これ?」
「蘭ちゃんがいない間に決まったんだよ」
茫然とする蘭に吉田の取り巻きの千晴がコソコソと忍び寄ってささやく。
元からの猫背を更に屈める姿勢が千晴のやや太めの体型をより丸く見せた。
エリを含む風采の上がらない生徒には辛辣な千晴だが、蘭には容姿、成績共に敵わないと一目置いているからか楯突くことはしなかった。
それゆえに『強きにへつらい弱きを挫くの典型例』と千晴を良く思わない教師と生徒は少なくなかったが、未就学児の頃から習っていたピアノは学習発表会やクラス対抗合唱コンクールでの伴奏に抜擢される腕前を誇り、美術の授業で描いた作品は軒並み美麗かつ独創的なセンスに定評があり、過去には賞をもらったこともある。
定期テストでも常に上位にランクインしていた。
他人への態度の悪さは差し置いて、芸事において信頼されているのは間違いない。
「みーちゃんが、決めたの?」
蘭の顔を見ずに、千晴は黒板を見たまま「そうだよ」と頷く。
千晴は中学校に入学したての頃は今ほど尖っておらず人当たりが良かった。
コソコソとした内向きの動作に猫背気味でどこか陰気くさいのは否めないが、誰に対しても丸腰であったし毒のきいたユーモアを交えたトークで友人達の笑いを取っていた。
蘭も、千晴を面白い子だと好意的に見ることができた。
夏休みが明けた頃か、それとも東北大会が終わった頃からか、千晴は自分より弱いと判断した生徒にトゲのある言葉を投げつけ、場合によってはすれ違い様に体当たりするなど攻撃的な振る舞いが目立つようになった。
弱そうに見えない相手でも、千晴が気に入らないと思った時点で陰口の対象になる。
対象者がその場にいなければ、いつでもどこでも近くにいる友人に悪口を聞かせるので「あいつは嫌いなやつしかいないのか?」と顰蹙を買った。
つるんでいる吉田と斎藤ですら陰口の対象だ。
噂では両親共に高校の教師で元々厳しく育てられていたが、中学生になってからは更に日常生活における親の監視が厳しくなったと聞く。
気に入らない生徒への八つ当たりじみた態度は厳しい両親が原因であると噂されるが、やられた側にしてみれば堪ったものではない。
才女と呼んでも遜色ないのに、性格が悪くなりすぎてもったいない。
現在の蘭から見た千晴の印象だ。
「あ、蘭ちゃん来てた」
「蘭ちゃん!」
「黒板見た!?」
何人かの一年生が蘭に集まってきた。揃って救いを求める眼差しだ。
「みーちゃん来てないから言えるけど、強引すぎるよね」
「んだから!」
「私だって塾で抜ける日あるのに」
「千晴ちゃん。これ、満場一致で決まったことなの?」
蘭は敢えて千晴に聞く。取り巻きの中では斎藤と並んで吉田に近しいポジションだからだ。
「違う違う」
見ただけで小憎らしくなる膨れっ面で千晴は言う。この同級生は日に日に仏頂面が増えている。
美人ではないが決して不器量でもないし笑うと福福しくて愛嬌があるのに、千晴の仏頂面はこの上なく醜く見える。
「みーちゃんは強いから言えないよ。私だって本当は反対したいけどさぁ」
「おかしいよ。逆らってお家断絶されたりヤクザに売られるならともかく、そこまでの権力もない人になんでみんなしてへつらうわけ?」
再び「おかしいよ!」と口にする蘭にぐうの音も出ない千晴達は黙り込んだ。
蘭と同じ小学校出身の部員が恐る恐る口を開いた。
「清水が丘の子らは蘭ちゃんの前例を知ってっから……」
「又小出身の子も、みーちゃんが清水が丘で蘭ちゃんを孤立させてたの噂で知ってる子が多いんだ。逆らって孤立するの怖いんだよ」
バカバカしい、と蘭は苛立った声で一蹴した。
「嫌がらせ受けたのはもう昔のことなんだよ? 噂が出回っているなら、仮にやられたとしても嘘だって擁護する人が出てくるよ。反対意見はなかったの?」
「ないに決まってんじゃん。日曜の部活が終わった時に一年生だけ音楽室に残れって言われて……」
「黒板に書き出して『来週から実行する。反対するなら退部ね』って勝手に決めてきたんだ」
こんなの独裁政治じゃん……。
蘭は口を閉じたまま歯を食い縛る。眉に力が入る。
荒川が話していた「部の私物化」が現実味を帯びていた。
「みんなの意見を聞いて決めるべきなのに……。塾通いで週に1、2回休む子だっているべよ?」
千晴も、ピアノ教室と塾通いを合わせて週に二度欠席するクチだ。
「みーちゃんってただでさえ副部長になってから調子こいてるのにさぁ、部長に気に入られてるしタケとかカッちゃんとかの男子と仲良くなって、ますます調子こいてるよね」
唐突に始まった千晴の愚痴。複数の部員が頷いている。セリフ内に出てきたのはいずれもスクールカースト上位者の男子の愛称だ。
そして、しかめっ面で「私、タケ嫌い」と千晴は語る。
一年生で一番かっこいいと評判の武田と千晴は同じクラスだった。
「なんとなく『感じ』がさぁ、気に入らないんだ」
千晴の言う『感じ』とは、武田の纏う飄々とした雰囲気を指しているのだろう。
見てくれは硬派で何事に秀でていながらもマイペースで自由奔放な武田は、雁字搦めな環境に置かれている千晴にとって癪に障るのかもしれない。
「部長や男子が甘やかすから、みーちゃんは自分は何をやっても許されるし周りは従って当たり前って思い込んでるよ、絶対。だから一人で勝手に決めているんだよ」
「そんなのおかしい。独裁政治でしかないよ! 間違ってる!」
激昂する蘭をすくい上げるように見上げる千晴は陰気そのものだ。
しばらく黙り込んで、千晴は陰気くさい口調でつぶやいた。
「……蘭ちゃんが副部長になれば良かったんだよ」
その場にいた部員全てが千晴に賛同した。
◇◇◇
蘭は吉田が音楽室に入ってくるなり考え直して欲しい、一年生達の意見に耳を傾けて欲しいと申し出た。
かつて全国大会出場まであと一歩の段階まで導いた兄は、部員を威圧し恐怖で支配など断じてしない。
むしろ、無理のあるスケジュールで体調を崩したり成績が下がったら本末転倒だからと部員を気づかう政策を立てていた。
部員と共に兄が築いた結果と栄光を、泥を塗りたくられ踏みにじられたようで腹立たしい。
兄が「生徒を代表する者が絶対にしてはいけない」と常々話していたことを、吉田は見事にやらかしたのである。
強い口調で「どういうこと!?」と問い質したい蘭だが、感情的になれば反感を買うのは免れないので冷静さを保ちながら吉田への直談判を決行したのだ。
「私もだけど習い事や塾通いで休んだり途中で抜ける子もいるの。急な用事で抜けざるを得ない場合もあり得るんだし、退部をちらつかせて脅すのは乱暴だよ」
蘭は棒立ちで傍観する千晴をちらりと見た。エリは聖良を含む何人かの部員と共に一触即発にならないかを見守っている。
「蘭ちゃんは全国行きたくないのぉ?」
反発するかと思いきや、吉田は涙ぐんでいる。
吉田は色白だ。それも青白い肌なので目の周りと鼻が赤らんでいるのが音楽室の隅からでも目立つ。
「行きたいよ。焦る気持ちもわかる。でも、遅くない時間帯……6時半に切り上げて全国出場に毎回している学校もあるって聞いた」
蘭は東北ブロックにある全国大会常連の高校が活動を18時半に切り上げている事例を挙げた。
「大会で結果を出しているから、吹奏楽部は特別に夜の7時まで許されてるの。でも部活終わった後に学校に残ると見回りの先生に怒られるの知ってるよね。あれ、上野先生も職員会議で注意されるんだよ。それから、雁字搦めすぎでは宿題にも影響が出かねないし、門限が厳しい家の子もいるの」
コンクールを控えた期間でないにもかかわらず、吹奏楽部員が20時近くまで校舎内に残ってお喋りをしていた事例があったらしい。
その件について顧問が生徒指導の教師から注意を受けたこと、顧問が保護者会にて「部活動が終わり次第早めに帰宅させますので、各家庭でもご指導願います」と話していたことを蘭は母親から聞いていた。
その部員こそ吉田であり、お気に入りのタケちゃんを含む男女交えた複数の生徒であったことまでは蘭は知らない。
「みーちゃんは平気でも、詰め込みすぎたスケジュールが負担になる子がいると思う」
吉田は学区外から来ている分だけ帰宅するのに時間かかるのではないか、と蘭は突き付ける。
「私は小学校の朝練でスケジュールギリギリの生活に慣れてるし。そんな、すぐに負担のかかる根性ナシ、辞めたらよくない?」
一年生の群れから「はぁ?」と不満の声。林だ。
「お前、一年の代表のくせに仲間大事にできねーのかよ!」
エリちゃんに辛辣な態度を取るあんたが言うなと蘭は不満を抱くも、林の発言はごもっともだと認めざるを得ない。
涙ぐんでいたのが嘘であるかのように、吉田は表情をガラリと変えた。
嘲るように目と口元を歪めた笑顔を林に向ける。
挑発的な笑顔は見る者を苛立たせ、薄気味悪いほどの役者ぶりに蘭は怖気立つ。
この怖気立つ感覚は、小学生の頃にも経験した。
前日までニコニコと笑って甘えた口調ですり寄ってきたのに、挨拶を無視された挙げ句横目で睨みながら無言で素通りされた瞬間、極端すぎる変わり様に小学三年生だった蘭は戸惑う。
戸惑うと同時に、怖い、気味悪いという感情が蘭の胸の中で渦巻いた。
「下手くそなくせに私に歯向かうって何ぃ? あと10年早いんだけど」
「だから、みんなの意見を聞けって話だろ! 事実、反対してるやつが多いんだぞ」
「下手くそは黙っててよ。転校生のよそ者くせに生意気」
自分だって小六の途中で転校したでしょうが、と言いたい部員はどれだけいるだろう。
「そういう態度が問題なんだっつーの、お前は!
あの後、みんなやりたくねーって文句言ってたんだ! 」
突然始まった言い争いに空気が重苦しくなる。
まずは蘭が、そして一年生の群れから三人ほど走り出て仲裁に入ったが言い争いは収まらない。
誰もが音楽室から逃げ出したい心持ちにさせられた。
意見を言わねば独裁政治に歯止めをかけられない。
誰か何か言ってよ……と、各々が放つ無言の圧力。
部員を取り囲む空気が更に重苦しくなる中で「ちょっと、いい?」と挙手したのは言い争いの仲裁に入っていた斎藤聖良だ。
吉田も林も、このタイミングで聖良が手を挙げてまで発言したがるなど余程の理由があると悟り、言い争いを中断する。
「私も、みーちゃんの提案には賛成しない」
右手を顔の高さに上げる聖良の口調は穏やかだが「どうにでもなれ!」とやけくそになった感情が強張った表情に見え隠れしている。
「無断遅刻が許せないのはわかるけど、帰りの学活が長引いて抜け出せなくて他のクラスの吹奏楽部員に遅れるって伝えられない場合があるの。他の部活の人達や先生方が吹奏楽部のやり方に理解あるわけじゃないし、退部にさせるのは無理があるよ」
淀みなく、どもることなく聖良はすらすらと自らの意見を述べた。
これは二年生で時々起きるのだが、放課後に突然学年集会を行うと宣言され(大概は少数の生徒の問題行動が原因。連帯責任として二年生全員が小一時間に渡り説教を喰らうパターンなのだ)、部活動に遅れた事例もある。
今年度だけでも二度起きており、この日も二年生が来る気配が訪れない。
聖良はこの件も例に挙げて
「私らの学年でも、同じことが起こらないとは限らないんだよ?」
と、吉田に考え直すようにと説得に入る。
私ごときが生意気と怒られるのは承知だけど……と、聖良に続いておずおずと口を開いたのはエリだった。
千晴が、林が、一年生の部員達が「あの、引っ込み思案な大槻エリが意見した」と目を見張る。
「合奏を続けるならまだ納得できるんだけど……校舎周りを5周走るのは暗くなる時間だし、足元が見えにくいから危ないと思う。さっき蘭ちゃんが言ってたけど、ただでさえ学校に残ると先生や用務員さんに早く帰れって言われるのに……」
基本的に大会を控えている期間は全ての部活動において19時半までの活動が黙認されているが、あくまでも大会前の話だ。
過去には遅い時間帯までの部活動が当たり前だったかもしれないが、時代の流れもあるのだろう。
蘭達が入学した時点で『部活動は18時半まで、冬季~新年度までは17時半まで』と定められていた。
不審者対策と帰宅中の事故を未然に防ぐためという名目によるものだった。
郊外の中でも利便性が高い地域だが、暗くなれば歩行者が少なくなるのはどの地区でも同じだ。
更には不審者が出たという物騒な噂が生じることもあるので、教師の目が厳しくなるのは無理もない。
蘭が話したとおり、吹奏楽部はコンクールで結果を出していることが評価され特例として19時までの活動が許可されているのだ。
他の部活動と比べて長い活動時間を得られているだけでも御の字といえよう。
「前に、外部の先生が指導に来てくれて練習が8時まで長引いた時あったべした? あれで帰りが遅いって親に怒られた子が何人か出たんだって。私も、お母さんにひどく怒られて部活を辞めろとまで言われた。携帯なんて持ってる子はほとんどいないし、休憩時間に職員室前の電話で連絡するにしても込み合ってて電話すらできなかった子がいたんだ」
複数の部員が「私も怒られた」と口々に述べた。
千晴もコソコソと進み出る。
「みーちゃんさぁ、私も塾とピアノで抜ける日があるのわかってるよね? 同じパートなんだから」
後に蘭が千晴の担当するクラリネットパートの二年生から聞いて知ったことだが、千晴が面と向かって吉田を非難するのは珍しいことだという。
「あと、みーちゃんだって土曜日に書道で練習抜けるじゃん」
「それは……週に一回だけだし……」
途中までなら練習に参加している、私は退部の条件に当てはまらないと反論する吉田を、千晴は眼光鋭く睨みつけた。
「部活のためと言ってるようだけど、実際は自分に都合のいいルール作ってるだけにしか思えない」
そして「自分勝手すぎるよ」と吐き捨てる。
「とにかく、みーちゃんのやり方も黒板の内容も横暴でしかないよ。退部という言葉で脅して、やってることが独裁者と変わらない。こんなの、恐怖政治だよ。みんなの話を聞かないで勝手に決めるのはどうかと思う」
蘭は声を荒らげたい衝動を押し殺しつつ、冷静に冷静にと言い聞かせながら吉田と対峙する。
「なんで、みんな反対だって言わなかったの?」
林に対抗した時の強気な姿とうってかわって、吉田は態度も語気も弱々しくなっている。
しわがれた唸り声が、一年生の部員の塊の隅から聞こえた。あたかも不快そうな唸り声。
「お前が、言えない雰囲気にしたんだろ!」
吠えるように言ったのは林だ。やはり林は気が強かった。
口調がきついとたしなめた部員もいたが、怒りが収まらない林は部員の制止もお構い無しだ。
「いきなり黒板に書き出して『逆らったら退部ね』って、反対だって言えるわけねえだろ! たかだか一年の分際で何様だよ」
たかだか一年の分際という言葉に、それまで植え付けられた屈辱感による反発心がこれでもかと詰め込まれていた。
居丈高な態度を取られて一方的に見下されていた鬱憤が溜まっていたので、この話し合いは吉田へ言いたいことをぶちまけるちょうど良い機会だった。
口調の乱暴さはさておき発言内容はごもっともであるが、林が吉田に楯突いた動機は正義感や義憤にかられてというよりは憂さ晴らしに近い。
吉田はついに嗚咽を漏らす。
一年生の部員達は自分を信頼し従っていると思いたかったのに、結局は虚構に過ぎなかったことを突き付けられた。
それだけでも愕然としたのに、下手だと見下している上に「男、約一名」だの「女男」と散々からかっていた林に怒鳴られて堪えたのだ。
「……反対意見があると見越した上で強行突破したのが丸わかりなんだよ。だから、敢えて意見を聞かないやり方を取ったんだ?」
千晴はもちろん、エリも聖良も林にとっても目から鱗が出る思いだった。
反対意見を見越しての強行突破。
蘭が話したとおり横暴なやり方だと思ってはいたが、まさかそこまで計算していたのかと一年生達は表情や言葉には出さないが吉田の思考に驚愕し畏怖していた。
吉田が独断で取り決めたシステムは二年生と顧問にも知れ渡り、無理があるから取り消すよう諭された。
◇◇◇
「蘭ちゃん」
パート練習が終わり、音楽室へ戻る途中だ。
忍者かと問いたくなる動きで千晴は斎藤を引き連れてコソコソと早足で寄ってきた。
陰口を叩いている相手との友達ごっこ。
千晴にとっては処世術として割り切っているだけかもしれないが、蘭には嫌いな人との友達ごっこなどやりたくもない。
複雑な思いで蘭は千晴と対峙する。
「蘭ちゃんのおかげでみーちゃんが決めたルール取り消しだってさ。ありがとう」
私だけじゃないと蘭は返した。
みんなが言うべきことを伝えたからだ、と
「林の言い方はきつかったけど、ああ言われたら腹立つのも無理ないしな……。先生と先輩達もやりすぎだって思ったようだし」
千晴の横にいた斎藤が、甘えた口調で言う。
「私も反対だったんだよねぇ。だって英語教室あるからぁ」
斎藤の母親は自宅で英語教室を開いている。
母親の教育方針で外国人と関わる機会があったらしい斎藤は海外に関心があり、特にアメリカへの憧れが強いと聞く。
小学生時代は夏休みを利用して毎年のようにアメリカ旅行へ出向いていたそうだが、中学校に入学して初めての夏休みは吹奏楽部との兼ね合いでアメリカへ行けなくなったと嘆いていた。
「私、将来アメリカに留学したいからぁ、みんなより英語頑張らないといけないんだぁ」
蘭は千晴を見る。妬み嫉みで気を悪くしていないだろうかと。
海外に憧れるのは自由である。母親が雪国に憧れたように、蘭も慧子から聞く思い出話に影響されドイツへ行ってみたい願望がある。
留学を目指すのも自由であるし斎藤が本心からアメリカ好きであるのは確かかもしれないが、斎藤は留学やアメリカ旅行という言葉を周囲と差をつけるためにわざと口にしている節があった。
斎藤は持ち物や特技で周りと差をつけている同級生を目の敵にし、難癖をつけて足を引っ張る言動が多く見られた。
例えば、模様のかわいい筆箱を持っている同級生に「その筆箱はダサいから見ていてイライラする。二度と学校に持ってこないでね」とヒステリックに喚き散らすのだ。
そのことが、荒川に目を付けられた原因であると一年生のほとんどが察している。
千晴が陰口を叩く原因であることも。
「ふーん、そうなんだ」
決して斎藤と目を合わせない蘭。棒読みのセリフに「この女と関わりたくない」という本心が見え隠れする。
早くこの場を去りたい。
「英語できたら有利だしね」
妬み嫉みの感情を鎮めるためか、敢えて社交辞令を千晴は口にする。
千晴は社交辞令を言うことを嫌いそうなのに意外だと蘭は驚くが、処世術として嫌いな人と友達付き合いをする千晴ならば躊躇いなく心にもないことを言えるのかもしれない。
千晴の社交辞令を額面どおり受け止めた斎藤は、足をバタつかせてセミロングの毛先を揺らしながら「でしょでしょ?」とはしゃいで言った。
年齢より幼い振る舞いが斎藤の得意技だ。
本人はかわいいと思われたいようだが見てくれは育ちの良いお嬢様なので、幼さを抱かせるリアクションは不釣り合いでしかなかった。
千晴が、尖った眼差しでチラリと斎藤を見ていた。
都合の良い時にだけかわいらしくすり寄るこの似非お嬢様を、蘭はどう頑張っても好きになれないと確信する。
吉田と一緒になって蘭を追い込んだ同級生のうち、最も積極的に煽ってきたのが斎藤だった。
ミッション系の女子中学を受験するも不合格となった負け惜しみで「女ばっかりじゃつまんないし」と発言した出来事は、未だに斎藤がいない場で語られる。
その時の様子を語る同級生は軒並み眉をひそめるか嘲笑うかのどちらかで、斎藤の評判が悪いことが窺えた。
◇◇◇
部活動を終えて、下駄箱で靴に履き換える蘭は背後から声をかけられた。
「私って、副部長の素質ないのかなあ」
赤らんだまぶたの吉田は俯いている。鼻も赤い。
黒髪は青白い肌に映えているが、髪質が硬く量が多いからか重い印象があった。
「蘭ちゃん、いいなぁ。リーダーに向いてるし恋も上手くいってるし」
蘭の表情が、凍りついた。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編)
◇いまいましい◇
何が2000年だ。何がミレニアムだ。
流行りの音楽もファッションも嫌いだ。
蘭は毎日を忌々しい気持ちで過ごしている。
今日も取り巻きの男子が蘭を遠巻きに見てヒソヒソと話し込んでいる。
吉田魅里を独裁者って言ったんだってな。
あいつ性格悪いんじゃねえ?
吹奏楽部での話し合いから数ヶ月が過ぎて、特に何のトラブルも起きなかった。
蘭はフルート四重奏でアンサンブルコンテストの全国大会出場を果たした。
二年生のパートリーダー自らが主旋律の担当を推した時は年功序列を理由に断ったが、自分より経験のある蘭ならば間違いないと言って譲らなかった。
このまま何も起きなければいい。
平穏な毎日が続けばいい。
その願いは二年生に進級したと同時に容易く潰えた。
吹奏楽部での話し合いの内容が曲解されたのか、蘭を悪者にする動きが見られるようになった。
蘭を悪者扱いする者は、主に吉田と仲の良い生徒。
まずは成績も身長も蘭に敵わない男子。
そして斎藤を筆頭とした、成績は人並み以上で友人もいる、環境面で恵まれているにもかかわらず不満が多く僻みっぽい性格の女子だった。
話し合いで反対派だった当事者のうち少数の吹奏楽部員が「違うよ」と詳細を語りつつ庇い立てた。その中には千晴もいた。
少数だったのも吉田の目を気にして行動できなかった者と、元々蘭に劣等感を抱いていた者が憂さ晴らしの機会とばかりに吉田について従っていたからだ。
世間には完全に孤立させられている者もいる。嘘だと思いたいほどの屈辱を与えられ、死すら願わざるを得ない仕打ちを受ける者もいる。
熾烈ないじめを受けている者と比べれば、味方がいるだけ自分はまだ良い方だと蘭は我が身に言い聞かせた。
連中は頑なに蘭を悪者だと言い張った。
蘭が教室に入ったり通りすぎるごとにヒソヒソ話をしながら目配せをするのを、毎日のように目にした。
「蘭ちゃん、気にしなくていいよ」
白沢小百合は陰口を叩く男子を一瞥し、舌打ちをする。
蘭の据わった目。
少し前までは朗らかに笑っていたのに、溌剌とした姿が輝いて見えたのに、今はどうだ。
険しい顔といえばよいのだろうか。美しいには変わりはないが、見る者を畏怖させる凄みを纏う。
「男子は成績で勝てねーから妬んでるだけだよ」
気づかう白沢に険のある顔で蘭は答えた。
「ああ、そうだね。みっともないよ」
蘭には分かっていた。二年生になってから嫌がらせが始まったのは、慧子が卒業したからだ。
その件についても「虎の威を借る狐」と陰口を叩かれた。
蘭は花の生徒会長が自分と血縁だ、などと自慢したこと一度もない。
噂の出所は知らないが、蘭と慧子は親戚同士であると聞き付けた同級生が「蘭ちゃんって生徒会長の慧子先輩と親戚なんだって!?」と人前で騒ぎ立てただけなのだ。
その張本人の中には吉田と斎藤も含まれ、更には慧子と親戚であることを自慢していると蘭を悪者に仕立てるためのネタにしていた。
自分はまだマシだ。そう思い込んだ。
エリは新入生に小馬鹿にされる仕打ちまで受けている。
よりによって、エリと同じパートに吹奏楽部経験者の一年生が入ってきた。
彼女は清水が丘小学校の出身者ではなかったが大会や演奏会で何度か顔を合わせている吉田と親しいようだった。
数年間の経験がある以上、中学校に入学してから吹奏楽を始めたエリよりも技術面で優れているのは仕方のないことだ。
それにもかかわらず、吉田とその取り巻き、新たに取り巻きに加わった新入生は数年間の経験の差を考慮することなく「新入生より下手くそ」「年長者ならば年下よりできて当たり前」と嘲笑った。
吉田と親しい新入生は面と向かって馬鹿にしないものの、離れた場所から当て付けがましくエリの耳に聞こえる声で嫌みを言ったり、エリのいない時には笑いながら陰口を叩いた。
蘭や聖良が長幼の序がなっていない、礼儀知らずにも程があると咎めれば表向きはしょげかえった顔で「スミマセン」と言うものの、自分達を咎める存在がいなくなれば吉田と一緒になって「二年生なのに威厳がないから悪い」と開き直る。
特別レッスンだと練習中に吉田から呼び出され、萎縮して失敗すると小一時間に渡り人格否定を含めた因縁をつけられ、泣きながら戻ってきた日もある。
蘭は休憩時間になるとエリを探した。いじめられていないかと。
いじめの現場に居合わせればエリを連れ戻し「自分だって荒川先輩から吊し上げを喰らって嫌な思いをしたのに!」と吉田と取り巻きに楯突いた。
数日前に、エリが真っ青な顔で黒いファイルを抱えて蘭の前に現れた。
「スコアなくなったの。ファイルに入れたのに……」
課題曲の譜面を入れた次のページに入れたと話したとおり、課題曲の譜面の隣にあるページが空になっている。
エリが譜面を紛失したことは一度だけあった。「私がズボラだからなくしたのかも」と身の回りを探し回ったが見つからず、暗譜しているからと練習は譜面なしで挑んだ。
中体連の、野球部の応援で使う譜面。ゴールデンウィーク明けに渡されたもの。
そして、衣替えの時期に譜面は見つかった。二年生の女子トイレの個室のゴミ箱。
あまり話したことのない女生徒が見つけ「まさかと思って……」とエリに報告したのだ。
女生徒が身体を震わせながら言った。
「これ、絶対に嫌がらせだよね?」
蘭とエリの前に立ち尽くす女生徒の顔は、蒼白になっていた。
「何のスコアなの?」
蘭の血の気が引く。エリがなくしたのではないと察した。前例が前例だ。
「自由曲。せっかく、写したのになぁ……」
顧問にも話した。顧問は終礼にて野球部の応援に使う譜面の件も含めてエリの譜面がなくなったことを部員にも話したが、譜面は見つからない。
部員からの反応は仁分した。探し回ったり見つかったかと聞く部員もいれば、冷ややかな部員もいた。
焦りが募る中、吉田についてはいないがエリの味方でもない二年生の部員が冷淡に告げた。
彼女は損得勘定で誰の味方につくかコロコロ変わる節があった。いわゆる、コウモリ人間。
「自分で勝手になくしたんだから、巻き込まないでくんない?」
夏服の、シアンの襟と揃いのタイが特徴のセーラー服を蘭はとても気に入っている。昨年は喜んで着ていたが今年は着る気にもならない。
課題曲が決まり、吹奏楽コンクールと中体連の応援の練習が重なる時期だ。
蘭とエリは野球部の応援で披露する曲の練習があると知らされず、爪弾きにされていたこともある。
◇◇◇
学生オーケストラの練習は心から楽しめた。誰も蘭の陰口を言わない。
しかし、この日の蘭は落ち着かなかった。
初夏から梅雨時へ移ろう頃だった。
学校から帰宅すると蘭に宛てた手紙が入っていた。手紙とはいってもノートの切れ端を四つ折りに畳んだだけのもので一番上の面には紺色のインクで『蘭さまへ』と書かれている。
蘭へ
久々に会わない?
パンドーラのパンおごるから、オーケストラの練習終わったら稲荷神社まで来てください。
おそらく朝方にポストに入れたのだろう。
手紙の空白には、蘭をモデルにしたのか物憂げな表情のセーラー服を着た少女の横顔が描かれていた。
「蘭ちゃん、今日も一緒に帰る?」
ビオラ担当の堀越梨穂子が声をかけた。彼女とは先週に一緒に帰宅した。
堀越は、蘭の学校での扱いを知ればどう思うだろうか。人当たりは穏やかながらも気性のハッキリとした堀越のことだ。
義憤にかられて「そんなの許せない!」と怒ってくれるだろう。
「ごめん、約束があるの」
「えーっ、誰? 彼氏?」
本当に彼氏だったら幸せだろうな……と蘭は切ない気持ちだ。
例大祭で神楽を舞う舞台の下に手紙の主がいた。
まっさらな半袖の開襟シャツ。黒いスラックスの脚が以前より長い気がする。
蘭が名を呼ぶ前に開襟シャツの少年が蘭の名を呼び、嬉しそうに笑いかけた。
「蘭」
若木のような立ち姿と、凛々しさに愛嬌を宿した端正な顔は新入生の女生徒達が放っておかないに違いない。蘭は胸が疼くのを堪える。
「どうしたの? 学校から帰ってきたら手紙来てたってお母さんが渡してきたの」
一哉はしまったと額を叩いた。
「え、マジかよ。おばさんに見つかった!」
頬を両手で覆って恥ずかしいと身悶える動作。美少年がおどける姿は滑稽だ。蘭はクスッと笑う。
「でも、そうしなかったら手紙に気付けなかったよ」
「あ、蘭ちゃん笑った」
歌うように蘭をからかう一哉も目を細めて笑った。安堵と嬉しい気持ちの混じった笑顔だった。
「手紙に描いてた絵、私を描いたの?」
そうだよと答えた。
「ありがとう……綺麗に描いてくれて」
「俺、心配してたんだよ。最近ハイタッチしてないし、蘭のことはゴウダとかハマちゃんとか久間木から聞いてるし」
蘭は黙り込んだ。学校での出来事は思い出したくない。
一哉と会っている時だけは、前を向いていたい。
何か違う話題を……と蘭が思い巡らせる最中で、一哉は学生鞄に手を突っ込んでいる。手紙には新町のパン屋でパンをおごると書いてあったはずだ。
大正時代から創業しているらしいその店舗で売っているパンの中でも蘭はチョコデニッシュが一番好きだが、一哉はくるみパンが好きなようだった。
彼は新町のパン屋に寄ると必ずくるみパンを買うのだ。パンに限らず「ゆべし」もくるみ入りを好み、蘭の母方の実家から届いたお中元の「クルミっ子」を渡したところ喜んで食べていた。
太巻きにくるみの佃煮を入れる食文化の関係らしい。
「はい。手紙ではパンドーラって書いたけど……」
蘭に元気を出して欲しくて、と手渡したのはリング状のパン生地に生クリームと固いプリンが嵌め込まれた菓子パンだった。
地元民のソウルフードとして愛される、プリンパン。
プリンパンを受け取った蘭は「きゃあ! 嬉しい!」と叫んで目を輝かせた。
豪華な見た目のとおり、パンなのにケーキを食べているような気持ちになれる。それがプリンパンなのだ。
「光月堂のプリンパン! ありがとう!」
こんなにはしゃいだ声を出したのは、いつぶりだろう。プリンパンから視線を移せば大きな瞳が蘭を見つめていた。
「俺、この前誕生日だったからこれで好きなもの買えって五千円もらえたんだよ。だから金回りいいの。チョコデニッシュも買いに行こうか?」
澄んだ瞳は我が事のように嬉しそうに輝いている。
いつもそうだ。彼は如何なる時も蘭を気にかける。
なんで、ここまでしてくれるの。
蘭の瞳の輝きは涙となり頬を流れ落ちる。
神楽殿の下で蘭は泣き崩れた。膝下丈の、紺色のスカートが蘭の足元をすっぽりと隠す。
「蘭ちゃん!」
頭の上で、蘭の名前を呼ぶ焦った声が聞こえた。
しばらくの間、蘭は膝に顔を埋めて泣いた。
スラックスの膝が汚れるのもお構い無しで一哉は蘭の斜め前に膝をつき、見守るしかできない。
気位の高い蘭のことだ。
私は強いから大丈夫と言い聞かせて無理ばかりしていたに違いない。
私は強い。だから自分を二の次にしてでも友達を守る、と。
確かに蘭は強い。身を挺して友達を守り助ける姿勢には感服するほかない。
しかし、強くあらねばならないと抗う者と、泣きたいのに強くあることを強いられた者ほど最悪の手段を選びがちであることを、一哉は知っていた。
精神科医として、追い詰められた末にドス黒く染まった傷ついた心を携えた者達を見てきた祖父と伯母から聞かされてきたのだ。
幼い頃はピンと来なかったが、今ならばわかる。
それだけは、嫌だ。
大好きな蘭が居なくなるぐらいならば、たとえ惨めでも泣き喚くなり愚痴をこぼすなり怒りに任せて暴れるなり、弱さをさらけ出した方がずっと良い。
抱き締めたい。憧れの艶やかな黒髪を撫でてあげたい。
しゃくり上げるごとに上下する肩に手を添えて、震える背中を支えてあげたかった。
蘭は間違っていない。
誰が、この高潔な少女を泣かせたのだ。
たった一人のつまらない妬み嫉みは、周囲を巻き込んで蘭を追い込んだ。
絶対に許すものか……!
恋い慕う女の子を傷つけた輩への怒りが募る。
唇を噛み締めたその時、蘭の伏せた顔と膝の隙間から声が漏れた。
「ごめんね」
蘭の唇から紡ぎ出される、謝罪の言葉。
「一哉ちゃんまで、巻き込んじゃった」
親友を悪く言われるだけでも堪えるのに、蘭を妬み煙たがる連中は一哉を引き合いにした陰口までも叩くようになった。
誰よりも慕わしい純真な少年を罵られるなど、蘭は自分のことを言われた以上に許せない。
連中は、あんな可愛げのない女のどこがいいんだと嘲笑った。
蘭と一緒にいたがるなど、勉強ばかりで頭がどうかしたのではないかと笑った。
蘭だけではなく、周りの生徒も理由を察している。
男子は一哉の容姿と進学校に通っているという事実にコンプレックスを抱くがゆえに陰口を叩くのだ。
女子は一哉が蘭ばかりを見ていて自分達に全く目もくれないことを面白く思わなかった。
彼はただ、自分に嘘がつけないだけなのに。
桜の下で会ったその日から、蘭だけを見つめている。
蘭以外の女の子には全く興味がない。
友達にはなれるが、それ以上の感情は抱けない。
一哉はアイドルでもないしプレイボーイでもない。
期待を持たせてぬか喜びさせる真似は、興味のない女の子達はおろか蘭までも傷つける。
一哉の前でこそ、本来の蘭でいられた。
制帽をかっさらい、垣根を飛び越えて花々の間を全力で走り抜けた十つの春の日。
風に逆らい春の香りを纏う空気を突き破るかの如く駆け抜けた。
蝶々か、または燕かカワセミか。
突き抜けるように空を舞う羽を生やした何かに生まれ変わった心持ちだった。
追い付いた一哉に制帽を取り返され、芝生にへたり込んで「あーっ! 最っ高に楽しい!」と大声で笑ったその日から、蘭は型に嵌まらず伸びやかに生きることを知ったような気がした。
一哉と出会わなければ、型に嵌まった生き方しかできなかったかもしれない。
共に過ごした幸せな時間が汚される。
それだけは、絶対に許せない。
「一哉ちゃんだけは、巻き込みたくない」
あるお節介焼きが、しれっとした顔で蘭に告げた。
蘭と仲良くするから一哉まで悪く言われる羽目になると男子が話していた、と。
嘘だと信じたい蘭に構わず、お節介焼きは続けた。
離れた方が彼のためじゃない、と。
膝に顔を埋めたまま、蘭は言った。
「一哉ちゃん、私から離れた方がいい」
そう告げると一哉は「絶対やだ」と言いきる。鬼気迫る表情で、大きな目を見開いて蘭に迫った。
「なんでそんなやつに従うの!? 俺は何言われても構わないよ! その程度のやつらなんか怖くねえよ!」
怒りを含んだ口調だった。
「誰が余計なこと言ったんだよ。まさか、あの……」
怪人クラッシャーだろと一哉が問い詰めたので蘭は頷く。
余計なお節介焼きの怪人クラッシャー=吉田は再び幸せな二人を引き裂こうと奔走する。
「あいつか……!」
悔しそうな顔で呻くように言い募ると、一哉は俯いた。
「探し回って、やっと会えたのに……」
脳裏をかすめた、薄桜色に佇む高貴な青。
幾年も前のことなのに、色鮮やかに甦る桜の下での刹那の邂逅。
一目で恋を覚え、探し回った末にやっと会えたプルシアンブルーの少女。
恋人になれなくてもいい。友達のままでいいから側にいたい。
蘭を支えたい。
蘭を支えるためならば、騎士にでも王子にでも、場合によっては悪にでもなる。
顔を伏せたままの一哉の瞳に力が宿る。
初めて会った時の蘭と同じ、鋼の如し頑とした力強さが大きな瞳に宿る。
「誰に何を言われようと、俺は意地でも俺のやりたいようにやる」
蘭は顔を上げた。
一哉は嘘をつくことが下手な少年である。
取り繕うための出任せを述べても表情と動作の不自然さで嘘がバレてしまうので、今となっては正直に生きるほかないのだ。
幸か不幸か、それらの経験は彼の素直な正直者という人格を作り上げた。
涙でぼやけた視界は次第に鮮明さを取り戻す。
愛しい少年の瞳が力強く語る。
――俺は、絶対に蘭の傍を離れない――
片膝をつく姿は女王に忠誠を誓う騎士にも見えた。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 2
◇決定打◇
帰宅するなり母親の星が深刻な顔でどこかへ電話をかけていた。
通話が終わり、戻した受話器に視線を向けたまま星が問いかける。
「あんた、明日の野球の応援に行くのよね?」
中体連の期間だった。
運動部は軒並み授業を抜ける。留美はテニス部、力丸は卓球部、ミヨシは柔道部だ。
蘭とエリだけが学校に残らざるを得ない。
いつだか、蘭を気づかって声をかけてきた白沢も剣道部の試合で学校にいない。
守りが手薄ではいじめが熾烈になるのは十二分にあり得るので、蘭は普段以上に周りを警戒していた。エリに危害を加える輩が出やしないかと。
教師陣にも中体連の期間はいじめの悪化が懸念されるからと吉田や取り巻きの生徒をマークするよう、必死に頭を下げて頼み込んだ。
その甲斐あってか、エリに対するいじめらしいいじめは起きなかった。
陰口は相変わらずだが。
小説で美女が怒りに染まる様子を夜叉に例える文章を見かけたことがあるが、蘭と対面する星は今、まさに夜叉の形相を綺麗な顔に刻んでいた。
低く小さな声で星は重々しく告げる。
「嘘の電話がかかってきたのよ」
星が蘭に問いかけたとおり、吹奏楽部は明日野球部の応援に出向くことになっている。
事前に学校に集合すると知らされていたが、蘭の帰宅前にかかってきた電話では「待ち合わせ時間が30分遅くなった」という内容だった。
連日、蘭からエリに対するいじめを聞いていた星だ。
更には中学校に入学したばかりのみちるからも蘭が陰口を叩かれていると知らされていた(蘭が嫌がると知っていたので、いない隙を見て報告していたらしい)ので不審に思うのは当然である。
学校に電話をかけ、吹奏楽部顧問に問い合わせたところ「待ち合わせ時間の変更はない」と驚いた声で返ってきた。
星は吹奏楽部の連絡網を片手にエリの自宅に電話をかけて同じ電話がかかってこなかったかを確かめていたのだ。
そこまでして、私を除け者にしたかったのか。
蘭が玄関から動かないまま立ち尽くす中で、再び電話がかかってきた。
星が苛立った様子で受話器を手に取りながらも冷静に応対する。
「蘭、千晴……さんって子から」
訝しがりつつ蘭は「お電話代わりました。蘭だけど何かあったの?」と返すなり、受話器からはひどく焦った声が聞こえた。
◇◇◇
エリの自宅を教えて欲しい。
待ち合わせ場所の交差点で蘭と鉢合わせるなり、焦った声で千晴は願い出た。
小学校入学以来何度か同じクラスになったことのある千晴だが、青ざめた顔も冷や汗を垂らす顔も初めて見た。
「千晴ちゃん! どうしたの?」
「蘭ちゃん。ごめん!」
嘘の電話をかけたのは自分だと、千晴は白状した。
蘭とエリを陥れる電話をかけようと提案をしたのは言うまでもなく吉田であった。
提案といっても「嘘の連絡を入れて本当に時間に遅れたら面白くない?」と軽い気持ちで口にしただけのようだが「やろうやろう!」と嬉々として乗ったのがエリと同じパートの新入生と斎藤だった。
二人以外の取り巻きの反応は様々だったという。
一人の取り巻きは乗り気だった。二年生の女子では蘭に次いで成績が良いと噂される部員だ。彼女は冷静なようで仲間内では羽目を外すところがある。そして興味のない者と嫌いな者には冷淡な態度を取った。
その部員が、蘭がいるおかげでいつも自分が二番手になると腹の底で煙たがっていることを蘭も察している。
一方で「バレたらまずいことになる」と二の足を踏んでいる取り巻きも存在したと千晴は語る。
乗り気だった部員は誰が電話をかけるかで盛り上がり、聞き役に徹していた千晴に「よくエリに毒づいているから」と嫌がらせ電話をかける役を押し付けた。
千晴は千晴で、吉田が内心で自分を疎んでいることに気付いている。
武田を中心としたお気に入りの男子達や、一緒にいると格が上がるからと積極的に友達面して接触を図るスクールカースト上位者の女子に「千晴ちゃん、強いから逆らえない」と弱音を吐くように愚痴をこぼしていたのを何度か目にしたことがあった。
確かに、虫の居所が悪くて冷たい口調で接したこと、話したい気になれなかったり話題についていけなくなって吉田を無視したことはあったかもしれない。
第一、旬のアイドルの話ばかりをする吉田とは話が合わなかった。
帰り道などで聞き役に徹するも千晴は芸能界にはイマイチ興味が抱けないだけに、アイドルグループの話を振られても誰が誰かわからない。
さも旬のアイドルの情報は知っていて当たり前とばかりに繰り広げられるやりとりが苦痛で仕方なくなり、何も言わずに早足で去る時もあった。
誠実さのない行動は反感を買われても仕方はないと千晴も理解しているが、興味がないと言えば吉田のことだから「え~、そんなことも知らないの~? 常識なのにぃ?」と嘲られるのが目に見える。
嘲られるのも不愉快だが、それ以上に吉田が人を嘲る顔が大嫌いで見たくもないので逃げ出すしかなかった。
◇◇◇
「いざとなれば実行役の千晴ちゃんだけを悪人にする魂胆か」
汚いやり方だと蘭は憤る。
「エリちゃんの家に行かなきゃ……。謝りたいんだ。電話だけじゃないよ。蘭ちゃんも知ってるじゃん」
蘭がいじめの現場に乗り込むと、だいたいは千晴も吉田と一緒にいる。
そして、吉田よりも辛辣な言葉をとめどなくぶつけてはエリを泣かせていた。
「エリちゃんも自分のどんくささで悩んでいるのは分かってたよ。でも、能天気だの親に甘やかされているだのありもしないことを決めつけて憂さ晴らししてたんだ」
してたね、と蘭はやや強い口調で返した。
「あれだけみーちゃんを煙たがっているくせに一緒になっていじめの実行役に成り下がって、私は心底ガッカリしたけど」
本当に見損なったよ。蘭の言葉が容赦なく千晴の心を抉るように突き刺さる。
「昔は、損得勘定もなく優しい態度を取れるエリちゃんが好きだったのにさ……だんだん妬ましくなってきたんだよ」
例えば、エリは同級生達が美術や技術・家庭の授業で作った造形物にケチをつけることを一切しなかった。
必ずといって良いほど作品の魅力を見つけては絵柄がかわいい、色使いが綺麗、デザインがかっこいいと褒めていた。
自分はどうだ。
粗探しをしては手近にいる同級生に「作りが甘くない?」「色が気持ち悪くない?」「小学生の落書きみたいな絵で恥ずかしいと思わない?」と聞き出して同意されれば嬉しくなる。
小学生の頃はエリと同じように、他人の作品を心から褒めることができたのに。
臆病者ながらも上級生から林を庇い立てた姿や体調を崩した者を放っておけず気づかう姿を目の当たりにする毎に、千晴は自分の狭量さを当て付けられてるような気がして耐え難い気持ちにさせられた。
「どうせ、親が厳しいからのんびりした子にイライラするようになって憂さ晴らししてただけだよね。甘ったれなのは千晴ちゃんだよ」
蘭の言うとおりだとうなだれる千晴は、蘭の後ろをついて行った。
◇◇◇
エリは千晴を見て一瞬だけ嫌そうに顔をしかめた。
反射的に出たとわかるしかめっ面。
千晴は如何に自分が酷い仕打ちを与えてきたかを突き付けられた気がして顔を上げられない。
以前にもしかめっ面を向けられた悔しさから「今、嫌な顔しただろ!」と恫喝まがいの態度でなじったことがある。
蘭がオーケストラの練習に出向いてその場にいなかった、合奏の場で。
あの時は、なぜ悔しかったのだろう。
嫌がられて当然の仕打ちを与えたにもかかわらずだ。
誰に対しても穏やかに、頼りなさそうな顔にほのかな微笑みをたたえて接するエリがあからさまな嫌悪感を露にしたことにショックを受けたからだろうか。
我ながら身勝手だと千晴は悔やむ。
恫喝の後、髪を掴んだり横っ面に筆箱を叩きつけた時もある。
なぜ、何も悪いことをしていないエリを相手に暴走してしまったのだろう。
今もエリの怯えた顔を思い出し、気が狂いそうな思いだ。
校内で顔を合わせた時の、まるで毛虫を見た時のようにエリの目の色と顔色がサッと変える様が癪に障った。
逆恨みとは自覚しながらも「何見てるんだよ!
気持ち悪い!」と口汚く的外れな因縁をつけては、蘭はもちろんだが留美と二階堂ミヨシからもいちいち注目しているのは千晴の方だろうと厳しい態度で返された。
力丸薫子からは軽蔑の眼差しで睨まれながら舌打ちをされた。千晴の目から見てもかわいい顔をしているはずの力丸だが、その時ばかりは背筋が凍りつくほどの険のある冷たい表情だった。
悔し紛れに力丸の小さな身体に体当たりをすれば、舌打ちの後に「人間のクズ」とボソリと言われた。
力丸薫子の言うとおりだ。
私は、人間のクズ。
蘭に肘で小突かれて促され、千晴はボソボソと告げる。
「電話をかけたの、私なんだ」
歌う時も、面前で発表をする時も、日直の司会進行も、千晴はいつでもボソボソ声だった。
エリをいじめて罵詈雑言を吐き散らす時以外は。
「実際には押し付けられたようなものなんだけど断らなかったのは事実だし……さすがに酷すぎると思い直して謝りたかったんだ。今までも、酷いことばかりしてきてごめんね」
許してくれなくてもいいからと千晴は土間にひれ伏し始めたので、蘭とエリは慌てて土下座をやめるよう求めた。
それでも土下座の態勢のまま動かないので二人がかりで腕を持ち引っ張り上げるが、太り気味の千晴を起こすには苦戦した。
「私さ、前は千晴ちゃんのこと好きだったよ。大会前にもメモ紙に面白いイラストを描いて笑わせてくれたじゃん。大会終わった頃から冷たくなって、戸惑ったんだよね……」
ようやく土下座をやめることにした千晴を前に、千晴の毒のきいたトークも少女漫画のような美麗な絵柄も好きだったのに……と怒り混じりの口調でエリは述べた。
「この際だから、もう言いたいこと言うね? どもっても笑わないで。私は千晴ちゃんにもみーちゃんにも何も悪いことしていないのに、ノロマなりに足掻きながら周りに追いつこうと頑張っていたのに……暴言吐かれたり髪を引っ張られたり酷いことばかりされたら、認めていたものも認めたくなくなる」
エリは玄関の段差に腰掛けた。
当たりどころのない怒りによるストレスで暴飲暴食に走ったのか、千晴ほどではないが一年生の頃よりエリは太った。
太ったとはいえポッチャリに留まっているものの太くなった二の腕と脚を気にしているのか、梅雨の晴れ間で蒸し暑いにもかかわらずエリは七分袖のカーディガンを羽織り、足首まで隠れるロングスカートを履いている。
「千晴ちゃんの絵、すごく綺麗だから好きだったけど今は嫌い。見習いたいほど羨まかったはずなのに、もう、千晴ちゃんの絵を見るのも辛いんだよ……。ただでさえ成績も楽器の上手い下手でも負けてるのに、なんでこんな性格の汚い子が綺麗な絵を描けるのって、悔しくなるんだ」
蘭はエリが泣くのではと気がかりではあったものの、今のところ涙は見せていない。
怒りを露にしてはいる。
肩が震えているのも、今まで溜まっていた怒りによるものだ
「両親が先生で躾が厳しいのは噂で聞いてたけど、そんなことと私は関係ない」
廊下の向こう側の台所から、エリの母親がチラチラと様子を窺う姿が見えた。
優しいには違いないが過保護すぎて、それでいて助けが欲しい時にはニコニコ笑いながら素通りするとエリが愚痴をこぼしていたのを思い出した。
今がそうだ。千晴に何か言うべきなのに、エリの肩を支えるべきなのに母親は傍観している。
エリの意志薄弱さは、この母親に原因があると蘭は確信する。
「おばさん!」
蘭は声をかけた。エリの母親は能天気に「はいはい~」と小走りで向かう。
「どうして、エリちゃんの肩を支えないのですか。エリちゃん、いじめられていることを親に話しても真剣に取り合ってくれなかったって泣いていたんです。一番支えて欲しいのにって。千晴さんだって……先ほどに嘘の電話をかけたことと今までいじめてきたことを謝りに来ているんです」
もういい、とエリが力なく蘭を止める。
「お母さんに言ったって無駄だよ。いつも周りを気にして、私に我慢ばかり押し付けるの」
お母さんは行ってて。
そのセリフにさすがのエリの母親もショックを受けたのかもしれない。
エリの母親は「力になれなくてごめんなさいね……」と、ふらふらとした足取りで引き返していった。
「わからないんだよ。千晴ちゃんは時々罪悪感を抱いていること仄めかしてきて、もう嫌なことしないだろうなと安心してるとまた繰り返す」
間を置いて、エリはうなだれた顔で告げる。
「今回だって、信用できないんだ……。千晴ちゃんも、お母さんも。本当は誰も恨みたくないし千晴ちゃんとはまた仲良くなりたかった。許したいけど、また同じことの繰り返しだと思うと、今は許す気になれない」
ごめんね、と言ったっきりエリは無言になる。
蘭は明日は敢えて待ち合わせより早く行くつもりだと告げた後、無表情のエリにどうするかを問いかけた。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 3
◇ジャンヌ・ダルクは白旗を上げる◇
野球部の応援には参加した。
当初の待ち合わせ時間より敢えて早く来た蘭とエリを見て取り巻きは驚き、取り巻きより少し遅れて母親の送迎で来た吉田は愕然とした顔だった。
昨日にエリの自宅から出た後に、千晴には待ち合わせにギリギリ間に合うタイミングで来た方が良いと蘭は提案した。
蘭とエリが時間どおりに来ていることは、千晴が取り巻き達を裏切ったも同然である。
吉田のことだから表立って千晴を非難しないかもしれないが「なんで蘭ちゃんとエリちゃんが来てるの?」「電話しなかったの?」と詰め寄る取り巻きはいるだろう。
蘭は生意気を承知で……と強気な表情で運転席の窓ガラスをノックする。
運転席に座ったままの吉田の母親に昨日の電話の件を告げ、顧問にも報告済みだ、顧問と嫌がらせ電話に関わった部員の保護者を交えて話し合いをしたいと慇懃無礼な態度と挑戦的な眼差しで真っ正面から睨みつけた。
慇懃無礼なのは事実だ。蘭は吉田の母親までも軽蔑しているのだから。
どのような教育をすれば、ここまで意地の悪い娘に育つのだと。
地元の有力者でもヤクザでもない、ただの一般人なのだから媚びへつらう必要はない。
長幼の序を重んじるはずの蘭がそのような考えに至らしめられるほど、この母子へ抱く憎しみは強すぎるものだった。
吉田の母親は俗にいうタヌキ顔を真っ青にさせている。
自分の娘が学校で何をしていたかを知らないようだった。
◇◇◇
緊急の保護者を交えた話し合いの末、蘭とエリは退部を決めた。
顧問は必死で引き留めたが、蘭は頑なに退部すると言い張る。
激昂した星は二度も娘を同じ手口で追い込んだと吉田とその母親に詰め寄り、エリの母親はただ泣くばかりだ。
エリは無言で蘭の傍にいた。何のアクションもなく泣いているだけの母親を諦めているように見える。
千晴は、よく似た体型の母親の隣にいる。高校教師である千晴の母親は保護者会でもしばしば部員を甘やかすなと厳しい意見を寄せてくるらしい。
少し前の時間帯になる。星は来客用の昇降口にて千晴の母親と出くわすと穏やかに訴え出た。
千晴を認めて向き合ってほしいと。
「千晴さんは確かにエリさんに対してひどいいじめを行っていました。ですが、昨日にエリさんの自宅まで出向いて心から詫びていたと娘から聞いています。土間に額をすりつけてまで詫びていたそうですよ。
根は優しい娘さんです。それなのに悪辣ないじめを行うようになってしまったのは、親御さんが厳しすぎるという噂が生徒達の間で流れているのですよ。
千晴さんは学業優秀な上にピアノや書道、更には絵の才能にも恵まれて……才女と言わずして何と言いましょう。立派な娘さんですよ。
どうか、千晴さんが元の優しさを取り戻すためにも向き合ってくださいませんか」
普段は冷淡なまでに手厳しい千晴の母親も、星からの訴えには何も言えなかった。
「私は音澤さんにもエリさんにも吹奏楽部にいて欲しいの。間違っているのはあなた方に嫌がらせを繰り返した部員達よ」
顧問は気品ある風情ながらも厳しさを纏う中年の女性だった。
ヒールの音を小気味よく響かせて歩く姿が物語るとおり顧問はいささかクールで時としては近寄り難くもあるが、一方で二人の幼い子供を抱える優しい母親でもあった。
どんな部員でも長所を見つけ、悩みがあれば親身になって耳を傾け、問題を起こした部員にも真剣に指導しつつ向き合う姿勢から、愛情深い性格であることは確かであろう。
蘭のフルートの技術を買い、エリに対しては頼りないなりに一生懸命に練習を頑張っているところを認めている。
何よりも、誰かが辛そうな様子を垣間見せれば大丈夫かと気づかう姿勢に感心していた。
「再三に渡って厳しく指導したのに自分は正しいと正当化して、嫌がらせをやめないのだから」
顧問自らが加害者サイドの部員に罰則を与えるのも厭わない所存だ、そして私の監督不行き届きであるから自身も上からの罰則を受けると居合わせた保護者に向かって毅然と告げる。
星が「先生が罰を受ける必要はない」と声を上げ、保護者達からも同意の声が上がる。
間違いなく、顧問はいじめの加害者達に対して懲りずに指導を繰り返した。
顧問自らの言葉どおり、厳しい態度だった。
蘭も指導の現場を遠巻きに見かけたことがある。
吹奏楽は皆で一つの音楽を作るもの。傷つけ合っては良いサウンドが生まれないのだ、と顧問は指導の毎に聞かせた。
馬鹿ではないはずなのに、この生徒達には心からの訴えが全く伝わらない……と、顧問もまた苦悩の日々を強いられていた。
蘭は「上野先生」と声をかける。
「仮に吉田さん達が退部させられれば、私達のせいで部活を追い出されたと逆恨みをされるのは目に見えています。それから……」
顧問から、吉田を筆頭とした加害者の部員達に顔を向けてキッパリと言い放った。
「人を蹴落として平気な顔をしていられる人が取り仕切る部活など、私から願い下げです」
顧問に「今までありがとうございました」と深々と一礼した後、蘭は再び加害者の部員を振り返って声を張り上げた。
「お望みどおりに事が進んでよかったね! これで気が済んだでしょう!?」
大きく息をつくと、蘭はつかつかと進み出て加害者の部員達がいる場所から一番近いテーブルに退部届けを文字通り叩きつける。
バァン! と天板から放たれる残響の中で蘭は凄んだ。
「もう二度と、私にもエリちゃんにも関わらないでね?」
◇◇◇
ドアの重い音が響く。足音が聞こえる。
敗者達を笑いに来たのか?
蘭は眉根を寄せる。エリの肩がビクッと動く。
いざとなれば傷ついた親友を守るために戦おうと蘭は身構える。
二人は音楽準備室に置いていた教則本やメトロノームを回収に来たのだ。
私は背が高いから、盾になろう。
蘭がエリを庇うように彼女の肩を抱いて背後に回ったその時に準備室の引き戸が開く。
「蘭さん、エリちゃん……!」
かわいらしいソプラノの声に二人は安堵した。蘭は横目で準備室の出入口を見やると視界の片隅に聖良が入り込んだ。
相変わらず、この優しい女の子は明るい青のセーラー服が似合っている。
「部活……辞めるの?」
ゆっくりと聖良に向かって身体ごと振り返ると、聖良のこぼれ落ちそうな大きな目が潤んでいた。
「人を蹴落として平気な顔していられるやつが取り仕切る部活なんて、こっちから願い下げ」
「ごめん。力になれなくて。でも私は……」
聖良は話し合いでも意見した。いつだか、吉田が口にした余計な一言で蘭を傷つけた時も言い過ぎだとたしなめた。
エリを嘲る後輩にも懲りずに指導した。
しかし、蘭のように自らが矢面に立つ勇気がなかったと聖良は己の非力さを悔やむ。
これからも蘭とエリの味方でい続ける、と告げる前に「セイラさんはどうするの? これから」と蘭に問いかけられた。
聖良は何も答えられない。
「今までありがとう。セイラさんが陰ながらいろいろと気づかってくれたのはすごく嬉しかったし励みになった。でも、私達もう限界なの。居場所のない部活に無理して居座る必要なんかない。行こ、エリちゃん」
待って、とエリが制止する。ちょこちょことした足取りで蘭より前に出た。
「セイちゃん、私からもありがとう。根性で三年間辞めないで頑張ろうとしたけど、あんなことされて限界来ちゃった。私は美術部に入ることにしたよ」
小学校卒業を控えた時期に、エリは得意分野を生かして美術部に入るか華のある雰囲気に憧れていた吹奏楽部に入るかで悩んでいたことがある。
地味なエリは、華やかで美しいものに憧れた。
新入生歓迎会にて吹奏楽部の体育館内の空気を揺さぶらんばかりに響き渡る演奏と、凛然とした姿で楽器を奏でる先輩達を目の当たりにした瞬間、彼女は吹奏楽部への入部を決めた。
入部届けを手に地味な私が吹奏楽部に入ったら笑われるかなと蘭に問いかけた時、蘭は地味も派手も関係ないと返した後に「一緒にやろうよ」と嬉しそうに笑った。
退部を決めた翌日に、かつて美術部か吹奏楽部かで迷っていた件を覚えていた美術部の同級生が美術部に入らないかと勧めたのだ。
ぺこりと頭を下げて、態勢を戻したエリは一応は笑っている。
エリを連れ立ち、蘭は準備室を後にする。
◇◇◇
2000年度の泉清中学校吹奏楽部は、シード校として県大会出場は叶ったものの東北大会出場を果たすことはできなかった。
顧問次第で大会の成績が左右されがちな公立中学校の吹奏楽部だが、顧問が代わっていないにもかかわらず突然の成績の下降に当時の県大会の会場内は異様なざわつきを見せたという。
あくまでも市内と近隣の市町村に住む吹奏楽に縁のある中学生の間だけではあるが、嘘と真実の入り交じった噂がささやかれるようになった。
泉清中学校吹奏楽部ではいじめが起きたらしい。
一部の生徒が部を私物化していたらしい。
部を私物化した生徒が嫌いな生徒をいじめて追い出したらしい。
追い出された生徒のうち一人は全国大会で賞を取ったほどの腕前らしい。
上手い生徒を追い出したから、演奏のレベルが下がった。
いじめが起きたせいでチームワークが乱れた。
そして「堕ちた名門」と揶揄された。
聖良は吹奏楽部を退部することにした。
表向きは学生オーケストラに転向すると理由付けたが、吉田の暴走に堪えられなかったことが最もたる理由だ。
県大会で銅賞という成績に焦った吉田は、一年生の時に満場一致で反対された独自ルールを再び強制したのだ。
更には返事の練習を加えた。帰宅前の反省会が終わると昇降口前に集められ、雨天時は音楽室に残される。
横並びになった部員が右端から「一人ずつその場で思い付いた短い質問文を大声で読み上げ、返事をする」を全員が終わるまで続ける。
聖良を中心とした一部の二年生からは「話し合いの結果を忘れたの?」と反対されたが「蘭のような場を乱す黒い羊がいないから」と強行した。
蘭がいなければ、あの話し合いで誰も反対意見を口にしなかっただろう。
吉田に怖じ気付き蘭を蔑ろにしたことで後悔に苛まれる部員が出たが、後の祭りだ。
ジャンヌ・ダルクがいなくなった吹奏楽部は、独裁政治がまかり通る無法地帯へと成り下がる。
「新入部員にオーボエの指導をまともにできる生徒が他にいないし、あなたには最後まで吹奏楽部に居て欲しかったのだけど……わかりました」
顧問は残念そうだったが退部届けを受け入れるほかない。
有望視していた蘭と人柄の優しさを買っていたエリが吹奏楽部を去っただけでも痛手である。
その上、若干名しかいないオーボエ奏者で周りへの気づかいを欠かさず「現二年生の吹奏楽部員では一番まとも」と生徒の間で評されている聖良まで去ってゆく。
蘭のように理不尽なことがあれば真っ向から切り込む勇気はないものの誠実な人柄から部員達に信頼され、まとめ役と同時に部員の暴走にに歯止めをかけるストッパー役としてふさわしいと顧問は認めていた。
「セイラさん。本当は別の理由があるんじゃないの?」
話してみて、と顧問に退部の理由を聞かれた聖良が告げたのはたったの一文。
「私は彼女の暴走を止められません」
――私は、ジャンヌ・ダルクになれない――
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 4
◇◇◇
これが中学校生活での最後の体育の授業かもしれない。
女子は体育館で各自好きな競技を行ってよいことになった。全クラスの女子が集まっているので体育館内はなかなか騒がしい。
「あー、また落としちゃった。ごめん」
蘭とバドミントンを楽しんでいたエリはシャトルを拾い上げる。手を負傷する心配が少なそうだからとエリがバドミントンをやると言い出し、それならばと蘭も乗ったのだ。
「今日ぐらいは勝ち負けもないから気楽にしていいんじゃない?」
「だから。自由にやってるんだし」と言う留美はバレーボールの球を壁打ちしていた。壁打ちに飽きればバスケットボールを手にロングシュートができるか試し始めた。
力丸はというとミヨシと卓球の球を打ち合っている。
楽しげなようでいて、蘭達が落ち着かないのは吉田が近くにいるからだ。
退部届けを叩きつけた日に二度と関わるなと言い放ったにもかかわらず、吉田も斎藤も粗探しをするためだけに蘭達の近くにやって来る。
関わるなと言えば「蘭ちゃんが冷たい」と被害者を装い、お気に入りの男子にすがりつく。
もう、わけわからない。
関わりたくないのに、つきまとう。
案の定、吉田はエリがシャトルを取り損ねる毎に嘲るような笑みを見せ、馬鹿にするような口調で揚げ足取りを始めた。
中三の今では高校受験を意識してか少なくなったが、中二の夏頃の吉田は吹奏楽部の件に限らず人間関係を引っ掻き回す内容の問題行動が目立っていた。
そのうち、教師陣を激しく失望させたのが罰ゲームでの告白。
仲間内で『中間テストの成績が一番低い者がターゲットに告白する』という内容で、ターゲットの野球部の男子への仕打ちがタチ悪いものであった。
野球部の男子が吉田からの告白にOKを出したことを、吉田と罰ゲームに参加した生徒は「ここまでチョロいとは思わなかった」と執拗に嘲笑った。
別にその男子に恨みがあるわけではない。
たまたま目についたので、軽い気持ちでターゲットに決めたという。
罰ゲーム参加者のみがいる場で野球部の男子の坊主頭を青カビみたいだと揶揄した話や、陰でカビと呼んでいた話は誰かの口から他の生徒に伝わり、ついには学年主任の耳に届く。
その日の放課後には廊下に集められ学年集会にまで発展した。
今もエリを小馬鹿にした態度を取る吉田を見て「まだやってる……」と眉をひそめる者が多数だが、蘭が二度も孤立されエリが吹奏楽部を去った実例を知れば吉田とその取り巻きに強く出る生徒はごく僅かだ。
「いい加減にして。私達に関わるなと何度も言ってるのにわざわざ乗り込んできたり近くをウロウロしたり、何がしたいわけ?」
「何怒ってんの? つーか、今の蘭ちゃんこそ自分を棚に上げてわざわざ寄ってきてるじゃん」
アンバランスに歪めた顔の吉田の傍らで「そうだよそうだよ」と斎藤が囃し立てた。
「蘭ちゃんって、自分を棚に上げて人に厳しい自己中なんだね」
もう、限界。
大股で踏み込む蘭を留美が腕を掴んで引き留める。続いてエリと力丸が。前からはミヨシが押さえ込む。
学年主任で女子保健体育担当の松井が「何やっているんだ!」と言いながら駆け寄るも、蘭と吉田の間へ割って入る前に「ダァン!!」と激しい音が響き、空気が揺らぐ。
爆音というべき音に驚いた生徒達は動きを止めて静まり返る。
沈黙の中を、吉田の足元をバスケットボールが転がった。
爆音の正体は、バスケットボールが壁に打ちつけられた音だった。
「ほんと、いい加減にしろで吉田ぁ!」
ドスのきいた声で叫ぶは骨格のガッシリとした大柄な女生徒、久間木春奈だった。
「あんたとだけは関わりたくなかったけど、もう限界だ。あんたの人をバカにした態度は毎回毎回頭に来るわ! 一部の男子と吹奏楽部の先輩から気に入られてるからって天狗になって周り傷つけて何様だよ!」
大した美人でもないくせに魔性の女ぶりやがってよぉ、と春奈は怒鳴る。
久間木春奈は如何なる時も冷静な生徒だったはずだ。
ヒグマを思わせる佇まいは威圧感があるものの、気のいい姉御肌と頼りにされている。
そんな春奈が冷静さを欠いて怒鳴り散らすほど、彼女は吉田を蛇蝎の如く嫌っていた。
「あんたが蘭さんとエリちゃんを追い出しておいて、県大会銅賞になったのは蘭さんみたいな上手い生徒が辞めたから? 他校生からいろいろ言われるようになったのは蘭さんとエリちゃんが辞めたから? 辞めさせるつもりはなかった?
二人が辞めたのも、うちの学校の吹奏楽部が他所から悪く言われるのも全部お前が悪いんだろ!」
春奈は吉田への恨み言を言い連ね、極めつけの最後の一文には吉田のみならず蘭の表情までもが凍りつく。
春奈は恨み言の最後にこう叫んだ。
「そんなだから飛鳥のやつに怒られたんだろーが!」
飛鳥のやつに怒られた。
蘭の学年に、アスカという名前の生徒はいない。
愛しい少年の面影と言葉が、蘭の脳裏を駆け巡る。
――俺はその程度のちっさいやつなんか怖くねえよ――
力強い頼もしい言葉は、これまでに二度聞いたことがある。
澄んだ瞳の奥に宿る、怒りの焔と共に。
当事者の名前を挙げて「後で話を聞くから放課後に職員室さ来い」と松井は言うと、鼻息の荒い春奈を背中を押して壁際で休むよう促した。
言われたまま壁に背をつけて体育座りで休む春奈。
白沢と由香理と絢が大丈夫かと駆け寄り、蘭も早足で春奈のいる方へ進み出た。
「春奈さん」
「あ……蘭さん?」
蘭は春奈の真ん前で片膝をついて問う。
同じ高校を受験する春奈とは夏休みに行われた体験入学で鉢合わせて以来、高校受験を口実に少しだけ会話を交わすようになった。
蘭と対面する春奈の表情に「照れ」が垣間見えるのは、気のせいか。
「どういうこと? アスカって、一哉ちゃんのことだよね?」
縮れた癖っ毛をかき上げて「やっちまった」と唸る春奈。
「そうだよ。……飛鳥のやつから口止めされたのになぁ」
「一哉ちゃんが怒ったって、何があったの?
シロちゃん達は知ってるの?」
白沢と由香理と絢は困った表情で互いの顔を見合わせる。この三人も知っているらしい。
まずは白沢が口を開いた。
「ハルちゃん、この際だから蘭ちゃんに話すべ」
由香理と絢も観念した顔で続けた。
「だから。たぶん飛鳥君も事情を話せば許してくれるべ」
「今までバレなかったのが奇跡なぐらいだし」
「それじゃ……長くなるから、松井先生の話終わってからでいいかい?」
◇◇◇
「中学校生活最後の体育だぞ。有終の美を飾るはずがこんな最悪な結果になって先生は情けないったらありゃしない」
職員室に呼び出されたのは吉田。
ズル賢い斎藤は蘭が詰め寄った時に人垣に紛れるように逃げたらしく職員室にはいない。
被害者サイドとして蘭とエリが、そして春奈がいた。
「吉田魅里、お前の言動はスポーツマンシップから外れすぎだ。できない人をバカにしてばかりいて。アンケート調査と生徒会への意見箱にも書いた生徒が何人かいてな、吹奏楽部でもそうだったようだな? 大会では他校生をバカにしていたらしいな。相手方の学校から苦情が来ていたんだ。うちの学校の夏服は目立つからな、すぐに泉清の生徒だと特定されやすいんだ」
ただでさえシアンブルーの襟のセーラー服は一際目を引く。
吹奏楽コンクール県北地区大会の会場では白襟のセーラー服を多く見かける中で、泉清中学校のセーラー服は相当に目立っていた。
一年生の頃、顧問からも周りを不愉快にさせないように、言動には気をつけるようにと釘を打たれたものだ。
東北大会常連校としての品位を傷つけてはならない、という真意が含まれていた。
「だいぶ前から音澤を目の敵にしている噂は聞いていたがな、お前は一体何をしたいんだ?」
松井はスポーツウェアのまま腰掛けている。式典を除いてはスポーツ用品店にあるようなスポーツウェアを着て過ごしているのだ。
この日はトリコロールカラーのトップスが洒落ているウェアで、お気に入りなのかよく着ている。
肝っ玉母さんのステレオタイプと呼ぶべき小太りで貫禄のある容姿は、一見して体育教師で女子バスケ部の顧問であることが想像がつきにくい。
松井からの質問を振られても吉田は黙りこくるが、松井は答えを急くことはしない。
代わりに次の質問を投げかけた。
「吹奏楽部で自分の提案をことごとく反対されたことが面白くなかったのか?」
「……いいえ」
蘭ちゃんは正しかったです、と吉田はうなだれて述べる。
「じゃあ何だ。嫌いなのか、音澤のことが?」
顔を横に振った。
「嫌いじゃないです……」
「それなら、どうしてありもしない噂を流してよぉ、孤立させて周りに悪者扱いさせるように仕向けたんだ? 確かに音澤は強いが、こんな嫌がらせを受ければ不登校になったっておかしくないぞ。よく卒業間近まで堪えてきた。
だがな、堂々としている風に見えるだろうけど、音澤もまだ15のガキだ。傷つかないわけないだろう」
松井は確かに憤っているが、まだ話し合いの序盤だ。冷静さが勝っていた。
「どう頑張っても、蘭ちゃんに勝てないから……」
松井の低い鼻がフンッと鳴る。軽蔑の感情の表れか。
「くだらない妬み嫉みか。そりゃあ音澤には敵わないわな。容姿も成績も、性格もな」
その発言は余計に敵対心を持たれるだろうと松井の無神経さに蘭は呆れる。
松井は時たま触れてはいけない事柄に触れたり、真意を確かめずに偏見で叱りつけるなど、無神経な言動で生徒からの反発を招くことがあった。
吉田はというとモゴモゴと口を動かして「そうじゃないです」と否定する。
「ぶりっ子しないで、ありのままで好きな男子と上手くいってて、友達を心から大事に思えるところが……」
羨ましくて憧れていたと告げた後に、吉田は弱々しく言い連ねる。
自分は元の性格が悪いから自然体で人と接することができない。
ぶりっ子という名の紛い物の魅力で自分を誤魔化してようやく友達を作ることができたし、男子からの関心を買えた。
自然体でいながら好きな人と相思相愛にまでこぎつけ、自分を犠牲にしてまで友人を大切にできる蘭の清さが羨ましかった。
自分は人の悪いところばかり目についてバカにしないと気が済まない。
そんな自分とは正反対に、蘭は正義感が強い。誰かがバカにされようものならば長所を挙げてフォローに入る。
蘭を見ていると自分の性格の悪さが際立つようで一緒にいて辛かった。
同じ理由で、誰に対しても優しく決して人を茶化したりしない大槻エリも妬むようになった。
元々は美人でかっこいい蘭も穏やかで優しいエリも好きだったと吉田は語るが、蘭は
「白々しい。全く信用できない。あんたの言葉は何もかもが嘘くさい」
と忌々しげに反論したので吉田はついに涙ぐんだ。
ふぇぇ……と少女漫画のヒロインがやりがちな泣き声を口に出す様ですら、蘭にもエリにも白々しい演技にしか見えない。
春奈が「泣き方まで嘘くさいな」とつぶやいた時には、吉田はこれ見よがしにしゃくり上げていた。
松井は強めの口調で泣くなと一喝し、コーヒーを一口すする。
「やった側がメソメソするなで。そうだね。あんたはぶりっ子で性格の悪さを誤魔化して、文化祭や三年生を送る会でハロプロのダンスの猿真似してやっと男子共から関心を買えたからな。それも天狗になった原因だろう?」
マグカップをコースターに置いて、更に松井は言った。
「先生も長年中学生達を見てきたからわかるけどな、男ってのは結局は正統派の美人よりも綺麗すぎない程度のかわいい子か、あんたみたいに雰囲気美人だけどよく見るとちょいブスだな~と思う子になびくんだよ。親しみやすい分だけ男の劣等感を刺激しないからな。だが、それ以上に綺麗すぎないかわいい女やちょいブスが男共から本命扱いされるのは、気負わない自然体の魅力があるからだよ」
言葉は悪いが核心を突いていたので、職員室にいる生徒はもちろんだがさほど切羽詰まっていない状況の教師ですら松井の話を盗み聞きしている。
「あくまでも、元々の性格が良い場合だ。当然、性格が悪けりゃチヤホヤしていた連中もいつかは去ってゆく。あんたは本当に性格が悪い。部活の後輩への面倒見が良いのは認めるが、ちょっとでも暗~い感じのする後輩には冷たかったよな? お気に入りに特別に親切にする人は確かに多いが、あんたはお気に入りとそうでない人への対応の差が極端すぎるんだ」
面倒見は良かっただろう。
吹奏楽関連で中学校入学前から吉田と関わりのあった一学年下の後輩達からは懐かれていた。
保護者からは「中学生が浮わついたことして……」と顰蹙を買ったが、文化祭の本番前に「指先を目立たせないと」と言っては後輩の爪にマニキュアを塗ってあげたり髪にラメの粉をかけてあげる姿は、まさしく世話焼きたがりのお姉さんだ。
吉田に懐いている後輩達もキャピキャピと騒ぎながらマニキュアを塗ってもらえて上機嫌だった。
一方で、見た目が野暮ったい後輩や雰囲気が暗い後輩をあからさまに冷遇するわけではなかったが、お気に入りの後輩と同じようにマニキュアを塗ることも髪にラメの粉をふりかけることもしない。
声をかけたり気づかう行動もない。
放任。吉田から彼女達への扱いはこの一言に尽きる。
放任された後輩は必然的に蘭とエリになびいた。
蘭とエリの退部後は、聖良が中心となり空気同然となった後輩を気づかう役割に回った。
聖良が吹奏楽部を去った後は聖良と仲良しの部員が受け継いだ。
昨年度と今年度の文化祭は、爪に色をつけた者と色のない者が混在した。
「なぜ気に入らないかというのも『冴えない人と一緒にいると自分の価値まで下がる気がするから』というくだらない理由だよな? そのくせ、劣等感を刺激する相手も嫌い? そりゃあ、友達付き合いに苦戦するわな。所詮な、紛い物の魅力なんざ自然体の魅力に勝てないんだ」
聞きたいんだが、と松井は質問を投げかける。
「友達を大事にできないってのは何だ。あんたも斎藤とか、いつもつるんでいる友達がいるだろう」
「別にあの人と好きで一緒にいるわけじゃないです……」
蘭は小学生の頃に聞いたことがある。
吉田は「新しい友達ができたら、前に仲良かった友達がどうでも良くなる」と話していたから吉田には気をつけろ、と。
更にはどうでも良くなった元友達から友達を奪い取るから気を付けて、と。
忠告してきたのは、橘織絵だった。
中学校に入学して以降の友達は斎藤と固定されている(ように見える)が、小学生時代は友達がコロコロ変わった。
学年が変わる節目で遊び仲間が変わるのはよくある話だが、吉田の場合は月単位、短いと週単位で変わった。
仲良くなったかと思えば、別の友達とつるんでいる。
そして、今までの関係はなかったことにしようとばかりに元の友達を冷淡に突き放すパターンである。
以前の友達が声をかけると冷たく横目で睨みつけて通りすぎる。その姿は感じの悪いものだった。
織絵が話していたように、元の友達から友達を奪い取っては爪弾きにして孤立する様子を笑い種にしたことも一度や二度ではない。
吉田魅里さえいなければ、平和だった。
その考えに至らしめられた者は、同級生でどれほど存在するだろう。
「たまたま幼稚園からの腐れ縁だから……あーちゃんも友達付き合いが長続きしないから、結局余り物同士で一緒にいる羽目になるだけ。蘭ちゃんやエリちゃんが羨ましかった。タイプが違うのに同じ友達と長く付き合えて……絆の固い友情に憧れとた」
「先生」
松井は「おっ」と軽く驚く。この話し合いの場で、蘭の背に隠れて聞き役に回っていたエリが初めて口を開いたのだ。
「もう、いいですよ。私も蘭ちゃんも何もしていないのにいじめられたのも、くだらないコンプレックスが理由だったんですね?」
言いづらそうな様子だが、松井は肯定するほかない。
エリはため息をついた。蘭が背に手を添える。
「このような時に話すのも恥ずかしいですが、私は中一の時、林君が好きでした」
「そんなの先生達はみんな知ってたでぇ。エリちゃんはわかりやすいからなぁ」
顔を赤くする様子が初々しくてねえ、と松井はからからと笑い声を立てた。
「蘭ちゃんが小学生の時もそうでしたが、私の時も林君との仲をこじれさせるように仕向けられました。なんで、あんなことしたの? みーちゃんは、林のことが好きだったの?」
涙と鼻水で汚れた顔のまま、吉田は動揺して否定した。そんなモヤシっ子は恋愛対象外だと。
「好きじゃないよ。でも、恋をしてキラキラしている人を見ていて、悔しかった」
「自分もキラキラしたかったのか?」
松井が問いかける。
こくり、と吉田が頷くとエリは聞こえよがしに大きなため息をついた。
「周りを見ても、ドキドキするような男子がいなかった」
何言っているんだよと春奈が毒づく。
「いつも男子とばかりつるんでるしタケとも仲良いだろーが。あいつ顔も頭も運動神経もいいだろ」
女子の中には引け目を感じるあまり、敢えて武田と距離を作る者すらいる。その事実を知っている春奈は「あんたは贅沢な方だ」と吉田に言う。
「男子の友達作るにも選り好みしてんだか知らないけど、男子で一番の秀才とか学年一のスポーツマンとも仲良いだろ」
「それでも友達止まりの感情しか持てなかったし、みんな他に好きな女子がいるっぽいし……」
どうしても、自分にとっても相手にとっても本命にはなれない。
だから、妬ましくなったのだ。
誰かのナンバーワンになれる者が。
「ふざけるのもいい加減にしてよ……」
下を向いたエリが、唸るように言った。
いつものかわいい声は、鬼に憑かれたかと疑いたくなるほどに低くドスがきいている。
震えた握り拳の爪が皮膚に食い込んでいるのが見て取れた。
「返してよ……貴重な青春時代を返してよ。私も蘭ちゃんもあんたのくっだらない嫉妬のために中学校生活ぶち壊されてどれだけ悔しかったかわかってんの」
「ごめ……」
言いかけた謝罪の言葉を遮るように、噛み付かんばかりにエリは叫ぶ。
「あんたのゴメンナサイは信用できない!!」
エリの優しさは生まれ持ったものだった。
嘘ではない、本心からのものだ。いじめを受けるまでは。
いつ如何なる時も、どんな人に対しても優しくしていないと、いつかはドス黒い感情に支配されてしまいそうだった。
エリはそうなることを危惧していた。
だから、どんなに辛くてもニコニコと笑顔でいることを努め、敵方にも優しく公平にと努めていた。
しかし、エリの頑張りは限界に達してしまった。
抑え込んでいた怒り、憎しみが今、暴発する。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 5
「一コ下の後輩に入学早々彼氏できた時も、あんたには全く関係ないのにその子が彼氏作ってムカつくとか調子に乗ってるって悪口言ってたもんね!? あの子だって何も悪いことしていないのに! ただの僻み根性こじらせてるだけじゃん! 調子に乗ってるのはあんただろ!」
吉田の胸ぐらに掴みかかったエリを教師達がなんとか引きはがし、若い女教師が気づかう言葉をかけながら怒りの収まらないエリの肩を支えて保健室へと連れ出した。
まさか大槻があんな行動に出るとはなあ。
ずっと溜め込んでいたのでしょうね、かわいそうに。
言い出せない性格でしたからね……。
優しすぎるのも、これから生きる上で考え物ですよ。
教師達のささやきは、エリを擁護する声ばかり。
堪えられなくなった吉田は嘘の理由をつけて退出を試みたが、松井に止められた。
「あんたは嘘をつくとひょっとこみたいに口が片側に寄るから丸分かりだ。久間木についても話がある」
春奈は手を後ろに組み、足を肩幅に開いて直立していた。
三年生の女子で三番目に背が高い春奈の身長は165センチに届く。
入学時には既に骨格がしっかりしていたが、剣道部で鍛え上げた筋肉質の体格は直立するだけでも堂々たる風格がある。
荒川から聞いた話では小学生の時分に吉田から髪型の件で執拗にバカにされていたというので、当時は今ほどガッシリはしていなかったのだろうと蘭は思う。
今現在の見るからに腕っぷしの強そうな春奈を見れば、誰もが手出しできないと怖じ気づくからだ。
「魅里と何かあったのか?」
はい、と春奈は答える。身に覚えがないと吉田は戸惑いながら反論するが、その発言が春奈の気に障ったらしく「すっとぼけるのも大概にしろで」と春奈に冷たく言い放たれた。
「あんた、本当に覚えてないのかい?」
「だって、小学校の吹奏楽部の行事で会ってた以外に……」
関わりなかったじゃん、と弱々しく訴えた。
「それだよ。吹奏楽部の行事で会う度に私の髪型をしつこくしつこくバカにしてきたべ」
これだよ、と春奈は肩の上で揃えた縮れた癖っ毛を指差す。
男みたいな顔と言われる自分に可憐な二つ結びは似合わないからと、常に肩からアゴにかけた長さを維持してきた。
黒光りするソバージュ風の癖っ毛は遠目からでも春奈だと分かるトレードマークでもあった。
「ビンボーパーマ、ってすれ違いざまに笑いながらバカにしてきやがったな」
吉田は無言だった。顔色が悪くなっているので朧気ながらも思い出したのだろう。
「あとはバブル期とも陰であだ名つけてたな?」
悪事がバレたような引きつった顔になる。
「……誰から聞いたのぉ?」
「たとえ仲間内でコソコソしてても聞こえよがしに言ってりゃ嫌でも耳さ入るわ」
仲間内。昨年の嫌がらせ電話に関わった部員も何人か含まれたであろう。
これまでの吉田率いるメンバーの行動を切り取れば、清水が丘小学校吹奏楽部は非常識なメンバーが集まっていると思われがちだが、非常識な行動で顰蹙を買う者はごく一部だ。
昨年度の部長だった舞は常識人であったし、清水が丘小学校吹奏楽部出身の上級生と吉田が親しいとはいえ、上級生達はエリに対するいじめに関して戒める発言を再三繰り返していたのだ。
「私さ、本当は中学でも吹奏楽やりたかったんだよ。でもさ、引っ越して別の学区の中学さ行くはずのあんたを音楽室で見かけて引き返した」
知らないだろうな、と前を向いたまま春奈は言う。
この時点で春奈は松井を交えた話し合いが始まってから、吉田を一切見ていない。
視界に入れたくないあまり、春奈は終始松井の頭越しに見える掲示板のあたりに視線を向けていた。
「吹奏楽部の三年生に又小吹奏楽部の出身者がいないのも、あんたと関わりたくなかったからだよ。又小吹奏楽部の同級生はみんな、あんたが嫌いだった。人をバカにするから。あんな感じ悪い子と一緒になりたくないってね」
エリからの攻撃に気圧されて一時は消えた泣き顔が、再び現れた。
「人づてに嫌われてるって言わないで欲しい……」
すごく傷つくし人を信じられなくなるから、と目をこすって吉田は言う。
若干タイミングはずれたが、春奈は「は?」と返す。怒りを含んだ語調だ。
蘭は反論することにした。
「自分だって、私とエリちゃんに誰々が悪口言ってたよ~って余計なこと言いまくってたくせに」
春奈が「そうだよ」と被せる。
「人を信じられなくなる? どの口が言うか。あんたこそ人間不信になる元凶作ってるじゃん」
思い出したくもない、忌々しい記憶が脳裏をぐるぐると渦巻く。
幸か不幸か蘭は気が強いのでキッパリと意見も反発もできたが、当時は十つに満たない幼子だ。性根をねじ曲げるのは容易かった。
彼らが一番そぎ落としたかったであろう正義感は維持できたものの、対人関係への、特に同じ年格好の男児への不信感という形で表れた。
「さぞかし悔しかっただろうね。男嫌いになりかけた私に、王子様が現れた現実がね!」
王子様の存在は吉田にだけは知られたくなかった。
いわゆる田舎ネットワークの弊害でいずれは知られてしまうことを蘭自身も覚悟はしていたが、一年生の二学期に話し合いを行った日に「恋もうまくいってるし」と涙目で言われた時、愕然とするほかなかった。
再び幸せを壊されると思うと、絶対に吉田にだけは知られたくなかった。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 6
◇◇◇
春奈と保健室へ向かう蘭は、職員室を出る前に交わした松井とのやりとりが頭から離れない。
話し合いもお開きになり「失礼しました」と一礼して退出しようとしたその時、蘭は松井に腕をつかまれた。
「先生も悪かったんだ。もう少し、あんたに声をかけてやれば良かったな」
反応に困り、しどろもどろになる蘭に構わず松井は言った。
「音澤は学年で一番勉強ができて、精神的にも強靭に見えたから、辛い時でも一人でなんとかできると甘えていたのかもしれないな。さっきも言ったけど、あんたは15のガキには変わりない。辛かったなぁ」
もっと早く、先生方の口から「辛かったなぁ」の言葉を聞きたかったな。
自分でも気付かなかった願望。
卒業間際にようやく自覚した愚かさに我ながらあきれるほかない。
蘭が無言のままでいると、見透かしたように「もっと早く聞きたかったろう?」と苦笑いしながら言い当てるので、蘭は戸惑う。
「甘えたくても、甘えられなかったろう? だから一人でなんとかするしかなかった。一人で戦うジャンヌ・ダルクにならざるを得なかったんだな。本当に、申し訳なかった」
椅子に腰掛けたまま、深々と頭を下げる。
「そうですね。先生方に頼ることが頭にありませんでした。私は強いと言い聞かせて、如何に今日を生き抜くかと精一杯でした」
それでも……と繋げて蘭は語り出す。
「幸い、家族は私を見捨てませんでしたし、友達も悪い噂に惑わされず私を信じてくれました。噂で聞いていると存じますが、私は小学生の頃の吉田さんを中心とした嫌がらせが原因で男性不信でした。そんな中である男の子と出会いました。学校は異なりますが、彼は私と会う度に名前を呼んで笑いかけてくれました。今でも……」
蘭は言葉に詰まる。
梅雨前の神楽殿の下と、夏の夕暮れに見た彼の眼差しは強い怒りに満ちていた。
そして、体育館での春奈が口を滑らせたであろう「飛鳥のやつに怒られた」は、あの状況で怒りに任せての発言なのだから、嘘ではないことは間違いない。
松井は何を勘違いしてか、真面目な話をしているというのに恋愛トークを聞いているようなニヤニヤとした笑みを見せている。
「彼は有言実行の人です。彼の言葉に嘘はないというより、嘘が下手で嘘をつけない人です。私から離れたくないと言い放ち、今でも私を気にかけてくれています。自ら矢面に立つことも厭わない……」
男気のある人だと話すと松井は「なるほど、あんたに似ている」と妙に納得した顔で相槌を打つ。
「先生があんたを放任していたのは否めない。でも、あんたを大切に思う人達がいるからこそ、辛い中でも生きてこられたんだよな。感謝するんだぞ。ご家族にも友達にも、あんたの王子様にもな」
ニカッと笑う松井につられ、蘭も照れの混じった笑顔を返す。
「あんた笑うとかわいいんだから、もっと笑い。な?」
◇◇◇
「春奈さん、私は半ば先生方に放任されてるな~ってのは感じていたの」
「蘭さん、手がかからない子って思われてそうだもんな」
私もなんだよ~と春奈は癖っ毛をかき上げる。
「見た目が年相応でねぇってのも損だべしたなぁ。私は見てのとおりゴツいから甘えたら気持ち悪いって外野に言わっちゃし、頼りたい時があっても頼りにくい」
甘えたくても甘えられない、不器用な15の少女は他にもいた。
「蘭さんはお兄さんいるんだっけか? 私もさ、兄がいるんだけどよく言われるんだ。全然妹のイメージじゃねえって。妹という肩書きが似合わないとしれっとした顔で言うやつまでいてさあ」
しれっとした顔での余計な一言。やられた側だからこそ容易に想像できた。
失礼すぎると蘭は不快感を露にする。
「何それ、馬鹿馬鹿しい。そりゃあ妹っぽいキャラクター像はあっても否定される理由なんかないよ」
だからぁ、と春奈は嬉しそうだ。
「たまたま兄弟の二番目に生まれただけなのにさあ。妹っつうものに夢見すぎなんだっつーの」
「春奈さんは姉御肌でしっかりしてそうだから妹っぽくないって意味ならば理解できるけど、肩書きって何なの? 生まれた順番なんて選べないんだから」
「蘭さんって、他人のことでも真剣に怒るよなあ」
シロちゃんの言ったとおりだ、との発言から白沢との会話内で蘭の名が出たことがあるとわかる。
「理不尽なことがあれば怒る。誰が言ったんだか知らないけど春奈さんへの発言だって他人事ながら納得できないよ」
「蘭さんってシロちゃんと幼稚園一緒だったってな? シロちゃん言ってたんだよ。蘭さんの怒りは優しさと紙一重だって」
白沢と春奈の間では自分自身についてどのような会話が展開されていたのだろうと蘭は気になった。
「しかし、松井先生も見るとこ見ていたんだなぁ。松井先生って生徒の好き嫌い激しいから実はあまり信用してなかったんだよ。兄ちゃんからも松井先生は基本的にいい先生だけど贔屓さえなけりゃな~って話を小学生ん頃から聞いていたしさ。……蘭さんのこと、見てくれていたんだな」
春奈と高校受験の話題以外で話したのは初めてだ。
この時点では、まだお互いに照れの感情があった。
「春奈さん、さっきはありがとう」
気まずそうに春奈は顔を下に向ける。
少女にしては骨の質感のある横顔だ。それゆえに、春奈からは少年っぽい中性的な印象が見受けられる。
「いやー、私は今まで何もしてこなかった。お礼言われるようなことなんてしてないよ」
してたよ、という蘭の台詞に弾かれたように春奈が顔を上げる。
「一哉ちゃんから聞いてた。学校で起きたこと話してくれてたんだってね?」
「あいつ、蘭さんを心配してたんだよ。様子が変わったってね。吉田と、そいつになびいてる連中のことすげえ怒ってたし、何度も学校さ乗り込んでやろうかって言ってたんだ」
はは……と蘭は苦笑いする。夏の夕暮れ、確かに一哉は言っていた。学校に乗り込んで説教してやろうか、と。
「そういや、飛鳥のやつが激怒した事件について話すんだったね。保健室出たら話す?」
「そうだね」
◇◇◇
保健室の引戸を開けるなり、蘭も春奈も驚く。
留美とミヨシと力丸が保健室にいるのはわかるが、白沢と由香理と絢もいるのは意外だ。
更に女生徒が複数人。その中には聖良と千晴、吹奏楽部員だった生徒が何人か含まれた。
敵方だった元部員は、いない。
「なんだぁ? みんな揃って何かあったのかい?」
いつもは強気な白沢が、頼りなげに頷く。
「私らも、みーちゃんのこと嫌いなくせに怖くて強く出なかったじゃん。だから……」
ちらりとエリを振り返って「ねぇ?」と言う白沢。
苦笑いのエリと隣に腰掛ける留美を背景に、由香理が済まなそうな顔で告げた。
エリに謝りに来た、と。
「本当に謝ることないってば。みんな気づかってくれたの分かってるからさ」
慌てた様子のエリは、普段どおりの優しい口調に戻っていた。
「私が何か言われたら怒ってくれたし、大丈夫か~っていろいろと声かけてくれたべ?」
男子にはな、と白沢が腕組みをする。
「男子にはやめろって言えたけど、みーちゃん相手だと何されっかわかんねえからよぉ」
私も陰で言われてっからよぉ、と打ち明ける白沢は腹立たしそうだ。
スクールカーストの上位者に属し、気が強くかつ口の立つ白沢に表向きではにこやかに接する吉田だが、本人のいないところで中傷していたのは周知の事実。
口が悪いから男子にモテない。背が低いくせに態度がデカイところが生意気でかわいくない。どうせ顔だけの女。などと好き勝手に白沢を罵った。
はては兄弟構成を持ち出し「男ばかりの中に女一人だから甘やかされてそう」と、偏見にまみれた思考を口に出したところを通りかかった白沢が聞いてしまった。
この件が決定打となり、吉田は完全に白沢から疎まれる羽目になる。
直後に吉田が家庭内で弟ばかり贔屓されているがゆえの「兄がいる妹」へ向けた嫉妬心によるもので本心ではないと言い繕っていたが。
「だから。事実ねじ曲げて変な噂流すの得意だし」
「あいつも前例があっから、二年生に上がった時に蘭ちゃんがいろいろと言われてた件もどうせ嘘だろーってみんな見抜いていたんだけどさ、嘘だと知ってて敢えて乗っかる馬鹿が必ずいるのが厄介なんだよな~」
由香理はそう話すと廊下側の窓越しに二人の女生徒を睨む。
廊下を歩いている二人の女生徒は、よく吉田や斎藤と一緒になっては気に入らない生徒や教師の悪口で盛り上がっていた。
変なあだ名をつけたり噂を流したり悪口を担当する者が吉田ならば、安全圏から囃し立てる担当が斎藤とこの二人の女生徒を筆頭とした取り巻きだ。
エリが体育でヘマをすればきつい口調で罵り、朗読でつっかえれば真っ先にクスクスと笑う。
彼女達は勉強はできるしスポーツもできる。ルックスも悪くない方だ。片方の女生徒には自身を溺愛してくれる彼氏もいる。
恵まれているように見える彼女達が何に不満を抱えているのかは定かではないが、とにかく何かへの不平不満をこじらせているらしく、憂さ晴らしの手段として下に見ている生徒を積極的にイビっていた。
「やることが嫁イビりする小姑みたいだよね。みっともな」
昔はああじゃなかったのに、と絢は言う。
いじめに荷担していた女生徒達と絢は自宅が近いという理由から小学生の頃は仲が良かったそうで、頻繁にボール遊びをしている姿を清水が丘小学校出身の生徒は知っている。
「なんで人って悪い方に変わってゆくんだろ」
絢のつぶやきの後、保健室内がしん……と静まる。
沈黙を破ったのは、図書委員の女生徒だった。
控えめながらもしっかり耳に届く声で話す。
「前に図書室で蘭ちゃん達と話したけど、戦わなかったことを後悔してるの」
今日だって……と図書委員は悔しそうに手を握り締めている。
「あんたはまだできた方だよ。私なんて何も言えてない」
「私も……」
あっけらかんとした顔で「あー、そうだねえ!」と言うは二階堂ミヨシ。
声が大きいと力丸薫子から脇腹に軽く肘打ちを受ける。
「だってそうじゃーん! いつもみんなして黙っててさあ!」
あっけらかんとした顔が、怒りに満ちた顔へと変わった。悔しそうに下唇を噛んでいる。
二、三歩進んで身振り手振りを交えるミヨシは春奈からも「私以上にいかつい女子を初めて見た……」と言わしめるほどの威圧感の持ち主。
柔道部で鍛えたその肉体は、元からの肩幅が広い逆三角形のスタイルに更に筋肉を盛り付けた。
通信制高校への進学を決めた時、ミヨシは体格を武器にガテン系の仕事をしながら通うと蘭達の前で口にしていた。
「そんなだからいつまで経ってもいじめをやめなかったんじゃんよーっ!」
ミヨシも、蘭やエリが悪口を言われると屁理屈で応戦した。それだけに保健室に集まった女生徒達はぐうの音も出ない。
無口な力丸はというと軽蔑を込めた眼差しでいじめっ子達を睨みつけることが常だ。または舌打ち。
「黙ってな」
手の甲でミヨシを軽く叩く力丸。
漫才師の突っ込みを真似た動作だが、力丸は真剣だ。薄い唇から発する小さな美声でボソリと言った。
上品な顔立ちの力丸は通りすがりの知らない人からもお人形さんみたいだと褒め称えられるが、可憐な容姿と裏腹な殺伐とした言葉遣いだ。
口を開けばガッカリする。この評価を何度下されたことだろう。
ミヨシ、と力丸は小声で呼ぶ。
「なに!」
「気持ちはわかるが、ここ保健室」
静かにしな、と囁き声で忠告した。
黒目がちな垂れ目で力丸は図書委員に目配せし、話を続けるよう促す。
「強くないだなんて、言い訳でしかなかったんだよね……。シロちゃん達は言えた方だよ。私なんか男子にすら言えなかったし。みーちゃんについてる男子って差別主義も甚だしいからさあ、私が言ったところでブスは黙ってろって逆ギレするの目に見えるもん」
複数人の口から納得した声が沸き上がった。
「言いそう。あいつら、自分に逆らう女と自分を立てない女を嫌いそうだよね」
「立ててもらえるほどの器じゃねえくせになぁ?」
白沢の発言にほぼ全員が「だからぁ!」と賛同し出した。
「性格ブス嫌い~悪口言う女子嫌い~とか雑誌でそんなコメント見るけどさ、結局は自分を立ててくれるコンパニオン役ならばどんな性格ブスでも構わないのな」
「ああいうやつらの言う性格が良いってのは『自分のイエスマンかつ愛玩になること』だからね」
蘭は言う。そんな器の小さい連中のコンパニオン役など願い下げだと。
「うわー。愛玩って何だよそれ、人扱いされてないじゃん。気持ち悪……」
由香理の嫌悪感丸出しの発言に続き、留美は「いつの時代の思考だっつーの」と憤る。
「本っ当、男って意味わかんない!」
荒々しく吐き捨てるのはエリだ。
林の手のひら返しといじめを通して男嫌いと成り果てたエリは、進学先が女子校でよかったと繰り返し口にしている。
もちろん、男の全てが憎いわけではない。
同級生の男子の中でも合田康範や浜津陽一郎などの無害な者には寛容であるが、今度は「相手を選んで話してかけている」だの「エリのくせに選民意識が強い」などといじめっ子からの非難が強まる羽目になった。
守ってくれる友達や止めに入る同級生もいるのだから自分はいじめられっ子の中でもマシな方だとエリは自身に聞かせるも、ダブルバインドも甚だしい仕打ちを受けたエリが対人関係において疑心暗鬼に陥るのは免れなかった。
「あの……そろそろ解散した方がいいかも。三年が雁首揃えてたら後輩がビビって入りにくいし……」
言いづらそうにエリが提案する。
「そうだな。退散すっか」
「解散じゃなくて?」
そうして保健室からぞろぞろと退散するも、忘れかけていた敵が待ち構えている。
敵は人垣からエリの姿を見つけるなり「エリちゃ~ん」と甘ったるい口調で呼びながら小走りで寄ってきた。斎藤だ。
少し離れた先には数分前に由香理が睨みつけた女生徒と、取り巻きの男子がいる。彼らはうなだれる吉田魅里を囲っていた。
「さっきは大丈夫だったぁ?」
すかさず蘭が斎藤の前に立ちはだかり、続け様に留美とミヨシ、春奈の順で背が高い者達がエリを取り囲むようにガードする。
取り巻きの男子が「人間の壁」「デカい女ってかわいくねえよな」と揶揄すると、感じの悪い笑い声が沸き上がった。
「大丈夫だった、ってどの口が言うか」
蘭が冷ややかに応じる。
「私が退部届け出した時、関わるなって言ったよね。どうせ私らと違う高校受けるんだし」
勉強のできる斎藤は、聖良と千晴が受験する県立のF女子高を志願している。
市内に複数ある女子高の中でもトップの偏差値を誇る、伝統ある女子高だ。
F女に通う先輩方の中でも斎藤を見知っている者達は、斎藤が受験する話を聞くなり「あのワガママ娘が入ろうものならF女子高の格が下がりかねない」と軒並み嫌そうな反応を示したという。
低い声で「この性悪女が」と凄むは留美。
春奈が一歩進み出て、やはり低い声で言った。
「あれだけイビり倒しておいて、都合悪いと手のひら返して味方面するのな」
気持ち悪いやつだな、と春奈に言われて斎藤も取り巻きに囲まれる吉田と同様にうなだれた。
「っていうかさぁ、あーちゃんズルくなーい?」
大声を出すミヨシに「なんでズルいのぉ?」とだだっ子のように身体を揺らして斎藤は抗議し出すが、エリを守る人垣の後方からつかつかと眼前へと歩み寄る白沢に驚いて動きを止める。
白沢の目元はつり目がちだ。細い顎に落ち着いた響きを持つ知的な声は、容姿の可憐さに加えて格好良さを補った。
それゆえ、白沢は小柄な者にありがちな幼い印象を感じさせない。
鋭さを帯びた瞳で、白沢小百合は斎藤を真っ向から睨みつける。
「松井先生からの説教逃れたべした。さっきの体育で一緒になって悪口言ったくせに、そそくさと逃げたの見てたから」
その口調からは苛立ちが垣間見える。
腕組みの由香理と絢も現れた。
「上手く隠れたようだけどね」
「あんた達には正直関わりたくなかったけど、さすがに見過ごせない」
白沢と同じくスクールカースト上位者の由香理と絢。
女子のリーダー的な位置付けにある二人に吉田も斎藤も仕切り屋だの威張りくさってるだのと陰口こそ叩きはするが、表立って楯突くことはできない。
「もう、いいよ。行こう?」
人垣の真ん中からエリが声を上げる。か細い声だった。
白沢が真っ先に口を出す。
「お人好しすぎるんだよ、エリちゃんはさ!」
「違う!」
うってかわって、エリはキッパリとした口調で返す。敵も味方もエリの変わり様に目を見張る。
「こんなやつらとは二度と関わりたくない! もう、一秒たりとも一緒にいたくないんだ。さっさと離れよう?」
そうだな。
そうだね。
各々が同意を口にしながら足を進めることにした。
蘭を先頭に、一同は前を見据えて無言で通り過ぎる。
これ以上、吉田と斎藤と取り巻きに何かを言えば「いじめ返された」と被害者ぶって武田などの男子に泣きつく姿が目に見えるからだ。
千晴だけが、横目で吉田達をジロリと見る。
蘭とエリが吹奏楽部を去り、聖良も去っていったが千晴は残った。
吉田との友達ごっこは煩わしいが、音楽は好きだったので三年生の夏のコンクールで引退するまで吹奏楽部に籍を置いた。
県予選は突破するも東北大会出場を果たせない結果となっても、涙は全く出なかった。
当然の報いだ。
二年生の吹奏楽コンクール県大会の翌日に、顧問の上野は「厳しい言葉ではありますが」と部員達に話した。
「傷つけ合っては良いサウンドが生まれないことが、今回の大会で証明されました」
成績の不振と一部の部員の素行不良により吹奏楽部の活動時間は18時半、冬季は17時半までと言い渡されたにもかかわらず吉田は暗い中でのランニングを強要した。
颪が吹き付けようが寒い屋外での合奏を強行し、風邪をひく部員が出れば根性が足りないと発破をかけた。
上野が懲りずに向き合っても、吉田は教師達の目を掻い潜って独裁政治を貫いた。
最後の手段として保護者からの苦情が出ている件や職員会議で問題視されている件を告げられても「泉清中学校吹奏楽部を再興させるため」と言い張り、聞く耳を持たなかった。
どの部活動にも関心を持てなかったが内申点を気にして消去法で吹奏楽部を選んだ斎藤は高校進学後は吹奏楽を続けないかもしれないが、吉田は高校に入学してからも吹奏楽を続けたいと公言していた。
謝恩会では顧問への感謝の作文を読み上げる際に「吹奏楽部のみんなが大好き」と白々しく述べた。
千晴は吹奏楽を続けるか否かは考えていないが、自分に楽器を吹く資格はないという考えは頭の片隅にあった。
小学生の頃に買ってもらったクラリネット。
大切な宝だったはずなのに、この楽器を武器にしてエリを小突いたことがある。
エリを気にして様子を見に来た蘭に見られ、蘭はすぐさまに駆け寄り千晴の腕を掴み上げて激昂した。
優雅さを纏うしなやかな細い指なのに、千晴のぽっちゃりした腕をひねり上げる蘭の手はものすごい力だった。
骨ごと潰されるのではという危機感にかられてしまうほどの力。
楽器は人を傷つける道具じゃない、あなたは楽器を穢している、恥ずかしくないのかと厳しい口調で咎め立てられた。
はい。恥ずかしいです。
大切な楽器を、人を傷つける武器に利用した事実は塗り替えられない。
私は、どこで踏み違えたのだろう。
辛くても優しいままでいるエリからも信用できないと突き放された。
蘭のような、気高いまでの正義感を持つことができない。
弱虫で小ずるい自分は、蘭のような女傑にもエリのような優しい女の子にもなれない。
「バイバイ」
冷たい眼差しで一瞥しながら、千晴はこの一言だけを冷淡に投げ掛ける。
ただの挨拶に聞こえる一言には、決別の意思が詰め込まれていた。
2002年 私のジャンヌ・ダルク(後編) 7
◇◇◇
一同は中学校近くの神社に集まった。神社の後ろ側を境に店舗は疎らになり、代わりに農地と住宅が点在する。
目を見張るのは広大すぎるススキ野原だ。冬の面影の残るこの季節は乾いた亜麻色が広がっているのみであるが、春になればススキ野原は緑に染まる。
遠景に、白い吾妻連峰を臨んだ。
「さっきの話だけどさ」
春奈が語り始めた。
春奈の説明では、2月に遡る。その日は土曜日。第三土曜日であった。
卒業式に向けて、私立中学に進学した元同級生達を含めて松川の河川敷で合唱の練習をしていた帰りだった。
合唱の練習の件は蘭も知っている。一哉から誘われたがオーケストラの練習があるので断ったのだ。
蘭と歌いたかった一哉は落胆したものの、蘭がオーケストラの練習を楽しみにしていることをよく知っていたので快く送り出した。
「飛鳥のやつ、蘭さんが参加できなくて凹んでいたもんなあ」
春奈に続けて白沢がニヤリと笑い「女子一同が歌声に聞き惚れてたぞぉ?」と、煽る。もちろん、蘭をからかうための作り話だ。
「えーっ!? 私も聞きたかった!」
前のめりになり大声を出す蘭の、セーラー服のスカーフが揺れる。
留美とエリ、ミヨシと力丸は恋する乙女さながらの蘭の姿を見慣れているが、由香理と絢も、千晴も初めて見たといっても過言ではない。
蘭の恋する乙女そのものの姿を知らない女生徒達は、あ然とした顔だ。
聖良はというと、オーケストラの仲間内での恋愛トークで蘭のノロケっぷりを見知っているので今さら驚かない。
「蘭ちゃんって、そんな反応するんだ……」
まずは千晴。ケッと言いたげな表情と冷ややかな眼差しが癪に障った蘭は「何、その顔?」と返した。
「軽蔑するほどでもないでしょうが? 誰だって好きな男が関われば大なり小なりそういう反応に出ると思うけど」
むくれて反発する蘭に「生憎、私は恋愛なんか興味ないし」と千晴は言った。
興味を持てないというよりは諦めに近いことを察している者は、今ここにいるメンバーに含まれているだろうか。
千晴を横目で眺めて「あんたらしいな」とボソリと言うは力丸。
「しかし蘭ちゃんも案外普通の中学生らしい反応するよね?」
「女って恋愛が絡むと人が変わるよねえ」
含み笑いの由香理に、あきれ顔の絢。
「あのー、みんな私にどんな印象持ってたの?」
「だって、ねえ」
同意を求めるように白沢がぐるりと見回して、最後に蘭を見上げる。その身長差は20センチに満たないが、白沢と対面すると蘭の長身がより際立った。
「学校での蘭ちゃんって変に突っ張ってて男子に冷たいしよ」
白沢の次に、力丸のか細い声。
「昔と比べて無愛想になったし」
早口でそう話す力丸はポーカーフェイスのままだ。力丸の足元でヤンキー座りをしているミヨシが「仕方ねえべしたぁ」と大声を出す。彼女は地声が大きいのだ。
「あいつら見てたら男嫌いにもなるっつーの、な~ぁ?」
ミヨシの言うあいつらとは言うまでもなく、吉田魅里の取り巻きだ。
さて、と春奈は話の続きを始めることにした。
「練習の後にゴウダがビクトリーでもらってきたパンの耳をかじって集まってたらよ」
「なんでだか知らないけど、あの日に限っていたんだよ。あいつら」
関わりたくなかったので、合唱の練習の参加者一同は吉田率いるグループに見つからないよう隠れたという。
「言いにくいんだけど、昔、蘭ちゃんが好きだった男子もいたんだよ……」
千晴がエリをいじめていた過去を塗り替えられないように、塗り替えたくても塗り替えられない思い出が蘭にもある。
あの苦い初恋は、なかったことにしたい。
消しゴムでまっさらに消し去れないならば、墨なりインクなり跡が見えなくなるほどに真っ黒に塗りつぶしたい。
それでも消えないならば炎で焼き尽くし土に深く埋めよう。
蘭は家族や小学校の教師陣から私立中学への受験を勧められたが、軒並み断った。
ただでさえ習い事で負担をかけているのだからと経済的な事情を理由に中学受験を辞退したが、翠楓学園を断った最もたる理由は初恋の男子と同じ中学に通いたくなかったからだ。
よりによって、あの憎い男は一哉と同じ学生服を着て過ごしている。
あの男さえいなければ中学受験を考えてもよかった。蘭は翠楓学園のセーラー服を見る毎に思う。
近所で会っても蘭は無視に徹した。
絶対に許さない、と。
「オリちゃんに聞いたんだけど、あの野郎、翠楓で何かと一哉君につっかかるらしいな」
据わった目の白沢の発言。蘭が嫌な気持ちにならないようにと気づかってか、一哉は蘭の初恋の相手のことを一切口に出さなかった。
聞き捨てならない事実に蘭の顔色が変わる。
あの男は、恋慕う少年までも傷つけるのか。
もしも初恋の男子がその場にいたならば、握り拳を振り上げて繰り返し横っ面を殴りつけていたかもしれない。
「なんで? まだ蘭に未練あるの?」
舌打ちの後に、留美が白沢に問う。
「未練あるというより、蘭ちゃんと和解した子もいるのに自分は許してもらえないままで……」
「ふざけないで!!」
白沢の話を遮るように声を張り上げて蘭は叫ぶ。
悪い噂に流されて蘭を悪者扱いした同級生の何割かとは和解したものの、蘭は吉田と斎藤、そして初恋の男子だけは許さなかった。
「許すわけないじゃん! 謝りもしなかったし男子では最も私にひどいことしてきたんだよ!?」
何様のつもりだと蘭は声を荒らげる。
「和解した子達はみんな謝ってきた! あいつは謝りもしない上にいつまで経ってもネチネチと嫌がらせを繰り返してきたくせに!」
吉田からの嫌がらせは収まっても、初恋の男子からのイビりは四年生が終わるまで続いた。
テストで高得点を取れば自慢していると罵倒された。
バレエの練習の話題になれば気取っていると言われ、容姿についてもプライドが高そうな顔つきや黒髪のロングヘアを「漫画で見かけるヒロインをいじめる悪役お嬢様にそっくりだから、どうせお前も本性は意地悪いのだろう」と笑いながら罵られた。
四年生への進級時に転校してきた留美は「こんな性格悪い男子は前の学校にはいなかった」と手厳しく責め立て、白沢や由香理や絢のような気の強い女子達も「いい加減しつこい」と咎めた。
出産後に復帰した担任からも再三指導を受け保護者へ知られるところと成り果てたが、一向に蘭へ言いがかりをつける仕打ちをやめる気配はなかった。
結果、初恋の男子は蘭と和解する以前に女子のほぼ全員からの反感を買い、嫌われた。
男子は表立って蘭を擁護はしないものの(女子を擁護すれば「好きなんだろう」と邪推して冷やかす者が必ずいるからだ)悪辣すぎる仕打ちは「やりすぎだ」と顰蹙を買い、遊び仲間が軒並み離れていった。
やがて同級生のみならず学年の近い児童からも「女子をしつこくいじめる最低なやつ」と鼻つまみ者とされ、あからさまないじめは受けなかったものの班別学習や席替えや学年の垣根を越えた交流会で同じグループになった児童から「仕方なく付き合ってやっている」とばかりに扱われる羽目となる。
「蘭ちゃんが男嫌いになった話もうちの小学校じゃ有名だべ。それなのに蘭ちゃんと一哉君が仲良くしているのを見て『なんで男嫌いの蘭と仲良くなってんだよ』って癪に障ったんだと」
当然ながら、大ブーイングが沸き上がった。
我が事のように怒りを露にした女生徒達が初恋の男子を非難し出す。
「意味わかんね。蘭ちゃんを信じなかったくせにさぁ?」
「許してもらいたかったら親の前で土下座して謝れってのなあ」
「誠意を見せないでおいて飛鳥君と張り合ったところで敵わないくせによぉ?」
膝の上で頬杖をついている留美が「そいつ、今度こそとっちめてやろうか?」とつぶやいた。
「お察しのとおり、連中は気に入らない同級生の悪口三昧さ。中には聞かせられないくらいひどい内容もあって……」
春奈は言いにくそうだ。歯切れが悪くなる。
「それって、生命の尊厳を踏みにじる類いの内容? 私も言われたの?」
蘭の問いかけに春奈も白沢も頷く。由香理も、絢も居合わせたメンバー全てが顔を縦に振った。
「そしたら、一哉君がひどく怒り出してさ……」
黒目がちな細い目で白沢が見回すと、由香理が詳細を続ける。
「すごかったよね。あいつらのところへ駆け出して……口だけで手は一切出さなかったから安心していいよ。『言っていいこと悪いことの分別もつかないやつが蘭に勝てるわけがない』とか『二度と蘭に関わるな』とか『蘭を信じてやらなかったくせに』って怒鳴り込んでたよ。もうね、機関銃のように蘭ちゃんを侮辱された恨み言をぶちまけてた」
度々「男の子なのによく喋る」と大人達から指摘されるだけに、お喋りに興じている時点で饒舌な一哉のことだ。
蘭が機関銃の如くまくし立てる一哉を想像するのは容易であった。
「私は一哉君があれだけの長ったらしいセリフをほとんど息継ぎもなしにすらすらと言えてたことにも驚いたけどね」
アドリブで言ったようなものでしょう、と回想する絢はげんなりとした顔である。
典型的な委員長タイプで冷静ながらもハッキリとした気性と物言いをする絢。彼女もまた淀みなく話せる方であるが「私には到底真似できない」と、あきれ気味であった。
「すぐにゴウダとハマちゃんに取り押さえられたけど振り切りそうな勢いだったな」
「まぁ……激怒してもイケメンはイケメンだった、よね」
目尻をゆるめて惚ける白沢。白沢が面食いなのは今に始まった話ではないので蘭も目くじらを立てたりはしない。
両手を組み合わせた聖良はうっとりとした面持ちで「ほんと、素敵……」と言うと
「愛する人を守るための怒りだもんねぇ」
と、繋げた。
更に眼鏡の奥で丸っこい瞳をキラキラと輝かせながら「あんなかっこいい人に守ってもらえるなんて夢の夢だよお」とまでつけ加える。
「おいお~い、セイちゃん」
ロマンチストにも程があると突っ込む春奈に構わず、聖良は集まっている女生徒一同へ同意を求めた。
「イケメンに守られたい願望って、うちらぐらいの年齢ならある程度は頭にあるんじゃない?」
すかさず千晴が「そんな願望ない」とふくれっ面で否定に入り、力丸が頷く。その後ろで留美が顔を背けて笑いを堪えた。
エリを巡って対立していたこの二人は、意外と気が合うらしい。
「蘭ちゃん怒るから今まで黙ってたけど、一哉君さ、うちの学校の女子の間じゃ自転車の貴公子って呼ばれててよぉ、後輩の中にはファンもいるぐらいなんだよ」
いつもチャリ乗って学校さ行くから自転車の貴公子だ、と白沢は語る。
似たり寄ったりのあだ名に覚えはあるが、蘭は口に出さないことにした。
でも、と言ったのはまたしても聖良。
「やっぱり、蘭さんと一哉君がニコイチだから映えるんだよねえ……」
「美男美女カップルが実在すると証明してるようなもんだし」
聞き役に回っていたエリもまたうっとりとした表情で「二人とも綺麗すぎて眺めているだけでドキドキするんだよねぇ」と惚ける。
恋愛にさほど興味を抱けない千晴と力丸を除いて、女生徒一同はニンマリと笑いながら「蘭ちゃん、うらやましい~」とからかい出した。
15の少女達がワイワイ騒ぐ中で覚めた顔の千晴がつぶやく。
「つーか、私その一哉君ってやつ知らない」
興味ないんだ、と仏頂面の千晴が言った。
「なら、なんでついて来た」
力丸は千晴を見上げる。
「なんとなく。なぜかみんなここに来たから」
案外流されやすいなと力丸に指摘された千晴は否定しなかった。
「そいつ、蘭ちゃんの好きなやつ」
「知ってるけどさぁ……」
「イケメンとかいう軽薄な言葉で表すのが申し訳なく思っちまうような美男子。蘭ちゃん、そいつといる時すごくいい顔すんだ」
千晴はあ然とする。力丸の口角が、僅かに上がっているのだ。
力丸は全く笑わないわけではない。
ただ、力丸が蘭をはじめとした普段からつるんでいるメンバーの前以外で口角を上げる姿を見たことがないのだ。
「うち、恋愛することには興味ないけど人様の恋模様の観察って面白いぞ?」
いつになく、力丸薫子は饒舌だった。
そして、力丸の一人称が「うち」であることを9年間同じ学校に通っていながら初めて知った。
◇◇◇
「約束って何のことか知らないけど、あの後で飛鳥のやつ『蘭との約束破っちまった』って落ち込んでたんだよ」
そう話す春奈もどこか沈んだ表情だ。自ら蚊帳の外を選んだ千晴と力丸も興味ないと口にしながらも聞き耳を立てている。
「一哉ちゃん、直談判して説教食らわしてやろうかって何回か持ちかけてきたの。でも、あいつらのことだから絶対に一哉ちゃんを悪者にして立場を悪くさせるに決まってる。私は、それだけは避けたかった」
だから、乗り込んで説教はしないでほしいと懇願したのだと蘭は語る。
「うん、……確かに約束破ったな」
そう話す留美の声に怒りは見受けられない。
「蘭さん。飛鳥のやつを責めたりしないでほしいんだ」
この通りだから、と春奈は深々と頭を下げる。
白沢も続け様に頭を下げた後、蘭のセーラー服の袖を掴んだ。
「一哉君、ずっと堪えてきたんだよ。蘭ちゃんのこと守りたくても約束破ったら蘭ちゃんが悲しむと言って抑えてきたんだ」
「いや……責めるつもりないから……」
約束を破られた怒りは湧かない。
「私は、知らないふりをすればいい?」
蘭が決めるべきだと至るところから声が上がる。
タイミングを見計らって、由香理が躊躇いがちに言った。
「私らも飛鳥君に言われたんだ。なんでいじめっ子に強く出ないで野放しにするんだよって」
「蘭さんと同じこと言ってる……」
図書委員の女生徒が苦笑いを浮かべた。
「責めるとか怒るなんて考えていないよ。感謝しかないもの」
蘭は冷静であるよう努めるが、内心は落ち着かない。
会いたい。
会って、言いたい。
守ってくれて、ありがとう。
2002年2月 約束
「飛鳥。お前、祥蘭受けるんだべ?」
一哉は同じ小学校の出身者からは飛鳥と呼ばれている。新潟に住んでいた頃も小学校では飛鳥で通っていた。
中学校近くのサンドイッチ専門店を出た直後に一哉に問うのは親友の合田康範。袋いっぱいに買い込んだカツサンドやらパンの耳やらが詰め込まれていた。
泉清中学校の三年生の男子で最も大柄な合田は170センチを少し超えた一哉よりも背が高い。おまけに合田はガタイが良かった。
やたらガッシリとした尻周りを見れば合田が元野球部であったことも頷ける。
「そうだよ? 意地悪りぃやつが女目当てとか陰口叩くけど別にいいだろって話だよ、マジで」
合田にはなんとなくだが、一哉にやっかみを抱く同性が陰口を叩いているのだとわかる。
基本的には同性の友人に恵まれるも、医学部志望なだけに学業優秀で何よりも容姿に優れた一哉だ。
内面はごく普通の男子中学生でたまたま美形に生まれついただけのことであるが、それだからこそ劣等感を抱く同性が現れるのも無理はない話かもしれない。
大概、学業も容姿も何もかもが中途半端な人間が劣等感による敵対心を向けることを、合田はこの中学生活を通して嫌でも理解した。
あくまでも第三者からの視点である。
「相手にしねえけど、くだらないと知ってても毎回やられりゃ疲れるわな」
蘭の気持ちがわかる、と一哉はマフラーに口元を埋めた。
マフラーは『くるみ割り人形』のミュージカルを見た帰り道でもらった、蘭からのクリスマスプレゼント。
無人駅での会話を覚えていたのか、帰り足に「この色なら男子でも違和感ないから」と限りなく白に近い薄桜色に藍鼠色でブロックチェックが大きく織り込まれたマフラーを肩にかけてくれたのだ。
雪の残る、薄曇り。
ただでさえ防寒具は有難いのに好きな女の子からもらったマフラーと思うとより暖かい。
ため息をつく親友の、美しいシルエットを描く横顔。
基本的に人をうらやむことはあるものの妬みはしない合田。
小学五年生の新学期。同じ日に、同じクラスに転校してきた一哉を合田は純粋に「かっこいいやつ」と感嘆したものだった。
イケメンという言葉がまだ存在しなかった90年代、小学生が美男子を褒め称える言葉といえば「かっこいい」の一辺倒だ。
端正な顔立ち、特に目力のある大きな瞳と高めの整った鼻筋は合田にとってもうらやましかったし、唇を引き結んだ表情の勇ましさには男ながらにハッとさせられる。
「陰険だよな。その女目当てってのも、女子が沢山いるからってわけじゃなくて音澤がいるからって意味だっぺ?」
「そうなんだよゴウダ君。そいつ、蘭と因縁のあるやつだから尚更なんだ」
「あー、やっぱりな……」
合田は何かしら察した様子だ。ギッと眉根を寄せて唇を噛む一哉は忌々しそうに言い募る。
「あの野郎……。蘭のこと、信じてやらなかったくせに」
誰かを憎んでいる顔には間違いない。
しかし、恋い慕う少女を想うがゆえの、親友の阿修羅の如し怒りの形相を合田は美しいとすら思った。
◇◇◇
「うーっす。待たせたな」
合田の口から野太い大声が発せられる。
学習センターにほど近い松川の河川敷には中学生が集まっていた。十人より、少し多い。
公立の昔ながらの制服を着た生徒に混じり、私立中学に通う生徒も複数名いる。
「何買ってきたの?」
制服に革靴を合わせた女生徒がちょこちょこと歩み寄り、目を光らせて合田が手に下げた袋を見る。コートの裾から覗く花紺色の長いスカートはミッションスクールの女子校の制服だった。
「カツサンド。お前らにも山分けする?」
「いや、ゴウダの分なくなるのも悪いし遠慮するよ」
「私らは後で買うべ?」
「賛成。飛鳥のやつ来るなら蘭さんも誘えばよかったな?」
「だから」
ニヤニヤと笑う女生徒達を軽くいなした一哉は「蘭も誘ったけどオーケストラの練習あるから来られないってよ」と言った。
「なんだぁ。アルト少ないから蘭さんがいると助かるんだよなぁ」
ベンチに腰掛けつつ膝の上で頬杖をついた春奈が言う。残念そうな春奈に続いて、大人びた雰囲気の少女が一哉と合田の前に進み出た。
低めの、色気のあるハスキーボイス。
「アルトが私とハルちゃんの二人だけでは心許ないからね」
大人びた雰囲気の少女は橘織絵だった。背丈は春奈と変わらない。
コートの下にはモノトーンのセーラー服を着ており、膝下丈のタータンチェックのスカートが裾から見える。
「橘も来たの?」
「んだ。シロちゃんに誘われて、迷ったけど来たよ。蘭ちゃん、音感あるから来てくれたら頼りになるんだけどな」
迷ったけど、のところで織絵の視線は一哉の隣へ向けられる。隣には合田がいた。
合田は「よお橘、久しぶりだな」と気さくに声をかけ、織絵は癖っ毛を耳にかけて静かに「そうだね」と返してはにかむ。
織絵は合田に気があるのでは、と推測する一哉は落ち着かない。いつも学校でつるんでいる奥山の好きな人が織絵だからだ。
板挟みで複雑な心持ちの一哉に公立の学生服を着た男生徒が声をかけた。
「飛鳥君って音澤と付き合ってんのかい?」
今ここで飲食していないことを一哉は幸いに思う。絶対に、吹き出していたからだ。
「えー、何だよ藪から棒に?」
外気は寒いのに、頬だけが場違いなほどに熱かった。
「だいぶ前から噂になってっぞ、な~あ?」
男生徒は同意を求めるとばかりに参加者一同を見回す。突然興味をそそられる話題に発展し「なになに?」と中学生達はわらわらと集まる。
音澤蘭と飛鳥川一哉が交際しているか否か。
86年度生まれの地元の中学生の共通の話題であり興味の的である。
「だから。堂々と二人でいるし」
「気になるけど蘭さんからは聞き出しにくいんだよなあ」
わかるわかる!
春奈の発言に同調する声が至るところから沸いて出た。
「んだから! 聞いたら絶対に怒られっぺした」
「音澤のやつ、関係ないでしょうって怒りそうだな」
「お前ら、蘭にどういう印象持っているんだよ……」
泉清中学校の生徒達と自身の抱く蘭の人物像との温度差に、一哉は戸惑う。
蘭と幼なじみの白沢と織絵を除いた彼らが口を揃えて近寄り難い、話しかけにくい、同い年なのに緊張すると評するあたりに、蘭が未だに周囲と壁を作って生活していることを思い知らされた。
由香理と絢に至っては「昔と比べて蘭に声をかけにくくなった」と語る始末だ。
しかしながら、神々しいまでの透明感と頑とした強さを纏う姿は浮世離れした趣があるゆえに、近寄り難く思えるのは無理もない話かもしれない。
十つの春に蘭と出会ったその日、一哉は雪の如し高潔さに圧倒されるあまり言葉が出なかったのだから。
本当は、笑うとかわいい可憐な女の子なのに……。
「俺の母ちゃん、犬の散歩してっ時に音澤と飛鳥君がふたつやま公園さいるの見たってよ」
ふたつやま公園でのデート。
セーラー服にストラップのついた革靴を合わせていたから、オーケストラか、フルートの練習の帰り道か。
あの時は同じベンチに並んで腰掛け、福島駅の書店にて買ったばかりの『星の王子様』の文庫本を蘭に見せてもらったのだ。
蘭はとりわけ気に入っている箇所を指先で指し示しては、伏した目を上げてちらりと一哉の顔を覗き込む。
どちらからともなく肩が触れ合い、指先が微かに重なり合った瞬間の高揚感は忘れ難い。
時々『星の王子様』ではなく蘭の横顔を、黒髪と桜色がかった白い肌のコントラストや高い鼻筋の高貴さに見惚れては何を見ているのだと苦笑いをされた。
「ごめんね、蘭ちゃん見せてくれたのに……」
横顔がきれいだからと焦って返すと、桜色の頬は薔薇の花の色へと変わりゆく。
秋が深まった頃だった。
「うちのお母さんも中合で見かけたって言ってた! あの二人お似合いだねぇ、だってさ」
『くるみ割り人形』のミュージカルを見に行った日以外にも中合百貨店に立ち寄ったことが何度かあるので、いつのことかは定かではない。
例えば京都物産展や加賀百万石物産展を見に行ったり、地下でモロゾフやMary'sのチョコレートを買い込んだりもした。
物産展は相当に込み合うので、学生服の裾を掴むようにと蘭に話すと、蘭は頬を真っ赤に染め上げて照れていた。
百貨店を見ることが好きな蘭に、新潟には伊勢丹があると話した折には「えー! 伊勢丹あるんだ、いいなー」と目を輝かせて羨ましがった。
「なんだかんだでいつでも一緒だからよぉ」
「付き合ってるようにしか見えねえべした」
「結局のところどうなんだい、飛鳥君?」
皆が好き勝手に騒ぎ立てる中で「おいおいおーい!」と小柄な少年が大きく両手を振った。
静止の合図らしい。
「みんな、やめっぺで。飛鳥のやつは音澤に関して口堅いんだから口割ろうとすんなで」
小柄な少年=浜津陽一郎の言葉どおり、一哉は頑なに口をつぐんでいる。口をつぐみすぎて、顎がくるみの殻のように凹んでいる始末だった。
気持ちの優しい浜津は一哉と合田が転校して以来の親友だ。
一哉は浜津の手を取り礼を述べる。
「いやー、ありがとうハマちゃん。助かったよ」
「どういたしまして。ほらほら、みんな気ぃ引き締めっぺした。練習やるべ」
ようやく変声期を終えたらしい、まだ幼さを残す声が響く。
苦笑い混じりで手を叩く浜津は場を仕切る行為に不慣れな様子で、中学生達は各々微笑ましそうな笑みを浮かべつつ従うほかない。
「ははっ。ハマちゃんが仕切るなんて珍しいよなぁ」
「だからぁ!」
卒業式に向けた合唱『旅立ちの日に』の練習が始まる。音楽の盛んなこの地域らしい光景だ。
2002年2月 約束 2
アカペラでも歌えなくはないが、白沢の持参したCDラジカセからはカセットテープに録音した伴奏が流れる。
MDが既に世に出ていたとはいえ、録音の手段としてカセットテープも現役だった時代だ。
元合唱部なだけに一哉は歌には自信がある。
幼い頃は毎日必ずといって良いほど何かしらを歌っていたと母親に聞かされていたが、確かにうっすらと記憶に残っている。デタラメな即興の歌も含めて。
蘭の影響で吹奏楽とオーケストラにも興味はあったが、楽器の演奏はからっきしの苦手だった。
毎年行われる鼓笛隊パレードで小学校名の書かれたプラカードを持つ役割を任された時などは幸いに思ったほど。
中学校入学を控えた頃に、器楽の類いは苦手でも実は吹奏楽にも興味があるのだと打ち明けると蘭は嬉しそうに「いいじゃん、やってみたら?」と言った。はしゃぐような口振りだった。
「一哉ちゃんが楽器吹いている図式って様になりそうなんだけどなあ」
「いやー、俺、リコーダー下手だったんだよ。入ったところで笑われるっつーの」
「初心者がいきなり吹けるなんてあり得ないよ。それにリコーダーと違うかもしれないし、あれ穴っコ半分だけ塞いだり意外と複雑なんだよね」
「それ! それが嫌なんだよぉ。半分だけ塞いだつもりが変な音出てクラスのやつらに笑われんの」
「だいたいの楽器はキー塞がってるんだし、やってみたら? ……一哉ちゃん、歌上手いから音感あるのは間違いないだろうし」
「どこで聞いたの!?」
「チャリ乗って歌ってたの聞いた」
経験者でたまに見かける嫌みな傲慢さが蘭にはなかった。むしろ、やってみないとわからないからと勧めた。
それだからこそ、大槻エリも吹奏楽部に入りたいことを蘭に打ち明けられたのだろう。
そんな彼女が、なぜ好きで入った吹奏楽部を追い出されねばならないのか。
真冬日なのに、歌っているうちに暑くなる。
そういえば、中一の頃に蘭とCMソングを歌い合ったなと一哉は回想し出す。あれは初夏の川縁を歩いていた時だろう。
清涼飲料水のCMで、女子高生の爽やかな合唱が印象的なものだった。蘭の歌う柔らかな主旋律に被せるように、一哉は女声合唱のアルトに相応する部分を歌った。
今は出せない、ボーイソプラノ。
歌いながら、薄桜色に藍鼠のチェック柄のマフラーをほどいた。
◇◇◇
日が西へ傾き、薄暗くなる。
合唱の練習はお開きとなるが、練習の参加者一同は離れがたいのか河川敷に入り浸っていた。
朱色に浮かぶ、黒に染まった山の影。
物悲しさを抱かせる冬の夕暮れを、蘭は好きだと話して聞かせた。
再びマフラーを首に巻いている一哉に、先ほどに蘭との関係性について質問してきた男生徒が声をかけた。背に負っている通学鞄の名前欄には村上と書き込まれている。
「しかし、飛鳥君って歌上手いよね」
歌に自信があるとはいえど、自慢と捉えられかねないので素直に肯定しにくい。
しどろもどろに「ありがと」と返した直後に隣から「当たり前だっぺよ」と豪快に笑う声がした。
笑う合田は「だってこいつ、元合唱部なんだからよ」とつけ加える。
村上はもじもじとした様子を見せると、秘密を打ち明けるような小さめの声で「あのさ……」と切り出した。
「俺、飛鳥君みたいになりたかったな。イケメンで頭良くて歌も上手くて……音澤みたいな美人の女子と仲良いだなんて夢の夢だよ」
眉上に詰められた短髪に、高くも低くもない背丈の村上はいかにもな男子中学生という特徴のない容姿だが、素直そうな面構えをしていた。
「あと、ゴウダ君から絵も上手いって聞いたよ」
イケメンって憧れるよなぁ、同じ学校のタケちゃんもかっこいいけど飛鳥君は軽薄さの欠片もない硬派な雰囲気があるよねと村上は心から羨ましそうに言い連ねる。
その様子を目にした女生徒達から「愛の告白かよ!」と笑いながら突っ込まれ、村上は「ちげーよ。俺はノンケだよ」と笑いながら慌てた動作を交えて否定した。
「……俺、言うほどの器じゃないよ。楽器は出来ねえしさ」
一哉が持ち合わせているもの全てを楽をして手に入れたと言うつもりではないことぐらいは存じ上げている。
女子は女子で学年を問わず織絵に憧れる者が多く存在し、学校内を歩いていると度々「橘先輩って美人でスタイル良くて羨ましいな~」だの「髪型がかわいい」だの「指揮振ってる姿がかっこいいよね」と仲間内で色めきながら話し込んでいる様子に否が応でも居合わせた。
村上も、無い物ねだりゆえの憧れが口をついて出たようなもの。村上の照れた顔は、軽々しく発言したわけではないと証明するも同然。
仮に小学生だったならば村上の発言が嬉しくて有頂天になったかもしれないが、15の少年となった今では戸惑うばかりで素直に喜べなかった。
一哉はただ、蘭に追い付きたかった。
蘭に釣り合う男になりたかった。
出会って日が経たないうちから、蘭は聡明で博識な少女だとわかる。
花の名前、色の名前、星の名前、宝石の名前、神話の神々と妖精の名前。聞いたことはあるが名も知らないクラシック音楽の曲名。
まるで頭の中に百科事典が内蔵されているかのように、蘭の唇からは様々なものの固有名詞が飛び出す。
蘭が好きだと話した朱鷺草が、一哉の誕生花であるという偶然も蘭の口から聞いて知った。
「知りたがりなの」
蘭はすごいな、何でも知っていると11歳の一哉は感心したままに口に出すと、十つの少女は溌剌と笑ってそう返した。
「図書館に行くの好きなんだ。気になると何でも調べ上げて、答えが分からないと気が済まないの」
そして、憧れの場所は美術館に併設されている県立図書館だと告げる。
「雑学でも何でも、身に付けた知識が増えるごとに快感を覚えるというか楽しくなってくるんだよね。もはや中毒だよ」
「蘭はすげえなぁ。俺なんて今が楽しければいいなんて思ってたよ。かっこ悪いだろ?」
そんなことはないと蘭はにこやかに返す。
「一哉ちゃん、風と雲の動きで天気読むじゃん。私、急に風が強くなって涼しくなったら雨が降るだなんて知らなかった」
「新潟は雨と雷多いんだよ。都会で便利なとこだけど気候はクレイジーだよ。だから知らないうちにそういう知識身に付いちまったの」
穏やかな秋空を見上げて「うん! 今日は何もない!」と大袈裟に頷く一哉がおかしかったのか、声を立てて蘭は笑い出す。
ひとしきり笑った後、蘭は真っ直ぐに一哉を見据えた。切れ長の瞳がキラキラと輝いていたのは、笑いすぎてにじみ出た涙の名残だろうか。
「かっこいいよ、そういうの。ファンタジーの世界の能力みたい」
知的好奇心と向学心の旺盛な蘭。
それまではマイペースに生きていた一哉は、何かに目覚めたかのように家にある辞書やら図鑑やら読み漁るようになった。
漫画の描き方のテキストを借りる以外は無関心だった図書館へ足繁く通うようにもなった。
漠然と地元の中学校へ行くのだろうと考えていた少年は、中学受験を意識するようになる。
表向きは医師の家系だから(父親は会社勤めのサラリーマンだが)医療関係の仕事に就きたいと理由付けた。
医療に携わる職業を意識したのは嘘ではなかったが、向学心が芽生えた根底には好きな女の子に追い付きたい、釣り合いたいという願望があった。
付け焼き刃の受験勉強とはいえど一哉は地頭が良かったので、塾通いを始めた途端に成績が伸び始めた。
国立大の附属中学と私立中学を受験する、塾通いもすると宣言した際に合田と浜津からは「お前、そこまでガリ勉だったっけか」と突っ込まれたが応援してくれた。
両親は理由はどうであれ向学心が芽生えたことを心から喜び、結果はどうであれ頑張った実績は糧になるからと励ました。
蘭が慧子に憧れて知識と教養を身に付けたように、一哉は蘭に釣り合うべく知識を頭に叩き込んだ。
いつも見上げている彼女と、肩を並べたい。
その思いだけを胸に、幼く純真な少年は日々の精進に精進を重ねて躍進する。
少年の内なる輝きは、一朝一夕で身に付けられるものではない。
楽をしているなど、誰が言えようか。
◇◇◇
いよいよ空が紺色へ染まり始めた頃に一同はようやく足を進めた。
合田の買い込んだパンの耳はかなりの分量はあったはずだが、10人を超える人数でパンの耳をつまんだ結果、短時間でなくなった。
これよぉ、砂糖と油で炒めっと旨いんだ。
マジかよ、やってみっぺ。
でもフライパン焦げっぞ?
少年の面影の残る浜津の声と野太い合田の声とのかけ合いが和やかだ。
「合格したら集まらないかい? 宴会ごっこやるべ」
「いいねー! そうそう、蘭ちゃんも呼ぶかい?」
由香理がそう話しながら顎をそびやかせて一哉を振り返るとニヤリと笑う。つられて他のメンバーも同様にニヤリと笑って「いいねー」と声を合わせた。
人垣の中で織絵が「ゴウダ君はF高だっけか」と訊ね、合田は「んだ」と返す。
「橘は祥蘭け?」
「うん。芸術科」
橘って吹奏楽部だったべ? なら、楽器やんのけ。
うん。クラリネット。
そこからの進展はなかった。
合田康範は、翠楓学園のマドンナ・橘織絵が向ける想いを知らない。
その後の織絵は合田に何かを言いたそうにするも、すぐに宴会の話に混ざることにしたようだ。
「ねえ、宴会の会場はどうする?」
静かなはずのハスキーボイスが人垣の間に冴え渡る。
「やっぱりシロちゃん家かい?」
「広いしな」
「なんだかんだでいつも私ん家だべした。母屋が使えない時は蔵でも宴会できるよ」
蔵。
いつだか白沢が蘭と一哉の逢瀬を覗き見した、あの白漆喰の蔵屋敷だ。
蔵で宴会と聞いて中学生達は色めいたので、白沢は蔵とは決まってないからと忠告した。蔵屋敷など、なかなか入れるものではない。
はーい、はいはい。手を挙げて一哉は「はい」を連呼した。
「それじゃ、俺が蘭に宴会さ来られるか聞いてみるよ」
その意気だ、と白沢がからかう。
今いるメンバーでも充分に楽しいのだが、好きな女の子がいると考えただけでも心が浮き立つ思いだ。
宴会には蘭の好きな甘味の類いも出るのだろうか。瞳をきらめかせて、頬を上気させて歓声を上げる蘭の姿が瞼に浮かぶ。
それなら、と白沢が言った。
「甘いもん用意しねっきゃな。宴会にデザートがないと寂しいべ?」
幼なじみだけに、白沢も蘭の甘党っぷりを存じ上げている。
「つぶあんと白玉粉か? いや、わらび餅でもいいな」
「なになに、白玉雑煮作るの?」
「クリームあんみつ出たら食べっかい?」
いいねー。女生徒を中心に賛成の声が上がった。
「よしきた。業務スーパーで白玉粉とアイス1キロ入った箱買い込むか。白玉団子、兄ちゃんとばあちゃんとで頑張って作っからよぉ」
白沢家は四世代同居で成り立つ。その分だけ人数が多く、業務スーパーにはお世話になっているのだ。
一哉にとって白沢小百合は織絵と合田を通じて知り合った公立中出身の友人のうち一人に過ぎない。
しかしながら、幼い頃から蘭と親しい白沢が羨ましかった。
自分が未だ知らないであろう蘭の姿を、知っているのだから。
「白沢も蘭のことよくわかってるよなぁ」
口をついて出た羨望。
当たり前だろうが、と返す白沢はどこか勝ち誇った様子だ。
当たり前のように「当たり前だろうが」と豪語された一哉は少しだけ、悔しい。
「伊達に幼稚園から付き合ってるわけでねえど? うちら兄ちゃん同士が仲良くてよぉ。みんなは他に食べたいもののリクエストあるかい」
でもさぁ、と不安げな声を出したのは絢。
「シロちゃんにばかり負担かけるのは申し訳ないから、私らも何か持ち寄るかい?」
「そうだね。それがいいよ」
織絵が賛同したのを皮切りに、次から次へと自分なら何を持って行くかと中学生達は話し込む。
合田は茨城の親戚から届いた干し芋、由香理と絢は何かしら作ると話している。
宴会はいわゆるケータリングの形式を取ることになった。
先ほどと同じように「はい」を連呼して一哉は手を挙げた。そして、はしゃいだ口調でこう言った。
「俺、コシヒカリの新米持ってくる!」
「生米持ち寄ってどうすんだよ!」
すかさず突っ込む合田と、沸き上がる笑い声。
なんだなんだ。
生米炊くのかい?
米持ち寄るって小学校の家庭科でなかった?
あったあった!
冗談だよ。俺も何か作ってくる。
「蘭ちゃんが来るなら留美ちゃん達も誘うかい?」
蘭と仲良しの親友達はエリを除いてアクの強い者達が揃っているが、一同はさほど嫌そうな反応はしていない。
「ミヨシも来たら賑やかになりそうだなぁ」
「力丸って宴会でも無表情なのかな」
あいつ顔自体はかわいいんだけどな、と言うは浜津だ。
「そうじゃないかい? 私ら9年間同じ学校だけど、未だにはっちゃける力丸を見たためしないもん」
春奈も手を挙げた。
「今いないメンバーならセイちゃんも呼びたい。私ら仲良いし」
いいねー。全員が賛成したあたりに、聖良の人となりの人畜無害さが垣間見える。
聖良もオーケストラの練習でこの場にいなかった。
「斎藤聖良? 希少な清涼剤的な存在だよなあ、あいつF女受けるんだっけか?」
「F女受けるってよ。セイちゃん家は教員の家系だし女は代々F女卒だって。あと、ここにいない人で呼びたい人はいるかい? 蔵屋敷パーティーなら4、5人は余裕あっぞ」
静かに!
眉をひそめ、口元に人差し指を立てるといういかにもなジェスチャーを交えて振り返ったのは由香理だった。短めの、内向きにまとまったポニーテールが後頭部で跳ねる。
張り詰めた声は、声量を抑えているにもかかわらず否が応でも耳に届いた。
2002年 2月 約束 3
由香理の声色から都合の悪いことが起きたとわかった一同は従うことにする。
松川にかかる橋のたもとからは複数の男女の笑い声。笑い声の主達の見てくれは至って普通の中学生なのに、口調のせいか軽薄そうな印象が拭えない。
ゲテモノを見たような歪んだ表情で、小さな声で白沢が言った。
「うっわ、吉田魅里」
その名前を耳にした途端、一哉は顔を強張らせた。
端正な顔に刻まれる、憎悪の感情。
落ち着かないのは合田と浜津。合田はたしなめるように一哉の肩に手を置いた。
飛鳥、落ち着けよ?
耳元で、そう囁く。
一方で春奈も絢も落ち着かない。
春奈の横では織絵もまた切れ長の細い目と弧を描いた眉をしかめているのだ。
その気になれば物陰に隠れる余裕のある距離感だ。足音を立てずに、一同は橋の下側へと寄る。
吉田は取り巻きの斎藤の他にも何人かの女子と男子を引き連れていた。
男子の中には武田がいて、人垣の中では最も背が高い。
やや長めのミディアムヘアのシルエットは特徴的で、人影が武田であることを象徴した。
「や~だぁ~、なんでタケちゃんまでいるんだよぉ?」
腹立たしそうな白沢は納得できないとだだっ子のように肩と腕を揺らして身動ぐ。絶望と怒りが混じった口調だった。
誤解されやすいが、白沢は決して武田に惚れているわけではない。あくまでも、芸能人へ憧れを向けるファンのようなものだ。
「タケちゃん頭いいしスポーツ万能だし見た目もかっこいいんだけどさぁ、ぶりっ子に弱いのが致命的なんだよなぁ」
苛立つ白沢に春奈があっけらかんと被せた。
「しかもマザコンだしな」
「マジで?」
絢の、日本人形に例えられる顔が気味悪いと言わんばかりに歪む。幻滅したと言いたげだ。
同じ小学校出身でも、一哉は武田と関わりがなかった。
武田の顔と名前と、文武両道であることと年の近い妹がそれなりの美少女であること以外はよく知らない。
二年間しか小学校が被っておらず卒業までクラスが異なったので、一哉が武田をよく知らないのも無理はない。
合田ほどではないが武田も一哉が転校してきた時点で女子中学生の平均並みに背が高く、更に手足が長いのでショートパンツの制服が様になっていた。
そこへもってきて顔つきの優れている武田は寡黙ながらも学年で目立つ存在だったので、一哉は転校したしりから「なんとなくだけど、かっこいい人」という印象を抱いている。
一哉のみならず合田も浜津も武田を「なんか、かっこいい人」と半ば雲上人のように思っていた。
雲上人のはずの武田は、入学当初はその寡黙な佇まいや飄々としながらも何事も器用にこなす優秀さから一目置かれていただろう。
そんな彼は二年生に進級する前頃から「言動がチャラくさくなったよね」と影で囁かれるようになる。
原因は、吉田魅里と親しくなったからだと多数の生徒が噂した。
吉田が気に入らない生徒を嘲笑えば、その対象が武田にとってよく知らない生徒でも一緒になって笑う。
それまでの武田は興味のない生徒に対しては無関心を決め込んでいたが、決して薄情な人物ではない。
例えば「給食当番の手が足りないから大鍋を運ぶのを手伝ってほしい」と声をかけられ、ひ弱そうな生徒が困った顔で「大量の煮物が入った熱くて重い大鍋」を持つ姿を目の当たりにすれば可哀想に思い、大鍋の片側の取っ手を持ってあげた。
背の低い生徒が黒板の高い所の文字を消すのに四苦八苦すれば、代わりに消してあげた。
誰かに頼られれば武田は嫌な顔一つもせずに丸腰で応じたので、生徒間では「頼りになる兄貴分」と認識されるようになる。
しかし、優秀な頼れる兄貴分も所詮は脆弱さの残る10代の子供に過ぎない。
せっかくの長所を打ち消しかねない致命的な弱点も当たり前のように持ち合わせ、他人の目から見ても丸分かりなほどの周りに左右されやすい性分、惚れっぽい体質、やや男尊女卑な思考がそれに当てはまった。
優秀だが、ブレの強い人物。
泉清中学校三年生の大半の生徒が抱く、現在の武田への印象だ。
「中一の頃はクールでかっこ良かったのによぉ」
残念そうな白沢だ。
周囲に頼られがちな武田は、分かりやすい態度で甘えられることに弱い。
女は少しばかり出来の悪い程度が一番かわいいと考えていた。
その、少しばかり出来の悪いちょっとかわいい女子に媚びた態度で声をかけられれば、武田は鼻の下を伸ばしては目をかけて甘やかした。
反面、著しく苦手分野が多い女子は面倒に思えて敬遠したが最も苦手意識を抱いたのは男を全く立てないであろう凛とした女傑タイプ。
勉強面で男子より優れていると、その時点で可愛げがないと不満に思った。
武田にとって、音澤蘭は可愛げのない女子の代表格。
美人だとは認めるが、心の奥底までを見透すような切れ長の瞳がいかにも一筋縄でいかなそうであるし、鼻筋の細い貴族的な顔立ちも気品の漂う仕草も気取っているように見えて鼻に付いた。
何よりも、男子を差し置いて定期テストで一番をキープしていることが武田は面白くない。
モデルみたいな美人と蘭を褒める者もいたが、蘭の最もたる特徴である長身も武田の目には可愛げがなく映る。
武田から見た何人かのかわいいと思う女子のうち一人が、吉田だった。
一年生の時のクラスが異なったはずの吉田魅里と仲良くなるきっかけはいくつかあっただろう。
武田は林と親しいので林つながりで吉田と会話を交わす機会は多かったが、二年生のクラス変えで同じクラスになったことが決定打となる。
自信家に見えて、周りの影響を受けやすく自分より優れた者に劣等感を抱えがちな二人は不思議と気が合った。
同じクラスになったその日に、何の考えもなく軽い気持ちで実は蘭が苦手なのだと口に出したその時から、吉田との精神的な距離は急激に縮まる。
双方の、利害が一致した瞬間だった。
「昔の硬派さが薄れてきたよね」
硬派なところが男の目線から見てもかっこ良かったのに、と浜津が残念そうにつぶやいた。
だから、と同調するは春奈。
「あれだべ? 吉田魅里と仲良くなったから」
「んなこと見りゃあ分かってるっつーの!」
合田の発言に白沢は噛み付くような口調と表情で返答する。そんな白沢は威嚇する小型犬の佇まいだ。
「しかもさ、あいつまでいるじゃん」
織絵が指さした先には一人だけ、異なる学生服を着た生徒がいる。
白沢も、由香理と絢の顔も嫌悪で歪む。春奈は「誰、あいつ?」とつぶやいた。
一哉と同じ、襟元に深緑のラインの入った学生服。
村上も、織絵が指さした少年を快く思わないのか苦虫を噛み潰したような顔で言った。
「音澤が来てなくて正解だったね……」
清水が丘小学校出身者は皆、顔を見合わせて頷く。
吉田が吹聴した嘘を信用し、蘭を傷つけた憎い「ゲス野郎」がそこにいた。
◇◇◇
一哉は、その「ゲス野郎」が嫌いだった。
二年生に進級したばかりの頃か。二年A組の教室に耳に覚えのない男子の声が響く。
「飛鳥川ってやついるー?」
はいはーい、俺だけど?
一哉と対面したのは、校内と飯坂線の車両内でで何度か姿を見かけたかもしれないが会話を交わしたことのない男生徒だった。
「どしたの? 何か用?」
一哉は気さくに声をかけたが目の前の男生徒は意地悪そうな笑みを浮かべていたので、一哉の顔からは笑顔が消え去る。
何なの、こいつ?
マジで気持ち悪りぃんですけど?
薄気味悪すぎた。
関わらないに越したことはないと悟る一哉は早々と切り上げたかったが、男生徒はいつまで経っても何も言わずにニヤニヤと薄ら笑いを顔面に張り付けたまま一哉を見ている。
不快感を抱いたのは一哉だけではなかった。
モジャ山とジョリ松、織絵を筆頭とした複数の友人が歩み寄り、まず織絵が「何?」と苛立った態度で男生徒に問う。
「冷やかしならさっさと出て行って」
時々激情的な姿を垣間見せる織絵だが、無闇に声を張り上げたりはしない。プライベートならばともかく学校内で織絵の怒鳴る姿を見た者は存在しないであろう。
この時も口調は静かだが、普段と異なるのは突き放す口調であることだった。声だけで相手をはね退けそうな、冷淡さを含んだ響きだ。
腕組みをし、鋭い眼差しで真っ向から睨みつけてわが事のように明らかに怒っている織絵。
その様子はただ事ではないことを、織絵が男生徒を嫌悪していることを物語る。
続けてモジャ山。
「お前よぉ、名乗りもしねぇで何なん? 何か言ったらどうなの?」
俺は奥山直樹っつーんだけど、あんたは何組の誰?
モジャ山なりの誠意のつもりか、ぶっきらぼうに名乗りつつ男生徒に名乗るよう促す。
「君さぁ……」
男生徒はモジャ山を無視して一哉を指さす。
スローモーションのように勿体つけて口を開いたかと思えば、ねちっこい口調で言った。
「女みてえな顔」
口が立つ一哉は、普段ならば何かしら口答えして応戦できた。
幼少の頃に友達をバカにしてかかるいじめっ子達を言い負かせたことなどは一度や二度ではなかった。
この時の一哉は、流行りの言い方をすれば「頭がフリーズした」といえば良いだろう。
あまりの出来事に頭が真っ白になり、言葉を失った。
「イイ気になるなよ」
男生徒はバカにするような薄ら笑いを浮かべたまま立ち去る。
「なんだよあの糞野郎、ムカつくやつだなぁ!」
モジャ山は憤り、教室から駆け出す。
「おい、そこのゲス野郎! あんた失礼すぎるだろ! アズは俺のマブダチなんだよ! 謝れよ! 謝んねーならお前のクラスの担任に言うぞぉ!」
と怒鳴り散らして件の男生徒を追いかけてしつこく食い下がった。
廊下からモジャ山の声が響く中でジョリ松は放心する一哉の肩を支え、怒りを隠せない織絵は「言いにくいんだけどさ」と前置きする。
「あいつ、蘭ちゃんが男嫌いになった原因作りやがった張本人だよ」
◇◇◇
三年生になった今では頻度は減ったものの、初対面にして難癖をつけられて以降、件の男生徒は一哉を見るなり突っかかるようになった。
そして、モジャ山が廊下で詰め寄った際に「そこのゲス野郎」と呼んだので一哉も腹の底で彼をゲス野郎と呼ぶことにした。
第一、ゲス野郎は一切名乗りもしなかった。同じ小学校という織絵が名前を口に出してはいたが、一哉はゲス野郎の正しい名前など呼ぶ気にも覚える気にもなれない。
詰めが甘いのか愚鈍なのかは知らないが、蘭を傷つけた憎きゲス野郎はわかりやすく一哉への敵対心を剥き出しにするので、他の生徒からは「イケメンに嫉妬して見苦しい」と後ろ指を差されて疎まれた。
見かねた生徒が何度か教師に報告したらしく、その毎指導を受けたそうだがゲス野郎は一哉に絡むことを止めない。
難癖もくだらない内容ばかりなので始めは無視に徹していたが、何も言い返してこないことを逆手に取り執拗に絡むので、一哉は正論混じりの屁理屈で返すことにした。
顔が女みたいだ、と言われれば「それじゃ、男くさい顔に整形するお金を全額支払えるの? 支払えないなら人の顔にケチつけるのやめて?」と言って返した。
男のくせに合唱部など女々しいと言われれば、まずは「男らしい部活って何なの?」と前置きし「合唱部の男の先輩を連れてくるから、同じセリフを目の前で言ってみなよ」と返した。
どこで情報を仕入れたのか絵が趣味などオタクくさいと揶揄されれば「オタクくさいっていかにも絵を描く人達をバカにしてるみたいな言い方だけど、美術の先生と美術部のやつの前でも言えるの? あんたは漫画どころか絵本すら読んだこともないの?」と返した。
更には「絵を生業とする著名人の前でも言えるの?」とつけ足して。
いつしか一哉に突っかかる理由が明らかになると、ゲス野郎は女子を中心に総スカンを喰らうようになる。
あいつ、小学生の時にアズの彼女が好きだったらしいよ。
でも、いじめてたって話じゃん。
他の女子もあいつのこと好きだったらしくて、アズの彼女への嘘の悪口を吹き込んだらすっかり真に受けて、手のひら返していじめたんだって。
あいつがしつこく嫌がらせしてきたせいで、その子は男嫌いに成り果てたらしいよ。
男嫌いになったのにアズと仲良くなったのが面白くないんだって。
何それ、自分から嫌がらせしておいて仲直りできない逆恨み?
自分ができなかったことをやり遂げた人を妬むやつっているじゃん? その類いでしょ。
それでアズに突っかかるわけ?
本っ当、気持ち悪いやつ。
嫌でも耳に入ってくる真相。
そして、ゲス野郎が執拗に一哉に突っかかる理由が「蘭を引き合いに因縁をつければ、一哉は蘭が疎ましくなって離れると思った」と人伝いに知った時には、殴りかかりたい衝動を抑えるのに精一杯だった。
中学二年生の、夏休みに入る前のことだった。
「残念でした。俺は好きな子に関しては意地っ張りなの。あんたが俺と蘭ちゃんを引き裂こうとすればするほど俺は意固地になるんでね」
ゲス野郎のいる教室へ出向いて、恨み節をお見舞いするだけに留めるのも一苦労だ。
掴みかかりたい、殴りつけたい、怒鳴り散らしてやりたい。
それほどまでに、蘭を傷つけられた恨みは凄まじい。
よくもまあ、掴みかかることもなく冷静さをキープできていたと一哉は我ながら当時の自分を褒めてやりたいと思ったという。
「俺は、蘭ちゃんを守ってやらねえどころかバカなやつの嘘八百に流されて蘭ちゃんを裏切ったあんたとは全然違うの」
その時のゲス野郎は、薄ら笑いを浮かべてはいるが顔色が悪かったと記憶している。
教室にいた生徒達は皆、無言だった。
囃し立てることもなく、止めに入ることもない。何も言わず、固唾を飲んで静観するだけだ。
「怪人クラッシャーこと吉田なんちゃらの差し金か知らねえけど、俺は意地でも蘭ちゃんから離れねえよ」
薄ら笑いが消える。
今回の一哉への嫌がらせじみた難癖攻撃に怪人クラッシャーこと吉田魅里が関わっていたかは定かではないが、怪人クラッシャーが目の前のゲス野郎に何らかの影響を与えていたのは確かだ。
「謝りもしねかったくせに、しつこくいじめたくせに、何が蘭ちゃんと仲良くしている俺が面白くねえだよ?」
鮮やかに、脳裏に甦る、神楽殿の下で泣き崩れる少女の姿。
「俺が離れればいいって、いかにも蘭ちゃんが孤立するのを願っているみたいな言い方だよな」
初めて見た、蘭の涙。
「蘭ちゃんがどれだけ苦しんできたかわかってんの? まだ10歳になるかならないかの年齢で毎日毎日周りの男子共を警戒しながら生きてるって考えただけで悲しくならねえの? 胸が痛まねえの? お前が蘭ちゃんにしてきたのはそういうことなんだよ」
桜の下に佇む少女の黒い瞳は警戒心に満ちていた。
何も知らない十つの少年だった一哉は単に見知らぬ者へ警戒心に過ぎないと考えていたが、共に過ごすうちに明らかになる真実。
大人びているとはいえ、十つになるかならないかの幼子が不信感を抱えながら生きてきたと考えただけで、胸が潰れそうになる。
桜、好きなの?
この一言だけで充分だった。
固く閉ざされた扉の鍵を開けるように。
春の陽射しが雪を解かすように。
少年の純粋な好奇心は、少女の凍てついた心を優しく解かしてゆく。
「また、寄ってたかって蘭ちゃんを傷つけるつもりかよ?」
あの時、声をかけなければ蘭が溌剌とした笑顔を見せることは未だになかったかもしれない。
蘭はいつも一哉の前では伏し目がちな目を上げて、輝かんばかりの笑顔を向ける。
脳裏をちらつく、恋い慕う少女。笑顔と泣き顔の蘭が入り乱れる。
名前を呼びながら笑いかける蘭と、両手で口元を覆って泣き崩れる蘭の対比が辛すぎた。
もう、堪えられなかった。
「バカにするのも大概にしろで!!」
この時、一哉は初めて他人様に大声を浴びせかけて凄んだ。
いじめられた友達を助け出す際にいじめっ子に屁理屈をぶちまけて楯突きはしたが、声を荒らげたことはなかった。
記憶の中の蘭とリンクするかのように、怒りに満ちた眼差しに不釣り合いな大粒の涙が頬を伝い落ちる。
――俺は意地でも、あの子から離れない!!――
そう吐き捨てた時、騒ぎを聞きつけた担任が背後から肩を抱いて「奴」の前から引き剥がした。
2002年2月 約束・4
◇◇◇
橋の下に隠れる一同の表情は様々だ。
拳を震わせ、顔に怒りを刻み込む者。
頑なに息を潜める者。
「でもぉ、みーちゃんさぁ、滑り止め受かって良かったじゃーん」
斎藤は相変わらずお嬢様然とした容姿にそぐわない幼い動作を交えている。普段の素行が素行なだけに、隠れている一同は腹黒い斎藤が心から喜んでいるかを疑わしく思う。
「松井とか上野先生が内申点がどうとか言ってたけど、高校入試なんてチョロいもんだっての」
薄暗がりでそれなりに離れた場所にいるので顔は見えないが、ねちっこく嘲るような口調からどんな表情をしているかを容易に想像できる。
三日月型に目を細め、鼻の下を間延びさせつつ口角をアンバランスな角度に上げ、上目遣いで目の前の相手をすくい上げるように見ながら笑う。
笑う毎に上唇からちらりと見える歯も童話に出てくる悪賢い小動物を連想させる。
吉田の顔の造りは平凡だ。
青白い肌と真っ黒い髪の毛のコントラストがハッキリしたところは和風美人の風情があるからか雰囲気に誤魔化されてちょっとかわいいと評する者もいれば、ズル賢い性分が滲みでた表情からちょいブスと評する者もいたりと評価は二分しがちだ。
しかし、人をバカにする時の悪巧みしているような笑顔をこの上なく醜いと不快に思うのは双方に共通した。
各々の不快だから思い出したくないという意思に反して、吉田が得意な他人を嘲る笑みは嫌でも目に浮かぶ。
吉田は、併願校である私立高校に合格していた。
合格通知を手に嬉し泣きをするのはよくある光景だが、涙ぐんで目をこすりながら教室に入る姿や、瞼を赤く染めて泣き笑いする吉田を一部の男子が取り囲んでいた光景に「これ見よがしに……」と眉をひそめる女子が存在するあたり、彼女の同性間での評判はこの三年の間で大幅に下がった。
本命は市内の県立高校だが、同じ高校を受験する者の中には良い顔をしない者もいる。
「あいつ、滑り止めどこ受かったっけかなぁ」
浜津が独り言のつもりで口に出したつもりが、合田が「仙台の私立だろ?」と答える。
「会津か郡山じゃなかった?」
「俺、いわきの高校とも聞いたけど」
さすがに会津といわきの高校はあり得ないとの声が上がる。
会津地方は福島以上に積雪する。夏生まれだから冬と積雪が嫌いだと公言する吉田がわざわざ豪雪地帯の高校を受験する物好きではないことを、泉清中学校の生徒達は皆知っていた。
いわきに至っては高速バスで片道2時間。下宿でもしない限りあり得ない話だ。
「ハッキリ言えるのは、福島市内の私立でねえってことだな」
なぜ他の市町村にこだわるのか、とつぶやくは一哉だ。
蘭も地元から離れた私立高校を受けたが、音楽科のある私立高校が市内にはなかったからという明確な理由によるものだ。
「この町に居づらくなったんじゃないの?」
態度には出さないけど、とつけ加えて織絵が言った。続けて発言したのは織絵と同じモノトーンのセーラー服を着た女子。
「市内の吹奏楽やってる中学生の間じゃ悪い意味で有名だし」
高潔なる雪の女王を追い出した張本人だから、と。
蘭はコンクール会場で相当な注目を浴びた。
吹奏楽コンクールならびにアンサンブルコンテストに出場したのは一年生の時のみ。
中学三年生の今ほど長身ではないが、冴え冴えとした容貌と気品溢れる立ち振舞いは見る者に鮮烈すぎる印象を与えた。
そんな彼女が翌年のコンクール会場にぱったりと姿を見せなくなれば、様々な噂が立ち上るのは自然なこと。
その中でもまことしやかに囁かれたのが「部員からのやっかみを買い、いじめられて追い出された」という噂だ。
一方で、吉田も市内の吹奏楽に関わる中学生の間では名の知れた生徒だった。
小学生時代の春奈との一件で既に南沢又小学校吹奏楽部の児童からの株を落としていたが、中学校進学以降もコンクール会場で他校の部員の容姿について陰口を叩く様は「感じ悪い」と他校生からの反感を買った。
文化祭や小規模な演奏会に組み込まれる部の代表による部活動紹介でも、アイドルを真似た口調と身体をくねらせる動作が知性も品格も見受けられないと酷評される始末だった。
顧問を紹介するコメントも「上野先生は、とーっても美人でぇ」とわざとらしく間延びした口調は敬意が全く感じられず、観客からは「今年の泉清の部長は一体何なんだね」と批判が相次いだ。
人気アイドルグループを意識したとはいえど、少しばかりの照れが残っていたのは誤魔化せないだけに思い切っておらず、見ていて恥ずかしいとの声も上がった。
二年生の吹奏楽コンクール県大会で東北大会出場を逃したことをきっかけに、地方都市ならではのネットワークによりいくつかの噂が広まり始める。
上手い生徒を妬んで追い出したらしい。
気に入らない部員をいじめていたらしい。
そして、泉清中学校吹奏楽部が地に堕ちた元凶である、と。
「尊大に見えるけど、吉田は案外小心者だよ」
「そうかい? 偉そうじゃん」
俺、見たんだと合田は語る。
蘭や留美達と会う約束をしていたのか私服姿で通学路を歩く大槻エリと、学校帰りの吉田が鉢合わせる様子を。
「なんで遅くなったか知らねえけど、どうせお気に入りの男子と道草食ってダベっていたんだっぺよ。大槻もビクビクしてたな。無理もねえけどよぉ」
◇◇◇
秋頃だったかな、と合田は回想ながら語る。
エリに対する恋愛感情を一切持たない合田だが、いざとなればエリを庇い応戦するつもりだった。
目の前にいじめを受ける者がいれば、仮に恋愛感情を抱く異性であろうとただの同級生だろうと関係性など一切無視して助け出すことが当たり前だ、合田はそう考えていた。
しかし、あからさまに異性を庇い立てれば妙な噂を流す不届きものは必ず現れる。
ましてや、恋愛で泣きを見たエリとなれば慎重にならざるを得ない。
だから合田は吉田とその取り巻きが怪しい動きを見せれば教師へ密告し、生徒会への意見箱に「吉田魅里が大槻エリをいじめている」と記した紙を複数回投げ込んだ。
エリは知らないが、意見箱への投書という行動に出た生徒は合田だけではない。
いじめに反発を抱く生徒達は、教師への密告を厭わず再三に渡り生徒会の意見箱に投書した。
学校での吉田は合田の視点から見ても腹立たしいほどに尊大で、こいつに人権などないと言わんばかりに毎日のようにエリをイビり倒している。
顔面に気持ちの悪い笑みを張り付けて行動を監視し、口調を真似して嘲笑うのだ。
御託を並べて苦手分野を押し付けたり(だいたいは他の女子に阻止されるが)嘘を言うなど口先で陥れるのは積極的だが、私物を隠したり落書きをするなどの手を使うことに関しては一切ノータッチだ。
自らの手を汚さずにいじめるやり方だが、その根底には「実行役になれば、バレた時に言い逃れできない」という考えがあった。
故に、お気に入りの男子と取り巻きの女子に「こんな展開になったら面白くない?」と軽い乗りでアイデアを出すという形でいじめた。
言葉と態度のいじめならば、証拠に残らない。
見抜いている者は、どれだけ存在するだろう。
どうせ、すれ違い様に吉田はエリをバカにした言葉を投げつけるのだろうと予想がつく。
服装のことも怯えた態度も、笑い種にするに違いない。
しかし、合田の心配とは裏腹の結果となる。
表情を強張らせたエリの横を吉田は後ろめたそうに、しおらしい顔で足早に通りすぎる。合田には気付いていないようであった。
合田は「大槻、大丈夫けー?」と敢えて大声で呼んだ。牽制のつもりだ。
その後も敢えての大声で「吉田に何かされなかったけー?」と言った。
そして深く息をつくエリに駆け寄る。
「よりによってあいつとニアミスだなんてヤバかったな」
ちらりと後方を振り返ると身を縮めるように吉田は背を丸めて、早歩きで北側へ向かう姿が見えた。
「ありがとう。何も言われなくてよかった」
胸を撫で下ろすエリ。
清楚でフェミニンな服装が好きなのか、この日のエリはアイボリーのアンサンブルニットにワインレッド系のタータンチェックがいかにも秋らしい膝下丈のスカートを履いていた。
「服装のこと、バカにされるかと思ったもん。この前ピンクのカーディガン着て買い物に行ったらタケちゃんと鉢合わせてさぁ。たぶんタケちゃんが言いふらしたっぽいんだけど、みーちゃんがニヤニヤ笑いながら『ピンクの服着てたんだって~?』って言ってきたんだ」
一緒にいた武田も含み笑いで見下ろしていた、とエリは不満そうに語った。
「みーちゃんに言わせると、制服以外でスカートを履くとかレースのついた服とか、ピンクの服を着るとか、女の子らしい格好をする時点でぶりっ子なんだって」
「難癖にも程があるっつーの。くだらねえなぁ」
合田はあきれた。自分の知らないところで、嫁イビりさながらのくだらない難癖をつけられていたと考えただけで他人事ながらエリが不憫でならない。
「ぶりっ子なのは吉田だっぺよ。服なんか好きなの着ればいいべに、バカにされる筋合いなんかねえっつーの。なぁ?」
そうだよね、と、いつになく力の入った口調で返答するエリ。
「ごめん。これから蘭ちゃん達と会うんだ。そうそう、蘭ちゃんで思い出したけど、蘭ちゃん羨ましいなぁ。あんなかっこいい人と仲良いんだもん」
「あ~、飛鳥のこと?」
「一哉君、すごい美少年だよね。蘭ちゃんとお似合いだよぉ」
蘭の容姿への憧れか、それとも相思相愛の関係性への憧れか心底羨ましそうな様子のエリは急に落ち込んだ顔となる。
「私みたいなブスには王子様なんて現れないから。恋なんてとうに諦めてっけど……」
「おいおい……」
取り繕うように笑顔を見せて「じゃ、行ってくる」と小走りで去るエリの後ろ姿が切なかった。
吉田を筆頭とした複数の生徒からのいじめを通して、エリの自己評価は格段に下がった。
林との一件も、元はといえば吉田が執拗にからかったからだ。
「まったく、言うほどブスじゃねえべよ」
◇◇◇
始めは尊大なやつだと思ったと合田は前置きする。
「吉田は周りに人がいると気が大きくなってターゲットの生徒にいろいろ言うんだけどよぉ、一人になるとビビって何もできなくなるんだよ」
思い当たる節があると春奈が言った。
「私の髪型をバカにした時も、決まって取り巻きがいる時だったな」
不機嫌そうな顔で春奈はフンッと鼻を鳴らし「一人じゃ意気がることのできねぇヘタレがよぉ」とつぶやく。
「女っぽい格好しただけでぶりっ子呼ばわりするのも短絡的すぎるな」
気の毒だわ、と一哉はエリに同情するほかない。
エリとは時々、通学路ですれ違った。
二年生の頃、一哉は通学路でエリに呼び止められて蘭が再び吉田からのやっかみを買い孤立されかけていることを告げられる。
「いつも蘭ちゃんに助けらっちぃ。なのに、私は守ってもらってばっかで何の力にもなれてない」
自嘲しながら己の無力さを嘆くエリの姿は目もあてられない。
「俺は、エリちゃんが蘭の傍らにいるだけで十分に貢献できてると思うよ」
慰めではない。
孤立する辛さを知っている蘭には、友達の存在が如何に心強いかを存じ上げているはずだ。
「味方がいると実感できること自体、蘭にとっての支えになるんじゃねえかな?」
ありがとうと告げると、エリは俯いたまま言った。
「男子はみーちゃん……吉田さんに乗っかっていろいろ悪く言うけど、一哉君だけは蘭ちゃんを信じてあげて欲しいんだ」
余裕綽々の笑顔と共に「もちろんだよ」返した一哉だが、腹の内では怒りと悲しみが交錯する。
エリと別れた後に涙があふれ出るのを堪えながら自転車を走らせた。
蘭がエリを庇い立てるように、エリは自身も傷つきながらも蘭を気にかける優しさを持ち続けた。
人から言われたのか、エリ自身がそう思うのかは定かではないが、エリは自分を弱いと卑下した。
弱いわけあるものか。
いじめを受けるという苦しい状況で、他者を気づかう優しさを持ち続ける者のどこが弱いというのだろう。
「似合わないやつの僻みだべした。どうせ」
腕組みしながら織絵はボソリとつぶやいた。
織絵にも身に覚えがある。
小学校高学年の頃か。ハーフアップにリボンをつけた日の放課後、吉田が吹奏楽部の1学年下の取り巻きと一緒になって「高学年にもなって頭にリボンをつけるなんてぶりっ子」と陰口を叩いていたことを思い出したのだ。
藍色が鮮やかなデニム地に、白い水玉柄がどことなく活動的な印象のあるリボンのバレッタ。
久方ぶりに会えた親戚からのプレゼントだった。
カジュアルな服装が多い織絵の趣味と、薄茶色の髪に映えることを考慮して選んでくれたのだろう。
大人びた容姿の自分には似合わないと敬遠していたリボンをカジュアルダウンさせるデニム地に、甘くなりすぎないアシンメトリーなデザインを織絵は気に入った。
陰口を言われた後も気付いていないふりに徹したが、優しい思い出を汚された怒りは収まらなかった。
陰口を叩く前に吉田は織絵のリボンを褒めただけに怒りは尚更深まる。
その後に聖良から「リボンが似合うから僻んでいるだけだよ」とフォローされたことも、芋づる式に思い出した。
「ああいうのがいっから女らしいものが好きって言いにくいんだよねぇ」
ミッションスクールに通う女生徒がうんざりした顔で言った。
「会社のお局でねぇんだからよぉ」
いちいち人の服装にケチつけるなってのなぁ、と白沢が言う。口々に「だから」と同感の声を上げるは女子一同。
「みーちゃんみたいな根性悪いやつが将来お局とか嫁イビりする小姑みたいになんのかね」
「わかんねえぞ。あいつ、荒川先輩に呼び出し喰らったことあっから……」
会社勤めでもした日には却って目を付けられてイビられていそうだと村上が予測する。
二年も前の、それも仲間内で起きたはずの出来事を部外者であるはずの生徒達が知っている。
何で聞きかじったかまでは覚えていない。
吹奏楽部員から広まったのかもしれないし、私はかわいそうな被害者と周囲に印象づけつつ荒川を悪者扱いさせたいがゆえに吉田本人が言い広めたのかもしれない。
漫画かドラマでしか見たことのない典型的な吊し上げが実際に起きたとなれば、記憶から忘れ去ることは難しい。
「第一、あいつを気に入っていたのって吹奏楽部の先輩だけだろ? 吹奏楽部以外の……特に男の先輩からの評判は最悪だったぞ。チャラくさい話し方が可愛げないとか、『モー娘。』のダンスの猿真似が下手くそだし生意気で鼻に付くってダメ出ししていたしな。それから……」
村上は、話しにくそうに一哉を見た。
「音澤の件であいつの根性の悪さが既に知れ渡ってっから、信用できねえって疑ってる先輩が多かったんだよ。その上、音澤の兄ちゃんすげえ有名だったから……」
「知ってる。うちのお姉ちゃんが言ってた」
遮るように口を挟む織絵。相手が話し終えるより先に腰を折る行為は織絵にしては甚だ珍しい。
織絵には姉がいる。蘭の兄と白沢の兄と同い年で、三人はとても仲が良いのだ。
「秀ちゃん、かっこ良かったもんねー。うちの兄ちゃんも憧れてたってよ」
続けて口を出した白沢も興奮気味だった。耳だけを白沢と織絵に傾け、村上は視線を一哉へと向ける。
不意打ちで視線が合う度にドキドキさせられると女子が口を揃えるのも頷ける、見る者を圧倒させる力強さを宿す大きな瞳。
かっこいいなぁ。
俺もこんな風になりたかったなぁ。
合田を通じて一哉と知り合ったその瞬間、村上は憧れを向けた。
その頃は一哉も村上も似たり寄ったりの背丈だったが、脚の長いしなやかな体躯、目鼻立ちの整った顔、引き結んだ口元も、柑橘の香りが似合いそうなさらさらの黒髪も、いずれも村上が持ち合わせていないものだった。
特に村上が羨んだのは、皆が彼の最大の特徴で魅力でもあると皆が口を揃える、人馴れした猫を思わせる大きな瞳だった。
凛とした中に愛嬌を宿す黒い瞳に蘭が映り込む時、その輝きは暖かく優しいものへと変化する。
美しい容貌も、心から恋慕う女の子がいる喜びを知っていることも羨ましい。
そんな彼の瞳の奥にドス黒く渦巻く、憎悪と怒り。
自分がされたわけでもないのに、一哉は我が事のように怒り、駆け出したい衝動と戦っている。
村上が気づかうより先に、合田が背に手を添えて一哉を気づかった。
「あいつの兄ちゃん……伝説の音澤会長ってイケメンで秀才でダンディな性格でモテてたからよぉ、音澤会長の妹いじめたってことで二個上の先輩の間でも評判が最悪だったんだで」
搾り出すように「わかんねえよ」と呻く声。
声は村上の視線の先から聞こえる。この時の一哉は俯いていた。
ひたすらに、怒りに堪えていたのだ。
「意味わかんねえよ。村上君、数だけならあいつより蘭についてるやつが多かったってことだよね?」
顔を上げた一哉と村上の視線がかち合う。仇討ちに向かう剣士の面影のある、燃え立つ怒りが瞳の奥に垣間見えた。
その気迫に、村上は頷くしかない。
「矛盾しすぎてるよ。なんで味方の多いはずの蘭ちゃんばっかり辛い思いして、あんな女がデカイ面晒して好き勝手やってるんだよ……」
まあまあ、と一哉をなだめすかす浜津の顔も、背を支える合田の顔も焦っている。
「自分も苦しんでる最中で身を挺していじめられてる友達助けて……周りも明らかに蘭ちゃんが正しいってわかっているんだよね?」
そうだよ、と弱々しく答えたのは白沢だ。
「それなのに、泉清のやつらは吉田なんちゃらを放任かよ。確かに、蘭ちゃんを気づかったり止めに入る人もいる話は聞いてるよ」
視線を合田に向けて「意見箱に書いた話も聞いてたよ」とも口にした。
「でも、あのバカな女に逆らうのが面倒くさいんだか自分は無関係だからってノータッチに徹しているんだか、蘭ちゃんは強いから大丈夫だろーって楽観視しているんだか知らねえけど、なあなあにして野放しにするやつが圧倒的に多いって話も聞いてる」
皆、ぐうの音が出なかった。
白沢も蘭を気づかう言葉を何回も何回もかけたが、吉田に楯突く勇気まではなかった。
由香理も、絢も春奈も、吉田に反発心を抱きつつも一切関わりたくないという気持ちが勝っていた。
男子一同も、変な噂を立てられたくないばかりに面と向かって「嫌がらせをやめろ」と言えなかった。
「それで吉田なんちゃらってバカな女が自分は容認されてると勘違いして調子に乗る。美人で頭が良くて背が高い蘭ちゃんを妬むあまり尻馬に乗るバカも出る。結局、みんなはどっちに勝って欲しいんだよ」
「分かってるよ。間違いなくみーちゃんが悪だよ」
由香里に続いて村上も口を開く。
「……でも、みんなが飛鳥君のように男気あるわけじゃないんだよ」
「蘭ちゃんが小学生の時に嫌がらせさっちぃきっかけが、みーちゃんを注意したからだってみんな知ってっから……」
だから、何だっていうんだよ。
眉根を寄せて、一哉は先ほどと同じく搾り出すような声で言った。怒鳴りたい気持ちを堪えながらの言葉だった。
「蘭ちゃん寄りのやつらが多いんじゃないの?
それなら数の力で応戦するって頭はなかったの?
そのやり方だと逆にいじめっぽいからやりたくないってか? どう考えても多勢に無勢だろ? 吉田なんちゃらが先に仲間募って蘭ちゃんを孤立させて部活を辞めるよう仕組んだんだろ?」
一同は黙り込んだ。
しばらく過ぎて
「どうする? 早く行かないと帰り遅くなっぞ?」
と、浜津。
「でもあいつらとすれ違わねえと帰れねえど?」
村上の言うとおりだ。
長々と話し込んで帰らない生徒がいると生徒指導の教師が全校集会を通して説教に出るほど、吉田率いるグループが一度おしゃべりを始めれば長時間居座る話は有名だ。
「はぁ、連中の脇っちょ通るのかい。一秒たりとも関わっちゃくねえなぁ」
気だるそうな春奈に「んだから」と絢が相槌を打つ。
2002年2月 約束・5
聞きたくもない声が近くなる。
やはり悪口三昧だった。最も口を動かしているのは吉田で、そのしわがれた声で荒川先輩がどうだ、犬がどうだと話す声が聞こえる。
その内容が荒川の愛犬の餌に毒物を仕込みたいというものだと確定した時、白沢の口からは「あのアマ、地獄へ落ちやがれ」と呪いの言葉が紡ぎ出される。
誰にとっても聞き捨てならない暴言だが、同じく犬を飼っている白沢には耐え難い内容だ。
悪口の対象は荒川から苦手な教師、生意気な後輩、更には気に入らない同級生へと入れ替わる。
「内申書に響くっていうけど、結局何もなかったし」
吉田が話していたのは私立高校の入試についてであろう。実技試験がない限り、私立高校は学力試験のみ。滑り止めならばよくあることだ。
「県立の一般入試はわからないだろ」と男子の声。県立高校を本命とする中学生の多くは、筆記試験と面接のある一般入試なるものを受ける。
三年生を受け持つ教師達は、面接試験は試験時の態度のみならず内申点も重要視されると言ってはプレッシャーをかけるのだ。
「蘭ちゃんとエリちゃんのことぉ?」
あの二人面倒くさかったよね~と斎藤が同意を求める声がした。
誰しもが「何が面倒くさかっただよ」と腹立たしさを堪えつつ、ヒヤヒヤしながら一哉が吉田率いるグループに乗り込んだりしないかと様子を窺う。
「電話かけたのは私じゃないのにさぁ」
提案したのは魅里なんだろ、と聞くは憎きゲス野郎。
それに対して吉田は「いやだぁ」と媚びた口調で反発した。台詞に反して顔は笑っている。
「だけど千晴のやつ、あの二人に謝ったらしいな」
わざわざ自宅にまで押し掛けたっていうぞ、と武田の口調は至って普段通りで嘲笑は含まれていない。
「裏切られた割には魅里、千晴と一緒にいること多いよな」
「だって……」
途端に吉田は弱々しい声色となる。
「千晴ちゃん、強いから逆らえないしぃ……」
白々しいほどの変化をつける吉田に続いて斎藤も「千晴ちゃんは、お父さんもお母さんも先生やってるからぁ……」と言った。
「千晴ってそんなに怖いか? 頭はいいしピアノ上手いけどデブだし無口だし」
別の男子が言うなり、由香理が「お前が言う筋合いないだろ」と吐き捨てる。不機嫌そのものの口調だ。
さりげなく千晴を下げた男子は見たところ背丈は160センチ台半ばである村上と同じか、それより低いか。
蘭より低いのは確かだ、とわかると一哉はこの男子は蘭の長身を妬んで吉田に便乗しているのだと悟る。
「だってぇ、中学校入ってから態度きついじゃん」
「ちょっとエリちゃんに対してやりすぎなところあったしさぁ」
考え込むジェスチャーを交える吉田。
どの口が言うか。絢がごく小さな声でつぶやきつつ顔をしかめる。
千晴が積極的にエリをいじめていた頃に、吉田は時折千晴のいない場で「千晴ちゃんもやりすぎるからさぁ」とエリと後輩達の眼前で批判しつつ僅かな良心が残っていることをちらつかせた。
自分よりいきすぎた行為を取る者を批判することで、自分はまだマシな方だと思いたいのか、エリから完全に嫌われては損だと計算しての行動かは定かではない。
いずれにせよ、それらの行動はいじめに反発を抱く生徒達から「気持ち悪い」と嫌悪感を抱かれる羽目になる。
蘭は、こんな気持ち悪いやつらに傷つけられたのか。
肩を支える合田の手の感触が遠退きかける。
心配そうに見上げる浜津の顔が視界に映らなくなる。
辛うじて「飛鳥君、大丈夫?」と気づかう村上の声が、かすかに耳に入った。
「相変わらず蘭ちゃんって一哉君と仲良いみたいだねー」
斎藤の声に、すかさず武田が反応する。
「飛鳥君もあんなデカい女の何がいいんだかなぁ」
武田のあきれたような口調に吉田も取り巻きもクスクスと笑い「だから」と同意の声を上げた。
「デカいし男子差し置いて学年で一番ってのが可愛げねーんだよなぁ」
合田も、織絵も白沢も、皆が引きつった顔をしていることに一哉は気づいていない。
「俺、乗り込んでいい?」
一同が心配していたとおりの言葉だった。
やめろ、と合田が肩を掴み、浜津が腕にしがみついた。
「やめとけ。あいつらズル賢いの知ってるだろ?
喧嘩吹っ掛けられたって触れ回られっぞ」
耳元でささやく合田。二年生の夏に「あいつらズル賢いから」と焦って一哉の腕を掴む蘭が甦る。
親友と、大好きな女の子の台詞は全くの同じ内容だった。
「デカいっていったらオリちゃんはどうなのぉ?」
「織絵? うちの学校の男子から無駄にモテるようだけど気取った女は好みじゃねえしなぁ」
男を立てないタイプなのに何故モテるのか、入れ込む男子連中の気が知れないと憎きゲス野郎は語る。
「え~、でも昔好きだって言ってたじゃ~ん」
「嘘」
吉田が信じられないと言いたそうにゲス野郎を見ていた。口調と表情からショックを受けたのが丸分かりだ。
過去のこととはいえ、好きだった男子が自分にとって目の上の瘤の存在と見なした女子ばかりを好きになっている事実。
ゲス野郎は「バカ、低学年の時だよ」と取り繕うが、吉田の表情、特に目付きが険を帯びる。
かつて蘭に向けた、陰険さに冷淡さを加えた醜悪な目付きだった。
「全っ然俺に見向きもしてくんねーし、もうあんなつまんねぇ女に興味ねえよ」
織絵としては甚だ迷惑な話だ。元から興味はなかったが、吉田に焚き付けられて蘭をいじめ始めて以来は関わりたくもない嫌いな男へと成り下がった。
思い当たるとすれば、「男気がないにも程がある」と咎め立てた時の彼の顔つきは他の女子が注意した時以上に憎々しげに歪んでいた。
「みんなしてオリちゃんばっかり贔屓しすぎなんだもん。私が先に小学校の吹奏楽部に入っていたのに、なんで五年から入ったオリちゃんが部長なわけ?」
吉田は不満げだ。どちらにしても六年生の途中で転校したので仮に部長に就けたとしても代わりを探さねばならないのだが。
「あいつが来る前は私が部長候補ってなってたんだかんね?」
「だからぁ! あの子、な~んか気取ってて昔っから嫌いだったぁ!」
「どうせ先生も贔屓してたんだろうけど」
実力じゃ私が上、と吉田は歪んだ笑顔で言った。
「酷い……」
小声でつぶやくはミッションスクールの制服を着た女子だった。
「人望とリーダーシップじゃ敵わないのにさ」
目を吊り上げたまま由香理は織絵を見上げる。
かくいう由香理も同じなのだが、織絵は小学生の頃から学級委員に推薦されるタイプである。
場を取り仕切る際の落ち着き払った態度を「でしゃばりすぎなくて好感が持てる」とクラスメート達に支持されていたのだ。
短気ゆえに厳しい態度で口を出しがちな由香理にとって、常に冷静に徹している織絵の姿勢は尊敬に値する。見習いたいと思いつつも、生来の短気さは治まらず真似することは叶わなかったが。
さて、当然ながら織絵は相当に気を悪くしていた。
なんとか冷静さを保っているようだが、苛立ちを誤魔化すかのように片足をパタパタと鳴らす動作を繰り返す。
「あー、なんか腹立ってきた。悪かったな、気取ってて」
小さく、ドスのきいた声だ。みるみるうちに切れ長の目が吊り上がり、震える薄い唇が途切れ途切れに言葉を紡ぐ。
「そんなつもり、ないんだけど、ねーぇ」
橘、と合田が声をかける。
「どうせお得意の妬み嫉みだからよ」
気にするなと合田は織絵をフォローに入るも、憎しみに苛まれる織絵には想い人の優しさも届かない。
「あのさ、アズ。私も乗り込んでいいかい?」
グーに握った片手をもう片方の手のひらに打ち付ける織絵の動作は、アニメで見かける殴りかかる前の動作そのもの。
「男子と女子代表して乗り込むか?」
だめだよ、内申書に響く、と白沢と絢が織絵の腕を掴んだ。
「ま、嫌いで結構。私だって吉田魅里も斎藤麻世も大嫌い」
家のポストに斎藤からの嫌がらせの手紙を入れらっちゃし、と話す織絵に白沢が「マジ?」と驚愕する。初めて話す事柄だったらしい。
「頼むから飛鳥君も落ち着けよぉ」
いつの間にか村上も臨戦態勢の一哉の腕をつかんでいた。
「ゴウダ、本っ当に飛鳥のやつを頼むよ。一番の力自慢のあんたが頼りなんだ」
女子の力自慢である春奈は前から織絵を押さえつけている。
「いや、でもそろそろまずいって……飛鳥のやつ意外と腕っぷし強えーんだよぉ」
吉田は織絵の悪口から蘭の悪口へと変えた。
「さっきもタケちゃん言ってたけどさあ、一哉君もあんなかわいくない女のどこがいいんだろうねー」
頼むから、悪口をやめてくれ。
余計な発言をしないでくれ。
一哉と織絵を除く一同の願いは、虚しく潰える。
軽い気持ちかもしれないが、本心かもしれない。
聞き捨てならない、絶対に言ってはならない言葉を吉田は嗤いながら口に出してしまった。
「どうせ蘭ちゃんが死んだら、さすがに一哉君も心変わりするんでしょ」
◇◇◇
「あなたの話を聞かせて」
探して探して、探し回ってようやく会えたプルシアンブルーの少女。
形の良い唇の両端を上げて、溌剌と笑う少女は自分の名前は蘭であると告げた。
「俺、一哉っていうんだ」
綺麗な目してるなあ。
黒いのに、透き通っていて綺麗だなあ。
少女の瞳の輝きをどこか見たことがある気がする一哉だが、すぐに本家で祖母がはめていた指輪のサファイアの輝きに似ていると気付く。
黒に近い紺色の宝石は深みがありながらも澄んでいて、どこか硬い印象があった。
当然、混血ではない蘭の瞳が青いなどあり得ない話だが、一哉は蘭の黒い瞳とサファイアの硬質な輝きが似ていると疑わない。
「一哉ちゃんって呼んでいい?」
宝石の瞳を煌めかせて蘭は問う。
「ちゃん付け!?」
「私ね、男子の友達いないの。でも、漫画やアニメで幼なじみの男の子をちゃん付けで呼ぶのあるじゃん。そういうの憧れていたんだ」
もし嫌なら別の呼び方にすると蘭は気づかうが、一哉はオッケーサインを出す。
「俺、あまり名前で呼ばれたことないから、なんか嬉しいな~」
「あのさ、公園で話さない?」
セーラーワンピースの襟をはためかせて、蘭は駆け出す。革靴を履いているとは信じ難い身軽さに舌を巻くばかりだ。
やはり、蘭は美しい女の子だった。
◇◇◇
友人達の手から伝わる体温も、名前を呼ぶ声も遠退く。
代わりに、蘭と過ごした幸せな時間が鮮やかに甦る。
絵を描くことが好きだとわかるなり、蘭は自身をモデルに描いてほしいと願い出た。
見たままを描いただけなのに、蘭は満面の笑顔で喜び「綺麗に描いてくれてありがとう!」とスケッチブックを抱き締めながら礼を述べた。
出会った当初は溌剌と明るい笑顔が多かった蘭は、互いの想いが同じであると知った晩夏の夕暮れを境に、はにかみの表情を見せることが増えた。
『くるみ割り人形』のミュージカルを見た帰り道、百貨店で見かけた蝶々のバレッタを諦めた蘭にプレゼントしたのは雪の結晶の髪飾り。
一目見て、雪の女王と渾名される蘭にうってつけだと確信した一哉はこの髪飾りを買うことに決めた。
「蘭ちゃん、これ買ってあげるよ」
艶消しの銀色の土台に青系のエナメルとガラスが煌めく髪飾りを蘭はとても気に入り、早速着けてみると言い出す始末だ。
「綺麗……! 雪の女王の王冠みたい。昔の男の人って、求婚する時に髪飾りを渡したんだって」
髪飾りの止め金は櫛状になっていた。櫛を贈るのは死ぬまで共に生きようって意味らしいよと語る蘭は、はにかみの笑顔を浮かべつつ器用に髪をまとめる。
二人だけの、高潔なる雪の女王の戴冠式。
人気のいない駅の構内で、蘭は薄桜色のマフラーを肩にかけてくれた。
マフラーを買う瞬間には居合わせたが、藍鼠色は蘭が好む色だったので蘭が使うものだと思い込んだ一哉は面食らう。
「一哉ちゃん、桜色好きだから。ピンクでもこの配色なら男子でも違和感ないと思う」
恥ずかしそうに目を伏せて、耳までも薔薇色に染め上げた可憐な姿に胸の疼きを覚え、抱き締めたい思いを堪えるのに精一杯だった。
一つのイヤホンで同じ音楽を聞くことも増えた。
14歳の誕生日に買ってもらったというMDプレイヤーを取り出しながら「13歳がケチついてばかりの一年だったから、神様もこれくらいの贅沢許してくれるでしょうってお母さんが言ってた」と蘭は笑って耳にイヤホンを着ける。
MDプレイヤーの、マットな銀色のボディにグレイッシュな水色がアクセントとなる配色はいかにも蘭好みだ。
楽曲で、その日の蘭の感情が読み取れた。
楽曲はだいたいはクラシックで、時々ジャズであったり80年代の懐メロの日もあった。
中学校入学以降に流行ったJ-POPは苦手と語る蘭は、懐メロではZARDとTHE ALFEEとTOM CATを好んだ。
腹の立つ出来事のあった日は決まって疾走感のある激しい楽曲。
そんな日は、クラシックでは『サムソンとデリラ』のバッカナールかヴィヴァルディ作曲の『冬』の第一楽章のどちらかで、懐メロでは『星空のディスタンス』だった。
一つのイヤホンで『韃靼人の踊り』を二人で聞いた日、蘭は瞳を輝かせて語る。
「この曲で普門館に行くの、難しいらしいよ」
東京にある普門館が吹奏楽部員にとっての甲子園に等しい位置付けであることも蘭を通して知った。
『韃靼人の踊り』は、この日の一哉にとって初めて耳にする楽曲。
憂いを帯びた流麗な旋律は勇壮なものへと変わり、壮大なクライマックスを迎えるのだが、素人判断でも難しそうな楽曲と予想はつく。
「いつか、やってみたいな」
夢を語る蘭の瞳。
普段ならばその煌めきに見惚れるのに、泣きたいほどに切なかった。
「他にはね……『シバの女王ベルキス』のフルートソロに憧れるな。あ、前話したっけか?」
泣きたい感情に抗う一哉に気付いていないのか、蘭は「いつか吹奏楽コンクールで演奏したい楽曲」という夢を語り続ける。
◇◇◇
優しい、幸せな思い出が汚されてゆく。
真白なる雪原を、泥にまみれた靴で容赦なく踏み荒らされた心持ちだった。
その苦痛に、一哉は耐えられなかった。
蘭ちゃん、ごめんね。
俺を守る為の約束だったのにね。
守ってくれて、ありがとう。
でも、俺、限界きちゃった。
思えば、いつも蘭は光の中にいた。
初めて桜の下で会った日もまばゆい陽光に照らされて佇み、無人駅の構内では窓から射し込む光を背景に待っていた。
歌うような愛らしい響きを持つ名の、誰よりも高潔で可憐な美しい少女。
共に生きた幸せな時間。
汚されて、踏みつけにされてなるものか。
激しい怒りと悲しみによって生み出された強い光が眼に宿る。
友人達の腕を振り切りって一哉は駆け出す。
鬨の声を上げる様は、敵方へ斬り込んでゆく軍人さながらの姿。
―――俺は蘭の為ならば、騎士にでも悪にでもなる―――
2002年2月 約束・6
◇◇◇
さすがに冗談がいきすぎているとたしなめたのは武田だが、声が小さすぎたからか届いていない。
武田を含む若干名を除き、取り巻きは吉田の発言に下品な笑い声を立てる。声だけを聞けば不良少年少女の集まりにしか思えない有り様だ。
「あんたも昔蘭ちゃんのこと好きだったっていうけどさぁ、あの時点で蘭ちゃん以外に好きだった女子が何人かいたんだってー?」
あの表情、人をバカにする時の嘲笑う顔で吉田はゲス野郎に話を振る。
「今思えばさぁ、蘭なんかどうせ何人かいたうちの一人に過ぎないからなぁ」
「惚れっぽいなんて知らなかったよー」
いいから、と話をはぐらかしたいゲス野郎が「蘭がいなくなりゃトップじゃん」と言いながら武田の隣にいる男子に目配せをする。
目配せされた相手は三年生の男子で成績トップといわれる男生徒だったが、その生徒も青い顔だ。
彼は目の上の瘤でしかない蘭が妬ましく、疎ましく思う時期があった。
二年生の頃、吉田が吹聴した嘘により蘭への風当たりが強まった時期などはすれ違い様に嫌味を言ったこともある。
大人げないと自覚したのか、または内申点を意識してか二年生の秋頃には蘭に対する嫌がらせを辞めたが、未だに蘭からは避けられる始末だ。
不意打ちで蘭と視線が合おうものならば、わかりやすいほどに軽蔑の感情を露にされて顔を背けられる。
照れくさいからと謝罪の言葉を述べなかった代償は、思いの外痛々しい。
幸か不幸か良識は残っているので、彼は今でも吉田のいきすぎた発言には賛同できなかった。
武田と男子で成績トップの生徒、そして女子の一人か二人が「いい加減やめろよ……」と願うも、前者以外の取り巻き達の反応が良かったことに気を良くした吉田は続けた。
「男って顔で女選ぶじゃん? 綺麗なお人形さん連れてるって感じ? どうせ一哉君もアクセサリー感覚で蘭ちゃんを連れ歩いているようなもんでしょ?」
その話題は長続きしなかった。
足音と「お前ら!」と叫ぶ声に吉田と取り巻きが振り返り、同時に表情を強張らせる。
「中三にもなって、言っていいことと悪いことの分別つかないのかよ!」
鋭い光を宿す眼に、眉をつり上げた一哉がいた。
「誰が蘭を連れて歩きたいお人形さんだと言った!? 蘭はただの小綺麗なお人形さんでねえ、血の通った人間だ! 息してんだよ! 心臓も動くし泣きもするし笑いもするんだよ!
確かに俺は蘭が好きだよ! 一目惚れだよ!
でも顔がどうたらでねえんだよ!
蘭は顔だけの人間でねえ、凛々しくて気高くてかっこいい、高潔な蘭に惚れたんだよ!
好きだから一緒にいて何が悪い! 自分が友達を自分に箔をつけるか否かで決める性格だって認めたくねえから、周りに自分に当てはまるであろう短所を無理にでも押し付けて憂さ晴らししてるだけなの見え見えなんだよ!
これ以上俺の大好きな蘭ちゃんを傷つけんでねー!!」
言い終えた時には既に一哉は合田に羽交い締めにされ、更に前からは浜津と村上に押さえつけられていた。
梃子でも動かないとは、このことだ。
三人がかりで引き戻そうにも一哉は地に膝をつけたまま抗うので元いた場所へ戻せないのだ。
眼光の鋭いままの一哉が、キッと見据えた先は武田だった。
「タケちゃんもタケちゃんだよ。昔はクールでかっこ良かったのに、なんでこんな女になびいて人をバカにした態度取っているんだよ。今のタケちゃんは全然かっこ良くねえよ。顔だけイケメンで性格ブサイクだなんて超絶ダサすぎるっつーの!」
先程とはうってかわっての、訴えかける口調。
武田は、何も言えない。
顔と名前だけを知っているが、それ以外は詳しく知らないただの元同級生から必死の形相で訴えかけられたという現実に面食らうだけだった。
県外から来た転校生という時点で一哉という名の少年がどのような人物であるかと少しばかりの興味を抱いたが、クラスも違えば交遊関係も異なるので接点らしい接点を持たないまま小学校卒業を迎えた。
そんな元同級生が、関わりのなかった自分に真摯な態度で過ちを指摘する行為が不思議でならない。
「蘭がタケちゃんに何をしたっていうんだよ?
変な嘘っぱちに乗っかって一方的に悪者扱いかよ。真偽を確かめもしないで、そんなのただのいじめでねえかよ。マジでダサすぎるよ。関わりのないやつから好き勝手に悪く言われるのがどれだけ悔しいか、タケちゃんはわかんないの? タケちゃんは頭いいんだろ? それくらいのこと察しがつくだろ?」
立ちつくす武田をよそに「何言ってんだ、こいつ?」と嘲笑うのは、憎きゲス野郎だ。
憎き男は、武田への真摯な訴えを鼻で嗤う。
しかし一哉は臆せずに「うるさい! お前に言ってない!」と一喝し、続けた。
「そんなに相手にしてほしいなら言ってやるよ!
お前は最低だよ。何人かいた好きな女のうちの一人に過ぎないってか。蘭がお前とくっつかなくて本っ当に良かったわ。仮にこの女の嫌がらせがなかったとしても、お前とくっついた蘭が不幸になるだけだもんな!!」
そして、怒りの矛先をゲス野郎一人から怪人クラッシャーこと吉田魅里とその取り巻き全員へと向ける。
「お前らの知らないところで蘭が泣いてたのわかんねえべ!? くだらない妬みのためだけに蘭がどれだけ傷ついて苦しんできたか考えたことあるの!? お前らは良心が欠落してんの!?」
取り巻きがいて気が大きくなっているのか、吉田は「良心が欠落って意味わかんないんですけど」と不満げに口に出すも、顔は一哉へ向けていない。隣にいた斎藤が「そうだよぉ!」と大袈裟に騒ぎ立てる。
「タケちゃんもそう思わなぁい?」
と、斎藤は甘えた口調で同意を求めるが武田は視線を逸らし、一切のリアクションを示さない。
「お前らが蘭を部活から追い出したせいで蘭の夢が叶わなくなったの知らねえべ!? やりたかった曲さ演奏する機会まで奪いやがってよぉ!?」
泉清の音澤さんって吹奏楽辞めたそうだね。
そうらしいよ、やっかみを買われていじめられて辞めたんだって。
知ってる! 吉田魅里が犯人でしょ? そいつ六年の途中でうちの小学校に転校してきたけど、人が気にしてるところをしつこくからかうの辞めないから最終的にクラスで嫌われて誰も寄り付かなくなったかんね。
あからさまに避けると逆にいじめっぽくなるからグループ作りで仕方なく入れたりしたけど、同情されるのも辛い~ってのたまって「昔の友達いるから~」って理由つけて泉清に学区外通学してるんだってさ。
えー、自業自得なのに被害者ぶって学区外通学してんの? それ学区外通学の理由として許されんの?
音澤さんが吹奏楽部に籍を置いていたら、泉清の顧問は『シバの女王ベルキス』を自由曲にするって計画してたらしいよ。
あの子、フルート上手いから『ベルキスの暁の踊り』で全国狙えたかもわかんねってよ。
もったいないよね。いじめたやつが辞めりゃよかったんだよ。
そもそも吉田とかいう人が間違ったコミュニケーション取りさえしなけりゃ始めっから避けられた話じゃん。
嫌だねー。なんで嫌なやつほど甘い思いして居座るのかね。
学校での、生徒間での噂話だった。
以前にも、一哉は蘭が『シバの女王ベルキス』のフルートソロに憧れていた話を本人の口から聞いていた。
蘭の夢、憧れの楽曲を演奏する夢を断たれたにも等しい残酷な現実。
噂話に興じていた女生徒達が、一哉に気づくなり気まずそうな顔で去っていく姿は瞼に焼き付いたまま離れない。
『韃靼人の踊り』を演奏してみたいと語る、蘭の輝いた瞳。
『シバの女王ベルキス』のフルートソロを夢見る蘭の生き生きとした表情。
もしも、蘭が吹奏楽部を追い出されていなければ……。
未だ見たことのない、仲間達に囲まれて笑顔を見せる蘭の姿。
銀色に輝くフルートに負けない、輝かんばかりの笑顔の蘭が幾度となく一哉の頭に浮かんだ。
「なんで蘭が辞めなきゃならないんだよ!? 辞めるべきなのはいじめたやつらだろ!? つまんねー嫉妬心でどれだけのものを蘭から奪い取ってきやがったんだよ! お前らみたいな人間のクズはどう足掻いても蘭には敵わないんだよ! 二度と蘭に関わるな! お前らのせいで……!」
腕が後方へ引き戻される。それを機に足も一哉の意思に反して引きずられる。
それでも一哉は蘭を傷つけられた恨み言を止めない。
「お前らのせいで蘭の貴重な青春時代が台無しなんだよ! 返せよ! 奪い取ったもの全部返してあの子に償え! 蘭の夢も台無しにされた青春も全部返せよ!」
飛鳥!
名前を呼ぶ、複数の声。頭の後ろから、一際大きな声が聞こえた。
「お前らが橘や音澤を悪く言ってた話、全部聞いてたかんな?」
合田康範の声だ。己れの重すぎる足取りに反して軽い足音がすれ違う。
足音が止まるなり聞こえたのは、橘織絵の落ち着いた声。
「今のやりとりを脚色してアズを悪者扱いする噂を流しても無駄だよ。私も見てたし、うちの学校の生徒も他校の生徒も隠れて聞いてたから」
一呼吸置いて織絵は「それから」と繋げる。
「私も、みーちゃんもあーちゃんも大嫌い。私が何かした? してもないのに好き勝手に陰口叩かれたり嫌がらせの手紙を投函されていい迷惑。だから、近所で会っても金輪際関わらないで」
2002年 約束・7
再び橋の下へと戻された一哉を責める者は誰もいなかった。
あの晩夏の夕暮れに、互いの想いが同じだと確信したその日の蘭は全力で走ったわけでもないのに額に汗を滲ませ息を弾ませていた。
今の自分のように、あの時の蘭も周りの声がかき消されるほどに心臓が大きく脈打っていたのだろうか。
耳まで響く心臓の音に一哉君、飛鳥、アズと名前を呼ぶ声が重なる。
「……飛鳥、大丈夫かい?」
橋桁に背をつけてへたり込む一哉の顔を、浜津の細い目が覗き込んでいた。
「俺、蘭との約束破っちまった」
「約束って何だい?」
視界の片隅で春奈が腕組みして問う姿が見える。
「蘭に、絶対に乗り込むのはやめろって言われたんだ。あいつらズル賢いから、変な噂流して悪者扱いするからって」
二、三回ほど息をついて一哉は続ける。
「俺はそんな小っさいやつら怖くないって言ったんだけど、俺の立場が悪くなるのは堪えられないって、必死な顔で腕掴んできた」
「仮に嘘っぱち吹き込んでも証拠人は複数いるんだしよ」
なぁ、と周りを見回して同意を求める合田。
即座に「だから」と答えたのは織絵。
「そうだよ。私も牽制したし」
「俺とハマちゃんの顔もあいつらに見られてるしさ」
少なくとも四人の証拠人はいると証明したわけだから、と村上。
「オリちゃん言ったべした? 翠楓の生徒も何人か聞いてたから~って」
「私らも聞いてたって知ったらさすがのみーちゃんもおとなしくなるんだべか」
「案外数の力に弱いかもわかんねえしよ?」
各々が「証拠人は複数いるから心配するな」と畳み掛けるが、これまで何回か口にしたおり一哉はただの小市民に過ぎない吉田など怖くもなんともない。
「いや、あの程度の連中は怖くもなんともないからいいんだ。蘭にひっ叩かれる覚悟だってある」
「じゃあ、なんで沈んだ顔なんだよ?」
問いかける合田を見上げた一哉。親友との視線が合うと膝に顔を伏せる。
「蘭がいじめられた時にも、今俺がされたみたいに味方がいると豪語してくれるやつがいれば良かった……いや、いたんだろうけど、敵方の声がでかすぎたんだな」
あからさまなため息の後、合田が言った。
「今日日、一人の女のためにここまで情熱注げる中学生なんぞ稀だろうな」
「だから、そんなやつ漫画の世界にしかいないと思った」
いや、と否定から入った織絵は「恋を知らないから、そう思うんだよ」と続けた。
橘は好きなやついるのかと浜津は問うも、織絵は「さぁ」と一言だけ返してはぐらかす。
「あんなひどいことを寄ってたかって言われた後にこう言うのは変だけど、蘭ちゃんもここまで想われて幸せ者だよなあ」
前置きもあるが、白沢が「幸せ者」と軽々しく発言したわけではないのは一哉にも伝わった。
「元々曲がったことが嫌いで放っておけない性分なのかもわからねえけど、一哉君が蘭ちゃんを何ほど好きなのはわかった。でなかったら、あいつらが固まってるところさ堂々と乗り込めねえべした?」
孤立する中で、味方がいると確信することは幸せなことかもしれない。
神楽殿の下で泣き崩れた理由も、晩夏の夕暮れにしがみついてすすり泣いた理由も、味方がいる幸せを確信したからだろうか?
真偽は、蘭にしかわからない。
「今日のことは、絶対に誰にも言わないで欲しいんだ。もしかしたらあいつらが学校で触れ回るかもわからないけど……」
いつか、俺の口から蘭に話すよ。
そう告げる一哉は膝に顔を埋めた。
視界は真っ暗い。冴える空気が冷たい。
頭の中をたくさんの記憶が、コマ送りの映像の如し巡り出す。
コマ送りの映像は、己の両の手が前方へスッと伸ばされるものから始まった。
◇◇◇
俺は、蘭の涙を拭うことを躊躇わない。
白百合の如し肌を滑り落ちる涙を、指先で拭う。
濡れ羽色の髪にそっと手を触れる。
不純な思いなどなかった。
蘭の平穏を祈るだけ。
「蘭ちゃん」
静かに名前を呼ぶと、蘭はおもむろに顔を上げた。睫毛の先には小さな涙の玉が乗る。
「たかだか中学生が"俺が守る"だなんておこがましいだろうし、今の蘭ちゃんには嘘くさく聞こえるだけかもしれないけど……」
泣き声こそ上げなかったが激しくすすり泣いた後ゆえに、蘭の呼吸は普段より荒くなっていた。時々、ひゃっくりのように身体が大きく動く。
蘭にしてみれば激しく泣いた後の姿など見られたくもないに違いないのに、白目の赤く染まった眼で蘭は一哉をしっかりと見据えている。
「初めて会った時から大好きな蘭ちゃんの生命と幸せは、絶対に守りたいんだ。蘭ちゃんを支えたい気持ちは、本当だよ」
小さな声で「信じて、いい?」との問いかけに一哉は頷く。
「何があっても」
蘭が大きく頷いて、赤い眼で二の句を待つ。
「蘭ちゃんが、大好きだよ」
偽りのない言葉に勝るものはなかった。
一哉が初めて聞いた慟哭こそ、蘭からの返答だった。
目元を覆う両手の隙間から涙が溢れ「あぁ!」と悲鳴に似た声を上げる蘭の肩を抱き寄せる。
涙と共に、蘭の唇は溢れ出す想いを紡ぐ。
「一哉ちゃんが好きです。初めて会った時からずっと好きでした。一哉ちゃんの綺麗な目が忘れられなかった。会う度に名前呼んで笑いかけてくれるのが嬉しかったの……離れたくない。一緒にいたい」
大好きです。
この一言を震える声で繰り返す。
肩に顔を埋める蘭の細い背中を、一哉は固く抱き締めた。
涙の熱さ。制服越しに伝わる心臓の音。
蘭が生きている証。
時を同じくして互いに恋を覚えた奇跡。
俺は生涯忘れはしない。
2002年 3月
「蘭ちゃん、セイラさんが来てるよ」
帰宅早々、妹のみちるが蘭に駆け寄る。
姉妹は互いに「蘭ちゃん」「みっちゃん」と呼び合った。兄の秀に対しても「秀ちゃん」と呼ぶなど、この家の三兄妹はお互いを名前+ちゃん付けで呼び合うのが常である。
玄関には指定の白いスニーカーが二足。
背負うタイプの通学鞄をコート掛けの下に置いた蘭がリビングへ向かうと、聖良はちんまりと正座しつつコタツに足を入れて暖を取っていた。
「あっ、蘭さん。お邪魔してます」
慌ててコタツから足を出して立ち上がる聖良に「遠慮しないでいいから」と笑って言うは星だ。
「そうだよ。寒いしコタツ入ってて」
「えーと、二人で話したいことがあって……」
それならばと蘭は二階の子供部屋で話すことを提案し、二階の電気ストーブを着けようと一足先に子供部屋へ向かう。
その間、星は台所でお茶菓子を用意していた。
ティーセットを食器棚から取り出す姿がいそいそと楽しげに見える。
大学を卒業して以降、百貨店にてデパートガールを勤めていた星は小学生の蘭が嫌がらせを受けた件をきっかけに退職を決めた。
自分が仕事にかまけていたばかりに、娘がSOSを出せなかったという自責の念にかられての退職だった。
階段へ足を踏み出すと、みちるが「ねえねえ」と声をかける。
切れ長の大きな目と気性のハッキリとした性格、平均より高い身長はよく似た姉妹と評されるが、双方の纏う雰囲気は全く異なる。
父親似と言われる蘭に対し、みちるは母親似だ。
母親譲りの口角の上がった唇は見るからに活発そうで、スレンダーな肢体と毛先を軽くすいたショートボブという、いかにもなスポーツ少女らしい容姿をしている。
事実、みちるは体育会系だ。
空手の有段者である父の泰造に影響されて入部した空手部では主将に抜擢され、それなりに良い成績を修めるなど活躍している。
いつだか、蘭は空手部の元主将だった絢から珍しく声をかけられた際には「みっちゃんは伸び代があるよね」と感心されたものだった。
「留美ちゃん達以外で蘭ちゃんの同級生が来るなんて珍しいよね?」
蘭のあとをついてきたみちるは電気ストーブのスイッチを入れる蘭の後ろにいた。
ゴワゴワした着心地で全く寛げないからと蘭は自宅では運動着を着ないが、着馴れているみちるは運動着のままで過ごすことが多く、今もみちるは運動着を着ていた。
代謝が良いのか下は指定のハーフパンツだが足元は分厚いハイソックスだ。
アイボリーの被りタイプのトップスに、襟元とボトムが学年ごとに色分けされている運動着は蘭の目から見ても「運動着としては比較的センスが良い方」なのでデザイン自体は嫌いではなかったが、自宅で寛ぐとなると着る気にはなれない。
「……まあね」
「あまり喋ったことなかったけど、セイラさんっていい人だね。目がパッチリしててかわいいし優しいし」
含み笑いの後「さっきセイラさんに美人だねって言われた!」と嬉しそうに跳びはねるみちるは、完全に有頂天になっていた。
「ごめん。悪いけどセイラさんが二人で話したいんだって」
私だけ除け者にして! と反発することもなく、みちるは蘭の申し出を素直に受け止めた。
「わかった。じゃ、お菓子食べてくる」
みちるは聖良に出されたお菓子が羨ましかったようだ。
それもそのはずで、お菓子というのも母方の祖母から送られてきた『クルミっ子』なのだ。
福島では取り寄せない限り手に入らないこのお菓子を姉妹はとても気に入っている。
そして、みちるの後に続いて蘭は聖良を呼ぶために一階へと降りていった。
◇◇◇
聖良はまずティーセットがかわいいと褒め出した。
ノリタケのティーセットで、両親が結婚祝いに頂いたものらしいと教えると「ノリタケかぁ、かわいいの多いよね」と答える。
「ウェッジウッドとかたち吉とかの食器も素敵だよねぇ」
「セイラさん、そういうの興味あるんだ。私もだよ。香蘭社や深川の食器が好きだな」
おばあちゃんが好きで影響を受けたと聖良は語る。
「あの、昔校長先生だったおばあちゃん?」
「そうそう。よくお客さんが来るんだけど、その度にかわいい食器を出してくるの。修学旅行の行き先のアンケートあったじゃん? 実は私ね、北海道と沖縄って書いたの。どっちもガラス細工が有名だからね」
北海道はともかく沖縄なんて高望みだけど、と聖良は苦笑いだ。
北海道ならば慧子達の学年の修学旅行先という実例があるが(地方の空港の利用率を上げるために修学旅行で飛行機を利用するパターンが増え初めた時代である)、沖縄は高校生の行き先として刷り込まれているのだった。
蘭と聖良の学年の修学旅行の行き先は京都と大阪。
二泊三日のうちの二日目は当時できたばかりのユニバーサル・スタジオ・ジャパンで丸一日遊ぶという豪勢な内容だった。
「京都も清水焼を買えたから良かった。……蘭さんの舞妓さん姿、綺麗だったね」
京都への滞在時は自由行動だったのだが、舞妓さん一日体験には修学旅行の数日前まで親友同士ですったもんだした記憶がある。
乗り気だった蘭を除く親友一同が口を揃えて「白塗りが恥ずかしい」とのたまい、舞妓さん一日体験を渋ったのだ。
「蘭ちゃんは美人だから舞妓さん似合いそうだけど、私がやったら絶対に笑い者だよ」
と、焦ったリアクションを交えてエリが言った。
続けて「私みたいな濃い顔が白塗りなんかしたらピエロかチンドン屋でしかねっつーの」と頬杖をついて拒否するは留美だ。
ミヨシは「ピエロなんかまだいいべよ! うちなんか化け物でしかねえべしたぁ!」と言うと「力丸は顔はかわいいから似合うだろうなぁ!」と力丸を見る。
一同は力丸を見て納得するも、力丸は可愛らしい顔にしかめっ面を刻んで「やだ」と一言だけ告げた。
結局、蘭だけが舞妓さん一日体験を実行し、その周りを留美達が歩いていたのだが、他校の修学旅行生から「美人の舞妓さんがいる!」と写真撮影をせがまれる事態に成り果てた。
「青い着物だったよね。似合ってたよ」
「七五三がアンティーク風の濃い紫の着物だったから違った雰囲気の色も考えたの。赤系とか淡い色の着物もかわいかったけど、あの青い着物がすごく好みの色柄で……」
何よりも四君子の柄が良かったんだ、と蘭は笑う。
「四君子、ああ……よく深川の食器にあるよね。蘭と梅と竹と菊だっけか?」
「そう。蘭の模様は珍しいから」
「だいたいの子が七五三だと赤かピンクだけど濃い紫ってチョイスが蘭さんらしいね。舞妓さんの写真、一哉君に渡したのかい?」
「なんでそんなこと聞くの!?」
舞妓さん体験の話を振られた時以上に蘭は狼狽えたが「渡した」と答える。
その時の一哉は、今現在の蘭よりも顔を真っ赤に染めつつ舞妓姿の蘭が写った写真に見惚れながら「生で蘭ちゃんの舞妓はんを見たかったよぉ!」と悔しがったことも話すと、聖良は「それなら」と考え込むポーズを取る。
「一哉君との結婚式で打ち掛け着たらどぉ?」
「セイラさ~ん!」
恥ずかしさのあまり焦って抗議する蘭の耳に、かわいらしい笑い声が届く。
聖良は「意外と」ジョークを言うタイプらしい。
◇◇◇
「ところで、話したいことって?」
それまで饒舌だった聖良が口ごもる。
「明日か明後日の放課後空いてるかなぁ」
「どっちも空いてるよ? あっ、明後日は卒業式の歌の練習だから明日がいいな」
三月に入ると蘭も卒業式の合唱の練習の誘いを受けるようになった。誘い出す者は一哉であったり白沢の時もあったが、今回は春奈だった。
練習の後は学習センターなり白沢宅なりに集まっては受験勉強に精を出す。
「そうだった。それじゃ、地下道のある交差点で待ち合わせしない?」
聖良との待ち合わせ先は、二年生の梅雨時に千晴と待ち合わせた交差点だ。
千晴の焦った顔は、それっきり目にしていない。
吉田率いるグループとの決別以降、千晴はというと単独か元吹奏楽部員で割とソリの合う若干名の生徒(なおかつ反吉田派の生徒)と行動するようになった。
特有のモソモソした動きとボソボソした話し方は相変わらずで、総合学習の時間に行われた面接の練習では「学力は申し分ないのに、そこまで陰気くさいと面接落とされっぞ?」と松井に脅しを交えた説教を食らい、千晴は相当に気を悪くしていた。
膨れっ面の千晴に「千晴ちゃんはピアノ上手いし書道で段を持っているし、強みをたくさん持ってるから面接も大丈夫だよ」とフォローに回ったのは、同じ女子高を受験する聖良。
続いて「松井先生もいちいち言い過ぎなんだよなぁ」と千晴に同情の意を表すは白沢だ。
変化といえば廊下で力丸薫子と出会すと一言二言の会話を交わす。二言以上に進展しないのは、力丸が無口すぎるあまり会話が続かないからだ。
そんな力丸に対して話が続かないと悪態をつく者は一人や二人ではなかったが、千晴は苦にならないのか咎めることはしなかった。
さて、大槻エリは千晴を許したであろうか。
三年生に進級すると、以前ほど千晴を拒絶する反応は見受けられなくなり、少しの会話ならば交わすなどの進歩は見られた。
蘭も親友達も、エリに向かって千晴を許したか否かを追及はしない。
千晴を許すも許さないも、エリが決めること。第三者がとやかく口を出す話ではないと静観しているのだ。
確信できるといえば、千晴がエリの自宅の玄関先で土下座をして以降、いじめ行為を一切やらなくなった。
エリのいない場に限るが、蘭やミヨシに出会せばエリについて話したり質問するようになる。
若干空気を読むことが苦手なミヨシが「千晴ちゃん、エリちゃんのことばかり話してたで」とエリに話すも、嫌な反応はなかった。
2002年 3月・2
◇◇◇
蘭が自室で聖良と談笑している頃、時を同じくして一哉もまた自室で友達と話し込んでいた。
プルシアンブルーの布団。カーテンは青みのグレー。
座布団は紺色で、調度品などはプラスチックの衣類ケースとガンメタリックのメタルラックだ。
青で統一した男子中学生の部屋に彩りを添えるは、通学鞄と共に引っかけてある薄桜色に藍鼠色のチェック柄のマフラー。
衣類の量販店でプルシアンブルーの布団カバーを選んだ際に濃い色はホコリが目立つと母親に難色を示されたが、全くそのとおりだ。
次に布団カバーを買い替える機会があれば一番好きな色であるピンクにしようと考えているが、プルシアンブルーも捨て難い。
プルシアンブルー=蘭。
五年前の春。桜の下で蘭と出会って以降、そのように刷り込まれていた。
深い湖の底を思わせる色彩の中、黒い学生服が四人いる有り様は華やぎに欠けた色彩を繰り出すが、彼らは和気藹々と談笑している。
「蘭、あまり笑ってないね」
一哉は合田に泉清中学校の卒業アルバムを見せてもらっていた。三年一組のクラス写真では最後から二番目に蘭の顔写真が載せてある。
現三年生の女子は顔面偏差値が高いと後輩達から噂されるだけあり美人と称しても遜色のない生徒が各クラスに複数名は存在しているが(その中には白沢小百合と力丸薫子、由香理が含まれる)、美少女と呼ばれる女生徒の中で蘭が群を抜いて美しいと一哉は疑わない。
アルバムに一通り目を通す一哉だが、時折忌々しそうに眉をしかめては素早く次のページをめくるのだ。
理由は合田も、居合わせている浜津と村上も察していた。
合田達は予め、各部活動の代表による「部活動の思い出を綴った作文」のページは読まないようにと釘を打つことも忘れない。
吹奏楽部代表による作文は、一哉の神経を逆撫でることは確実からだ。
アルバムから寄せ書きのページを読み終えて、卒業文集のページに差し掛かると一哉の口からは「納得できねー」と怒り混じりの声が上がる。
「白沢も力丸も中井も整った顔なのは認めるけど、なんで蘭が三年生全体を通した『かわいい人ランキング』の一位じゃないの? だいたい、俺史上最高の美少女の蘭ちゃんがかわいい人ランキングに名を連ねてないこと自体がおかしいでしょ?」
かわいい人ベスト3にランクインした中井という女生徒は南沢又小学校の出身とはいえ、転校生である一哉と合田と話した回数は少ない。
それだけに中井の人となりはよく知らなかった。
ただ、地方育ちの田舎娘にしては垢抜けた容姿であることは存じている。
育ちの良さが滲み出る気品ある佇まいは、学年全体にアンケートを取った『かわいい人ランキング』のベスト3にランクインするのも頷けた。
この中井は自身とタイプの似通う蘭に肩入れしている節がある。
三年生に進級したばかりの頃、一哉は珍しく中井と会話を交わす機会があった。
もう一人似たり寄ったりの雰囲気を纏う寡黙な少女も側にいて、名前は覚えていないものの見覚えのある顔だったので彼女も同じ小学校の卒業生であることは間違いなかった。
その際に中井と友人の少女は内心で蘭に憧れていることを告げた上で、吉田を筆頭とした吹奏楽部で問題を起こす生徒達を良く思わないことを打ち明ける。
中井も友人の少女も他人を悪く言うイメージがなかっただけに意外に思ったが、当時の会話のやりとりで一哉の記憶に最も色濃く残ったのは
「蘭さんは望んでもないのに派閥争いの渦中の人にさっちぃ、気の毒だ」
という中井の発言だった。
「音澤は綺麗だけど『かわいい』って柄じゃねえな」
座布団の上であぐらをかきつつ煎餅をかじる合田は、さながらエサにかじりつく巨大な熊の風情。
胴長短足とはいえ上背があり、脚の長さも平均より十分に備えているので合田の膝頭は座布団の縁からはみ出している。
うんうん、と浜津が合田の発言に頷く。
「背ぇ高けぇし大人っぽいからよぉ、むしろ『かっこいい』系だべした」
浜津と同じように村上も頷いた。
「その気になれば女子のファンがつきそうだよね。宝塚の男性役的な人気っていうの?」
「なんかもったいないよね。音澤のやつ、せっかく美人でかっこいいのによぉ」
村上が「んだから」相槌を打つと、一哉がその場で勢い良く立ち上がる。
浜津と村上は一哉の長い脚と若竹の如ししなやかな立ち姿を羨むが、一哉が口から出したセリフは凛々しい姿形にそぐわないものだった。
「いやいやいや、蘭はかわいいんだよ! ゴウダもハマちゃんも村上君も蘭のはにかんだ表情の可憐さを知らないの!?」
黙っていれば絶世の美男子なのにとあきれる三人だが、一哉は至って真剣な感情に基づいて発言している。
学校での蘭は周りと打ち解けないだけに甚だクールなイメージがつきまとうことを一哉も察している。
しかしながら、二度目の嫌がらせを受ける前の、一年生の頃の蘭は同級生達と笑い合う姿や年齢相応に無邪気な姿を見せていたはずだ。
親友達を除いた泉清中学校三年生一同の頭の中には「無邪気に笑い、時々可憐にはにかむ蘭」は存在しないのだろうか。
白沢家での勉強会にて橘織絵が「合田康範がどれほど男前な性格をしているか」を力説した時のように、一哉はひらりとベッドへ飛び乗って選挙の立候補者が演説をするがの如く
目を伏した時の長い睫毛がどうだ
はにかむ際の耳まで薔薇色に染め上げる様がどうだ
横顔の美しさがどうだ
などと、身振り手振りを加えて親友達に向けて力説し始めたのである。
一頻り言い終えてベッドの上で立ち尽くしたまま大きく息をついた一哉に、躊躇いがちに「あの~」と口を出すは村上。
「飛鳥君と音澤は相思相愛だから今みたいなセリフを言ってもギリギリ許せっけど、他のヤローが女の子相手に鼻息さ荒くして同じことのたまってたら気持ち悪りぃ以外の何物でもないよ?」
げんなりした顔は村上だけではない。
合田も浜津も、村上と同様にげんなりしていた。
「男嫌いの音澤がはにかむ姿なんぞ、泉清の男子連中が見た試しねえと思うぞ」
「いつも口つぐんでムッツリしてっぺした。なぁ?」
浜津に合田は一度は同調するも「でもよぉ」と返した。
「小学生ん時にチャンバラごっこさ乱入してきた時の音澤は笑っていたっぺよ」
「チャンバラごっこ懐かしナイ。あいつ、その頃から背ぇ高くてリーチあっからよ……」
フェンシングの要領で突きを喰らっちぃ一発で負けた、と語る浜津は懐かしそうだった。
「音澤のやつフットワークが良いんだ。俺なんか真っ向からぶち抜かれた上に刀が吹っ飛んだぞ」
チャンバラごっこの時の蘭を牛若丸さながらだと合田は回想すると「いや、あの身軽さはピーターパンに匹敵すっぞ?」と浜津が述べる。
「蘭ちゃんはバレエやってたからフットワーク軽いんだよ」
「俺だってフットワークの軽さなら自信あるのになぁ」
元陸上部で走り幅跳びの選手だった浜津。
小柄な体躯ゆえの体重の軽さを活かし、体育の授業と小学校の運動会の徒競走で活躍するなど発言に違わず身軽だが「チャンバラごっこに乱入した音澤には敵わない」と認めざるを得ない。
「男が三人揃って女の子に負けてんの。すげえだろ?」
かくいう一哉も蘭と刀を交えた結果負けた。それにもかかわらず誇らしげだ。
即座に一撃を喰らって負けた合田と浜津とは異なり、額の前で横向きにしたチャンバラの刀で蘭からの攻撃を防いだものの、結局は押されて負けた。
「あの時の蘭ちゃんの勇ましさつったら、さながらオスカル様か巴御前だろ」
幼き日の記憶に陶酔する一哉を差し置いて、村上は合田と浜津に「音澤ってチャンバラするのかい?」と問いかける。
蘭と同じ小学校を卒業した村上。
五年生に進級した頃から生来の溌剌とした煌めきが甦った蘭だが、どちらかといえばインドア派の蘭は屋外を走り回るよりも図書室で読書にいそしむ印象が強かった。
蘭=近寄り難いまでに生真面目な模範生と刷り込まれている村上にとって、お転婆娘を象徴するチャンバラごっこに蘭が興じるなど意外に思うのも無理はない。
「小五ん時に、一回だけだったけどな」
「なんか、すごく溌剌としてたよね」
中二に入ってからまた笑わなくなったけど、と浜津。
ギシッという音がして三人がベッドを振り向くと、一哉がベッドから降りる姿が見えた。そして、その場に正座する。
まず、一哉は合田が食べていたものと同じ煎餅に食らいつき、煎餅を食べ終えると烏龍茶の一気飲みを始める。
喋りすぎて喉が乾いたからか勢い良く飲んだらしく、コップの中身が空になったしりから「ぷはぁっ!」と息をついて再び喋り出す。
その有り様は近隣の女子中学生がつけた「貴公子」のあだ名にそぐわない、がさつで「おっさんくさい」姿だった。
「蘭ちゃんが笑わなくなった原因は明らかでしょうが。蘭ちゃんは学校の外じゃあ笑うんだよ。そりゃあ、もう、笑うと目が優しそうに細められて、白い歯が唇から微かに覗いてかわいいんだっつーの。はにかんだ時に口元が少しだけフニャッとするのも、ほっぺと耳元が桜色に染まる姿もかわいいんだよぉ!」
正座のまま一哉は村上に向かってにじり寄る。当然ながら、村上は「なんで俺が……」と困惑していた。
「村上も言ってたけど、お前だからギリギリ許されっけど発言内容だけを切り取りゃ確かに気持ち悪りぃ以外の何物でもねえな」
「んだから」
「気持ち悪りぃって言うなでぇ!」
一哉が新潟から福島へ引っ越してきて、この春で五年目に入ろうとしている。
すっかり「もっさりした響きながらもパンチのきいた福島弁」に毒された一哉は、新潟で刷り込まれた特有の言い回しに福島弁を加える話し方へと「進化」した。
正月に帰省した時などは当時の親友から「会うごとに訛っているよね?」と指摘され、彼らが中学校で仲良くなった同級生達に「東北地方に転校した友達が会う度に訛りがきつくなっている」とネタにしていることを笑いながら告白される始末である。
さて、怒るというよりは嘆く一哉を村上は「まあまあ」と言ってなだめすかしに入った。
今、一哉の部屋にいるメンバーで最も冷静に振る舞う者が村上晋であろう。
「それだけ音澤が飛鳥君に心開いてるってことだべした」
そして、「おいっ」という声と共にノックの音。一哉は村上の前からドアの前へと向かうが、ドアノブをひねったしりから一哉の顔が凍りつく。
「カズ、あんたの声うるさいわ」
地を這うような低い声。
女子高のセーラージャケットの制服が似合う清子が、ドアの隙間から鬼の形相で一哉を睨みつける。
パッと見は似ていない一哉と清子。
しかしながら、双方の黒目のハッキリとした瞳と濡れ羽色の艶やかな髪、直線的な眉に確かな血のつながりが認められる。
ドスのきいた声を繰り出し、清子は静かに凄んだ。
「さっきから『蘭ちゃんかわいい~、蘭ちゃんかわいい~』って、壁越しに響いて恥ずかしいったらないわ。友達が『あんたの弟おもしぃね~』って爆笑してんだけど?」
普段の清子の澄んだ声を知っている合田達は、いつもの美声はどこへやら……とガッカリするほかなかった。
清子の後ろで同じ制服を着た女子高生が三人ほど集まり「サーヤ、おっかねえど~」「イケメンの弟かわいそうだべした~」「んだからぁ」と笑う。
いずれも清子と似たり寄ったりな清純そのものの容姿だが、女子高生達の口振りはどこかアクが強そうだった。
一哉は頭の中で「類は友を呼ぶ」と繰り返す。
硬直する男子中学生達の姿を認めた清子は、引きつった笑顔に普段どおりの澄んだソプラノで「しっつれいしましたぁ~」と節をつけて言うとドアを締める。
サーヤ、あのイケメンがあんたの弟かい?
そうだよ。イケメンに見えっか、あいつ?
毎日顔さ見てっから感覚マヒしてんだっつーの。
あれだけイケメンなら彼女ぐらいいるべ?
彼女っつーかプラトニックを貫く関係っつーか、とにもかくにもいっつも超絶美少女連れてる。
その子かい、弟君の言ってた蘭ちゃんって子は。
ドア越しに響く足音と、女子高生達の会話。
清子の部屋のドアが閉まる音からしばらくが過ぎて、まず口を開いたのは合田だ。
「前から思ってたけど、お前の姉ちゃん、顔はかわいいのにおっかねぇな……」
「んだから、黙っていれば清楚な美人なのによぉ」
「姉という存在に対する憧れと幻想が消え失せるよね……」
「お前らのセリフと全くおんなじこと、新潟いた時の友達も言ってたわ」
一哉が指差した先には少年達の写真。かまくらを背景に羽目を外した様子の者もいれば、真っ赤な頬で棒立ちの者もいる。
「シスコンもののアニメとか漫画ってあるけど、俺としては姉妹に萌えるなんざ理解できねぇ……花梨は年が離れている分可愛げがあるんだけどよぉ」
現実の姉など鬼との同居に等しい、そう語る。
「『流浪の民』のソロん時の声と大違いだよ」
2002年3月・3
◇◇◇
二階から響く笑い声。時々、足音。
この喧騒もいつかは聞けなくなる。
まずは清子からだろう。
図書館司書になることが夢で、文学部への進学を志望する清子。
この街にも大学は何件かあるが、きっと清子は県外の大学へ行く。
「姉ちゃんと兄ちゃん、楽しそうだねー」
シューパイを頬張る花梨の声に母親の寧子は「そうだね」と笑って返す。
寧子は華奢な体躯で顔つきの優しげな女性だ。絵に描いた良妻賢母だが決して受け身ではないし気弱でもない。
幼稚園で清子が男子から執拗にいじめられた際には、園を通して相手サイドへ直談判を決行した。
相手の親に向けて
「幼稚園は子供にとって初めての社会に出る場でもあります。そんな中でよってたかっていじめられるのは恐怖でしかありませんし、人格形成に悪影響を及ぼしかねません」
と話した上で、加害者の園児には清子に一切関わらないよう言い聞かせるようにとキッパリと言い放つ気概があった。
翠楓学園から連絡があったのは一昨日のこと。
プライドがあるのか、特定の生徒から難癖をつけられている件を一哉は親に打ち明けることはなかった。
しかし橘織絵の母親や、小学校の同級生で翠楓学園に通う生徒の保護者が学校で何があったかを話すので、二年生の夏休み前には既に筒抜けであった。
皆、一哉を気づかっていた。
いつか、織絵の母親と星の口から聞いたことがある。
一哉に難癖をつける生徒は、かつて蘭をいじめていたと。
蘭は、寧子から見れば息子に勿体ないほどの素敵なお嬢様に映る。
転校早々に『恋煩い騒動』の引き金となった相手の少女はいかにも道を違えなさそうな、意志の強さを宿す瞳が印象強い、美しい少女だった。
図書館さ行ってくる。
塾通いしたいんだ。
俺、私立の学校受ける。
これらのセリフは全て蘭という少女がきっかけ。
利発で博識な蘭に追い付きたい。蘭と釣り合う男になる。
その思いが息子を躍進させた。
仮に、恋の相手が軽薄で浅はかな少女だとしたら心中穏やかではなかったであろう。
清子の口からたまに出てきた吹奏楽部を私物化した女生徒などは、一哉と関わり合いにならずに済んで良かったと心から思えたほどだった。
親離れを意識する年頃ゆえに根掘り葉掘り聞き出すのも気が引けるので、それとなく「学校で嫌なことがあったら私なりお父さんなり相談しなさい」と声をかけるも、一哉は何もないと笑って否定した。
「何かされたら応戦すっから」
と、つけ加えて。
この日の日中に寧子は学校へと向かった。
難癖をつける生徒の母親と両者の担任を交えての話し合いが行われ「再三指導しているが、未だに止める気配はない。最終通告だと伝えるように」と担任は「ゲス野郎」の母親へ告げた。
「ゲス野郎」の母親は常識人にも見えるが、いささか息子を甘やかしている節があるようだった。
「いやね、飛鳥君のお母さん。人付き合いが希薄になりがちなこのご時世に、一人の女の子相手に必死になれる中学生は珍しいですよ」
組長みたいだと一哉が評したとおり、長髪を襟足で纏めたいかつい面構えの担任はポーカーフェイスを装いつつも感心した様子は隠せない。口調に表れていた。
「もうね、涙ボロっボロ流して訴えていたんですよ。相手の女の子の名前は失念しましたがね、誰々ちゃんがどんだけ傷ついていたかって訴えてね」
話し合いの終わりに、寧子は柔和な顔に微笑みを貼り付けて言った。
「もうじき卒業なので四月からはお会いすることはないかと思いますが、息子と蘭ちゃんには今後一切関わらないようお子さんによ~く言い含めてください」
目の前の母親に恨まれて憎まれる覚悟はある。
我が子に危害を与えられるぐらいならば、自分自信が反感を買われる方がよほど良いと寧子は考えている。
どうせ、卒業すれば会うことはない。
微笑みは、煮えたぎる怒りの裏返し。
あくまでも母親の代弁であったが「ゲス野郎」が一哉に難癖をつけて憂さ晴らししていた理由も寧子にとってはあきれた言い訳でしかない。
かつていじめていた蘭と和解できないのに、男嫌いに成り果てたはずの蘭と当たり前のように仲良くしている一哉を見て、悔しさのあまり八つ当たりしてしまった。
蘭をいじめたことで、つるんでいた友達は皆「ここまでひどいやつとは思わなかった」と口を揃えて離れていき、クラスメートのみならず他学年の児童からも「しつこいいじめっ子」と警戒されて遠巻きにされた。
しまいには友達の作り方を忘れた。
中学校進学後に少数の友達はできたが、学年が上がるうちに減った。
ある児童と関わったことで、小学校三~四年生のうちの短期間で培われた「人に嫌われるだけのコミュニケーション」が友達をことごとく離れさせた。
常に他人を手厳しくジャッジし、当てずっぽうの的外れな憶測を無理にでも当てはめようとする。
好かれているものがあれば、まずは揚げ足取りに入る。
コンプレックスを見つけようものならば即座にいじり回し、相手が泣いても怒っても止めなかった。
現在まで関わっている唯一の友達からも「自分まで去ったらさすがにかわいそうだから、仕方なく側にいる」という本心が見え隠れしていたのも辛かった。
その点、一哉は入学以来継続して付き合える友達がいる。
時々、公立中の学区内では小学校時代からの親友らしき公立の生徒と楽しげに絡む姿も見かけた。
始めはただ、自分が成し遂げられなかったことを当然のようにやってのける一哉の人となりを知りたいだけだったかもしれなかった。
彼を真似すれば変われるかもしれない、と。
二年生に進級して初めて話すも、優れた容姿と人懐こそうな笑顔が妬ましくなり「女みたいな顔」と憎まれ口を叩いた。
口をついて出た嫌みに我が事のように憤る奥山直樹を見て、一哉を気づかい悲しげに眉をひそめる若松学志を見て、初恋の相手に等しい橘織絵からも怒りを露にされた挙げ句冷淡に突き放されたことで、自分との差を思い知らされた。
「アズは俺のマブダチなんだよ!」
憤る奥山直樹の言葉だ。自分が誰にも言われたためしのない「マブダチ」の言葉が胸の奥に深く突き刺さる。
謝れと食い下がる奥山。自分にはそこまで尽くしてくれる「マブダチ」など、いるだろうか。
負け惜しみとは存じているが、惨めったらしさを誤魔化すように執拗に嫌みを投げつけて攻撃を続けた。
ある時、蘭を引き合いにした嫌みを言うとそれまで嫌みを軽くかわしていたはずの一哉の顔色が変わった。
端正な顔が怒りと憎しみで歪む様に、快感を抱いた。
勝ったつもりになれた。
勝ったつもりになれた。
息子ったら、そう話していましたねぇ。
目の前の女がすっとぼけた顔と口調で代弁する。
寧子は胸ぐらをつかみ「加害者風情がいかにも他人事みたいな言い方をして!」と怒鳴りたいほどの怒りにかられたが、公共の場で実行した際のリスクを考えてどうにか抑えた。
十年以上前にも同様の黒い感情に襲われて必死に抑え込んだ記憶が甦ると、寧子は相当に気が狂いそうな心持ちになる。
幸か不幸か、蘭の母親である星も同じ気持ちだったにもかかわらず蛮行に走りたい衝動に耐えたのだから、と抑える理性は残っていた。
星の持ち味である女傑そのものの人柄が好ましかったのもあり、蘭の受けた仕打ちは他人事ながら許しがたい。
一哉が躍進するきっかけを作った聡明な少女には、出会ってくれて有難いという感情しかない。
気が早いのは承知だが、成人した一哉と蘭が神の前で愛を誓う姿が寧子の頭の片隅を掠めて頬が弛んでしまうこともあった。
「でも、昔はそうじゃなかったんですよ? 小学生の時にある女の子に入れ知恵されて……」
さて、「ゲス野郎の」母親はすっとぼけた顔のまま「本当は悪い子ではない」「意地の悪いクラスメートと関わったから変わってしまった」と、なよなよした口振りで「ゲス野郎」を庇い立てつつ元クラスメートの女子児童に責任転嫁する有り様。
寧子は清子の件も引き合いに出した上で、如何なる理由があっても男子からのいじめで男性不信に陥るのは当たり前と説き伏せた。
未だに清子の同年代の少年に対する不信感は健在だ。
現在は女子高に通っており女子大への進学という選択肢はあるものの、社会人になれば同じ組織に同じ年頃の男性が混ざっているなどザラである。
男性不信が治らないにしても軽くならない限り、先を思うと不安にかられることも告げる。
一哉の口が立つ性質上、清子の二の舞は免れたが「なぜ、私の子ばかりが悪意を受けねばならない?」という思いは拭えない。
学校からの帰り道は理不尽さに身悶えた。
つまらない、自己中心的な理由のために我が子が犠牲にされる苦痛は、加害者にはわからないであろう。
シューパイは、一駅乗り越して隣の校区の小学校前にある菓子店にて買ってきた。
気晴らしに、家族の誰にもバレないよう自分にだけケーキを買ったのは秘密である。
◇◇◇
「おばちゃん帰るねー。おやつおいしかったっす。ごちそうさまでした」
気安い口振りで声をかけるは合田。
続けて浜津と村上も「お邪魔しましたー」と挨拶をする。
愛想が良さが出ている声は浜津。
少しばかり緊張した声色は村上だった。
2002年3月・4
◇◇◇
合田達はというと、一哉の自宅からさほど離れていない公園に行った。二月に慧子を含めた三人で雑談に興じた、あの公園だ。
「この前の謝恩会の"アレ"を飛鳥のやつが聞いたらマジギレしただろうな」
「本当だよ。な~にが"吹奏楽部のみんなが大好きです"なんだか」
珍しく浜津の口調に怒りが露となっている。
数日前に行われた謝恩会。謝恩会のラストは各部活動の代表による顧問への感謝を綴った作文の発表が恒例だ。
テニス部のキャプテンだった由香理が感極まって泣いた時にはもらい泣きする生徒が続出し謝恩会のムードは最高潮に盛り上がったが、吹奏楽部代表による感謝のコメントに入るなり生徒達の間に白けた空気が広がった。
二年前まで泉清中学校随一の花形だった吹奏楽部。
退部者を出すほどのいじめ問題を発生させた挙げ句、顧問の目を誤魔化して遅い時間帯まで部員を帰宅させないなどの規則違反を繰り返した結果「吹奏楽部だけは入らない方がいい」という悪い噂が入学予定の小学生にまで広まった。
噂の出どころは様々で、例えば兄や姉の食卓での愚痴であったり、保護者達の井戸端会議を通行人が聞きつけて更に広める……というパターンも存在した。
著しいイメージダウンを象徴するかのように、今年度の新入部員は五人しかいない。
吉田は「私の一生懸命さを分かってくれない!」と逆恨みに似た感情を向ける上野に対し、白々しいまでの感謝の念を言い連ねた末に
「私は共に頑張ってきた吹奏楽部のみんなが大好きです」
の言葉で締めくくった。
二十年弱に渡る教員生活により負の感情を隠す術を身に付けたのか、上野は冷たいまでの気品ある顔に微笑みを"貼り付けて"「頑張りました」と返した。
合田も浜津も、村上も吹奏楽部を追い出されたに等しい蘭とエリを気にしながらも恐ろしくて彼女達を振り返ることすらままならない。
白沢小百合が言うには、恐る恐る後方を振り返ると蘭は目を吊り上げた険しい顔で美辞麗句をつらつらと述べる吉田を睨みつける姿が見えたそうだ。
エリはというと、出席番号の隣り合う女子から「大丈夫?」と気づかわれていたと聞く。
卒業アルバムの文集のページにて掲載された各部活動の代表による作文は、この謝恩会にて披露されたもの。
不意打ちで視界に入った顔写真ですら忌々しげに顔をしかめた一哉だ。
怪人クラッシャーの綴る嘘くさい美辞麗句を連ねた作文を見た日には、一哉は長ったらしいセリフと共に激しく怒りをぶちまけていたに違いない。
浜津の様子を意外だと思いながらも「怒るのも無理もないか」と納得した村上。
「二人も追い出しておいてな。大槻は来るもの拒まずだからともかく、音澤は寄せ書きのページに書かせたりしたのかな」
あいつ完全に人嫌いに成り果てたから……と言う村上は、蘭を気づかう感情が少なからずはあるのかもしれない。
「鵜沼達以外に斎藤聖良と久間木春奈が書いてたな」
合田は昇降口で白沢に混じって聖良と春奈が蘭の卒業アルバムに書き込んでいた姿を見たらしい。
春奈の名前を聞いて何かを思い出した浜津は「そういやさ」と話を振る。
「久間木で思い出したよ。あいつ、昨日の体育の授業で大激怒した話聞いたかい?」
聞いた聞いたと合田と村上が返す。
「吉田のやつが懲りずに大槻のことバカにしたから音澤が止めに入ったんだべ?」
「そして逆ギレした吉田が嫌みだか言ったら、久間木がキレたって……女子が喋ってたなぁ」
「あの冷静な久間木がね……」
小学校入学時から春奈を見知っている浜津が意外だと口にすることから、春奈はあまり声を荒らげないタイプとわかる。
「詳しくは知らないけど、久間木は前から吉田のことが嫌いだったようだね」
クラスの女子が噂していた、と村上が言う。
「それでよ、久間木のやつ怒りに任せて飛鳥のやつがマジギレした件を口滑らせっちまったんだと」
「音澤のやつ、どんな反応したんだろうな」
まずは蘭のリアクションが気にかかった合田。
浜津は「白沢の話によれば別に怒ってはいなかったみたいよ」と返した。
「後腐れあるまま卒業すんのかな音澤のやつ」
キィ……キィ……とブランコの音が村上のつぶやきに続いて聞こえる。いつの間にか浜津が立ち漕ぎをしていた。
立ち漕ぎのまま浜津は「謝罪されても許したくもないでしょうよ。あんな女のことなんか」と言った。
「いやいや、吹奏楽部の他の連中だよ」
2002年3月・5
◇◇◇
帰宅した合田。手洗いうがいを済ませて台所へ夕飯の確認へと向かうと年子の妹が憎まれ口で出迎える。
妹はどこにでもいそうな平凡な少女。
痩身で、テニス部で屋外を駆け回っているからか日焼けした肌がイヌ科のすばしこい動物を思わせる。
熊のように大柄な合田とは似ていない。
「受験生が遊び歩いていいのけ」
低学年の頃までは絵に描いた仲良し兄妹だったが、思春期を迎えた頃には如何に相手を出し抜くかと張り合うライバルに近い関係に至る。
更には反抗期に突入した影響もあり、こうして顔を見る毎に兄に向かって悪態をついているのだ。
「飛鳥ん家でちゃんと勉強やったわ」
「うっそぉ! 一哉先輩の家!?」
妹の殺伐とした態度が一変して、目の色が変わる。
兄の親友を「ハマちゃん」「飛鳥君」と呼んでいた妹だが、中学校入学以降は「浜津先輩」「一哉先輩」と呼ぶようになる。
妹の反応から察するとおり二年生の間でも一哉の人気は高いが、美人の彼女がいるという噂によりアタックする者が出た話は聞かない。
さて、発言に違わず合田は一哉達と二時間に渡り受験勉強に励んでいた。卒業アルバムを前にした談話は、ほぼ帰り際に近かった。
「一哉先輩、ますますかっこ良くなってるよね。ピンクのマフラー似合うしさ。あの人、みっちゃんのお姉さんと付き合ってるんだべ?」
妹が、みちるとわりかし仲が良いことは合田も知っている。時々、和やかに会話を交わす姿を見かけるからだ。
「お前らの学年、どんな噂出回ってんだよ?」
「え、一哉先輩とみっちゃんのお姉さん付き合ってるんだっぺよ? 違うの? 今時プラトニックな関係貫いててさぁ、先輩達本っ当にお似合いだよねえ」
「まあ、付き合ってるようにしか見えねえよなぁ……」
蘭と一哉は付き合っているか否かの真実はややこしく、説明するのも面倒くさい合田は伏せておくことにした。
夕飯は、スーパーのローストンカツ。太った体型がいかにも肝っ玉母さんらしい母親が「勉強はかどったけー?」と聞きながら付け合わせのナポリタンを作っていた。
「うっほ。うまそう!」
「ゴリラじゃねんだから」
舌打ちの後に冷淡につぶやく妹を相手に合田はゴリラのモノマネをするもあまり受けなかったようだ。
クラスメートならば目尻に涙を浮かべてまで笑い転げるというのに。
肩透かしの結果を面白くなく思う合田は、急に転校時の記憶が甦る。
転校生の自己紹介で「茨城県から来た合田康範です。特技はモノマネです!」と言ってゴリラになりきった。
モノマネは大成功し教室中に笑い声が轟く。
隣では自己紹介を終えた一哉がうずくまって、ひな壇を叩いて大爆笑していた。
好物が夕飯に出ることを確認した合田が自室へ鞄を置きに行こうとすると「あ、そうだ」と呼び止められた。
「何だで」
口をついて出た福島弁。
「やっぱり、みっちゃんのお姉さんって吹奏楽部の子達と関わりたくないんだっぺか」
「関わりたくねえに決まってっぺよ」
我が事のような口調で返す。
吹奏楽部員の二年生。特に吉田に懐いてエリを馬鹿にしていた二年生達は甚だ生意気で、合田の目から見ても印象が悪い。
見た目はさほど特徴がない割に、何を勘違いしているのか自分達を"イケてる"と思い込み、常に他人を見下す鼻に付く連中。合田はそのように思っている。
こんな生意気な後輩とは、できれば関わりたくない。
「部長やってた先輩に懐いてた連中じゃないよ。ちょっと暗めの子達なんだけど……」
連中と"子達"との呼び方の差。
妹が吹奏楽部の同級生にどんな感情を向けているかがよく表れている。
「みっちゃんのお姉さん、その子達に目をかけて面倒見てくれてたっぺよ。……それなのに何の力にもなれなかったって後悔してるみたい」
合田は力なく「はあ……」と返すほかない。
上級生。それも"思い通りに動いてくれない人"をあの手この手を使って追い込む輩には反発しにくいだろうと"ちょっと暗めの後輩達"には同情する。
◇◇◇
「セイラさん、私、わからないんだ」
蘭は西道路の交差点まで聖良を見送るすることにした。
街中に鎮座する信夫山を背景に、地下道の出入口と支所、消防車と救急車の待機する様が見える。
蘭の自宅から交差点まではさほど離れておらず5分もしないうちに着いてしまったが、互いに名残惜しくなったので地下道の脇で立ち話を始めたのである。
「後腐れあるまま卒業ってのもスッキリしないのに、いざ謝られたところで許したくない人もいるの」
蘭は「例えば……」と前置きし、エリがスコアを紛失した際に(正しくは嫌がらせによる盗難)自分で紛失したくせに他人を巻き込むなと突き放した同級生の名を上げた。
「自分がやられたわけではないけど、弱っている人に死体蹴りじみた態度を平気で取れる人は信用できない」
この同級生は学年でも目立たないポジションにいるが他人を見下す性格らしく、エリをはじめとした立場の弱い生徒だけを選んでは「弱い人は嫌い」「甘ったれている」だの口うるさく説教したがる生徒だ。
関わりさえしなければ毒にも薬にもならない人物に過ぎないが、本性を知れば蘭でなくても信用できないと見放したくなるだろう。
今、この場にいない者へ抱くやり場のない怒りに蘭は身悶えるほかない。
親友へ向けられた心ない暴言の後、エリは専用のファイルにスコアを保管していた件を告げ「盗難かもしれないのに、その態度はないと思う」と蘭がキッパリと意見する姿を聖良は目の当たりにした。
エリには辛辣に接したにもかかわらず、直後にへりくだった態度で蘭と対峙する姿は聖良から見てもみっともないもので、この時に聖良は"気高さを微塵とも感じられない"と軽蔑したものだ。
怒りに堪える蘭の凛とした横顔。
硬い輝きが蘭の瞳の奥底にギラリと煌めく様を、聖良は認める。
「無理に信じなくてもいいし、許さなくてもいいんじゃないかな」
許すも許さないも自分自身が決めることだし、と聖良は繋げた。
驚いたのか、蘭の伏した目が見開かれる。
「今のセリフ聞いてホッとした」
見開いた蘭の目が再び伏し目がちになり、微かに口元が微笑んだ。
「どうしても許したくない人がいるって話すと"許してあげなよ~"って軽々しく返す人多いでしょう? セイラさんみたいなこと言う人、珍しいよ」
少しの間だけ聖良は考え込む。彼女はいつでも真摯な姿勢で会話に臨むのだ。
話半分の対応は決してしない。
「許してあげなよって言う人はさ、いいことをしているつもりになりたいんじゃないかい?」
「そうだろうね。ただの自己満足に過ぎないのに」
「今思ったけど、蘭さんとつるんでいる人って"許してあげなよ~"って軽々しく言わなそうだよね?」
確かに、と蘭は同意する。
「特にミヨシは共感しすぎて本人以上に怒るからね。第一、私は無理強いする人は嫌いなの」
自己満足の為に本人の意志を無視してまで相手をコントロールするだなんておこがましいし薄気味悪い、と語る蘭は身震いがするとばかりに腕をクロスさせる格好で己の肩を抱いた。
「なんか……我が道を往く蘭さんらしいね」
そろそろ帰るね、と聖良と解散したのはそれから数分後。
地下道より反対側の歩道へ移り、自宅へ戻る蘭だがあと少しで門扉へ着くという段階で足が止まる。
二度と顔も見たくないし関わりたくもない女がそこにいた。
愕然とする蘭の脇を車が通り過ぎて、車庫へと入って行く。
女=吉田は気安く「あ、蘭ちゃん」と声をかけて歩み寄ろうとするが、すかさず蘭は脇を素通りすることにした。
紙を持っているが、何を書いているのかを知りたいとも思わない。
「これ、後輩が盗んだやつなんだけど、エリちゃんに返してほしいって……」
口調から馴れ馴れしさが消え失せ、消え入りそうな声と共に吉田は紙を差し出す。
蘭は門扉の鍵に手をかけている最中だが、図々しくも距離を縮めたので視界を紙が遮る。
紙の正体も、事の詳細も即座にわかった。
名前は伏せているが、吉田の腹心に等しい現吹奏楽部の部長を務める二年生が犯人だろう。
蘭や聖良の指導を無視してまで陰でエリを嘲る、慇懃無礼で生意気な後輩。
現二年生の中で最も経験がある、というよりは吉田の腹心として部長に抜擢されたと丸分かりな人選だ。
嫌がらせのつもりで盗んだ自由曲のスコア。
罪悪感にかられてか後味が悪いがゆえかは知らないが、持っていることが辛くなり慕っている吉田に泣きついて頼み込んだのだろう。
「しつこい」
鍵に手をかけて顔を向けないまま、ハッキリと告げる。
「関わらないでって言ったよね。なんで私に頼むの? あんたの親か上野先生に相談したら? あんたも、盗んだ後輩も、盗んだものを本人に返してほしいと他人に頼むだなんて厚かましいにも程がある」
関わりたくないと宣言したのに、なぜこの女はいつになってもつきまとうのか。
「私から返しにくいからぁ……」
「ふざけないで……! 必死で写したのに踏みつけにされた紙なんか、エリちゃんは絶対に受け取らない。今さら戻ってきたって全然嬉しくない」
エリが如何に優しい性格であろうと、謝罪の言葉をまともに聞かずに拒絶するほど憎む者が触れたものなど受け取るはずがないと蘭は言い募った。
「あんたは、私らの学年の部員の代表でありながら、後輩にどういう指導をしてきたわけ? 気に入らない人を追い詰めるための指導? 部長のくせに正しい指導を放棄して好き勝手やらかしたあんたが、よくもまあ"吹奏楽部のみんなが大好き"なんて平気で言えるよね!? 嘘くさい美辞麗句連ねていないで今まで部活でやらかした悪行三昧を洗いざらい白状すればよかったのに!」
ありったけの罵詈雑言を浴びせたい衝動に負けそうになる蘭を救ったのは「娘に何か用かね?」と問いかける野太い声。
車のドアを閉める音に遅れて、足音が響く。
父親の泰造だった。
同じ小学校の出身者ならば泰造の容姿は見知っている。
大柄で、コワモテを更に際立てる色付きの眼鏡。
いつだか一哉が「蘭の父ちゃんってハードボイルド漫画に出そうだな」と言っていたとおり、泰造もまた"組長"とあだ名されかねない、厳つい容姿の持ち主。
「君、今すぐに娘から離れなさい」
駆け足に近い早足で割って入る泰造の口調は静かだが、威圧感は拭えない。
ただでさえ相手方の保護者と話すつもりはなかったのに、よりによって見た目が怖いことで有名な蘭の父親を前にしたので吉田は青ざめた。
元からの青白い顔に冷や汗を垂らしながら、指示されたとおり蘭と泰造から距離を取る。
「蘭は家に入っていなさい。場合によってはお母さんを呼ぶといい」
蘭が門扉を通り抜けるや否や「申し訳ないが、娘には一切関わらないで欲しい」と、泰造がご丁寧に身体を45度に曲げながら静かな口調で立ち去るようにと促していた。
「話したいことがあるのかもしれないが、君は娘を二度も追い込んだ。君には、娘と関わる資格などないと理解していただきたい」
あくまでも泰造の腰は低い。
ありもしない話をでっち上げて注目を浴びたい吉田の性格を人づてに聞いている泰造は、下手に声を荒らげては不利になることも察している。
まだ十つに満たない蘭が、パジャマ姿のまま夜の物置小屋に潜んで除草剤を抱えて泣いていた様子は思い出したくもないほど辛い記憶なのに、嫌でも甦る。
我が子の敵に年齢も性別も関係ない。
死を意識させるまでに追い詰めた目の前の憎い"死神"を殴りつけて罵声を浴びせたい気持ちを堪え、泰造は紳士的な対応を努めた。
そのうち近隣に住む住民が「音澤さーん、何かあったのぉ?」「事故にでもあったのかい?」と次から次へと集まる。
野次馬よろしく集まってきた者達の年齢は壮年から高齢にかけている。
中年の男性がお辞儀をしながら十代の小娘を相手に懇願する姿は"甚だ"珍しいだけに、気にかける者が続出しても仕方がなかった。
この街は住民同士のコミュニケーションが濃密な地域であるが、そういった地域にありがちな排他的な空気は見受けられない。
むしろフレンドリーな者が多く、友達の友達の友達という関係性でも友好的に接するし、初対面にして旬の果物を渡すなどしょっちゅうだ。
困っている者がいれば「大丈夫かい?」と声をかける。
小さい子供を連れた母親を見れば「あららら、かわいいナイ。いくつ?」と頬を緩ませる。
見かけない顔触れを見かければ興味本位で「どこさ住んでるの?」と声をかけつつ「これからもよろしく」と挨拶をするのだ。
はては小学生自らが世間話がてら声をかけてくる。
一方でドライな付き合いを好む者には、煩わしく感じるだろう。
住民達が集まってきたのも蘭と泰造を気づかうがゆえの行動に過ぎないが、居心地の悪くなった吉田は突き返された紙を持って立ち去るしかない。
「あれ、あの中学生って……」
引き下がる吉田に気づいた住民に対し、複数の住民が「これ以上は言うな」と目配せと頭を振るジェスチャーでたしなめる。
たしなめられて始めは戸惑うも堅い表情のまま玄関先に立ち尽くす蘭を見て事情を察した。
「蘭ちゃん、そろそろ卒業だナイ」
「入試頑張んだよ?」
「蘭ちゃんは頭いいから大丈夫だべした。ナイ?」
フレンドリーなご近所様に「ご心配をおかけしました」と蘭は礼儀正しく頭を下げた。
「蘭ちゃん、学校で何か言われても私らが見てたから大丈夫だかんね」
「証拠人いっぱいいるんだからよ」
「んだからぁ」
この街の人達は相変わらずだ。
家族と、友達と好きな男の子の前以外で笑わなくなった蘭にも幼児期と変わらない優しい態度で接してくれる。
戸惑いながら、蘭は微かな笑みを返した。
玄関へと入る父娘を見届けた後も住民達は立ち話を続ける。
「蘭ちゃん、昔より笑わなくなったナイ」
「さっきの中学生だべ? 原因作ったの」
「妬まれたんだべ。蘭ちゃんは綺麗な顔さしてっからよぉ」
2002年3月・6
◇◇◇
案の定、翌日の学校は蜂の巣をつついた騒ぎになっていて、午前中の時点で蘭は甚だ疲れてしまった。
スコアの件は学校中に知れ渡った。
蘭が皮肉のつもりで吐き捨てた「自分の両親か上野先生に相談したら」を実行したのか、吉田と現吹奏楽部の部長は朝っぱらから職員室でひどく叱られたという。
その後に職員室へ呼び出されたエリが謝罪に一切応じなかったことも、盗まれたスコアを叩き落としたまま受け取らなかったことも全て生徒の口から広まった。
「吹奏楽部、年度末で解体すっち噂だで」
「解体ってなんだで?」
「一旦廃部して新年度に部員募るってよ」
「前の部長が規則破ったりいじめとかいろいろな悪行さやらかしたからだべ? ほら……」
体育館の渡り廊下で話し込む一年生の男子達。小学生の面影を残す彼らが目配せをする先には蘭がいる。
そして蘭も「なんか噂されてるな」と気づいていたが素知らぬふりに徹した。
「あの先輩、元吹奏楽部員でフルートめちゃめちゃ上手かったらしいけど、前の部長から嫌がらせさっち退部したってよ」
「知ってる。音澤先輩だべ」
うち一人が「あの先輩、美人だよなぁ」と惚けるも、すぐに「でも」と繋げる。
「綺麗な顔してっけど笑わねえし、なんかおっかないっつーか近寄りにくいんだよなぁ」
「嫌がらせ受けりゃ笑わねくなるのも当たり前だべした。むしろ同情すべきだかんな?」
「んだから。あの先輩、翠楓のイケメンと付き合ってるらしいね」
「三年生でトップの成績らしいしな」
「うちの学年の女子、あの先輩の髪型とか服装真似してるやつたまにいるよな」
「ある意味ファッションリーダーってやつか」
そりゃあの元部長から妬まれるわ、と誰かが言う。
「前の部長って四年の時に転校していったクラスメートの姉なんだよ。本人は至って普通のやつだけど、姉は清水が丘いた時から人と差ぁ付けたがるち有名だったで」
雰囲気だけは美人っぽいけど顔そのものは平凡だったな、と続けた。
「あいつ、この前矢野目のSATYで会ったよ。うちの中学さ来なかったのは姉のせいだって愚痴ってた」
「そりゃそうだよ。自分の兄弟姉妹が悪さしてる学校なんて居づれぇべした」
だから引っ越し先の学区にある中学校さ通ってんだと、と語る一年生は外出先で偶然に会った吉田の弟本人の口から聞いたという。
「上野先生、前の部長が好き勝手やった時点で解体さ考えたらしいけど、真面目にやってる部員まで巻き込むのはかわいそうだからって思い止まっていたんだと」
今の部長も上級生のスコアを盗んだことが発覚して解体さ決め込んだってよ。一年生がそう語る。
「でもよぉ、やらかした部員がまた入ったら意味ねえべした」
「やらかした部員は一切受け入れねぇって話だで」
「卒業式のリハーサルの前に臨時の集会やるって聞いたけど……」
「あれ、絶対に吹奏楽部解体の件だべした」
臨時の集会は一年生達の噂どおり、吹奏楽部解体についての報告であった。
部員達は朝早くに音楽室でミーティングがあると召集され、一足先に解体の件を告げられたという。
体育館内にいる吹奏楽部員と引退した三年生の反応は多様で、茫然自失とする者もいればどこか安堵した者。そして、いたたまれない様子で身を縮める者もいた。
◇◇◇
蘭が職員室に呼び出されたのは昼休み。
呼び出し主は、上野だった。
上野はこれまでも再三に渡り自身の監督不行き届きによる結果だと悔やんだが、その毎に保護者と生徒のうちの誰かが必ず「先生には非がない」と庇う。
今回は蘭がその役目を担った。
「吹奏楽部の解体にはかなりの間迷ったの。あなたのお兄さんが部長を務めた年には創部以来最高の結果を出せただけにね……」
「今の部長がスコアを盗んだ件が決定打となったのでしょうか?」
そうね、と上野は疲れきった表情で返答した。綺麗にセットした髪と憔悴した顔の対比が痛々しい。
「決断するのが遅すぎたわ。吉田さんの傍若無人な振る舞いを野放しにしたも同然の結果となってしまった」
そんなことはありませんと食い気味に返す蘭は「先生は、問題行動を起こす部員に対して誠実に指導なさりました」と続ける。
中学生とは思えない受け答えだ。
部活内でのいじめとなれば指導者もバッシングを受けがちだが、保護者達も職員会議で部活動を抜けざるを得ない日があることも存じ上げており、問題行動に対する指導を怠らなかったことも我が子の口から聞いていた。
更には家庭を持ち、幼い子供を抱えた身であることも保護者達から同情される要因となっていた。
「解体とはいっても、残りたい子で真面目に活動していた子は受け入れるつもりよ。あなたが面倒を見てきた二年生も」
複数の二年生の顔が浮かぶ。
いつも音楽室の片隅にいて、吉田からはあからさまに冷遇はされないものの相手にもされない。
放任される形で、現部長とその取り巻きとの扱いに差を付けられていた。
表情に乏しかったり、どこかオドオドしていたり、親しい者以外と打ち解けることが苦手であったりと内向的な彼女達だが、蘭を前にすると輝いた眼で見上げていた。
退部届を叩きつけた後も、蘭が面倒を見てきた後輩達は校内で蘭と会えば気づかいの言葉をかけてきた。
「音澤さん。あれだけ辛い思いをして退部したあなたに厚かましい申し出だとは承知だけど……」
時間のある時で構わないので、春休み中の後輩の指導をお願いしたい。
上野は両膝に手を置いて、深々と一礼した。
◇◇◇
前日に解散した交差点が聖良との待ち合わせ場所だった。
「やっぱり、セーラー服なんだ」
かくいう聖良もセーラー服だ。
「あと少しで着納めだからね」
蘭ははにかんで自身の胸元に目をやった。シアンブルーのタイが微かに揺れる。
「セーラー服にブーツって合うもんだね」
蘭の足元から頭までを見上げて、聖良はブーツがハイカラさんっぽいと感想を述べた。
スッと爪先を伸ばした蘭は「これ、雪靴」と言って足元を指差す。
「ハイカラさんいいよね。私、大正ロマンや昭和レトロの類いが好きなの」
例えば今現在のギブソン・タックに結った髪や、三つ編みをカチューシャ風に巻き付けて後ろ髪を襟足で結わえる髪型はそれらの時代の女学生を手本にしているのだと蘭は語る。
突然、聖良が含み笑いをするので蘭が理由を聞くと
「一年生が真似して学校にブーツを履いてきたことを思い出した」
と返ってきた。
校則では白いスニーカーが指定なので、翌日以降はブーツで登校しないようにと蘭の真似をした一年生は指導されたらしい。
「あくまでも学校の外だけなんだけどなあ。防寒と滑り止めを兼ねて」
「でも、一年生の気持ちわかるなぁ。蘭さんのセーラー服にブーツ合わせた姿ってかっこいいから真似したくなるもん」
蘭と聖良はお喋りをしながら足を進める。
地下道の中は交差点状に道が枝分かれし、二人は泉駅方面へ抜ける通路を目指した。
中学校周辺は昭和末期から平成初期にかけて建てられた住宅と店舗がひしめくが、泉駅付近となると景色は昭和期の下町にタイムスリップしたような様相を見せる。
時代背景が昭和50年代の国民的アニメの世界を再現したようだ一哉から言われた時、蘭は確かにと納得せざるを得なかった。
地下道を出てしばらくが過ぎると二人の耳にシグナルの音が届く。
シグナルは蘭と聖良の後方から。飯坂温泉駅方面へ向かう電車だ。
そわそわとし始めた蘭に「おや?」と不思議に思う聖良。
蘭より向かって東側に線路があり、速度を落とした電車が泉駅のホームへ入ろうとしている。
聖良は、蘭の目が見開かれる瞬間にありつけた。尊敬の念を抱く憧れの雪の女王は頬を染めて、小さな声で「あっ!」と叫ぶ。
車窓からは同じような表情の一哉が見えた。
橋上駅舎という特徴のある外観の駅舎から、まずは私立小学校の児童が駆け出した。
次いで部活動が休みか、あるいは部活動に所属していないと思しき中高生が悠然とした足取りで疎らに出てくる中で、学生服にピンクのマフラーを巻いた少年が早足で飛び出してくる。
「蘭ちゃん!?」
息を切らすまで走ることはないだろうと驚く聖良の横で、蘭は高鳴る心臓を鎮めるかのように無意識にセーラー服のスカーフ留めのあたりを掴んでいる。
「えーと、セイラさんつったっけか?」
肩で息をついたまま一哉は視線を聖良へと向けて蘭に聞いた。
「うん。斎藤聖良さん。同じオーケストラの子で……前に合唱の練習に居合わせてたの覚えてる?」
あー、やっぱりあの子ね。一哉は両手を叩いて言った。
「ハリー・ポッターみてえな子いたの覚えてるもん」
「あはは、髪の毛ショートにしっちからよくハリポタに似てるち言われんだぁ」
三年生の秋頃に、聖良はそれまで二つ結びにしていたセミロングの髪をショートヘアにした。
流行りの学園ドラマに登場する男装の生徒を意識したつもりだが、眼鏡っ娘な上に童顔で色白な聖良はその姿を「ハリー・ポッターみたいだ」と会う人会う人に評されることとなる。
含み笑いの聖良は、要約すると「貴方はうちの学校では有名だから顔と名前は既に知っている」との趣旨の発言を一哉に返した。
「いやー、話が早いねぇ。俺は蘭ちゃんの……」
「はーい知ってる。彼氏、兼、騎士様!」
真っ赤な顔の蘭が焦りながら、勢いよく手を上げてからかう聖良を肘で小突く。
蘭ちゃん蘭ちゃん。名前を呼ばれた蘭は真っ赤な顔のまま聖良から一哉へと視線を移した。彼はどこか安堵したような表情である。
「セイラさんって真面目っぽいイメージあったけど案外面白いこと言うよね?」
「意外と"おだつ(お調子者な)"ところあるんだ。私も最近知ったの……」
日頃から模範生でいる反動か……。蘭は考察する。
聖良は、打ち解けた相手の前では冗談を言ったりロマンチストを発動させるのだが最近は蘭の前でもそれらの言動を垣間見せるのだった。
2002年3月・7
「セイラさん、一哉ちゃんも連れて行っていい?」
ダメで元々だが蘭は聖良に一哉も同行させて欲しいと持ちかける。
昨日に聖良は話したいことがあると言っていたのだから、言葉は悪いが聖良にとって一哉は部外者に等しいのではないか、という蘭は不安にかられた。
「ノー・プロブレム。モウマンタイだよ」
くりくりした大きな目を光らせてOKサインを出す聖良に、蘭は胸を撫で下ろす。
「悪いね、セイラさん」
「蘭さんも気を許した人が同伴している方がいいべした」
そして、三人は川縁に沿って学習センター方面へ歩を進めるのだが、なぜか前後に分かれた二列で歩くことになった。
聖良が、蘭と一哉の後ろからついて行く形で。
聖良は時折、口元に手を添えて笑いながら二人を見守る。
笑うといっても微笑ましそうな表情であったり、この日だけでも数回見せた含み笑いだったりと様々だが、七割方は含み笑いだ。
カップルの観察など我ながら悪趣味とは理解しているが、見ていて飽きない二人だと聖良は思う。
蘭は決して、一哉の三歩後ろを歩かない。
如何なる時も肩を並べる。
聖良にはそう見えたが……。
「いやー、セイラさん。蘭と大事な話があるっていうのに気ぃ遣わせて悪いね」
「んふふ、お構い無く」
「蘭はね、昔は俺の三歩後ろを歩いてたの」
答えは単純だ。
蘭の背が高かったからだ。
出会った頃の蘭は頭半分ほど背が高かった。
前を歩けば視界を塞いでしまうからと斜め後ろを歩いた。蘭なりの気づかいである。
だが、一哉は蘭の隣を歩きたかった。
たとえ視界がプルシアンブルーのワンピースで塞がっても構わない。
顔が見たかった。
切れ上がった目尻が美しい曲線を描く様も、睫毛が影を作る様も、さらさらの髪が可憐に揺れる様も。
蘭の、白雪の如し美しい姿を全て目に焼き付けたかった。
斜め後ろを歩かれては、視界に入らない。
「優しいんだよ、蘭ちゃんは」
「だから」
聖良は三年間にかけて見続けてきた蘭の人となりを振り返る。
常に弱者を気にかけ、誰かが理不尽に傷つけられれば我が事のように怒り、躊躇いなく矢面に立つ強さを持つ者が優しくないわけがない。
蘭はというと「恥ずかしいから」と俯きながら手の甲で一哉の二の腕のあたりを小突いていた。
「俺ね、いろいろな意味で蘭と肩を並べるの夢だったの」
「じゃあ、夢叶ったんだ」
そうだよ。ちらりと見えた斜め向きの笑顔が答える。横で蘭がはにかむ。
蘭が隣町の小学校の男子と仲良いらしい、という内容の噂を耳にしたのはどれほど前になるだろう。
表向きでは「そんな噂は嘘だ」と否定する蘭だが、折襟の学生服に制帽を被ったレトロな出で立ちの少年と親しげに話す姿を偶然見かけてから、聖良は『恋』への強い憧れを抱くようになる。
軋轢の末に男嫌いと成り果てた蘭が、少年を相手に瞳を煌めかせて笑顔を向ける。
恋とは、人を前向きにさせるの魔法のようなもの?
答えは"人による"という事実を知ったのは中学生になってしばらくが過ぎた頃だが、蘭にとってはプラスに働いたのは一目瞭然だった。
それゆえに身勝手な妬みを買ったのは否めないが、聖良は美しい少年と少女が築き上げるひたむきな恋に憧れ、神格化するまでになる。
川縁には桜の木が並ぶ。
白沢の自宅で聞いた蘭と一哉のなれそめを思い出した聖良だが、口に出しては野暮なので頭の中にしまっておいた。
蘭の足が止まる。
一哉が蘭の顔を覗き込んで「どした?」と気づかう様が見えた。
「セイラさん、私、もしかしたら一部の人達にひどい言葉をぶちまけるかもしれない」
少しの間だけ聖良は黙るが「あの子達も覚悟の上だから」と自信なさげに告げる。
「どういうこと?」
一哉は蘭と聖良の双方に聞いたが、答えが返ってくる前にうっすらと察した。大切な話の全貌を。
「吹奏楽部の子達、蘭さんに謝りたいって私に相談してきたんだ」
数日前の保健室にて、元吹奏楽部員の何人かはエリに何もできなかったことを詫びたが、蘭には未だ謝れていないことを気に病んでいたらしい。
「吹奏楽部で一緒だった同級生の中には、仕方ないなぁって許せる人と行動が信用できなくて許せない人がいるの」
現在進行形で蘭が部活内での人間関係に悩んでいた頃に、一哉は断片的にだが聞いていた。
エリに辛辣な態度を取った者。
蘭についていながら保身の為に寝返った者。
他人事ながら、話を聞いているだけでむかっ腹の立つ連中だと認めざるを得なかった。
「セイラさんは無理して許す必要はないって言ってくれたからそうするつもりだけど……」
「俺もそれでいいと思うよ」
「ありがとう。……許さないだけならまだいい方。未だに信用できない人に対して感情を抑えられなくなって必要以上にきついこと言いそうなんだ」
前日の出来事を振り返ると、あり得る話だ。
蘭は正直に、聖良と別れた後の出来事を一哉と聖良に打ち明ける。
「あれほど関わるなって言ったのに家まで押し掛けたの!?」
蘭以上に憤る一哉だった。
「ちょうどお父さんが帰ってきたから、すぐに去っていったけど」
「なんだよ、あいつ! 蘭にどんだけのことやらかしたか自覚ないの?」
◇◇◇
一昨年になる。
14歳の誕生日を迎えたばかりの初夏。
汗ばむ日もあるのに冬服着用の期間から抜け出せない頃、一哉は意を決して蘭の自宅へ踏み込むことにした。
合田と浜津から聞く、学校での蘭の話を聞く度に気がかりで仕方なかった。
いざ蘭の自宅へ赴くと泰造が出てきたので一哉は戸惑う。
泰造は無口かつ口下手だと蘭に聞いていた。
口下手ゆえに気を遣わせてしまうと思うと気が引けた。何よりも厳つい容姿に威圧されてしまう。
この時、泰造以外の家族は部活なり所用なりで家を留守にしていた。
名乗りを上げるなり、泰造は静かに「ああ、君が……」とだけ言うと一哉を自宅に招き入れた。
客間に通され、畏まって正座する一哉の斜め前に泰造も正座をすると「君、いい面構えしてるナイ」と告げた。
「美醜の問題でねえだよ。目の光り方と口元のバランスがいい。純真で、嘘が苦手で正義感の強い者、ならぬことはならぬを地で行ぐ者の目ぇしてるナイ」
「真っ直ぐにつぐんだ口元でよ、君が"平気で人さ欺く言葉を吐ぐ者でねえ"のは一目でわかった」
口下手と聞いていたはずの泰造に唐突に褒められて気恥ずかしい反面、会津弁交じりの話し言葉がどこか懐かしく思えた一哉だが、その懐かしい気持ちが即座にかき消えるほどの話を一哉は泰造から聞かされる。
とりわけ一哉が堪え難いまでの怒りに身悶えたのは、小学生だった蘭が除草剤を抱えたまま物置小屋に潜んで泣いていた話だった。
除草剤の中には触れただけで死に至るものも存在することを一哉は知っている。
確か、担任が授業の合間に"昭和期の凶悪犯罪"として語り聞かせた、自身が生まれる前に起きた事件についての話で知った。
「こいつが恐ろしいんだ。触っただけで肺がやられち窒息しちまうんだと。こんな恐ろしい代物がよ、当時じゃ当たり前のように農協さ売られてんだ」
担任が話していた除草剤とは異なる種類のものかもしれないが、身の毛がよだつ事実には間違いない。
賢い蘭のことだ、早い時期から知識として身に付けていたのだろう。
泰造は、当時の様子をポツリポツリと一哉に話した。
帰宅早々、蘭は怒りながら学習発表会の担当を変えさせられたと泰造に告げる。
蘭の学年は合奏を披露することになっているのだが、産休に入った担任がまだ蘭のクラスを受け持っていた頃にフルートの腕を買われてソロを任されたはずなのに、代理として赴任してきた新しい担任は「依怙贔屓になるから」と蘭をソロの担当から外した。
後日に蘭を心配する児童の保護者から聞いた話では、担任は「あなたのような嫌われ者がソロを担当するなど反発を買うだけ」「調子に乗るきっかけになるだけだから」と高飛車な態度で言い放ち、一方的にフルートから他の児童と同じくリコーダーへ変更させたという。
蘭を欺いた児童達が笑い声を上げていたことも。
泣きながら、蘭は「死にたいのに死ねない」と言った。
バレエができなくなる。
フルートができなくなる。
私がいなくなったら、力丸が一人になる。
力丸は、クラスでの友達が私しかいない。
力丸が孤立するのは嫌だ。
「まだ年齢が一桁の子供がよ、死を意識するまで追い込まれたんだで。恐ろしいことこの上ねえべした。そんな時でも、蘭は友達のことさ気にかけてた」
冷静沈着に見える泰造の、煮えたぎる怒りが垣間見えたのは膝の上で握り締めた両手が震えていたからだ。
「そんな子供が、他人さ見下して馬鹿にするように見えっかい?」
全く見えませんと一哉は泰造を見据えて力強く答える。
「俺は、県の職員だがらよ。過激な真似さでぎねえ。俺一人の行動がよ、県そのものさ影響すっからよ。それでも自分の子が追い込まれたからには意地でも方つけねっきゃならねえだよ。誰にも文句さ言われねえように、正当なやり方さ徹して方さつけた」
「だげども、もしもこの世界が無法地帯だったり法律が許してくれっこっちゃ、蘭を傷つけた教師と"ガキ共"の首根っこさ片っ端から絞め上げていたナイ」
躊躇いなく「俺も同じです」と即答した。
「……君が、本当に蘭を好きなのはよぐわがった」
ありがとうナイ。
泣きそうな声で告げて、泰造は大きな身体をモソモソと動かしつつ客間を出た。
しばらくの間、一哉は泰造と同じように正座の上で固く握り締めた拳を震わせながら涙を流した。
2002年3月・8
◇◇◇
「うわ! あの超かっけぇ人もいる!」
「音澤先輩とお似合いだよねぇ」
「おいっ、バレっから黙ってな」
物陰に隠れる少女達は軒並み野暮ったさが勝る冴えない容姿だ。いずれもシアンブルーのタイが特徴のセーラー服、泉清中学校の制服を着ていた。
少女達の視界には蘭と一哉、そして聖良が映る。
「ついに来ちまったな」
「んだからぁ」
少女達は吹奏楽部の二年生。蘭に懐いていた後輩達だった。
三年生の先輩方が蘭に謝る計画を小耳に挟んだ彼女達は予め、上野からの許可を得た上で部活動を抜け出した。
現部長からはふざけるにも程があるとねちっこい口調でなじられたが、うち一人がそれまでのオドオドした態度を一変させた。
「エリ先輩のスコア隠したお前さ従うより音澤先輩さ謝る方がよっぽど価値あるわ!」
啖呵を切り、駆け足で学校から逃げ出したのである。
逃げ出す前には現部長の耳元にこれでもかと顔を接近させて
「仲間うちでしか威張れねぇくせに調子こくのも大概にしろで、バーッカ!!」
と、大声で叫ぶというオマケもつけた。
普段、音楽室の片隅に潜んで黙って指示を聞いている彼女達が同級生相手に楯突くなど"珍しすぎる事態"なので、現部長も取り巻きも固まったまま止めることができなかった。
自分達の行いが非常識とは承知している。
それでも、あのいけ好かない現部長に一矢報いてやりたかった。
部活内でも立場の強い吉田に気に入られていると自覚した現部長は、入部して早い時期から天狗になり同級生達を見下すようになった。
例えば、初戦敗退した部活動に所属する生徒やおとなしい雰囲気の生徒達を小馬鹿にするような目で睨んで蔑む様は見ているだけで気分が悪かった。
私は「花形」の吹奏楽部員だから。
周りへ向ける態度が、そう物語る。
その割には、ヒエラルキーの上位者と自分には敵わない存在。例えばクラス委員であったり、吹奏楽部以上の成果を部活動で出した同級生には腰が低かった。
煙たがっているはずの蘭の妹である音澤みちるに至っては、長身でいかにも気が強そうな目鼻立ちから太刀打ちできない相手と本能で理解したらしく、みちるが空手部で結果を出していることもあり廊下で誤ってぶつかればヘコヘコと詫びてくる。
小学生時代は特別好かれもしなければ嫌われもしなかった現部長は、今では同級生達からの評判がすこぶる悪いものと成り果てた。
いけ好かない現部長による部活内での自分達を軽くあしらう態度はいかにも仲間として認めていないと丸分かりであったし、その上優しく接してくれたエリまでも陰で呼び捨てにしては嘲笑う。
そのことを咎める蘭までも「口うるさい」と疎むようになり、蘭とエリを陥れる計画にも積極的に参加した現部長は、三人にとって絶対に許し難い存在だ。
駆け足で逃げ出す最中は笑いが止まらなかった。
普段の彼女達を見知っている同級生達が皆、化け物を見るような目で傍観する様が面白かった。
笑い声を上げながらセーラー服の襟をはためかせて走る姿は、端から見れば青春ドラマの1シーンに見えなくもない。
「しかし学校からここまで長い距離だったなぁ」
三人のうち太り気味の少女が言う。
少女はシゲヨという名前だが、このシゲヨこそ現部長に啖呵を切った少女だ。
シゲヨは自分に自信がなかった。
自分の容姿が大嫌いだった。
現部長と斎藤麻世含む意地の悪い連中から古臭いと揶揄される名前にも、全く愛着が持てなかった。
遺伝なのか太りやすく痩せにくい体質も、やはり遺伝なのか色黒でくすんだ肌も、手を尽くしても抑えきれない天然パーマも、思春期に入ってから目立つようになったニキビ面も、全てが大嫌いだ。
幼少期はそれほど内向的ではなかったが、自分の容姿を意識する年頃に差し掛かると、引け目を感じるあまり親しい者以外と打ち解けることを躊躇うようになった。
蘭の姿は小学校への登下校の際に見かけている。
色白で、華奢で、気品ある目鼻立ち。理想の容姿を具現化したも等しい蘭を「いいなぁ」と羨み、憧れた。
いざ吹奏楽部に入部したものの、気後れして音楽室の片隅で棒立ちになっていた自分に、真っ先に声をかけた先輩こそが蘭である。
「たまに道ですれ違ってたよね?」
この人、蘭さんっていうのかぁ。
かわいい名前だなぁ。
この時の、蘭の瞳の輝きをシゲヨは忘れはしないだろう。
「いつも不思議そうな目で見てたから覚えちゃったんだよね」
「んだからぁ。よく走ってこられたよね……」
シゲヨに同調する少女の名前はアスミといった。
アスミは、顔立ちはなかなかに愛らしいが気弱ゆえに周囲に馴染めなかった。
とりわけ攻撃的な性質の者は大の苦手であるし、オドオドした態度をあげつらって笑われる仕打ちを受けたこともある。
そんなアスミが吹奏楽部を選んだのは、自身とは正反対な華やかな世界観に憧れたからだ。
私も同じなんだと笑顔で応じるエリに親しみを抱き、実はフルートに憧れていると打ち明けた際に「吹いてみる?」と快くフルートを差し出した蘭の優しい眼差しを目の当たりにして、なぜか救われた気持ちになれた。
吹奏楽部に入りたいと言えば家族に「あんたみたいな地味くさいみそっかすが?」と茶化され、気の合わない同級生にフルートに憧れている話を聞かれれば「根暗なあんたに花形の楽器は似合わない」笑われたアスミは、一度も自分を笑わなかった蘭とエリが大好きだった。
来たぞと言うは、ワンレングスの長い前髪ごと襟足でひっつめた薄い顔立ちの少女。名前は亜依といった。
ポーカーフェイスで感情がわかりにくい彼女は、物心ついた頃から不必要に他人と馴れ合うことを好まず、物事に興味関心を抱くこともあまりない。
理由は亜依にもわからない。
親兄弟は良識的であるし、環境に不満があるわけでもない。
ただ、気持ちを揺さぶられる感覚にとらわれた経験に乏しかった。
例えば、親族から何かをプレゼントされれば礼を言うし、使いもする。壊れても修繕できれば再び壊れるまで使うが、好みというわけではないので今一つ愛着が湧かない。
好みのものは、と聞かれてもピンと来ない。
要するに、使えればいい。
髪の毛も邪魔にならないよう結えばいいし、服装だってTPOをわきまえていれば何だっていい。
亜依は『こだわり』を知らなかった。
そんな彼女が魂ごと揺さぶられる感覚を知ったのは、街中で聞いたどこかの学校の吹奏楽部による演奏だった。
小学校にも吹奏楽部は存在するが、それほど感激しなかったのに……と亜依は不思議に思うほかない。
「今年の吹奏楽部もすげえよ。フルートのアンサンブルが全国出っち聞いたけど一年がファースト……主旋律さ担当すんだと」
亜依が小学六年生の冬のこと。
当時中学校に在学していた兄が、夕飯の席で吹奏楽部の活躍について両親に語り聞かせていた。
様々な部活動で未だに年功序列の人選が息づく中、吹奏楽部のフルートアンサンブルに出場する団体が実力重視の人選に踏み切ったことを評価していた。
それも最後のアンサンブルコンテストへの出場となる二年生が自ら、一年生を主役にと推したのだ。
「そのファーストさ担当する一年、俺らが一年の時さ生徒会長やってた音澤先輩の妹なんだ。あ、ちなみにうちのクラスの橋本慧子の従妹だか又従妹だとよ」
「あらぁ、橋本さんってあんたの学年で生徒会長やってた子だべ。その一年生、相当綺麗な子なんだろうナイ」
「だから。サイトゥーが告白したっけよ、好きな人いるからってフラれたんだと」
「えっ。斎藤君、あんなにかっこいいのに振られたのかい?」
笑う兄とは対照的に一言も発さないまま黙々とすき焼きを食べている亜依が、箸を動かす手を止めた。
「一年生が主旋律やるのって、そんなにすごいことなのかい?」
だって一年生も二年生も同じ"中学生"だべした?
食い気味に質問しつつ自分なりの意見を述べる亜依の姿に、両親も兄も驚きを隠せなかった。
兄は鼻息を荒くしながら、事細かに年功序列がヒエラルキーがと亜依に語る。
更に「一年生と二年生ではたったの一学年の差とはいえど歴然とした差があるも同然。学年が上がるほど上級生としてのプライドが高まるのだから"同じ中学生"と括る考えは危険だ」とも聞かせた。
「音澤会長の妹がやってることはよ、高校野球でいうなら一年生にして一軍として甲子園さ出場するようなもんだかんな? お前も中学に上がりゃ俺が話したことの意味わかっからよ。しかし音澤会長の妹がフルート吹いてっとこ何度か聞いたことあっけど、素人が聞いても上手いってわかるわ」
その人の演奏を聞けば、気持ちが、魂が再び揺さぶられるかもしれない。
亜依は顔も知らない中学生の演奏を聞いてみたくなったが、ほどなくして実現することになる。
亜依の入部という形で。
「対面式のフルートアンサンブルの演奏に魂が揺さぶられる感じがしたんです。特に主旋律の人の」
だから、蘭の側で聞きたい。蘭に教えを請いたい。
自分も蘭と同じように魂を揺さぶられるような演奏ができるようになりたい。
亜依はどうしても蘭についてフルートをやりたいと希望を出すも、主旋律を担当する機会の多い花形の楽器といえば経験者が優先となる。
当然ながら亜依は別の楽器の担当となった。
同じ新入部員の中には身の程知らずだと笑う者もいた。
担当する楽器に不満はないが、やはり蘭の側にいられず残念だと思い巡らす帰り際。
亜依を上級生が呼び止める。
「魂を揺さぶられる演奏って言ってくれて、ありがとう」
無言のまま、顔も知らないまま憧れた上級生を見上げた。
大袈裟だと笑う者が出た言葉を、その人は喜んだ。
「奏者にとって、最大級の褒め言葉なの。とても嬉しい」
それから時が経たないうちに蘭は吉田からのやっかみを買ったがために嘘の噂を流される形で陥れられるのだが、新入部員の中で真っ先に蘭を擁護した者が亜依だった。
亜依は何度も吉田魅里と斎藤麻世に楯突こうとしたが、後が怖いからとシゲヨとアスミに止められる。
「亜依ちゃん、やめた方がいいよ……。吉田先輩、ヒステリー起こしてエリ先輩いじめたところ見たけどすごく怖かったから……」
あんな冷酷そうな顔する人見たためしないもん、とアスミは震えながら亜依を止めた。
「吉田先輩って、嘘ついてでも自分が気に入らない人の悪い噂を流して孤立させるち話だよ。だから二年生の先輩達も反抗できないんだよ。うちらは、エリ先輩と音澤先輩の味方だって言い続けることしかできないよ……」
シゲヨが手指をいじりながら自信なさそうに語る。
「あと、チクリ魔って言われるの覚悟で先生に報告するしかできないよね……」
はぁ? と亜依は低い声を出す。
「だから何だってんだよ。先輩達に泣き寝入りしろってのか? 心の汚い人が、あんなに魂を揺さぶられる演奏をできっかよ?」
眼鏡越しに、亜依の細い目が赤く腫れている様子がシゲヨとアスミにも見えた。
自分自身でも気付かなかった、内なる激しさ。
尊敬する先輩方が悪意を向けられるという形で亜依は自覚することとなる。
2002年3月・9
◇◇◇
「うちらさ、よくここまで耐えてきたよな?」
指をいじりながら、シゲヨはくぐもった声で言う。
「知ってんだっけえ。あの女が私らみたいな"暗いやつが同じ組織内さいると自分の価値が下がる"とかいう、変な考えさこだわってんの」
シゲヨは鼻息が荒いまま「私が言えた立場でねぇけど、あいつだって大した美人でもねぇくせによぉ」と言い募る。
続けてアスミがアニメ声にも似たかわいい声で繋げた。
「敢えて吹奏楽部さ居座ってきたのだって、私らなりの抗議だからだもんねぇ……」
放任されながらも現部長と取り巻きが「あの三人、さっさと辞めてくんないかな」と目で語っていたのを、シゲヨもアスミも亜依も気付いていた。
蘭とエリが吹奏楽部を辞め、更には聖良まで去っていった時には退部の文字が三人の頭をかすめたが「絶対に、大好きな先輩達を追い出した連中の思い通りにはさせない」という、彼女達なりの負けん気を強める結果となる。
「私はまだ腹のうちさ収まらないけどな」
憤ったままの亜依は何かをいじっていた。紫のグラデーションに梅が描かれた縮緬地の小銭入れ。
修学旅行のお土産だと、蘭とエリが選んでくれた。
二人は、見向きもされない少女達をよく見てくれていた。
その証拠が、各々にお土産として渡してきた小銭入れの色。
シゲヨは白とピンクのグラデーションに桜が描かれたものだった。
「表には出さないけど、シゲちゃんはピンクが好きみたいだからねぇ」
ニコニコと笑ってエリは言った。譜面を留めるクリップやハンカチがピンクだから、と。
エリの言うとおり、シゲヨが一番好きな色はピンク。
しかし、自分がピンクが好きだと知られたら笑われるからと隠していた。
実際に、中学校に入学したばかりの頃にピンクのスカートを履いて母親の買い物について行った先に吉田と出くわし「えーっ! シゲヨちゃんってピンク着るのぉ?」と大袈裟に騒がれた。
この時の吉田が「ブスのくせにピンクなんか着てさぁ」と言いたげにシゲヨを見下ろして小馬鹿にするような薄ら笑いを浮かべていたのも、シゲヨは絶対に忘れないし許さない。
普段は興味ないとばかりに見向きもしないくせに、茶化す時だけ注目してくる厄介な女。
この日を境に、吉田という上級生の印象はそう刷り込まれた。
救いなのは、周りの買い物客達が「失礼なおなごだ」と言わんばかりに吉田を睨みつけていたことと(そして、吉田は気まずそうな顔でその場から逃げ出した)、通りすがりの老婦人が「あんたはまだ若いんだから、好きな服さ着ればいいんだで」と声をかけてくれたこと。
アスミは水色に雪ウサギ。アクセントとしてクリーム色やラベンダー色のヱ霞模様が入り、彩雲の色を写し取ったような色合いをアスミはとても喜んだ。
「わぁ……かわいい! パステルカラー好きなんです!」
茶色を帯びた髪の毛にやや色白な肌、穏やかな顔立ちのアスミはパステルカラーが似合う少女だが、私服では暗い色を選びがちだった。
あんたは地味だから。
"みそっかす"には華やかなものは似合わない。
これらの扱いを家族から受け続けた結果だ。
「アスミちゃん、絶対にパステルカラー似合うのに。もったいない」
稲荷神社の例大祭だろうか。街中をシゲヨと亜依と一緒に歩いていたアスミに蘭が投げかけた言葉だ。
黒いハイネックに、黒いスカート。この時のアスミが着ていた服だ。
「先輩、かっこいいなぁ。地味ですよねぇ、私……」
蘭は紺色のニットワンピースで白い肌に映えているというのに……惨めな気持ちになるアスミを見て蘭が勧めたのがパステルカラーだった。
亜依は自分の手の中にある、薄藤色から菫色に染め上げたグラデーションが清楚な小銭入れを気に入っている。
梅の花も、知性の象徴と蘭に聞いてから好きになった。
「亜依ちゃんは色白で落ち着いた感じだから、紫のイメージだな~って思って」
絵を描くことが好きなだけにエリは色彩に関心が強いらしい。
「紫? 綺麗だけど似合いますかね、私」
「似合うよ。中学生ぐらいの年格好で紫が似合う子は珍しいよ」
かくいう蘭も紫が似合う人に入るだろうと亜依は思う。
「梅、かわいいっすね。でもなんで梅なんすか?」
満更でもなさそうな亜依に、蘭とエリは顔を見合せて笑う。
そして、蘭は亜依に言った。
「あくまでも私の見解だけど、梅は知性を象徴する花だと思うの。楊貴妃のライバルの梅妃は詩をいくつも書いた知的な女性だっていうし、学問の神様を奉っている太宰府天満宮といえば梅だからね」
兄が進学した地域トップの男子高も、校章が梅だったなぁと亜依は思い出した。
「亜依ちゃんは勉強が得意だし、見るからに知的そうな顔してるからねぇ」
だから梅を選んだ。二人は語る。
この二年間で亜依が知ったのは、自分が意外と激情的な性格であることと、紫が好きなこと。
そして、梅の花が好きなことだった。
2002年3月・10
シゲヨ達は隠れたまま様子を窺う。
吹奏楽部員だった三年生達が、たった今桜並木に沿って蘭のいる方へと向かって来たのだ。
もちろん全員ではない。
吉田についていた三年生達のうち、嫌がらせ電話に関わった者は蘭と教師陣と自分達の保護者共々から「一切関わるな」と厳しく言われた以上、この場に来ていないのだ。
林は、いない。
女子だけの問題だから、女子特有の面倒くさいトラブルに巻き込まれたくないと林は吹奏楽部を引退した後もノータッチを決め込んでいた。
来ているのは、蘭とエリを擁護しつつも吉田が怖くて反発できなかった者。
そして、コウモリ人間さながらにどっち付かずを貫いていた者だった。
蘭が信用できない人と話していた者こそ、後者の"どっち付かずのコウモリ人間"である。
聖良が同伴している件は予め知っていたようだが、予想外の同伴者に色めきつつも戸惑う。
謝罪の言葉からのスタートとなる。
シゲヨとアスミと亜依の三人の目には、厳しい眼差しを向ける蘭の横顔が見えた。
「正直に話すね」
蘭の声色は静かだ。
「仕方ないなって許せる人と、どうしても信用できなくて許せない人の両方がいるの」
そして、蘭はごめんなさいと頭を下げる。
一人が怯えた顔で「信用できないって、誰のこと?」と 消え入りそうな声で訊ねる。
蘭はまず一人の名前を口に出した。
当たり前だが、名指しされた女生徒が愕然とした顔へ変化する様子が見てとれる。
「私が何かされたわけではないけど、エリちゃんへの対応を見て信用できなくなった。
スコアを盗まれたのに"勝手になくしておいて他人を巻き込むな"って、突き放した態度を取ったよね。よくもまあ、弱った人を相手に冷酷な対応できるなってガッカリしたよ」
それだけに留まらず、この生徒が常日頃からエリを下に見る発言をサラッと口にするところも見ていて不愉快だと蘭は指摘する。
エリが傷つきながらも笑顔で誤魔化す姿を蘭は気の毒に思い、さりげなくフォローに回りつつ牽制した。
部活動を終えた帰り道で、何かに挑戦しようかなとエリがはにかみながら打ち明ければ「大丈夫、どうせあんたには無理だから」とアルカイック・スマイルを浮かべて返し、髪型を変えようかなと仲間内で話している時でも会話に割って入っては「今よりブスになったら意味がない」などのきつい言葉を投げつける仕打ちを止めなかった。
一緒にいることが苦痛だとエリ自らが距離を置くも、目敏く見つけては会話に割り込んで説教を始めたりあら探しをする。
そんな姿を亜依から「嫁に嫌がらせする小姑みたいで見苦しいですね」と面前で指摘を受けた際には相当に狼狽えていたが。
蘭が信用できないと名を挙げた者は三、四人。
強きにへつらい弱きをくじく思考と、その時の気分で誰の味方つくかをコロコロ変えるところが信用できないと蘭は言った。
聖良が、堅い表情で目を伏せる蘭の背に手を添える。
「自分の行動を臨機応変な賢い生き方と言い訳したり、弱い人は嫌いという考えを持ってるようだけど、私はずるい人と"弱い人は嫌いと言う人"が信用できないの」
人は誰しも弱さを持ち合わせて当たり前なのに"弱い人は嫌い"と口にする人ほど自分の弱さから目を反らす。
自分の弱さを認めたくないから、力の弱い人に辛く当たって強くなった気になっているだけ。
弱いからこそ、ずるい人に成り果てる。
低く、震えた声で蘭はそう告げる。
「一年生の時にあれだけ私に助けて欲しいような顔しておいて、二年生になった時に"みーちゃんに黙って従っていればいいのに、バカじゃないの"って私の陰口言ってたの、気付いていたから」
思い当たる節のある者達が、バツの悪そうな顔で下を向く。
それだけに留まらず"蘭が成績の件でいい気になっている"という事実無根の陰口を叩いたことも知っていると蘭が述べた際には該当の部員達は覇気もなくうなだれていた。
「今、こうして来てくれているのを見て気持ちが揺らいだけど……やっぱり無理、許せない。私が名前を出した子達は、エリちゃんには謝っていないよね?」
はぁ、と蘭は小さく息をついた。
軽いため息は、あきれているというより疲れたがゆえのもの。
「自分より弱い人には謝る必要はないって考えが透けて見える」
厳しい面持ちの蘭は、再三に渡り「信用できない」の言葉を繰り出すこととなる。
「名前を出したあなた達は、どう頑張っても信用できないし、許したくない」
自身の狭量さは十二分に承知している、と蘭はつけ足した。
はーい、はいはい。
芯の通った少年の声に亜依は「あの美男子、いい声してんな」とボソリと呟き、シゲヨとアスミも惚けた顔で「だからぁ」と返した。
聞き役に徹していた一哉が「俺も話していい?」と聞くので、謝りに来た三年生達は顔を赤くしながら頷く。
礼儀だからと一哉は名乗りを上げたが、既に顔も名前も知っているからと全員から返された。
「俺、蘭と泉清さ通ってる友達から吹奏楽部と学年内で何があったかを聞いてたんだ」
誰かが「ゴウダとハマちゃんと仲良いよね?」と問うので一哉は律儀に「そうだよ?」と返した。
「えーと、みんなは蘭ちゃん達が辞めた後、吉田なんちゃらが好き勝手やってるの見ていて止めたりした?」
沈黙が始まる。答えにくいのも当たり前だとわきまえていた一哉は、返事を急かす真似はしない。
そのうち、弱々しく「できなかった……」と白状する声が上がったのをきっかけに、蘭に謝りに来た三年生達はそれぞれの思いを吐露し始める。
「本当は、一年のコンクールが終わった時点で蘭ちゃんが副部長になってくれたらよかったんだよね」
「蘭ちゃんだけだったもん。みーちゃんにビシッと意見できた人は」
「あの時に蘭ちゃんが考え直してほしいって直談判してくれたから、一年の時だけだけど規則違反まがいな練習やらずに済んだし……」
「変に強いから逆らえないんだよねぇ……」
一哉は蘭の隣へと踏み込む。弾かれたように蘭は目を上げて右隣へ顔を向けた。
高い鼻筋の美しい横顔が、蘭の視界に入る。
凛とした眼差しで前を見据える様は誰よりも勇ましい。
キリッと引き結んでいる唇が動いた。
「言いたいことはわかったよ。でも、虫が良すぎるにも程がある。吉田なんちゃらに好き勝手に酷いことされているの見てみぬふりしておいて、しまいには事実無根の陰口叩いて裏切っておいて、いなくなった後に"蘭がいてくれればよかった"って勝手すぎるよ」
訴えかける一哉は落ち着いた口調であることには間違いないのだが、怒りと悲しみの混ざり合った感情は隠せない。
「ヤローが女子相手に問い詰めるのはかわいそうだから問い詰めなかったけど、俺はずっと"なんで蘭を助けなかったんだよ"って言いたくて仕方なかった。学校さ乗り込みたかったけど蘭に止められたから、やらなかっただけ」
蘭が小さく「一哉ちゃん」と名を呼ぶ。
蘭の手が宙を迷う。あと少しで学生服の背中に届くところで、触れるか触れないか彷徨う。
出会った時から、何度か頭の中で問いかけた。
どうして、ここまで私に尽くすのだと。
意を決して己の口から問いかけた後、一哉は間を置くことなく答えた。
「蘭が好きだからに、決まっているでしょう」
有言実行の人と評した彼は、律儀にも蘭の願いを守って学校へ乗り込むこと"だけ"はしなかった。
「それでも吉田なんちゃらとかいう女の聞き捨てならない暴言に堪えられなくて、この前ついにキレたよ。ゴウダに取り押さえられなかったら、奴の首根っこさ締め上げてた」
ようやく、蘭の手の行き先が定まる。
学生服の背中。
泰造に蘭の過去を聞いた日から互いが相思相愛であると確信する日まで、一哉は死を予感する悪夢を断続的に見た。
悪夢の内容はワンパターンで、うずくまったままの蘭の肩を動かすと毒物とわかるものを固く抱き抱えているのだ。
抱き抱えている毒物は劇薬の類であったり、致死率の高い毒を有する花を寄せ集めた花束であったりとその時により異なるが、引き止められた夢ならばまだましな方だ。
ひどい場合は揺り動かしても動かない……という夢も見た。
悪夢の中の、動かない蘭は決まって冷たかった。
◇◇◇
その冷たさに覚えがあるのは、医師だった祖父が亡くなった際に触れた手と同じ温度だったからだ。
亡くなる少し前に、病床の祖父は十つになるかならないかの一哉に聞かせた。
「強くなくてはならないと意地を張る者と、泣きたいのに泣くことも許されず、強くあることを強いられた者ほど、最悪の手段を選びがちなんだ。仮に最悪の手段から逃れられても、傷ついた末にドス黒く染まった心を抱えながら生きるのは、死ぬよりもしんどいことなんだよ」
ドス黒く染まった心を抱えるきっかけは様々だ。
災害に遭ったり、病気にかかったり、治りにくい怪我を負ったり、人付き合いで苦しんだり……惨めでもいいから泣き喚くなり弱音を吐くなり、弱さをさらけ出すことも必要なのだ、と祖父は言った。
「私達、精神科医は患者の抱える苦しみを受け入れて、さらけ出した弱さを受け止めて、ドス黒く染まった心をまっさらに戻すことが仕事だ」
私の見解だが、とつけ加えた後に祖父は一哉へ問う。
「お父さんから聞いてたぞ。幼稚園の頃から、いじめられている友達を庇い続けてきたそうだね?」
「うん。歯医者さん家のタッちゃん。優しくていいやつなんだよ。すごく気が合うんだ。なのに、いじめてくるやつがいるんだ。そいつらはタッちゃんが気が弱いから悪いって言うけど、いじめるやつこそ弱いんだよ」
「どうして、弱いと思うのかね?」
「俺と本間が来ると逃げるから!」
居合わせた看護師がクスクスと笑い「正義感の強いお孫さんですね」と声をかける。
「本当に、顔立ちも性格も先生によく似ていらっしゃいます」
「自慢の孫ですよ。その心意気を、一生忘れないで持ち続けてほしいものですね」
地元の名士ゆえ常に威厳を漂わす祖父だが、自身のもとで働く医師にもスタッフにも決して居丈高にならない、礼儀をわきまえた人格者だった。
入院時も、世話になるからと医療スタッフ全てに敬語で話していた。
若かりし頃は美しい容姿から同性からのやっかみを買うという苦労も味わったそうだが、それらの経験が祖父の持ち前の正義感を更に強めたと聞く。
幾らか痩せた手で一哉の髪の毛をくしゃくしゃと撫で回しながら「男前でしょう? うちの孫」と祖父は看護師に向けて自慢げに笑う。
頭を撫で回されることが恥ずかしい年齢に差し掛かった上、看護師もいる前なので「じいちゃ~ん」と困った口調で言っては抗議したが、一哉は祖父の手の温かさが好きだった。
あれだけ温かかったのに。
当たり前のように温もりを宿した手が雪かきの後ように冷たくなった事実に一哉は子供心に怖くなり、悲しかった。
「じいちゃん、冷たいね。夏だけどコタツ入りたいね」
悲しみを誤魔化すつもりのおどけた言葉は、より悲しみを際立せるのみ。
溢れ落ちる涙は、祖父の手に反して熱かった。
◇◇◇
泰造に蘭の過去を聞いたからこそ、大好きだった祖父の死を経験したからこそ、軽い気持ちで口にしたらしい『生命の尊厳を踏みにじる暴言』を、一哉は尚更許せなかった。
思い出したくもない出来事を改めて口に出して語り聞かせる泰造は、どれほどに苦しかっただろう。
泰造と星が口にした「蘭を好きでいてくれてありがとう」の言葉に、どれほどの重みがあるだろう。
心臓が潰れる思いを堪えて全身で受け止めた、蘭の慟哭。
「蘭の親父さんが、自分の子供が死を意識している現実を目の当たりにしてどれだけ苦しんだかわかる? 蘭の親父さんと母ちゃんがどんな思いで、蘭を好きでいてくれてありがとうって俺に言ってきたかわかる?」
指先で拭った涙の熱。
衝動に堪えきれず抱き寄せた、15歳の蘭の体温。
蘭が確かな"熱"を持っている真実が、この上なく嬉しかった。
生きている証と呼ぶべき蘭の温もりを、失わせるものか。
「悔しかったよ。これ以上、蘭ちゃんから音楽を奪い取るなって何度も願ったけど……」
もう、いいから。
「一哉ちゃん。もう、いいから」
蘭は恨み言を止めたいのではない。
約束を破った事実を口に出す苦しさを、蘭は察していた。
一哉は泣いてはいないが、その澄んだ瞳の奥には怒りの焔が揺らぎ、涙は角膜を濡らしている。
「結局、神様はあのバカな連中の味方だった。蘭ちゃんの夢も奪い取られた。蘭ちゃんがやりたかった『ベルキスの暁の踊り』だって、本来なら三年生の夏のコンクールで蘭ちゃんが吹いていたんだ」
噂の出どころは「音澤さんが吹奏楽部に在籍していれば、来年のコンクールは『シバの女王ベルキス』を自由曲にするつもりだったのよ」と職員室にて上野が副顧問に漏らした泣き言を生徒が耳にしたともいう説もあれば、泣き言を聞かせた相手が松井で、吉田や斎藤を指導する際に松井が涙ながらに引き合いに出した……という説もある。
「正直言って、俺はあのバカなやつを野放しにして、蘭ちゃんの強さに甘えて放ったらかしにしたも同然の吹奏楽部の三年生達が腹立たしい」
蘭が狭量になるのも当然だよ。一哉は言い切る。
「野放しに、したのは、私達も、同じですぅ……!」
途切れ途切れのかわいい声に次いで「アスミちゃ~ん!」「待てっつっただろーが!」と声が重なる。
土手を駆け上がったシゲヨ、アスミ、亜依の三人が息を切らして登場した。
初めて見た、というよりは学校の行き帰りで見た気がする突然の乱入者に一哉は「何があった?」と大きな目を見開いて驚く。
「私もぉ、先輩にお世話になったのにぃ、あの部長が怖くて何もできませんでしたっ!」
くぐもった声を張り上げたシゲヨが90度に身体を折り曲げる。無理やり結わえた二つ結びの天然パーマが耳の横でポンポンと跳ねた。
「先輩の力になれず、本当に申し訳ありませんでした!」
亜依もシゲヨと同様に深々と頭を下げる。
「部活は、どうしたの?」
やはり驚く聖良の質問に、亜依は気をつけの体勢に居ずまいを正し
「上野先生に許可をいただき、部活動を抜け出しましたっ!」
と軍人さながらの口調で答えた。
控えめに見えるが、亜依は勝ち気そうな響きを含む凛とした声の持ち主。
「私達は、どうしても先輩に謝りたかったんです!」
三人は改めて、揃って頭を下げた。
後ろでは元吹奏楽部員の三年生達が茫然としている。
あの、音楽室の片隅に潜んでいる子達が……?
一同の目が、そう物語る。
蘭は、身体の向きを駆けつけた後輩達へと変えた。
「謝ることなんてないよ。下級生があいつらに逆らうのが怖いのは、無理もないんだから」
蘭だって、下級生が上級生に楯突く行為は自殺行為に等しいことを理解している。
しかも、いじめっ子と名高い相手だ。
仮にシゲヨとアスミと亜依が楯突いたところで吉田からの返り討ち=嫌がらせに遭えば守り抜く所存の蘭であるが、無理な行動に出ることもなく済んで何よりだと思う。
「確かに怖いですけど、あの部長は誰がどう見ても悪でしかないんです!」
やたらハキハキした口振りの亜依。続いて口を開くアスミは半泣きの状態だった。
「それなのに、陰で先生にチクることしかできなくてぇ!」
さて、一哉も後輩が素行の悪い上級生に逆らえないのは仕方のないことと理解しているので、焦った様子で三人に気にしないようにと告げる。
「蘭ちゃん、この子達かい? 気づかってくれる後輩って」
「そうだよ」
2002年3月・11
地味と言われる三人だが、個性的な三人だと蘭は思う。
突然の乱入者により調子が狂った三年生達は、帰ることにした。
中には「みんな仲良し」とばかりに感動的なラストを期待した者もいたかもしれないが、クライマックスを大団円で終わらせるか決別で終わらせるかを決めるのは蘭だ。
三年生達が去り行く前に、蘭は言った。
「私が信用できないと言った子達は今は許せないし、関わる気になれない。外で会っても会わなかったことにするだろうね。でも、許せるとまではいかなくても"どうでもいい"と思えるようになる日が来るかもしれない」
間を置いて、あくまでも「かもしれない」の話だから確証はできないと繋ぎ、蘭は静かに続ける。
「どうでもよくなった暁には、再び対話できるようになるかもしれないね」
不承不承という様子で聞く者や蘭の導き出した答えに対して「どうでもいいって言葉は冷たすぎる」と抗議する者が出る中で(当然、一哉と亜依は反発したが)聖良が毅然とした態度で「私からも言わせて」と言い放つ。
「蘭さんに許してもらえない覚悟はできてると言ったはずだよ。文句は言わないって約束したの、忘れたの?」
厳しい眼差しで、眉をつり上げる。誰もが初めて目にした聖良の姿だ。
「あなた達がそんなだから、蘭さんが壁を作るんだよ。私も、文句を言った子達は前から信用できなかった。現状に不満があるのに、改善しようと奔走するどころか保身のために敵方にすり寄る。気高さの欠片もない姿には心底軽蔑してた。もう、付き合いきれなかった。だから……」
失望して、吹奏楽部を去った。
もう一つの真実を、聖良は言葉に表す。
「私に文句を言いたいなら、どうぞご自由に!」
華奢な容姿には似つかわしくないのに、全身に矢を受ける覚悟の武蔵坊弁慶の姿を聖良と照らし合わせたのは蘭だけではない。
うち一人が、意を決したように手を上げる。
この生徒は聖良が退部した後にシゲヨとアスミと亜依の面倒を見ていた部員の一人だった。
「蘭さんがそうなってしまったのは、私らのせいだとわかってる」
蘭の対応を冷たいと咎める資格など私達にはない、と断言しながら抗議した者を振り返る。
牽制ともとれる動作は、これ以上蘭を責めないでくれという意思表示。
「これだけは信じてほしいんだ。……蘭ちゃんを本気で心配している子がいたのは本当だよ」
私もそうだからと締めくくると、集団の中からポツリポツリと「私も」の声が上がった。
三年生達の姿が小さくなり、蘭は後輩に向き直った。
「何っすか、あれ。音澤先輩さ文句たれた先輩には本っ当にガッカリだよ」
文句を言った上級生を今日から先輩と認めないことにするとふんぞり返って憤る亜依と、なだめすかすシゲヨとアスミの耳に届くは手を叩く音。
三人が一斉に振り返る様は、人の気配を察して飛び立つ一歩手前のスズメに似ていたので蘭は微笑ましくなる。
「いつも気づかってくれて、ありがとう」
面食らった顔の三人に、蘭は言葉を続けた。
「みんなは何もできなかったと悔やんでいるようだけど、私はあなた達のおかげで味方がいる事実を実感することができた。それだからこそ、こうして"生きている"わけだし……」
部活動に戻りなさいと促す優しい声は、年長者らしい威厳をたたえながらも微かな震えを含んだ。
◇◇◇
「私も、帰るね」
シゲヨとアスミと亜依が学校へ戻る姿を見送った聖良も、自宅へ戻るからと告げて去っていった。
「セイラさん」
呼び止める声に振り返る聖良。蘭は戦友に向けて叫ぶ。
「さっきはありがとう! かっこ良かった!」
続けて、一哉も声をかける。
「俺も、マジでスカッとした!」
遠目に照れる姿が見えた。
川縁に残される蘭と一哉。
「青春ドラマみたいなハッピーエンド期待してた?」
いや、と一哉は答える。
「蘭なりに考え抜いた答えなんでしょう?」
恋い慕う少年の発言に応えるかのように、蘭は微笑みを返す。
「許したくもない人に対して"いつかはどうでもいいと思えるかも"だなんて、そこまで考えが及ばない人は多いと思うよ」
そして一哉は「充分に優しすぎる対応なのに文句つけやがってよぉ」と憤る。
裏切っておいて冷たいはないでしょう!
先刻に一哉が発した反論の言葉だ。
不満げな顔で蘭を冷たいと批判した部員に一哉が反論に出た際、蘭は内心嬉しかった。
更に一哉は
「どんだけ改心しようが被害者にとって加害者は悪者のままなの。あんた達が将来腹の底から申し訳なく思えても蘭ちゃんの中では手のひら返して敵方に寝返った裏切り者でしかねえの。外で見かけても無視したいほどの信用できない裏切り者から"どうでもいい人"に昇格するだけでも御の字でしょうが! あんた達贅沢すぎるのよ! 自分勝手も甚だしいのよ! 自分から蘭ちゃん傷つけておいて何を求めてんの? 加害者風情が被害者に温情を求めるって何様なの? 厚かましいにも程があるっつーの!」
と、相変わらずの長ったらしいセリフをつっかえることもなく流暢に繰り出した。
たたみかけるように「この人の言うとおりっすよぉ!」と亜依が一哉を指差しながら応戦した時には、蘭はヒヤヒヤした心持ちで「年長者をこの人呼ばわりして指を差すな」とたしなめたが。
「セイラさんが口さ出さなかったら、あの眼鏡ちゃんと応戦してたよ。利発そうな面構えしてっからよ、あの子も口が立つんだろうな。あ、名前わからないから眼鏡ちゃんって呼んだんだ」
蘭は、どうでもよくなれるかもしれないと思えたのは実体験に基づくからだと言った。
「さっきも少しだけ揺らいだし、あまり"あいつ"のことを口に出したくないけど泣きながら謝られて、絆されてチャラにしたのも事実だからね」
蘭は死を意識するほど苦しんだのに……。
「蘭は優しいから、許したんだよ」
「違う。愚かな世間知らずだったの」
過去のことだからと許した現実に、一哉は唇を噛む。
まだ十つにならない蘭が除草剤を抱えて逡巡した事実を、蘭を傷つけ陥れた連中に何度も何度も突き付けて責め立てたい衝動にかられた一哉だが、冗談半分で生命の尊厳を踏みにじる発言を軽々しく口にする奴らのことだ。
後悔に苛まれるどころか、笑い種にするだろう。
それこそ蘭を追い込んでしまいかねない。
「私は、どうでもいいと思えるようになってからが課題だと思う。気を許して泣きを見たのは本当だし、それで再び周りを信じられなくなった」
慎重にいかねば。
蘭は雪を頂く吾妻連峰へと視線を移す。
吾妻小富士の山肌から姿を見せる種まきウサギが見えないあたりに、未だ山は雪深いことが窺えた。
一哉が頭の中で度々サファイアの照り返しみたいだと例える硬質な輝きが、蘭の瞳から強く感じられた。
時折、山肌に積もる雪が陽光を白く照り返すので、この山にも近々雪解けが訪れる。
雪が解けて春の花が芽吹くように、蘭も許したくない人達を「どうでもいい」と許容できる日は来るのだろうか。
「蘭ちゃん、さっきあの子達に話したとおりなんけど」
何を話そうとしているかを蘭は察する。
「俺、蘭ちゃんとの約束破ったんだ」
「もう知ってる」
「俺が悪意を向けられないように守ってくれたのにね……」
ごめん……と言いかけた唇を、蘭は白い指先で塞ぐ。純真な少年は、たちどころに頬を染めた。
真新しいセーラー服を着た蘭が、薬指の別名は「紅差し指」であると教えてくれた出来事がフッと頭をよぎる。
左手で紅皿を持つ真似をしつつ、右手の薬指をそっと唇に当てて紅を点すジェスチャーを交えて「薬指は、女性にとって特別な指なの」と語る姿は高畠華宵の描く美少女さながらの色香を纏うので、一哉は相当に動揺したものだった。
12歳を迎えたばかりの、大人と子供の狭間を彷徨う幼子だった蘭。
今思えば、女性として意識してほしい願望の表れなのだとわかる。
そして、蘭と唇を触れ合わせたい願望が芽生え始めたのも、その頃からだった。
「謝らないで」
蘭は、敵意を向ける生徒のもとへ乗り込むなと懇願した時と同じ目で一哉を見据えた。
相違点といえば、その時は手首を掴んでいたが今は封をするように唇を押さえている。
「私の知らないところで、私を守ってくれてありがとう」
蘭の指先が、唇から離れた。残念な気がしたのは否めない。
この美しい少女は時折、大胆な行動に出る。
しかし、蘭は一哉の唇を指で塞いだ時と打って変わってしおらしい態度になり、顔を伏せてしずしずと一哉の左隣へ移った。
恥ずかしくなったからだ。
そんな姿を、一哉はかわいらしいと愛おしく思う。
自信に満ちた勝ち気そうな笑みをたたえる蘭も、耳まで桜の花の色に染め上げて恥じらう蘭も全て愛しい。
蘭の肩がグッと引き寄せられる。身体の右側が温かい。
「ごめんね。今だけ……蘭の肩を抱いていいかな?」
蘭は、愛しい少年の申し出に頷いて返す。
始めは、気恥ずかしかった。先ほどの我が身の取った行動を思い返すと、見つめていたいはずの横顔を見ることができない。
肩に乗せられた手に、蘭は己の手を重ねた。
一方で、一哉は頬を薔薇色に染め上げる蘭の姿を、夕日を跳ね返して薄赤く煌めく雪山のように神々しいと感嘆する。
しなやかな腕で蘭の肩を抱き、華奢な肢体を支える様は柱の如く頼もしい。
「ねえ、一哉ちゃん」
「なあに?」
かつて仰ぎ見た麗しい目元。
いつの間にか、蘭の目の高さは幾らか低くなっていた。
「ずっと言いたかった。守ってくれてありがとう、って」
足元の砂利が鳴る。蘭が身体の向きを変え、肩に頭を預けている。
「これからも、私の傍らにいてください。凛々しくて、気高くてかっこいい、私の騎士様」
―――大好きです―――
「蘭ちゃん、やるなぁ」
「静かにしろで、気付かれっぞ」
時を同じくして、学習センターの陰では合田が人差し指を唇に当てて声を出さぬよう指示を出し、聖良を含む勉強会のメンバー達が律儀に息を潜めて見守っていたのを二人は知らない。
2002年春 雪の果てに
中学校を卒業したというのに慌ただしい春休みだ。
学生オーケストラの公演は大成功を修め、蘭を含む引退する団員は涙ながらに別れを惜しまれた。
そう言いたいところだが、楽屋の入り口が騒がしいと思うと複数の見知った顔が漫画の1シーンさながらになだれ込んできた。
蘭に花束を渡そうと楽屋へ向かった一哉を合田とモジャ山、ミヨシと白沢がせっついた結果である。
白沢家の蔵屋敷で催された宴会は「合格おめでとう会」とも分散会とも呼べば良いだろうか。
蘭は泰造の実家で製造している甘酒を持ち寄ることにした。
コシヒカリの新米を持ち込むと冗談を述べた一哉はというとプチパンケーキを持ち込んだ。朝からパンケーキを大量に焼いていたら清子と花梨に見つかり、何枚か食われたと苦笑いで蘭に聞かせた。
「ほら、生クリームは昨日の夜頑張って作ったんだで! 見てみ!?」
皆が驚いたのはミヨシで、鍋いっぱいのつぶあんと半解凍状態の生クリームを持ち込んだ。つぶあんに至っては寸胴鍋の8割を占めている。
「あんこは母ちゃんが作ったんだで! 遠慮なく食いな!」
「いや、確かにあんこと生クリーム必要だけどよぉ……」
「これだけの生クリームをホイップする根性は認める」
「しかし、こんなおびただしいあんこどうすんだよ」
中学生達が唖然とする中で上手い具合に采配を振るったのが、分散会を楽しそうだと自ら手伝いに来た巧の彼女だった。
パティシエールを目指す彼女は巧と同じ農業高校を卒業した後に東京の製菓学校に通い、分散会当日は春休みを利用し帰省していたと聞く。
おびただしいつぶあんを目の当たりにした巧の彼女は「いいこと思い付いた」と輝いた表情でミヨシの持参したつぶあん入りの寸胴鍋を蔵屋敷から持ち出し、つぶあんに生クリーム、プチパンケーキ、そして白沢の祖母が作った白玉団子を見事に組み込んだ和風スイーツを完成させたのだ。
中学生達が歓声を上げたのは言うまでもない。
「蘭ちゃん、この前の宴会の写真できたよ」
白沢が渡した写真は、大団円と呼ぶべき光景が写っている。
笑顔でありがとうと述べる蘭は、嬉しさと照れの混じった表情で集合写真を受け取った。
照れている理由は様々だが、最もたる理由は蘭と一哉が"密着"して写っているからだと白沢は察した。
「あの後でエリちゃんと話す機会あったんだけどよ」
「うん」
「大なり小なり、私らに引け目感じていたらしいんだと」
女子のリーダー的存在でヒエラルキーの上位に属する白沢達を羨みつつも、住む世界の異なる人種だと引け目を感じていたこと、それにもかかわらず宴会に誘ってもらえて嬉しかったことを後片付けの際に打ち明けられたという。
「私さ、一部のやつから"カーストの上の方から周りさ見下している"ように思われてる節があるのは知ってたけど、全くそんなつもりなかったんだっけー」
「たまたま委員長タイプが集まってそうなっただけじゃんね」
「んだからぁ!」
蘭の言ったとおり"類は友を呼ぶ"で似た性質の者が集まっただけの話だ。
白沢は湿っぽい人は苦手で、気性のハッキリとした者同士で遠慮なく馴れ合う方が気楽だった。
冷静であったり短気だったりと個々の性質は異なるも、意思表示のわかりやすい絢や由香理といった委員長に抜擢されるタイプは白沢にとって気兼ねなく話せる存在なのだ。
「エリちゃんみたいなおとなしめの人達がとっつきにくそうにしているのも知ってるし、変な勘違いする連中が私らを威張りくさってるだの見下してるだの好き勝手なこと言ってるのも知ってた。前者はまだ許せるけど後者はねえ、正直、そういうの息苦しいって思ったんだっけ」
「妬みもあるんだよ。シロちゃんはかわいいし賢いから」
いやいや~と手を振って照れ出すが、即座に真面目な表情へと変わった。
「まあ、エリちゃんにああ言われてびっくりしたけど嬉しかった……かな」
蘭の脳裏にシゲヨとアスミと亜依の姿が浮かんだ。
我が道を往く亜依はともかく、自己評価の低いシゲヨとアスミも周囲に気後れしながら日々を過ごしている点はエリと共通しているのだ。
「ところで蘭ちゃんさ、高校の制服着てっけど、どこさ行くんだい?」
白沢の眼前にいる蘭はクレリックシャツの襟元にネクタイを締め、タータンを起用したキルトスカートを履いている。
卯の花色を下地に、縹色の太い格子と臙脂色の細いラインを組み合わせた複雑な配色は本格的なタータンらしさを醸し出す。
白沢も、春奈も織絵も4月から同じ制服を着る。制服の採寸をするために百貨店に出向いた際には、やはり同じ制服を採寸に来た堀越と再会した。
「吹奏楽部の指導に行ってくる」
腕にかけたブレザーはこれから羽織るところだ。光の加減で紫にも桜色にもグレーにも見えるその色の名は、鳩羽鼠。
それじゃあ……と考え込む白沢の表情はだんだんと明るくなってゆく。
「上野先生の申し出に応えることにしたんだね」
蘭は微笑みを返し、頷く。
キルトスカートの裾が膝頭で揺れる。
髪の毛先が背中で揺れる。
革靴の足取りは軽い。
雪は解けて季節外れとなってしまったが、雪の結晶の髪飾りで耳から上にかかる髪を軽くまとめた。
たとえ真夏でも錦繍の頃でも、桜が散って緑煌めく季節に変わっても蘭は構わず雪の結晶を髪に飾るだろう。
校庭では運動部員が好奇の眼差しで目配せをするが、蘭の眼中にはない。
「蘭さーん、こっちこっち」
来客用の昇降口から聖良が手招きをする。
紺色で統一されている、女子高のセーラージャケットの制服は聖良に似合っていた。
近くまで寄ってきた蘭の襟元を、聖良は大きな眼でまじまじと見つめる。
「襟の刺繍かわいいねぇ。桜に似てるけど……薔薇だっけか?」
問いかけに「そう」と軽快に相槌を打つ。
ブレザーの襟に花開くは高嶺薔薇だ。鳩羽鼠の生地に浅葱色の糸が映える。
この可憐な刺繍の制服に憧れて入学する女子がいる、という話は桜の季節が近づく毎に耳に入る。
「高嶺薔薇だよ。セイラさん、やっぱりF女の制服似合うね」
流行りの浮わついた着こなしは苦手だからと、蘭も聖良もスカートは膝頭が見える長さに留めた。
「ありがとう。来年から共学化するって話だけどこの制服は卒業まで着られるかな……」
「県内の公立が全部共学になるのかぁ。理由あって異性が苦手な子もいるんだし、男女別学の学校は残すべきだと思うな」
かくいう私は共学だけど、と聖良に苦笑いを見せる蘭。
しかしながら、蘭の受験した芸術科はほとんど女子高状態といえる環境だ。
「蘭さんが言うと説得力あるねぇ……」
でも、と前置きをする聖良は「うふふ」と笑って蘭を見上げた。
「一哉君も同じ学校受かって良かったねぇ」
「ちょっと、セイラさん」
入学式では、浅葱鼠色の詰襟学生服で蘭に笑いかける一哉を拝めるであろう。それを思うと胸がときめく。
灰色の、重い扉を引くのは未だ慣れない。白い光と共に視界が開け、号令がかかる。
幾らか少なくなった後輩達。指導を頼まれたのか、何人かの卒業生もいる。
そこから響く、凛とした声は亜依の声。
「よろしくお願いします!」
亜依に続けて後輩達の挨拶の声が轟き、顔色の艶々とした上野は微笑みをたたえて指揮台に立っていた。
雪の果てに生まれ変わった新生・泉清中学校吹奏楽部のメンバーが今、蘭を出迎える。
――中学生編 完――
雪と花の狭間に
お読みいただきありがとうございます。
中学生編は蘭が音楽と生きる姿よりは、人格形成の過程を描いた作品ともいえます。
容姿と才能から恵まれて見える蘭ですが、向けられる必要のないはずの悪意に晒されて傷つき、悪意に抗おうと足掻き、それこそ踏まれても立ち上がる雑草のように懸命に生きる姿が描かれています。
蘭は聡明な反面、愚直さを持ち合わせる少女です。
逃げてもいい環境ながら転校する手段を選ばなかったのは、同時にいじめを受けていた気の弱い親友のエリを見捨てるようで憚られたからでした。
自らが学年でトップの成績を誇る「出来の良い人間」にカテゴライズされながら出来の良い人間にありがちな弱者を切り捨てる冷淡さを嫌い、冷淡になるぐらいならば愚かでもいいから優しくありたいとの信念から弱者を見捨てられない、そんな少女でした。
例えば、現在でいう「陰キャ」にカテゴライズされるシゲヨとアスミと亜依の後輩三人衆。
集団から弾かれがちな日陰者である彼女達はそれぞれに理由があり生きにくさを抱えていましたが、蘭は親友のエリや音楽仲間の聖良と共に彼女達の不器用さに秘められた訳を理解し寄り添います。
純粋に自分を慕い敬うシゲヨを愛おしく思い、オドオドとした気弱なアスミに寄り添い、ロボットのように生きている亜依の内面に隠された自我を引き出してゆく。
日陰者だった三人は、蘭との交流を通して自分の「好き」に気付き、内に秘めたる強さと激しさに気付きます。
愚直なまでの篤さを持つ少女だからこそ、妬み嫉みによる悪意をぶつける者がいる一方で蘭を気にかける者も確かに存在したのです。
蘭は物語の終盤でシゲヨ、アスミ、亜依の後輩三人衆に「あなた達のおかげで私は生きている」と感謝の念を告げるシーンがあります。
小学生時代には死にたいぐらいに辛いけれど自分が死ねばクラスで孤立している親友が一人になってしまう、と泣きながら生と死のどちらを選ぶか逡巡するシーンもあります。
悪意に晒されても自分を支えてくれる存在がいると実感できたからこそ、蘭は自ら命を絶つことを選ばず生きることを諦めなかった。
次回から高校生編に入ります。


