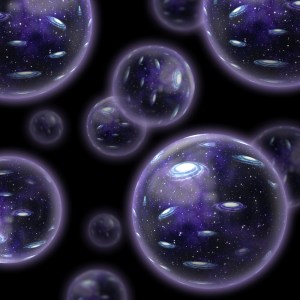第12話『調査員たちの物語』
第12話
『調査員たちの物語』
1
イターラン生体記録開始。
たぶんこれで僕の声が意識体に記録されていると思うので、今のこの感動を記録したい。
これがビッグバンなのかと私たちは驚いている。他の調査員たちは何人もビッグバンを目撃しているけど、僕が見るのは初めてだ。調査飛行にアイテンたちと出てもう数日になるけど、僕より先輩の彼にとって、ビッグバンは大したことではないらしい。
21世紀の物理学者、ホーキング博士はビッグバン理論を提唱した。生体デバイスはまさしくそれらの物理現象を捉えている。宇宙で最初の花火が僕の目の前で花開いた。
もう何度もビッグバンについては、あらゆる調査員が記録を上げているので、今更、僕がオムニバースタイムライン調査機構本部に上げる情報はない。
今回の調査の目的は、僕の視覚情報からも分かるとおり、あの黒い物体だ。
数千年の長い組織の歴史にあり、最も重要で危険視さている観測対象。僕は組織に入って日が浅いがこの任務に抜擢された。
対象を観察、調査、可能であるならば接触が今回の目的である。
しかしビックバンの瞬間、すでに存在して、こうして生命体反応を示すなんて、何なのだろうか、あれは。
個人的に言うなれば、ヘドロ。そうとしか見えない
第12話-2へ続く
2
アイデン生体記録開始
イターランの様子は落ち着いている。俺よりもあとに組織に入ったが、まあ俺と同期に近いイターランにとって、ビックバンは初めてなのだろう、興奮している。心拍数が上昇している。
だが今回の任務はそんなに甘いものではない。イターランにも時空移動の前に散々言い聞かせた。オムニバースすべてにこの事象は広がっている。
オムニバース。映像、文章、芸術、記録、データ。あらゆる物事は架空でも虚構でもなく現実である。本の向こうにはまた別のオムニバースが広がっており、そのオムニバースの本の中にもまた別のオムニバースがある。
もちろん我々が住んでいる宇宙の外側にも無限の宇宙がいくつも存在し、マルチバースがオムニバースを形成している。
あらゆる事柄は現実になり、その現実は今、危機的状況に陥っている。ビッグバンと共に誕生したあの黒い粘液がすべての現実に現れ、破壊し始めているのだ。
現に一緒に行動しているザイードがホロスクリーンで目の前に提示した書物、映像、データ、芸術などあらゆる創作物という現実に黒い粘液が染み込んでいた。時代も時間も場所もバラバラの現実に。
この現象を組織が把握したのが半年前のことだ。それからいくつの宇宙、現実が失われただろうか。俺の知る限りでも6000垓のマルチバースが消滅している。
黒い粘液はまるで意思を持っているかのように現実を侵食していく。
これまでに組織の調査員がサンプルを入手したという報告もなく、これがなんなのか、どういった性質の事象なのか、誰も把握できていなかった。
俺はビッグバンに感激しているイターランの肩を叩き、スキャンの実施を促した。前から思っていたことだがこの、肘が四つに分かれた赤色のマヒレアナ人という人種は、物事に没入しすぎるふしがある。
俺がイターランと幾度か時空調査を行ってきたが、その度に何かに感動したり、驚いたりして調査がはかどらない時がある。上に何度か報告したが指導係として担当を外してもらえることはなく、今回もこうして一緒にきている。
俺の態度で少しは緊張感を持ってくれればよいのだが。
第12話‐3へ続く
3
ザイード生体記録開始
時空移動ポッドを操作するには俺の8本の四肢と背中の職種でなければうまく操縦できない。こんなポッドを開発した人種の気が知れない。どんな時間、空間、次元にも三次元現出を可能にし、中の人間の時間軸も空間軸もゆがませることのない、防御フィールドを展開している。それを俺たちトロワイアン族に一任しているのだから、調査機構も何を考えているのかわからない。
ポッドの操縦車は定期的に心理調査、新体調査が義務づけられているが、たとえサイボーグ種族の我らとて、身体をいじくりまわされ、脳の中まで覗かれるのだから、いい気分にはならない。
そのうえ今回の任務ときたら、ビッグバンの調査だときている。操縦者が最も嫌う調査現場である。どんな時間、空間、次元だろうとも操縦する自身はある。
だが物理法則が全く効かない世界で何を操縦しろというのだろうか。
案の定、ポッドは時間と空間の高密度な爆発に流され始めている。節々の部品が焼け付くほど、機器類を操作しても、この流れに耐えきれる時間は限られている。
新人のイターランがスキャンをようやく始めたらしいが、この爬虫類種族の作業の遅さは誰もが知っていることだ。なぜ、ビッグバンの調査という難題をこの新人に与えたのか、上の連中の気が知れない。
しかし何度見てもあの黒い不気味な液体には、機械の俺の身体にも身震いが来る。あらゆるオムニバースに出現するこの生命体と思しき液体は、ビッグバンの時間と空間の爆発にも干渉されていないのか、不動であり、ただうごめいているだけなんだ。
しかしビッグバンと同時に現出したこの黒い物体と同じく、あらゆる次元で同時発生しているのは確かである。
この物体は瞬く間に世界を呑み込み、生物を食らいつくす。調査機構は何としてもこの現象を抑え込まなければならない。
第12話‐4へ続く
4
バッカド生体記録開始
こんな面倒な仕事を引き受けるのも、会社員の悲しいさがなのかもしれない。
ビッグバンの調査命令を受けた時、わたしは断りたかった。危険というのももちろんあるのだが、新人を連れて、しかもわずか4人での調査など、万が一のことがあった時、対応のしようがない。
しかもビッグバンは未だ調査機構でも解明されていない物理法則が働く場所だ。そんな場所、誰が好き好んでいくか。
ようやく目標のスキャンを始めたらしい。どうせなにも分かりしない。
いつもそうだ。黒いあいつは追いかけれ追いかけるほとんど遠のいていく。陽炎なんだ。
時空の波がいよいよ強くなってきている。
わたしの頭だけの肉体でも、ポッドが激しく揺らいでいるのがわかった。
「早くしろ。ビッグバンに塵にされるぞ」
わたしの急かす言葉も、計器には通用するはずもなく、スキャンの速度は上がらない。
揺れはいよいよポッドが破壊される瀬戸際まで来ていた。
「脱出する」
ザイードの叫び声が聞こえ、ポッドはビッグバンのインフレーションから抜け出し、次元の隙間へと入り込んだ。
このまま本部へ帰れば任務は終わる。
私の頭にそう安堵が拾った時、次元の間の光のカーテンが突然としてひび割れた。
長年、調査員をしているがそれは初めての光景だった。
第12話−5へ続く
5
アイデン生体記録
次元のカーテンがひび割れるという報告は聞いたことがない。でも俺たちの目の前でそれは起きた。
光にポッドが包まれたあとの記憶は定かではない。
ただ確かなのは、俺が20世紀の惑星ガロンのカイタナ国の街に立っていたことだけだ。
20世紀代の惑星ガロンは治安が変わるく、武装していなければ、いつ殺されてもおかしくない場所だったと記録にはある。
他惑星との貿易摩擦。国際連合の不和からくる、意見の相違。
そういったことから、各国が刃を向けあっている状態だったらしい。
でも、どうして俺がここにいるのかがわからない。
「カルビンさんよ。金の工面はできたかい」
身体が筋肉で風船のように膨らみ、体中、傷のあとだらけの男が叫んできた。
ここは広い道のど真ん中。コンクリートに巨大な男のブーツの音が響く。
男を見た時、見覚えがあった。というより見覚えがあるのも当然なのだ。
ジャビラビックコミックの人気コミックの一つ、アルカリーグのメインヴィランである。
アルカリーグでは、この筋肉の塊をジャコスと読んでいる。
だがあり得るのか、そんなこと。俺の眼前にコミックのキャラクターが現れるなんて。
「この街で金を貪るのは禁止したはずだがな」
俺を挟んで反対側から声が聞こえてきた。
カウボーイハットをかぶっている下の顔は半分、機械の骨格がむき出しになり、右腕が湾曲した汎用光線兵器になっているヒーロー、キッドバレッドがそこにいた。
「やはりこの世界に現れたか」
強い声で次にキッドバレッドの横に空中からロープで降りてきたのは、鷹をイメージした全身スーツをまとった、ホークバッドだ。
「今度もまた、5次元湾曲空間に帰ってもらうだけだ」
最後に現れたのは、コミック業界最強のヒーロー。全身が黄金で光った怪力、素粒子分解能力の持ち主、キャプテンオールだ。
俺が子供の頃から今も読んでいるヒーローたちが目の前にあらわれて、正直、俺は興奮していた。
ただこの興奮もすぐに消えた。あの粘液が、あのビッグバンで観測した有機体が雨となって降ってきたのだ。しかも地面に落ちるとともに、それから目玉や牙が現れ、ヒーローもヴィランも人々を喰らい始めたのである。
ヒーローたちの身体から鮮血が飛び散る。
そこで俺の意識は失われ、
「逃げろ」
と叫んだ時には、銃声が響く石畳の町中にかがんでいた。
第12話-6へ続く
6
イターラン生体記録
ひざまずき白い甲冑と赤いマントを羽織った姿で僕は気づいた。
周囲にも多くの同じ格好をした多種族の姿が見える。
ここで立ち上がり、どういう状況なのか戸惑ってもよかったけど、僕の少ない頭でも理解できる。そんなことをすれば、皆が腰にぶら下げたダスケード銃で穴だらけにサれてしまう。
それよりならば、このまま様子を見たほうが無難だと考えついた。
僕たちのような兵士らしい群衆の前に、丸い眉が2つあり、その前に絶つ男女が叫んでいた。きっとどこかの国王と王妃なのだろう。
ひざまずいていると、国王がマヒレアナ後で叫んだ。
「偽王を倒す好機を逃すダビス国ではない。偽王討伐の有志たちよ。立ち上がるのだ」
この叫びを聞いた瞬間、僕の中ですべてが繋がった気がした。このセリフ。子供の頃から何度も頭の中に響かせていたセリフ。
『ダビス国年代記』の中盤、偽王ライブに向かい真の国王が信頼できる家臣を集め、ようやく蜂起する場面だ。
フォトジャーノ・パルベスが50年前に書きいた、架空歴史小説の超大作である本書。その中に今、僕はいる。あの父から何度も聞かされ、自分でも何度も愛読したあの世界に。
国王が大剣を天に掲げると、騎士たちは一斉に立ち上がり、決起の声を発し、巨大な白い大理石のバルコニーに出ていく。
そこから見えるのは1000万を越える、熱気を帯びた民衆たちであった。
この場面幾度も頭の中で妄想した。しかし僕の妄想を大きく越えて、壮大で圧巻だった。
僕はこの時、異変に気づいていた。民衆の後ろからだから黒い霧のようなものが、津波の如く迫ってきていたのである。
あれが何かはすぐにわかった。黒い有機体。
それは民衆を一口に呑み込み、巨城をも呑み込んだ。
次の瞬間、僕は白い浜辺に立っていた。
第12話-7へ続く
7
ザイード生体記録
なぜ監獄にいるのかわからなかった。気づくと俺はライトールシールドに覆われた監獄に囚われていた。
型番は古いようだし、この形式の監獄が使用されていたのは、70年も前のライナン宙域だけのはず。
タイムトラベルでもしたのか。
「ベルダーヤ、ベルダーヤ」
俺のいる監獄の広大な正方形の棟で複数人の投獄された人々が騒ぎ始めた。
これにつられ次々と声が響く。
ここは映画の世界だ。俺は思い出していた。
「アカルガンダ」
本当に存在した惑星オリアス、フーラン国の牢獄で、宇宙で最も厳しい牢獄と称された。
そこから名前をとったこの映画は、俺の思い返す限り、100年近く前の古い映画で、まだ立体にもなっていない、二次元映像映画である。
映画の内容はアカルガンダで実際に発生した、囚人脱走事件を題材にしている。しかもこの脱走事件にはある噂があった。収監されたのは、ある銀行化の会計士だったのだが、そこで不正会計があったとされ、犯人として収監された。
しかし映画になるほどの物語が簡単であるはずもなく、会計士はただの生贄で、銀行家は国家の中枢の繋がっており、その大規模不正が明るみに出るのを恐れた国家権力があらゆる力を使って、彼を犯人に仕立て上げたというものだった。
少なくとも映画ではそういったストーリーであった。
勤勉な男はしかし諦めなかった。何度も再審を請求するなど努力をし、ついには脱獄するという偉業を成し遂げたのである。
これについては古い記録で、事件が事件なのでどこまで本当かわからないが、少なくとも映画では脱獄に成功した主人公が惑星外へ逃げ出し、それを称える現地の言葉で囚人たちが叫ぶシーンで終わって行くのであった。
俺はまさしくそのエンドロールにいる。
そう思ったときだ。牢獄の至るところから黒い粘液が噴射するように現れ、囚人たちを食らっていく。あの粘液が。
そう思った次の瞬間に、俺は薄暗い部屋にロウソク一本を持って立っていた。
第12話-8へ続く
8
バッカド生体記録
「敵地に潜入した。これよりコントロールルームへ向かう」
自分が何を口走っているのか、最初はわからなかった。敵地、潜入、コントロールルーム。こんなセリフ臭いことを口走ったことなどない。
わたしは周囲を見渡してしかし、この言葉の意味をすぐに理解することができた。
理解できたことに対する自分の失望も心にはあった。なんせ自分が口走った言葉は、ビデオゲームの主人公の言葉なのだから。
手足、身体を見ると、緑色のアーマーを着用していた。手には架空のサブマシンガンが握られていた。これは私が思春期の頃、夢中になってプレイしていたあのゲームの最初の場面であった。
ゴーグルをつけてグラフィックの世界に没入し、敵を銃撃しながら前へ進み、異星人の侵略を阻止する。それがこのゲームの目的である。
物語はオールドアースの人類が宇宙全域に版図を広げた40世紀の終わり、異星人が人類の植民地を次々に破壊する事態に陥る。異星人は単一種族ではなく、複数の種族であることを確認した人類は、攻勢に出るも玉砕が続く。
そこで遺伝子レベルで肉体、精神を改造し、宇宙条約に違反した改造を行い、人間兵器を作る。
それが主人公であり、敵の基地や植民地に潜入しては、奪還するというものであった。
物語の根幹は戦争がなぜ起こったのか、なぜ複数の種族に人類は責められられなければならなかったのか。
そういったサスペンス要素も交えながら、物語は進んでいく。
その最初がここの場面であった。
錆びついた鋼鉄の廊下。粘液がまとわりついた廃棄パイプ。
確か最初のステージは人間の奪われた前線基地だったと思ったが。
わたしがそう思っていると、十字路になった目の前の通路から5人の巨大なエイリアンが出現した。もちろん本当の宇宙には存在しない種族である。
身体はとっさに銃を構えると、敵の頭部めがけ弾丸を照射していた。ほんとうに反射的こういであった。
これはこの世界に入り込んだ、わたしのさがなのか、あるいは思春期にやり込んでいた肉体的記憶がそうさせていたのかはわからないが、激しい鮮血が壁や天井に飛び散ったのは確かだった。
ゴーグルをつけての体感ゲームだったあの頃よりも、生々しい鮮血に、わたしはこみ上げてくる物を口から吐き出しそうになるのを、必死にこらえた。
ゲームではない。これは現実なのだ。わたしは直感的にそう感じた。
すると眼前の通路を黒い液体が津波のように押し寄せてきて、私を呑み込んだ。
気がつくとわたしは夜の寝室に立っていた。
我らがハータン人の寝室である。
第12話-9へ続く
9
アイデン生体記録
石畳の上を弾丸が跳ねて、飛んでいくところの横に、俺は立っていた。
白を貴重とした宇宙スーツを着用したその姿は、子供の頃、好きだった小説、キャプテンローンズの格好である。
まさか自分がローンズになっているとは思わず、俺の頭の中は混乱とめまいでいっぱいだった。
「キャプテンもここまでのようだな」
灰色の醜いへしゃげた口でしゃべるのは、ヒューマン型エイリアン、ガガト人である。
キャプテンローンズの名シーンだ。
混乱する頭とは裏腹に肉体はガンベルトのレーザー銃を抜くなり、引き金を引いて、閃光がガガト人の右側の心臓を貫いていた。
ガガト人は緑色の鮮血を石畳に広げながら、倒れ込み周囲で完成が上がった。
ガガト人の賞金首をキャプテンが倒し、民衆が喜ぶシーンであった。
が、俺の夢はまたしても黒い霧に邪魔された。
何もかもを包み込んで、黒い霧は現実に俺を返したのだった。
第12話-10へ続く
10
イターラン生体記録
真っ青な海水は、白い浜辺を洗い、耳に心地良い音と風が染み渡ってくる。
僕には分かる。この後、何が起こるのか。
ほらやってきた。水面すれすれを3機の戦闘機が速度を上げて飛んできた。
そして僕の真上を飛んでいく。
ここは名作文学の中。
青空を3本の飛行機雲が伸びていく。
僕の憧れた世界。
あの空のどこまでも上に行きたかった。
この小説はある青年が少年時代に夢見た戦闘機パイロットを目指す小説。
青空をどこまでも登って行きたいと願いながらも、現実に叩き潰されながら、諦めそうになりながら、それでもまっすぐに戦闘機と向かい合う青年を書いている。
僕はこの小説を読んで、パイロットになることを目指した。
だけどこんなに真っ直ぐには飛べず、結局、夢は叶えられなかった。
調査員になれたことは名誉である。だけど心のどこかで、引っ掛かりが、節くれだっていた。
戦闘機を見送った時、僕の背後のそれまで真っ青なだった海が盛り上がり真っ黒になると、現実に僕を引き戻した。
第12話-11へ続く
11
ザイード生体記録
今にも自分の息で消えてしまいそうなロウソクの火を、俺は消さないようにもう一本の機械の腕で風よけを作った。
どうやら肉体は維持できているようだ。
ホッとしたのもつかの間、周囲からかび臭い臭いがしてきた。
それは生体記録に記載する何倍もの刺激臭で、流石の俺でも左手で口元を抑えるほどだった。
闇をロウソクてらし、ここがどういった構造なのが把握しようとして、壁紙が見えた瞬間、俺は嫌な予感しかしなかった。
一番恐れていた世界。
マキノ虫の巣に俺はいたのだ。
どこでも巣を作るマキノ虫のドキュメント番組を見た記憶がある。
さっきの世界といい、自分の記憶がもとになった世界が現実となるのであれば、俺はこれから地獄を味わうことになるはずだ。
そうあれは右足からだった。
俺は右足に視線を落とすと、そこには無数のマキノ虫がすでに這い上がってきていた。
芋虫の一種のこの虫は、大量の群れで移動するのが常であり、右足にひっついた虫はまたたく間に体の半分を呑み込んでいた。
気が狂いそうになった俺の目の前で、しかし虫の群れは突如、黒い粘液になり、ひんやりと冷たい物が身体を這い上がってきて、現実がようやく戻ってきた。
第12話-12へ続く
12
バッカド生体記録
金色のかごのようなものがぶら下がっているのが見えるがそれが、我らハータン人の寝床になる。
ハータン人は頭部だけの生物体であり、人間やその他の種族のようなベッドは必要なく、反重力能力を停止しても落ちることのないカゴのようなものがあれば、何でもよいのである。
極論を言えば床に転がっていても眠れるということだ。
しかし黄金のカゴを見たとき、わたしの中でこれがどれだけ大金持ちの家なのかすぐん理解出来た。黄金のカゴで眠れる身分の者は、ハータン人の中にあっても、そう多くはなく、財力に力のある人物だとわたしは推察した。
それもそうであろう、そこに眠るのは王族の姫君だったのだ。
私はこの部屋、この姫君、この夜に見覚えがあった。
ハータン人が人間のオペラを自分たちの種族に置き換えた、伝説の演目である。
地獄の復讐がわが心に煮え繰りかえる
死と絶望がわが身を焼き尽くす!
甲高い歌声とともに3人に侍女を引き連れ、夜の女王が現れた。
頭を半分剃り上げ、長い髪をたなびかせ、黒いベールを反重力で浮遊しながらも引ずっていた。
「魔笛」
わたしは思わず口にしていた。
この場面は夜の女王である母が娘に神官ザラストロを殺害するように迫る、魔笛最大の名シーンである。
それが目の前で繰り広げられている。
わたしは感無量だった。あの魔笛をこんな目の前で見ることができるとは。
しかしそれを邪魔するのは夜の闇。夜の女王も娘も呑み込み、傍観者であるわたしさえも呑み込んでしまった。
そして現実へと引き戻したのである。
第12話-13へ続く
13
イターラン生体記録
各々がなにをしていたのか、どこに行っていたのかわからないという様子で、茫然とポッドの中で動きを止めていた。
僕もそうであった。
全員の顔を確認し、意識はしっかりしているか、現実だということを認識しているかを確認してみると、アイデンは特に現実と別世界との境目がついていないらしく、誰よりもボーっとしていた。
「現実だ、わかるか」
わたしの四つに割れた肘に力が入り、鱗のついた右手がホモサピエンスの肩をつかみ揺さぶった。
「あれは……」
やはり衝撃が強すぎたらしい。
とにかく自分が現実に戻った、いや自分のいるべき現実に戻ったことを理解はしているらしいので、そのままにしておいた。
「次元のはざまに完全にはまったらしい。しかもあのしろものがどの現実にも入り込んできている」
冷静にザイードがサイボーグの脳で状況を判断した。
わたしが経験した現実にも黒い何かは侵入してきていた。それが初めてザイードの言葉で全員の現実、全員が経験した現実に入り込んでいたことを知ることができた。
「あれが不確定要素として存在するのは理解できるが、他の現実に我々が介入して、それが変化することを恐れるべきではないか」
頭部だけで浮遊するバッカドが左右に顔を開き、縦についた口で恐れるべき事実をのべたのに、わたしは気づいた。
そう。オムニバーズの中にはあらゆる現実がある。小説、漫画、映画、演劇、歌。そうした現実の宇宙は常に未来が不確定に流動している。そこに我々が介入することで、未来が、物語が変化することも十分あり得ることに、注意が向いていなかった。
「そうだな。今度は全員、冷静に判断するべきだ。わかったな、アイデン」
茫然としているアイデンの肩をわたしは軽く来ずいた。
その刹那であった。世界は再び別の現実をわたしにみせたのだ。
第12話‐14へ続く
14
アイデン生体記録
肩をイターランの鱗に覆われた腕で小突かれた記憶を境目に、目の前からポッドは消えていた。
なんの前触れもなく突然、俺は足の塗らるむ泥まみれの地面に立っていた。身体には同じく泥まみれのつなぎを着ていた。頭にはヘルメットをかぶり、まるで作業員のような様相である。
「君は従業員としてそちら側につくのかね」
声のする方に眼を向けると、スーツ姿の男が、銃器を手にした兵士の前に立ち、俺をにらみつけていた。
それからようやく周囲がどんな状況なのか把握するように、俺の脳は忙しく働いた。
遠くには山々がそびえ周囲にはジャングルが生い茂っている。その中に木材が転がり、森林伐採をしている途中の現場のど真ん中に自分が立っていることに気付いた。
「地球は悲鳴を上げている。その悲鳴に耳を傾けるべきなんだ」
兵士が銃口を向ける方向に首をひねると、ちょうど俺を挟んで反対側に、環境保護団体が自らを巨木に縛り付け、森林伐採を妨害していた。
慌てて俺はその場から離れようとするが泥から足が抜けなかった。
「君たちが行っているのは私有地への無断侵入と業務妨害に当たる。この国では重罪だ。軍隊もこうして動いていることだし、いいかげんわからないのかね」
ワイシャツに汗じみを作る、おそらく現場の偉い人間なのだろう、メガホンを使い環境保護団体に訴えかけていた。
が、木に身体を縛り付けてまで邪魔をするのだから退去することはまず、ありえないと俺にさえも分かった。
「二酸化炭素がこの10年でどれだけ増えているか、わかるか。ここは地球の肺だ。森林伐採を続けていたら、人間が住めなくなる。どうしてそれがわからない」
環境保護団体のリーダー、サングラスをかけて、肩まで紙を伸ばした白人の男は大声で叫んだ。
相容れぬ状況に、いよいよ銃口の鈍い光がリアルに感じられてきた時だ。アラブ人顔の大男が俺に近づいてきて、腕をつかみ泥から、野菜でも抜き取るように俺を抜き、銃口の射程がいへと連れて行った。
そこは作業員たちが軍隊と環境保護団体のにらみ合いを見守っている、巨木の下の日陰であった。
アラブ人顔の男は俺の手を放すと、耳元に顔を近づけてきた。
「僕だ、イターランだ」
マヒレアナ人のイターランが人間になっていることに、思わず声を上げそうになるのを、乾いた泥のついた手で口を押え、無理やり驚きを飲み込んだ。
小声でそして俺もイターランに答えた。
「今度は姿まで変わってるなんて、次元の間から早く出ないと、次は動物に帰られちまうかもしれないぞ」
「僕も同じことを考えていたが、この状況で僕たちができることは、待つことだけだ。さっきも待っていたら勝手に元に戻ったから、それを待つしかない」
「いつ戻れると思う」
俺の質問は愚問だった。
自分たちの意思で飛ばされたわけではないのに、こうしているのだからいつ、どんなタイミングで戻れるかなど、イターランにわかるはずがない。
「お前はこの場面に見覚えはあるか」
「俺が環境問題に関心があるように見えるか?」
イターランの質問の意図に俺はそう答えてから気づいた。
さっきまでは様々な作品、自分の想い入れのある場面に移動していた。しかしイターランの口ぶりからすると彼もこの状況に見覚えがないらしい。
「小説、映画、ゲーム。なんでもありなのに、2人ともしらない現実を見せられてる。どういうことだ。しかも今度は僕の種族まで変えられている」
12話‐15へ続く
15
イターラン生体記録
人間というのはこんな感覚なのだと僕は初めて理解した。関節が普段より少ないせいなのか、動きにくい気がする。
それよりも問題はどうして僕が人間になったかだ。しかもアイデンも知らない現実の中で。
さっきまでの傾向は自分たちの知っている物語、音楽の世界、現実に移動していた。そのままの姿で。
ここはなにか違う。なにか嫌な予感がする。
“解決しろ、解決するんだ”
僕は自分に何が起こったのか、一瞬わからなかった。
頭の中で声がした。とうとう次元の間を移動した弊害がでたか、と思った。けれどそれははっきり頭の中に響いていた。
何度も、何度も。
「これは損失に値します。会社側としては、もう一度、話し合いの席につくべきです」
自分でもとっさに口から出た言葉に、呆然とした。
横のアイデンは何を言い出したのかと、顔が蒼白になっているのが分かった。
「そうだ、そいつの言うとおりだ」
環境保護団体は大いに僕の言葉で盛り上がっていたが、会社側の、責任者と思しき、スーツの男は僕を苦い顔で睨みつけていた。
「話し合いは再三に渡り行ってきた。我社も譲歩はできるところまでした。今更、なにを話し合えというのかね」
責任者の男はこっちを睨みつつ、環境保護団体に叫んでいた。
「僕から提案があります」
提案などない。それなのに口から勝手に言葉が出ていた。
第12話-16へ続く
16
アイデン生体記録
俺は何がイターランに起こっているのか、理解できずにいた。
フルボランという企業がジャングル一帯の土地を買い占め、伐採した木材を、世界各地に売りさばいているらしい。
対する環境保護団体チャクラは、ジャングルが失われる事態は、地球の危機だと叫び、なんども伐採を妨害し、現地警察に逮捕されていたようだ。
今回の騒動はフルボランが起こした法廷闘争で、裁判所が下した伐採地への立入禁止を無視したチャクラのメンバーを排除するため、フルボランが現地軍隊を動員したものだった。
フルボランと軍隊の癒着は有名な話であるようだった。
伐採を依頼された林業会社の従業員から聞いた話してはこういうことらしい。
イターランがどうしてこの事件に首を突っ込んだのか、話しかけたが、俺の言葉はまるで届かない様子で、変な雰囲気だった。
戦いの場は、近くに建てられた林業会社の事務所で、話し合いという形で行われることとなった。
イターランの提案というのを聞くための話し合いでもあり、お冠の現場監督、イターラン、俺、チャクラの代表者、軍人も2人が事務所に席を並べた。
俺は肘で隣のパイプ椅子に座るイターランを小突くも、アラブ人顔の人間になった彼は、反応すらしなかった。
「それで、一現場従業員の君が、我々になにを提案しようと言うのかね」
現場監督は嫌味ったらしく、イターランを睨みつける。
「やめましょう、こんな争いは」
何を言い出すかと思ったら、俺でもわかるような、当たり前のことを彼は言い出した。
その場にいる誰もが、シラけた様子でイターランを見るなり、頭を抱えるなりした。
「そうだ、やめるべきなんだ、地球が悲鳴を上げているのがわからないんですか」
チャクラの代表者だけが彼の言葉に賛同した、
「君は何を言っているのかわかっているのかね? あれだけ人間を動かして置きながら、そんなことを言うために、わたしをここに呼びつけたのか」
「人間はいつもそうではありませんか。気づいてからでは遅いんですよ。気づく前に、手遅れになる前にやめるべきなんです。僕の惑星もそうでした。緑豊かで自然しかない惑星でしたよ。それが僕は嫌いだった。でもなくなったんです。人間が資材として伐採し、自然が消えた。そして僕は大切さに気づいた。
そうなってからじゃ遅いんです。だからこんなこと、やめましょう」
完全にイターランはマヒレアナ人としてこの場に立っていた。
「惑星? 君は夢でも見ているのか」
現場監督は怒って立ち上がった。
その時、俺にも予想できない行動をイターランはとった。
近くにいた兵士から拳銃を奪い、現場監督に突きつけたのである。
第12話-17へ続く
17
イターラン生体記録
頭の中からあの声が離れない。
解決しろ。解決しろ。
そればかりを頭の中で永遠と繰り返していた。
視界が歪んで何が自分の中で起こっているのか検討もつかなかった。
こうして記録しているのもやっと。
アイデンがなにかを話しかけてきている。それだのに身体が動かない。頭が割れそうに痛い。
その時、身体が勝手に動いた。兵士の拳銃を盗み、現場監督に突きつけていた。
「解決するにはこうするしかないんだ」
僕はそう口走っていた。
そう解決するしか方法はこれしかない。
迷いはなかった。引き金を引いて、現場監督の頭から血煙が上がる。
これに合わせたかのように、兵士たちは手に持ったAK47を事務所内で乱射した。
解決した。解決したんだ。
第12話−18へ続く
18
ザイード生体記録
「アイデンとイターランがどこに行ったのかわかったぞ」
俺はバッカド本を見せた。
そこにはある林業会社の社員が行った行為と、最後に残した意味不明な言動が記載されていた。
「森林がなくなった惑星ってのは、イターランの惑星のことだ。それにこの写真に写っている犠牲になった従業員の社員。アイデンだ。
その本は世界の都市伝説という、記録としては確かにあった事件だが、エンターテイメントとして事件を読み解く本であった。
「こんな本にどうして」
バッカドは戸惑いの顔をしていた。
しかし俺は確信した。今、俺たちがいる世界と歴史がつながった世界に彼らもいたということになる。
そして同じ現象が2人にも起こったのだろう。
人間化だ。
俺は黒人の男に、バッカドは白人の男になっていた。この姿のまま、数カ月を過ごしていた。
俺たちは人間の風習は理解していたから、そこまで不便ではなかった。
しかしここがどこなのか、どこに居るのかわからず、とりあえず近所にある図書館に通い詰め、歴史を漁っていた。
不思議と我々には家や仕事が用意されていた。それをこなす毎日の中で、歴史を探る。
その中でようやく、もとの世界との繋がり、アイデンたちを発見したわけである。
だが何十年も前の資料であり、2人は死亡している。
いったいいつまでこの世界に、現実に閉じ込められなければならないのか、不安になってくる。
「なんとかして合流できないか」
バッカドは合流を期待していたのだろうが、僕が見た限り、2人は数十年前にしんでいる。ポッドに戻っているか、あるいは――。
「俺たちは、俺たちで出口を探すべきだろうな」
バッカドにとって辛辣な言葉だったかもしれない。
だが俺は俺で頭の中が整理できておらず精一杯の言葉だった。
図書館からの帰り、俺たちの足取りは重かった。
アパートに到着すると、ちょうど俺のスマホのバイブレーションが振動した。編集長からの電話だった。
この現実で与えられた仕事、それは新聞記者である。俺たちは新聞記者として事件を追っていた。編集長からの電話は、追っている事件の進捗状況と、早く記事にしろ、というさいそくであった。
第12話-19へ続く
19
バッカド生体記録
この肉体になってから数ヶ月が経過する。だいぶ人間というのにもなれてきたところなのだが、ザイードと違う点が一つだけあった。それはこの体になってからずっと頭の中にあった。
記憶。自分とは違う記憶がこの肉体にはあったのである。
ある殺人事件を追いかけていた記憶が。
スマホで編集長らしい人物と電話を終えたザイードは、わたしの顔を見た。
「事件を追ってみよう。君の頭の中にある別の記憶、その記憶はこの現実から出る手がかりになるかもしれない」
わたしもそんな気がしていた。肉体がもしかすると別の人間の肉体で、わたしの意識体だけが入り込んだ可能性もある。その可能性の中で例の殺人事件だけが記憶に残っているということは、そこに意識体として抜け出るヒントがあるような気がしていた。
「事件を整理してみよう」
ザイードはタブレットを手に取り、これまでの取材履歴を確認した。
事件の概要は一人の男の死である。
正確にいうのであれば、中央銀行頭取が二年前の夏、日曜日。銀行に行く前にデパートで買い物をしたいといい、運転手にデパートまで送らせた。数分の買い物だ、といってデパートに入ったのが運転手の見た頭取の最後の姿となった。
翌日、頭取の家の近くの用水路で遺体となって発見された。警察の発表では、泥酔して歩いていたところ、用水路に落ちた事による溺死と判定だれた。
しかし事件はここで終わらなかった。デパートに入った頭取が複数人の男たちと会い、そのまま裏口からデパートを出た防犯カメラの映像が残っており、その後、一人で町中を歩いているのを複数の防犯カメラが捉えていた。さらに用水路での溺死とあったが、その日、用水路はおりからの日照り続きで、泥酔するほどの水量はなかったのであった。
こうしたこちは警察からは一切発表がなく、他殺の可能性は皆無、と警察は操作を打ち切っていた。
この情報はこの肉体の持ち主が独自に調べたものなのだろう、しっかりと記憶に刻まれていた。
「この頭取の出生地を調べてみたんだが、そこでも事件に突き当たったよ」
タブレットを動かしていた指が止まり、ある事件の古い新聞記事を見せられた。
「小島で大火災。生存者は絶望的か」
ザイードが詳細を要約してくれた。
半世紀前、小島という島で大火災が発生した。住民のほとんどが焼死体となって発見される中、数名だけが生き残った。その中にまだ幼かった頭取の姿もあったのだという。
他の人々は皆、老齢で亡くなり、大火事を知る人物は頭取ただ一人となったという。
「君はそこに事件の真相が隠されていると思うんだね」
わたしも大火事が何らかの事実を覆い隠しているのではないか、そんな気がしながらもザイードに聞いた。
「ああ。小島の大火事。事件の焦点はそこにあると確信している」
「だったら今から調べに向かおう。また図書館だ」
わたしたちはアイデンたちの記録を見つけた図書館に古い資料を探しにもう一度向かうべく、路地へでた。
「気づいたか」
ザイードも気づいたらしい。
「つけられてるな」
アパートを出た時点から図書館までの道すがらを、何度も黒いスーツの男を目撃した。間違いなく、わたしたちは何者かにつけられていた。
第12話-20へ続く
20
ザイード生体記録
尾行されている。
俺たちはそれを分かった上で、図書館に入った。尾行する人間たちはそれなりに風景に溶け込もうとしているが、スーツというのが図書館に入った似つかわしくなく、浮いていた。
間違いなく頭取殺人事件を調べている、俺たちを見ているのがわかる。多くの視線を感じた。
それを気にしないというのは無理があったが、作業に俺たちは集中することで、その視線から逃れた。
だが問題が発生したのだ。
「明らかな作為だな」
バッカドが新聞記事を調べつつ、日付が飛んでいるのを確認した。
それだけじゃない。小島での大火事は、まるで何かに覆い隠されるように、その詳細は概要だけしかわからなかった。
が、俺がネットで調べていたところ、怪しいサイトで、都市伝説界隈で噂されている記事を発見した。
小島には政府の軍事基地があり、毒ガス研修をしていた。そのガスが漏れ出し、島民に甚大な被害を及ぼしたので、火事ということにした。
頭取はその島の生き残り。何があったか知っていた。
この時、バッカドと俺の中で線がつながった気がした。
だが同時に、スーツ姿の男たちに肩を掴まれたのだった。
第12話-21へ続く
21
バッカド生体記録
“解決しろ、解決しろ”
なにか薬を打たれたのか、朦朧とする意識の中で、その声だけが頭の中にこだました。
気づくと暗い部屋に座らされた、ザイードとわたしはスポットライトを当てられていた。
ライトの向こう側に何人も人影が見える。
「どこまで知っていますか」
真ん中の椅子に座った影が穏やかに聞いてきた。
「全部だ。
あの小島には政府の軍事施設があった。法律で禁止されているVXガスの研究をしていた。だがそれが島内に漏れ出し、島民の殆どが亡くなった。
生き残った島民は政府に監視されながら生き続け、最後の生き残りが頭取だった。
その頭取も老年になりこのおぞましい事実を発表しようとした。
きっとデパートで落ち合ったのはマスコミの連中だろう。しかし頭取は遺体で発見された。マスコミの連中もおそらくは失踪しているはず」
「証拠はあるんですか」
また穏やかな声が聞こえてきた。
「この、仰々しい、拷問が証拠だ」
なんとか口走ったが、ザイードのように口が動かなかった。それに頭の中であの声が大きくなって響いていた。
「俺はなんとしてもここを出て、事実を公表する。このおぞましい事件を」
人影が怒りを顕にしたらしく、立ち上がり椅子が倒れた音がした。
その音がわたしの中のなにかをねじ切った。
「わたしは生きたい。この事件のことは忘れて、生きていく」
自分でも何を言っているのかわからなかった。
そんなわたしを驚きと軽蔑の視線でザイードは見ていた。
するとなにかがわたしの前に投げ出された。
スポットライトに浮かび上がったのは、リボルバー式ピストルだった。
「それで相棒を撃ってください。そうしたら信じましょう」
わたしはピストルをゆっくりと手にとった。
「おい、嘘だろ、バッカド」
ザイードが叫ぶ。
“解決しろ、解決だ”
わたしは引き金を引いていた。
身体の力が抜けたザイードの死体が、床に転がっていた。
そしてわたしはこめかみにピストルを突きつけた。
第13話へ続く
第12話『調査員たちの物語』