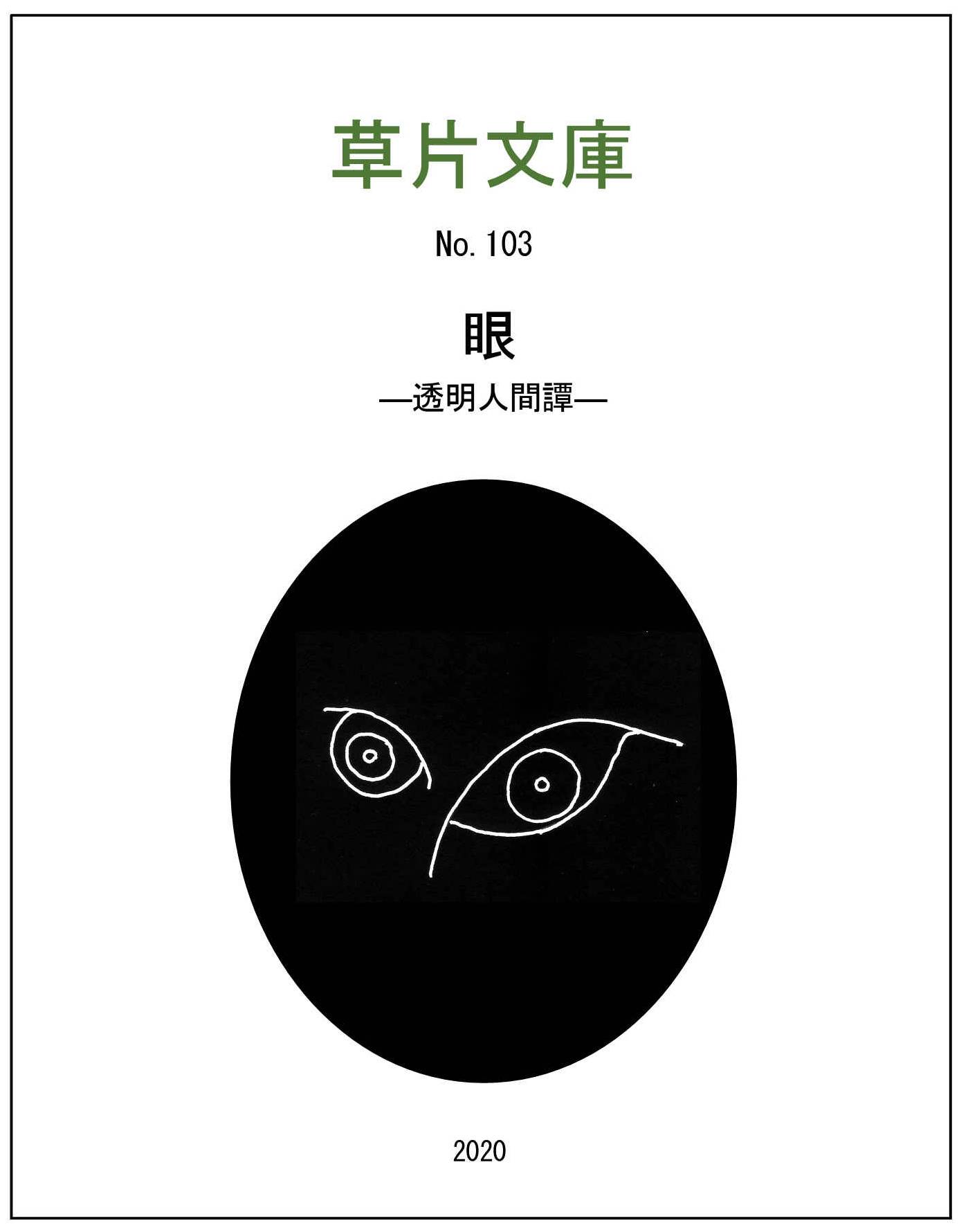
眼 - 透明人間譚
舞妓さんを希望する娘はかなり少ない。それでも全くいないわけではないらしい。
日本の舞踊の仕来り、和服の作法は生半可なものではない。それでもなりたいというのは相当覚悟を決めた娘だろう。
一方、少女マンガから抜け出たような格好で客をもてなす、メイド喫茶のウェイトレスになりたい子はかなり多いようだ。しかし華やかなようだが、常連客がつくのにはそれなりの作法と、おもてなしの心理を知らなければならない。
どのような世界でも、売れっ子になるには才覚がものをいう。程々にでも売れればいいなどと思っていると、あっという間に坂道を転げ落ちる運命を背負う。
テレビにでるアイドルは作り出された集団だが、人気は一時のもので、それを続かせるためには、イメージの作り手の手腕と、作られる本人たちの能力が相乗効果を生まなければならない。
いずれにしろ、どこの世界も底辺が広く、上に上がりたいとあがいている者たちがいる。一方、そのような中で、少数だが底辺にとどまっていたいという集団がある。
目立ちたくない、最低限の楽しい生活が送れればそれでいいという考えを持った人たちである。もちろんそうなるのには色々なわけがある。
ここは京都の一角にある置屋である。三人の舞妓を抱えている小さなものだ。お母さんと呼ばれるのは年の頃五十ちょっと、色白で少しばかり太り気味の、透美(すみ)である。旦那は透十(とおじゅう)と言い、やせた爺さんで、全く仕事をせずに昼間から酒を食らって寝ていたりする。舞妓は、霞(かすみ)、靄(もや)、霧(む)の三人で、長女の霞は年の頃三十ちょっと手前、三人とも透美と透十の子供である。
自宅をかねた置屋の外見は昔ながらの京の町屋に見えるが、玄関に続く、少しばかり広い稽古所兼客間以外は何とも近代的な住宅である。一階にはキッチンに居間、衣装をしまい着替える納戸、夫婦の部屋といったところに、これだけはかなりの広さのある浴室がある。二階は三人の娘のそれぞれの部屋がある。どの部屋も近代的な装備がなされているのだが、外見はそうは見えないような施しがある。昔ながらの建物を買い取り、どこからか連れてきた大工に改造させたようだ。
この店は古くからある組合に入っていない。独立した置屋である。小さなホテルや宿屋からの声掛けをまっている。安い料金で、一応白粉で固めた見栄えは悪くない舞妓たちがおり、彼女たちは踊りなどを器用にこなすのでそれなりに声はかかる。舞妓といっても芸妓なのだが、酌をするにしても話し上手で、間の取り方がうまいので客が喜ぶ。三人姉妹は見ようによってはかなりの美形である。意外と声がかかる。一流どころからはちょっとばかり蔑みの眼で見られ、枕芸者などと陰口が囁かれることもあるが、そのよう半分妬みの噂を一向に気にすることはない。三人姉妹は男からどのような誘いがあってもやんわりと上手に断ってしまう。「あらうれしい、おつきのものが控えていなけりゃついて行きたいわいな」などと言って引き下がる。たまにその意味の分からない男が、「付き添いなんか先に返しちまえ」などというが、「旦那さんの指先が、血に染まるのはみとうない」とかえす、そこでわかっている男はひきさがるが、裏に顔に傷のあるお兄さんを想像する男は、「何でえ、やくざか」などという。そこで、「女の性(さが)は、月に一度は血潮にまみれ、あなたのお姿かき抱き、一人寝をする日がありまする」と調子を整え、引き下がってくる。男はそこで、ああそうかと納得するといった案配である。
ともかく、本物とはいかないが、安くそれなりの京のもてなしを提供してくれる、それなりの評判のある置屋ということである。古くからある組合も、どのようなものにも底辺があるものと、悪行さえ働かなければと、みのがしていた。
置屋の名は隅屋という。お母さんの名前の透美からとったと思われているが、名付けた主人の透十は、「へえすみっこの屋形でございます」などと言っている。屋形というのは置屋のことをいう。
朝、透美は化粧をしマニキュアまで塗って、みなの朝食を用意していた。三人の娘も顔を白く塗り、手まで真っ白に白粉を塗って降りてきた。朝から仕事というわけではないだろうに。髪は三人ともショートカットだ。
「おはよう」
「ああ、おはよう」
「お父さん昨日遅かったの」
「3時頃よ、いつもよりたくさん稼いできた」
「あまりとらない方がいいのにね」
「大丈夫、昼間は飲んだくれているけど、夜はしっかりしているわよ」
三人の娘は食卓に着くと、トーストにハムとレタスを挟みマヨネーズをかけた。
長女の霞が「今日の予定は」と母親に尋ねた。いつものことのようだ。
「今日、霞は観光ホテル7時、七人の九州の団体さん、靄は6時いろは旅館の二人客、傘寿の人たち、霧はアマーダ国際ホテルのダイニングで8時、アメリカ人団体客で、人数が多いので、お酌の手伝いもやってほしいって、椅子だって」
透美が三人に今日の予定を手短に伝えた。
「それまでなにしよう」
「私は株を考えるわ」
「今どうなの」
「アメリカの馬鹿な大統領がいい加減なこと言うから混乱しているよ、だから儲けのチャンスよ」
「私テレビ見てる」
「またWOWOW」
「いやスターチャンネル、見たい映画があるから」
「私はどうしようかな、踊りの練習でもしよう」
それぞれ自分の部屋に行くと、母親の透美は三人の娘の車の手配をして、着ていくものをそろえはじめた。三人の娘は呼ばれた座敷に、近くであろうと必ず車を使う。大した稼ぎではないのに贅沢といえば贅沢だが、組合に入っていない置屋の芸子はやはり目が気にもなる。もちろん型が崩れないようにという配慮もある。
夕方になると、三人は舞妓姿の簪つけた頭、割れしのぶ、にして二階から降りてきた。鬘である。割れしのぶはまだ修行中の舞妓が結う頭である。上に行くと、おふくと呼ばれる頭になるが、三人はいつも割れしのぶにしている。これも目立たないようにということらしい。
口紅も下にしかつけていない。まだ若い舞妓さんの化粧方法だ。
三人とも迎えに来たタクシーに乗ってでかけた。そのころ、父親が「今日は寒くないといいがなあ」と言いながら風呂場に行った。
「よく暖まって行きなさいよ、風邪引かないようにね」
透美が亭主に声をかけた。秋の半ばだ。夜はそれなりに涼しいが寒いことはなかろうに。
「今日はどこにいくの」
「木屋町にしようと思うんだ」
「情報入ったの」
「ああ、市議の集まりがあって、その中の一人が会議の後によく行くところがあるんだ」
「そう、今日は魚煮とくよ」
「ああ」
おやじは風呂場にむかった。これから夜の仕事のようだ。
風呂から上がった透十がキッチンのテーブルで煮魚をつついている時、三人の娘はそれぞれの仕事をこなしていた。
観光ホテルのお座敷では流しの女性演歌歌手が、そこそこの歌手という触れ込みで、三曲を歌い。会社の親睦旅行で九州からきた七人の中年の男たちが、飲みながら手をたたく。そのあとに、霞はCDの音楽をバックに、それでも京都の舞を披露した。演歌の後の京都の舞は効果があった。本物に見えるから不思議である。もっとも霞の踊りは下手ではない。それなりの基礎はお母さんからきちんと教わっている。終わって拍手を受け、そのままの格好で七人それぞれに酌をすると、袖に入った。しばらくすると、もっと簡素な着物に着替えて酌の続きをする。
宿屋に行った靄のほうは、二人の老人の前で、踊りを披露した。ここでは、お母さんが差配してくれた年取ったおばあさんの三味線と唄で踊った。傘寿の老人はこういう席は初めてのようで、まじめな顔で料理をつついている。踊り終わった靄は座って深くお辞儀をして、「傘寿まことにおめでたきこと、ますますお二人の楽しきことが多くおとずれますこと、末永く、おあしますように」と言ったのだが。即興のようで、その上、舌たらずで何とも言葉のわかる人が聞いたら吹き出すだろう。だが老人はありがたそうに手をたたいた。いったん袖に入り、お酌をしながら話を聞くと、名古屋から来たという中学の同級生同士だった。初めての松茸の土瓶蒸しだとやっと笑顔がでた。
長女の霧が行った国際ホテルでは、大きなホールのステージで、専属の芸人が、太鼓持ちの演技、水芸、琵琶の語りとショウを続けていく。
アメリカ人たちは陽気にビールを飲みながら、おしゃべりをして、それでも、芸に手をたたく。
最後に、霧は専属の舞妓二人とともに京の舞を披露した。そのあとその姿のままでテーブルの脇に行き、ビールをついだり、ホテル専属のカメラマンがテーブルで客と一緒の写真を撮ったりする。アメリカ人たちは大喜びだが、後で写真を高く買わされるのだ。
こうして、その日、三人の娘はまた車を拾って家に帰り着く。
「ご苦労様」
女将であり母親の透美は娘が帰ってくると必ず迎えにでる。
娘は納戸で着物を脱ぐと二階に上がり自分の部屋に戻る。パジャマを持って、浴室に行くと、シャワーですべての化粧を落とし湯船に沈む。娘が湯に入っている間に女将は着物をたたみ、カツラを箱に収める。三人の帰りが重なると大忙しだ。
風呂から出た娘たちはパジャマを着て、キッチンのテーブルにつく。母親が用意したチョコレートを飲む。いつものことだ。
その様子を、もし他所の人が見ていたら腰を抜かすかもしれない。
テーブルの上を暖かい湯気を上げているチョコレートのカップが宙を舞っている。パジャマが椅子に腰掛けている。顔のあるところに眼玉が浮いている。一人の眼玉が女将を見る。
「今日のチョコレートいつもより濃いわね、おいしいわ」
「あ、そう、粉がちょっと多かったかもね」
母親は宙に浮いている二つの眼に向かっていった。もう一対の眼がカップの中を見ながら、「私もこれくらいがいい」と声を出した。口がないのに声がする。
三対の眼玉は霞、靄、霧の眼玉であることは間違いがない。
「お父さん今日はどこ」
「木屋町よ」
「またなの、先週もいったでしょ、ピンクサロンでしょ」
「そうね、市議がくるだろうって」
「それじゃあまり遅くならないわね」
「ええそう思うわ、あの市議さん、すぐ飲むのやめて、店の子を連れ出してホテルにいっちゃうでしょ」
「きっとそうよ、舞妓にもすぐちょっかい出す奴、私もお尻触られた、暮れの宴会の時」
「あの市議が一番とりやすいんだって」
「財布の中のお札の数なんて知らないものね」
「お母さんもお風呂はいってきたら」
「そうね」
女将さんも風呂にいった。
その間、パジャマと眼玉しか見えない娘たちは、居間に移ってテレビを見ている。
風呂からでた女将もパジャマになって居間に来た。手足は見えず、顔もなく、ただ眼だけ宙に浮いていた。
「お母さん、眼が充血しているよ」
「今日、おまえたちの着物を繕ったからよ」
「ありがとう」
そこへ、おやじの透十が帰ってきた。自分で鍵を開けて入ってくる。
「お父さんご苦労様、ずいぶん早かったわね」
「うん」
長女の霞が声をかける。亭主は、ほれと、一万円札の束をテーブルにおいた。
「こんなにどうしたの」
「二百万ある」
「見つかったらどうするの」
「風呂から出たら説明するよ」
おやじはそこで帽子を脱いだ。頭がない。眼玉だけが宙に浮いている。
「寒かったよ」
おやじの声だけが聞こえる。手袋を取ると手が消えた。厚手のブルゾンを脱いだ、上半身が消えた。ズボンを脱いだ。腰より下が消えた。
「じゃあ風呂に入ってくる」
眼玉だけが宙に浮いて風呂場に向かった。
透明人間だ。眼玉だけそのままだ。
「お父さん裸にズボンとブルゾンだけで働いていたのじゃ寒かったわね」
末娘の霧が言った。
「そうね」
透美が主人の脱いだ着物を拾ってたたんだ。日本酒の燗をつけると、つまみの用意をした。
「今日は私たちも飲もうか」
娘たちが立ち上がった。手足がない、頭もない、いや見えない。パジャマと眼玉が動いている。
「母さんも飲む」
「そうしようかね、イカの塩辛作ったの食べられるよ」
母親は刺身用のスルメイカを買ってきて、内臓に塩をまぶし一日おき、切った身を混ぜて自分で塩辛を作る。それがまた美味い。
用意ができたところに父親がパジャマを着てもどってきた。
女将が茶碗に酒をついだ。おやじはぐっと一気に飲み干した。
「お金どうしたの」
「いつものピンクサロンにいったんだ。ビルの狭い隙間で着てるものとって裸になった、眼が見つかるといけないので、はいずくばって、二階のサロンのドアをちょっと開けてみると、いつものように女を相手に市議のやつ飲んでいたよ。今日はいつもと違って、市議一人で貸し切りだ、そろそろ酔っぱらうという頃なのに、そのときはあまり飲んでいなかったらしく態度が変わっていない。すると店のママが「今日は終わりよ」と女の子に声をかけてな、女の子はわかっているらしく、奥に行くと着がえて、「お疲れー」と出て行ったよ、その前に市議のやつそれぞれに三万ずつ「うまいもん食えよ」ってわたしていた。
ママは戸に鍵をかけて、部屋の明かりを薄暗くしてね、酒を用意して市議の隣に腰掛けた。
「これあんたに」と市議は百万渡したよ。それから「この鞄に金が入っている、今日十一時頃、あの方が来るから渡してくれ」
そう言って黒い鞄をテーブルの下においた。
「いくらはいっているの」
「二千万以上だ」
「すごいのね」
「こんどおれ、衆議院に立候補する」
「出世ね」
「余計なことを言うんじゃないよ」
そこでママが部屋の明かりを消したんで、俺はあいつらが、ことをやっている間に、鞄から二束取り出すと陰に隠れていたんだ。しばらくして市議は出て行ったよ。ママが奥にいった隙に俺は外に出て戻ってきたわけだ」
「それじゃこのお金、収賄のお金なのね」
「そうだよ、だからだいじょうぶだ」
「みんなそうやって国会議員になるんだね」
「そんなこともないだろうが、国会議員になるには金がかかるのさ」
「さて私は寝るね」
「私も」
三人の透明人間娘は二階の自分の部屋に行った。
「来週、東京の菊池さん家族が京都に来るって」
「あ、そう、久しぶりだ、あいつと碁でも打つか」
菊池さんは透明人間仲間である。
「下の息子さんの弘君はまだ二十歳、上の明は三十三、娘は二十二と二十五よ」
「上の娘二人はストリッパーとマヌカンだったよな」
「そうよ、みんないい子、上の男の子、靄とどうかしらね」
「本人が決めることさ」
菊池さんの上の娘が霧と同じ年で、病院で知り合ったのだ。彼らもやはり眼玉だけ透明でない。男の子は父親と同じように、有り余っているところからお金をいただいてくる。女の子は手足、見えるところに化粧を施し、働けるところで働いている。ストリップすると透明になってしまうので、金粉を塗ってショウにでる。もう一人は化粧を施しマヌカンをやっている。洋服の宣伝だ。
この一族がいつどのように生まれたのかわかっていないが、縄文時代からいたのではないかと彼らは自ら考えている。今では各県に数家族はいるので、五百人ほどの人口だ。一般の人間には知られていない。
透明人間一族の間にはこういう伝説が伝わっている。縄文時代の頃だろう。ある部落に小さな隕石が落ち、そのとき青い閃光が一瞬光り、それを見た縄文人のからだが半透明になった。しかし体調には影響がなく、むしろ頑丈になった。今でも透明人間にはウイルスがつかない。透明人間の細胞の中の遺伝子が形を変えており、ウイルスが増殖できないのだろう。だから風邪も引かず、かなり長い寿命まで生きることができる。
半透明になった縄文人たちは自分の部落で生活をしていたのだが、半透明人間同士の結婚で、生まれる子供たちのからだの透明度が高くなった。弥生時代に至ったときには、眼を残してすべて透明になった。隕石の閃光を見たおかげで、眼はそのままになったともいわれている。そのために今でも眼だけ普通の人にも見える状態のままなのである。
土曜日の昼過ぎに菊池家族がやってきた。
透十が菊池の旦那に声をかけた。
「久しぶりだな、元気かい、東京はかせげるだろう」
「やろうと思えばな、だが警視庁はきびしいから、小銭でがまんしているよ」
「俺は収賄の金を少しばかり稼いだよ、京都に来たんだから、何でも買っていきなよ、使ってくれよ」
透明人間は金に困らない。仲間同士みなで共通に使うのが当たり前のようになっている。
「駆けつけ一杯だ、京都のビールどうだい」
菊池夫婦と二人の娘は隅屋の夫婦とテーブルの周りにすわった。二人の息子は一緒に来なかったようだ。隅屋の娘たちが枝豆とビールの用意をして、座った。
「乾杯だ、だけど息子さんたちはどうしんだい」
「京都についたとたん、パチンコ屋に入っちまってね、もうすぐ来ると思うけど」
菊池のだんながビールを口に運んだ。
「遥ちゃんも、深里ちゃんも久しぶりね、立派な女性になったわね」
隅屋の奥さん、透美が菊池の二人の娘を見た。菊池家の上の娘と下の娘である。遥が霧と同じ病院で生まれた。
「結構稼いでいるわよ、父ちゃんよりも稼ぎがいいの、遥の金粉ショウうけるのよ」
菊池の奥さんもビールをぐいいと飲んだ。
「うちのはまあまあね、でも男の子がいるといいわね、将来の心配ないでしょう」
「まあね、下の弘は好きなところにいって、お金を取ってくるわ、まあ、無理をしないからいいわね、上の明は上流ねらい、なかなかいいかもを見つけて、決して見つからないようにとってくるわ、父ちゃんはこのごろ、遊び人に見られるようになって、眼つけられているからあまり派手にはできない」
菊池のおやじは家でごろごろしているのに、いい服を着ているといわれているようだ。透美が菊池の母親に尋ねている。
「ねえ、息子さんは好きな人がいるのかしら」
「いないみたいよ、こういう体だから、お金もって遊びには行くけど、体が見せられないからかわいそうね」
「もう結婚してもいいんじゃないの」
「神奈川、千葉、山梨、関東の支部会には顔を出させているんだけど、何せ本当の顔が見えないとなかなかね、仲間のお見合いしかないわね」
透明人間の集まりは「透人会、とうじんかい」と言う。
「どうかしら、明君、うちの霞は」
「それはすてきね、霞さん落ち着いてていいわね」
「今日、ちょっといいとこから食事運ばせるから、お見合ね」
二人の息子はしばらくして隅屋にやってきて、みんなとテーブルを囲みビールを飲んだ。
本人たちにその旨は伝えられなかったが、老舗の料亭から十一人前の料理を運ばせ、夕飯はお見合いの席に仕立てられた。
隅屋の透十にすれば、ちょうど二百万が入ったんだ、使っちまえと思ったのだろう、一人八万の料理である。
夕方、運んできた料理店の者が、次はうちの座敷のほうでお願いします、と灘の生を二本サービスにもってきた。
「こりゃ父ちゃんたちだね、冷えたビールとワインを酒屋に持ってこさせてあるよ」
運ばせた料理をテーブルに並べ、隅屋の女将と菊池の女房が酒の用意をし、宴会が始まった。
「すごい料理だな」
次男の弘が目を丸くしている。
「おじさんがだいぶ稼いだんだって」
菊池の長女が説明している。
隅屋の三女、霧が菊池の二人の男の子にビールをついだ。下の弘の方が口が軽い。
「姉さん、眼が若いね」
年上の霧を姉さんと呼ぶ。
「何言ってるの弘ちゃん、透明人間の男の稼ぎ方勉強してるの」
「うん、おやじが教えてくれてる」
「明さんはうまくいってるんですって」
「うん、自分の島を持っているよ、ホストクラブに出入りする女性専門の店でね、若い娘はねらわないんだ、結構苦労している娘が多いからね、狙うのは、ひどい組み合わせのただ高いだけの服を着た社長の奥様たちだよ、ちょろいんだ」
「稼いでいるんでしょ」
「おやじより多いかもしれない、でも必要以上には無理しないから」
「偉いわね、どう、うちのお姉ちゃんあたりお嫁さんにしない」
明は照れながら、霞を見て「眼がすてきだ」と言った。
霞も照れて「やだ、明さんもてるもの、あたしなんて相手じゃないでしょう」とうつむいて笑った。
これを見ていて母親同士は眼をあわせて笑った。自然と二人のお見合いの場になりそうだ。姉思いのいい妹さんたちだ。
「このお料理上等ね」
金粉ダンサーの遥がお重のエビを口に入れた。
「さすが京都いいな、私なんかいつもイタリアン」
マネキンの深里は舞妓にあこがれている。
「私は東京暮らしをしてみたいわよ」
逆に霞は東京にあこがれている。
「今度はみなさん、東京に遊びに来てよ」
「行きたいわね」
「お姉ちゃんの結婚式は東京ね」
霧がお重の松茸をそういって口に入れた。
次の日、みんなで京都見物に出かけた。隅屋一家も家族そろっておおっぴらに京都の町を歩くようなことはほとんどない。出かける前に三姉妹は菊池の二人の娘から洋風の化粧の仕方を教わった。ずいぶん雰囲気が変わる。
「霞さんいい感じですね」
明が声をかけた。
「こういう化粧初めてで」
霞は恥ずかしそうに眼を落とす。
うまくいきそうと思ったのは、靄や霧だけではない。二人の母親もちょっとばかり期待していた。蚊帳の外は二人の父親である。
十一人で京都の町をぶらぶら歩き、茶菓子に抹茶を飲み、昼はにしん蕎麦を食べ、いくつか寺や神社を参拝し、狸横丁で土産を買った。
「今日は私の料理で我慢してもらう」
隅屋の女将がいうと、なぜか長女の霞が「あたしも手伝うわ」と珍しいことを言う。
こうしてこの即席の見合いは大成功に終わったのである。
菊池家が東京に戻り、まもなく、霞が「東京に遊びに行っていい」とお母さんに言った。「いいけど急だね」「うん、明さんからメイルもらった」「ああ、いっといで、東京にもなれなきゃね、泊まるとこは」「菊池さんとこ、明さんのお母さんが是非だって」
「そりゃいいね、電話しとくよ」
こうして、霞は東京に遊びに行った。一週間、その間、明がつきっきりで東京を案内したようだ。毎日のように東京の様子が透美のスマホに入った。遥の金粉ショウも見せてもらったらしい。女性もけっこう見ているのよ、遥さんとてもきれい、と書いてあった。深里ちゃんのマネキンは大変、お化粧の知識がたくさんないとできないし、きれいな歩き方するの、とてもあたしには向かないわ。などとも書いてきた。
瞬く間に一週間が過ぎ、霞がただいまと戻ってきたときには驚いた。東京土産をいっぱい抱えた明が一緒だった。
「まあ、荷物持ちさせて、すみませんね」
あがってきた明は、「お母さんとお父さんにお願いがあってきました」と言った。女将はもうお母さんとお父さんかと、ちょっとにこっとした。
「はいはい、まず休んでくださいな、お父さん、明さんがみえたわよ」
と奥に声をかけた。
座敷にみんな集まった。
「霞が世話になったようですな」
透十が明にお辞儀をすると、明がいきなり、
「霞さんをお嫁にください」と言った。それを聞いて返事をしたのは母親のほうだった。
「あれー、こちらからお願いしたいくらいですよ」
「うんうん」
ちょっと驚いたが父親もうなずいて「いや、よろしくお願いしますよ」
深くお辞儀をした。
明はそう言い終えると、その日のうちに東京に帰り、その後、結婚式は十一月十一日と決まった。東京の家はマンションなので、京都でしましょうというという、菊池家の申し出で、結局、芸子置き場、隅屋が結婚式場ということになった。
透明人間の結婚式は式場などでは行なえない。透明人間の仲間だけの式になる。東京本部と京都、それに隣県の透人会の支部長たちが参加してくれることになった。
十一月十一日、隅屋は珍しく人がこんでいた。といっても、結婚式そのものは質素なものである。結婚をする二人の紹介と、透明人間戸籍登録である。東京の本部に戸籍簿が保管されている。もちろん住むところに普通の人間の戸籍も作る。
隅屋の座敷には座布団が敷き詰められ、参加者はそれにすわった。床の間の前には、結婚する二人が、客のほうをむいて座っている。両隣はそれぞれの両親が座っている。
二人の兄弟は客席の一番前の席である。客席の真ん中には東京本部長と京都支部長が座った。
式は透明人間の仕来りに則って行われた。玄関の鍵は閉じられ、座敷の庭に面した障子はすべて閉められた。そこで参加者は着ているものをすべて脱ぐ。脱いだものを部屋の端にきちんとたたむと、座布団の上に座った。たくさんの眼玉だけが宙に浮いて、新郎新婦の宙に浮いた目玉を見つめる。
京都支部長より、霞と家族の紹介があった。東京本部長より明と家族の紹介がなされた。終わると二人並んでお辞儀をした。お辞儀をすると目が下を見るのである。もちろん記念写真なんて撮れない。眼玉だけ写ることになる。
それが終わると牛乳の乾杯になる。皆が牛乳のグラスをもち一気に飲み干す。透明人間たちは口に入れたものはすぐ透明になり、食べたものなどは見えなくなる。しかし牛乳だけは胃の中にはいるまで白く見えている。牛乳が口から食堂を通り、胃に落ちて貯まるのが見えるのである。霞も明も参加者全員の胃の中に牛乳が溜まった。やがて、五分もするとそれも消えていき結婚式は終わりになる。
再び参加者は洋服を着た。化粧の道具を透美が用意し、男も女も顔を塗り、手足を塗った。
透人会の人たちには京都のおみやげと旅費を渡した。挨拶の後、みな帰った。
それですべて終わりである。
菊池の人たちは一泊して東京に帰る。結婚した二人は京都のホテルに宿を取り、次の日、隅屋に泊った菊池家族と合流して東京に帰っていった。
京都の隅屋から透明人間家族から一人減った。だがこうして透明人間が増えていくことになる。
霞と明は巣鴨のマンションに住み、明は変わらず夜の仕事を続けている。舞妓をしていた霞は、菊池の長女、遥の指導と口利きで、ヌードダンスを覚えた。ヌードになったら見えなくなるので、遥と同じように体に色を塗った。金色ではなく銀色にした。一人で踊るのは恥かしいし難しい。まずは遥と一緒に踊るために銀色にぬったのである。それが大当たりで金粉銀粉ショウとして有名になった。それぞれ一人で踊った後で、デュエットで踊ると観客はたくさんの札をステージにおいた。
年が明けて三月、霞が妊娠した。透明人間の出生率は高くない。東京と京都に透人会の経営する病院がある。透人会病院という。働いているのは普通の人間の医師と看護師である。透明人間が医学部に受かっても、透明人間であることを隠したまま卒業することは難しい。経営人は透明人間で、透人会専任のスタッフがいる。透明人間はその病院を利用するが、病気をほとんどしないのでかかるとすれば出産時である。出産経過を医師と相談する。実際に産むのは自宅である。おなかの中の赤ちゃんの成長を見たり、母親の血液検査をするのは専門の技師たちである。技師たちは透明人間である。医師にはデーターが渡され、本人に会わずに状態を判断する。その病院では一部でそういう診察方法をとっている。遠隔診察の仕組みができている。
透明人間は金を稼ごうと思えばいくらでもできる。しかし、二つの病院の所有者は、盗んだ金で病院経営にのり出したわけではない。一つの発明をした。その特許料は馬鹿にならないもので、ある医大と契約を結び、大きな総合病院を設立したのである。
透明人間は出産や死亡時の証明書はその病院でだしてもらう。そこのところは、透明会専任スタッフが偽造することになる。だからすべての透明人間がその病院の診察カードを持っていることになる。専用の宿泊施設もあり、全国の透人会の会員がやってきて、病院を利用するのである。
霞もその病院で診察を受けた。全く問題がなかった。
透明人間の女性は赤子を取り上げることを学ぶ。昔は自分一人で産んだということである。母親は娘に出産の手順をすべて教えるのである。だから霞もそれは良く知っている。母親もいるので何も問題がない。
霞の出産は来年の1月の予定である。しばらくは銀粉ショウもできるだろうが、お腹が大きくなってくるとなかなかそうもいかない。それに子育てになると無理かもしれない。すると、すぐ下の妹の靄がしばらくやってもいいと言いだした。東京の空気を吸ってみたいようだ。いずれ一番下の霧が婿を迎えて、隅屋を継ぐだろう。
靄は菊池家に寝泊まりし、遥から踊りを教わった。体型も霧と似ていることから、客は変わったことがわからなかったようだ。靄は京都に戻ったときは隅屋の手伝いもした。
すべてがうまくおさまり、暮れに霧は子供を産むため明とともに京都に戻った。靄も一時もどり、霧の出産の手伝いをすることになった。
年も明け、京都の隅屋では、娘の出産の準備に追われた。東京から明と明のお母さんが来た。弘と菊池のだんなは留守番だ。
はちきれんほどふくらんだお腹をかかえた霞が、
「明日生まれるわ」と笑顔をみせた。透明人間は子供が出てくる日がわかるといわれている。さっそく母親は大量の牛乳を注文した。
次の朝、車で配達してきた牛乳屋のお兄ちゃんは何に使うのですかと、タンクにはいったミルクをおいていった。
透美は薬缶に牛乳を入れ沸かした。残った牛乳は大きな桶に入れた。
「明さんとお父さんは向こうで待っててね」
透美が声をかける。二人の妹が布団に寝かされている霧の足をさすっている。はだかで寝ている霞は透明で眼が枕の上に浮いている。
沸いた牛乳を桶に注ぎ、かき混ぜてミルクを温めた。
布団に寝かされた霞が「あ、生まれるわよ」と声を上げた。
「でてきた」二人の妹が言った。生まれたばかりの赤子の頭は透き通っているが輪郭が見える。
透明人間には陣痛がないようだ。
するりと出て来た。
上半身を起こした霞が自ら赤子をだきあげた。
赤子はおぎゃあと泣くと、透美の手の上で輪郭が薄くなっていく。
透美が赤子を受け取って、桶の牛乳の中に入れた。赤ん坊の形が白い牛乳の中でくっきりと分かる。赤子は手をばたばたさせた。
「透明人間はミルクが産湯なのね」
二人の妹はなるほどといった顔だ。
「お前たちの時の産湯は牛乳じゃなくて、ヤギさんの乳だったのよ」
母親はそういいながら、赤ちゃんを見てぎょっとした。
「みてごらん」
母親は二人の姉に赤ちゃんの顔を指さした。
「明さんと、お父さんを呼びなさい」
靄が大きな声で二人を呼んだ。
「どうしたの」
寝ている霞が心配そうに上半身をおこした。
「すごいのよ、この子」
男たちが部屋に入ってきた。
「男かい、女かい」
ミルクの中で赤ん坊の小さな透明なちんちんが飛び出している。
「男の子よ、それより、見てごらんなさい」
透美がミルクの中から赤ん坊をだきあげて、霞のところにつれていった。ミルクが畳に垂れている。赤ん坊は手を強くにぎって元気に泣いている。
「なあに」
霞が赤ん坊を見た。
「あ、眼がない」
透美が首を横に振った。
「あるわよ、眼も透明なのよ、この子、本当の透明人間になったのよ」
みんなはっとした。
霞が赤子をタオルでぬぐった。霞の腕の中の赤子は見えなくなった。ただ。おぎゃあ、おぎゃあという泣き声が聞こえた。霞が胸に透明の赤子をあてがうと、霞には赤子が乳首を吸うのが感じられた。赤子の口の中にミルクが溜まり、胃の中に流れていく。
みんな黙って、その様子をいつまでも見ていた。
透明人間の新たな世紀がはじまった一瞬である。
眼 - 透明人間譚
私家版透明人間小説集「透人譚、2020、276p、一粒書房」所収
絵:著者


