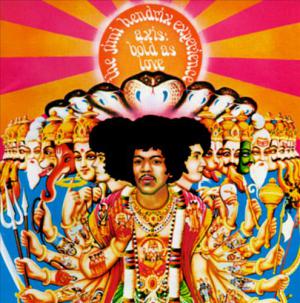夜明けの痴情
豊旗雲がうすく蜜柑色に焼けている。古都の夕暮は底冷えしていた。寝しずまったように軒が、しん、としていた、只、遠くで怪しい鼓の音が聞こえてくるのに、不思議である。繁盛している店もあるのに、 店の外は静寂している。一軒、酒屋に幾重の翳が揺らいでいるだけである。
雪のような小雨が降ってきた。路上に立ち往生した生徒の諸君と上沢先生は、桑淵先生が戻ってこないので、おおかた大便をしているのだろうとかんぐって交々笑いあった。上沢先生などは鼻に手をおさえてくすくす笑う。何人かの生徒が可愛らしい上沢先生の顔を観つけた。笑い声の密集が空気となり、路端に反響して、ぼんぼりに空蝉が浮いているかのように観えた。 みみたぶが痛くなった。指で挟むと神経が機能していない。瞼の感覚が失せた。帽子から洩れるしずくが唇を垂れていった。蒲崎高校伝統の三年生最後の冬の修学旅行は、第一夜の贅沢の代わり、紀行作文と云うものを五十枚しあげるために、第三夜までもつれこむのが常だった。でなければ資材がないのである。歴代の生徒はいつもこの五十枚に苦闘した。しかも不合格があると云うから猶更高校生には厳しい。その第一夜にカニめしを食べることができると云うことは、生徒たちにとってはたいへんな慶びであり、紀行文への恰好の資材の一つになるのであった。この紀行の面白いのは、第二夜になると高級旅館を離れ、場末の古い民宿に泊まることであろう。第三夜は野宿となっているから、愈々過酷だ。
集団がせつなわなわなして、街路の静寂が破裂した。凍えた風がサッととおりぬけたのだ。みな背筋がスウッと抜けるような感じがした。それに髪をなびかせる岩山美和子のうなじの美しいのを、東悟はしっかり観ていた。美和子の腹がぐるぐると鳴った。彼女の腹の虫には意想外で、みな笑いだした。また笑いの空気が生れた。空気は蒸気に変わって消散した。路地の曲がり角から桑淵が顔をだして、ひょこひょこと歩いてくる。
「先生トイレ行っとって。なっかなか見つかれへんよて。おでん屋さんに貸してもろて、しっかり『大』しとってんで。」
「先生、そないなことどうでもよろしわ、うちら。」おてんばな米田光子が云った。
「あたしら相当おなかすいとるんですわ。」今度は美和子が云った。 用足しの話なんてどうでもいいから、寒いし、はやく帰ろうよ、とみな口々に云った。
気圧されて「そやな。そしまひょ。」
と桑淵は先導した。花壇に座ってずっと金閣のスケッチをしていた英知の茂本が立ち上がって、「先生、旅館でええ嫁はん見つかりますか。」
とおどけ調子に云うもので、たぶんあの若女将のことを云っているのだと桑淵にはわかり、照れくさそうに笑った。それを観ているみながもっと笑った。旅館へ帰ると、うすぼんやりとした幾つもの燈の光が、この京の町を彩っていて 、見事なものにしあがっている。彼ら一同は『栄華』と云う高級旅館に泊まっていた。桑淵先生は若女将はおらぬかと仲居に訊ねている。
仲居は
「呼んでおります。」と云った。
「京都はほんまええとこですね。」
すると仲居は可愛らしく笑って「そうですねえ。」とはんなりに云った。
若女将がやや小走りで桑淵と上沢もとへやってくると、
「いやあ、えらい寒かったでしょうに。さあおあがりになって。」
若女将は桑淵のマフラーについた雪とも雨ともつかぬしずくを払い落とした。冷凍されたような手で桑淵の両の頬に触れ、
「もう生徒さんがたがお待ちでは。」
と色艶のある目で観つめた。桑淵はまんざらでもなく顔を紅潮させた。桑淵先生が若女将のとりこになっているあいだ、みなすっかり靴をスリッパにはきかえて、夕飯をもてなしてくれる大広間『雅 澱』に忍びこんでいた。桑淵先生はまだ若女将の美貌に陶酔している。大広間から歓声が上がった。生徒はそれぞれ適当に座布団につき、膳をまえにして生唾をんでいる。 そこに桑淵と上沢が入ってきて、「えらい おそうなりました。まだ七時やで。」と云うのに誰も反応を示さない。上沢が「サッ 始めよか。」と云うと生徒たちは飛びつくようにカニめしに食らいついた。白い息と湯気が混じりあい、温い部屋の空気が襖の外へ洩れでそうであった。
*
大理石で敷かれた湯殿に浸かるとき、男子生徒においては、男陰を隠すか隠さないか、大問題で、区分がはっきりしていた。 森新太郎は男陰を観せびらかしたいのか、タオルで隠さないはがりか半勃起さえさせている。芝孝太郎もなかなかのものをもっていて、やはり隠していない。東悟は仮性包茎なのだけれど、夜空を観わたせば星がこぼれおちそうな絶景の露天風呂であり、そんなことはどうでもよく思え、羞恥心を感じなくなったので、自然にタオルをとって男陰をあらわにした。ほかの生徒も東悟が曝すなら、オレもボクもと云っては男陰を観せあった。東悟はなぜ自分が切欠になったのか、ふしぎでしかたなかった。男子生徒のほとんどが包茎であった。
女性徒はほとんど隠すのが常識のようで、 レズビアンの本田咲子以外はきっちり裸体をタオルで覆っていた。
みな枕をおとすとそのままハタと布団に倒れこんだ。森新太郎は風呂場で観るかぎり最大のものをぶらさげていたので、それを誇らしく思ってか、持参したポルノ雑誌をひろげ、自慰を始めた。その物は筋立って隆々としていた。ぴかぴかのうつくしいペニスは、風呂場のときより輝いていた。 誰もすぐ寝つかなかった。トランプをしたり、携帯ゲームをしたり、菓子を食べたり、おのおのすることがあった。スケッチをしたり、もう紀行文を書いている生徒もいた。深夜一時には電灯は消され、暗闇となった。しかたなく臥した生徒は目をつむって十分もたたないうちに眠りに就いた。
*
夜明け頃、尿意で目覚めた東悟は暗がりのなか森新太郎のパンツを観た。その残酷に投げ捨てられた下着に東悟は異様な昂奮を感じた。すやすやと眠る新太郎の顔を確認すると、パンツをつかみあげ、においをかいだ。やはり尿のにおいがした。しかしその行為はあまりにもエロチックに思われた。
すると誰かが寝返る音がした。美和子の双子の弟新司である。「なにしてん。」新司は云いはなった。もはや言い訳する術はなかった。
東悟はかばんから財布をぬきだした。
「いくらやねん。」
新司は毛頭そんな気がなかったらしく、ぽかんとしている。
「おれそんなんいらんで。」
新司が云った。
「誰にも云わんといてくれるか。お姉ちゃんにも新太郎にも。」
新司は笑ってうなずいた。東悟は、はんぶん安心するとともに自分の醜態を思い出して鳥肌をたてた。
*
積雪のあさだった。民宿へ向かうバスでしめった窓に微睡む東悟がいた。まえの席には森新太郎がいる。ほんの悪ふざけだし、新司が云わなければ明るみになることのない痴情だった。
新司のほうをみやると、楽しそうに友達と話している。美和子も女生徒のみならず男子生徒にかこまれ、会話が弾んでいる。窓の外には壮麗な寺院が観える。仏像が君臨し、東悟を睨みつけている。
自分の変質的な性の萌芽に戸惑いながら、揺れるバスの中いつまでもいつまでも森新太郎のパンツの記憶を忘れられないでいた。そしてあの月光に輝く陰茎も。
バスはトンネルに入った。
夜明けの痴情