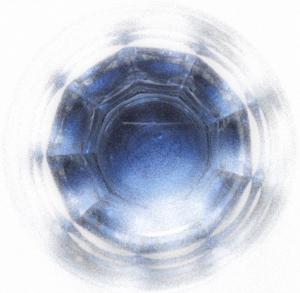奥の間
幼い頃、田舎の祖父の家は迷宮だった。
祖父の生家ということは、100年近く建っているのかもしれない。とても古いスタイルの建築で、複雑な構造になっている。私にはそもそも表玄関と勝手口のある家というのが珍しかったし、3度も角を曲がれば方角がわからなくなるほどの方向音痴なので、大きくなるまで、食堂と風呂とトイレの位置関係もよくわからなかった。
4歳の夏だったと思う。家族で帰省したある昼下がり、私はその全貌のよくわからない家を一人で探検していた。居間を出て中庭を囲う廊下をコの字に渡っていくと、怪しげな木戸に突き当たる。誘われるように、その蔵へと続く廊下に足を踏み入れると、不意に脇の障子戸が開き、中から誰かに腕を掴まれた。
「これやる。お食べ」
曾孫が通るのを聞きつけたのだろうか。囁くような声で、早口に、ひいばあさんが言った。しわくちゃの冷たい手には、それまで見たこともなかったお菓子――鈴カステラが、無造作に3つ4つ握られていた。
「他にもたくさんあってな」
ひいばあさんのお部屋がそこにある。それ以前に、そこに住んでおられることすら知らなかったので、びっくりしている私をよそに、ひいばあさんは、マーブルチョコなどのお菓子の入った袋をガサガサと見せた。なぜって、なぜだろう、ひいばあさんは皆で食事をする時にも姿を現さなかった。通りすがりに捕まったその瞬間まで、家の中でまったくその存在をにおわせなかったのである。
まだ呆然としているところへ、アッと息を呑むような気配があり、今度は祖母の鋭い声が上から降ってきた。
「こんなご飯を食べない子に、そんな甘いものを与えないでくださいっ!」
祖母は孫を姑から取り返そうとするみたいに、私の前に割り入ってひいばあさんの手を遮った。物心ついて神経質になり、病気でもないのに食事が喉を通らないというのを、はじめて経験していた夏だった。ひいばあさんはムッとしたように、
「ええじゃろうが」
とぶつぶつ言ったが、私はもう祖母に手を引かれて、居間の方へと連れられて行った。砂糖のまぶされた鈴カステラはいかにも魅力的で、食べたかったなぁ、と思いながら。
祖母とひいばあさんは、いわゆる昔の「嫁姑」で、控えめに言って犬猿の仲だった。ということを、知った出来事でもあった。私は祖母にとってはじめての女孫で、「内孫」で、溺愛されていたから、祖母は憎き姑に可愛い孫が取られる(お菓子で買収される)と思って、虫唾が走ったのかもしれない。あそこへ行っては駄目、と叱られた。ひいおばあちゃんはどうして皆と一緒にご飯を食べないの? と尋ねたが、答えてもらえなかった気がする。
いつからか、ひいばあさんは近くの病院で暮らすようになった。祖母が大病を繰り返したこともあり、本人か祖父が判断したらしい。大きくなって祖父とお見舞いに行った時にも、
「よう来ちゃったなぁ」
と喜びながら、やっぱり甘いお菓子をあれこれくれようとした。あの奥のお部屋はといえば、色々な大物が雑然と入れられて物置と化していた。こっそり様子を見に行って、何が置かれているのかもわからない部屋の前でしばらく立ち尽くしたものである。
ひいばあさんは、嫁である祖母に対して随分酷かったのだと祖母や親世代から聞かされているが、曾孫の目には、語られるほど残酷な人には見えなかった。迷路のような家の奥に、家の秘密がひっそりと息を潜めていることに気づいてしまった、そんな思い出として、あの夏の日の出来事は原色を留めている。
奥の間