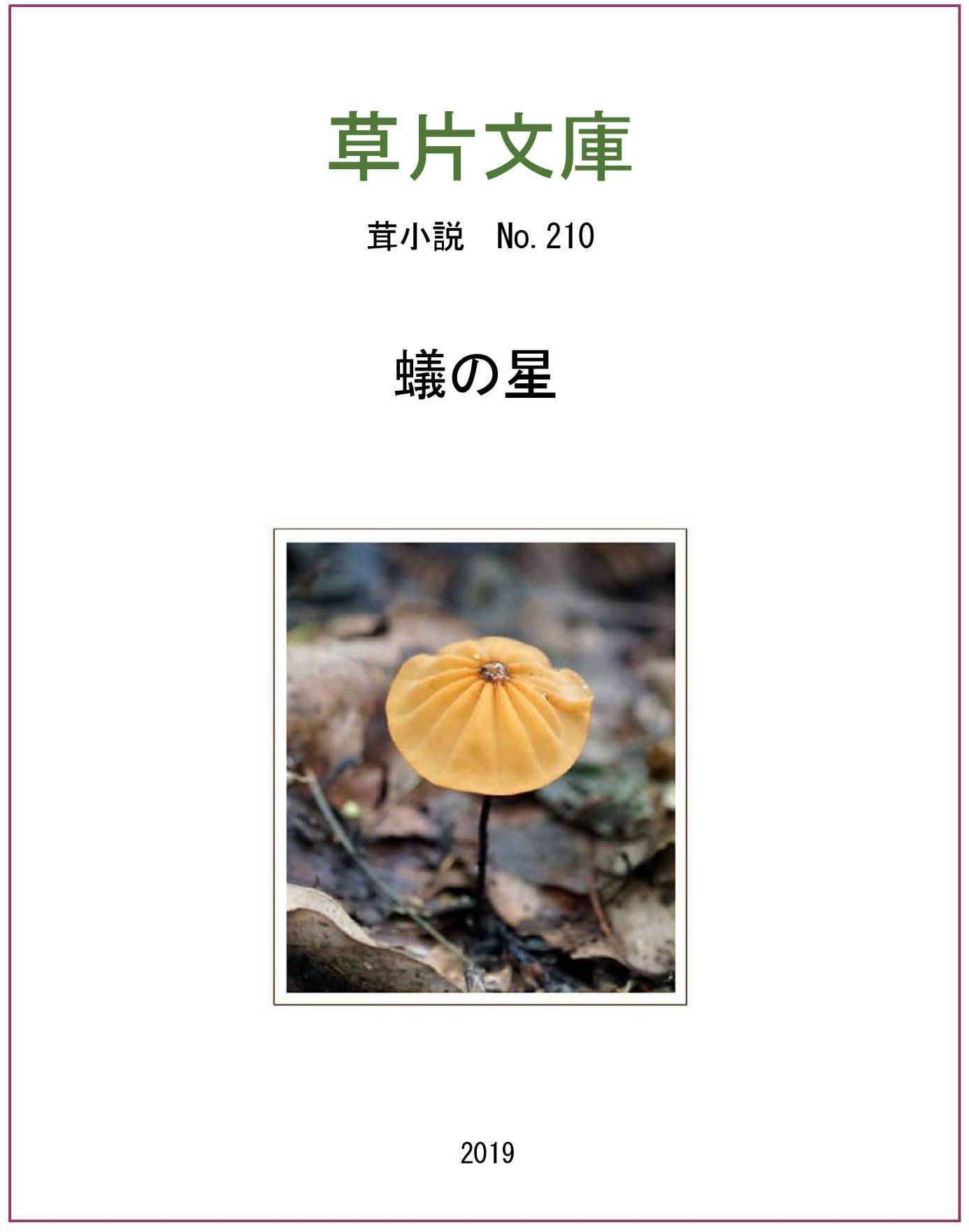
蟻の星
我が家の軒下に昔から蟻地獄がある。砂の具合が調度よいとみえて、その時期になるといくつも作られる。ところが蟻が捕まっているのをみたことがない。大きめの黒い蟻が足早に動いているのだが、皆うまくよけて通ってしまう。蟻地獄を作った薄羽蜻蛉の幼虫は中で干からびていると思われるが、時期が来れば必ずいくつかできている。なにを食べているのだろうと不思議に思っていたら、小さい赤っぽい蟻が蟻地獄に捕まってもがいていた。蟻もいろいろな種類があるが、よく砂糖にたかっている本当に小さい蟻ん子である。まあ食べられた方はかわいそうだが仕方がない。
そう思って見ていたら、どこからか緑に輝く大きな蟻が現われて、今にも砂の中に引きずり込まれる赤い蟻の触覚を咥えた。緑の蟻は二本足でぐっと立ち上がると、赤い小さな蟻を持ち上げた。
こりゃすごいと見入っていると、砂の中から赤い蟻にかみついている薄羽蜻蛉の幼虫も一緒につりあげられた。緑色の蟻は前足で蜻蛉の幼虫を払い落とし、さらに踏みつぶした。驚いた。
助かった赤い小さな蟻は緑色の蟻の前で頭を垂れている。まさかお礼を言っているわけではなかろうに。
そんな場面を見た次の日、軒下の蟻地獄はすべてなくなって、まっ平になっていた。あの緑色の蟻に退治されてしまったのだろう。他の蟻たちは安心して生活ができるようになったに違いない。
そのときは自然の厳しさを見た気になって驚いたのだが、すぐに蟻によって消滅させられた蟻地獄のことは忘れてしまった。
今年も暑い夏がやってきた。夏の間は信州など涼しいところの貸し別荘で仕事をする。普段は両親の残した蟻地獄があった郊外の一軒家で一人暮らしをしている。IT系の仕事をしているのでほとんど会社に行かず、ソフトの開発を自宅で行っているのだが、夏の暑さはたまらない。別荘でもどこででもできる。今年も信州と山梨の境にある八ヶ岳の麓の別荘を借りた。
別荘にいる間に会社の同僚や大学のサークルの友達などが泊まりにきて結構楽しく過ごし、仕事もはかどった。九月になると、週に一、二度は会社に行くことになるので、秋の八ヶ岳も楽しみたいのだが、家に帰ることにした。
家にもどって、数日たったときである。ふと軒下に目がいった。蟻地獄があったところの砂地がずいぶん広くなっている。軒下の小石の混じったごつごつしたところがきれいな砂でおおわれ、まるで小さな砂漠のようだ。夏の間に何者かがきれいにしたのだ。台風13号の風でさらされたのだろうか。まさかあの蟻がしたわけではあるまい、そんな思いで見ていたら、なんと緑色の蟻が数匹どこからともなくあらわれ、砂地の上を歩きだした。この蟻が巣穴を作って砂を外にかきだしたためか。
蟻の名前でも調べてみるかと考え部屋に戻った。
虫に興味があったわけではないので、蟻の名を調べるのは初めてである。
ずいぶん種類があるものだ。大きさもまちまち。よく見かける普通の黒い蟻は黒蟻、大きいのは山蟻だろう。そいつらはこのあたりでも見かけるが信州の別荘の周りにずいぶんいた。砂糖にたかる赤い小さい奴は姫蟻の仲間のようだ。こいつが蟻地獄にとっつかまっていたやつだ。最近は船に乗って毒をもった蟻まで上陸している。しかし緑色の蟻の名前がわからない。熱帯地方には様々な蟻がいるようだ。オーストラリアに草緑色の蟻がいて、名前もそのままグリーンアントとなっている。しかしわが家の緑色の蟻は濃い緑色で光っている。違いそうだ。みていくと茸を栽培する蟻までいる。すごいものだ。虫に頓着していなかった自分が虫を調べるなどとは思っていなかったが、新たな発見だ。蟻地獄のおかげである。
夏休みもあけソフトの開発にも拍車がかかった。
また台風がきた。今度はかなり大きそうだ。しかし電車が止まっても通信システムさえ遮断されなければ仕事は続けた。ただ一戸建てのやっかいなことは、台風となるととりあえずは家の周りをチェックしなければならない。飛ばされそうなものが外にでてないか、雨樋の状態は大丈夫かなどを気遣う。いつもそれなりの会社にメンテナンスしてもらっている。庭に置いてあるものもなく、さっぱりしているのだが、それでも小雨のうちに家の周りを見て回った。
蟻地獄のなくなった砂地はきれいなままである。相変わらず緑に輝く蟻が歩いている。何をしているのだろう。
蟻を見るためにしゃがんだ。蟻は元気よく触覚を動かして砂の上を歩き回っている。時々止まって口で砂粒を咥えてどかしている。目を近づけて見ると赤い粒が見える。砂地をもう一度見渡すと、ちいちゃな赤い点々がある。緑の蟻が砂粒を動かすと赤い点が増える。なんだろう。
雨が強くなってきた。幸いその軒下に雨がかからない。そういうところだから蟻地獄が作られたのだろう。家の中にもどった。
今日の夜半、このあたりが台風の目に入る。おとなしく自宅で仕事をして、夜はテレビ映画でも見て早寝をしよう。
台風は予定通りのコースでやってきた。昼近くになると家の中も蒸し暑くエアコンをかけた。庭木の揺れ方が激しくなってくる。
テレビのニュースでは小さな河川が氾濫しているようである。夕方になるとサイレンが聞こえてきた、近くの川に警報がでたようだ。わが家は丘の上だから氾濫の心配はないが、がけ崩れは心配だ。台風情報を見ながらウイスキーを飲んだ。
夜中の0時になると急に静かになった。予定通りこのあたりが台風の目に入ったようだ。急に静かになったら眠気がさしてきてベッドに入った。
次の朝、台風一過のすばらしい秋晴れだった。今日は9月9日である。寺がくれたカレンダーには菊の節句とある。
庭にでると、空は青く晴れ渡り薄い雲がたななびいている。木々は雨に洗われて気持ちよさそうである。
庭の周りを歩いて驚いた。軒下の砂地のところに小さな茸がびっしり生えている。高さ五センチほどで、緑色の細い柄の先に直径一センチほどのピンクの傘がのっている。上から見ると、茸が丸く敷き詰められている。それが砂場に二つある。茸の下を濃い緑色の蟻が何匹も歩いている。
昔から秋になると、庭に茸が生えた。普通の子供なみに茸に興味を持っていたが、名前を知ろうとは思ったことがない。両親は茸を食べるのが好きで、庭に生えた真っ赤な卵茸を喜んでオムレツに入れていたのを覚えている。
このピンクのランプシェードのような傘を持つ茸は庭で初めてみる。スマホで上や脇から何枚も写真を撮った。
PC上で拡大してみたらずいぶんきれいなかわいい茸である。
上から撮った一枚を見ると、丸い田圃の稲のように規則正しく列をして生えていた。
茸の名前も検索した。これは一発で出てきた。花落葉茸だ。黄色や真っ赤もあるようだ。ただどの図鑑を見ても柄のところは黒っぽい、緑色のものはない。ちょっと珍しいかもしれない。
撮った写真を会社の同僚に送った。都会暮らしをしている奴らばかりだから驚くだろうと思ったわけだ。やっぱり「きれいだ」とか「かわいい」とか感想をよこした。社長の秘書なんかは「どこか熱帯の島にでもいるのですか」と勘違いをしている。「種まいたのか」と茸のことをまるで知らない奴もいた。
しばらく連絡していない友達にも送った。一人がこんなメイルをかえした。
「作り物だろう、茸がそんなに正確に並ぶはずがない」
それを見たときあいつは何にも知らないんだなと思ったが、よく考えると、そいつが正しいことに気がついた。茸が前にならえをするはずはない。
蟻が胞子をきれいに並べて埋めたのだろうか。この考えに至ったときはちょっと得意になって、そのことを、作りものじゃないかと書いてきた友達にメイルした。
「種と胞子はまったく違うよ、種はそこから葉をだすが、胞子から茸はでないよ」と返事がきた。さらに「胞子から菌糸になり、そこから茸がでるんだ、土の中に網目のように発達しそれが固まって盛り上がり茸になるんだ、だから整列するなどありえないんだ」
自分は茸に根っこがあると思っていた。恥ずかしい限りだ。その友人には、
「茸のことを知らないことがわかったよ、感謝。だけどあの写真は本当に軒下の砂地に生えたものだよ」と書いた。
すると「そりゃすごいね」とメイルがきて終わりになった。
朝食をすますと、書斎で仕事をするため会社にアクセスして在宅勤務にチェックし、ソフトの開発を始めた。私がやっているのは、新しい会社がどのように延びるか推測するもので、資本金、売っているもの、会社の人数と社長の性格、社員の質、様々な情報を打ち込み、社会情勢、世界の動向を入れると、1年後から毎年会社がどのようになっていくか推測してくれるものである。3年後倒産とでたら、最初に入力した数字を変えて倒産しないようにやり直し、会社が発展する条件を探し出せばいいわけである。新しく商売を始める人には便利なもののはずである。さらにいろいろな商売、たとえばコーヒーショップ経営専門のソフトを作るなど、それぞれの領域で起業する人に便利なツールにするつもりである。
その日もそれに専念した。ただ、庭があるのはよいもので気分転換に時々庭にでる。外の空気をすい頭がすっきりする。軒下を見ると、花落葉茸が変わらずきれいに並んで生えている。
仕事は5時に切り上げた。在宅勤務は自由さがあるが自分で区切りをつけないと、仕事をやりすぎてしまう。場合によってはサボってしまう。
外は薄暗い。夕食は自分で作ることもあるが、駅の近くですますことが多い。駅のビルにはいろいろな食事どころがある。今日は外食にした。駅まで歩き、たまにいく店で生姜焼き定食を食べた。
家に戻ると軒下で緑色の光が点滅していた。何だろうと行ってみると、軒下の花落葉茸の二つの集団で、傘が緑色に光っている。ピンク色の傘だが光ると緑色だ。蛍の光に似ている。光る茸のことは聞いたことがあるが、点滅するのは聞いたことがない。ずいぶん綺麗だ。もっと暗くなるとよく目立つだろう
スマホをポケットからだして、光る茸の動画を撮った。上から見るとバラバラに光るので、まるでネオンサインのようだ。写真も撮った。
花落葉茸が夜になったら光ったと、作り物と言った友達にメイルに添付して送った。
そいつの反応には驚いた。動画もあると書いたからだろうが、それを送れといってきた。送るとすぐ見に行きたいと返事が来た。あいつがそれほど茸に興味を持っていたとは知らなかった。メイルをやり取りした上で、明日の午後にくることになってしまった。
その友人は高校の同級生で、数字にめっぽう強い男だった。大学は数学科に進み、数理論理学なる難しそうな学問を修め、遊びとして楽しんでいた暗号解読や暗号作成の専門家になってしまった。彼はいろいろな暗号作りに携わり、自分の暗号をいくつも考案して、それをセキュリティー会社などに利用権利を売る。セキュリティー会社がそれを使って、顧客のセキュリティー管理をおこなう。彼が作成した難解な暗号形式は必ずどこかの国が買い上げてくれ、その国にセキュリティー会社の支社ができて、そこで、その暗号形式をさらに発展させ暗号管理を行う。それはその国の中枢に入り込むことになり、会社とその開発や管理に関わった者はその国に命を供出したことになる。その暗号を生み出した者は売った時点で作ったものを忘れなければならず、また作者として名は残らない。いや誰が作ったのか知られると、その人間は暗号解読のためにさらわれる危険がある。そういうことで、作ったものはセキュリティー会社に売り、後は関与しないことにしているわけである。ただ高度なものだと、その暗号ソフト一本で一生暮らしていけるくらいのお金がはいるという。彼は一人で暗号を作り続けている。住まいが霞ヶ関なのも国の機密にも関与しているからだろう。
なぜ彼は光る茸に興味を持ったのだろう。彼の実家は同じ市内にあり、高校の時にはよく遊びに来たので我家の場所はよく知っている。
彼は大きなビデオ撮影器とやっぱり大きな機械を車に積んでやってきた。うちの駐車スペースは広く二台は楽における。
降りるとすぐに軒下の茸のところに行った。
「お、すごいな、昼間なのに光っているのがわかる、もう一つあるじゃないか」
彼は小さい茸の集団を指差した。
「そうなんだ、でもそっちは光っていないよ」
「なんだろうな、予備かな」予備とはどういう意味だろう。
「ずいぶん急いできたな、そんなに茸が好きだったっけ」
それを聞いて、笑いながら「生き物のことはからっきしだめだけど、茸はなぜか好きだよ」と車に戻り、機材を車から降ろした。
「すごい機械を持っていたな、整列した茸がそんなに珍しいかい」
「うん、光り方に規則性がありそうだ」
「どうしてわかった」
「送ってくれた動画をよく見たら同じパターンが何度か見られる、ただ光っているだけじゃない」
「暗号にでもなっているのかい」
冗談のつもりだった。しかし彼は、
「そうだよ、茸がシグナルを出している」
機材を肩に掛け軒下にもってきた。茸の前にブルーシートをひろげ、その上に機械類を並べた。ビデオカメラをセットし、配線が終わると、
「これで今夜中の茸の瞬きを記録できる」と私を見た。
「なにが撮れるんだ」
「こりゃ茸であって茸じゃない」
「なんだとんち問答だな」
「暗号を解読できりゃあ、はっきりする、この光り方は生命体じゃない、機械だ」
「見ただけでわかるのかい」
「一つの茸が光っている時間は一定だよ、腕時計を見てろ、俺がはいと言って、次にはいというまでの時間をはかってくれ」
時計を見た。彼がはいと言って次のはいまでの時間を計った。
「18秒だ」
「じゃあもう一度」
それを三回くりかえしたがいずれも18秒だった。
「撮影している映像を詳しく解析すると18秒の三桁したまで同調すると思うよ」
「何だろう、やっぱり作り物かな」
もしそうだったら大変である。誰かが埋めたことになる。
「いや本物の茸のようだが、栽培されている」
「それで規則正しく整列して生えているのか」
「この茸は俺もよく知ってるよ、花落葉茸だろう、かわいい茸だ、光るはずがない、改良され、刺激が行くと光るようになっているのだろう」
「誰が刺激しているんだ」
「わからない、ただ我々人間のことを無視している」
「どういうこと」
「花落葉茸を整列させ光るようにすると人は変に思うだろう、見つかってもかまわないと思ってそうさせたのだ、もしかすると人の存在を知らないんだ」
「俺にゃよくわからんな、ずーっとこれを見ているのか」
「いや、時々チェックすればいい」
「それじゃ中でいっぱいやるか」
「うん、あとは機械任せだ」
冷凍ピザを電子レンジに放り込み、ビールを開けた。
「仕事は順調そうだな」
彼には最近の私の仕事のことを話していない。
「会社の未来を予測するソフトを開発してるんだ、業種別のね、忙しくてね、嫁さんどころじゃないよ」
「俺も嫁さんには縁がないよ、そっちはあきらめた、でも一人で自由にやれてるから楽しいさ」
「実家にはご両親がいるの」
「いや妹が北海道にいるので、そっちの近くのマンションに移ってるよ、妹の子供の面倒を見ているようだ」
「霞ヶ関にいるのはどうしてだい、君の暗号開発の仕事もどこにいてもできるだろ」
「ああ、だけど地方で一人でやっているのが時々霞ヶ関に現れると、うさんくさいことをやっていると勘ぐられるが、いつも霞ヶ関に出入りしていれば逆に公官庁の一般の出入り業者だと思われるからいいよ、俺はコンピューターのメンテナンスの作業員と言うことになっている」
「Xファイルのような部署か」
「まあどうとでも推理してくれ」
「暗号を解くのは大変だろう」
「そりゃ簡単には行かないよ、それが暗号であることを見ぬかなければならない」
「俺でもできるかな」
「まずはいろいろな暗号の解説書を読んで、どのような種類があるか、頭の隅に置いておくこと、次にそれを見たとき、奇妙だと感じること、それが暗号の元になりうるか、規則性が感じられるか、動きがかちっと決まっているか。などとっさに感じる勘を持つことかな」
「うちの茸を見たときそれを感じたのか」
「最初に丸の中に並んでいる茸の写真を見た時、作り物かと思って暗号とは考えなかった、次に光る茸の動画を見てから可能性を感じて急いで来たってわけだ」
「だけどなぜわが家の軒下に茸を生やしたんだ」
「条件がよかったんだ、光が空から見える、軒下で砂地がよかったんだ」
「あそこは蟻地獄があったけど、いつの間にか平らになっていた」
「蟻地獄は始末されたな、あの砂の中になにがあるか、明日あたり掘ってみよう」
彼は一時間経ったからと言って、庭に機械の様子を見に行った。
それまでの映像を入れたSDを持って戻ってきた。それを自分のノートパソコンに入れた。
「手元用のパソコンだよ、これで映像を見ることができる、機械につないだコンピューターには暗合ではなく言語と結論がでていた」
「言葉って、どこの」
「それはわからない、きっと地球上ではないな、言葉は分からない人にとって、いうなれば暗合と同じ、日本語は他国の人にとっては暗号だよ、ただ言葉の場合には読まれないような変な仕組みはしていないからすぐ分かる」
確かにそうだが。パソコンの画面には茸を真上から撮った映像がでた。
「速度を十八倍にする。光が変わる時間だ」
茸の傘の光の像が一秒単位で変わる。上から見ているのでパターン模様になる。
「やっぱり二次元の暗号だな。言葉を発していることになる」
彼は楽しそうだ。
「誰がつくったのかが問題だな」
そういうと彼は真顔で「宇宙人しかいないね」と言った。
「宇宙人がそのあたりにいるっているのかい、近くの公園にでも隠れているのか」
「文字による通信装置をつくるとしたらどのくらいの大きさになる」
「スマホだったら手の平だ」
「いや空の上の方の相手に視覚だけで行うとしたらどうする」
「上空からだと大きな絵を書かなければならないな」
「アスカの地上絵だね、ということは、この茸の地上絵はこの茸よりかなり小さい人が作ったわけだ」
「なるほど小人か」
「その異星人は人の形をしていなくてもいいだろう」
彼がそういったので、私ははっとした。
「蟻か」
「これを見てごらん」
彼は別の映像を映した。
「茸の列を斜めから撮したものだよ」
茸の生えている周りを緑色の蟻がうろうろしている。
「緑の蟻が宇宙人かい、まさかな」
「おかしいか」
「いや、そういえば蟻地獄に落ちた姫蟻を助けていた」
「そうか、そりゃあ、地球の主人を蟻だと思って、助けたに違いない、人間の存在などわからなかったのだろう、それで地球の天敵である蟻地獄を全滅させたんだ」
彼の言うことは理にはかなっているが全くのSFである。信じろと言う方が無理である。
「明日の朝には外の暗号解読器が結論を出してくれるよ」
「それじゃ、飲んで、風呂はいって、ぐっすり寝てくれよ」
「明日は六時頃撮影を終わりにする、ちょっと早起きですまんな」
彼は十一時に寝る前に機械類を見に行って「茸は変わりなく光ってる」
そう言うと寝に行った。
翌朝彼は五時には起きたようだ。私が六時前に庭にでたら彼は茸を指さした。
「茸が少し萎れている、光っていない、この茸は2日ほどで枯れるだろう、もう終わりだな、機械を家の中に入れさせてもらうよ」
朝早いはずの蟻の姿もない。
「手伝おうか」
「それじゃ、このパソコン持ってくるかな」
彼は要領よくラインをはずしパソコンを私に渡した。かなり重量のあるものである」
「そのパソコンは二百万するよ、もちろん中に入っている僕のソフトを入れたら二千万だ」
大変なものだ。
「そっちのはなに」
ビデオはパソコンに、パソコンは黒い石油缶ほどの機械につながっている。
「これは暗号解読器、僕が作ったものだよ、会社は一億で売り出しているが、生産が間に合わないほどだそうだ」
「恐ろしい値段だ」
「戦闘機を一台アメリカから買うと何十億だよ、それよりも数段安い買い物さ、撃墜されないからな、ソフトを新しくしたら五千万でヴァージョンアップできる」
「どのくらいでバージョンが変わるの」
細かいのは不定期で、それは出張費ほどでいいんだが、二年に一度、バージョンを変える」
「すごいね」
家の中にもどると、客間に機器をセットし直した。
「これからすぐに暗号解読をかける、すでに自動で行われているので、ちょっとの時間で結論がでる」
彼がキーを押すと、暗号解読器がうなりはじめ、すぐに「解読可、難易度1とでた。
「文字数は少ないようだ、ということは、解読は難しくないよ」
すぐに解読された文字が日本語で出てきた。
それはこうだった。
「偵察艇の動力修理が終わった、発光器は直らない、だがこの星の住人が茸を教えてくれたので通信用に光るように改良した、つかえる、この連絡をとらえたら収納にこられたし」
「これは何だい」私にはわからなかった。
「解読器が言うとおりだとすると、もうじき母船がくる」
「なに言ってるんだ」
「庭に宇宙船が降りてくるぞ、庭に行く、スコップあるか」
彼について庭にでて、小屋からだしてスコップを渡した。
「どうするんだ」
「砂の中のものを掘り出すんだ」
「だって偵察艇だろう、そんなことをすると、彼らが帰れなくならないか」
「帰らないでほしい、話がしたい」
彼はスコップを茸の一つの集団の根本に差し入れすくい上げた。
スコップの上に丸く生えている茸のすべてがのった。
彼は茸の根本の土を指で払った。土がどかされると死んだたくさんの蟻が規則正しく丸く集まっていた、頭から花落ち葉茸がでている。
彼は目を丸くした。
「冬虫夏草、蟻茸か」
「なにそれ」
「蟻に寄生して茸をはやす菌類だ、寄生された蟻が丸く集まってそこからこの茸が生えたんだ」
「花落葉茸は冬虫夏草なのか」
「いや違う、新種だ、この下に偵察艇があると思っていた、もう一つのほうにあるかも知れない」
彼はもう一つの茸の集まりのところにいってスコップを差し込もうとした。
そのとき、稲光がして、雷鳴がごろごろと轟き、青空に黒い雲が湧いた。その中からワゴン車ほどの、緑に輝くワイン樽のようなものが庭に降りてきた。
「宇宙艇だ」
彼が叫ぶと同時に、掘ろうとしていた茸の集団がはじけて、砂煙が上がり、中から降りてきたものとよく似た魔法瓶ほどの樽状物体が飛び出した。そいつはいったん宙に停止した。
「こっちにあったんだ、これが偵察艇だ」
そういったと思ったら、彼は手を伸ばし、飛びかかってラグビーボールのようにつかんだ。そういえば彼はラグビーもやっていた。
それでも偵察艇はひゅんと音を残して大きな樽めがけて飛んでいく。
彼は手を離さなかった。つかまったままだ。庭に浮いている宇宙艇の脇に入り口が開くと、彼も一緒に母船の中に吸い込まれた。
入り口が閉まると、ぴょと言う音ともに樽状の宇宙艇は消えていた。後にはハッカの匂いが残っている。黒い雲も消えまた青空が一面に広がった。いなくなった。
蟻から比べたら巨大な彼は樽型宇宙船の中でどうなるんだ。
砂地を見た。彼の残したスコップの上には枯れた茸が残っていた。
私はどうしたらいいかわからなかったが、大きな空き瓶を持ってきて、枯れた茸の生えている蟻をすべて集め、入れると蓋を閉めた。
空を見上げたがなにもない。あいつが振り落とされて落ちてくるのではないかと器具をした。しばらく見つめていたがなにもおこらない。部屋にもどった。
高価な機材が客間に残っている。車も駐車場にある。どこに連絡をしたらいいのか途方に暮れた。警察に行って根掘り葉掘り聞かれ、宇宙船にさらわれたと言ったら、病院に連れて行かれるだろう。
この茸蟻が証明してくれるだろうか。茸の生えた蟻の入った瓶は大事にとっておかなければならない。よく見ると緑色できれいな蟻だ。目が大きくて真っ赤だ。このままおいておくと腐ってしまうかもしれない。後で写真を撮ろう、とりあえず冷蔵庫の隅に入れておくことをした。
あわててもしょうがない、コーヒーをいれた。
彼の機材をどうしたらいい。
我が家で考えていてもしょうがない。彼が戻る可能性があるところを考えなければ。機材や車は黙ってしばらくおいとくのがいい。
彼の両親を探して、連絡をすべきだろうか。
車のエンジンの音がした。うちの駐車場の方だ。あわてて玄関から飛び出した。すると彼の車が立ち去るところだった、でて追いかけると広い道路に曲がっていく。誰が運転しているんだ。彼はキーをつけたままだったのだろうか。いや確か降りたときエンジンを切ってキーを抜き取っていた。
彼は行動を見張られていたのだろうか。
書斎に行って自分のパソコンを開いた。彼のメイルアドレスはGメイルで一般に使われているアドレスだ。彼のパソコンを開くと何かわかるかもしれない。
客間に行ってまた驚いた。彼が持ってきたもの一切合切がなくなっている。車は誰かが持って行ってしまうし、高価な機材も持って行かれた。これで彼がここにいた証
拠が全くなくなってしまった。誰の仕業なのか。本当にXファイルなみのできごとだ。ああいった組織が彼を監視していたのか。などと考えてしまう。
それから一週間、仕事は何とかやりこなしていたが、かなりのストレスである。この出来事を誰か話すことのできる人がいれば。
一月たつと、何とか気持ちも落ち着き、同僚たちとも一時彼のことを忘れて話をすることができるようになった。
一年経った。軒下には新たに蟻地獄ができはじめた。黒蟻や赤蟻は歩いているが緑色の蟻はいない。たまに彼のアドレスにメイルを送っているが帰ってこない。
高校の同窓会があったので行ったが、彼を知っている者はだれもいなかったし、そればかりか、北海道の両親の住んでいる住所に同窓会通知がいってるそうだが、両親からは何の連絡もないということだった。
彼が連れ去られて五年が経つ、一年前に十年下の女性と結婚した。仕事も落ち着き、収入も安定した頃、電車の中で知りあった娘だ。文学好きのおとなしい女性で、いつか自分の小説を本にしたいと夢見ているという。夢を叶えてあげると言ったら、じゃ奥さんになると売り込まれた。そういうことに縁のない生活だったのでちょっと有頂天になった。
家事もよくやって明るいし、仕事のじゃまにならない。ともかくうまく行っている。
結婚して一週間ほど経った時、冷蔵庫に入っている茸の蟻を見つけ、何なのこれと聞いてきた。それで、軒下の砂地に生えた茸で珍しい茸だからとってあると答えた。
「冬虫夏草ね、私始めてみる、珍しいものが生えるのね」と、嬉しそうだった。
「これだけは冷蔵庫この隅に入れておいてくれるかな」
そう頼むと、うなずいて、「いつかこの茸も生えるかもしれないわね、きれいな蟻」と冷蔵庫に戻した。その後、彼女は茸に興味を持ち、庭を歩き回って茸を見つけるといちいち名前を調べていた。
9月に入り9日の結婚記念日の日である。居間に共通のパソコンがおいてある。書斎においてあるのは私の仕事だけに使う会社のパソコンで、家内は別に創作に使うパソコンを持っている。
朝、家内が共通のパソコンを開いた。
「今日は夜どこかで食事しよう」
「いいよ、なにがいい」
「イタリアン、レストラン探すわ」
彼女が立ち上がった画面をみて素っ頓狂な声を上げた。
「なにこれ、ヤフーの新しい広告なの、あの蟻がでている」
見ると確かに冷蔵庫に入れてある蟻が画面いっぱいにでている。カメラが引くと、人間の顔が現れた。「やー」
こちらに向かって手を挙げている。
「元気かー」と叫んでいる。
5年まえ宇宙船にさらわれた友人である。あわててキーをたたいた。
「どこにいる」
「八億光年離れた星だ」
「何でそんな遠くからなのに、すぐに返事がくるんだ」
「全く地球とは違う物理法則をこの星で教わった、その原理を使うと物の移動も同時限に行える」
「それで今なにしている」
「音声言語教育だ、この蟻に似ている人たちの会話は光だ。複眼の一つ一つが光り受容器で、また発光器だ、光の点滅でコミュニケーションをおこなう」
「だから茸が二ヶ所に集団で生えたのか」
「そうだよ、なあ、隣にいるきれいな女性は誰だい」
「あ、去年結婚した、家内だ」
「そりゃあ、おめでとう」
「今日が結婚記念日なんだ」
「おーますますおめでとう」
彼の隣にいる蟻が触覚を振った。
「これが俺の結婚相手だ」
私も家内も声が出そうになるのをぐっとこらえた。
小さな蟻が映った。
「俺の子供だ」
大写しになると、蟻の顔をしているが、六本の足の先に五本指があった。子供が茸を持っている。
「この星は蟻族と茸しかいなくてな、茸は食料だし、あらゆることに用いている」
「ところで連絡嬉しかった、ずーっと気になっていたんだ、このことを誰に伝えようか、妹さんかご両親」
「誰にも知らせなくていい、総理府の中のある部局はこのことを知っている」
「ああ、あのあと、君の車や機材が盗まれたのは、そのせいか」
「そうだよ、あいつらがやった」
「それで何で俺に連絡くれたんだ」
「目的は二つある」
「なに」
「まず、頭に茸をはやして死んだ蟻はどうした」
「すべて集めて瓶に入れて冷蔵庫に入れてある、そのままだ」
「それはうれしい、これで友好条約が結べる」
「なんだい」
「あの蟻たちは死ぬ覚悟で花落ち葉茸の胞子を飲み込み、茸をはやし連絡手段になったんだ。こちらの星では英雄なんだ、亡骸をぜひ星に戻したいと言うことで連絡したんだ、一人でもいいと思っていたんだが、全員あるとなるとこっちの国民は大喜びだがな。
二つ目はこの星のことをフィクションで紹介したい、下地を作ってからでないと、地球人はパニックになる、地球の人間には虫が嫌いなのがいるからね、その小説が広まってくれると平和条約が結びやすくなる」
一緒に見ていた家内の顔が輝いた。
「書いてみたい」
「お、奥さん文章を書くんだ、総理府に推挙しておくよ」
「ところで、五年前、君が宇宙船で行っちまったことを、総理府ではどうしてすぐに知ったんだ」
「俺の体にマイクロチップがはいっているんだよ、国の飼い猫のようなもの、俺が地球からいなくなったから、いなくなった場所、君の家に行って片付けたわけさ、国もあの茸の点滅ビデオを見ているから、少しわかってるだろう、これから、そっちに連絡する」
「蟻のご遺体はどうする」
「あした内にいるのなら、午前中にいく」
「いるよ、会社は休む」
「ところで、あの樽の形をした宇宙船は人間には小さかったのに、なぜ君は無事にそちらの星にいけたんだ」
「小さいほうが移動しやすいので、宇宙船もすべて縮小されて運行される、中にはいると光を浴びさせられて小さくなるんだ、星にもどると、元に戻す光を浴びるんだ。蟻族の大きさは人間とほぼおんなじだよ」
「そうなんだ」
そう言って映像が終わった。
聴いてみたいことがたくさんあるが、これからゆっくりと話してくれるだろう。家内の顔を見た。信じられない出来事なのに、ずいぶん喜んでいる。
「おどろいたろ」
「もちろんよ、でも私もよその星に行ってみたい」
「小説にするんだから、つれてってくれるかもしれないよ」
「そうだわね、冷蔵庫の蟻さん、もっと綺麗な箱にいれてあげたほうがいいわね、ちょっと都内にでて買ってくる」
「食事はどうする」
「それも何か買ってくるわ、すごい結婚記念日だわね」
彼女は嬉々として外出準備をすると、出かけていった。家内にこういう側面があったんだ。普通なら友人の画面をいたずらだと思うだろう。
夕方には、蟻の数だけの小さな桐箱を見つけて帰ってきた。シャンパンとロースとビーフも忘れなかった。その日はシャンパンを飲みながら、詳しく彼が宇宙船で行ってしまったときのことを話した。
次の日の朝、九時頃だったろう、いきなり稲光がした。来たと思った私は家内を引っ張って庭に出た。
ごろごろという音とともに、緑色の樽のような宇宙船が庭に降りてきた。家内がうわっという顔をしている。
入り口が開くと、小さな偵察艇が飛び出て、私と家内の前に浮かんだ。
「久しぶり、偵察艇とともに家の中に入っていいかな」
声がしたので「どうぞどうぞ」と玄関に回った。
玄関から宙に浮かんだまま中に入った偵察艇は居間のソファーの上におりた。入り口が開き、小さな蟻と小さな人間が飛び降りた。
突然蟻と人間が大きくなり、ソファーに座った。
彼が現れたれたのはいいが、蟻も我々と同じ大きさになると異様に見える。
「家内です」
彼はソファーに座った蟻を紹介した。蟻はお辞儀をして複眼を点滅させた。
「初めまして地球にくることができて嬉しいです、と言ってるんだ」彼が通訳した。私も挨拶をして、家内を紹介した」
「久しぶりの地球だけど何か食べたいものはないかな、奥さんはなにを食べるの」
「こいつの星は茸星と呼ばれる、茸が至る所に生えていて、それがおいしいんだ、地球よりいいよ、だけど俺は珈琲が飲みたいな、内のには角砂糖を試させたい」
家内が直ぐに用意してきた。
彼はうまそうにコーヒーを飲んで、蟻の妻は角砂糖を食べた。そのとたん複眼が赤く点滅した。
「角砂糖とても美味しいらしい」
「よかった、それじゃご遺体を返そう」
私は家内が用意してくれたたくさんの桐箱を、彼らの前に並べた。それぞれの蓋を開けた。中には干からびた茸を生やした蟻が横たわっている。
「みんな棺に入れてくれたんだ、ありがとう」
友人がお礼をいった。
「家内が用意してくれたんだ」
蟻の妻が立ち上がってお辞儀をして複眼から水をしたたらせた、
「感謝していると言ってるよ、中の一人は家内の父親で、船長だったそうだ、母船を長く待たせるわけにいかないから、そろそろ帰るけど、連絡の仕方をコンピューターでおしえるよ」
「うん、またきてください」
彼は懐中電灯のようなものを蟻の奥さんに照らすと、箱を持もったまま小さくなり、彼は自分にも照らして縮むと偵察艇に入った。偵察艇は宙に浮かぶとひゅと玄関からでて行った。
我々があとを追って、庭にでたとき、母船はもういなかった。
「やっぱり驚いたたわ、本当だっていう実感がわいたわ」
家内やっと信じられるという顔をしている。
「お友達はあの奥さんのどこがよかったのかしら」
「うん、わかんない、長く一緒に暮らしていると、いいとこ、悪いとこわかってくるからな、蟻の世界にはいって、蟻の性格がわかったからだろうな」
「私、蟻の雄も雌も区別が付かない」
それから毎日のようにパソコンに通信がきて、一時間ほど茸星の生活やら仕組みやらを友人が説明した。それを家内は端からまとめていった。いつか茸星の本を書くためである。
「蟻さんたちの恋愛のことを彼が説明してくれたわよ、香りが大事なんだって、人間の男の匂いは茸星の女性蟻にはとても刺激的らしい。一方で男性蟻は女性の匂いもだけど目の大きさに弱いらしい」
「そこは人間の男も同じだね、大きな目の娘の方が好まれる」
「あ、そう、私大きくないよ」
「俺は必ずしも大きくなくてもいいよ」
「蟻さんの星では、男は複眼が小さい方がもてるんだって、あなたは蟻さんと同じ」
そのような茸星の情報がたまっていった。
半年ほど経ったとき、総理府の第8部局と言うところから電話があり、出版のことで訪ねたいとのことだった。
やってきたのは三十代の女性と五十半ばと思われるロマンスグレイの男性だった。
彼は家内に「異星人の生活のことをお書きになっているとお聞ききしまして、場合によっては我々も資金の提供と校正者をおつけしようかと思い参りました」
「ありがとうございます、資料を集めていましたが、そろそろまとめようかと思っていたところです」
「それはよかった、この女性は編集者で手助けできると思います」
女性が頭を下げた。
「目次を最初に詰めておき、できたところまで送っていただけると、私の方でご意見を差し上げます、どうでしょう」
「はい、よろしくお願いします」
「一年でまとめる予定でいいでしょうか」
「はい、もう一つ書いてみたい小説があります」
家内は楽しそうだ。
「異星人と地球人が結婚する話です」
「面白そうですね、それもできたら見させてください」
そういうことで家内は「茸星の小さな村」と言うタイトルの本と、「異星の女性に恋した地球人」の二冊の本を書き始めた。
家のこともよくやっているし家内が輝いてきた。
「結婚の時の約束果たしてくれたわね、ありがと」とまじめに家内に言われた。
できあがった本は二つの本がそれぞれ大手の出版社から同時発売になり、さらに世界のあらゆる国の言葉に翻訳されたのである。
本がでて五年たった今、日本が中心になって茸星人を迎え、和平条約を結ぼうとしている。
緑色の樽型宇宙船が歓迎の渦に囲まれた国連広場に着陸した。中から人間の大きさになった緑色の蟻が出てきて、国連事務総長と握手を交わした。
茸星の蟻の形をした異星人はみやげにたくさんのいろいろな茸を持ってきた。
その日は地球人が宇宙人の仲間入りした国際宇宙記念日となった。
茸星の茸の胞子は強く、地球のいたるところで生えるようになった。地球の在来茸が生えなくなってきた。それで、地球茸保護地区が国連で制定された。日本もその中にはいっていた。
たくさんの茸星人が地球に観光しにくるようになった。
ところが、観光バスに乗った蟻の人たちは途中でいなくなった。小さな蟻の形になって林や森の中で暮らすようになったのである。森には茸が生えていたのでかれらは食料には困らなかった。
私の妻はあの本を書いて出したことが正しかったのかどうか疑問に思うようになっていた。
「茸星に占領されそう」
そういう本を書き始めた。総理府の第8部門に出版の依頼をしても、予算が付かないと帰されてきた。
今茸星の蟻人に宇宙船の理論を日本の企業が教わっているところである。そんな時にそのようなタイトルの本は出せないということなのだろう。
「俺がだしてやるよ」
家内の本を自費出版社に依頼し二千部刷って売り出した。
「これが本当の結婚の時の約束ね、ありがとう」
家内はこんなことも言った。
「あなたの友達から連絡がこなくなって長いわね、国際宇宙記念日に茸星の宇宙船に乗ってこなかったのはおかしいわ、無事ならいいけど」
今では、家内の本が売れて、地球人が目覚めて欲しいと強く願っているのである。
庭を見ても今までたくさんいた黒蟻や赤蟻が少なくなったような気もする。大丈夫だろうか。
蟻の星
私家版第二十二茸小説集「桃皮茸、2026、269p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2020-7-11


