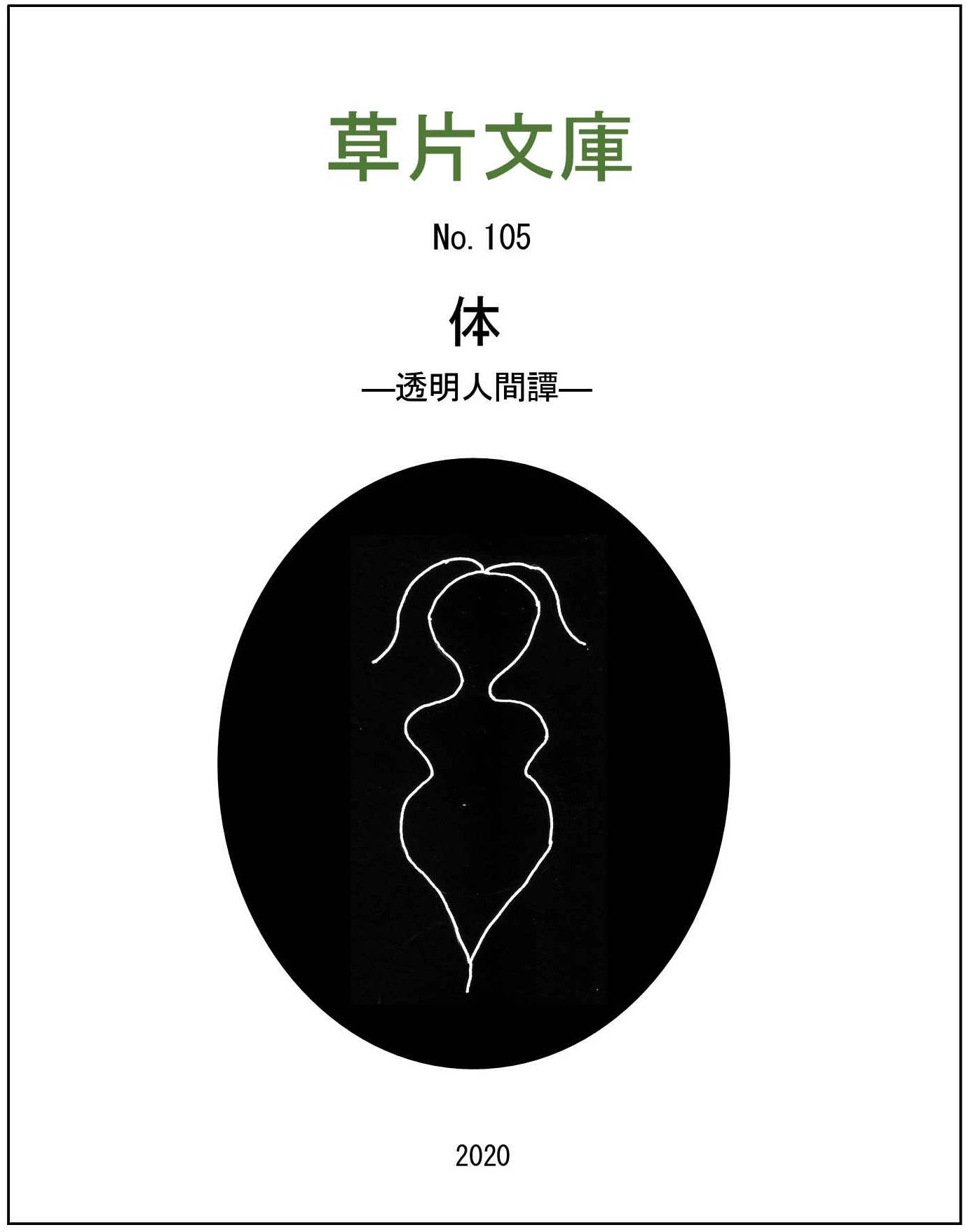
体 - 透明人間譚
温泉で有名なとある町の警察署である。
陽が落ちるまでにまだ一時間はある。
「大変だ」
地下の拘置室に隣接する管理室にいた警官が、一階の休憩室に飛び込んできた。
お茶を飲んでいた刑事と思しき男が立ち上がった。
「どうした」
「留置していた男が逃げました」
刑事は警官と留置室に行った。
「見回りにいくと、中に誰もいませんでした、鍵はかけてあります」
確かに鍵のかかった留置室には誰もいない。
「逃げるには、拘置室の隣の、私のいる管理室の中を通らなければ外にでられません、私はその部屋にずっと居ました、鼠一匹だって通りませんでした」
管理室の中に階段はある。
「俺もここでお茶を飲んでいたけど、誰も上がってこなかったな」
地下から階段を上がると休憩室の中にでることになる。したがって、刑事が気づかないわけはない。
「中の隅々まで調べたのです、がいません」
「開けて入ったのか」
「はい、鍵を開け、調べてからまた鍵をかけました」
刑事は鍵を開けさせて中に入った。きちんとたたまれた洋服がベッド兼ソファーにおいてあった。
「これは本人のか」
「はいそうです」
「じゃあ何を着て逃げたのだ」
警官はあれっという顔をした。
刑事がたたまれた上着を手に取ると、その下にシャツとパンツがあり、更に下に、ズボンが残されている。
「なんだこりゃ、何も着ていないじゃないか」
「おかしいですね、これじゃ裸だ」
警官も首を傾げた。
「こいつが置き引きの犯人か」
「はい、温泉地で観光客の財布を盗む窃盗犯で、全国に指名手配が回っていました、運良く巡回中の警官がこの町の駅のホームから出てきたばかりの男を捕まえたわけです。明日、中央署の刑事さんがきて、連れて行くことになっています、署長に言ってすぐ手配しなければ」
「まああわてなくていいよ、もしかすると、いくら捜索隊を出しても無駄かもしれない、署長とは今さっきまで一緒にお茶を飲んで話していたんだ、彼は呼ばれて署から出て行ったから、署長室にいないよ、署長には私が言うから、ともかく管理室に戻ろう」
警官と刑事は留置場の隣の部屋に行った。
「彼の持ち物はあるの」
「何もありませんでした、いや、薬瓶を持っていまして、持病があるので、夕食後にいつも飲んでいるというので、一つ飲ませました。残りは一粒しかなくて、空瓶はここにあります」
警官は引き出しを開けた。市販の風邪薬の瓶だった。
「病気持ちなのに、素っ裸で逃げたってわけだ」
「変ですね」
「その薬のせいかもしれんよ」
「何の薬ですか」
「透明になれる薬だ」
それを聞いて若い警官は驚いた。冗談かと思った。透明人間はSFで読んだ空想物語だ。こんな中年の刑事がどうしてそんなことを言うんだろう。
「三十年前に作り出されて、国連で禁止した薬だ、ただし一般には知られていない。極秘事項だったようだ。日本でも作られたという話しだ。一粒のめば永遠に透明だ、しかし、副作用はわからないし、寿命にどう影響するかわからない、その作り方は破棄されたと聞くが、一粒、一千万で売ってる奴がいるとも聞いたな、きっと偽物だろうと誰も買わんだろう、元に戻す薬ができると、また作られるようになると、世界の危険薬品リストに入っている、しかしサリンのようによく知られているわけではない」
「そんな金を持ってるような男には見えなかったです」
「そりゃわからんさ」
「でも、留置場には鍵がかかっていました」
刑事は笑った。
「お宅さん鍵開けて中を調べたんだろう」
警官ははっとなった。
「その隙に逃げた」
「まあいい、そいつのデータを見せてくれ」
若い警官はそこで、その刑事は今まで見たことがない人であることに気づいた。
一階の休憩室はここの職員なら誰でも使うことができる。所長室と事務室の間にあり、事務室を通らなければ入れないことから、警察所に勤めている者しか居ないはずである。地下の留置場へいくには休憩室を通らなければならない。二重にも三重にも逃亡を防ぐ工夫になっている。それで若い警官はお茶を飲んでいた男を風貌から刑事と思ったわけだ。
「すみません、いつもお見かけしないけど、刑事さんですか」
刑事は笑顔を見せて、
「あ、こりゃ悪かった」と警察手帳を出した。
「警部さんですか、すみません、休憩室に入れるのは警察関係者だけだから、刑事さんとは思ったのですけど」
「あ、いいよいいよ、私がその逃げた男を連れにきたんだ、今日この町についたんで、署長に挨拶したところだよ、ここでしばらく話をしていたんだ」
若い警官は驚いた。
「すみません」
「大丈夫、逃げられたのは困ったが、確証がえられた」
「何のですか」
「私の追いかけていることに関係がある男だとわかったからさ」
「なんでしょうか」
「後で説明しよう、逃げた男のデータを見せてもらえるかな、東京でちっとは見たけど細かいことはわからん、ここの出身だったよな」
「まず、部長に報告してきます」
「いいよ、騒がない方がいい、私があとで説明するよ、非常線を張っても、透明になった人間を捕まえることはできんからな」
「どうぞこちらへ」
とまどっていた警官はPCのある事務室のデスクへ刑事を連れて行った。逃げた男のデータを開いた。
「名前は三品圭児、ここの生まれ。生家はもう無い。この町の小学校と中学校卒業、高校は隣の町の県立高校か、その後、東京に出てるな、君はここのでかい」
刑事が聞いた。
「はい、高校まで犯人と全く同じ学校のようです、高校出て私は警察学校に行きました、卒業してから東京の警察署に三年いました」
「お、優秀だな」
「刑事さんもここですか」
「いや、東京だ、ここは初めてきた、いずれ調べにこようと思ったら、こそ泥が捕まったと連絡が入り、一度この地を見ておこうと思ってきたのだよ」
「どうしてここに来るつもりだったのですか」
「透明になる薬にかかわっている人間がいるという情報があったからね」
「私はここにきて一年です、こんなとこにそんな大きな事件があるのですか」
「透明になる薬の秘密工場があるかもしれないことがわかってね、そうしたらここへ連れにきたこそ泥が透明になった。重要な糸口ができたわけだ。そいつを追えば組織がわかるかもしれない」
若い警官はびっくりした。
「こいつは、東京で職を転々としてるが、最初に勤めた板金工場では三年がんばっている、相当器用なやつで腕をめきめき上げ、やめて欲しくなかったと工場長は言ってたな。そこをやめてから後はきちんとした職についていない、最初に警察に捕まったのは、板金工場を辞めてちょっとたってからだ、小さな会社の金庫が開けられて、金が盗まれ、それが何件か続いたとき、金庫に詳しい奴と目星をつけられたわけだ。
三品は板金工場で金庫も作っていて、そういった経験者から洗い出され、現場を予想され捕まっている。出所して地方の温泉地で旅館の男手として働いて、ほかの旅館の客から財布を盗んでいたんだ。そこで捕まりまた刑務所入りした。いろいろな温泉地で頻繁に起こっている被害が三品のやり口と似ていることと、被害者が三品を見ていることから指名手配になっている」
「透明になってしまったら、どこに逃げたかわかりませんね」
「こいつはこの温泉地からでてないねと思うよ」
「どうしてでしょう」
「今回は目的があって戻ってきている、なあ、こいつが中学まで、いや高校までで何かしでかしていないか調べるすべはないもんかな」
「刑事事件を起こしていればわかりますが、それがないと警察に経歴は残っていないので、出身校で聞くか、友達がわかればいいのですが」
「そうだよな」
「あ、私の高校の同級生が社会の先生になって高校に戻っています、聞いてみましょうか」
「それはいいアイデアだ、連絡たのみますよ」
「わかりました、電話してみます、だけどこの時間にいるかどうかわからないですけど」
警官は高校に電話を入れた。すぐに電話口に出た。刑事が電話を代わり、十二年前頃に卒業した者のことを知りたいので高校で話を聞きたいことを伝えた。
「これから高校に行くので一緒にきてくれる、君も私服に着替えてくれたまえ、高校には私の車で行くから道を教えてくれますか、パトカーだと目立って高校に迷惑だからね」
刑事は警官の案内で高校に向かった。
高校では警官の友人である社会科の先生と副校長が待っていた。
「当時、二年生の時の担任でした」
卒業アルバムを開きながら副校長が言った。
「彼ですね」
一人の髪を長くして眼鏡をかけたまじめそうな学生を指さした。
「その頃はどうでした」
「成績は普通でしたね、地学が好きで、石については教師よりよく知っているほどでしたよ、全く問題がない子でした」
「それなのに、大学に行かずに、就職したのですか」
「うーん、三年になって、警察沙汰になったことがあったんですよ、もっとも、表沙汰にはならず終わりましたけどね」
「どうしたんです」
「のぞき見ですわ」
「若い男ならやりそうですな」
「温泉旅館がたくさんあるでしょう、女湯をのぞいてたんです、花のや旅館でやったんですな、番頭に見つかって警察に突き出されました」
「花のやって、あの美人女将のいる旅館ですか」
警官が言った。
「そうです、ほら、彼と同じ写真に写っている子」
「このにこにこしたかわいらしい子ですか」
「その子が今の花のやの若女将です」
「同級生の子ののぞき見をしたんですか」
「その子に気持ちがあったんでしょうね、その子はまじめな子で、きっと彼は相手にされなかったようです、たまらずのぞきにいったのでしょう、調度その子が湯につかっていたときだそうですよ、番頭が捕まえて警察に連絡したんです、だけど、その同級生の娘が警察に訴えるのをいやがって、お説教だけで終わりました。それから受験勉強をしなくなり、東京に出て就職したのです」
刑事はうなずいた。
「今でも実家はここですか」
「いえ、彼の件があってすぐに引っ越したと聞いていますよ、警察沙汰にならなかったけど、周りの目が気になっていたんでしょうか、妹がいましたからね」
「いやありがとうございました、参考になりました」
そこで高校を出た。
「なにかわかりましたか」
若い警官が聞くと、刑事はうなずいた。
署に戻った刑事は警官に「花のやの女将は独り者かい」と尋ねた。
「そのようですね、人気があって繁盛してますよ、このあたりの女将の会でも、会計担当をしてますが、いずれ会長という声があるようです」
「頼みがあるのだが」
「はい、なんでしょう」
「花のやに行って、今の番頭さんが、三品ののぞきを捕まえた人かどうか調べてほしいんだ」
「警察に呼びますか」
「いや、君が警察官の制服を着て花のやに行って聞いてほしい、それで、その人がいなかったら、誰にでもいいから、昔花のやでのぞきをした男が、こそ泥になって町に戻っておるので注意するように言ってくれるかな、それと、もし、そのときの番頭さんだったら、どこからのぞいたのか聞き出してくれないか」
「はい、わかりました」
「決して、透明人間のことは言わないようにね」
「あいつがまた花のやにのぞきに行くでしょうか」
「かもしれないが、透明になったなら、もっと何でもするだろう、それを阻止しなければならない、俺は今日、花のやの客になって、泊まって様子を見るよ」
「予約しますか」
「いや、警察が予約したらまずい、君の報告を受けたら、自分で予約するよ、このことは後で署長に言っとくからたのみますよ」
「はい」
彼は巡査の格好にもどると、刑事と携帯番号を交換して出て行った。
三十分ほどすると警察官から電話がはいった。
「番頭さんはかわっていませんでした、三品の話をすると、当時宿の奥の方に家族と従業員用の掛け流しの室内風呂があったそうで、高校生だった若女将はいつも八時頃一人で入っていたそうです、その日、番頭さんが庭にでたとき、人影が奥の裏の方に動いていくのを見つけ、追いかけてみると、高校生の三品が、室内風呂の窓を開け、のぞこうとしていたのだそうです。その風呂は今でも宿の主人たちや従業員も使うけど、貸し切り風呂としても貸し出しているそうです。
あ、そうだ、三品がこそ泥になって戻ってきていることを話しているときに、女将も来て皆聞かれてしまいました、あら怖いと言ってました、まずかったでしょうか」
「それはかまわないよ」
「従業員は仕事が終わった夜中に、貸しきり風呂を使うそうです。女将さんは貸し切り風呂に一人で入るのが好きだといっていました、毎晩夜の2時頃と言ってました、気をつけるように言っておきました」
「それは上出来だよ、それじゃ、俺はこれから駅の案内所で花のやを予約する、明日うまく行けば、署長のほうから花のやに行くように言われると思うよ、どうもご苦労さまでした、助かりました」
電話を切った刑事は駅の案内所で花のやに予約を入れた。
彼は「ちぇ、一番高い部屋しか空いていやしねえ、一泊五万かよ、部屋食かぜいたくだな」とぼやきながらタクシーに乗った。
宿に着くと、二階の見晴らしのいい次の間つきの十二畳の部屋に案内された。
女中さんがお茶を入れてくれ、内湯と露天風呂の説明をしてくれた。今日は男性の団体が泊まるので男湯は混むだろうと謝られた。ただ内湯で貸し切りにできるところが一つあり、あまり大きい風呂じゃないけどきれいな風呂で、特別室にお泊まりになる方にはお貸しすることができるということだった。
女中さんが引っ込むと、女将さんが顔を出した。噂通りなかなかきれいだ。高校の副校長がまじめすぎるような娘だったと言っていたが、こんなにも変るものかと思うほど、色香の漂うやりての熟女の感がある。
「よくいらっしゃいました、お仕事でございますね」、と手を突いた。
「ええ、まあ。急用でして」
「そうでございましょ、でも特別室にお泊まりになるのですから、重要なお仕事にいらしたのでしょうね」
「ええ、まあ、明日になれば大きな問題が片付きます」
「今晩はゆっくりお休みください、食事は旬のものをふんだんに使った手前自慢の料理でございます」
「男風呂は混んでいるとか」
「そうでございますね、男性の団体様がおいでです、係りの者が申したと思いますが、内風呂に一つ貸し切りがございます。お使いいただけますので帳場にお申し付けください」
「ええ、先ほど女中さんからも聞きました、いい風呂のようですね」
「はい、こう申しては何ですが、一番きれいでございます。数年前、アンティークタイルを用いて新しくいたしました」
「それじゃ、入ってみたいものですな」
「お食事の後に予約をいれておきましょうか」
「それはいい、お願いします」
「九時頃でいいでしょうか」
「はい」
「どうぞごゆっくり」
刑事はなんだかとんとん拍子にうまい方向に話が進んでいるので、逆に心配になったくらいである。
部屋での食事は豪華だった。ビールを一本で我慢して、貸し切り風呂に入った。
木製の引き戸の鍵を開け、入ると中から鍵をかけた。脱衣室で着物を脱ぎ、湯殿の戸を開けると窓のステンドグラスが目に入った。壁はタイル張りで、昭和初期の洋式のレトロな雰囲気だ。掛け流しのタイルの風呂である。蛇口も真鍮製である。けばけばしさはない。ステンドグラスの下にある茶色のガラスの小さな引き戸が、当時は磨り硝子だったに違いない。三品はそこからのぞいたのだろう。
刑事は洗い場の目立たないところになにやらおいた。ゆっくりと風呂に浸かると、早々に上がって帳場で鍵を返した。
部屋にもどり布団の上にゴロンと横になる。2時ぐらいまで休むつもりだ。ちょっと眠くなる、ふっと気がつくと1時を回っている。
刑事は黒いバッグからトランシーバーのようなものを取り出した。
スイッチを入れると、湯の流れる音がする。ヘッドホンをジャックに差し込んで、耳にかけた。おいてきた機械は正常に働いているようだ。
三品は必ず現れる。
2時十五分ほど前だった。入り口の開く音がした。刑事は録音のボタンを押した。
風呂の引き戸が開く。湯をかける音がする。「今日も忙しかったわ」女将の独り言のようだ。シャワーの音が止まる、湯船に入る音が聞こえた。少しばかり風呂の中の女将を想像する。
いけないいけないと思ったとき、いきなりざぶんと水に飛び込む音がした。
「なに」と驚いたような女将の声が聞こえた。
「俺だよ」と男の声がする。きっと三品だ。
「あんた、あの薬飲んだの」
「ああ、しょうがなかったんだ」
「あ、さわらないで」
「あのときはよう、お前が見せてやると言ったから、のぞきに来たら、番頭につかまっちまったんだ」
「運が悪かったわね」
「お前、何人にああやって、体見せてたんだ、みんな見たがってたな」
「何人だっていいでしょ」
「先公たちは、お前のこと、まじめで、男のことなんて何にも知らないお嬢さんだと思っていたのだから、お前もたいしたものだよな」
「ほめたって何もでないわよ」
「それでよ、ためしにもらったこの薬は利くことがわかったが、元に戻す薬も作っているんだろ」
「まだ、できてないわよ」
「俺は透明だ、何だってできるんだ、ただ、薬の副作用はわかっていないって言ってたな」
「わかってないわよ、だけどなんで、ここにきたの」
「そろそろ、お前と一緒になりてえと思ってな」
「もどす薬ができてからよ、薬の材料は採ってきてよ」
「ああ、透明になる薬を作っている奴らにも、色仕掛けでやらせているんだろ」
「余計なこと言わなくてもいいじゃないの、みんなお金がほしいのよ、透明になる薬はほぼ完成よ、あんたが証明したじゃないの、だけど、元に戻す薬と抱き合わせじゃないと売れないのよ」
「なんかあったら使ってみてといわれたが、使っちまった、おれも元にもどりてえ、どこまでできているんだ」
「あと少しよ、北海道の女満別の温泉にでるLLSという物質がいるんだって、そこの石に含まれているらしい、それ採ってきてって言ったでしょう」
「ああ、途中でおまえさんに会いたくなって寄ったってわけだよ、三日も遊んだら行ってくるよ」
「透明薬は作るのに一年かかるのよ、一遍にたくさんできないのでまだ5つしかないのよ。あんたに一つ送ったから、今四つしかない、元に戻す薬は材料さえそろえば一月でできるって」
「温泉場で、薬の材料の石を採って運ぶのも楽じゃないぜ、見分けるのも大変だしな、ずいぶんいろいろなとこいったぜ」
「だけど余計なことするから、警察に目付けられて、しょうがないわね」
「遊ぶ金が欲しくなるんだよ、送ってもらう金じゃたりねえからな」
「ずいぶん渡していたのに、ともかくあんたが、石に強いから助かってるわよ、分け前の4分の1はあげるから、早く採ってきてね」
「わかってら、作っている奴ら、今何人いるんだ」
「十人がかりよ、男七人女三人、力はいらないけど忍耐がいるわね」
「まだ、あの薬局でやってるのか」
「新しく出した、花屋漢方よ、表向きは風呂に入れると温まる薬を作っているわ」
「裏でやってるわけか」
「そうよ、できあがれば、透明薬と解除薬一対で百万ドル出すって言ってる国があるのよ、たくさん作る方法を考えなければね」
「それじゃ安すぎるぜ」
「あっ」
その後、湯の音がじゃぼじゃぼ聞こえ、女将の声がちらちら聞こえ、しばらくすると、刑事は恥ずかしくなってきた。のぞきと同じだ。
「明後日まで、お前の部屋にいるからな」と三品の声がした。
刑事はそこまで聞くと、布団に入って寝てしまった。
明くる朝、部屋で朝食を食べ終えた刑事は、地元の警察に電話連絡して、すぐ警官たちを宿によこし、女将を逮捕するように言った。
その後、刑事は番頭を呼んで刑事手帳を見せ、音をたてないように言って、女将の部屋に案内させた。
女将は厨房で指揮をとっていて部屋にはいないはずである。
番頭は言われるまま、女将の部屋に案内すると、刑事が静かに戸を開けるようにうながした。番頭が戸を開けると布団が敷いたままになっている。布団が盛り上がっている。中に人が入っているようだ。
番頭に掛け布団を一気に引きはがすように言った。番頭が言われたとおり、布団をさっとめくると、刑事は持っていたスプレーをまいた。
布団からペンキで真っ赤になった人の形が立ち上がった。刑事はスプレーをかけ続けた。
「三品、逮捕する」
刑事が真っ赤なからだの透明人間を組み伏せ手錠をかけた。
番頭が呆気にとられているところに、巡査がやってきて「女将を逮捕しました」と報告した。
「ごくろうさま、透明人間もほら、逮捕したよ」
真っ赤なスプレーをかけられた人間の両手首には手錠がかかっていた。
「新聞には透明人間のことは出ないと思うよ、番頭さんにはあとで他言しないようにいっておくから、こいつはまた警察の拘置室にいれるから、東京に運びます」
刑事は三品に宿の着物を着せ、帽子をかぶらせた。
「さー、いこうぜ」
刑事と巡査が三品を引き連れてパトカーにのせた。
薬局花の屋のスタッフも全員逮捕され、この湯の町で透明薬を作っていた連中は警視庁に送られたのである。
新聞には湯の町で違法ドラッグが作られていたと、大々的に報じられたのである。
体 - 透明人間譚
私家版透明人間小説集「透人譚、2020、276p、一粒書房」所収
絵:著者


