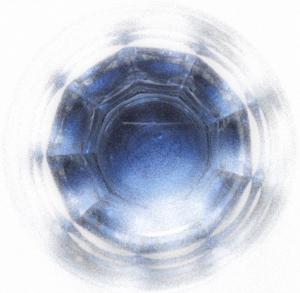おいしいは嬉しい、美しい
高校時代、時折、学校帰りに一人でカフェに立ち寄るのが好きだった。休みの日に遊び歩くことも趣味やファッションにお金をかけることもなかった分、それくらいの贅沢は許されるだろうと思っていた。高校生というのは、たとえば25歳から見れば子どもだけれど、自分ではオトナになったつもりでいるもんである。私も、中学生の間は期末試験を頑張ったご褒美に母に連れていってもらうのでなければ入れなかったお店に、一人で気まぐれに立ち寄るという、ちょっと背伸びした気分が嬉しいお年頃だった。
それで、その時に飲食したものというのが、これまでに出会った中でも最も美味しかった品々として、記憶の中で特別な輝きを放っている。身内で会食したレストランのコース料理などよりも、である。ガラスのボウルごと冷やされたサラダのセロリと、柑橘の利いたイタリアンドレッシングの香り。カットフルーツの盛り合わせは味だけでなく、スイカ、ブドウ、ルビーグレープフルーツの美しさが細部まで記憶されている。ちょうどテレビがきらきらしたエフェクトをかけて紹介するように、鮮明以上に光り輝いて思い起こされる。宝石のような思い出である。
より古い時代で印象に残っている食べ物はというと、幼少期、普段は厳しい母が気まぐれで買い与えてくれたおやつに偏る。エンドウ豆のスナック。フィンガーチョコレート。スーパーの地下のアイスクリーム屋の、メロンシャーベット。母も少女時代好きだったというパラソル型のチョコレート。あるいは、母が焼いたスワンのシュークリーム。どれも前後の脈絡なく棚ぼた的に恵まれた、しかもその一度きりしか味わえなかったものたちである。
ちゃんとした理由もなく、思いがけず出会った嬉しさと、ただ一度だけの幸運だったという貴重さが、「おいしい」の思い出を特別なものにするのだろうか。自分で稼ぎ、親から独立して、生活の中に理由のないことは少なくなった。今でも一人でカフェに立ち寄ることはあるが、特別に頑張った日だから、とか、大きな懸案が一段落したから、とか、尤もな理由のある時だけである。節約というより、何もないのに寄りたいと思うことがなくなった。
つまりおとなになった、といえるかもしれない。でも、気楽に外食できなくなってしまった昨今、高校時代のあのシーンがふと脳裏に蘇り、カフェへの憧れを募らせるんである。あれはとても幸せな時代だった、と今思う。そしてそういう思い出があるのはありがたいことだと思う。生活が彩を欠きそうになると、そうして色彩を補ってくれるのだから……。
おいしいは嬉しい、美しい