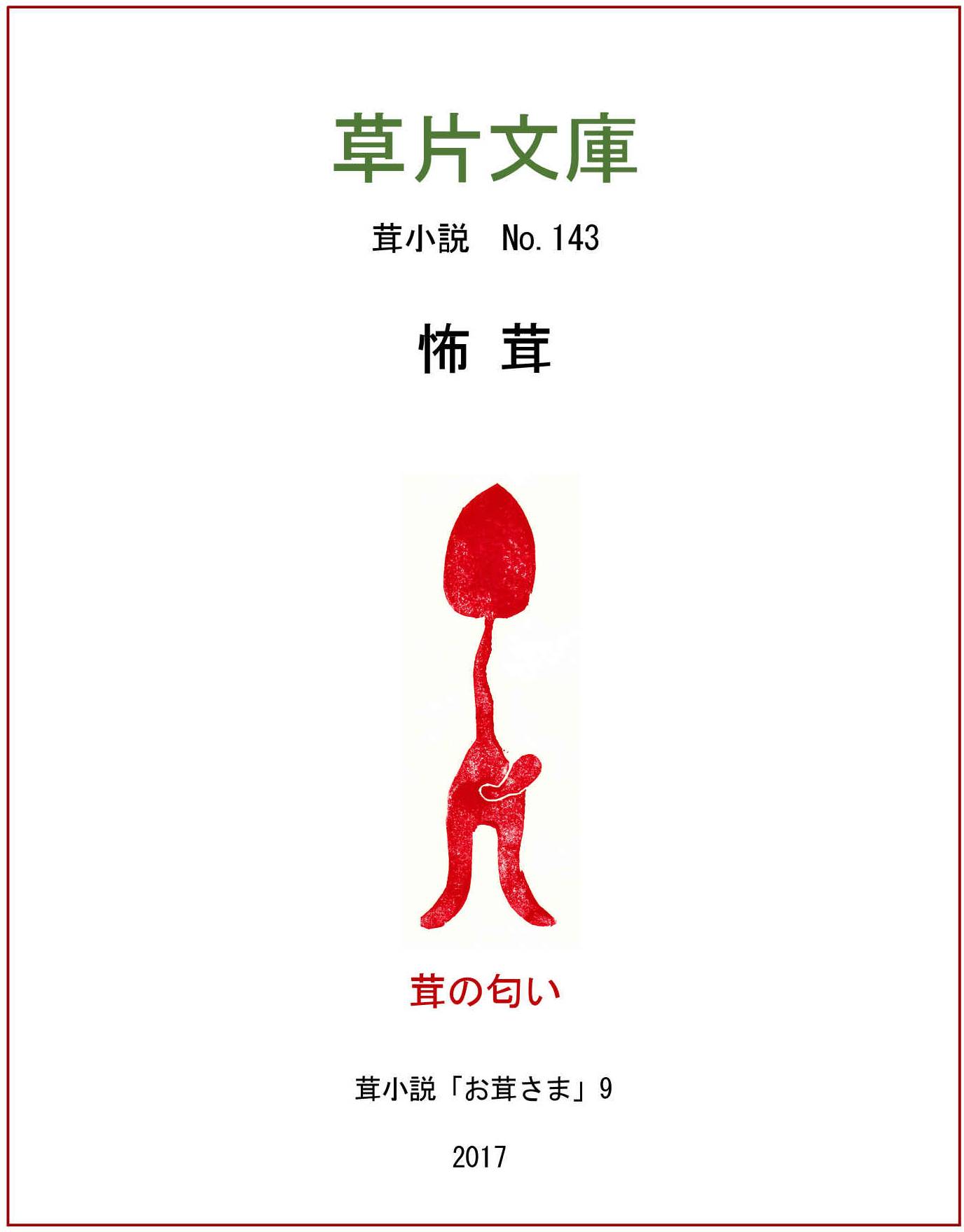
怖茸
八茸爺さんの家に、玄先生が遊びに来ています。
「この茸は旨いな」
玄先生が膳の上の煮た茸をつまんでいます。
「そりゃあそうですじゃ、長屋の鳥蔵が山奥から採ってきた黄色い舞茸だからの」
「黄色い舞茸とは見たこともないが」
「そうなんですわ、それを平助が煮てくれたのでな」
「鳥蔵も鳥撃ちから茸採りになってずいぶん経つから腕が上がったろう」
「面白い茸を採ってきますわ、それに、平助も瓢箪につとめて長いのでな、料理が親方並みに上手になった、いずれ暖簾わけをしてもらうじゃろうと思ってます」
「茸取長屋の脇にでも出せばよいのにのう」
「そうですな」
「ところで、八茸さん、私のところに相談があってな、話をきいたところ、医者よりも茸をよく知っている八茸さんのほうがいいかと思っているのだがな」
「そりゃ、なんでしょう」
「茸が怖いっていう侍がいるんで、それを直して欲しいということなんだ」
「ほう、そりゃ珍しいが、いくつになる侍ですかな」
「もう、三十じゃ」
「本人が言ってきなすったのですかね」
「いや、奥様だ」
「怖がりな男なのですな」
「いや、そんなことはないらしいぞ、腕っ節が強く、剣術は指南級、怖いもの知らずで通っているということで、茸だけが怖いそうだ」
「子どものころからですかな」
「いや、本人は何も言わないようだ、奥方の言うことには、嫁いで来たときにはわからなかったのだが、膳の上の丸ごと焼いた茸を見て、まっ青になって、そこから逃げてしまったそうだ、それでわかったということだ、ただ、茸の味が嫌いなのではなく、丸ごとの茸が怖いらしい」
「それだけなら、何も直す必要もあるまいにのう」
「それが、そうもいかんらしい、城で宴会があっても出たくないということで、付き合いの悪い男として、どうも仕事がうまくいかんらしい」
「それは、茸の料理がでるからですかね」
「そうらしいな、殿が茸好きだから、茸料理がよくでるらしい、そうなると、その場で倒れてしまうので、みっともない格好は見せたくないということだそうだ」
「だがなあ、わしが話をしても上手くいきますかな、わしの名前からして茸じゃからな」
「そういうのは大丈夫のようだ、茸の絵は大丈夫とのこと、丸ごとの本物の茸がだめなようですよ」
「わしになにができるかわかりませんが、一度お会いしてみますか、ただ一緒に連れて行きたい者が一人いまが、いいでしょうかな」
「そりゃ、いいが、誰かね」
「蓑吉の女房の紅ですじゃ」
「ああ、魚とりの蓑吉のかみさんか、まだ会ったことはないが、美形ときいたが」
「それもそうですが、茸のことをよく知っておりますのでな」
「八茸さんより知っているというと、こりゃすごいことだ」
玄先生には紅が紅天狗茸だったことは話しておりません。
「いやなに、その侍を女子から見てもらうのもよいかと思いましてな」
「そうかもしれませんな」
それからしばらくして、その侍が玄先生の養生所に来るという知らせがまいりました。
八茸爺さんは蓑助と紅にことの次第を話し、養生序に紅と一緒に行ってもらうことにしました。
「私は何をしたらよいのでしょう」
紅は久しぶりに紅天狗茸の模様のついた黒の小袖を粋に着こなしています。
「隣で話を聞いていておくれ、その後で、ちと相談させておくれ」
「はい」
こうして、玄先生の養生所、茸庵にまいりました。すでにお侍様と奥方様が見えており、玄先生と話をしております。
お手伝いさんが、二人を案内して部屋に通します。
二人が目にしたのは、大きなからだの四角い顔をしたお侍と、子どものような小さな丸顔のかわいらしい奥方です。卵に目鼻といったとこでしょう。
玄先生が「おー、来なすった、今話しておった、八茸殿と、紅さんです、紅さんは八茸殿の手助けをしております、八茸さん、紅さん、こちらは、橋爪九郎様と、奥方様の八(や)美(み)様じゃ」
八茸爺さんと紅は深々と頭を下げた。
「ああ、いや、こちらこそ世話をかけます」
九郎と八美が礼をする。どちらもにこにこと、笑顔の二人でございます。それを見て、八茸爺さんはほっとしたようでございます。それにしても、橋爪とはお城の殿と同じ苗字、ご親戚筋であろうか、かなりのお家の方のようでございます。
二人が玄先生の隣に座りますと、奥方の八美様が「紅さん、お奇麗な方ですね、その着物、すばらしい」と、紅に声をかけます。
「恐縮でございます」と紅は、頬を赤くして、頭を下げます。
「九郎様は茸を見ると、からだが震え、青くなり、ひどい時には意識をなくされてしまわれるとのこと、ご自分でも、何がなんだかわからないそうでございます。怖くない怖くないと、ずい分ご自分に言い聞かせたそうですが、これだけはからだがきいてくれず、今でも茸が怖いそうでございます、八茸殿いかがであろうかの」
「お子の頃から、茸が怖くていらっしゃいましたのでしょうか」
「いや、そんなことはない、子どものころは山に行って、茸と遊んだものでござる。元服をした後のことでござる。茸を見るのもいやになり、とうとう、怖くなった次第、お恥ずかしい話でござるな」
九朗は正直に話をされる方のようでございます。
「いえ、恥ずかしいことはないと思いますが、どうして、そうなったのか、九郎様はどうお思いなのでしょうか」
「それがさっぱりわかり申さぬ、ある日の夕餉、膳の上に松茸の焼いたものがでた。良い匂いと今まで思っていたのが、その時は匂いで、胸がなぜか苦しくなった、見ていると、松茸が笑ったように思えてな、その次には松茸に牙が生えて噛み付きそうに見えたのじゃ、怖さのあまり、膳をひっくりかえしてしまった。
家来の者たちが、料理をしたものに毒でも入っていたのかと痛く心配したのだが、そういうことはなかった」
「それからは、どのような茸でも怖くなられたのでございますな」
「うむ、そうなのだ、絵や彫り物で茸の形をしていても何も起きぬ、紅殿の着物のその真っ赤な茸は奇麗に思うが、怖くはない」
「本当の茸が怖くなるのでございますな、猿の腰掛けのような形をしたものでも怖くなるのでございますか」
「うむ、怖いが松茸などよりは怖くない」
そこで、「おそれながら」と紅が風呂敷を解きはじめ、
「八茸様、九郎様とお話をしてもよろしいございますか」と八茸爺さんにうかがいをたてた。少しばかり驚いたが、八茸爺さんはうなずいた。
「九郎様、目を閉じて、これからお渡しする茸を手で触っていただけますでしょうか、からだに悪いものではございません」
「おお、かまわぬ」
九郎は目を閉じた。紅は取り出した紅天狗茸を奥方にわたした。奥方が紅天狗茸を九郎にわたすと、九郎は紅天狗茸を触り、
「これはそれなりの大きさのしっかりした茸でござるな」と言った。
「はい、私の着物の模様の紅天狗茸でございます、お触りになっても怖くはお感じになりませぬでしょうか」
「見なければ大丈夫じゃ」
「どの色の茸が一番怖くお感じになりますか」
「山に行った時に赤い茸と出くわしての、心の臓がバクバクしおった、赤い茸が一番怖いのう」
「そうでございますか、それでは、お返しいただきたく存じます」
紅は紅天狗茸を受け取って風呂敷に包んだ。
「九郎さま、ありがとうございました」
紅は後ろに下がった。
「九郎様は匂いを嗅ぐでも、触るでもなく、茸を目で見ることが怖いのでございますね」と、八茸爺さんが言った。
「そうであるな」
「なぜそうなったのか明らかにして、それを取り除くように、致したいと存じます。しばらくのお時間をいただきたいのと、一度、紅を連れて、お屋敷にうかがってよろしいでしょうか」
「かまわぬぞ、いつでもまいって、調べて欲しい」
「では、玄先生と話をして、いずれ、お尋ねさせていただきたく存じます」
「よろしく頼む」
「それでは、私どもは、これで失礼をして、後のことを思案いたします」
八茸爺さんと紅は玄先生の養生所を後にいたしました。
「紅さん、なぜ紅天狗茸を九郎殿に触らせたのかな」
「紅天狗茸は気の乱れを引き起こすことがありますが、少々ならば、逆に気を大きくし、楽にしてもくれます、ちょっと慣れていただいただけです」
「おお、そうなのか」
「もし、九郎様がどうしてそうなられたか、明らかになりました時には、紅天狗茸が薬となるかもしれません」
「そうか、紅さんを連れていってよかった、今度は九郎殿の屋敷にまいるが、その時にも一緒に頼みたい」
「はい」
数日後、八茸は紅をともなって、橋爪九郎の屋敷を尋ねました。屋敷は立派な門構え、お城の近くにあります。門番が水をうっています。
「八茸と申します」と名を告げると、丁重に中に案内され、出てきた女中に部屋へ通された。庭の見える広い部屋です。庭は奇麗に刈り込まれ、塵一つないような静かな庭です。
「お待たせしました」
九郎が部屋に入ってきた。
「ずい分手入れの行き届いているお庭でございますな」
「母がうるさく庭師に刈らせておるのだが、わしはあまり好かんがな」
部屋もとても掃除が行き届いています。
「これでは茸は生えませぬな」
「母は、茸はみな毒と思っておるので、庭師が生えるとすぐとって、目に付かぬようにしてしまうのでござる」
「それでは、母君は茸を食べることはされないわけで」
「食べませぬの、それが似たのもしれんが、ただ、母は怖いとは思っていないようで、踏み潰してまうわ」
「九郎様の子どものころからそうでございますか」
「そうであったな、母は茸を食わなんだが、子どもの頃、わしは茸を食しておった。今でも、形がわからないものなら、喰えるし旨い」
「そうでございますか」
「この国は茸の国、怖いなどというのは恥でござるよ、叔父は大の茸好き、それなのに母はなぜか毛嫌いをする、兄(いも)妹(せ)とはいえ違うものでござるな」
「母君の兄上はそんなに茸がお好きでございますか」
「誰でも知っておると思うが、橋爪京之進じゃ」
三度の食事に必ず茸を食べるという、この国の殿様です。
「え、お殿様でございますか、すると、九郎さまは殿様の甥御様」
「そうだが、殿はわしが茸を怖がっていることを知っておってな、しょうがないとは仰せだが、一緒に楽しめないのをがっかりしておる、もしそれさえ治れば、重臣にするといっておるのだがな、わしは今のままでよいわ、だが丸ごとの茸をうまく喰いたいとは思っておる」
そこへ、年をとった大柄の女性が入ってきました。九郎殿の母君であることはすぐにわかります。
「九郎、怖がり病を直してくださる方がきたと、八美殿から聞いたので挨拶にまいった」
四角っぽい顔、造作が大作りで、目鼻口がみな大きい、九郎殿とよく似ている、ただ鼻がとても大きく目立つ。話をするたびに鼻の形が変わり、今は逆さ松茸のようだ。
八茸と紅は立ち上がると、腰をかがめた。
「これは、九郎様の母君様、初めてお目にかかります、八茸と申します、こちらは手伝いの紅でございます」
「おおこれは見事な着物を着ておられる、紅天狗茸はきれいじゃ、だが毒茸だわい」
そう言った母君の鼻が木に生えている猿の腰掛のように広がった。
母君は紅のそばによると、目を近づけた。
「本当によく織られておる、どこで作らしたのですか」
「はい、これは古くから我家にあったものでございます。言い伝えだけではございますが、猿が茸を糸にして織ったということでございます」
「面白い伝えじゃの、よくお似合いじゃ、八美殿にも、このようなものを作って差し上げたいものだが、今ではできぬのであろうな」
そう言った母君の鼻筋が細くなり、逆さにした一夜茸のようになった。
「知る者にきいてまいります、ただ、模様は茸しか出来ないと思います」
「そうじゃな、それであるならしかたがない、奇麗な茸ならよい」
「いや、大事なことを言い忘れていた、八茸殿、九郎のこの病直してくださいな、治ったなら、何でも差し上げようぞ」
そこへ、八美が茶菓子をもってきた。
「やはりお母様も、紅さんのお着物気に入られたのでしょう、素敵ですから」
「今、八美殿に作れないか訊いておったところじゃ」
「まあ、作れるのですか」
紅が答えた。
「わかりませぬが、当たってみます、ただ、茸の柄しかできません、八美様はどの茸がお好きでしょうか」
「私は、紅さんのように、背が高くすらっとしているわけではありません、とても紅天狗茸が似合うとは思わない、可愛い茸がよいでしょう」
「落葉茸はいかがでしょう、桃色や黄色や薄茶色、とても可愛い茸でございますが」
「葉っぱに生える細い茸で傘が透きとおって奇麗な茸ですね、知っています」
「そう、八美殿はかわいいのがいいでしょう」
九郎の母君も頷きます。その時の鼻は少し小さくなって、滑子のようです。
紅と八茸爺さんは八美の鼻を見ました。白い丸顔の真ん中に、鈴蘭の花がついているようです。
二人は顔を見合わせました。
「それでは、八茸殿、よろしくお願いしますよ」
母君は部屋を出て行かれました。
その後は四人で話をしたのですが、九郎様はずい分厳しく育てられたようで、よく母君にしかられたようです。一人っ子のせいでもあるのでしょうが、いつも姿勢を正して座ってないと、ぴしりと、頭を叩かれたり、それはそれは大変だったと、思い出すのもいやなようなそぶりでした。八美様がお嫁にこられ、とても楽になったとおっしゃっておりました。八美様は、柔らかな方で、紅にもとてもよくしてくださいます。
「九郎様、紅がこれから茸怖いを直すために、毎日通いますのでな、言う通りにしていただけますと、必ずよくなります」
「それは、どういうことでござるかな」
紅が説明した。
「簡単でございます。いつも、八美様のお顔を思い出していただきたいのでございます」
「あら、恥ずかしい、こんな、まん丸な顔」
「それが大事なことでございます」
「それと、お食事には必ず茸の料理を出してください。最初は茸の形をしていなくてもいいのですが、だんだんに、丸のままの料理にいたします。いつにするかは私におまかせください」
紅が続けます。
お食事の前に、薬になる茸を目をつぶって、少しかじっていただきます。その後、目を開けて、お食事をお召し上がりください。その茸は私が持ってまいります」
「わかり申した」
ということで、紅による治療が始まったのでございます。
「紅さんを連れてきてよかった、よろしく頼みますぞ」
「はい、九郎様は母君の鼻が茸に見えたのでしょう、厳しい母君を怖くはならずに、茸が怖くなったのですね、優しいお心をお持ちです」
「紅さんはよくわかっているのう」
「食事の時に、母君の鼻を思い出さないように、八美様のあの可愛らしい、鼻を思い出していただくと、治りは早いと思います、八美様のようなかわいい顔はうらやましい」
少し毒のある顔と全くない顔といったらいいのでしょうか。八茸爺さんは紅が言ったことがわかったような気がいたしました。
「後は、紅天狗茸の気持ちが大きくなる薬の働きで、茸を平気になってもらおうということじゃな」
「はい、うまく行くと思います」
「八美様の着物は大丈夫かね、もし金子が、入用なら私が出しておくが」
「ほほ、家主様、もうお分かりのはず、八美様の丈を、落葉茸に話せば、一肌脱ぐだけで、着物ができます」
八茸爺さんは返す言葉がありません、ただただ、茸に感謝するだけです。
「そのうち、茸取長屋のおかみさんたちにも作って差し上げましょう」
八茸爺さんはうなずくだけです。
「無理をせんでいいよ」
食事のたびに、九郎は目をつぶって紅天狗茸をかじります。紅がそれをしまうと、食事が始まります。八美さまには九郎様の前に座っていただき、お皿を手渡ししていただきます。そのたびに、九郎さまは八美様の顔をご覧になります。それが十日ほど続き、茸を半分にしたお料理を出してもらいました。それに、紅天狗茸をかじるときに、薄目を開けてもらうことにしたのです。
だんだんと、目を開けていても、紅天狗茸を手に持ってかじることができるようになり、そのころには、松茸を焼いて裂いたものや、滑子のおろしあえなど、そのままのものも食べることができるようになりました。
一月経ちますと、八美様は九郎様を山道の散歩に連れて行くようになりました。たもとには紅天狗茸をもっています。道端には茸が生えています。たくさん生えていると、ちょっと九郎様は怖そうな顔をなさいますので、その時は少し紅天狗茸をかじっていただくのです。
こうして、茸の季節が終わる頃、九郎様の茸への恐怖がなくなったのでございます。
落ち葉茸の着物も出来上がりました。
八茸爺さんと、紅が九郎殿のお屋敷にまいりました。
「八茸殿、茸が怖くなくなり申した。昨夜は、殿と茸で一杯やり申した。ありがたいことでござる、これでわしも存分に茸が味わえます」
「それはよございました、みんな、紅のお陰、私も助かっております」
「よい手助けをお持ちだ」
「それに、見てください」
八美が紅にもらった着物を着て現れました。薄緑の地にかわいらしい桃色の花落葉茸が散っております。
「おお、よく似合うぞ、八美」
九郎殿も八美様を穴があくように見つめます。
「それでは、これで、我々のお役目も終りました、また、来年の茸の季節に、茸取長屋に来ていただければ、紅がつくっている紅天狗茸の園で、茸見会をしております、どうぞお遊びにいらしてださい」
「おお、もちろん、茸の長屋に行って、茸に感謝せねばならぬからな」
「茸地蔵もございます」
二人が九朗の家をでますと、門の影から母君が二人のところにやってきます。
「よくぞ治してくださいました、あれは私の至らぬ育て方がそうさせたこと、もっと自由にさせればよかったものをと、いつもこれでは死に切れぬと、つらい思いをしておりました。ありがとう存じます、これは、着物の御代です」
包みを八茸爺さんにわたします。八茸爺さんは受け取りながら言いました。
「いや、わしではありません、紅の考えでござます」
「わかります、紅殿、あなたは茸の匂いが致します。きっと直してくださると信じておりました、なんと感謝を申してよいやら、これで母としての荷がおろせます」
母君が涙を流す。
ついつい、八茸爺さんももらい涙。母君は鼻がよく利くお方でございます。
「いえ、みなさまのお心持ちが、このような目出度いことにさせたのでございます」
「八茸殿、兄にこのことは伝えます、茸取長屋がいつまでも続くよう、なんでもいたします」
九郎様の母君に見送られ、二人は茸取長屋に帰ったのでございます。
「紅さんや、落葉茸に礼はどうしたらよいであろう」
「大丈夫でございます、落葉茸が、我々は旨い茸ではなく人の役にはたたぬが、このようなことで役立つのは嬉しいこと、と申しております」
「そうか、それでは、落葉茸を見かけたら、きれいだ、可愛いと言うことにしよう」
「それは喜びます」
「いただいた金子は、紅さん、あんたにわたすから、好きにしておくれ」
「それでは、長屋の宴会の時にでもお役にたてましょう」
こうして、この件は一件落着でございます。
次の秋、九郎殿と八美様は生まれたばかりの女の子、「桃葉」を連れて、母君と一緒に、紅天狗茸の茸見会にいらっしゃいました。
城からは、たくさんの酒樽と、お弁当がとどけられたのでございます。
怖茸
私家版第五茸小説集「お茸さま、2019、188p、一粒書房」所収
版画:著者


