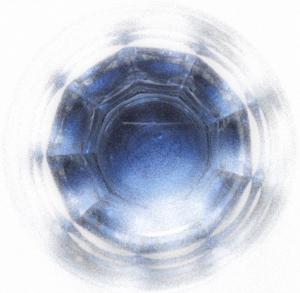夜に還る
少し前まで、お隣に「くーちゃん」というモップ犬がいた。ベルガマスコ・シェパード・ドッグというのだろうか。黒っぽい尨毛の、おっとりした、おじいちゃん犬だった。
『ご門の前に犬が出ていますけど』
ある夏の暮れ、夜八時過ぎにうちのインターホンが鳴った。母が応対すると、女性の声で、おたくの子じゃありませんか、と言う。
「もしかすると、お隣のわんちゃん……」
母が受話器越しに話しているのを聞きつけて、私が外に出た。
以前にもそんなことがあったのだ。
私が出かけようとして玄関を出ると、うちの門の前にくーちゃんがひとりで立っていて、目が合った。あれ、何しているんだろうと思ったが、自転車を押してガレージを出た時には、すでに通りから消えていた。彼のお家の、奥の方からきまり悪そうに振り向いていて、自転車の私と再び目が合うと、
(見なかったことにしてください)
というように、首をすくめた。ほんの出来心で、お忍びに出てみたところを、運悪く私に見つかったらしい。それ以来、私とくーちゃんは妙な秘密を共有している仲だった。
さて、サンダルをつっかけて出てみると、はたしてうちの門を少し過ぎたところにくーちゃんがひとりでいる。引き留めているのはインターホンを鳴らした通行人のおばさんで、彼の家の人は未だ気づいていないようだった。
彼は私を認め、そして、ゆっくりと歩き始めた。家とは反対の方向に。
「くーちゃん」
側に寄って、声をかけた。声はごく自然に出てきたが、私が彼の名前を呼んだのはそれがはじめてだった。くーちゃんのしっぽはゆらゆら揺れた。
(ちょっとそこまで、行ってみるよ)
柔らかく穏やかなおじいさんの声が、彼の背中から返ってきた。
つられて私も歩き出す。向かう先は町境の丁字路、街灯に照らされているのに、そこだけ闇が深い。アスファルトのほてりを鎮めるように、生ぬるい夜気が流れている。鈴を転がすような虫の音がいざなう。夏の夜の、闇の中へ。
「くーちゃん、帰ろう」
ちょっとも行かないうちに、私は再び話しかけていた。
(そうね)
くたびれた声が、また、返ってきた。
くーちゃんは、本当にくるりと向きを変えて、家に向かって歩き始めた。
母がお隣さんのインターホンを押して、彼の家の人が表に出てきたところだった。
くーちゃんは悪びれることなく、歩調を速めることもなく、ゆっくり、ゆっくりと歩いて、自分でお家に戻った。家の前まで一緒に歩くうち、私は彼の背中の痩せたことにじわじわと気がついた。長い毛で覆われているのでもともと体格のわかりにくい子だったが、それでも確かに背骨が浮き出し、老いと衰えが滲み出ていた。やんちゃでいたずらっ子で、よくママさんに叱られていた小さい頃の彼の姿が、私の瞼の裏を掠めた。
彼の散歩に付き合ったのは、それが最初で最後だった。
夜に還る