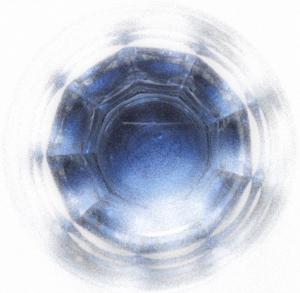about
髪を切りたい。
髪を切りたい思いに駆られながら切らないのは、私が今は女性として周りに受け入れられ、仕事をしているからだ。
性別は髪型と服装が九割だと誰かが言った。実際、髪が短いと私は男に見られる(長ければ女に見られるのだが)。しかも髪を短くしてしまうと自分を「女」に保ちにくくなるという、少々変った事情がある。
実は、私の頭の中の一人称は「僕」であったり「私」であったり、「俺」であったりする。「僕っ娘」は自分を僕という女の子のことで、僕の場合はそうではなく、月が満ち欠けを繰り返すように、あるいは日が射したり陰ったりするように心ごと人称が入れ替わる。男と女の間を揺れている。心の性が曖昧な人である。
だから、女らしくしていろといわれると、弱い。周りにそういう雰囲気の強かった学生時代の数年間、僕は女性装での生活ができなかった。――女子は女子力に磨きをかけ、オシャレをして恋をしていなければならず、女の子たちは性的な話ばかりしていた。彼女たちは決して直接的な言葉を使わず、それを彼氏の欲望のせいにするのだが、自分にも友人にもすでに性生活があり、それが正常であることを確認したがっていた。本当は、そんな状況は花盛りの数年間のことで、もう少し歳がゆけば男も女も女に「女」を求めなくなるのだったが、そうとは知らない当時の僕には「女は女であれ」という周囲の圧力を右から左へ受け流すことができなかった。それで十九の時、僕は少年のように髪を切り、メンズ服に袖を通した。
そうして鏡の前に立った時の静かな感動をよく覚えている。背丈は一六三センチたらずで胸がなくとても痩せていたから、十九歳の男子ではなく中学生くらいの少年に見えた。
少し話は逸れるが、僕にとっての中学時代は最も平和で楽しく幸せな時間だった。男子の中に中性的な雰囲気のとても綺麗でとても不思議な面白い人がいて、僕はその人が大好きだった。けれど彼女になりたい「好き」ではなく、そういう噂は立てられたくなかったので、自分が女子であるが故に積極的に話しかけられないことが大変もどかしく、悔しかった。あの頃も僕は男子の服装がしたかったのだ。私服中学だったからやればできたが、いじめが怖くてできなかった。そんなことを思い出した。鏡の中の少年が纏う中学生のような雰囲気は、そうでありたかった自分にようやく辿り着いたようなしみじみとした喜びを僕に与えた。
僕が「僕」と「私」を行き来しない人であったなら、そのままトランスジェンダーとしての生を選んでいたかもしれない。女から男へと越境する道を歩んだかもしれない。
〈中間〉でいるというのは、なかなか居心地の悪いものだった。
「どっち?」という問いかけに、私は日常的に出会った。それを口にする人はたいてい、本当に私が男であるのか女であるのか判別できず、真剣に迷って尋ねているのだった。
私は答えられなかった。
女です、とは言いたくなかった。かといって、男、と答える度胸もなかった。
そもそも、当時でさえ私はいつでも「僕」でいるわけではなかった。潮の満ち引きのように、私は時として「私」に返り、そしてまた少し経つと「僕」に戻っていた。不思議に思われるかもしれない。ただ、「私」と「うち」、「僕」と「俺」など、自然に話していて最もしっくりくる一人称が切り替わるタイミングは他の人にもあるのではないかと思う。僕の場合はそれが性を越境して起こり、そこに人格の性も付随するという感じで、それは再び女性装で暮らすようになった今も変わらずに続いている。
そういう状態だと、トランスジェンダーのように不可逆的な越境に踏み切ることはできないのだった。診断も下りないし、私自身、揺れはないことにして(医者を欺いて)死ぬまで続く医療の道へと足を踏み入れる決意がつかなかった。
私は少年の姿をしている自分が好きだった。今振り返ってみても当時の自分を不幸だったとは思わないし、時々家族がいうように愚かなことをしたとは思ったこともない。
それでも、「女」ではなく男でもない存在として存在することはストレスフルで、結局のところ自傷行動に結びついてしまった。私が愚かだったのは、服装のことではなく、一生残ることになるとは思わずに自分の身体に傷を刻んでしまったことだった。
大学を出て環境が変わるにつれ、私は段階的に女性装を取り戻していった。過度な女らしさを要求されることがなくなってしまえば、女の姿をしている方が面倒は少ないと気づいたから。髪が長くなると、私はまたレディースを着られるようになった。
かつて鏡の中の少年を気に入ったように、鏡の前に立ち、自分好みの女性がそこにいることに満足したりする。また別の時には、この女は誰だろうと思ったりする。
こないだ夢の中で鏡を覗いたとき、鏡の中の私はまだ少年の姿をしていた。
髪を切って、再び本来の僕に戻りたいと思うこともある。
低くつぶした声でBUMPや米津を歌いたいときもある。
真冬のメンズコートだけは暖かいので今でも使っているが、メンズを着ていると歩き方も男に戻っている。髪が長くても。相変わらず私は振り子のように振れている。
曖昧な性を生きる私たちは多かれ少なかれファンタジーの世界の生き物だと思われている。河童や人魚と同じである。小説や漫画に描かれ、ドラマや映画の中で名優が演じ、「本物」がテレビに出演したとしても、私たちは現実世界には存在しないと思われている。
あるいは他の少数者と同様、憐れむべき弱者とみなされ、その人生は悩み深く陰鬱なものであるに違いないと思われている。憐れみと蔑みは同じ偏見の表と裏なのだが。
私は自分について悲しんだことはない。不自由なことはいつも外界からやってくる。
不自由なこと、困ること。この話を敢えてしたくなるのはどんな時かというと、それは、性についての話題が長時間にわたって展開される時だ。
私には普通の男女の恋愛のことはわからない。
十九歳からの数年間は「女子」として生活していなかったから、その年頃の女の子の感覚がどんなものか私は知らない。私には「華の女子大生時代」は存在しなかったし、「ハタチ」も「振袖」も「卒業袴」もなかった。その辺りの話題になると、私は少し困る。当時は「僕」でいる時間が圧倒的に長かったから、「私」の記憶はほとんどなく空白のように見える。
それと、これは滑稽なことだが、再び女性装で生活するようになって、特に男性から女性として扱われると、僕は謎の後ろめたさを覚えるようになった。本当は男なのに、うまく女に化けられているような。いや、本当は女であって、何も間違っていないのだけど。
そういう場面に出会うとき、私は自分を他の人たちとは違った生き物に感じる。それ自体は別に、嫌な感じのすることではない。私は私が鬼でも妖怪でも、化け物でもいい。
でも、私は物語の世界ではなくこの現実世界に生きている。私も他の人と同じように人間である。私はそういう寂しさの中に生きている。
about