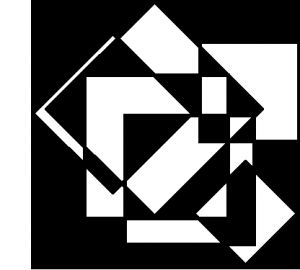夕暮れ
拙い文章ですがよろしくお願いします。
すべてが、一瞬に釘付けされたように、その動きを止めた。
鳥は飛び立つその瞬間で時間が止まり、今にも落下しそうな危うさだ。
落下した落ち葉は地面すれすれで浮いていて、噴水の水は空で雫となっている。
空に浮かぶ太陽は今にも沈みそうな位置でわたしたちの街を朱く照らしていた。
この世界の、すべての時間が止まっていた。ただ、わたしを除いて。
気付けばここにいた。見覚えのある、懐かしい公園だ。わたしが遊んでいたころと何ら変わってはいない。
ブランコにシーソー、すべり台が物淋しそうに見えた。
公園には人はいなかった。何の音も聞こえない。何の動きもなかった。
わたしは公園から商店街へと向かった。きっと、いつも賑わっている商店街なら誰かしらいるだろうと考えたのだ。
商店街に向かう途中、白い猫が道路に飛び出しているのを見た。アスファルトに着地しようと前足をついている状態だった。
わたしは猫を助けようと思って、その猫に触ろうとした。猫の白く美しい毛に手を触れようとした。
……だが、触れることは叶わなかった。
猫がわたしの手をすり抜けたのだ。わたしの手が猫の身体をすり抜けたのだ。
わたしは驚き、声が出なかった。
そのあと、何度も挑戦してみたのだが、結局猫に触れることはできなかった。
商店街についた。しかし、そこにも誰ひとり人の姿は認められなかった。
商店街を進む。八百屋や洋服屋の電気はついている。品物も置いてある。だが、やっぱり人はいない。
わたしは不安になった。なぜこんなにも人がいないのだろう。
自然と足が速くなる。呼吸も少し荒くなっていた。
わたしは商店街の先の丁字路に突き当たった。
目の前にはおしゃれな喫茶店がある。
「あれっ、こんなところに喫茶店なんてあったっけ」
わたしはその喫茶店に近づく。思い切って、ドアを開ける。
軋む音がしてドアが開いた。部屋の中の黄色みを帯びた電球の光が目に届く。
カウンターに、一人の男性が建っていた。どうやら、この喫茶店のマスターのようだ。
「いらっしゃいませ」
落ち着いた、低い声でその男の人は言った。
わたしはその人の方へ歩み寄った。
そして、わたしは手を伸ばすと、その人の肩に触れた。
わたしはその人に触れたのだ。道路にいた猫とは違う。本物の人がいたのだ。
その人は怪訝に思ったらしく、わたしを見てきた。わたしは手を引っ込めて、
「ごめんなさい」
とその人に謝った。
カウンターにわたしが座ると、マスターはティーカップをわたしの前に置いた。紅茶の香りが漂ってくる。
カップを口に近づけようとして、わたしは重大なことに気づいた。
「わたし、お金持ってないんですけど……」
「サービスです。お気になさらず」
と、笑ってマスターは言った。
一口、飲んでみる。夕焼け空のように澄んだ紅色の紅茶だった。香りが口いっぱいに広がって、心を落ち着かせてくれた。
「おいしい」
心からそう言うと、マスターは優しい笑顔を浮かべていた。
ほっと息を吐き出す。わたしはマスターに疑問を投げかけた。なぜか、マスターなら理由を知っていそうな気がしたのだ。
「街の人がどこに行ったか、知っていますか」
マスターは驚いた顔をして、
「どういうことですか」と訊きかえしてきた。
「さっきから、街の中で誰ひとり見かけないんです。一体どうしたのかなぁって……」
「そうですか」
マスターは腕を組んだ。しばらくして、
「ちょっと、ついてきてもらえますか」
とわたしに言った。わたしが頷くと、マスターは店の外へわたしの入ってきたドアから出て行った。わたしもあわててマスターの後を追った。
店を出て左。また突き当ったら右。
マスターは迷うことなく進んでいく。まるで、その道を何回も歩いてきたかのように。
くねくねと何回も曲がり、わたしは喫茶店がどっちの方にあったか見当もつかなくなっていた。でも、マスターは歩いていく。
「ここの道、何回も通ったことがあるんですか」
「いいえ。きょうがはじめてですよ」
そう答えて、マスターはこちらに向いた。
「大丈夫ですか」
と優しい、低い声で彼は言った。
しばらくして、ようやく私が知っている風景が見えてきた。家々の屋根から覗くのは、わたしの通っている高校だった。
そして、見慣れた道が続くようになるにつれ、マスターがどこへ向かっているのか見当がついてきた。たぶん、わたしの家の近くだろう。マスターは速度を緩めず歩いていた。
今もなお、太陽は動かないままわたしたちを照らしていた。
急にマスターが立ち止ったので、危うくぶつかりそうになった。
「着きましたよ」
そう言って彼が指差した先は、わたしの家の目の前のビルだった。
彼はビルのわきを通っていく。この先には確か、駐車場があったはずだ。
駐車場が近づいて、わたしは違和感に気づいた。
……なんだか、鉄のようなにおいがする。
そう思ったのと同時にわたしの目に衝撃的な光景が映った。
夕焼けの太陽よりも紅く、鮮明なその色は、紛れもなく血だった。
中心に黒い何かがあり、放射線状に紅く広がっている。
マスターは躊躇わずその黒い何かのところへ行く。直視など、できなかった。
マスターがそのものに触れると、そのもののことがはっきりと見えるようになった。
間違いない。これは。
これは。
わたし自身だ――。
するすると糸がほどけていくように、わたしの記憶は思い出されていった……。
わたしは、病気がちだった。月の大半は病院にいたし、学校にいても早退することがほとんどだった。
だから、なのだろうか。わたしはいじめられるようになった。ものを隠されるのは日常茶飯事だった。運の悪いことに、わたしをいじめていた人と二人きりの時に発作が起きて、生死の境さまよったこともあった。
いつしか友達と思っていた人も離れていき、わたしは一人になった。頼れる人など、もうどこにもいなかった。
だからわたしは自殺を決めた。そうするより他はなかった。
家の前のビルを決行場所に選んだ。
屋上に上って、手すりにつかまり身を乗り出す。呼吸を整え、一歩、空に足を踏み出す。
バランスを崩してわたしは駐車場に叩きつけられた――。
マスターはわたしの話を静かに聞いていた。そして、こう言った。
「君は、その世界に未練はないのかい」
その言葉の意味を理解するのに多少時間がかかった。
「未練はあるけど……」
今ではどうしようもないだろう。
「なら、生き返ればいいさ」
マスターがさらりと言う。
生き返る。確かに、そうできるものならそうしたい。
「でも、もうどうしようもないから」
わたしは諦めの混じった声で言った。
「そんなことはないさ。君は生き返ることができる」
そう言ってマスターはわたしの肩に手を置いた。
「君は生き返りたいかい」
わたしは大きく頷いていた。生きたかった。
「そうか。なら生き返らせてあげよう。君は、君自身の手で、自分を生き返らすんだ」
「どういうことですか」
「私は君を死ぬ前の時間に戻す。その死を食い止めればいい」
何の説明もなしに、彼はわたしを死ぬ前の時間に戻そうとする。
わたしはずっと気になっていたことを訊いた。
「ここは、一体何ですか」
「ここかい。ここは君が死んだときにできた、言わば空間のゆがみのような場所かな」
彼はわたしの肩にまた手を置くと、
「それじゃあ、頑張って」
と優しく言った。
視界がゆがんでいった。
わたしはコンクリートの上に仰向けになっていた。きっとここはビルの屋上だろう。
起き上がって周りを見た。
そこには、手すりをよじ登っている女の子がいた。
――わたしだ。
わたしはすぐさま立ち上がって今まさに自殺をしようとしているわたしのもとへ走って行った。
だが、一瞬遅かった。
わたしがもう一人のわたしに手が届きそうなところで、彼女は落下してしまった。
そして、わたしは手すりにぶつかった。全速力で走ったため体に衝撃が襲った。頭が投げ出されるようになる。手すりを軸にそのまま一回転しそうな勢いだった。
わたしはその勢いを殺すことができなかった。
もう、なす術などなかった。ただ、勢いに身を任せるだけしかできなかった。
わたしは空に投げ出された。
そして、その瞬間、一瞬ちらと屋上に見えたのは、紛れもなく、わたしだったのだ。
夕暮れが血のように紅い。世界を紅で染めている。
今にも飛び立ちそうな鳥の姿が目に映った。
…………今更、思い出した。
わたしはもう。
何万回も。
これを繰り返したということを――。
夕暮れ