
獣人戦記スイロイド
Radical Rights
地下鉄奉仕団の一同を照らす、星のあかりだけは彼らに極めて優しかった。
世間をありのままで歩こうとすれば後ろ指を指され、ありのままで生きるために戦えば指弾される。
そんな生活にはある程度慣れてはきたけれど、どう戦っていいのか、地下鉄奉仕団の仲間だってわかってはいない。
それでも、獣人が獣人らしく歌い、笑い、話すことができるように、人間界から独立するために、地下鉄奉仕団の仲間たちは様々に考え、社会とコミットしつつ、夜には闇と罪とをまとって戦っていた。
今日も、獣人界の都、アリス特別市に存在するこのグループたちは、せわしなく食卓の準備をし、食事を始めていた。
食事中の会話と言えば、何もなければ雑談が普通ではあるが、今日は週一度の集まりとして、報告会が開かれていた。
今日は報告会ということで、全員、獣人界で伝統的に着られている平服の獣人服を着ている。
胸の部分までしかない上着と、胸の部分から延びるスカート。
それをまとった獣人たちは、胸に獣の兵士であることを示す獣人文字の「獣」という文字を、誇らしげに飾っていた。
「教育隊。そちらはどうだ?」
今週の議長である、ホワイトタイガー族の男性、ルダルは、兎族の女性、ホルンを指す。
ホルンは獣人学校の獣人語教員をしており、教育からの独立を果たすべく、邁進していた。
「俺たちのところは音楽会が生徒を守るために中止になっちまったけど、代わりに演劇会になったぜ。タンビの作った演劇、生徒からも好評だ」
ホルンは言うと、自身の目から光を放ち、映像を見せる。
そこでは獣人初めての王である、タングンと、クマ族の女性であるウンニョの物語が描かれていた。
「ボクがプロデュースした奴、喜んでもらえてよかったよ!」タンビは満足そうに笑う。
しかし、ホルンとしては歌を歌えないということに、いささか心配そうに耳をひくつかせていた。
「どうしたのかにゃ?」黒猫族の男性獣人、セラはすり寄る。
「そうだな。歌が歌えないってのがなんてか、怖いな、って」
ホルンは言うと、全員が黙る。
「その話、ボクがあとでするね」
タンビは言うと、ホルンに微笑む。
そしてシャチ族の女性、ルカを見る。
「僕たち大学研究においては、獣人の抵抗運動を黒人や人間界の韓国人の運動の研究、あるいは障碍者や性的少数者、獣人、貧困層などの周縁文化を研究するだけでなく、それを伝える役割を行っている。人間の教化はやはり困難があるが、獣人たちは着実に獣人だけでなく困難にある人間たちにどのように向かったらいいのかを考えるようになっている」
ルカは言うと、いくつか資料を出し、説明を始める。
そして説明が終わると、タンビが立ち上がる。
「それで、教化を一番されたのが、大学院生で、ルカセンセの一番弟子のボク!ってわけ」
その言葉に、全員が温かく笑う。
タンビはその言葉を聞くと、にこりと笑って自席に戻った。
それを確認すると、ルダルはカワウソ族の獣人、イェスルを見た。
「イェスル。宣教部はどうだ」
その言葉に、イェスルは起立する。
イェスルは獣人の信仰する宗教である獣人教の指導者、モクサをしており、モクサとして
「まず、私たちの主を賛美したい。そして、私は主の導きに応じて、困難にあるものなど、捨てられたもの、詳しく言えば獣人や障碍者、野宿者などに福音を伝えるべく、宣教を行ってきた。数を誇るつもりなどないが、最近、洗礼を受けた獣人がいる。彼は獣人としてはまだ若いが、獣人記をよく読み、獣人としての喜びや、低くさせられた獣人のために頑張りたいという意思が強いようだ。そのほかにも獣人教団の内部でも独立協議会が発足し、徐々に獣人としての信仰、そして獣人教原理主義とのエキュメニカルを実現するべく鋭意進めている」
一同はその言葉に、力強い勇気を覚える。
そして一同、屈託のない笑顔で拍手をした。
「では、供給部の話はどうだ?」ルダルは聞く。
するとセラと、茶猫族のシイ、ブタ族のボラは立ち上がる。
そしてボラは説明を始める。
「獣人フェアトレード・賃金向上運動の成果ですが、品物のクオリティが安定してきたのもあり、売り上げはさらに上昇しています。しかしながら、まだ獣人の作ったものは汚い、獣人のフリー文化は人間社会を壊す、と言った誤解があり、これからの宣伝活動や、普及運動の加速化が必要不可欠な状態です」
獣人として初めての精神障害福祉士の称号を持つボラにとって、障碍者施設で困難にある獣人たちを訓練しながら思わされたこと。
そのことを思い出すと、このプロジェクトは別の意味での難易度を感じた。
「しかし……」ボラは息を吐く。
「障害者であれ、獣人であれ、どうして購入していただけないのか、と考えたとき、そこに差別があるのではないかと疑ってしまいます。しかしながら、獣人の生み出す商品は私たちが獣人であることを差し引いても素晴らしいものですし、となると私たちの営業不足であることを思わされてしまいます……」
ボラは言うと、ゆっくりと息を吐く。
よっぽどしんどかったのか、ボラの目には涙が浮かんでいた。
ルカは近づき、背中をさする。
そしてボラを引き連れて、奥の寝室へと消えていった。
「とりあえず人間の購入率は悪い。ただ、獣人からは圧倒的な支持を受けている。これを人間にいかに拡大していくか、今、私たちで商品の選定を行っている。獣人の農家を救うにはまだ足りていないけれど、頑張るつもり」
シイは言うと、ふう、と息を吐き、獣人が心を込めて作ったパルサンサイダーを飲んだ。
のど元から突き抜けるようなサイダーのさわやかさに、心のもやもやが晴れるような気がした。
「政治工作部。どうだ」
ルダルの言葉に、シャチ族の男性、サンムと、兎族の女性ナウンは立ち上がる。
「そうだな。でも、いったん芸術部に話してもらった方がいいかも」
その言葉に、ルダルは目をしかめる。
しかし、サンムはそれを無視してルダルに代わるように勧めた。
「芸術班。そっちはどんな感じだ?」
ルダルは言うと、タンビと、ソリを見た。
地下鉄奉仕団の仲間で動画を投稿し、獣人たちの思想の正当性や、獣人音楽のすばらしさ、獣人語の普及をもくろんでいる。
この活動により、少しばかり獣人への理解者が出てきているように、地下鉄奉仕団の仲間は感じていた。
「うーん、それがねぇ。著作権侵害で収益がごっそり持ってかれちゃって……」
ルダルはまさかと思い、動画投稿サイトにアクセスしてみる。
そこでは、獣人歌謡の曲が軒並み著作権侵害の申し出が出されており、聞けなくなっていた。
「著作権、なんか最近、やっぱり運用が変だ」
ルダルは言う、
ルダルは弁護士として、当然のこととして著作権には詳しい。
しかし、獣人の作品のことで著作権法違反になるとは、どう考えてもあり得ないことだ。
だが、よく考えてみると最近、妙に著作権がらみで逮捕される獣人が多くなった気がする。
それを思うと、なんだか著作権法の方に問題があるのではないと感じた。
「著作権法、なんか最近おかしくないか?」
あるとき、ルダルは仲間にそれを持ち掛けた。
「確かに最近、著作権法、おかしいよね。だって獣人は音楽をダウンロードした時点で処刑だもん。かつて獣人界じゃ音楽はみんなのものだったみたいだし、その音楽を禁止されちゃったら、獣人らしく文化を楽しめないよ」
タンビは言うと、口を膨らませる。
獣人界。
かつて、この世界に存在したケモノと人間の中間のような存在だ。
大昔にひきおこされた士禍と、魔女狩りで追放された人間たちが転生の上築いたいた世界。
オープンな社会を標榜し、オープンソースや、フリーカルチャーの概念を誇りとしていた。
二本足で歩く獣のような生き物である獣人たちは、何世代もかけて獣人と人間のどちらの特徴を持つ、「半獣」を作り上げようとしていた。
しかしある時、人間界で起こった原子力発電所の事故の結果、人間たちとの交流が発生。
やがて人間界でもっとも獣人界に近い国が人間界を統一し、そして獣人界を侵略してしまった。
その世界では今、厳しすぎる著作権法で音楽すらまともに聞けなくなってしまっていた。
「著作権法ねぇ……オープンソースとか、自由流通も人間界じゃ禁止されたからね……」黒い猫族の男性獣人、セラはクルリとその場でしっぽを巻く。
「オープンソースを禁止したのは獣人界を否定するため、そして著作権団体を保護するためだったはず。となると、そうとうひどい法律だ」
シイはゆっくりと息を吐く。
「それから讃美歌と獣人記も著作権の保護下だ。少し前まで教団がNIMCAと会談して教会で歌うぶんには免除されていた。ただ、最近では私の教会でもそんな騒ぎがあったりするんだよな。獣人教会に土足で侵入して音楽を止めさせて、獣人たちが逮捕されたりもする。」カワウソ族の女性獣人、イェスルはゆっくりと息を吐き、その動向を振り返る。
「俺たちの学校もそうだ。獣人学校で曲を使うことは禁止されてらぁ。だからよ、獣人学校にゃ音楽の授業がねえんだ」
ホルンは言うと、ゆっくりと息を吐く。
そしてルカを見ると、「な」と目を合わせる。
「ああ。僕たちの大学でも、下手に音楽が使えなくて困惑している。獣人の曲も使えないし、獣人であるから、という理由で人間の曲すらも使わせてもらえない。そしてほかの獣人であったことだが、無理やり使おうものならどこからかスパイが紛れ込んで、逮捕してしまう。こんなことが許されていいわけがない」
ルカは怒りに満ちた表情で答える。
「大体、音楽や映像と言ったすべてのものが産業化されているせいで、それから漏れ出たものが一切の保護を受けられなくなっているし、獣人と言い、人間と言い、消費者や弱者の立場に立ててなんていない。著作権者は私たちは弱者だ、というが、果たしてそれはどうやら」
ルカは言うと、手に持っていた獣人の飲み物、ユジャのジュースを飲んだ。
さわやかな酸味がのどで弾ける。
「アイドルとして、私も言うね。獣人が歌っていた曲は全部人間が勝手に著作権登録して、人間のものにされているわ。それに、獣人が歌う歌なんかも、全部人間の管理下。著作権法に獣人保護法の、獣人に対しての権利制限がかかるから歌なんて歌えないのよね。獣人だと。だから獣人には歌手がいない。みんな歌いたい、って言ってるのに」
ベルはゆっくりと、しかし大きな嘆息を吐く。
ボラはしばらく手を広げて魔法を使うと、様々な情報をルダル達に共有した。
魔法。
獣人たちの科学の結晶である魔法は、約百年前に体系化された。
身体をつくりかえるような実験を何度も繰り返し、ようやく生み出した独自の技術は、やがて世界に広がり、そして研究対象となった。
技術に関しても火を起こす、長く泳げるといった簡易的な物から始まり、現在では情報を集めたり、人の意識を変えたりといった、大きな魔術も扱えるようになっていた。
「こんな感じで著作権法を推進している団体と、それにどんな団体がかかわっているか、リスト化してみました」
ボラは言うと、説明を始める。
「まず、NIMCA、人間音楽協会は関係者は当然主張しますよね。それに、出版社、作家組合、キャラクタービジネス業者。彼らも主張をしています。ただ、それ以上天界人の関与がなんとなく疑われているように思えるのは、気のせいでしょうか、ね、出番待ちの方」
ボラは言うと、隣に座っていたサンムを見る。
「そう。年次改革要求書には毎年著作権の改正が盛り込まれている。それを政府は何も考えずに実行している節がある。ただ、どうも匂うんだよな」
「ああ、匂うな」ナウンも言う。
「どうもカネが動いているようだ。そのカネを目当てに、多くの人間と天界人が動き回っている」
サンムは言うと、画面を映し出す。
そこには政治家の使途不明金が一覧として表示されていた。
「ここの天界の映画界のやつを出すと」サンムは言う。
データには様々な、獣人界でも有名な映画会社が加入している全天映画組合とかかれた項目があった。
「このグループから金をもらっている奴が、たくさんいるし、改革派のリーダーもそうだ」
その言葉に全員が息を吐く。
そんな雰囲気を見て、ルダルは立ち上がる。
「そうだ。今回は著作権から獣人を解放してみようか」
ルダルは言うと、ゆっくりと立ち上がる。
「ひとまず、獣人は著作物をどうしていたのか。そこをルカ、教えてくれないか」ルダルは言う。
ルカはルダルを見て、「お前は法律家だろ」と言外に言ったが、ルダルはあくまでそれを無視した。
「獣人はかつて、作品を作ったら自分のアカウントで販売していた。そのシステムはまぁ、人間でいえばwordpressみたいにオープンソースのシステムで簡単に構築出来る。それができなければ組合に加入してシステムを共同利用していた。獣人界には料金という概念はないから、どれだけの感謝を受けて、どれだけ早く謝罪したかの履歴を審査される。だから人間界の感覚では無料だった。その宣伝はどちらにせよ魔術の杖のネットワークである、オープンテレパスを通じて自分で、魔力を使って怒っていた。そもそも金銭というものを持たなかった社会ではあったが、その人の自由にどのような権利にするかを決められた。さらに人間のように中間に業者を挟まないことで自由な権利表明が可能で、作った作品をはじめから著作権者なしで発表してしまうことも多かった。一般的にはクリエイティブコモンズに似た権利システムを用いて、原作者表示をさせることが多かった……だいたいこんな感じか」ルカは言うと、全員を見る。
全員は一気に語ったルカを称賛するように手を叩く。
それを合図に、様々な今後への議論や、質問などが飛び出す。
食事が終わってからも続いた話し合いが終わったのは、深夜二時を過ぎたころだった。
終わりに当たり、ルダルはこの作戦を実行するかを審議する。
実行に賛成するための手、そしてセラのしっぽは次々と上がり、可決。
ルダルはイェスルの目を見る。
イェスルはゆっくりと息を吐いた。
そして彼女は獣人記と獣人語で書かれた書物を開く。
獣人記。
獣人たちの歴史と信仰が書かれた本。
それを開き、イェスルは祝祷を述べる。
「荒れ狂う嵐の中、勇気をもって踏み出していこう。雨を我らは降らせ、その雨により、義と悪とを裁き給わん。神よ、我らに義の力と権能を与え給え。獣人の民を救うことを赦し給え!」
それから獣人たちは作戦会議を開き、どのように立ち向かっていくかを会議する。
そして最後、ルダルは「地下鉄奉仕団、愛の雨を降らそう!」と、戦いの宣言をした。
地下鉄奉仕団。
獣人として、人間に立ち向かうための戦線。
人間と戦う獣人であればどんな獣人であっても拒否はしない。
アリス奉仕団としての戦いの開始に、ホルンたちは武者震いをした。
Stella Analytics
セラとルカ、そしてタンビはひざを突き合わせ、一冊の冊子を読み込んでいた。
「社会調査の基礎」と書かれていたその冊子は、システム学という、ソーシャルサーベイをきちんと学ぶ必要のある学問を学んだセラにとっても難しさのあるものだった。
ルカはセラと、そして横で学んでいるタンビにわかりやすいよう、レジュメを切って配布している。
「このように、社会調査には質的調査と、量的調査がある。質的調査はかなり成果が出ているとはいえ、いまだに客観的な結果が出るとは言えない。ただし、生の声や、データでは見えない意識なども読み取ることができる。一方で量的調査は客観的だが、生の声を取ることができない。しかし、これは人間が行うときの話だ。魔法を使った調査をする際に必要な手段はあるだろうか?」ルカはホワイトボードにいろいろと書きつつ、二人を見る。
タンビははいはい、と楽しそうに手を挙げているが、セラはその場で丸くなり、眠っていた。
ルカはゆっくりと息を吐くと、「セラ、お前なら答えられるはずだ」と起こす。
するとセラはにゃん……と言って眠そうにルカを見る。
そして少しばかり黒板を見ると、ああ……と眠そうな声で言う。
「MRS(魔術ランダムサーベイ)を行うときは人間の手を加えないことが大切なことだよね。人間が手を加えることで恣意性が入ってしまうし。それを避けるために調査員は質問と意識魔術をしっかりプログラミングして、魔術使用者に対して有意な量のサンプルを取り出さなくちゃいけないね。まぁ、それは計算で出せるから簡単なんだけど」セラは言うと、再び眠ってしまう。
もう南中しているというのに眠ってしまうということは、前日オンラインゲームをやりすぎたか、あるいは女装仲間と話し込んだのだろう。
どちらであれ、翌日このような約束があるのに眠ってしまう事の内容にしてほしいものだ。
ルカはそう思い、長いため息を吐いた。
それでも魔術を使い、意識に直接入り込んで行う魔術サーベイのことを、少なくともセラはよく理解していることに、ルカは安どする。
「じゃあセラ、もう一つ聞こうか。統計的に優位というとき、何を見たらいいだろう? 特にMRSを行うことにおいて、どうすればそれは統計的に有意といえるだろうか?」ルカは不敵な笑顔で聞く。
これから行う作戦、社会統計において必要な知識を確認しつつ、ルカは質問によって自発的に授業に参加してもらうように工夫する。
授業は自発的に参加してこそ本人のため。
だから多少嫌がられても、ルカは授業で人を指すことをやめなかった。
その意識はセラであっても理解できる。
それでも、このような南中した太陽が温かく照り付ける春の気候のこの日くらい、ゆっくり寝かせてほしいとセラは思った。
統計的に有意。
例えばリンゴが大きいか小さいかということを、数字だけみて言うときに、それが本当に大きい、あるいは小さいかを示すものだ。
それが分からなければ統計学的な意味はない。
そして、このデータは意識改ざんを行う上で、把握しておくと非常に有利に働く。
だからこそ、社会学を教え、魔術を使うルカとしてはセラたちに再び認識してほしいと願っていた。
その瞬間、セラは「えーっ!」と激しい抗議の声を上げる。
「僕、昨日不眠で眠かったんだよ! ゆっくり寝かせてくれよ」セラは少しばかりきつい声で言う。
しかしルカも負けない。
ルカはいたずらで不敵な表情をすると、セラを見る。
セラはその表情にどこか威圧感を感じ、しっぽを激しく振る。
「今日、このような講習を開くことを僕は伝えたし、お前たちは約束した。約束したのならばきちんとその約束を果たさなければならない。それは獣人であれ人間であれ、礼儀だ」
ルカの言葉に、セラは長くて大きな息を再び漏らす。
そして眠たそうに立ち上がる。
心なしか彼の魔術着のスカートも力なく揺れていた。
「まずは平均値を出して、そこからt検定だけど、意識を魔術で解析するマジックサーベイを行うときはそれができない。だからスカイ=アース魔術で検定するんでしょ」セラは言うと、ゆっくりと座り込み、眠ろうとする。
しかしそれを見たルカは「じゃあセラ、スカイ=アース魔術はどうやって使ったらいい?」と、セラを起こす。
セラはついに不機嫌を隠さなくなり、癇癪気味に「あーーーーっ!」とうなったのち、シャー!と、しっぽを大きく膨らませた。
・・
ルカは魔術設計と実行を課題と称してセラとタンビに任せた。
二人はその時から研究室にこもり、魔術コンピュータを立ち上げる。
「僕まだ寝たいのに……」セラは眠そうに目をこすり、大きなあくびを何度も上げている。
「まぁ、仕方ないよ。きのう何していたのさ? 女装仲間とチャット? それともオンラインゲーム?」タンビはニコニコとした表情で聞く。
セラはなんともうっとうしそうにタンビを見て、息を大きく吐く。
「女装仲間とオンラインゲームだよ。昨日タイムアタックがあったんだ」セラは目をこすり、カップに入ったカッファ茶を飲む。
カフェインがコーヒーの5倍入っているという、獣人界の劇物だ。
それを煽るように飲むセラを見て、少しばかりタンビの胸はときめいた。
鼻をすんすんと動かし、セラを嗅ごうとする。
「きもちわるいにゃあ」セラはタンビの行動を手でいさめる。
「だって、美しかったんだもん」タンビは言う。
するとセラは犬歯を出し、「今度やったらシャー、だからね」と、タンビをみて妖艶に微笑んだ。
「んで、あんまり飲むと眠れなくなるよ?」タンビは苦笑いをする。
「僕は夜起きて朝寝る崇高な猫族なんだ! だから僕を真昼間に起こすのは理不尽かつ人権蹂躙なんだよ!」セラは相変わらず言葉が強い。
よっぽど彼にとって、先ほど起こされたことは不快な出来事だったのだろうと思い、タンビはまた苦笑いする。
自分も眠たい中無理やり起こされて、何度も発言を求められたらうっとうしいかもしれない。
そう思うと、セラを責めるのもなんだか気が引けるような気がした。
タンビは気持ちを変えるべく、
「それで、スカイ=アース魔術は組めたのかい?」と聞く。
スカイ=アース魔法。
かつて魔術社会統計学を研究していた虎族のスカイと、シャチ族のアースが二人で開発した統計魔術だ。
t検定とF検定の知識や、テキストマイニングの知識が必要になるものの、感情を示すコードや、言語にこもった発話者の意思をアカシックレコードから統計的に処理することで、当時の状況や意識を計算しやすくするものだ。
これを組むためにはそれなりの学習が必要とされている。
タンビは文献や、実地での調査が中心となるため、統計学はあまりよくわからない。
せいぜい学部で習う人間に対してのフィジカルサーベイだけだ。
一方でセラは大学院でシステム・意識魔術を研究するにあたってマジカルサーベイの方法を学び、それを何度も実行してきた。
その実績を思うと、分野が違うだけとはいえ、セラに対してどこか胸が痛くなるのを感じた。
しかしながらセラはタンビの不安に反してけろっとした顔でコンピュータを見て、しっぽを満足そうに揺らす、
「うん。一応組んださ。ただ僕としては仮説として、人間は著作権に賛成で、獣人は著作権に反対なんじゃないかって思うよ。SNSとかで人間の創作者を見た限りだけど」セラは少しばかり肩を落として言う。
タンビはその言葉を聞いて、思わずため息を吐いた。
人間の創作意欲というものは、著作権によって裏付けられている部分が往々にしてある。
例えば、小説サイトに掲載している多くの小説家の卵たちは自分たちの小説を多くの人に読んでもらいたいと願っている。
そしてあわゆくば自分たちの小説が書籍化され、さらにはアニメなどの映像になってほしいと願っている。
しかしながら、それは自分の投稿したサイトで、きちんと自分あてに結果が返ってくること、そして自分でその権利をコントールできることが前提となる。
その時、彼らの夢の前提には著作権がある。
実際、数年前に竜人界のドラゴニュートたちがWEB小説サイトのAPIを取得して小説サイトに転載したときなどは「パクられる」と大騒ぎし、ドラゴニュートたちの間で禁止されているという民主主義を訴える言葉を書き、抵抗しようとしていた。
また、イラストレーターや漫画家もまた、小説家や、クリエイティブを消費する人間にイラストや漫画を無断使用しようとするものならばこの世の終わりかのように騒ぎ立てる。
それが人間界の正義だとされ、それに盾をつく者には容赦なく人間のクリエイター様やアーチスト様から容赦のないサンクションが与えられる。
その感情が、獣人としての意識として、セラにはよくわからなかった。
あまつさえ人間はその著作権をひとに管理させ、自分のものにならなくなっても大きなレコード会社や出版社にその原稿を預け、発売する権利を分け与えてしまう。
そして権利を大資本に管理させ、はした金を得ようとする。
その考えを、セラも、タンビも理解したいとは思えなかった。
獣人界はフリーカルチャー・フリーソフトの世界だ。
誰かが開発したものはみんなで使おうという文化である。
もちろん彼らには著作権がないわけではない。
コモンライツという、自由に使うにあたってどのようなことを守ってほしいなのかを簡単に記した条件書を飲むことで自由に使えるという仕組みを用い、その反中であれば自由に使用できるというものであった。
例えば自由に使っていいけれども商用利用は禁止、その条件をコピー者も継承しなくてはならない、となると、その条件もコピーしたうえで新しく尽きたした部分も含めた公開の権利と、公開に当たっての義務を引き継がせるというものだった。
しかしながら獣人は商売をする、私有財産にする、というよりも共同で使うという意識が強く、知識を発展させるためには自由な文化が不可欠だと考えられている。
そのため、多くは仕組みや作品を作ったのちは「同じ条件で、原作者の名前を表記する」という条件で配布することが多かった。
このスカイ=アース魔術の大まかな設定がなされたパッケージ自体はコモンライツとして二人の魔術ネットワーク上にあるサイトから自由にダウンロードし、獣人の意識調査に使えるようになっていた。
また、このパッケージは多くの人によってジェネリックや快適にた
それだからこそ、文化を寡占しようとしたシンは斬新な人間であった。
彼はデータを独占し、強固なデータセキュリティを敷くことで、自分自身の放送をお金を払わない、彼の言う不届き物には見せないようになっていた。
さらにデータのコピーも行わせず、その代わりペイパービュー方式をとることで、番組をお金を払ってみるというビジネスモデルを取り入れた。
その結果、獣人はシンの放送局に寄り集るようになり、そして乞食のように人間界の放送を目当てにクレジットカードを作り、動画をみ始めた。
そしてペイパービュー方式を取ったことで視聴者が過去の情報を知るときはさらにお金を取ることもできるようになった。
人間がアニマリアンの奴隷であり、どんな極悪な行動をしても怒らないのは十分に二人には理解できている。
しかしながら、獣人の立場として、この搾取はひどく腹立たしいものだった。
そのように金を巻き集め、政府系の特殊会社として国の保護を受けた結果出来上がったものがアニマリアンであり、また、彼らは人間界の音楽として獣人の音楽を扱い、一方で楽曲の利用は外国人として法外な使用料を請求している。
そんな理不尽があってたまるか、と多くの獣人は思っていたが、それを訴えて死ぬよりかは、不愉快な真似に遭いつつも作り笑いをし続ける方がきっと心が楽なのではないかと、内心諦観していた。
そのことを思い出すと、やはり理解できないことだらけだ
努力したから何?
生活のためだから何?
そして、獣人だから何?
主権を忘れたの?
大切なことは文化を発展させるためじゃないのか?
人間たち、とりわけ海賊版を取り締まる立場の人間や、NIMCAはそれを願っているからこその銭ゲバだと世間様に公言していた。
そう考えると、セラの眠気でうかされた意識は、少しばかり波が立つ。
どうしてその銭ゲバに自分も付き合わなければならないのか。
ましてや抑圧している側から金を巻き上げたことで嫌な思いをするのではないか。
その怒りを鎮めようと息をすると、胸がひりひりした。
「なるほどねぇ。確かに人間って、獣人の権利は否定する癖に自分たちの権利には人一倍敏感だもんね……。となると仮定は人間は著作権違反に敏感、ってとこか。獣人の結果と比較すればいい感じで出るかな」タンビは言うと、真ん中の膨らんだ、俵のような独特なボトルからパララ牛乳を飲む。
甘くてこってりとした液体が、タンビの回転し始めた頭の過回転を防いでくれた。
Social Survey
その後、ルカとともにこの作戦の第一歩を実行することとなった。
著作権意識のデータは二〇一一年以降、人間についてはNIMCAの調査が存在することが分かり、それをハッキングして調査に活用する。
他の世界であればオープンソースにするようなデータですら著作権保護を訴えているところに、人間の劣後を感じる。
人間界のデータはだいたいにおいて手数料を徴収する。
他の世界が次々と情報公開の機運の高まりを受けてオープンソースや条件付きフリーソース、いわゆるコピーレフトにする中、いまだにかなり高額な手数料を徴収し、さらには研究者を守るためと著作権を主張する人間界には、かつてから軽蔑の目が世界各地から寄せられている。
しかし、あくまで人間界がかわいくて、特にドラゴニュートのすることと反対のことをすることが正義と考え、さらには独自ルールを考えることが正義と信じて疑わないサクラダ首相はじめ、人間たちにはその侮蔑を理解できないようだ。
その愚かさに、ルカは研究者として、そして国民としていら立ちと憐れみを感じていた。
そしてデータ盗用を行うことについて、ルカはこれが論文研究でなくてよかった、と胸をなでおろしつつ、そのデータをルカの脳の、意識ストレージから転載する。
学位論文などでこのような真似をしようものならルカの教職としての権威も、名誉も、そして職もすべてが吹き飛んでしまう。
そのことを考えてもデータを盗み出せるほど、ルカには勇気はなかった。
そして魔術コンピュータに表示されたそのデータを見て、セラたちはなんとも言えない、あえて近い言葉で言おうとすれば苦虫をかみつぶしたような表情をした。
獣人界と比べることはまだできておらず、どちらがどのように多いということはまだできないにせよ、総人口のうち八十六%の人間が著作権を尊重し、そして著作権料の支払いについても同意すると答えている。
この結果はおそらく人間たちがそれだけ盲目に著作権を信仰し、そして守ろうとしているという証左のように見えてならなかった。
さらにそれに寄せられているテキスト回答や設問調査を読んでいくと、著作権を守り、金を払うことで文化発展が促進される、著作権には何年もの間を掛けて作り出した作りてその人の技術や思いが詰まっている、といった素朴な感情が込められていた。
それをスカイ=アース魔術に掛けつつ、タンビは人間について逡巡してみる。
人間はおそらく、かなり素朴で感情的、情緒的なものを信じようとしているのかもしれない。
著作権を振りかざし、産業化することで文化が発達すること、著作権を無理やり延長してでも守ることで新しい文化が発展すること、著作物は皆、努力の塊なのだから、著作権を振りかざしても問題ない……。
産業化された、誰もが共感できると歌う文学や音楽のどこにその作り手の思いが込められているのだろうか。
そして誰にでも聞きなじみのいいような歌を歌い、言葉をつづって何が一体楽しいのであろうか。
タンビは考えてみるが、よく理解できなかった。
一端自分の感情の鍋をゴトクの外に外して、出来る限り客観的に人間を見つめてみる。
彼ら人間派、魔術を通したわけではないので印象論ではあるが、その情緒や、上から与えられることを盲目的に守り、それを違反するような、いわゆるコピーレフトには反対するのだ。
なぜか。
理由を考えてみると、いくつかありそうだ。
ただ、そのうちの一つとして人間は抵抗者を嫌い、いつまでも安寧のぬるま湯につかっていたいのだ。
そしてそれをもたらせてくれる権威に抵抗することをやめ、その権威に抵抗しようとする者、しそうなものには仮に冤罪であったとしても攻撃を仕掛けようとする。
また、外の世界でいろんなものを見て来た人間たちには余計なことを口出しするなと常日頃監視している。
人間界は世界でも進んだ民主主義だと人間たちは信じてやまない。
しかしながら彼らは、何も見ようとしていない。
そう思うと、タンビは情けなく感じ、ゆっくりと息を吐く。
一方で獣人界がどうであったかを考えてみる。
コピーレフトで海賊版だらけであった獣人界、そしてかつての人間界ではやった香港映画の文化は発展しなかったのであろうか。
それに人間界の多くの国でデッドコピーをしてきて成長したはずだ。
電車、音楽、小説……。
そのパクり方は尋常ではなかったはずだ。
それがあるとき、まだ人間界の国があった時に、国同士の取引を行う上で著作権が必要になり、やがて著作権を守らない世界や国家に対して蔑んだ目で見るようになった。
獣人界もあるときからパクり天国として人間から蔑視されるようになり、それを憂いた人間派の獣人たちが著作権と商標権、そして意匠権を整備しようと各種戦いに出ていたことを思い出す。
しかし、それらは実際には実現せず、その戦いに参加していた獣人たちはやがて、獣人界の売国に動いていくこととなる。
では、著作権は必要なのだろうか。
獣人の立場からしたらいらない。
というよりも意識したことのないものだ。
創作物であれば、二次創作をする人はそのもののファンであるわけだし、使おうとするということはそれが好きだからだということだ。
獣人たちはそれを理解し、雨後の筍も含めた多くのアイドルや作品を輩出しては消費し、そしてつぶしてきた。
それだからといって資源の無駄などは起こらず、勝ち残った資源に関しては多くの人がそれを使うようになった。
さらに負けたものからサービスの長所を鹵獲し、補うことでサービスをさらによくすることもできた。
そんな事情や、客観的なメリットを真剣に検討することなく盲目的に信じようとする人間たちを思うと、タルビはかわいそうに思えた。
「タンビ、考え事か」ルカは微笑む。
「うん。……人間って、かわいそうだな、って」タンビは言うと、ゆっくりと背のびをする。
ルカはしばし統計魔術の発動の準備をするセラを、パララウユを飲みつつ、タンビに耳を傾ける。
心なしかルカの尾ひれは楽しそうに動いていた。
「そうだな。盲目で、不自由を自由と錯覚している。そのコンプレックスをもしかしたら僕たちに向けているのかもしれないな」ルカは言うと、何か思うことがあったのか、杖を展開して指で文字をなぞっていた。
「さあ、始めようか」ルカは高らかに言う。
セラは「はいさっさー!」というと、コンピュータのエンターキーを勢い良くたたく。
今回はプライバシーを尊重するという宣言をしたうえで、その条件をごまかし、公開調査とする。
こうすることでこののちの作戦を有利にする意味があった。
また、合わせて人物特定のために人間に対しても調査魔術を行っている。
巨大なセラの青い魔法陣が展開され、徐々にデータが集まってくる。
今回の有意数である二百万人のうち、五分ほどで一%が集まった。
「結構いいペースだね。そのほかの調査もいい感じだよ」セラは楽しそうに言う。
一方、ルカはセラの言葉を聞いている余裕がないのか、生返事を軽く返すだけだった。
「セラ、長期戦になるかもしれない。お前のサポートは精一杯させてもらうから、どうか起きていてくれ」ルカは涼しそうに、しかし熱意を込めて言う。
ルカの意識のなかにも次々とデータが飛び込んでくる。
「本当にしんどいのは君だろ? 僕のことは気にしないで、自分のことを気にするにゃぁ」セラは言うと、ゆっくりとしっぽを振る。
セラはこれからの長期戦を覚悟してか、自身の杖に魔術コンピュータのゲームを接続し、遊び始めた。
タンビは何かすべきだろうかと考え、パタパタと走りだす。
しばらくすると彼女は大皿いっぱいのトックケーキという魔術菓子を持ってきた。
餅のような触感のトックと呼ばれるお菓子の上にクリームや果物を練り込んだあんこを載せた菓子。
それをテーブルに置いた瞬間、セラの手がそれに伸びる。
味が良かったのか、セラは黙ってしっぽを楽しそうにゆっくりと揺らす。
一方、サーバとなっているルカの脳内は今頃相当激しく回転しているはずだ。
脳に埋め込まれたSSDは問題ないだろうか。
自分の教員の心配をしたところで杞憂かつ、失礼なのかもしれない。
それでも、自分の先生が死んでしまうのではないかと思うと少し不安で、そして美しかった。
データマイニングで死んだ学者もいることは、ルカからよく聞かされていた。
あまりに大きなデータを扱い、SSDが吹き飛んでしまったのだそうだ。
今回も相当巨大なデータを取り扱っている。
そのデータに静かに耐え、分析をしているルカを見ていると、まるでフィラメントが切れかかった白熱灯が最後に派手な発光をするような美しさを感じた。
自分の師である教員にそんなことを思ってはいけないと思いつつ、その死を掛けた美しさが目に見えて美しい。
このまま教師の首を絞めて殺したらどれだけ美しく彼女は死ぬのだろう。
そしてその美しさこそ、自分の愛なのではないかと思う。
死の美しさは、先代のタンビの死でよく知っている。
むごたらしく死んだ彼女は、もうこれ以上悪くなることはない。
死はそこで悪化や変化を止め、いつまでも美しいままで人間を残しておいてくれる。
妹の死以降、それはタンビにとっての真実となった。
そして生を燃やし、最後まで真っ白になるまで燃えた。
その美しさを思い出すと、不思議と口元からよだれが漏れた。
――先生を、むしゃぶりたい。
タンビはふと、ルカの腕をなめる。
そしておいしそうな場所を見つけると、ゆっくりと歯を落とす。
柔らかな皮膚に、自分の犬歯の硬い刃が突き刺さる。
そして真っ赤な血がタンビの口の中に流れてくる。
こんなものでルカは死んだりしない。
それでも〇・一ミリでも死に近づくルカを見ると、心の中で美しさを感じた。
その瞬間、ルカは目を覚ます。
そして自分の腕に刻まれたタンビの歯型を見て、ゆっくりと息を吐く。
「お前の傷は、深いな。……イェスルに祈ってもらえ」ルカは言うと、タンビを抱きしめる。
その瞬間、タンビは「そうね」と口角を緩ませる。
・・
それからしばらく、タンビはセラとルカを眺め続けた。
生と死を駆け巡るような表情をした二人にくらくらしながら、自分の気がやられないようにビーフジャーキーをかみ砕き、様子を見る。
途中何度かルカが大きなデータを取り扱ったのか、苦しそうに目を閉じる。
その様子が、なんだかタンビにとってはとてもおいしそうに見えた。
その考えがまずいと首を横に振り、ジャーキーを再びかみちぎる。
それを繰り返しているうちに、五時間後が立つ。
二人は達成感と疲労をかみしめるように、長く、少し荒々しい息を吐く、
彼らの表情は疲れに満ちていたが、どこか充実していた。
「どうだった?」タンビは聞く。
「人間の意識の中からはもちろん、獣人が音楽や文化をどのようにして搾取されてきたかまでよくわかったにゃぁ」
セラは眠っていないからか、ひどく疲れた表情でタンビを見て、微笑む。
「人間は九十%が著作権に賛成、一方で獣人は三十%に留まる。獣人が著作権を認める理由は人間に迫害されるから、それだけだ。そして獣人から何か被害があったか、と聞いたら、これはパンガも言っていたが、障碍者施設などでキャラクターを無断利用して迫害された、イラストを描いてそれを外で、非営利で展示した姉が処刑された、野外でヤカグムで曲を弾いていたらNIMCAの人間に暴行された、といったケースがあった。特に目立つのがNIMCAまわりだ。作った音楽を勝手に著作権登録され、コンサートを開こうとしたら請求が着て、それに抗議をしたら逮捕された……。これは十件ある。さすがに音楽ヤクザと言われるだけある。そのNIMCA自体は音楽に関わる人を守るため、と宣わっているが、果たしてそれはどうなのだろうか」ルカは言うと、ゆっくりと息を吐く。
NIMCAの暴力、アニマリアンの横暴。
そのすべての記憶を一つ一つサルベージしてみていく。
そのたびに三人の表情は曇っていき、やがて怒りに変わる。
たかが創作物で命を奪い、さらにその創作物すらもすべて奪って行ってしまう。
その横暴をルカたちは許せるほど、大人ではなかった。
「もう少し分析する必要もあるだろうが、これに獣人の音楽や著作権が軒並み人間によって不正に著作権登録がなされている事実と合わせて鑑みると相当やはり問題だ」
ルカは言うと、セラを見る。
「獣人の九十%は著作権の奪取程度は願っているね。これのミソは著作権に賛成する獣人の多くも獣人から奪われた著作権を取り返してほしいと願っているね。となると著作物を取り返す、ということくらいは賛成しているみたい」セラは言う。
「勝機、あるね」
その言葉に、タンビはからからと笑う。
「じゃあ、雨、降らせちゃおうよ!」
タンビは言うと、手を高くつきだす。
その言葉にセラたちはゆっくりと首肯した。
Influencer Dominated
ルカ、セラ、タンビ、それにこれからの作戦を行うために呼ばれたソリは、先ほどの調査結果を評価するべく資料に注目していた。
「獣人が著作権団体に対して不満を強く抱いていることは非常に理解しやすい。t検定の結果を見ても十分に有意だ」ルカは言う。
ソリはその結果が掲載された電子レジュメを見る。
統計学を詳しく勉強したわけではないソリにとっては少しばかり読みづらさもあったが、それでもかなり充実したルカの注を読んでいくと、少なくともわかった気分になれた。
獣人に対しての不満について、ルカは検定の結果だと言っていた。
しかし、数字だけを見てもどう見ても獣人が不満を感じているのは理解できるし、それに獣人たちを搾取する人間の行動を見ていると、それに不満を持たない獣人などいるのだろうかという気持ちになる。
それでも獣人の中にはこれだけのことをさせられたとしても人間の行動を高く評価する者もいる。
そんな獣人に対して「理解できない」というだけなら簡単だが、いったいどのような理由で人間を支持していたのかが気になった。
ソリはそのまま結果を読んでいく。
そして「著作権賛成派獣人」という項目を読んでいく。
「身に着けるまで大変な時間とお金がかかるものを使う対価」「自分の商品を泥棒されないようにするため」と言った、資本主義と個人財産の概念に満ちた発言を読み、ソリは長い息を吐く。
獣人たちはかつての自由でシェアをする文化の概念ではなく。所有財産を主張し、自分たちの技術すらカネに変えてしまう。
それが一体どのように社会や個人を発達させるというのだろうか。
インターネットやソーシャルマジックの社会の中で、カネをちらつかせて発達したものは少なく、カネではなく賞賛とリスペクトで成り立つ社会こそが発達するのではないか。
そして、そこまで難しいことを言わなくとも、自分たちを抑圧する人間に対して、どうしてここまで隷属することができるのだろうか。
獣人はここまで隷属的で、愚かな存在だっただろうか。
そう思うと、ソリにとってはひどく悲しい出来事としてとらえられ、そして画面から目をそらし、遠くを見つめた。
「それに理由のテキストマイニングの結果を見てもかなり獣人作品の搾取と、それへの排他的な行動に、本来使えなくちゃいけない獣人たちが排除されてしまっているのと、皆で共有財産として使っていたのにも関わらず、それを独占物にされ、さらにそのマテリアルからアイテムを新しく自由に作れない、紹介できなくなったことに関して、かなり不満が上がっているね」
セラは魔術コンピュータに表示された魔術サーベイの結果を見て言う。
ソリもまたその記事を見てみると、そこには胸がきしむような事情が描かれていた。
いったいどうしてここまで獣人を追い詰め、文化を奪い、そして搾取したのだろうか。
論理は理解できたとしても、それがなぜ獣人に向いたのかという気持ちにすらなってしまう。
そして獣人からすべてを搾取し、人間は肥えて、獣人はやせ細っていく。
その姿を無視できるほど、ソリは成熟してはいなかった。
「あと、ボクも参考意見としてある獣人に非構造面接をして、その結果を魔術コンピュータで解析してみたけど、人間と、人間が主張する著作権に対しての違和感をすごく持っているみたいなんだよね」タンビは言うと、近くにあったセラのお気に入りの椅子におもむろに腰かける。
セラは一瞬不満そうに口を膨らませたが、すぐに息をついた。
それでも何とか平和に、穏便に抗議という形で済ますことはできないか。
ソリは考えてみる。
その一つの手段として、何か対話がないだろうか。
人間と獣人との間で対話ができないか。
ソリはしばらく考えてみようと思い、目を閉じた。
考えていることを表すように、ソリの尾ひれはゆっくりと、しかし大きく揺れた。
もし人間と獣人が対等な世界であれば獣人著作権法を人間は理解しただろうか。
その異文化に対して、リスクと感じて人間は獣人を蹂躙した。
一方、人間と獣人の対話のチャンネルはあるだろうか。
一度洗脳と社会魔術で人間の世論を誘導してから為政者にその力を見せればもしかしたらチャンスがあるかもしれない。
幸い、人間の多くはSNSや小説・動画・漫画サイトでダラダラして一日を終わらせるような非生産的で無知蒙昧を地で行くようなな生き方をしている。
だからこそ、洗脳はできるし、平和裏に自分たちの意識を通すことができるはずだ。
ソリはポケットから「デイジーとアニメ」という天界人の書いた人間界論の本を取り出す。
そこには天界語で「人間は他人の眼を気にして生きており、それが天界人や、さらに彼らが蹂躙した獣人とは違う、『恥』を原動力とした行動様式を見せている」と書かれている。
実際に適応しようと思えばいくらでも適応できる部分がある。
世界中でが十年前に経験した新型ウイルスによる感染症で人間と獣人の感染が、かなり政府の無能をさらしても感染者を少なくできた点もここだった。
政府は特に人間に対して行動自粛に対して罰則をかけることはしていない。
また、自分たちが感染することに対して恐怖を思っているわけではない。
少し前に洗脳魔術を学ぶ特に習った本によれば、多くの人間は「人にうつしたら申し訳ない」という理由だった。
そして感染した人間は世間にお詫びをする。
何らかの事情で遠出をした者にはここぞとばかりにサンクションを加える。
その点に関し、獣人をはじめ、世界各地はひどく疑問に思い、そして人によっては人間に対して愛想をつかした。
結局人間には自分がないのだ。
自分勝手なくせをして利己を否定する。
そして自分がしてほしくないことを人にするなとは言うが、その利己だってない。
流行に流され、情報に流され、「みんながそうするから」「みんなといたいから」「みんなに嫌われたくないから」人に合わせて自分を押し殺し、獣人を助けようともしない。
獣人の歌やアイドルがはやっているが、そのうちどれだけが獣人というものを考えているのだろうか。
一方、獣人を敵視するインターネットで跋扈する頭の悪い右翼は、果たしてどの程度客観的で実感的な判断をして獣人を攻撃しているのであろうか。
結局人間は周りの意思に流され、自分の正義感なんてものはないのだ。
あるいはそれらは教育や社会生活でつぶされることをよしとしているのだ。
それにつかれると自分探しといってあてのない旅をすることになり、それを防ぐために個性を伸ばす教育ということも試された。
しかし、それらは世の中を多く占める愚かな集団に目を付けられ、サンクションを加えられることになり、その新しい目をつぶした。
それは仕事ができない、という批判を真に受けて、一切何も考えずに周りに便乗した愚か者のせいだ。
誤解を恐れず、一言でいえば、人間は想像以上に馬鹿で、自分なんてものはないのだ。
となれば話は簡単だ。
ソリはタンビたちの話を聞きつつ、作戦を練る。
そしてアイデアを思いつき、タンビたちに提案する。
その意見を聞いたタンビとセラはお互いの眼を見合ったのち、「おぬしも悪よのう、ソリ屋」と、ねっとりとした、人間の時代劇のような口調で言った。
・・
ソリはその足で自分の所属しているレコード会社へと向かった。
かつて自分が世話になっていたアニマリアンの事務所とはずいぶん違った、小さな獣人資本のレコード会社。
しかしながら人間派の獣人であるクマ族の社長イオナな煙草をふかし、ソリを見る。
「お前さん、かつて人間に歯向かっていたのに今度は人間になびくのか」
イオナは企画書を持ち上げると、煙草を灰皿に押し付けて読み始める。
その目にはわずかな疑問と興味を感じる。
おそらくこの企画は通るだろう。
ソリはそう算段する。
今までソリが上げてきた様々な企画をイオナが否定したのを見たことがない。
企画はすべて成功してきたし、それに経営を盛り上げている
ドル箱として目覚ましい活躍も上げてきたつもりだ。
となれば、この記憶をごまかして「またやろう」と思わせる魔法をかけた方がいい。
ソリはそのタイミングをうかがい、こっそりと魔法をかける。
「ソリ、魔法をかけてまで意見を通そうとするのはどうかと思うぞ」イオナは眼鏡を整えるそぶりをする。
その段階でイオナの考えが理解でき、心なしか落胆する。
しかしイオナはゆっくりと息をつき、ソリを見る。
「ねえ、イオナさん。私、聞いてみたいことがあるんです」ソリは聞く。
イオナは不思議そうにソリを見る。
「獣人と人間の対話をしてみたいんです。一体どうして獣人を搾取するのか、そして何でイオナさんは人間の搾取を黙っているんですか?」
ソリの言葉に、イオナは考える。
「獣人、そして商売人はしなやかに生きなくちゃいけないんだ。どんな岩の上であっても私たちが生きるために、風や嵐に吹かれて生きなくてはいけないんだよ」
イオナは言うと、煙草に火を点け、何か自分の心を洗い流すように息を吐く。
「社会は少しずつにしか変わらない。差別だの、搾取だの、抵抗だのと宣うことは、結局その怪物になってしまうんだよ」
イオナの諭すような声に、ソリは息を吐く。
どうしてこのような当事者意識のない発言ができるのだろう。
自分が攻撃されるとしてもそのような言葉を言うことができるのだろうか。
かつて人間界にまだ国民国家があったころ、ある独裁国家の中で生きていたキリスト教会の牧師は、独裁政権に対して無知であったことを嘆く歌を残した。
その歌をソリが知った時、それはイオナのこと、そして自分自身を言っているような気がして、胸が裂けそうになった。
無知でいること、無関心でいること、そして無責任でいること。
それが大人なのであれば、ソリは大人にならなくても一切構わないと思った。
「私は無関心で、無関係で、無責任になることが大人なのならば、大人になりたくありません。それで私の同胞や、そして私を殺したくないんです」
ソリは言う。
その言葉を聞き、イオナは長い息を吐いた。
そして企画書をテーブルの上に置くと、煙草を再び灰皿に押し付けた。
「お前さんが何かしら別の考えがあることは理解している。残念だがお前さんは止められないだろう。それに私も誰かに言ったら獣人法で逮捕されてしまう。……くれぐれも私の名前とこの会社の名前は出さないでくれ。ただ資金と場所、それから招待客のアサインはしておくよ」
イオナは言うと、煙草を吸い、コーヒーをすする。
「あぁ、生き返るよ」とけだるそうに言うと、ソリを見る。
「お前の保守論壇デビューってことにしておいてやる。どうかこの努力を裏切らないように、見た目だけでも保守論壇にいてくれ」
イオナは言うと、ソリを追い払い、再び煙草に火をつける。
--彼女たちこそ、自分たちの世界に音楽をもたらしてくれるのだろうか。
そう考えると、ソリのことを首にしようかと考えたこともある自分が恨めしく感じ、わざとらしく大きな咳ばらいをする。
その声を聴き、ソリは肩をすくめて微笑んだ。
それからソリの準備は早かった。
世の中にはとんでもない馬鹿がいて、その馬鹿にそれ以上の馬鹿が連なっている。
そのメンバーをルカとタンビに魔法で調べてもらったソシオメトリーをもとに抽出し、合わせて誰を呼び出せばいいのかを抽出する。
それにより選ばれた人数は、たった百人ほどであることが分かった。
医者、金持ち、普通の主婦、人間党支持者……。
ネットの言論世界を牛耳るそうそうたる顔ぶれが抽出され、ソリは小躍りしたくなる。
彼らを殺すか、あるいは洗脳すればもしかしたら話は早いかもしれない。
しかし、物事には順序がある。
ここで人間を殺すことで、いつか人間が反逆する芽を生み出してしまう。
それを避けるためにも、一度人間に獣人の恐ろしさを刻み込んだ方がいいのかもしれない。
そうすることで人間に対しての攻撃をさらに激化させられる口実を作ることができるのだから。
そして著作権団体関係者やインフルエンサー百人にSNSのダイレクトメッセージや講演会窓口などを通じて連絡をする。
この際、獣人アイドルという言葉に嫌悪感を抱く保守陣営を巻き込むために、ソリは魔法をかけた。
メールフォームに魔法をかけ、あらかじめタンビが考えたメールをコピーペーストして送り付ける作業。
しかしながら意外と面白く、一時間ほどで対応ができた。
それから一言神に祈る。
その願いを聞いてくださるか、ソリにはわからない。
それでももし聞き入れてくれるなら、それはどれだけ大きな恵みであるかを彼女自身よく知っているつもりだった。
だからこそ祈り、また賛美する。
それこそが獣人らしい生き方なのかもしれないと思った。
それからしばらくして、立て続けにメールが到着した。
ほぼ百パーセントの人間が出席を了承し、集まることになる。
ソリは手を突き出して喜ぶと、さっそく準備を始めた。
ソリは抑えてもらった会場で歌われる曲を吟味し、そして踊りを仲間に教える。
運動神経がいい獣人たちばかりであるためか、ほとんど一発で踊りを覚え、さらにブレイクダンスを加えるなどのアレンジまで加えられるようになっていた。
さらに目玉となる保守的な理論の構築をルカとともに行い、保守論者ソリを誕生させる。
イェスルは心配して「狂気に飲み込まれるなよ。ミイラ取りがミイラになるようなことは現実によく起こりうることだ」と忠告する。
そのことを鑑み、ソリはイェスルに狂気に陥らないよう、祝福と呪術を受けた。
さらにボラとともに支配する店、「めいどりんぐ」の衣装を改造し、より人間の喜ぶ煽情的な服を作る。
ソリが服のサイズを測る際、久しぶりの体格検査に全員がひどく嫌そうな顔をしたが、今は作戦なのだからと納得させた。
準備を重ねていくたびに本番へと近づく。
ソリはプロ意識と、作戦への責任を胸に抱きしめ、ゆっくりと深呼吸をし、そこで生きていることを楽しんだ。
Perfoming Maiden
それ以降、話は順調に進んでいった。
獣人を非難し、著作権法闘争に関してあげつらっていた人間たちであっても、ソリの洗脳魔術には勝てない。
しかもソリにとっては保険として掛けたかなり弱い洗脳魔術のつもりだった。
ソリが思想を転向させ、人間の心を癒し、獣人の秘密をすべて暴露するというキャッチコピーにひかれているのだ。
その手はずとして、証人たるレベッカ・ウメという人間を呼び出し、さらにシンポジウムを開くということで「反人間の教祖」であるルカを呼び出した。
・・
人間界東都の電気街にあるライブハウス。
クールヒューマニカのコアであるオタクたちが集まるこのエリアの一つのメイドカフェ。
ソリはここの控室となっている階段の踊り場で、一人小言で歌を歌っている。
クールヒューマニカというIPを諸外界で売りさばく政策の裏に、このような不適切で不都合なことがある。
アニメもそうだが、人間のコンテンツというものはたいがいにおいてろくなものではない、というのがソリが芸能人を行っていて感じることだった。
ここは電気街でもかなり大型のメイドカフェであり、人間界にあこがれと好奇の目を抱いた人間たちが多く集まるところだ。
メイドが「萌えもえきゅん」だの「おかえりなさいませ」などといい、人工的な女性を侍らせて男を喜ばせる店だった。
本当を言えばこんな店を使うことなどないのだが、人間たちはどうもこのようにして女性を搾取するものが好きなようだということがルカの調査で理解されており、それを用いた。
ほかの建物ではやはりメイドたちが、階段の踊り場でメイドバーのメイドたちが煙草を吹かしたり、ラーメンをゆでている。
タンビはメイドカフェの現実としてそのような店があることを解説していたが、実際にその姿を見ていると、なんだか悲哀を感じた。
「ひゃっほい! どうかな! ボクのメイド服!」タンビは嬉しそうにフレンチメイドの服をひらひらさせる。
耳には犬のぴくぴくと動く耳、しっぽはゆらゆらと動くもふもふした犬のしっぽが生えている。
これも搾取されるとはいえ、タンビにとって自由に露出できることはとてもうれしかった。
タンビの若々しい感じと相まってとてもかわいらしいが、露出の多い服を見てみるといかに人間の女性が人間扱いされていないかを感じることができ、ソリはわずかにしっぽを緊張させた。
「ちとこれは恥ずいな……」ホルンは目のやり場に困ったのか、長い息をつきながらソリに救いを求める。
ルカに関してはその恥ずかしさが嫌悪感に達しているのか、何も話そうとしない。
一方でセラは楽しそうにくるくると回ってみせる。
「かわいいね」セラは言う。
しかしセラとてこの服装を本当の意味で楽しんでいるとは思えない。
時折ソリを見て、「こんなに露出が多くて、ましてや胸も少し見えているような服に身を包んで。この服って、男の人に胸を見せてエッチな気持ちにするためでしょ? なんだか男として、女として、気持ち悪いよね……」
しばらくするとメイドのスタンバイの時間になる。
彼女たちはケモガールメイド隊として店の歌を歌い、給仕をこなす。
歌は店のメイドたちが歌う歌ではあるが、その歌い方は獣人たちに任されていた。
サクラは咲き あなたを狙う
ここが私のレッドサイト フロントライン
あなたにロックオンして トリガーを放つ
私の思い 届け君へ
もう私は あなたを逃さないわ
獣人語ではなく、人間語ではあるが、歌詞自体に気持ち悪さは感じない。
そして聞いている人間たちはかなり楽しそうにフロアでぴょんぴょん跳ねている。
その姿が楽しくて、獣人歌謡にあるようなシャウトをホルンが行う。
獣人教のワーシップにあるように、サビを何度も繰り返す。
そのたびに人間は汗をかき、恍惚とした表情を浮かべる。
それが楽しくて何度もリフレインしている間に、時間を忘れてしまう。
「ホルンさんたちさぁ……」ソリは不満そうに言葉をつなげる。
「みんなで踊ろうぜ?」ホルンは楽しそうに返す。
ソリはもう当分現状が変わることはないと、缶コーヒーを飲んで、舞台に上がる。
思想を今から転向し、救国のヒロインとなってくれる最強の獣人のお出ましに、人間たちは歓喜し、フロアのバイブスが盛り上がる。
あなたはとらわれているの
もう二度と離れられないくらい
忘れないで
あなたは私のとりこ
だからあなたを狙うの
あなたが逃れないように
ほかになんていかないように
サクラは咲き あなたを狙う
ここが私のレッドサイト フロントライン
あなたにロックオンして トリガーを放つ
私の思い 届け君へ
もう私は あなたを逃さないわ
さらにソリは、歌詞に獣人語を混ぜる。
これは魔術のトリガーにもなるものだ。
著作権や著作者人格権などを無視して獣人語に翻訳し、勝手に歌いこなしていく獣人のアイドル。
彼女はその中にスパイがいることを知っている。
著作権を守り、育てるという名目のもと、虐殺を繰り返す獣人の敵、レコード会社の人間がいることを。
ソリはその姿を見つけたから獣人語に直してうたい、そして魔法をかける。
|Botkkoteun Jijianhna Seolhok Nega Jitppaljeodo《サクラは散らない たとえあなたに踏まれても》
ソリは他のメンバーたちをバックダンサーに、体をしなやかに動かす。
ホルンと手をつなぎ、いったん5人の身体を、背中側から寄せる。
すぐに一歩体をしなやかにくねらせて踏み出し、一列に。
ソリが手を胸に当てて切なそうな様子を見せている間、ホルンたちは銃を構えたような姿をとる。
獣人たちが大切にしていた獣人歌謡のダンス。
けもの友達では決して披露できなかった獣人たちの踊り、そして歌。
すでに集団的沸騰のるつぼの中にいた人間たちは興奮し、目をかっと見開いている。
ソリたちは二プラス三のフォーメーションに別れ、せつなそうに歌う。
そしてまるで曲の盛り上がりを示すかのように激しく腕を動かす。
ここでソリとそのほかの獣人たちの動作が分かれる。
ソリはマイクを握り、前へ。一方でほかの獣人たちは後ろに下がり、ソリを包み込む。
そしてまるで花が舞うようにその場からくるりと回って離れていく。
さらに列になり、何かを祈るように手を合わせて軽くステップを踏む……。
見事な律動に、すっかり人間たちはとりこになってしまう。
もうここまでくればこちらのものだ。
「ルカ、ラップで切るかしら?」
「ラップ!?」ルカは素っ頓狂な声を上げる。
ソリはにこりと微笑む。
それに対抗できないと考えたルカは鼻を鳴らす。
「やるしかないか……」ルカは言う。
その言葉にソリは満足し、さらにソリはセラを見る。
「音楽魔術お願いできるかしら?」
その言葉に、セラはしっぽを揺らして応答。
すぐに曲は歌謡曲のような曲調から、獣人歌謡にあるようなEDMベースの曲調に変わっていく。
|Jeojakgwoneun Geunyan Gaegatteo《著作権はただのクソだ》
|Neo Jayudo Jitbbalgeo Isseo《お前の自由も踏みにじる》
|Neehwideuldo Ingangwa Suine Jayureul Jikil Su Itso《お前たちは人間と獣人の自由を守ることができるんだ》
|Let's go beyond, Fly to the freedom fleet《一緒に超えよう 自由の地に飛び立て》
|Amudo Mageul su Eobseo《誰も止められない》
|Nuguna Neomeul su Itseo《誰でも乗り越えられるさ》
|Buseora Break Shit N Fucking Copyright and Music YAKUZA《壊せぶっつぶせクソみてぇな著作権と音楽やくざ》
しばらくインターリュードが続き、さらにブリッジまで戻る。
|Botkkoti Piwo Neol Nuryeo《サクラは咲き あなたを狙う》
|Yeogiga Nae Red Sight Frontline《ここが私のレッドサイト フロントライン》
|Neol Nuryo Chongeul Sseo《あなたを狙って銃を撃つ》
|Nae Sowoni Neoege Dahtdeorok《私の願いがあなたに届くように》
|kumkkwo Eonjedeun Eonjekkajina《夢を見る どんな時も どんな時も》
獣人語とEDMで伝えられる人間の歌。
その妙味に人間たちはとりこになっている。
久しぶりに歌い、騒ぐ獣人の歌。
勝手に翻訳し、さらにラップまで勝手に追加している。
作曲者の感情なんてどうでもいい。
著作権なんて知らない。
そんな思いで歌う歌は最高に気持ちよく、ソリの脳天を突き抜けそうな快楽に襲われる。
ソリは一瞬目を人間たちにやる。
彼らはすっかり洗脳された黄色の眼をしている。
使い魔契約はすっかり完了している。
これに今まで作っておいていたリベラル層のインフルエンサーである使い魔を使うことで、人間たちに十分なインフルエンスを行うことができる。
ソリはそれに喜ぶと、最後に大きくシャウトして曲を終えた。
・・
それからしばらくして、伝染するかのようにインターネット上には著作権というものの欺瞞を訴える声があふれてきた。
さらに尾ひれがつき、NIMCAは科学界人の手下であり、人間を襲おうとしているといった陰謀論、はてまたNIMCAが獣人を蹂躙しているという正しい認識が広まっていき、大変な騒ぎになった。
さらにそれをリベラル系のラジオが取りあげ、獣人や使用者に対しての横暴を訴えるようになった。
そのことで全く獣人と著作権の関係を知らなかった人間たちにもリーチし、SNSは大きく盛り上がり、何やら人間の為政者にとって不穏な雰囲気をとなっていた。
その日を抑えるべく、レコード会社やNIMCAは「そのような事実はございません」という声明を出す。
しかし、次から次にセラたちが証拠を上げ、それを風説が流布されるメカニズムで伝播すると、もはやNIMCAがどうこうできる状態ではなく、やがて沈黙してしまった。
NIMCAや音楽会社は謝罪をしたり、搾取を止めようとはしない。
--そうか、ならば。
けもレイドの面々はお互い示し合わせ、次の作戦へと進むことを決める。
その作戦は、NIMCAの平和の最後の砦だった。
Cohort Analysis
シイはSNSの様子が映し出された魔術コンピュータの画面を見つつ、じっと分析を行っていた。
コホート分析なども援用し、どのようなグループ、思想を持っているのかを判断する。
しばらくするとシイはにんまりと笑い、背もたれにもたれかかって大きく伸びをした。
「どういう感じかにゃぁー」セラが近づき、画面を見る。
その態度に気に食わなかったのか、シイはセラの顔に軽くパンチした。
「痛いなぁ……どうしたのさぁ」セラは不満そうに聞く。
しかしシイは何も言うことなく、画面を注視した。
「馬鹿なこと言わないで」シイは言うと、セラを見る。「これを見て」
少しばかりぶっきらぼうだが、腕は確かな技術者だ。
そんなシイを、セラは嫌いになるどころか、深く信頼していた。
画面にはたくさんのハッシュタグが書かれていた。
#著作権に抗議しますというタグのもとには、本来まとまるはずのない左右の陣営が、それぞれの立場からNIMCAを非難している。
さらに詳しく読んでいく。
NIMCAが人間相手に声明を出した日には、獣人だけではなく、人間からも「嘘」「誠意を見せろ」といった非難が強くなっており、それは収まっていない。
セラ、そしてシイの魔術コンピュータで24時間体制で魔術が送られているのもそうだが、それ以上にオートポイエーシスが起動し、もはやその生成にはどこへも、どこからも刺激を加えることなく憎悪を生み出している状態だった。
「バカ猫」シイはセラに言う。
バカっていうことないじゃないか、と抗議しようかとも思ったが、そんなことをするのも無粋だと思い、にゃあ、とあえて馬鹿を演じる。
「にゃあ、じゃないわよ。これ、どうしたい?」シイはじっと画面を見る。
「サイボーグ戦士の最後みたいだね」セラは茶化す。
シイは如実に不愉快だという表情になり、セラの股間にパンチを食らわす
セラは痛みで思わず目を大きく見開いて、叫ぶ。
「ごめんって!」セラの謝罪を受け、シイはふう、と長いため息を吐く。「そうだね。僕だったらデモを起こそう、っていう入力をするかな」
セラは言うと、シイを見る。
シイはセラを見ると、「なかなかやるわね」といって再び画面を見る。
「こういった感じでオートポイエーシスができているのはいいけれど、下手にここに入力をするとそれがほどけて洗脳がおじゃんになってしまう。となったらどうする?」
再びシイはセラを見る。
しかしセラはそのことを考えていたのもあり、「そうだにゃあ」というと、セラの顔を見た。
「誘導かな。例えば、今、ホルンがデモ隊のグループに参与しているけど、彼女がどうやってデモに持っていくかといったところにこの作戦が成功するかどうかがかかっているね」セラは言うと、シイに少しだけ誇ったような表情をする。
再びシイは不機嫌な顔になり、セラの脇腹を殴る。
「不愉快だわ」シイは相当不機嫌なのか、そののちにも口を大きく広げ、シャーと叫んだ。
「でも君の言っていることは悔しいけど正解。ホルンは口がうまいし、ソリはそう言った魔法を持っているから割とうまく誘導できるかもしれない。ただ、ほかのコア人物がこれ以外のことでほかの属性のコア人物を攻撃しないようにしなくちゃいけない。その魔法をかけておかないと」
シイは言うと、ゆっくりと立ち上がり、うなだれたような表情になる。
セラは自分に関係ないこと、と考えて立っていると、シイは再びセラの足を踏みにじる。
その痛みでシイが何を考えているかを察し、セラもうなだれ、そして手を組んだ。
そしてシイが行う通り、足元に魔力を込める。
紺色の魔法陣が展開され、そしてそれは拡大していく。
「私たちは確かに祈ります。我らの友を救うために、私たちの言葉のもとに、皆を集めてください!」
コンテンポラリー魔術を使うシイらしい、平易な言葉。
その魔術で問題なく動作させるパッチを作るまで、かなりの時間をかけたと彼女は饒舌に言っていた。
彼女の魔術で誘導される、セラの魔法。
その姿はまさに、似た魔術を使うもの同士の息の合った姿であった。
・・
ホルンは自分で初めてSNSに参加し、なんとも言えない新しい世界に目覚めたような気分だった。
杖を介する通信であればよく使うが、スマートフォンとインターネットを使うSNSにはあまりなじみがない。
獣人たちは携帯電話やインターネットを使うことも困難だ。
となればインターネットの類をほとんど使う機会がない。
そのうえで使って感じたことは、まるで仮面をかぶったように相手の存在の実在感がわからない世界が存在するという驚きだった。
そしてまるで朝にやっているヒーローもののテレビ番組のように正体がわからず、マジョリティの正義に従って敵を成敗していく姿。
獣人への暴言や憎悪にあふれ、それに抵抗する者たちの発言は勢いとして消されていく。
それがなんだか恐ろしく、そして怖いものを見てしまったような好奇心も感じてしまい、どうしたらいいかわからなくなりそうになる。
それでも自分の役割と正義を心に秘め、SNSのデモに参加する。
今のところ憲兵たちがインターネットを監視しているという情報は一切流れてこない。
人間たちに対しては、親獣人的でなければ禁止されることはない。
かつて人間たちはもっと自由だったというが、やはり60億人の思想をコントロールすることは困難であり、獣人たちという不確定要素を持っている現在としては、これが限界なのだという声も聞こえてくる。
それが何だか情けなく、ホルンは息をつく。
次から次へとホルンのSNSに搭載されたダイレクトメッセージのタイムラインにはNIMCAデモに対しての情報が流されてくる。
このタイムラインにホルンのみが知る情報を適宜流す。
適当にセンセーショナルな文章を書き、それにファイルとしてNIMCA内部をクラックして仕入れた情報、あるいはでっち上げた情報を流し込んでいく。
そうすることで沸騰し、怒りで前が見えなくなっている民衆たちは食いつき、それをSNSで拡散する。
すぐさまそれらは千回以上照会され、言及も1万をこえる。
これだけ参考にされ、さらに様々な人に拡散されていく姿に人々は快楽を感じ、つぎつぎとホルンたちの情報をまとめ、さらに尾ひれをつけて拡散する。
その結果さらにSNSは沸騰し、コントロールがつかない状態になっていく。
「ホルン、どんな感じかしら?」ソリは言う。
「ああ。なんてかさ、俺、ちと信じられねぇんだ。何でこんなに人間は騙されちまうんだろうな」
ホルンは言うと、近くにあったパルサンサイダーのプルトップを開ける。
シュコッ、というさわやかな音がホルンたちをいざなう。
「そうね。人間はやっぱり関係を持っていなくちゃいけないのよ。人間が見ているから自分はその視線や期待から逃れられない。みんながやるからやっちゃいけなくて、みんながしないいいことは絶対にしないものみたいね」ソリは息をつく。
一体人間はどこに「個」があるというのだろう。
みな人のことを見て、そして自分が目立たないようにしようとする。
そしてそうすることに屁理屈のような理由をつけて、自分自身が従う動機を作り出す。
操作する側の獣人としては簡単ではあるけれど、それでもどうしてこんなにも愚かなのだろうかと、ソリは疑問に思った。
ホルンもまた、よく似たようなことを考える。
人間の歴史を鑑みると、個人主義が長く続いた頃があった。
しかしながら、獣人界を併合し、人間が一つにまとまってから東洋とされるエリアの常識に合わせることになった。
それについて人間たちは相当嫌だったというが、結局長いものに巻かれて生きることを選んでしまった。
その結果が獣人たちへの強烈な行動であり、さらにほとんど何も考えない見せかけの民主主義だった。
誰も正しい歴史や正しい民主主義、正しい現状把握といったものを理解しようとしない。
それが一体どれだけの損失なのか、おそらくわかっていないかもしれない。
その恐ろしさを人間が気づいていないことに、なんとも言えない悲しさを覚えた。
「そっちはどうだ?」ホルンは言うと、フリッジ庫からタムナボンジュースを取り出し、ソリに渡した。
フリッジ庫はルカの冷凍魔術を刻んだタリスマンを使った冷蔵庫だ。
かつて獣人界がその自治を保っていたころには、エバーラストタリスマンという長寿命のタリスマンを組合に加入してもらい受けることが多かった。
また、タムナボンジュースはタムナ島の名産である柑橘類を絞って作ったジュースだ。
ソリの親戚が作ったジュースをソリ自身が購入し、皆にふるまっていた。
「この味よ」ソリはさっぱりとした表情で言う。
そしてホルンを見ると、にこりと微笑む。
「私の使い魔のオピニオンリーダーにプロテスターのみんなを連結させたわ。女の人なんだけどね、彼女があとはデモを呼びかければみんなデモ隊に参加するはずよ。彼の出ているレッドヒルメディアのラジオでも反NIMCA運動について取り上げていて、かなりのうねりになってきているわ。あとはもう少し社会的コンセンサスを作って、ゴーサインを出せばいい感じね」ソリは笑う。
「そうだな。それであとは……」ホルンはサイダーを飲むと、口角を上げる。
「そう。まだこれは仕込みなのよ」
ソリは言うと、ホルンにタムナボンジュースを飲ませる。
ホルンはその礼を返すように、ソリにパルサンサイダーを飲ませた。
Only You Cadaver
「タンビ、ちょっとお使いしてもらっていいかい?」
画面に向いていたセラはくるりとその椅子を回し、近くにいたタンビを見る。
いったいどのようなことだろうかと、セラの表情を見る。
セラは何か楽しいことを考えているのか、にやにやとした表情でタンビを見ていた。
「君に芸術品を作ってもらう作戦だよ」セラはにこりと笑う。
芸術品、と聞いて、なんだか嫌な予感が走る。
それが芸術としては非常に劣ったものであるにもかかわらず、それを作ってくれと頼む。
セラはにこやかにしているが、その内に秘められた憎悪と、はげしい悪意にタンビはくらくらとする。
しかしそれとともになぜか、パンドラの箱を開いたかのような喜びが心を締めようとしている。
その感情をタンビは一瞬コントロールしようかと考えたが、それはいま、もしかしたら必要にないのかもしれない。
タンビはその肉の誘惑を感じつつ、しっぽを大きく振った。
「どういうことかな?」タンビはしっぽを揺らす速度に気を付け、あくまでその誘惑に打ち勝とうする。
そんなタンビを見透かしてか、セラはゆっくりとしっぽを揺らし、もったいぶるかのような表情でタンビを見つめる。
お預けをいただいた状態のタンビは、我慢ができなくなり、眼に血が走る。
そしてワン、というとセラを見た。
セラは「知りたい?」とじらしを入れる。
しかしすぐさま、シイがふざけるセラの頭を、近くにあった鉄道雑誌で思いっきりぶん殴る。
セラはその瞬間、「アーバン!」と叫んで壁に激突した。
「壁に直結して壁様はお姫様とでもいえばいい」シイは深い息を吐きながら言う。
タンビはその瞬間、なんとなく、自分が何をさせられようとしているのかを察する。
「シイ、ボクの作戦って、つまりそういうことだよね」タンビは苦笑いする。
「そう、とは?」シイは某キャンディーを咥えたまま、じっとタンビを見る。
「そうだなぁ、命の輝きを芸術に変える、的な?」
タンビの言葉に、セラはしっぽをゆっくりと振ることで答える。
その意図を知ったタンビは、肩を軽くすくめて「そっかーぁ」と言い、伸びをするかのように手を突き上げてその場で転がった。
・・
タンビが渡されたリストには、前回の洗脳パーティには含まれていなかった面々が書かれていた。
その中でも重大な影響を及ぼしている二人を、命の輝きに変える。
ただ、興味深いのは一人は猫族、もう一人が人間という組み合わせだ。
獣人であるのにも関わらず、人間に警告を放つ。
これは昔、テレビで放映されていた昆虫型サイボーグが、人間に仇する仲間を次々闇の中に葬っていく作品にも似ているような気がする。
そして実際、彼は数々の人間に危害を加える獣人たちを闇に葬る、人間からしてみれば正義のヒーローだった。
とはいえ、今はSNSを見てもNIMCAへの反対意見が優勢になっている。
ここでNIMCA保護を訴えているのは、一部の著作権ホルダーと、一部の政治的な人間だった。
ただし、獣人たちに対して多くの場合同情的でいてくれるリベラル派すらも、今回の騒動で獣人が被害を被っていることを把握しきれていないこともあり、意見が分かれている。
そして今回殺害する人間は、多くの人間には「陰謀論者」として叩かれているものの、現在のことが獣人の仕業であることが理解されてしまっている。
下手に自分たちが表ざたになることで、その陰謀論が正しかったこととして処理されてしまいかねない……。
そうなると、今は無理やりであっても隠密に殺害をするしかなかった。
正義のヒーローである「マスクドキャット」こと、新井心寧の殺害はそれからでも構わない。
また、タンビ自身、マスクドキャットを隠密に殺害できる自信があった。
タンビは内地に侵入し、中都へと向かう。
人口250万人のこの街は、人間界の大都市であるにもかかわらず自動車の往来が激しい。
その姿はタンビにとってはアリスの縮小版にも見えるし、そしてどこか自分の生まれ故郷である東都に比べればいささか田舎のように感じられた。
中都中心街を地下鉄イエローラインで通り抜け、ホースポンド駅で降りる。
そこから少しばかり歩き、ショッピングセンターの横を入り、中華料理店の横を通り抜ける。
夜の輝きはこの街でも変わらない。
むしろ中都の商業地域であるためか、その賑わいはまるで線を自由に書いた子供のイラストのようだった。
ターゲットはその中華料理店、味舞の宴会室にいる。
タンビは人間の姿を取り、内部へ。
そしてリザードラーメンをカモフラージュに注文すると、化粧室の方角へと向かう。
しかしその手前で階段を加速装置を使って上り、宴会室へと上がる。
ここで事前に登録しておいた味舞の制服に着替え、小物として階段横の冷蔵庫から奪ってきた飲み物のピッチャーをお盆の上に乗せる。
「いらっしゃいませ」タンビは言う。
中にいた陰謀論を唱えている犯人である男性、「しおかぜラジオ」ことミョウジョウ・ウシオと、隣には中都直轄市の代表的なメディアである、中都新聞の社長である、アサクマ・リンガス、そしてアサクマの秘書であるファイブナリッジ・ジョンが席を囲み、中華料理を分け合っていた。
それぞれ楽しい話をしていたのか、顔は真っ赤にむくんでいる。
「彼らの話のログはとれたにゃ。このまま流れていたら僕の魔法が解けちゃうところだったよ」
セラはあくまで飄々とした様子で耳を動かす。
しかしそれがもし実現していたら、と思うと、タンビはとてもではないが笑えなかった。
そんな自分を無理やり奮い立たせて明るい笑顔を作るとその場で変身。
命の輝きを残す作業を行う。
命の輝きを残すために、対象の言葉は不要である。
タンビは息を飲んで動かなくなっている彼らに対し、麻酔銃を放つ。
彼らは何か命乞いをしようとしていたのだろうが、何もできずにそのまま眠り込んでしまった。
しかし、彼らは催眠解除魔術を使わない限り目を覚ますことはない。
タンビはそのまま彼らを転送魔術で転送先に送ると、店を出て再び地下鉄に乗る。
ステラヒル駅に着いたタンビはメモリアルパークの陸軍墓地の前に立つ。
ここは人間陸軍の兵士たちの亡骸が集められ、眠らされているところだ。
多くの人間の保守層が獣人界を侵略した、庚戌の恥と獣人たちが言う日である8月22日に集まり、万歳を叫ぶ。
その行為が獣人をどれだけ刺激し、悲しませているか、人間は理解できていない。
さらに悲しいのが、ここに集う人間たちは皆、戦争の勝利を口実に集まり、そしてみっともないファッションのコスプレをさらす。
腹の出た人間兵、異常に痩せた「救国」の偉人であるサクラダ……。
人間の不健康さ、そして愚かさをショールームのように人間界各地で楽しめることだけは、獣人が現状の痛みをなだめる唯一の機械だった。
そんな彼らに、人間のすばらしさ、命の輝きを見せることができる。
タンビはそう思うと、なんだかいてもたってもいられなかった。
タンビはストレージの中から3人の身体を取り出すと、彼らを立たせる。
そしてタイムフリーズ魔術を込めた弾丸を放つと、彼らはその場で静止する。
いざ立たせてみると彼らの姿は相当貧相で、老いて見える。
タンビは彼らを憐れむように祈りをささげると、作品作りを始めた。
銃弾に物質変化魔術を込め、それを発射。
相手に命中すると、次々と灰色や赤色とそれなりにカラフルだった体が次々と銅色になっていく。
そのうちの2人目、アサクマにはタイムシフト魔術をかけて緑青を発生させる。
止まった生と、これ以上腐ることのないその姿を保存できていることに感謝するように、タンビはゆっくりとそのディテールを見る。
細部に至るまで繊細な曲線と直線、そしてフォルムが調和し、なんとも言えない美しさを醸し出している。
タンビは以前、しおかぜラジオとして劣化の一途をたどっていたウシオの遺体を見て、ゆっくりとボディをさする。
もう二度と彼の身体、心、霊は劣化しないのだと考えると、なんとも喜ばしく感じた。
最後の仕上げとして、タンビは呪文を唱え、それによってできた魔力プログラムを自身の銃に送りこむ。
そしてそれの入った銃をウシオの身体に向けると、トリガーを引く。
弾丸は命中する前に炸裂し、そして込められていた炎が炸裂する。
その炎はウシオの頭部に引火し、真っ赤な炎を上げる。
魔術によって起こされた炎。
それは水や消火剤を巻いても消えることはない。
しかしながら銅で覆われた体を一切傷つけることはない。
銅化は今も相手の体内で行われており、時間を鑑みるに、敵の体はもはや二度と人間としての生を刻むことはない。
このようにして風化も発展もしない、今このままの身体を永遠に残している。
その達成感にタンビは満足にゆっくりと息を吸い、そして近くの自動販売機で買ってきたソーダ水を飲む。
人工甘味料のひどく刺激的な味わいに驚く。
しかし、その甘味ですら今のタンビを酔わせるには十分だった。
すでに敵はすっかり銅像と化し、どんな魔術でもってしてもその生を復活させることはできないだろう。
そのことを思うと、酒でもないのに気分が高揚し、ふわふわとした気持ちになっていった。
そしてタンビは自身のまたぐらをまさぐる。
ショーツをびっしょりと濡らす愛液を見て、タンビはゆっくりと息を吐き、そして性器を揉み始める。
目の前の死体はゆっくりと肉体を失っていく。
それを思うだけで心がほぐれていき、自身の意思は絶頂へとブレーキのないスーパーカーとなって向かっていく。
タンビの気持ちが高まり、息がなまめかしくなっていく。
その時、タンビの背後に気配を感じる。
甘ったたるいにおいや、わずかに聞こえるモーター音。
それらから彼女は自分と同じ、機械仕掛けの獣であることを察知する。
しばらくそのにおいを分析すると、猫族のものであることも理解できた。
タンビは振り向くことなく、じっと待機する。
どうやら敵も動きを止めたようだ。
タンビはその瞬間、興が覚め、ゆっくりと息を吐き、下着を整える。
「どうしたんだい?」タンビは聞く。
敵は何も言おうとしない。
それならばとじっと黙り、何も言わない。
二人の間を生暖かい風が吹いていく。
犬と猫のわずかなにおいと、お互いを流れる魔力液のふんわりと甘いにおい。
そのにおいを楽しむには短い時間の静寂を、敵の発言は切り裂く。
「ネクロフィリアを現実に実行するとはね」
彼女の正体がここでタンビの中で判明する。
タンビは鼻を鳴らし、自身の作品を見る。
「芸術家っていうのは、どこかしら狂っているものだよ」
タンビの言葉に、敵はしばらく言葉を返さない。
おそらくタンビの言葉に同意し、それをもって彼女にとっての正義の言葉を考えているのかもしれない。
--上等じゃないか。
タンビは その言葉を味わうように息をする。
「命を保存するよりも、劣化してでも生かす方が、僕は好きだな」猫族は言う。
その言葉に何か返そうとは、タンビは思わなかった。
美しさは人それぞれだ。
自分の作品をけなす人がいようと、それはその人の勝手なのだから。
その気持ちでタンビは何もことばを返さない。
敵の猫族はそれに業を煮やしたのか、荒く息をつく。
「貴様のように命を粗末に扱う獣人は、僕が許さない!」
猫族の少女は手をクロスさせると、「変身!」と叫ぶ。
激しい光にタンビはおもわず目をくらませる。
しかし、それに合わせてタンビも戦闘着に変身。
敵はぴっちりと体が出るような青いスーツに、赤いマスクをかぶる。
そのマスクは人と猫のキメラである獣人の特徴を、嫌が応にも認識させるようであった。
敵の赤いマフラーと、自分のオレンジのそれが風に揺れてはためく。
真夜中の星が二人を照らす。
極度の緊張感に満ちた、ふたりの間合い。
その間合いをはじめに埋めたのは……。
Doll Taker
先陣を切ったのは、マスクドキャットの方だった。
彼女はまっすぐにタンビめがけて駆けてくるとナイフを展開。
勢いよくタンビを一刀両断しようとする。
しかし、タンビはその瞬間、バック転をしてそれを回避。
さらに着地とともに呪文を込めて銃弾に込める。
そして銃を構え、照準を合わせて発射。
その間、わずか十秒の出来事である。
弾丸はすぐさま魔術を展開し、雷を帯びる。
しかしその弾丸はやはり直前になってマスクドキャットが回避したことで近くの墓石にぶつかり、それを粉砕する。
タンビはそれを確認するよりも早く手近な場所にある大型の墓石の裏に隠れる。
「どこbに行っちゃったんだろーう?」わざとらしく笑顔で言う、赤い仮面の少女が言う。
しかしタンビはそれには応じることはない。
それでも、精神的にはかなり追い詰められ、息が上がってくる。
高いBPMの鼓動を無理やり抑えるように、息をゆっくりと飲み込み、胸に手を押さえて才字を切る。
そうすることで神が守ってくれるような気がした。
しかし、神は試練を与える。
「あーっ、そんなところにいたんだねー!」マスクドキャットの声が聞こえる。
タンビはその場で目を大きく見開く。
彼女は次の瞬間、銃に弾丸を込め、マスクドキャットめがけて撃ち放つ。
しかしマスクドキャットはそれを回避し、クナイをタンビに投げつける。
クナイは見事にタンビの右肩に命中。
タンビはその場で肩をおさえて蹲る。
それをいいことに、マスクドキャットはもう一発タンビめがけてクナイを投げつける。
クナイはタンビの傷ついた右肩、そして左指を切り裂く。
タンビの腕からは三本の指がちぎれる。
「お前の正義とやらはそこまでみたいだね。じゃあ、あとは僕の正義を通させてもらうよ」
マスクドキャットは言うと、足から手りゅう弾らしきものを取り出した。
恐らく自分は爆殺させられる。
それなら。
タンビは舌を噛んで痛みを抑えると、ゆっくりと立ち上がる。
そしてカラ元気であることがよくわかるような作り笑いでマスクドキャットを見る。
「ボクの正義は……まだ……終わりじゃないさ……!」
タンビは告げると、銃を再び握る。
ぶらりとした右手では銃を持てず、左手でそれを握る。
もし左手がもがれたらそれで自分の戦いは終わってしまう。
だからこそ今、敵を討ち、我らが正義を刻むのだ――。
タンビはさらに口元を緩め、銃を握る。
敵はその様子に驚きをもったのか、眼をしかめる。
タンビはそれを合図と見るやいなや加速装置を起動させ、マスクドキャットの背後へ。
そして彼女の背後から電気弾を射出。
マスクドキャットの強化された魔眼をもってしても、タンビの高速移動を捕捉することができていないのか、彼女はきょろきょろと様子をうかがっている最中に被弾し、左腕の関節が爆発。
手と前腕が外れ、無残に打ち捨てられる。
わざとタンビはその腕の前に向かうと、それを執拗に踏みにじる。
「これでボクと君はドローだね」
タンビは不敵な笑みを浮かべる。
「何を言う。お前はすでに左指すらも失っている。それでもお前は悪をあきらめようとしない。そのネガティブな意思はどこからくる!」
マスクドキャットは叫ぶように言う。
タンビは一瞬考え、にやりと笑う。
そして再び加速装置を起動させると、マスクドキャットの後ろを取る。
しかし、マスクドキャットもただやられるだけではない。
マスクドキャットもまた加速装置を起動し、タンビへと接近する。
そしてタンビの胴体を蹴りつけ、タンビを吹き飛ばす。
タンビの身体は墓石を次々となぎ倒し、百メートル離れた平和観音像に大きな穴をあけて、その中で静止する。
衝突の衝撃ですでに接着が甘くなっていたタンビの腕はもげ、どこかに打ち捨てられてしまった。
マスクドキャットはタンビのもとへと近づくと、タンビの左足を踏みにじる。
「正義を踏みにじったことを後悔させてやる。社会を乱し、破壊しようとした罪をお前は数えろ!」
マスクドキャットは言うと、タンビの顔面、そして腹を執拗に殴っていく。
タンビの胴体はかなり強化されており、これくらいの暴力ではわずかに骨格がゆがむ程度だ。
しかし、そのパワーは普通の人間、さらには人間よりもいくらか強い獣人であればすぐに首から上がもがれてしまうだろう。
タンビはその暴力の嵐から逃れるべく、チャンスをうかがう。
しかし、タンビを殴る力はとどまることを知らない。
それでもタイミングをつかむと、マスクドキャットの心臓めがけて銃を向ける。
そして魔力を込め、発射。
マスクドキャットの心臓こそ外したが、彼女の目を射抜くことに成功する。
その痛みで思わず叫びをあげるマスクドキャット。
タンビはそれをチャンスとばかりに銃を次々射出。
敵の腕、足を射抜いていく。
すでに加速装置を破壊したようで、足の付け根からは煙が出ている。
それどころか加速装置のデッドウエイトのせいか、行動が以前よりも緩慢になっている。
自分の身体もまた、軽量化されているとはいえ、獣人の体重とは思えないほどの重さになっている。
そのことを思い出し、なんだか哀れな気持ちになる。
タンビはその気持ちを抑えるようにゆっくりと近づく。
そして「なぜ正義を犯すか。それは君を救うためだよ」と、静かな声で言う。
思いがけない言葉だったのか、マスクドキャットは驚いたような表情でタンビを見る。
「改造されて、自分のアイデンティティやプライド、そして自分自身すら傷つけてしまう正義というものから、獣人と、それどころか人間を救うためだよ」タンビは言う。
「人権が悪にされているなんて、おかしなことだと思わない?」
タンビの言葉に、マスクドキャットは不思議そうに見つめる。
「獣人が人に危害を掛けない限り、その責任において自由に行動して、自由な考えで物を話す。それどこかそれは人間にだって言えることだよ。サクラダと太陽神が国民を押さえつけるために作った法律とか、国民を洗脳した挙句に改正した憲法なんて、どこにその正当性があるんだい? それに、何でボクたち獣人はこんなにまで苦しめられなくちゃいけないんだい?」
タンビは問う。
一方、マスクドキャットは何も言おうとしない。
恐らくマスクドキャットも何かしらの矛盾を感じてくれているに違いない。
タンビはそう信じ、微笑みかける。
しかし、その表情がマスクドキャットには攻撃と伝わったのか、彼女はおぼつかない体の動きをなんとかコントロールし、立ち上がる。
そしてタンビめがけて足の太ももから魔弾を発射できるであろうガンを取り出す。
全身武器庫に改造されたマスクドキャットの身体が、タンビにはなんとも痛々しく感じた。
彼女は自分と同じように、永遠に劣化しない生きる命を与えられた。
自分もまた、改造によってこれ以上の老化は見込まれなくなった。
タンビはその時、大きく目を見開く。
――これこそが自分の求めていた命なんだ!
確かにものとして、何者かに破壊されてしまうかもしれない体だ。
それでも、自分の身体は永遠の命と、ものとしての強化された身体、そして人形のような自分を手に入れた。
そのことが今、タンビのなかで身を結び、喜びへと変わっていく。
自分は生きる人形で、戦うロボットで、かわいい獣人なのだ。
それがどれだけいとおしいことか。
今まで感じたことのない気持ちに、タンビの表情がぱっと明るくなる。
でも、だからこそマスクドキャットに問う。
「ボクたちは永遠の命を得ることになった。それでも、それまでの痛みとか、恐怖とか、それからの孤独に耐えられるほど、獣人は強くなんてない! だからこそ、ボクは人形を作ろうとする人形を狩るんだ。ドールテイカーとしてね!」
タンビの力強い宣言に、マスクドキャットは不審そうな表情で見る。
「ボクは、……僕は、どうぶつ人形として君に言う。獣人は、人形じゃない!」
タンビは宣言するとともに、攻撃のためにわずかに距離を開ける。
その瞬間、マスクドキャットは立ち上がり、銃を放つ。
5条の光がタンビめがけて向かってくる。
高速であるはずなのにゆっくりと近づいて見える。
それは人形になり、兵器として生きることを決意した、かわいい自分のクールな魔眼のおかげだ。
自分を強く握りしめ、信じる。
指三本吹き飛び、右手が落ちた自身の身体をしなやかに動かし、軽やかに砲撃を躱す。
そして軽い音を立てて着地すると、左手のわずかな指で機関銃モードの銃を握る。
両者ともにお互いを銃で狙う。
再び訪れる静寂。
どちらも片腕であり、機動性は普段よりかは劣る。
しかしながら現在、タンビは左手の自由もほとんど利かなくなっている。
倒すなら今しかない。
タンビはこの間に照準魔術を展開し、敵の心臓をロックオン。
こうすることで敵の心臓を確実に貫通させることができる。
それも、敵がいくらシールドを張っていたとしても。
しかしながら、もし敵も同じように心臓、あるいは脳を狙っていた場合にはその能力も意味がなくなってしまう。
それをリカバリーするため、タンビは加速装置をアイドリングモードに切り替え、さらにシールド魔術を何重にもかける。
こうすることでシールド魔術によって動作が緩慢になるのを押さえ、スピード感のある戦闘を行うことができる。
わずかに響くSiCインバーターの非同期音。
一方で敵は戦闘に慣れていないのか、いくら耳を澄ませてもインバータの音すら聞こえない。
二人の間を風が吹き抜け、誰かが飲み残した缶が転がる音が聞こえる。
その時、二人はほぼ同時に加速し、銃を放つ。
敵は加速装置をアイドルせずに起動しているためか、いささか緩慢な動きを見せる。
一方でタンビはそれをも上回る速度で一気にマスクドキャットとの間を埋め、そして銃を放つ。
敵もそれにわずかにワンテンポ遅れたタイミングで銃を放つ。
タンビはその軌道を見て、わずかに身をそらす。
一方で敵は心臓にタンビの電気弾を食らい、血液をぶちまけて崩れていく。
タンビの横をかすめた弾丸は後ろにあった墓石を砕き、破片をぶちまける。
それらが全て、魔眼のおかげでゆっくりと、スローモーションで見えてくる。
自分に与えられた、人形としての永遠の命。
その喜びと、そのプライド。
さらには獣人としての喜びと、自分のアイデンティティへの感謝。
それが全て力となり、線となっていく。
その喜びを胸に、タンビはゆっくりと速度を緩める。
マスクドキャットは胸から流れる血液を手で押さえつつ、タンビを睨んで転送魔法の魔法陣の中に消えていく。
タンビはその魔法陣のログを収集すると、片腕を探し、自分の身体のジョイントを探す。
「ジョイントごとかぁ」タンビはぼやくと、空を見上げる。
都会のまばらな星空が、タンビを精一杯祝福しているようだった。
Freedom Square
多くの獣人、そして音楽の自由を望むものたちがカンファ門広場に集まっている。
カンファ門広場はかつて獣人の王国があった際に王宮だった場所のすぐ前にある、二百メードル幅の道路の通称だ。
獣人の音楽公演が多く行われたヌリワン文化会館、テレビで獣人界と言ったら映し出されるヌリワン像といった獣人界の文化と思想の中心地は、多くの獣人が何か訴えたいことがあると集まり、デモ隊を結成することで昔から有名である。
今回、NIMCA反対デモには五万人規模の人数を動員することに成功していた。
集まった人員の多くは獣人ではあるが、その中で無視できない数の人間たちも集会の中に見受けられる。
それを見たホルンたちは、ゆっくりと通りのふもとにあるイェスルの教会、セラン教会の最上階である7階から眺めていた。
「すげえな……」ホルンは感嘆し、眼を大きく見開く。
タンビは「当然だよ。だってボクたち人間に詳しい獣人のプロデュースだもん!」と胸を張る。
その言葉にホルンは再び社会学、というものに関心を示すように、かぁーっ、と歓声を上げていた。
本来であればこんなことに社会学を使いたくない。
しかし、かつて国民国家があったころに出版されたルース・ベネディクトの『菊と刀』のように、社会学や文化人類学は得てして戦争に使われ、宣撫や敵の分析に使われている。
その宣撫の力が獣人を救うための力になるのであれば、それはもしかしたら愛の学問なのかもしれない。
ルカは自分をそう納得させつつ、ミルクを入れたカッファ茶を飲んだ。
苦い味わいとカッファの豊潤な香りが鼻を撫でてくる。
イェスルが教会で使うのに搾取のあるものはまずいと趣味で買いあさっているフェアトレード品ではあるが、それである以前においしく、いい買い物をしていると感じた。
「こちらイェスル。獣人教徒の宣撫は完了している」イェスルから連絡が入る。
イェスルは今日、獣人教徒を宣撫することも目標に礼拝説教を組み立てたと言っていた。
ベルたちはそれを事前に読んでいるが、至極自然に終末論を語る一方で、困難にいる人のために立ち向かうことを訴えていた。
その説教の中にベルは魔術を仕込み、獣人たちを洗脳する。
礼拝第一回目が終了したころには多くの獣人教徒が流れることも予想している。
礼拝には様々な獣人たちが三千人は集まるため、その集客力は無視できない。
そのために、イェスルはきちんとした礼拝をいつも以上に心がけていた。
テレパスでは讃美歌と聖歌隊の香り高くも短い声が聞こえてくる。
そして曲が終わると、ぞろぞろと教徒たちがデモ隊の方へと進んでいった。
「こちらルカ。イェスル。作戦成功だ」ルカは言う。
その言葉にイェスルは手を組み、祈りを始めた。
タンビやベルもまた、手を組んでイェスルの祈りに加わる。
そしてその祈りを待って、ホルンたちは屋上へと階段を使って上った。
「そろそろだね」ベルはテレパスを入れる。
その声を聴き、ホルンたちはじっと市民たちを見守る。
そして時間よりわずかに早いタイミングで、大声でデモ隊が叫び始めた。
「獣人、人間、そしてすべての音楽を搾取された民たちよ! 覚醒せよ!」
アジテーターが叫ぶ。
「覚醒せよ! 覚醒せよ!」聴衆たちは叫ぶ。
その姿を見ていると、なんだか血が騒ぐものがある。
ホルンは目立たないように小言で「覚醒せよ」というと、にかっとルカ達を見る。
ルカは楽しそうに口角を緩ませてホルンを見る。
列を見てみると、カンファムン広場を抜け、アリス広場の方にまで達している。
すでに地下鉄の市役所駅、そしてカンファ門駅は人数調整とデモ鎮圧のために閉鎖されており、次第に警察が集まり出している。
そろそろ危険な領域になりそうだ。
ホルンたちはじっとその様子を見守る。
人間界、そして植民地の獣人界ではデモをすることは「反人行為」として禁止されている。
逮捕されると人間であっても内乱罪などに問われかねない。
その罪を犯してでもこのデモに出ている、ということは、それだけ人間の怒りを醸成することができたということだ。
獣人よりも簡単に怒りのムードを醸成できてしまったことに、人間が心配になってくる。
ホルンはじっと集会の次第を見守りつつ、ルカが話していたことをじっと反芻していた。
人間はみな付和雷同的で、ほかの人間がいいと言えば何も言えなくなってしまう。
それが功を奏して、十年前のウイルス騒ぎの時は急激な患者の上昇を抑えることができた。
その一方で「みんなで渡れば怖くない」の精神のもと、人間はいつまでたってもサクライ首相を支持し、さらにはやらかしや不正までをもうやむやにする手伝いをしてしまっている。
この人間の自立心のなさと、自分に対しての責任のなさがこの社会の抑圧のすべての原因のような気がして、なんだか胸がむかむかとしてきたのを感じ、ホルンはゆっくりと長い息を吐いた。
「覚醒せよ!」という、アジテーターの声はいつまでも続いている。
さらに反著作権運動家がマイクを受け、演説を始める。
「著作権は人間たちの音楽、そして作品の発展を奪い、一般市民を抑圧しています。キャラクター、名称、そしてデザイン。私は漫画家を続けていましたが、そのすべてが出版社に奪われ、そして私の作品を出版社は自由に使っています。ですが、私は無料でみんなに漫画を読んでもらいたいのです。そしてみんなでパロディしあって、また新しい漫画ができることを楽しみにしているんです。第一、過去の人間界の歴史を振り返ってみても、ここまで厳しい法律を敷いてきたのは日本だけでした。他の国はパロディ権などを認めるなどして、表現の自由などを保証しつつ、作者の利益を認めてきました。それなのにも関わらずサクライ首相ら、旧日本国出身の人間たちが、あまたあるレコード会社やアニマリアンなどの著作権ホルダー、そして彼の好きなアダルトコミックを守るために著作権法のみ日本法を採用し、さらに厳しくなった人間憲法に結びつけたのです。その結果、例えば著作権団体に認可されていないSNSで画像リプをするだけで逮捕されるケース、同人誌を作っただけで家族離散になるほど追い込まれるケース、それに替え歌を謡っただけで拷問を受けたケースもあります。漫画のファンが作った同人誌をつぶして、替え歌を謡っただけで逮捕されるなんて、おかしいと思いませんか?」
女性の漫画家は叫ぶ。
「あっ! あの人、『マジカルデトロイズ』のカナメ・シホさんじゃん!」タンビは楽しそうに立ち上がり、くりくりした目を輝かせてその場でぴょんぴょん撥ねる。
「有名なのか?」ホルンは聞く。
タンビは信じられない、と言った目でホルンを見たのち「ボクたち人間文化好きの中ではもう神様だよ! ドラえもんとか、スーパーマンとかくらい!」と、やや早口でまくし立てる。
それだけでタンビがどれだけその作品に入れ込んでいるのかが分かり、ホルンは楽しそうにタンビを見た。
しかし、カナメの演説は獣人に対しての言及はなかった。
それが人間の限界なのかもしれないし、それでも人間が獣人のことを知るいい機会になる。
そのことを期待し、ホルンたちは見守る。
次のアジテーターは獣人だった。
獣人イーサー教団のリーダーである、トラ族のホ・スヨン議長が姿を見せる。
女性としての凛々しさを感じさせるのは、トラ族である以前に、イーサーの教えを現代に適用させ、虐げられた民である獣人を救うために長年尽力してきた結果なのだろうと思った。
「私たち獣人は歌、そして獣人記を奪われてしまいました。もちろん獣人漫画、獣人ドラマ、獣人映画も、すべての権利をです。獣人たちが長年築き上げ、大切にしてきた文化や信仰をすべて誰の許可もなく差し押さえ、それをクールヒューマニカ運動で用いるライツ事業の目玉にしてしまったのです。獣人たちの作ったSpopはかつて、飛ぶ鳥を落とす勢いで好評を得ていました。それらは動画共有サイトMyTuneにてコピーレフト音源として公開され、世界中の人々を楽しませてきました。そして獣人たちはコピーレフトで世界の地位と評判が上がり、ひいては獣人界に様々なものを恵んでくださったり、商売をしてくださる方も増えていました。しかしながらそれを人間たちがコピーライトで禁止し、さらに獣人たちからも取り上げてしまったことで、一切獣人たちが文化に触れる道筋を閉ざしてしまいました。さらに獣人記の出版権と、著作権を無理やり取り上げたことで、獣人記を自由に読む権利すらも無くなってしまいました」
スヨン議長の話は途切れることを知らない。
イェスルもこぼしていた、獣人記を自由にネットワークに乗せられない弊害。
さらに獣人讃美歌すらもすべて著作権の保護のもとに入ってしまったため、コンサートなどで自由に歌うことができなくなり、伝道にも影響が出てしまっている。
原作者を保護するためのものではあるが、それを使うことを過度に制限してマーチャンダイジングして、いったい何の得になるというのか。
ホルンやタンビたちには、その効果を理解しづらかった。
そのことを叫び続け、アジテーションし続けるスヨンの姿は、ホルンたちからしても輝いて見えた。
その後も様々に獣人と人間が交互にアジテーションを行い、さらには著作権保護を受けた音楽を大々的にかけるパフォーマンスが行われる。
「ぐるぐる」や「夜明け」といった獣人界の名曲はもちろん、Queenやポール・マッカートニー、と言った人間界の名曲も次々流されてくる。
その曲に聴衆たちは盛り上がり、踊り、手を振る。
まるでコンサート会場のような強烈な熱気と歓声、そして笑顔に思わずホルンたちも体を揺らす。
間もなく散会となるところで、三人組の人間たちが入り込んできた。
彼女たちはトラ、猫、狐の耳をそれぞれ持ち、それぞれのしっぽをゆらゆらと揺らしている。
華美な服装からは、彼女たちがアイドルであることを表していた。
ホルンたちはじっとその推移を見守るべく、武器を構えて注視する。
「なんで……」ベルは信じられないものを見たかのような表情で言う。
目の前にいたアイドル。
それはけもの友達と、レラを殺めた集団であった。
ホルンたちもその登場に、思わず目をしかめる。
「洗脳解除魔術の発動を確認。妨害魔術を発射する」シイが静かに伝える。
その二つの魔術のせめぎあいに、聴衆たちは混乱した様子を見せる。
おそらくこの混乱、そして動揺こそが目的であろう。
「作戦通りだにゃ」セラはほくそ笑む。
一方でシイは長いため息をつきながら棒キャンデーを口にくわえ、キーボードをはじく。
すると茶色の魔法陣が広がり、敵のピンクの魔法陣をなぎ倒していく。
ホルンはそれに合わせ登場し、アイドルたちの首に銃や刀、鎌を当てる。
「よくも俺たちの神聖な叫びの自由区を破壊してくれようとしたな」ホルンは宣言する。
ホルンにつかまったアイドル、ウンビは息を吐き捨て、ホルンを見る。
「そんな単細胞だから裏切られるのよ」
その言葉にホルンは目をしかめ、にらみつける。
その目をウンビは嘲笑うかのように目でなでた。
Charoset
「敵三人に味方三人……けっ、悪かねぇな」
ホルンは言うと、手に鎌をとる。
タンビやルカもそれぞれ武器を手に取り、戦闘態勢に入る。
「あら」敵のサイ族の獣人、リノはアイドルといった感じの澄ました声で言う。
「人間様も獣人を理解して、一緒に働こうとしてくれてる。それに著作権が私たちを抑圧するなんて、それ、作曲者とかあたしたちの前で言えるのかしら。獣人の歌はこれからは人間とともにつくっていくのよ。だから人間の法律に従うのは当然だわ」
ホルンはその言葉を聞き、少しばかり頭を逡巡させる。
果たしてそうなのであろうか。
獣人が主体になって新しい音楽を作れているだろうか。
作曲家は人間、プロデューサーも人間。
そんな作品に獣人歌謡らしい社会告発も、美しさもない。
ただアイドルというには未熟な獣人たちが、男たちの嘗め回すような目にさらされながら何にもならないような歌を歌う。
それの一体どこが文化なのだろうか。
獣人文化にも人間文化にも明るいタンビはどう考えるのか、ホルンは少しばかり気になった。
「人間の文化は多様性をはき違えているからねぇ……」タンビはテレパスで苦笑いをしながら敵を見つめている。
「人間の文化はすそ野が広いと言えば聞こえはいいけど、要はへたっぴがなんの訓練も受けずに、何の作戦もなしにスカウトされて、ほとんど練習もないまま、その素朴さをみんなで消費するのが特徴だからね……。獣人文化もそういった部分はあるけれど、デビューしたのちは厳しい競争にさらされる。でも人間はそんなことない。どっちもどっちなのかなぁ……」タンビはあきれた、という言葉を言外にもらしながら言う。
その何が正しいかは、人によって異なる。
しかし、ホルンとしてはただ人間の愚かさを感じずにはいられなかった。
「てめぇらみてぇな、文化祭でもやんねぇようなクソ文化に金なんざ払いたかねぇよ」ホルンは挑発するように、今の自分の気持ちを伝える。
その言葉に敵は逆上したのか武器を取り、そしてライノが武器である槍を手に取り、ホルンめがけてかかってくる。
「その言葉、とりけせ!」ライノは叫ぶ。
しかし、ホルンは何も言わずにライノの槍を飛んでかわすと、ライノの後ろにつく。
そこでホルンはかまいたちを起こし、敵へと向かう。
かまいたちはライノの腕を切り裂き、消滅。
しかしながらライノの分厚い装甲を切り裂くには至っていない。
それどころか自動修復機能が働き、すっかり傷は目立たなくなっている。
彼女らはセクサノイドであるはずだ。
それなのになぜ。
ホルンは目をしかめ、注視する。
考えられる点は二つ。
一つはソリのように再改造を受け、戦闘兵器になった。
もう一つは……。
ホルンはその「もう一つ」はあり得ないだろうと打ち消す。
「君、相当不思議に思っているね」ライノは言う。
しかし、それを言うだけでライノは槍の先から光線を作り出し、ホルンへ。
彼女は水魔術を使えるらしい。
となるとホルンの魔術は打ち消されかねない。
ホルンは警戒し、水魔術によるハイドロポンプをかわしつつ、自身も炎を鎌に宿らせ、それを放つ。
5つの鎌の残影はライノの首をめがけて飛んでいく。
炎であればいささか攻撃力を増しているはずだ。
ホルンは願う。
ライノに命中。ライノの甲冑はえんじ色の光を放ちながら燃えていく。
しかし、ライノはそれを脱ぐどこか、余裕のある笑みを浮かべる。
「私はそんなにやわじゃないんだよね」ライノは笑う。
ホルンはライノを緊張した目で見つめる。
その目を受けてか、ライノは槍を地面に突き付け、巨大な魔法陣を展開。
ホルンはそれを防ぐべく、鎌を構えて火炎放射魔術を準備。
そして敵が攻撃をくわえるよりも前に敵へと放つ。
その瞬間、ホルンの周囲に巨大な壁が四方に隆起する。
――何事だ?
ホルンは周囲を見渡す。
ロップイヤーの耳がひくひくと動き、本能も今の状態を確認しようとする。
しかし、音も、魔力も一切感じない。
この中でどのようにしていけばいいのか。
ホルンは考える。
「このまま水がこの中にたまっていったら、どうなるかな?」ライノは言う。
水責め。
考えたくない言葉が頭をよぎる。
ある程度の防水性能はホルンの体も完備している。
しかし、ルカほどの潜水能力はないし、獣人の体を強化したものであるから、人間の体に比べれば何倍も長く潜っていられる。
それでも。
しかも火炎魔術師として、深部温度が下がることはそれなりの問題を抱えることになる。
それを鑑みると、あまり余裕があるとは言えない。
すでに靴の、足を覆う部分まで水の高さは増している。
ホルンはロップイヤーの耳を立てて耳を澄まし、音波レーダーを起動。
周囲の音を聞く。
どこかでその間隙が割れていこうとしている音が聞こえる。
魔術のもろさや不完全さに驚くとともに、このチャンスを無駄にすることはできない。
ホルンはそのチャンスをつかむべく、できる限り石の箱の中で、高く飛行魔術を使う。
すでに足元どころか、くるぶしあたりまで水が溜まっている。
ホルンは少しずつ行き場のなくなっている状態にわずかな焦りを覚えつつも、思考をさらに回転させることにした。
・・
ルカは突然閉じ込められたホルンを見て、わずかな焦りを覚えた。
すでにコウモリ族のパクチーはルカを見下ろすかのように羽ばたき、あざ笑っていた。
空中と地上、その二つの間隙を埋めるためにできることは何か。
ルカは考え、そして決意。
魔法陣を展開する。
そして尾ひれで空気という水面を蹴ると、上空へとのぼる。
シャチ族の基礎魔術として、高度百メートルほどであれば簡単に上ることができる。
空中の高くない場所で浮遊していたパクチーは、すぐさま魔法陣を展開。
ルカのメロンに激しい痛みと、エラーが生じる。
シャチに限らず、クジラ系の獣人の誇りかつ武器を封じられてしまったことに、ルカは軽く息を吐く。
それでもできることはないかと考え、距離を詰め、腕のフィンカッターでパクチーの背中を狙い、突き刺す。
それを軸に空中で垂直方向に回転し、パクチーの翼や背中の筋肉をもいでいく。
真赤な鮮血と、きらきらした魔力の液体がルカの顔の仮面にとびかかる。
しかし、パクチーも負けてはいない。
自身の爪をルカの顔面にかけると、一気に目から口へと引っかく。
どちらかといえば色白なルカの顔に、四条の真っ黒な筋ができる。
さらにパクチーはルカの眼を集中的に攻撃し、ルカから視界を奪う。
ルカはパクチーを突き放すように押し飛ばす。
そしてパクチーを踏みつけ、蹂躙しようとする。
しかし目、そしてエコーロケーションを破壊させられたことで視界がすべてロストし、思うように動くことができない。
聴覚を頼りにパクチーのもとへと進むが、歩いていくことができない。
盲目歩行をしているルカは、すぐにその限界を感じ、その場で倒れこんでしまう。
「無様なシャチさんだぁ……」パクチーは言うと、ルカを吊り上げ、顔を見る。
そして魔術を掛け、ルカを浮上させる。
「皆さん、このような犯罪行為をするとですね、こうなるんですよ!」
パクチーは言うと、ルカを右ストレートで一発ぶん殴る。
さらに左ストレートを一発。
ルカの口からは真っ黒な血液が噴き出す。
右、左と、まるでサンドバッグのようにルカを殴りつける。
そのたびにルカは口から血をまき散らし、パクチーの顔を汚す。
「悪魔はね、栄えたためしがないんだよ!」
パクチーはさらに殴り、殴る。
ルカの体がこらえられないほどにまで殴りつけ、すでにルカの表情から生気が失われている。
それでもパクチーはしきりになぐりつける。
その様子を見ていた獣人や、人間の支持者たちは呆然と見つめ、なにもことばを発しない。
その様子に気づいたパクチーはルカを魔術で警察官のいる場所へと吹き飛ばす。
その場でルカは腕、そして足に枷と手錠をつけられ、ワンボックスカーの中に押し込められた。
・・
タンビはホルンやルカを見つつ、どうしようもできない自分に怒りを覚えつつも、目の前の敵、ウンビと戦っていた。
すでにウンビはタンビの脇腹、そして右太ももを切り裂いている。
タンビは足の切れ目から見える自身の銀色の人工筋肉や人工骨、そして血液を無視しつつ、ウンビを見つめる。
ウンビはすでに腹などになん十発ものタンビも銃弾を浴び、服に真っ赤なしみがついている。
普通のセクサノイドであれば彼女はすでに死んでいるはずだ。
しかしながら、彼女が今、ここで立っているのを鑑みると、彼女はもしかしたらソリと同じようにセクサノイドからウォーノイドに改造され、戦う体にさせられたのかもしれない。
同じ獣人のウォーノイド同士、選びたくなかったであろう運命を想像すると、胸がしくしくと痛んだ。
「胸が痛いのかしら」ウンビは言う。
余計なお世話だ、とタンビは思いつつも、にこりとタンビに微笑む。
「そりゃ、胸が痛いよ。同胞同士の戦いなんて。君もそうじゃないのかな?」
タンビは言葉を返す。
その言葉にウンビは押し黙り、ゆっくりと息をついた。
「それはあんたたちが起こしていることでしょうが。神様の福音と悪魔の導きを誤解して、太陽の神様に従うことに疑問を抱く。それでいて自由を望むなんて、ばかげたことだと思わないのかしら」ウンビは鼻を鳴らし言うと、タンビを見る。
その目は勝気な意思が込められており、タンビはその目に嫌悪感を抱いた。
タンビはすぐさま地面をけり、ウンビめがけて銃を発射。
機関銃モードの銃口からはなん十発もの火炎弾が発射される。
それらはウンビのもとで炸裂すると、猛烈な炎と煙をまき散らす。
しかしウンビはそれをものともせずに、タンビのいる上空10メートルの場所まで上昇し、タンビのみぞおちにナイフを突き立てる。
そして重力に任せ、ウンビは落下。
そのままタンビの腹や臓器をかっさいていく。
さらにその中に腕をつっこみ、魔術回路を切り裂き、さらに肝臓や膵臓をもぎ取る。
タンビはその瞬間、あまりの激痛で血を吐き、ウンビも頭部を汚す。
しかしウンビはそんなタンビの唇を奪うと、しばらく舌をこねくり回し、快楽をむさぼる。
タンビの性器に魔術で何かを込め、右指を動かす。
タンビはその不快感にウンビの肩を噛み切る。
しかしそれだけではウンビの行動を防ぐことができない。
ならばとタンビは銃を握り、ウンビに突き付ける。
「あら、そんな物騒なことをするの?」ウンビは言う。
そしてウンビは左腕でナイフを銃を握るタンビの右腕に突き刺し、切り裂く。
タンビはウンビをにらむ。
しかし、ウンビは嬉々とした表情で見つめると、さらに舌の動きを激しくした。
タンビの舌を犬歯で噛み千切る。
タンビの眼は血走り、大きく開けたその目からは怒りと驚き、そして痛みを感じさせる。
ウンビはその目に喜びを感じると、血にまみれた舌でタンビのほほをなめる。
「やめて……! ボクは君のおもちゃじゃない!」タンビは叫ぶ。
しかしウンビはタンビをむさぼるのに夢中で何も言おうとしない。
一方で、タンビの気持ちは少しずつ高まり、感情的に爆発しそうになってしまう。
力が抜けていき、もうほかのことはどうでもよくなってしまう。
それがタンビにとっては悔しく、そして悲しい。
その状況を打破するべく、タンビは銃を手に取ってウンビに突き付ける。
「ボクから離れてよ。死にたくなかったら」タンビは言う。
しかし、ウンビはそんなタンビを見ると、憐れんだ目で見つめる。
そして小さく腕をフリックさせる。
「やっちゃったねぇ。どうなるか、わかるかな?」
何が起こる?
タンビは意識を目と、耳、そして鼻に集中させる。
しかし、その痛みは自身の下腹部から始まった。
激しく熱くなり、痛くなってくる。
体が急に燃え上がるように火照り、気持ちが悪くなってくる。
そして次の瞬間、タンビの両脚はどこか遠くへと吹き飛び、さらに首から下の感覚がなくなった。
タンビはその瞬間、何が何だかわからず、足元に目を向ける。
タンビの身体は木っ端みじんに破壊され、わずかに心臓だけがどくどくと動いている。
その様子にタンビの脳は処理がオーバーフローし、そのまま目を閉じた。
もはや誰も戦えるものはいない。
それでも、シイとセラはその様子をじっと眺めていた。
Vernier Control
岩と水の監獄の中では、ホルンが一人、水と格闘していた。
ホルンが確認する限り、今、この現在で出入り口の類はどこにもなく、一切日差しも差していない。
それどころか足元には水魔術によって水が溜まってきており、ホルンの身体を少しずつ追い詰めていく。
火炎魔術用のサイボーグであるため、水魔術向けのサイボーグに比べれば耐水性能は劣る。
それどころかバーニヤなどが浸水してしまった場合、部品の取り換えか、あるいは回復魔術を受けるためにしばらく時間がかかってしまう。
それだけは何とか避けたいと思った。
ホルンは足元を確認する。
すでに水位は普通に立っていればホルンの腰ほどの高さになっている。
その状態でホルンがいようものならホルンのバーニヤが故障しかねない。
ホルンは長いため息をつき、さっと上空へと飛び上がる。
しかし、その水位は着々と飛行中のホルンをめがけて昇っていく。
このままではホルンの居場所はなくなってしまうかもしれない。
外部のテレパスもまた通じなくさせられているのか、声が一切聞こえてこない。
ホルンは「チッ」と舌打ちをすると、しばらく頭を巡らせる。
あまりに面倒な出来事だ。
ホルンはただため息をつき、周囲を見渡す。
その段階では何も出口がなく、もはや終わりなのかもしれない。
ホルンはそうあきらめたくも感じたが、すかさず首を振って再び周囲を見る。
こんな時に祈りでもささげれば、誰かカミサマが聞いてくれるのだろうか。
そう思うと、信仰を持つこともいいのかもしれないと苦笑いをした。
信仰を持とうか、持たないかは今でも迷い、逡巡している。
それでも、そんなことはいつでも、どうでもいいと先送りにしてしまう自分を鑑みると、何だか自分も相当つまらない、優柔不断な獣人だと思えてしまった。
しかしそんなことで落ち込んでいたところで何かになるわけではない。
ホルンはじっと周囲を見つめ、何かしらできることはないかと考える。
――それでも何とかできないか。
いま、自分を救う言葉はこの一言だ。
ホルンはその、神よりも今自分を救ってくれそうな言葉で自分を励まし、周囲を見渡す。
しかし、先ほどと同じく、何も見えるものはない。
ならば。
ホルンは耳を澄ます。
すると一か所だけ、魔力が弱くなっているのか水が漏れているような音が聞こえた。
それは福音か、あるいはニセのアクレイの声か。
その判断をするのは、自分の獣のカンと、そして機械の判断だ。
注意深くその場所を確認し一瞬だけ顔を水面に潜らせる。
水中は小さいころからあまり得意ではないが、この先水によって殺されるくらいなら、今、水に潜っておいた方が何倍もいい。
水中に潜り、魔眼のモードをマジカルアイに切り替える。
こうすることで魔力がどのようにかかっているのか、おおよそ判別させることができる。
余計な機能だと思っていたが、このようなときに役に立つのかと、ホルンは感心した。
すると自分の斜め前の場所で漏水がわずかに起こっているのを確認した。
なんと粗末な魔法なのだろうか、とホルンは思わないでもないが、それでも今、自分を救ってくれるかもしれない落ち度にホルンは感謝する。
そしてその場所を突き止めると、思いっ切り鎌を振るう。
その瞬間、もろくなっていた岩壁が崩れ、大量の水が流れていく。
幸いにも敵は気づいていないようだ。
ホルンはそれをチャンスにさらに鎌を振るい、ついに外部へと抜け出られるほどの穴を作り出すことに成功した。
やや小さな穴だが、ロップイヤーであるからあまり問題はない。
小さいころはなんだかウサギ族としては物足りない気がして好きでなかったこの耳も、このようなときには便利なのだと、久しぶりにその構造に喜びを感じた。
ホルンは穴から抜け出すと、そろそろ撤収準備をしているのであろうアイドルの一人、ウンビを確認。
ホルンは上空に一度舞い、誰も見ていない場所から敵に向かって切りかかる。
ウンビは周囲にいたアニマリアンエンターテイメントの人間たちが切り殺され、さらに彼女の腕が切り落とされたのを見て、すぐさま反応。
魔法陣を描き出す。
しかし、その速度よりも早くホルンは鎌をもう二振りし、ウンビを切り裂く。
ホルンが着地すると、ウンビの身体は4つに切り裂かれ、真っ赤な鮮血を出して崩れていった。
ホルンはすぐさまウンビたちが乗り込もうとしていた自動車に乗り込む。
腕のUSBポートを車に突き刺してハッキングすると、この車はルカのあとを追って走るようにプログラミングされている。
ホルンはすぐさま扉を閉めて車のスタートボタンを押すと、ルカに連絡を入れた
「ルカ、大丈夫か?」
ホルンの言葉に、ルカはやっと目を覚ます。
「僕は今どこかにさらわれていこうとしているのかもしれない。身体をガムテープかなにかで拘束され、さらに麻袋か何かで包み込まれている。おかげで動くことができない」
ルカの言葉に、ホルンは考え込む。
一方でタンビの様子も気になる。
「タンビ、そっちはどうだ?」
ホルンの言葉に、タンビは自嘲気味に言う。
「ボクは君の後ろで頭だけになってるよ」
どういう事だろうか。
ホルンは事情が分からず、後方を見る。
するとタンビの言うように頭部だけが完全に残っているタンビの姿があった。
内蔵はすでにくりぬかれ、足や腕はすでに取り外されている。
それどころか片方の肺も潰され、胴体部分できちんと残っているのは心臓、魔力炉、それからもう片方の肺だけだった。
凄惨な姿と化したタンビを見て、ホルンは思わず息を飲む。
「君さ、見ている暇があったらするべきことってあるんじゃないかな?」タンビは少しばかり意地悪くいい、そしてにやりと微笑む。
「そうだな」と、ホルンは言うと、そのまま回復術のタリスマンに魔力を込め、タンビを回復させる。
彼女の身体は1枚では回復せず、持っていたタリスマンをすべて使うことになった。
体中がもとに戻り、つながったタンビはゆっくりと伸びをする。
「これだよ、この体がボクだよ!」
愛嬌を振りまき、ホルンににこりと笑う。
その笑顔は同姓のホルンですらもどきどきとときめいてしまった。
「それで、ルカセンセはどこにいるのかな?」ホルンは問う。
ホルンは「おう」というとタンビにデータを転送し、そのデータと自分のデータを同期させる。
「この先200キロ先にオゾン岬がある。ここから恐らくルカを投げ捨てるんだと思う。仮にグンサンの港だったりしたら、おそらくルカは簡単に泳ぎ切っちまうだろ。それだと殺すことはできねぇ」
ホルンの言葉に、タンビはじっと聞き入る。
そしてしばらく聞いたのち、タンビは「向かう先が確定しているんだったら、さっさと始末した方がいいんじゃないかな?」
その言葉に、ホルンは少しばかり考える。
「でも、そんなことしたらルカが死んじまうじゃねぇか」ホルンは懸念を示す。
しかし、その懸念すらもタンビはしっぽを大きく振り、ちっちっと指を揺らして否定する。
「だからこそ、キミがいるんじゃないか。キミの鎌の有効活用だよ」
タンビの言葉に、ホルンは一瞬戸惑う。
しかし少し考えるとだいたい把握ができ、その考えがあっているかどうか、タンビにデータを送付する。
タンビは両腕で丸を作ったのを確認し、ホルンはにこりと微笑み、親指を立てた。
自動運転の自動車は先を走る、ルカを載せた自動車を追いかけて走りだす。
しかしながら追いつくことはおそらくなさそうな、ゆっくりとした速度である。
それに業を煮やしたホルンはセラに怒号を浴びせる。
セラは「しかたないにゃあ」と、のんびりした声で言うと、少しずつ自動運転システムを操作し、速度を上昇させていく。
そして15分ほどたったころには自動車のトップスピードとなり、次々と車を追い抜いていく。
「ホルン、Nシステムって知っているかい?」タンビは意地悪く近づき、話始める。
しかしホルンはそれを「しらねぇよ、んなもん」というと、じっと地図を見つめる。
すでにあと500メートルほどで敵に追いつく。
しかもすでにキョンドン高速道路上であり、かなりの速度を出すことも可能だ。
ホルンはじっと外と、地図を見比べ、そして5分ほどじっと外を凝視する。
そして「タンビ、いまだ!」とホルンは叫ぶ。
「今ってあれのこと?」タンビは一瞬当惑する。
しかし、ホルンが元気に頷くと、タンビは窓から銃とともにい顔を出し、そしてトリガーを引く。
前方を走る黒いワンボックスカーはタイヤを狙われてその場でパンク、はげしい蛇行を繰り返す。
一方で敵はそれに気づいたのか、後方を向いてホルンたちに銃撃を加える。
すかさずホルンはその場でフロントパネルに隠れる。
前輪がバーストしたのか、ホルンたちの車もキュルキュルという音がし始める。
かなり狙撃しづらい場面であり、ホルンは少しだけ心配そうな目でタンビを見る。
しかし、タンビは自身に満ちた表情でホルンを見て、再び窓から銃を出し、外を見る。
「ボクの銃の腕、なめないでほしいね」
タンビは言うと、前方を走る車に銃を向ける。
銃は機関銃モードとなっており、さらに銃弾ではなく魔弾を込めている。
こうすることでタンビの魔力の続く限り敵を仕留めることができる。
このような銃の切り替えをできるほど銃撃魔術に精通したタンビを見ると、なんだかホルンにとっても頼もしく感じた。
タンビはさらに照準魔術で敵をロックオン。
そして銃を放つ。
次々とオレンジの光を放ちながら発射されていく弾丸は前を走る自動車に命中し、炸裂。
進路を右へ、左へと動揺させる。
さらにタンビは赤い弾丸を込め、それをも放つ。
すると自動車はフロント部に命中し炎上。
さらに速度が低下していく。
それをチャンスと言わんばかりに、敵は銃の嵐を浴びせる。
ホルンたちが乗った自動車にも次々と着弾し、窓ガラスや屋根の鉄板に穴が開いていく。
わざと窓ガラスを自身の火炎魔術で溶かすと、ハンドルを握って自動運転を解除する。
そして銃を避けるように右、左へと操縦していく。
一方で速度が低下し、狙撃がしやすくなったのはタンビたちも同じであった。
タンビは窓から、狙撃してくる人間一人に向けて銃を放つ。
人間はタンビの銃弾を受けて真っ赤な血液を吹いて後方へと倒れていく。
その瞬間、敵兵もまた銃を放つ。
敵のなかに銃魔術師がいるのか、タンビに魔法陣が向けられる。
タンビはその相手を冷静に割り出し、その相手めがけて銃を放つ。
一方、敵もまたタンビめがけて銃を発射。
お互いの銃弾がすれ違い、そしてお互いを射抜く。
しかしタンビはすぐさまシールド魔術を展開し、それを防御。
一方で敵兵はそれを躱しきれず、そのまま倒れてしまった。
その後も敵からも銃弾は放たれるものの、コントロールがおぼつかなくなり、ホルンたちには一切命中しない。
ホルンはそれをいいことに窓から風となって飛び立つと、上空から敵の自動車を見る。
そして鎌を振るうと、自動車はその場で分断され、バラバラに砕ける。
すぐさまホルンは敵の中からルカを救出すると上空に持ち上げる。
今までホルンたちが乗っていた自動車がほかの人間たちを次々と撥ね飛ばし、内臓や脳、そして四肢をまき散らす。
路肩に止まった自動車から出てきたタンビは少しあきれた様子でその様子を見る。
次々と人間たちを自動車は引いていく。
「そんなに長居することもないな」ルカが言うと、ホルンは「そうだな」といって頷く。
そして3人はテレポートゲートを通り抜け、自分たちのアジトへと戻っていった。
「大丈夫だっただろう?」 アジトに帰ると、セラはしっぽをゆっくりとくねらせてにやにやと微笑む。
「何がだよ」とホルンは言うと、セラの頬を強くつねる。
「いたいにゃ!」セラは言う。
しかし、それが終わるとセラはじっとホルンたちを見つめる。
その目にセラの自信を感じたホルンは「そうだな」と微笑む。
セラは「良かった」というと、ゆっくりと伸びをする。
「これも作戦。笑わない」シイから連絡が入る。
セラはその作戦がどのような効果を上げているのか、ルカから継続した社会調査魔術の結果を見つめる。
そしてその結果に満足したセラは、ゆっくりと椅子に座って、パルサンサイダーを一口飲む。
しゅわしゅわと弾ける炭酸が、今のセラを祝福しているようだった。
Hymn Player
「この先三十メートルでターゲットだよ」セラの声がホルンの意識に響き渡る。
その声を聴き、ホルンはどこか深い安心感を覚えた。
ホルンは今、転送ゲートを通って人間の仮設監獄の中にいた。
人間政府が直接的に管理するこの監獄は、簡易ながらも人間の監視と支配の中に入れることができるよう、工夫がなされている。
今、ホルンが情報を受けながら侵入しているが、侵入できたとしても内部構造が尋常でなく複雑であるため、内部への侵入は困難を極める。
この構造こそが獣人をくじき、そして人間の支配の中に獣人を閉じ込めるための仕掛けの一つであった。
「アニマリアンの野郎は簡単だったけれど、モノホンの警察官はそうにゃいかねぇってわけか」
ホルンは言うと、ゆっくりと息を吐く。
警察が人間の手に渡ってしまったことで、かえって獣人界の支配はきついものになってしまっている。
その現実を見させられたようで、なんだか気分が悪くなった。
「魔術信号はどうだ?」ホルンは聞く。
「うん、大丈夫。問題なさそう」セラの言葉に、ホルンの口からわずかに安どの息が漏れる。
そして油断をしてはならないと自分をいさめると、ゆっくりと歩みを進めていく。
ホルンの耳が音をとらえ、わずかに動く。
その動きに合わせ、ホルンは顔をその音の方へと向ける。
隠れられる場所はどこにもない。
「しゃーねーや」ホルンはこぼすと、ジェット噴射を行い、上空へ。
しばらくするとそれに気づかなかった警察官がホルンの下を歩いていく。
相手が気付いていないことを確認すると、ホルンは着地。
それと同時に鎌を振り、警察官の首をはねる。
そして彼の身分証を奪い、遺体を火災通報機にかからないほどの弱い炎で燃やす。
それに気づいたのか、別の獣人兵が姿を現す。
「お前は誰だ!」犬族の、まだ改造されていない、獣の姿を持った獣人が魔法の杖を握る。
できることなら同胞を殺めるような真似はしたくない。
それでも今は。
ホルンは敵に名を名乗る前に鎌を振り、その斬撃で敵の命を奪う。
垂直方向に真っ二つに切り裂かれた遺体が、むなしく二方向に分かれて崩れていく。
その姿を、ホルンはじっと見つめた。
目的地である中央管制センターへと進んでいくうちに、警察官3人を地獄へと葬っていた。
いったいこれだけ殺しておいて、天国になんて行けるわけないと思うと、ホルンのは苦笑いを禁じえなかった。
中央管制センターは、獣人たちの監視のために用いられるロボット、人材を一度に管理する場所である。
ここで集中的に専門の訓練を受けた獣人や人間が管理することで、獣人収監者の監視を効率的かつ効果的に行えるようになっている。
目の前に見える大き目な画面には、すべての部屋の獣人たちが映し出されている。
まだ朝早いためか、多くの獣人たちは布団ももらえない環境で、縮こまりながら眠っている。
数人の獣人が理由のない暴力を受け、その痛みに目をむいており、さらに何人かは銃口を突きつけられ、そして真っ黒な鮮血をまき散らしてその場で倒れた。
ホルンはその様子を眺め、怒りと衝動に自分の身体と心が言うことを聞かなくなりそうになっているのをなだめ、もはや何度目かわからないほどついた息を再びつく。
ホルンは鎌を構え、ゆっくりと息を吸う。
そして上空を舞うと、画面を炎のかまいたちで切り裂く。
破壊されたモニターはピン、という音を立てて崩れ、破片を周囲にまき散らす。
それに気づいた獣人兵たちはホルンめがけて銃や魔法を発射。
ホルンはそれを躱していく。
一通り攻撃がやんだのを確認すると着地。すぐさま鎌を収納し、自身の拳に火を点け、それを敵に打ち込む。
一人が腹を貫かれ、ホルンの顔面に血液と吐しゃ物を吹きかける。
強烈なにおいに鼻が曲がりそうになるのを押さえ、、男からCQCナイフを奪い取る。
それを銃をは穴党としていた人間の警察官の心臓めがけて投てきし、命中させる。
さらに近くの人間の警察官から銃を奪い、発砲。
その遺体をホルンめがけて発砲された銃を避けるために用いる。
生命の塊がこのように簡単に破壊されるのを見ても、もはや何も思わない自分がいる。
それでも今は戦わなければならないと、次々と食って掛かってくる獣人たちを殺していく。
一人をブレイズパンチで燃やすと、敵のホルスターから銃を奪い取るた。
そして食って掛かる獣人を避けつつ、遠方の敵を死滅させる。
数発発射して銃弾が無くなったのを確認すると銃本体を投げ捨て、再び遺体を盾として前に突き出す。
その時、遠くから手を叩くような破裂音が聞こえた。
ホルンは耳を動かし、その音の方角へと顔を向ける。
その先ではツインテールに髪を結った羊族の獣人が、手を叩いて見つめていた。
ホルンは声を上げることなく前を向き、そして鎌を手に持つ。
「あら、こんなところにまで侵入してきて、何がしたいのかしら」
その女性は綿のようにふわふわした髪の毛をゆっくりとゆらしながらホルンに近づく。
そしてホルンから見て3メートルほどの距離を置いて動きを止めた。
「刑務所荒らしなんて感心しないわ」敵の女は言う。
しかしホルンはじっとその場で黙って留まる。
ホルンが何も言わないことを確認すると、羊族の女性はホルンの後ろに回り、軽く魔法陣を展開。
ホルンの身体にピリピリとした痛みを感じる。
意識で感電であることを察知し、ホルンは敵が電気使いであることを知った。
「私はカノン。私は何もしないわ。でも、これを見たらあなたはどうなるか、わかるわよね」
その瞬間、カノンの近くには武装した獣人たちが次々と姿を現した。
その様子にホルンは息を飲む。
隙間なく集められた獣人の兵士。
ざっと見ただけで百人近くいるだろうか。
彼らは皆、見慣れない甲冑を着用している。
自分の目標はとても簡単なはずだ。
しかしながらこれだけの獣人に囲まれてしまえば、自分の命を守ることすら難しさを感じてしまう。
ホルンはじっと周囲を見つめ、そして「やるじゃねぇかよ……」とつぶやくと、鎌を握り、足に魔力を込める。
そして紫の魔法陣を展開すると、すぐさま鎌を振った。
鎌から放たれる斬撃によって警察官十人程度が絶命し、真っ赤な血液を垂れ流す。
しかし、それを見た警察官たちはホルンめがけて魔法の杖を次々と向け、魔法を放つ。
何十条もの火炎魔術がホルンめがけて発射される。
ホルンはそのターゲットになっていることをわかりつつもその場に居座り、そして発射されるや否や飛び上がり、魔力を腕に込め、魔法を放つ。
さらにホルンは敵陣へと侵入し、ひとりの首を鎌で切り裂く。
すぐさま敵は反応。
ホルンの腹を突き刺す。
しかしすぐにホルンはその敵の顔面を垂直方向に鎌で切り裂く。
ホルンの顔、服、鎌など、あらゆる場所に人間の体液、そして体の破片が飛び散る。
彼女はそれを意にも留めず、さらに敵を葬る。
しかしながらいくら殺害をしても際限なく人間たちがホルンを取り囲み、ホルンに対して攻撃を仕掛けようとしてくる。
ホルンはそれらを躱し、命中せぬようにと対策を取る。
遠くからホルンめがけて屋が飛来する。
ホルンはそれをシールド魔術で防御すると、火炎球を作り、発射したもののもとへ。
その時、近くにいた人間がCQCナイフで切りかかる。
ホルンはその腕をつかむと背負い投げをし、腕からナイフを奪い、敵の心臓に投てき。
さらにその死体で敵からの矢を避けると、ホルンは炎で矢を作り、発射。
その隙を狙い、ひとりの獣人がホルンめがけて電撃魔術を発射。
ホルンはそれを手近にいた獣人の行動を奪い、前に出して防ぐ。
しかしながらホルンを亡き者にしようとするそのバイタリティに、ホルンは少しずつ疲弊してくる。
このままではらちが明かない。
ホルンは考えると、ゆっくりと目を閉じ、全身の魔力を足元に集中させ、魔法陣を展開。
その間にも弓矢や斬撃がホルンに向かい、ホルンの腕を切り裂き、胸に突き刺さる。
差された場所、突き刺さった場所からホルンの血液は流出し、少しずつ意識も飛んでいく。
分な魔力がいきわたったと感じたとき、ホルンは叫ぶ。
まだ生き残っている右手で鎌を持つと、敵めがけて駆けていく。
敵たちはホルンを剣で、弓で体中を狙う。
それをシールドで避けると、鎌をぐるりと振り回す。
「ブレイズスラッシュ!」
ホルンが叫ぶと、ホルンの斬撃の跡が赤く染まる。
その赤からは強い熱を発し、ホルンの視界に靄が入る。
ホルンが鎌を置くと、斬撃は敵めがけて発射され、次々と敵を切りつけ、真っ赤に燃やしていく。
さらにホルンは魔力を目いっぱい送り込み、魔法陣を展開。
魔法陣の、獣人語をデザインした模様に合わせて炎が吹きあがり、斬撃で死に絶えなかった警察官や獣人兵たちを焼き尽くす。
カノンが魔法陣から姿を現す。
彼女は相当いらだっているのか、ホルンの顔を見るや否や、荒く息を吐き捨てる。
「こうしてくれた代償、必ず払ってもらうから」
その言葉ののち、カノンは再び魔法陣の中に消えていく。
炎はやがて空間全体へと引火し、内部にいた者たちや、機械の類をすべて一様に燃えつくしてしまう。
ホルンはその場を立ちさり、次々と檻を解放するためのスイッチを操作していく。
がちゃり、という音ののち、次々とゲートが解放された旨を示すランプがつく。
「セラ!」ホルンは叫ぶ。
「わかってるニャー」セラはのんびりとした声でしっぽを揺らすと、手を画面にかざして
「我は確かに願う。囚人たちよ、その檻を超えよ!」
その言葉ののち、ホルンはパノプティコンの真ん中まで歩き、手を大きく上げる。
その瞬間、囚人たちは檻の扉を開き、次々と逃げ出していく。
それを止める獣人兵たちはいま、ここにいない。
そしてゲートの先には人間をだまして手配した観光バスが、すべての囚人たちを乗れるだけ停車している。
誰か添乗員がいるわけではないが、ソリが洗脳魔術を用い、遠隔魔術で囚人たちを行き先別に割り振っている。
囚人たちが全て乗り終えると、自動車は静かに発射する。
それを確認すると、ホルンは満足そうに息を吐き、残った右手を軽く一回転させた。
・・
一人の虎族の青年が、うんざりした表情でワニ族の獣人を見ていた。
人間に親しいとされている爬虫類人は、しばしアニマリアンや人間界でも雇用され、このように獣人を討伐する目的でも使われている。
そんなワニ族の男、ホーハを、青年はきっとした目で睨む。
「礼儀として君に聞きたい。一体なぜ獣人は独立しなければならない?」
メガネをかけ、飄々とした様子ではあるが、やはりその目には差別と、侮蔑の色があった。
「獣人への差別をなくしたい、と言っていたが、それはルダル君の方法では差別を生み出してしまうのではないだろうか?」
ホーハは言うと、煙草をおいしそうにふかし、長い息を吐く。
ルダルは余裕を浮かべつつも、何か冷たい違和感を覚えさせるホーハに怒りを抱き、それでもじっと聞き続けている。
しかし、どのように話したらいいのか、ルダルは考えることができなかった。
「それに、獣人を差別するからと人間を殺すなんて、それこそ人間への差別だろう」
人間への差別。
その差別の意味など、きっとホーハはわかっていない。
マジョリティをマイノリティが攻撃することの、いったいどこが差別だというのか。
しかし、政府に従属的な連中は皆、このように考え、獣人の意見をそいでいく。
それが一種のごはん論法のような、定義の誤解をわざと行い、相手の意見を否定しようとする。
その発言はルダルから事情を聴くのではなく、ルダルを洗脳し、そして人間に従順な存在を作ろうとしているように見えた。
「差別の定義をお前はわかっているか?」
ルダルは問う。
ホーハは「定義?」と問いかける。
「主に強い立場の人間が弱者に不利益を被らせることだ」ルダルは言うと、ゆっくりと息を吐く。
しかし、ホーハは鼻を鳴らす。
「獣人のどこが弱者? 獣人の権力者だっているし、それを思えば獣人は弱者ではないだろう」
その言葉に、ルダルは心が折れてしまいそうな錯覚を覚える。
獣人が弱者でなければ、いったい誰が弱者だというのか。
このように攻撃され、獣人であるだけで軽蔑され、酷使され、殺される。
それが差別でないのならば、何と言ったらいいのか。
ホルンはその怒りに力が抜け、ぼんやりとホーハを見つめる。
愚かな人間と話しているような感覚。
どちらが愚かで、どちらが賢いのかが分からなくなってくる。
それでも自分が言っていることに間違いなどはない。
しかしながら、その思いがあるだけに、敵の発言や行動が許せなかった。
「打ち砕かれる。獣人教で最も大切なことではなかっただろうか。打ち砕かれ、人間を愛せるようになれば君の人生も、独立を考えずとも幸せになれるはずだ」
ホーハは言う。
その言葉に、ルダルは牙を見せる。
ホーハは残念そうにルダルを見ると、ゆっくりと長い息を吐いて
「それに、そもそも差別がどうだ、こうだなんて、結局暇な金持ちの道楽でしかない。多くの獣人たちは現実を選んで、人間に従属しようと考えているのだよ? お前は結局、金持ちの獣人なんだよ。どうだね? 獣人はマイノリティではなく、そして人間界は君のような有閑な獣人を生み出せるほどの幸福な社会であることは理解できたのではないかな?」
と、話を続ける。
その言葉に目を大きく見開き、ゆっくりと息を吸い込む。
そして言葉を告げられなくなると、ホーハは「今日は疲れているんだ。疲れているからそういったことを言う」というと、部下の獣人兵を呼び出し、ホルンを牢獄に押し込んだ。
そこには別のレジスタンスから集められた改造獣人たちがルームメイトとして留め置かれている。
どんなことを考えてこのような雑居房に押し込んだのかは、ルダル達には理解できない。
しかし、何か理由があるような気がして、行動が起こせないでいる。
「どうだったんだよ?」シャチ族の男の獣人、アルデは笑う。
アルデもまた様々な拷問を受けたはずだが明るさは忘れない。
その態度が、ルダルにとってはまるで救いだった。
ルダルはアルデに一部始終を話し、ゆっくりと息を吐く。
「人間にはもう、差別や悪を判断する力なんてなくなっている。正義だと思っていたものが次々と無くなったり、正義ではないことが分かってきたし、そもそもそんなことを考える暇があったらどうやって食べていくかを考えていくしかない。それがサクラダ内閣の強さだしね……」
アルデは漏らすと、じっと天を見る。
「僕は政治思想をすべて否定された。いろいろと政治的になりそうな発言を誘導されてそれを回避するもんなんだけど、急に無菌な話をさせられるんだ。んで、話すと電気びりびり。それをずっと繰り返されて、なんだか政治的なことを考えることが嫌になっちまいそうなんだよね。よく考えられているよ。人間の癖に」
その言葉に、ルダルも天井を見たくなる。
ここで肉体への拷問よりもしんどい精神や思想に働きかける拷問を加えられ、しかも二度と出ることはできない。
訓練として読ませられる異世界に行き、人間の知恵で異世界をよくしてきたという、歴史書にしてはあまりにも粗末で、軽率な文章を読み、獣人記への尊敬や尊厳を忘れさせられる。
その物語はいずれかの段階で女性を大量に従え、性的な内容を含むものは何人もの相手と男は相手し、絶倫を見せつける。
いずれの小説も、小説を掲載しているウェブサイトで目立つために尋常以上に長いタイトルを持つ。
さらに小説にも女神はおり、こういった小説を愛さないことは、小説の女神を否定することになると教え込まれる。
人間界では異世界転生小説、としてもてはやされたともいうが、このような愚かなものが流行ること自体、獣人としてついてこれないものである。
それどころかそのような小説がウェブの中で、無料で時間つぶしに読まれるわけではなく、全国的・全世代的に読まれている。
そのことがどれだけ獣人二人を精神的に追い込んだか。
その話で盛り上がり、ルダルは楽し気な声を上げる。
「なぁ」アルデは天を見る。
天井のシミは、どこか才字架を思い浮かばせる。
「逃げ出してみない?」
アルデの言葉に、ルダルは信じられないといった表情で見る。
「逃げ出して、獣人を救い出すんだ。法律防衛、って名前で活動する」
法律で獣人を守る。
その言葉に、ルダルはなんともいえない魅力を感じ、ドキドキと胸が高鳴るのを感じる。
「俺の仲間に法律を学んでいる奴は私以外いない。だが、興味を持ちそうなやつはいる。そいつを頼ろうか。そいつ、女性で気性はものすごく荒いが、獣人語を愛する気持ちだけは本物だ」
その言葉に、アルデは耳ひれをパタパタと動かす。
「そうだな。紹介してもらっていい?」
その言葉を聞き、ルダルは「たぶん喜ぶだろう」と、微笑み、しっぽを揺らす。
「その前に脱出しなくちゃな」アルデは言う。
その言葉にルダルはゆっくりと息を吐き、「わかったよ」とうなった。
Summarization
デモ隊の機能を喜んでいたのは何もシステム班の二人だけではなかった。
このデモがある種失敗に終わったことによって虚無の感情が発生。
これを政府や「大きなもの」への抵抗の力に変えることでデモをもう一度行うだけの勢いと、そして自分たちの介入の隙を作ることに成功した。
イェスルはデモ後に結成された自由音楽協議会に宗教者代表として入り込んでいた。
「一体なぜ失敗したのか、総括しなければならない」
デモ隊の代表者であるクラーク・オトニアが舞台に昇り、はげしい熱量で話をしている。
イェスルはその勢いに感動するとともに、その直情で熱意だけがあふれる青年のことを、何とか利用し、そして応援したいと考えていた。
「大体宗教音楽を著作権で奪うなど、愚行だとNIMCAは思わないのか! 私たちはクリスチャンだが、讃美歌は伝道の手段であり、そして私たちが神を賛美する手段だ。それすら自由に歌うことができず、さらには聖書すら聖書組合によってがっちりと著作権が抑えられている。それでも伝道としているが、このように著作権で押さえてしまうことは私たちに対しての権利の侵害ではないのだろうか」
そのように叫ぶクラークは、拳を高く振り上げ、その怒りを見せつける。
そしてイェスルを見ると、「そうでしょう!」と同意を求めた。
「そうですね。私たちはクリスチャンではありませんが、同様に歌を重んじる宗教であり、著作権ですべての獣人歌謡どころか、獣人の宗教音楽すら奪われてしまっているのは看過できません」
そのように言うと、一同から拍手が沸き上がる。
ところどころで「獣人にしては良い考えをしている」といった差別的な発言が聞こえてきたが、それを無視してイェスルは壇上に登る。
クラークは一瞬驚いた表情でイェスルを見たが、すぐにマイクをイェスルに譲り渡す。
「私の友達が獣人の著作権による著作権侵害を調べているのだが、今まで獣人たちに愛唱されてきた歌のうち、九十九・九%がNIMCAやそれに準ずる企業、そしてレコード会社によって人間の歌として登録され、獣人が宗教的な集まりなどで歌っている際に著作権団体の人間が入り込み、逮捕されたという事案もある。それについてはレジスタンスが解放を行っているものの、それはもはや鼬ごっこの様子を見せている。その一方で人間の著作権被害は四十%ほど。ただし理不尽な集金がなされており、配分がほとんどなされていない。それでもNIMCAを盲目的に支持する音楽作家、そして出版社を妄信する作家や漫画家がいるせいで、この権利ビジネスの根を絶やすことは難しそうだ」
イェスルの言葉に、一同は静まり返る。
それを見て、イェスルは再び口を開く。
「さらに愉快なのが、二次創作で著作権侵害で訴えられるのではないかと恐れていた人々が、いざ出版社に認められたら著作権の亡者になることだ。確かに著作権による収入を糧に生きているわけだから、それが絶やされてしまおうものなら生きる糧を失う。しかし、それは虚業であり、それによって大衆迎合するあまり社会的な機能を失い、消費物となり果てた創作物を、まるで流行りの服のようにとっかえひっかえする時代をもたらしてしまった」
イェスルはけもレイドのグループとしての意見をこの場で伝える。
聴衆の中にいた小説家や音楽家たちはしばし押し黙る。
もしかしたら怒らせただろうか、とすこし考えたが、すぐにわきあがった歓声により、イェスルの予測は棄却された。
「そうだそうだ!」一人の小説家が叫ぶ。
そして小説家は朗々とした声で何やら演説を始めた。
その時、セラとシイからのテレパスが入電する。
「音楽家とか、出版社の人たちの意見を取りまとめたよ」
シイは特に誇張や自慢をするような言葉づかいではなく、ただ事務的に言う。
その言葉をセラは気にすることなく「んにゃん」と言ってしっぽでシイの鼻をこすると、シイはシャーとセラに牙を見せた。
「僕から報告するね」
いうとセラは書類をイェスルに転送した。
多くの作曲家、作家は音楽出版社、NIMCA、出版社を信じ切っており、その分配金がたとえ30%程度でしかなくとも、自分たちの権利を十分に守ってくれていると感じている。
その一方で実質的に著作権を握りしめている出版社などがどれだけピンハネをしていようとも、印税がもらえることに満足し、貧しい生活でも自分のことを満足させて生きている。
さらにルカの分析ではこの貧しさこそが著作権収入を求める原動力になっているという。
イェスルはそのことを考え、どのようにしたらいいのかを考える。
しかしどちらにせよ、著作権で金を稼ぐというビジネスモデルを変え、さらに自分たちが文化の作り主であるという自負心を打ち消さなければ結局いくら著作権の文化をリビルドしたところでうまくいかなくなってしまう。
さらに、クリエイティビティを求める人間が、それこそが自己責任で、自分であぶく稼業ではない仕事を見つけられないという甘えで生きている存在であることを認識しなければ、著作権をなくすことはできない。
あるいは、著作権を私有財産ではなく、半私有財産にするというある種のコピーレフト的な考えをできない以上、著作権に縛られて自由に行動できないという制約はいつまでたっても解除することができない。
コピーレフトの考えであれば、著作権を持ち、誰が原作者なのか、そして誰が一応の著作権を持っているのかを維持しつつ、自由に文化を共有させることができる。
これにより、人間の多くの文化をNIMCAなどから著作権を得ることができる。
一方で獣人の歌などは出版社が偽名で登録しており、それらを取り返すことはそれなりの努力が必要となる。
さらに出版社はその事実を認めようとしないだろう。
イェスルはそう考えると、少しばかりアンニュイな気持ちになった。
「聖職者でも憂鬱そうな気持になることって、あるのね」シイはじっと画面に向かい、話す。
「まあな。獣人の曲をすべて取り戻そうとすると天文学的な金額が必要になってくる。それに政府とNIMCAや音楽事業者がくっついているとなると、それは絶望的だ。どうしたらいいのか、と考えたのだが、それでも難しそうだな」
イェスルの珍しく現実的で、弱気な発言に、シイは少しだけコンピュータをタイプする速度を緩める。
「聖職者がそんなに弱気でどうするんだ。キミしかやれないことだろう」
シイはいらだった声で吠えると、イェスルを睨みつけた。
「作家一本で生きていくなんて、ふざけた生き方だ。そんなものに夢を見て、真っ白な履歴書を作り続ける。そんなことをして無駄な人生を送れるほど、人間は充実しているってことだ」
シイは普段とは異なる、怒りに満ちた目でセラ、そしてイェスルを見る。
確かにふざけた生き方だ。
創作物など、どれだけ上手なものがやろうとオナニーには変わりがない。
みっともなく自分自身の妄想で自身のペニスをいじり、精液をまき散らす。
そのまき散らした精液がおいしいか、あるいはまずいのかで人間はその創作物の良しあしを判断し、おいしい精液は出版社やレコード会社が買い取ってみんなに売りさばく。
そうセラは、こっそりとイェスルに告げ口をする。
その言葉に、イェスルは同意するほかなかった。
どれだけうまく描けようと、創作というオナニーはみっともない。
だから獣人の世界では「使ってもらう」ことに意義があった。
それを誰かのオナニーでとどめておくことを獣人たちは良しとしなかったし、逆にみんなでそのオナニーを芸術に高めて、そしてみんなでその味を楽しもうとしていた。
それでも、獣人たちは減ることのない感謝のやり取りはあったが、それでもそれが自分のもの、という意識は皆なかった。
それどころか、オナニーを自分のものだと判断する獣人たちは軽蔑される向きすらあった。
「自慰にふけって金をむしり取るって、確かに愚かなことだ」イェスルはつぶやく。
何ができるかを、イェスルはゆっくりと考える。
そして。
「私もやってみるか」
いうとイェスルはその場をすっくと立ちあがり、会場を後にする。
そして物陰で変身すると、移動術を使って獣人の音楽を支配する音楽出版社、アニマリアン・エンターテイメントへと向かった。
Copyleft
イェスルはイスラマ街のアニマリアンエンターテイメント社の地下駐車場にいた。
この建物は一階より侵入すると非常に警備員が多く、侵入が困難ではないとはいえ手数がかかる。
しかし、地下駐車場からであれば建物の地下より直接ターゲットフロアである6階まで向かうことができる。
地下駐車場の内部は、自動車の煙でむせ返りそうになっている。
人間界ではすでに電気自動車が普及し、だいぶクリーンな空気を取り戻しつつある。
しかしながら獣人界では自動車業界が自動車好きの楽園として獣人界を位置付けたため、一部の物好きたちのせいでガソリンを大量に使い、排気ガスをまき散らす自動車が無視できない台数となり、そしてこのように、獣人界の清浄な環境を破壊していた。
「イェスル。出入口は三時の方向に向かったところだよ。その先に警備員がいるけれど、彼はたぶんワンパンで死ぬにゃ。あとはエレベータに乗れば6階だよ。今日はアニマリアンの創立日だからみんなお休み。だから入りやすいかも」
アニマリアンの休日。
そんな日があったことに、イェスルは驚く。
ゆっくりとふぅと、息を吐くと、ゆっくりと出入口へと向かう。
そして出入り口に立つと、案の定警備員が二名立っていた。
イェスルはそのうちの一人を背後から羽交い絞めにして殺害。
慌てた様子でもう一人の人間がイェスルに銃を構え、発砲する。
しかしそれを死体で防ぐと、今度は死体から鹵獲した銃で頭部を狙撃。
彼はスイカが弾けるように頭部の肉片をまき散らし、その場で崩れた。
しかし、イェスルの服には血液がついており、そのまま上がってしまうと大変な事態になり寝ない。
イェスルはエレベータに向かう前に手洗いへと向かい、服を着替えて姿を現す。
その間に何台か監視カメラが設置されていたが、それらにはセラの魔法により、イェスルを認識できないようにしていた。
何人かの社員を自動販売機や柱の陰でやり過ごすと、エレベータに搭乗。
シースルーエレベーターはゆっくりとした速度で階を昇っていく。
エレベータを降りるとすぐ目の前に見えるドアを偽装したRFIDタグで開錠すると、内部に侵入した。
普通の事務所とは異なり、ひとりに一つドア付きの個室が与えられている部屋。
ここでアニマリアンの社員がいかに優雅に事務を行い、過ごしている。
そのことを思うと、まるで韓民記のドファンや、クンヘを見ているような気がして、いつの時代にもこのような、甘い蜜を吸い、民草を攻撃するような輩がいることに、嫌気がさした。
「カエサルのものはカエサルに、だにゃぁ」
皮肉っぽい冗談を飛ばすセラに、イェスルは同意せざるを得ないと感じた。
イーサーはかつて、自分たちを守るために、そして神を賛美するために王へと自分のものを返すように言った。
しかし、今ではその言葉を獣人すらも、従順に人間に生きることだと信じ込んでいる。
その情けない姿を見ると、イーサーの言葉が心に空しく響く。
イェスルはむなしさをかき消すように、詩編23編を口ずさんだ。
「四号室の中にデータがあるよぉ」
セラは言うと、くるりとしっぽを回し、それを手に取って遊ぶ、
その姿を見なかったかのように四号室に進んでいくと、そこには大型の棚が並べられていた。
部屋の隅にこの部屋の主である、ライセンスチーフ、スミン・ファイシター・ドンドの写真が掲げられている。
かつて獣人界でアイドル「FEM」として活躍していた時代の輝かしい時代の写真。
このような写真を掲げ、獣人として歌っていたはずなのに、なぜ今。
その変貌がなんとも信じられず、イェスルはゆっくりと顔を落とした。
イェスルはその中の書類をすべて盗み出し、それを転送ゲートを通じて送信する。
「うっひゃー! こんなに」セラは素っ頓狂な声を上げ、目を大きく見開く。
およそ十万枚にも及ぶ楽曲の権利契約書。
それらはすべて獣人の名前ではなく、人間の名前が書かれていた。
セラはそれらを魔術プログラムで精査する。
「すべてあるね。獣人界で作られた歌と、その権利」セラはゆっくりと息を吐く。
それにしても、と前置きをすると、「人間は民謡とか、歌謡曲だけじゃなくて、人が歌っていた桔梗歌とか、仮面劇の太鼓のリズムまで登録していたんだね……」
と、息を吐いた。
桔梗歌はある種の祭囃子だ。
そして仮面劇は太鼓を打ち鳴らし、仮面をかぶった獣人が為政者や権力者を叩く筋書きである。
どちらもリズムが違うだけで、アッサ、ルシガー、の二ことをリズムに合わせて歌うだけだ。
それらをも著作権登録し、さらにそれに法外な利用料金を課すことで音楽だけでなく、芸術を奪い去っていく。
その姿に、イェスルはなんとも言えない悲しみを覚えた。
セラはしばらくすると5千枚程度ずつ書類をイェスルに戻す。
イェスルはそれを丁寧に元の位置に戻すと、そっと部屋を出ようとした。
その時、部屋の外から声が聞こえる。
イェスルはすぐさま扉の陰に身を隠す。
そこに部屋の主であるスミンが大きな尾ひれを揺らし、入ってくる。
彼女の持つブランド品のかばんが、彼女が獣人としてどれだけの特権階級にいるかを指し示していた。
イェスルはゆっくりと彼女の後ろに立つ。
スミンはその場で携帯電話をかけ、話始める。
「獣人がまた獣人歌謡を勝手に歌ったですって」
その言葉に、イェスルは耳を立て、録音システムで音声を撮る。
さらにセラに電話越しの音声も含めて送信する。
カンサンの音楽家集団が著作権反対カンジュ獣人総蜂起というイベントで旅行という歌を流した。
その歌は獣人界で大流行した歌ではあったあ、やはり人間がその歌を奪い、人間側の獣人であるスミンが自らの歌として著作権登録を行い、さらに抗議していたデュオを逮捕し、殺害した。
そのことに誰も知らず、また、人間の魔術によって忘却させられている。
一方で10万曲近い獣人音楽をすべて手にしたスミン、そしてアニマリアンは大量の著作権料をものにし、さらに獣人から自由な音楽を奪い去った。
その張本人が今、目の前で著作権侵害を報告するNIMCAからの電話を受けている。
イェスルにとって、彼女の運命は決まっている。
たとえ相手が魔法のやり手であったとっしても。
イェスルは自身の決意を胸に離脱。
代わりにタンビを置く。
タンビはイェスルの様子を見ており、そして怒りに燃えていた。
彼女は自身の怒りを見せるべく、一発魔弾を敵に打ち込む。
その瞬間、その音にスミンは反応し、すぐさま変身。
魔術着に着替える。
「あんた、ボクたちの音楽をどうするつもりだい?」
タンビはふさふさしたしっぽと、結わいた湿った黒の髪を揺らす。
一方、スミンはそれなりの年を取っているにもかかわらず、改造の結果からかかなり若々しく、ウェーブのかかった髪を揺らす。
「私たちの音楽は、私たちが使うだけよ?」スミンは微笑む。
そのほほえみにどこかなまめかし嫌みを感じ、タンビは目をしかめる。
一方でスミンはその表情を見て、満足げに微笑む。
「私たち、って言葉にボクは入っていないんだよね、レンギョウさん」
タンビは言うと、にこりと微笑む。
それに怒りを覚えたスミンは尾ひれを激しく動かし、長い息を吐いた。
「泥棒民族」
スミンの漏らした言葉に、タンビの耳が動く。
泥棒はどちらか。
その答えは火を見るよりも明らかだ。
「泥棒はどっちだか。これを見たらわかるんじゃないかな?」タンビは言うと、書類をいくつか見せた。
それらには自分が集めて著作権を奪った曲の権利書があった。
それらはすべて元の作家の手に戻され、さらにコピーレフトである旨も記されていた。
「あんた……!」スミンは腕を振るわせながら書類を見て、そしてそれを投げ捨てる。
「ボクたちの曲はボクたちの手にあってこそ、だよ」
タンビは言うと、えへへと笑う。
その笑顔にさらに怒りを覚えたのか、スミンはタンビの胸のオッコルムをつかむ。
「この……音楽泥棒!」
いうとスミンはタンビの頬をはたく。
タンビは頬をゆっくりとなで、眼をなまめかしくしかめる。
「ボクたちの音楽を奪って、著作権を主張するから悪いんだよ。ボクたちの自由な音楽を返してよ」
タンビは生意気に、あえて高慢ちきに言う。
その時、タンビは腹に強い鈍痛を覚えた。
瞬間、タンビの口から血液がこぼれる。
「公正な音楽取引から、音楽家の権利を奪うんじゃないよ」
その言葉に続き、さらにスミンは左手でタンビの腹を殴る。
「文化の発展にはね、それに携わる人が自立して、お金を稼がなくちゃいけないの。それを仲介するのが私たち権利者なの」
スミンの目は血走り、怒りを湛えている。
その目にタンビは違和感を覚えるも、それを訴えるような精神的、肉体的な余裕はない。
タンビはなすがまま、されるがままに腹を殴られ、さらにその拳はタンビの顔面へと向いた。
スミンはすぐさま魔法陣を掛け、タンビを十字につるす。
「音楽泥棒め、私たちの音楽を奪ったこと、後悔しなさい!」
彼女は携帯電話のカメラ機能を起動し、それを台座に置く。
そしてタンビを見る。
足元には魔法陣が展開され、それは彼女の腕先にも伸びていた。
スミンは舌なめずりをし、蛇が獲物を狙うかのような目でタンビを見つめる。
さらにスミンは指の間にナイフを作ると、それをタンビに見せつける、
「ボクちゃんにいいこと教えてあげる。モノを作っている人にお金を払わないことはね、泥棒と一緒なの。そうやって文化を発展させてきたの、わかるかしら?」
タンビはその間にもどうすればいいのか、手段を考える。
手を動かしてみる。
するとわずかに腕の先が動くことに気づいた。
タンビはそれを敵に気づかれないよう、ゆっくりと動かし、そして銃を手に取る。
そしてターゲット魔術を起動し、スミンの心臓にノックオン。
銃の内部に爆発魔術を込め、人差し指と親指でトリガーを絞る。
魔弾はスミンめがけてノンストップで直進し、見事魔法陣の中心である、スミンの胸へと命中する。
銃弾はタンビの計算通りに心臓を貫いたのち爆発し、胸部の肉、骨、そして血液をまき散らし、スミンは世の場で絶命。
遺体はひっくり返るようにその場で倒れ込んだ。
タンビは見つからぬよう、魔術で銃弾を消し去る。
そして「秘密生物図鑑もオンライン百科事典もある種のコピーレフトだよ」といい残すと、その場から立ち去った。
地下階でイェスルと合流し、イェスルの運転する車でアジトへと戻る。
その道すがら、イェスルはタンビに問う。
すでに転送魔法を利用し、著作権契約書は原作者に返却し、パブリックドメインになるはずのものは弁護士の獣人、これまでも、これからも救ってくれそうな獣人に預けることにした。
「著作権を私たちは持っていなかったわけではない。ただ、それをお金にしようとしなかっただけだった。それをシンはマネタイズして、コンテンツ産業を生み出した。それで幸せになった獣人はいたのだろうか」
その言葉に、タンビはゆっくりとしっぽを振って考える。
タンビはそうだなぁ、と言ったのち、運転するイェスルを見る。
「コピーレフトの考えを広めていくのが一番かもね。まずは取り返した獣人に掛けた魔法で、コピーレフトを広げる。それから人間にそれをネズミ講式に魅力が広げられるようにするといいのかも」
タンビはわかんないけど、と言ってイェスルを見て微笑む。
コピーレフトは、コピーライトに代わる考え方だ。
著作権を保持する一方で、著作物の利用やコピー、再配布、二次創作物の再配布を制限せず、また、二次創作物の利用なども制限を禁止するという概念のもと、自由に作品の利用を認めるものだ。
これには原作と同一条件で引き継ぐこと、氏名を表示することなどもライセンスによっては含まれる。
プログラム開発の世界で多く取り入れられている技術ではあるが、それを音楽や文学などに適応することで、文化の改良が促進されるという考えのもと、一部の小説などでも取り入れられている。
このライセンスは獣人界では多用され、多くの派生コンテンツと、コンテンツの盛り上がりを実現することができた。
これを人間界で適応するとなると、商業主義が問題にはなってくるが、二次創作やリミックスと言った文化が再び花開くこととなり、結果コンテンツを大いに盛り上げることができるようになる。
すでに二〇二〇年ごろより、一部のアニメーションなどで独自の二次創作ガイドラインが敷かれていることがあったが、それをより広げ、多くの作家によって二次創作を作れるようにすること、そして画像や映像を利用したり、リミックスしたりすることを許可することが、この考え方の一番の肝となる。
それを実行できるように社会をセットしていくことで、著作権を実質的に封じることができる、というのがタンビの考えであった。
「なるほど」イェスルは静かに答える。
確かに著作権を向こうにしてしまうことは、文化を破壊してしまう。
しかし、著作権を維持しつつ、その利用と翻案の自由を認めることで、人間も獣人もお互いに幸福なのではないか。
イェスルはにわかに気持ちが沸き立つのを感じ、少しだけアクセルを踏んだ。
・・
ソリは電子黒板の前に立ち、8人のほかの獣人たちを前に立っていた。
「このように、アニマリアン、そしてそれに連なる音楽会社や出版社は回収した著作権を還元しない、そして獣人に対しては使わせないといった差別的な行動をとり、さらに自分たちの利益を独占するために著作権を百二十年まで延長しようとしていることまではわかりました。他に何かあるかしら」
その言葉に、ルカやタンビがしっぽや耳ひれを動かす。
「ほかにボクが最近あっている人がね、」タンビは言い出す。
しかしながら発言の許可を得ていなかったことに気づくと、少し気まずそうに顔を落とした。
「タンビちゃん、何かしら」ソリはしかしながら責めることなく、明るく微笑む。
その表情に救われ、タンビは「ボクがよくあっている人がね」と言葉を切り出す。
「ボクがあっている人が言っているんだけど、これを申し出たのがアニマリアンで、しかも結構理由がゲスいんだよね」
タンビは言うと、「ちょっと知り合いを呼んできた」という。
その言葉にホルンは「勝手に呼んで……」と言葉をはさむが、その言葉をイェスルは「まぁ、お前が見たらびっくりするような奴だ」と言って遮る。
姿を現した獣人は、白い大型の男性獣人とその仲間であるという、若い代議士だった。
特に白い大型の、トラ族の獣人を見て、ホルンたちは目を丸くし、ホルンは懐かしむように彼のもとに行った。
Rabbit Crisis
ホルンは今、東葉空港にいた。
ここから空港特急スカイアローで都心に向かう。
その道中が素晴らしいものになるよう、ホルンは柄にもないと思いつつ、祈りをささげた。
全く以前獣人格闘技の選手だった時もそうだが、いざ戦うとなるとどうしても神に祈りを捧げたくなる。
神様というものがどれだけ自分の祈りを聞いてくれているのか、ホルンにはわからない。
それでも祈ることで体が戦闘モードに切り替わるのであれば、それでいいのかもしれないと思った。
スカイアローが東都北駅に着くと、そこから環状線で副都心駅へと向かう。
副都心駅の前の、人間が世界で一番の交差点だと自慢する副都心スクランブル交差点を渡ると、今自分が東都にいることを実感することができた。
そこから消防署通りを上がっていくと、原子力発電所に似たような建物が見えてくる。
かつてはここに電力公社の博物館が入っていたが、二十年前の原発事故で撤退し、今は今回のターゲット、NIMCAが入っている。
ホルンは向かいにあるコーヒーチェーン店のオープンデッキに座り、資料を意識の中で展開する。
建物は八階建てで、中にはフルカワ音楽博物館も入っている。
博物館とNIMCA本部は出入り口を共有しているため、簡単に侵入することができる。
ここが著作権を暴力的に奪い取り、それで稼いだ金を浪費している施設かと思うと心の中の導火線に火がともった。
「この施設で一応気をつけないといけないところは出入り口だね。あとはNIMCAは人間しか採用しない方針だから非力な人間しかいないよ。魔術兵もいない。でもホルンだったら一番上の階の博物館と出入り口を燃やせばいいんじゃないかにゃ。ちょうど七月火災のようにどんどん燃やせるにゃん」セラは猫のようなポーズをとって言う。
「冗談にもならないことを言うんじゃねぇよ」と軽くセラをたしなめると、セラはにゃうん……。と言ってしょんぼりした表情をした。
それでも構造を理解したホルンは残ったニンジンジュースを飲み干すと、そのまま博物館へと向かった。
博物館は音楽好きであればだれでも興味を示すようなものが多く展示されていた。
かつて国というものがあった時の音楽の視聴コーナーや、獣人界の音楽についての展示、それからほかの世界の音楽についても展示がなされていた。
その中で特に、世界でも華々しい著作権への貢献を果たしたフルカワ・マサキという人物についての展示が多くなされていた。
ホルンはその一つ一つ、特に獣人についての差別的かつ独善的な記述に腹を立て、息を吐く。
そして地図を確認し、ここに発火魔術、爆発魔術を仕掛けることにした。
「我は確かに祈る。炎よ、我らを搾取する者を滅ぼせ」
その呪文はその場で展開され、魔法陣が床に消えていく。
数々の獣人の資料が無駄になることが悲しく、ホルンは展示ガラスを溶かして展示品を奪うと、それをシイの開発した時空ポケットに放り込んだ。
「ためになりました」とホルンは行って脱出すると、エレベーターを途中の階で下車する。
そしてエレベータの前にガス魔術を掛ける。
このガスはホルンの魔力による炎がかからない限り無色無臭、そして爆発も起こさない。
「ここの資料は奪うか?」ホルンは聞く。
しかしセラは「ある資料は全部うばえたにゃ。ざる警備~」と楽しそうに報告したため、そのままエレベータに乗り込む。
そして脱出口にも火炎魔術を掛けると、ホルンは何食わぬ顔で副都心駅へと向かった。
ホルンが副都心駅近くの割賦百貨店の前で振り返ると、NIMCA本部はまるで地割れのような音を立てて爆発し、土煙がホルンを襲う。人々は慌てて逃げまとう。土煙、そして様々な残骸を炸裂させ、さらに残った建物からは激しい炎が上がる。
警察官がそれに気づいたのか、大慌てで建物の方へと向かう。
副都心の電力施設が入っているのもあり、副都心一帯の電力も停止しているようで、信号なども消えてしまった。
ホルンの目の前で人間が自動車にはねられる。
恐らくNIMCA本部の近くにある消防署から派遣された消防隊が消火活動を始めているだろう。
ホルンは何事もなかったように電車に乗り、東都北駅へと向かった。
私鉄の東都北駅で下りのスカイアロー号を待っている間、ホルンはぼんやりと停車している普通電車を見た。
銀色に赤の帯を巻いた電車はひっきりなしに駅に到着し、そして出発していく。
せわしない電車のすがたを見ていると、なんだか自分は暇なのだろうかという気分になる。
そして暇ついでにいま行った行動を振り返る。
このようなことをしてカミサマは許しはしないだろう。
それでも仲間を救うためには必要なすべなのだと祈りをささげる。
一体どこまでカミサマといういるのかいないのかわからないものを信じようとするのか。
ホルンは考えると、なんだかおかしく感じられた。
しばらくすると電車の乗車が許可され、車内に乗り込む。
さすがに最近人気観光地になりつつある人間界であるからか、天使の輪を持つ天界人、スーツをばっちり決めた科学界人、そして多く見受けられる爬虫類人や竜人の姿があった。
しかしながら自分の乗った車両は不思議と獣人が多く、ふさふさしたしっぽを持った獣人がそれを隠しきれずに露出していた。
それにしても変だ。
ホルンは顔をしかめる。
ホルンは目立つことのないように人間の姿を取っていることに注意しつつ、椅子のリクライニングをわずかに倒した。
発車メロディがかかると列車は静かに動き出す。
自動放送ののち、人間の車掌が態度悪く接客に当たっているのが見えた。
ホルンは獣人界の下町を眺めつつ、少しだけまどろんだ。
車両は間もなく200キロの高速運転に入るというアナウンスがかかる。
ここから50分、寝ていようかとゆっくり息を吐いた瞬間、「チトセ・ヒビキさんですね」という声が掛けられた。
チトセ・ヒビキ。人間に、奪われた獣人名の代わりに与えられた人間名だ。
ホルンは不快だという表情で声をかけて来たものを見る。
彼はドーベルマン族の女性警官のようで、黒い耳と細いしっぽをみせていた。
ただ彼女もまた半獣に改造されているのか、姿はすらっとした人間女性のように見えた。
「何だ」ホルンは聞く。
警察官になんて用はない。
しかしその敵意を露骨に見せれば獣人法で逮捕される。
その瀬戸際で、ホルンは嫌悪感を示した。
「先ほど副都心で起こった爆発事件に関して、あなたが犯人であるという情報が出ています」
人間の捜査の早さには驚かされる。
しかしそのことに恐れを見せることなく、じっと警察官を見た。
「あなたをテロ等準備罪・破壊活動防止法・獣人法違反で逮捕する!」
言うと女性はめがけて銃を突きつけた。
「いやだ、って言ったらどうするんでい」
ホルンは言うと立ち上がり、鼻を鳴らす。
すると周囲の乗客たちも立ち上がり、ホルンめがけて銃を突きつけた。
「てやんでぃ。周りのやつもグルってことかよ」ホルンは舌を打つ。
道理で獣人が多く、しかも無防備だと思った。
彼らは全員半獣の戦闘員であり、ホルンをどこからか狙っていた。
恐らく捜査をしていたのはタラムだけではなかったのだろう。
心の中に殺意の赤い炎がわく。
「そうよ。あなたをずっと追いかけていたの。それこそ東葉空港からね。この電車が終点に着いたらあなたを警察署に引き渡すわ。無駄な抵抗はやめなさい」
しかしホルンはケッというと、近くの椅子に手を掛ける。
そして魔力を込めると、椅子は乗客を乗せたままあっという間に炎上した。
「こうなりてぇんなら、俺も捕まってやらぁ!」
それと同時に人間はホルンめがけて魔法弾を発射。
ホルンは火遁魔術でそれを躱すと、近くにいた人間の首に腕を当て、魔力ガスを首に注入。
「ポップ」と軽く言うと、人間は頭部をまるでスイカを棒で割ったように爆発し、胴体だけが残る。
ホルンはそれを盾に座席から離れる。
しかしながらその場で人間はホルンめがけて銀弾を胸に二発打ち込む。
ホルンはその場で倒れ込み、眼をぼんやりと開いて崩れ落ちる。
先ほどのドーベルマンが近づき、ホルンの検視をしようとする。
しかし彼女が目を離した瞬間、立ちあがり、彼女の首を絞める。
さらに魔術を込め、彼女の胸部から出火させる。
ドーベルマンの女性警官はその場で崩れ落ちた。
その瞬間、わずかにスペースを確保。
しかしそれと同時にホルンめがけて魔弾の集中砲火を浴びせる。
それをホルンはドーベルマン女性の胴体で防ぐ。
遺体はハチの巣にされ、まるでぼろ雑巾のようになった。
「我は確かに祈る、炎よ、敵を蹴散らせ!」
ホルンは叫ぶ。
それと同時に魔法陣が展開され、さらにそれから真っ赤な炎が現れる。
ホルンはそれを指揮者のように手を大きく広げ、炎の勢いを増す。
窓が溶け、車両に引火する。
しかし、敵兵はホルンの殺害をあきらめてはいない。
ホルンめがけて雷撃魔術を打つ。
ホルンの胴体に命中。
わずかにホルンの身体がスタン状態になる。
それと同時に敵兵はホルンの腕を押さえ、彼女の腹に銃を放つ。
身体を動かそうとするが、相当強く抑えているのか、動く気配はない。
その瞬間、3人の獣人兵がホルンめがけて魔弾を発射。
ホルンの胴体へと命中する。
運悪く数発がホルンの腕を射抜き、それらが炸裂する。
右手は完全に落ちてしまったが、左手はかろうじて骨格だけでつながっている。
こんな時に自分が半獣、サイボーグであることに感謝するのはなんだか悲しく感じられても、それでもそうせざるを得なかった。
ホルンはその瞬間、自分自身に火炎魔術を掛け、自身の身体を燃やす。
それと同時にホルンを押さえていた獣人に延焼し、やがて真っ赤な炎を上げて燃えだす。
ホルンはそのまま火遁の術に移行。
さらに銃撃をした獣人に接触し、彼らをも引火させる。
そして鹵獲した魔法の杖を鹵獲。
ホルンはその杖の魔獣VPNを通し、自分のものとして認証させる。
「我は祈る! 雷よ、敵を蹴散らせ!」
発するや否や発動した電力により、車内の獣人たちは感電。
さらにすぐに火炎魔術をかぶせることにより車内にいた獣人は軒並み死亡した。
「ホルン、前の車両に逃げて。この電車、八両を四両四両に分割しても問題なく動く!」
セラの早口が聞こえてくる。
そういえば彼は電車が好きだったっけ、と思うと、なんだか彼の電車好きも悪くないのかもしれないという気分になった。
ホルンは一両、車両を動く。
その瞬間、奥の車両から警察官が侵入してくる。
ホルンはその瞬間、火炎魔術で貫通路と連結器を溶解させ、車両を切り離す。
高速走行にともなう強い風が車内を突き抜ける。
切り離した車両に魔力を込める。
車両は見えづらくなったころに、走りながら大爆発を起こし、脱線していった。
一方で前方車両からも爬虫類人の、アニマリアンミリタリーの軍服を着た兵士がホルンめがけてやってくる。
そしてホルンを見るや否や「頭を下げろ!」と乗客に命じ、銃を構える。
「てやんでぃ!」ホルンは啖呵を切ると、動いている左手を突き出す。
そしてパイロキネシスを発射し、敵だけでなく、乗客もろとも焼いていく。
しかしその時、後方に気配を感じる。
それを見た瞬間、敵はホルンの左手を切り離し、さらにホルンの心臓めがけてパイロキネシスを放つ。
ホルンの身体に引火した炎はホルンの胸部を焼く。
その瞬間、魔力回路、そして魔力炉が熱を上げ、自動停止する。
魔力の供給が失われたホルンの身体は停止し、体が動かなくなる。
一方、頭巾をかぶった正体不明の敵兵はホルンの身体への攻撃をやめることをしない。
やがてホルンの心臓が熱で溶解し始め、血液が体内を狙うようになる。
さらに彼女の心臓は熱で弱った部品が血流に耐え切れなくなり爆発。
ホルンの皮膚を突き破る。
それでも敵は攻撃をやめない。
ホルンは脳に血液が回らなくなり、意識が少しずつ遠のいていく。
さらに魔力炉は熱に耐え切れなくなり爆発しそうになる。
「馬鹿なこと、してくれるじゃねぇか」
ホルンは言うと、ゆっくりと座席に身をもたれさせる。
一方、敵兵はホルンの顔面めがけ、嵐のような銃撃を浴びせる。
人工筋肉がすぐに露出し、眼などもぐちゃぐちゃになっていく。
さらに目の中に入っていた魔眼の魔力が漏れ、そのまま燃え始めた。
「畜生……!」
ならば。
ホルンはその場で魔法陣を描くと、眼から漏れる魔力と血液を手にためる。
そしてその液体を魔法陣にそそぐ。
ホルンはその瞬間、車端部に立つと、呪文を唱える
「我は確かに祈る、炎よ、我らの怒りで悪を燃やし尽くせ!」
その言葉を発した瞬間、魔法陣から真っ赤な炎が発生し、次の瞬間、激しい爆発を起こす。
ホルンはその爆発に弾き飛ばされて、車両の外に追い出される。
その瞬間、足のジェットパックを展開し、壁への激突を回避する。
ホルンはじっと、列車を見つめる。
ばらばらにされた車両はその場で炎上し、崩れ落ちてしまう。
その光景を見て、手を合わせて祈りをささげた。
大勢の乗客を乗せた車両は東都空港駅に二百キロで侵入し、まるで押しつぶされるように折り重なり、圧縮されて停止した。
Dirty Diva
ソリはVtuber計画に合わせ、もう一つの、汚い手段を担うこととなった。
汚い手段、それは世論において著作権とそれを手にがめつく金を稼ごうとする連中を処理するということだ。
検討した結果、著作権者を殺害する必要などは当分なさそうだ。
ただ、その意見の潮流に乗らないような連中も大勢いる。
特にクリエイターとされる類の人種や、世の中の風潮に逆張りをするような連中は、ソリたちの魔術が聞かない可能性がある。
そんな彼らを懐柔するための手段として、著作権の風潮を変える必要があった。
ただ、それの方法自体はもう難しさはない。
すでにホルンたちのおかげで著作権を過度に主張し、すべてを独占する愚かさの拡散はできている。
あとは至高を奪い、コピーレフトを広めることができれば、社会を変えることができる。
それをいかに行うかを考えるべく、ホルンはルカの部屋にいた。
「そういう事か」ルカは静かに言うと、椅子から少しばかり腰を浮かせて話す。
ソリはじっとルカを見ていたが、やがて「どうかしら」と言葉を続ける。
「そうだな。殺人をするのもいいかもしれない。ただ、それをやりすぎてしまうと広告魔術の利きが悪くなってしまう」
ソリはペンでメモを書くと、「そうねぇ」とつぶやく。
「となると殺害は先の方がいいかもしれないわね。そっちの方が効果が覚めにくい。あとはレタッチすれば消えないだろうし」
そこにセラがにゃあ、といって姿を現す。
そしておもむろに印刷した紙を見せると、しっぽをくるりと曲げてにこりと微笑んだ。
「レタッチは簡単にできるけど、死んだことをなかったことにはできないことだけは覚えておいてね。それをなかったことにしようとすると因果律が狂っちゃうからね」
セラの言葉を聞き、2人は言葉をつぐむ。
「殺害をする必要がある場合は先にした方がいいと思うんだにゃ。僕の魔法でなんとかしやすいのは先に殺害して、そのあと扇動宣撫をすることにゃ。こうすることで反対派が死んだことで詮索をされる心配が少しだけだけど低くなるし、それに殺しに出なくちゃいけない相手が少なくなってラクだよ」
セラの言葉に、ルカはやっぱりな、と考える。
そして、広告魔術や反対派のクリエイターに関してはあらかじめ調査し、その後、意見をした人間や獣人を様々な手段で殺害することを考えた。
調査方法としては著作権を取り扱う人間や獣人たちを調査し、SNSのダイレクトメッセージ機能やメール、あるいはラインなどをセラとシイが調査。
その後、著作権を主張したといった事実がある人間や獣人に対して殺害。
さらにその友人に対してもダミーとして殺害することになった。
セラはまず、SNSのビックデータを発信者情報と紐づけて調査。
さらに個人と法人とで分離させる。
法人は後程破滅させることとして、今は個人を死滅させればよい。
そのデータを集めるべく、SNSを横断的に見た。
彼らはまるでイナゴのように見てくれだけが美しいものに、まるで誘蛾灯のように集まる。
そしてそれをオタクは馬鹿にするが、結局オタクたちもまた、きれいめに見えるイラスト、面白い写真に群がり、自身の性器をいじっている。
その二つはまるで天と地が争うように戦っているが、結局のところはその違いなど、外から見ればほとんどないのだ。
そう思うと、セラは人間たちの浮世にうんざりし、長い息を漏らした。
データが次々集まって来て、統計を取るだけであれば十分に有意な人数が集まる。
それらのほとんどはSNSでフォトジェニックな画像を集めている頭の軽い人間か、体のラインや性的な部分を強調したイラストを描く、ウサギよりも発情したイラストレーターたちだった。
「みんな、目立ちたがりで、みんな承認してほしいのね」
承認欲求の塊。
それが人間の正体なのかもしれない。
それだけでも十分にセラにとってはくだらないと思えてくる。
しかし、さらにくだらなくておかしいのが、人間はしばしば承認欲求を否定し、承認欲求を満たそうとしている人間を攻撃していることだ。
その中には強い攻撃性をはらんでいるにもかかわらず、人間は攻撃性を隠し、自分たちは弱者であろうとする。
そんなことを考えると、何だか悲しさすら覚えてきて、セラは長い息を吐いた。
集まってきたデータをソリたちに共有し、集まって会議を始めた。
どのように殺害するか。
想像以上にクリエイター気取りをする人間が多く、あの時かなり刈り取ったのにも関わらず、まだ1000人は下らない人数が著作権を主張している。
セラはアカシックレコードを少しだけ操作し、彼らにコピーレフトに関して触れさせる。
しかし、それに肯定的な反応を示し、改心した人間はいなかった。
「千人かぁ……」ソリは力なく尾ひれと耳ひれを動かす。
そしてうーんと考えたのち、そうだ、と言って尾ひれをはためかせる。
「セラちゃんたち。ちょっとVtuberじゃなくて、動画配信者として活動していいですか?」
その言葉に、セラは不思議そうに首をかしげる。
そして事情を話すと、セラはルカの顔を見る。
ルカは「いいだろう」というと、黒い尾ひれを楽しそうにゆっくりと動かした。
久しぶりの動画配信者としての活躍。
それは自分の歌の、歌ってみた動画。
この曲自体の著作権は自分で持っており、しかもクリエイティブコモンズで公開していたものだ。
それでいてすでに多くのSNSユーザーに支持され、多くの人間が歌っている。
作曲者である自分自身がアレンジし、あえてピアノ曲として公開する。
有名人の歌であるからと、すでに生放送の公開サイトには大勢の人間たちが集まっている。
ソリはすでに、セラの力を借りて、自身のSNSから漏れ流すように自身の命令魔術を掛けている。
すでにターゲットはあと一人を残して集まっている。
ソリはオンライン上ではあれど、久しぶりに見る人々の視線に、心が疼き始める。
時間になるとソリはゆっくりと息を吐き、歌を歌う。
今日歌う曲にはすべて、ソリの洗脳魔術がかけられている。
それを歌うことで、早かれ遅かれ人間は自殺を選び、死んでいく。
あるいは呪術の力により交通事故などで死ぬこととなる。
そのために歌うことはなんだか一抹の悲しみを覚えつつも、やはりすべきこと、仕方がないことなのだと割り切る。
そして、せめて死の前に楽しんでもらおうと、精一杯明るい表情を見せる。
1曲目はSeems Dang Dang。
堂々と、という歌のタイトルのように、堂々と、シャウトなども交えて歌うことで観客を沸かせる。
曲が終わるころには多くの獣人たちが熱狂し、楽しそうにコメントを送る。
目の前で、自身の目で熱狂を感じられるわけではないけれど、相手が楽しんでいることは見て取れる。
そのコメントに反応することで、より強い一体感を得ることができる。
ここまでコンサートが楽しいことなどあっただろうか。
自問自答し、そして胸に手を置いて2曲目を歌う。
Thanksgivingと名付けられた歌は、すでに多くの動画配信者が歌ってみた動画で配信している。
この曲もソリが作り、そしてコピーレフトのライセンスで公開した曲だ。
「この曲はみんなへの感謝を込めて歌っています。だから、みんなももっと歌って、使ってください! あたしの曲じゃなくて、みんなの曲です!」
いうと、人間たちは「著作権をあまり気にしなくていい」という文言に驚き、そして歓喜の声を上げる。
それを見ていたターゲットのクリエイターたちは、「こんなことをしてもらっては困る!」と鼻息荒くコメントする。
しかし、それすらもほかの人間が「肩の力抜けよ」などと煽る。
それについてこれない、と言った人が次々と抜けていく。
「ここで立ち去られた皆さん、ありがとうございます。ゆっくりお休みください」
ソリは言う。
その瞬間、離脱した人間たちの目が洗脳中であることを示す緑に光る。
それこそがソリの計画であり、あとは時期を追って彼らが死ぬのを待つだけだ。
また、この魔術には話した人間の意見に巻き込まれ、著作権の完全保護を正しいものだと考えるようになった人間たちにも、まるでウイルスのように拡散する。
「さぁ、楽しい姿を見せてね」ソリはマイクも拾えないほどの小声で言うと、ゆっくりと舌なめずりをする。
ソリはすぐに、そんな態度がなかったかのように歌を始める。
その歌声に人間たちは引き寄せられ、そして大勢が感染していった。
・・
人間界、東都。
東都はこの日、ひどい雨に降られていた。
そのためか東都官庁街にはほとんど人もおらず、東都各地から集まってきた高速バスが、国会議事堂の前を通り、東都駅を目指していた。
国会議事堂からほど近い、内閣調査室獣人課。
ここでは獣人たちのレジスタンスや犯罪を取り締まり、危険情報として獣人界の独立を阻止するべく、様々な画策がなされていた。
獣人界の監視を行い、捜査を行っていたリッチェル・オオカ達調査官は大会議室に集まり、画面を見つめていた。
100インチはあるであろう画面には大きくサクラダ総理大臣が映し出されている。
そこで彼はイライラした表情で調査官たちを見ていた。
「現在獣人レジスタンスの中で極めて危険な一味を確認しており、調査中です」
しかしサクラダはイライラした目をじっと向けたままだ。
「現在インターネット上で活躍しており、獣人保護法違反による検挙を目指しております。しかしながらその活動を支持する人間も多く、むやみな逮捕は困難であるかと思われます」
その言葉にサクラダは目をむく。
「お前たちの体たらくで人間を危機にさらすな! 人間はどれだけあのケモノどもに辛酸を味わわされなければならないんだ! 愛すべき人間界を棄損しようとしている輩だぞ! 政府内部にもいるかもしれない。社会の芸能人もみんな獣人に支配されている! そうでなければ獣人にこびた報道などしないはずだ!」
獣人にこびた内容など、放送しているだろうか。
オオカは考える。
しかしながら、最近では獣人関連法を改正しようという声が一部からある。
そんな発言をした人間たちは適宜逮捕し、社会から排除している。
それでも沸き起こるということは少しずつ、確実に獣人に人間たちがシンパシーをよせ、サクラダ内閣に反感を抱いているのかもしれない。
そう思うと、それは小さな、しかし確実な危機のように感じられる。
しかしながら政府としては対話を行うよりもせん滅を考えており、この先どのようになっていくのか、オオカには予想が立てられなかった。
相変わらずサクラダは目を見開き、オオカをしかりつける。
溜まらずオオカは「私たちにはまだ兵器があります」というと、ひとりの少女を紹介する。
そこに映し出された獣人はひどく不健康そうに見えて、そして、どこかやり手に感じられる。
根っからのネット人間であるサクラダからしてみれば、どこか頼りがいすら感じさせるその姿。
サクラダは興味深そうに見つめる。
「さらにこの少女には師匠となる獣人もおります。リス族のナム・ソギョンというのですが」
「ナム・ソギョン……。そしてさっきのかわいこちゃんは?」
サクラダは鼻の下を伸ばし、身を乗り出す。
「兎族のト・リハですね」
ト・リハとナム・ソギョン……。
二人の魅力的で、強力な助っ人。
サクラダはやっと得た安心感に、ゆっくりと息を吐き、そしてブランデーを飲む。
その状況を「見て」、ボラはゆっくりと息を吐き、それをセラたちに報告する。
セラはゆっくりと口元を開き、笑う。
「体の中にまで入り込んだ針は、痛くないんだよね」
Kemono Function
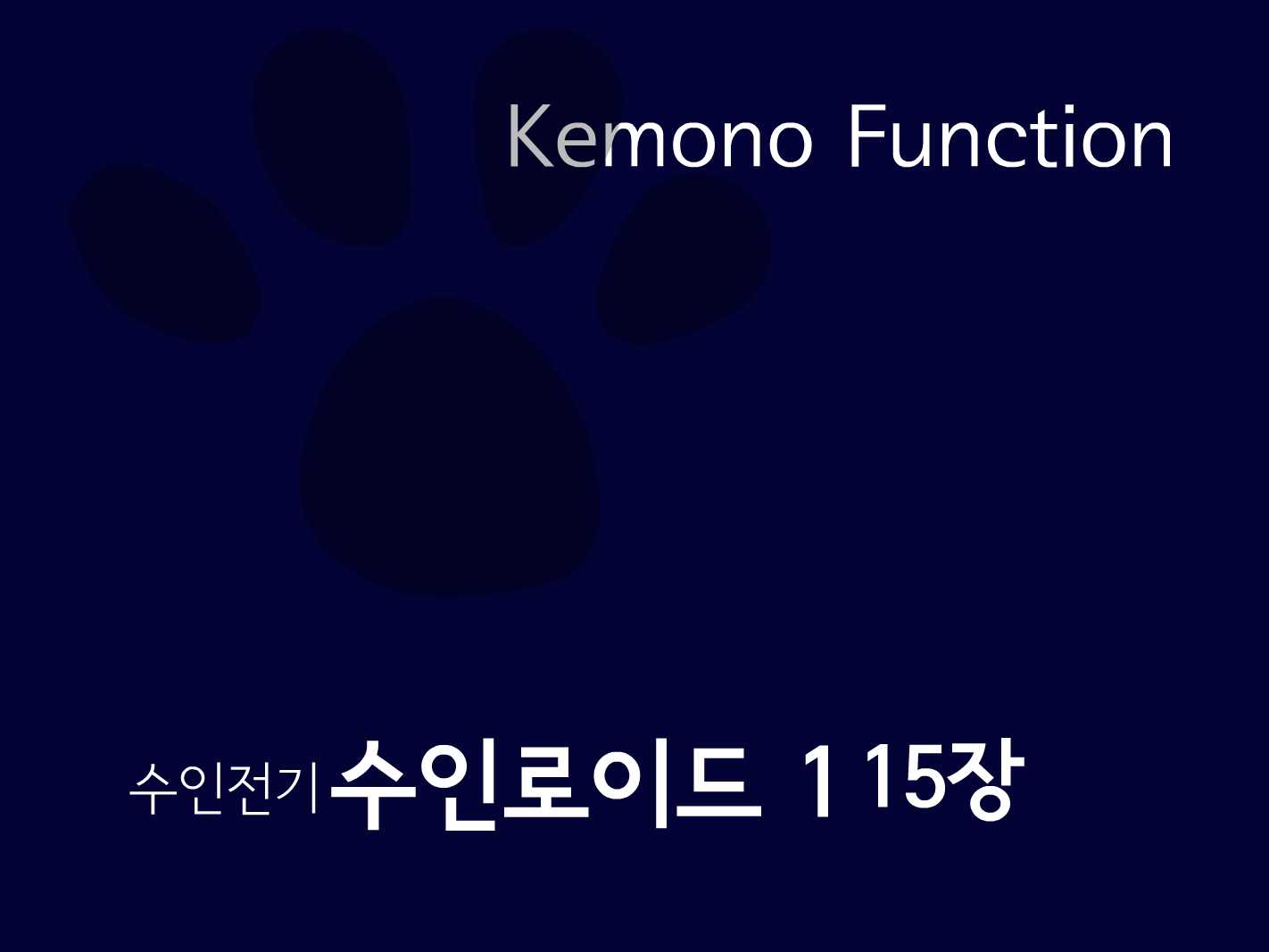
「ハローハロー?」
セラは言うと、ゆっくりと体を動かす。
するとセラの行動を読み取る魔術スキャナはセラの動きを完璧に読み取り、魔術コンピュータで駆動している配信用ソフトの中のアバターを動かす。
セラとシイが作ったものではあるが、いざ動かしてみるとここまで動くものかと感動し、眼をくりくりと大きく見開く。
そしてしっぽをくるりと回すと、「にゃあ」と言って猫っぽい態度をとる。
それに合わせるような形で多くの来場者が動画配信サイトのチャット機能を利用し、セラに声を送る。
「かわいいから継続決定」
「僕っ子?」
といった視聴者の声。
その声が気持ちよくて、セラはさらに猫のようなポーズをとった。
「そうだね、僕の自己紹介をしなくちゃね」
セラは言うと居直り、全員を見る。
そしてにこやかに微笑むと、「僕はセラだよ」という。
視聴者はどんな人物が動画配信をしているのかをじっと注視。
一方でセラはその注視にこたえ、いかに視聴者を楽しませるかを考えて演技をする。
この辺りはもちろん脚本を作ってはある。
しかしながら、Vtuberが脚本通りに行くかと言ったら、そこまで簡単な世界ではない。
だからこそ、演技は必要だ。
セラは今まで演劇を勉強したことなどない。
しかし、プロゲーマーとして、魔性の自分として研究してきたことはたくさんある。
それを生かせるか。
セラにとって、それを生かし、客をひとまず楽しませることが目下のミッションとなっていた。
「僕の趣味はねぇ……ゲームかなぁ。あと電車もすき! 東都鉄道の新型車両いいよね! 白い奴!」
鉄オタのVtuber。
居そうでなかなかいないキャラクターに、視聴者は釘付けになる。
余計なことは言わない。
ただ、楽しませ、そして洗脳魔術を掛けやすくする。
それを考慮して行動する。
洗脳魔術が一番かかりやすい時期と言えば、それは人が楽しんでいるときだ。
人が楽しんでいるときに呪文を唱えることで、人間たちは自分が魔術で洗脳されていることに気づくことなく、洗脳状態を作ることができる。
そうすることで著作権の反対運動を有利にすることができる。
また、自分たちのコンテンツ自体もクリエイティブコモンズにすることにより同人活動を通じて洗脳を拡大することも視野に入れている。
もちろんこれらは一朝一夕の魔術ではない。
むしろ魔術をほとんど使っていないと言っても過言ではない。
注目を浴びるための魔術を使ってSNSに投稿しているとはいえ、必ず引き寄せるような魔術は使っていない。
そのような機能を持つ魔術を使うことで簡単に集客できるものの、洗脳術がかかりにくくなってしまう。
何より、自分たちそのものの魅力で勝負したいという獣人たちの意思でもあった。
セラはその魅力を見せつけるかのようにしっぽをひょこひょこと動かし、耳をぴくぴくと動かす。
「その耳は本物ですか?」質問が届く。
セラは猫が居直るように向きを変えると、「獣人なので当然だよ!」という。
その言葉に観客は沸き、コメント欄がにわかに荒れる。
「獣人は帰れ」といったヘイトスピーチ。
それが多くなるのは視聴ターゲットであるオタク層の心理からして予想していた。
しかしながら、それ以上に「リアルケモミミキターッ!」と書いている人間が多く、セラ自身が内心驚いてしまう。
「獣人ってケモノ臭くて見てくれも毛むくじゃらというイメージがありました……」
その言葉にセラは「そうだにゃぁ」といって反応する。
「僕たちは人間に改造された半獣だからちょっと違うけど、獣人たちってきれい好きなんだよね。そうしないと目立っちゃうし」
半獣という言葉にまた沸き立つ。
そのような存在はいないというのがネット右翼やオタクたちの総意だ。
しかし、眼の前にいるのは人間と獣の姿を持った半獣。
その存在に人間たちは戸惑い、驚愕する。
そのような驚きを提供する放映を何度か続ける。
毎回衝撃や笑い、そして獣人の興味深い生活などを届ける番組は、政治的な関心のある人間からただ萌えられれば人まで、多くの人を集める。
さらに歌ってみた動画を上げたところ、カワイイ、曲がいいなどとさらなる評価を集めることに成功した。
その結果として企業案件なども来るようになり、それらもプロデュースを行っているタンビたちに許可を得て行う。
そして人間たちがセラを楽しむようになったのを確認し、セラは感染源となる洗脳者を作り上げる。
もちろん魔法を直接見せるわけにはいかない。
だからこそ、眼を使う魔術を掛けることにした。
画面の見えないところでゆっくりと目を閉じ、手を広げ、ゆっくりと目を閉じる。
魔力の拡散をイメージし、両腕の中でそれらを練っていく。
ある程度練りあがったところでゆっくりと手を広げると、魔法は勢いよく拡散。
まっすぐ人間一人一人へと向かっていく。
この呪術には前日の行動と同じく、呪術も込められている。
そのため、どうしてもセラたちの意見に同意できない人間は自殺か、あるいは事故が発生するようになっている。
魔術コンピュータに表示されている統計グラフは徐々に100%に近づいていき、そして20分ほどで100%になった。
セラはその瞬間、くるりと回りにゃあ、と鳴く。
その瞬間、映像が暗転した。
セラは何があったのかと思い、まず回線を疑う。
しかし魔術ネットワークはアタックされておらず、ダウンしていない。
となると、システムに直接侵入されたかもしれない。
セラは少しだけ焦る。
それでも、おそらく問題ないだろうとシステムに潜り、様子を見る。
内部では一人の少女が腕まくりをし、勝ち誇った表情でセラを見ていた。
オレンジの髪、そして青いマフラーが風に揺れる。
東都のサブカルオタクのようなショートヘアの少女。
しかしながら表情はそのような外見に関わらずあかるい。
その笑顔を見ていると、なんだかセラは脱力するのを感じた。
「あんた、あたいら人間をおかしくするのはやめなさいよ!」
まるで学級会の委員長のような言い方。
東都弁のような言い方ではあるが、思い切りが足りず、しかもアクセントに水都の訛りがある。
その姿を見ると、差別するなと言われているとしても、しょせん水都にコンプレックスを持った田舎者としか感じられなかった。
思いを込め、じっと敵を見つめる。
「君は誰だい?」セラは聞く。
すると敵の委員長ちゃんは腕を組んで居直り、まるで蔑むような眼でセラを見る。
その目に嫌気がさし、セラは目を合わせる。
不思議と猫の特性からだろうか、心の中に闘争心がわいてくる。
「あたしはリハ。犬族だよ!」
犬族らしい正三角形の耳をぴくつかせて言う。
特に完全な獣人ではないようだから、半獣といえる。
こんなところで半獣として人間に酷使され、戦わせられている。
そう思うと、なんとも残念な思いになる。
その時。
「こちらルカ。僕の大学に多数の戦闘員とリハと自称する犬族。僕のゼミ生や、獣人であることを隠して指導しているほかの学部の教員たちがタンビとともに拉致されようとしている。見た感じ特高警察だが、制服ではないため正体を見破れず。繰り返す……」
ルカがいま、戦闘を行うべく変身し、敵に向かっている。
すでにタンビは拉致されたのか、その場にはいない。
気になるのは、リハがリアル世界であるルカの大学にもいるということだ。
これが意味することとは。
システムウィッチとして状況を考える。
深い事情は分からないが、一つ言えることと言えば、意識の世界からリハを消すことができても、現実世界からリハを消すことができないかもしれない、そしてその逆もあり得る。
となると、少しばかり話が厄介になってくる。
急にシステムの世界が明るくなる。
そこには恐らく画面の向こう側であるのか、たくさんの顔が映し出されている。
「あんたの正体も、あんたの本当の目的ももう、みんなにばれているわ。だからもうあんたは悪さができない。そして、あんたという悪魔が地獄の烈火で焼かれるのをみんなが楽しみにしてるのよ」
リハは言うと、手を大きく広げる。
「黙示録がいま、果たされようとしている! イーサー、キリストに反駁し、人間に反駁したものは、間もなく私によって、私の福音によって滅ぼされる! 悪霊たる獣人よ、消え去れ! 奇跡を信じる人間よ、サクラダ様を信じる人間に永遠の命を!」
叫びをあげると、一歩、二歩とステップを刻み、飛び上がる。
そして腕に剣を握ると、その剣に炎をまとわせる。
一方、セラは片腕に水の剣を、左にオリハルコンの盾を持ち、飛び上がる。
二つのシステムの剣士はいま、お互いを呪うべく飛び上がった。
Suzy Do
「スージードゥ、そっちはどうだい?」シイの言葉がテレパスの中で撥ねる。
その言葉にスージードゥと呼ばれた女性は少しばかりはにかみ、そして「そうだな」と言葉を重ねる。
「やっぱり著作権を使って商売をしたい人間が集まってわいろを渡していたりするな。一方でオーキド文科相はその金を女に貢ぎこんでいる。その一人として、ちょっと一発やってみる」
いうとスージードゥ、ことト・ナウンは苦笑いをする。
シイは「そう」とだけ言うと、テレパスから離脱した。
夜になれば国会の委員会を終えたオーキドが電話をよこしてくるだろう。
彼は女を何人もとっかえひっかえして行為し、慰み者にする。
その態度が気にくわない人間たちは大勢おり、まるで大奥のような世界を構築している。
その中で誰がオーキドに愛されているかを競い合い、そしりあい、グループを作って陰口をたたきあう。
ルーク書22章にも穏やかにそのようなことをしている姿は描かれているが、しょせん人間の「誰が一番……」という言葉はイーサーの時代から現在に至るまで、誰もが経験することのようだ。
また、獣人の暗殺者がその大奥に紛れ込んでいることを、オーキドは知らない。
それを知ったらオーキドは人間不信にでもなるだろうか。
そう思うと、それはそれで試してみたくなってくる。
ナウンはレッドヒルエリアの議員会館に向かい、2階にあるオーキドの議員事務所を目指す。
出入口の警備員を笑顔でやり過ごすと、入館ゲートを偽造RFIDタグで通過。
エレベータに乗り込む。
中には与党の議員たちが何人か乗り込んでいる。
彼らの会話に耳を立てる。
「ナウン、セラ、シイ」今、審議中であろうサンムの声。
ナウンは何も答えることなく、テレパスに集中する。
「著作権法の改正案のメインは棄却になった。ただ、獣人作品の取り扱いはますます人間側が有利になってしまった。これから俺たちですぐに獣人への差別的法律を撤廃する運動を繰り広げようと思う」
悔しそうに息を吐き、その場に座り込むサンム。
ナウンは「お疲れ」とだけ残し、オーキドの部屋へと向かう。
オーキドの部屋には先客がいるようだ。
彼らはたとえ獣人の著作物製作禁止というイシューが棄却されたとしても、獣人の著作物はすべて著作権登録が義務付けられ、それに違反した場合の最高刑は処分、つまりは処刑だ。
このようにすることで獣人の著作権を人間へと完全に譲渡させ、獣人たちの正義である自由な利用を完全に禁止させる。
一方で人間に対しては著作権のフェアユースとガイドライン下での同人活動を認めることで、人間のガス抜きと、獣人との分断を図る。
そうすることで獣人の文化を奪い、破滅させる。
著作権団体と与党が考えそうな鬼畜な態度に、怒りではなく脱力してしまう。
ここまで人間は鬼畜になることができるようだ。
そう思うと、さらに人間嫌いが激しくなってきそうな気がした。
NIMCAの会長タグチ、レコード連盟の会長リチャード、業界最大手の企業であるサウンドレコードの社長パウロ、天界で映画などの配給を手掛けるアースエンターテイメントのCEOたるヨハネが、ナウンをオーキドと勘違いし、立ち上がる。
その姿をナウンは楽しむように見ると、ゆっくりと息を吐く。
「お茶出しできず、すみません」ナウンはうわべだけの謝罪をする。
そして「お茶用意しますね」というと、キッチンへと消える。
やることと言えば、一つしかない。
ナウンはキッチンの隅にある緑茶を急須に入れ、沸かした湯を入れる。
それを少しばかり煮だして入れると、ゆっくりと目を入れ、手を茶器の上にかざす。
腕の先に展開された群青の魔法陣が茶器を包むと、一瞬茶もその色に染まる。
しかしすぐに元の透き通ったオレンジがかった緑へと変わり、元の高級茶葉を煮出した茶の色へと変わる。
ナウンはそれをいそいそと運ぶと、恭しく人間たちに出す。
「召し上がってくださいね」ナウンは魔術を込めて言う。
すると遠慮がちにしていた人間たちは「じゃ、さっそく」というと茶器を手に取り、そして一同にすすり始めた。
中年層のおじ様たちが下世話に茶をすすり始める様子は少しばかり壮観で、ナウンは思わず感心してしまった。
「今回はどのようなご用件で?」ナウンは聞く。
すると4人の目はわずかに群青に光り、そしてヨハネが口を開く。
「この度は人間界のご英断と崇高な判断に感謝するとともに、これから人間の皆さんとともにビジネスをできると考えると大変エキサイティングに感じています。その感謝の気持ちをお伝えに参りました」
天界語でまくし立てるヨハネの言葉を聞き、ナウンはうんざりする。
天界語は獣人の常識として理解できる。
ただ、天界語などまるでわからない人間に対してこのようにまくしたてたところで、人間は「エウアリスト」と笑顔で言うだけだ。
国際感覚などまるでない人間の姿を見ていると、そのような種族に侵略された自分たち種族の姿が悲しく見えてしまう。
事実、とくにNIMCAの会長は何を言っているのかわからず、ただニコニコしているだけだ。
ナウンはその感情をゆっくりと心の奥にしまい込むと、妖艶に微笑む。
「ビジネス、って、差し支えなければ聞いても?」
ナウンは問いかける。
するとパウロは翻訳し、ヨハネに伝える。
ヨハネは楽しそうに微笑むと、ナウンを見る。
「はい、獣人界の豊富で魅力的なコンテンツを広め、そして私たちの手でよみがえらせることで獣人の皆さんの地位向上を図るつもりでおります」ヨハネはにこにこして言うと、パウロはそれを逐次翻訳する。
ナウンはその言葉をずっと一歩引いた眼で見て言うと、ゆっくりと頷く。
彼らに聞かせた薬がゆっくりと効いてくるはずだ。
それを楽しみに、ナウンは待機する。
5分ほどナウンはヨハネたちを適当に相手していると、まずヨハネがゆっくりと目を閉じる。
「おい、ヨハネさん!」タグチは驚いた様子でヨハネの身体をゆする。
その瞬間、パウロもゆっくりと目を閉じる。
その様子にタグチは驚いた様子でナウンを見る。
ナウンはゆっくりとほほ笑むと、タグチは「お、お前……!」と指をさしながらその場でひっくり返り、泡を吹く。
遺体はすぐさまきらきらと光を放ち始め、1分もしないうちに姿が消えてしまう。
「光、ねぇ」
ナウンは言うと、ゆっくりと遺体の転がっていた応接間を出た。
・・
それから10分ほどたったころ、この部屋の主であるオーキドが部屋の扉を開けた。
オーキドは「ったく、まだ来てねぇのかよ」と悪態をつくと、ネクタイを乱暴に取ってソファに投げ捨てる。
そして執務室に向かうと、胸ポケットをまさぐって煙草を取り出した。
オーキドは煙草に火をつけると、長く息をつく。
その荒々しい煙は、オーキドの怒りと、それをコントロールできない愚かな彼の姿を現しているようだった。
ナウンは一歩踏み出し、わざと靴音を鳴らす。
その瞬間、オーキドはゆっくりと椅子を回す。
「なんだ、お前は……!」オーキドは大きく目を開き、一歩、一歩とその場から離れていく。
ナウンはゆっくりと踏み出し、そして何も言うことなくオーキドの腕を真横に切り裂く。
彼は痛みのあまりその場で動きを止め、痛みのする腕を見る。
腕からは赤を通り越して黒くなった血液がとろとろと流れ、筋肉や真っ白の骨が姿を現す。
ナウンはその傷口に口をつけ、そしてゆっくりと、嘗め回すように血液をなめていく。
そして細くなった筋肉をあまがみする。
血液からはわずかにニコチンとタールの香ばしいにおいがする。
目の前で繰り広げられる狂気に目を疑い、オーキドは言葉を失っている。
ナウンはその目を見ると、わずかに口角を緩める。
彼女は脂のにおいに満ちた肉を噛み千切り、それからオーキドの唇を奪う。
そしてゆっくりと舌を絡めると、彼の手を胸に触らせる。
オーキドは理解できる状況ではないのか、じっとナウンの眼を見つめるだけだ。
彼の歯にまとわりついた脂のにおいが、乾いて腐った食べ物のにおいとともにナウンの口に伝わる。
ひとしきりキスを楽しむと、ナウンは自身のジャックナイフを彼の背中に突き立てる。
そして少しずつ体の下におろしていく。
そしてナウンが優しく目を細めるた次の瞬間、オーキドの身体からすべての内臓が飛び出し、真っ黒な血液とともに議員会館を汚す。
ナウンは脳を取り出すと、小さな機械を接続する。
その中には案の定、政府与党の人間の体に投与されているナノマシンが小さな塊を作っていた。
ナウンはそれを小さな容器にしまう。
小さな機械は甲高い音を立て、次々と情報をナウン、そしてセラたちに送信する。
そしてしばらくすると、セラから「事情聴取完了にゃ!」と笑顔で返事が来た。
ナウンはオーキドの脳を神棚に投げつける。
神棚はその重みで落下し、神酒や榊、札がまき散らされる。
ナウンはそれらに目もくれず、オーキドの、軽くなった胴体を握る。
中身を失い、唯一男性器の肉だけが残った遺体。
その生殖器に自身の生殖器を当て、ゆっくりと上下運動をする。
冷たく固まったオーキドの性器と、自身の暖かい肉体。
その二つがカクテルされ、快楽が増大されていく。
その快楽に何度も身を任せ、絶頂し、満足げな息を吐く。
ナウンは服を整えると、魔法陣を展開する。
遺体や血痕はすべて浄化され、後には何も残らない。
さらに壊れた神棚も、乱れた部屋も、そして魔法を使った形跡もすべてなくなる。
それを確認すると、ナウンは「作戦成功!」と小さく言い、部屋を堂々と飛び出した。
Devil Purple
ルダルとサンムは視察と称して天界の大都市、ヘブンズゲートにいた。
この街は天界一の大都市として知られており、しばし霧により紫色に見えることがあることから、デビルタウンと言われることもある。
獣人界とはまた違い、アールデコ調の超高層ビルが立ち並び、おしゃれに着飾った都会っ子がホットドッグを食べながら歩く姿は、獣人界のアリスとはまた違った大都市であることを二人に伝えていた。
ルダル達はその街の中心部、カーネル街にある、カーネルホールにいた。
ここでは全天著作権協会の会議が持たれることとなっており、天界における著作権政策への提言を採択するなどの活動がなされることとなっていた。
カーネルホールの隣にある、ナッツホテル。
獣人界にもチェーン展開をするだけの高級ホテルとあって、きらびやかなシャンデリアが輝く店内には、爬虫類人や竜人、鳥人と言った多種多様な人種が集まっている。
ルダル達はこのホテルに宿泊し、二人の天界人が部屋を出るのを待っていた。
部屋はセラの魔術操作もあり、彼ら、ウルスラ・スカイデンと、ルーク・スノーウィンの滞在している部屋のそれぞれ隣に泊まることができた。
しかしながら彼らはよっぽどこのホテルが気に入っているのか、ほとんど外に出ようとはしない。
食事などもケータリングを頼み、出てこない。
「この部屋から出たくないほど貧乏なのか、好きなのか……」ルダルは息を吐く。
それに対し、サンムは「まぁ、確かに快適だよな。椅子は背もたれが大きくてゆったり。ベッドは背中を支えてくれて気持ちがいい。あえて言えば部屋が狭いくらいだもんな」
確かに部屋はビジネスホテルと思いたくなるくらい狭い。
しかし、二人くらいならば、むしろゆったりと過ごすことができるだろう。
耳を澄ますと、二人は下ネタを言い合ったり、創作論を語り合ったりと、とても楽しそうにしている。
「まぁ、二人とも西海岸と東海岸で離れたところに住んでいるから、こうやって久しぶりに会えることがうれしいんだろうね」
サンムはそんな友情に苦笑いをして、耳をさらに澄ます。
すると二人は「うまいステーキ屋があるんだ」といって、部屋を出ようとする。
ルダルはその言葉を聞き逃さず、サンムに合図を送る。
そしておもむろに部屋を出ると、隣の部屋の扉の前に立った。
扉は案の定、ゆっくりと開かれる。
それをルダルは乱暴に開けると、剣を扉に挟む。
そしてそれを思いっきり開くと、二人は無理やり入り込む。
ウルスラとルークの二人は驚いて一歩ずつうしろずさりをする。
二人の天使の輪は危機を知らせるかのように白く点滅していた。
天界を生きる天使族たちは、頭の上にエンジェルリングを持つ。
それは感情や状況により、適宜点滅するようになっていた。
ルダル達はウルスラたちが恐怖におびえているのを見て、それをさらに心に刻み込むように、剣を向ける。
「何をする! 私たちは人間ではない! 獣人の友人として、一緒にいたではないか!」
しかし、ルダル、そしてサンムは何も言わない。
するとおびえていたルークはゆっくりと剣をわき腹から取り出し、ルダルに向ける。
「わ、私と勝負だ!」
その言葉に、サンムは息を吐く。
しかし、何も言わないサンムたちを見て、ルークはさらにおびえた様子で二人を見る。
ルークはそれでもゆっくりと立ち上がり、そしてルダルめがけて剣を突き刺そうとする。
それをルダルは躱すと、小声で呪文を詠唱。
剣を向けると、その先から激しい電気玉が発生。
それを放つと、ルークはその場で真っ黒に焦げてしまった。
ウルスラはその場で固まり、二人を見る。
「なぁ、二人に提案だ。私を助けてくれないか? そうしたら獣人のために歌を作ってあげよう。私の曲は世界で聞かれているし、その曲で世界でも一番の稼ぎをしている。その曲を聞けば獣人たちはきっと喜び、励まされるはずだ」
ウルスラの言葉に、二人は目を見合わせる。
獣人から金を巻き上げるために人間と示し合わせて、人間の著作権政策に協力した。
その罪を忘れたかのようなウルスラの発言に、ため息が漏れる。
また、ウルスラは獣人を差別するような歌を人間の要求で作り、歌い、それを人間界で流行らせた。
そんなアーチストの片隅にも置けないような奴を、生かしておくわけにはいかない。
二人は一瞬目を示し合わせると、剣を握る。
その様子にウルスラは引きつった顔をする。
「なぁ、冗談だろ?」ウルスラは言う。
しかし、二人はもう一度目を見あうと、ウルスラの心臓めがけて剣を向け、魔弾を放つ。
ウルスラはその場で真っ黒な血液を吐いて倒れてしまった。
ルダルは自身の魔眼で二人の様子を撮影する。
そして自身の手でセラの開発した新兵器をつかみ、データを送る。
新兵器はゆっくりとその姿をウルスラとルカに変えていく。
やがてルダル達が入れるほど大きくなったその中に、二人は着ぐるみを着るように潜り込む。
すると二人の身体はすっかり、ウルスラとルークに変わった。
二人は遺体の処理を済ませ、夜を待つ。
そして現地時間で午後五時になったのを確認すると、隣のカーネルホールへと向かった。
カーネルホールでは会議に出席している音楽や小説の著作権ホルダーが多数集まっている。
作家たちは思い思いに歓談し、交流を楽しむ。
そんなのどかな情景をこれから壊さなければならないと考えると、いささか罪悪感を覚えた。
ルダル達も作家たちと、着ぐるみに搭載された二人の記憶を用い、会話を楽しむ。
作家たちは皆、人間界の文化がより豊かになると言って獣人の文化の搾取を喜んでいる。
その無邪気な喜びは一体どこから来るのかと、ルダル達は怒りよりも先に不思議に思った。
ルダル達が席について五分ほどすると、会議が始まる。
会員であるという天使族、ジョン・マッカーソンが彼の世界的ヒット曲、「フォエーバーラブ」を熱唱する。
観衆たちはその曲に感心し、興奮した様子で聞き入っている。
ルダル達はなんだか聞き心地の良い、人間界の軽い言葉とは違った、しかし軽薄な言葉にむせ返りそうになる。
まるでアメリカンコーヒーのような、言葉の軽さ。
深みも渋みも感じられない、産業のために作られた言葉に、獣人も、人間も踊り、聞き入る。
人を軽く洗脳し、カネを払わせる産業構造を思うと、むせ返りそうだった。
曲が終わり、ばかばかしい拍手が終わると、さっそく会議が始まる。
しばらくの間、会則の変更や天界での著作権ロビーについての報告など、ある意味でどうでもいい会議が繰り広げられる。
その様子を、獣人である二人は生返事をしながら見守る。
まるでうれしいことのように著作権ロビーが認められ、著作権が守られるようになったことを喜ぶ会員たち。
消費者を置いて、こんなちっぽけなホールで話し合われたことで世界中の著作権が影響され、消費者が侵害され、さらには獣人たちが抑圧される。
そんなふざけた真似があっていいわけがない。
そう思うと、ルダルの心の中はひっかきまわされるような気分になった。
ルダルはサンムを見る。
サンムはまた、大きな息を吐いてゆっくりと首を振った。
そして次は、いよいよ人間への獣人著作物と、獣人への対策強化を図る審議だった。
著作権協会の獣人系天使である、カリョン・ソーが壇上に上がると、獣人による著作権侵害を訴え始めた。
「獣人による著作権侵害は、人間の四十五倍、天界人の百倍にもなります。それだけ人間界では獣人からの著作権徴収がおろそかになっており、私たちが得ることのできる対価を侵害しているのです。それを放っておくことは、やがて私たちの首をも締め付けることになります。そもそも、獣人という野蛮な生き物が音楽を作り、聞くこと自体が醜いということができるでしょう。私たちは世界の音楽著作者の権利を守るために、議会で議論をしています。幸いなことに賛同者も多く、近々人間に年次改革要求として出すことができるでしょう。野蛮な民の音楽ではなく、私たちの権利を守り、世界の文化をけん引していくことこそ、世界のリーダーである天界人に課せられた使命と言えるのではないでしょうか」
大きな身振り手振りでその訴えを効果的に伝えようとする、カリョン。
その姿を見て、ルダルはむずむずして、立ち上がって叫びたくなってくる。
しかし、そんなことをすれば彼らの始末が負えなくなってしまう。
「ルダル、落ち着け」サンムは言うと、ため息を吐く。
サンムは表情こそ落ち着き払っているが、怒りに満ちた声で話した。
レイシズムにまみれた、自分勝手な発言。
それをナチュラルにできてしまうところに、彼の福音党議員として身体化された理念を感じた。
それに対して、それ相応の怒りを覚える。
自分自身が獣人系なのにもかかわらず、獣人を抑圧する立場に立ち、同胞を破滅に追い込もうとしている。
その態度が、どうしても腹に据えかねるような気がして、思わず自身の杖の擬態である、腕輪を握りしめたくなった。
サンムもさすがに怒りを感じたのか、変身のために腕輪を握りしめる。
そしてレイシスト獣人の発表が終わろうとしたその時、二人は怒りを堪えずにすっくと立ちあがる。
その態度にほかの著作権者は驚き、注目する。
二人は歩きながらブレスレッドを回転させ、変身。
トラのしっぽ、シャチの尾ひれをみて、観衆たちは一同息を飲む。
「よくも獣人のことを腐してくれたな、先生」ルダルは言うと、議員の腕を握る。
そしてその手をねじると、議員は痛そうに眼をしかめる。
袖からシークレットサービスが姿を現し、ルダル達に銃を向ける。
彼らの足元から魔法陣が展開され、ルダルたちめがけて魔弾が飛ぶ。
ルダルたちはそれをバックステップで躱し、攻撃を往なす。
そしてそれが止んだせつなの間に剣先を向け、ルダルたちめがけて追加の銃撃を加えようとしたシークレットサービスを射殺。
それを合図に彼らは魔弾を放とうとするが、加速装置を用いて彼らの背後に回り、ひとりに剣を突き刺す。
その後、隣で振り返ろうとしていた天界人の腹に剣を突き刺し、銃を鹵獲。
それで一人、二人と天界人を殺害していく。
一方、その間に開錠係員が避難誘導をはじめ、著作権者たちが逃げ出そうとしていた。
サンムはそれを確認すると出入口へと向かい、彼らをふさぐ。
このホールの出入口はほかに緞帳の裏にしかない。
しかし、そこにはルダルがおり、逃げられない。
また、連絡はセラによって遮断されており、いわば孤立状態となっていた。
観衆たちは混乱に陥り、あるものはその場に座り込み、あるものは神への祈りをささげる。
そんな様子が申し訳ないと思いながらも愉快で、腹がスカッとするようだった。
手始めに避難を誘導していた司会者の首に剣を突き刺し、殺害。
それを合図に、天界人たちは絶叫する。
その間に飛び上がり、先頭の一人の首を斬る。
さらに二人目、三人目、四人目を冷凍光線で凍結させ、粉砕。
そして呪文を唱える。
「我は確かに願う。父なる神よ、獣人を破滅に追い込む異教徒たちを水の棺桶に閉じ込め、黄泉にて溺死させよ!」
それに合わせ、大量の水が会場に押し寄せる。
それはホールの高さいっぱいに満ちる。
著作権者たちはそれをみて絶望し、座り込む。
ところどころで「神よ、お救いください!」という祈りが聞こえる。
五分ほど彼らの苦しむ様子を見たのち、サンムは「獣人への狼藉と、著作権への強情、強欲をなくすか」と、著作者たちに問う。
一部の著作者たちは頷き、祈りをささげるが、他の人間たちは怒りのあまり叫び、サンムのむなぐらをつかもうとする。
しかしそんな権利者たちの首を剣で払っていく。
その様子に権利者たちは絶望し、そして立ち向かう勇気を失っていく。
その様子をたっぷり見たのちサンムは手で波を描く。
すると水の塊は、まるで津波のようにサンムの側へと打ち寄せる。
権利者たちはそれを見て手で顔を覆い、泣き叫ぶ。
やがて大波はすべてを洗い流し、権利者たちの腕をもぎ、胴を剥いでいく。
その様子を、サンムは水中でじっと、ゆったりと尾ひれを動かしながら眺めていた。
一方、ルダルはじっと敵である、元獣人を見ていた。
彼はおびえた様子を先ほどまで見せていたが、開き直ったのか、前のめりになって獣人語で叫ぶ。
「腐れ獣人め! こんな暴力をして恥ずかしくないのか! 獣人界なんて反重力爆弾で破滅させてやる! 俺は自由な世界の国会議員だぞ!」
彼は叫ぶが、ルダルはほとんど聞いていない。
叫び、荒れ狂うウシ族を見ていると、なんとも哀れな気持ちになってくる。
「腐った獣人はお前だろ? 私たちは誇りをもって獣人として、本物の自由を守っている。それを抑圧し、世界を人間に侵略させたのは、お前たちではないか」
かつてから言いたかった言葉。
その言葉を言えたことで、胸のつかえが少しばかり取れたような気がする。
それこそがハンプリというのだろうかと思うと、少しばかり納得がいった。
カリョンは手の先から矢を作り出し、それをルダルに向ける。
ルダルは一瞬警戒し、じっと見つめる。
しかし一歩も引くことはない。
その態度を見て、カリョンは舌なめずりをする。
「天界軍海兵隊の魔法を味わわせてやる」
威勢のいい言葉をカリョンは放つ。
ルダルはじっと彼を見つめると、ゆっくりと息を吐いた。
それを見ると、カリョンは光の矢を放つ。
天界人らしく、光属性の魔法か。
ルダルはそのクリシェにあきれ、逃げたくなる。
彼はそれを避けるために回り込むと、カリョンめがけて切りかかる。
しかし、その直前でカリョンは姿を消し、ルダルの背中に剣で切りかかる。
ルダルはそれを躱すことができず、背中に深い傷を負う。
背中を伝う血液のべとべとした感触に嫌悪感を覚え、痛みと共にその不快に目をしかめる。
しかし、ルダルはすぐに剣を持つと、ワープシステムを起動し、カリョンの後ろへ。
カリョンの背中にやり投げの要領で剣を突き刺すと、カリョンは口から真っ赤な血液を噴き出す。
「一対一だな」ルダルは笑う。
しかし、カリョンはすぐさま振り返るとルダルの胸に剣を突き刺し、えぐるようにルダルの体内にそれを突っ込んでいく。
「そうだな」カリョンは口元を大きく広げ、にんまりと笑う。
ルダルはその口に剣を突き刺し、延髄を破壊するように剣を突っ込む。
カリョンの舌や唾液が剣を伝い、ねちねちという粘着質な音を立てる。
お互いの臓器を破壊する行動はしばらく膠着し、動きを見せない。
ルダルの心臓や肺は傷つき、モニタリングシステムは臓器の損傷を訴える。
一方でカリョンは脳を突き破り、剣が頭から露出し、脳と思しき白い物質が漏れ出している。
どちらが先に死ぬか、ルダル達は確かめる。
そして倒れたのは、カリョンであった。
ルダルは剣が突き刺されて四分ほどたった時、呪文を唱えた。
電撃魔法を剣に唱え、電撃球をカリョンの脳の中で作る。
カリョンはその段階で脳を焼かれて絶命し、電撃球が破裂したときに頭部や脳を周囲にまき散らし、胴体も電撃に焼かれて何も残らなかった。
「派手にやったな」サンムは笑う。
ルダルは何も言わずに微笑むと、セラにレタッチを申請する。
セラは「はいにゃ」と喜んで犬歯を見せると、そのまま魔法陣を展開した。
その様子を見て、正義の意味を考える。
しかしながら、その答えは一生ものなのかもしれないと思い、そのまま現場から離脱した。
Jesus nor Buddha
セラの放った斬撃は、リハの上腕を切り取った。
彼女の腕の先からは無数のコードや、人工骨が姿をのぞかせる。
彼女もまた、セラたちと同じ半獣であることをよく示していた。
そんな彼女を見ると、なんともいえず、ため息ばかりが漏れてしまう。
一体どうして彼女は自らの身体を差し出し、あるいは差し出され、獣人を刈るものとして戦っているのか。
その正体が分かれば、自分自身の悲しみが言えるのだろうか。
セラは言葉にならない怒り、そして悲しみを胸に、ゆっくりと息を吐きつつ、居直る。
その時、セラの背中に激しい痛みが走る。
まるで内臓をつかまれたような痛み。
その痛みの正体がわからず、セラは目をただ大きく見開く。
セラはその痛みに耐えつつ、ゆっくりと顔を背中へと向ける。
するとリハは勝ち誇った表情でセラを見つめていた。
「あんた、あたしに勝てたとでも思っているのかしら?」
彼女はセラの腸を握り、それをゆっくりと握りつぶす。
そのたびに全身をつきぬけるような痛みが体に響く。
さらに彼女は腸に歯を当てる。
その瞬間、セラは痛みのあまり絶叫し、眼を大きく見開く。
セラは声にならないような叫びをあげ、息を絶やしそうになる。
それでも死ねない現況を見て、セラは目の前が真っ白になる。
そんなセラをリハは勝ち誇ったような表情で見ると、彼女はセラの口にペニス型のディルドを押し付ける。
口での呼吸を防ぐほど大きなディルドに、セラはむせそうになる。
それがのどの奥にまで突きつけられ、話されてくる。
呼吸を求めて口を大きく広げようにも、口は広がらない。
やがて意識がゆっくりと薄れていく。
虚ろな目になっていくセラを見て、リハはさらに恍惚とした表情へと変わっていく。
セラの脳裏には、ふわふわとした緊張感と、痛みの中に、過去の自分の姿を見た。
かつて自分は少年だった。
しかしながら外で遊ぶことはなく、お母さんごっこが好きだった。
お母さんとして子供をあやし、おっぱいをあげ、夫を甲斐甲斐しく癒す。
良妻賢母のロールモデルに乗っかり、女性としての立場に身をうずめる。
そのことが自分にとっては癒しであり、そして幸福をもたらすものであった。
何がよかったのかは、今でもわからない。
しかし、女としての自分が、まるで自分の家であるかのようにうれしい物であった。
やがて彼は小学生になり、ほかの学生たちとの付き合いも始まった。
彼らはセラの好きなおままごとではなく、体を思いっきり動かすような遊びに精を出していた。
そんな活発な少年たちに、セラはいじめを受けた。
ある時は首を絞められ、ある時は自身の志向をさげすまれた。
さらには自分自身が男性に恋をしたことを知られると、「ホモだ」と言っていじめられた。
そのいじめがちょうど、今の自分がされているような首絞めだった。
首を絞められ、窒息をしそうになった。
息が詰まり、なぜ自分自身がこのようなことをさせられているのか、わからなくなる。
好きな男ができたときには、その男によって踏みつけられ、彼のペニスを口に突っ込まれた。
その屈辱を、今のセラも晴らせてはいない。
ただ童貞のペニスにあるような、しょっぱさと独特の悪習に、セラはむせ返りそうになったことだけを思い出した。
今、セラの口を責めているものは、童貞のペニスではない。
その代わり、ひどいゴム臭がセラの鼻腔に届く。
そして今、むせ返ることも許されず、ただ呼吸困難になり、白目をむくことしか赦されない。
また、このようなことをしているたびに、自分がいかに女性でないかを経験させられていた。
一種のイラマチオ。
これに女性は快楽を得るのであろうか。
自分は男性だから。
自身の疑問に、男性だという言い訳が頭に浮かんでしまう。
その言い訳を頭から消そうにも、どうしても消すことができない。
その絶望感に、セラの気持ちは隘路へと進んでいってしまう。
隘路の先に何があるのか、セラにはわからない。
そのわからなさが、セラの気持ちを不思議と高める。
苦しみ、痛み。
それを訴えるべく、セラはディルドを飲んでいく。
ああ、ああ。
リハにディルドの感覚が伝わるのか、リハの表情も快楽に墜ちていく。
そしてセラをギラリとした目で見ると、口を大きく見開き、ディルドの先から苦く、そして甘い液体を放出した。
その液体を、セラは知っている。
かつて彼氏のペニスを咥えさせられたとき、彼が気持ちよさそうな表情で射出した液体。
その時とは違い、ゴムの匂いと、柔らかなそれ独特の匂い。
セラは今、自分自身が犯されていたことを再認識する。
心の中に走る静かな、しかし巨大な絶望感。
自分の大切にしていた何かを破壊され、自分のすべてが否定された瞬間。
その絶望感に、セラの目の前が真っ白になっていく。
今まで自分が好きだったもの。
大切な人にささげたかったもの、こと。
それらを再び破壊された。
その怒りと絶望に、セラの心は少しずつ支配されていく。
体の血液もかなり抜け、意識が吹き飛びそうになる、
その意識をどのように整えたらいいのか、セラはわからない。
ただ絶望に飲み込まれていこうとする自分の情けない姿が、なんとも悔しい。
それに対抗すべく、セラはうーん、うーんとうなる。
しかしリハはその声を愚弄するかのように、さらに激しくセラの口にディルドを押し付ける。
もう一度リハは射精すると、一体のゴーレムを召喚した。
リハはそれの目を、狐のような眼で見ると、ゴーレムは今までに感じたこともないような勢いでセラの顔を持ち上げ、彼の口に自身のペニスを押し詰める。
そして激しく腰を前後させる。
さらにリハはセラのペニスを握る。
その柔らかな、まるで搾乳するような手つきに、思わず体が疼く。
さらに別のゴーレムが胸に手を入れ、乳首をゆっくりとはじいて責める。
4か所から伝わる快楽に、セラは喘ぎ声をあげたいと抵抗する。
しかし、セラの口はゴーレムペニスの侵略に遭い、何も話すことができない。
そして疼き、痛みの走る身体は、揺れるたびに眠たい痛みが体を走り、ただその眠たさに身をゆだねなければならない。
リハの搾乳はとどまることを知らず、かなり柔らかなタッチでセラの精液を収集していく。
獣人の精液、そしてその愛液。
その中にはかなりの魔力がある。
それを搾取しようとしているのを見て、セラはさらにやるせない気持ちになっていく。
一体何をしようとしているのか。
その目的がなんとなくわかるようで、わからない。
その不安にセラは逃げたくなるものの、それから逃れることができず、セラは絶望感と、そして恥ずかしさに言葉を失う。
射精しないように我慢するその気持ちが、ますます自分自身をしんどくしてしまう。
すでに体は快楽を感じて疼き、脳ではドーパミンが次々と出ている。
その快楽は射精を求める。
突然、リハとゴーレムの責めが止まる。
その瞬間、セラの身体が急に火照りだす。
自身の顔には魔法陣が展開されており、何かしらの魔法がかけられているのが分かる。
しかし、何の魔法がかけられているのか、セラには理解ができなかった。
「体が疼くでしょ? これが今、あんたの構築したシステムを通じて全員に公開されているわけ。コメント見せてあげる」
セラの脳裏にコメントが走る。
「ふぅ……」といったコメントはもちろん、セラのセクシュアリティや、セラの身体についてのコメントが次々と流れる。
セラが犯されるたび、視聴者の男たちは自身のペニスを刺激し、セラを犯し続ける。
誰かがハイテクオナホールを接続したのか、セラのアナルや性器、口が犯されるたびに射精している。
その屈辱、そして絶望に、セラは目を再び大きく見開き、ぼんやりとゴーレムの顔を見る。
彼らの表情は、機械のように仏頂面だった。
神も、仏もいない。
自分自身が獣人になって以降信仰していた神は、自分を見捨てたのだろうか。
そんな絶望が体を、そして心をよぎる。
「さぁ、イッツ・ショータイム! 絶望に陥るこのキンキーボーイをさらに喘がせてみましょう!」
ゴーレムは再びセラの口にイラマチオを行い、さらに脇や胸を手でさする。
さらにわずかに指を立て、こしょこしょとくすぐる。
その快楽に耐えられず、セラは上気した表情でゴーレムを見つめる。
しかし、ゴーレムは何も言うことなく、無心でセラに自身の怒張したものを押し付ける。
一方でセラのペニスもぱんぱんに膨らんでおり、今にも爆発しそうになっている。
しかし、セラはイくことを赦されていないのか、絶頂に至った瞬間にその気持ちがなえてしまう。
そのたびに心には虚しさがたまり、そのやり場のない感情は、ますますリハのソフトタッチを求めてしまう。
その時、セラは激しい痛みを自身の肛門に覚える。
その痛みにセラは思わずゴーレムのペニスを強く噛む。
ゴーレムはその不快にセラの髪を強く握りしめ、セラの顔を持ち上げる。
するとセラの目に手を入れ、魔眼をぐりぐりとまさぐる。
セラはその瞬間、目の前の視界がおかしくなり、眼を大きく回す。
しかしゴーレムに容赦などはない。
さらにリハはナイフで腸を切り裂き、肛門から引き抜く。
その瞬間、セラは痛みのあまり、意識が飛んでしまう。
しかし、次の瞬間、セラは再び強いしびれとともに現実に引き戻される。
「気絶されちゃ困るんだよ!」乱暴な声でリハは叫ぶ。
しかし、すでにセラの視界は砂嵐で何も見えない。
何が起こっているのか把握ができず、ただ脳がくらくらして、頭が回転しているような気分になる。
セラはその意識に支配され、いま、自分が何をされているのか、判断できなくなる。
どれだけ経っただろうか。
かなり長い時間だったような気もするが、そうでない気もする。
そんなあいまいな時間の果て、目の前の視界を支配していた砂嵐が晴れる。
セラの身体に身体感覚が戻り、自分が自分であるような気がする。
その様子に、セラはひとまず息を吐く。
しかしながら、今、自分がどのような立場にいるのかを知り、セラは砂嵐の方が幸せだったことに気づいた。
自分自身の同性愛や女装、淫乱であること、そのようなことをことさら書き連ねた言葉を体中に書き込まれ、裸にさせられている。
生殖器には多数の虫が這い、ことあるごとに性欲を刺激する。
その恥ずかしさにセラの感情はオーバーフローし、眼を閉じる。
しかし、眼を見開くと視野には自身の「罪」が書かれた言葉がたくさん書かれていた。
セラをののしるコメントが次々と意識の中に入り込む。
その言葉にセラの心は無防備にぶつかり、セラは苦しくなってくる。
自分自身が、どうしてこんな人間だというだけで、何も非難されることをしているわけでもないのに差別されてしまうのか。
怒りどころか、絶望感で立ち上がれなくなる。
そしてこの暴力をコンテンツとして楽しんでいる人間たちがいる。
このように、気持ちをくじくことが人間たちの狙いなのだ。
そう思うと、立ち上がる勇気が少しずつ沸いてくる。
しかし、こんな気持ちで立ち上がることなどできるのだろうか。
セラは涙を流す。
その時、小さな光が目の中に映った。
力一杯目を閉じたからだろうか。
しかし、次の瞬間に聞こえた言葉で、セラ自身の光は本物であったと確信に変わる。
「神様、僕は救われるのでしょうか……」セラは問う。
「私は神様じゃないけれど、神様の代わりにこたえる。救われるに決まっている」冷たくも暖かく、か細くも強い声。
その声の主は知っている。
しかし、その声はその声の主が話しているというよりも、もっと力強い存在による声に聞こえた。
「セラ。よく思い出して。イーサーは誰と一緒にいた? 目が見えない人、姦淫を犯した人、ツァララトに苦しむものじゃないか。そしてイーサーは誰からうまれた? 神の子ではあったけれど、外から見れば間男と交わった女性からだ。君はどんな獣人だい?」
その言葉に、セラはゆっくりと自問自答をする。
そして「僕は……救われるべき存在です」とつぶやく。
次の瞬間、はげしい光に包まれる。
その光に合わせて出てきたのは、茶色と白、そして青で染められた、ぶちの猫の半獣。
「シイ……」
セラはつぶやくと、その姿に少しだけ元気が湧く。
そして少しでも自分が前に進めるよう、ゆっくりと前を向いた。
Tzarrath
ルカはもう一人のリハである、実態のリハの前に立っていた。
すでにルカは腕の刀を立て、それを十字にクロスし、今にでも書かれるような体勢にしている。
一方でリハは悠然と立ち、ルカの顔をまじまじと眺めていた。
「おいしそうな女のコ、発見」リハはにこりと笑う。
その意味が分からず、しかし一義の気持ち悪さを感じ、ルカはさらに力を込めて構える。
その態度にさらにリハはそそられるのか、マフラーを人差し指で自身の股間へと持って行き、マフラー越しに自慰を始める。
「あんまりにあんたがおいしそうで……。ああ、おいしそう!」
びちゃびちゃという音を立て、股間をまさぐるリハ。
ルカはそれに一瞬気持ち悪さを感じ、警戒する。
しかし、彼女がオナニーにふけっているのを見るや、地面をける。
そしてまっすぐ、姿を見せることなくリハへと飛んでいく。
右手を大きく構え、払う。
リハのマフラーが切り裂かれ、びりびりになる。
そして左手を薙ぎ払おうとする。
しかしその時、ルカは刀から激しい衝撃が伝わる。
思わずその様子を見ると、リハは剣を構えていた。
リハのマフラーは本当にわずかだというのに修復され、もはや先ほどのチャンスは残っていなさそうだ。
ルカは目を見開く。
「あたしにそんな甘っちょろい攻撃が聞くと思うのかい?」
快活な担架。
ルカはそれを相手にしないように、リハの腹を蹴り飛ばし、間を開く。
そして呪文を唱えると、足元に魔法陣が展開する。
ルカは腕を前に突き出す。
鋭い氷の粒が敵の胸めがけ、一直線に飛んでいく。
その攻撃を受ければ、少なくとも出血のために動作が緩慢になるはずだ。
ルカは次の魔術の手を考えつつ、敵の出方を伺う。
しかし、ルカの目論見は一気に崩れ去ってしまう。
リハはにこりと微笑むと、大きな緑色のシールド魔術を展開。
氷はその中へと吸い込まれ、敵へは一切命中しない。
ルカは目を見開き、じっと敵を見つめる。
「だから言ったじゃないか。あたしにゃそんな弱っちい魔法なんざ効かないよ」
ルカはすぐさま次の魔術を打つべく、じっとシールドを張りつつ考える。
しかし。
「ならこんどはあたしが」リハは言うと、足元に魔法陣を展開し、中からオークを三体召喚した。
それが何をするかわからない。
周囲にはすでに人だかりができており、興味深そうに携帯電話を向ける。
学生たちを守らなければ。
その使命感に、火がつく。
ルカは生徒たちのいる側に立ち、そして氷の結界を張る。
そしてオークめがけて魔法陣を展開。
冷凍弾を発射する。
冷凍弾はまっすぐにオークへとぶつかり、次々とオークたちを氷漬けにしていく。
しかし、リハも負けてはいない。
リハはオークを何体も召喚し、ルカの氷の壁を破ろうとする。
その敵を追い払うべく、何発もの冷凍弾を発射する。
あまりにしつこく冷凍弾を飛ばさなくてはならない。
ルカはゆっくりと目を閉じ、手を大きく広げる。
広げた手、そして足を円の中に含むように、巨大な魔法陣が発生。
ルカはその中で魔法を練っていく。
しかし、その時。
ルカは悲鳴を聞いた。
その悲鳴の先には、ひとりの女学生がオーク2体に犯され、辱められていた。
ルカは大きく、黙ったまま目を見開く。
何とかしなければ。
彼女は加速装置で向かい、オークの首に一発、二発と腕のフィン型カッターをお見舞いする。
しかしオークの姿は次々と増えていき、学生たちが次々と魔の手にかかる。
男子学生はあまりのことに茫然とし、リハたちを見ていた。
「いい? 見ていたわね。これが偽善者の正義の限界なの。人間に疑問を持ったまま、反人間的なことをひとに教えたらこうなるの。わかったかしら」
オークは女子学生だけにとどまらず、男子学生の肛門に自身の怒張を押し当て、上下に腰をふる。
ルカは一人のオークの首をつかむとそれを刀で飛ばしていく。
しかし何人ものオークが発生し、一部は階段を下り始めている。
――どうしたらいい
ルカはじっと考える。
彼女はそのまま階段の踊り場に向かうと、オークの身体をフィンカッターで斬る。
しかし、別のオークに腕をつかまれ、さらにがんじがらめにされる。
そのままルカの身体は階段を上り、リハの前に出される。
股側にオークの足がかけられ、両腕が別の2人のオークによってつかまれている。
いわば十字架のような形となり、ルカは身動きが取れない。
リハはゆっくりとルカに近づくと、ルカの脇を嗅いだ。
「海の、磯臭い匂い」
脇をかがれることがどれだけ屈辱か。
そしてどれだけ気持ちが悪いか。
その感情を伝えることもできず、にらみつける。
しかし、リハは楽しそうな目でルカを見ると、ルカのベルトを刀で斬る。
「へぇ、ズボンになっているのね」
ズボンを吊り上げていたベルトが切られ、ズボンが緩くなる。
ルカは危機を感じ、眼を大きく見開く。
しかし、リハはオークたちを見て、にこりと微笑むと、そのズボンに刀を突き刺す。
「おしっこしやすいようにしてあげるねー」
リハの吐き気を催すような甘ったるい声に合わせ、剣がゆっくりとルカのズボンの中に隠れた秘宮をあらわにしていく。
ショーツが姿を現すと、リハはそのもっとも湿った部分、膣口にショーツ越しに顔を当て、嘗め回す。
その気持ち悪さ、そしてわずかに感じる快楽に、ルカは顔をしかめる。
ルカはリハを蹴り飛ばすべく、足を動かそうとする。
しかし、しようとした瞬間にオークによって足をさらに大きく広げられ、蹴るどころではなくなってしまう。
さらにリハはルカのクリトリスを舌先でこね回す。
そのたびにルカはくぅ……と息を漏らす。
別に快楽が強いわけではない。
しかし、大勢の自分の学生たちがそれを見ているのを見ると、悔しさよりも、なぜか快楽が増してしまう。
ルカはそれが悔しくて、舌を何度も噛もうとする。
その時、ルカの口にオークは何かを入れた。
金属臭のするそれは、ルカから言葉を奪う。
さらにその金属はゆっくりと舌の上を滑り、そして咽頭へと達する。
快楽を呼吸で逃せられなくなったルカは、ついにそれで顔が少しずつ赤くなっていく。
クリトリスを舐めていたリハは、ショーツをナイフで切り裂く。
すると全く毛におおわれていない生まれたての性器がすがたを現す。
「うわぁー! パイパンなのね!」
あまりに恥ずかしいことを大声で言われ、それを抗議すべく声をあげたくなる。
しかし、声を発するための手段が奪われ、ボディーランゲージすらままならない。
ルカはそのもどかしさに目を大きく見開く。
さらにリハは陰唇を大きく開くと、中をじっくりと見る。
「うわぁ! 処女だ!」
その発言にルカの表情はさらに赤くなる。
そうだ。
見かけだけで言えば自分は処女のようなものだ。
厳密にいえば、何人もの男の相手をしたことがある。
しかし、改造された半獣の身体は回復システムのおかげで傷ついても元の戻ってしまう。
そのため、処女膜もまた、何度貫通させられようともとにもどってしまう。
ルカはあまりセックスを楽しむ方ではない。
しかし、何度も復活する処女膜は、愚かな男にとっては魅力的に映るようだ。
そのことを知ってから、ルカは人間をますます軽蔑するようになった。
リハはテレビ画面につなげたカメラを持ち出し、ルカの処女膜向けてカメラ付きの、男根のような形をしたカメラを突き刺す。
彼女がルカの膣へと、それをゆっくりと押し込めていくと、やがて処女膜にたどり着く、
リハは全員ににこりと微笑むと、思いっ切りカメラを押し当てる。
あまりにいたい痛みに、ルカはひっくり返りそうになる。
しかし、カメラを少し引いただけの間で処女膜は見事に封鎖され、まるで処女のようになる。
そんな機能を付けた人間を恨みたくなってくる。
その機能を人間たち全員に示すと、リハは軽くウインクをして見せる。
わずかに人間たちの姿が水色に光ると、ゆっくりと人間たちはルカに集まってくる。
そしてオークは顔を押し込むと、四つん這いの格好にルカをした。
すぐに人間は近づき、そしてルカの足をつかむ。
口元に一人、ルカの女性器に露出した怒張を押し当てる男が一人。
全員野獣のようになり、楽しそうな表情でルカに怒張を押し付ける。
そしてそれを前後させる。
ルカはあまりのことに目を大きく見開く。
しかし、その様子はほかの人間によって録画され、そして拡散されんとしている。
そのことに恐怖を感じ、目を再び大きく見開く。
しかし、人間たちはそれをやめることなく、順番にルカの穴に自身の棒を突っ込んで、サルのように快楽をむさぼっていく。
「さぁ、ルカちゃん。人間さんが撮影した先生の姿、これを公開したらどうなるかしらね」
ルカの目の前で、少年が一人、携帯電話のボタンを押そうとする。
彼女はそれをやめさせるべく、きっと睨む。
「どうする?」リハはその少年に言う。
メガネをかけた、さえない感じの少年がうーんと、と考えるそぶりを見せる。
すると少年は「単位、くれますか?」という。
単位を少年にやったところで、少年のためになるのであろうか。
少年のためになるのなら、単位くらいやったっていい。
しかし、それは本当に学習する学生のみに単位を与えたいという、自分のこだわりに反してしまう。
それでも、今は自分の危機なのだ。
ルカは自分に言い聞かし、ゆっくりと頷く。
「あれ、先生、らく単にしちゃうのー? アリス大学で最も厳しい先生が甘くなっちゃったー!」
それと同時に、他の人間たちは次々と自身の願い事を言う。
しかし、それを拒否することはできない。
えこひいきなどしたくないという、これも自分のちっぽけなプライドと正義感が、命を邪魔するからだ。
さらに、否定しようものなら何人もの人間が録画した自分のみっともない姿をSNS上にさらされてしまう。
それだけは、どんなに勇敢なレジスタンスであったとしても勝ち抜くことはできなかった。
次々と学生の無理難題を許可していく。
妹を大学院までタダで行かせてください、彼女になってください、性奴隷になってください……。
その無理難題を断ろうとするたびに、人間はスマートフォンを取り出し、先ほどの性暴力を収めた動画を送信しようとする。
それを防ぐべく、ルカは立ち上がろうとする。
しかし、そのたびに人間はボタンを押そうとする。
――どうすれば教育ができるか
ルカは静かに考え、そして一つのアイデアに達する。
情けない姿をさらしつつも、ゆっくりと息を吐いて精神を統一。
そして魔法陣を展開すると、その場でゆっくりと外気の温度を冷やす。
急に冷えてきたことに、学生たちはお互いの目を見やる。
しかし、すぐに寒さのために眠り、そして凍ってしまう。
冷凍睡眠魔術。
人間への仕置きは、またあとですればいい。
ルカはゆっくりと立ち上がると、じっと、静かな目でリハを見る。
「な、なによ」
リハは、ルカの姿に驚き、そして一歩引き下がる。
一方、ルカは一歩ずつその間合いを詰めていく。
リハはそんなルカから離れるように一歩ずつ引き下がり、壁際へと追い詰められていく。
そして彼女は剣を構えると、ルカめがけて突きつける。
しかし、リハは腕の先から力が抜けたのを感じる。
腕の先はきれいな断面で切断され、腕が地面に落ちる。
リハはルカを見る。
ルカの右腕のフィン型カッターの歯は血を湛えて真っ黒に染まり、ルカの顔にも血液が飛散している。
「何を……したのよ……」リハは静かに問う。
ルカはじっと見て、もう一度、今度はリハの顔面に斬撃。
スラッシュ状に切り裂かれた顔面からは、真っ赤な血液がこぼれ出る。
「僕を辱めた、お礼だ」
ルカは静かに、これからを宣言する。
そんなルカを、静かにリハは眺めていた。
Envision
ルカはゆっくり立ち上がると、じっと敵を見つめる。
リハたちは今、敵に対しての残忍な攻撃が跳ね返され、そして今、強い力でそれに抗おうとする、ルカの力を感じた。
そのことはリハにとってはひどく強いストレスであり、そのストレスの原因を排除したいと考える。
しかしながら、それはそれなりに困難なことであり、またルカの攻撃によっては自分自身が滅ぼされてしまいかねないことが予測される。
そのため、リハはじっくりと間合いを見つめる。
ルカは敵が間合いを詰め、立ち向かおうとしているのを察知し、少しずつ攻撃に移すべく、ゆっくりと間合いを詰めていく。
その時、敵は手を指し伸ばし、何かを召喚した。
現れたのは、黒い西洋甲冑を身にまとった獣人兵だった。
一人、二人と目視で数えてみる。
どうやらに十体近くいることが分かった。
これとの戦闘により、傷つくことはない。
しかしながら、少しばかり不利でもある。
「ホルン、こっちの手伝いをしてくれないか!」ルカは声を荒げる。
すぐにホルンは姿を現し、敵の前に立つ。
そして自身の鎌をひと振り、二振りすると、「てめえら、俺のかわいこちゃんを傷つけたみてぇじゃねえか」と、咆哮する。
しかしながら敵兵は一歩も引かない。
それを察知した二人はお互いの顔を見やると、攻撃態勢に入った。
ルカは手近な獣人兵の首をフィンカッターで切りつけると、その遺体を盾代わりにして、敵兵からの魔術攻撃を避ける。
しばらくして攻撃がやむと、今度はルカが呪文を唱え、冷凍光線を敵へと浴びせる。
それによって冷凍された獣人から魔法銃を奪うと、一発を獣人兵めがけて撃つ。
しかし、その時、敵兵からの銃弾に被弾。
ルカのわき腹に痛みが走る。
ルカはすぐさま敵兵を見て、銃を向ける。
敵兵はほかの敵兵に隠れ、見えなくなる。
その時、また別の兵士がルカめがけて銃を撃とうとする。
その時、ホルンはその敵の腹を炎に炎をまとった拳を入れ、攻撃。
敵は青白い炎を上げて燃えていく。
ルカはホルンに微笑みかけてお礼とすると、さらにほかの獣人兵たちにも立ち向かっていく。
一人の胸に右腕のフィンカッターを当て、降ろす。
心臓付近を抉られた敵はそのまま倒れ込んでしまう。
再び、遠くからルカめがけて銃が飛ぶ。
ルカはそれを遺体で防ぐと、彼らめがけて冷凍ビームを放つ。
そし手彼女は遺体を捨てると、壁に隠れて待ち伏せし、追ってきた獣人兵めがけてとびかかり、かかとのカッターで斬りかかる。
「我は確かに祈る、水よ、悪しき敵を吸い込め」ルカは呪文を唱え、祈る。
その瞬間、徐々に床面に水の波紋が起こり、ゆっくりと広がっていく。
そしてしばらくすると水面は渦を描き、椅子や死体など、様々なものを吸い込んでいく。
やがて獣人兵たちも吸い込まれて生き、手を伸ばして自身の救出を叫ぶ。
あるものはほかの獣人兵の足を握って生き延びようとし、あるものは吸い込まれないように手すりなどを握る。
ホルンはその間空中からそれらを見つけ出し、火炎弾を用いてその腕をほどいていく。
三分もすると彼らは完全に吸い込まれてしまい、水面はもとの穏やかなものになっていく。
ホルンとルカはお互いを見やる。
そして軽く会釈をすると、敵の前に立つ。
敵には先ほどセラたちの前にも出たと五、リハの師匠、ソギョンも立っている。
ソギョンは目の前の状態に驚くこともなく、腕を組んで立っている。
その余裕を持った様子に、ルカ達はわずかに威圧される。
「同胞に何しているんだ」ソギョンは言う。
ルカ達はあくまでじっとソギョンたちの行動を見るだけで、何も言ったりはしない。
そのじっと、黙っている様子に、ソギョンはゆっくりと息を吐く。
「なるほど。何も言いたくないならそれでいい。だが、この後始末は絶対につけさせてやる」
ソギョンはリハの顔を見る。
リハは「はい、師匠!」というと、その場から飛び上がり、ルカ達へと向かう。
リハは腕の先に剣を作ると、それをルカに向ける。
ルカはそれを冷凍ビームで応戦。
リハはビームを避けるべく、その場で一回転してフォーミングをキャンセルする。
しかし、リハは着地するや否やルカめがけて突進。
魔法陣を作り出し、ルカに照射する。
そして腕の先から電撃を放つ。
ルカはそれを避けるべく飛び上がる。
その途中、リハにすれ違った際に、彼女の顔面を蹴り飛ばす。
そのままひっくりがえったリハを、ルカは足のカッターを降ろして切りつける。
リハの幅部分にカッターは深く貫通し、リハは目を大きく見開く。
一方、ホルンはソギョンめがけて鎌で炎の斬撃を加える。
ソギョンはそれを軽い身のこなしで避けると、ホルンめがけて飛来する。
ホルンはそれを腕の先に作った熱線ビームで応戦。
ソギョンはそれに命中し、その場で着地する。
ソギョンの腹部に貫通した熱線の跡が痛々しい。
しかし、ソギョンは何事もなかったかのように立ち上がると、小さく呪文を唱える。
するとソギョンの肉体は回復していき、やがて痛々しかった傷の跡はすっかり消えてしまう。
ホルンはその様子を危機だととらえ、にらみを利かす。
「さて、ホルン君。君はどうするつもりだね?」
挑発するような言葉に、ホルンはにらみで答える。
「法。何も答えないとな。しょせんお前たちのしていることは暴れたいという、タナトスの発露でしかない。獣人を救うことなど、二の次なのだ」
その言葉に、ホルンの耳が反応する。
それを確かめると、ソギョンは鼻を鳴らす。
「暴れたい。その思いは私にだってある。ただ、それをコントロールしてこそ獣人だ。第一お前たちの愛読書であろう獣人記には復讐を禁じる箇所がいくつも出ているだろう。それを無視するなど、一体どこがお前は獣人記を守っていると言えるのか」
その言葉に、ホルンはさらに耳をピクリと動かす。
ゆっくりと微笑み、にこにこした目で敵を見つめる。
「暴れたいという欲求を押さえぬ限り、獣人からも、人間からの支持を得られないだろう。事実、そうではないか」
いうとソギョンはリハに命じ、映像を空間に映し出す。
そこには多くの人間の顔が映し出されていた。
チーズ牛丼を食べているだろう顔、略してチー牛とされるような、ぼっとしてぱっとしない顔がいくつも映し出される。
そんな彼らはコメントでセラやシイ、そしてルカやホルンを愚弄し、犯していく。
その言葉にホルンは腹を立てるも、どのようにそれを攻撃したらいいのかわからず、奥歯をかみしめ、どん、どんと地面を踏み鳴らす。
「ウサギらしい足ドンだね。でも、もう君たちの願い、著作権の解放についての議論は終わったんだよ」
その言葉にホルンは目をむく。
「著作権の議論なんざ終わっちゃいねぇよ! 俺たちは著作権を返してもらわにゃならねぇし、その著作権を開放しなくか俺たちが生きていられねぇんだよ!」
その言葉に、ソギョンは息を吐く。
「どうして君たちは物分かりが悪い? 著作権を主張することで多くの著作者が救われる。それのどこが悪い?」ソギョンは言う。
ホルンは思っていることを言おうとしたが、それをルカが遮る。
「著作権を主張することで、しかもそれを何重にもとることで文化の発展が遅くなっている現実がある。それこそかつて人間界でテレビのネット配信をしようとした際に、著作権の問題でできなくなったではないか。テレビは自分たちの出資しているNIMCAや、それに加盟しているテレビ局傘下の音楽会社を篭絡することもできないという愚かさをさらしたがな」
その言葉に、ソギョンはゆっくりと息を吐く。
「それが職業差別だということがどうしてわからない? プロとして著作権料で生きている人間、そして獣人がいる。いい作品を作ってそれで稼ぐことの何がいけない?」
ソギョンは言う。
一方、ルカはあまりに頑固で古い頭をした、獣人の皮をかぶった人間に内心腹が立ち始める。
「別にいけない、とは言っていない。セルフパブリッシングを行って自分の収入にしている漫画家や小説家だっている。音楽も同様だ。さらにそれを買い切りにして、クリエイティブコモンズにしている漫画家、著作権フリーにしている小説家も大勢いる。そのような試みができないことは、僕たち獣人からすれば化石のような頭としか言いようがない」
その言葉に、ソギョンは自身の小さな耳を引くひくと動かす。
「お前たちには職業の大切さというものが分からないようだな」
ソギョンは言うと、剣を召喚し、握る。
そしてかなりの速さでかかってくると、ルカの前で剣を構え、飛び上がり、ルカめがけて剣を振る。
ルカはそれを下方で躱すと、すぐに身を切り替え、ソギョンの背中に十字の傷を入れる。
そしてソギョンが着地する直前にルカはつま先に氷の魔術を掛け、ソギョンの首を蹴り飛ばす。
ソギョンの首にアイスピックが貫通したことを告げる、生ぬるい血と、氷の冷たさの混じった独特の感触が足にまとわりつく。
ルカはそれを確認すると、肩を踏みつけ、胴体と頭部を分離させる。
そして足を持ち上げると、胴体から頭部が切り離された。
リハは目の前で死亡したソギョンをぼんやりと見つめる。
「あたしの師匠……師匠……」リハはただ突っ立ってそういうと、ゆっくりと挫折する。
そして大きな声で泣き出した。
「るせーな」ホルンは言うと、彼女の首に鎌をかける。
リハはその場で泣き止み、じっとホルンを見つめる。
「あんたたちがあたしの師匠を殺したんだ……!」
リハは言うと、ゆっくりと立ち上がる。
「あたしの小説をほめてくれた師匠……」
ぼんやりとした表情でつぶやく。
そしてルカ達を見る。
「あたしの師匠を殺した! 著作権者のあたしのプライドを殺した!」
リハの言葉を、ホルンたちは聞き流す。
著作権者のプライドと、クリエイティブコモンズなどのフリーカルチャーは矛盾しない。
その概念すらも理解できない、矮小で無知な連中など、話の相手ではない。
リハはその態度を見るとさらに逆上し、ルカたちめがけて魔法の杖を向ける。
そして青い巨大な魔法陣をいくつも展開すると、そのすべての中心付近に魔法弾を起動した。
魔法陣から射出される魔弾が発射される。
それらはホルンたちを追撃し、そして命中。
彼女たちはその場で激しい痛みを感じ、眼をぎゅっと瞑る。
身体が分解されそうで、裂けてしまいそうな痛み。
それを緩和させることもできず、眼は血走る。
その姿をリハは腕を組み、眼を吊り上げて大きく笑う。
「あたしたち作家を愚弄した罰だよ! 作家の怒りを体験してみな!」
何が作家の怒りだ。
ホルンは目を大きく見開き、そうつぶやく。
しかし、自分を解体しようとしてくる力に抗うことができず、眼を大きく見開く。
その時、ホルンは目の前に暖かな存在がいるのを感じた。
「技術を使わせないようにする人間が、どうして発展することがあろうか」
その言葉に、大きなビジョンをホルンは見る。
テクノロジーが発展し、人間も獣人も様々な方法で映像や音楽といったメディアに触れることができるようになった。
しかし、それを消費者たる一般の獣人や人間がタッチすることなく決定され、恣意的な運用が行われていたことが意識の中に入ってくる。
これだけなら自分たちの学んできたことだ。
しかし、その先にさらにビジョンが浮かんでくる。
ある獣人は音楽をリミックスし、別のものを作り出す。あるいは、詩をリサイクルして自分の小説に組み込む。
これを自由なライセンスで公開することにより、自分たちの新しい文化が始まる。
それによって自分たちの表現の自由や、自己表現能力をさらに高められる。
さらに派生したものを原著作者がコピーすることで、新しくその作品もよみがえる。
そのビジョンを共有することが、おそらく自分の使命なのかもしれない。
エバンジェリストというには少しおこがましいけれど、そのビジョンを伝えたい。
その思いを意識のまま、さらに大きな人間の集合意識に接続する。
意識の中で獣人たちの意識が流れ込んでくる。
自由と、屈折した創作意識。
そして泥棒のようにこそこそと創作しなければならない恐怖感。
それらを自分たちは取り外そうとしているだけだ。
ホルンはそう、意識で伝える。
集合意識は原作者が……という懸念につながっていく。
ホルンはそれの対策を考えてあった。
例えば原作を購入した人に対して、クリエイティブコモンズの非営利の宣言をしておくこと。
こうすることで、小規模な同人活動程度ならば認められるようになるし、それに作者の商活動の自由を妨げることもない。
それを伝えると、意識は少しずつ、違和感を感じつつも頷く。
さらにホルンは今まで見たビジョンを共有する。
一つの作品が様々に拡散され、リミックスされていく。
そして派生作品から元の作品を見て、その魅力にハマっていく。
お金がない獣人も、それをもとに派生作品を作り出し、やがて自分のものを作り出すようになる。
それが文化にとっての利益なのではないか。
そのビジョンを見た人間たちは、楽しそうに微笑む、
それがワイアードたる、獣人、そしてウェブ2.0世界を生きるiGenらしい生き方なのだと、ホルンは語る。
次の瞬間、ホルンの目は覚め、ゆっくりと戦場に立つ。
すでにホルンたちを監視していた目は消え、目の前にいるのはリハだけだ。
リハは急に消えた自身の応援団に戸惑い、きょろきょろと周囲を見る。
一方、ホルンは「仕上げだ」と小声でつぶやくと、鎌を握る。
そして一歩、二歩と速い速度で駆け出すと、鎌に真っ赤な炎の魔法をかける。
真っ赤な炎を帯びた鎌を、敵めがけて振る。
次の瞬間、リハはその場で胴体を真っ二つにされ、その場で炎上した。
ホルンは長く電撃の中に閉じ込められ、疲弊しているルカを介抱する。
ルカの身体にはまだエネルギーが残っているようだ。
ホルンは安どの息を吐くと、そのままルカを抱えて飛び去った。
Instant Psalms
セラのバラバラの身体は今、リハのもとにある。
シイはそれを確認すると、真っ先にリハのもとへと駆けていく。
あと3メートルほどでリハにたどり着くその時、リハが目の前から姿を消す。
シイはきっと目を鋭くすると、じっとリハを見つめる。
今度はどちらに飛ぶか。
シイは自身のシステムを自分を包む大システムに接続し、その情報を読み込んでいく。
そしてある程度の計算可能性を感じると、シイは軽く口元を緩める。
その態度が何を示すのかわからず、リハはしかめ面をする。
「そんなに余裕ぶっこいて、大丈夫なのかしらね!」リハは今すでに勝ち誇っているかのような態度で言う。
しかし、シイはじっと敵を見つめたままだ。
その目には見えない闘志と、狂気を奥に湛えながら。
その狂気に気づかないのか、リハはシイめがけて剣を構え、大地を蹴る。
彼女の身体はまっすぐと、何の妨害もなく飛んでいく。
その剣はシイに向かい、胴を切る確かな手ごたえを腕に感じる。
リハは口元を緩める。
しかし。
そこにいたのはシイではなく、シイのような姿をした人形であった。
――やられた
リハは口元を真一文字にしてその悔しさを示す。
しかし、そんな彼女をあざ笑うかのように、リハは背後に気配を感じる。
その気配に振り返ったその時、激しい斬撃を体に感じる。
「油断のし過ぎだ」シイは言うと、リハの血を吸って真っ赤になった剣を抜く。
しかし、リハはその命を閉じることなく、ゆっくりと立ち上がると、再びシイめがけて斬撃を咥える。
シイはそれをバック転で躱すと、小さな声で魔術を唱える。
足元に彼女の茶色の魔法陣が広がり、それを蹴り込む。
再び剣を構えたままバック転をする。
その手には両手に短剣が握られており、それを振りかざそうとしていることは十分に把握できる。
リハはゆっくりと口元を緩める。
速度では向こうの方が強いかもしれない。
しかし、勝算は自分にだって十分ある……。
リハは剣を握り、こちらもまた、呪文を唱える。
そしてシイが着陸する直前に魔法陣を展開。
彼女の青い魔法陣が大きく開き、剣の先からは魔力によって生じた電力がスパークを起こしている。
一方、シイには敵がどうするかということはある程度予想が立っていた。
わずかなエントロピーの増大や、システムの生産の状況。
それらからだいたいどのようにこの先転がっていくか、システム遣いとしては手を取るように理解ができた。
巨大な斬撃。
それを避けるため、着地してすぐにシイは背中に翼を展開し、システムの内部を飛行。
青い、スパークを放つ斬撃はシイのすぐ下をかすめ、建物に命中し、破壊する。
しばらくそのエネルギーの反応で動けなくなっているリハめがけて飛行し、翼をパージ。
落下の勢いに合わせて短剣をクロスさせ、小さな斬撃を加える。
リハの顔面が十字に切られ、真っ赤な血液が漏れ出る。
さらにシイはその十字の真ん中に剣を突き立てると、中の筋肉を抉るようにゆっくりと十字から右下方四十五度の角度で切り裂いていく。
リハはあまりの激痛に目を大きく開けるが、その瞬間、ナイフはリハの口へと届き、口から頬が切り裂かれる。
さらにシイはもう片方の短剣でリハの右目を突き刺すと、ゆっくりと魔眼のカメラを取り出し、引き抜く。
その激痛に、リハは叫びをあげる。
「私の友達を痛めつけたんだ」
シイは言うと、剣をゆっくりと頬の方へと降ろし、そして裂けていないもう片方の口元へと斬撃は達する。
それを確認するとシイは上唇の部分から皮膚を切り裂いていく。
歯茎に剣を突き刺し、鼻をそいでいく。
あまりの激痛に耐えられないのか、リハはすでに言葉を失っている。
それをいいことにシイは顔を削ぐと、次は首に剣を突きつける。
真っ赤になった剣は少しばかり切れ味が悪くなってきていても、やはり十分に敵の身体の血を吸うことができる。
オリハルコンの剣を作っておいてよかった。
シイはそう感じ、わずかに微笑む。
首元からナイフを降ろし、心臓へと到達する。
そして切れ目から手をリハの内臓に突っ込み、心臓をつかみ、引き抜く。
その瞬間、リハは目を大きく見開き、口から吐血して白目をむく。
シイはその瞬間、彼女の死を把握する。
ゆっくりと息を吐くと、シイはシステムからログアウトするべく、魔法陣を作る。
「私の弟子をかわいがってくれたようだな」
その声に、シイはゆっくりと振り向く。
突然の声。
その声が誰のものか、シイは知らない。
しかし、その声にこもった悪意を感じ、じっとシイは振り向かず、たたずむ。
「君は私の名前を知らないようだが、私は君の名前を知っている」
ねっとりと、まとわりつくような話し方で話す敵。
その敵の存在に、シイは気持ち悪さを覚え、眼をゆっくりと閉じる。
「君は……」
かなりもったいぶって話す敵。
その態度にシイはイライラし、顔を振り向く。
その瞬間、シイの顔面目掛け、いくつかのナイフが飛来する。
敵が放ったのは間違いない。
数はいくつだ。
シイはシステムのログから情報を引き出す。
その情報を引き出せた次の瞬間、シイの顔面にナイフが命中。
さらに深くシイの顔面に突き刺さったナイフは、真っ赤な血液を流しながら円を描き、さらにその真ん中に六芒星を書いた。
何をしようとしているのか。
シイは気になり、言葉を放とうとする。
しかし、口は言うことを聞かず、それどころか口元から漏れる呼吸が、シイにその傷の深さと、緊急を要する旨を伝えていた。
それでも、負けるわけにはいかない。
シイは体の中に搭載されていいるリカバリファイルを展開し、意識をいったん自分の中からリジェクトする。
そして新しく作った体に自身の意識を込めると、ゆっくりと立ち上がる。
「僕の出番かにゃー?」どこかから声が聞こえる。
シイはきっと目を鋭くとがらせると、その声の主を見る。
システム主砲の彼は、元気そうにゆっくりと尾を揺らしていた。
「僕が来たからもう大丈夫さ!
いうとセラは腕の先を銃の形に変え、その先に魔力を貯める。
すぐさまそれは光で満ち、セラはまず、右手の光を発射。
さらに左手を発射する。
腕の先から射出された巨大な魔弾は、敵兵へとまっすぐに進んでいく。
しかし敵兵、リス族ソギョンも負けてはいない。
彼は砲弾を躱すと、斜めの体勢でセラめがけて砲撃を加える。
「あのね、そうやって意見の異なる人を排除したらいけないの」
その言葉に、セラはニッと笑って返す。
「それはどうかな。それなら僕を排除することもできないはずさ!」
その態度にソギョンは口を尖らす。
「もう一つ言う。お前たちのしていることは意見の破壊なの。社会が変化しないから、獣人としての人生がうまくいかないからって、そんな態度をとったらいけないの」
その発言に、セラの耳がぴくぴくと動く。
「あー、そう。僕たちの命の危機が差し迫っても、君たちは耐え忍んで、その恐怖の中で暮らせ、っていうんだね」
セラは意地悪く言うと、にんまりと微笑む。
その言葉にソギョンは返す言葉がないのか、イライラとした表情でセラを見る。
しかし、セラはあくまで笑っている。
こんな愚かで、かわいそうな大人を愚弄し、おちょくれる。
それがどれだけ楽しいか。
セラにはそのことが十分わかっており、それが自分自身の快楽であるのだと、今、はっきりと理解した。
人間に属したことを後悔させる技を何かできないか。
セラは口元をほころばせると、ゆっくりと技を練る。
そしてプログラムを完成させると、自らそのプログラムを実行させる。
その合図ともいえる信号がセラのなかを駆け巡る。
一方、シイもまた、剣を構えていた。
すでに彼女もまた、何かプログラムを組んだのか、眼がプログラム完了を示す真っ赤な色に目が変わっている。
「シイ、何の魔術だい?」セラは明るく聞く。
シイはそんなセラに牙を見せたが、「……簡単な魔術だ。敵のダメージを受けるだけ」という言葉をセラに発する。
その言葉に、セラは少しだけ喜びを感じ、そしてにんまりと微笑む。
シイはゆっくりと顔をセラから離すと、さっと飛び出ていく。
シイはそのままソギョンに銃を放つ。
ソギョンはその銃弾を華麗に躱すと、シイめがけて魔弾をいくつも放出する。
その弾丸をシイは回避すると、セラの後ろへとついた。
セラはその隙を見計らい、ソギョンの足めがけて銃を発射。
ソギョンの足に命中した銃弾が、コロンという音を立てて転がる。
その瞬間、ソギョンはセラを見て、指の先から魔弾を射出。
セラはプログラム通り、それを体で受けていく。
あまりのエネルギーにセラの服が耐え切れず、ちぎれていく。
それでも皮膚がめちゃくちゃになっていないことを確かめると、セラはにこりと微笑み、シイを見る。
シイは少しばかり恥ずかしそうに眼をそむけると、ソギョンめがけて飛んでいく。
そのままシイはソギョンめがけて嵐のような銃撃を行い、足、腕、そして腹をハチの巣にしていく。
しかし、その攻撃でもソギョンは歩みを止めることはしない。
ソギョンはその足で飛び立つと、シイめがけて弾丸を放つ。
セラはその弾丸がシイに着弾するのを待つと、魔術光線を放つ。
魔法弾はソギョンの腕に命中して炸裂し、彼の腕をもぐ。
しかし、ソギョンは動きを止めない。
今度はセラたち二人を相手に魔法陣を射出し、魔弾を発射。
セラとシイはそれをまともに受け、セラの右腕、シイの左腕がもがれてしまう。
さらにそれと同時にシイの翼も吹き飛んだせいで、シイはその場に墜落。
なんとか立ち上がれたものの、魔眼にひびが入り、目の前がまるでバラバラに見えてしまう。
それでも今、自分自身はプログラムに従って戦っているのだと感じると、シイは安どし、ゆっくりと息を吐く。
セラはその隙に腕の先を剣に変換し、ソギョンの腕を切り裂く。
ソギョンの右手がもげ、すでにソギョンの戦闘は難しくなっている。
そう判断すると、あえてセラは攻撃の手を休め、少しばかりステップバックする。
その瞬間、ソギョンはセラ、そしてシイを見る。
「人間の意思を踏みにじって、何が平和だ。お前たちの行おうとしていることは暴力による侵略だ」
ソギョンはあくまで冷静で、静かな口調で言う。
しかし、その言葉をセラたちはじっと、まるで病人が世迷いごとを言うかのような目で聞き流す。
それに激昂したソギョンは目に力を湛え、それを光線として放出する。
それらはセラたちに命中し、セラの腹を裂き、シイの方を射抜く。
しかし、その瞬間、セラたちの目にプログラミングされているデータは一つの攻撃を許可する。
それを確認し、セラとシイはお互いを見やる。
すぐさま二人の足元に魔法陣が展開され、茶色と濃紺、二つの強い魔法が炸裂する。
そしてセラとシイは手を取ると、その中に魔力を閉じ込めていく。
魔法がたまっていくのを確認すると、ゆっくりとそのサークルを拡大し、ソギョンを包み込む。
「ソギョン!」セラは言う。
「汝のけものびとへの罪を、今、償わせる! 我ら獣の民への狼藉を、神は救うだろうか」シイは叫ぶ。
「静かに神を称えよ!」セラは叫ぶ。
獣人記旧約書第2詩編に収録された、抗いの歌。
まさかここで歌うとは思わなかった歌。
その歌を歌うことに、セラはわずかな戸惑いを覚える。
しかし、シイはそんなセラを見ると、「安心して」と静かに言い、セラの腕を舐める。
「わが神はけものを屠るものを赦さず、天の怒りとして抗う力を授けた!」シイは叫ぶ。
シイにとっても、歌ったことのない歌だ。
しかし、自分が獣人界を救わんとしていることは今、自分からも理解している。
そして世界を救うものとして、シイは祝福を受けた。
もしかしたらイーサーはこんなことをしようものなら涙を流すだろう。
それでも、いま、ここで虐げられる同胞に涙を流し、抗わなければきっと滅ぼされてしまう。
そんな姿を、ただ指をくわえてみるわけにはいかない。
「我らはけもののため、命を捧げん!」
セラはさらに歌を重ねる。
獣人の勝利を信じ、歌を歌う。
その歌が永遠に響くように。
「我らは義のために同胞を救い、義のために生きんとす!」
腕の先に展開された魔術の弾はいよいよ大きくなり、激しい白の光を称える。
敵は少しずつ光に溶けていき、悲鳴を上げる。
「わが義の力、見せん! ビブリカルオーブ!」
その言葉とともに、光はさらに激しい球を作り出し、ソギョンをその中で光へと変えていく。
光がやがて空間に閉じ込められると、二人の目の前は真っ白になっていく。
二人はじっとその様子を見つめると、最後、何も残らない空間を見て、ゆっくりと息を吐く。
そして二人はシステムからログアウトした。
Conclusion
ルダルは東都にある最高裁判所へと向かっていた。
ここではこれから、著作権法に関しての裁判が行われる。
ここで著作権法の違憲性を訴えることで、著作権法を廃案にすることができるためだ。
原告はルダルをはじめ、著作権法の問題を訴えている市民、そして音楽家一同、被告は国とNIMCAである。
この裁判は最近の著作権法への注目の高まりもあり、多くの人が傍聴券を求めて列をなしていた。
ルダルはゆっくりと息を吐き、裁判の開始を待つ。
「この裁判が終わったら俺の仕事だな」サンムからのテレパスが入る。
ルダルは何も言わず、じっと法廷内を見る。
それが今の自分にできることだった。
法廷は白と茶色い木でできた、ルダルにとっては少しばかり陰気な感じがする場所だ。
しかし、ここで裁判を戦い、獣人を何人も救出してきた自分としては、一番の主戦場である。
ここで負けたくない。
ルダルは裁判をうまく運ばせるための魔術をこっそりとかけた。
しばらくすると黒い服を着たミルド裁判長をはじめ、人間の裁判員が入廷する。
その間、ルダルは被告の顔を見る。
NIMCAの法務部長であるロビン・コスナー、彼の弁護人ヤン・インギュ。
この二人は今のところ著作権法関連栽培んで負けたことがないという。
さらに噂としてはインギュは羊族の獣人であり、裁判中に魔法を使っているのだという。
「魔法戦か」ルダルはゆっくりと息を吐き、前を見る。
礼をすると、開廷した。
しばらく訴えの内容を裁判関係者が読んだのち、ルダルにまずは発言権が与えられた。
「現行の著作権法は、獣人の創作の自由、表現の自由を奪うだけでなく、人間の表現の自由なども奪っています。事実、公判(カ)二二一五番にて、獣人が自身の作業場で音楽を複製しただけで逮捕され、彼は処刑されてしまいました。このような人権侵害は、世界人権宣言に反するだけでなく、人間憲法上の生存権の侵害であると言えます」
ルダルはその瞬間、洗脳魔術を掛ける。
その瞬間、聴衆から静かな、同情のため息が漏れ聞こえてくる。
「被告側、陳述を」裁判官はインギュに指示を出す。
「はい」と静かに言うと、柔らかな足取りで証言台に立つ。
「著作権法を奪われることで、多くの作家が困難に陥るのは日の目を見ることよりも明らかでしょう。それに、獣人が処刑されたのは、著作権法違反ではありません。ただ単に獣人保護法に違反したのです。それによって人間の著作権をなくせ、ということは、人間の著作者にとっては死を命じられたことと同等であり、苦痛でしかありません」
インギュは柔らかくも、かなりの怒りを含んだ声で発する。
さらに彼女の目がピンク色に光り、うっすらとした魔法陣が展開される。
ルダルはそれを急いで反魔術魔術で吸収すると、じっと敵を見つめる。
それでも負けることはない。
ルダルは踏んでいる。
「何も私たちは著作権法そのものを否定しているわけではありません。ただ、獣人に対しての不平等、そして人間、獣人問わず行われているNIMCAの強権的な著作権料徴収をやめていただきたいのです」
ルダルは言うと、カメラをセットして映像を流す。
「おいごら、獣人のくせして音楽聞いてんじゃねえぞ」
映像に映し出された男は言うと、獣人相手に蹴り始める。
獣人は「何でですか!」と絶叫したものの、聞き入れるそぶりを見せない。
そして彼らは一通り暴力をふるうと、トラックに乗せてどこかに運んでいった。
ルダルはそのあとを追いかけ、車の行きつく先へと向かう。
そこでは男たちが穴を掘って獣人を埋め立て、持っていた金品などを奪ってしまっていた。
さらにルダルは彼らに「何しているんですか!」と声をかける。
すると「てめぇ、見てやがったな」と言って、持っていたジャックナイフをルダルに向ける。
ルダルはその手を握ると背負い投げで投げ飛ばし、さらにナイフを奪う。
それを見たもうひとりの男は、魔法陣を展開してルダルに照射する。
ルダルはその瞬間、敵意があることを察知。
一方で何も行動を起こさない。
「弱い姿を見せやがっているな。俺はNIMCAのサービサーだ!」
誇らしげに言う男を見て、ルダルは悲し気な表情を浮かべる。
たかがNIMCAのサービサーであるというだけでここまで威張り散らし、さらには獣人を暴行し、その体を土に埋めてしまう。
それのどこが誇りなのか。
ルダルには理解ができなかった。
敵は案の定、ルダルをめがけて魔弾を発射。
ルダルはそれをバック転で躱すと、光線の届かない場所まで移動する。
しかし、これだけの距離が開いてしまうとわずかに不利になってしまう。
それでも、正当防衛の原則から言えば、彼らの攻撃を避けるためにここまで逃げた方がいいだろう。
ルダルは判断すると、じっとその場で敵の様子を見計らう。
敵、ウシ族の男はゆっくりとルダルに近づき、そしてルダルの前で、自身の杖をルダルに向ける。
「もう、終わりだ」牛族の男は言う。
男はすぐに魔弾を放ち、さらに牛刀らしき非常に刃渡りの長い刀を持ってルダルにかけてくる。
ルダルはまず、魔弾をシールド魔術で防御すると、どれくらいの威力だったかを計算する。
そして魔法陣を展開すると、スタン程度の電力が敵にかかるよう、魔術を発動。
敵はその場で転がり、動きを止めた。
「その彼が、私たちの証人です」
ルダルが言うと、会衆は沸き立つ。
それを裁判官は「静粛に」といって抑え込む。
そして男二人の証人を裁判官が招いた。
ルダルは質問する。
「一体なぜ、獣人たちであるからと言って襲撃をしたのでしょうか?」
ルダルは言う。
その言葉に、男はブスッとした表情で言う。
「著作権法に引っかかったからだよ。獣人の作品は少なくとも知名度の高い作品すべてが人間によって登録され、さらに獣人が使えないように著作者人格権を設定してある。それと、獣人保護法に従って悪を裁いただけだ」
その証言に、一同は沸き立つ。
「では、もう一人証人を立てます」ルダルは言う。
そこに出てきたのは、獣人の作曲家として名高い、キリン族のキ・ユンだ。
彼は獣人としてたくさんの曲を作ってきたが、それらをすべてNIMCAによって奪われ、自分の曲が好きな人に自由に使っていただく、歌っていただくという、獣人らしい感情をすべて奪われていた。
しかも、自分の判断でNIMCAに曲を信託したのではなく、レコード会社に信託したところ、勝手にNIMCAに信託させられていた。
著作権を取り返すべく、二審まで裁判を進めていたが、一審も二審も敗訴してしまっていた。
「彼の場合、獣人歌謡であるという理由だけで、信託もしていないのにNIMCAに曲を奪われてしまっています。これについてレコード会社であるサンセットミュージック社は「当然のこと」ということばですべてを片付けています。また、この取引の裏に獣人であるからという理由で強制的に曲を奪い取ったという情報もあります。さらに、 NIMCAは獣人創作からの排除、および、人間も含めた消費者からの搾取を正当化する法律を毎年、天界からの年度改善要請と合わせて訴えています。さらに政府関係者が裏金を渡していることも、私たちの協力者からの情報で得ることができました。これが証拠です」
ルダルは言うと、資料を提出した。
この資料の存在は、ボラが探し当てたものだ。
それをタンビが奪いに行ったものだ。
NIMCAの人間たちは一堂に驚き、そして目を丸くする。
「これは……!」NIMCAの人間が発言を求める。
裁判官はNIMCAの関係者に発言の許可を与えると、堰を切ったかのように話始める。
「この資料はねつ造です! 事実、サインなどがないじゃないですか。このような資料を作って脅迫をすることは、論証として正しくないだけでなく、私たちへの脅迫ともとることができます」
しかし、ルダルは笑う。
「じゃあ、このサインは何なのでしょうか? これは魔術サインですが、魔獣サインにはNIMCAの社長名、NIMCAの押印、そのほかレコード会社の印が押されています。これらを魔術サインで行ったのには、何か意味があったのでしょうか? しかも魔術サインで、ブラインド設定をしていますよね。それを私の魔術で表示すると」というと、ルダルは指を鳴らす。
すると魔法陣が展開されると同時に、NIMCAなどの法人の印鑑や、NIMCA関係者のサインが表示された。
「このように、獣人を抑圧するだけでなく、魔術サインによって秘密裏に契約された法律でもって、守られる著作権とは何でしょうか? 獣人たちの教えで、作ったものはみんなに使わせろ、というものがあります。著作物に限らず、作ったものは獣人みんなのものです。そしてリミックスや各種翻案を自分勝手に行うことで、作品の幅を広げるというものがありました。クリエイターが死ぬという言葉がありますが、それらは個人事業主として著作物を自ら管理し、自らの権限で杖のネットワークで販売。ただプラットフォームを運営するだけのプラットフォーム組合に加入して作品を流通させてきていました。さらにファンたちはそれをもとに物事を剽窃・リミックスし、その作品や派生作品を作り出すことで、コンテンツの幅を広げ、同時にその自由な利用に原作者も行うことで、文化の厚みを増してきていました。では、なぜ人間の著作物はがっちりとまもられているのでしょうか。それは著作権を持つ人間たちの性格がゆがんでおり、何かのために抵抗をしたり、軽傷を鳴らすための、そして同時代を生きるもののためではなく、ただのオナニーと成り下がっているためではないでしょうか。作品がただのオナニーと成り下がり、それを商品として売ることで人間や獣人を消費者の立場から動けなくし、創作者と消費者の二極対立を生んでいるだけなのです。その体勢を打破することこそ、これからの文化につながるのではないのでしょうか? そのために私たちは、著作権法のデフォルトをSome Rights Reservedにすることを要求します」
さらにルダルはこれに合わせ、魔法陣を展開。
言葉の力をさらに強める。
NIMCAの側の獣人は言葉に窮したのか、何も話そうとしない。
「被告側は?」裁判官は発言を促す。
「しかし、そんなことをしてしまえば著作権を主張できなくなってしまいます……」
かなりトーンダウンし、言葉にも張り合いが無くなってしまっている。
ルダルはここに勝利を確信し、じっと判決を待つ。
それから何度か、短い間に裁判が繰り広げられ、同じように証言を行う機会があった。
ルダルはそこで自分たちの優位性を語り、対話と洗脳を行い続けた。
そして最後の判決の日。
ルダルはじっと裁判官を見つめる
「主文。著作権法は違憲。よって、被告、NIMCAは以下の通り、著作権業務を停止し、解散を命じる。また、レコード会社各社は著作権業務を停止し、一部権利確保への対策をとること、また、国は著作権法を改正すること……」
ルダルはその喜びをじっくりとかみしめ、見つめる。
魔法が使われたことはどうもばれていない。
一方、敵は魔法を使ったことを証明されてしまい、その分窮地に陥ったらしい。
ルダルはどんな形であれ、勝利できたことを味わうかのように、牙をゆっくりと動かした。
Creative Shareling
ルダルが引き出してきた違憲判決をもとに、サンムは国会へとそれを持ち出す。
その道中も様々な妨害にあうことも予想されたが、すべて裁判所の決定が下りたことが理由なのか、皆、じっとその法律の動向を見守っていた。
法律は一か月ほどで可決し、晴れて改正著作権法が施行された。
その中には差別禁止義務、著作権の自由利用、フェアユース、パロディ権などが盛り込まれており、また、期間も七十年から三十年へと半減させられた。
これにより著作物を作品に引用する際には支障なく引用することができるようになった。
また、NIMCAに代わる著作権管理会社として、トーンチューンという民間企業が誕生した。
この会社では獣人楽曲や作品を取り扱わないこととなり、さらに利用料金や著作物使用の定義などが明確化され、例えば演奏会で音楽を流す時に演奏と楽譜で別々に著作権がかかるといったことは起こらなくなった。
また、獣人においてはかつての獣人界のように著作権のSome Rights Reservedの考え方が全面的に認められるようになった。
このことは人間においても広く知られわたることとなり、獣人の楽曲を使う動画クリエイターなどが増加した。
また、獣人楽曲の良さが人間たちにも広がるようになり、獣人の楽曲が本当の意味で評価されることも起き始めていた。
その動向を見て、タンビは満足そうに鼻歌を歌う。
歌っている曲は獣人グループRELAの「ぐるぐる」だ。
少し前の曲ではあるが、ダンスポップを基調とした楽し気な様子が、タンビの鼻歌からも伝わってくる。
「楽しそうだな」新聞を読んでいたサンムは笑う。
「そりゃ、そうだよ。だって。獣人の曲が認められるようになったんだもん! それに自由に歌える。それのどこが悲しいことなのさ」
余裕を見せるタンビに、サンムは「そうだな」と微笑む。
一方、ベルはアイドルとしての活動を再び始めていた。
アリスの地下アイドルとして活動を始めたかつてのアイドル。
しかしながら、彼女の輝きは失せることはない。
地下の薄暗いライブハウスで開かれているからか、彼女の輝きはまるでサイケな色合いだと、ルカとホルンは思う。
「これでよかったんだよな」ホルンは言う。
「どうしてそんなことを悩む」ルカはにこりと微笑むと、再び手を叩く。
その先には地下アイドル「鏡の国のアリス」のメンバーとして歌を歌い、踊るベルの姿があった。
シイとセラはゲームに興じていた。
このゲームに関しても著作権法の改正の影響があり、いくつかのゲーム会社は、ソフトの一部を自主的に著作権フリーの宣言をした。
これにより自由に遊ぶことができるようになり、かえってそのタイトルが知れ渡ったり、会社名が知れ渡ったことでほかのソフトの売り上げが伸びたりした。
かつて人気だったパーティゲームでタイムアタックを行っているセラとシイ。
その目はあくまでゲーマーとして鋭く、本気だった。
しばらくするとセラが二位で負け、シイが一位を取っていた。
「コンさん気分はどう?」シイは自然な表情でセラを煽る。
その表情にセラは悔しそうに口を膨らませると、「もう一回戦しよ!」と声をかける。
シイはそれを拒否することなく、セラとゲームに興じ、何度も同じ運命をたどった。
イェスルはこのことにおいて死んだ霊のために、長い時間をかけて祈りをささげていた。
復讐をすることなかれと書いてはあるが、立ち向かうなとは書いていないと考えつつも、果たして聖霊がこのことをお許しになるのかと、祈りをささげる。
そして何かの啓示を受けたのか、イェスルは顔を上げる。
「神様。悔い改めます」
イェスルは言うと、再び祈りを始めた。
「隣、いいかしら」祈り続けているイェスルの隣に、ボラが座る。
「どうした?」イェスルが言うと、ボラは「そうですね」といって話始める。
「私にとっても神様は大事な方です。そんな神様を賛美し、その言葉を聞くことは私にとっては日課みたいなものです」
ボラは言うと、にこりとイェスルに微笑む。
そのほかにも何かあったのではないかと、ボラを見つめる。
ボラは「ばれちゃいますよね」というと、イェスルを見た。
「私たちは殺人も、社会の操作も、すべて行っています。ただ、それをしていいのかどうかは、私にはわかりません。だからこそ、神様にどうか認めてほしいと祈るんです」
ベルは言うと、獣人記を取り出す。
獣人記韓民記一章。
レジスタンスとして戦う人間たちが戦う姿。
その中に、神を崇めた人間たちも描かれている。
その姿を読んでいると、不思議と心が落ち着いた。
それを見計らい、イェスルは「祈ろうか」と近づく。
ボラは微笑むと、手を合わせて祈り始めた。
そんな仲間たちを、ルダルはじっとアジトの作戦室でコーヒーを飲んで見つめる。
獣人を救えた満足感と、手を下した気持ちの悪さ。
それらが重なって、心の中に苦みとなって流れてくる。
その苦みがどこかコーヒーにも通じるような気がして、ルダルはゆっくりと息を吐いた。
「ルダル、どうしたんだ?」サンムは言う。
「自分たちは正義でも、悪でもある。絶対的な義なんて、神にしか存在しない、か」ルダルは漏らす。
サンムはしばらくその言葉を考え、言う。
「最低限の正義ってものはあるさ。それを守るのが、俺たちの仕事だろ?」
サンムは微笑んでルダルを見る。
ルダルはその様子を見て、にこりと笑った。
獣人戦記スイロイド


