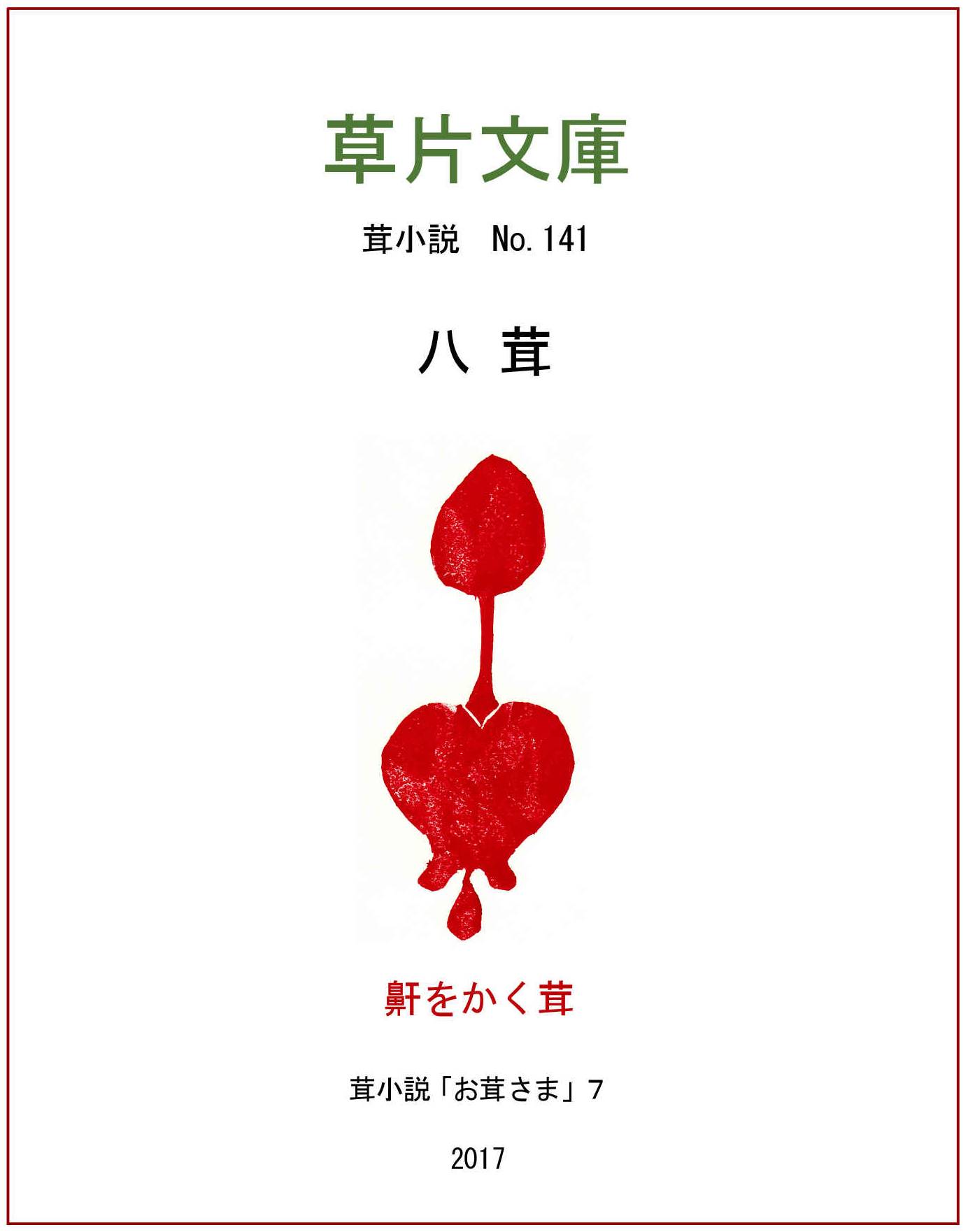
八茸
井戸端でおかみさんたちが噂話に興じております。いつものことです。
そこへ、長屋の入口から旅姿のお侍がやってまいりました。侍が茸取り長屋に入ってくることなどいまだかつてなかったことでしょう。
どこに行くのだろう、と物珍しげにおかみさんたちが一斉に侍を見ております。網笠をかぶっているので顔はわかりません。しかし、首の動きで、おかみさんたちに気づいたことがわかります。侍がささっとそばによってまいりました。
やだね、おかみさんたちは顔には出しませんが、そう思っていると、お侍が
「ちょっと尋ねるが」と声をかけてきます。
「茸取長屋とはここでござるか」
気丈な鶴が、「へえ、そうですがあ」
大きな声を出しますと、お侍さんのほうがびっくりしたようでございます。
「八茸殿はどこにお住まいか」と聞いた。
「大家さんなら、裏のほうの家だわな」
やっぱり、鶴が大きな声で答えます。
「おお、ここに住んでいるのではないのだな、どちらじゃ」
「あっちじゃよ」
春が八茸爺さんの家を指差します。
「そうか、かたじけない」
侍は長屋の入口にもどり、八茸爺さんの家に向かいます。
「八茸爺さんになんの用じゃろ」
おかみさんたち、興味津々、先回りとばかり、裏から大家さんの家に行きます。
八茸爺さんの家ではいつものように戸が開いており、黒犬の梅と黒猫の梅が外を眺めております。
「たのもう」
侍が襟を正して声をかけますと、
「どなたかな」
八茸爺さんが出てまいります。
「八茸殿でござるか、わしは、信濃よりまいった、松本権四郎と申すものでござる。教えをいただきたく、わが殿の使いで参った」
「ははあ、ご苦労様でございます、なんでございましょう」
八茸爺さんは珍しくかしこまって答えている。しかし、慣れたもので、なかなか堂に入ったじじいぶりでございます。犬と猫も神妙な面持ち。
「茸を見ていただけぬか」
それならば、と、八茸爺さん、内心はちょっと安心した様子でございます。
八茸爺さんは茸の達人ということで、江戸まで名前が知られております。
「むさくるしいところでございますが、どうぞお上がりください、やもめ暮らしゆえ、何ももてなしが出来ませぬが」
そうっと陰からみていた長屋のおかみさんたちが顔をだした。
「大家さん、何か手伝うことはないかね」
「おお、亀さん、鶴さん、春さん、いいとこに来てくれた、足洗いのたらいや、茶をたのめんかな」
「ほいきた」
鶴が急いで、水かめから、たらいに水を汲み、お侍さんの前にはこびます。
「松本様、どうぞ、足を洗ってください」
「かたじけない、おとといは江戸の屋敷に泊まりましたが、昨日は野宿をしました」
権四郎は荷物を置き、腰掛けるとわらじを脱いだ。亀が手ぬぐいをわたす。
「茶を入れようね」
春は八茸爺さんの部屋に上がり、慣れた様子で、沸いている湯で茶を入れる。
八茸爺さんが、権四郎を部屋に案内いたします。
権四郎が座ると、春が茶を入れて持ってきました。
「長屋の女子衆は働き者でござるな」
「何かの時はみなやってくれますのじゃ、みんな家族みたいなもんでございます」
「いや、いきなり参り申して、申し訳ござらん、わが殿の山で採れた茸が、もしやもすると、その昔、八茸殿が見つけたという、腹のできものによく効く茸ではないかと思われ、教えていただけとのご沙汰でござった」
「なぜ、わしの茸をご存知なのでございましょうや、信濃の国とは縁のない者でございますが」
「八茸殿が、八竹と名乗っておられた頃を、殿は良く覚えておいででござましてな」
「はて、それは、また、どこで」
「殿は元服前、お母上と江戸におられたのでござる」
「しかし、江戸とここは離れておりますな」
「わけがありましてな、わが藩と仲の良い相模の国の城主が腹に瘤の出来る奇病になられ、痛みがひどく、わが藩の江戸留守居役の家老に相談なされた」
「おお、もしやもすると、あの赤い茸を買っていかれたのは、松本様の薬師の方だったのでございますな」
八茸じいさんもそのときのことを思い出した。
「そうなのでござる。信濃は茸の豊富なところ、いろいろな病に効く茸を薬師が知っておったのだが、腹の瘤を押さえ、痛みをとる茸はない。さてどうしたらいいかと、それで、江戸から北のほうに茸を探しにまいったわけで」
「お侍姿の方が、子供の頃、わしの赤い茸をしげしげと見て、なんという茸かと尋ねられた、しかし、名前などわかんねえ、と言ったところ、この赤は痛みに良いかも知れぬとおっしゃいましたな」
「それは、その頃の薬師でござろう、その方はもう亡くなったが」
「赤い茸をずいぶん買っていただきました、しかし、その年だけで、それからはあの茸を見つけてはおりません」
「そうでありましたか、そのとき、薬師が子どもを連れておったのを覚えておいでではないですか」
「覚えております、そのお子は、奇麗な着物をめしておいででした、つんつるてんの汚い着物を着ていたわしは、羨ましく思ったものです」
「おお、その方が、今の私の殿でござる。その当時は、江戸におられ、しっかりした母君で、若にも旅をさせ、世間を学ばせねばと、薬師と指南役とともに、こちらの町にまいったのでござる」
「そうでしたか」
「八茸殿の赤い茸のおかげで相模の国の城主の病が癒えたのでござる」
「江戸のどこかのお殿様がご病になったと思っておりましたが、相模の殿様ですか」
「わが殿はさほど年が離れておらぬ八茸殿が働いているのを目にし、からだを動かしてみずから何かをせねばならぬと思うようにり、その時から、なんでも自分でするようになったとおっしゃっております」
八茸爺さんは何かこそばゆい思いをしておりました。
「あのときから、わしは茸採りになり、年を取り、いただいた金子をもとにこの八茸長屋を建てたのでございます、今では茸取長屋と呼ばれておりますが」
「そうでござったか」
「それで、茸はおもちになっておられるのでしょうか」
侍は包みの中から、紙にくるんだ乾いた茸を取り出した。
「殿が竹林で奇麗な竹を見つけ、若い頃の赤い茸を思い出し、えいやと竹を切ったところ、茸がころりと、いくつか転がりだしたものでござる」
「なるほど、私が見つけたときと同じようでございますが、色が、乾いているとしても、ちと橙色でございますな」
「やはりそうであるか、薬師が申すには、この茸もやはり病に効くそうだが、どうも八茸殿の赤い茸より効きは悪そうだ、そういうことで、ここに参ったわけでござる、赤い茸をもう一度探してはいただけまいか」
「どなたかが、悪くされましたかな」
「実は、殿のお子のお子様、お孫殿でござるが、病なのだ、やはり腹に瘤ができておる、わが町に赤い茸を採ってきた者には褒美を出すと触れをだした」
「そうでございますか、しかし、先ほど申しましたように、私もあれ以来、あの茸には出会っておりません」
「しかし、採れた場所を覚えておられるであろう、是非探していただきたい、わしも一緒に参ります」
「そこまでおっしゃるなら、探しましょう。どうでございましょうな、茸取長屋の者たちはみな茸採りが上手、手伝わせたいと思いますが」
「それは助かる、ぜひぜひ、礼は十分に致す所存でござる」
そういうことで、権四郎は八茸爺さんの食客になったのでございます。
八茸爺さんが、赤い茸の見つけ方を茸取長屋の者たちに説明します。
「赤い茸は、竹の中に生える茸じゃ」
「竹林には仙人帽が生えるけど、竹の中に生えるとは不思議だな」
仙人帽とは絹傘茸のことでございます。とても貴重な旨い茸と今でこそ知られておりますが、その当時は食べる者などおりません。ただ、奇麗な茸でございます。
鳥蔵は鳥撃ちから茸採りになった男、八茸爺さんの見つけた赤い茸を見たことがありません。その茸をぜひ見たいと常々思っておりました。
「八茸爺さま、おらもその茸探してえな」
「わしが見つけたときはまだ小童でな、驚いたよ、採れる竹林は一ヶ所で、その竹薮はその年で枯れてしまった、他の竹林の竹からは採れなんだな」
「孟宗竹かね、真竹かね」
植木職人の熊八が聞きます。
「真竹じゃった」
真竹というのは寿命があって、百何十年かで花が咲くと、みな枯れてしまうということでございます。
「だけど、またそこから竹林ができるというからな」
熊八が説明します。
「あったにしても、見つけるためには竹薮の竹をみんな切らなければならんだろ」
鳥蔵が聞きます。
「わしも始めはそうしたが、だんだん茸の入っている竹がわかるようになった」
「八茸爺さま、そりゃどうやるんじゃ」
「竹に耳を当てるとな、竹の中から何かが鼾(いびき)をかいているような音がするんじゃ」
「がーが、ごーごー、とかい」
「そんなに大きくないがな、猫がいびきをかくことがあるじゃろ、そんなもんじゃ」
「それで、家主さんが見つけたのはどこの竹林なんで」
「ああ、子どもでも行けるところだから、そんなに遠くない。おむすび山の麓じゃ」
おむすびのような形をした山で、確かに竹林があります。茸橋を渡って、突き当りのところです。
「あんな、近くにあったんだ」
「そうじゃよ、わしの家が昔あったところだ」
そういうことで、長屋のみなは、権四郎を囲んで、おむすび山にむかいました。八茸爺さんも一緒にまいります。
「このあたりはのんびりしていいのう」
「へえ、おむすび山より、もう少しいくと、茸湯という、日本一の湯治場があります、一度おためしください」
平助が自慢げに言います。
「ここは湯が良いと聞いておる、是非入りたい、信濃も湯が良いところであるぞ」
おむすび山の麓についた。
八茸爺さんが「確かこのあたりだが」と見渡すが、竹は生えておりません。
植木職人の熊八があたりを探します。
「ないねえ」
「やはりだめだったか」八茸爺さんもちょっと肩をおとします。
小さな蛇がちょろちょろと出てきます。
「きゃあ」誰かの悲鳴がきこえました。
「なんだい」、とみなが声のほうを見ますと、権四郎が後ろを向いて逃げようとしております。
「お侍さん、子どもの蛇じゃ」
熊八のかみさんのとめが尾っぽをつかんでぶら下げます。それを見た、ごついががたいで、いかつい顔、小さな目で怖そうなこの侍、権四郎の目がさらに点になっています。
「恐ろしいことをするものじゃ」
それを聞いて、長屋のみなが心の中で笑って、一生懸命声を出さぬように我慢を致しております。
とめは子蛇を山の中に投げ入れました。
熊八が、「あそこに、竹林が見えるが」と八茸爺さんに声をかけます。
おむすび山と隣の山の境目に竹が生えているのが見えます。
「あれは、胡桃山じゃ、山胡桃の木が多くてな、やっぱり子どものころ胡桃の実を拾いに行ったものよ、大事な食料じゃった、その頃竹は生えておらなんだ」
胡桃山の竹林に行きますと、若い真竹が生えております。出来たばかりの竹林です。
「まだあまり太くはないが、竹に耳をあてて、聞いてみるとするかい」
八茸爺さんは、中でも太い竹に耳をあてます。
「ふむ、おらんな」
長屋のみなも、同じように竹に耳を当てました。
すると、おかみさんたちが、そろって「おーお、子どもの寝息が聞こえる」といったのでございます。
「なになに」八茸爺さんは、とめさんの竹に耳を押し付けました。
「お、聞こえますぞ」
それを聞いて、権四郎も耳を当てます。おかみさんたちの竹に、亭主も耳をあててみます。
確かに、ぐーぐーではないが、すーすーと寝息に近いものが聞こえています。
「うむ、この竹の中に赤い茸がはいっているのであろうか」
権四郎は首を傾げます。
「おそらく、まだ、子どものようでございますな、あと一月もすると、採れるやも知れません」
「そんなに待てぬが、いかがしたものか」
「熊、竹を早く大きく出来ないかね」
さすがに植木職人の熊八も首を横に振ります。
「寝ている赤い茸の子供を取り出して、育てればよいかも知れぬな、茸は一晩で傘を開く」
まあ、長屋に帰れば、何か良い考えも出てこようと、とりあえず、赤い茸が入っているのかどうか、切ってみようということになり、一本の竹を切ります。
すると、丸っこい、小さい赤い茸の子供がコロコロと転がり出てまいりまして、スースーと寝息をたてております。
「おー、はいっていたな」
八茸爺さんは懐かしそうに赤い茸をみつめます。
「採っていこう、子供のままでも薬になるかも知れぬしな」
こうして、子供の赤い茸をたくさん集めたのでございます。
みなそろって八茸爺さんの家に戻りました。
「さて、どのように、この赤い茸を育てたらよいかな」
八茸爺さんは茸を採る方法はよく知っておりますが、茸を育てたことはありません。
熊八が「苔玉で羊歯育てるけど、茸も育つんじゃないかい」と申します。
「じゃが、竹の中でしか育たぬものを、それだけで大丈夫であろうか」
権四郎が言いますと、「苔玉を竹の中につめたらいいんじゃねえのか」と平助が言います。
鳥蔵がうなずいた「そうだな、茸の入っていた竹をもってくるのがいい」
ということで、みんなして、もう一度胡桃山にいき、赤い茸の子どもが出てきた竹をもって大家さんの家にもどってまいりました。
「苔はどうするね」
おかみさんの一人が聞きますと、「そりゃ、裏にいけばいくらでもある」と八茸爺さんが答えます。
男衆が竹を半分に割り、おかみさんたちが、苔をしきました。その中に、赤い茸の子供をいれ、残り半分の竹をかぶしたのでございます。
八茸爺さんの庭の日陰にならべ、塀に立てかけます。
赤い茸がすーすーと寝息をたてています。
「かわゆいものよ」
権四郎は可愛いものが好きなようです。黒犬と黒猫の梅が権四郎によってきます。好かれたようです。
「いつ茸が大きくなるかわかりません、その間、おくつろぎください」
八茸爺さんに言われた権四郎は「茸湯にいってみたい」と言います。
「少しばかり歩きますが、私もまいります」
みんな暇とみえ男も女もぞろぞろと、茸湯にまいります。
そこには何十人も入ることのできる野天湯があります。裸の付き合いです。
「ほほう、気持ちの良いところだ」
「へえ、茸を採った帰りにちょっと浴びて家に戻ります」
「この町では湯はここだけか」
「いえ、いろいろあります」
「それでは、茸が大きくなるまで、湯を楽しむこととしよう、しかし、茸取長屋のあたりに湯は出ぬのかな」
「裏山に出そうなところはありますが、それには、財が必要でございます」
「もし、赤い茸が育って、殿のお孫殿の病が癒えれば、それくらいは礼ができる」
それを聞いたみんなから「おー」とどよめきが起きました。
「ところで、なぜあの茸は鼾をかくのであろうのう、鼾茸でござるな」
「そりゃ、茸だって疲れることもあろうさね」
乱暴なことを言うのは、竹五郎でございます。
「確かにな」
それをまじめに聞くのが権四郎でございます。
「子どもはみんなすーすーよく寝るよ、寝る子は育つだ、茸だって同じだろうに、竹の中は寝心地がいいのさね」
子どもを持っているおかみさんたちが言います。混浴でございます。
「竹の香りがいいのでさあ、気持が良くなると、つい寝込んじまう」
とは植木職人の熊八。
確かに青竹の香りはすがすがしい。
「寝言は言わぬのか」
権四郎は、変にまじめでございます。
「さて、聞いたことはないが、茸はどんな寝言をいうのでしょうかな」
八茸爺さんも、まじめに受けてたつ。
「きっと、奇麗な女子に食われたいとでも思っておるのだろう」
権四郎はちょっと自虐的です。余計なことを言うと、おかみさんたちの目が、湯の中から権四郎を睨んでいます。
それから毎日、権四郎はいろいろな湯を楽しみ、赤い茸を見守っておりました。
竹の中かから聞こえる鼾が少しばかり大きくなってきました。並べて立て掛けてある子供の入った竹のところに、黒犬の梅と黒猫の梅がやってきて、やたらとかぎまわります。
「こやつらは何をしているのかな」
権四郎が梅たちの頭をなでていると、八茸爺さんが顔を出し、
「もしやもすると、茸が育っているのかもしれませんぞ」
そう言いながら一つの竹の蓋をちょっと開けてみます。
「お、立派になっておる」
赤い茸が苔玉の中で大きく成長して、傘も開いております。
「確かに、大きくなり申したな」
「これは確かに、わしが昔採った赤い茸にございます」
八茸爺さんが太鼓判を押した。
長屋の人たちも集まってまいります。
「ほー、これが、八茸爺さまの茸か、俺もこういう新しい茸をみつけたいものだな」
鳥蔵がしげしげと見つめます。
その後は、みんなして赤い茸を陰干しにいたしました。
「松本様、鼾の聞こえる若い竹を根っ子ごとお持ちになり、お国で植えてみたらいかがでしょう」
「それはよい考えでござる、とりあえず、二、三本若いものをいただいていきます」
「そうしてください、今回採れた茸は薬として数年分あると思われますが、来年、この時期にいらっしゃって、また、持っていかれると良いと思います」
こうして、権四郎は干した赤い茸を背負い、根のついた若い真竹を数本担いで、信濃に帰っていきました。
それから一年経った秋、権四郎が馬に乗り、家来や供の者を連れて茸取長屋にやってまいりました。
「権四郎様、久しぶりでございますな、赤い茸はいかがでしたか」
「八茸殿、あの茸はよく効きましてな、殿が大喜びでござる、それに、あの竹が城の裏山に根づきました、しかし竹林になるには時が必要じゃが、これからが楽しみでござる」
権四郎が連れてきた供の者たちを紹介しました。
「この者たちは信濃のすぐれた温泉掘りの名人でござる、この長屋の裏山で温泉を見つけ掘らせようと思っております」
それから、長屋の者たちも手伝い、ほどなく湯が良く出る場所を見つけました。いつでも入れる野天湯ができあがったのでございます。湧き出る湯はからだに良い薬湯でございました。
その野天湯は八茸湯と呼ばれ、長屋の人たちばかりではなく、町の人たちの憩いの場ともなりました。雪が降る寒い冬には猿たちも入りに来るようになったのです。
権四郎が信濃で作った草片の図譜を八茸爺さんに送ってまいりました。八茸爺さんの赤い茸は「八茸(はちたけ)」と名付けられ。腹のできものに良く効く、竹の中に生える鼾をかく世にも希なる茸なりと書かれています。八茸(やたけ)翁がみいだしたる茸ゆえ、八茸と呼ぶことにしたと名前の由来も書かれておりました。
八茸
私家版第五茸小説集「お茸さま、2019、188p、一粒書房」所収
版画:著者


