夏がおわらない子ども
むねざわめく砂浜で

夏の砂浜を男の子がひとり、歩いていた。
砂浜と、空と海とが、ただどこまでも広がっている。
かなたには雲がとどこおって、とりでのようだった。空は、とても高くて、とても遠くて、辿り着けそうもなかった。だれかが呼んでくれる声もしない。
あたりを見渡してみても、砂浜に人のすがたはなかった。何も、動くものはない。海の上には影のひとつさえない。打ち寄せる波にも、男の子をさらってくれる気はないらしかった。
男の子が砂浜に腰かけると、沖合いの海と空のあいまに、ぽっかりと四角い窓が口をあけた。窓の向こうはまっ黒だった。やがてその窓は映画館のスクリーンくらいのおおきさになって、こことは違う別の砂浜が映った。
たくさんの人達が動いていた。パラソルがあった。ビーチサンダルがあった。ジュースやアイスキャンディーがあった。かにがいた。スイカがわれていた。そこにいる人は皆、楽しそうに笑っていた。
皆、知らない顔ばかりだった。
かいのくに

かいのなかのくににいた。
すこし、はきそうになった。
はきそうになりながら、なみだをながしてだれかにいのっていた。
はきそうになったのは、しおのにおいがきつすぎたせいだとおとこのこはおもっただろう。
いのるべきはなんのためか、いのるあいてはだれか、かいのなかのくうきはみなみへながれて。かいのみなみのさいはては、りゅうのすみかだった。
いのるべきはおれぢゃない。いのるはひがし。ひがしだ。
ひがしにはかいばしらがごうもんにかけられたあとがあった。もうだれもいなかった。
いのるはにし。にしだ。
にしで、たいようがふたつにわかれるのをみた。ひとつは、とちゅうでしんでしまった。いきのこったほうは、いのるはきた。きただといった。
きたには、さっきいきのこったほうのたいようがいっしょにながれてきて、そらにのぼると、いのるはみなみ。みなみだといった。
かいのなかにでぐちはなく、あんしんしておとこのこはすこし、はいた。
ゆめの女の子

ゆめでずっといっしょだった女の子が、いつのまにかいなくなってしまったんだ……。あの子、はねがはえていたのに、とばないで、ずっとぼくといっしょに、あるいてくれていたの……。だのに、もうどこにもいない。むかし、いっしょにいよう、ずっといっしょにいようって言った仔猫が、おおきなすいそうのなかに落ちて、ふたがしまってひらかなくなったことがあった。ぼくはいくらすいそうをたたいても、たたいても、どうにもならない。仔猫はすいそうのいちばんしたにしずんで、うごかなくなった。赤や白や黄色のきんぎょが、しらん顔して泳いでいたっけ。きれいだった。ぼくはじっとじっとうごかずにいて、すいそうをながめていて、きんぎょはぼんやりと夜にうかぶあかりのようだったな。あのときからぼくはゆめをさまよっているような気がする。仔猫、たしかおすだったかめすだったか。ぼくにはわからない。ただいつしか、ゆめでぼくをはげましてくれる女の子がいるようになった。まわりには、いくつもあかりがともって、めまぐるしく色がかわってぼくをのみこもうとしたこともあった。女の子はいちどぼくにかぎをくれたことがあったけど、ぼくはその使いかたがおもいあたらないでいた。かぎのさきっぽはナイフの切っ先のようにするどくて、ぼくはそれで女の子を傷つけるべきかどうかまよった。ほんとうに使いかたがわからなかったのだもの。ゆめのなかはくらいけど、たしかにうっすらぴんくいろをしていた。ぼくはぴんくがしろくかげっている一点に、かぎをすててしまった。女の子はやさしくほほえんでいた。おおきなきんぎょの死骸がいっぴき、そらをながれていった。あめだまのにおいがした。それから、ゆめの女の子がいなくなった。
カシランの城

どこまでも続く、夏雲のいちばん深みに、カシランの城がある。
カシランの城はゼンマイ仕掛けで、とらわれた子ども達が永遠にそのねじをまきつづけているのだという。
子ども達は、うさぎやねこやいたちのすがたをしているけど、みんなもとは人間の子どもだった。
カシランはなぜか、うさぎやねこやいたちになるべき子どもを知っていて、ある時が来ると、雲の中から長い機械の腕をのばして、その子をさらっていってしまう。
カシランの城につくと、子どもはもうちいさなどうぶつにすがたを変えていて、ものがいっさいしゃべれなくなっている。
カシランは大きなくまほどもあるからだで、時計のかたちをしている。いつも平気で三時の顔をしている。三本のふとい足もある。
カシランはじぶんの子ども達を〝失われた子ども達〟と呼ぶ。
カシランは子どもらに、ねじをまくよろこびをおしえるのだ。
子ども達はねじをまきつづける――永遠の中の一瞬に、はみだす機会を見つけて、カシランの腕をのがれるまで。
その機会をのがせば、また果てることない時空のねじをまきつづけるのだ。
ものもしゃべれない、ちいさきどうぶつのかたちで。
〝失われた子ども達〟のままで。
夏のおわりに
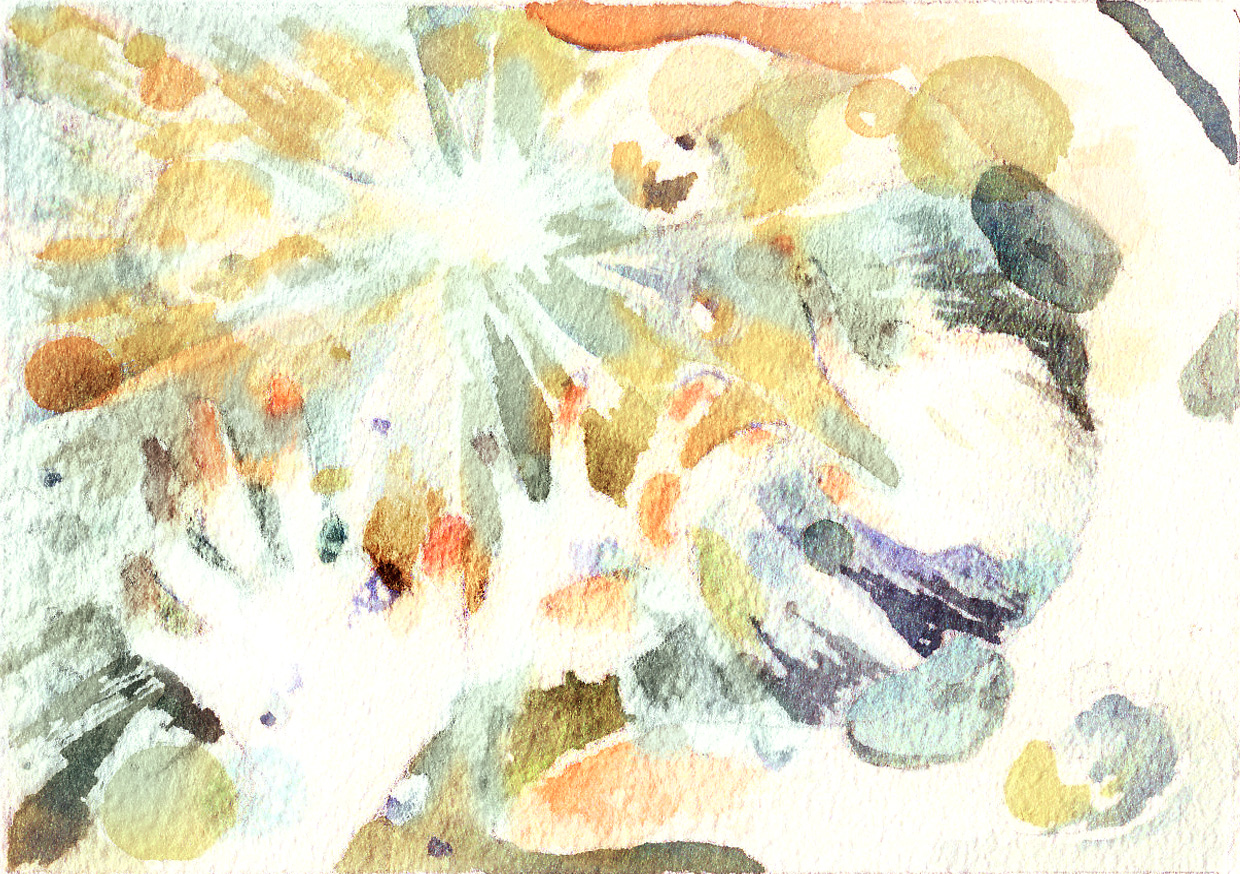
「ずっとなくしていたものはこれだったのか」
「わあ……ほんとうにきれい。まるで……」
「まるで……なに?」
「ん……ん。わすれてしまった。なにか、とてもきれいなものがあった。それをわすれてしまった」
「なくしてしまったんだ。思い出して、すぐに思い出して。とりかえしのつかないことになるよ」
「もう、いけない……あんなに……とおくへいってしまった……」
「なくしてしまったんだ」
「……」
「……かなしいのかい」
「ううん。またこれであたらしい旅がはじめられる」
「……うん。そうだね。そう思うと……なんとなくうれしい」
「わたしも……うれしい」
「……」
「……」
「……このいまぼくが手にもっているものはなに? がらくたみたいだけど」
「わからない。でも、もういらないものの気がするわ」
「ぼくらは旅にでるんだ。旅のはじまりにはなにもいらない。旅のおわりにきみがなくしたものをみつけるだろう」
「すてていこう。いらなくなったものは、みんな、すてて……」
ぼくをもう探さないで
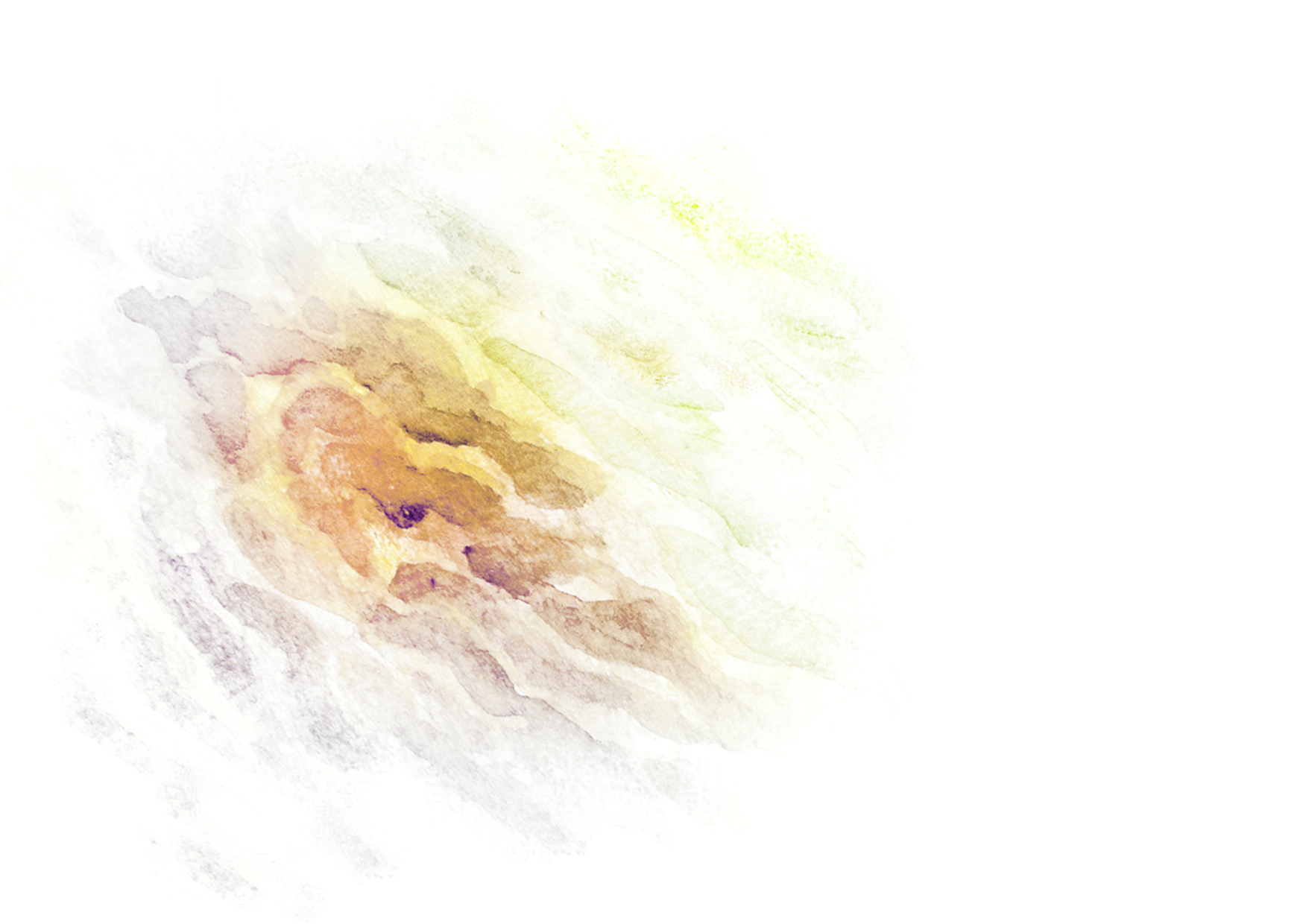
夕ぐれの砂浜に、ひとつのちっちゃな子どもの骨があって、一度ずがいこつのすぐ近くにまで波が寄せた。
(夏、おわらせてもいいかい……)
子どもの骨は、かちゃかちゃ音を立てて、まだもう少しあそびたいの。でも、もう、行かなくちゃ……
もう一度波が寄せると、それはやさしく、でも一気に、骨をつつみこんで、去ったあとにはもう何もなかった。
ただ、骨があったあとの砂地にしわくちゃな模様が残っていて、それは遠い子どもの想い出のようでも、あるいはその子が実際どこかに負っていた傷痕のようでもあった。
まもなく夜が来ると、くりかえしていた波は皆、海の向こうへ行ったっきりもう戻ってこなくなった。
海は死んだ。
海水はすこしずつ、白く細かい粒になって、すべてくずれ去っていった。
魚も貝もすでにいなかった。
この海は命を抱くこととは無縁だったのだ。
やがて海底も、その下の砂も粒も、何もかもがくずれて消えていった。
何も、聴こえない。
世界は、いちばんはじめに戻された。
……戻された、はずだった。
だけど、ひとつのちいさくてしわくちゃな模様だけが、色も音も何もかもなくなった世界に、どうしても消えることができずに、焼きついていた。それは……それは、遠い子どもの――
――そう言えばもう、夏はおわったんだった」
夏がおわらない子ども


