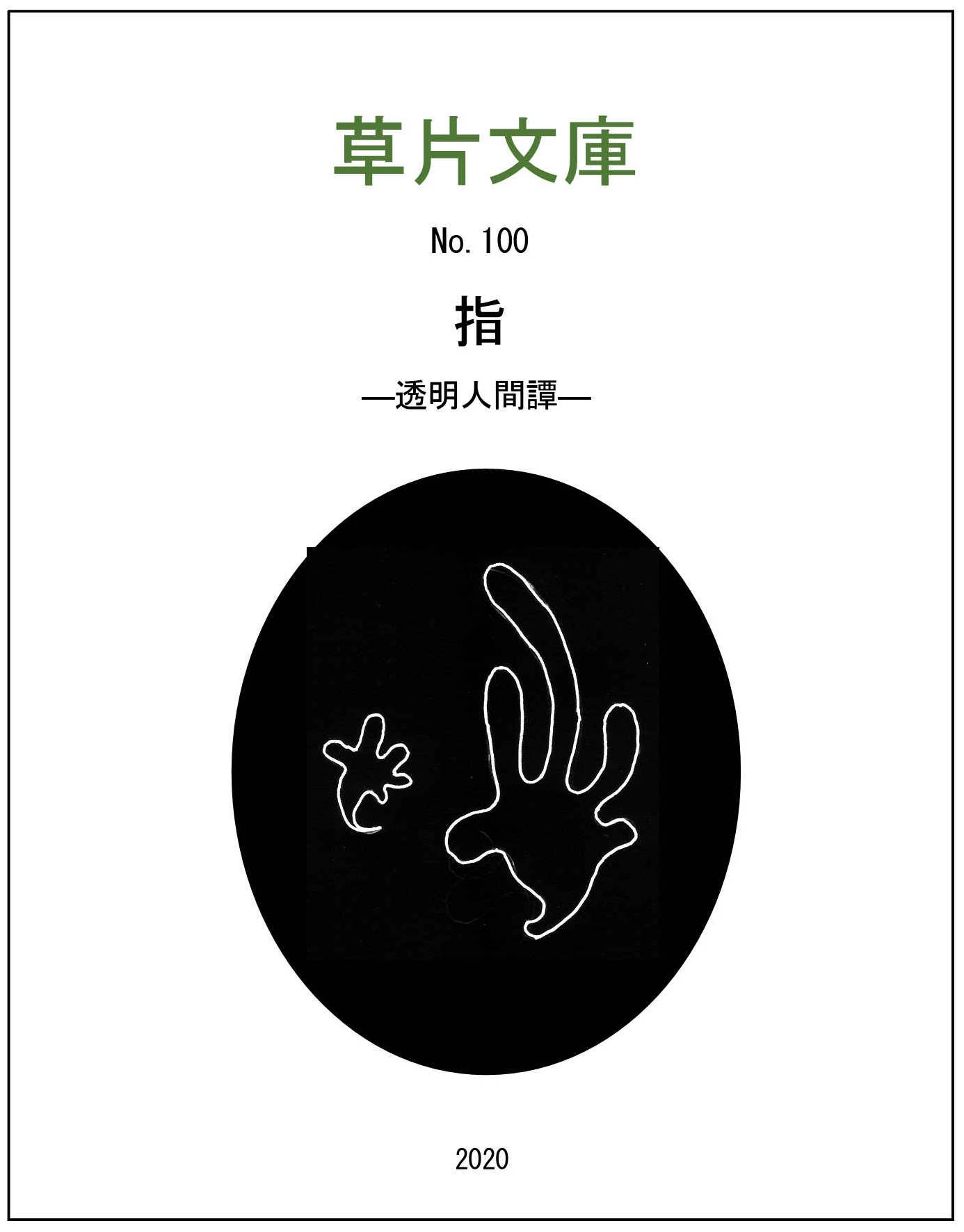
指 - 透明人間譚
水色視衣(みしきしい)が農協に勤めて八年になる。中堅どころの経理主任だ。都会の大学をそれなりの成績で卒業し、一流の商社に内定をもらっていた。しかし彼女はそれを袖にして、山形の田舎の農協に勤めた。農協としては有能な人間が勤めてくれたと大いに喜んだ。予想にたがわず、彼女は有能な経理士となった。寡黙でよく気が回った。誰の目も視衣はこの地の土地持ちの息子と結婚をして、仕事場から去って行くものと見ていた。
彼女には不思議な魅力があった。遠慮っぽく黒目がちな目で見られた男は一瞬ドキッとする。色の白いゆったりした頬に手を触れたくなるに違いない。絹のような肌、張りつめたふっくらとしていてそれで長い足が、ちょっと短めのタイトスカートから伸びているのを目にすれば、どんな男でも手を伸ばし、ちょっとでよいから触れたいと思うに違いない。
ところが、後から農協に勤めた女の子がどんどん結婚をして退職していくなかで、彼女は毎日毎日8時には自分の机の前に座り、5時丁度に帰り支度を始める日々を淡々とおくっていた。
あの名の知れた大学の四年のとき、彼女が大手商社の内定を蹴った理由は簡単だった。大学時代つきあっていた男子学生が、同じ会社の内定をもらった。ふつうなら喜ぶだろう。ところが内定の通知が届く一週間前、その男が彼女の知っている女子学生と腕を組んで、ホテル街に行くのを目撃してしまった。ただそれだけならよかった。偶然、自分の歩いている近くで急ブレーキをかけた車があった。年寄りが歩道から車道に出てきたためだ。その音は腕を組んでホテルに向かう彼らを立ち止まらせ、振り返らせた。彼らの目が彼女を見た。ほんの少し驚いたような顔を見せたが、その後あわてる様子もなく、笑顔すらみせて、腕を組んだまま行ってしまった。
その時、彼女は自分が悪いことをしたわけでもないのに、見られたくないと思った。穴があったら飛び込みたい、隠れたいと普通の人なら思う。彼女は違った。空気になりたい、言うなれば透明になりたいと思い、立ちすくんでしまったのだ。
悪いことには、彼と腕を組んでいた女の子は、視衣と同じ会社の内定をもらっていた。すなわち視衣とも彼とも同じ会社である。それが山形の自分の生まれた田舎に帰った理由である。
農協に勤める事になったが、彼女は実家には住まなかった。親はまだ若い。下の妹は高校生である。農協から歩けば二十五分ほどのところなのだが、わざわざバスで五分ほど離れた海岸沿いのアパートの一室を借りた。一人になりたかったのである。
アパートからほんの少し歩けば海岸にでることができる。日本海の海は太平洋と違って寒々しい。砂浜を歩いても、友達と旅行した沖縄の海辺のように色とりどりの貝殻が落ちているわけではない。黒っぽい石が砂に埋まっていたり、何の変哲もない貝の欠片が落ちていたりするだけである。それでも海に沈む夕日はどこにも負けないほどきれいだ。晴れた日、音もなくただ輝いて、海の水平線につぶれて溶けこんでいく太陽を終わりまで見届けるのが好きだった。
三十を過ぎた視衣が、いつものように夕飯の材料を買って帰り、下拵えをして、海岸に散歩にでた時である。うす曇の天気で、沈む夕日は見栄えがしない。それでも赤く輝く雲の間から海に向かって刺さるように落ちるだいだい色の光の筋は、ゆっくりと変化してきれいだ。
波打ち際を歩いていると、足元の砂の中から橙色の光線が視衣の目を射った。何だとかがんでみると、波に洗われたガラスのようだ。涙の雫のような形をして、すべすべになったガラスが陽の光を反射している。
拾い上げて空にかざしてみる。薄い雲の中を沈んでいく太陽の光がもっと橙色に輝く。太陽のいない方にガラスを向けてみた。ただ透明なガラスがそこにあった。そのときふっと、あのときの感覚が頭の中をよぎった。見えなくなりたい、透明になりたい。もう忘れたと思っていたことが思い出されてしまった。あの男と女は結婚したのだろうか。いやもういい。視衣は涙の形のガラスをズボンのポケットに入れアパートにもどった。
食事の用意をしてテレビをつける。キッチンで食べながらニュースを見る。いつものことである。今日は民放のニュースにした。余計なコマーシャルの入らないNHKを見ることが多いが、たまには違った民放局も見る。頭を和らげるためだが、民放のもったいぶった声優の説明には閉口する。
ふっと箸をとめた。内定をもらった会社の宣伝がはじまった。今日は何日だっけ。カレンダーを見る。9月9日。あっと視衣はまた驚いた。あの同期生の男と初めてホテルに行った日だ。十年近くになるのにまだ思い出す。
「俺、あの会社に入るつもりだ」
「それじゃ、あたしもそうしようかなあ」
終わった後そんな話をした。視衣にとって初めての男でもあった。箸をおくと、ポケットに入れたガラスを取り出した。ほんとね、涙の雫ね、そう言いながら、左手の親指と人差し指でガラスをつまむと、キッチンの電灯を見た。昼光色のLEDが小さな太陽のように輝いた。きれいだ。
ふっと気持ちがさっぱりした。頭の中が透明になった。また箸を手にして煮物の中の椎茸を口に入れた。おいしい、さっきは感じなかった茸の味が口に広がった。
ニュースでは新しいウイルスが中国で発生したことを伝えている。やがて世界に広がるかもしれない暗い話だ。それにもかかわらず、今日みたいに夕食をおいしく感じたことがなかった。浜辺で拾った涙の雫。宝物になりそうだ。
次の朝。仕事に行く用意をして、キッチンのテーブルに置いたままだった涙の雫を、左の人差し指と親指で挟んでキッチンの窓を見た。窓から透き通ったように赤い太陽の光が視衣の目にとどいた。体がすっと軽くなった。彼女はガラスをテーブルにおいた。少しばかりにっこりして仕事に出かけた。
その日は一日、気分が良く、仲間との会話も楽しく仕事がはかどった。
家に戻り、そのままキッチンにいくと、テーブルの上の涙の雫に気がついた。バッグをテーブルに放り投げ、左指でガラスを持つと居間兼寝室に行き、ベッドに腰掛けた。ベッド脇の窓を開け空を見た。まだ陽の落ちる前である。晴れている空がガラスを透いて青く目に輝いた。仕事の疲れが肩から霧となって消えていく。
「さ、おいしいもの作ろう」
視衣はキッチンで夕食を作り始めた。
「このガラスをしまう場所を決めなくちゃ」
独り言を言いながらピーマンと豚肉を炒めた。机の引き出しに入れておくか、いや宝石箱を買おう、いや違うな。
台所の棚を開け、炒めたものを載せる皿を取りだした。
棚かあ、家には神棚があったな。父親がよく灯明をつけて拝んでいた。
視衣は宝石箱ではなく小さな机の上に乗る神棚を買おうと思った。
朝、夕方帰ってきた時、寝る時、視衣は涙の雫のガラスを通して、窓から空を見た。それが日課になった。それからというものなぜかすべてが順調だった。
日曜日の朝、食事をしたあとに、テーブルに腰掛け、いつものように開けた窓からガラスを目にかざし、少し寒い空の透明な青を吸い込んだ。さー行こう、立ち上がった。すっきりした気分で町に出かけた。神棚を買うつもりだ。
バスを降り、和菓子屋でいつもの栗最中を買って実家に寄った。
「元気」
玄関からあがると、自宅の飼い猫の虎がニャアと擦り寄ってきた。神棚に眼鏡をおいて、お辞儀をしていた父親が、「あ、視衣か、元気だけんど、こんとこ眼が疲れての、神さんにメガネを眼にうまくあうようにしてくれと頼んどった」
そう言って眼鏡を神棚からとってかけた。
「神様って、そんなこともやってくれるの」
眼鏡屋でレンズを変えた方がいいんじゃない、と思ったが口には出さなかった。
「そりゃ何でもかなえてくれるさ、長く使ったものは疲れる、そういったものを元気にしてくれるんさ」
それを聞いて視衣はあのガラスも疲れているだろうなと思った。毎日私に覗かれている。やっぱり神棚を買おう。
「お母ちゃん元気」
「ああ、今買いもん行ってる」
「用事じゃないの、ちょっと町に来たから、これ栗最中」
「いつも悪いな、茶入れようか」
「うんいい、神棚どこで売ってるかな、デパートにあるかな」
「何だ、神棚買うんか、信心深くなったな、婿さん探してもらうんか」
「やだ、そんなんじゃないよ」
「神社の脇の道をちょっと行くと、花屋があるだろう、あそこのじいさん、元は宮大工だ、娘が花屋やってるが、神棚もおいてある、作ってもくれるんだ」
「高いんでしょ」
「しんねえな」
「行ってみる、帰りにまた寄るわ」
「ああ、あいつ戻ってるよ」
母ちゃんのことだ。
視衣は花屋に行った。確かに神棚が三つほどおいてある。視衣が神棚を見ていたら、女主人が「神棚を探しているんけ」と声をかけてきた。
「あ、ええ、小さいのがあったらと思って」
「ここにあるのは小さい方なんだけどね」
と言っているところに、老人が奥から出てきた。
「なにするだね」
「壁には付けれんで、机の上にちょっと載せるくらいのがあったらと思って」
「若けぇ人なのにえれえね、どのくらいんかね」
視衣は両手で大きさを示した。
「おもちゃのような奴だな、造ってやんべえか」
いくらかかかるかわからない視衣は返事に困った。
じいさんは笑いながら「三千円くらいだべ」と補足した。
「あ、それじゃ、お願いします」
あわてて財布からお金を出そうとすると、「出来てからでええ、三日もあればできる」と言った。
「それじゃ、次の日曜日にきます、水色といいます」
「金具は金色がいいかね、銀色にしたいという人もいるが、木は杉だよ」
と聞かれた。
涙の雫はどちらを喜ぶだろう、きっと銀だ。
「銀でお願いします」
「本物でかい」
どのような意味だろう。女主人が口を出した。
「純銀で作ると、ちょっと高くなります」
「といってもたいしたことはねえよ、それもわしが作るから、銀を使えば五千円だ」
視衣は喜んで、本当の銀でお願いをして実家もどった。
高さが二十センチほどのミニチュアの神棚は格子の扉がついたしゃれたものだった。開くと中は涙の雫を入れておくのに丁度いい広さだ。気に入ったハンカチを持ち出すと、中に敷きガラスをおいた。
こうして、そうしたくなったときに、神棚を拝み、ガラスをとりだし、左手の指でつまんで空を見た。雨の日でもそのガラスを通すと明るい空が見えた。
神棚を作って二ヶ月経った。年の瀬がせまっている。
その日、奇妙なことが起きた。
朝、仕事にでかける前にいつものように神棚からガラスを取りだし、ふと、指に挟んだガラスを通して神棚の中が見えた。丸くなにか光った。なんだと思い、ガラスから目をはなした。神棚の中を見た。光はなかったが、自分の左手のガラスを見て、おどろいた。
。涙の雫が宙に浮いている。
自分の人差し指と親指が見えない。指を動かすと、空中をガラスだけが動いた。ガラスを目にかざした。宙に浮いたガラスが目の前にある。指はある、動かそうとすると、ガラスが動く。
ガラスが宙に浮いているのではない。左手の人差し指と親指が見えなくなっている。そう気づくのに少しばかり時間がかかった。
彼女はガラスを神棚に戻した。二本の指がゆっくりと現れてきて、もとにもどった。
なにが起きたのか。狐につままれた気持ちで扉を閉めた。そのまま農協にでかけた。
ともかく仕事は順調で、体の調子もよく、おまけに、自分より一つ年下の男が私に近づいている。大きな農家の長男で、最近銀行勤めから農協に転職してきた。その家は広い田畑をもち、米を中心として大きく事業を展開している。まだ農協の中で話をするだけだが、食事でもと誘われている。そのうちと答えている。実直な男である。
12月29日、農協は4日まで仕事が休みである。視衣は休みになって、一日に三度はガラスを見て神棚に灯明をあげるようになっていた。父親の血が流れているのかと自分で思うことがある。
もうなれたことだが、ガラスを持つと必ず左手の人差し指と親指が透明になる。ガラスが宙に浮く。指が見えなくなるのである。ガラスを神棚に戻すと元に戻る。
いつものことで、元日に実家に泊まりに行くが、暮れは、自分の好きなことをする。
今年は何度か一つ年下の男と食事をしたり映画を見たりした。ゆったりとした包容力のある男だと好ましく思うようになっていた。
大晦日は一人で過ごす、おそらく来年は新しい家族に囲まれることになりそうだ。
除夜の鐘の音がテレビから聞こえてくる。
湯船に浸かって視衣は自分の身体をゆっくりと眺めた。三十一歳、身体は二十二の頃と比べれば少し太った感はあるが、それでも白い皮膚は艶があり、手足はしまってしっとりとしている。乳房はむしろ張りがでて、自分で触れてもゴム鞠のようで好ましい。
左手の人差し指と親指で右の乳首を摘まんだ。大学を出てからは男っ気がなかったが、これからは普通の女になれる。指で乳首を摘まんだときである。ふと目をやると乳首がない。指は確かに乳首を摘まんでいる。
すると、見る間に乳房が消え、身体がだんだん消えていく。湯船の中に伸ばしていた足が消えた。とうとう自分の身体がなくなってしまった。いや見えなくなった、顔はあるのだろうか、右手を顔に触れるとある。湯船の中を見ると、透き通った自分の体の形をしている物が横座りになっている。
視衣は乳首から指をはなし、湯船からあがると、脱衣場の鏡の前に立った。自分がいるのはわかっているのに、鏡にはなにも映っていない。
透明人間、昔読んだSF小説を思い出した。コナンドイルでなく、そうウエルズだ。
見ている間に自分が現れてきた。乳首が宙に浮き乳房が現れ、顔が、手が現れ、へそが出てくると黒々とした股間が現れ、白い足が指先まで現れた。
あわててバスタオルをとって体を拭いた。
なんということか。指で乳首を摘まんだとたん起きたことだ。右手の人差し指と親指で乳首をつまんでみた。なにも起きない。当たり前である。目の具合、いや、頭の具合がおかしくなったのだろうか。
左手で乳首を摘まんだ。
「あ」声がでてしまった。
鏡の中で、乳首から自分が消えていくのが見えた。あわてて手を離した。身体が現れた。今度は左手で鼻の頭を摘まんでみた。顔から透明になってくる。指をはなした。元に戻る。今度は左手で右手をつかんだ。視衣は透明になった。長く右手をつかんだままにしておいてはなすと、身体が現れてくるまで時間がかかった。左手の人差し指だけで触ってもかわらないし、親指だけでも変わらない、左手の二つの指で触ると透明になる。
神棚のガラスに乗り移った神の仕業なのだろうか。
湯冷めしそうだ。もう一度湯船に入った。左手の人差し指と親指、ここに何かが宿ってしまった。湯上がりタオルを持ったり、湯船にさわってもどうにもならない。自分を触ると透明になる。
視衣は風呂から上がると、ビールをあけた。たくさん飲めないが、少しなら楽しむことができる。この指はなにを意味するのだろう。もし、あのガラスの雫がそうしたなら、悪いことではないのかもしれない。
そう思いながらテレビを消した。
いい天気の元旦だ、両親と妹に買っておいた土産を持って朝食を食べずに部屋を出た。父親には有名な日本酒、母親にはしゃれたショール、妹には化粧道具のセットとお年玉だ。妹は大学受験である。自分とちがって福祉のほうにすすみたいということだった。視衣はどうせなら看護師の大学がいいよと言っている。
家につくと雑煮の用意をしていた。いつも元旦の朝は雑煮だ。
「おめでとうございます、はいおみやげ」
父親はまた神棚に何かを載せてお拝んでいる。
「なにやってんの」
「爪切りが切れなくなったんで、おがんでんさ」
「買い換えればいいじゃない」
「前もこうやったら切れるようになった」
自分で神様を馬鹿にしているようなことを言ったのだが、透明になったことを思い出した。
「神様もよくやってくれるわね」
「ありがたいことだよ」
そう言いながら、日本酒の包みを開けた。
「いい酒だな、早速飲むか」
父親はうれしそうだ。
「はい母ちゃん」
薄紫色のショールは、いつも青系統の洋服を好む母にはよくあうはずだ。
「いいわねえ、それより、お前、前より顔艶がよくなったねえ、いいことあるんじゃないかい」
母親はめざとい。
「ちょっとね」
妹には、「これ」といってお金と化粧セットを渡すと、大喜びで自分の部屋にとんでいった。紅花の口紅も一緒に入れておいたのだ。
自分の荷物をもって、二階の客間にあがった。ここで一晩やっかいになる。猫の虎もいっしょについてきた。
座って「とら」と呼ぶと擦りついてくる。左手で長い尾っぽをつかむと、振り向いて丸い目で自分を見た。
そのとき、トラの尾っぽが透明になり、すぐに身体ごと見えなくなった。透明猫が座っている視衣に擦りついてくる。
こりゃいけないと、手を離すと、尾っぽからだんだんと猫のからだが現れてきた。
左手の人差し指と親指で生き物を触ってはいけないようだ。
人差し指にハンカチを巻いて、トラの尾っぽをつまんだ。透明にならない。普段は人差し指か親指にバンドエイドか包帯でも巻いておかないと、つい誰かにふれてしまうと大変なことになりそうだ。
その夜、実家の桧の風呂に浸かりながら、もう一度乳首を摘まんでみた。風呂桶にしゃがんだまま自分の身体が形だけ残して湯の中に消えてしまった。左手の指の力はいつまであるのだろうか。結婚したら旦那に触れるときに気をつけなきゃ。
その年の正月元旦にはそんなことがあった。
自分が透明になれる、それでなにができるのだろう。ずーっと左手で触れていれば誰にも見られなくなる。左手で耳をつかんで、食事をしてみた。食べ物が食道から胃に落ちていくのが見えると思ったのだ。ところが飲み込んだ食べ物が身体に入っていくのは見えなかった。鏡をおいて、耳をつまんだまま大根の煮たのを口にいれた。大根は途端に消えた。よく考えるとそうでなくてはおかしい、うんちがたまっていたら見えるかというと、透明になった自分を見ても見えない。口にはいったものは見えなくなるわけだ。
1月はあっという間にすぎ、2月になると、視衣は求婚された。これも毎日、神棚のガラスで空を見ているおかげかと、机の上の神棚に向かって手を合わせた。そのころになると、左手の二つの指で人や生き物に触ることは無意識のうちに避けることができるようになった。
結婚式は妹の受験があることから、来年の4月過ぎにしたいことを伝えると、快く承諾してくれ、結納は5月の連休にする事にした。
両親は大喜びである。
視衣は彼と食事をしたり、映画を見に行ったり楽しく過ごした。会えば会うほどいい人であることがわかってきて幸運に感謝をした。
ある日、夕日を見に涙の雫を持って、砂浜の一部の岩が突き出ているところに行った。そこだけ岩礁になっていて、潮だまりができている。カニが岩の上をちょろちょろしている。視衣は左手でカニを捕まえた。カニはすぐ透明になった。それを水の中に放すと、はじめは形だけだが、だんだんとカニの姿が現れてきて面白い。
視衣は潮だまりの水の中に手を入れた。岩についている緑っぽいイソギンチャクを左手の二本の指で触れた。イソギンチャクは透明になり、離すと次第に姿が現れた。
ちょっと大きいカニが水からあがってきた。摘まみ上げると、だんだんに透明になってきたのだが、大きなはさみを振り上げてあばれたので、右手もカニに添えた。カニは手の中で透明になって水の中に落ちた。
ところが、カニはなかなか姿を現さなかった。どこかに逃げたのだろうか。
もしかするとと思い、水の中にいた小さな赤いカニを左手でつまみあげ、透明になったカニを右手で同時につつんだ。両手の指でカニを逃がさないようにしていると、手の中のカニはごそごそと動いていたが、いつまでたっても透明のままだった。
カニを水の中に放すとどこかにいってしまった。いつかは元に戻るのだろうか。
自分の手がちょっと怖くなった。自分を両手でつかむと永久に透明になってしまうかもしれない。とても怖いことである。
しかし、水の中を見ていると、赤いカニが歩いているのが見えた。時間はかかったが、元に戻ったのだ。よかった。
もう一度、白っぽいカニを捕まえて、同じように左手の人差し指と親指で摘まんで、さらに右手の指で摘まんだ。それで今度は、「ずーっと透明でいなさい」と言ってみた。冗談のつもりである。
透明になったカニを小さな潮だまりに離した。カニはいつまでも現われなかった。
夕日がもう沈もうとしている。涙の雫をポケットから取り出して、夕日を見た。さわやかな橙色の光が視衣の目を柔らかくつつんだ。きれいだ。
そのまま、潮だまりの中を見た。透明になった白いカニが歩いているのが見えた。やっぱり戻ったんだ、と思って直接潮だまりを見た。カニはいない。ガラスで見た。カニが見えた。カニは透明のままなのだ。ずーっと透明になれといったからだろうか。
それに、このガラスは透明になった生き物を見ることができる。
今日はいろいろなことがわかった。私の指は気をつけなければ、視衣はそう思った。
5月の連休最初の日、結納も無事終わり、結婚相手は家族旅行にでかけた。彼には妹が一人いて、すでに嫁に行っているが、一年に一度、両親と彼と、妹の家族で二泊ほどの旅行に行くことにしているという。来年は私も加わることになる。
連休をどのように過ごそうか。妹は看護大学に受かり、連休といえども忙しそうだ。大学のある東京から帰ってこない。両親は家でのんびりしている方が好きなタイプだ。連休中一度くらい泊りに行ってやろう。
最後の一人の連休である。思い出に一泊の一人旅でもしようと視衣は計画をたてた。急なことで空いているかどうか分からないが、直接熱海のホテルに電話をしたら、うまく予約できた。学生の頃は18切符で気ままな旅をしたが、卒業してからは農協一筋、仲間と一泊の温泉親睦旅行に行くだけの生活をしていた。東京の大学に行っているときにも、箱根や熱海など東京近郊の温泉のある宿など泊ったことがない。東北の温泉とはまた違った雰囲気なのだろう。そう思って熱海の海岸沿いの一泊二食で五万もするホテルを予約した。初めての贅沢である。
連休も終りに近いその日、親にも黙って熱海に向かった。もちろん、ガラスの雫もポケットに忍ばした。熱海の海を涙の雫ごしに見るとまた新たな力をもらえそうに思えたからだ。
熱海に着き、迎えのマイクロバスに乗るとホテルへはいった。ホテルは西洋風な建物で、海が見渡せるいい場所に建っていた。錦ヶ浦に近いところである。気を使ってくれる気持ちのよい待遇で、視衣はいいところを選んだとすぐに気にいった。シングルの部屋といってもベッドはセミダブルである。もちろん、掛け流しの内風呂と十階には露天風呂もあった。一人旅の女性も多いようだ。
熱海の海岸は尾崎紅葉の有名な貫一、お宮が歩いたところだ。来年の今月今夜の、この月を僕の涙で曇らせる、といった女々しいせりふじゃなかったっけ。どこがいいんだろう。別れの松はどこにあるのだろう。なにも調べてこなかったのでよくわからないが、ホテルの近くではなさそうだ。明日帰る前に寄ろう。
夕食の時間まではまだ間がある。
ホテルから出て海沿いの道にでると錦ヶ浦だ。高い崖の岩場で、下をのぞくと波が打ち砕かれる様子が見える。海際まで降りることができるようになっており、段々をおりていくと、途中ベンチが置いてある広場があり木戸があった。関係者以外通ることを禁ずと書いてある。木戸から下を覗くと、小さな入り江の水際に建つ立派なホテルに行く道だった。木戸とは違う方向に海際のほうに降りていける道があるが、だいぶ降りないと下までいけないようだ。今日はそこまででやめることにした。下をのぞくだけで迫力がある。自殺の名所だったということに頷ける荒々しい場所だ。
視衣はベンチに腰掛けて、ガラスを通して熱海の海を見ていた。ホテルのある湾をみると、波のはねる白い泡が目にしみる。気持がいい。ガラスの中にふわっと、波が泡のようになって浮き出て、人の形になった。今までここで死んだ人の魂のようだ。
食事は七時からだ。まだ明るい。
ベンチから立ち上がったとき、「視衣ちゃんじゃないか」と男の声がした。
ふっと振り向くと、白いポロシャツを着て紺のコットンズボンをはいた男がにこにこと立っていた。
視衣はどきっとした。あの男だ。
「久ぶりだねえ、元気そうだ、きれいになった」
ずいぶんおべんちゃらを言うようになった。もともとそういう性格だったんだ。
「おどろいたわね、お元気そう、今もあの会社」
「ああ、視衣ちゃんはどうしたの、当然同じ会社にはいると思ってたのに」
どうして当然なんだろう。自信があったのね。
「私は田舎で就職したの」
「ご両親に言われたんだ」
なに言ってるんだろう。わかってるのに。
「ご旅行なの」
「そう、家族でね、そこのホテル、家内の両親と一緒でね、よく来るんだ」
下に見える水際の高級ホテルである。
「奥さん、あの時の人」
「いや、部長の娘で」
やっぱりあの時私が見ていたの知ってたのね。あの子も放り出されたんだ。
「お子さんたち待っているんでしょ」
「いや義理の親だけだよ、家内と子供は明日くるんだが、部長と奥さんは先に俺が車で連れてきたんだ。視衣ちゃんも家族とかい」
「私一人よ」
彼の目が光った。この目の光はあのころはすてきだと思ったのだが、女をねらう目の光りにすぎなかったのだ。
「一人旅か、同じホテルかな」
「いいえ、上にあるホテルよ」
「今日、夜、暇なんだ、そのホテルにバーはないの」
「ちゃんと見てないけどあると思うわ」
「どう、食後にちょっと飲まない」
学生時代はこういう人だとは思わなかった。私が初心だったんだ。視衣は「いいわよ」と明るくうなずいた。「親は8時になれば寝ちまうから、8時半頃ロビーに行くけどいいかい」
視衣はうなずいた。
彼はうれしそうに「それじゃ」と足取りも軽く、岸壁をくり抜いたようなところに建てられたホテルの木戸をあけて下に降りて行った。
自分のホテルに戻った視衣は食事をするためにレストランに行った。
「洋食とうけたまわっていますが、変更することもできますか、いかがしますか」
田舎では洋食を食べる機会は少ない。洋食でいいと答えた。
伊勢エビがでて、フィレステーキがでた。やはり赤ワインをもらった。こういう贅沢はなかなかできない。
食事に満足して部屋に戻った。十一階の窓から見る遠くの海はまた違ったよさがある。田舎の日本海とは違う。なぜだろう、なぜか明るい。涙の雫を通して見ると、陽が落ちて暗いはずの海がエメラルドに輝いた。きれいだ。
テレビをつけてニュースをみた。明日も天気のようだ。
八時半になり、ロビーに降りると彼はすでに来ていた。ロビーのソファーに腰掛けている。視衣を認めるとすぐに立ち上がりよって来た。
「よかった、また君と飲めるとは思わなかったよ」
最上階にラウンジがあった。海の見えるいいところだ。
「おごるから好きなの飲んでよ」
「私強くないの知ってるでしょ、ワインを少しいただくわ」
「でもきれいになったね、結婚して子供もいると思っていた」
「そう、おとなしく実家の近くで暮らしてるわ」
「あの子、以外とわがままでね」
一緒に会社にはいった女の子のことである。本当かどうかわからない。
「あれからいろいろあって、部長の娘が別の課にいて、こうなっちまったんだ」
自分から仕掛けたのだろう。勝手なことを言っている。
それから、彼のグチやらをいろいろ聞かされた。彼はウイスキーをストレートで何杯も飲んでいる。昔から酒は強かった。手を視衣の足にのばしてきた。
「きれいな足してたよな、いまもきれいだよ」
「そろそろ、帰りましょうか」
声をかけると、小声で「部屋によっていいかい」と耳打ちした。
何とも返事をしないで立ち上がった。彼はカウンターに行って料金を払うと、視衣のあとをおってきた。視衣はだまってついてこさせた。
部屋の鍵を開けると、彼は視衣の肩を押すように部屋に入ってきた。
「いい部屋じゃん」
視衣がソファーに腰掛けると、酔っぱらった彼も腰掛けて、いきなり、首に手を回して口を寄せてきた。視衣はよけて立ち上がった。
明かりの下で立ったまま靴を脱ぎ、ストッキングを脱ぎ、ブラウスを脱いだ。スカートもブラもみんなとった。
男は驚いた顔で、「かわったなあ、でもきれいだよ」と言った。
「あなたも全部とってよ」
男はちょっとにやっとしたようだが、よろけながらベルトをはずし、ポロシャツを脱ぎ、全部とった。ちょっと腹が出始めている。
男が裸の視衣の胸に手を当てようとした。視衣は左手でその手をつかんだ。右手で男の肩を強くつかんだ。ずーっと透明になれと思いながら。
男の身体がだんだん透けてきた。最後に透明になったのは充血してそそり立った陽物だった。
男は気がついていないようだった。
視衣は左手で自分の乳首を摘まんだ。視衣のからだがだんだんと消えていき見えなくなった。
視衣は涙の雫を目に当てた。裸の男が呆然としていた。
「視衣、どこにいった」
視衣はドアを開けた。酔っぱらった裸の男はドアが開いたのを見て、入口にくると廊下をのぞいた。視衣は男を廊下に押しだして鍵をかけた。
男は驚いたように立ちすくんだ。
視衣のからだが見えるようになった。急いで服を着ると、男の脱いだものを紙袋に入れた。
男がどんどんと戸をたたいた。視衣は紙袋をもってガラスをのぞいた。裸の男が戸の前で戸惑った顔で突っ立っている。彼の手をとって、エレベータに連れて行った。ロビーにおりた。
ロビーの前を散歩に行くような振りをして通り過ぎた。
透明になった男は「どこにいくんだい」といいながら引っ張られ道にでた。今日歩いた錦ヶ浦の階段を降り、彼のホテルの木戸まで連れて行った。
木戸を開け、透明の彼をホテルの敷地にいれると、ガラスをのぞきながら、服の入った紙袋を渡した。彼は受け取って呆然としていたが、視衣は「さよなら」と言って、さっさとホテルに戻った。
終わった。視衣は上の階にある露天風呂につかった。透明のままの彼の人生はどうなるか私の知ったことではない。露天風呂から暗い海が見えた。
日本海の海岸で拾った、海の水に洗われたガラスは忘れたい気持ちを透明にしてくれた。これからは日本海の海が明るく見えるようになる。
次の朝、ホテルのバスで熱海の駅にいき、キャリーケースをコインロッカーにいれ、熱海の海岸を歩いた。貫一とお宮の歩いたところだ。お宮の松も見た。
いい旅だった。気持ちが透明になった。新たな生活が始まる。
自分の家に戻った。これからは相手を透明にするようなこと断じてない。そう思いながら涙の雫を神棚の中にしまい、手を合わせた。
熱海では家族でホテルに泊まっていた男が行方不明になっていた。その一週間後、ぶよぶよの海月のような半透明のものにからまった、行方不明の男の服が海に浮いていたのが発見された。視衣はそのようなことを知る由もなかった。
指 - 透明人間譚
私家版透明人間小説集「透人譚、2020、276p、一粒書房」所収
絵:著者


