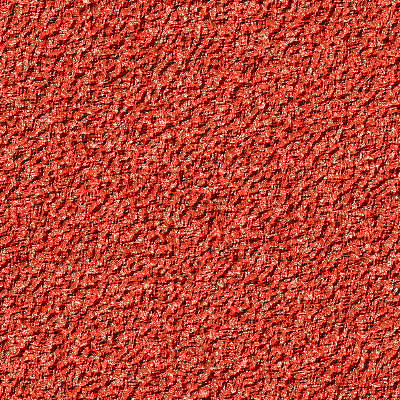
脂肪
脂肪
「困った。完全に迷った」
大山は一人呟くと、大きな体を揺すりながら「よいしょ」と車から降りた。
うっそうと茂る木々の中、ぐねぐねと曲がりくねりながらアップダウンを繰り返す狭い山道、周囲に人の気配は全くない。徐々に狭くなった道は、ここの先で行き止まりとなっていた。街中ではまだまだ暑い日が続くが、まだ朝ということもあるのか、このあたりはすっかり涼やかな秋の気配になっている。
下手に近道しようとしたのが失敗だった。どこかで道を誤ったに違いない。もっと早く気づくべきだった。あの橋の手前まで戻るしかないだろう。三十分ほどかかるかもしれない。だが、問題は所要時間ではなかった。
「ガソリンがないな」
大山の車の燃料計の針はEを指していた。よく走れてもせいぜい二十キロ程度といったところだろう。しかも、平らで真っ直ぐな道ならまだしも、このような山道では、橋のところまでも戻れるかどうかもあやしい。給油しようにもここまでの道でガソリンスタンドは見かけなかった。いや、ガソリンスタンドどころか民家も商店も、建物が何もなかった。電話ボックスもなければJAFを呼ぶこともできない。一部の高級車に搭載されている自動車電話や、最近にわかに脚光を浴び始めている携帯電話などがあれば、あるいは助けを呼べるかもしれないが、平凡な中流サラリーマンの大山がそんなもの持っていようはずもない。
とりあえず一服して落ち着こうと、大山はタバコに火を点けて深く吸い込んだ。
戻れるところまで走り、ガス欠になったらそこから歩いて助けを呼べるような民家か商店、あるいは公衆電話を探すしかないということか。だがそれは、体中に大量の贅肉を付けてでっぷり太った大山には厳しいと思えた。できれば車を置いて歩くなんてことはしたくない。だが、他に手はない。何とかならないだろうか。
そうやってあれこれ頭を巡らせつつ、三本目のタバコを灰にしたころだった。突如、林の中から一人の老人が現れた。やたらとやせ細ったガリガリでひょろひょろの男だった。
「お困りのようじゃの」
「あっ、ええ。道に迷ってしまって、ガソリンもなくなりそうで」
「ガソリンがあればよいか」
「そうですが、このあたりはガソリンスタンドもなさそうですよね」
「わしがガソリンやろうか」
「えっ?」大山は一瞬耳を疑った。「ガソリンを、あなたが?」
「うむ、わしは何でも持っておる。ガソリンもいくらでもある。百リットルもあればよいか?」
「い、いえいえ、そんなたくさんいりません。それに、この車のガソリンタンクにはそんなに入りません。二〇、いや、一〇リットルも売っていただければ十分です」
「売る、とな? だが、わしは銭は要らん。その代わり、お前さんの持っているもので欲しい物がある」
「それは何でしょうか」
「その腹についた脂肪じゃ。それをわしにくれるというのであれば、今すぐおぬしの車の燃料タンクを一杯にして進ぜよう」
「はぁ?」大山は再び耳を疑った。たしかにこの腹にはでっぷり脂肪がついている。だが、それをくれとはどういうことだろうか「それはもしかして、腹を切れということでしょうか」
「いや、お前さんは何もせんでもよい。そのまま普通に生活しておれば後日こちらでひそかに少し脂肪をいただく」
よくわからないが、もしかしたら何かの冗談かもしれない。だがどの道こんな脂肪、邪魔なだけで全く不要なものだ。それに今はガソリンがなければどうしようもない。
「わかりました、この腹の脂肪とガソリンを交換しましょう」
「取引成立じゃな。車の燃料計を見てみるとよい」
どういうことだろうか。てっきり近くに老人の家か何かがあって、そこからガソリンをタンクに入れて持ってくるのだろうと思っていたが、いきなり燃料計を見てみろとは。
それでも念のためと思い、車に戻って見てみると、たしかに燃料計はFを指していた。
「これは……」
一体どんな不思議な力によるものだろうか。あるいはこれならば、この腹の脂肪も本当に持って行ってもらえるのかもしれない。そうであればラッキーだ。いずれにしても、このガソリンで走ることができる。大山は老人に礼を言おうとして振り向いた。だが、そこに老人の姿はなかった。ただ初秋の風が吹くだけだった。
◇ ◇ ◇
大山が異変に気づいたのはその年の暮れ、職場の忘年会の席で後輩に言われた一言がきっかけだった。
「大山さん、最近やせたんじゃないですか」
すると他の人たちも口々に「そういわれてみれば」「なるほどたしかに」「うん、そんな気がする」などと言い出した。そこで大山はあの老人のことを思い出した。実は、話したところでだれも信じてくれないだろうと思い、誰にも話さず黙っていたのだが、そうこうするうちにしばらく忘れていたのだった。
やはりあの老人が何やら不思議な力で脂肪を抜き取ってくれたのだろうか。あの時、いつの間にかガソリンを満タンにしてくれたのと同じような不思議な力で。そう考えると、たしかに最近ほんの少しズボンのウェストが楽になった気がした。
翌日、大山は押入れの奥からほこりをかぶった古いヘルスメーターを引きずり出した。十年ほど前に一念発起してダイエットにチャレンジしたときに買ったもので、一五〇キロまで測れる高級品だ。しかしダイエットは三日でくじけ、このヘルスメーターもそのまま押入れの奥で眠っていたのだった。
おそるおそる乗ってみると、針は一一五キロの少し下あたりを指した。五月に定期健診で測った時は一一六キロだったので、二キロほどやせたことになる。
「なんだ、たった二キロか」
一瞬少しガッカリしたが、ほんの少しでも体重が減ったのはラッキーだったと考えることにした。あのピンチの状況でただでガソリンをもらえただけでもよかったとしよう。
だがその後も少しずつ、本当にゆっくりではあるが、大山の体重減少は続いた。山道の老人に会った日の二年後に一一〇キロになり、五年後にはついに一〇〇キロを切った。
ある日、ためしにタンスの奥から昔の服を着てみると、面白いようにだぶだぶだった。実はこれまでとくにダイエットのようなことはしていない。それどころかむしろ、こってりしたものを毎日大量に食べていたのだった。普通に考えればどんどん太っていてしかるべきなのだが、逆にやせている。
「これはいいぞ、おもしろい」
ガソリンと引き換えにあの老人に脂肪を引き渡したというのは、一時的なものではなく日々徐々に渡していたということのようだ。すると、これからも徐々にやせ続けるに違いない。
「体重も腹回りも気にせず、毎日好きなだけ食べれる。これは素晴らしい」
そしてあの日から一〇年後、四〇歳になったときには、八〇キロにまで減っていたのだった。
◇ ◇ ◇
「困ったことになった」
大山は体重計の目盛りを見て思わず呟いた。大山は今年七〇歳。体重計の目盛りが指しているのは四〇キロ。年々体重は減り続け、ついにここまでやせてしまった。最近知り合った人に昔の写真を見せると「別人でしょう」と笑われる。健康診断では医師から「やせすぎなので、もっと栄養をたくさん摂るように心がけてください」と言われる。だが、毎日こってりたっぷり食べているのだ。それでも太れず、やせる一方だ。
こうなると、あの日以来あの老人に日々栄養を搾り取られている呪いのようだ。何とかせねばこのまま搾り取られて文字通り骨と皮になってしまう。
何とかせねば。
そういえば最近、業界誌で体の脂肪を吸収して燃料にするシステムの研究の記事を読んだ。まだ研究の途上と言うことだが、将来これが実用化されれば、その技術を応用して誰かの脂肪を奪うこともできるかもしれない。問題はそれまでこの体がもつかどうかだが。
大山はその研究所がシルバー枠で経験者採用の募集をしているのを見て、迷わず応募することにした。
応募サイトのフォームに必要事項を記入し、送信ボタンをクリックする……
脂肪


