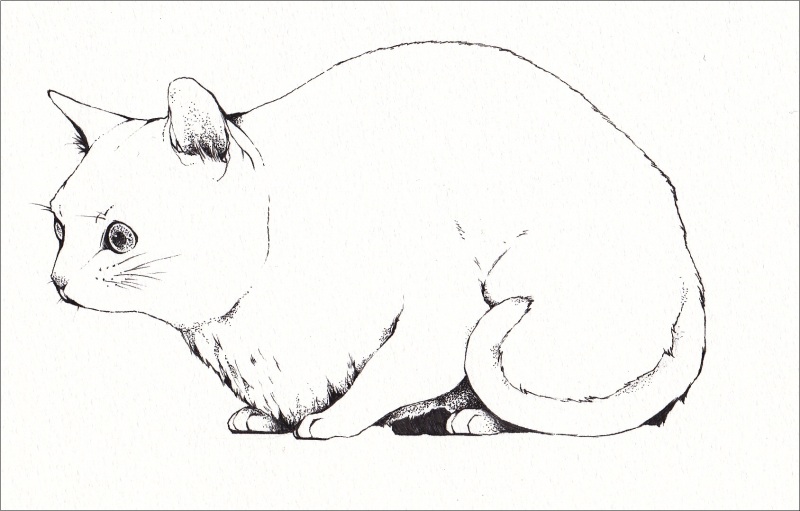
Remember me? ~children~
ただ、こんな小説を書いてみたい。
そんな思いを巡らせ、自身の幼い日を頭に浮かべて書きました。
※Episode4と5に過度な性暴力表現を含みます。
平井優子(Yuko Hirai)
沙耶原麗太(Reita Sayahara)
天美マミ(Mami Amami)
光原綾瀬(Ayase Mitsuhara)
平井香奈(Kana Hirai)
藤原博美(Hiromi Fujiwara)
沙耶原楓(Kaede Sayahara)
Prologue Afternoon
小学五年生への進学を間近に控えた、春の昼下がりの事。
トラックの大きなクラクションと、タイヤの擦れる音が、自宅前の道路に響いた。
気付いた頃には、もう遅かった。
道路の真ん中には、長い髪を乱れさせ、額から真っ赤な血を垂らす母さんの姿がある。
周りには野次馬ができ始め、トラックの運転手はあまりの衝撃に混沌としていた。
僕は手に持っていたサッカーボールを、その場に落とし母さんの元へ駆け寄った。
母さんの体を軽く揺らす。
手に触れた母さんの体には、温もりと言うには程遠い冷たさを感じた。
「ねぇ、母さん?」
次は一声掛けてみた。
それでも、何も反応がない。
「母さん! 母さん!」
どれだけ声を掛けても、母さんは起き上がらない。
『母さん!』
その言葉を発したつもりだった。
『母さん!』
何度も、そう言い続けたつもりだった。
それでも、聞こえて来る筈の自分の声は、聞こえて来ない。
暫くして、ようやく気付いた。
僕は声を失っていたのだ。
これは母さんを死に追い合ってしまった、自分への代償。
自然と、そんな考えが頭に浮かんでいた。
転がるサッカーボールを追い掛けて、道路に飛び出した僕を、母さんは迫るトラックから身を挺して守ってくれたのだ。
罪悪感で堪える事の出来ない涙を流し、小さな腕で冷たくなった体を抱える。
そして、声なく叫び続けた。
Episode1 Yuko Hirai
隣の家に住む、同級生の麗太君のママが亡くなった。
その事を知ったのは、麗太君が私の家に預けられる事が決まった日であった。
=^_^=
自宅の玄関先で、麗太君のパパと私のママが何かを話している。
その場の空気は、今年から小学五年生へ進学する私にとっては、居合わせたら泣いてしまいそうな位に重苦しかった。
「それじゃあ、今日から息子を宜しくお願いします」
とても背の高いスーツ姿の、麗太君のパパ。
彼の後ろから、ひょっこりと麗太君が顔を覗かせた。
どうやら、先程からそこにいた様だ。
彼の手には、なぜか大きな旅行鞄がある。
ママが麗太君に顔を近付けて、にっこりと笑う。
「麗太君、よろしくね。今日からは、私と優子と一緒に暮らすのよ。ここを自分の家だと思って、好きに使ってちょうだいね」
麗太君は首を縦に振る。
「えぇ!?」
廊下の隅から玄関を見ていた私は、唐突な自宅への入居者に、つい驚きの声を上げていた。
ママ、麗太君のパパ、麗太君の三人がこちらを振り向く。
「あら、優子。いたんだ。ほらこっちに来なさい。麗太君に挨拶して」
言われた通りに玄関へ行き、麗太君の前に立つ。
「さあ、麗太。優子ちゃんに挨拶しなさい」
背中をパパにぽんと押された麗太君は、私に一礼した。
どんな対応をしていいのか分からず、私はママの方を向いた。
ママは何かを察した様に、私に言う。
「じゃあ、挨拶も済んだ訳だし。ママは麗太君のパパと大事なお話があるから、優子は麗太君と部屋に行ってなさい。麗太君の部屋は、後で用意するから」
「ちょっと……えぇ!?」
ママに押され、私は麗太君を二階の自室に招いてしまった。
そういえば、部屋に男の子を上げるのは初めてだ。
中央に置かれている小さなテーブルの周りに、クッションが三つ置いてある。
私はいつも座っている、キティちゃんの可愛らしいプリントが成されたクッションに、逸早く座った。
なんとなく、これだけは男子に譲れないのだ。
「どうぞ」
そう言うと、彼は私の向かいのクッションに座る。
「えっと……麗太君。お母さんは、大丈夫だった? えっと……ほら! あの……この前、事故に遭っちゃったでしょ? それで……えぇっと……今日から私と住むっていうのは……」
訊きたい事は多々あるのに、言葉が上手く出て来ない。
ぶっきらぼうな私の言葉に、麗太君は俯いてしまった。
「あぁ、ごめんね。そんな事を聞かれても困るよね……」
どうして、私がこんなに喋っているのに、麗太君は無口なんだろう。
これでは、沈黙を作るまいと頑張って話をしている私が馬鹿みたいだ。
こんな麗太君を見たのは、今日が初めてだった。
学校で見る彼はもっと明るく、クラスではムードメーカーの様な存在であった筈だ。
やはり、ママの安否が心配なのだろうか。
そんな考えを浮かべている内に、既に部屋には沈黙が下りていた。
どうしよう……。
なんか、お腹が痛くなってきた。
昔から、こんな堅苦しい状況に陥ると、いつも私はお腹を壊す。
「ごめんね。ちょっと、トイレに行ってくるね」
立ち上がり、私は逃げる様に自分の部屋から出た。
二階のトイレで用を済ませた。
そういえば、ママと麗太君のパパは、まだ玄関で話しているのだろうか。
階段の上から玄関を覗くと、そこには誰もいない。
どうやら、話は終わった様だ。
一階のリビングへ行くと、ママは頭を抱えた状態でソファーに座っていた。
「ちょっと、どうしたの!?」
ママはゆっくりと顔を私の方へ向ける。
その表情は、涙に濡れていた。
「麗太君のママ……。さっき、病院で息を引き取ったんですって」
「そんな……」
私には、直接の接点はない。
しかし、ママにとっての麗太君のママは、近所付き合いでありながら親友の様に仲の良かった存在だ。
勿論、麗太君にとっては、それ以上の存在でもある。
身近な人が亡くなった。
きっと、これは私の人生経験では初めての事だ。
少しだけ、気分が悪くなった。
「麗太君に……何て言うの?」
「あの子には今日の夕食の後で、私からどうにか言って聞かせるわ」
ママは私の頭を強く抱いた。
豊満な胸部が、私の顔面を包む。
それと同時に、少しだけきつめの香水の香りが私の鼻を突いた。
いつもと同じ、ママの香り。
なんだか安心した。
「優子、よく聞いて。あなたが麗太君の支えになってあげるの。あの子のパパは、仕事が多くて家に帰れないの。それに、まだ言っていなかったけど、今の麗太君は喋る事が出来ないのよ」
ようやく理解した。
私がどれだけ喋っても、彼が口を開こうともしなかった理由。
「麗太君のママが交通事故に遭った事は知ってるでしょ?」
「うん、知ってる……」
しかし、私とママはその現場を直接見た訳ではない。
丁度その頃、私達は買い物に出掛けていた。
買い物から家に帰った時、麗太君の自宅前には警察がいて、私達は初めて事情を知ったのだ。
「麗太君は、その現場を見てショックを受けちゃったの?」
「そうよ。麗太君を一番に支える事が出来るのは、あなただけ。これから一緒に住んで、一緒に学校へ行って、大変な事もあるだろうけど、麗太君の事をお願いね」
胸部に埋めていた顔面を離し、ママを見た。
やはり、まだ涙を浮かべている。
「大丈夫だよ、ママ。麗太君の事は、私に任せて」
泣いているママに代わって、歯を出して笑って見せた。
とりあえず部屋に戻ろう。
でも、私が部屋に戻って麗太君とお話するにしても、彼が喋れないのでは、どうしようもない。
ふと、電話の隣に置いてある、メモ用紙の束とシャーペンが視界に入った。
「ねえ、このメモ用紙とシャーペンなんだけど、貰って良い?」
ママは私の考えを理解してくれたのか
「頑張ってね」
とだけ言って笑い掛けた。
部屋に戻り、麗太君に一本のシャーペンとメモ用紙の束を差し出した。
「これを使って。言いたい事が伝わらないと、不便だから」
麗太君は、私が差し出したそれを横目で見たかと思うと、勢いよく左手で振り払った。
メモ用紙の束を挟んでいたピンが外れ、部屋中にメモ用紙が散らばる。
一緒に払われたシャーペンは壁に強くぶつかり、欠けてしまった。
「ちょっと、何て事するの!?」
散らばったメモ用紙を、そのままにしておく訳にもいかず、仕方なしにそれを拾う。
腰を屈めてメモ用紙を拾う私を、麗太君は表情を変えずに見つめていた。
どうして、こんな事をしたのか。
しっかりと、その事を訊かなければならないと思った。
しかし、訊く事が出来なかった。
彼の表情が、あまりにも悲しげで、それでいて辛そうに見えたから。
私は一段ベットの上で漫画を読み、麗太君はクッションの上でずっと俯いている。
どうして自分の家で、こんな嫌な想いをしなきゃいけないんだろう。
もう最悪。
暫くして、ママが私の部屋に来た。
「麗太君、部屋の準備ができたわよ。いらっしゃい」
ママが麗太君を部屋から連れ出す。
私も、その後に付いて行った。
麗太君が案内された部屋。
それは二階の一番奥の部屋で、かつてパパが使っていた書斎だった。
私のパパは仕事の都合で、今は海外に単身赴任中だ。
だから今、この部屋は誰も使っていない。
壁際に、ぎっしりと難しい本が詰まった棚が一つ。
窓際に置かれた殺風景な机と、その隣に位置する一段ベット。
これらは全て、かつてパパが使っていた物だ。
「この部屋は好きに使ってくれて構わないからね。棚の本も読んで良いし」
麗太君は頷き、一段ベットの上に弾みを確かめる様に座った。
そんな光景を見たママは、安心した様に部屋を出てしまう。
一段ベットに座る麗太君をそのままにして、私も部屋を出た。
「ママ、どうして麗太君の部屋をパパの書斎に選んだの? まだ空いてる部屋が一つあるでしょ?」
ママが私の方を向く。
「あれで良いのよ。あの部屋に誰かがいてくれる。あの部屋から物音がする。それだけで、パパがいた時の事を思い出せるの」
パパが単身赴任をして、まだ一年も経っていないというのに、どうしてママは、こんな事を言うのだろう。
これでは、まるでパパがもう帰って来ないみたいじゃないか。
「パパは……帰って来るんだよね?」
恐る恐る訊く私に、ママはからかい気味に笑う。
「馬鹿ね。パパは只の単身赴任よ。仕事の都合によっては、すぐに帰って来るわよ」
私の額に軽くデコピンをして、その痕にキスをした。
「はぁ、う……」
つい、そんな声を上げてしまった。
額がむずむずしていて……何と言ったら良いのだろう……よく分からないが、少しだけ気持ち良い。
「パパの事は、あなたが気にする事じゃないわ。まず麗太君の事を考えなさいね」
「……うん」
頭に霧がかかった様な感覚になり、少しだけボーっとしてしまった。
「二人とも、ご飯よ!」
夕日が沈み切った七時頃、ママが一階から私と麗太君を呼んだ。
私が部屋から出ると同時に、彼も部屋から出て来た。
一瞬だけ目が合い、すぐに反らした。
なんとなく、彼の事を直視する事が出来なかったのだ。
リビングでは、ママがテーブルに夕飯と数枚の皿を置いていた。
テーブルの上に置かれた夕飯を見る。
今日は野菜炒めだ。
あと、いつも通り茶碗に盛られたご飯と味噌汁が置かれている。
私とママはいつもの様に、向かい合って椅子に座った。
「麗太君は、ここよ」
ママが隣の椅子を引いて、麗太君を招く。
彼は頷き椅子に座った。
私、ママ、麗太君、全部で合わせて三つの椅子。
麗太君が座っている椅子は、かつてパパが座っていた物だ。
この家に、確かにパパがいたという証拠が、麗太君という存在によって埋められていく。
ママを事故で亡くしてしまい、更には声まで失ってしまった麗太君。
不幸で、可哀想な子。
彼を見る度に、そう思う。
しかし、私のパパの存在と摩り替わる様にして、今ここにいる麗太君。
いつまで続くか分からない同居生活を共にする同居人としては、あまり好きになれなかった。
テレビを点けると、ポケモンがやっていた。
私は、この番組を毎週見ている。
ママには「もう、五年生なんだから」と、よく茶化されるていたけれど、最近ではそれもなくなった。
ママ自身も、私と一緒に毎週見ているから、それが決まりになっているのだろう。
小皿に野菜炒めを盛り、テレビを見ながらご飯を食べる。
いつもと同じ光景。
ただ、ママの隣に麗太君がいなければ。
なんとなく、麗太君が気になってしまう。
もう小学五年生だというのに、ポケモンなんて見てる私を、内心では嘲笑しているのかもしれない。
喋る事が出来ないから、その事を伝えようとしないだけ。
勝手な想像をしただけで、勝手に頬が熱くなる。
まったく、私は何を考えているのだろう。
彼の事など気にせず、いつも通りにご飯を食べよう。
そう思っていた矢先、ママが麗太君に話し掛ける。
「うちのご飯、お口に合うかな? 野菜炒めとかは、わりと自信作なんだけど。おいしい?」
ゆっくりと、麗太君は頷く。
「そう! 良かったぁ! ご飯のおかわり、いっぱいあるからね」
そんな遣り取りを前に、私はテレビに視線を集中させた。
食事が終わった後、ママは麗太君をリビングへ呼び出した。
きっと、麗太君のママに関する事を話すのだろう。
私はママに言われ、その場を外した。
一度は部屋に戻ったものの、どうしてもリビング内での出来事が気になってしまってしょうがない。
少しだけ。
そう思い、私は擦り足で階段を降り、リビングのドアのすぐ横に立った。
ママの声が聞こえて来る。
「あなたのママに関しては、私もとってもショックを受けたわ。勿論、麗太君。あなたもそうなのよね」
数秒の沈黙が下り、再び声が聞こえて来る。
「落ち着いて、聞いてちょうだい。今日、あなたのママが亡くなったわ」
その知らせと同時に、椅子やテーブルをバンバンと叩く音がした。
きっと、麗太君が取り乱しているのだろう。
当然だ。
隣の家に預けられて、その日の晩にママの死を知ってしまうなんて……残酷過ぎる。
やがて、椅子やテーブルを叩く音が止んだ。
「辛いのは麗太君だけじゃないの! 私も辛いのよ。でも、過ぎた事はどうにもならない。だから……」
麗太君を宥める為の勢い付いた声は、やがて弱々しい泣き声の様なものに変わった。
「だから、あなたはこれからの事を考えるの。過ぎた事は……どうにもならないんだから……」
ママと麗太君は、このドアの向こうで泣いている。
麗太君のママを、親しい仲と捉える事が出来ず、あの二人と共に悲しむ事が出来ない自分が、嫌でしょうがなかった。
部屋に戻り、ベットに飛び込み枕に顔を埋めた。
なぜか、麗太君に関する悩みが次々に浮かんでくる。
私は、これから麗太君にどう接していけばいいんだろう。
麗太君と、どうやって会話をすればいいんだろう。
これから麗太君は、私を頼れる同居人として受け入れてくれるだろうか。
「あー、もう! どうして、こんなにモヤモヤするの!?」
部屋の中で、一人で叫んでみても何も変わらない。
麗太君と二人で話をしないと。
ふと、階段を上がる足音が聞こえた。
階段を上がり切ったその足音は、一番奥の部屋へ向かって行った。
この足音は、麗太君だ。
その事を確信するなり、私は先程のメモ用紙の束とシャーペンを持って、彼の部屋へ向かった。
廊下の一番奥の部屋の前で、呼吸を整える。
「よし!」と小声で言い、ドアをノックした。
「入るよ」
ドアノブを引いたが開かない。
部屋に鍵はない筈だ。
おそらく、麗太君がドアを押さえているのだろう。
「麗太君……」
私には、彼の名前を呼ぶ事しか出来ない。
彼自身が、ドアを押さえて私を拒絶しているのだから。
きっと、こういう時は怒ってはいけないのだ。
なんとなく、そう直感した。
一回だけ呼吸を整えて、再び言葉を発する。
「ねえ、そうやってるだけじゃ何も変わらないんだよ? 確かに、麗太君のママの事は辛いと思う。でも、このままじゃ何も変わらないよ……」
私の言葉に、彼は物音一つ返さない。
落ち着いて。
イライラしちゃ駄目。
そう自分に言い聞かせ、話を切り出した。
「麗太君がいる部屋。そこって、元々はパパの部屋だったの……」
ドアの向こうから、少しだけ床の軋む音がする。
「この部屋に誰かがいてくれるだけで、パパがいてくれた時の事を思い出せる。ママが、そう言ってたの。馬鹿だよね。パパは、只の単身赴任なのにね」
いつもはにこにこと笑っているけれど、きっと一番に泣き出したいのはママの筈だ。
「だから、麗太君にはパパに代わって、私達を守って欲しい。そう思って、この部屋を麗太君に選んでくれたんじゃないかな?」
麗太君の息使いが、段々と荒くなっているのが、ドア越しからでも分かる。
それほど動揺しているのだろう。
「だから麗太君は、もう私達の家族なんだよ」
我乍ら、かなり恥ずかしい事を言ったと思う。
頬が熱くなってくるのが、なんとなく分かる。
きっと、真赤に赤面してるんだろうなぁ。
ふと、ゆっくりと部屋のドアが開いた。
麗太君は頬を赤らめ、必死に涙を堪えている。
しかし彼の目蓋には、僅かに涙が浮かんでいた。
私から必死に視線を反らそうとしているのを見るに、強がっているのだろう。
俯く麗太君に、先程、部屋から持ちだしたメモ用紙の束と、シャーペンを手渡した。
「伝えたい事があったら、これを使って」
麗太君は、メモ用紙の上にシャーペンを走らせる。
書き終えた様で、それを見せる。
『僕は、平井の家族になって良いの?』
不安そうな表情を浮かべて問う麗太君に、私は笑顔で答えた。
「勿論だよ。ママも言ってたでしょ? 麗太君が、パパに代わって私達を守ってくれるって。何も遠慮しなくて良いんだよ。麗太君は、私達の家族なんだから」
その瞬間、何かが外れた様に麗太君の目蓋からポロポロと涙が零れ出す。
やがて、彼は床に膝を付き、大きく泣いた。
麗太君が声を失っていなければ、きっと大きな声を出していた事だろう。
しかし、麗太君に声はない。
いくら叫びたくても、泣きたくても、声には出せないのだ。
ならママに言われた通り、私が彼の支えになってあげるんだ。
春休みが終わったら、一緒に学校へ行って、友達と遊んで。
休みの日には麗太君と、ママに買い物に連れて行ってもらおう。
きっと、これから毎日がもっと楽しくなる。
麗太君の悲しい気持ちを消せる様に、私が頑張らないと。
床に膝を付いて大泣きする彼の前に、目高を合わせてしゃがみ、頭を撫でてやった。
少しだけ長めに伸ばされた彼の髪は、程良くサラサラで、私から見ても羨ましい位に柔らかかった。
なんだか、麗太君って女の子みたいだ。
見ていて、私が逆に守ってあげたくなる。
「今は泣いて良いんだよ。私は、笑ったりしないから」
どうしてだろう。
麗太君を見ていると、妙に親近感が湧く。
その原因を考える程に、なぜか胸が苦しくなった。
=^_^=
麗太君が私の家に預けられて、三日が経った。
今日は、麗太君が私の家で迎える初めての日曜日という訳だ。
私の日曜日の朝は、いつも早い。
八時半より少しだけ前に起きて、テレビの前にスタンバイしなくてはならないのだ。
何度寝も出来る日曜日の朝から、なぜ、そんな事をしなくてはならないのかというと、八時半からプリキュアを見る為だ。
ママからは「もう、小学五年生なんだから。そんなの、小学校低学年が見る番組よ」と、以前はよく茶化されたものだが、最近ではそれもなくなった。
きっと、何を言っても無駄だと気付いたのだろう。
懸命な判断だ。
私にとって、週に一度の楽しみにしている番組へ掛ける情熱は、他人からとやかく言われて揺らぐものではないのだから。
パジャマのまま部屋を出て、階段を駆け下りてリビングへ行くと、テレビ前のソファーには先客がいた。
麗太君だ。
私と同じで、まだパジャマを着ている。
「おはよう」と挨拶をし、麗太君の隣に座った。
麗太君は私に、軽くお辞儀をする。
やはり喋れない事ほど不便な事はない。
挨拶をされても、それを単純に返す事すら出来ないなんて。
しかし、いつも麗太君は笑い掛けてくれた。
そういえば、私より早く起きて、麗太君は何を見ているのだろう。
テレビに視線を向ける。
どうやら、プリキュアの前の時間に放送中の特撮番組の様だ。
この番組、なんとなく知っている。
たしか……クラスの男子達が、よくポーズを決めて『俺、参上!』等と言っていた事があった。
おそらく、それだろう。
麗太君も、やっぱりこういうのが好きなんだ。
「やっぱり、男の子なんだなぁ……」
テレビの画面を見ながら呟いた時だ。
「優子だって、プリキュアとか見てるじゃないの」
私と麗太君が座るソファーの後ろには、いつの間にかママが立っていた。
「ちょっと、いつからいたの?」
「少し前よ。来てみたらリビングのドアが開いてて、覗いてみたら……」
少しの間を置いて、ママは「キャー!」とわざとらしく黄色い声で叫んだ。
「二人でソファーに座って、テレビ観てるんだもの。なんか、ママが入り込む隙がないっていうかぁ」
「違うよ! そんなんじゃなくて……」
麗太君は、メモ用紙とシャーペンを片手に慌てている。
「まあ、二人とも仲が良いって事よね。そうでしょ?」
私達二人の頭を、ママはワシャワシャと撫でた。
「うん……まあ」
麗太君も、私に合わせて頷いた。
「そういえば、これって新しい仮面ライダーでしょ?」
テレビに目を向けたママが、麗太君に訊いた。
仮面ライダーという特撮ヒーローの話題を振られた事が嬉しかったのか、麗太君は嬉しそうに頷く。
「え? 仮面ライダーって、昭和のヒーローなんじゃないの?」
「そんな事ないわよ。平成になっても続いてるのよ。こう見えてもママは、昭和の仮面ライダーと平成の仮面ライダーを網羅してるの!」
胸を張って自慢げに語るママに、麗太君は輝かしい眼差しを向け、何かの書かれたメモ用紙を見せる。
『電王』
メモ用紙に書かれた意味不明な単語を見て、私は目を丸くする。
「これ何?」
「ああ、仮面ライダー電王ね!」
ママは彼の手を握り、一気に体を抱き上げた。
「気が合って嬉しいわ! 麗太君は電王が好きなのね。私は平成のライダーでいうとカブトが一番好きなの! 電王役の佐藤健君も良いけど、カブトの水嶋ヒロ君も格好良かったわぁ!」
仮面ライダーカブトこと水嶋ヒロを、抱きあげられた事が恥ずかしかったのか、やや赤面する麗太君に熱く語るママが……二人がどこか遠く見えた。
ただ、話に付いていけないだけ、という事もあるけれど。
そういえば、私が幼稚園の頃の事だ。
私に見せる為にと言って、ママが仮面ライダーのDVDをレンタルして来た事があったっけ。
それで、仮面ライダーが気に入らなくて、なんだか凄く感じの悪い事を言った様な気がする。
いったい、何を言ったんだろう……。
記憶が曖昧過ぎて、思い出す事が出来なかった。
=^_^=
一週間後、麗太君のママの葬儀が行われた。
私を含め、皆が黒くて堅苦しい服装をしている。
黒という色が、余計に気分を沈める。
葬儀場には、麗太君のママの親類や友人、もちろんママや私も参列した。
しかし、ただ一人だけ。
一番いなくてはならない人が、そこにはいなかった。
麗太君のパパだ。
ママは彼に関して、何かを言う事はなかった。
「あの子、沙耶原麗太君でしょ?」
「そうそう。まだ、小さいのにお母さんを亡くしちゃって。沙耶原さん家のお母さん、随分と若かったのにねぇ」
周りからの同情の眼差しや声が、麗太君に集中する。
彼は私の服の袖を、ギュッと握った。
そういえば、ママはどこへ行ったのだろう。
周りを見渡すと、他の参列者の人達と何かを話しているのが見える。
今、麗太君を守ってあげられるのは、私しかいないのだ。
お坊さんの棒なお経と共に、参列者が線香をあげる為に、列を作って仏壇を周る。
ママの番が来ると、私と麗太君に「こうするのよ」と言い、線香に蝋燭の火を灯し、灰の積もる線香立てに差した。
次の番が周って来た私も、ママと同じ事をする。
線香を差した時、棺の中で眠る麗太君のママが僅かに見えた。
透き通った白い肌や穏やかな寝顔、およそ遺体には見えなかった。
葬儀が終わると、火葬場へ遺体を運ぶのだそうだ。
参列者も、それに同行する事になっている。
つまり遺体を焼いた後、出て来た遺骨を参列者が専用の箸で拾う、という事らしい。
それを聞いて、背筋が凍った。
遺骨の骨を箸で拾うなんて……そんな光景を見ただけで、私は泣いてしまうかもしれない。
逃げ出したい。
しかし、そんな事をすれば周りの人達に迷惑が掛かる。
麗太君のママの死に、皆が悲しんでいるのだ。
私の自己中心的な行動で、場の空気を壊す訳にはいかない。
今は我慢するしかないのだ。
葬儀場から、参列者貸し切りのバスで、火葬場まで行く事になった。
窓側に私、真ん中にママ、その隣に麗太君で、バスの一番後ろの席に座った。
バスが走り出す。
窓の外では、見慣れた街の景色が流れていた。
ぼーっと眺めている内に、徐々に見慣れない景色へと変わっていく。
街の郊外へ来たのだ。
窓の外の見慣れない景色を見るうちに、私の中では少しずつ恐怖心が膨らんでいた。
暫くすると、火葬場に到着した。
広い駐車場と、その隣に芝生が茂る広い平野。
その中心に、石造りの綺麗な建物から、長い煙突を空に向かって真っ直ぐ伸ばした火葬場があった。
おそらく、燃やした遺体から出る煙は、あの煙突を通って空へ登るのだろう。
停車場に着くと、私達はバスを降りた。
参列者が、ぞろぞろと建物の中へ入って行く。
私達も、それに続く。
近くにいるママや麗太君は勿論、皆が顔色を悪くしている。
先日まで生きていた近しい人が突然死に、遺体を焼かれる。
その有様を、私達は見届けなくてはならない。
誰も良い気分には、なれない筈だ。
目の前には、五つの固い金属扉が並んでいた。
手前には柵で仕切りがされており、私達は柵を挟んで扉の前に立っている。
棺桶に入った遺骨が、火葬場の人達によって運ばれて来た。
扉が開かれ、棺桶が中に入れられる。
そして、扉が閉められた。
「一時間程で火葬は終わります。待合室がありますので、そちらでお待ち下さい。火葬が終わったら、知らせますので」
皆が待合室へ歩いて行く中、麗太君だけはその場を動こうとはしなかった。
ただ強く拳を握り、扉を見ている。
ママは察した様に私に言う。
「麗太君の事、今は一人にしてあげましょう」
私は黙って頷き、ママの後に付いて行った。
火葬が終わったという報告が届き、皆が待合室を出る。
その頃には、麗太君も私の隣に戻って来ていた。
しかし、戻って来ても言葉を交わす事はなく、私もママもずっと黙っていた。
いつもの様に笑いながら、言葉を交わす気分にはなれなかったのだ。
重い足取りで歩く私と麗太君に、ママはこっそりと言う。
「二人とも、収骨が終わるまで外にいなさい」
「いいの?」
「あなた達は、まだ小学五年生じゃない。収骨をする所なんて、残酷すぎて見せたくないの。特に、麗太君には……」
麗太君は何か言いたげな顔をして、メモ用紙を出す。
一度、横目で私を見てメモ用紙をしまい、ママに一礼した。
きっと、私の事を考えてくれたのだろう。
火葬場に来てから、収骨の事ばかりを考えてしまって、ずっと気分が優れなかったから。
「それじゃあ、待合室は閉められちゃったから、あなた達は外で待ってなさい」
ママは私達の頭を撫で「じゃあね」とだけ言って、収骨に向かった。
外に出ると、春の風が優しく頬を撫でた。
駐車場の隣には芝生がある。
「麗太君、あそこ行こう」
麗太君を連れて芝生の上に立った。
気持ちの良い風、草の匂い、先程までの嫌な気分が嘘の様だ。
しかし、私の隣にいる麗太君はずっと俯いている。
折角、重苦しい雰囲気を抜けられたんだ。
何か明るい言葉を掛けなくちゃ……。
「気持ち良いね。風とか草の匂いとか。家の近くに大きな公園があるんだけど、今度、ママと行こうよ。とっても気持ちが良いの。緑がいっぱいで、噴水とかがあって」
必死に言葉を投げかける私を余所に、麗太君は火葬場の煙突の方を見た。
さっきまでは、あそこから遺体を焼いた煙が上がっていたのだろう。
麗太君は私の方へ向き直り、メモ用紙に何かを書いて、それを見せた。
『母さんを殺したのは僕』
良く晴れた日の昼時。
麗太君は、家の庭でサッカーボールで遊んでいた。
麗太君のママは花に水をあげながら、その光景を見ていたという。
誤ってボールを道路に出してしまった麗太君は、慌ててそれを追い掛けた。
自身では気付かなかったのだそうだ。
そこにトラックが走って来ていた事を。
麗太君のママは、ボールを持って道路に立っている彼を突き飛ばし、自分が身代りになった。
これが麗太君の言い分だった。
「でも、こんなの……麗太君が殺した事になんてならないよ。こんなの、ただの事故だよ」
『本当は僕が死ぬ筈だった』
「駄目だよ……そんな事言っちゃ……」
『本当は僕が死んだ方が良かったんだ』
泣きながらメモ用紙に、苦悩の言葉を書きならべる。
「やめて……」
静止する様に言っても、麗太君は聞かずに書き続ける。
『死ぬのは僕で良かった。僕が死ねば良かった。こんな事になるのなら』
麗太君は新しいメモ用紙のページを捲り、その続きを書いた。
『生まれて来なければ良かったんだ』
「やめて!」
気付いた時、私は彼の頬を強く叩いていた。
「そんな事言わないで! 麗太君のママは、麗太君を守る為に犠牲になったんだよ! それなのに、生まれて来なければ良かったなんて……言わないでよ! 麗太君のママは、そんな事望んでないよ!」
麗太君は唖然としている。
私が手をあげるなんて、思ってもみなかったのだろう。
「……ごめん」
怒鳴って手をあげた次には、謝っていた。
男の子の頬を叩いたのなんて、始めてだ。
でも、きっとクラスメイトのマミちゃんなら容赦しないんだろうなぁ……。
ボールをぶつけて来た男子をビンタで泣かせちゃう様な子だし。
『ごめん。もう言わない』
「うん。自分の事を悪く言っちゃ駄目。前にも言ったでしょ? 私達は、家族なんだって」
麗太君は頷いて涙を拭う。
辛い事が重なったからなんだろうけど、麗太君って意外と涙脆い。
震える手で、再びメモ用紙に何かを書く。
『公園の話、もっと聞きたい。皆で行きたい』
麗太君は、堪え切れない涙を目蓋に残しながらも、私に笑い掛けた。
=^_^=
朝の目覚ましの音が部屋に響く。
重い目蓋で時計を見ると、どうやら二、三度の目覚ましが鳴った後の様だ。
私は跳び起きて箪笥をあさり、今日の分の洋服を取り出す。
「もう! どうしてママも麗太君も起こしてくれないの!?」
春休みの反動があったせいか、目覚ましのベルを二、三度も逃すとは不覚だった。
今日が五年生の一学期初登校だというのに。
新しく買ってもらった春物のお洋服。
いつもは殆どママが選んでくれている。
私に可愛い服を着せて喜んでは、また別の物を着せる。
ママはしょっちゅう、私を使ってファッションショーをしているのだ。
近頃は麗太君も、その被害に遭っている。
廊下に出ると、麗太君も部屋から出て来ていた。
「おはよう。今、起きたの?」
麗太君は頷く。
二人でリビングへ行くと、隣のママの部屋から悲鳴が聞こえた。
何事かと思った次の瞬間、ママはリビングへ入り込むなり私達に言う。
「二人とも、このままじゃ遅刻よ! 急いで!」
ママに急かされ、身支度を整える。
朝ご飯は抜きで良いと思っていたのだが
「朝ご飯だけは食べて行きなさいよ!」
というママの言葉には逆らえず、黙々とトーストを齧る。
「優子、髪梳かしてあげる」
「え? いいよ。自分で出来るから」
「時間がないんだから私に任せて! それに、優子は髪が長いんだから、余計に時間が掛かるでしょ!」
麗太君の前でママに髪を梳かされていると思うと、少しだけ恥ずかしかった。
学校へ行く前、ママは必ず玄関先まで着いて来る。
「二人とも、忘れ物はない?」
「大丈夫だよ」
隣で麗太君も頷く。
「じゃあ、頑張ってね。二人とも仲良くね。いつも言ってるけど、知らない人に声掛けられても付いて行っちゃ駄目よ。えっと、あとは……」
このまま言われると限がなさそうだ。
「ママ。時間、時間」
「ああ、そうね。よし! それじゃあ、行ってらっしゃい!」
元気良く言うママに、私も笑顔で言う。
「行ってきます!」
隣で麗太君も、メモ用紙を見せる。
『行ってきます』
玄関の扉を開けると、朝の眩しい光が私達を照らし出す。
春の日差しや風は、私達を祝福しているかの様に暖かく心地よく感じられた。
Episode2 Fifth grade
久しぶりに来た学校の門前には、桜が舞っていた。
しかし、今はそんな物を観賞している暇はない。
朝の会の始まるチャイムが、既に鳴っているのだ。
五年生一学期の初日からの遅刻は、さすがに拙い。
担任の先生の高感度は左右されるし、何しろ皆が席に着いている教室にドアを開けて入るのだ。
注目される事は間違いないだろう。
思いっ切り走ったせいか、息切れが激しい。
「麗太君、ちょっと、待ってよ! 足、速いよ!」
その場に立ち止まって膝に手を着く。
先にいる麗太君は立ち止まり、私の側に駆け寄った。
胸を押さえて呼吸を整える私に、手が差し伸べられる。
「ありがとう」
差し伸べられた彼の手を取る。
麗太君は私に笑い掛け、昇降口まで歩きながら手を引いてくれた。
もう完全に遅刻だというのに、焦る様子もなく。
昇降口のガラス張りのドアには、新クラスの生徒表が貼られていた。
この学校は市内で最も小さく、クラスは二つしかない。
しかも一クラスにつき、生徒は二十余人程しかいなののだ。
出席番号の一番目から順に名前を見てみる。
五年二組の欄に私の名前がある。
クラスも少ないせいか、知っている友人の名前ばかりが目に止まる。
「あ、マミちゃんの名前がある! マミちゃんも一緒なんだ!」
マミちゃん。
私の幼稚園の頃からの親友で、五年生になった今でも、クラスが離れた事はない。
きっと毎年、先生がクラス替えの時に気を廻してくれているのだろう。
そういえば麗太君は……。
沙耶原麗太。
男子の番号列を見ると、彼の名前も私と同じクラスの表に書かれていた。
「良かった。麗太君と同じクラスだよ!」
麗太君も嬉しそうだ。
しかし彼の声の事や、これからの友人関係を、クラスメイト達はどう受け止めるのだろうか。
今までの様に会話が出来ない事を考えると、その影響は多大なものに違いない。
それでも麗太君と出会ってからの短い期間、彼を嫌う様な事はなかった。
きっとクラスの皆も、彼の事を受け入れてくれる筈だ。
窓から注ぐ春の日差しは、教室の並ぶ長くて一直線な廊下を照らしていた。
やはり廊下には誰もいない。
皆が教室に入っているのだろう。
二人で歩を忍ばせて廊下を歩く。
二階廊下の一番奥。
そこに五年二組の教室はあった。
後ろには麗太君が、しっかりと付いて来ている。
やはり、五年二組の教室は静かで、皆が席に座っている様だ。
どうしよう、こんな状況で教室に入るなんて、なんだか恥ずかしい。
それに麗太君もいるし。
朝から男の子と一緒に登校なんて、きっと何か変に思われるに違いない。
でも、このままでもいられない。
「行くよ」
振り返る事なく、後ろの麗太君に小声で言うと、私は教室へ入った。
皆の視線が私に集中する。
恥ずかしくて頬が火照る。
教室に入って、最初に目に着いたのは担任の先生だった。
若くて、表情にはどこか幼さが残っている女の人だ。
「あら、初日に遅刻とはやってくれるわね」
先生は、僅かに笑みを浮かべながらそう言った。
笑みを浮かべているからこそ、どこか怖い。
「あの……えぇっと、寝坊……しちゃって……その……」
言葉を探している私に笑い掛ける。
「分かったわ。いつまでも春休みの気分じゃ駄目よ」
教室中がざわつく。
笑っている人もいれば、どこか上の空な人もいる。
そういえば、マミちゃんは……。
教室内を見渡すと、窓際の一番奥の席に彼女の姿がある。
マミちゃんは私を見る事なく、ただ無感情に窓の外を眺めていた。
「えっと、平井優子ちゃんね」
「え? あ、はい」
「私は藤原博美。今年から五年二組の担任をさせてもらいます。宜しくね」
私は慌ててお辞儀をする。
「あっ、はい! 宜しくお願いします!」
おかしい。
どうして先生は、麗太君の名前を出さないのだろう。
さっきから一緒にいるのに。
「麗太君」
彼の名前を呼んで振り返ったが、そこに麗太君はいなかった。
「あれ?」
「どうしたの?」
「あの……私……」
麗太君が、ここにいた筈。
そう言おうと思った。
「……なんでもないです」
しかし言えなかった。
なんとなく、男の子と登校したという事実を、誰かに知られるのが嫌だったのだ。
麗太君、どこに行ったんだろう。
彼の事を心配しているうちに、朝の会は終了した。
始業式は一時間目に始まる。
皆が移動しようと廊下に出る最中、麗太君はこっそりと教室に入って来た。
教室に入って来た麗太君に出くわした先生は、何かを察したように自分の自己紹介だけをして、彼を廊下に誘導した。
おそらく先生は、麗太君の事情を考えた上で、あの対応をしたのだろう。
今年の担任の先生は、なかなか親しみのある人の様だ。
「今朝の事です。皆さんがランドセルを背負って元気良く登校する姿。いやぁー、晴々しく思いますねぇ」
壇上の上に立つ校長先生は、シワだらけの顔でにっこりと笑う。
ママから聞いた話によると、校長先生は今年で定年なのだそうだ。
だからPTAや若い先生達は、よぼよぼで今にも死んでしまいそうな校長先生に、かなり気を遣っているとかどうとか。
「あの人の話って長過ぎ。今年一杯なんて言わずに早く辞めれば良いのに」
私の後ろで、冷たく呟いたのはマミちゃんだった。
クールで、どこかお姉さんっぽくて、ちょっと毒舌なマミちゃん。
それでも男女共に評判が良く、教師受けも良いらしい。
密かな私の憧れでもある。
「話長い。あの校長、本当に辞めてくれないかなぁ」
しかし、友人として性格や言動は理解しているつもりだ。
「マミちゃん、そんな事言ったら駄目だよ。校長先生は、もうあんなにおじいちゃんなんだから」
「おじいちゃんだからって、優しくする通りはないよ。老害って言葉、知らないの?」
老害なんて言葉を聞いたのは初めてだ。
「え? えぇっと……」
言葉に詰まる私に、マミちゃんは頬笑む。
「優子は優しいね。でも、優し過ぎると損する事もあるんだよ……」
「どういう事?」
問い返した時、マミちゃんは私から目を反らしていた。
マミちゃんは、知り合った時から妙な事を度々口にしている。
彼女との付き合いは長いが、その言葉に隠された意味も、考えも、私には知る由もなかった。
始業式の後、クラスで学級活動が行われた。
当然の様に、最初はクラスメイト全員の自己紹介から始まる。
どうせ、たった二クラスしかないんだから、殆どが顔見知りな訳だけど。
麗太君はどうするのだろう。
言葉を発する事が出来ないのだから、自己紹介以前の問題だ。
そういえば、始業式の時にクラスの男の子達と楽しそうに笑っている姿を見た。
もしかしたら、私がそこまで心配する必要はないのかもしれない。
皆が順に席を立ち、その場で自己紹介をする。
数人の自己紹介が終わり、麗太君の番になった。
おそらく、先生がフォローを入れてくれるに違いない。
先生がどんな行動を取るのか、少しだけ気になった。
「次は……沙耶原麗太君ね」
麗太君が席を立つと、教室に所々からひそひそと小さな声が聞こえて来る。
「沙耶原君、声が出せなくなっちゃったんだって」
「あ、それ知ってる。でも、どうして?」
「よく分からないけど、交通事故がどうとか」
以外にも、麗太君が喋れなくなったという事に関しては、クラス中に広まっている様だ。
声の主の大半が、クラスでは活発そうなグループの女の子達だった。
そんな女の子達を、どうしてか男の子達は睨んでいる。
その一方で他の女の子達は「私は関係ない」といった表情で、目線を反らしている。
麗太君の事に関して、勝手に何かを言われるのが気にくわないのだろう。
しかし、ここで目立つような行動を取れば、これから女の子達から敵視される。
きっと怖い筈。
勿論、私もそうだ。
同じ女の子をクラス内で敵に廻せば、教室で肩身の狭い思いをするのは間違いない。
そうだ、マミちゃんなら。
彼女なら、女の子からの評価も良くて人望も厚い。
もしかしたら、どうにかしてくれるかも。
そう思い、マミちゃんの席の方を見た。
やはり、相変わらず窓の外ばかりを眺めていて、何かをしようとする気配は見られない。
ここは先生に任せるしかない様だ。
教室の脇で、今まで皆の自己紹介を聞いていた先生が、麗太君に代わって喋り出した。
「沙耶原麗太君は、春休み中に色々あって、声が出せなくなっちゃったの。でも、声が出せないだけで、今までの麗太君とは何の変わりもないの。だから皆、沙耶原君の支えになってあげてね」
納得した様に皆が「はい!」と返事をする。
それを聞いて、麗太君は安心した様に席に座った。
クラスメイトの皆が、先生の話を納得したかの様に思えた。
しかし聞こえて来る。
「色々って何だろう」
「ママとパパの事とかじゃないの?」
「あ! それ有り得るかも!」
女の子達の、麗太君に関する勝手な妄想話は未だに続く。
もう我慢ならないよ!
女の子達を敵に回したら、その時は何か打開策を考えれば良い事だ。
立ち上がろうとした瞬間。
「いい加減にしろよ」
男の子の怒り気味の声と、椅子を強く退かして立ち上がる音が聞こえた。
私は数センチだけ浮かしたお尻を、再び椅子に落ち着かせる。
声のした方を振り返ると、そこにはまるで中学生の様な容姿をした男の子がいた。
男の子にしては少しだけ長い髪、高い背丈。
たしか、光原綾瀬君だったかな。
成績優秀でスポーツ万能な優等生。
おまけに顔立ちも良いから女の子にモテモテ。
男女問わず皆の人気者。
そんな少女漫画のヒーロー的な存在、光原綾瀬君の事は、友達の話題によく出て来るので、なんとなく知っていた。
同じクラスになったのは、今年が初めてだ。
光原君が席を立ったからだろう。
皆が彼に注目している。
「麗太の何が分かるっていうんだよ? 何も知らない癖に、麗太の事を勝手にどうこう言うのは気に入らないな」
皆が光原君を見る目、それは男女問わず正義の味方でも見ているかの様な、期待に満ち溢れた眼差しだった。
先生は光原君を止めようともせず、その光景をただ見ている。
「ごめん」
一人が謝罪した。
それに続いて、先程の女子グループの内全員が「ごめん」と口にした。
光原君に注意された事がショックだったのか、彼女達は浮かない顔をしている。
「分かれば良いから」
そう言って、彼は笑顔を振り撒く。
彼女達は機嫌を取り戻したのか頬を赤らめて、それから何かを言う事はなかった。
今日は初日という事もあり、昼前に学校は終わった。
どうやら麗太君は、光原君や男の子達と帰る様だ。
帰る家が同じだからといって、別に一緒に帰る義理はない。
それなら、私はいつも通りマミちゃんと帰るべきだろう。
学校に来る前に、ママにもいつも通りに帰ると言ってあるし、問題はない筈だ。
教室の後ろのドアには、ランドセルを背負い、左手に巾着袋をぶら下げているマミちゃんが私を待っていた。
「優子、早くしないと先に帰っちゃうよ」
そんな事を言っているが実際のところ、マミちゃんが私を置いて先に帰った事はない。
新しく配られた教科書をランドセルに詰め込み、マミちゃんの元へ駆け寄った。
「よし、じゃあ帰ろっか」
マミちゃんは少しだけ笑んで、「……うん」とだけ言葉を返した。
学校からの帰り道である通りは、人や車の通りが多く、それに加えて帰宅中の私達と同じ小学生も、ちらほらと見られた。
もう昼時だ。
この時間になると無償にお腹が空く。
「今日のお昼は何かなぁ」
呑気に呟くと、隣にいたマミちゃんはクスッと笑った。
「優子は呑気だね。その頭の中には三食の事しか入ってないのかな?」
「そんな事ないよ。昼時だから考えてるだけ」
「優子の母さんが作ってくれる昼ご飯?」
「うん!」
「そっか、美味しいよね。優子の母さんが作ってくれる物なら何でも」
マミちゃんは、私のママと仲が良い。
というより、マミちゃんが一方的に憧れている、とでも言うのだろうか。
どうしてかママの前では、マミちゃんはいつもの様なクールな表情は見せず、敬語まで使って楽しそうに話しているのだ。
それは私達がまだ小学二年生の頃、マミちゃんが初めて私の家を訪れた時からだった。
「ねえ、優子の家に寄っても良い?」
「え? なんで?」
「前に優子の家に行った時、優子の母さんから料理本を借りたから返そうかと思って。あんまり長く借りてるのも悪いし。それに、ほら」
左手に持っていた金着袋を半開きにし、中身を見せてくれた。
中には綺麗にラッピングされた数個のクッキーが入っている。
「優子の母さんに借りた料理本で作ってみたの。本を返すついでに食べてもらおうと思って」
そういえばママは、マミちゃんの作ったクッキーを早く食べてみたいと言っていた。
しかし、私の家には麗太君が一緒に住んでいる。
もし、マミちゃんと麗太君が家で鉢合わせでもしたら……彼女はどう思うだろうか。
クラスメイトの男の子と一緒に住んでいるなんて、マミちゃんは私の事をどう思うだろうか。
せっかく、クッキーを作って来てくれたのだ。
帰ってもらうにしても、なんだかマミちゃんに悪い。
結局、マミちゃんを家まで連れて来てしまった。
どうしよう……。
今更、マミちゃんに帰ってもらうにしても、きっと彼女は聞かない筈だ。
麗太君が先に帰って来ていませんように。
無駄な祈りを込めて、玄関のドアを開けてマミちゃんを招いた。
「ただいま」
「お邪魔します」
玄関に麗太君の靴がないという事は、まだ帰って来ていないのだろう。
「おかえりないさい」
奥からママが出て来る。
「マミちゃん、いらっしゃい」
ママを見るなり、マミちゃんは頬を少しだけ赤く染めて、料理本とクッキーの入った巾着袋を差し出した。
「あの、これ……作ってみたんです。よかったら……食べてみて、下さい」
ママの前でのマミちゃんって、なんだか素が現われている様で可愛いな。
「はい、ありがとうね。そろそろお昼だから、マミちゃんも一緒に食べてく? 今日はチャーハンよ」
「良いんですか?」
「ええ、勿論よ」
私とママ、その向かいにマミちゃん、
テーブルの上には三人分の皿に盛られたチャーハン。
どうやら麗太君の分はキッチンに置かれている様だ。
どうにかして、麗太君が帰って来る前にマミちゃんには帰ってもらわないと。
「このチャーハン、凄く美味しいです!」
「そう、良かった。いっぱい食べてね。おかわりもあるから」
「はい!」
ママの前でのマミちゃんは活気があって、学校では露わにする事のない表情を見せる。
今から「帰って」だなんて、無茶なお願いは出来そうにない。
麗太君が帰って来る前に、マミちゃんをどうにかしなければと考えを巡らせ、チャーハンを一口二口と口に運んでいた矢先、玄関のドアが開く音がした。
「あ、麗太君が帰って来たみたいね」
ママは立ち上がり、玄関の方へ行った。
「え? 麗太君って……沙耶原……」
驚いた様な顔をした後、マミちゃんはそう呟いた。
麗太君が帰って来てしまった。
もう、マミちゃんに何を言っても誤魔化す事は出来ない。
そう悟った。
ママは「花壇に水をあげて来る」等と言って、残したチャーハンをラップに掛けて外へ出て行ってしまった。
私、マミちゃん、麗太君をリビングに残して。
出されたチャーハンを黙々と食べている麗太君を、マミちゃんは怖い目でジッと見ている。
どうやら麗太君は、ここにマミちゃんがいる事に関して、全く気にしていない様だ。
「あの……マミちゃん……」
情けなく呼び掛けると、マミちゃんはテーブルを手の平で強く叩いた。
「どういう事か説明して欲しいんだけど」
彼女の表情はいつも以上に不機嫌そうだ。
正直に話せば、きっと分かってくれる筈。
「あの、これには事情があって」
「事情? じゃあ話してよ。大方、予想は付くんだけど」
「え?」
「沙耶原の母さんが死んだから、沙耶原は優子の家で面倒になってる訳でしょ?」
彼女の言葉を聞いた麗太君は、チャーハンを食べる手を止め、マミちゃんを睨んだ。
マミちゃんは、前から男の子に対しては常に敵対心を剥き出しにしていたけれど、今の発言はさすがに酷過ぎる。
「そういう事なんだけど……マミちゃん……駄目だよ。そんな言い方……」
「は? 優子も、優子の母さんも甘すぎるんだよ。いくら家が隣同士だからって、優子の家に沙耶原を居座らせる事はないと思う。それに、沙耶原の父さんは? どうして息子だけを隣の家に預けてるの? 沙耶原、父さんはどうしたの?」
麗太君は今まで見せた事のない様な、不機嫌極まりない顔をして、メモ用紙にシャーペンを走らせた。
『天美には、僕の父さんの事も母さんの事も関係ない。お前にどうこう言われる筋合いなんてない』
そう書かれたメモ用紙を見せられたマミちゃんは軽く舌打ちを鳴らし、麗太君を睨む。
「はぁ? 私は、あんたが優子の家にいる事が気に喰わないって言ってんの! 分かる?!」
『優子と優子の母さんは、ここにいて良いって言った』
「え?」
拍子抜けした様な声を上げ、マミちゃんは悲しげに私を見た。
「優子……」
「マミちゃん……あの……」
少しの沈黙が下りたすぐ後、ママが戻って来た。
「あらあら、どうしたの? なんか雰囲気が暗いわよ。もしかした、優子とマミちゃんで麗太君の取り合いでもしてたの?」
「ち、違います! そんな訳ないじゃないですか!」
からかい気味なママへ、真っ先に反論したのはマミちゃんだった。
それに続いて焦り気味に答える。
「からかわないでよ! そんな話してないから!」
「えぇー? つまんないの。私が皆位の頃は、興味本意でチューとかしてたんだけどねぇ」
「え? チュー?!」
ママの言葉を聞いた瞬間、頬が熱くなった。
きっと、かなり赤面している事だろう。
しかし、マミちゃんと麗太君は先程と変わらず不機嫌そうだ。
ママはそれを見兼ねたのか、私達に言った。
「食後だけど、お茶にしない? さっき、マミちゃんが持って来てくれたクッキーもあるし」
四人分の高そうなカップに入った紅茶と、先程のクッキーを皿に盛った物を、ママはテーブルの上に並べた。
普段は紅茶を飲む際に、こんなカップは使わない。
マミちゃんに対して見栄でも張っているのだろうか。
皿に盛られた数個のクッキーから一つを摘まみ、口に運んだ。
美味しい。
口に広がった甘い味は、以前にママが作ってくれた物と同じ味がした。
ママや麗太君も、私に続いてクッキーを食べる。
「凄い。私が作るクッキーと同じ味だわ」
「本当ですか!? 嬉しいです!」
マミちゃんは嬉しそうに笑い、紅茶を飲む。
「この紅茶も美味しいですよ」
「そうでしょ。庭にあるプランターで植えた葉を使ってるの。前に、優子と麗太君で葉を摘んだのよ」
そういえば、春休みに手伝わされた覚えがある。
毛虫やらミミズで大騒ぎしている私やママを横に、麗太君は平気な顔をして虫を追い払ってくれたんだっけ。
あの時は、さすが男の子だなぁと関心したものだ。
「え? 沙耶原が?」
「うん。麗太君、凄く頼りになったんだよ。私やママが虫を見て大騒ぎしてたら、麗太君が追い払ってくれたの!」
「そうそう。やっぱり男の子ね」
麗太君は照れ臭そうに微笑み、紅茶を飲んだ。
「そう……沙耶原が……」
それから私達は暫くの間、世間話やテレビゲームで盛り上がった。
マミちゃんが麗太君と少しだけ距離を置いているのは、やっぱり気になったけれど。
「私、そろそろ帰りますね」
「あ、もう五時じゃない。そうね、そろそろ帰らないとね」
「……はい」
帰り際、なぜかマミちゃんは、どこか悲しげな表情を浮かべていた。
私はマミちゃんを外まで見送った。
空はすっかり真っ赤な夕焼け色に染まり、遠くの方の空から見えるオレンジ色の陽が、とても綺麗で眩しい。
「マミちゃん、また来てね」
「うん。ありがとう、優子。またね」
帰り道を一人で歩くマミちゃん。
赤いランドセルを背負ったその背中は、学校で見せる強気な言動や表情とは裏腹に、とても小さく見えた。
麗太君と光原君は、よく一緒にいる。
あと、周りに男の子が数人。
休み時間には、そのメンバーでサッカーをしている様だ。
教室のベランダからは、校庭が一望できる。
「麗太、行ったぞ!」
跳んで来たサッカーボールを麗太君は胸で受け止め、迫って来る相手チームの男の子達を、凄いペースで抜いて行く。
そして、あっと言う間に点を決めてしまった。
麗太君って、サッカー上手いんだ。
「優子、いつから男子の生態を観察する様な子になっちゃったの?」
隣で一緒に試合を見ていたマミちゃんは、いつも通り不機嫌そうな口調で問うた。
「生態って……動物じゃないんだから……」
今まで、こんな事をして休み時間を過ごす事はなかった。
マミちゃんや他の女の子達と適当に何かを話し、ダラダラと過ごすだけ。
今日は休み時間に陽の光に当ったせいか、どこか新鮮だ。
「沙耶原君って、今まであんまり目立つ様な子じゃなかったけど、凄く格好良いかも」
「えー、そうかな? 私は光原君かなぁ」
隣にいた女の子達は男の子達の試合を見て、あの子が良いだのと議論している。
皆、私よりも遥かに考えが大人だ。
「ねえ、優子は誰が好みなの?」
「は!?」
いきなり質問を振られた為、そんな間の抜けた声を上げてしまった。
「で、どうなの?」
「うーん……私には、まだそういうのは早いかな……」
「またまた、優子はいつもあやふやだなぁ」
「じゃあさ、マミちゃんは?」
次は、ベランダの箸でボーっとしていたマミちゃんに質問が向けられる。
「男子とか……敵でしかないでしょ?」
逆に返された冷たい一言で、その場の空気が張り詰めた。
自分自身がこの場にいては、空気が悪くなる。
そう思ってしまったのか、マミちゃんは教室に戻ってしまった。
「マミちゃん!」
呼んでも何も反応せず、そのまま教室のドアを開けて廊下へ出て行った。
マミちゃんは機嫌が悪くなると、いつも一人でどこかへ行ってしまう。
しかも、かなり長く根に持ってしまって、酷い時には三日間、誰にも口を利かなかった事がある。
「……どうしよう……」
「放っておけば良いじゃん」
「え?」
「勝手にベランダから出て行ったの、マミちゃんなんだから」
その口調は、どこか冷たかった。
「そんな……放っておけないよ!」
ベランダから教室を抜けて廊下に出ると、マミちゃんはまだ見える距離を歩いている。
「マミちゃん」
追い掛けてマミちゃんへ呼び掛けた。
しかし、マミちゃんを歩を止めず、振り返る事もなく歩く。
「マミちゃん!」
いくら彼女の名前を呼んでも、こちらを振り返ってはくれない。
ダメだ。
この調子だと、以前の様に口を利いてくれなくなってしまう。
どうしたら良いのだろう。
マミちゃんが私に耳を傾けてくれる言葉。
もしくは、マミちゃんの心情が大きく動く言葉……。
頭の中で展開された私の考え。
マミちゃんが動揺する言葉。
それと言ったら、もうあの渾名しかない!
「ま……マミマミ!」
私に背を向けていたマミちゃんは、渾名を叫ばれた瞬間、勢いよく振り返った。
天美マミ……あまみまみ……まみまみ……マミマミ。
それは以前、マミちゃんが初めて私の家に来た時、ママが付けた渾名だ。
からかい気味にマミマミと呼ぶママに対して、マミちゃんは頬を真赤に染めて右往左往としていたものだ。
それからというもの、マミマミという渾名で彼女を呼ぶと、その日の事を思い出してしまうのか、確実に頬を真赤に染めて動揺を隠し切れなくなる。
「あ……ま、マミマミって……。それ、いつの渾名よ! 馬鹿じゃないの! どうして今、その渾名で呼んだの?!」
どうやら渾名で呼んだのは効果抜群だった様だ。
マミちゃんの表情が柔らかくなった。
頬を真赤にして焦っちゃって、なんだか可愛い。
私はケロリと答える。
「可愛いと思って」
「馬鹿……そんな事……ない」
口ではそう言っているが、照れているのを隠し切れていない。
マミちゃんが、これ以上機嫌を悪くする事はなさそうだ。
機嫌を損ねた理由。
それは先程の皆の態度もあるかもしれないが、何より麗太君の事だろう。
「麗太君の事……もしかして怒ってる?」
「別に怒ってはいないよ。怒る事でもないし……」
「ただ」とマミちゃんは続ける。
「何て言うか……。ちょっとだけ不安だったのかも」
「何が?」
「その……」
マミちゃんは少しだけ言葉を詰まらせ、目を反らした。
「優子が……沙耶原と一緒に住んでるなんて……」
隣に住んでいた男の子と同居する。
最初は少しだけ抵抗があったけれど、もう既に慣れてしまった。
というより、私、ママ、麗太君の三人の生活は、今までになかった様などこか異質な楽しさがある。
今のところは、それほど嫌な想いもしていないし、生活に支障もない。
何も問題はないのだ。
「マミちゃんは、何をそんなに心配してるの?」
私の質問に、少しだけ間を開けて、マミちゃんは突然、安心した様に息を吐いた。
「……何でもないよ。もう、いいよ。優子は、何だかんだで楽しくやってるんだね」
「うん、まあね」
「そっか。それなら、良いんだ」
普段、マミちゃんから見る私はどう見えているのだろう。
マミちゃんは、私や麗太君をどう見ているのだろう。
一つだけ、確信した事がある。
きっと、マミちゃんは私の事を大事に思ってくれている。
それがとても嬉しかった。
=^_^=
廊下、教室、校庭、夕日が何もかもをオレンジ色に染めていた。
教室へ降り注ぐ夕陽はとても眩しくて、それでいてどこか心地良い。
こんな夕暮れ時まで学校に残っているのは、おそらく去年の運動会以来だろう。
というのも、私達は授業が終わった後、友人数人で時間を忘れてお喋りをしているのだ。
もうクラス内では情報通なキャラで定着している由美ちゃんの話は、とても面白くてのめり込んでしまう。
私とマミちゃんは、彼女の話に夢中だった。
「ここだけの話なんだけどね。担任の藤原先生、今までで彼氏が五人もできていたらしいよ」
「五人?! それって……凄いの?」
驚く私に、マミちゃんは何ら変わらぬ口振りで言う。
「まあ、大人の女の人ならそれくらいは普通なんじゃないの」
「へぇ、普通なんだ……」
「まあ、今年で二十五だもんね。二十五年間も生きていれば、それくらいはねぇ」
「え? 藤原先生って今年で二十五歳?!」
「あ! これは言う筈じゃなかったんだけどなぁ」
由美ちゃんはキッキッキと、作った様な笑い声を出す。
「由美ちゃんはいろんな事を知ってるね」
「でもそれ、クラス内の事だけでしょ? ていうか、それしか知らないでしょ?」
そんな彼女の冷たい一言に、由美ちゃんはケロリと答える。
「そんな事ないよ。クラスだけじゃなく他の事も知ってるよ」
「え、何? 聞きたいなぁ!」
「どうしようかなぁ。優子ちゃんやマミちゃんの事だから、きっと夜中にトイレに行けなくなっちゃうんじゃないかぁ」
「ちょっ、わ、私、ほん怖とか見ても一人でお風呂にもトイレにも入れたから!」
彼女のからかい気味な言葉に反応して、つい焦ってしまった。
本当は、お風呂にはママと一緒に入ったし、夜中のトイレには、ママを起こして付いて来てもらった事がある。
怖い話に、あまり耐性がある訳ではないのだ。
しかし、一番慌てていたのはマミちゃんの方だった。
「え? えっと、やっぱり……その話、私は……いいかな……なんて……」
明らかに怖がっている様にしか見えない。
まったく、昔からクールに振る舞ってはいるけれど、どこか抜けてるんだから。
「マミちゃん、もしかして怖いの?」
私の問いに、マミちゃんは更に大慌てする。
「そ、そんな訳ないでしょ! 私は……優子とは違うの……」
「へぇ、それじゃあマミちゃんのお手並み拝見といきますかぁ。どこまで私の話に耐えられるかなぁ」
私達は息を呑んで、由美ちゃんの話を聞き始めた。
ここ最近の話なんだけどね、隣のクラスの子が塾の帰りに変な女の人を見掛けたらしいよ。
その女の人は、真赤なコートを着て真っ赤なハイヒールを履いて、黒いサングラスに真っ白なマスク、それと物凄く長い髪をしてたんだって。
それでね、隣のクラスの子が、その女の人に話し掛けられたの。
「早くお家に帰りなさい。さもないと食べちゃうわよ」って。
女の人にしては凄く怖そうな低い声で……。
怖くなって逃げ出したんだけど、追い掛けては来なかったらしいよ。
ママにこの話をしたらね、この街では十何年か前にも同じ様な人がその時間に住宅街とか公園をうろついてたんだって。
これって、巷で言う口裂け女って奴だと思うんだ。
口裂け女。
その呼び名が出た瞬間、私はマミちゃんの手を咄嗟に握った。
マスク越しの耳まで裂けた痛々しい口、サングラスの下の血走った目、不気味な程に真っ赤な服。
話を聞き想像した口裂け女は、あまりにも恐ろしい。
「マミちゃん……帰りは……一緒だよね?」
たぶん、私は震えていると思う。
自分の住んでいる街に、そんな異質な存在がいるなんて事を考えたら、背筋が寒くなって来る。
「う、うん。勿論、帰る時は一緒に……」
どうやらマミちゃんも私と一緒で、怖がっていた様だ。
「まったく、二人とも怖がりだなぁ」
由美ちゃんは相も変わらず、私達を見てニヤニヤと嫌らしい笑みを浮かべている。
「由美ちゃんは怖くないの?」
「こういうのには慣れてるもん。もっと怖い話も知ってるし。聞きたい?」
全力で首を横に振った。
「それにね、今日はもうすぐお母さんが迎えに来てくれて、塾まで送ってくれるから、とりあえずは口裂け女に会う事もないしね」
「いいなぁー、由美ちゃんは」
私の家の車は、パパが出張先に乗って行ってしまった為、今はない。
でも、こんな噂話を本気で怖がって親を呼ぶなんて、小学五年生としては恥ずかしい。
それにまだ五時ちょっと前だ。
春の最初というだけあって、まだ陽は僅かに出ている。
帰るのなら今だろう。
「マミちゃん、そろそろ帰ろうか?」
「うん。今、私も帰ろうと思ってた」
由美ちゃんは、「口裂け女に食べられないようにね」と私達をからかいつつも、学校の少し外まで見送ってくれた。
先程よりも陽は沈み、辺りは薄暗くなっている。
たしか由美ちゃんは、口裂け女が出るのは住宅街や公園だと言っていた。
まさか本当に出て来るとは思っていないのだが……どうしても先程の話を意識してしまう。
商店街を抜け住宅街へ入ると、道を通る人の数は一層少なくなった。
「優子、なんか近いんだけど」
「え? そうかな……別に近寄ってたつもりはないんだけど……」
嘘だ。
本当は怖くて、先程からマミちゃんの方へ無意識のうちに寄っていた。
「出て来るわけないよね……口裂け女なんて……」
「まさか……住宅街なんだから怪しい人がいればすぐに目に付く筈……」
言葉が止まる。
「え、何? どうしたの?」
「……あれ」
マミちゃんは人差し指で前方を指差した。
前方の道の隅に建っている電柱。
その隣に誰かが立っている。
真っ赤なコートを着込み真っ赤なハイヒールを履き、顔にはサングラスとマスク、長く伸ばした髪を腰より下まで垂らしている。
口裂け女だ!
間違いない!
そう確信した。
マミちゃんは酷く震えた手で、私の手を握る。
目の前にいる見た事もない異形の存在、それを前に、私も怖くて動く事が出来ない。
マミちゃんは私に問う。
「あれ、口裂け女?」
「分かんないよ……。でも、そう決まった訳ではないし……走れば越せるかな……」
「馬鹿! そんな事して、もし捕まったら食べられちゃうよ」
「でも……このままここにいるわけにもいかないし……。回り道したら、時間かかって真っ暗になっちゃうし……」
マミちゃんの手に力が籠る。
「行こう。優子、私から離れないで」
そうは言っているものの、彼女の声はかなり震えている。
しかし、マミちゃんが自分に任せて欲しいと言っている以上、勝手な行動を取ったら結果は良い事には成り得ない。
それなら、マミちゃんに付いて行くだけだ。
「行くよ!」
マミちゃんの言葉を合図に、私達は走り出した。
手を繋いで、口裂け女と思しき女性の横を通り過ぎた時。
とても低い、まるで女性とは思えない様な声が聞こえた。
「もう暗くなるわ。早くお家に帰りなさい」
それを聞いた瞬間、背筋に悪寒が走り、とても嫌な気分になった。
マミちゃんの歩がより速まる。
手を繋いでる状態で、マミちゃんと私の距離が少しだけ空く。
私はマミちゃんに引っ張られる様にして、後ろを振り返らず走った。
家に着くと、私達は無我夢中で玄関に上がった。
すぐ後ろまで口裂け女が付いて来ている。
そんな気がしたのだ。
背負っているランドセルが重くて熱い。
汗のせいだ。
私とマミちゃんは息を切らしながら、ランドセルを背中から降ろした。
慌てて帰って来た私達が、どうやら騒がしかったのだろう。
リビングからママと麗太君が出て来た。
「ちょっと、二人とも。どうしたの? そんなに息切らして。かけっこでもしてきた?」
呑気なママの問いに、私は口調を荒げる。
「そんなんじゃないの! 出たの!」
「何かの当たりくじでも引いた?」
「違うの! 口裂け女!」
ママと麗太君は顔を見合わせ、次の瞬間笑い出した。
「まったくもう、この子は……口裂け女だって! いつの時代よ! 麗太君もそう思うでしょ?」
口を押さえて堪えながら麗太君は頷く。
「……本当に出たんです!」
マミちゃんがそう言うと、ママは少しだけ難しい顔をした。
「もしかして、赤いコートとハイヒール、それとマスクにサングラス……あとは……もの凄く低い声の……女の人?」
「はい、そうです! その人です!」
「なんで分かったの?」
「同じ人が出たのよ。私が高校生だった頃に……。あぁ、懐かしいわ……」
ママの表情はどこか切なげに見えた。
それでいて小学生である私には、到底理解する事の出来ない様な何かを秘めている。
そんな気がした。
「まあ、私に任せて!」
ママは胸を張って言い出した。
「どうするの?」
「口裂け女をね、この街から追い出すの。そりゃもう、ボッコボコにして」
「そんな、危ないよ!」
「そうです! 口裂け女に食べられちゃいますよ!」
私とマミちゃんの頭に手を置いて、ママは「うりうり!」と言いながら強く撫でた。
「大丈夫よ。明日には口裂け女なんて出て来なくなってるから」
根拠はないが、ママの言葉には何故か説得力があった。
ママの言う通り、次の日の夕方、その次の日の夕方も、口裂け女が出て来る事はなかった。
二週間程過ぎて、ママにその事に関して聞いてみると
「出て来ない? 当たり前よ。私が追い払ったんだから。私は街の平和を守るヒーローなの! 仮面ライダーよ!」
等と言って、妙に手の込んだ変身ポーズをとって見せた。
この街から口裂け女はいなくなり、彼女の噂を学校で聞く事もなくなった。
しかし、私の内では未だに疑問だけが残っている。
口裂け女の正体とその経緯。
そして何より……ママの正体だ。
ママに口裂け女が出没したと話した翌日から、それはこの街から姿を消した。
本当に口裂け女がいなくなった事が、ママの起こした一つの行動であるのなら、一体どのようにして……また、口裂け女を街から追い出す程の力量を持つ私のママは、一体何者なのか、全ては謎である。
=^_^=
春も終盤に差し掛かり、少しずつではあるが季節の移りを予感させていた。
そんな日曜日の午後の事。
「高校の頃の友達と会う約束をしてるの。夕飯までには帰って来るわ」
それだけ言うと、ママはテーブルの上に一枚のメモ用紙を置いて、出掛けて行ってしまった。
テーブルの上のメモ用紙……何が書いてあるのだろう。
手を伸ばしたが、寸前で止めた。
いくらママの物でも、勝手に見てはいけない。
我慢しよう。
そういえば、ママの高校時代の友達って、昔の彼氏とかだろうか。
再会を機にお付き合いする様な関係にでもなったら……。
まさか、パパがいるんだから、ママに限って妙な事はしない筈だ。
きっと、そうに違いない。
リビングのソファに寝転がり、テレビの電源を入れた。
適当にチャンネルを回すが、やはりこんな時間だ。
面白い番組なんて、あまりやっていない。
強いて上げるとすれば、ベタベタな展開の刑事ドラマだろうか。
回したチャンネルで放送している刑事ドラマが気になったので、番組表を見てみた。
『湯けむり温泉サスペンス 若おかみの事件簿』
なんてベタなんだろう。
逆に面白い。
こういったタイトルだと、何となくオチが見えて来るというものだ。
夏頃になると、年齢層の広いドラマが頻繁に見られるのだが。
「ああ……暇だなぁ。今年の夏はキッズウォ―とか五つ子とかやるのかなぁ……」
そんなどうでも良い事を呟いていた時、階段から音がした。
麗太君が二階から降りて来たのだ。
ドアを開けて、麗太君がリビングに入って来た。
麗太君は周りを見回している。
ママがいないからだろう。
「ママなら、高校の頃の友達に会うとか言って、出掛けて行ったよ」
麗太君は頷いて、お菓子の入っている戸棚を開けたが、それを見て溜息を吐く様にして戸を閉めた。
「何かお菓子ある?」
麗太君は首を横に振る。
「そっかぁ……」
「……」
部屋の中が静まる。
暇だ。
お菓子はないし、誰かと遊ぶにしても近場のマミちゃんは日曜日は塾だし。
本当に暇だ。
ソファーから半身を少しだけ浮かして伸びをした時、テーブルの上のメモ用紙がチラッと見えた。
それは、見てくださいとでも言わんばかりの位置に置いてある。
そういえば麗太君は……
今度は冷蔵庫を物色している。
「見ちゃえ」
ソファから体を起こしテーブルへ寄る。
裏返しになっているメモ用紙を手に取り、書いてあるものを見た。
丁寧に書かれた地図だ。
おそらく、家の裏を真っ直ぐに進んだ小さな通りだろう。
そこは大通りから大分離れていて、さらに特に立ち寄る目的もないので、そこには行った事がなかった。
端の一軒に赤いペンで二重丸が記されている。
「どこだろう……ここ」
「麗太君、ちょっと来て」
もしかしたら分かるかもしれないので、麗太君にも聞いてみる。
「ここ、どこだか分かる?」
麗太君は常に携帯しているシャーペンで、メモ用紙にそれを書いた。
『駄菓子屋』
「え? 駄菓子屋?」
麗太君は頷く。
「そんな所があったんだ。よく行ったりするの?」
『うん。僕も知ったのは最近。綾瀬とよく行くんだ。そんなに混む事もないし、静かだし、好きなんだ。あの駄菓子屋』
「そっか……光原君と……」
喋れない事で、あらゆる障害を生んでしまった麗太君の為に、光原君は静かで居心地の良い駄菓子屋を紹介してくれたのだろう。
なるほど、光原君がクラスメイトや先生から慕われる理由がよく分かる。
さすがだ、騒がしいだけの男子とは一味違う。
マミちゃんも、そういう男子の一面を見れば、少しは考えを変えてくれるかもしれない。
そういえば、どうしてママは駄菓子屋の位置を、地図に書いてまでメモに残したのだろう。
高校の頃の友達に会って来ると言っていたのも、何か引っ掛かる。
わざわざメモに位置を記して残したという事は、私……いや、私と麗太君をそこへ誘導する為?
分からない。
でも今、私達がする事はただ一つ。
「麗太君、駄菓子屋まで案内して!」
麗太君は、待ってましたと言わんばかりに頷いた。
どうやら彼も乗り気の様だ。
私達は、日常から外れた様な少しばかりの冒険心を抱いて、自宅を後にした。
麗太君に案内されて着いた駄菓子屋は、自宅から十分程の場所にあった。
表の大きな通りから外れ、裏の通りを行き、古そうな民家の連なる通りの一角。
外には、何種類かのアイスが詰められたケースが置かれている。
入口の硝子戸はというと、閉まってはいるが、営業中という木製の小さな掛札が戸に引っ掛かっている。
どうやら営業中の様だ。
しかし……どうも人を寄せ付けまいとしている様な雰囲気が、入り口全体に漂っている。
「ねぇ、この駄菓子屋……営業中って書いてあるけど、普通に入って大丈夫なの?」
頷くと、普通に駄菓子屋の硝子戸を開けてみせた。
薄暗い店内の壁や小さなケースには、幾つもの駄菓子が詰め込まれている。
よく見ると駄菓子だけではない。
文房具やエアガン等、種類は様々だ。
店の人は店内にはいない。
代わりに、店の奥に障子で閉まっている座敷から人の声が聞こえる。
店を放っておくなんて、悪い人でも入って来たらどうするのだろう。
不用心だなぁ。
天井からは鈴の付いた紐がぶらさがっている。
物を買う時は、これを鳴らして呼んでくれ、という事なのだろうか。
麗太君はそれの先端を持ち、揺らして鈴を鳴らした。
すると、少しの間を置いて障子が開き、よぼよぼのお婆ちゃんが出て来た。
床に杖を突いて、今にも倒れそうだ。
「あら、麗太君。来てくれたんだね。それと、隣にいる女の子は優子ちゃんかな」
よぼよぼのお婆ちゃんは、私を見てにっこりと笑う。
「え? 私?」
「そうだよ。あんた達が今日ここに来る事は、さっき香奈ちゃんから聞いたんだよ」
「香奈ちゃん?」
香奈……平井香奈。
私のママの名前だ。
「どういう事? どうしてママが? だってママは、高校の頃の友達に会うって言って……」
「リビングのテーブルの上に、ここを示したメモがあったでしょう」
確かに私達はメモを見て、ここまで来た。
全部、ママとこのお婆ちゃんが仕組んだのだろうか。
でも、どうして?
「香奈! 博美! こそこそしてないで出て来なさい!」
「え?!」
突然、お婆ちゃんは名前を呼んだ。
「ネタばらしには早いと思うんだけどなぁ」
そう言って座敷の奥から出て来たのは、ママだった。
隣にもう一人。
「でも、優子ちゃん。困っちゃってますよ」
藤原先生だ。
「藤原先生?!」
私と麗太君は顔を見合わせる。
「麗太君、もしかしてママから何か聞いてるの?」
麗太君は首を横に振る。
良かった。
私だけが何も知らない訳ではないようだ・
藤原先生とママが座敷から降りる。
「こんにちは。優子ちゃん、麗太君。二人とも、学校以外で会うのは初めてね」
「え……あ、はい。そうですね」
色々な事が突然に起こり過ぎて、上手く言葉が出せない。
「ちょっと、優子。先生の前なんだからハキハキしなさいよ」
ママはからかう様に私に言った。
「で、でも……あの」
「まあまあ上がりなさいよ。長い立ち話なんかしてたら腰にくるわ」
お婆ちゃんは私達を座敷の奥の部屋に招いた。
表の駄菓子屋の外観とは打って変わって、招き入れられた座敷の奥には、普通の居間があった。
中央には縦長な卓袱台が置かれていて、部屋の隅には大きなテレビがある。
卓袱台の上に置かれた駄菓子の束や、三つの湯のみ茶碗と急須を見るに、三人ともさっきまでここで談義していたのだろうか。
「さぁ座って」
お婆ちゃんに言われ、皆が縦長な卓袱台を囲んで座る。
「はい、どうぞ」
お婆ちゃんは私達の前に、粉の入った小さな市販の袋を二つ置いた。
袋には、よく見るコーラとサイダーの模様が描かれている。
「これは?」
「知らないのかい。ちょっと待ってなよ」
お婆ちゃんはゆっくりと立ち上がり、暫くしてから水の入ったコップを二つ持って来た。
袋をポンポンと叩き、コーラと書かれている方の袋の粉を水の中に入れ、かき混ぜる。
すると、コップの中の水はたちまち泡を発し、コーラと同様黒く染まった。
「飲んでごらん」
お婆ちゃんはコップを私達の前に差し出す。
怪しいとは思ったのだが興味の方が勝り、コップの中のコーラらしき液体を一口飲んだ。
おいしい。
というより、これは普通のコーラだ。
「どうだい?」
「おいしい!」
「そうかい、良かった」
藤原先生は微笑ましそうに言う。
「やっぱり似てますね。香奈さんと優子ちゃん」
「そうね。私も昔は、よくこれを飲んでいたものね」
昔……そういえば、ママと藤原先生はどういう関係なのだろう。
それにこのお婆ちゃんは?
「ママは、藤原先生とお婆ちゃんとは、どういう関係なの?」
「そうねぇ、一番に話さなくちゃならない事が抜けてたわね」
ママは駄菓子を一つ取り自分の側に置き、お茶を一口飲むと話を切り出した。
ママの話によると、高校の頃の友達、つまり藤原先生とは、この駄菓子屋で知り合ったのだそうだ。
その頃、ママは高校生。
藤原先生は、まだ小学生だった。
年を経ても、藤原先生との付き合いは長く、今日の様に大人になった今でも頻繁に会っている。
私が見たテーブルの上に置かれたメモ用紙は、全てママの計算で、私と麗太君を駄菓子屋に誘導する為の物であった。
「あの頃が懐かしいわ。友達は皆、この街を離れて都心に引っ越しちゃったし。今となっては、残る私の友達は博美だけね」
ママは少しだけ悲しそうな顔をしていた。
数週間前、麗太君のママは亡くなっている。
きっとママの心には、その事も大きな傷として残っているのだろう。
ママの周りにいた人は、少しずつではあるがいなくなっていく。
きっと、大人になれば私も……。
でも今は、ママの周りにはたくさんの人達がいて、ママを支えている。
「今は、私が……いるから」
「え?」
恥ずかしくて、顔が火照ってきた。
「私がいるから。麗太君も、マミちゃんだって。パパだって、すぐに出張から帰って来るよ」
私は何て事を勢いで言ってしまったのだろう。
本当に恥ずかしい。
麗太君だって側にいるのに。
「……ありがとう、優子」
赤面して俯く私に、ママはいつもの様にからかう事もなく、穏やかに微笑んでくれた。
高校時代のママ、その頃の藤原先生の話。
私や麗太君の学校での話。
長い話に明け暮れた後、私達は座敷から降りた。
既に陽は傾き始めていて、駄菓子屋の入り口である硝子戸からは、オレンジ色の光が真っ直ぐに差し込んでいる。
帰り際、お婆ちゃんは私と麗太君に言った。
「何か好きなお菓子を一つ持って行きなさい。今日はタダで良いからね」
「お婆ちゃん、ありがとう!」
棚の上には、スーパーで買える様なお菓子もある。
どうせなら食べた事のない様なのが良いなぁ。
「麗太君は、どんなのが好きなの?」
振り返ってみると、麗太君は店の隅にしゃがんで何かを見ていた。
「どうしたの?」
近寄ってみると、隅には丸く太った白い猫が座っていた。
目の前だけをじっと見つめていて、まるで動こうとしない。
なんでこんな所に猫が……さっき店に入った時には、いなかった様な……。
もしかしたら、気付かなかっただけかもしれない。
そもそも、この猫は本物なのだろうか。
恐る恐る猫の頭を撫でてみた。
すると、ニャアァ―という、なんとも脱力気味な、それでいてどこか可愛らしい泣き声を発すると、大口を開けて大きなあくびをした。
「この猫……本物だよ!」
喜んでいる私に続いて、麗太君も猫を撫で始める。
気持ちが良いのか、猫は太った体を床に倒し、寝そべって腹を出して見せた。
「可愛い!」
興奮している私の声を聞き付け、座敷の前で話していたママ達が来た。
「なんだマル、また来たのかい」
お婆ちゃんは上の棚に置いてあった猫の餌の入った皿を取り出して、床に置いた。
皿に盛られた餌を、猫は尻尾をゆっくり振りながら食べ始めた。
ご機嫌なのだろうか。
「マルって?」
「太くて丸いからマル。こいつの名前さ。ずっと前から、勝手に入って来るのが習慣になっちまったのさ」
「ずっと前?」
「私が高校生の時からよ」
ママは屈んで、ゆっくりと猫の頭を撫でる。
「ママが?」
「そうよ。さすがに、同じ猫ではないと思うけど。そうねぇ、もしかしたら、今ここに来てるマルは、私が高校生の時のマルの子供かもしれないわね」
マルには飼い主が付けてくれる鈴がない。
おそらく野良だ。
そういえば、入り口の硝子戸は閉まっていたのに、どこから入って来たのだろうか。
ふと、上の方に位置する開いた窓から、外の光が差し込んでいる事に気付いた。
なるほど、あそこから入って来たのか。
「お婆ちゃん、あの窓」
「あれは、マルが好きな時に入って来れる様にする為の物さ。マルも親子揃って大事なお客さんだからね」
マルも、私達と同じだ。
親から子へ、自分の好きな場所や物は伝えられていく。
ママもこの場所が好きで、私達をここに呼んだのだろう。
勿論、私もこの場所が好きになった。
だから今度は、マミちゃんにも教えてあげよう。
ママや麗太君、藤原先生も、皆でここに集まればきっと楽しいから。
Episode3 First love
七月になると、日射しは更に強くなり、外に出る事が億劫になる。
特に放課後の帰宅は、時間的に日差しが強いから、家に着いた頃には体は汗まみれになってしまう。
家に帰り、リビングの戸を開けると、とても気持ちの良い冷風が体をすり抜ける。
ああ、幸せ。
ここは天国か?
暑い外から涼しい部屋に入る度に思う。
「あら、おかえり」
ソファに寝転がって、ママは雑誌を読んでいた。
すぐ隣のテーブルにはアイスコーヒーが置かれている。
良いなぁ……ママは……。
「汗かいたからシャワー浴びて来るね」
「その前に、部屋にランドセル置いて来なさいよ」
「はーい」
部屋に戻り、ランドセルを降ろした。
「熱っ」
直射日光がランドセルの表面に当たっていた為、かなりの熱を帯びている。
触らないで置いておいた方が良いかな。
洗面所で汗まみれの服や下着を脱ぎ、洗濯機に突っ込んだ。
「ふぅ……」
汗びっしょりの服や下着を脱いだからか、なんだか重荷が外れた気分がして、とても気持ちが良い。
洗面台の鏡に自分が映る。
長くて黒い髪、膨らみのない小柄な体。
他の子達は、少しずつではあるが体に変化がある。
クラスには、所々膨らんで来ている子もいるし……。
私は、どうなるのだろう。
鏡で自分の裸を眺めて数分、唐突に洗面所のドアが開いた。
「優子、ちょっと用事ができたから出掛けて来るわ……」
ママは唖然した表情で私を見ている。
「……ち、違うの! これは、そういう事じゃなくて……」
慌てて弁解する私に、ママは含み笑いを浮かべる。
「自分の体に魅入られちゃった? まあ、女の子だしね。でも、その体型じゃ十年早いわよ」
それだけ言うと、ママはドアを閉めた。
恥ずかしい!
きっと私は、外の暑さでどうかしてしまっているんだ。
さっさとシャワーを浴びて、夕飯まで寝ていよう。
シャワーを浴びた後、バスタオルを体に巻き、暫くボーっとした。
風邪をひいてしまいそうだけれど、これがとても涼しくて気持ちが良い。
「さて、と……あれ?」
服を着ようと辺りを見回したところ、パジャマは置いてあるが、下着を持って来ていない事に気付いた。
バスタオルを巻いた状態で、パジャマを持って部屋まで下着を取りに行く事には抵抗があるが、今はママも麗太君も帰って来ていないし、問題はないだろう。
サッサと部屋に行けば良いだけの話だ。
パジャマを片手に、部屋を出た。
やっぱり廊下は暑い。
でも、ずっと涼しい場所にいたから丁度良いかもしれない。
裸だし。
二階へ続く階段は、玄関から然程距離はない。
階段を一段登ろうとした瞬間の事だ。
突然、玄関のドアが開いた。
まずい‼
慌てて階段を登ろうとしたが、二段目で踏み外して床に転倒した。
パジャマとバスタオルが派手に宙を舞う。
「痛っ……腰打ったぁ」
打った部分を押さえながら、咄嗟に瞑っていた目を開けると、玄関には唖然とした表情で私を見る、学校帰りの麗太君の姿があった。
暫くの沈黙。
麗太君は我に返ったのか、慌てて後ろを向いた。
しかし、その頃には遅かった。
バスタオルは体から完全に離れ、私は何も身に着けていない無防備な状態で床にへたり込んでいた。
「あ……あ、わ、わあああああああああ!!」
家中に響く程の大きな声で叫び、その場に散らばっているバスタオルとパジャマを拾って階段を駆け上がった。
部屋に戻った頃には、恥ずかしさで頬は火照り、ジッとしていられないような衝動に駆られた。
ベットの上に倒れ、枕に赤面した顔を押し付ける。
今日は最悪だ。
ママに裸を見られた上に、麗太君にまで……。
しかも……全部。
全部、見られてしまった。
胸も、腰も、お腹も、お尻も……その、お尻の前の方とか……。
どうしよう、次に麗太君に会う時にいつも通りの自分でいられる自信がない。
次に会う時……夕飯……。
もう、今日の夕飯はいらない。
とりあえずパジャマを着て、朝まで寝よう。
目が覚めると、部屋の中は真っ暗で、淡く暗い光が窓辺から差し込んでいた。
どうやら、眠っている間に夜になっていたようだ。
放置されていた冷房から吹く風が、部屋の中を完全に冷やしていた。
「寒い……」
枕元に置いてある目覚まし時計の針は、九時を示している。
朝まで寝ようと思っていたのだが、もう眠れそうにない。
やっぱりお腹も減ったし、とりあえずリビングに行ってみよう。
麗太君には、ちゃんと話をしないと。
あんな格好でうろついていた私が悪い訳だし。
リビングへ行くと、麗太君とママはテーブルで向かい合って何か談義をしていた。
どうやら夕飯は食べ終わっている様だ。
私の分は、テーブルの隅にラップを被せた状態で置いてある。
テーブルの中央には数枚のメモ用紙。
麗太君は、それに言葉を書いてママと話しているのだ。
部屋に入って来た私を見るなり麗太君は、私を横切って部屋から出て行ってしまった。
「ねぇ、麗太君と何を話してたの?」
「そうねぇ……なんていうのかしら……。まあ、麗太君にも色々と事情があるのよ」
「やっぱり、私があんな事をしたから……」
ポツリと呟いた一言に、ママは興味津々な反応をする。
「何? 麗太君と何かあったの?」
どうやら、麗太君は学校から帰って来た後の出来事をママに話していない様だ。
「うぅん。何でもないよ」
本当に良かった。
それにしても、私に関した麗太君の話でないのだとすれば、ママと麗太君はどんな話をしていたのだろうか。
聞いてみても、ママは誤魔化すばかりで何も教えてはくれなかった。
翌日、昨日の一件もあってか、ママを除いて私達は、朝からどことなく気まずかった。
家を出る時も、登校中も、学校でも、何となく距離を置いていた。
まあ、学校ではあまり麗太君とは話したりしないし、そもそも男子と二人っきりのところを皆に見られたら、からかわれる事間違いなしだ。
「優子、今日は何か変だよ」
マミちゃんに、直々そう言われた。
私は、いつも通りにしているつもりなのだけれど……。
昼休み、今日一日の半分、頭から麗太君の事が離れなかった。
やはり昨日の一件のせいだ。
もう、思い出すと頬が熱くなってくる。
頭を抱えて机に突っ伏していると、マミちゃんが心配そうに声を掛けてくれた。
「優子、今日やっぱり何か変だよ。熱でも出たんじゃないの?」
「そんな事ないよ。私は大丈夫……たぶん」
「たぶんって……ほら、おでこ出して」
額にマミちゃんの手が添えられる。
「うーん、熱はないみたいだけど……給食もあんまり食べてなかったでしょ?」
「……うん」
「何かあった?」
「……」
黙ってしまった私に、マミちゃんは小声で聞いた。
「もしかして、沙耶原と何かあった?」
沙耶原。
その名前が出た瞬間、反射的に机から体を起こしていた。
「ち、違うよ! 麗太君とは、そういうのじゃなくて……その……」
そして頬を真赤に染めて弁解していた。
まずい、誰かに聞かれちゃったかな。
教室を見渡してみると、運良く男子は一人もおらず、数人の女の子がちらほらといるだけだった。
どうやら今の話は、誰にも聞かれていない様だ。
「優子は分かりやすいなぁ」
マミちゃんは溜息を吐き、私をゆっくりと椅子に座らせた。
「よし、落ち着いて。今、教室にはあんまり人がいないし、大きな声を出さない限り大丈夫だから」
「あの……えっと……」
昨日あった事なんて、マミちゃんに言える訳がない。
もし言ったとして、マミちゃんは男子だからという理由だけではなく、心の底から本気で麗太君を敵視する筈だ。
「あの、麗太君は……」
「沙耶原君がどうしたって?」
どうにか誤魔化そうと言葉を探していたところ、話を聞き付けたのか、由美ちゃんがこちらへ来た。
さっきから私達の遣り取りを見ていたのだろうか。
「聞いた分だと、優子ちゃんは麗太君のせいで、食欲がなくて、頬が火照って、他の事に手が付けられないって状況なんでしょ?」
大まかな話では当たっているけれど、何か妙な勘違いをされている気がする。
「つまり恋なんでしょ?!」
由美ちゃんの目はいつになく輝いている。
「はぁ?!」
私より先に、マミちゃんが言葉を発した。
「そんな、このクラスの男子なんて……しかも沙耶原?! 優子が沙耶原を好きになる訳ないでしょ! 絶対にない!」
私の意見を聞く事なく全否定するマミちゃんに、由美ちゃんは挑発的に言葉を返す。
「分からないよぉ? 沙耶原君、あんな癒し系なくせにサッカー上手くて格好良いし。それにほら、喋れないし……。そういうところって、女の子からしたら母性本能擽られるものなんじゃないのかな?」
「知らない! あんな、なよなよした奴。そうでしょ?! 優子?!」
「え、私?!」
急に話を振られて、言葉に詰まってしまった。
まあ、他人事ではないのだけれど。
「優子ちゃん、ぶっちゃけどうなの? 沙耶原君の事どう思ってるの?」
確かに由美ちゃんの言う通り、麗太君は格好良い、というよりは癒し系で優しいし、悪い個所を見つける方が難しい位だ。
でも私にとっての麗太君は、今や家族も同然で、それ以上の関係なんて想像も付かない。
しかし、なぜだろう。
昨日の一件のせいかもしれないが、麗太君を見る度に変に意識してしまう。
麗太君と一緒に住み始める前は、こんな事なんて全くなかったのに。
「もしかしたら……由美ちゃんの言う通りかもしれない……」
私は小さく呟いた。
「本当?! じゃあ、ちょっくら行って来ますわ!」
今にも走り出そうとしていた由美ちゃんを、マミちゃんが袖を引っ張って止める。
「ちょっと、どこへ行く気?」
「麗太君を呼んでくるに決まってるじゃん!」
「呼んで来てどうするつもり?」
「優子ちゃんの想いの丈を打ち明ける!」
次の瞬間、袖を掴んでいたマミちゃんの手は、斜め四十五度からのチョップとなり、由美ちゃんの頭に直撃していた。
「馬鹿じゃないの! そんな事して、困るのは優子なんだよ! 分からない?!」
説教をするマミちゃんを前に、由美ちゃんは叩かれた所を摩りながらぺこぺこと頭を下げる。
「いやぁ、伝える事があるのなら早い方が良いかと。てか、地味に痛い」
「それじゃあ駄目なんだよ! ちゃんと順を追わなきゃ! ていうか、そもそも馬鹿なのは優子だよ!」
「え、私?」
「あんな、なよっちい奴のどこが良いわけ?」
マミちゃんは、いつになく真剣だ。
なら、私もしっかりと自分の想う麗太君の事を話さなくちゃ!
「麗太君は……少し前にママを亡くして、声も出せなくなっちゃって、落ち込んでた時もあった」
あの日、麗太君が私の家に来た日、私が彼の支えになってあげると決めたんだ。
「落ち込んでいても、しっかりと立ち直って、ちゃんと学校にも来てる」
日常生活に言葉を発せない障害があっても、麗太君はしっかりと学校へ来て、昼休みには今まで通り、元気に外でサッカーをしている。
そんな麗太君を日々、私は本当に凄いと思っている。
凄いと思っているだけ。
別に恋人とか、そういう意味での好きではなくて……。
どうしてだろう、内心では否定しているのに、麗太君に対する想いが溢れて来る。
「私は……そんな麗太君が……」
無意識のうちに、言ってしまいそうな言葉があった。
次の瞬間、頭がくらくらして、視界がぼやけた。
体中が熱くて、頬もかなり火照っている。
まるで風邪を引いた時に熱が出る様な感覚だ。
さっきまでは平気だったのに。
姿勢を保つ事が出来ず、私の半身は机に倒れた。
「ちょっと優子?! どうしたの?! ねぇ!」
「優子ちゃん! どうしたの?! 話が大人過ぎてショートしちゃったの?!」
二人の声が聞こえる。
なんとなく、体を揺すられている事も分かる。
でも、だるくて体が動かせない。
「あ、ちょっと来て、優子ちゃんが……優子ちゃんが!」
由美ちゃんが誰かを呼んでくれたみたいだ。
誰かの背中におんぶされた。
体を密着させている背中からは、何となく知っている香りがした。
これは……私の家の香り。
ママ?
それともパパ?
まさか、ママやパパがここにいる訳がない。
じゃあ、もしかして……。
気が付くと、目の前には白い天井が見えた。
体を預けた真っ白なベット。
それを仕切る真っ白なカーテン。
額に貼られている冷えピタ。
ここが保健室だという事に、ようやく気付いた。
私が倒れた後、どうなったんだろう。
たしか、誰かの背中におんぶされて……。
その後の事が思い出せない。
いや、そこで意識がなくなったんだ。
額に手を添えてみるとまだ熱いが、歩けない程ではない。
ベットから降り上履きを履いて、カーテンを開けた。
保健室には誰もいない。
私以外に寝ている人も保険医の先生も。
ただ、保健室の外から声が聞こえて来る。
どこかのクラスが音楽の授業で、合唱をしているのだろう。
まだダルイし、合唱を聴きながら眠ろう。
「平井さん」
暫くして、保険医の先生に起こされた。
「大丈夫? 熱は?」
額に手を添えられる。
「熱は……まだ少しあるかもね。担任の先生に頼んで、お母さん呼んで貰えるけど、お母さんは今、家にいるの?」
「はい……たぶん」
「そう、良かった。こんな状態で歩いて帰るなんて辛いものね。荷物は、さっき友達が持って来てくれたからね」
部屋の隅に置かれている椅子には、私のランドセルが置いてある。
いったい、誰が持って来てくれたんだろう。
マミちゃんかな。
保険医の先生は藤原先生の所へ、連絡を取ってもらいに行ってくれた。
手を添えられた額をさする。
保険医の先生って、なんだかお婆ちゃんみたいで可愛い。
とりあえず、椅子に座って待ってようかな。
椅子に腰掛け、意味もなくぐるぐると周る。
外で蝉がうるさく鳴いている。
もうすぐ夏休みか。
夏休みには、麗太君と過ごす時間が格段に増える。
それまでには、麗太君の前では普通でいられる様にならないと。
暫くすると、保険医の先生が藤原先生を連れて戻って来た。
「優子ちゃん。大丈夫? まだ熱あるんでしょ?」
「はい。でも大分、良くなりましたから」
「そう、良かった。もう暫くしたら、ママが迎えに来るからね」
藤原先生は、机を挟んで私の向かいに座った。
「優子ちゃん、ちゃんと後でお礼言っておくのよ」
「え? 誰にですか?」
「麗太君に決まってるじゃない」
麗太君?
何かしてもらったっけ?
「あなたをここまで運んだの、麗太君よ」
「え?!」
私は麗太君におんぶされていたのか。
恥ずかしくて頬が熱くなってきた。
熱が上がりそうだ。
「あと、マミちゃんにもね」
「マミちゃん?」
「そうよ。あなたが寝ている間に、ここまで荷物を持って来てくれたんだから」
二人には、迷惑掛けちゃったかな。
あと由美ちゃんにも。
「後で、皆に言っておきます」
「そうしておきなさい。それにしても麗太君、格好良かったみたいよ。皆の前で躊躇いもなく優子ちゃんをおんぶして運んだんだから」
「へぇ、あの麗太君が」
藤原先生は、笑みを浮かべて私を見る。
「麗太君って、もしかして優子ちゃんの事、好きだったりしてね」
「そ、そんな訳ないじゃないですか! もう!」
「あらそう。でも、全く気がないっていうなら、真っ先に優子ちゃんの所へ行って、運び出すなんて事はしないと思うわよ」
赤面してあたふたしている私に先生は「もう、背伸びしちゃって」と笑っていた。
確かに、先生の言う事にも一理あるのだ。
麗太君は、私の事をどう思っているのだろう。
私は……。
そういえばあの時、私がマミちゃんに言おうとした言葉を思い出した。
倒れる寸前、私が言おうとしていた言葉。
私は麗太君の事が……。
そうだ。
きっともう、私は麗太君の事が好きになってしまっているんだ。
この短い期間を一緒に過ごすうちに、私は無意識のうちに彼を理解し出して、好きになってしまっていた。
これはたぶんもしかしたら、よく聞くが今まで経験のなかった初恋というやつだ。
ママはタクシーで、学校まで迎えに来てくれていた。
そういえば、うちの車はパパが出張先へ乗って行ってしまったんだ。
タクシーなんて、お金も掛かっただろうに。
「タクシー代、優子のお小遣いから削らなきゃね」
無邪気に笑いながら、そう言っていた。
本当にお小遣いを削られる事はないと思うけど。
家に帰るとシャワーだけ浴びて、私はすぐ布団に入った。
麗太君はまだ帰って来ていなかった。
きっと、クラスの男の子達とどこかで遊んでいるのだろう。
それか光原君と、あの駄菓子屋に行っているか。
ああ、また麗太君の事が頭に浮かぶ。
私は本当に麗太君の事が好きなんだな。
そう改めて実感した。
麗太君の事を考えながら、私はゆっくりと目を瞑った。
眼が覚めた時、周りは完全に暗くなっていて、冷房の弱風だけが、無造作に吹いていた。
なんだか体が熱い。
熱がぶり返してしまったのだろうか。
パジャマが汗で濡れていて、気持ちが悪い。
それに喉も乾いている。
ママの所へ行って、何か飲ませてもらおう。
体に掛かっている布団を避けて、ふらふらとベットから立ち上がった。
やばい、頭がくらくらする上に、一歩が重い。
ちょっとずつドアの方へ進み、部屋から出ようとした時だ。
私がドアを開けるより先に、ドアが開いた。
誰かが来たのだ。
ドアが開くと、そこには麗太君がいた。
彼の両手にはお盆、その上にポカリスウェットとコップがある。
「麗太君……」
掠れた小さな声で呟いてすぐ、麗太君が来てくれた為の安堵感からか、全身の力が一気に抜け、私は彼の胸に倒れた。
麗太君は今、どんな表情をしているのだろう。
いきなり倒れ込んじゃったから、びっくりしているのかな。
見上げると、麗太君は今にも泣き出しそうな顔をしている。
「大丈夫だよ……ただの風邪なんだから」
掠れた小さな声で言い聞かせた。
麗太君は手に持っていたお盆を近くにある棚の上に置くと、両手で私の体をゆっくりと抱き締めた。
感じたその香りは、やはりママとパパの香りと一緒だった。
麗太君は、机の上にさっき手に持っていたお盆を置き、箪笥から替えのパジャマを出してくれた。
「ありがとう……」
麗太君は首を横に振り、メモ用紙を見せる。
『どうって事ない。冷えるから早く着替えた方が良いよ。僕は部屋に戻るから、何かあったら呼んで』
去ろうとする麗太君の腕を、私は咄嗟に抱き寄せた。
「行かないで……一緒にいて……」
もし、麗太君に私の事を少しでも思ってくれている気持ちがあるのなら、一緒にいて欲しい。
何より、抱かれた感覚が忘れられない。
腕を必死に抱く私を見て、麗太君はゆっくりと頷いてくれた。
お互いに反対方向を向き、私はベットの上で替えのパジャマに着替えた後、麗太君が持って来てくれたポカリスウェットで喉を潤した。
「麗太君、昼休みの事なんだけど……」
しっかりと言っておきたかった。
あの後、私は麗太君と話す暇さえなかったから。
「さっきは、ありがとう。麗太君が、私を保健室まで運んでくれたんだよね。ビックリしたよね? いきなり倒れちゃうんだから」
『どうって事ない』
言葉を発する事が出来るのなら麗太君は、咄嗟にそう言っているのだろう。
きっと、咄嗟に思い付いた言葉も、相手に訴える事も、本来なら容易なのだ。
それなのに、今の麗太君にはそれが出来ない。
他人は麗太君に対して、必要最低限な言葉だけを求めてしまう。
私は……そんな他人にはなりたくない。
「あの時……いや……今も感じているけど、麗太君からは、ママやパパと同じ香りがするの。だから私は、麗太君の事を家族も同然だと思ってる」
きっと、麗太君もそう思っている。
でも私は、もういつからか分からないけれど、それ以上の関係を彼に対して望む様になっていた。
「でもね、私は……それだけで終わりたくはないって思ってる」
麗太君と過ごして来た今日までの短い日々、それを胸に焼き付けて、今こそ言おう。
「私……麗太君の事、友達や家族としてじゃなくて、それ以上の意味で好きになっちゃったの! 裸を見られたからとかじゃなくて……本当に!」
私は麗太君の事が好き。
好きで堪らない。
もう、言わずにはいられなかったのだ。
顔を真赤にして、私は俯いた。
麗太君、私の事どう思ったかな。
もしかして……退いちゃったかな……。
幾つもの不安が込み上げて来る。
でも次の瞬間には、赤面して火照った私の頬に、麗太君の手が添えられていた。
そのまま抱き合ってしまいそうな位に、彼との距離が縮まる。
頬に当てられた手は、冷たくて気持ちが良い。
「麗太君……私……」
今、こういう時、私は麗太君に何と言えば良いのだろう。
全く、言葉が浮かばない。
それでも、彼が好きだという事は変わらない。
この事だけは、麗太君に分かってもらいたい。
抱き合ってしまいそうな位の距離を更に縮め、私達はお互いに唇を重ねた。
私が幼い頃に交わした、ママやパパとの経験を除けばファーストキス。
まさか、こんなに早く時が来るとは思ってもいなかった。
ちょっと前まで麗太君の事は、ただのクラスメイト程度にしか思っていなかったのに、それが今では……こんなに愛おしいなんて……。
お互いに唇を離した後も、私達は何度かキスを繰り返した。
翌日の朝、私の体調は完全に回復していた。
熱も下がっているみたいだし、ダルくもない。
リビングへ行くと、私とは逆にダルそうにソファに座っている麗太君の姿が目に入った。
「あれ? 麗太君、どうしたの?」
「きっと、優子のが移ったのね」
ママは体温計を用意し、麗太君に差し出した。
彼はそれを受け取ると脇に挟み、またぐったりと背にもたれる。
ああ、なるほど。
原因は昨日のキスか。
そのせいで、菌が麗太君の方へ行ってしまったんだ。
麗太君の事が気掛かりで、学校なんて行く気になれない。
「麗太君、私のせいで……」
俯く私にの頭に、ママはポンッと軽く手を置いた。
「優子。あなたは今日、休んだ方が良いと思うんだけど」
「え?」
「様子見よ。学校へ行って、風邪がぶり返しちゃったらいけないからね」
「それじゃあ……」
ママはニコッと笑い、私の頭を優しく撫でた。
「移したのは優子なんだから、麗太君の側にいてあげなさいよ。まあ、程々にね」
「うん!」
夏休み直前の平日。
私達は、二人揃って学校を欠席した。
麗太君と二人っきりになっても、もう妙な感覚を覚える事はない。
だって、私が麗太君を好きだという気持ちは、私達二人、お互いの中で確定しているのだから。
きっと、これから毎日がもっと楽しくなる。
夏休みだって間近なんだ。
そうだ!
夏休みになったら、麗太君と夏祭りに行こう。
綺麗な花火を二人で見るんだ。
学校のプールだって、夏休みになれば自由に使えるし。
何よりも麗太君と一緒にいれる時間が増える事が、楽しみでしょうがない。
=^_^=
夏休み直前に起きた、ちょっとした一件。
麗太君に裸を見られたり、異常に彼を意識してしまったり、その後にキスをしたり。
私みたいな小学五年生には、少しばかり早かったかもしれないけれど、これが私にとっての初恋だった。
True Episode1 Kana Hirai
「初担任、お疲れ様」
カウンター越しのバーテンダーさんは、博美にカクテルを差し出した。
綺麗な水色が、グラスの中で光っている。
「ありがとうございます、啓太郎さん」
「おいおい、名前で呼ばれたら格好付かないじゃないか」
私と博美の座るバーカウンターの向こうにいる彼、啓太郎は愛想良く笑う。
「あら、私にはないの? ご褒美」
「勿論、香奈の分もあるよ」
そう言うと彼は、博美と同じ物を私に差し出した。
「気前が良いのね」
「勿論! 高校時代の友達が来てれくれたんだから、これくらいは当然だよ」
優子と麗太君が、小学校に入って五度目の夏休みを迎えた日の深夜。
私は二人が眠ったのを見計らって家を出た。
博美と啓太郎で、このバーで集まる約束をしていたのだ。
啓太郎は、私の高校時代の同級生で、当時はよくつるんでいた。
ここは、そんな啓太郎が今年の春からオープンしたショットバー。
名前はブラックサン。
本人曰く、夜に活動する大人っぽいクールなイメージにしたかったらしい。
他にも理由はありそうだけど、そう思っている時点で考え方はまだまだ中二病だ。
啓太郎は昔からそうだった。
下手に格好を付けようとして、逆にそれが空回りしてしまう。
前の仕事、ホストクラブでの経験を生かしてバーを開いたそうだが、いつまで続く事か。
まあ、顔だけは良い。
引き締まった細身の体にバーテン服、ワックスで自然に整えた、ガキっぽさのない髪型。
それほど格好は悪くないのだ。
「それにしても啓太郎。高校の時から随分、雰囲気変わったわね」
「そうかな?」
「そうよ。男らしくなったわ。気前も良くなったしね」
先程出されたカクテルを、私は口に運んだ。
お酒なんて、飲んだのは久しぶりだ。
あの人が家を出て行ってから、ずっと飲んでいなかった。
あの人……平井皓……。
優子の父親であり、私の夫。
「皓……」
その名を呟いていた。
「皓さん、まだ戻って来ないんですか?」
「ええ、麗太君がうちに預けられる、ちょっと前に出て行ったわ。優子には単身赴任って言ってあるけど……実際のところ、どう思われてるのかしらね」
「こんな時、楓さんがいれば……」
沙耶原楓。
麗太君の母親であり、私の高校時代からの親友。
彼女には、今まで何度も励まされて来た。
それがあったからこそ、私はめげずに今日まで生き続ける事が出来たんだと思う。
「あの時も楓が止めていなかったら私は……ここにいなかったかもしれないしね」
「優太君の事か……。本当に残念な事だったよ」
「そんな事があったからこそ、優子には絶対に辛い想いはさせないって決めたの。あの子には……絶対に……」
話が暗過ぎて、博美は今にも泣き出しそうだ。
「ごめん、ちょっとお手洗いに行ってくるわね」
一度、気分を切り替えて、それからまた戻って来よう。
用を済ませた後、手を洗っている最中に、ふと鏡に映る自分を見た。
背中まで伸ばした長くて黒い髪や、薄く頬にのばした化粧。
年相応の体。
全部、皓が好きだった私の一部。
あの時の皓は、私を愛して已まなかった。
たぶん今でも……。
だからこそ皓は私達を置いて、あの家を出て行ったんだと思う。
=^_^=
私と楓は小学校からの幼馴染。
二人でこの街の高校に入学して、私達は皓と啓太郎に出会った。
休み時間や放課後、授業をサボったり、どこへ遊びに行くにも、私達は一緒だった。
今、優子達が学校帰りによく寄っている駄菓子屋は、既にその頃からあった。
カラオケやゲームセンターよりも異質な場所を好んでいた皓は、私達をその場所に連れ出した。
そこで私達が出会った小学生の女の子。
それが博美だ。
喧嘩っ早くて、口より先に手が出る博美は、学校では浮いた存在だった。
一緒に遊ぶ相手もいなければ勿論、誰も相手にしてくれない。
そんな博美を、駄菓子屋のお婆ちゃんは嫌な顔一つせず面倒を見ていた。
博美にとって、店に来る客、つまりお婆ちゃん以外の人間全てが自分にとっては邪魔な存在だった様で、私達が駄菓子屋に来る度に、彼女は嫌な顔をしていた。
でも色々あって、結局は博美が皓に懐いて、しだいに私達と打ち解けていったんだっけ。
夏休みには皆でお祭りに行って、遠くへ出掛けて。
あの頃は本当に楽しかった。
しかし高校二年生の後半になると、私達の関係はしだいに軋み始める。
私は皓と二人でいる事が多くなり、博美を含めていつものメンバーで集まる事は少なくなっていった。
あの時の私は、誰よりも皓を特別に思っていた。
楓や啓太郎や博美よりも……何よりも……。
私は楓達に内緒で、皓の家に二人で泊まり、ついに彼と肉体関係を持ってしまった。
何もかもが衝動的な出来事で、悪い様には感じなかった。
楓達も誰も知らない、私と皓の二人だけの関係。
ただ、皓に触れていてもらえる、私が皓に触れている。
それだけで嬉しかった。
自分のお腹に赤ちゃんがいると分かったのは、私が皓と関係を持ってから、数週間後の事だった。
不安ばかりが込み上げて、死んでしまいたいとすら思った。
こんな事、皓以外の誰かに言える筈がない。
だから真っ先に、この事を皓に伝えた。
皓はあまりにも辛そうな顔をして「ごめん……ごめんなさい」と、泣きながら私に謝り続けていた。
もしかしたら私達は、こんな結末を望んでいたのかもしれない。
二人だけの関係から生まれた、お腹の中の存在。
それは私と皓しか知らない、私達の赤ちゃんだ。
二人でこれからの事を考えて出した結論は、互いの親や楓達、誰にも見つからないどこか遠くの街へ行く事。
私達は平日の始発の電車に乗り、自分達の街を離れた。
親にも、友人にも、誰にも別れを告げずに……。
=^_^=
カウンターに戻った時、博美はグラスを片手に突っ伏していた。
「飲んで泣いて、さんざん愚痴をこぼして寝ちゃったよ」
啓太郎は洗ったグラスを拭きながら、微笑している。
どんな話をされたのだろう。
博美にも、色々とあるんだなぁ……。
彼女の隣に座り、飲み掛けだったお酒を口に運んだ。
「啓太郎は最近どう? 何か変わった事はある?」
「最近は落ち着いてきたかな。経営も、彼女との関係も」
「一緒にこの店を切盛りしてるんでしょ?」
「うん。ホスト時代に付き合って、突然この店を任された。元々はおじいさんの店だったらしいけど」
啓太郎も何かと苦労している。
ある意味、楽をしているのは私だけかもしれない。
子供達と楽しく日々を過ごして、私だけは何もせずに、ただ皓の帰りだけを待ち続けている。
何もせずに……。
「そういえば口裂け女の噂、覚えてる?」
「ああ、小学校近くの住宅地にいるっていう、あれか」
今年の夏前、この街に再び流れ出した噂。
口裂け女。
この噂が、私達の身近で最初に広まったのは、私達がまだ高校生の頃だった。
「そう。あれの真相、知りたくない?」
「え?!」
彼の目の色が変わる。
たしか、啓太郎はこんな噂話が大好きで、私達は彼の妙な噂談義に、しょっちゅう付き合わされていたものだ。
ただし、彼にとっては話限定。
実際に肝試しや心霊スポットへ行く事を、強く拒む事が度々あったものだ。
=^_^=
「ねえ、皓。やっぱりやめた方がいいよ……」
「何言ってんだよ! 博美に何かあってからじゃ遅いんだぜ?」
私と皓は、小学校近くの住宅街の公園のベンチに座っていた。
もう陽は西に傾いていて、空はオレンジと青で半々の色に染まっている。
傍から見れば、私達はどう見ても夏場に身を寄せ合っている暑苦しいカップルだ。
実際は違うけれど。
目の前でサッカーをして遊んでいる小学生の集団が、公園から出て行く。
「やばい、口裂け女が来るよ!」
「早く帰らないと!」
等と騒いでいた。
もうこの噂は、街では誰もが知っている様だ。
口裂け女。
赤いコートを身に纏い、サングラスとマスクで顔を隠した怪人。
誰がこんな古臭い噂を広めたのかは知らないけれど、地元の小学生には彼女を見たという子が何人もいる。
この噂を聞いた皓は「博美が……。博美を守らないと!」
等と言って、放課後になるなり私を、この口裂け女の出没地と言われる公園に連れ出したのだった。
実害があったっていう話は聞かないし、博美にも直接の被害はないと思うんだけどなぁ。
公園の時計を見上げると、時間は六時を回っていた。
空は完全に夕暮れ色に染まり、辺りは薄暗くなっている。
「ねぇ、皓。もう帰ろうよ。口裂け女なんて出て来ないよ」
「いいよ、帰っても。俺はまだ、ここにいるから」
もし私が帰ったとして、皓は一人でいつまでここに居続けるつもりなのだろうか。
私は首を横に振った。
「やっぱり帰らない。皓が帰るまで、一緒にいるよ」
「悪いな、こんな所に連れ出して……こんな時間まで……」
「私は大丈夫だよ。皓は? 無茶して、いつも体壊してるんだから」
「そうか?」
「そうだよ」
「……そうだったかも。ありがとな、心配してくれて」
皓は私に笑い掛ける。
やっぱり、皓の笑顔は癒されるなぁ。
楓も、啓太郎も言っていた。
皓は周りを明るくするって。
博美なんて皓が大好きで、彼にべったりだし。
ちょっとだけ……博美は小学生だけど、そんな彼女の気持ちも分かるかも。
てっ、何て事考えてるんだ私は!
私が皓の事を好きだなんて……そんな事、絶対にある筈がない。
あって堪るものか!
別に、全く気がないという訳ではないが、友達としてなら良い人だし……。
「香奈、顔が赤いぞ?」
「え?!」
ああ、まただ。
こんな事を考えただけで、頬が火照ってしまう。
その度に思う。
きっと、私には誰かと付き合ったりする事なんて到底、無理な事なんだろうなって。
「大丈夫?」
「うん、ちょっと熱くなっちゃっただけだから」
頬に自分の手の甲を添える。
ちょっとだけど、冷たくて気持ちが良い。
こんな時、男の子が何とかしてくれるものだけど、きっと皓は私に触りすらしない。
私達に対して、変に気を使ってしまう事があるから。
「香奈!」
「え?!」
突然、私の名前を発したと思うと、皓は私を抱き寄せていた。
「え?! ちょっ、何で?! え?!」
気が動転してしまって、まともに言葉が出せない。
どうして?
なんで、いきなり私を抱き締めたりしたの?
今までで、こんな事をされたのは初めてだ。
耳元で、皓が小さく囁く。
「公園の外、ベンチの背もたれの向こう。赤いコートの変な女が歩いてる」
「え?」
抱き寄せられた状態で、ベンチの背もたれ越しを除く。
足の半分以上まで覆う赤いコート、顔を覆うサングラスとマスク、長く伸ばした真っ黒な長髪、赤いハイヒールのコツコツという足音。
きっと、あれが口裂け女だ。
周りには近所の人も通行人もいない。
道に口裂け女が一人。
そんな光景が、より彼女の不気味さを強調している。
「香奈、ここで待ってろ」
皓は抱き締めていた私を突き放し、公園の外へ駆け出した。
「ちょっと! 危ないよ!」
口裂け女が皓と私の存在に気付く。
彼女の恐ろしい眼光が私達を睨む。
それでも皓は、口裂け女に向かって全力で疾走する。
「おい、コラ! そこのお前‼」
陸上部並みの猛スピード、ヤンキー並みの気迫。
そんな彼を見た口裂け女は、ビクッと肩を震わせ、赤いハイヒールをコツコツと鳴らしながら慌てて逃げ出す。
「待てよ! 逃げんのかよ!」
コツコツとハイヒールを鳴らして不器用に走る口裂け女に、皓は追い付いたかと思うと、一気に彼女の背中に飛び掛かった。
二人が大袈裟に道を転がる。
「ちょっと!」
慌てて二人の元へ駆け寄った。
その時は、口裂け女への恐怖よりも、こんな無茶をした皓への呆れの方が強かった。
まったく、皓は行動したら何をしでかすか分かったものじゃない。
皓は上から腕や足で口裂け女を押さえ付け、彼女の動きを封じた。
「香奈! 今だ! マスク! これ取って!」
「え? う、うん」
逃げ出そうと暴れている彼女のマスクを、私は恐る恐る取った。
「あれ?」
マスクを取った下、そこには普通の口があった。
勿論、口は裂けていない。
それ以前に、その口周り。
主に鼻の下や顎には、黒い粒々の何かがある。
これって髭……だよね……。
皓の下でもがく内に、口裂け女の正体が明らかになる。
サングラスは徐々に顔からずれ、長くて黒い長髪は不自然に乱れた。
やがて黒い長髪はすっぽりと外れ、サングラスも完全に外れた。
皓の下でもがいている異形の存在、口裂け女。
その正体は、僅かに頭に髪が残っていて、顔の口周りには黒い粒々の髭が生えている、赤いコートを着てハイヒールを履いた……五十代半ば程の只のオジサンだった。
「正体がばれたのでは仕方がないな。全部話すよ」
女装壁剥き出しのオジサンは、公園のベンチの中央に腰掛けた。
それに向かい合う様に、私と皓は前に立つ。
訳が分からなく唖然と立ち尽くす私達に、彼は話を切り出した。
「君達が何を思っているのか。それは大体分かるよ。口裂け女の正体が、僕の様なオジサンだった事だろ?」
彼の目線が皓に集中する。
「まさか、君みたいな勇敢な子がいるとは……。まだ、世の中も捨てたもんでもないみたいだね」
皓は丁寧に頭を下げる。
「すいませんでした。……いきなり暴言吐いて、飛び掛かったりして……。でも、どうして、あんな格好を?」
「その事に関しては、まず以前この街で起こった事件を話しておくべきかな」
「事件?」
「かなり前の事だから、君達は知らないだろうけどね」
今から三十数年前の事。
この街で一つの事件が起きた。
とても残酷で、聞いただけで吐き気がする程に気分の悪くなる様な事件。
被害者の女の子の名前は美弥。
事件当日の夕方の事、美弥はいつも通り小学校から自宅までの帰路を、友人達と共に歩いていた。
友人達と別れてすぐ、美弥は異質な男性に出くわした。
男の容姿は、一言で言えば汚らしかった。
中年の小太りした体、無造作に剥げ散らかした頭。
みてすぐに、汗や臭い等の言葉を連想してしまう程に、汚らしい容姿をしていたのだ。
初め、美弥はその男を横目に通り過ぎたのだが、咄嗟に腕を掴まれ、近くに駐車してあったバンに連れ込まれてしまった。
僅か小学生女子の力では、中年の腕力に勝る事が出来なかったのだろう。
口や手足をガムテープで巻かれ、おまけに目隠しまでされた。
そこからの記憶は殆どが曖昧で、なんとなく感じていたのは、嫌らしい声と異臭、男が肌に触れた感覚だけ。
手足が動かない。
声も上げる事が出来ない。
狭い空間でジッとしている時が、時間を想定する事さえも諦めてしまう程に長く続いた。
その後、暫くして美弥は、ようやく手足を自由にされ光を見た。
しかし、そこに広がっていた光景は、決して彼女にとって幸福なものではなかったのだ。
見た事もない倉庫だった。
後ろには、自分をバンに連れ込んだ男の姿がある。
男の息が荒くなると共に、美弥にとって本当に長くて辛い日々が始まった。
服を千切られ、臭くて気持ちの悪い男の慰み者にされる。
こんな事が何日も続いた。
美弥の精神が完全に壊れ掛けた頃、男は彼女を川沿いの橋の下に捨て、去って行った。
それから数時間後、近隣の通報により美弥は警察に引き取られ、現在捜索中の少女である事が判明した。
「美弥は、僕の娘だったんだ」
悲しげな顔をして、オジサンは私を見る。
「美弥も生きていれば、君の様に制服を着られたんだろうね」
「じゃあ、その美弥って子は……」
「自殺したんだ。美弥は精神が回復しきって、警察に自分が受けた男からの虐待を告白した後、手首を切ってね」
あまりにも衝撃的な事件の全貌を前に、私は彼に対して何も言う事が出来なかった。
きっと、皓も同じだ。
「こんな事を二度と繰り返してはいけないんだ。だから僕は、かつて流行った口裂け女の噂を利用した。子供達に恐怖感を与え、夕方には口裂け女が出没するから、なるべく早く家に帰らなければならない、という決まり付けを狙ってね」
この人は自分が悪を演じる事で、子供達に迫る本当の悪を、今まで退けてきたんだ。
「アンチヒーローってやつか」
皓は唐突に言った。
「アンチヒーロー?」
「そう。香奈は分かるだろ? 仮面ライダーブラックでいうところのシャドウムーンみたいなものだよ。あとは……ブラックジャックでいうところのドクター・キリコとか。大切なものを守る為、自分の信念の為、どんな悪行でもする。まあ、別の角度から捉えた正義の味方ってとこかな」
皓は本当にそういう話が好きだ。
正義の味方やヒーローの話になると、いつも目の色を変える。
ちょくちょく皓のヒーロー談義を聞いているからだろうか。
なんとなく分かってしまう自分が悔しい。
「アンチヒーローか。でも、それも今日で終わりだ」
「どうして? 今日までここら一帯を守って来たんじゃないですか?」
オジサンは腕を組み、溜め息交じりに言う。
「僕の職業は、この街の小学校の先生なんだ。でも三週間程前、持病が発覚して手術を受ける事になってね。長い闘病生活になるだろうし、どのみち今日を最後と決めていたんだ。それにもしかしたら、口裂け女なんていなくて良かったのかもしれないしね」
諦めきっている。
そんな表情をしているオジサンを、皓は真っ直ぐに見据えた。
「あの……俺、何の取り柄もない只の高校生ですけど……こんな事、誰かに言える立場じゃないかもしれないんですけど……。オジサンのやってきた事、絶対に無駄な事ではないと思います」
彼は私達に笑顔で「ありがとう」とだけ言い残し、公園を去って行った。
家族で過ごす、最も幸せである筈の時期に娘を失った彼の苦しみは、その時の私や皓には到底、想像も付かない事だった。
それでも私達は、いずれ知ってしまうのかもしれない。
いや、きっと避けては通れないのだ。
=^_^=
「そんな事があったのか」
啓太郎は数本のお酒の瓶とグラスを並べながら、怪訝そうに呟いた。
「そう。思えば、皓が人とは少しずれた考え方を、本格的に抱く様になったのは、その頃からだったかも」
「正統派ヒーローよりもアンチヒーローの方に肩入れするっていう、皓の考え方か。確かに、あいつが言ってた事も一理あるな。悪役が必ずしも本当の悪だとは限らない」
「ていうより皓は、人を庇う事を覚えたんだと思うわ。他人のミスを何もかも自分で抱え込んで、庇って……自分だけが悪者になって」
高校時代から今に掛けて、そんな事を繰り返してきたから、家を出て行くまでの最近の彼は、精神的にボロボロだった。
それでも優子の前では、自分の惨めな姿を見せまいと強がって、あの子が寝た深夜には、毎夜の様に私に甘えていた。
互いに身を寄せ合い泣く日々。
私達の間に確かにいた子、優太。
その記憶が皓の頭から消えない限り、きっと彼が心から笑える日は来ない。
それでも、私達は優太の事を忘れてはならない。
だから後に産まれて来た娘に優子と名付け、決して優太を忘れる事のないよう胸に留めて、日々を過ごしてきた。
皓から優太の記憶が消える日はない。
故に、皓が心から笑える日は、きっとこない。
もう私は、諦めてしまっているんだ。
「ブラックサン」
「え?」
啓太郎は唐突に、店の名前を口にした。
「この店の名前、大人っぽい雰囲気にしたかった事以外にも、理由があるんだ」
「なんとなく分かるわ」
ブラックサン。
それは皓が大好きだった特撮ヒーローの主人公、仮面ライダーブラックの別名。
「世紀王ブラックサン」
「やっぱりね。啓太郎の事だから、そなんところからの引用だとは思ったわ」
啓太郎は自身あり気に頷く。
「二人とも、好きだっただろ、仮面ライダー。とくにブラックといえば皓が。あいつがこの街に戻って来て、もし、この店のブラックサンって看板を見つけたら、もしかしたら来てくれるんじゃないかって……。そう思っただけだよ。名前なんて、とりあえず付けた様なものだし」
「皓ったら、仮面ライダーブラック大好きだったものね。彼の部屋の本棚の裏、私と優子に内緒でフィギュアが隠してあったのよ。笑っちゃうでしょ?」
「皓らしいな」
先程から、啓太郎は何やら大きめのグラスに入っている桃を磨り潰している。
それが終わると酒の瓶を数本並べ、壁に掛けられている時計を覗っている。
時計の針は、もうすぐで十二時を回ろうとしていた。
「そろそろかな」
啓太郎は言うと、店の入り口に目をやった。
入口のドアが開く。
店に入って来たのは、見覚えのある老人だった。
口周りの所々に生えた髭、顔に浮き出た多くのしわ、かなり年期の籠った薄毛の頭。
優子や麗太君が通う学校の校長先生だ。
彼が、ここを訪れる事は私も啓太郎も分かっていた。
たぶん、知らなかったのは博美だけ。
おぼつかない足取りでカウンター席まで来ると、彼は私の隣に座った。
「こんばんは」
「ええ、どうも」
私と啓太郎は軽く会釈する。
博美の方を見た。
職場の上司が来たというのに……まったく、この子は。
昔から一度寝てしまうと、なかなか起きないんだから。
「博美、起こしましょうか?」
「いや、けっこう。藤原さんにはいつも頑張ってもらってますから。今日くらいは、ね」
「そうですか」
「マスター、いつもと同じ物を貰えますか?」
啓太郎は意気揚々に「はい!」と答え、シェーカーに先程、磨り潰した桃を入れ、数種類のお酒を少しずつ入れていく。
最後に大きめの氷を数個入れ、蓋を閉じた。
両手でシェーカーを持ち、顔くらいの高さまで上げると、啓太郎はそれを横に振った。
シェーカーの中で氷がカラカラと鳴る。
いつもの啓太郎とはどこか違う。
シェーカーを振る手も、表情も、全てがいつもとは違う彼だった。
「お待ちどうさま」
綺麗にグラスに注がれたカクテルを、啓太郎は校長先生に差し出した。
「桃をベースに、ウォッカとサトウキビシロップを多めに使いました」
「うん、ありがとうございます」
校長先生は一口、グラスに入ったカクテルを口に運んだ。
ホッと安心したように呟く。
「うん、いつも通りで安心だ」
「いつも通り?」
「ええ。最近では、登校する子供達に挨拶をする事と、週に何回かここに来てお酒を飲む事くらいが楽しみなんもんでしてね。何も変わっていないというのは、とても素晴らしい事です」
彼は私を見て笑い掛ける。
「現に、平井さんには毎日の楽しみを一つ。先日、潰されてしまいましたがね」
つい、私も笑ってしまう。
「当然ですよ。もう六十になるんですから。すね毛を剃ったって、ウィッグを被っても、さすがに無茶ですよ。五十代でも無理があるっていうのに」
「え、何? どういう事?」
口裂け女の噂に関して、どうやら啓太郎は先程の私の話までしか知らない様だ。
まあ、当然か。
この人と啓太郎は、今までここでしか関わりがなかったわけだし。
「口裂け女の話ですよね?」
「ええ。十数年程前のあの日、口裂け女を辞めた後、六、七年ほどの闘病生活を経て、この街の小学校の校長として再度、赴任する事になったんです」
「啓太郎、どういう事か分かるかしら?」
手に持っていた布巾をひとまず置き、啓太郎は腕を組む。
「それって……つまり、口裂け女の正体のオジサンって、このお客さんだったの?!」
「その通り。人の縁って不思議よね」
「そうですね」
校長先生は少しだけ躊躇う様に私に問う。
「そういえば、旦那さんは帰って来ましたか?」
「いいえ、まだ」
「……」
「夏祭り、間に合うと良いんだけどな」
「夏祭り? 毎年、八月の終わり頃に大通りでやってる……あれですか? 花火やら露店で賑わう」
「はい。毎年、楽しみにしていたんですよ」
私達の学生時代、夏の終わりの楽しみといえば、街主催の大規模な夏祭りだった。
皓、楓、啓太郎、博美、私。
この五人で夏祭りへ最初に行った年は、博美を除いて私達がまだ高校一年生の頃だった。
その年を境にずっと、私達は一人も欠ける事なく夏祭りに足を運んだ。
高校を卒業した後も、ずっと。
でも、それも去年が最後。
楓はもういない。
皓は帰って来ない。
バラバラになった私達は、もう全員揃って夏祭りに行く事なんて出来ないんだ。
「きっと、皓は来るよ」
啓太郎はそう言って、私に笑い掛けてくれた。
私にとって憶えのある、啓太郎の笑顔。
高校時代、何かと馬鹿な事をやっては笑い合っていた、あの頃を思い出すと、自然と心の中で僅かな安心感が芽生えた。
「そういえば、啓太郎は憶えてる? 会社に勤め始めた皓が、仕事で遅れて来た夏祭り」
「憶えてるよ。あいつ、仕事で夏祭りに遅れても、全力疾走で俺達の所に駆けて来てくれたからなぁ」
「それで、皓だけが花火を見逃しちゃって。啓太郎は『花火の代わりに星を見ろ』って、天体望遠鏡を担いで私と皓を川沿いの土手に連れ出したと思うと、私と皓だけ取り残して行っちゃって」
「なかなか粋な事しますねぇ」
にやつく校長先生を前に、啓太郎は私達から目を反らして、照れた様に頬をぽりぽりと掻く。
「まあ、僕も香奈達を見ているだけで満足しちゃってたんで。たしか、その時だよな? 優子ちゃんがお腹にいるって皓に言ったのは」
私のお腹に優子が……いた。
……いたんだ。
「……うん。その後に両親の家を離れて、二人で優子と過ごして……私達って、いろんな人達に迷惑を掛けちゃったわね」
友達にも両親にも。
「でも、楽しかったよ」
迷惑を掛けられた筈の彼が、そう言ってくれた。
「そんな事があったから、今があるんだよ」
「うん」
「今まで僕達がしてきた事とか全部、忘れないで信じようよ。去年の夏祭りの時、皓が言ってたじゃん」
そう。
あの日の夜、皓は言っていた。
『また来年の夏、皆で来ような』
信じてみよう。
今まで私達がしてきた事。
皓の事。
家に着いた頃には、深夜の三時を回っていた。
勿論、優子と麗太君はとっくに寝ている。
リビングの電気を点け、バッグをソファの上に置き、一杯のコップに水を汲んで一気に飲んだ。
「はぁ」
かなり酔いが回っている様で、頭がクラクラする。
帰る少し前に、いきなり飲み過ぎたみたい。
とりあえず、シャワーだけ浴びておこう。
だらしない格好でソファーなんかに寝ているところを、麗太君に見られるわけにはいかないし。
シャワーを浴びた後、私はすぐに布団に入った。
布団に入ると毎晩、同じ事を考える。
布団の中で考える事。
大体は皓の事。
彼が今、どうしているのか。
ちゃんと食べているのか。
しっかりと仕事をしているのか。
彼の事を考えているだけで、彼に包まれている様な気がして、少しだけ心地が良かった。
=^_^=
翌日、熱い部屋の熱気に起こされた。
ダルイ半身をのそのそと起こして、時計を見る。
「十時?」
いつの十時だろう。
窓際のカーテンの隙間からは光が漏れている。
外が明るくて時計は十時……。
「やば! もう十時?!」
立ち上がってリビングへ行くと、テーブルの上には書き置きが残されていた。
『麗太君と学校のプールに行ってきます』
そういえば昨日、二人が帰って来た時に
「明日は麗太君と学校のプールで遊んで来るね!」
優子がはしゃぎながら、そんな事を言っていた。
「良いなぁ、大好きな人が側にいて……」
呟いても、どうにかなる事ではない。
エアコンを点け、キッチンに置いてある食パンを一枚食べた。
袋が開封されているところを見ると、朝にあの子達が食べたのだろう。
そういえば、あの子達のお昼は?
お弁当を頼まれたので、昨日の間に作り置きを冷蔵庫に保管していたのだが。
冷蔵庫の中にはそれがない。
二人分のお弁当箱も棚から消えている。
どうやら二人で全部やってくれた様だ。
「やるなぁ、あの子達」
知らない間に、自分の事は何でも出来る様になって……。
「私も何かしなくちゃ!」
昨日の分の洗濯がまだだった筈だ。
洗濯機を回し、その間に部屋の掃除をした。
ベランダに洗濯物を干して、昼は昨日の夕飯の残り物で済ませた。
小学校が夏休みであっても、私にとってはいつも通りだ。
取りこんだ後に、ソファの上に重ねておいた昨日の分の洗濯物。
優子の分と麗太君の分だ。
後で箪笥に仕舞わせるのに、二人の部屋の前に置いておこう。
そう思い、重ねておいた二人分の服を二階へ持って行くと、優子の部屋のドアが開いているのが真っ先に目に付いた。
「閉めるの忘れちゃったのかな? 部屋のドアは閉めておいてって、いつも言ってるんだけどなぁ」
部屋の前に優子の分の服を置き、ドアを閉めようとした。
その瞬間、部屋の真ん中に落ちている何かに、私の目は釘付けになった。
何か、というよりは、もう明確な答えは見てすぐに出るものの、それが本来であれば何であるかは、一見すると動物に例える事が出来る物。
柔らかく白い布に印刷された可愛いパンダの顔。
それがジッと、部屋の真ん中から私を見ている。
そう、パンダだ。
しかし、ただのパンダではない。
柔らかい布地……。
優子のパンツだ。
部屋に入って、それを拾い上げる。
「そういえば、あの子……まだ、こんな動物さんパンツ履いてるんだっけ……」
それにしても、どうしてここにパンツが?
内側を見ても、臭いを嗅いでも、特に違和感はない。
履いた後ではない様だ。
「ていうか、何やってるんだろう……私」
娘のパンツの臭いを嗅ぐって……変態か、私は……。
優子は麗太君と学校のプールへ遊びに行った。
部屋の中央に置かれたパンツ。
優子の事だから、服の下に水着を着て行った筈だ。
学校の授業で水泳がある日も、そうだったから。
じゃあ、このパンツは……。
持って行く筈が、ここに置いて行ってしまったのだろうか。
いや、もしかしたら只、ここに置いてあるだけかもしれない。
いや、でも本当にパンツを家に忘れていたとして、その後ノーパンで家に帰って来るとか洒落にならないし、麗太君にも妙な影響が……。
水着から服に着替える時に下着がなかったとして、優子の事だから焦りと動揺を隠せないんだろうなぁ。
恥ずかしい想いをするのは優子だし。
仕方ない。
今日はもうやる事もないし、どうせ今からする事といったらコーヒー飲みながらテレビ見るくらいだし。
「持って行ってあげよう」
パンダの絵が印刷された一枚のパンツを袋に入れ、それを持って家を出た。
外の日差しは夏休み始めという事もあってか強く、その上、蝉の鳴き声もうるさいくらいに聞こえてくる。
庭の隅に置いてある自転車を外に出し、籠に袋で包んだパンツを入れて、ペダルを踏んだ。
自転車が走り出す。
ペダルを踏む度に向かいから緩やかに吹く風は気持ちがよく、夏である筈なのに涼しくも感じられた。
周りのいろんな風景が、私の両横を通り過ぎていく。
自転車で近場を走るのも、たまには悪くないかもしれない。
小学校の近場の駐輪場に自転車を停め、パンツの入った袋を持って正門を通った。
たしか校内に来客用の窓口があった筈だけど……。
校舎付近をうろうろしていると
「香奈さん!」
と、後ろから声を掛けられた。
振り向くと、すぐ側に博美がいた。
「博美? ここで何してるの?」
「それは私の台詞です。香奈さんこそ、どうして?」
「優子に、これをね」
紙袋を見せる。
「これ、なんです?」
「優子のパンツ」
「えぇ?!」
予想通りの反応だ。
博美は昔から分かりやすい。
「優子が水着を服の中に着て行っちゃったから、パンツだけ家に忘れたのよ。プールに来てるでしょ?」
「はい、来てますけど……。今日は私がプールで泳いでる子供達を見守る当番なんで」
校舎には誰かがいる気配がないのは、そのせいか。
「へぇ、昨日、あんなに遅くまで店にいたのに、頑張るのね」
「あ! そうですよ!」
何かを思い出したように、博美の声が大きくなる。
「昨日の夜。なんで、起こしてくれないで先に帰っちゃったんですか?!」
「何でって、博美。あなたが起きそうになかったからよ。校長先生だって、起こさない方が良いって」
「校長先生?」
そうか。
博美はずっと寝ていたから、校長先生が来ていた事に気付いていなかったんだ。
「何でもないわ。で、私が先に帰った事に、何か不都合でも?」
「ありましたよ! 起きたら啓太郎さんの店のベットの上だし」
昨日、私と校長先生が帰る時、博美を啓太郎の店のベットに寝かせてから帰った。
『彼女さん、今日はいないの? 博美をベットに寝かせて大丈夫?』
そう聞いたところ啓太郎は
『あいつは、香奈達が来る前に家に帰ったから大丈夫だよ。それに、明日は店を休みにする予定だし』
と言っていたが……。
「ベットで寝てただけでしょ? 啓太郎に何かされたの?」
「違います! 私が起きてすぐ、啓太郎さんの彼女さんが、私の寝てた部屋に入って来て……」
「どうなったの?」
「啓太郎さんを呼んで、二人で昨日の事を説明したんですよ。もう、大変でしたよ」
大方、啓太郎は彼女さんが帰って来る事を予想しきれていなかったのだろう。
まったく、彼女以外の女の子を自分の店のベットに招くというのに、詰めが甘いんだから。
よく見ると、博美の顔色はあまりよろしくない。
朝方にそんな事があった後に、学校に来たのだから当然か。
頑張るなぁ、博美は。
さて、そんな博美にはもう少しだけ頑張ってもらおう。
「博美」
「はい?」
「これ頼むわね」
袋に包まれたパンツを差し出すと、博美は少しだけ恥ずかしそうに頬を染めた。
「あの、これをどうしろと?」
「こっそり優子の荷物に入れておいてちょうだい。学校までママにパンツを届けてもらうなんて、本人も恥ずかしいだろうし」
「こ、こんなの持ってる私の方が恥ずかしいです!」
目を潤ませて声を荒げる。
やっぱり博美も、啓太郎と同じで昔と変わらないなぁ。
今でもいじりがいがある。
「お願いね、博美。今度、何か買ってあげるから。何がいい? 駄菓子屋のお菓子?」
「い、いつまでも子供扱いしないで下さい!」
「ごめん、ごめん。じゃあ、お願いね」
「は、はい」
恥ずかしそうに頬を染めながら、博美は私の行く逆方向へと歩いて行った。
小学校からの帰り道、近場のスーパーマーケット付近でマミちゃんを見掛けた。
買い物帰りだろうか、買い物鞄を持っている。
「マミちゃん」
自転車を降りて、後ろから呼び掛けた。
「あ、優子のお母さん。こんにちは」
暑さのせいか、かなり気だるそうだ。
「買い物の帰り?」
「はい」
「買い物鞄、重くない? 途中まででよければ、籠に入れて一緒に帰らない?」
「いいんですか?」
「勿論よ」
彼女の持っていた買い物鞄を自転車の籠に入れ、二人で並んで歩いた。
「マミちゃんは、学校のプールには行かないの?」
「いえ、私は……あんまり好きじゃないんです。学校のプール……。それに優子は……」
親友が友人よりも恋人の方へ揺らいでしまう。
よくある事だ。
でもきっと、そんな意識は優子にはないんだろうなぁ。
皆、仲良く楽しく過ごせれば良い。
そういう考えの典型的な持ち主だから。
「でも、マミちゃんにもいるじゃない? 優子が麗太君を好きっていう想いに、負けないくらいの想いを抱ける相手が」
「綾瀬の事ですか?!」
マミちゃんは少しだけ焦り気味に、私から目を反らす。
「そうよ。学校では喋る事もない。友達も、先生も、皆が知らない二人だけの時間が、マミちゃんと綾瀬君の間にはあるんでしょ?」
「綾瀬は……日曜日の教会へお祈りに行く時に一緒なだけで……」
「でも、私にクッキーの作り方を教わったのは、綾瀬君に食べてもらいたかったからでしょ?」
「はい……」
マミちゃんと綾瀬君の家は、それぞれがキリスト教の家計で、毎週日曜日は教会へ通っている。
クラスメイトの綾瀬君とは、学校では話したりはしないものの、日曜日だけは二人で教会へお祈りへ行くらしい。
なんでも、互いの両親がお祈りには参加しない代わりに、二人揃って行かせているとか。
「前に作ったクッキー。綾瀬……美味しいって言ってくれてました。あと、教会のシスターさんや他のクリスチャンの人達も」
先程まで気だるそうだった彼女だが、綾瀬君の話になると、どこか嬉しそうだ。
普段からクールを装ってはいるが、素が出ると可愛い。
優子から聞く学校でのマミちゃんとは大違いだ。
変に気取らないで、普段から素の自分を曝け出せば良いのに。
買い物鞄をマミちゃんに返し別れた後、真っ直ぐ家に帰った。
昼時よりも陽は少しだけ低い位置に傾いてきていて、暑さもかなりマシになっている。
庭の隅に自転車を停め、家に入ろうとしたところ「にゃぁー」という、鈍い猫の鳴き声が道路側から聞こえた。
鈍く鳴きながら、四本の足を地に着け背中を伸ばす。
「ああ! マルだ!」
はしゃいで私は駆け寄った。
マルの前でしゃがんで、頭や背中を軽く撫でる。
すると、また「にゃぁー」と鈍く鳴く。
「可愛い!」
マルは本当に可愛いなぁ。
ウチでも猫か何か飼おうかしら……。
無理かな。
世話も大変そうだし。
マルは大きく口を開けてあくびをした。
「マルはいいわね。猫って悩みとかあるの?」
また眠そうに鈍く鳴く。
「……まったく、私は猫に何を言ってるのかしらね。マルに相談してもしょうがないのに」
撫でるのを止めると、マルはピョンッと家を仕切る塀の上に跳んで、隣の家の塀の上を器用に歩いて行った。
こんな愚痴を話されたら、猫だって逃げ出してしまうわね。
冷房の電源を入れ、リビングを冷やした。
まず、部屋が涼しくないと夏は過ごせない。
こんな事、冷房なしの教室で勉強している優子に話したら、本気で怒られそうだ。
なんだか情けないなぁ、私って。
常々そう思う。
ソファに寝そべって、ジーンズのポケットに入れていた携帯を床に放り出す。
着信は一件もない。
最近、誰かとしたメールといえば、博美や啓太郎と会う予定を確認したっきり。
あと、今は誰にも言っていないけど、夏休みの少し前に皓から一通。
『心配掛けてごめん。仕事はしっかりやってるし、飯もちゃんと食べてる。だから俺は大丈夫。楓の事は俺も残念だと思ってる。すぐにでも、そっちへ帰りたい。でも今は駄目なんだ。まだ家には戻れない。一人で大変かもしれないけど、優子の事、頼んだからね」
皓が家を出て行って、約六カ月後に来たメールだった。
そのメールには、文の下に長いスペースが開けられていて、決まってこう書かれている。
『俺の事は探さないで。あとメールの返信もしないで』
私は皓の言う通り、居場所を探る為に仕事場に連絡を取って所在を聞いたりはしていない。
そんな事をすれば、なんとなく皓の事を裏切った様な気がしてしまいそうだから。
こちらの友人達にもメールの事は話さないようにと、最初のメールで言われた。
このメールを知れば、啓太郎や博美にアドレスがばれてしまうからだろう。
皓から来たメールのアドレスは、新しい物に変えられていた。
きっと私以外の、啓太郎や博美に連絡を取られる事を避ける為だ。
あの二人ならきっと、少しの手掛かりを掴んだ時点で、それを火種に皓の居場所を全力で探そうとする筈。
私の為に。
私は中途半端だ。
皓に帰って来て欲しいと願う毎日を過ごしているくせして、友人には皓の全てを打ち明けられないでいる。
こんな生活が、いつまで続くのだろうか?
長く続く筈もない。
優子も、麗太君も、やがて大人になって私から離れていく。
啓太郎や博美の様な友人達も、やがて家庭を持って私から離れていく。
博美は、もう何人かと付き合い別れを繰り返している。
啓太郎なんて、付き合っている今の彼女と同居までしているのだ。
皆、私から離れていく……皓も……。
「嫌だよ……皓」
ソファにうつ伏せになって目を瞑る。
皓の事が頭に思い浮かぶ。
嫌だ、皓の事が頭から離れない。
彼の笑顔、泣き顔、可愛い一面、かっこいい一面、色々な彼。
それらが思い浮かぶ度に切なくなって、溜まっていた涙がこぼれ出す。
「嫌だ……皓、どこにも行かないで……。私の所にいて……。私、寂しいの……皓」
小さな声で呟き続けた。
どれほどの時間、ソファに寝そべっていたのだろう。
外からの陽の光は、あまり変化がない。
私が思っていた程、時間は経っていないようだ。
こんな事ばっかりしていられない。
とりあえず体を起こそう。
ゆっくりとソファから起きあがった時、ふと、リビングの電話が鳴りだした。
慌てて駆け寄り受話器を取る。
街の総合病院の脳神経科の先生だ。
声の出せない麗太君のかかりつけ医でもある。
麗太君を私の家に預ける様に計画したのは、麗太君のパパだった。
仕事上、忙しい立ち位置でもあった彼は、麗太君を私に預け、会社近くのアパートに居を構えたそうだ。
親戚や両親の家に預けるという手もあったが、それは他県にある為に麗太君の生活環境を大きく変えてしまう事になる。
住む街や学校、何よりも友人関係。
その事を考慮して、麗太君は私の家に預けられる事になった。
妻である楓と親しかった私を信頼していた、というのも理由の一つだ。
それに、あの時は色々な事情が混在していた。
事故を起こした相手との事に関して、麗太君のパパも忙しかった様だし。
麗太君を脳神経科に通わせる事は、彼からの約束だった。
だから私は麗太君を預かってすぐ、彼を専門のかかりつけ医のいる病院へ連れて行った。
診断結果は一時的なショックやストレス。
今の生活に少しずつ慣れさせる事が必要なのだそうだ。
事故の時の事を思い出させる様な事は絶対にしてはいけないし、事故を起こした相手、そういった人物や関係者にも合う事は厳禁らしい。
麗太君はカウンセリングの為、一週間に一度、病院へ通う事になっている。
『自分が病院に通っている事は、優子には内緒にしてほしい』
そう麗太君から頼まれた。
だから優子には、麗太君の病院通いについては何も言っていない。
それで一時的なバランスは取れているのだ。
電話を掛けてきた先生の話は、麗太君の容体についての事だった。
先生の話では、ここ最近の麗太君は少しではあるが、愛想や雰囲気が明るくなったと言っていた。
今の生活に慣れてきた事もあるだろうけど、きっと大半は優子のおかげだ。
優子は、私が言った通り麗太君の支えになってくれた。
いや、それ以上の存在になったのだ。
嬉しい事ではあるのだけれど、なぜか少しだけ悲しくも思えた。
暫くして、優子と麗太君が帰ってきた。
余程、楽しかったのだろう。
二人は帰って来てもプールの話題で楽しそうに笑っていた。
麗太君は知ってすらいないのだ。
自分の母親を目の前でひき殺した男の存在を。
麗太君のパパは、彼に何も話していない筈だ。
本人は、事故を起こした相手を、どう思っているのだろう。
その真意は、私が踏み込んでいいような範囲ではない。
「ママ、目が赤いよ! どうしたの?!」
優子が私の顔を覗き込む。
麗太君も、心配そうに私の方を見ている。
「何でもないわ」
軽く目を擦る。
先程までソファの上で泣いていたからか。
格好悪いところ見せちゃったなぁ。
「ママ」
「何?」
「寂しかったら、いつでも言って。私も麗太君も、出来る事があったら何でもするから」
優子と麗太君は、私に笑い掛ける。
「そうね。二人とも、頼りにしてるわ」
そうだ。
私には、まだまだ信頼してくれる家族や友人がいる。
どんなに状況が変わっても、私は一人じゃないんだ。
それに優子だって、まだまだ子供だし。
私がいないとダメね。
「そういえば優子。今日のパンツは、何の動物なの?」
優子は恥ずかしそうに頬を赤らめる。
「当ててあげようか?」
「もう、ママ! 麗太君の前で何て事言い出すの?!」
「私には分かるわ。パンダでしょ?」
「ちょっ、しかも当たってる!」
「あなた達の事なんて、私にとっては筒抜けよ」
恥ずかしそうに騒ぐ優子、少しだけ赤面して苦笑いする麗太君、優子をからかって楽しんでいる私。
私は今、とっても幸せだ。
=^_^=
皆で買い物に行ったり、プールに行ったり。
たまにマミちゃんも交えて、たくさん遊んだ。
麗太君は、よくクラスの男の子達と公園にサッカーをしに行く。
その度に泥んこの汗びっしょりで帰って来る。
よく外へ遊びに行く為か、年齢の為か、麗太君も優子もかなり陽に焼けた。
若いって良い事だわ。
夏休みも終わりに近付いてきた頃、街ではお祭りの話題で持ち切りになっている。
商店街も、住宅地も、街の学校も病院も役場も。
『ごめんね。メールしちゃった。皓の言い付け、守れなかったよ。でもね、これだけは言いたくて……。私、今年も皓と皆で夏祭りに行きたい。だから帰って来て。遅れてもいい。その時は、あの土手の上で待ってるから。お願い』
数日前、私は皓にメールを送った。
いけない事だとは分かっていたけど、もしかしたら来てくれるんじゃないかって思ったから。
返信はまだ来ていないけど。
薄暗くなった街。
建物の間に張られた提灯。
歩行者が優先された道路。
大通りの両脇に構えられた露店。
そして聞こえて来る、祭りの花火や太鼓の音。
今年の祭りも去年と同様、優子はマミちゃんと行くそうだ。
麗太君は光原君やクラスの男の子達と。
何やら優子と麗太君は祭りの最中に、こっそり合流するらしいとの相談を、二人は出掛ける前にしていた。
面白そうでいいなぁ。
私はというと、まず啓太郎の店に集まって、それから先はテキトウに考えようとの事。
まあ、毎年そんな感じだけど。
「ママ、浴衣やって」
隣の部屋から優子が私を呼ぶ。
かなり焦っている様だ。
マミちゃんとの約束の時間まで、あと僅かだし。
麗太君は既に家を出ているし。
「あーあ、これは酷いなぁ」
帯の巻き方はめちゃくちゃだし、せっかくの青いアジサイ柄の綺麗な浴衣は、はだけちゃってるし。
「浴衣くらい、自分で着れるようにならないとダメよ」
優子の体に手を回し、浴衣を着せる。
帯を小さな腰に回し、しっかりと締めた。
「これで、よし!」
「ありがとう!」
小走りで玄関へ向かう優子を見送った後、家の戸締りをして、少しだけ時間を置いてから家を出た。
家の前の小さな通りには、露店や提灯はないものの、いつも以上に人の通りは多い。
やっぱり、お祭りだから。
啓太郎の店は、いつも以上に客が入っている。
「香奈さん、こっちこっち!」
バーカウンターを挟んで、啓太郎と香奈は楽しそうに話していた。
二人の元へ行き、博美の隣に座る。
「結局、集まったのはこの三人だけね」
「その分、私達で楽しみましょうよ」
「そうだよ。祭りは始まったばかりなんだからさ」
楽しそうに笑っている。
内心では寂しい筈なのに。
去年までは五人いた筈の友人が、私を含め三人だけになってしまうなんて。
悲観していても仕方がない。
今日は三人で楽しもう。
折角のお祭りなんだから。
啓太郎は店を彼女さんに任せ、私達とお祭りへ赴いた。
「啓太郎の事、よろしくお願いしますね」
彼女さんは、私と博美にそう言っていた。
信頼してくれているのだろうか。
私や博美が啓太郎と間違いを犯す事はないと。
啓太郎との関係なんて、絶対にないと思うけど。
彼もそれは承知の上だろうし。
それにしても啓太郎の彼女さん、綺麗な人だったなぁ。
啓太郎と同じバーテン服を着ていて、体も引き締まっていた。
それに声も落ち着いる。
そのせいか、あまり表情に上下がないというか……。
私より少し年下ってところだろうか。
二十代後半の若々しさの中に儚げな雰囲気もある。
僅かな年の差である筈なのに、彼女が羨ましくも思えた。
三人で幾つか露店を周った。
啓太郎は何かと露店を出している人と顔知りが良い様で、何件かで代金をサービスしてもらえた。
なんだか申し訳ない。
博美は完全に甘えていたけど……。
露店で買った物をバーに持ち帰り、ここ最近の自分の経過を三人で話しながら、少しではあるがお酒も飲んだ。
優子や麗太君の事や博美のここ最近の男性との付き合い。
博美の事に関しては、私も気になってはいたところではあったのだが、最近は男性との付き合いが全くと言っていい程ないらしい。
なんでも、両親にお見合いを勧められているそうで、それに甘えてしまおうだとか。
あと啓太郎の彼女さんの事も。
「啓太郎は、どうなの?」
啓太郎の彼女さんは、何やらテーブル席で数人の女性客と楽しそうに話している。
「僕は……そうだなぁ……」
啓太郎は少しだけ声を潜める。
「付き合って同居はしてるけど……結婚を前提ってわけじゃないんだ。ただ、あの時の彼女にとってはお酒の知識のある人が必要だったんだ。それで僕と仲良くなってね。前にも言ったけど、この店は彼女のお祖父さんの店だったわけだし。それで今は僕が切盛りしてる感じ。もし、僕にお酒の知識がなかったとしたら……彼女の僕へ対する態度は変わっていたかも」
「……そう」
啓太郎は笑ってはいるが、あまり面白い話ではない。
すぐにでも彼女の心理が知りたい筈だ。
「一応は……結婚の事も考えてるつもりだよ。もう暫くしたら、彼女に言ってみようと思う」
「啓太郎さん、頑張ってください。私も頑張りますから」
「そうよ。啓太郎は、もう三十路を過ぎてるんだから。博美だって、若いからって調子にのってたら、すぐに私みたいになっちゃうわよ」
「そんな! 香奈さんは、まだまだ綺麗ですよ!」
さすが博美だ。
嬉しい事を言ってくれる。
「お世辞でも嬉しいわ。ありがとうね」
「そんな事ないと思いますよ」
落ち着いていて綺麗な声。
横から話に入ってきたのは、啓太郎の彼女さんだった。
「平井香奈さん? ですよね。啓太郎からよく話は聞いています」
「あ、どうも」
「啓太郎の言う通り、やっぱり綺麗ですね。羨ましいです」
「え? 啓太郎?」
彼は少しだけ赤面して、私達から目を反らす。
「啓太郎、話があるの」
「ん? 何?」
彼女は一つ息を吐いて、私達の前で言い放った。
「そろそろ結婚の事、考えたい」
恥ずかしそうに私から顔を背けていた彼の表情が活気付く。
それは驚きや喜びに満ちた……そう、幸せそうに笑っていた。
「本当に?! でも、どうして急に」
「私、知ってるから。啓太郎が結婚の事で悩んでるの。もう三十路過ぎなんだから、ね?」
私達の話が聞こえていたのだろうか。
いや、もしかしたら本当に彼女さんからの告白?
「うん! そうだよ! そうだね! 一緒に頑張ろう!」
啓太郎は彼女の手をカウンター越しから握る。
その時、彼女は笑っていた。
まだ知り合って間もなかったけれど、表情に上下のないクールな彼女よりも、やっぱりこっちの笑った顔の方が可愛いなぁ、と私は思った。
店内にいる私達以外のお客さんが、拍手交じりに二人を茶化す。
「二人とも、熱いねぇ」
「やっと告白しましたかぁ」
彼女の啓太郎への結婚話の告白を祝うかの様に、外では打ち上がる花火の音が聞こえてきた。
さて、今からが私の今日一番の頑張り時だ。
「じゃあ、私はそろそろ行くわね」
「香奈さん、どうして? まだ、ぜんぜん飲んでないじゃないですか」
「いや……その、優子達とも約束があるから」
博美や啓太郎を誤魔化して、私は打ち上がる花火とは逆方向へ歩いた。
大勢の人が向かう逆方向へ。
露店や提灯が並ぶ通りとは逆方向へ。
住宅街や商店街とは逆方向へ。
目的地は決まっていた。
あの日、毎年、同じ時間、皓と星を見た河川沿いの土手だ。
コンクリートで舗装された道が、土手の上に真っ直ぐ伸びている。
普段、優子達にはここへ立ち入らないように言い付けている。
子供達だけで、土手の下の河川へ下りてしまう事もあるからだ。
人の気配は全くしない。
当然だ。
誰しもがお祭りへ足を運ぶ中、私だけがここにいるのだから。
辺り一面は、どこからか漏れている人家の明かりや、向こう側に見える花火や祭りの明かりで、かろうじて足元が見える程度の明るさを保っている。
街灯。
祭りの提灯。
花火。
人家。
そんな街に活気を溢れさせる強い光達の中で、儚く街を照らしている光があった。
見上げればそこにある無数の光。
夜空に輝く星達だ。
毎年、この場所で、欠かさず皓と見上げていた星々。
皓は、やっぱり来ない。
今年は、私一人だけで星を見る事になっちゃったなぁ。
皓の事が頭に浮かぶ。
まただ。
目蓋が熱くなってくる。
彼の事を考えると、いつもこうだ。
目を瞑っても、隙間から涙は溢れ出て来る。
泣き出す私。
そんな私を星々は容赦なく照らす。
溢れ出て来る涙を、私は人差し指で少しずつ拭い続ける。
「皓……」
その名を囁き続けて。
「香奈」
ふと、聞き覚えのある声が聞こえた。
皓だ。
間違いない。
この声の主は皓だ。
どこ?
「皓、どこにいるの?」
涙でぼやけていて、その上暗くて前がよく見えない。
「まったく香奈は、しょうがない奴だなぁ」
私の頭にポンッと軽く手が置かれる。
その後でわしゃわしゃと髪をかきまわされる。
「やっ、ちょっ!」
この感覚、間違いない。
こんな事を私にするのも、この手の大きさも……。
振り返れば、そこにいた。
長い間、私が側にいて欲しいと望んだ人。
「皓……」
「久しぶりだな、香奈」
強気な口調、それでいて優しさがこもっている。
皓が家を出て行った日から、彼自身は何も変わっていなかった。
仕事の帰りに直接来たのか、皓はスーツ姿だった。
やはり忙しいのだろうか。
私や優子と一緒にいられない理由も、もしかしたら仕事と何か関係が……。
聞けない。
私に、そんな事を聞ける度胸なんてない。
家を出て行く前までの皓は、とっても辛そうで、優子の前では必死に辛さを隠していたんだ。
もう、あんな辛そうな皓は見たくない。
「香奈、見てみろよ。今年も凄いな」
皓は夜空を見上げている。
綺麗な星々、それらをよそ目に私は皓の横顔ばかりを見つめていた。
今、純粋な気持ちで幸せそうに笑う皓を、ずっと見ていたい。
「皓……」
彼の手を握り、そっと寄り添う。
「星、凄く綺麗……。よかった。今年も皓と一緒に星を見る事が出来て……」
「でも、望遠鏡はなしだけどな」
「仕方がないわよ。今年は啓太郎や博美を誤魔化して、ここまで一人で来たんだから」
「そっか。やっぱり俺の……」
皓は私を真っ直ぐに見つめる。
「香奈、俺の事……怒ってる?」
ゆっくりと首を横に振る。
「そんな事ないわ。皓には、私達には言えない自分の考えがあるんでしょ? でもね、その考えが自分一人で抱えきれなくなったら、いつでも……私と優子の所に戻って来て良いんだからね」
彼の手が私の体に回される。
次の瞬間、体は皓に抱き寄せられていた。
彼の温もりが一身に伝わる。
もう、夏夜の蒸し暑さも感じない。
今、感じているのは直に触れている皓の温もりだけ。
それだけを受け入れる事で精一杯だった。
「ごめん……ごめんな……」
震えた彼の声が聞こえる。
皓ったら、また泣いてるんだ。
きっと、私の知らないところで、また何か辛い事があったんだろうなぁ。
皓には隠し事が多過ぎる。
でも今の私は、そんな彼さえも愛おしく思えていた。
「じゃあ香奈、そろそろ行くね」
そっと私から離れようとする皓の手を、私は咄嗟に握る。
「待って、まだ……」
まだ話したい事がいっぱいある。
もっと一緒にいて欲しい。
そう思った時だ。
眩暈と共に視界がぼやけ、そのまま皓の胸部に寄り掛かった。
なんてタイミングで酔いが回って来たんだろう。
啓太郎の店で、ちょっと飲み過ぎたかな。
完全に酔いが回っていた為、それから先の記憶はない。
気付いた時、私は自宅のソファーの上に寝かされていた。
全部、夢だったのか……。
いや、私は確かに、あの土手で皓を感じていた。
彼も同じ様に私を感じていた筈だ。
皓の笑顔、皓の体温、皓の匂い。
ああ、皓はまた私の前からいなくなってしまった。
それでもいつか、再び私のところに帰って来てくれると信じている。
その日がくる事を信じて待ち続けよう。
たとえ皆が私から離れて行っても、私がお婆ちゃんになっても……。
Episode4 Mami Amami
「神様わね、いつもマミの事を見守ってくれているの。マミが良い子にしていれば、神様は喜んでくれる。きっと神様はマミにご褒美を与えてくれるわ。だから、神様に微笑んでもらえる様な、立派な子になりなさいね」
小学校へ入る前、お母さんは私に度々そう言っていた。
私の家の家系はクリスチャンで、日曜日になると必ず、お母さんとお父さんと私の三人で教会のお祈りに参加した。
いつからだろう。
お母さんとお父さんが、私と一緒にお祈りへ行ってくれなくなったのは……。
=^_^=
夏休みが終わっても、鬱陶しい夏の暑さは、まだまだ留まる事を知らなかった。
今日は小学五年生二学期の始業式。
たった三時間の授業を終えて下校。
行く意味がない。
でも家にはいたくない。
だから私は学校へ行った。
「あの態度がムカつくんだよねぇ」
「あ、それ分かる。なんか見下してる感じがするっていうかぁ」
「そうそう。ちょっと顔が良くて、先生からの評判が良いからって。いつも一緒にいるけどきっと、内心では優子ちゃんの事、見下してるに決まってるよ」
クラス内の数人の女子が、そんな事を密かに話しているのを偶然にも聞いてしまったのは、今年の夏休みが始まる少し前だった
きっと、話の話題は私に関した事だ。
あの連中は、クラス内の女子の中では気の強い方のメンバ―だ。
その中の一人、見知っている顔がいる。
愛想笑いで皆の話に合わせている子、私の方を申し訳なさそうにちらちらと見ている。
由美だ。
由美は私や優子以外にも、構わず誰とでも話せる様な子だ。
しかしそれが原因で、逆に苦労する事もある。
見下した態度か……。
別に私は誰かを見下している訳ではない。
その人自身と関わる事で、私にどんな影響があるのかを見極めているだけだ。
とは言ったものの、関わりたくない人と友人の区別はしっかりと出来ている。
関わりたくない人……私に対して妙なレッテルを貼っているクラスの女子達だ。
彼女達が私を嫌っているのなら、私が近付かなければいいだけの話だ。
由美はどうだか知らないが……。
それとは逆に、私にとっての友人である優子。
彼女は私にとって、本当に良い友達だ。
勿論、私は彼女に対して人間として下等に評価した事など一度もない。
しかし周りの目は、私の思う通りには思ってくれないようだ。
夏休み開け一日目の学校を終え家に帰ると、お母さんは声を荒げて誰かと電話をしていた。
「どうして?! マミは来年は六年生に進級するのよ?! 受験が控えてるの!」
来年に控えている、私の中学受験の話だ。
「何でよ?! どうして私にマミの事を押し付けるの?!」
「……お母さん」
呼んでも、お母さんは受話器に怒鳴るばかり。
どうやら私が帰って来た事に気付いていないようだ。
いつもそう。
この人は平気で人の悪口を言う。
お母さんは、かつて愛してやまなかった筈のお父さんの悪口までも、いつからか私に言う様になった。
それも私とお母さんが顔を合わせる夕飯時に。
お父さんは家に帰る事が少ないので、面と向かった喧嘩を見る事は少ないが、今の様な電話越しの言い争いなら嫌と言うほど目にしている。
私はお母さんのゴミ箱だ。
内に溜めこまれた汚ない物の捌け口。
それがお母さんにとっての私。
自室へ向かい、背負っていたランドセルをベットに投げだした。
いつもの事。
いつもの事なんだ。
そう思っていないと、日々を過ごしていられない。
「マミ。あなたの父親は本当に最低よ。あなたと家の事を全て私に押し付けて……」
お母さんと私の二人で囲む食卓。
二人分の市販の弁当。
缶コーヒーと缶のオレンジジュース。
「あなたも思うでしょ? あの人は最低の人間なの。家にお金を入れるだけで、まるで私を家畜の様に扱っている」
「うん」
絶えずお母さんの口から出るお父さんへの悪口。
私は、それに無感情に頷く。
同情する事もなく。
「そういえば勉強の方は進んでいるの?」
「うん」
「そう。しっかりやらないとダメよ。あんな市立の小学校で一番の成績も取れない様じゃ、あなたが行きたいと思う私立中学には入学できないんだから」
別に、私が行きたいと望んだわけではない。
この人が私を行かせたいと望んでいるのだ。
しかし、そんな事を言えば、この人は私ではなく別の人間に対して怒りを抱く。
私に『こんな考えを押し付けたのは誰か』と。
「そういえば前の保護者会で、あなたの担任の藤原って先生。何て言ってたと思う?」
「何?」
「子供達には大らかに楽しく毎日を過ごして欲しいって。おかしいわ! これだから経験のない若い先生は馬鹿なのよ!」
「……うん」
この人が、私の親しい人達への暴言を吐いても、私は頷く事しかない。
そうしないと、この人は私以外の当人に対して、余計に怒りを増幅させるから。
たとえそれが優子の事であっても。
=^_^=
九月二十三日。
晴れ。
二学期最初の行事である運動会が終わって、一段落した翌週の日曜日。
私は綾瀬と二人、朝方に隣街を訪れていた。
電車で二駅の所にある新都市。
街に据え付けられた街灯や、大通りに並ぶお店やオブジェは西洋風の作りをしていて、まだ新しい。
駅から出てすぐのロータリーにあるバス停留所。
ここから出るバスで二つの停留所を通り過ぎた所。
そこが私達の目的地。
教会だ。
私と綾瀬は、教会のミサに来たのだ。
互いに、両親が日曜日の教会へ行かなくなっても、私と綾瀬は必ず、一緒にミサには参加している。
日曜日という事もあり、バスは人の乗降も少なく、すんなりと乗れる。
私達はいつも通り、一番後ろの席に腰を降ろした。
「マミ、今日は何を作ってきたの?」
綾瀬はいつも、私が作って来るお菓子を楽しみにしている。
期待に満ちている表情も仕草も、普段では学校では見れない彼だ。
なんだか可愛い。
「今日はワッフル。食べるのは、教会に着いて、お祈りが終わってからね」
優子のお母さんから作り方を教わった、ホイップクリームと苺を乗せたワッフル。
綾瀬に食べてもらうのが楽しみだ。
「ちょっとだけ、ここで俺が味見してやるから。お願い!」
綾瀬は笑顔でぺこぺことおねだりをする。
「だめ。教会でミサを済ませてから、シスターさんや皆と食べるんだから。綾瀬も、その時にね」
チェーっと言って、綾瀬はそっぽを向いた。
頭が良くて友達思いで、かっこいい。
綾瀬は、そんな印象を学校では皆に与えている。
でも日曜日に私の隣にいる綾瀬は、どこか子供っぽくて可愛い。
やはり人というのは、一緒にいる相手によって態度が変わるものだ。
勿論、私も……。
教会には、既に私達以外のキリシタンの人達も来ていた。
所々の長椅子に座っているのは、殆どが少数人の年寄りや小さな子供だ。
前の方の席には二人、シスターさんが座っている。
私達は後ろから二番目の長椅子に座った。
やはり見渡したところ、顔ぶれはいつもと同じ。
日曜日のミサに来るか来ないかなんて、私や綾瀬の両親と同じで、当人の自由だから仕方がないのだけれど。
聖壇に神父さんが立ち、説教が始まった。
黒い大きな縁の眼鏡、男の人にしては長く伸ばした長髪。
他の教会では知らないが、ここの神父さんは服装以外では、あまり聖職者と呼べる様な風貌はしていない様に思える。
それでも説教はしっかりとしているし、クリスチャンの人達は皆が、神父さんを聖職者として信頼している。
長い説教が終わると、最後にお祈りをする事が決まりになっている。
両手を組んで目を閉じ、私達はキリストの銀に光る十字が飾られた聖壇へ祈りを奉げた。
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever.
Amen.
天にまします我らの父よ
願わくは
み名をあがめさせたまえ
み国を来たらせたまえ
み心の天に成る如く地にもなさせたまえ
我らの日用の糧を今日も与えたまえ
我らに罪を犯す者を我らが赦す如く我らの罪をも赦したまえ
我らを試みに遭わせず悪より救い出したまえ
国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり
アーメン
聖体という一口サイズの小さなパンのような物が配られ、皆で閉祭の歌を歌って解散となる。
聖体というのは、見た目も食感も小さな白いパンで、味は全くない。
神父さんの話では、これはイエス様の体の一部であり、食す事によって彼の人生を私達の体に刻み込む事を意味しているらしい。
一口で食べられるから、味はなくてもあまり苦ではない。
解散し、皆が散らばっていく中、私と綾瀬、それとよく見知った顔の人達が神父さんやシスターさんの元へ集まる。
「マミさん。今日は何を作って来たんでしょうか? 実は私、朝ご飯はさっきの聖体しか食べていなくて、もうお腹がペコペコで」
私が作って来るお菓子を楽しみに待っている聖職者……なんだか面白くて笑えてしまう。
「はい、ちゃんと作って来ましたよ」
鞄から、箱に包んだワッフルを渡した。
「ワッフルです。皆に分けるんで、包丁とお皿を用意して下さい」
「分かりました。少しだけ、待っていて下さいね。すぐに準備をするんで」
その後、神父さんが切り分けてくれたワッフルを、皆で分けて食べた。
綾瀬、神父さん、シスターさん、他のクリスチャンの人達。
皆が美味しそうに食べてくれた。
笑い合い、他愛もない世間話をしながら。
「マミさんの作ってきてくれるお菓子は、皆を笑顔にしてくれますね。私のミサに皆が集まって来てくれるのは、あなたのおかげでもあるのかもしれません」
教会からの帰り際、神父さんは私にそう言ってくれた。
皆が美味しそうに食べてくれていたのもあるけど、僅かに自信が持てた様な気がした。
また作って来よう。
次は何が良いだろうか。
また優子のお母さんに、他のお菓子の作り方も教えてもらおう。
帰りの電車の中、右側のドアの側で。
綾瀬はジッと外の景色だけを眺めていた。
何か思い詰めたように。
こんな風に外の景色を眺めるのは、今日に始まった事ではない。
こういう彼は、今までで何度も目にしてきた。
学校での授業中も、今日の朝に私と待ち合わせていた時も……いつも。
この行動の意味を、私は探求した事はない。
それを問うてしまうと、今まで積み上げて来た彼との何か、時間や関係、色々なものが崩れてしまいそうな気がしたから。
「なぁ、マミ」
「何?」
「困った事とか……あったら、いつでも相談とかしていいんだから、な」
突然、何を言い出すのかと思えば、先程までの思い詰めていた表情は、これを言う為だったのか。
困った事……悩み……。
そんなもの、あり過ぎて何を言うべきか分からなくなる。
中学受験、お母さん、クラスの女子。
というか、綾瀬は私の何の悩みについての相談を持ち掛けているのだろう。
「ほら、由美とかの事……。お前、気付いてるんだろ?」
密かに悪口を言われているだけで、今のところ私には直接の被害はない。
というか、私が彼女達に近付かなければ、何も起こらない筈だ。
その事を綾瀬に告げると、彼の頬がホッと緩んだ。
「そっか、よかった。この前、あいつらがマミの事……その、マミの悪口を言ってたから……」
「考え過ぎ。私は何度も陰口を叩かれた事はあるけど、被害にあった事はないんだから」
「本当に、何かあったら言えよ」
綾瀬は本当に私の事を心配してくれている。
心配してくれる人がいる。
優子とはどこか違う、別の友人。
そんな綾瀬の事を、私はクラス内の男子の誰よりも気に入っていた。
=^_^=
学校の帰りに、優子の家に寄った。
優子のお母さんに、マフィンを作ったから食べにいらっしゃい、と呼ばれたから。
なんだか優子のお母さんに対して、いつも家にお邪魔してしまって申し訳ない。
学校からの帰りも一緒の優子には、気を張る必要はないけれど。
「すみません。今日はこの後に用事があって」
少しだけ早かったけれど、夕方前に優子の家を後にした。
帰りに「いっぱいあるから」と言って、マフィンも持たしてくれた。
用事がある、なんていうのは嘘だ。
優子のお母さんは優し過ぎる。
だからこそ辛い。
ここ最近の私は何かおかしい。
苦である事にはとっくに慣れていた。
でも、どうしてか優しくされるのは……逆に辛い。
優子の母さんが持たせてくれたマフィンを持って、家に帰った。
玄関の鍵は閉まっている。
お母さんは出掛けているのだろうか。
普段、持たされている鍵を使って、家に上がった。
誰もいない静かな家。
それほど古くなく、いや、むしろ新しい方の家の筈が、どこか空気が淀んでいて重苦しかった。
誰かがいて皆が笑顔で過ごしている、優子の家とは大違いだ。
優子のお母さんがくれたマフィンを冷蔵庫の中に入れ、リビングでお母さんの帰りを待った。
きっと夕飯までには帰って来る。
そしたら一緒にマフィンを食べよう。
美味しい物を一緒に食べれば、きっとお母さんも少しは機嫌がよくなる筈だ。
玄関から誰かが入って来る音で、ビクッと体が震え起きる。
どうやらお母さんの帰りを待つ間、ソファの上に座ったまま寝てしまっていたみたいだ。
リビングにお母さんが入って来る。
「あらマミ、帰ってたのね」
「うん。ねえ、お母さん。今日、学校の帰りに優子のお母さんの家に行ってね」
キッチンの冷蔵庫から袋に包まれたマフィンを見せる。
「優子のお母さんが一緒に持たせてくれたの。だから一緒に」
一緒に食べよ!
そう言いたかった。
しかしお母さんは、それを言う前に、私が両手に持っていたマフィンを床に叩き落とした。
「マミ。あなた最近、学校が終わっても帰ってくるのが遅かったのって、こういう事だったのね」
「あの……お母さん……」
「そんな事してる暇があるのなら、すぐ家に帰って勉強でもしていなさいよ‼」
お母さんは私の肩を掴み、声を荒げる。
床に落ちてしまったマフィンを構わず踏みつけ、私に迫る。
「来年は受験なの‼ 私の気持ちも分かってよ‼」
お母さんは声を荒げて私に迫ったかと思うと、いきなり泣き出した。
「皆……みんな私の気持ちも知らないで……。あなたみたいな出来損ないを、私一人で育てろなんて無理な話なのよ‼ あの人は仕事、仕事って……家の事は全部、私に押し付けて‼」
その後、私達はいつもの様に夕飯を食べた。
床に落ちてボロボロになったマフィンは、私が片付けて捨てた。
翌日、私はお母さんが起きる前に家を出た。
こんな家、もう帰りたくない。
でも、私は一人じゃ生きていけない。
だから家にいる時間を最小限にする。
私には、それしか出来なかった。
早朝の通学路には、私の様にランドセルを背負った小学生なんて一人もいない。
早朝の静かな街。
夏が終わった後の、涼しい十月中旬の空気。
「学校……行きたくないなぁ……」
学校へ行っても正直、楽しくない。
優子や綾瀬もいるけど……何よりも私の事を良く思わない連中がいるから。
皆が学校へ登校する時間を、隠れるように学校近くの廃れた公園にある、土管型をした遊具の中で過ごした。
一時間目が始まったであろう頃、隠れるのも飽きたので、こそこそと街中をテキトウにぶらついているうちに、駄菓子屋に辿り付いていた。
入るか迷ったけど、結局はドアを開けて中に入っていた。
ドアの開く音に気付いたのか、奥の部屋からおばあちゃんが来た。
「おや、マミちゃん。今日は学校じゃなかったのかい?」
「サボって来ちゃった」
私は笑顔で返した。
「そうかい。やっぱり気の合わない友達も、クラスに一人や二人はいるものさ」
私の学校での境遇。
家での事。
綾瀬との事
この際だから全てを打ち明けた。
私のどんな話にも、おばあちゃんは驚く事もなく、いつも通りの穏やかそうな表情で聞いてくれた。
「うん。だから今日は……学校をサボって来ちゃって……。こんな気持ちの良い日だからかな。なんか、学校へ行って嫌な気分になるのが勿体なくて」
「まだまだ若いんだから。今のうちから、なんでもするといいよ。ほら、サイダー飲みな」
冷蔵庫から出した瓶のサイダーを私に手渡す。
「あ、お金」
おばあちゃんは首を横に振る。
「お金はいらないよ。お代はマミちゃんのお話って事で、勘弁してあげるよ」
サイダーを飲み終えた後、駄菓子屋を後にした。
そういえば、今日はマルはいないのだろうか。
帰り際、おばあちゃんは私に言っていた。
「そういえばマル……最近ここに来てなくてねぇ。見掛けたら知らせてちょうだい」
マル……事故とかに合ってなきゃいいけど。
翌日から、私は再び学校へ行き始めた。
私が休んだ理由を聞いてきたのは、博美先生と優子と綾瀬だけ。
二人には、体調を崩した、というテキトウな理由で誤魔化した。
綾瀬だけには、本当の事を話した。
いや、話す事が出来たんだ。
次の時間は体育だ。
男子は更衣室で。
女子は教室で着替える事になっている。
私は授業合間で、体育着に着替える前の休み時間にトイレへ行った。
ドアを開けトイレに入ると、そこには私が最も関わりたくないと思っていた連中がいた。
四人の女子の中には由美もいる。
由美の表情が一気に青褪め、三人が私に敵意を向ける。
くだらない。
由美も、こんな連中に始めから関わらなければよかったのに。
四人を横切って、私は個室に入り用を足した。
トイレにいた分だけ、少しだけ遅くなってしまった。
トイレから出ると、皆が体育着姿で外へ向かっている。
「マミちゃん、先に行ってるからね」
私に駆け寄り言うと、優子も外へ向かって行った。
早く着替えないと。
教室のドアを開けた時だ。
その中にポツンと、一人だけ。
私の机の脇に由美が立っている。
「由美」
呼ぶと、彼女は私を横切って教室から出て行った。
どうしたんだろう。
体育着に着替えようと、自分の机に行くと、そこには無残にも切り裂かれた、私の体育着が机の周りに散らばっていた。
鋏かカッターナイフで裂いたのだろう。
犯人は、探るまでもない。
由美だ。
それから数日間、同じ様な事が繰り返された。
教科書やノートを裂かれたり、鉛筆を全て折られたり、物を隠されたり。
体育着が裂かれたりしていた為、体育の時間は何かと理由を付けて休んだ。
私の境遇を、優子や周りに知られない様にするだけで精一杯だった。
連中に話をしようという気は、その時はどうしてか起こらなかった。
ただ、嫌だった。
周りから、虐められっ子のレッテルを貼られるのが。
しだいに確信犯は由美だけには留まらなくなってきた。
由美以外の三人も関与している事が、日々の経過を見るごとに明かされていく。
授業中に私を見つめる数人の視線。
皆が私に牙を剥いている。
ただ、私が自意識過剰なだけ?
=^_^=
日々を耐え抜き、気付けば十一月になっていた。
時間が経つに従って、由美を含めた連中の動きにも、何らかのアクションが起こり始める。
私への攻撃がエスカレートし始めた。
放課後、私は由美を含めた連中に呼びだされた。
校舎裏の隅、外トイレとプールサイド近くだ。
今日は優子の家に行くという約束があるのだが、今まで間接的に攻撃をしてきた連中が、私に直接声を掛けるなんて珍しい機会だ。
だから約束を無視して連中に連れられるまま、ここに来た。
由美は気分の悪そうな顔で私から視線を反らす。
「マミちゃんは凄いね。私達にこれだけの事をされて、ちゃんと学校に来るんだから」
なるほど、ここまでされた私が、どうして登校拒否に陥らないかを言及したいわけか。
「別に。あんた達がやりたい事なら、それを私にやればいいじゃん。関わりたくないなら、私に関わらなければいいだけの話なのにね。勿論、私もあんた達となんか関わりたくないけど」
三人の敵意が私に集中する。
その瞬間を見て咄嗟に確認を掛けた。
「そうでしょ? 由美」
確認の意を求めたのは由美に対してだけ。
由美はビクッと肩を震わせ、泣きそうな表情を浮かべて私を見る。
「ちょっと由美。あんたも何か言ってやんなよ‼」
一人が由美を横から突く。
「私は……」
「私達、友達でしょ? みたいな事を言われたんでしょ? だから仕方なく、一緒になって私の持ち物を隠したり、体育着を切り刻んだりした。そうでしょ? 由美」
「ちょっと、あんたは黙ってよ‼」
図星だった様だ。
「由美。皆と仲良くする事なんて出来ない。だからこういう事になったんだよ」
それだけを言い残し、引き止めようとする三人を無視して、私はその場を後にした。
その後の数日間、連中からの攻撃は止まった。
言葉攻めで由美だけを責めたのに効果があったのだろうか。
もしかしたら、ターゲットを私から他の誰かに変更したか。
例えば由美。
あれだけ私に対して挙動不審になっていたんだ。
連中が由美に対して苛立ちを感じ、ターゲットを由美に変える事も有り得る。
そうなってしまった場合、原因は私にある。
一応、今日中に由美に話をしてみよう。
昼休み後の掃除の時間。
連中の目を盗んで、私は由美に近付いた。
「由美、ちょっといい?」
半ば強引に由美を連れて、ベランダに出た。
十一月下旬の為、かなり肌寒い。
「最近、元気ないよね。優子とも、あんまり話してないみたいだし……」
「……」
「ほら私達、最近あんまり話してなかったから」
「……」
由美は、ただ雲掛かった空を見上げている。
ここ最近の彼女は、以前よりも活気が感じられなくなっている事が、見ているだけで分かる。
「ねえ、マミ」
「何?」
「掃除が終わったら一緒に来て。皆で話したい事があるの」
皆……とは、連中の事だろうか。
「もうマミに何もしないから。だから皆で……マミに謝ろうかと思って……」
「あれだけの事をしておいて……どうして急に?」
「本当なの‼ お願い、信じて‼」
泣きそうな目で私を見て懇願している。
「……分かったよ」
掃除が終わった後に由美と二人で学校を出た。
もうじき冬という事もあり、空は既に夕暮れ色に染まっていた。
連中は先に学校を出て、私達を近くの公園で待っているそうだ。
公園には、土管型の遊具や、ブランコ、すべり台がある。
ここに来たのは先日、学校をサボった時以来だ。
普段、この公園には誰もいない。
すっかり廃れてしまっていて、遊具もペンキの塗装が剥げ、寄り付く子供がいなくなってしまったからだ。
おまけに住宅街からも離れていて、人の通りも少ない。
近いうちに撤去され、駐車場になるという話を聞いている。
土管の上に、連中が座って私達を待っていた。
三人が降りて来る。
「ありがとう、由美」
由美を含めて四人が、私を半円に囲む。
「マミちゃん……ごめんね……」
「私……何でも出来る子が、ただ羨ましかっただけなの! 許して!」
一人が泣き出す。
「私……本当に……ごめんね。……マミちゃん……」
泣いている……。
とりあえず、もう私に危害を加えないのならそれでいい。
この連中と関わるのも、今日を最後にすればいい事だし。
「うん……。もう何もしないっていうんなら、それで……」
一人が私にアイスを差し出す。
棒状のアイスの真ん中を折って、半分こにして食べる物だ。
その半分。
紫色のブドウ味。
「受け取って。一緒に食べよ」
「……うん」
これで仲直り……というわけか。
もう十一月だが、やっぱりアイスはいつ食べても美味しい。
夏場には、これと同じ物を駄菓子屋でよく食べたものだ。
由美は、ホッと安心したように微笑んでいる。
こんな彼女の表情を見たのは久しぶりだ。
しかし次の瞬間、その表情は困惑へ変わる。
一緒にアイスを食べていた一人が、私の手を強く叩き、アイスを地面に落した。
空気が凍り付く。
「あーあー、落としちゃったぁ」
「やっちゃったぁ」
「本当に性格、悪いんだね」
笑っている。
三人が私の腕を両方向から掴む。
三人の力は私の力の三倍。
そんな力には勝てる筈もなく、ランドセルを投げ捨てられ、土管型の遊具の中へ押し込まれた。
土管は大きく、子供なら一気に五人は入れてしまう。
私を囲む様に、三人が土管の中へ入って来て、半屈みの状態の私の腕や足を掴んだ。
土管の外からは声が聞こえてくる。
「ちょっと、どうして?!」
由美は三人に訴える。
「なんで?! ここでマミちゃんに謝って終わりじゃないの?!」
私を掴んだ一人が笑う。
「はぁ? だってマミちゃんが、私がせっかくあげたアイスを落としちゃうんだもん」
「仲直りしようってのに、本当にマミちゃんは人を見下すのが好きだよねぇ」
「やめて! お願い!」
由美は無理やり土管の中へ入り、三人の手を揺する。
「由美ちゃぁん、いいの? こんな事して。せっかくマミちゃんへの嫌がらせをしていない間、由美ちゃんには何もしてあげなかったのに。今のターゲットは由美ちゃん。それなのに、マミちゃんが由美ちゃんに話し掛けちゃったから。次はマミちゃんだ!」
「由美ちゃんのせいでマミちゃんは、私達に痛めつけられるんだよ‼」
その一言だけで、由美は膝を抱えて蹲ってしまった。
「そうだ! じゃあ、マミちゃんにチャンスをあげる」
私の髪を横から引っ張り、耳元で囁く。
「別の子を、マミちゃんの代わりに私達に差し出してくれたら、マミちゃんだけは許してあげるよ。例えば優子ちゃんなんて、どうかなぁ?」
何かが込み上げてくる。
私を押さえ付けている三人への怒りが。
優子が頭に浮かぶ。
私の……大切な友達。
「やめて! 優子には……何もしないで……」
「友達想いなんだねぇ。いつも一緒にいるけど、何? 同性愛者ってやつ?」
「マジ?! きもぉい!」
違う、優子は親友だ。
そんな事を考えた事なんてない。
「マミちゃんはレズなんだ! これから先、女の人としかシナいんだ!」
「え?」
両方向からジーンズのベルトを解き、一気に下半身の肌を晒された。
寒さで鳥肌が立つ。
「へぇ、マミちゃんって、スカートとか履いてるとこ、あんまり見ないから珍しいなぁ」
「脚、綺麗なんだねぇ」
恥ずかしさで一気に頬が熱くなる。
すぐにでも跳び出して逃げたい。
しかし、どれだけ足掻いても、動きずらい土管の中で、腕も脚も抑えられていては、どうしようもない。
「じゃあ、その下は?」
「やめて……嫌だ‼」
そのままパンツも脱がされ、自身の膣が向き出しにされる。
「じゃあ、これから先、男の人とはスる事のないマミちゃんに、味わえない事してあげる!」
そう言って手に持ったのは、先程のアイスだった。
切り口の吸い出し部分からは、アイスの液体が少しだけ零れ出している。
「何? ……何をするの?」
私の声は震えていた。
他人に対して、こんなにも恐怖心を抱いた事があっただろうか。
こんな気持ちは初めてだ。
「じゃあマミちゃん、いくよ!」
何をするのかと思いきや、手に持っていたアイスを一気に私の膣に挿入した。
信じられない位の痛さと冷たさが、私の下腹部を刺激する。
「痛いっい、嫌ぁ……ぃあ‼」
今まで味わった事のない感覚。
痛さ。
冷たさ。
そして何よりも憎い、という彼女達への気持ちが込み上げてくる。
「マミちゃん、大人ぁ」
そう言いながら数回、膣に挿入されたアイスを抜き差しする。
「嫌だ‼ お願い、やめて‼ あ、あああぁぁ‼」
溶けかけた紫色のアイスに血が滲み、それがポタポタと地面に零れる。
アイスが挿入されたまま、その手は止まった。
一人が立ち上がる。
「これで終わりにしてあげる」
そう言った次の瞬間、彼女は私の腹部を強く蹴った。
先程までの冷たさと痛みに重なって、更なる痛みが込み上げる。
「ぃぁぁぁあ、ぃっあ……ぁあ……ぁああああ‼」
次の瞬間に土管の中に響いたのは、私の泣き叫ぶ声。
誰も来ない。
誰も助けに来てくれない。
三人は笑いながら土管から出て行った。
残ったのは私と由美だけ。
「ごめん、ね……ごめん……ね。……ごめんね……」
由美は泣きながら、ひたすら私に謝り続けていた。
地面に手を着いて、ただ頭を埋めて。
「おい、マミ!」
眼が覚めると、目の前には綾瀬がいた。
「綾瀬……どうして……」
私の声は思った以上に掠れていた。
「マミを探してたんだよ! 他のクラスのやつに聞いたら、ここの辺りに歩いて行ったっていうから!」
膣からはアイスが抜かれている。
側には膝を丸めて蹲っている由美の姿がある。
「あいつらに犯られたんだろ?! そうなんだろ?!」
綾瀬は必死に私に呼び掛けている。
私は綾瀬の呼び掛けを無視して、掠れる様な声で言った。
「……私、幸せになりたくて……日曜日に、綾瀬と教会に行って……私……綾瀬に喜んでもらいたくて……。それなのに、どうして? ねえ、綾瀬。神様って……」
『神様わね、いつもマミの事を見守ってくれているの』
「神様って……いると思う?」
綾瀬の表情が一気に変わる。
それは今までに見た事のないくらいの、恐ろしい表情。
「いない。神様なんて……いない」
Episode5 Ayase Mitsuhara
マミの異変に気付いたのは、二学期の最大行事である運動会が終わって、暫くしてからの平日の事だった。
クラス内での一部の女子連中に目を付けられているという事は知っていたが、まさか、あれほどの事になるとは思っていなかった。
体育着を裂かれたり。
ノートや教科書を捨てられたり。
彼女への虐めは日に日にエスカレートしていく。
俺は出来るだけ、それを止めようと尽くした。
女子や男子から向けられる、俺への好評を利用し、出来るだけ連中やクラスメイトに探りを入れてみたり。
それでも意味はなかった。
特にマミは、まるで何事もなかったかのように俺に対して振る舞った。
何よりも、平井にだけは自分の置かれている状況を知られたくはなかったようだ。
平井優子。
俺の友人、麗太にべったりな、まるで不幸というものを知らなくていつも呑気そうに、にこにこと笑っている。
今まで表には出していなかったが、俺は平井が嫌いだ。
麗太と一緒にいるところを見ると、本気で殺意までもが湧くほどだ。
あんな奴がいるから……マミや麗太は……。
幸せな奴がいるから、不幸な奴がいる。
幸せな奴の下に、不幸な奴がいる。
あの日、俺は親父からの暴力に耐えられず、隣町にある叔母の家に一人で逃げ込んだ。
おふくろは仕事に出掛けていて、家に戻る事は少ない。
当然だ。
あんな親父と俺だけがいる家、帰って来ても苦痛を感じるだけだから。
半年ほど前の事だ。
親父は会社をリストラされた。
元々、共働きであった両親は、互いに擦れ違う事が多く、あまり仲の良い方とは言えなかった。
それでもおふくろの収入は充分であり、生活には何ら問題はない。
しかし既にその時に、親父からの暴力は始まっていた。
気が付けばおふくろは、たまにしか家に顔を出さなくなっていた。
そんな生活が始まって、もう半年。
蹴られた脇腹が痛い。
思いっ切り肘で突かれた胸部が痛い。
煙草の火を据え付けられた右脇が痛い。
俺の体はボロボロだ。
腕や脚や顔は、傍から見れば外傷が目立ってしまう。
だから親父は、服を着ていれば目立たない様な胴体だけを集中的に攻撃する。
どうやら俺は、世間では人当たりも良く顔も運動も勉強も完璧といった、漫画の様な設定で通っているらしい。
近所にも、学校にも。
だからこの傷痕は、誰にも打ち明ける事は出来ない。
おかげで今年の夏は、皆とプールにも行けなかったなぁ。
「はい、綾瀬君」
叔母はテーブルの上に、お茶と茶菓子を置いた。
「綾瀬君が遊びに来てくれるなんて嬉しいわ」
そう言って叔母はにっこりと笑う。
幸せそうな、悩みなんてなさそうな……。
俺は……こんな表情を知っている。
学校でも、よく目にする……ウザったらしい表情。
平井優子。
いつも笑っていて、どこか能天気な……そして、いつも麗太の側にいる。
嫌ではあるが学校ではなるべく、こんな表情を作るように努力してきた。
人との関わり、それを良い方向に保つには笑っている事が一番だから。
だから俺も叔母に笑い返す。
言えない。
こんな幸せそうな人に今、自分が置かれている状況なんて。
叔母も、親父の話はなるべくしないように話題を反らし続けている。
「そういえば、教会にはまだ通っているの?」
「はい、マミと二人で……」
「そう。仲が良いのね」
昔から、マミと二人で通ってきた教会。
通ってはいるものの、俺には未だ崇拝する理由が理解出来ないでいた。
祈り続けても報われた事など一度もない。
年を経る毎に両親は祈る事を止め、俺と由美だけが教会へ通っている。
通ってはいるが、もしかしたら俺自身は気付いているんだ。
ただ認めたくないだけ。
神様なんていない。
もしかしたら、マミも同じかもしれない。
平井に虐めの事を打ち明けないわけも。
それは、あまりにも彼女が幸せそうだからだ。
自分の様な不幸な人間が、幸運な人間に対して内を晒してはいけない。
そう思っての事だろう。
幸福な人間がいれば、不幸な人間は必ずいる。
でも俺は、なるべく周りからの評価を下げない為、幸福な人間を演じ続けている。
誰に対しても愛想笑いを浮かべ、なるべく他人から見て良い人であり続ける。
これからも、ずっと。
脇腹に激痛が走る。
眼を開けると、すぐ側には親父が立っていた。
ああ、そうか。
床で寝ていたところで脇腹を蹴られたんだ。
親父は俺の髪の毛を引っ張り、俺を立たせる。
無造作に生やされた髭や髪の毛、鼻を突く酒の臭い。
「なんでテメエみてぇなガキが産まれてきたんだ?」
低く沈んだ声で言う。
俺は親父から目を反らす。
「おい、なんだよ。その態度は」
「別に……」
「そういうのがうぜぇってんだよ‼」
俺の頭を床に叩き落とす。
脳が震盪する。
周りの景色がぼやける。
さすがにまずいと思ったのか、親父は俺から一歩引く。
床に這いつくばる俺は、徐々に開く視界の中で親父を睨む。
「そうやって、子供みたいに喚いて……だから、おふくろは……」
俺の小さく呟いた一言が、親父の勘に触った様だ。
「あいつはこの家に金を入れるだけで、帰って来ねぇ。それはなぁ、テメエがいるからだ! いつでも殺してやっていいんだぞ?! もう俺の人生、滅茶苦茶なんだからよ‼」
強い痛みが脇腹を突く。
また数回、蹴られる。
「この野郎! お前がいれば金が入ると思って、良い気になりやがって! どうせあの女、俺以外の男と寝てるんだよ‼ テメエも俺も、どうせすぐに捨てられるさ‼」
こいつ、何を根拠に浮気話を?
おふくろが仕事を口実に帰って来ないのは、大半が親父のせいだ。
いつか俺が大人になったら……このクソ親父を殺して……誰に対しても愛想笑いなんかしなくて済む、どこか遠くの街に逃げてやる。
夜中、家を抜け出した。
痣や擦り傷が痛んで、あまり寝付けなかった。
俺の痣や傷は、綺麗に胴体にだけ残っている。
見る限り、もう感心してしまう。
親父は酒が入っていたせいか、大きく鼾をかいて寝ていた。
耳障りな鼾で気分を害するより、外に出て解放感に浸った方がよっぽど体にも良い。
人のいない道には、虫の鳴き声だけが響いている。
時間的にもかなり遅い為、周りに並ぶ住宅には明かりすら点いていない。
たまに車道を車が通るだけ。
ものすごく心地が良い。
そろそろ涼しくなる時期だ。
そしたらきっと、今よりも外にいる時間が増えるんだろうなぁ。
咄嗟に歩を止めた。
夜の闇に紛れ、二つの光る目玉は真正面から俺をジッと見つめている。
道の真ん中で、座ってジッと俺を見ている。
「……マルか」
マルは答えるように、いつものおっとりした鳴き声を返す。
「こんな時間に出くわすなんてな……」
近寄ってみると、いつも目にする白くて丸っこい体が露わになる。
「お前はいいな。駄菓子屋に世話になって、皆に可愛がってもらえて……」
屈んで、マルに手を伸ばす。
いつも皆がマルの背中をさすったり、頭を撫でたりする様に、いつもと同じ様にマルへ手を伸ばした。
あまりマルには触った事はなかったが、たまには皆みたいに触ってみるか。
しかし、俺だけは皆の様にはいかなかった。
指先に鋭い痛みを感じる。
マルに噛まれた。
今までにない位に相手を敵視する様な唸り声を上げ、伸ばされた指先を噛んでいる。
「痛っ……」
噛まれた指先を外そうと、マルの口から指先をずらす。
すると更なる痛みが走る。
なんだよ、これは?!
いつもなら皆が触っても、こんな事はされていなかった。
マルにとって、俺は敵視するべき人間だとでもいうのだろうか?
噛まれている指先から、ポタポタと血が垂れる。
こいつ‼
強引に外せば痛みは一瞬。
俺はマルの口から一気に指を引き抜いた。
その反動で、マルの体は地面に転がる。
指先にはマルの歯で噛まれた、血の滲む二か所の傷痕。
一瞬の激痛の後の鈍い痛みが、指先に残っていた。
ああ、そうか……分かった。
こいつは俺の事を本能的に拒んでいたんだ。
俺みたいな汚らしい人間を拒んでいた。
いつも他人へ愛想笑いを浮かべて、人気者であろうと周りを意識して良い人ぶる。
こいつは、そんな俺を見抜いていたんだ。
本当は、ただ自分が幸福であると演じ続け、その反面で幸福な人間を忌み嫌い、それを隠してきた俺をの正体を、こいつは見抜いていた。
猫って、人が分かるんだな。
だから平井には、あんなにも懐いていたんだ。
幸福な奴が憎い‼
楽しそうに笑う平井が憎い‼
この猫が憎い‼
俺はマルの背中の皮を両手で鷲掴み、丸い体を持ち上げた。
苦しそうに唸り、前足や後ろ足をバタつかせる。
しかし、そんな事をしてもマルの体を制した俺には、もう傷一つ付けられやしない。
「良い人を演じ続けるのも大変なんだ。お前みたいに人を見抜く奴は邪魔なんだよ」
掴んでいたマルの体を、一気に地面に叩き付ける。
今までに聞いた事のない様な猫の叫び声が響く。
「お前が俺を見抜いたから悪いんだよ! 全部、お前が悪い!」
そう連呼して、マルを数回地面に叩き付けた。
皮が擦り剥け、地面に血が飛ぶ。
鳴き声が小さくなり、動きも少なくなったところで止めた。
近くにあったゴミ捨て場に置かれていたゴミ袋にマルを詰め、河川敷沿いの土手に持って行った。
一先ず川沿いの草むらに隠した。
ここなら誰かに見つかる事もない。
こんな所に来る奴としたらホームレスか、自己満足でゴミを拾って河川を掃除するような奴くらい。
もし見つかったとして、勝手にこれを誰かが処理してくれるわけだが……。
見つからなければ、この薄い呼吸で生きている袋に詰められた猫は、水や餌を与えなければ、おそらく数日で勝手に死ぬ。
……この程度じゃ面白くない。
もう少しだけ痛めつけてやろう。
最小限に水や餌を与えて毎日、少しずつ少しずつ嬲り殺してやる。
お前は平井の代わりだ。
人間を殺せば罪になる。
でも猫なら大丈夫。
「お前は平井の為に、俺に殺されるんだ」
『マルを知らない?』
麗太はメモ用紙で俺に伝えた。
「マルが? どうかした?」
聞き返す俺に麗太は最近、全くマルを見なくなったと言う。
平井もかなり心配していると。
ああ、そうだよ。
街で見つかる筈なんてない。
今は俺が飼っているんだから。
数本のソーセージとペットボトルに入った水、それと夏休みに使ったきり余った数本の花火を持って、マルのいる土手を訪れた。
放課後に皆でサッカーをするのも断り、ここへ来た。
今の俺にとって、マルを痛め付けるという事に、それ程の快感が生じていたのだ。
今日は学校で良い知らせがあった。
マミへの嫌がらせが止まったらしい。
マミは自分で、そう俺に言ってくれた。
これでもう、マミが悩む必要なんてない。
マミへの嫌がらせが止まった原因は分からないが、それが終わったのなら良いに越した事はない。
だから今日はお祝い。
今日はマルには優しくしてあげよう。
袋を開けると、マルは傷だらけの体を丸めてぐったりとしていた。
体の各所の毛は剥げ、見える範囲の地肌には幾つも傷がある。
かつて見た事のある、駄菓子屋にいた頃の活気はない。
昨日、袋の中に入れておいたソーセージがなくなっているのを見るに、しっかりと食べたようだ。
このまま死なれるのも面白くない。
そうこなくては。
袋の中のマルへ語り掛ける。
「ねえ、今日さぁ。マミへの虐めが止まったんだよ。マルも嬉しいでしょ? だからさぁ、今日は一緒にお祝いしようよ」
ソーセージと一緒に持ってきた数個の花火の中から、線香花火を手に取り、先端に親父からくすねたライターで火を点けた。
線香花火から、綺麗な火花が散る。
「今日はお祝い。だから花火だよ」
先端を下に向け、マルの入っている袋の上にかざした。
火花が袋の中へ入り、マルを少しずつ焦がす。
真っ白な毛。
先日、痛めつけた時にできた傷痕。
大きな目。
柔らかい肉球。
全てを少しずつ焦がす。
マルは小さく鳴きながら、身を震わしている。
もう大きな動作をする事すら出来ないようだ。
側にはソーセージと水と数個の花火が置いてある。
数個の花火の中には、ロケット花火もある。
これは、また今度にしよう。
線香花火から、終わりを告げる一粒の小さな火玉が、袋の中へ落ちる。
それがマルの背中を、最後に焦がした。
微かに肉の焼ける様な臭いが周囲に発ちこめる。
「今日はこれで終わりにしてやるよ」
ソーセージを袋に投げ入れ、その上からペットボトルの水を半分かけた。
袋の口を縛り、狂った愉悦を感じながらその場を後にした。
=^_^=
「そっか……今度はあいつが……」
「うん……」
授業合間の休み時間、俺はマミに連れられ、、なるべく人目につかない一番奥の廊下にいた。
マミは俺に由美の話をした。
マミへの虐めが止まって数日後、由美の様子がおかしくなったと。
前々から由美の様子はおかしかったが、最近ではより酷いものになったと。
まるで何かに怯えている様な……。
「もしかして連中、私から由美にターゲットを変えたんじゃ……」
「あいつは皆して、マミの事を虐めていた奴だろ? そんな奴、もう放っておけよ」
これ以上、マミには虐めを楽しむ様なグループとは、関わって欲しくない。
「そういう訳にも……いかないって」
あんな奴に、どんな思い入れがあるっていうんだ。
あんな奴らにかまっていたら、もう次は何をされるか分からないのに。
放課後になると、数人のクラスメイトが俺にサッカーをしようと誘ってきた。
今日は土手までマルの様子を見に行く日だ。
サッカーなんてしている場合じゃない。
「ごめん。今日は用事があってさ」
「何だよ? 綾瀬、最近付き合い悪いよ」
まあ、たしかに。
これ以上、皆に不信がられるわけにはいかない。
終わりにする日も近いかもしれない。
ランドセルを背負い、教室を出ようとした時だ。
麗太に引き止められた。
「麗太、どうした? 今日はちょっと用事があって」
麗太は手で『違う』とジェスチャーし、隣の平井を指差す。
麗太の隣には平井がいる。
それを見た瞬間、何かが込み上げた。
麗太と一緒にいるからだろうか。
より一層、こいつが憎たらしい。
「あの、綾瀬君……。マミちゃん知らない?
今日は一緒に帰って、寄り道しようって、約束……してたんだけど……。どこにもいなくて……それで、皆に聞いてるんだけど……」
マミがいない。
その言葉が、不安となって頭を過ぎる。
辺りを見回すと、教室にはまだクラスメイトは残っているが、マミは勿論、由美を含めたあの連中がいなくなっている。
まさか‼
他のクラスメイトに聞いて回り、一人で学校中を探し回った。
「さっき、学校の裏の方に歩いて行ったのを見たけど」
学校の裏門を出て、住宅街や商店街とは反対方向。
ここら一帯は、工事現場や水路が多く、人気が少ない。
そんな辺鄙な所に何の用があるというのか。
もし俺達の様な小学生が行く所としたら……あの廃れた公園くらいだが……。
学校の裏門を出て、今は放置されている工事現場や用水路を渡り、公園に辿り着いた。
もう冬も近いからか、辺りは既に薄暗くなっている。
公園の敷地に植えられた数本の枯木の形、そこから織り成される影が、人気のないここら一帯の薄気味悪さを強調している。
やっぱり誰もいない。
じゃあ、マミはどこへ……。
「ごめんね……」
小さな声が聞こえてくる。
「ごめんね……」
気のせいかと思ったが一度、聞き取ってしまうと頭から離れない。
「ごめんね……ごめんね……」
泣きながら謝っている様だ。
誰に?
「ごめんね……」
声は確かに聞こえてくる。
「ごめんね……」
聞こえてくる方向へと、俺は歩き出した。
「ごめんね……」
歩く度に、声は大きくなる。
土管型の大きな遊具。
この中から聞こえてくる。
遊具の右側へ周り、中を除いた。
そこには信じられない様な光景が広がっていた。
今まで生きて来て、これ程までに無残な光景を見た事があっただろうか。
声の主は地面に頭を埋めて、ただ泣きながら謝り続ける由美。
謝っていた相手は、すぐ側で横たわっているマミだった。
ズボンとパンツを脱がされ、下半身の二つに割れた軟肌の間には、二つに割って食べるブドウ味のアイスの片方が刺さっている。
紫色の溶けかけたアイスの液体と、赤く滲んだ血が混ざり、軟肌を伝って垂れていた。
マミは宙を向き放心している。
「マミ!」
彼女の名を呼び掛け寄る。
何が起こっているのか分からない。
この光景が衝撃的過ぎて、うまく頭が回らない。
彼女の二つに割れた軟肌に刺さっているアイスを抜かなければ。
そうだ、抜くんだ。
マミの前で屈み、アイスをゆっくりと抜く。
アイスを放り出し、マミを揺する。
「おい、マミ!」
マミはやがて俺の存在に気付く。
「綾瀬……どうして……」
彼女の声は小さく微かなものだった。
「マミを探してたんだよ! 他のクラスのやつに聞いたら、ここの辺りに歩いて行ったって言うから!」
隣で謝り続ける由美と一緒に……。
という事は、マミを虐めていた連中もいた筈だ。
「あいつらに犯られたんだろ?! そうなんだろ?!」
あの連中……絶対に許さない……。
マミをこんなにまでして、ただじゃ済ませない!
マミの口がゆっくりと動く。
「……私、幸せになりたくて……日曜日に、綾瀬と教会に行って……私……綾瀬に喜んでもらいたくて……。それなのに、どうして?」
マミの口からこんな言葉が出るなんて……信じられない。
こんなに……追い詰められて……。
やはり、マミも気付いていたのだろうか。
「ねえ、綾瀬。神様って……」
「?」
「神様って……いると思う」
いる筈なんてない。
いるのなら、俺達はもっと報われた人生を送れていた。
神様なんていない。
俺達がこんな目に合ったのも全部、幸福な奴がいるから。
幸福な奴が、そんな日常に飽きて、俺やマミの様な奴にちょっかいを出す。
だからマミは連中に虐められた。
平井だって……どうせ外面だけを気にして、能天気を気取っているに違いない。
そうやって友達の振りをして、マミを騙し続けていたんだ。
「いない。神様なんて……いない」
マミの表情が一変する。
それは何もかもを失ったかの様な……いや、失ったんじゃない。
解放されたんだ。
もう神様なんて信じない。
もう教会へ行く必要もない。
マミには、俺がいる。
幸福な事に飽きた意地汚い連中からマミを守るんだ。
「マミは……俺が守るから……」
マミを強く抱き締める。
普段の強気な口調や態度とは相まって、彼女の体は俺を受け入れていた。
「大丈夫? 立てる?」
マミにパンツとジーンズを履かせ、手を取って土管の外に立ち上がらせた。
どうにか動ける様だ。
「由美……」
マミは彼女の名を呼び、手を差し伸べる。
彼女は埋めていた土塗れの顔をマミに向ける。
こいつが……マミを……あいつらと一緒に……。
こいつも同罪だ。
マミを押し退け、俺は土管の中で半身を起していた彼女を押し倒し、馬乗りになって胸倉を掴んだ。
「お前が……お前がマミを‼」
握り拳を作り、彼女の頬を殴る。
彼女から生気は感じられない。
虚ろな目をして、ただ殴られながら俺を見ている。
「お前がマミを売ったんだろ?!」
後ろからマミが俺に抱き付き叫ぶ。
「やめて! 由美も被害者だから! 由美も虐められてたの‼」
彼女を殴る手を止め、土管から出た。
「綾瀬も由美も、とりあえず今日は帰ろう! ねぇ!」
由美の頬は赤く腫れている。
罪悪感はない。
マミをこんな目に遭わせたのは、こいつも同じなんだから。
帰り道で、マミから放課後にあった事を聞いた。
連中に騙された事や、由美も虐められていた事も全部。
マミのされた事は犯罪だ。
親や先生に言う事を勧めたところ「マミは絶対に誰にも言わないで」と俺に懇願した。
世間からの目を気にしているのだろうか。
おそらく今日の事が世間にバレれば、担任へ責任が問われたり、生徒の転校沙汰にもなりかねない。
マミはそれを恐れているのだ。
そんな彼女の願いなら従うしかない。
これからは連中から目を離さず、マミの事だけを何よりも優先しよう。
クラスメイトに怪しまれても構わない。
今までの様に、極力マミとは学校で話さないなんてルールはお終いだ。
絶対に、マミに辛い思いはさせない。
=^_^=
マミを家に送り届けた後、一度家に帰り、懐中電灯と残りの花火を持って、河川敷沿いの土手へ走った。
懐中電灯の明かりで、草むらに隠してあったマルの入っている袋を探す。
見つけた袋にはハエがたかっている。
元々、汚らしいのは承知の上だ。
袋を開け、衰弱しきったマルを袋から草むらに転がす。
僅かに一回の呼吸と共に体は動いているが、もう死にかけだろう。
目玉は飛び出し、口からはドロドロと黄色い液体が垂れている。
「今日で終わりにしてやるよ」
これは俺達をコケにした幸福な奴らへの仕返し。
それの足がかりだ。
マルの口から喉より下に、ロケット花火の先端を差し込み、それの後箸に付いている着火線にライターで火を点けた。
五メートル程の距離を置き、それを見守る。
やがて着火火はロケット花火の本体に到達し、激しい火花がマルの体を内側から突き破った。
肉や血や目玉が辺りの草むらに散り、ミミズの様な内蔵だけがそこに残っていた。
マルは完全に死んだ。
そこら中に散らばった肉塊には、かつての面影はない。
俺は歓喜の声を上げながら、散らばった肉塊を袋に詰め込んだ。
Episode6 Each view
True view ~Kana Hirai~
今まで、優子に隠してきた秘密がある。
いや、優子だけじゃない。
楓、啓太郎、博美、いろんな人に。
秘密を知っているのは私と皓、極少数の大人だけ。
他の誰かにバレないよう、たくさんの嘘をついてきた。
事実が明かされる日が、いつか来るのではないかと怯えてきた。
優子は、今は亡き優太の存在すら知らないというのに。
それは、まだいい。
私や皓には、他の誰にも言っていない秘密がある。
私の娘、平井優子。
今まで『この子は実の娘だ』と自分に言い聞かせて育ててきた。
でも実際は違う。
現実から目を反らし、自分に言い聞かせていただけ。
やがて彼女は、優子を迎えに来る。
そう。
平井優子は、私の実の娘ではない。
Main view ~Yuko Hirai~
冬場の放課後というのは、なぜだか物寂しい。
暗くなるのが早い為、皆が早々に帰宅してしまうからだ。
授業が終わって間もなく、教室の窓からは夕陽が差している。
薄暗い教室の窓から見えるオレンジ色の空。
私はそれをジッと見ていた。
誰もいない教室で、ただ私一人だけで。
授業が終わってすぐの事だ。
『ごめん。校庭で六年生とサッカーの試合する事になっちゃって。だから先に帰っててもいいから』
麗太君は申し訳なさそうに、メモ帳の謝罪文を私に差し出す。
「いい、待ってる」
私は彼の肩を軽く叩く。
「頑張ってね」
そう言って笑顔で見送った。
少し前まで、私は学校では麗太君と一緒に帰る事はあまりなかった。
どうせ家で会える。
だから、今まで通りマミちゃんと帰っていたのだが……。
いつからだろうか。
ああ、あれはたしか十一月の半ばくらい。
マミちゃんの様子がおかしくなってからだ。
「マミちゃん。一緒に帰ろ!」
その日の放課後も、いつもと同じ様にマミちゃんに話しかけた。
「ごめん。一人で帰って」
私を見る彼女の目は、どこか虚ろで、何かに怯えている様だった。
その頃からだ。
マミちゃんの隣には、必ず光原君がいた。
朝、学校に来るのを見掛けた時も。
放課後の帰り道で見掛けた時も。
麗太君に相談したところ「最近のあいつは付き合いが悪い。それになんだか近寄りがたい」との事だった。
クラスの皆も、その二人に対しての態度が少し変わった。
私の親友、マミちゃん。
私やマミちゃんとは特別な接点もなかった筈の光原君。
せめて言うなら、ただのクラスメイト。
あの二人がどうして……。
ここ最近、私はマミちゃんには話し掛けていない。
ただ、怖かった。
マミちゃんと光原君、二人の関係を知ってしまう事で、マミちゃんとの友人という関係をも壊してしまいそうで。
試合はすぐに終わった様で、二十分程度で麗太君は戻ってきた。
私と帰る為、クラスメイトの男子達とは校庭で分かれたそうだ。
「帰る?」
聞くと、麗太君は頷いた。
家々の間で僅かに顔を出している夕陽が、まだ眩しい。
それでいて、学校帰りの路道はしきりに影で覆われていて薄暗かった。
麗太君と二人だけの帰り道。
最近ではこれが普通になっている。
放課後、どうしても麗太君がサッカー等の試合に必要な時、私は彼を待った後で一緒に帰る。
麗太君といるとホッとする。
彼には最近のマミちゃんの様な恐ろしさはない。
というのも、由美ちゃんや他の少数の女の子達の態度が、どこか重苦しいものに変わっていた。
何かに怯える様な、そんな仕草をするのをよく見る。
だからクラスの雰囲気も、夏場に比べるとかなり淀んで見えた。
麗太君といる時だけ、かつての明るかった日々を思い起こす事が出来る。
きっと、麗太君と一緒にいれば私は大丈夫。
「ねぇ、麗太君。こんな事がいつまで続くのかな……。なんだかクラスの雰囲気も前と比べて……暗くなってるし……。それに光原君だって……」
麗太君も光原君の事で悩んでいたのだろう。
彼は麗太君にとっての親友でもあるのだ。
私にとってはマミちゃんと同じ事。
やだ。
また麗太君の前で弱音を吐いちゃった。
こんなんじゃ、また悲しくなって……。
何か楽しい事を考えなくちゃ。
それでも何も浮かばない。
楽しい事なんて、考えようとして思い付くものではない。
だめ、涙が溢れてくる……最近、いつもこうだ。
麗太君の前なのに。
寒さで悴んだ手に、温度が伝わる。
「麗太君?」
見ると、私の手は彼の手と繋がっている。
温かくて、ホッとした。
言葉なんて、交わせなくたっていい。
ただ、ここに麗太君がいる。
それだけで、今の私にとっては幸せだった。
なんだか麗太君って、恋人っていうよりお兄ちゃんみたいだ。
僅かな夕陽が私達の背中を照らし、目の前には手を繋ぐ私と彼の影が、長く真っ直ぐに伸びていた。
家の中ではママに対して、マミちゃんや学校の事に関しては、なるべく触れない様に務めた。
マミちゃんが最近、うちに来ないというのは、受験勉強で忙しいのだろうとか、常に何かしらの理由を用意した。
でも博美先生の事だ。
もしかしたらママに相談でもしているのかもしれない。
=^_^=
「優子。あなたの名前は優子よ」
綺麗な女の人。
彼女は涙を浮かべて、私を抱きかかえていた。
「私と、あの人が以前に同じ夢を、優太に託した様に……。今度はあなたに託すわ。優しい子に育って……優子」
緩やかに落下する彼女の涙が、私の頬を濡らす。
やがて視界は閉じ、私は今まで見ていた光景が夢であったと気付く。
=^_^=
翌日の朝。
いつもと同じ目覚ましの音。
窓から差し込む、乾いた冬の朝陽。
私と麗太君とママで囲む、いつもと同じ朝食。
そして、いつもと同じ麗太君と歩く通学路。
そう、いつもと同じなんだ。
ただ……。
優太。
今朝の夢に出て来た女の人が囁いた名前。
それがどうしても頭から離れない。
「優太……」
不意に、その名を呟いていた。
隣にいる麗太君は、ポカンとした顔で私を見ている。
「ごめん! なんでもないの! ちょっとボーっとしてたっていうか……その……」
麗太君はメモ用紙を取り出し、サラサラとペンを走らせて私に渡す。
『余計な事を考えちゃダメ。悩みばかり詰め込んだらパンクする』
「あんまり考え過ぎるなって事?」
私の問いに頷く。
たしかに、たかが夢に出て来た知りもしない名前に悩むなんて、どうかしていたのかも。
先程のメモ用紙に重ねて、もう一枚。
『僕は、悩みなんてない能天気で馬鹿な優子が好きだから』
麗太君は笑っている。
ああ、そうか。
悩みなんて、気にしなければどうって事はないし、自分一人で悩んでいても何も解決はしないんだ。
かつての私は、悩みというか今の現状……何かモヤモヤした妙な感覚を持っていなかった。
つまりは能天気で……馬鹿だった。
「ちょっと麗太君! 馬鹿は言い過ぎなんじゃないの?!」
麗太君は「それ逃げろ!」とでも言わんばかりの勢いで楽しそうに駆ける。
私もそれを追い掛ける。
楽しい。
変な事ばかりを考えずに、楽しい事だけを考えて麗太君と一緒にいる。
それだけの事が、こんなにも楽しかったなんて。
用は気の持ち様というやつで、つまり私は馬鹿な方が性に合ってるって事だ。
通学路の半分を走った頃には、既に息が切れていた。
「麗太君って足、速いんだね」
まあ、伊達にサッカーをしているって訳ではないし、第一に麗太君は男の子なんだ。
思いっ切り走ったせいか、なんだか気分が良い。
「せっかくだし……学校、サボってみよっか?」
冗談半分で麗太君に聞いてみた。
まあ、どっちかっていうとサボりたいんだけど。
こんなに気分が良いんだし、なんだか学校へ行くのが勿体ない気もするし、何よりも麗太君との二人きりでいる時間が、もっと欲しい。
学校にはちゃんと行こうって、断られるかと思った。
きっと、いつもの麗太君ならそう言っていただろう。
でもなぜだか今日の麗太君は、私のお願いを聞き入れてくれた。
人気の多い商店街や大通りでは、私達のような小学生が昼過ぎに出歩いていたら注意を受けてしまう。
注意をするような大人の目に触れられず、長くいられる場所。
旧街の方の駄菓子屋だ。
元々、駄菓子屋の周辺の住宅地は、私達の住む住宅より古く、商店街に比べればあまり人通りも多くない。
きっと、おばあちゃんなら分かってくれると期待を胸に、駄菓子屋の戸を開けた。
やはり店先には誰もいない。
いつも通りだ。
いつも通りだからこそ、ここに来ると安心する。
「お婆ちゃーん!」
「はーい!」
店先より奥の部屋から、すぐに私への返事が返ってきた。
おばあちゃんはサイダーを手に二本持って、奥の部屋から出て来た。
「優子ちゃんが来るとしたら、麗太君も一緒だろうと思ってね。ほら二人とも、サイダー飲みな。金はいらないよ」
「ありがとう」
私と麗太君はサイダーを受け取る。
炭酸が溢れ出ないように、そっとキャップに埋め込まれたビー玉を中へ押し出した。
けっこう慣れてきたものだ。
麗太君は慣れた手付きでさっそく開けて、もう飲んでるけど。
お婆ちゃんは側に置いてあった椅子に腰掛けた。
「ほら、あんたらも座んな」
私達も側にあった椅子を寄せて、そこに座る。
「あの、お婆ちゃん……今日は、私達……」
一応、話しておこうと思った。
学校をサボった事……出来る事ならマミちゃんや光原君の事も。
でもお婆ちゃんは、出掛かった私の言葉を遮った。
「いいよ。なんとなく事情は分かるさ。第一、私に話してもしょうがない。まだ若いんだから、今のうちに悩めるだけ悩んでおく事さね」
言っている事は正しい。
私達が誰かに話したところで、その誰かが問題を解決してくれるわけではない。
やはり最終的には自分達の問題になるんだ。
「そういえば前にも……確か、あれは今日みたいな平日の昼だったかな。マミちゃんが訪ねて来たんだよ。学校をサボって来たってね。あんたらと同じだよ」
「嘘? マミちゃんが?」
「そうだよ。あの真面目なマミちゃんだって、学校をサボりたくなる日くらいあるのさ」
マミちゃんも……私達と同じだったのだろうか。
どこか空気の重くなったクラスの雰囲気も、マミちゃんと光原君も……ずっとこのままなんて絶対に嫌だ。
今の悪い状況を変えるには、まず学校へ行かない事には始まらない。
「麗太君」
彼はメモ用紙を示し、私に合図する。
『たぶん今、優子と同じ事を考えてた』
麗太君も分かっているんだ。
このままではいけない事。
私と麗太君で寄り添って、マミちゃんや光原君から逃げるのではなく、向き合う事を。
ちょっと前までは、腹を割って話せた友達だったんだ。
きっと大丈夫。
私達はお婆ちゃんにお礼を良い、駄菓子屋を後にした。
どうしてか足取りが軽い。
ここ最近、学校へ行く事が億劫になっていたせいかもしれない。
何の目的もなく学校へ行き、マミちゃんの様子を覗い、時には麗太君の元へ逃げていた。
でも、もう大丈夫。
明確な目的が出来たから。
=^_^=
駄菓子屋から出て暫く、なぜだか麗太君は背後を覗っていた。
「どうしたの?」
こっそりと麗太君は筆談する。
『駄菓子屋を出てすぐ、後ろから知らない女が着けてきてる』
「え?!」
麗太君は『静かに』とジェスチャーする。
僅かに背後を振り返ると、誰もいない歩道の中央を歩いている私達よりも五十メートル程離れた所に、スーツ姿の女の人がいる。
全ての髪を後ろで束ね、きっちりと黒いスーツを着込み、険しい表情で私達をジッと見ている。
昼過ぎに、こんな所を小学生が歩いているんだ。
大人が私達に注意を払うのも無理はないだろう。
「麗太君、走ろ!」
私達は背後の女の人から逃げるように学校へ走った。
学校に着いた頃には、もう給食の時間だった。
こんな時間に来たんじゃ、博美先生に「給食だけ食べにきたでしょ」ってからかわれてしまう……いや、もしかしたら怒られちゃうかも。
上履きに履き替えて、麗太君と騒がしくなったお昼時の廊下を歩く。
ふと、前からクラスメイトの女の子が三人歩いて来た。
擦れ違い様に話し掛けようとしたが、三人は私を素通りして見向きもせずに行ってしまった。
どうしたんだろ。
気付かなかったのかな。
そんな筈はない。
あんなに近い距離にいたのに。
嫌な予感がする……。
麗太君は心配そうに、すぐ後ろで私を見つめていた。
教室に入り、机の上にランドセルを置いて気付いた。
いつもなら、私に会えば誰かしら話しかけてくれる筈なのに、今日は誰も話し掛けてくれない。
もしかして……皆が私を避けている?
試しに、近くにいる二人の女の子に話し掛けてみた。
「ねえ」
私が話し掛けるまで楽しそうに会話をしていた二人は、横目で私を見るなり会話を止め、席を立ってどこかへ行ってしまった。
嘘だ……。
だって昨日まで、普通に楽しく話していたじゃないか。
他の子も、そうだった。
男女共に、誰に話し掛けても応えてくれない。
麗太君は?
咄嗟に、彼の元へ逃げたくなった。
しかし彼の姿は教室にはない。
机の上には黒いランドセルが置かれてあるだけ。
教室に取り残された私。
給食を各席に配っている当番の子達が、私の方をちらちら見ながら小声で何かを話している。
「ほら、平井の分の給食、持ってけよ。早くしないと先生が来ちゃうし」
「えー、私……嫌だよ」
「俺も嫌だよ。でも、やらなきゃ……綾瀬が……」
綾瀬?
光原君は、この状況に関して何か知っているのだろうか。
そんな考えが頭に浮かんだ時、男子が一人、私に給食を持ってきてくれた。
「あ、ありがとう」
受け取ろうとした瞬間、給食を持ってきた男子は私の目の前で、食器を乗せていた盆を一気に引っ繰り返した。
ご飯やおかずや汁物が、一気にランドセルを乗せてあった机の上に浴びせられる。
「え?」
唖然とした。
目の前の光景が信じられなかった。
何よりも他人から、こんな仕打ちをされたのは生まれて来て初めてだったから。
どうして良いのか分からず途方に暮れ、考えれば考える程に目蓋が熱くなってくる。
なんで?
嫌だ。
こんな所で泣くなんて……恥ずかしい……。
涙で歪む視界の中で、私を見つめる親友の姿が目に止まった。
マミちゃん。
助けてくれる……なんて期待したのが運の尽き。
マミちゃんは私を見て数秒、顔色一つ変えず教室から出て行ってしまった。
そんな、どうして?
「早く片付けろよ」
「泣いて済む問題じゃないし」
「ちょっと顔が良いからって調子に乗ってるんだよ。泣いて許してもらおうって」
駄目だ。
こんな所にいてはいけない。
麗太君もいない……私を理解してくれる人のいない、こんな教室になんて。
私は教室を飛び出した。
溢れる涙を拭い、必死に走った。
昨日まで親しかったクラスメイト達。
ちょっと遅刻して来ただけじゃないか。
それがどうして、いつの間にかこんな事に……。
頭の中に先程の彼等の言葉が湧いてくる。
それはまるで嗚咽の様に、私の頭の中にひたすら響いていた。
学校を抜け出した所で、誰かにぶつかった。
まずい。
こんな所で大人に見つかったら……。
見上げると、昼前に私達をつけていた女の人だった。
「あ、あの……」
泣いていた上に思いっ切り走った為、上手く言葉が出せない。
女の人は前に屈んで、そっと私の頬をなぞる。
彼女の細い指が、微かに私の涙を拭う。
この人……先程は遠めだった為に分からなかったが、ママよりは少し年上だろうか。
それよりも何よりも、どこかママとは違う、でも覚えのある香りがする。
その為か、少しだけ安心した。
女の人は泣いている。
どうして?
私が泣いているから?
今日、初めて会ったばかりなのに。
「あ、あの……私……えっと……」
何か話さなければならない。
そう思った時、女の人が口を開いた。
「会いたかった、優子」
「どうして……私の名前を?」
立ち上がり私の手を取る。
「ちょっと、歩こうか」
女の人に手を引かれ、私は少しずつ学校から離れて行った。
暫く歩いた所で、彼女の閉じていた口が突然開く。
「どうして泣いているの?」
まず聞かれるであろう筈の質問が今になってきた。
私は取り繕う様に、未だ目蓋に溜まっている涙を拭いつつ笑ってみせた。
「大丈夫です。ちょっと嫌な事があって、学校を出て来ただけですから」
初対面の人に先程の事情を説明したところで、どうにかなる訳でもあるまい。
女の人の手に僅かに力が籠る。
「何か悩みがあったら、私に言ってちょうだいね。きっと役に立つと思うから。いや、立ってみせる」
この人は一体、何者なのだろう。
私の名前を知っている上に、私の為になろうとしているなんて。
「あの……あなたは……」
女の人は、その場で立ち止まり私に笑顔を向ける。
「私の名前は小宮順子。あなたのお母さんから、何か聞いてない?」
今までママの口から、こんな人の話題が出る事はなかった
それ以前に私は、親戚のお祖母ちゃんやお祖父ちゃん、叔母さんや叔父さん、従姉妹の話すらも聞かされた事がない。
かつて、私がママにした質問を、何となく覚えている。
『私にはお祖母ちゃんはいないの?』
その質問の答えは、うちには母方も父方も、親戚はいない、というものだった。
もしかしたら、この人はママやパパと何か深い関係が?
「もしかして親戚の人か、それともママの友達ですか?」
考えられるとしたら親戚か友人という線が妥当だった。
しかし彼女は首を横に振る。
「やっぱり何も聞いていないのね。可哀想に……」
可哀想という言葉が、なぜか引っ掛かった。
「全部、話してあげる。あなたが母親だと信じている香奈の事。そして……皓の事も」
=^_^=
マイナス思考が頭に絡み付く。
嫌な事しか浮かばない。
今は、とにかく走るんだ。
家に帰ろう。
そうすれば全てが分かる。
『香奈は、あなたの実の母親じゃないわ』
先程の言葉が頭に蘇る。
『あなたは、皓と私の間に生まれた子なの』
嫌だ!
考えたくない!
『優子という名前は、香奈と皓の流産した息子、優太という男の子の名前から取ったの』
私にお兄ちゃんなんていない!
聞いた事もない!
『もしかして優太の事も聞いていなかったの? 本当に……可哀想』
違う!
私は可哀想なんかじゃない!
小谷順子という女の人と繋いでいた手を振り払い、私は思いっ切り家に向かって走っていた。
彼女は追って来ない。
私はひたすら家まで走る。
寒々しい冬の日の空の下を。
家にママはいなかった。
買い物にでも出掛けているのだろうか。
ポケットに入っている合鍵を使い、家に入った。
時計は1時半を周っている。
今、学校はどうなっているのだろう。
どうでもいい、学校なんて。
今は真実を確かめるんだ。
一階のママの部屋へ行き、本棚を漁る。
三段目の棚にアルバムがある。
アルバムを引き抜き、床に広げた。
開いた一ページにつき、二枚の写真が貼ってある。
一番新しい写真。
小学五年生の運動会で撮った写真だ。
そこに写る、私とマミちゃんの笑顔。
「どうして、こんな事になっちゃったんだろう……。私、マミちゃんに何か嫌な想い……させちゃったのかな……」
涙で視界が霞む。
今日、泣いたのは何度目だろう……。
ページを捲ると運動会よりも前の写真。
夏休みにマミちゃんが、私の家に遊びに来た時のものだ。
あの時は、麗太君とマミちゃんの仲があんまり良くなくて、二人を仲良くさせようと私が頑張ったんだっけ。
皆で行ったプール。
夏祭り。
記憶に残る思い出は、遡る程に何かを忘れている事に気付く。
だからアルバムがある。
小学四年生、三年生、二年生、一年生。
ページを捲る度に、写真に写る私は小さくなっていく。
五年生より前の写真には、ちょくちょくパパの姿も写っている。
小学一年生の私の隣で、にこにこ笑いながらカメラ目線なパパ。
幼稚園の年長、年中、年少。
まだ幼稚園に入る前。
次のページを捲ったところで……そこより前のページはなかった。
そういえば、どうして私は自分の赤ん坊の頃の写真を見た事がなかったのだろう。
この家にある私の写真が三歳くらいから始まっていて、それよりも前がないという事は、私はママやパパと共にこの家には住んでいなかったという事になる。
嫌だ。
信じたくない。
また本棚を漁り、もう一冊の分厚いアルバムを取り出す。
もしかしたら、これに……。
ページを開くと、そこに写るのは若い男女の写真。
二人が同じ制服を着ているのを見るに、高校生だろうか。
女の人が男の人に飛び付いている感じだ。
ページを捲る度に、同じ様な男女がじゃれ合っている写真が目に付く。
女の人が浴衣を着ている。
これは夏祭りか何かの時の写真だろうか。
男の人が二人と、浴衣を着た女の人が二人、それと可愛らしい小学校低学年くらいの小さな浴衣を着た女の子が一人。
この人達は誰なんだろう。
どこかで見た事のある様な……ページを飛ばし飛ばしで捲っていく。
なんとなく分かってきた。
これは高校時代のパパとママの写真だ。
ずっと……こうやって二人の思い出を写真に撮ってきたんだ。
ふと、ある写真が目に着いた。
お腹を膨らませた妊婦の写真。
ママだ。
公園のベンチに座り、幸せそうに笑っている。
写真の端には、ペンで短い文章が書かれていた。
『香奈、皓、優太。ずっと一緒だよ』
じゃあ、このお腹にいるのは……。
あの人が言っていた、ママとパパの本来の子供。
唐突に玄関で物音がした。
ママが帰って来たんだ。
こんな時間に家にいるのが知られては厄介だ。
どうしたものかと慌てている間に、異変に気付いたママは私のいる部屋に入って来る。
「優子?」
「ママ……これは……」
「どうしたの? あ、もしかして熱が出て早退して来たとか?」
近付いて、私の額に手を添える。
「熱は……ないみたいだけど」
「違うの……そうじゃなくって……」
ママは床に視線を落とす。
その時、表情が凍りついた。
今までに見た事のないような、困惑した表情。
「優子……このアルバム、見たの?」
黙る私に、ママは問う。
「見たのね?!」
怒鳴られた。
いつも大らかで穏やかな、あのママが私を怒鳴った。
そして私の両肩を強く掴み問い詰める。
「どうして?! 勝手にこんな物を見るなんて! ねえ、どうして?!」
数度、肩を揺らされ、私はママの手を振り払う。
そうか。
やっぱり、ママの反応を見る限り、小谷順子という女の人が言っていた事は本当だったんだ。
この家にない、赤ん坊の頃の私の写真。
お腹の膨れたママの写真に、ペンで書かれた文章。
そこには明らかに優太と書かれていた。
「ねえ、ママ……。小谷順子さんって、誰?」
その名前を聞いた途端に、ママは私から一歩引く。
「それに優太って? 私は何なの? 今まで、ママとパパで私に隠し事してきたって事?」
ママは答えようとしない。
「ねえ、嘘って言ってよ。いつもみたいに……笑って誤魔化してよ……」
部屋に降りる沈黙。
その数秒後、ママは重い口を開いた。
「そう。小谷が……来たのね」
「あの人と知り合いなの?」
「あの人、小谷順子は、皓が高校生の時にバイトしていたお店の人。そして……あなたの本当のママ」
「嘘……」
今まで頭の中では否定してきたけれど、ここにいるママの言い分を聞いてしまっては、否定のしようがない。
微かに浮かぶ、幼い頃の記憶。
私を見つめる悲しそうな、本当のママの表情。
私の頬にこぼれていた、今ここにいるママの涙。
その時のママの言葉。
『優子。あなたの名前は優子よ』
近所の人達の噂話。
『優子ちゃんも可哀想にねぇ』
『でも、仕方のない事なんじゃない? だって、香奈ちゃんが流産しちゃったの、あの順子って子のせいだって、噂になってるじゃない』
パパの泣き顔。
『ねえ、どうして泣いてるの?』
『ああ、いや……ちょっとな。嫌な事を思い出しちまって……』
泣きながらも笑い掛けるパパに、私も笑い掛けた。
『大丈夫! 嫌な事は、私とママで一緒にいれば、ぜーんぶ消えちゃうから!』
まるで、自分とは程遠い世界の事の様に感じていた。
ありえない。
さっきまでママだって信じて一緒にいた人が、実のママじゃなかったなんて。
「優子」
ママは私に手を差し伸べる。
今まで感じてきたものと同じ。
同じ匂い、同じ温もり。
けれど、それは偽物。
「嫌!」
叫び、私はママの手を振り払った。
「今まで、ずっと騙してたんだね。優太君って子の事も全部、隠して。私は……私の優子っていう名前も……全部、優太って子の代わりだったんでしょ!」
怒鳴る私を前に、ママは微動だにしない。
まるで、いつかこうなる事が分かっていたかのような、覚悟の様な何かが感じられた。
あの後、ママは何も言わずに、私を取り残して部屋から出て行った。
部屋に残された私は、あれからずっと床に深く座り込んでいる。
キッチンの方から聞こえてくる晩ご飯の支度をする音。
いつもと同じ。
でも、その時の私とママの間には、大きな歪の様なものが出来上っていた。
夕暮れの光が部屋に差し込み始める。
ああ、もう学校が終わる時間だ。
どれほどの間、ここに座り込んでいたんだろう。
立ち上がり部屋から出た。
リビングを通してキッチンから聞こえてくる音。
そんな普段、癒されていた筈の音が、今の私にとっては不気味な音にしか聞こえなかった。
それら全てが偽物だから。
偽物の家族。
偽物の家。
偽物の日常。
偽物の通学路。
偽物の学校。
偽物の友達。
偽物の街。
優太という子の代わりとして、今ここにいる偽物の私。
全てが偽物だ。
キッチンの方からは、先程と同じ音は未だ止まない。
聞こえてくる音に耐えかね、我慢ならずに立ち上がった。
おぼつかない足取りで玄関のドアを開け、外へ出ると、寒々しい冬の夕暮れ時の風が頬を鋭く切った。
全部、偽物。
なら、私がここにいる理由なんて、今はいない優太っていう子の埋め合わせにしかならない。
辺りは暗くなり、人家と街灯の明かりだけが辺りを照らしていた。
こんな時間に一人で、人通りの多い所にいては気が滅入るだけだ。
だから人のいる場所とは逆方向へ、誰もいない場所を求めて歩き続けた。
ふらふらになり辿り着いた場所は、河川沿いの土手だった。
普段、ここはママや先生からは、川に落ちたら危険だから絶対に立ち入ってはならないと、しつこく言われていた。
でも今の私にとって、そんな事はどうでもよかった。
坂になっている草むらを登り切り、コンクリートで舗装された、街灯も何にもない土手の道に出る。
土手の下から向こう側に掛けて見える街の明かり。
偽物の……街。
反対を振り返ると、川を挟んだ向こう側には隣町の夜景が見えた。
もっと向こう側には、僅かにビル群も見える。
そうか。
もっと向こう側は、ここよりも都会なんだ。
その時、私は思った。
こんな街から出て行きたい。
今ここにいる私の成す意味が偽物というのなら、こんな偽物の街から逃げ出せば、私はきっと本当の自分になれるのだと。
そうだ、遠くへ行こう。
自分自身が偽物だと気付いてしまった今、私にはこの街で今まで通りに過ごせる自信なんてない。
ママの私に対する態度や、学校で私が受けた扱いも……全て今の私が偽物だと自身に気付かせる為の出来事だったんだ。
河川沿いに隣接する草むらに座り、夜景を眺めた。
向こう側には、きっと新しい何かがある。
そんな想いを胸に。
「どうしてだろう」
頬を伝う涙を拭い、呟く。
「どうして……こんな……」
どうして今更、涙なんかが出るんだろう。
あの夜景を見る度に、余計に溢れ出る。
ついさっき、決心したばかりじゃないか。
それでも本音を言えば、この街から離れる事なんて有り得ない事だった。
だって生まれてからずっと、この街で過ごして、この街でマミちゃんや麗太君と出会って……。
でも、もう私に友達なんていない。
麗太君も……きっと私の事なんか……。
「どうして、こんな事になっちゃったんだろう……」
今まで、家で麗太君とママとで楽しく過ごし、学校でマミちゃん達と遊び、家に帰って三人で楽しく晩ご飯を食べる。
次の日も、その次の日も……ずっと。
そんな事が、ずっと続くと思っていたのに。
「どうして……今まで、あんなに楽しかったのに……家も学校も……どうして皆……」
「皆、平井を騙していたんだよ」
泣きながら呟き続ける私の後ろで、誰かが言った。
「マミも麗太も……クラスの奴らも、皆」
振り返ったすぐ後ろには光原君がいた。
かつて学校で、皆に振りまいていた様な笑顔とは逆の、曇り掛かった虚ろな表情。
どうして、こんな所に?
立ち上がり光原君と向かい合う。
「この際だから打ち明けるよ。クラスの奴ら皆、平井の事を嫌っていたんだよ」
「?」
「能天気で、いつも笑っていて。……勉強も出来てしっかりしているマミのくっ付き虫。おまけに麗太と付き合いだす始末だ。皆、そんな平井に嫌気が差してたんだよ」
今まで私は、誰かに嫌われている事にすら気付けずに、毎日をのうのうと過ごしてきたとでもいうのだろうか。
その結果が今日の私。
「皆、平井への態度を偽っていたけど、とうとう爆発したんだな。平井にだけは偽物の態度をとって」
偽物……それこそが今の私。
「付いて来て。見せたい物がある」
光原君は言い、川沿いにより近付いた。
私もそれに続く。
川沿いスレスレの草むらに、汚らしいゴミ袋が転がっている。
光原君はそれを足で蹴りながら、私のすぐ前に転がした。
嫌な予感がする。
このゴミ袋の中だけは、絶対に見てはいけない。
そう直感した。
「光原君……これ……」
手が汚れるのも気にもせず、光原君は袋の結びを解く。
中にある物が、やがて姿を現した。
赤黒く腐った肉塊、焦げ爛れ破れた皮から生える白い毛。
集る蝿や蛆虫の群れ。
見てすぐに分かった。
何かの動物の死骸だ。
立ち込める悪臭と、それを見てすぐに湧きだった悪寒。
反射的に吐き気が込み上げたところで、堪らず必死に口を押さえて目を反らした。
光原君は淡々と喋り出す。
「これ、俺がやったんだ」
こんな事、人間のする事じゃない。
この時、私は初めて人を軽蔑した。
今までに感じた事のない様な、憎悪の対象がすぐ目の前にいるのだ。
「最近、駄菓子屋の猫。見掛けないだろ?」
問いに無言で頷く。
「そうだよ。これがマルなんだから……」
言葉を失うと同時に、更なる恐怖心が私の中で増大した。
光原君が少しずつ、私の方へ進んでくる。
その度に、私の足は一歩ずつ後ろへ下がる。
「全部、平井が悪かったんだ。この猫だって、平井が触る時は普通だったのに、俺が触ったら噛みついて来やがった。だから口にロケット花火を押しこめて、殺してやった」
「やめて……もう何も言わないで!」
「マミだって、裏でクラスの奴らに虐められてたんだ」
「嘘だよ! マミちゃんなら、私に相談してくれた筈だよ!」
「平井が宛にならなかったんだろ」
沈み切った光原君の声は、ズキズキと私の心を次第に突き刺していく。
「麗太は、俺にこう伝えてくれた」
麗太君まで……。
「いちいち鬱陶しい」
麗太君の本音。
それが私にとって、最後に耳にした言葉だった。
もう一歩下がった所に、足場はなかった。
景色が一気に急降下して一転する。
目の前には暗闇が広がり、体中をナイフで刺されたような感覚を覚える冷たさが、私の頭から爪先までを覆っていた。
川に落ちたのだと、ようやく気付いた。
岸に這い上がろうとするが、体が思う様に動かない。
苦しくて目も開けられず、ただ手足をバタつかせる事しか出来なかった。
もう落ち着いた思考を巡らせていられる余裕は、今の私にはなかったのだ。
やがて全身の力が抜け、体が動かなくなる。
私、ここで死ぬんだ。
今までの事を思い出してみると、胸が痛んだ。
私はいつもマミちゃんのオマケで、引っ付き虫だった。
マミちゃんに構ってもらえなかったここ最近は、麗太君の元へ逃げてばかりだった。
やっぱり鬱陶しかったんだ。
それにママ……。
優太っていう子の代わりになれなくて……馬鹿で、ごめんなさい……。
皆、ごめんなさい。
Next view ~Reita Sayahara~
クラスの様子がどこか違うと感じたのは、優子と学校に来てすぐの事だった。
廊下で友人達に無視された優子。
ただ気付かれなかっただけだと思っていた。
その時までは……。
教室に入ってすぐ、僕と優子はそれぞれ自分の席へ向かった。
僕の席と彼女の席はほぼ反対方向で、優子が窓側で、僕が廊下側に位置している。
クラス内では既に給食を配り始めていた。
そんな最中、綾瀬が話し掛けて来た。
「お前、給食だけ食べに来ただろ? もう授業だって一時間しかないし。まあ、いいか。ちょっと体育倉庫の鍵を閉めに行くんだけど、罰として一緒に来てくれよ」
久々に話し掛けて来た極普通の会話。
僕は僅かに安堵していたのかもしれない。
優子を教室に置き去りにし、綾瀬と外の体育倉庫付近へ向かった。
体育倉庫付近には誰もいない。
それを見計らったのか、綾瀬は僕を連れて倉庫の裏に周り、そこで話を切り出した。
なるほど、体育倉庫の鍵を閉めるというのは只の口実か。
そこまでしなければならなかった理由を、彼の言葉から知りたい。
「なあ、麗太。お前は俺の親友……だよな?」
当たり前だ。
もし喋る事が出来たのなら、そう断言していた。
今は頷く事しか出来ないけど。
「ありがとう。……優子の事なんだけど……。お前にとってはショックな話になるかもしれない。でも、お前をこのままにしてはおけないんだよ。だから……話すよ」
数日前から、クラス内で男女共に物がなくなる事が多かった。
俺と優子が学校をサボった、そんな今朝の事。
その日は週に一度の朝清掃の日だった。
優子の机を運んでいた女子が、誤って彼女の机を倒し、中の教科書等をばら撒いてしまったそうだ。
そこに入っていたらしい。
数日間、クラスの男女共に失くしていた色々な物が。
ある男子は、大事にしていたサイン入りの野球ボール。
ある女子は、大事にしていたキーホルダーや携帯。
その他にも、机の中からは色々な物が見つかったそうだ。
綾瀬と天美がよく一緒にいたのは、優子の事で相談事があったからであり、今までの綾瀬の僕に対しての対応は、平井が苦手だったからとの事らしい。
そういった点を踏まえれば、今までの二人の態度にも説明が付く。
それでも信じられなかった。
あの穏和な性格の優子が、そんな狼藉を働く筈がない。
何かの間違いに決まっている。
綾瀬が僕をここに呼んだ理由……。
それは僕を優子から遠ざける為だとすると、最も最悪な彼女の状況が浮かんだ。
このままでは優子が危ない。
何かの間違いであったとしても、こんな状況下の教室に優子を一人でいさせるなんて危険過ぎる。
教室へ走り出そうとした瞬間、綾瀬は僕の腕を掴み声を荒げた。
「行くな! あいつは猫被ってんだぞ?! お前も、そのうち何されるか分かったもんじゃない!」
それでも……優子は……僕の大切な人だから。
綾瀬の手を振り払い、そのまま教室へ向かった。
階段を駆け上がり廊下を走り、辿り着いた教室の中を見渡す。
優子の姿がない。
彼女の机の上にはランドセルが置かれているのだが、その上に給食がぶちまけられている。
駆け寄り、ランドセルに掛かったおかずや汁物等の具材を手で拭き取り、床に捨てた。
ポケットからシャーペンとメモ用紙を取り出し、筆談の為の文章を書いて、ちょうど近くにいた男子にそれを渡す。
『誰がこんな事をした? 優子はどこ?』
答えずらそうに俯く。
今は一大事だ。
どんな手でも使って見せる。
メモ用紙を片手に俯く男子の胸倉を、僕は強引に掴んだ。
周りがざわめく。
「おい、麗太……ちょっと待てよ……。いくらお前の彼女でも、犯人は平井なんだぜ? あんな奴……もう縁切りした方が身の為だぜ?」
こんな奴に……僕と優子の何が分かるっていうんだ!
胸倉を掴んだまま、思いっ切りそいつ目掛けてジャンプして体重を掛けた。
こいつと僕の体格は同じくらいか、僕の方が劣っているか。
それでも全体重を掛けて、体の一点に目掛けて飛び掛かれば、こちらが圧倒するなんて容易な事。
以前、上級生ともめ事になった時、綾瀬が同じ様な事をしていたのを覚えている。
そのまま彼の腹を潰す態勢で、胸倉を掴んだまま床に倒れ込んだ。
今まで大人しかった僕が、こんな事をしているんだ。
珍しさから来る恐怖で、既に彼は悲痛な呻き声を上げている。
「やめろ! やめてくれ! 平井は、俺が給食をぶちまけてやったらどっか行っちゃったよ! 俺は何も知らない!」
こいつが……優子を……。
拳を握り、一発だけ殴ってやった。
集まってきたクラスメイトの野次馬を掻き分け、先生が来る前に教室を出て、外へ向かった。
その後、ひたすら街中を探し回った。
商店街、駄菓子屋、郊外、公園。
家に帰っているのかと覗いてはみたが、優子の母さんしかいない様だ。
優子の母さんには、今は先程の出来事は話さない方が良いと判断した。
余計な心配を掛けたくなかったのだ。
一人で優子を見つけ出して、クラスメイトの誤解を晴らし、全てを元に戻す。
そんな無謀な考えを、この時の僕は本気で実行しようとしていた。
しかし、優子が見つからないのでは話にならない。
いったい、どこへ?
彼女の行く宛てのある場所は全て潰した筈。
とにかく今は、一刻も早く見つけ出すのが先決だ。
走っても走っても、優子は見つからない。
辺りは暗くなり、完全に夜になっている。
先程、公園で時間を確認した時は、夜中の十一時を周っていただろうか。
長時間、街中を駆けまわった為、もう歩くだけで精一杯だった。
住宅街を一人、ふらふらと歩く。
とりあえず家に帰ろう。
もしかしたら、優子が帰って来ているかもしれない。
僕自身が皆に心配を掛けるわけにもいかないし。
でも、もし……まだ優子が帰っていなかったら……。
視界がぼやける。
くそ!
なんで泣いてるんだよ!
僕自身が挫けたら終わりじゃないか!
涙を拭い、疲れ切った足でもう一度走り出した。
早く優子に会いたいという一心で……。
優子の家には、電気が点いていなかった。
それは外から確認する事が出来た。
優子の母さんもいないのだろうか。
もしくは、やはり優子は戻っておらず、探しに行っているか。
玄関の鍵は開いていた。
真っ暗な廊下の電気を点け、リビングへ進む。
リビングのドアは閉められているが、そこに誰かがいる気配がある。
テレビだけは点いているのか、音が部屋から漏れ出している様に聞こえる上、その音と共に、よく知る名前を連呼する声が聞こえてくる。
「優子……」
一歩ずつ近づく度に、その声はより聞き取り易くなる。
「優子……」
冷や汗の滲む手でドアノブを握り、意を決してリビングのドアを開けた。
テレビの青白い光と共に、その光景が視界に入る。
テレビに映る、幼い日の優子。
それを見ている一人の女性。
優子の母さんだ。
床のあちらこちらには、ワインやウィスキー、日本酒等、その他諸々の酒瓶が転がっている。
テレビにはビデオカメラが繋がれている。
ずっと、優子の帰りをこうして待ち続け、大量の酒を飲んでいたとでも言うのだろうか。
「優子……優子……優子……」
テレビの前でひたすら、その名前を連呼する姿は、普段の優子の母さんからは想像も付かない様な光景だった。
どうやら、こちらの存在には気付いていないようだ。
近付こうと一歩踏み出した時、電話が鳴りだした。
彼女は電話の音にも全く動じる事なく、ひたすら名前を連呼し、画面を見続けている。
もし、警察に捜索願を出していたのなら、その報告かもしれない。
喋る事は出来ないが、今の状況下で電話に出られるのは僕だけだ。
受話器を取り耳に当てる。
「平井さんのお宅ですか? こちら先程、お電話頂いた――――お宅の娘さん――――」
何もかもが信じられなかった。
どうして優子が、こんな目に遭わなければならなかったのか。
僕の母さんも、どうしてあんな目に遭わなければならなかったのか。
死ぬのは……僕でよかったのに……。
「落ち着いて聞いて下さい。娘さんが、河川で死体となって見つかりました――――」
電話を受けた数時間後。
どうにか持ち直した優子の母さんを連れて、優子が運ばれた近場の病院を訪れた。
小さな優子の顔に掛けられた布。
青白く変色した肌。
霊安室に、死体となった優子は眠っていた。
優子の母さんはまだ酔いが回っていたせいもあるかもしれないが、始めは状況を把握出来ていなかった。
しかし、次第にその表情は悲哀に染まり、大きな鳴き声が室内に響いていた。
僕だけが、先に家に帰された。
優子、優子の母さん、僕。
いつも三人でいた家。
でも今は自室に僕一人だけ。
目蓋に涙が溢れ出し、やがて大粒が頬を伝った。
母さんの時と同じだ。
僕のせいで……僕が優子を守れなかったから……。
玄関のドアが開く音がした。
優子の母さんが帰って来たようだ。
それでも動く気にはなれない。
椅子の上で背中を丸めて、ひたすら泣いた。
「あなたが泣いて、どうにかなる事じゃないのよ」
低い声と共にドンッと、床を打ち付ける大きな音が部屋に響いた。
床に背中から打ちつけられたかと思うと、喉に激痛が走った。
首を絞められている。
誰に?
痛みで瞑っていた目を開けて、驚愕した。
床に倒れている僕に馬乗りになり、優子の母さんは恐ろしい形相で僕の首を絞めていたのだ。
「全部、あなたが悪いのよ。どうして優子を守ってくれなかったの? あの子にとっては、あなたこそ全てだった。あなた自身も、優子が全てだった筈」
僕の首に掛けられた手は、力の加減を知らない。
それどころか、彼女の言葉の一言一言が発せられる度に、その力は増していく。
「そう、あなたのママ。……楓だって、あなたさえいなければ死なずに済んだ。全部、あなたが悪いのよ!」
そうだ。
死ぬのは僕だけで良かった。
母さんも、優子も……きっと僕さえいなければ死ぬ事はなかった。
僕さえ、いなければ……。
「香奈! 何やってるんだ!」
突然、男の人の声が部屋に響いた。
優子の母さんはそれを聞いて咄嗟に、僕の首から手を離す。
呼吸が元に戻り、苦しさから解放される。
「皓! 戻って来てくれたのね!」
皓と呼ばれた男の人の元へ、彼女は抱き付く。
「皓! 優子が! 優子が!」
「分かってる。辛かったよな……本当に……」
男の人は泣いている。
「大丈夫だ。今は、俺が付いていてやるから」
「皓、あいつが……あのガキが優子を! 優子を!」
彼女は僕を指差し、男の人に訴え掛けている。
「分かった。そうだな」
僕の方を見る。
「君が麗太君か。香奈がすまなかったな。今夜は少々、取り込みが多いから、このまま寝てくれ。詳しい事は明日にでも話そう」
そう言うと男の人は、彼女を慰める様に頭を撫でながら、共に部屋を出て行った。
翌朝、皓という男の人とリビングで話をした。
優子の母さんは部屋で寝ている。
「俺は平井皓。優子の父親だよ」
優子の父さん。
会ったのは昨晩が初めてだ。
見たところの印象は、優子の母さんと年は同じくらいだろうか。
僕の母さんとも年は近そうだ。
『沙耶原麗太です』
いつも通りに筆談で返事をした。
どうやら僕の事情も踏まえている様だ。
「ああ、聞いてるよ。優子の事、今までありがとうな」
深々と頭を下げる彼に、僕は首を横に振る。
「昨日の事、気にしているのか? 麗太君のせいで、ああなったとは思っていないよ。香奈には、よく言い聞かせておくし」
この人も、優子を亡くして辛い筈なんだ。
それでも、こうやって僕と向かい合って話をしてくれている。
たったそれだけの事が、今の僕にとっては大きな慰めとなっていた。
「これからの事なんだが……俺はこの家で香奈と暮らす事にするよ。寂しい思いを……させたからね……。それに、まだまだやる事も残っているし」
この人が、今日からここで暮らす。
優子のいない、この家で……。
「昨日の夜。香奈を寝かした後。麗太君の父さんから連絡がきたんだ」
父さんが?
母さんの葬式にも参加する事もなかったのに、どうして今になって?
「もし、麗太君が望むのなら……だけど」
彼は一瞬の間を置いて言った。
「この街を出て、一緒に暮さないか? って。短い間ではあったけど、仕事の都合上で息子を一人にしてしまった事は申し訳ないと思ってる。そう言っていたよ」
おそらく、この家には、もう僕と一緒にいる事を望んでくれている人は一人もいない。
僕がいたとして、この家に住む二人とは何の接点もないのだ。
ましてや優子の母さんは、僕の首に手を掛けた程の人だ。
この家は僕の居場所じゃない。
『この街を出て、父さんと暮らします』
それが僕の出した答えだった。
優子も、優子の母さんも、家族同然の様に思っていた。
僕がこの家に預けられた日、二人は僕に対して家族同然の様に接してくれた。
それなのに今は……。
所詮、隣近所というだけの関係でしかなかったのだと、改めて思い知らされた。
その時、まるで鬱陶しかった重荷が外れた解放感と、自分自身の中で大切な何かを失ってしまった喪失感を覚えた翌日の朝。
声が出せるようになっていた。
声を取り戻した日。
この日が、優子の家で過ごす最後の日という事になる。
夕方に父さんが、僕を迎えに来るらしい。
それまでに学校へ行き、荷物等の整理をしなければならなかったのだが、今の僕にとって、いつも通りに学校へ行く気になど到底なれず、早朝に優子の父さんと二人で学校へ行き、先生への挨拶や荷物の処理をした。
その後に今まで通っていた脳外科医にも行った。
「今回の場合は……何かしらのショックや、ストレスからの解放等の精神的な変動が原因かもしれませんね」
かかり医は、さも当然の様に淡々と話していた。
僕の様な症状を出す人は、極稀というわけでもないらしい。
学校と病院、行くべき場所には全て行ったので、今日はずっと家にいる事になる。
優子の父さんと母さん、そして二人とは何の接点もない僕の、昨日と今日の数時間ではあるが三人で過ごす最後の一日は、なんとも奇妙な生活だった。
僕は声を取り戻していたにも関わらず、その事を優子の父さんに告げただけで、それ以外の場で言葉を発する事はしなかった。
第一に、優子の母さんは、もう僕と言葉を交わす気になんてなれない筈だ。
やがて陽は傾き、西日が窓から差し込む。
ずっと自室の椅子に座ってボーっとしていた。
まあ、どうせもうすぐ僕の部屋じゃなくなるんだけど。
そろそろ父さんが迎えに来る頃だ。
早いところ、この家……いや、この街から逃げ出したい。
この街には忘れたい事が沢山あるから。
そう思ってはいるのだが、まだこの街でやる事は残っている様に思える。
これで、良いのか?
こっそりと学校へ行き、荷物を全てまとめて先生にだけ会って、友達には何も言わずにこの街を去る。
この街で生まれて、この街で生きて、この街で友達を作って……親友もできた。
このまま街を出たら、きっとこれから先ずっと後悔する。
「忘れちゃいけない事も……あったんだ……」
部屋から出て階段を駆け下り、家を出た。
外では優子の父さんが一人、煙草を吸っていた。
「麗太君、どこかへ行くのか? もうじき、父さんが迎えに来るぞ?」
「この家を……この街を出る前に、どうしても会っておきたい人がいるんです」
彼は左腕の時計で時間を確認し言った。
「まだ余裕があるな。行ってくると良い。自転車だってある」
庭の隅には自転車が置かれている。
たまに優子の母さんが使っていたママチャリだ。
「誰だって、後悔だけは……したくないからな」
それだけ言うと、彼は煙草を片付けて家に戻った。
好きにしろ、という事だろうか。
何にせよ時間がない。
自転車を走らせ、――――の家に行ってみた。
インターフォンを押したのだが応答がないところを見ると、まだ家には帰っていない様だ。
夕方……この時間、放課後に――――が行きそうな場所といえば……。
あいつを探し自転車を走らせていたところ、偶然にも数人のクラスメイトに出くわした。
転校の事やこれからの事、喋れる様になった事、色々な事を聞かれた。
やはり小学校生活を共にした仲だ。
いざ会ってみると、別れが辛くなるものだ。
この後の事を考えると余計に……。
しかし時間は待ってはくれない。
早急に事を済ませる為に、彼等に聞いた。
「――どこにいるか分かる?」
「そうだなぁ……あいつ、お前が転校するって聞いて、かなり落ち込んでたし。俺等が放課後に遊びに誘ったんだけど、やっぱり断られたよ」
「そっか……」
「あ、もしかしたら、あの駄菓子屋とか。よく一緒に行ってたじゃん?」
駄菓子屋。
そこに――――と始めて行ったのは、まだ僕が喋る事が出来なくなってすぐの事だった。
駄菓子屋の外に置かれているベンチに、――――は座っていた。
何も買っていなかった様で、ただ俯いて座っている。
すぐ側に自転車を止め、近付く。
「綾瀬……」
呼ぶと、ハッと我に返った様に僕の方へ顔を上げる。
「麗太……」
一度だけ驚いた表情を浮かべて、すぐに微笑んだ。
「隣、座っていい?」
「おう」
綾瀬の隣に、少しだけの間隔を保ちつつ座った。
「喋れるように、なったんだな?」
「うん。……色々あって……」
少しだけ沈黙が降りる。
いざ会ってみたはいいが、何を話すべきか分からなくなってしまう。
きっと、綾瀬も同じだ。
「……そういえば、今日限りで引っ越すって、本当なのか?」
「うん。引っ越して、父さんと二人で暮らすんだよ。もう、優子もいないし……。優子の母さんと父さんの事もあるから……」
「そっか。平井の事……悪かったな」
「どうして綾瀬が謝るの?」
「あの時、麗太を外に連れ出さなければ良かった。お前が付いていれば、平井は勝手に学校を抜け出して……あんな事には……」
俯く綾瀬の肩に手を置く。
「綾瀬のせいじゃないよ。でも、やっぱり辛かった。優子は、僕の大事な人で……家族だったから……」
綾瀬は立ち上がり、僕に手を差し出す。
「麗太、お前はまだ一人じゃない。俺だって、お前の事は家族も同然だと思ってた。だから……」
僕は彼の手を握り立ち上がる。
「綾瀬は僕にとって親友……勿論、家族でもある。だから、いつか必ず帰ってくる」
握っていた彼の手に力が込もる。
「ありがとう」
そう言った、綾瀬の瞳は涙で濡れていた。
きっと、綾瀬に会わなかったら公開していたと思う。
僕が生まれてからずっと過ごしてきた、この街での思い出は、こんなにも陳腐なものだったのかと。
でも、最後に綾瀬に会えて良かった。
母さんや優子の死までもが、ただの出来事であったと成り果てた今、綾瀬に会えた事で、全ては意味のある出来事であったと気付けたのだから。
この街で過ごしてきた今日までの出来事は、絶対に忘れはしない。
そして、いつか必ず戻って来ると心に固く誓った。
七年後。
僕は、再びこの街を訪れる事になる。
でもそれは、また別の話。
Epilogue Memories
ただ、毎日を惰性の様に過ごしていた。
朝早くから別段理由もなく学校へ行き、友達と駄弁り、将来の為になるかも分からない授業を聞いて、また家に帰る。
家に帰れば家事全般。
親父は仕事で週に三度程しか帰って来ない。
まるで日常に色がなかった。
いや、モノクロとでも言うべきだ。
いつの事だっただろうか。
大きくどこまでも広がっている真っ青な空に想いを馳せ、自分が何にでもなれそうな予感に浸っていた頃。
そんな時期が、俺にもあったんだ。
今や高校一年生の秋。
そんな事を考えていられる余裕なんて、ありはしない。
学校からの帰りの電車。
ボックス席に向かう彼女。
気持ち良さそうに寝ていやがる。
日々変わらない日常に飽き飽きして、いざ彼女を作ってはみたが、特に変わり栄えもしなかった。
いや、俺を引っ張ってくれる女の人が、より親しい存在になったとだけと考えれば、かなりの変化にはなるのかな。
それに反して、かつて隣にいた筈の優子の存在は、結局は一時的な関係でしかなかったのだと、あの日に思い知らされた。
小学生の頃の思い出なんて、所詮その程度のものだ。
窓から見える、折り重なったビルの隙間から夕暮れの差す都心の風景。
あの頃の俺に、こんな光景を見せてやりたいよ。
きっと大はしゃぎする筈さ。
それに、隣にいた優子も……。
To be continued in Next episode.
Remember me? ~children~
読んで下さった、ご苦労さまでした。
これで一先ず完結です。
色々な事がありましたね。
序盤の優子ちゃんと麗太君の、ほのぼのとした日常は書いていて楽しかったです。
中盤の優子ちゃんのお母さんの話は、なるべく大人な雰囲気を出したくてアダルティーに。
終盤のマミちゃんや綾瀬君の話は、もう救いようのないくらいに鬱々と。
最後の話は続編への繋げなので、謎を残しまくりました。
はい勿論、続編はやりますよ。
だって、あれじゃあ皆が可哀相じゃないですか!
綾瀬君に関しては別ですが。(彼も可哀想な子です)
ていうか麗太君と綾瀬君がお別れをする最後の場面。
読者様の、こいつ。彼女の仇同然の奴とお別れの挨拶して感動してる。こいつ面白れぇ(笑)」みたいな。
全部、続編でケリを付けるつもりです。
「綾瀬君には墓前で土下座させてやりますよ!」くらいな意気込みで\(*`∧´)/
今後も執筆を続けていきます。
続編も手に取っていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。


