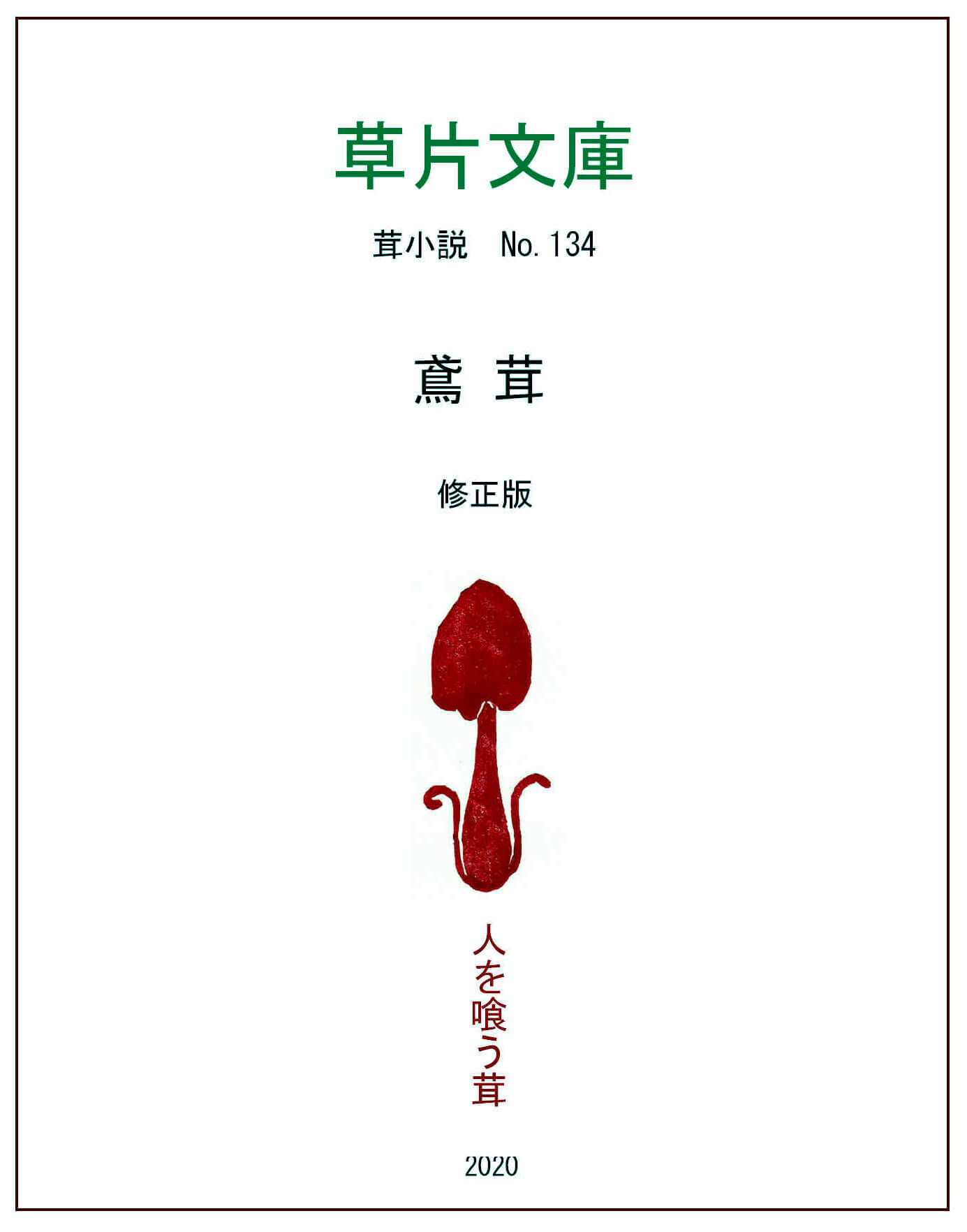
鳶茸(とびたけ)
茸長屋のどたばた小咄 縦書きでお読みください。
夏の終り、秋の兆しが見えてきた今日この頃でございます。
ここは江戸よりいくつもの山を越えて歩くと二日ほどの北の国、山間に開けた、小さなお城のある町でございます。この町は温泉がいたるところに出ておりまして、山の幸に恵まれている、とても住みやすいところでございます。
このお城の奥方様は京都より興入れされた方、そのお陰をもちまして、町並みは、小さな京の都のような雰囲気をもつものでもございます。みな小さいながら、商人の家にしても、なかなかしゃれたものが建てられております。それに、江戸の町とも似たところがあり、暮らす人たちは、明るい気風がよろしゅうございます。
町の真ん中を通る熊井川の辺に小奇麗なお城がございます。平城で、堀もなく、大きなお屋敷といった佇まいでございます。城を中心として町は山際まで広がっており、山裾には、町民たちの住む長屋が建てられております。そのつくりは江戸深川あたりとよく似たものでございます。
川を渡りますと、こちら側は農業を営むもの達が住んでおり、山際まで田が広がっております。所々に田を所有する庄屋の家がちらほらと点在しております。山裾には田で働いている小作人の家がございます。
町は秋祭りの準備、なにやら楽しそうに人々が行きかいます。長屋では夕ご飯を食べ終えた連中が、縁台で夕涼をしております。
茸(たけ)取(とり)長屋の一角で、松五郎と竹五郎が将棋板をはさんで、へぼ将棋の最中です。二人は長屋の隣同士、どちらも腕のいい鳶職で同じ親方のところで働いていることから仲がいい。年も同じくらいの独り者でございます。
この長屋に住んでいる人たちは年も様々、子持ちもいれば、やもめもいる。しかし、どの男たちも手に職を持ち、よく働く者たちで、女房、女たちも気の利く優しい者ばかりでございます。面白いのはみな茸を採るのが上手。それぞれに自分の得意の茸山があり、そこで、旨い茸を採ってくる。朝市に出して、副収入にしているわけでございます。
長屋の本当の名前は八(や)茸(たけ)長屋。八茸爺さんが造った長屋です。この長屋、ちょっとそこいらの長屋とは違います。便所がそれぞれの家にある、それに、ゆったりとした土間と、かなりの広さの部屋が二つと、かなり上等なものでございます。
茸取長屋と呼ばれるのには訳がありました。
八茸爺さんの若い頃の名前は八(や)竹(たけ)ででございます。八竹がまだ小さい頃、十か十一でしたでしょうか、ある日、竹を採ってくるようにいいつかりました。近くの山に入り、一本の大きな竹を切ったところ、中から真っ赤な茸がいくつも転がり出てまいりました。
なんだ、この赤い茸は、竹の中に生えているとは摩訶不思議。子どもながら、きっと面白い茸に違いないと思った八竹は、赤い茸を懐に入れ、切り採った竹を家にもち帰りました。親には黙っていたのでございます。
熊井川の茸橋の袂では、朝市が行なわれています。八竹は隅っこで、赤い茸をならべました。すると、子供をつれた旅姿のお侍が、八竹の前に立ち「この茸をどうした」と訊ねたのでございます。八竹は「竹の中からでてきた」と答えたところ、「みなもらおう」と、法外な値段で買い取ったそうでございます。
後で知ったことですが、その方は江戸の高名な薬師だそうで、なんでも、江戸のえらい殿様が奇病にかかり、それに利くとされる茸を探しにこの町にまで旅をしてきたそうでございます。
八竹の採った、竹から出た赤い茸が探していた茸だったわけです。その後、八竹は何度も竹から赤い茸を採りました。その茸は江戸から使いが来て、すべて買い上げたのでございます。その茸のお陰で殿様は回復し、いつもの暮らしに戻ったということでございます。
八竹はそのことも親には言わず、もらった金は壷に入れ、柿の木の根元に埋めておいたそうです。いつか、何かの役に立てようと思ってのことでした。
十三になった八竹はもっぱら茸採りに専念して、山の奥から薬になる茸をずい分見つけてまいりました。そのお陰で八竹は茸とりの名人といわれるようになり、その時から、名前の字を八茸と変えました。
八茸の名前は茸採りの名人として知れ渡ることになり、やがて、年老いた両親を看取った後は、茸採りの弟子までかかえ、楽な生活をしたということでございます。
年を重ね、山に入るのが億劫になった八茸爺さんは、柿の木の下から壷を掘り出し、竹から採った赤い茸の代金と、茸採りで貯めたお金で八茸長屋を建てたのでございます。それが周りからは茸取長屋と呼ばれるゆえんでございます。
こうしたことから、この長屋には自然と茸の好きな連中が集まった次第でございます。今でも長屋だけではなく、町の人たちは、面白い茸にでくわすと、八茸爺さんのところに、食べられるものか、薬になるか相談にまいります。この八茸爺さん、百姓の小倅にもかかわらず、書を読むことができ、書くこともできるだけではなく、たくさんの茸の図譜をもっておりました。
「竹、明日あたり、茸採りでも行くか」
「うん、明日は仕事がないって親方が言ってたな」
大工の仕事は家一軒建て始めると休みもなくなりますが、後は、家の養生を頼まれた時ぐらいのもので、結構、のんびりとしておりました。
「舞茸が出るかも知れねえな」
ということで、松五郎と竹五郎は、次の日の朝早く、熊おいの鈴を腰に吊るすと、籠を背負って出かけました。長屋から出ると、熊井川にかかる茸橋を渡り、田んぼをつっきると山沿いの道を歩いていきます。途中から山道にはいり、一時間ほど歩きますと、辰巳山になります。そこが松と竹の茸山でございます。
「そろそろ、いつもの楢の木の下に舞茸が生えているだろうな」
「うん、去年はあまり大きくなかったけど、今年は良さそうだな」
「そうだな、夏は暑かったからな」
ぶな林の入口にまいりますと、細いぶなの根元に白っぽい舞茸が生えています。
「竹、ほら、白いのが生えてら」
「あまり美味そうじゃないね、白っぽくて売れそうもないじゃないか」
「もっといいのがあるだろう、籠が空いてたら後でこいつも採っていこう」
そう言いまして、二人とも、林の奥に入っていきます。
水(みず)楢(なら)の大木が立ち並んでいるところに出ますと、なんと、いたるところに大きな黒い舞茸が、空に舞いあがるような勢いで生えております。
「やっぱりあった、こりゃあ、すごいね、大もうけだよ、この籠に入りきらねえな」
さて、採ろうと、二人は林に足を踏み入れます。と、ボソッと大きな音とともに、二人とも大きな穴の中に落っこちてしまいました。
「おおいてえ、どうなってるんだ、こんなところに穴がありやがる」
「誰が掘ったんだ」
見上げますと、何本かの水楢の木が天高く聳え立っているのが見えます。その先にに青空がのぞきます。穴は二人がゆったり入るほどの大きさですが、あまり深くありません。ちょっと背伸びをすると手が穴の周りに届くくらいです。
「怪我はねえかい」
「うん、大丈夫だ、危ないね、なんだろう、猪や狐のわなをしかけようとしたのかもしれねえな」
その時、穴の上でかさかさと音がする。二人が上を見ますと、なにやら動いている様子。
「人がいるみたいだ」
「いや、動物みてえだ」
白っぽいものがぴょこぴょこ、穴の回りを飛んでいるようです。
「竹、ちょっと肩車してくれ、穴の外をのぞいてみらあ」
松五郎が首にまたがると、竹五郎はよいしょと持ち上げます。
松五郎の顔が穴から外に出る、
「ひゃあ、ありゃなんだ」
松五郎の目玉が飛び出します。
「どうしたい」
「白い舞茸が飛び跳ねて、俺の顔を見て笑って喜んでる」
「なにおかしなこと言ってるんだ、茸が笑うか」
竹五郎は松五郎を下に下ろします。
「お前、見てみろよ」
今度は松五郎が肩車をします。
顔を出した竹五郎も「ひゃあ」と素っ頓狂な声を上げます。
「白舞茸が笑ってらあ」
と言ったとき、竹五郎の頭の上に白舞茸が飛び乗ってきました。
竹五郎は頭の舞茸を振り払うと「下ろしてくれ」と叫びます。
竹五郎は穴の中に戻ると、穴の入口を指差しました。
「ほんとに、何だあいつらは、茸の化け物か」
松五郎が穴の入口を見上げると、白舞茸がくるくると空を舞っています。白舞茸が一つ、穴の中に降りてきて、松五郎の頭の上に止まりました。
「ひゃ、ひゃ、こいつは出来が悪い人間だね」と人の言葉をしゃべりました。
松五郎が追い払うと、白舞茸は舞い上がって、笑います。いや、笑っているように見えたのでございます。
もう一つ白舞茸が飛んでくると竹五郎の頭に止まりました。
「この二人はあまり旨そうじゃないな」
その白い舞茸が、松五郎の頭上にいる白舞茸に言います。
「ああ、今年は不出来だな」
「どうする」
「もう少し大きくしてから喰おう」
二つの舞茸はそう言うと、飛び上がって、穴から出ていきました。
「おい、逃げよう」
「そうだな、逃げよう」
松五郎が肩車をしてもらい穴から顔を出すと、たくさんの大きな白舞茸が空高く舞い上がって、踊っています。この時とばかり、松五郎は穴から出て、竹五郎を引っ張りあげ、一目散に山から駆け下りたのです。
それに気付いた白舞茸は列をなし、松五郎と竹五郎の後を追いかけます。
あまりにもあわてていたものですから、二人は、木の根につまずいてころんでしまいました。
「ひゃあー」という二人の叫び声。
白舞茸はどーっと舞い降りると、二人のからだに取り付いて、じょろじょろと舐め始めたのです。
「気持ちわりい」
舞茸の涎が二人の着ているものをびしょびしょにしてしまいました。
「ほら、立てよ、逃げよう」
松五郎と竹五郎は舞茸を振り払い、立ち上がると、ほうほうの体で駆け出しました。辰巳山を出て、隣の山に入ると、舞茸は空中で停止し、あかんベーをしています。そのように二人には見えたのでした。
「おー、怖かった」
「からだが、べたべたする」
「湯にはいらなきゃ、茸臭いなあ」
「ありゃなんだったのだろう」
「人食い舞茸だ」
家に戻った松五郎と竹五郎は、早速湯屋に行きまして、さっぱり致します。
「怖かったな、何かに化かされたのかな」
「あんなとこにゃ、狸はいねえし、なんだろう」
その晩、二人で飯を食おうと、秋刀魚を焼いて、味噌汁をつくり、松五郎の家で晩御飯を食べておりますと、とんとんと、戸をたたく音がする。
「だれだい、入ってこいよ」と松が声をかけます。
入口の戸がすーっと開くと、辰巳山で最初に見つけた?の根元にあった小さな白舞茸が、ふわふわと宙に浮いております。
「わー、でた、人食い舞茸だあ」、二人は「喰わないでください」と、白舞茸に向かって頭を下げます。
白舞茸は床の上に音もなくすーっと降りてまいります。
白舞茸がにーっと笑いました。松五郎が白舞茸に手を合わせました。
「舞茸様、なんかあっちらが、悪いことをしたのなら、謝ります、どうか喰わないでください」
小さな白舞茸が言いました。
「今日は、驚かしてすまんでしたな、仲間がおいらをかばってくれましてな、お二人にいたずらをしちまった、おいらは白いが、旨いのだよ」
そこで、松五郎と竹五郎は小さな白舞茸を採らなかったことに思い至りました。
「いえ、わっちらが悪いんで、馬鹿にしちまってすみません」
平身低頭、松と竹は白い舞茸に謝りました。
「いやいや、今日の夕飯に茸がないのは寂しいでしょう、まだ秋刀魚を焼いた火が残っておりますな、あの上に乗りますから、食べてください」
そう言うと、白舞茸は飛び上がって、七輪の上に乗る。すると、白舞茸の焼けるいい香りがしてまいります。
白舞茸は焼けながら「早くお食べなさい」と二人に言います。
松五郎と竹五郎は焼けた白い舞茸を、醤油に漬けていただきました。いい香がして、お飯を三膳も食べてしまったのです。それにいくら食べても白舞茸は減りません。
「旨かったな、竹」
「ああ、旨かった」
食べ終わった松と竹が目の前をみますと、白舞茸が宙に浮かんで笑っている。周りを見ますと、たくさんの黒い舞茸が板の間の上で笑い転げています。
松と竹がなんだと、見ますと、床の上に、焼けた黄色い茸が山盛りになっているのに気がつきました。
白舞茸はすーっと消えていきました。
「おい、おれたちゃ、あの茸を食っていたんだ」
「なんだ、あの黄色い茸は」
松五郎が言ったとたん、二人のお腹がごろごろと鳴り、厠に駆け込んだのでございます。
そのあと、何回か厠にはいりますと、二人はやっと落ち着きました。
「あの茸は腹を下す茸じゃないか」
いうなれば、下剤にする茸です。
「白舞茸にやられちまった」
「だけど、喰われなかっただけよかったかもしれねえな」
「これから、茸を採りに行ったときに、どんないたずらをされるかわかったものじゃない」
「八茸爺さんに相談しよう、あの家主は物知りだからね」
「そうしよう」
二人は大家さんの家に参ります。
「どうしたんじゃ、二人そろって、茸が採れなかったんかい」
二人が大家さんちの入口に入りますと、黒犬の梅と、黒猫の、これまた梅がそばに寄ってまいります。大家さんの庭には紅白の奇麗な梅の木があり、犬にも猫にも梅と言う名前をつけてしまったのです。黒猫の梅は松五郎が大好き、黒犬の梅は竹五郎を贔屓にしております。二人が家に来ますと、松竹梅だ、と八茸爺さんは喜びます。
「いえね、辰巳山に行ったら、舞茸がそこらじゅうに生えていたんですがね、大きな穴があって、あっちら、二人ともそこにおっこちまった」
「それで、いってえ誰が掘ったんだとちょっと腹が立ったのですがね、なんと、白い舞茸が飛び跳ね、宙に舞って、俺たちを笑いやがったんで、それだけじゃねえんで、じょろじょろ舐められちまった、気持ち悪いっちゃないんで」
「ほうそれで、どうしたい」
「白舞茸のやつ、俺達のことを、今年は人間が不出来だから、もっと大きくなったら喰おう、なんていっておりやした」
「それに、さっき、飯を食っていたら、白舞茸が飛んできて、自分を食えって七輪の上に乗って焼けちまったので、食ったら、腹を下す茸だったんで、白舞茸のやつ大笑いしてやがった」
「舞茸にいたずらをされたのだな、しかし、命拾いをしたものじゃな、その白い舞茸は何に生えておった」
「へえ、?の木の根元にありやした」
「そうか、その白い舞茸は?舞茸ともいうが、本当は鳶舞茸というのだ。出羽のほうでは、鳶茸と申してな、舞茸より旨いと好む者が多いとのことだ」
「でも、白くて旨そうじゃなかった」
「茸というものは食われるのが大好きなのじゃ、特にあの鳶茸は自分たちは舞茸一族の味の大様だと思っておる。馬鹿にすると、人食い茸になるという話じゃ」
そこで二人は顔を見合わせたのです。
「鳶茸に喰われた人ってのはいるんですかい」
「その昔な、信州の老人に聞いたことがある」
「信州も茸が採れるんで」
「そりゃあ、よく採れるところだ、ここと同じようにな」
「それで、どんな話で」
「その老人は江戸まで旅をしてこの町のことを聞き、いい湯があるということで、湯治に来なすった」
この町には温泉宿も外の温泉も豊富にあります。
「たまたま、儂もその湯に入っておってな、お前達も知ってるじゃろ、茸湯にな」
川を渡って、反対側の山際にある、大きな湯治場で、今日、二人が登った辰巳山に入る山道の入り口にありました。いろいろな病に効くということで、江戸の人たちも、わざわざその湯に入りに参ります。もちろん、この町の人たちも、よく利用いたします。辰巳山を始め、そのあたりの山はみな茸がよく採れることから、茸採りの人たちが秋になると集まり、それで、茸湯という名がついたのだそうでございます。
「それでな、その御仁をふと見ると、左手首がない、こりゃ、きっと悪いやつらに切られたのだろうと思って、
『怪我の治療に湯に入りにこられたのかな』
ときいたのじゃ、するとな、その老人はうなずいて、
『確かに、この手の治療に参った」、と言いなすった。
裸になっちまうとわからないものでな、話の中で分かったのじゃよ、信州の小さいながら城の主だったのだよ、侍だ、伴もいなかったので、どこぞの商人かと思ったのじゃ、
『それは失礼しました』と、離れようとすると、
『いや、かまわぬ、話を聞いてほしいのだ』
と言うのじゃよ、それで、湯につかって、その老人の話を聞いた。
その老人は楽隠居の身じゃった。楽しみといえば食うことでな、朝、昼、晩と食いたい三昧、あるとき、煮た舞茸がでてきたのじゃが、色が黒っぽくて何か旨そうじゃなさそうと思ったそうだ、それで、、本物の舞茸をもってこい、と黒い舞茸をなげちまったそうだ。そう、それが鳶茸だったのだ、鳶舞茸は生えているときには白っぽいが、採ると黒くなる。家来は舞茸より旨い茸と知っておってだしたのだ。
その夜のことだった、寝ている老人の上にどしんと落ちてきたものがあった。老人は驚いて目を開けると、大きな鳶茸が布団の上に乗っている、その鳶茸が笑ったそうだ、なぜ喰わなかった、なぜ放り投げたといって、老人の顔に飛び上がってきた。それで、老人は起き上がり、刀を抜いて、この妖怪茸め、と切りつけたそうだ、すると、鳶茸が刀を持つ左手に食いつき食っちまったそうだ。お前はもう、茸の味は楽しめぬ、と言ってな、それで、すーっと消えたそうだ。
その老人は、痛く反省しておってな、鳶茸を馬鹿にすると、人食い茸になる、儂が悪かったのだ、自然の恵みを粗末にした罰だ、そう言っておったよ」
「茸の味がしなくなったら、おまんま旨くない、どうしよう、竹」
「明日、辰巳山に行って、謝ってこよう」
「そうじゃな、それがいい」
ということで、二人は、犬の梅と猫の梅に見送られて、長屋に帰っていきました。
あくる朝早く、松五郎と竹五郎は籠を背負って、また辰巳山に登りました。林の入口の白い舞茸、鳶茸に、
「昨日は申し訳ありませんでした、鳶茸さま、私どもが美味しくいただきます」
そう言って、深々とお辞儀をし、丁寧にその鳶茸を採ると、籠に入れたのでございます。
さて、そうしたら、その林の中に生えている鳶茸が宙に舞い、あっというまに二人の籠に飛び込んで、一杯になりました。
二人は鳶茸を煮て食べてみました。それは美味しい茸でした。
それを朝市に出すと、飛ぶように売れてしまいました。
「鳶茸は旨いね」
それから、二人が辰巳山にいくと、鳶茸が自分達から集まってきて、松五郎と竹五郎は鳶茸採りの名人といわれるようになったのでございます。
二人は鳶茸を売った金で、茸長屋の木戸口に、茸地蔵を建てました。
長屋の人たちは、茸を採りに行く前には、「おいしくいただきます」、と必ず茸地蔵に手を合わせるようになったということでございます。
鳶茸採りの名人、松五郎と竹五郎は、後に本職の鳶としても、腕のいい職人としてそれぞれが親方になったということでございます。
鳶茸(とびたけ)


